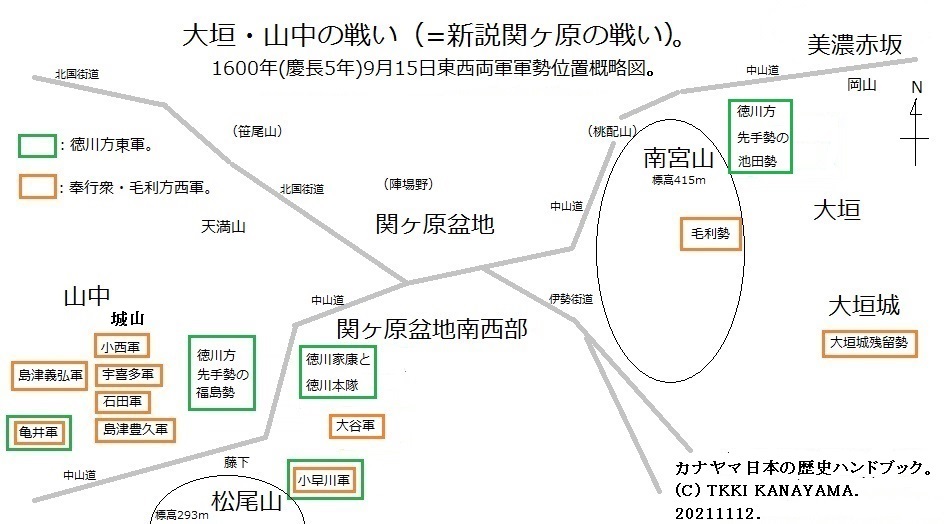
پںپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}پ@ƒIƒtƒBƒVƒƒƒ‹پ@ƒzپ[ƒ€ƒyپ[ƒWپBپ@پ@پ@ پ@
پ@پ@ ‚s‚j‚j‚hپ@‚j‚`‚m‚`‚x‚`‚l‚`پf‚rپ@‚n‚e‚e‚h‚b‚h‚`‚kپ@‚g‚n‚l‚d‚o‚`‚f‚dپD
پںپ@ƒJƒiƒ„ƒ}“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒNپB
‚j‚`‚m‚`‚x‚`‚l‚`پf‚rپ@‚i‚`‚o‚`‚m‚d‚r‚dپ@‚g‚h‚r‚s‚n‚q‚xپ@
پ@پ@ ‚g‚`‚m‚c‚a‚n‚n‚jپD
پ@
پ@
پ@ƒJƒiƒ„ƒ} “ْ–{—ًژjژ«“Tپ@
پ@“ْ–{Œê”إپ@پ@
پ@Œ©ڈo‚µŒêپ@پwپ@‚µپ@پxپB
پ@
پ@
#jpmenuپ@ پ@
ƒپ ƒjƒ…پ[ پi–عژںپjپBپ@پ@
پ@پ،پ@ژں‚جچ€–ع‚ً‘I‚رپAƒNƒٹƒbƒN‚µ‚ؤ‰؛‚³‚¢پBپ@پ@پ@پ@
پ@
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T پi‘چچ‡پjپB
پ@
پ پ@‚µپ@پ@پ@پ@ پœپ@Œـڈ\‰¹ڈ‡ پi ‚ ‚¢‚¤‚¦‚¨ڈ‡پjپB
پ@
پ@پ پ@Œ©ڈo‚µŒêپ@‚µ‚³پB
پ@پ پ@Œ©ڈo‚µŒêپ@‚µ‚بپB
پ@پ پ@Œ©ڈo‚µŒêپ@‚µ‚ـپB
پ@پ پ@Œ©ڈo‚µŒêپ@‚µ‚م‚ئپB
پ@پ پ@Œ©ڈo‚µŒêپ@‚µ‚çپB
پ@
پ@
پ@
پZپ@‚¶‚ پ@پ@ژ،ˆہپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚ ‚ٌپjپBپ@پ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚s‚g‚dپ@‚i‚h‚`‚mپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@‚P‚O‚Q‚P”Nپ[‚P‚O‚Q‚S”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@‚P‚O‚Q‚P”NپEژ،ˆہŒ³”NپE‚QŒژپ@‚Q“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚O‚Q‚S”NپEژ،ˆہ ‚S”NپE‚VŒژ‚P‚R“ْپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@•½ˆہژ‘م’†ٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژ،ˆہ پi‚¶‚ ‚ٌپA‰pپF‚s‚g‚dپ@‚i‚h‚`‚mپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚d‚q‚`پjپ@‚ئ‚حپAپ@کa—ï‚إ‚ ‚èپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•½ˆہژ‘م’†ٹْ‚جکa—ï”Nچ†‚إ‚ ‚èپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚O‚Q‚P”NپEژ،ˆہ Œ³”NپE‚QŒژ‚Q“ْ‚©‚ç
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚O‚Q‚S”NپEژ،ˆہپ@‚S”NپE‚VŒژ‚P‚R“ْ‚ـ‚إ
پ@‚جٹْٹش‚إ‚ ‚éپBپ@پ@
پ@
پZپ@‚µ‚¢پ@پ@ ژlˆتپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚¢پjپBپ@پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پiپث ˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@‹كپEŒ»‘م“ْ–{‚جپAگEˆُ—كپi‚Q‚O
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆتٹKپjپAڈ–ˆتڈً—لپi‚P‚UˆتٹKپjپAˆت
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹK—كپi‚P‚UˆتٹKپj‚جˆتٹKپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پƒ‚P‚W‚U‚X”Nچ پ`Œ»چفپAژg—pپ„پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@گ³ژlˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚¢پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@ڈ]ژlˆتپ@پi‚¶‚م‚µ‚¢پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ˆتٹK—ك‚جˆتٹKپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ڈ–ˆتڈً—ل‚جˆتٹKپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث گEˆُ—ك‚جˆتٹKپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹كپEŒ»‘م“ْ–{گ•{‚جˆتٹKپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚Pپjپ@ژlˆتپ@پi‚µ‚¢پj‚حپAپ@‹كپEŒ»‘م“ْ–{‚جپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@گEˆُ—كپi‚Q‚OˆتٹKپjپAڈ–ˆتڈً—لپi‚P‚UˆتٹKپjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆتٹK—كپi‚P‚UˆتٹKپj‚إپAپ@گ³ژlˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¢پjپ@‚ئپ@ڈ]ژlˆتپ@پi‚¶‚م‚µ‚¢پj پ@‚ج‚Q‚آ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆتٹK‚ئ‚µ‚ؤپAپ@‚P‚W‚U‚X”Nپi–¾ژ،‚Q”Nپjچ ‚©‚ç
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ»چف‚ـ‚إژg—p‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جپA’©’ى‚ج—¥—ك
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹ¯گ§ ‚جˆتٹKپi‚R‚OˆتٹKپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پƒ‚V‚O‚P”Nچ پ`‚P‚W‚U‚X”Nچ پAژg—pپ„پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@گ³ژlˆتڈمپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@گ³ژlˆت‰؛پ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚¢‚ج‚°پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@ڈ]ژlˆتڈمپ@پi‚¶‚م‚µ‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@ڈ]ژlˆت‰؛پ@پi‚¶‚م‚µ‚¢‚ج‚°پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ’©’ى‚ج—¥—كٹ¯گ§‚جˆتٹKپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ژQ‹cپAŒِ‹¨پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚Qپjپ@ژlˆتپ@پi‚µ‚¢پj‚حپAپ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’©’ى‚ج—¥—كٹ¯گ§‚جˆتٹKپi‚R‚OˆتٹKپj‚إ پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ³ژlˆتڈمپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ³ژlˆت‰؛پ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚¢‚ج‚°پjپAپ@ڈ]ژlˆتڈمپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚µ‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپAپ@ڈ]ژlˆت‰؛پ@پi‚¶‚م‚µ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¢‚ج‚°پj‚ج‚S‚آ‚جˆتٹK‚ئ‚µ‚ؤپA‚V‚O‚P”Nچ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚©‚ç‚P‚W‚U‚X”Nچ ‚ـ‚إژg—p‚³‚ꂽپB
پ@
پZپ@‚¶‚¢پ@پ@ ‚f‚g‚pپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚¢‚¦‚¢‚؟‚«‚مپ[پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پsچف“ْگè—جŒRپtپB
پi= کAچ‡چ‘ŒRچإچ‚ژi—كٹ¯
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘چژi—ك•”پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚P‚X‚S‚T”Nپ`‚P‚X‚T‚Q”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کAچ‡چ‘ŒR“ْ–{گè—جپjپB
پ›پ@چف“ْپiگè—جپjکAچ‡چ‘ŒR‚ج
‘چژi—ك •”پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ پ،پ@‚f‚g‚p پi‚¶‚¢‚¦‚¢‚؟‚«‚مپ[پj‚ئ‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@کAچ‡چ‘ŒRچإچ‚ژi—كٹ¯‘چژi—ك•”‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@کAچ‡چ‘ŒR‚ھ“ْ–{‚ًگè—ج‚µ‚½‚P‚X‚S‚T”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiڈ؛کa‚Q‚O”Nپj‚©‚çƒTƒ“ƒtƒ‰ƒ“ƒVƒXƒRڈً
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–ٌ‚ھ”Œّ‚µ‚½‚P‚X‚T‚Q”N پiڈ؛کa‚Q‚V”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ـ‚إ“ْ–{‚ة‚ ‚ء‚½پAچف“ْپiگè—جپjکAچ‡
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ‘ŒR‚ج‘چژi—ك•”‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚¶پ[پ@پ@‚f‚g‚pگè—ج“ژ،پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶پ[‚¦‚¢‚؟‚«‚مپ[‚¹‚ٌ‚è‚ه‚¤‚ئ‚¤‚؟پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پsچف“ْگè—جŒRپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚P‚X‚S‚T”Nپ`‚P‚X‚T‚Q”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث کAچ‡چ‘ŒR“ْ–{گè—جپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@‚P‚X‚S‚T”N‚ج–³ڈًŒڈچ~•ڑ‚©‚çپA‚P‚X‚T‚Q
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ”N‚جƒTƒ“ƒtƒ‰ƒ“ƒVƒXƒR•½کaڈً–ٌ‚ج”Œّ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚P‚X‚T‚P”N’÷Œ‹پA‚P‚X‚T‚Q”N”Œّپj‚ـ‚إ‚جٹْ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ٹشپA‚f‚g‚p‚ھ“ْ–{‚ًگè—ج“ژ،‚µ‚½پ@پi“ْ–{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ گ•{‚ً’ت‚µٹشگع“ژ،‚µ‚½پjپB
پZپ@‚µ‚¦پ@پ@ ژ‡ˆكژ–ŒڈپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚¦‚¶‚¯‚ٌپjپBپ@پsژ–ŒڈپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚U‚Q‚V”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث Œمگ…”ِ“VچcپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚©پ@پ@ ژچ‰جپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚©پjپBپ@پsژچ‰جپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@کa‰جپAکA‰جپA”oو~پi= ”oو~کA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰جپjپA”o‹ه‚ب‚اپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@کa‰جپثکA‰جپث”oو~پث”o‹هپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa‰جپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@ژچ‰جپ@پi‚µ‚©پj‚ئ‚حپAپ@کa‰جپi‚ي‚©پjپAکA‰ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚ê‚ٌ‚ھپjپA”oو~پi‚ح‚¢‚©‚¢پA= ”oو~کA‰جپjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”o‹هپi‚ح‚¢‚پjپ@‚ب‚ا‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@ژچ‰جپ@پi‚µ‚©پj‚حپAپ@کa‰جپi‚ي‚©پj‚©‚çکA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰جپi‚ê‚ٌ‚ھپj‚ضپAپ@کA‰ج‚©‚ç”oو~پi‚ح‚¢‚©‚¢پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@= ”oو~کA‰جپj‚ضپAپ@”oو~‚©‚ç”o‹هپi‚ح‚¢‚پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ضپ@‚ئ”hگ¶‚µ‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@
پZپ@‚µ‚ھپ@پ@ ژ©ٹQ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚ھ‚¢پjپBپ@پs گ¶–½پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژ©ٹQپ@پi‚¶‚ھ‚¢پA= ژ©ژEپj‚ة‚حپA “ْ–{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج—ًژj‚ة‚¨‚¢‚ؤپAژ©گnپi‚¶‚¶‚ٌپjپAژ©”ڑ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚خ‚پj‚ب‚ا‚ھ‚ ‚éپBپ@‘½‚‚ج‘¸‚¢–½پi‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‚؟پj‚ھژ¸‚ي‚ꂽپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ژ©گnپi‚¶‚¶‚ٌپjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ژ©”ڑپi‚¶‚خ‚پjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”ڑژ€ژ©ٹQپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژ©گnپ@پi‚¶‚¶‚ٌپj‚ئ‚حپAپ@“ْ–{‚ج—ًژj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ة‚¨‚¢‚ؤپAپ@“پŒ•‚ً—p‚¢‚ؤژ©ٹQپi‚¶‚ھ‚¢پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ©ژEپj‚·‚邱‚ئ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژ©”ڑپ@پi‚¶‚خ‚پj‚ئ‚حپAپ@“ْ–{‚ج—ًژj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ة‚¨‚¢‚ؤپAپ@‰خ–ٍ—ق‚ً—p‚¢‚ؤژ©ٹQپi‚¶‚ھ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¢پAژ©ژEپj‚·‚邱‚ئ‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚ھپ@پ@ ژ ‰êŒ§پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ھ‚¯‚ٌپjپBپ@پsŒ»’nˆو–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپà ٹT‚ثپA‹كچ]چ‘‚ج‘ٹ“–’nˆوپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiŒ»“s“¹•{Œ§پjپB
پ@پ@ ‚r‚g‚h‚f‚`پ@‚o‚q‚d‚e‚d‚b‚s‚t‚q‚dپD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژ ‰êŒ§پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپà ‘O‹ك‘م‚جپA‹Œچ‘–¼پi—كگ§چ‘پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جپA‹كچ] چ‘پ@پi‚¨‚¤‚ف ‚ج‚‚ةپAچ]ڈB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚²‚¤‚µ‚م‚¤پjپAژ ‰êŒ§پjپ@‚ةٹT‚ثپA‘ٹ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“–‚·‚é’nˆوپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹كچ]چ‘پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ‹ك‹E’n•ûپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ پiپث “ŒژR“¹پE ‹ŒچLˆو’n•ûپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ پiپث Œـ‹Eژµ“¹پjپB
پiپث “s“¹•{Œ§پjپB
پ@پ@پ@پ@ پ@پiپث ‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹Œ’nˆو–¼پA’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث “ْ–{‚ج’n–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژ ‰êŒ§‚حپAپ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جپA‹Œچ‘
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi—كگ§چ‘پj‚جپA‹كچ] چ‘ پ@پi‚¨‚¤‚ف‚ج‚‚ةپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@= چ]ڈBپi‚²‚¤‚µ‚م‚¤پjپjپ@‚ةٹT‚ث‘ٹ“–‚·‚é
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’nˆو‚إ‚ ‚éپB
پ@ پ@پ،پ@پi‚q‚v‚lپjپ@“ْ–{‚جپA’†’nˆو–¼‚ج•د‘JپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@چ‘‘¢پEŒ§ژه•ھچ‘پثپ@‹Œچ‘پi—كگ§چ‘پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پثپ@‹Œ“s“¹•{Œ§پثپ@Œ»‚S‚V“s“¹•{Œ§پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژ ‰êŒ§پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پƒ‹ك‹E’n•ûپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پƒ“ْ–{چ‘پB
پ@
پZپ@‚µ‚«پ@پ@ ’¼ڈ‘پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚«‚µ‚هپjپB پsŒِ•¶ڈ‘پtپB
پ@پ@ پi= ’¼ڈَپi‚¶‚«‚¶‚ه‚¤پjپA’¼ژDپi‚¶‚«‚³‚آپjپj پB
پ›پ@پuچ‚‹M‚بگg•ھ‚جژزپvپiچ‚ˆتژزپj‚ھ
’¼پi‚¶‚©پj‚ةچ‚ˆتژز‚ج–¼‹`‚إچ‚ˆتژز‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژïژ|‚ً‹L‚µ‚ؤ”‹‹‚·‚éŒِ•¶ڈ‘ پB
پiپث Œن‹³ڈ‘پi‚ف‚¬‚ه‚¤‚µ‚هپA‚ف‚«‚ه‚¤‚¶‚هپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@(چL‹`پjپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚°پ@پ@’n‰؛پA’n‰؛گlپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚°پA‚¶‚°‚ة‚ٌپjپB پs’©’ىپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= کZˆتˆب‰؛‚ج’©’ى‚جٹ¯گlپi–ًگlپjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ’©’ىپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@’n‰؛پA’n‰؛گl‚ئ‚حپAپ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚إ‚حپiچ]
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œثژ‘م‚ـ‚إ‚حپjپAˆتٹKپEکZˆتˆب‰؛‚ج’©’ى‚جٹ¯
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گlپi–ًگlپj‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@’n‰؛پA’n‰؛گl‚ئ‚حپA’n‰؛‚جگl‚جˆس‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@‹·‹`‚إ‚حپA’n‰؛پA’n‰؛گl‚ئ‚حپAپ@“VچcŒنڈٹ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جگ´—ء“a‚ةڈ¸“a‚·‚邱‚ئ‚ً‹–‚³‚ê‚ب‚¢ٹ¯گl
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‹{گlپi‚«‚م‚¤‚¶‚ٌپjپAچ‘‰ئŒِ–±ˆُ‚ة‘ٹ“–پjپ@‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@‹·‹`‚إ‚حپA’n‰؛پA’n‰؛گl‚ئ‚حپA“aڈمگl
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚ؤ‚ٌ‚¶‚ه‚¤‚ر‚ئپjˆبٹO‚جٹ¯گl پ@‚إ‚ ‚éپBپ@
پœپ@‹·‹`‚إ‚حپA’n‰؛پA’n‰؛گl‚ئ‚حپAپ@“°ڈم‰ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚ا‚¤‚¶‚ه‚¤‚¯پjˆبٹO‚جٹ¯گl‚إ‚ ‚éپB
پ،پ@چL‹`‚إ‚حپA’n‰؛پA’n‰؛گl‚ئ‚حپAپ@‹{’†‚ة
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•ٍژd‚·‚éگlˆبٹO‚جژز‚إ‚ ‚éپBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@
پZپ@‚¶‚°پ@پ@’n‰؛گ؟پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚°‚¤‚¯پjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiگ؟ڈٹپjپ@پs”Nچvگ؟•‰گ§“xپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پs“ْ–{‚ج“y’nژx”zگ§“xپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= •Sگ©گ؟پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث •Sگ©گ؟پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‘‘‰€پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث گ؟ڈٹپA’n“ھگ؟پAژçŒىگ؟پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•Sگ©گ؟پi= ’n‰؛گ؟پjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ، ’n‰؛گ؟پi‚¶‚°‚¤‚¯پj‚ئ‚حپA•Sگ©گ؟‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚°پ@پ@ ’n‰؛‰ئپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پi‚¶‚°‚¯پjپBپ@ پs’©’ىپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ’n‰؛Œِ‰ئپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ڈ¸“a‚ً‹–‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œِ‰ئپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پiپث Œِ‰ئپA’©’ىپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@’n‰؛‰ئپi‚¶‚°‚¯پj‚ئ‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژه‚ة‹Vژ®‚ئ•¶ژ،‚ً‚à‚ء‚ؤ“Vچc‰ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ةژdپi‚آ‚©پj‚¦‚é’©’ى‚جٹ¯گlپi–ً
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گlپj‚إ‚ ‚éپuچL‹`‚جŒِ‰ئپv‚ج’†‚إپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ¸“a‚ً‹–‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢پi“à— پi“V
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چcŒنڈٹپj‚جگ´—ء“a‚ةڈ¸“a‚·‚邱
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ئ‚ً‹–‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢پjŒِ‰ئ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@’n‰؛‰ئ‚ئ‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¾‚¢‚½‚¢پAژه‚ة‹Vژ®‚ئ•¶ژ،‚ً‚à‚ء
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ؤ“Vچc‰ئ‚ةژdپi‚آ‚©پj‚¦‚éپA‘O‹ك
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘م“ْ–{‚ج’©’ى‚جپA ’n‰؛‚جٹ¯گl
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi–ًگlپjپi’n‰؛گlپAˆتٹKپEکZˆتˆب‰؛
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جژزپjپA–³ˆت‚جٹ¯گlپi–ًگlپj‚ب‚ا
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@پuچL‹`‚جŒِ‰ئپv‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“°ڈم‰ئ‚ئ’n‰؛‰ئ‚ة•ھ‚©‚ê‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœ پ@چL‹`‚جŒِ‰ئ‚ة‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ژه‚ة‹Vژ®‚ئ•¶ژ، ‚ً‚à‚ء‚ؤ“Vچc‰ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ةژdپi‚آ‚©پj‚¦‚éپAڈ¸“a‚ھ‹–‚³‚ê
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚½“°ڈم‰ئپi‚ا‚¤‚¶‚ه‚¤‚¯پj‚جŒِ‰ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ئپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ¸“a‚ھ‹–‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢’n‰؛‰ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚°‚¯پj‚جŒِ‰ئپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ھ‚¢‚½پB
پ@
پZپ@‚µ‚°پ@پ@پ@ژ ژqپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پi‚µ‚°‚±)پBپ@پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پi= •½ ژ ژqپi‚½‚¢‚ç‚ج ‚µ‚°‚±)پAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ Œڑڈt–ه‰@پi‚¯‚ٌ‚µ‚م‚ٌ‚à‚ٌ‚¢‚ٌپjپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ Œڑڈt –ه‰@ژ ژqپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiˆةگ¨•½ژپ‚جڈ—گ«پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚P‚P‚S‚Q”Nپ`‚P‚P‚V‚U”NپjپB
‚r‚ˆ‚‰‚‡‚…‚‹‚ڈپC
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚s‚`‚h‚q‚`پ@‚ژ‚ڈپ@‚r‚ˆ‚‰‚‡‚…‚‹‚ڈپD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث •½ ژ ژqپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@•½ ژ ژq‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ْ–{‚ج—ًژj‚ً•د‚¦‚½”ü
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ—پEچثڈ—‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@•½ ژ ژq‚حپA
•½گ´گ·پEگ³ژ؛•vگl‚ج•½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژژq‚جˆظ•ê–…‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@•½ ژ ژq‚حپA
Œم”’‰حڈمچc‚جگ³ژ؛•vگlپE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’”ـ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@•½ ژ ژq‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ‚‘q“Vچc‚جگ¶•ê‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@•½ ژ ژq‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆہ“؟پi‚ ‚ٌ‚ئ‚پj“Vچc‚â
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ Œم’¹‰Hپi‚²‚ئ‚خپjڈمچc
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‘c•ê‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@•½ ژ ژq‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•½‰ئگŒ ‚ًژ÷—§‚·‚éژ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚ج‘bپi‚¢‚µ‚¸‚¦پj‚ئ‚ب‚ء‚½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ڈ—گ«‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@•½ ژ ژqپ@پi‚½‚¢‚ç‚ج ‚µ‚°‚±)
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚حپAپ@“ْ–{‚ج—ًژj‚ً•د‚¦‚½”üڈ—پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چثڈ—‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@ژ ژq پi‚µ‚°‚±)پ@پi= •½ ژ ژq
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚½‚¢‚ç‚ج‚µ‚°‚±)پAپ@Œڑڈt–ه‰@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¯‚ٌ‚µ‚م‚ٌ‚à‚ٌ‚¢‚ٌپjپA Œڑڈt–ه
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰@ژ ژqپA‚P‚P‚S‚Q”Nپ` ‚P‚P‚V‚U”Nپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ئ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@•½گ´گ·پEگ³ژ؛•vگlپE•½ژژq‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ˆظ•ê–…‚إ‚ ‚èپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ Œم”’‰حڈمچc‚جگ³ژ؛•vگlپE’”ـ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚إ‚ ‚èپAپ@چ‚‘q“Vچc‚جگ¶•ê‚إ‚
‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@•½ ژ ژq‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ •½‰ئگŒ ‚ًژ÷—§‚·‚éژ‚ج‘bپi‚¢‚µ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚¸‚¦پj‚ئ‚ب‚ء‚½ڈ—گ«‚إ‚ ‚èپAپ@ˆہ“؟
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚ ‚ٌ‚ئ‚پj“Vچc‚âŒم’¹‰Hپi‚²‚ئ‚خپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ڈمچc‚ج‘c•ê‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚°پ@پ@ ڈdگmگe‰¤پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚°‚ذ‚ئ‚µ‚ٌ‚ج‚¤پjپBپsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@گ’“؟ڈمچcپi‚·‚ئ‚‚¶‚ه‚¤
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚±‚¤پj‚جچcژqپi‚ف‚±پjپj پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ’“؟ڈمچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@ڈdگmگe‰¤پ@پi‚µ‚°‚ذ‚ئ‚µ‚ٌ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¤پj‚حپAپ@گ’“؟ڈمچcپi‚·‚ئ‚‚¶‚ه‚¤
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚±‚¤پj‚جچcژqپi‚ف‚±پj‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚°پ@پ@ ڈdŒُپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚°‚ف‚آپjپBپ@پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ’¼چ]ڈdŒُپA’¼چ]Œ“‘±‚ب‚¨‚¦
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚©‚ث‚آ‚®پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث’¼چ] Œ“‘±پjپB
پ@
پZپ@‚µ‚°پ@پ@ ’n‰؛کQگlپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚°‚낤‚ة‚ٌپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پs•گژm‚جگg•ھپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= چف‘؛کQگlپAچف‹½کQگlپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@’n‰؛کQگl‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ]Œثژ‘م‚ةپA•n‚µ‚گ¶ٹˆ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‚½‚ك‚ةپA‹½ژmژ‘ٹiپiٹ”پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ً”„‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پAŒ³‹½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژm‚ج‰؛‹‰•گژm‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پZپ@—ل‚¦‚خپA“yچ²”ث‚ج–‹
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@––‚جپAٹâچè–ي‘¾کYپA‘ٍ‘؛
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘y”Vڈه‚ب‚ا‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@’n‰؛کQگlپi‚¶‚°‚낤‚ة‚ٌپj‚ئ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ]Œثژ‘م‚ج•گژm‚جگg•ھ‚إ‚ ‚èپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چف‘؛کQگlپAچف‹½کQگl‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@’n‰؛کQگlپi‚¶‚°‚낤‚ة‚ٌپj‚ئ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ]Œثژ‘م‚ةپA•n‚µ‚گ¶ٹˆ‚ج‚½‚ك‚ة
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹½ژmژ‘ٹiپiٹ”پj‚ً”„‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ³‹½ژmگg•ھ‚ج‰؛‹‰•گژm‚إ‚ ‚éپBپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ةپA•گژmگg•ھ‚ة‚حپAپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”_‘؛‹ڈڈZ•گژm‚جپu‹½ژmپvپi‚²‚¤‚µپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ئپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈé‰؛’¬‚ةڈZ‚قپu‰ئ’†•گژmپvپi‚©‚؟
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚م‚¤‚ش‚µپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ھ‚¢‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@–‹––‚ج’n‰؛کQگl‚ج—ل‚ئ‚µ‚ؤ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚حپA“yچ²”ث‚جپAٹâچè–ي‘¾کYپi‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ي‚³‚«‚₽‚낤پAژO•Hچà”´‘nژn
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژزپjپA‘ٍ‘؛‘y”Vڈهپi‚³‚ي‚ق‚ç‚»‚¤
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‚¶‚ه‚¤پj‚ب‚ا‚ھ‚¢‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚±پ@پ@ ژچڈپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚±‚پjپBپ@پs“ْژپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@(پث ژچڈ–@پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@(پث “ْژپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژچڈ‚ة‚حپAپ@گ¼—mژ®ژچڈپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈ‚ھ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@گ¼—mژ®ژچڈ‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P’‹–é‚Q‚S“™•ھژٹشگ§‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P’‹–é‚ً‚Q‚S“™•ھ‚µ‚ؤپA‚Pژٹش–ˆ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ة‹وگط‚ء‚ؤژچڈ‚ً•\ژ¦‚·‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{‚إ‚حپA‚P‚W‚V‚R”Nپi–¾ژ،‚U”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚©‚猻چف‚ـ‚إژg—p‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P’‹–é‚P‚Q“™•ھژٹشگ§‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P’‹–é‚ً‚P‚Q“™•ھ‚µ‚ؤپA‚Qژٹش–ˆ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ة‹وگط‚ء‚ؤژچڈ‚ً•\ژ¦‚·‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚Qژٹش‚ة‹وگط‚ء‚½ژچڈ‚ًڈ\“ٌژx
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ة“–‚ؤ‚ح‚ك‚ؤŒؤ‚ٌ‚إ‚¢‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{‚إ‚حپAŒأ‘م‚©‚ç‚P‚W‚V‚Q”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi–¾ژ،‚T”Nپj‚ـ‚إژg—p‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژچڈ“`’B•û–@‚ج‚P‚آ‚ئ‚µ‚ؤپAژڈà
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚µ‚ه‚¤پj•\ژ¦ژچڈ‚ھ‚ ‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژچڈ‚ة‚حپAپ@’èژ–@پ@‚ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•s’èژ–@‚ھ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{‚ة‚حپA’èژ–@‚جگ¼—mژ®ژچڈپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’èژ–@‚جڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈپA•s’è
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ–@‚جڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈ‚ھ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@’èژ–@‚حپAژٹش‚ج’·‚³‚ھڈي‚ة
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆê’è‚ج•\ژ¦ژچڈ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{‚إ‚حپAŒأ‘م‚©‚猻‘م‚ـ‚إژg—p
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@•s’èژ–@‚حپAژٹش‚ج’·‚³‚ھ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆê’肵‚ؤ‚¢‚ب‚¢•\ژ¦ژچڈ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{‚إ‚حپAŒأ‘م‚©‚ç‚P‚W‚V‚Q”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi–¾ژ،‚T”Nپj‚ـ‚إژg—p‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•s’èژ–@‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–é–¾‚¯‚ئ“ْ•é‚ê‚ً‹«‚ة‚µ‚ؤ’‹‚ئ–é‚ً
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹و•ت‚µپA‹Gگك‚ة‚و‚è’·‚³‚جˆل‚¤’‹‚ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–é‚ً‚»‚ꂼ‚ê‚U“™•ھ‚µ‚ؤژچڈ‚ًŒˆ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ك‚é•û–@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ\“ٌژx‚جˆêچڈ‚ج’·‚³‚ھ‚Qژٹش‚و‚è
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’·‚©‚ء‚½‚èپA‚Qژٹش‚و‚è’Z‚©‚ء‚½‚è
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@“ْژ‚ة‚حپA”NŒژ“ْ‚ئژچڈ‚ھ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@”NŒژ“ْ‚ج”N•\ژ¦‚ة‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ¼—m”NپAکa—ï”NپAٹ±ژxپi‚©‚ٌ‚µپj”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ب‚ا‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚±پ@پ@ ژچڈگV‹Œٹ·ژZ•\پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚±‚‚µ‚ٌ‚«‚م‚¤‚©‚ٌ‚³‚ٌ‚ذ‚ه‚¤پjپB پsژچڈپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ‘O‹ك‘م“ْ–{‚جژچڈپE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@ ژ–@پjپB
پ@
پZپ@‚µ‚±پ@پ@ ژlچ‘’n•ûپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚±‚‚؟‚ظ‚¤پjپBپ@پsŒ»’nˆو–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= چپگىŒ§پA“؟“‡Œ§پAچ‚’mŒ§پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ˆ¤•QŒ§پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiŒ»’n•ûپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚r‚g‚h‚j‚n‚j‚tپ@‚q‚d‚f‚h‚n‚mپD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث Œ»‚W’n•ûپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث Œ»’n•û–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث Œ»’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹Œچ‘پi= —كگ§چ‘پjپjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹Œ’nˆو–¼پA’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث “ْ–{‚ج’n–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژlچ‘’n•ûپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پà ‡@پ@“ىٹC“¹پi ‚ب‚ٌ‚©‚¢‚ا‚¤پjپE‹ŒچL
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ˆو’n•û‚جˆê•”‚جپA چپگىŒ§پiژ]ٹٍ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ‘پjپA“؟“‡Œ§پiˆ¢”g چ‘پjپAچ‚’mŒ§
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi“yچ² چ‘پjپAˆ¤•QŒ§پiˆة—\ چ‘پj ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’nˆوپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث “ىٹC“¹پE‹ŒچLˆو’n•ûپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژlچ‘’n•ûپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پƒ“ْ–{–{“yپi–{ڈBپAژlچ‘پA‹مڈBپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پƒ“ْ–{چ‘پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژlچ‘’n•ûپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپà ‹ŒچLˆو’n•û‚جپA“ىٹC“¹‚جˆê•”پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پƒŒـ‹Eژµ“¹پ@پi‚²‚«‚µ‚؟‚ا‚¤پA“ْ–{–{“yپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚±پ@پ@ ژچڈ–@پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚±‚‚ظ‚¤پjپBپ@پsژچڈپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= ژ–@پj پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‘O‹ك‘م“ْ–{‚جژچڈپEژ–@پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@ژچڈ–@پiژ–@پj‚حپAژٹش‹و•ھŒ`ژ®پAژٹشٹش
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹu–@پi’èژ–@پE•s’èژ–@پjپAژچڈ•\ژ¦•ûژ®‚ة‚و
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚èپA•ھ—ق‚³‚ê‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@“ْ–{‚إژg‚ي‚ꂽژچڈپBپ@“ْ–{‚إ‚حپA‚Q‚آ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژٹش‹و•ھŒ`ژ®پA‚Q‚آ‚جژٹشٹشٹu–@پi’èژ–@پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•s’èژ–@پjپA‚R‚آ‚جژچڈ•\ژ¦•ûژ®‚ھژg—p‚³‚ê
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@‹كŒ»‘م“ْ–{ژg—p‚ج‚P“ْ‚Q‚Sژٹشگ§پE’èژ–@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پEگ¼—mژ®•\ژ¦ژچڈپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{ژg—p‚ج‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§پE’èژ–@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ^•s’èژ–@پEڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈپi= ڈ\“ٌژxŒؤ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈجژچڈپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{ژg—p‚ج‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§پE•s’èژ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–@پEژڈàگ”•\ژ¦ژچڈپi= گ”ŒؤڈجژچڈپjپB
پ@
پ@
پZ ‚¶‚´پ@ ’nژکپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚´‚ق‚ç‚¢پjپBپ@پs•گژm‚جگg•ھپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚P‚Sپ`‚P‚Uگ¢‹IپjپB
پi= ’nŒ³‚ج“y’…‚ج•گژmپjپB
پ@
پZ ‚µ‚µپ@پ@ ژuژmپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚µپjپBپ@پs–‹––پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= –‹––‚جژuژmپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث –‹––‚جژuژmپjپB
پ@
پZ ‚µ‚µپ@پ@ ژlگE‰ئپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚µ‚«‚¯پjپBپ@پs–ًگEپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= ژlگEپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ژکڈٹپAژ؛’¬–‹•{پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژlگE‰ئپ@پi‚µ‚µ‚«‚¯پA= ژlگEپj‚ئ‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ؛’¬–‹•{‚جژکڈٹپi‚³‚ق‚ç‚¢‚ا‚±‚ëپj‚جڈٹژi
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚µپA’·ٹ¯پj‚ة”C‚¶‚ç‚ê‚éپA‚Sژپ ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ژlگE‰ئپ@پi‚µ‚µ‚«‚¯پj‚حپAپ@ژ؛’¬–‹•{‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒRژ–پEŒxژ@پ@‚âپ@‹پi“sپj‚جŒx”ُپEچظ”»‚ً’S
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¤‹@ٹض‚إ‚ ‚éپuژکڈٹپi‚³‚ق‚ç‚¢‚ا‚±‚ëپj‚جڈٹ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژiپi‚µ‚ه‚µپA ’·ٹ¯پjپv‚ةŒً‘م‚إ”C‚¶‚ç‚ꂽپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژR–¼پi‚â‚ـ‚بپjپAگشڈ¼پi‚ ‚©‚ـ‚آپjپAˆêگFپi‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ء‚µ‚«پjپA‹‹ةپi‚«‚ه‚¤‚²‚پj‚ج‚Sژپ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ژ؛’¬–‹•{‚إ‚حپAپ@ژکڈٹ‚جڈٹژi پi’·ٹ¯پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚حپAپ@ٹا—جپi‚©‚ٌ‚ê‚¢پj‚ةژں‚®ڈdگE‚إ‚ ‚ء‚½پB
پZپ@‚µ‚¶پ@پ@ ژjژہ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚¶‚آپjپBپ@پs—ًژjٹwپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@ژjژہپ@پi‚µ‚¶‚آپj‚ئ‚حپAپ@—ًژj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ژ–ژہ‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZ ‚¶‚µپ@پ@ ژ›ژذپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚µ‚لپjپB پsژ›ژذپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ژ›‰@‚ئگ_ژذپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژ›ژذ‚ج‘m—µ‚âگ_ٹ¯‚حپAژ›ژذپAژ›‰@‚âگ_
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژذ‚ةڈ]ژ–‚·‚éژز‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZ ‚µ‚µپ@پ@ ژqژفپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚µ‚ل‚پjپBپ@پs‹Œژذ‰ïگg•ھپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‰ط‘°پjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژqژف‚حپAپ@‹ك‘م“ْ–{پi–¾ژ،پA‘هگ³پAڈ؛
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@کaگي‘Oژ‘مپj‚جژذ‰ï“Iگg•ھ‚ج‹M‘°‚إ‚ ‚é
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰ط‘°پi‚©‚¼‚پj‚إ‚ ‚èپAپ@‰ط‘°‚جŒِپEŒٍپE”ŒپE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژqپE’jژفپi‚±‚¤پE‚±‚¤پE‚ح‚پE‚µپE‚¾‚ٌپE‚µ‚ل‚پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‚S”ش–ع‚ج’nˆتپEگg•ھ‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZ ‚¶‚µپ@پ@ ژuڈBپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚µ‚م‚¤پjپB پs‹Œ’nˆو–¼پtپB
پi= ژu–ƒچ‘پi‚µ‚ـ‚ج‚‚ةپjپj پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپà Œ»پEژOڈdŒ§’†‰›“Œ•”پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‘O‹ك‘م‹Œ’nˆو–¼‚ج‹Œچ‘پi—كگ§
چ‘پj‚ج•تڈجپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ژu–ƒچ‘پjپBپ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ژOڈdŒ§پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹Œچ‘پi= —كگ§چ‘پjپjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹Œ’nˆو–¼پA’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث “ْ–{‚ج’n–¼پjپB
پ@پ،پ@ژuڈBپ@پi‚µ‚µ‚م‚¤= ژu–ƒچ‘پi‚µ‚ـ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@‚ج‚‚ةپjپjپ@ ‚حپAپ@‘O‹ك‘م‹Œ’nˆو–¼‚ج
پ@پ@پ@ ‹Œچ‘پi—كگ§چ‘پj‚ج•تڈج‚إ‚ ‚èپAپ@“ŒٹC
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “¹پi‚ئ‚¤‚©‚¢‚ا‚¤‚¢‚ا‚¤پjپE‹ŒچLˆو’n•û
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚ة‘®‚µپAپ@Œ»پE‹ك‹E’n•û‚جپAŒ»پEژOڈd
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@ Œ§’†‰›“Œ•”‚ة‘ٹ“–‚·‚é’nˆو‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZ ‚¶‚µپ@پ@ ژxڈéپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚¶‚ه‚¤پjپBپ@پs ڈéپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژxڈéپ@پi‚µ‚¶‚ه‚¤پj‚ئ‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–{ڈé‚ً–h‰q‚·‚邽‚ك‚جڈé‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ڈé‚ة‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚پپjپ@–{ڈéپ@پi‚ظ‚ٌ‚¶‚ه‚¤پA–{‹’’n
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚جڈéپjپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚‚پjپ@ژxڈéپ@پi‚µ‚¶‚ه‚¤پA–{ڈé‚ً–h
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‰q‚·‚邽‚ك‚جڈéپjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚ƒپjپ@گ–±‹ڈڈéپ@پi‚¹‚¢‚ق‚«‚ه‚¶‚ه
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚¤پAگ–±‚ًچs‚¤‚½‚ك‚جڈéپjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ب‚ا‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پZ ‚¶‚µپ@پ@ ژ،ڈ³پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚µ‚ه‚¤ پA‚¶‚¶‚ه‚¤پjپBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï‚ج“ٌڈd”Nچ†‘¶—§پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@Œ¹•½‹£چ‡“ٌڈd”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‚P‚P‚W‚P”N‚©‚ç‚P‚P‚W‚T”N‚ـ‚إپA“ْ–{‚إپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ¹•½ پi‚°‚ٌ‚ط‚¢پj‹£چ‡“ٌڈd”Nچ†‚ھژg—p
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚³‚ê‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ ˆةگ¨•½ژپگŒ پiˆہ“؟“Vچc—i
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ —§پj•û‚ج—ï”Nچ†پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‚P‚P‚V‚V”Nپ`‚P‚P‚W‚P”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚P‚P‚V‚V”NپEژ،ڈ³Œ³”NپE‚WŒژپ@‚S“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚P‚W‚P”NپEژ،ڈ³ ‚T”NپE‚VŒژ‚P‚S“ْپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@•½ˆہژ‘مŒمٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ˆةگ¨•½ژپپi‚¢‚¹‚ض‚¢‚µپjگŒ پiˆہ“؟
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚ ‚ٌ‚ئ‚پj“Vچc—i—§پj•û‚ج—ï ”Nچ†پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ˆہŒ³پi‚ ‚ٌ‚°‚ٌپjŒ³”Nپ`‚R”N پ@پi‚P‚P‚V‚T
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”Nپ`‚P‚P‚V‚V”Nپjپ@پثپ@ژ،ڈ³پi‚¶‚µ ‚ه‚¤پjŒ³”Nپ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚T”Nپ@پi‚P‚P‚V‚V”Nپ`‚P‚P‚W‚P”Nپjپ@پثپ@—{کaپi‚و
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¤‚يپjŒ³”Nپ`‚Q”Nپ@پi‚P‚P‚W‚P”Nپ`‚P‚P‚W‚Q ”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پثپ@ژُ‰iپi‚¶‚م‚¦‚¢پjŒ³”Nپ`‚S”Nپ@پi‚P‚P‚W‚Q ”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ`‚P‚P‚W‚T”Nپjپ@پثپ@ —ï”Nچ†•زگ¬’†ژ~پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@‰ح“àŒ¹ژپپEŒ¹—ٹ’©گŒ پiŒم’¹
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰H“Vچc—i—§پj•û‚ج—ï”Nچ†پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@‚P‚P‚V‚V”Nپ`‚P‚P‚W‚S”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚P‚P‚V‚V”NپEژ،ڈ³Œ³”NپE‚WŒژپ@‚S“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚P‚W‚S”NپEژ،ڈ³ ‚W”NپE‚SŒژ‚P‚U“ْپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@•½ˆہژ‘مŒمٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‰ح“àŒ¹ژپپi‚©‚ي‚؟‚°‚ٌ‚¶پjپEŒ¹—ٹ’©گŒ پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiŒم’¹‰H“Vچc—i—§پj•û‚ج—ï”Nچ†پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ˆہŒ³پi‚ ‚ٌ‚°‚ٌپjŒ³”Nپ`‚R”N پ@پi‚P‚P‚V‚T
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”Nپ`‚P‚P‚V‚V”Nپjپ@پثپ@ژ،ڈ³پi‚¶‚µ‚ه ‚¤پjŒ³”Nپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ`‚W”Nپ@پi‚P‚P‚V‚V”Nپ` ‚P‚P‚W‚S”Nپjپ@پثپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ³—ïپi‚°‚ٌ‚è‚ل‚پjŒ³”Nپ`‚Q”N پ@پi‚P‚P‚W‚S”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ`‚P‚P‚W‚T”Nپjپ@پثپ@•¶ژ،پi‚ش‚ٌ‚¶ پjŒ³”Nپ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚U”Nپ@پi‚P‚P‚W‚T”Nپ`‚P‚P‚X‚O”NپjپB
پ@
پZ ‚¶‚µپ@پ@ ژœڈئژ›پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚µ‚ه‚¤‚¶پjپBپ@پs•§‹³ژ›‰@پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ پi= ‹âٹtژ›پi‚¬‚ٌ‚©‚‚¶پA’تڈجپjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ŒژR“aپi ‚ذ‚ھ‚µ‚â‚ـ‚إ‚ٌپjپA“ŒژR
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ ژR‘‘پi‚ذ‚ھ‚µ‚â‚ـ‚³‚ٌ‚»‚¤پjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ژœڈئژ›‚ج’تڈج‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹âٹtژ›‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹âٹtژ›پA“ŒژR“aپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹âٹtپA“ŒژR•¶‰»پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘«—ک ‹`گپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ،پ@ژœڈئژ›پi‚¶ ‚µ‚ه‚¤‚¶پj‚ئ‚حپAپ@
’تڈج‚ح‹âٹt ژ›پi‚¬‚ٌ‚©‚‚¶پj‚إ‚ ‚èپAپ@
‹âٹtپi‚¬‚ٌ‚©‚پA = ٹد‰¹“aپi‚©‚ٌ‚ج‚ٌ
‚إ‚ٌپjپj‚ج‚ ‚éپAژœڈئژ›پi= ‹âٹtژ›پj‚إ
‚ ‚èپAپ@‹âٹtپi= ٹد‰¹“aپj‚ًٹـ‚قژ›‰@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‘S‘ج‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ،پ@ژœڈئژ›پi‚¶‚µ‚ه‚¤‚¶پA= ‹âٹtژ›پj‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@“ŒژR“aپ@پi‚ذ‚ھ‚µ‚â‚ـ‚إ‚ٌپA“ŒژRژR‘‘
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚ذ‚ھ‚µ‚â‚ـ‚³‚ٌ‚»‚¤پjپjپ@‚ئ‚¢‚¤‘«—ک
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@‹`گ پi‚ ‚µ‚©‚ھ‚و‚µ‚ـ‚³پAژ؛’¬–‹•{پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘و‚W‘مڈ«ŒRپA–@–¼پi‰ْ–¼پjپFژœڈئ‰@پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚ج•ت‘‘پiژR‘‘پj‚إ‚ ‚ء‚½‚ھپAپ@‘«—ک
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‹`گژ€ŒمپAŒ»چف‚جژœڈئژ›پi= ‹âٹtژ›پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚ئ‚¢‚¤‘Tڈ@•§‹³ژ›‰@‚ئ‚ب‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ،پ@ژœڈئژ›پi= ‹âٹtژ›پj‚ج ‹âٹt‚حپA
ٹد‰¹“a‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@ٹد‰¹“aپ@پi‚©‚ٌ‚ج‚ٌ‚إ‚ٌپj‚ئ‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ٹد‰¹‘œ‚ًˆہ’u‚·‚éŒڑ•¨‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZ ‚¶‚µپ@پ@ ژœڈئژ›‹âٹtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚µ‚ه‚¤‚¶‚¬‚ٌ‚©‚پjپBپ@پsٹد‰¹“aپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= ‹âٹtپA‹âٹtژ›‹âٹtپiٹد‰¹
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“aپjپA“ŒژR“aپi= “ŒژRژR‘‘پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‹âٹtپiٹد‰¹“aپjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث “ŒژR•¶‰»پA
‘«—ک‹`گپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ،پ@ژœڈئژ›پi‚¶‚µ‚ه‚¤‚¶پA= ‹âٹtژ›پj‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@“ŒژR“aپ@پi‚ذ‚ھ‚µ‚â‚ـ‚إ‚ٌپA“ŒژRژR‘‘
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚ذ‚ھ‚µ‚â‚ـ‚³‚ٌ‚»‚¤پjپjپ@‚ئ‚¢‚¤‘«—ک
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@‹`گ پi‚ ‚µ‚©‚ھ‚و‚µ‚ـ‚³پAژ؛’¬–‹•{پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‘و‚W‘مڈ«ŒRپA–@–¼پi‰ْ–¼پjپFژœڈئ‰@پj
‚ج•ت‘‘پiژR‘‘پj‚إ‚ ‚ء‚½‚ھپA ‘«—ک‹`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ گژ€ŒمپAŒ»چف‚جژœڈئژ›پi= ‹âٹtژ›پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚ئ‚¢ ‚¤‘Tڈ@•§‹³ژ›‰@‚ئ‚ب‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ،پ@ژœڈئژ›پi= ‹âٹtژ›پj‚ج ‹âٹt‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ٹد‰¹“a‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹد‰¹“aپi‚©‚ٌ‚ج‚ٌ‚إ‚ٌپj ‚ئ‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ٹد‰¹‘œ‚ًˆہ’u‚·‚éŒڑ•¨ ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹âٹtپ@پi= ژœڈئژ›پi= ‹âٹtژ›پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ٹد‰¹“aپj‚حپAپ@“ŒژR•¶‰»‚ج‘م•\چى‚ج
‚P‚آ‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZ ‚¶‚µپ@پ@ ژ،ڈ³پEژُ‰i‚ج—گ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚µ‚ه‚¤پE‚¶‚م‚¦‚¢‚ج‚ç‚ٌپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پsگي‚¢پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚P‚P‚W‚O”Nپ[‚P‚P‚W‚T”N‚ـ‚½‚ح
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚P‚P‚W‚X”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث •½ˆہژ‘م––ٹْپE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈعچ×”N•\پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژ،ڈ³پEژُ‰i‚ج—گ پi‚¶‚µ‚ه‚¤پE‚¶‚م
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚¦‚¢‚ج‚ç‚ٌپA= Œ¹•½‚ج‘ˆ—گپA‚P‚P‚W‚O
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”Nپ[‚P‚P‚W‚T”N‚ـ‚½‚ح‚P‚P‚W‚X”Nپj‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹·‹`‚إ‚حپA‰ح“àŒ¹ژپ‚ئˆةگ¨•½ژپ‚ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جگي‚¢ پi= Œ¹•½‚ج‘ˆ—گپAŒ¹•½چ‡گيپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚âپ@Œ¹ژپ“¯ژmپiŒ¹پi–ط‘]پj‹`’‡•û‚ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ¹—ٹ’©•ûپj‚ج‘ˆ‚¢‚إ‚ ‚èپAپ@چL‹`‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ح‰œڈB“،Œ´ژپ•û‚ئ‰ح“àŒ¹ژپ•û‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘ˆ‚¢‚ً‚àٹـ‚ق‘ˆ‚¢‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ژ،ڈ³پEژُ‰i‚ج—گ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚P‚W‚O”N‚جŒ¹—ٹ’©•½‰ئ‘إ“|‹“•؛‚©
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚çپAپ@‹·‹`‚إ‚حپA‚P‚P‚W‚T”N‚ج’dƒm‰Y
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جگي‚¢‚ـ‚إ‚إ‚ ‚é‚ھپAپ@چL‹`‚إ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚P‚W‚X”N‚ج‰œڈBچ‡گي‚ـ‚إ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ژ،ڈ³پEژُ‰i‚ج—گ‚إ‚حپA پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–kڈًژپ‚ً‚ح‚¶‚ك‘½‚‚جچâ“Œپi‚خ‚ٌ‚ا
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¤پAٹض“Œپj•گژm‚حپA‰ح“à Œ¹ژپ‚جŒ¹—ٹ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’©‚ة–،•û‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ژ،ڈ³پEژُ‰i‚ج—گ‚إ‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆةگ¨•½ژپپi—c’é‚جˆہ“؟“Vچc—i—§پj‚àپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰ح“àŒ¹ژپپi—c”N‚جŒم’¹‰H“Vچc—i—§پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚àپA —c’é‚ً—i—§‚µ‚ؤپA“ْ–{‚ج”eŒ ‚ً
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘ˆ‚¤پB
پ@
پZپ@‚µ‚µپ@پ@ژڈàگ”•\ژ¦ژچڈ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚µ‚ه‚¤‚·‚¤‚ذ‚ه‚¤‚¶‚¶‚±‚پjپBپ@پsژچڈپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= گ”ŒؤڈجژچڈپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ژچڈ–@پA‘O‹ك‘م“ْ–{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚جژچڈپEژ–@پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژڈàگ”•\ژ¦ژچڈپ@پi‚¶‚µ‚ه‚¤‚·‚¤‚ذ‚ه‚¤‚¶
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¶‚±‚پA= گ”Œؤڈجژچڈپj‚حپAپ@“ْ–{‚إژg‚ي‚ê
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚½ژ–@پiژچڈ–@پj‚جپAژچڈ•\ژ¦•ûژ®پiگ¼—m
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ®•\ژ¦ژچڈپAڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈپAژڈàگ”•\ژ¦پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژچڈپj‚ج‚R‚آ‚ج‚¤‚؟‚ج‚P‚آ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ژڈàگ”•\ژ¦ژچڈپ@پi= گ”Œؤڈجژچڈپj‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚إژg‚ي‚ꂽپA•s’èژ–@‚جپA ژ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈàپi‚¶‚µ‚ه‚¤پj‚جگ”‚إ•\ژ¦‚·‚éژچڈ ‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ژڈàگ”•\ژ¦ژچڈپ@پi= گ”Œؤڈجژچڈپj‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘O‹ك‘م“ْ–{ژg—p‚ج‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§‚جپA•s’è
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ–@پEژڈàگ”•\ژ¦ژچڈ‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@
پZ ‚¶‚µپ@پ@ ’nگkپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚µ‚ٌپjپB پ@پsچذٹQپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “Œ“ْ–{‘ه’nگkپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚µپ@پ@ ژ©گn
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚¶‚ٌپjپBپ@پs ژ©ٹQپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گط• پi‚¹‚ء‚ص‚پjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث گ´گ…ڈ@ژ،پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ژ©ٹQپi‚¶‚ھ‚¢پjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ژ©”ڑپi‚¶‚خ‚پjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژ©گnپ@پi‚¶‚¶‚ٌپj‚ئ‚حپAپ@“ْ–{‚ج—ًژj‚ة‚¨
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¢‚ؤپAپ@“پŒ•‚ً—p‚¢‚ؤژ©ٹQپi‚¶‚ھ‚¢پAژ©ژEپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚·‚邱‚ئ‚إ‚ ‚éپBپ@‘½‚‚ج‘¸‚¢–½پi‚¢‚ج‚؟پj‚ھ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ¸‚ي‚ꂽپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژ©گn‚ة‚حپAپ@“ْ–{‚ج—ًژj‚ة‚¨‚¢‚ؤپAگط
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@• پi‚¹‚ء‚ص‚پjپA‚»‚ج‘¼‚ج‘½‚‚جژ©ٹQ‚ج•û–@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ھ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژ©ٹQپ@پi‚¶‚ھ‚¢پA= ژ©ژEپj‚ة‚حپA “ْ–{‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—ًژj‚ة‚¨‚¢‚ؤپAژ©گnپi‚¶‚¶‚ٌپjپAژ©”ڑپi‚¶‚خ‚پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ب‚ا‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚µپ@پ@ ژ‡›‚“aپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚µ‚ٌ‚إ‚ٌپjپBپ@پs“à— پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= •½ˆہ‹‚ج“à— پi‚¾‚¢‚èپj“à
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جگ³“aپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث “à— پi‚¾‚¢‚èپjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@ژ‡›‚“a‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•½ˆہ‹‚جپA“à— پi‚¾‚¢‚èپj‚ج“a
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژةپiŒڑ•¨پj‚ج‚P‚آ‚إپAگ³“a‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@“à— پi‚¾‚¢‚èپj‚ئ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جپA“Vچc‚جڈZ‹ڈپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“VچcŒنڈٹ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@•½ˆہ‹پ„•½ˆہ‹{پi‘ه“à— پjپ„
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“à— پ„گ´—ء“aپAژ‡›‚“aپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@ پiپث •½ˆہ‹پi‹“sپj‚ج“à— پi‚¾‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚èپj“à‚جپAگ´—ء“aپAژ‡›‚“aپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@ پiپث •½ˆہ‹پi‹“sپj‚ج“à—
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¾‚¢‚èپjپAگ´—ء“aپAژ‡›‚“aپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹پA‹{ڈéپA“à— پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹پA”ٍ’¹‹پA“،Œ´‹پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•½ڈé‹پA’·‰ھ‹پA•½ˆہ‹پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹پA‹{ڈéپi‚«‚م‚¤‚¶‚ه‚¤ پjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‘ه“à— پi‚¾‚¢‚¾‚¢‚èپjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@ پiپث ‹پA‹{ڈéپA“à— پi‚¾‚¢‚èپjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‘ه‹ة“aپi‚¾ ‚¢‚²‚‚إ‚ٌپjپA’©“° ‰@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚؟‚ه‚¤‚ا‚¤‚¢‚ٌپjپA‘‚ژiپi‚¼‚¤‚µپjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@ پiپث “VچcپA“Vچc‰ئپA’©’ىپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژ‡›‚“a پ@پi‚µ‚µ‚ٌ‚إ‚ٌپj‚حپA•½ˆہ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹‚ج“à— پi‚¾‚¢‚èپj‚جگ³“a‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژ‡›‚“aپi‚µ‚µ‚ٌ‚إ‚ٌپj‚حپAپ@•½ˆہ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹پi= ‹“sپA‹‚ج“sپj‚جپA“à— پi‚¾‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚èپA“Vچc‚جڈZ‹ڈپj‚ج“aژةپiŒڑ•¨پj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚آ‚إ‚ ‚èپAپ@•½ˆہ‹‚ج“à— ‚جگ³“a
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ ‚èپAپ@“Vچc‚جچ‘‰ئ“I‹Vژ®پiŒِ“I پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چsژ–پj‚ًچs‚¤Œڑ•¨‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژ‡›‚“a پ@پi‚µ‚µ‚ٌ‚إ‚ٌپj‚حپA•½ˆہ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹پi‚ض‚¢‚ ‚ٌ‚«‚ه‚¤پA= ‹“sپA‹‚ج“sپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“à‚جپA•½ˆہ‹{پi‚ض‚¢‚ ‚ٌ‚«‚م‚¤پA= ‘ه
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“à— پi‚¾‚¢‚¾‚¢‚èپjپj“à‚ة‚ ‚éپA“à—
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جŒڑ•¨‚إ‚ ‚èپAپ@“à— ‚ج“aژة‚ج‚P‚آ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إپAپ@•½ˆہ‹‚ج“à— ‚جگ³“a‚إ‚ ‚èپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“Vچc‚جچ‘‰ئ“I‹Vژ®پiŒِ“Iچsژ–پj‚ًچs
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¤Œڑ•¨‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•½ˆہژ‘م––ٹْ‚ج‘ه‹ة“aپi‚¾‚¢‚²‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ٌپj‚جڈءژ¸پiڈؤژ¸پjŒمپA“Vچc‚جچ‘‰ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“I‹Vژ®پiŒِ“Iچsژ–پj‚حپA‘ه‹ة“a‚ة‘م‚ي
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚èپAژ‡›‚“a ‚إچs‚ي‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@“à— پ@پi‚¾‚¢‚èپj‚ئ‚حپAپ@“Vچc‚جڈZ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹ڈپA‹{‹ڈ‚إ‚ ‚èپA“Vچc‚جڈZ‚قŒن“aپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“VچcŒنڈٹ‚إ‚ ‚èپAپ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج“V
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چcŒنڈٹ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@گ´—ء“aپi‚¹‚¢‚è‚ه‚¤‚إ‚ٌپj‚حپA •½ˆہ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹پi= ‹“sپA‹‚ج“sپj‚جپA“à— پi‚¾‚¢‚èپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“Vچc‚جڈZ‹ڈپj‚ج“aژة‚ج‚P‚آ‚إ‚ ‚èپA“V
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چc‚ج“ْڈي‚ج‹ڈڈٹ‚إ‚ ‚èپA“Vچc‚جگ–±پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹Vژ®“™‚àچs‚¤Œڑ•¨‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‘ه‹ة“aپ@پi‚¾‚¢‚²‚‚إ‚ٌپj‚حپAپ@‹{ڈé
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚«‚م‚¤‚¶‚ه‚¤پA= “Vچc‚ج‹{“aپA•ت–¼پF“s
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹{پi‚ئ‚« ‚م‚¤پjپA‘ه“à— پi‚¾‚¢‚¾‚¢‚èپjپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج’†‚ة‚ ‚éپA“Vچc‚جچ‘‰ئ“I‹Vژ®پiŒِ“Iپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چsژ–پj‚ًچs‚¤گ³“a‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘ه‹ة“a‚حپAپ@•½ˆہژ‘م––ٹْ‚ج‚P‚P‚V‚V
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”Nپiژ،ڈ³Œ³”Nپj‚ج‰خچذˆبچ~پAچؤŒڑ‚³‚ꂸپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚»‚جŒمپA“Vچc‚جچ‘‰ئ“I‹Vژ®پiŒِ“Iچsژ–پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚حپA“à— پi‚¾‚¢‚èپj‚جژ‡›‚“aپi‚µ‚µ‚ٌ‚إ‚ٌپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ةˆع‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‘ه‹ة“aپi‚¾‚¢‚²‚‚إ‚ٌپj‚حپAپ@“،Œ´‹{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆبŒم‹{ڈé‚ةگف’u‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éژ{گف‚إپA“V
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چc‚جŒِ“Iچsژ–پiچ‘‰ئ“I‹Vژ®پj‚ًچs‚¤ڈê‚ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚µ‚ؤ—ک—p‚³‚ꂽپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“–ڈ‰پA’©“°‰@‚حپA‘ه‹ة“a‚ئ‚ح•ت‚ةپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ`گ¬‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½‚ھپA•½ˆہ‹{‚©‚çپA“ى–ت‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰ٌکL‚ھ“P‹ژ‚³‚êپA‘ه‹ة“a‚حپA’©“°‰@‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ³“a‚ئ‚ب‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پںپ@•½ˆہ‹پi= ‹“sپA‹‚ج“sپj‚ج“à— پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@•½ˆہ‹پi= ‹“sپA‹‚ج“sپjپ„
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•½ˆہ‹{پi= ‘ه“à— پjپ„پ@“à— پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‹“s‚ج•½ˆہ‹پi‚ض‚¢‚ ‚ٌ‚«‚ه‚¤پj‚إ‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•½ˆہ‹‚ج’†‚ةپA•½ˆہ‹{پi‚ض‚¢‚ ‚ٌ‚«‚م‚¤پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@= ‘ه“à— پi‚¾‚¢‚¾‚¢‚èپA= •½ˆہ‹‚ج‹{ڈé
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi ‚«‚م‚¤‚¶‚ه‚¤پA“Vچc‚ج‹{“aپj‚ج•½ˆہ‹{پi=
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘ه“à— پj‚ھ‚ ‚èپAپ@•½ˆہ ‹{پi= ‘ه“à— پj‚ج’†
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ةپA“à— پ@پi‚¾‚¢‚èپA“VچcŒنڈٹپA“Vچcژ„“@پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ھ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@•½ˆہ‹پ@پi‚ض‚¢‚ ‚ٌ‚«‚ه‚¤پA= ‹“sپA‹
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج“sپi‚«‚ه‚¤‚ج‚ف‚₱پjپjپ@‚ج“à— پ@پi‚¾‚¢‚èپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚حپAپ@•½ˆہ‹{پ@پi‚ض‚¢‚ ‚ٌ‚«‚م‚¤پA= ‘ه“à—
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¾‚¢‚¾‚¢‚èپjپj“à‚ة‚ ‚ء‚½پA“Vچc‚جڈZ‹ڈ‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚èپAŒ»چف‚ج‹“sژsڈم‹‹وپi‚©‚ف‚¬‚ه‚¤‚پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰؛—§”„’ت“y‰®’¬•t‹ك‚ة‚ ‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@•½ˆہ‹{ پi‚ض‚¢‚ ‚ٌ‚«‚م‚¤پj‚ئ‚حپA‘ه“à
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@— پi‚¾‚¢‚¾‚¢‚èپj‚إ‚ ‚èپAپ@•½ˆہ‹‚ج‹{ڈé
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚«‚م‚¤‚¶‚ه‚¤پA“Vچc‚ج‹{“aپj‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@پi‚Tپjپ@‹“s‚ج•½ˆہ‹“à‚جپA•½ˆہ‹{پi‚ض
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¢‚ ‚ٌ‚«‚م‚¤پA=‘ه“à— پi‚¾‚¢‚¾‚¢‚èپjپj“à‚جپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“à— پ@پi‚¾‚¢‚èپA“VچcŒنڈٹپj‚حپA–{—ˆ‚ج“à—
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج’n‚إ’f‘±“I‚ة‘¶چف‚µ‚½‚ھپAپ@ٹ™‘qژ‘م
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’†ٹْˆبŒمپA•½ˆہ‹‚ج–{—ˆ‚ج“à— ‚ج’n‚ة
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“à— ‚ھچؤŒڑ‚³‚ê‚邱‚ئ‚ح‚ب‚‚ب‚èپAپ@•½ˆہ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹‚ج“à— ‚حپA‹“sپi= •½ˆہ‹پj‚جٹeڈٹ‚ةپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—¢“à— پ@پi‚³‚ئ‚¾‚¢‚èپA“Vچc‚ج‰¼ŒنڈٹپA•½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆہ‹‚ج–{—ˆ‚ج“à— ‚ج’nˆبٹO‚جڈêڈٹ‚ة‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚é—صژ‚ج“à— پjپ@‚ئ‚µ‚ؤپA’u‚©‚ꂽپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@—¢“à— پ@پi‚³‚ئ‚¾‚¢‚èپj‚ئ‚حپA“Vچc‚ج‰¼
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œنڈٹ‚إ‚ ‚èپAپ@•½ˆہ‹‚ج–{—ˆ‚ج“à— ‚ج’n
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆبٹO‚جڈêڈٹ‚ة‚ ‚é—صژ‚ج“à— پi= “Vچc‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈZ‹ڈپj‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@•½ˆہ‹پi= ‹“sپA‹‚ج“sپj‚إ‚حپAپ@—¢“à
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@— ‚حپAڈ‰‚كپA•½ˆہ‹‚ج–{—ˆ‚ج“à— ‚ج’n‚ة
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œڑ‚آ“à— ‚ھ‰خچذ‚ب‚ا‚إژg—p•s”\‚ئ‚ب‚ء‚½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ‚ةپA‚»‚ج‘¼‚ج’n‚إپA—صژ‚ةژg—p‚³‚ê‚é“à
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@— ‚إ‚ ‚ء‚½‚ھپAژں‘و‚ةپA“à— ‚ح•½ˆہ‹پi= ‹
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“sپA‹‚ج“sپj‚ج–{—ˆ‚ج“à— ‚ج’n‚ةچؤŒڑ‚³‚ê
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚邱‚ئ‚ھڈ‚ب‚‚ب‚èپAپ@ٹ™‘qژ‘م’†ٹْˆبŒمپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–¾ژ،‚Q”N‚ـ‚إپA•½ˆہ‹‚ج–{—ˆ‚ج“à— ‚ج’n
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ةپA“à— ‚ھچؤŒڑ‚³‚ê‚邱‚ئ‚ح‚ب‚‚ب‚‚ب‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ،پ@•½ˆہ‹پ@پi‚ض‚¢‚ ‚ٌ‚«‚ه‚¤پj‚حپA •ت–¼
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@‚حپA‹“sپA‹‚ج“sپi‚«‚ه‚¤‚ج‚ف‚₱پj‚ئŒ¾‚¢پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@•½ˆہژ‘م‚©‚ç–¾ژ،ژ‘مڈ‰ٹْ‚ـ‚إپA‚V‚X‚S”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@‚©‚ç‚P‚W‚U‚X”N‚ـ‚إ‚جٹشپAپ@‹“s•{پE‹“sژs
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@•t‹ك‚جپA“Vچc‚ج ڈZ‹ڈپi= “à— پjپA“Vچc‚ج‹{
پ@پ@پ@پ@ “aپi= ‹{ڈéپj‚ھ‚ ‚ء‚½“sژs‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ،پ@•½ˆہ‹{پ@پi‚ض‚¢‚ ‚ٌ‚«‚م‚¤پj‚ئ‚حپA•ت–¼
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚حپA‘ه“à— پi‚¾‚¢‚¾‚¢‚èپj‚ئŒ¾‚¢پAپ@“ْ–{‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•½ˆہژ‘مپi‚V‚X‚S”Nپ`‚P‚P‚X‚Q”Nپj‚جپA‚V‚X‚S”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚©‚ç‚P‚P‚V‚V”Nچ ‚ـ‚إپA“ْ–{‚ج‹“sژsڈم‹
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹وپi‚©‚ف‚¬‚ه‚¤‚پj•t‹ك‚ة‚ ‚ء‚½پA‹{ڈéپi= “V
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چc‚ج‹{“a پj‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚¸پ@پ@گأ‰ھŒ§پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚¸‚¨‚©‚¯‚ٌپjپBپ@پsŒ»’nˆو–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپà ˆة“¤چ‘ ‚ئ ڈx‰ح چ‘ ‚ئ ‰“چ]
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ‘‚ج‘ٹ“–—جˆوپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiŒ»“s“¹•{Œ§پjپBپ@
پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@‚r‚g‚h‚y‚t‚n‚j‚`پ@‚o‚q‚d‚e‚d‚b‚s‚t‚q‚dپD
پiپث “s“¹•{Œ§پjپB
پiپث ˆة“¤چ‘ ‚ئ ڈx‰ح چ‘
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚ئ ‰“چ] چ‘پjپB
پ@پiپث ‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹Œ’nˆو–¼پA’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث “ْ–{‚ج’n–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@گأ‰ھŒ§پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپà ‘O‹ك‘م‚جپA‡@پ@ˆة“¤چ‘پi‚¢‚¸
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‚‚ةپA“¤ڈBپi‚¸‚µ‚م‚¤پjپjپEˆة“¤”¼“‡پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiگأ‰ھŒ§“Œ•”پEˆة“¤”¼“‡پjپAپ@‚ئپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‡Aپ@ڈx‰ح چ‘پ@پi‚·‚é‚ھ ‚ج‚‚ةپAڈxڈB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚·‚ٌ‚µ‚م‚¤پjپAگأ‰ھŒ§’†•”پj پAپ@‚ئپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‡Bپ@‰“چ] چ‘ پi‚ئ‚¨‚ئ‚¤‚ف ‚ج‚‚ة پA‰“
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈBپi‚¦‚ٌ‚µ‚م‚¤پjپAگأ‰ھŒ§گ¼•”پjپ@ ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‘ٹ“–—جˆوپjپBپ@
پ@
پZپ@‚µ‚¸پ@پ@گأŒن‘OپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚¸‚©‚²‚؛‚ٌپjپBپ@ پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@Œ¹‹`Œo‚ج’ˆ¤‚·‚鑤ژ؛•vگlپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@•‘پi‚ـ‚¢پj‚ج–¼ژèپA”üگlپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث Œ¹ ‹`ŒoپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@گأŒن‘O پ@پi‚µ‚¸‚©‚²‚؛‚ٌپj‚حپAپ@Œ¹‹`Œo‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’ˆ¤‚·‚鑤ژ؛•vگl‚إ‚ ‚èپAپ@•‘پi‚ـ‚¢پj ‚ج–¼
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژè‚إپAپ@”üگl‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@
پZپ@‚µ‚¸پ@پ@وثƒ–ٹx‚جژµ–{‘„پ@
پi‚µ‚¸‚ھ‚½‚¯‚ج‚µ‚؟‚ظ‚ٌ‚â‚èپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پs•گڈ«پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث •ں“‡ گ³‘¥پA‰ء“، گ´گ³پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ •½–ى ’·‘×پA•ذ‹ث ٹژŒ³پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@پuوثƒ–ٹx‚جژµ–{‘„پvپi‚µ‚¸‚ھ‚½‚¯ ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚µ‚؟‚ظ‚ٌ‚â‚èپj‚ئ‚حپAپ@‚P‚T‚W‚R”Nپi“Vگ³
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚P”Nپj‚SŒژ‚جوثƒ–ٹx ‚جگي‚¢پi‚µ‚¸‚ھ‚½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¯‚ج‚½‚½‚©‚¢پj‚إگي‚¢پAڈG‹g•û‚إŒ÷–¼
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ً‚ ‚°‚½•؛‚ج“à‚جپAڈG‹gژqژ”‚¢‚ج•گ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ«‚ج‚Vگl‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@•ˆ‘م‚ج‰ئگb‚ًژ‚½‚ب‚©‚ء‚½‰Hژؤ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈG‹gپi–LگbڈG‹gپj‚ھژ©•ھ‚جژqژ”‚¢‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•گڈ«‚ً‰ك‘ه‚ةگé“`‚µ‚½Œ‹‰تپAڈG‹gژq
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ”‚¢‚ج‚Vگl‚ج•گڈ«‚ھوثƒ–ٹx‚جگي‚¢‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ÷–¼‚ً‚½‚ؤ‚½پi—E–¼‚ً‚ح‚¹‚½پj•گڈ«‚ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚µ‚ؤپA—L–¼‚ئ‚ب‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@پuوثƒ–ٹx‚جژµ–{‘„پv‚ج•گڈ«‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•ں“‡ گ³‘¥پA‰ء“، گ´گ³پA ‰ء“، ‰أ–¾پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@کeچâ ˆہژ،پA•½–ى ’·‘×پA‘Œ‰® •گ‘¥پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•ذ‹ث ٹژŒ³‚ج‚Vگl‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚¸پ@پ@ وثƒ–ٹx‚جگي‚¢پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚¸‚ھ‚½‚¯‚ج‚½‚½‚©‚¢پjپ@پsچ‡گيپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚T‚W‚R”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ،پ@وثƒ–ٹx‚جگي‚¢ پi‚µ‚¸‚ھ‚½‚¯‚ج‚½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚½‚©‚¢پjپ@‚حپAپ@
گM’·–S‚«Œم‚جگD“cژپ‚جژه“±Œ ‚ً‚ك
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚®‚ء‚ؤپA‚P‚T‚W‚R”Nپi“Vگ³‚P‚P”Nپj‚SŒژ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ةپA‹كچ]چ‘پi‚¨‚¤‚ف‚ج‚‚ةپj‚جوثƒ–ٹxپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚¸‚ھ‚½‚¯پAŒ»چف‚جژ ‰êŒ§’·•lژs پjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•t‹ك‚إپAپ@ژؤ“cڈں‰ئ•û‚جŒR‚ئ‰HژؤڈG
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹g•û‚جŒR‚ھŒƒگي‚ًŒً‚¦‚½گي‚¢‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@وثƒ–ٹx‚جگي‚¢پ@پi‚µ‚¸‚ھ‚½‚¯‚ج‚½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚½‚©‚¢پj‚حپA ‚P‚T‚W‚R”Nپi“Vگ³‚P‚P”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ةپA–k‹كچ]پi‚«‚½‚¨‚¤‚فپAŒ»پEژ ‰êŒ§
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–k•”‚ج‘ٹ“–’nˆوپj‚جوثƒ–ٹx•t‹ك‚إپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گD“cگM’·‚جڈdگb‚¾‚ء‚½‰HژؤڈG‹g
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚ح‚µ‚خ‚ذ‚إ‚و‚µپA–LگbڈG‹gپj‚جŒRپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ئپAپ@گD“cگM’·‚جڈdگb‚¾‚ء‚½ژؤ“cڈں
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰ئپi‚µ‚خ‚½‚©‚آ‚¢‚¦پj‚جŒR‚ھگي‚ء‚½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ‡گي‚إ‚ ‚éپBپ@ژؤ“cڈں‰ئژه—حŒR‚ح
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”s‘ق‚·‚é
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰HژؤڈG‹gپi–LگbڈG‹gپjŒR‚ھگي‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ةڈں‚؟پAژؤ“cڈں‰ئŒR‚ھگي‚¢‚ة”s‚ê
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‰HژؤڈG‹g‚ھڈں—ک‚ً‚¨‚³‚كپA”s‚ê
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚½ژؤ“cڈں‰ئ‚حپA’ا‘–‚³‚êپA‚SŒژ‚ة‹ڈ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈé‚ج‰z‘Oچ‘پi‚¦‚؟‚؛‚ٌ‚ج‚‚ةپj‚ج–k
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ¯ڈéپi‚«‚½‚ج‚µ‚ه‚¤‚¶‚ه‚¤پj‚إژ©گnپi‚¶
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¶‚ٌپj‚µ‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ڈG‹g‚ة‚و‚éپAژؤ“cڈں‰ئژه—حŒR‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”s‘ق‚ئژؤ“cڈں‰ئ‚ج–{‹’’n‚ج–kڈ¯ڈé
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚«‚½‚ج‚µ‚ه‚¤‚¶‚ه‚¤پj‚ج—ژڈé‚ة‚و‚èپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰HژؤڈG‹gپi–LگbڈG‹gپj‚حپA“ْ–{’†‰›
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•”‚ًژx”z‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@چ‡گي‚جڈں—ک‚جŒ‹‰تپAڈG‹g‚ھگD“c
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گM’·‚جŒpڈ³ژز‚ئ‚µ‚ؤ‚ج’nˆت‚ًŒإ‚ك‚½پBپ@
پ@
پZپ@‚µ‚¹پ@پ@ژپگ©پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚¹‚¢پjپBپ@پsگl–¼پtپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@‘O‹ك‘م‚جˆê‘°–¼‚ج‚P‚آپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جپAژپ‘°–¼‚âگ©
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚©‚خ‚ثپj‚ئ‚¢‚¤ˆê‘°–¼پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‘O‹ك‘م“ْ–{‚جگl–¼پj پB
پ@
پZپ@‚µ‚¹پ@ ژپگ©گ§“xپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚¹‚¢‚¹‚¢‚اپj پBپ@پsگژ،گ§“xپtپB
پi‚Tپ`‚Vگ¢‹Iپj پB
پ@
پZپ@‚µ‚¼پ@پ@ژپ‘°–¼پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚¼‚‚ك‚¢پjپBپ@پsژپ–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‘O‹ك‘م“ْ–{‚جژپ‘°–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پ@ پiپث ˆê‘°–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جگl•¨ژپ–¼‚ة‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆê‘°–¼پiژپ‘°–¼پA‰ئ–¼پjپ@‚ئپ@Œآگl–¼
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚¾پ@پ@ژ‘م‹و•ھپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚¾‚¢‚‚ش‚ٌپjپBپ@پs—ًژjژ‘م‹و•ھپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= “ْ–{—ًژj‚جژ‘م‹و•ھپjپB
پ@ پiپث “ْ–{—ًژj‚جژ‘م‹و•ھپjپB
پ@ پiپث “ْ–{—ًژjژ‘م‹و•ھ•\پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث “ْ–{‚ج—ًژjپj پB
پ@
پZپ@‚µ‚½پ@پ@‰؛’n’†•ھپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚½‚¶‚؟‚م‚¤‚ش‚ٌپjپBپ@پs‘‘‰€پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ’n“ھپAچ‘گlپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‰؛’n’†•ھپi‚µ‚½‚¶‚؟‚م‚¤‚ش‚ٌپj‚ئ‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’†گ¢“ْ–{پiٹ™‘qپEŒڑ•گپEژ؛’¬ژ‘مپj‚إپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘‘‰€‚ً“ٌ•ھ‚µ‚ؤپA’n“ھ‚ئ–{ڈٹپE—ج‰ئ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘‘‰€—جژه‚إپA‘‘‰€‚ً•ھٹ„ژx”z‚·‚éگ§
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“x‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚؟پ@پ@ژµˆتپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚؟‚¢پjپB پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@‹كپEŒ»‘م“ْ–{‚جپAگEˆُ—كپi‚Q‚O
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆتٹKپjپAڈ–ˆتڈً—لپi‚P‚UˆتٹKپjپAˆت
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹK—كپi‚P‚UˆتٹKپj‚جˆتٹKپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پƒ‚P‚W‚U‚X”Nچ پ`Œ»چفپAژg—pپ„پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@گ³ژµˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚؟‚¢پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@ڈ]ژµˆتپ@پi‚¶‚م‚µ‚؟‚¢پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ˆتٹK—ك‚جˆتٹKپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ڈ–ˆتڈً—ل‚جˆتٹKپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث گEˆُ—ك‚جˆتٹKپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹كپEŒ»‘م“ْ–{گ•{‚جˆتٹKپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚Pپjپ@ژµˆتپ@پi‚µ‚؟‚¢پj‚حپAپ@‹كپEŒ»‘م“ْ–{‚جپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@گEˆُ—كپi‚Q‚OˆتٹKپjپAڈ–ˆتڈً—لپi‚P‚UˆتٹKپjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆتٹK—كپi‚P‚UˆتٹKپj‚إپAپ@گ³ژµˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚؟‚¢پj پ@‚ئپ@ڈ]ژµˆتپ@پi‚¶‚م‚µ‚؟‚¢پjپ@‚ج‚Q‚آ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جˆتٹK‚ئ‚µ‚ؤپAپ@‚P‚W‚U‚X”Nچ ‚©‚猻چف‚ـ‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژg—p‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جپA’©’ى‚ج—¥—ك
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹ¯گ§‚جˆتٹKپi‚R‚OˆتٹKپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پƒ‚V‚O‚P”Nچ پ`‚P‚W‚U‚X”Nچ پAژg—pپ„پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@گ³ژµˆتڈمپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚؟‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@گ³ژµˆت‰؛پ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚؟‚¢‚ج‚°پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ڈ]ژµˆتڈمپ@پi‚¶‚م‚µ‚؟‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ڈ]ژµˆت‰؛پ@پi‚¶‚م‚µ‚؟‚¢‚ج‚°پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ’©’ى‚ج—¥—كٹ¯گ§‚جˆتٹKپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚Qپjپ@ژµˆتپ@پi‚µ‚؟‚¢پj‚حپAپ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’©’ى‚ج—¥—كٹ¯گ§‚جˆتٹKپi‚R‚OˆتٹKپj‚إ پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ³ژµˆتڈمپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚؟‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپAپ@گ³ژµ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆت‰؛پ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚؟‚¢‚ج‚°پjپAپ@ڈ]ژµˆتڈمپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚µ‚؟‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپA پ@ڈ]ژµˆت‰؛پ@پi‚¶‚م
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚µ‚؟‚¢‚ج‚°پjپ@‚ج‚S‚آ‚جˆتٹK‚ئ ‚µ‚ؤپAپ@‚V‚O‚P
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”Nچ ‚©‚ç‚P‚W‚U‚X”Nچ ‚ـ‚إژg—p‚³‚ꂽپB
پ@
پZپ@‚µ‚أپ@پ@ژu’أپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚أپjپB پ@پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= ‚¨گأپA‚¨ژu’أپjپB
پ›پ@“؟گىڈG’‰‚ج‘¤ژ؛•vگl پB
پ›پ@‰ï’أ”ث‘cپE •غ‰بگ³”Vپi‚ظ‚µ‚ب
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@‚ـ‚³‚ن‚«پj‚جگ¶•êپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ‚¨ گأپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚ءپ@ ڈ\ٹ±پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ء‚©‚ٌپjپBپ@پsڈ\ٹ±ڈ\“ٌژxپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ٹ±ژxپi‚©‚ٌ‚µپjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@چbپA‰³پA•¸پA’ڑپA•èپAŒبپAچMپAگhپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گpپAل،‚ج‚P‚Oژي—ق‚©‚ç‚ب‚éگ”ژŒپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ٹ±ژxپi‚©‚ٌ‚µپA‚¦‚ئپAڈ\ٹ±ڈ\“ٌژxپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جˆê•”پB
پ@
پZپ@‚µ‚ءپ@ ژ·Œ پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ء‚¯‚ٌپjپBپ@پsٹ™‘q–‹•{‚جگE–¼پtپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= ٹ™‘q–‹•{‚جڈ«ŒR•âچ²گEپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@ژ·Œ ‚ئ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹ™‘q–‹•{‚جڈ«ŒR‚ً•âچ² ‚µپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–‹گ‚ً“ٹچپi‘چٹ‡پj‚·‚é–ًگE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پiپث ٹ™‘qڈ«ŒRپAŒن‰ئگlپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پiپث –kڈًژپ“¾ڈ@پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–kڈً“¾ڈ@‰ئپA“¾ڈ@گêگ§پA
پ@پ@پ@پ@ٹٌچ‡پA“àٹا—جپA’·چèژپپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ Œن“àگlپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ژ·Œ پAژ·Œ –kڈًژپپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‰ح“àŒ¹ژپپAٹ™‘q–kڈًژپپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث Œ¹ژپگŒ پA–kڈًگŒ پA
پ@پ@پ@پ@ٹ™‘q–‹•{پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث –‹•{پAڈ«ŒRپA•گ‰ئگŒ پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ْ–{‚جگŒ پEگ•{پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@ٹ™‘q–‹•{‚جژ·Œ پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژ·Œ پB
پ@پ@ پ@پ@پœ ٹ™‘q–‹•{‚جژ·Œ پi‚µ‚ء‚¯‚ٌپA=
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹ™‘q–‹•{‚جڈ«ŒR•âچ²گEپj‚ئ‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹ™‘q–‹•{‚جڈ«ŒR‚ً•âچ²‚µ‚ؤ–‹گ‚ً
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ٹچپi‘چٹ‡پj‚·‚é–ًگE‚إ‚ ‚èپAٹ™‘qپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–kڈًژپ‚ھژ·Œ ‚ً‘مپXگ¢ڈP‚·‚éپBپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœ ژ·Œ پi‚µ‚ء‚¯‚ٌپA= ٹ™‘q–‹•{‚ج
پ@پ@پ@پ@ڈ«ŒR•âچ²گEپj‚ئ‚حپAپ@ٹ™‘q–‹•{‚جڈ«
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒR‚ً•âچ²‚µ‚ؤ–‹گ‚ً“ٹچپi‘چٹ‡پj‚·
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚é–ًگE‚إ‚ ‚èپAپ@ٹ™‘q–kڈًژپ‚ھ‘مپX
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ¢ڈP‚·‚éپBپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ژ·Œ گE‚حپAپ@ٹ™‘qژ‘مڈ‰ٹْ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ¹ژپڈ«ŒR‚جژٹْ‚ة‚حپAٹ™‘q–‹•{‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ«ŒR‚ً•âچ²‚µ‚ؤ ’P‚ةٹ™‘q–‹•{‚جگ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–±‚ًچs‚¤پi‘چ——‚·‚éپj–ًگE‚إ‚ ‚ء‚½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ھپAپ@ٹ™‘qژ‘م’†ٹْپEŒمٹْ‚جگغ‰ئپE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹{ڈ«ŒR‚جژٹْ‚ة‚حپAپ@ٹ™‘q–‹•{‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ«ŒR‚جŒمŒ©گl‚ئ‚µ‚ؤپAڈ«ŒR‚ة‘م‚ي
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ء‚ؤپA‚»‚جŒ —ح‚ً‘مچs‚·‚é–ًگE‚ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@‚ب‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@“¾ڈ@ˆبٹO‚جژ·Œ پB
پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ژ·Œ گE‚حپAپ@“¾ڈ@پi‚ئ‚‚»‚¤پAٹ™
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘q–kڈًژپ–{‰ئ‚ج“–ژهپj‚ھ‘مپXگ¢ڈP
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚µڈA”C‚·‚é‚ھپAپ@“¾ڈ@‰ئپi‚ئ‚‚»‚¤‚¯پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹ™‘q–kڈًژپ–{‰ئپj‚ةژ·Œ گE“K”Cژز
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ھ‚¢‚ب‚¢ٹشپAٹ™‘q–kڈًژپ•ھ‰ئ‚جژز
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ھڈA”C‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@“¾ڈ@ˆبٹO‚جژ·Œ پi‘و‚UپE‚V‘مپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘و‚P‚Oپ`‚P‚R‘مپA‘و‚P‚TپE‚P‚U‘مپj‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چفگE’†پA“¾ڈ@‚ج•û‚ھگژ،Œ —ح‚ھ‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚èپAپ@ٹ™‘q–‹•{‚إ‚جŒ —ح‚ھژم‚پAچإ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ‚Œ —ح‚ً‚à‚½‚ب‚¢ژ·Œ ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ژ·Œ گE‚حپAپ@“¾ڈ@پi‚ئ‚‚»‚¤پAٹ™
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘q–kڈًژپ–{‰ئ‚ج“–ژهپj‚ھ‘مپXگ¢ڈP
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚µڈA”C‚·‚é‚ھپAپ@“¾ڈ@‰ئپiٹ™‘q–kڈً
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژپ–{‰ئپj‚ةژ·Œ گE“K”Cژز‚ھ‚¢‚ب‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹشپAٹ™‘q–kڈًژپ•ھ‰ئ‚جژز‚ھڈA”C‚·
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ٹ™‘q–‹•{‚جژ·Œ ‚P‚U‘مˆê——•\پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹ™‘q–‹•{‚جٹ™‘q–kڈًژپ‚جژ·Œ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚U‘م‚حپAڈ‡‚ةپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ڈ‰‘مپ@پ@ژ·Œ پE–kڈً ژگ پi‚ئ‚«‚ـ‚³پjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘و‚Q‘مپ@ژ·Œ پE–kڈً ‹`ژ پi‚و‚µ‚ئ‚«پjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘و‚R‘مپ@ژ·Œ پE–kڈً ‘×ژ پi‚â‚·‚ئ‚«پjپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘و‚S‘مپ@ژ·Œ پE–kڈً Œoژ پi‚آ‚ث‚ئ‚«پjپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘و‚T‘مپ@ژ·Œ پE–kڈً ژ—ٹ پi‚ئ‚«‚و‚èپj پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘و‚U‘مپ@ژ·Œ پE–kڈً ’·ژ پi‚ب‚ھ‚ئ‚«پjپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘و‚V‘مپ@ژ·Œ پE–kڈً گ‘؛ پi‚ـ‚³‚ق‚çپjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘و‚W‘مپ@ژ·Œ پE–kڈً ژڈ@ پi‚ئ‚«‚ق‚ثپjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘و‚X‘مپ@ژ·Œ پE–kڈً ’هژ پi‚³‚¾‚ئ‚«پjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘و‚P‚O‘مژ·Œ پE–kڈً ژtژ پi‚à‚ë‚ئ‚«پjپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘و‚P‚P‘مژ·Œ پE–kڈً ڈ@گé پi‚ق‚ث‚ج‚شپjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘و‚P‚Q‘مژ·Œ پE–kڈً ê¤ژ پi‚ذ‚ë‚ئ‚«پjپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘و‚P‚R‘مژ·Œ پE–kڈً ٹîژ پi‚à‚ئ‚ئ‚«پjپAپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘و‚P‚S‘مژ·Œ پE–kڈً چ‚ژ پi‚½‚©‚ئ‚«پjپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘و‚P‚T‘مژ·Œ پE–kڈً ’هŒ° پi‚³‚¾‚ ‚«پjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘و‚P‚U‘مژ·Œ پE–kڈً ژçژ پi‚à‚è‚ئ‚«پjپAپ@پ@ پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚ءپ@ ژ·Œ –kڈًژپپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ء‚¯‚ٌ‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤‚µپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پs ٹ™‘q–kڈًژپپtپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= ٹ™‘qژ‘م‚جٹ™‘q–kڈًژپپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@ژ·Œ –kڈًژپ‚ئ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹ™‘qژ‘م‚جٹ™‘q–kڈًژپ‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚èپA ٹ™‘qژ‘م‚جپAٹ™‘q
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–‹•{‚جژ·Œ گEپiڈ«ŒR•âچ²
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گEپj‚ً‘مپXگ¢ڈP‚·‚éٹ™‘q
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–kڈًژپ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پiپث ٹ™‘qڈ«ŒRپAŒن‰ئگlپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پiپث –kڈًژپ“¾ڈ@پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–kڈً“¾ڈ@‰ئپA“¾ڈ@گêگ§پA
پ@پ@پ@پ@ٹٌچ‡پA“àٹا—جپA’·چèژپپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ Œن“àگlپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ژ·Œ پAژ·Œ –kڈًژپپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‰ح“àŒ¹ژپپAٹ™‘q–kڈًژپپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث Œ¹ژپگŒ پA–kڈًگŒ پA
پ@پ@پ@پ@ٹ™‘q–‹•{پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث –‹•{پAڈ«ŒRپA•گ‰ئگŒ پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ْ–{‚جگŒ پEگ•{پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژ·Œ –kڈًژپپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژ·Œ –kڈًژپپi‚µ‚ء‚¯‚ٌ‚ظ‚¤‚¶‚ه
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¤‚µپA‚P‚Q‚O‚R”Nپ[‚P‚R‚R‚R”Nپj ‚ئ‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹ™‘qژ‘م‚جٹ™‘q–kڈًژپ‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹ™‘qژ‘م‚جپAٹ™‘q–‹•{‚جژ·Œ گE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiڈ«ŒR•âچ²گEپj‚ً‘مپXگ¢ڈP‚·‚éٹ™
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘q–kڈًژپ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژ·Œ –kڈًژپ‚حپAٹ™‘q–‹•{‚إ‘ه
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚«‚بگژ،Œ —ح‚ً‚à‚آپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ژ·Œ –kڈًژپ‚حپAپ@ٹ™‘qژ‘م‚ةپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹ™‘q–‹•{‚جژ·Œ گEپiڈ«ŒR•âچ²گEپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ً‘مپXگ¢ڈP‚µپAپ@ٹ™‘q–‹•{‚جگڈٹ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ـ‚½‚حژکڈٹ‚ج•ت“–پi‚ׂء‚ئ‚¤پA’·
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹ¯پj‚ًپ@‚àŒ“‚ثپAپ@ٹ™‘qژ‘م’†ٹْپE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œمٹْ‚ةپAٹ™‘q–‹•{‚جژہژ؟“I‚ب
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چإچ‚ژw“±ژز‚ئ‚ب‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ٹ™‘q–‹•{‚ج‘و‚R‘مڈ«ŒR‚جŒ¹
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژہ’© پi‚ف‚ب‚à‚ئ‚ج‚³‚ث‚ئ‚àپjژ€‹ژŒمپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ·Œ –kڈًژپ‚جپA“ٍŒن‘نپi‚ ‚ـ‚ف‚¾
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¢پA“ٍڈ«ŒRپj‚ج–kڈًگژqپAژ·Œ پE“¾
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ@‚ج–kڈً‹`ژˆبŒم‚جپAژ·Œ –kڈً
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژپ‚حپAپ@ٹ™‘q–‹•{‚جژہژ؟“I‚بچإچ‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژw“±ژز‚ئ‚ب‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚ءپ@ ژہگ¬‰@پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚ء‚¹‚¢‚¢‚ٌ پA‚¶‚آ‚¶‚ه‚¤‚¢‚ٌپjپBپsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚P‚W‚Q‚Pپ`‚P‚X‚O‚S”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@چ]Œث–‹•{پE‘و‚P‚S‘مڈ«ŒRپE“؟گى
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰ئ–خپi‚¢‚¦‚à‚؟ پj‚جگ¶•ê پB
پ@
پZپ@‚µ‚ءپ@پ@ƒVƒbƒ_پ[ƒ‹ƒ^پB
پs•§‹³پtپB پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= ƒKƒEƒ^ƒ}پEƒVƒbƒ_پ[ƒ‹ƒ^ پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ƒuƒbƒ_پi•§‘ةپjپAƒVƒƒƒJپiژك‰قپjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi•§‹³‚ج‹³‘cپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiگ¶–v”NپFپ@‹IŒ³‘O‚T‚U‚R”Nچ پ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘O‚S‚W‚R”Nچ پjپ@پiڈ”گà‚ ‚èپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚f‚`‚t‚s‚`‚l‚`پ@‚r‚h‚c‚c‚g‚`‚q‚s‚g‚`پB
پiپث •§‹³پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ›پ@•ت–¼پF ƒSپ[ƒ^ƒ}پEƒVƒbƒ_پ[ƒ‹ƒ^پAپ@ƒV
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒƒƒJƒ€ƒjپiژك‰ق–´“ٍپjپAپ@ژك‰ق–´“ٍپi‚µ‚ل‚©
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ق‚ةپjپA ƒVƒƒƒJپiژك‰قپjپAپ@ژك‰قپi‚µ‚ل‚©پjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژك‘¸پi‚µ‚ل‚‚»‚ٌپjپAپ@‚¨ژك‰ق—lپi‚¨‚µ‚ل‚©
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚³‚ـپjپAپ@ƒuƒbƒ_پi•§‘ةپjپAپ@•§‘ةپi‚ش‚ء‚¾پj پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•§پi‚ظ‚ئ‚¯پjپAپ@•§—lپi‚ظ‚ئ‚¯‚³‚ـپjپAپ@Œن•§
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚ف‚ظ‚ئ‚¯پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@ƒKƒEƒ^ƒ}پEƒVƒbƒ_پ[ƒ‹ƒ^‚حپA•§‹³‚ج‹³ پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‘cپi‚«‚ه‚¤‚»پAٹJ‘cپA‘nژnژزپjپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@‹³‘c‚ئ‚حپAپ@‚»‚جڈ@‹³پAڈ@”h‚ً‚ذ‚ç‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚½گl‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@ڈ@‹³‚ة‚حپAپ@‹³‘cپi‚«‚ه‚¤‚»پjپAپ@‹³‹`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‹³‚¦پjپAپ@‹³“Tپi‚«‚ه‚¤‚ؤ‚ٌپjپAپ@ڈ@‹³“àƒO
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ƒ‹پ[ƒvپiڈ@‹³“à•ھ”hپjپ@‚ب‚ا‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚ءپ@ ژ·Œ پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ء‚¯‚ٌپjپBپ@پsٹ™‘q–‹•{‚جگE–¼پtپB
پi= ڈ«ŒR•âچ²پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ٹ™‘q–‹•{‚جڈ«ŒR‚ً•âچ²‚·‚é
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–ًگEپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث –kڈًژپپA–kڈًگŒ پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹ™‘q–‹•{پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژ·Œ پi‚µ‚ء‚¯‚ٌپj‚ئ‚حپA ٹ™‘q–‹•{‚جڈ«
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒR‚ً•âچ²‚·‚é–ًگE‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ٹ™‘q–‹•{‚إ‚حپAپ@پuڈ«ŒRپvپAپ@پuژ·Œ پvپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پu—L—حŒن‰ئگlپvپAپ@پu“àٹا—جپvپ@‚ئ‚جٹش‚إپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ـ‚½پAپ@–kڈًژپ“¾ڈ@‰ئ‚ئ–kڈًژپ•ھ‰ئ‚ئ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹش‚إپAپ@‚و‚Œ —ح‘ˆ‚¢‚ھ‹N‚±‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹ™‘q–‹•{‚إ‚حپAپ@پuڈ«ŒRپvپiٹ™‘q–‹•{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ«ŒRپjپAپ@پuژ·Œ پvپi‚µ‚ء‚¯‚ٌپAڈ«ŒR•âچ²پA–k
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈًژپگ¢ڈPپjپAپ@Œن‰ئگlپi‚²‚¯‚ة‚ٌپAڈ«ŒR‰ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گbپj‚ج’†‚جپu—L—حŒن‰ئگlپvپAپ@Œن“àگlپi‚ف‚¤
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚؟‚ر‚ئپA= –kڈًژپ“¾ڈ@‰ئپi‚ئ‚‚»‚¤‚¯پA–{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰ئپj‰ئگbپj‚ج’·پi•M“ھپjپA“¾ڈ@‰ئژ·ژ–پj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پu“àٹا—جپvپ@پi‚¤‚؟‚©‚ٌ‚ê‚¢پA‚ب‚¢‚©‚ٌ‚ê‚¢پj پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ئ‚جٹش‚إپA‚ـ‚½پAپ@–kڈًژپ“¾ڈ@‰ئپi–kڈًژپ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–{‰ئپj‚ئ–kڈًژپ•ھ‰ئ‚ئ‚جٹش‚إپAپ@‚و‚Œ —ح
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘ˆ‚¢‚ھ‹N‚±‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@Œ —ح‘ˆ‚¢‚ج—ل‚ً‚ ‚°‚é‚ئپAپ@ٹ™‘qژ‘م
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’†ٹْ‚جپA“àٹا—جپE •½—ٹچ|پi‚½‚¢‚ç‚ج‚و‚è‚آ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚بپj‚ئ—L—حŒن‰ئگlپEˆہ’B‘×گ·پi‚ ‚¾‚؟‚â‚·‚à
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚èپj‚جŒ —ح‘ˆ‚¢ پi‘ڑŒژ‘›“®پi‚µ‚à‚آ‚«‚»‚¤‚ا
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¤پjپjپAپ@ٹ™‘qژ‘م––ٹْ‚جپA“àٹا—جپE’·چèژپ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ئ—L—حŒن‰ئگlپE‘«—کژپ‚ئ‚جŒ —ح‘ˆ‚¢پ@‚ب‚ا
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚ءپ@ ژ·Œ گژ،پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ء‚¯‚ٌ‚¹‚¢‚¶پjپBپ@پsگژ،گ§“xپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= –kڈًژپژ·Œ گژ،پjپB
پi‚P‚Q‚P‚Xپ`‚P‚R‚R‚R”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@ٹ™‘q–‹•{‚ج–kڈًژپژ·Œ ‚ة‚و‚é
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گژ،پB
پ@
پZپ@‚¶‚ئپ@ ’n“ھپAچ‘گlپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚ئ‚¤پA‚±‚‚¶‚ٌپjپBپ@پs•گژm‚ج—جژهپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚P‚Qپ|‚P‚Vگ¢‹IپjپB
پ@پ@پ@پ،پ@’n“ھپi‚¶‚ئ‚¤پj‚ئ‚حپAپ@’n•û“yچ‹پi‚ا
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚²‚¤پjپAچف’n—جژه‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ،پ@ٹ™‘qژ‘م‚ج’n“ھ‚حپAژ؛’¬ژ‘مˆبŒمپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ‘گlپi‚±‚ ‚¶‚ٌپA= چ‘ڈOپi‚‚ة‚µ‚م‚¤پjپj‚ئ
پ@پ@پ@‚àŒؤ‚خ‚ê‚éپB
پ@پ@پ@پ،پ@’n“ھپi‚¶‚ئ‚¤پj‚ة‚حپAپ@–‹•{‚ة‚و‚èپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œِ—جپi‚±‚¤‚è‚ه‚¤پAچ‘هة—جپi‚±‚‚ھ‚è‚ه‚¤پjپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جŒSژiپi‚®‚ٌ‚¶پjپ@‚âپ@‘‘‰€‚ج‰؛ژiپi‚°‚µپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ب‚ا‚ھ”C‚¶‚ç‚ê‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚ئپ@ ’n“ھگ؟پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ئ‚¤‚¤‚¯پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiگ؟ڈٹپjپ@پs ”Nچvگ؟•‰گ§“xپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پs“ْ–{‚ج“y’nژx”zگ§“xپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ’n“ھپAچ‘گlپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ‘‘‰€پAŒِ—جپi= چ‘هة—جپjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث گ؟ڈٹپi‚¤‚¯‚µ‚هپjپAژçŒىگ؟پA
•Sگ©گ؟پi= ’n‰؛گ؟پjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@’n“ھگ؟پB
پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@’n“ھگ؟پi‚¶‚ئ‚¤‚¤‚¯پj‚ئ‚حپAپ@’†گ¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{‚إپA’n“ھ‚ھ‘‘‰€‚âŒِ—جپiچ‘هة
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—جپj‚ج”Nچv‚ج”[“ü‚ًگ؟‚¯•‰‚¤گ§“x‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@’n“ھگ؟پi‚¶‚ئ‚¤‚¤‚¯پj‚ئ‚حپAپ@’†گ¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{پiٹ™‘qپEŒڑ•گپEژ؛’¬ژ‘مپj‚إپAپ@’n
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ھ‚ھˆê’è‚ج”Nچvپi‚ث‚ٌ‚®پj‚ً”[“ü‚·‚é
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ئ‚¢‚¤ڈًŒڈ‚إپAپ@–{ڈٹپE—ج‰ئ‚ج‘‘‰€—ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژه‚âچ‘ژiپE’mچsچ‘ژه‚ھپA’n“ھ‚ة‘‘‰€
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚âŒِ—جپiچ‘هة—جپj‚جŒo‰c‚ًˆد”C‚·‚é
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ§“x‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚ئپ@ ژ““VچcپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚ئ‚¤‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پjپBپ@پsڈ—گ«“VچcپtپB
پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@‚d‚l‚o‚d‚q‚n‚qپ@‚i‚h‚s‚nپD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@ژ““VچcچفˆتپF
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚U‚X‚O”Nپ[‚U‚X‚V”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ڈ—گ«“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژ“پi‚¶‚ئ‚¤پj“Vچcپ@پiچفˆتپF‚U‚X‚O ”Nپ[‚U‚X‚V
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”NپA‰pپF‚s‚g‚dپ@‚d‚l‚o‚q‚d‚r‚rپ@‚i‚h‚s‚nپj‚حپAپ@”ٍ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’¹”’–Pژ‘م‚جڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپj‚إ ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژ““Vچc‚حپAپ@“V•گ“Vچcپiچفˆت‚U‚V‚Rپ[
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚U‚W‚U”Nپj‚جچcچ@‚إ‚ ‚èپAپ@“V•گ“Vچc‚جژ€Œم
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ·گپi‚µ‚ء‚¹‚¢پAڈA”CپF‚U‚W‚Uپ[‚U‚X‚O”Nپj‚ئ‚ب‚èپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚»‚جŒمپAڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپj‚ئ‚ب‚éپBپ@ڈٍŒنŒ´
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—ك‚جژ{چsپA“،Œ´‹پi‚س‚¶‚ي‚ç‚«‚ه‚¤پA‚U‚X‚Sپ[
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚V‚P‚O”Nپj‘J“sپA‚»‚ج‘¼‘½‚‚جگچô ‚ًچs‚¢پAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—¥—كچ‘‰ئ‚جٹî”صچى‚è‚ة“w—ح‚µپA‚ـ‚½پA”’–P
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚ح‚‚ظ‚¤پj•¶‰»‚ًŒ»ڈo‚³‚¹‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پںپ@ڈ—گ«“Vچcپ@پi‚Wگl‚P‚O‘مپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ڈ—گ«“VچcپjپBپ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث گ„Œأپi‚·‚¢‚±پj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث چc‹ةپiگؤ–¾پjپi‚±‚¤‚¬‚ه‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚³‚¢‚ك‚¢پjپj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ژ“پi‚¶‚ئ‚¤پj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث Œ³–¾پi‚°‚ٌ‚ك‚¢پj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث Œ³گ³پi‚°‚ٌ‚µ‚ه‚¤پj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث چFŒھپiڈج“؟پjپi‚±‚¤‚¯‚ٌ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚ئ‚پjپj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث –¾گ³پi‚ك‚¢‚µ‚ه‚¤پj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث Œمچ÷’¬پi‚²‚³‚‚ç‚ـ‚؟پj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@“ْ–{‚جŒأ‘م‚©‚猻‘م‚ـ‚إ‚جٹش‚ةپAڈ—گ«
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“Vچc‚حپAپ@”ٍ’¹”’–Pپi‚ ‚·‚©‚ح‚‚ظ‚¤پjژ‘مپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ق—اپi‚ب‚çپjژ‘م‚ة“Vچc‚ة‘¦ˆتپiڈA ”Cپj‚µ‚½پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ„Œأپi‚·‚¢‚±پjپAچc‹ةپiگؤ–¾پjپi‚±‚¤‚¬‚ه‚پi‚³‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ك‚¢پjپjپAژ“پi‚¶‚ئ‚¤پjپAŒ³–¾پi‚°‚ٌ‚ك‚¢پjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ³گ³پi‚°‚ٌ‚µ‚ه‚¤پjپAچFŒھپiڈج“؟پjپi‚±‚¤‚¯‚ٌ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚ئ‚پjپj‚ج‚Uگl‚W‘م‚ج“Vچcپ@‚âپ@چ]Œث
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¦‚اپjژ‘م‚ة“Vچc‚ة‘¦ˆتپiڈA ”Cپj‚µ‚½پA–¾
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ³پi‚ك‚¢‚µ‚ه‚¤پjپAŒمچ÷’¬پi‚²‚³‚‚ç‚ـ‚؟پj‚ج‚Q
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گl‚Q‘م‚ج“Vچc‚ھ‚¢‚ؤپAچ‡Œv‚µ‚ؤ‚Wگl‚P‚O‘م‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپj‚ھ‚¢‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚ئپ@ ژٹ“؟پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ئ‚پj پBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚r‚g‚h‚s‚n‚j‚tپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ ‚P‚R‚W‚S”Nپ[‚P‚R‚W‚V”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ى–k’©‹£چ‡“ٌڈd”Nچ†پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï‚ج“ٌڈd”Nچ†‘¶—§پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\ پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@“ى–k’©‹£چ‡“ٌڈd”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@–k’©پ@پiژ–¾‰@“پj•û‚ج—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚P‚R‚W‚S”NپEژٹ“؟Œ³”NپE‚QŒژ‚Q‚V“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚R‚W‚V”NپEژٹ“؟ ‚S”NپE‚WŒژ‚Q‚R“ْپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ژ؛’¬ژ‘م‘Oٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@پi’چˆسپjپ@“¯ژٹْ‚ةپA“ى’©پ@پi‘هٹoژ›“پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œم‘çŒي“VچcŒn“پj•û‚ج—ï”Nچ†‚جپAپ@چOکa
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚±‚¤‚يپjŒ³”Nپ`‚S”Nپi‚P‚R‚W‚Pپ`‚P‚R‚W‚S”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ئپAپ@Œ³’†پi‚°‚ٌ‚؟‚م‚¤پjŒ³”Nپ`‚X”Nپi‚P‚R‚W
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚Sپ`‚P‚R‚X‚Q”Nپjپ@‚à‘¶—§‚·‚éپBپ@
پ@
پ@
پ›پ@‚µ‚بپ@پ@گM”Z چ‘پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ب‚ج ‚ج‚‚ةپjپB پs‹Œ’nˆو–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= گMڈBپi‚µ‚ٌ‚µ‚م‚¤پjپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپà Œ»پE’·–ىŒ§‚ج‘ٹ“–—جˆوپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi—¥—كگ§’èŒمپEŒأ‘مپE’†گ¢پE‹كگ¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ْ–{پE‹Œ’nˆو–¼‚ج‹Œچ‘–¼پi—كگ§
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ چ‘پj‚جگ³ژ®–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚r‚g‚h‚m‚`‚m‚nپ@‚o‚q‚n‚u‚h‚m‚b‚dپD
پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث گMڈBپi‚µ‚ٌ‚µ‚م‚¤پjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ’·–ىŒ§پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹Œچ‘پi= —كگ§چ‘پjپjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹Œ’nˆو–¼پA’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث “ْ–{‚ج’n–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@گM”Z چ‘پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پƒ“ŒژR“¹پ@پiچLˆو’n•ûپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پƒŒـ‹Eژµ“¹پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@گM”Z چ‘پ@پi‚µ‚ب‚ج ‚ج‚‚ةپj‚حپA—¥—ك
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ§’èŒمپEŒأ‘مپE’†گ¢پE‹كگ¢“ْ–{پE‹Œ’nˆو
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–¼‚جپA‹Œچ‘–¼پi—كگ§چ‘پj‚جگ³ژ®–¼‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@گMڈBپ@پi‚µ‚ٌ‚µ‚م‚¤پj‚حپA پ@—¥—كگ§’è
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒمپEŒأ‘مپE’†گ¢پE‹كگ¢“ْ–{پE‹Œ’nˆو–¼‚جپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹Œچ‘–¼پi—كگ§چ‘پjگ³ژ®–¼‚جپAگM”Z چ‘پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ب‚ج‚ج‚‚ةپjپ@‚ج•تڈج‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@گM”Z چ‘پi= گMڈBپj‚حپAپ@Œ»پE’†•”’n
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•û‚جپAŒ»چف‚ج’·–ىŒ§پ@‚ة‘ٹ“–‚·‚é ’nˆو
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@گM”Z چ‘پi= گMڈBپj‚حپAپ@Œـ‹Eژµ“¹
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚²‚«‚µ‚؟‚ا‚¤پj‚ج“ŒژR“¹پi‚ئ‚¤‚³‚ٌ‚ا‚¤پj پE
پ@چLˆو’n•û‚ة‘®‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@
پZپ@‚¶‚تپ@پ@’nژهپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ت‚µپjپBپ@پs‹ك‘م“ْ–{پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= ’nژهٹK‹‰پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‹ك‘م“ْ–{پi–¾ژ،پA‘هگ³پAگي‘OپE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ؛کaژ‘مپj‚ج“ءŒ ٹK‹‰پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ڈ¬چىگl‚ًچïژوپi‚³‚‚µ‚مپj‚µ‚ؤپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”_’nŒo‰c‚ًچs‚¤پB
پ@
پZپ@‚µ‚جپ@ ”E‚ر‚جژزپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ج‚ر‚ج‚à‚جپjپBپ@پs”EژزپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= ”EژزپA‚ç‚ء‚دپA‚·‚ء‚دپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘گپi‚‚³پjپAŒ¬‰ژپi‚ج‚«‚´‚éپjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ”EژزپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@ پ،پ@”E‚ر‚جژزپ@پi‚µ‚ج‚ر‚ج‚à‚جپj‚ئ‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”Eژز‚إ‚ ‚èپA‘¼‚ةپA”Eژز‚ج•تڈج‚ة‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@‚·‚ء‚دپA‚ç‚ء‚دپA‘گپi‚‚³پj پAŒ¬‰ژپi‚ج‚«
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚´‚éپj‚ب‚ا‚ھ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@”Eژز‚حپAپ@ڈî•ٌ‚جژûڈW‚ًژه‚ب”C–±
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ئ‚µپAژ‚ة‚حپAŒظ‚¢ژه‚جژwژ¦‚إپA“G’n
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚جٹh—گپi‚©‚‚ç‚ٌپj‚âˆأژE‚ب‚ا‚àچs‚ء
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚½پB
پ@
پZپ@‚µ‚خپ@پ@ژ©”ڑ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚خ‚پjپBپ@پs ژ©ٹQپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ”ڑژ€ژ©ٹQپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ”ڑژ€ژ©ٹQپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ژ©ٹQپi‚¶‚ھ‚¢پjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ژ©گnپi‚¶‚¶‚ٌپjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژ©”ڑپ@پi‚¶‚خ‚پj‚ئ‚حپAپ@“ْ–{‚ج—ًژj‚ة‚¨
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¢‚ؤپAپ@‰خ–ٍ—ق‚ً—p‚¢‚ؤژ©ٹQپi‚¶‚ھ‚¢پAژ©ژEپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚·‚邱‚ئ‚إ‚ ‚éپBپ@‘½‚‚ج‘¸‚¢–½پi‚¢‚ج‚؟پj‚ھ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ¸‚ي‚ꂽپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژ©ٹQپ@پi‚¶‚ھ‚¢پA= ژ©ژEپj‚ة‚حپA “ْ–{‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—ًژj‚ة‚¨‚¢‚ؤپAژ©گnپi‚¶‚¶‚ٌپjپAژ©”ڑپi‚¶‚خ‚پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ب‚ا‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚خپ@پ@ژz”gژپپB
پi ‚µ‚خ ‚µپjپBپ@پs•گ‰ئپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚P‚Sگ¢‹Iپ`‚P‚Uگ¢‹IپjپB
پ@پ@پ@ ‚s‚g‚dپ@‚r‚g‚h‚a‚`پ@‚b‚k‚`‚mپD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@•گ‰ئ‚جژz”gژپپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ژz”gژپ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘«—کژپ‚جژx‘°‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ژz”gٹا—ج‰ئ‚ئ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ؛’¬–‹•{‚جٹا—ج گE‚ةڈA”C
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚µ‚½پAژ؛’¬ژ‘م‚جژz”gژپ–{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰ئپiڈ@‰ئپj‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@•گ‰ئ‚جژz”gژپپ@(‚µ‚خ‚µپA‚P‚Sگ¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹Iپ`‚P‚Uگ¢‹Iپj‚حپA‘«—کژپ‚جژx‘°‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژz”gٹا—ج‰ئپ@پi‚µ‚خ‚©‚ٌ‚ê‚¢‚¯پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ئ‚حپAپ@ژ؛’¬–‹•{پi= ‘«—ک–‹•{پj‚جٹا
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—جگE‚ةڈA”C ‚µ‚½پAژ؛’¬ژ‘م‚جژz”g
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژپ–{‰ئپiڈ@‰ئپj‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚خپ@پ@ژؤ“c ڈں‰ئپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚خ‚½ ‚©‚آ‚¢‚¦پjپBپ@پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@گD“cگM’·‚جڈdگbپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@گD“c‰ئ•M“ھ‰ئکVپB
پ@
پZپ@‚µ‚رپ@پ@ƒVƒrƒٹƒAƒ“پEƒRƒ“ƒgƒچپ[
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒ‹پBپi= •¶–¯“گ§پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiگ•{‚جŒR“گ§پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پs‹كŒ»‘م“ْ–{پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث •¶–¯“گ§پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@ƒVƒrƒٹƒAƒ“پEƒRƒ“ƒgƒچپ[ƒ‹پ@پi= •¶
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ –¯“گ§پj‚ئ‚حپAپ@گ•{‚ج•¶–¯ٹ¯—»
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ھپA•گٹ¯‚ً“گ§‚·‚邱‚ئ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•¶–¯‚ئ‚حپAگE‹ئŒRگl‚جŒo—ً‚ً
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ‚½‚ب‚¢گl‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@گي‘O‚إ‚حپAپ@“àٹt‚إپuŒR–±‘هگbŒ»
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–ً•گٹ¯ڈA”Cگ§پv‚ھگ§’肳‚ꂽŒم‚ةپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒVƒrƒٹƒAƒ“پEƒRƒ“ƒgƒچپ[ƒ‹پi= •¶–¯“
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ گ§پj‚ھ–³—ح‚ئ‚ب‚èپA‹Œ“ْ–{ŒR‚ھ–\‘–
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚µپAپ@“ْ–{‚حپAŒRچ‘ژه‹`چ‘‰ئپiپ|‚P‚X
‚S‚T”Nپj‚ئ‚ب‚éپB پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@
پZپ@‚¶‚شپ@پ@ژ،•”ڈ•مپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚ش‚µ‚ه‚¤‚نپjپBپ@پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= گخ“cژOگ¬پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گخ“cژOگ¬پjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@ژOگ¬‚ھپA‚P‚T‚W‚Tپ`‚P‚U‚O‚O”NپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ژ،•”ڈ•م‚جٹ¯ˆت‚ةڈ–”C‚³‚ê‚ؤ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¢‚½‚½‚كپB
پ@
پZپ@‚¶‚ظپ@پ@ژ–@پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚ظ‚¤پjپBپ@پsژچڈپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= ژچڈ–@پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‘O‹ك‘م“ْ–{‚جژچڈپEژ–@پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@ژ–@پiژچڈ–@پj‚حپAژٹش‹و•ھŒ`ژ®پAژٹشٹش
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹu–@پi’èژ–@پE•s’èژ–@پjپAژچڈ•\ژ¦•ûژ®‚ة‚و
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚èپA•ھ—ق‚³‚ê‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@“ْ–{‚إژg‚ي‚ꂽژچڈپBپ@“ْ–{‚إ‚حپA‚Q‚آ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژٹش‹و•ھŒ`ژ®پA‚Q‚آ‚جژٹشٹشٹu–@پi’èژ–@پE•s
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’èژ–@پjپA‚R‚آ‚جژچڈ•\ژ¦•ûژ®‚ھژg—p‚³‚ꂽپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@‹كŒ»‘م“ْ–{ژg—p‚ج‚P“ْ‚Q‚Sژٹشگ§پE’èژ–@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پEگ¼—mژ®•\ژ¦ژچڈپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{ژg—p‚ج‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§پE’èژ–@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ^•s’èژ–@پEڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈپi= ڈ\“ٌژxŒؤ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈجژچڈپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{ژg—p‚ج‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§پE•s’èژ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–@پEژڈàگ”•\ژ¦ژچڈپi= گ”ŒؤڈجژچڈپjپB
پ@
پ@
پZ ‚µ‚ـپ@پ@“‡’أ “ؤژqپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ـ‚أ ‚ ‚آ‚±پjپBپ@ پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= “ؤ•Pپi‚ ‚آ‚ذ‚كپjپA‹ك‰q Œhژqپi‚±
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‚¦‚·‚ف‚±پjپA“Vàِ‰@پi‚ؤ‚ٌ‚µ‚ه‚¤‚¢‚ٌپjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@چ]Œث–‹•{پE‘و‚P‚R‘مڈ«ŒRپE“؟
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گى‰ئ’è‚جگ³ژ؛•vگlپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@–‹––‚جژF–€”ثڈoگg‚ج•PپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“‡’أ‰ئ•ھ‰ئڈoگgپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ژF–€”ثژهپE“‡’أ گؤ•j‚ج—{ڈ—پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ؤ•PپjپB
پ@
پZ ‚µ‚ـپ@پ@“‡’أ ‰ئ‹vپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ـ‚أ ‚¢‚¦‚ذ‚³پjپBپ@پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‚P‚U‚O‚X”N‚ةپA—®‹…‰¤چ‘‚ًگھ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•‚·‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@چ]Œثژ‘مڈ‰ٹْ‚جژF–€”ثپE”ث
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژهپA“‡’أژپ“–ژهپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‚P‚U‚O‚X”N‚©‚ç‚P‚W‚V‚P”N‚ـ‚إپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—®‹…‰¤چ‘‚حپAژF–€”ث‚جژx”z‰؛‚ة
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ü‚èپA”¼“ئ—§چ‘‚ئ‚ب‚éپB
پ@
پZ ‚µ‚ـپ@پ@“‡’أ گؤ•jپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ـ‚أ ‚ب‚è‚ ‚«‚çپjپB پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚W‚O‚Xپ`‚P‚W‚T‚W”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ژF–€”ثپE‘و‚P‚P‘مژF–€”ثژهپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@–‹––‚جژF–€”ث”ثژهپA“‡’أژپ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“–ژهپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@گ¼‹½—²گ·‚ًˆّ‚«—§‚ؤپA‘¤‹ك
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ة‚µ‚½ژF–€”ثژهپB
پ@
پZ ‚µ‚ـپ@پ@“‡’أ گؤ‹»پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ـ‚أ ‚ب‚肨‚«پjپB پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚V‚X‚Pپ`‚P‚W‚T‚X”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ژF–€”ثپE‘و‚P‚O‘مژF–€”ثژهپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@–‹––‚جژF–€”ث”ثژهپA“‡’أژپ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“–ژهپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@“‡’أگؤ•jپE“‡’أ‹vŒُ‚جژہ•ƒپB
پ@
پZ ‚µ‚ـپ@پ@“‡’أ ‹vŒُپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ـ‚أ ‚ذ‚³‚ف‚آپjپB پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= “‡’أ ’‰‹³پi‚½‚¾‚ن‚«پjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚W‚P‚Vپ`‚P‚W‚W‚V”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ژF–€”ثپE‘و‚P‚Q‘مژF–€”ثژهپE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “‡’أ –خ‹vپi‚à‚؟‚ذ‚³پA’‰‹`پi‚½‚¾‚و
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚µپjپj‚ج•ƒپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@–‹––پE–¾ژ،ڈ‰ٹْ‚جژF–€”ث‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ژہŒ ژزپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ژF–€”ثپE”ثژه‚ج•ƒپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ژF–€”ثژهپE“‡’أ–خ‹vپi’‰‹`پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚ة‘م‚ي‚ء‚ؤپA–‹––‚ةپAژF–€”ث‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ژہŒ ‚ًˆ¬‚éپB
پ@
پZ ‚µ‚ـپ@پ@“‡’أ –خ‹vپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ـ‚أ ‚à‚؟‚ذ‚³پjپB پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= “‡’أ ’‰‹`پi‚½‚¾‚و‚µپjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ژF–€”ثپE‘و‚P‚Q‘مژF–€”ثژهپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@–‹––پE–¾ژ،ڈ‰ٹْ‚جژF–€”ث
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”ثژهپA“‡’أژپ“–ژهپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@“‡’أ ‹vŒُپi‚ذ‚³‚ف‚آپA’‰‹³
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚½‚¾‚ن‚«پjپj‚جژqپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@•ƒپE“‡’أ ‹vŒُ‚ةژF–€”ث‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژہŒ ‚ًˆ¬‚ç‚ê‚éپB
پ@
پZ ‚µ‚ـپ@پ@“‡’أ ‹`‹vپE‹`چOŒZ’ي
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ـ‚أ ‚و‚µ‚ذ‚³پE‚و‚µ‚ذ‚ë ‚«‚ه‚¤‚¾‚¢پjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@“‡’أ ‹`‹vپE‹`چOŒZ’ي‚حپA“‡’أژپ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘ه–¼‚ئ•گڈ«‚ئ‚ب‚èپAپ@گيچ‘پEˆہ“y“چژRژ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘م‚ةٹˆ–ô‚µ‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “‡’أ ‹`‹vپA“‡’أ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‹`چOپjپB
پ@
پZ ‚µ‚ـپ@پ@“‡’أ ‹`‹vپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ـ‚أ ‚و‚µ‚ذ‚³پjپBپ@پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚T‚R‚Rپ`‚P‚U‚P‚P”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‹مڈB‚ج‚ظ‚ع‘S“y‚ًگ§ˆ³ŒمپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈG‹g‚ج‹مڈBگھ”°‚إ‚P‚T‚W‚V”N‚ة
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ~•ڑپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@گيچ‘پEˆہ“y“چژRژ‘م‚ج‹مڈB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج“‡’أ ژپ“–ژه‚إپA•گڈ«پA‘ه–¼پB
پ@
پZ ‚µ‚ـپ@پ@“‡’أ ‹`چOپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ـ‚أ ‚و‚µ‚ذ‚ëپjپBپ@پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚T‚R‚Tپ`‚P‚U‚P‚X”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@گخ“c•û‚جگ¼ŒR‚ة–،•û‚µپAٹض
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒ–Œ´‚جگي‚¢‚إ‚ح“ŒŒR‚ج“Gگw‚ً“ث
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”j‚µ‚ؤ‹Aچ‘پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@گيچ‘پEˆہ“y“چژRژ‘م‚ج‹مڈB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج“‡’أ ژپ‚ج•گڈ«پA‘ه–¼پB
پ@
پZپ@‚µ‚ـپ@پ@“‡چھŒ§پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ـ‚ث‚¯‚ٌپjپBپ@پsŒ»’nˆو–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپà ‰Bٹٍ چ‘پAڈo‰_ چ‘پAگخŒ© چ‘پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiŒ»“s“¹•{Œ§پjپB
پ@پ@ ‚r‚g‚h‚l‚`‚m‚dپ@‚o‚q‚d‚e‚d‚b‚s‚t‚q‚dپD
پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‰Bٹٍ چ‘پAڈo‰_ چ‘پA
گخŒ© چ‘پjپB
پiپث “s“¹•{Œ§پjپB
پ@پ@پ@پ@ پ@پiپث ‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹Œ’nˆو–¼پA’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث “ْ–{‚ج’n–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@“‡چھŒ§پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپà ‘O‹ك‘م‚جپA‰Bٹٍ چ‘پ@پi‚¨‚«
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚ج‚‚ةپA‰BڈBپi‚¨‚ٌ‚µ‚م‚¤پA‚¢‚ٌ‚µ‚م‚¤پjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“‡چھŒ§‰Bٹٍ“‡پjپ@‚ئپAپ@ڈo‰_ چ‘پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¢‚¸‚à ‚ج‚‚ةپA‰_ڈBپi ‚¤‚ٌ‚µ‚م‚¤پjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“‡چھŒ§ –{“y“Œ•”پj پ@‚ئپAپ@گخŒ©
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ‘پ@پi‚¢‚ي‚ف ‚ج‚‚ةپAگخڈBپi ‚¹‚«‚µ‚م
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¤پjپA“‡چھŒ§ –{“yگ¼•”پjپ@‚ج‘ٹ“–
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’nˆوپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚ـپ@پ@ژu–€ چ‘پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ـ ‚ج‚‚ةپjپB پs‹Œ’nˆو–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= ژuڈB پi‚µ‚µ‚م‚¤پjپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپà Œ»پEژOڈdŒ§’†‰›“Œ•”
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‘ٹ“–—جˆوپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‘O‹ك‘م‹Œ’nˆو–¼‚ج‹Œچ‘–¼
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi—كگ§چ‘پj‚ج گ³ژ®–¼پjپBپ@
پ@پ@ پ@ ‚r‚g‚h‚l‚`پ@‚o‚q‚n‚u‚h‚m‚b‚dپD
پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ژuڈB پi‚µ‚µ‚م‚¤پjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ژOڈdŒ§پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹Œچ‘پi= —كگ§چ‘پjپjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹Œ’nˆو–¼پA’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث “ْ–{‚ج’n–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژu–€ چ‘پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پƒ“ŒٹC“¹پ@پiچLˆو’n•ûپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پƒ“ْ–{–{“yپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژu–€ چ‘پ@پi‚µ‚ـ ‚ج‚‚ةپj‚حپAپ@‹Œچ‘–¼
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi—كگ§چ‘پj‚جگ³ژ®–¼‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژuڈBپ@پi‚µ‚µ‚م‚¤پj‚حپAپ@‹Œچ‘–¼پi—كگ§
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ‘پjگ³ژ®–¼‚جپAژu–€ چ‘پ@پi‚µ‚ـ ‚ج‚‚ةپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج•تڈج‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژu–€ چ‘پi= ژuڈBپj‚حپAپ@Œ»پE‹ك‹E’n
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•û‚جژOڈdŒ§’†‰›“Œ•”پ@‚ة‘ٹ“–‚·‚é—جˆو
‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژu–€ چ‘پi= ژuڈBپj‚حپAپ@Œـ‹Eژµ“¹ پi‚²
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚«‚µ‚؟‚ا‚¤پj‚ج“ŒٹC“¹پi‚ئ‚¤‚©‚¢‚ا‚¤پj‚جچL
پ@ˆو’n•û‚ة‘®‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@
پZپ@‚µ‚فپ@پ@گ´گ… ڈ@ژ،پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ف‚¸ ‚ق‚ث‚ح‚éپjپB پ@پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiگيچ‘•گڈ«پjپB
پ@پ@ پi‚P‚T‚R‚Vپ`‚P‚T‚W‚Q”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ’†چ‘‘ه•ش‚µپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث گط• پi‚¹‚ء‚ص‚پjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ژ©گnپi‚¶‚¶‚ٌپjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ژ©ٹQپi‚¶‚ھ‚¢پjپjپB
پ›پ@”ُ’†پEچ‚ڈ¼ڈéپEڈéژهپB
پ›پ@چ‚ڈ¼ڈéگ…چU‚كژپAگط• ‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@ژ؛’¬ژ‘مŒمٹْپiگيچ‘ژ‘مپjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆہ“y“چژRژ‘م‚جپA”ُ’†‚ج•گڈ«پB
پ@
پZپ@‚¶‚فپ@پ@ژ–¾‰@“پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚ف‚ه‚¤‚¢‚ٌ‚ئ‚¤پjپBپ@پ@پsچc“پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= Œمگ[‘گ“Vچc‚جچc“پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚P‚Q‚T‚X”Nپ|‚P‚R‚X‚Q”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚i‚h‚l‚x‚n‚h‚m‚s‚nپ@‚k‚h‚m‚d‚`‚f‚dپD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث چc“‚ج•ھ—§پA—¼““R—§پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‘هٹoژ›“پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@Œمچµ‰م“Vچc‚جچcژqپEپuŒمگ[‘گ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“Vچcپv‚©‚çŒمڈ¬ڈ¼“Vچc‚ـ‚إ‚جچc“پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@‚P‚Q‚T‚X”Nپ|‚P‚R‚X‚Q”NپA‘هٹo
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ›“‚ئژ–¾‰@“‚جچc“‚ج•ھ—§پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@ پ،پ@ژ–¾‰@“پ@پi‚¶‚ف‚ه‚¤‚¢‚ٌ‚ئ‚¤پjپ@‚ئ‚حپA‹v
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گmپi‚ذ‚³‚ذ‚ئپjگe‰¤ ‚إ‚ ‚éپAŒمگ[‘گپi‚²‚س‚©‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚³پj“Vچcپ@پi“VچcچفˆتپF‚P‚Q‚S‚Uپ| ‚P‚Q‚T‚X”Nپj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چc“‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@ پœپ@ژ–¾‰@“‚حپAپ@Œمچµ‰مپi‚²‚³‚ھپj “Vچcپi“V
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چcچفˆتپF‚P‚Q‚S‚Qپ|‚S‚U”Nپj‚جچcژqپEپuŒمگ[‘گ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚²‚س‚©‚‚³پj“Vچcپv‚©‚çŒمڈ¬ڈ¼پi‚²‚±‚ـ‚آپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“Vچc‚ـ‚إ‚جچc“پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@ پœپ@’©’ى‚إ‚حپAپ@‚P‚Q‚T‚X”Nپi ‹ˆّ“Vچcڈ÷ˆتپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@ ‚©‚ç‚P‚R‚X‚Q”Nپi“ى–k’©‚جچ‡‘جپj‚ـ‚إپAژ–¾
پ@پ@پ@پ@‰@“پ@پi‚¶‚ف‚ه‚¤‚¢‚ٌ‚ئ‚¤پjپ@‚ئپAپ@‘هٹoژ›“
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¾‚¢‚©‚‚¶‚ئ‚¤پjپ@‚جچc“‚ج•ھ—§‚ھ‘±‚¢‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@چc“•ھ—§‚ج‹N‚±‚èپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚Q‚S‚U”N‚ةپAپ@Œمچµ‰م“Vچcپ@پi“Vچcچف
ˆتپF‚P‚Q‚S‚Qپ|‚S‚U”NپAگ¶–v”NپF‚P‚Q‚Q‚Oپ|‚V‚Q
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”Nپj‚ھپAپ@چcژqپiژں’jپj‚ج‹vگmپi‚ذ‚³‚ذ‚ئپjگe
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰¤‚ة“Vچc‚جˆت‚ًڈ÷‚èپAپ@‹vگmپi‚ذ‚³‚ذ‚ئپjگe
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰¤‚حپAŒمگ[‘گپi‚²‚س‚©‚‚³پj“Vچcپj پ@پi“Vچc
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چفˆتپF‚P‚Q‚S‚Uپ|‚T‚X”Nپjپ@‚ئ‚ب‚èپAپ@Œمچµ‰م“V
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چc‚حپAŒمچµ‰مڈمچc‚ئ‚ب‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚µ‚©‚µپA‚P‚Q‚T‚X”N‚ةپAپ@Œمچµ‰مڈمچc‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چcژqپiژں’jپj‚جپAŒمگ[‘گ“Vچc‚ً‹ˆّ‚ة‘قˆت
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚³‚¹پAپ@‘¼‚جچcژqپiژO’jپj‚جچPگmپi‚آ‚ث‚ذ‚ئپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گe‰¤‚ً“Vچc‚ة‚µپA‹TژRپi‚©‚ك‚â‚ـپj “Vچcپi“V
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چcچفˆتپF‚P‚Q‚T‚Xپ|‚V‚S”Nپjپ@‚ھ’aگ¶‚µ‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚»‚جŒمپA‹TژRپi‚©‚ك‚â‚ـپj “Vچc‚حپAژں‚ج“V
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چc‚ًژ©•ھ‚جژqپ@پiŒم‰F‘½پi‚²‚¤‚¾پj“Vچcپi“V
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چcچفˆتپF‚P‚Q‚V‚Sپ|‚W‚W”Nپjپ@‚ئ‚µ‚½‚½‚كپ@پi—§
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘¾ژq‚ئ‚µ‚½‚½‚كپjپAپ@‘قˆت‚µ‚½Œمگ[‘گ“Vچc
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚حپAژ©•ھ‚جژq‚جچcˆتŒpڈ³‚ھ‚إ‚«‚¸پA”ٌڈي
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ة•s–‚ً‚à‚؟پAٹ™‘q–‹•{‚ة’‡چظ‚ًˆث—ٹ‚µپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚Q‚W‚W”N‚ةپAŒمگ[‘گ“Vچc‚جژqپi•ڑŒ© پi‚س‚µ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚فپj“Vچcپj‚ھ“Vچc‚ة‘¦ˆت‚·‚邱‚ئ‚ھژہŒ»‚µ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚½پBپ@‚±‚¤‚µ‚ؤپA‚»‚جŒم‚حپAٹ™‘qژ‘م‚جٹشپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹ™‘q–‹•{‚ج‰î“üپE’‡چظ‚ة‚و‚éپA—¼““R—§پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚è‚ه‚¤‚ئ‚¤‚ؤ‚آ‚è‚آپA—¼“‚جچcژq‚ھŒًŒف‚ة
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“Vچc‚ة‚ب‚é•ûژ®پjپ@‚ئ‚ب‚ء‚½پB
پ@
پZپ@‚µ‚كپ@پ@ژپ–¼پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ك‚¢پjپBپ@پsژپ–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ‘O‹ك‘م“ْ–{‚جگl–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‘O‹ك‘م“ْ–{‚جژپ–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پ@ پiپث Œآگl–¼پAوپپi‚¢‚ف‚بپjپA’تڈجپj پB
پ@پ@پ@پ@ پ@ پiپث ژپ‘°–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پ@ پ@پiپث ژپ–¼پiژپ‘°–¼پ{Œآگl–¼پjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ پiپث ‘O‹ك‘م“ْ–{‚جگl–¼پj پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جگl•¨ژپ–¼‚ة‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژپ‘°–¼پi‰ئ–¼پj‚ئŒآگl–¼‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚àپ@پ@‰؛‘چ چ‘پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚à‚¤‚³پ@‚ج‚‚ةپjپB پs‹Œ’nˆو–¼پtپB
پi= ‘چڈBپi‚»‚¤‚µ‚م‚¤پj‚ج‚Pچ‘پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپà Œ»پEگç—tŒ§–k•”‚ج‘ٹ“–’nˆوپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi—¥—كگ§’èŒمپEŒأ‘مپE’†گ¢پE‹كگ¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ْ–{پE‹Œ’nˆو–¼‚ج‹Œچ‘پi—كگ§
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ چ‘پj‚جگ³ژ®–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‘چڈBپi‚»‚¤‚µ‚م‚¤پjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث گç—tŒ§پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹Œچ‘پi= —كگ§چ‘پjپjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹Œ’nˆو–¼پA’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث “ْ–{‚ج’n–¼پjپB پ@پ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‰؛‘چ چ‘پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پƒ“ŒٹC“¹پ@پiچLˆو’n•ûپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‰؛‘چ چ‘پ@پi‚µ‚à‚¤‚³ ‚ج‚‚ةپj‚حپA—¥—كگ§
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’èŒمپEŒأ‘مپE’†گ¢پE‹كگ¢“ْ–{پE‹Œ’nˆو–¼‚جپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹Œچ‘پi—كگ§چ‘پj‚جگ³ژ®–¼‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‘چڈBپ@پi‚»‚¤‚µ‚م‚¤پj‚حپA پ@—¥—كگ§’èŒمپE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œأ‘مپE’†گ¢پE‹كگ¢“ْ–{پE‹Œ’nˆو–¼‚جپA‹Œچ‘
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–¼پi—كگ§چ‘پjگ³ژ®–¼‚جپA‰؛‘چچ‘پ@پi‚µ‚à‚¤‚³
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‚‚ةپAگç—tŒ§–k•”پj‚ئڈم‘چ چ‘پ@پi‚©‚¸‚³
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‚‚ةپAگç—tŒ§’†•”پjپ@‚ج‚¢‚¸‚ê‚©پA‚ـ‚½‚ح
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—¼چ‘‚ًچ‡‚ي‚¹‚ؤŒؤ‚ش•تڈج‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‰؛‘چ چ‘‚حپAپ@Œ»پE ٹض“Œ’n•û‚جپAŒ»چف‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گç—tŒ§–k•”‚ة‘ٹ“–‚·‚é’nˆو‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‰؛‘چ چ‘‚حپAپ@Œـ‹Eژµ“¹ پi‚²‚«‚µ‚؟‚ا‚¤پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج“ŒٹC“¹پi‚ئ‚¤‚©‚¢‚ا‚¤پjپE‹ŒچLˆو’n•û‚ة‘®
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚·‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚àپ@پ@‰؛–ى چ‘پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚à‚آ‚¯ ‚ج‚‚ةپjپB پs‹Œ’nˆو–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= –ىڈBپi‚₵‚م‚¤پjپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپà Œ»پE“ب–طŒ§‚ج‘ٹ“–’nˆوپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi—¥—كگ§’èŒمپEŒأ‘مپE’†گ¢پE‹كگ¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ْ–{پE‹Œ’nˆو–¼‚ج‹Œچ‘پi—كگ§
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ چ‘پj‚جگ³ژ®–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث –ىڈBپi‚₵‚م‚¤پjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث “ب–طŒ§پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹Œچ‘پi= —كگ§چ‘پjپjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹Œ’nˆو–¼پA’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث “ْ–{‚ج’n–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‰؛–ى چ‘پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پƒ“ŒژR“¹پ@پiچLˆو’n•ûپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‰؛–ى چ‘پ@پi‚µ‚à‚آ‚¯ ‚ج‚‚ةپj‚حپA—¥—ك
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ§’èŒمپEŒأ‘مپE’†گ¢پE‹كگ¢“ْ–{پE‹Œ’nˆو–¼
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جپA‹Œچ‘پi—كگ§چ‘پj‚جگ³ژ®–¼‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@–ىڈBپ@پi‚₵‚م‚¤پj‚حپA پ@—¥—كگ§’èŒمپE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œأ‘مپE’†گ¢پE‹كگ¢“ْ–{پE‹Œ’nˆو–¼‚جپA‹Œ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ‘پi—كگ§چ‘پjگ³ژ®–¼‚جپA‰؛–ى چ‘پ@پi‚µ‚à‚آ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¯ ‚ج‚‚ةپj‚ج •تڈج‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‰؛–ى چ‘پi= –ىڈBپj‚حپAپ@Œ»پEٹض“Œ’n•û
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جپAŒ»چف‚ج“ب–طŒ§‚ة‘ٹ“–‚·‚é ’nˆو‚إ‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‰؛–ى چ‘پi= –ىڈBپj‚حپAپ@Œـ‹Eژµ“¹‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ŒژR“¹پi‚ئ‚¤‚³‚ٌ‚ا‚¤پj‚جچLˆو’n•û‚ة‘®
پ@‚·‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚àپ@پ@‰؛“¹ گ^”ُپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚à‚آ‚ف‚؟‚ج ‚ـ‚«‚رپjپBپ@پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ‹g”ُ گ^”ُ پi‚«‚ر‚ج ‚ـ‚«‚رپjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ‹g”ُ گ^”ُپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚àپ@پ@‰؛‰®•~پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚à‚₵‚«پjپBپ@پsŒڑ•¨پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ”ثپi‘ه–¼پj‚جچ]Œث‚إ‚جژ„“@پjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@چ]Œثژ‘م‚جپAٹe”ثپi”ثژهپjپi‘ه
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–¼پj‚جپAچ]Œث‚إ‚جژ„“@پA•ت“@پA•ت
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘îپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ”ث“@پjپB
پ،پ@‰؛‰®•~پ@پi‚µ‚à‚₵‚«پjپ@‚ئ‚حپAپ@”ث“@‚ج‚P‚آ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إپAپ@چ]Œثژ‘م‚جپAٹe”ثپi”ثژهپjپi‘ه–¼پj‚جپAچ]
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œث‚إ‚جژ„“@پA•ت“@پA•ت‘îپ@‚إ‚ ‚éپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚جپA‘ه–¼پi”ثپj‚جچ]Œث‚إ‚ج“@‘î
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ ‚é”ث“@‚ة‚حپAپ@Œِ“@‚جڈم‰®•~پAپ@ژ„“@‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’†‰®•~پA‰؛‰®•~پ@‚ھ‚ ‚ء‚½پB
پ@
پZپ@‚µ‚لپ@پ@ƒVƒƒپ[ƒ}ƒ“پEƒٹپ[پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ƒ‰ƒ“ƒOƒhƒ“پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒEƒHپ[ƒiپ[پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ƒEƒHپ[ƒiپ[ƒٹƒXƒgپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@ƒVƒƒپ[ƒ}ƒ“پEƒٹپ[‚حپAپ@گيŒمپAکAچ‡چ‘ŒR“ْ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–{گè—جٹْ‚ةپAپ@“ْ–{‚ج•¶‰»چà‚جچ‘ٹO—¬ژ¸‚ً–h
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¢‚¾پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@ƒVƒƒپ[ƒ}ƒ“پEƒٹپ[‚حپAپ@“ْ–{”üڈp‚جگê–ه‰ئ
‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@گيŒمپAکAچ‡چ‘ŒR“ْ–{گè—جٹْ‚ةپAƒVƒƒپ[ƒ}
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒ“پEƒٹپ[‚حپAپ@‚f‚g‚pپiکAچ‡چ‘ŒR‘چژi—ك•”پj‚ج”ü
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈp‹L”O•¨‰غ‚ج’S“–ٹ¯‚ئ‚ب‚èپAپ@‚f‚g‚p”üڈp‹L”O
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•¨‰غ‚جŒع–â‚جƒ‰ƒ“ƒOƒhƒ“پEƒEƒHپ[ƒiپ[‚ئ‹¤‚ةپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{‚ج•¶‰»چà‚ھ”…ڈ•i‚ئ‚µ‚ؤ—¬ژ¸‚·‚é‚ج‚ة”½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘خ‚µپA“ْ–{‚جڈd—v•¶‰»چà‚جچ‘ٹO—¬ژ¸‚ً–h‚¢‚¾پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@
پZپ@‚µ‚لپ@پ@ƒVƒƒƒJپB
پs•§‹³پtپB پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ƒVƒbƒ_پ[ƒ‹ƒ^پAƒVƒƒƒJپiژك‰قپjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ƒuƒbƒ_پi•§‘ةپjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi•§‹³‚ج‹³‘cپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiگ¶–v”NپFپ@‹IŒ³‘O‚T‚U‚R”Nچ پ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘O‚S‚W‚R”Nچ پjپ@پiڈ”گà‚ ‚èپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚f‚`‚t‚s‚`‚l‚`پ@‚r‚h‚c‚c‚g‚`‚q‚s‚g‚`پB
پiپث ƒVƒbƒ_پ[ƒ‹ƒ^پjپB
پiپث •§‹³پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@•ت–¼پF ƒVƒbƒ_پ[ƒ‹ƒ^پAپ@ƒKƒEƒ^ƒ}پEƒVƒb
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@ƒ_پ[ƒ‹ƒ^پAپ@ƒSپ[ƒ^ƒ}پEƒVƒbƒ_پ[ƒ‹ƒ^پAپ@ƒV
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒƒƒJƒ€ƒjپiژك‰ق–´“ٍپjپAپ@ژك‰ق–´“ٍپi‚µ‚ل‚©
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ق‚ةپjپA ƒVƒƒƒJپiژك‰قپjپAپ@ژك‰قپi‚µ‚ل‚©پjپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژك‘¸ پi‚µ‚ل‚‚»‚ٌپjپAپ@‚¨ژك‰ق—lپi‚¨‚µ‚ل‚©
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚³‚ـپjپA پ@ƒuƒbƒ_پi•§‘ةپjپAپ@•§‘ةپi‚ش‚ء‚¾پjپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•§پi‚ظ‚ئ‚¯پjپAپ@•§—lپi‚ظ‚ئ‚¯‚³‚ـپjپAپ@Œن•§
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚ف‚ظ‚ئ‚¯پjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ƒKƒEƒ^ƒ}پEƒVƒbƒ_پ[ƒ‹ƒ^‚حپA•§‹³‚ج‹³‘cپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚«‚ه‚¤‚»پAٹJ‘cپA‘nژnژزپjپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‹³‘c‚ئ‚حپAپ@‚»‚جڈ@‹³پAڈ@”h‚ً‚ذ‚ç‚¢‚½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ گl‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ڈ@‹³‚ة‚حپAپ@‹³‘cپi‚«‚ه‚¤‚»پjپAپ@‹³‹`پi‹³
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚¦پjپAپ@‹³“Tپi‚«‚ه‚¤‚ؤ‚ٌپjپAپ@ڈ@‹³“àƒOƒ‹پ[
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ƒvپiڈ@‹³“à•ھ”hپjپ@‚ب‚ا‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚لپ@پ@ژلڈBپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚ل‚‚µ‚م‚¤پjپBپ@پs‹Œ’nˆو–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= ژل‹·چ‘پi‚ي‚©‚³‚ج‚‚ةپjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپà Œ»پE•ںˆنŒ§گ¼•”پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‘O‹ك‘م‹Œ’nˆو–¼‚ج‹Œچ‘–¼پi—كگ§
چ‘پj‚ج•تڈجپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ژل‹·چ‘پjپBپ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث •ںˆنŒ§پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹Œچ‘پi= —كگ§چ‘پjپjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹Œ’nˆو–¼پA’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث “ْ–{‚ج’n–¼پjپB
پ،پ@ژلڈBپi= ژل‹· چ‘پj‚حپAپ@–k—¤“¹پi‚ظ‚‚è‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚ا‚¤پjپEچLˆو’n•û‚ة‘®‚µپAپ@Œ»پE’†•”’n•û‚جپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@Œ»پE•ںˆنŒ§ گ¼•”‚ة‘ٹ“–‚·‚é—جˆو‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@
پZپ@‚µ‚مپ@پ@ژéپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚مپjپBپ@پs“ْ–{—¬’ت‰ف•¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@چ]Œثژ‘م‚جپA’èˆتپi’èٹzپj‰ف
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ •¼’Pˆت پi—¼پA•ھپAژéپA•¶پj‚ج‚P‚آپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@ ‚P—¼ڈ¬”» پi‹àپjپà‚S•ھپà‚P‚Uژéپà
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@ ‚S‚O‚O‚O•¶پà Œ»چف‚ج–ٌ‚P‚O–œ‰~پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ پiپث ژé’PˆتپE’èٹzپi’èˆتپjپE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’تڈي‰ف•¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث چ]Œثژ‘م‚ج“ْ–{—¬’ت‰ف•¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث “ْ–{—¬’ت‰ف•¼پjپBپ@
پ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]ˆêˆتپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚¢‚؟‚¢پjپBپ@پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ˆêˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚مپ@پ@ڈCچD’تڈ¤ڈً–ٌپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚م‚¤‚±‚¤‚آ‚¤‚µ‚ه ‚¤‚¶‚ه‚¤‚â‚پjپB پsڈً–ٌپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ‚P‚W‚T‚W”N‚جˆہگ‚ج‚TƒJچ‘ڈً–ٌپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‚±‚جڈً–ٌ‚إپA“ْ–{‚حپAٹ®‘SٹJچ‘
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث “ْ•ؤ ڈCچD’تڈ¤ڈً–ٌپjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ٹJچ‘پAˆنˆة ’¼•JپA–x “c گ³–rپA
پ@پ@ ڈً–ٌ‰üگ³پj پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‚P‚W‚T‚W”N‚ة“ْ–{‚جچ]Œث–‹•{‚ھ•ؤپE—–پEکIپE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‰pپE•§‚ج‰¢•ؤڈ”چ‘‚ئŒ‹‚ٌ‚¾پAڈCچD’تڈ¤ڈً–ٌ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚حپAپ@ˆہگ‚ج‚TƒJچ‘ڈً–ٌ‚إ‚ ‚èپAپ@—جژ–چظ”»Œ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiژ،ٹO–@Œ پjپAٹضگإژ©ژهŒ ‚جŒ‡”@‚ج‹K’è‚ب‚ا
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚ھ‚ ‚éپA•s•½“™ڈً–ٌ‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@
پZپ@‚µ‚مپ@پ@ ژüڈBپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚م‚¤‚µ‚م‚¤پjپBپ@پs‹Œ’nˆو–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= ژü–h چ‘پi‚·‚¨‚¤ ‚ج‚‚ةپjپA–hڈBپi‚ع
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¤‚µ‚م‚¤پjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپà Œ»پEژRŒûŒ§“Œ•”پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi—¥—كگ§’èŒمپEŒأ‘مپE’†گ¢پE‹كگ¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ْ–{پE‹Œ’nˆو–¼‚ج‹Œچ‘–¼پi—كگ§
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ چ‘پj‚ج•تڈجپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ژü–h چ‘پjپBپ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ژRŒûŒ§پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹Œچ‘پi= —كگ§چ‘پjپjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹Œ’nˆو–¼پA’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث “ْ–{‚ج’n–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@–hڈBپi ‚ع‚¤‚µ‚م‚¤پj‚âژüڈBپi‚µ‚م‚¤‚µ‚م‚¤پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚حپA —¥—كگ§’èŒمپEŒأ‘مپE’†گ¢پE‹كگ¢“ْ–{پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹Œ’nˆو–¼‚جپA‹Œچ‘ –¼پi—كگ§چ‘پjگ³ژ®–¼‚جپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژü–h چ‘پ@پi ‚·‚¨‚¤ ‚ج‚‚ةپj‚ج•تڈج‚إ‚ ‚éپB
پœپ@ژüڈBپi= ژü–h چ‘پA–hڈBپj‚حپAپ@ژR—z“¹
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚³‚ٌ‚و‚¤‚ا‚¤پjپEچLˆو’n•û‚ة‘®‚µپAŒ»پE’†چ‘
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@’n•û‚جپAŒ»چف‚ج ژRŒûŒ§“Œ•”‚ة‘ٹ“–‚·‚é’n
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ˆو‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@
پZپ@‚µ‚مپ@پ@ڈIگيپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚م‚¤‚¹‚ٌپjپB پsگي‚¢پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚X‚S‚T”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‘¾•½—mگي‘ˆپE“ْ’†گي‘ˆ‚جڈIگيپB
پ@
پZپ@‚¶‚مپ@ ڈ\“ٌژxپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚¤‚ة‚µپjپBپ@پsڈ\ٹ±ڈ\“ٌژxپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@ژqپA‰NپA“ذپA‰KپA’CپA–¤پAŒكپA–¢پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ\پA“رپAœْپAˆه‚ج‚P‚Qژي—ق‚©‚ç‚ب‚é
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ”ژŒپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@ٹ±ژxپi‚©‚ٌ‚µ پA‚¦‚ئپAڈ\ٹ±ڈ\“ٌژxپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جˆê•”پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ٹ±ژxپi‚©‚ٌ‚µپjپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚¤‚ة‚µ‚ذ‚ه‚¤‚¶‚¶‚±‚پjپBپ@پsژچڈپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ڈ\“ٌژxŒؤڈجژچڈپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ژچڈ–@پA ‘O‹ك‘م“ْ–{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جژچڈپEژ–@پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@“ْ–{‚إژg‚ي‚ꂽژ–@پiژچڈ–@پj‚جپAژچڈ•\
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ¦•ûژ®پiگ¼—mژ®•\ژ¦ژچڈپAڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژڈàگ”•\ژ¦ژچڈپj‚R‚آ‚ج‚P‚آپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚إژg‚ي‚ꂽپA’èژ–@‚ئ•s’èژ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–@‚جپAڈ\“ٌژx‚إ•\ژ¦‚·‚éژچڈپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{ژg—p‚ج‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§‚جپAپ@’è
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ–@پEڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈپ@‚ئپ@•s’èژ–@پEڈ\“ٌ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژx•\ژ¦ژچڈپ@‚ج‚Q‚آ‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈY‚ج|پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚م‚¤‚ج‚¨‚«‚ؤپjپBپ@پs‰ï’أ”ثپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@‰ï’أ”ث‚جگ¶ٹˆ‹K”حپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‰ï’أ”ثپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚نپ@پ@ژ©—R–¯Œ ‰^“®پB
پ@پi‚¶‚ن‚¤‚ف‚ٌ‚¯‚ٌ ‚¤‚ٌ‚ا‚¤پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پsگژ،‰^“®پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚P‚W‚V‚Sپ`‚P‚W‚W‚X”NپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚نپ@پ@ڈ\•¶‘KپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚¤‚à‚ٌ‚¹‚ٌپjپBپ@پs“ْ–{—¬‰ف•¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiچ]Œثژ‘م—¬’ت‰ف•¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@چ]Œثژ‘م‚جپA‚P‚O•¶پi‚à‚ٌپj’Pˆت
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج“؛‰فپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@چ]Œثژ‘م‚جپAچ]Œث–‹•{‚ج’èˆت
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@چ]Œثژ‘م‚ج•¶‘K“؛پE“S‰ف‚ج‚P‚آپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@•َ‰i’ت•َڈ\•¶‘K“؛‰ف‚ج‚فپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@ڈ\•¶‘KپàŒ»چف‚ج–ٌ‚Q‚T‚O‰~ پB
پi‚P‚O•¶‘K‚S‚O‚O –‡پà‚P—¼ڈ¬”»پi‹àپjپà
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚S•ھپà‚P‚Uژéپà‚S‚O‚O‚O•¶ پi‚Sٹر•¶پjپà
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ Œ»چف‚ج–ٌ‚P‚O–œ‰~پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث •¶پi‚à‚ٌپj’PˆتپE’èٹzپi’èˆتپjپE’ت
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@ ڈي‰ف•¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث چ]Œثژ‘م‚ج“ْ–{—¬’ت‰ف•¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث “ْ–{—¬’ت‰ف•¼پjپBپ@
پ@
پZپ@‚¶‚نپ@پ@ژ©—R—ِˆ¤پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@(‚¶‚ن‚¤‚ê‚ٌ‚ ‚¢پjپBپ@پs—ِˆ¤پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جڈم‘wٹK‘w‚إ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ژ©—R—ِˆ¤‚حڈ‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@ژ©—R—ِˆ¤ƒJƒbƒvƒ‹‚ج—لپB
Œ¹‹`Œo‚ئگأپi‚µ‚¸‚©پjپAپ@Œ¹—ٹ’©‚ئ–k
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈًگژqپAپ@–LگbڈG‹g‚ئ‚¨‚ثپi‚ث‚ثپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ ژُ‰i
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚¦‚¢پj پBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚i‚t‚d‚hپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‚P‚P‚W‚Q”Nپ[‚P‚P‚W‚T”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï‚ج“ٌڈd”Nچ†‘¶—§پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@Œ¹•½‹£چ‡“ٌڈd”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‚P‚P‚W‚P”N‚©‚ç‚P‚P‚W‚T”N‚ـ‚إپA“ْ–{‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚حپA Œ¹•½‹£چ‡“ٌڈd”Nچ†‚ھژg—p‚³‚ê‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ ˆةگ¨•½ژپگŒ پiˆہ“؟“Vچc
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ —i—§پj•û‚ج—ï”Nچ†پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‚P‚P‚W‚Q”Nپ[‚P‚P‚W‚T”NپBپ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚P‚P‚W‚Q”NپEژُ‰iŒ³”NپE‚TŒژ‚Q‚V“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚P‚W‚T”NپEژُ‰i ‚S”NپE‚RŒژ‚Q‚S“ْپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆةگ¨•½ژپ–إ–S‚ة‚و‚è—ï”Nچ†•زگ¬’†ژ~پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@•½ˆہژ‘مŒمٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@پi’چˆسپjپ@“¯ژٹْ‚ةپA‰ح“àŒ¹ژپپEŒ¹—ٹ’©
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گŒ پiŒم’¹‰H“Vچc —i—§پj•û‚ج—ï”Nچ†‚جژ،
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ³پi‚¶‚µ‚ه‚¤پjŒ³”Nپ`‚W”Nپi‚P‚P‚V‚Vپ`‚P‚P‚W‚S
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”Nپj پ@‚ئپ@Œ³—ïپi‚°‚ٌ‚è‚ل‚پjŒ³”Nپ`‚Q”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚P‚W‚Sپ`‚P‚P‚W‚T”Nپjپ@‚à‘¶—§‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@پuژُ‰iپv”Nچ†پiژُ‰iŒ³”Nپ`‚S”NپA‚P‚P‚W‚Q
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ`‚P‚P‚W‚T”Nپj‚و‚èŒم‚حپAˆةگ¨•½ژپگŒ پiˆہ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“؟“VچcŒn“پj•û‚حپAپ@—ï”Nچ†•زگ¬‚ً’†ژ~
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚·‚éپBپ@‚P‚P‚W‚T”N‚ج’dƒm‰Y‚جگي‚¢‚إپAˆةگ¨
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•½ژپ‚ھ–إ–S‚µپAˆہ“؟“Vچc‚ھ•ِŒن‚µ‚½‚½‚كپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ˆةگ¨•½ژپگŒ پiˆہ“؟“Vچc—i—§پj•û‚ج—ï
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”Nچ†پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ˆہŒ³پi‚ ‚ٌ‚°‚ٌپjŒ³”Nپ`‚R”N پ@پi‚P‚P‚V‚T
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”Nپ`‚P‚P‚V‚V”Nپjپ@پثپ@ژ،ڈ³پi‚¶‚µ ‚ه‚¤پjŒ³”Nپ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚T”Nپ@پi‚P‚P‚V‚V”Nپ`‚P‚P‚W‚P”Nپjپ@پثپ@—{کaپi‚و
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¤‚يپjŒ³”Nپ`‚Q”Nپ@پi‚P‚P‚W‚P”Nپ`‚P‚P‚W‚Q ”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پثپ@ژُ‰iپi‚¶‚م‚¦‚¢پjŒ³”Nپ`‚S”Nپ@پi‚P‚P‚W‚Q ”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ`‚P‚P‚W‚T”Nپjپ@پثپ@ —ï”Nچ†•زگ¬’†ژ~پB
پ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ ژُ‰i‚ج—گپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚¦‚¢‚ج‚ç‚ٌپj پBپ@پsگي‚¢پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= Œ¹•½چ‡گي“™پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚i‚t‚d‚h‚m‚nپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‚P‚P‚W ‚O”Nپ[‚P‚P‚W‚X”NپB
پ@
پZپ@‚µ‚مپ@پ@ژٍ‹³پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚«‚ه‚¤پjپBپ@پ@پsژv‘zپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “؟گىچj‹gپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@“ْ–{‚جچ]Œثژ‘م‘Oٹْ‚ةپAچ]Œث–‹•{‚ھپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{‚ً’پڈک‚¾‚ء‚½ژذ‰ï‚ةچى‚è•د‚¦‚ؤ‚¢‚‚ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚«‚ةپAژٍ‹³‚ھ‘ه‚«‚ب–ًٹ„‚ً‰ت‚½‚µپA‚»‚جŒمپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژٍ‹³‚حپAچ]Œثژ‘م‚جگlپX‚جٹî–{—”O‚ج‚P
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚آ‚ئ‚ب‚ء‚½ژv‘z‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژٍٹwپi‚¶‚م‚ھ‚پj‚ئ‚حپAژٍ‹³‚ًڈC“¾‚·‚é
پ@ٹw–â‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“؟گى چj‹g‚حپAپ@ژٍٹw‚جژéژqٹwپi‚µ‚م‚µ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ھ‚پj‚ًٹ¯ٹw‰»‚µ‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژٍ‹³‚ئ‚حپAپ@Œـ—دŒـڈيپi‚²‚è‚ٌ‚²‚¶‚ه‚¤پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‹³‚¦‚إ‚ ‚èپAپ@Œـڈيپi‚²‚¶‚ه‚¤پj‚ئ‚¢‚¤“¹“؟
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ًڈCپi‚¨‚³پj‚ك‚邱‚ئ‚إŒـ—دپi‚²‚è‚ٌپj‚ئ‚¢‚¤
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹضŒW‚ًˆغژ‚·‚邱‚ئ‚إ‚ ‚èپAپ@‚T‚آ‚ج“؟‚ً‚ف
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ھ‚‚±‚ئ‚ة‚و‚è‚T‚آ‚جگlٹشٹضŒW‚ًژç‚邱‚ئ‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@Œـڈيپi‚²‚¶‚ه‚¤پj‚ئ‚حپAپ@‚T‚آ‚ج“؟‚إ‚ ‚èپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گmپi‚¶‚ٌپA”ژˆ¤پjپA‹`پi‚¬پA“¹—پjپA—çپi‚ê‚¢پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—ç‹VپjپA’qپi‚؟پA’mگ«پjپAگMپi‚µ‚ٌپAگM—pپj‚إ‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@Œـ—دپi‚²‚è‚ٌپj‚ئ‚حپAپ@‚T‚آ‚جگlٹشٹضŒW‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚èپAپ@•ƒژq‚جگeپi‚س‚µ‚ج‚µ‚ٌپjپAŒNگb‚ج‹`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚‚ٌ‚µ‚ج‚¬پjپA•v•w‚ج•تپi‚س‚¤‚س‚ج‚ׂآپjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’·—c‚جڈکپi‚؟‚ه‚¤‚و‚¤‚ج‚¶‚هپjپA•ü—F‚جگMپi‚ظ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¤‚ن‚¤‚ج‚µ‚ٌپjپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚مپ@پ@ژé‹àپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚م‚«‚ٌپjپBپ@پs“ْ–{—¬’ت‰ف•¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiچ]Œثژ‘م—¬’ت‰ف•¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚r‚g‚t-‚t‚m‚h‚sپ@‚f‚n‚k‚cپ@‚f‚n‚h‚mپD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@چ]Œثژ‘م‚جژéپi‚µ‚مپj’Pˆت
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‹à‰فپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@چ]Œثژ‘م‚ج’èˆتپi’èٹzپj’تڈي‰ف•¼پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@ پœپ@‚Pژéپà Œ»چف‚ج –ٌ‚U,‚Q‚T‚O‰~پA‚P‚Uژéپà
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚P—¼ڈ¬”»پBپ@‚P—¼ڈ¬”»پà‚S•ھپà‚P‚U ژéپà
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚S‚O‚O‚O•¶پàŒ»چف‚ج–ٌ‚P‚O–œ‰~پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ پiپث ژé’PˆتپE’èٹzپi’èˆتپjپE’تڈي
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰ف•¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث چ]Œثژ‘م‚ج“ْ–{—¬’ت‰ف•¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث “ْ–{—¬’ت‰ف•¼پjپBپ@
پ@
پZپ@‚µ‚مپ@پ@ژé‹âپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚م‚¬‚ٌپjپBپ@پs“ْ–{—¬’ت‰ف•¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiچ]Œثژ‘م—¬’ت‰ف•¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚r‚g‚t-‚t‚m‚h‚sپ@‚r‚h‚k‚u‚d‚qپ@‚f‚n‚h‚mپD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@چ]Œثژ‘م‚جژéپi‚µ‚مپj’Pˆت
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‹â‰فپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@چ]Œثژ‘م‚ج’èˆتپi’èٹzپj’تڈي‰ف•¼پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پœپ@‚Pژéپà Œ»چف‚ج –ٌ‚U‚Q‚T‚O‰~پA‚P‚Uژé
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پà‚P—¼ڈ¬”»پBپ@‚P—¼ڈ¬”»پà‚S•ھپà‚P‚Uژé
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پà‚S‚O‚O‚O•¶پàŒ»چف‚ج–ٌ‚P‚O–œ‰~پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ژé’Pˆت’èٹzپi’èˆتپjپE’تڈي
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰ف•¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث چ]Œثژ‘م‚ج“ْ–{—¬’ت‰ف•¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ْ–{—¬’ت‰ف•¼پjپB
پ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]‹مˆتپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚‚¢پjپB پ@پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ‹مˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@پ@ژُŒj“ٍپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚¯‚¢‚ةپjپBپ@پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiگ¶”N•sڈعپ|‚P‚T‚U‚W”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@‚i‚•‚‹‚…‚‰‚ژ‚‰پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ڈx‰ح‚جگيچ‘‘ه–¼پEچ،گىژپگe
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¤‚¶‚؟‚©پj‚جگ³ژ؛•vگlپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@چ،گىژپ‹Pپi‚¤‚¶‚ؤ‚éپj‚âچ،گى‹`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ³پi‚و‚µ‚à‚ئپj‚جگ¶•ê پAچ،گىژپگ^
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¤‚¶‚´‚ثپj‚ج‘c•êپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ژُŒj“ٍ‚ج•vپEچ،گىژپگeژ€ŒمپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ،گىژپ‹PپAچ،گى‹`Œ³پAچ،گىژپ
پ@پ@پ@پ@ گ^‚جچ،گىژپ‚R‘م‚ة“n‚èپAچ،گىژپ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“–ژه‚جگ–±‚ً•âچ²‚µ‚½‚èپA‘م—
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚µ‚½‚肵‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ڈ—گيچ‘‘ه–¼‚ج‚PگlپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث چ،گى‹`Œ³پA‘¾Œ´گل
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ چضپA“؟گى‰ئچNپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژُŒj“ٍپ@پi‚¶‚م‚¯‚¢‚ةپAگ¶”N•sڈعپ`‚P‚T
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚U‚W”Nپj‚حپAپ@ڈx‰ح‚جگيچ‘‘ه–¼پEچ،گىژپگe
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¤‚¶‚؟‚©پj‚جگ³ژ؛•vگl‚إ‚ ‚èپAپ@چ،گىژپ‹P
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¤‚¶‚ؤ‚éپj‚âچ،گى‹`Œ³پi‚و‚µ‚à‚ئپj‚جگ¶•ê‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚èپAچ،گىژپگ^پi‚¤‚¶‚´‚ثپj‚ج‘c•ê‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ژُŒj“ٍ‚حپAپ@چ،گىژپگeژ€ŒمپAچ،گىژپ‹PپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ،گى‹`Œ³پAچ،گىژپگ^ ‚جچ،گىژپ‚R‘م‚ة“n‚èپA
پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@چ،گىژپ“–ژه‚جگ–±‚ً•âچ²‚µ‚½‚èپA‘م—‚µ‚½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚肵‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ژُŒj“ٍ‚حپAپ@ڈ—گيچ‘‘ه–¼‚ج‚Pگl‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚مپ@پ@ژçŒىپAژçŒى‘ه–¼پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚م‚²پA‚µ‚م‚²‚¾‚¢‚ف‚ه‚¤پjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پsگژ،گ§“xپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚Qپ`‚P‚Uگ¢‹IپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ‘ه–¼پAگيچ‘‘ه–¼پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹كگ¢‘ه–¼پj پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژçŒىپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ژçŒىپi‚µ‚م‚²پj‚ئ‚حپAپ@’†گ¢“ْ–{‚إپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ چ‘پi—كگ§چ‘پj’Pˆت‚إگف’u‚³‚ꂽŒRگ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ –ًگE‚إ‚ ‚èپAٹ™‘q–‹•{پAژ؛’¬–‹•{‚ھ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ”C–½‚µ‚½•گ‰ئپE•گژm‚ھڈA”C‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@ژçŒى‘ه–¼پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@ژçŒى‘ه–¼پ@پi‚µ‚م‚²‚¾‚¢‚ف‚ه‚¤پj‚ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚حپAٹT‚ثپAژ؛’¬ژ‘م‘OٹْپE’†ٹْپ@پi‚P‚R
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚R‚W”Nچ پ`‚P‚S‚U‚V”Nچ پj‚جژٹْ‚ةپAژ؛
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ’¬–‹•{پi= ‘«—ک–‹•{پj‚جڈ«ŒR‚ة‚و‚èژç
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ Œى‚ة”C–½‚³‚ꂽ’n•û—جچ‘—جژه‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@ ژçŒى‘ه–¼‚ئژçŒى—جچ‘گ§پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@ژ؛’¬ژ‘م‘OٹْپE’†ٹْ‚ةپAژ؛’¬–‹
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•{پi= ‘«—ک–‹•{پj‚جڈ«ŒR‚ة”C–½‚³‚ê
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚½ژçŒى‘ه–¼‚حپAپ@”¼چدپi‚ح‚ٌ‚؛‚¢پj‚â
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژçŒى’i‘Kپi‚µ‚م‚²‚½‚ٌ‚¹‚ٌپjپAژçŒىگ؟
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚م‚²‚¤‚¯پj‚ب‚ا‚ً—ک—p‚µ‚ؤپAŒoچد“I
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹî‘b‚ً’z‚«پAژx”zŒ ‚ًٹg‘ه‚µپAژçŒى
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—جچ‘گ§‚ًگ¬—§‚³‚¹‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@ژçŒى—جچ‘گ§‚©‚ç‘ه–¼—جچ‘گ§‚ضپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‰گm‚ج—گ‚إژçŒى—جچ‘گ§‚ح•ِ‰َ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚µپAژ؛’¬ژ‘مŒمٹْپi= گيچ‘ژ‘مپj‚ةپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘½‚‚جژçŒى‘ه–¼‚ھپAژçŒى‘م‚âچ‘گlڈo
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گg‚ب‚ا‚جگيچ‘‘ه–¼‚ة—جچ‘‚ً’D‚ي‚ê
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–v—ژ‚µپA‘ه–¼—جچ‘گ§پ@پi‚P‚S‚U‚Vچ پ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚W‚U‚W”Nچ پj‚ج—جچ‘ژx”z‘جگ§پiگژ،
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘جگ§پj‚ضˆع‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‘ه–¼‚ج•د‘J‚جٹT—ھپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘ه–¼‚ج•د‘J‚إ‚حپAپ@ژ؛’¬ژ‘م‘O
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹْپE’†ٹْ‚ةپAژ؛’¬–‹•{پi= ‘«—ک–‹•{پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جڈ«ŒR‚ةگbڈ]‚µ‚½پAٹe’n‚ج—جچ‘ژx
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”zژز‚ج•گ‰ئپA•گژm‚ھپAژçŒى‘ه–¼‚ئ‚ب
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚èپAپ@ژ؛’¬ژ‘مŒمٹْپi= گيچ‘ژ‘مپj‚ةپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ؛’¬–‹•{‚جڈ«ŒR‚âژçŒى‘ه–¼‚جŒ —ح
‚ھ’ل‰؛‚µپiژم‚ـ‚èپjپA‘½‚‚جژçŒى‘ه–¼
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ح–v—ژ‚µپA‘م‚ي‚ء‚ؤپAژہ—ح‚إ—جچ‘‚ً
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژx”z‚·‚éگيچ‘‘ه–¼‚ھ‘½‚‚جڈoŒ»‚µپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆہ“y“چژRژ‘م‚ةپA‘½‚‚جگيچ‘‘ه–¼
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ھ‘Sچ‘‚ً“ˆê‚µ‚½–Lگbژپ‚ةگbڈ]‚µ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ؤ‹كگ¢‘ه–¼‚ئ‚ب‚èپAپ@چ]Œثژ‘م‘Oٹْ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ةپAچ]Œث–‹•{ژ÷—§ŒمپA‘½‚‚ج‹كگ¢‘ه
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–¼‚حپAچ]Œث–‹•{پi= “؟گى–‹•{پj‚جڈ«
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒR‚ةگbڈ]‚µ‚ؤپA”ثژهپi‚ح‚ٌ‚µ‚مپj‚ئ‚ب
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]ŒـˆتپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚²‚¢ پjپB پ@پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ŒـˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]Œـˆت‰؛پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚²‚¢‚ج‚°پjپB پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@ پiپث ŒـˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹M‘°پA“aڈمگlپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚”‚ˆ‚…پ@‚i‚•‚ژ‚‰‚ڈ‚’پ@‚e‚‰‚†‚”‚ˆپ@‚b‚ڈ‚•‚’‚”پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚q‚پ‚ژ‚‹پC ‚k‚ڈ‚—‚…‚’پ@‚f‚’‚پ‚„‚… ‚ڈ‚†پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚”‚ˆ‚…پ@‚h‚چ‚گ‚…‚’‚‰‚پ‚Œپ@‚b‚ڈ‚•‚’‚”پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ڈ]Œـˆت‰؛پ@پi‚¶‚م‚²‚¢‚ج‚° پC‚”‚ˆ‚…
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚i‚•‚ژ‚‰‚ڈ‚’پ@‚e‚‰‚†‚”‚ˆپ@‚b‚ڈ‚•‚’‚”پ@‚q‚پ‚ژ‚‹پC
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚k‚ڈ‚—‚…‚’پ@‚f‚’‚پ‚„‚…پjپ@‚حپAپ@‘O‹ك‘م “ْ–{‚جپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj‚جˆتٹKپ@پi‚V‚O‚P”N چ پ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚W‚U‚X”Nچ پEژg—pپj‚ج‚R‚OˆتٹK‚جپAڈمˆت
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚S”ش–ع‚جˆتٹKپi‚¢‚©‚¢پj‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ڈ]Œـˆت‰؛ ‚جˆتٹK‚حپAپ@‘O‹ك‘م“ْ–{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جپA’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj‚جˆتٹK‚ئ‚µ‚ؤپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚V‚O‚P”Nچ ‚©‚ç‚P‚W‚U‚X”Nچ ‚ـ‚إپAژg—p‚³
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ꂽپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@ پ،پ@‹M‘°پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘O‹ك‘م‚ج’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj‚جپAڈ]
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œـˆت‰؛‚حپA’تڈيپA’©’ىپi‚؟‚ه‚¤‚ؤ‚¢پj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆتٹKپE‚Tˆتپi‚¢‚©‚¢پE‚²‚¢پjˆبڈم‚جژز‚ً‹M
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘° پi‚«‚¼‚پj‚ئŒؤ‚ش‚ج‚إپAڈ]Œـˆت‰؛‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’©’ى‚ج‹M‘°‚ة‚ب ‚邽‚ك‚جچإ‰؛ˆت‚جˆت
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹK‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‘O‹ك‘م‚ج’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj‚جپAڈ]Œـ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆت‰؛‚حپAپ@‘ گlپi‚‚낤‚اپj‚ًڈœ‚«پAپ@’©’ى
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جپA“à— پi‚¾‚¢‚èپA“VچcŒنڈٹپj‚جپA“aڈم
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گlپi‚ؤ‚ٌ‚¶‚ه‚¤‚ر‚ئپj‚ة‚ب‚邽‚ك‚جچإ’لڈً
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œڈ‚ج’©’ى‚جˆتٹK‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@ پ،پ@“aڈمگlپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘O‹ك‘م‚ج’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj‚جپA“à
پ@ پ@— پi‚¾‚¢‚èپj‚جپA“aڈمگlپi‚ؤ‚ٌ‚¶‚ه‚¤‚ر‚ئپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ئ‚حپAپ@ˆتٹKپEŒـˆتپi‚¢‚©‚¢پE‚²‚¢پjˆبڈم
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جژز‚إڈ¸“aپi‚µ‚ه‚¤‚إ‚ٌپj‚ً‹–‰آ‚³‚ꂽژزپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚âپAپ@ˆتٹKپEکZˆتپi‚¢‚©‚¢پE‚ë‚‚¢پjˆبڈم
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جژز‚إ‘ گl پi‚‚낤‚اپA“Vچc”éڈ‘ٹ¯پj‚ة
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ–”C پi‚¶‚ه‚ة‚ٌپj‚³‚ꂽژز‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]ŒـˆتڈمپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚م‚²‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپB پ@پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ŒـˆتپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚مپ@پ@ژçŒىگ؟پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚م‚²‚¤‚¯پjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiگ؟ڈٹپjپ@پs”Nچvگ؟•‰گ§“xپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پs“ْ–{‚ج“y’nژx”zگ§“xپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ژçŒىپAژçŒى‘ه–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‘‘‰€پAŒِ—جپi= چ‘هة—جپjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث گ؟ڈٹپi‚¤‚¯‚µ‚هپjپA’n“ھگ؟پA
پ@پ@پ@پ@پ@•Sگ©گ؟پi= ’n‰؛گ؟پjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژçŒىگ؟پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژçŒىگ؟پi‚µ‚م‚²‚¤‚¯پj‚ئ‚حپAپ@ ژ؛’¬
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ‘م‚ةپAژçŒى‚ھپA‘‘‰€‚âŒِ—جپiچ‘هة
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—جپj‚ج”Nچv‚ج”[“ü‚ًگ؟‚¯•‰‚¤گ§“x‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ژçŒىگ؟پi‚µ‚م‚²‚¤‚¯پj‚ئ‚حپAپ@ ژ؛’¬
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ‘م‚ةپAژçŒى‚ھˆê’è‚ج”Nچvپi‚ث‚ٌ‚®پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ً”[“ü‚·‚é‚ئ‚¢‚¤ڈًŒڈ‚إپAپ@–{ڈٹپE—ج‰ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‘‘‰€—جژه‚âچ‘ژiپE’mچsچ‘ژه‚ھپAژç
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œى‚ةپA‘‘‰€‚âŒِ—جپiچ‘هة—جپj‚جŒo‰c‚ً
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆد”C‚·‚éگ§“x‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚مپ@پ@ژçŒىچف‹گ§پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚م‚²‚´‚¢‚«‚ه‚¤‚¹‚¢پjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پs ژ؛’¬–‹•{پtپB
پ@پ@پ@پ@پiپث ژ؛’¬–‹•{پAژçŒى‘ه–¼پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‰گm‚ج—گپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ژ؛’¬ژ‘مپAگيچ‘ژ‘مپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@ژ؛’¬–‹•{‚©‚ç”C–½‚³‚ꂽپAژçŒى‘ه–¼
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚حپAژ؛’¬ژ‘م‘OٹْپE’†ٹْ‚إ‚حپAچف‹‚ھŒ´
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‘¥‚إ‚ ‚ء‚½‚ھپAپ@‰گmپE•¶–¾‚ج—گپi‚P‚S‚U‚V
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ”Nپ[‚P‚S‚V‚V”NپjŒمپAژ©‚ç—جچ‘ ‚ًژç‚邽‚ك
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‹پi“sپj‚و‚è—جچ‘‚ة‰؛‚èپ@پi—جچ‘‚جگڈî•s
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ˆہ‚ج‚½‚ك‹Aچ‘‚µ‚½‚ـ‚ـپA‹پi“sپj‚ة–ك‚炸پjپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ژ؛’¬–‹•{‚جژçŒىچف‹گ§‚ح•ِ‰َ‚µپAژçŒى
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‘ه–¼‚حپA –‹•{‚ج“گ§‚ً—£‚ê‚éپB ‚و‚ء‚ؤپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‰گmپE•¶–¾‚ج—گˆبŒم‚جگيچ‘ژ‘مپiژ؛’¬ژ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‘مŒمٹْپj‚ةپAژçŒىچف‹گ§‚ح•ِ‰َ‚µپAژ؛’¬
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ –‹•{‚جŒ ˆذ‚ح’ل‰؛‚·‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚مپ@پ@ژçŒىپE’n“ھ‚جگف’uپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚م‚²پE‚¶‚ئ‚¤‚ج‚¹‚ء‚؟پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚P‚W‚T”NپjپBپ@پs گژ،گ§“xپtپB
پ›پ@Œ¹—ٹ’©پE‘¤‹ك‚ج‘هچ]چLŒ³‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ Œ£چô‚ة‚و‚èپAŒ¹—ٹ’©‚ھپA‘Sچ‘‚ة
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ گف’u‚·‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚مپ@پ@ژçŒى‘مپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚م‚²‚¾‚¢پjپBپ@پs—جچ‘گ§“xپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ژçŒىپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ژçŒى‘ه–¼پA‰گm‚ج—گپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گيچ‘ژ‘مپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ژ؛’¬ژ‘مپAژ؛’¬–‹•{پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژçŒى‘مپi‚µ‚م‚²‚¾‚¢پj‚ئ‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’†گ¢“ْ–{‚جژ؛’¬ژ‘م‚إپAژ؛’¬–‹•{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جژçŒى‚ج•âچ²گE‚إ‚ ‚èپAژ؛’¬–‹•{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جژçŒىچف‹گ§‚ج‚½‚كپAژçŒى‚ة‘م‚ي
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ء‚ؤپAژçŒى‚ج—جچ‘‚ً“ژ،‚µ‚½•گ‰ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ ‚èپAژçŒى‚ج• گS‚ج•”‰؛‚إ‚ ‚ء
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژçŒى‘م‚حپAپ@ژ؛’¬ژ‘م‘OٹْپE’†
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹْ‚ة‚حپAژçŒىچف‹گ§‚ج‚½‚كپAژçŒى
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘ه–¼‚ج‘م—‚ئ‚µ‚ؤپAژçŒى‘ه–¼‚ج—ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ‘‚ً“ژ،‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ھپAپ@‰گm‚ج—گ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إژçŒى—جچ‘گ§‚ھ•ِ‰َ‚µپA‰؛™ژڈم‚ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ب‚èپAژ؛’¬ژ‘مŒمٹْپi= گيچ‘ژ‘مپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ة‚حپAپ@چ‘گl—جژه‚ب‚ا‚جگيچ‘‘ه–¼
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ھپA‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚جژçŒى‘ه–¼‚ج—جچ‘‚ً
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’D‚¢پAپ@ژçŒى‘م‚ھٹاٹچ‚·‚é‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج—ج“y‚àپAگيچ‘‘ه–¼‚ھ—ج“y‚ً’D‚¤پB
پ@
پZپ@‚µ‚مپ@پ@ژçŒى—جچ‘گ§پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚م‚²‚è‚ه‚¤‚²‚‚¹‚¢پjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiگژ،‘جگ§پjپBپs ژ؛’¬–‹•{پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپثپ@ژçŒى‘ه–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ‰گm‚ج—گپAگيچ‘ژ‘مپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ژ؛’¬ژ‘مپAژ؛’¬–‹•{پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ژ؛’¬ژ‘مپAگيچ‘ژ‘مپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ، ژçŒى—جچ‘گ§پ@پi‚µ‚م‚²‚è‚ه‚¤‚²‚‚¹
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚¢پj‚ئ‚حپAپ@ژ؛’¬ژ‘م‘OٹْپE’†ٹْ‚جپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ؛’¬–‹•{پi= ‘«—ک–‹•{پj‚جڈ«ŒR‚ھ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”C–½‚µ‚½ژçŒى‘ه–¼‚ھپA“ْ–{–{“y‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ظ‚ع‘Sچ‘‚ً“ژ،‚·‚éگژ،‘جگ§پA—ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ‘ژx”z‘جگ§‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@ژçŒى—جچ‘گ§پ@پi‚µ‚م‚²‚è‚ه‚¤‚²‚‚¹
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚¢پj‚ئ‚حپAپ@ژ؛’¬ژ‘م‘OٹْپE’†ٹْپ@پi‚P‚R
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚R‚W”Nچ پ`‚P‚S‚U‚V”Nچ پj‚جپAژçŒى‚ة‚و
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚é—جچ‘ژx”z‘جگ§‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@ژ؛’¬ژ‘م‘OٹْپE’†ٹْ‚ةپA ژçŒى‘ه–¼
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚حپAپ@”¼چدپi‚ح‚ٌ‚؛‚¢پj‚âژçŒى’i‘Kپi‚µ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚م‚²‚½‚ٌ‚¹‚ٌپjپAژçŒىگ؟پi‚µ‚م‚²‚¤‚¯پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ب‚ا‚ً—ک—p‚µ‚ؤپAŒoچد“Iٹî‘b‚ً’z‚«پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژx”zŒ ‚ًٹg‘ه‚µپAژçŒى—جچ‘گ§‚ًگ¬—§
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚³‚¹‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@ژçŒى—جچ‘گ§‚حپA‰گm‚ج—گ‚إ•ِ‰َ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚µپAژ؛’¬ژ‘مŒمٹْپi= گيچ‘ژ‘مپjˆبŒمپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گيچ‘‘ه–¼‚â‹كگ¢‘ه–¼‚ھ“ژ،‚·‚é‘ه–¼
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—جچ‘گ§پ@پi‚P‚R‚R‚W”Nچ پ`‚P‚W‚U‚W”Nچ پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جگژ،‘جگ§پi—جچ‘ژx”z‘جگ§پj‚ةˆع‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚مپ@پ@ژéگ‘àپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚م‚´‚‚½‚¢پjپBپ@پs‰ï’أگي‘ˆپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= ‰ï’أ”ثپEژéگ‘àپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@‰ï’أگي‘ˆ‚إ‰ï’أ”ثپE”ثژm‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ’†ٹj•”‘à‚ج‚P‚آپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث‰ï’أگي‘ˆپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]ژOˆتپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚³‚ٌ‚فپjپB پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پiپث ژOˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پiپث Œِ‹¨پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ڈ]ژOˆت پi‚¶‚م‚³‚ٌ‚فپj‚حپAپ@‹كپEŒ»‘م“ْ–{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جپAگEˆُ—كپi‚Q‚OˆتٹKپjپAڈ– ˆتڈً—ل‚âˆتٹK—ك
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚UˆتٹKپj‚جˆتٹKپ@پi‚P‚W‚U ‚X”Nچ پ`Œ»چفپEژg
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—pپjپA‹y‚رپ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جپA’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جˆتٹKپi‚R‚OˆتٹKپA‚V‚O‚P”Nچ پ`‚P‚W‚U‚X”Nچ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژg—pپjپ@‚جˆتٹK’†‚إپAپ@ڈمˆت‚U”ش–ع‚جˆتٹKپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ڈ]ژOˆت‚حپAپ@‚V‚O‚P”Nچ ‚©‚猻چف‚ـ‚إپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژg—p‚³‚ê‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘O‹ك‘م‚ج’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj‚جپAڈ]ژOˆت
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚حپAپ@ژQ‹cپi‚³‚ٌ‚¬پj‚ًڈœ‚«پAپ@’©’ى‚جپA“à
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@— پi‚¾‚¢‚èپA“VچcŒنڈٹپj‚جپAŒِ‹¨پi‚‚¬‚ه‚¤پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ة‚ب‚邽‚ك‚جڈًŒڈ‚ج’©’ى‚جˆتٹK‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@‘O‹ك‘م‚ج’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj‚جپAŒِ‹¨پi‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¬‚ه‚¤پj‚ئ‚حپAژOˆتˆبڈم‚جژز‚âژQ‹c‚جٹ¯گE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ة‚ ‚éژز‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’©’ى‚جپA“à— پi‚¾‚¢‚èپA“VچcŒنڈٹپj‚جپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œِ‹¨‚حپAپ@’©’ى‚جˆتٹKپEژOˆتپi‚³‚ٌ‚فپjˆبڈم
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جژز‚âپAپ@’©’ى‚جˆتٹKپEژlˆتپi‚µ‚¢پj‚جژز‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژQ‹cپi‚³‚ٌ‚¬پj‚جٹ¯گE‚ةڈ–”C‚³‚ꂽژزپiڈ–
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¹‚ç‚ꂽژزپjپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]ژOˆت“ü“¹
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚م‚³‚ٌ‚ف‚ة‚م‚¤‚ا‚¤پjپBپ@پsگl–¼پtپB
پi= Œ¹ —ٹگ پi‚ف‚ب‚à‚ئ‚ج‚و‚è‚ـ‚³پjپj پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث Œ¹ —ٹگپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]ژlˆتپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚µ‚¢پjپB پsˆتٹKپtپB
پ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]ژlˆت‰؛پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚µ‚¢‚ج‚°پjپB پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پiپث ژlˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پiپث Œِ‹¨پAژQ‹cپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جپA’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj‚جˆت
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹKپi‚V‚O‚P”Nچ پ`‚P‚W‚U‚X”Nچ پEژg—pپj‚ج‚R‚O
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆتٹK‚جپAپ@ڈمˆت‚P‚O”ش–ع‚جˆتٹKپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‚V‚O‚P”Nچ ‚©‚ç‚P‚W‚U‚X”Nچ ‚ـ‚إپAژg—p
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚³‚ꂽپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘O‹ك‘م‚ج’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj‚جپAڈ]ژlˆت
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰؛‚حپA’©’ى‚جŒِ‹¨پi‚‚¬‚ه‚¤پj ‚ة‚ب‚邽‚ك‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چإ’لڈًŒڈ‚جˆتٹK‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ]ژlˆت‰؛‚حپA’©’ى‚جŒِ‹¨پi‚‚¬‚ه‚¤پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جژQ‹cپi‚³‚ٌ‚¬پj‚ة‚ب‚邽‚ك‚جچإ’لڈًŒڈ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆتٹKپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@‘O‹ك‘م‚ج’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj‚جپAŒِ‹¨پi‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¬‚ه‚¤پj‚ئ‚حپAژOˆتˆبڈم‚جژز‚âژQ‹c‚جٹ¯گE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ة‚ ‚éژز‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’©’ى‚جپA“à— پi‚¾‚¢‚èپA“VچcŒنڈٹپj‚جپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ Œِ‹¨‚حپAپ@’©’ى‚جˆتٹKپEژOˆتپi‚³‚ٌ‚فپjˆبڈم
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚جژز‚âپAپ@’©’ى‚جˆتٹKپEژlˆتپi‚µ‚¢پj‚جژز‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژQ‹cپi‚³‚ٌ‚¬پj‚جٹ¯گE‚ةڈ–”C‚³‚ꂽژز ‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]ژlˆتڈمپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚µ‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپB پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ژlˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]ژµˆتپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚µ‚؟‚¢پjپB پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ژµˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@
پ›پ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]ژµˆت‰؛پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚µ‚؟‚¢‚ج‚°پjپB پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ژµˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]ژµˆتڈمپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚µ‚؟‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپB پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ژµˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚مپ@پ@پ@ژهڈمپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚م‚¶‚ه‚¤پjپB پs“Vچc‰ئپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= “VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “VچcپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@پ@“ü“àپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚¾‚¢پjپBپ@پs“Vچc‰ئپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث گ³ژ؛•vگlپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث “Vچc‰ئپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@“ü“àپi‚¶‚م‚¾‚¢پj‚ئ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “Vچc‚جگ³ژ؛•vگlپiچcچ@پA’†‹{پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ڈ—Œنپj‚Rگl‚جˆêگl‚ئ‚ب‚邱‚ئ‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@“ü“àپi‚¶‚م‚¾‚¢پj‚ئ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@“Vچc‚جگ³ژ؛•vگl‚ئ‚ب‚é‚ׂ«گl‚ھپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ³ژ®‚ة“à— پi‚¾‚¢‚èپA“Vچc‚جŒن“a
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi“Vچc‚ھڈZ‚قڈZ‹ڈپj‚ة“ü‚邱‚ئ‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚مپ@پ@ ژé’PˆتپE’èˆتپi’èٹzپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پi‚µ‚م‚½‚ٌ‚¢پE‚ؤ‚¢‚¢پi‚ؤ‚¢‚ھ‚پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚آ‚¤‚¶‚ه‚¤‚©‚ض‚¢پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پs“ْ–{—¬’ت‰ف•¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiچ]Œثژ‘م—¬’ت‰ف•¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث چ]Œثژ‘م‚ج“ْ–{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—¬’ت‰ف•¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث “ْ–{—¬’ت‰ف•¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پœپ@چ]Œثژ‘م‚جپAچ]Œث
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@–‹•{’’‘¢‚جپAژé’Pˆت
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ’èˆتپi’èٹzپj’تڈي‰ف•¼پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ،پ@‚Pژéپà Œ»چف‚ج –ٌ‚U‚Q‚T‚O‰~پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ ‚P‚Uژéپàˆê—¼ڈ¬”»پi‹àپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ،پ@‚P—¼ڈ¬”» پi‹àپjپà‚S•ھپà‚P‚Uژé
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ پà‚S‚O‚O‚O•¶پàŒ»چف‚ج–ٌ‚P‚O–œ‰~پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ،پ@ژé’Pˆت‚ج‰ف•¼‚ة‚حپA‚Qژé‹àپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@1ژé‹à‚ئ‚¢‚¤ژé‹àپi‚µ‚م‚«‚ٌپAژé’P
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆت‚ج‹à‰فپj‚ئپ@‚Qژé‹âپA1ژé‹â‚ئ‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¤ژé‹âپi‚µ‚م‚¬‚ٌپAژé’Pˆت‚ج‹â‰فپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ھ‚ ‚ء‚½پB
پ@
پZپ@‚µ‚مپ@پ@ژé’¹پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚م‚؟‚ه‚¤پA‚·‚؟‚ه‚¤پjپBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚r‚g‚t‚b‚g‚nپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@‚U‚W‚U”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پœپ@‚U‚W‚U”NپEژé’¹Œ³”NپE‚VŒژ‚Q‚O“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@‚U‚W‚U”NپEژé’¹Œ³”NپE‚XŒژپ@‚X“ْپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پœپ@”ٍ’¹”’–Pژ‘مŒمٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@
پZپ@‚µ‚مپ@پ@پ@ڈo‰ئپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚م‚ء‚¯پjپBپ@پs•§‹³پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= •§“¹‚جگ¶ٹˆ‚ة“ü‚邱‚ئپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@‚P‚Oگ¢‹Iپ`‚P‚Xگ¢‹I
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚م‚ء‚¹‚¢‚«پ` ‚¶‚م‚¤ ‚«‚م‚¤‚¹‚¢‚«پjپBپsگ¢‹IپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= ‚X‚O‚P”Nپ`‚P‚X‚O‚O”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث گ¢‹IپAگ¢‹IپEگ¼—ï”Nچ†‘خ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ڈئˆê——•\پjپB
پ›پ@‚P‚O گ¢‹Iپ@پiپ@‚X‚O‚P”Nپ`‚P‚O‚O‚O”NپjپB
پ›پ@‚P‚P گ¢‹Iپ@پi‚P‚O‚O‚P”Nپ`‚P‚P‚O‚O”NپjپB
پ›پ@‚P‚Q گ¢‹Iپ@پi‚P‚P‚O‚P”Nپ`‚P‚Q‚O‚O”NپjپBپ@
پ›پ@‚P‚R گ¢‹Iپ@پi‚P‚Q‚O‚P”Nپ`‚P‚R‚O‚O”NپjپBپ@
پ›پ@‚P‚S گ¢‹Iپ@پi‚P‚R‚O‚P”Nپ`‚P‚S‚O‚O”NپjپBپ@
پ›پ@‚P‚T گ¢‹Iپ@پi‚P‚S‚O‚P”Nپ`‚P‚T‚O‚O”NپjپBپ@
پ›پ@‚P‚U گ¢‹Iپ@پi‚P‚T‚O‚P”Nپ`‚P‚U‚O‚O”NپjپBپ@
پ›پ@‚P‚V گ¢‹Iپ@پi‚P‚U‚O‚P”Nپ`‚P‚V‚O‚O”NپjپBپ@
پ›پ@‚P‚W گ¢‹Iپ@پi‚P‚V‚O‚P”Nپ`‚P‚W‚O‚O”NپjپBپ@
پ›پ@‚P‚X گ¢‹Iپ@پi‚P‚W‚O‚P”Nپ`‚P‚X‚O‚O”NپjپBپ@
پ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ\ژèژ‚؟پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚ء‚ؤ‚à‚؟پjپB پsچ]Œثژ‘م‚جژ،ˆہپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= ‰ھ‚ءˆّ‚«پjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ‰ھ‚ءˆّپjپB
پ@
پ@
پZپ@‚µ‚مپ@پ@ ژٌ“sپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚م‚ئپjپBپ@پs “sژsپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث Œأ“sپi‚±‚ئپjپAپjپB
پ@“sپi‚ف‚₱پjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث “sڈéپi‚ئ‚¶‚ه‚¤پjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹پi‚«‚ه‚¤پjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ”ٍ’¹پi”ٍ’¹‹پjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹ€Œ´پi“،Œ´‹پjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ق—اپi•½ڈé‹پjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ Œü“ْپi’·‰ھ‹پjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹“sپi•½ˆہ‹پjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹ™‘qپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆہ“yپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘هچمپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ]ŒثپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“Œ‹پ@پjپB
پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ پ@“ْ–{Œأ“sƒKƒCƒhƒuƒbƒNپB
پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ پ@“ْ–{Œأ“s ٹضکA”N‘مڈ‡
پ@پ@ ڈo—ˆژ–ƒuƒbƒNپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ پ@”ٍ’¹‹پ@‰و‘œƒAƒ‹ƒoƒ€پ@
پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚m‚ڈپD‚PپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ پ@“،Œ´‹پ@‰و‘œƒAƒ‹ƒoƒ€
پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚m‚ڈپD‚PپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ پ@•½ڈé‹پ@‰و‘œƒAƒ‹ƒoƒ€پ@
پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚m‚ڈپD‚PپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ پ@’·‰ھ‹پ@‰و‘œƒAƒ‹ƒoƒ€پ@
پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚m‚ڈپD‚PپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ پ@•½ˆہ‹پ@‰و‘œƒAƒ‹ƒoƒ€
پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚m‚ڈپD‚PپBپ@
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژٌ“sپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@ژٌ“s‚ئ‚حپA
پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ‘‰ئگژ،پEچsگ‚ج’†گS’n‚إ‚ ‚èپAپ@
پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ‘‰ئƒŒƒxƒ‹‚جگژ،پEچsگ‚ج’†ٹj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“sژs‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ژٌ“s‚ئ‚حپA
پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚éچ‘‚جپAچ‘‰ئگŒ پEگ•{‚ج–{‹’
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’n‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚éچ‘‘S“y‚ً“ژ،‚·‚é‘Sچ‘گŒ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ•{‚ج’†‰›گ•{‚ج’†ٹj“sژs‚إ‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@“ْ–{‚جژٌ“sپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@“ْ–{‚جژٌ“s‚ئ‚حپA
پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{‚جچ‘‰ئگŒ پEگ•{‚ج–{‹’’n
پ@پ@ ‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{–{“y‚ً“ژ،‚·‚é‘Sچ‘گŒ پEگ
پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•{‚ج’†ٹj“sژs‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@“ْ–{‚جپAژٌ“s‚ئ“sڈé
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚â‹پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@“ْ–{‚جژٌ“s‚ئ‚حپA
پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{–{“y‚ً“ژ،‚·‚é‘Sچ‘گŒ پE
پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ•{‚ج’†ٹj“sژs‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج“sڈéپE‹پ@پi‚ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@‚¶‚ه‚¤پE‚«‚ه‚¤پj‚ئ‚حپAپ@“Vچc‚جڈZ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹ڈ‚ھ‚ ‚é“sژs‚إ‚ ‚éچc‹ڈ“sژs‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@“ْ–{‚جپAٹ™‘qژ‘مپAˆہ“y“چ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ژRژ‘مپAچ]Œثژ‘م‚إ‚حپA“ْ–{‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژٌ“sپiگژ،پEچsگ‚ج’†گS’nپj‚ئچc
‹ڈ“sژsپi“sڈéپE‹پj‚ئ‚ح•ت‚ة‚ب‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]“ٌˆتپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚ة‚¢پjپBپ@پs ˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ٌˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ƒWƒ…ƒٹپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پs—Vڈ—پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپF‰«“ê‚ج—Vٹs‚ج—Vڈ—پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ‰«“ê‚ج—ًژjپA—®‹…
‰¤چ‘پjپB
پ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]”ھˆتپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚ح‚؟‚¢پjپB پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ”ھˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@
پ›پ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]”ھˆت‰؛پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚ح‚؟‚¢‚ج‚°پjپB پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ”ھˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚”‚ˆ‚…پ@‚i‚•‚ژ‚‰‚ڈ‚’پ@‚W‚”‚ˆپ@‚b‚ڈ‚•‚’‚”پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚q‚پ‚ژ‚‹پC ‚k‚ڈ‚—‚…‚’پ@‚f‚’‚پ‚„‚… ‚ڈ‚†پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚”‚ˆ‚…پ@‚h‚چ‚گ‚…‚’‚‰‚پ‚Œپ@‚b‚ڈ‚•‚’‚”پD
پ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]”ھˆتڈمپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚ح‚؟‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپB پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ”ھˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@معٹy‘وپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚ç‚‚¾‚¢پA‚¶‚م‚ç‚‚ؤ‚¢پjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پsڈéپA“@‘îپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚T‚W‚V”Nپ[‚P‚T‚X‚T”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث –Lگb ڈG‹gپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث –Lگb ڈGژںپjپB
‚m‚ڈپD‚PپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚m‚ڈپD‚QپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@معٹy‘وپ@پi‚¶‚م‚ç‚‚¾‚¢پA‚¶‚م‚ç‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ؤ‚¢پA ‚P‚T‚W‚V”Nپ[‚P‚T‚X‚T”Nپj‚ئ‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–LگbڈG‹g‚ھ‹پi‚«‚ه‚¤پA‹“sپj‚ة‘¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰c‚µ‚½•½ڈéپi‚ذ‚炶‚ëپA•½’n‚جڈéپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@–LگbڈG‹g‚حپA‚P‚T‚W‚V”Nپi–Lگb‘هچم
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈé‚©‚çˆع‚éژپj‚و‚è‚P‚T‚X‚P”Nپi‰B‹ڈ‚µ‚ؤ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘¾ٹt‚ئ‚ب‚éژپj‚ـ‚إپAپ@“ْ–{‚جگ–±‚ً‚±
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚±‚إچs‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹض”’گE‚ة‚ ‚éژز‚حپA’©’ى‚ج‚ ‚é
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹پi‚«‚ه‚¤پA‹“sپj‚ةچفڈZ‚·‚é•K—v‚ھ‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚é‚كپA–LگbڈG‹g‚ھٹض”’‚إ‚ ‚éٹشپA‹
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‹“sپj‚جمعٹy‘و‚إپA“ْ–{‚جگ–±‚ًچs
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@معٹy‘وپ@پi‚¶‚م‚ç‚‚¾‚¢پA‚¶‚م‚ç‚‚ؤ‚¢پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚T‚W‚V”Nپ[‚P‚T‚X‚T”Nپj‚حپAپ@–LگbڈG‹g‚ھ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹پi“sپj‚ة‘¢‰c‚µ‚½ڈéٹsŒ`ژ®‚ج“@‘î‚إ‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@–LگbگŒ ‚ج•گ‰ئ‚جگ’،‚حپA–Lگb‘ه
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چمڈé‚إ‚ ‚èپAپ@–LگbگŒ ‚جŒِ‰ئ‚جگ’،
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚حپA‹پi‚«‚ه‚¤پA‹“sپj‚جمعٹy‘و‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@معٹy‘و‚حپA‚P‚T‚W‚V”Nپi“Vگ³‚P‚T”Nپj‚ة
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹ®گ¬‚µ‚½چ‹“@‚إ‚ ‚èپAپ@معٹy‘وژü•س‚ةڈ”
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘ه–¼‚ج“@‘î‚àŒڑگف‚³‚ꂽپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@معٹy‘و‚حپAڈG‹g‚ھ‚P‚T‚W‚W”N‚ةŒم—z
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ¬پi‚²‚و‚¤‚؛‚¢پj“Vچc‚ًڈµ‚«پi“Vچc‚جچs
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چKپjپA‚P‚T‚X‚P”N‚و‚èڈG‹gپE‰™پi‚¨‚¢پj‚جٹض
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”’پE–LگbڈGژںپi‚ذ‚إ‚آ‚®پj‚ھ‹ڈڈٹ‚ئ‚µپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚T‚X‚T”N(•¶ک\‚S”Nپj‚جڈGژںژ¸‹rپiژ©گn
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚¶‚ٌپAژ©ٹQپjŒمپAڈG‹g‚حمعٹy‘و‚ً”j
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰َ‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@–LگbڈG‹g‚حپA‚P‚T‚X‚T”Nپi•¶ک\‚S”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ةپAپ@‹پi‚«‚ه‚¤پA‹“sپj‚ة‚ ‚é–LگbگŒ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جŒِ‰ئ‚جگ’،‚إٹض”’‚ج–LگbڈGژں‚ج‹ڈ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈٹ‚إ ‚ ‚ء‚½پAمعٹy‘وپi‚¶‚م‚ç‚‚¾‚¢ پA‚¶
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚م‚ç‚‚ؤ‚¢پA ‚P‚T‚W‚V”Nپ[‚P‚T‚X‚T”Nپj‚ً”j
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰َ‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚»‚جŒمپAڈG‹g’zڈé‚جژwŒژ•ڑŒ©ڈé
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚°‚آ‚س‚µ‚ف‚¶‚ه‚¤پA‚P‚T‚X‚Q”Nپ|‚P‚T
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚X‚U”Nپjپ@‚âپ@‘OٹْپE–ط”¦ژR•ڑŒ©ڈéپi‚؛
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ٌ‚«پE‚±‚ح‚½‚â‚ـ‚س‚µ‚ف‚¶‚ه‚¤پA‚P‚T‚X‚V
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”Nپ[‚P‚U‚O‚O”Nپjپ@‚ھپAپ@–LگbگŒ ‚جŒِ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰ئ‚جگ’،‚ًŒ“‚ث‚éپBپ@‚µ‚©‚µپAڈG‹g‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–LگbگŒ ‚جŒِ‰ئگê—p‚جگ’،‚ًچؤ‚رپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œڑ‚ؤ‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@معٹy‘و‚حپAپ@ٹOŒ©‚ح‹“s‚ةŒ»‘¶‚·
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚é“؟گى‰ئچN’zڈé‚ج“ٌڈًڈéپiپuŒ³—£‹{“ٌ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈًڈéپv‚ج‚و‚¤‚ةپAچٹپi‚²‚¤پj‚ئگخٹ_پi‚¢‚µ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ھ‚«پj‚إˆح‚ـ‚ꂽڈé‚ج‚و‚¤‚بŒڑ’z•¨‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚èپAپ@’†‚ةپAچsچKŒن“aپA“VژçŒن“aپA’ƒ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰®پA‚»‚ج‘¼‚ج‰®•~ŒQ‚ھŒڑ‚ؤ‚ç‚êپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’r‚ئ’뉀‚ھ‚ ‚èپAچ‹‰طˆ؛ࣂبŒڑ’z•¨‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚ء‚½پB “Œگ¼–ٌ‚Q‚T‚O‚چ‚ج‘ه‚«‚³‚إ‚ ‚ء
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@معٹy‘و‚جڈêڈٹپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@معٹy‘و‚حپAپ@Œ»چف‚ج‹“sŒنڈٹ‚جگ¼
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•û‚ج’†—§”„’ت‚è‚ج•ûŒü‚ج’nˆو‚ة‚ ‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@معٹy‘و‚حپAپ@“à–ىپi‚¤‚؟‚جپA•½ˆہ‹
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج•½ˆہ‹{پi=‘ه“à— پj’nˆوپj‚ج–kگ¼•”•t
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹ك‚ة‚ ‚èپAپ@معٹy‘و‚جپA“Œ‘¤‚جچٹ‚حŒ»چف
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‘ه‹{’ت‚è•t‹ك‚ة‚ ‚èپAƒnƒچپ[ƒڈپ[ƒNŒü
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¦‚ة“Œچٹگص‚جگخ”è‚ھ‚ ‚èپAپ@گ¼‘¤‚جچٹ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ح— –ه’ت‚è•t‹ك‚ة‚ ‚èپAٹwچZ‚ج‘O‚ةگ¼
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ چٹگص‚جگخ”è‚ھ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“Œ‘¤‚جچٹ‚ھ‚ ‚ء‚½ڈêڈٹ‚ة‚ ‚錻
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چف‚جƒnƒچپ[ƒڈپ[ƒN‚إپAŒڑ’z’†‚ة’n–ت‚ً
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ@‚ء‚½ژپAمعٹy‘و‰®•~‚ج‹à”“ٹ¢پi‚«‚ٌ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚خ‚‚ھ‚ي‚çپj‚ھڈo“y‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚مپ@پ@ژٌ—¢ڈéپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚م‚肶‚ه‚¤پjپBپ@پsڈéپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@—®‹…‰¤چ‘‚ج‰¤•{‚ھ‚ ‚éڈéپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@‰«“ê–{“‡“ى•”‚ة‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@ژٌ—¢ڈéپ@پi‚µ‚م‚肶‚ه‚¤پj ‚حپA‰«“ê–{“‡
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ى•”‚ة‚ ‚éپA—®‹…‰¤چ‘‚ج‰¤•{‚ھ‚ ‚éڈé
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ‰«“ê‚ج—ًژjپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚مپ@پ@ƒVƒ…ƒٹƒeƒ“ƒKƒiƒVپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پs—®‹…‰¤چ‘پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= —®‹…‰¤چ‘‚جچ‘‰¤پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث —®‹…‰¤چ‘پA‰«“ê‚ج
—ًژjپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚مپ@پ@ژç—ç–هپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚م‚ê‚¢‚à‚ٌپjپBپ@پs—®‹…‰¤چ‘پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‰«“ê‚ج—ًژjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@—®‹…پi‰«“êپj‚إپA’†چ‘‚جچû••
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ژgپi‚³‚‚ظ‚¤‚µ پA‚³‚ء‚غ‚¤‚µپj‚ًڈoŒ}‚¦‚é
‚½‚ك‚ةگف‚¯‚ç‚ꂽ–هپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@ژç—ç–هپ@پi‚µ‚م‚ê‚¢‚à‚ٌپj‚حپA—®‹…پi‰«“êپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚إپAپ@’†چ‘‚جچû••ژgپi‚³‚‚ظ‚¤‚µ پA‚³‚ء‚غ‚¤‚µپj
پ@پ@پ@ ‚ًڈoŒ}‚¦‚邽‚ك‚ةگف‚¯‚ç‚ꂽ–هپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]کZˆتپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚ë‚‚¢پjپBپ@پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کZˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]کZˆت‰؛پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚ë‚‚¢‚ج‚°پjپBپ@پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث کZˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‘ گlپA“aڈمگlپA’©’ى‚جˆتٹKپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ڈ]کZˆت‰؛ پ@پi‚¶‚م‚ë‚‚¢‚ج‚°پj‚حپA‘O‹ك
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘م“ْ–{‚جپA’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj‚جˆتٹKپi‚V‚O‚P
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”Nچ پ`‚P‚W‚U‚X”Nچ پEژg—pپj‚ج‚R‚O ˆتٹK‚جپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚W”ش–ع‚جˆتٹK‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ڈ]کZˆت‰؛ پ@پi‚¶‚م‚ë‚‚¢‚ج‚°پj‚حپA‚V‚O‚P
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”Nچ ‚©‚ç‚P‚W‚U‚X”Nچ ‚ـ‚إپAژg—p‚³‚ꂽپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘O‹ك‘م‚ج’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj‚جپAڈ]کZˆت
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‰؛پi‚¶‚م‚ë‚‚¢‚ج‚°پj‚حپA“à— پi‚¾‚¢‚èپA“Vچc
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ Œنڈٹپj‚جپA“aڈمگlپi‚ؤ‚ٌ‚¶‚ه‚¤‚ر‚ئپj‚جپA ‘ گl
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚‚낤‚اپj‚ة‚ب‚邽‚ك‚جپA’©’ى‚جچإ’لڈًŒڈ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جˆتٹK‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@ پœپ@‘O‹ك‘م‚ج’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj‚جپA“à— ‚جپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“aڈمگl‚ئ‚حپAپ@ˆتٹKپEŒـˆتˆبڈم‚جژز‚إڈ¸“a
پ@ پ@‚ً‹–‰آ‚³‚ꂽژزپ@‚âپ@ˆتٹKپEکZˆتˆبڈم‚جژز
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‘ گl‚ةڈ–”C‚³‚ꂽژز‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]کZˆتڈمپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚ë‚‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپBپ@پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کZˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈƒگˆ‘¾‰A—ïپBپ@
پ@پi‚¶‚م‚ٌ‚·‚¢‚½‚¢‚¢‚ٌ‚ê‚«پjپBپ@پs—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‘¾‰A—ïپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ڈƒگˆ‘¾‰A—ï “V•¶ٹwژ«“TپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ‘¾‰A‘¾—z—ïپA‘¾‰A —ïپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘¾‰A—ï‚ج‚P‚آپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@Œژ‚ج–‚؟Œ‡‚¯‚ًٹî‚ة‚µ‚½—ïپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ڈƒگˆ‘¾‰A—ï‚حپAپ@چٌ–]Œژپi‚³ ‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ع‚¤‚°‚آپAŒژ‚ج–‚؟Œ‡‚¯‚ج‚Pژüٹْپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ةٹî‚أ‚¢‚½—ï‚إ‚ ‚èپA—ï‚ئژہچغ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‹Gگك‚ئ‚ھ‚¸‚ê‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘¾‰A—ïپi= ‰A—ïپj‚ة‚حپAڈƒگˆ‘¾
‰A—ïپ@‚ئپ@‘¾‰A‘¾—z—ïپ@‚ھ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@Œ»چs‚جƒCƒXƒ‰ƒ€—ï‚جƒqƒWƒ…ƒ‰—ï
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚حپA‘¾‰A—ïپi= ‰A—ïپj‚جپAڈƒگˆ‘¾
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‰A—ï‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚إ‚حپA‘¾‰A—ïپi=‰A
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—ïپj‚جپA‘¾‰A‘¾—z—ï‚ھپAژg‚ي‚ꂽپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘¾‰A—ïپ@پi‰pپF‚s‚g‚dپ@‚k‚t‚m‚`‚qپ@‚b‚`‚k‚d‚m-
‚c‚`‚qپj ‚حپAپ@Œژ‚ج–‚؟Œ‡‚¯‚ًٹî‚ة‚µ‚½—ïپ@‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚éپBپ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ڈƒگˆ‘¾‰A—ï‚حپAپ@چٌ–]Œژپi‚³‚‚ع‚¤‚°‚آپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œژ‚ج–‚؟Œ‡‚¯‚ج‚Pژüٹْپj‚ةٹî‚أ‚¢‚½—ï‚إ‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پuڈƒگˆ‘¾‰A—ï‚ج—ïپvپ@پi‚P”N–ٌ‚R‚T‚S“ْپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚Pƒ–Œژ–ٌ‚Q‚XپD‚T“ْX‚P‚Qƒ–Œژپjپ@‚ئپAپ@پuژہچغ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹Gگكپvپ@پi‚P”N=‚R‚U‚TپD‚Q‚S‚Q‚Q“ْپiژہچغ‚ج‚P‘¾
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—z”Nپjپjپ@‚ئ‚حپAپ@‚P”N‚إ–ٌ‚P‚P“ْ‚¸‚ê‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘¾‰A‘¾—z—ï‚حپAپ@‘¾‰A—ï‚ج‚P‚آ‚إپAڈƒ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گˆ‘¾‰A—ï‚ً•âگ³‚µ‚½—ï‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘¾‰A‘¾—z—ï‚حپAپ@ڈƒگˆ‘¾‰A—ï‚ةپA‚P‚X”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ة‚V‰ٌپA–ٌ‚QپA‚R”N‚ة‚P‰ٌپi“xپjپA‰[Œژپi‚¤‚邤
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚أ‚«پj‚Pƒ–Œژپi‚Q‚X“ْ‚ـ‚½‚ح‚R‚O“ْپj‚ً‰ء‚¦‚ؤ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‘}“ü‚µ‚ؤپjپA”N‚P‚R‚©Œژ‚ة‚µ‚ؤپAپ@پuڈƒگˆ‘¾
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰A—ï‚ج—ïپvپ@‚ئپ@پuژہچغ‚ج‹Gگكپvپ@‚ئ‚ج‚¸‚ê
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ً’²گ®‚µ‚½پA‘¾‰A—ïپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@“ْ–{‚إ‚حپAپ@‘¾‰A—ïپi=‰A—ïپj‚جپA‘¾‰A‘¾
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—z—ï‚ًپAپi‹IŒ³Œمپj‚U‚X‚O”Nچ ‚©‚ç‚P‚W‚V‚Q”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi–¾ژ،‚T”Nپj‚ـ‚إپAژg—p‚µ‚½پB
پ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈy•êپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚ٌ‚عپjپB پs“Vچc‰ئپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ (= “Vچc‚جŒ`ژ®ڈم‚ج‹`•êپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ڈy•êپ@پi‚¶‚م‚ٌ‚عپj‚حپAپ@“Vچc‚جŒ`ژ®ڈم
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‹`•ê‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “Vچc‰ئپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈ‰ˆتپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ه‚¢پA‚»‚¢پjپB پsˆتٹKپtپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚”‚ˆ‚…پ@‚k‚ڈ‚—‚…‚“‚”پ@‚b‚ڈ‚•‚’‚”پ@‚q‚پ‚ژ‚‹پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚ڈ‚†پ@‚”‚ˆ‚…پ@‚h‚چ‚گ‚…‚’‚‰‚پ‚Œپ@‚b‚ڈ‚•‚’‚”پD
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@ڈ–ˆتپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¢پjپBپ@پsˆتٹKپtپB
پ@پi= ˆتٹK‚ًژِ—^‚·‚邱‚ئپAˆتٹK‚ة
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ–‚·‚邱‚ئپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پiپث ˆتٹKپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ڈ–ˆتپ@پi‚¶‚ه‚¢پj‚ئ‚حپAپ@ˆتٹK‚ًژِ—^‚·‚邱
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ئپAˆتٹK‚ةڈ–‚·‚邱‚ئ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ˆتٹKپi‚¢‚©‚¢پj‚حپAپ@‹كŒ»‘م“ْ–{‚إ‚ح‰h“T
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جˆت‚ًژ¦‚µپAپ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚إ‚ح’©’ىپiٹ¯ˆت‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆتٹKپAٹ¯گEپj‚إ‚جڈک—ٌ‚ًژ¦‚·پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پiپث ˆêˆتپA“ٌˆتپAژOˆتپi‚³‚ٌ‚فپjپAژlˆت
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚¢پjپAŒـˆتپAکZˆتپAژµˆتپi‚µ‚؟‚¢پjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”ھˆتپA‹مˆتپi‚‚¢پjپAڈ‰ˆتپi‚»‚¢پA‚µ‚ه‚¢پjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‹كپEŒ»‘م“ْ–{گ•{‚جپAˆتٹK—كپi‚P‚X‚Q‚U”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ§’èپA‚P‚X‚S‚V”N‰üگ³پj‚جˆتٹKپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پƒ‚P‚X‚Q‚U”Nچ پ`Œ»چفپ„پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆêˆت‚©‚ç”ھˆت‚ـ‚إ‚جپA‚P‚UˆتٹKپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ˆتٹK—ك ‚جˆتٹKپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‹ك‘م“ْ–{گ•{‚جپAڈ–ˆتڈً—لپi‚P‚W‚W‚V”Nگ§
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’èپj‚جˆتٹKپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پƒ‚P‚W‚W‚V”Nچ پ`‚P‚X‚Q‚U”Nچ پ„پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆêˆت‚©‚ç”ھˆت‚ـ‚إ‚جپA‚P‚UˆتٹKپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ڈ–ˆتڈً—ل‚جˆتٹKپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‹ك‘م“ْ–{گ•{‚جپA‘¾گٹ¯گ§‚جگEˆُ—ك
پi‚P‚W‚U‚X”Nگ§’èپj‚جˆتٹKپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پƒ‚P‚W‚U‚X”Nچ پ`‚P‚W‚W‚V”Nچ پ„ پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆêˆت‚©‚ç”ھˆتپA‹مˆتپAڈ‰ˆت‚ـ‚إ‚جپA‚Q‚OˆتٹKپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گEˆُ—ك‚جˆتٹKپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج پA’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj‚جˆتٹKپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پƒ‚V‚O‚P”Nچ پ`‚P‚W‚U‚X”Nچ پ„ پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆêˆتپ`”ھˆتپAڈ‰ˆت‚ـ‚إ‚جپA‚R‚OˆتٹKپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj ‚جˆتٹKپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@پ@ڈ–ˆتڈً—ل‚جˆتٹKپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ پi‚¶‚ه‚¢‚¶‚ه‚¤‚ê‚¢‚جˆتٹKپjپBپ@پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ڈ–ˆتڈً—لپ@پi‚¶‚ه‚¢‚¶‚ه‚¤‚ê‚¢پj‚حپAپ@‹ك‘م
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{گ•{‚جپAˆتٹK‚ب‚ا‚ً’è‚ك‚½–@—ك‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‹ك‘م“ْ–{‚جپAڈ–ˆتڈً—لپi‚P‚W‚W‚V
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”Nگ§’èپj‚ج‚P‚UˆتٹK پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@پƒ‚P‚W‚W‚V”Nچ پ`‚P‚X‚Q‚U”Nچ پ„پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚P‚W‚W‚V”Nگ§’è‚جڈ–ˆتڈً—ل‚©‚ç
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚X‚Q‚U”Nگ§’è‚جˆتٹK—ك‚ض‚ج•دچX‚ـ‚إپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‹ك‘م“ْ–{‚جپAڈ–ˆتڈً—لپi‚P‚W‚W‚V”Nگ§’èپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‚P‚UˆتٹK‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈمˆتڈ‡‚ةپAپ@گ³ˆêˆتپAپ@ڈ]ˆêˆتپAپ@گ³“ٌˆتپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ڈ]“ٌˆتپAگ³ژOˆتپAڈ]ژOˆتپAگ³ژlˆتپAڈ]ژlˆتپA
پ@پ@ پ@گ³ŒـˆتپAڈ]ŒـˆتپAگ³کZˆتپAڈ]کZˆتپAگ³ژµˆتپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ڈ]ژµˆتپAگ³”ھˆتپAڈ]”ھˆتپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ˆêˆتپA“ٌˆتپAژOˆتپAژlˆتپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ŒـˆتپAکZˆتپAژµˆتپA”ھˆتپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ˆتٹK—ك ‚جˆتٹKپAگEˆُ—ك‚جˆت
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹKپA’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj ‚جˆتٹKپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ڈ–ˆتڈً—ل‚جˆتٹKپ@ پi‚¶‚ه‚¢‚¶‚ه‚¤‚ê‚¢‚ج‚¢
‚©‚¢پj ‚حپAپ@‹ك‘م“ْ–{‚جˆتٹK‚إ‚ ‚èپA‚P‚U ˆتٹK
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ ‚èپAپ@‚P‚W‚W‚V”Nچ ‚©‚ç‚P‚X‚Q‚U”Nچ ‚ـ‚إژg
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—p‚³‚ꂽپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‹ك‘م“ْ–{‚جڈ–ˆتڈً—ل‚ج ‚P‚UˆتٹK‚حپAپ@‹كپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘م“ْ–{‚جپAگEˆُ—كپi‚P‚W‚U‚X”Nگ§ ’èپA‚Q‚OˆتٹKپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ً‰ü‚ك‚ؤپA‚P‚W‚W‚V”N‚ةگ§’肳‚êپAپ@‚P‚W‚W‚V”Nگ§
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’è‚جڈ–ˆتڈً—ل‚©‚ç‚P‚X‚Q‚U”Nگ§’è‚جˆتٹK—ك‚ض
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج•دچX‚ـ‚إپAژg—p‚³‚ꂽپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³ˆہپBپ@
پi‚µ‚ه‚¤‚ ‚ٌپjپBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚r‚g‚n‚`‚mپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ ‚P‚Q‚X‚X”Nپ[‚P‚R‚O‚Q”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚P‚Q‚X‚X”NپEگ³ˆہŒ³”NپEپ@‚SŒژ‚Q‚T“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚R‚O‚Q”NپEگ³ˆہ ‚S”NپE‚P‚PŒژ‚Q‚P“ْپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ٹ™‘qژ‘مŒمٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@ڈ³ˆہپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚ ‚ٌپA‚¶‚ه‚¤‚ ‚ٌپjپBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚r‚g‚n‚`‚mپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@پi‚P‚P‚V‚Pپ` ‚P‚P‚V‚T”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚P‚P‚V‚P”NپEڈ³ˆہŒ³”NپE‚SŒژ‚Q‚P“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚P‚P‚V‚T”NپEڈ³ˆہ ‚T”NپE‚VŒژ‚Q‚W“ْپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@•½ˆہژ‘مŒمٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@ڈمˆسپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚¢پjپBپ@پs••Œڑگ§“xپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ژهŒN‚ج‚¨‚ع‚µ‚ك‚µپE–½—كپAڈمˆت
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚جژز‚جˆسŒüپE–½—كپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ••Œڑگ§“xپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@µˆخپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚ه‚¤‚¢پjپBپ@پsگژ،ژv‘zپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ٹO“G‚ً’ا‚¢•¥‚¤‚±‚ئپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‘¸چcپi‰¤پjµˆخ”hپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈ®ˆçپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ه‚¤‚¢‚پjپBپ@ پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ‰«“ê‚ج—ًژjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ڈ®‘×پi‚µ‚ه‚¤‚½‚¢پj‚ج•ƒپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@—®‹…‰¤چ‘پi‚P‚S‚Q‚Xپ`‚P‚W‚V‚Q”Nپj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ چ‘‰¤پEڈ®ˆç‰¤پiچفˆت‚P‚W‚R‚Tپ`‚S‚V”NپjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‘و“ٌڈ®ژپ‰¤“‚P‚W‘مچ‘‰¤پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ڈ®ˆç پi‚µ‚ه‚¤‚¢‚پj‚حپAپ@ڈ®‘×پi‚µ‚ه‚¤‚½‚¢پj‚ج•ƒ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ ‚èپAپ@—®‹…‰¤چ‘پi‚P‚S‚Q‚Xپ`‚P‚W‚V‚Q”Nپj‚جچ‘‰¤پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@ڈ®ˆç‰¤پiچفˆت‚P‚W‚R‚Tپ`‚S‚V”Nپj‚إ‚ ‚èپAپ@‘و“ٌڈ®ژپ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‰¤“‚P‚W‘مچ‘‰¤‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@پ@گ³ˆêˆتپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پi‚µ‚ه‚¤‚¢‚؟‚¢پjپBپ@پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚”‚ˆ‚…پ@‚r‚…‚ژ‚‰‚ڈ‚’پ@‚P‚“‚”پ@‚b‚ڈ‚•‚’‚”پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚q‚پ‚ژ‚‹پC ‚t‚گ‚گ‚…‚’پ@‚f‚’‚پ‚„‚… ‚ڈ‚†پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚”‚ˆ‚…پ@‚h‚چ‚گ‚…‚’‚‰‚پ‚Œپ@‚b‚ڈ‚•‚’‚”پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ˆتٹK—ك‚جˆتٹKپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پƒ‚P‚X‚Q‚U”Nچ پ`Œ»چف پ„پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ڈ–ˆتڈً—ل‚جˆتٹKپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پƒ‚P‚W‚W‚V”Nچ پ`‚P‚X‚Q‚U”Nچ پ„پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘¾گٹ¯گ§‚جگEˆُ—ك‚جˆتٹK پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پƒ‚P‚W‚U‚X”Nچ پ`‚P‚W‚W‚V”Nچ پ„پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj‚جˆتٹKپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پƒ‚V‚O‚P”Nچ پ`‚P‚W‚U‚X”Nچ پ„پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ˆêˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج پA’©’ى‚جˆتٹK‚ج‚R‚OˆتٹKپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ڈمˆتڈ‡‚ةپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ³ˆêˆتپAپ@ڈ]ˆêˆتپAپ@گ³“ٌˆتپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ]“ٌˆتپAپ@گ³ژOˆتپAپ@ڈ]ژOˆتپAپ@گ³ژlˆتڈمپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ³ژlˆت‰؛پAڈ]ژlˆتڈمپAڈ]ژlˆت‰؛پAگ³ŒـˆتڈمپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ³Œـˆت‰؛پAڈ]ŒـˆتڈمپAڈ]Œـˆت‰؛پAگ³کZˆتڈمپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ³کZˆت‰؛پAڈ]کZˆتڈمپAڈ]کZˆت‰؛پAگ³ژµˆتڈمپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ³ژµˆت‰؛پAڈ]ژµˆتڈمپAڈ]ژµˆت‰؛پAگ³”ھˆتڈمپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ³”ھˆت‰؛پAڈ]”ھˆتڈمپAڈ]”ھˆت‰؛پA‘هڈ‰ˆتڈمپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘هڈ‰ˆت‰؛پAڈڈ‰ˆتڈمپAڈڈ‰ˆت‰؛پB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@µˆخ”hپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚¢‚حپjپB پsگژ،ژv‘zپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@–‹––پAµˆخ‰^“®پi‚¶‚ه‚¤‚¢‚¤‚ٌ‚ا‚¤پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹOچ‘گ¨—ح‚ً•گ—ح‚إ”rڈœ‚·‚é‰^“®پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ًچs‚¤گlپiژزپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@پi—لپjپ@“yچ²”ثژm‚جپA•گژs
”¼•½‘¾پB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@µˆخ”h‚ئٹJچ‘”h‚ج‘خ—§پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚ه‚¤‚¢‚ح‚ئ‚©‚¢‚±‚‚ح‚ج‚½‚¢‚è‚آپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پs–‹––‚جگ‘ˆ”h”´پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚P‚W‚T‚Rپ`‚P‚W‚U‚V”Nچ پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث –‹––“ْ–{گژ،پEگ‘ˆ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ •د‘Jˆê——•\پjپB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@’ه‰iپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚ه‚¤‚¦‚¢پjپBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚i‚n‚d‚hپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ ‚P‚Q‚R‚Q”Nپ[‚P‚Q‚R‚R”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚P‚Q‚R‚Q”NپE’ه‰iŒ³”NپE‚SŒژپ@‚Q“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚Q‚R‚R”NپE’ه‰i ‚Q”NپE‚SŒژ‚P‚T“ْپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ٹ™‘qژ‘م‘Oٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@‘‘‰€پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚¦‚ٌپj پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پs“y’nگl–¯“ژ،گ§“xپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚Wپ`‚P‚Uگ¢‹IپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‹M‘°پEژ›ژذ“™‚ھژx”z‚·‚é
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ —جˆوپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈ®‰~پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚¦‚ٌپjپBپ@پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ‹àٹغپi‚©‚ب‚ـ‚éپjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ƒNپ[ƒfƒ^پ[‚ة‚و‚èپA‰¤ˆت‚ة‚آ‚«پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—®‹…‰¤چ‘‚جڈ®ژپ‘و“ٌ‰¤’©‚ً‚½‚ؤ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث —®‹…‰¤چ‘پA
‰«“ê‚ج—ًژjپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@‘‘‰€پEŒِ—جگ§پBپ@
پ@پi‚µ‚ه‚¤‚¦‚ٌپE‚±‚¤‚è‚ه‚¤‚¹‚¢پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پs“y’nگl–¯“ژ،گ§“xپtپB
پ@پi‚P‚Oپ`‚P‚Uگ¢‹IپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ْ–{‚ج“y’nگl–¯“ژ،گ§“xپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@‘‘‰€گ§“xپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚¦‚ٌ‚¹‚¢‚اپj پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پs“y’nگl–¯“ژ،گ§“xپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚Oپ`‚P‚Uگ¢‹IپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³‰پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚¨‚¤پjپBپ@پ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚r‚g‚n‚nپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ ‚P‚Q‚W‚W”Nپ[‚P‚Q‚X‚R”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚P‚Q‚W‚W”NپEگ³‰Œ³”NپE‚SŒژ‚Q‚W“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚P‚Q‚X‚R”NپEگ³‰ ‚U”NپE‚WŒژپ@‚T“ْپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ٹ™‘qژ‘مŒمٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@’ه‰پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚¨‚¤پjپBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚i‚n‚nپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ ‚P‚Q‚Q‚Q”Nپ[‚P‚Q‚Q‚S”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚P‚Q‚Q‚Q”NپE’ه‰Œ³”NپEپ@‚SŒژ‚P‚R“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚P‚Q‚Q‚S”NپE’ه‰ ‚R”NپE‚P‚PŒژ‚Q‚O“ْپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ٹ™‘qژ‘م‘Oٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@ڈ³‰پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚¨‚¤پj پBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚i‚n‚nپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ ‚P‚U‚T‚Q”Nپ[‚P‚U‚T‚T”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚P‚U‚T‚Q”NپEڈ³‰Œ³”NپE‚XŒژ‚P‚W“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚P‚U‚T‚T”NپEڈ³‰ ‚S”NپE‚SŒژ‚P‚R“ْپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@چ]Œثژ‘م‘Oٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³‰أپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚©پjپBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚r‚g‚n‚j‚`پ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ ‚P‚Q‚T‚V”Nپ[‚P‚Q‚T‚X”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚P‚Q‚T‚V”NپEگ³‰أŒ³”NپE‚RŒژ‚P‚S“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚P‚Q‚T‚X”NپEگ³‰أ ‚R”NپE‚RŒژ‚Q‚U“ْپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ٹ™‘qژ‘م’†ٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@ڈٍٹCپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚ه‚¤‚©‚¢پjپB پ@پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= •½گ´گ·پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@•½گ´گ·‚جپAڈo‰ئŒم‚جŒآگl–¼پB
پ@پ@پ@پ@پiپث •½گ´گ·پjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈ¼‰؛‘؛ڈmپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚©‚»‚ٌ‚¶‚م‚پjپBپ@پsژ„ڈmپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ڈ¼‰؛‘؛ڈm‚حپA”‹پi‚ح‚¬پAژRŒûŒ§پE”‹پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ة‚ ‚èپA‚P‚W‚T‚V”N‚©‚ç‚P‚W‚T‚W”N ‚ـ‚إ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹْٹش‚ةپA‹g“c ڈ¼‰A‚ھچu‹`‚ًچs‚ء‚½پAژ„
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈm‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‹g“c ڈ¼‰A‚جڈf•ƒپE‹ت–ط •¶”Vگi‚ھپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚W‚S‚Q”N‚ةپAژ„ڈm‚جڈ¼‰؛‘؛ڈmپ@پi‚P‚W‚S‚Q
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”Nپ`‚P‚W‚T‚W”NپA‚P‚W‚U‚X”Nپ`‚P‚W‚V‚U”Nپj‚ً
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹJگف‚µپAپ@‚P‚W‚V‚U”Nپi–¾ژ،‚X”Nپj‚ـ‚إ‰^‰c
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚·‚éپBپ@
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@’هٹدپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚ھ‚ٌپjپBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚i‚n‚f‚`‚mپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‚W‚T‚X”Nپ[‚W‚V‚V”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚W‚T‚X”NپE’هٹد Œ³”NپE‚SŒژ‚P‚T“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚W‚V‚V”NپE’هٹد‚P‚X”NپE‚SŒژ‚P‚U“ْپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@•½ˆہژ‘م‘Oٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@ڈ³‹vپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚«‚م‚¤پjپBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚i‚n‚j‚x‚tپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ ‚P‚Q‚P‚X”Nپ[‚P‚Q‚Q‚Q”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚P‚Q‚P‚X”NپEڈ³‹vŒ³”NپE‚SŒژ‚P‚Q“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚Q‚Q‚Q”NپEڈ³‹v ‚S”NپE‚SŒژ‚P‚R“ْپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ٹ™‘qژ‘م‘Oٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@ڈ³‹v‚ج—گپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚«‚م‚¤‚ج‚ç‚ٌپjپBپ@پsگي‚¢پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‚P‚Q‚Q‚P”N‚ةپAپ@ڈ³‹v‚ج—گ‚حپA’©
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ’ى•û‚ھپAپ@ٹ™‘q–‹•{•û‚ة‘خ‚µ‚ؤ‹N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚±‚µ‚½گي‚¢پBپ@
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³ŒcپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚«‚ه‚¤پA‚µ‚ه‚¤‚¯‚¢پjپBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚r‚g‚n‚j‚x‚nپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï‚ج“ٌڈd”Nچ†‘¶—§پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@Œم‘çŒيپEٹ™‘q–‹•{‹£چ‡“ٌڈd
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‚P‚R‚R‚Q”Nپ[‚P‚R‚R‚R”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ŒُŒµپi‚±‚¤‚²‚ٌپj“Vچcپ@پiٹ™‘q–‹ •{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—i—§پAژ–¾‰@“پi‚¶‚ف‚ه‚¤‚¢‚ٌ‚ئ‚¤پjپj•û
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚R‚R‚Q”NپEگ³ŒcŒ³”NپE‚SŒژ‚Q‚W“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚R‚R‚R”NپEگ³Œc ‚Q”NپE‚TŒژ‚Q‚T“ْپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ٹ™‘qژ‘مŒمٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@پi’چˆسپjپ@“¯ژٹْ‚ةپAŒم‘çŒيپi‚²‚¾‚¢‚²پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“Vچcپ@پi‘هٹoژ›“پi‚¾‚¢‚©‚‚¶‚ئ‚¤پjپjپ@•û‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—ï”Nچ†‚جپAŒ³چOپi‚°‚ٌ‚±‚¤پjŒ³”Nپ`‚S”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚R‚R‚Pپ`‚P‚R‚R‚S”Nپjپ@‚à‘¶—§‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@گ³Œc”Nچ†پiگ³ŒcŒ³”Nپ`‚Q”NپA‚P‚R‚R‚Qپ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚R‚R‚R”Nپj‚و‚èŒم‚حپAپ@ŒُŒµپi‚±‚¤‚²‚ٌپj“Vچc
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiٹ™‘q–‹•{—i—§پAژ–¾‰@“ پj•û‚حپA—ï”Nچ†
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•زگ¬‚ً’†ژ~‚·‚éپBپ@‚P‚R‚R‚R”N‚ةپA–kڈًژ·Œ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جٹ™‘q–‹•{پi‚P‚P‚X‚Qپ`‚P‚R‚R‚R”Nپj‚ھ–إ–S‚µ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚½‚½‚كپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ŒُŒµپi‚±‚¤‚²‚ٌپj“Vچcپ@پiٹ™‘q–‹•{—i—§پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ–¾‰@“پi‚¶‚ف‚ه‚¤‚¢‚ٌ‚ئ‚¤پjپj•û‚ج—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰أ—ïپi‚©‚è‚ل‚پjپ@پثپ@Œ³“؟پi‚°‚ٌ‚ئ‚پjŒ³
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”Nپ`‚S”Nپ@پi‚P‚R‚Q‚Xپ`‚P‚R‚R‚Q”Nپjپ@پثپ@گ³Œc
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚«‚ه‚¤پjŒ³”Nپ`‚Q”Nپ@پi‚P‚R‚R‚Qپ`‚P‚R‚R
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚R”Nپjپثپ@—ï”Nچ†•زگ¬’†ژ~پB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@’ه‹پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚«‚ه‚¤پj پBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚i‚n‚j‚x‚nپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ ‚P‚U‚W‚S”Nپ[‚P‚U‚W‚W”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚P‚U‚W‚S”NپE’ه‹Œ³”NپE‚QŒژ‚Q‚P“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚P‚U‚W‚W”NپE’ه‹ ‚T”NپE‚XŒژ‚R‚O“ْپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@چ]Œثژ‘م‘Oٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ ’ه‹إپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚ه‚¤‚¬‚ه‚¤پ^‚ؤ‚¢‚¬‚ه‚¤پjپB
پ@پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@’ه‹إپ@پi‚¶‚ه‚¤‚¬‚ه‚¤پ^‚ؤ‚¢‚¬‚ه‚¤پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹ™‘q–@ˆَپAگ¶–v”NپF‚P‚P‚W‚U”Nپ`‚P‚Q
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚R‚P”Nپj ‚حپAپ@Œ¹—ٹ’©‚ج’jژq‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@’ه‹إ‚حپAپ@Œ¹—ٹ’©‚ئپA‘هگi‹اپi‚¾
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¢‚µ‚ٌ‚ج‚آ‚ع‚ثپj‚ئ‚جٹش‚ج’jژq‚إ‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@’ه‹إ‚حپAپ@گ”‚¦”N‚Vچخ‚إڈo‰ئ‚µ‚ؤپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•§‘m‚ئ‚ب‚éپBپ@چ‚–ىژR‚ة‚ؤپAگ”‚¦”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚S‚Uچخ‚إژ€‹ژ‚·‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³‹مˆتپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚‚¢پjپBپ@پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ‹مˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈ«ŒRپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚®‚ٌپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پs•گٹ¯پi•گگlپjپA•گژm‚جگg•ھپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ŒR‚ج“—¦ژزپA•گٹ¯پi•گگlپj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژٌ’·پAگھˆخ‘هڈ«ŒRپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ڈ«ŒR‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒR‚ج“—¦ژز‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ڈ«ŒR‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•گٹ¯‚جژٌ’·‚جٹ¯گEپiگE–¼پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@Œأ‘م“ْ–{‚إ‚حپAڈ«ŒR‚ئ‚حپA’©’ى
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جگھ“¢پA‹V‰qپAچsچKژ‚ج—صژ‚ج•گٹ¯
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جژٌ’·‚جŒR–±ٹ¯گE‚إ‚ ‚ء‚½پBپ@Œأ‘م
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{‚إپAڈ«ŒR‚ج‚P‚آ‚ةپAگھˆخ‘هڈ«ŒR
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ھ‚ ‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ڈ«ŒRپiگھˆخ‘هڈ«ŒRپj‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’©’ى‚ھگف‚¯‚½ڈ«ŒR‚ج‚P‚آ‚إپA
گھˆخ‘هڈ«ŒR‚ج•تڈجپA—ھڈج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ڈ«ŒRپiگھˆخ‘هڈ«ŒRپj‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•گ‰ئ‚ج“ڈ—ہپi‚ئ‚¤‚è‚ه‚¤پA“—¦ژزپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“—جپA“ھ—جپj‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ ڈ«ŒRپiگھˆخ‘هڈ«ŒRپj‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹ™‘q–‹•{‚جٹeڈ«ŒRپAŒڑ•گٹْ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جŒى—اگe‰¤پi‚à‚è‚و‚µ‚µ‚ٌ‚ج‚¤پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘ه“ƒ‹{پi‚¨‚¨‚ئ‚¤‚ج‚ف‚âپjپjپAژ؛’¬پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–‹•{‚âچ]Œث–‹•{‚جٹeڈ«ŒR‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ڈ«ŒRپiگھˆخ‘هڈ«ŒRپj‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–‹•{‚جژٌ’·‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹ™‘q–‹•{پAژ؛’¬–‹•{پAچ]Œث
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–‹•{پA‚جڈ«ŒR‚ب‚ا‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@گھˆخ‘هڈ«ŒRپ@پi‚¹‚¢‚¢‚½‚¢‚µ‚ه‚¤
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚®‚ٌپA•ت–¼پFگھˆخڈ«ŒRپjپj‚حپAپ@“ق—اژ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘م‚©‚çچ]Œثژ‘م‚ـ‚إپA’©’ى‚©‚ç”C–½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚³‚ꂽپA•گٹ¯پi•گ گlپj‚جژٌ’·‚جٹ¯گE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiگE–¼پj‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ڈ«ŒR‚ج‚P‚آ‚جپAگھˆخ‘هڈ«ŒR‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“–ڈ‰‚حپA“ق—اژ‘مپE•½ˆہژ‘مڈ‰ٹْ‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚حپA—¤‰œپi‚ق‚آپA“Œ–k’n•ûپj‚ج‰عˆخ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¦‚¼پj“¢”°‚ج‚½‚ك‚ج’©’ى‚ج—صژ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒR“—¦ژز‚جٹ¯گE‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚»‚جŒمپAگھˆخ‘هڈ«ŒR‚حپAٹ™‘q
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ‘م‚و‚èپA•گ‰ئ‚ج“ڈ—ہپi‚ئ‚¤‚è‚ه‚¤پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“—¦ژزپA“—جپA“ھ—جپj‚ج’nˆتپA‚ـ‚½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚حپA–‹•{‚جژٌ’·‚ج’nˆت‚ًˆس–،‚·‚é
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚و‚¤‚ة‚ب‚éپBپ@
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈ«ŒR‰ئپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚®‚ٌ‚¯پjپBپ@پs–‹•{پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ‘«—کڈ«ŒR‰ئپA“؟گىڈ«ŒR‰ئپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ڈ«ŒR‰ئ‚ئ‚حپAپ@‘«—کڈ«ŒR‰ئپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“؟گىڈ«ŒR‰ئ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‘«—کڈ«ŒR‰ئ‚ئ‚حپAژ؛’¬–‹•{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جڈ«ŒRگE‚ةڈA”C ‚µ‚½پAژ؛’¬ژ‘م
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‘«—کژپ–{‰ئپiڈ@‰ئپj‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@“؟گىڈ«ŒR‰ئ‚ئ‚حپAچ]Œث–‹•{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جڈ«ŒRگE‚ةڈA”C ‚µ‚½ پAچ]Œثژ‘م
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج“؟گىژپ–{‰ئپiڈ@‰ئپj‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ڈ«ŒRپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “؟گى ڈ«ŒR‰ئپA‘«—ک ڈ«ŒR‰ئپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “؟گى ژپپA‘«—ک ژپپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ڈ«ŒR‰ئپ@پi‚µ‚ه‚¤‚®‚ٌ‚¯پj‚ئ‚حپAˆê”ت
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“I‚ةپA’·‚–‹•{‚جڈ«ŒRگE‚ةڈA”C‚µ‚½•گ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰ئ‚إ‚ ‚èپAپ@‘«—کڈ«ŒR‰ئپ@‚âپ@“؟گىڈ«ŒR
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰ئ‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ڈ«ŒR‰ئپ@پi‚µ‚ه‚¤‚®‚ٌ‚¯پj‚ئ‚حپA–‹•{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جڈ«ŒRگE‚ةڈA”C ‚µ‚½ژ‘م‚ج‘«—کژپ‚â
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“؟گىژپ‚ج–{‰ئپiڈ@‰ئپj‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@‘«—کڈ«ŒR‰ئپ@پi‚ ‚µ‚©‚ھ‚µ‚ه‚¤‚®
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚ٌ‚¯پj‚ئ‚حپAپ@ژ؛’¬–‹•{پi= ‘«—ک–‹•{پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚جڈ«ŒRگE‚ةڈA”C ‚µ‚½پAژ؛’¬ژ‘م‚ج‘«
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—کژپ–{‰ئپiڈ@‰ئپj‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@“؟گىڈ«ŒR‰ئپ@پi‚ئ‚‚ھ‚ي‚µ‚ه‚¤‚®‚ٌ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¯پj‚ئ‚حپAپ@چ]Œث–‹•{پi= “؟گى–‹•{پj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ«ŒRگE‚ةڈA”C‚µ‚½پAچ]Œثژ‘م‚ج“؟گى
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژپ–{‰ئپiڈ@‰ئپj‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³Œ³پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚°‚ٌپjپBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚r‚g‚n‚f‚d‚mپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ ‚P‚Q‚T‚X”Nپ[‚P‚Q‚U‚O”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚P‚Q‚T‚X”NپEگ³Œ³Œ³”NپE‚RŒژ‚Q‚U“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚Q‚U‚O”NپEگ³Œ³ ‚Q”NپE‚SŒژ‚P‚R“ْپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ٹ™‘qژ‘م’†ٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@ڈ³Œ³پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚°‚ٌپjپBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚i‚n‚f‚d‚mپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‚P‚Q‚O‚V”Nپ[‚P‚Q‚P‚P”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚P‚Q‚O‚V”NپEڈ³Œ³Œ³”NپE‚P‚OŒژ‚Q‚T“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚Q‚P‚P”NپEڈ³Œ³ ‚T”NپEپ@‚RŒژپ@‚X“ْپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ٹ™‘qژ‘م‘Oٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@’هŒ³پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚°‚ٌپjپBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚i‚n‚f‚d‚mپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‚X‚V‚U”Nپ[‚X‚V‚W”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚X‚V‚U”NپE’هŒ³Œ³”NپE‚VŒژ‚P‚R“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚X‚V‚W”NپE’هŒ³ ‚R”NپE‚P‚PŒژ‚Q‚X“ْپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@•½ˆہژ‘م’†ٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³ŒـˆتپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚²‚¢پjپB پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ŒـˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³Œـˆت‰؛پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi ‚µ‚ه‚¤‚²‚¢‚ج‚°پjپB پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ŒـˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³ŒـˆتڈمپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi ‚µ‚ه‚¤‚²‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپB پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ŒـˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@ڈمچcپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پjپBپ@پs“Vچc‰ئپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ‰@پi‚¢‚ٌپjپAŒ³“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ڈمچcپi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پj‚ئ‚حپAپ@‘O“Vچc‚إ‚ ‚èپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–@‰¤‚ئ‚حپAڈo‰ئ‚µ‚½‘O“Vچc‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث –@‰¤پjپB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@ڈيچ‚‰@پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤‚¢‚ٌپjپBپ@پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@ پi= ‚¨ڈ‰پAڈ‰پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@گَˆنژOژo–…پ@پi= ’ƒپXپAڈ‰پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ چ]پi‚؟‚؟‚لپA‚ح‚آپA‚²‚¤پjپjپ@‚جˆêگlپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ‚¨ڈ‰ ‚¨‚ح‚آپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@ڈمچcگŒ پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤‚¹‚¢‚¯‚ٌپjپBپ@پs گŒ پEگ•{پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= ‰@گگŒ پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‚P‚O‚W‚U”Nچ پ`‚P‚P‚T‚U”Nچ پB
پ›پ@”’‰حڈمچc‚ئ’¹‰HڈمچcپBپ@
پ@پ@ پiپث “ْ–{‚جگŒ پEگ•{پjپB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@ڈمچcگژ،پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤‚¹‚¢‚¶پjپBپ@پsگژ،Œ`‘شپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ‰@گگژ،پjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈ¬چ‘ژٌ’·گژ،
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚±‚‚µ‚م‚؟‚ه‚¤‚¹‚¢‚¶پjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پs گژ،Œ`‘شپtپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‹IŒ³‘O‚Pگ¢‹Iپ`‹IŒ³پiŒمپj‚Tگ¢‹IپjپB
پiپث “ْ–{‚جگژ،Œ`‘شپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈ¬چ‘•ھ—§ژ©ژ،گ§پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚±‚‚ش‚ٌ‚è‚آ‚¶‚؟‚¹ ‚¢پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پs“y’nگl–¯“ژ،گ§“xپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‹IŒ³‘O‚Pگ¢‹Iپ`‹IŒ³پiŒمپj‚Tگ¢‹IپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ْ–{‚ج“y’nگl–¯“ژ،گ§“xپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈ¬چ‘•ھ—§گŒ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ه‚¤‚±‚‚ش‚ٌ‚è‚آ‚¹‚¢‚¯‚ٌپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پs“y’nگl–¯“ژ،گ§“xپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ڈ¬چ‘•ھ—§ژ©ژ،گŒ پj پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‘O‚Pگ¢ ‹Iپ`‹IŒ³پiŒمپj‚Tگ¢‹Iپj پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ْ–{‚جگŒ پEگ•{پjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈ¬چ‘•ھ—§ژ©ژ،گŒ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ه‚¤‚±‚‚ش‚ٌ ‚è‚آ‚¶ ‚؟‚¹‚¢‚¯‚ٌپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پsگژ،Œ`‘شپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ڈ¬چ‘•ھ—§گŒ پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‹IŒ³‘O‚Pگ¢‹Iپ`‹IŒ³پiŒمپj‚Tگ¢‹IپjپB پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ْ–{‚جگŒ پEگ•{پjپB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@پ@ڈمگ¼–ه‰@پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚³‚¢‚à‚ٌ‚¢‚ٌپjپBپsگl–¼پtپB
پ@ پi= “ژq“àگe‰¤پi‚ق‚ث‚±‚ب‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚µ‚ٌ‚ج‚¤پjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پiپث ’¹‰HڈمچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پi‚P‚P‚Q‚Uپ|‚P‚P‚W‚X”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ڈمگ¼–ه‰@‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’¹‰Hڈمچc‚جژںڈ—‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@پ@گ³ژOˆتپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚³‚ٌ‚فپjپBپ@پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پiپث ژOˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈ®ژپپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚µپjپBپ@پs—®‹…‰¤چ‘پtپB
پ›پ@—®‹…‰¤چ‘پi‚P‚S‚Q‚Xپ`‚P‚W‚V‚Q”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‰¤‘°پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ‰«“ê‚ج—ًژjپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@àِژqپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚µپA‚½‚ـ‚±پjپBپ@پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= “،Œ´ àِژqپi‚س‚¶‚ي‚ç‚ج‚µ‚ه‚¤‚µپE‚½‚ـ
‚±پjپAپ@‘زŒ«–ه‰@ پi‚½‚¢‚¯‚ٌ‚à‚ٌ‚¢‚ٌپjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘زŒ«–ه‰@àِژqپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@’¹‰Hڈمچc‚جگ³ژ؛•vگlپi’†‹{پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@گ’“؟ڈمچcپAŒم”’‰حڈمچc‚جگ¶•êپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “،Œ´ àِژqپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@ڈمژmپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚µپjپBپ@پs•گژm‚جگg•ھپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= چ]Œثژ‘م‚ج“yچ²”ث‚جڈم‹‰•گژmپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚Vپ`‚P‚Xگ¢‹IپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@ پ،پ@ڈمژmپi‚¶‚ه‚¤‚µپj‚ئ‚حپAپ@چ]Œثژ‘م‚جپA“yچ²”ث
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جڈم‹‰•گژm‚إ‚ ‚èپAڈم‹‰”ثژm‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@ پ،پ@“yچ²”ث‚ج•گژm‚ة‚حپAڈمژmپi‚¶‚ه‚¤‚µپj‚ئ‰؛ژm
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚©‚µپj‚جگg•ھ‚ھ‚ ‚èپAپ@–‹––‚ةپAچâ–{—´”nپAٹâ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چè–ي‘¾کY‚ب‚ا‚حپA‰؛‹‰•گژm‚ج‰؛ژm‚إ‚ ‚èپAŒم“،
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈغ“ٌکY‚ب‚ا‚حپAڈم‹‰”ثژm‚جڈمژm‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³ژ،پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚¶پjپBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚r‚g‚n‚i‚hپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@ ‚P‚P‚X‚X”Nپ[‚P‚Q‚O‚P”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پœپ@‚P‚P‚X‚X”NپEگ³ژ،Œ³”NپE‚SŒژ‚Q‚V“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@ ‚P‚Q‚O‚P”NپEگ³ژ، ‚R”NپE‚QŒژ‚P‚R“ْپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پœپ@ٹ™‘qژ‘م‘Oٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@’هژ،پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚¶پA‚ؤ‚¢‚¶پjپBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚i‚n‚i‚hپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‚P‚R‚U‚Q”Nپ[‚P‚R‚U‚W”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ى–k’©‹£چ‡“ٌڈd”Nچ†پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï‚ج“ٌڈd”Nچ†‘¶—§پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@“ى–k’©‹£چ‡“ٌڈd”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@–k’©پ@پiژ–¾‰@“پj•û‚ج—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚R‚U‚Q”NپE’هژ،Œ³”NپE‚XŒژ‚Q‚R“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚R‚U‚W”NپE’هژ، ‚V”NپE‚QŒژ‚P‚W“ْپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ژ؛’¬ژ‘م‘Oٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@پi’چˆسپjپ@“¯ژٹْ‚ةپA“ى’©پ@پi‘هٹoژ›“پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œم‘çŒي“VچcŒn“پj•û‚ج—ï”Nچ†‚جپAگ³•½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚ض‚¢پjŒ³”Nپ`‚Q‚T”Nپi‚P‚R‚S‚Uپ`‚P‚R
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚V‚O”Nپjپ@‚à‘¶—§‚·‚éپBپ@
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³ژlˆتپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚¢پjپB پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ژlˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³ژlˆت‰؛پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚¢‚ج‚°پjپB پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ژlˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³ژlˆتڈمپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپB پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ژlˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@–؛ژq‘àپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚µ‚½‚¢پj پB پsگي“¬•”‘àپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ‰ï’أ”ثپE–؛ژq‘àپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‰ï’أگي‘ˆ‚إ•±گي‚µ‚½ڈ—گ«•؛
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ •”‘àپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‰ï’أگي‘ˆپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈ®ژپ‘وˆê‰¤’©پB
پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚¾‚¢ ‚¢‚؟‚¨‚¤‚؟‚ه‚¤پjپB پs‰¤’©پtپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚S‚Q‚Xپ` ‚P‚S‚V‚O”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‰«“ê‚ج—®‹…‰¤چ‘‚ج‰¤’©پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث —®‹…‰¤چ‘پA‰«“ê‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@—ًژjپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈ®ژپ‘و“ٌ‰¤’©پB
پ@ پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚¾‚¢‚ة‚¨‚¤‚؟‚ه‚¤پjپB پs‰¤’©پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚S‚V‚Oپ`‚P‚W‚V‚Q”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‰«“ê‚ج—®‹…‰¤چ‘‚ج‰¤’©پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث —®‹…‰¤چ‘پA‰«“ê‚ج
پ@پ@—ًژjپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³ژµˆتپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚؟‚¢پjپB پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ژµˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@
پ›پ@‚µ‚هپ@پ@گ³ژµˆت‰؛پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚؟‚¢‚ج‚°پjپB پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ژµˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³ژµˆتڈمپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚؟‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپBپsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ژµˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@ڈمڈBپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚µ‚م‚¤پjپBپ@پs‹Œ’nˆو–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ڈم–ىچ‘پi ‚±‚¤‚¸‚¯‚ج‚‚ةپjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپà Œ»پEŒQ”nŒ§‚ج‘ٹ“–’nˆوپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‘O‹ك‘م‹Œ’nˆو–¼‚ج‹Œچ‘–¼پi—ك
گ§چ‘پj‚ج•تڈجپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ڈم–ىچ‘پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ŒQ”nŒ§پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹Œچ‘پi= —كگ§چ‘پjپjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹Œ’nˆو–¼پA’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث “ْ–{‚ج’n–¼پjپB
پ،پ@ڈمڈBپ@پi‚¶‚ه‚¤‚µ‚م‚¤پA= ڈم–ىچ‘پi ‚±‚¤‚¸‚¯
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‚‚ةپjپj‚حپAپ@“ŒژR “¹پi‚ئ‚¤‚³‚ٌ‚ا‚¤پjپE‹ŒچL
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆو’n•û‚ة‘®‚µپAپ@Œ»پEٹض“Œ’n•û‚جپAŒ»پEŒQ”n
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@Œ§‚ة‘ٹ“–‚·‚é’nˆو‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@ ڈéڈBپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚ه‚¤‚µ‚م‚¤پjپBپ@پs‹Œ’nˆو–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= ژRڈéچ‘پi ‚â‚ـ‚µ‚ë‚ج‚‚ةپjپj پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپà Œ»پE‹“s•{“ى•”‚ج‘ٹ“–’nˆوپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi—¥—كگ§’èŒمپEŒأ‘مپE’†گ¢پE‹كگ¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ْ–{پE‹Œ’nˆو–¼‚ج‹Œچ‘–¼پi—كگ§
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ چ‘پj‚ج•تڈجپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ژRڈéچ‘پjپBپ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹“s•{پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹Œچ‘پi= —كگ§چ‘پjپjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹Œ’nˆو–¼پA’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث “ْ–{‚ج’n–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ڈéڈBپi ‚¶‚ه‚¤‚µ‚م‚¤پjپAژRڈBپi‚³‚ٌ‚µ‚م‚¤پjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@è´ڈBپi‚و‚¤‚µ‚م‚¤پj‚حپA پ@—¥—كگ§’èŒمپEŒأ‘مپE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’†گ¢پE‹كگ¢“ْ–{پE‹Œ’nˆو–¼‚جپA‹Œچ‘–¼پi—ك
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ§چ‘پjگ³ژ®–¼‚جپAژRڈé چ‘پ@پi‚â‚ـ‚µ‚ë ‚ج‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ةپjپ@‚ج •تڈج‚إ‚ ‚éپB
پ@پœپ@ڈéڈBپi= ژRڈéچ‘پj‚ح پAپ@‹E“àپi‚«‚ب‚¢پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ Œـ‹EپjپE‹ŒچLˆو’n•û‚ة‘®‚µپAپ@Œ»پE‹ك‹E’n•û
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@‚جپAŒ»پE‹“s•{“ى•”‚ة‘ٹ“–‚·‚é ’nˆو‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@ ”ZڈBپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚ه‚¤‚µ‚م‚¤پA‚ج‚¤‚µ‚م‚¤پjپBپs‹Œ’nˆو–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= ”ü”Z چ‘پi ‚ف‚ج ‚ج‚‚ةپjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپà Œ»پEٹٍ•ŒŒ§“ى•”‚ج‘ٹ“–’nˆوپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi—¥—كگ§’èŒمپEŒأ‘مپE’†گ¢پE‹كگ¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ْ–{پE‹Œ’nˆو–¼‚ج‹Œچ‘–¼پi—كگ§
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ چ‘پj‚ج•تڈجپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ”ü”Z چ‘پjپBپ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ٹٍ•ŒŒ§پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹Œچ‘پi= —كگ§چ‘پjپjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹Œ’nˆو–¼پA’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث “ْ–{‚ج’n–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@”ZڈBپ@پi ‚¶‚ه‚¤‚µ‚م‚¤پA‚ج‚¤‚µ‚م‚¤پj‚حپA پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—¥—كگ§’èŒمپEŒأ‘مپE’†گ¢پE‹كگ¢“ْ–{پE‹Œ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’nˆو–¼‚جپA‹Œچ‘ –¼پi—كگ§چ‘پjگ³ژ®–¼‚جپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”ü”Z چ‘پ@پi‚ف‚ج ‚ج‚‚ةپj‚ج •تڈج‚إ‚ ‚éپB
پ@پœپ@”ZڈBپi= ”ü”Z چ‘پj‚حپAپ@“ŒژR“¹پi‚ئ‚¤‚³
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚ٌ‚ا‚¤پjپE‹ŒچLˆو’n•û‚ة‘®‚µپAپ@Œ»پE’†•”’n
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@•û‚جپAŒ»چف‚جٹٍ•ŒŒ§“ى•”‚ة‘ٹ“–‚·‚é ’nˆو
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@ ڈيڈBپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚µ‚م‚¤پjپBپ@پs‹Œ’nˆو–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= ڈي—¤ چ‘پi ‚ذ‚½‚؟ ‚ج‚‚ةپjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپà Œ»پEˆïڈ錧‚ج‘ٹ“–’nˆوپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi—¥—كگ§’èŒمپEŒأ‘مپE’†گ¢پE‹كگ¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ْ–{پE‹Œ’nˆو–¼‚جپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‹Œچ‘–¼پi—كگ§چ‘پj‚ج•تڈجپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ڈي—¤ چ‘پjپBپ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ˆïڈ錧پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹Œچ‘پi= —كگ§چ‘پjپjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹Œ’nˆو–¼پA’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث “ْ–{‚ج’n–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ڈيڈBپ@پi‚¶‚ه‚¤‚µ‚م‚¤پj‚حپA —¥—كگ§’è
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒمپEŒأ‘مپE’†گ¢پE‹كگ¢“ْ–{پE‹Œ’nˆو–¼‚جپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹Œچ‘–¼پi—كگ§چ‘پjگ³ژ®–¼‚جپAڈي—¤ چ‘پi ‚ذپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚½‚؟ ‚ج‚‚ةپjپ@‚ج•تڈج‚إ‚ ‚éپB
پœپ@ڈيڈBپi= ڈي—¤ چ‘پj‚حپAپ@“ŒٹC“¹پi‚ئ‚¤
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚©‚¢‚ا‚¤پjپE‹ŒچLˆو’n•û‚ة‘®‚µپAŒ»پEٹض“Œ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@’n•û‚جپAŒ»چف‚ج ˆïڈ錧‚ة‘ٹ“–‚·‚é’nˆو
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈ¼ژُٹغپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ه‚¤‚¶‚م‚ـ‚éپjپB پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= چ•“c’·گپA—c–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث چ•“c ’·گپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@ڈمگM‰z’n•ûپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚µ‚ٌ‚¦‚آ‚؟‚ظ‚¤پjپB پsŒ»’nˆو–¼پtپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ŒQ”nŒ§‚ئ’·–ىŒ§‚ئگVٹƒŒ§پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ŒQ”nŒ§پiڈم–ىچ‘پjپA’·–ىŒ§پiگM
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ”Zچ‘پjپAگVٹƒŒ§پi‰zŒمچ‘پAچ²“nچ‘پj
‚ج’nˆوپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ،پ@ڈمگM‰z’n•ûپ@پi ‚¶‚ه‚¤‚µ‚ٌ‚¦‚آ‚؟‚ظ‚¤پj‚ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@ ‚حپAپ@ŒQ”nŒ§پiڈم–ىچ‘پj پA’·–ىŒ§پiگM”Zچ‘پjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گVٹƒŒ§پi‰zŒمچ‘پAچ²“nچ‘پj‚ج’nˆو ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ،پ@گM‰z’n•ûپ@پi‚µ‚ٌ‚¦‚آ‚؟‚ظ‚¤ پj‚ئ‚حپA ’·–ى
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@Œ§پiگM”Zچ‘پj پAگVٹƒŒ§پi‰zŒمچ‘پAچ²“nچ‘پj‚ج’n
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ˆو‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پœپ@ڈمگM‰z’n•ûپ@پi ‚¶‚ه‚¤‚µ‚ٌ‚¦‚آ‚؟‚ظ‚¤پj‚ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@ ‚حپAپ@ŒQ”nŒ§پiڈم–ىچ‘پj پA’·–ىŒ§پiگM”Zچ‘پjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گVٹƒŒ§پi‰zŒمچ‘پAچ²“nچ‘پj‚ج’nˆو ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پœپ@چbگM‰z’n•ûپ@پi‚±‚¤‚µ‚ٌ‚¦‚آ‚؟‚ظ‚¤ پj‚ئ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژR—œŒ§پiچb”مچ‘پj پA’·–ىŒ§پiگM”Zچ‘پjپAگVٹƒ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@ Œ§پi‰zŒمچ‘پAچ²“nچ‘پj‚ج’nˆو ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پœپ@–k—¤’n•ûپ@پi‚ظ‚‚è‚‚؟‚ظ‚¤ پj‚ئ‚حپAپ@گVٹƒ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@Œ§پE•xژRŒ§پEگخگىŒ§پE•ںˆنŒ§‚ج–k—¤‚SŒ§پA‚ـ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚½‚حپA•xژRŒ§پEگخگىŒ§پE•ںˆنŒ§‚ج–k—¤‚RŒ§پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi–k—¤“¹پE ‹ŒچLˆو’n•ûپjپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پœپ@–kگM‰z’n•ûپi‚ظ‚‚µ‚ٌ‚¦‚آ‚؟‚ظ ‚¤پj‚ئ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ –k—¤گM‰z’n•ûپ@پi‚ظ‚‚è‚‚µ‚ٌ‚¦‚آ‚؟‚ظ‚¤پj‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚ ‚èپAپ@•xژRŒ§پEگخگىŒ§پE•ںˆنŒ§‚ج–k—¤‚RŒ§
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi–k—¤“¹پE ‹ŒچLˆو’n•û‚جˆê•”پjپA’·–ىŒ§پiگM
پ@ ”Zچ‘پjپAگVٹƒŒ§پi‰zŒمچ‘ پAچ²“nچ‘پj‚ًچ‡‚ي‚¹‚½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’nˆو‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³ڈ•پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ه‚¤‚·‚¯پjپB پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ‘ه‹v•غ —ک’ت ‚¨‚¨‚‚ع ‚ئ‚µ‚ف‚؟پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‘ه‹v•غ—ک’تپj پB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈجگ§پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚¹‚¢پjپB پsگژ،گ§“xپtپB
پi= ژ·گ پA‘ه‰¤پi“Vچcپj‘م—پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ”ٍ’¹”’–Pژ‘مپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@پi—لپjپ@’†‘هŒZچcژqپi‚ب‚©‚ج‚¨
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¨‚¦‚ج‚ف‚±پE‚¨‚¤‚¶پjڈجگ§پiژ·گپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@پi—لپjپ@鸕–ىژ]—اپi‚¤‚ج‚ج‚³‚³‚çپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چcڈ—پEڈجگ§پiژ·گپj پi= ژ“ڈجگ§پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ڈجگ§پi‚µ‚ه‚¤‚¹‚¢پj‚ئ‚حپAژ·گ‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘ه‰¤پi‚¨‚¨‚«‚فپA“Vچcپj‘م—‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@ڈمگ¼–ه‰@“ژqپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚¹‚¢‚à‚ٌ‚¢‚ٌ‚ق‚ث‚±پjپB پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚P‚Q‚Uپ`‚P‚P‚W‚X”Nپj پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ڈ—‰@پAŒم”’‰حڈمچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@’¹‰Hڈمچc‚ج–؛پi“àگe‰¤‚ب‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚µ‚ٌ‚ج‚¤پj پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@Œم”’‰حڈمچc‚ج“¯•êژoپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‘زŒ«–ه‰@àِژqپi‚½‚¢‚¯‚ٌ‚à‚ٌ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚¢‚ٌ‚µ‚ه‚¤‚µپE‚½‚ـ‚±پj‚ج–؛پj پB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈڈ‰ˆتپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚»‚¢پA‚µ‚ه‚¤‚µ‚ه‚¢پjپB پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ڈ‰ˆتپi‚»‚¢پjپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ’©’ى‚جˆتٹKپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈڈ‰ˆت‰؛پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚»‚¢‚ج‚°پjپB پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ڈ‰ˆتپi‚»‚¢پjپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ’©’ى‚جˆتٹKپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚ˆ‚…پ@‚i‚•‚ژ‚‰‚ڈ‚’پ@‚k‚ڈ‚—‚…‚“‚”پ@‚b‚ڈ‚•‚’‚”پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚q‚پ‚ژ‚‹پCپ@‚k‚ڈ‚—‚…‚’پ@‚f‚’‚پ‚„‚…پ@‚ڈ‚†پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚”‚ˆ‚…پ@‚h‚چ‚گ‚…‚’‚‰‚پ‚Œپ@‚b‚ڈ‚•‚’‚”پD
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈڈ‰ˆتڈمپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚»‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپB پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ڈ‰ˆتپi‚»‚¢پjپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ’©’ى‚جˆتٹKپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈ®‘×پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚½‚¢پjپB پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@—®‹…‰¤چ‘پi‚P‚S‚Q‚Xپ`‚P‚W‚V‚Q”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جچإŒم‚جچ‘‰¤پEڈ®‘׉¤پ@پiچ‘‰¤چف
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆت‚P‚W‚S‚Wپ`‚V‚Q”NپA—®‹…پE’†ژR‰¤چ‘
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘و“ٌڈ®ژپ‰¤“‚P‚X‘مچ‘‰¤پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@—®‹…”ثپi‚P‚W‚V‚Qپ`‚V‚X”Nپj‚ج”ث
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰¤پEڈ®‘×”ث‰¤پi”ث‰¤چفˆت‚P‚W‚V‚Qپ`
‚V‚X”NپjپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈ¹‘×پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚½‚¢پjپBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚r‚g‚n‚s‚`‚hپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ ‚W‚X‚W”Nپ[‚X‚O‚P”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚W‚X‚W”NپEڈ¹‘׌³”NپE‚SŒژ‚Q‚U“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚X‚O‚P”NپEڈ¹‘× ‚S”NپE‚VŒژ‚P‚T“ْپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@•½ˆہژ‘م‘Oٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³’†پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚؟‚م‚¤پjپBپ@پ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚r‚g‚n‚b‚g‚tپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‚P‚R‚Q‚S”Nپ[‚P‚R‚Q‚U”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚P‚R‚Q‚S”NپEگ³’†Œ³”NپE‚P‚QŒژپ@‚X“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚R‚Q‚U”NپEگ³’† ‚R”NپEپ@‚SŒژ‚Q‚U“ْپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ٹ™‘qژ‘مŒمٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³’·پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚؟‚ه‚¤پjپBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚r‚g‚n‚b‚g‚nپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‚P‚S‚Q‚W”Nپ[‚P‚S‚Q‚X”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚P‚S‚Q‚W”NپEگ³’·Œ³”NپE‚SŒژ‚Q‚V“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@‚P‚S‚Q‚X”NپEگ³’· ‚Q”NپE‚XŒژپ@‚T“ْپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ژ؛’¬ژ‘م’†ٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³“؟پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚ئ‚پjپBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚r‚g‚n‚s‚n‚j‚tپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‚P‚V‚P‚P”Nپ[‚P‚V‚P‚U”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚P‚V‚P‚P”NپEگ³“؟Œ³”NپE‚SŒژ‚Q‚T“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚V‚P‚U”NپEگ³“؟ ‚U”NپE‚UŒژ‚Q‚Q“ْپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@چ]Œثژ‘م’†ٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@ڈ³“؟پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚ئ‚پjپBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚r‚g‚n‚s‚n‚j‚tپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‚P‚O‚X‚V”Nپ[‚P‚O‚X‚X”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚P‚O‚X‚V”NپEڈ³“؟Œ³”NپE‚P‚PŒژ‚Q‚P“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚P‚O‚X‚X”NپEڈ³“؟ ‚R”NپEپ@‚WŒژ‚Q‚W“ْپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@•½ˆہژ‘مŒمٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³“؟ژ›‰ïŒ©پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚ئ‚‚¶‚©‚¢‚¯‚ٌپj پBپ@پs‰ï’kپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@گ³“؟ژ›‰ïŒ©‚ئ‚حپAپ@چض“،“¹ژOپi—کگپj ‚ئگD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“cگM’·‚ئ‚ج‰ï’k‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‚P‚T‚T‚R”Nپi“V•¶‚Q‚Q”Nپj‚ةپ@پiˆظگà‚إ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚T‚S‚X”Nپi“V•¶‚P‚W”Nپj‚ةپjپAپ@“–ژپA”ü”Zچ‘‚ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”ِ’£چ‘‚جچن•t‹ك‚ة‚ ‚ء‚½پAگ³“؟ژ›پ@پi‚µ‚ه‚¤‚ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚‚¶پAŒ»پE–¼Œأ‰®ژs“V”’‹و‚جگ¹“؟ژ›پj‚ئ‚¢‚¤ژ›
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إپAپ@”ü”Zچ‘چ‘ژهپEچض“،“¹ژOپi—کگپjپi‚³‚¢‚ئ‚¤
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ا‚¤‚³‚ٌپi‚ئ‚µ‚ـ‚³پjپjپ@‚ئپ@”ِ’£چ‘‚جگD“cگM’·
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ھ‰ïŒ©‚µ‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰ïŒ©ˆبŒم‚جپAچض“،“¹ژOپi—کگپj ‚حپAپ@‹A
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’±پi‚«‚؟‚ه‚¤پA”Z•Pپj‚ج–؛–¹‚إ‚ ‚èپAگي—ھ‰ئ‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰üٹvژز‚جگD“cگM’·‚ةپA“¯–؟ژز‚ئ‚µ‚ؤپAچDˆس‚ً
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚à‚آ‚و‚¤‚ة‚ب‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ¹“؟‘¾ژqپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚ئ‚‚½‚¢‚µپj پBپ@پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ‰XŒث‰¤ پi‚¤‚ـ‚â‚ئ‚¨‚¤پjپj پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‰XŒث‰¤ پi‚¤‚ـ‚â‚ئ‚¨‚¤پjپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈج“؟“VچcپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚ئ‚‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پjپ@پsڈ—گ«“VچcپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ˆ¢”{“àگe‰¤پA‘O‚جچFŒھپi‚±
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¤‚¯‚ٌپj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiگ¶–v”NپF‚V‚P‚W”Nپ[‚V‚V‚O”NپjپB
پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚d‚l‚o‚q‚d‚r‚rپ@‚r‚g‚n‚s‚n‚j‚tپD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث چFŒھپi‚±‚¤‚¯‚ٌپj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ڈ—گ«“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‚Q‰ٌپA“Vچc‚ة‘¦ˆتپB
پi‚Pپjپ@‘و‚P‰ٌ“Vچc‘¦ˆتپAڈ‰‘¦ˆت
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چFŒھ“VچcچفˆتپF
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚V‚S‚X”Nپ[‚V‚T‚W”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚Qپjپ@‘و‚Q‰ٌ“Vچc‘¦ˆتپAچؤ‘¦ˆت
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈج“؟“VچcچفˆتپF
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚V‚U‚S”Nپ[‚V‚V‚O”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@‘ه•§ٹJٹلژ‚ج“VچcپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@گ¹•گپi‚µ‚ه‚¤‚قپj“Vچc‚جچcڈ—پi–؛پj پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ڈج“؟“Vچcپ@پi‚µ‚ه‚¤‚ئ‚‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پAچفˆتپF
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚V‚U‚S”Nپ[‚V‚V‚O”NپA‰pپF‚s‚g‚dپ@‚d‚l‚o‚q‚d‚r‚rپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚r‚g‚n‚s‚n‚j‚tپj‚حپAپ@“ق—اژ‘م‚جڈ—گ«“Vچc
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ڈ—’éپj‚إ‚ ‚èپAپ@‘O‚جچFŒھ“Vچcپ@پi‚±‚¤
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¯‚ٌ‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پAچفˆتپF‚V‚S‚X”Nپ[‚V‚T‚W”Nپj‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚à‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@چFŒھپiڈج“؟پj“VچcپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@چFŒھپiڈج“؟پj“Vچcپ@پi‚±‚¤‚¯‚ٌپi‚µ‚ه‚¤‚ئ‚پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پAچفˆتپF‚V‚S‚X”Nپ[‚V‚T‚W”NپA‚V‚U‚S”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ[‚V‚V‚O”Nپj‚حپAپ@ˆ¢”{“àگe‰¤پi‚ ‚×پi‚جپj‚ب‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚µ‚ٌ‚ج‚¤پj‚إ‚ ‚èپAپ@گ¹•گپi‚µ‚ه‚¤‚قپj“Vچc‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چcڈ—پi–؛پj‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@چFŒھپiڈج“؟پj“Vچc‚حپAپ@‚V‚T‚Q”Nپi“V•½ڈں•َ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚S”Nپj‚ج‘ه•§ٹJٹلژ‚ج“Vچc‚إ‚ ‚èپAپ@•ƒ‚جگ¹
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•گ“Vچcپiگ¹•گ‘¾ڈمپi‚¾‚¶‚ه‚¤پj“VچcپjپAپ@‹kڈ”ŒZ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚½‚؟‚خ‚ب‚ج‚à‚낦پjپAپ@‹g”ُگ^”ُپi‚«‚ر‚ج‚ـ‚«
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚رپjپAپ@“،Œ´’‡–ƒکCپi‚س‚¶‚ي‚ç‚ج‚ب‚©‚ـ‚ëپjپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“¹‹¾پi‚ا‚¤‚«‚ه‚¤پjپ@‚ئ‹¦—ح‚µ‚ؤپAپ@‘½‚‚جگچô
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ًچs‚¢پAپ@“Œ‘هژ›‘ه•§‘¢‰c‚ًگ„گi‚µٹ®گ¬‚³‚¹پAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•§‹³’ءŒىپi‚؟‚ٌ‚²پjچ‘‰ئ‚ة‚و‚éچ‘‰ئ‚جˆہ’è‚ً
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ح‚©‚èپAپ@‚ـ‚½پA“V•½پi‚ؤ‚ٌ‚ز‚ه‚¤پj•¶‰»‚ًŒ»ڈo
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚³‚¹‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پںپ@ڈ—گ«“Vچcپ@پi‚Wگl‚P‚O‘مپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ڈ—گ«“VچcپjپBپ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث گ„Œأپi‚·‚¢‚±پj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث چc‹ةپiگؤ–¾پjپi‚±‚¤‚¬‚ه‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚³‚¢‚ك‚¢پjپj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ژ“پi‚¶‚ئ‚¤پj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث Œ³–¾پi‚°‚ٌ‚ك‚¢پj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث Œ³گ³پi‚°‚ٌ‚µ‚ه‚¤پj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث چFŒھپiڈج“؟پjپi‚±‚¤‚¯‚ٌ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚ئ‚پjپj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث –¾گ³پi‚ك‚¢‚µ‚ه‚¤پj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث Œمچ÷’¬پi‚²‚³‚‚ç‚ـ‚؟پj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@“ْ–{‚جڈ—گ«“VچcپE‚Wگl‚P‚O‘مپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@“ْ–{‚جŒأ‘م‚©‚猻‘م‚ـ‚إ‚جٹش‚ةپAڈ—گ«
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“Vچc‚حپAپ@”ٍ’¹”’–Pپi‚ ‚·‚©‚ح‚‚ظ‚¤پjژ‘مپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ق—اپi‚ب‚çپjژ‘م‚ة“Vچc‚ة‘¦ˆتپiڈA ”Cپj‚µ‚½پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ„Œأپi‚·‚¢‚±پjپAچc‹ةپiگؤ–¾پjپi‚±‚¤‚¬‚ه‚پi‚³‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ك‚¢پjپjپAژ“پi‚¶‚ئ‚¤پjپAŒ³–¾پi‚°‚ٌ‚ك‚¢پjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ³گ³پi‚°‚ٌ‚µ‚ه‚¤پjپAچFŒھپiڈج“؟پjپi‚±‚¤‚¯‚ٌ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚ئ‚پjپj‚ج‚Uگl‚W‘م‚ج“Vچcپ@‚âپ@چ]Œث
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¦‚اپjژ‘م‚ة“Vچc‚ة‘¦ˆتپiڈA ”Cپj‚µ‚½پA–¾
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ³پi‚ك‚¢‚µ‚ه‚¤پjپAŒمچ÷’¬پi‚²‚³‚‚ç‚ـ‚؟پj‚ج‚Q
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گl‚Q‘م‚ج“Vچc‚ھ‚¢‚ؤپAچ‡Œv‚µ‚ؤ‚Wگl‚P‚O‘م‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپj‚ھ‚¢‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث گ„Œأپi‚·‚¢‚±پj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث چc‹ةپiگؤ–¾پjپi‚±‚¤‚¬‚ه‚پi‚³‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ك‚¢پjپj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ژ“پi‚¶‚ئ‚¤پj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث Œ³–¾پi‚°‚ٌ‚ك‚¢پj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث Œ³گ³پi‚°‚ٌ‚µ‚ه‚¤پj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث چFŒھپiڈج“؟پjپi‚±‚¤‚¯‚ٌپi‚µ‚ه
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¤‚ئ‚پjپj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث –¾گ³پi‚ك‚¢‚µ‚ه‚¤پj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث Œمچ÷’¬پi‚²‚³‚‚ç‚ـ‚؟پj“VچcپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³“ٌˆتپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚ة‚¢پjپBپ@پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ٌˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈ®”JپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ه‚¤‚ث‚¢پjپBپ@پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@—®‹…‰¤چ‘پi‚P‚S‚Q‚X”Nپ`‚P‚W‚V‚Q”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚ج’†ٹْ‚جچ‘‰¤پEڈ®”J‰¤‚إپA‚P‚U‚O‚X
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ”N‚ةژF–€”ث‚ئگي‚¢پA”s‚ê‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث —®‹…‰¤چ‘پA‰«“ê‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—ًژjپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ ڈ¬‚جŒژپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚ج‚آ‚«پjپBپ@پ@پs—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@ڈ¬‚جŒژ‚جŒژ––‚ح‚Q‚X“ْ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆب‰؛‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‘¾‰A‘¾—z—ïپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@“ْ–{‚ج‹Œ—ïپi‘¾‰A‘¾—z—ïپj‚إ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆê‚©Œژ‚ج“ْگ”‚ھ‚R‚O“ْ‚ ‚éŒژ‚ًپu‘ه
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جŒژپvپi‚¾‚¢‚ج‚آ‚«پjپAˆê‚©Œژ‚ج“ْگ”
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ھ‚Q‚X“ْˆب‰؛‚جŒژ‚ًڈ¬‚جŒژپi‚µ‚ه‚¤‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚آ‚«پj‚ئ‚¢‚¤پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@“ْ–{‚ج‹Œ—ïپi‘¾‰A‘¾—z—ïپj‚إ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پu‘ه‚جŒژپvپi‚¾‚¢‚ج‚آ‚«پj‚ئ‚³‚ꂽŒژ‚ح
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œژ––‚ھ‚R‚O“ْ‚إ‚ ‚èپAپ@پuڈ¬‚جŒژپvپi‚µ‚ه
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¤‚ج‚آ‚«پj‚ئ‚³‚ꂽŒژ‚حپAŒژ––‚ھ‚Q‚X“ْ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆب‰؛‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ˆ×گژز‚ھپA‚ا‚جŒژٹش‚ًپAپu‘ه‚جŒژپvپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پuڈ¬‚جŒژپv‚ة‚·‚é‚©Œˆ‚ك‚ؤ‚¢‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‘¾‰A‘¾—z—ïپi‚½‚¢‚¢‚ٌ‚½‚¢‚و‚¤‚ê
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚«پj‚إ‚حپAŒژٹش‚حپA•½‹د–ٌ‚Q‚XپD‚T“ْ‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚إ‚حپA‘¾‰A‘¾—z—ï‚ھ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژg—p‚³‚êپA‚»‚ê‚ھپA“ْ–{‚ج‹Œ—ï‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جپA‹IŒ³پiŒمپj‚Vگ¢‹Iچ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚©‚ç‚P‚W‚V‚Q”Nپi–¾ژ،‚T”Nپj‚ـ‚إپA‘¾‰A‘¾
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—z—ï‚ھژg—p‚³‚êپA‚»‚ê‚ھ“ْ–{‚ج‹Œ—ï‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈ®”bژuپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚ح‚µپjپB پ@پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@—®‹…‰¤چ‘پi‚P‚S‚Q‚Xپ`‚P‚W‚V‚Q”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جŒڑچ‘ژزپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@—®‹…‰¤چ‘‚جڈ®ژپپi‚µ‚ه‚¤‚µپj‘وˆê
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰¤’©پi‚P‚S‚Q‚Xپ`‚V‚O”Nپj‚ً‚½‚ؤ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث —®‹…‰¤چ‘ پA‰«“ê‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—ًژjپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³”ھˆتپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚ح‚؟‚¢پjپBپ@پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ”ھˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@
پ›پ@‚µ‚هپ@پ@گ³”ھˆت‰؛پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚ح‚؟‚¢‚ج‚°پjپB پ@پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پiپث ”ھˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³”ھˆتڈمپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚ح‚؟‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپBپ@پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پiپث ”ھˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈئ•ں‰@پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚س‚‚¢‚ٌپjپBپ@پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ‹ù‹´ ŒُپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‹ù‹´ Œُپi‚‚µ‚ح‚µ ‚ؤ‚éپE‚ف‚آپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج–@ –¼پi‚ظ‚¤‚ف‚ه‚¤پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ‹ù‹´ŒُپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ چ•“cٹ¯•؛‰qپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³•½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚ض‚¢پjپBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚r‚g‚n‚g‚d‚hپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ ‚P‚R‚S‚U”Nپ[‚P‚R‚V‚O”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ى–k’©‹£چ‡“ٌڈd”Nچ†پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï‚ج“ٌڈd”Nچ†‘¶—§پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@“ى–k’©‹£چ‡“ٌڈd”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@“ى’©پi‘هٹoژ›“پj•û‚ج—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚R‚S‚U”NپEگ³•½ Œ³”NپE‚P‚QŒژپ@‚W“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚R‚V‚O”NپEگ³•½‚Q‚T”NپEپ@‚VŒژ‚Q‚S“ْپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ژ؛’¬ژ‘م‘Oٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@پi’چˆسپjپ@“¯ژٹْ‚ةپA–k’©پ@پiژ–¾‰@“پA
ŒُŒµپi‚±‚¤‚²‚ٌپjپEŒُ–¾پi‚±‚¤‚ف‚ه‚¤پj“VچcŒn
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“پjپ@•û‚ج—ï”Nچ†‚جپA پ@’هکaپi‚¶‚ه‚¤‚يپjŒ³
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”Nپ`‚U”Nپi‚P‚R‚S‚Tپ`‚P‚R‚T‚O”NپjپAپ@ٹد‰پi‚©
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ٌ‚ج‚¤پjŒ³”Nپ`‚R”Nپi‚P‚R‚T‚Oپ`‚P‚R‚T‚Q”NپjپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•¶کaپi‚ش‚ٌ‚بپjŒ³”Nپ`‚T”Nپi‚P‚R‚T‚Qپ`‚P‚R‚T
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚U”Nپjپثپ@‰„•¶پi‚¦‚ٌ‚ش‚ٌپjŒ³”Nپ`‚U”Nپi‚P‚R
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚T‚Uپ`‚P‚R‚U‚P”Nپjپثپ@چNˆہپi‚±‚¤‚ ‚ٌپjŒ³”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ`‚Q”Nپi‚P‚R‚U‚Pپ`‚P‚R‚U‚Q”Nپjپثپ@’هژ،پi‚¶‚ه
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¤‚¶پjŒ³”Nپ`‚V”Nپi‚P‚R‚U‚Qپ`‚P‚R‚U‚W”Nپjپثپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰ˆہپi‚¨‚¤‚ ‚ٌپjŒ³”Nپ`‚W”Nپi‚P‚R‚U‚W”Nپ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚R‚V‚T”Nپjپ@‚à‘¶—§ ‚·‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@ڈ³•½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚ض‚¢پA‚µ‚ه‚¤‚ض‚¢پjپBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚r‚g‚n‚g‚d‚hپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‚X‚R‚P”Nپ[‚X‚R‚W”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚X‚R‚P”NپEڈ³•½Œ³”NپE‚SŒژ‚Q‚U“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚X‚R‚W”NپEڈ³•½ ‚W”NپE‚TŒژ‚Q‚Q“ْپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@•½ˆہژ‘م’†ٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³•غپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚ظ‚¤پjپBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚r‚g‚n‚g‚nپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‚P‚U‚S‚S”Nپ[‚P‚U‚S‚W”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚P‚U‚S‚S”NپEگ³•غŒ³”NپE‚P‚QŒژ‚P‚U“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚U‚S‚W”NپEگ³•غ ‚T”NپEپ@‚QŒژ‚P‚T“ْپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@چ]Œثژ‘م‘Oٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@ڈ³•غپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚ظ‚¤پjپBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚i‚n‚g‚nپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‚P‚O‚V‚S ”Nپ[‚P‚O‚V‚V”NپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚P‚O‚V‚S”NپEڈ³•غŒ³”NپEپ@‚WŒژ‚Q‚R“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚P‚O‚V‚V”NپEڈ³•غ ‚S”NپE‚P‚PŒژ‚P‚V“ْپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@•½ˆہژ‘م’†ٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@ ڈً–Vگ§پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚ه‚¤‚ع‚¤‚¹‚¢پjپB پs‹پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ‹پAژéگ‘هکHپjپBپ@
پ@پ@پ،پ@ڈً–Vگ§پi‚¶‚ه‚¤‚ع‚¤‚¹‚¢پj‚ئ‚حپAپ@’†چ‘پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’©‘N”¼“‡پA“ْ–{“™‚إŒ©‚ç‚ê‚é‚ج‹{ڈé“sژs
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‹{ڈé‚ً’†گS‚ئ‚·‚é“sڈéپi= ‹پjپjپ@‚ج“sژs
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œv‰و‚إ‚ ‚éپBپ@“ْ–{‚إ‚حپA“،Œ´‹پA•½ڈé
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹پA’·‰ھ‹پA•½ˆہ‹“™‚إچج—p‚³‚ꂽپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ڈً–Vگ§‚حپAپ@“ى–k’†‰›‚ةژéگ‘هکHپi‚·
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚´‚‚¨‚¨‚¶پj‚ً”z‚µپAپ@“ى–k‚ج‘هکHپi‚¨‚¨‚¶پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= –Vپjپ@‚ئپ@“Œگ¼‚ج‘هکHپi= ڈًپj‚ًٹî”ص‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–عڈَ‚ة‘g‚فچ‡‚ي‚¹‚½چ¶‰E‘خڈج‚إ•ûŒ`‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“sژsŒ`‘ش‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ¹•گ“VچcپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚ق‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پjپBپ@پs“VچcپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiگ¶–v”NپF‚V‚O‚Pپ`‚V‚T‚U”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚d‚l‚o‚d‚q‚n‚qپ@‚r‚g‚n‚l‚tپD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@“VچcچفˆتپF‚V‚Q‚Sپ`‚V‚S‚X”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@گ¹•گ“Vچc پ@پi‚µ‚ه‚¤‚ق‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پAگ¶–v”NپF
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚V‚O‚Pپ`‚V‚T‚U”NپA“VچcچفˆتپF‚V‚Q‚Sپ`‚V‚S‚X”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚حپA پ@چ‘‰ئ‚جˆہ’è‚ً‚ح‚©‚邽‚كپAپ@“ق—اپE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“Œ‘هژ›‘ه•§‚ً‘¢—§پi‚¼‚¤‚è‚م‚¤پj‚µپAپ@چ‘•ھ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ›پEچ‘•ھ“ٍژ›‚ًڈ” چ‘‚ة‚آ‚‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@“ꕶپE–kƒAƒWƒAڈ”–¯‘°پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ چ¬ŒŒŒnپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚à‚ٌپE‚«‚½‚ ‚¶‚ ‚µ‚ه‚ف‚ٌ‚¼ ‚پE‚±
پ@‚ٌ‚¯‚آ‚¯‚¢پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ŒأپEگVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhچ¬ŒŒ‚جپu“ꕶپE–k
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒAƒWƒAڈ”–¯‘°پEچ¬ŒŒŒn‚جپuƒAƒCƒkگlپv‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گl—قپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiگl—قٹwڈم‚ج•ھ—قپE“ء’¥پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi“ْ–{گl‚جƒ‹پ[ƒcپjپB
پs“ْ–{ڈيڈZ–¯‚ج“ْ–{گlپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚s‚g‚dپ@‚i‚n‚l‚n‚m-‚m‚n‚q‚s‚gپ@‚`‚r‚h‚`‚mپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚o‚d‚n‚o‚k‚d‚rپ@‚l‚h‚w‚d‚cپ@‚q‚`‚b‚h‚`‚kپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚o‚d‚n‚o‚k‚dپD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ƒAƒCƒkگlپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@“ꕶŒnپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚à‚ٌ‚¯‚¢پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiگl—قٹwڈم‚ج•ھ—قپE“ء’¥پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi“ْ–{گl‚جƒ‹پ[ƒcپjپB
پs“ْ–{ڈيڈZ–¯‚ج“ْ–{گlپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚i‚n‚l‚n‚m‚j‚d‚hپ@‚o‚d‚n‚o‚k‚dپD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= “ꕶگl‚ئ‚»‚جژq‘·پjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= Œأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپi= “ى•ûƒ‚ƒ“ƒS
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒچƒCƒhپj‚ج“ْ–{’nˆو“y’…پEڈيڈZ–¯پjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= Œأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh‚جپAپ@پu“ꕶگlپvپAپ@پu“ꕶ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œnپiچف—ˆŒnپj–يگ¶گlپvپAپ@پu“ꕶŒnپiچف—ˆŒnپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œأ‘م“ْ–{گlپvپAپ@‚جگl—قپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@“ْ–{‚ج“ꕶژ‘م‚ج“ꕶگl‚ئ‚»‚جژq‘·پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@پu“ꕶŒnپvپ@پi‚¶‚ه‚¤‚à‚ٌ‚¯‚¢پA‰pپF‚s‚g‚dپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚i‚n‚l‚n‚m‚j‚d‚hپ@‚o‚d‚n‚o‚k‚dپjپ@‚جگlپX‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{‚ج“ꕶژ‘م‚ج“ꕶگl‚ئ‚»‚جژq‘·‚إ‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚èپAپ@Œأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپi= “ى•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج“ْ–{’nˆو“y’…پEڈيڈZ–¯پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@“ꕶŒn‚جگlپX‚حپAپ@“ْ–{‚ج“ꕶژ‘م‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جپu“ꕶگlپv‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@“ꕶŒn‚جگlپX‚حپAپ@“ْ–{‚ج–يگ¶ژ‘م‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جپu“ꕶŒnپiچف—ˆŒnپj–يگ¶گlپvپAپ@پu“ꕶپE–ي
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒn–يگ¶گlپvپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@“ꕶŒn‚جگlپX‚حپAپ@Œأ‘م“ْ–{پiŒأ•ژ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘مپ`•½ˆہژ‘مپj‚إ‚جپAپu“ꕶŒnپiچف—ˆŒnپjŒأ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘م“ْ–{گlپvپAپ@پu“ꕶپE–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒnŒأ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘م“ْ–{گlپvپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@“ꕶŒn‚جگlپX‚حپAپ@’†گ¢“ْ–{‚©‚猻‘م
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{‚ـ‚إپiٹ™‘qژ‘م‚©‚畽گ¬ژ‘م‚ـ‚إپj‚جپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ꕶپE–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒn‚جپAپu–{“y“ْ–{گlپv
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚âپu—®‹…گlپvپ@‚ئپAپ@“ꕶپE–kƒAƒWƒAڈ”–¯‘°پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ¬ŒŒŒn‚جپAپuƒAƒCƒkگlپvپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@–ٌ‚U‚O‚O‚O”N‘Oپi‹IŒ³‘O‚S‚O‚O‚O”Nچ پj‚©
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ç–ٌ‚V‚O‚O”N‘Oپi‹IŒ³پiŒمپj‚P‚Rگ¢‹Iچ پj‚ـ‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جٹش‚ةپAپ@ƒ‚ƒ“ƒSƒ‹’nˆوپA–ڈB’nˆوپi’†چ‘
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“Œ–k•”پjپA’†چ‘–{“y’nˆوپA’©‘N”¼“‡پA–kƒA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒWƒAپA“ْ–{’nˆو‚إ‚حپAپ@Œأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh‚جگl
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پXپ@پi“ْ–{‚إ‚ح“ꕶŒn‚جگlپXپjپ@‚ئپAپ@گVƒ‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒ“ƒSƒچƒCƒh‚جگlپXپ@پi“ْ–{‚إ‚ح–يگ¶“n—ˆŒn
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جگlپXپjپ@‚حپAپ@ڈ‰‚ك‚حپA‘خ—§‚µپA•تپX‚ة‹ڈ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈZ‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ھپAپ@—¼ژز‚حڈ™پX‚ةچ¬ŒŒ‚µ‚ؤ‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚«پAپ@ƒ‚ƒ“ƒSƒ‹–¯‘°پA–ڈB–¯‘°پAٹ؟–¯‘°پA’©
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘N–¯‘°پA–kƒAƒWƒAڈ”–¯‘°پA–{“y“ْ–{گlپA—®
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹…گlپAƒAƒCƒkگlپ@‚ب‚ا‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@“ꕶŒnپi“ْ–{ڈيڈZ–¯پj‚ض‚جگi‰»•\پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰»گخ—قگl‰ژپi= ’†گVگ¢ƒzƒ~ƒmƒCƒhپjپثپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گl—ق‚جپA‰ژگlپثپ@Œ´گlپi= ƒzƒ‚پEƒGƒŒƒNƒgپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒX—قپjپثپ@‹Œگlپi= ‘Oƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒX—قپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پثپ@Œ»گ¶گl—قپi= گVگlپAƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒX
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژيپjپثپ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپثپ@“ꕶگlپثپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–يگ¶گlپثپ@Œأ‘م“ْ–{گlپثپ@پu–{“y“ْ–{گlپv
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= –{“yگlپjپA پu—®‹…گlپvپAپuƒAƒCƒkگlپvپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@Œ»‘م“ْ–{گlپi“ْ–{ڈيڈZ–¯پj‚ض‚جگi‰»•\پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰»گخ—قگl‰ژپi= ’†گVگ¢ƒzƒ~ƒmƒCƒhپjپثپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گl—ق‚جپA‰ژگlپثپ@Œ´گlپi= ƒzƒ‚پEƒGƒŒƒNƒg
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒX—قپjپثپ@‹Œگlپi= ‘Oƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒX—قپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پثپ@Œ»گ¶گl—قپi= گVگlپAƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒX
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژيپjپثپ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپثپ@“ꕶگlپثپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–يگ¶گlپثپ@Œأ‘م“ْ–{گlپثپ@’†گ¢“ْ–{گlپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پثپ@‹كگ¢“ْ–{گlپثپ@‹ك‘م“ْ–{گlپثپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ»‘م“ْ–{گlپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh‚ض‚جگi‰»•\پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰»گخ—قگl‰ژپi= ’†گVگ¢ƒzƒ~ƒmƒCƒhپjپثپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گl—ق‚جپA‰ژگlپثپ@Œ´گlپi= ƒzƒ‚پEƒGƒŒƒNƒg
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ƒX—قپjپثپ@‹Œگlپi= ‘Oƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒX—قپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پثپ@Œ»گ¶گl—قپi= گVگlپAƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒX
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژيپjپثپ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh‚جŒأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒC ƒh
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= “ى•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپjپثپ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپi= –k•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث “ꕶگlپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث Œ´“ْ–{گlپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ْ–{گlپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ْ–{گlƒ‹پ[ƒcپEƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث Œأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@ “ꕶŒn–يگ¶گlپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚à‚ٌ‚¯‚¢‚â‚و‚¢‚¶‚ٌپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= چف—ˆŒn–يگ¶گlپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiگl—قٹwڈم‚ج•ھ—قپE“ء’¥پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi“ْ–{گl‚جƒ‹پ[ƒcپjپB
پs“ْ–{ڈيڈZ–¯ ‚ج“ْ–{گlپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= –يگ¶ژ‘م‚ةپA“ْ–{’nˆو‚ة‹ڈڈZ‚µ‚ؤ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¢‚½پAپ@Œأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh‚جپu“ꕶŒnپiچف—ˆ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œnپj–يگ¶گlپvپ@‚جگl—قپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث “ꕶŒnپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث –يگ¶گlپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث “ꕶگlپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ْ–{گlپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ْ–{گlƒ‹پ[ƒcپEƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث Œأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@ “ꕶŒnŒأ‘م“ْ–{گlپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚à‚ٌ‚¯‚¢‚±‚¾‚¢‚ة‚ظ‚ٌ‚¶‚ٌپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= چف—ˆŒnŒأ‘م“ْ–{گlپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiگl—قٹwڈم‚ج•ھ—قپE“ء’¥پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi“ْ–{گl‚جƒ‹پ[ƒcپjپB
پs“ْ–{ڈيڈZ–¯‚ج“ْ–{گlپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= Œأ‘م“ْ–{‚جژٹْ‚ةپA“ْ–{’nˆو‚ة‹ڈڈZ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚µ‚ؤ‚¢‚½پAپ@Œأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh‚ج“ꕶŒn‚ج“ْ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ –{گlپ@‚جگl—قپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث “ꕶŒnپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث Œأ‘م“ْ–{گlپjپBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث “ꕶگlپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ْ–{گlپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ْ–{گlƒ‹پ[ƒcپEƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث Œأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@“ꕶژ‘مپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚à‚ٌ‚¶‚¾‚¢پjپB
پi= –ٌ‚P–œ‚Q‚O‚O‚O”N‘Oپ[‹IŒ³
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‘O‚Sگ¢‹Iچ پi–ٌ‚Q‚S‚O‚O”N‘OپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پs“ْ–{—ًژj‚جژ‘م‹و•ھپtپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚i‚n‚l‚n‚mپ@‚o‚d‚q‚h‚n‚cپD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پƒŒ´ژnژ‘مپE“ْ–{پB
پiپث Œ´ژnژ‘مپE“ْ–{پj پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ْ–{—ًژj‚جژ‘م‹و•ھپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ꕶگlپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@“ꕶژ‘مپ@پi‚¶‚ه‚¤‚à‚ٌ‚¶‚¾‚¢پj‚ئ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–ٌ‚P–œ‚Q‚O‚O‚O”N‘O‚©‚ç‹IŒ³‘O‚Sگ¢‹I
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ پi–ٌ‚Q‚S‚O‚O”N‘Oپj‚ـ‚إ‚جٹْٹش‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@“ꕶژ‘م‚حپAپ@Œ´ژnژ‘مپE“ْ–{پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ‹Œگخٹيژ‘مپA“ꕶژ‘مپA–يگ¶ژ‘م پGپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–ٌ‚R–œ‚T‚O‚O‚O”N‘Oپ[‹IŒ³پiŒمپj‚Rگ¢‹Iچ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi–ٌ‚P‚V‚O‚O”N‘Oپjپ@‚جˆêژٹْ‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@“ꕶگlپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚à‚ٌ‚¶‚ٌپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiگl—قٹwڈم‚ج•ھ—قپE“ء’¥پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi“ْ–{گl‚جƒ‹پ[ƒcپjپB
پs“ْ–{ڈيڈZ–¯‚ج“ْ–{گlپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚i‚n‚l‚n‚m‚i‚h‚mپ@‚o‚d‚n‚o‚k‚dپD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@“ꕶگl= “ꕶژ‘م“ْ–{’nˆو“y’…پEڈي
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈZ–¯پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@پuŒأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپi= “ى•ûƒ‚ƒ“
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ƒSƒچƒCƒhپj‚ج“ꕶگlپvپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@“ꕶگl‚ئ‚حپAپ@“ꕶژ‘م“ْ–{’nˆو“y’…پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ڈيڈZ–¯‚إ‚ ‚èپAپ@“ْ–{‚ج“ꕶژ‘م‚ةپA“ْ–{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ’nˆو‚ة‹ڈڈZ‚µ‚ؤ‚¢‚½پAŒأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh‚جگl
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ —ق‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@“ꕶگlپi= “ꕶژ‘م“ْ–{’nˆو“y’…پEڈي
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈZ–¯پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پƒƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پƒŒ»گ¶گl—قپi= گVگlپAƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒXژيپjپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پƒƒqƒg‘®پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پƒگl—قپi= ƒqƒgˆں‘°پjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@“ꕶگl‚ج’nˆو“IپE•¶‰»“I“ء’¥پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiگl—قٹwڈم‚ج•ھ—قپE“ء’¥پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@“ꕶگl‚حپAپ@“ْ–{‚ج“ꕶژ‘م‚جژٹْ‚ة
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi–ٌ‚P–œ‚Q‚O‚O‚O”N‘O‚©‚ç–ٌ‚Q‚S‚O‚O”N‘Oپi‹I
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ³‘O‚Sگ¢‹Iچ پj‚ـ‚إ‚جٹش‚ةپjپAپ@“ْ–{’nˆو
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi“ْ–{–{“yپA“ىگ¼ڈ”“‡پA–kٹC“¹پj‚ة‹ڈڈZ‚µ‚ؤ
‚¢‚½پAŒأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپi= “ى•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپj
‚جگl—ق‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ꕶگl‚حپAپ@“ْ–{–{“yپi–{ڈBپAژlچ‘پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹مڈBپj‚ة‹ڈڈZ‚µ‚ؤ‚¢‚½پu“ꕶŒnپiچف—ˆŒnپjپv
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جگl—ق‚إ‚ ‚èپAپ@“ىگ¼ڈ”“‡‚ة‹ڈڈZ‚µ‚ؤ‚¢‚½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پu“ꕶŒnپiچف—ˆŒnپjپv‚جگl—ق‚إ‚ ‚èپAپ@–kٹC
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“¹‚ة‹ڈڈZ‚µ‚ؤ‚¢‚½پu“ꕶŒnپiچف—ˆŒnپjپv‚جگl
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—ق‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@–ٌ‚P–œ‚Q‚O‚O‚O”N‘O‚ةپAپ@“ْ–{’nˆو‚ة‹ڈ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈZ‚·‚éŒأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپi= “ى•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جگl—ق‚حپAپ@“ꕶ•¶‰»‚ًگ¬—§‚³‚¹پA“ꕶگl
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ئ‚ب‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@“ꕶگlپi“ْ–{ڈيڈZ–¯پj‚ض‚جگi‰»•\پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰»گخ—قگl‰ژپi= ’†گVگ¢ƒzƒ~ƒmƒCƒhپjپثپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گl—ق‚جپA‰ژگlپثپ@Œ´گlپi= ƒzƒ‚پEƒGƒŒƒNƒgپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒX—قپjپثپ@‹Œگlپi= ‘Oƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒX—قپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پثپ@Œ»گ¶گl—قپi= گVگlپAƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒX
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژيپjپثپ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپثپ@“ꕶگlپثپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–يگ¶گlپثپ@Œأ‘م“ْ–{گlپثپ@پu–{“y“ْ–{گlپv
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= –{“yگlپjپA پu—®‹…گlپvپAپuƒAƒCƒkگlپvپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@Œ»‘م“ْ–{گlپi“ْ–{ڈيڈZ–¯پj‚ض‚جگi‰»•\پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰»گخ—قگl‰ژپi= ’†گVگ¢ƒzƒ~ƒmƒCƒhپjپثپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گl—ق‚جپA‰ژگlپثپ@Œ´گlپi= ƒzƒ‚پEƒGƒŒƒNƒg
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒX—قپjپثپ@‹Œگlپi= ‘Oƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒX—قپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پثپ@Œ»گ¶گl—قپi= گVگlپAƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒX
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژيپjپثپ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپثپ@“ꕶگlپثپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–يگ¶گlپثپ@Œأ‘م“ْ–{گlپثپ@’†گ¢“ْ–{گlپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پثپ@‹كگ¢“ْ–{گlپثپ@‹ك‘م“ْ–{گlپثپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ»‘م“ْ–{گlپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh‚ض‚جگi‰»•\پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰»گخ—قگl‰ژپi= ’†گVگ¢ƒzƒ~ƒmƒCƒhپjپثپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ گl—ق‚جپA‰ژگlپثپ@Œ´گlپi= ƒzƒ‚پEƒGƒŒƒNƒg
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ƒX—قپjپثپ@‹Œگlپi= ‘Oƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒX—قپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پثپ@Œ»گ¶گl—قپi= گVگlپAƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒX
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ژيپjپثپ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh‚جŒأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پi= “ى•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپjپثپ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ گVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپi= –k•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپjپB
پiپث “ꕶŒnپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث Œأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= “ى•ûƒ‚ƒ“ ƒSƒچƒCƒhپjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث Œ´“ْ–{گlپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث “ْ–{گlپjپBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ْ–{گlƒ‹پ[ƒcپEƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@“ꕶ•¶‰»پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚à‚ٌ‚ش‚ٌ‚©پjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پs“ْ–{‚ج•¶‰»پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚i‚n‚l‚n‚mپ@‚b‚t‚k‚s‚t‚q‚dپD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@“ꕶ•¶‰»‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–ٌ‚P–œ‚Q‚O‚O‚O”N‘Oپ`‹IŒ³‘O
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚Sگ¢‹Iچ پi–ٌ‚Q‚S‚O‚O”N‘Oپj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژٹْ‚ج•¶‰»‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث “ْ–{‚ج•¶‰»پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@“ꕶ•¶‰»‚ئ‚حپAپ@“ْ–{‚ج“ꕶژ‘م
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جژٹْ‚ةپ@پi–ٌ‚P–œ‚Q‚O‚O‚O”N‘O‚©‚ç‹I
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ³‘O‚Sگ¢‹Iچ پi–ٌ‚Q‚S‚O‚O”N‘Oپj‚ـ‚إ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ٹش‚ةپjپAپ@“ْ–{’nˆوپ@پi“ْ–{–{“yپA“ىگ¼
ڈ”“‡پA–kٹC“¹پjپ@‚ة‹ڈڈZ‚µ‚ؤ‚¢‚½پAŒأ
ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپi= “ى•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپj‚ج
گlپXپiگl—قپjپA‘¦‚؟پA“ꕶگl‚ھ’z‚«ڈم
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚°‚½•¶‰»‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@“ꕶپE–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒnپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚à‚ٌپE‚â‚و‚¢‚ئ‚ç‚¢پE‚±‚ٌ‚¯‚آ‚¯‚¢پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ŒأپEگVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhچ¬ŒŒ‚جپu“ꕶپE–يگ¶
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“n—ˆپEچ¬ŒŒŒn‚ج–يگ¶گlپvپAپ@ŒأپEگVƒ‚ƒ“ƒSƒچ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒCƒhچ¬ŒŒ‚جپu“ꕶپE–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒn‚جŒأ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘م“ْ–{گlپvپAپ@ŒأپEگVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhچ¬ŒŒ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پu“ꕶپE–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒn‚جپu–{“y“ْ–{گlپv
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚âپu—®‹…گlپvپ@‚جگl—قپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiگl—قٹwڈم‚ج•ھ—قپE“ء’¥پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi“ْ–{گl‚جƒ‹پ[ƒcپjپB
پs“ْ–{ڈيڈZ–¯‚ج“ْ–{گlپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚s‚g‚dپ@‚i‚n‚l‚n‚m‚j‚d‚h-‚x‚`‚x‚n‚h‚s‚n‚q‚`‚h‚j‚d‚hپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚l‚h‚w‚d‚cپ@‚q‚`‚b‚h‚`‚kپ@‚o‚d‚n‚o‚k‚dپD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@“ْ–{‚جپA“ꕶپE–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒn‚جگlپX
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚حپAپ@Œأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپi= “ى•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپj‚جپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ꕶگl‚ئ‚»‚جژq‘·‚جپA“ꕶŒn‚جگlپXپ@‚ئپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ گVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپi= –k•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپj‚جپA“n
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ —ˆŒn–يگ¶گl‚ئ‚»‚جژq‘·‚جپA–يگ¶“n—ˆŒn‚جگl
پX‚ھچ¬ŒŒ‚µ‚ؤŒ`گ¬‚³‚ꂽگl—ق ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@“ْ–{‚جپA“ꕶپE–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒn‚جگlپX
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚حپAپ@–يگ¶ژ‘م‚إ‚حپu“ꕶپE–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ Œn–يگ¶گlپv‚إ‚ ‚èپAپ@Œأ‘م“ْ–{‚إ‚حپu“ꕶپE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ –يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒnŒأ‘م“ْ–{گlپv‚إ‚ ‚èپAپ@’†
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ گ¢“ْ–{‚©‚猻‘م“ْ–{‚ـ‚إ‚جژٹْ‚إ‚حپu–{“y
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{گlپA—®‹…گlپv‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@“ꕶپE–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒn‚جگlپXپi“ْ–{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈيڈZ–¯پj‚ض‚جگi‰»•\پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰»گخ—قگl‰ژپi= ’†گVگ¢ƒzƒ~ƒmƒCƒhپjپثپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گl—ق‚جپA‰ژگlپثپ@Œ´گlپi= ƒzƒ‚پEƒGƒŒƒNƒgپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒX—قپjپثپ@‹Œگlپi= ‘Oƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒX—قپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پثپ@Œ»گ¶گl—قپi= گVگlپAƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒX
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژيپjپثپ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپثپ@“ꕶگlپثپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–يگ¶گlپثپ@Œأ‘م“ْ–{گlپثپ@پu–{“y“ْ–{گlپv
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= –{“yگlپjپA پu—®‹…گlپvپAپuƒAƒCƒkگlپvپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@Œ»‘م“ْ–{گlپi“ْ–{ڈيڈZ–¯پj‚ض‚جگi‰»•\پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰»گخ—قگl‰ژپi= ’†گVگ¢ƒzƒ~ƒmƒCƒhپjپثپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گl—ق‚جپA‰ژگlپثپ@Œ´گlپi= ƒzƒ‚پEƒGƒŒƒNƒg
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒX—قپjپثپ@‹Œگlپi= ‘Oƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒX—قپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پثپ@Œ»گ¶گl—قپi= گVگlپAƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒX
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژيپjپثپ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپثپ@“ꕶگlپثپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–يگ¶گlپثپ@Œأ‘م“ْ–{گlپثپ@’†گ¢“ْ–{گlپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پثپ@‹كگ¢“ْ–{گlپثپ@‹ك‘م“ْ–{گlپثپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ»‘م“ْ–{گlپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh‚ض‚جگi‰»•\پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰»گخ—قگl‰ژپi= ’†گVگ¢ƒzƒ~ƒmƒCƒhپjپثپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ گl—ق‚جپA‰ژگlپثپ@Œ´گlپi= ƒzƒ‚پEƒGƒŒƒNƒg
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ƒX—قپjپثپ@‹Œگlپi= ‘Oƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒX—قپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پثپ@Œ»گ¶گl—قپi= گVگlپAƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒX
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ژيپjپثپ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh‚جŒأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒC ƒh
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پi= “ى•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپjپثپ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ گVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپi= –k•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث Œأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث “ꕶگlپA“ꕶŒnپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث “n—ˆŒn–يگ¶گlپA–يگ¶“n—ˆŒnپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث Œ´“ْ–{گlپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ْ–{گlپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ْ–{گlƒ‹پ[ƒcپEƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@ “ꕶپE–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒn
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–يگ¶گlپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚à‚ٌپE‚â‚و‚¢‚ئ‚ç‚¢پE‚±‚ٌ‚¯‚آ‚¯‚¢
‚â‚و‚¢‚¶‚ٌپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= –يگ¶ژ‘م‚ةپA“ْ–{’nˆو‚ة‹ڈڈZ‚µ‚ؤ‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚½پAپ@ŒأپEگVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhچ¬ŒŒ‚ج“ꕶپE–يگ¶
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “n—ˆپEچ¬ŒŒŒn‚ج–يگ¶گl‚جگl—قپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiگl—قٹwڈم‚ج•ھ—قپE“ء’¥پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi“ْ–{گl‚جƒ‹پ[ƒcپjپB
پs“ْ–{ڈيڈZ–¯‚ج“ْ–{گlپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚s‚g‚dپ@‚i‚n‚l‚n‚m‚j‚d‚h-‚x‚`‚x‚n‚h‚s‚n‚q‚`‚h‚j‚d‚hپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚l‚h‚w‚d‚cپ@‚q‚`‚b‚h‚`‚kپ@‚x‚`‚x‚n‚hپ@‚o‚d‚n‚o‚k‚dپD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@“ꕶپE–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒn–يگ¶گl‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{‚ج–يگ¶ژ‘م‚جژٹْ‚ةپAپ@“ْ–{’nˆو‚ة
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‹ڈڈZ‚µ‚ؤ‚¢‚½پAپ@ŒأپEگVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhچ¬ŒŒ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ꕶپE–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒn‚جگlپXپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث “ꕶپE–يگ¶“n—ˆپEچ¬
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒŒŒnپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث –يگ¶گlپjپBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث Œأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث “ꕶگlپA“ꕶŒnپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث “n—ˆŒn–يگ¶گlپA–يگ¶“n—ˆŒnپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث Œ´“ْ–{گlپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ْ–{گlپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ْ–{گlƒ‹پ[ƒcپEƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@ “ꕶپE–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒn
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œأ‘م“ْ–{گlپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚à‚ٌپE‚â‚و‚¢‚ئ‚ç‚¢پE‚±‚ٌ‚¯‚آ‚¯‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚±‚¾‚¢‚ة‚ظ‚ٌ‚¶‚ٌپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= Œأ‘م“ْ–{‚جژٹْ‚ةپA“ْ–{’nˆو‚ة‹ڈڈZ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚µ‚ؤ‚¢‚½پAپ@ŒأپEگVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhچ¬ŒŒ‚ج“ê
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ •¶پE–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒn‚ج“ْ–{گl‚جگl—قپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiگl—قٹwڈم‚ج•ھ—قپE“ء’¥پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi“ْ–{گl‚جƒ‹پ[ƒcپjپB
پs“ْ–{ڈيڈZ–¯‚ج“ْ–{گlپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚s‚g‚dپ@‚i‚n‚l‚n‚m‚j‚d‚h-‚x‚`‚x‚n‚h‚s‚n‚q‚`‚h‚j‚d‚hپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚l‚h‚w‚d‚cپ@‚q‚`‚b‚h‚`‚kپ@‚`‚m‚b‚h‚d‚m‚sپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚i‚`‚o‚`‚m‚d‚r‚dپ@‚o‚d‚n‚o‚k‚dپD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= Œأ‘م“ْ–{‚جژٹْ‚ةپA“ْ–{’nˆو‚ة‹ڈڈZ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚µ‚ؤ‚¢‚½پAپ@ŒأپEگVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhچ¬ŒŒ‚ج“ê
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ •¶پE–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒn‚ج“ْ–{گl‚جگl—قپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@“ꕶپE–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒnŒأ‘م“ْ–{گl
‚حپA Œأ‘م“ْ–{‚جژٹْ‚ةپA“ْ–{’nˆو‚ة‹ڈ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ڈZ‚µ‚ؤ‚¢‚½پAپ@ŒأپEگVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhچ¬ŒŒ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ꕶپE–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒn‚ج‚جگlپX‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث “ꕶپE–يگ¶“n—ˆپEچ¬
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒŒŒnپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث Œأ‘م“ْ–{گlپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث Œأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث “ꕶگlپA“ꕶŒnپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث “n—ˆŒn–يگ¶گlپA–يگ¶“n—ˆŒnپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث Œ´“ْ–{گlپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ْ–{گlپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ْ–{گlƒ‹پ[ƒcپEƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@“ꕶ•¶‰»پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚à‚ٌ‚ش‚ٌ‚©پjپBپ@پs“ْ–{‚ج•¶‰»پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚i‚n‚l‚n‚mپ@‚b‚t‚k‚s‚t‚q‚dپD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@–ٌ‚P–œ‚Q‚O‚O‚O”N‘Oپ`–ٌ‚Q‚S‚O‚O
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”N‘Oپi‹IŒ³‘O‚Sگ¢‹Iچ پjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث “ْ–{‚ج•¶‰»پjپB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@ڈً–ٌ‰üگ³پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚â‚‚©‚¢‚¹‚¢پjپBپ@پsڈً–ٌپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ڈً–ٌ‰üگ³‚ئ‚حپA–¾ژ،ژ‘م
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جڈً–ٌ‰üگ³–â‘è‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ڈً–ٌ‰üگ³‚ئ‚حپA–‹––پA“ْ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ –{‚ھ‰¢•ؤ‚ئ’÷Œ‹‚µ‚½•s•½“™
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ڈً–ٌ‚ج‰üگ³پiژ،ٹO–@Œ ‚ج“P”pپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ٹضگإژ©ژهŒ ‚ج‰ٌ•œ‚ب‚اپj‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@پuڈً–ٌ‰üگ³پvپ@پi‚¶‚ه‚¤‚â‚‚©‚¢‚¹
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¢پj‚ئ‚حپAپ@ –‹––پA“ْ–{‚ھ‰¢•ؤ‚ئ’÷Œ‹
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚µ‚½•s•½“™ڈً–ٌ‚ج‰üگ³پ@پiژ،ٹO–@Œ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج“P”pپAٹضگإژ©ژهŒ ‚ج‰ٌ•œ‚ب‚اپj‚إپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚èپA–¾ژ،ژ‘م‚جڈً–ٌ‰üگ³–â‘è‚إ‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@•s•½“™ڈً–ٌ‚ج‰üگ³‚ئ‚حپAپ@–‹––
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ة“ْ–{‚جچ]Œث–‹•{‚ھ‰¢•ؤڈ”چ‘‚ئ’²
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆَ‚µ‚½پuکaگeڈً–ٌپvپAپuڈCچD’تڈ¤ڈً–ٌ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiˆہگ‚جŒـƒJچ‘ڈً–ٌپjپvپAپu‰üگإ–ٌڈ‘پv
پ@پ@‚ج•s•½“™ڈً–ٌ‚ة‘خ‚µچs‚ي‚ꂽپA“ْ–{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹ك‘مگ•{‚ج–¾ژ،ژ‘م‚ج‰üگ³چsˆ×‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@کaگeڈً–ٌ‚جپuˆê•û“IچإŒbچ‘‘ز
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹ِپvپi‚¢‚غ‚¤‚ؤ‚«‚³‚¢‚¯‚¢‚±‚‚½‚¢‚®‚¤پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جڈًٹ¼‚ھپA•s•½“™ڈً–ٌ‰üگ³‚ًچ¢“ï
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ة‚µ‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@–¾ژ،ژ‘م––‚ـ‚إ‚ةپA“ْ–{‚ھ–‹––
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ة‰¢•ؤڈ”چ‘‚ئ’²ˆَ‚µ‚½•s•½“™ڈً–ٌ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ظ‚ع‰üگ³‚³‚ꂽپB
پ@
پ›پ@‚µ‚هپ@پ@گ³—ïپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚è‚ل‚پjپBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚r‚g‚n‚q‚x‚`‚j‚tپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ ‚X‚X‚O”Nپ[‚X‚X‚T”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚X‚X‚O”NپEگ³—”NپE‚P‚PŒژپ@‚V“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚X‚X‚T”NپEگ³—ï ‚U”NپEپ@‚QŒژ‚Q‚Q“ْپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@•½ˆہژ‘م’†ٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@ڈ³—ïپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚è‚ل‚پjپBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚i‚n‚q‚x‚`‚j‚tپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ ‚P‚O‚V‚V”Nپ[‚P‚O‚W‚P”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚P‚O‚V‚V”NپEڈ³—”NپE‚P‚PŒژ‚P‚V“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚P‚O‚W‚P”NپEڈ³—ï ‚T”NپEپ@‚QŒژ‚P‚O“ْپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@•½ˆہژ‘م’†ٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@
پ›پ@‚µ‚هپ@پ@ ”‰—ت‰ف•¼پB
پ@پi‚µ‚ه‚¤‚è‚ه‚¤‚©‚ض‚¢پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پs“ْ–{—¬’ت‰ف•¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث چ]Œثژ‘م‚ج“ْ–{—¬’ت
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@‰ف•¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث “ْ–{—¬’ت‰ف•¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@پu”‰—ت‰ف•¼پvپi‚µ‚ه‚¤‚è‚ه‚¤‚©‚ض‚¢پj‚ئ‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹M‹à‘®‚ج•iˆت‚ًˆê’è‚ة’è‚كژوˆّ‚«‚ج“s“x
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈd—ت‚ً‚ح‚©‚ء‚ؤژg—p‚µ‚½‰ف•¼‚إ‚ ‚èپAپ@‹M
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹à‘®‰ف•¼‚جڈd—ت‚ً—تپi‚ح‚©پj‚ء‚ؤژg—p‚³‚ê
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚½‚¨‹àپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@پuچ]Œثژ‘م‚ج”‰—ت’تڈي‰ف•¼ پv‚ئ‚حپAچ]
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œثژ‘م‚ةپA“ْ–{‚إپA ‹â‰ف‚ب‚ا‚ج‹M‹à‘®‰ف
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•¼‚جڈd—ت‚ً—تپi‚ح‚©پj‚ء‚ؤژg—p‚³‚ꂽ’تڈي
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰ف•¼پi‚¨‹àپjپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@پuچ]Œثژ‘م‚ج”‰—ت’تڈي‰ف•¼پv‚حپAپ@چ]
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œث–‹•{’’‘¢پE”چsپE‘Sچ‘’ت—pپE—¬’ت‰ف•¼‚جپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’ڑ‹âپi‚؟‚ه‚¤‚¬‚ٌپjپAپ@“¤”آ‹âپi‚ـ‚ك‚¢‚½‚¬
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ٌپjپAپ@Œـ–و‹âپi‚²‚à‚ٌ‚ك‚¬‚ٌپjپ@‚ب‚ا‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ›پ@‚µ‚هپ@پ@پ@ڈ—رژ›پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚è‚ٌ‚¶پjپB پ@پsژ›‰@پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ‹àچ„‘Tڈ—رژ›پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ’ژRڈ—رژ›پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ ڈ—رژ›‚ئ‚حپA‹àچ„‘T
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚±‚ٌ‚²‚¤‚؛‚ٌپjڈ—رژ›پi“ْ–{پjپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ’ژRپi‚·‚¤‚´‚ٌپjڈ—رژ›پi’†
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ‘پj‚ب‚ا‚ج•§‹³ژ›‰@‚إ‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‹àچ„‘Tڈ—رژ›پi“ْ–{پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚حپAپ@“ْ–{پEژlچ‘‚جچپگى
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ§‘½“x’أ’¬‚جڈ—رژ›‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‹àچ„‘Tڈ—رژ›پi“ْ–{پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚حپAپ@“ْ–{گlپEڈ@“¹گbپi‚»‚¤
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ا‚¤‚µ‚ٌپj‚ھپA گيŒمپA–k‘T‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘Tڈ@‚ًٹJ‚¢‚½ژ›‰@ ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‹àچ„‘Tڈ—رژ›پi“ْ–{پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚حپAپ@ڈ@–ه‚جچsپi‚µ‚م‚¤‚à‚ٌ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚¬‚ه‚¤پj‚ج پuڈ—رژ›Œ–@پv‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’†گS’n‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@
پ›پ@‚µ‚هپ@پ@پ@ڈ—رژ›Œ–@پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚è‚ٌ‚¶‚¯‚ٌ‚غ‚¤پj پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پsˆص‹طچsپAڈ@–ه‚جچsپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ڈ—رژ›Œ–@‚ئ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–k‘T‚ج‘Tڈ@ژ›‰@‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پu‹àچ„‘Tڈ—رژ›پi“ْ–{پjپv
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إپAچہ‘Tچs‚ئ•ہ‚رپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پuڈ@–ه‚جچsپvپi‚µ‚م‚¤‚à‚ٌ‚ج‚¬‚ه
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¤پj‚ئ‚µ‚ؤچs‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚é
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ–@پiˆص‹طچsپi‚¦‚«‚«‚ٌ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¬‚ه‚¤ پjپAŒڈp‚ئڈ_ڈpپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ڈ—رژ›Œ–@‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ’ژRڈ—رژ›پi’†چ‘پj‚جپuڈ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–ه‚جچsپv‚جپuڈ—رŒپv‚ئ‚ح
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘S‚•ت‚ج‹Z–@‘جŒn‚ً‚à‚آپB
پ@
پ›پ@‚µ‚هپ@پ@گ¶—ق—÷‚ف‚ج—كپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚é‚¢‚ ‚ي‚ê‚ف‚ج‚ê‚¢پjپBپ@پs–@—كپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “؟گىچj‹gپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@چ]Œث–‹•{پE‘و‚T‘مڈ«ŒRپE“؟گى
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چj‹g‚ھڈo‚µ‚½پAگlٹشپE“®•¨‚جگ¶–½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘¸ڈdٹضŒW‚ج‘½گ”‚ج–@—كپi‚¨گG‚êپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‘چڈجپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@پuگ¶—ق—÷‚ê‚ج—كپvپ@پi‚µ‚ه‚¤‚é‚¢‚ ‚ي‚ê‚ف
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‚ê‚¢پj‚ئ‚حپAپ@چ]Œث–‹•{پE‘و‚T‘مڈ«ŒRپE“؟گى
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چj‹g‚ھڈo‚µ‚½پAگlٹشپE“®•¨‚جگ¶–½‘¸ڈdٹضŒW
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‘½گ”‚ج–@—كپi‚¨گG‚êپj‚ج‘چڈج‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@پuگ¶—ق—÷‚ê‚ج—كپvپi‚µ‚ه‚¤‚é‚¢‚ ‚ي‚ê‚ف‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ê‚¢پj‚ئ‚حپAپ@چ]Œث–‹•{پE‘و‚T‘مڈ«ŒR“؟گىچj‹g
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ھ‚P‚U‚W‚T”N‚©‚ç‚Q‚O”Nˆبڈم‚ة‚©‚¯‚ؤپA–ٌ‚P‚R‚T
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰ٌ‚ة•ھ‚¯‚ؤ”—ك‚µ‚½ŒنگGڈ‘پi‚¨‚س‚ê‚ھ‚«پj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘چڈج‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ›پ@‚µ‚هپ@پ@گ³کZˆتپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚ë‚‚¢پjپB پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کZˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@
پ›پ@‚µ‚هپ@پ@گ³کZˆت‰؛پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚ë‚‚¢‚ج‚°پjپB پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کZˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³کZˆتڈمپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚ë‚‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپB پsˆتٹKپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کZˆتپAˆتٹKپAڈ–ˆتپjپB
پ@
پ›پ@‚µ‚هپ@پ@گ³کaپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚يپjپBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ ‚P‚R‚P‚Q”Nپ[‚P‚R‚P‚V”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚P‚R‚P‚Q”NپEگ³کaŒ³”NپE‚RŒژ‚Q‚O“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚P‚R‚P‚V”NپEگ³کa ‚U”NپE‚QŒژپ@‚R“ْپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ٹ™‘qژ‘مŒمٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@’هکaپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚يپA‚ؤ‚¢‚يپjپBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‚P‚R‚S‚T ”Nپ[‚P‚R‚T‚O”N پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ى–k’©‹£چ‡“ٌڈd”Nچ†پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï‚ج“ٌڈd”Nچ†‘¶—§پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@“ى–k’©‹£چ‡“ٌڈd”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@–k’©پ@پiژ–¾‰@“پj•û‚ج—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚P‚R‚S‚T”NپE’هکaŒ³”NپE‚P‚OŒژ‚Q‚P“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚R‚T‚O”NپE’هکa ‚U”NپEپ@‚QŒژ‚Q‚V“ْپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ژ؛’¬ژ‘م‘Oٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@پi’چˆسپjپ@“¯ژٹْ‚ةپA“ى’©پ@پi‘هٹoژ›“پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œم‘çŒي“VچcŒn“پj•û‚ج—ï”Nچ†‚جپA‹»چ‘
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚±‚¤‚±‚پjŒ³”Nپ`‚V”Nپi‚P‚R‚S‚Oپ`‚P‚R‚S‚U”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پثپ@گ³•½پi‚µ‚ه‚¤‚ض‚¢پjŒ³”Nپ`‚Q‚T”Nپi‚P‚R‚S
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚Uپ`‚P‚R‚V‚O”Nپjپ@‚à‘¶—§‚·‚éپBپ@
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@ڈ³کaپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚يپjپBپ@پ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚s‚g‚dپ@‚i‚n‚v‚`پ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ ‚W‚R‚S”Nپ[‚W‚S‚W”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚W‚R‚S”NپEڈ³کa Œ³”NپE‚PŒژپ@‚R“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚W‚S‚W”NپEڈ³کa‚P‚T”NپE‚UŒژ‚P‚R“ْپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@•½ˆہژ‘م‘Oٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@
پ›پ@‚µ‚هپ@پ@ڈ؛کaپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚يپjپBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚r‚g‚n‚v‚`پ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ ‚P‚X‚Q‚U”Nپ[‚P‚X‚W‚X”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚P‚X‚Q‚U”NپEڈ؛کa Œ³”NپE‚P‚QŒژ‚Q‚T“ْپ`
پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚X‚W‚X”NپEڈ؛کa‚U‚S”NپEپ@‚PŒژپ@‚V“ْپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ڈ؛کaژ‘م‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@ڈ؛کaپ@پi‚µ‚ه‚¤‚يپA‰pپF ‚s‚g‚dپ@
‚r‚g‚n‚v‚`پ@‚d‚q‚`پjپ@‚ئ‚حپAکa—ï‚إ‚ ‚èپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ؛کaژ‘م‚جکa—ï”Nچ†‚إ‚ ‚èپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚X‚Q‚U”NپEڈ؛کaŒ³”NپE‚P‚QŒژ‚Q‚T“ْ‚©‚ç
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚X‚W‚X”NپEڈ؛کa‚U‚S”NپE‚PŒژپ@‚V“ْ‚ـ‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ ‚éپBپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@پqڈ؛کa”Nچ†‚جپAکa—ïپ¨گ¼—ïپ^
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ¼—ïپ¨کa—ï‚ج‘¬ژZ–@پrپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ڈ؛کa ‚`”Nپ{‚P‚X‚Q‚T”Nپپگ¼—ï ‚a”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@گ¼—ï ‚a”Nپ[‚P‚X‚Q‚T”Nپپڈ؛کa ‚`”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@پuڈ؛کaپv‚ج‘OŒم‚جکa—ï”Nچ†پiŒ³چ†پjپF
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@‘هگ³پ@پi‚½‚¢‚µ‚ه‚¤پjپF
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚X‚P‚Q”Nپ|‚P‚X‚Q‚U”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚X‚P‚Q”NپE‘هگ³ Œ³”NپEپ@‚VŒژ‚R‚O“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚P‚X‚Q‚U”NپE‘هگ³‚P‚T”NپE‚P‚QŒژ‚Q‚T“ْپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@•½گ¬پ@پi‚ض‚¢‚¹‚¢پjپF
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚X‚W‚X”Nپ|‚P‚X‚P‚Q”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚X‚W‚X”NپE•½گ¬ Œ³”NپEپ@‚PŒژپ@‚W“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚Q‚O‚P‚X”NپE•½گ¬‚R‚P”NپEپ@‚SŒژ‚R‚O“ْپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‹كŒ»‘م“ْ–{‚جکa—ï”Nچ†پiŒ³چ†پjپF
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œc‰Œ³”Nپ`پ@‚S”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚W‚U‚T”Nپ`‚P‚W‚U‚W”Nپjپثپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–¾ژ،Œ³”Nپ`‚S‚T”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚W‚U‚W”Nپ`‚P‚X‚P‚Q”Nپjپث
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘هگ³Œ³”Nپ`‚P‚T”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚X‚P‚Q”Nپ`‚P‚X‚Q‚U”Nپjپث
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ؛کaŒ³”Nپ`‚U‚S”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚X‚Q‚U”Nپ`‚P‚X‚W‚X”Nپjپث
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•½گ¬Œ³”Nپ`‚R‚P”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚X‚W‚X”Nپ` ‚Q‚O‚P‚X”Nپjپث
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—كکaŒ³”Nپ` Œ»چف
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚Q‚O‚P‚X”Nپ`Œ»چفپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ ڈ؛کaژ‘مپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ه‚¤‚ي‚¶‚¾‚¢پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پi= ‚P‚X‚Q‚U”Nپ[‚P‚X‚W‚X”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پiڈ؛کaپEگي‘Oژ‘مپ@‚ئپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ؛کaپEگيŒمژ‘مپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پs“ْ–{—ًژj‚جژ‘م‹و•ھپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚r‚g‚n‚v‚`پ@‚o‚d‚q‚h‚n‚cپD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پƒ‹ك‘م“ْ–{پAŒ»‘م“ْ–{پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ڈ؛کaپEگي‘Oژ‘مپjپB پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ‹ك‘م“ْ–{پjپB پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ڈ؛کaپEگيŒمژ‘مپjپB پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث Œ»‘م“ْ–{پjپB پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ْ–{—ًژj‚جژ‘م‹و•ھپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ڈ؛کaژ‘مپ@پi‚µ‚ه‚¤‚ي‚¶‚¾‚¢پj ‚ئ‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚X‚Q‚U”Nپiڈ؛کaŒ³”Nپj‚©‚ç‚P‚X‚W‚X”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiڈ؛کa‚U‚S”Nپj‚ـ‚إ‚جٹْٹش‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ڈ؛کaژ‘م‚حپAپ@‹ك‘م“ْ–{پi= –¾
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ،ژ‘مپA‘هگ³ژ‘مپAڈ؛کaپEگي‘Oژ‘مپG
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚W‚U‚W”Nپ[‚P‚X‚S‚T”Nپjپ@‚âپAپ@Œ»‘م پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{پi= ڈ؛کaپEگيŒمژ‘مپA•½گ¬ژ‘مپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—كکaژ‘مپG‚P‚X‚S‚T”Nپ[Œ»چفپjپ@‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆêژٹْ‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ڈ؛کaژ‘مپ@ پi‚µ‚ه‚¤‚ي‚¶‚¾‚¢پj‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚X‚Q‚U”Nپiڈ؛کaŒ³”Nپj‚©‚ç‚P‚X‚W‚X”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiڈ؛کa‚U‚S”Nپj‚ـ‚إ‚جٹْٹش‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ؛کaپE گي‘Oژ‘مپi‚P‚X‚Q‚U”Nپ|‚P‚X‚S‚T
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”Nپjپ@‚ئپAپ@ڈ؛کaپEگيŒمژ‘مپi‚P‚X‚S‚T”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ|‚P‚X‚W‚X”Nپjپ@‚ة•ھ‚©‚ê‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ ڈ؛کaپEگيŒمژ‘مپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ه‚¤‚يپE‚¹‚ٌ‚²‚¶‚¾‚¢پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ پi= ‚P‚X‚S‚T”Nپ[‚P‚X‚W‚X”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پs“ْ–{—ًژj‚جژ‘م‹و•ھپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚o‚n‚r‚s‚v‚`‚qپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚r‚g‚n‚v‚`پ@‚o‚d‚q‚h‚n‚cپD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پƒڈ؛کaژ‘مپAŒ»‘م“ْ–{پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ڈ؛کaژ‘مپjپB پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث Œ»‘م“ْ–{پjپB پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ڈ؛کaپEگي‘Oژ‘مپjپB پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ْ–{—ًژj‚جژ‘م‹و•ھپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ڈ؛کaپEگيŒمژ‘مپ@ پi‚µ‚ه‚¤‚يپE‚¹‚ٌ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@‚²‚¶‚¾‚¢پj‚ئ‚حپAپ@‚P‚X‚S‚T”Nپiڈ؛کa‚Q‚O
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@”Nپj‚©‚ç‚P‚X‚W‚X”Nپiڈ؛کa‚U‚S”Nپj‚ـ‚إ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ٹْٹش‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ڈ؛کaپEگيŒمژ‘م‚حپAپ@Œ»‘م“ْ–{پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ڈ؛کaپEگيŒمژ‘مپA•½گ¬ژ‘مپA—كکa
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ‘مپG‚P‚X‚S‚T”Nپ[Œ»چفپjپ@‚جˆêژٹْ‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ڈ؛کaژ‘مپ@ پi‚µ‚ه‚¤‚ي‚¶‚¾‚¢پj‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚X ‚Q‚U”Nپiڈ؛کaŒ³”Nپj‚©‚ç‚P‚X‚W‚X”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiڈ؛کa‚U‚S”Nپj‚ـ‚إ‚جٹْٹش‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ؛کaپEگي‘Oژ‘مپi‚P‚X‚Q‚U”Nپ|‚P‚X‚S‚T
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”Nپjپ@‚ئپAپ@ڈ؛کaپEگيŒمژ‘مپi‚P‚X‚S‚T”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ|‚P‚X‚W‚X”Nپjپ@‚ة•ھ‚©‚ê‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ ڈ؛کaگي‘Oٹْ‚ج‹Œ“ْ–{ŒR
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ه‚¤‚ي‚¹‚ٌ‚؛‚ٌ‚«‚ج‚«‚م‚¤‚ة‚ظ‚ٌ‚®‚ٌ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¶‚ء‚½‚¢‚ھ‚¢‚ا‚ش‚ء‚پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پs‹ك‘م“ْ–{ƒKƒCƒhƒuƒbƒNپtپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ ڈ؛کaپEگي‘Oژ‘مپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ پi‚µ‚ه‚¤‚يپE‚¹‚ٌ‚؛‚ٌ‚¶‚¾‚¢پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ پi= ‚P‚X‚Q‚U”Nپ[‚P‚X‚S‚T”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پs“ْ–{—ًژj‚جژ‘م‹و•ھپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚s‚g‚dپ@‚o‚q‚d‚v‚`‚qپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚r‚g‚n‚v‚`پ@‚o‚d‚q‚h‚n‚cپD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پƒڈ؛کaژ‘مپA‹ك‘م“ْ–{پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ڈ؛کaژ‘مپjپB پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ‹ك‘م“ْ–{پj پB پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ڈ؛کaپEگيŒمژ‘مپjپB پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ْ–{—ًژj‚جژ‘م‹و•ھپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ڈ؛کaپEگي‘Oژ‘مپ@پi‚µ‚ه‚¤‚يپE‚¹‚ٌ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚؛‚ٌ‚¶‚¾‚¢پj‚ئ‚حپAپ@‚P‚X‚Q‚U”Nپiڈ؛کaŒ³
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”Nپj‚©‚ç‚P‚X‚S‚T”Nپiڈ؛کa‚Q‚O”Nپj‚ـ‚إ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹْٹش‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ڈ؛کaپEگي‘Oژ‘م‚حپAپ@‹ك‘م“ْ–{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= –¾ژ،ژ‘مپA‘هگ³ژ‘مپAڈ؛کaپEگي‘O
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ‘مپG‚P‚W‚U‚W”Nپ[‚P‚X‚S‚T”Nپjپ@‚جˆêژ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹْ‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ڈ؛کaژ‘مپ@ پi‚µ‚ه‚¤‚ي‚¶‚¾‚¢پj‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚X ‚Q‚U”Nپiڈ؛کaŒ³”Nپj‚©‚ç‚P‚X‚W‚X”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiڈ؛کa‚U‚S”Nپj‚ـ‚إ‚جٹْٹش‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ؛کaپE گي‘Oژ‘مپi‚P‚X‚Q‚U”Nپ|‚P‚X‚S‚T
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”Nپjپ@‚ئپAپ@ڈ؛کaپEگيŒمژ‘مپi‚P‚X‚S‚T”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ|‚P‚X‚W‚X”Nپjپ@‚ة•ھ‚©‚ê‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ ڈ؛کa“VچcپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚ي‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پjپBپ@پs“VچcپtپB
پ@پi= —Tگm“Vچc ‚ذ‚ë‚ذ‚ئ‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث —Tگm“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ڈ؛کa“Vچcپi= —Tگm“Vچcپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚ج“VچcچفˆتپF
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚P‚X‚Q‚U ”Nپ`‚P‚X‚W‚X”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ڈ؛کa“Vچcپi‚µ‚ه‚¤‚ي‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“VچcچفˆتپF‚P‚X‚Q‚U ”Nپ`‚P‚X‚W‚X”Nپj‚ئ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—Tگm“Vچcپi‚ذ‚ë‚ذ‚ئ‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پj ‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@پ@ڈ—‰¤پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¨‚¤پjپBپ@پs“Vچc‰ئپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@چc‘°‚جڈ—ژqپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@پi—لپjپ@”اژqڈ—‰¤پ@پi‚ح‚ٌ‚µ‚¶‚ه‚¨
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¤پA ٹ؛•گ“Vچc‚ج‘·–؛پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث “Vچc‰ئپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث چc‘°پA‰¤پAڈ—‰¤پAچcژqپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ گe‰¤پA“àگe‰¤پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ڈ—‰¤پi‚¶‚ه‚¨‚¤پj‚ئ‚حپAچc‘°‚جڈ—ژq‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جپA“àگe‰¤‚ئڈ—‰¤پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘O‹ك‘م“ْ–{پi“ق—اپ`چ]Œثژ‘مپj‚جپA“à
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گe‰¤پi‚ب‚¢‚µ‚ٌ‚ج‚¤پj‚حپA“àگe‰¤گé‰؛‚ًژَ‚¯
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚½چc‘°‚إ‚ ‚èپAژه‚ةپA“Vچc‚جڈ—گ«چcژq‚âژo
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–…‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆê•ûپA‘O‹ك‘م“ْ–{ پi”ٍ’¹پ`چ]Œثژ‘مپj‚جپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ—‰¤پi‚¶‚ه‚¨‚¤پj‚ئ‚حپA ڈ—گ«چc‘°‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جپi“ق—اپ`چ]Œثژ‘مپj‚جپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“àگe‰¤‚ئڈ—‰¤پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج“ق—اژ‘م‚©‚çچ]Œثژ‘م
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ـ‚إ‚حپA‘ه•َ—ك‚ج—¥—كگ§ˆبŒم‚حپA“àگe‰¤
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گé‰؛پi‚ب‚¢‚µ‚ٌ‚ج‚¤‚¹‚ٌ‚°پj‚ًژَ‚¯‚½چc‘°
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ—ژqپ@پiژه‚ة“Vچc‚جڈ—گ«چcژqپi‚ف‚±پAچcڈ—پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚âژo–…پj‚ًپA“àگe‰¤پi‚ب‚¢ ‚µ‚ٌ‚ج‚¤پj‚ئŒؤ‚رپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚»‚êˆبٹO‚جچc‘°‚جڈ—ژqپi“àگe‰¤گé‰؛‚ھ‚ب
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¢چc‘°ڈ—ژqپj‚ًڈ—‰¤ پi‚¶‚ه‚¨‚¤پj‚ئŒؤ‚شڈêچ‡
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ھ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پqڈ—‰¤پi‚¶‚ه‚¨‚¤پj‚ج—لپrپ@“Vچc‚ج‘·
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚ـ‚²پjپA‘\‘·پi‚ذ‚ـ‚²پj‚جڈ—ژqپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گEˆُ—ك‚جˆتٹKپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ه‚‚¢‚ٌ‚ê‚¢‚ج‚¢‚©‚¢پjپBپ@پsˆتٹKپtپB
پ@پ،پ@گEˆُ—كپ@پi‚µ‚ه‚‚¢‚ٌ‚ê‚¢پj‚ئ‚حپAپ@‹ك‘م
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{گ•{‚جپAˆتٹK‚ب‚ا‚ً’è‚ك‚½–@—ك‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‹ك‘م“ْ–{‚جپAگEˆُ—كپi‚P‚W‚U‚X”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ§’èپj‚ج‚Q‚OˆتٹKپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@پƒ‚P‚W‚U‚X”Nچ پ`‚P‚W‚W‚V”Nچ پAژg—pپ„پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚P‚W‚U‚X”Nگ§’è‚جگEˆُ—ك‚©‚ç‚P‚W‚W‚V”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ§’è‚جڈ–ˆتڈً—ل‚ض‚ج•دچX‚ـ‚إپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‹ك‘م“ْ–{‚جپAگEˆُ—كپi‚P‚W‚U‚X”Nگ§’èپj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚Q‚OˆتٹK‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈمˆتڈ‡‚ةپAپ@گ³ˆêˆتپAپ@ڈ]ˆêˆتپAپ@گ³“ٌˆتپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ڈ]“ٌˆتپAگ³ژOˆتپAڈ]ژOˆتپAگ³ژlˆتپAڈ]ژlˆتپA
پ@پ@ پ@گ³ŒـˆتپAڈ]ŒـˆتپAگ³کZˆتپAڈ]کZˆتپAگ³ژµˆتپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ڈ]ژµˆتپAگ³”ھˆتپAڈ]”ھˆتپAگ³‹مˆتپAڈ]‹مˆتپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‘هڈ‰ˆتپAڈڈ‰ˆتپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ˆêˆتپA“ٌˆتپAژOˆتپAژlˆتپAŒـˆتپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ کZˆتپAژµˆتپA”ھˆتپA‹مˆتپAڈ‰ˆتپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ˆتٹK—ك ‚جˆتٹKپAڈ–ˆتڈً—ل ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆتٹKپA’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj ‚جˆتٹKپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@گEˆُ—ك‚جˆتٹKپi‚µ‚ه‚‚¢‚ٌ‚ê‚¢‚ج ‚¢‚©
‚¢پj‚حپAپ@‹ك‘م“ْ–{‚جˆتٹK‚إ‚ ‚èپAپ@‚Q‚OˆتٹK
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ ‚èپAپ@‚P‚W‚U‚X”Nچ ‚©‚ç‚P‚W‚W‚V”Nچ ‚ـ‚إژg
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—p‚³‚ꂽپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‹ك‘م“ْ–{‚جگEˆُ—ك‚ج ‚Q‚OˆتٹK‚حپAپ@‘O‹ك
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘م“ْ–{‚جپA’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj‚جˆتٹKپi‚V‚O‚P”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ پ`‚P‚W‚U‚X”Nچ ژg—pپA‚R‚OˆتٹKپj‚ً‰ü‚ك‚ؤپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚W‚U‚X”N‚ةگ§’肳‚êپAپ@‚P‚W‚U‚X”Nگ§’è‚جگEˆُ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—ك‚©‚ç‚P‚W‚W‚V”Nگ§’è‚جڈ–ˆتڈً—ل ‚ض‚ج•دچX‚ـ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إژg—p‚³‚ꂽپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گD–Lژ‘مپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚‚ظ‚¤‚¶‚¾‚¢پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ˆہ“y“چژRژ‘مپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پs“ْ–{—ًژj‚جژ‘م‹و•ھپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ˆہ“y“چژRژ‘مپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گD–LگŒ پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚‚ظ‚¤‚¹‚¢‚¯‚ٌپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پs“ْ–{—ًژj‚جگŒ پEگ•{پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= گD“cپiژپپjگŒ ‚ئ–LگbپiژپپjگŒ پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث گD“cگŒ پA–LگbگŒ پjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈٹژiپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚µپjپBپ@پs•گژmگŒ ‚جگE–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ پ@ژ؛’¬–‹•{‚جژکڈٹ‚ج’·ٹ¯پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ژ؛’¬–‹•{‚جŒRژ–پEŒxژ@پ@‚âپ@‹پi“sپj‚جŒx
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”ُپEچظ”»پ@‚ً’S‚¤ گژ،‹@ٹض‚إ‚ ‚éپAژکڈٹپi‚³
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ق‚ç‚¢‚ا‚±‚ëپj‚ج’·ٹ¯پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ پ@ٹ™‘q–‹•{‚جژکڈٹ‚جژںٹ¯پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ٹ™‘q–‹•{‚جپAŒن‰ئگlپiڈ«ŒR‰ئگbپj‚ج“گ§
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚âپ@ŒRژ–پEŒxژ@پ@‚ً’S‚¤گژ،‹@ٹض‚إ‚ ‚éپAژک
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈٹپi‚³‚ق‚ç‚¢‚ا‚±‚ëپj‚جژںٹ¯پB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@پ@ڈ—گ«‚جژپ–¼پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚ه‚¹‚¢‚ج‚µ‚ك‚¢پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پs‘O‹ك‘م“ْ–{‚جژپ–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گl–¼پjپB
پ@پ@پ@ پ@پ@پ@ پiپث ‘O‹ك‘م“ْ–{‚جڈ—گ«
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژپ–¼پjپB
پ@پ@پ@ پ@پ@پ@ پiپث ‰ئ•ƒ’·گ§‚ج•v•w•تگ©پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جڈ—گ«‚حپAٹµڈK
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إپA’تڈيپAŒآگl–¼‚إ‚ج‚فژ©‘¼Œؤ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈج‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚إ‚حپiچ]Œثژ‘م
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆب‘O‚إ‚حپjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ—گ«‚حپA’تڈيپi“ْڈيگ¶ٹˆ‚إ‚حپjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–¼ژڑ‚ًژg‚ي‚¸پA–¼‚ج‚ف‚إژ©‘¼
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œؤڈج‚·‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi—لپjپ@چض“،”üچط‚ئ‚¢‚¤ڈ—گ«‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پuژ„‚حپA”üچط‚إ‚·پBپv
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘¼گl‚©‚ç‚حپAپu‚¨”üچطپv‚ئŒؤ‚خ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ê‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{پiچ]Œثژ‘مˆب‘Oپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‰ئ•ƒ’·گ§‚ج•v•w•تگ©پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج‰ئ•ƒ’·گ§‚جژ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹْ‚جڈ—گ«‚حپAپ@•v•w•تگ©‚إ‚ ‚è
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiŒ‹چ¥‚µ‚ؤ‚à–¼ژڑ‚ً•د‚¦‚¸پjپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ—گ«‚ج•ƒ‚جˆê‘°–¼پiژپپE–¼ژڑپj‚ً
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ¶ٹUڈٹژ‚µ‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@‚P‚W‚V‚Q”Nپi–¾ژ،‚T”Nپj‚PŒژ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œثگذ–@پiگpگ\Œثگذپjژ{چsژپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œµٹi‚ب••Œڑژذ‰ï‚ج‰ئ•ƒ’·گ§‚ھژc
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚é“–ژپAŒ‹چ¥‚ة‚و‚èپA‘¼‰ئ‚جڈ—گ«
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ةپA–¼—_‚ ‚éپA‰ئ–¼پiˆê‘°–¼پj‚ً—^
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¦‚邱‚ئ‚ة‚حپA–¾ژ،ژ‘مڈ‰ٹْ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{ژذ‰ï‚إ‚حپA”ٌڈي‚ة”½‘خ‚ھ‹
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚©‚ء‚½‚ھپAپ@“ْ–{‹ك‘م‰»گچô پi•¶
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–¾ٹJ‰»پj‚ج‚½‚كپA‹ك‘م•v•w“¯گ©‚ھپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژں‘و‚ة”F‚ك‚ç‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ء‚½پB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@پ@ڈ—گ«“VچcپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¹‚¢‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پjپBپ@پs“VچcپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پi= ڈ—’éپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپj‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚Wگl‚P‚O‘م‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ پ@“ْ–{‚جڈ—گ«“Vچcپ@
پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰و‘œƒAƒ‹ƒoƒ€پ@‚m‚ڈپD‚PپB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پںپ@ڈ—گ«“Vچcپ@پi‚Wگl‚P‚O‘مپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث گ„Œأپi‚·‚¢‚±پj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث چc‹ةپiگؤ–¾پjپi‚±‚¤‚¬‚ه‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚³‚¢‚ك‚¢پjپj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ژ“پi‚¶‚ئ‚¤پj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث Œ³–¾پi‚°‚ٌ‚ك‚¢پj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث Œ³گ³پi‚°‚ٌ‚µ‚ه‚¤پj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث چFŒھپiڈج“؟پjپi‚±‚¤‚¯‚ٌ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚ئ‚پjپj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث –¾گ³پi‚ك‚¢‚µ‚ه‚¤پj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث Œمچ÷’¬پi‚²‚³‚‚ç‚ـ‚؟پj“VچcپjپB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@“ْ–{‚إ‚حپA—DڈG‚بڈ—گ«“Vچc
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ڈ—’éپj‚ھ‘½‚¢پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@“ْ–{‚إ‚حپA”ٍ’¹”’–Pژ‘مپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ق—اژ‘مپAچ]Œثژ‘م‚ة“Vچc‚ة
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘¦ˆت‚µ‚½پA‚Wگl‚P‚O‘م‚جڈ—گ«“Vچc
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ڈ—’éپj‚ھ‚¢‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ڈdâNپi‚؟‚ه‚¤‚»پAچؤ‘¦ˆتپj‚µ‚½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپj‚ھ‚Qگl‚¢‚é
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‚إپA‚P‚O‘م‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@•ƒŒnڈ—گ«“Vچc‚حپA‚Vگl‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”ٍ’¹”’–Pژ‘م‚جگ„Œأ“VچcپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چc‹ةپiگؤ–¾پj“VچcپAژ““VچcپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ق—اژ‘م‚جŒ³–¾“VچcپAچFŒھ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiڈج“؟پj“VچcپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ]Œثژ‘م‚ج–¾گ³“VچcپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œمچ÷’¬“Vچc‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@•êŒnڈ—گ«“Vچc‚حپA1گl‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ق—اژ‘م‚جŒ³گ³“Vچc‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@“ْ–{‚جڈ—گ«“Vچc‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژں‚ج‚Wگl‚P‚O‘م ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@Œأ‘م“ْ–{‚ج”ٍ’¹”’–Pژ‘مپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ق—اژ‘م‚جڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚Pپjپ@گ„Œأپi‚·‚¢‚±پj“Vچcپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiچفˆتپF‚T‚X‚Q”Nپ`‚U‚Q‚W”NپjپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚Qپjپ@چc‹ةپiگؤ–¾پjپi‚±‚¤‚¬‚ه‚پi‚³‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ك‚¢پjپj“Vچcپ@
پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiچفˆتپF‚U‚S‚Q”Nپ`‚U‚S‚T”NپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚U‚T‚T”Nپ`‚U‚U‚U”NپjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚Rپjپ@ژ“پi‚¶‚ئ‚¤پj“Vچcپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiچفˆتپF‚U‚X‚Oپ`‚U‚X‚V”NپjپAپ@
پi‚Sپjپ@Œ³–¾پi‚°‚ٌ‚ك‚¢پj“Vچcپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiچفˆتپF‚V‚O‚Vپ`‚V‚P‚T”NپjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚Tپjپ@Œ³گ³پi‚°‚ٌ‚µ‚ه‚¤پj“Vچcپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiچفˆتپF‚V‚P‚Tپ`‚V‚Q‚S”NپjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚Uپj چFŒھپiڈج“؟پjپi‚±‚¤‚¯‚ٌ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚ئ‚پjپj“Vچc
پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پiچفˆتپF‚V‚S‚X”Nپ`‚V‚T‚W”NپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚V‚U‚S”Nپ`‚V‚V‚O”NپjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‹كگ¢“ْ–{‚جچ]Œثژ‘م
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚Vپjپ@–¾گ³پi‚ك‚¢‚µ‚ه‚¤پj“Vچcپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiچفˆتپF‚P‚U‚Q‚X”Nپ`‚P‚U‚S‚R”NپjپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚Wپjپ@Œمچ÷’¬پi‚²‚³‚‚ç‚ـ‚؟پj“Vچcپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiچفˆتپF‚P‚V‚U‚Q”Nپ`‚P‚V‚V‚O”NپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈ”‘àپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚½‚¢پjپBپ@پs’·ڈB”ثپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ڈ”‘à‚ئ‚حپAپ@–‹––‚جپA’·ڈB”ث‚ج–¯•؛
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ”•”‘à‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ”‘à‚حپAپ@’·ڈB”ث‚جگ³‹KŒR‚إ‚ح‚ب‚¢پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”_چHڈ¤‚ئ•گژm‚ئ‚جچ¬گ¬–¯•؛ڈ”•”‘à‚إ‚ ‚ء
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚½پBپ@چ‚گ™گWچى‘nگف‚جٹï•؛‘à‚àپAڈ”‘à‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚آ‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@پ@ڈ—’éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚ؤ‚¢پjپBپ@پs“VچcپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ڈ—گ«“VچcپjپB
پ@پ@پ@ پ@پiپث ڈ—گ«“VچcپjپBپ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ڈ—’éپi= ڈ—گ«“Vچcپj‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚Wگl‚P‚O‘م‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پںپ@ڈ—گ«“Vچcپ@پi‚Wگl‚P‚O‘مپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ڈ—گ«“VچcپjپBپ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث گ„Œأپi‚·‚¢‚±پj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث چc‹ةپiگؤ–¾پjپi‚±‚¤‚¬‚ه‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚³‚¢‚ك‚¢پjپj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ژ“پi‚¶‚ئ‚¤پj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث Œ³–¾پi‚°‚ٌ‚ك‚¢پj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث Œ³گ³پi‚°‚ٌ‚µ‚ه‚¤پj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث چFŒھپiڈج“؟پjپi‚±‚¤‚¯‚ٌ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚ئ‚پjپj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث –¾گ³پi‚ك‚¢‚µ‚ه‚¤پj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث Œمچ÷’¬پi‚²‚³‚‚ç‚ـ‚؟پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“VچcپjپB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@“ْ–{‚إ‚حپA—DڈG‚بڈ—گ«“Vچc
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ڈ—’éپj‚ھ‘½‚¢پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@“ْ–{‚إ‚حپA”ٍ’¹”’–Pژ‘مپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ق—اژ‘مپAچ]Œثژ‘م‚ة“Vچc‚ة
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘¦ˆت‚µ‚½پA‚Wگl‚P‚O‘م‚جڈ—گ«“Vچc
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ڈ—’éپj‚ھ‚¢‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ڈdâNپi‚؟‚ه‚¤‚»پAچؤ‘¦ˆتپj‚µ‚½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپj‚ھ‚Qگl‚¢‚é
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‚إپA‚P‚O‘م‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@•ƒŒnڈ—گ«“Vچc‚حپA‚Vگl‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”ٍ’¹”’–Pژ‘م‚جگ„Œأ“VچcپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چc‹ةپiگؤ–¾پj“VچcپAژ““VچcپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ق—اژ‘م‚جŒ³–¾“VچcپAچFŒھ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiڈج“؟پj“VچcپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ]Œثژ‘م‚ج–¾گ³“VچcپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œمچ÷’¬“Vچc‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@•êŒnڈ—گ«“Vچc‚حپA1گl‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ق—اژ‘م‚جŒ³گ³“Vچc‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈں”¦ڈéپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚خ‚½‚¶‚ه‚¤پjپBپ@پsڈéپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ڈں”¦ڈéپi‚µ‚ه‚خ‚½‚¶‚ه‚¤پj‚حپAگD“cگM
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’·‚ھگ¶‚ـ‚ꂽڈé‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ڈں”¦ڈéپi‚µ‚ه‚خ‚½‚¶‚ه‚¤پj‚حپA”ِ’£چ‘
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¨‚ي‚è‚ج‚‚ةپAˆ¤’mŒ§گ¼•”‚ج‘ٹ“–’nˆوپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جٹC“ŒŒS‚ئ’†“‡ŒSپ@پiŒ»پEˆ¤’mŒ§ˆ¤گ¼ژs
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈں”¦’¬‚ئˆî‘ٍژs•½کa’¬پj‚ةˆت’u‚·‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@ڈ—کYپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚낤پA‚¶‚ه‚ëپjپBپ@پs—Vڈ—پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= —Vڈ—پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث —Vڈ—پjپB
پ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@ƒWƒ‡ƒ“–œژںکYپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚ٌ‚ـ‚ٌ‚¶‚낤پjپBپ@پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ’†•l–œژںکYپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚W‚Q‚Vپ`‚P‚W‚X‚W”NپjپB
پ@
پ@
پZپ@‚µ‚çپ@پ@”’‰ح–@‰¤پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ç‚©‚ي‚ظ‚¤‚¨‚¤پjپBپ@پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ”’‰ح‰@پA
”’‰حڈمچcپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”’‰ح“Vچcپi”’‰ح’éپjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’هگmپi‚³‚¾‚ذ‚ئپjگe‰¤پj پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi•½ˆہژ‘مŒمٹْ‚ج–@‰¤پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ڈمچcپA“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiگ¶–v”NپF
‚P‚O‚T‚R”Nپ`‚P‚P‚Q‚X”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‰@گگژ،ٹْپF
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚O‚W‚U”Nپ`‚P‚P‚Q‚X”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@–@چc پF
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚O‚X‚U”Nپ`‚P‚P‚Q‚X”NپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ڈمچc پF
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚O‚W‚U”Nپ`‚P‚P‚Q‚X”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@“VچcچفˆتپF
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚O‚V‚Q”Nپ`‚P‚O‚W‚U”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@”’‰ح–@‰¤پiڈمچcپA“Vچcپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi’هگmپi‚³‚¾‚ذ‚ئپjگe‰¤ پj‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒمژOڈًپi‚²‚³‚ٌ‚¶‚ه‚¤پj“Vچc‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چcژqپi‚ف‚±پj‚إ‚ ‚éپB
پ›پ@”’‰ح–@‰¤پiڈمچcپA“Vچcپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚حپA–x‰ح“Vچc‚ج•ƒ‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@”’‰ح–@‰¤پiڈمچcپA“Vچcپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚حپA’¹‰H“Vچc‚ج‘c•ƒ‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ› ”’‰ح–@‰¤پiڈمچcپA“Vچcپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚حپAگ’“؟پE‹ك‰qپEŒم”’‰ح“V
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چc‚ج‘]‘c•ƒ‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚çپ@پ@”’ڈF ژںکYپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ç‚· ‚¶‚낤پjپBپ@پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‹كŒ»‘م‚جگژ،‰ئپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚X‚O‚Qپ`‚P‚X‚W‚T”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‹ك‰q •¶–›‚جƒuƒŒپ[ƒ“پB
پ@ پ›پ@‹g“c –خ‚ج‘¤‹كپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@“ْ–{گ•{‚ج‘خ‚f‚g‚pŒًڈآ–ًپB
پ@
پZپ@‚µ‚çپ@پ@”’”ڈژqپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ç‚ر‚ه‚¤‚µپjپBپ@پs—Vڈ—پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@•½ˆہژ‘مپ`ژ؛’¬ژ‘م‚جپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ •‘‚¢‰ج‚¤—Vڈ—پB
پ@
پZپ@‚µ‚èپ@پ@ژ،—ïپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚è‚ل‚پjپBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚s‚g‚dپ@‚i‚h‚q‚x‚`‚j‚tپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ ‚P‚O‚U‚T”Nپ[‚P‚O‚U‚X”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚P‚O‚U‚T”NپEژ،—”NپE‚WŒژپ@‚Q“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚P‚O‚U‚X”NپEژ،—ï ‚T”NپE‚SŒژ‚P‚R“ْپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@•½ˆہژ‘مŒمٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@
پZپ@‚µ‚èپ@پ@ژj—؟
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚è‚ه‚¤پjپBپ@پs—ًژjٹwپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@ژj—؟پ@پi‚µ‚è‚ه‚¤پj‚ئ‚حپAپ@—ًژj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ژ‘—؟پAƒfپ[ƒ^‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚ëپ@پ@ڈéپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ëپjپBپ@پs“ْ–{‚جڈéپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi—جژه‚جŒRژ–پE“ژ،پiژx
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”zپjپE‹ڈڈZ‹’“_پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@ڈé‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ گي‚¢‚جچشپi‚ئ‚è‚إپj‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@••Œڑ—جژه‚جŒRژ–‹’“_پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ژ،پiژx”zپj‹’“_پA‹ڈڈZ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹’“_‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@ڈé‚ة‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژRڈéپi‚â‚ـ‚¶‚ëپj‚ئ•½ڈéپi‚ذ‚ç
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¶‚ëپj‚ھ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@ڈé‚ة‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–{ڈéپi‚ظ‚ٌ‚¶‚ه‚¤پj‚ئژxڈéپi‚µ‚¶
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ه‚¤پAڈoڈéپj‚ھ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@گيڈê‚إ‚حپAگwڈéپi‚¶‚ٌ‚¶
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ëپj‚ھ‘¢‚ç‚ê‚邱‚ئ‚ھ‚ ‚éپB
پiپث ڈ¬’JڈéپA–kڈ¯ڈéپjپB
پiپث •PکHڈéپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جڈéپ@پi‚µ‚ëپj‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“G‚ئگي‚¤‚½‚كپA“G‚©‚çژç‚邽‚ك‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œڑ’z•¨‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@ڈéپ@پi‚µ‚ëپj‚ئ‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گي‚¢‚جچشپi‚ئ‚è‚إپj‚إ‚ ‚èپA••Œڑ—ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژه‚جŒRژ–‹’“_پA“ژ،پiژx”zپj‹’“_پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹ڈڈZ‹’“_ ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœ چ]Œث–‹•{‚جˆêچ‘ˆêڈé—ك‚ھڈo‚³
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ê‚é‘O‚جپAژ؛’¬ژ‘مŒمٹْپi=گيچ‘
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ‘مپjپAˆہ“y“چژRژ‘مپAچ]Œثژ‘م
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ‰ٹْ‚ةŒکŒإپi‚¯‚ٌ‚²پj‚بڈé‚ھ‘½‚‚آ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚‚ç‚êپA‚»‚جŒڑ•¨‚ھŒ»چف‘½‚ژc‚ء‚ؤ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¢‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@ڈé‚ة‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژRڈéپi‚â‚ـ‚¶‚ëپAژR‚ةŒڑ‚ؤ‚½ڈéپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ئپ@•½ڈéپi‚ذ‚炶‚ëپA•½’n‚ةŒڑ‚ؤ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚½ڈéپj‚ھ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@ڈé‚ة‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–{ڈéپ@پi‚ظ‚ٌ‚¶‚ه‚¤پA–{‹’’n‚جڈéپjپ@
پ@پ@ پ@‚ئپAپ@ژxڈéپi‚µ‚¶‚ه‚¤پA= ڈoڈéپi‚إ‚¶
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ëپjپjپ@‚ھ‚ ‚éپB
پ@پ@پœپ@–{ڈéپ@پi‚ظ‚ٌ‚¶‚ه‚¤پj‚ئ‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—جژه‚ھ–{‹’’n‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚éڈé‚إ‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚èپAپ@ژxڈéپ@پi‚µ‚¶‚ه‚¤پA= ڈoڈéپi‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¶‚ëپjپj‚ئ‚حپAپ@–{ڈé‚ًژç‚é‚و‚¤‚ة
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”z’u‚³‚ꂽ•âڈ•“I–ًٹ„‚ً‚à‚آڈé
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@گ–±‹ڈڈéپ@پi‚¹‚¢‚ق‚«‚ه‚¶‚ه
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¤پj‚ئ‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–{ڈé‚ج‘¼‚ةپAگ–±‚ًچs‚¤‚½‚ك
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ة—جژه‚ھ‹ڈڈZ‚µ‚½ڈé‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ڈé‚ة‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚پپjپ@–{ڈéپ@پi‚ظ‚ٌ‚¶‚ه‚¤پA–{‹’’n
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚جڈéپjپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚‚پjپ@ژxڈéپ@پi‚µ‚¶‚ه‚¤پA–{ڈé‚ً–h
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‰q‚·‚邽‚ك‚جڈéپjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚ƒپjپ@گ–±‹ڈڈéپ@پi‚¹‚¢‚ق‚«‚ه‚¶‚ه
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚¤پAگ–±‚ًچs‚¤‚½‚ك‚جڈéپjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ب‚ا‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚ëپ@پ@پ@ژںکY–@ژtپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚낤‚ظ‚¤‚µپjپBپ@پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ˆنˆة’¼ŒصپA—S‰~پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@‚i‚‰‚’‚ڈ‚ˆ‚ڈ‚“‚ˆ‚‰پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ˆنˆة’¼ŒصپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پiپث ˆنˆةژپپAˆنˆة’¼گپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ›پ@ˆنˆة’¼Œص‚جڈo‰ئ–¼پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ،پ@ژںکY–@ژtپ@پi‚¶‚낤‚ظ‚¤‚µپj‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiˆنˆة’¼Œصپ@‚¢‚¢ ‚ب‚¨‚ئ‚çپA—S‰~پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆنˆةژپژb’è“–ژهپF‚P‚T‚U‚T”Nپ[
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚T‚W‚Q”NپAگ¶–v”NپFگ¶”N•sڈعپ[
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚T‚W‚Q”NپA‰“چ]چ‘پEˆنˆة’J پi‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¢‚ج‚âپj‚جڈ——جژهپj ‚جڈo‰ئ–¼‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚ëپ@پ@پ@ڈéژRپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ë‚â‚ـپjپBپ@پsژR’n–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@‚l‚”پD‚r‚ˆ‚‰‚’‚ڈ‚™‚پ‚چ‚پپD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ‹تڈéپi‚½‚ـ‚¶‚ه‚¤پjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پiپثپ@گwڈéپi‚¶ ‚ٌ‚¶‚ëپjپjپB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ،پ@ڈéژRپ@پi‚µ‚ë‚â‚ـپj‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹٍ•ŒŒ§ٹضƒPŒ´’¬‚جژR’†’n‹وپE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹ت’n‹و‚ة‚ ‚éژR‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈéژR‚حپA ”ü”Zچ‘پi‚ف‚ج‚ج‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ةپj‚جژR’†‘؛پ@پi‚â‚ـ‚ب‚©‚ق‚çپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ٹٍ•ŒŒ§ٹضƒ–Œ´’¬ژR’†’n‹وپj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@•t‹ك‚ة‚ ‚é’لژR‚إ‚ ‚éپBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ،پ@ڈéژRپ@پi‚µ‚ë‚â‚ـپj‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پuژjژہپiگVگàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚إپAگ¼ŒR پi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ھپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ’z‚¢‚½ٹùگ¬ڈ€”ُگw’n‚إ‚ ‚é
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‹تڈéپi‚½‚ـ‚¶‚ه‚¤پj‚ھ’u‚©‚ꂽ
ڈêڈٹ‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@ پ،پ@‹تڈéپ@پi‚½‚ـ‚¶‚ه‚¤پj‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ژjژہپiگVگàپjٹضƒPŒ´‚جگي‚¢پi‘هٹ_پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ژR’†‚جگي‚¢پj‚جŒˆگي‚جژR’†‚جگي
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚¢‚إ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹تڈé‚ًژg—p‚µ‚½‚ھپA‹تڈé‚©‚ç
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ گ¼ŒR‚ھڈoŒ‚‚µ‚ؤگي‚ء‚½‚©پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ـ‚½‚حپA‹تڈé‚ًژg—p‚µ‚ب‚©‚ء‚½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚©پA‚ا‚؟‚ç‚©‚ج‰آ”\گ«‚ھچ‚‚¢پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@گ¼ŒR‚ح‹تڈé‚إâؤڈ邹‚¸پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ژR’†‘؛•t‹ك‚ة‚حپAپ@ٹضƒ–Œ´
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جگي‚¢ژپAڈéژRپi‚µ‚ë‚â‚ـپj‚ة
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ھ’z‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚½ٹùگ¬ڈ€”ُگw’n‚جپAگwڈéپi‚¶‚ٌ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¶‚ëپAگw’n‚جڈéپj‚ج‹تڈéپi‚½‚ـ‚¶
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ه‚¤پj‚ھ‚ ‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚µ‚©‚µپA‹تڈé‚ة‚حپAڈ\•ھ‚ب
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•؛—ئپi‚ذ‚ه‚¤‚è‚ه‚¤پj‚ئگ…پiˆنŒثپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—N‚«گ…پj‚ھ‚ب‚پAپ@گ¼ŒRپi•ٍچs
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج–ٌ‚Q–œگl‚ج•؛‚ھ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@âؤڈé‚·‚é‚ة‚حپA•sڈ\•ھ‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œك‘O‚P‚Oژچ پ`گ³Œكچ ‚جژR’†
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘؛‚إ‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢‚جŒˆگيژ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ة‚حپAگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚حپA
‹تڈé‚ًژg—p‚µ‚ب‚©‚ء‚½‚©پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚ـ‚½‚حپA‹تڈé‚ًژg—p‚µ‚½‚ھپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گD“cڈGگM‚جٹٍ•ŒڈéڈoŒ‚‚ج‚و‚¤‚ةپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹تڈé‚©‚çگ¼ŒR‚ھڈoŒ‚‚µ‚ؤگي‚ء‚½
‰آ”\گ«‚ھچ‚‚¢پB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@پuژjژہپiگVگàپjٹضƒ–Œ´‚جگي
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپv‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@Œˆگي‚إ‚ج پAگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@—ک•ûپj‚جژه—حŒR‚ج“®‚«پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جژه—حŒRپ@پiڈ¬گ¼پAگخ“cپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰Fٹى‘½پA“‡’أ“™‚جŒRپjپ@‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‡@پ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جژه—حŒR‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚S“ْ–é‚ةپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘هٹ_ƒGƒٹƒA‚ج‘هٹ_ڈéپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¨‚¨‚ھ‚«‚¶‚ه‚¤پAٹضƒ–Œ´
–~’n‚ج“Œ•ûپj‚ًڈo”
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚XŒژ‚P‚S“ْ–éپjپث
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ›پ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚XŒژ‚P‚S“ْ–é‚ةپA‘هٹ_ڈé‚إپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹¦‹c‚µ‚ؤپAگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•ûپj‚ًپAژه—حŒR‚ئ‘هٹ_ڈéژç”ُ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژc—¯ŒR‚ج‚Q‚آ‚ة•ھ‚¯‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ›پ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژه—حŒR‚حپAژR’†‘؛پ@پi‚â‚ـ‚ب‚©
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ق‚çپAٹضƒ–Œ´–~’n‚جگ¼•ûپE–ٌ‚Q
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚‹‚چپjپ@‚ةŒü‚©‚¤پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ›پ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘هٹ_ڈéژç”ُژc—¯ŒR‚حپA‘هٹ_ڈé
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ةژc—¯‚µپA‘هٹ_ڈé‚ًژç”ُ‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‡Aپ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژه—حŒR‚حپA‚XŒژ‚P‚T“ْ–¢–¾‚ةپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژR’†‘؛پ@پi‚â‚ـ‚ب‚©‚ق‚çپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹضƒ–Œ´–~’n‚جگ¼•ûپE–ٌ‚Q‚‹‚چپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ة•zگw‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پZپ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژه—حŒR‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژR’†‘؛•t‹ك‚جڈéژR‚ة‚ ‚é
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹù‘¶ڈ€”ُگw’n‚ج‹تڈéپi‚½‚ـ‚¶
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ه‚¤پj‚ًپAڈoŒ‚گw’n‚ئ‚µ‚ؤژg—p
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚µ‚½‰آ”\گ«‚ھ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚XŒژ‚P‚T“ْ–¢–¾پjپث
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‡Bپ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژه—حŒR‚حپA‚XŒژ‚P‚T“ْŒك‘O‚P‚O
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژچ ‚©‚çگ³Œكچ ‚ـ‚إپAژR’†‘؛
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إپA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚جژه—حŒR‚ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒًگيپiŒˆگي‚ًچs‚¤پjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚XŒژ‚P‚T“ْŒك‘O‚P‚Oژچ پ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ³Œكچ پjپث
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‡Cپ@‚XŒژ‚P‚T“ْگ³Œكچ پAژR’†‘؛
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إپAگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE –ر—ک•ûپj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژه—حŒR‚حپA‘چ•ِ‚êپA”s‘–پA”s
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گي‚ئ‚ب‚èپA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژه—حŒR‚ھ‚ةگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE –ر
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—ک•ûپj‚جژه—حŒR‚ة‘خ‚µŒˆگي‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈں—ک‚ً“¾‚é
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚XŒژ‚P‚T“ْگ³Œكچ پjپB
پ@
پZپ@‚µ‚ٌپ@پ@گM‰z’n•ûپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ٌ‚¦‚آ‚؟‚ظ‚¤پjپBپ@ پsŒ»’nˆو–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= ’·–ىŒ§‚ئگVٹƒŒ§پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= ’·–ىŒ§پiگM”Zچ‘پj پAگVٹƒŒ§
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‰zŒمچ‘ پAچ²“nچ‘پj‚ج’nˆوپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ،پ@گM‰z’n•ûپ@پi‚µ‚ٌ‚¦‚آ‚؟‚ظ‚¤ پj‚ئ‚حپA ’·–ى
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@Œ§پiگM”Zچ‘پj پAگVٹƒŒ§پi‰zŒمچ‘پAچ²“nچ‘پj‚ج’n
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ˆو‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پœپ@ڈمگM‰z’n•ûپ@پi ‚¶‚ه‚¤‚µ‚ٌ‚¦‚آ‚؟‚ظ‚¤پj‚ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@ ‚حپAپ@ŒQ”nŒ§پiڈم–ىچ‘پj پA’·–ىŒ§پiگM”Zچ‘پjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گVٹƒŒ§پi‰zŒمچ‘پAچ²“nچ‘پj‚ج’nˆو ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پœپ@چbگM‰z’n•ûپ@پi‚±‚¤‚µ‚ٌ‚¦‚آ‚؟‚ظ‚¤ پj‚ئ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژR—œŒ§پiچb”مچ‘پj پA’·–ىŒ§پiگM”Zچ‘پjپAگVٹƒ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@ Œ§پi‰zŒمچ‘پAچ²“nچ‘پj‚ج’nˆو ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پœپ@–k—¤’n•ûپ@پi‚ظ‚‚è‚‚؟‚ظ‚¤ پj‚ئ‚حپAپ@گVٹƒ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@Œ§پE•xژRŒ§پEگخگىŒ§پE•ںˆنŒ§‚ج–k—¤‚SŒ§پA‚ـ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚½‚حپA•xژRŒ§پEگخگىŒ§پE•ںˆنŒ§‚ج–k—¤‚RŒ§پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi–k—¤“¹پE ‹ŒچLˆو’n•ûپjپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پœپ@–kگM‰z’n•ûپi‚ظ‚‚µ‚ٌ‚¦‚آ‚؟‚ظ ‚¤پj‚ئ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ –k—¤گM‰z’n•ûپ@پi‚ظ‚‚è‚‚µ‚ٌ‚¦‚آ‚؟‚ظ‚¤پj‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚ ‚èپAپ@•xژRŒ§پEگخگىŒ§پE•ںˆنŒ§‚ج–k—¤‚RŒ§
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi–k—¤“¹پE ‹ŒچLˆو’n•û‚جˆê•”پjپA’·–ىŒ§پiگM
پ@ ”Zچ‘پjپAگVٹƒŒ§پi‰zŒمچ‘ پAچ²“nچ‘پj‚ًچ‡‚ي‚¹‚½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’nˆو‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚ٌپ@پ@گV‰E‰q–هپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ٌ‚¦‚à‚ٌپjپBپ@پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ’ثŒ´–m“`پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@گV‰E‰q–ه‚حپAŒ•چ‹‚ج’ثŒ´–m
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“`پi‚آ‚©‚ح‚ç‚ع‚‚إ‚ٌپj‚ج’تڈجپiژڑپi‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚´‚بپjپA‚ ‚¾–¼پj‚ج‚P‚آ ‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@
پZپ@‚µ‚ٌپ@پ@“aپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ (‚µ‚ٌ‚ھ‚èپjپBپ@پsŒR‘àپtپB
پ@پi= ˆê”شŒم‚ëپAچإŒمپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹àƒ–چè‚ج‘ق‚«ŒûپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ’r“cڈںگ³پA–LگbڈG‹gپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–¾’qŒُڈGپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@“a(‚µ‚ٌ‚ھ‚èپj ‚ئ‚حپAŒR‘à‚ًˆّ‚«ڈم‚°‚é
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چغپiŒR‘à‚ھ‘ق‚‚ئ‚«پjپAŒR‘à‚جچإŒم”ِ‚ة‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ء‚ؤپA’ا‚ء‚ؤ‚‚é“G‚ً–h‚®‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@“a(‚µ‚ٌ‚ھ‚èپjŒR‚حپA‘ق‹p‚·‚é–{‘à‚ًپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”wŒم‚©‚ç—ˆ‚é“G‚©‚çژç‚é–ً–عپi–ًٹ„پj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•”‘à‚إ‚ ‚éپBپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@‹àƒ–ْ±‚ج‘قŒûپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“a(‚µ‚ٌ‚ھ‚èپj‚ج—ل‚ئ‚µ‚ؤپA‹àƒ–چè‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘ق‚«Œûپi‚©‚ث‚ھ‚³‚«‚ج‚«‚®‚؟پj‚جچغپA’r“c
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈںگ³پi‚¢‚¯‚¾‚©‚آ‚ـ‚³پjپA–ط‰؛“،‹gکYڈG
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹gپi–LگbڈG‹gپjپA–¾’qŒُڈG‚ب‚ا‚ج•”‘à‚ھپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“aپi‚µ‚ٌ‚ھ‚èپj‚ً–±پi‚آ‚ئپj‚ك‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گيچ‘ژ‘مپiژ؛’¬ژ‘مŒمٹْپj‚ج‚P‚T
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚V‚O”NپiŒ³‹TŒ³”Nپj‚SŒژ‚ةپA‰z‘Oچ‘پE“ض‰ê
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¦‚؟‚؛‚ٌ‚ج‚‚ةپE‚آ‚é‚ھپA•ںˆنŒ§“Œ•”
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج“ض‰êژsپj‚ج‹àƒ–چèپi‚©‚ث‚ھ‚³‚«پj‚إپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گD“cگM’·ŒR‚ھپA’©‘qŒR‚ئگَˆنŒR‚ة‹²
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚ح‚³پj‚ـ‚ê‚ؤچUŒ‚‚³‚êپA‹‡’n‚ة—§‚ء‚½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژپAگD“cگM’·ŒR‚جپA’r“cڈںگ³پi‚¢‚¯‚¾
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚©‚آ‚ـ‚³پjژwٹِ‰؛پA–ط‰؛“،‹gکYڈG‹g
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹gپi–LگbڈGپjپA–¾’qŒُڈG‚ب‚ا‚ج•”‘à‚ھپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“aپi‚µ‚ٌ‚ھ‚èپj‚ً–±پi‚آ‚ئپj‚كپAگD“cگM’·
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚âگD“c–{‘à‚ًژç‚èپA–³ژ–‚ة“¦‚ھ ‚·Œ÷‚ً
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚°‚½پB
پ@
پZپ@‚¶‚ٌپ@پ@گ_‹TپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚ٌ‚«پjپBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚s‚g‚dپ@‚i‚h‚m‚j‚hپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@‚V‚Q‚S”Nپ[‚V‚Q‚X”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@‚V‚Q‚S”NپEگ_‹TŒ³”NپE‚QŒژ‚S“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚V‚Q‚X”NپEگ_‹T ‚U”NپE‚WŒژ‚T“ْپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پœپ@“ق—اژ‘م‘Oٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@
پZپ@‚µ‚ٌپ@پ@گV‹پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ٌ‚«‚ه‚¤پjپBپ@پs“sژsپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ’·ڈtپi‚؟‚ه‚¤‚µ‚م‚ٌپAƒ`ƒƒƒ“ƒ`ƒ…ƒ“پjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi–ڈBپi’†چ‘“Œ–k•”پj‚ج“sژsپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@’·ڈtپi‚؟‚ه‚¤‚µ‚م‚ٌپAƒ`ƒƒƒ“ƒ`ƒ…ƒ“پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج•ت–¼پi‹Œ–¼پA‚P‚X‚R‚Qپ`‚S‚T”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@گV‹پi ‚µ‚ٌ‚«‚ه‚¤پj‚حپAپ@’·ڈtپi‚؟‚ه‚¤‚µ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚م‚ٌپAƒ`ƒƒƒ“ƒ`ƒ…ƒ“پj‚ج•ت–¼پi‹Œ–¼پA‚P‚X‚R‚Q
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ`‚S‚T”Nپjپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@گV‹پi ‚µ‚ٌ‚«‚ه‚¤پA’·ڈtپj‚حپA–ڈB(= ’†
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ‘“Œ–k•”پj‚ج‹g—رپi‚«‚آ‚è‚ٌپAƒ`پ[ƒٹƒ“پjڈب
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج“sژsپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@گV‹پi ‚µ‚ٌ‚«‚ه‚¤پA’·ڈtپj‚حپAپ@“ْ–{‚جکّ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@™Sپi‚©‚¢‚ç‚¢پjچ‘‰ئپE–ڈBچ‘پi‚ـ‚ٌ‚µ‚م‚¤‚±‚پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚X‚R‚Qپ`‚S‚T”Nپj‚جژٌ•{پiژٌ“sپj‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@
پZپ@‚µ‚ٌپ@پ@گV‹{ڈ\کYپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ٌ‚®‚¤‚¶‚م‚¤‚낤پjپBپ@پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= Œ¹ چs‰ئپi‚ف‚ب‚à‚ئ‚ج ‚ن‚«‚¢‚¦پjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‰ح“àŒ¹ژپپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث Œ¹ چs‰ئپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚ٌپ@پ@گ_ŒNپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ٌ‚‚ٌپjپB پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= “؟گى‰ئچNپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “؟گى‰ئچNپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚ٌپ@پ@گ_ŒNˆة‰ê‰z‚¦پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ٌ‚‚ٌ‚¢‚ھ ‚²‚¦پjپB پs“؟گى‰ئچNپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ˆة‰ê‰z‚¦پA“؟گى‰ئچN
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جˆة‰ê‰z‚¦پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ˆة‰ê‰z‚¦پjپBپ@
پ@
پZپ@‚µ‚ٌپ@پ@گMŒ؛پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ٌ‚°‚ٌپjپB پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= •گ“cگMŒ؛پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث •گ“cگMŒ؛پjپBپ@
پ@
پZپ@‚¶‚ٌپ@پ@گoچ…‹LپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚ٌ‚±‚¤‚«پjپB پ@پsژj—؟پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کaژZپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@گoچ…‹Lپ@پi‚¶‚ٌ‚±‚¤‚«پj‚حپAپ@چ]Œث
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ژ‘م‚ةگ”ٹwƒuپ[ƒ€‚ج‰خ•t‚¯–ً‚ئ‚ب
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ء‚½پAژZڈpڈ‘پEژہ—pگ”ٹwڈ‘‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚ٌپ@پ@گ_ŒىŒi‰_پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚ٌ‚²‚¯‚¢‚¤‚ٌپjپBپ@پsکa—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚s‚g‚dپ@‚i‚h‚m‚f‚n‚j‚d‚h‚t‚mپ@‚d‚q‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@‚V‚U‚Vپ`‚V‚V‚O”NپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@‚V‚U‚V”NپEگ_ŒىŒi‰_Œ³”NپE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚WŒژ‚P‚U“ْپ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚V‚V‚O”NپEگ_ŒىŒi‰_ ‚S”NپE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚OŒژپ@‚P“ْپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@ پœپ@“ق—اژ‘مŒمٹْ‚جکa—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گ¼—ïکa—ï‘خڈئ•\ پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ï”Nچ†•\پE“ْ–{Œê”إپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث کa—ïƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپBپ@
پ@
پZپ@‚µ‚ٌپ@پ@گVŒأچ،کa‰جڈWپBپ@
پi‚µ‚ٌ‚±‚«‚ٌ‚ي‚©‚µ‚م‚¤پjپBپ@پsکa‰جڈWپtپBپ@
پiپث ’؛گïکa‰جڈWپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚ٌپ@پ@گMڈBپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ٌ‚µ‚م‚¤پjپBپ@پs‹Œ’nˆو–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= گM”Z چ‘پi‚µ‚ب‚ج ‚ج‚‚ةپjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپà Œ»پE’·–ىŒ§‚ج‘ٹ“–’nˆوپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi—¥—كگ§’èŒمپEŒأ‘مپE’†گ¢پE‹كگ¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ْ–{پE‹Œ’nˆو–¼‚جپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‹Œچ‘–¼پi—كگ§چ‘پj‚ج•تڈجپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚r‚g‚h‚m‚r‚g‚tپ@‚`‚q‚d‚`پD
پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث گM”Z چ‘پjپBپ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ’·–ىŒ§پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹Œچ‘پi= —كگ§چ‘پjپjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹Œ’nˆو–¼پA’nˆو–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@ پiپث “ْ–{‚ج’n–¼پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@گMڈBپ@پi‚µ‚ٌ‚µ‚م‚¤پj‚حپA پ@—¥—كگ§’è
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒمپEŒأ‘مپE’†گ¢پE‹كگ¢“ْ–{پE‹Œ’nˆو–¼‚جپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹Œچ‘پi—كگ§چ‘پjگ³ژ®–¼‚جپAگM”Z چ‘پ@ پi‚µ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ب‚ج‚ج‚‚ةپjپ@‚ج•تڈج‚إ‚ ‚éپB
پ،پ@گMڈBپi= گM”Z چ‘پj‚حپAپ@“ŒژR“¹پi‚ئ‚¤
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚³‚ٌ‚ا‚¤پjپEچLˆو’n•û‚ة‘®‚µپAŒ»پE’†•”’n
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@•û‚جپAŒ»چف‚ج’·–ىŒ§‚ة‘ٹ“–‚·‚é ’nˆو‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚ٌپ@پ@ گwڈéپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚ٌ‚¶‚ëپjپBپ@پsچ‡گيپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‹تڈéپi‚½‚ـ‚¶‚ه‚¤پjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ژR’†‚جگي‚¢پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث گVگàپiژjژہپjٹضƒPŒ´‚ج
گي ‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي
‚¢پjپjپB
پ@ پ،پ@گwڈéپ@پi‚¶‚ٌ‚¶‚ëپj‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ژ؛’¬ژ‘مŒمٹْپiگيچ‘ژ‘مپj‚âˆہ“y
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“چژRژ‘م‚ةپAگي’n‚ة—صژ‚ةچ\’z
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚³‚ꂽڈé‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@گwڈé‚إ‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گطٹفپi‚«‚肬‚µپjپA’GŒ@پi‚½‚ؤ‚ع‚èپjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“y—غپi‚ا‚é‚¢پj‚ب‚ا‚ج’n–ت‚ج‰ü‘¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ھچs‚ي‚êپAپ@ŒRژwٹِژز“ڈپA‰ïچ‡
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ڈپA•؛ژm‹ڈڈZ‚جگwڈ¬‰®پi‚¶‚ٌ‚²‚âپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ب‚ا‚جƒvƒŒƒnƒu‚جŒڑ•¨‚ھŒڑ‘¢‚³‚ê
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@گwڈé‚ج—ل‚ئ‚µ‚ؤ ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژjژہپiگVگàپjٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پi= ‘هٹ_پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژR’†‚جگي‚¢پjژ‚ة’z‚©‚ꂽپAگ¼ŒR
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج‹تڈéپi‚½‚ـ‚¶
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ه‚¤پj‚ب‚ا‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚ٌپ@پ@گpگ\ŒثگذپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚ٌ‚µ‚ٌ‚±‚¹‚«پjپBپ@پsŒثگذپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ (‚P‚W‚V‚P”Nپ|‚P‚W‚X‚W”Nژہژ{پjپB
پ›پ@گpگ\Œثگذ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹ك‘م“ْ–{‚جچإڈ‰‚ج‘Sچ‘“I
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚بŒثگذ–@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@گpگ\Œثگذپ@پi‚¶‚ٌ‚µ‚ٌ‚±‚¹‚«پA‚P‚W
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚V‚P”Nپ|‚P‚W‚X‚W”Nژہژ{پjپ@‚حپAپ@‹ك‘م
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{‚جچإڈ‰‚ج‘Sچ‘“I‚بŒثگذ–@‚إ‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@گpگ\Œثگذ‚ئ‚حپAپ@‹ك‘م“ْ–{گ•{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi–¾ژ،گVگ•{پj‚ة‚و‚èپAپ@‚P‚W‚V‚P”Nپi–¾
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ،‚S”Nپj‚ةŒِ•z‚³‚êپA‚P‚W‚V‚Q”Nپi–¾ژ،
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚T”Nپj‚ةژہژ{‚³‚ꂽŒثگذ–@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گpگ\Œثگذ‚حپAپ@‘Sچ‘“I‚ةپAچ‘–¯
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆêگlˆêگl‚ً‰وˆê“I‚ة”cˆ¬‚·‚é‰وٹْ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“I‚بŒثگذ–@‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@گpگ\Œثگذ‚حپAپ@‚P‚W‚W‚U”N‚ة‘S–ت
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“I‚ة‰üگ³‚³‚êپAپ@‚P‚W‚X‚W”N‚ة–¯–@ژ{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چs‚ة”؛‚¤گVŒثگذ–@‚ة‚و‚è”pژ~‚³‚ê‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚ٌپ@پ@گpگ\‚ج—گپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚ٌ‚µ‚ٌ‚ج‚ç‚ٌپjپBپ@پsگي‚¢پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiچcˆتŒpڈ³‚جگي‚¢پjپB
پ›پ@گpگ\‚ج—گ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚U‚V‚Q”N‚جچcˆتŒpڈ³‚ً‚ك‚®‚é
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گي‚¢‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ،پ@گpگ\‚ج—گپ@پi‚¶‚ٌ‚µ‚ٌ‚ج‚ç‚ٌپj‚ئ‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ¼—ï‚U‚V‚Q”N‚جپA“V’q“Vچc‚ج’ي‚ئ“V’q
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“Vچc‚ج’jژq‚ئ‚جپAچcˆتŒpڈ³‚ً‚ك‚®‚éگي
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¢‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚ٌپ@پ@گMگ¼پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ٌ‚؛‚¢پjپBپ@پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= “،Œ´ ’تŒ› پi‚س‚¶‚ي‚ç‚ج ‚ف‚؟‚ج‚èپjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ‚ٹK “¹Œ› پi‚½‚©‚µ‚ب‚ج ‚ف‚؟‚ج‚èپjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ پ@Œم”’‰حڈمچc‚ج‰@‹كگbپi‚¢‚ٌ‚ج‚«
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ٌ‚µ‚ٌپAڈمچc‚جڈdگbپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ پ@•½ژ،‚ج—گپi‚ض‚¢ ‚¶‚ج‚ç‚ٌپj‚إگيژ€پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@•½گ´گ·‚ًڈ]‚¦‚ؤپA•½ژ،‚ج—گپi‚ض
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚¢‚¶‚ج‚ç‚ٌپj‚ًگي‚¤پB—گ‚ج’†‚إپAژ€‹ژپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@ژOڈًŒِ‹³پi‚³‚ٌ‚¶‚ه‚¤‚«‚ٌ‚ج‚èپj‚ئ‹¤
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚ةپA•½ژ،‚ج—گپi‚ض‚¢‚¶‚ج‚ç‚ٌپj‚إگي‚¤
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ھپAپ@گي‘ˆ’†’ا‚¢‹l‚ك‚ç‚êژ©ٹQپB
پ@پ@پ،پ@گMگ¼پ@پi‚µ‚ٌ‚؛‚¢پA“،Œ´ ’تŒ› پi‚س‚¶‚ي‚ç
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‚ف‚؟‚ج‚èپjپAچ‚ٹK “¹Œ› پi‚½‚©‚µ‚ب‚ج ‚ف‚؟
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‚èپjپj ‚حپAپ@Œم”’‰حڈمچc‚ج‰@‹كگbپi‚¢‚ٌ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚«‚ٌ‚µ‚ٌپAڈمچc‚جڈdگbپj‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@پ@پœپ@گMگ¼‚حپAپ@•½ژ،‚ج—گپi‚ض‚¢ ‚¶‚ج‚ç‚ٌپj‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گيژ€‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گMگ¼‚حپAپ@•½گ´گ·‚ًڈ]‚¦‚ؤپA•½ژ،‚ج—گپi‚ض
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¢‚¶‚ج‚ç‚ٌپj‚ًگي‚¤‚ھپA—گ‚ج’†‚إپAژ€‹ژ‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گMگ¼‚حپAژOڈًŒِ‹³پi‚³‚ٌ‚¶‚ه‚¤‚«‚ٌ‚ج‚èپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@‚ئ‹¤‚ةپA•½ژ،‚ج—گپi‚ض‚¢‚¶‚ج‚ç‚ٌپj‚إگي‚¤ ‚ھپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گي‘ˆ’†’ا‚¢‹l‚ك‚ç‚ê‚ؤژ©ٹQ‚·‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚ٌپ@پ@گbگذچ~‰؛پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ٌ‚¹‚«‚±‚¤‚©پjپBپ@پs“Vچc‰ئپtپB
پ@
پZپ@‚µ‚ٌپ@پ@ گVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ٌ‚¹‚آ‚¹‚«‚ھ‚ح‚ç‚ج‚½‚½‚©‚¢پjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پsگي‚¢پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¨‚¨‚ھ‚«پE‚â‚ـ‚ب‚©‚ج‚½‚½‚©‚¢پjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚m‚d‚vپ@‚s‚g‚d‚n‚q‚xپ@‚n‚eپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚r‚d‚j‚h‚f‚`‚g‚`‚q‚`پ@‚v‚`‚qپD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@پuگVگàپiژjژہپjٹضƒ–Œ´‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گي‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپv
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚حپAپ@ٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چL‹`‚إ‚حپA‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”Nپj‚WŒژ‚Q‚U“ْچ ‚©‚ç‚XŒژ‚Q‚R
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ‚ـ‚إ‚إپA”ü”Zچ‘پi‚ف‚ج‚ج‚‚ةپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‘هٹ_پi‚¨‚¨‚ھ‚«پj•t‹ك‚âژR’†
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚â‚ـ‚ب‚©پj•t ‹ك‚إ‚جگي‚¢‚إ‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚جŒˆگيپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گVگàپiژjژہپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‘هٹ_‚جگي‚¢پAژR’†‚جگي‚¢پjپB
پ@ (پث Œc’·‚T”N‚ج
“V‰؛•ھ‚¯–ع‚جگي‚¢پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ پ@پuژjژہپiگVگàپj
پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپv پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‰و‘œƒAƒ‹ƒoƒ€پ@‚m‚ڈپD‚QپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ پ@پu“`گàپiڈ]—ˆگàپj
پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‰و‘œƒAƒ‹ƒoƒ€ پ@‚m‚ڈپD‚RپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@ (پث –LگbژپپA–LگbگŒ پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ (پث –LگbژپŒـ‘هکVپEŒـ•ٍ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@چsپAŒـ‘هکVپAŒـ•ٍچsپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ (پث “à•{‚؟‚ھ‚ذ‚جڈًپXپjپB
پ@پ@ (پث ڈ¬ژR•]’èپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ×گىƒKƒ‰ƒVƒƒپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “؟گى‰ئچNپA•ں“‡گ³‘¥پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’r“c‹PگپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث –ر—کڈGŒ³پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گخ“cژOگ¬پA‰Fٹى‘½ڈG‰ئپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ‘ه’J‹gŒpپAڈ¬‘پگىڈGڈHپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ”ü”ZگشچâپA‘هٹ_ڈéپA
“ى‹{ژRپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ژR’†پAڈéژRپA‹تڈéپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ڈ¼”ِژRپA“،‰؛‚جژ©ٹQ•ُپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ٹضƒ–Œ´–~’nپA“چ”zژRپA
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ›پ@ٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پuŒc’·‚T”Nپi‚P‚U‚O‚O”Nپj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“V‰؛•ھ‚¯–ع‚جگي‚¢پv‚ج‚P‚آ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ ‚èپAپuŒc’·‚T”Nپi‚P‚U‚O‚O
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”Nپj‚ج“V‰؛•ھ‚¯–ع‚جگي‚¢پv
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج’†گS“I‚بگي‚¢‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@ٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢‚ة‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پuژjژہپiگVگàپjٹضƒ–Œ´‚جگي
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپvپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ئپAپ@پu“`گàپiڈ]—ˆگàپj‚جٹض
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚ئ‚¢‚¤‚Q‚آ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—L—ح‚بگà‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@“Œگ¼—¼ŒR‚ج‚P‚U‚O‚O”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژR’†Œˆگي’n‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹضƒPŒ´–~’n‚©‚çگ¼•ûپE–ٌ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚Q‚‹‚چ‚ة‚ ‚ء‚½ژR’†‘؛
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•t‹كپiŒ»چف‚جٹٍ•ŒŒ§ٹضƒPŒ´’¬
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj’n‹وپE‹تپi‚½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ـپj’n‹وپAڈ¼”ِپi‚ـ‚آ‚¨پjپE“،‰؛
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚ئ‚¤‚°پj’n‹وپj‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@گ¼ŒR‚جگخ“cپE‰Fٹى‘½پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ¬گ¼پE“‡’أŒR“™•zگw’n‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈéژRپi ‚µ‚ë‚â‚ـپAŒ»چف‚جٹٍ•ŒŒ§
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹضƒPŒ´’¬ژR’†’n‹وپE‹ت’n‹وپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•t‹ك‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈéژR ‚ة‚حپAٹùگ¬ڈ€”ُگw’n‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گwڈéپi‚¶‚ٌ‚¶‚ëپj‚ج‹تڈéپi‚½‚ـ‚¶
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ه‚¤پjپj‚ھ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@گ¼ŒR‚ج‘ه’JŒR•zگw’n
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚حپAٹضƒPŒ´–~’n“ىگ¼•”پiŒ»
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چف‚جٹضƒPŒ´’¬ڈ¼”ِ’n‹وپE“،‰؛’n
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹وپj‚إ ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@گ¼ŒR‚©‚ç“ŒŒR‚ةگQ•ش
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ء‚½ڈ¬‘پگىŒR•zگw’n‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ¼”ِژR‚جژR’¸ پA–k•”‚ج’†
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@• پEژRک[پiŒ»چف‚جٹضƒPŒ´’¬ڈ¼”ِ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’n‹وپE“،‰؛’n‹وپj‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@“ŒŒR‚ج•ں“‡گ¨‚ج •z
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گw’n‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈéژRپi ‚µ‚ë‚â‚ـپAŒ»چف‚جٹٍ•ŒŒ§
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹضƒPŒ´’¬ژR’†’n‹وپE‹ت’n‹وپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج“Œ•ûپiŒ»چف‚جٹضƒPŒ´’¬ژR’†
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’n‹وپj‚إ ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@“ŒŒR‚ج‰ئچN‚ج—¦‚¢‚é
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“؟گىŒR–{‘à‚ج•zگw’n‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹضƒPŒ´–~’n“ىگ¼•”پiٹضƒPŒ´
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’¬ڈ¼”ِ’n‹وپE“،‰؛’n‹وپjپA“–“ْ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚»‚جŒمپAڈéژRپi ‚µ‚ë‚â‚ـپAŒ»چف
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جٹٍ•ŒŒ§ٹضƒPŒ´’¬ژR’†’n‹وپE‹ت
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’n‹وپj‚ج“Œ•ûپiŒ» چف‚جٹضƒPŒ´’¬
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژR’†’n‹وپj‚إ ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ج“Œگ¼—¼ŒR‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘هٹ_‘خگي’nپi‚ة‚ç‚فچ‡‚¢پAچ‡
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گي‚¹‚¸پj‚حپA‘هٹ_•t‹كپiŒ»چف
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جٹٍ•ŒŒ§پEگ‚ˆنپi‚½‚é‚¢پj’¬پj‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@گ¼ŒR‚ج–ر—کڈGŒ³ ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–ر—کگ¨‚حپA ٹضƒPŒ´–~’n
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج“Œ•û‚ة‚ ‚é“ى‹{ژRپi‚ب
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ٌ‚®‚¤‚³‚ٌپj‚جژRک[پiŒ»چف‚جٹٍ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•ŒŒ§گ‚ˆن’¬پj‚ة•zگw‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@“ŒŒR‚ج’r“cگ¨‚ج •z
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گw’n‚حپAپ@“ى‹{ژRپi‚ب‚ٌ‚®‚¤
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚³‚ٌپj‚ج–k•”پiŒ»چف‚جٹٍ•ŒŒ§گ‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆن’¬پj‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@گVگàپiژjژہپjٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ٌ‚¹‚آ‚¹‚«‚ھ‚ح‚ç‚ج‚½‚½‚©‚¢پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ئ‚حپA ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پi‚¨‚¨‚ھ
‚«پE‚â‚ـ‚ب‚©‚ج‚½‚½‚©‚¢پj‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢‚ة‚حپAپuگVگàپiژj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژہپjٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†‚ج
گي‚¢پjپvپ@‚ئپAپ@پu“`گàپiڈ]—ˆگàپj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پvپ@‚ئ‚¢‚¤‚Q‚آ‚ج—L—ح
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚بگà‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@گVگàپiژjژہپjٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پi= ‘ه
ٹ_پEژR’†‚جگي‚¢)‚حپAپ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚T”Nپj‚ة“ْ–{ٹe’n‚إچs‚ي‚ꂽپuŒc’·‚T
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”Nپi‚P‚U‚O‚O”Nپj‚ج“V‰؛•ھ‚¯–ع‚جگي‚¢پv
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‚P‚آ‚إ‚ ‚èپAپ@پuŒc’·‚T”N پi‚P‚U‚O‚O”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج“V‰؛•ھ ‚¯–ع‚جگي‚¢پv‚ج’†گS“I‚بگي
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¢‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@‚»‚µ‚ؤپAگVگàپiژjژہپjٹضƒ–Œ´‚جگي
‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢)‚جŒ‹‰تپA“؟گى
•û‚ج“ŒŒR‚ھڈں—ک‚ً“¾پA“؟گى‰ئچN‚ھگ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ ٹî”ص‚ًŒإ‚كپA‚»‚جŒمپA‚P‚U‚O‚R”NپiŒc
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’·‚V”Nپj‚ةپA‰ئچN‚ھڈ«ŒRگé‰؛پi‚¹‚ٌ‚°پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ًژَ‚¯پA چ]Œث–‹•{‚ھڈoŒ»‚µ‚½پB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@پuگVگà پiژjژہپjٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پi=
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپv‚إ‚حپAپ@•ٍچsڈOپE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–ر—ک•û‚جگ¼ŒR‚ج’†گSگl•¨‚حپA ‘ه’J
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹gŒpپA•ٍچsڈOپE‚Sگlپi‘“c’· گ·پA’·
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘©گ³‰ئپA‘O“cŒ؛ˆبپAگخ“cژOگ¬پjپA‰F
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹى‘½ڈG‰ئپA–ر—ک‹PŒ³‚إ‚ ‚èپAپ@گ¼ŒR
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚حپA”½“؟گى‚إ’cŒ‹‚µپAڈW’cژw“±‘جگ§
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆê•ûپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ج’†گSگl
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•¨‚حپA“؟گى‰ئچN‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚حپAپ@گخ“c•û‚جگ¼ŒR‚ج’†گSگl•¨
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚حگخ“cژOگ¬‚إ‚ ‚èپAˆê•ûپA“؟گى•û‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ŒŒR‚ج’†گSگl•¨‚حپA“؟گى‰ئچN‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@پuژjژہپiگVگàپj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚جŒˆگي“ْ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚ج“Œگ¼—¼ŒR‚ج—v“_•\پB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پںپ@ˆêژںژj—؟‚ةٹî‚أ‚پuژjژہپiگV
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گàپjٹضƒ– Œ´‚جگي‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚جگي‚¢پjپv‚جŒˆگيپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@ŒˆگيڈêڈٹپFپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹضƒ–Œ´–~’n‚جگ¼•ûپE–ٌ‚Q‚‹‚چ‚ج
ژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‘؛پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@Œˆگي“ْژپFپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œك‘O‚P‚Oژچ پ`گ³Œكچ پBپ@
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@پuژjژہپiگVگàپjٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپv‚جŒˆگي
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘هٹ_ƒGƒٹƒA‚ج”ü”Zگشچâ•t‹ك‚©‚ç
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆع“®‚µژR’†‘؛‚ج“Œ‘¤‚ة•zگw‚·‚éپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ŒŒRپi“؟گى•û پj‚جژه—حŒRپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ئپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘هٹ_ƒGƒٹƒA‚ج‘هٹ_ڈé‚©‚çˆع“®‚µ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژR’†‘؛‚جگ¼‘¤‚ة•zگw‚·‚éگ¼ŒR
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جژه—حŒRپ@‚ھپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚O”N پiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جŒك‘O‚P‚Oژچ ‚©‚çگ³Œكچ ‚ـ‚إپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”ü”Zچ‘‚جژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‘؛‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گي‚¤پiŒˆگي‚ًچs‚¤پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚»‚جگي‚¢‚جŒ‹‰تپAگ¼ŒRپi•ٍ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جژه—حŒR‚ھ‘چ•ِ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ê‚ئ‚ب‚èپA”s‘–پA”sگي‚µپA“ŒŒR
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi“؟گى•ûپj ‚جژه—حŒR‚ھڈں—ک‚ً“¾
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پںپ@پuژjژہپiگVگàپj‚جٹضƒ–Œ´‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ گي‚¢پv‚جŒˆگي‚إ‚جپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “Œگ¼—¼ŒR‚جژه—حŒR‚ج“®‚«پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@پuژjژہپiگVگàپjٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپv‚جŒˆگي
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚إ‚جپA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج ژه—حŒR
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚ج“®‚«پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚جژه—حŒR
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiگوژèگ¨‚ج•ں“‡‘gگ¨‚ئ‰ئچN
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج“؟گى–{‘àپjپ@‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‡@پ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚جژه—حŒR‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ‘پ’©‚ةپA‘هٹ_ƒGƒٹƒA‚ج”ü”Z
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گشچâپi‚ف‚ج‚ ‚©‚³‚©پj•t‹كپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiٹضƒ–Œ´–~’n‚ج“Œ•ûپj‚ًڈo”
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚XŒژ‚P‚T“ْ‘پ’©پjپث
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@“؟گى‰ئچN‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚XŒژ‚P‚T“ْ‘پ’©‚ةپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘هٹ_ƒGƒٹƒA‚ج”ü”Zگشچâ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•t‹ك‚إپA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ً‚R‚آ‚ة•ھ‚¯‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰ئچN‚ئ“؟گى–{‘à‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹضƒ–Œ´–~’n“ىگ¼•”پ@‚ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژR’†‘؛پ@پi‚â‚ـ‚ب‚©‚ق‚çپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹضƒ–Œ´–~’n‚جگ¼•ûپE–ٌ‚Q‚‹‚چپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ةŒü‚©‚¤پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گوژèگ¨‚ج’r“c‘gگ¨‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘هٹ_ƒGƒٹƒA‚ج“ى‹{ژRپi‚ب‚ٌ‚®
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¤‚³‚ٌپAٹضƒ–Œ´–~’n‚ج“Œ•ûپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‘O–ت‚ةŒü‚©‚¢پA•zگw‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گوژèگ¨‚ج•ں“‡‘gگ¨‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژR’†‘؛پ@پi‚â‚ـ‚ب‚©‚ق‚çپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹضƒ–Œ´–~’n‚جگ¼•ûپE–ٌ‚Q‚‹‚چپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ةŒü‚©‚¤پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‡Aپ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚جژه—حŒR‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚XŒژ‚P‚T“ْ‚جŒك‘O‚P‚Oژچ ‚©‚ç
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ³Œكچ ‚ـ‚إپAژR’†‘؛پ@پi‚â‚ـ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ب‚©‚ق‚çپAٹضƒ–Œ´–~’n‚جگ¼•ûپE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–ٌ‚Q‚‹‚چپj‚إپAگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—ک•ûپj‚جژه—حŒR‚ئŒًگيپiŒˆگي‚ً
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چs‚¤پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚XŒژ‚P‚T“ْ‚جŒك‘O‚P‚Oژچ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ`گ³Œكچ پjپث
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‡Bپ@‚XŒژ‚P‚T“ْگ³Œكچ ‚ةپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جژه—ح
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒR‚ھپA‘چ•ِ‚ê‚ئ‚ب‚èپA”s‘–پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”sگي‚µپA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚جژه—ح
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒR‚حپAژR’†‘؛‚إپAگ¼ŒRپi•ٍچs
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈOپE–ر—ک•ûپj‚جژه—حŒR‚ة‘خ‚µ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œˆگي‚إڈں—ک‚ً“¾‚é
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚XŒژ‚P‚T“ْگ³Œكچ پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@پuژjژہپiگVگàپjٹضƒ–Œ´‚جگي
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپv‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@Œˆگي‚إ‚ج پAگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@—ک•ûپj‚جژه—حŒR‚ج“®‚«پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جژه—حŒRپ@پiڈ¬گ¼پAگخ“cپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰Fٹى‘½پA“‡’أ“™‚جŒRپjپ@‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‡@پ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جژه—حŒR‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚S“ْ–é‚ةپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘هٹ_ƒGƒٹƒA‚ج‘هٹ_ڈéپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¨‚¨‚ھ‚«‚¶‚ه‚¤پAٹضƒ–Œ´
–~’n‚ج“Œ•ûپj‚ًڈo”
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚XŒژ‚P‚S“ْ–éپjپث
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ›پ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚XŒژ‚P‚S“ْ–é‚ةپA‘هٹ_ڈé‚إپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ًپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژه—حŒR‚ئ‘هٹ_ڈéژç”ُژc—¯ŒR
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‚Q‚آ‚ة•ھ‚¯‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ›پ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژه—حŒR‚حپAژR’†‘؛پ@پi‚â‚ـ‚ب‚©
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ق‚çپAٹضƒ–Œ´–~’n‚جگ¼•ûپE–ٌ‚Q
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚‹‚چپjپ@‚ةŒü‚©‚¤پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ›پ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘هٹ_ڈéژç”ُژc—¯ŒR‚حپA‘هٹ_ڈé
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ةژc—¯‚µپA‘هٹ_ڈé‚ًژç”ُ‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‡Aپ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژه—حŒR‚حپA‚XŒژ‚P‚T“ْ–¢–¾‚ةپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژR’†‘؛پ@پi‚â‚ـ‚ب‚©‚ق‚çپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹضƒ–Œ´–~’n‚جگ¼•ûپE–ٌ‚Q‚‹‚چپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ة•zگw‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پZپ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژه—حŒR‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژR’†‘؛•t‹ك‚جڈéژR‚ة‚ ‚é
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹù‘¶ڈ€”ُگw’n‚ج‹تڈéپi‚½‚ـ‚¶
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ه‚¤پj‚ًپAڈoŒ‚گw’n‚ئ‚µ‚ؤژg—p
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚µ‚½‰آ”\گ«‚ھ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚XŒژ‚P‚T“ْ–¢–¾پjپث
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‡Bپ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژه—حŒR‚حپA‚XŒژ‚P‚T“ْŒك‘O‚P‚O
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژچ ‚©‚çگ³Œكچ ‚ـ‚إپAژR’†‘؛
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إپA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚جژه—حŒR‚ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒًگيپiŒˆگي‚ًچs‚¤پjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚XŒژ‚P‚T“ْŒك‘O‚P‚Oژچ پ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ³Œكچ پjپث
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‡Cپ@ژR’†‘؛‚إپAگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–ر—ک•ûپj‚جژه—حŒR‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘چ•ِ‚êپA”s‘–پA”sگي‚ئ‚ب‚èپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚جژه—حŒR
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ة‘خ‚µŒˆگي‚إ”sگي‚·‚é
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚XŒژ‚P‚T“ْگ³Œكچ پjپB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@پuژjژہپiگVگàپj‚جٹضƒ–Œ´
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚جگي‚¢پv‚ج“Œگ¼—¼ŒR‚جٹT
—v•\پB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@پuگVگàپiژjژہپjٹضƒ–Œ´ ‚جگي‚¢پv
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پj‚حپAچL‹`‚إ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj ‚ج‚WŒژ‚Q‚U“ْچ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi“ŒŒR‚ج”ü”Zگشچâ•zگwپj‚©‚ç‚XŒژ‚Q‚R
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْپiگ¼ŒR‚ج‘هٹ_ڈé—ژڈéپj‚ـ‚إ‚جٹشپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”ü”Zچ‘‚إ‚جگي‚¢‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚Pپjپ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚WپA‚XŒژ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ“_‚إپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚حپA”ِ’£چ‘
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¨‚ي‚è‚ج‚‚ةپAŒ»پEˆ¤’mŒ§گ¼•”‚ج‘ٹ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“–’nˆوپj‚جگ´گ{ڈéپi‚«‚و‚·‚¶‚ه‚¤پAگ´
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈBڈéپj‚ً–{‹’’n‚ة‚µپAپ@•ٍچsڈOپE–ر—ک
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•û‚جگ¼ŒR‚ح پA”ü”Zچ‘پi‚ف‚ج ‚ج‚‚ةپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ»پEٹٍ•ŒŒ§“ى•”‚ج‘ٹ“–’nˆوپj‚ج‘هٹ_
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈéپi‚¨‚¨‚ھ‚«‚¶‚ه‚¤پj‚ً–{‹’’n‚ة‚µپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹô–{‚à‚جگى‚ً‹²‚ٌ‚إ‘خ›³‚µ‚ؤ‚¢‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚Qپjپ@“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚حپA گ´گ{ڈé‚ً
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈo‚ؤپA‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚WŒژ‚Q‚R“ْ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ة•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚جگ¼ŒR‚جٹٍ•Œڈé
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ً—ژڈ邳‚¹پAپ@“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚حپA‚WŒژ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚Q‚U“ْچ ‚و‚èپA‘هٹ_•t‹ك‚ج”ü”Zگشچâ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚ف‚ج‚ ‚©‚³‚©پj‚ةˆع“®‚µ•zگw‚µ‚ؤپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ـ‚إ•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚جگ¼
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒR‚ج‘هٹ_ڈé‚ًچUŒ‚‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚Rپjپ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–é‚ةپA•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚جگ¼ŒR‚ج‘هٹ_
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈé‚ة‚¢‚½‘ه•”•ھ‚جŒR‚ح‘هٹ_ڈé‚ً”²‚¯
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈo‚µٹض ƒ–Œ´–~’nپEژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj•û
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–ت‚ضˆع“®‚µپA‚ـ‚½پA‚XŒژ‚P‚S“ْ–é‚ةپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘هٹ_•t‹ك‚ج”ü”Zگشچâ‚ة‚¢‚½“؟گى•û
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج“ŒŒR‚ج‘½‚‚جŒR‚حپAگ¼ŒRژه—حŒR‚ً
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’ا‚ء‚ؤپAٹضƒ–Œ´–~’nپEژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•û–ت‚ضˆع“®‚µپA‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ةپA“Œگ¼
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—¼ژه—حŒR‚حپA”ü”Z‚ج•½–ى‚جژR’†پi‚â
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ـ‚ب‚©پj‚إŒˆگي‚ًچs‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚جگي‚¢‚ج“Œگ¼
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—¼ژه—حŒR‚جŒˆگي‚إ‚حپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژه—حŒR‚ھڈں—ک‚ً“¾‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚Sپjپ@‘هٹ_•t‹ك‚ج”ü”Zگش چâ‚ة‚¢‚é“؟
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گى•û‚ج“ŒŒR‚حپA‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚XŒژ‚P‚T“ْ‚©‚ç‚XŒژ‚Q‚R“ْ‚ـ‚إ•ٍچsڈOپE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–ر—ک•û‚جگ¼ŒR‚ج‘هٹ_ڈé‚ًچUŒ‚‚µپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚XŒژ‚Q‚R“ْ‚ةگ¼ŒR‚ج‘هٹ_ڈé‚ً—ژڈ邳
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¹‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@پuگVگàپiژjژہپjٹضƒ–Œ´ ‚جگي‚¢پv
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پj‚حپAچL‹`‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚حپAژٹْ‚ح‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚WŒژ‚Q‚U“ْچ پi“ŒŒR‚ج”ü”Zگشچâ•z
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گwپj‚©‚ç‚XŒژ‚Q‚R“ْپiگ¼ŒR‚ج‘هٹ_
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈé—ژڈéپj‚ـ‚إ‚إ‚ ‚èپAپ@گي‚¢‚جڈêڈٹ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ح”ü”Zچ‘ پ@پi‚ف‚ج‚ج‚‚ةپAŒ»پEٹٍ•Œ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ§“ى•”‚ج‘ٹ“–’nˆوپj‚ج‘هٹ_پi‚¨‚¨
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ھ‚«پj•t‹ك‚âژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj•t ‹ك
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ ‚èپAپ@”ü ”Zچ‘‚ةڈWŒ‹‚µ‚½پA“؟گى
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•û‚ج“ŒŒRپE–ٌ‚V–œ‚R‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚جگ¼ŒRپE–ٌ‚T–œ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚S‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ج“Œگ¼—¼ŒRپE–ٌ‚P‚Q–œ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚V‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ھگي‚¤پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚»‚جŒˆگي‚حپAژهگيڈêپiŒˆگيڈêپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پA”ü”Zچ‘ژR’†‘؛پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ ‚èپAپ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚T“ْ‚جŒك‘O‚P‚Oژچ ‚©‚çگ³Œكچ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ـ‚إپA“؟گى•û‚ج“ŒŒRژه—حŒR‚ئ•ٍچs
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈOپE–ر—ک•û‚جگ¼ŒRژه—حŒR‚ئ‚جٹش‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چs‚ي‚ê ‚½پBپ@گي‚¢‚جŒ‹‰تپA“؟گى•û
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج“ŒŒRژه—حŒR‚ھڈں—ک‚ً“¾‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@پu“`گàپiڈ]—ˆگàپj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚ج“Œگ¼—¼ŒR‚جٹT—v•\پB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپjٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚حپAچL‹`‚إ‚حپAژٹْ‚ح‚P‚U‚O‚O”NپiŒc
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’·‚T”Nپj‚ج‚WŒژ‚Q‚U“ْچ پi“ŒŒR‚ج”ü
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”Zگشچâ•zگwپj‚©‚ç‚XŒژ‚Q‚R“ْپiگ¼ŒR
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‘هٹ_ڈé—ژڈéپj‚ـ‚إ‚إ‚ ‚èپAگي‚¢‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈêڈٹ‚ح”ü”Zچ‘پi‚ف‚ج‚ج‚‚ةپAŒ»پEٹٍ•Œ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ§“ى•”‚ج‘ٹ“–’nˆوپj‚جٹضƒ–Œ´–~’n
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ئٹضƒ–Œ´–~’n‚جژü•س’nˆو‚إ‚ ‚èپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”ü”Zچ‘‚ةڈWŒ‹‚µ‚½پA “؟گى•û‚ج“ŒŒRپE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–ٌ‚V–œگl‚ج•؛‚ئگخ“c•û‚جگ¼ŒRپE–ٌ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚W–œگl‚ج•؛‚ج“Œگ¼—¼ŒRپE–ٌ‚P‚T–œگl
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج•؛‚ھگي‚¤پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚»‚جŒˆگي‚حپAژهگيڈêپiŒˆگي’nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جٹضƒ–Œ´–~’n‚إ‚ ‚èپAپ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ‚جŒك‘O‚Wژچ ‚©‚ç
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒكŒم‚Qژچ ‚ـ‚إپA“؟گى•û ‚ج“ŒŒRژه
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—حŒR‚ئگخ“c•û‚جگ¼ŒRژه—حŒR‚ئ‚جٹش
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إچs‚ي‚ê ‚½پBپ@گي‚¢‚جŒ‹‰تپA“؟گى
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•û‚ج“ŒŒRژه—حŒR‚ھڈں—ک‚ً“¾‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚ٌپ@پ@ گVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjٹضکA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈo—ˆژ–پi”N‘مڈ‡پEڈعچ×پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ٌ‚¹‚آ‚¹‚«‚ھ‚ح‚ç‚ج‚½‚½‚©‚¢‚©‚ٌ‚ê‚ٌ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚«‚²‚ئپi‚ث‚ٌ‚¾‚¢‚¶‚م‚ٌپE‚µ‚ه‚¤‚³‚¢پjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پsگي‚¢ٹضکAڈo—ˆژ–پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پiپث ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= گVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پjٹضکA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈo—ˆژ–پi”N‘مڈ‡پEڈعچ×پjپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚ٌپ@پ@گV‘I‘gپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ٌ‚¹‚ٌ‚®‚فپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پsژ،ˆہŒx”ُ‘àپEŒR‘àپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= گVگï‘gپAگpگ¶کQژm‘gپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚P‚W‚U‚R”Nپ`‚P‚W‚U‚X”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@گV‘I‘g‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ چ]Œث–‹•{پi“؟گىژپپjگ¨—ح‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@کQژm‘à‚إ‚ ‚èپAپ@چ]Œث–‹•{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi“؟گىژپپjگ¨—ح‚جژ،ˆہŒx”ُ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘àپEŒR‘à‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@گV‘I‘g‚حپA
ڈ‰‚كپA‰ï’أ”ث—a‚èکQژm‘à‚إپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ Œم‚ةپAچ]Œث–‹•{پi“؟گىژپپj’¼
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘®‚جکQژm‘à‚ئ‚ب‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@گV‘I‘g‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹضگ¼‚إ‚حپA‹پi“sپj‚جژ،ˆہˆغ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژŒx”ُ‘à‚إ‚ ‚èپA –‹––‚ج‹
پi“sپj‚جژ،ˆہˆغژ‚ةچvŒ£‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “Œ“ْ–{‚إ‚حپAŒR‘à‚ئ‚µ‚ؤپAٹˆ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–ô‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@گV‘I‘gپ@پi‚µ‚ٌ‚¹‚ٌ‚®‚فپA= گVگï
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘gپAگpگ¶کQژm‘gپA‚P‚W‚U‚R”Nپ`‚P‚W ‚U‚X
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”Nپj‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ]Œث–‹•{پi“؟گىژپپjگ¨—ح‚جکQژm‘à‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚èپAپ@چ]Œث–‹•{پi“؟گىژپپjگ¨—ح‚جژ،
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆہŒx”ُ‘àپEŒR‘à‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گV‘I‘g‚حپAڈ‰‚كپA‰ï’أ”ث—a‚èکQ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژm‘à‚إ‚ ‚èپAŒم‚ةپAچ]Œث–‹•{پi“؟گىژپپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’¼‘®‚جکQژm‘à‚ئ‚ب‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@گV‘I‘g‚حپAپ@‚P‚W‚U‚V”NپiŒc‰‚R”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ـ‚إپA‹ك‹E’n•û‚إپAچ]Œث–‹•{پi“؟گىژپپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ¨—ح‚جژ،ˆہŒx”ُ‘à‚ئ‚µ‚ؤپA–‹––‚ج‹
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi“sپj‚جژ،ˆہŒx”ُ‚ةچvŒ£‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گV‘I‘g‚حپA‚P‚W‚U‚W”NپiŒc‰‚S”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆبŒم‚حپA‹ك‹EپAٹض“ŒپA“Œ–kپA–kٹC“¹’n
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•û‚إپA‹Œچ]Œث–‹•{پi“؟گىژپپjگ¨—ح‚جŒR
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘à‚ئ‚µ‚ؤپAٹˆ–ô‚·‚éپBپ@پ@—E‹C‚ ‚éگيژm
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚½‚؟‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ˆê•ûپAگV’¥‘gپ@پi‚µ‚ٌ‚؟‚ه‚¤‚®‚فپj‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ]Œث–‹•{پi“؟گىژپپjگ¨—ح‚جکQژm‘à‚إ‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚èپAپ@–‹––‚جچ]Œث‚جژ،ˆہŒx”ُ‚ة‚ ‚½‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پZپ@‚µ‚ٌپ@پ@گV’¥‘gپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ٌ‚؟‚ه‚¤‚®‚فپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پsژ،ˆہŒx”ُ‘àپEŒR‘àپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚P‚W‚U‚S”Nپ`‚P‚W‚U‚W”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@گV’¥‘g‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ چ]Œث–‹•{پi“؟گىژپپjگ¨—ح‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@کQژm‘à‚إ‚ ‚èپAپ@چ]Œث–‹•{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi“؟گىژپپjگ¨—ح‚جژ،ˆہŒx”ُ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘àپEŒR‘à‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@گV’¥‘gپ@پi‚µ‚ٌ‚؟‚ه‚¤‚®‚فپj‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ]Œث–‹•{پi“؟گىژپپjگ¨—ح‚جکQژm‘à‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚èپAپ@چ]Œث–‹•{گ¨—ح‚جژ،ˆہŒx”ُ‘àپE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒR‘à‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گV’¥‘g‚حپAپ@–‹––‚جچ]Œث‚جژ،
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆہŒx”ُ‚ة‚ ‚½‚éپBپ@•è’Cگي‘ˆ‚إ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ¯“à”ث•؛‚ئ‹¤‚ةپA“Œ–kٹe’n‚إگي‚¤پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@گV’¥‘g‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ¯“à”ثپi‚µ‚ه‚¤‚ب‚¢‚ح‚ٌپj—a‚èکQژm‘à
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ˆê•ûپAگV‘I‘g‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ]Œث–‹•{پi“؟گىژپپjگ¨—ح‚جکQژm‘à‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚èپAپ@–‹––‚ج‹پi“sپj‚جژ،ˆہŒx”ُ‚ة
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚½‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚ٌپ@پ@گM’·Œِ‹LپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ٌ‚؟‚ه‚¤‚±‚¤‚«پjپBپ@پsژj—؟پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@ژ؛’¬ژ‘مŒمٹْپiگيچ‘ژ‘مپjپA
پ@پ@پ@پ@ ˆہ“y“چژRژ‘م‚ً’m‚éژj—؟پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@‘¾“c‹چˆê‚ھ’کچى‚µپAچ]Œث ژ
‘مڈ‰ٹْ‚ةگ¬—§‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث “ْ–{ژjپE‘وˆê‹‰ژj—؟ƒٹƒXƒgپjپB
پ@پ@پ،پ@گM’·Œِ‹Lپ@پi‚µ‚ٌ‚؟‚ه‚¤‚±‚¤‚«پj‚حپAژ؛’¬
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ‘مŒمٹْپiگيچ‘ژ‘مپjپAˆہ“y“چژRژ‘م‚ً’m
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚éژj—؟‚إ‚ ‚èپAپ@‘¾“c‹چˆê‚ھ’کچى‚µپAچ]Œث
پ@پ@پ@پ@ ژ‘مڈ‰ٹْ‚ةگ¬—§‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‘¾“c‹چˆêپi‚¨‚¨‚½‚¬‚م‚¤‚¢‚؟پj‚جگM’·
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œِ‹L‚ة‚حپAپ@پuˆہ“y“ْ‹LپvپiŒأٹْپEگM’·Œِ‹LپA
پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œc’·چ ‚جژتپjپAپ@پuگM’·‹Lپvپi’†ٹْپEگM’·Œِ
پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹LپAŒc’·‚P‚W”Nپi‚P‚U‚P‚R”Nپjچ پjپAپ@پuگM’·Œِ
پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹LپvپiگVٹْپEگM’·Œِ‹LپAŒ³ک\‚P‚Q”Nپi‚P‚U‚X‚X
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”Nپjژتپj‚ھ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پuˆہ“y“ْ‹LپvپiŒأٹْپEگM’·Œِ‹LپAŒc’·چ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جژتپj‚ھˆêژںژj—؟‚ئ‚µ‚ؤپAگM—ٹ‚ھچ‚‚¢پB
پ@
پZپ@‚µ‚ٌپ@پ@گ_“¹–³”O—¬پB
پi‚µ‚ٌ‚ئ‚¤‚ق‚ث‚ٌ‚è‚م‚¤پj پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پsŒ•ڈp‚ج—¬”hپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@–‹––‚ةگ·‚ٌ‚إ‚ ‚ء‚½Œ•ڈp‚ج—¬
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ”h‚ج‚P‚آپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@Œjڈ¬ŒـکYپi‚©‚آ‚炱‚²‚낤پA–طŒث
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ چFˆٍپjپAپ@•iگى–ي“ٌکYپi‚µ‚ب‚ھ‚ي‚₶ ‚ë
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚¤پjپAپ@‹ع‘ٍٹ›پi‚¹‚è‚´‚ي‚©‚à پAگV‘I‘gپjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‰i‘qگV”ھپiگV‘I‘gپjپAپ@ˆة“Œچbژq‘¾کY
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiگV‘I‘gپjپ@‚ب‚ا‚ھ–‹––‚ةڈCچs‚µ‚ؤ‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚½Œ•ڈpپB
پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث –‹––‚جچ]ŒثŒ•ڈp“¹ڈêپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@گ_“¹–³”O—¬ پi‚µ‚ٌ‚ئ‚¤‚ق‚ث‚ٌ‚è‚م
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¤پj ‚حپAپ@“ْ–{‚جŒ•ڈp‚ج—¬”h‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•َ‰i”Nٹشپi‚P‚V‚T‚P”Nپ`‚P‚V‚U‚S”Nپj‚ة
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•ںˆن‰أ•½‚ة‚و‚ء‚ؤ‘nژn‚³‚êپAپ@–‹––‚ةگ·‚ٌ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@ ‚إ‚ ‚ء‚½Œ•ڈp‚ج—¬”h‚ج‚P‚آ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@گ_“¹–³”O—¬‚حپAپ@Œjڈ¬ŒـکYپ@پi‚©‚آ‚炱
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@‚²‚낤پA–طŒثچFˆٍپjپAپ@•iگى–ي“ٌکY پ@پi‚µ‚ب‚ھ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ي‚₶‚ë ‚¤پjپAپ@‹ع‘ٍٹ›پ@پi‚¹‚è‚´‚ي‚©‚à پAگV
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘I‘gپjپAپ@‰i‘qگV”ھپiگV‘I‘gپjپAپ@ˆة“Œچbژq‘¾
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@کYپiگV‘I‘gپjپ@‚ب‚ا‚ھ–‹––‚ةڈCچs‚µ‚ؤ‚¢ ‚½Œ•
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈp‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚µ‚ٌپ@پ@گ_ڈ—پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ٌ‚ة‚هپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پs‰«“êپi—®‹…پj‚جڈ—گ«ژiچصپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= ڈjڈ—پi‚ج‚ëپjپAژiپi‚آ‚©‚³پjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ (= —®‹…گ_“¹‚إ‹F“ک‚·‚éڈ—گ«ژiچصپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث —®‹…‰¤چ‘پA‰«“ê‚ج—ًژjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@—®‹…‰¤چ‘‚ھگ§’肵‚½Œِ“Iگ_ژ–پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ چصژ–‚ًژi‚éپA‘½‚ ‚ج—®‹…گ_“¹‚جگ_
ڈ—پiŒِ“IƒVƒƒپ[ƒ}ƒ“پj پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@چإچ‚گ_ڈ—‚حپA•·“¾‘هŒNپi‚«‚±‚¦‚¨
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¨‚«‚فپjپj پB
پ@
پZپ@‚µ‚ٌپ@پ@گe‰¤پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ٌ‚ج‚¤پjپBپ@پs“Vچc‰ئپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@گe‰¤‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘O‹ك‘م“ْ–{پi“ق—اپ[چ]Œثژ‘مپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚حپAپuگe‰¤گé‰؛پv‚ًژَ‚¯‚½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’jگ«چc‘°پiژه‚ة“Vچc‚ج’jژq‚â
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒZ’يپj‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث “Vچc‰ئپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث چc‘°پA‰¤پAڈ—‰¤پAچcژqپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گe‰¤پA“àگe‰¤پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جپAگe‰¤‚ئ‰¤پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘O‹ك‘م“ْ–{پi“ق—اپ`چ]Œثژ‘مپj‚جپAگe
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰¤پi‚µ‚ٌ‚ج‚¤پj‚ئ‚حپAپ@گe‰¤گé‰؛‚ًژَ‚¯‚½’j
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ«چc‘°‚إ‚ ‚èپAژه‚ةپA“Vچc‚ج’jگ«چcژq‚âŒZ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’ي‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆê•ûپA‘O‹ك‘م“ْ–{پi”ٍ’¹پ`چ]Œثژ‘مپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جپA‰¤پi‚¨‚¤پj‚ئ‚حپA’jگ«چc‘°‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{پi“ق—اپ`چ]Œثژ‘مپj‚جپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گe‰¤‚ئ‰¤پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج“ق—اژ‘م‚©‚çچ]Œثژ‘م
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ـ‚إ‚حپA‘ه•َ—ك‚ج—¥—كگ§ˆبŒم‚حپAگe‰¤گé
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰؛پi‚µ‚ٌ‚ج‚¤‚¹‚ٌ‚°پj‚ًژَ‚¯‚½’jگ«چc‘°پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiژه‚ة“Vچc‚ج’jگ«چcژqپi‚ف‚±پj‚âŒZ’يپj‚ًپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گe‰¤پi ‚µ‚ٌ‚ج‚¤پj‚ئŒؤ‚رپAپ@‚»‚êˆبٹO‚ج’jگ«
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چc‘°پiگe‰¤گé‰؛‚ھ‚ب‚¢’jگ«چc‘°پj‚إپA“Vچc
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚و‚è‚Tگ¢ˆب‰؛‚جچc‘°’jژq‚ً‰¤پi‚¨‚¤پj‚ئŒؤ‚ش
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈêچ‡‚ھ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پq‰¤پi‚¨‚¤پj‚ج—لپrپ@“Vچc‚ج‘·پi‚ـ‚²پjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘\‘·پi‚ذ‚ـ‚²پj‚ج’jژqپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@‹كŒ»‘م“ْ–{پi–¾ژ،ژ‘مپ`Œ»چفپj‚جپAگe‰¤پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹كŒ»‘م“ْ–{‚إ‚حپA‘O‹ك‘م“ْ–{‚جگe‰¤
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گé‰؛‚جگ§‚ً”pژ~‚µپAچcژ؛“T”ح‚ة‚و‚èپA‹ك‘م
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{پi–¾ژ،پE‘هگ³پEڈ؛کaگي‘Oژ‘مپj‚إ‚حپA“V
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چc‚جژq‚و‚èچcŒ؛‘·‚ةژٹ‚é‚Sگ¢‚ـ‚إ‚ج’jگ«‚ھ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گe‰¤پi‚µ‚ٌ‚ج‚¤پj‚إ‚ ‚èپAپ@Œ»‘م“ْ–{پiڈ؛کaگي
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒمپE•½گ¬پE—كکaژ‘مپj‚إ‚حپA“Vچc‚جژqپE‘·‚ـ‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج’jگ«‚ھگe‰¤‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚ٌپ@پ@ گwڈê–ى
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚ٌ‚خ‚جپjپBپ@پs’n–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@پu“`گàپiڈ]—ˆگàپj‚جٹض
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚إپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ گwڈê–ىپi‚¶‚ٌ‚خ‚جپj‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “؟گى‰ئچN‚ھ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚Q”ش–ع‚ج–{گwپiگw’nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiچإڈI–{گwپj ‚ً’u‚¢‚½ڈêڈٹ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚جŒˆگيپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گVگàپiژjژہپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‘هٹ_‚جگي‚¢پAژR’†‚جگي‚¢پjپB
پ@ (پث Œc’·‚T”N‚ج
“V‰؛•ھ‚¯–ع‚جگي‚¢پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ پ@پuژjژہپiگVگàپj
پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپv پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‰و‘œƒAƒ‹ƒoƒ€پ@‚m‚ڈپD‚QپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ پ@پu“`گàپiڈ]—ˆگàپj
پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‰و‘œƒAƒ‹ƒoƒ€ پ@‚m‚ڈپD‚RپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “؟گى‰ئچNپA•ں“‡گ³‘¥پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’r“c‹PگپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث –ر—کڈGŒ³پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گخ“cژOگ¬پA‰Fٹى‘½ڈG‰ئپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ‘ه’J‹gŒpپAڈ¬‘پگىڈGڈHپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ”ü”ZگشچâپA‘هٹ_ڈéپA
“ى‹{ژRپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ژR’†پAڈéژRپA‹تڈéپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ڈ¼”ِژRپA“،‰؛‚جژ©ٹQ•ُپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ٹضƒ–Œ´–~’nپA“چ”zژRپA
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@گwڈê–ىپ@پi‚¶‚ٌ‚خ‚جپj‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹضƒ–Œ´–~’n‚ج’†‰›•”‚ةˆت’u‚·‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ»چف‚جٹٍ•ŒŒ§ٹضƒ–Œ´’¬‚جٹضƒ–Œ´
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–~’n‚ج’†‰›•”‚ة‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¢پv‚جŒˆگي‚إ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گwڈê–ىپ@پi‚¶‚ٌ‚خ‚جپj‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ةپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ŒŒR‚ج“؟گى‰ئ چN‚ھپA‚Q”ش–ع‚ج–{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گwپiگw’nپjپi‰ئچNچإڈIگw’nپAچإڈI
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–{گwپj‚ً’u‚¢‚½ڈêڈٹ‚إ ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@گwڈê–ى‚ة•zگw‚·‚é“ŒŒR‚ج“؟پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گى‰ئچN‚حپAگ³Œكچ پAڈ¼”ِژRپi‚ـ‚آ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¨‚â‚ـپj‚ة•zگw‚·‚éگخ“c•û‚جگ¼
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒR‚جڈ¬‘پگىڈGڈHپi‚±‚خ‚â‚©‚ي‚ذ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ ‚«پjپv‚ة–â“S–Cپi‚ئ‚¢‚ؤ‚ء‚غ‚¤پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ًچs‚¢پA “؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ةگQ•ش
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚点پAگي‹ا‚ً چD“]‚³‚¹‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@پu“`گàپiڈ]—ˆگàپj‚جٹضƒ–Œ´
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚جگي‚¢پv‚جŒˆگي‚إ‚جپA“ŒŒR
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi“؟گى•ûپj‚جژه—حŒR‚ج“®‚«پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚جژه—حŒR
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiگوژèگ¨‚ج•ں“‡‘gگ¨‚ئ‰ئچN
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج“؟گى–{‘àپjپ@‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‡@پ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚جژه—حŒR‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‘پ’©‚ةپAپ@‘هٹ_ƒGƒٹƒA‚ج”ü”Z
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ گشچâپi‚ف‚ج‚ ‚©‚³‚©پj•t‹ك
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiٹضƒ–Œ´–~’n‚ج“Œ•ûپj‚ًڈo”
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚XŒژ‚P‚T“ْ‘پ’©پjپث
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پZپ@“؟گى‰ئچN‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‘پ’©‚ةپA‘هٹ_ƒGƒٹƒA‚ج”ü”Zگش
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ چâ•t‹ك‚إپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ً‚Q‚آ‚ة•ھ‚¯پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ٹضƒ–Œ´–~’n‚ةŒü‚©‚¤گوژèگ¨‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ •ں“‡‘gگ¨پA‰ئچN‚ج“؟گى–{‘à‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚جژه—حŒRپ@‚ئپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ى‹{ژRژRک[‚ةŒü‚©‚¤’r“c‘gگ¨
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚ج‚Q‚آ‚ة•ھ‚¯‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‡Aپ@ “ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚جژه—حŒR‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ج’©‚ةپAٹضƒ–Œ´–~’n
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج“Œ‘¤‚ة•zگw‚·‚é
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ج’©پjپثپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‡Bپ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚جژه—حŒR‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚XŒژ‚P‚T“ْŒك‘O‚Wژچ ‚©‚çŒكŒم
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚Qژچ ‚ـ‚إپAٹضƒ–Œ´–~’n‚إ پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ گ¼ŒRپiگخ“c•ûپj‚جژه—حŒR‚ئŒًگي
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiŒˆگي‚ًچs‚¤پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚XŒژ‚P‚T“ْŒك‘O‚Wژچ پ`
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒكŒم‚Qژچ پjپثپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ج’©‚©‚çŒك‘O
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚Oژچ ‚ـ‚إپA‰ئچN‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“چ”zژR پi‚à‚à‚‚خ‚è‚â‚ـپAٹضƒ–
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ´–~’n‚ج“Œ‘¤پj‚إŒˆگي‚ًژwٹِ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@‚XŒژ‚P‚T“ْŒك‘O‚P‚Oژچ ‚©‚ç
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒكŒم‚Qژچ ‚ـ‚إپA‰ئچN‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گwڈê–ىپ@پi‚¶‚ٌ‚خ‚جپAٹضƒ–Œ´–~
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’n’†‰›•”پj‚إŒˆگي‚ًژwٹِ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‡Cپ@‚XŒژ‚P‚T“ْŒكŒم‚Qژچ ‚ةپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹضƒ–Œ´–~’n‚إپAگ¼ŒRپiگخ“c•ûپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جژه—حŒR‚حپA‘چ•ِ‚ê‚ئ‚ب‚èپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”s‘–پA”s–k‚µپA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جژه—حŒR‚حپAگ¼ŒRپiگخ“c•ûپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جژه—حŒR‚ة‘خ‚µŒˆگي‚إڈں—ک
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ً“¾‚é
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚XŒژ‚P‚T“ْŒكŒم‚Qژچ پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@‚XŒژ‚P‚T“ْŒكŒم‚Qژچ پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گwڈê–ى‚إپA‰ئچN‚حŒˆگيڈں—ک پB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@پuژjژہپiگVگàپjٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپv‚جŒˆگي
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚إ‚جپA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج ژه—حŒR
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚ج“®‚«پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚جژه—حŒR
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiگوژèگ¨‚ج•ں“‡‘gگ¨‚ئ‰ئچN
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج“؟گى–{‘àپjپ@‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‡@پ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚جژه—حŒR‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ‘پ’©‚ةپA‘هٹ_ƒGƒٹƒA‚ج”ü”Z
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گشچâپi‚ف‚ج‚ ‚©‚³‚©پj•t‹كپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiٹضƒ–Œ´–~’n‚ج“Œ•ûپj‚ًڈo”
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚XŒژ‚P‚T“ْ‘پ’©پjپث
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@“؟گى‰ئچN‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚XŒژ‚P‚T“ْ‘پ’©‚ةپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘هٹ_ƒGƒٹƒA‚ج”ü”Zگشچâ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•t‹ك‚إپA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ً‚R‚آ‚ة•ھ‚¯‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰ئچN‚ئ“؟گى–{‘à‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹضƒ–Œ´–~’n“ىگ¼•”پ@‚ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژR’†‘؛پ@پi‚â‚ـ‚ب‚©‚ق‚çپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹضƒ–Œ´–~’n‚جگ¼•ûپE–ٌ‚Q‚‹‚چپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ةŒü‚©‚¤پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گوژèگ¨‚ج’r“c‘gگ¨‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘هٹ_ƒGƒٹƒA‚ج“ى‹{ژRپi‚ب‚ٌ‚®
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¤‚³‚ٌپAٹضƒ–Œ´–~’n‚ج“Œ•ûپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‘O–ت‚ةŒü‚©‚¢پA•zگw‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گوژèگ¨‚ج•ں“‡‘gگ¨‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژR’†‘؛پ@پi‚â‚ـ‚ب‚©‚ق‚çپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹضƒ–Œ´–~’n‚جگ¼•ûپE–ٌ‚Q‚‹‚چپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ةŒü‚©‚¤پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‡Aپ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚جژه—حŒR‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚XŒژ‚P‚T“ْ‚جŒك‘O‚P‚Oژچ ‚©‚ç
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ³Œكچ ‚ـ‚إپAژR’†‘؛پ@پi‚â‚ـ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ب‚©‚ق‚çپAٹضƒ–Œ´–~’n‚جگ¼•ûپE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–ٌ‚Q‚‹‚چپj‚إپAگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—ک•ûپj‚جژه—حŒR‚ئŒًگيپiŒˆگي‚ً
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چs‚¤پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚XŒژ‚P‚T“ْ‚جŒك‘O‚P‚Oژچ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ`گ³Œكچ پjپث
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‡Bپ@‚XŒژ‚P‚T“ْگ³Œكچ ‚ةپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جژه—ح
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒR‚ھپA‘چ•ِ‚ê‚ئ‚ب‚èپA”s‘–پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”sگي‚µپA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚جژه—ح
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒR‚حپAژR’†‘؛‚إپAگ¼ŒRپi•ٍچs
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈOپE–ر—ک•ûپj‚جژه—حŒR‚ة‘خ‚µ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œˆگي‚إڈں—ک‚ً“¾‚é
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚XŒژ‚P‚T“ْگ³Œكچ پjپB
پ@
پZپ@‚µ‚ٌپ@پ@گe”ث‘ه–¼پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ٌ‚د‚ٌ‚¾‚¢‚ف‚ه‚¤پjپBپ@پsچ]Œث–‹•{پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@گe”ث‘ه–¼پ@پi ‚µ‚ٌ‚د‚ٌ‚¾‚¢‚ف‚ه‚¤پjپ@‚ئ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“؟گىژپˆê–هپiˆê‘°پj‚ج‘ه–¼پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@چ]Œث–‹•{‚ج–‹”ث‘جگ§‚إ‚ج‘ه–¼‚حپAگe”ث
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘ه–¼پ@پi‚µ‚ٌ‚د‚ٌ‚¾‚¢‚ف‚ه‚¤پjپAپ@•ˆ‘م‘ه–¼پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi ‚س‚¾‚¢‚¾‚¢‚ف‚ه‚¤پjپAپ@ٹO—l‘ه–¼پ@پi‚ئ‚´‚ـ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¾‚¢‚ف‚ه‚¤پjپ@‚ج‚R‚آ‚ة•ھ‚¯‚ç‚ê‚éپBپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@گe”ث‘ه–¼‚ح“؟گىژپˆê–هپiˆê‘°پj‚ج‘ه
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–¼‚إ‚ ‚èپAپ@•ˆ‘م‘ه–¼‚حڈ‰‚ك‚©‚ç“؟گىژپ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰ئگbپiگb‰؛پj‚إ‚ ‚ء‚½‘ه–¼‚إ‚ ‚èپAپ@ٹO—l‘ه
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–¼‚ح‚P‚U‚O‚O”NپiŒc‰‚T”Nپj‚ج“V‰؛•ھ‚¯–ع‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گي‚¢پiٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پA‘¼پj‘OŒم‚و‚è“؟گىژپ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ةڈ]‚ء‚½پi“؟گىژپ‚جگb‰؛‚ة‚ب‚ء‚½پj‘ه–¼‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@چ]Œث–‹•{‚ج–‹”ث‘جگ§‚إ‚جپA‘ه–¼پi‚¾‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ف‚ه‚¤پj‚ئ‚حپAپ@چ]Œث–‹•{‚جڈ«ŒR‚ئژهڈ]ٹض
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒW‚ًŒ‹‚ٌ‚¾پA‚P–œگخˆبڈم‚ج•گژm‚إ‚ ‚éپB
پ@
پZپ@‚¶‚ٌپ@پ@گr•؛‰qپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚ٌ‚ׂ¢پjپBپ@پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= •›“cپi‚»‚¦‚¾پjگr•؛‰qپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@–LگbڈG‹g‚ج–…پE‚ ‚³‚ذپi’©“ْ•Pپj
‚ج‘و‚P”ش–ع‚ج•vپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث •›“c گr•؛‰qپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚ٌپ@پ@گl–¼پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ٌ‚ك‚¢پjپBپ@پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ‘O‹ك‘م‚ج“ْ–{‚جگl–¼پjپB
پ@
پZپ@‚µ‚ٌپ@پ@گVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ٌ‚à‚ٌ‚²‚ë‚¢‚اپj پBپ@پsگl—قپtپB
پi= –k•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپA–يگ¶“n—ˆŒnپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiگl—قٹwڈم‚ج•ھ—قپE“ء’¥پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚s‚g‚dپ@‚m‚n‚q‚s‚g‚d‚q‚mپ@‚l‚n‚m‚f‚n‚k‚n‚h‚cپD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث گVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپiŒأگl—قٹwژ«“TپjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@گVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپi= –k•ûƒ‚ƒ“ƒS
ƒچƒCƒhپjپ@‚ئپAپ@Œأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپi= “ى
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ •ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپjپ@‚ج‚QƒOƒ‹پ[ƒv‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh‚ج‚P‚آپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@“ْ–{‚جپAپu“n—ˆŒn–يگ¶گlپvپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پu–يگ¶“n—ˆŒnŒأ‘م“ْ–{گlپv‚ب‚ا
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جپAپu–يگ¶“n—ˆŒnپv‚جگlپXپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@گVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپi= –k•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپj‚ج
پ@گlپX‚حپAپ@–ٌ‚Q–œ”N‘O‚ةپAƒVƒxƒٹƒA“Œ•”‚إپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپi= “ى•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپj‚©‚ç
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گi‰»‚µ‚½گl—ق‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@گVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپi= –k•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپj‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@–ٌ‚Q–œ”N‘O‚ةپAƒVƒxƒٹƒA“Œ•”پi–kƒAƒWƒA“Œ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@ پ@•”پj‚إپAپ@Œ»گ¶گl—قپi= گVگlپAƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒXپj‚جپAŒأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپi= “ى•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپj
پ@پ@‚جپA—eژpپEٹOŒ©پi‘ج گFپE‘جŒ^پj‚ھٹ¦—â’n“K‰
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ة•د‰»‚µپAپ@Œأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپi= “ى•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچ
پ@ƒCƒhپj‚©‚çگi‰»‚µ‚ؤڈoŒ»‚µ‚½گl—ق ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@–ٌ‚S–œ”N‘O‚ةƒAƒWƒA“ى“Œ•”‚إڈoŒ»‚µ ‚½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ Œأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپi= “ى•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپj‚حپA–k
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ڈم‚µپAٹ¦—â’n‚جƒVƒxƒٹƒA“Œ•”‚ة’·‚‹ڈڈZ‚µپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ –ٌ‚Q–œ”N‘O‚ةƒVƒxƒٹƒA“Œ•”‚إپA—eژp‚ھٹ¦—â
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ’n“K‰‚ئ‚ب‚èپAگVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپi= –k•ûƒ‚ƒ“ƒS
پ@پ@پ@پ@ ƒچƒCƒhپj‚ھپAڈoŒ»‚µ‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@ پœپ@گVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپi= –k•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپj‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ»گ¶گl—قپi= گVگlپAƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒXپj‚جگl
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژي•ھ—قƒOƒ‹پ[ƒv‚جپAƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh پiŒأƒ‚ƒ“ƒS
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒچƒCƒh‚ئگVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh‚ج‚Qژيپj‚ج‚P‚آ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@ پœپ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh‚حپA –ٌ‚S–œ”N‘O‚ةƒAƒWƒA“ى
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“Œ•”‚إڈoŒ»‚µ‚½پAŒأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپi= “ى•û ƒ‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒ“ƒSƒچƒCƒhپjپ@‚ئپAپ@–ٌ‚Q–œ”N‘O‚ةƒVƒxƒٹƒA“Œ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•”‚إڈoŒ»‚µ‚½پAگVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپi= –k•ûƒ‚ƒ“
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒSƒچƒCƒhپj‚ج‚Qژي—ق‚جگl—ق‚ة•ھ—ق‚³‚ê‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@ پœپ@گVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپi= –k•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپj‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{ ’nˆو‚جپAپu“n—ˆŒn–يگ¶گlپvپAپu–يگ¶“n—ˆ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒnŒأ‘م“ْ–{گlپv‚ب‚ا‚جپAپu–يگ¶“n—ˆŒnپv‚جگl
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پX‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@ƒAƒWƒA‘ه—¤‚©‚çگو‚ةپA–ٌ‚P‚Q‚O‚O‚O”N‘O‚©
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ç“ꕶژ‘م‚ةپA“ْ–{’nˆو‚ضˆع“®‚µ ‚ؤ‚«‚½پAŒأ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپi= “ى•û ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپj‚جگlپX‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ْ–{’nˆوپi“ْ–{–{“yپA“ىگ¼ڈ”“‡پA–kٹC“¹پj‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پu“ꕶگlپvپAپu“ꕶŒnپv‚جگlپX‚ئ‚ب‚èپAپ@ƒAƒWƒA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘ه—¤‚©‚çŒم‚©‚çپA–ٌ‚Q‚S‚O‚O”N‘O‚©‚ç–يگ¶ژ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘م‘Oٹْ‚ةپA“ْ–{–{“y‚ضˆع“®‚µ‚ؤ‚«‚½پAگVƒ‚ƒ“
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒSƒچƒCƒhپi= –k•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپj‚جگlپX‚حپA“ْ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–{–{“y‚إپAپu“n—ˆŒn–يگ¶گlپvپAپu–يگ¶“n—ˆŒnپv
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جگlپX‚ئ‚ب‚èپAپ@Œأ‘م“ْ–{Œمٹْپi“ق—اپE•½ˆہ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ‘مپj‚ةپAŒأپEگVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh‚جپu“ꕶŒnپv‚ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پu–يگ¶“n—ˆŒnپv‚ھپA“ْ–{–{“y‚إچ¬ŒŒ‚µ‚ؤپAپu–{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“y“ْ–{گlپvپi= –{“yگlپjپiŒ»چف‚ج‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚ج“ْ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–{گlپj‚ئ‚ب‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@گVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh‚ض‚جگi‰»•\پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰»گخ—قگl‰ژپi= ’†گVگ¢ƒzƒ~ƒmƒCƒhپjپثپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ گl—ق‚جپA‰ژگlپثپ@Œ´گlپi= ƒzƒ‚پEƒGƒŒƒNƒg
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ƒX—قپjپثپ@‹Œگlپi= ‘Oƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒX—قپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پثپ@Œ»گ¶گl—قپi= گVگlپAƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒX
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiژيپjپjپثپ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh‚جŒأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒC ƒh
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پi= “ى•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپjپثپ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ گVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپi= –k•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@“ْ–{گlپi“ْ–{چفڈZ–¯پj‚ض‚جگi‰»•\پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰»گخ—قگl‰ژپi= ’†گVگ¢ƒzƒ~ƒmƒCƒhپjپثپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گl—ق‚جپA‰ژگlپثپ@Œ´گlپi= ƒzƒ‚پEƒGƒŒƒNƒgپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒX—قپjپثپ@‹Œگlپi= ‘Oƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒX—قپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پثپ@Œ»گ¶گl—قپi= گVگlپAƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒX
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiژيپjپjپثپ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپثپ@“ꕶگlپثپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–يگ¶گlپثپ@Œأ‘م“ْ–{گlپثپ@پu–{“y“ْ–{گlپv
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= –{“yگlپjپA پu—®‹…گlپvپAپuƒAƒCƒkگlپvپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ،پ@Œ»‘م“ْ–{گlپi“ْ–{چفڈZ–¯پj‚ض‚جگi‰»•\پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰»گخ—قگl‰ژپi= ’†گVگ¢ƒzƒ~ƒmƒCƒhپjپثپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گl—ق‚جپA‰ژگlپثپ@Œ´گlپi= ƒzƒ‚پEƒGƒŒƒNƒg
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒX—قپjپثپ@‹Œگlپi= ‘Oƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒX—قپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پثپ@Œ»گ¶گl—قپi= گVگlپAƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒX
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiژيپjپjپثپ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپثپ@“ꕶگlپثپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–يگ¶گlپثپ@Œأ‘م“ْ–{گlپثپ@’†گ¢“ْ–{گlپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پثپ@‹كگ¢“ْ–{گlپثپ@‹ك‘م“ْ–{گlپثپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ»‘م“ْ–{گlپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث “ْ–{گlپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث Œ´“ْ–{گlپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “n—ˆŒn–يگ¶گlپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث –يگ¶“n—ˆŒnپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث –{“y“ْ–{گlپi= –{“yگlپjپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث “ْ–{گlƒ‹پ[ƒcپEƒKƒCƒhƒuƒbƒNپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث Œأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپjپB
پ@
پZپ@‚µ‚ٌپ@پ@گV–ه ’CŒـکYپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ٌ‚à‚ٌ‚½‚آ‚²‚낤پjپBپ@پsگl–¼پtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@’¬‰خڈء‚µپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@چ]Œث–‹•{پE‘و‚P‚T‘مڈ«ŒRپE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “؟گىŒcٹىپi‚و‚µ‚ج‚شپj‚ج‹¦—حژزپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@چ]Œث‚ج’¬‰خڈء‚µ‚ج“ھ—ج‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚PگlپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث چ]Œث‚ج’¬‰خڈءپjپBپ@
پ@
پZپ@‚µ‚ٌپ@پ@گw‰®پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ٌ‚âپjپBپ@پsچشپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@گw‰®پ@پi‚¶‚ٌ‚âپj‚ئ‚حپA•گ‰ئ‚ج‹ڈڈٹ‚إ‚
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ]Œثژ‘م‚إ‚حپAپ@چ]Œث–‹•{‚جˆêچ‘ˆêڈé
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—ك‚ة‚و‚èپA••Œڑ—جژه‚حپAڈé‚ً‚P‚آ‚ج‚فژ‚؟پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚»‚êˆبٹO‚جچشپi‚ئ‚è‚إپjپAٹظ‚حپAگw‰®‚ئŒؤ‚خ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ê‚éپBپ@‚ـ‚½پAگw‰®‚حپAڈéژ‚؟‚إ‚ب‚¢•گ ‰ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‹ڈڈٹ‚إ‚à‚ ‚éپBپ@
پ@
پZپ@‚µ‚ٌپ@پ@گV—ïپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ٌ‚ê‚«پjپBپ@پs—ïپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= “ْ–{‚إ‚حپAگV—ï‚حپA‘¾—z—ï
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جƒOƒŒƒSƒٹƒI—ïپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚m‚d‚vپ@‚b‚`‚k‚d‚m‚c‚`‚qپD
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث ‘¾—z—ï “ْ–{ژjژ«“TپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپث —ïپi‚±‚و‚فپj “V•¶ٹwژ«“TپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@“ْ–{‚إ‚حپAپ@گV—ï‚حپA‘¾—z—ï
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جƒOƒŒƒSƒٹƒI—ïپBپ@‹Œ—ï‚حپA‘¾‰A
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—ïپi=‰A—ïپj‚ج‘¾‰A‘¾—z—ïپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@“ْ–{‚إ‚حپAپ@گV—ïپiŒ»چsگ¼—ïپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚حپA‘¾—z—ï‚جƒOƒŒƒSƒٹƒI—ï‚إپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚W‚V‚R”Nپi–¾ژ،‚U”Nپj‚©‚猻چف‚ـ
‚إپAژg—p‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{‚إ‚حپA ‹Œ—ï‚حپA‘¾‰A—ï
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi=‰A—ïپj‚ج‘¾‰A‘¾—z—ï‚إپA‹IŒ³
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiŒمپj‚U‚X‚O”Nچ ‚©‚ç‚P‚W‚V‚Qپi–¾ژ،
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚T”Nپj”N‚ـ‚إپAژg—p‚³‚ꂽپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@“ْ–{‚â’†چ‘‚إ‚حپAپ@گV—ï‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‘¾—z—ï‚جƒOƒŒƒSƒٹƒI—ï‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@“ْ–{‚â’†چ‘‚إ‚حپAپ@‹Œ—ï‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘¾‰A—ï‚ج‘¾‰A‘¾—z—ï‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‰¢•ؤ‚إ‚حپAپ@گV—ï‚حپA‘¾—z—ï
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚جƒOƒŒƒSƒٹƒI—ï‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@‰¢•ؤ‚إ‚حپAپ@‹Œ—ï‚حپA‘¾—z—ï
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚جƒ†ƒٹƒEƒX—ï ‚â ‘¾‰A—ï‚ج‘¾‰A
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‘¾—z—ï‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@‰¢•ؤپA“ْ–{پA’†چ‘ˆبٹO‚جگ¢ٹE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚ج—ل‚إ‚حپAپ@Œ»چفپAƒCƒXƒ‰ƒ€Œ—‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚حپA‘¾‰A—ï‚جڈƒگˆ‘¾‰A—ï‚جƒCƒX
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ƒ‰ƒ€—ï‚جƒqƒWƒ…ƒ‰—ïپ@‚ئپ@‘¾—z—ï
‚جƒOƒŒƒSƒٹƒI—ï‚جŒ»چsگ¼—ïپ@‚ھپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ •¹—p‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‘¾—z—ï “V•¶ٹwژ«“TپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ƒOƒŒƒSƒٹƒI—ïپAƒ†ƒٹƒEƒX—ïپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپث ‘¾‰A—ïپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پiپث ‘¾‰A‘¾—z—ïپAڈƒگˆ‘¾‰A—ïپjپB
پ@
پ@
پ@
پ@پ@پ@پœپ@Œـڈ\‰¹ڈ‡ پi‚ ‚¢‚¤‚¦‚¨ڈ‡پjپB
پ@
پ@
پ@پ@پ@پ، پwپ@Œ»چف‚حپA‰ك‹ژ‚جگ¬‰ت‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–¢—ˆ‚حپAŒ»چف‚جگ¬‰ت‚إ‚ ‚éپBپ@پx
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi—ا‚«Œ»چف‚حپA‰ك‹ژ‚جگlپX‚ج—ا‚«“w—ح
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚âٹˆ“®‚جگد‚فڈd‚ث‚جگ¬‰ت‚إ‚ ‚èپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ –¾‚é‚¢—ا‚«–¢—ˆ‚حپAŒ»چف‚جگlپX‚جپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ —ا‚«“w—ح‚âٹˆ“®‚جگد‚فڈd‚ث‚ة‚و‚ء‚ؤ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ Œ`گ¬‚³‚ê‚éپBپj
پ@
پ@
پ،پ@ڈمˆت‚ج‚v‚d‚aƒTƒCƒgپBپ@
پ پ@پi‚j‚n‚gپjپ@ƒJƒiƒ„ƒ}پ@ƒIƒtƒBƒVƒƒƒ‹پ@ پ@پ„
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒzپ[ƒ€ƒyپ[ƒWپB
پ پ@پi‚b‚“‚…پjپ@ چ‘چغ—‰ً‘چچ‡ƒTƒCƒgپ@پ@پ@ پ„
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚ي‚ê‚ç’n‹…ژs–¯پjپBپ@
پ پ@پi‚j‚…پjپ@ پ@•S‰بژ–“TپBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ„
پ پ@پi‚j‚ˆ‚ˆپjپ@ —ًژjٹwƒnƒ“ƒhƒuƒbƒNپBپ@پ@پ@ پ„
پ پ@پi‚j‚ٹ‚ˆ‚ˆپjپ@“ْ–{ژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒNپBپ@پ@پ@ پ„
پ پ@پi‚j‚ٹ‚ˆ‚ˆپjپ@“ْ–{ژjژ«“Tپi‘چچ‡”إپjپBپ@پ@ پ„
پ پ@پi‚j‚ٹ‚ˆ‚ˆپjپ@“ْ–{ژjژ«“TپE“ْ–{Œê”إپBپ@ پ„
پ پ@پi‚j‚ٹ‚ˆ‚ˆپjپ@‚±‚ج“ْ–{Œêƒyپ[ƒWپBپ@
پ@
پ@
پ@
پ@
پ،پ@“–ƒzپ[ƒ€ƒyپ[ƒW‚جگ§چىپE’کچىŒ پ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}پB
پ@
پ،پ@‚b‚ڈ‚گ‚™‚’‚‰‚‡‚ˆ‚”پi‚bپjپ@‚s‚j‚j‚hپ@‚j‚پ‚ژ‚پ‚™‚پ‚چ‚پپD
پ@پ@ ‚`‚Œ‚Œپ@‚q‚‰‚‡‚ˆ‚”‚“پ@‚q‚…‚“‚…‚’‚–‚…‚„پD
پ@پ@
پ@
پ@
پں “ْ–{ژjژ«“T
پ@
پœپ@Œ©ڈo‚µŒê‚حپAƒOƒٹپ[ƒ“‚إƒ}پ[ƒN‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[پi–عژںپj‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژjژ«“TپE“ْ–{Œê”إ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپB
پ پ@“ْ–{ژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒNپE“ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ پ@“ْ–{ژjژ«“TپE‰pŒê”إ ‚ضپB
پ پ@“ْ–{ژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒNپE‰pŒê”إ ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پں ”hگ¶Œ©ڈo‚µŒêƒTƒCƒgپB
پ،پ@پu‚µپv ٹî–{پEŒ©ڈo‚µŒê‚v‚d‚aƒTƒCƒgپ@‚m‚ڈپD ‚ٹ‚پپ|‚“‚ˆ‚‰پ@
پ@پ@‚جپA”hگ¶Œ©ڈo‚µŒêƒTƒCƒgپB
پ@
پ،پ@‚m‚ڈپD‚ٹ‚پپ|‚“‚ˆ‚‰پ|‚R‚P‚T‚OپB
پœپ@Œ©ڈo‚µŒêچ€–عپ@‚µپ@‚ـپ@‚أپ@پiپ@‚R‚Pپ@‚ـ پ^پ@‚أپ@‚T‚O
پ@پ@•t‹كپ@پ@‘و‚P•”پE‚ـپE‘چچ‡ƒOƒ‹پ[ƒvپAپ@پu‚µ‚ـ‚أپvڈWچ‡
پ@پ@ƒOƒ‹پ[ƒvپ@پjپBپ@
پZ ‚µ‚ـپ@پ@“‡’أگؤ•jپ@پi‚µ‚ـ‚أ‚ب‚è‚ ‚«‚çپjپB
پZ ‚µ‚ـپ@پ@“‡’أگؤ‹»پ@پi‚µ‚ـ‚أ‚ب‚肨‚«پjپB
پZ ‚µ‚ـپ@پ@“‡’أ‹vŒُپ@ پi‚µ‚ـ‚أ‚ذ‚³‚ف‚آپjپB
پ@
پ،پ@‚m‚ڈپD‚ٹ‚پپ|‚“‚ˆ‚‰پ|‚R‚W‚P‚QپB
پœپ@Œ©ڈo‚µŒêچ€–عپ@‚¶پ@‚مپ@‚¢پ@پiپ@‚مپ@‚R‚W پ^پ@‚¢پ@‚P‚Q
پ@پ@پ@•t‹كپ@‘و‚P•”پE‚نپEƒAچsƒOƒ‹پ[ƒv پjپB
پZپ@‚¶‚نپ@پ@ڈ]ˆêˆتپ@پi‚¶‚م‚¢‚؟‚¢پjپBپ@
پ@
پ،پ@‚m‚ڈپD‚ٹ‚پپ|‚“‚ˆ‚‰پ|‚R‚W‚Q‚TپB
پœپ@Œ©ڈo‚µŒêچ€–عپ@‚¶پ@‚مپ@‚²پ@پiپ@‚مپ@‚R‚W پ^پ@‚²پ@‚Q‚Tپ@پ@پ@
پ@پ@•t‹كپ@پ@‘و‚P•”پE‚نپEƒJچsƒOƒ‹پ[ƒvپjپB
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]‹مˆت پi‚¶‚م‚‚¢پjپB
پ@
پ،پ@‚m‚ڈپD‚ٹ‚پپ|‚“‚ˆ‚‰پ|‚R‚W‚Q‚XپB
پœپ@Œ©ڈo‚µŒêچ€–عپ@‚µپ@‚مپ@‚²پ@پiپ@‚مپ@‚R‚W پ^پ@‚²پ@‚Q‚X
پ@پ@•t‹كپ@پ@‘و‚P•”پE‚نپEƒJچsƒOƒ‹پ[ƒvپjپB
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]Œـˆت پi‚¶‚م‚²‚¢ پjپB
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]Œـˆتڈم پi‚¶‚م‚²‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپB
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]Œـˆت‰؛ پi‚¶‚م‚²‚¢‚ج‚°پj پB
پ@
پ،پ@‚m‚ڈپD‚ٹ‚پپ|‚“‚ˆ‚‰پ|‚R‚W‚R‚PپB
پœپ@Œ©ڈo‚µŒêچ€–عپ@‚¶پ@‚مپ@‚³پ@پiپ@‚مپ@‚R‚W پ^پ@‚³پ@‚R‚Pپ@پ@پ@
پ@پ@•t‹كپ@پ@‘و‚P•”پE‚نپEƒTچsƒOƒ‹پ[ƒvپjپBپ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]ژOˆت پi‚¶‚م‚³‚ٌ‚فپjپB
پ@
پ،پ@‚m‚ڈپD‚ٹ‚پپ|‚“‚ˆ‚‰پ|‚R‚W‚R‚RپB
پœپ@Œ©ڈo‚µŒêچ€–عپ@‚¶پ@‚مپ@‚µپ@پiپ@‚مپ@‚R‚W پ^پ@‚µپ@‚R‚Rپ@پ@پ@
پ@پ@•t‹كپ@پ@‘و‚P•”پE‚نپEƒTچsƒOƒ‹پ[ƒvپjپBپ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]ژlˆت پi‚¶‚م‚µ‚¢پjپB
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]ژlˆتڈم پi‚¶‚م‚µ‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپB
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]ژlˆت‰؛ پi‚¶‚م‚µ‚¢‚ج‚°پjپB
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]ژµˆت پi‚¶‚م‚µ‚؟‚¢پjپB
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]ژµˆتڈم پi‚¶‚م‚µ‚؟‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپB
پ›پ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]ژµˆت‰؛ پi‚¶‚م‚µ‚؟‚¢‚ج‚°پjپB
پ@
پ،پ@‚m‚ڈپD‚ٹ‚پپ|‚“‚ˆ‚‰پ|‚R‚W‚T‚OپB
پœپ@Œ©ڈo‚µŒêچ€–عپ@‚µپ@‚مپ@‚¤پ`‚²پ@پiپ@‚مپ@‚R‚W پ^پ@‚¤پ`‚²پ@‚T‚Oپ@
پ@پ@پ@•t‹كپ@پ@‘و‚P•”پE‚نپE‘چچ‡ƒOƒ‹پ[ƒvپjپBپ@
پZپ@‚µ‚مپ@پ@ڈIگيپ@پi‚µ‚م‚¤‚¹‚ٌپjپ@پi‘¾•½—mگي
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘ˆپE“ْ’†گي‘ˆ‚جڈIگيپA ‚P‚X‚S‚TپjپB
پZپ@‚µ‚مپ@پ@ژçŒىپAژçŒى‘ه–¼پ@پi‚µ‚م‚²پA‚µ‚م
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚²‚¾‚¢‚ف‚ه‚¤پjپi ‚P‚Qپ`‚P‚Uگ¢‹IپjپB
پZپ@‚µ‚مپ@پ@ژçŒىپE’n“ھ‚جگف’uپ@پi‚µ‚م‚²پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¶‚ئ‚¤‚ج‚¹‚ء‚؟پjپi ‚P‚P‚W‚TپjپB
پ@
پ،پ@‚m‚ڈپD‚ٹ‚پپ|‚“‚ˆ‚‰پ|‚R‚W‚T‚RپB
پœپ@Œ©ڈo‚µŒêچ€–عپ@‚¶پ@‚مپ@‚ةپ@پiپ@‚مپ@‚R‚W پ^پ@‚ةپ@‚T‚Rپ@
پ@پ@پ@•t‹كپ@پ@‘و‚P•”پE‚نپEƒiچsƒOƒ‹پ[ƒvپjپBپ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]“ٌˆتپ@پi‚¶‚م‚ة‚¢پj پBپ@
پ@
پ،پ@‚m‚ڈپD‚ٹ‚پپ|‚“‚ˆ‚‰پ|‚R‚W‚U‚PپB
پœپ@Œ©ڈo‚µŒêچ€–عپ@‚¶پ@‚مپ@‚حپ@پiپ@‚مپ@‚R‚W پ^پ@‚حپ@‚U‚Pپ@پ@پ@
پ@پ@پ@•t‹كپ@پ@‘و‚P•”پE‚نپEƒnچsƒOƒ‹پ[ƒvپjپBپ@پ@
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]”ھˆت پi‚¶‚م‚ح‚؟‚¢پjپB
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]”ھˆتڈم پi‚¶‚م‚ح‚؟‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپB پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ›پ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]”ھˆت‰؛ پi‚¶‚م‚ح‚؟‚¢‚ج‚°پjپB
پ@
پ،پ@‚m‚ڈپD‚ٹ‚پپ|‚“‚ˆ‚‰پ|‚R‚W‚X‚WپB
پœپ@Œ©ڈo‚µŒêچ€–عپ@‚¶پ@‚مپ@‚ëپ@پiپ@‚مپ@‚R‚W پ^پ@‚ëپ@‚X‚Wپ@پ@پ@
پ@پ@پ@•t‹كپ@پ@‘و‚P•”پE‚نپEƒ‰چsپEƒڈپEƒ“پEƒOƒ‹پ[ƒvپjپB
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]کZˆت پi‚¶‚م‚ë‚‚¢پjپB
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]کZˆتڈم پi‚¶‚م‚ë‚‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپB
پZپ@‚¶‚مپ@پ@ڈ]کZˆت‰؛ پi‚¶‚م‚ë‚‚¢‚ج‚°پjپB
پ@
پ،پ@‚m‚ڈپD‚ٹ‚پپ|‚“‚ˆ‚‰پ|‚S‚O‚P‚QپB
پœپ@Œ©ڈo‚µŒêچ€–عپ@‚¶پ@‚هپ@‚¢پ@پiپ@‚هپ@‚S‚O پ^پ@‚¢پ@‚P‚Qپ@پ@پ@
پ@پ@پ@•t‹كپ@پ@‘و‚P•”پE‚وپEƒAچsƒOƒ‹پ[ƒvپjپBپ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@ڈ–ˆت پi‚¶‚ه‚¢پjپB
پ@
پ،پ@‚m‚ڈپD‚ٹ‚پپ|‚“‚ˆ‚‰پ|‚S‚O‚P‚TپB
پœپ@Œ©ڈo‚µŒêچ€–عپ@‚¶پ@‚هپ@‚¤پ@پiپ@‚هپ@‚S‚O پ^پ@‚¤پ@‚P‚Tپ@پ@پ@
پ@پ@پ@•t‹كپ@پ@‘و‚P•”پE‚وپEƒAچsƒOƒ‹پ[ƒvپjپBپ@
پZپ@‚¶‚هپ@پ@“ꕶژ‘مپ@ پi‚¶‚ه‚¤‚à‚ٌ‚¶‚¾‚¢پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P–œ‚Q‚O‚O‚O”N‘Oچ پ`‹IŒ³‘O‚Sگ¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹Iچ پjپB
پZپ@‚¶‚هپ@پ@“ꕶگlپ@پi‚¶‚ه‚¤‚à‚ٌ‚¶‚ٌپjپB
پZپ@‚¶‚هپ@پ@“ꕶ•¶‰»پ@ پi‚¶‚ه‚¤‚à‚ٌ‚ش‚ٌ‚©پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P–œ‚Q‚O‚O‚O”N‘Oچ پ`‹IŒ³‘O‚Sگ¢
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹Iچ پjپB
پ@
پ،پ@‚m‚ڈپD‚ٹ‚پپ|‚“‚ˆ‚‰پ|‚S‚O‚P‚VپB
پœپ@Œ©ڈo‚µŒêچ€–عپ@‚µپ@‚هپ@‚¤پ@پiپ@‚هپ@‚S‚O پ^پ@‚¤پ@‚P‚Vپ@پ@پ@
پ@پ@پ@•t‹كپ@پ@‘و‚P•”پE‚وپEƒAچsƒOƒ‹پ[ƒvپjپBپ@
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³ˆêˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚¢‚؟‚¢پjپB
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³“ٌˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚ة‚¢پjپB
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³ژOˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚³‚ٌ‚فپjپB
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³ژlˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚¢پjپB
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³ژlˆتڈمپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپB
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³ژlˆت‰؛پ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚¢‚ج‚°پjپB
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³Œـˆت پi ‚µ‚ه‚¤‚²‚¢پjپB
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³Œـˆتڈم پi ‚µ‚ه‚¤‚²‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپB
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³Œـˆت‰؛ پi ‚µ‚ه‚¤‚²‚¢‚ج‚°پjپB
پ›پ@‚µ‚هپ@پ@گ³کZˆت پi‚µ‚ه‚¤‚ë‚‚¢پjپB
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³کZˆتڈم پi‚µ‚ه‚¤‚ë‚‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپB
پ›پ@‚µ‚هپ@پ@گ³کZˆت‰؛ پi‚µ‚ه‚¤‚ë‚‚¢‚ج‚°پjپB
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³ژµˆت پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚؟‚¢پjپB
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³ژµˆتڈم پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚؟‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپB پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ›پ@‚µ‚هپ@پ@گ³ژµˆت‰؛ پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚؟‚¢‚ج‚°پjپB
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³”ھˆت پi‚µ‚ه‚¤‚ح‚؟‚¢پjپB
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³”ھˆتڈم پi‚µ‚ه‚¤‚ح‚؟‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپB
پ›پ@‚µ‚هپ@پ@گ³”ھˆت‰؛ پi‚µ‚ه‚¤‚ح‚؟‚¢‚ج‚°پjپB
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ³‹مˆت پi‚µ‚ه‚¤‚‚¢پjپB
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈڈ‰ˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚»‚¢پA‚µ‚ه‚¤‚µ‚ه‚¢پjپB
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈڈ‰ˆتڈمپ@پi‚µ‚ه‚¤‚»‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپB
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈڈ‰ˆت‰؛پ@پi‚µ‚ه‚¤‚»‚¢‚ج‚°پjپB
پ@
پ،پ@‚m‚ڈپD‚ٹ‚پپ|‚“‚ˆ‚‰پ|‚S‚O‚Q‚VپB
پœپ@Œ©ڈo‚µŒêچ€–عپ@‚µپ@‚هپ@‚¤پ@پiپ@‚هپ@‚S‚O پ^پ@‚¤پ@‚Q‚Vپ@پ@پ@
پ@پ@پ@•t‹كپ@پ@‘و‚P•”پE‚وپE‘چچ‡ƒOƒ‹پ[ƒvپAپ@پu‚µ‚ه‚¤‚¦‚ٌپv
پ@پ@پ@ڈWچ‡ƒOƒ‹پ[ƒvپ@پjپB
پZپ@‚µ‚هپ@پ@‘‘‰€ پi‚µ‚ه‚¤‚¦‚ٌپj پi‚Wپ`‚P‚Uگ¢‹Iپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‹M‘°پEژ›ژذ“™‚ھژx”z‚·‚é—جˆوپjپB
پZپ@‚µ‚هپ@پ@‘‘‰€پEŒِ—جگ§پ@پi‚µ‚ه‚¤‚¦‚ٌپE‚±‚¤‚è
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ه‚¤‚¹‚¢پjپ@پi‚P‚Oپ`‚P‚Uگ¢‹IپjپB
پZپ@‚µ‚هپ@پ@‘‘‰€گ§“xپ@پi‚µ‚ه‚¤‚¦‚ٌ‚¹‚¢‚اپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚P‚Oپ`‚P‚Uگ¢‹IپjپB
پ@
پ،پ@‚m‚ڈپD‚ٹ‚پپ|‚“‚ˆ‚‰پ|‚S‚O‚R‚OپB
پœپ@Œ©ڈo‚µŒêچ€–عپ@‚µپ@‚هپ@‚¤‚µپ`‚¤‚قپ@پiپ@‚هپ@‚S‚O پ^پ@‚¤‚µپ`‚¤‚قپ@
پ@پ@‚R‚Oپ@•t‹كپ@پ@‘و‚P•”پE‚وپE‘چچ‡ƒOƒ‹پ[ƒvپjپB
پZپ@‚¶‚هپ@پ@ڈمژmپ@پi‚¶‚ه‚¤‚µپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= چ]Œثژ‘م‚جڈم‹‰•گژmپjپB
پZپ@‚µ‚هپ@پ@گ¹•گ“Vچc پi‚µ‚ه‚¤‚ق‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پj پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚Wگ¢‹IپjپB
پ@
پ،پ@‚m‚ڈپD‚ٹ‚پپ|‚“‚ˆ‚‰پ|‚S‚O‚R‚RپB
پœپ@Œ©ڈo‚µŒêچ€–عپ@‚µپ@‚هپ@‚¤‚يپ@پiپ@‚هپ@‚S‚O پ^پ@‚¤‚يپ@‚R‚Rپ@پ@پ@
پ@پ@•t‹كپ@پ@‘و‚P•”پE‚وپE‘چچ‡ƒOƒ‹پ[ƒvپAپ@پu‚µ‚ه‚¤‚يپvڈWچ‡
پ@پ@ƒOƒ‹پ[ƒv پjپB
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈ؛کaپEگيŒمژ‘مپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚يپE‚¹‚ٌ‚²‚¶‚¾‚¢پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚X‚S‚Tپ`‚P‚X‚W‚XپjپB
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈ؛کaپEگي‘Oژ‘مپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚يپE‚¹‚ٌ‚؛‚ٌ‚¶ ‚¾‚¢پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚X‚Q‚Uپ`‚P‚X‚S‚TپjپB
پZپ@‚µ‚هپ@پ@ڈ؛کa“Vچc پi‚µ‚ه‚¤‚ي‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پj پB
پi=—Tگmپi‚ذ‚ë ‚ذ‚ئپj“VچcپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپثپ@—Tگm“VچcپjپBپ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژjژ«“TپE“ْ–{Œê”إ ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{ژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN پE “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ژٌ“sپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚م‚ئپjپB
پ@
پ،پ@ژٌ“sپBپ@
پ@
پ،پ@–¼ڈج پFپ@ژٌ“sپ@پi‚µ‚م‚ئپjپB
پ@
پ،پ@پs“sژsپtپB
پ@
پ،پ@ژٌ“s‚ئ‚حپA
پ@پ@ چ‘‰ئگژ،پEچsگ‚ج’†گS’n‚إ‚ ‚èپAپ@چ‘‰ئ
پ@پ@ ƒŒƒxƒ‹‚جگژ،پEچsگ‚ج’†ٹj“sژs‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@ژٌ“s‚ئ‚حپA
پ@پ@ ‚ ‚éچ‘‚جپAچ‘‰ئگŒ پEگ•{‚ج–{‹’’n‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@ ‚ ‚éچ‘‘S“y‚ً“ژ،‚·‚é‘Sچ‘گŒ پEگ•{‚ج
’†‰›گ•{‚ج’†ٹj“sژs‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@“ْ–{‚جژٌ“s‚ئ‚حپA
پ@پ@ “ْ–{‚جچ‘‰ئگŒ پEگ•{‚ج–{‹’’n‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@ “ْ–{–{“y‚ً“ژ،‚·‚é‘Sچ‘گŒ پEگ•{‚ج
پ@پ@ ’†ٹj“sژs‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@‹IŒ³Œم‚Vگ¢‹Iچ ‚©‚猻چف‚ـ‚إپA
پ@پ@پ@“ْ–{‚جژٌ“s‚حپAژه‚ةپAپ@پ@
پ@پ@پ@”ٍ’¹پ@پi‚ ‚·‚©پA”ٍ’¹‹پAŒ»پE“ق—اŒ§–¾“ْچپ‘؛پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚Vگ¢‹Iچ پ[‚U‚X‚S”NپjپA
پ@پ@پ@ٹ€Œ´پ@پi‚©‚µ‚ح‚çپA“،Œ´‹پAŒ»پE“ق—اŒ§ٹ€Œ´ژsپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚U‚X‚S”Nپ[‚V‚P‚O”NپjپA
پ@پ@پ@“ق—اپ@پi•½ڈé‹پAŒ»پE“ق—اŒ§“ق—اژsپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚V‚P‚O”Nپ[‚V‚S‚O”NپA‚V‚S‚T”Nپ[‚V‚W‚S”NپjپA
پ@پ@پ@Œü“ْپ@پi‚ق‚±‚¤پA’·‰ھ‹پAŒ»پE‹“s•{Œü“ْژs
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚V‚W‚S”Nپ[‚V‚X‚S”NپjپA
پ@پ@پ@‹“sپ@پi•½ˆہ‹پAŒ»پE‹“s•{‹“sژsپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚V‚X‚S”Nپ[‚P‚P‚W‚T”NپA‚P‚R‚R‚R”Nپ[
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚T‚V‚U”NپA‚P‚T‚W‚Q”Nپ[‚P‚T‚W‚R”NپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚W‚U‚V”Nپ[‚P‚W‚U‚X”NپjپA
پ@پ@پ@ٹ™‘qپ@پiٹ™‘q–‹•{–{‹’’nپAŒ»پEگ_“قگىŒ§ٹ™‘qژs
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚P‚W‚T”Nپ[‚P‚R‚R‚R”NپjپA
پ@پ@پ@ˆہ“yپ@پi‚ ‚أ‚؟پAگD“cگŒ –{‹’’nپAŒ»پEژ ‰êŒ§
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆہ“y’¬پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚T‚V‚U”Nپ[‚P‚T‚W‚Q”NپjپA
پ@پ@پ@‘هچمپ@پi–LگbگŒ –{‹’’nپAŒ»پE‘هچم•{‘هچمژsپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚T‚W‚R”Nپ[‚P‚U‚O‚R”NپjپA
پ@پ@پ@چ]Œثپ@پiچ]Œث–‹•{–{‹’’nپAŒ»پE“Œ‹“sگç‘م“c‹وپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚R”Nپ[‚P‚W‚U‚V”NپjپA
پ@پ@پ@“Œ‹پ@پi‹كŒ»‘مگ•{–{‹’’nپAŒ»پE“Œ‹“s
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گç‘م“c‹وپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚W‚U‚X”Nپ[Œ»چفپjپA
پ@پ@‚ب‚ا‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@‚و‚è—‰ً‚ًگ[‚ك‚邽‚ك‚ةپA“ْ–{ژjژ«“T‚جپAپ@
پ@پ@پ@Œأ“sپi‚±‚ئپjپA“sپi‚ف‚₱پjپA
پ@پ@پ@“sڈéپi‚ئ‚¶‚ه‚¤پjپA‹پi‚«‚ه‚¤پjپA
پ@پ@پ@ٹ™‘qپA
پ@پ@پ@ˆہ“yپA
پ@پ@پ@‘هچمپA
پ@پ@ چ]ŒثپA
پ@پ@پ@“Œ‹پAپ@
پ@پ@‚جچ€–ع‚àژQڈئ‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“Tپ@‚S‚P‚T‚Q‚VپB
پ@
پ@
پ@پ@پ پ@“ْ–{Œأ“sƒKƒCƒhƒuƒbƒNپB
پ@ پ پ@“ْ–{Œأ“s ٹضکA”N‘مڈ‡
پ@
پ@پ@پ پ@”ٍ’¹‹پ@‰و‘œƒAƒ‹ƒoƒ€پ@
پ@پ@پ@پ@ ‚m‚ڈپD‚PپB
پ@پ@پ پ@“،Œ´‹پ@‰و‘œƒAƒ‹ƒoƒ€
پ@پ@پ@پ@ ‚m‚ڈپD‚PپB
پ@پ@پ پ@’·‰ھ‹پ@‰و‘œƒAƒ‹ƒoƒ€پ@
پ@پ@پ@پ@ ‚m‚ڈپD‚PپB
پ@پ@پ پ@•½ˆہ‹پ@‰و‘œƒAƒ‹ƒoƒ€
پ@
پ@
پ@پ،پ@ژٌ“sپB
پ@
پ@پ@پ،پ@ژٌ“s‚ئ‚حپA
پ@پ@ پ@چ‘‰ئگژ،پEچsگ‚ج’†گS’n‚إ‚ ‚èپAپ@چ‘‰ئ
پ@پ@ پ@ƒŒƒxƒ‹‚جگژ،پEچsگ‚ج’†ٹj“sژs‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@ژٌ“s‚ئ‚حپA
پ@پ@ پ@‚ ‚éچ‘‚جپAچ‘‰ئگŒ پEگ•{‚ج–{‹’’n‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@ پ@‚ ‚éچ‘‘S“y‚ً“ژ،‚·‚é‘Sچ‘گŒ پEگ•{‚ج
پ@’†‰›گ•{‚ج’†ٹj“sژs‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@
پ@پ،پ@“ْ–{‚جژٌ“sپB
پ@
پ@پ@پ،پ@“ْ–{‚جژٌ“s‚ئ‚حپA
پ@پ@ پ@“ْ–{‚جچ‘‰ئگŒ پEگ•{‚ج–{‹’’n‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@ پ@“ْ–{–{“y‚ً“ژ،‚·‚é‘Sچ‘گŒ پEگ•{‚ج
پ@پ@ پ@’†ٹj“sژs‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@“ْ–{‚جپAژٌ“s‚ئ“sڈé‚â‹پB
پ@
پ@پ@پ،پ@“ْ–{‚جژٌ“s‚ئ‚حپA
پ@پ@ پ@“ْ–{–{“y‚ً“ژ،‚·‚é‘Sچ‘گŒ پEگ•{‚ج
پ@پ@پ@ ’†ٹj“sژs‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج“sڈéپE‹پ@پi‚ئ‚¶‚ه‚¤پE‚«‚ه‚¤پj
پ@پ@پ@پ@‚ئ‚حپAپ@“Vچc‚جڈZ‹ڈ‚ھ‚ ‚é“sژs‚إ‚ ‚éچc‹ڈ
پ@پ@پ@پ@“sژs‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ،پ@“ْ–{‚جپAٹ™‘qژ‘مپAˆہ“y“چژRژ‘مپAچ]Œث
پ@پ@پ@پ@ژ‘م‚إ‚حپA“ْ–{‚جژٌ“sپiگژ،پEچsگ‚ج’†گS
’nپj‚ئچc‹ڈ“sژsپi“sڈéپE‹پj‚ئ‚ح•ت‚ة‚ب‚éپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@“ْ–{‚جژٌ“sپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‹IŒ³Œم‚Vگ¢‹Iچ ‚©‚猻چف‚ـ‚إپA
پ@پ@پ@پ@“ْ–{‚جژٌ“s‚حپAژه‚ةپA
پ@پ@پ@پ@”ٍ’¹پ@پi‚ ‚·‚©پA”ٍ’¹‹پAŒ»پE“ق—اŒ§–¾“ْچپ‘؛پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚Vگ¢‹Iچ پ[‚U‚X‚S”NپjپA
پ@پ@پ@پ@ٹ€Œ´پ@پi‚©‚µ‚ح‚çپA“،Œ´‹پAŒ»پE“ق—اŒ§ٹ€Œ´ژsپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚U‚X‚S”Nپ[‚V‚P‚O”NپjپA
پ@پ@پ@پ@“ق—اپ@پi•½ڈé‹پAŒ»پE“ق—اŒ§“ق—اژsپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚V‚P‚O”Nپ[‚V‚S‚O”NپA‚V‚S‚T”Nپ[‚V‚W‚S”NپjپA
پ@پ@پ@پ@Œü“ْپ@پi‚ق‚±‚¤پA’·‰ھ‹پAŒ»پE‹“s•{Œü“ْژs
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚V‚W‚S”Nپ[‚V‚X‚S”NپjپA
پ@پ@پ@پ@‹“sپ@پi•½ˆہ‹پAŒ»پE‹“s•{‹“sژsپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚V‚X‚S”Nپ[‚P‚P‚W‚T”NپA‚P‚R‚R‚R”Nپ[
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚T‚V‚U”NپA‚P‚T‚W‚Q”Nپ[‚P‚T‚W‚R”NپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚W‚U‚V”Nپ[‚P‚W‚U‚X”NپjپA
پ@پ@پ@پ@ٹ™‘qپ@پiٹ™‘q–‹•{–{‹’’nپAŒ»پEگ_“قگىŒ§ٹ™‘qژs
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚P‚W‚T”Nپ[‚P‚R‚R‚R”NپjپA
پ@پ@پ@پ@ˆہ“yپ@پi‚ ‚أ‚؟پAگD“cگŒ –{‹’’nپAŒ»پEژ ‰êŒ§
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆہ“y’¬پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚T‚V‚U”Nپ[‚P‚T‚W‚Q”NپjپA
پ@پ@پ@پ@‘هچمپ@پi–LگbگŒ –{‹’’nپAŒ»پE‘هچم•{‘هچمژsپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚T‚W‚R”Nپ[‚P‚U‚O‚R”NپjپA
پ@پ@پ@پ@چ]Œثپ@پiچ]Œث–‹•{–{‹’’nپAŒ»پE“Œ‹“sگç‘م“c‹وپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚R”Nپ[‚P‚W‚U‚V”NپjپA
پ@پ@پ@پ@“Œ‹پ@پi‹كŒ»‘مگ•{–{‹’’nپAŒ»پE“Œ‹“s
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گç‘م“c‹وپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚W‚U‚X”Nپ[Œ»چفپjپA
پ@پ@پ@پ@‚ب‚ا‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@Œأ“sƒKƒCƒhƒuƒbƒNپB
پ@
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژjژ«“TپE“ْ–{Œê”إ ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{ژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN پE “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ@
پ،پ@”’‰ح–@‰¤پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ç‚©‚ي‚ظ‚¤‚¨‚¤پjپB
پ@
پ،پ@”’‰ح–@‰¤پBپ@
پ،پ@–¼ڈج پFپ@”’‰ح–@‰¤پ@پi‚µ‚ç‚©‚ي‚ظ‚¤‚¨‚¤پjپB
پ@پ@ پi‰pپF‚”‚ˆ‚…پ@‚s‚ڈ‚ژ‚“‚•‚’‚…‚„پ@‚…‚ک-‚d‚چ‚گ‚…‚’‚ڈ‚’پ@
پ@پ@پ@پ@پ@ ‚r‚ˆ‚‰‚’‚پ‚‹‚پ‚—‚پپjپD
پ@پ@”’‰ح‰@پA
”’‰حڈمچcپA
پ@پ@”’‰ح“Vچcپi”’‰ح’éپjپA
پ@پ@’هگmپi‚³‚¾‚ذ‚ئپjگe‰¤پB
پ،پ@گ¶–v”Nپ@پFپ@
پ@پ@ ‚P‚O‚T‚R”Nپ`‚P‚P‚Q‚X”NپB
پ،پ@”’‰ح–@‰¤پiڈمچcپA“Vچcپj‚ج‰@گگژ،ٹْپ@پF
پ@پ@ ‚P‚O‚W‚U”Nپ`‚P‚P‚Q‚X”NپB
پ،پ@”’‰ح–@چcپ@پF
پ@پ@ ‚P‚O‚X‚U”Nپ`‚P‚P‚Q‚X”NپBپ@
پ،پ@”’‰حڈمچcپ@پF
پ@پ@ ‚P‚O‚W‚U”Nپ`‚P‚P‚Q‚X”NپB
پ،پ@”’‰ح“Vچcپi”’‰ح’éپj‚ج“Vچcچفˆتپ@پF
پ@پ@ ‚P‚O‚V‚Q”Nپ`‚P‚O‚W‚U”NپBپ@
پ،پ@•ت–¼پ@پFپ@
پ@پ@ پœپ@”’‰ح‰@پ@پi‚µ‚ç‚©‚ي‚¢‚ٌپj‚ئ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@”’‰ح–@‰¤پA”’‰حڈمچc‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پi‰pپF‚”‚ˆ‚…پ@‚s‚ڈ‚ژ‚“‚•‚’‚…‚„پ@‚…‚ک-‚d‚چ‚گ‚…‚’‚ڈ‚’پ@
پ@پ@پ@پ@پ@ ‚r‚ˆ‚‰‚’‚پ‚‹‚پ‚—‚پپ@‚n‚qپ@
پ@پ@پ@پ@پ@ ‚”‚ˆ‚…پ@‚…‚ک-‚d‚چ‚گ‚…‚’‚ڈ‚’پ@‚r‚ˆ‚‰‚’‚پ‚‹‚پ‚—‚پپjپD
پ@پ@ پœپ@”’‰حڈمچcپ@پi‚µ‚ç‚©‚ي‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پi‰pپF‚”‚ˆ‚…پ@‚…‚ک-‚d‚چ‚گ‚…‚’‚ڈ‚’پ@‚r‚ˆ‚‰‚’‚پ‚‹‚پ‚—‚پپjپD
پ@پ@ پœپ@”’‰ح“Vچcپ@پi‚µ‚ç‚©‚ي‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پjپB
پ@پ@پi‰pپF‚”‚ˆ‚…پ@‚d‚چ‚گ‚…‚’‚ڈ‚’پ@‚r‚ˆ‚‰‚’‚پ‚‹‚پ‚—‚پپjپD
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“Tپ@‚R‚P‚R‚R‚XپB
پ@
پ@
پ@پ پ@“ْ–{‚ج•½ˆہژ‘مŒمٹْ‚ج—ً‘م“Vچc
پ@پ@پ@ ڈعچ׈ꗗ•\پB
پ@پ@پ@پ@پi“Vچc–¼پAگe‰¤–¼پA“VچcچفˆتٹْٹشپAگ¶–v”NپjپBپ@
پ@
پ@پ پ@•½ˆہژ‘مŒمٹْ‚ج“ْ–{گژ،پB
پ@
پ@
پ@
پ@پ،پ@”’‰ح–@‰¤پiڈمچcپA“VچcپjپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@”’‰ح–@‰¤پiڈمچcپA“Vچcپj
پiگ¶–v”NپF‚P‚O‚T‚R”Nپ`‚P‚P‚Q‚X”Nپj‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@•½ˆہژ‘مŒمٹْ‚ج–@‰¤پAڈمچcپA“Vچc‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@”’‰ح–@‰¤پiڈمچcپA“Vچcپjپi‚µ‚ç‚©‚ي‚ظ‚¤‚ظ‚¤
پi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پA‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پjپAگ¶–v”NپF‚P‚O‚T‚R”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ`‚P‚P‚Q‚X”Nپj‚حپAپ@•ت–¼‚حپA”’‰ح‰@پ@پi‚µ‚ç
پ@پ@پ@پ@پ@‚©‚ي‚¢‚ٌپj‚ئ‚àŒ¾‚¤پBپ@
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@”’‰ح–@‰¤پiڈمچcپA“Vچcپj‚ج‰@گگژ،ٹْ ‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚O‚W‚U”N‚©‚ç‚P‚P‚Q‚X”N‚ـ‚إ‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@”’‰ح–@‰¤‚ج‰p–¼‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@‚”‚ˆ‚…پ@‚s‚ڈ‚ژ‚“‚•‚’‚…‚„پ@‚…‚ک-‚d‚چ‚گ‚…‚’‚ڈ‚’پ@
پ@پ@پ@پ@پ@‚r‚ˆ‚‰‚’‚پ‚‹‚پ‚—‚پپ@‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@پ@پ@پ@”’‰حڈمچc‚ج‰p–¼‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@‚”‚ˆ‚…پ@‚…‚ک-‚d‚چ‚گ‚…‚’‚ڈ‚’پ@‚r‚ˆ‚‰‚’‚پ‚‹‚پ‚—‚پ‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@پ@پ@پ@”’‰ح“Vچc‚ج‰p–¼‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@‚”‚ˆ‚…پ@‚d‚چ‚گ‚…‚’‚ڈ‚’پ@‚r‚ˆ‚‰‚’‚پ‚‹‚پ‚—‚پپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@”’‰ح–@‰¤پiڈمچcپA“Vچcپj‚حپA
پ@پ@ پ@پ@“ْ–{‚ج‰@گگŒ پi=ڈمچcگŒ پjژ‘م ‚ج
پ@پ@پi”’‰ح –@‰¤پiڈمچcپjپA’¹‰H –@‰¤پiڈمچcپjپj
پ@پ@پ@پ@پ@‚ج–@‰¤پAڈمچc‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@ڈمچc‚ئ‚حپAپ@Œ³“Vچcپi“Vچcˆت‚ً‘قˆت‚µ‚½
پ@پ@پ@پ@پ@“Vچcپj‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@پ@پ@پ@–@‰¤‚ئ‚حپAپ@ڈo‰ئ‚µ‚½ڈمچc‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@”’‰ح‰@‚ئ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@”’‰ح–@‰¤پA”’‰حڈمچc‚ج‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@”’‰ح–@‰¤پiڈمچcپA“Vچcپj‚جˆê‘°پB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@”’‰ح–@‰¤پiڈمچcپA“Vچcپj
پ@پ@پ@پ@پ@پi’هگmپi‚³‚¾‚ذ‚ئپjگe‰¤ پj‚حپA
پ@پ@پ@ŒمژOڈًپi‚²‚³‚ٌ‚¶‚ه‚¤پj“Vچc‚جچcژqپi‚ف‚±پj
پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ ‚éپB پ@
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@”’‰ح–@‰¤پiڈمچcپA“Vچcپj‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@–x‰ح“Vچc‚ج•ƒ‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@”’‰ح–@‰¤پiڈمچcپA“Vچcپj‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@’¹‰H“Vچc‚ج‘c•ƒ‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@”’‰ح–@‰¤پiڈمچcپA“Vچcپj‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@گ’“؟“VچcپA‹ك‰q“VچcپAŒم”’‰ح“Vچc‚ج‘]‘c•ƒ
پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ ‚éپBپ@پ@پ@
پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@”’‰ح–@‰¤پiڈمچcپA“Vچcپj‚ج‘¤ژ؛•vگl‚ة‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‹_‰€ڈ—Œنپi‚¬‚¨‚ٌ‚ة‚ه‚¤‚²پjپAپ@‹_‰€ڈ—Œن‚ج–…
پ@پ@پ@پ@پ@‚ب‚ا‚ھ‚¢‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹_‰€ڈ—Œن‚ج–…‚حپAپ@•½گ´گ·‚جگ¶•ê‚ئ‚¢‚¤
پ@پ@پ@پ@پ@گà‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@”’‰ح–@‰¤پiڈمچcپA“Vچcپj‚جژq‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@–x‰حپi‚ظ‚è‚©‚يپj“Vچc‚ب‚ا‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@”’‰ح–@‰¤پiڈمچcپA“Vچcپj‚ج‘·‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@’¹‰H پi‚ئ‚خپj–@‰¤پiڈمچcپA“Vچcپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi= –x‰ح“Vچc‚جچcژqپj‚ب‚ا‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@”’‰ح–@‰¤پiڈمچcپA“Vچcپj‚ج‘\‘·پi‚ذ‚ـ‚²پj‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@گ’“؟“VچcپA‹ك‰q“VچcپAŒم”’‰ح“Vچc‚ب‚ا‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚éپBپ@پ@پ@
پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@”’‰ح–@‰¤پiڈمچcپA“VچcپjپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@‰@گ‚ئ‚حپA–@‰¤پAڈمچc ‚ھپA “Vچc‚ًŒمŒ©پi‚±‚¤
پ@پ@پ@پ@پ@‚¯‚ٌپj‚µ‚ب‚ھ‚ç’©’ى‚جگژ،‚جژہŒ ‚ً‚ة‚¬‚é
پ@پ@پ@پ@پ@گژ،Œ`‘ش‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ،پ@ڈمچc پi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پj‚ئ‚حپAپ@Œ³“Vچcپi“Vچcˆت‚ً
پ@پ@پ@پ@پ@ڈ÷ˆت‚µ‚½پi‘قˆت‚µ‚½پj“Vچcپj‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@–@چcپ@پi‚ظ‚¤‚¨‚¤پj‚ئ‚حپAپ@•§–ه‚ة“ü‚ء‚½ڈمچcپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@”’‰ح–@‰¤پiڈمچcپA“VچcپjپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@“Vچc‚ة‰إپi‚ئ‚آپj‚¢‚¾پAگغٹض‰ئ‚ج“،Œ´—ٹ“¹
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚س‚¶‚ي‚ç‚ج‚و‚è‚ف‚؟پj‚ج–؛‚ة‚حپAپ@چcژqپi‚ف
پ@پ@پ@پ@پ@‚±پj‚ھگ¶‚ـ‚ê‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚إپAگغگپEٹض”’پi‚¹
پ@پ@پ@پ@پ@‚ء‚µ‚ه‚¤پE‚©‚ٌ‚د‚پj‚ًٹOگتپi‚ھ‚¢‚¹‚«پj‚ئ‚µ‚ب
پ@پ@پ@پ@پ@‚¢پAŒمژOڈًپi‚²‚³‚ٌ‚¶‚ه‚¤پj“Vچc‚ھپA‚P‚O‚U‚W”N
پ@پ@پ@پ@پ@‚ةپA‘¦ˆت‚µپA“Vچcگeگپi‚P‚O‚U‚W”Nپ`‚P‚O‚V‚Q
پ@پ@پ@پ@پ@”Nپj‚ًچs‚ء‚½پBپ@پ@
پ@
پ@پ@پ@پ@پ،پ@”’‰ح“Vچc‚àپAگغٹضگ¨—ح‚جگٹ‘ق‚ةڈو‚¶‚ؤپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@•ƒ‚جŒمژOڈً“Vچc‚ًˆّŒp‚¬پA“¯—l‚ة“Vچc
پ@پ@پ@پ@پ@پ@گeگپi‚P‚O‚V‚Q ”Nپ`‚P‚O‚W‚U”Nپj‚ًچs‚¢پAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚O‚W‚U”N‚جڈ÷ˆتŒم‚حپA”’‰حڈم چc‚ئ‚ب‚èپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@”’‰حڈمچcپi–@‰¤پj‚حپA‰@گ‚ًچs‚¢پA‚³‚ç‚ةپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{‚جگژ،‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚èپA‰@گگژ، پi‰@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@گگژ،ٹْپF‚P‚O‚W‚U”Nپ`‚P‚P‚Q‚X”Nپj‚ًچs ‚¤پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@”’‰حڈمچcپi–@‰¤پj‚حپA‚P‚O‚W‚U”N‚و‚èپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–x‰حپi‚ظ‚è‚©‚يپj“VچcپA’¹‰Hپi‚ئ‚خپj“VچcپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ’“؟پi‚·‚ئ‚پj“Vچc‚ج‚R‘م‚ة‚ي‚½‚èپA–ٌ‚S‚R
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”NٹشپA‰@گ‚ًچs‚¢پA‚³‚ç‚ةپA“ْ–{‚جگژ،
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚èپA‰@گگژ،پi‰@گگژ،ژٹْپF
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚O‚W‚U”Nپ`‚P‚P‚Q‚X”Nپj‚ًچs‚¤پB
پ@
پ@
پ@پ،پ@”’‰ح–@‰¤پiڈمچcپA“VچcپjپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@”’‰ح–@‰¤پiڈمچcپA“Vچcپj‚حپAپ@“Vچc‚ًŒمŒ©پi‚±
پ@پ@پ@پ@پ@‚¤‚¯‚ٌپj‚µ‚ب‚ھ‚ç’©’ى‚جگژ،‚جژہŒ ‚ً‚ة‚¬‚é
پ@پ@پ@پ@پ@‰@گ‚ج“¹‚ًٹJ‚¢‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ـ‚½پA”’‰ح–@‰¤پiڈمچcپA“Vچcپj‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@‰@’،پi‚¢‚ٌ‚ج‚؟‚ه‚¤پj‚ًٹJ‚«پA“ْ–{‚جگژ،‚جژہ
پ@پ@پ@پ@پ@Œ ‚ًˆ¬‚èپA‰@گگژ،پi‰@گگژ،ژٹْ پF‚P‚O‚W‚U”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ`‚P‚P‚Q‚X”Nپj‚ًڈ‰‚ك‚ؤچs‚¤پB
پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@”’‰ح–@‰¤پiڈمچcپA“Vچcپj‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@چ‘ژiپiژَ—جپi‚¸‚è‚ه‚¤پjپj‚½‚؟‚ًژxژگ¨—ح‚ة‚ئ
پ@پ@پ@پ@پ@‚肱‚فپAپ@ڈمچcپi=‰@پi‚¢‚ٌپjپj‚جŒنڈٹپi‚²‚µ‚هپj
پ@پ@پ@پ@پ@‚ة–k–ت‚ج•گژmپi‚ظ‚‚ك‚ٌ‚ج‚ش‚µپj‚ً‘gگD‚µ‚½‚èپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@Œ¹•½‚ج•گژm‚ً‘¤‹ك‚ة‚·‚é‚ب‚اپAڈمچcپi=‰@پj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@Œ —ح‚ً‹‰»‚·‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@”’‰ح–@‰¤پiڈمچcپA“Vچcپj‚حپAپ@گ’•§‚ج”Oپi‚ث‚ٌپj
پ@پ@پ@پ@پ@‚ھŒْ‚پi•§‹³‚ًŒْ‚گM‹آ‚µپjپA‘¢ژ›‘¢•§‚ًچs‚¤پB
پ@
پ@
پ@پ،پ@”’‰ح–@‰¤پiڈمچcپA“VچcپjپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@”’‰حڈمچc‚حپAپ@ŒمژOڈًپi‚²‚³‚ٌ‚¶‚ه‚¤پj“Vچc
پ@پ@پ@پ@پ@‚جچcژqپi‚ف‚±پj‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@”’‰ح“Vچc‚حپA‚P‚O‚V‚Q”N‚ة‘¦ˆت‚µپA‚P‚O‚W‚U”N
پ@پ@پ@پ@‚ةڈ÷ˆت‚µ‚ؤپi‘قˆت‚µ‚ؤپjپA”’‰حڈمچcپi‚P‚O‚W‚U”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ`‚P‚P‚Q‚X”Nپj‚ئ‚ب‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@”’‰حڈمچc‚حپAپ@‚P‚O‚X‚U”N‚ةڈo‰ئ‚µ‚ؤ–@چc
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚ظ‚¤‚¨‚¤پj‚ئ‚ب‚éپ@پi”’‰ح–@چcپF‚P‚O‚X‚U”Nپ`
پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚P‚Q‚X”NپjپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@”’‰ح–@‰¤پiڈمچcپA“VچcپjپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@”’‰ح–@‰¤پA”’‰حڈمچcپA”’‰ح“Vچc‚ج‰pŒê–¼‚ة‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@ژں‚ج‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پœپ@‰pپF”’‰ح–@‰¤پ@
پ@پ@پ@پ@پ@‚”‚ˆ‚…پ@‚s‚ڈ‚ژ‚“‚•‚’‚…‚„پ@‚…‚ک-‚d‚چ‚گ‚…‚’‚ڈ‚’پ@‚r‚ˆ‚‰‚’‚پ‚‹‚پ‚—‚پپD
پ@پ@پ@پœپ@‰pپF”’‰ح–@‰¤پ@
پ@پ@پ@پ@پ@‚”‚ˆ‚…پ@‚b‚Œ‚ڈ‚‰‚“‚”‚…‚’‚…‚„پ@‚d‚چ‚گ‚…‚’‚ڈ‚’پ@‚r‚ˆ‚‰‚’‚پ‚‹‚پ‚—‚پپD
پ@پ@پ@پœپ@‰pپF”’‰حڈمچcپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‚”‚ˆ‚…پ@‚…‚ک-‚d‚چ‚گ‚…‚’‚ڈ‚’پ@‚r‚ˆ‚‰‚’‚پ‚‹‚پ‚—‚پپD
پ@پ@پ@پœپ@‰pپF”’‰حڈمچcپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‚”‚ˆ‚…پ@‚e‚ڈ‚’‚چ‚…‚’پ@‚d‚چ‚گ‚…‚’‚ڈ‚’پ@‚r‚ˆ‚‰‚’‚پ‚‹‚پ‚—‚پپD
پ@پ@پ@پœپ@‰pپF”’‰حڈمچcپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‚”‚ˆ‚…پ@‚q‚…‚”‚‰‚’‚…‚„پ@‚d‚چ‚گ‚…‚’‚ڈ‚’پ@‚r‚ˆ‚‰‚’‚پ‚‹‚پ‚—‚پپD
پ@پ@پ@پœپ@‰pپF”’‰ح“Vچcپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‚”‚ˆ‚…پ@‚d‚چ‚گ‚…‚’‚ڈ‚’پ@‚r‚ˆ‚‰‚’‚پ‚‹‚پ‚—‚پپD
پ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پœپ@‰pŒê‚جڈمچc‚إ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پu‚”‚ˆ‚…پ@‚q‚…‚”‚‰‚’‚…‚„پ@‚d‚چ‚گ‚…‚’‚ڈ‚’پv‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‚q‚…‚”‚‰‚’‚…‚„‚ة‚حژdژ–پiگ–±پj‚ًˆّ‘ق‚µ‚½‚ئ‚¢‚¤
پ@پ@پ@پ@پ@ˆس–،‚ھ‚ ‚èپAپ@‰@گ‚ًچs‚¤ڈمچc‚ج—ھŒê‚ئ‚µ‚ؤ
پ@پ@پ@پ@پ@‚ح“K“–‚إ‚ح‚ب‚¢پB
پ@پ@پ@ “–ڈ‘‚إ‚حپAڈمچc‚حپA‚…‚ک-‚d‚چ‚گ‚…‚’‚ڈ‚’
پ@پ@پ@پ@پ@پiŒ³“Vچcپj‚ًژg—p‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پœپ@‰pŒê‚ج–@‰¤‚إ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پu‚”‚ˆ‚…پ@‚b‚Œ‚ڈ‚‰‚“‚”‚…‚’‚…‚„پ@‚d‚چ‚گ‚…‚’‚ڈ‚’پv‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‚b‚Œ‚ڈ‚‰‚“‚”‚…‚’‚…‚„‚حگ¢‚ًژج‚ؤ‚½‚ئ‚¢‚¤ˆس–،‚ً‚à‚؟پA
پ@پ@پ@پ@پ@گ¢‘‚ج‰@گ‚ًچs‚¤–@‰¤‚ج—ھŒê‚ئ‚µ‚ؤ‚ح“K“–
پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ح‚ب‚¢پB
پ@پ@پ@ پ@“–ڈ‘‚إ‚حپA–@‰¤‚حپA‚”‚ˆ‚…پ@‚s‚ڈ‚ژ‚“‚•‚’‚…‚„پ@
پ@پ@پ@پ@پ@‚…‚ک-‚d‚چ‚گ‚…‚’‚ڈ‚’پ@پi‘m‚ج’ن”¯‚ً‚µ‚½Œ³“Vچcپj
پ@پ@پ@پ@پ@‚ًژg—p‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@
پ@
پ@
#theton.exemp.shira.-table2715
پ@
پ@پ،پ@“ْ–{‚ج•½ˆہژ‘مŒمٹْ‚جگŒ پE
پ@پ@ پ@گژ،ژہŒ ژز‚ج•د‘Jڈعچ׈ꗗ•\
پ@پ@پ@پi‚Pپjپi‚Qپj‚ج‚ف”²گˆپB
پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پœپ@“ْ–{‚ج•½ˆہژ‘مŒمٹْ‚جگŒ ‚âگژ،ژہŒ
پ@پ@پ@پ@پ@ •غ—Lژز‚ج•د‘J‚جˆê——•\پB
پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“Tپ@‚R‚P‚R‚R‚TپB
پ@
پ@پ،پ@پi‚Pپjپ@پs‚P‚O‚W‚U”Nپ[‚P‚P‚Q‚X”Nپt
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”’‰حڈمچcپi–@‰¤پj‚ج‰@گگژ،پE
پ@پ@پ@ پ@گŒ ٹْپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@‚P‚O‚W‚U”Nپi‰“؟‚R”Nپj‚ةپA’©’ى‚ج”’‰حڈمچc
پ@پ@پ@پ@پ@‚ھپA“ْ–{‚جگژ،‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚èپA
پ@پ@پ@پ@پ@‰@گگژ،‚ًژn‚ك‚éپB
پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@”’‰ح“Vچc‚حپAپ@‚P‚O‚W‚U”Nپi‰“؟‚R”Nپj‚P‚PŒژ
پ@پ@پ@پ@پ@‚ةپAچcˆت‚ً–x‰ح“Vچc‚ةڈ÷‚èپAڈمچc‚ئ‚ب‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@”’‰حڈمچcپi“Vچcپj‚حپAپ@ژ©‚ç‚ج“Vچcگeگ
پ@پ@پ@پ@پ@گژ،پ@پi“Vچc‚ھ“ْ–{‚جگژ،‚جژہŒ ‚ًˆ¬
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚ة‚¬پj‚è’¼گع“ْ–{‚ًژx”z‚·‚éگژ،پj‚ًپA
پ@پ@پ@پ@پ@‚و‚è‹Œإ‚ة‚·‚邽‚كپAپ@‰@گگژ،پ@پi‰@
پ@پ@پ@پ@پ@گ‚ة‚و‚èپA“ْ–{‚جگژ،‚جژہŒ ‚ًˆ¬پi‚ة‚¬پj
پ@پ@پ@پ@پ@‚èپA“ْ–{‚ًژx”z‚·‚éگژ،پjپ@‚ًچs‚¤پB
پ@
پ@
پ@پ،پ@پi‚Qپjپ@پs‚P‚P‚Q‚X”Nپ[‚P‚P‚T‚U”NپtپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’¹‰Hڈمچcپi–@‰¤پj‚ج‰@گگژ،پE
پ@پ@پ@ پ@گŒ ٹْپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@‚P‚P‚Q‚X”Nپi‘¾ژ،‚S”Nپj‚ةپA’©’ى‚ج’¹‰Hڈمچc
پ@پ@پ@پ@پ@‚ھپA“ْ–{‚جگژ،‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚èپA
پ@پ@پ@پ@پ@‰@گگژ،‚ًژn‚ك‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@”’‰ح–@چc‚ھ•ِŒنپi‚ظ‚¤‚¬‚هپAژ€‹ژپj‚µپA
پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚P‚Q‚X”Nپi‘¾ژ،‚S”Nپj‚ةپA’¹‰Hڈمچc‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@ˆّ‚«‘±‚«پA‰@گگژ،‚ًچs‚¤پB
پ@
پ@
پ@
#theton.exemp.shira.-table2725
پ@
پ@
پ@پ،پ@•½ˆہژ‘مŒمٹْ‚ج“ْ–{‚ج—ً‘م“Vچc
پ@پ@پ@ ڈعچ׈ꗗ•\پB
پ@پ@پ@ پi“Vچc–¼پAگe‰¤–¼پA“VچcچفˆتٹْٹشپjپBپ@
پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“Tپ@‚R‚P‚S‚P‚VپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@“ْ–{‚ج•½ˆہژ‘مŒمٹْ‚ةچفˆت‚µ‚½“Vچc
پ@پ@پ@پ@پ@‚حپAچcˆتŒpڈ³ڈ‡‚ةپAژں‚ج’ت‚è‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ@‡@پ@”’‰حپi‚µ‚ç‚©‚يپj“Vچcپ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi’هگmپi‚³‚¾‚ذ‚ئپjگe‰¤پj
پ@پ@ŒمژOڈًپi‚²‚³‚ٌ‚¶‚ه‚¤پj“Vچc‚جچcژqپi‚ف‚±پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پi“VچcچفˆتپF‚P‚O‚V‚Q”Nپ`‚P‚O‚W‚U”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پi“VچcچفˆتپF‰„‹v‚S”Nپi‚P‚O‚V‚Q”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚QŒژ‚W“ْپ`‰“؟‚R”Nپi‚P‚O‚W‚U”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚PŒژ‚Q‚U“ْپj
پ@پ@پ@پ@ پiگ¶–v”Nپ@ پF‚P‚O‚T‚R”Nپ`‚P‚P‚Q‚X”NپjپB
پ@
پ@پ@پ@‡Aپ@–x‰حپi‚ظ‚è‚©‚يپj“Vچcپ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‘Pگmپi‚½‚é‚ذ‚ئپjگe‰¤پj پ@
پ@پ@پ@پ@پ@”’‰ح–@‰¤پiڈمچcپA“Vچcپj‚جچcژqپB
پ@پ@پ@پ@پ@پi“VچcچفˆتپF‚P‚O‚W‚U”Nپ`‚P‚P‚O‚V”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پi“VچcچفˆتپF‰“؟‚R”Nپi‚P‚O‚W‚U”Nپj‚P‚PŒژ
پ@پ@پ@پ@پ@‚Q‚U“ْپ`‰أڈ³‚Q”Nپi‚P‚P‚O‚V”Nپj‚VŒژ‚P‚X“ْپj
پ@پ@پ@پ@ پiگ¶–v”Nپ@ پF‚P‚O‚V‚X”Nپ`‚P‚P‚O‚V”NپjپB
پ@
پ@پ@پ@‡Bپ@’¹‰Hپi‚ئ‚خپj“Vچc
پ@پ@ پ@پ@ پiڈ@گmپi‚ق‚ث‚ذ‚ئپjگe‰¤پj
پ@پ@پ@پ@پ@–x‰ح“Vچc‚جچcژqپB
پ@پ@ پi“VچcچفˆتپF‚P‚P‚O‚V”Nپ`‚P‚P‚Q‚R”NپjپB
پ@پ@پ@پ@ پiگ¶–v”Nپ@ پF‚P‚P‚O‚R”Nپ`‚P‚P‚T‚U”NپjپB
پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پ@پ@‡Cپ@گ’“؟پi‚·‚ئ‚پj“Vچcپ@پ@پ@پ@ پ@
پ@پ@پ@پ@پ@ پiŒ°گmپi‚ ‚«‚ذ‚ئپjگe‰¤پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@’¹‰H–@‰¤پiڈمچcپA“Vچcپj‚جچcژqپB
پ@پ@ پi“VچcچفˆتپF‚P‚P‚Q‚R”Nپ`‚P‚P‚S‚P”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@ پiگ¶–v”Nپ@ پF‚P‚P‚P‚X”Nپ`‚P‚P‚U‚S”NپjپB
پ@
پ@پ@پ@‡Dپ@‹ك‰qپi‚±‚ج‚¦پj“Vچcپ@پ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‘جگmپi‚ب‚è‚ذ‚ئپjگe‰¤پjپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@’¹‰H–@‰¤پiڈمچcپA“Vچcپj‚جچcژqپB
پ@پ@پ@پ@پ@پi“VچcچفˆتپF‚P‚P‚S‚P”Nپ`‚P‚P‚T‚T”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پiگ¶–v”Nپ@ پF‚P‚P‚R‚X”Nپ`‚P‚P‚T‚T”NپjپB
پ@
پ@پ@پ@‡Eپ@Œم”’‰حپi‚²‚µ‚ç‚©‚يپj“Vچcپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‰ëگmپi‚ـ‚³‚ذ‚ئپjگe‰¤پjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@ ’¹‰H–@‰¤پiڈمچcپA“Vچcپj‚جچcژqپB
پ@پ@پ@پ@پ@پi“VچcچفˆتپF‚P‚P‚T‚T”Nپ`‚P‚P‚T‚W”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پiگ¶–v”Nپ@ پF‚P‚P‚Q‚V”Nپ`‚P‚P‚X‚Q”NپjپB
پ@
پ@پ@پ@‡Fپ@“ٌڈًپi‚ة‚¶‚ه‚¤پj“Vچcپ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پiژçگmپi‚à‚è‚ذ‚ئپjگe‰¤پjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@Œم”’‰ح–@‰¤پiڈمچcپA“Vچcپj‚جچcژqپB
پ@پ@پ@پ@پ@پi“VچcچفˆتپF‚P‚P‚T‚W”Nپ`‚P‚P‚U‚T”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پiگ¶–v”Nپ@ پF‚P‚P‚S‚R”Nپ`‚P‚P‚U‚T”NپjپB
پ@
پ@پ@پ@‡Gپ@کZڈًپi‚ë‚‚¶‚ه‚¤پj“Vچcپ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پiڈ‡گmپi‚ج‚ش‚ذ‚ئپjگe‰¤پjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@“ٌڈً“Vچc‚جچcژqپB
پ@پ@پ@پ@پ@پi“VچcچفˆتپF‚P‚P‚U‚T”Nپ`‚P‚P‚U‚W”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پiگ¶–v”Nپ@ پF‚P‚P‚U‚S”Nپ`‚P‚P‚V‚U”NپjپB
پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پ@پ@‡Hپ@چ‚‘qپi‚½‚©‚‚çپj“Vچcپ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پiŒ›گmپi‚ج‚è‚ذ‚ئپjگe‰¤پj پ@
پ@پ@پ@پ@پ@Œم”’‰ح–@‰¤پiڈمچcپA“Vچcپj‚جچcژqپB
پ@پ@پ@پ@پ@پi“VچcچفˆتپF‚P‚P‚U‚W”Nپ`‚P‚P‚W‚O”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پiگ¶–v”Nپ@ پF‚P‚P‚U‚P”Nپ`‚P‚P‚W‚P”NپjپB
پ@
پ@پ@پ@‡Iپ@ˆہ“؟پi‚ ‚ٌ‚ئ‚پj“Vچcپ@ پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پiŒ¾گmپi‚ئ‚«‚ذ‚ئپjگe‰¤پjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@چ‚‘qڈمچcپi“Vچcپj‚جچcژqپB
پ@پ@پ@پ@پ@پi“VچcچفˆتپF‚P‚P‚W‚O”Nپ`‚P‚P‚W‚T”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پiگ¶–v”Nپ@ پF‚P‚P‚V‚W”Nپ`‚P‚P‚W‚T”NپjپB
پ@
پ@پ@پ@‡Jپ@Œم’¹‰Hپi‚²‚ئ‚خپj“Vچcپ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‘¸گ¬پi‚½‚©‚ذ‚çپjگe‰¤پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@چ‚‘qڈمچcپi“Vچcپj‚جچcژqپB
پ@پ@پ@پ@پ@پi“VچcچفˆتپF‚P‚P‚W‚R”Nپ`‚P‚P‚X‚W”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پiگ¶–v”Nپ@ پF‚P‚P‚W‚O”Nپ`‚P‚Q‚R‚X”NپjپB
پ@
پ@
#theton.exemp.shira.-appearingscenes
پ@
پôپôپ@”’‰ح–@‰¤پiڈمچcپA“Vچcپj‚ھ“oڈê‚·
پ@پ@پ@پ@‚éپA‹»–،گ[‚¢ٹضکAƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپA
پ@پ@پ@پ@ƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پBپ@
پ@
پ@پڑپ@”’‰حڈمچc‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢
پ@پ@پ@ ٹضکAƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پBپ@
پ@
پ@پ،پ@—ًژj”éکbƒqƒXƒgƒٹƒAپ@پwپ@ژ„‚½‚؟پA
پ@پ@پ@‘گگHŒn•گژm‚إ‚·پBپ`گVپE•½‰ئ‰ئ
پ@پ@پ@‘°•¨Œêپ`پ@پxپBپ@
پ@پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚O‚X”Nپi•½گ¬‚Q‚P”Nپj
پ@پ@پ@پ@‚P‚QŒژ‚P‚U“ْپE–{•ْ‘—پA‘و‚Q‚V‰ٌپjپB
پ@
پ@پ@پ،پ@”’‰حڈمچc‚ھ“oڈê‚·‚éپB
پ@
پ@
پ@پڑپ@”’‰حڈمچc‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢پA
پ@پ@پ@ ٹضکAƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپB
پ@
پœپ@پi’چˆسپjپ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAƒtƒBƒNƒVƒ‡ƒ“‚إ‚·پBپ@
پ@پ@پ@ —ًژj‚جƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAژjژہپi—ًژjڈم‚جژ–ژہپjپ@
پ@پ@پ@ ‚ئ‰ث‹َ‚جڈo—ˆژ–‚ھپ@چ¬‚¶‚ء‚ؤ•`‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپ@
پ@پ@پ@ ‚ـ‚½پAŒ»‘م•—‚ةƒAƒŒƒ“ƒW‚µ‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚·پB
پ@
پ@پ،پ@پwپ@•½گ´گ·پ@پi‚½‚¢‚ç‚ج‚«‚و‚à‚èپjپ@پx پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒr‚ج‚Q‚O‚P‚Q”N‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پjپB
پ@
پ@پ@پ،پ@”’‰حڈمچcپA’¹‰HڈمچcپAŒم”’‰حڈمچc‚ھ
پ@پ@“oڈê‚·‚éپB
پ@پ@پ،پ@•½ˆہژ‘مŒمٹْ‚ج“–ژٹˆ–ô‚µ‚½گl•¨‚â
پ@پ@ پ@پ@“–ژ‚جژ‘مڈَ‹µ‚ً•`‚¢‚½ƒhƒ‰ƒ}•`‚پB
پ@پ@پ،پ@•½گ´گ·‚جگ¶ٹU‚ً•`‚¢‚½ƒhƒ‰ƒ}پB
پ@
پ@پ@پœپ@”’‰حڈمچcپi–@‰¤پj‚حپA
پ@پ@پ@پ@‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}‚جڈ‰“ھ•”‚ة“oڈê‚·‚éپB
پ@پ@پœپ@”’‰حڈمچc‚ً‰‰‚¶ ‚½”o—D–¼پFپ@ˆة“Œپ@ژlکYپB
پ@
پ@پ@پœپ@•½ گ´گ·‚ً‰‰‚¶‚é”o—D–¼ پF ڈ¼ژRپ@ƒPƒ“ƒCƒ`پB
پ@
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ@
پ،پ@گVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ٌ‚¹‚آ‚¹‚«‚ھ‚ح‚ç‚ج‚½‚½‚©‚¢پjپB
پ@
پ،پ@گVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پBپ@
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@گVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ٌ‚¹‚آ‚¹‚«‚ھ‚ح‚ç‚ج‚½‚½‚©‚¢پjپB
پ،پ@•ت–¼پ@پFپ@‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¨‚¨‚ھ‚«پE‚â‚ـ‚ب‚©‚ج‚½‚½‚©‚¢پjپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“Tپ@‚S‚P‚U‚R‚TپB
پ@
پ@
پ@پ پ@پu ژjژہپiگVگàپjٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢
پ@پ@ پ@پi= ‘هٹ_پE ژR’†‚جگي‚¢پjپv پ@
پ@پ@پ@پ@‰و‘œƒAƒ‹ƒoƒ€‚m‚ڈپD‚QپB
پ@
پ@پ پ@پu “`گàپiڈ]—ˆگàپjٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv
پ@پ@ پ@‰و‘œƒAƒ‹ ƒoƒ€پ@‚m‚ڈپD‚RپBپ@
پ@
پ@پ پ@ژjژہ پiگVگàپjٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢
پ@پ@ پ@پi= ‘هٹ_پEژR ’†‚جگي‚¢پjپ@پi‘چچ‡پjپB
پ@
پ@پ پ@“`گàپiڈ]—ˆگàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پB
پ@
پ@پ پ@ژjژہ پiگVگàپjٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢
پ@پ@ پ@پi= ‘هٹ_پEژR ’†‚جگي‚¢پjپ@
پ@پiگl•¨•تپjپB
پ@
پ@پ پ@‘هٹ_‚جگي‚¢ پi= ژjژہپiگVگàپj
پ@پ@ پ@ٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢‚ج‘هٹ_‚جگي‚¢پjپB
پ@
پ@پ پ@ژR’†‚جگي‚¢ پi= ژjژہپiگVگàپj
پ@پ@ پ@ٹضƒ–Œ´‚ج گي‚¢‚جژR’†‚جگي‚¢پjپB
پ@
پ@پ پ@ژjژہپiگVگàپjٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢
پ@پ@ پ@پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjٹضکA
پ@پ@ پ@”N‘مڈ‡ ڈo—ˆژ– پiڈعچ×پjپB
پ@
پ@پ پ@ژjژہپiگVگàپjٹض ƒ–Œ´‚جگي‚¢
پ@پ@ پ@پi= ‘هٹ_پE ژR’†‚جگي‚¢پjٹضکA
پ@ƒhƒLƒ…ƒپƒ^ƒٹپ[پAƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپB
پ@
پ@
پ@پ@پ،پ@پuگVگàپiژjژہپjٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv
پ@پ@پ@پ@پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پj‚ج•zگwگ}پB
پ@
پ@پ@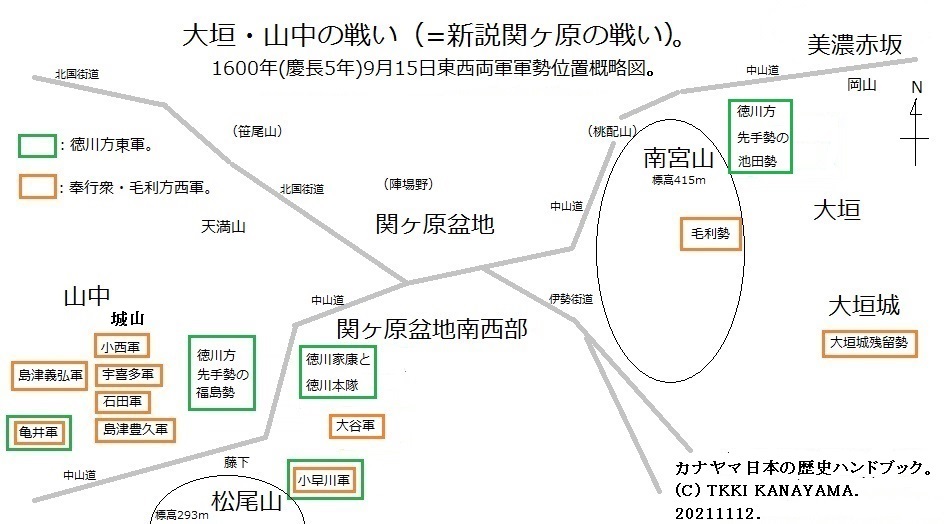
پ@
پ@
پ@
پ@
پ@پ،پ@پuگVگàپiژjژہپjٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv
پ@پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پj‚جŒˆگيپB
پ@
پ@پ@پ،پ@ˆêژںژj—؟‚ةٹî‚أ‚پuگVگàپiژjژہپjٹضƒ–Œ´‚ج
پ@پ@گي‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپi‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·
پ@پ@‚T”Nپj‚WŒژ‚Q‚U“ْچ پ[‚XŒژ‚Q‚R“ْپj‚إ‚حپAپ@‚à‚µ
پ@پ@•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚جگ¼ŒR‚ج“ى‹{ژR•zگw‚ج‘هٹ_
پ@پ@ڈéŒم‹lŒR‚ج–ر—کگ¨‚ھ ‚XŒژ‚P‚T“ْˆبŒم‚ة—\
پ@پ@‘z‚³‚ê‚é“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚©‚çچUŒ‚‚ًژَ‚¯”s
پ@پ@–k‚·‚é‚ئپAپ@•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚جگ¼ŒR‚ھ’“—¯
پ@پ@‚·‚é‘هٹ_ڈé‚ھŒا—§‚µ”ٌڈي‚ة•s—ک‚ئ‚ب‚é‚ج‚إپAپ@
پ@پ@‘هٹ_ڈé‚ة’“—¯‚µ‚ؤ‚¢‚½•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚ج
پ@پ@گ¼ŒR‚جڈ¬گ¼پE‰Fٹى‘½پEگخ“cپE“‡’أگ¨“™‚جŒR
پ@پ@‚حپAپ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْˆبŒم‚ة
پ@پ@—\‘z‚³‚ê‚é“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚ة‚و‚é“ى‹{ژR‚ج
پ@پ@•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚جگ¼ŒR‚ج–ر—کگ¨‚ض‚جچUŒ‚
پ@پ@‚ة”ُ‚¦‚ؤپi‚جŒم‹l‚ئ‚µ‚ؤپjپA•ٍچsڈOپE–ر—ک•û
پ@پ@‚جگ¼ŒR‚جڈ¬ گ¼پE‰Fٹى‘½پEگخ “cپE“‡’أگ¨“™
پ@پ@‚جگ¼ŒRژه—حŒRپE–ٌ‚R–œگl‚ج•؛‚حپA‚P‚U‚O‚O”N
پ@پ@پiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ج“ْ–vŒمپA‘هٹ_ڈé‚ً
پ@پ@ڈo‚ؤپAٹضƒ–Œ´–~’nپEژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj•û–ت‚ض
پ@پ@Œü‚¤پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@ˆê•ûپA‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ج“ْ–vŒمپA‚»‚جگ¼ ŒR
پ@پ@ژه—حŒR‚ً’ا‚ء‚ؤ“؟گى•û‚ج•ں“‡گ¨‚ئ‰ئچN‚ج
پ@پ@“؟گى–{‘à‚ج“ŒŒRژه—حŒRپE–ٌ‚T–œ‚P‚O‚O‚Oگl
پ@پ@‚ج•؛‚ح‘هٹ_•t‹ك‚©‚çٹضƒ–Œ´–~’nپEژR’†پi‚â
پ@پ@‚ـ‚ب‚©پj•û–ت‚ضŒü‚¤پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚جگ¼ŒRژه—حŒR‚ح‚XŒژ
پ@پ@‚P‚T“ْ‚جŒك‘O‚Sژچ پAژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj•t‹ك
پ@پ@‚ة•zگw‚·‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‚»‚جŒمپAگ¼ŒRژه—حŒR‚ً’ا‚ء‚ؤˆع“®‚µ
پ@پ@‚ؤ‚«‚½“؟گى•û‚ج“ŒŒRژه—حŒRپE–ٌ‚T–œ‚P‚O‚O‚O
پ@پ@گl‚ج•؛پ@‚ئپ@•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚جگ¼ŒRژه—حŒRپE
پ@پ@–ٌ‚R–œگl‚ج•؛‚ئ‚ھپA‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj
پ@پ@‚XŒژ‚P‚T“ْ‚جŒك‘O‚P‚Oژچ ‚©‚çگ³Œكچ ‚ـ‚إپAپ@
پ@پ@ٹضƒ–Œ´–~’n‚ج“ىگ¼•ûŒüپE–ٌ‚Q‚‹‚چ‚ة‚ ‚éپA
پ@پ@ژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‘؛‚إŒˆگي‚ًچs‚¢پA“؟گى•û
پ@پ@‚ج“ŒŒRژه—حŒR‚ھڈں—ک‚ً“¾پA•ٍچsڈOپE–ر—ک
پ@پ@•û‚جگ¼ŒRژه—حŒR‚ھ”s–k‚·‚éپB
پ@
پ@
پ@پںپ@پuٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚جگVگàپiژjژہپj
پ@پ@پ@پ@‚ئڈ]—ˆگàپi“`گàپjپB
پ@پ@پ،پ@ٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢‚ة‚حپAژjژہ‚جپuگVگàٹضƒ–Œ´‚ج
پ@پ@گي‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†پi‚¨‚¨‚ھ‚«پE‚â‚ـ‚ب‚©پj‚ج
پ@پ@گي‚¢پjپvپ@ ‚ئپAپ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپjٹضƒ–Œ´‚جگي
پ@پ@‚¢پvپ@‚ئ‚¢‚¤‚Q‚آ‚ج—L—ح‚بگà‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@پuگVگàپiژjژہپjٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†
پ@پ@‚جگي‚¢پv‚حپAپ@ٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢’¼Œم‚جˆêژںژj—؟
پ@پ@پi‚¢‚؟‚¶‚µ‚è‚ه‚¤پA“¯ژ‘م“ْ‹LپEژèژ†‚ب‚اپj‚ة
پ@پ@ٹî‚أ‚پAژjژہ‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پuگVگàپiژjژہپjٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پi= ‘هٹ_پE
پ@پ@ژR’†‚جگي‚¢پjپv‚إ‚حپAپ@پwپ@—ًژjŒQ‘œپE‚Q‚O‚P‚V
پ@پ@”N‚P‚OŒژچ†Œfچع‚جپu’تگà‘إ”jپIٹضƒ–Œ´چ‡گي
پ@پ@‚جگ^ژہپvپi”’•ôڈ{‹³ژِ’کپjپ@پxپA‚»‚ج‘¼‚ج‘½‚
پ@پ@‚جˆêژںژj—؟‚àپAژQچlژ‘—؟پEƒfپ[ƒ^‚ئ‚µ‚ؤپA—ک
پ@پ@—p‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپjٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚حپAŒمگ¢‚ج
پ@پ@‘nچى‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپjٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚حپAچ]Œث
پ@پ@ژ‘م‚ةژ©–کb‚ھڈd‚ب‚ء‚ؤ‚آ‚‚ç‚ꂽŒمگ¢‚ج‘n
پ@پ@چى‚جٹضƒ– Œ´‚جگي‚¢‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@
پ@پںپ@گVگàپiژjژہپjپEڈ]—ˆگàپi“`گàپj‹¤’ت
پ@پ@پ@ ‚جپuٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پvپB
پ@
پ@پ@پ،پ@ٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پi‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پj‚حپA‚P‚U‚O‚O
پ@پ@”N(Œc’·‚T”Nپj‚ة“ْ–{ٹe’n‚إچs‚ي‚ꂽپAپuŒc’·
پ@پ@‚T”Nپi‚P‚U‚O‚O”Nپj‚ج“V‰؛•ھ ‚¯–ع‚جگي‚¢پv‚ج‚P‚آ
پ@پ@‚إ‚ ‚èپAپ@پuŒc’·‚T”Nپi‚P‚U‚O‚O”Nپj‚ج“V‰؛•ھ ‚¯–ع
پ@پ@‚جگي‚¢پv‚ج’†گS“I‚بچ‡گي‚إ‚ ‚ء‚½پBپ@‚»‚µ‚ؤپA
پ@پ@ٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢‚جŒ‹‰تپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ھڈں—ک
پ@پ@‚ً“¾پA“؟گى‰ئچN‚ھگŒ ٹî”ص‚ًŒإ‚كپA‚»‚ج
پ@پ@ŒمپA‚P‚U‚O‚R”NپiŒc’·‚V”Nپj‚ةپA‰ئچN‚ھڈ«ŒRگé‰؛
پ@پ@پi‚¹‚ٌ‚°پj‚ًژَ‚¯پA چ]Œث–‹•{‚ھڈoŒ»‚µ‚½پB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پ@پ،پ@ٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢‚حپAپ@چL‹`‚إ‚حپA‚P‚U‚O‚O”N
پ@پ@پiŒc’·‚T”Nپj‚ج‚WŒژ‚Q‚U“ْچ پi“ŒŒR‚ج”ü”Zگشچâ•z
پ@پ@گwپj‚©‚ç‚XŒژ‚Q‚R“ْپiگ¼ŒR‚ج‘هٹ_ڈé—ژڈéپj‚ـ‚إ
پ@پ@‚جٹشپA”ü”Zچ‘‚إ‚جگي‚¢‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پi‚Pپjپ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚WپA‚XŒژ‚جژ“_‚إپA
پ@پ@“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚حپA”ِ’£چ‘پi‚¨‚ي‚è‚ج‚‚ةپAŒ»پE
پ@پ@ˆ¤’mŒ§ گ¼•”‚ج‘ٹ“–’nˆوپj‚جگ´گ{ڈéپi‚«‚و‚·
پ@پ@‚¶‚ه‚¤پAگ´ڈBڈéپj‚ً–{‹’’n‚ة‚µپA گ¼ŒR‚حپA”ü
پ@پ@”Zچ‘پi‚ف ‚ج‚ج‚‚ةپAŒ»پEٹٍ•ŒŒ§“ى•”‚ج‘ٹ“–
پ@پ@’nˆوپj‚ج‘هٹ_ڈéپi‚¨‚¨‚ھ‚«‚¶‚ه‚¤پj‚ً–{‹’’n‚ة
پ@پ@‚µپAٹô–{‚à‚جگى‚ً‹²‚ٌ‚إ‘خ›³‚µ‚ؤ‚¢‚½پBپ@
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پ@پi‚Qپjپ@“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚حپAگ´گ{ڈé‚ًڈo‚ؤپA‚P‚U
پ@پ@‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚WŒژ‚Q‚R“ْ‚ةگ¼ŒR‚جٹٍ•Œ
پ@پ@ڈé‚ً—ژڈ邳‚¹پAپ@“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚حپA‚WŒژ‚Q‚U
پ@پ@“ْچ ‚و‚èپA‘هٹ_•t‹ك‚ج”ü”Zگشچâپi‚ف‚ج‚ ‚©
پ@پ@‚³‚©پj‚ةˆع“®‚µ•zگw‚µ‚ؤپA‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ـ‚إگ¼ŒR
پ@پ@‚ج‘هٹ_ڈé‚ًچUŒ‚‚·‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@پ@پi‚Rپjپ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ–é‚ةپA
پ@پ@پ@گ¼ŒR‚ج‘هٹ_ڈé‚ة‚¢‚½‘ه•”•ھ‚جŒR‚ح‘هٹ_
پ@پ@پ@ڈé‚ً”²‚¯ڈo‚µٹضƒ–Œ´–~’n•û–ت‚ضˆع“®‚µپA
پ@پ@پ@‚ـ‚½پA‚XŒژ‚P‚S“ْ–é‚ةپA‘هٹ_•t‹ك‚ج”ü”Zگش
پ@پ@پ@چâ‚ة‚¢‚½“ŒŒR‚ج‘½‚‚جŒR‚حٹضƒ–Œ´–~’n•û
پ@پ@پ@–ت‚ضˆع“®‚µپA‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ةپA“Œگ¼—¼ژه—حŒR
پ@پ@پ@‚حپA”ü”Zچ‘‚ج•½–ى‚إŒˆگي‚ًچs‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@“Œگ¼—¼ژه—حŒR‚جŒˆگي‚إ‚حپA“؟گى•û‚ج
پ@پ@پ@“ŒŒRژه—حŒR‚ھڈں—ک‚ً“¾‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پ@پi‚Sپjپ@‘هٹ_•t‹ك‚ج”ü”Zگشچâ‚ة‚¢‚é“؟گى•û‚ج
پ@پ@پ@“ŒŒR‚حپA‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ‚©
پ@پ@پ@‚ç‚XŒژ‚Q‚R“ْ‚ـ‚إگ¼ŒR‚ج‘هٹ_ڈé‚ًچUŒ‚‚µپA
پ@پ@پ@‚XŒژ‚Q‚R“ْ‚ةگ¼ŒR‚ج‘هٹ_ڈé‚ً—ژڈ邳‚¹‚éپB
پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ@پںپ@گVگàپiژjژہپjپEڈ]—ˆگàپi“`گàپj‹¤’ت
پ@پ@پ@پ@‚جپuٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پvپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‹‹ةچ‚ژںپ@پi‚« ‚ه‚¤‚²‚‚½‚©‚آ‚®پj‚حپA“ŒŒR
پ@پ@‚ج“؟گى•û‚ة–، •û‚µپA‘ه’أڈéپi‚¨‚¨‚آ‚¶‚ه‚¤پj
پ@پ@‚ةâؤڈéپi‚낤‚¶‚ه‚¤پj‚µ‚ؤپ@پi‘ه’أڈéچU–hگيپjپA
پ@پ@”ü”Zچ‘•û–تپi‘هٹ_پEٹضƒ–Œ´–~’nپEژR’†•û–تپj
پ@پ@‚ةŒü‚©‚¤گ¼ŒR‚جŒR‘à‚جˆê•”‚ًپA ‘ه’أپi‚¨‚¨
پ@پ@‚آپj‚إ‚‚¢ژ~‚ك‚½پBپ@Œ‹‰ت“I‚ةپA”ü”Zچ‘‚إگي
پ@پ@‚¤گ¼ŒR‚جگ¨—ح‚جˆê•”‚ھچيپi‚»پj‚ھ‚ꂽپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پ@پ،پ@ٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢‚إ‚حپAپ@گي‚¢ŒمپAگ¼ŒR‚جگخ“c
پ@پ@پ@ژOگ¬پAڈ¬گ¼چs’·پAˆہچ‘ژ› Œbàùپi‚ ‚ٌ‚±‚‚¶ ‚¦‚¯
پ@پ@پ@‚¢پj‚حڈˆŒY‚³‚êپiژaژٌ‚³‚êپjپAپ@‚»‚ج‘¼‚ج ‘½‚
پ@پ@پ@‚جگ¼ ŒR‚جڈ”ڈ«‚حپAپ@‰üˆصپi‚©‚¢‚¦‚«پA—ج’n–v
پ@پ@پ@ژûپjپAŒ¸••پi‚°‚ٌ‚غ‚¤پA—ج’nچيŒ¸پEڈkڈ¬پj“™‚ج
پ@پ@پ@ڈˆ•ھ‚ًژَ‚¯پAپ@ٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢‚حپA–{—ˆ‚حپA
پ@پ@پ@–Lگb‰ئ‚ج‰ئگb’c‚جگي‚¢‚إ‚ح‚ ‚ء‚½‚ھپA“؟گى
پ@پ@پ@•û‚ج“ŒŒR‚جڈں—ک‚ة‚و‚èپAژ–ژہڈمپA“؟گىگŒ
پ@پ@پ@‚جٹî‘b“Iٹî”ص‚ھ‚إ‚«پAŒ‹‰ت“I‚ةپAپu“V ‰؛•ھ‚¯
پ@پ@پ@–ع‚جگي‚¢پv‚ئ‚ب ‚èپA‚»‚جŒمپA‘½‚‚جگ¼ŒR‚جڈ”
پ@پ@پ@ڈ«‚ج‰üˆصپEŒ¸••ڈˆ•ھپA‘½‚‚ج“ŒŒR‚جڈ”ڈ«‚ج
پ@پ@پ@‰ء‘پA‰ئچN‚جڈ«ŒRگEڈA”C‚ب‚ا‚ج“؟گى‰ئچN
پ@پ@پ@‚جگŒ ٹî”ص‹‰»‚ة‚و‚èپA‚P‚U‚O‚R”NپiŒc’·‚W”Nپj
پ@پ@پ@‚ةچ]Œث–‹•{‚ھگ¬—§‚µ‚½پB
پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ@پںپ@پuگVگàپiژjژہپjٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv
پ@پ@ پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپ@پi‘چچ‡پjپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@پuگVگàپiژjژہپjٹضƒ–Œ´ ‚جگي‚¢پvپi= ‘هٹ_پE
پ@پ@پ@ژR’†‚جگي‚¢پj‚حپAچL‹`‚إ‚حپAژٹْ‚ح‚P‚U‚O‚O
پ@پ@پ@”NپiŒc’·‚T”Nپj‚ج ‚WŒژ‚Q‚U“ْچ پi“ŒŒR‚ج”ü
پ@پ@پ@”Zگشچâ•zگwپj‚©‚ç‚XŒژ‚Q‚R“ْپiگ¼ŒR‚ج‘هٹ_
پ@پ@پ@ڈé—ژڈéپj‚ـ‚إ‚إ‚ ‚èپAپ@گي‚¢‚جڈêڈٹ‚ح”ü
پ@پ@پ@”Zچ‘پi‚ف‚ج‚ج‚‚ةپAŒ»پEٹٍ•ŒŒ§“ى•”‚ج‘ٹ“–
پ@پ@پ@’nˆوپj‚ج‘هٹ_پi‚¨‚¨‚ھ‚«پj•t‹ك‚âژR’†پi‚â
پ@پ@پ@‚ـ‚ب‚©پj•t ‹ك‚إ‚ ‚èپAپ@”ü”Zچ‘‚ةڈW Œ‹‚µ
پ@پ@پ@‚½پA“؟گى•û‚ج“ŒŒRپE–ٌ‚V–œ‚R‚O‚O‚Oگl‚ج•؛
پ@پ@پ@‚ئ•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚جگ¼ŒRپE–ٌ‚T–œ‚S‚O‚O‚Oگl
پ@پ@پ@‚ج•؛‚ج“Œگ¼—¼ŒRپE–ٌ‚P‚Q–œ‚V‚O‚O‚Oگl‚ج•؛
پ@پ@پ@‚ھگي‚¤پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚»‚جŒˆگي‚حپAژهگيڈêپiŒˆگيڈêپj‚ج
پ@پ@پ@ژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پA”ü”Zچ‘ژR’†‘؛پj‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@پ@پi‚P‚U‚O‚O”NŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ‚جŒك‘O‚P‚O
پ@پ@پ@ژچ ‚©‚çگ³Œكچ ‚ـ‚إپA“؟گى•û‚ج“ŒŒRژه—ح
پ@پ@پ@ŒR‚ئ•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚جگ¼ŒRژه—حŒR‚ئ‚جٹش
پ@پ@پ@‚إچs‚ي‚ê ‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گي‚¢‚جŒ‹‰تپA“؟گى•û‚ج“ŒŒRژه—حŒR
پ@پ@پ@‚ھڈں—ک‚ً“¾‚éپB
پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ@پںپ@پuگVگàپiژjژہپjٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv
پ@پ@ پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپ@پi‘چچ‡پjپB
پ@
پ@پ@پ،پ@پuگVگàپiژjژہپjٹضƒ–Œ´ ‚جگي‚¢پvپi= ‘هٹ_پEژR
پ@پ@’†‚جگي‚¢پj‚حپAٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢’¼Œم‚جˆêژںژj—؟
پ@پ@پi“¯ژ‘م“ْ‹LپEژèژ†‚ب‚اپj‚ةٹî‚أ‚پA‘هٹ_پEژR
پ@پ@’†پi‚¨‚¨‚ھ‚«پE‚â‚ـ‚ب‚©پj‚جگي‚¢‚إ‚ ‚èپAپ@
پ@پ@ژjژہ‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢‚إ‚ ‚éپB
پ@پiپث گVگàپiژjژہپjٹضƒ–Œ´
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جگي‚¢پjپB
پ@پiپث ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپB
پ@
پ@پ@پ،پ@پuگVگàپiژjژہپjٹضƒ–Œ´ ‚جگي‚¢پvپi= ‘هٹ_پEژR
پ@پ@’†‚جگي‚¢پj‚حپA“؟گى•û‚ج“ŒŒRپ@‚ئپA•ٍچsڈOپE–ر
پ@پ@—ک•û‚جگ¼ŒRپ@‚ئ‚ج–Lگbژپ‰ئگbٹش‚ج“à•”چR‘ˆ
پ@پ@‚إ‚ ‚èپAپ@“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ھڈں—ک‚ً“¾‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“Tپ@‚P‚P‚Q‚R‚WپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‘S‘ج‚جگي‚¢‚ج’†گSگl•¨پ@پFپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‘S‘ج‚جگي‚¢‚ج•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚جگ¼ŒR‚ج
پ@پ@’†گSگl•¨‚حپA‘ه’J‹gŒpپA•ٍچsڈOپE‚Sگlپi‘“c
پ@پ@’·گ·پA’·‘©گ³‰ئپA‘O“cŒ؛ˆبپAگخ“cژOگ¬پjپA
پ@پ@‰Fٹى‘½ڈG‰ئپA–ر—ک‹PŒ³‚إ‚ ‚èپAگ¼ŒR‚حپA
پ@پ@”½“؟گى‚إ’cŒ‹‚µپAڈW’cژw“±‘جگ§‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@ˆê•ûپA‘S‘ج‚جگي‚¢‚ج“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ج
پ@پ@’†گSگl•¨‚حپA“؟گى‰ئچN‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‘S‘ج‚جگي‚¢‚جگlگ”پ@پFپ@
پ@پ@ “؟گى•û‚ج“ŒŒRپE–ٌ‚V–œ‚R‚O‚O‚Oگlپ@‚ئپAپ@
پ@پ@ •ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚جگ¼ŒRپE–ٌ‚T–œ‚S‚O‚O‚Oگl‚جگي‚¢پBپ@
پ@
پ@پ@پ،پ@‘S‘ج‚جگي‚¢‚جژٹْپ@پFپ@پiچL‹`پj
پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚WŒژ‚Q‚U“ْچ پ`‚XŒژ‚Q‚R“ْپBپ@
پ@
پ@پ@پ،پ@‘S‘ج‚جگي‚¢‚جڈêڈٹپ@پFپ@
پ@پ@پ@”ü”Zچ‘پ@پi‚ف‚ج‚ج‚‚ةپAŒ»پEٹٍ•ŒŒ§“ى•”
پ@پ@پ@‚ج‘ٹ“–’nˆوپj‚جپA
پ@پ@پ@‘هٹ_پi‚¨‚¨‚ھ‚«پj•t‹ك‚ئژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj•t‹كپB
پ@
پ@پ@پ،پ@Œˆگي‚جژٹْپ@پF
پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ
پ@پ@پ@Œك‘O‚P‚Oژچ پ`گ³Œكچ پB
پ@
پ@پ@پ،پ@Œˆگي‚جڈêڈٹپ@پF
پ@پ@پ@ژR’†پ@پi‚â‚ـ‚ب‚©پA”ü”Zچ‘ژR’†‘؛پjپB
پ@
پ@پ@پ،پ@Œˆگي‚إ‚جژQ‰ءگlگ”پ@پF
پ@پ@ “؟گى•û‚ج“ŒŒRژه—حŒRپE–ٌ‚T–œ‚P‚O‚O‚Oگlپ@‚ئپAپ@
پ@پ@ •ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚جگ¼ŒRژه—حŒRپE–ٌ‚R–œگl‚جگي‚¢پBپ@
پ@
پ@پ@پ،پ@پuگVگàپiژjژہپjٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†‚ج
پ@پ@پ@گي‚¢پjپv‚جپA‘هٹ_‚جگي‚¢پ@‚ئپ@ژR’†‚جگي‚¢پB
پ@
پ@پ@پœپ@‘هٹ_‚جگي‚¢پBپ@“؟گى•û‚جڈں—کپB
پ@پ@ژٹْپ@پFپ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj ‚WŒژ‚Q‚U“ْچ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚©‚ç‚XŒژ‚Q‚R“ْ‚ـ‚إپB
پ@پ@ڈêڈٹپ@پFپ@”ü”Zچ‘‚ج‘هٹ_•t‹كپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi”ü”Zگشچâپi‚ف‚ج‚ ‚©‚³‚©پjپA‘هٹ_ڈé
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¨‚¨‚ھ‚«‚¶‚ه‚¤پjپA“ى‹{ژRپi‚ب‚ٌ‚®‚¤
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚³‚ٌپj‚ب‚ا‚ج’nˆوپjپB
پ@
پ@پ@پœپ@ژR’†‚جگي‚¢پBپ@“؟گى•û‚جڈں—کپB
پ@پ@ژٹْپ@پFپ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج–é–¾‚¯‚©‚çگ³Œكچ ‚ـ‚إپB
پ@پ@ڈêڈٹپ@پFپ@”ü”Zچ‘‚جژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj•t‹ك پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiٹضƒ–Œ´–~’n“ىگ¼•”پAژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“،‰؛پi‚ئ‚¤‚°پjپAڈ¼”ِژRپi‚ـ‚آ‚¨‚â‚ـپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژRک[‚ب‚ا‚ج’nˆوپj پB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ@پںپ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپjٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv
پ@پi‘چچ‡پjپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپjٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚حپAچL‹`
پ@پ@پ@‚إ‚حپA ژٹْ‚ح‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚ج‚WŒژ
پ@پ@پ@‚Q‚U“ْچ پi“ŒŒR‚ج”ü”Zگشچâ•zگwپj‚©‚ç‚XŒژ
پ@پ@پ@‚Q‚R“ْپiگ¼ŒR‚ج‘هٹ_ڈé—ژڈéپj‚ـ‚إ‚إ‚ ‚èپAگي
پ@پ@پ@‚¢‚جڈêڈٹ‚ح”ü”Zچ‘پi‚ف‚ج‚ج‚‚ةپAŒ»پEٹٍ•Œ
پ@پ@پ@Œ§“ى•”‚ج‘ٹ“–’nˆوپj‚جٹضƒ–Œ´–~’n‚ئ ٹضƒ–
پ@پ@پ@Œ´–~’n‚جژü•س’nˆو‚إ‚ ‚èپAپ@”ü”Zچ‘‚ةڈW
پ@پ@پ@Œ‹‚µ‚½پA “؟گى•û‚ج“ŒŒRپE–ٌ‚V–œگl‚ج•؛‚ئ
پ@پ@پ@گخ“c•û‚جگ¼ŒRپE–ٌ‚W–œگl‚ج•؛‚ج“Œگ¼—¼ŒRپE
پ@پ@پ@–ٌ‚P‚T–œگl‚ج•؛‚ھگي‚¤پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚»‚جŒˆگي‚حپAژهگيڈêپiŒˆگي’nپj‚جٹضƒ–
پ@پ@پ@Œ´–~’n‚إ‚ ‚èپAپ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ
پ@پ@پ@‚P‚T“ْ‚جŒك‘O‚Wژچ ‚©‚çŒكŒم‚Qژچ ‚ـ‚إپA
پ@پ@پ@“؟گى•û ‚ج“ŒŒRژه—حŒR‚ئگخ“c•û‚جگ¼ŒRژه
پ@پ@پ@—حŒR‚ئ‚جٹش‚إچs‚ي‚ê ‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@گي‚¢‚جŒ‹‰تپA“؟گى•û‚ج“ŒŒRژه—حŒR‚ھ
پ@پ@پ@ڈں—ک‚ً“¾‚éپB
پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ@پںپ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپjٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv
پ@پi‘چچ‡پjپB
پ@
پ@پ@پ،پ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپjٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚حپA
پ@پ@پu“ْ–{گيژjپvپi–¾ژ،‚Q‚U”N‚ج‹Œ“ْ–{—¤ŒRژQ–d
پ@پ@–{•”’کچىپj‚جژ‘—؟‚ةٹî‚أ‚پAٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢
پ@پ@‚إ‚ ‚èپA‘nچى‚ھ‘½‚پAگMœكگ«پi‚µ‚ٌ‚ز‚ه‚¤‚¹‚¢پj
‚ھ‚ب‚¢پB
پ@پiپث ٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پjپB
پ@
پ@پ@پ،پ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپjٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚حپA“؟گى•û‚ج
پ@پ@“ŒŒR‚ئگخ“c•û‚جگ¼ŒR‚ئ‚ج–Lگbژپ‰ئگbٹش‚ج“à
پ@پ@•”چR‘ˆ‚إ‚ ‚èپAپ@“؟گى•û‚جگ¼ŒR‚ھڈں—ک‚ً“¾‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“Tپ@‚P‚P‚Q‚R‚XپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‘S‘ج‚جگي‚¢‚ج’†گSگl•¨پ@پFپ@
پ@پ@پ@پ@‘S‘ج‚جگي‚¢‚جگخ“c•û‚جگ¼ŒR‚ج’†گSگl•¨‚حپAپ@
پ@پ@گخ“cژOگ¬‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@ˆê•ûپA‘S‘ج‚جگي‚¢‚ج“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ج’†گS
پ@پ@گl•¨‚حپA“؟گى‰ئچN‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‘S‘ج‚جگي‚¢‚جگlگ”پ@پFپ@پ@
پ@پ@“؟گى•û‚ج“ŒŒRپE–ٌ‚V–œگlپ@‚ئپAپ@
پ@پ@گخ“c•û‚جگ¼ŒRپE–ٌ‚W–œگl‚جگي‚¢پBپ@
پ@
پ@پ@پ،پ@‘S‘ج‚جگي‚¢‚جژٹْپ@پFپ@پiچL‹`پjپ@
پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚WŒژ‚Q‚U“ْچ پ`‚XŒژ‚Q‚R“ْپBپ@
پ@
پ@پ@پ،پ@‘S‘ج‚جگي‚¢‚جڈêڈٹپ@پFپ@
پ@پ@پ@”ü”Zچ‘پ@پi‚ف‚ج‚ج‚‚ةپAŒ»پEٹٍ•ŒŒ§“ى•”
پ@پ@پ@‚ج‘ٹ“–’nˆوپj‚جپA
پ@پ@پ@ٹضƒ–Œ´–~’n‚ئٹضƒ–Œ´–~’n‚جژü•سپB
پ@
پ@پ@پ،پ@Œˆگي‚جژٹْپ@پF
پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ
پ@پ@پ@Œك‘O‚Wژچ پ`ŒكŒم‚Qژچ پB
پ@
پ@پ@پ،پ@Œˆگي‚جڈêڈٹپ@پF
پ@پ@پ@”ü”Zچ‘‚جٹضƒ–Œ´–~’nپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@پuگVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚ئپu‘هٹ_‚جگي‚¢پvپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@گVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢‚إ‚حپAپ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj
پ@پ@پ@‚XŒژ‚ةپA”ü”Zگشچâپi‚ف‚ج‚ ‚©‚³‚©پjƒGƒٹƒA‚ة‚حپA
پ@پ@پ@ٹù‚ةپA“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚جگوژèگ¨پi–Lگb‰¶Œع‚ج‘ه–¼پj
پ@پ@پ@–ٌ‚S–œگl‚ج•؛‚ھ‚¢‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ةپA“؟گى‰ئچN‚ج
پ@پ@پ@—¦‚¢‚é“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚ج“؟گى–{‘àپE–ٌ‚R–œ‚Q‚O‚O‚Oگl
پ@پ@پ@‚ج•؛‚ھ”ü”ZگشچâƒGƒٹƒA‚ة“’…‚µ‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ةپA“ى‹{ژRپi‚ب‚ٌ
پ@پ@پ@‚®‚¤‚³‚ٌپj‚ة•zگw‚µپA–ٌ‚P–œ‚R‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ً—¦‚¢‚é
پ@پ@پ@گ¼ŒR‚ج•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚ج–ر—کڈGŒ³پi‚à‚¤‚è‚ذ‚إ‚à‚ئپj
پ@پ@پ@‚حپA”ü”ZگشچâƒGƒٹƒA‚ة‚¢‚éپA“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚جگوژè
پ@پ@پ@گ¨پE–ٌ‚S–œگl‚ج•؛پi•ں“‡گ¨پE–ٌ‚P–œ‚X‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ئ
پ@پ@پ@’r“cگ¨پE–ٌ‚Q–œ‚P‚O‚O‚Oگl‚ج•؛پjپ@‚ئپ@“ŒŒR‚ج“؟گى•û
پ@پ@پ@‚ج“؟گى–{‘àپE–ٌ‚R–œ‚Q‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ج“ŒŒR‚ج“؟گى•ûپE
پ@پ@پ@Œv–ٌ‚V–œ‚Q‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ًپA“ى‹{ژR‚©‚猩‚½پBپ@
پ@پ@پ@‚»‚µ‚ؤپAگ¼ŒR‚ج•ٍچsڈOپE–ر—ک•û ‚ج–ر—کڈGŒ³‚حپA“ى
پ@پ@پ@‹{ژR‚جگw‚و‚èپA–ىگي‚ة‹‚¢“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚ج‘هŒR
پ@پ@پ@‚ًŒ©‚ؤپAگ¼•û‚©‚ç‚جگ¼ŒR‚ج‰‡ŒR‚ً‘ز‚آ‚±‚ئ‚ة‚µپA
پ@پ@پ@“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚ئگي‚¢‚ً”ً‚¯پA“®‚©‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@چX‚ةپA‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ‚àپA–ٌ
پ@پ@پ@‚P–œ‚R‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ً—¦‚¢‚é“ى‹{ژR•zگw‚جگ¼ŒR‚ج
پ@پ@پ@•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚ج–ر—کڈGŒ³‚حپAپ@“؟گى•û‚جگوژè
پ@پ@پ@گ¨‚ج’r“cگ¨پE–ٌ‚Q–œ‚P‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ھ“ى‹{ژR‚ج‘O
پ@پ@پ@–ت‚ةژc—¯‚µپAچs‚ژè‚ً‘j‚فپAگ¼ŒR‚جژه—حŒRپE–ٌ‚R
پ@پ@پ@–œگl‚ج•؛‚ج‰‡ŒR‚ة‹ى‚¯‚آ‚¯‚ç‚ꂸپAپ@ٹضƒ–Œ´–~
پ@پ@پ@’nپEژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj•û–ت‚ةڈoگw‚µ‚½“ŒŒR‚ج“؟گى
پ@پ@پ@•û‚جژه—حŒRپE–ٌ‚T–œ‚P‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ً‹²‚فŒ‚‚؟‚ة
پ@پ@پ@‚إ‚«‚ب‚©‚ء‚½پB
‘هٹ_ڈéپi‚¨‚¨‚ھ‚«‚¶‚ه‚¤پj‚ًڈo‚½گ¼ŒR‚ج•ٍچs
پ@پ@پ@ڈOپE –ر—ک•û‚جژه—حŒRپE–ٌ‚R–œگl‚ج•؛‚حپAپ@“ى‹{
پ@پ@پ@ژR•zگw‚ج –ر—کŒR‚جŒم‹lپi‚²‚¸‚كپj‚ئ‚µ‚ؤپAگ¼•û‚ج
پ@پ@پ@ژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚ة•zگw‚µپA“Œ•û‚ج“ى‹{ژR•zگw‚ج
پ@پ@پ@گ¼ŒR‚ج–ر—کڈGŒ³‚ج–ٌ‚P–œ‚R‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ئ‹¦—ح‚µپA
پ@پ@پ@ٹضƒ–Œ´–~’n‚âژR’†‚ةڈo‚ؤ‚«‚½“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚ج
پ@پ@پ@ژه—حŒRپE–ٌ‚T–œ‚P‚O‚O‚Oگl‚ج•؛پ@پi“؟گى–{‘àپE–ٌ‚R
پ@پ@پ@–œ‚Q‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ئ•ں“‡گ¨پE–ٌ‚P–œ‚X‚O‚O‚Oگl‚ج•؛پj
پ@پ@پ@‚ً‹²‚فŒ‚‚؟‚ة‚µ‚و‚¤‚ئچl‚¦‚ؤ‚¢‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚µ‚©‚µپA‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ةپA
پ@پ@پ@“Œ•û‚ج“ى‹{ژR•zگw‚جگ¼ŒR‚ج–ر—کڈGŒ³‚حپA “ŒŒR
پ@پ@پ@‚ج“؟گى•û‚جگوژèگ¨‚ج’r“cگ¨‚ةچs‚ژè‚ً‘jپi‚ح‚خپj
پ@پ@پ@‚ـ‚ê‚ؤپA“®‚¯‚ب‚©‚ء‚½پBپ@‚±‚ج‚½‚كپAگ¼ŒR‚ج•ٍچs
پ@پ@پ@ڈOپE –ر—ک•û‚ج“ى‹{ژR‚ج–ر—کڈGŒ³‚ج‰‡ŒR‚à‚ب‚پA
پ@پ@پ@گ¼ŒR‚ج•ٍچsگlڈOپE–ر—ک•û‚جژه—حŒRپE–ٌ‚R–œ ‚ج•؛
پ@پ@پ@‚حپAژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚إ‚جŒˆگي‚إپAˆê•û“I‚ةچU‚ك
پ@پ@پ@‚ç‚êپA‘چ•ِ‚ê‚ئ‚ب‚èپA‚»‚جŒ‹‰تپAگ¼ŒR‚ج•ٍچsڈOپE
پ@پ@پ@–ر—ک•û‚ج ژه—حŒR‚حپAپ@“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚جژه—حŒR‚ة
پ@پ@پ@”s–k‚µ‚½پB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
#thenewtheoryofsekigaharawar-general
پ@
پںپ@پuگVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢
پ@پ@ پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپvپBپ@
پ@
پ@پ،پ@پuگVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢
پ@پ@ پ@پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپvپ@پi‘چچ‡پjپBپ@
پ@
پ@پ@پ،پ@پuگVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پvپ@پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پi‚¨
پ@پ@‚¨‚ھ‚«پE‚â‚ـ‚ب‚©‚ج‚½‚½‚©‚¢پjپAŒc’·چMژq‚ج‘ه
پ@پ@—گپi‚¯‚¢‚؟‚ه‚¤‚±‚¤‚µ‚ج‚½‚¢‚ç‚ٌپjپjپ@‚حپAپ@ٹضƒ–Œ´
پ@پ@‚جگي‚¢’¼Œم‚جˆêژںژj—؟پi“¯ژ‘مژèژ†پE“ْ‹L‚ب‚اپj
پ@پ@‚ةٹî‚أ‚پAپuژjژہ‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@پuگVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپv‚ة‚حپA
پ@پ@پu‘هٹ_پi‚¨‚¨‚ھ‚«پj ‚جگي‚¢پvپ@‚ئپ@پuژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj
پ@پ@‚جگي‚¢پvپ@‚ج‚Q‚آ‚جچ‡گي‚ھ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پ@پ،پ@پuگVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پvپi= ‘هٹ_پEژR’† ‚جگي‚¢پj‚إ
پ@پ@پ@‚حپAپ@•ٍچsڈOپE –ر—ک•û‚جگ¼ŒR‚ج’†گSگl•¨‚حپAپ@
پ@پ@پ@•ٍچsڈO‚Rگlپi‘“c’·گ·پA’·‘©گ³‰ئپA‘O“cŒ؛ˆبپj
پ@پ@ ‚ئ–ر—ک‹PŒ³‚إ‚ ‚éپBپ@ˆê•ûپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ج’†
پ@پ@پ@گSگl•¨‚حپA“؟گى‰ئچN‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@•ٍچsڈO‚Rگl‚ئ‚حپAپ@Œـ•ٍچs‚ج’†‚ج‚Rگl‚إ
پ@پ@پ@‚ ‚èپA‘“c’·گ·پ@پi‚ـ‚µ‚½‚ب‚ھ‚à‚èپjپAپ@’·‘©گ³پ@
پ@پ@پ@‰ئپi‚ب‚آ‚©‚ـ‚³‚¢‚¦پjپAپ@‘O“cŒ؛ˆبپ@پi‚ـ‚¦‚¾‚°
پ@پ@پ@‚ٌ‚¢پjپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@پuگVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپv‚ج
پ@پ@پ@Œˆگي‚حپA‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ‚جŒك‘O
پ@پ@پ@‚P‚Oژچ ‚©‚çگ³Œكچ ‚ـ‚إ‚ج–ٌ‚Qژٹش‚جٹشپA
پ@پ@پ@”ü”Zچ‘‚جژهگيڈê‚جژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚إپA“؟گى
پ@پ@پ@•û‚ج“ŒŒR‚ئ•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚جگ¼ŒR‚ئ‚جٹش‚إچs
پ@پ@پ@‚ي‚ꂽگي‚¢‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚حپAگي‚¢‚ً—L—ک‚ة‚·‚·‚كپA
پ@پ@پ@ڈں—ک‚ً“¾‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پ@پ،پ@“؟گى‰ئچN‚حپAپ@ژ©گg‚جڈ‘ڈَ‚إپAٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢
پ@پ@‚جژهگيڈê‚حپAپ@پu”ZڈBژR’†پvپ@پi‚ج‚¤‚µ‚م‚¤‚â‚ـ‚ب‚©پA
پ@پ@”ü”Zچ‘‚جژR’†‘؛پjپjپ@‚ئڈq‚ׂؤ‚¢‚éپ@پiپuŒc’·Œـ”N
پ@پ@‹مŒژڈ\Œـ“ْ•tˆة’Bگڈ@ˆ¶“؟گى‰ئچNڈ‘ڈَپv‚و‚èپjپB
پ@
پ@پ@پ،پ@پuگVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚حپAپ@پu‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پv
پ@پ@‚ج•ت–¼‚إ‚ ‚èپAپ@ٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢’¼Œم‚جˆêژںژj—؟
پ@پ@پi“¯ژ‘م“ْ‹LپEژèژ†‚ب‚اپj‚ةٹî‚أ‚«پAپ@”ü”Zچ‘پ@
پ@پ@‚ج‘هٹ_ •t‹ك‚âژR’†•t‹ك‚إپAپ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·
پ@پ@‚T”Nپj‚WŒژ‚Q‚U“ْچ ‚©‚ç‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ـ‚إپA“؟گى•û
پ@پ@‚ج“ŒŒR‚ئ•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚جگ¼ŒR‚ئ‚جٹش‚إچs‚ي
پ@پ@‚ꂽچ‡گي‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@Œ‹‰ت‚حپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ھڈں—ک‚ً“¾‚½پB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@پuگVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پvپi= ‘هٹ_پEژR’† ‚جگي‚¢پj‚حپA
پ@پ@پ@ژٹْ‚ح‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚جپi“ŒŒR‚ج”ü”Zگش
پ@پ@پ@چâپi‚ف‚ج‚ ‚©‚³‚©پj•zگw‚جپj‚WŒژ‚Q‚U“ْچ ‚©‚ç
پ@پ@پ@پi“Œگ¼—¼ŒR‚جŒˆگي‚جپj‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ـ‚إ‚ ‚èپAپ@
پ@پ@پ@ڈêڈٹ‚ح”ü”Zچ‘پi‚ف‚ج‚ج‚‚ةپAŒ»پEٹٍ•ŒŒ§“ى•”‚ج
پ@پ@پ@‘ٹ“–’nˆوپj‚ج‘هٹ_پi‚¨‚¨‚ھ‚«پj•t‹ك‚âژR’†پi‚â‚ـپ@
پ@پ@پ@‚ب‚©پj•t‹ك‚إ‚ ‚èپAپ@”ü”Zچ‘‚ةŒ‹ڈW‚µ‚½پA“ŒŒRپE
پ@پ@پ@–ٌ‚V–œ‚R‚O‚O‚OگlپAگ¼ŒRپE–ٌ‚T–œ‚S‚O‚O‚Oگl‚ج“Œگ¼
پ@پ@پ@—¼ŒRپE–ٌ‚P‚Q–œ‚V‚O‚O‚Oگl‚ھگي‚¢پAپ@‚»‚جŒˆگي‚حپA
پ@پ@پ@”ü”Zچ‘‚جژهگيڈê‚جژR’†‚إ‚ ‚èپA‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·
پ@پ@پ@‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ‚جŒك‘O‚P‚Oژچ ‚©‚çگ³Œكچ ‚ـ‚إپA
پ@پ@پ@“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ئ•ٍچs ڈOپi‚ش‚¬‚ه‚¤‚µ‚م‚¤پjپE–ر—ک
پ@پ@پ@پi‚à‚¤‚èپj•û‚جگ¼ŒR‚ئ‚جٹش‚إچs‚ي‚ꂽپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@گي‚¢‚جŒ‹‰تپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ھڈں—ک‚ً“¾‚éپB
پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ،پ@پuگVگà‚جٹضƒ–Œ´ ‚جگي‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپv
پ@پ@پ@‚حپAپ@“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ئ•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚جگ¼ŒR
پ@پ@پ@‚ئ‚جٹش‚جپA–Lگbژپ‰ئگbٹش‚ج“à•”چR‘ˆ‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پuگVگà‚جٹضƒ–Œ´ ‚جگي‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†‚ج
پ@پ@پ@گي‚¢پjپv‚إ‚حپA “–ڈ‰‚حپA‘هٹ_ڈéپi‚¨‚¨‚ھ‚«‚¶‚ه‚¤پj
پ@پ@پ@‚ًچU‚ك—ژ‚ئ‚·‚±‚ئ‚ھ پu“V‰؛”Vڈں•‰پvپi“V‰؛•ھ‚¯
پ@پ@پ@–ع‚جگي‚¢‚جڈں”s‚ًŒˆ‚ك‚邱‚ئپj‚إ‚ ‚ء‚½پBپ@‚µ‚©
پ@پ@پ@‚µپA‚»‚جŒˆگي‚حپA”ü”Zچ‘‚جژهگيڈê‚جژR’†پi‚â‚ـ
پ@پ@پ@‚ب‚©پj‚إچs‚ي‚ꂽپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ھ—L—ک‚ةگي‚¢‚ً‚·‚·‚كپAڈں
پ@پ@پ@—ک‚ً“¾‚½پB
پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ@پںپ@پuگVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†
پ@پ@پ@‚جگي‚¢پjپvپBپ@
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@پuگVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپv
پ@پ@پ@‚حپA‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚WŒژ‚Q‚U“ْچ ‚©‚ç‚XŒژ‚P‚T“ْ
پ@پ@پ@‚ـ‚إپAپ@”ü”Zچ‘پ@پi‚ف‚ج‚ج‚‚ةپAٹT‚ثپAŒ»پEٹٍ•Œ
پ@پ@پ@Œ§“ى•”‚ج‘ٹ“–’nˆوپjپ@‚ج‘هٹ_پi‚¨‚¨‚ھ‚«پj•t‹ك
پ@پ@پ@‚âژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj•t‹ك‚إپA پ@“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ئ
پ@پ@پ@•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚جگ¼ŒR‚ھ ‚ء‚½چ‡گي‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پuگVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپv
پ@پ@پ@‚ة‚حپAپ@پu‘هٹ_‚جگي‚¢پvپ@‚ئپAپ@پuژR’†‚جگي‚¢پv ‚ج
پ@پ@پ@‚Q‚آ‚جچ‡گي‚ھ‚ ‚éپBپ@
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@‘هٹ_‚جگي‚¢‚حپA ‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj ‚WŒژ
پ@پ@پ@‚Q‚U“ْچ ‚©‚ç‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ـ‚إ‚جگي‚¢‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@چإڈ‰‚حپA“ŒŒRپi“؟ گى•ûپj‚ج“؟گى•ûگوژèگ¨‚ج
پ@پ@پ@’r“cگ¨پE•ں“‡گ¨‚ج–Lگb‰¶Œع‚ج‘ه–¼‚جŒRپ@‚ئپAپ@
پ@پ@پ@گ¼ŒR(•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج–{‘à‚ج‘هٹ_ڈéâؤڈéڈOپ@
پ@پ@پ@پi’“—¯ŒRپj‚ئ‚ج‘هٹ_ڈé‚جچU–hگي‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژں‚ةپA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج“؟گى•ûگوژèگ¨‚ج’r
پ@پ@پ@“cگ¨پE•ں“‡گ¨‚ج–Lگb‰¶Œع‚ج‘ه–¼‚جŒRپ@‚âپ@پiŒم‚©
پ@پ@پ@‚ç—ˆ‚½پj“؟گى–{‘à‚جŒRپ@‚ئپAپ@گ¼ŒR(•ٍچsڈOپE–ر—ک
پ@پ@پ@•ûپj‚جپA–{‘à‚ج‘هٹ_ڈéâؤڈéڈOپi’“—¯ŒRپjپ@‚âپ@پi‘ه
پ@پ@پ@ٹ_ڈéŒم‹lŒR‚ئ‚µ‚ؤŒم‚©‚ç—ˆ‚½پj“ى‹{ژR پi‚ب‚ٌ‚®‚¤
پ@پ@پ@‚³‚ٌپj“Œ‘¤‚ة•zگw‚·‚é–ر—کگ¨‚جŒRپ@‚ئ‚ج‘خ›³‚إ‚
پ@پ@پ@‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژں‚ةپA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج“؟گى•ûگوژèگ¨‚ج
پ@پ@پ@•ں“‡گ¨‚ج–Lگb‰¶Œع‚ج‘ه–¼‚جŒRپ@‚âپ@“؟گى–{‘à
پ@پ@پ@‚جŒRپ@‚ئپ@گ¼ŒR(•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج–{‘à‚ج‘هٹ_
پ@پ@پ@ڈéâؤڈéڈOپi’“—¯ŒRپj‚حپAٹضƒ–Œ´•ھ’nپEژR’†•û–ت‚ة
پ@پ@پ@ˆع“®‚µپAپ@‘هٹ_•t‹ك‚ةژc—¯‚µ‚½پA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj
پ@پ@پ@‚ج“؟گى•ûگوژèگ¨‚ج’r“cگ¨‚ج–Lگb‰¶Œع‚ج‘ه–¼‚ج
پ@پ@پ@ŒRپ@‚ئپAپ@‘هٹ_•t‹ك‚ةژc—¯‚µ‚½پAگ¼ŒR(•ٍچsڈOپE
پ@پ@پ@–ر—ک•ûپj‚جپA‘هٹ_ڈéڈگ”ژc—¯ŒRپ@‚âپ@“ى‹{ژR“Œ
پ@پ@پ@‘¤‚ة•zگw‚·‚é–ر—کگ¨‚جŒRپ@‚ئ‚ج‘خ›³‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گي‚¢‚جŒ‹‰تپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ھڈں—ک‚ً“¾پA
پ@پ@پ@•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚جگ¼ŒR‚ھ”s–k‚·‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@ژR’†‚جگي‚¢‚حپAپ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ
پ@پ@پ@‚P‚T“ْ‚ج–é–¾‚¯‚©‚ç گ³Œكچ ‚ـ‚إ‚جٹش‚جگي‚¢‚إ‚
پ@پ@پ@‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@چإڈ‰‚ةپAٹضƒ–Œ´–~’n“ىگ¼•”‚إپAپ@پi‘هٹ_•t‹ك
پ@پ@پ@‚©‚ç—ˆ‚½پj“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج“؟گى–{‘à پ@‚âپ@پiگ¼ŒR
پ@پ@پ@‚©‚ç“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ةگQ•ش‚èٹضƒ–Œ´–~’n“ى•û‚ج
پ@پ@پ@ڈ¼”ِژRژRک[•zگw‚جپjڈ¬‘پگى ‘àپ@‚ئپAپ@گ¼ŒR(•ٍچs
پ@پ@پ@ڈOپE–ر—ک•ûپj‚جپiٹضƒ–Œ´–~’n“ىگ¼•”•zگw‚جپj‘ه’J
پ@پ@پ@ŒR‚ئ‚جچ‡گي‚إ‚ ‚èپA‘ه’JŒR‚ھ‘S–إ‚·‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژں‚ةپAٹض‚ھŒ´–~’n‚ج“ىگ¼•ûŒüپE–ٌ‚Q‚‹‚چ
پ@پ@پ@‚ة‚ ‚éژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚إپAپ@“ŒŒR پi“؟گى•ûپj‚ج
پ@پ@پ@پi‘هٹ_•t‹ك‚ج”ü”Zگشچâ‚©‚ç—ˆ‚½پj“؟گى•ûگوژèگ¨پ@
پ@پ@پ@‚ج•ں“‡گ¨پ@‚âپ@“؟گى–{‘à“™‚جŒRپ@‚ئپAپ@گ¼ŒR(•ٍ
پ@پ@پ@چsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جپi‘هٹ_•t‹ك‚ج‘هٹ_ڈé‚©‚ç—ˆ‚½پj
پ@پ@پ@ڈ¬گ¼پE‰Fٹى‘½پEگخ“cپE “‡’أگ¨“™‚جŒRپ@‚ئ‚جٹش‚إچs
پ@پ@پ@‚ي‚ꂽچ‡گي‚إ‚ ‚èپAگ¼ŒR‚ھ‘چ•ِ‚ê‚ئ‚ب‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@گي‚¢‚جŒ‹‰تپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ھڈں—ک‚ً“¾پA
پ@پ@پ@•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚جگ¼ŒR‚ھ”s–k‚·‚éپB
پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پںپ@پu‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پi= گVگàٹضƒ–Œ´
پ@پ@پ@پ@‚جگي‚¢پjپvپBپ@
پ@
پ@پ@پ،پ@پu‘هٹ_‚جگي‚¢پvپ@‚ئپ@پuژR’†‚جگي‚¢پvپB
پ@پ@پ،پ@پu‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پi= گVگà‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پjپv‚حپA
پ@پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚WŒژ‚Q‚U“ْچ ‚©‚ç‚XŒژ‚P‚T“ْ ‚ـ‚إپAپ@
پ@پ@”ü”Zچ‘پi‚ف‚ج‚ج‚‚ةپAŒ»پEٹٍ•ŒŒ§“ى•”‚ج‘ٹ“–’nˆوپj
پ@پ@‚ج‘هٹ_پi‚¨‚¨‚ھ‚«پj•t‹ك‚âژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj•t‹ك‚إ
پ@پ@“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ئ•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚جگ¼ŒR‚ھگي ‚ء‚½چ‡
پ@پ@گي‚إ‚ ‚éپBپ@گي‚¢‚جŒ‹‰تپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ھڈں—ک‚ً‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پu‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پi= گVگà‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پjپv
پ@پ@‚ة‚حپAپ@پu‘هٹ_‚جگي‚¢پvپ@‚ئپAپ@پuژR’†‚جگي‚¢پvپ@‚ج
پ@پ@‚Q‚آ‚جچ‡گي‚ھ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‘هٹ_‚جگي‚¢‚حپAپ@‚P‚U‚O‚O”N پiŒc’·‚T”Nپjپj‚WŒژ
پ@پ@‚Q‚U“ْ‚©‚ç‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ـ‚إ‚ج‘هٹ_پi‚¨‚¨‚ھ‚«پj•t‹ك‚إ
پ@پ@‚جگي‚¢‚إ‚ ‚èپAپ@چإڈ‰‚ةپA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj ‚ج“؟گى•û
پ@پ@گوژèڈO‚ج•ں“‡گ¨‚â’r“cگ¨‚جŒRپ@‚ئپ@گ¼ŒR(•ٍچsڈOپE
پ@پ@–ر—ک•ûپj‚ج‘هٹ_ڈéچف—¯ŒR‚ئ‚ج‘هٹ_ڈé‚جچU–hگي‚إ
پ@پ@‚ ‚èپAپ@ژں‚ةپA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج“؟گى–{‘à‚â“؟گى•û
پ@پ@گوژèڈO‚ج•ں“‡گ¨پE’r“cگ¨‚جŒRپ@‚ئپAپ@گ¼ŒR(•ٍچsڈOپE
پ@پ@–ر—ک•ûپj‚جپA‘هٹ_ڈéŒم‹lŒR‚ئ‚µ‚ؤ“ى‹{ژR پi‚ب‚ٌ‚®‚¤
پ@پ@‚³‚ٌپj“Œ‘¤‚ة•zگw‚·‚é–ر—کگ¨پ@‚âپ@‘هٹ_ڈéچف—¯ŒRپ@
پ@پ@‚ئ‚ج‘خ›³‚إ‚ ‚éپBپ@گي‚¢‚جŒ‹‰تپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ھ
پ@پ@ڈں—ک‚ً‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@ژR’†‚جگي‚¢‚حپA‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T
پ@پ@“ْ‚ج–é–¾‚¯‚©‚ç گ³Œكچ ‚ـ‚إ‚جٹش‚جگي‚¢‚إ‚ ‚èپAپ@
پ@پ@چإڈ‰‚ةپAٹضƒ–Œ´–~’nگ¼“ى•”‚إپAژں‚ةپAٹض‚ھŒ´–~
پ@پ@’n‚ج“ىگ¼•ûŒüپE–ٌ‚Q‚‹‚چ‚ة‚ ‚éژهگيڈê‚جژR’†پi‚â
پ@پ@‚ـ‚ب‚©پj‚إچs‚ي‚ꂽگي‚¢‚إ‚ ‚éپBپ@گي‚¢‚جŒ‹‰تپA
پ@پ@“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ھڈں—ک‚ً“¾‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@پu‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پi= گVگà‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پjپv
پ@پ@‚حپAپ@‘هٹ_پi‚¨‚¨‚ھ‚« پj•t‹ك‚âژR’†پi‚â‚ـ ‚ب‚©پj
پ@پ@•t‹ك‚إگي‚ي‚ꂽچ‡گي‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘هٹ_‚جگي‚¢‚حپAچإڈ‰‚ةپA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj
پ@پ@‚ج“؟گى•ûگوژèگ¨پ@‚ئپAپ@گ¼ŒR(•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج
پ@پ@‘هٹ_ڈéâؤڈéڈOپi’“—¯ŒRپj‚ھگي‚ء‚½‘هٹ_ڈéچU–hگي
پ@پ@‚جچ‡گي‚إ‚ ‚èپAپ@ژں‚ةپA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج“؟گى–{
پ@پ@‘àپE“؟گى•ûگوژèگ¨پ@‚ئپAپ@گ¼ŒR(•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj
پ@پ@‚ج“ى‹{ژRپi‚ب‚ٌ‚®‚¤‚³‚ٌپj“Œ‘¤•zگw‚ج‘هٹ_ڈéŒم
پ@پ@‹lŒR‚ج–ر—کگ¨‚â‘هٹ_ڈéâؤڈéڈOپi’“—¯ŒRپjپ@‚ئ‚ج
پ@پ@‘خ›³‚إ‚ ‚éپBپ@گي‚¢‚جŒ‹‰تپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ھڈں
پ@پ@—ک‚ً“¾‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚جگي‚¢‚حپAپ@چإڈ‰‚ةپA“Œ
پ@پ@ŒRپi“؟گى•ûپj‚ج“؟گى–{‘à‚âگ¼ŒR‚©‚ç“ŒŒR‚ةگQ
پ@پ@•ش‚èڈ¬‘پگى‚جŒRپ@‚ئپAپ@گ¼ŒR(•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj
پ@پ@‚ج‘ه’JŒR‚ئ‚ھگي‚ء‚½ٹضƒ–Œ´–~’n“ىگ¼•”‚جچ‡گي
پ@پ@‚إ‚ ‚èپAپ@ژں‚ةپA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج“؟گى•ûگوژèگ¨
پ@پ@‚ج•ں“‡گ¨‚â“؟گى–{‘à“™‚جŒRپ@‚ئپAپ@گ¼ŒR(•ٍچsڈO
پ@پ@پE–ر—ک•ûپj‚جڈ¬گ¼پE‰Fٹى‘½پEگخ“cپE “‡’أگ¨“™‚جŒR
پ@پ@‚ئ‚ھگي‚ء‚½پAژهگيڈê‚جژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚إ‚جچ‡گي
پ@پ@‚إ‚ ‚éپBپ@گي‚¢‚جŒ‹‰تپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ھڈں—ک‚ً
پ@پ@“¾‚éپB
پ@
پ@
پ@پںپ@پu‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢
پ@پ@پ@پ@پi= گVگà‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پjپvپBپ@
پ@
پ@پ@پ،پ@پu‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پi= گVگà‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پjپv‚إ‚حپA
پ@پ@پu“à•{‚؟‚ھ‚ذ‚جڈًپXپvپi‚ب‚¢‚س‚؟‚ھ‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤‚¶‚ه‚¤پj
پ@پ@‚ًڈo‚µ‚½–LگbژپپE•ٍچsڈO‚Rگlپ@پi’·‘©گ³‰ئپi‚ب‚آ‚©‚ـ
پ@پ@‚³‚¢‚¦پjپA‘“c’·گ·پi‚ـ‚µ‚½‚ب‚ھ‚à‚èپjپA‘O“cŒ؛ˆبپi‚ـ
پ@پ@‚¦‚¾‚°‚ٌ‚¢پj‚ج–Lگbژپ‚ج‚R•ٍچsپjپ@‚ھپAپ@“؟گى‰ئچN‚ً
پ@پ@’eٹNپi‚¾‚ٌ‚ھ‚¢پj‚µپA‚»‚ê‚ةژ^“¯‚µ‚½‘ه–¼پE•گڈ«‚ھ
پ@پ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ئ‚ب‚èپAپ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر
پ@پ@—ک•ûپj‚ج–ر—ک‹PŒ³پi‚à‚¤‚è‚ؤ‚é‚à‚ئپj‚ح–Lگb‘هچâڈé‚ة
پ@پ@“ü‚èپAپ@گ¼ŒR(•ٍچs ڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج‰Fٹى“cڈG‰ئپi‚¤‚«‚½
پ@پ@‚ذ‚إ‚¢‚¦‚¢پj‚â گخ“cژOگ¬‚حپA•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚جگ¼ŒR
پ@پ@‚ً—¦‚¢‚ؤپA“Œ•û‚ةڈoگw‚µپA”ü”Zچ‘‚إ•zگw‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@ˆê•ûپA’eٹN‚³‚ꂽ“؟گى‰ئچN‚ة–،•û‚µ‚½‘ه–¼پE
پ@پ@پ@•گڈ«‚حپA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ئ‚ب‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@پu‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پi= گVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پjپv‚حپA
پ@پ@گ¼ŒR(•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ئ“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ئ‚ج–Lگb
پ@پ@ژپ‰ئگbٹش‚ج“à•”چR‘ˆ‚إ‚ ‚éپBپ@“؟گى•û‚ھ—L—ک‚ة
پ@پ@گي‚¢‚ً‚·‚·‚كپAڈں—ک‚ً“¾‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پu‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پi= گVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پjپv
پ@پ@‚إ‚حپA‘هٹ_ڈé ‚ًچU‚ك—ژ‚ئ‚·‚±‚ئ‚ھپu“V‰؛”Vڈں•‰پv
پ@پ@پi“V‰؛•ھ‚¯–ع‚جگي‚¢‚جڈں”s‚ًŒˆ‚ك‚邱‚ئپj‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@“؟گى•û‚ھ—L—ک‚ةگي‚¢‚ً‚·‚·‚كپAڈں—ک‚ً“¾‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پu‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پi= گVگàٹضƒ–Œ´‚جگي
پ@پ@‚¢پjپv‚إ‚حپAپ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚جŒ»ڈêژwٹِژز‚حپA“؟
پ@پ@گى‰ئچNپA•ں“‡گ³‘¥پA’r“c‹Pگ‚إ‚ ‚èپAپ@گ¼ŒR(•ٍ
پ@پ@چsڈO•ûپj‚جŒ»ڈêژwٹِژز‚حپA‰Fٹى‘½ڈG‰ئپAگخ“cژO
پ@پ@گ¬پA‘ه’J‹gŒpپA–ر—کڈGŒ³‚إ‚ ‚èپAپ@‚ـ‚½پAگ¼ŒR(•ٍ
پ@پ@چsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جڈ¬‘پگىڈGڈH‚حپA “ŒŒRپi“؟گى•ûپj
پ@پ@‚ةگQ•ش‚éپB
پ@
پ@
#thenewtheoryofsekigaharawar-thetraditionaltheory
پ@
پںپ@پu“`گàپiڈ]—ˆگàپj‚جٹضƒ–Œ´
پ@پ@پ@‚جگي‚¢پvپB
پ@
پ@
پ@پ@پ،پ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚حپAپu“ْ–{گي
پ@پ@ژjپvپ@پi–¾ژ،‚Q‚U”N‚ج‹Œ“ْ–{—¤ŒRژQ–d–{•”’کچىپj
پ@پ@‚جژ‘—؟‚ةٹî‚أ‚پAŒمگ¢‚ة•زڈW‚³‚ꂽپAٹضƒ–Œ´‚ج
پ@پ@گي‚¢‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پi’چˆسپjپ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚حپAŒم
پ@پ@گ¢‚ة‚آ‚‚ç‚êپA‘nچى‚ھ‘½‚پAگMœكگ«پi‚µ‚ٌ‚ز‚ه‚¤‚¹
پ@پ@‚¢پj‚ھ‚ ‚ـ‚è‚ب‚¢پBپ@پu•¨Œêپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv
پ@پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پ@پ،پ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚إ‚حپAپ@
پ@پ@پ@گخ“c•û‚جگ¼ŒR‚ج’†گSگl•¨‚حپAپ@
پ@پ@پ@گخ“cژOگ¬‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆê•ûپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ج’†گSگl•¨‚حپA
پ@پ@پ@“؟گى‰ئچN‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚جŒˆگي‚حپA
پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ ‚جŒك‘O‚Wژچ ‚©
پ@پ@پ@‚çŒكŒم‚Qژچ ‚ـ‚إ‚ج–ٌ‚Uژٹش‚جٹشپA”ü”Zچ‘‚ج
پ@پ@پ@ژهگيڈê‚جٹضƒ–Œ´–~’n‚إپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ئگخ“c
پ@پ@پ@•û‚جگ¼ŒR‚ئ‚جٹش‚إچs‚ي‚ꂽگي‚¢‚إ‚ ‚éپBپ@“؟گى
پ@پ@پ@•û‚ج“ŒŒR‚حپA‹êگي‚ً‚µ‚ؤپAڈں—ک‚ً“¾‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پ@پ،پ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚حپAچL‹`‚إ‚حپA
پ@پ@پ@ژٹْ‚ح‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚جپi“ŒŒR‚ج”ü”Z گشچâ
پ@پ@پ@•zگw‚جپj‚WŒژ‚Q‚U“ْچ ‚©‚ç‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ـ‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@پ@ڈêڈٹ‚ح”ü”Zچ‘‚جٹضƒ–Œ´–~’n‚ئٹضƒ–Œ´–~’n‚ج
پ@پ@پ@ژü•س’nˆو‚إ‚ ‚èپAپ@”ü”Zچ‘‚ةڈWŒ‹‚µ‚½پA“ŒŒRپE–ٌ
پ@پ@پ@‚V–œگlپAگ¼ŒRپE–ٌ‚W–œگl‚ج“Œگ¼—¼ŒRپE–ٌ‚P‚T–œگl
پ@پ@پ@‚ھگي‚¢پAپ@‚»‚جŒˆگي‚حپAژهگيڈê‚جٹضƒ–Œ´–~’n‚إ
پ@پ@پ@‚ ‚èپAپ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ‚جŒك‘O‚W
پ@پ@پ@ژچ ‚©‚çŒكŒم‚Qژچ ‚ـ‚إپAپ@“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ئگخ
پ@پ@پ@“c•û‚جگ¼ŒR‚ئ‚جٹش‚إچs‚ي‚ꂽپBپ@گي‚¢‚جŒ‹ ‰تپA
پ@پ@پ@“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ھڈں—ک‚ً“¾‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پ@پ،پ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚حپA‚P‚U‚O‚O”N
پ@پ@پ@پiŒc’·‚T”Nپj‚WŒژ‚Q‚U“ْچ ‚©‚ç‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ـ‚إپA”ü
پ@پ@پ@”Zچ‘پi‚ف‚ج‚ج‚‚ةپAŒ»پEٹٍ•ŒŒ§“ى•”‚ج‘ٹ“–’nˆوپj
پ@پ@پ@‚جٹضƒ–Œ´–~’n‚ئٹضƒ–Œ´–~’n‚جژü•س’nˆو‚إ پAپ@
پ@پ@پ@“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ئگخ“c•û‚جگ¼ŒR‚ئ‚جٹش‚إچs‚ي‚ê
پ@پ@پ@‚½گي‚¢‚إ‚ ‚éپBپ@Œ‹‰ت‚حپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ھڈں—ک
پ@پ@پ@‚ً“¾‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ،پ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚حپAپ@“؟گى•û‚ج
پ@پ@“ŒŒR‚ئگخ“c•û‚جگ¼ŒR‚ئ‚ج–Lگbژپ‰ئگbٹش‚ج“à•”چR
پ@پ@‘ˆ‚إ‚ ‚éپBپ@پ@Œ‹‰ت‚حپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ھپAڈں—ک‚ً
پ@پ@“¾‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
#thenewtheoryofsekigaharawar-byperson
پ@
پںپ@پu‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پi= گVگàٹضƒ–Œ´
پ@پ@پ@‚جگي‚¢پjپvپBپ@
پ@
پ@پ،پ@“؟گى‰ئچNپB
پ@
پ@پ@پ،پ@پu‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پi= گVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پjپv
پ@پ@‚إ‚حپAپ@“Œ•û‚©‚ç‚â‚ء‚ؤ—ˆ‚½پA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج“؟
پ@پ@گى‰ئچN‚حپA“؟گى–{‘à‚ئ‹¤‚ةپA‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj
پ@پ@‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ةپAپiٹضƒ–Œ´–~’n‚ج“چ”zژR‚ج–k“Œ•ûŒü
پ@پ@‚ة‚ ‚éپj”ü”Zگشچâپi‚ف‚ج‚ ‚©‚³‚©پj‚ئ‚¢‚¤ڈêڈٹ‚إ
پ@پ@•zگw‚µپAپ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج“ى‹{ژRپi‚ب‚ٌ
پ@پ@‚®‚¤‚³‚ٌپj“Œ‘¤‚ة•zگw‚·‚é–ر—کگ¨‚جŒR‚â‘هٹ_ڈé
پ@پ@âؤڈéڈOپi’“—¯ŒRپjپ@‚ئ‘خ›³‚µپAپ@‚»‚جŒمپA‚XŒژ‚P‚S“ْ
پ@پ@–é‚ةپAگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ً’ا‚ء‚ؤˆع“®‚µپA
پ@پ@‚XŒژ‚P‚T“ْ–é–¾‚¯‚ة“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج “؟گى‰ئچN‚ئپ@
پ@پ@“؟گى–{‘à‚حپAٹضƒ–Œ´’nگ¼“ى•”‚ة ˆع“®‚µ‚»‚±‚إگ¼
پ@پ@ŒR(•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج‘ه’JŒR‚ئ‘خ›³‚µگي‚¢ڈں—ک
پ@پ@‚ً“¾پAژں‚ةپAژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚ةˆع“®‚µپAگ¼ŒR(•ٍ
پ@پ@چsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جڈ¬گ¼پE‰Fٹى‘½پEگخ“cپE “‡’أگ¨“™
پ@پ@‚جŒR‚ئ‘خ›³‚µ‚»‚±‚إگي‚¢پAڈں—ک‚ً“¾‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@“؟گى‰ئچNپB
پ@
پ@پ@پ،پ@پu‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پi= گVگà‚جٹضƒ–Œ´‚جگي
پ@پ@‚¢پjپv‚إ‚حپAپ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ةپA
پ@پ@“Œ•û‚©‚ç‚â‚ء‚ؤ—ˆ‚½“؟گى‰ئچN‚حپA“؟گى–{‘à‚ئ‹¤
پ@پ@‚ةپAپiٹضƒ–Œ´‚ج“چ”zژR‚ج–k“Œ•ûŒü‚ة‚ ‚éپj”ü”Zگش
پ@پ@چâپi‚ف‚ج‚ ‚©‚³‚©پj ‚ئ‚¢‚¤ڈêڈٹ‚إ•zگw‚µپAپ@“ى‹{
پ@پ@ژRپi‚ب‚ٌ‚® ‚¤‚³‚ٌپj“Œ‘¤‚ة•zگw‚·‚é–ر—کگ¨‚جŒR
پ@پ@‚â‘هٹ_ڈéâؤڈéڈOپi’“—¯ŒRپj‚ئ‘خ›³ ‚·‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ–é‚ةپA‰ئچN‚ئ
پ@پ@“؟گى–{‘àپi–ٌ‚R–œ‚Q‚O‚O‚Oگlپj‚حپAپ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر
پ@پ@—ک•ûپj‚جژه—حŒR‚جٹضƒ–Œ´–~’nپEژR–¼•û–ت‚ض‚جˆع“®
پ@پ@‚جڈî•ٌ‚ً•·‚«‚آ‚¯پAپ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈO•ûپj‚ً’ا‚ء‚ؤپA
پ@پ@“؟گى•ûگوژèگ¨‚ج•ں“‡گ¨پi–ٌ‚P–œ‚X‚O‚O‚Oگlپj‚ئ‹¤‚ةپA
پ@پ@ٹضƒ–Œ´–~’nپEژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj•û–ت‚ضˆع“®‚µپA‚XŒژ
پ@پ@‚P‚T“ْ–é–¾‚¯‚ةٹضƒ–Œ´–~’n“ىگ¼•”‚ةˆع“®‚µپAٹضƒ–
پ@پ@Œ´گ¼“ى•”‚ة•zگw‚·‚éگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج‘ه
پ@پ@’J ŒRپi–ٌ‚P‚Q‚O‚Oگlپj‚ئ‘ک‹ِ‚µگي‚¢ڈں—ک‚ً“¾پAپ@‚»‚ج
پ@پ@ŒمپAژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚ةˆع“®‚µپAژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚ة
پ@پ@‚¢‚½گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جڈ¬گ¼پE‰Fٹى‘½پEگخ“cپE
پ@پ@“‡’أگ¨“™‚جŒRپi–ٌ‚R–œگlپj‚ئگي‚¢پAڈں—ک‚ً“¾‚éپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@‘ه’J‹gŒpپB
پ@
پ@پ@پ،پ@پu‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پi= گVگà‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پjپv
پ@پ@‚إ‚حپAپ@گ¼ŒR(•ٍچsڈO پE–ر—ک•ûپj‚ج‘ه’J‹gŒpپi‚¨‚¨‚½
پ@پ@‚ة‚و‚µ‚آ‚®پj ‚ئ‘ه’JŒRپi–ٌ‚P‚Q‚O‚Oگlپj‚حپA–k—¤•û–ت
پ@پ@‚©‚çˆع“®‚µ‚ؤ‚«‚ؤپA‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ
پ@پ@‚ج–é‚ةپAٹضƒ–Œ´–~’nگ¼“ى•”‚ة•zگw‚µ‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پuژR’†‚جگي‚¢پv‚جچ‡گي‚ج‘و‚P’iٹK‚ئ‚µ‚ؤپA ‚P‚U
پ@پ@‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ–é–¾‚¯‚ةپAپ@ٹضƒ–Œ´–~’n
پ@پ@“ىگ¼•”‚إپAپ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جگو•û‘à‚ج‘ه
پ@پ@’JŒR‚حپAپ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج“؟گى–{‘à‚جŒR‚ئگي‚¢پAپ@
پ@پ@چX‚ةڈ¼”ِژRژRک[‚©‚çˆع“®‚µ‚ؤ—ˆ‚½پA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj
پ@پ@‚ةگQ•ش‚ء‚½ڈ¬‘پگىŒR‚ئگي‚¢پAپ@‹²‚فŒ‚‚؟‚ة‚³‚ê‚ؤپA
پ@پ@‘ه’J‹gŒp‚حژ©ٹQپiژ©گnپj ‚µپA‘ه’JŒR‚حپA‘S–إ‚µ‚½پB
پ@پ@
پ@
پ@پ،پ@گخ“cژOگ¬پB
پ@
پ@پ@پ،پ@پu‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پi= گVگà‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پjپv
پ@پ@‚إ‚حپAگخ“cژOگ¬‚حپAپ@گ¼ŒRŒ‹گ¬پi‹“•؛پj‚جژٌ–dژز
پ@پ@‚إ‚ح‚ب‚پAپ@‰ئچN‚ئ—اچD‚بٹضŒW‚ة‚ ‚ء‚½‚ھپAپ@گ¼
پ@پ@ŒRپi•ٍچsڈO پE–ر—ک•ûپj‚ج‘ه’J‹gŒp‚جگà“¾‚إگ¼ŒR
پ@پ@‚ة‰ء‚ي‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@پuگVگà‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپv
پ@پ@‚إ‚حپAپ@گخ“cژOگ¬‚حپAپ@–LگbڈG‹g ‚جژ€ŒمپA“؟گى‰ئ
پ@پ@چN‚ئ‚ح—FچD‚بٹضŒW‚إ‚ ‚ء‚½‚ھپAپ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·
پ@پ@‚ج‚T”Nپj“V‰؛•ھ‚¯–ع‚جگي‚¢پ@پiٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پi‘هٹ_پE
پ@پ@ژR’†‚جگي‚¢پjپA‘¼‚جگي‚¢پj‚إ‚حپAپ@‘ه’J‹gŒp‚جگà
پ@پ@“¾‚إپAپ@ گ¼ŒRپi•ٍچsڈO پE–ر—ک•ûپj‚ة‰ء‚ي‚èپA”s‚ê‚ؤپA
پ@پ@•ك‚ـ‚èپAڈˆŒY‚³‚ê‚éپiژaژٌ‚³‚ê‚éپjپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@پuگVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚جŒˆگيژ‚ج
پ@پ@ پ@گخ“cژOگ¬‚ج“®‚«پBپ@
پ@
پ@پ@پ،پ@گ¼ŒR‚ج•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚جگخ“cژOگ¬‚حپA ‚P‚U
پ@پ@‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ج“ْ–vŒم‚ةپA‘هٹ_
پ@پ@ڈé‚©‚çڈo‚ؤپAˆب‘O‚©‚ç’z‚¢‚ؤ‚¨‚¢‚½پAژR’†پi‚â
پ@پ@‚ـ‚ب‚©پj•t‹ك‚ج“،‰؛پi‚ئ ‚¤‚°پAٹضƒ–Œ´–~’n‚جچù
پ@پ@”ِژR‚©‚ç“ى‚R‚‹‚چپj‚جژ©ٹQ•ُپi‚¶‚ھ‚¢‚ف‚ثپj‚ئ
پ@پ@‚¢‚¤ڈêڈٹ‚ةŒك‘O‚Sژچ پA•zگw‚µپAگخ“cژOگ¬‚حپA
پ@پ@‚»‚جŒمپA‘¼‚جگ¼ŒR‚جڈ”ڈ«‚ئچ‡—¬‚·‚邽‚كپA
پ@پ@ژ©ٹQ•ُ‚ج‚·‚®‹ك‚‚جژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚ةˆع“®‚µپA
پ@پ@‘هٹ_•t‹ك‚©‚çˆع“®‚µ‚ؤ‚‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢“ŒŒR
پ@پ@‚ج“؟گى•û‚ج“ŒŒRژه—حŒRپ@‚âپ@— گط‚é‚©‚à‚µ‚ê
پ@پ@‚ب‚¢ڈ¼”ِژRژRک[‚ة•zگw‚·‚éگ¼ŒRپi•ٍچsڈO•ûپj
پ@پ@‚جڈ¬‘پگىڈGڈH‚جŒR‚ة”ُ‚¦,پA‚»‚µ‚ؤپAگخ“cژO
پ@پ@گ¬‚حپAŒك‘O‚P‚Oژچ ‚©‚çگ³Œكچ ‚ـ‚إپAژR’†پi‚â
پ@پ@‚ـ‚ب‚©پj‚إپAگ¼ŒRژه—حŒR‚جˆê—ƒ‚ً’S‚¢پA‘هٹ_
پ@پ@•t‹ك‚©‚çˆع“®‚µ‚ؤ‚«‚½“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚ج“ŒŒR
پ@پ@ژه—حŒR‚ئŒˆگي‚ًچs‚¢پA”s–k‚·‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@گخ“cژOگ¬پB
پ@
پ@پ@پ،پ@پu‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پi= گVگà‚جٹضƒ–Œ´‚جگي
پ@پ@‚¢پjپv‚إ‚حپAپ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جگخ“cژOگ¬
پ@پ@‚حپA‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚WŒژ‚Q‚U“ْ‚©‚ç‚XŒژ‚P‚S“ْ
پ@پ@‚ـ‚إپAپ@‘هٹ_ڈé‚إâؤڈ邵پA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ئ‘هٹ_
پ@پ@ڈéچU–hگي‚ًچs‚¤پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج“ى‹{ژR‚ج‘هٹ_
پ@پ@ڈéŒم‹lŒR‚ج–ر—کگ¨‚ھ‚XŒژ‚P‚T“ْ ˆبŒم‚ة—\‘z‚³‚ê
پ@پ@‚é“ŒŒRپi“؟گى •ûپj‚©‚çچUŒ‚‚ًژَ‚¯”s–k‚·‚é‚ئگ¼
پ@پ@ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ھ’“—¯‚·‚é‘هٹ_ڈé‚ھŒا—§‚µ
پ@پ@•s—ک‚ة‚ب‚é‚ج‚إپAپ@گخ“cژOگ¬‚حپA‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ج“Œ
پ@پ@ŒRپi“؟گى•ûپj‚ة‚و‚éگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج“ى
پ@پ@‹{ژR•zگw‚ج–ر—کگ¨‚ض‚جچUŒ‚‚ة”ُ‚¦‚ؤپi‚جŒم‹l
پ@پ@‚ئ‚µ‚ؤپjپAپ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ج“ْ–v
پ@پ@ŒمپA‘هٹ_ڈé‚ًڈo‚ؤپAٹضƒ–Œ´–~’nپEژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj
پ@پ@•û–ت‚ضŒü‚¤پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@گخ“cژOگ¬‚حپA‚XŒژ‚P‚T “ْ‚جŒك‘Oژlژچ پA
پ@پ@ژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‹ك‚‚جپAپiٹضƒ–Œ´‚جچù”ِژR‚©‚ç
پ@پ@“ى‚R‚‹‚چ‚جپj“،‰؛پi‚ئ‚¤‚°پj‚ج پiˆب‘O‚و‚èگ®”ُ‚µ‚ؤ
پ@پ@‚¢‚½پjژ©ٹQ•ُپi‚¶‚ھ‚¢‚ف‚ثپj‚ئ‚¢‚¤ڈêڈٹ‚ة•zگw‚µپAپ@
پ@پ@گخ“cژOگ¬‚حپA‘هٹ_•t‹ك‚©‚ç—ˆ‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢
پ@پ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚جŒRپ@‚âپ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ةگQ•ش
پ@پ@‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢ڈ¼”ِژRژRک[‚ة•zگw‚·‚éگ¼ŒRپi•ٍ
پ@پ@چsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جڈ¬‘پگىڈGڈH‚جŒR‚ئ‘خ›³‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@گخ“cژOگ¬‚حپA‚·‚®‹ك‚‚جژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚ة
پ@پ@ˆع“®‚µپAپ@‚XŒژ‚P‚T“ْ‚جŒك‘O‚P‚Oژچ ‚©‚çگ³Œكچ ‚ـ
پ@پ@‚إپA پ@‘هٹ_•t‹ك‚©‚ç’ا‚ء‚ؤ—ˆ‚ؤژR’†‚ةŒ»‚ꂽ“Œ
پ@پ@ŒRپi“؟گى•ûپj‚ج“؟گى•ûگوژèگ¨‚ج•ں“‡گ¨‚â“؟گى–{
پ@پ@‘à“™‚جŒR‚ئگي‚¢پA”s–k‚·‚éپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@گخ“cژOگ¬پB
پ@
پ@پ@پ،پ@ˆêژںژj—؟‚ةٹî‚أ‚پuگVگà‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پi= ‘ه
پ@پ@ٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپvپi‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚WŒژ‚Q‚U
پ@پ@“ْپ[‚XŒژ‚P‚T“ْپj‚إ‚حپAپ@‚XŒژ‚P‚T“ْˆبŒم‚ةگ¼ŒRپi•ٍ
پ@پ@چsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج“ى‹{ژRپi‚ب‚ٌ‚®‚¤‚³‚ٌپj‚ج ‘هٹ_ڈé
پ@پ@Œم‹lŒR‚ج–ر—کگ¨‚ھ“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚©‚çچUŒ‚‚ًژَ
پ@پ@‚¯‚ؤ”s–k‚·‚é‚ئگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj ‚ج‹’“_‚ج
پ@پ@‘هٹ_ڈé‚ھŒا—§‚µ•s—ک‚ئ‚ب‚é‚ج‚إپAپ@‘هٹ_ڈé‚ة’“
پ@پ@—¯‚µ‚ؤ‚¢‚½گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جڈ¬گ¼پE‰Fٹى
پ@پ@‘½پEگخ “cپE“‡’أگ¨“™‚جŒR‚حپA‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj
پ@پ@‚XŒژ‚P‚T“ْˆبŒم‚ة—\‘z‚³‚ê‚é“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ة‚و‚é
پ@پ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj ‚ج“ى‹{ژR‚ج–ر—کگ¨‚ض‚ج
پ@پ@چUŒ‚‚ة”ُ‚¦‚ؤپi‚جŒم‹l‚ئ‚µ‚ؤپjپAپ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·
پ@پ@‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ج“ْ–vŒمپA‘هٹ_ڈé‚ًڈo‚ؤپAٹضƒ–Œ´
پ@پ@–~’nپEژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj•û–ت‚ضŒü‚¢پAپ@گ¼ŒRپi•ٍچs
پ@پ@ڈO•ûپj‚جڈ¬گ¼پE‰Fٹى‘½پEگخ “cپE“‡’أگ¨“™‚جŒR‚حپA
پ@پ@‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ج–¢–¾‚ةپA ژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj•t‹ك‚ة•z
پ@پ@گw‚µپAپ@‘هٹ_•t‹ك‚©‚ç—ˆ‚é‚©‚à ‚µ‚ê‚ب‚¢“ŒŒR
پ@پ@پi“؟گى•ûپj‚جŒRپ@‚âپ@ڈ¼”ِژRژRک[‚ة•zگw‚µ— گط
پ@پ@‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جڈ¬‘پگى
پ@پ@ڈGڈH‚جŒR‚ة”ُ‚¦‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈO پE–ر—ک•ûپj‚جڈ¬‘پگىڈGڈH‚حپA
پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ةپAڈ¼”ِژRژRک[
پ@پ@‚ة•zگw‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@گخ“cژOگ¬‚حپA ‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S
پ@پ@“ْ‚ج“ْ–vŒم‚ةپA‘هٹ_ڈé‚©‚çڈo‚ؤپAژR’†پi‚â‚ـ‚ب
پ@پ@‚©پj•t‹ك‚جپiٹضƒ–Œ´–~’n‚جچù”ِژR‚©‚ç“ى‚R‚‹‚چ‚ة
پ@پ@‚ ‚éپj“، ‰؛پi‚ئ‚¤‚°پj‚ج ژ©ٹQ•ُپi‚¶‚ھ‚¢‚ف‚ثپj‚ئ‚¢پ@
پ@پ@‚¤ڈêڈٹ‚ةپAŒك‘O‚Sژچ پA•zگw‚µپAگخ“cژOگ¬‚حپA
پ@پ@‘هٹ_•t‹ك‚©‚ç—ˆ‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج
پ@پ@ŒRپ@‚âپ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ةگQ•ش‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢ڈ¼”ِ
پ@پ@ژRژRک[‚ة•zگw‚·‚éگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جڈ¬‘پ
پ@پ@گىڈGڈH‚جŒR‚ئ‘خ›³‚·‚éپBپ@‚»‚جŒمپAگخ“cژOگ¬‚حپAپ@
پ@پ@‚·‚®‹ك‚‚جژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚ةˆع“®‚µپA‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ج
پ@پ@Œك‘O‚P‚Oژچ ‚©‚çگ³Œكچ ‚ـ‚إپA پ@‘هٹ_•t‹ك‚©‚ç’ا‚ء
پ@پ@‚ؤ—ˆ‚ؤژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚ةŒ»‚ꂽ“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج
پ@پ@“؟گى•ûگوژèگ¨‚ج•ں“‡گ¨‚â“؟گى–{‘à“™‚جŒR‚ئگي‚¢پA
پ@پ@”s–k‚·‚éپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@ڈ¬‘پگىڈGڈHپB
پ@پ@پ،پ@پu‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پi= گVگà‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پjپv
پ@پ@‚إ‚حپAپ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj ‚جڈ¬‘پگىڈGڈH‚حپA
پ@پ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ةگQ•ش‚éپBپ@
پ@
پ@پ@پ،پ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جڈ¬‘پگىڈGڈH‚حپAپ@‚P‚U
پ@پ@‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ةپAٹضƒ–Œ´–~’n‚ج“ى
پ@پ@گ¼•ûŒü‚جپAڈ¼”ِژRپi‚ـ‚آ‚¨‚â‚ـپj‚ة•zگw‚·‚éگ¼
پ@پ@ŒRپi•ٍ چsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جˆة“،گ·گ³پi‚¢‚ئ‚¤‚à‚è‚ـ
پ@پ@‚³پj‚ً’ا‚¢‚¾‚µپAڈ¼”ِژRژRک[‚ة•zگw‚·‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ج–é–¾‚¯‚ةپA
پ@پ@ٹضƒ–Œ´–~’n“ىگ¼•”‚إپA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج“؟گى–{‘à
پ@پ@‚ھپAگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj ‚ج‘ه’JŒR‚ًچUŒ‚‚µ‚ؤ‚¢
پ@پ@‚éژپAپ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جڈ¬‘پگىڈGڈH‚حپA
پ@پ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ةگQ•ش‚èپA‘ه’JŒR‚ًچUŒ‚‚µپA‹²‚فŒ‚
پ@پ@‚؟‚ة‚µ‚ؤپA‘ه’JŒR‚ً‘S–إ‚³‚¹‚éپB
پ@
پ@
#thenewtheoryofsekigaharawar-oogakibattle
پ@
پ@
پںپ@‘هٹ_‚جگي‚¢پB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@‘هٹ_‚جگي‚¢‚جڈêڈٹپ@پFپ@”ü”Zچ‘‚ج‘هٹ_پi‚¨‚¨‚ھ‚« پj
پ@پ@پ@‚ج•t‹ك پi”ü”ZگشچâپA‘هٹ_ڈéپA“ى‹{ژRپi‚ب‚ٌ‚®‚¤‚³
پ@پ@پ@‚ٌپj“Œ‘¤‚ج•t‹كپjپB
پ@پ@پ@‘هٹ_‚جگي‚¢‚جژٹْپ@پFپ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj ‚WŒژ
پ@پ@پ@‚Q‚U“ْپ`‚XŒژ‚P‚T“ْپB
پ@
پ@پ@پœپ@پi‚rپjپ@پu‘هٹ_‚جگي‚¢‚جگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژQ‰ءŒRپv‚حپA
پ@پ@‡@پ@‘هٹ_ڈéâؤڈéڈOپi’“—¯ŒRپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi ‚WŒژ‚Q‚U“ْپ`‚XŒژ‚P‚S“ْپF–ٌ‚R–œ‚R‚T‚O‚OگlپA
پ@پ@پ@پ@پ@ڈ¬گ¼پE‰Fٹى‘½پEگخ“cپE“‡’أگ¨“™‚جŒRپE–ٌ‚R–œگlپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‚âپ@•ںŒ´پEŒF’JپEٹ_Œ©پEڈHŒژپE‘ٹ—ا“™‚جŒRپE–ٌ
پ@پ@پ@پ@پ@‚R‚T‚O‚OگlپAپ@‚XŒژ‚P‚T“ْپF–ٌ‚R‚T‚O‚Oگl‚ج‚فپA
پ@پ@پ@پ@پ@•ںŒ´پEŒF’JپEٹ_Œ©پEڈHŒژپE‘ٹ—ا“™‚جژc—¯ŒRپjپ@پ@پ@پ@پ@
پ@پ@‡Aپ@“ى‹{ژR‚ج–ر—کگ¨‚جŒRپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚XŒژ‚V“ْپ`‚XŒژ‚P‚T“ْپA–ٌ‚P–œ ‚R‚O‚O‚OگlپA–ر—ک
پ@پ@پ@پ@پ@ڈGŒ³پE‹gگىپEˆہچ‘ژ›پE’·‘©پE’·ڈ@‰ن•”“™‚جŒRپj
پ@پ@‚جŒv–ٌ‚S–œ‚U‚T‚O‚Oگl‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پœپ@پi‚sپjپ@پu‘هٹ_‚جگي‚¢‚ج“ŒŒRپi“؟گى•ûپjژQ‰ءŒRپv‚حپA
پ@پ@‡@پ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج“؟گى•ûگوژèگ¨‚ج•ں“‡گ¨‚ج ŒR
پ@پ@پ@پ@ پi‚WŒژ‚Q‚U“ْپ`‚XŒژ‚P‚S“ْپA–ٌ‚P–œ‚X‚O‚O‚OگlپA
پ@پ@پ@پ@پ@•ں“‡پEچ•“cپEچ×گىپE“،“°پE“›ˆنپE“c’†پE‰ء“،
پ@پ@پ@پ@پ@‰أ–¾پE‹‹ةچ‚’m“™‚جŒRپj
پ@پ@‡Aپ@“؟گى•ûگوژèگ¨‚ج’r“cگ¨‚جŒR پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi ‚WŒژ‚Q‚U“ْپ`‚XŒژ‚P‚T“ْپA–ٌ‚Q–œ‚P‚O‚O‚OگlپA
پ@پ@پ@پ@پ@ ’r“cپEژR“àپE–x”ِپE—L”nپEڈ¼‰؛پEگَ–ىچK’·“™
پ@پ@پ@پ@پ@‚جŒRپj پA
پ@پ@‡Bپ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج“؟گى–{‘àپ@
پi‚XŒژ‚P‚S“ْپA–ٌ‚R–œ‚Q‚O‚O‚OگlپA“؟گى‰ئچNپAˆنˆة
پ@پ@پ@پ@پ@’¼گپA–{‘½’‰ڈںپA‰ئچN”n‰ô‚èڈO“™‚جŒRپj
پ@پ@‚جŒv–ٌ‚V‚Q‚O‚O‚Oگl‚إ‚ ‚éپBپ@پ@
پ@
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚ةپA”ü”Zگشچâپi‚ف‚ج‚ ‚©
پ@پ@پ@‚³‚©پjƒGƒٹƒA‚ة‚حپAٹù‚ةپA“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚جگوژèگ¨پi–L
پ@پ@پ@گb‰¶Œع‚ج‘ه–¼پj–ٌ‚S–œگl‚ج•؛‚ھ‚¢‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ةپA“؟گى‰ئچN‚ج
پ@پ@پ@—¦‚¢‚é“ŒŒR‚ج“؟گى–{‘àپE–ٌ‚R–œ‚Q‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ھ”ü”Z
پ@پ@پ@گشچâƒGƒٹƒA‚ة“’…‚µ‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ةپA“ى‹{ژRپi‚ب‚ٌ
پ@پ@پ@‚®‚¤‚³‚ٌپj‚ة•zگw‚µپA–ٌ‚P–œ‚R‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ً—¦‚¢‚é–ر
پ@پ@پ@—کڈGŒ³پi‚à‚¤‚è‚ذ‚إ‚à‚ئپj‚حپA”ü”ZگشچâƒGƒٹƒA‚ة‚¢‚éپA
پ@پ@پ@“؟گى•û‚جگوژèگ¨پE–ٌ‚S–œگlپi•ں“‡گ¨پE–ٌ‚P–œ‚X‚O‚O‚O
پ@پ@پ@گl‚ئ’r“cگ¨پE–ٌ‚Q–œ‚P‚O‚O‚Oگlپj‚ئ“؟گى–{‘àپE–ٌ‚R–œ
پ@پ@پ@‚Q‚O‚O‚Oگl‚ج“ŒŒR‚جŒv–ٌ‚V–œ‚Q‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ًپA“ى‹{
پ@پ@پ@ژR‚©‚猩‚½پBپ@‚»‚µ‚ؤپAگ¼ŒR‚ج–ر—کڈGŒ³‚حپA“ى‹{ژR
پ@پ@پ@‚جگw‚و‚èپA–ىگي‚ة‹‚¢پA“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚ج‘هŒR‚ًŒ©
پ@پ@پ@‚ؤپA“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚ئگي‚¤‚ج‚ًçSçOپi‚؟‚م‚¤‚؟‚هپj‚µ‚½پA
پ@پ@پ@‘¦‚؟پA‹—ح‚ب“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚ج‘هŒR‚ًŒ©‚ؤپAڈں‚؟–ع
پ@پ@پ@‚ھ‚ب‚¢‚ئ‚ف‚ؤپAگ¼•û‚©‚ç‚جگ¼ŒR‚ج‰‡ŒR‚ج“’…‚ً‘ز
پ@پ@پ@‚؟پAگي‚¢‚ً”ً‚¯‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@چX‚ةپA‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ‚àپAگ¼ŒR
پ@پ@پ@‚ج–ر—کڈGŒ³‚حپAپ@“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚ئگي‚¤‚ج‚ًçSçOپi‚؟
پ@پ@پ@‚م‚¤‚؟‚هپj‚µ‚½پB
‘هٹ_ڈéپi‚¨‚¨‚ھ‚«‚¶‚ه‚¤پj‚ًڈo‚½•ٍچsڈOپE –ر—ک•û
پ@پ@پ@‚جگ¼ŒR‚جژه—حŒRپE–ٌ‚R–œگl‚ج•؛‚حپAپ@“ى‹{ژR•zگw‚ج
پ@پ@پ@–ر—کŒR‚جŒم‹lپi‚²‚¸‚كپj‚ئ‚µ‚ؤپAگ¼•û‚جژR’†پi‚â‚ـ‚ب
پ@پ@پ@‚©پj‚ة•zگw‚µپA“Œ•û‚ج“ى‹{ژR•zگw‚جگ¼ŒR‚ج–ر—کڈGŒ³
پ@پ@پ@‚ج–ٌ‚P–œ‚R‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ئ‹¦—ح‚µپAٹضƒ–Œ´–~’n‚âژR’†
پ@پ@پ@‚ةڈo‚ؤ‚«‚½“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚جژه—حŒRپE–ٌ‚T‚PپC‚O‚O‚Oگl
پ@پ@پ@‚ج•؛پ@پi“؟گى–{‘àپE–ٌ‚R–œ‚Q‚O‚O‚Oگl‚ئ•ں“‡گ¨پE–ٌ‚P–œ
پ@پ@پ@‚X‚O‚O‚Oگlپj‚ً‹²‚فŒ‚‚؟‚ة‚µ‚و‚¤‚ئچl‚¦‚ؤ‚¢‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚µ‚©‚µپA‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ةپA“Œ•û
پ@پ@پ@‚ج“ى‹{ژR•zگw‚جگ¼ŒR‚ج–ر—کڈGŒ³‚حپA“®‚©‚¸پAگي‚¢
پ@پ@پ@‚ًگأٹد‚µ‚½پBپ@‚±‚ج‚½‚كپA•ٍچsڈOپE –ر—ک•û‚جگ¼ŒR‚ج
پ@پ@پ@ژه—حŒRپE–ٌ‚R–œگl‚ج•؛‚حپAژR’†‚إپAˆê•û“I‚ةچU‚ك‚ç
پ@پ@پ@‚êپA‘چ•ِ‚ê‚ئ‚ب‚èپA‚»‚جŒ‹‰تپA•ٍچsڈOپE –ر—ک•û‚جگ¼
پ@پ@پ@ŒR‚حپAگVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢‚جŒˆگي‚جپuژR’†‚جگي‚¢پv‚إپA
پ@پ@پ@”s–k‚µ‚½پB
پ@
پ@
پ@پ@پœپ@پq‘و‚P’iٹKپrپ@
پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚WŒژ‚Q‚U“ْ‚©‚ç‚XŒژ‚P‚R“ْ‚ـ‚إپAپ@
پ@پ@”ü”Zچ‘‚ج‘هٹ_ڈéژü•س‚إپA
پ@پ@پi‚rپjپ@گ¼ŒR(•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جپA‘هٹ_ڈéâؤڈéڈO
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi’“—¯ŒRپjپi–ٌ‚R–œ‚R‚T‚O‚Oگlپjپ@‚âپ@“ى‹{ژR
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج–ر—کگ¨‚جŒRپi–ٌ‚P–œ‚R‚O‚O‚OگlپA‚XŒژ‚V“ْ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ`‚P‚R“ْپj
پ@پ@‚ئپA
پ@پ@پi‚sپjپ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚جپA“؟گى•ûگوژèگ¨‚ج•ں“‡گ¨
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جŒRپi–ٌ‚P–œ‚X‚O‚O‚Oگlپjپ@‚âپ@“؟گى•ûگوژè
پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ¨‚ج’r“cگ¨‚جŒR پi–ٌ‚Q–œ‚P‚O‚O‚Oگlپj
پ@پ@‚ئ‚ھ‘خ›³‚µگي‚¤پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@Œ‹‰تپA‘هٹ_ڈéچU–hگي‚إ‘هٹ_ڈé‚ح—ژڈ邹‚¸پB
پ@
پ@پ@پœپ@پq‘و‚Q’iٹKپrپ@
پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ج’‹ٹش‚ةپA
پ@پ@”ü”Zچ‘‚ج“ى‹{ژR“Œ‘¤‚â‘هٹ_ڈéژü•س‚إپA
پ@پ@پi‚rپjپ@گ¼ŒR(•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جپA ‘هٹ_ڈéâؤڈéڈO
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi’“—¯ŒRپjپi–ٌ‚R–œ‚R‚T‚O‚Oگlپjپ@‚âپ@“ى‹{ژR
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج–ر—کگ¨‚جŒRپi–ٌ‚P–œ‚R‚O‚O‚Oگlپj
پ@پ@‚ئپAپ@
پ@پ@پi‚sپjپ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚جپA“؟گى–{‘àپi–ٌ‚R–œ‚Q‚O‚O‚O
پ@پ@پ@پ@پ@گlپjپ@‚âپ@“؟گى•ûگوژèگ¨‚ج•ں“‡گ¨‚جŒRپi–ٌ
پ@پ@پ@پ@پ@‚P–œ‚X‚O‚O‚OگlپjپA“؟گى•ûگوژèگ¨‚ج’r“cگ¨ ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@ŒR پi–ٌ‚Q–œ‚P‚O‚O‚Oگlپjپ@
پ@پ@‚ئ‚ھ‘خ›³‚·‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@Œ‹‰تپAپ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج“ى‹{ژR•z
پ@پ@گw‚ج–ر—کگ¨پi–ٌ‚P–œ‚R‚O‚O‚Oگlپj‚حپA ‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ج
پ@پ@’‹ٹشپA“ŒŒRپi“؟گى•ûپjچ‡ŒvپE–ٌ‚V–œ‚Q‚O‚O‚Oگl‚ج‘ه
پ@پ@ŒR‚ة‹°‚ê‚ً‚ب‚µ‚ؤگي‚ي‚¸پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@ˆê•ûپAپ@گ¼ŒR(•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚حپA‚XŒژ‚P‚T
پ@پ@“ْˆبŒم‚ج“ى‹{ژR‚ج–ر—کگ¨چUŒ‚‚ة”ُ‚¦‚ؤپ@پi“ى‹{
پ@پ@ژR•zگw‚ج–ر—کگ¨‚ھ”s‘ق‚·‚ê‚خگ¼ŒR‚ج‘هٹ_ڈé‚ھ
پ@پ@Œا—§‚µ•s—ک‚ئ‚ب‚é‚ج‚إپA“ى‹{ژR‚ج–ر—کگ¨‚جŒم‹l
پ@پ@ŒRپiŒم‰‡ŒRپj‚ئ‚µ‚ؤپjپAپ@گ¼ŒR(•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج
پ@پ@‘هٹ_ڈéâؤڈéڈOپi’“—¯ŒRپjپi–ٌ‚R–œ‚R‚T‚O‚Oگlپj‚حپAپ@
پ@پ@‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ج“ْ–vŒمپA‘هٹ_ڈé‚ةژc—¯چف”شڈO•”‘à
پ@پ@پi–ٌ‚R‚T‚O‚Oگlپj‚ًژc‚µ‚ؤپA ‘هٹ_ڈé‚ًڈo‚ؤپAٹضƒ–Œ´
پ@پ@–~’nپEژR’†•û–ت‚ضŒü‚¤پBپ@‚»‚ê‚ً’m‚ء‚½“ŒŒRپi“؟
پ@پ@گى•ûپj‚حپA‚XŒژ‚P‚S“ْ–éپAپ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj
پ@پ@‚جڈ¬گ¼پE‰Fٹى‘½پEگخ “cپE“‡’أگ¨“™‚جŒRپi–ٌ‚R–œگlپj
پ@پ@‚جژه—حŒR‚ً’اŒ‚‚·‚邽‚كپAپ@“؟گى•ûگوژèگ¨‚ج’r
پ@پ@“cگ¨‚ج ŒRپi–ٌ‚Q–œ‚P‚O‚O‚Oگlپj‚ً‘هٹ_•t‹ك‚ةژc‚µ‚ؤپAپ@
پ@پ@“؟گى–{‘àپi–ٌ‚R–œ‚Q‚O‚O‚Oگlپj‚ئ“؟گى•ûگوژèگ¨‚ج
پ@پ@•ں“‡گ¨‚جŒRپi–ٌ ‚P–œ‚X‚O‚O‚Oگlپj‚جژه—حŒR‚ھپAٹضƒ–
پ@پ@Œ´–~’nپEژR’†•û–ت‚ضŒü‚¤پB
پ@
پ@پ@پœپ@پq‘و‚R’iٹKپrپ@
پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ةپA
پ@پ@”ü”Zچ‘‚ج“ى‹{ژR“Œ‘¤‚â‘هٹ_ڈéژü•س‚إپA
پ@پ@پi‚rپjپ@گ¼ŒR(•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جپA“ى‹{ژR ‚ج–ر—کگ¨
پ@پ@پ@پ@پ@‚جŒRپi–ٌ‚P–œ‚R‚O‚O‚Oگlپjپ@‚âپ@‘هٹ_ڈéژc—¯گ¨
پ@پ@پ@پ@پ@پi–ٌ‚R‚T‚O‚Oگlپj
پ@پ@‚ئپAپ@
پ@پ@پi‚sپjپ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج“؟گى•ûگوژèگ¨‚ج’r“cگ¨‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒR پi–ٌ‚Q–œ‚P‚O‚O‚Oگlپjپ@
پ@پ@‚ئ‚ھ‘خ›³‚·‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@Œ‹‰تپAپ@ژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚جگي‚¢‚إ‚جگ¼ŒRپi•ٍ
پ@پ@چsڈO•ûپj‚ج”s–k‚ً’m‚èپA گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج
پ@پ@“ى‹{ژR‚ج–ر—کگ¨‚حگيڈê‚ً—£’E‚µپi’اŒ‚‚³‚êپjپA
پ@پ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ھڈں—ک‚ً“¾‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@ˆê•ûپA‘هٹ_ڈéژc—¯گ¨پ@پi–ٌ‚R‚T‚O‚OگlپA•ںŒ´پEŒF
پ@پ@’JپEٹ_Œ©پEڈHŒژپE‘ٹ—ا“™‚جŒRپj‚حپAگي‚¢‚ً‘±‚¯‚éپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@پuگVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚ئپu‘هٹ_‚جگي‚¢پvپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@گVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢‚إ‚حپAپ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj
پ@پ@پ@‚XŒژ‚ةپA”ü”Zگشچâپi‚ف‚ج‚ ‚©‚³‚©پjƒGƒٹƒA‚ة‚حپA
پ@پ@پ@ٹù‚ةپA“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚جگوژèگ¨پi–Lگb‰¶Œع‚ج‘ه–¼پj
پ@پ@پ@–ٌ‚S–œگl‚ج•؛‚ھ‚¢‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ةپA“؟گى‰ئچN‚ج
پ@پ@پ@—¦‚¢‚é“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚ج“؟گى–{‘àپE–ٌ‚R–œ‚Q‚O‚O‚Oگl
پ@پ@پ@‚ج•؛‚ھ”ü”ZگشچâƒGƒٹƒA‚ة“’…‚µ‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ةپA“ى‹{ژRپi‚ب‚ٌ
پ@پ@پ@‚®‚¤‚³‚ٌپj‚ة•zگw‚µپA–ٌ‚P–œ‚R‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ً—¦‚¢‚é
پ@پ@پ@گ¼ŒR‚ج•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚ج–ر—کڈGŒ³پi‚à‚¤‚è‚ذ‚إ‚à‚ئپj
پ@پ@پ@‚حپA”ü”ZگشچâƒGƒٹƒA‚ة‚¢‚éپA“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚جگوژè
پ@پ@پ@گ¨پE–ٌ‚S–œگl‚ج•؛پi•ں“‡گ¨پE–ٌ‚P–œ‚X‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ئ
پ@پ@پ@’r“cگ¨پE–ٌ‚Q–œ‚P‚O‚O‚Oگl‚ج•؛پjپ@‚ئپ@“ŒŒR‚ج“؟گى•û
پ@پ@پ@‚ج“؟گى–{‘àپE–ٌ‚R–œ‚Q‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ج“ŒŒR‚ج“؟گى•ûپE
پ@پ@پ@Œv–ٌ‚V–œ‚Q‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ًپA“ى‹{ژR‚©‚猩‚½پBپ@
پ@پ@پ@‚»‚µ‚ؤپAگ¼ŒR‚ج•ٍچsڈOپE–ر—ک•û ‚ج–ر—کڈGŒ³‚حپA“ى
پ@پ@پ@‹{ژR‚جگw‚و‚èپA–ىگي‚ة‹‚¢“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚ج‘هŒR
پ@پ@پ@‚ًŒ©‚ؤپAگ¼•û‚©‚ç‚جگ¼ŒR‚ج‰‡ŒR‚ً‘ز‚آ‚±‚ئ‚ة‚µپA
پ@پ@پ@“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚ئگي‚¢‚ً”ً‚¯پA“®‚©‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@چX‚ةپA‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ‚àپA–ٌ
پ@پ@پ@‚P–œ‚R‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ً—¦‚¢‚é“ى‹{ژR•zگw‚جگ¼ŒR‚ج
پ@پ@پ@•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚ج–ر—کڈGŒ³‚حپAپ@“؟گى•û‚جگوژè
پ@پ@پ@گ¨‚ج’r“cگ¨پE–ٌ‚Q–œ‚P‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ھ“ى‹{ژR‚ج‘O
پ@پ@پ@–ت‚ةژc—¯‚µپAچs‚ژè‚ً‘j‚فپAگ¼ŒR‚جژه—حŒRپE–ٌ‚R
پ@پ@پ@–œگl‚ج•؛‚ج‰‡ŒR‚ة‹ى‚¯‚آ‚¯‚ç‚ꂸپAپ@ٹضƒ–Œ´–~
پ@پ@پ@’nپEژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj•û–ت‚ةڈoگw‚µ‚½“ŒŒR‚ج“؟گى
پ@پ@پ@•û‚جژه—حŒRپE–ٌ‚T–œ‚P‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ً‹²‚فŒ‚‚؟‚ة
پ@پ@پ@‚إ‚«‚ب‚©‚ء‚½پB
‘هٹ_ڈéپi‚¨‚¨‚ھ‚«‚¶‚ه‚¤پj‚ًڈo‚½گ¼ŒR‚ج•ٍچs
پ@پ@پ@ڈOپE –ر—ک•û‚جژه—حŒRپE–ٌ‚R–œگl‚ج•؛‚حپAپ@“ى‹{
پ@پ@پ@ژR•zگw‚ج –ر—کŒR‚جŒم‹lپi‚²‚¸‚كپj‚ئ‚µ‚ؤپAگ¼•û‚ج
پ@پ@پ@ژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚ة•zگw‚µپA“Œ•û‚ج“ى‹{ژR•zگw‚ج
پ@پ@پ@گ¼ŒR‚ج–ر—کڈGŒ³‚ج–ٌ‚P–œ‚R‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ئ‹¦—ح‚µپA
پ@پ@پ@ٹضƒ–Œ´–~’n‚âژR’†‚ةڈo‚ؤ‚«‚½“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚ج
پ@پ@پ@ژه—حŒRپE–ٌ‚T–œ‚P‚O‚O‚Oگl‚ج•؛پ@پi“؟گى–{‘àپE–ٌ‚R
پ@پ@پ@–œ‚Q‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ئ•ں“‡گ¨پE–ٌ‚P–œ‚X‚O‚O‚Oگl‚ج•؛پj
پ@پ@پ@‚ً‹²‚فŒ‚‚؟‚ة‚µ‚و‚¤‚ئچl‚¦‚ؤ‚¢‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚µ‚©‚µپA‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ةپA
پ@پ@پ@“Œ•û‚ج“ى‹{ژR•zگw‚جگ¼ŒR‚ج–ر—کڈGŒ³‚حپA “ŒŒR
پ@پ@پ@‚ج“؟گى•û‚جگوژèگ¨‚ج’r“cگ¨‚ةچs‚ژè‚ً‘jپi‚ح‚خپj
پ@پ@پ@‚ـ‚ê‚ؤپA“®‚¯‚ب‚©‚ء‚½پBپ@‚±‚ج‚½‚كپAگ¼ŒR‚ج•ٍچs
پ@پ@پ@ڈOپE –ر—ک•û‚ج“ى‹{ژR‚ج–ر—کڈGŒ³‚ج‰‡ŒR‚à‚ب‚پA
پ@پ@پ@گ¼ŒR‚ج•ٍچsگlڈOپE–ر—ک•û‚جژه—حŒRپE–ٌ‚R–œ ‚ج•؛
پ@پ@پ@‚حپAژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚إ‚جŒˆگي‚إپAˆê•û“I‚ةچU‚ك
پ@پ@پ@‚ç‚êپA‘چ•ِ‚ê‚ئ‚ب‚èپA‚»‚جŒ‹‰تپAگ¼ŒR‚ج•ٍچsڈOپE
پ@پ@پ@–ر—ک•û‚ج ژه—حŒR‚حپAپ@“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚جژه—حŒR‚ة
پ@پ@پ@”s–k‚µ‚½پB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@پu‘هٹ_‚جگي‚¢پvپB
پ@پ@پ،پ@پu‘هٹ_‚جگي‚¢پ@پi‚¨‚¨‚ھ‚«‚ج‚½‚½‚©‚¢پjپv‚ئ‚حپAپ@
پ@پ@”ü”Zچ‘پ@پi‚ف‚ج‚ج‚‚ةپAŒ»پEٹٍ•ŒŒ§“ى•”‚ج‘ٹ“–’n
پ@پ@ˆوپj‚ج‘هٹ_پi‚¨‚¨‚ھ‚«پj•t‹كپ@پi”ü”ZگشچâپA‘هٹ_ڈéپA
پ@پ@“ى‹{ژR“Œ‘¤‚ج•t‹كپj‚إپAپ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj
پ@پ@‚WŒژ‚Q‚U“ْ‚©‚ç‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ـ‚إپAپ@“؟گى•û‚ج“ŒŒRپ@‚ئ
پ@پ@•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚جگ¼ŒRپ@‚ئ‚جٹش‚إچs‚ي‚ꂽچ‡گي‚إ
پ@پ@‚ ‚éپBپ@گي‚¢‚جŒ‹‰تپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ھڈں—ک‚ً“¾‚é پB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@‘هٹ_‚جگي‚¢پB
پ@
پ@پ@پ،پ@پu‘هٹ_‚جگي‚¢پv‚إ‚حپAپ@‘وˆê’iٹK‚ئ‚µ‚ؤپA‘هٹ_
پ@پ@ڈé‚جچU–hگي‚إپA‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚WŒژ‚Q‚U“ْ‚©
پ@پ@‚ç‚XŒژ‚P‚R“ْ‚ـ‚إپA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج“؟گى•ûگوژè
پ@پ@گ¨‚ج•ں“‡گ¨پA’r“cگ¨‚ج–Lگb‰¶Œع‘ه–¼‚جŒR پi–ٌ
پ@پ@‚S–œگlپj‚ئگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج‘هٹ_ ڈéچف—¯
پ@پ@ŒR‚ئ‚جٹش‚إ‘هٹ_ڈéچU–hگي‚ھگي‚ي‚êپAپ@‚P‚U‚O‚O”N
پ@پ@پiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ ‚V“ْ‚ة“ى‹{ ژRپi‚ب‚ٌ‚®‚¤‚³‚ٌپj‚ة
پ@پ@‘هٹ_ڈéŒم‹lŒR‚جگ¼ŒRپi•ٍچsڈO•ûپj‚ج–ر—کگ¨‚ھ•z
پ@پ@گw‚·‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‘و‚Q’iٹK‚ئ‚µ‚ؤپAگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج
پ@پ@‘هٹ_ڈéŒم‹lŒR‚ج–ر —کگ¨‚ًچ~ژQ‚³‚¹گ¼ŒRپi•ٍچs
پ@پ@ڈOپE–ر—ک•ûپj‹’“_‚ج‘هٹ_ڈé‚ًŒا—§‚³‚¹‚邽‚كپAپ@
پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ةپA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj
پ@پ@‚ج“؟گى‰ئچN‚حپA“Œ•û ‚©‚ç—ˆ‚ؤ”ü”Zگشچâپi‚ف‚ج‚ ‚©
پ@پ@‚³‚©پj•t‹ك‚ة•zگw‚µپAگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج–ر
پ@پ@—کگ¨‚â‘هٹ_ڈéâؤڈéڈOپi’“—¯ŒRپj‚ئ‘خ›³‚µپAپ@گ¼ŒR
پ@پ@پi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج“ى‹{ژR‚ج‘هٹ_ڈéŒم‹lŒR‚ج
پ@پ@–ر—کگ¨‚حپA‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ةپA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج‘هŒR‚ً
پ@پ@‹°‚ê‚ؤگي‚ي‚¸پA‘¦‚؟پA‹—ح‚ب“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚ج‘ه
پ@پ@ŒR‚ًŒ©‚ؤپAڈں‚؟–ع‚ھ‚ب‚¢‚ئ‚ف‚ؤپAگ¼•û‚©‚ç‚جگ¼ŒR
پ@پ@‚ج‰‡ŒR‚ج“’…‚ً‘ز‚؟پAگي‚¢‚ً”ً‚¯‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‘و‚R’iٹK‚ئ‚µ‚ؤپA‚»‚جŒمپAگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک
پ@پ@•ûپj‚ج“ى‹{ژR‚ج–ر—کگ¨‚حپA‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ةپAگيڈê‚ً—£
پ@پ@’E‚µپi’اŒ‚‚³‚êپjپA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚حڈں—ک‚ً“¾‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@‘هٹ_‚جگي‚¢پB
پ@پ@پ،پ@‘هٹ_پi‚¨‚¨‚ھ‚« پj‚جگي‚¢‚إ‚حپAپ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc
پ@پ@’·‚T”Nپj‚WŒژ‚Q‚U“ْچ ‚©‚çپA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج“؟گى•û
پ@پ@گوژèگ¨‚ج•ں“‡گ¨پA’r“cگ¨‚ج–Lگb‰¶Œع‘ه–¼‚جŒR
پ@پ@‚حپA”ü”Zگشچâپi‚ف‚ج‚ ‚©‚³‚©پj•t‹ك‚ة•zگw‚µپA
پ@پ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج‹’“_‚ج‘هٹ_ڈéپi‚¨‚¨‚ھ
پ@پ@‚«‚¶‚ه‚¤پj‚ضŒü‚¢پAگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج‘هٹ_
پ@پ@ڈéâؤڈéڈOپi’“—¯ŒRپj‚ض‚جچU–hگي‚ھٹJژn‚³‚ê‚éپBپ@
پ@پ@‚»‚جŒمپA‘هٹ_ڈé‚جگ¼•û‚ة‚ ‚é“ى‹{ژRپi‚ب‚ٌ‚®‚¤
پ@پ@‚³‚ٌپj“Œ‘¤‚ة‚XŒژ‚V“ْ‚و‚è•zگw‚·‚é‘هٹ_ڈéŒم‹lŒR
پ@پ@‚ج–ٌ‚P–œ‚R‚O‚O‚Oگl‚جگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج
پ@پ@–ر—ک گ¨‚ًچU‚كچ~•ڑ‚³‚¹‘هٹ_ڈé‚ًŒا—§‚³‚¹‚邽
پ@پ@‚كپA‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ ‚ج’‹ٹش‚ةپA
پ@پ@“Œ•û‚©‚ç—ˆ‚ؤ”ü”Zگشچâ‚ة“ü‚ء‚½“ŒŒRپi“؟گى•ûپj
پ@پ@‚ج“؟گى‰ئچN—¦‚¢‚é–ٌ‚R–œ‚Q‚O‚O‚Oگl‚ج“؟گى–{‘à پ@
پ@پ@پiˆنˆة’¼گپA–{‘½’‰ڈںپA‰ئچN”n‰ô‚è ڈO“™‚جŒRپjپ@
پ@پ@‚حپAپ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج“؟گى•ûگوژèگ¨‚ج•ں“‡گ¨پE
پ@پ@’r“cگ¨پiŒvپE–ٌ‚S–œگlپj‚ئ‹¤‚ةپAپ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE
پ@پ@–ر—ک•ûپj‚ج–ر—کگ¨‚جŒR پi–ٌ‚P–œ‚R‚O‚O‚Oگlپj‚â‘ه
پ@پ@ٹ_ڈéâؤڈéڈOپi’“—¯ŒRپjپi–ٌ‚R–œ‚R‚T‚O‚Oگlپjپ@‚ئ‘خ
پ@پ@›³‚·‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚µ‚©‚µپA‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ج’‹ٹشپAگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE
پ@پ@–ر—ک•ûپj‚ج“ى‹{ژR“Œ‘¤•zگw‚ج–ر—کگ¨‚جŒRپi–ٌ‚P
پ@پ@–œ‚R‚O‚O‚Oگlپj‚حپAپ@‘هٹ_•t‹ك‚ة‚¢‚é“ŒŒRپi“؟گى•ûپj
پ@پ@‚ج‘هŒRپEŒv–ٌ‚V–œ‚Q‚O‚O‚Oگl‚ة‹°‚ê‚ً‚ب‚µگي‚ي‚¸ پA
پ@پ@‘¦‚؟پA–ر—کڈGŒ³‚حپA‹—ح‚ب“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚ج‘هŒR
پ@پ@پEŒv–ٌ‚V–œ‚Q‚O‚O‚Oگl‚ً“ى‹{ژR‚و‚茩‚ؤپAڈں‚؟–ع‚ھ
پ@پ@‚ب‚¢‚ئ‚ف‚ؤپAگ¼•û‚©‚ç‚جگ¼ŒR‚ج‰‡ŒR‚ج“’…‚ً‘ز
پ@پ@‚؟پAگأٹد‚µپAگي‚¢‚ً”ً‚¯‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@ˆê•ûپAپ@گ¼ŒR‚جڈ¬گ¼پE‰Fٹى‘½پEگخ“cپE “‡’أ
پ@پ@گ¨ ‚ب‚ا‚جŒRپi–ٌ‚R–œگlپj‚ھ‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ج“ْ–vŒم
پ@پ@‚ةپA‘هٹ_ڈé‚ًڈo‚ؤٹضƒ–Œ´–~’nپEژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj
پ@پ@•û–ت‚ة“]گiپiˆع“®پj‚µ‚½‚±‚ئ‚ً“ŒŒRپi“؟گى•û پj ‚ح
پ@پ@’m‚èپAپ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚حپAپ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک
پ@پ@•ûپj‚ج“ى‹{ژR‚ج–ر—کگ¨‚â‘هٹ_ڈéژc—¯گ¨‚ة‘خ›³
پ@پ@‚³‚¹‚邽‚كپA“؟گى•ûگوژèگ¨‚ج’r“cگ¨پi–ٌ‚Q–œ
پ@پ@‚P‚O‚O‚Oگlپj‚ً“ى‹{ژR“Œ‘¤‚ةژc‚µپAپ@‚XŒژ‚P‚S“ْ–éپA
پ@پ@‘هٹ_•t‹ك‚ج“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج“؟گى–{‘à‚â“؟گى•û
پ@پ@گوژèگ¨‚ج•ں“‡ گ¨“™‚جŒR‚حپAپ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر
پ@پ@—ک•ûپj‚ً’ا‚ء‚ؤپi’اŒ‚‚·‚邽‚كپjپAٹضƒ–Œ´–~’nپEژR
پ@پ@’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj•û–ت‚ضˆع“®‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ةپAژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚جگي‚¢‚إ‚ج
پ@پ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚جڈں—کپEگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج
پ@پ@”sگي‚ً’m‚èپAپ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج “ى‹{ژR‚ج
پ@پ@–ر—کگ¨‚جŒR‚حپAگيڈê‚ً—£’E‚·‚éپ@پi‚»‚µ‚ؤپA’اŒ‚‚³
پ@پ@‚ê‚éپjپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@‘هٹ_‚جگي‚¢پB
پ@
پ@پ@پ،پ@پu‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پi= گVگà‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پjپv
پ@پ@‚ج‚P‚آ‚جپAپu‘هٹ_‚جگي‚¢پv‚إ‚حپA پ@چ‡گي‚ج‘و‚P’iٹK‚ئ
پ@پ@‚µ‚ؤپA‘هٹ_ڈé‚جچU–hگي‚إپA‚P‚U‚O‚O”NپiŒc ’·‚T”Nپj
پ@پ@‚WŒژ‚Q‚U“ْ‚©‚ç ‚XŒژ‚P‚R“ْ‚ـ‚إپA “ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج
پ@پ@“؟گى•ûگوژèگ¨‚ج•ں“‡گ¨پE’r“cگ¨‚ج–Lگb‰¶Œع‘ه
پ@پ@–¼‚جŒRپi–ٌ‚S–œگlپj‚حپAپ@”ü”Zگشچâپi‚ف‚ج‚ ‚©‚³
پ@پ@‚©پj•t‹ك‚ة•zگw‚µپAگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج‹’
پ@پ@“_‚ج‘هٹ_ڈéپi‚¨‚¨‚ھ‚«‚¶‚ه‚¤پj‚ج‘هٹ_ڈéâؤڈéڈO
پ@پ@پi’“—¯ŒRپjپi–ٌ‚R–œ‚R‚T‚O‚Oگlپj‚ًچU‚كپA‘هٹ_ڈé‚جچU
پ@پ@–hگي‚ًچs‚¤‚ھپA ‘هٹ_ڈé‚ح—ژڈ邹‚¸پBپ@ˆê•ûپA
پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚V“ْ‚ةپA“ى‹{ژRپi‚ب‚ٌ‚®
پ@پ@‚¤‚³‚ٌپj‚ةپAگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج‘هٹ_ڈé Œم
پ@پ@‹lŒR‚ج–ر—کگ¨پi–ٌ‚P–œ‚R‚O‚O‚Oگlپj‚ھ•zگw‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پu‘هٹ_‚جگي‚¢پv‚إ‚حپA”ü”Zچ‘پi‚ف‚ج‚ج‚‚ةپA
پ@پ@Œ»پEٹٍ•ŒŒ§“ى•”‚ج‘ٹ“–’nˆوپj‚إپAپ@–Lگb‰¶Œع‚ج
پ@پ@“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚جڈ”ڈ«‚حپAپ@ٹٍ•ŒڈéچU—ھپE—ژڈé
پ@پ@ŒمپAپ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج”ü”Z‚ج–{‹’’n‚ج
پ@پ@‘هٹ_ڈéپi‚¨‚¨‚ھ‚«‚¶‚ه‚¤پj‚ة‹ك‚¢”ü”Zگشچâپi‚ف‚ج
پ@پ@‚ ‚©‚³‚©پj•t‹ك‚ة•zگw‚µپA‘هٹ_ڈéچU–hگي‚ًچs‚ءپ@
پ@پ@‚ؤ‚¢‚½‚ھپA‚XŒژ‚V“ْ‚ة‘هٹ_ڈé‚جگ¼•û‚ج“ى‹{ژR
پ@پ@پi‚ب‚ٌ‚®‚¤‚³‚ٌپj‚ة‘هٹ_ڈéŒم‹l•”‘à‚ج–ر—کگ¨پi–ٌ
پ@پ@‚P–œ‚R‚O‚O‚Oگlپj‚ھ•zگw‚µپA‚»‚êˆبŒمˆ³—ح‚ًژَ‚¯پA
پ@پ@‘چ‘هڈ«‚ج“؟گى‰ئچN‚ئ“؟گى–{‘àپi–ٌ‚R–œ‚Q‚O‚O‚Oگlپj
پ@پ@‚ج“’…‚ً‘ز‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ‡گي‚ج‘و‚Q’iٹK‚ئ‚µ‚ؤپAگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک
پ@پ@•ûپj‚ج‘هٹ_ڈéŒم‹lŒR‚ج–ر—کگ¨پi–ٌ‚P–œ‚R‚O‚O‚Oگlپj‚ً
پ@پ@چ~ژQ‚³‚¹‘هٹ_ڈé‚ًŒا—§‚³‚¹‚邽‚كپAپ@‚P‚U‚O‚O”N
پ@پ@پiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ةپA“Œ•û‚©‚ç—ˆ‚½“ŒŒRپi“؟
پ@پ@گى•ûپj‚ج“؟گى‰ئچN‚حپA“؟گى–{‘àپi–ٌ‚R–œ‚Q‚O‚O‚OگlپA
پ@پ@ˆنˆة’¼گپE–{‘½’‰ڈںپE‰ئچN”n‰ô‚èڈO“™‚جŒRپj‚ئ‹¤
پ@پ@‚ةپA”ü”Zگشچâپi‚ف‚ج‚ ‚©‚³‚©پj•t‹ك‚ة•zگw‚µپAپ@
پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ ‚ج’‹ٹش‚ةپA“ŒŒR
پ@پ@پi“؟گى•ûپj‚ج“؟ گى‰ئچN‚ئ“؟گى–{‘àپi–ٌ‚R–œ‚Q‚O‚O‚O
پ@پ@گlپjپ@‚âپ@“؟گى•ûگوژèگ¨‚ج•ں“‡گ¨پE’r“cگ¨ پi–ٌ‚S
پ@پ@–œگlپj‚حپAپ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج“ى‹{ژR‚ج
پ@پ@‘هٹ_ڈéŒم‹lŒR‚ج–ر—کگ¨پi–ٌ‚P–œ‚R‚O‚O‚Oگlپjپ@‚âپ@
پ@پ@‘هٹ_ڈéâؤڈéڈOپi’“—¯ŒRپjپi–ٌ‚R–œ‚R‚T‚O‚Oگlپjپ@‚ئ‘خ
پ@پ@›³‚µپAپ@‚XŒژ‚P‚T “ْˆبچ~‚ةپAپ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚حپA
پ@پ@“ى‹{ژR‚ج–ر—ک گ¨‚â‘هٹ_ڈéâؤڈéڈO‚ج’“—¯ŒR‚ً
پ@پ@‘چچUŒ‚‚·‚é—\’è‚إ‚ ‚ء‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚µ‚©‚µپA‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ج’‹ٹشپA“ى‹{ژR ‚جگ¼ŒR
پ@پ@پi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج“ى‹{ژR“Œ‘¤•zگw‚ج–ر—کگ¨
پ@پ@‚جŒRپi–ٌ‚P–œ‚R‚O‚O‚Oگlپj‚حپAپ@‘هٹ_•t‹ك‚ة‚¢‚é“Œ
پ@پ@ŒRپi“؟گى•ûپj‚ج‘هŒRپEŒv–ٌ‚V–œ‚Q‚O‚O‚Oگl‚ة‹°‚ê‚ً
پ@پ@‚ب‚µگي‚ي‚¸پA‘¦‚؟پA‹—ح‚ب“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚ج‘هŒR
پ@پ@‚ًŒ©‚ؤپAڈں‚؟–ع‚ھ‚ب‚¢‚ئ‚ف‚ؤپAگ¼•û‚©‚ç‚جگ¼ŒR
پ@پ@‚ج‰‡ŒR‚ج“’…‚ً‘ز‚؟پAگي‚¢‚ً”ً‚¯‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆê•ûپA‚XŒژ‚P‚T“ْˆبچ~‚ة—\‘z‚³‚ê‚é“ŒŒR
پ@پ@پi“؟گى•ûپj‚ة‚و‚éگ¼ŒR(•ٍچsڈO•ûپj‚ج“ى‹{ژR‚ج–ر
پ@پ@—کگ¨چUŒ‚‚ة”ُ‚¦‚ؤپA‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ةپA“ْ–vŒمپA–ر—ک
پ@پ@گ¨Œم‹lŒRپiŒم‰‡ŒRپj‚ئ‚µ‚ؤپAگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک
پ@پ@•ûپj‚ج‘هٹ_ڈéâؤڈéڈOپi’“—¯ŒRپj‚جڈ¬گ¼پE‰Fٹى‘½پE
پ@پ@گخ“cپE“‡’أگ¨“™‚جŒRپi–ٌ‚R–œگlپj‚حپAپ@‘هٹ_ڈé‚ة
پ@پ@ژc—¯گ¨پi–ٌ‚R‚T‚O‚Oگlپj‚ًژc‚µ‚ؤپAپ@‘هٹ_ڈé‚ًڈo‚ؤ پA
پ@پ@ٹضƒ–Œ´–~’nپEژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj•û–ت‚ض“]گi ‚·‚é
پ@پ@پiˆع“®‚·‚éپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‚»‚جŒمپAچ‡گي‚ج‘و‚R’iٹK‚ئ‚µ‚ؤپA‚P‚U‚O‚O”N
پ@پ@پiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ةپAژR’† پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚جگي
پ@پ@‚¢‚إ‚جگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج”s–k‚ً’m‚èپAپ@
پ@پ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج“ى‹{ژR‚ج–ر—کگ¨‚حگي
پ@پ@ڈê‚ً—£’E‚µ پi’اŒ‚‚³‚êپjپA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚حڈں—ک‚ً
پ@پ@“¾‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‚ـ‚½پA‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ‚جژR’†
پ@پ@پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚جگي‚¢‚إ“Œگ¼—¼ŒR‚جگي‚¢‚جگ¼ŒRپi•ٍ
پ@پ@چsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج”s–k‚جگ–گ¨‚ھŒˆ‚µ‚½Œم‚àپA پ@گ¼
پ@پ@ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج•ںŒ´پE ٹ_Œ©پEŒF’JپEڈHŒژپE
پ@پ@‘ٹ—ا‚ج‘هٹ_ڈéژc—¯ گ¨پi–ٌ‚R‚T‚O‚Oگlپj‚حپAگي‚¢‚ً
پ@پ@‘±‚¯پA گQ•ش‚è‚àڈo‚ؤپAچإŒم‚ةپA‚XŒژ‚Q‚R“ْ‚ةپA“ŒŒR
پ@پ@پi“؟گى•ûپj‚ةچ~•ڑ‚µپA‘هٹ_ڈé‚حٹJڈé‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@گي‚¢‚جŒ‹‰تپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ھڈں—ک‚ً“¾پA
پ@پ@پ@•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚جگ¼ŒR‚ھ”s–k‚·‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
#thenewtheoryofsekigaharawar-yamanakabattle
پ@
پںپ@ژR’†‚جگي‚¢پB
پ@
پ@پ@پ،پ@ژR’†‚جگي‚¢‚جژٹْپ@پFپ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj
پ@پ@‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ج–é–¾‚¯پ`گ³Œكچ پB
پ@پ@ژR’†‚جگي‚¢‚جڈêڈٹپ@پFپ@”ü”Zچ‘‚جژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj
پ@پ@•t‹كپ@پiٹضƒ–Œ´–~’nگ¼“ى•”پAژR’†‚ج•t‹كپj پB
پ@
پ@پ@پœپ@پi‚rپjپ@پuژR’†‚جگي‚¢‚جگ¼ŒRپi•ٍچsڈO•ûپjژQ‰ءŒRپv‚حپA
پ@پ@‡@پ@ٹضƒ–Œ´–~’n“ىگ¼•”•zگw‚جگو•û‘à‚ج‘ه’JŒR
پ@پ@پ@پ@ پi–ٌ‚P‚Q‚O‚OگlپjپA
پ@پ@‡Bپ@ژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj•t‹ك‚ة•zگw‚µپAژR’†‚ةˆع“®
پ@پ@پ@پ@پ@‚µ‚ؤگي‚ء‚½ڈ¬گ¼پE‰Fٹى‘½پEگخ “cپE“‡’أگ¨“™‚جŒR
پ@پ@پ@پ@ پi–ٌ‚R–œگlپj
پ@پ@‚جŒv–ٌ‚R–œ‚P‚Q‚O‚Oگl‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پœپ@پi‚sپjپ@پuژR’†‚جگي‚¢‚ج“ŒŒRپi“؟گى•ûپjژQ‰ءŒRپv‚حپA
پ@پ@‡@پ@ٹضƒ–Œ´–~’nگ¼“ى•”پAژں‚ةژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj ‚ة
پ@پ@پ@پ@ ˆع“®‚µ‚ؤگي‚ء‚½“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج“؟گى–{‘à
پ@پ@پ@پ@پi–ٌ‚R–œ‚Q‚O‚O‚OگlپA“؟گى‰ئچNپAˆنˆة’¼گپA
پ@پ@پ@پ@پ@–{‘½’‰ڈںپA‰ئچN”n‰ô‚èڈO“™‚جŒRپjپA
پ@پ@‡Aپ@ڈ¼”ِژRژRک[‚ة•zگw‚µپAگ¼ŒR‚©‚ç“ŒŒR‚ةگQ•ش‚èپA
پ@پ@پ@پ@پ@ٹضƒ–Œ´–~’n“ىگ¼•”‚ةˆع“®‚µگي‚ء‚½ڈ¬‘پگىŒR
پ@پ@پ@پ@پi–ٌ‚W‚O‚O‚OگlپjپA
پ@پ@‡Bپ@ژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚ةˆع“®‚µ‚ؤگي‚ء‚½“ŒŒRپi“؟گى
•ûپj‚ج“؟گى•ûگوژèگ¨‚ج•ں“‡گ¨‚جŒRپi–ٌ‚P–œ
پ@پ@پ@پ@‚X‚O‚O‚OگlپA•ں“‡پEچ•“cپEچ×گىپE“،“°پE“›ˆنپE“c’†پE
پ@پ@پ@پ@‰ء“،‰أ–¾پE‹‹ةچ‚’m“™‚جŒRپj
پ@پ@‚جŒv–ٌ‚T–œ‚X‚O‚O‚Oگl‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@
پ@پ@پœپ@پq‘و‚P’iٹKپrپ@
پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ج–é–¾‚¯پAپ@
پ@پ@”ü”Zچ‘‚جٹضƒ–Œ´–~’n گ¼“ى•”‚إپA
پ@پ@پi‚rپjپ@گ¼ŒR(•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جگو•û‘à‚ج‘ه’JŒR
پ@پ@پ@پ@پ@پi–ٌ‚P‚Q‚O‚Oگlپj
پ@پ@‚ئپAپ@
پ@پ@پi‚sپjپ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج“؟گى–{‘àپi–ٌ‚R–œ‚Q‚O‚O‚O
پ@پ@پ@پ@پ@گlپjپ@‚âپ@‚±‚جژ“ŒŒR‚ةگQ•ش‚ء‚½گ¼ŒR(•ٍچs
پ@پ@پ@پ@پ@ڈOپE–ر—ک•ûپj‚جڈ¬‘پگىŒRپi–ٌ‚W‚O‚O‚Oگlپj
پ@پ@‚ئ‚ھ‘خ›³‚µپAگي‚¤پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@Œ‹‰تپAپ@گ¼ŒR(•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج‘ه’JŒR‚ح
پ@پ@‘S–إ‚µپAپ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚حڈں—ک‚ً“¾‚éپB
پ@
پ@پ@پœپ@پq‘و‚Q’iٹKپrپ@
پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ‚جŒك‘O‚P‚Oژچ ‚©‚ç
پ@پ@گ³Œكچ ‚ـ‚إپAپ@
پ@پ@”ü”Zچ‘‚جژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚إپA
پ@پ@پi‚rپjپ@گ¼ŒR(•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جڈ¬گ¼پE‰Fٹى‘½پEگخ“cپE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@“‡’أگ¨“™‚جŒRپi–ٌ‚R–œگlپj
پ@پ@‚ئپAپ@
پ@پ@پi‚sپjپ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج“؟گى•ûگوژèگ¨‚ج•ں“‡گ¨‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@ŒRپi–ٌ‚P–œ‚X‚O‚O‚Oگlپj‚â“؟گى–{‘àپi–ٌ‚R–œ‚Q‚O‚O‚O
پ@پ@پ@پ@پ@گlپj
پ@پ@‚ئ‚ھ‘خ›³‚µپAگي‚¤پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@Œ‹‰تپAپ@گ¼ŒR(•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚حپA‘چ•ِ‚ê‚ئ‚ب
پ@پ@‚è”s‘–‚µپA”s–k‚µپA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ھڈں—ک‚ً“¾‚éپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@پuگVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚ئپu‘هٹ_‚جگي‚¢پvپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@گVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢‚إ‚حپAپ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj
پ@پ@پ@‚XŒژ‚ةپA”ü”Zگشچâپi‚ف‚ج‚ ‚©‚³‚©پjƒGƒٹƒA‚ة‚حپA
پ@پ@پ@ٹù‚ةپA“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚جگوژèگ¨پi–Lگb‰¶Œع‚ج‘ه–¼پj
پ@پ@پ@–ٌ‚S–œگl‚ج•؛‚ھ‚¢‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ةپA“؟گى‰ئچN‚ج
پ@پ@پ@—¦‚¢‚é“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚ج“؟گى–{‘àپE–ٌ‚R–œ‚Q‚O‚O‚Oگl
پ@پ@پ@‚ج•؛‚ھ”ü”ZگشچâƒGƒٹƒA‚ة“’…‚µ‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ةپA“ى‹{ژRپi‚ب‚ٌ
پ@پ@پ@‚®‚¤‚³‚ٌپj‚ة•zگw‚µپA–ٌ‚P–œ‚R‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ً—¦‚¢‚é
پ@پ@پ@گ¼ŒR‚ج•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚ج–ر—کڈGŒ³پi‚à‚¤‚è‚ذ‚إ‚à‚ئپj
پ@پ@پ@‚حپA”ü”ZگشچâƒGƒٹƒA‚ة‚¢‚éپA“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚جگوژè
پ@پ@پ@گ¨پE–ٌ‚S–œگl‚ج•؛پi•ں“‡گ¨پE–ٌ‚P–œ‚X‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ئ
پ@پ@پ@’r“cگ¨پE–ٌ‚Q–œ‚P‚O‚O‚Oگl‚ج•؛پjپ@‚ئپ@“ŒŒR‚ج“؟گى•û
پ@پ@پ@‚ج“؟گى–{‘àپE–ٌ‚R–œ‚Q‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ج“ŒŒR‚ج“؟گى•ûپE
پ@پ@پ@Œv–ٌ‚V–œ‚Q‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ًپA“ى‹{ژR‚©‚猩‚½پBپ@
پ@پ@پ@‚»‚µ‚ؤپAگ¼ŒR‚ج•ٍچsڈOپE–ر—ک•û ‚ج–ر—کڈGŒ³‚حپA“ى
پ@پ@پ@‹{ژR‚جگw‚و‚èپA–ىگي‚ة‹‚¢“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚ج‘هŒR
پ@پ@پ@‚ًŒ©‚ؤپAگ¼•û‚©‚ç‚جگ¼ŒR‚ج‰‡ŒR‚ً‘ز‚آ‚±‚ئ‚ة‚µپA
پ@پ@پ@“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚ئگي‚¢‚ً”ً‚¯پA“®‚©‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@چX‚ةپA‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ‚àپA–ٌ
پ@پ@پ@‚P–œ‚R‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ً—¦‚¢‚é“ى‹{ژR•zگw‚جگ¼ŒR‚ج
پ@پ@پ@•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚ج–ر—کڈGŒ³‚حپAپ@“؟گى•û‚جگوژè
پ@پ@پ@گ¨‚ج’r“cگ¨پE–ٌ‚Q–œ‚P‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ھ“ى‹{ژR‚ج‘O
پ@پ@پ@–ت‚ةژc—¯‚µپAچs‚ژè‚ً‘j‚فپAگ¼ŒR‚جژه—حŒRپE–ٌ‚R
پ@پ@پ@–œگl‚ج•؛‚ج‰‡ŒR‚ة‹ى‚¯‚آ‚¯‚ç‚ꂸپAپ@ٹضƒ–Œ´–~
پ@پ@پ@’nپEژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj•û–ت‚ةڈoگw‚µ‚½“ŒŒR‚ج“؟گى
پ@پ@پ@•û‚جژه—حŒRپE–ٌ‚T–œ‚P‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ً‹²‚فŒ‚‚؟‚ة
پ@پ@پ@‚إ‚«‚ب‚©‚ء‚½پB
‘هٹ_ڈéپi‚¨‚¨‚ھ‚«‚¶‚ه‚¤پj‚ًڈo‚½گ¼ŒR‚ج•ٍچs
پ@پ@پ@ڈOپE –ر—ک•û‚جژه—حŒRپE–ٌ‚R–œگl‚ج•؛‚حپAپ@“ى‹{
پ@پ@پ@ژR•zگw‚ج –ر—کŒR‚جŒم‹lپi‚²‚¸‚كپj‚ئ‚µ‚ؤپAگ¼•û‚ج
پ@پ@پ@ژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚ة•zگw‚µپA“Œ•û‚ج“ى‹{ژR•zگw‚ج
پ@پ@پ@گ¼ŒR‚ج–ر—کڈGŒ³‚ج–ٌ‚P–œ‚R‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ئ‹¦—ح‚µپA
پ@پ@پ@ٹضƒ–Œ´–~’n‚âژR’†‚ةڈo‚ؤ‚«‚½“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚ج
پ@پ@پ@ژه—حŒRپE–ٌ‚T–œ‚P‚O‚O‚Oگl‚ج•؛پ@پi“؟گى–{‘àپE–ٌ‚R
پ@پ@پ@–œ‚Q‚O‚O‚Oگl‚ج•؛‚ئ•ں“‡گ¨پE–ٌ‚P–œ‚X‚O‚O‚Oگl‚ج•؛پj
پ@پ@پ@‚ً‹²‚فŒ‚‚؟‚ة‚µ‚و‚¤‚ئچl‚¦‚ؤ‚¢‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚µ‚©‚µپA‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ةپA
پ@پ@پ@“Œ•û‚ج“ى‹{ژR•zگw‚جگ¼ŒR‚ج–ر—کڈGŒ³‚حپA “ŒŒR
پ@پ@پ@‚ج“؟گى•û‚جگوژèگ¨‚ج’r“cگ¨‚ةچs‚ژè‚ً‘jپi‚ح‚خپj
پ@پ@پ@‚ـ‚ê‚ؤپA“®‚¯‚ب‚©‚ء‚½پBپ@‚±‚ج‚½‚كپAگ¼ŒR‚ج•ٍچs
پ@پ@پ@ڈOپE –ر—ک•û‚ج“ى‹{ژR‚ج–ر—کڈGŒ³‚ج‰‡ŒR‚à‚ب‚پA
پ@پ@پ@گ¼ŒR‚ج•ٍچsگlڈOپE–ر—ک•û‚جژه—حŒRپE–ٌ‚R–œ ‚ج•؛
پ@پ@پ@‚حپAژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚إ‚جŒˆگي‚إپAˆê•û“I‚ةچU‚ك
پ@پ@پ@‚ç‚êپA‘چ•ِ‚ê‚ئ‚ب‚èپA‚»‚جŒ‹‰تپAگ¼ŒR‚ج•ٍچsڈOپE
پ@پ@پ@–ر—ک•û‚ج ژه—حŒR‚حپAپ@“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚جژه—حŒR‚ة
پ@پ@پ@”s–k‚µ‚½پB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@پuگVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚ئپuژR’†‚جگي‚¢پvپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@گVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢‚جپuژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پjگي‚¢پv‚إ‚حپAپ@
پ@پ@پ@‘و‚P’iٹK‚إ‚حپA‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ ‚P‚T“ْ‚ج–é
پ@پ@پ@–¾‚¯‚ةپAٹضƒ–Œ´–~’n“ىگ¼•”‚ة•zگw‚·‚éگ¼ŒR‚ج•ٍ
پ@پ@پ@چsڈOپE–ر—ک•û‚جگو•û‘àپE‘ه’J‹gŒpŒR‚ًپA‘هٹ_•t‹ك
پ@پ@پ@‚©‚çˆع“®‚µ‚ؤ—ˆ‚½“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚ج“؟گى–{‘à‚ئڈ¼
پ@پ@پ@”ِژRک[•zگw‚جگ¼ŒR‚ج•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚إ“ŒŒRگQ•ش
پ@پ@پ@‚è‚جڈ¬‘پگىڈGڈHپi‚±‚خ‚â‚©‚ي‚ذ‚إ‚ ‚«پj‚جŒR‚ھ‹²
پ@پ@پ@‚فŒ‚‚؟‚ة‚µ‚ؤ‘S–إ‚³‚¹پAپ@‚»‚جŒمپA‘و‚Q’iٹK‚إ‚حپA
پ@پ@پ@‚XŒژ‚P‚T“ْ‚جŒك‘O‚P‚Oژچ ‚و‚èپA‘هٹ_•t‹ك‚©‚ç—ˆ‚½
پ@پ@پ@“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚جپAگوژèڈOپE•ں“‡گ¨‚ئ“؟گى–{‘à‚ج
پ@پ@پ@“ŒŒRژه—حŒR‚ھپAژR’†‘؛‚ة•zگw‚·‚é‰Fٹى‘½ڈG‰ئپA
پ@پ@پ@گخ“c ژOگ¬“™‚ج—¦‚¢‚éگ¼ŒRژه—حŒR‚ئŒˆگي‚ًچs‚¢پA
پ@پ@پ@گ³Œكچ ‚ةگ¼ŒRژه—حŒR‚ھ‘چ•ِ‚ê‚ئ‚ب‚èپAپ@گ¼ŒR‚ج
پ@پ@پ@•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚جژه—حŒR‚حپAچإڈI“I‚ةپA“؟گى‰ئ
پ@پ@پ@چN‚ج—¦‚¢‚é“ŒŒR‚ج“؟گى•û‚جژه—حŒR‚ة”s–k‚µ‚½پB
پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@پuژR’†‚جگي‚¢پvپB
پ@
پ@پ@پ،پ@پuژR’†‚جگي‚¢پi ‚â‚ـ‚ب‚©‚ج‚½‚½‚©‚¢پjپvپ@‚ئ‚حپA
پ@پ@”ü”Zچ‘پ@پi‚ف‚ج‚ج‚‚ةپAŒ»پEٹٍ•ŒŒ§“ى•”‚ج‘ٹ“–’n
پ@پ@ˆوپj‚جژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj•t‹كپ@پiٹضƒ–Œ´–~’nگ¼“ى•”پA
پ@پ@ژR’†‚ج•t‹كپj‚إپA‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj ‚XŒژ‚P‚T“ْ
پ@پ@‚ج–é–¾‚¯‚©‚çگ³Œكچ ‚ـ‚إپAپ@“؟گى•û‚ج“ŒŒRپ@‚ئپ@
پ@پ@•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚جگ¼ŒRپ@‚ئ‚جٹش‚إچs‚ي‚ꂽچ‡گي
پ@پ@‚إ‚ ‚éپBپ@گي‚¢‚جŒ‹‰تپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ھڈں—ک‚ً
پ@پ@“¾‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@پuگVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپv‚جپA
پ@پ@پuژR’†‚جگي‚¢پv‚جپAژهگيڈê‚حپA ”ü”Zچ‘پi‚ف‚ج‚ج‚
پ@پ@‚ةپAŒ»پEٹٍ•ŒŒ§“ى•”‘ٹ“–’nˆوپj‚جپAٹضƒ–Œ´–~’n‚إ
پ@پ@‚ح‚ب‚پAپ@ٹضƒ–Œ´–~’n‚ج“ىگ¼ •ûŒüپE–ٌ‚Q‚‹‚چ‚ة‚
پ@پ@‚é”ü”Zچ‘‚جژR’†پi‚â‚ـ ‚ب‚©پj‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@
پ@
پ@پ،پ@پuژR’†‚جگي‚¢پvپB
پ@
پ@پ@پ،پ@پu‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پi= گVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پjپv
پ@پ@‚ج‚P‚آ‚جپuژR’†‚جگي‚¢پv‚حپAپ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj
پ@پ@‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ةپAپ@ ”ü”Zچ‘‚جپAٹضƒ–Œ´–~’nگ¼“ى•”پ@پ@
پ@پ@‚âپ@ٹضƒ–Œ´–~’n‚ج“ىگ¼•ûŒüپE–ٌ‚Q‚‹‚چ‚ة‚ ‚é
پ@پ@”ü”Zچ‘پEژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚إپAپ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE
پ@پ@–ر—ک•ûپj‚جڈ¬گ¼پE‰Fٹى‘½پEگخ“cپE“‡’أگ¨“™‚جŒRپ@
پ@پ@‚â‘ه’JŒRپ@‚ئپAپ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج“؟گى•ûگوژè
پ@پ@گ¨‚ج•ں“‡گ¨پA “؟گى–{‘àپAپiگ¼ŒR‚©‚ç“ŒŒR‚ةگQ
پ@پ@•ش‚ء‚½پjڈ¬‘پگىŒR‚ب‚ا‚جŒRپ@‚ھگي‚ء‚½چ‡گي‚إ‚
پ@پ@‚èپA پ@گي‚¢‚جŒ‹‰تپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ھڈں—ک‚ً“¾پA
پ@پ@•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚جگ¼ŒR‚ھ”s–k‚·‚éپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@پuژR’†‚جگي‚¢پvپB
پ@
پ@پ@پ،پ@پuژR’†‚جگي‚¢پv‚إ‚حپAپ@‘وˆê’iٹK‚ئ‚µ‚ؤپAٹضƒ–
پ@پ@Œ´–~’n“ىگ¼•”‚إپA‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ
پ@پ@‚ج–é–¾‚¯‚ةپAپ@ٹضƒ–Œ´–~’nگ¼“ى•”‚إپA“ŒŒRپi“؟
پ@پ@گى•ûپj‚ج “؟گى–{‘à‚âپiگ¼ŒR‚©‚ç“ŒŒR‚ضگQ•ش‚ء
پ@پ@‚½پjڈ¬‘پگىŒRپ@‚ئپAپ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج
پ@پ@‘ه’JŒR‚ئ‚جٹش‚إگي‚ي‚êپAپ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک
پ@پ@•ûپj‚ج‘ه’JŒR‚ھ‘S–إ‚µ‚½پBپ@
پ@
پ@پ@پ،پ@پuژR’†‚جگي‚¢پv‚إ‚حپAپ@‘و‚Q’iٹK‚ئ‚µ‚ؤپA
پ@پ@ٹض‚ھŒ´–~’n‚ج“ىگ¼•ûŒüپE–ٌ‚Q‚‹‚چ‚ة‚ ‚éژهگيڈê
پ@پ@‚جژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚إپA‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj ‚XŒژ
پ@پ@‚P‚T“ْ‚جŒك‘O‚P‚Oژچ ‚©‚çگ³Œكچ ‚ـ‚إ‚جٹشپA
پ@پ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج“؟گى•ûگوژèگ¨‚ج•ں“‡گ¨پA“؟گى
پ@پ@–{‘à ‚ب‚ا‚جŒRپ@‚ئپAپ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج
پ@پ@ڈ¬گ¼پE‰Fٹى‘½پEگخ“cپE“‡’أگ¨ ‚ب‚ا‚جŒR‚ئ‚جٹش‚إ
پ@پ@گي‚ي‚êپAپ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈO پE–ر—ک•ûپj‚ھ‘چ•ِ‚ê‚ئ‚ب
پ@پ@‚è”s‘–‚µپA”s–k‚µپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ھڈں—ک‚ً“¾‚éپB
پ@
پ@پ،پ@ژR’†‚جگي‚¢پB
پ@
پ@پ@پ،پ@ژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚جگي‚¢‚إ‚حپAگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر
پ@پ@—ک•ûپj ‚جڈ¬‘پگى ڈGڈH‚حپAپ@ڈ¼”ِژRپi‚ـ‚آ‚¨‚â‚ـپj‚ة
پ@پ@‚¢‚½گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جˆة“،گ·گ³پi‚¢‚ئ‚¤‚à
پ@پ@‚è‚ـ‚³پj‚ً’ا‚¢‚¾‚µڈ¼”ِژR‚ًگè‹’‚µپA‚P‚U‚O‚O”NپiŒc
پ@پ@’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ةپAڈ¼”ِژRژRک[‚ة•zگw‚·‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@ژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚جگي‚¢‚إ‚حپAپ@گ¼ŒR پi•ٍچsڈOپE
پ@پ@–ر—ک•ûپj‚حپAپ@‚XŒژ‚P‚S“ْ–é‚ة‘ه’J‹gŒp‚جŒR‚حٹضƒ–
پ@پ@Œ´–~’n“ىگ¼•”‚ة•zگw‚µپAپ@‚XŒژ‚P‚T“ْ–¢–¾‚ةڈ¬گ¼
پ@پ@چs’·پA‰Fٹى‘½ڈG‰ئپAگخ“cژOگ¬پA“‡’أگ¨پi“‡’أ‹`چOپE
پ@پ@“‡’أ–L‹vپj‚جŒR‚حپAپ@ژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj•t‹ك‚ة•zگw
پ@پ@‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@گخ“cژOگ¬‚جŒR‚حپAپ@ژR’†•t‹ك‚ج“،‰؛پi‚ئ‚¤‚°پj
پ@پ@‚جپiˆب‘O‚و‚èگ®”ُ‚µ‚ؤ‚¢‚½پjژ©ٹQ•ôپi‚¶‚ھ‚¢‚ف‚ثپj
پ@پ@‚ئ‚¢‚¤ڈêڈٹ‚ة•zگw‚µپA‚»‚جŒمپA‚·‚®‹ك‚‚جژR’†پi‚â
پ@پ@‚ـ‚ب‚©پj‚ةˆع“®‚µپAژR’†‚ضچU‚ك‚ؤ‚«‚½“ŒŒRپi“؟گى
پ@پ@•ûپj‚ئگي‚¤پB
پ@پ@پ@پ@پ@‘و‚P’iٹK‚ئ‚µ‚ؤپAٹضƒ–Œ´–~’n“ىگ¼•”‚إپA“ŒŒR
پ@پ@پi“؟گى•ûپj‚ج “؟گى–{‘à‚ھپA‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚X
پ@پ@Œژ‚P‚T“ْ‚ج–é–¾‚¯‚ةگ¼ŒRپi•ٍچsڈO پE–ر—ک•ûپj‚جگو
پ@پ@•û‘à‚ج‘ه’JŒR‚ئگي‚¢پAپ@چX‚ةگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک
پ@پ@•ûپj‚جڈ¬‘پگىڈGڈH‚جڈ¬‘پگىŒR‚ھ“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ة
پ@پ@گQ•ش‚èپAŒم •û‚©‚çگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج‘ه’JŒR
پ@پ@‚ًچU‚كپA ‹²‚فŒ‚‚؟‚ة‚µ‚ؤپA‘ه’JŒR‚ً‘S–إ‚³‚¹‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@‘و‚Q’iٹK‚ئ‚µ‚ؤپA‚»‚جŒمپA‚XŒژ‚P‚T“ْŒك‘O‚P‚O
پ@پ@ژچ ‚©‚çگ³Œكچ ‚ـ‚إ‚ج–ٌ‚QژٹشپAپ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj
پ@پ@‚ج“؟گى•ûگوژèگ¨‚ج•ں“‡گ¨‚â“؟گى–{‘à“™‚جŒR‚حپAپ@
پ@پ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈO•ûپj‚جڈ¬گ¼پE‰Fٹى‘½پEگخ“cپE“‡’أگ¨“™
پ@پ@‚جŒR‚ئژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚إگي‚¢پAپ@ژR’†‚إ–hگي‚·‚é
پ@پ@گ¼ ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جڈ¬گ¼پE‰Fٹى‘½پEگخ “cپE
پ@پ@“‡’أگ¨“™‚جŒR‚حپA‘چ•ِ‚ê‚ئ‚ب‚è”s‘–‚µپA”s–k‚µپA
پ@پ@“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ھڈں—ک‚ً“¾‚éپB
پ@پ@
پ@
پ@پ،پ@ژR’†‚جگي‚¢پB
پ@
پ@پ@پ،پ@پu‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پi= گVگà‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پjپv
پ@پ@‚ج‚P‚آ‚جپAپuژR’†‚جگي‚¢پv‚إ‚حپA پ@‘و‚P’iٹK‚ئ‚µ‚ؤپA
پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj ‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ج–é–¾‚¯‚ةپAٹض ƒ–
پ@پ@Œ´–~’nگ¼“ى•”‚إپA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج“؟گى–{‘àپi–ٌ
پ@پ@‚R–œ‚Q‚O‚O‚Oگlپjپ@‚âپ@گ¼ŒR(•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚إ“ŒŒR
پ@پ@‚ةگQ•ش‚ء‚½ڈ¬‘پگىپi–ٌ‚W‚O‚O‚Oگlپj“™‚جŒRپ@‚ئپAپ@گ¼
پ@پ@ŒR(•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جگو•û‘à‚ج‘ه’JŒRپi–ٌ‚P‚Q‚O‚O
پ@پ@گlپjپ@‚ئ‚جٹش‚إگي‚ي‚êپAپ@گ¼ŒR(•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج
پ@پ@‘ه’JŒR‚ھ‘S–إ‚µ‚½پB
پ@پ@پ،پ@‘و‚Q’iٹK‚ئ‚µ‚ؤپAٹض‚ھŒ´–~’n‚ج“ىگ¼•ûŒüپE
پ@پ@–ٌ‚Q‚‹‚چ‚ة ‚ ‚éژهگيڈê‚جژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚إپAپ@
پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj ‚XŒژ‚P‚T“ْ‚جŒك‘O‚P‚Oژچ ‚©
پ@پ@‚çگ³Œكچ ‚ـ‚إ‚جٹشپAپ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج“؟گى•ûگو
پ@پ@ژèگ¨‚ج•ں“‡گ¨پi–ٌ‚P–œ‚X‚O‚O‚Oگlپj‚â“؟گى–{‘àپi–ٌ
پ@پ@‚R–œ‚Q‚O‚O‚Oگlپj“™‚جŒRپ@‚ئپAپ@گ¼ŒR(•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj
پ@پ@‚جڈ¬گ¼پE‰Fٹى‘½پEگخ“cپE “‡’أگ¨“™‚جŒRپi–ٌ‚R–œگlپj
پ@پ@‚ئ‚جٹش‚إگي‚¢‚ھچs‚ي‚êپAپ@گ¼ŒR(•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj
پ@پ@‚ھ‘چ•ِ‚ê‚ئ‚ب‚è”s‘–‚µ”s–k‚µپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ھڈں
پ@پ@—ک‚ً“¾‚½پB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پ،پ@ژR’†‚جگي‚¢پB
پ@پ@پ@پ،پ@پuگVگà‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپv
پ@پ@پ@‚ج‚P‚آ‚جپAپuژR’†‚جگي‚¢پv‚حپAپ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·
پ@پ@پ@‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ج–é–¾‚¯‚©‚çگ³Œكچ ‚ـ‚إ‚جگي‚¢
پ@پ@پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚XŒژ‚P‚T“ْˆبŒم‚ة—\‘z‚³‚ê‚é“ŒŒRپi“؟گى•ûپj
پ@پ@پ@‚ج“ى‹{ژRپi‚ب‚ٌ‚®‚¤‚³‚ٌپjچUŒ‚‚ة”ُ‚¦‚ؤپi‚جŒم‹l
پ@پ@پ@‚ئ‚µ‚ؤپjپAگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج ڈ¬گ¼چs’·پA‰F
پ@پ@پ@ٹى‘½ڈG‰ئپAگخ“cژOگ¬پA “‡’أگ¨پi“‡’أ‹`چOپE“‡’أ
پ@پ@پ@–L‹vپj“™‚جŒRپi–ٌ‚R–œگlپj‚حپAپ@‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ج“ْ–v
پ@پ@پ@ŒمپAپ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج‘هٹ_ڈé‚©‚çڈo‚ؤپA
پ@پ@پ@–é‚ً“O‚µ‚ؤ‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْŒك‘O‚S
پ@پ@پ@ژچ ‚ةپAژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj•t‹ك‚ةˆع“®‚µپA•zگw‚·
پ@پ@پ@‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆê•ûپA‘ه’J‹gŒp‚جŒR‚حپAٹù‚ةپA‚XŒژ‚P‚S“ْ
پ@پ@پ@–é‚ةپAگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جگو•û‘à‚ئ‚µ‚ؤپA
پ@پ@پ@ٹضƒ–Œ´–~’nگ¼“ى•”‚ةˆع“®‚µپA•zگw‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚جگي‚¢‚إ‚حپAگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE
پ@پ@پ@–ر—ک•ûپj‚حپAپ@‘ه’J‹gŒp‚جŒR‚حٹض‚ھŒ´–~’nگ¼“ى
پ@پ@پ@•”‚ة•zگw‚µپAپ@ڈ¬گ¼چs’·پAگخ“cژOگ¬پA‰Fٹى‘½ڈG
پ@پ@پ@‰ئ پA“‡’أگ¨پi“‡’أ‹`چOپE“‡’أ–L‹vپj“™‚جŒR‚حژR
پ@پ@پ@’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj•t‹ك‚ة•zگw‚·‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ¼ŒR پi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جگخ“cژOگ¬‚جŒR‚حپAپ@
پ@پ@ژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj•t‹ك‚ج“،‰؛پi‚ئ‚¤‚°پj‚جژ©ٹQ•ôپi‚¶
پ@پ@‚ھ‚¢‚ف‚ثپj‚ة•zگw‚·‚éپBپ@‚»‚جŒمپA‚·‚®‹ك‚‚جژR’†
پ@پ@‚ةˆع“®‚µپAژR’†‚إ“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ئگي‚¤پB
پ@پ@پ@پ@پ@ˆê•ûپAپ@گ¼ŒR‚جڈ¬گ¼پE‰Fٹى‘½پEگخ“cپE “‡’أگ¨
پ@پ@‚ب‚ا‚جŒRپi–ٌ‚R–œگlپj‚ھ‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ج“ْ–vŒم‚ة‘هٹ_
پ@پ@ڈé‚ًڈo‚ؤٹضƒ–Œ´–~’nپEژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj•û–ت‚ة“]گi
پ@پ@پiˆع“®پj‚µ‚½‚±‚ئ‚ً“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ح’m‚èپAپ@“ŒŒRپi“؟
پ@پ@گى•ûپj‚حپAپ@“ى‹{ژR‚ج–ر—کگ¨‚ة‘خ›³‚³‚¹‚邽‚ك“؟
پ@پ@گى•ûگوژèگ¨‚ج’r“cگ¨پi–ٌ ‚Q–œ‚P‚O‚O‚Oگlپj‚ً“ى‹{ژR
پ@پ@“Œ‘¤‚ةژc‚µپAپ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج“؟گى•ûگوژèگ¨‚ج
پ@پ@•ں“‡گ¨پi–ٌ‚P–œ‚X‚O‚O‚Oگlپj‚â“؟گى–{‘àپi–ٌ‚R–œ‚Q‚O
پ@پ@‚O‚Oگlپj“™‚جŒR‚حپAپ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ً’اŒ‚
پ@پ@‚·‚邽‚كپAپ@ٹضƒ–Œ´–~’nپEژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj•û–ت‚ض
پ@پ@ˆع“®‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@ژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚جگي‚¢‚إ‚حپAپ@“ŒŒRپi“؟گى
پ@پ@•ûپj‚ج“؟گى–{‘à‚جŒR‚حپAپ@ٹضƒ–Œ´–~’nگ¼“ى•”‚إپA
پ@پ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جگو•û‘à‚ج‘ه’JŒR‚ئ‘خ
پ@پ@›³‚µپAپ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج“؟گى•ûگوژèگ¨‚ج•ں“‡ گ¨
پ@پ@‚جŒR‚حپAژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚إپAگ¼ŒR‚جڈ¬گ¼پE ‰Fٹى
پ@پ@‘½پEگخ“cپE “‡’أگ¨“™‚جŒR‚ئ‘خ›³‚µ‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@چ‡گي‚ج‘و‚P’iٹK‚ئ‚µ‚ؤپA‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj
پ@پ@‚XŒژ‚P‚T“ْ–é–¾‚¯‚ةپAٹضƒ–Œ´ –~’nگ¼“ى•”‚إپA “ŒŒR
پ@پ@پi“؟گى•ûپj‚ج“؟گى–{‘à‚جŒR‚ھگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک
پ@پ@•ûپj‚جگو•û‘à‚ج‘ه’JŒR‚ئگي‚¢پAپ@چX‚ة ڈ¼”ِژRژR
پ@پ@ک[‚ة•zگw‚µ‚ؤ‚¢‚½گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جڈ¬‘پ
پ@پ@گىŒR‚ح“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ةگQ•ش‚èپAٹضƒ–Œ´–~’nگ¼“ى
پ@پ@•”‚ةڈoŒ‚‚µ‚ؤپA“ى‘¤‚©‚çگ¼ŒR پi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj
پ@پ@‚ج‘ه’JŒR‚ًچU‚كپA‹²‚فŒ‚‚؟‚ة‚µ‚ؤپA‘ه’JŒR‚ً‘S
پ@پ@–إ‚³‚¹‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@‚»‚جŒمپAچ‡گي‚ج‘و‚Q’iٹK‚ئ‚µ‚ؤپA“ŒŒR‚ج“؟
پ@پ@گى•ûگوژèگ¨‚ج•ں“‡گ¨‚جŒRپi–ٌ‚P–œ‚X‚O‚O‚Oگlپj‚â
پ@پ@“؟گى–{‘àپi–ٌ‚R–œگlپj‚حپAپ@ژR’†پi‚â ‚ـ‚ب‚©پj‚إپAپ@
پ@پ@‚XŒژ‚P‚T“ْŒك‘O‚P‚Oژچ ‚©‚çگ³Œكچ ‚ـ‚إ‚ج–ٌ‚Q
پ@پ@ژٹشپAپ@ڈ¬گ¼پE‰Fٹى‘½پEگخ“cپE “‡’أگ¨ ‚ب‚ا‚جŒR
پ@پ@پi–ٌ‚R–œگlپj‚ًچU‚كپAپ@چإڈI“I‚ةپAژR’†‚إ–hگي‚·
پ@پ@‚éگ¼ŒRپi•ٍچsڈO•ûپj‚جڈ¬گ¼پE‰Fٹى‘½پEگخ“cپE “‡’أ
پ@پ@گ¨“™‚جŒR‚ً”s‘– ‚³‚¹پA”s–k‚³‚¹پA“؟گى•û‚ج“ŒŒR
پ@پ@‚ھڈں—ک‚ً“¾‚éپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@پuژR’†‚جگي‚¢پvپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@پu‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پi= گVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پjپv
پ@پ@پ@‚ج‚P‚آ‚جپuژR’†‚جگي‚¢‚إ‚حپA‘وˆê’iٹK‚ئ‚µ‚ؤپA
پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ةپA–é–¾‚¯‚ةپA
پ@پ@پ@‘Oڈ£گي‚ئ‚µ‚ؤپA ژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚ج“Œ‚جٹضƒ–Œ´
پ@پ@پ@–~’nگ¼“ى•”‚إپA‘ه’J‹gŒp‚ھ—\ٹْ‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء
پ@پ@پ@‚½پA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج“؟گى–{‘à‚ھ‹}‚ةŒ»‚êپA
پ@پ@پ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جگو•û‘à‚ج‘ه’J‹gŒp
پ@پ@پ@ŒR‚ئŒƒ“ث‚µپA‚»‚±‚ة“ى‘¤‚ج‘¤–ت‚©‚çڈ¼”ِژRژR
پ@پ@پ@ک[‚©‚çڈoŒ‚‚µ‚½گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جڈ¬‘پ
پ@پ@پ@گىڈGڈHŒR‚ھپA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ةگQ•ش‚èپA‘ه’J‹g
پ@پ@پ@ŒpŒR‚ةڈP‚¢‚©‚©‚èپA‘ه’J‹gŒpŒR‚حپA‹²پi‚ح‚³پj
پ@پ@پ@‚ف‘إ‚؟‚ئ‚ب‚èپA‘S–إ‚µ‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@‚»‚جŒمپA‘و‚Q’iٹK‚ئ‚µ‚ؤپA‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T
پ@پ@پ@”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ‚جŒك‘O‚P‚Oژچ ‚©‚çگ³Œكچ ‚ـ‚إپA
پ@پ@پ@ژهگيڈê‚جژR’n‚جژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚إپAپ@ژR’†‚â
پ@پ@پ@—ׂج“،‰؛پi‚ئ‚¤‚°پj‚ة•zگw‚µ‚ؤ‚¢‚½گ¼ŒRپi•ٍچs
پ@پ@پ@ڈOپE–ر—ک•ûپj‚جڈ¬گ¼پE‰Fٹى“cپEگخ“cپE“‡’أگ¨‚ب
پ@پ@پ@‚ا‚جŒRپ@‚ئپAپ@ژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚ج“Œ‘¤‚ةŒ»‚ê
پ@پ@پ@‚½“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج “؟گى•ûگوژèگ¨‚ج•ں“‡گ¨
پ@پ@پ@‚â“؟گى–{‘à‚ب‚ا‚جŒR‚ھپAگي‚¢پA“Œ ŒRپi“؟گى•ûپj
پ@پ@پ@‚ھ—Dگ¨‚ج’†‚إپA•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚جگ¼ŒRپi•ٍچs
پ@پ@پ@ڈOپE–ر—ک•ûپj‚ھ”s‘ق‚µپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ھڈں—ک
پ@پ@پ@‚ً“¾‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژR’†‚ة‚¢‚½گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج‹T
پ@پ@پ@ˆنŒR‚حپA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ةگQ•ش‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@“‡’أگ¨‚ج“G’†“ث”jپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژR’†‚ة‚¢‚½گ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج“‡
پ@پ@پ@پ@’أگ¨پi“‡’أ‹`چOپE“‡’أ–L‹v‚جŒRپj‚حپA پ@پu‘هٹ_
پ@پ@پ@پ@ڈé‚ض‚ج‘ق‹pپv‚ًŒˆˆس‚µپAپ@ژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚ج
پ@پ@پ@پ@“Œ‘¤‚ة‚¢‚½“؟گى•û‚ج“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج’†‚ً
پ@پ@پ@پ@پu“G’†“ث”j پv‚µپA“¦‘–‚µپA‘هٹ_ڈé‚ةŒü‚ء‚ؤ’E
پ@پ@پ@پ@ڈo‚µپA’اŒ‚‚³‚êپA“r’†‚إ‘هٹ_ڈé‚àٹë‚ب‚¢ ‚ئ’m
پ@پ@پ@پ@‚é‚âˆةگ¨ٹX“¹‚ً’ت‚èپA“ى‰؛‚µپA‘هچم‚ةŒü‚¢پA
پ@پ@پ@پ@‘هچمکp‚إ‘D‚ةڈو‚èپAژF–€‚ة‹Aچ‘‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”s‘–“r’†پA“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج’اŒ‚‚إ“‡
پ@پ@پ@پ@’أگ¨‚ج‘½‚‚ج•؛‚ھ—Eٹ¸‚ةگي‚¢گيژ€‚µپA“‡’أ
پ@پ@پ@پ@‹`چOپi‚µ‚ـ‚أ‚و‚µ‚ذ‚ëپj‚ج‰™پE“‡’أ–L‹vپi‚µ‚ـ
پ@پ@پ@پ@‚أ‚ئ‚و‚ذ‚³پj‚àگيژ€‚µپAŒ‹‹اپA”s‘–“r’†پA“ŒŒR
پ@پ@پ@پ@پi“؟گى•ûپj‚ج’اŒ‚‚â—ژ‚؟•گژزژë‚è ‚ب‚ا‚إپA–ٌ
پ@پ@پ@پ@‚P‚T‚O‚Oگl‚¢‚½“‡’أگ¨‚ج•؛‚ج‚¤‚؟–³ژ–‹Aچ‘‚إ‚«
پ@پ@پ@پ@‚½‚ج‚حپA“‡’أ‹`چO‚ئ–ٌ‚V‚Oگl‚ج“‡’أژپ‰ئگb ‚¾
پ@پ@پ@پ@‚¯‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@
پ@
پ@پ،پ@پuگVگà‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢
پ@پ@پ@پ@پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپvپB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ،پ@ˆêژںژj—؟‚ةٹî‚أ‚پuگVگà‚جٹضƒ–Œ´‚جگي
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپvپi‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚T”Nپj‚WŒژ‚Q‚U“ْپ[‚XŒژ‚P‚T“ْپj ‚إ‚حپAپ@گ¼ŒR
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi•ٍچsڈO•ûپj‚ج“ى‹{ژR‚ج‘هٹ_ڈéŒم‹lŒR‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–ر—کگ¨‚ھ“ŒŒRپi“؟گى•ûپj ‚©‚çچUŒ‚‚ًژَ‚¯”s
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–k‚·‚é‚ئگ¼ŒRپi•ٍچsڈO•ûپj‚ھ’“—¯‚·‚é‘هٹ_
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈé‚ھŒا—§‚µ•s—ک‚ئ‚ب‚é‚ج‚إپAپ@‘هٹ_ڈé‚ة ’“
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—¯‚µ‚ؤ‚¢‚½گ¼ŒRپi•ٍچsڈO•ûپj‚جڈ¬گ¼پE ‰Fٹى
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘½پEگخ “cپE“‡’أگ¨“™‚جŒR‚حپA‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ة—\‘z‚³‚ê‚é“ŒŒRپi“؟گى•ûپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ة‚و‚é“ى‹{ژR‚جگ¼ŒR‚ج–ر—کگ¨‚ض‚جچUŒ‚‚ة
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”ُ‚¦‚ؤپi‚جŒم‹l‚ئ‚µ‚ؤپjپAپ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ج“ْ–vŒمپA‘هٹ_ڈé‚ًڈo‚ؤپA ٹض
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒ–Œ´–~’nپEژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj•û–ت‚ضŒü‚¢پAگ¼
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒRپi•ٍچsڈO•ûپj‚جڈ¬گ¼پE‰Fٹى‘½پEگخ “cپE“‡’أ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ¨“™‚جŒR‚حپA‚XŒژ‚P‚T“ْ‚جŒك‘O‚Sژچ پA ژR
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj•t‹ك‚ة•zگw‚µپA‚»‚جŒمپA‘هٹ_
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•t‹ك‚©‚ç—ˆ‚½“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚جŒR‚ئ‘خ›³‚·
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ¼ŒRپi•ٍچsڈO•ûپj‚جڈ¬‘پگىڈGڈH‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ةپAڈ¼”ِژR
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ًگè‹’‚µپAڈ¼”ِژRژRک[‚ة•zگw‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@پuگVگà‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جگي‚¢پjپv‚إ‚حپAپ@“ŒŒR‚جڈ¬‘پگىڈGڈH‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚OپiŒc’·‚T”Nپj”N‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ةپAٹضƒ–Œ´ –~
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’n‚جگ¼“ى•ûŒü ‚ة‚ ‚éپAڈ¼”ِژRپi‚ـ‚آ‚¨‚â‚ـپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ة•zگw‚·‚éگ¼ŒR‚جˆة“،گ·گ³پi‚¢‚ئ‚¤‚à‚è‚ـ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚³پj‚ً’ا‚¢‚¾‚µپAڈ¼”ِژR‚ًگè‹’‚µپAڈ¼”ِژRژR
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ک[‚ة–{گwپiگw’nپj‚ً’u‚«پA ڈ¬گ¼پE‰Fٹى‘½پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گخ“cپEژF–€گ¨ “™‚جگ¼ŒRژه—حŒR‚حپA‘هٹ_ڈé
‚©‚ç–é‚ً“O‚µ‚ؤژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj•t‹ك ‚ةˆع
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“®‚µپA ‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ‚جژR
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’†‚جگي‚¢پi–é–¾‚¯‚©‚çگ³Œكچ ‚ـ‚إپj‚إ‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ گ¼ŒR‚جڈ¬گ¼پE‰Fٹى‘½پEگخ“cپEژF–€گ¨“™‚جŒR
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ھپA‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ةژR’† •t‹ك‚ة•zگw‚µپA ‘هٹ_
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•t‹ك‚©‚ç—ˆ‚é“ŒŒRپ@‚âپ@— گط‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ب
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¢ڈ¼”ِژRژRک[‚ة•zگw‚·‚éڈ¬‘پگىڈGڈH‚جŒR
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ئ‘خ›³‚µ‚½پB
پ@
پ@
#thenewtheoryofsekigaharawar-appearingscenes
پ@
پ@
پôپôپ@پuگVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†
پ@پ@پ@پ@‚جگي‚¢پjپv‚ً•`‚¢‚½پA‹»–،گ[‚¢ٹض
پ@پ@پ@پ@کAƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پAƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپB
پ@پ@پ@پ@پ@
پ@پڑپ@پuگVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†
پ@پ@پ@ ‚جگي‚¢پjپv‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢پA
پ@پ@ ƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پB
پ@
پ@پ،پ@ڈ”گà‚ ‚èپIٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢
پ@پ@پ@ ƒXƒyƒVƒƒƒ‹
پ@پ@پ@ پwپ@ٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢‚جگ^ژہپ@پxپ@پi‚QپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚s‚a‚rƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚P‚W”N‚PŒژ‚U“ْپE–{•ْ‘—پE
پ@پ@پ@ پ@پ@—ًژjƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[”ش‘gپjپB
پ@
پ@پ@پ،پ@پuگVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپv
پ@پ@پ@پ@‚ئپAپ@پuڈ]—ˆگàپi’تگàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚ج
پ@پ@پ@پ@‚Q‚آ‚ج—L—ح‚بگà‚ًڈعچׂةڈq‚ׂéپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@ڈ”گà‚ ‚èپI
پ@پ@ پ@پwپ@ٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢‚جگ^ژہپ@پxپ@پi‚PپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚s‚a‚rƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚P‚V”N‚XŒژ‚Q“ْپE–{•ْ‘—پE
پ@پ@پ@ پ@پ@—ًژjƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[”ش‘gپjپB
پ@
پ@پ@پ،پ@پuگVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپv
پ@پ@پ@‚ئپAپ@پuڈ]—ˆگàپi’تگàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚ج
پ@پ@پ@‚Q‚آ‚ج—L—ح‚بگà‚ًڈعچׂةڈq‚ׂéپB
پ@
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژjژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
#thenewtheoryofsekigaharawar-thehappenings
پ@
پںپ@گVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پi= ‘هٹ_پE
پ@پ@پ@ ژR’†‚جگي‚¢پjٹضکAڈo—ˆژ–
پ@پ@ پi”N‘مڈ‡پEڈعچ×پjپB
پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ٌ‚¹‚آ‚¹‚«‚ھ‚ح‚ç‚ج‚½‚½‚©‚¢
پ@پ@پ@پ@ پi‚ث‚ٌ‚¾‚¢‚¶‚م‚ٌپE‚µ‚ه‚¤‚³‚¢پjپjپB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ،پ@‚±‚±‚إ‚حپAپ@ˆêژںژj—؟‚ةٹî‚أ‚ژjژہ‚ج
پuگVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي
پ@پ@پ@پ@‚¢پjپv‚ًڈq‚×پAپ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´
پ@پ@پ@پ@‚جگي‚¢پv‚ئˆظ‚ب‚é‰سڈٹ‚حپA‚»‚جڈ]—ˆگà
پ@پ@پ@پ@پi“`گàپj‚à’ا‰ء•¹‹L‚µ‚½پB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ،پ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚حپA
پ@پ@پ@پ@Œمگ¢‚ج‘nچى‚إ‚ ‚èپAگMœكگ«پi‚µ‚ٌ‚ز‚ه‚¤
پ@پ@پ@پ@‚¹‚¢پj‚ھ‚ب‚¢پB
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚جپAپuگVگàٹضƒ–
پ@پ@پ@پ@Œ´‚جگي‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپv
پ@پ@ پ@‘O‚جڈَ‹µپA“®ŒüپB
پ@
پ@
پںپ@گVگàٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پi= ‘هٹ_پE
پ@پ@پ@ ژR’†‚جگي‚¢پjٹضکAڈo—ˆژ–
پ@پ@ پi”N‘مڈ‡پEڈعچ×پjپB
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚جپAپuگVگàٹضƒ–
پ@پ@پ@ Œ´‚جگي‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپv
پ@پ@پ@ ‚جŒˆگي‘O‚جڈَ‹µپA“®ŒüپB
پ@
پ@پ،پ@‚P‚T‚X‚W”N(Œc’·‚R”NپjپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚P‚T‚X‚W”N(Œc’·‚R”Nپj‚WŒژ‚P‚W“ْ‚ةپA–LگbڈG‹g ‚ھ
پ@پ@ژ€‹ژ‚·‚éپBپ@
پ@
پ@
پ@پ،پ@‚P‚T‚X‚X”N(Œc’·‚S”NپjپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚P‚T‚X‚X”N(Œc’·‚S”Nپj‰[‚RŒژ‚P ‚O“ْ‚ةگخ“cژOگ¬‚ھپA
پ@پ@پ@‹كچ]چ‘‚جچ²کaژRڈé‚إه‹ڈپi‚؟‚ء‚«‚هپj‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”NپjپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚ةپA“؟گى‰ئچN‚حپAپ@‰ï’أپE
پ@پ@ڈمگ™“¢”° ˆب‘O‚ةپA”½“؟گىگ¨—ح‚ج•ٍچsڈOپE–ر—ک
پ@پ@•û‚ئ‚جگي‚¢‚ة”ُ‚¦‚ؤپAپ@‘½‚‚ج‘ه–¼‚ةپA“؟گىژپ
پ@پ@‚ج–،•û‚ة‚ب‚é‚و‚¤‚ةپA‘½‚‚جژèژ†‚ًڈ‘‚پB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@پ@
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚UŒژپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚UŒژ‚P‚W“ْ‚ةپA“؟گى‰ئچN
پ@پ@پ@‚ھپA•ڑŒ©ڈé‚ً”‚؟پA‰ï’أ‰“گھ‚ةŒü‚©‚¤پi‚ًٹJژn
پ@پ@پ@‚·‚éپjپB
پ@
پ@پ@پœپ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚UŒژ‚ةپA–Lگb‰ئپEŒـ‘هکV‚ج
پ@پ@پ@‚PگlپE“؟گى‰ئچN‚حپAپ@‰ï’أپEڈمگ™“¢”°‚ًژہژ{‚·‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚ئ”½–ع‚·‚鑽‚‚ج–Lگb‰¶
پ@پ@پ@Œعپi‚¨‚ٌ‚±پj‚ج‘ه–¼‚ھ‰ئچN‚ة•t‚«ڈ]‚ء‚ؤپA‰ï’أپE
پ@پ@پ@ڈمگ™“¢”°‚جŒR‚ة‰ء‚ي‚ء‚ؤپA‘هچمڈé‚©‚çڈoگw‚µ
پ@پ@پ@‚½پB
پ@
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚VŒژپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚VŒژ‚P‚P“ْچ ‚ةپA•ٍچs
پ@پ@ڈOپE –ر—ک•û‚ج‘ه’J‹gŒpپi‚¨‚¨‚½‚ة‚و‚µ‚آ‚®پjپj پ@
پ@پ@‚ھپA‹كچ]چ‘‚جچ²کaژRڈéپi‚³‚ي‚â‚ـ‚¶‚ه‚¤پj‚ً
پ@پ@—ˆ–K‚µپAپ@“؟گى‰ئچN“¢”°‚ً‘إ‚؟–¾‚¯پAگخ“c
پ@پ@ژOگ¬‚ًگà“¾‚µ ‚ؤپAگخ“cژOگ¬‚حپA•ٍچsڈOپE–ر
پ@پ@—ک•û‚ة‰ء‚ي‚éپB
پ@
پ@پ@پœپ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚VŒژ‚P‚Q“ْچ ˆبچ~پA•ٍچsپ@
پ@پ@ڈOپE–ر—ک•û‚ج‘ه’J‹gŒp‚ھپAپ@‹كچ]چ‘‚جچ²کaژRڈé
پ@پ@‚إپAگخ“cژOگ¬‚ئŒv—ھ‚ً‚ك‚®‚ç‚·پB
پ@
پ@
پ@پ@پںپ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پvپB
پ@پ@پ،پ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚إ‚حپA‚P‚U‚O‚O
پ@پ@”N(Œc’·‚T”Nپj‚VŒژ‚P‚P“ْ چ ‚ةپAگخ“cژOگ¬پi‚¢‚µ ‚¾
پ@پ@‚ف‚آ‚ب‚èپj‚ھپAپ@‹كچ]چ‘‚جچ²کaژRڈéپi‚³‚ي‚â‚ـ‚¶
پ@پ@‚ه‚¤پj‚إپA—ˆ–K‚µ‚½‘ه’J‹gŒpپi‚¨‚¨‚½‚ة‚و‚µ‚آ‚®پj
پ@پ@‚ةپA“؟گى‰ئچN“¢”°‚ً‘إ‚؟–¾‚¯پAگà“¾‚µ‚ؤپA‘ه’J
پ@پ@‹gŒp‚حپAگخ“c•û‚ة‰ء‚ي‚éپB
پ@
پ@پ@پœپ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚إ‚حپA‚P‚U‚O‚O
پ@پ@پ@”N(Œc’·‚T”Nپj‚VŒژ‚P‚Q“ْچ ˆبچ~پAگخ“c•û‚جگخ“c
پ@پ@پ@ژOگ¬‚ھپA‹كچ]چ‘‚جچ²کaژRڈé‚إپA‘ه’J‹gŒp‚ئŒv
پ@پ@پ@—ھ‚ً‚ك‚®‚ç‚·پB
پ@
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚VŒژ‚P‚V“ْپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚VŒژ‚P‚V“ْ‚ةپA•ٍچsڈOپE–ر
پ@پ@پ@—ک•û‚ج –ر—ک‹PŒ³پi ‚à‚¤‚è‚ؤ‚é‚à‚ئپj‚ھپA–Lگb
پ@پ@پ@‘هچمڈé‚ة“ü‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚VŒژ‚P‚V“ْ‚ةپAپu“à•{‚؟ ‚ھ
پ@پ@‚ذ‚جڈًپXپvپi‚ب‚¢‚س‚؟‚ھ‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤‚¶‚ه‚¤پA‚P‚R
پ@پ@‚©ڈًپj‚ھپAپ@•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚ج’·‘©گ³‰ئپE‘“c
پ@پ@’·گ·پE‘O“cŒ؛ˆبژO•ٍچs–¼‚إپAŒِ•z‚³‚ê‚éپB پ@
پ@پ@پ@پ@پ@‚»‚جŒمپA‚»‚ê‚ھپA‘Sچ‘‚ج‘ه–¼‚ة‘—•t‚³‚ê
پ@پ@‚éپiڈo‰ٌ‚éپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@“؟گى‰ئچN‚حپA‚±‚جژ“_‚©‚çپAŒِ‹VڈمپA–L
پ@پ@گbژپ‚ج“G‚ئ‚ب‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚VŒژ‚P‚V“ْ‚ةپA•ٍچsڈOپE –ر
پ@پ@—ک•û‚جگ¼ŒR‚ھپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ة‘خ‚µ‚ؤپA‹“•؛
پ@پ@‚·‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@•ٍچsڈOپE –ر—ک•û‚جگ¼ŒR‚ج’†گSگl•¨‚حپAپ@•ٍچs
پ@پ@پ@ڈO‚Rگlپi‘“c’·گ·پA’·‘©گ³‰ئپA‘O“cŒ؛ˆبپj‚ئ
پ@پ@ –ر—ک‹PŒ³‚إ‚ ‚éپBپ@پ@ˆê•ûپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ج’†
پ@پ@گSگl•¨‚حپA“؟گى‰ئچN‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@•ٍچsڈO‚Rگl‚ئ‚حپAپ@Œـ•ٍچs‚ج’†‚ج‚Rگl‚إ
پ@پ@پ@‚ ‚èپA‘“c’·گ·پ@پi‚ـ‚µ‚½‚ب‚ھ‚à‚èپjپAپ@’·‘©گ³پ@
پ@پ@پ@‰ئپi‚ب‚آ‚©‚ـ‚³‚¢‚¦پjپAپ@‘O“cŒ؛ˆبپ@پi‚ـ‚¦‚¾‚°
پ@پ@پ@‚ٌ‚¢پjپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پںپ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پvپB
پ@پ@پ،پ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚إ‚حپA‚P‚U‚O‚O
پ@پ@پ@”N(Œc’·‚T”Nپj‚VŒژ‚P‚V“ْ‚ةپAپ@گخ“cژOگ¬‚âگخ“c
پ@پ@پ@•ûگ¼ŒR‚ھپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ة‘خ‚µ‚ؤپA‹“•؛‚·‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚إ‚حپAپ@گخ“c
پ@پ@پ@•û‚جگ¼ŒR‚ج’†گSگl•¨‚حپAپ@گخ“cژOگ¬‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@ˆê•ûپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ج’†گSگl•¨‚حپA“؟گى‰ئچN
پ@پ@پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚VŒژ‚P‚X“ْپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚VŒژ‚P‚X“ْ‚ةپA•ٍچsڈOپE–ر—ک
پ@پ@•û‚جگ¼ŒR‚ھپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ج•ڑŒ©ڈé‚ًچUŒ‚‚·
پ@پ@‚éپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚VŒژ‚Q‚T“ْپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚VŒژ‚Q‚T“ْ ‚ةپA“؟گى•û“ŒŒR
پ@پ@‚ة‚ؤپAڈ¬ژR•]’èپi‚¨‚â‚ـ‚ذ‚ه‚¤‚¶‚ه‚¤پj‚ھٹJ‚©‚ê
پ@پ@‚éپBپ@
پ@
پ@پ@پœپ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚VŒژ‚Q‚T“ْ‚ةپA‰؛–ىچ‘پ@پi‚µ
پ@پ@‚à‚آ‚¯‚ج‚‚ةپAŒ»پE“ب–طŒ§‚ج‘ٹ“–’nˆوپjپ@‚ج
پ@پ@ڈ¬ژRپi‚¨‚â‚ـپj‚إپAپ@“؟گى‰ئچN‚ھپA‰ï’أ‰“گھ‚ج
پ@پ@ڈ”ڈ«‚ًڈW‚كŒR‹c‚ًٹJ‚«پAپ@گ¼ŒR(•ٍچsڈOپE–ر—ک
پ@پ@•ûپj‚ً“¢‚آ‚½‚ك‚جگ¼ڈم‚ًŒˆ’è‚·‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@ڈ¬ژR•]’èŒمپAپ@“؟گى‰ئچN‚حپA“؟گىژپ‚جŒR‚ًپA
پ@پ@پ@ٹّ–{–h‰q•”‘à‚ئژه—حچUŒ‚•”‘à‚ج“ٌژè‚ة•ھ‚¯پAپ@
پ@پ@پ@گو‚ةپA“؟گىڈG’‰‚ج—¦‚¢‚é“؟گىژپژه—حچUŒ‚•”
پ@پ@پ@‘àپiگ¸‰s•”‘àپjپE–ٌ‚R–œ‚W‚O‚O‚Oگl‚ًپA•ٍچsڈOپE
پ@پ@پ@–ر—ک•ûگ¼ŒR‚ج–k•û‚جڈمگ™ژپ‚ة”ُ‚¦‚ب‚ھ‚çپA
پ@پ@پ@“ŒژR“¹پi‚ئ‚¤‚³‚ٌ‚ا‚¤پA’†ژR“¹پi‚ب‚©‚¹‚ٌ‚ا‚¤پjپjپ@
پ@پ@پ@Œo—R‚إپA“؟گىژپ—ج’n‚جٹض“Œ’n•û‚ج‹؛ˆذ‚ئ‚ب
پ@پ@پ@‚é•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûگ¼ŒR‚جگ^“cژپ“¢”°‚ةŒü‚ي
پ@پ@پ@‚¹‚½پB
پ@
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚WŒژ‚T“ْپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚WŒژ‚T“ْ‚ةپA“؟گى‰ئچN‚ھپA
پ@پ@چ]Œثڈé‚ة–ك‚éپB
پ@
پ@پ@پœپ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚WŒژ‚T“ْ‚ةپA“؟گى‰ئچN‚حپA
پ@پ@“؟گىژپٹّ–{–h‰q•”‘à‚ئ‹¤‚ةپAˆê’UپAچ]Œثڈé‚ة
پ@پ@–ك‚ء‚½پB
پ@
پ@پ@پœپ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚WŒژ‚T“ْ‚ةپAچ]Œث‚ة–ك‚ء‚½
پ@پ@پ@“؟گى‰ئچN‚حپAپ@گو‚ةگ¼ڈم‚µ‚ؤ‚¢‚é‰ئچN‚ة•t‚«
پ@پ@پ@ڈ]‚ء‚½“؟گى•û“ŒŒR‚ج–Lگb‰¶Œعپi‚¨‚ٌ‚±پj‚جڈ”
پ@پ@پ@ڈ«پE‘ه–¼‚ج“®Œü‚ً’چژ‹‚µ‚ؤ‚¢‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ئ‚¢‚¤‚ج‚àپAڈ¬ژR•]’èپi‚¨‚â‚ـ‚ذ‚ه‚¤‚¶‚ه‚¤پj
پ@پ@پ@‚جژ“_‚إپA•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûگ¼ŒR‚جپu“à•{‚؟‚ھ‚ذ
پ@پ@پ@‚جڈًپXپv‚â•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûگ¼ŒR‚ھڈW‚ك‚½–ٌ‚P‚O
پ@پ@پ@–œگl‚ج‘هŒRگ¨‚ج‹K–ح‚ًپA“؟گى‰ئ چN‚â‰ئچN‚ة•t
پ@پ@پ@‚«ڈ]‚ء‚½“؟گى•û“ŒŒR‚ج–Lگb‰¶Œع‚جڈ”ڈ«پE‘ه–¼
پ@پ@پ@‚حپAڈع‚µ‚’m‚ç‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@“؟گى‰ئچN‚ة•t‚«ڈ]‚ء‚½“؟گى•û“ŒŒR‚ج–L
پ@پ@پ@گb‰¶Œع‚جڈ”ڈ«پE‘ه–¼‚ھ‰ئچN‚ة–،•û‚·‚é‚ئ–ٌ‘©
پ@پ@پ@‚µ‚½پAڈ¬ژR•]’èŒمپA“؟گى•û“ŒŒR‚ج–Lگb‰¶Œع پ@
پ@پ@پ@‚جڈ”ڈ«پE‘ه–¼‚ھپA‰ئچN‚ً”ل”»‚·‚éپu“à•{‚؟‚ھ
پ@پ@پ@‚ذ‚جڈًپXپvپ@ ‚âپ@•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûگ¼ŒR‚ھ–ٌ‚P‚O
پ@پ@پ@–œگl‚à‚ج•؛‚ًڈW‚ك‚½‚±‚ئ‚ً’m‚èپA“؟گى•û“ŒŒR‚ج
پ@پ@پ@–Lگb‰¶Œع‚جڈ”ڈ«پE‘ه–¼‚ھ‰ئچN‚ً— گط‚é‚ج‚إ‚ح
پ@پ@پ@‚ب‚¢‚©‚ئ“؟گى‰ئچN‚حپA‹°‚ê‚ؤ‚¢‚½‚½‚ك‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ¬ژR•]’èŒمپAپ@•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûگ¼ŒR‚ج–L
پ@پ@پ@گbژپژO•ٍچs‚ج–¼‚إŒِ•z‚³‚ê ‚½پu“à•{ ‚؟‚ھ‚ذ
پ@پ@پ@‚جڈًپXپvپi‚ب‚¢‚س‚؟‚ھ‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤‚¶‚ه‚¤پj‚ھپAپ@
پ@پ@پ@“؟گى•û“ŒŒR‚ج–Lگb‰¶Œع‚جڈ”ڈ«پE‘ه–¼‚ةڈع‚µ
پ@پ@پ@‚“`‚ي‚èپAپ@“؟گى‰ئچN‚ةگ³“–گ«‚ھ‚ب‚¢‚ئژه’£
پ@پ@پ@‚·‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئ‰ئچN‚حˆؤ‚¶‚ؤ‚¢‚½پBپ@“؟
پ@پ@پ@گى‰ئچN‚حپAڈ¬ژR•]’è‚إ–،•û‚ئ‚ب‚ء‚½“؟گى•û
پ@پ@پ@“ŒŒR‚ج–Lگb‰¶Œع‚جڈ”ڈ«پE‘ه–¼‚ج— گط‚è‚ً‹°‚ê
پ@پ@پ@‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½پB
پ@
پ@پ@پœپ@“؟گى‰ئچN‚حپAپ@‰ئچN‚ة•t‚«ڈ]‚ء‚½“؟گى•û“ŒŒR
پ@پ@پ@‚ج–Lگb‰¶Œع‚جڈ”ڈ«پE‘ه–¼‚ھگ¼ڈم‚µ‚ؤ•ٍچsڈOپE–ر
پ@پ@پ@—ک•ûگ¼ŒR‚ئژہچغ‚ة–{“–‚ةگي‚¤‚ج‚©‹^‚¢پA‚±‚ê
پ@پ@پ@‚ًŒ©‹ة‚ك‚邽‚كپAپ@گو‚ةپA‰ئچN‚ة•t‚«ڈ]‚ء‚½“؟
پ@پ@پ@گى•û“ŒŒR‚ج–Lگb‰¶Œع‚جڈ”ڈ«پE‘ه–¼‚جŒR‚ًگ¼•û
پ@پ@پ@‚ةŒü‚©‚ي‚¹پAپ@“؟گى‰ئچN‚حپAچ]Œثڈé‚ة–ٌ‚Pƒ–Œژ
پ@پ@پ@‚ظ‚ا—¯‚ـ‚èپAڈîگ¨‚ً‚ف‚ب‚ھ‚çپA‚P‚O‚O’تˆبڈم‚جڈ‘
پ@پ@پ@ڈَ‚ً‘Sچ‘‚جڈ”‘ه–¼‚ة‘—‚ء‚½پBپ@
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚WŒژ‚P‚O“ْپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚WŒژ‚P‚O“ْ‚ة پA•ٍچsڈOپE–ر
پ@پ@پ@—ک•ûگ¼ŒR‚ھپAپ@”ü”Zچ‘پi‚ف‚ج‚ج‚‚ةپAŒ»پE ٹٍ•Œ
پ@پ@پ@Œ§“ى•”‚ج‘ٹ“–’nˆوپj‚ج‘هٹ_ڈéپi‚¨‚¨‚ھ‚«‚¶
پ@پ@پ@‚ه‚¤پj‚ة“ü‚éپB
پ@
پ@پ@پœپ@•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûگ¼ŒR‚حپAپ@“؟گى•û“ŒŒR‚ئ‚ج’·
پ@پ@پ@ٹْگي‚ة”ُ‚¦پAپ@“؟گى•û“ŒŒR‚ً”ü”Zچ‘پ@پi‚ف‚ج‚ج‚
پ@پ@پ@‚ةپAŒ»پEٹٍ•ŒŒ§“ى•”‚ج‘ٹ“–’nˆوپjپ@‚إ‘ز‚؟چ\‚¦پA
پ@پ@پ@‘هٹ_ڈéپi‚¨‚¨‚ھ‚«‚¶‚ه‚¤پj‚ً•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûگ¼ŒR
پ@پ@پ@‚ج”ü”Zچ‘‚ج–{‹’’n‚ئ‚µپAپ@چ²کaژRڈéپE–Lگb‘هچم
پ@پ@پ@ڈé•û–ت‚ضچs‚“ŒژR“¹پi’†ژR“¹پj‚ًژç‚é‹’“_‚ئ‚µ
پ@پ@پ@‚ؤپAپ@“ى‹{ژRپi‚ب‚ٌ‚®‚¤‚³‚ٌپj‚ةپA•ٍچsڈOپE–ر—ک
پ@پ@پ@•ûگ¼ŒR‚ج–ر—کڈGŒ³‚جŒR‚ً•zگw‚³‚¹پAپ@چX‚ةپA
پ@پ@پ@ڈ¼”ِژRپi‚ـ‚آ‚¨‚â‚ـپj‚ةپA•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûگ¼ŒR
پ@پ@پ@‚ج–ر—ک‹PŒ³‚جŒR‚ً•zگw‚³‚¹‚é—\’è‚إ‚ ‚ء‚½پBپ@
پ@پ@پ@‚µ‚©‚µپA•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûگ¼ŒR‚ج–ر—ک‹PŒ³‚حپA
پ@پ@پ@–Lگb‘هچâڈé‚ً“®‚©‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚WŒژپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚WŒژ‚ةپA“؟گى‰ئچN‚ئڈ¬ژR
پ@پ@پ@پi‚¨‚â‚ـپj‚إ•ھ‚©‚êگ¼ڈم‚µ‚½•ں“‡گ³‘¥پi‚س‚‚µ‚ـ‚ـ
پ@پ@پ@‚³‚ج‚èپj‚ح‚¶‚ك“؟گى•û“ŒŒR‚ج–Lگb‰¶Œع‚جڈ”ڈ«پE‘ه
پ@پ@پ@–¼‚حپAپ@”ِ’£چ‘پi‚¨‚ي‚è‚ج‚‚ةپAŒ»پEˆ¤’mŒ§گ¼•”
پ@پ@پ@‚ج‘ٹ“–’nˆوپj‚ج•ں“‡گ³‘¥‚ج‹ڈڈéپEگ´گ{ڈéپi‚«‚و
پ@پ@پ@‚·‚¶‚ه‚¤پj‚ةڈWŒ‹‚µپA“؟گى‰ئچN‚جڈoگw‚ً‘ز‚؟‚ي
پ@پ@پ@‚ر‚ؤ‚¢‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ]Œثڈé‚ة‚¢‚é“؟گى‰ئچN‚حپAپ@”ِ’£‚ة‚¢‚é
پ@پ@پ@“؟گى•û“ŒŒR‚ج–Lگb‰¶Œع‚جڈ”ڈ«پE‘ه–¼‚ةپA”ü”Z
پ@پ@پ@پi‚ف‚جپAŒ»پEٹٍ•ŒŒ§“ى•”پj‚ج•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûگ¼
پ@پ@پ@ŒR‚ًچUŒ‚‚·‚é‚و‚¤‚ة‘£‚·پB
پ@
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚WŒژ‚Q‚R“ْپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚WŒژ‚Q‚R“ْ‚ة پA•ں“‡گ³‘¥
پ@پ@‚ح‚¶‚ك“؟گى•û“ŒŒR‚ج–Lگb‰¶Œع‚جڈ”ڈ«پE‘ه–¼‚ھپAپ@
پ@پ@•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûگ¼ŒR‚ج”ü”Z‚ج‹’“_‚ج‚P‚آ‚جٹٍ
پ@پ@•Œڈéپi‚¬‚س‚¶‚ه‚¤پj‚ًچUŒ‚‚µپA‚P“ْ‚إ—ژڈ邳‚¹‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚WŒژ‚Q‚U“ْپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚WŒژ‚Q‚U“ْ‚ةپA •ں“‡گ³‘¥
پ@پ@پ@‚ح‚¶‚ك“؟گى•û“ŒŒR‚ج–Lگb‰¶Œع‚جڈ”ڈ«پE‘ه–¼‚ھپAپ@
پ@پ@پ@•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûگ¼ŒR‚ج”ü”Z‚ج–{‹’’nپE‘هٹ_ڈé
پ@پ@پ@‚ة‹ك‚¢پA”ü”Zگشچâپi‚ف‚ج‚ ‚©‚³‚©پj•t‹ك‚ةڈWŒ‹
پ@پ@پ@‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚»‚جŒمپA“؟گى•û“ŒŒR‚ج–Lگb‰¶Œع‚جڈ”ڈ«پE
پ@پ@پ@‘ه–¼‚حپAپ@•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûگ¼ŒR‚ج”ü”Z‚ج–{‹’
پ@پ@پ@’n‚ج‘هٹ_ڈé‚ج’“—¯ŒR‚ًچUŒ‚‚µپA‘هٹ_ڈéچU–h
پ@پ@پ@گي‚ًچs‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ھپAپ@‚XŒژ‚V“ْ‚ة‘هٹ_ڈé‚جگ¼•û
پ@پ@پ@‚ج“ى‹{ژRپi‚ب‚ٌ‚®‚¤‚³‚ٌپj‚ةپA•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûگ¼
پ@پ@پ@ŒR‚ج–ر—کڈGŒ³پi‚à‚¤‚è‚ذ‚إ‚à‚ئپj‚ھ—¦‚¢‚é–ر—ک
پ@پ@پ@گ¨‚ھ•zگw‚·‚éپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P“ْپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P“ْ‚ةپA“؟گى‰ئچN‚ھپA
پ@پ@چ]Œثڈé‚ًڈo”‚µپAڈم•ûپi‚©‚ف‚ھ‚½پj‚ةŒü‚¤پB
پ@
پ@پ@پœپ@گخ“c•ûگ¼ŒR‚ج‹’“_‚ج‚P‚آ‚جٹٍ•ŒڈéچU—ھ‚ب‚ا
پ@پ@‚إپAگ¼ڈم‚µ‚½–Lگb‰¶Œع‚ج“؟گى•û“ŒŒR‚جڈ”ڈ«‚ھگخ
پ@پ@“c•û‚جگ¼ŒR‚ئژہچغ‚ةگي‚¤‹C‚ھ‚ ‚èژ©•ھ‚ً— گط‚ç‚ب
پ@پ@‚¢‚ئ’m‚é‚ئپAپ@“؟گى‰ئچN‚حپAچQ‚ؤ‚ؤپA“؟گىژپٹّ–{
پ@پ@–h‰q•”‘àپE–ٌ‚R–œگl‚ئ‹¤‚ةپAچ]Œثڈé‚ًڈo”‚µپAپ@
پ@پ@ˆê•ûپAگ^“cژپ“¢”°‚ةŒü‚ء‚½“؟گىژپژه—حچUŒ‚•”
پ@پ@‘à‚ةپA“ŒژR “¹پi’†ژR“¹پjŒo—R‚إڈم•ûپi‚©‚ف‚ھ‚½پj
پ@پ@‚ضŒü‚¤‚و‚¤‚ة“`—ك‚ً‘—‚ء‚½پB
پ@
پ@پ@پœپ@”ü”Zچ‘پ@پi‚ف‚ج‚ج‚‚ةپAŒ»پEٹٍ•ŒŒ§“ى•”‚ج‘ٹ“–’n
پ@پ@ˆوپj‚إپA–Lگb‰¶Œع‚ج“؟گى•û“ŒŒR‚جڈ”ڈ« ‚حپAپ@ٹٍ•Œ
پ@پ@ڈéچU—ھپE—ژڈéŒمپAپ@گخ“c•û‚جگ¼ŒR‚ج”ü”Z‚ج–{‹’
پ@پ@’n‚ج‘هٹ_ڈéپi‚¨‚¨‚ھ‚«‚¶‚ه‚¤پj‚ة‹ك‚¢”ü”Zگشچâپi‚ف
پ@پ@‚ج‚ ‚©‚³‚©پj•t‹ك‚ة•zگw‚µ‘چ‘هڈ«‚ج‰ئچN‚ج“’…
پ@پ@‚ً‘ز‚½‚¸پAگخ“c•ûگ¼ŒR‚ئŒˆگي‚ًژn‚ك‚éگ¨‚¢‚ً ’m
پ@پ@‚èپA‰ئچN‚حپAچQ‚ؤ‚ؤپA‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P“ْ
پ@پ@‚ةپA“؟گى‰ئچN ‚ج—¦‚¢‚é“؟گىژپٹّ–{–h‰q•”‘àپE–ٌ
پ@پ@‚R–œگl‚ئ‹¤‚ةپAچ]Œثڈé‚ً ڈo”‚µپA“ŒٹC“¹‚ً’ت‚èپA
پ@پ@”ِ’£پE”ü”Z‚ضŒü‚©‚ء‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‰ئچN‚جچ]ŒثڈéڈoگwژپAپ@‰ئچN‚حپAگ^“cژپ“¢
پ@پ@”°‚ةŒü‚©‚ء‚½ڈG’‰‚ج“؟گىژپژه—حچUŒ‚•”‘àپE–ٌ‚R
پ@پ@–œ‚W‚O‚O‚Oگl‚ةپAپuگ^“cژپ “¢”°‚ً‚â‚كپAˆêچڈ‚à‘پ‚
پ@پ@“ŒژR“¹پi’†ژR“¹پjŒo—R‚إ”ِ’£پE”ü”Z‚ةŒü‚©‚¢“ٌژè
پ@پ@‚ة•ھ‚©‚ꂽ“؟گىژپ‚جŒR‚ح”ِ’£پE”ü”Z‚ ‚½‚è‚إ
پ@پ@چ‡—¬‚·‚éپv‚ئ‚¢‚¤‰ئچN‚ج“`’B‚جژgژز‚ً‘—‚ء‚½پBپ@
پ@پ@‚µ‚©‚µپAژgژز‚حپA—کچھگى‚جچ^گ…‚ة‘j‚ـ‚ê‚ؤپA“`’B
پ@پ@‚ھ’x‚ꂽپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚P“ْپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚P“ْ‚ةپA“؟گى•û“ŒŒR
پ@پ@پ@‚جپA“؟گى‰ئچN‚ھپA”ِ’£‚جگ´ڈBڈé‚ة“’…‚·‚éپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚R“ْپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚R“ْ‚ةپA“؟گى•û“Œ
پ@پ@ŒR‚ج“؟گى‰ئچN‚ھپAپ@”ِ’£‚جگ´ڈBڈé‚ًڈo”‚·‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@“؟گى•û“ŒŒR‚ج“؟گى‰ئچN‚حپAپ@“؟گى–{‘àپi–ٌ‚R
پ@پ@–œ‚Q‚O‚O‚OگlپA“؟گى‰ئچNپAˆنˆة’¼گپA–{‘½’‰ڈںپA
پ@پ@‰ئچN”n‰ô‚èڈO“™‚جŒRپjپ@‚ئپ@ “ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج
پ@پ@“؟گى•ûگوژèگ¨‚ج–Lگb‰¶Œع‘ه–¼‚ج•ں“‡گ¨پE’r
پ@پ@“cگ¨‚جŒRپiŒv–ٌ‚S–œگlپj‚ج‘چŒvپE–ٌ‚V–œ‚Q‚O‚O‚Oگl
پ@پ@‚ج“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚إپAپ@”ü”Zچ‘پi‚ف‚ج‚ج‚‚ةپAŒ»پE
پ@پ@ٹٍ•ŒŒ§“ى•”‚ج‘ٹ“–’nˆوپj‚إپAپ@–ٌ‚T–œ‚S‚O‚O‚Oگl
پ@پ@‚جگ¼ŒR(•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ئŒˆگي‚ً‚·‚錈ˆس‚ً
پ@پ@Œإ‚ك‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚O”N‚XŒژ‚P‚R“ْ‚ةپA“؟گى‰ئچN‚حپA“؟گى
پ@پ@ڈG’‰‚ج—¦‚¢‚é“؟گىژپ•ت“®‘àپiژه—حچUŒ‚•”‘àپjپE
پ@پ@–ٌ‚R–œ‚W‚O‚O‚Oگl‚ً‘ز‚½‚¸پA”ِ’£‚جگ´ڈBڈé‚ًڈo‚ؤپAپ@
پ@پ@‚XŒژ‚P‚S“ْ‚جگ³Œكچ ‚ةپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚جڈWŒ‹‚·
پ@پ@‚éپA”ü”Zگشچâ•t‹ك‚ة“’…‚·‚éپB
پ@
پ@
پ@پ@پںپ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پvپB
پ@پ@پ،پ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚إ‚حپA‚P‚U‚O‚O
پ@پ@پ@”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚R“ْ‚ةپA“؟گى•û“ŒŒR‚ج“؟گى
پ@پ@پ@‰ئچN‚ھپA”ِ’£‚جگ´ڈBڈé‚ًڈo”‚·‚éپB
پ@
پ@پ@پœپ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚إ‚حپA“؟گى•û
پ@پ@“ŒŒR‚ج“؟گى‰ئچN‚حپAپ@“؟گىژپٹّ–{–h‰q•”‘àپE–ٌ‚R–œپ@
پ@پ@گlپ@‚ئپ@“؟گى•û“ŒŒR‚ج ‰ئچN‚ة•t‚«ڈ]‚ء‚½–Lگb‰¶Œع
پ@پ@‚جڈ”ڈ«‘ه–¼پE–ٌ‚S–œگl‚ج ŒvپE–ٌ‚V–œگl‚ج“؟گى•û“Œ
پ@پ@ŒR‚إپAپ@”ü”Zچ‘پi‚ف‚ج‚ج‚‚ةپAŒ»پEٹٍ•ŒŒ§“ى•”‚ج‘ٹ
پ@پ@“–’nˆوپj‚إپAپ@–ٌ‚W–œگl‚جگخ“c•ûگ¼ŒR‚ئŒˆگي‚ً‚·
پ@پ@‚錈ˆس‚ًŒإ‚ك‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚O”N‚XŒژ‚P‚R“ْ‚ةپA“؟گى‰ئچN‚حپA“؟گى
پ@پ@ڈG’‰‚ج—¦‚¢‚é“؟گىژپژه—حچUŒ‚•”‘àپE–ٌ‚R–œ‚W‚O‚O‚O
پ@پ@گl‚ً‘ز‚½‚¸پA”ِ’£‚جگ´ڈBڈé‚ًڈo‚ؤپAپ@‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ج
پ@پ@گ³Œكچ ‚ةپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚جڈWŒ‹‚·‚éپA”ü”Zگشچâ
پ@پ@•t‹ك‚ة“’…‚·‚éپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ةپAپ@گ¼ŒRپi•ٍ
پ@پ@چsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جڈ¬‘پگىڈGڈH‚ھپAڈ¼”ِژR‚جگw
پ@پ@’n‚جگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ً‰ں‚µ‚ج‚¯‚ؤپAڈ¼
پ@پ@”ِژR‚ة“’…‚µپAڈںژè‚ةڈ¼”ِژR‚ًگè—ج‚µپAڈ¼”ِ
پ@پ@ژRژRک[‚ة•zگw‚·‚éپB
پ@
پ@
پ@پ@پںپ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پvپB
پ@پ@پ،پ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚إ‚حپA
پ@پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ةپAگخ“c•ûگ¼ŒR
پ@پ@‚جڈ¬‘پگىڈGڈH‚ھپAڈ¼”ِژR‚جگw’n‚جگخ“c•ûگ¼
پ@پ@ŒR‚جŒRگ¨‚ً‰ں‚µ‚ج‚¯‚ؤپAڈ¼”ِژR‚ة“’…‚µپAڈںژè
پ@پ@‚ةڈ¼”ِژR‚ًگè—ج‚µپAڈ¼”ِژRژR’¸‚ة•zگw‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@ڈ¼”ِژR‚جگw’n‚حپAگخ“c•ûگ¼ŒR‚ھپAگخ“c
پ@پ@•ûگ¼ŒR‚ج–ر—ک‹PŒ³‚ج‚½‚ك‚ة—pˆس‚µ‚½گw’n‚إ
پ@پ@‚ ‚ء‚½پB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ’‹ٹشپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ةپA“؟گى•û“ŒŒR
پ@پ@‚ج“؟گى‰ئچN‚ھپA‚XŒژ‚P‚R“ْ‚ةگ´ڈBڈé‚ًڈo‚½ŒمپA‚XŒژ
پ@پ@‚P‚S“ْ‚جگ³Œكچ پA”ü”Zگشچâ•t‹ك‚ة“’…‚·‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ج’‹ٹشپAگ¼ŒRپi•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج
پ@پ@“ى‹{ژR “Œ‘¤•zگw‚ج–ر—کگ¨ پi–ٌ‚P–œ‚R‚O‚O‚Oگlپj
پ@پ@‚حپA‘هٹ_•t‹ك‚ة‚¢‚é“ŒŒRپi‰ئچN•ûپjچ‡ŒvپE–ٌ‚V
پ@پ@–œ‚Q‚O‚O‚Oگl‚ج‘هŒR‚ة‹°‚ê‚ً‚ب‚µ‚ؤگي‚ي‚¸پB
پ@
پ@
پ@پ@پںپ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پvپB
پ@پ@پ،پ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚إ‚حپA
پ@پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ةپA“؟گى‰ئچN‚حپA
پ@پ@“؟گى•û“ŒŒR‚ة“à’ت‚µ–ر—کڈGŒ³ŒR‚جگو–N‘à‚إ
پ@پ@“ى‹{ژR‚ج‰؛ژR“¹‚ً‰ں‚³‚¦‚éپAگخ“c•û‚جگ¼ŒR‚ج
پ@پ@‹gگىچL‰ئ‚ةپAپ@گخ“c•û‚جگ¼ŒR‚ج–ر—کڈGŒ³‚ج
پ@پ@“ى‹{ژR‰؛ژRپE“؟گى•û“ŒŒRچUŒ‚‚ً‘jپi‚ح‚خپj‚فپA
پ@پ@–ر—کڈGŒ³‚ًگي‚¢‚إگأٹد‚³‚¹‚é‚و‚¤‚ة—vگ؟‚µ‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@“؟گى‰ئچN‚حپAژ–‘O‚ةپAچ•“c’·گ‚ج’‡‰î
پ@پ@‚إپA“ى‹{ژRپi‚ب‚ٌ‚®‚¤‚³‚ٌپj‚ة•zگw‚·‚éگخ“c•û
پ@پ@‚جگ¼ŒR‚ج‹gگىچL‰ئپi‚«‚ء‚©‚ي‚ذ‚ë‚¢‚¦پA‚P‚T‚U‚P
پ@پ@پ|‚P‚U‚Q‚T”Nپj‚ً’²—ھ‚µپA‹gگىچL‰ئ‚ة–ر—کژپ–{‰ئ
پ@پ@—جچ‘ˆہ“g‚ج“؟گىژپ‚ج‹Nگ؟•¶پi‚«‚µ‚ه‚¤‚à‚ٌپj‚ً
پ@پ@“n‚µپA“à’ت‚³‚¹‚ؤ‚¢‚½پB
پ@
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ’‹ٹشپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ةپA”ü”Zگشچâ
پ@پ@•t‹ك‚ةڈWŒ‹‚µ‚½گ¼ŒR(•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج“؟گى
پ@پ@–{‘àپi–ٌ‚R–œ‚Q‚O‚O‚Oگlپj‚â“؟گى•ûگوژèگ¨پi–ٌ‚S
پ@پ@–œگlپjپ@‚ئپAپ@‘هٹ_ڈéâؤڈéگ¨پi–ٌ‚R–œ‚R‚T‚O‚Oگlپj
پ@پ@‚â“ى‹{ژR‚ج–ر—کگ¨پi–ٌ‚P–œ‚R‚O‚O‚Oگlپj‚ئ‚جٹش‚إپA
پ@پ@ڈ¬‹£‚èچ‡‚¢‚ھ‚ ‚ء‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‚µ‚©‚µپA‚»‚جˆê•”‚ھپAچRگ£گى‚جگي‚¢‚إ‚
پ@پ@‚ء‚½‚©‚ا‚¤‚©‚ح•s–¾‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@
پ@پ@پںپ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پvپB
پ@پ@پ،پ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚إ‚حپA
پ@پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ‚ةپA“‡چ¶‹ك‚ج—¦
پ@پ@‚¢‚é گخ“c•ûگ¼ŒR‚ھپAچRگ£گى‚جگي‚¢‚إ“؟گى•û
پ@پ@“ŒŒR‚ةڈں—ک‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“؟گى•û“ŒŒR‚ج’†‚ج“؟گى–{‘à‚ئگخ“c•û
پ@پ@پ@گ¼ŒR‚ج‘هٹ_ٹ_ڈéâؤڈéگ¨پi’“—¯ŒRپj‚ج’†‚جگخ“c
پ@پ@پ@‘à‚ھپ@چRگ£گى•t‹ك‚إگي‚¢پAگخ“c•ûگ¼ŒR‚ج“‡چ¶
پ@پ@پ@‹ك‚ج—¦‚¢‚éگخ“c‘à‚ھڈں‚آپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ–éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ–é‚ةپAپ@“ŒŒR
پ@پ@پ@پi“؟گى•ûپj‚ج“؟گى‰ئچN‚ئ“؟گى–{‘àپ@پi–ٌ‚R–œ
پ@پ@پ@‚Q‚O‚O‚Oگlپjپ@‚âپ@“؟گى•ûگوژèگ¨‚ج•ں“‡گ¨‚جŒRپ@
پ@پ@پ@پi–ٌ‚P–œ‚X‚O‚O‚Oگlپjپ@ ‚حپAپ@”ü”Zگشچâ•t‹ك‚©‚ç
پ@پ@پ@ڈoگw‚µپAپ@ٹضƒ–Œ´–~’nپEژR’†•û–ت‚ةˆع“®پi“]
پ@پ@پ@گiپj‚·‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ–é‚ةپAگ¼ŒR(•ٍ
پ@پ@پ@چsڈOپE–ر—ک•ûپj ‚جڈ¬گ¼پE‰Fٹى‘½پEگخ“cپE“‡’أگ¨
پ@پ@پ@“™‚جŒRپi–ٌ‚R–œگlپj‚حپA‘هٹ_ڈé‚ًڈo‚ؤپAٹضƒ–Œ´پ@
پ@پ@پ@–~’nپEژR’†•û–ت‚ةˆع“®پi“]گiپj‚·‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ–é‚ة•ٍچsڈOپE
پ@پ@پ@–ر—ک•ûگ¼ŒR‚جژه—حŒR‚ھگ¼•û‚جٹضƒ–Œ´پEژR’†•û
پ@پ@پ@–ت‚ةˆع“®‚µ‚½‚ج‚ً“؟گى•û“ŒŒR‚ح’m‚èپA“؟گى
پ@پ@پ@•û“ŒŒR‚جژه—حŒR‚حپA‚XŒژ‚P‚S“ْ –é‚ةپA•ٍچsڈOپE
پ@پ@پ@–ر—ک•ûگ¼ŒR‚جژه—حŒR‚ً’ا‚ء‚ؤپAگ¼•û‚جٹضƒ–
پ@پ@پ@Œ´پEژR’†•û–ت‚ةˆع“®‚·‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚XŒژ‚P‚T“ْˆبچ~‚ة—\‘z‚³‚ê‚é“ى‹{ژR‚ج–ر—ک
پ@پ@پ@گ¨‚ض‚ج“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚جچUŒ‚‚ة”ُ‚¦‚ؤپA“ى‹{
پ@پ@پ@ژR‚ج–ر—کگ¨Œم‹lŒRپiŒم‰‡ŒRپj‚ئ‚µ‚ؤگ¼ŒR(•ٍچs
پ@پ@پ@ڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج‘هٹ_ڈé‚ج‘ه•”•ھ‚جŒR‚ح‚XŒژ
پ@پ@پ@‚P‚S“ْ‚ج–é‚ةٹضƒ–Œ´–~’nپEژR’†•û–ت‚ةˆع“®
پ@پ@پ@‚µ‚½‚ج‚ً“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ح’m‚èپAپ@‚XŒژ‚P‚S“ْ–é
پ@پ@پ@‚ةپAپ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚جژه—حŒR‚حپAپ@گ¼ŒR(•ٍچs
پ@پ@پ@ڈOپE–ر—ک•ûپj‚جژه—حŒR‚ً’ا‚ء‚ؤپAٹضƒ–Œ´–~’nپE
پ@پ@پ@ژR’†•û–ت‚ةˆع“®‚·‚éپB
پ@
پ@
پ@پ@پںپ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پvپB
پ@پ@پ،پ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚إ‚حپA‚P‚U‚O‚O”N
پ@پ@پ@(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ–é‚ةپA پ@“؟گى‰ئچN‚ئ“؟گى
پ@پ@پ@•û“ŒŒR‚حپA”ü”Zگشچâ•t‹ك‚©‚çڈoگw‚µپAٹضƒ–Œ´–~
پ@پ@پ@’n•û–ت‚ةˆع“®‚·‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚إ‚حپA‚P‚U‚O‚O”N
پ@پ@(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ –é‚ةپAگخ“cژOگ¬‚âگخ“c•û
پ@پ@گ¼ŒR‚ج‘هٹ_ڈé‚ج’“—¯ŒR‚ھپA‘هٹ_ڈé‚©‚çڈoگw‚·‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚إ‚حپA‚P‚U‚O‚O”N
پ@پ@پ@(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ –é‚ة“؟گى•û“ŒŒR‚جژه—حŒR
پ@پ@پ@‚ھگ¼•û‚جٹضƒ–Œ´•û–ت‚ةˆع“®‚µ‚½‚ج‚ًگخ“c•ûگ¼
پ@پ@پ@ŒR‚ح’m‚èپAپ@‚XŒژ‚P‚S“ْ –é‚ةپAگخ“c•ûگ¼ŒR‚جژه—ح
پ@پ@پ@ŒR‚حپAپ@‘هٹ_ڈé‚ًڈo‚ؤپA“؟گى•û“ŒŒR‚ً’ا‚ء‚ؤپAگ¼
پ@پ@پ@•û‚جٹضƒ–Œ´•û–ت‚ةˆع“®‚·‚éپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ–éپB
پ@
پ@پ@پœپ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚S“ْ–é‚ةپAگ¼ŒR(•ٍ
پ@پ@چsڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج‘ه’J‹gŒp‚ھپAٹضƒ–Œ´–~’n“ىگ¼•”
پ@پ@‚ة•zگw‚·‚éپB
پ@
پ@
پ@پ@پںپ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پvپB
پ@پ@پ،پ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚إ‚حپA‚P‚U‚O‚O
پ@پ@”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚R“ْ‚ةپAگخ“c•ûگ¼ŒR‚ج‘ه’J‹g
پ@پ@Œp‚ھپAژR’†‘؛‹{ڈم‚ة•zگw‚·‚éپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚جپAپuگVگàٹضƒ–
پ@پ@پ@پ@Œ´‚جگي‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپv
پ@پ@پ@پ@‚جŒˆگيژ‚جڈَ‹µپA“®ŒüپB
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P ‚T“ْ’©پB
پ@
پ@پ@پ،پ@“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚جژه—حŒR‚âگ¼ŒR(•ٍچsڈOپE–ر—ک
پ@پ@•ûپj‚جژه—حŒR‚حپAپ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P ‚T
پ@پ@“ْ‚ج’©‚ةپAٹضƒ–Œ´–~’n“ىگ¼•”‚âژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj
پ@پ@‚ة“’…‚·‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@ژR’†‚جگي‚¢‚إ‚حپAŒˆگي‘O‚ةپAچإڈ‰‚ةپAٹضƒ–Œ´–~
پ@پ@پ@’n“ىگ¼•”‚إپA‚P‚U ‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ‚جپ@
پ@پ@پ@–é–¾‚¯‚ةپAپ@‘هٹ_•t‹ك‚©‚çˆع“®‚µ‚ؤ‚«‚½ “ŒŒR
پ@پ@پ@پi“؟گى•ûپj‚ج“؟گى–{‘àپ@‚âپ@ ٹù‚ةڈ¼”ِژRژRک[‚ة
پ@پ@پ@•zگw‚·‚éگ¼ŒR‚©‚ç“ŒŒR‚ةگQ•ش‚ء‚½ڈ¬‘پگىŒRپ@‚ئپA
پ@پ@پ@ٹù‚ةٹضƒ–Œ´–~’n“ىگ¼•”‚ة•zگw ‚·‚éگ¼ŒR(•ٍچs
پ@پ@پ@ڈOپE–ر—ک•ûپj‚ج‘ه’JŒRپ@‚ئ‚جٹش‚إچ‡گي‚ھچs‚ي‚ê
پ@پ@پ@‚éپBپ@Œ‹‰ت‚حپA‘ه’JŒR‚ھ‘S–إ‚·‚éپB
پ@
پ@
پ@پ@پںپ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پvپB
پ@پ@پ،پ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚إ‚حپAگخ“c
پ@پ@پ@•ûگ¼ŒR‚جژه—حŒR‚â“؟گى•û“ŒŒR‚جژه—حŒR‚حپA
پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P ‚T“ْ‚ج’©‚ةپAٹضƒ–Œ´
پ@پ@پ@–~’n‚ة“’…‚·‚éپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ’‹ٹش
پ@پ@پ@پ@‚جپuٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚جŒˆگيپB
پ@
پ@پ@پ،پ@ٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢‚جŒˆگي‚حپAژهگيڈê‚حژR’†‚إ‚ ‚èپAپ@
پ@پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ‚جŒك‘O‚P‚Oژچ
پ@پ@پ@‚©‚çگ³Œكچ ‚ـ‚إپAپ@“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ئ•ٍچsڈOپE–ر
پ@پ@پ@—ک•û‚جگ¼ŒR‚ئ‚جٹش‚إچs‚ي‚ê ‚½پBپ@گي‚¢‚جŒ‹‰تپA
پ@پ@پ@“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ھڈں—ک‚ً“¾‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@ٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢‚جŒˆگي‚إ‚حپAپ@ٹض‚ھŒ´–~’n‚ج“ى
پ@پ@پ@گ¼•ûŒüپE–ٌ‚Q‚‹‚چ‚ة‚ ‚éژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚إپA
پ@پ@پ@Œك‘O‚P‚Oژچ ‚©‚çگ³Œكچ ‚ـ‚إپAپ@‘هٹ_ •t‹ك‚©
پ@پ@پ@‚çˆع“®‚µ‚ؤ‚«‚½“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج“؟گى•ûگوژèگ¨پ@
پ@پ@پ@‚ج•ں“‡گ¨پ@‚âپ@“؟گى–{‘àپ@‚ئپAپ@‘هٹ_•t‹ك‚ج‘ه
پ@پ@پ@ٹ_ڈé‚©‚çˆع“®‚µ‚ؤ—ˆ‚½گ¼ŒR(•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj
پ@پ@پ@‚جڈ¬گ¼پE‰Fٹى‘½پEگخ“cپE“‡’أگ¨“™‚جŒRپ@‚ئ‚ھگي
پ@پ@پ@‚ء‚½پBپ@Œ‹‰ت‚حپAگ¼ŒR(•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جڈ¬گ¼پE
پ@پ@پ@‰Fٹى‘½پEگخ“cپE“‡’أگ¨“™‚جŒR‚حپA‘چ•ِ‚ê‚ئ‚ب‚è
پ@پ@پ@”s‘–‚µپA”s–k‚µپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ھڈں—ک‚ً“¾‚éپB
پ@
پ@پ@پœپ@ٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢‚جŒˆگي‚إ‚حپAپ@ٹض‚ھŒ´–~’n‚ج“ى
پ@پ@پ@گ¼•ûŒüپE–ٌ‚Q‚‹‚چ‚ة‚ ‚éژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚إپA
پ@پ@پ@Œك‘O‚P‚Oژچ ‚©‚çگ³Œكچ ‚ـ‚إپAپ@‘هٹ_•t‹ك ‚©‚ç
پ@پ@پ@ˆع“®‚µ‚ؤ‚«‚½“ŒŒRپi“؟گى•ûپj‚ج“؟گى•ûگوژèگ¨
پ@پ@پ@‚ج•ں“‡گ¨پ@پi–ٌ‚P–œ‚X‚O‚O‚OگlپA•ں“‡پEچ•“cپEچ×گىپE
پ@پ@پ@“،“°پE“›ˆنپE“c’†پE‰ء“،‰أ–¾پE‹‹ةچ‚’m“™پjپ@‚âپ@
پ@پ@پ@“؟گى–{‘àپ@پi–ٌ‚R–œ‚Q‚O‚O‚OگlپA“؟گى‰ئچNپAˆنˆة
پ@پ@پ@’¼گپA–{‘½’‰ڈںپA‰ئچN”n‰ô‚èڈO“™‚جŒRپjپ@‚ج
پ@پ@پ@Œv‚T–œ‚P‚O‚O‚Oگl‚جŒRپ@‚ئپAپ@‘هٹ_•t‹ك‚ج‘هٹ_ڈé
پ@پ@پ@‚©‚çˆع“®‚µ‚ؤ—ˆ‚½گ¼ŒR(•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جڈ¬
پ@پ@پ@گ¼پE‰Fٹى‘½پEگخ“cپE“‡’أگ¨“™‚ج–ٌ‚R–œگl‚جŒRپ@
پ@پ@پ@‚ئ‚ھ‘ˆ‚ء‚½گي‚¢‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ‹‰ت‚حپAگ¼ŒR(•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûپj‚جڈ¬گ¼پE
پ@پ@پ@‰Fٹى‘½پEگخ“cپE“‡’أگ¨“™‚جŒR‚حپA‘چ•ِ‚ê‚ئ‚ب‚è
پ@پ@پ@”s‘–‚µپA”s–k‚µپA“؟گى•û‚ج“ŒŒR‚ھڈں—ک‚ً“¾‚éپB
پ@
پ@
پ@پ@پںپ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پvپB
پ@پ@پ،پ@پuڈ]—ˆگàپi“`گàپj‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢پv‚إ‚حپAٹضƒ–
پ@پ@Œ´‚جگي‚¢‚جŒˆگي‚حپAژهگيڈê‚جٹضƒ–Œ´–~’n‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@‚P‚U‚O‚O”NپiŒc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ‚جŒك‘O‚Wژچ ‚©‚ç
پ@پ@ŒكŒم‚Qژچ ‚ـ‚إپA“؟گى•û“ŒŒR‚ئگخ“c•ûگ¼ŒR‚ئ‚ج
پ@پ@ٹش‚إچs‚ي‚ê ‚½پBپ@گي‚¢‚جŒ‹ ‰تپA“؟گى•û“ŒŒR‚ھ
پ@پ@ڈں—ک‚ً“¾‚éپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚جپAپuگVگàٹضƒ–Œ´
پ@پ@پ@پ@‚جگي‚¢پi= ‘هٹ_پEژR’†‚جگي‚¢پjپv‚ج
پ@پ@پ@پ@ŒˆگيŒم‚جڈَ‹µپA“®ŒüپB
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P ‚V“ْپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚V“ْ‚ةپA“؟گى•û“ŒŒR
پ@پ@پ@‚ھپAپ@•ٍچsڈOپE–ر—ک•û‚جگ¼ŒR‚ج‹كچ]چ‘‚جگخ“c
پ@پ@پ@ژOگ¬‚جچ²کaژRڈé‚ًچU‚ك‚ؤپA—ژڈ邳‚¹‚éپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P ‚X“ْپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚X“ْ‚ةپA “؟گى•û“ŒŒR‚جپA
پ@پ@“؟گى‰ئچN‚ھپA‘گ’أ‚ة“ü‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚X“ْ‚ةپA•ٍچsڈOپE–ر—ک
پ@پ@•ûگ¼ŒR‚جڈ¬گ¼چs’·‚ھپA‘§گپژRژR’†‚إ•ك‚¦‚ç‚ê‚éپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ ‚Q‚P“ْپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚Q‚P“ْ‚ةپA•ٍچsڈOپE–ر—ک
پ@پ@پ@•ûگ¼ŒR‚جگخ“cژOگ¬‚ھپAپ@Œأ‹´‘؛پ@پiŒ»پEژ ‰êŒ§
پ@پ@پ@–ط”V–{’¬‚ج‘ٹ“–’nˆوپj‚إ“؟گى•û“ŒŒR‚ة•ك‚¦‚ç
پ@پ@پ@‚ê‚éپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ ‚Q‚R“ْپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚Q‚R“ْ‚ةپA•ٍچsڈOپE–ر
پ@پ@پ@—ک•ûگ¼ŒR ‚ج‘هٹ_ڈé‚جژc—¯ŒR‚ھچ~•ڑ‚µپA‘هٹ_ڈé
پ@پ@پ@‚ھٹJڈ邳‚ê‚éپB
پ@
پ@پ@پœپ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚P‚T“ْ‚ةٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢
پ@پ@پ@‚جژR’†پi‚â‚ـ‚ب‚©پj‚جگي‚¢‚إ‚ج“Œگ¼—¼ŒR‚جŒˆ
پ@پ@پ@گي‚إ•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûگ¼ŒR‚ج”s–k‚جگ–گ¨‚ھŒˆ
پ@پ@پ@‚µ‚½Œم‚àپAپ@•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûگ¼ŒR ‚ج•ںŒ´پEٹ_Œ©پE
پ@پ@پ@ŒF’JپEڈHŒژپE‘ٹ—ا‚ج‘هٹ_ڈéژc—¯گ¨پi–ٌ‚R‚T‚O‚O
پ@پ@پ@گlپj‚حپAپ@گي‚¢‚ً‘±‚¯پA پ@گQ•ش‚è‚àڈo‚ؤپAچإŒم‚ةپA
پ@پ@پ@‚XŒژ‚Q‚R“ْ‚ةپA“؟گى•û“ŒŒR‚ةچ~•ڑ‚µپA‘هٹ_ڈé‚ح
پ@پ@پ@ٹJڈé‚·‚éپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ ‚Q‚R“ْپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚XŒژ‚Q‚R“ْ‚ةپA •ٍچsڈOپE–ر
پ@پ@پ@—ک•ûگ¼ŒR‚جˆہچ‘ژ› Œbàùپi‚ ‚ٌ‚±‚‚¶ ‚¦‚¯‚¢پj‚ھپA
پ@پ@پ@‹پi“sپj‚إ•ك‚¦‚ç‚ê‚éپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚P‚OŒژ‚P“ْپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”Nپj‚P‚OŒژ‚P“ْ‚ةپA“؟گى•û“Œ
پ@پ@پ@ŒR‚ج“؟گى‰ئچN‚حپAپ@•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûگ¼ŒR‚جپA
پ@پ@پ@گخ“cژOگ¬پAڈ¬گ¼چs’·پAˆہچ‘ژ› Œbàùپi‚ ‚ٌ‚±‚‚¶
پ@پ@پ@‚¦‚¯‚¢پj‚ًپA‹پi“sپjکZڈً‰حŒ´‚إ ڈˆŒY‚·‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚O”N(Œc’·‚T”NپjپB
پ@
پ@پ@پœپ@گيŒمڈˆ—‚إپA پ@“؟گى•û“ŒŒR‚ج“؟گى‰ئچN‚حپAپ@
پ@پ@پ@•ٍچsڈOپE–ر—ک•ûگ¼ŒR‚ج ‘ه–¼پE•گڈ«‚©‚ç–vژû‚µ‚½
پ@پ@پ@–ٌ‚W‚Oپ“‚ج—ج’n‚ًپAگي‚¢‚جڈں—ک‚ج‰¶ڈـ‚ئ‚µ‚ؤپAپ@
پ@پ@پ@“؟گى•û“ŒŒR‚جپA‰ئچN‚ة•t‚«ڈ]‚ء‚½–Lگb‰¶Œع
پ@پ@پ@‚ج‘ه–¼(ٹO—l‘ه–¼پjپE•گڈ«‚ة—^‚¦‚ث‚خ‚ب‚ç‚ب
پ@پ@پ@‚©‚ء‚½پB
پ@
پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚R”N(Œc’·‚W”NپjپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‚P‚U‚O‚R”N(Œc’·‚W”Nپj‚QŒژ‚P‚Q“ْ‚ةپA “؟گى‰ئچN
پ@پ@پ@‚حپAپ@گھˆخ‘هڈ«ŒR‚ئ‚ب‚èپAپ@چ]Œث–‹•{‚ًٹJ‚پB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژjژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ڈéپ@
پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ëپjپB
پ@
پ،پ@ڈéپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ڈé پi‚µ‚ëپjپB
پ،پ@پs“ْ–{‚جڈéپtپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“Tپ@‚P‚P‚W‚R‚TپB
پ@
پ پ@ˆہ“yڈéپ@‰و‘œƒAƒ‹ƒoƒ€پ@‚m‚ڈپD‚PپB
پ پ@ڈ¬’Jڈéپ@‰و‘œƒAƒ‹ƒoƒ€ ‚m‚ڈپD‚PپB
پ@
پ پ@گD“cژپپ@‰و‘œƒAƒ‹ƒoƒ€پ@‚m‚ڈپD‚PپB
پ پ@گD“cژپپ@‰و‘œƒAƒ‹ƒoƒ€پ@‚m‚ڈپD ‚QپB
پ@پ@پiگ´ڈBڈéپA‘¼پjپB
پ پ@–Lگbژپپ@‰و‘œƒAƒ‹ƒoƒ€پ@‚m‚ڈپD‚PپB
پ پ@–Lگbژپپ@‰و‘œƒAƒ‹ƒoƒ€پ@‚m‚ڈپD‚QپB
پ@پ@پi•ڑŒ©ڈéپAگخٹ_ژRˆê–éڈéپA
پ@پ@ ڈ¬“cŒ´ڈéپAچ²کaژRڈéپA
پ@پ@ •ى’ٌژRڈéپAمعٹy‘وپA‘¼پjپB
پ پ@“؟گىژپپ@‰و‘œƒAƒ‹ƒoƒ€پ@‚m‚ڈپD‚PپB
پ@پ@پiچ]ŒثڈéپA‘¼پjپB
پ پ@•گ“cژپپ@‰و‘œƒAƒ‹ƒoƒ€پ@‚m‚ڈپD‚PپB
پ@پ@پiچ‚“Vگ_ڈéپA‘¼پjپB
پ@
پ@
پ،پ@ڈéپB
پ@پ@پ،پ@ڈéپ@پi‚µ‚ëپj‚ئ‚حپAپ@••Œڑ—جژه‚جŒRژ–‹’“_پA“
پ@پ@ پ@ژ،‹’“_پA‹ڈڈZ‹’“_ پAچشپi‚ئ‚è‚إپj‚إ‚ ‚éپB
پœپ@چ]Œث–‹•{‚جˆêچ‘ˆêڈé—ك‚ھڈo‚³‚ê‚é‘O‚جپA
پ@پ@ پ@گيچ‘ژ‘مپi= ژ؛’¬ژ‘مŒمٹْپjپAˆہ“y“چژRژ‘مپA
پ@پ@ پ@چ]Œثژ ‘مڈ‰ٹْ‚ةŒکŒإپi‚¯‚ٌ‚²پj‚بڈé‚ھ‘½‚‚آ
پ@پ@ پ@‚‚ç‚êپA‚»‚جŒڑ•¨‚ھŒ»چف‘½‚ژc‚ء‚ؤ‚¢‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ،پ@ڈé‚ة‚حپAپ@ژRڈéپi‚â‚ـ‚¶‚ëپAژR‚ةŒڑ‚ؤ‚½ڈéپjپ@‚ئپA
پ@پ@پ@پ@•½ڈéپi‚ذ‚炶‚ëپA•½’n‚ةŒڑ‚ؤ‚½ڈéپjپ@‚ھ‚ ‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@ڈéپB
پ@پ@پ،پ@ڈé پi‚µ‚ëپj‚حپAپ@گي‚¤‚½‚كپAڈéژه‚جŒ ˆذ‚ًژ¦‚·
پ@پ@پ@پ@‚½‚ك‚ة‚ ‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈé‚ة‚حپAگي‚¤‚½‚كپAŒ ˆذ‚ًژ¦‚·‚½‚كپA‚½‚
پ@پ@پ@پ@‚³‚ٌ‚ج•‘‘ن‘•’u‚ھ‚ ‚ء‚½پB
پ@
پ@پ@پ،پ@ڈé‚حپAپ@••Œڑ—جژه‚جŒRژ–‹’“_پA“ژ،‹’“_پA‹ڈ
پ@پ@پ@پ@ڈZ‹’“_‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{‚إ‚حپAپ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚إپAپ@“ْ–{ٹe’n‚ج
پ@پ@پ@پ@••Œڑ—جژه‚ھپAڈé‚ًŒڑ‚ؤ‚½‚èپA‘‰ü’z‚µ‚½پBپ@•PکH
پ@پ@پ@پ@ڈé‚ً‚ح‚¶‚كپAچ]Œثژ‘م ڈ‰ٹْ‚ةپAڈé‚جŒڑ’zƒuپ[ƒ€
پ@پ@پ@پ@‚ھ‹N‚«‚½پB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ،پ@Œٹ‘¾ڈOپB
پ@پ›پ@“ْ–{‚ج—DڈG‚بگخچHڈW’cپB
پ@پ@پ،پ@Œٹ‘¾ڈOپi‚ ‚ج‚¤‚µ‚م‚¤پj‚حپAپ@“ْ–{‚ج—DڈG‚ب
پ@پ@پ@پ@گخچHپi‚¢‚µ‚پjڈW’c‚إ‚ ‚èپAپ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚إ
پ@پ@پ@پ@‚حپAڈé‚جگخٹ_‚ب‚اپAڈé‚ج’zڈé‚ةچvŒ£‚µ‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ»‘م“ْ–{‚إ‚حپAچ‚‘¬“¹کH‚ج‘د‹vگ«‚ج
پ@پ@پ@پ@‚ ‚éٹî‘b“y‘ن‚ج‘¢چى‚ب‚ا‚ةچ‚‚¢•]‰؟‚ً“¾
پ@پ@پ@پ@‚ؤ‚¢‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@’zڈé‚ج–¼ژè‚جپA“،“° چ‚ŒصپB
پ@پ@پ،پ@“،“°چ‚Œصپi‚ئ‚¤‚ا‚¤‚½‚©‚ئ‚çپj‚حپAپ@ڈé‚جپA’zڈé
پ@پ@پ@پ@‚ج–¼ژè‚إ‚ ‚ء‚½پB
پœپ@“،“° چ‚Œص‚حپA“ْ–{‚إˆê”شپAڈé‚ً‚آ‚‚ء‚½’j
پ@پ@پ@پ@‚ئŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
پ@پ@پœپ@“،“° چ‚Œص‚حپAپ@“G‚ھچU‚ك‚é‹C‚ً‹N‚±‚³‚¹‚ب‚¢
پ@پ@پ@پ@ڈé‚ً‚آ‚‚ء‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ،ژ،ڈéپi‚¢‚ـ‚خ‚肶‚ه‚¤پj‚ج‚و‚¤‚ةپAپ@‚T‚O‚چ
پ@پ@پ@پ@•ˆبڈم‚ج•چL‚¢–xپi–x‚ھچL‚¢‚ئ“G‚ج–î‚ج–½’†
پ@پ@پ@پ@—¦‚ھ‚ي‚é‚‚ب‚éپjپAپ@‚ئ‚ؤ‚àچ‚‚¢گخٹ_پi“G‚ھ‚و‚¶
پ@پ@پ@پ@“o‚é‚ج‚ً‚ ‚«‚ç‚ك‚éپjپAپ@چإ‹–hŒن‚ج’تکH‚جe
پ@پ@پ@پ@پi‚ـ‚·پj‹و‰وپi“G‚ھ‘O‚ةگi‚ك‚ب‚¢پjپ@‚ب‚ا‚جچH•v
پ@پ@پ@پ@‚ًڈé‚ةژ{پi‚ظ‚ا‚±پj‚µ‚½پB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@ڈé‚جپA“VژçپB
پ@پ›پ@ڈé‚ج’†گS‚ئ‚ب‚éچ‚‘wŒڑ’z‚جŒڑ•¨پB
پ@پ@پ،پ@“Vژçپi‚ؤ‚ٌ‚µ‚مپj‚حپAپ@ڈé‚ج’†گS‚ئ‚ب‚éچ‚‘wŒڑ
پ@پ@پ@پ@’z‚جŒڑ•¨‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@“Vژç‚حپAڈé‚جƒVƒ“ƒ{ƒ‹‚إ‚ ‚èپAپ@ڈéژه‚جŒ
پ@پ@پ@پ@—ح‚جڈغ’¥‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@پ@
پ@پ@پ،پ@چ]Œثڈé‚ج“Vژç‚حپAپ@‚R‚آ‚ ‚èپA“ٌ“xŒڑ‚ؤ‘ض‚¦
پ@پ@پ@‚ç‚ꂽپBپ@‘¦‚؟پA“؟گى‰ئچN‚جŒڑ‚ؤ‚½“Vژç‚ًڈG’‰
پ@پ@پ@‚ھŒڑ‚ؤ‘ض‚¦پA“؟گىڈG’‰‚جŒڑ‚ؤ‚½“Vژç‚ً“؟گى‰ئ
پ@پ@پ@Œُ‚ھŒڑ‚ؤ‘ض‚¦‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰ئŒُ‚جŒڑ‚ؤ‚½چ]Œثڈé‚ج“Vژç‚حپAپ@چ]Œثژ
پ@پ@پ@‘م‘Oٹْ‚ج–¾—ïپi‚ك‚¢‚ê‚«پj‚ج‘ه‰خ‚إڈؤژ¸‚µپA‚»
پ@پ@پ@‚جŒمپAچؤŒڑ‚³‚ꂸپAŒ»چف‚ة“‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پںپ@—lپX‚بڈéپB
پ،پ@•PکHڈéپB
پ@پ@پ،پ@•PکHڈéپ@پi‚ذ‚ك‚¶‚¶‚ه‚¤پj‚حپA Œ³پXپA”d–پچ‘پi‚ح‚è‚ـ‚ج‚‚ةپA
پ@پ@•؛ŒةŒ§“ى•”پj‚جژçŒىپEگشڈ¼ژپ‚ج‘®ڈé‚إ‚ ‚ء‚½‚ھپAپ@گشڈ¼ژپ
پ@پ@•ھ‰ئ‚جڈ¬ژ›ژپ‚جڈé‚ئ‚ب‚èپAپ@ڈ¬ژ›ژپ–إ–S‚ج‚P‚T‚W‚O”N‚ة‰Hژؤ
پ@پ@ڈG‹gپi–LگbڈG‹gپj‚ھڈéژه‚ئ‚ب‚è’†چ‘’n•û‰“گھ‚جچھ‹’’n‚ئ‚µ
پ@پ@‚ؤ‘’z‚µپAپ@‚»‚جŒمپA‚P‚U‚O‚P”N‚ة’r“c‹Pگپi‚¢‚¯‚¾‚ؤ‚é‚ـ‚³پj
پ@پ@‚ج‹ڈڈé‚ئ‚ب‚èپAپ@چ]Œثژ‘مڈ‰ٹْ‚ةپA“؟گى‰ئچNپiچ]Œث–‹•{پj‚ھپA
پ@پ@’r“c‹Pگ‚ة–½پi‚ك‚¢پj‚¶پAپ@“؟گىژپپiچ]Œث–‹•{پj‚جگ¼“ْ–{‚ج
پ@پ@ŒRژ–‹’“_‚ئ‚·‚邽‚كپA‘ه‘‰ü’z‚µ‚ؤپA‚P‚U‚O‚X”N‚ةٹ®گ¬‚³‚¹
پ@پ@‚½ڈéپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@چ]ŒثڈéپB
پ@پ@پ،پ@چ]Œثڈé‚حپAپ@چ]Œث–‹•{‚ج –{‹’’nپA–{ڈéپ@‚إ‚ ‚èپA“؟گىڈ«ŒR
پ@پ@‰ئپ@ پi“؟گى ژپڈ@‰ئپA“؟گىژپ–{‰ئپj‚ج‹ڈڈé‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@چ]Œثڈéپ@پi‚¦‚ا‚¶‚ه‚¤پj‚حپAپ@‚P‚T‚X‚O”N‚ةپA–LگbڈG‹g‚ج
پ@پ@–½—ك‚إٹض“Œ‚ةˆع••‚³‚ꂽ“؟گى‰ئچN‚ھپA’zڈé‚ًژn‚كپA‚»‚ج
پ@پ@ŒمپA“؟گىژپ‚ھپA–ٌ‚T‚O”N‚ً‚©‚¯‚ؤٹ®گ¬‚³‚¹‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@“؟گىژپ‚ھپA‚P‚U‚O‚O”N‚ج“V‰؛•ھ‚¯–ع‚جگي‚¢پiٹض‚ھŒ´‚جگي‚¢پA
پ@پ@‘¼پj‚إڈں—ک‚ً“¾پAپ@“ْ–{‚جگژ،‚جژہŒ ‚ًڈ¶ˆ¬‚µ‚½‚ج‚؟پAپ@‘Sچ‘
پ@پ@‚ج‘ه–¼پi”ثژهپj‚ةپAژè“`‚¢‚جڈé•پگ؟پi‚µ‚ë‚ش‚µ‚ٌپj‚ً‚³‚¹پAپ@“ْ–{
پ@پ@ˆê‚ج‹K–ح‚جڈé‚ئ‚ب‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ]Œثڈé‚ج“ْ–{ˆê‚ج“Vژç‚حپAچ]Œثژ‘م‘Oٹْ ‚ةپAڈؤژ¸‚µپA
پ@پ@‚»‚êˆبŒمچؤŒڑ‚³‚ꂸپAپ@‚ـ‚½پA–‹––‚ج‘ه‰خ‚إپAچ]Œثڈé‚جŒڑ•¨
پ@پ@‚جˆê•”‚ھڈؤژ¸‚µ‚½پB
پ@پ@پ@پ@چ]Œثڈé‚حپAپ@–¾ژ،ژ‘مˆبŒمپAچc‹ڈپi‚±‚¤‚«‚هپj‚ئ‚µ‚ؤژg‚ي‚êپAپ@
پ@پ@Œ»چف‚ةژٹ‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ،پ@ˆہ“yڈéپB
پ@پ@پ،پ@ˆہ“yڈéپ@پi‚ ‚أ‚؟‚¶‚ه‚¤پj‚حپAپ@‹كچ]چ‘پi‚¨‚¤
پ@پ@پ@پ@‚ف‚ج‚‚ةپAŒ»پEژ ‰êŒ§‚ج‘ٹ“–’nˆوپj‚ة‚ ‚ء‚½پA
پ@پ@پ@پ@گD“cگM’·پi‚¨‚¾‚ج‚ش‚ب‚ھپjپ@‚ج–{‹’’n‚جڈé
پ@پ@پ@پ@پi–{ڈéپi‚ظ‚ٌ‚¶‚ه‚¤پjپjپA‹ڈڈé‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ پ@ˆہ“yڈéپ@‰و‘œƒAƒ‹ƒoƒ€پ@‚m‚ڈپD‚PپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@ڈ¬’JڈéپB
پ@پ@پ،پ@ڈ¬’Jڈéپ@پi‚¨‚¾‚ة‚¶‚ه‚¤پj‚حپAپ@–k‹كچ]پ@پi‚«‚½
پ@پ@پ@پ@‚¨‚¤‚فپAŒ»پEژ ‰êŒ§–k•”‚ج‘ٹ“–’nˆوپjپ@‚ة‚
پ@پ@پ@پ@‚ء‚½پAگَˆن’·گپi‚ ‚´‚¢‚ب‚ھ‚ـ ‚³پj‚ج–{‹’’n
پ@پ@پ@پ@‚جڈéپi–{ڈéپi‚ظ‚ٌ‚¶‚ه‚¤پjپj‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ پ@ڈ¬’Jڈéپ@‰و‘œƒAƒ‹ƒoƒ€پ@ ‚m‚ڈپD‚PپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@–kڈ¯ڈé پB
پ@پ@پ،پ@–kڈ¯ڈéپ@پi‚«‚½‚ج‚µ‚ه‚¤‚¶‚ه‚¤پj‚حپAپ@‰z‘Oپ@پi‚¦
پ@پ@پ@پ@‚؟‚؛‚ٌپAŒ»پE•ںˆنŒ§–k•”‚ج‘ٹ“–’nˆوپjپ@‚ة‚
پ@پ@پ@پ@‚ء‚½پAژؤ“cڈں‰ئ‚ج–{‹’’n‚جڈéپi–{ڈéپj‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@•ڑŒ©ڈéپB
پ@پ@پ،پ@•ڑŒ©ڈéپi‚س‚µ‚ف‚¶‚ه‚¤پj‚حپAپ@‚P‚T‚X‚Q”Nپi•¶ک\
پ@پ@پ@پ@Œ³”Nپj‚©‚ç‚P‚U‚Q‚R”NپiŒ³کa‚X”Nپj‚ـ‚إپA‹پi‚«
پ@پ@پ@پ@‚ه‚¤پA‹“sپj“ى•”پiŒ»پE‹“sژs•ڑŒ©‹وپj‚ة‚ ‚ء
پ@پ@پ@پ@‚½ڈé‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•ڑŒ©ڈé‚ة‚حپAپ@–LگbژwŒژ•ڑŒ©ڈéپ@پi‚ئ‚و
پ@پ@پ@پ@‚ئ‚ف‚µ‚°‚آ‚س‚µ‚ف‚¶‚ه‚¤پA‚P‚T‚X‚Q”Nپ|‚P‚T‚X‚U
پ@پ@پ@پ@”NپjپAپ@–Lگb–ط”¦ژR•ڑŒ©ڈéپ@پi‚ئ‚و‚ئ‚ف‚±‚ح‚½
پ@پ@پ@پ@‚â‚ـ‚س‚µ‚ف‚¶‚ه‚¤پA‘Oٹْ–ط”¦ژR•ڑŒ©ڈéپA‚P‚T
پ@پ@پ@پ@‚X‚V”Nپ|‚P‚U‚O‚O”NپjپAپ@“؟گى–ط”¦ژR•ڑŒ©ڈé
پ@پ@پ@پ@پi‚ئ‚‚ھ‚ي‚±‚ح‚½‚â‚ـ‚س‚µ‚ف‚¶‚ه‚¤پAŒمٹْ–ط
پ@پ@پ@پ@”¦ژR•ڑŒ©ڈéپA‚P‚U‚O‚Q”Nپ[‚P‚U‚Q‚R”Nپj‚ھ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–ط”¦ژR•ڑŒ©ڈéگص’n‚جژه—v•”‚حپAŒ»چفپA
پ@پ@پ@پ@“Vچc—ث‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@معٹy‘وپBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ،پ@معٹy‘وپ@پi‚¶‚م‚ç‚‚ؤ‚¢پA‚¶‚م‚ç‚‚¾‚¢پA‚P‚T‚W‚V
پ@پ@پ@پ@”Nپ[‚P‚T‚X‚T”Nپj‚حپA پ@–LگbڈG‹g‚ھ ‹پi‚«‚ه‚¤پA
پ@پ@پ@پ@‹“sپj‚ة‘¢‰c‚µ‚½ڈéٹsŒ`ژ®‚ج“@‘î‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@معٹy‘و‚حپA‹“sŒنڈٹ‚جگ¼‘¤‚ج’nˆو‚ة‚
پ@پ@پ@پ@‚ء‚½پB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ،پ@گخٹ_ژRˆê–éڈéپB
پ@پ@پ،پ@گخٹ_ژRˆê–éڈé پi‚¢‚µ‚ھ‚«‚â‚ـ‚¢‚؟‚₶‚ه‚¤پA
پ@پ@پ@پ@= گخٹ_ژRڈéپj ‚حپA ‚P‚T‚X‚O”Nپi“Vگ³‚P‚W”Nپj‚ةپA
پ@پ@پ@ڈ¬“cŒ´چ‡گي’†‚ةپAڈ¬“cŒ´ڈé‚ًŒ©‰؛‚ë‚·گخٹ_
پ@پ@پ@ژR‚ةپA–LگbڈG‹g‚ھ’zڈ邵‚½ڈé‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@‘هچمڈéپB
پ@پ@پ،پ@‘هچمڈé‚ة‚حپAپ@–LگbڈG‹g’zڈé‚ج–Lگb‘هچم
پ@پ@پ@پ@ڈéپ@‚ئپAپ@“؟گىژپ’zڈé‚ج“؟گى‘هچمڈé‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@Œ»چف‚ج“؟گى‘هچمڈéپi‚¨‚¨‚³‚©‚¶‚ه‚¤پj‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@‘هچم‚ج‰ؤ‚جگw‚إڈؤژ¸‚µ‚½پA–LگbڈG‹g‚ھ’zڈé
پ@پ@پ@پ@‚µ‚½–Lگb‘هچمڈé‚جگص’n پi“O’ê“I‚ة”j‰َ‚³‚ê
پ@پ@پ@پ@‚½پjپ@‚ةپAپ@چ]Œث–‹•{‚ھپAگ¼“ْ–{‚جŒRژ–‹’ “_
پ@پ@پ@پ@‚ئ‚·‚邽‚كپAپ@گV‚½‚ةŒڑ’z‚µ‚½ڈé‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‘هچمڈéپ@پi‚¨‚¨‚³‚©‚¶‚ه‚¤پj‚حپA Œ»چف‚ج‘هچم
پ@پ@پ@پ@•{’†‰›‹و‚ة‚ ‚èپA “؟گى‘هچمڈé‚جˆâچ\‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پœپ@’A‚µپAŒ»چف‚ج‘هچمڈé“Vژçپi‚ؤ‚ٌ‚µ‚مپj‚حپA
پ@پ@پ@پ@–Lگb‘هچمڈé‚ج“Vژç‚ً•œŒ³‚µ‚½‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚X‚R‚P”Nپiڈ؛کa‚U”Nپj‚ةپA‘هچم‰ؤ‚جگwگ}
پ@پ@پ@پ@› •—پi‚¨‚¨‚³‚©‚ب‚آ‚ج‚¶‚ٌ‚¸‚ر‚ه‚¤‚شپA‘هچم
پ@پ@پ@پ@ڈé“Vژçٹt‘ پj‚ب‚ا‚ًژQچl‚ةپA–Lگb‘هچمڈé‚ج
پ@پ@پ@پ@“Vژç‚ھچؤŒڑ‚³‚ê‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@–Lگb‘هچمڈéپB
پ@پ@پ،پ@–Lگb‘هچمڈéپ@پi‚ئ‚و‚ئ‚ف‚¨‚¨‚³‚©‚¶‚ه‚¤پj‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@گغ’أپ@پi‚¹‚ء‚آپAŒ»پE‘هچم•{–kگ¼•”‚ج‘ٹ“–
پ@پ@پ@پ@’nˆوپjپ@‚ة‚ ‚ء‚½پA–Lگbژپ‚ج–{‹’’n‚جڈé
پ@پ@پ@پ@پi–{ڈéپjپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–Lگb‘هچمڈé‚حپA‚P‚T‚W‚X”Nچ ‚ةٹ®گ¬‚µپAپ@
پ@پ@پ@پ@–LگbڈG‹g‚ج–{ڈéپi–{‹’’n‚جڈéپj‚ئ‚ب‚èپAپ@
پ@پ@پ@پ@ڈG‹gژ€ŒمپA–LگbڈG—ٹ‚ج–{ڈé‚ئ‚ب‚éپB
پ@پ@پœپ@‚P‚U‚P‚T”N‚ج‘هچم‰ؤ‚جگw‚إ–Lگbژپ–إ–SŒمپA
پ@پ@پ@پ@–Lگb‘هچمڈé‚حپA“؟گىژپ‚ة‚و‚è”j‰َ‚³‚ê‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@“؟گى‘هچمڈéپB
پ@پ@پ،پ@“؟گى‘هچمڈéپ@پi‚ئ‚‚ھ‚ي‚¨‚¨‚³‚©‚¶‚ه‚¤پj ‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@گغ’أپ@پi‚¹‚ء‚آپAŒ»پE‘هچم•{–kگ¼•”‚ج‘ٹ“–
پ@پ@پ@پ@’nˆوپjپ@‚ة‚ ‚éپA–Lگb‘ه چمڈé‚جگص’n پ@پi“O
پ@پ@پ@پ@’ê“I‚ة”j‰َ‚³‚ꂽ–Lگb‘هچâڈé‚جگص’nپj‚ة
پ@پ@پ@پ@’zڈ邳‚ꂽپA“؟گىژپ‚جگ¼چ‘‚ج‹’“_‚جڈé‚إ
پ@پ@پ@پ@‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پœپ@–‹––‚ةپA•è’Cگي‘ˆژپA “؟گى‘هچمڈé‚جŒڑ
پ@پ@پ@پ@’z•¨‚حپAڈؤژ¸‚·‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پôپôپ@ڈé‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢ٹضکAƒhƒL
پ@پ@پ@پ@ƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پAƒhƒ‰ƒ}پA‰f ‰وپBپ@
پ@
پڑپ@ڈé‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢ٹضکAƒhƒLƒ…
پ@پ@ ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پBپ@
پ@
پ،پ@گV“ْ–{•—“y‹LƒXƒyƒVƒƒƒ‹پ@
پ@پ@ پwپ@”ü‚جڈéپ@گي‚جڈéپ@پxپBپ@
پ@ پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚P‚P”N‚SŒژ‚P“ْپE–{•ْ‘—پE
پ@پ@پ@پ@ƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[”ش‘gپjپB
پ@پ،پ@“ْ–{‚جڈé‚جڈعچׂâ“ْ–{ٹe’n‚جڈé‚ج‚ة‚آ
پ@پ@‚¢‚ؤڈq‚ׂéپB
پ@
پ،پ@ƒUپEƒvƒŒƒ~ƒAƒ€پ@
پ@پ@ پwپ@‚و‚ف‚ھ‚¦‚éچ]Œثڈéپ@پxپB
پ@ پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚P‚S”N‚PŒژ‚S“ْپE–{•ْ‘—پE
پ@پ@پ@پ@ƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[”ش‘gپjپB
پ@پ،پ@چ]Œثڈé‚جڈعچׂة‚آ‚¢‚ؤڈq‚ׂéپB
پ@پ،پ@چ]Œثڈé‚ج–{ٹغŒن“a‚ًپAپ@چ]Œثژ‘م‚ةگ»چى
پ@پ@‚³‚ꂽŒڑ’zگ}–تپA‰؛ٹG“™‚ةٹî‚أ‚¢‚ؤپA‚b‚f
پ@پ@پiƒRƒ“ƒsƒ…پ[ƒ^پEƒOƒ‰ƒtƒBƒbƒNƒXپj‚إپAچؤŒ»‚µ‚½پB
پ@پ،پ@گش•نژ–Œڈپi‚P‚V‚O‚Pپ`‚P‚V‚O‚R”Nپj‚جپAچ]Œثڈé
پ@پ@‚جڈ¼”VکL‰؛‚جگَ–ى“àڈ “ھپi’·‹é پj‚جگnڈ
پ@پ@پi‚ة‚ٌ‚¶‚ه‚¤پj‚ة‚آ‚¢‚ؤڈq‚ׂéپB
پ@پ،پ@چ]Œث–‹•{‚جڈ«ŒR‚جˆê“ْ‚جگ¶ٹˆ‚ًڈq‚ׂéپB
پ@
پ،پ@—ًژj”éکbƒqƒXƒgƒٹƒAپ@
پ@پ@پwپ@گيچ‘پ@‚¨ڈé’aگ¶‚à‚ج‚ھ‚½‚èپ`
پ@پ@پ@ڈé‚أ‚‚èƒvƒچƒtƒFƒbƒVƒ‡ƒiƒ‹پ@
پ@پ@پ@•گڈ«پE“،“°چ‚Œصپ`پ@پxپBپ@
پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚P‚Q”N پi‚g‚Q‚S”Nپj‚SŒژ
پ@پ@پ@‚P‚P“ْپE–{•ْ‘—پEƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[”ش‘gپjپB
پ@پ،پ@’zڈé‚ج–¼گl‚ج“،“°چ‚Œصپi‚ئ‚¤‚ا‚¤‚½‚©‚ئ‚çپj
پ@پ@‚ھپAˆہ“y“چژRژ‘م‚âچ]Œثژ‘مڈ‰ٹْ‚ةŒgپi‚½
پ@پ@‚¸‚³پj‚ي‚ء‚½پAچ]ŒثڈéپA“؟گىپE‘هچمڈé‚ً‚ح‚¶
پ@پ@‚كپA‚Q‚Oˆبڈم‚جڈé‚ج’zڈé‚جکb‚ھ“oڈê‚·‚éپB
پ@
پ،پ@گوگl‚½‚؟‚ج’ê—حپ@’mŒbگٍپ@
پ@پ@پwپ@ƒLƒƒƒٹƒAƒAƒbƒv‚ج‹ةˆس‚ئ‚حپHپ@
پ@پ@پ@پ`“،“°چ‚Œصپ@Œµ‚µ‚¢گ¢‚ًچs‚«
پ@پ@پ@”²‚¯پIپ@پxپBپ@پ@
پ@پ@ پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚P‚T”N‚SŒژ‚P‚S“ْپE
پ@پ@ پ@–{•ْ‘—پEƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[”ش‘gپjپB
پ@پ،پ@“،“° چ‚Œص‚جڈé‚أ‚‚è‚ب‚ا‚ًڈq‚ׂéپB
پ@پ،پ@“،“° چ‚Œص‚جگ¶ٹU‚ً•`‚پB
پ@پ،پ@“،“°ژپ‚جˆة‰ê”Eژزژg—p’³•ٌٹˆ“®پB
پ@پ@پ@پ@پ@“،“° چ‚Œص‚حپAچ]Œثژ‘مڈ‰ٹْ‚ةپA
پ@پ@چ]Œث–‹•{‚ج‚½‚ك‚ةپAˆة‰ê‚ج”Eژز‚ً
پ@پ@ژg‚¢پAڈ”چ‘‚ج’³•ٌٹˆ“®‚ًچs‚¢پAژ©•ھ
پ@پ@‚ة•ٌچگ‚³‚¹پA–‹•{‚ة’تچگ‚µ‚ؤ‚¢‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@‚»‚جŒمپAˆةگ¨پEˆة‰ê‚ًژx”z‚·‚éپA
پ@پ@“،“°ژپ‚ج’أ”ث‚حپAپ@چ]Œثژ‘م‚ً’ت‚µ
پ@پ@–‹––‚ـ‚إپAˆة‰ê‚ج”Eژز‚ًژg‚¢پAڈ”چ‘
پ@پ@‚ج’³•ٌٹˆ“®‚ًچs‚¢پA”ثژه‚ة•ٌچگ‚³‚¹پA
پ@پ@–‹•{‚ة’تچگ‚µپAچ]Œث–‹•{‚ج’³•ٌ‹@ٹض
پ@پ@‚ج–ًٹ„‚ً‰ت‚½‚·پB
پ@
پ@
پڑپ@ڈé‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢ٹضکAƒhƒ‰
پ@پ@ ƒ}پA‰f‰وپBپ@
پ@
پ،پ@پwپ@Œ÷–¼‚ھ’زپ@پi‚±‚¤‚ف‚ه‚¤‚ھ‚آ‚¶پjپ@پx پBپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiŒ´چىپFژi”n—ة‘¾کY‚جپuŒ÷–¼‚ھ’زپvپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹r–{پF‘هگخگأپjپB
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒr‚ج‚Q‚O‚O‚U”N‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پjپB
پ@پ،پ@‘هچمڈé‚ًڈq‚ׂéپB
پ@پ،پ@‚Q‚O‚O‚U”N‚P‚OŒژ‚P“ْپE–{•ْ‘—‚جپuŒ÷–¼‚ھ’زپv
پ@پ@پ@‘و‚R‚X‰ٌ‚جپwڈG‹gژ€‚·پx‚ج––•”‰ًگà‚إپA
پ@پ@پ@ژjژہ‚ج‘هچمڈé‚جٹT—v‚ً•`‚«پAڈq‚ׂéپB
پ@پ@پ@ڈ؛کa‚U”N‚ج–Lگb‘هچمڈé‚ج“VژçچؤŒڑ‚ب‚ا
پ@پ@پ@‚ًڈq‚ׂéپB
پ@
پ،پ@پwپ@Œ÷–¼‚ھ’زپ@پi‚±‚¤‚ف‚ه‚¤‚ھ‚آ‚¶پjپ@پx پBپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiŒ´چىپFژi”n—ة‘¾کY‚جپuŒ÷–¼‚ھ’زپvپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹r–{پF‘هگخگأپjپB
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒr‚ج‚Q‚O‚O‚U”N‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پjپB
پ@پ،پ@•ڑŒ©ڈé‚ًڈq‚ׂéپB
پ@پ،پ@‚Q‚O‚O‚U”N‚XŒژ‚P‚V“ْپE–{•ْ‘—‚جپuŒ÷–¼‚ھ’زپv
پ@پ@پ@‘و‚R‚V‰ٌ‚جپw‘¾چ}‘خٹض”’پx‚ج––•”‰ًگà‚إپA
پ@پ@پ@ژjژہ‚ج•ڑŒ©ڈé‚جٹT—v‚ً•`‚«پAڈq‚ׂéپB
پ@
پ،پ@پwپ@‰خ“V‚جڈéپ@پxپB
پ@پ@پ@پi“ْ–{‚ج‰f‰وپjپB
پ@پ،پ@ˆہ“yڈé‚ج’zڈé‚ج•¨Œê‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ژ©ٹQپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚ھ‚¢پjپB
پ@
پ،پ@ژ©ٹQپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ژ©ٹQپ@پi‚¶‚ھ‚¢پjپB
پ،پ@•ت–¼پ@پFپ@ژ©ژEپB
پ،پ@پsگ¶–½پtپBپ@‘½‚‚ج‘¸‚¢–½پi‚¢‚ج‚؟پj‚ھژ¸‚ي‚ꂽپB
پ،پ@ژ©گnپi‚¶‚¶‚ٌپjپAژ©”ڑپi‚¶‚خ‚پj ‚ب‚اپB
پ@
پ@
پ،پ@ژ©ٹQپ@پi‚¶‚ھ‚¢پA= ژ©ژEپj‚ة‚حپA “ْ–{‚ج—ًژj‚ة‚¨
پ@پ@‚¢‚ؤپAپ@ژ©گnپi‚¶‚¶‚ٌپjپAژ©”ڑپi‚¶‚خ‚پj‚ب‚ا‚ھ‚ ‚éپB
پ@پ@‘½‚‚ج‘¸‚¢–½پi‚¢‚ج‚؟پj‚ھژ¸‚ي‚ꂽپB
پ@
پںپ@ژ©”ڑپB
پ،پ@ژ©”ڑپ@پi‚¶‚خ‚پj‚ئ‚حپAپ@“ْ–{‚ج—ًژj‚ة‚¨ ‚¢‚ؤپAپ@
پ@پ@‰خ–ٍ—ق‚ً—p‚¢‚ؤژ©ٹQپi‚¶‚ھ‚¢پAژ©ژEپj‚·‚邱‚ئ
پ@پ@‚إ‚ ‚éپBپ@‘½‚‚ج‘¸‚¢–½پi‚¢‚ج‚؟پj‚ھژ¸‚ي‚ꂽپB
پ@
پ،پ@”ڑژ€ژ©ٹQ”ڑژ€ژ©ٹQپ@پi‚خ‚‚µ‚¶‚ھ‚¢= ژ©”ڑپj‚ئ‚حپAپ@
پ@پ@‰خ–ٍ—ق‚ب‚ا‚ج”ڑ–ٍ‚إژ©ٹQ‚µژ€–S‚·‚邱‚ئ‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@
پ،پ@”ڑژ€ژ©ٹQپi= ژ©”ڑپj‚ھ‘½‚©‚ء‚½ژٹْپB
پ@پ@پi‚Pپjپ@ژ؛’¬ژ‘مŒمٹْپiگيچ‘ژ‘مپjپ`چ]Œثژ‘م
پ@پ@پ@‚ج”ڑژ€ژ©ٹQپB
پ@پ@پ@پ@پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚إ‚حپA”ڑژ€ژ©ٹQپi= ژ©”ڑپj‚حپAپ@
پ@پ@پ@‰خ–ٍ—ق‚ب‚ا‚ج”ڑ–ٍ‚ھ—A“ü‚ـ‚½‚حگ»‘¢‚إ‚«‚éپA
پ@پ@پ@ژ؛’¬ژ‘مŒمٹْپiگيچ‘ژ‘مپj‚©‚çچ]Œثژ‘م‚ـ‚إ
پ@پ@پ@چs‚ي‚êپAژ€‘جڈء–إ‚ج‚½‚كپAژ€‘ج‚ھ‚³‚炵‚à‚ج
پ@پ@پ@‚ة‚³‚ê‚邱‚ئ‚ً”ً‚¯‚邽‚كپi‹°‚ê‚ؤپjپA‚»‚ج‘¼
پ@پ@پ@‚ج——R‚إپAگl‚ھپA‘ه—ت‚ج‰خ–ٍ—ق‚ج”ڑ–ٍ‚ًژg
پ@پ@پ@‚ء‚ؤ”ڑژ€ژ©ٹQ‚·‚éپi= ژ©”ڑ‚·‚éپjپB
پ@
پ@پ@پœپ@‰خ–ٍ‚ھ“ْ–{‚إ–{ٹi“I‚ةژg—p‚³‚ê‚é‚و‚¤‚ة
پ@پ@پ@‚ب‚ء‚½گيچ‘ژ‘مپiژ؛’¬ژ‘مŒمٹْپjˆبŒم‚©‚ç
پ@پ@پ@چ]Œثژ‘م‚ـ‚إپA‘ه—ت‚جچ•گF‰خ–ٍ‚ًژg‚ء‚½”ڑ
پ@پ@پ@ژ€ژ©ٹQپi= ژ©”ڑپj‚ھ”گ¶‚µ‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@گيچ‘ژ‘مپiژ؛’¬ژ‘مŒمٹْپj‚©‚çچ]Œثژ‘م
پ@پ@پ@‚ـ‚إچs‚ي‚êپAژ€‘جڈء –إ‚ج‚½‚كپA‘ه—ت‚ج”ڑ–ٍ
پ@پ@پ@‚ًژg‚ء‚ؤپA”ڑژ€ژ©ٹQ‚·‚éپi= ژ©”ڑ‚·‚éپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@“–ژپA“G‚┽چRژز‚جژ€‘ج‚ًŒ©‚¹‚µ‚ك‚ج‚½
پ@پ@پ@‚كŒِڈO‚ج–ت‘O‚ة‚³‚ç ‚·پiŒ©‚¹‚éپjٹµڈK‚ھ‚ ‚ء
پ@پ@پ@‚½‚½‚ك پAژ€‘ج‚ً‚³‚炵‚à‚ج‚ة‚ب‚é‚ج‚ً‚س‚¹‚®
پ@پ@پ@‚½‚كپA”ڑ–ٍ‚إ“÷•ذ‚ًژU—گ‚³‚¹‚ؤپAژ€‘ج‚ًڈء–إ
پ@پ@پ@‚³‚¹‚é•K—v‚ھ‚ ‚ء‚½پBپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژہ—ل‚ئ‚µ‚ؤپAڈ¼‰i‹vڈGپAچ×گىƒKƒ‰ ƒVƒƒپA
پ@پ@پ@‚¨ژsپA‘ه‰–•½”ھکY‚ب‚ا‚ج”ڑژ€ژ©ٹQ‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پ@پi‚Qپjپ@‘¾•½—mپE“ْ’†گي‘ˆ’†‚ج”ڑژ€ژ©ٹQپB
پ@پ@پ@پ@پ@‘¾•½—mپE“ْ’†گي‘ˆ’†‚ةچs‚ي‚êپA •ك—¸‚ة‚ب
پ@پ@پ@‚邱‚ئ‚ً’p‚ئ‚µ‚ؤ‹‘‚فپAژèض’eپi‚ؤ‚è ‚م‚¤‚¾‚ٌپj
پ@پ@پ@“™‚ًژg‚ء‚ؤگيڈê‚إپA“ْ–{گl‚ج•؛ژm ‚â–¯ٹشگl
پ@پ@پ@‚ھ”ڑژ€ژ©ٹQ‚·‚éپi= ژ©”ڑ‚·‚éپjپB
پ@
پ@
پںپ@ژ©گnپB
پ،پ@ژ©گnپ@پi‚¶‚¶‚ٌپj‚ئ‚حپAپ@“ْ–{‚ج—ًژj‚ة‚¨ ‚¢‚ؤپAپ@
پ@پ@“پŒ•‚ً—p‚¢‚ؤژ©ٹQپi‚¶‚ھ‚¢پAژ©ژEپj‚·‚邱‚ئ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@‘½‚‚ج‘¸‚¢–½پi‚¢‚ج‚؟پj‚ھژ¸‚ي‚ꂽپB
پ@پ@
پ،پ@ژ©گn‚ة‚حپAپ@“ْ–{‚ج—ًژj‚ة‚¨‚¢‚ؤپAگط• پi‚¹‚ء
پ@پ@‚ص‚پjپA‚»‚ج‘¼‚ج‘½‚‚جژ©ٹQ‚ج•û–@‚ھ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ،پ@گط• پ@پi‚¹‚ء‚ص‚پj‚حپA‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج•گژm‚جژ©
پ@پ@ٹQ‚ج•û–@‚ج‚P‚آ‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@ˆہ“y“چژRژ‘مŒمٹْ‚©‚çپAگط• ‚جڈKٹµ‚ھچL‚ـ‚èپA
پ@پ@گط• ‚جچى–@‚ھ’è‚ـ‚éپB
پ@
پ،پ@•گژm‚جژ©ٹQپBپ@
پ،پ@گ´گ…ڈ@ژ،پi‚µ‚ف‚¸‚ق‚ث‚ح‚éپj‚جگط• ‚جژ©ٹQ‚حپAپ@
پ@پ@•گژm‚ة‚ئ‚ء‚ؤپAپuگط• ‚ھ–¼—_‚ ‚éژ€‚إ‚ ‚éپv‚ئ‚¢‚¤
پ@پ@چl‚¦•û‚ً’è’…‚³‚¹‚éگط‚ءٹ|‚¯‚ئ‚ب‚éپBپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@Œ©ژ–‚بگ´گ…ڈ@ژ،‚جگط• ‚ھپAگط• ‚جچى–@‚ج
پ@پ@‚¨ژè–{‚ج‚P‚آ‚ئ‚ب‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@ˆہ“y“چژRژ‘مŒمٹْˆبŒم‚©‚çچ]Œثژ‘م‚ـ‚إپA
پ@پ@•گژm‚ًژEٹQ‚·‚éڈêچ‡پAپ@چكگl‚ئ‚µ‚ؤ‚جژ€‚جپu‘إ‚؟
پ@پ@ژٌپvپ@‚ئپAپ@–¼—_‚ ‚éژ€‚جپuگط• پv‚ھ‹و•ت‚³‚ê‚é‚و
پ@پ@‚¤‚ة‚ب‚éپB
پ@
پ،پ@“ْ–{‚جˆہ“y“چژRژ‘م‘Oٹْ‚ـ‚إپAگط• ‚جچى–@‚à
پ@پ@’è‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@Œ©ژ–‚بگ´گ…ڈ@ژ،پi‚µ‚ف‚¸‚ق‚ث‚ح‚éپj‚جگط• ‚ھپAپ@
پ@پ@گط• ‚جچى–@‚ج‚¨ژè–{‚ج‚P‚آ‚ئ‚ب‚ء‚½پB
پ@
پ،پ@پuگط• ‚ھ–¼—_‚ ‚éژ€‚إ‚ ‚éپv‚ئ‚¢‚¤چl‚¦•û‚ً’è’…
پ@پ@‚³‚¹‚éگط‚ءٹ|‚¯‚ئ‚ب‚ء‚½پAگ´گ… ڈ@ژ،‚جگط• ‚جژ©
پ@پ@ٹQپB
پ@
پ،پ@گ´گ… ڈ@ژ،‚جگط• ‚جژ©ٹQ‚حپAپ@•گژm‚ة‚ئ‚ء‚ؤپA
پ@پ@پuگط• ‚ھ–¼—_‚ ‚éژ€‚إ‚ ‚éپv‚ئ‚¢‚¤چl‚¦•û‚ً’è’…
پ@پ@‚³‚¹‚éگط‚ءٹ|‚¯‚ئ‚ب‚éپBپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@ˆہ“y“چژRژ‘مŒمٹْˆبŒم‚©‚çچ]Œثژ‘م‚ـ‚إپA
پ@پ@•گژm‚ًژEٹQ‚·‚éڈêچ‡پAپ@چكگl‚ئ‚µ‚ؤ‚جژ€‚جپu‘إ‚؟
پ@پ@ژٌپvپ@‚ئپAپ@–¼—_‚ ‚éژ€‚جپuگط• پv‚ھ‹و•ت‚³‚ê‚é‚و
پ@پ@‚¤‚ة‚ب‚éپB
پ@
پ،پ@•گژm‚جژ©ٹQ‚حپAپ@“ْ–{‚جˆہ“y“چژRژ‘م‘Oٹْ‚ـ
پ@پ@‚إپAŒ`ژ®‚ح’è‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½پBپ@گط• ‚àژ©ٹQ
پ@پ@‚ج’P‚ب‚éژè’i‚ج‚P‚آ‚ة‰ك‚¬‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@
پ،پ@Œ©ژ–‚بگ´گ…ڈ@ژ،‚جگط• ˆبŒمپAپ@“ْ–{‚جˆہ“y“چ
پ@پ@ژRژ‘مŒمٹْˆبŒمپAپ@گط• ‚حپA•گژm‚ة‚ئ‚ء‚ؤپu–¼
پ@پ@—_‚ ‚éژ€پv‚إ‚ ‚é‚ئ‚¢‚¤”Fژ¯‚ھ•گژm‚ةچL‚ـ‚ء‚ؤ
پ@پ@‚¢‚ء‚½پBپ@
پ،پ@Œ©ژ–‚بگ´گ…ڈ@ژ،‚جگط• ˆبŒمپAپ@ŒY”±‚ئ‚µ‚ؤ‚à
پ@پ@گط• ‚ً–½‚¶‚éڈKٹµ‚ھچL‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@ˆہ“y“چژRژ‘م‘Oٹْ‚ـ‚إپAپ@گي‚¢‚إ•ك‚炦‚ç
پ@پ@‚ꂽ•گژm‚حپAپ@ŒY”±‚ئ‚µ‚ؤپAژٌ‚ً™†پi‚حپj‚ث‚ç‚ê
پ@پ@‚é‚©پAل÷پi‚ح‚è‚آ‚¯پj‚ة‚³‚ê‚é‚©پ@‚ب‚ا‚ھ•پ’ت‚إ
پ@پ@‚ ‚ء‚½پBپ@گط• ‚³‚¹‚éڈKٹµ‚ح–³‚©‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ©ژ–‚بگ´گ… ڈ@ژ،‚جگط• ˆبŒمپAپ@ŒY”±‚ئ‚µ
پ@پ@‚ؤ•گژm‚ًژ©ٹQ‚³‚¹‚éژè’i‚ج‚P‚آ‚ئ‚µ‚ؤپAپuگط• پv
پ@پ@‚ھچL‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚½پBپ@—ل‚ئ‚µ‚ؤپA–LگbڈG‹g‚ھ‰™
پ@پ@‚ج–LگbڈGژں‚ةگط• ‚ً–½‚¶‚ؤ‚¢‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@گ´گ… ڈ@ژ،پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ف‚¸ ‚ق‚ث‚ح‚éپjپB
پ@
پ،پ@گ´گ… ڈ@ژ،پB
پ،پ@–¼ڈجپ@پF گ´گ… ڈ@ژ، پi ‚µ‚ف‚¸ ‚ق‚ث‚ح‚éپjپB
پ،پ@گ¶–v”Nپ@پF ‚P‚T‚R‚V”Nپ[‚P‚T‚W‚Q”NپB
پ،پ@”ُ’†پEچ‚ڈ¼ڈéپEڈéژهپB
پ،پ@ڈG‹g‚جچ‚ڈ¼ڈéگ…چU‚كژپAگط• ‚µژ©ٹQ‚·‚éپB
پ@پ@‚»‚ê‚ًŒ©“ح‚¯‚½ŒمپA–¾’qŒُڈG“¢”°‚ج‚½‚كپAڈG
پ@پ@‹g‚حپAپ@’†چ‘‘ه•ش‚µپi‚P‚T‚W‚Q”N‚UŒژ‚Sپ`‚P‚R“ْپj‚ً
پ@پ@ژn‚ك‚éپB
پ،پ@پuگط• ‚ھ–¼—_‚ ‚éژ€‚إ‚ ‚éپv‚ئ‚¢‚¤چl‚¦•û‚ً’è’…
پ@پ@‚³‚¹‚éگط‚ءٹ|‚¯‚ئ‚ب‚ء‚½پAگ´گ… ڈ@ژ،‚جگط• ‚جژ©
پ@پ@ٹQپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ،پ@گ´گ… ڈ@ژ،پ@پi‚µ‚ف‚¸ ‚ق‚ث‚ح‚éپAگ¶–v”NپF ‚P‚T‚R‚V
پ@پ@پ`‚P‚T‚W‚Q”Nپjپ@‚حپAپ@ژ؛’¬ژ‘مŒمٹْپiگيچ‘ژ‘مپjپA
پ@پ@ˆہ“y“چژRژ‘م‚جپA”ُ’†‚ج•گڈ«‚إپAپ@”ُ’†پi‚ر‚ء‚؟
پ@پ@‚م‚¤پA‰ھژRŒ§گ¼•”پj‚جچ‚ڈ¼ڈéپEڈéژهپ@‚إ‚ ‚ء‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@گ´گ… ڈ@ژ،‚جگط• ‚جژ©ٹQ‚حپAپ@•گژm‚ة‚ئ‚ء‚ؤپA
پ@پ@پuگط• ‚ھ–¼—_‚ ‚éژ€‚إ‚ ‚éپv‚ئ‚¢‚¤چl‚¦•û‚ً’è’…
پ@پ@‚³‚¹‚éگط‚ءٹ|‚¯‚ئ‚ب‚éپBپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@Œ©ژ–‚بگ´گ…ڈ@ژ،‚جگط• ‚ھپAگط• ‚جچى–@‚ج
پ@پ@‚¨ژè–{‚ج‚P‚آ‚ئ‚ب‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@ˆہ“y“چژRژ‘مŒمٹْˆبŒم‚©‚çچ]Œثژ‘م‚ـ‚إپA
پ@پ@•گژm‚ًژEٹQ‚·‚éڈêچ‡پAپ@چكگl‚ئ‚µ‚ؤ‚جژ€‚جپu‘إ‚؟
پ@پ@ژٌپvپ@‚ئپAپ@–¼—_‚ ‚éژ€‚جپuگط• پv‚ھ‹و•ت‚³‚ê‚é‚و
پ@پ@‚¤‚ة‚ب‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@
پ،پ@گ´گ… ڈ@ژ،‚حپAژO‘؛ژپ‘خ–ر—کژپ‚جˆê‘هگي‚جپA“V
پ@پ@گ³‚ج”ُ’†•؛—گ‚جچغپAژO‘؛ژپ‰ئگb‚إ‚ح‚ ‚ء‚½‚ھپA
پ@پ@–ر—کژپ‚ة–،•û‚µپi‰ء’S‚µپjپAچ‚ڈ¼ڈéژه‚ج’nˆت‚ً“¾
پ@پ@‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ´گ… ڈ@ژ،‚حپAپ@–ر—کژپ‚ج‰ئگb‚ئ‚ب‚ء‚ؤˆبŒمپA
پ@پ@ڈ¬‘پگى—²Œiپi‚±‚خ‚â‚©‚ي‚½‚©‚©‚°پj‚ج”z‰؛‚ئ‚µ‚ؤپA
پ@پ@–ر—کژپ‚ج’†چ‘’n•û‚ج•½’è‚ةڈ]ŒR‚µپA’‰گ½گSŒْ‚پA
پ@پ@ڈ¬‘پگى—²Œi‚ً‚ح‚¶‚ك–ر—کژپ‚جژٌ”]گw‚©‚çگ[‚گM
پ@پ@—ٹ‚³‚ꂽپB
پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{“ˆêگچô‚ًگi‚ك‚éگD“cگM’·‚ج‰ئگbپE‰H
پ@پ@ژؤڈG‹gپi–LگbڈG‹gپj‚ھ’†چ‘چU‚ك‚ًچs‚¤پBپ@‚P‚T‚W‚Q”N
پ@پ@پi“Vگ³‚P‚O”Nپj‚ةپAگ´گ… ڈ@ژ،‚حپAپ@”ُ’†پEچ‚ڈ¼ڈé‚ة
پ@پ@âؤڈéپi‚낤‚¶‚ه‚¤پj‚µ‚ؤڈG‹gŒR‚ةچRگي‚·‚éپBپ@ڈG‹g
پ@پ@‚حپAگ´گ… ڈ@ژ،‚ةپAچ~•ڑ‚·‚ê‚خپA”ُ’†چ‘پi‚ر‚ء‚؟‚م
پ@پ@‚¤‚ج‚‚ةپA‰ھژRŒ§گ¼•”پj‚ً—^‚¦‚é‚ئ‚¢‚¤ڈًŒڈ‚ًڈo‚µ
پ@پ@‚½‚ھ‰‚¶‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@ڈG‹gŒR‚جپAچ•“cٹ¯•؛‰qپiچFچ‚پi‚و‚µ‚½‚©پjپj‚ھ
پ@پ@چô‚µ‚½گ…چU‚ك‚ة‚ ‚¢پA”ُ’†پEچ‚ڈ¼ڈé‚حپA—ژڈéگ،‘O
پ@پ@‚ة’ا‚¢چ‚ـ‚ê‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@ڈG‹g‚جچ‚ڈ¼ڈéگ…چU‚كژپiچإ’†پjپAپ@‚P‚T‚W‚Q”N
پ@پ@پi“Vگ³‚P‚O”Nپj‚UŒژ‚Q“ْ–¢–¾‚ة–{”\ژ›‚ج•د‚ھ‹N‚±‚èپA
پ@پ@گD“cگM’·‚ھژ€‹ژ‚µپA‚»‚ج•ٌ‚ً’m‚ء‚½ڈG‹g‚حپAگ´گ…
پ@پ@ڈ@ژ،‚جژ©ٹQ‚ًڈًŒڈ‚ةڈé•؛‚ًڈ•–½‚·‚éچuکa‚ًژ¦‚µپA
پ@پ@‚±‚ê‚ة‰‚¶‚½گ´گ… ڈ@ژ،‚حپAگD“cگM’·‚جژ€‚ً’m‚ç‚ت
پ@پ@‚ـ‚ـپA“¯”N‚UŒژ‚S“ْŒك‘O‚ةپAŒZ‚جگ´گ…ڈ@’mپiŒژگ´“ü
پ@پ@“¹پj‚ئ‹¤‚ةپAچ‚ڈ¼ڈé‚ًˆح‚قگ…ڈم‚جپAڈMڈم‚إگط• پEژ©
پ@پ@ٹQ‚µ‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@‚P‚T‚W‚Q”Nپi“Vگ³‚P‚O”Nپj‚UŒژ‚S“ْ‚ةپAگ´گ… ڈ@ژ،‚حپAپ@
پ@پ@ڈG‹g‚جچ‚ڈ¼ڈéگ…چU‚كژپAپ@چ‚ڈ¼ڈé‚ًˆح‚قگ…ڈم‚إپA
پ@پ@ڈMڈم‚إپAگط• ‚µژ©ٹQ‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@گ´گ… ڈ@ژ،‚جژگ¢‚ج‹ه‚حپAپ@پwپ@•‚گ¢پi‚¤‚«‚وپj
پ@پ@‚ً‚خپ@چ،‚±‚»“n‚êپ@•گژmپi‚à‚ج‚ج‚سپj‚جپ@–¼‚ًچ‚
پ@پ@ڈ¼پi‚½‚©‚ـ‚آپj‚جپ@‘غپi‚±‚¯پj‚ةژc‚µ‚ؤپ@پxپ@‚إ‚ ‚ء
پ@پ@‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@گ…ڈم‚ةڈM‚ً‘†‚¬ڈo‚µپAپ@ڈMڈم‚إگط• ‚ج‘O‚ة‚ذ‚ئ
پ@پ@‚³‚µ•‘‚ء‚½‚ج‚؟پAپ@Œ‰پi‚¢‚³‚¬‚وپj‚• ‚ًگط‚èپA‰îچِ
پ@پ@گlپi‚©‚¢‚µ‚ل‚‚ة‚ٌپj‚ةژٌ‚ً™†پi‚حپj‚ث‚ç‚ê‚éپAگ´
پ@پ@گ… ڈ@ژ،‚جچى–@‚حپAŒ©ژ–‚إ‚ ‚é‚ئ‚µ‚ؤپA‚»‚ê‚ًژہ
پ@پ@چغ‚ةŒ©‚½•گژm’B‚جڈـژ^‚ًژَ‚¯‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@گ´گ… ڈ@ژ،‚ج•وڈٹ‚حپAپ@ژRŒûŒ§Œُژs‚جگ´‹¾ژ›‚ة
پ@پ@‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@‚P‚T‚W‚Q”Nپi“Vگ³‚P‚O”Nپj‚ةپAپ@گD“cگM’·‚ج•”ڈ«پE
پ@پ@‰HژؤڈG‹gپi–LگbڈG‹gپj‚ج’†چ‘چU‚ك‚إپAپ@–ر—کژپ
پ@پ@‚ئگي‚¤‰HژؤڈG‹gپi–LگbڈG‹gپj‚حپAپ@–ر—کژپ‚ة–،
پ@پ@•û‚·‚éپAگ´گ…ڈ@ژ،پi‚µ‚ف‚¸‚ق‚ث‚ح‚éپj‚جچ‚ڈ¼ڈé
پ@پ@‚ًگ…چU‚ك‚ة‚·‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@ˆê•ûپA‰HژؤڈG‹gپi–LگbڈG‹gپj‚حپAگ´گ… ڈ@ژ،
پ@پ@‚ض‚ج‰‡ŒR‚ج–ر—کŒR‚ً‘«ژ~‚ك‚³‚¹‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚T‚W‚Q”N‚UŒژ‚Q“ْ‚ج–{”\ژ›‚ج•د‚إژهŒN‚جگD
پ@پ@“cگM’·‚ًژ¸‚ء‚½‚±‚ئ‚ً‚UŒژ‚R“ْ‚ة’m‚ء‚½‰HژؤڈG‹g
پ@پ@پi–LگbڈG‹gپj‚حپAژ–ژہ‚ً‰B‚µپA‘پ‹}‚ةپA–ر—کژپ‚ئ‚ج
پ@پ@چuکaپiکa‰ًپj‚ً‹پ‚كپAپ@‰HژؤڈG‹gپi–LگbڈG‹gپj•û‚ج
پ@پ@چ•“cٹ¯•؛‰qپiچFچ‚پj‚ئ–ر—ک•û‚جˆہچ‘ژ›Œbàùپi‚ ‚ٌ
پ@پ@‚±‚‚¶ ‚¦‚¯‚¢پj‚ھŒًڈآ‚µپA‚P‚T‚W‚Q”N‚UŒژ‚S“ْ‘پ’©‚ةپA
پ@پ@گ´گ…ڈ@ژ،‚جگط• ‚ئچ‚ڈ¼ڈé•؛‚جڈ•–½پA‹y‚ر–ر—کژپ
پ@پ@‚ج—ج“y‚جˆê•”پi”ُ’†پA”üچىپA”Œمثپjٹ„ڈ÷‚ًڈًŒڈ‚ةپA
پ@پ@–ر—ک•û‚ئڈG‹g•û‚حپAچuکa‚ھگ¬—§‚µپAگ¾ژ†‚ًŒً‚ي‚µ
پ@پ@‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚T‚W‚Q”Nپi“Vگ³‚P‚O”Nپj‚UŒژ‚S“ْŒك‘O’†‚ةپiŒك
پ@پ@‘O‚P‚Oژچ ‚ئگ„’肳‚ê‚éپjپAپ@گ´گ…ڈ@ژ،‚حپAگ…چU‚ك
پ@پ@‚جچ‚ڈ¼ڈé‚ًˆح‚قگ…ڈم‚إپAپ@ڈ¬ڈM‚جڈMڈم‚إپA‚ذ‚ئ‚³
پ@پ@‚µ•‘‚ء‚½Œمپi‹ب•‘‚ً•‘‚¢”[‚ك‚½Œم‚ةپjپAپ@گط• ‚µ‚ؤ
پ@پ@ژ©ٹQ‚µ‚½پiژ©گnپi‚¶‚¶‚ٌپj‚µ‚½پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚T‚W‚Q”N‚UŒژ‚S“ْ‚ةپA‰HژؤڈG‹gپi–LگbڈG‹gپj
پ@پ@‚حپAپ@‚»‚ê‚ًŒ©‚ئ‚ا‚¯‚½ŒمپA–¾’qŒُڈG“¢”°‚ج‚½
پ@پ@‚كپAڈG‹gŒR‚ًژRڈéپi‚â‚ـ‚µ‚ëپA‹“s•{“ى•”پj‚ةŒü
پ@پ@‚¯ڈo”‚³‚¹پA’†چ‘‘ه•ش‚µپi‚P‚T‚W‚Q”N‚UŒژ‚Sپ`‚P‚R
پ@پ@“ْپj‚ًژn‚ك‚éپBپ@’A‚µپAڈG‹g‚حپAچ‚ڈ¼ڈé•t‹ك‚ةپA
پ@پ@ڈG‹gŒR‚جˆê•”‚ًگ™Œ´‰ئژںپi‚·‚¬‚ح‚ç‚¢‚¦‚آ‚¬پj
پ@پ@‚ة”Cپi‚ـ‚©پj‚¹پA—¯‚ك’u‚¢‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚T‚W‚Q”N‚UŒژ‚S“ْ—[•û‚ةپA–ر—ک•û‚حپA–{”\
پ@پ@ژ›‚ج•د‚ئگD“cگM’·‚جژ€‚ً’m‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ،پ@’†چ‘‘ه•ش‚µپB
پ،پ@’†چ‘‘ه•ش‚µپi‚P‚T‚W‚Q”N‚UŒژ‚Sپ`‚P‚R“ْپj‚جڈo”
پ@پ@“_‚ج”ُ’†پEچ‚ڈ¼‚إ‚جڈَ‹µپi‚P‚T‚W‚Q”N‚UŒژ‚Q“ْپ`
پ@پ@‚S“ْپjپB
پ،پ@–ر—کŒR‚ئ‚ج’âگي‚ةˆê‰گ¬Œ÷‚µ‚½پAڈG‹gŒRپB
پ@
پ،پ@‚P‚T‚W‚Q”Nپi“Vگ³‚P‚O”Nپj‚ةپAپ@گD“cگM’·‚ج•”ڈ«پE
پ@پ@‰HژؤڈG‹gپi–LگbڈG‹gپj‚ج’†چ‘چU‚ك‚إپAپ@–ر—کژپ
پ@پ@‚ئگي‚¤‰HژؤڈG‹gپi–LگbڈG‹gپj‚حپAپ@–ر—کژپ‚ة–،
پ@پ@•û‚·‚éپAگ´گ…ڈ@ژ،پi‚µ‚ف‚¸‚ق‚ث‚ح‚éپj‚جچ‚ڈ¼ڈé
پ@پ@‚ًگ…چU‚ك‚ة‚·‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@ˆê•ûپA‰HژؤڈG‹gپi–LگbڈG‹gپj‚حپAگ´گ… ڈ@ژ،
پ@پ@‚ض‚ج‰‡ŒR‚ج–ر—کŒR‚ً‘«ژ~‚ك‚³‚¹‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@‚P‚T‚W‚Q”N‚ج”ُ’†پEچ‚ڈ¼ڈé‚جگي‚¢‚إ‚حپA‰HژؤڈG‹g
پ@پ@پi–LگbڈG‹gپj•û‚جŒR‚ئگي‚¤پA–ر—ک‹PŒ³•û‚جŒRپE–ٌ
پ@پ@‚R–œگl‚ًپAپ@‹gگىŒ³ڈt‚ئڈ¬‘پگى —²Œi‚ھپA—¦‚¢‚ؤ
پ@پ@‚¢‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@”ُ’†چ‚ڈ¼ڈé‚جگي‚¢‚حنP’…پi‚±‚¤‚؟‚ل‚پjڈَ‘ش
پ@پ@‚ة‚ب‚èپA–ر—ک•û‚حپAکa–r‚ًچl‚¦‚ؤ‚¢‚½پBپ@–ر—ک•û
پ@پ@‚حپAگD“cگM’·‚جژ€‚ً’m‚炸‚ةپAڈG‹g•û‚و‚èکa–r
پ@پ@‚جڈًŒڈ‚ھژ¦‚³‚ê‚P‚T‚W‚Q”N‚UŒژ‚S“ْ‘پ’©‚ةکa–r‚µ
پ@پ@‚½پBپ@‚»‚جŒمپAڈG‹gŒR“P‘ق‚ج’†چ‘‘ه•ش‚µژ‚ة’ا
پ@پ@Œ‚‚µ‚ب‚©‚ء‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پuگىٹp‘¾چ}‹Lپv‚إ‚حپAگD“cŒR“P‘ق‚ج’†چ‘‘ه
پ@پ@•ش‚µژپA‹gگىŒ³ڈt‚ح’اŒ‚‚ًژه’£‚µ‚½‚ھپAڈ¬‘پ
پ@پ@گى —²Œi‚ةگأژ~‚³‚ꂽ‚ئ‹Lڈq‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB‚ـ‚½پA
پ@پ@پu‹gگى‰ئ•¶ڈ‘پv‚إ‚حپA—¼–¼‚ھپA’اŒ‚‚ح–³–d‚إ‚
پ@پ@‚èپAژ¸”s‚·‚ê‚خپA–ر—ک‚ح–إ‚ر‚é‚ئŒœ”O‚µ’اŒ‚‚µ
پ@پ@‚ب‚©‚ء‚½‚ئ‹Lڈq‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپBپ@پ@
پ@
پ،پ@–{”\ژ›‚ج•د‚إگD“cگM’·‚ھژ©ٹQ‚·‚é‚P‚T‚W‚Q”N
پ@پ@پi“Vگ³‚P‚O”Nپj‚UŒژ‚Q“ْ‚ةپAگD“cژپ”z‰؛‚ج‰HژؤڈG
پ@پ@‹g‚جŒR‚حپAپ@ژR‰AپEژR—z‚ج’†چ‘’n•û‚جچU—ھ‚ج‚½
پ@پ@‚كپAپ@”ُ’†پi‚ر‚ء‚؟‚م‚¤پA‰ھژRŒ§پj‚ج“G‚ج–ر—ک•û
پ@پ@‚جچ‚ڈ¼ڈéپi‚½‚©‚ـ‚آ‚¶‚ه‚¤پj‚ًگ…چU‚ك‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@‰HژؤڈG‹gپi–LگbڈG‹gپj‚ھپA–{”\ژ›‚ج•د‚إ‚ج
پ@پ@گD“cگM’·‚جژ€‚ً’m‚ء‚½‚ج‚حپAپ@‚P‚T‚W‚Q”N‚ج‚UŒژ
پ@پ@‚R“ْ‚إ‚ ‚èپAپ@ڈG‹g‚حپAگM’·‚جژ€‚جڈî•ٌ‚ھکR‰k
پ@پ@پi‚낤‚¦‚¢پj‚µ‚ب‚¢‚و‚¤‚ةپAپ@”ُ’†پE”ُ‘O‚ض‚ج“¹‚ً
پ@پ@ٹ®‘S‚ةژص’fپi‚µ‚ل‚¾‚ٌپj‚µپAپ@ژ©گwپi‚¶‚¶‚ٌپj‚ة‘خ‚µ
پ@پ@‚ؤ‚àمgŒû—كپi‚©‚ٌ‚±‚¤‚ê‚¢پj‚ً‚µ‚¢‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@‰HژؤڈG‹gپi–LگbڈG‹gپj‚حپAپ@–ر—ک•û‚ةگM’·
پ@پ@‚جژ€‚ً”邵‚ؤچuکa‚ًŒ‹‚رپAپ@ˆêچڈ‚à‚ح‚â‚ڈم—Œ‚µ
پ@پ@‚ؤپAژهŒN‚ج’¢‚¢چ‡گيپi‚ئ‚à‚ç‚¢‚ھ‚ء‚¹‚ٌپj‚ًچs‚¨
پ@پ@‚¤‚ئ‚µ‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@‰HژؤڈG‹gپi–LگbڈG‹gپj‚ة‚ئ‚ء‚ؤچK‰^‚¾‚ء‚½‚±
پ@پ@‚ئ‚حپAپ@–ر—ک•û‚àپAگ…چU‚ك‚ة‚³‚ꂽپAگ´گ…ڈ@ژ،
پ@پ@پi‚µ‚ف‚¸‚ق‚ث‚ح‚éپj‚جچ‚ڈ¼ڈéپi‚½‚©‚ـ‚آ‚¶‚ه‚¤پj‚ج
پ@پ@‹~‰‡‚ھچ¢“‚ئ‚جŒ‹ک_‚ة’B‚µپA‚ـ‚½پA‚»‚ج‘¼‚ج
پ@پ@—lپX‚بگي‹µ‚©‚çپAکa–rپi‚ي‚ع‚پj‚ةŒX‚¢‚ؤ‚¢‚½‚±
پ@پ@‚ئ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@‰HژؤڈG‹gپi–LگbڈG‹gپj‚حپA‚P‚T‚W‚Q”N‚ج‚UŒژ‚R
پ@پ@“ْ‚ج–é‚ج‚¤‚؟‚ةپA–ر—ک•û‚جٹOŒً‘mپEˆہچ‘ژ›Œbàù
پ@پ@پi‚ ‚ٌ‚±‚‚¶‚¦‚¯‚¢پj‚ًپAپ@ژ©گw‚ةڈµ‚«پAڈG‹g•û‚ج
پ@پ@چ•“cٹ¯•؛‰qپiچFچ‚پi‚و‚µ‚½‚©پjپj‚ئŒًڈآ‚³‚¹‚½پB
پ@پ@کa–r‚ج‰ï’k‚إپAپ@ڈG‹g•û‚جچ•“cٹ¯•؛‰qپiچFچ‚پj
پ@پ@‚حپA”ُ’†پE”üچىپE”Œمثپi‚ر‚ء‚؟‚م‚¤پE‚ف‚ـ‚³‚©پE‚ظ
پ@پ@‚¤‚«پA‰ھژRŒ§گ¼•”پE‰ھژRŒ§“Œ–k•”پE’¹ژوŒ§گ¼•”پj
پ@پ@‚ج‚RƒJچ‘‚جگD“cژپ‚ض‚جٹ„ڈ÷‚âچ‚ڈ¼ڈéژهپEگ´گ…
پ@پ@ڈ@ژ،پi‚µ‚ف‚¸‚ق‚ث‚ح‚éپj‚جگط• ‚ئچ‚ڈ¼ڈé‚جڈé•؛
پ@پ@‚جڈ•–½‚ئ‚¢‚¤کa–r‚جڈًŒڈ‚ً–ر—ک•û ‚جˆہچ‘ژ›Œb
پ@پ@àùپi‚ ‚ٌ‚±‚‚¶‚¦‚¯‚¢پj‚ة’ٌژ¦‚µ‚½پB پ@
پ@پ@پ@پ@Œًڈآ‚حپA‚P‚T‚W‚Q”N‚ج‚UŒژ‚R“ْ‚ج–é‚©‚ç‚UŒژ‚S
پ@پ@“ْ‚ج‘پ’©‚ـ‚إ‘±‚«پAپ@ڈG‹g•û‚حپA–ر—ک•û‚ة“à“،
پ@پ@چLڈr‚ًچuکa‚جژgژز‚ة—§‚ؤپAپ@’ٌژ¦ڈًŒڈ‚ً’m‚ء‚½
پ@پ@–ر—ک•û‚حپAپ@’‰‹`‚ًگsپi‚آ‚پj‚µ‚½گ´گ…ڈ@ژ،‚جگط
• ‚جڈًŒڈ‚ة‚ح“ïگF‚ًژ¦‚µ‚½‚ھپAˆہچ‘ژ›Œbàù‚ھپA
چ‚ڈ¼ڈé‚جڈé•؛‚جڈ•–½‚ًڈًŒڈ‚ةٹJڈé‚ًگàپi‚ئپj‚«پA
گ´گ…ڈ@ژ،‚ًگà“¾‚µ‚ؤپAگ´گ…ڈ@ژ،‚àگط• ‚ًŒˆ’f‚µ,
گ‹‚ةپAڈG‹g•û‚ئ–ر—ک•û‚جچuکa‚ھŒ‹‚خ‚ꂽپB
پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚T‚W‚Q”Nپi“Vگ³‚P‚O”Nپj‚UŒژ‚S“ْŒك‘O’†‚ة
پ@پ@پiŒك‘O‚P‚Oژچ ‚ئگ„’肳‚ê‚éپjپAپ@گ´گ…ڈ@ژ،‚حپA
پ@پ@گ…چU‚ك‚جچ‚ڈ¼ڈé‚ًˆح‚قگ…ڈم‚إپAپ@ڈ¬ڈM‚جڈMڈم
پ@پ@‚إپA‚ذ‚ئ‚³‚µ•‘‚ء‚½Œمپi‹ب•‘‚ً•‘‚¢”[‚ك‚½Œم‚ةپjپA
پ@پ@گط• ‚µ‚ؤژ©ٹQ‚µ‚½پiژ©گnپi‚¶‚¶‚ٌپj‚µ‚½پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚T‚W‚Q”N‚UŒژ‚S“ْ‚ةپA‰HژؤڈG‹gپi–LگbڈG‹gپj
پ@پ@‚حپAپ@–¾’qŒُڈG“¢”°‚ج‚½‚كپA’†چ‘‘ه•ش‚µپi‚P‚T‚W‚Q
پ@پ@”N‚UŒژ‚Sپ`‚P‚R“ْپj‚ًژn‚ك‚éپBپ@’A‚µپAڈG‹g‚حپAچ‚
پ@پ@ڈ¼ڈé•t‹ك‚ةپAڈG‹g‚جˆê•”‚جŒR‚ًگ™Œ´‰ئژںپi‚·‚¬
پ@پ@‚ح‚ç‚¢‚¦‚آ‚¬پj‚ة”Cپi‚ـ‚©پj‚¹پA—¯‚ك’u‚¢‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@‚ـ‚½پA‰HژؤڈG‹gپi–LگbڈG‹gپj‚حپAپ@–œˆê–ر—ک
پ@پ@گ¨‚©‚ç’اŒ‚‚³‚ê‚éڈêچ‡‚ً‘z’肵‚ؤپA”ُ‘Oپi‚ر‚؛‚ٌپA
پ@پ@‰ھژRŒ§“Œ“ى•”پj‚ةپAپ@ڈG‹g•û‚جپA‰Fٹى‘½ڈG‰ئپi‚¤
پ@پ@‚«‚½‚ذ‚إ‚¢‚¦پj‚جŒR‚ً—¯‚ك’u‚¢‚½پB
پ@پ@پ@پ@‚P‚T‚W‚Q”N‚UŒژ‚S“ْ‚ج—[•û‚ةپA–ر—ک•û‚حپA–{”\
پ@پ@ژ›‚ج•د‚ئگD“cگM’·‚جژ€‚ً’m‚邱‚ئ‚ة‚ب‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@‚±‚جژپAپ@–ر—ک•û‚ج‹gگىŒ³ڈtپi‚«‚ء‚©‚ي‚à‚ئ
پ@پ@‚ح‚éپj‚©‚çڈG‹gŒR‚ً’اŒ‚‚µ‚و‚¤‚ئ‚¢‚¤گ؛‚ھ‚ ‚ھ‚ء
پ@پ@‚½‚ھپAŒ³ڈt‚ج’ي‚جڈ¬‘پگى —²Œiپi‚±‚خ‚â‚©‚ي‚½‚©
پ@پ@‚©‚°پj‚حپA‚±‚ê‚ًگ§‚µپAگ¾ژ†پi‚¹‚¢‚µپj‚ًŒًٹ·‚µ‚ؤ
پ@پ@‚¢‚éڈم‚حکa–r‚ًڈ…ژçپi‚¶‚م‚ٌ‚µ‚مپj‚·‚ׂ«‚¾‚ئژه
پ@پ@’£‚µ‚½‚½‚كپA–ر—ک•û‚حپAڈG‹g•û‚ئ‚جŒًگي‚ة‚حژٹ
پ@پ@‚ç‚ب‚©‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤گà‚ھ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@–ر—ک•û‚جŒR‚حپAپ@ڈG‹g‚جگD“cŒR“P‘ق‚ج’†چ‘
پ@پ@‘ه•ش‚µژ‚ة’اŒ‚‚µ‚ب‚©‚ء‚½پBپ@–ر—ک‹PŒ³‚à‚±‚ê‚ً
پ@پ@—¹ڈ³‚µ‚½پBپ@‚»‚µ‚ؤپA–ر—ک•û‚ئڈG‹g•û‚إگlژ؟‚ھŒً
پ@پ@ٹ·‚³‚ꂽپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ،پ@•گژm‚جژ©ٹQپBپ@
پ،پ@“ْ–{‚جˆہ“y“چژRژ‘م‘Oٹْ‚ـ‚إپAگط• ‚جچى–@‚à
پ@پ@’è‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@Œ©ژ–‚بگ´گ…ڈ@ژ،پi‚µ‚ف‚¸‚ق‚ث‚ح‚éپj‚جگط• ‚ھپAپ@
پ@پ@گط• ‚جچى–@‚ج‚¨ژè–{‚ج‚P‚آ‚ئ‚ب‚ء‚½پB
پ@
پ،پ@پuگط• ‚ھ–¼—_‚ ‚éژ€‚إ‚ ‚éپv‚ئ‚¢‚¤چl‚¦•û‚ً’è’…
پ@پ@‚³‚¹‚éگط‚ءٹ|‚¯‚ئ‚ب‚ء‚½پAگ´گ… ڈ@ژ،‚جگط• ‚جژ©
پ@پ@ٹQپB
پ@
پ،پ@گ´گ… ڈ@ژ،‚جگط• ‚جژ©ٹQ‚حپAپ@•گژm‚ة‚ئ‚ء‚ؤپA
پ@پ@پuگط• ‚ھ–¼—_‚ ‚éژ€‚إ‚ ‚éپv‚ئ‚¢‚¤چl‚¦•û‚ً’è’…
پ@پ@‚³‚¹‚éگط‚ءٹ|‚¯‚ئ‚ب‚éپBپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@ˆہ“y“چژRژ‘مŒمٹْˆبŒم‚©‚çچ]Œثژ‘م‚ـ‚إپA
پ@پ@•گژm‚ًژEٹQ‚·‚éڈêچ‡پAپ@چكگl‚ئ‚µ‚ؤ‚جژ€‚جپu‘إ‚؟
پ@پ@ژٌپvپ@‚ئپAپ@–¼—_‚ ‚éژ€‚جپuگط• پv‚ھ‹و•ت‚³‚ê‚é‚و
پ@پ@‚¤‚ة‚ب‚éپB
پ@
پ،پ@•گژm‚جژ©ٹQ‚حپAپ@“ْ–{‚جˆہ“y“چژRژ‘م‘Oٹْ‚ـ
پ@پ@‚إپAŒ`ژ®‚ح’è‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½پBپ@گط• ‚àژ©ٹQ
پ@پ@‚ج’P‚ب‚éژè’i‚ج‚P‚آ‚ة‰ك‚¬‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@
پ،پ@Œ©ژ–‚بگ´گ…ڈ@ژ،‚جگط• ˆبŒمپAپ@“ْ–{‚جˆہ“y“چ
پ@پ@ژRژ‘مŒمٹْˆبŒمپAپ@گط• ‚حپA•گژm‚ة‚ئ‚ء‚ؤپu–¼
پ@پ@—_‚ ‚éژ€پv‚إ‚ ‚é‚ئ‚¢‚¤”Fژ¯‚ھ•گژm‚ةچL‚ـ‚ء‚ؤ
پ@پ@‚¢‚ء‚½پBپ@
پ،پ@Œ©ژ–‚بگ´گ…ڈ@ژ،‚جگط• ˆبŒمپAپ@ŒY”±‚ئ‚µ‚ؤ‚à
پ@پ@گط• ‚ً–½‚¶‚éڈKٹµ‚ھچL‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@ˆہ“y“چژRژ‘م‘Oٹْ‚ـ‚إپAپ@گي‚¢‚إ•ك‚炦‚ç
پ@پ@‚ꂽ•گژm‚حپAپ@ŒY”±‚ئ‚µ‚ؤپAژٌ‚ً™†پi‚حپj‚ث‚ç‚ê
پ@پ@‚é‚©پAل÷پi‚ح‚è‚آ‚¯پj‚ة‚³‚ê‚é‚©پ@‚ب‚ا‚ھ•پ’ت‚إ
پ@پ@‚ ‚ء‚½پBپ@گط• ‚³‚¹‚éڈKٹµ‚ح–³‚©‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ©ژ–‚بگ´گ… ڈ@ژ،‚جگط• ˆبŒمپAپ@ŒY”±‚ئ‚µ
پ@پ@‚ؤ•گژm‚ًژ©ٹQ‚³‚¹‚éژè’i‚ج‚P‚آ‚ئ‚µ‚ؤپAپuگط• پv
پ@پ@‚ھچL‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚½پBپ@—ل‚ئ‚µ‚ؤپA–LگbڈG‹g‚ھ‰™
پ@پ@‚ج–LگbڈGژں‚ةگط• ‚ً–½‚¶‚ؤ‚¢‚éپB
پ@
پ@
پôپô گ´گ…ڈ@ژ، ‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢پA
پ@پ@ƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پAƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپB
پ@
پڑپ@گ´گ…ڈ@ژ،‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢ٹض
پ@پ@کAƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پB
پ@
پ،پ@ƒUپEƒvƒچƒtƒ@ƒCƒ‰پ[پ@
پ@پ@ پwپ@چ•“cپ@ٹ¯•؛‰qپ@پxپBپ@
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚P‚S”N‚PŒژ‚P“ْپE–{•ْ‘—پE
پ@پ@پ@—ًژjƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[”ش‘gپjپBپ@
پ@
پڑ گ´گ…ڈ@ژ، ‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢پA
پ@پ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f ‰وپB
پœپ@پi’چˆسپjپ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAƒtƒBƒNƒVƒ‡ƒ“پ@‚إ‚·پBپ@
پ@پ@—ًژj‚جƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAژjژہپi—ًژjڈم‚جژ–ژہپjپ@
پ@پ@‚ئپ@‰ث‹َ‚جڈo—ˆژ–‚ھپ@چ¬‚¶‚ء‚ؤ•`‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ
پ@پ@‚·پBپ@‚ـ‚½پAپ@Œ»‘م•—‚ةƒAƒŒƒ“ƒW‚µ‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚·پB
پ@
پ،پ@پwپ@ŒRژtپ@ٹ¯•؛‰qپ@پxپBپ@
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚P‚S”N‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پjپBپ@
پ،پ@ژ؛’¬ژ‘مŒمٹْپiگيچ‘ژ‘مپjپAˆہ“y“چژRژ‘مپA
پ@پ@چ]Œثژ‘مڈ‰ٹْ‚ً•`‚¢‚½ƒhƒ‰ƒ}پB
پ@
پœپ@گ´گ… ڈ@ژ،پ@پi‚µ‚ف‚¸ ‚ق‚ث‚ح‚éپA–ر—ک‰ئ‰ئگbپA
پ@پ@”ُ’†پEچ‚ڈ¼ڈéڈéژهپjپ@‚ً‰‰‚¶‚½”o—D–¼ پFپ@
پ@پ@‰Fٹپ چ„ژmپ@پi‚¤‚©‚¶ ‚½‚©‚µپjپB
پ@
پœپ@ˆہچ‘ژ› Œbàù‚ً‰‰‚¶‚½”o—D–¼پF ژRکH کaچOپB
پœپ@ڈ¬‘پگى—²Œi‚ً‰‰‚¶‚½”o—D–¼پF ’كŒ© ’CŒلپB
پœپ@‹gگىŒ³ڈt‚ً‰‰‚¶‚½”o—D–¼پF ‹gŒ©ˆê–LپB
پœپ@–ر—ک‹PŒ³‚ً‰‰‚¶‚½”o—D–¼پF ژO‰YچF‘¾پB
پœپ@چ•“c ٹ¯•؛‰q‚ً‰‰‚¶‚½”o—D–¼پF ‰ھ“cپ@ڈyˆêپB
پœپ@‰HژؤڈG‹gپi–LگbڈG‹gپj‚ً‰‰‚¶‚½”o—D–¼پF
’|’† ’¼گlپB
پ@
پ،پ@پwپ@گيچ‘ژ¾•—“` پi‚¹‚ٌ‚²‚‚µ‚ء‚ص‚¤‚إ‚ٌپjپ@
پ@پ@پ@“ٌگl‚جŒRژtپ`ڈG‹g‚ة“V‰؛‚ًٹl‚ç
پ@پ@پ@‚¹‚½’j‚½‚؟پ@پxپ@
پ@پ@پ@پ@پi“ْ–{‚ج‚Q‚O‚P‚P”NƒeƒŒƒr“Œ‹پE•ْ‰fƒeƒŒƒr
پ@پ@پ@پ@ƒhƒ‰ƒ}پjپBپ@
پ،پ@ژ؛’¬ژ‘مŒمٹْپiگيچ‘ژ‘مپjپAˆہ“y“چژRژ‘مپA
پ@پ@چ]Œثژ‘مڈ‰ٹْ‚ً•`‚¢‚½ƒhƒ‰ƒ}پB
پ،پ@گيچ‘پEˆہ“y“چژRژ‘م‚ً•`‚¢‚½ƒhƒ‰ƒ}پB
پ@پ@پ@چ•“c ٹ¯•؛‰qپiچFچ‚پi‚و‚µ‚½‚©پjپjپA’|’† ”¼•؛
پ@پ@‰qپiڈdژ،پi‚µ‚°‚ح‚éپjپj‚ج‚Qگl‚جŒRژt‚ً’†گS‚ةپA
پ@پ@•`‚پB
پœپ@گ´گ…ڈ@ژ،‚ً‰‰‚¶‚½”o—D–¼پ@پFپ@’†‘؛‰ëڈr
پ@پ@پi‚ب‚©‚ق‚ç‚ـ‚³‚ئ‚µپjپB
پ@
پœپ@–Lگb ڈG‹gپi‰HژؤڈG‹gپj‚ً‰‰‚¶‚½”o—D–¼پ@پFپ@
پ@پ@گ¼“c•qچsپB
پœپ@چ•“c ٹ¯•؛‰q‚ً‰‰‚¶‚½”o—D–¼پF چ‚‹´پ@چژ“Tپ@
پ@پ@پi‚½‚©‚ح‚µپ@‚©‚آ‚ج‚èپjپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ڈ—گ«“Vچcپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¹‚¢‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پjپB
پ@
پ،پ@ڈ—گ«“VچcپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ڈ—گ«“Vچcپ@پi‚¶‚ه‚¹‚¢‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پjپB
پ،پ@•ت–¼پFپ@ڈ—’éپ@پi‚¶‚ه‚ؤ‚¢پjپB
پ،پ@پs“VچcپtپB
پ،پ@“ْ–{‚جڈ—گ«“Vچc‚حپAژں‚ج‚Wگl‚P‚O‘م ‚إ‚ ‚éپB
پœپ@Œأ‘م“ْ–{‚ج”ٍ’¹”’–Pژ‘مپA“ق—اژ‘م‚جڈ—گ«
پ@پ@“Vچcپi= ڈ—’éپjپB
پi‚Pپjپ@گ„Œأپi‚·‚¢‚±پj“Vچcپ@
پ@پ@پ@ پiچفˆتپF‚T‚X‚Qپ`‚U‚Q‚W”NپjپAپ@
پi‚Qپjپ@چc‹ةپiگؤ–¾پjپi‚±‚¤‚¬‚ه‚پi‚³‚¢‚ك‚¢پjپj“Vچcپ@
پ@پ@پ@ پiچفˆتپF‚U‚S‚Qپ`‚U‚S‚T”NپA‚U‚T‚Tپ`‚U‚U‚U”NپjپA
پi‚Rپjپ@ژ“پi‚¶‚ئ‚¤پj“Vچcپ@
پiچفˆتپF‚U‚X‚Oپ`‚U‚X‚V”NپjپAپ@
پi‚Sپjپ@Œ³–¾پi‚°‚ٌ‚ك‚¢پj“Vچcپ@
پ@پ@پ@پiچفˆتپF‚V‚O‚Vپ`‚V‚P‚T”NپjپA
پi‚Tپjپ@Œ³گ³پi‚°‚ٌ‚µ‚ه‚¤پj“Vچcپ@
پ@پ@پ@پiچفˆتپF‚V‚P‚Tپ`‚V‚Q‚S”NپjپA
پi‚Uپj چFŒھپiڈج“؟پjپi‚±‚¤‚¯‚ٌپi‚µ‚ه‚¤‚ئ‚پjپj“Vچc
پ@پ@پ@پiچفˆتپF‚V‚S‚Xپ`‚V‚T‚WپA‚V‚U‚Sپ`‚V‚V‚O”NپjپA
پœپ@‹كگ¢“ْ–{‚جچ]Œثژ‘م‚جڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپjپB
پi‚Vپjپ@–¾گ³پi‚ك‚¢‚µ‚ه‚¤پj“Vچcپ@
پ@پ@پ@پiچفˆتپF‚P‚U‚Q‚Xپ`‚P‚U‚S‚R”NپjپAپ@
پi‚Wپjپ@Œمچ÷’¬پi‚²‚³‚‚ç‚ـ‚؟پj“Vچcپ@
پ@پ@پ@پiچفˆتپF‚P‚V‚U‚Qپ`‚P‚V‚V‚O”NپjپBپ@
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“Tپ@‚W‚P‚X‚Q‚RپB
پ@
پ@
پ پ@“ْ–{‚جڈ—گ« “Vچcپ@‰و‘œƒAƒ‹ƒoƒ€پ@
پ@پ@ ‚m‚ڈپD‚PپB
پ پ@ڈ—گ«“Vچc ‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢پA
پ@پ@پ@ ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپAƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ ƒٹپ[پB
پ پ@“ق—اژ‘م“ْ–{گژ،ژہŒ ژز•د‘J
پ@
پ،پ@—DڈG‚بڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپj‚ھ‘½‚¢پB
پ@
پ،پ@“ْ–{‚جŒأ‘م‚©‚猻‘م‚ـ‚إ‚جٹش‚ةپAڈ—گ«“Vچc‚حپA
پ@پ@”ٍ’¹”’–Pپi‚ ‚·‚©‚ح‚‚ظ‚¤پjژ‘مپA“ق—اپi‚ب‚çپj
پ@پ@ژ‘م‚ة“Vچc‚ة‘¦ˆتپiڈA ”Cپj‚µ‚½پAگ„Œأپi‚·‚¢‚±پjپA
پ@پ@چc‹ةپiگؤ–¾پjپi‚±‚¤‚¬‚ه‚پi‚³‚¢‚ك‚¢پjپjپAژ“پi‚¶‚ئ‚¤پjپA
پ@پ@Œ³–¾پi‚°‚ٌ‚ك‚¢پjپAŒ³گ³پi‚°‚ٌ‚µ‚ه‚¤پjپAچFŒھپiڈج“؟پj
پ@پ@پi‚±‚¤‚¯‚ٌپi‚µ‚ه‚¤‚ئ‚پjپj‚ج‚Uگl‚W‘م‚ج“Vچcپ@‚âپ@چ]
پ@پ@Œثپi‚¦‚اپjژ‘م‚ة“Vچc‚ة‘¦ˆتپiڈA ”Cپj‚µ‚½پA–¾گ³پi‚ك
پ@پ@‚¢‚µ‚ه‚¤پjپAŒمچ÷’¬پi‚²‚³‚‚ç‚ـ‚؟پj‚ج‚Qگl‚Q‘م‚ج“V
پ@پ@چc‚ھ‚¢‚ؤپAچ‡Œv‚µ‚ؤ‚Wگl‚P‚O‘م‚جڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپj
پ@پ@‚ھ‚¢‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@ڈ—گ«“Vچcپi‚¶‚ه‚¹‚¢‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پj‚ئ‚حپA ڈ—’éپ@پi‚¶‚ه
‚ؤ‚¢پj‚إ‚ ‚èپAپ@“ْ–{‚إ‚حپA“ْ–{‚جŒأ‘م‚©‚猻‘مپ@
پ@پ@‚ـ‚إ‚جٹش‚إپA”ٍ’¹”’–Pپi‚ ‚·‚©‚ح‚‚ظ‚¤پjژ‘مپA
“ق—اپi‚ب‚çپjژ‘مپAچ]Œثپi‚¦‚اپjژ‘م‚ة“Vچc‚ة‘¦ˆت
پiڈA”Cپj‚µ‚½‚Wگl ‚P‚O‘م‚جڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپj‚ھ
پ@پ@‚¢‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈdâNپi‚؟‚ه‚¤‚»پAچؤ‘¦ˆتپj‚µ‚½ڈ—گ«“Vچc
پ@پ@پi= ڈ—’éپj‚ھ‚Qگl‚¢‚é‚ج‚إپA ‚P‚O‘م‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@“ْ–{‚ج‚Wگl‚P‚O‘م‚جڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپj‚حپAپ@”ٍ
پ@پ@’¹”’–Pژ‘مپA“ق—اژ‘م‚جپAگ„Œأپi‚·‚¢‚±پjپAچc‹ة
پ@پ@پiگؤ–¾پjپi‚±‚¤‚¬‚ه‚پi‚³‚¢‚ك‚¢پjپjپAژ“پi‚¶‚ئ‚¤پjپ@“V
پ@پ@چcپjپAŒ³–¾پi‚°‚ٌ‚ك‚¢پjپAŒ³گ³پi‚°‚ٌ‚µ‚ه‚¤پjپAچFŒھ
پ@پ@پiڈج“؟پjپi‚±‚¤‚¯‚ٌپi‚µ‚ه‚¤‚ئ‚پjپjپ@“Vچcپj‚ج‚Uگl‚W‘م‚ج
پ@پ@ڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپj‚إ‚ ‚èپAپ@چ]Œثژ‘م‚جپA–¾گ³
پ@پ@پi‚ك‚¢‚µ‚ه‚¤پjپAŒمچ÷’¬پi‚²‚³‚‚ç‚ـ‚؟پj“Vچcپj‚ج‚Qگl‚Q
پ@پ@‘م‚جڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپj‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@“ْ–{‚جڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپj‚حپAپ@ ‚Qگl‚حڈdâNپi‚؟‚ه‚¤
پ@پ@‚»پAچؤ‘¦ˆتپj‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إپAپ@‚Wگl‚P‚O‘م‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@ڈdâNپi‚؟‚ه‚¤‚»پAچؤ‘¦ˆتپj‚µ‚½ڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپj
پ@پ@‚حپAپ@چc‹ةپiگؤ–¾پj“Vچcپ@‚ئپ@چFŒھپiڈج“؟پj“Vچcپ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@پ@
پںپ@“ْ–{‚ج‚Wگl‚P‚O‘م‚جڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپjپB
پ،پ@“ْ–{‚جڈ—گ«“Vچc‚حپAژں‚ج‚Wگl‚P‚O‘م ‚إ‚ ‚éپB
پ،پ@گ„Œأپi‚·‚¢‚±پj“Vچcپ@پ@پ@ پ@پiچفˆت‚T‚X‚Qپ`‚U‚Q‚W”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چإڈ‰‚جڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپjپB
پ،پ@چc‹ةپi‚±‚¤‚¬‚ه‚پj“Vچcپ@ پ@پiچفˆت‚U‚S‚Qپ`‚U‚S‚T”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“V’qپi‚ؤ‚ٌ‚¶پjپE“V•گپi‚ؤ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ٌ‚قپj“Vچc‚جگ¶•êپB
پ،پ@گؤ–¾پi‚³‚¢‚ك‚¢پj“Vچcپ@ پ@پiچفˆت‚U‚T‚Tپ`‚U‚U‚U”Nپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چc‹ة“Vچc‚ھچؤ‘¦ˆتپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“V’qپE“V•گ“Vچc‚جگ¶•êپB
پ،پ@ژ“پi‚¶‚ئ‚¤پj“Vچcپ@پ@پ@ پiچفˆت‚U‚X‚Oپ`‚U‚X‚V”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“V’q“Vچc‚جچcڈ—پi–؛پjپB
پ،پ@Œ³–¾پi‚°‚ٌ‚ك‚¢پj“Vچcپ@ پiچفˆت‚V‚O‚Vپ`‚V‚P‚T”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“V’q“Vچc‚جچcڈ—پi–؛پjپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•¶•گپi‚à‚ٌ‚قپjپEŒ³گ³“V
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چc‚جگ¶•êپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ¹•گ“Vچc‚ج‘c•êپB
پ،پ@Œ³گ³پi‚°‚ٌ‚µ‚ه‚¤پj“Vچc پiچفˆت‚V‚P‚Tپ`‚V‚Q‚S”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ³–¾“Vچc‚جچcڈ—پi–؛پjپB
پ،پ@چFŒھپi‚±‚¤‚¯‚ٌپj“Vچcپ@ پiچفˆت‚V‚S‚Xپ`‚V‚T‚W”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ¹•گپi‚µ‚ه‚¤‚¤‚قپj“Vچc‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چcڈ—پi–؛پjپjپB
پ،پ@ڈج“؟پi‚µ‚ه‚¤‚ئ‚پj“Vچcپ@ پiچفˆت‚V‚U‚Sپ`‚V‚V‚O”Nپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چFŒھ“Vچc‚ھچؤ‘¦ˆتپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ¹•گ“Vچc‚جچcڈ—پi–؛پjپB
پ،پ@–¾گ³پi‚ك‚¢‚µ‚ه‚¤پj“Vچcپ@پ@پ@ پiچفˆت‚P‚U‚Q‚Xپ`‚P‚U‚S‚R”Nپjپ@
پ@پ@پ@Œمگ…”ِ“Vچc‚جچcڈ—پi–؛پjپB
پ،پ@Œمچ÷’¬پi‚²‚³‚‚ç‚ـ‚؟پj“Vچcپ@پiچفˆت‚P‚V‚U‚Qپ`‚P‚V‚V‚O”Nپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ÷’¬“Vچc‚جچcڈ—پi–؛پjپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پںپ@“ْ–{‚جڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپjپB
پ،پ@“ْ–{‚إڈd—v‚ب–ًٹ„‚ً‰ت‚½‚µ‚½ڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپj
پ@پ@‚حپAپ@گ„Œأپi‚·‚¢‚±پj“Vچcپ@پiچفˆتپF‚T‚X‚Q”Nپ`‚U‚Q‚W”NپA
پ@پ@چإڈ‰‚جڈ—’éپi= ڈ—گ«‚ج“VچcپjپjپAپ@چc‹ةپiگؤ–¾پjپi‚±‚¤‚¬
پ@پ@‚ه‚پi‚³‚¢‚ك‚¢پjپj“Vچcپ@پiچc‹ة“VچcچفˆتپF‚U‚S‚Qپ`‚U‚S‚T”NپA
پ@پ@گؤ–¾“VچcچفˆتپF‚U‚T‚Tپ`‚U‚U‚U”NپjپjپAپ@ژ“پi‚¶‚ئ‚¤پj
پ@پ@“Vچcپ@پiچفˆتپF‚U‚X‚Oپ`‚U‚X‚V”NپjپAپ@Œ³–¾پi‚°‚ٌ‚ك‚¢پj
پ@پ@“Vچcپ@پiچفˆتپF‚V‚O‚Vپ`‚V‚P‚T”NپjپAپ@چFŒھپiڈج“؟پjپi‚±‚¤‚¯
پ@پ@‚ٌپi‚µ‚ه‚¤‚ئ‚پjپj“Vچcپ@پiچFŒھ“VچcچفˆتپF‚V‚S‚Xپ`‚V‚T‚W”NپA
پ@پ@ڈج“؟“VچcپFچفˆت‚V‚U‚Sپ`‚V‚V‚O”Nپjپ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@گ„Œأپi‚·‚¢‚±پj“Vچcپ@پiچفˆتپF‚T‚X‚Q”Nپ`‚U‚Q‚W”Nپjپ@‚حپA
”ٍ’¹”’–Pژ‘م‚جڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپj‚إ‚ ‚èپAپ@“ْ–{
پ@پ@‚جچإڈ‰‚جڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپj‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ„Œأ“Vچc‚حپA‰™پi‚¨‚¢پj‚ج‰XŒثچcژqپi‚¤‚ـ‚â‚ا
پ@پ@‚ج‚ف‚±پE‚¨‚¤‚¶پAگ¹“؟‘¾ژqپj‚â‘h‰ن”nژq‚ئ‹¦—ح‚µ‚ؤپA
پ@پ@ڈ¬چ¤“c‹{پi‚¨‚ي‚肾‚ج‚ف‚âپj‘J“sپA‚»‚ج‘¼‘½‚‚جگ
پ@پ@چô‚ًچs‚¢پA‚ـ‚½پA”ٍ’¹پi‚ ‚·‚©پj•¶‰»‚ًŒ»ڈo‚³‚¹‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@چc‹ةپiگؤ–¾پj“Vچcپ@ پiچc‹ةپi‚±‚¤‚¬‚ه‚پj“VچcچفˆتپF
پ@پ@‚U‚S‚Qپ`‚U‚S‚T”NپAگؤ–¾پi‚³‚¢‚ك‚¢پj“Vچc پi“VچcچفˆتپF
پ@پ@‚U‚T‚Tپ`‚U‚U‚U”Nپjپjپ@‚حپAپ@”ٍ’¹”’–Pژ‘م‚جڈ—گ«“V
پ@پ@چcپi= ڈ—’éپj‚إ ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@چc‹ةپiگؤ–¾پj“Vچc‚حپAپ@ک®–¾پi‚¶‚ه‚ك‚¢پj“Vچc‚ج
پ@پ@چcچ@‚إ‚ ‚èپAپ@“V’qپi‚ؤ‚ٌ‚¶پj“Vچc‚â“V•گپi‚ؤ‚ٌ‚قپj
پ@پ@“Vچc‚جگ¶•ê‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@چc‹ةپiگؤ–¾پj“Vچc‚حپA ‚U‚S‚T”N‚ج‰³–¤‚ج•دپi‚¢
پ@پ@‚ء‚µ‚ج‚ض‚ٌپj‚جژ‚ج“Vچc‚إ‚ ‚èپAپ@ژq‚ج’†‘هŒZچc
پ@پ@ژqپi‚ب‚©‚ج‚¨‚¨‚¦‚ج‚ف‚±پi‚¨‚¤‚¶پjپAŒم‚ج“V’q“Vچcپj
پ@پ@‚ئ‹¦—ح‚µ‚ؤپAپ@‘½‚‚جگچô‚ًژہژ{‚µپA‘ه‰»‚ج‰üگV‚ً
پ@پ@گ„گi‚µپA‚ـ‚½پA”ٍ’¹پi‚ ‚·‚©پj•¶‰»‚ً”“W‚³‚¹‚éپBپ@
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@ژ“پi‚¶‚ئ‚¤پj“Vچcپ@پiچفˆتپF‚U‚X‚Oپ[‚U‚X‚V”Nپj‚حپAپ@”ٍ
پ@پ@’¹”’–Pژ‘م‚جڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپj‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@ژ““Vچc‚حپAپ@“V•گ“Vچcپiچفˆت‚U‚V‚Rپ[‚U‚W‚U”Nپj
پ@پ@‚جچcچ@‚إپA“V•گ“Vچc‚جژ€Œمژ·گپi‚µ‚ء‚¹‚¢پAڈA”CپF
پ@پ@‚U‚W‚Uپ`‚U‚X‚O”Nپj‚ئ‚ب‚èپAپ@‚»‚جŒمپAڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپj
پ@پ@‚ئ‚ب‚éپBپ@ڈٍŒنŒ´—ك‚جژ{چsپA“،Œ´‹پi‚س‚¶‚ي‚ç‚«‚ه
پ@پ@‚¤پA‚U‚X‚Sپ`‚V‚P‚O”Nپj‘J“sپA‚»‚ج‘¼‘½‚‚جگچô ‚ًچs‚¢پAپ@
پ@پ@—¥—كچ‘‰ئ‚جٹî”صچى‚è‚ة“w—ح‚µپA‚ـ‚½پA”’–Pپi‚ح‚‚ظ
پ@پ@‚¤پj•¶‰»‚ًŒ»ڈo‚³‚¹‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@Œ³–¾پi‚°‚ٌ‚ك‚¢پj“Vچcپ@پiچفˆتپF‚V‚O‚Vپ[‚V‚P‚T”Nپj‚حپA
پ@پ@”ٍ’¹”’–Pژ‘مپA“ق—اژ‘مڈ‰ٹْ‚جڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپj
پ@پ@‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@Œ³–¾“Vچc‚حپAپ@“V’q“Vچc‚جچcڈ—پi–؛پj‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@•¶•گپi‚à‚ٌ‚قپj“Vچc‚⌳گ³پi‚°‚ٌ‚µ‚ه‚¤پj“Vچcپiڈ—’éپj
پ@پ@‚جگ¶•ê‚إ‚ ‚èپAگ¹•گ“Vچc‚ج‘c•ê‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@Œ³–¾“Vچc‚حپAپ@پ@•½ڈé‹پ@پi‚ض‚¢‚¶‚ه‚¤‚«‚ه‚¤پA
پ@پ@‚V‚P‚O”Nپ[‚V‚W‚S”Nپj‘J“sپA‚»‚ج‘¼‘½‚‚جگچô ‚ًچs‚¢پA
پ@پ@—¥—كچ‘‰ئ‚جٹî‘b‚ً’z‚پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@Œ³گ³“Vچcپ@پi‚°‚ٌ‚µ‚ه‚¤‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پA“VچcچفˆتپF‚V‚P‚T”N
پ@پ@پ@پ[‚V‚Q‚S”NپA‰pپF‚s‚g‚dپ@‚d‚l‚o‚q‚d‚r‚rپ@‚f‚d‚m‚r‚g‚nپj‚حپA
پ@پ@“ق—اژ‘م‘Oٹْ‚جپAڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپj‚إ ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@Œ³گ³“Vچc‚حپAپ@Œ³–¾پi‚°‚ٌ‚ك‚¢پj“VچcپiچفˆتپF
پ@پ@پ@‚V‚O‚Vپ[‚V‚P‚T”Nپj‚جچcڈ—پi–؛پj‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@Œ³گ³“Vچc‚حپAپ@•ê‚جŒ³–¾پi‚°‚ٌ‚ك‚¢پj“Vچc‚جگ
پ@پ@پ@چô‚ًˆّ‚«Œp‚¬پAپ@‘½‚‚جگچô‚ًچs‚¢پA—¥—كچ‘‰ئ‚جٹî
پ@پ@پ@‘b‚ًٹm—§‚·‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ،پ@چFŒھپiڈج“؟پj“Vچcپ@پi‚±‚¤‚¯‚ٌپi‚µ‚ه‚¤‚ئ‚پj‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پA
پ@پ@چفˆتپF‚V‚S‚X”Nپ[‚V‚T‚W”NپA‚V‚U‚S”Nپ[‚V‚V‚O”Nپj‚حپAپ@
پ@پ@“ق—اژ‘م‚جڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپjپ@‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@چFŒھپiڈج“؟پj“Vچc‚حپAپ@ˆ¢”{“àگe‰¤پi‚ ‚×پi‚جپj
پ@پ@‚ب‚¢‚µ‚ٌ‚ج‚¤پj‚إ‚ ‚èپAپ@گ¹•گپi‚µ‚ه‚¤‚قپj“Vچc‚جچcڈ—
پ@پ@پi–؛پj‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@چFŒھپiڈج“؟پj“Vچc‚حپAپ@‚V‚T‚Q”Nپi“V•½ڈں•َ‚S”Nپj
پ@پ@‚ج‘ه•§ٹJٹلژ‚ج“Vچc‚إ‚ ‚èپAپ@•ƒ‚جگ¹•گ“Vچcپiگ¹
پ@پ@•گ‘¾ڈمپi‚¾‚¶‚ه‚¤پj“VچcپjپAپ@‹kڈ”ŒZپi‚½‚؟‚خ‚ب‚ج‚à‚ë
پ@پ@‚¦پjپAپ@‹g”ُگ^”ُپi‚«‚ر‚ج‚ـ‚«‚رپjپAپ@“،Œ´’‡–ƒکCپi‚س
پ@پ@‚¶‚ي‚ç‚ج‚ب‚©‚ـ‚ëپjپAپ@“¹‹¾پi‚ا‚¤‚«‚ه‚¤پjپ@‚ئ‹¦—ح‚µ‚ؤپAپ@
پ@پ@‘½‚‚جگچô‚ًچs‚¢پAپ@“Œ‘هژ›‘ه•§‘¢‰c‚ًگ„گi‚µٹ®گ¬
پ@پ@‚³‚¹پAپ@•§‹³’ءŒىپi‚؟‚ٌ‚²پjچ‘‰ئ‚ة‚و‚éچ‘‰ئ‚جˆہ’è‚ً
پ@پ@‚ح‚©‚èپAپ@‚ـ‚½پA“V•½پi‚ؤ‚ٌ‚ز‚ه‚¤پj•¶‰»‚ًŒ»ڈo‚³‚¹‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@پ@
پ،پ@–¾گ³پi‚ك‚¢‚µ‚ه‚¤پj“Vچcپ@پiچفˆتپF‚P‚U‚Q‚X”Nپ[‚P‚U‚S‚R”NپA
پ@پ@‰pپF‚s‚g‚dپ@‚d‚l‚o‚q‚d‚r‚rپ@‚l‚d‚h‚r‚g‚nپj‚حپAپ@چ]Œثژ
پ@پ@‘م‚جڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپj‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@–¾گ³پi‚ك‚¢‚µ‚ه‚¤پj“Vچc‚حپAپ@‚¨چ]پi‚¨‚²‚¤پj‚ئچ]
پ@پ@Œث–‹•{‘و‚Q‘مڈ«ŒRپE“؟گىڈG’‰‚ئ‚جٹش‚ج–؛پE“؟گىکaژq
پ@پ@پi‚ـ‚³‚±پj‚جژq‚إ‚ ‚éپBپ@
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ،پ@Œمچ÷’¬پi‚²‚³‚‚ç‚ـ‚؟پj“Vچcپ@پiچفˆتپF‚P‚V‚U‚Q”Nپ[‚P‚V‚V‚O
پ@پ@”NپA‰pپF‚s‚g‚dپ@‚d‚l‚o‚q‚d‚r‚rپ@‚f‚n‚r‚`‚j‚t‚q‚`‚l‚`‚b‚g‚hپj
پ@پ@‚حپAپ@چ]Œثژ‘م‚جڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپj‚إ‚ ‚éپBپ@
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@
پ،پ@پƒƒRƒپƒ“ƒgپ„پ@Œ»چف‚جڈغ’¥“Vچcگ§‚إ‚حپAپ@چcژ؛
پ@پ@“T”حپi‚±‚¤‚µ‚آ‚ؤ‚ٌ‚د‚ٌپj‚ة‚و‚èڈ—گ«“Vچc‚ھ‘¦ˆت
پ@پ@پiڈA”Cپj‚إ‚«‚ب‚¢‚ھپAپ@گ¢ٹE‚إ‚حپAƒGƒٹƒUƒxƒXڈ—
پ@پ@‰¤‚ً‚ح‚¶‚ك‘½‚‚ج—§Œ›‰¤چ‘‚إڈ—‰¤‚ھŒ»ڈo‚µ‚ؤ‚¢
پ@پ@‚éپBپ@’jڈ—•½“™‚⌻چc‘°’¼Œn‚ج’fگâ–hژ~‚جٹد
پ@پ@“_‚©‚çپA“ْ–{‚àگ§“x‚ً‰ü‚كپAڈ—گ«“Vچc‚ھ‘¦ˆت
پ@پ@پiڈA”Cپj‚إ‚«‚é‚و‚¤‚ة‚·‚ׂ«‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚إ‚حپAپ@“Vچc‚جگ³ژ؛•vگl‚ح‚ذ
پ@پ@ژم‚بڈ—گ«‚ھ‘½‚پA‘ج‚جڈن•v‚ب‘¤ژ؛•vگl‚ھگ¶•ê
پ@پ@‚إ‚ ‚é“Vچc‚ھ‘½‚پA‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج“Vچc‰ئ‚جˆê
پ@پ@•v‘½چبگ§‚ئˆظ‚ب‚èپAŒ»چف‚ج“Vچc‰ئ‚حˆê•vˆê•w
پ@پ@گ§‚إ‘¤ژ؛•vگl‚ھ‚¢‚ب‚پAپ@Œ»چc‘°’¼Œn‚ج’jگ«‚ھ
پ@پ@“rگ₦’fگâ‚·‚é‰آ”\گ«‚ھ‚ ‚èپAپ@Œ»چc‘°’¼Œn‚ج
پ@پ@’fگâ‚ً–h‚®‚½‚ك‚ة‚àپAڈ—گ«“Vچc‚ً—i—§‚·‚é•K—v
پ@پ@‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پ@
پ@
پôپôپ@ڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپj‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»
پ@پ@–،گ[‚¢پAƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپAƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پB
پ@
پڑپ@ڈ—گ«“Vچcپi= ڈ—’éپj‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،
پ@پ@گ[‚¢پAƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپB
پœپ@پi’چˆسپjپ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAپ@ƒtƒBƒNƒVƒ‡ƒ“پ@‚إ‚·پBپ@
پ@پ@—ًژj‚جƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپ@‚حپAژjژہپi—ًژjڈم‚جژ–ژہپjپ@
پ@پ@‚ئپ@‰ث‹َ‚جڈo—ˆژ–پ@‚ھچ¬‚¶‚ء‚ؤ•`‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپ@پ@
پ@پ@‚ـ‚½پAپ@Œ»‘م•—‚ةƒAƒŒƒ“ƒW‚µ‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚·پB
پ@
پ،پ@پwپ@‘ه•§ٹJٹلپ@پi‚¾‚¢‚ش‚آ‚©‚¢‚°‚ٌپjپ@پx پBپ@
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚P‚O”NŒأ‘مژjƒhƒ‰ƒ}
پ@پ@پ@ƒXƒyƒVƒƒƒ‹پjپB
پœپ@چFŒھ“Vچc پi= ڈج“؟“VچcپAˆ¢•”“àگe‰¤پj‚ً‰‰‚¶
پ@پ@پ@‚½ڈ——DپFپ@گخŒ´پ@پi‚¢‚µ‚ح‚çپjپ@‚³‚ئ‚فپB
پœپ@چFŒھپiڈج“؟پjپi‚±‚¤‚¯‚ٌپi‚µ‚ه‚¤‚ئ‚پjپj“Vچcپ@پiچف
پ@پ@پ@ˆت‚V‚S‚Xپ`‚V‚T‚WپA‚V‚U‚Sپ`‚V‚V‚O”Nپjپ@‚ھپA“oڈê
پ@پ@پ@‚·‚éپBپ@چFŒھپiڈج“؟پj“Vچc‚ج‘¦ˆت‘O‚ج–¼ڈج‚حپAپ@
پ@پ@پ@ˆ¢•”“àگe‰¤پi‚ ‚ׂج‚ب‚¢‚µ‚ٌ‚¨‚¤پjپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ژُŒj“ٍپ@پ@
پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚م‚¯‚¢‚ةپjپB
پ@
پ،پ@ژُŒj“ٍپBپ@
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ژُŒj“ٍپ@پi‚¶‚م‚¯‚¢‚ةپjپB
پ،پ@‰pŒê–¼پ@پFپ@‚i‚•‚‹‚…‚‰‚ژ‚‰پD
پ،پ@پsگl–¼پtپ@ڈ—گيچ‘‘ه–¼پB
پ،پ@گ¶–v”NپFپ@گ¶”N•sڈعپ|‚P‚T‚U‚W”NپB
پ،پ@ڈx‰ح‚جگيچ‘‘ه–¼پEچ،گىژپگeپi‚¤‚¶‚؟‚©پj‚جگ³ژ؛•vگlپB
پ،پ@چ،گىژپ‹Pپi‚¤‚¶‚ؤ‚éپj‚âچ،گى‹` Œ³پi‚و‚µ‚à‚ئپj‚جگ¶•ê پA
پ@پ@چ،گىژپگ^پi‚¤‚¶‚´‚ثپj‚ج‘c•êپB
پ،پ@ژُŒj“ٍ‚ج•vپEچ،گىژپگeژ€ŒمپA چ،گىژپ‹PپAچ،گى‹`Œ³پA
پ@پ@چ،گىژپگ^‚جچ،گىژپ‚R‘م‚ة“n‚èپAچ،گىژپ“–ژه‚جگ–±‚ً
پ@پ@•âچ²‚µ‚½‚èپA‘م—‚µ‚½‚肵‚½پB
پ،پ@ چ،گى‹`Œ³پA‘¾Œ´گلچضپAچ،گىژپگ^پA“؟گى‰ئچN‚ةٹض‚µ‚ؤ
پ@پ@‚حپAپuچ،گى‹`Œ³پvپAپu‘¾Œ´گلچضپvپA پuچ،گىژپگ^پvپAپu“؟گى
پ@پ@‰ئچNپv‚ًژQڈئ‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢.
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“Tپ@‚W‚P‚R‚P‚TپB
پ@
پ،پ@ژُŒj“ٍپ@پi‚¶‚م‚¯‚¢‚ةپAگ¶”N•sڈعپ`‚P‚T ‚U‚W”Nپj‚حپAپ@
پ@پ@ڈx‰ح‚جگيچ‘‘ه–¼پEچ،گىژپگeپi‚¤‚¶‚؟‚©پj‚جگ³ژ؛•vگl‚إ
پ@پ@‚ ‚èپAپ@چ،گىژپ‹Pپi‚¤‚¶‚ؤ‚éپj‚âچ،گى‹`Œ³پi‚و‚µ‚à‚ئپj‚ج
پ@پ@گ¶•ê‚إ‚ ‚èپAچ،گىژپگ^پi‚¤‚¶‚´‚ثپj‚ج‘c•ê‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@ژُŒj“ٍ‚حپAپ@چ،گىژپگeژ€ŒمپAچ،گىژپ‹PپA چ،گى‹`Œ³پA
پ@پ@چ،گىژپگ^ ‚جچ،گىژپ‚R‘م‚ة“n‚èپAچ،گىژپ“–ژه‚جگ–±
پ@پ@‚ً•âچ²‚µ‚½‚èپA‘م—‚µ‚½‚肵‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@ژُŒj“ٍ‚حپAپ@ژ؛’¬ژ‘مŒمٹْپiگيچ‘ژ‘مپj‚جڈ—گي
پ@پ@چ‘‘ه–¼‚ج‚Pگl‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@ژُŒj“ٍپ@پi‚¶‚م‚¯‚¢‚ةپAگ¶”N•sڈع پ[‚P‚T‚U‚W”Nپj
پ@پ@‚حپAچ،گىژپگeپi‚¤‚¶‚؟‚©پj‚جگ³ژ؛•vگl‚إپAپ@چ،گى
پ@پ@ژپ‹Pپi‚¤‚¶‚ؤ‚éپj‚âچ،گى‹`Œ³پi‚و‚µ‚à‚ئپj‚جگ¶•ê‚إپA
پ@پ@چ،گىژپگ^پi‚¤‚¶‚´‚ثپj‚ج‘c•ê‚إ‚ ‚èپAپ@ژُŒj“ٍ‚ج
پ@پ@•vپEچ،گىژپگeژ€ŒمپAپ@چ،گىژپ‹PپAچ،گى‹`Œ³پAچ،گى
پ@پ@ژپگ^‚جچ،گىژپ‚R‘م‚ة“n‚èپAگ–±‚ً•âچ²‚µ‚½پB
پ@پ@پ@پ@ژُŒj“ٍ‚حپAپ@گيچ‘ژ‘مپiژ؛’¬ژ‘مŒمٹْپj‚ةپA
پ@پ@’jگ«“–ژه‚ً—§‚ؤ‚ؤپAپ@ŒمŒ©گl‚ئ‚µ‚ؤژہژ؟“I‚ة—ج
پ@پ@چ‘گژ،ژہŒ ‚ًˆ¬‚ء‚½ڈ—گ«‚إ‚ ‚èپAڈ—گيچ‘‘ه–¼
پ@پ@‚ج‚Pگlپ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پôپôپ@ژُŒj“ٍ‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[ ‚¢پAƒhƒL
پ@پ@پ@پ@ƒ…ƒپƒ^ƒ“ƒٹپ[پAƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپB
پ@
پڑپ@ژُŒj“ٍ‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[ ‚¢پAƒhƒ‰ƒ}پA
پ@پ@ ‰f‰وپB
پœپ@پi’چˆسپjپ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAپ@ƒtƒBƒNƒVƒ‡ƒ“‚إ‚·پBپ@
پ@پ@پ@—ًژj‚جƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAپ@ژjژہپi—ًژjڈم‚جژ–ژہپj
پ@پ@پ@‚ئپ@‰ث‹َ‚جڈo—ˆژ–پ@‚ھپ@چ¬‚¶‚ء‚ؤ•`‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@پ@پ@‚ـ‚½پAپ@Œ»‘م•—‚ةƒAƒŒƒ“ƒW‚µ‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚·پB
پ@
پ،پ@پwپ@‚¨‚ٌ‚بڈéژهپ@’¼Œصپ@پi‚¨‚ٌ‚ب
پ@پ@پ@پ@پ@ ‚¶‚ه‚¤‚µ‚مپ@‚ب‚¨‚ئ‚çپjپ@پx پBپ@
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚P‚V”N‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پjپB
پ،پ@“ْ–{‚جژ؛’¬ژ‘مŒمٹْپiگيچ‘ژ‘مپjپAˆہ“y“چژR
پ@پ@ ژ‘م‚جژ‘مڈَ‹µ‚â‚»‚جژ‘م‚ةٹˆ–ô‚µ‚½گlپX
پ@پ@‚ً•`‚پB
پœپ@ژُŒj“ٍپi‚¶‚م‚¯‚¢‚ةپj‚ً‰‰‚¶‚éڈ——Dپ@پFپ@پ@
پ@پ@پ@گَ‹uƒ‹ƒٹژqپB
پœپ@چ،گى ‹`Œ³‚ً‰‰‚¶‚é”o—D پFپ@ڈt•—’àپ@ڈ¸‘¾پB
پœپ@چ،گىژپگ^پi‚¤‚¶‚´‚ثپj‚ً‰‰‚¶‚é”o—Dپ@ پF
پ@پ@پ@”ِڈمپ@ڈ¼–çپB
پ@
پ،پ@پwپ@•——ر‰خژRپ@پi‚س‚¤‚è‚ٌ‚©‚´‚ٌپjپ@پx پBپ@
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚O‚V”N‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پjپB
پ،پ@“ْ–{‚جژ؛’¬ژ‘مŒمٹْپiگيچ‘ژ‘مپj‚جژ‘م
پ@پ@ڈَ‹µ‚â‚»‚جژ‘م‚ةٹˆ–ô‚µ‚½گlپX‚ً•`‚پB
پ،پ@چ،گى ‹`Œ³‚جپAڈx‰حپiگأ‰ھŒ§پj‚جژçŒىپiچ‘ژهپj
پ@پ@ڈA”C‚©‚çپAپ@•گ“cژپ‚â–k ڈًژپ‚ئ‚جگي‚¢پA
پ@پ@•گ“cژپ‚جگM”Z‚جگھ•‚ب‚ا‚ً•` ‚¢‚ؤ‚¢‚éپB
پœپ@ژُŒj“ٍ‚ً‰‰‚¶‚½ڈ——Dپ@پ@پ@پFپ@“،‘؛ ژu•غپB
پœپ@چ،گىژپ‹P‚ً‰‰‚¶‚½”o—Dپ@ پF Œـ•َ چFˆêپB
پœپ@چ،گى ‹`Œ³‚ً‰‰‚¶‚½”o—Dپ@پFپ@’JŒ´ ڈح‰îپB
پœپ@‘¾Œ´گلچض‚ً‰‰‚¶‚½”o—Dپ@ پFپ@ˆة•گ ‰ë“پپ@
پ@پ@پi‚¢‚ش ‚ـ‚³‚ئ‚¤پjپB
پœپ@چ،گىژپگ^‚ً‰‰‚¶‚½”o—Dپ@ پF •—ٹش —RژںکYپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
#edictsoncompassionforlivingthings
پ@
پ،پ@گ¶—ق—÷‚ف‚ج—كپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚é‚¢‚ ‚ي‚ê‚ف‚ج‚ê‚¢پjپB
پ@
پ،پ@گ¶—ق—÷‚ê‚ج—كپBپ@
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@گ¶—ق—÷‚ê‚ج—كپ@پi‚µ‚ه‚¤‚é‚¢‚ ‚ي‚ê‚ف‚ج
پ@پ@‚ê‚¢پjپB
پœپ@‰p–¼پFپ@‚s‚ˆ‚…پ@‚d‚„‚‰‚ƒ‚”‚“پ@‚ڈ‚ژپ@‚b‚ڈ‚چ‚گ‚پ‚“‚“‚‰‚ڈ‚ژپ@‚†‚ڈ‚’پ@
پ@پ@پ@‚k‚‰‚–‚‰‚ژ‚‡پ@‚s‚ˆ‚‰‚ژ‚‡‚“پB
پ،پ@چ]Œث–‹•{‚T‘مڈ«ŒRپE“؟گىچj‹gپi‚ئ‚‚ھ‚ي‚آ‚ب‚و‚µپAڈ«
پ@پ@ŒRچف”C‚P‚U‚W‚O”Nپ`‚P‚V‚O‚X”Nپj‚ھپA‚P‚U‚W‚T”N‚©‚ç‚P‚V‚O‚X
پ@پ@”N‚ـ‚إ‚جٹش‚ةڈo‚µ‚½پAگlٹشپE“®•¨‚جگ¶–½‘¸ڈdٹضŒW‚ج
پ@پ@‘½گ”‚ج–@—كپi‚¨گG‚êپj‚ج‘چڈجپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپBپ@
پ@
پ@
پ،پ@‚±‚جگ¶—ق—÷‚ف‚ج—ك‚ة‚و‚èپA‚±‚êˆبŒمپAپ@“ْ–{‚حپA•گ
پ@پ@—ح‚ًڈd‚ٌ‚¶•گ—ح‚إ‘ٹژè‚ًژEڈ‚µ•¨ژ–‚ً‰ًŒˆ‚µ‚و‚¤‚·‚é
پ@پ@پuگيچ‘‚جگ¢پv‚حڈI‚ي‚è‚ً‚آ‚°پAپ@ژEگ¶پi‚¹‚ء‚µ‚ه‚¤پj‚ًŒ™
پ@پ@‚¢پAگl–½‘¸ڈdپAژمژز•غŒىپAگl‚ةگeگط‚ة‚µپA‚₳‚µ‚¢گS
پ@پ@‚ًژ‚آ‚±‚ئ‚ھ”ü“؟‚ئ‚³‚ê‚éژ‘مپ@‚ئ‚ب‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپBپ@
پ@
پ،پ@پuگ¶—ق—÷‚ê‚ج—كپvپi‚µ‚ه‚¤‚é‚¢‚ ‚ي‚ê‚ف‚ج‚ê‚¢پj‚ئ‚حپA
پ@پ@چ]Œث–‹•{پE‘و‚T‘مڈ«ŒR“؟گىچj‹g‚ھ‚P‚U‚W‚T”N‚©‚ç‚Q‚O
پ@پ@”Nˆبڈم‚ة‚©‚¯‚ؤپA–ٌ‚P‚R‚T‰ٌ‚ة•ھ‚¯‚ؤ”—ك‚µ‚½ŒنگG
پ@پ@ڈ‘پi‚¨‚س‚ê‚ھ‚«پjپ@‚ج‘چڈج‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پuگ¶—ق—÷‚ê‚ج—كپv‚حپAپ@چ]Œث–‹•{پE‘و‚T‘مڈ«ŒR“؟
پ@پ@گىچj‹g“ژ،’†‚جپA‚P‚U‚W‚T”Nپi’ه‹پi‚¶‚ه‚¤‚«‚ه‚¤پj‚Q”Nپj
پ@پ@‚VŒژ‚ةچإڈ‰‚ةڈo‚³‚êپAپ@‚»‚êˆبŒمپAچj‹g‚جژ€‹ژ‚µ‚½
پ@پ@‚P‚V‚O‚X”Nپi•َ‰iپi‚ظ‚¤‚¦‚¢پj‚U”Nپj‚ـ‚إ‚جٹش‚ةڈo‚³‚ꂽپA
پ@پ@گlٹشپE“®•¨‚جگ¶–½‘¸ڈdٹضŒW‚ج‘½گ”‚ج–@—كپi‚¨گG‚êپj
پ@پ@‚ج‘چڈجپ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپBپ@
پ@
پ،پ@گ¶—ق—÷‚ê‚ج—كپ@پi‚µ‚ه‚¤‚é‚¢‚ ‚ي‚ê‚ف‚ج‚ê‚¢پjپ@‚حپA
پ@پ@چ]Œث–‹•{‚T‘مڈ«ŒRپE“؟گىچj‹gپ@پi‚ئ‚‚ھ‚ي‚آ‚ب‚و‚µپA
پ@پ@ڈ«ŒRچف”C‚P‚U‚W‚O”Nپ`‚P‚V‚O‚X”Nپj‚ھپAپ@‚P‚U‚W‚T”N‚©‚ç
پ@پ@‚P‚V‚O‚X”N‚ـ‚إ‚جٹش‚ةڈo‚µ‚½پAگlٹشپE“®•¨‚جگ¶–½‘¸ڈd
پ@پ@ٹضŒW‚ج‘½گ”‚ج–@—كپi‚¨گG‚êپj‚ج‘چڈج پ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@گ¶—ق—÷‚ê‚ج—ك‚جپA‰p–¼‚حپAپ@ ‚s‚ˆ‚…پ@‚d‚„‚‰‚ƒ‚”‚“پ@‚ڈ‚ژپ@
پ@پ@پ@‚b‚ڈ‚چ‚گ‚پ‚“‚“‚‰‚ڈ‚ژپ@‚†‚ڈ‚’پ@‚k‚‰‚–‚‰‚ژ‚‡پ@‚s‚ˆ‚‰‚ژ‚‡‚“پ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپBپ@
پ@
پ@
پ،پ@“؟گىچj‹g‚جپAپuگ¶—ق—÷‚ف‚ج—كپvپB
پ،پ@“؟گىپ@چj‹g‚حپAپ@“ْ–{گl‚جˆسژ¯‰üٹv‚ًژہچs‚µ‚½
پ@پ@ڈ«ŒR‚إ‚ ‚èپAپ@ژمژز•غŒىپAگlŒ ‘¸ڈdپA“®•¨ˆ¤Œى‚ج
پ@پ@گ¸گ_‚ً“ْ–{گl‚ةگA‚¦•t‚¯پAپ@پu‚₵‚گeگط‚بگSپv‚ً
پ@پ@“ْ–{گl‚ةگA‚¦‚آ‚¯‚½گژ،‰ئپ@‚إ‚ ‚ء‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ،پ@پuگ¶—ق—÷‚ف‚ج—كپv‚إپAڈˆ”±‚³‚ꂽژز‚حپA‚Q‚S”Nٹش
پ@پ@‚إپA‚½‚ء‚½–ٌ‚V‚OŒڈ‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@
پ،پ@گâ‘خ“IŒ —ح‚ًژ‚آڈ«ŒR‚جپA“؟گىپ@چj‹g‚حپAپ@ژم‚ء
پ@پ@‚ؤ‚¢‚éگlٹشپE“®•¨‚ًŒ©‚آ‚¯‚½‚çپA‹~چد‚·‚é–@—ك‚ً
پ@پ@‚آ‚‚èپA“ْ–{‘Sچ‘‚إپAژہچs‚³‚¹‚½پBپ@‚±‚ê‚ة‚و‚èپA‚»
پ@پ@‚ê‚ـ‚إ•ْ’u‚³‚ꂽپA•aگlپAگgڈلژزپAکVگlپAŒاژ™پA
پ@پ@چs‚«“|‚ê‚ج—·گl“™‚ج•غŒى‚ھپA“ْ–{‘Sچ‘‚إچs‚ي‚êپAپ@
پ@پ@“ْ–{گl‚جˆسژ¯‚àپAگط‚è‘ض‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@
پ،پ@“؟گىچj‹g‚حپAپ@پuگ¶—ق—÷‚ف‚ج—كپvپ@پi‚µ‚ه‚¤‚é‚¢‚
پ@پ@‚ي‚ê‚ف‚ج‚ê‚¢پAچ]Œث–‹•{‚T‘مڈ«ŒRپE“؟گىچj‹g‚ھ
پ@پ@ڈo‚µ‚½پAگlٹشپE“®•¨‚جگ¶–½‘¸ڈdٹضŒW‚ج‘½گ”‚ج–@
پ@پ@—كپi‚¨گG‚êپj‚ج‘چڈجپjپ@‚ًڈo‚µپAƒqƒg‚ًٹـ‚كگ¶‚«•¨
پ@پ@‚ض‚ج—÷پi‚ ‚يپj‚ê‚ف‚ًگà‚¢‚½پAچ]Œث–‹•{‚جڈ«ŒRپ@
پ@پ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@“؟گىپ@چj‹g‚حپAپ@گlپX‚ةŒ¢گH‚¢‚ج•—ڈK‚ً‚â‚ك‚³
پ@پ@‚¹پiˆê”ت‚جگl‚ح“–ژŒ¢‚ًگH‚ׂؤ‚¢‚½‚ج‚إپjپAپ@چ]
پ@پ@Œث‚إ–ىŒ¢‚ةگlپX‚ھڈP‚ي‚ê‚é‚ج‚ً–h‚®‚½‚كپAپ@’†
پ@پ@–ى‚ة–ىŒ¢‚جژû—eژ{گف‚ً‚آ‚‚èپA‘½گ”‚جŒ¢‚ًژû—e
پ@پ@‚µ‚½پB
پ@پ@
پ،پ@“؟گىپ@چj‹g‚حپAگ¶–½پAگlŒ ‘¸ڈd‚ً‘إ‚؟ڈo‚µپAˆê
پ@پ@”تڈژ–¯‚جژ€‘ج•ْ’uپAژج‚ؤژqپAژمژزگطژج‚ؤپAگlٹش
پ@پ@“¯ژm‚إ‚جژE‚µچ‡‚¢پA•گٹي‚ً‚ئ‚茖‰ـپEژEڈ‚ً‚·‚éپA
پ@پ@ژE”°پi‚³‚آ‚خ‚آپj‚ئ‚µ‚½ژم“÷‹گH‚جگيچ‘ژ ‘م‚جچl
پ@پ@‚¦•û‚ً‘S–ت”غ’肵پAپ@ژمژز•غŒىپA•½کa‹¤‘¶‚ً‘إ‚؟
پ@پ@ڈo‚µپAگچô‚ة”½‰f‚³‚¹‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@“؟گىپ@چj‹g‚حپAپ@گ¶–½پEگl–½‘¸ڈd‚ًڈ¥‚¦پAپ@پuگ¶—ق
پ@پ@—÷‚ف‚ج—كپvپ@پi‚µ‚ه‚¤‚é‚¢‚ ‚ي‚ê‚ف‚ج‚ê‚¢پAگlٹشپE
پ@پ@“®•¨‚جگ¶–½‘¸ڈdٹضŒW‚ج‘½گ”‚ج–@—كپi‚¨گG‚êپj‚ج
پ@پ@‘چڈجپjپ@‚ًڈo‚µ‚½ڈ«ŒRپ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@“؟گىپ@چj‹g‚ج‚±‚جگچô‚ة‚و‚èپAپ@“ْ–{‚ج–¯ڈOپiگl
پ@پ@پXپj‚جژvچl‚ھپAپ@گlٹش‚â“®•¨‚جژEڈ‚ًچD‚فپA•غŒى
پ@پ@‚µ‚ب‚¢پAگ¶–½Œyژ‹‚جپAگيچ‘ژ‘م‚ج•—’ھپEŒXŒü‚©‚çپAپ@
پ@پ@گlٹش‚â“®•¨‚جژEڈ‚ًŒ™‚¢پA•غŒى‚·‚éپA گ¶–½ڈdژ‹
پ@پ@‚ج•—’ھپEŒXŒü‚ض‚ئ•د‚ي‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ،پ@“؟گىپ@چj‹g‚حپAپ@گlپX‚ةŒ¢گH‚¢‚ج•—ڈK‚ً‚â‚ك‚³‚¹پiˆê”ت
پ@پ@‚جگl‚ح“–ژŒ¢‚ًگH‚ׂؤ‚¢‚½‚ج‚إپjپAپ@چ]Œث‚إ–ىŒ¢‚ةگlپX
پ@پ@‚ھڈP‚ي‚ê‚é‚ج‚ً–h‚®‚½‚كپAپ@’†–ى‚ة–ىŒ¢‚جژû—eژ{گف‚ً‚آ
پ@پ@‚‚èپA‘½گ”‚جŒ¢‚ًژû—e‚µ‚½پB
پ@
پ@
پ،پ@’†–ى‚جŒ¢‰®•~پB
پ،پ@“؟گى چj‹g‚حپAپ@چ]Œث‚ج’¬‚إپAƒqƒg‚ةٹëٹQ‚ً‰ء‚¦‚éپA–ىŒ¢
پ@پ@‚ً‚·‚ׂؤپAچ]Œث‚ج’†–ى‚ةژû—e‚µپAپu‚¨Œ¢‰®•~پv‚ً‚آ‚‚éپB
پ@پ@‚ـ‚½پAˆê”تڈژ–¯‚جپAŒ¢گH‚¢‚جڈKٹµ‚ً‚â‚ك‚³‚¹‚éپB
پ@پ@
پ،پ@“؟گى چj‹g‚حپAپ@Œ¢‚ً‘هگط‚ة‚µپAŒ¢‚ج‚½‚ك‚ةپA‘ه‚«‚بژ{
پ@پ@گف‚ئژd‘g‚ف‚ً‚آ‚‚ء‚½پB
پ،پ@’†–ى‚جŒ¢‰®•~‚حپAپ@Œ¢‚ً•غŒى‚·‚邱‚ئ‚ھ–ع“I‚إ‚ ‚èپAپ@
پ@پ@“؟گى چj‹g‚حپAپ@گê—p‚جŒ¢‰يâؤپi‚¢‚ٌ‚©‚²پj‚ً‚آ‚‚èپA–ى
پ@پ@Œ¢‚ب‚ا‚ً‰^‚خ‚¹پA’†–ى‚جŒ¢‰®•~‚ةژû—e‚µ‚½پB
پ،پ@’†–ى‚جŒ¢‰®•~‚حپAپ@پu’†–ىŒن—pŒن‰®•~پv‚ئ‚àŒؤ‚خ‚êپA“؟
پ@پ@گى چj‹g‚جژwژ¦‚إپAپ@چ]Œث‚ج’†–ى’nˆوپ@پiŒ»پE“Œ‹“sپE’†
پ@پ@–ى‹و‚ج‘ٹ“–’nˆوپj‚ةŒڑ‚ؤ‚ç‚ꂽپA‹گ‘ه‚بŒ¢‰®•~‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@’†–ى‚جŒ¢‰®•~‚حپA“Œ‹ƒhپ[ƒ€‚Q‚OŒآ•ھ‚جچL‚³‚ھ‚ ‚èپA
پ@پ@–ٌ‚P‚O–œ“ھ‚جŒ¢‚ھ‚¢‚½پBپ@Œڑگف”ï‚ئˆغژ”ïپEŒ¢‚جگH”ï
پ@پ@‚حپA”œ‘ه‚ج”ï—p‚ھ‚©‚©‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@’†–ى‚جŒ¢‰®•~‚جŒڑگف‚ة‚حپA‰„‚×–ٌ‚P‚O‚O–œگl‚ھژQ
پ@پ@‰ءپEڈ]ژ–‚µپA–ٌ‚S‚S‰‰~‚ج”ï—p‚ھ‚©‚©‚ء‚½پB
پ@
پ@
پ،پ@“؟گىچj‹g‚جپAپuگ¶—ق—÷‚ف‚ج—كپvپB
پ،پ@“؟گىچj‹g‚حپAپ@چ]Œث–‹•{‚T‘مڈ«ŒR‚ة‚ب‚ء‚½ŒمپA“؟ گى
پ@چj‹g‚ج‘¤ژ؛•vگl‚ج‚¨“`‚ج•ûپi‚¨‚إ‚ٌ‚ج‚©‚½پj‚ج’jژq
پ@‚ھپA‘پگ¢‚µپAپ@“؟گىچj‹g‚ح پAگ¢Œp‚¬‚ھ‚¢‚ب‚‚ب‚èپAگ¢Œp‚¬
پ@‚ج’aگ¶‚ً–]‚فپAپ@•§‹³‚ًŒْ‚گM‹آ‚·‚éپA“؟گىچj‹g‚جگ¶•ê
پ@‚جپA‚¨‹ت پiŒjڈ¹‰@پj‚حپAگ¢Œp‚¬‚ج’aگ¶‚ًگط–]‚µپAپuŒ÷“؟پv
پ@پi‚‚ا‚پj‚ھ‘«‚è‚ب‚¢‚ئچl‚¦پAŒ÷“؟‚ًگد‚ق‚±‚ئ‚ھڈd—v‚ئژv
پ@‚¢پA“ْ–{‘Sچ‘‚ج‘½‚‚ج•§‹³‚جژ›‰@‚جچؤŒڑپEڈC•œ‚ًچs‚¢پAپ@
پ@‚ـ‚½پAپ@•êگe‘z‚¢‚ج‚T‘مڈ«ŒR‚ج“؟گىچj‹g‚ةگ¶—ق—÷‚ف‚ج
پ@—كپi‚µ‚ه‚¤‚é‚¢‚ ‚ي‚ê‚ف‚ج‚ê‚¢پj‚ًڈo‚³‚¹پAپ@گlٹش‚ً‚ح‚¶
پ@‚كپAگ¶‚«•¨‚جژEگ¶پi‚¹‚ء‚µ‚ه‚¤پj‚ً‹ض‚¶پAپ@ژœ”ك‚جگS‚ًژ‚؟پA
پ@گl–½‘¸ڈdپAگ¶‚«•¨‚جگ¶–½‘¸ڈdپAگ¶ٹˆچ¢‹‡ژزپA•aگlپAŒاژ™پA
پ@چs‚«“|‚ê‚ج—·گl‚جگ¢کb‚ب‚اژمژز•غŒى‚جگچô‚ً‹—ح‚ةگ„
پ@گi‚µپA“ْ–{‘Sچ‘‚ةچs‚ي‚¹‚½پBپ@
پ@پ@پ@‚±‚جگ¶—ق—÷‚ف‚ج—ك‚ة‚و‚èپA‚±‚êˆبŒمپAپ@“ْ–{‚حپAپ@•گ—ح
پ@‚ًڈd‚ٌ‚¶•گ—ح‚إ‘ٹژè‚ًژEڈ‚µ•¨ژ–‚ً‰ًŒˆ‚µ‚و‚¤‚·‚éپuگيچ‘
پ@‚جگ¢پv‚حڈI‚ي‚è‚ً‚آ‚°پAپ@ژEگ¶پi‚¹‚ء‚µ‚ه‚¤پj‚ًŒ™‚¢پAگl–½‘¸
پ@ڈdپAژمژز•غŒىپAگl‚ةگeگط‚ة‚µپA‚₳‚µ‚¢گS‚ًژ‚آ‚±‚ئ‚ھ”ü
پ@“؟‚ئ‚³‚ê‚éژ‘مپ@‚ئ‚ب‚éپB
پ@پ@پ@‚ـ‚½پAچ]Œث–‹•{‚حپA•§‹³‚جژ›‰@‚جچؤŒڑپEڈC•œ‚âپAگl–½
پ@پEگ¶‚«•¨‚جگ¶–½‘¸ڈdپEژمژز•غŒى‚ب‚ا‚جŒِ‹¤ژ–‹ئ‚ج‚½‚ك‚ة
پ@‘½ٹz‚جڈo”ï‚ًچs‚¢پAپ@Œoچد‚ھٹˆگ«‰»‚³‚êپA‰ط‚â‚©‚بŒ³ک\
پ@•¶‰»‚ًڈoŒ»‚³‚¹‚éپB
پ@پ@پ@‚µ‚©‚µپA‚¨‹تپiŒjڈ¹‰@پj‚جپuŒ÷“؟پvپi‚‚ا‚پj‚جچb”م‚à‚ب‚پA
پ@Œ‹‹اپAپ@“؟گىچj‹g‚جگ³ژ؛پE‘¤ژ؛•vگl‚ة ‚حپA“؟گىچj‹g‚جگ¢
پ@Œp‚¬‚حگ¶‚ـ‚ꂸپAپ@‚¨‹تپiŒjڈ¹‰@پj‚حپAچj‹g‚ج ژq‚جگصŒp‚¬
پ@‚جٹç‚ًŒ©‚邱‚ئ‚à‚ب‚پAژ¸ˆس‚ج‚¤‚؟‚ة‚±‚جگ¢‚ً‹ژ‚éپBپ@‚»‚ج
پ@ŒمپA“؟گىچj‹g‚àپAچj‹g‚جژq‚جگ¢Œp‚¬‚ً“¾‚邱‚ئ‚ب‚پA‚±‚ج
پ@گ¢‚ً‹ژ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپBپ@
پ@
پ@
#edictsoncompassionforlivingthings-appearingscenes
پ@
پôپôپ@گ¶—ق—÷‚ف‚ج—كپ@‚ھ“oڈê‚·‚éپA ‹»–،گ[‚¢پAƒh
پ@پ@پ@پ@ƒ‰ƒ}پA‰f‰وپAƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پB
پ@
پڑپ@گ¶—ق—÷‚ف‚ج—ك‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢ƒhƒLƒ…ƒپ
پ@پ@پ@ƒ“ƒ^ƒٹپ[پBپ@
پ@
پ،پ@”ِڈمڈ¼–ç‚جŒأ’nگ}‚إ“ن‰ً‚«پ@
پ@پ@ ‚ة‚ء‚غ‚ٌ’T‹†پ@پwپ@‚ب‚؛–¼ŒNپE“؟گىچj
پ@پ@ ‹g‚ةپuŒ¢Œِ•ûپv‚ج‰ک–¼پ@پxپBپ@
پ@پ@پ@پi‚a‚r‚P‚PƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚P‚U”N‚XŒژ‚Q‚W“ْ پE–{•ْ
پ@پ@پ@پ@‘—‚ج—ًژjƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[”ش‘gپjپB
پœپ@چ]Œث–‹•{‚T‘مڈ«ŒRپE“؟گىچj‹g‚âچj‹g‚ج
پ@پ@ گ¶•êپEŒjڈ¹‰@پi‚¨‹تپj‚ًڈq‚ׂéپB
پœپ@“؟گىچj‹g‚جگژ،‰üٹv‚â‘Pگ‚ًڈq‚ׂéپB
پœپ@“؟گىچj‹g‚جگ¶—ق—÷‚ف‚ج—ك‚ة‚آ‚¢‚ؤڈq‚ׂéپB
پœپ@ژٍ‹³‚âژٍٹw‚ة‚آ‚¢‚ؤڈq‚ׂéپB
پ@
پ،پ@—ًژj”éکbƒqƒX‚ئƒٹƒAپ@پwپ@‘ه‰œ ƒVƒ“ƒfƒŒ
پ@پ@ƒ‰پEƒXƒgپ[ƒٹپ[پ`ڈ«ŒR‚ج•êپEŒjڈ¹‰@پ@Œ³‘c
پ@پ@پu‹ت‚ج—`پv•¨Œêپ`پ@پxپB
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚P‚Q”Nپi‚g‚Q‚Sپj‚QŒژ‚W“ْپE–{•ْ‘—‚ج
پ@پ@پ@—ًژjƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[”ش‘gپjپB
پ@
پڑپ@گ¶—ق—÷‚ف‚ج—كپ@‚ھ“oڈê‚·‚éپA ‹»–،گ[‚¢ٹضکAƒh
پ@پ@ƒ‰ƒ}پA‰f‰وپBپ@
پœپ@پi’چˆسپjپ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAƒtƒBƒNƒVƒ‡ƒ“‚إ‚·پBپ@—ًژj
پ@پ@ƒh‚جƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAپ@ژjژہپi—ًژjڈم‚جژ–ژہپjپ@‚ئپ@‰ث
پ@پ@‹َ‚جڈo—ˆژ–‚ھپAپ@چ¬‚¶‚ء‚ؤپA•`‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپ@‚ـ‚½پA
پ@پ@Œ»‘م•—‚ةƒAƒŒƒ“ƒW‚µ‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚·پB
پ@
پ،پ@پwپ@‘ه‰œپE‰ط‚ج—گپ@پxپBپ@
پ@پ@پ@پiƒtƒWƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚O‚T”Nگ§چىƒeƒŒƒrƒhƒ‰ƒ}پjپB
پœپ@Œjڈ¹‰@پi‚¨‹تپj‚ً‰‰‚¶‚½”o—D–¼پ@پFپ@چ]”gˆاژqپB
پœپ@‚S‘مڈ«ŒR‰ئچjپA‚T‘مڈ«ŒRچj‹gپ@ژ‘مپ@‚ئپ@‚»‚جژ‘م
پ@پ@‚ج‘ه‰œپ@‚ً•`‚¢‚½ƒhƒ‰ƒ}پB
پœپ@“àژR—–¼پA“،Œ´‹IچپپAڈ¬’r‰hژqپAچ‚‰ھ‘پ‹Iپ@‚ب‚ا
پ@پ@”üگlڈ——D‚ھڈo‰‰پB
پœپ@‚T‘مڈ«ŒR‚جگ¶•ê‚إ‚ ‚éپA”س”N‚ج‚¨‹تپiŒjڈ¹‰@پj‚ھ
پ@پ@“oڈê‚·‚éپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ژ–¾‰@“پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ف‚ه‚¤‚¢‚ٌ‚ئ‚¤پjپB
پ@
پ،پ@ژ–¾‰@“پB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ژ–¾‰@“پ@پi‚¶‚ف‚ه‚¤‚¢‚ٌ‚ئ‚¤پjپB
پ،پ@‰pŒê–¼پ@پFپ@‚s‚g‚dپ@‚i‚h‚l‚x‚n‚h‚m‚s‚nپ@‚k‚h‚m‚d‚`‚f‚dپD
پ،پ@پsچc“پtپBپ@
پ،پ@ژ–¾‰@“پ@پFپ@‚P‚Q‚T‚X”Nپ|‚P‚R‚X‚Q”NپB
پ،پ@ژ–¾‰@“پ@پFپ@Œمگ[‘گ“Vچc‚جچc“پB
پ،پ@ژ–¾‰@“پ@پFپ@Œمچµ‰مپi‚²‚³‚ھپj“Vچc‚جچcژqپE
پ@پ@پuŒمگ[‘گپi‚²‚س‚©‚‚³پj“Vچcپv‚©‚çŒمڈ¬ڈ¼پi‚²‚±
پ@پ@‚ـ‚آپj“Vچc‚ـ‚إ‚جچc“پB
پ،پ@ژ–¾‰@“پ@پFپ@‘هٹoژ›“‚ئچcˆت‚ً‘ˆ‚ء‚½Œمگ[‘گ“Vچc
پ@پ@پ@‚جچc“پB
پ،پ@‚P‚Q‚T‚X”Nپ[‚P‚R‚X‚Q”NپA
ژ–¾‰@“پ@پi‚¶‚ف‚ه‚¤‚¢‚ٌ‚ئ‚¤پjپ@‚ئپAپ@‘هٹoژ›“پ@پi‚¾
پ@پ@‚¢‚©‚‚¶‚ئ‚¤پjپ@‚جچc“‚ج•ھ—§پB
پœپ@‚P‚R‚R‚U”Nپ[‚P‚R‚X‚Q”NپA
پ@پ@’©’ى‚حپAپ@ژ–¾‰@“‚ج–k’©پ@‚ئپAپ@‘هٹoژ›“‚ج“ى’©
پ@پ@‚ة•ھ—ô‚µپA‘خ—§‚·‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“Tپ@‚V‚P‚R‚P‚QپB
پ@
پ@
پ،پ@ژ–¾‰@“پB
پ،پ@ژ–¾‰@“پ@پi‚¶‚ف‚ه‚¤‚¢‚ٌ‚ئ‚¤پjپ@‚ئ‚حپAپ@‹vگmپi‚ذ‚³‚ذ
پ@پ@‚ئپjگe‰¤‚إ‚ ‚éپAŒمگ[‘گپi‚²‚س‚©‚‚³پj“Vچcپ@پi“Vچcچف
پ@پ@ˆتپF‚P‚Q‚S‚Uپ|‚P‚Q‚T‚X”Nپj‚جچc“‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@ژ–¾‰@“‚حپAپ@Œمچµ‰مپi‚²‚³‚ھپj “Vچcپ@پi“VچcچفˆتپF
پ@پ@‚P‚Q‚S‚Qپ|‚S‚U”Nپj‚جچcژqپEپuŒمگ[‘گ پi‚²‚س‚©‚‚³پj“Vچcپv
پ@پ@پ@‚©‚çŒمڈ¬ڈ¼پi‚²‚± ‚ـ‚آپj“Vچc‚ـ‚إ‚جچc“پ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ،پ@چc“‚ج•ھ—§پBپ@
پ،پ@’©’ى‚إ‚حپAپ@‚P‚Q‚T‚X”Nپi ‹ˆّ“Vچcڈ÷ˆتپj‚©‚ç‚P‚R‚X‚Q”N
پ@پ@پi“ى–k’©‚جچ‡‘جپj‚ـ‚إپAپ@ژ–¾‰@“پ@پi‚¶‚ف‚ه‚¤‚¢‚ٌ‚ئ
‚¤پjپ@‚ئپAپ@‘هٹoژ›“پ@پi‚¾‚¢‚©‚‚¶‚ئ‚¤پjپ@‚جچc“‚ج•ھ—§
پ@پ@‚ھ‘±‚¢‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@
پ،پ@’©’ى‚حپAپ@‚P‚R‚R‚U”Nپi‘«—ک‘¸ژپ‚جŒُ–¾پi‚±‚¤‚ف‚ه‚¤پj“V
پ@پ@چc—i—§پj‚©‚ç‚P‚R‚X‚Q”Nپi“ى–k ’©‚جچ‡‘جپj‚ـ‚إپAپ@ژ–¾
پ@پ@‰@“پi‚¶ ‚ف‚ه‚¤‚¢‚ٌ‚ئ‚¤پj‚ج–k’©پ@‚ئپAپ@‘هٹoژ›“پi‚¾
پ@پ@‚¢‚©‚‚¶‚ئ‚¤پj‚ج“ى’©پ@‚ة•ھ—ô‚µپA‘خ—§‚µ‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ،پ@ژ–¾‰@“پB
پ،پ@ژ–¾‰@“ پi‚¶‚ف‚ه‚¤‚¢‚ٌ‚ئ‚¤پjپ@‚ئ‚حپAپ@Œمگ[
پ@پ@‘گ“Vچc‚جچc“پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@ژ–¾‰@“‚حپAٹ™‘qژ‘م’†ٹْ‚©‚çژ؛’¬ژ‘م
پ@پ@‘Oٹْ‚ـ‚إ‚ ‚ء‚½“Vچc‰ئ‚جچc“پ@پi‚Q‚آ‚ج‘ه
پ@پ@ٹoژ›“پEژ–¾‰@“پjپ@‚ج‚P‚آ‚إپAپ@‘هٹoژ›“
پ@پ@‚ئچcˆت‚ً‘ˆ‚ء‚½Œمگ[‘گ“Vچc‚جچc“پ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ،پ@ژ–¾‰@“ ‚حپAŒمچµ‰مپi‚²‚³‚ھپj“Vچc‚جچcژq
پ@پ@پEپuŒمگ[‘گپi‚²‚س‚©‚‚³پj“Vچcپv‚©‚çŒمڈ¬ڈ¼پi‚²
پ@پ@‚±‚ـ‚آپj“Vچc‚ـ‚إ‚جچc“پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@Œمگ[‘گ“Vچc‚ھڈ÷ˆتŒم‹پi“sپj‚جژ–¾‰@
پ@پ@پi‚¶‚ف‚ه‚¤‚¢‚ٌپj‚ًŒنڈٹپi‚²‚µ‚هپj‚ئ‚µ‚½‚ج‚إپAپ@
پ@پ@‚±‚ج–¼‚ھ‚ ‚éپ@پiŒمگ[‘گ“Vچc‚جچc“‚ًپAژ
پ@پ@–¾‰@“‚ئŒ¾‚¤پjپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ،پ@چc“‚ج•ھ—§پBپ@
پ،پ@چc“‚ج•ھ—§پ@پi‚±‚¤‚ئ‚¤‚ج‚ش‚ٌ‚è‚آپjپ@‚ئ‚حپA ‚P‚Q‚T‚X”N
پ@پ@‚©‚ç‚P‚R‚X‚Q”N‚ـ‚إپAپ@ٹ™‘qژ‘م’†ٹْ‚©‚çژ؛’¬ژ‘م‘O
پ@پ@ٹْ‚ـ‚إپAپ@“Vچc‰ئ‚ھپAپ@ژ–¾‰@“پ@‚ئپ@‘هٹoژ›“پ@‚ج
پ@پ@‚Q‚آ‚جچc“‚ة•ھ—§‚µ‚½‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@چX‚ةپAپ@‚P‚R‚R‚U”N‚©‚ç‚P‚R‚X‚Q”N‚ـ‚إپAپ@Œڑ•گژ‘م
پ@پ@‚©‚çژ؛’¬ژ‘م‘Oٹْ‚ـ‚إپAپ@’©’ى ‚حپAپ@ژ–¾‰@“پi‚¶‚ف
پ@پ@‚ه‚¤‚¢‚ٌ‚ئ‚¤پj‚ج–k’©پi‚ظ‚‚؟‚ه‚¤پjپ@‚ئپAپ@‘هٹoژ›“پi‚¾
پ@پ@‚¢‚©‚‚¶‚ئ‚¤پj‚ج“ى’©پi‚ب‚ٌ‚؟‚ه‚¤پjپ@‚ة•ھ—ô‚µپA‘خ—§‚µ
پ@پ@‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپBپ@
پ@
پ@
پ،پ@چc“•ھ—§‚ج‹N‚±‚èپB
پ،پ@چc“•ھ—§‚ج‹N‚±‚èپB
پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚Q‚S‚U”N‚ةپAپ@Œمچµ‰م“Vچcپ@پi“VچcچفˆتپF‚P‚Q‚S‚Q
پ|‚S‚U”NپAگ¶–v”NپF‚P‚Q‚Q‚Oپ|‚V‚Q”Nپj‚ھپAپ@چcژqپiژں’jپj
پ@پ@‚ج‹vگmپi‚ذ‚³‚ذ‚ئپjگe‰¤‚ة“Vچc‚جˆت‚ًڈ÷‚èپAپ@‹vگmپi‚ذ
پ@پ@‚³‚ذ‚ئپjگe‰¤‚حپAŒمگ[‘گپi‚²‚س‚©‚‚³پj“Vچcپjپ@پi“Vچcچف
پ@پ@ˆتپF‚P‚Q‚S‚Uپ|‚T‚X”Nپjپ@‚ئ‚ب‚èپAپ@Œمچµ‰م“Vچc‚حپAŒمچµ
‰مڈمچc‚ئ‚ب‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@‚µ‚©‚µپA‚P‚Q‚T‚X”N‚ةپAپ@Œمچµ‰مڈمچc‚حپAچcژqپiژں
پ@پ@’jپj‚جپAŒمگ[‘گ“Vچc‚ً‹ˆّ‚ة‘قˆت‚³‚¹پAپ@‘¼‚جچcژq
پ@پ@پiژO’jپj‚جچPگmپi‚آ‚ث‚ذ‚ئپjگe‰¤‚ً“Vچc‚ة‚µپA‹TژRپi‚©
پ@پ@‚ك‚â‚ـپj “Vچcپi“VچcچفˆتپF‚P‚Q‚T‚Xپ|‚V‚S”Nپjپ@‚ھ’aگ¶‚µ
پ@پ@‚½پBپ@‚»‚جŒمپA‹TژRپi‚©‚ك‚â‚ـپj “Vچc‚حپAژں‚ج“Vچc‚ً
پ@پ@ژ©•ھ‚جژqپ@پiŒم‰F‘½پi‚²‚¤‚¾پj“Vچcپi“VچcچفˆتپF‚P‚Q‚V‚S
پ@پ@پ|‚W‚W”Nپjپ@‚ئ‚µ‚½‚½‚كپ@پi—§‘¾ژq‚ئ‚µ‚½‚½‚كپjپAپ@‘قˆت
پ@پ@‚µ‚½Œمگ[‘گ“Vچc‚حپAژ©•ھ‚جژq‚جچcˆتŒpڈ³‚ھ‚إ‚«‚¸پA
پ@پ@”ٌڈي‚ة•s–‚ً‚à‚؟پAٹ™‘q–‹•{‚ة’‡چظ‚ًˆث—ٹ‚µپA‚P‚Q
پ@پ@‚W‚W”N‚ةپAŒمگ[‘گ“Vچc‚جژqپi•ڑŒ© پi‚س‚µ‚فپj“Vچcپj‚ھ
پ@پ@“Vچc‚ة‘¦ˆت‚·‚邱‚ئ‚ھژہŒ»‚µ‚½پBپ@‚±‚¤‚µ‚ؤپA‚»‚جŒم
پ@پ@‚حپAٹ™‘qژ‘م‚جٹشپAپ@ٹ™‘q–‹•{ ‚ج‰î“üپE’‡چظ‚ة‚و‚éپA
پ@پ@—¼““R—§پ@ پi‚è‚ه‚¤‚ئ‚¤‚ؤ‚آ‚è‚آپA—¼“‚جچcژq‚ھŒًŒف
پ@پ@‚ة“Vچc‚ة‚ب‚é•ûژ®پjپ@‚ئ‚ب‚ء‚½پB
پ@
پ،پ@چc“‚ج•ھ—§‚جŒ´ˆِپB
پ@پ@پ@پ@ٹ™‘q–‹•{‚جژه“±‚إپA‚P‚Q‚S‚Q”N‚ةپAپ@Œم
پ@پ@چµ‰مپi‚²‚³‚ھپj“Vچcپ@پi“VچcچفˆتپF‚P‚Q‚S‚Qپ`
پ@پ@‚S‚U”NپAگ¶–v”NپF‚P‚Q‚Q‚Oپ`‚P‚Q‚V‚Q”Nپj‚ھپA
پ@پ@‘¦ˆت‚µ‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@Œمچµ‰م“Vچc‚حپA‘قˆتŒمپAڈمچc‚ئ‚ب‚èپA‚Q‚Oپ@
پ@پ@گ””N‚ة‚ي‚½‚èپAپ@‰@گپ@پi‚¢‚ٌ‚¹‚¢پAڈمچc‚ھ
پ@پ@’©’ى‚جژہŒ ‚ً‚ة‚¬‚è’©’ى‚ً“®‚©‚·‚±‚ئپjپ@‚ً
پ@پ@چs‚¤پ@پiڈمچcپE‰@گٹْپF‚P‚Q‚S‚Uپ`‚P‚Q‚V‚Q”NپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@Œمچµ‰مپi‚²‚³‚ھپj“Vچc‚ة‚حپAپ@‚Rگl‚جچcژq
پ@پ@پi‚ف‚±پj‚ھ‚¢‚½پBپ@ˆêگl‚جچcژq‚حپAڈ@‘¸پi‚ق‚ث
پ@پ@‚½‚©پjگe‰¤‚إپAٹ™‘q–‹•{‚ج‹{‰ئڈ«ŒR‚ة‚³‚¹
پ@پ@‚éپBپ@‘¼‚ج‚Qگl‚جچcژq‚حپAپ@“Vچc‚ة‘¦ˆت‚³‚¹پA
پ@پ@Œمگ[‘گ“Vچcپiچفˆت‚P‚Q‚S‚Uپ`‚T‚X”Nپjپ@‚ئپ@‹TژR
پ@پ@“Vچcپiچفˆت‚P‚Q‚T‚Xپ`‚V‚S”Nپjپ@‚ة‚ب‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@Œمچµ‰م“Vچcپiڈمچcپj‚حپAپ@چcژq‚جŒمگ[‘گ
پ@پ@“Vچcپiچفˆت‚P‚Q‚S‚Uپ`‚T‚X”Nپj‚ةڈ÷ˆتŒمپAپ@ژں
پ@پ@‚ةپAŒمگ[‘گ“Vچc‚ًپA‹گ§“I‚ة‘قˆت‚³‚¹پA“¯
پ@پ@‚¶چcژq‚إŒمگ[‘گ“Vچc‚ج’يپ@پi‹TژR“Vچcپiچف
پ@پ@ˆت‚P‚Q‚T‚Xپ`‚V‚S”Nپj‚ةڈ÷ˆت‚³‚¹‚½پBپ@‚±‚¤‚µ‚ؤپA
پ@پ@—¼ژزپi—¼“پj‘خ—§‚جŒ´ˆِ‚ً‚آ‚‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚Q‚V‚Q”N‚جŒمچµ‰مڈمچcپi“Vچcپj‚جژ€ŒمپA
پ@پ@Œمچµ‰مڈمچcپi“Vچcپj‚ج‚Qگl‚جچcژq‚جŒمگ[‘گ
پ@پ@“Vچcپ@‚ئپ@‹TژR“Vچcپ@‚حپAپ@“Vچc‚جچcˆتŒpڈ³پA
پ@پ@‰@گ‚جŒ —کپAچcژ؛—ج‘‘‰€‚ج‘ٹ‘±‚ب‚ا‚ً‚ك‚®
پ@پ@‚ء‚ؤ‘خ—§‚µپAپ@—¼ژز‚ئ‚à‚ةٹ™‘q–‹•{‚ة“‚«‚©
پ@پ@‚¯—L—ک‚ب’nˆت‚ً“¾‚و‚¤‚ئ‚µ‚½پBپ@ٹ™‘q–‹•{‚ج
پ@پ@‰î“ü‚إپAپ@Œ‹‹اپAپ@—¼ژز‚ج“Vچc‚جژq‘·‚حپAچ،
پ@پ@ŒمپAŒً‘ضپi‚±‚¤‚½‚¢پj‚إپAپ@“Vچc‚جچcˆت‚ًŒpڈ³
پ@پ@‚·‚邱‚ئ‚ئ‚ب‚ء‚½پ@پi—¼““R—§پi‚è‚ه‚¤‚ئ‚¤‚ؤ‚آ
پ@پ@‚è‚آپj‚ئ‚ب‚ء‚½پjپBپ@
پ@پ@پ@پ@Œمچµ‰م“Vچc‚جچcژq‚جŒمگ[‘گپi‚²‚س‚©‚‚³پj
پ@پ@“Vچc‚حپAپ@ژ–¾‰@“پi‚¶‚ف‚ه‚¤‚¢‚ٌ‚ئ‚¤پj‚جچإ
پ@پ@ڈ‰‚ج“Vچc‚ئ‚ب‚èپAپ@‚à‚¤ˆêگl‚جŒمچµ‰م“Vچc‚ج
پ@پ@چcژq‚ج‹TژRپi‚©‚ك‚â‚ـپj“Vچc‚حپAپ@‘هٹoژ›“
پ@پ@پi‚¾‚¢‚©‚‚¶‚ئ‚¤پj‚جچإڈ‰‚ج“Vچcپ@‚ئ‚ب‚ء‚½پBپ@
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ،پ@—¼““R—§پBپ@
پ،پ@ٹ™‘q–‹•{‚جژه“±‚إپAپ@ژ–¾‰@“‚ئ‘هٹoژ›“
پ@پ@‚ج—¼“‚جچc‘°‚ھŒً‘ضپi‚±‚¤‚½‚¢پj‚إ“Vچc‚جچc
پ@پ@ˆتŒpڈ³‚ًچs‚¤‚±‚ئ‚ًپAپ@—¼““R—§پ@پi‚è‚ه‚¤‚ئ‚¤
پ@پ@‚ؤ‚آ‚è‚آپjپ@‚ئ‚¢‚¤پBپ@
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ@
پ،پ@Œم‘çŒي“Vچc‚ئٹ™‘q–‹•{‚ج‘خ—§پB
پœپ@Œم‘çŒي“Vچc‚حپAپ@—¼““R—§‚ة‚و‚éŒم‘çŒي
پ@پ@“Vچc‚جچcژqچcˆتŒpڈ³Œ©چ‚ف‚ب‚µ‚ًŒ_‹@پi‚¯
پ@پ@‚¢‚«پjپi‚«‚ء‚©‚¯پj‚ةپAٹ™‘q–‹•{‚ئ‘خ—§‚µپA‚â
پ@پ@‚ھ‚ؤپA“|–‹‚ًŒˆˆس‚·‚éپB
پœپ@–kڈًژ·Œ ‚جٹ™‘q–‹•{‚ج‰î“ü‚ة‚و‚éپA‚P‚R
پ@پ@‚P‚V”N‚جپu•¶•غ‚جکa’kپvپi‚ش‚ٌ‚غ‚¤‚ج‚ي‚¾‚ٌپj
پ@پ@‚إپAپ@ژ–¾‰@“‚ج‰ش‰€“Vچc‚ھچcˆت‚ً‘هٹoژ›
پ@پ@“‚ج‘¸ژ،پi‚½‚©‚ح‚éپjگe‰¤پiŒم‘çŒي“Vچcپj‚ة
پ@پ@ڈ÷‚邱‚ئ‚ھŒˆ‚ـ‚éپBپ@‚»‚ج‘¼‚ةپAپu•¶•غ‚جکa
پ@پ@’kپv‚إ‚حپAپ@‘هٹoژ›““à‚جچcˆتŒpڈ³Œَ•â‚جچc
پ@پ@‘°‚ح•،گ”‚¢‚ؤپAŒم‘çŒي“Vچc‚جŒZ’ي‚جژqپE–M
پ@پ@—اپi‚‚ة‚و‚µپjگe‰¤پi‘هٹoژ›“‚جŒم“ٌڈً“Vچc‚ج
پ@پ@چcژqپj‚ھپAŒم‘çŒي“Vچc‚جژں‚جچcˆت‚ًŒpڈ³‚µپAپ@
پ@پ@‚»‚جŒم‚حپ@—¼““R—§پi‚è‚ه‚¤‚ئ‚¤‚ؤ‚آ‚è‚آپj‚إپAپ@
پ@پ@ژ–¾‰@“‚ج—تگmپi‚©‚¸‚ذ‚ئپjگe‰¤‚ھچcˆت‚ًŒp
پ@پ@‚®‚±‚ئ‚ھŒˆ‚ـ‚ء‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پu•¶•غ‚جکa’kپv‚ة‚و‚èپA‚P‚R‚P‚W”N‚ةŒم‘çŒي
پ@پ@“Vچcپ@پiچفˆت‚P‚R‚P‚Wپ`‚R‚QپA‚P‚R‚R‚Rپ`‚R‚X”Nپj‚حپA
پ@پ@“Vچc‚ة‘¦ˆت‚·‚é‚ھپAپ@Œم‘çŒي“Vچc‚جژq‘·‚ة
پ@پ@‚حپAچcˆتŒpڈ³‚جŒ©چ‚ف‚ھ‚ب‚©‚ء‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‘هٹoژ›“‚جŒم‘çŒي“Vچc‚حپAژ©•ھ‚جچcژq
پ@پ@‚ً“Vچc‚ة‚·‚邱‚ئ‚ًگط–]‚µپAٹ™‘q–‹•{‚ئ‘خ—§
پ@پ@‚µ‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@Œم‘çŒي“Vچc‚حپAپ@ژ©•ھ‚جچcژq‚جچcˆتŒpڈ³
پ@پ@‚â“Vچcگeگگژ،‚ً‚ك‚´‚µپAپ@ٹ™‘q–‹•{‚ج“|–‹
پ@پ@‚ًŒv‰و‚µپAپ@‚P‚R‚Q‚S”N‚جگ³’†‚ج•دپi‚µ‚ه‚¤‚؟‚م
پ@پ@‚¤‚ج‚ض‚ٌپjپ@‚ئپ@‚P‚R‚R‚P”N‚جŒ³چO‚ج•دپi‚°‚ٌ‚±
پ@پ@‚¤‚ج‚ض‚ٌپjپ@‚ج‚Q‚آ‚ج“|–‹Œv‰و‚ً‹N‚±‚·‚ھپA‚¢
پ@پ@‚¸‚ê‚àژ¸”s‚·‚éپB پ@ٹ™‘q–‹•{‚ة‚و‚èپA‚P‚R‚R‚Q
پ@پ@”N‚ةپA‰Bٹٍپi‚¨‚«پj‚ة”z—¬پi‚ح‚¢‚éپj‚³‚ê‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@ˆê•ûپA–M—اپi‚‚ة‚و‚µپjگe‰¤‚ح‹}ژ€‚µ‚½‚ج
پ@پ@‚إ‚P‚R‚R‚Q”N‚ةژ–¾‰@“‚ج—تگmپi‚©‚¸‚ذ‚ئپjگe
پ@پ@‰¤‚ھپAŒُŒµپi‚±‚¤‚²‚ٌپj“Vچcپiچفˆت‚P‚R‚R‚Qپ`‚R‚R
پ@پ@”Nپj‚ئ‚µ‚ؤ‘¦ˆت‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚R‚R‚R”N‚ةپAŒم‘çŒي“Vچc‚حپA‰Bٹٍپi‚¨‚«پj
پ@پ@پ@‚ً’Eڈo‚µپAپ@‘«—ک‘¸ژپپi‚ ‚µ‚©‚ھ‚½‚©‚¤‚¶پjپA
پ@پ@پ@گV“c‹`’هپi‚ة‚ء‚½‚و‚µ‚³‚¾پj‚ب‚ا‚ج”½–‹•{گ¨
پ@پ@پ@—ح‚ئژè‚ً‘g‚فپAپ@–kڈًژ·Œ ‚جٹ™‘q–‹•{‚ً“|
پ@پ@پ@‚µپA‚P‚R‚R‚R”N‚ةپAŒڑ•گپi‚¯‚ٌ‚قپjگŒ پi‚P‚R‚R‚R
پ@پ@پ@پ`‚R‚U”Nپj‚ًگ¬—§‚³‚¹‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ@
پ،پ@’©’ى‚ج“ى–k’©•ھ—ô‚ئچ‡‘جپB
پ،پ@’©’ى‚ج“ى–k’©•ھ—ôپ@پi‚P‚R‚R‚Uپ`‚P‚R‚X‚Q”NپjپB
پœپ@‚P‚R‚R‚U”N‚ةپA’©’ى‚حپAپ@‘هٹoژ›“پi‚¾‚¢‚©
پ@پ@‚‚¶‚ئ‚¤پj‚جپu“ى’©پvپi‚ب‚ٌ‚؟‚ه‚¤پjپ@‚ئپ@ژ–¾‰@“
پ@پ@پi‚¶‚ف‚ه‚¤‚¢‚ٌ‚ئ‚¤پj‚جپu–k’©پvپi‚ظ‚‚؟‚ه‚¤پjپ@‚ج
پ@پ@‚Q‚آ‚ة•ھ—ô‚·‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پœپ@‚P‚R‚R‚U”N‚ةپAŒڑ•گپi‚¯‚ٌ‚قپjگŒ پi‚P‚R‚R‚Rپ`
پ@پ@‚R‚U”Nپj‚ھ•ِ‰َ‚µپA‘هٹoژ›“‚جŒم‘çŒي“Vچc‚ھپA
پ@پ@‹پi“sپj‚و‚è‹g–ىپi‚و‚µ‚جپj‚ةˆع‚é‚ئپAپ@‚P‚R‚R‚U
پ@پ@”N‚ةپA‹پi“sپj‚إ‚حپA‘«—ک‘¸ژپ‚ة—i—§‚³‚ꂽپA
پ@پ@ژ–¾‰@“‚جŒُ–¾پi‚±‚¤‚ف‚ه‚¤پj“Vچcپiچفˆت‚P‚R‚R
پ@پ@‚Uپ`‚S‚W”Nپj‚ھپA‘¦ˆت‚µپAپ@‚±‚±‚ةپA’©’ى‚حپA‹g
پ@پ@–ى‚ج‘هٹoژ›“‚جپu“ى’©پvپ@‚ئپ@‹پi“sپj‚جژ–¾پ@
پ@پ@‰@“‚جپu–k’©پv‚ة•ھ—ô‚µپA“ى–k’©ژ‘مپ@پi‚P‚R
پ@پ@‚R‚U”Nپ`‚P‚R‚X‚Q”Nپjپ@‚ئ‚ب‚éپB
پ@
پ،پ@’©’ى‚جچ‡‘جپ@پi“ى–k’©‚جچ‡ˆêپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚R‚X‚Q”N‚ةپAژ؛’¬–‹•{‘و‚R‘مڈ«ŒRپE‘«—ک
پ@پ@‹`–پi‚ ‚µ‚©‚ھ‚و‚µ‚ف‚آپj‚حپAپ@“ى’©‘¤‚ئŒًڈآ
پ@پ@‚µ‚ؤپA‘هٹoژ›“‚جپu“ى’©پvپ@‚ئپ@ژ–¾‰@“‚جپu–k
پ@پ@’©پv‚ًچ‡ˆê‚³‚¹‚é‚ج‚ةپAگ¬Œ÷‚µپAپ@‘هٹoژ›“‚ئ
پ@پ@ژ–¾‰@“‚ج‘خ—§‚حپAپ@‚±‚±‚ة‰ًڈء‚µ‚½پB
پ@پ@پ@پ@‘«—ک‹`–‚ح“ى’©‘¤‚ئŒًڈآ‚µپA‘هٹoژ›“‚ج
پ@پ@“ى’©‚جŒم‹TژRپi‚²‚©‚ك‚â‚ـپj“Vچc‚ھ‚P‚R‚X‚Q”N
پ@پ@‚ةپAچcˆت‚ً•ْٹü‚µ‚ؤ“ü‹‚µپAپ@’©’ى‚ج“Vچc‚حپA
پ@پ@ژ–¾‰@“‚ج–k’©‚جŒمڈ¬ڈ¼پi‚²‚±‚ـ‚آپj“Vچcˆê
پ@پ@گl‚ئ‚ب‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚R‚X‚Q”N‚ج“ى–k’©چ‡‘جŒم‚حپA‘هٹoژ›“
پ@پ@‚ج“ى’©‚حڈء–إ‚µپA“ى–k’©‚ئ‚¢‚¤‹و•ت‚ح‚ب‚‚ب‚èپAپ@
پ@پ@Œمڈ¬ڈ¼“Vچc‚جژ–¾‰@“‚ج–k’©‚ج“Vچc‚ھپA’©’ى
پ@پ@‚جچcˆت‚ً‘مپX‚ًŒp‚®پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ژlچ‘’n•ûپ@
پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚±‚‚؟‚ظ‚¤پjپB
پ@
پ،پ@ژlچ‘’n•ûپBپ@
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ژlچ‘’n•ûپ@پi‚µ‚±‚‚؟‚ظ‚¤پjپB
پ،پ@‰pŒê–¼پ@پFپ@‚r‚g‚h‚j‚n‚j‚tپ@‚q‚d‚f‚h‚n‚mپD
پ،پ@Œ»’n•û–¼پBپ@پsŒ»’nˆو–¼پtپB
پ،پ@ژlچ‘’n•ûپB
پ@پ@پƒ“ْ–{–{“yپi–{ڈBپAژlچ‘پA‹مڈBپjپB
پ@پ@پƒ“ْ–{چ‘پB
پ،پ@ژlچ‘’n•û‚ةٹضŒW‚·‚éپA“ىٹC“¹پi‚ب‚ٌ‚©‚¢‚ا‚¤پj
پ@پ@‚ج‹ŒچLˆو’n•û‚ةٹض‚µ‚ؤ‚حپAپu“ىٹC“¹پv‚ًژQڈئ
پ@پ@‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
پ،پ@‘O‹ك‘مپE‹Œ’nˆو–¼‚ةٹض‚µ‚ؤ‚حپA پu‘O‹ك‘م“ْ–{
پ@پ@‚ج’nˆو–¼پv‚ًژQڈئ‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“Tپ@‚U‚P‚W‚P‚VپB
پ@
پ@
پ،پ@ژlچ‘’n•ûپ@پi‚µ‚±‚‚؟‚ظ‚¤پj‚حپAپ@چپگىŒ§پA “؟“‡Œ§پA
پ@پ@چ‚’mŒ§پAˆ¤•QŒ§پ@‚ج’nˆو‚إ‚ ‚éپB
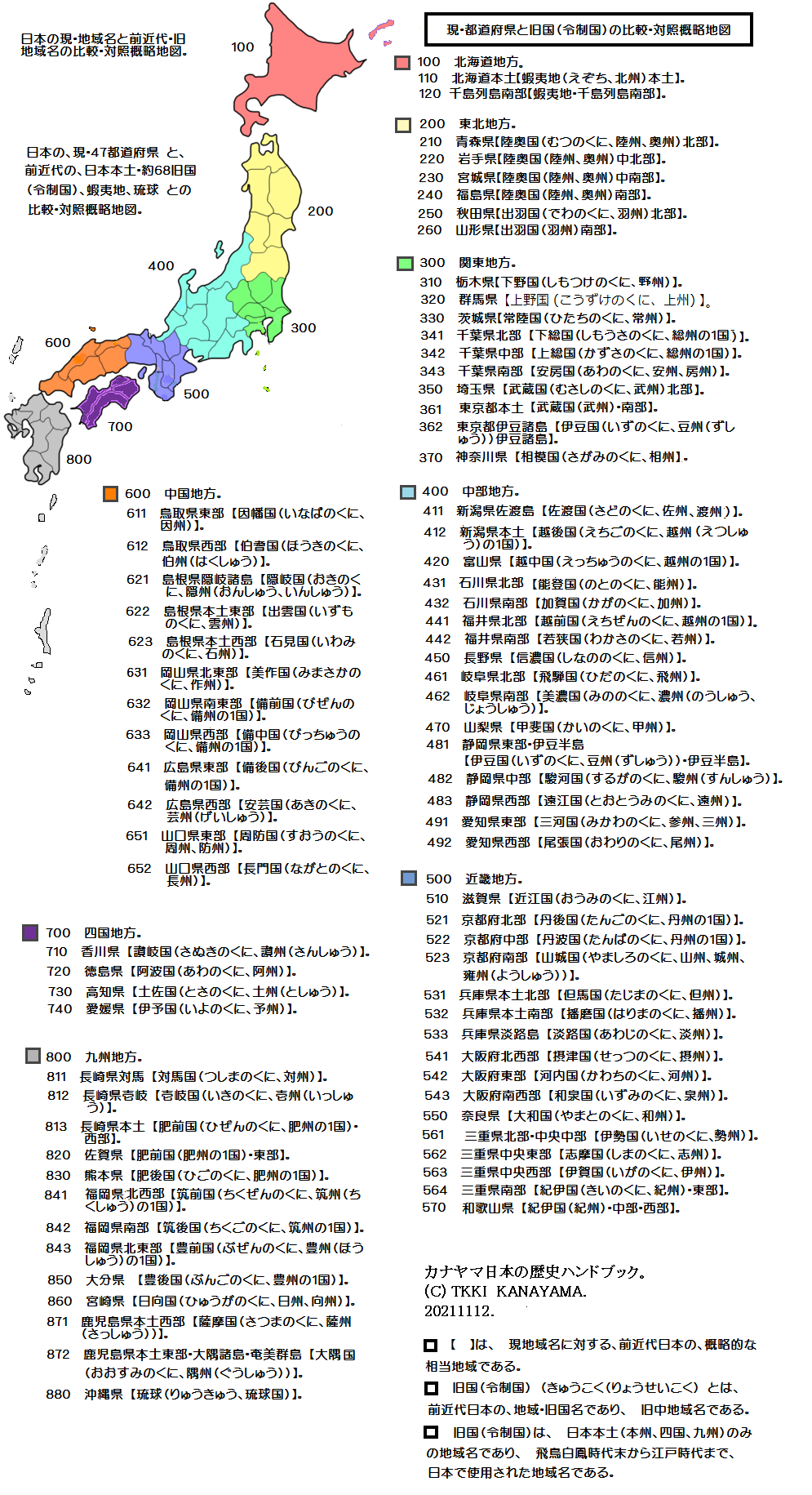
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ژlچ‘’n•ûپ@پi‚µ‚±‚‚؟‚ظ‚¤پj‚حپAپ@
پ@پ@‡@پ@“ىٹC“¹پi‚ب‚ٌ‚©‚¢‚ا‚¤پjپE‹ŒچL ˆو’n•û‚ج ˆê•”
پ@پ@‚جپAچپگىŒ§پ@پiژ]ٹٍ چ‘پi‚¨‚«‚ج‚‚ةپjپjپAپ@“؟“‡Œ§
پ@پ@پiˆ¢”g چ‘پi‚ ‚ي‚ج‚‚ةپjپjپAپ@چ‚’mŒ§پ@پi“yچ² چ‘
پ@پ@پi‚ئ‚³‚ج‚‚ةپjپjپAپ@ˆ¤•QŒ§پ@پiˆة—\ چ‘پi‚¢‚و‚ج‚‚ةپjپj
پ@پ@‚ج’nˆو پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@’n‰؛کQگlپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚°‚낤‚ة‚ٌپjپB
پ@
پ،پ@’n‰؛کQگlپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@پu’n‰؛کQگlپvپ@پi‚¶‚°‚낤‚ة‚ٌپjپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ةپA•گژmگg•ھ‚ً”„‚ء‚½‰؛‹‰•گژmپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ج‰؛‹‰•گژm‚جٹK‹‰گg•ھ‚ج‚P‚آپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ةپA•n‚µ‚گ¶ٹˆ‚ج‚½‚ك‚ةپA‹½ژmٹ”‚ً”„
پ@پ@‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½Œ³‹½ژm‚ج‰؛‹‰•گژmپBپ@
پ،پ@پiپu’n‰؛کQگlپv‚ج—لپjپ@
پ@پ@“yچ²”ث‚ج–‹––‚جپAٹâچè –ي‘¾کYپi‚¢‚ي‚³‚«‚₽‚ë
پ@پ@‚¤پjپA‘ٍ‘؛‘y”Vڈهپi‚³‚ي‚ق‚ç‚»‚¤‚ج‚¶‚ه‚¤پjپ@‚ب‚اپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“Tپ@‚U‚P‚W‚P‚QپB
پ@
پ@
پ،پ@’n‰؛کQگlپi‚¶‚°‚낤‚ة‚ٌپj‚ئ‚حپAپ@چ]Œثژ‘م‚ةپA•n
پ@پ@‚µ‚گ¶ٹˆ‚ج‚½‚ك‚ةپA‹½ژmٹ”‚ً”„‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½Œ³‹½
پ@پ@ژmگg•ھ‚ج‰؛‹‰•گژm‚إ‚ ‚éپBپ@پ@
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@’n‰؛کQگl‚حپAپ@–³ک\–³–ً‚إ‚ح‚ ‚é‚ھپAژm•ھ‚جٹi
پ@پ@ژ®‚ًˆغژ‚µپA•cژڑ‘ر“پ‚ح‹–‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½پB
پ@
پ،پ@’n‰؛کQگl‚حپAپ@“c”¨‚ًچk‚µ‚½‚èپA’¬گl‚ئ‚µ‚ؤگ¶Œv
پ@پ@‚ً‚½‚ؤ‚é‚ب‚ا‚µ‚ؤ‚¢‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@’n‰؛کQگl‚ج—ل‚ئ‚µ‚ؤپAپ@“yچ²”ث‚ج–‹––‚جپAٹâچè
پ@پ@–ي‘¾کYپi‚¢‚ي‚³‚«‚₽‚낤پjپAپ@‘ٍ‘؛‘y”Vڈهپi‚³‚ي
پ@پ@‚ق‚ç‚»‚¤‚ج‚¶‚ه‚¤پjپ@‚ب‚ا‚ھ‚¢‚éپB
پœپ@ٹâچè–ي‘¾کY‚حپAپ@–‹––‚ةپA“yچ²”ثگف—§‚جپu“yچ²
پ@پ@ڈ¤‰ïپv‚جژه”C‚ئ‚ب‚èپA چâ–{—´”n‚جپuٹC‰‡‘àپv‚ج‰ï
پ@پ@ŒvŒW‚ًچs‚¢پAپ@–¾ژ،ٹْ‚ة‚حپAپ@ژO•Hچà”´‚ج‘nژn
پ@ژز‚ئ‚ب‚ء‚½پBپ@
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ةپAپ@•گژmگg•ھ‚ة‚حپAپ@”_‘؛‹ڈڈZ•گژm
پ@پ@‚ج‹½ژmپi‚²‚¤‚µپjپ@‚ئپAپ@ڈé‰؛’¬‚ةڈZ‚ق‰ئ’†•گژm
پ@پ@پi‚©‚؟‚م‚¤‚ش‚µپjپ@‚ھ‚¢‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@‹½ژm‚حپAپ@ڈé‰؛’¬‚ةڈZ‚ق‰ئ’†•گژm‚و‚è’ل‚¢گg
پ@پ@•ھ‚ئ‚³‚ꂽ‚ھپAپ@گ¶ژY‚ة’¼Œ‹‚µ‚ؤ‚¢‚½‚½‚كپA•x
پ@پ@—T‚بژز‚à‘½‚©‚ء‚½پB
پ@
پ،پ@’n‰؛کQگlپ@پi‚¶‚°‚낤‚ة‚ٌپj‚ئ‚حپA چ]Œثژ‘م‚ج•گ
پ@پ@ژm‚جٹK‹‰گg•ھ‚ج‚P‚آ‚إ‚ ‚èپAپ@چ]Œثژ‘م‚ة•گژm
پ@پ@گg•ھ‚ً”„‚ء‚½‰؛‹‰•گژm‚إ‚ ‚èپAپ@ژه‚ة پA•n‹‡پi‚ذ
پ@پ@‚ٌ‚«‚م‚¤پj‚©‚狽ژmٹ” پi‚²‚¤‚µ‚©‚شپA‹½ژm‚ج•گژm
پ@پ@گg•ھپj‚ً”„‚ء‚½‰؛‹‰•گژmپ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@پu’n‰؛کQگlپvپ@پi‚¶‚°‚낤‚ة‚ٌپj‚حپAپ@چ]Œثژ‘م‚ج
پ@پ@‰؛‹‰•گژmپi= ‰؛ژmپi‚©‚µپjپj‚جٹK‹‰گg•ھ‚ج‚P‚آ‚إ
پ@پ@‚ ‚èپAپ@“yچ²”ثژmپi‚ئ‚³‚ح‚ٌ‚µپj‚جپu’n‰؛کQگlپv‚ھ
پ@پ@‚و‚’m‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
پ@پ@
پ،پ@‹½ژm‚حپAچ]Œثژ‘م‚جپA”¼”_”¼•گژmٹK‹‰‚ج‰؛‹‰
پ@پ@•گژm‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@چ]Œثژ‘م‚ةپAˆê”ت“I‚ة”_‘؛“™‚ة‹ڈڈZ‚µ‚ؤ
پ@پ@‚¢‚½‰؛‹‰•گژm‚ًپAپ@چ]Œثژ‘م‚ةپA‹½ژmپi‚²‚¤‚µپjپ@
پ@پ@‚ئŒؤ‚ٌ‚¾پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@‹½ژmپi‚²‚¤‚µپjپ@‚ئ‚حپAپ@چ]Œثژ‘م‚ج•گژm‚جٹK‹‰
پ@پ@گg•ھ‚ج‚P‚آ‚إپAپ@ˆê”ت“I‚ةپAڈé‰؛‚إ‚ح‚ب‚پAپ@”_
پ@پ@‘؛“™‚ة‹ڈڈZ‚µ‚ؤ‚¢‚½ ‰؛‹‰•گژmپ@‚آ‚ـ‚èپAچف‹½‰؛پ@
پ@پ@‹‰•گژm‚إ‚ ‚éپB
پœپ@چ]Œثژ‘مپAپ@چ]Œث–‹•{‚جˆêچ‘ˆêڈé—ك‚ة‚و‚èپAپ@
پ@پ@ٹe”ث‚حپA ˆê”ث‚ة‚P‚آ ‚جڈ邾‚¯‚ًژ‚؟پAپ@”ثژm
پ@پ@پi”ث‚ة‘®‚·‚é•گژmپj‚حپAپ@ڈé‰؛’¬پi‚¶‚ه‚¤‚©‚ـ‚؟پj
پ@پ@‚ةڈZ‚ق‰ئ’†•گژmپi‚©‚؟‚م‚¤‚ش‚µپjپ@‚ئپAپ@”_‘؛‹ڈ
پ@پ@ڈZ•گژm‚ج‹½ژmپi‚²‚¤‚µپjپ@‚ة•ھ‚©‚ꂽپB
پ@پ@پ@پ@پ@‰؛‹‰•گژm‚جˆê•”‚حپAپ@”_‘؛“™‚ةڈZ‚ٌ‚¾پBپ@
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پôپôپ@’n‰؛کQگl‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢پA
پ@پ@پ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپAƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پB
پ@
پڑپ@’n‰؛کQگlپi‚¶‚°‚낤‚ة‚ٌپj‚ھ“oڈê‚·‚éپA
پ@پ@‹»–،گ[ ‚¢پAƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپB
پœپ@پi’چˆسپjپ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAپ@ƒtƒBƒNƒVƒ‡ƒ“پ@‚إ‚·پBپ@
پ@پ@—ًژj‚جƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAژjژہپi—ًژjڈم‚جژ–ژہپjپ@
پ@پ@‚ئپ@‰ث‹َ‚جڈo—ˆژ–پ@‚ھپ@چ¬‚¶‚ء‚ؤ•`‚©‚ê‚ؤ‚¢
پ@پ@‚ـ‚·پBپ@‚ـ‚½پAŒ»‘م•—‚ةƒAƒŒƒ“ƒW‚µ‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚·پB
پ@
پ،پ@پwپ@—´”n“`پ@پi‚è‚ه‚¤‚ـ‚إ‚ٌپjپ@پx پBپ@
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚P‚O”N‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پjپB
پœپ@“yچ²”ث‚ج‰؛‹‰•گژm‚ج’n‰؛کQگlپi‚¶‚°
پ@پ@‚낤‚ة‚ٌپj‚جپAٹâچè–ي‘¾کYپi‚¢‚ي‚³‚«‚â
پ@پ@‚½‚낤پj‚â‘ٍ‘؛‘y”Vڈهپi‚³‚ي‚ق‚ç‚»‚¤‚ج
پ@پ@‚¶‚ه‚¤پj‚ھ“oڈê‚·‚éپBپ@
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ژé’PˆتپE’èˆتپi’èٹzپjپE
پ@پ@ ’تڈي‰ف•¼پ@
پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚م‚½‚ٌ‚¢پE‚ؤ‚¢‚¢پi‚ؤ‚¢‚ھ‚پjپE
پ@پ@پ@پ@پ@‚آ‚¤‚¶‚ه‚¤‚©‚ض‚¢پjپB
پ@
پ،پ@ژé’Pˆت پE’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي
پ@پ@ ‰ف•¼پB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ژé’Pˆت’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼پ@
پ@پ@پi‚µ‚م‚½‚ٌ‚¢‚ؤ‚¢‚¢پi‚ؤ‚¢‚ھ‚پjپE‚آ‚¤‚¶‚ه‚¤‚©‚ض‚¢پjپB
پ،پ@پs“ْ–{—¬’ت‰ف•¼پtپB
پ@پ@پ@چ]Œثژ‘م‚ج“ْ–{—¬’ت‰ف•¼پB
پ،پ@چ]Œث–‹•{‚ھ’’‘¢پE”چs‚µ‚½پAژéپi‚µ‚مپj’Pˆت‚جپA
پ@پ@چ]Œثژ‘م‚ج’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼ پA’·•ûŒ`
پ@پ@پuژé‹à‹â‰فپvپB
پ،پ@ژé‹à‹âپi‚µ‚م‚«‚ٌ‚¬‚ٌپAژé’Pˆت‚ج‹à‰فپE‹â‰فپjپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ،پ@“ٌژé‹àپi‚RژيپjپAپ@ˆêژé‹àپi‚PژيپjپAپ@“ٌژé‹â
پ@پ@پi‚RژيپjپAپ@ˆêژé‹âپi‚Pژيپjپ@‚ج‚Sژي—قپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ة—¬’ت‚µ‚½پAژé’Pˆت‚ج‰ف•¼‚ة‚حپA
پ@پ@“ٌژé‹àپi‚RژيپjپAˆêژé‹àپi‚Pژيپj‚جپAژé‹àپi‚Sژيپj
پ@پ@پi‚µ‚م‚«‚ٌپAژé’Pˆت‚ج‹à‰فپjپ@‚ئپAپ@“ٌژé‹âپi‚R
پ@پ@ژيپjپAˆêژé‹âپi‚Pژيپj‚جژé‹âپi‚Sژيپjپi‚µ‚م‚¬‚ٌپA
پ@پ@ژé’Pˆت‚ج‹â‰فپj‚ھ‚ ‚éپB
پ،پ@“ٌژé‹à‹â‰فپàŒ»چف‚ج–ٌ‚P–œ‚Q‚T‚O‚O‰~پB
پ@پ@ ˆêژé‹à‹â‰ف پàŒ»چف‚ج–ٌ‚U‚Q‚T‚O‰~پB
پ@پ@پ@ˆê—¼ڈ¬”»پi‹àپjپ@پà‚S•ھپ@پà‚P‚Uژéپ@پà‚S‚O‚O‚O•¶پ@
پ@پ@پi‚Sٹر•¶پjپ@پàپ@Œ»چف‚ج–ٌ‚P‚O–œ‰~پB
پ،پ@ژé’Pˆت پE’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼پB
پ@پ@پƒ•ھژé‹à‹â‰فپ@پi= •ھژé‹à‹âپjپB
پ@پ@پƒچ]Œثژ‘مپE’èˆتپi’èٹzپj’تڈي‰ف•¼پB
پ@پ@پƒچ]Œثژ‘مپE“ْ–{—¬’ت‰ف•¼پB
پ@پ@پƒ‹كگ¢پE“ْ–{—¬’ت‰ف•¼پB
پ@پ@پƒ“ْ–{—¬’ت‰ف•¼پB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ج•ھژé‹à‹â‰ف‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAپu•ھژé‹à‹â
پ@پ@‰فپv‚ًژQڈئ‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ج•ھ’Pˆت‰ف•¼‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAپu•ھ’Pˆت’è
پ@پ@ˆتپi’èٹzپj’تڈي‰ف•¼پv‚ًژQڈئ‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ج‰ف•¼‚ج‘S‘ج‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAپuچ]Œثژ‘م
پ@پ@‚ج“ْ–{—¬’ت‰ف•¼پv‚ًژQڈئ‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
پ،پ@“ْ–{‚ج—¬’ت‰ف•¼‚ج‘S‘ج‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAپu“ْ–{—¬’ت
پ@پ@‰ف•¼پv‚ًژQڈئ‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“Tپ@‚U‚P‚V‚Q‚UپB
پ@
پ@
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ةپAژé’Pˆت‚ج‰ف•¼‚إ‚حپAژé‹àپi‚Sژيپj‚ئژé
پ@‹âپi‚Sژيپj‚ھ’’‘¢‚³‚êپAپ@ژé‹àپiژé’Pˆت‚ج‹à‰فپj‚إ‚حپA
پ@“ٌژé‹àپi‚Rژيپjپ@‚ئپ@ˆêژé‹àپi‚Pژيپjپ@‚ج‚Qژي—ق‚ج‰ف•¼
پ@‚ھ—¬’ت‚µپAژg—p‚³‚ꂽپBپ@ژé‹âپiژé’Pˆت‚ج‹â‰فپj‚إ‚حپA
پ@“ٌژé‹âپi‚Rژيپjپ@‚ئپ@ˆêژé‹âپi‚Pژيپjپ@‚ج‚Qژي—ق‚ج‰ف•¼‚ھ
پ@—¬’ت‚µپAژg—p‚³‚ꂽپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ة—¬’ت‚µ‚½پAژé’Pˆت‚ج‰ف•¼‚ة‚حپA
پ@پ@“ٌژé‹àپi‚RژيپjپAˆêژé‹àپi‚Pژيپj‚جپAژé‹àپi‚Sژيپj
پ@پ@پi‚µ‚م‚«‚ٌپAژé’Pˆت‚ج‹à‰فپjپ@‚ئپAپ@“ٌژé‹âپi‚R
پ@پ@ژيپjپAˆêژé‹âپi‚Pژيپj‚جژé‹âپi‚Sژيپjپi‚µ‚م‚¬‚ٌپA
پ@پ@ژé’Pˆت‚ج‹â‰فپj‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پ@
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ج‰ف•¼پB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ج—¼پi‚è‚ه‚¤پjپE•ھپi‚شپjپEژéپi‚µ‚مپjپE•¶پi‚à‚ٌپj
پ@‚ج’èٹzپi’èˆتپjپE’تڈي‰ف•¼پB
پ،پ@چ]Œثژ‘مپi‚P‚U‚O‚R”Nپ`‚P‚W‚U‚W”Nپj‚ةپAپ@چ]Œث–‹•{‚ة
پ@‚و‚è’’‘¢پi”چsپj‚³‚êپAپ@‘Sچ‘‚ة—¬’ت‚µپAپ@ژg—p‚³‚ꂽ
پ@’èٹzپi’èˆتپjپE’تڈي‰ف•¼پ@‚حپAپ@‚T—¼”»‹àپi‚PژيپjپAپ@
پ@ˆê—¼ڈ¬”»پi‹àپjپi‚P‚PژيپjپAپ@پ@“ٌ•ھ‹àپi‚RژيپjپAپ@ ˆê•ھ‹à
پ@پi‚P‚PژيپjپAپ@ˆê•ھ‹âپi‚QژيپjپAپ@“ٌژé‹àپi‚RژيپjپAپ@ˆêژé‹à
پ@پi‚PژيپjپAپ@پ@“ٌژé‹âپi‚RژيپjپA پ@ˆêژé‹âپi‚PژيپjپAپ@•S•¶‘K
پ@پi‚PژيپjپAپ@پ@ڈ\•¶‘Kپi‚PژيپjپAپ@ژl•¶‘Kپi‚QژيپjپAپ@ˆê•¶‘K
پ@پi‚Pژيپjپ@‚ب‚ا‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ،پ@ژé‹àپB
پ،پ@ژé‹àپB
پ،پ@“ٌژé‹àپB
پ،پ@“ٌژé‹àپ@پi‚ة‚µ‚م‚«‚ٌپjپ@‚حپAپ@‚Qژé‚ج’Pˆت‚ج‹à‰ف‚إپA
پ@چ]Œثژ‘م‚ج’èٹzپi’èˆتپjپE’تڈي‰ف•¼پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@“ٌژé‹à‚حپAپ@Œ»چف‚ج ‰ف•¼‰؟’l‚إ–ٌ‚P‚Q,‚T‚O‚O‰~‚ة
پ@‘ٹ“–‚·‚éپBپ@‚Rژي‚ ‚èپAپ@چ]Œثژ ‘م‚ج‘Oٹْ‚و‚èŒمٹْ‚ـ‚إ
پ@’’‘¢‚³‚ꂽپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@ˆêژé‹àپB
پ،پ@ˆêژé‹àپ@پi‚¢‚ء‚µ‚م‚«‚ٌپjپ@‚حپAپ@‚Pژé‚ج’Pˆت‚ج‹à‰ف
پ@‚إپA چ]Œثژ‘م‚ج’èٹzپi’èˆتپjپE’تڈي‰ف•¼پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@ˆêژé‹à‚حپAپ@Œ»چف‚ج ‰ف•¼‰؟’l‚إ–ٌ‚U,‚Q‚T‚O‰~‚ة
پ@‘ٹ“–‚·‚éپB
پ@
پ،پ@ژé‹àپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ةپAپ@ژé‹àپ@پi‚µ‚م‚«‚ٌپA= ژéپi‚µ‚مپj’Pˆت‚ج
پ@پ@‹à‰فپjپi‚Sژيپj‚جپA“ٌژé‹àپi‚Rژيپj پ@‚ئپAپ@ ˆêژé‹àپi‚Pژيپj
پ@پ@‚ج‚Qژي—ق‚ج‰ف•¼‚ھپA’’‘¢‚³‚êپA—¬’ت‚µپAژg—p‚³‚ꂽپB
پ@
پ،پ@“ٌژé‹àپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ة—¬’ت‚µ‚½پA“ٌژé‹àپi‚ة‚µ‚م‚«‚ٌپjپ@‚حپAپ@
پ@پ@ژں‚ج‚Rژي—قپ@‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@Œ³ک\“ٌژéپi”»پj‹àپi‚°‚ٌ‚ë‚‚ة‚µ‚مپi‚خ‚ٌپj‚«‚ٌپjپA
پ@پ@“V•غ“ٌژéپi”»پj‹àپi‚ؤ‚ٌ‚غ‚¤‚ة‚µ‚مپi‚خ‚ٌپj‚«‚ٌپjپA
پ@پ@–œ‰„“ٌژéپi”»پj‹àپi‚ـ‚ٌ‚¦‚ٌ‚ة‚µ‚مپi‚خ‚ٌپj‚«‚ٌپjپ@‚إ
پ@پ@‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@ˆêژé‹àپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ة—¬’ت‚µ‚½پAˆêژé‹àپi‚¢‚ء‚µ‚م‚«‚ٌپj‚حپAپ@
پ@‚Pژي—قپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@•¶گˆêژéپi”»پj‹àپi‚ش‚ٌ‚¹‚¢‚¢‚ء‚µ‚مپi‚خ‚ٌپj‚«‚ٌپj
پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@
پ،پ@ژé‹âپB
پ،پ@ژé‹âپB
پ،پ@“ٌژé‹âپB
پ،پ@“ٌژé‹âپ@پi‚ة‚µ‚م‚¬‚ٌپjپ@‚حپAپ@‚Qژé‚ج’Pˆت‚ج‹â‰ف‚إپA
پ@چ]Œثژ‘م‚ج’èٹzپi’èˆتپjپE’تڈي‰ف•¼پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@“ٌژé‹â‚حپAپ@Œ»چف‚ج ‰ف•¼‰؟’l‚إ–ٌ‚P‚Q,‚T‚O‚O‰~‚ة
پ@‘ٹ“–‚·‚éپB
پ@
پ،پ@ˆêژé‹âپB
پ،پ@ˆêژé‹âپ@پi‚¢‚ء‚µ‚م‚¬‚ٌپjپ@‚حپAپ@‚Pژé‚ج’Pˆت‚ج‹â‰ف
پ@‚إپA چ]Œثژ‘م‚ج’èٹzپi’èˆتپjپE’تڈي‰ف•¼پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@ˆêژé‹â‚حپAپ@Œ»چف‚ج ‰ف•¼‰؟’l‚إ–ٌ‚U,‚Q‚T‚O‰~‚ة
پ@‘ٹ“–‚·‚éپB
پ@
پ،پ@ژé‹âپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ةپAپ@ژé‹âپi‚µ‚م‚¬‚ٌپA= ژéپi‚µ‚مپj’Pˆت‚ج‹â
پ@پ@‰فپjپi‚Sژيپj‚جپAپ@“ٌژé‹âپi‚Rژيپj پ@‚ئپA پ@ˆêژé‹âپi‚Pژيپj
پ@پ@‚ج‚Qژي—ق‚ج‰ف•¼‚ھپA’’‘¢‚³‚êپA—¬’ت‚µپAژg—p‚³‚ꂽپB
پ@
پ،پ@“ٌژé‹âپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ة‘Sچ‘‚ة—¬’ت‚µ‚½پA“ٌژé‹âپi‚ة‚µ‚م‚¬‚ٌپjپ@
پ@پ@‚حپAپ@ژں‚ج‚Rژي—قپ@‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@Œأ“ىè`“ٌژé‹âپ@پi‚±‚ب‚ٌ‚è‚ه‚¤‚ة‚µ‚م‚¬‚ٌپjپAپ@گV
پ@پ@“ىè`“ٌژé‹âپ@پi‚µ‚ٌ ‚ب‚ٌ‚è‚ه‚¤‚ة‚µ‚م‚¬‚ٌپjپAپ@ˆہگ
پ@پ@“ٌژé‹âپ@پi‚ ‚ٌ‚¹‚¢‚ة‚µ‚م‚¬‚ٌپjپ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@ˆêژé‹âپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ة‘Sچ‘‚ة—¬’ت‚µ‚½پAˆêژé‹âپi‚¢‚ء‚µ‚م‚¬
پ@‚ٌپj‚حپAپ@ژں‚ج‚Pژي—قپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@•¶گ“ىè`ˆêژé‹âپ@پi‚ش‚ٌ‚¹‚¢‚ب‚ٌ‚è‚ه‚¤‚¢‚ء
پ@پ@‚µ‚م‚¬‚ٌپjپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@
پ،پ@ڈ¬”»پB
پ،پ@‚P—¼ڈ¬”»پi‹àپj‚حپA پ@چ]Œثژ‘م‚جٹîژ²‰ف•¼‚إ‚ ‚èپAپ@
پ@پ@چ]Œثژ‘م‚جٹeژٹْ‚إ‰؟’l‚ح•د“®‚µ‚½‚ھپAپ@Œ»چف‚ج
پ@پ@‰ف•¼‰؟’l‚إ–ٌ‚P‚O–œ‰~پ@‚إ ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@ پ@پ@چ]Œثژ‘م‚ةپAپ@‚P—¼ڈ¬”»پi‹àپj‚حپA‚¨‚و‚»‚S•ھپA
پ@پ@‚P—¼ڈ¬”»پi‹àپj‚حپA‚¨‚و‚»‚P‚UژéپAپ@‚P—¼ڈ¬”»پi‹àپj‚حپA
پ@پ@‚¨‚و‚»‚S‚O‚O‚O•¶ پi‚Sٹر•¶پjپ@‚ئŒًٹ·‚³‚ꂽپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ج‰ف•¼پB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ج’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼پB
پ@
پ،پ@—¼‹à‰فپA•ھژé‹à‹â‰فپA•¶‘K“؛پE“S‰ف‹و•ھ‚ج•ھ—قپB
پœپ@چ]Œثژ‘م‚ج’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚ًپAپi‚Pپj—¼
پ@پ@‹à‰فپAپi‚Qپj•ھژé‹à‹â‰فپAپi‚Rپj•¶‘K“؛پE“S‰ف‚ة‚و
پ@پ@‚èپA‚R‚آ‚ة•ھ—ق‚·‚éپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ج’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚حپAپ@ پi‚Pپjپ@
پ@پ@—¼‹à‰ف‚جپAپ@Œـ—¼”»پi‹àپjپi‚PژيپjپAپ@ ˆê—¼ ڈ¬”»
پ@پ@پi‹àپjپi‚P‚PژيپjپAپ@پi‚Qپjپ@•ھژé‹à‹â‰ف‚جپAپ@“ٌ•ھ‹à
پ@پ@ پi‚RژيپjپAˆê•ھ‹àپi‚P‚PژيپjپAپ@“ٌژé‹àپi‚RژيپjپAپ@
پ@پ@ˆêژé‹àپi‚PژيپjپAپ@ˆê•ھ‹âپi‚QژيپjپAپ@“ٌژé‹âپi‚RژيپjپA
پ@پ@ˆêژé‹âپi‚PژيپjپAپ@ پi‚Rپjپ@•¶‘K“؛پE“S‰ف‚جپA•S•¶‘K
پ@پ@“؛‰فپi= “V•غ‘Kپjپi‚PژيپjپAپ@ڈ\•¶‘K“؛‰فپi‚PژيپjپAپ@
پ@پ@ژl•¶‘K“؛پE“S‰فپi‚QژيپjپAپ@ˆê•¶‘K“؛پE“S‰فپi‚Pژيپj پ@
پ@پ@ ‚ج‚R‚آ‚ة•ھ—ق‚³‚ê‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@—¼پE•ھپEژéپE•¶‹و•ھ‚ج•ھ—قپB
پœپ@چ]Œثژ‘م‚ج’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚ًپAپi‚Pپj—¼پA
پ@پ@پi‚Qپj•ھپAپi‚RپjژéپAپi‚Sپj•¶پi‚è‚ه‚¤پA‚شپA‚µ‚مپA‚à‚ٌپj
پ@پ@‚ة‚و‚èپA‚S‚آ‚ة•ھ—ق‚·‚éپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ج’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚حپAپ@ پi‚Pپjپ@
پ@پ@—¼’PˆتپE’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚جپAŒـ—¼”»پi‹àپj
پ@پ@پi‚PژيپjپAپ@ ˆê—¼ ڈ¬”»پi‹àپjپi‚P‚PژيپjپAپ@پi‚Qپjپ@•ھ’P
پ@پ@ˆتپE’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚جپAپ@“ٌ•ھ‹àپi‚RژيپjپAپ@
پ@پ@ ˆê•ھ‹àپi‚P‚PژيپjپAپ@ˆê•ھ‹âپi‚QژيپjپA پ@پi‚Rپjپ@ژé’P
پ@پ@ˆتپE’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚جپAپ@“ٌژé‹àپi‚RژيپjپAپ@
پ@پ@ ˆêژé‹àپi‚PژيپjپAپ@“ٌژé‹âپi‚RژيپjپA ˆêژé‹âپi‚PژيپjپAپ@
پi‚Sپjپ@‘K’PˆتپE’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚جپAپ@•S•¶
‘K“؛‰فپi= “V•غ‘Kپjپi‚PژيپjپAپ@ڈ\•¶‘K“؛‰فپi‚PژيپjپAپ@
ژl•¶‘K“؛پE“S‰فپi‚QژيپjپAپ@ˆê•¶‘K“؛پE“S‰فپi‚Pژيپjپ@
پ@پ@پ@‚ج‚S‚آ‚ة•ھ—ق‚³‚ê‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@‚P‚Rژي—ق‹و•ھ‚ج•ھ—قپB
پœپ@چ]Œثژ‘م‚ج’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚ًپAٹz–تپAچق
پ@پ@ژ؟“™‚ة‚و‚èپA‚P‚Rژي—ق‚ة•ھ—ق‚·‚éپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ج’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚حپAپ@Œـ—¼”»
پ@پ@پi‹àپjپi‚PژيپjپAپ@ ˆê—¼ ڈ¬”»پi‹àپjپi‚P‚PژيپjپAپ@“ٌ•ھ‹à
پ@پ@پi‚RژيپjپAپ@ ˆê•ھ‹àپi‚P‚PژيپjپAپ@“ٌژé‹àپi‚RژيپjپAپ@
پ@پ@ˆêژé‹àپi‚PژيپjپAپ@پ@ˆê•ھ‹âپi‚QژيپjپAپ@“ٌژé‹âپi‚RژيپjپA
پ@پ@ˆêژé‹âپi‚PژيپjپAپ@•S•¶‘K“؛‰فپi= “V•غ‘Kپjپi‚PژيپjپA
پ@پ@ڈ\•¶‘K“؛‰فپi‚PژيپjپAپ@ژl•¶‘K“؛پE“S‰فپi‚QژيپjپAپ@
پ@پ@ˆê•¶‘K“؛پE“S‰فپi‚Pژيپjپ@ ‚ج‚P‚Rژي—ق‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@چ]Œثژ‘مپi‚P‚U‚O‚R”Nپ`‚P‚W‚U‚W”Nپj‚ةپAپ@چ]Œث–‹•{
پ@پ@‚ة‚و‚è’’‘¢پi”چsپj‚³‚êپAپ@‘Sچ‘‚ة—¬’ت‚µپAژg—p‚³
پ@پ@‚ꂽ’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚حپAپ@Œـ—¼”»پi‹àپjپi‚²
پ@پ@‚è‚ه‚¤‚خ‚ٌپi‚«‚ٌپjپjپi‚PژيپjپAپ@ ˆê—¼ ڈ¬”»پi‹àپjپi‚¢‚؟
پ@پ@‚è‚ه‚¤‚±‚خ‚ٌپi‚«‚ٌپjپjپi‚P‚PژيپjپAپ@“ٌ•ھ‹àپi‚ة‚ش‚«‚ٌپj
پ@پ@پi‚RژيپjپAپ@ ˆê•ھ‹àپi‚¢‚؟‚ش‚«‚ٌپjپi‚P‚PژيپjپAپ@پ@“ٌژé
پ@پ@‹àپi‚ة‚µ‚م‚«‚ٌپjپi‚RژيپjپAپ@ ˆêژé‹àپi‚¢‚ء‚µ‚م‚«‚ٌپj
پ@پ@پi‚PژيپjپAپ@پ@ˆê•ھ‹âپi‚¢‚؟‚ش‚¬‚ٌپjپi‚QژيپjپAپ@“ٌژé‹â
پ@پ@پi‚ة‚µ‚م‚¬‚ٌپjپi‚RژيپjپA پ@ˆêژé‹âپi‚¢‚ء‚µ‚م‚¬‚ٌپj
پ@پ@پi‚PژيپjپAپ@•S•¶‘K“؛‰فپi= “V•غ‘Kپjپi‚ذ‚ل‚‚à‚ٌ‚¹‚ٌ
پ@پ@‚ا‚¤‚©پi= ‚ؤ‚ٌ‚غ‚¤‚¹‚ٌپjپi‚PژيپjپAپ@پ@ڈ\•¶‘K“؛‰ف
پ@پ@پi‚¶‚م‚¤‚à‚ٌ‚¹‚ٌپjپi‚PژيپjپAپ@ژl•¶‘K“؛پE“S‰فپi‚و‚ٌ‚à
پ@پ@‚ٌ‚¹‚ٌ‚ا‚¤پE‚ؤ‚ء‚©پjپi‚QژيپjپAپ@ˆê•¶‘K“؛پE“S‰فپi‚¢
پ@پ@‚؟‚à‚ٌ‚¹‚ٌ‚ا‚¤پE‚ؤ‚ء‚©پjپi‚Pژيپjپ@‚ج‚P‚Rژي—ق‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
#shuunitregularmoney-appearingscenes
پ@
پôپôپ@ژé’Pˆت’èٹzپi’èˆتپjپE’تڈي‰ف•¼پ@‚ھ“o
پ@پ@پ@پ@ڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢پAƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپAƒh
پ@پ@پ@پ@ƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[ پB
پ@
پڑپ@ژé’Pˆت’èٹzپi’èˆتپjپE’تڈي‰ف•¼پ@‚ھ“oڈê
پ@پ@ ‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢پAƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپB
پœپ@پi’چˆسپjپ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAپ@ƒtƒBƒNƒVƒ‡ƒ“پ@‚إ‚·پBپ@—ًپ@
پ@پ@پ@ژj‚جƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAپ@ژjژہپi—ًژjڈم‚جژ–ژہپjپ@‚ئپ@
پ@پ@پ@‰ث‹َ‚جڈo—ˆژ–‚ھپ@چ¬‚¶‚ء‚ؤ•`‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپ@‚ـ‚½پAپ@
پ@پ@پ@Œ»‘م•—‚ةƒAƒŒƒ“ƒW‚µ‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚·پB
پ@
پ،پ@پwپ@—z‰ٹ‚ج’زپE‹ڈ–°‚è”ض‰¹پEچ]Œث‘oژ†پ@
پ@پ@پ@ پi‚©‚°‚낤‚ج‚آ‚¶پE‚¢‚ث‚ق‚è‚¢‚ي‚ثپE‚¦‚ا‚¼‚¤‚µپjپ@پx پBپ@
پ@پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚a‚rƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒhƒ‰ƒ}پA‘SŒv‚P‚P‰ٌپjپB
پ@پ@پ@‘و‚Q‰ٌپ@پuپ@مJپ@پi‚«‚¸‚بپjپ@پv
پœپ@“ْ–{‚جچ]Œثژ‘م‚ً•`‚¢‚½پAƒhƒ‰ƒ}پB
پœپ@ژé‹â‚جپA“ىè`“ٌژé‹âپi‚ب‚ٌ‚è‚ه‚¤‚ة‚µ‚م‚¬‚ٌپj‚ھ“o
پ@پ@ڈê‚·‚éپBپ@ڈ¬”»‚ئ“ىè`“ٌژé‹â‚جŒًٹ·”ن—¦پiڈ¬”»‚P–‡
پ@پ@‚ئ“ٌژé‹â‚W–‡پj‚ً‚ك‚®‚èپA‘›“®‚ھ‹N‚«‚éپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ژé‹àپ@
پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚م‚«‚ٌپjپB
پ@
پ،پ@ژé‹àپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ژé‹àپ@پi‚µ‚م‚«‚ٌپjپB
پ،پ@پs“ْ–{—¬’ت‰ف•¼پtپB
پ@پ@پ@چ]Œثژ‘م‚ج“ْ–{—¬’ت‰ف•¼پB
پ،پ@ژé‹àپ@پi‚µ‚م‚«‚ٌپAژéپi‚µ‚مپjژé’Pˆت‚ج‹à‰فپjپB
پ،پ@“ٌژé‹àپi‚RژيپjپAپ@ˆêژé‹àپi‚PژيپjپA‚ج‚Qژي—قپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ة—¬’ت‚µ‚½پAژé’Pˆت‚ج‰ف•¼‚ة‚حپA
پ@پ@“ٌژé‹àپi‚RژيپjپAˆêژé‹àپi‚Pژيپj‚جپAژé‹àپi‚Sژيپj
پ@پ@پi‚µ‚م‚«‚ٌپAژé’Pˆت‚ج‹à‰فپjپ@‚ئپAپ@“ٌژé‹âپi‚R
پ@پ@ژيپjپAˆêژé‹âپi‚Pژيپj‚جژé‹âپi‚Sژيپjپi‚µ‚م‚¬‚ٌپA
پ@پ@ژé’Pˆت‚ج‹â‰فپj‚ھ‚ ‚éپB
پ@پ@پiپث پuژé’Pˆت ’èˆتپi’èٹzپj’تڈي‰ف•¼پvپjپB
پ،پ@چ]Œث–‹•{‚ھ’’‘¢پE”چs‚µ‚½پAژéپi‚µ‚مپj’Pˆت‚جپA
پ@پ@چ]Œثژ‘م‚ج’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼ پA’·•ûŒ`
پ@پ@پuژé‹à‰فپvپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ،پ@“ٌژé‹àپ@پàپ@Œ»چف‚ج–ٌ‚P‚Q,‚T‚O‚O‰~ پB
پ@پ@پ@ˆêژé‹àپ@پàپ@Œ»چف‚ج–ٌ ‚U,‚Q‚T‚O‰~پB
پ@پ@پ@ˆê—¼ڈ¬”»پi‹àپjپ@پà‚S•ھپ@پà‚P‚Uژéپ@پà‚S‚O‚O‚O•¶پ@
پ@پ@پi‚Sٹر•¶پjپ@پàپ@Œ»چف‚ج–ٌ‚P‚O–œ‰~پB
پ،پ@ژé‹àپB
پ@پ@پƒژé’Pˆت پE’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼پB
پ@پ@پƒ•ھژé‹à‹â‰فپ@پi= •ھژé‹à‹âپjپB
پ@پ@پƒچ]Œثژ‘مپE’èˆتپi’èٹzپj’تڈي‰ف•¼پB
پ@پ@پƒچ]Œثژ‘مپE“ْ–{—¬’ت‰ف•¼پB
پ@پ@پƒ‹كگ¢پE“ْ–{—¬’ت‰ف•¼پB
پ@پ@پƒ“ْ–{—¬’ت‰ف•¼پB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚جژé’Pˆت‰ف•¼‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAپuژé’Pˆت
پ@پ@’èˆتپi’èٹzپj’تڈي‰ف•¼پv‚ًژQڈئ‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ج•ھژé‹à‹â‰ف‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAپu•ھژé‹à
پ@پ@‹â‰فپv‚ًژQڈئ‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ج‰ف•¼‚ج‘S‘ج‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAپuچ]Œثژ
پ@پ@‘م‚ج“ْ–{—¬’ت‰ف•¼پv‚ًژQڈئ‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
پ،پ@“ْ–{‚ج—¬’ت‰ف•¼‚ج‘S‘ج‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAپu“ْ–{—¬
پ@پ@’ت‰ف•¼پv‚ًژQڈئ‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“Tپ@‚U‚P‚V‚Q‚UپB
پ@
پ@
پ،پ@ژé‹àپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ةپAژé’Pˆت‚ج‰ف•¼‚إ‚حپAژé‹àپi‚Sژيپj‚ئ
پ@پ@ژé‹âپi‚Sژيپj‚ھ’’‘¢‚³‚êپAپ@ژé‹àپiژé’Pˆت‚ج‹à‰فپj
پ@پ@‚إ‚حپA“ٌژé‹àپi‚Rژيپjپ@‚ئپ@ˆêژé‹àپi‚Pژيپjپ@‚ج‚Qژي
پ@پ@—ق‚ج‰ف•¼‚ھ—¬’ت‚µپAژg—p‚³‚ꂽپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ة—¬’ت‚µ‚½پAژé’Pˆت‚ج‰ف•¼‚ة‚حپA
پ@پ@“ٌژé‹àپi‚RژيپjپAˆêژé‹àپi‚Pژيپj‚جپAژé‹àپi‚Sژيپj
پ@پ@پi‚µ‚م‚«‚ٌپAژé’Pˆت‚ج‹à‰فپjپ@‚ئپAپ@“ٌژé‹âپi‚R
پ@پ@ژيپjپAˆêژé‹âپi‚Pژيپj‚جژé‹âپi‚Sژيپjپi‚µ‚م‚¬‚ٌپA
پ@پ@ژé’Pˆت‚ج‹â‰فپj‚ھ‚ ‚éپB
پ@پ@پiپث پuژé’Pˆت ’èˆتپi’èٹzپj’تڈي‰ف•¼پvپjپB
پ@
پ@
پ،پ@ژé‹àپB
پ،پ@“ٌژé‹àپ@پi‚ة‚µ‚م‚«‚ٌپjپ@‚حپAپ@‚Qژé‚ج’Pˆت‚ج‹à‰ف‚إپA
پ@چ]Œثژ‘م‚ج’èٹzپi’èˆتپjپE’تڈي‰ف•¼پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@“ٌژé‹à‚حپAپ@Œ»چف‚ج ‰ف•¼‰؟’l‚إ–ٌ‚P‚Q,‚T‚O‚O‰~‚ة
پ@‘ٹ“–‚·‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@ˆêژé‹àپ@پi‚¢‚ء‚µ‚م‚«‚ٌپjپ@‚حپAپ@‚Pژé‚ج’Pˆت‚ج‹à‰ف
پ@‚إپA چ]Œثژ‘م‚ج’èٹzپi’èˆتپjپE’تڈي‰ف•¼پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@ˆêژé‹à‚حپAپ@Œ»چف‚ج ‰ف•¼‰؟’l‚إ–ٌ‚U,‚Q‚T‚O‰~‚ة
پ@‘ٹ“–‚·‚éپB
پ@
پ،پ@ژé‹àپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ةپAپ@ژé‹àپ@پi‚µ‚م‚«‚ٌپA= ژéپi‚µ‚مپj’Pˆت‚ج
پ@پ@‹à‰فپjپi‚Sژيپj‚جپA“ٌژé‹àپi‚Rژيپj پ@‚ئپAپ@ ˆêژé‹àپi‚Pژيپj
پ@پ@‚ج‚Qژي—ق‚ج‰ف•¼‚ھپA’’‘¢‚³‚êپA—¬’ت‚µپAژg—p‚³‚ꂽپB
پ@
پ،پ@“ٌژé‹àپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ة—¬’ت‚µ‚½پA“ٌژé‹àپi‚ة‚µ‚م‚«‚ٌپjپ@‚حپAپ@
پ@پ@ژں‚ج‚Rژي—قپ@‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@Œ³ک\“ٌژéپi”»پj‹àپi‚°‚ٌ‚ë‚‚ة‚µ‚مپi‚خ‚ٌپj‚«‚ٌپjپA
پ@پ@“V•غ“ٌژéپi”»پj‹àپi‚ؤ‚ٌ‚غ‚¤‚ة‚µ‚مپi‚خ‚ٌپj‚«‚ٌپjپA
پ@پ@–œ‰„“ٌژéپi”»پj‹àپi‚ـ‚ٌ‚¦‚ٌ‚ة‚µ‚مپi‚خ‚ٌپj‚«‚ٌپjپ@‚إ
پ@پ@‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@ˆêژé‹àپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ة—¬’ت‚µ‚½پAˆêژé‹àپi‚¢‚ء‚µ‚م‚«‚ٌپj‚حپAپ@
پ@‚Pژي—قپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@•¶گˆêژéپi”»پj‹àپi‚ش‚ٌ‚¹‚¢‚¢‚ء‚µ‚مپi‚خ‚ٌپj‚«‚ٌپj
پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ج‰ف•¼پB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ج—¼پi‚è‚ه‚¤پjپE•ھپi‚شپjپEژéپi‚µ‚مپjپE•¶پi‚à‚ٌپj
پ@‚ج’èٹzپi’èˆتپjپE’تڈي‰ف•¼پB
پ،پ@چ]Œثژ‘مپi‚P‚U‚O‚R”Nپ`‚P‚W‚U‚W”Nپj‚ةپAپ@چ]Œث–‹•{‚ة
پ@‚و‚è’’‘¢پi”چsپj‚³‚êپAپ@‘Sچ‘‚ة—¬’ت‚µپAپ@ژg—p‚³‚ꂽ
پ@’èٹzپi’èˆتپjپE’تڈي‰ف•¼پ@‚حپAپ@‚T—¼”»‹àپi‚PژيپjپAپ@
پ@ˆê—¼ڈ¬”»پi‹àپjپi‚P‚PژيپjپAپ@پ@“ٌ•ھ‹àپi‚RژيپjپAپ@ ˆê•ھ‹à
پ@پi‚P‚PژيپjپAپ@ˆê•ھ‹âپi‚QژيپjپAپ@“ٌژé‹àپi‚RژيپjپAپ@ˆêژé‹à
پ@پi‚PژيپjپAپ@پ@“ٌژé‹âپi‚RژيپjپA پ@ˆêژé‹âپi‚PژيپjپAپ@•S•¶‘K
پ@پi‚PژيپjپAپ@پ@ڈ\•¶‘Kپi‚PژيپjپAپ@ژl•¶‘Kپi‚QژيپjپAپ@ˆê•¶‘K
پ@پi‚Pژيپjپ@‚ب‚ا‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@ڈ¬”»پB
پ،پ@‚P—¼ڈ¬”»پi‹àپj‚حپAچ]Œثژ‘م‚جٹîژ²‰ف•¼‚إپAپ@چ]Œث
پ@ژ‘م‚جٹeژٹْ‚إ‰؟’l‚ح•د“®‚µ‚½‚ھپAپ@Œ»چف‚ج ‰ف•¼
پ@‰؟’l‚إ–ٌ ‚P‚O–œ‰~پ@‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@پ@پ@چ]Œثژ‘م‚ةپAپ@‚P—¼ڈ¬”»پi‹àپj‚حپA‚¨‚و‚»‚S•ھپA‚P—¼
پ@ڈ¬”» پi‹àپj‚حپA‚¨‚و‚»‚P‚UژéپAپ@‚P—¼ڈ¬”»پi‹àپj‚حپA‚¨‚و
پ@‚»‚S‚O‚O‚O•¶ پi‚Sٹر•¶پjپ@‚ئŒًٹ·‚³‚ꂽپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ج‰ف•¼پB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ج’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼پB
پ@
پ،پ@—¼‹à‰فپA•ھژé‹à‹â‰فپA•¶‘K“؛پE“S‰ف‹و•ھ‚ج•ھ—قپB
پœپ@چ]Œثژ‘م‚ج’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚ًپAپi‚Pپj—¼
پ@پ@‹à‰فپAپi‚Qپj•ھژé‹à‹â‰فپAپi‚Rپj•¶‘K“؛پE“S‰ف‚ة‚و
پ@پ@‚èپA‚R‚آ‚ة•ھ—ق‚·‚éپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ج’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚حپAپ@ پi‚Pپjپ@
پ@پ@—¼‹à‰ف‚جپAپ@Œـ—¼”»پi‹àپjپi‚PژيپjپAپ@ ˆê—¼ ڈ¬”»
پ@پ@پi‹àپjپi‚P‚PژيپjپAپ@پi‚Qپjپ@•ھژé‹à‹â‰ف‚جپAپ@“ٌ•ھ‹à
پ@پ@ پi‚RژيپjپAˆê•ھ‹àپi‚P‚PژيپjپAپ@“ٌژé‹àپi‚RژيپjپAپ@
پ@پ@ˆêژé‹àپi‚PژيپjپAپ@ˆê•ھ‹âپi‚QژيپjپAپ@“ٌژé‹âپi‚RژيپjپA
پ@پ@ˆêژé‹âپi‚PژيپjپAپ@ پi‚Rپjپ@•¶‘K“؛پE“S‰ف‚جپA•S•¶‘K
پ@پ@“؛‰فپi= “V•غ‘Kپjپi‚PژيپjپAپ@ڈ\•¶‘K“؛‰فپi‚PژيپjپAپ@
پ@پ@ژl•¶‘K“؛پE“S‰فپi‚QژيپjپAپ@ˆê•¶‘K“؛پE“S‰فپi‚Pژيپj پ@
پ@پ@ ‚ج‚R‚آ‚ة•ھ—ق‚³‚ê‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@—¼پE•ھپEژéپE•¶‹و•ھ‚ج•ھ—قپB
پœپ@چ]Œثژ‘م‚ج’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚ًپAپi‚Pپj—¼پA
پ@پ@پi‚Qپj•ھپAپi‚RپjژéپAپi‚Sپj•¶پi‚è‚ه‚¤پA‚شپA‚µ‚مپA‚à‚ٌپj
پ@پ@‚ة‚و‚èپA‚S‚آ‚ة•ھ—ق‚·‚éپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ج’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚حپAپ@ پi‚Pپjپ@
پ@پ@—¼’PˆتپE’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚جپAŒـ—¼”»پi‹àپj
پ@پ@پi‚PژيپjپAپ@ ˆê—¼ ڈ¬”»پi‹àپjپi‚P‚PژيپjپAپ@پi‚Qپjپ@•ھ’P
پ@پ@ˆتپE’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚جپAپ@“ٌ•ھ‹àپi‚RژيپjپAپ@
پ@پ@ ˆê•ھ‹àپi‚P‚PژيپjپAپ@ˆê•ھ‹âپi‚QژيپjپA پ@پi‚Rپjپ@ژé’P
پ@پ@ˆتپE’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚جپAپ@“ٌژé‹àپi‚RژيپjپAپ@
پ@پ@ ˆêژé‹àپi‚PژيپjپAپ@“ٌژé‹âپi‚RژيپjپA ˆêژé‹âپi‚PژيپjپAپ@
پi‚Sپjپ@‘K’PˆتپE’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚جپAپ@•S•¶
‘K“؛‰فپi= “V•غ‘Kپjپi‚PژيپjپAپ@ڈ\•¶‘K“؛‰فپi‚PژيپjپAپ@
ژl•¶‘K“؛پE“S‰فپi‚QژيپjپAپ@ˆê•¶‘K“؛پE“S‰فپi‚Pژيپjپ@
پ@پ@پ@‚ج‚S‚آ‚ة•ھ—ق‚³‚ê‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@‚P‚Rژي—ق‹و•ھ‚ج•ھ—قپB
پœپ@چ]Œثژ‘م‚ج’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚ًپAٹz–تپAچق
پ@پ@ژ؟“™‚ة‚و‚èپA‚P‚Rژي—ق‚ة•ھ—ق‚·‚éپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ج’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚حپAپ@Œـ—¼”»
پ@پ@پi‹àپjپi‚PژيپjپAپ@ ˆê—¼ ڈ¬”»پi‹àپjپi‚P‚PژيپjپAپ@“ٌ•ھ‹à
پ@پ@پi‚RژيپjپAپ@ ˆê•ھ‹àپi‚P‚PژيپjپAپ@“ٌژé‹àپi‚RژيپjپAپ@
پ@پ@ˆêژé‹àپi‚PژيپjپAپ@پ@ˆê•ھ‹âپi‚QژيپjپAپ@“ٌژé‹âپi‚RژيپjپA
پ@پ@ˆêژé‹âپi‚PژيپjپAپ@•S•¶‘K“؛‰فپi= “V•غ‘Kپjپi‚PژيپjپA
پ@پ@ڈ\•¶‘K“؛‰فپi‚PژيپjپAپ@ژl•¶‘K“؛پE“S‰فپi‚QژيپjپAپ@
پ@پ@ˆê•¶‘K“؛پE“S‰فپi‚Pژيپjپ@ ‚ج‚P‚Rژي—ق‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@چ]Œثژ‘مپi‚P‚U‚O‚R”Nپ`‚P‚W‚U‚W”Nپj‚ةپAپ@چ]Œث–‹•{
پ@پ@‚ة‚و‚è’’‘¢پi”چsپj‚³‚êپAپ@‘Sچ‘‚ة—¬’ت‚µپAژg—p‚³
پ@پ@‚ꂽ’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚حپAپ@Œـ—¼”»پi‹àپjپi‚²
پ@پ@‚è‚ه‚¤‚خ‚ٌپi‚«‚ٌپjپjپi‚PژيپjپAپ@ ˆê—¼ ڈ¬”»پi‹àپjپi‚¢‚؟
پ@پ@‚è‚ه‚¤‚±‚خ‚ٌپi‚«‚ٌپjپjپi‚P‚PژيپjپAپ@“ٌ•ھ‹àپi‚ة‚ش‚«‚ٌپj
پ@پ@پi‚RژيپjپAپ@ ˆê•ھ‹àپi‚¢‚؟‚ش‚«‚ٌپjپi‚P‚PژيپjپAپ@پ@“ٌژé
پ@پ@‹àپi‚ة‚µ‚م‚«‚ٌپjپi‚RژيپjپAپ@ ˆêژé‹àپi‚¢‚ء‚µ‚م‚«‚ٌپj
پ@پ@پi‚PژيپjپAپ@پ@ˆê•ھ‹âپi‚¢‚؟‚ش‚¬‚ٌپjپi‚QژيپjپAپ@“ٌژé‹â
پ@پ@پi‚ة‚µ‚م‚¬‚ٌپjپi‚RژيپjپA پ@ˆêژé‹âپi‚¢‚ء‚µ‚م‚¬‚ٌپj
پ@پ@پi‚PژيپjپAپ@•S•¶‘K“؛‰فپi= “V•غ‘Kپjپi‚ذ‚ل‚‚à‚ٌ‚¹‚ٌ
پ@پ@‚ا‚¤‚©پi= ‚ؤ‚ٌ‚غ‚¤‚¹‚ٌپjپi‚PژيپjپAپ@پ@ڈ\•¶‘K“؛‰ف
پ@پ@پi‚¶‚م‚¤‚à‚ٌ‚¹‚ٌپjپi‚PژيپjپAپ@ژl•¶‘K“؛پE“S‰فپi‚و‚ٌ‚à
پ@پ@‚ٌ‚¹‚ٌ‚ا‚¤پE‚ؤ‚ء‚©پjپi‚QژيپjپAپ@ˆê•¶‘K“؛پE“S‰فپi‚¢
پ@پ@‚؟‚à‚ٌ‚¹‚ٌ‚ا‚¤پE‚ؤ‚ء‚©پjپi‚Pژيپjپ@‚ج‚P‚Rژي—ق‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ژé‹âپ@
پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚م‚¬‚ٌپjپB
پ@
پ،پ@ژé‹âپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ژé‹âپ@پi‚µ‚م‚¬‚ٌپjپB
پ،پ@پs“ْ–{—¬’ت‰ف•¼پtپB
پ@پ@پ@چ]Œثژ‘م‚ج“ْ–{—¬’ت‰ف•¼پB
پ،پ@ژé‹âپ@پi‚µ‚م‚¬‚ٌپAژéپi‚µ‚مپjژé’Pˆت‚ج ‹â‰فپjپB
پ،پ@“ٌژé‹âپi‚RژيپjپAˆêژé‹âپi‚PژيپjپA‚ج‚Qژي—قپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ة—¬’ت‚µ‚½پAژé’Pˆت‚ج‰ف•¼‚ة‚حپA
پ@پ@“ٌژé‹àپi‚RژيپjپAˆêژé‹àپi‚Pژيپj‚جپAژé‹àپi‚Sژيپj
پ@پ@پi‚µ‚م‚«‚ٌپAژé’Pˆت‚ج‹à‰فپjپ@‚ئپAپ@“ٌژé‹âپi‚R
پ@پ@ژيپjپAˆêژé‹âپi‚Pژيپj‚جژé‹âپi‚Sژيپjپi‚µ‚م‚¬‚ٌپA
پ@پ@ژé’Pˆت‚ج‹â‰فپj‚ھ‚ ‚éپB
پ@پ@پiپث پuژé’Pˆت ’èˆتپi’èٹzپj’تڈي‰ف•¼پvپjپB
پ،پ@چ]Œث–‹•{‚ھ’’‘¢پE”چs‚µ‚½پAژéپi‚µ‚مپj’Pˆت‚جپA
پ@پ@چ]Œثژ‘م‚ج’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼ پA’·•ûŒ`
پ@پ@پuژé‹â‰فپvپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ،پ@“ٌژé‹âپ@پàپ@Œ»چف‚ج–ٌ‚P‚Q,‚T‚O‚O‰~ پB
پ@پ@پ@ˆêژé‹âپ@پàپ@Œ»چف‚ج–ٌ ‚U,‚Q‚T‚O‰~پB
پ@پ@پ@ˆê—¼ڈ¬”»پi‹àپjپ@پà‚S•ھپ@پà‚P‚Uژéپ@پà‚S‚O‚O‚O•¶پ@
پ@پ@پi‚Sٹر•¶پjپ@پàپ@Œ»چف‚ج–ٌ‚P‚O–œ‰~پB
پ،پ@ژé‹âپB
پ@پ@پƒژé’Pˆت پE’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼پB
پ@پ@پƒ•ھژé‹à‹â‰فپ@پi= •ھژé‹à‹âپjپB
پ@پ@پƒچ]Œثژ‘مپE’èˆتپi’èٹzپj’تڈي‰ف•¼پB
پ@پ@پƒچ]Œثژ‘مپE“ْ–{—¬’ت‰ف•¼پB
پ@پ@پƒ‹كگ¢پE“ْ–{—¬’ت‰ف•¼پB
پ@پ@پƒ“ْ–{—¬’ت‰ف•¼پB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚جژé’Pˆت‰ف•¼‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAپuژé’Pˆت
پ@پ@’èˆتپi’èٹzپj’تڈي‰ف•¼پv‚ًژQڈئ‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ج•ھژé‹à‹â‰ف‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAپu•ھژé‹à
پ@پ@‹â‰فپv‚ًژQڈئ‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ج‰ف•¼‚ج‘S‘ج‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAپuچ]Œثژ
پ@پ@‘م‚ج“ْ–{—¬’ت‰ف•¼پv‚ًژQڈئ‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
پ،پ@“ْ–{‚ج—¬’ت‰ف•¼‚ج‘S‘ج‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAپu“ْ–{—¬
پ@پ@’ت‰ف•¼پv‚ًژQڈئ‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“Tپ@‚U‚P‚V‚Q‚UپB
پ@
پ@
پ،پ@ژé‹âپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ةپAژé’Pˆت‚ج‰ف•¼‚إ‚حپAژé‹àپi‚Sژيپj‚ئژé
پ@‹âپi‚Sژيپj‚ھ’’‘¢‚³‚êپAپ@ژé‹âپiژé’Pˆت‚ج‹â‰فپj‚إ‚حپA
پ@“ٌژé‹âپi‚Rژيپjپ@‚ئپ@ˆêژé‹âپi‚Pژيپjپ@‚ج‚Qژي—ق‚ج‰ف•¼‚ھ
پ@—¬’ت‚µپAژg—p‚³‚ꂽپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ة—¬’ت‚µ‚½پAژé’Pˆت‚ج‰ف•¼‚ة‚حپA
پ@پ@“ٌژé‹àپi‚RژيپjپAˆêژé‹àپi‚Pژيپj‚جپAژé‹àپi‚Sژيپj
پ@پ@پi‚µ‚م‚«‚ٌپAژé’Pˆت‚ج‹à‰فپjپ@‚ئپAپ@“ٌژé‹âپi‚R
پ@پ@ژيپjپAˆêژé‹âپi‚Pژيپj‚جژé‹âپi‚Sژيپjپi‚µ‚م‚¬‚ٌپA
پ@پ@ژé’Pˆت‚ج‹â‰فپj‚ھ‚ ‚éپB
پ@پ@پiپث پuژé’Pˆت ’èˆتپi’èٹzپj’تڈي‰ف•¼پvپjپB
پ@
پ@
پ،پ@ژé‹âپB
پ،پ@“ٌژé‹âپB
پ،پ@“ٌژé‹âپ@پi‚ة‚µ‚م‚¬‚ٌپjپ@‚حپAپ@‚Qژé‚ج’Pˆت‚ج‹â‰ف‚إپA
پ@چ]Œثژ‘م‚ج’èٹzپi’èˆتپjپE’تڈي‰ف•¼پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@“ٌژé‹â‚حپAپ@Œ»چف‚ج ‰ف•¼‰؟’l‚إ–ٌ‚P‚Q,‚T‚O‚O‰~‚ة
پ@‘ٹ“–‚·‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@ˆêژé‹âپB
پ،پ@ˆêژé‹âپ@پi‚¢‚ء‚µ‚م‚¬‚ٌپjپ@‚حپAپ@‚Pژé‚ج’Pˆت‚ج‹â‰ف
پ@‚إپA چ]Œثژ‘م‚ج’èٹzپi’èˆتپjپE’تڈي‰ف•¼پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@ˆêژé‹â‚حپAپ@Œ»چف‚ج ‰ف•¼‰؟’l‚إ–ٌ‚U,‚Q‚T‚O‰~‚ة
پ@‘ٹ“–‚·‚éپB
پ@
پ،پ@ژé‹âپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ةپAپ@ژé‹âپi‚µ‚م‚¬‚ٌپA= ژéپi‚µ‚مپj’Pˆت‚ج‹â
پ@پ@‰فپjپi‚Sژيپj‚جپAپ@“ٌژé‹âپi‚Rژيپj پ@‚ئپA پ@ˆêژé‹âپi‚Pژيپj
پ@پ@‚ج‚Qژي—ق‚ج‰ف•¼‚ھپA’’‘¢‚³‚êپA—¬’ت‚µپAژg—p‚³‚ꂽپB
پ@
پ،پ@“ٌژé‹âپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ة‘Sچ‘‚ة—¬’ت‚µ‚½پA“ٌژé‹âپi‚ة‚µ‚م‚¬‚ٌپjپ@
پ@پ@‚حپAپ@ژں‚ج‚Rژي—قپ@‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@Œأ“ىè`“ٌژé‹âپ@پi‚±‚ب‚ٌ‚è‚ه‚¤‚ة‚µ‚م‚¬‚ٌپjپAپ@گV
پ@پ@“ىè`“ٌژé‹âپ@پi‚µ‚ٌ ‚ب‚ٌ‚è‚ه‚¤‚ة‚µ‚م‚¬‚ٌپjپAپ@ˆہگ
پ@پ@“ٌژé‹âپ@پi‚ ‚ٌ‚¹‚¢‚ة‚µ‚م‚¬‚ٌپjپ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@ˆêژé‹âپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ة‘Sچ‘‚ة—¬’ت‚µ‚½پAˆêژé‹âپi‚¢‚ء‚µ‚م‚¬
پ@‚ٌپj‚حپAپ@ژں‚ج‚Pژي—قپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@•¶گ“ىè`ˆêژé‹âپ@پi‚ش‚ٌ‚¹‚¢‚ب‚ٌ‚è‚ه‚¤‚¢‚ء
پ@پ@‚µ‚م‚¬‚ٌپjپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ج‰ف•¼پB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ج—¼پi‚è‚ه‚¤پjپE•ھپi‚شپjپEژéپi‚µ‚مپjپE•¶پi‚à‚ٌپj
پ@‚ج’èٹzپi’èˆتپjپE’تڈي‰ف•¼پB
پ،پ@چ]Œثژ‘مپi‚P‚U‚O‚R”Nپ`‚P‚W‚U‚W”Nپj‚ةپAپ@چ]Œث–‹•{‚ة
پ@‚و‚è’’‘¢پi”چsپj‚³‚êپAپ@‘Sچ‘‚ة—¬’ت‚µپAپ@ژg—p‚³‚ꂽ
پ@’èٹzپi’èˆتپjپE’تڈي‰ف•¼پ@‚حپAپ@‚T—¼”»‹àپi‚PژيپjپAپ@
پ@ˆê—¼ڈ¬”»پi‹àپjپi‚P‚PژيپjپAپ@پ@“ٌ•ھ‹àپi‚RژيپjپAپ@ ˆê•ھ‹à
پ@پi‚P‚PژيپjپAپ@ˆê•ھ‹âپi‚QژيپjپAپ@“ٌژé‹àپi‚RژيپjپAپ@ˆêژé‹à
پ@پi‚PژيپjپAپ@پ@“ٌژé‹âپi‚RژيپjپA پ@ˆêژé‹âپi‚PژيپjپAپ@•S•¶‘K
پ@پi‚PژيپjپAپ@پ@ڈ\•¶‘Kپi‚PژيپjپAپ@ژl•¶‘Kپi‚QژيپjپAپ@ˆê•¶‘K
پ@پi‚Pژيپjپ@‚ب‚ا‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@ڈ¬”»پB
پ،پ@‚P—¼ڈ¬”»پi‹àپj‚حپAچ]Œثژ‘م‚جٹîژ²‰ف•¼‚إپAپ@چ]Œث
پ@ژ‘م‚جٹeژٹْ‚إ‰؟’l‚ح•د“®‚µ‚½‚ھپAپ@Œ»چف‚ج ‰ف•¼
پ@‰؟’l‚إ–ٌ ‚P‚O–œ‰~پ@‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@پ@پ@چ]Œثژ‘م‚ةپAپ@‚P—¼ڈ¬”»پi‹àپj‚حپA‚¨‚و‚»‚S•ھپA‚P—¼
پ@ڈ¬”» پi‹àپj‚حپA‚¨‚و‚»‚P‚UژéپAپ@‚P—¼ڈ¬”»پi‹àپj‚حپA‚¨‚و
پ@‚»‚S‚O‚O‚O•¶ پi‚Sٹر•¶پjپ@‚ئŒًٹ·‚³‚ꂽپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ج‰ف•¼پB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ج’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼پB
پ@
پ،پ@—¼‹à‰فپA•ھژé‹à‹â‰فپA•¶‘K“؛پE“S‰ف‹و•ھ‚ج•ھ—قپB
پœپ@چ]Œثژ‘م‚ج’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚ًپAپi‚Pپj—¼
پ@پ@‹à‰فپAپi‚Qپj•ھژé‹à‹â‰فپAپi‚Rپj•¶‘K“؛پE“S‰ف‚ة‚و
پ@پ@‚èپA‚R‚آ‚ة•ھ—ق‚·‚éپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ج’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚حپAپ@ پi‚Pپjپ@
پ@پ@—¼‹à‰ف‚جپAپ@Œـ—¼”»پi‹àپjپi‚PژيپjپAپ@ ˆê—¼ ڈ¬”»
پ@پ@پi‹àپjپi‚P‚PژيپjپAپ@پi‚Qپjپ@•ھژé‹à‹â‰ف‚جپAپ@“ٌ•ھ‹à
پ@پ@ پi‚RژيپjپAˆê•ھ‹àپi‚P‚PژيپjپAپ@“ٌژé‹àپi‚RژيپjپAپ@
پ@پ@ˆêژé‹àپi‚PژيپjپAپ@ˆê•ھ‹âپi‚QژيپjپAپ@“ٌژé‹âپi‚RژيپjپA
پ@پ@ˆêژé‹âپi‚PژيپjپAپ@ پi‚Rپjپ@•¶‘K“؛پE“S‰ف‚جپA•S•¶‘K
پ@پ@“؛‰فپi= “V•غ‘Kپjپi‚PژيپjپAپ@ڈ\•¶‘K“؛‰فپi‚PژيپjپAپ@
پ@پ@ژl•¶‘K“؛پE“S‰فپi‚QژيپjپAپ@ˆê•¶‘K“؛پE“S‰فپi‚Pژيپj پ@
پ@پ@ ‚ج‚R‚آ‚ة•ھ—ق‚³‚ê‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@—¼پE•ھپEژéپE•¶‹و•ھ‚ج•ھ—قپB
پœپ@چ]Œثژ‘م‚ج’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚ًپAپi‚Pپj—¼پA
پ@پ@پi‚Qپj•ھپAپi‚RپjژéپAپi‚Sپj•¶پi‚è‚ه‚¤پA‚شپA‚µ‚مپA‚à‚ٌپj
پ@پ@‚ة‚و‚èپA‚S‚آ‚ة•ھ—ق‚·‚éپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ج’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚حپAپ@ پi‚Pپjپ@
پ@پ@—¼’PˆتپE’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚جپAŒـ—¼”»پi‹àپj
پ@پ@پi‚PژيپjپAپ@ ˆê—¼ ڈ¬”»پi‹àپjپi‚P‚PژيپjپAپ@پi‚Qپjپ@•ھ’P
پ@پ@ˆتپE’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚جپAپ@“ٌ•ھ‹àپi‚RژيپjپAپ@
پ@پ@ ˆê•ھ‹àپi‚P‚PژيپjپAپ@ˆê•ھ‹âپi‚QژيپjپA پ@پi‚Rپjپ@ژé’P
پ@پ@ˆتپE’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚جپAپ@“ٌژé‹àپi‚RژيپjپAپ@
پ@پ@ ˆêژé‹àپi‚PژيپjپAپ@“ٌژé‹âپi‚RژيپjپA ˆêژé‹âپi‚PژيپjپAپ@
پi‚Sپjپ@‘K’PˆتپE’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚جپAپ@•S•¶
‘K“؛‰فپi= “V•غ‘Kپjپi‚PژيپjپAپ@ڈ\•¶‘K“؛‰فپi‚PژيپjپAپ@
ژl•¶‘K“؛پE“S‰فپi‚QژيپjپAپ@ˆê•¶‘K“؛پE“S‰فپi‚Pژيپjپ@
پ@پ@پ@‚ج‚S‚آ‚ة•ھ—ق‚³‚ê‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@‚P‚Rژي—ق‹و•ھ‚ج•ھ—قپB
پœپ@چ]Œثژ‘م‚ج’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚ًپAٹz–تپAچق
پ@پ@ژ؟“™‚ة‚و‚èپA‚P‚Rژي—ق‚ة•ھ—ق‚·‚éپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ج’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚حپAپ@Œـ—¼”»
پ@پ@پi‹àپjپi‚PژيپjپAپ@ ˆê—¼ ڈ¬”»پi‹àپjپi‚P‚PژيپjپAپ@“ٌ•ھ‹à
پ@پ@پi‚RژيپjپAپ@ ˆê•ھ‹àپi‚P‚PژيپjپAپ@“ٌژé‹àپi‚RژيپjپAپ@
پ@پ@ˆêژé‹àپi‚PژيپjپAپ@پ@ˆê•ھ‹âپi‚QژيپjپAپ@“ٌژé‹âپi‚RژيپjپA
پ@پ@ˆêژé‹âپi‚PژيپjپAپ@•S•¶‘K“؛‰فپi= “V•غ‘Kپjپi‚PژيپjپA
پ@پ@ڈ\•¶‘K“؛‰فپi‚PژيپjپAپ@ژl•¶‘K“؛پE“S‰فپi‚QژيپjپAپ@
پ@پ@ˆê•¶‘K“؛پE“S‰فپi‚Pژيپjپ@ ‚ج‚P‚Rژي—ق‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@چ]Œثژ‘مپi‚P‚U‚O‚R”Nپ`‚P‚W‚U‚W”Nپj‚ةپAپ@چ]Œث–‹•{
پ@پ@‚ة‚و‚è’’‘¢پi”چsپj‚³‚êپAپ@‘Sچ‘‚ة—¬’ت‚µپAژg—p‚³
پ@پ@‚ꂽ’èˆتپi’èٹzپjپE’تڈي‰ف•¼‚حپAپ@Œـ—¼”»پi‹àپjپi‚²
پ@پ@‚è‚ه‚¤‚خ‚ٌپi‚«‚ٌپjپjپi‚PژيپjپAپ@ ˆê—¼ ڈ¬”»پi‹àپjپi‚¢‚؟
پ@پ@‚è‚ه‚¤‚±‚خ‚ٌپi‚«‚ٌپjپjپi‚P‚PژيپjپAپ@“ٌ•ھ‹àپi‚ة‚ش‚«‚ٌپj
پ@پ@پi‚RژيپjپAپ@ ˆê•ھ‹àپi‚¢‚؟‚ش‚«‚ٌپjپi‚P‚PژيپjپAپ@پ@“ٌژé
پ@پ@‹àپi‚ة‚µ‚م‚«‚ٌپjپi‚RژيپjپAپ@ ˆêژé‹àپi‚¢‚ء‚µ‚م‚«‚ٌپj
پ@پ@پi‚PژيپjپAپ@پ@ˆê•ھ‹âپi‚¢‚؟‚ش‚¬‚ٌپjپi‚QژيپjپAپ@“ٌژé‹â
پ@پ@پi‚ة‚µ‚م‚¬‚ٌپjپi‚RژيپjپA پ@ˆêژé‹âپi‚¢‚ء‚µ‚م‚¬‚ٌپj
پ@پ@پi‚PژيپjپAپ@•S•¶‘K“؛‰فپi= “V•غ‘Kپjپi‚ذ‚ل‚‚à‚ٌ‚¹‚ٌ
پ@پ@‚ا‚¤‚©پi= ‚ؤ‚ٌ‚غ‚¤‚¹‚ٌپjپi‚PژيپjپAپ@پ@ڈ\•¶‘K“؛‰ف
پ@پ@پi‚¶‚م‚¤‚à‚ٌ‚¹‚ٌپjپi‚PژيپjپAپ@ژl•¶‘K“؛پE“S‰فپi‚و‚ٌ‚à
پ@پ@‚ٌ‚¹‚ٌ‚ا‚¤پE‚ؤ‚ء‚©پjپi‚QژيپjپAپ@ˆê•¶‘K“؛پE“S‰فپi‚¢
پ@پ@‚؟‚à‚ٌ‚¹‚ٌ‚ا‚¤پE‚ؤ‚ء‚©پjپi‚Pژيپjپ@‚ج‚P‚Rژي—ق‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ@
پôپôپ@ژé‹âپ@‚ھ“oڈê‚·‚éپA–ت”’‚پA‹»–،گ[
پ@‚¢پAƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپAƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[ پB
پ@
پڑپ@ژé‹âپ@‚ھ“oڈê‚·‚éپA–ت”’‚پA‹»–،گ[‚¢پA
پ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپB
پœپ@پi’چˆسپjپ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAپ@ƒtƒBƒNƒVƒ‡ƒ“پ@‚إ‚·پBپ@—ًپ@
پ@ژj‚جƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAپ@ژjژہپi—ًژjڈم‚جژ–ژہپjپ@‚ئپ@‰ث
پ@‹َ‚جڈo—ˆژ–پ@‚ھپ@چ¬‚¶‚ء‚ؤ•`‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپ@‚ـ‚½پAپ@
پ@Œ»‘م•—‚ةƒAƒŒƒ“ƒW‚µ‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚·پB
پ@
پ،پ@پwپ@—z‰ٹ‚ج’زپE‹ڈ–°‚è”ض‰¹پEچ]Œث‘oژ†پ@
پ@پ@پi ‚©‚°‚낤‚ج‚آ‚¶پE‚¢‚ث‚ق‚è‚¢‚ي‚ثپE‚¦‚ا‚¼‚¤‚µپjپ@پxپ@
پ@پ@پi‚m‚g‚jپE‚a‚rƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒhƒ‰ƒ}پA‘SŒv‚P‚P‰ٌپjپB
پ@پ@‘و‚Q‰ٌپ@پuپ@مJپ@پi‚«‚¸‚بپjپ@پv
پœپ@“ْ–{‚جچ]Œثژ‘م‚ً•`‚¢‚½پAƒhƒ‰ƒ}پB
پœپ@ژé‹â‚جپA“ىè`“ٌژé‹âپi‚ب‚ٌ‚è‚ه‚¤‚ة‚µ‚م‚¬‚ٌپj‚ھ“o
پ@ڈê‚·‚éپBپ@ڈ¬”»‚ئ“ىè`“ٌژé‹â‚جŒًٹ·”ن—¦پiڈ¬”»‚P–‡
پ@‚ئ“ٌژé‹â‚W–‡پj‚ً‚ك‚®‚èپA‘›“®‚ھ‹N‚«‚éپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ڈ¼‰؛‘؛ڈmپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚©‚»‚ٌ‚¶‚م‚پjپB
پ@
پ،پ@ڈ¼‰؛‘؛ڈmپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ڈ¼‰؛‘؛ڈmپ@پi‚µ‚ه‚¤‚©‚»‚ٌ‚¶‚م‚پjپB
پ@
پ@
پ،پ@ڈ¼‰؛‘؛ڈm‚حپAپ@”‹پi‚ح‚¬پAژRŒûŒ§”‹پj‚ة‚ ‚èپA
پ@پ@‚P‚W‚T‚V”N‚©‚ç‚P‚W‚T‚W”N ‚ـ‚إ‚جٹْٹش‚ةپA‹g“c
پ@پ@ڈ¼‰A‚ھچu‹`‚ًچs‚ء‚½پAژ„ڈm‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@‹g“c ڈ¼‰A‚جڈf•ƒپE‹ت–ط •¶”Vگiپ@پiگ¶–v”NپF
پ@پ@‚P‚W‚P‚Oپ`‚P‚W‚V‚U”Nپjپ@‚ھپAپ@‚P‚W‚S‚Q”N‚ةپAژ„ڈm
پ@پ@‚جڈ¼‰؛‘؛ڈmپ@پi‚P‚W‚S‚Q”Nپ`‚P‚W‚T‚W”NپA‚P‚W‚U‚X
پ@پ@”Nپ`‚P‚W‚V‚U”Nپjپ@‚ًٹJگف‚µپAپ@‚P‚W‚V‚U”Nپi–¾ژ،
پ@پ@‚X”Nپj‚ـ‚إ‰^‰c‚·‚éپBپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ،پ@‹g“c ڈ¼‰Aپ@پi‚و‚µ‚¾ ‚µ‚ه‚¤‚¢‚ٌپA•ت–¼پF‹g“c
پ@پ@“ذژںکYپAگ¶–v”NپF‚P‚W‚R‚Oپ`‚P‚W‚T‚X”Nپjپ@‚حپA
پ@پ@‚P‚W‚T‚V”N‚©‚ç‚P‚W‚T‚W”N‚ـ‚إ‚جٹْٹش‚ةپAڈ¼‰؛
پ@پ@‘؛ڈmپi‚µ‚ه‚¤‚©‚»‚ٌ‚¶‚م‚پj ‚إچu‹`‚ًچs‚¢پA‘½
پ@پ@‚‚ج‹ك‘م“ْ–{‚جƒٹپ[ƒ_پ[‚جگlچق‚ًˆçگ¬‚µ‚½پB
پ@
پ،پ@ڈ¼‰؛‘؛ڈmپ@پi‚µ‚ه‚¤‚©‚»‚ٌ‚¶‚م‚ پj‚حپAپ@’·ڈB
پ@پ@”ث‚ج’·–هچ‘پi‚ب‚ھ‚ئ‚ج‚‚ةپj‚ج”‹پi‚ح‚¬پAژRŒû
پ@پ@Œ§”‹پj‚ة‚ ‚èپAپ@–‹––‚ةپA‚P‚W‚T‚V”N‚©‚ç‚P‚W‚T‚W
پ@پ@”N‚ـ‚إ‚جٹْٹش‚ةپA‹g“c ڈ¼‰A‚ھچu‹`‚ً‚µ‚½ پA
پ@پ@ژ„ڈmپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@‹g“c ڈ¼‰A‚ھپA‚P‚W‚T‚V”N‚©‚ç‚P‚W‚T‚W”N ‚ـ
پ@پ@‚إ‚جٹْٹش‚ةپAڈf•ƒپE‹ت–ط •¶”Vگi‚ھٹJ‚¢‚ؤ‚¢
پ@پ@‚½ڈ¼‰؛‘؛ڈm‚إپAچu‹`‚ًچs‚ء‚½پBپ@‚P‚W‚T‚W”N‚P‚P
پ@پ@Œژ‚ةˆê’U•آچ½‚³‚ꂽپB
پ@پ@پ@پ@پ@‹g“c ڈ¼‰A‚حپAڈmگ¶پi–ه‰؛گ¶پj‚ةپAژژ––â
پ@پ@‘èپA‘¸µپi‚»‚ٌ‚¶‚ه‚¤پA‘¸چcµˆخپjژv‘z‚ب‚ا‚ً‹³
پ@پ@‚¦پAپ@‘½‚‚ج–¾ژ،ˆغگV‚جژuژm‚ًڈo‚µ‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@‹ت–ط •¶”Vگiپ@پi‚½‚ـ‚« ‚ش‚ٌ‚ج‚µ‚ٌپj‚حپA‹g“c
پ@پ@ڈ¼‰A‚جڈf•ƒپi‚¨‚¶پj‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‹ت–ط •¶”Vگi‚حپAپ@ڈ¼‰؛‘؛ڈmپi‚µ‚ه‚¤‚©‚»‚ٌ‚¶
پ@پ@‚م‚پA‚P‚W‚S‚Q”Nپ`‚P‚W‚T‚W”NپA‚P‚W‚U‚X”Nپ`‚P‚W
پ@پ@‚V‚U”Nپj‚جٹJگفژز‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‹ت–ط •¶”Vگi‚حپA‚P‚W‚S‚Q”N‚ةپAژ„ڈm‚جڈ¼‰؛
پ@پ@‘؛ڈm‚ًٹJگف‚·‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@‹ت–ط •¶”Vگi‚حپAپ@ڈ¼‰؛‘؛ڈm‚ً‚P‚W‚T‚W”N‚ة
پ@پ@ˆê’U•آچ½‚·‚é‚ھپA‚P‚W‚U‚X”Nپi–¾ژ،‚Q”Nپj‚ةچؤ
پ@پ@ٹJ‚µپA‚P‚W‚V‚U”Nپi–¾ژ،‚X”Nپj‚ـ‚إ‘±‚¯‚½پB
پœپ@‚P‚W‚T‚V”N‚©‚ç‚P‚W‚T‚W”N‚ـ‚إپA‹g“cڈ¼‰A‚حپAڈf
پ@پ@•ƒپE‹ت–ط •¶”Vگi‚ھٹJ‚¢‚ؤ‚¢‚½ڈ¼‰؛‘؛ڈm‚إچu
پ@پ@‹`‚ًچs‚¢پA‘½‚‚جگlچق‚ًˆç‚ؤ‚éپB
پ@
پ،پ@‹g“c ڈ¼‰A‚حپAپ@’·ڈB”ث‚إپAپ@”ثچZپE–¾—دٹظپi‚ح
پ@پ@‚ٌ‚±‚¤پE‚ك‚¢‚è‚ٌ‚©‚ٌپj‚ة‚ؤ•؛ٹwژt”ح‚ئ‚µ‚ؤچu
پ@پ@‹`‚ًچs‚¢پAپ@Œم‚ةپAژ„ڈmپEڈ¼‰؛ ‘؛ڈm‚إچu‹`‚ًچs
پ@پ@‚ء‚½پB
پœپ@Œjڈ¬ŒـکYپ@پi‚©‚آ‚炱‚²‚낤پA–طŒثچFˆٍپi‚«‚ا
پ@پ@‚½‚©‚و‚µپjپj‚حپAپ@”ثچZ–¾—دٹظ‚إپA‚P‚W‚S‚X”N‚ةپA
پ@پ@‹g“c ڈ¼‰A‚ج‹³‚¦پi•؛ٹw‚ب‚اپj‚ًژَ‚¯‚éپB
پœپ@ڈGچث‚ج‹vچâŒ؛گگپ@پi‚‚³‚©‚°‚ٌ‚¸‚¢پjپAپ@چ‚گ™
پ@پ@گWچىپ@پi‚½‚©‚·‚¬‚µ‚ٌ‚³‚پjپAپ@ˆة“،”ژ•¶پ@پi‚¢
پ@پ@‚ئ‚¤‚ذ‚ë‚ش‚فپjپAپ@ژRŒ§—L•üپ@پi‚â‚ـ‚ھ‚½‚ ‚è‚ئ
پ@پ@‚àپjپA•iگى–ي“ٌکYپ@‚ب‚ا‚حپA‚P‚W‚T‚V”N‚©‚ç‚P‚W‚T
پ@پ@‚W”N‚ـ‚إ‚جٹْٹش‚ةپAپ@ڈ¼‰؛‘؛ڈm‚ج–ه‰؛گ¶پiڈm
پ@پ@گ¶پj‚ئ‚µ‚ؤپAپ@‹g“c ڈ¼‰A‚ج‹³‚¦‚ًژَ‚¯‚½پB
پœپ@‹g“c ڈ¼‰A‚حپAپ@‹³ژِ‚جٹْٹش‚ح’Z‚©‚©‚ء‚½‚ھپAپ@
پ@پ@‘½‚‚ج‹ك‘م“ْ–{‚جƒٹپ[ƒ_پ[‚جگlچق‚ًˆçگ¬‚µ‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@‹g“c ڈ¼‰A‚ج‹³‚¦‚ًژَ‚¯‚½گl•¨‚ة‚حپAپ@Œjڈ¬
پ@پ@ŒـکYپ@پi–طŒثچFˆٍپA–¾ژ،گVگ •{ژٌ”]‚ج‚PگlپjپA
پ@پ@ڈGچث‚ج‹vچâŒ؛گگپAپ@چ‚گ™گWچىپ@پi–‹––‚ج’·ڈB
پ@پ@”ث‚جƒٹپ[ƒ_پ[‚ج‚PگlپjپAپ@ˆة“،”ژ•¶پAژRŒ§—L•üپ@
پ@پ@پi–¾ژ،ٹْ‚جژٌ”]پA“àٹt‘چ—‘هگbپjپAپ@•iگى–ي
پ@پ@“ٌکYپ@پi‚µ‚ب‚ھ‚ي‚₶‚낤پA–¾ژ،ٹْ‚ج“à–±‘هگbپjپ@
پ@پ@‚ب‚ا‚ھ‚¢‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ،پ@‹g“c ڈ¼‰A‚حپAپ@’·ڈB”ث”ثژm‚إپAپ@–‹––‚ج•؛ٹw
پ@پ@ژزپAژv‘z‰ئپA‹³ˆçژز‚إ‚ ‚èپAپ@–‹––ژuژm‚إ‚ ‚ء
پ@پ@‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@‹g“c ڈ¼‰Aپ@پi‚و‚µ‚¾ ‚µ‚ه‚¤‚¢‚ٌپj‚حپA’·ڈB”ث
پ@پ@”ثژm‚إپAپ@’·ڈB”ث‚ج•؛ٹwژt”ح‚إ‚ ‚èپAچs“®”h
پ@پ@‚جٹwژز‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@
پ،پ@‹g“c ڈ¼‰Aپ@پi‚و‚µ‚¾ ‚µ‚ه‚¤‚¢‚ٌپjپ@‚حپAپ@–‹––
پ@پ@‚جژv‘z‰ئپA‹³ˆçژزپAژuژmپ@‚إپAپ@”‹‚ج ژ„ڈmپEڈ¼
پ@پ@‰؛‘؛ڈmپi‚µ‚ه‚¤‚©‚»‚ٌ‚¶‚م‚پA‚P‚W‚T‚V”Nپ`‚T‚W”Nپj
پ@پ@‚إپAپ@ژژ––â‘èپA‘¸µپi‚»‚ٌ‚¶‚ه‚¤‘¸چcµˆخپjژv
پ@پ@‘z‚ب‚ا‚ً‹³‚¦‚½پBپ@
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@ ‹g“c ڈ¼‰Aپ@پi‚و‚µ‚¾‚µ‚ه‚¤‚¢‚ٌپAگ™ “ذ”Vڈ•پi‚·
پ@پ@‚¬ ‚ئ‚ç‚ج‚·‚¯پA—c–¼پjپA‹g“c‰ئ‚ة—{ژqŒمپE‹g“c
“ذژںکYپi‚و‚µ‚¾ ‚ئ‚炶‚낤پA’تڈج‚ح“ذژںکYپAوپ
پ@پ@پi‚¢‚ف‚بپj‚ح‹é•ûپi‚ج‚è‚©‚½پjپAچ†پi‚²‚¤پj‚حڈ¼‰AپA
پ@پ@گ¶–v”NپF‚P‚W‚R‚Oپ|‚T‚X”Nپjپ@‚حپAپ@’·ڈB”ثژmپEگ™
پ@پ@•Sچ‡”Vڈ•پi‚·‚¬ ‚ن‚è‚ج‚·‚¯پAڈي“¹پi‚آ‚ث‚ف‚؟پjپA
پ@پ@گ¶–v”NپF‚P‚W‚O‚Sپ|‚U‚T”Nپjپj ‚جژں’j‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚W‚R‚S”N‚ةپA ‹g“c ڈ¼‰Aپ@پiگ™ “ذژںکYپi‹é
پ@پ@•ûپjپj‚حپAپ@ڈf•ƒپi‚¨‚¶پj‚جژRژ—¬•؛ٹwژt”ح‚ج‹g
پ@پ@“c‘هڈ•‚ج—{ژq‚ئ‚ب‚èپAˆبŒمپA‹g“c“ذژںکY‚ئڈج
پ@پ@‚·پB پ@‚P‚W‚R‚T”N‚ةپA‹g“c‘هڈ•‚ھژ€‹ژ‚µ‚½‚½‚كپAپ@
پ@پ@•ت‚جڈf•ƒ‚ج‹ت–ط•¶”Vگi‚جژ„ڈmپEڈ¼‰؛‘؛ڈm‚إ
پ@پ@ژw“±‚ًژَ‚¯‚½پB
پ@
پ،پ@µژو ”üکaژqپi‚©‚ئ‚è ‚ف‚ي‚±پA‹Œگ©پEگ™ •¶پi‚·
پ@پ@‚¬ ‚س‚فپjپA‚P‚W‚S‚Rپ|‚P‚X‚Q‚P”Nپj پ@‚حپAپ@–‹––‚ج
پ@پ@ژv‘z‰ئپE ‹g“c ڈ¼‰Aپ@‚ج–…پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@µژو ”üکaژq‚ج•ت–¼‚حپAپ@•¶پi‚س‚فپj‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@µژو ”üکaژqپiگ™ •¶پj‚حپA ’·ڈB”ثژmپEگ™ •S
چ‡”Vڈ•‚جژlڈ—‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@
پ،پ@‹g“c ڈ¼‰A‚حپAپ@چ²‹vٹشڈغژRپ@پi‚³‚‚ـ‚µ‚ه‚¤‚´
پ@پ@‚ٌپj‚ةٹw‚رپAپ@‚P‚W‚T‚S”N‚ةƒyƒٹپ[—ˆچq‚ة“–‚½‚èپA
پ@پ@‰؛“c‚©‚çٹCٹO“nچq‚ًٹé‚ؤ‚ؤژ¸”s‚µ‘ك•ك‚³‚êپA
پ@پ@’·ڈB”ث‚ج–ىژRچ–‚ة—Hژْپi“ٹچ–پj‚³‚êپA‚P‚W‚T‚T”N
پ@پ@‚ةڈoچ–‚µ‚½پB
پ@پ@پ@پ@‚»‚جŒمپA‹g“c ڈ¼‰A‚حپA‚P‚W‚T‚Vپ`‚T‚W”N‚ةپA
پ@پ@‹½—¢‚ج”‹ پi‚ح‚¬پA’·–هچ‘پiژRŒûŒ§پj”‹پj‚جڈ¼‰؛
پ@پ@‘؛ڈm‚إچu‹`‚ًچs‚¢پAڈmگ¶پi–ه‰؛گ¶پj‚©‚瑽‚‚ج
پ@پ@–‹––ژuژm‚ًگ¶‚قپBپ@‚P‚W‚T‚W”N‚ةپAکV’†ˆأژE‚ً
پ@پ@ٹé‚ؤپAچؤ‚رپA’·ڈB”ث‚ج–ىژRچ–‚ة—Hژْپi“ٹچ–پj‚³
پ@پ@‚êپAپ@‚P‚W‚T‚X”N‚ةپAˆہگ‚ج‘هچ–‚إپAچ]Œث‚ة‘—‚ç
پ@پ@‚êپAŒY ژ€‚µ‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@ˆہگ‚ج‘هچ–‚إپAپ@چ]Œث–‹•{‘هکVپEˆنˆة’¼•J
پ@پ@پi‚¢‚¢‚ب‚¨‚·‚¯پj‚ج–½پi‚ك‚¢پA–½—كپj‚إپA‚P‚W‚T‚X
پ@پ@”N‚ةپA‹g“c ڈ¼‰A‚حپAڈˆŒY‚³‚ê‚éپB
پ@
پ@
پôپôپ@ڈ¼‰؛‘؛ڈm‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[ ‚¢پA
پ@پ@ƒhƒLƒ…ƒپƒ^ƒ“ƒٹپ[پAƒhƒ‰ƒ}پA ‰f‰وپB
پ@
پڑپ@ڈ¼‰؛‘؛ڈm ‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢پA
پ@پ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپB
پœپ@پi’چˆسپjپ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAپ@ƒtƒBƒNƒVƒ‡ƒ“پ@‚إ‚·پBپ@
پ@پ@پ@—ًژj‚جƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAپ@ژjژہپi—ًژjڈم‚جژ–
پ@پ@پ@ژہپjپ@‚ئپ@‰ث‹َ‚جڈo—ˆژ–پ@‚ھپ@چ¬‚¶‚ء‚ؤ•`‚©‚ê
پ@پ@پ@‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپ@‚ـ‚½پAپ@Œ»‘م•—‚ةƒAƒŒƒ“ƒW‚µ‚ؤ‚
پ@پ@پ@‚è‚ـ‚·پB
پ@
پ،پ@پwپ@‰ش”R‚نپ@پi‚ح‚ب‚à‚نپjپ@پxپ@
پ@پ@پ@پi“ْ–{‚ج‚m‚g‚j‚Q‚O‚P‚T”N‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پjپB
پ،پ@“ْ–{‚ج–¾ژ،ˆغگVپA–‹––پA–¾ژ،ژ‘م‚جژ‘م
پ@پ@ڈَ‹µ‚â‚»‚جژ‘م‚ةٹˆ–ô‚µ‚½گlپX‚ً•`‚پB
پ،پ@‹g“cڈ¼‰A‚ج–…پE•¶پi‚س‚فپj‚جگ¶ٹU‚ً•`‚پB
پ@
پœپ@‹ت–ط •¶”Vگi‚ً‰‰‚¶‚é”o—D پFپ@ پ@
پ@پ@ ‰œ“c ‰l“ٌپ@پi‚¨‚‚¾ ‚¦‚¢‚¶پjپB
پ@پ@ ‹ت–ط •¶”Vگiپ@پi‚½‚ـ‚« ‚ش‚ٌ‚ج‚µ‚ٌپj‚حپA
گ™•¶پi‚·‚¬‚س‚فپj‚â‹g“c ڈ¼‰Aپ@پi‚و‚µ‚¾ ‚µ
پ@پ@ ‚ه‚¤‚¢‚ٌپj‚جڈf•ƒپi‚¨‚¶پj‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‹g“c ڈ¼‰Aپi‹g“c “ذژںکYپj‚ً‰‰‚¶‚é”o—D پFپ@ پ@
پ@پ@ ˆةگ¨’J —F‰îپ@پi‚¢‚¹‚â ‚ن‚¤‚·‚¯پjپB
پ@پ@ ‹g“c ڈ¼‰Aپ@پi‚و‚µ‚¾ ‚µ‚ه‚¤‚¢‚ٌپAگ™ “ذ”V
پ@پ@ڈ•پi‚·‚¬ ‚ئ‚ç‚ج‚·‚¯پjپA‹g“c “ذژںکYپi‚و‚µ
پ@پ@‚¾‚ئ‚炶‚낤پjپjپ@‚حپA•¶پi‚س‚فپj‚جژہŒZ‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@
پœپ@•¶‚ً‰‰‚¶‚éڈ——D پFپ@
ˆنڈم گ^‰›پ@پi‚¢‚ج‚¤‚¦ ‚ـ‚¨پjپB
•¶پ@پi‚س‚فپAگ™ •¶پi‚·‚¬ ‚س‚فپjپAگ™ ”üکa
پ@پ@پi‚·‚¬ ‚ف‚يپjپAµژو ”üکaژqپi‚©‚ئ‚è‚ف‚ي‚±پjپjپ@
پ@پ@‚حپAپ@‹g“cڈ¼‰A‚ج–…‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@“ꕶŒnپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚à‚ٌ‚¯‚¢پjپBپ@
پ@
پ،پ@“ꕶŒnپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@“ꕶŒnپ@پi‚¶‚ه‚¤‚à‚ٌ‚¯‚¢پjپBپ@
پ،پ@‰p–¼پ@پFپ@‚s‚g‚dپ@‚i‚n‚l‚n‚m‚j‚d‚hپ@‚o‚d‚n‚o‚k‚dپD
پ،پ@“ْ–{گl‚جƒ‹پ[ƒc‚ةٹض‚µ‚ؤ‚حپAپu“ْ–{گlپvپi“ْ–{گl‚ج
پ@پ@ƒ‹پ[ƒcپjپAپuŒ´“ْ–{گlپvپAپu“ْ–{گlƒ‹پ[ƒcپEƒKƒCƒhƒuƒb
پ@پ@ƒNپv‚àژQڈئ‚µ ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“Tپ@‚T‚P‚O‚P‚RپB
پ@
پ پ@“ꕶŒnپi “ْ–{ڈيڈZ–¯پj‚جٹwڈp•ھ—ق•\پBپ@پ@
پ پ@“ꕶŒn‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[ ‚¢پA ƒhƒL
پ@پ@ ƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پAƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپB
پ@
پ@
پ،پ@“ꕶŒnپ@پi‚¶‚ه‚¤‚à‚ٌ‚¯‚¢پjپ@‚جگlپX‚حپAپ@پu“ꕶ
پ@پ@گlپv‚ئ‚»‚جژq‘·‚إ‚ ‚èپAپ@Œأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپA“ى•ûƒ‚
پ@پ@ƒ“ƒSƒچƒCƒh‚جگlپX‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@“ꕶŒn‚جگlپX‚حپAپ@“ْ–{‚ج“ꕶژ‘م‚ج“ꕶگl
پ@پ@‚ئ‚»‚جژq‘·پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{‚ج“ꕶژ‘م‚إ‚حپAپ@“ꕶŒn‚جگlپX‚حپAپ@
پ@پ@پu“ꕶگlپv‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{‚ج–يگ¶ژ‘م‚إ‚حپAپ@“ꕶŒn‚جگlپX‚حپAپ@
پ@پ@پu“ꕶŒnپiچف—ˆŒnپj–يگ¶گlپvپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@Œأ‘م“ْ–{پiŒأ•پ`•½ˆہژ‘مپj‚إ‚حپAپ@“ꕶ
پ@پ@Œn‚جگlپX‚حپAپ@پu“ꕶŒnپiچف—ˆŒnپjŒأ‘م“ْ–{گlپv
پ@پ@‚إ‚ ‚èپAپ@پu“ꕶپE–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒnŒأ‘م“ْ–{گlپvپ@
پ@پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@’†گ¢“ْ–{‚©‚猻‘م“ْ–{پiٹ™‘qپ`•½گ¬ژ‘مپj
پ@پ@‚ـ‚إ‚جژٹْ‚إ‚حپAپ@“ꕶŒn‚جگlپX‚حپAپ@“ꕶپE–ي
پ@پ@گ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒn‚جپAپu–{“y“ْ–{گlپv‚âپu—®‹…گlپvپ@
پ@پ@‚ئپAپ@“ꕶŒn‚جپAپuƒAƒCƒkگlپvپ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ،پ@“ْ–{گlپi“ْ–{ڈيڈZ–¯پj‚ض‚جگi‰»•\پB
پ@پ@‰ژگlپثپ@
پ@پ@Œ´گlپi= ƒzƒ‚پEƒGƒŒƒNƒgƒX—قپjپث
پ@پ@‹Œگlپi= ‘Oƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒX—قپjپثپ@
پ@پ@Œ»گ¶گl—قپi= گVگlپAƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒXپjپثپ@
پ@پ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپثپ@
پ@پ@“ꕶگlپثپ@
پ@پ@–يگ¶گlپثپ@
پ@پ@Œأ‘م“ْ–{گlپثپ@
پ@پ@پu–{“y“ْ–{گlپvپi= –{“yگlپjپAپu—®‹…گlپvپA
پ@پ@پuƒAƒCƒkگlپvپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“dژqڈ‘گذپB
پ@
پ،پ@Œ»‘م“ْ–{گlپi“ْ–{ڈيڈZ–¯پj‚ض‚جگi‰»•\پB
پ@پ@‰ژگlپثپ@
پ@پ@Œ´گlپi= ƒzƒ‚پEƒGƒŒƒNƒgƒX—قپjپث
پ@پ@‹Œگlپi= ‘Oƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒX—قپjپثپ@
پ@پ@Œ»گ¶گl—قپi= گVگlپAƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒXپjپثپ@
پ@پ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپثپ@
پ@پ@“ꕶگlپثپ@
پ@پ@–يگ¶گlپثپ@
پ@پ@Œأ‘م“ْ–{گlپثپ@
پ@پ@’†گ¢“ْ–{گlپثپ@
پ@پ@‹كگ¢“ْ–{گlپثپ@
پ@پ@‹ك‘م“ْ–{گlپث
پ@پ@Œ»‘م“ْ–{گlپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“dژqڈ‘گذپB
پ@
پ،پ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh‚ض‚جگi‰»•\پB
پ@پ@‰ژگlپثپ@
پ@پ@Œ´گlپi= ƒzƒ‚پEƒGƒŒƒNƒgƒX—قپjپث
پ@پ@‹Œگlپi= ‘Oƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒX—قپjپثپ@
پ@پ@Œ»گ¶گl—قپi= گVگlپAƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒXپjپثپ@
پ@پ@Œأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒC ƒhپi= “ى•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپjپث
گVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپi= –k•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپjپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@Œأگl—قٹwژ«“TپB
پ@
پ@
#thejomonkeipeople-theclassificationtable
پ@
پ،پ@“ꕶŒn‚جٹwڈp•ھ—ق•\ پBپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پiڈعچ×ڈمˆت•ھ—قپAڈمˆتڈٹ‘®‚ج•ھ—قپA“ْ–{
پ@پ@پ@پ@ Œê–¼پEٹw–¼پE‰pŒê–¼‘خڈئپjپB
پ›پ@‚s‚g‚dپ@‚r‚b‚h‚d‚m‚s‚h‚e‚h‚bپ@‚b‚k‚`‚r‚r‚h‚e‚h‚b‚`‚s‚h‚n‚mپ@
پ@پ@‚s‚`‚a‚k‚dپ@‚n‚eپ@‚s‚g‚dپ@‚i‚n‚l‚n‚m‚j‚d‚h
‚o‚d‚n‚o‚k‚dپD
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“T ‚V‚P‚T‚Q‚TپB
پ@
پ،پ@“ꕶŒn‚جگlپXپiگl—قپjپB
پ@ پi‰pŒê–¼پF ‚s‚g‚dپ@‚i‚n‚l‚n‚m‚j‚d‚hپ@‚o‚d‚n‚o‚k‚dپjپB
پ@
پ،پ@’n‹…گ¶•¨پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@‚k‚h‚e‚dپ@‚n‚mپ@‚d‚`‚q‚s‚gپB
پثپ@گ^ٹjگ¶•¨پBپ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پiƒhƒپƒCƒ“پFپ@گ^ٹjگ¶•¨ˆوپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚c‚ڈ‚چ‚پ‚‰‚ژپ@‚d‚•‚‹‚پ‚’‚™‚ڈ‚”‚پپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‰p–¼پF ‚d‚t‚j‚`‚q‚x‚n‚s‚dپi‚rپjپjپB
پثپ@“®•¨پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپ@ٹEپ@پFپ@“®•¨ٹEپ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚j‚‰‚ژ‚‡‚„‚ڈ‚چپ@‚`‚ژ‚‰‚چ‚پ‚Œ‚‰‚پپjپ@
پ@پ@ پi‰p–¼پF‚`‚m‚h‚l‚`‚k پi‚rپjپjپB
پثپ@گزچُپi‚¹‚«‚³‚پj“®•¨پBپ@پiپ@–هپ@پFپ@گزچُ“®•¨–ه پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚o‚ˆ‚™‚Œ‚•‚چپ@‚b‚ˆ‚ڈ‚’‚„‚پ‚”‚پپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ پi‰p–¼پF‚b‚g‚n‚q‚c‚`‚s‚d پi‚rپjپjپB
پثپ@گز’إپi‚¹‚«‚آ‚¢پj“®•¨پB پiˆں–ه پFپ@گز’إ“®•¨ˆں–هپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚r‚•‚‚‚گ‚ˆ‚™‚Œ‚•‚چپ@‚u‚…‚’‚”‚…‚‚‚’‚پ‚”‚پپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‰p–¼پF‚u‚d‚q‚s‚d‚a‚q‚`‚s‚dپi‚rپjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’ک “ْ–{ژj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ«“TپB
پثپ@—Lٹ{پi‚ن‚¤‚ھ‚پj“®•¨پ@ پi‰؛–ه پFپ@—Lٹ{“®•¨‰؛–هپ@
پ@پ@پiٹ{Œû—قپA—Lٹ{—قپjپBپ@پ@ ‚h‚ژ‚†‚’‚پ‚گ‚ˆ‚™‚Œ‚•‚چ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚f‚ژ‚پ‚”‚ˆ‚ڈ‚“‚”‚ڈ‚چ‚پ‚”‚پپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‰p–¼پFپ@‚u‚d‚q‚s‚d‚a‚q‚`‚s‚d پi‚rپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚v‚h‚s‚gپ@‚i‚`‚vپjپB
پثپ@ژlژˆپi‚µ‚µپj“®•¨پBپ@پ@پ@ پiڈمچj پFپ@ژlژˆ“®•¨ڈمچjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚r‚•‚گ‚…‚’‚ƒ‚Œ‚پ‚“‚“پ@‚s‚…‚”‚’‚پ‚گ‚ڈ‚„‚پ پjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‰p–¼پF‚s‚d‚s‚q‚`‚o‚n‚c پi‚rپjپjپBپ@پ@
پثپ@—L—r–Œ—قپBپ@پ@ پ@پ@پ@پ@ پiƒ‰ƒ“ƒNپiٹK‹‰پj‚ب‚µپ@پ@پ@
پ@ پi‚ن‚¤‚و‚¤‚ـ‚‚é‚¢پjپ@پ@پ@پ@ ‚`‚چ‚ژ‚‰‚ڈ‚”‚پپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‰p–¼پF‚`‚l‚m‚h‚n‚s‚d پi‚rپjپjپBپ@ پ@
پثپ@ڑM“û—قپBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپ@ چj پFپ@ڑM“ûچj پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ ‚b‚Œ‚پ‚“‚“پ@‚l‚پ‚چ‚چ‚پ‚Œ‚‰‚پپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‰p–¼پF‚l‚`‚l‚l‚`‚kپi‚rپjپjپB
پثپ@ڈb—قپBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiˆںچj پFپ@ڈbˆںچj پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚r‚•‚‚‚ƒ‚Œ‚پ‚“‚“پ@‚s‚ˆ‚…‚’‚‰‚پپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‰p–¼پF‚s‚g‚d‚q‚h‚`‚mپi‚rپjپjپB
پثپ@گ^ڈb—قپ@پiگ³ڈb—قپjپ@پ@ پi‰؛چj پFپ@گ^ڈb‰؛چjپiگ³ڈb‰؛چjپjپ@پ@
پ@پ@پi—L‘ظ”ص—قپA—L‘ظ”صپ@پ@پ@ پ@‚h‚ژ‚†‚’‚پ‚ƒ‚Œ‚پ‚“‚“پ@‚d‚•‚”‚ˆ‚…‚’‚‰‚پپjپ@ پ@پ@پ@پ@پ@ پ@
پ@پ@ڑMپi‚ظپj“û—قپjپBپ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‰p–¼پF‚d‚t‚s‚g‚d‚q‚h‚`‚mپi‚rپjپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‰p–¼پF‚o‚k‚`‚b‚d‚m‚s‚`‚kپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚l‚`‚l‚l‚`‚kپi‚rپjپj پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’ک “ْ–{ژj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ«“TپB
پثپ@—ى’·—قپBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپ@–ع پFپ@—ى’·–عپiƒTƒ‹–عپj پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ ‚n‚’‚„‚…‚’پ@‚o‚’‚‰‚چ‚پ‚”‚…‚“پjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‰p–¼پF‚o‚q‚h‚l‚`‚s‚dپi‚rپjپjپB
پ@
پثپ@’¼•@‰ژ—قپ@پiگV•ھ—ق–@پjپBپiˆں–ع پFپ@’¼•@‰ژˆں–عپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚r‚•‚‚‚ڈ‚’‚„‚…‚’پ@‚g‚پ‚گ‚Œ‚ڈ‚’‚’‚ˆ‚‰‚ژ‚‰پjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‰p–¼پF‚g‚`‚o‚k‚n‚q‚q‚g‚h‚m‚dپi‚rپjپjپB
پ@پ@ گ^‰ژ—قپ@پ@ پiگV•ھ—ق–@پjپBپi‰؛–ع پFپ@گ^‰ژ‰؛–عپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚h‚ژ‚†‚’‚پ‚ڈ‚’‚„‚…‚’پ@‚r‚‰‚چ‚‰‚‰‚†‚ڈ‚’‚چ‚…‚“پjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‰p–¼پF ‚r‚h‚l‚h‚`‚mپi‚rپjپjپB
پ@پ@ ‹·•@‰ژ—قپ@پiگV•ھ—ق–@پjپBپiڈ¬–ع پFپ@‹·•@ڈ¬–عپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚o‚پ‚’‚–‚ڈ‚’‚„‚…‚’پ@‚b‚پ‚”‚پ‚’‚’‚ˆ‚‰‚ژ‚‰ پjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‰p–¼پF ‚b‚`‚s‚`‚q‚q‚g‚h‚m‚dپi‚rپjپjپB
پ@‚ـ‚½‚حپA
پ@پ@ گ^‰ژ—قپ@پ@ پi‹Œ•ھ—ق–@پjپBپiˆں–ع پFپ@گ^‰ژˆں–ع پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚r‚•‚‚‚ڈ‚’‚„‚…‚’پ@‚r‚‰‚چ‚‰‚‰‚†‚ڈ‚’‚چ‚…‚“پjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‰p–¼پF ‚r‚h‚l‚h‚`‚mپi‚rپjپjپB
پ@ ‹·•@‰ژ—قپ@پi‹Œ•ھ—ق–@پj پBپi‰؛–ع پFپ@‹·•@‰؛–ع پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚h‚ژ‚†‚’‚پ‚ڈ‚’‚„‚…‚’پ@‚b‚پ‚”‚پ‚’‚’‚ˆ‚‰‚ژ‚‰پjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‰p–¼پF ‚b‚`‚s‚`‚q‚q‚g‚h‚m‚dپi‚rپjپjپB
پثپ@ƒzƒ~ƒmƒCƒh پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiڈم‰ب پFپ@ƒqƒgڈم‰بپ@ پ@
پ@پ@پi—قگl‰ژ‚ئگl—قپjپBپ@پ@پ@پ@پ@ پ@‚r‚•‚گ‚…‚’‚†‚پ‚چ‚‰‚Œ‚™پ@‚g‚ڈ‚چ‚‰‚ژ‚ڈ‚‰‚„‚…‚پپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ پ@پi‰p–¼پF ‚g‚n‚l‚h‚m‚n‚h‚cپi‚rپjپjپB
پثپ@‘هŒ^—قگl‰ژ‚ئگl—قپ@پ@پ@ پiپ@‰بپ@پFپ@ƒqƒg‰بپ@پ@پ@ پ@
پ@پiƒIƒ‰ƒ“ƒEپ[ƒ^ƒ“پAƒSƒٹƒ‰پA پ@پ@‚e‚پ‚چ‚‰‚Œ‚™پ@‚g‚ڈ‚چ‚‰‚ژ‚‰‚„‚پ‚…پjپ@ پ@پ@پ@پ@
پ@ƒ`ƒ“ƒpƒ“ƒWپ[‚ئگl—قپjپBپ@پ@پ@پ@پi‰p–¼پF ‚m‚n‚m‚g‚t‚l‚`‚mپ@‚f‚q‚d‚`‚sپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@‚`‚o‚dپi‚rپjپ@‚`‚m‚cپ@‚g‚t‚l‚`‚mپi‚rپjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’ک “ْ–{ژjژ«“TپB
پثپ@ƒSƒٹƒ‰‚ئƒ`ƒ“ƒpƒ“ƒWپ@پ@پ@پiˆں‰ب پFپ@ƒqƒgˆں‰بپ@پ@پ@
پ@پ@پ[‚ئگl—قپBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚r‚•‚‚‚†‚پ‚چ‚‰‚Œ‚™پ@‚g‚ڈ‚چ‚‰‚ژ‚‰‚ژ‚پ‚…پjپ@ پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‰p–¼پF ‚g‚n‚l‚h‚m‚h‚m‚dپi‚rپjپjپB
پثپ@ƒ`ƒ“ƒpƒ“ƒWپ[‚ئگl—قپBپ@پiپ@‘°پ@پFپ@ ƒqƒg‘°پ@پ@پ@ پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚s‚’‚‰‚‚‚…پ@‚g‚ڈ‚چ‚‰‚ژ‚‰‚ژ‚‰پjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‰p–¼ پF‚g‚n‚l‚h‚m‚h‚mپi‚rپjپjپB
پثپ@گl—قپBپ@پ@پ@ پ@پ@پiˆں‘° پFپ@ƒqƒgˆں‘°پ@پ@ پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚r‚•‚‚‚”‚’‚‰‚‚‚…پ@‚g‚ڈ‚چ‚‰‚ژ‚‰‚ژ‚پپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‰p–¼پFپ@‚g‚t‚l‚`‚mپi‚rپjپjپBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پثپ@ƒqƒg‘®پi= ƒzƒ‚‘®پj پ@پ@پ@پi ‘® پFپ@ƒqƒg‘®پi= ƒzƒ‚‘®پjپ@پ@ پ@پ@ پ@
پ@پ@‚جگl—قپBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚f‚…‚ژ‚•‚“پ@‚g‚ڈ‚چ‚ڈپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‰p–¼پFپ@‚g‚t‚l‚`‚mپi‚rپj ‚n‚eپ@ پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚f‚d‚m‚t‚rپ@‚g‚n‚l‚nپjپBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پثپ@ƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒX پ@پiپ@ژي پF ƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒXژيپ@ پ@پ@
پ@پi= Œ»گ¶گl—قپAگVگlپjپBپ@پ@پ@ ‚r‚گ‚…‚ƒ‚‰‚…‚“پ@‚g‚ڈ‚چ‚ڈپ@‚“‚پ‚گ‚‰‚…‚ژ‚“پjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پi‰p–¼پFپ@‚g‚n‚l‚nپ@‚r‚`‚o‚h‚d‚m‚rپC
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚d‚w‚s‚`‚m‚sپ@‚g‚t‚l‚`‚m پ@‚r‚o‚d‚b‚h‚d‚rپjپB
پثپ@ƒzƒ‚¥ƒTƒsƒGƒ“ƒX پ@پ@ پ@پiپ@ˆںژي پF ƒzƒ‚¥ƒTƒsƒGƒ“ƒXپEƒTƒs
پ@پ@ƒTƒsƒGƒ“ƒXپBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ƒGƒ“ƒXˆںژيپ@ پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚r‚•‚‚‚“‚گ‚…‚ƒ‚‰‚…‚“پ@‚g‚ڈ‚چ‚ڈپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚“‚پ‚گ‚‰‚…‚ژ‚“پ@‚“‚پ‚گ‚‰‚…‚ژ‚“پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پi‰p–¼پFپ@‚g‚n‚l‚nپ@‚r‚`‚o‚h‚d‚m‚r پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚r‚`‚o‚h‚d‚m‚rپjپB
پثپ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh پ@پ@ پ@پ@پ@ پiƒOƒ‹پ[ƒvپFپ@ ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپEƒOƒ‹پ[ƒv
پ@پ@پi= ƒAƒWƒAگlژيپjپBپ@پ@پ@پ@پ@ ‚f‚’‚ڈ‚•‚گپ@‚l‚ڈ‚ژ‚‡‚ڈ‚Œ‚ڈ‚‰‚„پjپB
پ›پ@پuŒأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپvپ@پ@پ@پ@پ@پi‰p–¼پFپ@‚l‚n‚m‚f‚n‚k‚n‚h‚cپi‚rپjپjپB پ@
پ@‚ئپ@پuگVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپvپBپ@پ@پ@ پ›پ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh‚حپA—eژpپEٹOŒ©
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‘جگFپE‘جŒ^پj ‚ة‚و‚éپAگlژي•ھ—ق
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒOƒ‹پ[ƒv‚ج‚P‚آ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh‚حپA Œأƒ‚ƒ“ƒSƒچ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒCƒhپi= “ى•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپA‰pپF
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚r‚n‚t‚s‚g‚d‚q‚mپ@‚l‚n‚m‚f‚n‚k‚n‚h‚c
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚rپjپjپ@‚ئپAپ@گVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپi= –k
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپA‰pپF‚m‚n‚q‚s‚g‚d‚q‚m
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚l‚n‚m‚f‚n‚k‚n‚h‚cپi‚rپjپjپ@‚ج‚Qژي—ق
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ة•ھ‚©‚ê‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’ک “ْ–{ژjژ«“TپB
پثپ@“ꕶگlپBپ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiƒOƒ‹پ[ƒvپ@پFپ@“ꕶگlƒOƒ‹پ[ƒv
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚f‚’‚ڈ‚•‚گپ@‚i‚ڈ‚چ‚ڈ‚ژ‚ٹ‚‰‚ژپ@‚o‚…‚ڈ‚گ‚Œ‚…پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پi‰pŒê–¼پFپ@‚s‚g‚dپ@‚i‚n‚l‚n‚m‚i‚h‚mپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚o‚d‚n‚o‚k‚dپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@پu“ꕶگlپv‚حپAپ@Œأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒC
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒhپi= “ى•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپj‚ج“ْ–{گو
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈZ–¯‚إ‚ ‚èپAپ@Œ´“ْ–{گlپ@پi‰pپF
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚o‚q‚n‚s‚n-‚i‚`‚o‚`‚m‚d‚r‚dپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚o‚d‚n‚o‚k‚dپA“ꕶگl‚ئ“n—ˆŒn–يگ¶گlپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‚PƒOƒ‹پ[ƒv‚إ‚ ‚èپAپu“ꕶŒnپv پi‰pپF
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚i‚n‚l‚n‚m‚j‚d‚hپ@پ@‚o‚d‚n‚o‚k‚dپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جگlپXپiگl—قپj‚إ‚ ‚éپB
پثپ@–يگ¶گlپBپ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پiƒOƒ‹پ[ƒvپ@پFپ@–يگ¶گlƒOƒ‹پ[ƒv
پ›پ@پu“ꕶŒnپiچف—ˆŒnپjپ@پ@پ@ ‚f‚’‚ڈ‚•‚گ پ@‚x‚پ‚™‚ڈ‚‰‚ٹ‚‰‚ژ ‚o‚…‚ڈ‚گ‚Œ‚…پjپB
پ@–يگ¶گlپvپ@ ‚ئپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‰pŒê–¼پFپ@‚s‚g‚dپ@‚x‚`‚x‚n‚h‚i‚h‚m
پ@پu“n—ˆŒn–يگ¶گlپvپBپ@پ@پ@پ@پ@‚o‚d‚n‚o‚k‚dپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@–يگ¶گl‚ئ‚حپAپ@پu“ꕶŒnپiچف—ˆ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ Œnپj–يگ¶گlپvپ@‚ئپ@پu“n—ˆŒn–يگ¶گlپv
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@–يگ¶گl‚حپA“ꕶژ‘مپi–ٌ‚P–œ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚Q‚O‚O‚O”N‘Oپ`–ٌ‚Q‚S‚O‚O”N‘Oپj‚©‚ç
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ْ–{‚جگوڈZ–¯‚جŒأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒC ƒh
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= “ى•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپj‚جپu“ꕶ Œn
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiچف—ˆŒnپj–يگ¶گlپvپ@ ‚ئپAپ@–يگ¶ژ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‘مپi–ٌ‚Q‚S‚O‚O”N‘Oپ`–ٌ‚P‚V‚O‚O”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‘Oپj‚ةƒAƒWƒA‘ه—¤‚©‚ç‚جˆعڈZ–¯‚ج
پ@ گVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپi= –k•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒC
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ƒhپj‚جپu“n—ˆŒn–يگ¶گlپv پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@ پ@پ›پ@پu“n—ˆŒn–يگ¶گlپv‚حپAŒ´“ْ–{گl
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚ج‚PƒOƒ‹پ[ƒv‚إ‚ ‚èپAپ@پu–يگ¶“n—ˆ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ Œnپvپi‰pپF‚s‚g‚dپ@‚x‚`‚x‚n‚hپ@‚s‚n‚q‚`‚h‚j‚d‚h
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚o‚d‚n‚o‚k‚dپjپ@‚جگl پXپiگl—قپj‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’ک “ْ–{ژjژ«“TپB
پثپ@“ْ–{گlپB پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiƒOƒ‹پ[ƒvپ@پFپ@“ْ–{گlپ@پi= “ْ–{ڈيڈZ–¯پA
پ›پ@پuŒأ‘م“ْ–{گlپvپ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{’nˆو“y’…پEڈيڈZ–¯پjپ@ƒOƒ‹پ[ƒv
پ¨پ@پu–{“y“ْ–{گlپvپA ‚f‚’‚ڈ‚•‚گپ@‚i‚پ‚گ‚پ‚ژ‚…‚“‚…پ@‚m‚پ‚”‚‰‚–‚…پ@
پ@پu—®‹…گlپvپAپuƒAƒCƒkگlپvپBپ@ پi‚h‚ژ‚„‚‰‚‡‚…‚ژ‚ڈ‚•‚“پjپ@‚o‚…‚ڈ‚گ‚Œ‚…پjپB
پ›پ@پuŒأ‘م“ْ–{گlپvپ@پ@ پ@پ@پ@ پi‰pŒê–¼پF‚s‚g‚dپ@‚i‚`‚o‚`‚m‚d‚r‚d
پ@پ¨پ@پu’†گ¢“ْ–{گlپvپ@پ@پ@پ@پ@‚m‚`‚s‚h‚u‚dپ@پi‚h‚m‚c‚h‚f‚d‚m‚n‚t‚rپjپ@
پ@پ¨پ@پu‹كگ¢“ْ–{گlپvپ@پ@پ@پ@پ@‚o‚d‚n‚o‚k‚dپjپB
پ@پ¨پ@پu‹ك‘م“ْ–{گlپvپ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@“ْ–{گlپi= “ْ–{ڈيڈZ–¯پj‚حپAŒأ‘م
پ@پ¨پ@پuŒ»‘م“ْ–{گlپvپBپ@پ@پ@پ@“ْ–{‚إŒ`گ¬‚³‚ꂽپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@“ْ–{گlپi= “ْ–{ڈيڈZ–¯پj‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ŒأپEگVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒC ƒhچ¬ŒŒ‚جپAپu“ꕶپE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒnپv‚جپAپu–{“y“ْ–{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گlپv‚âپu—®‹…گlپv پ@‚ئپAپ@ŒأپEگVƒ‚ƒ“ƒS
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒچƒCƒhچ¬ŒŒ‚جپAپu“ꕶپE –kƒAƒWƒAڈ”–¯
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘°پEچ¬ŒŒŒnپv‚جپAپuƒAƒC ƒkگlپv‚ج‚Rژي—ق
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جگl—ق‚ة•ھ‚©‚ê‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@Œ»چف‚ج‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚ج“ْ–{گl‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پu–{“yپ@“ْ–{گlپv‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@پu–{“y“ْ–{گlپv‚حپAپ@Œأ‘م“ْ–{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œمٹْ‚ةŒ`گ¬‚³‚ꂽپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@پu–{“y“ْ–{گlپv‚حپAپ@ پu“ꕶگlپv
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ئ‚»‚جژq‘·‚جپu“ꕶŒnپvپ@‚ئپAپ@پu“n
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—ˆŒn–يگ¶گlپv‚ئ‚»‚جژq‘·‚جپu–يگ¶
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“n—ˆŒnپvپ@‚ئ‚جچ¬ŒŒ‚جگl—ق‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@پu–{“y“ْ–{گlپv‚حپAپ@ŒأپEگV پi“ى
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•ûپE–k•ûپjƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhچ¬ŒŒ‚جپAپu“ê
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•¶پE–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒnپvپ@پi‰pپF‚s‚g‚dپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚i‚n‚l‚n‚m‚j‚d‚h-‚x‚`‚x‚n‚h‚s‚n‚q‚`‚h‚j‚d‚hپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚l‚h‚w‚d‚cپ@‚q‚`‚b‚h‚`‚kپ@‚o‚d‚n‚o‚k‚dپj ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گlپXپiگl—قپj‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@“ْ–{گlپi= “ْ–{ڈيڈZ–¯پj‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒأپEگVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒC ƒhچ¬ŒŒ‚جپAپu“ꕶپE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒnپv‚جپAپu–{“y“ْ–{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گlپv‚âپu—®‹…گlپv پi‰pپF‚s‚g‚dپ@‚l‚`‚h‚m-
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚k‚`‚m‚cپ@‚i‚`‚o‚`‚m‚d‚r‚d‚o‚d‚n‚o‚k‚dپCپ@
پ@ ‚s‚g‚dپ@‚q‚x‚t‚j‚x‚tپ@‚i‚`‚o‚`‚m‚d‚r‚dپ@
‚o‚d‚n‚o‚k‚dپjپ@‚ئپAپ@Œأ پEگVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒC
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒhچ¬ŒŒ‚جپAپu“ꕶپE –kƒAƒWƒAڈ”–¯‘°پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ¬ŒŒŒnپv‚جپA پuƒAƒCƒkگlپvپ@پi‰pپF‚s‚g‚dپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚`‚h‚m‚tپ@‚i‚`‚o‚`‚m‚d‚r‚dپ@‚o‚d‚n‚o‚k‚dپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‚Rژي—ق‚جگl—ق‚ة•ھ‚©‚ê‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@Œأ‘م“ْ–{‚إŒ`گ¬‚³‚ꂽ“ْ–{ گl
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= “ْ–{ڈيڈZ–¯پj‚حپAپ@ژ‘م‚ئ‹¤‚ةپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پuŒأ‘م“ْ–{گlپv‚©‚çپAپ@پu’†گ¢“ْ–{گlپvپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پu‹كگ¢“ْ–{گlپvپAپu‹ك‘م“ْ–{گlپvپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پuŒ»‘م“ْ–{گlپv‚ض‚ئپ@پ@ ڈ‚µ‚¸‚آپA•½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹دگg’·‚ھگL‚ر‚é‚ب‚اپA—eژpپEٹOŒ©
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‘جŒ^پE‘جگFپj‚ً•د‰»‚³‚¹‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’ک “ْ–{ژjژ«“TپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@Œأ‘م“ْ–{‚إŒ`گ¬‚³‚ꂽ“ْ–{ گl
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= “ْ–{ڈيڈZ–¯پj‚حپAپ@ژ‘م‚ئ‹¤‚ةپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پuŒأ‘م“ْ–{گlپvپi‰pپF‚s‚g‚dپ@‚`‚m‚b‚h‚d‚m‚sپ@ پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚i‚`‚o‚`‚m‚d‚r‚d‚o‚d‚n‚o‚k‚dپjپ@‚©‚çپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پu’†گ¢“ْ–{گlپvپAپu‹كگ¢“ْ–{گlپvپAپu‹ك‘م
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{گlپvپAپuŒ»‘م“ْ–{گlپvپ@پi‰pپF‚s‚g‚dپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚l‚d‚c‚h‚d‚u‚`‚kپ@‚i‚`‚o‚`‚m‚d‚r‚dپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚o‚d‚n‚o‚k‚dپCپ@ ‚s‚g‚dپ@‚d‚`‚q‚k‚xپ@‚l‚n-
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚c‚d‚q‚mپ@‚i‚`‚o‚`‚m‚d‚r‚dپ@‚o‚d‚n‚o‚k‚dپCپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚l‚n‚c‚d‚q‚mپ@‚i‚`‚o‚`‚m‚d‚r‚dپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚o‚d‚n‚o‚k‚dپCپ@ ‚s‚g‚d ‚o‚q‚d‚r‚d‚m‚s-‚c‚`‚xپ@
پ@‚i‚`‚o‚`‚m‚d‚r‚dپ@‚o‚d‚n‚o‚k‚dپjپ@‚ض‚ئڈ‚µ‚¸
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚آپA•½ ‹دگg’·‚ھگL‚ر‚é‚ب‚اپAپ@—eژpپEٹO
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ Œ©پi‘جŒ^پE‘جگFپj‚ً•د‰»‚³‚¹‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@
پôپôپ@“ꕶŒnپ@‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢پAƒhƒL
پ@پ@پ@پ@ƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پAƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپB
پ@
پڑپ@“ꕶŒnپ@‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[ ‚¢پAƒhƒLƒ…
پ@پ@پ@ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پB
پ@
پ،پ@ƒTƒCƒGƒ“ƒX‚y‚d‚q‚nپ@
پ@پ@پw “ْ–{گl‚جƒ‹پ[ƒc”Œ©پIپ`
پ@پ@پ@پeپeٹj‚c‚m‚`پfپf‚ھ‰ً‚«–¾‚©‚·
پ@پ@پ@“ꕶگlپ` پxپB
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚P‚U”N‚SŒژ ‚R“ْپE–{•ْ‘—پE
پ@پ@پ@ ‰بٹwƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[”ش‘gپjپB
پœپ@“ْ–{گl‚جƒ‹پ[ƒcپi‹NŒ¹پj‚ًڈع‚µ‚ڈq‚ׂéپB
پœپ@“ꕶگlپi= Œأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپj‚â“n—ˆŒn–يگ¶گl
پ@پ@پi= گVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپj‚جگlپX‚ًڈq‚ׂéپB
پœپ@”Œ@‚µ‚½پA“ꕶگl‚جٹj‚c‚m‚`•ھگح‚ة‚و‚èپAŒ»گ¶پ@
پ@پ@گl—قپi= گVگlپAƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒXپj‚ج‹NŒ¹پEˆع“®
پ@پ@ƒ‹پ[ƒg‚â“ْ–{گl‚ج‹NŒ¹‚ً’m‚éپB
پ@
پ،پ@پw ‹³‰بڈ‘‚ھ•د‚ي‚éپIپHپ@“ْ–{گl
پ@پ@پ@ ‚جƒ‹پ[ƒc‚ً‚³‚®‚é—· پxپB
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚P‚T”N‚P‚QŒژ‚Q‚V“ْپE–{•ْ‘—پE
پ@پ@پ@ ‰بٹwƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[”ش‘gپjپB
پœپ@“ْ–{‚جŒ´ژnژ‘م‚ًگ¶‚«‚½پA‹Œگخٹيگl‚â“ꕶگl
پ@پ@ ‚ًڈq‚ׂéپB
پœپ@“ꕶگl‚ًڈع‚µ‚ڈq‚ׂéپBپ@“ꕶگl‚جˆâگص”Œ@‚â
پ@پ@ ƒ~ƒgƒRƒ“ƒhƒٹƒA‚c‚m‚`‚ة‚و‚èپAŒ»‘م“ْ–{گl‚جƒ‹پ[ƒc
پ@پ@پi‹NŒ¹پj‚ج‚PƒOƒ‹پ[ƒv‚إ‚ ‚éپA“ꕶگl‚ج‹NŒ¹پAگ¶
ٹˆپAˆع“®ƒ‹پ[ƒg‚ب‚ا‚ً’m‚éپB
پ@
پ،پ@ƒTƒCƒGƒ“ƒX‚y‚d‚q‚nپ@
پ@پ@ پw “ْ–{گl‚ج‹NŒ¹‚ة”—‚é پxپB
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚O‚V”N‚P‚QŒژ‚Q“ْپE–{•ْ‘—پE
پ@پ@پ@ ‰بٹwƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[”ش‘gپjپB
پœپ@ƒ~ƒgƒRƒ“ƒhƒٹƒA‚c‚m‚`‚ة‚و‚èپAŒ»گ¶گl—قپi= گVگlپA
پ@پ@ƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒXپj‚ج‹NŒ¹پEˆع“®ƒ‹پ[ƒg‚â“ْ–{
پ@پ@گl‚ج‹NŒ¹‚ً’m‚éپB
پ@
پ،پ@ƒTƒCƒGƒ“ƒX‚y‚d‚q‚nپ@
پ@پ@ پw ƒVƒٹپ[ƒYپ@ƒqƒg‚ج“ن‚ة”—‚é پxپB
پœپ@‘و‚PڈWپ@پu‚PپD‚c‚m‚`‚ھ‰ً‚«–¾‚©‚·پI
پ@پ@ گl—ق‚ج—·پv
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚O‚W”N‚P‚OŒژ‚P‚O“ْپE–{•ْ
پ@پ@پ@ ‘—پE‰بٹwƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[”ش‘gپjپB
پœپ@ƒ~ƒgƒRƒ“ƒhƒٹƒA‚c‚m‚`پA‚xگُگF‘جپAŒ¾Œê“™‚ة‚و‚èپA
پ@پ@Œ»گ¶گl—قپi= گVگlپAƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒXپj‚ج‹NŒ¹پE
پ@پ@ˆع“®ƒ‹پ[ƒg‚â“ْ–{گl‚ج‹NŒ¹‚ً’m‚éپB
پœپ@Œ»گ¶گl—قپi= گVگlپAƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒXپj‚جپAڈo
پ@پ@ƒAƒtƒٹƒJ‚ئگ¢ٹE‚ض‚جٹgژU‚ئˆعڈZ‚ً’m‚éپB
پ@
پ،پ@ƒTƒCƒGƒ“ƒX‚y‚d‚q‚nپ@پwپ@“ء•ٌپI
پ@پ@‹Œگخٹيژ‘م‚جگlچœپ@‘ه—ت”Œ@پ@پxپBپ@
پ@پ@ پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚P‚R”N‚P‚PŒژ‚P‚V“ْپE–{•ْ‘—
پ@پ@ ƒeƒŒƒrپE‰بٹwƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[”ش‘gپjپB
پœپ@“ْ–{‚ج‹Œگخٹيگlپ@پi–ٌ‚R‚T‚O‚O‚O”N‘Oپ`–ٌ‚P‚Q
پ@پ@‚O‚O‚O”N‘O‚ة“ْ–{’nˆو‚ة‚¢‚½گl—قپjپ@‚ة‚آ‚¢‚ؤ
پ@پ@ڈq‚ׂéپB
پœپ@چ`گىگl‚â‹Œگخٹيگl‘S‘ج‚ة‚آ‚¢‚ؤڈq‚ׂéپB
پœپ@‰«“ꌧپEگخٹ_“‡پi‚¢‚µ‚ھ‚«‚¶‚ـپj‚ج”’•غٹئچھ
پ@پ@“cŒ´“´Œٹˆâگصپi‚µ‚ç‚ظ‚³‚¨‚ث‚½‚خ‚é‚ا‚¤‚¯‚آ
پ@پ@‚¢‚¹‚«پj‚إپA‚Q‚O‚O‚X”N‚و‚蔌@‚ھٹJژn‚³‚êپA‹Œ
پ@پ@گخٹيگl‚جگlچœ‚ھ‘ه—ت‚ة”Œ©‚³‚êپA‚ظ‚عŒ´Œ`
پ@پ@‚ً‚ئ‚ا‚ك‚é‹Œگخٹيگl‚ج“ھچœ‚جچœ‚ً“¾‚ç‚ê‚é‰آ
پ@پ@”\گ«‚à‚ ‚邱‚ئ‚ة‚آ‚¢‚ؤڈq‚ׂéپBپ@
پ@
پ،پ@پwپ@“ْ–{گlپ@‚ح‚é‚©‚ب—·پ@پxپBپ@
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚O‚P”Nگ§چىƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^
پ@پ@پ@ ƒٹپ[”ش‘gپjپBپ@
پ@پ@پ@پu‘وŒـڈWپ@‚»‚µ‚ؤپeپe“ْ–{گlپfپf‚ھ
پ@پ@پ@گ¶‚ـ‚ꂽپvپB
پ،پ@–يگ¶ژ‘م‘Oٹْ‚ةپAگ…“cˆîچى‚ًچs‚¤پA”_چkژه
پ@پ@‘ج‚جگVƒ‚ƒ“ƒSƒچ ƒCƒhپi= –k•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپj‚ج
پ@پ@گlپX‚ھپAƒAƒWƒA‘ه—¤‚و‚è“ْ–{’nˆوپiڈ‰‚ك‹مڈB
پ@پ@–{“yپj‚ة“n—ˆ‚µپA“ْ–{‚جپu“n—ˆŒn–يگ¶گlپvپi–ي
پ@پ@گ¶“n—ˆŒn‚جگlپXپj‚ئ‚ب‚èپAپ@ژë—آپEچجڈWژه‘ج
پ@پ@‚ج“ْ–{‚جگوڈZ–¯‚جŒأƒ‚ƒ“ƒSƒچ ƒCƒhپi= “ى•ûƒ‚
پ@پ@ƒ“ƒSƒچƒCƒhپj‚جپu“ꕶŒn–يگ¶گlپv‚ئ‘خ—§‚µ‚ب‚ھ
پ@پ@‚çپA“ْ–{–{“y‚ً–kڈمپE“Œگi‚µ‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‚»‚جŒمپA–يگ¶ژ‘مŒمٹْ‚ة‚حپAپu“n—ˆŒn–ي
پ@پ@گ¶گlپv‚ئپu“ꕶŒn–يگ¶گlپv‚حپA‹¦—ح‚µپAگ…“cˆî
پ@پ@چى‚ًچs‚¤‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½پB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@“ꕶپE–يگ¶“n—ˆپEپ@
چ¬ŒŒŒnپ@
پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚ه‚¤‚à‚ٌپE‚â‚و‚¢‚ئ‚ç‚¢پE‚±‚ٌ‚¯
‚آ‚¯‚¢پjپBپ@
پ@
پ،پ@“ꕶپE–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒnپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@“ꕶپE–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒnپ@
پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚à‚ٌپE‚â‚و‚¢‚ئ‚ç‚¢پE‚±‚ٌ‚¯‚آ‚¯‚¢پjپB
پ،پ@‰pŒê–¼پ@پFپ@
پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚i‚n‚l‚n‚m‚j‚d‚h-‚x‚`‚x‚n‚h‚s‚n‚q‚`‚h‚j‚d‚hپ@
پ@پ@‚l‚h‚w‚d‚c ‚q‚`‚b‚h‚`‚kپ@‚o‚d‚n‚o‚k‚dپD
پ،پ@“ْ–{گl‚جƒ‹پ[ƒc‚ةٹض‚µ‚ؤ‚حپAپu“ْ–{گlپvپi“ْ–{گl‚جƒ‹
پ@پ@پ[ƒcپjپAپuŒ´“ْ–{گlپvپAپu“ْ–{گlƒ‹پ[ƒcپEƒKƒCƒhƒuƒbƒNپv‚à
پ@پ@ژQڈئ‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
پ@
پ پ@“ꕶپE–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒnپiگlژيپj
‚جٹwڈp•ھ—ق•\پBپ@پ@
پ@
پ@
پ،پ@“ْ–{‚جپA“ꕶپE–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒn‚حپAپ@Œأƒ‚ƒ“
پ@پ@ƒSƒچƒCƒhپi= “ى•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپj‚جپA“ꕶگl‚ئ‚»
پ@پ@‚جژq‘·‚جپA“ꕶŒn‚جگlپXپ@‚ئپAپ@گVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh
پ@پ@پi= –k•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپj‚جپA“n—ˆŒn–يگ¶گl‚ئ‚»‚ج
پ@پ@ژq‘·‚جپA–يگ¶“n—ˆŒn‚جگlپXپ@‚ھچ¬ŒŒ‚µ‚ؤŒ`گ¬
پ@پ@‚³‚ꂽگl—ق ‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@“ْ–{‚جپA“ꕶپE–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒn‚حپAپ@–يگ¶ژ
پ@پ@‘م‚إ‚حپu“ꕶپE–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒn–يگ¶گlپvپAپ@Œأپ@
پ@پ@‘م“ْ–{‚إ‚حپu“ꕶپE–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒnŒأ‘م“ْ–{
پ@پ@گlپvپAپ@’†گ¢“ْ–{‚©‚猻‘م“ْ–{‚ـ‚إ‚جژٹْ‚إ‚ح
پ@پ@پu–{“y“ْ–{گlپvپi= –{“yگlپjپAپu—®‹…گlپvپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@
پںپ@گi‰»•\پB
پ،پ@“ْ–{گlپi“ْ–{ڈيڈZ–¯پj‚ض‚جگi‰»•\پB
پ@پ@‰ژگlپثپ@
پ@پ@Œ´گlپi= ƒzƒ‚پEƒGƒŒƒNƒgƒX—قپjپث
پ@پ@‹Œگlپi= ‘Oƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒX—قپjپثپ@
پ@پ@Œ»گ¶گl—قپi= گVگlپAƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒXپjپثپ@
پ@پ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپثپ@
پ@پ@“ꕶگlپثپ@
پ@پ@–يگ¶گlپثپ@
پ@پ@Œأ‘م“ْ–{گlپثپ@
پ@پ@پu–{“y“ْ–{گlپvپi= –{“yگlپjپAپu—®‹…گlپvپA
پ@پ@پuƒAƒCƒkگlپvپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“dژqڈ‘گذپB
پ@
پ،پ@Œ»‘م“ْ–{گlپi“ْ–{ڈيڈZ–¯پj‚ض‚جگi‰»•\پB
پ@پ@‰ژگlپثپ@
پ@پ@Œ´گlپi= ƒzƒ‚پEƒGƒŒƒNƒgƒX—قپjپث
پ@پ@‹Œگlپi= ‘Oƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒX—قپjپثپ@
پ@پ@Œ»گ¶گl—قپi= گVگlپAƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒXپjپثپ@
پ@پ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپثپ@
پ@پ@“ꕶگlپثپ@
پ@پ@–يگ¶گlپثپ@
پ@پ@Œأ‘م“ْ–{گlپثپ@
پ@پ@’†گ¢“ْ–{گlپثپ@
پ@پ@‹كگ¢“ْ–{گlپثپ@
پ@پ@‹ك‘م“ْ–{گlپث
پ@پ@Œ»‘م“ْ–{گlپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“dژqڈ‘گذپB
پ@
پ،پ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh‚ض‚جگi‰»•\پB
پ@پ@‰ژگlپثپ@
پ@پ@Œ´گlپi= ƒzƒ‚پEƒGƒŒƒNƒgƒX—قپjپث
پ@پ@‹Œگlپi= ‘Oƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒX—قپjپثپ@
پ@پ@Œ»گ¶گl—قپi= گVگlپAƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒXپjپثپ@
پ@پ@Œأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒC ƒhپi= “ى•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپjپث
گVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپi= –k•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپjپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@Œأگl—قٹwژ«“TپB
پ@
پ@
#thejomon.yayoi.mi.ra,people-theclassificationtable
پ@
پ،پ@“ꕶپE–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒn
پ@پ@ ‚جٹwڈp•ھ—ق•\ پBپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پiڈعچ×ڈمˆت•ھ—قپAڈمˆتڈٹ‘®‚ج•ھ—قپA“ْ–{
پ@پ@پ@پ@ Œê–¼پEٹw–¼پE‰pŒê–¼‘خڈئپjپB
پ›پ@‚s‚g‚dپ@‚r‚b‚h‚d‚m‚s‚h‚e‚h‚bپ@‚b‚k‚`‚r‚r‚h‚e‚h‚b‚`‚s‚h‚n‚mپ@
پ@پ@‚s‚`‚a‚k‚dپ@‚n‚eپ@‚s‚g‚dپ@‚i‚n‚l‚n‚m‚j‚d‚h-
پ@پ@‚x‚`‚x‚n‚h‚s‚n‚q‚`‚h‚j‚d‚hپ@‚l‚h‚w‚d‚c ‚q‚`‚b‚h‚`‚kپ@
‚o‚d‚n‚o‚k‚dپD
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“T ‚V‚P‚T‚Q‚QپB
پ@
پ،پ@“ꕶپE–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒn‚جگl—قپiگlپXپjپB
پ@ پi‰pŒê–¼پF ‚s‚g‚dپ@‚i‚n‚l‚n‚m‚j‚d‚h-
پ@پ@پ@‚x‚`‚x‚n‚h‚s‚n‚q‚`‚h‚j‚d‚hپ@‚l‚h‚w‚d‚cپ@‚q‚`‚b‚h‚`‚kپ@
پ@‚o‚d‚n‚o‚k‚dپjپB
پ@
پ،پ@’n‹…گ¶•¨پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@‚k‚h‚e‚dپ@‚n‚mپ@‚d‚`‚q‚s‚gپB
پثپ@گ^ٹjگ¶•¨پBپ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پiƒhƒپƒCƒ“پFپ@گ^ٹjگ¶•¨ˆوپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚c‚ڈ‚چ‚پ‚‰‚ژپ@‚d‚•‚‹‚پ‚’‚™‚ڈ‚”‚پپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‰p–¼پF ‚d‚t‚j‚`‚q‚x‚n‚s‚dپi‚rپjپjپB
پثپ@“®•¨پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiپ@ٹEپ@پFپ@“®•¨ٹEپ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚j‚‰‚ژ‚‡‚„‚ڈ‚چپ@‚`‚ژ‚‰‚چ‚پ‚Œ‚‰‚پپjپ@
پ@پ@ پi‰p–¼پF‚`‚m‚h‚l‚`‚k پi‚rپjپjپB
پثپ@گزچُپi‚¹‚«‚³‚پj“®•¨پBپ@پiپ@–هپ@پFپ@گزچُ“®•¨–ه پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚o‚ˆ‚™‚Œ‚•‚چپ@‚b‚ˆ‚ڈ‚’‚„‚پ‚”‚پپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ پi‰p–¼پF‚b‚g‚n‚q‚c‚`‚s‚d پi‚rپjپjپB
پثپ@گز’إپi‚¹‚«‚آ‚¢پj“®•¨پB پiˆں–ه پFپ@گز’إ“®•¨ˆں–هپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚r‚•‚‚‚گ‚ˆ‚™‚Œ‚•‚چپ@‚u‚…‚’‚”‚…‚‚‚’‚پ‚”‚پپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‰p–¼پF‚u‚d‚q‚s‚d‚a‚q‚`‚s‚dپi‚rپjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’ک “ْ–{ژj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ«“TپB
پثپ@—Lٹ{پi‚ن‚¤‚ھ‚پj“®•¨پ@ پi‰؛–ه پFپ@—Lٹ{“®•¨‰؛–هپ@
پ@پ@پiٹ{Œû—قپA—Lٹ{—قپjپBپ@پ@ ‚h‚ژ‚†‚’‚پ‚گ‚ˆ‚™‚Œ‚•‚چ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚f‚ژ‚پ‚”‚ˆ‚ڈ‚“‚”‚ڈ‚چ‚پ‚”‚پپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‰p–¼پFپ@‚u‚d‚q‚s‚d‚a‚q‚`‚s‚d پi‚rپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚v‚h‚s‚gپ@‚i‚`‚vپjپB
پثپ@ژlژˆپi‚µ‚µپj“®•¨پBپ@پ@پ@ پiڈمچj پFپ@ژlژˆ“®•¨ڈمچjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚r‚•‚گ‚…‚’‚ƒ‚Œ‚پ‚“‚“پ@‚s‚…‚”‚’‚پ‚گ‚ڈ‚„‚پ پjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‰p–¼پF‚s‚d‚s‚q‚`‚o‚n‚c پi‚rپjپjپBپ@پ@
پثپ@—L—r–Œ—قپBپ@پ@ پ@پ@پ@پ@ پiƒ‰ƒ“ƒNپiٹK‹‰پj‚ب‚µپ@پ@پ@
پ@ پi‚ن‚¤‚و‚¤‚ـ‚‚é‚¢پjپ@پ@پ@پ@ ‚`‚چ‚ژ‚‰‚ڈ‚”‚پپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‰p–¼پF‚`‚l‚m‚h‚n‚s‚d پi‚rپjپjپBپ@ پ@
پثپ@ڑM“û—قپBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپ@ چj پFپ@ڑM“ûچj پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ ‚b‚Œ‚پ‚“‚“پ@‚l‚پ‚چ‚چ‚پ‚Œ‚‰‚پپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‰p–¼پF‚l‚`‚l‚l‚`‚kپi‚rپjپjپB
پثپ@ڈb—قپBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiˆںچj پFپ@ڈbˆںچj پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚r‚•‚‚‚ƒ‚Œ‚پ‚“‚“پ@‚s‚ˆ‚…‚’‚‰‚پپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‰p–¼پF‚s‚g‚d‚q‚h‚`‚mپi‚rپjپjپB
پثپ@گ^ڈb—قپ@پiگ³ڈb—قپjپ@پ@ پi‰؛چj پFپ@گ^ڈb‰؛چjپiگ³ڈb‰؛چjپjپ@پ@
پ@پ@پi—L‘ظ”ص—قپA—L‘ظ”صپ@پ@پ@ پ@‚h‚ژ‚†‚’‚پ‚ƒ‚Œ‚پ‚“‚“پ@‚d‚•‚”‚ˆ‚…‚’‚‰‚پپjپ@ پ@پ@پ@پ@پ@ پ@
پ@پ@ڑMپi‚ظپj“û—قپjپBپ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‰p–¼پF‚d‚t‚s‚g‚d‚q‚h‚`‚mپi‚rپjپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‰p–¼پF‚o‚k‚`‚b‚d‚m‚s‚`‚kپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚l‚`‚l‚l‚`‚kپi‚rپjپj پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’ک “ْ–{ژj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ«“TپB
پثپ@—ى’·—قپBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiپ@–ع پFپ@—ى’·–عپiƒTƒ‹–عپj پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ ‚n‚’‚„‚…‚’پ@‚o‚’‚‰‚چ‚پ‚”‚…‚“پjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‰p–¼پF‚o‚q‚h‚l‚`‚s‚dپi‚rپjپjپB
پ@
پثپ@’¼•@‰ژ—قپ@پiگV•ھ—ق–@پjپBپiˆں–ع پFپ@’¼•@‰ژˆں–عپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚r‚•‚‚‚ڈ‚’‚„‚…‚’پ@‚g‚پ‚گ‚Œ‚ڈ‚’‚’‚ˆ‚‰‚ژ‚‰پjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‰p–¼پF‚g‚`‚o‚k‚n‚q‚q‚g‚h‚m‚dپi‚rپjپjپB
پ@پ@ گ^‰ژ—قپ@پ@ پiگV•ھ—ق–@پjپBپi‰؛–ع پFپ@گ^‰ژ‰؛–عپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚h‚ژ‚†‚’‚پ‚ڈ‚’‚„‚…‚’پ@‚r‚‰‚چ‚‰‚‰‚†‚ڈ‚’‚چ‚…‚“پjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‰p–¼پF ‚r‚h‚l‚h‚`‚mپi‚rپjپjپB
پ@پ@ ‹·•@‰ژ—قپ@پiگV•ھ—ق–@پjپBپiڈ¬–ع پFپ@‹·•@ڈ¬–عپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚o‚پ‚’‚–‚ڈ‚’‚„‚…‚’پ@‚b‚پ‚”‚پ‚’‚’‚ˆ‚‰‚ژ‚‰ پjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‰p–¼پF ‚b‚`‚s‚`‚q‚q‚g‚h‚m‚dپi‚rپjپjپB
پ@‚ـ‚½‚حپA
پ@پ@ گ^‰ژ—قپ@پ@ پi‹Œ•ھ—ق–@پjپBپiˆں–ع پFپ@گ^‰ژˆں–ع پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚r‚•‚‚‚ڈ‚’‚„‚…‚’پ@‚r‚‰‚چ‚‰‚‰‚†‚ڈ‚’‚چ‚…‚“پjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‰p–¼پF ‚r‚h‚l‚h‚`‚mپi‚rپjپjپB
پ@ ‹·•@‰ژ—قپ@پi‹Œ•ھ—ق–@پj پBپi‰؛–ع پFپ@‹·•@‰؛–ع پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚h‚ژ‚†‚’‚پ‚ڈ‚’‚„‚…‚’پ@‚b‚پ‚”‚پ‚’‚’‚ˆ‚‰‚ژ‚‰پjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‰p–¼پF ‚b‚`‚s‚`‚q‚q‚g‚h‚m‚dپi‚rپjپjپB
پثپ@ƒzƒ~ƒmƒCƒh پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiڈم‰ب پFپ@ƒqƒgڈم‰بپ@ پ@
پ@پ@پi—قگl‰ژ‚ئگl—قپjپBپ@پ@پ@پ@پ@ پ@‚r‚•‚گ‚…‚’‚†‚پ‚چ‚‰‚Œ‚™پ@‚g‚ڈ‚چ‚‰‚ژ‚ڈ‚‰‚„‚…‚پپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ پ@پi‰p–¼پF ‚g‚n‚l‚h‚m‚n‚h‚cپi‚rپjپjپB
پثپ@‘هŒ^—قگl‰ژ‚ئگl—قپ@پ@پ@ پiپ@‰بپ@پFپ@ƒqƒg‰بپ@پ@پ@ پ@
پ@پiƒIƒ‰ƒ“ƒEپ[ƒ^ƒ“پAƒSƒٹƒ‰پA پ@پ@‚e‚پ‚چ‚‰‚Œ‚™پ@‚g‚ڈ‚چ‚‰‚ژ‚‰‚„‚پ‚…پjپ@ پ@پ@پ@پ@
پ@ƒ`ƒ“ƒpƒ“ƒWپ[‚ئگl—قپjپBپ@پ@پ@پ@پi‰p–¼پF ‚m‚n‚m‚g‚t‚l‚`‚mپ@‚f‚q‚d‚`‚sپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@‚`‚o‚dپi‚rپjپ@‚`‚m‚cپ@‚g‚t‚l‚`‚mپi‚rپjپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’ک “ْ–{ژjژ«“TپB
پثپ@ƒSƒٹƒ‰‚ئƒ`ƒ“ƒpƒ“ƒWپ@پ@پ@پiˆں‰ب پFپ@ƒqƒgˆں‰بپ@پ@پ@
پ@پ@پ[‚ئگl—قپBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚r‚•‚‚‚†‚پ‚چ‚‰‚Œ‚™پ@‚g‚ڈ‚چ‚‰‚ژ‚‰‚ژ‚پ‚…پjپ@ پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‰p–¼پF ‚g‚n‚l‚h‚m‚h‚m‚dپi‚rپjپjپB
پثپ@ƒ`ƒ“ƒpƒ“ƒWپ[‚ئگl—قپBپ@پiپ@‘°پ@پFپ@ ƒqƒg‘°پ@پ@پ@ پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚s‚’‚‰‚‚‚…پ@‚g‚ڈ‚چ‚‰‚ژ‚‰‚ژ‚‰پjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‰p–¼ پF‚g‚n‚l‚h‚m‚h‚mپi‚rپjپjپB
پثپ@گl—قپBپ@پ@پ@ پ@پ@پiˆں‘° پFپ@ƒqƒgˆں‘°پ@پ@ پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚r‚•‚‚‚”‚’‚‰‚‚‚…پ@‚g‚ڈ‚چ‚‰‚ژ‚‰‚ژ‚پپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‰p–¼پFپ@‚g‚t‚l‚`‚mپi‚rپjپjپBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پثپ@ƒqƒg‘®پi= ƒzƒ‚‘®پj پ@پ@پ@پi ‘® پFپ@ƒqƒg‘®پi= ƒzƒ‚‘®پjپ@پ@ پ@پ@ پ@
پ@پ@‚جگl—قپBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚f‚…‚ژ‚•‚“پ@‚g‚ڈ‚چ‚ڈپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‰p–¼پFپ@‚g‚t‚l‚`‚mپi‚rپj ‚n‚eپ@ پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚f‚d‚m‚t‚rپ@‚g‚n‚l‚nپjپBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پثپ@ƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒX پ@پiپ@ژي پF ƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒXژيپ@ پ@پ@
پ@پi= Œ»گ¶گl—قپAگVگlپjپBپ@پ@پ@ ‚r‚گ‚…‚ƒ‚‰‚…‚“پ@‚g‚ڈ‚چ‚ڈپ@‚“‚پ‚گ‚‰‚…‚ژ‚“پjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پi‰p–¼پFپ@‚g‚n‚l‚nپ@‚r‚`‚o‚h‚d‚m‚rپC
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚d‚w‚s‚`‚m‚sپ@‚g‚t‚l‚`‚m پ@‚r‚o‚d‚b‚h‚d‚rپjپB
پثپ@ƒzƒ‚¥ƒTƒsƒGƒ“ƒX پ@پ@ پ@پiپ@ˆںژي پF ƒzƒ‚¥ƒTƒsƒGƒ“ƒXپEƒTƒs
پ@پ@ƒTƒsƒGƒ“ƒXپBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ƒGƒ“ƒXˆںژيپ@ پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚r‚•‚‚‚“‚گ‚…‚ƒ‚‰‚…‚“پ@‚g‚ڈ‚چ‚ڈپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚“‚پ‚گ‚‰‚…‚ژ‚“پ@‚“‚پ‚گ‚‰‚…‚ژ‚“پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پi‰p–¼پFپ@‚g‚n‚l‚nپ@‚r‚`‚o‚h‚d‚m‚r پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚r‚`‚o‚h‚d‚m‚rپjپB
پثپ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh پ@پ@ پ@پ@پ@ پiƒOƒ‹پ[ƒvپFپ@ ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپEƒOƒ‹پ[ƒv
پ@پ@پi= ƒAƒWƒAگlژيپjپBپ@پ@پ@پ@پ@ ‚f‚’‚ڈ‚•‚گپ@‚l‚ڈ‚ژ‚‡‚ڈ‚Œ‚ڈ‚‰‚„پjپB
پ›پ@پuŒأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپvپ@پ@پ@پ@پ@پi‰p–¼پFپ@‚l‚n‚m‚f‚n‚k‚n‚h‚cپi‚rپjپjپB پ@
پ@‚ئپ@پuگVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپvپBپ@پ@پ@ پ›پ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh‚حپA—eژpپEٹOŒ©
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‘جگFپE‘جŒ^پj ‚ة‚و‚éپAگlژي•ھ—ق
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒOƒ‹پ[ƒv‚ج‚P‚آ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@ƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒh‚حپA Œأƒ‚ƒ“ƒSƒچ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒCƒhپi= “ى•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپA‰pپF
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚r‚n‚t‚s‚g‚d‚q‚mپ@‚l‚n‚m‚f‚n‚k‚n‚h‚c
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚rپjپjپ@‚ئپAپ@گVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپi= –k
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپA‰pپF‚m‚n‚q‚s‚g‚d‚q‚m
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚l‚n‚m‚f‚n‚k‚n‚h‚cپi‚rپjپjپ@‚ج‚Qژي—ق
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ة•ھ‚©‚ê‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’ک “ْ–{ژjژ«“TپB
پثپ@“ꕶگlپBپ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiƒOƒ‹پ[ƒvپ@پFپ@“ꕶگlƒOƒ‹پ[ƒv
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚f‚’‚ڈ‚•‚گپ@‚i‚ڈ‚چ‚ڈ‚ژ‚ٹ‚‰‚ژپ@‚o‚…‚ڈ‚گ‚Œ‚…پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پi‰pŒê–¼پFپ@‚s‚g‚dپ@‚i‚n‚l‚n‚m‚i‚h‚mپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚o‚d‚n‚o‚k‚dپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@پu“ꕶگlپv‚حپAپ@Œأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒC
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒhپi= “ى•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپj‚ج“ْ–{گو
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈZ–¯‚إ‚ ‚èپAپ@Œ´“ْ–{گlپ@پi‰pپF
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚o‚q‚n‚s‚n-‚i‚`‚o‚`‚m‚d‚r‚dپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚o‚d‚n‚o‚k‚dپA“ꕶگl‚ئ“n—ˆŒn–يگ¶گlپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‚PƒOƒ‹پ[ƒv‚إ‚ ‚èپAپu“ꕶŒnپv پi‰pپF
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚i‚n‚l‚n‚m‚j‚d‚hپ@پ@‚o‚d‚n‚o‚k‚dپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جگlپXپiگl—قپj‚إ‚ ‚éپB
پثپ@–يگ¶گlپBپ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پiƒOƒ‹پ[ƒvپ@پFپ@–يگ¶گlƒOƒ‹پ[ƒv
پ›پ@پu“ꕶŒnپiچف—ˆŒnپjپ@پ@پ@ ‚f‚’‚ڈ‚•‚گ پ@‚x‚پ‚™‚ڈ‚‰‚ٹ‚‰‚ژ ‚o‚…‚ڈ‚گ‚Œ‚…پjپB
پ@–يگ¶گlپvپ@ ‚ئپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‰pŒê–¼پFپ@‚s‚g‚dپ@‚x‚`‚x‚n‚h‚i‚h‚m
پ@پu“n—ˆŒn–يگ¶گlپvپBپ@پ@پ@پ@پ@‚o‚d‚n‚o‚k‚dپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@–يگ¶گl‚ئ‚حپAپ@پu“ꕶŒnپiچف—ˆ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ Œnپj–يگ¶گlپvپ@‚ئپ@پu“n—ˆŒn–يگ¶گlپv
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@–يگ¶گl‚حپA“ꕶژ‘مپi–ٌ‚P–œ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚Q‚O‚O‚O”N‘Oپ`–ٌ‚Q‚S‚O‚O”N‘Oپj‚©‚ç
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ْ–{‚جگوڈZ–¯‚جŒأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒC ƒh
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi= “ى•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپj‚جپu“ꕶ Œn
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiچف—ˆŒnپj–يگ¶گlپvپ@ ‚ئپAپ@–يگ¶ژ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‘مپi–ٌ‚Q‚S‚O‚O”N‘Oپ`–ٌ‚P‚V‚O‚O”N
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‘Oپj‚ةƒAƒWƒA‘ه—¤‚©‚ç‚جˆعڈZ–¯‚ج
پ@ گVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپi= –k•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒC
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ƒhپj‚جپu“n—ˆŒn–يگ¶گlپv پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@ پ@پ›پ@پu“n—ˆŒn–يگ¶گlپv‚حپAŒ´“ْ–{گl
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚ج‚PƒOƒ‹پ[ƒv‚إ‚ ‚èپAپ@پu–يگ¶“n—ˆ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ Œnپvپi‰pپF‚s‚g‚dپ@‚x‚`‚x‚n‚hپ@‚s‚n‚q‚`‚h‚j‚d‚h
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚o‚d‚n‚o‚k‚dپjپ@‚جگl پXپiگl—قپj‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’ک “ْ–{ژjژ«“TپB
پثپ@“ْ–{گlپB پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پiƒOƒ‹پ[ƒvپ@پFپ@“ْ–{گlپ@پi= “ْ–{ڈيڈZ–¯پA
پ›پ@پuŒأ‘م“ْ–{گlپvپ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{’nˆو“y’…پEڈيڈZ–¯پjپ@ƒOƒ‹پ[ƒv
پ¨پ@پu–{“y“ْ–{گlپvپA ‚f‚’‚ڈ‚•‚گپ@‚i‚پ‚گ‚پ‚ژ‚…‚“‚…پ@‚m‚پ‚”‚‰‚–‚…پ@
پ@پu—®‹…گlپvپAپuƒAƒCƒkگlپvپBپ@ پi‚h‚ژ‚„‚‰‚‡‚…‚ژ‚ڈ‚•‚“پjپ@‚o‚…‚ڈ‚گ‚Œ‚…پjپB
پ›پ@پuŒأ‘م“ْ–{گlپvپ@پ@ پ@پ@پ@ پi‰pŒê–¼پF‚s‚g‚dپ@‚i‚`‚o‚`‚m‚d‚r‚d
پ@پ¨پ@پu’†گ¢“ْ–{گlپvپ@پ@پ@پ@پ@‚m‚`‚s‚h‚u‚dپ@پi‚h‚m‚c‚h‚f‚d‚m‚n‚t‚rپjپ@
پ@پ¨پ@پu‹كگ¢“ْ–{گlپvپ@پ@پ@پ@پ@‚o‚d‚n‚o‚k‚dپjپB
پ@پ¨پ@پu‹ك‘م“ْ–{گlپvپ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@“ْ–{گlپi= “ْ–{ڈيڈZ–¯پj‚حپAŒأ‘م
پ@پ¨پ@پuŒ»‘م“ْ–{گlپvپBپ@پ@پ@پ@“ْ–{‚إŒ`گ¬‚³‚ꂽپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ›پ@“ْ–{گlپi= “ْ–{ڈيڈZ–¯پj‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ŒأپEگVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒC ƒhچ¬ŒŒ‚جپAپu“ꕶپE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒnپv‚جپAپu–{“y“ْ–{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گlپv‚âپu—®‹…گlپv پ@‚ئپAپ@ŒأپEگVƒ‚ƒ“ƒS
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒچƒCƒhچ¬ŒŒ‚جپAپu“ꕶپE –kƒAƒWƒAڈ”–¯
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘°پEچ¬ŒŒŒnپv‚جپAپuƒAƒC ƒkگlپv‚ج‚Rژي—ق
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚جگl—ق‚ة•ھ‚©‚ê‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@Œ»چف‚ج‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚ج“ْ–{گl‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پu–{“yپ@“ْ–{گlپv‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@پu–{“y“ْ–{گlپv‚حپAپ@Œأ‘م“ْ–{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œمٹْ‚ةŒ`گ¬‚³‚ꂽپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@پu–{“y“ْ–{گlپv‚حپAپ@ پu“ꕶگlپv
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ئ‚»‚جژq‘·‚جپu“ꕶŒnپvپ@‚ئپAپ@پu“n
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—ˆŒn–يگ¶گlپv‚ئ‚»‚جژq‘·‚جپu–يگ¶
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“n—ˆŒnپvپ@‚ئ‚جچ¬ŒŒ‚جگl—ق‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@پu–{“y“ْ–{گlپv‚حپAپ@ŒأپEگV پi“ى
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•ûپE–k•ûپjƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhچ¬ŒŒ‚جپAپu“ê
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•¶پE–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒnپvپ@پi‰pپF‚s‚g‚dپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚i‚n‚l‚n‚m‚j‚d‚h-‚x‚`‚x‚n‚h‚s‚n‚q‚`‚h‚j‚d‚hپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚l‚h‚w‚d‚cپ@‚q‚`‚b‚h‚`‚kپ@‚o‚d‚n‚o‚k‚dپj ‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گlپXپiگl—قپj‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@“ْ–{گlپi= “ْ–{ڈيڈZ–¯پj‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒأپEگVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒC ƒhچ¬ŒŒ‚جپAپu“ꕶپE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒnپv‚جپAپu–{“y“ْ–{
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گlپv‚âپu—®‹…گlپv پi‰pپF‚s‚g‚dپ@‚l‚`‚h‚m-
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚k‚`‚m‚cپ@‚i‚`‚o‚`‚m‚d‚r‚d‚o‚d‚n‚o‚k‚dپCپ@
پ@ ‚s‚g‚dپ@‚q‚x‚t‚j‚x‚tپ@‚i‚`‚o‚`‚m‚d‚r‚dپ@
‚o‚d‚n‚o‚k‚dپjپ@‚ئپAپ@Œأ پEگVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒC
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒhچ¬ŒŒ‚جپAپu“ꕶپE –kƒAƒWƒAڈ”–¯‘°پE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چ¬ŒŒŒnپv‚جپA پuƒAƒCƒkگlپvپ@پi‰pپF‚s‚g‚dپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚`‚h‚m‚tپ@‚i‚`‚o‚`‚m‚d‚r‚dپ@ ‚o‚d‚n‚o‚k‚dپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‚Rژي—ق‚جگl—ق‚ة•ھ‚©‚ê‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@Œأ‘م“ْ–{‚إŒ`گ¬‚³‚ꂽ“ْ–{ گl
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= “ْ–{ڈيڈZ–¯پj‚حپAپ@ژ‘م‚ئ‹¤‚ةپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پuŒأ‘م“ْ–{گlپv‚©‚çپAپ@پu’†گ¢“ْ–{گlپvپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پu‹كگ¢“ْ–{گlپvپAپu‹ك‘م“ْ–{گlپvپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پuŒ»‘م“ْ–{گlپv‚ض‚ئپ@پ@ ڈ‚µ‚¸‚آپA•½
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹دگg’·‚ھگL‚ر‚é‚ب‚اپA—eژpپEٹOŒ©
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‘جŒ^پE‘جگFپj‚ً•د‰»‚³‚¹‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’ک “ْ–{ژjژ«“TپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ›پ@Œأ‘م“ْ–{‚إŒ`گ¬‚³‚ꂽ“ْ–{ گl
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi= “ْ–{ڈيڈZ–¯پj‚حپAپ@ژ‘م‚ئ‹¤‚ةپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پuŒأ‘م“ْ–{گlپvپi‰pپF‚s‚g‚dپ@‚`‚m‚b‚h‚d‚m‚sپ@ پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚i‚`‚o‚`‚m‚d‚r‚d‚o‚d‚n‚o‚k‚dپjپ@‚©‚çپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پu’†گ¢“ْ–{گlپvپAپu‹كگ¢“ْ–{گlپvپAپu‹ك‘م
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{گlپvپAپuŒ»‘م“ْ–{گlپvپ@پi‰pپF‚s‚g‚dپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚l‚d‚c‚h‚d‚u‚`‚kپ@‚i‚`‚o‚`‚m‚d‚r‚dپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚o‚d‚n‚o‚k‚dپCپ@ ‚s‚g‚dپ@‚d‚`‚q‚k‚xپ@‚l‚n-
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚c‚d‚q‚mپ@‚i‚`‚o‚`‚m‚d‚r‚dپ@‚o‚d‚n‚o‚k‚dپCپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚s‚g‚dپ@‚l‚n‚c‚d‚q‚mپ@‚i‚`‚o‚`‚m‚d‚r‚dپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚o‚d‚n‚o‚k‚dپCپ@ ‚s‚g‚d ‚o‚q‚d‚r‚d‚m‚s-‚c‚`‚xپ@
پ@‚i‚`‚o‚`‚m‚d‚r‚dپ@‚o‚d‚n‚o‚k‚dپjپ@‚ض‚ئڈ‚µ‚¸
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚آپA•½ ‹دگg’·‚ھگL‚ر‚é‚ب‚اپAپ@—eژpپEٹO
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ Œ©پi‘جŒ^پE‘جگFپj‚ً•د‰»‚³‚¹‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@
#thejomonkeipeople-appearingscenes
پ@
پôپôپ@“ꕶپE–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒn‚ھ“oڈê‚·‚éپA
پ@پ@پ@ ‹»–،گ[‚¢پAƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پAƒhƒ‰ƒ}پA
‰f‰وپB
پ@
پڑپ@“ꕶپE–يگ¶“n—ˆپEچ¬ŒŒŒnپ@‚ھ“oڈê‚·‚éپA
پ@پ@ ‹»–،گ[‚¢پAƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پB
پ@پ@
پ،پ@ƒTƒCƒGƒ“ƒX‚y‚d‚q‚nپ@
پ@پ@پw “ْ–{گl‚جƒ‹پ[ƒc”Œ©پIپ`
پ@پ@پ@پeپeٹj‚c‚m‚`پfپf‚ھ‰ً‚«–¾‚©‚·
پ@پ@پ@“ꕶگlپ` پxپB
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚P‚U”N‚SŒژ ‚R“ْپE–{•ْ‘—پE
پ@پ@پ@ ‰بٹwƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[”ش‘gپjپB
پœپ@“ْ–{گl‚جƒ‹پ[ƒcپi‹NŒ¹پj‚ًڈع‚µ‚ڈq‚ׂéپB
پœپ@“ꕶگlپi= Œأƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپj‚â“n—ˆŒn–يگ¶گl
پ@پ@پi= گVƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپj‚جگlپX‚ًڈq‚ׂéپB
پœپ@”Œ@‚µ‚½پA“ꕶگl‚جٹj‚c‚m‚`•ھگح‚ة‚و‚èپAŒ»گ¶پ@
پ@پ@گl—قپi= گVگlپAƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒXپj‚ج‹NŒ¹پEˆع“®
پ@پ@ƒ‹پ[ƒg‚â“ْ–{گl‚ج‹NŒ¹‚ً’m‚éپB
پ@
پ،پ@پw ‹³‰بڈ‘‚ھ•د‚ي‚éپIپHپ@“ْ–{گl
پ@پ@پ@ ‚جƒ‹پ[ƒc‚ً‚³‚®‚é—· پxپB
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚P‚T”N‚P‚QŒژ‚Q‚V“ْپE–{•ْ‘—پE
پ@پ@پ@ ‰بٹwƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[”ش‘gپjپB
پœپ@“ْ–{‚جŒ´ژnژ‘م‚ًگ¶‚«‚½پA‹Œگخٹيگl‚â“ꕶگl
پ@پ@ ‚ًڈq‚ׂéپB
پœپ@“ꕶگl‚ًڈع‚µ‚ڈq‚ׂéپBپ@“ꕶگl‚جˆâگص”Œ@‚â
پ@پ@ ƒ~ƒgƒRƒ“ƒhƒٹƒA‚c‚m‚`‚ة‚و‚èپAŒ»‘م“ْ–{گl‚جƒ‹پ[ƒc
پ@پ@پi‹NŒ¹پj‚ج‚PƒOƒ‹پ[ƒv‚إ‚ ‚éپA“ꕶگl‚ج‹NŒ¹پAگ¶
ٹˆپAˆع“®ƒ‹پ[ƒg‚ب‚ا‚ً’m‚éپB
پ@
پ،پ@ƒTƒCƒGƒ“ƒX‚y‚d‚q‚nپ@
پ@پ@ پw “ْ–{گl‚ج‹NŒ¹‚ة”—‚é پxپB
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚O‚V”N‚P‚QŒژ‚Q“ْپE–{•ْ‘—پE
پ@پ@پ@ ‰بٹwƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[”ش‘gپjپB
پœپ@ƒ~ƒgƒRƒ“ƒhƒٹƒA‚c‚m‚`‚ة‚و‚èپAŒ»گ¶گl—قپi= گVگlپA
پ@پ@ƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒXپj‚ج‹NŒ¹پEˆع“®ƒ‹پ[ƒg‚â“ْ–{
پ@پ@گl‚ج‹NŒ¹‚ً’m‚éپB
پ@
پ،پ@ƒTƒCƒGƒ“ƒX‚y‚d‚q‚nپ@
پ@پ@ پw ƒVƒٹپ[ƒYپ@ƒqƒg‚ج“ن‚ة”—‚é پxپB
پœپ@‘و‚PڈWپ@پu‚PپD‚c‚m‚`‚ھ‰ً‚«–¾‚©‚·پI
پ@پ@ گl—ق‚ج—·پv
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚O‚W”N‚P‚OŒژ‚P‚O“ْپE–{•ْ
پ@پ@پ@ ‘—پE‰بٹwƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[”ش‘gپjپB
پœپ@ƒ~ƒgƒRƒ“ƒhƒٹƒA‚c‚m‚`پA‚xگُگF‘جپAŒ¾Œê“™‚ة‚و‚èپA
پ@پ@Œ»گ¶گl—قپi= گVگlپAƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒXپj‚ج‹NŒ¹پE
پ@پ@ˆع“®ƒ‹پ[ƒg‚â“ْ–{گl‚ج‹NŒ¹‚ً’m‚éپB
پœپ@Œ»گ¶گl—قپi= گVگlپAƒzƒ‚پEƒTƒsƒGƒ“ƒXپj‚جپAڈo
پ@پ@ƒAƒtƒٹƒJ‚ئگ¢ٹE‚ض‚جٹgژU‚ئˆعڈZ‚ً’m‚éپB
پ@
پ،پ@ƒTƒCƒGƒ“ƒX‚y‚d‚q‚nپ@پwپ@“ء•ٌپI
پ@پ@ ‹Œگخٹيژ‘م‚جگlچœپ@‘ه—ت”Œ@پ@پxپBپ@
پ@پ@ پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚P‚R”N‚P‚PŒژ‚P‚V“ْپE–{•ْ‘—
پ@پ@ ƒeƒŒƒrپE‰بٹwƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[”ش‘gپjپB
پœپ@“ْ–{‚ج‹Œگخٹيگlپ@پi–ٌ‚R‚T‚O‚O‚O”N‘Oپ`–ٌ‚P‚Q
پ@پ@‚O‚O‚O”N‘O‚ة“ْ–{’nˆو‚ة‚¢‚½گl—قپjپ@‚ة‚آ‚¢‚ؤ
پ@پ@ڈq‚ׂéپB
پœپ@چ`گىگl‚â‹Œگخٹيگl‘S‘ج‚ة‚آ‚¢‚ؤڈq‚ׂéپB
پœپ@‰«“ꌧپEگخٹ_“‡پi‚¢‚µ‚ھ‚«‚¶‚ـپj‚ج”’•غٹئچھ
پ@پ@“cŒ´“´Œٹˆâگصپi‚µ‚ç‚ظ‚³‚¨‚ث‚½‚خ‚é‚ا‚¤‚¯‚آ
پ@پ@‚¢‚¹‚«پj‚إپA‚Q‚O‚O‚X”N‚و‚蔌@‚ھٹJژn‚³‚êپA‹Œ
پ@پ@گخٹيگl‚جگlچœ‚ھ‘ه—ت‚ة”Œ©‚³‚êپA‚ظ‚عŒ´Œ`
پ@پ@‚ً‚ئ‚ا‚ك‚é‹Œگخٹيگl‚ج“ھچœ‚جچœ‚ً“¾‚ç‚ê‚é‰آ
پ@پ@”\گ«‚à‚ ‚邱‚ئ‚ة‚آ‚¢‚ؤڈq‚ׂéپBپ@
پ@
پ،پ@پwپ@“ْ–{گlپ@‚ح‚é‚©‚ب—·پ@پxپBپ@
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚O‚P”Nگ§چىƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^
پ@پ@پ@ ƒٹپ[”ش‘gپjپBپ@
پ@پ@پ@پu‘وŒـڈWپ@‚»‚µ‚ؤپeپe“ْ–{گlپfپf‚ھ
پ@پ@پ@گ¶‚ـ‚ꂽپvپB
پ،پ@–يگ¶ژ‘م‘Oٹْ‚ةپAگ…“cˆîچى‚ًچs‚¤پA”_چkژه
پ@پ@‘ج‚جگVƒ‚ƒ“ƒSƒچ ƒCƒhپi= –k•ûƒ‚ƒ“ƒSƒچƒCƒhپj‚ج
پ@پ@گlپX‚ھپAƒAƒWƒA‘ه—¤‚و‚è“ْ–{’nˆوپiڈ‰‚ك‹مڈB
پ@پ@–{“yپj‚ة“n—ˆ‚µپA“ْ–{‚جپu“n—ˆŒn–يگ¶گlپvپi–ي
پ@پ@گ¶“n—ˆŒn‚جگlپXپj‚ئ‚ب‚èپAپ@ژë—آپEچجڈWژه‘ج
پ@پ@‚ج“ْ–{‚جگوڈZ–¯‚جŒأƒ‚ƒ“ƒSƒچ ƒCƒhپi= “ى•ûƒ‚
پ@پ@ƒ“ƒSƒچƒCƒhپj‚جپu“ꕶŒn–يگ¶گlپv‚ئ‘خ—§‚µ‚ب‚ھ
پ@پ@‚çپA“ْ–{–{“y‚ً–kڈمپE“Œگi‚µ‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‚»‚جŒمپA–يگ¶ژ‘مŒمٹْ‚ة‚حپAپu“n—ˆŒn–ي
پ@پ@گ¶گlپv‚ئپu“ꕶŒn–يگ¶گlپv‚حپA‹¦—ح‚µپAگ…“cˆî
پ@پ@چى‚ًچs‚¤‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½پB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@“‡’أ ‹`‹vپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ـ‚أ ‚و‚µ‚ذ‚³پjپBپ@
پ@
پ،پ@“‡’أ ‹`‹vپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@“‡’أ ‹`‹vپ@پi‚µ‚ـ‚أ ‚و‚µ‚ذ‚³پjپBپ@
پ،پ@گ¶–v”Nپ@پFپ@‚P‚T‚R‚Rپ`‚P‚U‚P‚P”NپB
پ،پ@‹مڈB‚ج‚ظ‚ع‘S“y‚ًگ§ˆ³ŒمپAپ@ڈG‹g‚ج‹مڈBگھ
پ@پ@”°‚إ‚P‚T‚W‚V”N‚ةچ~•ڑپB
پ،پ@گيچ‘پEˆہ“y“چژRژ‘م‚ج“‡’أژپ“–ژه‚إپA‹مڈB
پ@پ@‚ج•گڈ«پA‘ه–¼پB
پ،پ@“‡’أ ‹`چO‚جŒZپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“Tپ@‚T‚P‚X‚R‚SپB
پ@
پ@
پ،پ@“‡’أ ‹`‹vپ@پi‚µ‚ـ‚أ ‚و‚µ‚ذ‚³پAگ¶–v”NپF‚P‚T‚R
پ@پ@‚Rپ`‚P‚U‚P‚P”Nپjپ@‚حپAپ@گيچ‘پEˆہ“y“چژRژ‘م‚ةٹˆ
پ@پ@–ô‚µ‚½پA‹مڈB‚ج•گڈ«پA‘ه–¼‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@“‡’أ ‹`‹v‚حپAپ@“‡’أ ‹`چO‚جŒZ‚إپAپ@“‡’أژپ“–
پ@پ@ژه‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@
پ،پ@“‡’أ ‹`‹v‚حپAپ@’يپE“‡’أ ‹`چO‚ئ‚ئ‚à‚ةپA‹مڈB‚ج
پ@پ@‚ظ‚ع‘S“y‚ًگ§ˆ³ŒمپAپ@–LگbڈG‹g‚ج‹مڈBگھ”°پi“‡
پ@پ@’أگھ”°پj‚إ‚P‚T‚W‚V”N‚ةچ~•ڑ‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@“‡’أ ‹`‹v‚حپAپ@ڈG‹g‚ةچ~•ŒمپA“‡’أژپ“–ژه
پ@پ@‚ًˆّ‘ق‚µپA’يپE“‡’أ ‹`چO‚ةڈ÷‚éپB
پ@
پ@
پôپô “‡’أ ‹`‹v ‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢پA
پ@پ@ ƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پAƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپB
پ@
پڑپ@“‡’أ ‹`‹vپ@‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢
پ@پ@ٹضکAƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپBپ@
پœپ@پi’چˆسپjپ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAƒtƒBƒNƒVƒ‡ƒ“پ@‚إ‚·پBپ@
پ@پ@—ًژj‚جƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAپ@ژjژہپi—ًژjڈم‚جژ–
پ@پ@ژہپjپ@‚ئپ@‰ث‹َ‚جڈo—ˆژ–پ@‚ھچ¬‚¶‚ء‚ؤ•`‚©‚ê
پ@پ@‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپ@‚ـ‚½پAپ@Œ»‘م•—‚ةƒAƒŒƒ“ƒW‚µ‚ؤ‚
‚è‚ـ‚·پB
پ@
پ،پ@پw ŒRژt ٹ¯•؛‰qپ@پi‚®‚ٌ‚µ ‚©‚ٌ‚ׂ¦پj پxپ@
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚j‚Q‚O‚P‚S”N‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پjپBپ@
پ،پ@ژ؛’¬ژ‘مŒمٹْپiگيچ‘ژ‘مپjپAˆہ“y“چژRژ‘مپA
پ@پ@چ]Œثژ‘مڈ‰ٹْ‚ً•`‚¢‚½ƒhƒ‰ƒ}پB
پœپ@“‡’أ ‹`‹vپi‚µ‚ـ‚أ ‚و‚µ‚ذ‚³پj‚ً‰‰‚¶‚½پ@
پ@پ@”o—D–¼پF ‰iàV ڈr–îپ@پi‚ب‚ھ‚³‚ي ‚ئ‚µ‚âپjپB
پ@
پœپ@“‡’أ ‹`چO پi‚µ‚ـ‚أ ‚و‚µ‚ذ‚ëپj‚ً‰‰‚¶‚½
پ@پ@”o—D–¼پF پB
پœپ@‘ه—F ڈ@—ظ پi‚¨‚¨‚ئ‚à ‚»‚¤‚è‚ٌپj‚ً‰‰‚¶‚½
پ@پ@”o—D–¼پF ڈمٹ چP•Fپ@پi‚©‚ف‚¶‚ه‚¤ ‚آ‚ث‚ذ‚±پjپB
پœپ@چ•“c ٹ¯•؛‰q‚ً‰‰‚¶‚½”o—D–¼پF ‰ھ“cپ@ڈyˆêپB
پœپ@–LگbڈG‹gپi–ط‰؛“،‹gکYپA‰HژؤڈG‹gپj‚ً‰‰‚¶
پ@پ@‚½”o—D–¼پF ’|’†’¼گlپ@پi‚½‚¯‚ب‚©پE‚ب‚¨‚ئپjپB
پœپ@چ•“c ٹ¯•؛‰q‚ج’„’j‚جچ•“c’·گپi‚ب‚ھ‚ـ‚³پA
پ@پ@گ¬گlژپj‚ً‰‰‚¶‚é”o—DپFپ@ڈ¼چâپ@“چ‹Gپ@پi‚ـ‚آ
پ@پ@‚´‚©پ@‚ئ‚¨‚èپjپB
پœپ@“؟گى ‰ئچN‚ً‰‰‚¶‚½”o—D–¼پFپ@ژ›”ِ مà
پi‚ؤ‚炨 ‚ ‚«‚çپjپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@“‡’أ ‹`چOپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ـ‚أ ‚و‚µ‚ذ‚ëپjپBپ@
پ@
پ،پ@“‡’أ ‹`چOپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@“‡’أ ‹`چOپ@پi‚µ‚ـ‚أ ‚و‚µ‚ذ‚ëپjپBپ@
پ،پ@گ¶–v”Nپ@پFپ@‚P‚T‚R‚Tپ`‚P‚U‚P‚X”NپB
پ،پ@گخ“c•û‚جگ¼ŒR‚ة–،•û‚µپAٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢‚إ‚حپA
پ@پ@“ŒŒR‚ج“Gگw‚ً“ث”j‚µ‚ؤ‹Aچ‘پB
پ،پ@گيچ‘پEˆہ“y“چژRژ‘م‚ج“‡’أژپ“–ژه‚إپA‹مڈB
پ@پ@‚ج•گڈ«پA‘ه–¼پB
پ،پ@“‡’أ ‹`‹v‚ج’يپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“Tپ@‚T‚P‚X‚R‚TپB
پ@
پ@
پ،پ@“‡’أ ‹`چOپ@پi‚µ‚ـ‚أ ‚و‚µ‚ذ‚ëپAگ¶–v”NپF‚P‚T‚R‚T
پ@پ@پ`‚P‚U‚P‚X”Nپjپ@‚حپAپ@گيچ‘پEˆہ“y“چژRژ‘م‚ةٹˆ
پ@پ@–ô‚µ‚½پA‹مڈB‚ج•گڈ«پA‘ه–¼‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@“‡’أ ‹`چO‚حپAپ@ŒZپE“‡’أ ‹`‹v‚ئ‚ئ‚à‚ةپAپ@‹مڈB
پ@پ@‚ج‚ظ‚ع‘S“y‚ًگ§ˆ³‚µ‚½ŒمپAپ@–LگbڈG‹g‚ج‹مڈB
پ@پ@گھ”°پi“‡’أگھ”°پj‚إ‚P‚T‚W‚V”N‚ةچ~•ڑ‚·‚éپB
پ@
پ،پ@“‡’أ ‹`چO‚حپAپ@“‡’أ ‹`‹v‚ج’ي‚إپAپ@“‡’أ ‹`
پ@پ@چO‚ج“–ژهˆّ‘قŒمپAپ@“‡’أژپ“–ژه‚ة‚ب‚ء‚½پB
پ@
پ،پ@“‡’أ ‹`چO‚حپAپ@•¶ک\پEŒc’·‚ج–ًپi‚ش‚ٌ‚ë‚پE‚¯
پ@پ@‚¢‚؟‚ه‚¤‚ج‚¦‚«پA’©‘N‚ج–ًپAڈG‹g‚ج’©‘Nڈo•؛پj
پ@پ@‚إ‚حپAپ@ں™گىپi‚µ‚¹‚ٌپj‚جگي‚¢‚إ—E–¼پ@پi‚ن‚¤‚ك
پ@پ@‚¢پA—Eژز‚ئ‚µ‚ؤ‚ج–¼گ؛پjپ@‚ً‚ح‚¹‚éپB
پ@
پ،پ@“‡’أ ‹`چO‚حپAپ@گخ“c•û‚جگ¼ŒR‚ة–،•û‚µپA‚P‚U‚O
پ@پ@‚O”N‚جٹضƒ–Œ´‚جگي‚¢‚إ‚ح“ŒŒR‚ج“Gگw‚ً“ث”j‚µ
پ@پ@‚ؤ‹Aچ‘‚·‚éپB
پ@
پ@
پôپô “‡’أ ‹`چO ‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢پA
پ@پ@ ƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پAƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپB
پ@
پڑپ@“‡’أ ‹`چOپ@‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢
پ@پ@ٹضکAƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپBپ@
پœپ@پi’چˆسپjپ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAƒtƒBƒNƒVƒ‡ƒ“پ@‚إ‚·پBپ@
پ@پ@—ًژj‚جƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAپ@ژjژہپi—ًژjڈم‚جژ–
پ@پ@ژہپjپ@‚ئپ@‰ث‹َ‚جڈo—ˆژ–پ@‚ھچ¬‚¶‚ء‚ؤ•`‚©‚ê
پ@پ@‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپ@‚ـ‚½پAپ@Œ»‘م•—‚ةƒAƒŒƒ“ƒW‚µ‚ؤ‚
‚è‚ـ‚·پB
پ@
پ،پ@پw ŒRژt ٹ¯•؛‰qپ@پi‚®‚ٌ‚µ ‚©‚ٌ‚ׂ¦پj پxپ@
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚j‚Q‚O‚P‚S”N‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پjپBپ@
پ،پ@ژ؛’¬ژ‘مŒمٹْپiگيچ‘ژ‘مپjپAˆہ“y“چژRژ‘مپA
پ@پ@چ]Œثژ‘مڈ‰ٹْ‚ً•`‚¢‚½ƒhƒ‰ƒ}پB
پœپ@“‡’أ ‹`چO پi‚µ‚ـ‚أ ‚و‚µ‚ذ‚ëپj‚ً‰‰‚¶‚½
پ@پ@”o—D–¼پF پB
پ@
پœپ@“‡’أ ‹`‹v پi‚µ‚ـ‚أ ‚و‚µ‚ذ‚³پj‚ً‰‰‚¶‚½پ@
پ@پ@”o—D–¼پF ‰iàV ڈr–îپ@پi‚ب‚ھ‚³‚ي ‚ئ‚µ‚âپjپB
پœپ@‘ه—F ڈ@—ظ پi‚¨‚¨‚ئ‚à ‚»‚¤‚è‚ٌپj‚ً‰‰‚¶‚½
پ@پ@”o—D–¼پF ڈمٹ چP•Fپ@پi‚©‚ف‚¶‚ه‚¤ ‚آ‚ث‚ذ‚±پjپB
پœپ@چ•“c ٹ¯•؛‰q‚ً‰‰‚¶‚½”o—D–¼پF ‰ھ“cپ@ڈyˆêپB
پœپ@–LگbڈG‹gپi–ط‰؛“،‹gکYپA‰HژؤڈG‹gپj‚ً‰‰‚¶
پ@پ@‚½”o—D–¼پF ’|’†’¼گlپ@پi‚½‚¯‚ب‚©پE‚ب‚¨‚ئپjپB
پœپ@چ•“c ٹ¯•؛‰q‚ج’„’j‚جچ•“c’·گپi‚ب‚ھ‚ـ‚³پA
پ@پ@گ¬گlژپj‚ً‰‰‚¶‚é”o—DپFپ@ڈ¼چâپ@“چ‹Gپ@پi‚ـ‚آ
پ@پ@‚´‚©پ@‚ئ‚¨‚èپjپB
پœپ@“؟گى ‰ئچN‚ً‰‰‚¶‚½”o—D–¼پFپ@ژ›”ِ مàپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@“‡’أ ‰ئ‹vپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ـ‚أ ‚¢‚¦‚ذ‚³پjپBپ@
پ@
پ،پ@“‡’أ ‰ئ‹vپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@“‡’أ ‰ئ‹vپ@پi‚µ‚ـ‚أ ‚¢‚¦‚ذ‚³پjپBپ@
پ،پ@‚P‚U‚O‚X”N‚ةپA—®‹…‰¤چ‘‚ًگھ•‚·‚éپBپ@
پ،پ@ژF–€”ث‚ج—®‹…پi‰«“êپjژx”z‚ةڈعچׂةٹض‚µ‚ؤ‚حپA
پ@پ@پu‰«“ê‚ج—ًژjپv‚ًژQڈئ‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“Tپ@‚T‚P‚X‚R‚UپB
پ@
پ@
پ،پ@ژF–€”ث‚ج”ثژهپE“‡’أ‰ئ‹vپi‚µ‚ـ‚أ‚¢‚¦‚ذ‚³پj‚ھپA
پ@پ@‚P‚U‚O‚X”N‚ةپAپ@—®‹…‰¤چ‘‚ًگھ•‚·‚éپBپ@
پ@
پ،پ@‚P‚U‚O‚X”N‚©‚ç‚P‚W‚V‚P”N‚ـ‚إپA—®‹…‰¤چ‘‚حپAژہژ؟
پ@پ@“I‚ةپAژF–€”ث‚جژx”z‰؛‚ة“ü‚èپA”¼“ئ—§چ‘‚ئ‚ب‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@“‡’أ ‰ئ‹v‚حپAپ@چ]Œثژ‘مڈ‰ٹْ‚جژF–€”ثپE”ثژهپA
پ@پ@‚إپA“‡’أژپ“–ژه‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@
پ@
پ،پ@‚P‚U‚O‚U”N پiŒc’·‚P‚P”Nپj‚ةپAپ@ژF–€”ث‚ج”ثژهپE“‡
پ@پ@’أ‰ئ‹vپi‚µ‚ـ‚أ‚¢‚¦‚ذ‚³پj‚ھپAپ@“؟گى‰ئچNپiچ]Œث
پ@پ@–‹•{‚ج‘nگفژزپj‚و‚èپA پ@—®‹…‰¤چ‘‚جگھ•‚ً‹–‰آ
پ@پ@‚³‚ê‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@‚P‚U‚O‚X”N پiŒc’·‚P‚S”Nپj‚ةپA“‡’أ‰ئ‹v‚ج–½—ك‚إ
پ@پ@“‡’أژپ‚ھ—®‹…‰¤چ‘‚ةگiچU‚µپAپ@—®‹…‰¤چ‘‚جچ‘
پ@پ@‰¤پEڈ®”Jپi‚µ‚ه‚¤‚ث‚¢پj‚حچ~•ڑ‚·‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‚±‚êˆبŒمپA‚P‚W‚V‚P”Nپi–¾ژ،‚S”Nپj‚ـ‚إپA—®‹…
پ@پ@پi‰«“êپj‚حپAژہژ؟ڈمپAژF–€”ث‚ھ“ژ،‚·‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@‚P‚U‚P‚P”N پiŒc’·‚P‚U”Nپj‚ةپAپ@ژF–€”ث‚حپA—®‹…
پ@پ@پi‰«“êپj‚إŒں’nپi—®‹…Œں’nپj‚ًژہژ{‚·‚éپB
پ،پ@‚P‚U‚P‚P”N پiŒc’·‚P‚U”Nپj‚ةپAپ@ژF–€”ث‚حپA—®‹…
پ@پ@‰¤چ‘‚ھژç‚éپu|پi‚¨‚«‚ؤپjپv‚P‚Tڈً‚ًگ§’è‚·‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ،پ@‚P‚U‚P‚P”N پiŒc’·‚P‚U”Nپj‚ةپAپ@ژF–€”ث‚حپA‰‚”ü
پ@پ@پi‚ ‚ـ‚فپjڈ”“‡‚ً’¼ٹچ—ج‚ئ‚·‚éپB
پ@
پ@
#historyofokinawa-appearingscenes
پ@
پôپôپ@“‡’أ ‰ئ‹vپ@‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–، گ[
پ@پ@‚¢پAƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پAƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپB
پ@
پڑپ@“‡’أ ‰ئ‹vپ@‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢پA
پ@پ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپB
پœپ@پi’چˆسپjپ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAپ@ƒtƒBƒNƒVƒ‡ƒ“پ@‚إ‚·پBپ@
پ@پ@—ًژj‚جƒhƒ‰ƒ}پAپ@‰f‰و‚حپAپ@ژjژہپi—ًژjڈم‚جژ–
پ@پ@ژہپjپ@‚ئپ@‰ث‹َ‚جڈo—ˆژ–پ@‚ھپ@چ¬‚¶‚ء‚ؤ•`‚©‚ê
پ@پ@‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپ@‚ـ‚½پAپ@Œ»‘م•—‚ةƒAƒŒƒ“ƒW‚µ‚ؤ‚ ‚è
پ@پ@‚ـ‚·پB
پ@
پ،پ@پwپ@—®‹…‚ج•—پ@‚c‚q‚`‚f‚n‚mپ@‚r‚o‚h‚q‚h‚sپ@
پ@پ@پi‚è‚م‚¤‚«‚م‚¤‚ج‚©‚؛پ@ƒhƒ‰ƒSƒ“پ@ƒXƒsƒٹƒbƒgپjپ@پx
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚j ‚P‚X‚X‚R”N‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پjپB
پœپ@‚P‚Uگ¢‹I––‚©‚ç‚P‚Vگ¢‹Iڈ‰“ھ‚ـ‚إ‚جٹ®‘S“ئ—§
پ@پ@‚ج—®‹…پi‰«“êپjپ@‚ئپAپ@‚»‚جŒم‚جژF–€”ثژx”z‰؛
پ@پ@‚ج”¼“ئ—§‚ج—®‹…پi‰«“êپj‚ً•`‚¢‚½پAƒhƒ‰ƒ}پB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@گEˆُ—ك‚جˆتٹKپ@
پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚‚¢‚ٌ‚ê‚¢‚ج‚¢‚©‚¢پjپB
پ@
پ،پ@گEˆُ—ك‚جˆتٹKپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@گEˆُ—ك‚جˆتٹKپ@پi‚µ‚ه‚‚¢‚ٌ‚ê‚¢‚ج‚¢‚©‚¢پjپB
پ،پ@گEˆُ—ك‚حپA‚P‚W‚U‚X”Nگ§’èپB
پ،پ@گEˆُ—ك‚حپA‹ك‘م“ْ–{گ•{‚جپAˆتٹK‚ب‚ا‚ً
پ@پ@’è‚ك‚½–@—كپB
پ،پ@‚P‚W‚U‚X”Nگ§’è‚جگEˆُ—ك‚©‚ç‚P‚W‚W‚V”N
پ@پ@گ§’è‚جڈ–ˆتڈً—ل‚ض‚ج•دچX‚ـ‚إپB
پ،پ@گEˆُ—ك‚جˆتٹK‚حپA‚P‚W‚U‚X”Nپi–¾ژ،‚Q”Nپjچ ‚©
پ@پ@‚ç‚P‚W‚W‚V”Nپi–¾ژ،‚Q‚O”Nپjچ ‚ـ‚إپAژg—p‚³‚ꂽپB
پ،پ@‹ك‘م“ْ–{‚جگEˆُ—ك‚ج‚Q‚OˆتٹK
پ@پ@پƒ‚P‚W‚U‚X”Nچ پ`‚P‚W‚W‚V”Nچ پAژg—pپ„پB
پ@پ@پ›پ@ڈمˆتڈ‡‚ةپAگ³ˆêˆتپAڈ]ˆêˆتپAگ³“ٌˆتپA
پ@پ@ڈ]“ٌˆتپAگ³ژOˆتپAڈ]ژOˆتپAگ³ژlˆتپAڈ]ژlˆتپA
پ@پ@گ³ŒـˆتپAڈ]ŒـˆتپAگ³کZˆتپAڈ]کZˆتپAگ³ژµˆتپA
پ@پ@ڈ]ژµˆتپAگ³”ھˆتپAڈ]”ھˆتپAگ³‹مˆتپAڈ]‹مˆتپA
پ@پ@‘هڈ‰ˆتپAڈڈ‰ˆتپB
پ،پ@ˆتٹKپi‚¢‚©‚¢پjپAڈ–ˆتپi‚¶‚ه‚¢پj‚ةٹض‚µ‚ؤ‚حپA
پ@پ@پuˆتٹKپvپAپuڈ–ˆتپv‚ًژQڈئ‚‚¾‚³‚¢پB
پ،پ@‹كپEŒ»‘م“ْ–{‚جپA‹كپEŒ»‘م“ْ–{گ•{‚جˆت
پ@پ@ٹK‚ةٹض‚µ‚ؤ‚حپAپu‹كپEŒ»‘م“ْ–{گ•{‚جˆتٹKپv
پ@پ@‚ًژQڈئ‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جپA’©’ى‚جˆتٹK‚ةٹض‚µ‚ؤ‚حپA
پu’©’ى‚جˆتٹKپv‚ًژQڈئ‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“Tپ@‚T‚P‚V‚Q‚RپB
پ@
پ پ@‹ك‘م‚جگEˆُ—ك‚جˆتٹKپB
پ@پ@پ@پi‚P‚W‚U‚X”Nچ پ`‚P‚W‚W‚V”Nچ پjپBپ@
پ@
پ@
پ،پ@گEˆُ—كپ@پi‚µ‚ه‚‚¢‚ٌ‚ê‚¢پj‚حپAپ@‹ك‘م“ْ–{گ
پ@پ@•{‚جپAˆتٹK‚ب‚ا‚ً’è‚ك‚½–@—كپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@گEˆُ—ك‚حپA‚P‚W‚U‚X”N‚ةگ§’肳‚êپA‚P‚W‚W‚V
پ@پ@”Nگ§’è‚جڈ–ˆتڈً—ل‚ض‚ج•دچX‚ـ‚إپAŒّ—ح‚ً‚à
پ@پ@‚ء‚½پB
پ،پ@گEˆُ—ك‚جˆتٹK‚حپA‚P‚W‚U‚X”Nپi–¾ژ،‚Q”Nپjچ ‚©
پ@پ@‚ç‚P‚W‚W‚V”Nپi–¾ژ،‚Q‚O”Nپjچ ‚ـ‚إپAژg—p‚³‚ꂽپB
پ@
پ@
پ،پ@ˆتٹK‚حپAپ@–¾ژ،ژ‘م’†ٹْˆبŒم‚ج‹كپEŒ»‘م“ْ
پ@پ@–{‚إ‚حپA‰h“T‚جˆت‚ًژ¦‚µپAپ@‘O‹ك‘م‚â–¾ژ،ژ
پ@پ@‘مڈ‰ٹْ‚ج“ْ–{‚إ‚حپAٹ¯گE‚جڈک—ٌ‚ًژ¦‚·پB
پ@
پ،پ@‹كپEŒ»“ْ–{‚جڈ–ˆتڈً—لپi‚P‚W‚W‚V”Nگ§’èپj‚âˆت
پ@پ@ٹK—كپi‚P‚X‚Q‚U”Nگ§’èپj‚جڈ–ˆت‚إ‚حپAپ@ˆتٹK‚حپA
پ@پ@گ³ˆêˆتپi‚µ‚ه‚¤‚¢‚؟‚¢پj‚©‚çڈ]”ھˆتپi‚¶‚م‚ح‚؟‚¢پj
پ@پ@‚ـ‚إ‚ج‚P‚UˆتٹKپ@‚ھ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@گيŒم‚حپAˆتٹK—ك‚ح‰üگ³‚³‚êپi‚P‚X‚S‚V”N‚ج
پ@پ@‰üگ³ˆتٹK—ك‚إپjپAپ@گ¶‘¶ژز‚ض‚جڈ–ˆت‚ً’âژ~‚µپAپ@
پ@پ@“Vچc‚ةڈ–ˆت‚جŒˆ’èŒ ‚ح‚ب‚پA“ْ–{چ‘Œ›–@‰؛پA
پ@پ@“àٹt‚جڈ•Œ¾‚ئڈ³”F‚ة‚و‚èپA“Vچc‚ھچ‘ژ–چsˆ×
پ@پ@‚ئ‚µ‚ؤپAŒ÷گر‚ج‚ ‚ء‚½پAŒجگlپiژ€–Sژزپj‚ض‚ج‚فپA
پ@پ@ڈ–ˆت‚ًچs‚ء‚ؤ‚¢‚éپB
پ@
پ،پ@‚P‚W‚V‚P”Nپi–¾ژ،‚S”Nپj‚ةپAٹ¯ˆت‘ٹ“–گ§پ@پi’©’ى
پ@پ@‚إپAˆتٹK‚ة‘خ‰‚µ‚½ٹ¯گE‚ةڈA‚‚±‚ئ‚ًŒ´‘¥‚ئ‚·
پ@پ@‚éگ§“xپjپ@‚حپA”pژ~‚³‚êپAپ@ˆتٹK‚ئٹ¯گE‚جٹضŒW
پ@پ@‚ح’f‚½‚êپAˆتٹK‚حپA‚P‚W‚W‚V”N‚جڈ–ˆتڈً—ل‚جŒِ
پ@پ@•z‚ة‚و‚èپAˆبŒمپA‰h“T‚ج–ًٹ„‚ة“ء‰»‚µ‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‚ـ‚½پAگيŒمپAگ¶‘¶ژز‚ض‚جڈ–ˆت‚حپAچs‚ي‚ê
پ@پ@‚ب‚‚ب‚èپAŒجگlپiژ€–Sژزپj‚ج‚ف‚ض‚جڈ–ˆت‚ھچs‚ي
پ@پ@‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
پ@
پ،پ@ڈ–ˆتپ@پi‚¶‚ه‚¢پj‚ئ‚حپAپ@ˆتٹK‚ًژِ—^‚·‚邱‚ئپA
پ@پ@ˆتٹK‚ةڈ–پi‚¶‚هپj‚·‚邱‚ئپ@‚إ‚ ‚éپB “Vچc‚ھ
پ@پ@ˆتٹK‚ًژِ—^‚·‚邱‚ئ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@ˆتٹK‚ة‚حپAپ@ژ‘م•ت‚ةپA‚RƒOƒ‹پ[ƒv‚جˆتٹK
پ@پ@‚ھ‚ ‚éپBپ@ پi‚Pپjپ@‚V‚O‚P”Nچ ‚©‚ç‚P‚W‚U‚X”Nچ ‚ـ‚إ
پ@پ@‚ج‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj‚جˆتٹKپA پ@
پ@پ@پi‚Qپj ‚P‚W‚U‚X”Nچ ‚©‚ç‚P‚W‚W‚V”Nچ ‚ـ‚إ‚جپA‘¾گ
پ@پ@ٹ¯گ§‚جگEˆُ—كپi‚P‚W‚U‚X”Nگ§’èپj‚جˆتٹK پAپ@پi‚Rپjپ@
پ@پ@‚P‚W‚W‚V”Nچ ‚©‚猻چف‚ـ‚إ‚جپAڈ–ˆتڈً—لپi‚P‚W‚W‚V
پ@پ@”Nگ§’èپj‚جˆتٹK ‚ئ ˆتٹK—كپi‚P‚X‚Q‚U”Nگ§’èپA‚P‚X
پ@پ@‚S‚V”N‰üگ³پj‚جˆت ٹKپ@‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پ@
پ،پ@گEˆُ—ك‚جˆتٹKگ§“x‚ئ‘¼‚جژٹْ‚ج
پ@پ@ˆتٹKگ§“x‚ئ‚ج”نٹr•\پB
پœپ@ژ‘م•تپA‚RƒOƒ‹پ[ƒv‚جˆتٹKپB
پ@
پi‚Pپjپ@‹كپEŒ»‘م‚جڈ–ˆتڈً—ل‚âˆتٹK—ك
پ@پ@‚جˆتٹKپB
پ@پ@پ@‹كپEŒ»‘م“ْ–{گ•{‚جپAڈ–ˆتڈً—لپi‚P‚W‚W‚V
پ@پ@”Nگ§’èپj‚âˆتٹK—كپi‚P‚X‚Q‚U”Nگ§’èپA‚P‚X‚S‚V
پ@پ@”N‰üگ³پj‚جˆتٹKپB
پ@پ@پ@پƒ‚P‚W‚W‚V”Nچ پ`Œ»چفپAژg—pپ„پB
پ@پ@پ@ˆêˆت‚©‚ç”ھˆت‚ـ‚إ‚جپA‚P‚UˆتٹKپB
پiپث ˆتٹK—ك ‚جˆتٹKپjپB
پiپث ڈ–ˆتڈً—ل‚جˆتٹKپjپB
پ@
پi‚Qپjپ@‹ك‘م‚جگEˆُ—ك‚جˆتٹKپB
پ@پ@پ@پ@‹ك‘م“ْ–{گ•{‚جپA‘¾گٹ¯گ§‚جگEˆُ—ك
پ@پ@‚جپi‚P‚W‚U‚X”Nگ§’èپj‚جˆتٹKپB
پ@پ@پ@پƒ‚P‚W‚U‚X”Nچ پ`‚P‚W‚W‚V”Nچ پAژg—pپ„پB
پ@پ@ˆêˆت‚©‚ç”ھˆتپA‹مˆتپAڈ‰ˆت‚ـ‚إ‚جپA‚Q‚OˆتٹKپB
پ@پ@پiپث گEˆُ—ك‚جˆتٹKپjپB
پ@
پi‚Rپjپ@‘O‹ك‘م‚ج’©’ىپi—¥—ك ٹ¯گ§پj‚ج
پ@پ@ˆتٹKپB
پ@پ@پ@پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جپA’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj‚جˆتٹKپB
پ@پ@پ@پƒ‚V‚O‚P”Nچ پ`‚P‚W‚U‚X”Nچ پAژg—pپ„پBپ@
پ@پ@ˆêˆت‚©‚ç”ھˆتپAڈ‰ˆت‚ـ‚إ‚جپA‚R‚OˆتٹKپB
پ@پ@پ@پiپث ’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj ‚جˆتٹKپjپB
پ@
پ،پ@پi‚Pپjپ@‹كپEŒ»‘م‚جڈ–ˆتڈً—ل‚âˆتٹK—ك‚جˆتٹKپB
پ@پ@پ@‹كپEŒ»‘م“ْ–{‚جڈ–ˆتڈً—لپi‚P‚W‚W‚V”Nگ§’èپjپA
پ@پ@پ@ˆتٹK—كپi‚P‚X‚Q‚U”Nگ§’èپA‚P‚X‚S‚V”N‰üگ³پj‚إ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@ˆتٹK‚حپAگ³ˆêˆتپi‚µ‚ه‚¤‚¢‚؟‚¢پj‚©‚çڈ]”ھ
پ@پ@پ@ˆتپi‚¶‚م‚ح‚؟‚¢پj‚ـ‚إ‚ج‚P‚UˆتٹKپ@‚ھ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@گيŒم‚حپAŒ÷گر‚ج‚ ‚ء‚½Œجگlپiژ€–Sژزپj‚ض
پ@پ@پ@‚ج‚فپAڈ–ˆت‚ھچs‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
پiپث ˆتٹK—ك ‚جˆتٹKپjپB
پiپث ڈ–ˆتڈً—ل‚جˆتٹKپjپB
پ@
پ،پ@پi‚Qپjپ@‹ك‘م‚جگEˆُ—ك‚جˆتٹKپB
پ@پ@پ@پ@پ@‹ك‘م“ْ–{‚ج‘¾گٹ¯گ§‚جگEˆُ—ك پi‚P‚W‚U‚X
پ@پ@پ@”Nگ§’èپj‚جڈ–ˆت‚إ‚حپA
پ@پ@پ@ˆتٹK‚حپAگ³ˆêˆتپi‚µ‚ه‚¤‚¢‚؟‚¢پj‚©‚çڈڈ‰ˆت
پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚»‚¢پj‚ـ‚إ‚ج‚Q‚OˆتٹKپ@‚ھ‚ ‚éپB
پ@پ@پiپث گEˆُ—ك‚جˆتٹKپjپB
پ@
پ،پ@پi‚Rپjپ@‘O‹ك‘م‚ج’©’ىپi—¥—ك ٹ¯گ§پj‚جˆتٹKپB
پ@پ@پ@پ@پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj‚جڈ–ˆت
پ@پ@پ@‚إ‚حپAپ@’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj‚جˆتٹK‚حپAگ³ˆêˆت
پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚¢‚؟‚¢پj‚©‚çڈڈ‰ˆت‰؛پi‚µ‚ه‚¤‚»‚¢‚ج
پ@پ@پ@‚°پj‚ـ‚إ‚ج‚R‚OˆتٹKپ@‚ھ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پiپث ’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj ‚جˆتٹKپjپB
پ@
پ@
پ@
پ@
پںپ@‹ك‘م“ْ–{گ•{‚جپA‘¾گٹ¯گ§‚ج
پ@پ@گEˆُ—كپi‚P‚W‚U‚X”Nگ§’èپj‚جˆتٹKپB
پ@پ@پiپث گEˆُ—ك‚جˆتٹKپjپB
پ@
پ،پ@پƒ‚P‚W‚U‚X”Nچ پ`‚P‚W‚W‚V”Nچ پ„پ@‚Q‚OˆتٹKپB
پ،پ@‹ك‘م“ْ–{گ•{‚جˆتٹK‚جپAپuˆêˆتپ` ”ھˆتپA
پ@پ@‹مˆتپi‚‚¢پjپAڈ‰ˆتپi‚»‚¢پjپv ‚ج‚P‚OƒOƒ‹پ[ƒv‚جپA
پ@پ@‚Q‚OˆتٹKپBپ@
پœپ@‹ك‘م‚جگEˆُ—ك‚جˆتٹK‚ة‚حپAپ@ˆêˆت‚©‚ç”ھˆت‚ـ
پ@پ@‚إپA‹مˆتپAڈ‰ˆتپi‚»‚¢پj‚ـ‚إ‚ج‚P‚O’iٹK‚ھ‚ ‚èپA
پ@پ@گ³پi‚µ‚ه‚¤پjپEڈ]پi‚¶‚مپj‚ً‚آ‚¯‚ؤپA‚Q‚OˆتٹK‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@‹ك‘م‚جگEˆُ—ك‚ج‚Q‚OˆتٹKپ@
پ@پ@پiڈمˆتڈ‡‚ةپAپ@گ³ˆêˆتپAپ@ڈ]ˆêˆتپAپ@گ³“ٌˆتپA
پ@پ@ڈ]“ٌˆتپAگ³ژOˆتپAڈ]ژOˆتپAگ³ژlˆتپAڈ]ژlˆتپA
پ@پ@گ³ŒـˆتپAڈ]ŒـˆتپAگ³کZˆتپAڈ]کZˆتپAگ³ژµˆتپA
پ@پ@ڈ]ژµˆتپAگ³”ھˆتپAڈ]”ھˆتپAگ³‹مˆتپAڈ]‹مˆتپA
پ@پ@‘هڈ‰ˆتپAڈڈ‰ˆتپjپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@ˆêˆتپ@پi‚¢‚؟‚¢پjپBپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‰pپFپ@‚s‚ˆ‚…پ@‚P‚“‚”پ@‚h‚‹‚پ‚‰پ@‚q‚پ‚ژ‚‹پjپB
پ@پ@پœپ@گ³ˆêˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚¢‚؟‚¢پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‰pپFپ@‚s‚ˆ‚…پ@‚n‚’‚„‚‰‚ژ‚پ‚’‚™پ@‚P‚“‚”پ@‚h‚‹‚پ‚‰پ@‚q‚پ‚ژ‚‹پjپB
پ@پ@پœپ@ڈ]ˆêˆتپ@پi‚¶‚م‚¢‚؟‚¢پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‰pپFپ@‚s‚ˆ‚…پ@‚r‚•‚‚‚ڈ‚’‚„‚‰‚ژ‚پ‚”‚…پ@‚P‚“‚”پ@‚h‚‹‚پ‚‰پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚q‚پ‚ژ‚‹پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@پ،پ@“ٌˆتپ@پi‚ة‚¢پjپBپ@پ@
پ@پ@پœپ@گ³“ٌˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚ة‚¢پjپB
پ@پ@پœپ@ڈ]“ٌˆتپ@پi‚¶‚م‚ة‚¢پjپB
پ@پ،پ@ژOˆتپ@پi‚³‚ٌ‚فپjپBپ@پ@
پ@پ@پœپ@گ³ژOˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚³‚ٌ‚فپjپB
پ@پ@پœپ@ڈ]ژOˆتپ@پi‚¶‚م‚³‚ٌ‚فپjپB
پ@پ،پ@ژlˆتپ@پi‚µ‚¢پjپBپ@پ@
پ@پ@پœپ@گ³ژlˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚¢پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‰pپFپ@‚s‚ˆ‚…پ@‚n‚’‚„‚‰‚ژ‚پ‚’‚™پ@‚S‚”‚ˆپ@‚h‚‹‚پ‚‰پ@‚q‚پ‚ژ‚‹پjپB
پ@پ@پœپ@ڈ]ژlˆتپ@پi‚¶‚م‚µ‚¢پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‰pپFپ@‚s‚ˆ‚…پ@‚r‚•‚‚‚ڈ‚’‚„‚‰‚ژ‚پ‚”‚…پ@‚S‚”‚ˆپ@‚h‚‹‚پ‚‰پ@
پ@پ@پ@ پ@پ@پ@‚q‚پ‚ژ‚‹پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@پ،پ@Œـˆتپ@پi‚²‚¢پjپBپ@پ@
پ@پ@پœپ@گ³Œـˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚²‚¢پjپB
پ@پ@پœپ@ڈ]Œـˆتپ@پi‚¶‚م‚²‚¢پjپB
پ@پ،پ@کZˆتپ@پi‚ë‚‚¢پjپBپ@پ@
پ@پ@پœپ@گ³کZˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚ë‚‚¢پjپB
پ@پ@پœپ@ڈ]کZˆتپ@پi‚¶‚م‚ë‚‚¢پjپB
پ@پ،پ@ژµˆتپ@پi‚µ‚؟‚¢پjپBپ@پ@
پ@پ@پœپ@گ³ژµˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚؟‚¢پjپB
پ@پ@پœپ@ڈ]ژµˆتپ@پi‚¶‚م‚µ‚؟‚¢پjپB
پ@پ،پ@”ھˆتپ@پi‚ح‚؟‚¢پjپBپ@پ@
پ@پ@پœپ@گ³”ھˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚ح‚؟‚¢پjپB
پ@پ@پœپ@ڈ]”ھˆتپ@پi‚¶‚م‚ح‚؟‚¢پjپB
پ@پ،پ@‹مˆتپ@پi‚‚¢پjپBپ@پ@
پ@پ@پœپ@گ³‹مˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚‚¢پjپB
پ@پ@پœپ@ڈ]‹مˆتپ@پi‚¶‚م‚‚¢پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@پ،پ@ڈ‰ˆتپ@پi‚»‚¢پA‚µ‚ه‚¢پjپBپ@پ@
پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پi‰pپFپ@‚s‚ˆ‚…پ@‚k‚ڈ‚—‚…‚“‚”پ@‚h‚‹‚پ‚‰پ@‚q‚پ‚ژ‚‹پjپBپ@
پ@پ@پœپ@‘هڈ‰ˆتپ@پi‚¾‚¢‚»‚¢پA‚¾‚¢‚µ‚ه‚¢پjپB
پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پi‰pپFپ@‚s‚ˆ‚…پ@‚n‚’‚„‚‰‚ژ‚پ‚’‚™پ@‚k‚ڈ‚—‚…‚“‚”پ@‚h‚‹‚پ‚‰پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚q‚پ‚ژ‚‹پjپB
پ@پ@پœپ@ڈڈ‰ˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚»‚¢پA‚µ‚ه‚¤‚µ‚ه‚¢پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‰pپFپ@‚s‚ˆ‚…پ@‚r‚•‚‚‚ڈ‚’‚„‚‰‚ژ‚پ‚”‚…پ@‚k‚ڈ‚—‚…‚“‚”
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚h‚‹‚پ‚‰پ@‚q‚پ‚ژ‚‹پ@پjپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ،پ@‹ك‘م“ْ–{گ•{‚جپA‘¾گٹ¯گ§‚جپA
پ@پ@گEˆُ—ك‚جˆتٹKپB
پ@پ@پƒ‚P‚W‚U‚X”Nچ پ`‚P‚W‚W‚V”Nچ پ„پ@
پ@پ@ˆêˆت‚©‚ç‹مˆتپAڈ‰ˆت‚ـ‚إ‚ج‚Q‚OˆتٹKپB
پ@
پ،پ@‹ك‘م“ْ–{گ•{‚جپA‘¾گٹ¯گ§‚جپAگEˆُ—ك پi‚P‚W
پ@پ@‚U‚X”Nگ§’èپj‚جˆتٹK‚حپAپ@ˆêˆت‚©‚ç ”ھˆتپA‹مˆتپA
پ@پ@ڈ‰ˆت‚ـ‚إ‚جپA‚Q‚OˆتٹK‚إ‚ ‚èپAپ@‚P‚W‚U‚X”Nپi–¾ژ،
پ@پ@‚Q”Nپjچ ‚©‚ç‚P‚W‚W‚V”Nپi–¾ژ،‚Q‚O”Nپjچ ‚ـ‚إپAژg
پ@پ@—p‚³‚ꂽپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@‹ك‘م“ْ–{‚ج‘¾گٹ¯گ§پi‚¾‚¶‚ه‚¤‚©‚ٌ‚¹‚¢پj‚ج
پ@پ@گEˆُ—كپi‚P‚W‚U‚X”Nگ§’èپj‚جڈ–ˆت‚إ‚حپA پ@ˆتٹK
پ@پ@‚حپAپ@گ³ˆêˆتپi‚µ‚ه‚¤‚¢‚؟‚¢پj‚©‚çڈڈ‰ˆتپi‚µ‚ه
پ@پ@‚¤‚»‚¢پj‚ـ‚إ‚ج‚Q‚OˆتٹKپ@‚ھ‚ ‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj‚جˆتٹK‚جˆتٹK‚جپAگ³ژlˆت
پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚¢پj‚©‚çڈ]”ھˆتپi‚¶‚م‚ح‚؟‚¢پj‚ـ‚إ‚جڈم
پ@پ@‰؛‚ھ‚ب‚‚ب‚èپAپ@‘هڈ‰ˆت پi‚¾‚¢‚»‚¢پj‚âڈڈ‰ˆت
پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚»‚¢پj‚جڈم‰؛‚ھ‚ب‚‚ب‚èپAپ@گ³‹مˆت پi‚µ‚ه
پ@پ@‚¤‚‚¢پj‚ئڈ]‹مˆتپi‚¶‚م‚‚¢پj‚ھ’ا‰ء‚³‚êپAپ@‚Q‚O
پ@پ@ˆتٹK‚ئ‚ب‚ء‚½پB
پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپBپ@
پ@
پ،پ@گEˆُ—ك‚جˆتٹKپBپ@
پ@پ@پƒ‚P‚W‚U‚X”Nچ پ`‚P‚W‚W‚V”Nچ پ„پB
پ@پœپ@گEˆُ—كپi‚P‚W‚U‚X”Nگ§’èپj‚جˆتٹK‚حپA‹ك‘م
پ@پ@“ْ–{گ•{‚جˆتٹK‚جپuˆêˆتپ`‹مˆتپAڈ‰ˆتپv‚ج
پ@پ@‚P‚OƒOƒ‹پ[ƒv‚جˆتٹK‚إ‚ ‚éپB
پ@پœپ@گEˆُ—كپi‚P‚W‚U‚X”Nگ§’èپj‚جˆتٹK‚حپAپ@گ³ˆê
پ@پ@ˆتپi‚µ‚ه‚¤‚¢‚؟‚¢پj‚©‚çڈڈ‰ˆتپi‚µ‚ه‚¤‚»‚¢پA‚µ
پ@پ@‚ه‚¤‚µ‚ه‚¢پj‚ـ‚إ‚جپA‹ك‘م“ْ–{گ•{پi–¾ژ،گ
پ@پ@•{پj‚ج‚Q‚OˆتٹKپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ڈ–ˆتڈً—ل‚جˆتٹKپ@
پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¢‚¶‚ه‚¤‚ê‚¢‚ج‚¢‚©‚¢پjپB
پ@
پ،پ@ڈ–ˆتڈً—ل‚جˆتٹKپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ڈ–ˆتڈً—ل‚جˆتٹKپ@پi‚¶‚ه‚¢‚¶‚ه‚¤‚ê‚¢پjپB
پ،پ@ڈ–ˆتڈً—ل‚حپA‚P‚W‚W‚V”Nگ§’èپB
پ،پ@ڈ–ˆتڈً—ل‚حپA‹ك‘م“ْ–{گ•{‚جپAˆتٹK‚ب‚ا‚ً
پ@پ@’è‚ك‚½–@—كپB
پ،پ@‚P‚W‚W‚V”Nگ§’è‚جڈ–ˆتڈً—ل‚©‚ç
پ@پ@‚P‚X‚Q‚U”Nگ§’è‚جˆتٹK—ك‚ض‚ج•دچX‚ـ‚إپB
پ،پ@ڈ–ˆتڈً—ل‚جˆتٹK‚حپA‚P‚W‚W‚V”Nپi–¾ژ،‚Q‚O”Nپj
پ@پ@چ ‚©‚ç‚P‚X‚Q‚U”Nپiڈ؛کaŒ³”Nپjچ ‚ـ‚إپAژg—p‚³
پ@پ@‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
پ،پ@‹ك‘م“ْ–{‚جڈ–ˆتڈً—ل‚ج‚P‚UˆتٹK
پ@پ@پƒ‚P‚W‚W‚V”Nچ پ`‚P‚X‚Q‚U”Nچ پ„پB
پ›پ@ڈمˆتڈ‡‚ةپAگ³ˆêˆتپAڈ]ˆêˆتپAگ³“ٌˆتپA
پ@پ@ ڈ]“ٌˆتپAگ³ژOˆتپAڈ]ژOˆتپAگ³ژlˆتپAڈ]ژlˆتپA
گ³ŒـˆتپAڈ]ŒـˆتپAگ³کZˆتپAڈ]کZˆتپAگ³ژµˆتپA
پ@پ@ ڈ]ژµˆتپAگ³”ھˆتپAڈ]”ھˆتپB
پ،پ@ˆتٹKپi‚¢‚©‚¢پjپAڈ–ˆتپi‚¶‚ه‚¢پj‚ةٹض‚µ‚ؤ‚حپA
پ@پ@پuˆتٹKپvپAپuڈ–ˆتپv‚ًژQڈئ‚‚¾‚³‚¢پB
پ،پ@‹كپEŒ»‘م“ْ–{‚جپA‹كپEŒ»‘م“ْ–{گ•{‚جˆت
پ@پ@ٹK‚ةٹض‚µ‚ؤ‚حپAپu‹كپEŒ»‘م“ْ–{گ•{‚جˆتٹKپv
پ@پ@‚ًژQڈئ‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جپA’©’ى‚جˆتٹK‚ةٹض‚µ‚ؤ‚حپA
پu’©’ى‚جˆتٹKپv‚ًژQڈئ‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“Tپ@‚X‚P‚R‚R‚WپB
پ@
پ پ@‹كپEŒ»‘م‚جڈ–ˆتڈً—ل‚âˆتٹK—ك‚ج
پ@پ@ ˆتٹKپB
پ@پ@پ@پi‚P‚W‚W‚V”Nچ پ`Œ»چفپjپBپ@
پ@
پ@
پ،پ@ڈ–ˆتڈً—لپ@پi‚¶‚ه‚¢‚¶‚ه‚¤‚ê‚¢پj‚حپAپ@‹ك‘م“ْ
پ@پ@–{گ•{‚جپAˆتٹK‚ب‚ا‚ً’è‚ك‚½–@—كپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@ڈ–ˆتڈً—ل‚حپA‚P‚W‚W‚V”N‚ةگ§’肳‚êپA‚P‚X
پ@پ@‚Q‚U”Nگ§’è‚جˆتٹK—ك‚ض‚ج•دچX‚ـ‚إپAŒّ—ح‚ً
پ@پ@‚à‚ء‚½پB
پ،پ@ڈ–ˆتڈً—ل‚جˆتٹK‚حپA‚P‚W‚W‚V”Nپi–¾ژ،‚Q‚O”Nپj
پ@پ@چ ‚©‚ç‚P‚X‚Q‚U”Nپiڈ؛کaŒ³”Nپjچ ‚ـ‚إپAژg—p‚³
پ@پ@‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
پ@
پ،پ@ˆتٹK‚حپAپ@–¾ژ،ژ‘م’†ٹْˆبŒم‚ج‹كپEŒ»‘م“ْ
پ@پ@–{‚إ‚حپA‰h“T‚جˆت‚ًژ¦‚µپAپ@‘O‹ك‘م‚â–¾ژ،ژ
پ@پ@‘مڈ‰ٹْ‚ج“ْ–{‚إ‚حپAٹ¯گE‚جڈک—ٌ‚ًژ¦‚·پB
پ@
پ،پ@‹كپEŒ»“ْ–{‚جڈ–ˆتڈً—لپi‚P‚W‚W‚V”Nگ§’èپj‚âˆت
پ@پ@ٹK—كپi‚P‚X‚Q‚U”Nگ§’èپj‚جڈ–ˆت‚إ‚حپAپ@ˆتٹK‚حپA
پ@پ@گ³ˆêˆتپi‚µ‚ه‚¤‚¢‚؟‚¢پj‚©‚çڈ]”ھˆتپi‚¶‚م‚ح‚؟‚¢پj
پ@پ@‚ـ‚إ‚ج‚P‚UˆتٹKپ@‚ھ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@گيŒم‚حپAˆتٹK—ك‚ح‰üگ³‚³‚êپi‚P‚X‚S‚V”N‚ج
پ@پ@‰üگ³ˆتٹK—ك‚إپjپAپ@گ¶‘¶ژز‚ض‚جڈ–ˆت‚ً’âژ~‚µپAپ@
پ@پ@“Vچc‚ةڈ–ˆت‚جŒˆ’èŒ ‚ح‚ب‚پA“ْ–{چ‘Œ›–@‰؛پA
پ@پ@“àٹt‚جڈ•Œ¾‚ئڈ³”F‚ة‚و‚èپA“Vچc‚ھچ‘ژ–چsˆ×
پ@پ@‚ئ‚µ‚ؤپAŒ÷گر‚ج‚ ‚ء‚½پAŒجگlپiژ€–Sژزپj‚ض‚ج‚فپA
پ@پ@ڈ–ˆت‚ًچs‚ء‚ؤ‚¢‚éپB
پ@
پ،پ@‚P‚W‚V‚P”Nپi–¾ژ،‚S”Nپj‚ةپAٹ¯ˆت‘ٹ“–گ§پ@پi’©’ى
پ@پ@‚إپAˆتٹK‚ة‘خ‰‚µ‚½ٹ¯گE‚ةڈA‚‚±‚ئ‚ًŒ´‘¥‚ئ‚·
پ@پ@‚éگ§“xپjپ@‚حپA”pژ~‚³‚êپAپ@ˆتٹK‚ئٹ¯گE‚جٹضŒW
پ@پ@‚ح’f‚½‚êپAˆتٹK‚حپA‚P‚W‚W‚V”N‚جڈ–ˆتڈً—ل‚جŒِ
پ@پ@•z‚ة‚و‚èپAˆبŒمپA‰h“T‚ج–ًٹ„‚ة“ء‰»‚µ‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‚ـ‚½پAگيŒمپAگ¶‘¶ژز‚ض‚جڈ–ˆت‚حپAچs‚ي‚ê
پ@پ@‚ب‚‚ب‚èپAŒجگlپiژ€–Sژزپj‚ج‚ف‚ض‚جڈ–ˆت‚ھچs‚ي
پ@پ@‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
پ@
پ،پ@ڈ–ˆتپ@پi‚¶‚ه‚¢پj‚ئ‚حپAپ@ˆتٹK‚ًژِ—^‚·‚邱‚ئپA
پ@پ@ˆتٹK‚ةڈ–پi‚¶‚هپj‚·‚邱‚ئپ@‚إ‚ ‚éپB “Vچc‚ھ
پ@پ@ˆتٹK‚ًژِ—^‚·‚邱‚ئ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@ˆتٹK‚ة‚حپAپ@ژ‘م•ت‚ةپA‚RƒOƒ‹پ[ƒv‚جˆتٹK
پ@پ@‚ھ‚ ‚éپBپ@ پi‚Pپjپ@‚V‚O‚P”Nچ ‚©‚ç‚P‚W‚U‚X”Nچ ‚ـ‚إ
پ@پ@‚ج‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj‚جˆتٹKپA پ@
پ@پ@پi‚Qپj ‚P‚W‚U‚X”Nچ ‚©‚ç‚P‚W‚W‚V”Nچ ‚ـ‚إ‚جپA‘¾گ
پ@پ@ٹ¯گ§‚جگEˆُ—كپi‚P‚W‚U‚X”Nگ§’èپj‚جˆتٹK پAپ@پi‚Rپjپ@
پ@پ@‚P‚W‚W‚V”Nچ ‚©‚猻چف‚ـ‚إ‚جپAڈ–ˆتڈً—لپi‚P‚W‚W‚V
پ@پ@”Nگ§’èپj‚جˆتٹK ‚ئ ˆتٹK—كپi‚P‚X‚Q‚U”Nگ§’èپA‚P‚X
پ@پ@‚S‚V”N‰üگ³پj‚جˆت ٹKپ@‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پ@
پ،پ@ڈ–ˆتڈً—ل‚جˆتٹKگ§“x‚ئ‘¼‚جژٹْ
پ@پ@‚جˆتٹKگ§“x‚ئ‚ج”نٹr•\پB
پœپ@ژ‘م•تپA‚RƒOƒ‹پ[ƒv‚جˆتٹKپB
پ@
پi‚Pپjپ@‹كپEŒ»‘م‚جڈ–ˆتڈً—ل‚âˆتٹK—ك
پ@پ@‚جˆتٹKپB
پ@پ@پ@‹كپEŒ»‘م“ْ–{گ•{‚جپAڈ–ˆتڈً—لپi‚P‚W‚W‚V
پ@پ@”Nگ§’èپj‚âˆتٹK—كپi‚P‚X‚Q‚U”Nگ§’èپA‚P‚X‚S‚V
پ@پ@”N‰üگ³پj‚جˆتٹKپB
پ@پ@پ@پƒ‚P‚W‚W‚V”Nچ پ`Œ»چفپAژg—pپ„پB
پ@پ@پ@ˆêˆت‚©‚ç”ھˆت‚ـ‚إ‚جپA‚P‚UˆتٹKپB
پiپث ˆتٹK—ك ‚جˆتٹKپjپB
پiپث ڈ–ˆتڈً—ل‚جˆتٹKپjپB
پ@
پi‚Qپjپ@‹ك‘م‚جگEˆُ—ك‚جˆتٹKپB
پ@پ@پ@پ@‹ك‘م“ْ–{گ•{‚جپA‘¾گٹ¯گ§‚جگEˆُ—ك
پ@پ@‚جپi‚P‚W‚U‚X”Nگ§’èپj‚جˆتٹKپB
پ@پ@پ@پƒ‚P‚W‚U‚X”Nچ پ`‚P‚W‚W‚V”Nچ پAژg—pپ„پB
پ@پ@ˆêˆت‚©‚ç”ھˆتپA‹مˆتپAڈ‰ˆت‚ـ‚إ‚جپA‚Q‚OˆتٹKپB
پ@پ@پiپث گEˆُ—ك‚جˆتٹKپjپB
پ@
پi‚Rپjپ@‘O‹ك‘م‚ج’©’ىپi—¥—ك ٹ¯گ§پj‚ج
پ@پ@ˆتٹKپB
پ@پ@پ@پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جپA’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj‚جˆتٹKپB
پ@پ@پ@پƒ‚V‚O‚P”Nچ پ`‚P‚W‚U‚X”Nچ پAژg—pپ„پBپ@
پ@پ@ˆêˆت‚©‚ç”ھˆتپAڈ‰ˆت‚ـ‚إ‚جپA‚R‚OˆتٹKپB
پ@پ@پ@پiپث ’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj ‚جˆتٹKپjپB
پ@
پ،پ@پi‚Pپjپ@‹كپEŒ»‘م‚جڈ–ˆتڈً—ل‚âˆتٹK—ك‚جˆتٹKپB
پ@پ@پ@‹كپEŒ»‘م“ْ–{‚جڈ–ˆتڈً—لپi‚P‚W‚W‚V”Nگ§’èپjپA
پ@پ@پ@ˆتٹK—كپi‚P‚X‚Q‚U”Nگ§’èپA‚P‚X‚S‚V”N‰üگ³پj‚إ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@ˆتٹK‚حپAگ³ˆêˆتپi‚µ‚ه‚¤‚¢‚؟‚¢پj‚©‚çڈ]”ھ
پ@پ@پ@ˆتپi‚¶‚م‚ح‚؟‚¢پj‚ـ‚إ‚ج‚P‚UˆتٹKپ@‚ھ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@گيŒم‚حپAŒ÷گر‚ج‚ ‚ء‚½Œجگlپiژ€–Sژزپj‚ض
پ@پ@پ@‚ج‚فپAڈ–ˆت‚ھچs‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
پiپث ˆتٹK—ك ‚جˆتٹKپjپB
پiپث ڈ–ˆتڈً—ل‚جˆتٹKپjپB
پ@
پ،پ@پi‚Qپjپ@‹ك‘م‚جگEˆُ—ك‚جˆتٹKپB
پ@پ@پ@پ@پ@‹ك‘م“ْ–{‚ج‘¾گٹ¯گ§‚جگEˆُ—ك پi‚P‚W‚U‚X
پ@پ@پ@”Nگ§’èپj‚جڈ–ˆت‚إ‚حپA
پ@پ@پ@ˆتٹK‚حپAگ³ˆêˆتپi‚µ‚ه‚¤‚¢‚؟‚¢پj‚©‚çڈڈ‰ˆت
پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚»‚¢پj‚ـ‚إ‚ج‚Q‚OˆتٹKپ@‚ھ‚ ‚éپB
پ@پ@پiپث گEˆُ—ك‚جˆتٹKپjپB
پ@
پ،پ@پi‚Rپjپ@‘O‹ك‘م‚ج’©’ىپi—¥—ك ٹ¯گ§پj‚جˆتٹKپB
پ@پ@پ@پ@پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj‚جڈ–ˆت
پ@پ@پ@‚إ‚حپAپ@’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj‚جˆتٹK‚حپAگ³ˆêˆت
پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚¢‚؟‚¢پj‚©‚çڈڈ‰ˆت‰؛پi‚µ‚ه‚¤‚»‚¢‚ج
پ@پ@پ@‚°پj‚ـ‚إ‚ج‚R‚OˆتٹKپ@‚ھ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پiپث ’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj ‚جˆتٹKپjپB
پ@
پ@
پ@
پںپ@‹كپEŒ»‘م“ْ–{گ•{‚جپAڈ–ˆتڈً—ل
پ@پ@پi‚P‚W‚W‚V”Nگ§’èپj‚âˆتٹK—كپi‚P‚X‚Q‚U”Nگ§
پ@پ@پ@’èپA‚P‚X‚S‚V”N‰üگ³پjپ@‚جˆتٹKپB
پiپث ˆتٹK—ك ‚جˆتٹKپjپB
پiپث ڈ–ˆتڈً—ل‚جˆتٹKپjپB
پ@
پ،پ@پƒ‚P‚W‚W‚V”Nچ پ`Œ»چفپ„پ@‚P‚UˆتٹKپB
پ،پ@‹كپEŒ»‘م“ْ–{گ•{‚جˆتٹK‚جپAپuˆêˆتپ`”ھˆتپv
پ@پ@‚ج‚WƒOƒ‹پ[ƒv‚جپA‚P‚UˆتٹKپBپ@
پœپ@‹كپEŒ»‘م‚جڈ–ˆتڈً—ل‚âˆتٹK—ك‚جˆتٹK‚ة‚حپA
پ@پ@ˆêˆت‚©‚ç”ھˆت‚ـ‚إ‚ج‚W’iٹK‚ھ‚ ‚èپAگ³پi‚µ‚ه‚¤پjپE
پ@پ@ڈ]پi‚¶‚مپj‚ً‚آ‚¯‰ء‚¦‚ؤپA‚P‚UˆتٹK‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@‹كپEŒ»‘م‚جڈ–ˆتڈً—ل‚âˆتٹK—ك‚ج‚P‚UˆتٹKپ@
پ@پ@پiڈمˆتڈ‡‚ةپAپ@گ³ˆêˆتپAپ@ڈ]ˆêˆتپAپ@گ³“ٌˆتپA
پ@پ@ڈ]“ٌˆتپAگ³ژOˆتپAڈ]ژOˆتپAگ³ژlˆتپAڈ]ژlˆتپA
پ@پ@گ³ŒـˆتپAڈ]ŒـˆتپAگ³کZˆتپAڈ]کZˆتپAگ³ژµˆتپA
پ@پ@ڈ]ژµˆتپAگ³”ھˆتپAڈ]”ھˆتپjپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@ˆêˆتپ@پi‚¢‚؟‚¢پjپBپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‰pپFپ@‚s‚ˆ‚…پ@‚P‚“‚”پ@‚h‚‹‚پ‚‰پ@‚q‚پ‚ژ‚‹پjپB
پ@پ@پœپ@گ³ˆêˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚¢‚؟‚¢پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‰pپFپ@‚s‚ˆ‚…پ@‚n‚’‚„‚‰‚ژ‚پ‚’‚™پ@‚P‚“‚”پ@‚h‚‹‚پ‚‰پ@‚q‚پ‚ژ‚‹پjپB
پ@پ@پœپ@ڈ]ˆêˆتپ@پi‚¶‚م‚¢‚؟‚¢پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‰pپFپ@‚s‚ˆ‚…پ@‚r‚•‚‚‚ڈ‚’‚„‚‰‚ژ‚پ‚”‚…پ@‚P‚“‚”پ@‚h‚‹‚پ‚‰پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚q‚پ‚ژ‚‹پjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@پ،پ@“ٌˆتپ@پi‚ة‚¢پjپBپ@پ@
پ@پ@پœپ@گ³“ٌˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚ة‚¢پjپB
پ@پ@پœپ@ڈ]“ٌˆتپ@پi‚¶‚م‚ة‚¢پjپB
پ@پ،پ@ژOˆتپ@پi‚³‚ٌ‚فپjپBپ@پ@
پ@پ@پœپ@گ³ژOˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚³‚ٌ‚فپjپB
پ@پ@پœپ@ڈ]ژOˆتپ@پi‚¶‚م‚³‚ٌ‚فپjپB
پ@پ،پ@ژlˆتپ@پi‚µ‚¢پjپBپ@پ@
پ@پ@پœپ@گ³ژlˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚¢پjپB
پ@پ@پœپ@ڈ]ژlˆتپ@پi‚¶‚م‚µ‚¢پjپB
پ@پ،پ@Œـˆتپ@پi‚²‚¢پjپBپ@پ@
پ@پ@پœپ@گ³Œـˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚²‚¢پjپB
پ@پ@پœپ@ڈ]Œـˆتپ@پi‚¶‚م‚²‚¢پjپB
پ@پ،پ@کZˆتپ@پi‚ë‚‚¢پjپBپ@پ@
پ@پ@پœپ@گ³کZˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚ë‚‚¢پjپB
پ@پ@پœپ@ڈ]کZˆتپ@پi‚¶‚م‚ë‚‚¢پjپB
پ@پ،پ@ژµˆتپ@پi‚µ‚؟‚¢پjپBپ@پ@
پ@پ@پœپ@گ³ژµˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚؟‚¢پjپB
پ@پ@پœپ@ڈ]ژµˆتپ@پi‚¶‚م‚µ‚؟‚¢پjپB
پ@پ،پ@”ھˆتپ@پi‚ح‚؟‚¢پjپBپ@پ@
پ@پ@پœپ@گ³”ھˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚ح‚؟‚¢پjپB
پ@پ@پœپ@ڈ]”ھˆتپ@پi‚¶‚م‚ح‚؟‚¢پjپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ،پ@‹كپEŒ»‘م“ْ–{گ•{‚جپAڈ–ˆتڈً—ل
پ@پ@‚âˆتٹK—ك‚جˆتٹKپB
پ@پ@پ@پƒ‚P‚W‚W‚V”Nچ پ`Œ»چفپ„پ@
پ@پ@پ@ˆêˆت‚©‚ç”ھˆت‚ـ‚إ‚ج‚P‚UˆتٹKپB
پ@
پ،پ@‹كپEŒ»‘م“ْ–{گ•{‚جپAڈ–ˆتڈً—لپi‚P‚W‚W‚V”N
پ@پ@گ§’èپj‚âˆتٹK—كپi‚P‚X‚Q‚U”Nگ§’èپA‚P‚X‚S‚V”N‰ü
پ@پ@گ³پj‚جˆتٹK‚حپAپ@ˆêˆت‚©‚ç”ھˆت‚ـ‚إ‚جپA‚P‚U
پ@پ@ˆتٹKپ@‚إ‚ ‚èپAپ@‚P‚W‚W‚V”Nچ ‚©‚猻چف‚ـ‚إپA
پ@پ@ژg—p‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@ڈ–ˆتڈً—ل‚âˆتٹK—ك‚جˆتٹKپBپ@
پ@پ@پ@پƒ‚P‚W‚W‚V”Nچ پ`Œ»چفپ„پB
پ@پœپ@ڈ–ˆتڈً—ل‚âˆتٹK—ك‚جˆتٹK‚حپAپ@‹كپEŒ»‘م“ْ
پ@پ@–{گ•{‚جˆتٹK‚جپuˆêˆتپ`”ھˆتپv‚ج‚WƒOƒ‹پ[ƒv
پ@پ@‚جˆتٹK‚إ‚ ‚éپB
پ@پœپ@ڈ–ˆتڈً—ل ‚âˆتٹK—ك‚جˆتٹK‚حپAپ@گ³ˆêˆتپi‚µ
پ@پ@‚ه‚¤‚¢‚؟‚¢پj‚©‚çڈ]”ھˆتپi‚¶‚م‚ح‚؟‚¢پj‚ـ‚إ‚ج
پ@پ@‹كپEŒ»‘م“ْ–{گ•{‚ج‚P‚UˆتٹKپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@’nژهپ@پ@
پ@پ@پ@پ@ پi‚¶‚ت‚µپjپ@پi= ’nژهٹK‹‰پjپB
پ@
پ،پ@’nژهپBپ@
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@’nژهپ@پi‚¶‚ت‚µپjپB
پ،پ@‰pŒê–¼پ@پFپ@‚k‚پ‚ژ‚„‚Œ‚ڈ‚’‚„پi‚“پjپB
پ،پ@•ت–¼پ@پFپ@’nژهٹK‹‰پB
پ@پ@ پi‰pپFپ@‚s‚ˆ‚…پ@‚k‚پ‚ژ‚„‚ڈ‚—‚ژ‚‰‚ژ‚‡پ@‚b‚Œ‚پ‚“‚“پjپB
پ،پ@‹ك‘م“ْ–{پi–¾ژ،پA‘هگ³پAگي‘OپEڈ؛کaژ‘مپj‚ج“ء
پ@پ@Œ ٹK‹‰پB
پ،پ@ڈ¬چىگl‚ًچïژوپi‚³‚‚µ‚مپj‚µ‚ؤپA”_’nŒo‰c‚ًچs‚¤پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“Tپ@‚T‚P‚V‚P‚RپB
پ@
پ@
پ،پ@’nژهپ@پi‚¶‚ت‚µپjپ@‚حپAپ@‹ك‘م“ْ–{پi–¾ژ،پA‘هگ³پA
پ@پ@گي‘OپEڈ؛کaژ‘مپj‚ج“ءŒ ٹK‹‰‚إ‚ ‚èپAپ@ڈ¬چىگl‚ً
پ@پ@چïژوپi‚³‚‚µ‚مپj‚µ‚ؤپA”_’nŒo‰c‚ًچs‚¤پB
پ@پ@پ@پ@’nژه‚ج•ت–¼‚حپAپ@’nژهٹK‹‰‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@’nژه‚ج‰pŒê–¼‚حپA‚k‚پ‚ژ‚„‚Œ‚ڈ‚’‚„پi‚“پj‚إپA’nژهپ@
پ@پ@ٹK‹‰‚ج‰pŒê–¼‚حپA‚s‚ˆ‚…پ@‚k‚پ‚ژ‚„‚ڈ‚—‚ژ‚‰‚ژ‚‡پ@‚b‚Œ‚پ‚“‚“پ@
پ@پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ڈ³‹v‚ج—گپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚«‚م‚¤‚ج‚ç‚ٌپjپB
پ@
پ،پ@ڈ³‹v‚ج—گپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ڈ³‹v‚ج—گپ@پi‚¶‚ه‚¤‚«‚م‚¤‚ج‚ç‚ٌپjپB
پ،پ@گي‘ˆ‚جٹْٹشپ@پFپ@‚P‚Q‚Q‚P”Nپiڈ³‹v‚R”NپjپB
پ،پ@ٹ™‘qژ‘م‘Oٹْ‚ج“à—گپB
پ،پ@’©’ىگ¨—ح‚ھپAپ@ٹ™‘q–‹•{گ¨—ح‚ئ‘خ—§‚µپA‹N‚±
پ@پ@ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“Tپ@‚S‚Q‚R‚R‚UپB
پ@
پ@
پ،پ@ڈ³‹v‚ج—گپ@پi‚¶‚ه‚¤‚«‚م‚¤‚ج‚ç‚ٌپjپ@‚حپAپ@ٹ™‘qژ
‘م‘Oٹْ‚ج“à—گ‚إپAپ@‚P‚Q‚Q‚P”Nپiڈ³‹v‚R”Nپj‚ةپA
پ@پ@’©’ىگ¨—ح‚ھپAپ@ٹ™‘q–‹•{گ¨—ح‚ئ‘خ—§‚µپA‹N‚±‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@ڈ³‹v‚ج—گ‚حپAپ@’©’ى•ûپiڈمچc•ûپj‚ھپAپ@ٹ™‘q
پ@پ@–‹•{•û‚ة‘خ‚µ‚ؤ‹N‚±‚µ‚½گي‚¢پ@‚إ‚ ‚éپBپ@
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ،پ@‚P‚P‚X‚Q”N‚ة‘n—§‚µ‚½ٹ™‘q–‹•{‚ة‚و‚ء‚ؤپAپ@’©’ى
پ@پ@گ¨—ح‚حپAپ@‘إŒ‚‚ًژَ‚¯‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@’©’ىگ¨—ح‚حپAپ@گ¨—ح‰ٌ•œ‚ًٹéپi‚‚ي‚¾پj‚ؤپA
پ@پ@‚P‚Q‚Q‚P”Nپiڈ³‹v‚R”Nپj‚ةپAپ@Œم’¹‰Hڈمچcپi‚²‚ئ‚خ
پ@پ@‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پj‚ً’†گS‚ةپAپ@–kڈً‹`ژ’ا“¢‚ج•؛‚ً‹N
پ@پ@‚±‚µ‚½پBپ@–kڈً‹`ژپi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤‚و‚µ‚ئ‚«پj‚حپAپ@ٹ™
پ@پ@‘q–‹•{‚جژ·Œ پi‚µ‚ء‚¯‚ٌپAژ·Œ ڈA”CپF‚P‚Q‚O‚Tپ`
پ@پ@‚Q‚S”NپA–‹•{پEڈ«ŒR•âچ²پjپ@‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@‚µ‚©‚µپA’©’ى•ûپiڈمچc•ûپj‚جŒR‚حپAپ@ٹ™‘q–‹
پ@پ@•{•û‚ج–kڈً‘×ژپEژ–[‚جŒR‚ة‘ه”s‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@–kڈً‘×ژپi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤‚â‚·‚ئ‚«پj‚حپAپ@–kڈً
پ@پ@‹`ژپi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤‚و‚µ‚ئ‚«پj‚جژq‚إ‚ ‚èپAپ@–kڈًژ
پ@پ@–[پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤پE‚ئ‚«‚س‚³پj‚حپAپ@–kڈً‹`ژ‚ج’ي‚إ
پ@پ@‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚Q‚Q‚P”Nپiڈ³‹v‚R”Nپj‚ةپAپ@’©’ى‚جپAŒم’¹‰H
پ@پ@ڈمچc‚حپAپ@‹E“àپi‚«‚ب‚¢پjپEگ¼چ‘پi‚³‚¢‚²‚پj‚ج•گ
پ@پ@ژmپAپ@‘هژ›‰@‚ج‘m•؛پAپ@چX‚ة–kڈًژپ‚جگ¨—ح‹‰»
پ@پ@‚ة”½”‚·‚é“Œچ‘•گژm‚جˆê•”‚ً‚à–،•û‚ةˆّ‚«“ü
پ@پ@‚ê‚ؤپA–kڈً‹`ژ’ا“¢‚ج•؛‚ً‹N‚±‚µ‚½پBپ@‚µ‚©‚µپA
پ@پ@’©’ى•ûپiŒم’¹‰Hڈمچc•ûپj‚جٹْ‘ز‚ة”½‚µ‚ؤپAپ@“Œ
پ@پ@چ‘•گژm‚ج‘ه‘½گ”‚حپAپ@–kڈًژپ‚ج‚à‚ئ‚ةŒ‹ڈW‚µ‚ؤپA
پ@پ@گي‚¢‚ة—صپi‚ج‚¼پj‚ٌ‚¾پBپ@ٹ™‘q–‹•{‚حپAپ@–kڈً‹`
پ@پ@ژ‚جژqپE‘×ژ‚â‹`ژ‚ج’يپEژ–[‚ç‚ج—¦‚¢‚éŒR‚ً
پ@پ@‚¨‚‚èپAپ@‹پi“sپj‚ًچU‚ك‚½پBپ@‚Pƒ–Œژ‚جŒمپAگي‚¢‚حپA
پ@پ@ٹ™‘q–‹•{‚جˆ³“|“I‚بڈں—ک‚ةڈI‚ي‚éپB
پ@
پ،پ@ٹ™‘q–‹•{•û‚ھ’©’ى•ûپiڈمچc•ûپj‚ةڈں—ک‚ً“¾‚½
پ@پ@ŒمپAپ@ٹ™‘q–‹•{پEژ·Œ ‚ج–kڈً‹`ژپi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤‚و
پ@پ@‚µ‚ئ‚«پj‚ً’†گS‚ئ‚·‚éپAٹ™‘q–‹•{‚حپAپ@’©’ىگ¨—ح
پ@پ@‚ًچيŒ¸‚·‚é‘خچô‚ً‚ئ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@ٹ™‘q–‹•{‚حپAپ@’‡‹±“Vچcپi‚؟‚م‚¤‚«‚ه‚¤‚ؤ‚ٌ
پ@پ@‚ج‚¤پj‚ً”p‚µ‚ؤپAپ@Œم–x‰ح“Vچcپi‚²‚ظ‚è‚©‚ي‚ؤ‚ٌ
پ@پ@‚ج‚¤پj‚ً—§‚ؤ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@ٹ™‘q–‹•{‚حپAپ@Œم’¹‰HپE“yŒن–هپEڈ‡“؟پi‚²‚ئ
پ@پ@‚خپE‚آ‚؟‚ف‚©‚اپE‚¶‚ٌ‚ئ‚پj‚ج‚Rڈمچc‚ً—¬چكپi‚é‚´
پ@پ@‚¢پj‚ئ‚µ‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@ٹ™‘q–‹•{‚حپAپ@’©’ى•ûپiڈمچc•ûپj‚ج‹M‘°پA
پ@پ@•گژm‚جڈٹ—جپi‚µ‚ه‚è‚ه‚¤پj‚ً–vژû‚µپAپ@–vژû’n‚ةگV
پ@پ@•â’n“ھپi‚µ‚ٌ‚غ‚¶‚ئ‚¤پj‚ً’u‚¢‚½پBپ@ٹ™‘q–‹•{‚حپAپ@
پ@پ@’©’ى•ûپiڈمچc•ûپj‚ة‚آ‚¢‚½‹M‘°‚â•گژm‚جڈٹ—ج–ٌ
پ@پ@‚R‚O‚O‚O‰سڈٹ‚ً–vژû‚µپAگيŒ÷‚ج‚ ‚ء‚½Œن‰ئگl‚ç‚ً
پ@پ@‚»‚ج’n‚ج’n“ھ‚ة”C–½‚µ‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@ٹ™‘q–‹•{‚حپAپ@‹پi“sپj‚ج’©’ى‚ًٹؤژ‹‚·‚邽
پ@پ@‚كپAکZ”g—…’T‘èپi‚ë‚‚ح‚炽‚ٌ‚¾‚¢پj‚ً’u‚¢‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‚±‚ê‚ç‚ة‚و‚èپAپ@‹پi“sپj‚ج’©’ى‚جŒِ‰ئگŒ
پ@پ@‚حگٹ‚¦پAپ@‹E“àپEگ¼چ‘‚ج‘‘‰€پEŒِ—ج‚ة‚à–‹•{‚ج
پ@پ@—ح‚ھچL‚‹y‚ش‚و‚¤‚ة‚ب‚èپAپ@ٹ™‘q–‹•{‚ج–‹•{Œ
پ@پ@—ح‚ھٹm—§‚µ‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‚ـ‚½پA‚±‚êˆبŒمپAٹ™‘q–‹•{‚حپAپ@’©’ى‚و‚è—D
پ@پ@ˆت‚ة—§‚ء‚ؤپAپ@چcˆت‚جŒpڈ³‚â’©’ى‚جگژ،‚ة‚àٹ±
پ@پ@ڈآ‚·‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½پB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ڈٹژiپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚µپjپB
پ@
پ،پ@ڈٹژiپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ڈٹژiپ@پi‚µ‚ه‚µپjپB
پ،پ@ژ؛’¬–‹•{‚جژکڈٹ‚ج’·ٹ¯پB
پ@پ@ژR–¼پAگشڈ¼پAˆêگFپA‹‹ة‚ج‚Sژپ‚جژlگE‰ئپi‚µ‚µ
پ@پ@‚«‚¯پj‚ھپAŒً‘م‚µ“ئگ肵‚½پB
پ،پ@ٹ™‘q–‹•{‚جژکڈٹ‚جژںٹ¯پB
پ@پ@–kڈًژپ‚ج‰ئچةپi‚©‚³‚¢پjپE’·چèژپ‚ھپA گ¢ڈP‚µ‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“Tپ@‚S‚Q‚R‚R‚SپB
پ@
پ@
پ،پ@ڈٹژiپ@پi‚µ‚ه‚µپj‚حپAپ@ژ؛’¬–‹•{‚جژکڈٹ‚ج’·ٹ¯‚إ
پ@پ@‚ ‚èپAپ@ٹ™‘q–‹•{‚جژکڈٹ‚جژںٹ¯پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@ڈٹژi‚حپAپ@ژ؛’¬–‹•{‚جژکڈٹ‚ج’·ٹ¯پ@‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@ژ؛’¬–‹•{‚جŒRژ–پEŒxژ@پ@‚âپ@‹پi“sپj‚جŒx”ُپEچظ”»پ@
پ@پ@‚ً’S‚¤گژ،‹@ٹض‚إ‚ ‚éپAژکڈٹپi‚³‚ق‚ç‚¢‚ا‚±‚ëپj‚ج
پ@پ@’·ٹ¯پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@ژ؛’¬–‹•{‚جژکڈٹ‚جڈٹژiپi’·ٹ¯پj‚ًپAژR–¼پAگش
پ@پ@ڈ¼پAˆêگFپA‹‹ة‚ج‚Sژپ‚جژlگE‰ئپi‚µ‚µ‚«‚¯پj‚ھپAŒً
پ@پ@‘م‚µ“ئگ肵‚½پB
پ@
پ،پ@ڈٹژi‚حپAپ@ٹ™‘q–‹•{‚جژکڈٹ‚جژںٹ¯پ@‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@ٹ™‘q–‹•{‚جپAŒن‰ئگlپiڈ«ŒR‰ئگbپj‚ج“گ§پ@‚âپ@ŒR
پ@پ@ژ–پEŒxژ@پ@‚ً’S‚¤گژ،‹@ٹض‚إ‚ ‚éپAژکڈٹپi‚³‚ق‚ç‚¢
پ@پ@‚ا‚±‚ëپj‚جژںٹ¯پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@ٹ™‘q–‹•{‚جژکڈٹ‚جڈٹژiپiژںٹ¯پj‚ًپA–kڈًژپ‚ج
پ@پ@‰ئچةپi‚©‚³‚¢پjپE’·چèژپ‚ھپAگ¢ڈP‚µ‚½پB
پ@
پ،پ@ژکڈٹپ@پi‚³‚ق‚ç‚¢‚ا‚±‚ëپj‚حپAپ@ٹ™‘q–‹•{پAژ؛’¬
پ@پ@–‹•{‚جگژ،‹@ٹضپ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@ژکڈٹ‚حپAپ@ژ؛’¬ژ‘م‚ةپAپ@ژ؛’¬–‹•{‚إ‚حپAژ؛’¬
پ@پ@–‹•{‚جŒRژ–پEŒxژ@پ@‚âپ@‹پi“sپj‚جŒx”ُپEچظ”»پ@‚ً
پ@پ@’S‚¤‹@ٹض‚إ‚ ‚ء‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@ژ؛’¬–‹•{‚جژکڈٹ‚جڈٹژiپi‚µ‚ه‚µپA’·ٹ¯پj‚ة
پ@پ@‚حپAپ@ژR–¼پi‚â‚ـ‚بپjپAگشڈ¼پi‚ ‚©‚ـ‚آپjپAˆêگFپi‚¢
پ@پ@‚ء‚µ‚«پjپA‹‹ةپi‚«‚ه‚¤‚²‚پj‚ج‚Sژپ‚جژlگE‰ئپi‚µ‚µ
پ@پ@‚«‚¯پj‚ھپAŒً‘م‚إپA”C‚¶‚ç‚ê‚ؤپAŒ گ¨‚ً‚س‚é‚ء‚½پBپ@
پ@پ@ژ؛’¬–‹•{‚إ‚حپAپ@ژکڈٹ‚جڈٹژiپi’·ٹ¯پj‚حپAٹا—ج
پ@پ@پi‚©‚ٌ‚ê‚¢پj‚ةژں‚®ڈdگE‚إ‚ ‚ء‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@ژکڈٹ‚حپAپ@ٹ™‘qژ‘م‚ةپAپ@ٹ™‘q–‹•{‚إ‚حپAٹ™‘q
پ@پ@–‹•{‚جپAŒن‰ئگlپiڈ«ŒR‰ئگbپj‚ج“گ§پ@‚âپ@ŒRژ–پE
پ@پ@Œxژ@پ@‚ً’S‚¤‹@ٹضپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@ٹ™‘q–‹•{‚جپAژکڈٹ‚حپA‚P‚P‚W‚O”N‚ةپAŒ¹ —ٹ’©
پ@پ@‚ھپAپ@ٹ™‘q‚ةگفپi‚à‚¤پj‚¯پAپ@Œ¹ —ٹ’©‚حپAپ@کa“c‹`
پ@پ@گ·پi‚ي‚¾‚و‚µ‚à‚èپj‚ًپAڈ‰‘م•ت“–پi‚ׂء‚ئ‚¤پA’·ٹ¯پj
پ@پ@‚ئ‚µپAپ@ٹپŒ´Œiژپi‚©‚¶‚ي‚ç‚©‚°‚ئ‚«پj‚ًپAڈ‰‘م‚جپA
پ@پ@•ت“–‚ً•âچ²‚·‚éڈٹژiپi‚µ‚ه‚µپAژںٹ¯پj‚ئ‚µ‚ؤپAپ@Œن
پ@پ@‰ئگlپi‚²‚¯‚ة‚ٌپAڈ«ŒR‰ئگbپj‚ج“گ§پ@‚âپ@ŒRژ–پE
پ@پ@Œxژ@پ@‚ة“–‚½‚点‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@Œم‚ةپA–kڈًژپ‚ھپAپ@ژکڈٹ ‚ج•ت“–‚ًگ¢ڈP‚µ‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@Œم‚ةپA–kڈًژپ‚ج‰ئچةپi‚©‚³‚¢پjپE’·چèژپپ@‚ھپA
پ@پ@ٹ™‘q–‹•{ ‚جپAژکڈٹ‚جڈٹژiپi‚µ‚ه‚µپAژںٹ¯پj‚ًگ¢ڈP‚µ
پ@پ@‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پôپôپ@ڈٹژi ‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢پAƒhƒL
پ@پ@پ@پ@ƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پAƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپB
پ@
پڑپ@ڈٹژiپ@‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢پAƒhƒLƒ…
پ@پ@پ@ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پB
پ@
پ،پ@‚a‚r—ًژjٹظپ@پwپ@ƒVƒٹپ[ƒY“ْ–{‚ج“]
پ@پ@ٹ·“_‡@پ@‹“s‰ٹڈمپIپ@‰گm‚ج—گپ`
پ@پ@‚»‚ج‚ئ‚«پeپe“ْ–{گlپfپf‚ھگ¶‚ـ‚ꂽپ`پxپB
پ@پ@ پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚P‚R”N‚P‚OŒژ‚P‚O“ْپE
پ@پ@پ@–{•ْ‘—پEƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[”ش‘gپjپB
پœپ@‰گm‚ج—گ‚جŒ´ˆِپAگط‚ءٹ|‚¯پA“à—eپAŒ‹‰ت‚â‰گm
پ@پ@‚ج—گ‚ج‰e‹؟‚ًڈq‚ׂéپB
پ@
پ،پ@‚»‚جژ—ًژj‚ھ“®‚¢‚½پ@پwپ@‰گm‚ج—گپA
پ@پ@“V‰؛‚ً–إ‚ع‚·پ`ڈI‚ي‚è‚ب‚«پeپe گي‚¢
پ@پ@‚جکAچ½ پfپfپ` پxپBپ@
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚O‚W”Nپi‚g‚Q‚Oپj‚VŒژپE–{•ْ
پ@پ@پ@‘—پEƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[”ش‘gپAپ@‘و‚R‚R‚Q‰ٌپjپB
پ@
پ@
پڑپ@ڈٹژiپ@‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢پAƒhƒ‰ƒ}پA
پ@پ@پ@‰f‰وپBپ@
پœپ@پi’چˆسپjپ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپ@‚حپAƒtƒBƒNƒVƒ‡ƒ“‚إ‚·پBپ@
پ@پ@—ًژj‚جƒhƒ‰ƒ}‚â‰f‰و‚حپAژjژہپi—ًژjڈم‚جژ–ژہپjپ@
پ@پ@‚ئپ@‰ث‹َ‚جڈo—ˆژ–‚ھپAپ@چ¬‚¶‚ء‚ؤپA•`‚©‚ê‚ؤ‚¢
پ@پ@‚ـ‚·پBپ@‚ـ‚½پAŒ»‘م•—‚ةƒAƒŒƒ“ƒW‚µ‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚·پB
پ@
پ،پ@پwپ@‘¾•½‹Lپ@پi‚½‚¢‚ض‚¢‚«پjپ@پx پBپ@
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚P‚X‚X‚P”N‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پjپB
پ،پ@ٹ™‘q–‹•{‚جپAژکڈٹ ‚جڈٹژiپi‚µ‚ه‚µپAژںٹ¯پj‚ًگ¢
پ@پ@ڈP‚·‚éپA–kڈًژپ‚ج‰ئچةپi‚©‚³‚¢پjپE’·چèژپپ@‚ھپA
پ@پ@“oڈê‚·‚éپB
پ،پ@ژ؛’¬–‹•{‚جژکڈٹ‚جڈٹژiپi’·ٹ¯پj‚ً“ئگè‚·‚éپA
پ@پ@ژlگE‰ئپi‚µ‚µ‚«‚¯پj‚جژR–¼پAگشڈ¼پAˆêگFپA‹‹ة
پ@پ@‚ج‚Sژپ‚ھپA“oڈê‚·‚éپB
پ@
پ،پ@ٹ™‘qژ‘م––ٹْ‚ئژ؛’¬ژ‘مڈ‰ٹْ‚جژذ‰ïڈَ‹µ‚â
پ@پ@گl•¨‚جٹˆ–ô‚ً•`‚¢‚½ƒhƒ‰ƒ}پB
پ،پ@‘«—ک‘¸ژپ‚جگ¶ٹUپ@‚ئپ@‘¸ژپ‚جٹ™‘q–‹•{“|–‹پAپ@
پ@پ@Œڑ•گگ•{‚ئ‚ج‘خ—§پAپ@ژ؛’¬–‹•{‚ج‘n—§‚ئٹî‘b
پ@پ@ٹm—§پ@‚ً•`‚¢‚½پ@ƒeƒŒƒrƒhƒ‰ƒ}پ@‚إ‚·پB
پ،پ@‘«—ک ‘¸ژپ‚جگ¶ٹUپA‹y‚رپ@‘¸ژپ‚ھپAٹ™‘q–‹•{
پ@پ@‘إ“|‚ةگs—ح‚µپAپ@Œم‘çŒي“Vچc‚ئهشپi‚½‚à‚ئپj‚ً
پ@پ@‚ي‚©‚؟پAپ@–k’©‚ً‚½‚ؤپAژ؛’¬–‹•{پi‘«—ک–‹•{پj
پ@پ@‚ًژ÷—§‚µپAپ@–‹•{‚جٹî‘b‚ًٹm—§‚·‚éٹˆ–ô‚ً•`
پ@پ@‚¢‚½ƒeƒŒƒrƒhƒ‰ƒ}پB
پœپ@‘«—ک ‘¸ژپ ‚ً‰‰‚¶‚½”o—D–¼پ@پFپ@گ^“c چL”Vپ@
پ@پ@پi‚³‚ب‚¾ ‚ذ‚ë‚ن‚«پjپB
پ@
پ@پ@
پ@پ@پ›پ@‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پu‘¾•½‹Lپv‚ج‘«—ک‘¸ژپپB
پ›پ@‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پu‘¾•½‹Lپv‚ج‚o‚qƒtƒHƒgپB
پ@
پ،پ@پwپ@‰ش‚ج—گپ@پi‚ح‚ب‚ج‚ç‚ٌپjپ@پxپBپ@
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚P‚X‚X‚S”N‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پjپB
پ،پ@ژ؛’¬–‹•{‚جژکڈٹ‚جڈٹژiپi’·ٹ¯پj‚ً“ئگè‚·‚éپA
پ@پ@ژlگE‰ئپi‚µ‚µ‚«‚¯پj‚جژR–¼پAگشڈ¼پAˆêگFپA‹‹ة
پ@پ@‚ج‚Sژپ‚ھپA“oڈê‚·‚éپB
پ@
پ،پ@ژ؛’¬ژ‘م‚ج’†ٹْ‚ً•`‚¢‚½ƒhƒ‰ƒ}‚إپAپ@ژ؛’¬ژ‘م
پ@پ@‚ج’†ٹْ‚ةٹˆ–ô‚µ‚½گlپX‚âپ@ڈ«ŒR‚جچبپA“ْ–ى•xژq
پ@پ@پi‚ذ‚ج‚ئ‚ف‚±پjپAپ@•xژq‚ج•v‚جژ؛’¬–‹•{ڈ«ŒR‚ج‘«
پ@پ@—ک‹`گپi‚و‚µ‚ـ‚³پjپA‰گm‚ج—گپ@‚ب‚ا‚ً•`‚¢‚½ƒhƒ‰
پ@پ@ƒ}پB
پ@
پ@پ@
پ@پ›پ@ƒhƒ‰ƒ}پu‰ش‚ج—گپv‚إ‚جپA“ْ–ى•xژqپiچ¶پj‚ئ‘«—ک‹`گپi‰EپjپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پB
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ژ·Œ پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ء‚¯‚ٌپjپBپ@
پ@
پ،پ@ژ·Œ پB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ژ·Œ پ@پi‚µ‚ء‚¯‚ٌپjپB
پ،پ@‰p–¼پ@پFپ@‚r‚ˆ‚ڈ‚‡‚•‚ژ‚پ‚Œپ@‚q‚…‚‡‚…‚ژ‚”پi‚“پjپB
پ،پ@‘¶—§ٹْٹشپ@پFپ@ٹ™‘qژ‘مڈ‰ٹْپ`‚P‚R‚R‚R”NپB
پ،پ@ٹ™‘q–‹•{‚جگE–¼پB
پ،پ@ڈ«ŒR‚ً•âچ²‚·‚é–ًگEپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“Tپ@‚S‚Q‚R‚R‚SپB
پ@
پ@
پ،پ@ژ·Œ پ@پi‚µ‚ء‚¯‚ٌپjپ@‚حپAپ@ٹ™‘q–‹•{‚جگE–¼‚إپA
پ@پ@ڈ«ŒR‚ً•âچ²‚·‚é–ًگEپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@ژ·Œ ‚ج‘¶—§ٹْٹش‚حپAپ@ٹ™‘qژ‘مڈ‰ٹْ‚©‚ç
پ@پ@‚P‚R‚R‚R”N‚ـ‚إپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@ژ·Œ ‚ج‰p–¼‚حپAپ@‚r‚ˆ‚ڈ‚‡‚•‚ژ‚پ‚Œپ@‚q‚…‚‡‚…‚ژ‚”پi‚“پj
پ@پ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@ژ·Œ ‚حپAپ@‚Q‘مژ·Œ پE–kڈً‹`ژ‚جژ‚و‚èپAپ@گڈٹپ@
پ@پ@پi‚ـ‚ٌ‚ا‚±‚ëپAٹ™‘q–‹•{‚جپAگژ،پAچàگ‹@ٹضپjپ@‚ج
پ@پ@•ت“–پ@پi‚ׂء‚ئ‚¤پA’·ٹ¯پjپ@‚ئپ@ژکڈٹپ@پi‚³‚ق‚ç‚¢‚ا
پ@پ@‚±‚ëپAٹ™‘q–‹•{‚جپAŒن‰ئگlپiڈ«ŒR‰ئگbپj‚ج“گ§‚â
پ@پ@ŒRژ–پEŒxژ@‚ً’S‚¤‹@ٹضپjپ@‚ج•ت“–پ@‚ًŒ“‚ث‚½گE–¼پ@
پ@پ@‚ئ‚ب‚ء‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@چإڈ‰‚حپAپ@گڈٹپ@پi‚ـ‚ٌ‚ا‚±‚ëپAٹ™‘q–‹•{‚جگ
پ@پ@–±پEچà–±‹@ٹضپjپ@‚جپ@•ت“–پi‚ׂء‚ئ‚¤پA’·ٹ¯پjپ@‚ج
پ@پ@‘هچ]چLŒ³پ@پi‚¨‚¨‚¦‚ذ‚ë‚à‚ئپjپ@‚ھپAپ@ڈ«ŒR‚ج•â
پ@پ@چ²–ً‚ئ‚¢‚¤ˆس–،‚إپAژ·Œ ‚ئڈج‚µپAپ@ژں‚ةپA‚P‚Q‚O‚R
پ@پ@”N‚ةگڈٹ‚ج•ت“–‚ة‚ب‚ء‚½پA–kڈًژگ‚ھژ·Œ ‚ئڈج
پ@پ@‚µپAپ@‚P‚Q‚P‚R”N‚ةپ@گڈٹ‚ج•ت“–پ@‚ئپ@ژکڈٹپ@پi‚³
پ@پ@‚ق‚ç‚¢‚ا‚±‚ëپAٹ™‘q–‹•{‚جپAŒن‰ئگlپiڈ«ŒR‰ئ
پ@پ@گbپj‚ج“گ§پAŒRژ–پEŒxژ@پA‚ج‹@ٹضپjپ@‚ج•ت“–‚ً
پ@پ@Œ“‚ث‚½–kڈً‹`ژپ@‚ھپAژ·Œ ‚ئڈج‚µ‚½پBپ@ˆبŒمپA
پ@پ@ژ·Œ ‚حپAپ@گڈٹ•ت“–‚ئژکڈٹ•ت“–‚ًŒ“‚ث‚½گE–¼
پ@پ@‚ئ‚ب‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@ˆبŒمپA–kڈًژپ‚ھپAپ@ٹ™‘q–‹•{‚جپAژ·Œ ‚ج
پ@پ@–¼ڈجپE–ًگE‚ًگ¢ڈP‚µپAپ@ژ·Œ گژ،‚ً“WٹJ‚µ‚ؤ‚¢
پ@پ@‚پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پںپ@ٹ™‘q–‹•{‚ج–kڈًژپپEژ·Œ –¼
پiڈ‰‘مپ` ‚P‚U‘مپjˆê——•\پB
پ@
پ،پ@ٹ™‘q–‹•{‚جژ·Œ پi‚µ‚ء‚¯‚ٌپjپB
پ،پ@پ@ڈ‰‘مژ·Œ پ@پ@–kڈً ژگپ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤ ‚ئ‚«‚ـ‚³پjپB
پ،پ@پ@‚Q‘مژ·Œ پ@پ@ –kڈً ‹`ژپ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤ ‚و‚µ‚ئ‚«پjپB پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–kڈً“¾ڈ@پi‚ئ‚‚»‚¤پA–{‰ئپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–@–¼پ@“؟ڈ@پB
پ،پ@پ@‚R‘مژ·Œ پ@پ@ –kڈً ‘×ژپ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤ ‚â‚·‚ئ‚«پjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ –kڈً“¾ڈ@پi–{‰ئپjپB
پ،پ@پ@‚S‘مژ·Œ پ@پ@ –kڈً Œoژپ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤ ‚آ‚ث‚ئ‚«پjپBپ@
–kڈً“¾ڈ@پi–{‰ئپjپB
پ،پ@پ@‚T‘مژ·Œ پ@پ@ –kڈً ژ—ٹپ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤ ‚ئ‚«‚و‚èپjپB
–kڈً“¾ڈ@پi–{‰ئپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ،پ@پ@‚U‘مژ·Œ پ@پ@ –kڈً ’·ژپ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤ ‚ب‚ھ‚ئ‚«پjپBپ@
پ،پ@پ@‚V‘مژ·Œ پ@پ@ –kڈً گ‘؛پ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤ ‚ـ‚³‚ق‚çپjپB
پ،پ@پ@‚W‘مژ·Œ پ@پ@ –kڈً ژڈ@پ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤ ‚ئ‚«‚ق‚ثپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ –kڈً“¾ڈ@پi–{‰ئپjپB
پ،پ@پ@‚X‘مژ·Œ پ@پ@ –kڈً ’هژپ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤ ‚³‚¾‚ئ‚«پjپB
–kڈً“¾ڈ@پi–{‰ئپjپBپ@
پ،پ@‚P‚O‘مژ·Œ پ@پ@ –kڈً ژtژپ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤ ‚à‚ë‚ئ‚«پjپBپ@
پ،پ@‚P‚P‘مژ·Œ پ@پ@ –kڈً ڈ@گéپ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤ ‚ق‚ث‚ج‚èپjپ@پ@
پi= ‘ه•§پi‚¨‚³‚炬پjڈ@گéپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ،پ@‚P‚Q‘مژ·Œ پ@پ@ –kڈً ê¤ژپ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤ ‚ذ‚ë‚ئ‚«پjپBپ@
پ،پ@‚P‚R‘مژ·Œ پ@پ@ –kڈً ٹîژپ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤ ‚à‚ئ‚ئ‚«پjپB
پ،پ@‚P‚S‘مژ·Œ پ@پ@ –kڈً چ‚ژپ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤ ‚½‚©‚ئ‚«پjپBپ@
–kڈً“¾ڈ@پi–{‰ئپjپB
پ،پ@‚P‚T‘مژ·Œ پ@پ@ –kڈً ’هŒ°پ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤ ‚³‚¾‚ ‚«پjپ@پ@پ@
پi= ‹à‘ٍ’هŒ°پjپB
پ،پ@‚P‚U‘مژ·Œ پ@پ@ –kڈً ژçژپ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤ ‚à‚è‚ئ‚«پjپBپ@پ@
‘«—ک‘¸ژپپi‚½‚©‚¤‚¶پj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ گ³ژ؛•vگl‚جŒZپB
پ@
پ@
پôپôپ@ژ·Œ پ@‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢پA
پ@پ@پ@پ@ƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پAƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپB
پ@
پڑپ@ژ·Œ پ@‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢ƒhƒ‰
پ@پ@پ@ƒ}پC‰f‰وپBپ@
پ@پ@پœپ@پi’چˆسپjپ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAƒtƒBƒNƒVƒ‡ƒ“‚إ‚·پBپ@
پ@پ@—ًژj‚جƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAپ@ژjژہپi—ًژjڈم‚جژ–
پ@پ@ژہپjپ@‚ئپ@‰ث‹َ‚جڈo—ˆژ–‚ھپAپ@چ¬‚¶‚ء‚ؤپA•`‚©
پ@پ@‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپ@‚ـ‚½پAŒ»‘م•—‚ةƒAƒŒƒ“ƒW‚µ‚ؤ‚
پ@پ@‚è‚ـ‚·پB
پ@
پ،پ@پwپ@–kڈًژڈ@پ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤‚ئ‚«‚ق‚ثپjپ@پx پBپ@
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚j‚Q‚O‚O‚P”N‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پjپB
پ،پ@ٹ™‘q–‹•{‚جژ·Œ ‚جپA‚T‘مژ·Œ پE–kڈً ژ—ٹپA
پ@پ@‚U‘مژ·Œ پE–kڈً ’·ژپA‚V‘مژ·Œ پE–kڈً گ‘؛پA
پ@پ@‚W‘مژ·Œ پE–kڈً ژڈ@پ@‚ھپA “oڈê‚·‚éپB
پ@
پ،پ@–kڈً ژڈ@‚جپAگ¶ٹUپ@‚âپ@ژڈ@‚ج–ضŒأڈP—ˆپiŒ³
پ@پ@›„پi‚°‚ٌ‚±‚¤پjپjژ‚جٹˆ–ô‚ً•`‚¢‚½ƒeƒŒƒrƒhƒ‰ƒ}پB
پ@
پ@پ@پ@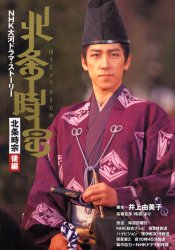
پ@پ@ پZپ@ƒhƒ‰ƒ}پu–kڈًژڈ@پv‚ج–kڈًژڈ@پB
پ@پ@ پ›پ@ƒhƒ‰ƒ}پu–kڈًژڈ@پv‚جڈ‘گذ”ج‘£‚o‚qƒtƒHƒgپB
پ@
پ@
پ،پ@پwپ@‘¾•½‹Lپ@پi‚½‚¢‚ض‚¢‚«پjپ@پx پBپ@
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚j‚P‚X‚X‚P”N‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پjپB
پ،پ@ٹ™‘q–‹•{‚جژ·Œ ‚جپA‚P‚S‘مژ·Œ پE–kڈًچ‚ژپA
پ@پ@‚P‚T‘مژ·Œ پE–kڈًپi‹à‘ٍپj’هŒ°پA‚P‚U‘مژ·Œ پE–k
پ@پ@ڈًپiگش‹´پjژçژ‚ھپA“oڈê‚·‚éپB
پ@
پ،پ@ٹ™‘qژ‘م––ٹْ‚ئژ؛’¬ژ‘مڈ‰ٹْ‚جژذ‰ïڈَ‹µ‚â
پ@پ@گl•¨‚جٹˆ–ô‚ً•`‚¢‚½ƒhƒ‰ƒ}پB
پ،پ@‘«—ک‘¸ژپ‚جگ¶ٹUپ@‚ئپ@‘¸ژپ‚جٹ™‘q–‹•{“|–‹پAپ@
پ@پ@Œڑ•گگ•{‚ئ‚ج‘خ—§پAپ@ژ؛’¬–‹•{‚ج‘n—§‚ئٹî‘b
پ@پ@ٹm—§پ@‚ً•`‚¢‚½پ@ƒeƒŒƒrƒhƒ‰ƒ}پ@‚إ‚·پB
پ،پ@‘«—ک ‘¸ژپ‚جگ¶ٹUپA‹y‚رپ@‘¸ژپ‚ھپAٹ™‘q–‹•{
پ@پ@‘إ“|‚ةگs—ح‚µپAپ@Œم‘çŒي“Vچc‚ئهشپi‚½‚à‚ئپj‚ً
پ@پ@‚ي‚©‚؟پAپ@–k’©‚ً‚½‚ؤپAژ؛’¬–‹•{پi‘«—ک–‹•{پj
پ@پ@‚ًژ÷—§‚µپAپ@–‹•{‚جٹî‘b‚ًٹm—§‚·‚éٹˆ–ô‚ً•`
پ@پ@‚¢‚½ƒeƒŒƒrƒhƒ‰ƒ}پB
پœپ@‘«—ک ‘¸ژپ ‚ً‰‰‚¶‚½”o—D–¼پ@پFپ@گ^“c چL”Vپ@
پ@پ@پi‚³‚ب‚¾ ‚ذ‚ë‚ن‚«پjپB
پ@
پ@پ@
پ@پ@پ›پ@‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پu‘¾•½‹Lپv‚ج‘«—ک‘¸ژپپB
پ›پ@‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پu‘¾•½‹Lپv‚ج‚o‚qƒtƒHƒgپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ژچڈ–@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚±‚‚ظ‚¤پjپBپ@پi= ژ–@پjپB
پ@
پ،پ@ژچڈ–@پB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ژچڈ–@پ@پi‚¶‚±‚‚ظ‚¤پjپB
پœپ@•ت–¼پ@پFپ@ژ–@پ@پi‚¶‚ظ‚¤پjپB
پ،پ@ژچڈ–@پiژ–@پj‚حپAژٹش‹و•ھŒ`ژ®پAژٹشٹشٹu
پ@پ@–@پi’èژ–@پE•s’èژ–@پjپAژچڈ•\ژ¦•ûژ®‚ة‚و‚èپA
پ@پ@•ھ—ق‚³‚ê‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ،پ@“ْ–{‚إژg‚ي‚ꂽژچڈپBپ@“ْ–{‚إ‚حپA‚Q‚آ‚ج
پ@ژٹش‹و•ھŒ`ژ®پA‚Q‚آ‚جژٹشٹشٹu–@پi’èژ–@پE•s
پ@’èژ–@پjپA‚R‚آ‚جژچڈ•\ژ¦•ûژ®‚ھژg—p‚³‚ꂽپB
پœپ@‹كŒ»‘م“ْ–{ژg—p‚ج‚P“ْ‚Q‚Sژٹشگ§پE’èژ–@
پ@پ@پEگ¼—mژ®•\ژ¦ژچڈپB
پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{ژg—p‚ج‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§پE’èژ–@
پ@پ@پ^•s’èژ–@پEڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈپi= ڈ\“ٌژxŒؤ
پ@پ@ڈجژچڈپjپB
پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{ژg—p‚ج‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§پE•s’èژ
پ@پ@–@پEژڈàگ”•\ژ¦ژچڈپi= گ”ŒؤڈجژچڈپjپB
پ@
پ پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جژچڈپEژ–@پB
پ@
پ@
پںپ@ژچڈ–@ پ@پi= ژ–@پjپB
پ،پ@ژچڈ–@‚حپAپ@ˆê“ْ‚ً•ھ‚¯‚ؤژپiژچڈپj‚ًŒˆ‚ك‚é
پ@پ@•û–@‚إپAپ@ژپiژچڈپj‚جگ”‚¦•ûپAپ@‚»‚µ‚ؤپAژ–@
پ@پ@‚ئ‚¢‚¤ˆس–،‚إ‚ ‚éپBپ@
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ،پ@ژ–@پi‚¶‚ظ‚¤پjپ@‚ئ‚حپAپ@ژچڈ–@ پAژٹش‹و•ھ–@
پ@پ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@ژچڈ–@پiژ–@پj‚حپA‰pŒê–¼‚إپAپ@‚”‚ˆ‚…پ@‚چ‚…‚”‚ˆ‚ڈ‚„پ@
پ@پ@‚ڈ‚†پ@‚ƒ‚ڈ‚•‚ژ‚”‚‰‚ژ‚‡پ@‚ˆ‚ڈ‚•‚’‚“پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@
پںپ@ژٹشٹشٹu–@پ@پi’èژ–@‚ئ•s’èژ–@پjپB
پ،پ@“ْ–{‚إ—ک—p‚³‚ꂽپA‚Q‚آ‚جژٹشٹشٹu–@پB
پ،پ@ژچڈ–@پiژ–@پj‚جژٹشٹشٹu–@‚ة‚حپAپ@‚Q‚آ‚ج
پ@پ@ژٹشٹشٹu–@پi’èژ–@پE•s’èژ–@پj‚ھ‚ ‚éپB
پœپ@ژچڈ–@پiژ–@پj‚جژٹشٹشٹu–@‚ة‚حپAپ@’èژ–@پ@
پ@پ@پi‚ؤ‚¢‚¶‚ظ‚¤پjپ@‚ئپ@•s’èژ–@پ@پi‚س‚ؤ‚¢‚¶‚ظ‚¤پjپ@
پ@پ@‚ج‚Qژي—ق‚ھ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پœپ@ژچڈ–@پiژ–@پj‚جژٹشٹشٹu–@‚ة‚حپAگ¢ٹE“I‚ةپA
پ@پ@’èژ–@‚ئ•s’èژ–@‚ھ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@“ْ–{‚إ‚حپA’èژ–@‚à•s’èژ–@‚àپAژg‚ي‚ꂽپB
پœپ@’èژ–@‚حپA‰pŒê–¼‚إپAپ@‚”‚ˆ‚…پ@‚چ‚…‚”‚ˆ‚ڈ‚„پ@‚ڈ‚†پ@
پ@پ@‚ƒ‚ڈ‚•‚ژ‚”‚‰‚ژ‚‡پ@‚…‚‘‚•‚پ‚Œپ@‚Œ‚…‚ژ‚‡‚”‚ˆپ@‚ˆ‚ڈ‚•‚’‚“پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@•s’èژ–@‚حپA‰pŒê–¼‚إپAپ@‚”‚ˆ‚…پ@‚چ‚…‚”‚ˆ‚ڈ‚„پ@
پ@پ@‚ڈ‚†پ@‚ƒ‚ڈ‚•‚ژ‚”‚‰‚ژ‚‡پ@‚•‚ژ‚…‚‘‚•‚پ‚Œپ@‚Œ‚…‚ژ‚‡‚”‚ˆپ@‚ˆ‚ڈ‚•‚’‚“پ@
پ@پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@ژٹشٹشٹuŒإ’è•û–@‚جپA’èژ–@پB
پ،پ@’èژ–@‚ئ‚حپA‹GگكپA’‹–é‚ةٹضŒW‚ب‚پAژٹش‚ً
پ@پ@چڈ‚قٹشٹu‚ھڈي‚ةˆê’è‚إ‚ ‚éژ–@پiژچڈ–@پj
پ@پ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پœپ@’èژ–@‚حپAپ@ژٹش‚ًچڈ‚قٹشٹu‚ھڈي‚ةˆê’è‚إ
پ@پ@‚ ‚éژچڈ–@‚إ‚ ‚èپAپ@‹GگكپA’‹–é‚ةٹضŒW‚ب‚پA
پ@پ@ˆê“ْپiˆê“ْ‚ج’·‚³پj‚ً“™•ھ‚µ‚ؤژپiژچڈپj‚ًŒˆ
پ@پ@‚ك‚éژ–@پiژچڈ–@پjپ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‹كپEŒ»‘م“ْ–{پi–¾ژ،ژ‘مپ`Œ»چفپj‚جژٹْ‚ةپA
پ@پ@‚P“ْ‚Q‚Sژٹشگ§پE’èژ–@پEگ¼—mژ®•\ژ¦ژچڈ‚ھ
پ@پ@ژg‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{پi‚Vگ¢‹Iپ`چ]Œثژ‘مپj‚جژٹْ‚ةپA
پ@پ@‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§پE’èژ–@پEڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈ‚ھپ@
پ@پ@ژg‚ي‚ꂽپB
پ@
پ،پ@ژٹشٹشٹu•د“®•û–@‚جپA•s’èژ–@پB
پ،پ@•s’èژ–@‚حپA‹GگكپA’‹–é‚ة‚و‚èپAژٹش‚ًچڈ‚ق
پ@پ@ٹشٹu‚ھˆê’è‚إ‚ب‚¢پAژچڈ–@پiژ–@پjپ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پœپ@•s’èژ–@‚حپAپ@‹GگكپA’‹–é‚ة‚و‚èپA‹و•ھ‚³‚ê
پ@پ@‚½ژٹش‚ج’·‚³‚ھˆل‚ء‚ؤ‚‚éژ–@پiژچڈ–@پjپ@‚إ
پ@پ@‚ ‚éپB
پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{پiژ؛’¬ژ‘مپ`چ]Œثژ‘مپj‚ة‚ؤپA
پ@پ@‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§‚جپu“ْ‚جڈo‚â“ْ–v‚ًٹîڈ€‚ئ‚·
پ@پ@‚é•s’èژ–@ پv ‚جژچڈپ@پiڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈپ@‚ئپ@
پ@پ@ژڈàگ”پE•\ژ¦ژچڈپjپ@‚ھˆê”تڈژ–¯‚ة—ک—p‚³‚ê
پ@پ@‚½پB
پ@
پ@
پںپ@ژٹش‹و•ھŒ`ژ®پB
پ،پ@“ْ–{‚إ—ک—p‚³‚ꂽپA‚Q‚آ‚جژٹش‹و•ھŒ`ژ®پB
پ،پ@ژچڈ–@پiژ–@پj‚جژٹش‹و•ھŒ`ژ®‚ة‚حپA‚Q‚آ‚ج
پ@پ@ژٹش‹و•ھŒ`ژ®پ@‚ھ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ،پ@ژچڈ–@پiژ–@پj‚جژٹش‹و•ھŒ`ژ®‚ة‚حپA‚P“ْ
پ@پ@‚Q‚Sژٹشگ§پA‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§پ@‚ب‚ا‚ھ‚ ‚éپB
پœپ@“ْ–{‚إ—ک—p‚³‚ꂽژٹش‹و•ھŒ`ژ®‚ة‚حپA‹كپEŒ»
پ@پ@‘م“ْ–{ژg—p ‚جپA‚P“ْ‚Q‚Sژٹشگ§‚جژ–@پ@‚ئپA‘O
پ@پ@‹ك‘م“ْ–{ژg—p‚جپA‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§‚جژ–@ ‚ج‚Q
پ@پ@‚آ‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پ@
پںپ@ژچڈ•\ژ¦•ûژ®پB
پ،پ@“ْ–{‚إ—ک—p‚³‚ꂽپA‚R‚آ‚جژچڈ•\ژ¦•ûژ®پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ،پ@ژچڈ–@پiژ–@پj‚جژچڈ•\ژ¦•ûژ®‚ة‚حپAپ@‚R‚آ
پ@پ@‚جژچڈ•\ژ¦•ûژ®‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@ژچڈ–@پiژ–@پj‚جژچڈ•\ژ¦•ûژ®‚ة‚حپAپ@گ¼—m
پ@پ@ژ®•\ژ¦ژچڈپAپ@ڈ\“ٌژxپi‚¶‚م‚¤‚ة‚µپj•\ژ¦ژچڈپAپ@
پ@پ@ژڈàگ”پi‚¶‚µ‚ه‚¤‚·‚¤پj•\ژ¦ژچڈپ@‚ب‚ا‚ھ‚ ‚éپB
پœپ@“ْ–{‚إ—ک—p‚³‚ꂽژچڈ•\ژ¦•ûژ®‚ة‚حپA‹كŒ»
پ@پ@‘م“ْ–{ژg—p ‚جگ¼—mژ®•\ژ¦ژچڈپ@‚ئپAپ@‘O‹ك‘م
پ@پ@“ْ–{ژg—p‚جڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈپ@‚ئپAپ@‘O‹ك‘م“ْ
پ@پ@–{ژg—p‚جژڈàگ”•\ژ¦ژچڈپ@‚ج‚R‚آ‚ھ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پœپ@‹كŒ»‘م“ْ–{ژg—p‚ج‚P“ْ‚Q‚Sژٹشگ§پE’èژ–@
پ@پ@پEگ¼—mژ®•\ژ¦ژچڈپB
پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{ژg—p‚ج‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§پE’èژ–@
پ@پ@پ^•s’èژ–@پEڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈپi= ڈ\“ٌژxŒؤ
پ@پ@ڈجژچڈپjپB
پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{ژg—p‚ج‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§پE•s’èژ
پ@پ@–@پEژڈàگ”•\ژ¦ژچڈپi= گ”ŒؤڈجژچڈپjپB
پ@
پ،پ@ڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈپi= ڈ\“ٌژxŒؤڈجژچڈپjپ@‚حپA
پ@پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚إژg‚ي‚ꂽپA’èژ–@‚ئ•s’èژ–@‚جپA
پ@پ@ڈ\“ٌژxپi‚¶‚م‚¤‚ة‚µپj‚إ•\ژ¦‚·‚éژچڈپ@‚إ‚ ‚éپBپ@
پœپ@ڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈپi= ڈ\“ٌژxŒؤڈجژچڈپj‚ة‚حپAپ@
پ@پ@‘O‹ك‘م“ْ–{ژg—p‚ج‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§پE’èژ–@پEڈ\
پ@پ@“ٌژx•\ژ¦ژچڈپ@‚ئپAپ@‘O‹ك‘م“ْ–{ژg—p‚ج‚P“ْ
پ@پ@‚P‚Q“™•ھگ§پEپu“ْ‚جڈo‚â“ْ–v‚ًٹîڈ€‚ئ‚·‚é•s’è
پ@پ@ژ–@پvپEڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈپ@‚ج‚Q‚آ‚ھ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ،پ@ژڈàگ”•\ژ¦ژچڈپi= گ”Œؤڈجژچڈپj‚حپAپ@‘O‹ك‘م
“ْ–{‚إژg‚ي‚ꂽپA پu“ْ‚جڈo‚â“ْ–v‚ًٹîڈ€‚ئ‚·‚é
پ@پ@•s’èژ–@پv‚جپAژڈàپi‚¶‚µ‚ه‚¤پj‚جگ”‚إ•\ژ¦‚·‚é
پ@پ@ژچڈ‚إ‚ ‚éپBپ@
پœپ@ژڈàگ”•\ژ¦ژچڈپi= گ”Œؤڈجژچڈپj‚حپAپ@‘O‹ك‘م
پ@پ@“ْ–{ژg—p‚ج‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§پE•s’èژ–@پEژڈàگ”
پ@پ@•\ژ¦ژچڈپ@‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@
پ@
پںپ@“ْ–{‚إژg‚ي‚ꂽپA’èژ–@‚ئ•s’èژ
پ@پ@–@‚جژچڈپB
پ،پ@“ْ–{‚إژg—p‚³‚ꂽژچڈ–@پiژ–@پj‚جژٹشٹشٹu–@
پ@پ@پi’èژ–@‚ئ•s’èژ–@پj‚جژچڈ‚ة‚حپAپ@‹كپEŒ»‘م“ْ
پ@پ@–{‚إژg—p‚µ‚ؤ‚¢‚éپA‚P“ْ‚Q‚Sژٹشگ§‚ج’èژ–@‚ج
پ@پ@گ¼—mژ®•\ژ¦ژچڈپAپ@‘O‹ك‘م“ْ–{پiژ؛’¬ژ‘مپ`چ]
پ@پ@Œثژ‘مپj‚جˆê”تڈژ–¯‚ةژg—p‚³‚ꂽپA‚P“ْ‚P‚Q“™
پ@پ@•ھگ§‚جپu“ْ‚جڈo‚â“ْ–v‚ًٹîڈ€‚ئ‚·‚é•s’èژ–@پv
پ@پ@‚جڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈ‚âژڈàگ”•\ژ¦ژچڈپAپ@‘O‹ك
پ@پ@‘م“ْ–{پi‚Vگ¢‹Iپ`چ]Œثژ‘مپj‚ة—ک—p‚³‚ꂽ—lپX
پ@پ@‚ب’èژ–@‚جڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈپ@‚ھ‚ ‚ء‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ@
پ،پ@“ْ–{‚إژg‚ي‚ꂽپA’èژ–@‚جژچڈپB
پœپ@’èژ–@‚حپA‹GگكپA’‹–é‚ةٹضŒW‚ب‚پAژٹش‚ًچڈ
پ@پ@‚قٹشٹu‚ھڈي‚ةˆê’è‚إ‚ ‚éژچڈ–@پiژ–@پjپ@‚إ
پ@پ@‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ،پ@“ْ–{‚إژg‚ي‚ꂽ’èژ–@‚جژچڈ‚ة‚حپAپ@‹كŒ»
پ@پ@‘م“ْ–{ژg—p‚ج‚P“ْ‚Q‚Sژٹشگ§پE’èژ–@پEگ¼—mژ®
پ@پ@ژچڈپ@‚ئپAپ@‘O‹ك‘م“ْ–{ژg—p‚ج‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§پE
پ@پ@’èژ–@پEڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈپ@‚ج‚Q‚آ‚ج’èژ–@‚ج
پ@پ@ژچڈپ@‚ھ‚ ‚ء‚½پB
پ،پ@‹كپEŒ»‘م“ْ–{‚إ‚حپA
پ@پ@‚P“ْ‚Q‚Sژٹشگ§‚ج’èژ–@‚جگ¼—mژ®•\ژ¦ژچڈ‚ھ
پ@پ@ژg‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚éپBپ@
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚إ‚حپA
پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{پi‚Vگ¢‹Iپ`‚P‚W‚S‚R”NپE“V•غ‚P‚S”Nپj
پ@پ@‚إ‚حپAŒِژ®‚ج’èژ–@‚ھ—ک—p‚³‚ꂽپB
پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{پi‚Vگ¢‹Iپ`چ]Œثژ‘مپj‚إ‚حپA—lپX
پ@پ@‚ب’èژ–@‚جژچڈ‚ھژg‚ي‚ꂽپBپ@ژ؛’¬ژ‘م‚©‚ç
پ@پ@چ]Œثژ‘م‚ـ‚إپAڈم‘wٹK‘w‚ج‚ف‚ھ’èژ–@‚ً—ک
پ@پ@—p‚µ‚½پB
پ@
پ،پ@“ْ–{‚إژg‚ي‚ꂽپA•s’èژ–@‚جژ
پ@پ@چڈپB
پœپ@•s’èژ–@‚حپA‹GگكپA’‹–é‚ة‚و‚èپAژٹش‚ًچڈ‚ق
پ@پ@ٹشٹu‚ھˆê’è‚إ‚ب‚¢پAژچڈ–@پiژ–@پj‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ،پ@“ْ–{‚إژg‚ي‚ꂽ•s’èژ–@‚جژچڈ‚ة‚حپAپ@‘O
پ@پ@‹ك‘م“ْ–{ژg—p‚ج‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§پE•s’èژ–@پE
پ@پ@ڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈپ@‚ئپAپ@‘O‹ك‘م“ْ–{ژg—p‚ج‚P
پ@پ@“ْ‚P‚Q“™•ھگ§پE•s’èژ–@پEژڈàگ”•\ژ¦ژچڈ‚ج
پ@پ@‚Q‚آ‚ج•s’èژ–@‚جژچڈ‚ھ‚ ‚ء‚½پB
پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{پiژ؛’¬ژ‘مپ`چ]Œثژ‘مپj‚ة‚ؤپA
پ@پ@‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§‚جپu“ْ‚جڈo‚â“ْ–v‚ًٹîڈ€‚ئ‚·
پ@پ@‚é•s’èژ–@ پv ‚جژچڈپ@پiڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈپ@‚ئپ@
پ@پ@ژڈàگ”پE•\ژ¦ژچڈپjپ@‚ھˆê”تڈژ–¯‚ة—ک—p‚³‚ê
پ@پ@‚½پB
پ@
پ@
پںپ@ٹeژٹْ‚ج“ْ–{‚إژg‚ي‚ꂽژچڈپB
پ،پ@“ْ–{‚إ‚حپA’èژ–@‚جژچڈ‚à•s’èژ–@‚جژچڈ
پ@پ@‚àپA—ک—p‚³‚ꂽپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ،پ@‹كŒ»‘م“ْ–{‚إ‚حپA
پœپ@‹كپEŒ»‘م“ْ–{پi–¾ژ،ژ‘مپ`Œ»چفپj‚جژٹْ‚ةپA
پ@پ@‚P“ْ‚Q‚Sژٹشگ§پE’èژ–@پEگ¼—mژ®•\ژ¦ژچڈ‚ھ
پ@پ@ژg‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
پ@
پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚إ‚حپA
پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{پi‚Vگ¢‹Iپ`چ]Œثژ‘مپj‚جژٹْ‚ةپA
پ@پ@‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§پE’èژ–@پEڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈ‚ھپ@
پ@پ@ژg‚ي‚ꂽپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{پiژ؛’¬ژ‘مپ`چ]Œثژ‘مپj‚جژٹْ
پ@پ@‚ةپA ‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§پE•s’èژ–@پEڈ\“ٌژx•\ژ¦
پ@پ@ژچڈپ@‚ئپAپ@‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§پE•s’èژ–@پEژڈà
پ@پ@گ”•\ژ¦ژچڈپ@‚ج‚Q‚آ‚ھژg‚ي‚ꂽپB
پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{پiژ؛’¬ژ‘مپ`چ]Œثژ‘مپj‚ة‚ؤپA‚P
پ@پ@“ْ‚P‚Q“™•ھگ§‚جپu“ْ‚جڈo‚â“ْ–v‚ًٹîڈ€‚ئ‚·‚é
پ@پ@•s’èژ–@پv‚جژچڈپ@پiڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈپ@‚ئپ@ژ
پ@پ@ڈàگ”•\ژ¦ژچڈپj‚ھپAˆê”تڈژ–¯‚ةپA–{ٹi“I‚ة—ک
پ@پ@—p‚³‚ꂽپB
پ@
پ،پ@Œ³ک\گش•نژ–Œڈ‚جپA‹g—ا“@“¢‚؟“ü‚è‚ج“ْپB
پ@پ@پ@پ@‚P‚V‚O‚Q”NپiŒ³ک\‚P‚T”Nپj‚P‚QŒژ‚P‚T“ْ–¢–¾پEŒك
پ@پ@‘O‚Sژچ ‚ةپAگش•نکQژm‚حپA•\–ه‘à‚ئ— –ه‘à‚ج“ٌ
پ@پ@ژè‚ة•ت‚ê‚ؤپA‹g—ا“@‚ًڈPŒ‚‚µ‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@چ]Œثژ‘م“–ژ‚حپA•گ‰ئ‚إ‚حŒ»‘م‚ئ“¯—l‚ة
پ@پ@Œك‘O‚Oژ‚ھ1“ْ‚جژn‚ـ‚è‚إ‚ ‚é‚ھپAڈژ–¯‚إ‚حپA“ْ
پ@پ@‚جڈo‚ھ1“ْ‚جژn‚ـ‚è‚ئ‚³‚ꂽپBپ@‚»‚ج‚½‚كپA•گ‰ئ
پ@پ@‚جژ–@‚إ‚حپAگش•نکQژm‚ج‹g—ا“@“¢‚؟“ü‚è‚جڈP
پ@پ@Œ‚‚حپA‚P‚V‚O‚Q”NپiŒ³ک\‚P‚T”Nپj‚جپA‚P‚QŒژ‚P‚T“ْ–¢
پ@پ@–¾‚ئ‚ب‚èپAپ@ڈژ–¯‚جژ–@‚إ‚حپA‹g—ا“@“¢‚؟“ü‚è‚ج
پ@پ@ڈPŒ‚‚حپA‚P‚QŒژ‚P‚S“ْگ[–é‚ئ‚ب‚éپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ڈً–ٌ‰üگ³پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚â‚‚©‚¢‚¹‚¢پjپB
پ@
پ،پ@ڈً–ٌ‰üگ³پB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ڈً–ٌ‰üگ³پ@پi‚¶‚ه‚¤‚â‚‚©‚¢‚¹‚¢پjپB
پ،پ@–¾ژ،ژ‘م‚جڈً–ٌ‰üگ³–â‘èپB
پ،پ@•s•½“™ڈً–ٌ‚ج‰üگ³پB
پ،پ@–‹––‚ة“ْ–{‚جچ]Œث–‹•{‚ھ‰¢•ؤڈ”چ‘‚ئ’²ˆَ
پ@پ@‚µ‚½پuکaگeڈً–ٌپvپAپuˆہگ‚ج‚TƒJچ‘ڈً–ٌپv پA
پ@پ@پu‰üگإ–ٌڈ‘پv‚ج•s•½“™ڈً–ٌ‚ج‰üگ³پB
پ،پ@—جژ–چظ”»Œ پiژ،ٹO–@Œ پj‚âٹضگإژ©ژهŒ ‚جŒ‡
پ@پ@”@‚ج‹K’èپAپ@’ل—¦ٹضگإ‚ج‹K’èپAˆê•û“IچإŒb
پ@پ@چ‘‘ز‹ِ‚جڈًٹ¼پ@‚ب‚ا‚ج‰üگ³پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“Tپ@‚U‚P‚V‚R‚TپB
پ@
پ@
پ،پ@‰¢•ؤڈ”چ‘‚ئ’÷Œ‹‚µ‚½کaگeڈً–ٌ‚جپuˆê•û“IچإŒb
پ@پ@چ‘‘ز‹ِپvپi‚¢‚غ‚¤‚ؤ‚«‚³‚¢‚¯‚¢‚±‚‚½‚¢‚®‚¤پj‚جڈً
پ@پ@ٹ¼‚ھپAپ@•s•½“™ڈً–ٌ‘S‘ج‚ج‰üگ³‚ًچ¢“ï‚ة‚µ‚½پB
پ@
پ،پ@ڈً–ٌ‰üگ³پ@پi‚¶‚ه‚¤‚â‚‚©‚¢‚¹‚¢پjپ@‚ئ‚حپA–¾ژ،
پ@پ@ژ‘م‚جڈً–ٌ‰üگ³–â‘è‚إپAپ@–‹––‚ة“ْ–{‚جچ]Œث
پ@پ@–‹•{‚ھ‰¢•ؤڈ”چ‘‚ئ’²ˆَ‚µ‚½پAپuکaگeڈً–ٌپvپAپuˆہ
پ@پ@گ‚ج‚TƒJچ‘ڈً–ٌپvپAپu‰üگإ–ٌڈ‘پv‚ج•s•½“™ڈً–ٌ
پ@پ@‚ج‰üگ³پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@ڈً–ٌ‰üگ³‚حپAپ@پuˆہگ‚ج‚TƒJچ‘ڈً–ٌپv‚ج—جژ–
پ@پ@چظ”»Œ پiژ،ٹO–@Œ پjپAٹضگإژ©ژهŒ ‚جŒ‡”@‚ج‹K
پ@پ@’è‚ب‚اپ@‚âپAپ@پu‰üگإ–ٌڈ‘پv‚ج’ل—¦ٹضگإ‚ج‹K’èپA
پ@پ@کaگeڈً–ٌ‚جپuˆê•û“IچإŒbچ‘‘ز‹ِپv‚جڈًٹ¼پ@‚ب‚ا
پ@پ@‚ج•s•½“™ڈً–ٌ‚ج‹K’è‚ج‰üگ³‚ً‹پ‚ك‚é‚à‚ج‚إ‚
پ@پ@‚ء‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ،پ@–‹––پA“ْ–{‚جچ]Œث–‹•{‚ھ‰¢•ؤڈ”چ‘‚ئŒ‹‚ٌ‚¾پA
پ@پ@پuکaگeڈً–ٌپvپAپuˆہگ‚ج‚TƒJچ‘ڈً–ٌپv پAپu‰üگإ–ٌڈ‘پv
پ@پ@‚حپA•s•½“™ڈً–ٌ‚إ‚ ‚èپAپ@چ]Œث–‹•{ڈء–إŒمپAپ@–¾
پ@پ@ژ،ژ‘م‚ةپAپ@ڈً–ٌ‰üگ³–â‘è‚ًپA“ْ–{‚ج–¾ژ،گ•{
پ@پ@پi‹ك‘م“ْ–{گ•{پj‚ةژc‚µ‚½پB
پ@
پ،پ@ڈً–ٌ‰üگ³پ@پi‚¶‚ه‚¤‚â‚‚©‚¢‚¹‚¢پjپ@‚ئ‚حپAپ@–‹––
پ@پ@‚ة“ْ–{‚جچ]Œث–‹•{‚ھ‰¢•ؤڈ”چ‘‚ئ’²ˆَ‚µ‚½پuکaگe
پ@پ@ڈً–ٌپvپAپuˆہگ‚ج‚TƒJچ‘ڈً–ٌپv پAپu‰üگإ–ٌڈ‘پv‚ج•s
پ@پ@•½“™ڈً–ٌ‚ً‰üگ³‚·‚邱‚ئ‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ@
پ،پ@کaگeڈً–ٌپB
پœپ@پuکaگeڈً–ٌپv‚حپAپ@‚P‚W‚T‚S”N‚©‚ç‚P‚W‚T‚T”N‚ـ‚إ‚ج
پ@پ@ٹشپA“ْ–{‚جچ]Œث–‹•{‚ھ•ؤپE‰pپEکIپE—–‚ج‰¢•ؤ‚SƒJ
پ@پ@چ‘‚ئŒ‹‚ٌ‚¾کaگeڈً–ٌ‚ج‘چڈج‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@کaگeڈً–ٌ‚حپAپ@پuˆê•û“IچإŒbچ‘‘ز‹ِپv‚ج‹K’è
پ@پ@‚ب‚ا‚ھ‚ ‚éپA•s•½“™ڈً–ٌ‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@
پ،پ@ڈCچD’تڈ¤ڈً–ٌپ@پiˆہگ‚جŒـƒJچ‘ڈً–ٌپjپB
پœپ@پuˆہگ‚ج‚TƒJچ‘ڈً–ٌپvپ@پi‚ ‚ٌ‚¹‚¢‚ج‚²‚©‚±‚‚¶
پ@پ@‚ه‚¤‚â‚پjپ@‚حپAپ@‚P‚W‚T‚W”Nپiˆہگ‚T”Nپj‚ةپAپ@“ْ–{
پ@پ@‚جچ]Œث–‹•{‚ھ•ؤپE—–پEکIپE‰pپE•§‚ج‰¢•ؤ‚TƒJچ‘‚ئ
پ@پ@Œ‹‚ٌ‚¾پAڈCچD’تڈ¤ڈً–ٌ‚ج‘چڈجپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@ˆہگ‚جŒـƒJچ‘ڈً–ٌ‚حپAپ@—جژ–چظ”»Œ پiژ،ٹO
پ@پ@–@Œ پjپAپ@ٹضگإژ©ژهŒ ‚جŒ‡”@‚ج‹K’èپ@‚ب‚ا‚ھ‚
پ@پ@‚éپA•s•½“™ڈً–ٌ‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@
پ،پ@پu‰üگإ–ٌڈ‘پvپB
پœپ@پu‰üگإ–ٌڈ‘پvپ@پi‚©‚¢‚؛‚¢‚â‚‚µ‚هپjپ@‚حپAپ@‚P‚W‚U
پ@پ@‚U”N‚ةپAپ@“ْ–{‚جچ]Œث–‹•{‚ھ‰pپE•§پE•ؤپE—–‚ج‰¢
پ@پ@•ؤڈ”چ‘‚ئŒ‹‚ٌ‚¾پA–fˆص‹¦–ٌپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@‰üگإ–ٌڈ‘‚حپAپ@’ل—¦ٹضگإ‚ج‹K’è‚ھ‚ ‚éپA•s
پ@پ@•½“™ڈً–ٌپ@‚إ‚ ‚ء‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ@
پ،پ@“ْ–{‚ج–¾ژ،گ•{پi‹ك‘م“ْ–{گ•{پj‚جپA’·”N‚ج
پ@پ@“xڈd‚ب‚éپAڈً–ٌ‰üگ³Œًڈآ‚جŒ‹‰تپA‚â‚ء‚ئپAپuˆہ
پ@پ@گ‚ج‚TƒJچ‘ڈً–ٌپv‚âپu‰üگإ–ٌڈ‘پv‚ج•s•½“™ڈً
پ@پ@چ€‚جٹ®‘S‚ب“P”p‚ھچإڈI“I‚ةژہŒ»‚³‚ꂽ‚ج‚حپA
پ@پ@“ْکIگي‘ˆپi‚P‚X‚O‚Sپ`‚O‚T”NپjŒم‚جپA–¾ژ،ژ‘م––
پ@پ@‚ج‚P‚X‚P‚P”Nپi–¾ژ،‚S‚S”Nپj‚ج‚±‚ئ‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@‚»‚جˆê—ل‚ئ‚µ‚ؤپA–‹––‚ج•s•½“™ڈً–ٌ‚إ‚ ‚é
پ@پ@“ْ•ؤڈCچD’تڈ¤ڈً–ٌ‚ج•s•½“™‚ب‹K’è‚ھ“P”p‚³
پ@پ@‚ꂽ‚ج‚حپAپ@‚P‚X‚P‚P”Nپi–¾ژ،‚S‚S”Nپj‚إ‚ ‚ء‚½پBپ@
پ@پ@–¾ژ،گ•{پi‹ك‘م“ْ–{گ•{پj‚جٹO‘ٹ‚جڈ¬‘؛ژُ‘¾
پ@پ@کYپ@ پi‚±‚ق‚炶‚م‚½‚낤پjپ@‚ھپAƒAƒپƒٹƒJ‚ئڈً–ٌ‰ü
پ@پ@گ³‚جŒًڈآ‚ًچs‚¢پAپ@‚P‚X‚P‚P”N‚ةپA“ْ•ؤ’تڈ¤چq
پ@پ@ٹCڈً–ٌ‚ً’²ˆَ‚µپAپ@ٹضگإژ©ژهŒ ‚ج‰ٌ•œ‚ً‰ت‚½
پ@پ@‚µ‚½پBپ@
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ڈCچD’تڈ¤ڈً–ٌپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚م‚¤‚±‚¤‚آ‚¤‚µ‚ه‚¤‚¶‚ه‚¤‚â‚پjپB
پ@
پ،پ@ڈCچD’تڈ¤ڈً–ٌپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ڈCچD’تڈ¤ڈً–ٌپ@پi‚µ‚م‚¤‚±‚¤‚آ‚¤‚µ‚ه‚¤
پ@پ@‚¶‚ه‚¤‚â‚پjپB
پ،پ@‰pŒê–¼پ@پFپ@‚”‚ˆ‚…پ@‚s‚’‚…‚پ‚”‚™پ@‚ڈ‚†پ@ ‚`‚چ‚‰‚”‚™پ@‚پ‚ژ‚„پ@
پ@پ@‚b‚ڈ‚چ‚چ‚…‚’‚ƒ‚…پ@‚‚‚…‚”‚—‚…‚…‚ژپ@‚i‚پ‚گ‚پ‚ژپ@‚پ‚ژ‚„
پ@پ@‚e‚ڈ‚’‚…‚‰‚‡‚ژپ@‚b‚ڈ‚•‚ژ‚”‚’‚‰‚…‚“پ@‚إ‚ ‚éپB
پ،پ@•ت–¼پ@پFپ@ˆہگ‚ج‚TƒJچ‘ڈً–ٌپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ،پ@‚P‚W‚T‚W”N‚جˆہگ‚ج‚TƒJچ‘ڈً–ٌپB
پ،پ@‚P‚W‚T‚W”N‚ةپA“ْ–{‚جچ]Œث–‹•{‚ھ•ؤپE—–پEکI
پ@پ@پE‰pپE•§‚ج‰¢•ؤڈ”چ‘‚ئŒ‹‚ٌ‚¾پAڈCچD’تڈ¤ڈً–ٌپB
پ،پ@—جژ–چظ”»Œ پiژ،ٹO–@Œ پjپAٹضگإژ©ژهŒ ‚جŒ‡”@
پ@پ@‚ج‹K’è‚ب‚ا‚ھ‚ ‚éپA•s•½“™ڈً–ٌپB
پ@
پ@
پ،پ@ڈCچD’تڈ¤ڈً–ٌ‚حپA‚P‚W‚T‚W”N‚ة’²ˆَ‚³‚ꂽپuˆہ
پ@پ@گ‚ج‚TƒJچ‘ڈً–ٌپvپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@ڈCچD’تڈ¤ڈً–ٌ‚حپA‚P‚W‚T‚W”N‚ةپA“ْ–{‚جچ]Œث
پ@پ@–‹•{‚ھ•ؤپE—–پEکIپE‰pپE•§‚ج‰¢•ؤڈ”چ‘‚ئŒ‹‚ٌ‚¾پA
پ@پ@ڈCچD’تڈ¤ڈً–ٌپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@ڈCچD’تڈ¤ڈً–ٌ‚حپAپ@ —جژ–چظ”»Œ پiژ،ٹO–@Œ پjپA
پ@پ@ٹضگإژ©ژهŒ ‚جŒ‡”@‚ج‹K’è‚ب‚ا‚ھ‚ ‚éپA•s•½“™
پ@پ@ڈً–ٌپ@‚إ‚ ‚ء‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ،پ@ڈCچD’تڈ¤ڈً–ٌپ@پi‚µ‚م‚¤‚±‚¤‚آ‚¤‚µ‚ه‚¤‚¶‚ه‚¤‚â‚پjپ@
پ@پ@‚ئ‚حپAپ@‚P‚W‚T‚W”Nپiˆہگ‚T”Nپj‚ةپA“ْ–{‚ئ‰¢•ؤ‚TƒJ
پ@پ@چ‘‚ئ‚جٹش‚إ’²ˆَ‚³‚ꂽپAڈCچD’تڈ¤ڈً–ٌپ@‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@ڈCچD’تڈ¤ڈً–ٌ‚ج‰pŒê–¼‚حپA‚”‚ˆ‚…پ@ ‚s‚’‚…‚پ‚”‚™پ@‚ڈ‚†پ@
پ@پ@‚`‚چ‚‰‚”‚™پ@‚پ‚ژ‚„پ@‚b‚ڈ‚چ‚چ‚…‚’‚ƒ‚…پ@‚a‚…‚”‚—‚…‚…‚ژپ@‚i‚پ‚گ‚پ‚ژپ@
پ@پ@‚پ‚ژ‚„پ@‚e‚ڈ‚’‚…‚‰‚‡‚ژپ@‚b‚ڈ‚•‚ژ‚”‚’‚‰‚…‚“پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@‚P‚W‚T‚W”N‚ج“ْ•ؤڈCچD’تڈ¤ڈً–ٌ‚جژو‚茈‚ك‚جژه
پ@پ@‚ب“à—eپ@‚حپAپ@پi‚Pپjپ@گ_“قگىپA’·چèپAگVٹƒپi‚ة‚¢‚ھ
پ@پ@‚½پjپA•؛Œةپi‚ذ‚ه‚¤‚²پjپ@‚جٹJچ`پ@‚ئپAپ@چ]ŒثپA‘هچم
پ@پ@‚جٹJژsپi‚©‚¢‚µپjپAپ@پi‚Qپjپ@’تڈ¤‚حپAژ©—R–fˆص‚ئ‚·
پ@پ@‚邱‚ئپAپ@پi‚Rپjپ@ٹJچ`ڈê‚ة‹ڈ—¯’nپi‚«‚ه‚¤‚è‚م‚¤‚؟پj
پ@پ@‚ًگف‚¯پAپ@ˆê”تٹOچ‘گl‚جپAچ‘“à—·چs‚ً‹ض‚¶‚邱‚ئپAپ@
پ@پ@پi‚Sپjپ@‹ڈ—¯’n“à‚إ‚جپA—جژ–چظ”»Œ پi‚è‚ه‚¤‚¶‚³‚¢
پ@پ@‚خ‚ٌ‚¯‚ٌپj‚ً”F‚ك‚邱‚ئپ@پiژ،ٹO–@Œ پi‚؟‚ھ‚¢‚ظ‚¤
پ@پ@‚¯‚ٌپjپjپAپ@پi‚Tپjپ@ٹضگإ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA“ْ–{‚ةگإ—¦‚ج
پ@پ@Œˆ’èŒ ‚ح‚ب‚پAپ@‘ٹŒف‚إ‹¦’肵‚ؤŒˆ‚ك‚鋦’èٹض
پ@پ@گإ‚ئ‚·‚邱‚ئپ@پiٹضگإژ©ژهŒ ‚جŒ‡”@پi‚©‚ٌ‚؛‚¢‚¶
پ@پ@‚µ‚م‚¯‚ٌ‚ج‚¯‚آ‚¶‚هپjپ@‚ب‚ا‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@Œم‚ة“ْ–{‚ة‚ئ‚ء‚ؤ–â‘è‚ئ‚ب‚é‚ج‚ھپAپ@پi‚Sپj‚ج
پ@پ@ژ،ٹO–@Œ پ@‚ئپ@پi‚Tپj‚جٹضگإژ©ژهŒ ‚جŒ‡”@پ@‚إ‚
پ@پ@‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@‚»‚جŒمپAپ@چ]Œث–‹•{‚حپAپ@‚P‚W‚T‚W”N‚ةپAƒIƒ‰
پ@پ@ƒ“ƒ_پAƒچƒVƒAپAƒCƒMƒٹƒXپAƒtƒ‰ƒ“ƒX‚ئ‚àپAپ@“¯—l‚ج
پ@پ@“à—e‚جڈCچD’تڈ¤ڈً–ٌ‚ًŒ‹‚ٌ‚¾پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@ƒAƒپƒٹƒJ‚ئ‚جڈCچD’تڈ¤ڈً–ٌ‚ًٹـ‚كپA‚±‚ê‚ç‚T
پ@پ@ƒJچ‘‚جڈCچD’تڈ¤ڈً–ٌ‚ًپAپuˆہگ‚ج‚TƒJچ‘ڈً–ٌپv‚ئ
پ@پ@‚¢‚¤پB
پ@پ@پ@پ@چ]Œث–‹•{‚حپAکV’†ژٌچہپE–x“cگ³–r‚جڈً–ٌ’÷
پ@پ@Œ‹ژ¸”sŒمپA‘هکVپEˆنˆة’¼•J‚جڈً–ٌ’÷Œ‹ژہژ{‚ة‚و
پ@پ@‚èپA–ٌ‚Q‚O‚O”Nˆبڈم‚ة‚ي‚½‚éچ½چ‘گچô‚ً‚â‚كپAٹ®
پ@پ@‘S‚ةٹJچ‘‚µ‚½پB
پ@پ@پ@پ@“ْ–{‚حپAپ@چ]Œث–‹•{پE‘هکV‚جˆنˆة’¼•J‚جŒˆ’f
پ@پ@‚ة‚و‚艢•ؤ‚TƒJچ‘‚ئڈCچD’تڈ¤ڈً–ٌ‚ة’²ˆَ‚µپAپ@ٹ®
پ@پ@‘SٹJچ‘‚µ‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ،پ@“ْ•ؤڈCچD’تڈ¤ڈً–ٌ‚ًٹـ‚كپA‚P‚W‚T‚W”N‚جڈCچD’ت
ڈ¤ڈً–ٌپiˆہگŒـ‚©چ‘ڈً–ٌپj‚حپAپ@—جژ–چظ”»Œ ‚ً
پ@پ@”F‚ك‚éپAٹضگإژ©ژهŒ ‚ھ‚ب‚¢پA‚ب‚ا‚ئ‚¢‚ء‚½•s•½
پ@پ@“™ڈً–ٌپ@‚إ‚ ‚ء‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@“ْ–{‚ج–¾ژ،گ•{پi‹ك‘م“ْ–{گ•{پj‚جپA’·”N
پ@پ@‚ج“xڈd‚ب‚éپAڈً–ٌ‰üگ³Œًڈآ‚جŒ‹‰تپA‚â‚ء‚ئپA
پ@پ@پuˆہگ‚ج‚TƒJچ‘ڈً–ٌپv‚âپu‰üگإ–ٌڈ‘پv‚ج•s•½“™
پ@پ@ڈًچ€‚جٹ®‘S‚ب“P”p‚ھچإڈI“I‚ةژہŒ»‚³‚ꂽ‚ج‚حپA
پ@پ@“ْکIگي‘ˆپi‚P‚X‚O‚Sپ`‚O‚T”NپjŒم‚جپA–¾ژ،ژ‘م––
پ@پ@‚ج‚P‚X‚P‚P”Nپi–¾ژ،‚S‚S”Nپj‚ج‚±‚ئ‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@‚»‚جˆê—ل‚ئ‚µ‚ؤپA–‹––‚ج•s•½“™ڈً–ٌ‚إ‚ ‚é
پ@پ@“ْ•ؤڈCچD’تڈ¤ڈً–ٌ‚ج•s•½“™‚ب ‹K’è‚ھ“P”p‚³‚ê
پ@پ@‚½‚ج‚حپAپ@‚P‚X‚P‚P”Nپi–¾ژ،‚S‚S”Nپj‚إ‚ ‚ء‚½پBپ@–¾
پ@پ@ژ،گ•{پi‹ك‘م“ْ–{گ•{پj‚جٹO‘ٹ‚جڈ¬‘؛ژُ‘¾کYپ@
پ@پ@پi‚±‚ق‚炶‚م‚½‚낤پjپ@‚ھپAƒAƒپƒٹƒJ‚ئڈً–ٌ‰üگ³‚ج
پ@پ@Œًڈآ‚ًچs‚¢پAپ@‚P‚X‚P‚P”N‚ةپA“ْ•ؤ’تڈ¤چqٹCڈً–ٌ
پ@پ@‚ً’²ˆَ‚µپAپ@ٹضگإژ©ژهŒ ‚ج‰ٌ•œ‚ً‰ت‚½‚µ‚½پBپ@
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@گbگذچ~‰؛پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ٌ‚¹‚«‚±‚¤‚©پjپB
پ@
پ،پ@گbگذچ~‰؛پB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@گbگذچ~‰؛پ@پi‚µ‚ٌ‚¹‚«‚±‚¤‚©پjپB
پ@
پ@
پ،پ@چc‘°ژ’گ©پ@پi‚±‚¤‚¼‚‚µ‚¹‚¢پjپ@‚ئ‚حپAپ@چc‘°‚ھ“V
پ@پ@چc‚و‚èژ’پi‚½‚ـ‚يپj‚éژپپiژپ‘°–¼پj‚إپAپ@چc‘°‚ھگb
پ@پ@‰؛‚ة‰؛‚éچغ‚ة“Vچc‚و‚èژ’پi‚½‚ـ‚يپj‚éژپپiژپ‘°–¼پj
پ@پ@‚إ‚ ‚èپAپ@Œ¹ژپپA•½ژپپAچفŒ´پi‚ ‚è‚ي‚çپjژپ‚ب‚ا‚ھ
پ@پ@‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ،پ@گbگذچ~‰؛پB
پ@پ@پ@پ@گbگذچ~‰؛‚حپAپ@چc‘°‚ھپA“Vچc‚و‚èچc‘°ژ’گ©پi‚±
پ@پ@‚¤‚¼‚‚µ‚¹‚¢پj‚جژپپiژپ‘°–¼پj‚ًژ’پi‚½‚ـ‚يپj‚ء‚ؤپA
پ@پ@“Vچc‚جگb‰؛‚ة‰؛‚邱‚ئ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@’©’ى‚حپAپ@•½ˆہژ‘م‘OٹْپE’†ٹْ‚ةپAچàگژ–ڈî‚»
پ@پ@‚ج‘¼‚ج——R‚إپA‘‚¦‚½چc‘°‚ةپAپ@Œ¹ژپپA•½ژپپAچف
پ@پ@Œ´پi‚ ‚è‚ي‚çپjژپ‚ب‚ا‚جچc‘°ژ’گ©‚جژپپiژپ‘°–¼پj‚ً
پ@پ@—^‚¦‚ؤپAگbگذچ~‰؛‚³‚¹‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@•½ˆہŒمٹْˆبŒمپAپ@چcˆتŒpڈ³‚ةٹض‚ي‚è‚ج‚ب‚¢چc
پ@پ@‘°پiچcژqچcڈ—’Bپj‚حڈo‰ئ‚·‚éٹµ—ل‚ھگ¶‚ـ‚ꂽ‚½‚كپA
پ@پ@چc‘°‚ةŒ¹ژپپA•½ژپپAچفŒ´ژپ‚ب‚ا‚جچc‘°ژ’گ©‚جژپ
پ@پ@پiژپ‘°–¼پj‚ً—^‚¦‚ؤگbگذچ~‰؛‚³‚¹‚邱‚ئ‚حپAڈ‚ب‚
پ@پ@‚ب‚ء‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ژ–@پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ظ‚¤پjپ@پi= ژچڈ–@پjپB
پ@
پ،پ@ژ–@پB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ژ–@پ@پi‚¶‚ظ‚¤پjپB
پœپ@•ت–¼پ@پFپ@ژچڈ–@پ@پi‚¶‚±‚‚ظ‚¤پjپB
پ،پ@ژ–@پiژچڈ–@پj‚حپAژٹش‹و•ھŒ`ژ®پAژٹشٹشٹu
پ@پ@–@پi’èژ–@پE•s’èژ–@پjپAژچڈ•\ژ¦•ûژ®‚ة‚و‚èپA
پ@پ@•ھ—ق‚³‚ê‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ،پ@“ْ–{‚إژg‚ي‚ꂽژچڈپBپ@“ْ–{‚إ‚حپA‚Q‚آ‚ج
پ@ژٹش‹و•ھŒ`ژ®پA‚Q‚آ‚جژٹشٹشٹu–@پi’èژ–@پE•s
پ@’èژ–@پjپA‚R‚آ‚جژچڈ•\ژ¦•ûژ®‚ھژg—p‚³‚ꂽپB
پœپ@‹كŒ»‘م“ْ–{ژg—p‚ج‚P“ْ‚Q‚Sژٹشگ§پE’èژ–@
پ@پ@پEگ¼—mژ®•\ژ¦ژچڈپB
پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{ژg—p‚ج‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§پE’èژ–@
پ@پ@پ^•s’èژ–@پEڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈپi= ڈ\“ٌژxŒؤ
پ@پ@ڈجژچڈپjپB
پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{ژg—p‚ج‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§پE•s’èژ
پ@پ@–@پEژڈàگ”•\ژ¦ژچڈپi= گ”ŒؤڈجژچڈپjپB
پ@پ@
پ پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جژچڈپEژ–@پB
پ@
پ@
پںپ@ژ–@ پ@پi= ژچڈ–@پjپB
پ،پ@ژ–@پi‚¶‚ظ‚¤پj‚حپAپ@ˆê“ْ‚ً•ھ‚¯‚ؤژپiژچڈپj‚ً
پ@پ@Œˆ‚ك‚é•û–@‚إپAپ@ژپiژچڈپj‚جگ”‚¦•ûپAپ@‚»‚µ‚ؤپA
پ@پ@ژچڈ–@‚ئ‚¢‚¤ˆس–،‚إ‚ ‚éپBپ@
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ،پ@ژ–@پi‚¶‚ظ‚¤پjپ@‚ئ‚حپAپ@ژچڈ–@ پAژٹش‹و•ھ–@
پ@پ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@ژ–@پiژچڈ–@پj‚حپA‰pŒê–¼‚إپAپ@‚”‚ˆ‚…پ@‚چ‚…‚”‚ˆ‚ڈ‚„پ@‚ڈ‚†پ@
پ@پ@‚ƒ‚ڈ‚•‚ژ‚”‚‰‚ژ‚‡پ@‚ˆ‚ڈ‚•‚’‚“پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@
پںپ@ژٹشٹشٹu–@پ@پi’èژ–@‚ئ•s’èژ–@پjپB
پ،پ@“ْ–{‚إ—ک—p‚³‚ꂽپA‚Q‚آ‚جژٹشٹشٹu–@پB
پ،پ@ژ–@پiژچڈ–@پj‚جژٹشٹشٹu–@‚ة‚حپAپ@‚Q‚آ‚ج
پ@پ@ژٹشٹشٹu–@پi’èژ–@پE•s’èژ–@پj‚ھ‚ ‚éپB
پœپ@ژ–@پiژچڈ–@پj‚جژٹشٹشٹu–@‚ة‚حپAپ@’èژ–@پ@
پ@پ@پi‚ؤ‚¢‚¶‚ظ‚¤پjپ@‚ئپ@•s’èژ–@پ@پi‚س‚ؤ‚¢‚¶‚ظ‚¤پjپ@
پ@پ@‚ج‚Qژي—ق‚ھ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پœپ@ژ–@پiژچڈ–@پj‚جژٹشٹشٹu–@‚ة‚حپAگ¢ٹE“I‚ةپA
پ@پ@’èژ–@‚ئ•s’èژ–@‚ھ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@“ْ–{‚إ‚حپA’èژ–@‚à•s’èژ–@‚àپAژg‚ي‚ꂽپB
پœپ@’èژ–@‚حپA‰pŒê–¼‚إپAپ@‚”‚ˆ‚…پ@‚چ‚…‚”‚ˆ‚ڈ‚„پ@‚ڈ‚†پ@
پ@پ@‚ƒ‚ڈ‚•‚ژ‚”‚‰‚ژ‚‡پ@‚…‚‘‚•‚پ‚Œپ@‚Œ‚…‚ژ‚‡‚”‚ˆپ@‚ˆ‚ڈ‚•‚’‚“پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@•s’èژ–@‚حپA‰pŒê–¼‚إپAپ@‚”‚ˆ‚…پ@‚چ‚…‚”‚ˆ‚ڈ‚„پ@
پ@پ@‚ڈ‚†پ@‚ƒ‚ڈ‚•‚ژ‚”‚‰‚ژ‚‡پ@‚•‚ژ‚…‚‘‚•‚پ‚Œپ@‚Œ‚…‚ژ‚‡‚”‚ˆپ@‚ˆ‚ڈ‚•‚’‚“پ@
پ@پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@ژٹشٹشٹuŒإ’è•û–@‚جپA’èژ–@پB
پ،پ@’èژ–@‚ئ‚حپA‹GگكپA’‹–é‚ةٹضŒW‚ب‚پAژٹش‚ً
پ@پ@چڈ‚قٹشٹu‚ھڈي‚ةˆê’è‚إ‚ ‚éژ–@پiژچڈ–@پj
پ@پ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پœپ@’èژ–@‚حپAپ@ژٹش‚ًچڈ‚قٹشٹu‚ھڈي‚ةˆê’è‚إ
پ@پ@‚ ‚éژچڈ–@‚إ‚ ‚èپAپ@‹GگكپA’‹–é‚ةٹضŒW‚ب‚پA
پ@پ@ˆê“ْپiˆê“ْ‚ج’·‚³پj‚ً“™•ھ‚µ‚ؤژپiژچڈپj‚ًŒˆ
پ@پ@‚ك‚éژ–@پiژچڈ–@پjپ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‹كپEŒ»‘م“ْ–{پi–¾ژ،ژ‘مپ`Œ»چفپj‚جژٹْ‚ةپA
پ@پ@‚P“ْ‚Q‚Sژٹشگ§پE’èژ–@پEگ¼—mژ®•\ژ¦ژچڈ‚ھ
پ@پ@ژg‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{پi‚Vگ¢‹Iپ`چ]Œثژ‘مپj‚جژٹْ‚ةپA
پ@پ@‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§پE’èژ–@پEڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈ‚ھپ@
پ@پ@ژg‚ي‚ꂽپB
پ@
پ،پ@ژٹشٹشٹu•د“®•û–@‚جپA•s’èژ–@پB
پ،پ@•s’èژ–@‚حپA‹GگكپA’‹–é‚ة‚و‚èپAژٹش‚ًچڈ‚ق
پ@پ@ٹشٹu‚ھˆê’è‚إ‚ب‚¢پAژ–@پiژچڈ–@پjپ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پœپ@•s’èژ–@‚حپAپ@‹GگكپA’‹–é‚ة‚و‚èپA‹و•ھ‚³‚ê
پ@پ@‚½ژٹش‚ج’·‚³‚ھˆل‚ء‚ؤ‚‚éژ–@پiژچڈ–@پjپ@‚إ
پ@پ@‚ ‚éپB
پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{پiژ؛’¬ژ‘مپ`چ]Œثژ‘مپj‚ة‚ؤپA
پ@پ@‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§‚جپu“ْ‚جڈo‚â“ْ–v‚ًٹîڈ€‚ئ‚·
پ@پ@‚é•s’èژ–@ پv ‚جژچڈپ@پiڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈپ@‚ئپ@
پ@پ@ژڈàگ”پE•\ژ¦ژچڈپjپ@‚ھˆê”تڈژ–¯‚ة—ک—p‚³‚ê
پ@پ@‚½پB
پ@
پ@
پںپ@ژٹش‹و•ھŒ`ژ®پB
پ،پ@“ْ–{‚إ—ک—p‚³‚ꂽپA‚Q‚آ‚جژٹش‹و•ھŒ`ژ®پB
پ،پ@ژ–@پiژچڈ–@پj‚جژٹش‹و•ھŒ`ژ®‚ة‚حپA‚Q‚آ‚ج
پ@پ@ژٹش‹و•ھŒ`ژ®پ@‚ھ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ،پ@ژ–@پiژچڈ–@پj‚جژٹش‹و•ھŒ`ژ®‚ة‚حپA‚P“ْ
پ@پ@‚Q‚Sژٹشگ§پA‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§پ@‚ب‚ا‚ھ‚ ‚éپB
پœپ@“ْ–{‚إ—ک—p‚³‚ꂽژٹش‹و•ھŒ`ژ®‚ة‚حپA‹كپEŒ»
پ@پ@‘م“ْ–{ژg—p ‚جپA‚P“ْ‚Q‚Sژٹشگ§‚جژ–@پ@‚ئپA‘O
پ@پ@‹ك‘م“ْ–{ژg—p‚جپA‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§‚جژ–@ ‚ج‚Q
پ@پ@‚آ‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پ@
پںپ@ژچڈ•\ژ¦•ûژ®پB
پ،پ@“ْ–{‚إ—ک—p‚³‚ꂽپA‚R‚آ‚جژچڈ•\ژ¦•ûژ®پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ،پ@ژ–@پiژچڈ–@پj‚جژچڈ•\ژ¦•ûژ®‚ة‚حپAپ@‚R‚آ
پ@پ@‚جژچڈ•\ژ¦•ûژ®‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@ژچڈ–@پiژ–@پj‚جژچڈ•\ژ¦•ûژ®‚ة‚حپAپ@گ¼—m
پ@پ@ژ®•\ژ¦ژچڈپAپ@ڈ\“ٌژxپi‚¶‚م‚¤‚ة‚µپj•\ژ¦ژچڈپAپ@
پ@پ@ژڈàگ”پi‚¶‚µ‚ه‚¤‚·‚¤پj•\ژ¦ژچڈپ@‚ب‚ا‚ھ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پœپ@“ْ–{‚إ—ک—p‚³‚ꂽژچڈ•\ژ¦•ûژ®‚ة‚حپA‹كŒ»
پ@پ@‘م“ْ–{ژg—p ‚جگ¼—mژ®•\ژ¦ژچڈپ@‚ئپAپ@‘O‹ك‘م
پ@پ@“ْ–{ژg—p‚جڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈپ@‚ئپAپ@‘O‹ك‘م“ْ
پ@پ@–{ژg—p‚جژڈàگ”•\ژ¦ژچڈپ@‚ج‚R‚آ‚ھ‚ ‚éپB
پœپ@‹كŒ»‘م“ْ–{ژg—p‚ج‚P“ْ‚Q‚Sژٹشگ§پE’èژ–@
پ@پ@پEگ¼—mژ®•\ژ¦ژچڈپB
پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{ژg—p‚ج‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§پE’èژ–@
پ@پ@پ^•s’èژ–@پEڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈپi= ڈ\“ٌژxŒؤ
پ@پ@ڈجژچڈپjپB
پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{ژg—p‚ج‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§پE•s’èژ
پ@پ@–@پEژڈàگ”•\ژ¦ژچڈپi= گ”ŒؤڈجژچڈپjپB
پ@
پ،پ@ڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈپi= ڈ\“ٌژxŒؤڈجژچڈپjپ@‚حپA
پ@پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚إژg‚ي‚ꂽپA’èژ–@‚ئ•s’èژ–@‚جپA
پ@پ@ڈ\“ٌژxپi‚¶‚م‚¤‚ة‚µپj‚إ•\ژ¦‚·‚éژچڈپ@‚إ‚ ‚éپBپ@
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پœپ@ڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈپi= ڈ\“ٌژxŒؤڈجژچڈپj‚ة‚حپAپ@
پ@پ@‘O‹ك‘م“ْ–{ژg—p‚ج‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§پE’èژ–@پEڈ\
پ@پ@“ٌژx•\ژ¦ژچڈپ@‚ئپAپ@‘O‹ك‘م“ْ–{ژg—p‚ج‚P“ْ
پ@پ@‚P‚Q“™•ھگ§پEپu“ْ‚جڈo‚â“ْ–v‚ًٹîڈ€‚ئ‚·‚é•s’è
پ@پ@ژ–@پvپEڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈپ@‚ج‚Q‚آ‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@ژڈàگ”•\ژ¦ژچڈپi= گ”Œؤڈجژچڈپj‚حپAپ@‘O‹ك‘م
“ْ–{‚إژg‚ي‚ꂽپA پu“ْ‚جڈo‚â“ْ–v‚ًٹîڈ€‚ئ‚·‚é
پ@پ@•s’èژ–@پv‚جپAژڈàپi‚¶‚µ‚ه‚¤پj‚جگ”‚إ•\ژ¦‚·‚é
پ@پ@ژچڈ‚إ‚ ‚éپBپ@
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پœپ@ژڈàگ”•\ژ¦ژچڈپi= گ”Œؤڈجژچڈپj‚حپAپ@‘O‹ك‘م
پ@پ@“ْ–{ژg—p‚ج‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§پE•s’èژ–@پEژڈàگ”
پ@پ@•\ژ¦ژچڈپ@‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@
پ@
پںپ@“ْ–{‚إژg‚ي‚ꂽپA’èژ–@‚ئ•s’èژ
پ@پ@–@‚جژچڈپB
پ،پ@“ْ–{‚إژg—p‚³‚ꂽژ–@پi‚¶‚ظ‚¤پj‚جژٹشٹشٹu–@
پ@پ@پi’èژ–@‚ئ•s’èژ–@پj‚جژچڈ‚ة‚حپAپ@‹كپEŒ»‘م“ْ
پ@پ@–{‚إژg—p‚µ‚ؤ‚¢‚éپA‚P“ْ‚Q‚Sژٹشگ§‚ج’èژ–@‚ج
پ@پ@گ¼—mژ®•\ژ¦ژچڈپAپ@‘O‹ك‘م“ْ–{پiژ؛’¬ژ‘مپ`چ]
پ@پ@Œثژ‘مپj‚جˆê”تڈژ–¯‚ةژg—p‚³‚ꂽپA‚P“ْ‚P‚Q“™
پ@پ@•ھگ§‚جپu“ْ‚جڈo‚â“ْ–v‚ًٹîڈ€‚ئ‚·‚é•s’èژ–@پv
پ@پ@‚جڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈ‚âژڈàگ”•\ژ¦ژچڈپAپ@‘O‹ك
پ@پ@‘م“ْ–{پi‚Vگ¢‹Iپ`چ]Œثژ‘مپj‚ة—ک—p‚³‚ꂽ—lپX
پ@پ@‚ب’èژ–@‚جڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈپ@‚ھ‚ ‚ء‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ،پ@“ْ–{‚إژg‚ي‚ꂽپA’èژ–@‚جژچڈپB
پœپ@’èژ–@‚حپA‹GگكپA’‹–é‚ةٹضŒW‚ب‚پAژٹش‚ًچڈ
پ@پ@‚قٹشٹu‚ھڈي‚ةˆê’è‚إ‚ ‚éژ–@پiژچڈ–@پjپ@‚إ
پ@پ@‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ،پ@“ْ–{‚إژg‚ي‚ꂽ’èژ–@‚جژچڈ‚ة‚حپAپ@‹كŒ»
پ@پ@‘م“ْ–{ژg—p‚ج‚P“ْ‚Q‚Sژٹشگ§پE’èژ–@پEگ¼—mژ®
پ@پ@ژچڈپ@‚ئپAپ@‘O‹ك‘م“ْ–{ژg—p‚ج‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§پE
پ@پ@’èژ–@پEڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈپ@‚ج‚Q‚آ‚ج’èژ–@‚ج
پ@پ@ژچڈپ@‚ھ‚ ‚ء‚½پB
پ،پ@‹كپEŒ»‘م“ْ–{‚إ‚حپA
پ@پ@‚P“ْ‚Q‚Sژٹشگ§‚ج’èژ–@‚جگ¼—mژ®•\ژ¦ژچڈ‚ھ
پ@پ@ژg‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚éپBپ@
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚إ‚حپA
پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{پi‚Vگ¢‹Iپ`‚P‚W‚S‚R”NپE“V•غ‚P‚S”Nپj
پ@پ@‚إ‚حپAŒِژ®‚ج’èژ–@‚ھ—ک—p‚³‚ꂽپB
پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{پi‚Vگ¢‹Iپ`چ]Œثژ‘مپj‚إ‚حپA—lپX
پ@پ@‚ب’èژ–@‚جژچڈ‚ھژg‚ي‚ꂽپBپ@ژ؛’¬ژ‘م‚©‚ç
پ@پ@چ]Œثژ‘م‚ـ‚إپAڈم‘wٹK‘w‚ج‚ف‚ھ’èژ–@‚ً—ک
پ@پ@—p‚µ‚½پB
پ@
پ،پ@“ْ–{‚إژg‚ي‚ꂽپA•s’èژ–@‚جژ
پ@پ@چڈپB
پœپ@•s’èژ–@‚حپA‹GگكپA’‹–é‚ة‚و‚èپAژٹش‚ًچڈ‚ق
پ@پ@ٹشٹu‚ھˆê’è‚إ‚ب‚¢پAژ–@پiژچڈ–@پj‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ،پ@“ْ–{‚إژg‚ي‚ꂽ•s’èژ–@‚جژچڈ‚ة‚حپAپ@‘O
پ@پ@‹ك‘م“ْ–{ژg—p‚ج‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§پE•s’èژ–@پE
پ@پ@ڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈپ@‚ئپAپ@‘O‹ك‘م“ْ–{ژg—p‚ج‚P
پ@پ@“ْ‚P‚Q“™•ھگ§پE•s’èژ–@پEژڈàگ”•\ژ¦ژچڈ‚ج
پ@پ@‚Q‚آ‚ج•s’èژ–@‚جژچڈ‚ھ‚ ‚ء‚½پB
پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{پiژ؛’¬ژ‘مپ`چ]Œثژ‘مپj‚ة‚ؤپA
پ@پ@‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§‚جپu“ْ‚جڈo‚â“ْ–v‚ًٹîڈ€‚ئ‚·
پ@پ@‚é•s’èژ–@ پv ‚جژچڈپ@پiڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈپ@‚ئپ@
پ@پ@ژڈàگ”پE•\ژ¦ژچڈپjپ@‚ھˆê”تڈژ–¯‚ة—ک—p‚³‚ê
پ@پ@‚½پB
پ@
پ@
پںپ@ٹeژٹْ‚ج“ْ–{‚إژg‚ي‚ꂽژچڈپB
پ،پ@“ْ–{‚إ‚حپA’èژ–@‚جژچڈ‚à•s’èژ–@‚جژچڈ
پ@پ@‚àپA—ک—p‚³‚ꂽپB
پ@
پ،پ@‹كŒ»‘م“ْ–{‚إ‚حپA
پœپ@‹كپEŒ»‘م“ْ–{پi–¾ژ،ژ‘مپ`Œ»چفپj‚جژٹْ‚ةپA
پ@پ@‚P“ْ‚Q‚Sژٹشگ§پE’èژ–@پEگ¼—mژ®•\ژ¦ژچڈ‚ھ
پ@پ@ژg‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
پ@
پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚إ‚حپA
پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{پi‚Vگ¢‹Iپ`چ]Œثژ‘مپj‚جژٹْ‚ةپA
پ@پ@‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§پE’èژ–@پEڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈ‚ھپ@
پ@پ@ژg‚ي‚ꂽپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{پiژ؛’¬ژ‘مپ`چ]Œثژ‘مپj‚جژٹْ
پ@پ@‚ةپA ‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§پE•s’èژ–@پEڈ\“ٌژx•\ژ¦
پ@پ@ژچڈپ@‚ئپAپ@‚P“ْ‚P‚Q“™•ھگ§پE•s’èژ–@پEژڈà
پ@پ@گ”•\ژ¦ژچڈپ@‚ج‚Q‚آ‚ھژg‚ي‚ꂽپB
پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{پiژ؛’¬ژ‘مپ`چ]Œثژ‘مپj‚ة‚ؤپA‚P
پ@پ@“ْ‚P‚Q“™•ھگ§‚جپu“ْ‚جڈo‚â“ْ–v‚ًٹîڈ€‚ئ‚·‚é
پ@پ@•s’èژ–@پv‚جژچڈپ@پiڈ\“ٌژx•\ژ¦ژچڈپ@‚ئپ@ژ
پ@پ@ڈàگ”•\ژ¦ژچڈپj‚ھپAˆê”تڈژ–¯‚ةپA–{ٹi“I‚ة—ک
پ@پ@—p‚³‚ꂽپB
پ@
پ،پ@Œ³ک\گش•نژ–Œڈ‚جپA‹g—ا“@“¢‚؟“ü‚è‚ج“ْپB
پ@پ@پ@پ@‚P‚V‚O‚Q”NپiŒ³ک\‚P‚T”Nپj‚P‚QŒژ‚P‚T“ْ–¢–¾پEŒك
پ@پ@‘O‚Sژچ ‚ةپAگش•نکQژm‚حپA•\–ه‘à‚ئ— –ه‘à‚ج“ٌ
پ@پ@ژè‚ة•ت‚ê‚ؤپA‹g—ا“@‚ًڈPŒ‚‚µ‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@چ]Œثژ‘م“–ژ‚حپA•گ‰ئ‚إ‚حŒ»‘م‚ئ“¯—l‚ة
پ@پ@Œك‘O‚Oژ‚ھ1“ْ‚جژn‚ـ‚è‚إ‚ ‚é‚ھپAڈژ–¯‚إ‚حپA“ْ
پ@پ@‚جڈo‚ھ1“ْ‚جژn‚ـ‚è‚ئ‚³‚ꂽپBپ@‚»‚ج‚½‚كپA•گ‰ئ
پ@پ@‚جژ–@‚إ‚حپAگش•نکQژm‚ج‹g—ا“@“¢‚؟“ü‚è‚جڈP
پ@پ@Œ‚‚حپA‚P‚V‚O‚Q”NپiŒ³ک\‚P‚T”Nپj‚جپA‚P‚QŒژ‚P‚T“ْ–¢
پ@پ@–¾‚ئ‚ب‚èپAپ@ڈژ–¯‚جژ–@‚إ‚حپA‹g—ا“@“¢‚؟“ü‚è‚ج
پ@پ@ڈPŒ‚‚حپA‚P‚QŒژ‚P‚S“ْگ[–é‚ئ‚ب‚éپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ژlˆتپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚¢پjپB
پ@
پ،پ@ژlˆتپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ژlˆتپ@پi‚µ‚¢پjپB
پ،پ@ˆتٹK‚جƒOƒ‹پ[ƒvپB
پ،پ@ژg—pٹْٹشپiڈ–ˆتٹْٹشپjپ@پFپ@
پœپ@Œأ‘م“ْ–{‚ج”ٍ’¹”’–Pژ‘م‚©‚猻‘م“ْ–{‚ج
پ@پ@Œ»چف‚ـ‚إپBپ@
پœپ@پiگ¼—ï‹IŒ³Œمپj‚V‚O‚P”Nچ ‚©‚猻چف‚ـ‚إپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ،پ@’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پjپAگEˆُ—كپAڈ–ˆتڈً—لپAˆتٹK
پ@پ@—ك‚جˆتٹKپ@پi‚V‚O‚P”Nچ پ`Œ»چفپAڈ–ˆت‚ةژg—pپjپB
پœپ@گ³ژlˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚¢پj پ@‚ئپ@ڈ]ژlˆتپ@پi‚¶‚م‚µ
پ@پ@‚¢پjپ@‚ج‚Q‚آ‚جˆتٹKپB
پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj‚جˆتٹKپB
پœپ@گ³ژlˆت
پ@پ@پ›پ@گ³ژlˆتڈمپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپB
پ@پ@پ›پ@گ³ژlˆت‰؛پ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚¢‚ج‚°پjپB
پœپ@ڈ]ژlˆت
پ@پ@پ›پ@ڈ]ژlˆتڈمپ@پi‚¶‚م‚µ‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپB
پ@پ@پ›پ@ڈ]ژlˆت‰؛پ@پi‚¶‚م‚µ‚¢‚ج‚°پjپB
پ@
پ پ@‘O‹ك‘م‚ج’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj‚جˆتٹKپB
پ پ@ˆتٹKپB
پ پ@ڈ–ˆتپB
پ@
پ@
پ،پ@ژlˆتپB
پ،پ@ژlˆتپ@پi‚µ‚¢پjپ@‚ئ‚حپAپ@گ³ژlˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚¢پjپ@
پ@پ@‚ئپ@ڈ]ˆêˆتپ@پi‚¶‚م‚µ‚¢پjپ@‚ج‚Q‚آ‚جˆتٹKپ@‚إ
پ@پ@‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@چX‚ةپA‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj‚ج
پ@پ@ˆتٹK‚إ‚حپAژlˆت‚ة‚حپAپ@گ³پEڈ]پi‚µ‚ه‚¤پE‚¶‚مپj
پ@پ@ژlˆت‚ج‚Q‚آ‚جˆتٹK‚ةڈم‰؛‚ً•t‚¯‚ؤپAژں‚ج‚و
پ@پ@‚¤‚ب‚S‚آ‚جˆتٹK‚ھ‚ ‚ء‚½پB
پ@پ@پ›پ@گ³ژlˆتڈمپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپB
پ@پ@پ›پ@گ³ژlˆت‰؛پ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚¢‚ج‚°پjپB
پ@پ@پ›پ@ڈ]ژlˆتڈمپ@پi‚¶‚م‚µ‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپB
پ@پ@پ›پ@ڈ]ژlˆت‰؛پ@پi‚¶‚م‚µ‚¢‚ج‚°پjپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ،پ@ژlˆتپ@پi‚µ‚¢پjپ@‚حپAپ@Œأ‘م“ْ–{‚ج”ٍ’¹”’–P
پ@پ@ژ‘م‚©‚猻‘م“ْ–{‚جŒ»چف‚ـ‚إ‚جٹْٹش‚جڈ–
پ@پ@ˆت‚ةژg—p‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éˆتٹKپ@‚إپAپ@پiگ¼—ï‹IŒ³
پ@پ@Œمپj‚V‚O‚P”Nچ ‚©‚猻چف‚ـ‚إ‚جٹْٹش‚جڈ–ˆت‚ةپA
پ@پ@ژg—p‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپBپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@Œ»چف‚حپA‚P‚X‚S‚V”N‚ج‰üگ³ˆتٹK—ك‚ة‚و‚èپA
پ@پ@Œ÷گر‚ج‚ ‚ء‚½پAŒجگlپiژ€–Sژزپj‚ض‚ج‚فپAڈ–ˆت
پ@پ@‚ھچs‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ،پ@ژlˆتپB
پ،پ@—¥—كٹ¯گ§‚جˆتٹKپBپ@
پ@پ@پ@پƒ‚V‚O‚P”Nچ پ`‚P‚W‚U‚X”Nچ پ„
پ@پœپ@’©’ى‚جˆتٹK‚جپuˆêˆتپ`”ھˆتپAڈ‰ˆتپv‚ج
پ@پ@‚XƒOƒ‹پ[ƒv‚ج‚S”ش–ع‚جƒOƒ‹پ[ƒv‚جˆتٹKپB
پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@پœپ@’©’ى‚ج‚R‚OˆتٹKپi‚¢‚©‚¢پj‚جپA
پ@پ@‚V”ش–ع‚جگ³ژlˆتڈمپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپA
پ@پ@‚W”ش–ع‚جگ³ژlˆت‰؛پ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚¢‚ج‚°پjپA
پ@پ@‚X”ش–ع‚جڈ]ژlˆتڈمپ@پi‚¶‚م‚µ‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپA
پ@پ@‚P‚O”ش–ع‚جڈ]ژlˆت‰؛پ@پi‚¶‚م‚µ‚¢‚ج‚°پjپA
پ@پ@‚ج‚S‚آ‚جˆتٹK‚إ‚ ‚éپB
پ،پ@گEˆُ—كپi‚P‚W‚U‚X”Nگ§’èپj‚جˆتٹKپB
پ@پ@پ@پƒ‚P‚W‚U‚X”Nچ پ`‚P‚W‚W‚V”Nچ پ„
پ@پœپ@‹ك‘م“ْ–{گ•{‚جˆتٹK‚جپuˆêˆتپ`‹مˆتپA
پ@پ@ڈ‰ˆتپv‚ج‚P‚OƒOƒ‹پ[ƒv‚ج ‚S”ش–ع‚جƒOƒ‹پ[ƒv
پ@پ@‚جˆتٹKپB
پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@پœپ@‹ك‘م“ْ–{گ•{‚ج‚Q‚OˆتٹK‚جپA
پ@پ@‚V”ش–ع‚جگ³ژlˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚¢پjپA
پ@پ@‚W”ش–ع‚جڈ]ˆêˆتپ@پi‚¶‚م‚µ‚¢پjپA
پ@پ@‚ج‚Q‚آ‚جˆتٹK‚إ‚ ‚éپB
پ،پ@ڈ–ˆتڈً—لپi‚P‚W‚W‚V”Nگ§’èپjپAˆتٹK—ك
پ@پ@پi‚P‚X‚Q‚U”Nگ§’èپA‚P‚X‚S‚V”N‰üگ³پj‚ج
پ@پ@ˆتٹKپB
پ@پ@پ@پƒ‚P‚W‚W‚V”Nچ پ`Œ»چفپ„
پ@پœپ@‹كپEŒ»‘م“ْ–{گ•{‚جˆتٹK‚جپuˆêˆتپ`”ھˆتپv
پ@پ@‚ج‚WƒOƒ‹پ[ƒv‚ج ‚S”ش–ع‚جƒOƒ‹پ[ƒv‚جˆتٹKپB
پ@پœپ@‹كپEŒ»‘م“ْ–{گ•{‚ج‚P‚UˆتٹK‚ج پA
پ@پ@‚V”ش–ع‚جگ³ژlˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚¢پjپA
پ@پ@‚W”ش–ع‚جڈ]ˆêˆتپ@پi‚¶‚م‚µ‚¢پjپA
پ@پ@‚ج‚Q‚آ‚جˆتٹK‚إ‚ ‚éپB
پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ،پ@ژlˆتپB
پ،پ@—¥—كٹ¯گ§‚جˆتٹKپBپ@
پ@پ@پƒ‚V‚O‚P”Nچ پ`‚P‚W‚U‚X”Nچ پ„
پ@پœپ@ژlˆت‚حپAپ@’©’ى‚جˆتٹK‚جپuˆêˆتپ`”ھˆتپAڈ‰
پ@پ@پ@ˆتپv‚ج ‚XƒOƒ‹پ[ƒv‚ج‚¤‚؟‚جپAڈم‚©‚ç‚S”ش–ع‚ج
پ@پ@پ@ƒOƒ‹پ[ƒv‚جˆتٹK‚إ‚ ‚éپB
پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@پœپ@ژlˆت‚حپAپ@گ³ˆêˆتپi‚µ‚ه‚¤‚¢‚؟‚¢پj‚©‚çڈڈ‰ˆت
پ@پ@پ@‰؛پi‚µ‚ه‚¤‚»‚¢‚ج‚°پj‚ـ‚إ‚ج’©’ى‚ج‚R‚OˆتٹKپi‚¢
پ@پ@پ@‚©‚¢پj‚جپA
پ@پ@پ@‚V”ش–ع‚جگ³ژlˆتڈمپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپA
پ@پ@پ@‚W”ش–ع‚جگ³ژlˆت‰؛پ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚¢‚ج‚°پjپA
پ@پ@پ@‚X”ش–ع‚جڈ]ژlˆتڈمپ@پi‚¶‚م‚µ‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپA
پ@پ@پ@‚P‚O”ش–ع‚جڈ]ژlˆت‰؛پ@پi‚¶‚م‚µ‚¢‚ج‚°پjپA
پ@پ@پ@‚ج‚S‚آ‚جˆتٹK‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@گEˆُ—كپi‚P‚W‚U‚X”Nگ§’èپj‚جˆتٹKپB
پ@پ@پƒ‚P‚W‚U‚X”Nچ پ`‚P‚W‚W‚V”Nچ پ„
پ@پœپ@ژlˆت‚حپAپ@‹ك‘م“ْ–{گ•{‚جˆتٹK‚جپuˆêˆتپ`
پ@پ@پ@‹مˆتپAڈ‰ˆتپv‚ج‚P‚OƒOƒ‹پ[ƒv‚ج ‚¤‚؟‚جڈم‚©‚ç
پ@پ@پ@‚S”ش–ع‚جƒOƒ‹پ[ƒv‚جˆتٹK‚إ‚ ‚éپB
پ@پœپ@ژlˆت‚حپAپ@گ³ˆêˆتپi‚µ‚ه‚¤‚¢‚؟‚¢پj‚©‚çڈڈ‰ˆت
پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚»‚¢پA‚µ‚ه‚¤‚µ‚ه‚¢پj‚ـ‚إ‚ج‹ك‘م“ْ–{گ
پ@پ@پ@•{‚ج‚Q‚OˆتٹK‚جپA
پ@پ@پ@‚V”ش–ع‚جگ³ژlˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚¢پjپA
پ@پ@پ@‚W”ش–ع‚جڈ]ˆêˆتپ@پi‚¶‚م‚µ‚¢پjپA
پ@پ@پ@‚ج‚Q‚آ‚جˆتٹK‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ،پ@ڈ–ˆتڈً—لپi‚P‚W‚W‚V”Nگ§’èپjپAˆتٹK—ك
پ@پ@پi‚P‚X‚Q‚U”Nگ§’èپA‚P‚X‚S‚V”N‰üگ³پj‚جˆتٹKپB
پ@پ@پƒ‚P‚W‚W‚V”Nچ پ`Œ»چفپ„
پ@پœپ@ژlˆت‚حپAپ@‹كپEŒ»‘م“ْ–{گ•{‚جˆتٹK‚جپuˆêˆت
پ@پ@پ@پ`”ھˆتپv‚ج‚WƒOƒ‹پ[ƒv‚ج ‚¤‚؟‚جڈم‚©‚ç‚S”ش–ع
پ@پ@پ@‚جƒOƒ‹پ[ƒv‚جˆتٹK‚إ‚ ‚éپB
پ@پœپ@ژlˆت‚حپAپ@گ³ˆêˆتپi‚µ‚ه‚¤‚¢‚؟‚¢پj‚©‚çڈ]”ھˆت
پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚ح‚؟‚¢پj‚ـ‚إ‚ج‹كپEŒ»‘م“ْ–{گ•{‚ج‚P‚U
پ@پ@پ@ˆتٹK‚جپA
پ@پ@پ@‚V”ش–ع‚جگ³ژlˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚¢پjپA
پ@پ@پ@‚W”ش–ع‚جڈ]ˆêˆتپ@پi‚¶‚م‚µ‚¢پjپA
پ@پ@پ@‚ج‚Q‚آ‚جˆتٹK‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ@
پںپ@—¥—كٹ¯گ§‚جˆتٹKپBپ@
پ،پ@ڈ]ژlˆت‰؛پB
پœپ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج’©’ى‚إپAŒِ‹¨‚إ‚ ‚éپAژQ‹c‚ة
پ@پ@‚ب‚邽‚ك‚جچإ’لڈًŒڈ‚جˆتٹKپB
پ@
پ،پ@ڈ]ژlˆت‰؛پi‚¶‚م‚µ‚¢‚ج‚°پj ‚حپA’© ’ى‚جˆتٹK‚إپA
پ@ گ³ˆêˆت‚©‚çڈڈ‰ˆت‰؛پi‚µ‚ه‚¤‚»‚¢‚ج‚°پj‚ـ‚إ‚ج
پ@پ@’© ’ى‚ج‚R‚OˆتٹKپi‚¢‚©‚¢پj‚جڈمˆت‚P‚O”ش–ع‚جˆت
پ@پ@ٹK‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ،پ@Œِ‹¨پi‚‚¬‚ه‚¤پj‚حپAˆتٹKپEژOˆتˆبڈم‚جژز‚إŒِ
پ@پ@‹¨‚جٹ¯گE‚ةڈ–”C‚³‚ꂽژزپA‚ـ‚½‚حپAˆتٹKپEژl
ˆتˆبڈم‚جژز‚إŒِ‹¨‚جژQ‹c‚ةڈ–”C‚³‚ꂽژز ‚إ
‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@ڈ]ژlˆت‰؛‚حپAپ@Œِ‹¨پi‚‚¬‚ه‚¤پj‚جچإ‰؛ˆت‚ج
پ@پ@ژQ‹c‚ة‚ب‚邽‚ك‚جپA ’©’ى‚جچإ’لڈًŒڈ‚جˆتپ@
پ@پ@ٹKپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@Œِ‹¨پi‚‚¬‚ه‚¤پj‚حپAپ@’©’ى‚جˆتٹKپEژOˆت
پ@پ@ˆبڈم‚جژز‚إ“Vچc‚و‚èŒِ‹¨‚جٹ¯گE‚ةڈ–”C‚³‚ê
پ@پ@‚½ژزپA‚ـ‚½‚حپA’©’ى‚جˆتٹKپEژlˆتˆبڈم‚جژز‚إ
پ@پ@“Vچc‚و‚èŒِ‹¨‚جژQ‹c‚ةڈ–”C‚³‚ꂽژز‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ژµˆتپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚؟‚¢پjپB
پ@
پ،پ@ژµˆتپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ژµˆتپ@پi‚µ‚؟‚¢پjپB
پ،پ@ˆتٹK‚جƒOƒ‹پ[ƒvپB
پ،پ@ژg—pٹْٹشپiڈ–ˆتٹْٹشپjپ@پFپ@
پœپ@Œأ‘م“ْ–{‚ج”ٍ’¹”’–Pژ‘م‚©‚猻‘م“ْ–{‚ج
پ@پ@Œ»چف‚ـ‚إپBپ@
پœپ@پiگ¼—ï‹IŒ³Œمپj‚V‚O‚P”Nچ ‚©‚猻چف‚ـ‚إپB
پ،پ@’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پjپAگEˆُ—كپAڈ–ˆتڈً—لپAˆتٹK
پ@پ@—ك‚جˆتٹKپ@پi‚V‚O‚P”Nچ پ`Œ»چفپAڈ–ˆت‚ةژg—pپjپB
پœپ@گ³ژµˆتڈمپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚؟‚¢پj پ@‚ئپ@ڈ]ژµˆتڈمپ@
پ@پ@پi‚¶‚م‚µ‚؟‚¢پjپ@‚ج‚Q‚آ‚جˆتٹKپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj‚جˆتٹKپB
پœپ@گ³ژµˆت
پ@پ›پ@گ³ژµˆتڈمپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚؟‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپB
پ@پ›پ@گ³ژµˆت‰؛پ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚؟‚¢‚ج‚°پjپB
پœپ@ڈ]ژµˆت
پ@پ›پ@ڈ]ژµˆتڈمپ@پi‚¶‚م‚µ‚؟‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپB
پ@پ›پ@ڈ]ژµˆت‰؛پ@پi‚¶‚م‚µ‚؟‚¢‚ج‚°پjپB
پ@
پ پ@ˆتٹKپB
پ پ@ڈ–ˆتپB
پ@
پ@
پ،پ@ژµˆتپB
پ،پ@ژµˆتپ@پi‚µ‚؟‚¢پjپ@‚ئ‚حپAپ@گ³ژµˆتڈمپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µپ@
پ@پ@‚؟‚¢پj پ@‚ئپ@ڈ]ژµˆتڈمپi‚¶‚م‚µ‚؟‚¢پjپ@‚ج‚Q‚آ‚ج
پ@پ@ˆتٹKپ@‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@چX‚ةپA‘O‹ك‘م“ْ–{‚ج’©’ىپi—¥—كٹ¯گ§پj‚ج
پ@پ@ˆتٹK‚إ‚حپAژµˆت‚ة‚حپAپ@گ³پEڈ]پi‚µ‚ه‚¤پE‚¶‚مپj
پ@پ@ژµˆت‚ج‚Q‚آ‚جˆتٹK‚ةڈم‰؛‚ً•t‚¯‚ؤپAژں‚ج‚و
پ@پ@‚¤‚ب‚S‚آ‚جˆتٹK‚ھ‚ ‚ء‚½پB
پ@پœپ@گ³ژµˆت
پ@پ›پ@گ³ژµˆتڈمپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚؟‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپB
پ@پ›پ@گ³ژµˆت‰؛پ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚؟‚¢‚ج‚°پjپB
پ@پœپ@ڈ]ژµˆت
پ@پ›پ@ڈ]ژµˆتڈمپ@پi‚¶‚م‚µ‚؟‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپB
پ@پ›پ@ڈ]ژµˆت‰؛پ@پi‚¶‚م‚µ‚؟‚¢‚ج‚°پjپB
پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ،پ@ژµˆتپ@پi‚µ‚؟‚¢پjپ@‚حپAپ@Œأ‘م“ْ–{‚ج”ٍ’¹”’–P
پ@پ@ژ‘م‚©‚猻‘م“ْ–{‚جŒ»چف‚ـ‚إ‚جٹْٹش‚جڈ–
پ@پ@ˆت‚ةژg—p‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éˆتٹKپ@‚إپAپ@پiگ¼—ï‹IŒ³
پ@پ@Œمپj‚V‚O‚P”Nچ ‚©‚猻چف‚ـ‚إ‚جٹْٹش‚جڈ–ˆت‚ةپA
پ@پ@ژg—p‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپBپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@Œ»چف‚حپA‚P‚X‚S‚V”N‚ج‰üگ³ˆتٹK—ك‚ة‚و‚èپA
پ@پ@Œ÷گر‚ج‚ ‚ء‚½پAŒجگlپiژ€–Sژزپj‚ض‚ج‚فپAڈ–ˆت
پ@پ@‚ھچs‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ،پ@ژµˆتپB
پ،پ@—¥—كٹ¯گ§‚جˆتٹKپBپ@
پ@پ@پƒ‚V‚O‚P”Nچ پ`‚P‚W‚U‚X”Nچ پ„
پ@پœپ@’©’ى‚جˆتٹK‚جپuˆêˆتپ`”ھˆتپAڈ‰ˆتپv‚ج
پ@پ@پ@‚XƒOƒ‹پ[ƒv‚ج‚V”ش–ع‚جƒOƒ‹پ[ƒv‚جˆتٹKپB
پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپBپ@
پ@پœپ@’©’ى‚ج‚R‚OˆتٹKپi‚¢‚©‚¢پj‚جپA
پ@پ@پ@‚P‚X”ش–ع‚جگ³ژµˆتڈمپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚؟‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپA
پ@پ@پ@‚Q‚O”ش–ع‚جگ³ژµˆت‰؛پ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚؟‚¢‚ج‚°پjپA
پ@پ@پ@‚Q‚P”ش–ع‚جڈ]ژµˆتڈمپ@پi‚¶‚م‚µ‚؟‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپA
پ@پ@پ@‚Q‚Q”ش–ع‚جڈ]ژµˆت‰؛پ@پi‚¶‚م‚µ‚؟‚¢‚ج‚°پjپA
پ@پ@پ@‚ج‚S‚آ‚جˆتٹK‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@گEˆُ—كپi‚P‚W‚U‚X”Nگ§’èپj‚جˆتٹKپB
پ@پ@پƒ‚P‚W‚U‚X”Nچ پ`‚P‚W‚W‚V”Nچ پ„
پ@پœپ@‹ك‘م“ْ–{گ•{‚جˆتٹK‚جپuˆêˆتپ`‹مˆتپA
پ@پ@پ@ڈ‰ˆتپv‚ج‚P‚OƒOƒ‹پ[ƒv‚ج ‚V”ش–ع‚جƒOƒ‹پ[ƒv
پ@پ@پ@‚جˆتٹKپB
پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپBپ@
پ@پœپ@‹ك‘م“ْ–{گ•{‚ج‚Q‚OˆتٹK‚جپA
پ@پ@پ@‚P‚R”ش–ع‚جگ³ژµˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚؟‚¢پjپA
پ@پ@پ@‚P‚S”ش–ع‚جڈ]ژµˆتپ@پi‚¶‚م‚µ‚؟‚¢پjپA
پ@پ@پ@‚ج‚Q‚آ‚جˆتٹK‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@ڈ–ˆتڈً—لپi‚P‚W‚W‚V”Nگ§’èپjپAˆتٹK—ك
پ@پ@پi‚P‚X‚Q‚U”Nگ§’èپA‚P‚X‚S‚V”N‰üگ³پj‚ج
پ@پ@ˆتٹKپB
پ@پ@پƒ‚P‚W‚W‚V”Nچ پ`Œ»چفپ„
پ@پœپ@‹كپEŒ»‘م“ْ–{گ•{‚جˆتٹK‚جپuˆêˆتپ`”ھˆتپv
پ@پ@پ@‚ج‚WƒOƒ‹پ[ƒv‚ج ‚V”ش–ع‚جƒOƒ‹پ[ƒv‚جˆتٹKپB
پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپBپ@
پ@پœپ@‹كپEŒ»‘م“ْ–{گ•{‚ج‚P‚UˆتٹK‚ج پA
پ@پ@پ@‚P‚R”ش–ع‚جگ³ژµˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚؟‚¢پjپA
پ@پ@پ@‚P‚S”ش–ع‚جڈ]ژµˆتپ@پi‚¶‚م‚µ‚؟‚¢پjپA
پ@پ@پ@‚ج‚Q‚آ‚جˆتٹK‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@
پ،پ@ژµˆتپB
پ،پ@—¥—كٹ¯گ§‚جˆتٹKپBپ@
پ@پ@پƒ‚V‚O‚P”Nچ پ`‚P‚W‚U‚X”Nچ پ„
پ@پœپ@ژµˆت‚حپAپ@’©’ى‚جˆتٹK‚جپuˆêˆتپ`”ھˆتپAڈ‰
پ@پ@پ@ˆتپv‚ج‚XƒOƒ‹پ[ƒv‚ج‚¤‚؟‚جپAڈم‚©‚ç‚V”ش–ع‚ج
پ@پ@پ@ƒOƒ‹پ[ƒv‚جˆتٹK‚إ‚ ‚éپB
پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@پœپ@ژµˆت‚حپAپ@گ³ˆêˆتپi‚µ‚ه‚¤‚¢‚؟‚¢پj‚©‚çڈڈ‰
پ@پ@پ@ˆت‰؛پi‚µ‚ه‚¤‚»‚¢‚ج‚°پj‚ـ‚إ‚ج’©’ى‚ج‚R‚Oˆت
پ@پ@پ@ٹKپi‚¢‚©‚¢پj‚جپA
پ@پ@پ@‚P‚X”ش–ع‚جگ³ژµˆتڈمپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚؟‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپA
پ@پ@پ@‚Q‚O”ش–ع‚جگ³ژµˆت‰؛پ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚؟‚¢‚ج‚°پjپA
پ@پ@پ@‚Q‚P”ش–ع‚جڈ]ژµˆتڈمپ@پi‚¶‚م‚µ‚؟‚¢‚ج‚¶‚ه‚¤پjپA
پ@پ@پ@‚Q‚Q”ش–ع‚جڈ]ژµˆت‰؛پ@پi‚¶‚م‚µ‚؟‚¢‚ج‚°پjپA
پ@پ@پ@‚ج‚S‚آ‚جˆتٹK‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@گEˆُ—كپi‚P‚W‚U‚X”Nگ§’èپj‚جˆتٹKپB
پ@پ@پƒ‚P‚W‚U‚X”Nچ پ`‚P‚W‚W‚V”Nچ پ„
پ@پœپ@ژµˆت‚حپAپ@‹ك‘م“ْ–{گ•{‚جˆتٹK‚جپuˆêˆتپ`
پ@پ@پ@‹مˆتپAڈ‰ˆتپv‚ج‚P‚OƒOƒ‹پ[ƒv‚ج‚¤‚؟‚جڈم‚©‚ç
پ@پ@پ@‚V”ش–ع‚جƒOƒ‹پ[ƒv‚جˆتٹK‚إ‚ ‚éپB
پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپBپ@
پ@پœپ@ژµˆت‚حپAپ@گ³ˆêˆتپi‚µ‚ه‚¤‚¢‚؟‚¢پj‚©‚çڈڈ‰
پ@پ@پ@ˆتپi‚µ‚ه‚¤‚»‚¢پA‚µ‚ه‚¤‚µ‚ه‚¢پj‚ـ‚إ‚ج‹ك‘م“ْ
پ@پ@پ@–{گ•{‚ج‚Q‚OˆتٹK‚جپA
پ@پ@پ@‚P‚R”ش–ع‚جگ³ژµˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚؟‚¢پjپA
پ@پ@پ@‚P‚S”ش–ع‚جڈ]ژµˆتپ@پi‚¶‚م‚µ‚؟‚¢پjپA
پ@پ@پ@‚ج‚Q‚آ‚جˆتٹK‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@ڈ–ˆتڈً—لپi‚P‚W‚W‚V”Nگ§’èپjپAˆتٹK—ك
پ@پ@پi‚P‚X‚Q‚U”Nگ§’èپA‚P‚X‚S‚V”N‰üگ³پj‚جˆتٹKپB
پ@پ@پƒ‚P‚W‚W‚V”Nچ پ`Œ»چفپ„
پ@پœپ@ژµˆت‚حپAپ@‹كپEŒ»‘م“ْ–{گ•{‚جˆتٹK‚جپuˆê
پ@پ@پ@ˆتپ`”ھˆتپv‚ج‚WƒOƒ‹پ[ƒv‚ج ‚¤‚؟‚جڈم‚©‚ç‚V
پ@پ@پ@”ش–ع‚جƒOƒ‹پ[ƒv‚جˆتٹK‚إ‚ ‚éپB
پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپBپ@
پ@پœپ@ژµˆت‚حپAپ@گ³ˆêˆتپi‚µ‚ه‚¤‚¢‚؟‚¢پj‚©‚çڈ]”ھ
پ@پ@پ@ˆتپi‚¶‚م‚ح‚؟‚¢پj‚ـ‚إ‚ج‹كپEŒ»‘م“ْ–{گ•{‚ج
پ@پ@پ@‚P‚UˆتٹK‚جپA
پ@پ@پ@‚P‚R”ش–ع‚جگ³ژµˆتپ@پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚؟‚¢پjپA
پ@پ@پ@‚P‚S”ش–ع‚جڈ]ژµˆتپ@پi‚¶‚م‚µ‚؟‚¢پj
پ@پ@پ@‚ج‚Q‚آ‚جˆتٹK‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN“ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ژُ‰iپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚¦‚¢پjپB
پ@
پ،پ@ژُ‰iپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ژ،ڈ³پ@پi‚¶‚م‚¦‚¢پjپB
پ،پ@“ْ–{—ï”Nچ†پiکa—ï”Nچ†پAŒ³چ†پjپB
پ،پ@ˆةگ¨•½ژپگŒ پiˆہ“؟“Vچc—i—§پj•û‚ج—ï”Nچ†پBپ@
پœپ@پuژُ‰iپvŒ³”Nپ`‚S”Nپi‚P‚P‚W‚Qپ`‚P‚P‚W‚T”NپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@‚P‚P‚W‚Q”NپEژُ‰iŒ³”NپE‚TŒژ‚Q‚V“ْپ`
پ@پ@پ@پ@‚P‚P‚W‚T”NپEژُ‰i ‚S”NپE‚RŒژ‚Q‚S“ْپB
پ@پ@پ@پ@ˆةگ¨•½ژپ–إ–S‚ة‚و‚è—ï”Nچ†•زگ¬’†ژ~پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ،پ@Œ¹•½‹£چ‡“ٌڈd”Nچ†پi‚P‚P‚W‚P”Nپ`‚P‚P‚W‚T”Nپj
پ@پ@‚ج‚P‚آپB
پœپ@پuژ،ڈ³پv”Nچ†‚حپA‰ح“àŒ¹ژپپEŒ¹—ٹ’©گŒ پiŒم
پ@پ@’¹‰H“Vچc —i—§پj•û‚ج—ï”Nچ†‚جپuژ،ڈ³پv‚âپuŒ³
پ@پ@—ïپv‚ئ“¯ژ‘¶—§پB
پ،پ@Œأ‘م“ْ–{‚ج•½ˆہژ‘مŒمٹْ‚ج”Nچ†پB
پ،پ@پuژُ‰iپv”Nچ†‚و‚èŒم‚حپAˆةگ¨•½ژپگŒ پiˆہ“؟
پ@پ@“Vچc—i—§پj•û‚حپA—ï”Nچ†•زگ¬‚ً’†ژ~ پB
پ@
پ@
پ،پ@ژ،ڈ³پ@پi‚¶‚م‚¦‚¢پjپ@‚حپAپ@“ْ–{—ï”Nچ†پiکa—ï
پ@پ@”Nچ†پAŒ³چ†پj‚إپAپ@Œأ‘م“ْ–{‚ج•½ˆہژ‘مŒمٹْ
پ@پ@‚ج”Nچ†‚إ‚ ‚èپAپ@ˆةگ¨•½ژپگŒ پiˆہ“؟“Vچc—i
پ@پ@—§پj•û‚ج—ï”Nچ†‚ئ‚µ‚ؤژg—p‚³‚êپAپ@پuژُ‰iپvŒ³
پ@پ@”N‚©‚ç‚S”N‚ـ‚إپi‚P‚P‚W‚Q”N‚©‚ç‚P‚P‚W‚T”N‚ـ‚إپj
پ@پ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ،پ@ژ،ڈ³پ@پi‚¶‚م‚¦‚¢پjپ@‚حپAپ@“ْ–{—ï”Nچ†پiکa—ï
پ@پ@”Nچ†پAŒ³چ†پj‚إپAپ@Œأ‘م“ْ–{‚ج•½ˆہژ‘مŒمٹْ
پ@پ@‚ج”Nچ†پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@ژ،ڈ³پ@پi‚¶‚م‚¦‚¢پjپ@‚حپAپ@Œ¹•½‹£چ‡“ٌڈd”Nچ†
پ@پ@پi‚P‚P‚W‚P”Nپ`‚P‚P‚W‚T”Nپj‚ج‚P‚آ‚إپAپ@ˆةگ¨•½ژپ
پ@پ@گŒ پiˆہ“؟“Vچc—i—§پj•û‚ج—ï”Nچ†‚ئ‚µ‚ؤژg—p
پ@پ@‚³‚ꂽپB
پ@پœپ@پuژ،ڈ³پv”Nچ†‚حپA‰ح“àŒ¹ژپپEŒ¹—ٹ’©گŒ
پ@پ@پiŒم’¹‰H“Vچc—i—§پj•û‚ج—ï”Nچ†‚جپuژ،ڈ³پv‚â
پ@پ@پuŒ³—ïپv‚ئ“¯ژ‘¶—§‚·‚éپB
پ@پœپ@پi’چˆسپjپ@پuژ،ڈ³پv”Nچ†‚ئ“¯ژٹْ‚ةپA‰ح“àŒ¹
پ@پ@ژپپEŒ¹—ٹ’©گŒ پiŒم’¹‰H“Vچc —i—§پj•û‚ج—ï
پ@پ@”Nچ†‚جژ،ڈ³پi‚¶‚µ‚ه‚¤پjŒ³”Nپ`‚W”Nپi‚P‚P‚V‚Vپ`
پ@پ@‚P‚P‚W‚S”Nپj پ@‚ئپ@Œ³—ïپi‚°‚ٌ‚è‚ل‚پjŒ³”Nپ`‚Q
پ@پ@”Nپi‚P‚P‚W‚Sپ`‚P‚P‚W‚T”Nپjپ@‚à‘¶—§‚·‚éپB
پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ،پ@ˆةگ¨•½ژپگŒ پiˆہ“؟“Vچc—i—§پj•û‚ج—ï”Nچ†
پ@پ@‚جپAپ@ژ،ڈ³پ@پi‚¶‚م‚¦‚¢پjپ@‚حپAپ@پuژُ‰iپvŒ³”N‚©
پ@پ@‚ç‚S”N‚ـ‚إپ@پi‚P‚P‚W‚Q”N‚©‚ç‚P‚P‚W‚T”N‚ـ‚إپj‚إ
پ@پ@‚ ‚èپAپ@‚P‚P‚W‚Q”NپEژُ‰iŒ³”NپE‚TŒژ‚Q‚V“ْ‚©‚ç
پ@پ@‚P‚P‚W‚T”NپEژُ‰i ‚S”NپE‚RŒژ‚ـ‚إپ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ،پ@پuژُ‰iپv”Nچ†‚و‚èŒم‚حپAˆةگ¨•½ژپگŒ پiˆہ“؟
پ@پ@“Vچc—i—§پj•û‚حپA—ï”Nچ†•زگ¬‚ً’†ژ~ پB
پ@پœپ@پuژُ‰iپv”Nچ†پiژُ‰iŒ³”Nپ`‚S”NپA‚P‚P‚W‚Qپ`
پ@پ@‚P‚P‚W‚T”Nپj‚و‚èŒم‚حپAˆةگ¨•½ژپگŒ پiˆہ“؟“V
پ@پ@چcŒn“پj•û‚حپAپ@—ï”Nچ†•زگ¬‚ً’†ژ~ ‚·‚éپB
پ@پ@‚P‚P‚W‚T”N‚ج’dƒm‰Y‚جگي‚¢‚إپAˆةگ¨•½ژپ‚ھ–إ
پ@پ@–S‚µپAˆہ“؟“Vچc‚ھ•ِŒن‚µ‚½‚½‚كپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ،پ@ˆةگ¨•½ژپگŒ پiˆہ“؟“Vچc—i—§پj•û‚ج—ï”Nچ†پB
پ@پ@پ@پ@ˆہŒ³پi‚ ‚ٌ‚°‚ٌپjŒ³”Nپ`‚R”Nپ@پثپ@ژ،ڈ³
پ@پ@پi‚¶‚µ‚ه‚¤پjŒ³”Nپ`‚T”Nپ@پi‚P‚P‚V‚Vپ`‚P‚P‚W‚P”Nپj
پ@پ@پثپ@—{کaپi‚و‚¤‚يپjŒ³”Nپ`‚Q”Nپ@پi‚P‚P‚W‚Pپ`
پ@پ@‚P‚P‚W‚Q”Nپjپ@پثپ@ژُ‰iپi‚¶‚م‚¦‚¢پj Œ³”Nپ`‚S”N
پ@پ@پi‚P‚P‚W‚Qپ`‚P‚P‚W‚T”Nپjپثپ@ —ï”Nچ†•زگ¬’†ژ~پB
پ@
پ،پ@Œ¹•½‹£چ‡“ٌڈd”Nچ†پB
پ@پ@پ@‚P‚P‚W‚P”N‚©‚ç‚P‚P‚W‚T”N‚ـ‚إپAپ@پuژ،ڈ³پvپi‚¶‚µ
پ@پ@‚ه‚¤پjپAپu—{کaپvپi‚و‚¤‚يپjپAپuژُ‰iپvپi‚¶‚م‚¦‚¢پj پA
پ@پ@پuŒ³—ïپvپi‚°‚ٌ‚è‚ل‚پj‚ج”Nچ†‚إپAپ@“ْ–{—ï”Nچ†
پ@پ@پiکa—ï”Nچ†پAŒ³چ†پj‚ج“ٌڈd‘¶—§‚ھ‹N‚±‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@پ@
پ،پ@“Œ“ْ–{‚ج‰ح“àŒ¹ژپپEŒ¹—ٹ’©گŒ پ@‚ئپ@گ¼“ْ
پ@پ@–{‚جˆةگ¨•½ژپگŒ پ@‚ج‚Q‚آ‚جگŒ ‚ھپAپ@‚P‚P
پ@پ@‚W‚O”N‚©‚ç‚P‚P‚W‚T”N‚ـ‚إ‚جٹشپAپ@•ہ—§‚µپA‘خ
پ@پ@—§‚µ‚½پBپ@‚»‚جٹْٹش‚جپA‚P‚P‚W‚P”N‚©‚ç‚P‚P‚W‚T
پ@پ@”N‚ـ‚إپAپ@“¯ژٹْ‚ةپA‚Q‚آ‚ھ”Nچ†‚ھ‘¶—§‚µ‚½پB
پ@
پ@
پںپ@Œ¹•½‹£چ‡“ٌڈd”Nچ†ˆê——•\پB
پ،پ@‚P‚P‚W‚P”N‚©‚ç‚P‚P‚W‚T”N‚ـ‚إپA“ْ–{—ï”Nچ†
پ@پ@پiکa—ï”Nچ†پAŒ³چ†پj‚حپA“ٌڈd‘¶—§‚·‚éپB
پ@
پ،پ@ˆةگ¨•½ژپگŒ پ@پiˆہ“؟“Vچc—i—§پjپ@•û‚ج—ï”N
پ@پ@چ†پB
پ@پ¥پ@ژ،ڈ³پi‚¶‚µ‚ه‚¤پjپثپ@—{کaپi‚و‚¤‚يپjپثپ@ژُ‰i
پ@پ@پi‚¶‚م‚¦‚¢پjپثپ@—ï”Nچ†•زگ¬’†ژ~پB
پ@پœپ@پuژ،ڈ³پvپ@پi‚¶‚µ‚ه‚¤پjپ@
پ@پ@پ@پiژ،ڈ³Œ³”Nپ`ژ،ڈ³‚T”NپA‚P‚P‚V‚Vپ`‚P‚P‚W‚P”NپjپB
پ@پœپ@پu—{کaپvپ@پi‚و‚¤‚يپjپ@
پ@پ@پ@پi—{کaŒ³”Nپ`—{کa‚Q”NپA‚P‚P‚W‚Pپ`‚P‚P‚W‚Q”NپjپB
پ@پœپ@پuژُ‰iپvپ@پi‚¶‚م‚¦‚¢پjپ@
پ@پ@پ@پiژُ‰iŒ³”Nپ`ژُ‰i‚S”NپA‚P‚P‚W‚Qپ`‚P‚P‚W‚T”NپjپB
پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ،پ@‰ح“àŒ¹ژپپEŒ¹—ٹ’©گŒ پ@پiŒم’¹‰H“Vچc—i—§پj
پ@پ@•û‚ج—ï”Nچ†پBپ@
پ@پ¥پ@ژ،ڈ³پi‚¶‚µ‚ه‚¤پjپثپ@Œ³—ïپi‚°‚ٌ‚è‚ل‚پjپB
پ@پœپ@پuژ،ڈ³پvپ@پi‚¶‚µ‚ه‚¤پjپ@
پ@پ@پ@پiژ،ڈ³Œ³”Nپ`ژ،ڈ³‚W”NپA‚P‚P‚V‚Vپ`‚P‚P‚W‚S”Nپj پB
پ@پœپ@پuŒ³—ïپvپ@پi‚°‚ٌ‚è‚ل‚پjپ@
پ@پ@پ@پiŒ³—”Nپ`Œ³—ï‚Q”NپA‚P‚P‚W‚Sپ`‚P‚P‚W‚T”NپjپB
پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ژ،ڈ³پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚µ‚ه‚¤پjپB
پ@
پ،پ@ژ،ڈ³پB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ژ،ڈ³پ@پi‚¶‚µ‚ه‚¤پAپ@‚¶‚¶‚ه‚¤پjپB
پ،پ@“ْ–{—ï”Nچ†پiکa—ï”Nچ†پAŒ³چ†پjپB
پ،پ@Œ¹•½‹£چ‡“ٌڈd”Nچ†پi‚P‚P‚W‚P”Nپ`‚P‚P‚W‚T”Nپj
پ@پ@‚ج‚P‚آپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ،پ@ˆةگ¨•½ژپگŒ پiˆہ“؟“Vچc—i—§پj•û‚ج—ï”Nچ†پBپ@
پ@پœپ@پuژ،ڈ³پvŒ³”Nپ`ژ،ڈ³‚T”Nپi‚P‚P‚V‚Vپ`‚P‚P‚W‚P”NپjپB
پ@پ@پ@پ@‚P‚P‚V‚V”NپEژ،ڈ³Œ³”NپE‚WŒژپ@‚S“ْپ`
پ@پ@پ@پ@‚P‚P‚W‚P”NپEژ،ڈ³ ‚T”NپE‚VŒژ‚P‚S“ْپB
پ،پ@‰ح“àŒ¹ژپپEŒ¹—ٹ’©گŒ پ@پiŒم’¹‰H“Vچc—i—§پj
پ@پ@•û‚ج—ï”Nچ†پBپ@
پ@پœپ@پuژ،ڈ³پvŒ³”Nپ`ژ،ڈ³‚W”Nپi‚P‚P‚V‚Vپ`‚P‚P‚W‚S”NپjپB
پ@پ@پ@پ@‚P‚P‚V‚V”NپEژ،ڈ³Œ³”NپE‚WŒژپ@‚S“ْپ`
پ@پ@پ@پ@‚P‚P‚W‚S”NپEژ،ڈ³ ‚W”NپE‚SŒژ‚P‚U“ْپB
پ،پ@Œأ‘م“ْ–{‚ج•½ˆہژ‘مŒمٹْ‚ج”Nچ†پB
پ@
پ@
پ،پ@ژ،ڈ³پ@پi‚¶‚µ‚ه‚¤پA‚¶‚¶‚ه‚¤پjپ@‚حپAپ@“ْ–{—ï”Nچ†
پ@پ@پiکa—ï”Nچ†پAŒ³چ†پj‚إپAپ@Œأ‘م“ْ–{‚ج•½ˆہژ‘م
پ@پ@Œمٹْ‚ج”Nچ†‚إ‚ ‚èپAپ@ˆةگ¨•½ژپگŒ پiˆہ“؟“V
پ@پ@چc—i—§پj•û‚ج—ï”Nچ†‚إ‚حپAپ@پuژ،ڈ³پvŒ³”N‚©‚ç
پ@پ@ژ،ڈ³‚T”N‚ـ‚إپ@پiگ¼—ï‚P‚P‚V‚V”N‚©‚ç‚P‚P‚W‚P”N‚ـ
پ@پ@‚إپjپ@‚إ‚ ‚èپAپ@‰ح“àŒ¹ژپپEŒ¹—ٹ’©گŒ پ@پiŒم’¹
پ@پ@‰H“Vچc—i—§پjپ@•û‚ج—ï”Nچ†‚إ‚حپAپ@پuژ،ڈ³پvŒ³
پ@پ@”N‚©‚çژ،ڈ³‚W”N‚ـ‚إپ@پi‚P‚P‚V‚V”N‚©‚ç‚P‚P‚W‚S”N
پ@پ@‚ـ‚إپjپ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ،پ@ژ،ڈ³پ@پi‚¶‚µ‚ه‚¤پA‚¶‚¶‚ه‚¤پjپ@‚حپAپ@“ْ–{—ï”Nچ†
پ@پ@پiکa—ï”Nچ†پAŒ³چ†پj‚إپAپ@Œأ‘م“ْ–{‚ج•½ˆہژ‘م
پ@پ@Œمٹْ‚ج”Nچ†پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@پuژ،ڈ³پv‚حپAپ@Œ¹•½‹£چ‡“ٌڈd”Nچ†پi‚P‚P‚W‚P”Nپ`
پ@پ@‚P‚P‚W‚T”Nپj‚ج‚P‚آ‚إپAپ@ˆةگ¨•½ژپگŒ پiˆہ“؟“Vچc
پ@پ@—i—§پj•û‚ج—ï”Nچ†‚ئ‚µ‚ؤ‚àژg—p‚³‚êپAپ@‰ح“àŒ¹ژپ
پ@پ@پEŒ¹—ٹ’©گŒ پ@پiŒم’¹‰H“Vچc—i—§پjپ@•û‚ج—ï”Nچ†
پ@پ@‚ئ‚µ‚ؤ‚àژg—p‚³‚ꂽپB
پ@پœپ@Œ¹•½‹£چ‡“ٌڈd”Nچ†پB
پ@پ@پ@‚P‚P‚W‚P”N‚©‚ç‚P‚P‚W‚T”N‚ـ‚إپAپ@پuژ،ڈ³پvپi‚¶‚µ
پ@پ@‚ه‚¤پjپAپu—{کaپvپi‚و‚¤‚يپjپAپuژُ‰iپvپi‚¶‚م‚¦‚¢پj پA
پ@پ@پuŒ³—ïپvپi‚°‚ٌ‚è‚ل‚پj‚ج”Nچ†‚إپAپ@“ْ–{—ï”Nچ†
پ@پ@پiکa—ï”Nچ†پAŒ³چ†پj‚ج“ٌڈd‘¶—§‚ھ‹N‚±‚éپB
پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ،پ@ˆةگ¨•½ژپگŒ پiˆہ“؟“Vچc—i—§پj•û‚ج—ï”Nچ†
پ@پ@‚جپAپuژ،ڈ³پv‚حپAپ@پuژ،ڈ³پvŒ³”N‚©‚çژ،ڈ³‚T”N‚ـ
پ@پ@‚إپ@پiگ¼—ï‚P‚P‚V‚V”N‚©‚ç‚P‚P‚W‚P”N‚ـ‚إپjپ@‚إ‚
پ@پ@‚èپAپ@‚P‚P‚V‚V ”NپEژ،ڈ³Œ³”NپE‚WŒژ‚S“ْ‚©‚çپ@‚P‚P
پ@پ@‚W‚P”NپEژ،ڈ³‚T”NپE‚VŒژ‚P‚S“ْ‚ـ‚إپ@‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@
پ،پ@ˆةگ¨•½ژپگŒ پiˆہ“؟“Vچc—i—§پj•û‚ج—ï”Nچ†پBپ@
پ@پ@پ@پ@ˆہŒ³پi‚ ‚ٌ‚°‚ٌپjŒ³”Nپ`‚R”Nپ@پثپ@ژ،ڈ³
پ@پ@پi‚¶‚µ‚ه‚¤پjŒ³”Nپ`‚T”Nپ@پi‚P‚P‚V‚Vپ`‚P‚P‚W‚P”Nپj
پ@پ@پثپ@—{کaپi‚و‚¤‚يپjŒ³”Nپ`‚Q”Nپ@پi‚P‚P‚W‚Pپ`
پ@پ@‚P‚P‚W‚Q”Nپjپ@پثپ@ژُ‰iپi‚¶‚م‚¦‚¢پj Œ³”Nپ`‚S”N
پ@پ@پi‚P‚P‚W‚Qپ`‚P‚P‚W‚T”Nپjپثپ@ —ï”Nچ†•زگ¬’†ژ~پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ،پ@‰ح“àŒ¹ژپپEŒ¹—ٹ’©گŒ پ@پiŒم’¹‰H“Vچc—i—§پj
پ@پ@•û‚ج—ï”Nچ†‚جپAپuژ،ڈ³پv‚حپAپ@پuژ،ڈ³پvŒ³”N‚©‚ç
پ@پ@ژ،ڈ³‚W”N‚ـ‚إپ@پi‚P‚P‚V‚V”N‚©‚ç‚P‚P‚W‚S”N‚ـ‚إپjپ@
پ@پ@‚إ‚ ‚èپAپ@‚P‚P‚V‚V”NپEژ،ڈ³Œ³”NپE‚WŒژ‚S“ْ ‚©‚ç
پ@پ@‚P‚P‚W‚S”NپEژ،ڈ³‚W”NپE‚SŒژ‚P‚U“ْ‚ـ‚إپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@‰ح“àŒ¹ژپپEŒ¹—ٹ’©گŒ پ@پiŒم’¹‰H“Vچc—i—§پj
پ@پ@•û‚ج—ï”Nچ†پBپ@
پ@پ@پ@پ@ˆہŒ³پi‚ ‚ٌ‚°‚ٌپjŒ³”Nپ`‚R”Nپ@پثپ@ژ،ڈ³پ@
پ@پ@پi‚¶‚µ‚ه‚¤پjŒ³”Nپ`‚W”Nپ@پi‚P‚P‚V‚Vپ` ‚P‚P‚W‚S
پ@پ@”Nپjپ@پثپ@Œ³—ïپi‚°‚ٌ‚è‚ل‚پjŒ³”Nپ`‚Q”N
پ@پ@پi‚P‚P‚W‚Sپ`‚P‚P‚W‚T”Nپjپ@پثپ@•¶ژ،پi‚ش‚ٌ‚¶پjپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ،پ@‚P‚P‚W‚O”N‚ةپA“Œ“ْ–{‚جٹض“Œ‚ةپA‰ح“àŒ¹ژپپEŒ¹
پ@پ@—ٹ’©گŒ ‚ھگ¬—§‚µپAپ@‚P‚P‚W‚O”N‚©‚ç‚P‚P‚W‚T”N‚ـ
پ@پ@‚إ‚جٹشپAپ@“ْ–{‚إ‚حپAپ@گ¼“ْ–{‚جˆةگ¨•½ژپگŒ
پ@پ@‚ئپ@“Œ“ْ–{‚ج‰ح“àŒ¹ژپپEŒ¹—ٹ’©گŒ پ@‚ج‚Q‚آ‚ج
پ@پ@گŒ ‚ھ•ہ—§‚µ‚½پBپ@‚»‚ج‚½‚كپAپ@‚»‚جٹْٹش‚جپA
پ@پ@‚P‚P‚W‚P”N‚©‚ç‚P‚P‚W‚T”N‚ـ‚إپAپ@‚Q‚آ‚ھ”Nچ†‚ھ‘¶
پ@پ@—§‚µ‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ@
پںپ@Œ¹•½‹£چ‡“ٌڈd”Nچ†ˆê——•\پB
پ،پ@‚P‚P‚W‚P”N‚©‚ç‚P‚P‚W‚T”N‚ـ‚إپA“ْ–{—ï”Nچ†
پ@پ@پiکa—ï”Nچ†پAŒ³چ†پj‚حپA“ٌڈd‘¶—§‚·‚éپB
پ،پ@ˆةگ¨•½ژپگŒ پ@پiˆہ“؟“Vچc—i—§پjپ@•û‚ج—ï”N
پ@پ@چ†پB
پ@پ¥پ@ژ،ڈ³پi‚¶‚µ‚ه‚¤پjپثپ@—{کaپi‚و‚¤‚يپjپثپ@ژُ‰i
پ@پ@پi‚¶‚م‚¦‚¢پjپثپ@—ï”Nچ†•زگ¬’†ژ~پB
پ@پœپ@پuژ،ڈ³پvپ@پi‚¶‚µ‚ه‚¤پjپ@
پ@پ@پ@پiژ،ڈ³Œ³”Nپ`ژ،ڈ³‚T”NپA‚P‚P‚V‚Vپ`‚P‚P‚W‚P”NپjپB
پ@پœپ@پu—{کaپvپ@پi‚و‚¤‚يپjپ@
پ@پ@پ@پi—{کaŒ³”Nپ`—{کa‚Q”NپA‚P‚P‚W‚Pپ`‚P‚P‚W‚Q”NپjپB
پ@پœپ@پuژُ‰iپvپ@پi‚¶‚م‚¦‚¢پjپ@
پ@پ@پ@پiژُ‰iŒ³”Nپ`ژُ‰i‚S”NپA‚P‚P‚W‚Qپ`‚P‚P‚W‚T”NپjپB
پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ،پ@‰ح“àŒ¹ژپپEŒ¹—ٹ’©گŒ پ@پiŒم’¹‰H“Vچc—i—§پj
پ@پ@•û‚ج—ï”Nچ†پBپ@
پ@پ¥پ@ژ،ڈ³پi‚¶‚µ‚ه‚¤پjپثپ@Œ³—ïپi‚°‚ٌ‚è‚ل‚پjپB
پ@پœپ@پuژ،ڈ³پvپ@پi‚¶‚µ‚ه‚¤پjپ@
پ@پ@پ@پiژ،ڈ³Œ³”Nپ`ژ،ڈ³‚W”NپA‚P‚P‚V‚Vپ`‚P‚P‚W‚S”Nپj پB
پ@پœپ@پuŒ³—ïپvپ@پi‚°‚ٌ‚è‚ل‚پjپ@
پ@پ@پ@پiŒ³—”Nپ`Œ³—ï‚Q”NپA‚P‚P‚W‚Sپ`‚P‚P‚W‚T”NپjپB
پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژj ژ«“TپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@گM’·Œِ‹Lپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پi‚µ‚ٌ‚؟‚ه‚¤‚±‚¤‚«پjپB
پ@
پ،پ@گM’·Œِ‹LپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@گM’·Œِ‹Lپ@پi‚µ‚ٌ‚؟‚ه‚¤‚±‚¤‚«پjپB
پ،پ@’کژزپ@پFپ@‘¾“c ‹چˆêپBپ@
پ،پ@چ]Œثژ‘مڈ‰ٹْ‚ةگ¬—§پBپ@
پ،پ@ˆہ“y“چژRژ‘م‚ً’m‚éˆêژں“Iژj—؟پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“Tپ@‚W‚Q‚R‚P‚VپB
پ@
پ@
پ،پ@‘¾“c‹چˆêپi‚¨‚¨‚½‚¬‚م‚¤‚¢‚؟پj‚جگM’·Œِ‹L‚ة‚حپA
پ@پ@پuˆہ“y“ْ‹LپvپiŒأٹْپEگM’·Œِ‹LپAŒc’·چ ‚جژتپjپAپ@
پ@پ@پuگM’·‹Lپvپi’†ٹْپEگM’·Œِ‹LپAŒc’·‚P‚W”Nپi‚P‚U‚P‚R
پ@پ@”Nپjچ پjپAپ@پuگM’·Œِ‹LپvپiگVٹْپEگM’·Œِ‹LپAŒ³ک\
پ@پ@‚P‚Q”Nپi‚P‚U‚X‚X”Nپjژتپjپ@‚ھ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پuˆہ“y“ْ‹LپvپiŒأٹْپEگM’·Œِ‹LپAŒc’·چ ‚ج
پ@پ@ژتپj‚ھˆêژںژj—؟‚ئ‚µ‚ؤپAگM—ٹ‚ھچ‚‚¢پB
پ@
پ،پ@گM’·Œِ‹L‚حپAپ@ˆہ“y“چژRژ‘م‚ً’m‚éˆêژں“Iژj—؟پ@
پ@پ@‚إ‚ ‚éپB
پ،پ@گM’·Œِ‹Lپ@پi‚µ‚ٌ‚؟‚ه‚¤‚±‚¤‚«پj‚حپAپ@’کژز‚ح‘¾“c
پ@پ@‹چˆê‚إپAپ@چ]Œثژ‘مڈ‰ٹْ‚ةگ¬—§‚µ‚½پBپ@
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ،پ@پuگM’·Œِ‹Lپvپ@پi‚µ‚ٌ‚؟‚ه‚¤‚±‚¤‚«پj‚حپAپ@گD“cگM’·
پ@پ@‚ج‰ئگb‚ج‘¾“c‹چˆê‚ھپAپ@گD“cگM’·‚جˆê‘م‹L‚ً‹L
پ@پ@‚µ‚½ژj—؟پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@‘¾“c‹چˆê‚حپAپ@ƒپƒ‚–‚‚إپA“ْ‹L‚إپAپ@گD“cگM’·
پ@پ@‚ج‹Lک^‚ًژc‚·پB
پ@پ@پ@پ@پ@‘¾“c‹چˆê‚حپA”ِ’£ژ‘م‚و‚èپA“ْ‹L‚ًڈ‘‚«پAپ@
پ@پ@گD“cگM’·‚ج“ْڈيگ¶ٹˆ‚ً‹Lک^‚µ‚ؤ‚¢‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ،پ@گM’·Œِ‹Lپ@پi‚µ‚ٌ‚؟‚ه‚¤‚±‚¤‚«پj‚حپAپ@‚P‚TٹھپA–ٌ
پ@پ@‚P‚T”Nٹش‚إپAپ@گM’·‚جڈم—Œ‚جژٹْ‚©‚çپAپ@–{”\ژ›
‚ج•د‚جژٹْ‚ـ‚إ‚ً‹Lک^‚µ‚ؤ‚¢‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@گM’·ژ€Œم‚àپA‘¾“c‹چˆêپ@‚حپAژوچقٹˆ“®‚ًچs
پ@پ@‚¢پAپ@گM’·‚جŒ¾چs‚ًڈع‚µ‚’²‚ׂ ‚°‚ؤپAپ@گM’·Œِ
پ@پ@‹L‚ًڈ‘‚«ڈم‚°‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@‘¾“c‹چˆê‚جژوچق‹Lک^‚ج—ل‚إ‚حپAپ@–{”\ژ›
پ@پ@‚ج•د‚إگM’·‚ھژ©ٹQ‘O‚ةڈq‚ׂ½پuگ¥”ٌ‚ة‹y‚خ‚·پv
پ@پ@پi‚؛‚ذ‚ة‚¨‚و‚خ‚¸پAپ@“V‚ھ‰؛‚µ‚½‰^–½‚ب‚炵‚©‚½
پ@پ@‚ھ‚ب‚¢پjپ@‚حپAپ@گM’·‚ھ–{”\ژ›‚إژ€‚ت’¼‘O‚ـ‚إگg
پ@پ@‹ك‚ة‚¢‚½ژکڈ—پi‚¶‚¶‚هپj‚©‚çژوچق‚µ‚ؤ•·‚«ڈo‚µ‚½‚à
پ@پ@‚ج‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ@
پôپôپ@گM’·Œِ‹L ‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢
پ@پ@ٹضکAƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پAƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپBپ@
پ@
پڑپ@گM’·Œِ‹Lپ@‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢پA
پ@پ@ٹضکAƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پBپ@
پ@
پ،پ@—ًژj”éکbƒqƒXƒgƒٹƒAپ@پwپ@‰p—Y‚ً
پ@پ@ ‹Lک^‚µ‚½’jپ@‘¾“c‹چˆêپ@پxپBپ@
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚P‚R”N‚P‚QŒژ‚S“ْپE
–{•ْ‘—پE—ًژj ƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[”ش‘gپjپBپ@پ@
پœپ@گD“cگM’·‚âˆہ“y“چژRژ‘م‚جڈo—ˆژ–‚ً‹Lک^
پ@پ@‚µپAŒمگ¢‚ةژc‚µ‚½پA‘¾“c‹چˆê‚جگ¶ٹU‚ًڈq‚ׂéپB
پ@
پ،پ@‰ً–¾پI•ذ‰ھˆ¤”Vڈ•‚ج—ًژj‘{چ¸
پ@پ@پwپ@پq“؟گى‰ئ–¢‰ًŒˆژ–Œڈƒtƒ@ƒCƒ‹پr
پ@پ@پ@‰ئچN‚ج’„’jگMچN‚جگط• پ@
پ@پ@پ@گ³ژ؛’zژR“aپ@ژEٹQژ–Œڈ
پ@پ@پ@‚جگ^‘ٹ‚ً’ا‚¦پIپ@پxپBپ@
پ@ پ@ پi“ْƒeƒŒپEƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚P‚V”N‚P‚PŒژ‚Q‚R“ْپE
پ@پ@پ@پ@–{•ْ‘—پEƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[”ش‘gپjپB
پ،پ@‘¾“c‹چˆêپi‚¨‚¨‚½‚¬‚م‚¤‚¢‚؟پj‚جگM’·Œِ
پ@پ@‹L‚ة‚حپAپ@پuˆہ“y“ْ‹LپvپiŒأٹْپEگM’·Œِ‹LپA
پ@پ@Œc’·چ ‚جژتپjپAپ@پuگM’·‹Lپvپi’†ٹْپEگM’·Œِ
پ@پ@‹LپAŒc’·‚P‚W”Nپi‚P‚U‚P‚R”Nپjچ پjپAپ@پuگM’·
پ@پ@Œِ‹LپvپiگVٹْپEگM’·Œِ‹LپAŒ³ک\‚P‚Q”Nپi‚P‚U
پ@پ@‚X‚X”Nپjژتپj‚ھ‚ ‚éپB
پ،پ@ڈ¼•½گMچNژ©ٹQپE’zژR“aژEٹQژ–Œڈپi= •گ“c
پ@پ@ژپ“à’ت‹^کfژ–Œڈپj‚ًڈعچׂةڈq‚ׂéپB
پ،پ@“؟گى‰ئچN‚ج—c”NٹْپAگآ”NٹْپA‘O”¼گ¶‚â
پ@پ@’zژR“aپEڈ¼•½گMچN‚ًپAڈع‚µ‚ڈq‚ׂéپB
پ،پ@“؟گى‰ئچN‚ج‰ü–¼پi’|گç‘مپثڈ¼•½Œ³گMپث پ@
پ@پ@ڈ¼•½Œ³چNپث ڈ¼•½‰ئچNپث “؟گى‰ئچNپj‚ًڈq
پ@پ@‚ׂéپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@
پ،پ@گpگ\‚ج—گپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ٌ‚µ‚ٌ‚ج‚ç‚ٌپjپB
پ@
پ،پ@گpگ\‚ج—گپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@گpگ\‚ج—گ پi‚¶‚ٌ‚µ‚ٌ‚ج‚ç‚ٌپjپB
پœپ@‰p–¼پ@پFپ@‚”‚ˆ‚…پ@‚i‚‰‚ژ‚“‚ˆ‚‰‚ژپ@‚c‚‰‚“‚”‚•‚’‚‚‚پ‚ژ‚ƒ‚…پB
پ،پ@‚U‚V‚Q”N‚جچcˆتŒpڈ³‚ً‚ك‚®‚éگي‚¢پB
پ@
پ@
پ،پ@گpگ\‚ج—گپ@پi‚¶‚ٌ‚µ‚ٌ‚ج‚ç‚ٌپjپ@‚حپA‚U‚V‚Q”N
پ@پ@‚ة‹N‚±‚ء‚½چcˆتŒpڈ³‚ً‚ك‚®‚éگي‚¢پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@گpگ\‚ج—گ‚ج‰p–¼‚حپAپ@‚”‚ˆ‚…پ@‚i‚‰‚ژ‚“‚ˆ‚‰‚ژپ@
پ@پ@‚c‚‰‚“‚”‚•‚’‚‚‚پ‚ژ‚ƒ‚…پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@‚U‚V‚P”N‚ةپA“V’qپi‚ؤ‚ٌ‚¶پj“Vچcپ@پiچفˆت‚U‚U‚W
پ@پ@پ`‚U‚V‚P”NپA’†‘هŒZچcژqپj‚ھپ@•ِŒنپi‚ظ‚¤‚¬‚هپA
پ@پ@ژ€‹ژپj‚µپAپ@‚U‚V‚Q”N‚ةپAپ@“V’q“Vچcپi’†‘هŒZچc
پ@پ@ژqپj‚ج’ي‚ج‘هٹCگlچcژqپi‚¨‚¨‚ ‚ـ‚ج‚ف‚±پAŒم
پ@پ@‚ج“V•گ“VچcپA‚U‚R‚PپHپ`‚U‚W‚U”Nپjپ@‚ئپ@“V’q“V
پ@پ@چcپi’†‘هŒZچcژqپj‚جژq‚ج‘ه—Fچcژqپi‚¨‚¨‚ئ‚à
پ@پ@‚ج‚ف‚±پA‚U‚S‚Wپ`‚U‚V‚Q”Nپj‚جٹش‚إپAپ@گpگ\‚ج—گ
پ@پ@پi‚¶‚ٌ‚µ‚ٌ‚ج‚ç‚ٌپj‚ھ‹N‚±‚èپAپ@‘هٹCگlچcژq‚ھ
پ@پ@ڈں—ک‚ً“¾‚éپBپ@‚U‚V‚Q”N‚جگpگ\‚ج—گŒمپAپ@—‚”N
پ@پ@‚U‚V‚R”N‚ةپA‘هٹCگlچcژq‚حپAپ@”ٍ’¹ڈٍŒنŒ´‹{
پ@پ@پi‚ ‚·‚©‚«‚و‚ف‚ح‚ç‚ج‚ف‚âپj‚إپA“V•گ“Vچcپi‚ؤ
پ@پ@‚ٌ‚ق‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پj‚ئ‚µ‚ؤ‘¦ˆت‚µ‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@گpگ\‚ج—گ‚إ‘ه—Fچcژq‚ج‹كچ]’©’ىپi‚¨‚¤‚ف
پ@پ@‚؟‚ه‚¤‚ؤ‚¢پj‚ة–،•û‚µ‚½—L—ح’†‰›چ‹‘°‚ھ–v—ژ
پ@پ@‚µپAپ@‹—ح‚بŒ —ح‚ًژè‚ة‚µ‚½پA“V•گ“Vچc‚حپA’©
پ@پ@’ى‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚èپAپ@گژ،‰üٹv‚ً–{ٹi“I‚ةژہژ{
پ@پ@‚µپAپ@“V•گ“Vچcژ‘مپiچفˆت‚U‚V‚Rپ`‚U‚W‚U”Nپj‚©پ@
پ@پ@‚çپAپ@’†‰›ڈWŒ ‰»پi’†‰›ڈWŒ “Iچ‘‰ئ‘جگ§‚جŒ`
پ@پ@گ¬پjپA—¥—كگ§“x‚جٹî‘b‚ھگi‚ٌ‚¾پ@پi–{ٹi“I‚ةŒ`
پ@پ@گ¬‚³‚êژn‚ك‚éپjپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ڈ—رژ›Œ–@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚è‚ٌ‚¶‚¯‚ٌ‚غ‚¤پjپB
پ@
پ،پ@ڈ—رژ›Œ–@پB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ڈ—رژ›Œ–@ پi‚µ‚ه‚¤‚è‚ٌ‚¶‚¯‚ٌ‚غ‚¤پjپB
پ،پ@–k‘T‚ج‘Tڈ@پE•§‹³ژ›‰@‚جپu‹àچ„‘Tڈ—رژ›پi“ْ–{پjپv
پ@‚إپAپ@چہ‘Tچs‚ئ‹¤‚ةپAڈ@–ه‚جچs‚ئ‚µ‚ؤچs‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚é
پ@Œ–@پB
پ@
پ@
پ،پ@ڈ—رژ›Œ–@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚è‚ٌ‚¶‚¯‚ٌ‚غ‚¤پj ‚حپAپ@–k‘T‚ج‘T
پ@ڈ@پE•§‹³ژ›‰@‚جپu‹àچ„‘Tڈ—رژ›پi“ْ–{پjپv‚إپAپ@چہ‘Tچs‚ئ
پ@‹¤‚ةپAڈ@–ه‚جچs‚ئ‚µ‚ؤچs‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚錖@پ@پiˆص‹طچsپi‚¦
پ@‚«‚«‚ٌ‚¬‚ه‚¤پjپAŒڈpپAڈ_ڈpپjپjپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@پuڈ—رژ›Œ–@پvپ@‚حپAپ@’†چ‘‚جگ’ژRڈ—رژ›‚جڈ@–ه‚جچs
پ@‚جڈ—رŒ‚ئ‚ح‘S‚•ت‚ج‹Z–@‘جŒn‚ً‚à‚آپB
پ@پ@پ@“ث‚پE‚¤‚آ‚ب‚ا‚جŒڈpپ@‚ئپ@“ٹ‚°‚éپE‰ں‚³‚¦چ‚ق‚ب‚ا‚ج
پ@ڈ_ڈp‚ج—¼•û‚جپuچ„ڈ_ˆê‘جپv‚ج‹Z–@‚ً‚à‚آپB
پ@
پ،پ@گي‘O‚ة’†چ‘‚إٹˆ“®‚µگ’ژRڈ—رژ›‚إ‚àڈCچs‚µڈ—رŒ‚à
پ@‘ج“¾‚µ‚½“ْ–{گlŒ–@‰ئپEڈ@“¹گbپi‚»‚¤‚ا‚¤‚µ‚ٌپj‚ھپAپ@گي
پ@ŒمپA“ْ–{‚ة‹àچ„‘Tڈ—رژ›‚ًŒڑ‚ؤپAڈ—رŒ‚⑼‚ج’†چ‘Œn
پ@Œ–@‚ً—Zچ‡‚µچج‚è“ü‚êڈ@–ه‚جچsپiŒ‘Tˆê”@پj‚ئ‚µ‚½Œ–@
پ@‚إ‚ ‚éپAپuڈ—رژ›Œ–@پv‚ً“ْ–{‚ة•پ‹y‚µپAپ@‚»‚جŒمپAگ¢ٹE
پ@ٹeچ‘‚ة“¹ڈê‚ً‚à‚¤‚¯پAڈ—رژ›Œ–@‚ھپA گ¢ٹE‚ةچL‚ـ‚éپBپ@
پ@
پ@
پ،پ@ˆص‹طچsپ@پi‚¦‚«‚«‚ٌ‚¬‚ه‚¤پj‚حپAپ@’†چ‘‚جگ’ژRڈ—رژ›‚إپAپ@
پ@•§‹³‚ج•z‹³‚ج‚½‚ك’†چ‘‚ً–K‚ꂽپA‘Tڈ@‚جٹJ‘c‚جƒCƒ“ƒh
پ@گl•§‘mپE’B–پ‘هژt‚⑼‚جƒCƒ“ƒhگl•§‘m‚ھپAƒCƒ“ƒhŒ–@‚ً
پ@ٹî‘b‚ةپAپ@ڈCچs‚ج‚P‚آ‚ئ‚µ‚ؤچs‚ء‚ؤ‚¢‚½Œ–@پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@‘Tڈ@پi‚؛‚ٌ‚µ‚م‚¤پj‚حپA‘هڈو•§‹³‚جˆê”h‚إپA’B–پ‘هژt
پ@ˆبŒمپA’†چ‘‚إ”“W‚µپAڈCچs‚ًˆص‹طچsپi‚¦‚«‚«‚ٌ‚¬‚ه‚¤پj‚ة
پ@ڈd“_‚ً’u‚پu–k‘T‚ج‘Tڈ@پvپ@‚ئپ@ڈCچs‚ًچہ‘Tچs‚ةڈd“_‚ً‚¨
پ@‚پu“ى‘T‚ج‘Tڈ@پvپ@‚ة•ھ‚©‚ê‚éپB
پœپ@پu–k‘T‚ج‘Tڈ@پvپ@‚حپA’†چ‘‚إ‚حپA’B–پ‘هژtˆبŒمپAگ’ژR
پ@ڈ—رژ›‚ب‚ا‚ً’†گS‚ةپA‰h‚¦پAŒ»چف‚ةژٹ‚éپBپ@ˆê•ûپAپu–k
پ@‘T‚ج‘Tڈ@پv‚حپAپ@گيŒمپA’†چ‘‚©‚ç“ْ–{‚ة“`‚¦‚ç‚êپA“ْ–{
پ@‚إپA‹àچ„‘Tڈ—رژ›پi‚±‚ٌ‚²‚¤‚؛‚ٌ‚µ‚ه‚¤‚è‚ٌ‚¶پj‚ب‚ا‚جژ›
پ@‰@‚ھŒ`گ¬‚³‚êپA‰h‚¦پAŒ»چف‚ةژٹ‚éپBپ@
پœپ@پu“ى‘T‚ج‘Tڈ@پv‚حپA’†چ‘‚إ‚حپA’B–پ‘هژtˆبŒمپA“‚پE‘v
پ@‘م‚ة‰h‚¦پA–¾‘م‚ةگٹ‚¦پAŒ»چف‚ةژٹ‚éپBپ@ˆê•ûپAپu“ى‘T‚ج
پ@‘Tڈ@پv‚حپA’†چ‘‚ج‘v‚جژ‘مپi‚X‚U‚Oپ`‚P‚Q‚V‚XپA–k‘vپE“ى‘v
پ@ژ‘مپj‚ةپAپ@’†چ‘‚©‚ç“ْ–{‚ة“`‚¦‚ç‚êپA‚»‚جŒمپA“ْ–{‚إپA
پ@‘‚“´ڈ@پi‚»‚¤‚ئ‚¤‚µ‚م‚¤پjپA—صچدڈ@پi‚è‚ٌ‚´‚¢‚µ‚م‚¤پjپA‰©ں@
پ@ڈ@پi‚¨‚¤‚خ‚‚µ‚م‚¤پj‚ب‚ا‚جژ›‰@‚ھŒ`گ¬‚³‚êپA‰h‚¦پAŒ»چف
پ@‚ةژٹ‚éپBپ@
پ@
پ،پ@Œ–@ پi‚¯‚ٌ‚غ‚¤پj‚ئ‚حپAپ@Œڈp‚إپAپ@گ¢ٹE‚ة‚حپA’†چ‘
پ@Œn‚جŒ–@پiƒJƒ“ƒtپ[پj‚جپu’†چ‘Œ–@پiƒ`ƒƒƒCƒjپ[ƒYپEƒJƒ“
پ@ƒtپ[پjپvپ@‚âپ@پuڈ—رژ›Œ–@پvپA “ْ–{Œn‚جŒ–@‚جپu“ْ–{
پ@Œ–@پvپ@‚ب‚ا‚ھ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@ڈ—رŒ‚حپAپ@پu’†چ‘Œ–@پiƒ`ƒƒƒCƒjپ[ƒYپEƒJƒ“ƒtپ[پjپv
پ@‚جˆê—¬”hپ@‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@ڈ—رژ›Œ–@‚حپAپ@’†چ‘Œn‚جŒ–@پiƒJƒ“ƒtپ[پj‚إ‚ح‚
پ@‚é‚ھپAپ@پu’†چ‘Œ–@پiƒ`ƒƒƒCƒjپ[ƒYپEƒJƒ“ƒtپ[پjپv‚ئ‚ح‘S
پ@‚•ت‚ج‹Z–@‘جŒn‚ً‚à‚آپB
پ،پ@’†چ‘Œn‚جŒ–@پiƒJƒ“ƒtپ[پj‚ة‚حپAپ@پu’†چ‘Œ–@پiƒ`ƒƒƒC
پ@ƒjپ[ƒYپEƒJƒ“ƒtپ[پjپvپ@‚âپ@پuڈ—رژ›Œ–@پvپ@‚ب‚ا‚ھ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@ڈ—ر Œ‚حپAپ@پu’†چ‘Œ–@پiƒ`ƒƒƒCƒjپ[ƒYپEƒJƒ“ƒtپ[پjپv
پ@‚جˆê—¬”hپ@‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@پ@پ@ڈ—رژ›Œ–@‚حپAپ@’†چ‘Œn‚جŒ–@پiƒJƒ“ƒtپ[پj‚إ‚ح‚
پ@‚é‚ھپAپ@پu’†چ‘Œ–@پiƒ`ƒƒƒCƒjپ[ƒYپEƒJƒ“ƒtپ[پjپv پ@‚ئ‚ح‘S
پ@‚•ت‚ج‹Z–@‘جŒn‚ً‚à‚آپB
پ@
پ@
پںپ@‹àچ„‘Tڈ—رژ›پB
پ،پ@‹àچ„‘Tڈ—رژ› پi‚±‚ٌ‚²‚¤‚؛‚ٌ‚µ‚ه‚¤‚è‚ٌ‚¶پjپ@‚حپA
پ@گ³ژ®–¼‚ح‹àچ„‘T‘چ–{ژRڈ—رژ›‚إپAپ@–k‘T پi‚ظ‚‚؛‚ٌپj
پ@‚ج‘Tڈ@پE•§‹³‚جژ›‰@پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@‹àچ„‘T‚ج‹³‚¦‚ج’†گSژv‘z‚حپAپ@پuژ©Œبٹm—§پvپAپuژ©‘¼
پ@‹¤ٹyپvپAپuŒ‘Tˆê”@پvپAپu—حˆ¤•s“ٌپvپ@‚ب‚ا‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@
پ،پ@‹àچ„‘Tڈ—رژ›پi“ْ–{پjپ@‚إ‚حپAپ@چہ‘TچsپAپ@ˆص‹طچsپi‚¦
پ@‚«‚«‚ٌ‚¬‚ه‚¤پj‚جڈ—رژ›Œ–@پAپ@‚»‚ج‘¼‚ج•û–@‚إپA ڈCچs
پ@‚ًچs‚ء‚ؤ‚¢‚éپB
پ@
پ،پ@‹àچ„‘Tڈ—رژ›پi“ْ–{پjپ@‚حپAپ@“ْ–{پEژlچ‘‚جچپگىŒ§‘½
پ@“x’أ’¬‚ة‚ ‚èپAپ@“ْ–{گlپEڈ@“¹گbپi‚»‚¤‚ا‚¤‚µ‚ٌپj‚ھپA گي
پ@ŒمپA–k‘T‚ج‘Tڈ@‚ًٹJ‚¢‚½ژ›‰@‚إپAپ@ڈ@–ه‚جچs‚جپuڈ—ر
پ@ژ›Œ–@پv‚ج’†گS’n‚إ‚ ‚éپB
پ،پ@‘Tڈ@‚ة‚ح–k‘T‚ئ“ى‘T‚ھ‚ ‚éپBپ@‹àچ„‘Tڈ—رژ› پi‚±‚ٌ
پ@‚²‚¤‚؛‚ٌ‚µ‚ه‚¤‚è‚ٌ‚¶پj‚حپAپ@“ْ–{‚ج–k‘T‚ج‘Tڈ@‚ج•§‹³
پ@ژ›‰@‚إ‚ ‚èپAپ@’†چ‘‚جگ’ژRڈ—رژ›‚ئ•ہ‚شپAپu–k‘T‚ج‘T
پ@ڈ@پv‚جگ¢ٹE‚ج‚Q‘ه•§‹³ژ›‰@پv‚ج‚P‚آپ@‚إ‚ ‚éپBپ@“ْ–{‚ج
پ@‹àچ„‘Tڈ—رژ›‚حپAپ@’†چ‘‚جگ’ژRڈ—رژ›‚ئ‚حپAŒً—¬پi—F
پ@چDٹضŒWپj‚ح‚ ‚é‚ھپAپ@’¼گعپAٹضŒW‚ح‚ب‚¢پB
پ@
پ،پ@“ْ–{‚ج‹àچ„‘Tڈ—رژ›‚â’†چ‘‚جگ’ژRڈ—رژ›‚ب‚ا‚ة
پ@‹¤’ت‚·‚é–k‘T‚ج‘Tڈ@پE•§‹³‚ج–ع“I‚ج‚P‚آ‚حپAپ@Œµپi‚«
پ@‚رپj‚µ‚¢پA“÷‘ج‚ئگ¸گ_‚ج’bکBپi‚½‚ٌ‚ê‚ٌپj‚ً’ت‚¶‚ؤپAپ@
پ@گl‚ھگlگ¶‚ج”@‰½پi‚¢‚©پj‚بڈَ‹µپEچ¢“ï‚ة‚à‚ك‚°‚¸—§‚؟
پ@Œü‚©‚¢پA‘إ‚؟ڈں‚آ‚½‚ك‚جپ@پu•s‹ü‚جگ¸گ_—حپvپ@‚ً—{‚¤‚±
پ@‚ئ‚ة‚ ‚éپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@
پ@
#thefreedomandpeoplesrightsmovement
پ@
پ،پ@ژ©—R–¯Œ ‰^“®پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ن‚¤‚ف‚ٌ‚¯‚ٌ‚¤‚ٌ‚ا‚¤پjپB
پ@
پ،پ@ژ©—R–¯Œ ‰^“®پB
پ،پ@ژٹْپFپ@‚P‚W‚V‚Sپi–¾ژ،‚V”Nپjپ`‚P‚W‚W‚X”Nپi–¾ژ،‚Q‚Q”NپjپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ژ©—R–¯Œ ‰^“®پ@پi‚¶‚ن‚¤‚ف‚ٌ‚¯‚ٌ‚¤‚ٌ‚ا‚¤پjپB
پœپ@‰p–¼پFپ@‚”‚ˆ‚…پ@‚e‚’‚…‚…‚„‚ڈ‚چپ@‚پ‚ژ‚„پ@‚o‚…‚ڈ‚گ‚Œ‚…پf‚“پ@‚q‚‰‚‡‚ˆ‚”‚“پ@
پ@‚l‚ڈ‚–‚…‚چ‚…‚ژ‚”پB
پ،پ@–¾ژ،ژ‘م‘Oٹْ‚جپA”ث”´گ•{‚ة‘خ‚·‚é–¯ژهژه‹`“Iگ
پ@ژ،‰^“®پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ،پ@ژ©—R–¯Œ ‰^“®پ@پi‚¶‚ن‚¤‚ف‚ٌ‚¯‚ٌ‚¤‚ٌ‚ا‚¤پjپ@‚حپAپ@ژ
پ@ٹْ‚حپA‚P‚W‚V‚Sپi–¾ژ،‚V”Nپjپ`‚P‚W‚W‚X”Nپi–¾ژ،‚Q‚Q”Nپjپ@‚إپA
پ@–¾ژ،ژ‘م‘Oٹْ‚جپA”ث”´گ•{‚ة‘خ‚·‚é–¯ژهژه‹`“Iگژ،
پ@‰^“®پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@‰p–¼پFپ@‚”‚ˆ‚…پ@‚e‚’‚…‚…‚„‚ڈ‚چپ@‚پ‚ژ‚„پ@‚o‚…‚ڈ‚گ‚Œ‚…پf‚“پ@‚q‚‰‚‡‚ˆ‚”‚“پ@
پ@‚l‚ڈ‚–‚…‚چ‚…‚ژ‚”پ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@ژ©—R–¯Œ ‰^“®‚حپAپ@ˆê”ت‚جگlپX‚ھپAگ¼—mŒ[–ضژv‘z‚ج
پ@‰e‹؟‚ًژَ‚¯پAپ@”ث”´‘إ”jپAچ‘‰ïٹJگفپA’n‘dپi‚؟‚»پjŒyŒ¸پA
پ@ڈً–ٌ‰üگ³‚ب‚ا‚ً—v‹پ‚µ‚½‰^“®پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@ژ©—R–¯Œ ‰^“®‚جژw“±ژز‚حپA”آٹ_‘قڈ•پAŒم“،ڈغ“ٌکY
پ@پi‚µ‚ه‚¤‚¶‚낤پjپA‰ح–ىچL’†پA‘هˆنŒ›‘¾کYپAگA–طژ}گ·‚ب‚ا
پ@‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ،پ@ژ©—R–¯Œ ‰^“®‚حپAپ@‚P‚W‚V‚S”N‚ج–¯گï‹cˆُگف—§Œڑ”’
پ@‚ةژn‚ـ‚èپA‚P‚W‚W‚Vپ`‚W‚X”N‚جژO‘هژ–ŒڈŒڑ”’پE‘ه“¯’cŒ‹
پ@‰^“®‚إڈI‚ي‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@گ¼“ىگي‘ˆپi‚¹‚¢‚ب‚ٌ‚¹‚ٌ‚»‚¤پjپ@‚ئ‚حپAپ@–¾ژ،گVگ•{
پ@پi‹ك‘م“ْ–{گ•{پj‚ة‘خ‚·‚éچإ‘ه‚ج”½“®“Iژm‘°”½—گپ@‚إپAپ@
پ@‚P‚W‚V‚V”Nپi–¾ژ،‚P‚O”Nپj‚جپA•s•½ژm‘°پi‰pپF‚„‚‰‚“‚پ‚†‚†‚…‚ƒ‚”‚…‚„پ@
پ@‚“‚پ‚چ‚•‚’‚پ‚‰پ@‚—‚پ‚’‚’‚‰‚ڈ‚’پi‚“پjپjپ@‚ج”½گ•{•گ—ح“¬‘ˆ‚جگي‘ˆ‚إ
پ@‚ ‚éپB
پ@پ@پ@گ¼“ىگي‘ˆŒمپA”½گ•{‰^“®‚ج’†گS‚حپAژ©—R–¯Œ ‰^“®
پ@پi‚P‚W‚V‚Sپ`‚W‚X”Nپj‚ةˆع‚ء‚½پB
پ،پ@گ¼“ىگي‘ˆ‚ج”s–kŒمپAپ@•s•½ژm‘°‚حپA•گ—ح‚ة‚و‚éگVگ
پ@•{‘إ“|‚ً’ْپi‚ ‚«‚çپj‚كپAپ@ژ©—R–¯Œ ‰^“®‚ب‚اŒ¾ک_‚ة‚و
پ@‚èپA–¾ژ،گVگ•{‚ة‰üٹv‚ً—v‹پ‚µ‚ؤ‚¢‚پi‘خچR‚µ‚ؤ‚¢‚پjپB
پ@پ@پ@گ¼“ىگي‘ˆŒمپi‚P‚W‚V‚V”NˆبŒمپjپAپ@•s•½ژm‘°‚حپA•گ—ح‚إ
پ@‚ح‚ب‚پAŒ¾ک_‚ة‚و‚èپAپ@–¾ژ،گVگ•{پi‹ك‘م“ْ–{گ•{پj‚جگ
پ@چô‚ً•د‚¦‚و‚¤‚ئ‚·‚éپBپ@‚»‚µ‚ؤپAژ©—R–¯Œ ‰^“®پi‚P‚W‚V‚Sپ`
پ@‚W‚X”Nپj‚ھ–{ٹi“I‚ةچs‚ي‚ê‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ڈo‰ئپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚م‚ء‚¯پjپB
پ@
پ،پ@ڈo‰ئپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ڈo‰ئپ@پi‚µ‚م‚ء‚¯پjپB
پ،پ@•§“¹‚جگ¶ٹˆ‚ة“ü‚邱‚ئپB
پ،پ@•گ“cگMŒ؛پAپ@ڈمگ™ŒھگMپAپ@“Vàِ‰@پE“ؤ•PپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ،پ@ڈo‰ئپ@پi‚µ‚م‚ء‚¯پjپ@‚ئ‚حپAپ@•§“¹‚جگ¶ٹˆ‚ة“ü‚邱‚ئ
پ@‚إ‚ ‚éپB
پ،پ@ڈo‰ئ‚ئ‚حپAپ@•§–ه‚ة“ü‚èپAپ@Œآگl–¼‚ً•د‚¦پi‘گ¢‚ج
پ@–¼‚ًژج‚ؤپA‰ْ–¼‚ً–¼ڈو‚èپjپAپ@گ¶ٹˆ‘ش“x‚ً‰ü‚ك‚邱‚ئ
پ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚إ‚حپAڈم‘wٹK‘w‚ج’jڈ—‚حپAگlگ¶‚ةˆظ
پ@•د‚ھ‹N‚«‚½‚ئ‚«پAپ@‚و‚ڈo‰ئ‚µ‚½پ@پi•§–ه‚ة“ü‚èپAŒآگl
پ@–¼‚ً•د‚¦پAگ¶ٹˆ‘ش“x‚ً‰ü‚ك‚½پjپB
پ@
پ،پ@’jگ«‚ھڈo‰ئ‚·‚邱‚ئ‚ًپA“ü“¹پi‚ة‚م‚¤‚ا‚¤پj‚·‚éپAپ@
پ@ڈ—گ«‚ھڈo‰ئ‚·‚邱‚ئ‚ًپAپ@—ژڈüپi‚ç‚‚µ‚ه‚پj‚·‚é‚ئŒ¾‚¤پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@•گ“cگMŒ؛‚حپAڈo‰ئ‚µ‚ؤپi“ü“¹‚µ‚ؤپjپAپu“؟‰hŒ¬گMŒ؛پv
پ@‚ً–¼ڈو‚èپAگ¶ٹˆ‘ش“x‚ً‰ü‚ك‚éپB
پ@پ@ڈمگ™ŒھگM‚حپAڈo‰ئ‚µ‚ؤپi“ü“¹‚µ‚ؤپjپAپu•sژ¯ˆءپi•sژ¯
پ@‰@پjŒھگMپv‚ً–¼ڈو‚èپAگ¶ٹˆ‘ش“x‚ً‰ü‚ك‚éپBپ@
پœپ@پi’چˆسپjپ@•گ“cگMŒ؛پAڈمگ™ŒھگM‚حپAŒمگ¢‚جگl‚ھ•t‚¯
پ@‚½ژپ–¼‚إپAپ@“–ژپAپ@–{گl’B‚حپAپu“؟‰hŒ¬گMŒ؛پvپAپu•s
پ@ژ¯ˆءپi•sژ¯‰@پjŒھگMپvپ@‚ئ–¼ڈو‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
پ@
پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جڈم‘wٹK‘w‚جڈ—گ«‚حپA•v‚ھژ€‹ژ‚µ‚½
پ@‚ئ‚«پA‚ـ‚½‚حپAگlگ¶‚ةˆظ•د‚ھ‹N‚«‚½‚ئ‚«پAپ@‚و‚پ@—ژڈü
پ@‚µ‚½پ@پi”¯‚ً‚¨‚낵‚ؤپi’Z‚‚·‚é‚©‚»‚肨‚ئ‚µ‚ؤپjŒآگl
پ@–¼‚ً•د‚¦•§–ه‚ة“ü‚ء‚½پAڈo‰ئ‚µ‚½پjپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جڈم‘wٹK‘w‚جڈ—گ«‚حپAپ@•v‚ھژ€‹ژ‚µ
پ@‚½‚ئ‚«پAپ@—ژڈü‚µ‚ؤپ@پi”¯‚ً‚¨‚낵‚ؤپi’Z‚‚·‚é‚©‚»‚è
پ@‚¨‚ئ‚µ‚ؤپjŒآگl–¼‚ً•د‚¦•§–ه‚ة“ü‚èپAڈo‰ئ‚µ‚ؤپjپAپ@
پ@•v‚ج•ى’ٌپi‚ع‚¾‚¢پj‚ً’¢پi‚ئ‚ق‚çپj‚¤پ@ٹµڈK‚ھ‚ ‚ء‚½پBپ@پ@
پ@
پ،پ@پi—لپjپ@–‹––‚ج“Vàِ‰@پE“ؤ•Pپi‚ؤ‚ٌ‚µ‚ه‚¤‚¢‚ٌپE‚ ‚آ
پ@‚ذ‚كپjپB
پœپ@“ؤ•Pپ@پi‚ ‚آ‚ذ‚كپA‹ك‰qŒhژqپi‚·‚ف‚±پjپA“‡’أ“ؤژqپjپ@
پ@‚حپAپ@“ؤ•P‚ج•v‚جپAچ]Œث–‹•{‚P‚R‘مڈ«ŒRپE“؟گى‰ئ’è
پ@پi‚¢‚¦‚³‚¾پj‚ھژ€‹ژŒمپA—ژڈü‚µ‚ؤپA“Vàِ‰@پi‰ْ–¼پj‚ئ–¼
پ@ڈو‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@ˆê•”‚جڈo‰ئژز‚حپAپ@Œ»گ¢‚ًژج‚ؤپAگ¢ژج‚ؤگl‚ئ‚ب‚ء
پ@‚½پB
پ@پ@پi—لپjپ@‹g“cŒ“چDپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ژ›ژذ پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚µ‚لپjپB
پ@
پ،پ@ژ›ژذپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ژ›ژذ پ@پi‚¶‚µ‚لپjپB
پœپ@‰p–¼پ@پFپ@ ‚”‚ˆ‚…پ@‚s‚…‚چ‚گ‚Œ‚…پ@‚پ‚ژ‚„پ@‚r‚ˆ‚’‚‰‚ژ‚…پB
پ،پ@ژ›‰@‚âگ_ژذپB
پ،پ@ژ›ژذ‚ج‘m—µپEگ_ٹ¯‚حپAژ›ژذپAژ›‰@‚âگ_ژذ‚ةڈ]
پ@پ@ژ–‚·‚éژزپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ،پ@ژ›ژذ‚حپAپ@ژ›‰@‚âگ_ژذپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@ژ›ژذپi‚ج‘m—µپEگ_ٹ¯پjپ@‚حپAپ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جگژ،‚ً
پ@ژx”z‚µ‚½گ¨—ح‚إ‚ ‚éپAپ@“Vچc‰ئپAپ@Œِ‰ئپAپ@•گ‰ئپAپ@ژ›
پ@ژذپi‚ج‘m—µپEگ_ٹ¯پjپ@‚ج‚P‚آ‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@ژ›ژذ‚ج‘m—µ‚âگ_ٹ¯‚حپAپ@ژ›ژذپAژ›‰@‚âگ_ژذ‚ةڈ]ژ–
پ@پ@‚·‚éژزپ@‚إ‚ ‚éپ@پi‰pپF‚o‚…‚ڈ‚گ‚Œ‚…پ@‚ڈ‚†پ@‚”‚ˆ‚…پ@‚s‚…‚چ‚گ‚Œ‚…پ@
پ@پ@‚پ‚ژ‚„پ@‚r‚ˆ‚’‚‰‚ژ‚…پ@‚b‚Œ‚پ‚“‚“پjپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@‘هژ›‚جژ›–±‚ً“ٹ‡‚·‚é‘mٹ¯‚ًپA•ت“–پi‚ׂء‚ئ‚¤پj‚ئ
پ@پ@Œؤ‚ٌ‚¾پ@پi—لپA“Œ‘هژ›•ت“–پjپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@Œنژtپ@پi‚¨‚µپj‚حپAپ@گ_ژذ‚جگ_ٹ¯‚جژwژ¦‚إپAگ_ژذ‚ج
پ@پ@ژDپi‚¨ژç‚è“™پj‚ًگM‹آژز‚ة”z•z‚·‚éژزپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژjژ«“T “ْ–{Œê”إ ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپBپ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ڈ\•¶‘Kپ@
پ@پ@پ@پi‚¶‚م‚¤‚à‚ٌ‚¹‚ٌپjپB
پ@
پ،پ@ڈ\•¶‘KپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ڈ\•¶‘Kپ@پi‚¶‚م‚¤‚à‚ٌ‚¹‚ٌپjپB
پ،پ@ڈ\•¶پi‚à‚ٌپj’Pˆت‚ج’èٹzپi’èˆتپjپE’تڈي‰ف•¼پB
پ،پ@•¶‘Kپi‚à‚ٌ‚¹‚ٌپA•¶’Pˆت‚ج”ٌ‹M‹à‘®‰ف•¼پjپB
پ،پ@چ]Œث–‹•{‚ھ’’‘¢پE”چs‚µ‚½پAچ]Œثژ‘م‚جڈ\•¶’P
پ@پ@ˆت‚ج’èٹzپi’èˆتپjپE’تڈي‰ف•¼پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ةپAڈ\•¶’Pˆت‰ف•¼‚إ‚حپAپ@پ@پu•َ‰i’ت•َ
پ@ڈ\•¶‘K“؛‰فپvپ@‚ھ—¬’ت‚µپAژg—p‚³‚ꂽپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ةپA•¶’Pˆت‰ف•¼‚إ‚حپAپ@•¶‘Kپi•¶’Pˆت‚ج
پ@”ٌ‹M‹à‘®‰ف•¼پj‚ھ’’‘¢‚³‚êپAپ@•¶‘K‚جٹz–ت•ت‚ةپA
پ@ˆê•¶‘Kپi‚PژيپjپAژl•¶‘Kپi‚QژيپjپAڈ\•¶‘Kپi‚PژيپjپA•S•¶
پ@‘Kپi‚Pژيپjپ@‚ج‚Sژي—ق‚ج‰ف•¼‚ھ پA—¬’ت‚µپAژg—p‚³‚ꂽپB
پ،پ@ˆê—¼ڈ¬”»پi‹àپjپ@پàپ@‚S•ھپ@پàپ@‚P‚Uژéپ@پàپ@‚S‚O‚O‚O•¶پ@
پ@پ@پi‚Sٹر•¶پjپ@پàپ@Œ»چف‚ج–ٌ‚P‚O–œ‰~پB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ج‰ف•¼‚جڈعچׂة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAپu“ْ–{—¬’ت
پ@پ@‰ف•¼پv‚ًژQڈئ‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
پ@
پ@
پ،پ@ڈ\•¶‘Kپ@
پ@پ@پ@ڈ\•¶‘Kپ@پi‚¶‚م‚¤‚à‚ٌ‚¹‚ٌپj‚حپAپ@‚P‚O•¶’Pˆت‚ج‰ف•¼
پ@‚إپAپ@Œ»چف‚ج‰ف•¼‰؟’l‚ح–ٌ‚Q‚T‚O‰~ ‚إپAپ@•َ‰i’ت•َپi‚ظ
پ@‚¤‚¦‚¢‚آ‚¤‚ظ‚¤پjڈ\•¶‘K“؛‰فپi•َ‰i‘Kپj‚ج‚ف‚Pژي‚إپAپ@‚¨
پ@‚و‚»•َ‰i’ت•َ‚S‚O ‚O–‡‚ئ‚P—¼ڈ¬”»پi‹àپj‚ئ‚ھŒًٹ·‚³‚ꂽپBپ@
پ@•َ‰i’ت•َڈ\•¶‘K“؛‰ف‚حپAپ@‚P‚O•¶’ت—p‚ج“؛‰ف‚إپAپ@چ]
پ@Œث’†ٹْ‚ج•َ‰iٹْ‚ج’Zٹْٹش‚ة‚ج‚ف’’‘¢ ‚³‚ꂽپBپ@
پ@
پ،پ@•َ‰i’ت•َڈ\•¶‘K“؛‰فپ@پi•َ‰i‘KپjپB
پ@پ@•َ‰i’ت•َڈ\•¶‘K“؛‰فپi•َ‰i‘Kپj‚حپAپ@ڈ\•¶‘Kپi‚¶‚م‚¤
پ@‚à‚ٌ‚¹‚ٌپj‚إپA پ@‚P‚O•¶’Pˆت‚ج‰ف•¼‚إپAپ@Œ»چف‚ج‰ف•¼‰؟
پ@’l‚ح–ٌ‚Q‚T‚O‰~ ‚إپAپ@‚¨‚و‚»•َ‰i’ت•َ‚S‚O‚O–‡‚ئ‚P—¼ڈ¬
پ@”»پi‹àپj‚ئ‚ھŒًٹ·‚³‚ꂽپBپ@•َ‰i’ت•َڈ\•¶‘K“؛‰ف ‚حپAپ@
پ@‚P‚O•¶’ت—p‚ج“؛‰ف‚إپAپ@چ]Œث’†ٹْ‚ج•َ‰iٹْ‚ج ’Zٹْٹش
پ@‚ة‚ج‚ف’’‘¢‚³‚ꂽپBپ@
پ@
پ@
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ج‰ف•¼پB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ج—¼پi‚è‚ه‚¤پjپE•ھپi‚شپjپEژéپi‚µ‚مپjپE•¶پi‚à‚ٌپj
پ@‚ج’èٹzپi’èˆتپjپE’تڈي‰ف•¼پB
پ،پ@چ]Œثژ‘مپi‚P‚U‚O‚R”Nپ`‚P‚W‚U‚W”Nپj‚ةپAپ@چ]Œث–‹•{‚ة
پ@‚و‚è’’‘¢پi”چsپj‚³‚êپAپ@‘Sچ‘‚ة—¬’ت‚µپAپ@ژg—p‚³‚ꂽ
پ@’èٹzپi’èˆتپjپE’تڈي‰ف•¼پ@‚حپAپ@‚T—¼”»‹àپi‚PژيپjپAپ@
پ@ˆê—¼ڈ¬”»پi‹àپjپi‚P‚PژيپjپAپ@پ@“ٌ•ھ‹àپi‚RژيپjپAپ@ ˆê•ھ‹à
پ@پi‚P‚PژيپjپAپ@ˆê•ھ‹âپi‚QژيپjپAپ@“ٌژé‹àپi‚RژيپjپAپ@ˆêژé‹à
پ@پi‚PژيپjپAپ@پ@“ٌژé‹âپi‚RژيپjپA پ@ˆêژé‹âپi‚PژيپjپAپ@•S•¶‘K
پ@پi‚PژيپjپAپ@پ@ڈ\•¶‘Kپi‚PژيپjپAپ@ژl•¶‘Kپi‚QژيپjپAپ@ˆê•¶‘K
پ@پi‚Pژيپjپ@‚ب‚ا‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@•¶’Pˆت’èٹzپi’èˆتپjپE’تڈي‰ف•¼ پB
پ،پ@•¶’Pˆت’èٹzپi’èˆتپjپE’تڈي‰ف•¼ ‚حپAٹz–ت•ت‚ةپAژں‚ج
پ@‚Sژي—ق‚ھ‚ ‚éپBپ@ˆê•¶‘KپAپ@ژl•¶‘K پAپ@ڈ\•¶‘KپAپ@•S•¶
پ@‘Kپ@‚ج‚Sژي—ق‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ةپA•¶’Pˆت‰ف•¼‚إ‚حپAپ@•¶‘Kپi•¶’Pˆت‚ج
پ@”ٌ‹M‹à‘®‰ف•¼پj‚ھ’’‘¢‚³‚êپAپ@•¶‘K‚جٹz–ت•ت‚ةپA
پ@ˆê•¶‘Kپi‚PژيپjپAژl•¶‘Kپi‚QژيپjپAڈ\•¶‘Kپi‚PژيپjپA•S•¶
پ@‘Kپi‚Pژيپjپ@‚ج‚Sژي—ق‚ج‰ف•¼‚ھ پA—¬’ت‚µپAژg—p‚³‚ꂽپB
پ@
پ،پ@•¶’Pˆت’èٹzپi’èˆتپjپE’تڈي‰ف•¼ پB
پ،پ@•¶’Pˆت’èٹzپi’èˆتپjپE’تڈي‰ف•¼ ‚حپA‰ف•¼ƒOƒ‹پ[ƒv•ت
پ@‚ةپAژں‚ج‚Tژي—ق‚ھ‚ ‚éپBپ@ٹ°‰i’ت•َˆê•¶‘K“؛‰فپE“S‰فپAپ@
پ@ٹ°‰i’ت•َژl•¶‘K“؛‰فپE“S‰فپAپ@•¶‹v‰i•َژl•¶‘K“؛‰فپA
پ@•َ‰i’ت•َڈ\•¶‘K“؛‰فپAپ@“V•غ’ت•َ•S•¶‘K“؛‰فپ@‚ج‚T
پ@ژي—ق‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ةپA•¶’Pˆت‰ف•¼‚إ‚حپAپ@•¶‘Kپi•¶’Pˆت‚ج
پ@”ٌ‹M‹à‘®‰فپj‚ھ’’‘¢‚³‚êپAپ@•¶‘K‚ج‰ف•¼ƒOƒ‹پ[ƒv
پ@•ت‚ةپAپ@ٹ°‰i’ت•َˆê•¶‘K“؛‰فپE“S‰فپAپ@ٹ°‰i’ت•َژl
پ@•¶‘K“؛‰فپE“S‰فپAپ@•¶‹v‰i•َژl•¶‘K“؛‰فپAپ@•َ‰i’ت
پ@•َڈ\•¶‘K“؛‰فپAپ@“V•غ’ت•َ•S•¶‘K“؛‰فپ@‚ج‚Tژي—ق‚ج
پ@‰ف•¼‚ھ—¬’ت‚µپAژg—p‚³‚ꂽپB
پ@
پ،پ@ڈ¬”»پB
پ،پ@‚P—¼ڈ¬”»پi‹àپj‚حپAچ]Œثژ‘م‚جٹîژ²‰ف•¼‚إپAپ@چ]Œث
پ@ژ‘م‚جٹeژٹْ‚إ‰؟’l‚ح•د“®‚µ‚½‚ھپAپ@Œ»چف‚ج ‰ف•¼
پ@‰؟’l‚إ–ٌ ‚P‚O–œ‰~پ@‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@پ@پ@چ]Œثژ‘م‚ةپAپ@‚P—¼ڈ¬”»پi‹àپj‚حپA‚¨‚و‚»‚S•ھپA‚P—¼
پ@ڈ¬”» پi‹àپj‚حپA‚¨‚و‚»‚P‚UژéپAپ@‚P—¼ڈ¬”»پi‹àپj‚حپA‚¨‚و
پ@‚»‚S‚O‚O‚O•¶ پi‚Sٹر•¶پjپ@‚ئŒًٹ·‚³‚ꂽپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ژ©—R—ِˆ¤پ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ن‚¤‚ê‚ٌ‚ ‚¢پjپB
پ@
پ،پ@ژ©—R—ِˆ¤پBپ@
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ژ©—R—ِˆ¤پ@پi‚¶‚ن‚¤‚ê‚ٌ‚ ‚¢پjپB
پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جڈم‘wٹK‘w‚جژ©—R—ِˆ¤پB
پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جڈم‘wٹK‘w‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپAژ©—R—ِˆ¤‚حپA
پ@ڈ‚ب‚©‚ء‚½پB
پ،پ@ژ©—R—ِˆ¤ƒJƒbƒvƒ‹‚ج—لپAپ@Œ¹‹`Œo‚ئگأپi‚µ‚¸‚©پjپA Œ¹
پ@پ@—ٹ’©‚ئ–kڈًگژqپAپ@–LگbڈG‹g‚ئ‚ث‚ثپi‚¨‚ثپjپB
پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚إ‚حپAڈ—گ«‚حپA‚P‚O‘م‚ھŒ‹چ¥“K—îٹْپA
پ@پ@‘پچ¥‘½ژYپA•v•w•تگ©پAڈم‘wٹK‘w‚حŒµٹi‚ب‰ئ•ƒ’·گ§پB
پœپ@Œ»‘م“ْ–{‚ئˆل‚¢پA‘O‹ك‘م“ْ–{‚إ‚حپAگlپX‚ج•½‹دژُ
پ@پ@–½پ@پiڈم‘wٹK‘w‚S‚Oپ`‚T‚OچخپAˆê”تڈژ–¯‚R‚Oپ`‚S‚Oچخپj
پ@پ@‚ح’Z‚پAپ@ˆم—أپE‰h—{ٹw‚ھ–¢”’B‚إ•aژ€‚ھ‘½‚پA‘پ‚
پ@پ@Œ‹چ¥‚µ‚ؤپAژq‹ں‚ً‘ٍژRگ¶‚فپAژq‘·‚ًژc‚»‚¤‚ئ‚µ‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ@
پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جڈم‘wٹK‘w‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپAژ©—R—ِˆ¤‚حپAڈ
پ@‚ب‚©‚ء‚½پBپ@‰ئ’·‚ـ‚½‚حگe‚ھپA’jژq‚ج•vگlپAڈ—ژq‚ج•v‚ً
پ@Œˆ‚ك‚邱‚ئ‚ھ‘½‚©‚ء‚½‚½‚كپBپ@
پ@
پ،پ@ڈم‘wٹK‘w‚جژ©—R—ِˆ¤‚جƒJƒbƒvƒ‹‚ج—ل‚ئ‚µ‚ؤپAپ@Œ¹‹`
پ@Œoپ@پi‚ف‚ب‚à‚ئ‚ج‚و‚µ‚آ‚ثپjپ@‚ئپ@گأپ@پi‚µ‚¸‚©پjپAپ@Œ¹ —ٹ
پ@’©پ@پi‚ف‚ب‚à‚ئ‚ج‚و‚è‚ئ‚àپjپ@‚ئ پ@–kڈًگژqپ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤‚ـ
پ@‚³‚±پjپAپ@–LگbڈG‹gپ@پi‚ئ‚و‚ئ‚ف‚ذ‚إ‚و‚µپj پ@‚ئپ@پu‚ث‚ثپi‚¨
پ@‚ثپjپvپ@‚ب‚ا‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ@Œ¹‹`Œoپi‚ف‚ب‚à‚ئ‚ج‚و‚è‚ئ‚àپj‚ئگأپi‚µ‚¸‚©پj‚ئ‚جٹضŒW
پ@‚إ‚حپAپ@پuŒلچب‹¾پvپi‚ ‚¸‚ـ‚©‚ھ‚فپA–kڈًژپ•زژ[‚جٹ™‘q
پ@–‹•{‚جگ³ژ®—ًژjڈ‘پjˆبٹO‚ةپAپ@ˆêژں“Iژj—؟‚ھڈ‚ب‚¢‚½
پ@‚كپ@پiژ؛’¬ژ‘مڈ‰ٹْ‚ةڈ‘‚©‚ꂽپu‹`Œo‹Lپv‚ح‘nچىپjپA‚¢
پ@‚آ‚ا‚±‚إ’m‚èچ‡‚ء‚½‚©‚ح•s–¾‚إ‚ ‚é‚ھپAپ@Œ¹‹`Œo‚ھپA ”’
پ@”ڈژqپi‚µ‚ç‚ر‚ه‚¤‚µپj‚جگأپi‚µ‚¸‚©پj‚ج•‘پi‚ـ‚¢پj‚ة–£کfپi‚ف
پ@‚ي‚پj‚³‚êپAپ@گأپi‚µ‚¸‚©پj‚àŒ¹ژپ‚ج‹MŒِژq‚ة–£—ح‚ًٹ´‚¶پA
پ@“ٌگl‚ح—ِ‚ة—ژ‚؟‚½‚ئگ„‘ھ‚³‚ê‚éپB
پ@پ@پ@گأ‚ئŒ¹‹`Œo‚ج‚Qگl‚حپA‚P‚P‚W‚T”Nچ پAپ@‹پ@پi‹“s’†‹
پ@‹وپi‚ب‚©‚¬‚ه‚¤‚پjپj‚إپA’m‚èچ‡‚¢پi—ِ‚ة—ژ‚؟پjپAگأ‚حپA‹`
پ@Œo‚ج—ِگlپiŒم‚ة‘¤ژ؛•vگlپj‚ئ‚ب‚ء‚½پ@‚ئŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ@پ@پ@–kڈًگژqپi‚P‚P‚T‚V”Nپ`‚P‚Q‚Q‚T”Nپj‚حپAپ@ˆة“¤چ‘پi‚¢‚¸
پ@‚ج‚‚ةپAŒ»چف‚جگأ‰ھŒ§“Œ•”پj‚جپAچâ“Œ•½ژپپi‚خ‚ٌ‚ا‚¤‚ض
پ@‚¢‚µپj‚جچ‹‘°پi‚²‚¤‚¼‚پA—L—حژزپj‚جپA–kڈًژگپi‚ظ‚¤‚¶‚ه
پ@‚¤‚ئ‚«‚ـ‚³پA‚P‚P‚R‚Wپ`‚P‚Q‚P‚T”Nپj‚ج’·ڈ—‚ئ‚µ‚ؤپAگ¶‚ـ‚êپA
پ@ˆç‚ء‚½پBپ@
پ@پ@پ@–kڈًگژq‚حپAپ@چâ“Œ•گژmپi‚خ‚ٌ‚ا‚¤‚ش‚µپAٹض“Œ•گژmپj
پ@‚ج–؛‚إپAپ@“cژةˆç‚؟‚إ‚ ‚èپAپ@‹‚ج“sپi‚ف‚₱پjڈoگg‚جŒ¹
پ@ژپ‚ج‹MŒِژq‚ة–£—ح‚ًٹ´‚¶پAپ@“–ژ—¬گlپi‚é‚ة‚ٌپj‚إ‚ ‚ء
پ@‚½Œ¹ —ٹ’©پi‚P‚P‚S‚Vپ`‚X‚X”Nپj‚حپA‚à‚جژâپi‚³‚رپj‚µ‚پAپ@–k
پ@ڈًگژq‚ھچâ“Œ•گژmپiٹض“Œ•گژmپj‚ج–؛‚إپAپ@ڈں‹Cپi‚©‚؟‚«پj
پ@‚إ—ٹ‚èچb”م‚ج‚ ‚éڈ—گ«‚ئٹ´‚¶پAپ@“ٌگl ‚ح—ِ‚ة—ژ‚؟‚½‚ئ
پ@گ„‘ھ‚³‚ê‚éپB
پ@پ@پ@پ@–kڈًگژq‚ج•ƒپE–kڈًژگ‚حپAپ@ˆة“¤چ‘پi‚¢‚¸
پ@پ@‚ج‚‚ةپAپ@گأ‰ھŒ§“Œ•”‚جˆة“¤”¼“‡پj‚جچف’،ٹ¯گlپ@
پ@پ@پi‚´‚¢‚؟‚ه‚¤‚©‚ٌ‚¶‚ٌپA’n•û–ًگlپj‚إپAپ@‚P‚P‚T‚X”N
پ@پ@‚ج•½ژ،‚ج—گپi‚ض‚¢‚¶‚ج‚ç‚ٌپjŒمپA پ@”sپi‚â‚شپj‚ê
پ@پ@ˆة“¤‚ة—¬‚³‚ꂽپAŒ¹—ٹ’©‚جٹؤژ‹–ًپ@‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@–kڈًژگ‚ھپA‘ه”ش–ًپi‚¨‚¨‚خ‚ٌ‚â‚پj‚إپAچف
پ@پ@‹’†پi‹“s‘طچف’†پj‚ج—¯ژç‚جٹش‚ةپAپ@–kڈًگژq
پ@پ@‚حپAŒ¹—ٹ’©‚ئ—ِ’‡‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚P‚V‚V”Nپiژ،ڈ³Œ³”Nپj‚ةپAŒ¹—ٹ’©‚ئ–kڈًگژq
پ@پ@‚جٹضŒW‚ً’m‚ء‚½–kڈًژگ‚حپAپ@ˆةگ¨•½ژپ‚ض‚ج
پ@پ@–d”½پi‚ق‚ظ‚ٌپj‚ئ‹^‚ي‚ê‚é‚ج‚ً‹°‚êپAپ@–kڈًگژq
پ@پ@‚ًˆة“¤پE–ع‘مپi‚à‚‚¾‚¢پA‘مٹ¯پj‚جژR–طŒ“—²‚ئچ¥
پ@پ@‹V‚ًŒ‹‚خ‚¹‚و‚¤پiŒ‹چ¥‚³‚¹‚و‚¤پj‚ئ‚·‚éپBپ@–kڈًگ
پ@پ@ژq‚حپAپ@ژR–طŒ“—²‚ج“@‘î‚ض—`“üپi‚±‚µ‚¢پj‚ꂳ‚¹
پ@پ@‚ç‚ê‚و‚¤‚ئ‚·‚é‚ھپAپ@‰®•~‚ً”²‚¯ڈo‚µپAژR‚ًˆê‚آ
پ@پ@‰z‚¦پAŒ¹—ٹ’©‚جŒ³‚ض‘–‚ء‚½پBپ@‚آ‚ـ‚èپA–kڈًگژq
پ@پ@‚حپAپ@Œ¹—ٹ’©‚ئ‹يپi‚©پj‚¯—ژ‚؟‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@—ٹ’©‚ئگژq‚ج“ٌگl‚حپAˆة“¤ژR‚ة“¦‚°چ‚فپA
پ@پ@ˆة“¤ژRŒ Œ»پi‚¢‚¸‚³‚ٌ‚²‚ٌ‚°‚ٌپAˆة“¤ژRگ_ژذپj
پ@پ@‚ة“½پi‚©‚‚ـپj‚ي‚ꂽپBپ@ˆة“¤ژR‚حپA‘m•؛پi‚»‚¤‚ض
پ@پ@‚¢پj‚ج—ح‚ھ‹‚پA–kڈًژپ‚â–ع‘م‚جژR–ط‚àژè‚ًڈo
پ@پ@‚¹‚ب‚©‚ء‚½‚½‚ك‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@‚»‚جŒمپA‚ـ‚à‚ب‚پA–kڈًژگ‚حپA‚Qگl‚جچ¥‹V
پ@پ@پiŒ‹چ¥پj‚ً”F‚كپAپ@–kڈًژپ‚حپAپ@Œ¹—ٹ’©‚جڈd—v‚ب
پ@پ@Œم‰‡ژز‚ئ‚ب‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@‚P‚P‚W‚O”Nپiژ،ڈ³‚S”Nپj‚ةپAˆبگm‰¤پi‚à‚؟‚ذ‚ئ‚¨
پ@پ@‚¤پAŒم”’‰حڈمچc‚جچcژqپi‚ف‚±پjپj‚ھپ@Œ¹ —ٹگپi‚ف
پ@پ@‚ب‚à‚ئ‚ج ‚و‚è‚ـ‚³پj‚ئ•½ژپ‘إ“|‚ج‹“•؛‚ً‚µژ¸”s
پ@پ@‚·‚é‚ئپA پ@Œ¹—ٹ’©‚جگg‚ة‚àٹë‹@‚ھ”—‚è‹“•؛‚¹‚´
پ@پ@‚é‚ً“¾‚ب‚‚ب‚èپAپ@Œ¹—ٹ’©‚ح–kڈًژگ‚ج—ح‚ً‚©‚è
پ@پ@‚ؤپA‹“•؛‚·‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ،پ@–LگbڈG‹g‚ئ‚ث‚ثپi‚¨‚ثپjپB
پ@پ@پ@پ@“،‹gکYپi‚ئ‚¤‚«‚؟‚낤پAŒم‚ج–LگbڈG‹gپA“ْ–{ˆê‚جڈoگ¢
پ@’jپA‚P‚T‚R‚Uپ`‚X‚W”Nپj‚حپAپ@”_–¯ڈoگg‚إپAپ@گD“cگM’·‚جژG
پ@•؛پi‚¼‚¤‚ذ‚ه‚¤پj‚إپAپ@‚ث‚ثپi‚¨‚ثپA‚P‚T‚S‚Q”NپHپ`‚P‚U‚Q‚S”Nپj
پ@‚حپAپ@گD“cگM’·‚ج‰ئگb‚جگَ–ى–”‰E‰q–ه’·ڈں‚ج—{ڈ—‚إ‚
پ@‚èپAپ@”ِ’£پi‚¨‚ي‚èپAˆ¤’mŒ§گ¼•”پj‚إپA’m‚èچ‡‚¢پAپ@“،‹gکY
پ@پi–LگbڈG‹gپj‚حپAپ@“‚«ژز‚ج‚¨‚ثپi‚ث‚ثپj‚ھ‹C‚ة“ü‚èپA‚ث‚ث
پ@پi‚¨‚ثپj‚حپAپ@‚¦‚½‚¢‚ج’m‚ê‚ب‚¢“،‹gکYپi–LگbڈG‹gپj‚ة–£
پ@—ح‚ًٹ´‚¶پAپ@“ٌگl‚ح—ِ‚ة—ژ‚؟‚½‚ئگ„‘ھ‚³‚ê‚éپBپ@پ@
پ@پ@پ@پ@‚P‚T‚U‚P”Nپi‰iک\‚S”Nپj‚WŒژ‚ةپA“،‹gکYپi–LگbڈG‹gپj‚ئ‚ث
پ@‚ثپi‚¨‚ثپj‚ج“ٌگl‚حپAچ¥‹V‚ًŒ‹‚شپBپ@“–ژڈG‹g‚و‚èگg•ھ‚ج
پ@چ‚‚©‚ء‚½پAپu‚¨‚ثپi‚ث‚ثپjپv‚جژہ‰ئپEگ™Œ´‰ئ‚جپu‚ث‚ثپi‚¨‚ثپjپv
پ@‚جژہ•êپE’©“ْ‚ج”½‘خ‚ً‰ں‚µگط‚èپA“ٌگl‚حپAچ¥‹V‚ًŒ‹‚ٌ‚¾
پ@پiŒ‹چ¥‚µ‚½پjپBپ@“،‹gکYپiڈG‹gپj‚ئ‚ث‚ثپi‚¨‚ثپj‚جƒJƒbƒvƒ‹‚حپA
پ@–ىچ‡پ@پi‚₲‚¤پA‰ئ’·‚âگe‚جڈ³‘ّ‚ب‚µ‚ةڈںژè‚ةŒ‹چ¥‚·‚邱
پ@‚ئپjپ@‚إ‚ ‚èپAپ@چ¥‹V‚ج‹Vژ®پiŒ‹چ¥ژ®پj‚ًچs‚ء‚½‚©‚ا‚¤‚©‚حپA
پ@•s–¾‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{پiŒأ‘مپ`چ]Œثژ‘مپj‚إ‚حپAپ@ڈم‘wٹK‘w‚¨‚¢‚ؤ
پ@‚حپAژ©—R—ِˆ¤‚حپAڈ‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جپAŒµٹi‚ب‰ئ•ƒ’·گ§ژذ‰ïپEگg•ھگ§ژذ‰ï‚إ
پ@‚حپAپ@ڈم‘wٹK‘w‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپA‰ئ’·‚ـ‚½‚حگe‚ج‹–‰آپEڈ³‘ّ‚ب
پ@‚µ‚ةپAڈ—گ«‚حپAŒ´‘¥‚ئ‚µ‚ؤپA’jگ«‚ئŒًچغ‚إ‚«‚¸پA‚ـ‚½پAچ¥‹V
پ@پiŒ‹چ¥پj‚ج‘ٹژè‚àپAŒ´‘¥‚ئ‚µ‚ؤپA‰ئ’·‚ـ‚½‚حگe‚ھŒˆ‚ك‚½پB
پ@پ@پ@پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚إ‚حپAژ©—R—ِˆ¤‚حپA–ىچ‡پi‚₲‚¤پj‚ئŒؤ‚خ
پ@‚êپAڈم‘wٹK‘w‚جژز‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚حپA–]‚ـ‚µ‚‚ب‚¢‚à‚ج‚ئ‚³‚ꂽپB
پ@پ@پ@ڈم‘wٹK‘w‚ج’jڈ—‚حپAŒ´‘¥‚ئ‚µ‚ؤپA‰ئ’·‚ـ‚½‚حگe‚ج‹–‰آپE
پ@ڈ³‘ّ‚ً“¾‚ؤپAŒًچغ‚µ‚½‚èپAچ¥‹VپiŒ‹چ¥پj‚ًŒ‹‚ٌ‚¾‚肵‚½پB
پ@
پ@
پôپ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جڈم‘wٹK‘w‚جژ©—R—ِˆ¤
پ@‚ھ•`‚©‚ê‚ؤ‚¢‚éپA‹»–،گ[‚¢ ٹضکAƒhƒ‰ƒ}پA
پ@پ@‰f‰وپAƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پB
پ@
پڑپ@ژ©—R—ِˆ¤‚ھ•`‚©‚ê‚ؤ‚¢‚éپA‹»–،گ[‚¢
پ@پ@پ@ƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پBپ@
پ@
پ،پ@—ًژj”éکbƒqƒXƒgƒٹƒAپ@
پ@پ@پwپ@ˆ¤‚ ‚éƒeƒ“ƒJ•گژm‚جگ¢‚ً‚ذ‚ç‚
پ@پ@پ@–kڈًگژqپEŒ¹—ٹ’© •v•w‚جٹv–½پ`پ@پx پB
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚O‚X”N‚SŒژ1“ْپE–{•ْ‘—پE
پ@پ@پ@پ@ƒeƒŒƒrپEƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[”ش‘gپE‘و‚P‰ٌپjپB
پœپ@–kڈًگژq‚ئŒ¹ —ٹ’©‚ھ’m‚èچ‡‚ء‚½“–ژ‚ج
پ@پ@پ@—lژq‚ھڈع‚µ‚•`‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@
پڑپ@ژ©—R—ِˆ¤ ‚ھ•`‚©‚ê‚ؤ‚¢‚éپA‹»–،
پ@پ@ گ[‚¢ٹضکAƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپBپ@
پœپ@پi’چˆسپjپ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAƒtƒBƒNƒVƒ‡ƒ“پ@‚إ‚·پBپ@
پ@پ@—ًژj‚جƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپ@‚حپAژjژہپi—ًژjڈم‚جژ–ژہپjپ@
پ@پ@‚ئپ@‰ث‹َ‚جڈo—ˆژ–پ@‚ھچ¬‚¶‚ء‚ؤ•`‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپ@
پ@پ@‚ـ‚½پAپ@Œ»‘م•—‚ةƒAƒŒƒ“ƒW‚µ‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚·پB
پ@
پ،پ@پwپ@•½گ´گ·پ@پi‚½‚¢‚ç‚ج‚«‚و‚à‚èپjپ@پx پBپ@
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚P‚Q”N‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پjپB
پ،پ@•½ˆہژ‘م––ٹْ‚ً•`‚¢‚½ƒhƒ‰ƒ}‚إپA•½ˆہ
پ@پ@پ@ژ‘م––ٹْ‚ةٹˆ–ô‚µ‚½گl•¨پA“–ژ‚جژ
پ@پ@پ@‘مڈَ‹µ‚ب‚ا‚ً•`‚پB
پ،پ@•½گ´گ·‚جگ¶ٹU‚ً•`‚پB
پ@
پœپ@–kڈًگژq‚ً‰‰‚¶‚½ڈ——D–¼پ@پFپ@ˆاپ@پi‚ ‚ٌپjپB
پœپ@•½پ@گ´گ·‚ً‰‰‚¶‚é”o—D–¼پ@پFپ@ڈ¼ژRپ@ƒPƒ“ƒCƒ`پB
پ@
پ،پ@پwپ@‹`Œoپ@پi‚و‚µ‚آ‚ثپjپ@پx پBپ@
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚O‚T”N‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پjپB
پ،پ@Œأ‘م“ْ–{‚ج•½ˆہژ‘م––ٹْ‚ً•`‚¢‚½ƒhƒ‰ƒ}
پ@پ@‚إ‚ ‚èپAپ@•½ˆہژ‘م––ٹْ‚جگFپX‚ب•گژm‚ج
پ@پ@ٹˆ–ô‚ً•`‚¢‚½ƒhƒ‰ƒ}پB
پ،پ@Œ¹ ‹`Œoپi‚ف‚ب‚à‚ئ‚ج‚و‚µ‚آ‚ثپj‚جگ¶ٹU‚ً
پ@پ@•`‚¢‚½ƒhƒ‰ƒ}پB
پ،پ@گأŒن‘O‚ئŒ¹ ‹`Œo‚ھ’m‚èچ‡‚ء‚½“–ژ‚ج
پ@پ@—lژq‚ھڈع‚µ‚•`‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@
پœپ@گأŒن‘Oپ@پi‚µ‚¸‚©‚²‚؛‚ٌپj‚ً‰‰‚¶‚½ڈ——D–¼پFپ@
پ@پ@گخŒ´ ‚³‚ئ‚فپB
پœپ@Œ¹ ‹`Œo ‚ً‰‰‚¶‚½”o—D–¼پ@پFپ@
پ@پ@‘ê‘ٍپ@ڈG–¾پ@پi‚½‚«‚´‚يپ@‚ذ‚إ‚ ‚«پjپB
پ@
پ،پ@پwپ@”JپXپ`‚¨‚ٌ‚ب‘¾چ}‹Lپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚ث‚ثپ@‚¨‚ٌ‚ب‚½‚¢‚±‚¤‚«پjپ@پx پBپ@
پ@پ@پ@پ@پiƒeƒŒƒr“Œ‹پE‚Q‚O‚O‚X”Nگ§چىƒeƒŒƒr
پ@پ@پ@پ@ƒhƒ‰ƒ}پjپBپ@
پ،پ@ڈG‹g‚ئ‚ث‚ثپi‚¨‚ثپj‚ئ‚جژ©—R—ِˆ¤‚ھ•`‚©
پ@پ@‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
پ@
پœپ@‚ث‚ثپi‚¨‚ثپj‚ً‰‰‚¶‚½”o—D–¼پ@پFپ@’‡ٹش —R‹IŒbپB
پœپ@–Lگb ڈG‹g‚ً‰‰‚¶‚½”o—D–¼پ@پFپ@ژsگى ‹Tژ،کYپB
پœپ@‚ث‚ثپi‚¨‚ثپj‚ئ“،‹gکY‚ھ’m‚èچ‡‚ء‚½“–ژ‚ج—lژq
پ@پ@‚ھڈع‚µ‚•`‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@گأŒن‘Oپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚¸‚©‚²‚؛‚ٌپjپB
پ@
پ،پ@گأŒن‘OپBپ@
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@گأŒن‘Oپ@پi‚µ‚¸‚©‚²‚؛‚ٌپjپB
پœپ@•ت–¼پFپ@گأپ@پi‚µ‚¸‚©پjپB
پ،پ@گ¶–v”N•sڈعپB
پ،پ@•‘پi‚ـ‚¢پj‚ج–¼ژèپBپ@”üگlپB
پ،پ@Œ¹ ‹`Œo‚ج’ˆ¤‚·‚鑤ژ؛•vگlپB
پ@پ@Œ¹پ@‹`Œo‚ئگأ‚حژ©—R—ِˆ¤‚إچ¥‹V‚ًŒ‹‚شپB
پ،پ@”’”ڈژqپi‚µ‚ç‚ر‚ه‚¤‚µپj‚إپA•‘پi‚ـ‚¢پj‚ج–¼ژèپB
پ،پ@گ¶•ê‚حپA”’”ڈژq‚إ•‘پi‚ـ‚¢پj‚ج–¼ژè‚جپAˆé‘Tژtپ@پi‚¢‚»
پ@‚ج‚؛‚ٌ‚¶پAگ¶–v”N•sڈعپA•ت–¼پFâE–ى‘T“ٍپjپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ٹ™‘q‚ج’ك‰ھ”ھ”¦‹{‚إپAŒ¹—ٹ’©پA–kڈًگژqپAŒ¹—ٹ’©‚ج
پ@‰ئگb‚ج‘O‚إپAپ@ژں‚ج‚و‚¤‚بŒ¹ ‹`Œo‚ً•çپi‚µ‚½پj‚¤‰ج‚ً‰S
پ@پi‚¤‚½پj‚¢‚ب‚ھ‚çپAگأپi‚µ‚¸‚©پj‚حپA•‘پi‚ـپj‚ء‚½پB
پ@پwپ@‚µ‚أ‚₵‚أپ@‚µ‚أ‚ج‚ً‚¾‚ـ‚«‚‚è•ش‚µپ@گج‚ًچ،‚ةپ@‚ب‚·
پ@پ@‚و‚µ‚à‚ھ‚بپ@پx
پ@پwپ@‹g–ىژRپ@•ô‚ج”’گلپ@‚س‚ف‚ي‚¯‚ؤپ@“ü‚è‚ة‚µگl‚جپ@گص‚¼
پ@پ@—ِ‚µ‚«پ@پx
پ@
پ،پ@Œ¹‹`Œo‚ج‘¤ژ؛•vگl‚ة‚حپA•‘‚ج–¼ژè‚جگأŒن‘Oپi‚µ‚¸‚©
پ@‚²‚؛‚ٌپj‚ھ‚¢‚½پBپ@Œ¹—ٹ’©‚ئ‘خ—§‚µ‹پi“sپj‚©‚ç—ژ‚؟‚ج‚ر
پ@‚é‹`Œo‚ئˆêڈڈ‚ةپAگأŒن‘O‚حپA“¦–S‚·‚é‚ھپA‹g–ى‚إ‹`Œo‚ئ
پ@ˆêژ•ت‚êپA‹پi“sپj‚ض–ك‚é“r’†•ك‚炦‚ç‚êپAپ@‚P‚P‚W‚T”N
پ@پi•¶ژ،Œ³”Nپj‚P‚QŒژ‚ةپAٹ™‘q•û‚ةˆّ‚«“n‚³‚ê‚éپ@پiپuŒلچب
پ@‹¾پvپi‚ ‚أ‚ـ‚©‚ھ‚فپAٹ™‘q–‹•{‚جŒِژ®‚ج—ًژjڈ‘پj‚إ‚حپjپB
پ@پ@پ@گأپi‚µ‚¸‚©پj‚حپA‚P‚P‚W‚U”Nپi•¶ژ،‚Q”Nپj‚RŒژ‚ةپAگأ‚ج•êپE
پ@ˆé‘Tژtپi‚¢‚»‚ج‚؛‚ٌ‚¶پj‚ئ‹¤‚ةپAٹ™‘q‚ة‘—‚ç‚ê‚éپBپ@‚P‚P
پ@‚W‚U”Nپi•¶ژ،‚Q”Nپj‚SŒژ‚ةپAٹ™‘q‚ج’ك‰ھ”ھ”¦‹{‚إپA”’”ڈژq
پ@پi‚µ‚ç‚ر‚ه‚¤‚µپj‚ج•‘پi‚ـ‚¢پj‚ً‚ـ‚¤‚و‚¤‚ةŒ¹—ٹ’©‚ة–½‚¶‚ç
پ@‚êپAپ@Œ¹—ٹ’©پA–kڈًگ³ژqپA Œ¹—ٹ’©‚ج‰ئگb‚ج‘O‚إپA‹`Œo‚ً
پ@•çپi‚µ‚½پj‚¤‰ج‚ً‚¤‚½‚¢پA•‘‚ً”âکIپi‚ذ‚낤پj‚·‚éپBپ@‚»‚جژپA
پ@گأپi‚µ‚¸‚©پj‚حپAپ@Œ¹‹`Œo‚جژq‚ً‰ù”D‚µ‚ؤ‚¢‚½ پiپuŒلچب‹¾پv
پ@‚إ‚حپjپB
پ@پ@پ@پ@Œم‚ةپA‚P‚P‚W‚U”Nپi•¶ژ،‚Q”Nپj‰[پi‚¤‚邤پj‚VŒژ‚ةپAگأ‚حپA
پ@‹`Œo‚جژq‚ًڈoژY‚·‚é‚ھپA’jژq‚إ‚ ‚ء‚½‚½‚كپAژq‚حٹ™‘q•û
پ@‚ةژE‚³‚ê‚éپBپ@ڈoژYŒمٹش‚à‚ب‚ٹ™‘q‚ج—R”نƒ–•lپi‚ن‚¢‚ھ‚ح
پ@‚ـپj‚ةˆâٹü‚³‚ꂽپ@پiŒلچب‹¾‚إ‚حپjپBپ@
پ@پ@پ@‚P‚P‚W‚U”Nپi•¶ژ،‚Q”Nپj‚XŒژ‚ةپAگأ‚ئˆé‘Tژt‚ح پA‹پi“sپj
پ@‚ة‹A‚³‚ꂽپBپ@پ@گأ‚ئˆé‘T ژt‚ھپAٹ™‘q‚ً—£‚ê‚éژ‚ةپAˆ£
پ@پi‚ ‚يپj‚ê‚ٌ‚¾–kڈًگژq‚ئ‘ه•Pپi‚¨‚¨‚ذ‚كپA—ٹ’©‚ئگژq
پ@‚ئ‚جٹش‚ج–؛پj‚حپAڈd•َ‚ًژ‚½‚¹پAŒ©‘—‚ء‚½ پ@پiپuŒلچب‹¾پv‚إ
پ@‚حپjپBپ@
پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@پ@پ@‚»‚جŒمپAگأپi‚µ‚¸‚©پj‚حپAپ@ˆé‘Tژt‚ج—¢ پ@پi“ق—اŒ§‘ه
پ@کaچ‚“cژsâE–ىپjپ@‚ةگg‚ًٹٌ‚¹‚½‚ئ‚à“`‚¦‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
پ@پ@پ@پ@گأ‚ج•‘پi‚µ‚¸‚©‚ج‚ـ‚¢پj‚جڈê–ت‚حپAƒhƒ‰ƒ}پE‰f‰و“™‚ج
پ@ƒtƒBƒNƒVƒ‡ƒ“‚إ‚حپAگأپi‚µ‚¸‚©پj‚ج”ك‚µ‚ف‚ً‹’²‚·‚邽‚كپA
پ@ژq‹ں‚ھژE‚³‚ꂽ‚ ‚ئپA•‘‚ً”âکI‚·‚é‚ئ‚¢‚¤گف’è‚ة‚ب‚ء‚ؤ
پ@‚¢‚邱‚ئ‚ھ‘½‚¢پB
پ@
پ،پ@گأ‚ئŒ¹‹`Œo‚ج‚Qگl‚حپA‚P‚P‚W‚T”Nچ پAپ@‹پ@پi‹“s’†‹
پ@‹وپi‚ب‚©‚¬‚ه‚¤‚پjپj‚إپA’m‚èچ‡‚¢پi—ِ‚ة—ژ‚؟پjپAگأ‚حپA‹`
پ@Œo‚ج—ِگlپiŒم‚ة‘¤ژ؛•vگlپj‚ئ‚ب‚ء‚½‚ئŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
پ@
پ،پ@گأŒن‘Oپ@پi‚µ‚¸‚©‚²‚؛‚ٌپjپ@‚حپAپ@•ت–¼‚حپAپ@گأپi‚µ‚¸
پ@‚©پj‚إپAپ@گ¶–v”N•sڈعپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@گأŒن‘Oپ@‚حپAپ@Œ¹ ‹`Œo‚ج’ˆ¤‚·‚鑤ژ؛•vگl پ@‚إپA
پ@”’”ڈژqپi‚µ‚ç‚ر‚ه‚¤‚µپj‚إپA•‘پi‚ـ‚¢پj‚ج–¼ژè پ@‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@پ@پ@گأŒن‘O‚جپAگ¶•ê‚حپAپ@”’”ڈژq‚إ•‘پi‚ـ‚¢پj‚ج–¼ژè‚جپA
پ@ˆé‘Tژtپ@پi‚¢‚»‚ج‚؛‚ٌ‚¶پAگ¶–v”N•sڈعپj‚ئŒ¾‚¤پBپ@•ت–¼
پ@‚حپAپ@âE–ى‘T“ٍپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@
پôپôپ@گأŒن‘Oپ@‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢ٹضکAƒhƒ‰
پ@پ@پ@پ@ƒ}پA‰f‰وپAƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پBپ@
پ@
پڑپ@گأŒن‘Oپ@‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢ٹضکAƒhƒLƒ…
پ@پ@پ@ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پBپ@
پ@
پ،پ@—ًژj”éکbƒqƒXƒgƒٹƒAپ@پwپ@ٹC‚ج‰¤ژزپ@•½ژپ
پ@پ@ ‚ً‘إ‚؟“|‚¹پ@پ`ŒˆگيپI’dƒm‰Yپ@‹`Œo‚ج‹ê
پ@ ”Yپ`پ@پxپBپ@
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚P‚Q”Nپi‚g‚Q‚S”Nپj‚PŒژ‚P‚W“ْپE
پ@پ@پ@–{•ْ‘—پEƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[”ش‘gپjپB
پ@
پ،پ@—ًژj”éکbƒqƒXƒgƒٹƒAپ@پwپ@Œ¹‹`Œoپ@‚‰‚ژپ@‚”‚ˆ‚…
پ@پ@پ@‚c‚پ‚’‚‹پ@پ`“`گà‚جƒqپ[ƒچپ[‚حˆإ‚©‚çگ¶‚ـ‚ê
پ@پ@پ@‚½پ`پ@پxپBپ@
پ@پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚P‚O”N‚XŒژ1“ْپE–{•ْ‘—پEƒhƒL
پ@پ@پ@پ@پ@ƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[”ش‘gپE‘و‚S‚X‰ٌپjپB
پ@
پڑپ@گأŒن‘Oپ@‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢ٹضکAƒhƒ‰ƒ}پA
پ@پ@پ@‰f‰وپBپ@
پœپ@پi’چˆسپjپ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAƒtƒBƒNƒVƒ‡ƒ“پ@‚إ‚·پBپ@—ًژj‚ج
پ@پ@پ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAژjژہپi—ًژjڈم‚جژ–ژہپjپ@‚ئپ@‰ث‹َ‚جڈo
پ@پ@پ@—ˆژ–‚ھپ@چ¬‚¶‚ء‚ؤ•`‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپ@‚ـ‚½پAپ@Œ»‘م•—‚ة
پ@پ@پ@ƒAƒŒƒ“ƒW‚µ‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚·پB
پ@
پ،پ@پwپ@‹`Œoپ@پi‚و‚µ‚آ‚ثپjپ@پx پB
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚O‚T”N‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پjپB
پœپ@Œأ‘م“ْ–{‚ج•½ˆہژ‘م––ٹْ‚ً•`‚¢‚½ƒhƒ‰ƒ}‚إپAپ@Œ¹ ‹`Œoپ@
پ@پi‚ف‚ب‚à‚ئ‚ج‚و‚µ‚آ‚ثپj‚جگ¶ٹUپ@‚âپA •½ˆہژ‘م––ٹْ‚جگFپX
پ@‚ب•گژm‚جٹˆ–ô‚ً•`‚¢‚½ƒhƒ‰ƒ}پ@‚إ‚·پB
پœپ@گأŒن‘Oپ@پi‚µ‚¸‚©‚²‚؛‚ٌپj‚ً‰‰‚¶‚½ڈ——D–¼پ@پFپ@گخŒ´ ‚³‚ئ‚فپB
پ@
پœپ@گأ‚ج•êپEˆé‘Tژt‚ً‰‰‚¶‚½ڈ——D–¼پ@پFپ@پ@ڈ°“ˆ ‰ہژqپB
پœپ@Œ¹ ‹`Œo ‚ً‰‰‚¶‚½”o—D–¼پ@پFپ@‘ê‘ٍپ@ڈG–¾پ@پi‚½‚«‚´‚يپ@‚ذ
پ@‚إ‚ ‚«پjپB
پ@پ@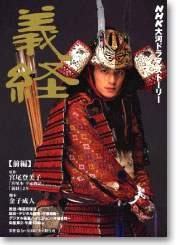
پ@پ@پiƒhƒ‰ƒ}پu‹`ŒoپvٹضکA‚جڈ‘گذ‚ج”ج‘£‚ج‚o‚qƒtƒHƒgپj
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ڈمچcپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پjپB
پ@
پ،پ@ڈمچcپBپ@
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ڈمچcپ@پi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پjپB
پœپ@•ت–¼پ@پFپ@‰@پ@پi‚¢‚ٌپjپB
پ،پ@ڈمچc پi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پjپ@‚ئ‚حپAپ@ڈ÷ˆت‚µ‚½پi‘قˆت‚µ‚½پj“Vچc
پ@پiŒ³“VچcپjپB
پ،پ@–@چcپi‚ظ‚¤‚¨‚¤پjپ@‚ئ‚حپAپ@•§–ه‚ة“ü‚ء‚½ڈمچcپ@‚إ‚ ‚éپB
پ،پ@پi—لپjپ@”’‰حڈمچcپA’¹‰HڈمچcپAŒم”’‰حڈمچcپAŒم’¹‰Hڈم
پ@چcپAŒمگ…”ِڈمچcپ@‚ب‚اپB
پ،پ@‰@گپ@‚ئ‚حپAپ@ڈمچcپ@پi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پAŒ³“Vچcپjپ@‚ھپAپ@’©’ى
پ@‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚éگژ،Œ`‘شپB
پ،پ@ڈمچcپ@پi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پAˆّ‘ق‚µ‚½“Vچcپj‚حپAپ@‰@’،‚ًژg‚ء‚ؤپA
پ،پ@ڈمچcپ@‚حپAپ@‰@گéپi‚¢‚ٌ‚؛‚ٌپjپAپ@‰@’،‰؛•¶پi‚¢‚ٌ‚ج‚؟
پ@‚ه‚¤‚‚¾‚µ‚ش‚فپjپ@‚ب‚ا‚ة‚و‚ء‚ؤپA’ت’B‚ًڈo‚µ‚½پB
پ@
پ@
پ،پ@ڈمچc پi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پjپ@‚ئ‚حپAپ@ڈ÷ˆت‚µ‚½پi‘قˆت‚µ‚½پj“Vچc
پ@پiŒ³“Vچcپj‚إپA•ت–¼‚إپA‰@پi‚¢‚ٌپj‚ئ‚àŒ¾‚¤پBپ@پ@–@چcپi‚ظ‚¤
پ@‚¨‚¤پj‚ئ‚حپAپ@•§–ه‚ة“ü‚ء‚½ڈمچcپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@‰@گپ@‚ئ‚حپA“Vچc‚ًŒمŒ©پi‚±‚¤‚¯‚ٌپj‚µ‚ب‚ھ‚ç’©’ى‚جژہ
پ@Œ ‚ً‚ة‚¬‚éگژ،Œ`‘شپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@“ْ–{‚إ‚حپAپ@گغٹضگژ،پ@پi‚P‚Oگ¢‹IŒم”¼پ`‚P‚Pگ¢‹IŒم
پ@”¼پj‚ھپAگٹ‚¦‚ؤپAپ@‰@گگژ،پ@پi‚P‚Pگ¢‹IŒم”¼پ`‚P‚Qگ¢‹IŒم
پ@”¼پjپ@‚ھپAپ@ژn‚ـ‚éپB
پ،پ@‚P‚O‚W‚U”N‚و‚èپA‰@گپi‚P‚O‚W‚Uپ`‚P‚P‚T‚U”Nپj‚ھٹJژn‚³‚êپAپ@
پ@ڈمچc‚ھپA’©’ى‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚èپAپ@”’‰حڈمچc‚â’¹‰Hڈمچcپ@‚ھپ@
پ@“ْ–{‚جگژ،‚جژہŒ ‚ًژ‚؟پA“ْ–{‚ًژہژ؟“I‚ةژx”z‚µ‚½پB
پ@پ@پ@‚µ‚©‚µپA•½ژ،‚ج—گپi‚P‚P‚T‚X”NپjˆبŒمپAپ@Œ —حپi“ْ–{‚ًژx
پ@”z‚·‚éژہŒ پj‚حگٹ‚¦‚½‚ھپi“ْ–{‚جگژ،‚جژہŒ ‚حژ‚½‚ب‚©
پ@‚ء‚½‚ھپjپAپ@‚»‚جŒمپA’f‘±“I‚ةپAڈمچc‚ھ’©’ى‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚éپA
پ@‰@گ‚حپAپ@چ]Œث––ٹْ‚ج‚P‚W‚S‚O”N‚ـ‚إپAچs‚ي‚ꂽپB
پ@
پ،پ@‰@گ‚حپAڈمچcپi‘قˆت‚µ‚½“Vچcپj‚ھ“Vچc‚ة‘م‚ي‚ء‚ؤ
پ@’©’ى‚جگ–±‚ًچs‚¤‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@“Vچc‚ھپAڈمچc‚جژqپA‚ـ‚½‚حڈمچc‚ج‘·‚ب‚ا‚جڈêچ‡پA
پ@‰@گ‚ًچs‚¤‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ،پ@“`““I‚ب“Vچc‚ئ‚¢‚¤’nˆت‚حپA—lپX‚ب–ٌ‘©ژ–‚ھ‚آ‚¢
پ@‚ؤ‰ٌ‚èپAپ@گV‚µ‚¢ژ‘م‚ج—¬‚ê‚ة‘خ‰‚µ‚ة‚‚¢—lپX‚ب‚±
پ@‚ئ‚ھ‹N‚±‚éپBپ@‚»‚±‚إپA“Vچc‚حپA‘قˆت‚µ‚ؤپAڈمچc‚ئ‚¢‚¤
پ@ژ©—R‚ب—§ڈê‚ة—§‚؟پAگ¢‚ج’†‚ج“®‚«‚ة‘¦‰‚·‚éگژ،‚ً
پ@چs‚¨‚¤‚ئ‚µ‚½پB
پ@
پ،پ@ڈمچcپ@پi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پAˆّ‘ق‚µ‚½“Vچcپj‚حپAپ@‰@’،‚ًژg‚ء‚ؤپA
پ@پ@پ@پ@‰@’،‚ئ‚حپAڈمچcپ@پi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پAˆّ‘ق‚µ‚½“Vچcپj‚جژ–
پ@پ@–±‹@ٹض‚إپAپ@‰@گژ‚حپAگ–±‹@ٹض‚ئ‚ب‚éپB
پ@پ@پ@پ@‰@’،‚جگEˆُ‚ھپAپ@‰@ژiپi‚¢‚ٌ‚µپj‚إ‚ ‚éپBپ@‰@’،‚ة
پ@‚¨‚¢‚ؤپAڈمچc‚جژ––±پAگ–±‚ًچs‚ء‚½ٹ¯گl‚إ‚ ‚éپB
پ@•ت“–پi‚ׂء‚ئ‚¤پjپA”N—aپi‚ث‚ٌ‚وپjپA”»ٹ¯‘مپAژه“T‘مپA
پ@–k–ت‚ج•گژmپ@‚ب‚ا‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@‰@گéپ@‚ئپ@‰@’،‰؛•¶پB
پœپ@‰@گéپ@پi‚¢‚ٌ‚؛‚ٌپj‚حپAپ@ڈمچcپi= ‰@پj‚ج–½—ك‚ً‰؛’B
پ@‚·‚镶ڈ‘پ@‚إ‚ ‚éپBپ@‰@ژiپi‚¢‚ٌ‚µپj‚ھپAڈمچc‚ج‹آ‚¹‚ً
پ@•ٍپi‚ظ‚¤پj‚¶‚ؤڈo‚·•ٍڈ‘پi‚ظ‚¤‚µ‚هپj‚جŒ`ژ®‚ً‚ئ‚éپB
پ@پ@پ@‰@’،‰؛•¶پ@پi‚¢‚ٌ‚ج‚؟‚ه‚¤‚‚¾‚µ‚ش‚فپjپ@‚حپA‰@’،
پ@پi‚¢‚ٌ‚ج‚؟‚ه‚¤پj‚©‚çڈo‚³‚ê‚éŒِ•¶ڈ‘پ@‚إپAپ@‰@گéپi‚¢
پ@‚ٌ‚؛‚ٌپj‚و‚è‚àŒِ“I‚إپAپ@ڈظ’؛پi‚µ‚ه‚¤‚؟‚ه‚پjپAٹ¯•„‚ئ
پ@“¯“™‚جŒّ—ح‚ً—L‚µپAپ@ڈd—v‚بˆس–،‚ً‚à‚ء‚½پB
پ@
پ@
پںپ@ڈمچc‚ئ‰@گ‚ج—لپB
پ،پ@”’‰حڈمچcپi‚µ‚ç‚©‚ي‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پj‚حپA‚P‚O‚W‚U”N‚و‚èپAپ@–x
پ@‰حپi‚ظ‚è‚©‚يپj“VچcپAپ@’¹‰Hپi‚ئ‚خپj“VچcپAپ@گ’“؟پi‚·‚ئ‚پj
پ@“Vچc‚ج‚R‘م‚ة‚ي‚½‚èپA–ٌ‚S‚R”NٹشپA‰@گپi‚P‚O‚W‚U”Nپ`‚P‚P
پ@‚Q‚X”Nپj‚ًچs‚¢پA‚ـ‚½پA“ْ–{‚جگژ،‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚éپB
پ@
پ،پ@’¹‰Hڈمچcپi‚ئ‚خ‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پj‚حپAپ@”’‰حڈمچcپi‚µ‚ç‚©‚ي‚¶
پ@‚ه‚¤‚±‚¤پj‚جژ€ŒمپAپ@گ’“؟پi‚·‚ئ‚پj“VچcپAپ@‹ك‰qپi‚±‚ج‚¦پj
پ@“VچcپAپ@Œم”’‰حپi‚²‚µ‚ç‚©‚يپj“Vچc‚ج‚R‘م‚ة‚ي‚½‚èپA–ٌ‚Q
پ@‚V”NٹشپA‰@گپi‚P‚P‚Q‚Xپ`‚T‚U”Nپj‚ًچs‚¢پA ‚ـ‚½پA“ْ–{‚جگ
پ@ژ،‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚éپB
پ@
پ،پ@Œم”’‰حڈمچcپi‚²‚ئ‚خ‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پj‚حپAپ@‚P‚P‚T‚W”N‚و‚èپA “ٌ
پ@ڈًپi‚ة‚¶‚ه‚¤پj“VچcپAپ@کZڈًپi‚ë‚‚¶‚ه‚¤پj“VچcپAپ@چ‚‘qپi‚½‚©
پ@‚‚çپj“VچcپAپ@ˆہ“؟پi‚ ‚ٌ‚ئ‚پj“VچcپAپ@Œم’¹‰Hپi‚²‚ë‚خپj“V
پ@چc‚ج‚T’©‚ة‚ي‚½‚èپAپ@‰@گپi‚P‚P‚T‚Wپ`‚P‚P‚X‚Q”Nپj‚ًچs‚¤پB
پ@
پ،پ@“Vچc‚جچcˆتŒpڈ³ڈ‡پ@‚حپAپ@”’‰حپi‚µ‚ç‚©‚يپj“Vچcپ@پث
پ@–x‰حپi‚ظ‚è‚©‚يپj“Vچcپ@پثپ@’¹‰Hپi‚ئ‚خپj“Vچcپ@پثپ@گ’“؟
پ@پi‚·‚ئ‚پj“Vچcپ@پثپ@‹ك‰qپi‚±‚ج‚¦پj“Vچcپ@پثپ@Œم”’‰حپi‚²
پ@‚µ‚ç‚©‚يپj“Vچcپ@پثپ@“ٌڈًپi‚ة‚¶‚ه‚¤پj“Vچcپ@پثپ@کZڈًپi‚ë
پ@‚‚¶‚ه‚¤پj“Vچcپ@پثپ@چ‚‘qپi‚½‚©‚‚çپj“Vچcپ@پثپ@ˆہ“؟پi‚
پ@‚ٌ‚ئ‚پj“Vچcپ@پثپ@Œم’¹‰Hپi‚²‚ئ‚خپj“Vچcپ@‚جڈ‡‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@Œمگ…”ِڈمچcپi‚²‚ف‚¸‚ج‚¨‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پj‚حپAپ@‚P‚U‚Q‚X”N‚و
پ@‚èپA–¾گ³پi‚ك‚¢‚µ‚ه‚¤پj“Vچc‚©‚ç—ىŒ³“Vچc‚ـ‚إ‚ج‚S‘م‚ة‚ي
پ@‚½‚èپAپ@‰@گپi‚P‚U‚Q‚X”Nپ`‚P‚U‚W‚O”Nپj‚ًچs‚¤پB
پ@
پ@
پںپ@ڈمچcگژ،پi‰@گگژ،پjپAڈمچcگŒ پi‰@گ
پ@گŒ پjپB
پ،پ@‰@گپ@‚ئ‚حپAپ@ڈمچcپ@پi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پAŒ³“Vچcپjپ@‚ھپA’©’ى
پ@‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚éگژ،Œ`‘شپ@‚إ‚ ‚éپB
پ،پ@‰@گگژ،پiڈمچcگژ،پA‚P‚O‚W‚U”Nچ پ`‚P‚P‚T‚U”Nچ پjپ@‚ئ
پ@‚حپAپ@ڈمچcپi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پAŒ³“Vچcپj‚ھپA’©’ى‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚èپA
پ@‚³‚ç‚ةپA“ْ–{‚جگژ،‚جژہŒ ‚ًژ‚؟پAپ@“ْ–{‚ًژx”z‚µ‚½گ
پ@ژ،Œ`‘ش‚إ‚ ‚éپB
پ،پ@‰@گگŒ پiڈمچcگŒ پA‚P‚O‚W‚U”Nچ پ`‚P‚P‚T‚U”Nچ پjپj‚ئ
پ@‚حپAپ@ڈمچcپi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پAŒ³“Vچcپj‚ھپA’©’ى‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚èپA
پ@‚³‚ç‚ةپA“ْ–{‚جگژ،‚جژہŒ ‚ًژ‚؟پA“ْ–{‚ًژx”z‚µ‚½گ
پ@Œ پ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‰@گگŒ پiڈمچcگŒ پA‚P‚O‚W‚U”Nچ پ`‚P‚P‚T‚U”Nچ پj‚حپA
پ@”’‰حڈمچcپi‰@گ گژ،ٹْپA‚P‚O‚W‚U”Nپ`‚P‚P‚Q‚X”NپjپA’¹‰H
پ@ڈمچcپi‰@گ گژ،ٹْپA‚P‚P‚Q‚X”Nپ`‚P‚P‚T‚U”Nپjپ@‚ھپA’©’ى‚ج
پ@ژہŒ ‚ًˆ¬‚èپA‚³‚ç‚ةپA“ْ–{‚جگژ،‚جژہŒ ‚ًژ‚؟پA“ْ–{‚ً
پ@ژہژ؟“I‚ةژx”z‚µ‚½گŒ پ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ،پ@”’‰حڈمچc‚ھپA‚P‚O‚W‚U”N‚ةپA‰@گ‚ً‘nژn‚µپA‚³‚ç‚ةپA‰@
پ@گگŒ پiڈمچcگŒ پA‚P‚O‚W‚U”Nچ پ`‚P‚P‚T‚U”Nچ پj‚ًژ÷—§
پ@‚·‚éپBپ@
پ@
پ@
پںپ@•½ˆہژ‘م––ٹْ‚ج—ً‘م“Vچcˆê——پB
پ،پ@“Vچc‚جچcˆتŒpڈ³ڈ‡پ@‚حپAژں‚ج’ت‚è‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
‡@پ@”’‰حپi‚µ‚ç‚©‚يپj“Vچcپ@پ@پ@پ@پi’هگmپi‚³‚¾‚ذ‚ئپjگe‰¤پj پث
پ@پ@پi“VچcچفˆتپA‚P‚O‚V‚Q”Nپ`‚P‚O‚W‚U”Nپj
‡Aپ@–x‰حپi‚ظ‚è‚©‚يپj“Vچcپ@پ@پ@پ@پi‘Pگmپi‚½‚é‚ذ‚ئپjگe‰¤پj پثپ@
پ@پ@پi“VچcچفˆتپA‚P‚O‚W‚U”Nپ`‚P‚P‚O‚V”Nپj
‡Bپ@’¹‰Hپi‚ئ‚خپj“Vچcپ@پ@پ@پ@پ@پ@ پiڈ@گmپi‚ق‚ث‚ذ‚ئپjگe‰¤پj پثپ@
پ@پ@پi“VچcچفˆتپA‚P‚P‚O‚V”Nپ`‚P‚P‚Q‚R”Nپj
‡Cپ@گ’“؟پi‚·‚ئ‚پj“Vچcپ@پ@پ@پ@ پ@پiŒ°گmپi‚ ‚«‚ذ‚ئپjگe‰¤پj پث
پ@پ@پi“VچcچفˆتپA‚P‚P‚Q‚R”Nپ`‚P‚P‚S‚P”Nپj
‡Dپ@‹ك‰qپi‚±‚ج‚¦پj“Vچcپ@پ@پ@پ@پ@پi‘جگmپi‚ب‚è‚ذ‚ئپjگe‰¤پjپ@پثپ@
پ@پ@پi“VچcچفˆتپA‚P‚P‚S‚P”Nپ`‚P‚P‚T‚T”Nپj
‡Eپ@Œم”’‰حپi‚²‚µ‚ç‚©‚يپj“Vچcپ@پi‰ëگmپi‚ـ‚³‚ذ‚ئپjگe‰¤پjپ@پثپ@
پ@پ@پi“VچcچفˆتپA‚P‚P‚T‚T”Nپ`‚P‚P‚T‚W”Nپj
‡Fپ@“ٌڈًپi‚ة‚¶‚ه‚¤پj“Vچcپ@پ@پ@پ@ پiژçگmپi‚à‚è‚ذ‚ئپjگe‰¤پjپ@پثپ@
پ@پ@پi“VچcچفˆتپA‚P‚P‚T‚W”Nپ`‚P‚P‚U‚T”Nپj
‡Gپ@کZڈًپi‚ë‚‚¶‚ه‚¤پj“Vچcپ@پ@پ@ پiڈ‡گmپi‚ج‚ش‚ذ‚ئپjگe‰¤پj پثپ@
پ@پ@پi“VچcچفˆتپA‚P‚P‚U‚T”Nپ`‚P‚P‚U‚W”Nپj
‡Hپ@چ‚‘qپi‚½‚©‚‚çپj“Vچcپ@پ@پ@پ@پiŒ›گmپi‚ج‚è‚ذ‚ئپjگe‰¤پj پثپ@
پ@پ@پi“VچcچفˆتپA‚P‚P‚U‚W”Nپ`‚P‚P‚W‚O”Nپj
‡Iپ@ˆہ“؟پi‚ ‚ٌ‚ئ‚پj“Vچcپ@ پ@پiŒ¾گmپi‚ئ‚«‚ذ‚ئپjگe‰¤پjپ@پثپ@
پ@پ@پi“VچcچفˆتپA‚P‚P‚W‚O”Nپ`‚P‚P‚W‚T”Nپj
‡Jپ@Œم’¹‰Hپi‚²‚ئ‚خپj“Vچcپ@پ@پ@پ@پi‘¸گ¬پi‚½‚©‚ذ‚çپjگe‰¤پjپB
پ@پ@پi“VچcچفˆتپA‚P‚P‚W‚R”Nپ`‚P‚P‚X‚W”Nپj
پ@
پ@
پںپ@•½ˆہژ‘مŒمٹْ‚جڈمچc‚ئ‰@گگژ،پi‚P‚O‚W‚U
پ@”Nچ پ`‚P‚P‚T‚U”Nچ پjپB
پ،پ@ڈمچc‚حپAپ@چ‘ژiپiژَ—جپi‚¸‚è‚ه‚¤پjپj‚½‚؟‚ًژxژگ¨—ح‚ة‚ئ
پ@‚肱‚فپAڈمچcپi=‰@پi‚¢‚ٌپjپj‚جŒنڈٹپi‚²‚µ‚هپj‚ة–k–ت‚ج•گژm
پ@پi‚ظ‚‚ك‚ٌ‚ج‚ش‚µپj‚ً‘gگD‚µ‚½‚èپAپ@Œ¹•½‚ج•گژm‚ً‘¤‹ك‚ة
پ@‚·‚é‚ب‚اپAڈمچcپi=‰@پj‚جŒ —ح‚ً‹‰»‚µ‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ،پ@‰@گ‚حپA–@‚âٹµ—ل‚ة‚±‚¾‚ي‚炸‚ةپAڈمچc‚ھپAگژ،‚جژہ
پ@Œ ‚ًگêگ§“I‚ةچsژg‚µ‚½پBپ@پ@
پ@پ@پ@پ@‰@گ‚إ‚حپAڈمچc‚ھپA‰@’،پi‚¢‚ٌ‚ج‚؟‚ه‚¤پj‚ً’u‚«پAڈم
پ@چc‚ج–½—ك‚ً“`‚¦‚é‰@گéپi‚¢‚ٌ‚؛‚ٌپj‹y‚رپAپ@‰@’،‚©‚ç‰؛
پ@پi‚‚¾پj‚³‚ê‚镶ڈ‘‚ج‰@’،‰؛•¶پi‚¢‚ٌ‚ج‚؟‚ه‚¤‚‚¾‚µ‚ش‚فپj
پ@‚ھپAچ‘گˆê”ت‚ةژں‘وپi‚µ‚¾‚¢پj‚ةŒّ—ح‚ًژ‚آ‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@گغٹض‰ئ‚حپAگ¨—ح‚جگٹ‘ق‚ًپAڈمچcپi‰@پj‚ئŒ‹‚ر‚آ‚‚±‚ئ
پ@‚إگ·‚è‚©‚¦‚»‚¤‚ئ“w‚ك‚½پB
پ@
پ،پ@‰@گپ@‚إ‚حپAپ@ڈمچcپ@‚ھپA‰@’،پi‚¢‚ٌ‚ج‚؟‚ه‚¤پj‚إگ–±‚ً
پ@‚ئ‚èپAپ@‰@گéپi‚¢‚ٌ‚؛‚ٌپj‚â‰@’،‰؛•¶پi‚¢‚ٌ‚ج‚؟‚ه‚¤‚‚¾‚µ
پ@‚ش‚فپj‚إ‰؛’B‚µ‚½پBپ@‰@‹كگb‚ة‚حپAژَ—جپi‚¸‚è‚ه‚¤پAچ‘ژiپj
پ@‚ھپA‘½‚ژQ‰ء‚µپAگ–±‚ح‰@’،‚إچs‚ء‚½پBپ@
پ@پ@پ@‰@’،‚إگ–±‚ً‚ئ‚éپAڈمچc‚ئ‰@‹كگb‚حپAپ@“Vچc‚âگغٹض‰ئ
پ@‚ئ‘خ—§‚µ‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ،پ@‰@گ‚إڈمچcپi=‰@پi‚¢‚ٌپjپj‚جŒRژ–—ح‚ئ‚µ‚ؤگف‚¯‚ç‚ꂽپA
پ@–k–تپi‚ظ‚‚ك‚ٌپj‚ج•گژm‚حپAپ@•گژmٹK‹‰گ¬’·‚جˆêˆِ‚ئ‚ب
پ@‚ء‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ،پ@•غŒ³‚ج—گپi‚P‚P‚T‚U”NپjپE•½ژ،‚ج—گپi‚P‚P‚T‚X”NپjŒمپA•گژm
پ@‚ھ‘ن“ھ‚µپA‰@گگŒ پiڈمچcگŒ پA‚P‚O‚W‚U”Nچ پ`‚P‚P‚T‚U”N
پ@چ پj‚ھگٹ‚¦‚ؤپAپ@‘م‚ي‚ء‚ؤپA•گ‰ئگژ،‚ج•½ژپگŒ پ@پi‚P‚P‚U
پ@‚O”Nچ پ`‚P‚P‚W‚T”Nچ پjپ@‚ھپC “ْ–{‚ًژx”z‚·‚éپB
پœپ@‰@گگŒ پ@پi‚¢‚ٌ‚¹‚¢‚¹‚¢‚¯‚ٌپjپ@‚حپAپ@‚P‚O‚W‚U”N چ
پ@‚©‚ç‚P‚P‚T‚U”Nچ ‚ـ‚إ‚إپAپ@‚P‚O‚W‚U”N‚ةپA”’‰ح“Vچc‚ھ–x
پ@‰ح“Vچc‚ةڈ÷ˆت‚µپAپ@”’‰حڈمچc‚ئ‚ب‚èپAپ@‰@گ‚ًٹJژn‚µپA
پ@‰@’،‚ً’u‚«پA‰@گگŒ پiڈمچcگŒ پj‚ًژ÷—§‚µپA‚»‚ê‚ً’¹
پ@‰Hڈمچc‚ھˆّ‚«Œp‚¢‚¾‚ھپA‚P‚P‚T‚U”N‚ج’¹‰Hڈمچc‚جژ€‹ژ
پ@‚ئ‚ئ‚à‚ةپA‰@گگŒ پiڈمچcگŒ پj‚حپAڈء–إ‚µپA‚P‚P‚T‚U”N
پ@‚ج•غŒ³‚ج—گ‚ھ‹N‚±‚èپAپ@چXپi‚³‚çپj‚ةپAپ@‚P‚P‚T‚X”N‚ج•½ژ،
پ@‚ج—گ‚ھ‹N‚±‚èپAˆةگ¨•½ژپ‚ج•½گ´گ·پi‚½‚¢‚ç‚ج ‚à‚«‚و‚èپj
پ@‚ھپAپ@‰ح“àŒ¹ژپ‚جŒ¹‹`’© پi‚ف‚ب‚à‚ئ‚ج‚و‚µ‚ئ‚àپj‚ةڈں‚؟پA
پ@‚P‚P‚U‚O”N‚ةپAپ@•½گ´گ·‚حپA گ³ژOˆت‚ةڈ–پi‚¶‚هپj‚¹‚ç‚êŒِ
پ@‹¨پi‚‚¬‚ه‚¤پj‚ة—ٌ‚µپAپ@“ْ–{‚جگژ،‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚èپA •½ژپ
پ@گŒ ‚ھڈoŒ»‚·‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پںپ@پi‚rپjپ@“ْ–{‚جگژ،Œ`‘شپB
پ،پ@پi‚rپjپ@“ْ–{‚جگژ،Œ`‘شپB
پ@پi‚r‚P‚„پjپ@ڈ¬چ‘ژٌ’·گژ،پ@پi‘O‚Pگ¢‹Iپ`‹IŒ³Œم‚Tگ¢‹Iپjپث
پ@پi‚r‚P‚‡پjپ@چ‹‘°کAچ‡گژ،پ@پi‚Tپ`‚Vگ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚r‚Qپjپ@—¥—ك
پ@گژ،پ@پi‚Vپ`‚P‚Oگ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚r‚Rپjپ@گغٹضگژ،پ@پi‚P‚Oپ`‚P‚P
پ@گ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚r‚Sپjپ@‰@گگژ،پ@پi‚P‚Pپ`‚P‚Qگ¢‹Iپj پثپi‚r‚Tپj
پ@•گ‰ئگژ،پ@پi‚P‚Qپ`‚P‚Xگ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚r‚Uپjپ@‹ك‘م“Vچcگeگ
پ@گژ،پ@پi‹ك‘م“Vچcگâ‘خژه‹`گژ،پjپ@پi‚P‚Xپ`‚Q‚Oگ¢‹Iپjپ@پث
پ@پi‚r‚Vپjپ@Œ»‘مچ‘–¯ژهŒ گژ،پ@پiŒ»‘مژهŒ چف–¯گژ،پj پi‚Q‚O
پ@پ`‚Q‚Pگ¢‹I‚جŒ»چفپjپB
پœپ@ڈم‹Lچ€–ع‚جڈعچׂةٹض‚µ‚ؤ‚حپAپ@“–“ْ–{Œêژ«“T‚جٹeچ€
پ@–ع‚ًژQڈئ‚µ‚ؤ‰؛‚³‚¢پB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@
پ،پ@پi‚r‚Rپjپ@پثپ@پi‚r‚Sپjپ@گغگپEٹض”’‚ة‘م‚ي‚ء‚ؤپAڈمچc‚ھپAگ
پ@ژ،‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚ء‚½‚½‚كپAپ@پi‚r‚Rپjپ@گغٹضگژ، پi‚P‚Oپ`‚P‚Pگ¢پ@
پ@‹Iپj‚حپAپ@پi‚r‚Sپjپ@‰@گ گژ،پ@پi‚P‚Pپ`‚P‚Qگ¢‹Iپjپ@‚ةˆعچs‚·‚é
پ@پi‚ض•د‚ي‚éپjپBپ@پ@
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ،پ@پi‚r‚Sپjپ@‰@گگژ،پ@‚ئ‚حپAپ@ڈمچcپ@پi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پAŒ³“Vچcپj
پ@‚ھپA’©’ى‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚èپA‚³‚ç‚ةپA“ْ–{‚جگژ،‚جژہŒ ‚ًژ
پ@‚؟پA“ْ–{‚ًژx”z‚µ‚½گژ،Œ`‘شپ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@”’‰حڈمچcپi‰@گ گژ،ٹْپA‚P‚O‚W‚U”Nپ`‚P‚P‚Q‚X”Nپj‚â’¹‰H
پ@ڈمچcپi‰@گگژ،ٹْپA‚P‚P‚Q‚X”Nپ`‚P‚P‚T‚U”Nپjپ@‚ھپA’©’ى‚ج
پ@ژہŒ ‚ًˆ¬‚èپA‚³‚ç‚ةپA“ْ–{‚جگژ،‚جژہŒ ‚ًژ‚؟پA“ْ–{‚ً
پ@ژہژ؟“I‚ةژx”z‚µ‚½گژ،Œ`‘شپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@پi‚r‚Sپjپ@پثپ@پi‚r‚Tپjپ@‚P‚P‚T‚X”Nپi•½ژ،Œ³”Nپj‚ج•½ژ،‚ج—گ
پ@‚إ•گژm‚ج•گ—ح‚ج—ح‚إگژ،‚ج‘ˆ‚¢‚ھŒˆ’…ŒمپAپ@پi‚r‚Sپjپ@‰@
پ@گپ@پi‚P‚Pپ`‚P‚Qگ¢‹Iپjپ@‚حپAپi‚r‚Tپjپ@•گ‰ئگژ،پ@پi‚P‚Qپ`‚P‚X
پ@گ¢‹Iپjپ@‚ةˆعچs‚·‚éپi‚ض•د‚ي‚éپjپBپ@پ@
پœپ@•غŒ³‚ج—گپi‚P‚P‚T‚U”NپjپE•½ژ،‚ج—گپi‚P‚P‚T‚X”NپjŒمپAپ@•گژm
پ@‚ھ‘ن“ھ‚µپA‰@گگŒ پiڈمچcگŒ پA‚P‚O‚W‚U”Nچ پ`‚P‚P‚T‚U”N
پ@چ پj‚ھگٹ‚¦‚ؤپA‘م‚ي‚ء‚ؤپAپ@•گ‰ئگژ،‚ج•½ژپگŒ پ@پi‚P‚P‚U
پ@‚O”Nچ پ`‚P‚P‚W‚T”Nچ پjپ@‚ھپC“ْ–{‚ًژx”z‚·‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ@
پôپôپ@ڈمچcپ@‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–، گ[‚¢ٹضکA
پ@پ@پ@پ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپAƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پBپ@
پ@
پڑپ@ڈمچcپ@‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–، گ[‚¢ٹضکA
پ@پ@پ@ƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پBپ@
پ@
پ،پ@‚ة‚ء‚غ‚ٌپI—ًژjٹس’èپ@
پ@پ@پwپ@Œ¹•½‚ً‘€‚ء‚½Œم”’‰ح–@چcپ@پxپB
پ@پ@پ@پi‚s‚a‚rƒeƒŒƒrپE ‚Q‚O‚P‚V”N‚P‚PŒژ‚Q‚V“ْپE
پ@پ@پ@–{•ْ‘—پE—ًژjƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[”ش‘gپjپB
پ،پ@’¹‰HڈمچcپAگ’“؟ڈمچcپAŒم”’‰حڈمچc‚ب‚ا‚ج
پ@پ@ڈمچc‚ًڈq‚ׂéپB
پ،پ@Œم”’‰حڈمچcپi“VچcپA–@‰¤پj‚ًڈعچׂةڈq‚ׂéپB
پ،پ@•½ˆہژ‘مŒمٹْ‚جگژ،ڈَ‹µپAژ‘مڈَ‹µ‚âٹˆ
پ@پ@ –ô‚µ‚½گlپX‚ًڈعچׂةڈq‚ׂéپB
پ@
پ،پ@—ًژj”éکbƒqƒXƒgƒٹƒAپ@پwپ@ژ„‚½‚؟پA
پ@پ@‘گگHŒn•گژm‚إ‚·پBپ`گVپE•½‰ئ‰ئ
پ@پ@‘°•¨Œêپ`پ@پxپBپ@
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚O‚X”Nپi•½گ¬‚Q‚P”Nپj
پ@پ@پ@‚P‚QŒژ‚P‚U“ْپE–{•ْ‘—پA‘و‚Q‚V‰ٌپjپB
پ@
پڑپ@ڈمچcپ@‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢پAٹضکA
پ@پ@پ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپB
پœپ@پi’چˆسپjپ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAƒtƒBƒNƒVƒ‡ƒ“پ@‚إ‚·پBپ@
پ@پ@پ@—ًژj‚جƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپ@‚حپAژjژہپi—ًژjڈم‚جژ–ژہپjپ@
پ@پ@پ@‚ئ‰ث‹َ‚جڈo—ˆژ–‚ھپ@چ¬‚¶‚ء‚ؤ•`‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپ@
پ@پ@پ@‚ـ‚½پAپ@Œ»‘م•—‚ةƒAƒŒƒ“ƒW‚µ‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚·پB
پ@
پ،پ@پwپ@•½گ´گ·پ@پi‚½‚¢‚ç‚ج‚«‚و‚à‚èپjپ@پx پBپ@
پ@پ@پ@پ@پi‚m‚g‚j‚Q‚O‚P‚Q”N‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پjپB
پ،پ@•½ˆہژ‘مŒمٹْ‚ج“–ژٹˆ–ô‚µ‚½گl•¨‚â
پ@پ@ “–ژ‚جژ‘مڈَ‹µ‚ً•`‚¢‚½ƒhƒ‰ƒ}•`‚پB
پ،پ@•½گ´گ·‚جگ¶ٹU‚ً•`‚¢‚½ƒhƒ‰ƒ}پB
پ،پ@”’‰حڈمچcپA’¹‰HڈمچcپAŒم”’‰حڈمچc‚ھ
“oڈê‚·‚éپB
پ@
پœپ@”’‰حڈمچc‚ً‰‰‚¶‚½”o—D–¼پ@پFپ@ˆة“Œپ@ژlکYپB
پœپ@’¹‰Hڈمچc‚ً‰‰‚¶‚½”o—D–¼پ@پFپ@ژOڈمپ@”ژژjپB
پœپ@Œم”’‰حڈمچc ‚ً‰‰‚¶‚½”o—D–¼پ@پFپ@ڈ¼“c مؤ‘¾پB
پœپ@•½پ@گ´گ· ‚ً‰‰‚¶‚½”o—D–¼پ@پFپ@ڈ¼ژRپ@ƒPƒ“ƒCƒ`پB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ڈ®ˆçپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚¢‚پjپB
پ@
پ،پ@ڈ®ˆçپBپ@
پ،پ@گ¶–v”Nپ@پFپ@‚P‚W‚P‚R”Nپ`‚P‚W‚S‚V”NپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ڈ®ˆç پi‚µ‚ه‚¤‚¢‚پjپB
پœپ@•ت–¼پFپ@ڈ®ˆç‰¤ پi‚µ‚ه‚¤‚¢‚‚¨‚¤پjپB
پ،پ@‰«“êپi—®‹…پj‚ً“ژ،‚µ‚½—®‹…‰¤چ‘پi‚P‚S‚Q‚Xپ` ‚P‚W‚V‚Q”Nپj‚ج––
پ@ٹْ‚جچ‘‰¤پ@پiچفˆت‚P‚W‚R‚Tپ`‚S‚V”NپjپBپ@پ@
پ،پ@‘و“ٌڈ®ژپ‰¤“‚P‚W‘مچ‘‰¤پEڈ®ˆç‰¤ پi‚µ‚ه‚¤‚¢‚‚¨‚¤پjپB
پ،پ@—®‹…‰¤چ‘‚ج‘و“ٌڈ®ژپ‰¤“‚P‚X‘مچ‘‰¤‚إچإŒم‚جچ‘‰¤پEڈ®‘׉¤
پ@پi‚µ‚ه‚¤‚½‚¢‚¨‚¤پj‚ج•ƒپB
پ،پ@‰«“ê‚ج—ًژj‚àژQڈئ‚µ‚ؤ‰؛‚³‚¢پB
پ@
پ@
پ،پ@ڈ®ˆç پi‚µ‚ه‚¤‚¢‚پj‚حپAپ@‰«“êپi—®‹…پj‚ً“ژ،‚µ‚½—®‹…‰¤چ‘پi‚P
پ@‚S‚Q‚Xپ`‚P‚W‚V‚Q”Nپj‚جچ‘‰¤پEڈ®ˆç‰¤ پi‚µ‚ه‚¤‚¢‚‚¨‚¤پj‚إپAچفˆت‚حپAپ@
پ@‚P‚W‚R‚Tپ`‚P‚W‚S‚V”N‚إپAپ@‘و“ٌڈ®ژپ‰¤“‚P‚W‘مچ‘‰¤‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@ڈ®ˆç‰¤‚حپAپ@—®‹…‰¤چ‘‚ج––ٹْ‚جچ‘‰¤‚إپAپ@—®‹…‰¤چ‘‚جچإŒم
پ@‚جچ‘‰¤پEڈ®‘׉¤پi‚µ‚ه‚¤‚½‚¢‚¨‚¤پj‚ج•ƒپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@ڈ®ˆç‚ج•ƒ‚حپAڈ®灝پi‚µ‚ه‚¤‚±‚¤پAچ‘‰¤پjپA•ê‚حپAژv‹T’M‹àپiڈ®
پ@灝‚ج‰¤”ـپEگ³ژ؛•vگlپj
پ@پ@پ@ڈ®ˆç‚ج‰¤”ـپEگ³ژ؛•vگlپiچ²•~ˆآژi‰ء“كژuپj‚حپAŒ³’هپi–LŒ©
پ@ڈ鉤ژq’©ڈt‚ج–؛پjپAپ@‘¤ژ؛•vگl‚حپAگ^“ى•—پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@ڈ®ˆç‚جژq‚حپA‚R’j‚Tڈ—‚إپAپ@’·’j‚حپAڈ®à\پi‚µ‚ه‚¤‚µ‚م‚ٌپA‚P‚R
پ@چخ‚إژ€‹ژپjپAپ@ژں’j‚حپAڈ®‘×پi‚µ‚ه‚¤‚½‚¢پA•ê‚ح‰¤”ـپEگ³ژ؛•vگlپA
پ@’·’j‚جڈ®à\‚جژ€‹ژ‚إژں‘مچ‘‰¤‚ئ‚ب‚éپjپAپ@ژO’j‚حپAڈ®•Jپi•ê‚ح
پ@‘¤ژ؛•vگl‚جگ^“ى•—پjپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ڈ®‘×پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚½‚¢پjپB
پ@
پ،پ@ڈ®‘×پBپ@
پ،پ@گ¶–v”Nپ@پFپ@‚P‚W‚S‚Rپ`‚P‚X‚O‚P”NپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ڈ®‘× پi‚µ‚ه‚¤‚½‚¢پjپB
پœپ@•ت–¼پFپ@ڈ®‘׉¤ پi‚µ‚ه‚¤‚½‚¢‚¨‚¤پjپBپ@ڈ®‘×”ث‰¤پ@پi‚µ‚ه‚¤‚½‚¢
پ@‚ح‚ٌ‚¨‚¤پjپB
پ،پ@‰«“êپi—®‹…پj‚ً“ژ،‚µ‚½—®‹…‰¤چ‘پi‚P‚S‚Q‚Xپ` ‚P‚W‚V‚Q”Nپj‚ج––
پ@ٹْ‚جچ‘‰¤پiچفˆت‚P‚W‚S‚Wپ`‚V‚Q”NپA‚Uچخچ ‘¦ˆتپjپB
پ،پ@‘و“ٌڈ®ژپ‰¤“‚P‚X‘مچ‘‰¤پB
پ،پ@—®‹…‰¤چ‘پi‚P‚S‚Q‚Xپ` ‚P‚W‚V‚Q”Nپj‚جچإŒم‚جچ‘‰¤پB
پ،پ@—®‹…”ثپi‚P‚W‚V‚Qپ`‚V‚X”Nپj‚ج”ث‰¤پiچفˆت‚P‚W‚V‚Qپ`‚V‚X”Nپj
پ،پ@‘و“ٌڈ®ژپ‰¤“‚P‚W‘مچ‘‰¤پEڈ®ˆç‰¤ پi‚µ‚ه‚¤‚¢‚‚¨‚¤پj‚جژqپB
پ،پ@‰«“ê‚ج—ًژj‚àژQڈئ‚µ‚ؤ‰؛‚³‚¢پB
پ@
پ@
پ،پ@ڈ®‘×پ@‚حپAپ@—®‹…‰¤چ‘پi‚P‚S‚Q‚Xپ` ‚P‚W‚V‚Q”Nپj‚ج––ٹْ‚جچ‘‰¤
پ@ ‚إپAپ@—®‹…‰¤چ‘‚جچ‘‰¤پEڈ®ˆç‰¤ پi‚µ‚ه‚¤‚¢‚‚¨‚¤پj‚جژq ‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@ڈ®‘× پi‚µ‚ه‚¤‚½‚¢پjپ@‚حپAپ@‰«“êپi—®‹…پj‚ً“ژ،‚µ‚½—®‹…‰¤چ‘
پ@پi‚P‚S‚Q‚Xپ`‚P‚W‚V‚Q”Nپj‚جچ‘‰¤ پEڈ®‘׉¤ پi‚µ‚ه‚¤‚½‚¢‚¨‚¤پj‚إپAچف
پ@ˆت‚حپA‚P‚W‚S‚Wپ`‚P‚W‚V‚Q”N‚إپAپ@‘و“ٌڈ®ژپ‰¤“‚P‚X‘مچ‘‰¤‚إ‚
پ@‚èپA—®‹…‰¤چ‘‚جŒمگg‚ج—®‹…”ثپi‚P‚W‚V‚Qپ`‚V‚X”Nپj‚ج”ث‰¤پiچفˆت
پ@‚P‚W‚V‚Qپ`‚V‚X”Nپjپ@‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@
پ،پ@ڈ®‘ׂج•ƒ‚حپAڈ®ˆçپi‚µ‚ه‚¤‚¢‚پAچ‘‰¤پjپA•ê‚حپAŒ³’هپiڈ®ˆç‚ج
پ@‰¤”ـپEگ³ژ؛•vگlپjپB
پ@پ@پ@ڈ®‘ׂج‰¤”ـپEگ³ژ؛•vگlپiچ²•~ˆآژi‰ء“كژuپj‚حپAپ@ڈحژپژvگ^
پ@’ك‹àپAپ@‘¤ژ؛•vگl‚حپAپ@گ^’ك‹àپEڈ¼گىپAگ^’ك‹àپE•½—اپA‚»‚ج‘¼
پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@ڈ®‘ׂجژq‚حپAژµ’j‚P‚Pڈ—‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ژ·Œ گژ،پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ء‚¯‚ٌ‚¹‚¢‚¶پjپB
پ@
پ،پ@ژ·Œ گژ،پBپ@
پ،پ@ژٹْپ@پFپ@ٹ™‘qژ‘م‚جپA‚P‚Q‚P‚X”Nپ`‚P‚R‚R‚R”NپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ژ·Œ گژ، پi‚µ‚ء‚¯‚ٌ‚¹‚¢‚¶پjپB
پ،پ@–kڈًژپ‚ة‚و‚éژ·Œ گژ،پB
پ،پ@ڈ«ŒR•âچ²‚إ‚ ‚éژ·Œ ‚ھپA–‹•{‚جگژ،‚ًچs‚¤‚±‚ئپB
پ،پ@ٹ™‘q–‹•{‚ج–kڈًژپژ·Œ ‚ة‚و‚éگژ،پB
پ@
پ پ@ٹ™‘q–‹•{‚جژ·Œ ˆê——•\پB
پ پ@ٹ™‘q–‹•{‚جڈ«ŒRˆê——•\پB
پ@
پ@
پ،پ@ژ·Œ گژ، پi‚µ‚ء‚¯‚ٌ‚¹‚¢‚¶پjپ@‚ئ‚حپAڈ«ŒR•âچ²‚إ‚ ‚éژ·Œ ‚ھپA–‹•{
پ@‚جگژ،‚ًچs‚¤‚±‚ئ‚إپAپ@–kڈًژپ‚ھٹ™‘q–‹•{‚جژ·Œ پiڈ«ŒR•âچ²پjپ@‚ئ‚ب
پ@‚èپA–‹•{‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚èپAپ@گژ،‚ً‚¨‚±‚ب‚¤‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ، –kڈًژپ‚ج‚و‚éژ·Œ گژ،پ@پi‚µ‚ء‚¯‚ٌ‚¹‚¢‚¶پjپ@‚حپAٹ™‘qژ‘م‚جپA‚P‚Q‚P
پ@‚X”N‚©‚ç‚P‚R‚R‚R”N‚ـ‚إپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@‚P‚Q‚P‚X”Nپiڈ³‹vپi‚¶‚ه‚¤‚«‚م‚¤پjŒ³”Nپj‚ة پAپ@ٹ™‘q–‹•{‚R‘مڈ«ŒR‚إŒ¹ژپ
پ@ڈ«ŒR‚جŒ¹ژہ’©پi‚ف‚ب‚à‚ئ‚ج‚³‚ث‚ئ‚àپj‚ھˆأژE‚³‚ꌹ—ٹ’©‚جŒ¹ژپ’„—¬‚ھ
پ@’fگ₵پA–¼ژہ‚ئ‚à‚ةپA–kڈًژپ‚ھٹ™‘q–‹•{‚جژ·Œ پi‚µ‚ء‚¯‚ٌپAڈ«ŒR•âچ²پj
پ@‚ئ‚ب‚ء‚ؤگژ،‚ًچs‚¢پA‚Q‘مژ·Œ ‚ج–kڈً‹`ژپi‚و‚µ‚ئ‚«پj ‚ھپA–kڈًژپ‚ة‚و
پ@‚éژ·Œ گژ،‚ًچs‚¢پA‚P‚R‚R‚R”N‚ةپA‚P‚U‘مژ·Œ ‚ج–kڈً ژçژپi‚à‚è‚ئ‚«پj‚ج
پ@ژپAٹ™‘q–‹•{‚ھ–إ–S‚µپAپ@–kڈًژپ‚جژ·Œ گŒ ‚حپAڈء–إ‚µ‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ،پ@Œ¹ژپ‚جڈ«ŒR‚حپAپ@Œ¹—ٹ’©پAŒ¹—ٹ‰ئپAŒ¹ژہ’©‚جژO‘م‚إ–إ‚رپA‚»‚جŒمپA
پ@–kڈًژپ‚جژ·Œ ‚ھپ@ٹ™‘q–‹•{‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚ء‚½پBپ@Œ¹ژپ‚جڈ«ŒR–إ–SŒمپA
پ@–kڈًژپ‚ھپAپ@–¼–ع“I‚بڈ«ŒR‚جگغ‰ئپi‚¹‚ء‚¯پjڈ«ŒR‚Q‘مپA‹{پi‚ف‚âپjڈ«ŒR
پ@‚S‘م‚ج‰؛‚إپA ژ·Œ پiڈ«ŒR•âچ²پj‚ئ‚µ‚ؤپAپ@ٹ™‘q–‹•{‚جگژ،‚جژہŒ ‚ًˆ¬
پ@‚ء‚½پB
پ،پ@‚P‚R‚R‚R”N‚ةپAگV“c‹`’هپ@پi‚ة‚ء‚½‚و‚µ‚³‚¾پjپ@‚ھپAپ@ٹ™‘q‚ًچU‚كپAٹ™
پ@‘q–‹•{‚ج ژہŒ ‚ًˆ¬‚éژ·Œ پi‚µ‚ء‚¯‚ٌپj‚ج–kڈًژپ‚ً–إ‚ع‚µ‚ؤپAپ@–‹•{‚حپA
پ@ڈء–إ‚µ‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ@
#kamakurabakufunoshikkenichiranhyo
پ@
پںپ@ٹ™‘q–‹•{‚ج–kڈًژپپEژ·Œ –¼
پiڈ‰‘مپ` ‚P‚U‘مپjˆê——•\پB
پ@
پ،پ@ٹ™‘q–‹•{‚ج–kڈًژپپEژ·Œ
پi‚µ‚ء‚¯‚ٌپAڈ«ŒR•âچ²پjپB
پ@
پ،پ@پ@ڈ‰‘مژ·Œ پ@پ@–kڈً ژگپ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤ ‚ئ‚«‚ـ‚³پjپB
پ،پ@پ@‚Q‘مژ·Œ پ@پ@ –kڈً ‹`ژپ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤ ‚و‚µ‚ئ‚«پjپB پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–kڈً“¾ڈ@پi‚ئ‚‚»‚¤پA–{‰ئپjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–@–¼پ@“؟ڈ@پB
پ،پ@پ@‚R‘مژ·Œ پ@پ@ –kڈً ‘×ژپ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤ ‚â‚·‚ئ‚«پjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ –kڈً“¾ڈ@پi–{‰ئپjپB
پ،پ@پ@‚S‘مژ·Œ پ@پ@ –kڈً Œoژپ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤ ‚آ‚ث‚ئ‚«پjپBپ@
–kڈً“¾ڈ@پi–{‰ئپjپB
پ،پ@پ@‚T‘مژ·Œ پ@پ@ –kڈً ژ—ٹپ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤ ‚ئ‚«‚و‚èپjپB
–kڈً“¾ڈ@پi–{‰ئپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ،پ@پ@‚U‘مژ·Œ پ@پ@ –kڈً ’·ژپ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤ ‚ب‚ھ‚ئ‚«پjپBپ@
پ،پ@پ@‚V‘مژ·Œ پ@پ@ –kڈً گ‘؛پ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤ ‚ـ‚³‚ق‚çپjپB
پ،پ@پ@‚W‘مژ·Œ پ@پ@ –kڈً ژڈ@پ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤ ‚ئ‚«‚ق‚ثپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ –kڈً“¾ڈ@پi–{‰ئپjپB
پ،پ@پ@‚X‘مژ·Œ پ@پ@ –kڈً ’هژپ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤ ‚³‚¾‚ئ‚«پjپB
–kڈً“¾ڈ@پi–{‰ئپjپBپ@
پ،پ@‚P‚O‘مژ·Œ پ@پ@ –kڈً ژtژپ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤ ‚à‚ë‚ئ‚«پjپBپ@
پ،پ@‚P‚P‘مژ·Œ پ@پ@ –kڈً ڈ@گéپ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤ ‚ق‚ث‚ج‚èپjپ@پ@
پi= ‘ه•§پi‚¨‚³‚炬پjڈ@گéپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ،پ@‚P‚Q‘مژ·Œ پ@پ@ –kڈً ê¤ژپ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤ ‚ذ‚ë‚ئ‚«پjپBپ@
پ،پ@‚P‚R‘مژ·Œ پ@پ@ –kڈً ٹîژپ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤ ‚à‚ئ‚ئ‚«پjپB
پ،پ@‚P‚S‘مژ·Œ پ@پ@ –kڈً چ‚ژپ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤ ‚½‚©‚ئ‚«پjپBپ@
–kڈً“¾ڈ@پi–{‰ئپjپB
پ،پ@‚P‚T‘مژ·Œ پ@پ@ –kڈً ’هŒ°پ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤ ‚³‚¾‚ ‚«پjپ@پ@پ@
پi= ‹à‘ٍ’هŒ°پjپB
پ،پ@‚P‚U‘مژ·Œ پ@پ@ –kڈً ژçژپ@پi‚ظ‚¤‚¶‚ه‚¤ ‚à‚è‚ئ‚«پjپBپ@پ@
‘«—ک‘¸ژپپi‚½‚©‚¤‚¶پj‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ گ³ژ؛•vگl‚جŒZپB
پ@
پ@
#kamakurabakufunoshogunichiranhyo
پ@
پںپ@ٹ™‘q–‹•{‚جڈ«ŒR–¼پiڈ‰‘مپ`‚X‘مپj
ˆê——•\پB
پ@
پ،پ@Œ¹ژپڈ«ŒR پi‚°‚ٌ‚¶‚µ‚ه‚¤‚®‚ٌپjپB
پ،پ@ڈ‰‘مڈ«ŒRپ@پ@Œ¹—ٹ’©پ@پi‚ف‚ب‚à‚ئ‚ج‚و‚è‚ئ‚àپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ«ŒRچف”C‚P‚P‚X‚Qپ`‚P‚P‚X‚X”NپjپB
پ،پ@‚Q‘مڈ«ŒRپ@پ@Œ¹—ٹ‰ئپ@پi‚ف‚ب‚à‚ئ‚ج‚و‚è‚¢‚¦پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ«ŒRچف”C‚P‚Q‚O‚Qپ`‚P‚Q‚O‚R”NپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ،پ@‚R‘مڈ«ŒRپ@پ@Œ¹ژہ’©پ@پi‚ف‚ب‚à‚ئ‚ج‚³‚ث‚ئ‚àپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ«ŒRچف”C‚P‚Q‚O‚Rپ`‚P‚Q‚P‚X”NپjپB
پ@
پ،پ@گغ‰ئڈ«ŒRپAچc‘°ڈ«ŒR
پ@پ@ پiژ·Œ پi‚µ‚ء‚¯‚ٌپjگژ،‚ة‚¨‚¯‚é ژہŒ ‚ج‚ب‚¢
پ@پ@ –¼–ع“I‚بڈ«ŒRپjپB
پںپ@گغ‰ئڈ«ŒRپ@ پi‚¹‚ء‚¯‚µ‚ه‚¤‚®‚ٌپA“،Œ´ڈ«ŒRپA“،Œ´ژپپEگغٹض‰ئ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¹‚ء‚©‚ٌ‚¯پjڈoگg ‚جڈ«ŒRپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚Q‚Q‚U”Nپ`‚P‚Q‚T‚Q”NپjپB
پ،پ@‚S‘مڈ«ŒRپ@پ@“،Œ´—ٹŒoپ@پi‚س‚¶‚ي‚ç‚ج‚و‚è‚آ‚ثپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ«ŒRچف”C‚P‚Q‚Q‚Uپ`‚P‚Q‚S‚S”Nپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi=‹مڈً—ٹŒoپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ْ–{ژjژ«“TپB
پ،پ@‚T‘مڈ«ŒRپ@پ@“،Œ´—ٹژkپ@پi‚س‚¶‚ي‚ç‚ج‚و‚è‚آ‚®پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ«ŒRچف”C‚P‚Q‚S‚Sپ`‚P‚Q‚T‚Q”Nپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi=‹مڈً—ٹژkپjپB
پ@
پںپ@چc‘°ڈ«ŒRپ@پi‚±‚¤‚¼‚‚µ‚ه‚¤‚®‚ٌپAگe‰¤ڈ«ŒRپA‹{پi‚ف‚âپj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ«ŒRپAگe‰¤ڈoگg‚جڈ«ŒRپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚Q‚T‚Q”Nپ`‚P‚R‚R‚R”NپjپB
پ،پ@‚U‘مڈ«ŒRپ@پ@ڈ@‘¸گe‰¤پ@پi‚ق‚ث‚½‚©پ@‚µ‚ٌ‚ج‚¤پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ڈ«ŒRچف”C‚P‚Q‚T‚Qپ`‚P‚Q‚U‚U”NپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ Œمچµ‰م“Vچc‚جچcژqپjپB
پ،پ@‚V‘مڈ«ŒRپ@پ@ˆزچNگe‰¤پ@پi‚±‚ê‚â‚·پ@‚µ‚ٌ‚ج‚¤پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ«ŒRچف”C‚P‚Q‚U‚Uپ`‚P‚Q‚W‚X”NپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ@‘¸گe‰¤‚جژqپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ “ْ–{ژjژ«“TپB
پ،پ@‚W‘مڈ«ŒRپ@پ@‹v–¾گe‰¤پ@پi‚ذ‚³‚ ‚« پ@‚µ‚ٌ‚ج‚¤پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ«ŒRچف”C‚P‚Q‚W‚Xپ`‚P‚R‚O‚W”NپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œمگ[‘گ“Vچc‚جچcژqپjپB
پ،پ@‚X‘مڈ«ŒRپ@پ@ژç–Mگe‰¤پ@پi‚à‚è‚‚ةپ@‚µ‚ٌ‚ج‚¤پA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ«ŒRچف”C‚P‚R‚O‚Wپ`‚P‚R‚R‚R”NپA
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹v–¾گe‰¤‚جژqپjپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ڈج“؟ “Vچcپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚ئ‚ ‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پjپB
پ@
پ،پ@ڈج“؟ “VچcپB
پ،پ@گ¶–v”Nپ@پFپ@‚V‚P‚Wپ`‚V‚V‚O”NپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ڈج“؟“Vچcپ@پi‚µ‚ه‚¤‚ئ‚‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پjپ@پiچفˆت‚V‚U‚Sپ`‚V‚V‚O”NپjپB
پ@چFŒھ“Vچcپ@(‚±‚¤‚¯‚ٌ‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پjپ@ پiچفˆت‚V‚S‚Xپ`‚V‚T‚W”Nپj‚حپAپ@ڈdâN
پ@پi‚؟‚ه‚¤‚»پj‚µ‚ؤپi “Vچcچؤ‘¦ˆت‚µ‚ؤپjپAپ@ڈج“؟“Vچcپ@پi‚µ‚ه‚¤‚ئ‚‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پjپ@
پ@‚ئ‚ب‚éپB
پœپ@‰p–¼پFپ@‚r‚g‚n‚s‚n‚j‚tپ@‚d‚l‚o‚q‚d‚r‚rپB
پœپ@ڈج“؟“Vچcپiڈ—’é پj‚ج‘¦ˆت‘O‚ج–¼ڈجپ@‚حپAپ@ˆ¢•”“àگe‰¤ پi‚ ‚ׂب‚¢‚µ
پ@‚ٌ‚ج‚¤پA‚ ‚ׂج‚ب‚¢‚µ‚ٌ‚ج‚¤پjپB
پœپ@‰ü–¼پ@‚حپAپ@ˆ¢•”“àگe‰¤پ@پثپ@چFŒھ “Vچcپ@پi‚V‚S‚X”Nپ`پjپ@پثچFŒھ ڈم
پ@چcپi‘¾ڈم“Vچcپjپ@پi‚V‚T‚W”Nپ`پjپ@پثپ@ڈج“؟ “Vچcپ@پi‚V‚U‚S”Nپ`پjپB
پ،پ@“ق—اژ‘م‚جڈ—’é پi‚¶‚ه‚ؤ‚¢پAڈ—گ«‚ج“VچcپjپB
پ،پ@گ¹•گپi‚µ‚ه‚¤‚قپj“Vچc‚جچcڈ—پi‚±‚¤‚¶‚هپA–؛پjپB
پ،پ@•ƒپ@‚حپAپ@گ¹•گ“Vچcپi‚µ‚ه‚¤‚ق‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پjپAپ@•êپ@‚حپAپ@Œُ–¾چcچ@پ@پi‚±
پ@‚¤‚ف‚ه‚¤‚±‚¤‚²‚¤پjپB
پ@
پ پ@“ق—اژ‘م“ْ–{گژ،ژہŒ ژز•د‘J
ˆê——•\پB
پ “Œ‘هژ›‘ه•§پ@ƒAƒ‹ƒoƒ€پ@‚m‚nپD‚P
پ پ@ڈ—’é‚جڈج“؟“Vچcپi= چFŒھ“Vچcپjپ@
پ@پ@‚ھپ@“oڈê‚·‚éپA –ت”’‚پA‹»–،گ[‚¢پA
پ@پ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپAƒhƒL ƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پB
پ@
پ@
پ،پ@چFŒھپiڈج“؟پj“Vچcپ@پi‚±‚¤‚¯‚ٌپi‚µ‚ه‚¤‚ئ‚پj‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پAپ@چفˆت‚V‚S‚Xپ`‚V
پ@‚T‚WپAپiچفˆت‚V‚U‚Sپ`‚V‚V‚O”Nپjپjپ@‚حپAپ@“ق—اژ‘م‚جڈ—’éپ@‚إ‚ ‚éپBپ@گ¹
پ@•گپi‚µ‚ه‚¤‚قپj“Vچc‚ج–؛‚إپAپ@گ¹•گ“Vچcپ@پiگ¹•گ ڈمچcپi‘¾ڈم“VچcپjپA‚µ‚ه
پ@‚¤‚ق ‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پi‚¾‚¢‚¶‚ه‚¤‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پjپAپ@‹kڈ”ŒZپ@پi‚½‚؟‚خ‚ب‚ج‚à‚낦پjپA
پ@‹g ”ُگ^”ُپ@پi‚«‚ر‚ج‚ـ‚«‚رپjپAپ@“،Œ´’‡–ƒکCپ@پi‚س‚¶‚ي‚ç‚ج‚ب‚©‚ـ‚ëپjپAپ@
پ@“¹ ‹¾پ@پi‚ا‚¤‚«‚ه‚¤پjپ@‚ئ‹¤‚ةپAپ@‘½‚‚جگچô‚ًچs‚¢پAپ@“Œ‘هژ›‘ه•§‘¢‰c
پ@‚ًگ„گi‚µٹ®گ¬‚³‚¹پAپ@•§‹³’ءŒىپi‚؟‚ٌ‚²پjچ‘‰ئ‚ة‚و‚éچ‘‰ئ‚جˆہ’è‚ً‚ح
پ@‚©‚èپAپ@‚ـ‚½پAپ@“V•½پi‚ؤ‚ٌ‚ز‚ه‚¤پj•¶‰»‚ًŒ»ڈo‚³‚¹‚½پB
پ@
پ،پ@‚V‚T‚Q”Nپ@پi“V•½ڈں•َپi‚ؤ‚ٌ‚ز‚ه‚¤‚µ‚ه‚¤‚ظ‚¤پj‚S”Nپj‚ةپAپ@ڈج“؟“Vچc‚ھپ@
پ@چFŒھ“Vچcپ@(‚±‚¤‚¯‚ٌ‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پAچفˆت‚V‚S‚Xپ`‚V‚T‚W”Nپj‚ئڈج‚µ‚½ژ،گ¢‚ةپAپ@
پ@“Œ‘هژ›‘ه•§‚جŒڑ—§پi‚±‚ٌ‚è‚م‚¤پj‚ھ‚ ‚é’ِ“xپAٹ®گ¬‚µپAپ@“Œ‘هژ›‘ه•§
پ@‚جٹJٹلپi‚©‚¢‚°‚ٌپj‚ھچs‚ي‚ꂽپB
پœپ@ڈج“؟“VچcپiچFŒھ“Vچcپj‚ج•ƒپAگ¹•گ ڈمچcپi‘¾ڈم“Vچcپjپ@پi‚µ‚ه‚¤‚ق ‚¶‚ه
پ@‚¤‚±‚¤پi‚¾‚¢‚¶‚ه‚¤‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پjپjپ@‚حپA ‘ج—ح‚ھگٹ‚¦پAپ@گ¶‘O‚ةپA‘ه•§ٹJٹل
پ@‚ً–]‚فپAپ@‚ ‚é’ِ“xٹ®گ¬‚µ‚½ژ“_‚إپA‘ه•§ٹJٹلپi‚¾‚¢‚ش‚آ‚©‚¢‚°‚ٌپj
پ@‚ھچs‚ي‚ꂽپB
پ@
پ،پ@ڈج“؟“VچcپiچFŒھ“Vچcپjپ@‚حپAپ@چFŒھ“Vچc‚ئ‚µ‚ؤپAپ@ڈ‰‚كپAپ@“،Œ´’‡–ƒ
پ@کCپi‚س‚¶‚ي‚ç‚ج‚ب‚©‚ـ‚ëپj‚ًڈd—pپi‚؟‚ه‚¤‚و‚¤پj‚µپAپ@“،Œ´’‡–ƒکC‚ةˆ³”—
پ@‚³‚ê‚ؤپAپ@ڈ~گmپi‚¶‚م‚ٌ‚ة‚ٌپj“Vچcپiچفˆت‚V‚T‚Wپ`‚V‚U‚S”Nپjپ@‚ضڈ÷ˆتپi‚¶‚ه
پ@‚¤‚¢پj‚·‚éپBپ@
پ@پ@پ@‚»‚جŒم پAپ@چFŒھ“Vچcپiڈج“؟“Vچcپjپ@‚حپAپ@چFŒھڈمچcپi‘¾ڈم“Vچcپjپi‚±
پ@‚¤‚¯‚ٌپ@‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پi‚¾ ‚¢‚¶‚ه‚¤‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پjپ@‚ئ‚ب‚èپA“¹‹¾پi‚ا‚¤‚«‚ه‚¤پj‚ً’
پ@ˆ¤پi‚؟‚ه‚¤‚ ‚¢پj‚µپAپ@چؤ‚رگژ،‚جژہŒ ‚ًژو‚è–ك‚»‚¤‚ئ‚µ‚ؤ“،Œ´’‡–ƒکCپ@
پ@‚ئ‘خ—§‚µپAپ@“،Œ´’‡–ƒکC‚ج—گ‚ًڈµ‚¢‚½پ@پiŒb”ü‰ںڈں‚ج—گپjپB
پ@پ@پ@چFŒھڈمچcپiڈج“؟“Vچcپj‚حپAپ@—گ‚ج’ءˆ³ŒمپAپ@ڈ~گm“Vچc‚ً”p‚µ‚ؤپAڈج
پ@“؟“Vچcپi‚µ‚ه‚¤‚ئ‚‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پAچفˆت‚V‚U‚Sپ`‚V‚V‚O”Nپjپ@‚ئ‚µ‚ؤچؤ‚ر‘¦ˆت‚µپA
پ@ڈج“؟“Vچc‚ج’ˆ¤‚·‚éپA“¹‹¾پ@‚ھپAپ@گêگ§گژ،‚ًچs‚ء‚½پB
پ@
پ،پ@‚V‚U‚S”N‚جŒb”ü‰ںڈںپi‚¦‚ف‚ج‚¨‚µ‚©‚آپj‚ج—گ
پœپ@چFŒھڈمچcپiڈج“؟“Vچcپj•ûپ@‚ھپAپ@ژ–‘O‚ةŒv‰و‚µپA“،Œ´’‡–ƒکCپiŒb”ü‰ں
پ@ڈںپj•û‚ضگي‚¢‚ً‚µ‚©‚¯‚éپB
پœپ@چFŒھڈمچcپiڈج“؟“Vچcپj•ûپ@‚حپAپ@‚V‚U‚S”N‚XŒژ‚ةپA“ق—ا‚ج•½ڈé‹‚إپA“،
پ@Œ´’‡–ƒکCپiŒb”ü‰ںڈںپj•û‚©‚çپA‰w—كپi‚¦‚«‚ê‚¢پA‰wگ§‚ج—éپjپ@‚ئپ@“VچcŒن
پ@ژ£پi‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤‚¬‚ه‚¶پA“VچcŒِˆَپj‚ً’D‚¢پAپ@‚»‚جŒمپAپ@“،Œ´’‡–ƒکCپiŒb”ü
پ@‰ںڈںپj•û‚ھپA•½ڈé‹‚ً’Eڈo‚·‚é‚ئپAپ@چFŒھڈمچcپiڈج“؟“Vچcپj •ûپ@‚حپ@‚»
پ@‚ê‚ً’اŒ‚‚µپAپ@“،Œ´’‡–ƒکCپiŒb”ü‰ںڈںپjپ@‚حپAپ@”ْ”iŒخ‚جگ¼ٹف‚إپA”sژ€پ@
پ@‚·‚éپ@پiپ@‘±“ْ–{‹Iپi‚µ‚ه‚‚ة‚ظ‚ٌ‚¬پj‚و‚èپ@پjپB
پ@
پ،پ@ڈج“؟“VچcپiچFŒھ“Vچcپjپ@‚حپAپ@گ¹•گپi‚µ‚ه‚¤‚قپj“Vچc‚جچcڈ—پi‚±‚¤‚¶‚هپA
پ@–؛پj‚إپA“ق—اژ‘م‚جڈ—’é پi‚¶‚ه‚ؤ‚¢پAڈ—گ«‚ج“Vچcپjپ@‚إ‚ ‚éپB
پ،پ@ڈج“؟“VچcپiچFŒھ“Vچcپj‚ج•ƒپ@‚حپAپ@گ¹•گ“Vچcپi‚µ‚ه‚¤‚ق‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پjپA•êپ@
پ@‚حپAپ@Œُ–¾چcچ@پi‚±‚¤‚ف‚ه‚¤‚±‚¤‚²‚¤پjپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@ڈج“؟“Vچcپ@پi‚µ‚ه‚¤‚ئ‚‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پAپ@چفˆت‚V‚U‚Sپ`‚V‚V‚O”NپAپ@گ¶–v”Nپ@
پ@‚V‚P‚Wپ`‚V‚V‚O”Nپjپ@‚حپAپ@چFŒھ“Vچcپ@(‚±‚¤‚¯‚ٌ‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پAچفˆت‚V‚S‚Xپ`‚V
پ@‚T‚W”Nپj‚ئ‚µ‚ؤ“Vچc‚ةچفˆت‚µپAپ@‚»‚جŒمپAپ@چFŒھ ڈمچcپi‘¾ڈم“Vچcپj‚ئ‚ب
پ@‚èپAپ@ڈdâNپi‚؟‚ه‚¤‚»پj‚µ‚ؤپi“Vچc‚ةچؤ‘¦ˆت‚µ‚ؤپjپAپ@ڈج“؟“Vچcپ@پi‚µ‚ه‚¤‚ئ
پ@‚‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پjپ@پiچفˆت‚V‚U‚Sپ`‚V‚V‚O”Nپjپ@‚ئڈج‚µ‚½پB
پ،پ@ڈج“؟“Vچcپ@‚حپAپ@“Vچcچفˆت‘O‚حپAپ@ˆ¢•”“àگe‰¤پ@پi‚ ‚×پi‚جپj‚ب‚¢‚µ
پ@‚ٌ‚ج‚¤پjپ@‚ئڈج‚µپAپ@‚V‚S‚X”N‚©‚çپ@چFŒھ “Vچcپ@(‚±‚¤‚¯‚ٌ‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پjپ@‚ئ
پ@ڈج‚µپAپ@‚V‚T‚W”N‚©‚çپ@چFŒھ ڈمچcپi‘¾ڈم“Vچcپjپ@پi‚±‚¤‚¯‚ٌ ‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پi‚¾
پ@‚¢‚¶‚ه‚¤‚ؤ‚ٌ‚ج‚¤پjپ@‚ئڈج‚µپAپ@‚V‚U‚S”N‚©‚çپ@ڈج“؟ “Vچcپ@پi‚µ‚ه‚¤‚ئ‚‚ؤ‚ٌ
پ@‚ج‚¤پjپ@‚ئڈج‚µ‚½پB
پ@
پ@
پںپ@“ق—اژ‘م’†ٹْ‚جگŒ ‚جگ„ˆعپB
پ،پ@“،Œ´•s”ن“™پi‚U‚T‚Xپ`‚V‚Q‚O”Nپj‚جژ€ŒمپAپ@چc‘°‚ج’·‰®‰¤پi‚ب‚ھ‚₨‚¤پA
پ@‚U‚V‚UپHپ`‚V‚Q‚X”Nپj‚ھگŒ ‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚ء‚½پ@پi’·‰®‰¤گŒ ‚V‚Q‚Oپ`‚V‚Q‚X
پ@”NپjپBپ@“،Œ´•s”ن“™‚جژq‚ج‚SŒZ’ي‚ھپAٹOگت‚ج’nˆت‚ھٹ낤‚‚ب‚é‚ج‚ً‹°
پ@‚ê‚ؤپAپ@‚V‚Q‚X”N‚ةپAچô–d‚ة‚و‚ء‚ؤپAپ@’·‰®‰¤‚ًژ©ژE‚³‚¹ پi’·‰®‰¤‚ج•دپjپA
پ@گŒ ‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚ء‚½پ@پi“،Œ´•گ’q–ƒکCگŒ ‚V‚Q‚Xپ`‚V‚R‚V”NپjپB
پ@
پ،پ@‚V‚R‚V”N‚ةپAپ@“،Œ´ژپ‚SŒZ’ي‚ئ‚àپA—¬چs‚µ‚ؤ‚¢‚½“V‘R“—پi‚ؤ‚ٌ‚ث‚ٌ‚ئ‚¤پjپ@
پ@‚إپA•aژ€‚µ‚ؤپ@پi‚»‚ج‚Sگl‚جژq‹ں’B‚جˆê•”‚حگ¶‚«ژc‚ء‚½‚ھپjپAپ@گŒ “à‚إ
پ@‚ج“،Œ´ژپ‚جگ¨—ح‚حپAˆêژپAŒم‘ق‚µ‚½پB
پ@پ@پ@“،Œ´‚SŒZ’ي‚ھ•aژ€ŒمپA‚©‚ي‚ء‚ؤپAچc‘°ڈoگg‚ج‹kڈ”ŒZپi‚½‚؟‚خ‚ب‚ج‚à
پ@‚낦پA‚U‚W‚Sپ`‚V‚T‚V”Nپj‚ھگŒ ‚جژہŒ ‚ًˆ¬پi‚ة‚¬پj‚ء‚½پBپ@پi‹kڈ”ŒZگŒ ‚V
پ@‚R‚V”Nپ`‚V‚T‚V”NپjپB
پ@
پ،پ@Œُ–¾چcچ@پ@پi‚±‚¤‚ف‚ه‚¤‚±‚¤‚²‚¤پAگ¶–v”N‚V‚O‚Pپ`‚V‚U‚O”Nپjپ@‚حپAپ@“،Œ´
پ@•s”ن“™‚ج–؛‚إپAپ@Œُ–¾ژq پi‚±‚¤‚ف‚ه‚¤‚µپj ‚ئ‚¢‚¢پAپ@گ¹•گپi‚µ‚ه‚¤‚قپj“Vچc
پ@پiچفˆت‚V‚Q‚Sپ`‚V‚S‚X”Nپj‚جچcچ@‚إپAپ@‚ج‚؟پAŒُ–¾چc‘¾چ@پ@پi‚±‚¤‚ف‚ه‚¤‚±‚¤
پ@‚½‚¢‚²‚¤پjپ@‚ئ‚ب‚éپBپ@Œُ–¾چcچ@پ@‚حپAپ@چFŒھپi‚±‚¤‚¯‚ٌپj“Vچcپiچفˆت‚V‚S‚Xپ@
پ@پ`‚V‚T‚W”Nپj‚جگ¶•ê‚إ‚ ‚èپAپ@“،Œ´’‡–ƒکC‚جڈf•êپi‚¨‚خپjپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@“،Œ´“ى‰ئ‚ج“،Œ´•گ’q–ƒکCپi‚س‚¶‚ي‚ç‚ج‚ق‚؟‚ـ‚ëپj‚جژq‚ج“،Œ´’‡–ƒکC
پ@‚حپAپ@ڈf•êپi‚¨‚خپj‚جŒُ–¾چc‘¾چ@پ@‚ئŒ‹‚رپAپ@ژں‘و‚ةگژ،‚جژہŒ ‚ً“¾‚ؤ
پ@‚¢‚«پAپ@“،Œ´’‡–ƒکCپ@‚ھپA‚V‚T‚V”N‚ةپAپ@‹k“ق—ا–ƒکCپi‚½‚؟‚خ‚ب‚ج‚ب‚ç‚ـ‚ëپA
پ@‹kڈ”ŒZ‚جژqپj‚ج—گ‚ً—}‚¦‚ؤپ@پi‹k“ق—ا–ƒکC‚ج•دپjپAپ@ڈ~گmپi‚¶‚م‚ٌ‚ة‚ٌپj“V
پ@چcپiچفˆت‚V‚T‚Wپ`‚V‚U‚S”Nپjپ@‚ً—i—§‚µ‚ؤپAپ@گŒ ‚جگêگ§‚ًٹm—§‚·‚éپ@پi“،Œ´
پ@’‡–ƒکCگŒ پi‚V‚T‚Vپ`‚V‚U‚S”NپjپjپB
پ@
پ،پ@‚V‚U‚O”N‚ةپA“،Œ´’‡–ƒکC‚حپAŒم‚ëڈ‚‚إ‚ ‚ء‚½‚جڈf•êپi‚¨‚خپj‚جŒُ–¾چc‘¾
پ@چ@‚ھژ€‹ژ‚·‚é‚ئŒا—§‚ًگ[‚كپAپ@چFŒھ‘¾ڈم“Vچcپi‚±‚¤‚¯‚ٌ‚¾‚¢‚¶‚ه‚¤‚ؤ‚ٌ‚ج
پ@‚¤پj‚ھ’ˆ¤‚·‚éپA“¹‹¾پ@‚ھگiڈo‚µ‚½‚ج‚إپAپ@“،Œ´’‡–ƒکC‚ھپAپ@‚V‚U‚S”N‚ة—گ
پ@‚ً‹N‚±‚µ‚½‚ھپ@پiŒb”ü‰ںڈں‚ج—گپjپAپ@”sژ€‚µ‚½پBپ@“¹‹¾پi‚ا‚¤‚«‚ه‚¤پj‚حپAڈج
پ@“؟پi‚µ‚ه‚¤‚ئ‚پj“Vچcپ@پiچفˆت‚V‚U‚Sپ`‚V‚V‚O”Nپj‚جژxژ‚ً“¾‚ؤپAپ@‚V‚U‚S”N‚ةگ
پ@Œ ‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚ء‚½پ@پi“¹‹¾گŒ ‚V‚U‚Sپ`‚V‚V‚O”NپjپBپ@
پ@
پ،پ@ڈج“؟پi‚µ‚ه‚¤‚ئ‚پj“Vچc‚ھژ€‹ژ‚·‚é‚ئپAپ@“¹‹¾پ@‚حپAŒم‚ëڈ‚‚ًژ¸‚ء‚ؤپAژ¸
پ@‹r‚µپAپ@‚©‚ي‚ء‚ؤپAپ@“،Œ´ژ®‰ئ‚ج“،Œ´•Sگىپ@پi‚س‚¶‚ي‚ç‚ج‚à‚à‚©‚يپA‚V‚R‚Q
پ@پ`‚V‚V‚X”Nپjپ@‚ç‚ھ‚ح‚©‚ء‚ؤپAپ@Œُگmپi‚±‚¤‚ة‚ٌپj“Vچcپiچفˆت‚V‚V‚Oپ`‚V‚W‚P”Nپj
پ@‚ً—i—§‚µپAپ@گŒ ‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚ء‚½پ@پi“،Œ´•SگىگŒ ‚V‚V‚O”Nپ`‚V‚V‚X”NپjپB
پ@
پ@
#shotokuempressappearingscenes
پ@
پôپôپ@ڈ—’é‚جڈج“؟“Vچcپi= چFŒھ“Vچcپj‚ھپ@
پ@پ@پ@پ@“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢پAƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپA
پ@پ@پ@پ@ƒhƒL ƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پB
پ@
پڑپ@ڈ—’é‚جڈج“؟پi‚µ‚ه‚¤‚ئ‚پj“Vچcپ@پi= چFŒھ
پ@پ@پ@(‚±‚¤‚¯‚ٌپj“Vچcپj‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[
پ@پ@پ@‚¢پAƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپB
پœپ@پi’چˆسپjپ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAپ@ƒtƒBƒNƒVƒ‡ƒ“‚إ‚·پBپ@
پ@پ@پ@—ًژj‚جƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAپ@ژjژہپi—ًژjڈم‚جژ–ژہپjپ@
پ@پ@پ@‚ئپ@‰ث‹َ‚جڈo—ˆژ–‚ھپ@چ¬‚¶‚ء‚ؤ•`‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپ@
پ@پ@پ@‚ـ‚½پAŒ»‘م•—‚ةƒAƒŒƒ“ƒW‚µ‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚·پB
پ@
پ،پ@پwپ@‘ه•§ٹJٹلپ@پi‚¾‚¢‚ش‚آ‚©‚¢‚°‚ٌپjپ@پx پBپ@
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚P‚O”NŒأ‘مژjƒhƒ‰ƒ}
پ@پ@پ@ƒXƒyƒVƒƒƒ‹پjپB
پ،پ@چFŒھپiڈج“؟پjپi‚±‚¤‚¯‚ٌپi‚µ‚ه‚¤‚ئ‚پjپj“Vچcپ@
پ@پ@پiچفˆت‚V‚S‚Xپ`‚V‚T‚WپA‚V‚U‚Sپ`‚V‚V‚O”Nپjپ@‚ھپA
پ@پ@پ@“oڈê‚·‚éپBپ@چFŒھپiڈج“؟پj“Vچc‚ج‘¦ˆت‘O
پ@پ@‚ج–¼ڈج‚حپAپ@ˆ¢•”“àگe‰¤پi‚ ‚×پi‚جپj‚ب‚¢
پ@پ@‚µ‚ٌ‚ج‚¤پjپB
پ@
پœپ@ڈج“؟“Vچc پi= ˆ¢•”“àگe‰¤پi‚ ‚×پi‚جپj‚ب
پ@پ@پ@‚¢‚µ‚ٌ‚ج‚¤پjپAچFŒھ“Vچcپj‚ً‰‰‚¶‚½ڈ——D پFپ@
پ@پ@پ@گخŒ´پi‚¢‚µ‚ح‚çپjپ@‚³‚ئ‚فپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ڈمچcگŒ پ@
پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤‚¹‚¢‚¯‚ٌپjپB
پ@
پ،پ@ڈمچcگŒ پB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ڈمچcگŒ پ@پi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤‚¹‚¢‚¯‚ٌپjپB
پœپ@•ت–¼پ@پFپ@‰@گگŒ پ@پi‚¢‚ٌ‚¹‚¢‚¹‚¢‚¯‚ٌپjپAپ@‰@گŒ پ@
پ@پi‚¢‚ٌ‚¹‚¢‚¯‚ٌپjپB پ@
پœپ@‰p–¼پ@پFپ@‚”‚ˆ‚…پ@‚f‚ڈ‚–‚…‚’‚ژ‚چ‚…‚ژ‚”پ@‚ڈ‚†پ@‚پپ@‚’‚…‚”‚‰‚’‚…‚„پ@
پ@‚…‚چ‚گ‚…‚’‚ڈ‚’پB
پ،پ@ژٹْپ@پFپ@•½ˆہژ‘مŒمٹْ‚ج‚P‚O‚W‚U”Nچ پ`‚P‚P‚T‚U”Nچ پBپ@
پ،پ@‰@گپ@‚ئ‚حپAپ@ڈمچcپ@پi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پAŒ³“Vچcپjپ@‚ھپAپ@’©’ى
پ@‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚éگژ،Œ`‘شپB
پ،پ@ڈمچcگژ،پi‰@گگژ،پjپ@‚ئ‚حپAپ@ڈمچcپi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پAŒ³“Vپ@
پ@چcپj‚ھپA’©’ى‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚èپA‚³‚ç‚ةپA“ْ–{‚جگژ،‚جژہŒ پ@
پ@‚ًژ‚؟پA“ْ–{‚ًژx”z‚µ‚½گژ،Œ`‘شپB
پ،پ@ڈمچcگŒ پi‰@گگŒ پjپ@‚ئ‚حپAپ@ڈمچcپi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پAŒ³“Vپ@
پ@چcپj‚ھپA’©’ى‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚èپA‚³‚ç‚ةپA“ْ–{‚جگژ،‚جژہŒ
پ@‚ًژ‚؟پA“ْ–{‚ًژx”z‚µ‚½گŒ پB
پœپ@ڈمچcگŒ پi‰@گگŒ پA‚P‚O‚W‚U”Nچ پ`‚P‚P‚T‚U”Nچ پj‚حپA
پ@”’‰حڈمچcپi‰@گ‚P‚O‚W‚U”Nپ`‚P‚P‚Q‚X”NپjپA’¹‰Hڈمچcپi‰@گ
پ@‚P‚P‚Q‚X”Nپ`‚P‚P‚T‚U”Nپjپ@‚ھپA’©’ى‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚èپA‚³‚ç‚ةپA
پ@“ْ–{‚جگژ،‚جژہŒ ‚ًژ‚؟پA“ْ–{‚ًژہژ؟“I‚ةژx”z‚µ‚½گ
پ@Œ پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ،پ@”’‰حڈمچc‚ھپA‚P‚O‚W‚U”N‚ةپA‰@گ‚ً‘nژn‚µپA‚³‚ç‚ةپA‰@
پ@گگŒ پiڈمچcگŒ پA‚P‚O‚W‚U”Nچ پ`‚P‚P‚T‚U”Nچ پj‚ًژ÷—§‚·
پ@‚éپBپ@
پ،پ@ڈمچcپ@پi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پAˆّ‘ق‚µ‚½“Vچcپj‚حپAپ@‰@’،‚ًژg‚ء‚ؤپA
پ،پ@ڈمچcپ@‚حپAپ@‰@گéپi‚¢‚ٌ‚؛‚ٌپjپAپ@‰@’،‰؛•¶پi‚¢‚ٌ‚ج‚؟
پ@‚ه‚¤‚‚¾‚µ‚ش‚فپjپ@‚ب‚ا‚ة‚و‚ء‚ؤپA’ت’B‚ًڈo‚µ‚½پB
پ@
پ@
پ،پ@‰@گ‚حپAڈمچcپi‘قˆت‚µ‚½“Vچcپj‚ھ“Vچc‚ة‘م‚ي‚ء‚ؤ
پ@’©’ى‚جگ–±‚ًچs‚¤‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@“Vچc‚ھپAڈمچc‚جژqپA‚ـ‚½‚حڈمچc‚ج‘·‚ب‚ا‚جڈêچ‡پA
پ@‰@گ‚ًچs‚¤‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ،پ@“`““I‚ب“Vچc‚ئ‚¢‚¤’nˆت‚حپA—lپX‚ب–ٌ‘©ژ–‚ھ‚آ‚¢
پ@‚ؤ‰ٌ‚èپAپ@گV‚µ‚¢ژ‘م‚ج—¬‚ê‚ة‘خ‰‚µ‚ة‚‚¢—lپX‚ب‚±
پ@‚ئ‚ھ‹N‚±‚éپBپ@‚»‚±‚إپA“Vچc‚حپA‘قˆت‚µ‚ؤپAڈمچc‚ئ‚¢‚¤
پ@ژ©—R‚ب—§ڈê‚ة—§‚؟پAگ¢‚ج’†‚ج“®‚«‚ة‘¦‰‚·‚éگژ،‚ً
پ@چs‚¨‚¤‚ئ‚µ‚½پB
پ@
پ،پ@ڈمچcپ@پi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پAˆّ‘ق‚µ‚½“Vچcپj‚حپAپ@‰@’،‚ًژg‚ء‚ؤپA
پ@پ@پ@پ@‰@’،‚ئ‚حپAڈمچcپ@پi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پAˆّ‘ق‚µ‚½“Vچcپj‚جژ–
پ@پ@–±‹@ٹض‚إپAپ@‰@گژ‚حپAگ–±‹@ٹض‚ئ‚ب‚éپB
پ@پ@پ@پ@‰@’،‚جگEˆُ‚ھپAپ@‰@ژiپi‚¢‚ٌ‚µپj‚إ‚ ‚éپBپ@‰@’،‚ة
پ@‚¨‚¢‚ؤپAڈمچc‚جژ––±پAگ–±‚ًچs‚ء‚½ٹ¯گl‚إ‚ ‚éپB
پ@•ت“–پi‚ׂء‚ئ‚¤پjپA”N—aپi‚ث‚ٌ‚وپjپA”»ٹ¯‘مپAژه“T‘مپA
پ@–k–ت‚ج•گژmپ@‚ب‚ا‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@‰@گéپ@‚ئپ@‰@’،‰؛•¶پB
پœپ@‰@گéپ@پi‚¢‚ٌ‚؛‚ٌپj‚حپAپ@ڈمچcپi= ‰@پj‚ج–½—ك‚ً‰؛’B
پ@‚·‚镶ڈ‘پ@‚إ‚ ‚éپBپ@‰@ژiپi‚¢‚ٌ‚µپj‚ھپAڈمچc‚ج‹آ‚¹‚ً
پ@•ٍپi‚ظ‚¤پj‚¶‚ؤڈo‚·•ٍڈ‘پi‚ظ‚¤‚µ‚هپj‚جŒ`ژ®‚ً‚ئ‚éپB
پ@پ@پ@‰@’،‰؛•¶پ@پi‚¢‚ٌ‚ج‚؟‚ه‚¤‚‚¾‚µ‚ش‚فپjپ@‚حپA‰@’،
پ@پi‚¢‚ٌ‚ج‚؟‚ه‚¤پj‚©‚çڈo‚³‚ê‚éŒِ•¶ڈ‘پ@‚إپAپ@‰@گéپi‚¢
پ@‚ٌ‚؛‚ٌپj‚و‚è‚àŒِ“I‚إپAپ@ڈظ’؛پi‚µ‚ه‚¤‚؟‚ه‚پjپAٹ¯•„‚ئ
پ@“¯“™‚جŒّ—ح‚ً—L‚µپAپ@ڈd—v‚بˆس–،‚ً‚à‚ء‚½پB
پ@
پ،پ@ڈمچc‚حپAپ@چ‘ژiپiژَ—جپi‚¸‚è‚ه‚¤پjپj‚½‚؟‚ًژxژگ¨—ح‚ة‚ئ
پ@‚肱‚فپAڈمچcپi=‰@پi‚¢‚ٌپjپj‚جŒنڈٹپi‚²‚µ‚هپj‚ة–k–ت‚ج•گژm
پ@پi‚ظ‚‚ك‚ٌ‚ج‚ش‚µپj‚ً‘gگD‚µ‚½‚èپAپ@Œ¹•½‚ج•گژm‚ً‘¤‹ك‚ة
پ@‚·‚é‚ب‚اپAڈمچcپi=‰@پj‚جŒ —ح‚ً‹‰»‚µ‚½پB
پ@
پ،پ@ڈمچcگژ،پi‰@گگژ،پj‚حپA–@‚âٹµ—ل‚ة‚±‚¾‚ي‚炸‚ةپA
پ@ڈمچc‚ھپAگژ،‚جژہŒ ‚ًگêگ§“I‚ةچsژg‚µ‚½پBپ@پ@
پ@پ@پ@پ@ڈمچcگژ،پi‰@گگژ،پj‚إ‚حپA‰@’،پi‚¢‚ٌ‚ج‚؟‚ه‚¤پj‚ً
پ@’u‚«پAڈمچc‚ج–½—ك‚ً“`‚¦‚é‰@گéپi‚¢‚ٌ‚؛‚ٌپj‹y‚رپAپ@‰@’،
پ@‚©‚ç‰؛پi‚‚¾پj‚³‚ê‚镶ڈ‘‚ج‰@’،‰؛•¶پi‚¢‚ٌ‚ج‚؟‚ه‚¤‚‚¾‚µ
پ@‚ش‚فپj‚ھپAچ‘گˆê”ت‚ةژں‘وپi‚µ‚¾‚¢پj‚ةŒّ—ح‚ًژ‚آ‚و‚¤‚ة
پ@‚ب‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@گغٹض‰ئ‚حپAگ¨—ح‚جگٹ‘ق‚ًپAڈمچcپi‰@پj‚ئŒ‹‚ر‚آ‚‚±‚ئ
پ@‚إگ·‚è‚©‚¦‚»‚¤‚ئ“w‚ك‚½پB
پ@
پ،پ@ڈمچcگژ،پi‰@گگژ،پjپ@‚إ‚حپAڈمچcپ@‚ھپA‰@’،پi‚¢‚ٌ‚ج
پ@‚؟‚ه‚¤پj‚إگ–±‚ً‚ئ‚èپAپ@‰@گéپi‚¢‚ٌ‚؛‚ٌپj‚â‰@’،‰؛•¶پi‚¢
پ@‚ٌ‚ج‚؟‚ه‚¤‚‚¾‚µ‚ش‚فپj‚إ‰؛’B‚µ‚½پBپ@‰@‹كگb‚ة‚حپAژَ—ج
پ@پi‚¸‚è‚ه‚¤پAچ‘ژiپj‚ھپA‘½‚ژQ‰ء‚µپAگ–±‚ح‰@’،‚إچs‚ء‚½پBپ@
پ@پ@پ@‰@’،‚إگ–±‚ً‚ئ‚éپAڈمچc‚ئ‰@‹كگb‚حپAپ@“Vچc‚âگغٹض
پ@‰ئ‚ئ‘خ—§‚µ‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ،پ@ڈمچcگژ،پi‰@گگژ،پj‚إپ@ڈمچcپi=‰@پi‚¢‚ٌپjپj‚جŒRژ–
پ@—ح‚ئ‚µ‚ؤگف‚¯‚ç‚ꂽپA–k–تپi‚ظ‚‚ك‚ٌپj‚ج•گژm‚حپAپ@•گ
پ@ژmٹK‹‰‚جگ¬’·‚جˆêˆِ‚ئ‚ب‚ء‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ،پ@‰@گپ@‚ئ‚حپAڈمچc‚ھپA “Vچc‚ًŒمŒ©پi‚±‚¤‚¯‚ٌپj‚µ‚ب‚ھ‚ç
پ@’©’ى‚جژہŒ ‚ً‚ة‚¬‚éگژ،Œ`‘شپ@‚إ‚ ‚éپB
پ،پ@ڈمچc پi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پjپ@‚ئ‚حپAپ@ڈ÷ˆت‚µ‚½پi‘قˆت‚µ‚½پj“Vچc
پ@پiŒ³“Vچcپj‚إپAپ@–@چcپi‚ظ‚¤‚¨‚¤پj‚ئ‚حپAپ@•§–ه‚ة“ü‚ء‚½ڈم
پ@چcپ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ@
پںپ@•½ˆہژ‘مŒمٹْ‚ج‰@گگŒ پi‚P‚O‚W‚U”Nچ
پ@پ`‚P‚P‚T‚U”Nچ پjپB
پ،پ@“ْ–{‚إ‚حپAپ@گغٹضگژ،پ@پi‚P‚Oگ¢‹IŒم”¼پ`‚P‚Pگ¢‹IŒم
پ@”¼پj‚ھپAگٹ‚¦‚ؤپAپ@‰@گگژ،پ@پi‚P‚Pگ¢‹IŒم”¼پ`‚P‚Qگ¢‹I
پ@Œم”¼پjپ@‚ھپAپ@ژn‚ـ‚éپB
پ،پ@‚P‚O‚W‚U”N‚و‚èپA‰@گگژ،پi‚P‚O‚W‚Uپ`‚P‚P‚T‚U”Nپj‚ھٹJ
پ@ژn‚³‚êپAپ@ڈمچcپi”’‰حڈمچc‚â’¹‰Hڈمچcپj‚ھپA’©’ى‚جژہ
پ@Œ ‚ًˆ¬‚èپA‚³‚ç‚ةپA“ْ–{‚جگژ،‚جژہŒ ‚ًژ‚؟پA“ْ–{‚ً
پ@ژہژ؟“I‚ةژx”z‚µ‚½پB
پ@پ@پ@‚µ‚©‚µپA•½ژ،‚ج—گپi‚P‚P‚T‚X”NپjˆبŒمپAپ@ڈمچc‚جŒ —ح
پ@پi“ْ–{‚ًژx”z‚·‚éژہŒ پj‚حگٹ‚¦‚½‚ھپ@پiڈمچc‚ح“ْ–{‚ج
پ@گژ،‚جژہŒ ‚حژ‚½‚ب‚©‚ء‚½‚ھپjپAپ@‚»‚جŒمپA’f‘±“I‚ةپA
پ@ڈمچc‚ھ’©’ى‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚éپA‰@گ‚حپAپ@چ]Œث––ٹْ‚ج‚P‚W
پ@‚S‚O”N‚ـ‚إپAچs‚ي‚ꂽپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ،پ@”’‰حڈمچc‚حپA‚P‚O‚W‚U”N‚و‚èپAپ@–x‰حپi‚ظ‚è‚©‚يپj“VچcپA
پ@’¹‰Hپi‚ئ‚خپj“VچcپAگ’“؟پi‚·‚ئ‚پj“Vچc‚ج‚R‘م‚ة‚ي‚½‚èپA–ٌ
پ@‚S‚R”NٹشپA‰@گ‚ًچs‚¢پA‚³‚ç‚ةپA“ْ–{‚جگژ،‚جژہŒ ‚ًˆ¬
پ@‚èپA‰@گگژ،پi‰@گگژ،ٹْپA‚P‚O‚W‚U”Nپ`‚P‚P‚Q‚X”Nپj‚ًچs
پ@‚ء‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ،پ@’¹‰Hڈمچc‚حپAپ@”’‰حڈمچcپi‚µ‚ç‚©‚ي‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پj‚جژ€ŒمپA
پ@گ’“؟پi‚·‚ئ‚پj“VچcپA‹ك‰qپi‚±‚ج‚¦پj“VچcپAŒم”’‰حپi‚²‚µ‚ç
پ@‚©‚يپj“Vچc‚ج‚R‘م‚ة‚ي‚½‚èپA–ٌ‚Q‚V”NٹشپA‰@گ‚ًچs‚¢پA‚³
پ@‚ç‚ةپA“ْ–{‚جگژ،‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚èپA‰@گگژ،پi‰@گگژ،
پ@ٹْپA‚P‚P‚Q‚Xپ`‚T‚U”Nپjپj‚ًچs‚ء‚½پB
پ@
پ،پ@“Vچc‚جچcˆتŒpڈ³ڈ‡پ@‚حپAپ@”’‰حپi‚µ‚ç‚©‚يپj“Vچcپ@پث
پ@–x‰حپi‚ظ‚è‚©‚يپj“Vچcپ@پثپ@’¹‰Hپi‚ئ‚خپj“Vچcپ@پثپ@گ’“؟
پ@پi‚·‚ئ‚پj“Vچcپ@پثپ@‹ك‰qپi‚±‚ج‚¦پj“Vچcپ@پثپ@Œم”’‰حپi‚²
پ@‚µ‚ç‚©‚يپj“Vچcپ@پثپ@“ٌڈًپi‚ة‚¶‚ه‚¤پj“Vچcپ@پثپ@کZڈًپi‚ë
پ@‚‚¶‚ه‚¤پj“Vچcپ@پثپ@چ‚‘qپi‚½‚©‚‚çپj“Vچcپ@پثپ@ˆہ“؟پi‚
پ@‚ٌ‚ئ‚پj“Vچcپ@پثپ@Œم’¹‰Hپi‚²‚ئ‚خپj“Vچcپ@‚جڈ‡‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@”’‰حپE’¹‰Hڈمچc‚ئ‚àپAگ’•§‚ج”Oپi‚ث‚ٌپj‚ھŒْ‚پi•§‹³‚ً
پ@Œْ‚گM‹آ‚µپjپA‘¢ژ›‘¢•§‚ًچs‚¤پBپ@‚ـ‚½پA‹پi“sپj‚جچxٹO‚ة
پ@—£‹{پi‚è‚«‚م‚¤پj‚ً‘¢‰c‚·‚éپBپ@‚±‚ê‚ç‚ج”ï—p‚ً’²’B‚·‚é
پ@‚½‚كپAپ@گ¬Œ÷پi‚¶‚ه‚¤‚²‚¤پA”„ˆتپA”„ٹ¯‚ب‚اپj‚ھ‚³‚©‚ٌ‚ة‚ب
پ@‚èپAگژ،‚ھ—گ‚ꂽپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ@
پ،پ@•غŒ³‚ج—گپi‚P‚P‚T‚U”NپjپE•½ژ،‚ج—گپi‚P‚P‚T‚X”NپjŒمپA •گ
پ@ژm‚ھ‘ن“ھ‚µپA‰@گگŒ پiڈمچcگŒ پA‚P‚O‚W‚U”Nچ پ`‚P‚P
پ@‚T‚U”Nچ پj‚ھگٹ‚¦‚ؤپAپ@‘م‚ي‚ء‚ؤپA•گ ‰ئگژ،‚ج•½ژپگ
پ@Œ پ@پi‚P‚P‚U‚O”Nچ پ`‚P‚P‚W‚T”Nچ پj‚ھپC“ْ–{‚ًژx”z‚·‚éپB
پœپ@ڈمچcگŒ پA‘¦‚؟پA‰@گگŒ پ@پi‚¢‚ٌ‚¹‚¢‚¹‚¢‚¯‚ٌپjپ@
پ@‚حپAپ@‚P‚O‚W‚U”N چ ‚©‚ç‚P‚P‚T‚U”Nچ ‚ـ‚إ‚إپAپ@‚P‚O‚W‚U”N
پ@‚ةپA”’‰ح“Vچc‚ھ–x‰ح“Vچc‚ةڈ÷ˆت‚µپA”’‰حڈمچc‚ئ‚ب‚èپA
پ@‰@گگژ،‚ًٹJژn ‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@”’‰حڈمچc‚حپA‰@’،‚ً’u‚«پA‰@گگŒ پiڈمچcگŒ پj
پ@‚ًژ÷—§‚µپA‚»‚ê‚ً’¹‰Hڈمچc‚ھˆّ‚«Œp‚¢‚¾‚ھپA‚P‚P‚T‚U”N
پ@‚ج’¹‰Hڈمچc‚جژ€‹ژ‚ئ‚ئ‚à‚ةپA‰@گگŒ پiڈمچcگŒ پj‚حپA
پ@ڈء–إ‚µپA‚P‚P‚T‚U”N‚ج•غŒ³‚ج—گ‚ھ‹N‚±‚èپAپ@چXپi‚³‚çپj‚ةپA
پ@‚P‚P‚T‚X”N‚ج•½ژ،‚ج—گ‚ھ‹N‚±‚èپAˆةگ¨•½ژپ‚ج•½گ´گ·پi‚½
پ@‚¢‚ç‚ج‚à‚«‚و‚èپj‚ھپA‰ح“àŒ¹ژپ‚جŒ¹‹`’© پi‚ف‚ب‚à‚ئ‚ج
پ@‚و‚µ‚ئ‚àپj‚ةڈں‚؟پAپ@‚P‚P‚U‚O”N‚ةپA•½گ´گ·‚حپA گ³ژOˆت‚ة
پ@ڈ–پi‚¶‚هپj‚¹‚ç‚êŒِ‹¨پi‚‚¬‚ه‚¤پj‚ة—ٌ‚µپA“ْ–{‚جگژ،‚ج
پ@ژہŒ ‚ًˆ¬‚èپA •½ژپگŒ ‚ھڈoŒ»‚·‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ@
پ،پ@ڈمچcگŒ پ@پi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤‚¹‚¢‚¯‚ٌپjپ@‚حپAژٹْ‚حپA•½ˆہژ
پ@‘مŒمٹْ‚ج‚P‚O‚W‚U”Nچ پ`‚P‚P‚T‚U”Nچ پ@‚إپA‰@گگŒ پ@پi‚¢
پ@‚ٌ‚¹‚¢‚¹‚¢‚¯‚ٌپjپAپ@‰@گŒ پ@پi‚¢‚ٌ‚¹‚¢‚¯‚ٌپjپ@‚ئ‚àŒ¾‚¤پB پ@
پ@‰p–¼‚حپAپ@‚”‚ˆ‚…پ@‚f‚ڈ‚–‚…‚’‚ژ‚چ‚…‚ژ‚”پ@‚ڈ‚†پ@‚پپ@‚’‚…‚”‚‰‚’‚…‚„پ@
پ@‚…‚چ‚گ‚…‚’‚ڈ‚’پ@‚إ‚ ‚éپB
پ،پ@‰@گپ@‚ئ‚حپAپ@ڈمچcپ@پi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پAŒ³“Vچcپjپ@‚ھپAپ@’©’ى
پ@‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚éگژ،Œ`‘شپ@‚إ‚ ‚éپB
پ،پ@‰@گگژ،پiڈمچcگژ،پjپ@‚ئ‚حپAپ@ڈمچcپi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پAŒ³“Vپ@
پ@چcپj‚ھپA’©’ى‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚èپA‚³‚ç‚ةپA“ْ–{‚جگژ،‚جژہŒ
پ@‚ًژ‚؟پAپ@“ْ–{‚ًژx”z‚µ‚½گژ،Œ`‘شپ@‚إ‚ ‚éپB
پ،پ@‰@گگŒ پiڈمچcگŒ پjپ@‚ئ‚حپAپ@ڈمچcپi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پAŒ³“Vپ@
پ@چcپj‚ھپA’©’ى‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚èپA‚³‚ç‚ةپA“ْ–{‚جگژ،‚جژہŒ
پ@‚ًژ‚؟پA“ْ–{‚ًژx”z‚µ‚½گŒ پ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‰@گگŒ پiڈمچcگŒ پA‚P‚O‚W‚U”Nچ پ`‚P‚P‚T‚U”Nچ پj‚حپA
پ@”’‰حڈمچcپi‰@گ‚P‚O‚W‚U”Nپ`‚P‚P‚Q‚X”NپjپA’¹‰Hڈمچcپi‰@گ
پ@‚P‚P‚Q‚X”Nپ`‚P‚P‚T‚U”Nپjپ@‚ھپA’©’ى‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚èپA‚³‚ç‚ةپA
پ@“ْ–{‚جگژ،‚جژہŒ ‚ًژ‚؟پA“ْ–{‚ًژہژ؟“I‚ةژx”z‚µ‚½گ
پ@Œ پ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ،پ@”’‰حڈمچc‚ھپA‚P‚O‚W‚U”N‚ةپA‰@گ‚ً‘nژn‚µپA‚³‚ç‚ةپA‰@
پ@گگŒ پiڈمچcگŒ پA‚P‚O‚W‚U”Nچ پ`‚P‚P‚T‚U”Nچ پj‚ًژ÷—§
پ@‚·‚éپBپ@
پ@
پںپ@پi‚rپjپ@“ْ–{‚جگژ،Œ`‘شپB
پ،پ@پi‚rپjپ@“ْ–{‚جگژ،Œ`‘شپB
پ@پi‚r‚P‚„پjپ@ڈ¬چ‘ژٌ’·گژ،پ@پi‘O‚Pگ¢‹Iپ`‹IŒ³Œم‚Tگ¢‹Iپjپث
پ@پi‚r‚P‚‡پjپ@چ‹‘°کAچ‡گژ،پ@پi‚Tپ`‚Vگ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚r‚Qپjپ@—¥—ك
پ@گژ،پ@پi‚Vپ`‚P‚Oگ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚r‚Rپjپ@گغٹضگژ،پ@پi‚P‚Oپ`‚P‚P
پ@گ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚r‚Sپjپ@‰@گگژ،پ@پi‚P‚Pپ`‚P‚Qگ¢‹Iپj پثپi‚r‚Tپj
پ@•گ‰ئگژ،پ@پi‚P‚Qپ`‚P‚Xگ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚r‚Uپjپ@‹ك‘م“Vچcگeگ
پ@گژ،پ@پi‹ك‘م“Vچcگâ‘خژه‹`گژ،پjپ@پi‚P‚Xپ`‚Q‚Oگ¢‹Iپjپ@پث
پ@پi‚r‚Vپjپ@Œ»‘مچ‘–¯ژهŒ گژ،پ@پiŒ»‘مژهŒ چف–¯گژ،پj پi‚Q‚O
پ@پ`‚Q‚Pگ¢‹I‚جŒ»چفپjپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پœپ@ڈم‹Lچ€–ع‚جڈعچׂةٹض‚µ‚ؤ‚حپAپ@“–“ْ–{Œêژ«“T‚جٹeچ€–ع
پ@‚ًژQڈئ‚µ‚ؤ‰؛‚³‚¢پB
پ@
پ،پ@پi‚r‚Rپjپ@پثپ@پi‚r‚Sپjپ@گغگپEٹض”’‚ة‘م‚ي‚ء‚ؤپAڈمچc‚ھپAگ
پ@ژ،‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚ء‚½‚½‚كپAپ@پi‚r‚Rپjپ@گغٹضگژ، پi‚P‚Oپ`‚P‚Pگ¢پ@
پ@‹Iپj‚حپAپ@پi‚r‚Sپjپ@‰@گ گژ،پ@پi‚P‚Pپ`‚P‚Qگ¢‹Iپjپ@‚ةˆعچs‚·
پ@‚éپi‚ض•د‚ي‚éپjپBپ@پ@
پ@
پ،پ@پi‚r‚Sپjپ@‰@گگژ،پ@‚ئ‚حپAپ@ڈمچcپ@پi‚¶‚ه‚¤‚±‚¤پAŒ³“Vچcپj
پ@‚ھپA’©’ى‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚èپA‚³‚ç‚ةپA“ْ–{‚جگژ،‚جژہŒ ‚ًژ
پ@‚؟پA“ْ–{‚ًژx”z‚µ‚½گژ،Œ`‘شپ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@”’‰حڈمچcپi‰@گ گژ،ٹْپA‚P‚O‚W‚U”Nپ`‚P‚P‚Q‚X”Nپj‚â’¹
پ@‰Hڈمچcپi‰@گگ¶ژٹْپA‚P‚P‚Q‚X”Nپ`‚P‚P‚T‚U”Nپjپ@‚ھپA’©’ى
پ@‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚èپA‚³‚ç‚ةپA“ْ–{‚جگژ،‚جژہŒ ‚ًژ‚؟پA“ْ–{
پ@‚ًژہژ؟“I‚ةژx”z‚µ‚½ٹْٹش‚جگژ،Œ`‘شپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@پi‚r‚Sپjپ@پثپ@پi‚r‚Tپjپ@‚P‚P‚T‚X”Nپi•½ژ،Œ³”Nپj‚ج•½ژ،‚ج—گ
پ@‚إ•گژm‚ج•گ—ح‚ج—ح‚إگژ،‚ج‘ˆ‚¢‚ھŒˆ’…ŒمپAپ@پi‚r‚Sپjپ@‰@
پ@گگژ،پ@پi‚P‚Pپ`‚P‚Qگ¢‹Iپjپ@‚حپAپi‚r‚Tپjپ@•گ‰ئگژ،پ@پi‚P‚Q
پ@پ`‚P‚Xگ¢‹Iپjپ@‚ةˆعچs‚·‚éپi‚ض•د‚ي‚éپjپBپ@پ@
پœپ@•غŒ³‚ج—گپi‚P‚P‚T‚U”NپjپE•½ژ،‚ج—گپi‚P‚P‚T‚X”NپjŒمپAپ@•گژm
پ@‚ھ‘ن“ھ‚µپAڈمچcگŒ پi‰@گگŒ پA‚P‚O‚W‚U”Nچ پ`‚P‚P‚T‚U”N
پ@چ پj‚ھگٹ‚¦‚ؤپA‘م‚ي‚ء‚ؤپAپ@•گ‰ئگژ،‚ج•½ژپگŒ پ@پi‚P‚P‚U
پ@‚O”Nچ پ`‚P‚P‚W‚T”Nچ پjپ@‚ھپC“ْ–{‚ًژx”z‚·‚éپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ژپگ©پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚¹‚¢پjپB
پ@
پ،پ@ژپگ©پB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@پi‘O‹ك‘م“ْ–{‚جپjپ@ژپگ© پi‚µ‚¹‚¢پjپB
پ،پ@ژٹْپ@پFپ@Œأ‘م“ْ–{ پ` ‹كگ¢“ْ–{‚جژٹْچ پ@
پiŒأ•پE”ٍ’¹”’–Pژ‘مپi‘هکaژ‘مپjپ` چ]Œثژ‘م
پ@پ@چ پjپB
پ،پ@‘O‹ك‘م‚جپAژپ‘°–¼‚âگ©پi‚©‚خ‚ثپj‚ئ‚¢‚¤ˆê‘°–¼پB
پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جپAˆê‘°–¼‚ج‚P‚آپB
پ@
پ@
پ،پ@ژپگ© پi‚µ‚¹‚¢پjپ@‚حپAپ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚إ‚حپAپ@ˆê‘°
پ@پ@–¼‚ج‚P‚آ‚إپAپ@‘O‹ك‘م‚جپAژپ‘°–¼‚âگ©پi‚©‚خ‚ثپj
پ@پ@‚ئ‚¢‚¤ˆê‘°–¼پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@ˆê‘°–¼پ@پiژپپi‚¤‚¶پjپAگ©پi‚¹‚¢پjپjپ@‚ة‚حپAپ@ژپگ©
پ@پ@پi‚µ‚¹‚¢پjپAپ@–¼ژڑپi‚ف‚ه‚¤‚¶پjپA‰®چ†پi‚₲‚¤پjپ@“™
پ@پ@‚ھ‚ ‚èپA پ@پuژپگ©پi‚µ‚¹‚¢پAگ©ژپپj‚جژپ‘°–¼پi‚µ‚¼
پ@ ‚‚ك‚¢پj‚ئگ©پi‚©‚خ‚ثپjپvپ@‚إ‚ ‚èپAپ@پu–¼ژڑپi‚ف‚ه‚¤
پ@پ@‚¶پj‚ج‰ئ–¼پi‚©‚ك‚¢پjپvپAپ@پuڈ¤چ†“™‚ج‰®چ†پi‚₲
پ@پ@‚¤پjپvپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@ژپگ©پi‚µ‚¹‚¢پAگ©ژپپj‚جپAژپ‘°–¼پi‚µ‚¼‚‚ك‚¢پjپ@‚حپA
پ@پ@‰ئ‚·‚¶‚ً•\‚·–¼ڈج‚إ‚ ‚èپAپ@ژپگ©پi‚µ‚¹‚¢پAگ©ژپپj‚جپA
پ@پ@گ©پi‚©‚خ‚ثپjپ@‚حپAپ@‰ئ•؟‚ج‘¸”ع‚ج‹و•ت‚ً•\‚·–¼ڈجپ@
پ@پ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ،پ@گ¼‹½—²گ·‚جڈêچ‡پB
پœپ@گ¼‹½—²گ·‚جژپگ©پ@‚حپAپ@پu•½’©گbپvپ@پi‚½‚¢‚ç‚ج ‚
پ@پ@‚»‚ٌپjپ@ ‚إ‚ ‚èپAپ@’©’ى‚جŒِ•¶ڈ‘‚إ‚حپAپ@گ¼‹½—²گ·
پ@پ@‚حپAپu•½پ@’©گbپ@—²گ·پvپ@پi‚½‚¢‚ç‚ج ‚ ‚»‚ٌ ‚½‚©‚à
پ@پ@‚èپj ‚ئپ@‹L‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½پB
پœپ@پu•½پ@’©گbپ@—²گ·پvپ@‚حپAپ@ˆê‘°–¼‚جپuژپگ©‚جژپ‘°
پ@پ@–¼پi‚µ‚¼‚‚ك‚¢پjپ{ˆê‘°–¼‚جپuژپگ©‚جگ©پi‚©‚خ‚ثپjپv
پ@پ@پ{Œآگl–¼‚جپuوپپi‚¢‚ف‚بپj‚جژہ–¼پvپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@گD“cگM’·‚جڈêچ‡پB
پœپ@گD“cگM’·‚جژپگ©پ@‚حپAپ@پu•½’©گbپvپ@پi‚½‚¢‚ç‚ج
پ@پ@‚ ‚»‚ٌپjپ@ ‚إ‚ ‚èپAپ@’©’ى‚جŒِ•¶ڈ‘‚إ‚حپAپ@گD“c
پ@پ@گM’·‚حپAپu•½پ@’©گbپ@گM’·پvپ@پi‚½‚¢‚ç‚ج ‚ ‚»‚ٌ
پ@پ@‚ج‚ش‚ب‚ھپj ‚ئپ@‹L‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½پB
پœپ@پu•½پ@’©گbپ@گM’·پvپ@‚حپAپ@ˆê‘°–¼‚جپuژپگ©‚جژپ‘°
پ@پ@–¼پi‚µ‚¼‚‚ك‚¢پjپ{ˆê‘°–¼‚جپuژپگ©‚جگ©پi‚©‚خ‚ثپjپv
پ@پ@پ{Œآگl–¼‚جپuوپپi‚¢‚ف‚بپj‚جژہ–¼پvپ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ@
پ،پ@“ْ–{‚إ‚حپA‘O‹ك‘م‚ئŒ»‘م‚جژپ–¼‚ً”نٹr‚·‚é‚ئپAپ@
پ@پ@‘O‹ك‘م‚جˆê‘°–¼پiپuژپپi‚¤‚¶پjپvپj‚ة‚حپAپ@ژپگ© پi‚µ
پ@پ@‚¹‚¢پjپAپ@–¼ژڑ پi‚ف‚ه‚¤‚¶پjپAپ@‰®چ† پi‚₲‚¤پjپ@“™
پ@پ@‚ھ‚ ‚èپAپ@‚ـ‚½پAپ@‘O‹ك‘م‚جŒآگl–¼پiپu–¼پi‚بپjپvپj
پ@پ@‚ة‚حپAپ@وپ پi‚¢‚ف‚بپAژہ–¼پjپAپ@’تڈج پi‚ ‚¾–¼پjپAپ@
پ@پ@چ† پi‚²‚¤پjپAپ@پ@—¥—كٹ¯–¼ پi‚è‚آ‚è‚ه‚¤‚©‚ٌ‚ك‚¢پjپAپ@
پ@پ@–@–¼ پi‚ظ‚¤‚ف‚ه‚¤پjپ@“™‚ھ‚ ‚ء‚½پBپ@
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جگl–¼پB
پ،پ@‘O‹ك‘م“ْ–{‚جڈم‘wٹK‘w‚ج“ْ–{گlگ¬گl’jگ«پ@
پ@پ@‚حپAپ@Œ»‘م“ْ–{گl‚ج–¼ژڑ‚ئ–¼‚جƒڈƒ“ƒpƒ^پ[ƒ“
پ@پ@چ\گ¬‚جژپ–¼‚إ‚ح‚ب‚پAپ@پu•،گ”ƒpƒ^پ[ƒ“پi‘gچ‡
پ@پ@‚¹پjچ\گ¬‚جژپ–¼پvپ@‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
پ¥پ@ˆê‘°–¼پ@پiژپپi‚¤‚¶پjپjپ@پ{پ@Œآگl–¼پ@پi–¼پi‚بپjپjپ@
پ@پ@‚ج‘g‚فچ‡‚ي‚¹پB
پ،پ@‡@پ@پuپ@–¼ژڑپi‚ف‚ه‚¤‚¶پjپ@پ{پ@’تڈجپi‚آ‚¤‚µ‚ه‚¤پjپvپBپ@پ@
پ@پ@ ‡Aپ@پuپ@–¼ژڑپ@پ{پ@—¥—كٹ¯–¼پi‚è‚آ‚è‚ه‚¤‚©‚ٌ‚ك‚¢پjپ@پv پBپ@
پ@پ@ ‡Bپ@پuپ@ژپگ©پi‚µ‚¹‚¢پj‚جژپ‘°–¼پEگ©پi‚©‚خ‚ثپjپ@پ{پ@
پ@پ@پ@پ@پ@وپپi‚¢‚ف‚بپj‚جژہ–¼پ@پvپBپ@
پ@پ@ ‡Cپ@پuپ@–¼ژڑپ@پ{پ@وپپi‚¢‚ف‚بپj‚جژہ–¼پ@پvپBپ@
پ@پ@ ‡Dپ@پuپ@–¼ژڑپ@پ{پ@چ†پi‚²‚¤پjپ@پvپB
‡Eپ@پuپ@–¼ژڑپ@پ{پ@–@–¼پi‚ظ‚¤‚ف‚ه‚¤پjپ@پvپiŒمگ¢‚جŒؤ‚ر–¼پjپB
پ@پ@ ‡Fپ@پuپ@‰®چ†پi‚₲‚¤پjپ@پ{پ@’تڈجپ@پvپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ،پ@پi—لپjپ@گيچ‘‘ه–¼‚جگD“c گM’· پi‚¨‚¾ ‚ج‚ش‚ب‚ھپjپ@
پ@پ@پ@‚جڈêچ‡پBپ@
پ@پ@‡@پ@پuپ@گD“cپ@ژOکYپ@پvپi‚¨‚¾پ@‚³‚ش‚낤پjپAپ@
پ@پ@‡Aپ@پuپ@گD“cپ@’eگ³’‰ پ@پvپi‚¨‚¾پ@‚¾‚ٌ‚¶‚ه‚¤‚ج‚؟‚م‚¤پjپA
پ@پ@‡Bپ@پuپ@•½پ@’©گbپ@گM’·پ@پvپi‚½‚¢‚ç‚جپ@‚ ‚»‚ٌپ@‚ج‚ش
پ@پ@پ@پ@‚ب‚ھپjپAپ@
پ@پ@‡Cپ@پu پ@گD“cپ@گM’·پ@پvپi‚¨‚¾پ@‚ج‚ش‚ب‚ھپjپ@
پ@پ@پ@“™‚جژپ–¼‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚½پBپ@
پZپ@Œ»چف‚جگ³ژ®–¼‚جپ@‡Cپ@پuپ@–¼ژڑپ{وپپi‚¢‚ف‚بپj‚ج
پ@پ@ژہ–¼پ@پvƒpƒ^پ[ƒ“‚ج Œؤ‚ر•ûپAپ@‡Cپ@پuپ@گD“cپ@گM’·پ@پv
پ@پ@‚ئŒؤ‚خ‚ê‚éƒPپ[ƒX ‚حپAپ@“–ژ‚حپAڈ‚ب‚©‚ء‚½پB
پ،پ@پi—لپjپ@‰z‘O”ثژه‚جڈ¼•½ Œc‰iپ@پi‚ـ‚آ‚¾‚¢‚ç ‚و
پ@پ@‚µ‚ب‚ھپjپ@‚جڈêچ‡پBپ@
پ@پ@ ‡Dپ@پu پ@ڈ¼•½پ@ڈt›شپ@پvپi‚ـ‚آ‚¾‚¢‚çپ@‚µ‚م‚ٌ‚ھ‚پjپ@
پ@پ@“™‚جژپ–¼‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ،پ@پi—لپjپ@گيچ‘‘ه–¼‚جڈمگ™ ŒھگMپ@پi‚¤‚¦‚·‚¬ ‚¯‚ٌ
پ@پ@‚µ‚ٌپjپ@‚جڈêچ‡پBپ@
پ›پ@–@–¼ پu•sژ¯ˆءپi•sژ¯‰@پjŒھگMپvپ@‚و‚èپ@ŒھگM‚ً‚ئ
پ@پ@‚ء‚ؤپAپ@‡Eپ@پu ڈمگ™پ@ŒھگMپ@پvپ@پi‚¤‚¦‚·‚¬ ‚¯‚ٌ
پ@پ@‚µ‚ٌپjپ@‚ئŒمگ¢‚جگl‚ةŒؤ‚خ‚ꂽپBپ@
پ›پ@“–ژ‚حپA‘گ¢‚ج–¼ژڑ‚ئ–@–¼پi‚ظ‚¤‚ف‚ه‚¤پj‚ًˆêڈڈ
پ@پ@‚ةŒؤ‚ش‚±‚ئ‚ح‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@–{گl‚حپA“–ژ‚حپAپuپ@•sژ¯ˆءپi•sژ¯‰@پjŒھگMپ@پv
پ@پ@‚ئڈج‚µ‚ؤ‚¢‚½پB
پ،پ@پi—لپjپ@چ‹ڈ¤‚ج’ƒ‰® ژlکYژںکYپ@پi‚؟‚ل‚â ‚µ‚낤‚¶
پ@پ@‚낤پjپ@‚جڈêچ‡پBپ@
پ@پ@‡Fپ@پuپ@’ƒ‰® پ@ژlکYژںکYپ@پvپi‚؟‚ل‚âپ@‚µ‚낤‚¶‚낤پjپ@
پ@پ@“™‚جژپ–¼‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ƒWƒ‡ƒ“–œژںکYپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚ٌ‚ـ‚ٌ‚¶‚낤پj
پ@
پ،پ@ƒWƒ‡ƒ“–œژںکYپB
پ،پ@گ¶–v”Nپ@پFپ@‚P‚W‚Q‚Vپ`‚X‚W”NپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ƒWƒ‡ƒ“–œژںکYپ@پi‚¶‚ه‚ٌ‚ـ‚ٌ‚¶‚낤پjپB
پ@پ@•ت–¼پ@پFپ@’†•l–œژںکYپ@پi‚ب‚©‚ح‚ـ‚ـ‚ٌ‚¶‚낤پjپB
پ،پ@–‹––پA–¾ژ،ڈ‰ٹْ‚جپA‚ج’ت–َپA–|–َژزپB
پ،پ@–‹––پA–¾ژ،ڈ‰ٹْ‚جپAگV’mژ¯‚جˆع“ü‚ةچvŒ£پB
پ،پ@“yچ²چ‘پi‚ئ‚³‚ج‚‚ةپAچ‚’mŒ§پj‚ج’†•l‘؛پi‚ب‚©‚ح‚ـ‚ق
پ@پ@‚çپj‚ج‹™–¯ڈoگgپB
پ@
پ@
پ،پ@ƒWƒ‡ƒ“–œژںکYپ@پi‚¶‚ه‚ٌ‚ـ‚ٌ‚¶‚낤پAپ@گ¶–v”N‚P‚W‚Q‚Vپ`
پ@‚P‚W‚X‚W”Nپjپ@‚حپA•ت–¼‚حپA پ@’†•l–œژںکYپ@پi‚ب‚©‚ح‚ـ‚ـ
پ@‚ٌ‚¶‚낤پjپ@‚ئŒ¾‚¤پB
پ@
پ،پ@ƒWƒ‡ƒ“–œژںکYپ@‚حپA–‹––پA–¾ژ،ڈ‰ٹْ‚ةپA’ت–َپA–|–َژز
پ@‚إپAپ@“ْ–{‚جگV’mژ¯‚جˆع“ü‚ةچvŒ£‚·‚éپB
پ@
پ،پ@ƒWƒ‡ƒ“–œژںکYپ@‚حپAپ@“yچ²چ‘پi‚ئ‚³‚ج‚‚ةپAچ‚’mŒ§پj‚ج
پ@’†•l‘؛پi‚ب‚©‚ح‚ـ‚ق‚çپj‚ج‹™–¯پ@‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@پ@پ@ƒWƒ‡ƒ“–œژںکYپ@‚حپAپ@‚P‚W‚S‚P”N‚ةپAڈo‹™’†‚ةپA“ï”j‚µپA
پ@ƒAƒپƒٹƒJ‚ج•كŒ~‘Dپi‚ظ‚°‚¢‚¹‚ٌپj‚ة‹~‚ي‚êپAپ@ƒAƒپƒٹƒJ‚إ
پ@‹³ˆç‚ًژَ‚¯پA‚P‚W‚T‚P”N‚ة“ْ–{‚ة‹Aچ‘‚·‚éپB
پ@
پ،پ@–‹––پAƒWƒ‡ƒ“–œژںکYپ@‚حپAپ@‹Aچ‘ŒمپAپ@“yچ²”ثژm‚ة”C—p
پ@‚³‚êپAپ@‚»‚جŒمپAƒyƒٹپ[پEƒAƒپƒٹƒJٹح‘à‚ج—ˆچq‚ة‚ ‚½‚èپA–‹
پ@گb‚ة“o—p‚³‚êپAپ@’ت–َپA–|–َ‚ةڈ]ژ–‚·‚éپB
پ@پ@پ@–‹––پAƒWƒ‡ƒ“–œژںکYپ@‚حپAپ@‚P‚X‚U‚O”N‚ةپA–‹•{ŒٹOپi‚¯
پ@‚ٌ‚ھ‚¢پjژgگك‚ةگڈچs‚·‚éپB
پ@پ@پ@–¾ژ،ٹْ‚ةپAٹJگ¬ٹwچZپi‚©‚¢‚¹‚¢‚ھ‚ء‚±‚¤پA“Œ‹‘هٹw‚ج
پ@‘Oگgپjپ@‚ج‹³ژِ‚ئ‚ب‚éپB
پ@
پ@
پڑپ@ƒWƒ‡ƒ“–œژںکYپ@‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢پAƒh
پ@ƒ‰ƒ}پA‰f‰وپB
پœپ@پi’چˆسپjپ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAپ@ƒtƒBƒNƒVƒ‡ƒ“پ@‚إ‚·پBپ@—ًژj
پ@‚جƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپ@‚حپAژjژہپi—ًژjڈم‚جژ–ژہپjپ@‚ئپ@‰ث‹َ‚ج
پ@ڈo—ˆژ–پ@‚ھپ@چ¬‚¶‚ء‚ؤ•`‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپ@‚ـ‚½پAŒ»‘م•—‚ة
پ@ƒAƒŒƒ“ƒW‚µ‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚·پB
پ@
پ،پ@پwپ@—´”n“`پ@پi‚è‚ه‚¤‚ـ‚إ‚ٌپjپ@پxپ@
پ@پ@پi“ْ–{‚ج‚Q‚O‚P‚O”N‚m‚g‚j‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پjپB
پ@
پ،پ@پwپ@“ؤ•Pپ@پi‚ ‚آ‚ذ‚كپjپ@پxپ@پ@
پ@پ@پi‚m‚g‚j‚Q‚O‚O‚W”N‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پjپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ڈ«ŒRپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚®‚ٌپjپ@
پ@
پ،پ@ڈ«ŒRپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ڈ«ŒRپ@پi‚µ‚ه‚¤‚®‚ٌپjپB
پ،پ@ŒR‚ج“—¦ژزپB
پ،پ@’©’ى‚ج•گٹ¯پi•گگlپj‚جژٌ’·پB
پ،پ@پs •گٹ¯پA•گژm‚جگg•ھپtپB
پ،پ@’©’ى‚ھگف‚¯‚½ڈ«ŒR‚ج‚P‚آ‚ةپAگھˆخ‘هڈ«ŒRپ@پi‚¹
پ@پ@‚¢‚¢‚½‚¢‚µ‚ه‚¤‚®‚ٌپA•ت–¼پFگھˆخڈ«ŒRپjپ@‚ھ‚ ‚éپB
پ،پ@گھˆخ‘هڈ«ŒRپi•ت–¼پFگھˆخڈ«ŒRپj‚ج‘¶چفژٹْپ@پF
پ@پ@ ‚V‚Q‚O”Nپ`‚P‚W‚U‚V”NپB
پ،پ@گھˆخ‘هڈ«ŒR‚حپAپ@“ق—اژ‘مپE•½ˆہژ‘مڈ‰ٹْ‚إ
پ@پ@‚حپAپ@‰عˆخپi‚¦‚¼پA“Œ–k’n•ûپjگھ”°‚ج“—¦ژزپiڈ«
پ@پ@ŒRپj ‚إ‚ ‚èپAپ@•½ˆہژ‘م––ٹْ‚©‚çچ]Œثژ‘م‚ـ‚إ
پ@پ@‚إ‚حپAپ@•گ‰ئپi•گژmپj‚ج“—¦ژزپiڈ«ŒRپjپ@‚إ‚ ‚éپBپ@
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“Tپ@‚P‚P‚V‚P‚WپB
پ@
پ@
پ،پ@ڈ«ŒRپi‚µ‚ه‚¤‚®‚ٌپj ‚ئ‚حپAپ@ŒR‚ج“—¦ژز‚إ‚ ‚èپA’©
پ@پ@’ى‚ج•گٹ¯پi•گگlپj‚جژٌ’·‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@’©’ى‚ھگف‚¯‚½ڈ«ŒR‚ج‚P‚آ‚ةپAپ@گھˆخ‘هڈ«ŒR
پ@پ@پi‚¹‚¢‚¢‚½‚¢‚µ‚ه‚¤‚®‚ٌپAگھˆخڈ«ŒRپj‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پںپ@ڈ«ŒRپB
پ،پ@•گٹ¯پi•گگlپj‚جژٌ’·‚جٹ¯گEپiگE–¼پjپB
پ،پ@Œأ‘م“ْ–{‚إ‚حپAڈ«ŒR‚ئ‚حپAپ@’©’ى‚جگھ“¢پA‹V‰qپA
پ@پ@چsچKژ‚ج—صژ‚ج•گٹ¯پi•گگlپj‚جژٌ’·‚إ‚ ‚éŒR–±
پ@پ@ٹ¯گE‚إ‚ ‚ء‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@Œأ‘م“ْ–{‚إپAڈ«ŒR‚ج‚P‚آ‚ةپAگھˆخ‘هڈ«ŒR
پ@پ@پi•ت–¼پAگھˆخڈ«ŒRپj‚ھ‚ ‚ء‚½پB
پ@
پںپ@ڈ«ŒRپiگھˆخ‘هڈ«ŒRپjپB
پ،پ@گھˆخ‘هڈ«ŒR‚ج•تڈجپA—ھڈج‚جڈ«ŒRپB
پ›پ@•گ‰ئ‚ج“ڈ—ہپi‚ئ‚¤‚è‚ه‚¤پA“—¦ژزپA“—جپA
پ@پ@“ھ—جپj‚إ‚ ‚éڈ«ŒRپB
پ@پ@پ@پ@پ@گھˆخ‘هڈ«ŒR‚حپAپ@•گ‰ئ‚ج“ڈ—ہپ@پi‚ئ‚¤‚è‚ه‚¤پA
پ@پ@“—¦ژزپA“—جپA“ھ—جپj‚إ‚ ‚èپAپ@ٹ™‘q–‹•{‚جٹeڈ«
پ@پ@ŒRپAپ@Œڑ•گٹْ‚جŒى—اگe‰¤پi‚à‚è‚و‚µ‚µ‚ٌ‚ج‚¤پA‘ه“ƒ
پ@پ@‹{پi‚¨‚¨‚ئ‚¤‚ج‚ف‚âپjپjپAپ@ژ؛’¬–‹•{‚âچ]Œث–‹•{‚ج
پ@پ@ٹeڈ«ŒR‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@–‹•{‚جژٌ’·‚إ‚ ‚éڈ«ŒRپB
پ@پ@پ@پ@پ@ٹ™‘q–‹•{پAژ؛’¬–‹•{پAچ]Œث–‹•{پA
پ@پ@‚جڈ«ŒR‚ب‚اپB
پ،پ@گھˆخ‘هڈ«ŒR‚حپAپ@–‹•{‚جژٌ’·‚إ‚ ‚èپAپ@ٹ™‘q–‹
پ@پ@•{پAژ؛’¬–‹•{پAچ]Œث–‹•{پA‚جٹeڈ«ŒR‚ب‚ا‚إ‚ ‚éپB
پ@
پںپ@ڈ«ŒRپiگھˆخ‘هڈ«ŒRپjپB
پ،پ@گھˆخ‘هڈ«ŒRپi‚¹‚¢‚¢‚½‚¢‚µ‚ه‚¤‚®‚ٌپj‚حپAپ@“ق—ا
پ@پ@ژ‘م‚©‚çچ]Œثژ‘م‚ـ‚إپA’©’ى‚©‚ç”C–½‚³‚ꂽپA
پ@پ@•گٹ¯پi•گگlپj‚جژٌ’·‚جٹ¯گEپiگE–¼ پj‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@ڈ«ŒR‚ج‚P‚آپAگھˆخ‘هڈ«ŒRپi•ت–¼پAگھˆخڈ«
پ@پ@ŒRپj‚حپA“–ڈ‰‚حپA“ق—اژ‘مپE•½ˆہژ‘مڈ‰ٹْ‚إ‚حپAپ@
پ@پ@—¤‰œپi‚ق‚آپA“Œ–k’n•ûپj‚ج‰عˆخپi‚¦‚¼پj“¢”°‚ج
پ@پ@‚½‚ك‚ج’©’ى‚ج—صژ‚جٹ¯گE‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@‚»‚جŒمپAگھˆخ‘هڈ«ŒR‚حپAٹ™‘qژ‘م‚و‚èپA
پ@پ@•گ‰ئ‚ج“ڈ—ہپi‚ئ‚¤‚è‚ه‚¤پA“—¦ژزپA“—جپA“ھ—جپj‚ج
پ@پ@’nˆتپA‚ـ‚½‚حپA–‹•{‚جژٌ’·‚ج’nˆت‚ًˆس–،‚·‚é‚و
پ@پ@‚¤‚ة‚ب‚éپBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پںپ@ڈ«ŒRپiگھˆخ‘هڈ«ŒRپjپB
پ@پ@پ@پ@گھˆخ‘هڈ«ŒRپ@پi‚¹‚¢‚¢‚½‚¢‚µ‚ه‚¤‚®‚ٌپA•ت–¼
پ@پ@پFگھˆخڈ«ŒRپjپ@‚حپAپ@“ق—اژ‘مپE•½ˆہژ‘مڈ‰ٹْ
پ@پ@‚إ‚حپAپ@‰عˆخپi‚¦‚¼پA“Œ–k’n•ûپjگھ”°‚جŒRژ–“
پ@پ@—¦ژز‚ئ‚¢‚¤ˆس–،‚إ‚ ‚èپAپ@—صژ‚ج’©’ى“Œ–k”h
پ@پ@ŒŒR‘چ‘هڈ«‚ج•گٹ¯‚جٹ¯گE–¼‚إ‚ ‚ء‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@گھˆخ‘هڈ«ŒR‚حپAپ@ٹ™‘qژ‘م‚©‚çچ]Œث
پ@پ@ژ‘م‚ـ‚إ‚حپAپ@•گژm‚ج“—¦ژزپi“—جپA“ڈ—ہپi‚ئ
پ@پ@‚¤‚è‚ه‚¤پjپj‚ئ‚¢‚¤ˆس–،‚إ‚ ‚èپAپ@•گژm‚جژٌ’·‚ج
پ@پ@ڈجچ†‚إپAپ@•گ‰ئگŒ ‚جژٌ’·پi–‹•{‚ج’·پj‚جٹ¯
پ@پ@گE–¼‚إ‚ ‚èپAپ@•گژm‚إ“V‰؛‚جŒ —ح‚ًˆ¬پi‚ة‚¬پj
پ@پ@‚éژز‚إ‚ ‚èپAپ@’©’ى‚©‚ç”C‚؛‚ç‚êپA•گ—ح‚ًˆ¬‚èپA
پ@پ@گژ،‚جژہŒ ‚ً‚à‚ء‚ؤ‚¢‚½پAŒR‚ج“—¦ژز‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@ڈ«ŒRپiگھˆخ‘هڈ«ŒRپj‚حپAپ@ڈ‰‚كپA“ق—اژ‘مپE•½
پ@پ@ˆہژ‘مڈ‰ٹْ‚إ‚حپAپ@’©’ى‚ج‰عˆخپi‚¦‚¼پA“Œ–k’n
پ@پ@•ûپj“¢”°‚ج—صژ‚ج–ًگE‚إ‚ ‚èپAپ@ٹ™‘qژ‘مˆبŒمپA
پ@پ@•گ‰ئگŒ ‚جژٌ’·‚جگE–¼‚ئ‚ب‚èپAپ@چ]Œثژ ‘م––
پ@پ@‚ة”pژ~‚ئ‚ب‚ء‚½پB
پ@
پ،پ@ڈ«ŒR‚ض‚ج‘¸ڈج‚ة‚حپAپ@ڈم—lپi‚¤‚¦‚³‚ـپjپ@‚ب‚ا‚ھپ@
پ@پ@‚ ‚èپAپ@چ‚‹M‚جگl‚ج‘¸ڈج‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پںپ@ڈ«ŒRپiگھˆخ‘هڈ«ŒRپjپB
پ@پ@پ،پ@“ق—اژ‘مپA•½ˆہژ‘مڈ‰ٹْ‚ةپAپ@گھˆخ‘هڈ«ŒR
پ@پ@پi•ت–¼پAگھˆخڈ«ŒRپj‚حپAپ@‚V‚Q‚O”NپA‘½ژ،”نŒ§ژç
پ@پ@پi‚½‚¶‚ذ‚ ‚ھ‚½‚à‚èپjپAپ@‚V‚X‚S”NپA‘ه”؛’ي–ƒکC
پ@پ@پi‚¨‚¨‚ئ‚à‚ج‚¨‚ئ‚ـ‚ëپjپAپ@‚W‚O‚P”NپAچâڈم“c‘؛–ƒ
پ@پ@کCپi‚³‚©‚ج‚¤‚¦‚ج‚½‚ق‚ç‚ـ‚ëپjپ@‚ب‚ا‚ھپAگھˆخ‘ه
پ@پ@ڈ«ŒRپi•ت–¼پAگھˆخڈ«ŒRپj‚ةڈA”C‚µ‚½پBپ@’ءˆ³‚ھ
پ@پ@ˆê‰ڈI‚ي‚ء‚½‚W‚P‚P”NˆبŒمپA”pژ~‚³‚ꂽپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پ@پ،پ@•½ˆہژ‘م––ٹْ‚جŒ¹پi–ط‘\پj‹`’‡‚حپAگھˆخ
پ@پ@پ@‘هڈ«ŒR‚إ‚ح‚ب‚پAگھ“Œ‘هڈ«ŒR‚ةڈ–”Cپi”Cٹ¯پjپ@
پ@پ@پ@‚³‚ê‚éپ@پiپuژRإ‹LپvپAپu‹ت—tپv‚و‚èپjپB
پ@پ@پ@پ@پ@•½ˆہژ‘م––ٹْ‚ج‚P‚P‚W‚S”N‚ة‹پi“sپj‚ة“ü
پ@پ@پ@‚ء‚½Œ¹‹`’‡پi‚ف‚ب‚à‚ئ‚ج‚و‚µ‚ب‚©پA–ط‘]‹`’‡پj
پ@پ@پ@‚ھپA‚»‚جŒمپAگھ“Œ‘هڈ«ŒR‚جگé‰؛پi‚¹‚ٌ‚°پj‚ً
پ@پ@پ@ژَ‚¯‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ٌژںژ‘—؟‚جپuŒلچب‹¾پv‚ب‚ا‚جڈ]—ˆگà‚إ‚حپA
پ@پ@پ@Œ¹پi–ط‘\پj‹`’‡‚حپAگھˆخ‘هڈ«ŒR‚ةڈ–”Cپi”Cٹ¯پj
پ@پ@پ@‚³‚ꂽ‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ھپAپuژRإ‹LپvپiŒڑ‹v‚R”N
پ@پ@پ@پi‚P‚P‚X‚Q”Nپj‚جˆêژںژ‘—؟‚إ‚حپA‹`’‡‚حپAگھ“Œ
پ@پ@پ@‘هڈ«ŒR‚ةڈ–”Cپi”Cٹ¯پj‚³‚ꂽ‚ئ‚ ‚èپAپu‹ت—tپv
پ@پ@پ@‚ئ‹Lڈq‚ھˆê’v‚µپA‹ك”N‚حپA‚±‚جگà‚ھ—L—ح‚ئ‚ب
پ@پ@پ@‚ء‚ؤ‚¢‚éپB
پ@
پ،پ@ٹ™‘qژ‘م‚ةپAپ@ڈ«ŒRپiگھˆخ‘هڈ«ŒRپj‚حپAپ@ٹ™‘q
پ@پ@–‹•{‚جپAŒ¹—ٹ’©پi‚ف‚ب‚à‚ئ ‚ج‚و‚è‚ئ‚àپj‚ً‚ح‚¶‚ك
پ@پ@Œ¹ژپڈ«ŒRپi‚R‘مپjپA‚»‚جŒمپAگغ‰ئڈ«ŒRپA‹{ڈ«ŒR
پ@پ@‚ھپAڈA”C‚µ‚½پB
پ@
پ،پ@Œڑ•گژ‘م‚ةپAپ@ڈ«ŒRپiگھˆخ‘هڈ«ŒRپj‚حپAپ@Œم‘ç
پ@پ@Œي“Vچc‚جچcژqپi‚ف‚±پj‚جپAŒى—اگe‰¤پi‚à‚è‚و‚µ‚µ
پ@پ@‚ٌ‚ج‚¤پA‘ه“ƒ‹{پi‚¨‚¤‚ئ‚¤‚ج‚ف‚âپjپj‚ھپAڈ«ŒRپiگھ
پ@پ@ˆخ‘هڈ«ŒRپjپ@‚ةڈA”C‚µ‚½پB
پ@
پ،پ@ژ؛’¬ژ‘م‚ةپAپ@ڈ«ŒRپiگھˆخ‘هڈ«ŒRپj‚حپAپ@ژ؛’¬
پ@پ@–‹•{‚جپA‘«—کژپ‚ھ پA—ً‘مڈ«ŒRپiگھˆخ‘هڈ«ŒRپj‚ة
پ@پ@ڈA”C‚µ‚½پB
پ@
پ،پ@چ]Œثژ‘م‚ةپAپ@ڈ«ŒRپiگھˆخ‘هڈ«ŒRپj‚حپAپ@چ]Œث
پ@پ@–‹•{‚جپA“؟گىژپ‚ھ پA—ً‘مڈ«ŒRپiگھˆخ‘هڈ«ŒRپj
پ@پ@‚ةڈA”C‚µ‚½پB
پ@
پ،پ@چ]Œثژ‘م––ٹْ‚ج‚P‚W‚U‚V”NپiŒc‰‚R”Nپj‚P‚QŒژ
پ@پ@‚ةپA‰¤گ•œŒأ‚ج‘هچ†—كپi‚¨‚¤‚¹‚¢‚س‚ء‚±‚ج‚¾
پ@پ@‚¢‚²‚¤‚ê‚¢پj‚ج”•z‚إپAپ@ڈ«ŒRپiگھˆخ‘هڈ«ŒRپj
پ@پ@‚حپA”pژ~‚³‚ꂽپB
پ@
پ@
پںپ@ڈ«ŒRپiگھˆخ‘هڈ«ŒRپjپB
پ،پ@گھˆخ‘هڈ«ŒR‚حپAپ@ڈ‰‚كپA“ق—اژ‘مپA•½ˆہژ‘مڈ‰
پ@پ@ٹْ‚ةپAپ@‰عˆخپi‚¦‚¼پA“Œ–k’n•ûپjگھ”°پ@پi“Œ–k’n•û
پ@پ@چU—ھپj‚ج‚½‚ك‚ة’u‚©‚ꂽپA’©’ى‚ج—صژ‚ج–ًگEپiٹ¯
پ@پ@گEپj‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@
پ،پ@‚»‚جŒمپAگھˆخ‘هڈ«ŒR‚حپAپ@پu•گژm‚إ“V‰؛‚جŒ —ح
پ@پ@‚ًˆ¬‚éژزپv‚جˆس‚ئ‚ب‚èپAپ@‚»‚êˆبŒمپA•گ‰ئگŒ ‚ج
پ@پ@ژٌ’·‚جگE–¼ ‚ئ‚ب‚éپB
پ@
پ،پ@‚P‚P‚X‚Q”NپiŒڑ‹v‚R”Nپj‚ةپAپ@Œ¹—ٹ’©پi‚ف‚ب‚à‚ئ‚ج
پ@پ@‚و‚è‚ئ‚àپj‚ھپA“V‰؛‚جŒ —ح‚ًˆ¬‚ء‚ؤپAپ@ڈ«ŒRگé‰؛
پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚®‚ٌ‚¹‚ٌ‚°پAگھˆخ‘هڈ«ŒR‚جگé‰؛پj‚ًژَ‚¯پA
پ@پ@ڈ«ŒRپiگھˆخ‘هڈ«ŒRپj‚ة”C–½‚³‚êپAٹ™‘q–‹•{‚ًٹJ ‚پB
پ@پ@پ@پ@‚»‚êˆبŒمپAپ@ڈ«ŒRپiگھˆخ‘هڈ«ŒRپj‚حپAپ@ٹ™‘qژ
پ@پ@‘م‚ةپAٹ™‘q–‹•{‚جپAŒ¹ژپڈ«ŒRپAگغ‰ئڈ«ŒRپA‹{ڈ«
پ@پ@ŒR‚ھڈA”C‚µپAپ@Œڑ•گژ‘م‚ةپAŒى—اگe‰¤پi‚à‚è‚و‚µپE
پ@پ@‚à‚è‚ب‚ھپ@‚µ‚ٌ‚ج‚¤پA‘ه“ƒ‹{پj‚ھپAڈ«ŒRپiگھˆخ‘هڈ«
پ@پ@ŒRپj‚ئ‚ب‚èپAپ@ژ؛’¬ژ‘م‚ةپAپ@ژ؛’¬–‹•{‚جپA‘«—ک
پ@پ@ژپ‚ھ—ً‘مڈ«ŒR‚ةڈA”C‚µپAپ@چ]Œثژ‘م‚ةپAچ]Œث–‹
پ@پ@•{‚جپA“؟گىژپ‚ھ—ً ‘مڈ«ŒR‚ةڈA”C‚µ‚½پB
پ@
پœپ@‚ب‚¨پAچ]Œث–‹•{‚جڈ«ŒR‚حپAپ@’©’ى‚و‚èپAپ@پuگھˆخ
پ@پ@‘هڈ«ŒRپv‚ج‘¼‚ةپAپuŒ¹ژپ’·ژزپvپi‚°‚ٌ‚¶‚؟‚ه‚¤‚¶‚لپj
پ@پ@‚جڈجچ†‚à“¾‚ؤپAپ@•گژm‚جژٌ’·‚ئ‚µ‚ؤ‚ج—§ڈê‚ً‹
پ@پ@‰» ‚µ‚½پB
پ@
پ،پ@‚P‚W‚U‚V”NپiŒc‰‚R”Nپj‚P‚QŒژ‚ةپA’©’ى‚جŒن‘O‰ï‹c
پ@پ@‚جپA‰¤گ•œŒأ‚ج‘هچ†—كپi‚¨‚¤‚¹‚¢‚س‚ء‚±‚ج‚¾‚¢
پ@پ@‚²‚¤‚ê‚¢پj‚ج”•z‚إپAپ@–‹•{پAگھˆخ‘هڈ«ŒRپAگغگپE
پ@پ@ٹض”’‚ب‚ا‚حپA”pژ~‚³‚ꂽپB
پ@پ@پ@پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ڈdŒُپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚°‚ف‚آپjپB
پ@پi’¼چ] ڈdŒُپjپ@پi’¼چ] Œ“‘±پj
پ@
پ،پ@ڈdŒُپ@پi‚µ‚°‚ف‚آپjپ@‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAپ@پwپ@’¼چ] Œ“‘±پ@پi‚ب‚¨‚¦پ@‚©‚ث‚آ
پ@‚®پjپ@پxپ@‚ًژQڈئ‚µ‚ؤ‰؛‚³‚¢پB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جŒ©ڈo‚µŒêپ@پu‚بپv ‚ج ƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پœپ@ڈdŒُپ@پi‚µ‚°‚ف‚آپAپ@’¼چ] ڈdŒُپi‚P‚U‚O‚W”N‚و‚è–¼ژg—pپ`پjپjپ@‚حپAپ@”َ
پ@Œû —^کZ پi‚ذ‚®‚؟ ‚و‚ë‚پA—c–¼پjپAپ@”َŒû Œ“‘± پiŒ³•ŒمپAڈ‰–¼پjپAپ@’¼چ]
پ@Œ“‘±پ@پi‚P‚T‚W‚P”Nپ`پA’¼چ]‰ئ‚ً‘ٹ‘±ŒمپjپAپ@’¼چ] ڈdŒُ پi‚P‚U‚O‚W”Nپ`پjپ@‚ئپ@
پ@“¯ˆê ‚جگl•¨پ@‚إ‚·پB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@
پ@
پ@
پ،پ@’nژکپ@
پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚´‚ق‚ç‚¢پjپB
پ@
پ،پ@’nژکپBپ@
پ،پ@’nژک‚ج‘¶‘±ژٹْپFژ؛’¬ژ‘مپ@‚ئپ@ˆہ“y“چژRژ‘مپB
پ،پ@–¼‘Oپ@پFپ@’nژکپ@پi‚¶‚´‚ق‚ç‚¢پjپB
پ،پ@’nŒ³‚ج“y’…‚ج•گژmپB
پ،پ@ژ؛’¬ژ‘م‚âˆہ“y“چژRژ‘م‚جپAچف‹½“y’…‚ج•گژm
پ@پ@پi”¼”_”¼•گژmپjپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@’nژکپ@پi‚¶‚´‚ق‚ç‚¢پjپ@‚ئ‚حپAپ@ژ؛’¬ژ‘م‚âˆہ“y“چ
پ@پ@ژRژ‘م‚جپAچف‹½“y’…‚ج•گژmپ@پi”¼”_”¼•گژmپj‚إ‚
پ@پ@‚éپB
پ@پ@پ@پ@’nژکپ@‚حپAپ@ژ؛’¬ژ‘م‚âˆہ“y“چژRژ‘م‚جپA•؛
پ@پ@”_–¢•ھ—£‚جژٹْ‚جپ@چف‹½“y’…‚ج•گژm‚إپAپ@”¼”_
پ@پ@”¼•گژm‚جگlپXپ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ،پ@’nژکپ@پi‚¶‚´‚ق‚ç‚¢پjپ@‚ئ‚حپAپ@”_–¯‚ئ‚µ‚ؤپA‘‘‰€
پ@پ@—جژه‚â’n“ھ‚ب‚ا‚ة”Nچv“™‚ً”[پi‚¨‚³پj‚ك‚ب‚ھ‚çپAپ@
پ@پ@ژçŒى‘ه–¼پAگيچ‘‘ه–¼“™ ‚جچ‘ژه‚ئژهڈ]ٹضŒW‚ًŒ‹
پ@پ@‚ٌ‚إپAپ@•گژmپiژکپi‚³‚ق‚ç‚¢پjپjگg•ھ‚ًٹl“¾‚µ‚½ژزپ@
پ@پ@‚ًŒ¾‚¤پB
پ@
پ،پ@’nژکپ@‚حپAپ@—L—ح–¼ژهپi‚ف‚ه‚¤‚µ‚مپj‚إ”_‹ئŒo‰c
پ@پ@‚ًچs‚¤ˆê•ûپAڈ¬—جژه‰»‚µپA‘yپi‚»‚¤پj‚جژw“±ژزپA
پ@پ@“yˆê„پi‚ا‚¢‚ء‚«پj‚جژهگ¨—ح‚إپAپ@‰؛چژڈمپi‚°‚±
پ@پ@‚‚¶‚ه‚¤پj‚جŒ´“®—ح‚إ‚ ‚ء‚½پBپ@’nژکپ@‚حپA‚â‚ھ‚ؤپAپ@
پ@پ@گيچ‘‘ه–¼‚ج‰ئگb‚ئ‚µ‚ؤپAپ@ڈé‰؛’¬‚ةڈZ‚ق‚©پA‹½
پ@پ@ژm‚ئ‚µ‚ؤ”_‘؛‚ةڈZ‚ٌ‚¾پB
پ@
پ،پ@گيچ‘‘ه–¼‚ج‰ئگb’cپ@‚حپAپ@ڈم‘w‚ج‰ئگbپ@‚حپAپ@
پ@پ@چ‘گlپ@پi‚±‚‚¶‚ٌپAچ‘گl—جژهپjپ@‘wپ@‚إپAپ@’†ٹش‘w
پ@پ@‚ج‰ئگbپ@‚حپA’nژکپ@پi‚¶‚´‚ق‚ç‚¢پjپ@‘w‚إپA‰؛‘w
پ@پ@‚ج‰ئگbپ@‚حپAپ@•؛ژm‚ئ‚ب‚ء‚½ˆê”ت”_–¯پ@‘wپ@پiژG
پ@پ@•؛پi‚¼‚¤‚ذ‚ه‚¤پjپA‘«Œy“™پjپ@‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پœپ@گيچ‘‘ه–¼پ@‚ةٹض‚µ‚ؤ‚حپAپ@“ْ–{ژjژ«“T‚جپ@پwپ@گي
پ@پ@چ‘‘ه–¼پ@پi‚¹‚ٌ‚² ‚‚¾‚¢‚ف‚ه‚¤پjپ@پ@پxپ@‚جچ€–ع‚ًپ@
پ@پ@ژQڈئ‚µ‚ؤ‰؛‚³‚¢پB
پ@
پœپ@چ‘گlپi—جژهپjپ@‚ةٹض‚µ‚ؤ‚حپA“ْ–{ژjژ«“T‚جپ@پwپ@’n
پ@پ@“ھپAچ‘گlپ@پi‚¶‚ئ ‚¤پA‚±‚‚¶‚ٌپjپ@‚âپ@ژçŒىپE’n“ھ‚جگف
پ@پ@’uپ@پi‚µ‚م‚²‚¶‚ئ‚¤‚ج‚¹‚ء‚؟پjپ@پxپ@‚جچ€–ع‚ًژQڈئ‚µ
پ@پ@‚ؤ‰؛‚³‚¢پB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ژپگ©گ§“xپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚¹‚¢‚¹‚¢‚اپjپB
پ@
پ،پ@ژپگ©گ§“xپBپ@
پ،پ@گ§’èژٹْپ@‚Tگ¢‹Iپ`‚Uگ¢‹IپB
پ،پ@‘¶‘±ژٹْپ@‚Tگ¢‹Iپ`‚Vگ¢‹IŒم”¼پB
پ،پ@–¼‘Oپ@پFپ@ژپگ©گ§“xپ@پi‚µ‚¹‚¢‚¹‚¢‚اپjپB
پ،پ@Œأ‘م“ْ–{‚جپAƒ„ƒ}ƒgگŒ پ@پi‘هکa’©’ىپj‚جپAگژ،گ§“xپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ،پ@ƒ„ƒ}ƒgگŒ پ@پi‘هکa’©’ىپjپ@‚حپAپ@‚Rگ¢‹IŒم”¼‚ةپAپ@‘هکa’n•û‚جڈ¬چ‘
پ@‰ئگژ،کAچ‡‚ئ‚µ‚ؤگ¬—§‚µپAپ@’x‚‚ئ‚àپAپ@‚Sگ¢‹IŒم”¼‚ـ‚إ‚ةپAپ@“ْ–{‚ج
پ@“ˆê‚ً‚ظ‚عڈI‚èپAپ@‚Tگ¢‹I‚²‚ëپAپ@ژپگ©گ§“x‚ةٹî‚أ‚چ‘‰ئ‘gگD‚ھپAˆê‰پA
پ@ٹ®گ¬‚µ‚½پBپ@
پ@
پ،پ@ژپگ©گ§“xپ@‚ئ‚حپAپ@‚Tگ¢‹I‚©‚ç‚Vگ¢‹IŒم”¼‚ـ‚إ‚جپAپ@ƒ„ƒ}ƒgگŒ پi‘هکa
پ@’©’ىپjپ@‚جگژ،پEژذ‰ï‘gگDپ@‚إپAپ@چ‹‘°’B‚ًپAژپپi‚¤‚¶پj‚ئگ©پi‚©‚خ‚ثپjپ@‚إ
پ@گژ،“I‚ة‘gگD‚µ‚½پB
پ@
پ،پ@Œأ‘م“ْ–{‚جپAƒ„ƒ}ƒgگŒ پi‘هکa’©’ىپj‚إ‚حپAپ@‚Tگ¢‹I‚©‚ç‚Vگ¢‹I‚ـ‚إپAپ@
پ@پuژپگ©گ§“xپv‚ةٹî‚أ‚گژ،پ@‚ھچs‚ب‚ي‚ê‚ـ‚µ‚½پB
پœپ@ƒ„ƒ}ƒgگŒ پi‘هکa’©’ىپjپ@‚ج‘ه‰¤پ@پi‚¨‚¨‚«‚فپA‚¾‚¢‚¨‚¤پA“Vچcپjپ@‚حپAپ@
پ@چ‹‘°’B‚ًپAپ@ŒŒ‰ڈ‚â‚»‚ج‘¼‚جٹضŒW‚ً‚à‚ئ‚ةچ\گ¬‚³‚ꂽپAژپپi‚¤‚¶پj‚ئŒؤ
پ@‚خ‚ê‚é‘gگD‚ة•زگ¬‚µپAپ@چ‹‘°’B‚ةپAپ@گ©پi‚©‚خ‚ثپjپ@‚ً—^‚¦‚ؤپAپ@ƒ„ƒ}ƒg
پ@گŒ ‚جگE–±‚ً•ھ’S‚³‚¹‚½پB
پœپ@’†‰›‚جگژ،‚حپAپ@گbپi‚¨‚فپjپAکAپi‚ق‚炶پj‚جگ©‚ً—L‚·‚é‘هچ‹‘°پ@‚âپ@پ@
پ@”؛‘¢پi‚ئ‚à‚ج‚ف‚â‚آ‚±پjپA‘¢پi‚ف‚â‚آ‚±پj‚ب‚ا‚جگ©‚ً—L‚·‚éڈ¬چ‹‘°پ@‚ھ
پ@“–‚½‚èپAپ@’n•û‚جگژ،‚حپAپ@ŒِپEŒNپi‚«‚فپjپA’¼پi‚ ‚½‚¢پj‚ب‚ا‚جگ©‚ً—L
پ@‚·‚éچ‘‘¢پi‚‚ة‚ج‚ف‚â‚آ‚±پjپ@‚âپ@Œ§ژهپi‚ ‚ھ‚½‚ت‚µپjپAˆî’uپi‚¢‚ب‚«پj‚ب
پ@‚ا‚جژپپ@‚ھ“–‚½‚èپAپ@چ‘‚⌧پi‚ ‚ھ‚½پj‚ًژx”z‚µ‚½پB
پ@
پœپ@چcژ؛‚âچ‹‘°‚حپA•”–¯‚ًڈٹ—L‚µپAپ@چcژ؛‚حپAپ@’¼ٹچ—ج‚ج“ش‘qپ@پi‚ف‚â
پ@‚¯پjپA‚â’¼ٹچ–¯‚ج–¼‘مپi‚ب‚µ‚ëپjپEژq‘مپi‚±‚µ‚ëپj‚ً—L‚µپAپ@چ‹‘°‚حپAژ„—L
پ@’n‚ج“c‘‘پi‚½‚ا‚±‚ëپj‚âژ„—L–¯‚ج•”‹بپi‚©‚«‚×پj‚ً—L‚µپA‚»‚ꂼ‚êپAŒo
پ@چد“Iٹî‘b‚ئ‚µ‚½پBپ@
پœپ@ژپگ©گ§“x‚حپAپ@‚Vگ¢‹IŒم”¼‚ج‘ه‰»‚ج‰üگVˆبŒم‚ج‰üٹv‚إپAپ@”pژ~‚³
پ@‚ꂽپB
پ@
پœپ@ƒ„ƒ}ƒgگŒ پi‘هکa’©’ىپj‚ج“ْ–{“ˆêپ@‚ةٹض‚µ‚ؤ‚حپAپ@“ْ–{ژjژ«“T‚جپ@
پ@پwپ@ƒ„ƒ}ƒgگŒ ‚ج“ْ–{“ˆêپ@پi‚â‚ـ‚ئ‚¹‚¢‚¯‚ٌ‚ج‚ة‚ظ‚ٌ‚ئ‚¤‚¢‚آپjپ@پxپ@‚ج
پ@چ€–ع‚ًپ@ژQڈئ‚µ‚ؤ‰؛‚³‚¢پB
پ@
پ،پ@‚Vگ¢‹IŒم”¼‚©‚ç‚Wگ¢‹Iڈ‰‚ك‚ةپAپ@پuژپگ©گ§“xپv‚ة‘م‚ي‚èپAپ@ٹ¯—»گ§‚ئ
پ@Œِ’nŒِ–¯گ§‚جپu—¥—كگ§“xپv‚ھŒ`گ¬‚³‚ê‚éپBپ@
پœپ@‚Vگ¢‹IŒم”¼‚©‚ç‚Wگ¢‹Iڈ‰‚ك‚ةپAپ@پu—¥—كگ§“xپvٹî‚أ‚—¥—كگژ،پ@‚ھپA
پ@چs‚ي‚êپAپ@—¥—كچ‘‰ئپiپu—¥—كگ§“xپv‚ًٹî–{‚ة‚µ‚½چ‘‰ئپj‚ھپAپ@گ¬—§‚·‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پœپ@—¥—كگ§“x‚ةٹض‚µ‚ؤ‚حپAپ@“ْ–{ژjژ«“T‚جپ@پwپ@—¥—كگ§“xپ@پi‚è‚آ‚è‚ه‚¤
پ@‚¹‚¢‚اپjپ@پxپ@‚جچ€–ع‚ًپ@ژQڈئ‚µ‚ؤ‰؛‚³‚¢پB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ژہگ¬‰@ پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ء‚¹‚¢‚¢‚ٌپjپB
پ@
پ،پ@ژہگ¬‰@پBپ@
پœپ@گ¶–v”Nپ@‚P‚W‚Q‚Pپi•¶گ‚S”Nپjپ`‚P‚X‚O‚Sپi–¾ژ،‚R‚V”NپjپB
پœپ@–¼‘Oپ@پFپ@ژہگ¬‰@ پi‚¶‚ء‚¹‚¢‚¢‚ٌپA‚¶‚آ‚¶‚ه‚¤‚¢‚ٌپjپBپ@
پ@گ³ژ®–¼پ@پFپ@›‰گ¬‰@ پi‚¶‚ء‚¹‚¢‚¢‚ٌپA‚¶‚آ‚¶‚ه‚¤‚¢‚ٌپjپBپ@پ@
پ@•ت–¼پFپ@”üچ²پ@پi‚ف‚³پjپAپ@‘€ژqپAپ@”üٹىپAپ@‰—”üٹىپ@پB
پœپ@چ]Œث–‹•{پE‚P‚S‘مڈ«ŒRپE“؟گى‰ئ–خپi‚¢‚¦‚à‚؟پj‚جگ¶•êپBپ@
پœپ@گ«ٹiپ@پFپ@‚©‚ب‚è”hژèچD‚«پB
پ@
پ پ@ژہگ¬‰@ ‚ھ“oڈê‚·‚éپA–ت”’‚پA‹»–،گ[‚¢پAƒhƒ‰ƒ}پA
پ@
پ@
پ،پ@ژہگ¬‰@ پi‚¶‚ء‚¹‚¢‚¢‚ٌپA‚¶‚آ‚¶‚ه‚¤‚¢‚ٌپjپ@‚حپAپ@گ¶–v”N‚حپ@‚P‚W‚Q‚P
پ@پi•¶گ‚S”Nپjپ`‚P‚X‚O‚Sپi–¾ژ،‚R‚V”Nپj‚إپAپ@گ³ژ®–¼‚حپA›‰گ¬‰@‚إپAپ@
پ@•ت–¼‚حپAپ@”üچ²پ@پi‚ف‚³پjپAپ@‘€ژqپAپ@”üٹىپAپ@‰—”üٹىپ@‚ئڈج‚µ‚½پB
پ،پ@ژہگ¬‰@‚حپAپ@چ]Œث–‹•{پE‚P‚S‘مڈ«ŒRپE“؟گى‰ئ–خپi‚¢‚¦‚à‚؟پj‚جگ¶•ê‚إ
پ@‚ ‚èپAپ@گ«ٹi‚حپAپ@‚©‚ب‚è”hژèچD‚«پ@‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@
پ،پ@‚¨”üچ²پiژہگ¬‰@پj‚جژqپ@‚ھپA“؟گىŒc•ںپi‚و‚µ‚ئ‚فپj‚ئ–¼‚ً‰ü‚كپA‚Sچخ‚إ
پ@‚P‚R‘م‹IڈB”ثژه‚ئ‚ب‚èپA‰ئ“آ‚ًŒp‚®‚ئپAپ@”üچ²‚حپA—ژڈü‚µ‚ؤپAپ@ژہگ¬‰@‚ئ
پ@–¼ڈو‚éپB
پ،پ@‚P‚W‚T‚W”Nپiˆہگ‚T”NپjپAپ@ژہگ¬‰@‚جژqپAپ@“؟گىŒc•ںپi‚و‚µ‚ئ‚فپjپ@‚ھپA
پ@‚P‚Rچخ‚إپA‚P‚S‘مڈ«ŒRپE“؟گى‰ئ–خپi‚¢‚¦‚à‚؟پj‚ئ‚µ‚ؤپAچ]Œثڈé‚ة“ü‚é‚ئپA
پ@ژہگ¬‰@‚حپAپ@ڈ«ŒRگ¶•ê‚ئ‚µ‚ؤپAپ@‘ه‰œ‚ة“ü‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ،پ@‚P‚W‚U‚U”NپiŒc‰‚Q”Nپj‚ةپAژہگ¬‰@‚جژqپA“؟گى‰ئ–خ‚ھ‘هچمڈé‚إپA‚Q‚Pچخ
پ@‚إ–v‚µ‚½Œم‚àپAپ@ژہگ¬‰@پ@‚حپAپ@چ]Œثڈé‚ة‹ڈڈZ‚µپA‚P‚W‚U‚W”Nپ@پiŒc‰‚S”NپA
پ@Œم‚ة–¾ژ،Œ³”Nپj‚ةپAپ@ٹ¯ŒR‚ة‚و‚éچ]ŒثڈéٹJڈéŒم‚حپAپ@گأٹ°‰@‹{پiکa‹{پj
پ@‚ئ‹¤‚ة“cˆہ‰ئ‚ج‰®•~‚ضˆع‚éپB
پ@
پ،پ@‚P‚X‚O‚S”Nپi–¾ژ،‚R‚V”NپjپAپ@ژہگ¬‰@پ@‚حپA“Œ‹پEگç‘تƒ–’J‚ج‹IڈBپE“؟گى
پ@“@‚ة‚ؤپA‚W‚Sچخ‚إژ€‹ژ‚µپAپ@ٹ°‰iژ›‚ةپAپ@–{ژُ‰@پi‚P‚R‘مڈ«ŒR‰ئ’èپEگ¶•êپj
پ@‚ئ•ہ‚ٌ‚إ‘’‚ç‚ꂽپB
پ@
پ@
پ@
پôپôپ@ژہگ¬‰@ ‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢پA
پ@پ@پ@پ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپAƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پB
پ@
پ@پڑپ@ژہگ¬‰@‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢پA
پ@پ@پ@پ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپB
پ@
پ@پ@پ@پœپ@پi’چˆسپjپ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAپ@ƒtƒBƒNƒVƒ‡ƒ“‚إ‚·پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@—ًژj‚جƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAپ@ژjژہپi—ًژjڈم‚جژ–ژہپjپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ئپ@‰ث‹َ‚جڈo—ˆژ–‚ھپ@چ¬‚¶‚ء‚ؤ•`‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ـ‚½پAپ@Œ»‘م•—‚ةƒAƒŒƒ“ƒW‚µ‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚·پB
پ@
پ،پ@پwپ@‘ه‰œپE–‹––‚جڈ—‚½‚؟پ@پxپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پiƒtƒWƒeƒŒƒr‚ج‚Q‚O‚O‚R”NپE‚Q‚O‚O‚S”Nگ»چى
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒeƒŒƒrƒhƒ‰ƒ}پjپB
پ@
پ@پ@پœپ@ژہگ¬‰@‚ً‰‰‚¶‚½ڈ——D–¼پ@پFپ@–ىچغ—zژqپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@’n“ھپAچ‘گlپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ئ‚¤ پA‚±‚‚¶‚ٌپjپB
پ@
پ،پ@’n“ھپAچ‘گlپBپ@
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@’n“ھپ@پi‚¶‚ئ‚¤پjپAپ@چ‘گlپ@پi‚±‚‚¶‚ٌپjپB
پ،پ@’n“ھپAچ‘گl‚ج‘¶چفٹْٹشپ@پFپ@
پ@پ@‚P‚P‚W‚T”Nپi•¶ژ،Œ³”Nپj‚و‚èپA’†گ¢“ْ–{پ@پiٹ™‘qپE
پ@پ@Œڑ•گپEژ؛’¬ژ‘مپjپAˆہ“y“چژRژ‘مپAچ]Œثژ‘م
پ@پ@ڈ‰ٹْ‚ـ‚إپBپ@
پ،پ@’n“ھپAچ‘گl‚حپAپ@
پ@پ@’n•û“yچ‹پi‚ا‚²‚¤پjپAچف’n—جژه‚إ‚ ‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“Tپ@‚P‚P‚V‚Q‚XپB
پ@
پ@
پ،پ@’n“ھپAچ‘گlپB
پ،پ@’n“ھپi‚¶‚ئ‚¤پjپAچ‘گlپi‚±‚‚¶‚ٌپj‚ئ‚حپAپ@’n•û
پ@پ@پ@پ@“yچ‹پi‚ا‚²‚¤پj‚إ‚ ‚èپAپ@چف’n—جژه‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@’n“ھپi‚¶‚ئ‚¤پj‚ئ‚حپAپ@’†گ¢“ْ–{پiٹ™‘qپEŒڑ•گپE
پ@پ@ ژ؛’¬ژ‘مپjپAˆہ“y“چژRژ‘مپAچ]Œثژ‘مڈ‰ٹْ‚جپAپ@
چ‘هة—جپi‚±‚‚ھ‚è‚ه‚¤پAŒِ—جپj‚â‘‘‰€‚جپAŒ»’nٹا
پ@پ@ —ژزپiٹ™‘qپEŒڑ•گژ‘مپjپA‚ـ‚½‚حپAŒ»’nژx”zژز
پ@پ@پiژ؛’¬ژ‘مˆبŒمپj‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@’n“ھ‚حپAپ@’†گ¢‚جٹ™‘qژ‘م‚ةپAپ@“y’nٹا—پE
پ@پ@پ@پ@”Nچv’¥ژû‚ب‚ا‚جŒ Œہ‚ً—ک—p‚µپA‘‘‰€‚âŒِ—ج
پ@پ@پ@پ@پiچ‘هة—جپj‚ج”Nچv‚ج•s–@—}—¯پA“y’n‰،—ج‚ً
پ@پ@پ@پ@ٹé‚ؤ‚邱‚ئ‚ھ‘½‚پA–{ڈٹپE—ج‰ئ‚ج‘‘‰€—جژه‚â
پ@پ@پ@پ@چ‘ژiپE’mچsچ‘ژه‚ئ‚ج•´‘ˆ‚ھگ₦‚ب‚©‚ء‚½‚ج
پ@پ@پ@پ@‚إپAپ@‚±‚ê‚ً”ً‚¯‚邽‚كپA–{ڈٹپE—ج‰ئ‚ج‘‘‰€
پ@پ@پ@پ@—جژه‚âچ‘ژiپE’mچsچ‘ژه‚حپAپ@’n“ھگ؟پi‚¶‚ئ‚¤
پ@پ@پ@پ@‚¤‚¯پj‚â‰؛’n’†•ھپi‚µ‚½‚¶‚؟‚م‚¤‚ش‚ٌپj‚ج•û–@
پ@پ@پ@پ@‚ً‚ئ‚éپB
پ@پ@پ،پ@’†گ¢‚جٹ™‘qژ‘م‚ةپA’n“ھ‚حپA‘‘‰€‚âŒِ—ج
پ@پ@پ@پ@پiچ‘هة—جپj‚إپA’n“ھگ؟پi‚¶‚ئ‚¤‚¤‚¯پj‚â‰؛’n’†
پ@پ@پ@پ@•ھپi‚µ‚½‚¶‚؟‚م‚¤‚ش‚ٌپj‚ب‚ا‚ة‚و‚èپA‘‘‰€‚âŒِپ@
پ@پ@پ@پ@—جپiچ‘هة—جپj‚جگN—ھ‚ًگi‚كپAژx”zŒ ‚ًˆ¬‚èپA
پ@پ@پ@پ@چف’n—جژه‰»‚·‚éپi’n“ھ‚ج—جژه‰»پjپBپ@
پ@
پ@پ@پ،پ@چ‘گlپ@پi‚±‚‚¶‚ٌپAچ‘گl—جژهپj‚ئ‚حپAپ@چ‘ڈOپi‚
پ@پ@پ@‚ة‚µ‚م‚¤پj‚ئ‚à‚¢‚¢پAپ@ژ؛’¬ژ‘مپAˆہ“y“چژRژ
پ@پ@پ@‘مپAچ]Œثژ‘مڈ‰ٹْ‚ج’n“ھ‚إ‚ ‚èپAپ@’n•û‚ج“y
پ@پ@پ@چ‹‚إپAچف’n—جژه‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@’n“ھ‚حپAژ؛’¬ژ‘مˆبŒم‚حپAپ@چ‘گlپi‚±‚ ‚¶‚ٌپA
پ@پ@پ@= چ‘ڈOپi‚‚ة‚µ‚م‚¤پjپj‚ئ‚àŒؤ‚خ‚ê‚éپB
پ@پ@پ@
پ،پ@’n“ھپi‚¶‚ئ‚¤پj‚ة‚حپAپ@ٹ™‘qژ‘م‚ةپAپ@ٹ™‘q–‹•{
پ@پ@پ@پ@‚ة‚و‚èپAپ@‘‘‰€پi‚µ‚ه‚¤‚¦‚ٌپj‚ج‰؛ژiپi‚°‚µپjپ@‚âپ@
پ@پ@پ@پ@Œِ—جپi‚±‚¤‚è‚ه‚¤پAچ‘هة—جپi‚±‚‚ھ‚è‚ه‚¤پjپj‚جŒSژi
پ@پ@پ@پ@پi‚®‚ٌ‚¶پj‚ب‚ا‚ھ”C‚¶‚ç‚ê‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@’n“ھپAچ‘گlپB
پ@پ@پ،پ@’n“ھگ؟‚â‰؛’n’†•ھ‚ة‚و‚é’n“ھ‚جژx”zŒ
پ@پ@پ@پ@‹‰»پB
پ@پ@پœپ@’†گ¢“ْ–{پiٹ™‘qپEŒڑ•گپEژ؛’¬ژ‘مپj‚ةپA’n
پ@پ@پ@“ھ‚حپA‰؛’n’†•ھ‚â’n“ھگ؟‚ب‚ا‚ة‚و‚ء‚ؤپA‘‘
پ@پ@پ@‰€‚âŒِ—جپiچ‘هة—جپj‚جژx”zŒ ‚ً‹‰»‚·‚éپB
پ@پ@پœپ@’n“ھ‚حپA’†گ¢“ْ–{‚إپA“y’nٹا—پE”Nچv’¥
پ@پ@پ@پ@ژû‚ب‚ا‚جŒ Œہ‚ً—ک—p‚µپA‘‘‰€‚âŒِ—جپiچ‘ هة
پ@پ@پ@پ@—جپj‚ج”Nچv‚ج•s–@—}—¯پA“y’n‰،—ج‚ًٹé‚ؤ
پ@پ@پ@پ@‚邱‚ئ‚ھ‘½‚پA–{ڈٹپE—ج‰ئ‚ج‘‘‰€—جژه‚âچ‘
پ@پ@پ@پ@ژiپE’mچsچ‘ژه‚ئ‚ج•´‘ˆ‚ھگ₦‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚إپA
پ@پ@پ@پ@‚±‚ê‚ً”ً‚¯‚邽‚كپA–{ڈٹپE—ج‰ئ‚ج‘‘‰€—جژه
پ@پ@پ@پ@‚âچ‘ژiپE’mچsچ‘ژه‚حپA’n“ھگ؟‚â‰؛’n’†•ھ
پ@پ@پ@پ@‚ج•û–@‚ً‚ئ‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@‰؛’n’†•ھپB
پ@پ@پ،پ@‰؛’n’†•ھپi‚µ‚½‚¶‚؟‚م‚¤‚ش‚ٌپj‚ئ‚حپAپ@’†گ¢
پ@پ@پ@“ْ–{پiٹ™‘qپEŒڑ•گپEژ؛’¬ژ‘مپj‚إپA‘‘‰€‚ً“ٌ•ھ
پ@پ@پ@‚µ‚ؤپA’n“ھ‚ئ–{ڈٹپE—ج‰ئ‚ج‘‘‰€—جژه‚إپA‘‘‰€
پ@پ@پ@‚ً•ھٹ„ژx”z‚·‚éگ§“x‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@’n“ھگ؟پB
پ@پ@پ،پ@’n“ھگ؟پi‚¶‚ئ‚¤‚¤‚¯پj‚ئ‚حپAپ@’†گ¢“ْ–{‚إپA’n
پ@پ@پ@پ@“ھ‚ھ‘‘‰€‚âŒِ—جپiچ‘هة—جپj‚ج”Nچv‚ج”[“ü‚ً
پ@پ@پ@پ@گ؟‚¯•‰‚¤گ§“x‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پœپ@’n“ھگ؟پi‚¶‚ئ‚¤‚¤‚¯پj‚ئ‚حپAپ@’†گ¢“ْ–{پiٹ™‘qپE
پ@پ@پ@پ@Œڑ•گپEژ؛’¬ژ‘مپj‚إپAپ@’n“ھ‚ھˆê’è‚ج”Nچv
پ@پ@پ@پ@پi‚ث‚ٌ‚®پj‚ً”[“ü‚·‚é‚ئ‚¢‚¤ڈًŒڈ‚إپAپ@–{ڈٹپE
پ@پ@پ@پ@—ج‰ئ‚ج‘‘‰€—جژه‚âچ‘ژiپE’mچsچ‘ژه‚ھپA’n“ھ
پ@پ@پ@پ@‚ة‘‘‰€‚âŒِ—جپiچ‘هة—جپj‚جŒo‰c‚ًˆد”C‚·‚é
پ@پ@پ@پ@گ§“x‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@’n“ھپAچ‘گlپB
پ@پ@پ،پ@ژçŒىپE’n“ھ‚âژçŒىپAژçŒى‘ه–¼‚ةٹض‚µ‚ؤ‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@“–“ْ–{ژjژ«“T‚جپwپ@ژçŒىپE’n“ھ‚جگف’uپ@
پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚م‚²‚¶‚ئ‚¤‚ج‚¹‚ء‚؟پjپ@‚âپ@ژçŒىپAژçŒى‘ه–¼پ@
پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚م‚²پA‚µ‚م‚²‚¾‚¢‚ف‚ه‚¤پjپ@پxپ@‚جچ€–ع‚ًژQڈئ
پ@پ@پ@پ@‚µ‚ؤ‰؛‚³‚¢پB
پ@پ@پ@پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جŒ©ڈo‚µŒêپu‚µپv ‚ج ƒyپ[ƒW‚ضپBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@
پ،پ@’n“ھپAچ‘گlپB
پ@پ@پ،پ@‚P‚P‚W‚T”Nپi•¶ژ،Œ³”Nپj‚ةپAپ@Œ¹—ٹ’© پi‚ف‚ب‚à‚ئ
پ@پ@پ@پ@‚ج‚و‚è‚ئ‚àپj‚حپAپ@’©’ى‚و‚èپ@پi’©’ى‚جژہŒ ‚ًˆ¬‚ء
پ@پ@پ@پ@‚ؤ‚¢‚½پA–@‰¤پiڈo‰ئ‚µ‚½ڈمچcپj‚جŒم”’‰ح–@‰¤‚و
پ@پ@پ@پ@‚èپjپAپ@ڈ”چ‘‚ةپAژçŒىپi‚µ‚م‚²پj‚ًپAپ@Œِ—جپiچ‘هة
پ@پ@پ@پ@—جپj‚â‘‘‰€‚ة‚حپ@’n“ھپi‚¶‚ئ‚¤پj‚ً”C–½‚·‚éŒ —ک
پ@پ@پ@پ@‚ًٹl“¾‚·‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ،پ@’n“ھپAچ‘گlپB
پ@پ@پ،پ@’n“ھپAچ‘گl‚حپAپ@’†گ¢“ْ–{پA‹كگ¢‘Oٹْ‚إ‘¶چف
پ@پ@پ@‚µپA–‹•{‚جژxژگ¨—ح‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@
پ@پ@پ،پ@ٹ™‘qژ‘م‚ج’n“ھپB
پ@پ@پ@پ@پwپ@‹ƒ‚ژq‚ئ’n“ھ‚ة‚ح‚©‚ؤ‚ب‚¢پ@پx پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•½ˆہژ‘م––ٹْ‚و‚èپAٹ™‘qژ‘م‚ـ‚إپAپ@
پ@پ@پ@پ@’n“ھ‚حپAڈ‰‚كپA‘‘‰€‚âچ‘هة—جپiŒِ—جپj‚جŒ»’n
پ@پ@پ@پ@ٹا—ژز‚إ‚ ‚èپAپ@”Nچv’¥ژûپAŒxژ@پAچظ”»پA ’¥
پ@پ@پ@پ@گإŒ پA“y’n‚جٹا—پi‰؛’nٹا—Œ پj‚جŒ Œہ‚ً
پ@پ@پ@پ@ژ‚ء‚ؤ‚¢‚½پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’n“ھ‚حپAپ@’n“ھ‚ج’¼‰c’n‚ً‰؛گl‚ç‚ةچk
پ@پ@پ@پ@چى‚³‚¹پAپ@Œ Œہ‚ً‚ك‚®‚ء‚ؤپA–{ڈٹپE—ج‰ئ‚ج‘‘
پ@پ@پ@پ@‰€—جژه‚âچ‘ژiپE’mچsچ‘ژه‚ئ‚à‘ˆ‚ء‚½پBپ@’n“ھ
پ@پ@پ@پ@‚حپAپ@‘‘‰€‚ج‘‘ٹ¯‚âŒِ—جپiچ‘هة—جپj‚ج—L—ح–¼
پ@پ@پ@پ@ژهپi‚ف‚ه‚¤‚µ‚مپj‚ئ‚à‘خ—§‚µ‚½پBپ@
پ@پ@پ@پœپ@ٹ™‘qژ‘م‚ج‘‘‰€‚âŒِ—ج“à‚إ‚ج“ٌڈdژx”zپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘‘‰€‚إ‚حپAٹ™‘qژ‘م‚ةپA“¯ˆê‚ج“y’n‚ج’†
پ@پ@پ@پ@‚ةپA–{ڈٹپE—ج‰ئ‘¤‚جٹا—ژز‚ئ–‹•{‘¤‚ج’n“ھ‚ھ
پ@پ@پ@پ@‚¢‚ؤپAژx”z‚ج‘خ—§‚ً‚à‚½‚炵‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œِ—جپiچ‘هة—جپj‚إ‚حپAٹ™‘qژ‘م‚ةپA“¯ˆê‚ج
پ@پ@پ@پ@“y’n‚ج’†‚ةپAپ@—L—ح–¼ژهپAچ‘•{پiچ‘هةپj‚ج–ًگl پ@
پ@پ@پ@پ@‚ئپ@–‹•{‘¤‚ج’n“ھ‚ھ‚¢‚ؤپAژx”z‚ج‘خ—§‚ً‚à‚½‚ç
پ@پ@پ@پ@‚µ‚½پB
پ@
پ@پ@پ،پ@ژ؛’¬ژ‘مˆبŒم‚ج’n“ھپAچ‘گlپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’n“ھ‚حپAژ؛’¬ژ‘مˆبŒمپAچ‘گlپi‚±‚‚¶‚ٌپA
پ@پ@پ@پ@چ‘گl—جژهپAچ‘ڈOپj‚ئ‚àŒؤ‚خ‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ؛’¬ژ‘م‘OٹْپE’†ٹْ‚إ‚حپAژçŒى—جچ‘گ§‰؛‚إپA
پ@پ@پ@پ@’n“ھ‚حپAپ@‘‘‰€‚âچ‘هة—جپiŒِ—جپj‚جŒ»’nژx”zژز
پ@پ@پ@پ@‚ئ‚ب‚èپAپ@’n•û‚ج“yچ‹پAچف’n—جژه‚ئ‚ب‚éپBپ@’n“ھ
پ@پ@پ@پ@پiچ‘گl—جژهپj‚حپAژ©—§‚ج‹Cژ؟‚ھ‹‚پAپ@ژçŒى‘ه–¼
پ@پ@پ@پ@‚جژx”z‚ة”½”‚·‚é’n“ھپiچ‘گl—جژهپj‚à‘½‚Œ»‚ي
پ@پ@پ@پ@‚ê‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ؛’¬ژ‘مŒمٹْپiگيچ‘ژ‘مپj‚ة“ü‚é‚ئپA‘ه–¼
پ@پ@پ@پ@—جچ‘گ§‰؛پA’n“ھپiچ‘گl—جژهپj‚حپAگيچ‘‘ه–¼‚ج‰ئ
پ@پ@پ@پ@گb’cپiڈم‹‰‰ئگbپj‚ةŒ‹ڈW‚³‚êپAپ@ژ؛’¬ژ‘مŒمٹْ
پ@پ@پ@پ@پiگيچ‘ژ‘مپjپAˆہ“y“چژRژ‘مپAچ]Œثژ‘مڈ‰ٹْ‚ةپA
پ@پ@پ@پ@گيچ‘‘ه–¼پA‹كگ¢‘ه–¼‚ج‰ئگb’cپiڈم‹‰‰ئگbپj‚ئ‚ب
پ@پ@پ@پ@‚éپB
پ@
پ@پ@پ،پ@چ‘گlپ@پi‚±‚‚¶‚ٌپAچ‘گl—جژهپAچ‘ڈOپj‚ئ‚حپAپ@ژ؛’¬
پ@پ@پ@پ@ژ‘مˆبŒم‚ج’n“ھ‚إ‚ ‚èپAپ@’n•û‚ج“yچ‹پAچف’n—ج
پ@پ@پ@پ@ژه‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@
پ@
پ@
پ،پ@µˆخ”hپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¶‚ه‚¤‚¢‚حپjپB
پ@
پ،پ@µˆخ”hپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@µˆخ”hپ@پi‚¶‚ه‚¤‚¢‚حپjپB
پ،پ@–‹––‚ةپAپ@µˆخ‰^“®پi‚¶‚ه‚¤‚¢‚¤‚ٌ‚ا‚¤پAٹOچ‘گ¨—ح‚ً•گ—ح‚إ”rڈœ‚·‚é‰^“®پj
پ@‚ًچs‚¤گl(ژزپjپBپ@µˆخپ@‚ئ‚حپAپ@ٹOچ‘گ¨—ح‚ً”rڈœ‚·‚éپ@‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپB
پ،پ@µˆخ‰^“®پ@پi–‹––‚ج”½–‹•{“IپE”rٹO“Iگژ،‰^“®پjپ@‚ًچs‚ء‚½گl(ژزپjپB
پ،پ@گTڈd”h‚جµˆخ”hپ@‚ئپ@‹}گi”h‚جµˆخ”hپ@‚ة•ھ‚©‚ê‚ؤ‚¢‚½پB
پ،پ@ٹJچ‘”hپ@‚ئ‘خ—§‚µ‚½پB
پ،پ@چX‚ةپA–‹––‚ةپA‘¸‰¤ژv‘zپi‚»‚ٌ‚ج‚¤‚µ‚»‚¤پAچcژ؛گ’”q‚جژv‘zپj‚ًڈd‚ٌ‚¶پAپ@
پ@µˆخ‰^“®پi‚¶‚ه‚¤‚¢‚¤‚ٌ‚ا‚¤پAٹOچ‘گ¨—ح‚ً•گ—ح‚إ”rڈœ‚·‚é‰^“®پjپ@‚ًچs‚ء‚½
پ@گlپiژزپjپ@‚ًپAپ@‘¸‰¤µˆخ”hپ@‚ئŒ¾‚¤پB
پ،پ@‹}گi”h‚جµˆخ”h‚جگl•¨‚ج—لپ@پFپ@پ@“yچ²”ثژm‚جپA•گژs”¼•½‘¾پ@پi‚½ ‚¯‚؟
پ@‚ح‚ٌ‚ط‚¢‚½پjپAپ@’·ڈB”ثژm‚ج‹vچâŒ؛گگپ@پi‚‚³‚©‚°‚ٌ‚¸‚¢پjپAپ@ژF–€”ثژm‚ج
پ@—L”nگVژµپi‚ ‚è‚ـ‚µ‚ٌ‚µ‚؟پjپAپ@Œِ‰ئ‚جژOڈًژہ”üپ@پi‚³‚ٌ‚¶‚ه‚¤‚³‚ث‚ئ‚فپjپ@‚ب
پ@‚اپB
پ،پ@گTڈd”h‚جµˆخ”h‚جگl•¨‚ج—لپ@پFپ@پ@“yچ²”ثژm‚جچâ–{—´”nپ@پi‚³‚©‚à‚ئ ‚è‚ه
پ@‚¤‚ـپjپAپ@’·ڈB”ثژm‚جŒjڈ¬ŒـکYپ@پi‚©‚آ‚炱‚²‚낤پA–طŒثچFˆٍپjپ@پ@‚ب‚اپB
پ،پ@–‹––‚ةچفˆت‚µ‚ؤ‚¢‚½پAچF–¾پi‚±‚¤‚ك‚¢پj“Vچcپ@پiچفˆت‚P‚W‚S‚Uپ`‚U‚U”NپAµˆخ
پ@”hپAŒِ•گچ‡‘ج”hپjپ@‚ھپAپ@پuˆظگlپi‚¢‚¶‚ٌپAٹOچ‘گlپjŒ™‚¢پv‚إ‚ ‚ء‚½‚±‚ئ‚àپA µ
پ@ˆخ”h‚ًٹˆ‹C‚أ‚©‚¹‚½پB
پ،پ@–‹––‚جٹJچ‘پ@’¼Œم‚ة‘½‚©‚ء‚½µˆخ”h‚àپAپ@‚»‚جŒمپAپ@‰¢•ؤ—ٌ‹گ¨—ح‚ةگع
پ@‚µ‚ؤپAµˆخ‚ج•s‰آ”\‚ً’m‚èپ@ٹJچ‘”h‚ض“]Œü‚·‚éژز‚ھ‘½‚ڈo‚½پBپ@
پ،پ@µˆخ”h‚جˆê•”‚حپAپ@ˆہگ‚ج‘هچ–پi‚P‚W‚T‚Wپ`‚T‚X”Nپj‚جژn‚ـ‚é‚P‚W‚T‚W”Nچ
پ@‚و‚èپAپ@–‹•{‚ة”½ٹ´‚ً‹‚كپAپ@چ]Œث–‹•{‚إ‚ح“ْ–{‚جگژ،‰üٹv‚ح‚إ‚«‚ب‚¢‚ئ
پ@چl‚¦‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚èپAڈ™پX‚ةپA“|–‹”h‚ة‚à‚ب‚èپAپ@µˆخپE“|–‹”h‚ھ‘‚¦‚ؤ‚¢‚پB
پ@
پ پ@‘¸‰¤µˆخ”hپi‘¸µ”hپj ‚ھ“oڈê‚·‚éپA–ت”’‚پA‹»–،گ[
پ@پ@‚¢پAƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپAƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پB
پ@
پ@
پ،پ@–‹––‚جٹJچ‘پ@پi‚P‚W‚T‚Sپ`‚T‚T”N‚ج‚S‚©چ‘کaگeڈً–ٌ’÷Œ‹پjپ@’¼Œم‚ة‘½‚©‚ء‚½
پ@µˆخ”h‚àپAپ@‚»‚جŒمپAپ@‰¢•ؤ—ٌ‹گ¨—ح‚ةگع‚µ‚ؤپAپ@µˆخ‚ج•s‰آ”\‚ً’m‚èپ@ٹJ
پ@چ‘”h‚ض“]Œü‚·‚éژز‚ھ‘½‚ڈo‚½پBپ@‚P‚W‚U‚R”N‚جژF‰pگي‘ˆ‚إ‚ج”s–k‚ة‚و‚èژF–€
پ@”ث‚جµˆخ”h‚جˆê•”‚ھٹJچ‘”h‚ض“]Œü‚·‚éپBپ@‚P‚W‚U‚S”N‚جژlچ‘ٹح‘à‰؛ٹض–CŒ‚
پ@ژ–Œڈ‚إ‚ج”s–k‚ة‚و‚èپAپ@’·ڈB”ث‚جµˆخ”h‚جˆê•”‚ھٹJچ‘”h‚ض“]Œü‚·‚éپB
پ@
پ،پ@µˆخ”h‚جژuژm‚جˆê•”‚ة‚حپAŒم‚ةپAµˆخپ@پi‚¶‚ه‚¤‚¢پAٹOچ‘گ¨—ح‚ً•گ—ح‚إ”r
پ@ڈœ‚·‚邱‚ئپjپ@‚ح–³—‚¾‚ئچl‚¦پAپ@ٹJچ‘”h‚ة“]Œü‚·‚éگlپX‚à‚¢‚½پB
پœپ@چâ–{—´”nپi‚³‚©‚à‚ئ‚è‚ه‚¤‚ـپj‚âŒjڈ¬ŒـکYپi‚©‚آ‚炱‚²‚낤پjپ@‚حپAپ@ڈ‰‚ك‚حپA
پ@µˆخ”h‚جژuژm‚إ‚ ‚ء‚½‚ھپAپ@‚»‚جŒمپAٹJچ‘”h‚جژuژm‚ة“]Œü‚·‚éپBپ@‚»‚ج‚½
پ@‚ك‚ةپAپ@Œم‚ةپAµˆخ”h‚ة–½‚ً‘_پi‚ث‚çپj‚ي‚ê‚邱‚ئ‚ة‚à‚ب‚éپB
پ@
پ،پ@µˆخ”hپ@پi‚¶‚ه‚¤‚¢‚حپjپ@‚حپAپ@–‹––‚ةپAپ@µˆخ‰^“®پ@پi‚¶‚ه‚¤‚¢‚¤‚ٌ‚ا‚¤پAٹO
پ@چ‘گ¨—ح‚ً•گ—ح‚إ”rڈœ‚·‚é‰^“®پjپ@‚ًچs‚¤گl(ژزپjپ@‚إ‚ ‚éپB
پ،پ@µˆخ”hپ@‚حپAپ@µˆخ‰^“®پ@پi–‹––‚ج”½–‹•{“IپE”rٹO“Iگژ،‰^“®پAپ@ٹOچ‘گl
پ@‚ً•گ—ح‚إ“ْ–{‚©‚ç’ا‚¢ڈo‚·‰^“®پjپ@‚ًچs‚ء‚½گl(ژزپjپ@‚إ‚ ‚éپBپ@‹}گi”h‚جµ
پ@ˆخ”h‚جگl•¨‚ة‚حپAپ@“yچ²”ث”ثژm‚جپA•گژs”¼•½‘¾پ@پi‚½‚¯‚؟‚ح‚ٌ‚ط‚¢‚½پjپA
پ@Œِ‰ئ‚جژOڈًژہ”üپ@پi‚³‚ٌ‚¶‚ه‚¤‚³‚ث‚ئ‚فپjپ@پ@‚ب‚ا‚ھ‚¢‚éپB
پ@
پ،پ@‚³‚ç‚ةپA–‹––‚ةپA‘¸‰¤ژv‘zپ@پi‚»‚ٌ‚ج‚¤‚µ‚»‚¤پAچcژ؛گ’”q‚جژv‘zپjپ@‚ًڈd‚ٌ
پ@‚¶پAپ@µˆخ‰^“®پ@پi‚¶‚ه‚¤‚¢‚¤‚ٌ‚ا‚¤پAٹOچ‘گ¨—ح‚ً•گ—ح‚إ”rڈœ‚·‚é‰^“®پjپ@‚ًچs
پ@‚¤گl(ژزپj‚ًپAپ@‘¸‰¤µˆخ”hپ@پi‚»‚ٌ‚ج‚¤‚¶‚ه‚¤‚¢‚حپjپ@‚ئŒ¾‚¤پBپ@—ھ‚µ‚ؤپAپ@‘¸µ
پ@”hپ@پi‚»‚ٌ‚¶‚ه‚¤‚حپjپ@‚ئ‚àŒ¾‚¤پBپ@“yچ²”ثژm‚جپA•گژs”¼•½‘¾‚àپA‘¸µ”h‚ج‚Pگl
پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@–‹––پiچ]Œثژ‘م––ٹْپj‚ةپAپ@چ]Œث–‹•{‚ھ‚P‚W‚T‚Sپ`‚T‚T”N‚ةپAکaگeڈً–ٌ‚ً‰¢
پ@•ؤ—ٌ‹‚ئŒ‹‚رپAپ@چ½چ‘‚ً‚â‚كٹJچ‘‚ة“¥پi‚سپj‚فگط‚é‚ئپAپ@ٹJچ‘”hپ@پi‚©‚¢‚±‚
پ@‚حپj ‚ئ µˆخ”hپi‚¶‚ه‚¤‚¢‚حپjپ@ ‚ھپAپ@“ْ–{چ‘“à‚إپAپ@Œƒ‚µ‚‘خ—§‚µ‚½پBپ@پ@µˆخ
پ@”hپi‚¶‚ه‚¤‚¢‚حپj‚ج‘½‚‚جگl(ژزپj‚حپAپ@چ]Œث–‹•{”ل”»‚جŒXŒü‚ً‹‚‚µپAپ@‘¸‰¤ژv
پ@‘z‚ًŒfپi‚©‚©پj‚°‚ؤپAµˆخ‰^“®پ@‚ًچs‚¢پAپ@‘¸‰¤µˆخ”hپi‘¸µ”hپjپ@‚ئ‚àŒؤ‚خ‚ê
پ@‚½پBپ@
پ@
پ@
پ@
پôپôپ@‘¸‰¤µˆخ”hپi‘¸µ”hپj ‚ھ“oڈê‚·‚éپA
پ@پ@پ@پ@‹»–،گ[‚¢پAƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پAƒhƒ‰ƒ}پA
پ@پ@پ@پ@‰f‰وپB
پœپ@پi’چˆسپjپ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAپ@ƒtƒBƒNƒVƒ‡ƒ“پ@‚إ‚·پBپ@
پ@پ@پ@—ًژj‚جƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAپ@ژjژہپi—ًژjڈم‚جژ–ژہپjپ@‚ئپ@
پ@پ@پ@‰ث‹َ‚جڈo—ˆژ–‚ھپ@چ¬‚¶‚ء‚ؤ•`‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپ@‚ـ‚½پAپ@
پ@پ@پ@Œ»‘م•—‚ةƒAƒŒƒ“ƒW‚µ‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚·پB
پ@
پ،پ@پwپ@—´”n“`پ@پi‚è‚ه‚¤‚ـ‚إ‚ٌپjپ@پx پBپ@
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚P‚O”N‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پjپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ژؤ“c ڈں‰ئپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚خ‚½ ‚©‚آ‚¢‚¦پjپB
پ@
پ،پ@ژؤ“c ڈں‰ئپB
پ،پ@گ¶–v”Nپ@پFپ@‚P‚T‚Q‚Q”Nپ`‚P‚T‚W‚R”NپB
پ،پ@ژؤ“c ڈں‰ئپ@پi‚µ‚خ‚½ ‚©‚آ‚¢‚¦پjپB
پ،پ@گيچ‘پAˆہ“y“چژRژ‘م‚ج•گڈ«پB
پ،پ@گD“cگM’·‚جڈdگbپB
پ@
پ@
پ،پ@ژؤ“c ڈں‰ئپ@پi‚µ‚خ‚½ ‚©‚آ‚¢‚¦پAگ¶–v”Nپ@‚P‚T‚Q‚Qپ`‚W‚R”Nپjپ@‚حپAگيچ‘
پ@ژ‘مپAˆہ“y“چژRژ‘م‚ج•گڈ«پ@‚إپAپ@گD“cگM’·‚جڈdگbپ@‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@
پ،پ@ژؤ“c ڈں‰ئ‚حپAپ@‚P‚T‚W‚Q”N‚ج–{”\ژ›‚ج•د‚إ‚جژهŒN‚جگD“cگM’·‚جژ€ŒمپAپ@
پ@–LگbڈG‹gپi‰HژؤڈG‹gپjپ@‚ئ‘خ—§‚·‚éپBپ@گM’·‚ج–…‚ج‚¨ژs‚ئچ¥‹V‚ًŒ‹‚رپAپ@
پ@‚P‚T‚W‚R”N‚ةپAڈG‹gŒR‚ئ‚جگي‚¢‚إ‚ ‚éپAوثƒ–ٹx‚جگيپi‚µ‚¸‚ھ‚½‚¯‚ج‚½‚½‚©
پ@‚¢پj‚ة”s‚êپAپ@ڈں‰ئ‚حپAپ@‘ق‹p‚µ‚½–{‹’’n‚ج‰z‘Oپi‚¦‚؟‚؛‚ٌپA•ںˆنŒ§پj‚ج
پ@–kڈ¯ڈéپi‚«‚½‚ج‚µ‚ه‚¤‚¶‚ه‚¤پA–kƒmڈ¯ڈéپA–k‚جڈ¯ڈéپA•ںˆنŒ§•ںˆنژs‚جڈں‰ئ
پ@‚ج‹ڈڈéپj‚إپAپ@ڈں‰ئ‚حپAپ@ڈG‹gŒR‚ةˆح‚ـ‚ê‚ؤپAپ@‚¨ژs‚ئ‹¤‚ةپAژ©ٹQپiژ©ژEپj
پ@‚·‚éپB
پ،پ@ژؤ“c ڈں‰ئ‚ئڈں‰ئ‚ج•vگl‚ج‚¨ژsپi‚¨‚¢‚؟پAگM’·‚ج–…پj‚حپAپ@–kڈ¯ڈé‚ج
پ@“Vژçٹt‚إپAپ@”ڑژ€‚µ‚ؤپi‘ه—ت‚ج‰خ–ٍ‚ً”ڑ”j‚³‚¹‚ؤپjژ©ٹQ‚·‚éپBپ@
پ@
پ@
پôپôپ@ژؤ“cڈں‰ئپ@‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[
پ@پ@پ@پ@‚¢ٹضکAƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پAƒhƒ‰ƒ}پA
پ@پ@پ@پ@‰f‰وپBپ@
پ@
پڑپ@ژؤ“cڈں‰ئ‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢ٹض
پ@پ@ کAƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپBپ@
پœپ@پi’چˆسپjپ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAپ@ƒtƒBƒNƒVƒ‡ƒ“پ@‚إ‚·پBپ@
پ@پ@پ@—ًژj‚جƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAژjژہپi—ًژjڈم‚جژ–ژہپjپ@
پ@پ@پ@‚ئپ@‰ث‹َ‚جڈo—ˆژ–‚ھپ@چ¬‚¶‚ء‚ؤ•`‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ
پ@پ@پ@‚·پBپ@‚ـ‚½پAپ@Œ»‘م•—‚ةƒAƒŒƒ“ƒW‚µ‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚·پB
پ@
پ،پ@پwپ@ŒRژt ٹ¯•؛‰q پi‚®‚ٌ‚µ ‚©‚ٌ‚ׂ¦پjپ@پx پBپ@پ@پ@
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚P‚S”N‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پjپBپ@
پ،پ@ژ؛’¬ژ‘مŒمٹْپiگيچ‘ژ‘مپjپAˆہ“y“چژRژ‘مپA
پ@پ@چ]Œثژ‘مڈ‰ٹْ‚ً•`‚¢‚½ƒhƒ‰ƒ}پB
پœپ@ژؤ“c ڈں‰ئ‚ً‰‰‚¶‚é”o—D–¼پ@پFپ@‹ك“، –Fگ³
پ@پ@پi‚±‚ٌ‚ا‚¤ ‚و‚µ‚ـ‚³پjپB
پ@
پœپ@گD“cگM’·‚ً‰‰‚¶‚½”o—D–¼پ@پFپ@چ]Œû—m‰î
پ@پ@پi‚¦‚®‚؟پE‚و‚¤‚·‚¯پjپB
پ@
پ،پ@پwپ@چ]پi‚²‚¤پjپ`•P‚½‚؟‚جگيچ‘پ`پ@پx پBپ@
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚P‚P”N‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پjپBپ@
پœپ@ژؤ“c ڈں‰ئ‚ً‰‰‚¶‚é”o—D–¼پ@پFپ@‘ه’nپ@چN•vپB
پ@
پ،پ@پwپ@“V’nگlپ@پi‚ؤ‚ٌ‚؟‚¶‚ٌپjپ@پx پBپ@پ@
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚O‚X”N‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پjپB
پ@
پ،پ@پwپ@”JپXپ`‚¨‚ٌ‚ب‘¾چ}‹Lپ@
پ@پ@پ@پ@پi‚ث‚ثپ@‚¨‚ٌ‚ب‚½‚¢‚±‚¤‚«پjپ@پx پBپ@
پ@پ@پ@پiƒeƒŒƒr“Œ‹پE‚Q‚O‚O‚X”Nگ§چىپE
پ@پ@پ@پ@ƒeƒŒƒrƒhƒ‰ƒ}پjپBپ@
پœپ@ژؤ“c ڈں‰ئ‚ً‰‰‚¶‚½”o—D–¼پ@پFپ@ژؤپ@ڈr•vپB
پ@
پ،پ@پwپ@گM’·پ@‚j‚h‚m‚fپ@‚n‚eپ@‚y‚h‚o‚`‚m‚f‚tپ@پx پBپ@
پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚P‚X‚X‚Q”N‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پjپB
پ،پ@ژ؛’¬ژ‘مŒمٹْپiگيچ‘ژ‘مپjپAˆہ“y“چژRژ‘م‚ج
پ@پ@ژ‘مڈَ‹µ‚â‚»‚جژ‘م‚ةٹˆ–ô‚µ‚½گl•¨‚ً•`‚پB
پœپ@ژؤ“c ڈں‰ئ‚ً‰‰‚¶‚½”o—D–¼پ@پF ‘ê“c ‰hپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ڈ¬چ‘ژٌ’·گژ،پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚±‚‚µ‚م‚؟‚ه‚¤‚¹‚¢‚¶پjپB
پ@
پ،پ@ڈ¬چ‘ژٌ’·گژ،پB
پ،پ@ژٹْپ@پFپ@‹IŒ³‘O‚Pگ¢‹Iپ`‹IŒ³‚Tگ¢‹IپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ڈ¬چ‘ژٌ’·گژ،پ@پi‚µ‚ه‚¤‚±‚‚µ‚م‚؟‚ه‚¤‚¹‚¢‚¶پjپB
پ@
پ@
پ،پ@ڈ¬چ‘ژٌ’·گژ،پ@پi‚µ‚ه‚¤‚±‚‚µ‚م‚؟‚ه‚¤‚¹‚¢‚¶پjپ@‚حپAپ@‹IŒ³‘O‚Pگ¢‹Iپ`
پ@‹IŒ³‚Tگ¢‹I‚جژٹْ‚جپA“ْ–{‚جگژ،Œ`‘شپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@پi‚r‚P‚„پjپ@ڈ¬چ‘ژٌ’·گژ،پ@‚ئ‚حپAپ@“ْ–{پiک`چ‘پjٹe’n‚جڈ¬’nˆو‚جژہ—حژز
پ@‚إ‚ ‚éپAڈ¬چ‘‚جژٌ’·‚ھپAپ@‚»‚جڈ¬’nˆو‚ً“ٹ‡‚·‚éگژ،Œ`‘شپ@‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@
پ،پ@پi‚r‚P‚„پjپثپi‚r‚P‚‡پjپ@‘هکa’n•û‚ةگ¬—§‚µ‚½ڈ¬چ‘کAچ‡‚جƒ„ƒ}ƒg‰¤Œ پ@پi‘ه
پ@کa’©’ىپjپ@‚ھپA“ْ–{پiک`چ‘پj‚ج‘¼‚جڈ¬چ‘‚âڈ¬چ‘کAچ‡‚ًژںپX‚ةگھ•‚µپA “ْ
پ@–{‚ً‚ظ‚ع“ˆê‚µ‚½‚½‚كپAپ@پi‚r‚P‚„پjپ@ڈ¬چ‘ژٌ’·گژ،پ@پi‘O‚Pپ`‚Tگ¢‹Iپjپ@‚حپAپ@
پ@پi‚r‚P‚‡پjپ@چ‹‘°کAچ‡گژ،پ@پi‚Tپ`‚Vگ¢‹Iپjپ@‚ةˆعچs‚·‚éپi‚ض•د‚ي‚éپjپB
پ@
پ،پ@پi‚rپjپ@“ْ–{‚جگژ،Œ`‘شپB
پ،پ@پi‚rپjپ@“ْ–{‚جگژ،Œ`‘شپB
پ@پi‚r‚P‚„پjپ@ڈ¬چ‘ژٌ’·گژ،پ@پi‘O‚Pگ¢‹Iپ`‹IŒ³Œم‚Tگ¢‹Iپjپث
پ@پi‚r‚P‚‡پjپ@چ‹‘°کAچ‡گژ،پ@پi‚Tپ`‚Vگ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚r‚Qپjپ@—¥—ك
پ@گژ،پ@پi‚Vپ`‚P‚Oگ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚r‚Rپjپ@گغٹضگژ،پ@پi‚P‚Oپ`‚P‚P
پ@گ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚r‚Sپjپ@‰@گ گژ،پ@پi‚P‚Pپ`‚P‚Qگ¢‹Iپj پثپi‚r‚Tپj
پ@•گ‰ئگژ،پ@پi‚P‚Qپ`‚P‚Xگ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚r‚Uپjپ@‹ك‘م“Vچcگeگ
پ@گژ،پ@پi‹ك‘م“Vچcگâ‘خژه‹`گژ،پjپ@پi‚P‚Xپ`‚Q‚Oگ¢‹Iپjپ@پث
پ@پi‚r‚Vپjپ@Œ»‘مچ‘–¯ژهŒ گژ،پ@پiŒ»‘مژهŒ چف–¯گژ،پj پi‚Q‚O
پ@پ`‚Q‚Pگ¢‹I‚جŒ»چفپjپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ڈ¬چ‘•ھ—§ژ©ژ،گ§پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚±‚‚ش‚ٌ‚è‚آ‚¶‚؟‚¹‚¢پjپB
پ@
پ،پ@ڈ¬چ‘•ھ—§ژ©ژ،گ§پB
پ،پ@ژٹْپ@پFپ@‹IŒ³‘O‚Pگ¢‹Iپ`‹IŒ³‚Tگ¢‹IپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ڈ¬چ‘•ھ—§ژ©ژ،گ§پ@پi‚µ‚ه‚¤‚±‚‚ش‚ٌ‚è‚آ‚¶‚؟‚¹‚¢پjپB
پ@
پ@
پ،پ@ڈ¬چ‘•ھ—§ژ©ژ،گ§پ@پi‚µ‚ه‚¤‚±‚‚ش‚ٌ‚è‚آ‚¶‚؟‚¹‚¢پjپ@‚حپAپ@‹IŒ³‘O‚Pگ¢
پ@‹Iپ`‹IŒ³‚Tگ¢‹I‚جژٹْ‚جپA“ْ–{‚ج“y’nگl–¯“ژ،گ§“xپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@پi‚s‚P‚„پjپ@ڈ¬چ‘•ھ—§ژ©ژ،گ§پ@ پi‘O‚Pپ`پ@‚Tگ¢‹Iپjپ@‚ئ‚حپAپ@—]ڈèگ¶ژY•¨
پ@‚ً‚ك‚®‚鑈‚¢‚ج’†‚إپA‹—ح‚بڈW—ژ‚حژü•س‚ج‚¢‚‚آ‚©‚جڈW—ژ‚ً“چ‡‚µ
پ@“ْ–{پiک`چ‘پjٹe’n‚ةڈ¬چ‘‚ھ‚إ‚«‚½‚ھپAپ@‚»‚جڈ¬چ‘‚جژٌ’·‚ھپAپ@–¯ڈO‚ً
پ@“ژ،‚·‚éگ§“xپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@پi‚s‚P‚„پjپ@پثپ@پi‚s‚P‚‡پjپ@‘هکa’n•û‚ةگ¬—§‚µ‚½ڈ¬چ‘کAچ‡‚جƒ„ƒ}ƒg‰¤Œ
پ@پi‘هکa’©’ىپjپ@‚ھپAپ@“ْ–{پiک`چ‘پj‚ج‘¼‚جڈ¬چ‘‚âڈ¬چ‘کAچ‡‚ًژںپX‚ةگھ•
پ@‚µپAپ@“ْ–{‚ً‚ظ‚ع“ˆê‚µ‚½‚½‚كپAپ@پ@پi‚s‚P‚„پjپ@ڈ¬چ‘•ھ—§ژ©ژ،گ§پ@ پi‘O‚P
پ@پ`‚Tگ¢‹Iپjپ@‚حپAپ@پi‚s‚P‚‡پjپ@چ‹‘°“y’nگl–¯ژx”zگ§پ@پi‚Tپ`‚Vگ¢‹Iپjپ@‚ةˆع
پ@چs‚·‚éپi‚ض•د‚ي‚éپjپBپ@
پ@
پ@
پ،پ@پi‚sپjپ@“ْ–{‚ج“y’nگl–¯“ژ،گ§“xپB
پ@پi‚s‚P‚„پjپ@ڈ¬چ‘•ھ—§ژ©ژ،گ§پ@پi‘O‚Pپ`پ@‚Tگ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚s‚P‚‡پjپ@چ‹‘°“y’nگl
پ@–¯ژx”zگ§پ@پi‚Tپ`‚Vگ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚s‚Qپjپ@Œِ’nŒِ–¯گ§پ@پi‚Vپ`‚P‚Oگ¢‹Iپjپ@پثپ@
پ@پi‚s‚Rپjپ@‘‘‰€پEŒِ—جگ§پ@پi‚P‚Oپ`‚P‚Uگ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚s‚Sپjپ@‘ه–¼—جچ‘گ§پ@پi‚P‚U
پ@پ`‚P‚Xگ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚s‚Tپjپ@‹ك‘مگ§Œہ‹c‰ï“àٹtگ§پ@پi‚P‚Xپ`‚Q‚Oگ¢‹Iپjپ@پثپ@
پ@پi‚s‚Uپjپ@Œ»‘مچ‘–¯ژهŒ –¯ژهگ§پi‚Q‚Oپ`‚Q‚Pگ¢‹I‚جŒ»چفپjپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ڈ¬چ‘•ھ—§ژ©ژ،گŒ پ@
پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚±‚‚ش‚ٌ‚è‚آ‚¶‚؟‚¹‚¢‚¯‚ٌپjپB
پ@
پ،پ@ڈ¬چ‘•ھ—§ژ©ژ،گŒ پB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ڈ¬چ‘•ھ—§ژ©ژ،گŒ پ@پi‚µ‚ه‚¤‚±‚‚ش‚ٌ‚è‚آ‚¶‚؟‚¹‚¢‚¯‚ٌپjپB
پ،پ@ژٹْپ@پFپ@‹IŒ³‘O‚Pگ¢‹Iپ`‹IŒ³‚Tگ¢‹IپB
پ،پ@ڈ¬چ‘•ھ—§گŒ پB
پ،پ@‹IŒ³‘O‚Pگ¢‹I‚ةپA“ْ–{ٹe’n‚ةپAڈ¬چ‘‚ھگ¶‚ـ‚êپAڈ¬چ‘•ھ—§ژ©ژ،گŒ ‚ھژ÷—§‚³
پ@‚êپAپ@‹IŒ³‚Tگ¢‹I‚ةپA‚»‚ê‚ç‚جڈ¬چ‘‚ھپAƒ„ƒ}ƒg‰¤Œ پi‘هکa’©’ىپj‚ة‚و‚蓈ꂳ‚êپA
پ@“ْ–{ٹe’n‚جڈ¬چ‘•ھ—§ژ©ژ،گŒ پ@‚حپAڈء–إ‚·‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ@
پ،پ@ڈ¬چ‘•ھ—§ژ©ژ،گŒ پ@پi‚µ‚ه‚¤‚±‚‚ش‚ٌ‚è‚آ‚¶‚؟‚¹‚¢‚¯‚ٌپjپ@‚حپA‹IŒ³‘O‚Pگ¢‹I
پ@‚©‚ç‹IŒ³‚Tگ¢‹I‚ـ‚إ‚إپAپ@‹IŒ³‘O‚Pگ¢‹I‚ةپA“ْ–{ٹe’n‚ةپAڈ¬چ‘‚ھگ¶‚ـ‚êپAڈ¬چ‘
پ@•ھ—§ژ©ژ،گŒ ‚ھژ÷—§‚³‚êپAپ@‹IŒ³‚Tگ¢‹I‚ةپA‚»‚ê‚ç‚جڈ¬چ‘‚ھپAƒ„ƒ}ƒg‰¤Œ پi‘ه
پ@کa’©’ىپj‚ة‚و‚蓈ꂳ‚êپAپ@“ْ–{ٹe’n‚جڈ¬چ‘•ھ—§ژ©ژ،گŒ پ@‚حپAڈء–إ‚·‚éپB
پ@
پ،پ@ڈ¬چ‘ژٌ’·گژ،پ@پi‚µ‚ه‚¤‚±‚‚µ‚م‚؟‚ه‚¤‚¹‚¢‚¶پjپ@‚حپAپ@‹IŒ³‘O‚Pگ¢‹Iپ`‹IŒ³‚T
پ@گ¢‹I‚جژٹْ‚جپA“ْ–{‚جگژ،Œ`‘شپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@پi‚r‚P‚„پjپ@ڈ¬چ‘ژٌ’·گژ،پ@‚ئ‚حپAپ@“ْ–{پiک`چ‘پjٹe’n‚جڈ¬’nˆو‚جژہ—حژز‚إ‚ ‚éپA
پ@ڈ¬چ‘‚جژٌ’·‚ھپAپ@‚»‚جڈ¬’nˆو‚ً“ٹ‡‚·‚éگژ،Œ`‘شپ@‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@
پ،پ@ڈ¬چ‘•ھ—§ژ©ژ،گ§پ@پi‚µ‚ه‚¤‚±‚‚ش‚ٌ‚è‚آ‚¶‚؟‚¹‚¢پjپ@‚حپAپ@‹IŒ³‘O‚Pگ¢‹Iپ`‹IŒ³
پ@‚Tگ¢‹I‚جژٹْ‚جپA“ْ–{‚ج“y’nگl–¯“ژ،گ§“xپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@پi‚s‚P‚„پjپ@ڈ¬چ‘•ھ—§ژ©ژ،گ§پ@ پi‘O‚Pپ`پ@‚Tگ¢‹Iپjپ@‚ئ‚حپAپ@—]ڈèگ¶ژY•¨‚ً‚ك‚®‚é
پ@‘ˆ‚¢‚ج’†‚إپA‹—ح‚بڈW—ژ‚حژü•س‚ج‚¢‚‚آ‚©‚جڈW—ژ‚ً“چ‡‚µ“ْ–{پiک`چ‘پjٹe’n‚ة
پ@ڈ¬چ‘‚ھ‚إ‚«‚½‚ھپAپ@‚»‚جڈ¬چ‘‚جژٌ’·‚ھپAپ@–¯ڈO‚ً“ژ،‚·‚éگ§“xپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@پi‚s‚P‚„پjپ@پثپ@پi‚s‚P‚‡پjپ@‘هکa’n•û‚ةگ¬—§‚µ‚½ڈ¬چ‘کAچ‡‚جƒ„ƒ}ƒg‰¤Œ پi‘ه
پ@کa’©’ىپjپ@‚ھپAپ@“ْ–{پiک`چ‘پj‚ج‘¼‚جڈ¬چ‘‚âڈ¬چ‘کAچ‡‚ًژںپX‚ةگھ•‚µپAپ@
پ@“ْ–{‚ً‚ظ‚ع“ˆê‚µ‚½‚½‚كپAپ@پ@پi‚s‚P‚„پjپ@ڈ¬چ‘•ھ—§ژ©ژ،گ§پ@ پi‘O‚Pپ`پ@‚T
پ@گ¢‹Iپjپ@‚حپAپ@پi‚s‚P‚‡پjپ@چ‹‘°“y’nگl–¯ژx”zگ§پ@پi‚Tپ`‚Vگ¢‹Iپjپ@‚ةˆعچs‚·
پ@‚éپi‚ض•د‚ي‚éپjپBپ@
پ،پ@پi‚sپjپ@“ْ–{‚ج“y’nگl–¯“ژ،گ§“xپB
پ@پi‚s‚P‚„پjپ@ڈ¬چ‘•ھ—§ژ©ژ،گ§پ@پi‘O‚Pپ`پ@‚Tگ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚s‚P‚‡پjپ@چ‹‘°“y’nگl–¯
پ@ژx”zگ§پ@پi‚Tپ`‚Vگ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚s‚Qپjپ@Œِ’nŒِ–¯گ§پ@پi‚Vپ`‚P‚Oگ¢‹Iپjپ@پثپ@
پ@پi‚s‚Rپjپ@‘‘‰€پEŒِ—جگ§پ@پi‚P‚Oپ`‚P‚Uگ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚s‚Sپjپ@‘ه–¼—جچ‘گ§پ@پi‚P‚U
پ@پ`‚P‚Xگ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚s‚Tپjپ@‹ك‘مگ§Œہ‹c‰ï“àٹtگ§پ@پi‚P‚Xپ`‚Q‚Oگ¢‹Iپjپ@پثپ@
پ@پi‚s‚Uپjپ@Œ»‘مچ‘–¯ژهŒ –¯ژهگ§پi‚Q‚Oپ`‚Q‚Pگ¢‹I‚جŒ»چفپjپB
پ@
پ@
پ،پ@پi‚r‚P‚„پjپثپi‚r‚P‚‡پjپ@‘هکa’n•û‚ةگ¬—§‚µ‚½ڈ¬چ‘کAچ‡‚جƒ„ƒ}ƒg‰¤Œ پ@پi‘هکa
پ@’©’ىپjپ@‚ھپA“ْ–{پiک`چ‘پj‚ج‘¼‚جڈ¬چ‘‚âڈ¬چ‘کAچ‡‚ًژںپX‚ةگھ•‚µپAپ@“ْ
پ@–{‚ً‚ظ‚ع“ˆê‚µ‚½‚½‚كپAپ@پi‚r‚P‚„پjپ@ڈ¬چ‘ژٌ’·گژ،پ@پi‘O‚Pپ`‚Tگ¢‹Iپjپ@‚حپAپ@
پ@پi‚r‚P‚‡پjپ@چ‹‘°کAچ‡گژ،پ@پi‚Tپ`پ@‚Vگ¢‹Iپjپ@‚ةˆعچs‚·‚éپi‚ض•د‚ي‚éپjپB
پ،پ@پi‚rپjپ@“ْ–{‚جگژ،Œ`‘شپB
پ@پi‚r‚P‚„پjپ@ڈ¬چ‘ژٌ’·گژ،پ@پi‘O‚Pپ`‚Tگ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚r‚P‚‡پjپ@چ‹‘°کAچ‡گژ،پ@
پ@پi‚Tپ`‚Vگ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚r‚Qپjپ@—¥—كگژ،پ@پi‚Vپ`‚P‚Oپ@گ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚r‚Rپjپ@گغ
پ@ٹضگژ،پ@پi‚P‚Oپ`‚P‚Pگ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚r‚Sپjپ@‰@گپi‚P‚Pپ`‚P‚Qگ¢‹Iپjپ@ پثپ@پi‚r‚Tپjپ@
پ@•گ‰ئگژ،پ@پi‚P‚Qپ`‚P‚Xگ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚r‚Uپjپ@‹ك‘م“Vچcگeگگژ،پ@پi‹ك‘م“V
پ@چcگâ‘خژه‹`گژ،پjپi‚P‚Xپ`‚Q‚Oگ¢‹Iپjپ@پثپi‚r‚Vپjپ@Œ»‘مچ‘–¯ژهŒ گژ،پ@پiŒ»
پ@ژه‘مŒ چف–¯گژ،پjپ@پi‚Q‚Oپ`‚Q‚Pگ¢‹I‚جŒ»چفپjپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@
پ@
پ@
پ،پ@ڈ¬چ‘•ھ—§گŒ پ@
پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ه‚¤‚±‚‚ش‚ٌ‚è‚آ‚¹‚¢‚¯‚ٌپjپB
پ@
پ،پ@ڈ¬چ‘•ھ—§گŒ پB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@ڈ¬چ‘•ھ—§گŒ پ@پi‚µ‚ه‚¤‚±‚‚ش‚ٌ‚è‚آ‚¹‚¢‚¯‚ٌپjپB
پ،پ@ژٹْپ@پFپ@‹IŒ³‘O‚Pگ¢‹Iپ`‹IŒ³‚Tگ¢‹IپB
پ،پ@ڈ¬چ‘•ھ—§ژ©ژ،گŒ پB
پ،پ@‹IŒ³‘O‚Pگ¢‹I‚ةپA“ْ–{ٹe’n‚ةپAڈ¬چ‘‚ھگ¶‚ـ‚êپAڈ¬چ‘•ھ—§گŒ ‚ھژ÷—§‚³
پ@‚êپAپ@‹IŒ³‚Tگ¢‹I‚ةپA‚»‚ê‚ç‚جڈ¬چ‘‚ھپAƒ„ƒ}ƒg‰¤Œ پi‘هکa’©’ىپj‚ة‚و‚蓈ê
پ@‚³‚êپA“ْ–{‚جڈ¬چ‘•ھ—§گŒ پ@‚حپAڈء–إ‚·‚éپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ@
پ،پ@ڈ¬چ‘•ھ—§گŒ پ@پi‚µ‚ه‚¤‚±‚‚ش‚ٌ‚è‚آ‚¹‚¢‚¯‚ٌپjپ@‚حپAپ@‹IŒ³‘O‚Pگ¢‹I‚©‚ç
پ@‹IŒ³‚Tگ¢‹I‚ـ‚إ‚إپAپ@‹IŒ³‘O‚Pگ¢‹I‚ةپA“ْ–{ٹe’n‚ةپAڈ¬چ‘‚ھگ¶‚ـ‚êپAڈ¬چ‘
پ@•ھ—§گŒ ‚ھژ÷—§‚³‚êپAپ@‹IŒ³‚Tگ¢‹I‚ةپA‚»‚ê‚ç‚جڈ¬چ‘‚ھپAƒ„ƒ}ƒg‰¤Œ پ@پi‘ه
پ@کa’©’ىپj‚ة‚و‚蓈ꂳ‚êپAپ@“ْ–{ٹe’n‚جڈ¬چ‘•ھ—§گŒ پ@‚حپAڈء–إ‚·‚éپB
پ@
پ،پ@ڈ¬چ‘ژٌ’·گژ،پ@پi‚µ‚ه‚¤‚±‚‚µ‚م‚؟‚ه‚¤‚¹‚¢‚¶پjپ@‚حپAپ@‹IŒ³‘O‚Pگ¢‹Iپ`‹IŒ³
پ@‚Tگ¢‹I‚جژٹْ‚جپA“ْ–{‚جگژ،Œ`‘شپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@پi‚r‚P‚„پjپ@ڈ¬چ‘ژٌ’·گژ،پ@‚ئ‚حپAپ@“ْ–{پiک`چ‘پjٹe’n‚جڈ¬’nˆو‚جژہ—حژز‚إ
پ@‚ ‚éپAڈ¬چ‘‚جژٌ’·‚ھپAپ@‚»‚جڈ¬’nˆو‚ً“ٹ‡‚·‚éگژ،Œ`‘شپ@‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@
پ،پ@ڈ¬چ‘•ھ—§ژ©ژ،گ§پ@پi‚µ‚ه‚¤‚±‚‚ش‚ٌ‚è‚آ‚¶‚؟‚¹‚¢پjپ@‚حپAپ@‹IŒ³‘O‚Pگ¢‹Iپ`
پ@‚T‹IŒ³گ¢‹I‚جژٹْ‚جپA“ْ–{‚ج“y’nگl–¯“ژ،گ§“xپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@پi‚s‚P‚„پjپ@ڈ¬چ‘•ھ—§ژ©ژ،گ§پ@ پi‘O‚Pپ`پ@‚Tگ¢‹Iپjپ@‚ئ‚حپAپ@—]ڈèگ¶ژY•¨‚ً‚ك
پ@‚®‚鑈‚¢‚ج’†‚إپA‹—ح‚بڈW—ژ‚حژü•س‚ج‚¢‚‚آ‚©‚جڈW—ژ‚ً“چ‡‚µ“ْ–{پiک`
پ@چ‘پjٹe’n‚ةڈ¬چ‘‚ھ‚إ‚«‚½‚ھپAپ@‚»‚جڈ¬چ‘‚جژٌ’·‚ھپAپ@–¯ڈO‚ً“ژ،‚·‚éگ§“x
پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@پi‚s‚P‚„پjپ@پثپ@پi‚s‚P‚‡پjپ@‘هکa’n•û‚ةگ¬—§‚µ‚½ڈ¬چ‘کAچ‡‚جƒ„ƒ}ƒg‰¤Œ پi‘ه
پ@کa’©’ىپjپ@‚ھپAپ@“ْ–{پiک`چ‘پj‚ج‘¼‚جڈ¬چ‘‚âڈ¬چ‘کAچ‡‚ًژںپX‚ةگھ•‚µپAپ@
پ@“ْ–{‚ً‚ظ‚ع“ˆê‚µ‚½‚½‚كپAپ@پ@پi‚s‚P‚„پjپ@ڈ¬چ‘•ھ—§ژ©ژ،گ§پ@ پi‘O‚Pپ`پ@‚T
پ@گ¢‹Iپjپ@‚حپAپ@پi‚s‚P‚‡پjپ@چ‹‘°“y’nگl–¯ژx”zگ§پ@پi‚Tپ`‚Vگ¢‹Iپjپ@‚ةˆعچs‚·
پ@‚éپi‚ض•د‚ي‚éپjپBپ@
پ،پ@پi‚sپjپ@“ْ–{‚ج“y’nگl–¯“ژ،گ§“xپB
پ@پi‚s‚P‚„پjپ@ڈ¬چ‘•ھ—§ژ©ژ،گ§پ@پi‘O‚Pپ`پ@‚Tگ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚s‚P‚‡پjپ@چ‹‘°“y’nگl–¯
پ@ژx”zگ§پ@پi‚Tپ`‚Vگ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚s‚Qپjپ@Œِ’nŒِ–¯گ§پ@پi‚Vپ`‚P‚Oگ¢‹Iپjپ@پثپ@
پ@پi‚s‚Rپjپ@‘‘‰€پEŒِ—جگ§پ@پi‚P‚Oپ`‚P‚Uگ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚s‚Sپjپ@‘ه–¼—جچ‘گ§پ@پi‚P‚U
پ@پ`‚P‚Xگ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚s‚Tپjپ@‹ك‘مگ§Œہ‹c‰ï“àٹtگ§پ@پi‚P‚Xپ`‚Q‚Oگ¢‹Iپjپ@پثپ@
پ@پi‚s‚Uپjپ@Œ»‘مچ‘–¯ژهŒ –¯ژهگ§پi‚Q‚Oپ`‚Q‚Pگ¢‹I‚جŒ»چفپjپB
پ@
پ@
پ،پ@پi‚r‚P‚„پjپثپi‚r‚P‚‡پjپ@‘هکa’n•û‚ةگ¬—§‚µ‚½ڈ¬چ‘کAچ‡‚جƒ„ƒ}ƒg‰¤Œ پ@پi‘هکa
پ@’©’ىپjپ@‚ھپA“ْ–{پiک`چ‘پj‚ج‘¼‚جڈ¬چ‘‚âڈ¬چ‘کAچ‡‚ًژںپX‚ةگھ•‚µپAپ@“ْ
پ@–{‚ً‚ظ‚ع“ˆê‚µ‚½‚½‚كپAپ@پi‚r‚P‚„پjپ@ڈ¬چ‘ژٌ’·گژ،پ@پi‘O‚Pپ`‚Tگ¢‹Iپjپ@‚حپAپ@
پ@پi‚r‚P‚‡پjپ@چ‹‘°کAچ‡گژ،پ@پi‚Tپ`پ@‚Vگ¢‹Iپjپ@‚ةˆعچs‚·‚éپi‚ض•د‚ي‚éپjپB
پ،پ@پi‚rپjپ@“ْ–{‚جگژ،Œ`‘شپB
پ@پi‚r‚P‚„پjپ@ڈ¬چ‘ژٌ’·گژ،پ@پi‘O‚Pپ`‚Tگ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚r‚P‚‡پjپ@چ‹‘°کAچ‡گژ،پ@
پ@پi‚Tپ`‚Vگ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚r‚Qپjپ@—¥—كگژ،پ@پi‚Vپ`‚P‚Oپ@گ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚r‚Rپjپ@گغ
پ@ٹضگژ،پ@پi‚P‚Oپ`‚P‚Pگ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚r‚Sپjپ@‰@گپi‚P‚Pپ`‚P‚Qگ¢‹Iپjپ@ پثپ@پi‚r‚Tپjپ@
پ@•گ‰ئگژ،پ@پi‚P‚Qپ`‚P‚Xگ¢‹Iپjپ@پثپ@پi‚r‚Uپjپ@‹ك‘م“Vچcگeگگژ،پ@پi‹ك‘م“V
پ@چcگâ‘خژه‹`گژ،پjپi‚P‚Xپ`‚Q‚Oگ¢‹Iپjپ@پثپi‚r‚Vپjپ@Œ»‘مچ‘–¯ژهŒ گژ،پ@پiŒ»
پ@ژه‘مŒ چف–¯گژ،پjپ@پi‚Q‚Oپ`‚Q‚Pگ¢‹I‚جŒ»چفپjپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@”’ڈFژںکYپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ç‚·‚¶‚낤پjپB
پ@
پ،پ@”’ڈFژںکYپB
پ،پ@گ¶–v”NپF‚P‚X‚O‚Q”Nپ`‚P‚X‚W‚T”NپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@”’ڈFپ@ژںکYپ@پi‚µ‚ç‚·پ@‚¶‚낤پjپB
پ،پ@‹ك‰q•¶–›‚جƒuƒŒپ[ƒ“پAپ@‹g“c–خ‚ج‘¤‹كپBپ@
پ،پ@ڈIکAپiڈIگيکA—چ’†‰›ژ––±‹اپj‚جژQ—^پAژں’·پi‚P‚X
پ@پ@‚S‚Tپ`‚S‚V”Nپj‚ئ‚µ‚ؤپAپ@“ْ–{گ•{‚ج‘خ‚f‚g‚pŒًڈآ
پ@پ@–ًپ@‚ئ‚ب‚éپB
پ،پ@–fˆص’،ڈ‰‘م’·ٹ¯پi‚P‚X‚S‚W”NپjپBپ@’تڈ¤ژY‹ئڈبپiŒo
پ@پ@چدژY‹ئڈبپj‚جگف—§‚ةگs—حپB
پ،پ@‹g“c–خ‚ئ‹¤‚ةپAپ@ƒTƒ“ƒtƒ‰ƒ“ƒVƒXƒR•½کaڈً–ٌ‚ج’÷
پ@پ@Œ‹‚ةگs—ح‚·‚éپ@پi‚P‚X‚T‚Oپ`‚T‚P”NپjپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ@
پ،پ@”’ڈF ژںکYپ@پi‚µ‚ç‚· ‚¶‚낤پAپ@گ¶–v”NپF‚P‚X‚O‚Q”N
پ@پ@پ`‚P‚X‚W‚T”Nپjپ@‚حپAپ@گي‘O‚حپA‹ك‰q•¶–›‚جƒuƒŒپ[ƒ“پA
پ@پ@گيŒم‚حپA‹g“c–خ‚ج‘¤‹ك پ@‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@
پ،پ@”’ڈF ژںکYپ@‚حپAگيŒمپAپ@ڈIکAپiڈIگيکA—چ’†‰›ژ––±
پ@پ@‹اپj‚جژQ—^پAژں’·پi‚P‚X‚S‚Tپ`‚S‚V”Nپj‚ئ‚µ‚ؤپAپ@“ْ–{
پ@پ@گ•{‚ج‘خ‚f‚g‚pŒًڈآ–ًپ@‚ئ‚ب‚éپBپ@‚»‚جŒمپAپ@گيŒم
پ@پ@‚ج“ْ–{‚ج—AڈoگU‹»‚ةگs—ح‚µپAپ@–fˆص’،ڈ‰‘م’·ٹ¯‚ئ
پ@پ@‚ب‚èپAپ@’تڈ¤ژY‹ئڈبپiŒ»چف‚جŒoچدژY‹ئڈبپj‚جگف—§‚ة
پ@پ@’†گS“I–ًٹ„‚ً‚ح‚½‚·پB
پ پ@ƒ}ƒbƒJپ[ƒTپ[ڈ«ŒRپ@‰و‘œپ@‚m‚nپD‚P
پ@
پ،پ@”’ڈF ژںکYپ@پi‚µ‚ç‚·‚¶‚낤پjپ@‚حپAپ@‹g“c–خ‚ئ‹¤‚ةپAپ@
پ@پ@ƒTƒ“ƒtƒ‰ƒ“ƒVƒXƒR•½کaڈً–ٌ‚ج’÷Œ‹‚ةگs—ح‚·‚éپ@
پ@پ@پi‚P‚X‚T‚Oپ`‚T‚P”NپjپB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ} ’کپ@“ْ–{ژjپ@ژ«“TپB
پ@
پ،پ@”’ڈF ژںکYپ@‚حپAژشچD‚«‚إپAپ@ƒPƒ“ƒuƒٹƒbƒW‘ه‘²پi‚P‚X
پ@پ@‚Q‚T”Nپj‚إ‚ ‚èپAپ@ƒCƒMƒٹƒX‚جƒXƒgƒ‰ƒbƒtƒHپ[ƒh”Œژفƒچ
پ@پ@ƒoپ[ƒgپEƒZƒVƒ‹پEƒrƒ“ƒOپ@پiˆ¤ڈجپFƒچƒrƒ“پj‚ئگe—F‚إپAپ@
پ@پ@ˆêڈڈ‚ةƒˆپ[ƒچƒbƒp‘ه—¤‚ًƒhƒ‰ƒCƒu—·چs‚µ‚½پB
پ@
پ@
پôپôپ@”’ڈF ژںکYپ@‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢پA
پ@پ@ƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پAƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپB
پ@
پôپôپ@”’ڈF ژںکYپ@‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢پA
پ@پ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپB
پ@
پ،پ@پwپ@”’ڈFژںکYپ@پi‚µ‚ç‚·‚¶‚낤پjپ@پxپ@
پ@پ@پ@پi‚Q‚O‚O‚X”N‚m‚g‚jƒhƒ‰ƒ}ƒXƒyƒVƒƒƒ‹پjپB
پ،پ@”’ڈFژںکY‚ً‰‰‚¶‚½”o—Dپ@پFپ@ˆةگ¨’J —F‰îپB
پ،پ@”’ڈFگ³ژq‚ً‰‰‚¶‚½”o—Dپ@پFپ@’†’J ”ü‹IپB
پ،پ@‹g“c–خ‚ً‰‰‚¶‚½”o—Dپ@پ@ پFپ@Œ´“c –F—YپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@”’”ڈژqپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ç‚ر‚ه‚¤‚µپjپB
پ@
پ،پ@”’”ڈژqپB
پ،پ@ژٹْپ@پFپ@•½ˆہژ‘مپ`ژ؛’¬ژ‘مپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@”’”ڈژqپ@پi‚µ‚ç‚ر‚ه‚¤‚µپjپB
پ،پ@•‘‚¢‰ج‚¤—Vڈ—پ@پiƒ_ƒ“ƒTپ[پA‰جژè‚ًŒ“‚ث‚½پAڈ©•wپjپB
پ@
پ@
پ،پ@”’”ڈژqپ@پi‚µ‚ç‚ر‚ه‚¤‚µپjپ@‚حپA•½ˆہژ‘م‚©‚çژ؛’¬ژ‘م‚ـ‚إ‚ج
پ@ژٹْ‚ةŒ»‚ꂽپA•‘‚¢‰ج‚¤—Vڈ—پ@‚إپAپ@ƒ_ƒ“ƒTپ[پA‰جژè‚ًŒ“‚ث‚½پA
پ@ڈ©•wپ@‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ،پ@”’”ڈژqپ@پi‚µ‚ç‚ر‚ه‚¤‚µپjپ@‚حپA‰G–Xژqپi‚¦‚ع‚µپjپAگ…ٹ±پi‚·‚¢‚©
پ@‚ٌپj‚ج’j‘•‚ً‚µپAپ@چ،—l‚ب‚ا‚ً‰ج‚¢‚ب‚ھ‚çپAپ@”ü‚µ‚•‘‚ء‚½پB
پ@
پ،پ@”’”ڈژq‚ئ‚µ‚ؤپAپ@Œ¹‹`Œoپi‚ف‚ب‚à‚ئ‚ج‚و‚µ‚آ‚ثپj‚ج—ِگl‚جگأŒن
پ@‘Oپi‚µ‚¸‚©‚²‚؛‚ٌپjپ@‚ھپA—L–¼‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@
پôپôپ@”’”ڈژqپ@‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢پAƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپB
پ،پ@پwپ@‹`Œoپ@پi‚و‚µ‚آ‚ثپjپ@پxپ@پi‚m‚g‚j‚Q‚O‚O‚T”N‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پjپB
پ@
پ،پ@پwپ@‘¾•½‹Lپ@پi‚½‚¢‚ض‚¢‚«پjپ@پxپ@پi‚m‚g‚j‚P‚X‚X‚P”N‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پjپB
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ،پ@گV‘I‘g پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ٌ‚¹‚ٌ‚®‚فپjپBپ@
پ@
پ@پ@
پ@پ@پ›پ@ƒhƒ‰ƒ}پuگV‘I‘gŒŒ•—ک^پv‚إپA‹پi“sپj‚جژ،ˆہ‚ًژç‚éگV‘I‘gپB
پ@
پ،پ@گV‘I‘gپB
پ،پ@–¼ڈجپ@پFپ@گV‘I‘gپi‚µ‚ٌ‚¹‚ٌ‚®‚فپjپB
پœپ@•ت–¼پ@پFپ@گVگï‘gپi‚µ‚ٌ‚¹‚ٌ‚®‚فپjپBپ@
پ،پ@گV‘I‘g‚ج‘Oگg‚حپAگpگ¶کQژm‘g‚إ‚ ‚éپB
پ،پ@پsژ،ˆہŒx”ُ‘àپEŒR‘àپtپB
پ،پ@‘¶چفٹْٹشپ@پFپ@
پ@پ@‚P‚W‚U‚R”Nپi•¶‹v‚R”Nپjپ`‚P‚W‚U‚X”Nپi–¾ژ،‚Q”NپjپB
پ،پ@‚P‚W‚U‚R”N‚RŒژ‚ةپAگpگ¶کQژm‘gپi‚ف‚ش‚낤‚µ‚®‚فپj
پ@پ@‚ئ‚µ‚ؤŒ‹گ¬‚³‚êپA‚P‚W‚U‚R”N‚XŒژ‚ةپAگV‘I‘g‚ئ‰ü ڈج
پ@پ@‚·‚éپB
پ،پ@گV‘I‘g‚حپA
پ@پ@چ]Œث–‹•{پi“؟گىژپپjگ¨—ح‚جکQژm‘à‚إ‚ ‚èپAچ]Œث
پ@پ@–‹•{پi“؟گىژپپjگ¨—ح‚جژ،ˆہŒx”ُ‘àپEŒR‘à‚إ‚ ‚éپB
پ،پ@گV‘I‘g‚حپA
ڈ‰‚كپA‰ï’أ”ث—a‚èکQژm‘à‚إپA
پ@پ@Œم‚ةپAچ]Œث–‹•{پi“؟گىژپپj’¼‘®‚جکQژm‘à‚ئ‚ب‚éپB
پ،پ@گV‘I‘g‚حپA
پ@پ@–‹––‚جٹضگ¼‚إ‚حپA‹پi“sپj‚جژ،ˆہŒx”ُ‘à‚إ‚ ‚èپA
–‹––‚ج‹پi“sپj‚جژ،ˆہˆغژ‚ةچvŒ£‚·‚éپB
پ@پ@–¾ژ،ڈ‰ٹْ‚ج“Œ“ْ–{‚إ‚حپAŒR‘à‚ئ‚µ‚ؤپAٹˆ–ô‚·‚éپB
پ،پ@گV‘I‘g‚حپAپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@پ@—E‹C‚ ‚éگيژm‚½‚؟‚إ‚ ‚ء‚½پB
پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@ٹضکA‰و‘œپB
پ@پ پ@پwپ@‹ك“، —Eپ@ پ@پxپ@‰و‘œپ@‚m‚nپD‚PپBپ@
پ@پ پ@پwپ@“y•û چخژOپ@پxپ@‰و‘œپ@‚m‚nپD‚PپBپ@پ@
پ@
پ@پ پ@گV‘I‘g‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[‚¢پA
پ@ ƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پAƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@گV‘I‘gپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@گV‘I‘gپ@پi‚µ‚ٌ‚¹‚ٌ‚®‚فپA= گVگï‘gپAگpگ¶کQ
پ@پ@پ@پ@پ@ژm‘gپA‚P‚W‚U‚R”Nپ`‚P‚W‚U‚X”Nپj‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@چ]Œث–‹•{پi“؟گىژپپjگ¨—ح‚جکQژm‘à‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@پ@پ@پ@چ]Œث–‹•{پi“؟گىژپپjگ¨—ح‚جژ،ˆہŒx”ُ‘àپEŒR‘à
پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@گV‘I‘g‚حپAڈ‰‚كپA‰ï’أ”ث—a‚èکQژm‘à‚إ‚ ‚èپA
پ@پ@پ@پ@پ@Œم‚ةپAچ]Œث–‹•{پi“؟گىژپپj’¼‘®‚جکQژm‘à‚ئ‚ب‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@پ@پ@پ،پ@گV‘I‘g‚حپAپ@‚P‚W‚U‚V”NپiŒc‰‚R”Nپj‚ـ‚إپA‹ك‹E
پ@پ@پ@پ@پ@’n•û‚إپAچ]Œث–‹•{پi“؟گىژپپjگ¨—ح‚جژ،ˆہŒx”ُ
پ@پ@پ@پ@پ@‘à‚ئ‚µ‚ؤپA–‹––‚ج‹پi“sپj‚جژ،ˆہŒx”ُ‚ةچvŒ£
پ@پ@پ@پ@پ@‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گV‘I‘g‚حپA‚P‚W‚U‚W”NپiŒc‰‚S”NپjˆبŒم‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@‹ك‹EپA“Œ“ْ–{‚جٹض“ŒپA“Œ–kپA–kٹC“¹’n•û‚إپA
پ@پ@پ@پ@پ@‹Œچ]Œث–‹•{پi“؟گىژپپjگ¨—ح‚جŒR‘à‚ئ‚µ‚ؤپAٹˆ
پ@پ@پ@پ@پ@–ô‚·‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—E‹C‚ ‚éگيژm‚½‚؟‚إ‚ ‚ء‚½پBپ@پ@پ@
پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@ˆê•ûپAگV’¥‘gپ@پi‚µ‚ٌ‚؟‚ه‚¤‚®‚فپj‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@چ]Œث–‹•{پi“؟گىژپپjگ¨—ح‚جکQژm‘à‚إ‚ ‚èپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@–‹––‚جچ]Œث‚جژ،ˆہŒx”ُ‚ة‚ ‚½‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@
پ@پ،پ@گV‘I‘gپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@گV‘I‘g‚حپAپ@‚P‚X‚U‚R”Nپi•¶‹vپi‚ش‚ٌ‚«‚م‚¤پj‚R”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@‚ةŒ‹گ¬‚³‚êپAپ@‰ï’أ”ث—a‚©‚è‚ئ‚ب‚èپA پ@چ]Œث–‹
پ@پ@پ@پ@پ@•{گ¨—ح‚ج‹“sژçŒىگE‚ج‰ï’أ”ث”z‰؛‚ئ‚ب‚èپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‰ï’أ”ث—a‚è‚جکQژm‘gپA‚P‚W‚U‚R”Nپ`‚P‚W‚U‚V”NپjپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@Œم‚ةپAچ]Œث–‹•{”z‰؛پi–‹•{’¼‘®کQژm‘àپA‚P‚W‚U‚V
پ@پ@پ@پ@پ@”Nپ`‚P‚W‚U‚X”Nپjپ@‚ئ‚ب‚éپB
پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پ@پ@پ، گV‘I‘g‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@–‹––‚ج‚P‚W‚U‚R”Nپi•¶‹v‚R”Nپj‚©‚ç‚P‚W‚U‚V”NپiŒc‰
پ@پ@پ@پ@پ@‚R”Nپj‚ـ‚إپAچ]Œث–‹•{پi“؟گىژپپjگ¨—ح‚ة‚و‚é‹پi“sپj
پ@پ@پ@پ@پ@‚جژ،ˆہ‚جˆê•”‚ً’S‚¤پB
پ@
پ@پ@پ@پ، گV‘I‘g‚ج‹ا’·‚حپAپ@‹ك“، —Eپ@پi‚±‚ٌ‚ا‚¤‚¢‚³‚فپj
پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ ‚èپAپ@گV‘I‘g‚ج•›’·‚حپAپ@“y•û چخژOپ@پi‚ذ‚¶
پ@پ@پ@پ@پ@‚©‚½ ‚ئ‚µ‚¼‚¤پj پ@‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@گV‘I‘gپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@گV‘I‘g‚حپAپ@‚P‚W‚U‚R”Nپi•¶‹v‚R”Nپj‚©‚ç‚P‚W‚U‚X”N
پ@پ@پ@پ@پ@پi–¾ژ،‚Q”Nپj‚ـ‚إ‘¶‘±‚µ‚½چ]Œث–‹•{پi“؟گىژپپjگ¨
پ@پ@پ@پ@پ@—ح‚جکQژm‘à‚إ‚ ‚éپBپ@
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@گV‘I‘gپi‚µ‚ٌ‚¹‚ٌ‚®‚فپj‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@گVگï‘gپi‚µ‚ٌ‚¹‚ٌ‚®‚فپj‚ئ‚à‹L‚³‚ê‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚W‚U‚R”Nپi•¶‹vپi‚ش‚ٌ‚«‚م‚¤پj‚R”Nپj‚ةپAگV‘I
پ@پ@پ@پ@پ@‘g‚ھپAŒ‹گ¬‚³‚ê‚éپB
پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@گV‘I‘g‚حپAپ@–‹––پAپ@چ]Œث–‹•{پi“؟گىژپپjگ¨
پ@پ@پ@پ@پ@—ح‚جژ،ˆہ•”‘à‚ئ‚µ‚ؤپAپ@‹پi“sپj‹y‚ر‹پi“sپj
پ@پ@پ@پ@پ@ژü•س‚جژ،ˆہˆغژپiŒxژ@ٹˆ“®پj‚ةٹˆ–ô‚µپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@”ھŒژڈ\”ھ“ْ‚جگ•دپA‹ض–ه‚ج•دپA•è’Cپi‚ع‚µ
پ@پ@پ@پ@پ@‚ٌپjگي‘ˆ‚إ‚حپAچ]Œث–‹•{پi“؟گىژپپjگ¨—ح‚جŒR
پ@پ@پ@پ@پ@‘à‚ئ‚µ‚ؤپAٹˆ–ô‚·‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@گV‘I‘g‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‚»‚ج’†ٹj‚جƒپƒ“ƒoپ[‚ةپA‹ك“،—E‚ھ“¹ڈêژه‚جپA
پ@پ@پ@پ@پ@پuژژ‰qٹظپvپiژژ‰qڈêپj‚ج–ه’ي‚âگH‹q‚ھ‘½‚‚¢‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پuژژ‰qٹظپvپ@پi‚µ‚¦‚¢‚©‚ٌپA•ت–¼پFژژ‰qڈêپA
پ@پ@پ@پ@پ@Œ»پE“Œ‹“sگVڈh‹وژs’J–ِ’¬‚Q‚T”ش’nپj‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@چ]Œثژ‘م––ٹْ‚ةچ]Œثژs’†‚ة‚ ‚ء‚½پA“V‘R—
پ@پ@پ@پ@پ@گS—¬Œ•ڈp‚ج“¹ڈê‚إ‚ ‚éپBپ@‹ك“،ژüڈ•‚ھ“¹ڈêژه
پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚ ‚èپAŒم‚ةپAژüڈ•‚ج—{ژq‚ئ‚ب‚ء‚½‹ك“،—E‚ھ
پ@پ@پ@پ@پ@‚S‘م–ع‚ًŒp‚®پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژژ‰qٹظپiژژ‰qڈêپj‚ج–ه’ي‚ة‚حپA“y•ûچخژOپA
پ@پ@پ@پ@پ@‰«“c‘چژiپAˆنڈمŒ¹ژOکYپAژR“ىŒhڈ•‚ب‚ا‚ھ‚¨‚èپA
پ@پ@پ@پ@پ@ژژ‰qٹظ‚جگH‹q‚ة‚حپA‰i‘qگV”ھپAŒ´“cچ²”Vڈ•پA
پ@پ@پ@پ@پ@“،“°•½ڈ•پAچض“،ˆê‚ب‚ا‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ@پ،پ@گV‘I‘g‚جٹeگlپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@گV‘I‘g‚جپA‹ك“،—EپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@‹ك“،—Eپ@پi‚±‚ٌ‚ا‚¤‚¢‚³‚فپA‚P‚W‚R‚S”Nپ`‚P‚W
پ@پ@پ@پ@پ@‚U‚W”Nپj‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@•گ‘ چ‘پi‚ق‚³‚µ‚ج‚‚ةپAŒ»پE“Œ‹“sپEچé‹تŒ§
پ@پ@پ@پ@پ@‘ٹ“–’nˆوپj‚ج‘½–€پi‚½‚ـپAŒ»پE“Œ‹“s‘½–€
پ@پ@پ@پ@پ@’n‹وپj‚ج”_–¯ڈoگg‚إپAچ]Œثژ‘م––ٹْ‚ةچ]
پ@پ@پ@پ@پ@Œثژs’†‚ة‚ ‚ء‚½پA“V‘R—گS—¬Œ•ڈp‚ج“¹
پ@پ@پ@پ@پ@ڈêپuژژ‰qٹظپvپi‚µ‚¦‚¢‚©‚ٌپj‚ج“¹ڈêژه‚ئ‚ب‚èپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‚»‚جŒمپAگV‘I‘g‚ج‹ا’·‚ئ‚ب‚èپAگV‘I‘g‚ً
پ@پ@پ@پ@پ@ژw“±‚·‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@‰؛‘چ—¬ژRپi‚µ‚à‚¤‚³‚ب‚ھ‚ê‚â‚ـپj‚جگي‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚W‚U‚W”N‚SŒژ‚Qپ`‚R“ْپj‚إپAگV‘I‘g‚ج‹ا’·
پ@پ@پ@پ@پ@‚ج‹ك“،—Eپi‚±‚¤‚ٌ‚ا‚¤‚¢‚³‚فپj‚حپA‚SŒژ‚R“ْ‚ة
پ@پ@پ@پ@پ@“ٹچ~‚µپAپ@‚P‚W‚U‚W”N‚SŒژ‚Q‚T“ْ‚ةپA”آ‹´ŒYڈê
پ@پ@پ@پ@پ@پi“Œ‹“s”آ‹´‹و•t‹كپj‚إپAژaژٌ‚³‚ê‚éپB
پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@گV‘I‘g‚جپA“y•ûچخژOپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@“y•ûچخژOپi‚ذ‚¶‚©‚½‚ئ‚µ‚¼‚¤پj‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@•گ‘ چ‘پi‚ق‚³‚µ‚ج‚‚ةپAŒ»پE“Œ‹“sپEچé‹تŒ§
پ@پ@پ@پ@پ@‘ٹ“–’nˆوپj‚ج‘½–€پi‚½‚ـپAŒ»پE“Œ‹“s‘½–€
پ@پ@پ@پ@پ@’n‹وپj‚ج”_–¯ڈoگg‚إپAچ]Œث‚ج“¹ڈêپuژژ‰q
پ@پ@پ@پ@پ@ٹظپvپiژژ‰qڈêپj‚ج–ه’ي‚إپA‘½–€“¹ڈêپiچ²“،
پ@پ@پ@پ@پ@•FŒـکY‚جژژ‰qٹظ‘½–€ژx•”“¹ڈêپj‚إŒ•ڈp‚ً
پ@پ@پ@پ@پ@ڈK‚¢پA‚»‚±‚ةŒmŒأ‚جژw“±‚ة—ˆ‚ؤ‚¢‚½‹ك“،
پ@پ@پ@پ@پ@—E‚ئŒً—¬‚ًگ[‚كپAپ@‚»‚جŒمپAگV‘I‘g‚ج•›
پ@پ@پ@پ@پ@’·‚ئ‚ب‚èپAگV‘I‘g‚ج‘gگD‚ًژx‚¦‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@” ٹظپi”ںٹظپjگي‘ˆپi‚P‚W‚U‚X”N‚Sپ`‚TŒژپj‚إپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚W‚U‚X”Nپi–¾ژ،‚Q”Nپj‚TŒژ‚P‚P“ْ‚ةپAپ@” ٹظ
پ@پ@پ@پ@پ@پi”ںٹظ‚ج‹Œ–¼پj‚جˆê–{–طٹض–ه•t‹ك‚جگي‚¢‚إپA
پ@پ@پ@پ@پ@ڈe’e‚ة‚ ‚½‚èپAگيڈê‚إپAگيژ€‚·‚éپBپ@
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@گV‘I‘g‚جپA‰«“c‘چژi‚ئ‰i‘qگV”ھپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@‰«“c‘چژi‚حپAچ]Œث‚ج“¹ڈêپuژژ‰qٹظپv‚ج–ه’ي
پ@پ@پ@پ@پ@‚إپA‰i‘qگV”ھ‚حپAپuژژ‰qٹظپv‚جگH‹q‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@گV‘I‘g‚جژEگlŒ•‚ج’†‚إپAپ@‚±‚ئ‚ة‰«“c‘چژi
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¨‚«‚½‚»‚¤‚¶پjپA‰i‘qگV”ھپi‚ب‚ھ‚‚炵‚ٌ‚د‚؟پj
پ@پ@پ@پ@پ@‚جکr‘O‚حپA‹°‚낵‚پAپ@Œ•‚ج–¼ژè‚ئ‚¢‚¤‚و‚è‚ح
پ@پ@پ@پ@پ@گlژa‚è–¼گl‚ئ‚µ‚ؤ—L–¼‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@گV‘I‘g‚جپAچض“، ˆêپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@چض“، ˆêپi‚³‚¢‚ئ‚¤ ‚ح‚¶‚كپj‚حپAپ@ژRŒû“ٌکYپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@“،“cŒـکY‚ئ‚àڈج‚·پB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@–‹––پA–¾ژ،ڈ‰ٹْ‚ةپAچض“، ˆê‚حپAپ@گV‘I‘g‘à
پ@پ@پ@پ@پ@ˆُپEٹ²•”‚ئ‚µ‚ؤپA‹پi“sپj‚جژ،ˆہپA‰ï’أگي‘ˆ‚إ
پ@پ@پ@پ@پ@ٹˆ–ô‚·‚éپBپ@‹Œ‰ï’أ”ثژm‚ج–؛‚ئŒ‹چ¥‚·‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@چض“، ˆê‚حپAپ@‰ï’أگي‘ˆژ‚ة•ك—¸پi‚ظ‚è‚هپj‚ئ
پ@پ@پ@پ@پ@‚ب‚èپAپ@‚»‚جŒمپA“،“cŒـکY‚ئڈج‚µپA–¾ژ،ٹْ‚ة‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@–¾ژ،گ•{‚جŒxٹ¯‚ئ‚ب‚èپA پ@‚P‚W‚V‚V”Nپi–¾ژ،‚P‚O
پ@پ@پ@پ@پ@”Nپj‚جگ¼“ىگي‘ˆ‚إ‚حپA–¾ژ،گ•{ŒRŒxژ@•”‘à‚إپA
پ@پ@پ@پ@پ@گ¼‹½ŒR‚ئگي‚¢پAٹˆ–ô‚·‚éپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@گV‘I‘g‚جŒ‹گ¬پB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@‚P‚W‚U‚R”Nپi•¶‹vپi‚ش‚ٌ‚«‚م‚¤پj‚R”Nپj‚RŒژ‚ةپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@گpگ¶کQژm‘gپi‚ف‚ش‚낤‚µ‚®‚فپj‚ھپAŒ‹گ¬‚³‚êپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‚»‚جŒمپA‰ï’أ”ث—a‚è‚ئ‚ب‚èپAپ@‚»‚جŒمپA“¯”N
پ@پ@پ@پ@پ@‚XŒژ‚ةگV‘I‘g‚ئ‰üڈج‚·‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گpگ¶کQژm‘gپi‚ف‚ش‚낤‚µ‚®‚فپj‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚W‚U‚R”Nپi•¶‹v‚R”Nپj‚ةپA‰ï’أ”ثژهپEڈ¼•½—e
پ@پ@پ@پ@پ@•غپi‚ـ‚آ‚¾‚¢‚ç‚©‚½‚à‚èپj‚ج‘O‚إ•گ—ح‚ً”âکI
پ@پ@پ@پ@پ@‚µپA•]‰؟‚³‚êپAپ@‰ï’أ”ث—a‚è‚ج•”‘àپiڈ¼•½”ى
پ@پ@پ@پ@پ@ŒمژçŒن—aپj‚ئ‚ب‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@‹پi“sپj‚إپAپ@‚P‚W‚U‚R”Nپi•¶‹v‚R”Nپj‚RŒژ‚P‚Q“ْ
پ@پ@پ@پ@پ@‚ةŒ‹گ¬‚³‚ꂽگpگ¶کQژm‘gپi‚ف‚ش‚낤‚µ‚®‚فپj‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‚»‚جŒمپA‰ï’أ”ث—a‚è‚ئ‚ب‚èپAپ@‚P‚W‚U‚R”Nپi•¶‹v
پ@پ@پ@پ@پ@‚R”Nپj‚XŒژ‚Q‚T“ْ‚ةپAگV‘I‘g‚ئ‰üڈج‚·‚éپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گV‘I‘g‚ج–¼ڈج‚حپAچ]Œث’†ٹْ‚ة‰ï’أ”ث‚ة
پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚ء‚½گ¸‰s•”‘à‚ج–¼ڈج‚إ‚ ‚èپAپ@‰ï’أ”ث‚و‚è
پ@پ@پ@پ@پ@—^‚¦‚ç‚ꂽ–¼ڈج‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@‹پi“sپj‚إپA‚P‚W‚U‚R”Nپi•¶‹v‚R”Nپj‚RŒژ‚P‚Q“ْ‚ةپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‹ك“، —Eپi‚±‚ٌ‚ا‚¤‚¢‚³‚فپjپAپ@“y•û چخژOپi‚ذ‚¶
پ@پ@پ@پ@پ@‚©‚½ ‚ئ‚µ‚¼‚¤پjپAپ@ ‹ع‘ٍ ٹ›پi‚¹‚è‚´‚ي ‚©‚àپjپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@“a“à ‹`—YپAپ@‰ئ—¢ ژںکY ‚ç‚ھپA’†گS‚ئ‚ب‚ء‚ؤپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@گpگ¶کQژm‘g پi‚ف‚ش‚낤‚µ‚®‚فپj‚ھپAپ@Œ‹گ¬‚³‚ê
پ@پ@پ@پ@پ@‚éپ@پi‘nگفژ–ٌ‚Q‚S–¼پjپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@گpگ¶کQژm‘g‚إ‚حپAپ@“à•”چR‘ˆ‚إپAپ@“a“à‹`—Y
پ@پ@پ@پ@پ@‚حپA‚P‚W‚U‚R”Nپi•¶‹v‚R”Nپj‚RŒژ‚Q‚T“ْ‚ةپAڈlگ´
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚م‚‚¹‚¢پj‚³‚êپAپ@‰ئ—¢ژںکY‚حپA‚P‚W‚U‚R”N
پ@پ@پ@پ@پ@پi•¶‹v‚R”Nپj‚SŒژ‚Q‚S“ْ‚ةپAڈlگ´‚³‚êپAپ@‹ع‘ٍٹ›
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¹‚è‚´‚ي‚©‚àپj‚حپA‚P‚W‚U‚R”Nپi•¶‹v‚R”Nپj‚XŒژ
پ@پ@پ@پ@‚P‚W“ْ‚ةپAڈlگ´پi‚µ‚م‚‚¹‚¢پj‚³‚ê پAپ@ژ€‹ژ‚·‚éپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@–‹––‚ج‹‚جژ،ˆہˆغژ‚إٹˆ–ô‚·‚é
پ@پ@پ@ گV‘I‘gپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@‹پi“sپjژ،ˆہˆغژ‚إ‚جگV‘I‘g‚جٹˆ–ôپB
پ@پ@پ@پ،پ@گV‘I‘g‚حپA–‹––پA–¾ژ،ژ‘مڈ‰‚ك‚ج–‹•{گ¨—ح
پ@پ@پ@پ@پ@‚جژ،ˆہŒx”ُ‘àپAŒR‘à‚إ‚ ‚éپB
پ@پ@پ@پ،پ@گV‘I‘g‚حپA–‹––‚ج‹پi“sپj‹y‚ر‹پi“sپjژü•س
پ@پ@پ@پ@پ@‚جژ،ˆہˆغژ‚ةچvŒ£‚·‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@گV‘I‘g‚حپAپ@چ]Œث–‹•{پi“؟گىژپپjگ¨—ح‚ج‹“s
پ@پ@پ@پ@پ@ڈٹژi‘مپA‰ï’أ”ث•؛پAŒ©‰ô‘gپi‚ف‚ـ‚ي‚è‚®‚فپj‚ئ
پ@پ@پ@پ@پ@‹¤‚ةپAپ@–‹––‚ج‹پi“sپj‹y‚ر‹پi“sپjژü•س‚جژ،
پ@پ@پ@پ@پ@ˆہ‚ً‰ٌ•œ‚³‚¹پAپ@–‹––‚ج‹پi“sپj‹y‚ر‹پi“sپjژü
پ@پ@پ@پ@پ@•س‚جژ،ˆہˆغژ‚ةچvŒ£‚·‚éپBپ@
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@گV‘I‘g‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@چ]Œث–‹•{پi“؟گىژپپjژx”z‰؛‚ج‹پi“sپj‚â‹پi“sپj
پ@پ@پ@پ@پ@ژü•س‚جژ،ˆہˆغژ‚ة‚ ‚½‚èپAپ@‚ـ‚½پA‘¸چcپi‰¤پjµ
پ@پ@پ@پ@پ@ˆخ”hپA‘¸چcپi‰¤پj“|–‹”h‚جژuژm‚ب‚ا”½–‹•{گ¨
پ@پ@پ@پ@پ@—ح‚ً’eˆ³‚·‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@‚©‚ء‚ؤ‚حپA‘¸‰¤µˆخ”hژuژm‚حپAپ@‹پi“sپj‚إپA
پ@پ@پ@پ@پ@پu“Vوnپi‚ؤ‚ٌ‚؟‚م‚¤پjپv‚ئڈج‚µ‚ؤپAچ²–‹”hپAŒِ•گ
پ@پ@پ@پ@پ@چ‡‘ج”h‚جگlپX‚ًژECپi‚³‚آ‚è‚پj‚µ‚½‚èپAˆذٹd
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚¢‚©‚پj‚µ‚½‚肵‚½‚ھپAپ@‚P‚W‚U‚R”Nپi•¶‹v‚R”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@‚©‚çچ،“x‚ح‹t‚ةپAپ@گV‘I‘g‚ج‘àˆُ‚جگnپi‚â‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@‚خپj‚ھپAپ@‘¸‰¤µˆخ”hژuژm‚ةڈP‚¢‚©‚©‚éپBپ@
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@‚P‚W‚U‚Q”Nپi•¶‹v‚Q”Nپjپ`‚P‚W‚U‚R”Nپi•¶‹v‚R”Nپj
پ@پ@پ@پ@پ@‚ةپAپ@‘¸چcپi‰¤پjµˆخ”h‚جپA•گژs”¼•½‘¾‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‹پi“sپj‚إ‚جپAگ“G‚âچ²–‹”hپAŒِ•گچ‡‘ج”hپAٹJ
پ@پ@پ@پ@پ@چ‘”h‚ب‚ا‚جگ”پX‚جگlپX‚جˆأژE‚ةٹض—^‚µپA“¯ژu
پ@پ@پ@پ@پ@‚جژh‹q‚ً•ْ‚؟پA“Vوnپi‚ؤ‚ٌ‚؟‚م‚¤پjپAژa›@‚ئڈج‚µ
پ@پ@پ@پ@پ@‚ؤپA ”ق‚ç‚ًˆأژE‚³‚¹‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•گژs”¼•½‘¾‚ج‰؛‚إ“®‚¢‚ؤ‚¢‚½گl•¨‚إ‚حپA
پ@پ@پ@پ@پ@“yچ²”ث‚جگlژa‚èˆب‘ پi‰ھ“cˆب‘ پjپA پ@ژF–€”ث
پ@پ@پ@پ@پ@‚ج“c’†گV•؛‰q‚ب‚ا‚ھ—L–¼‚إ‚ ‚éپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@‚P‚W‚U‚R”Nپi•¶‹v‚R”Nپj‚WŒژ‚©‚ç‚حپi‚P‚W‚U‚V”N
پ@پ@پ@پ@پ@پiŒc‰‚R”Nپj‚ـ‚إپjپAپ@‹پi“sپj‹y‚ر‹پi“sپjژü•س
پ@پ@پ@پ@پ@‚إ‚حپA پ@‹“sڈٹژi‘م‚ج‘¼‚ةپAپ@چ²–‹”h‚جپA‰ï’أ
پ@پ@پ@پ@پ@”ث•؛پAŒ©‰ô‘gپi‚ف‚ـ‚ي‚è‚®‚فپjپA‰ï’أ”ث—a‚è‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@گV‘I‘gپi‚µ‚ٌ‚¹‚ٌ‚®‚فپj‚ب‚ا‚ھپAپ@‹پi“sپj‹y‚ر
پ@پ@پ@پ@پ@‹پi“sپjژü•س‚إ‚جژ،ˆہ‚ًژç‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚é‚ئپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‘¸چcپi‰¤پjµˆخ”hپA‘¸چcپi‰¤پj“|–‹”h‚ج‘¸چc
پ@پ@پ@پ@پ@پi‰¤پjژuژm’B‚حپAپ@‹پi“sپj‚إ‚جٹˆ“®پ@‚âپ@چ²–‹
پ@پ@پ@پ@پ@”hپAŒِ•گچ‡‘ج”h‚جگlپX‚جˆأژE‚âˆذٹdپi‚¢‚©
پ@پ@پ@پ@پ@‚پj‚ھ“‚‚ب‚èپAپ@‹t‚ةپA’ا‚ي‚ê‚é—§ڈê‚ة ‚ب‚ء
پ@پ@پ@پ@پ@‚ؤ‚¢‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@’r“c‰®ژ–ŒڈپB
پ@پ@پ@پœپ@‚P‚W‚U‚S”NپiŒ³ژ،پi‚°‚ٌ‚¶پjŒ³”Nپj‚ج’r“c‰®ژ–Œڈ
پ@پ@پ@پ@پ@‚إپA“ْ–{’†‚ةپ@گV‘I‘g‚ج–¼‚ھپA’m‚ê“n‚éپB
پ@پ@پ@پœپ@‚P‚W‚U‚S”NپiŒ³ژ،پi‚°‚ٌ‚¶پjŒ³”Nپj‚UŒژ‚T“ْ‚ةپA
پ@پ@پ@پ@پ@‹پi“sپj‚ج’r“c‰®‚ةڈW‚ـ‚ء‚½‘¸‰¤µˆخ”hژu
پ@پ@پ@پ@پ@ژm‚ةپAپ@گV‘I‘g‚ج‘àژmپE–ٌ‚Q‚Oگl‚ھژa‚èچ‚قپBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@گV‘I‘g‚ھپAژuژm‚ج‚Xگl‚ًژEٹQ‚µپA‚Q‚Rگl‚ً•ك
پ@پ@پ@پ@پ@”›‚·‚éپBپ@
پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@–¾ژ،ڈ‰ٹْ‚ج•è’Cگي‘ˆپi‚ع‚µ‚ٌ‚¹‚ٌ‚»‚¤پA
پ@پ@پ@پ@ ‚P‚W‚U‚W”N‚PŒژپ`‚P‚W‚U‚X”N‚TŒژپj‚إ‚ج
پ@پ@پ@ گV‘I‘g‚جژQگي‚ئٹˆ–ôپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@‚P‚W‚U‚W”NپiŒc‰‚S”NپA–¾ژ،Œ³”Nپj‚ةپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@’¹‰H•ڑŒ©‚جگي‚¢پi‚P‚W‚U‚W”N‚PŒژ‚R“ْپjپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@—„گç—¼ڈ¼‚جگي‚¢پi‚P‚W‚U‚W”N‚PŒژ‚T“ْپjپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‹´–{‚جگي‚¢پi‚P‚W‚U‚W”N‚PŒژ‚U“ْپjپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@چb”مڈںڈہ‚جگي‚¢پi‚P‚W‚U‚W”N‚RŒژ‚U“ْپjپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‰؛‘چ—¬ژRپi‚µ‚à‚¤‚³‚ب‚ھ‚ê‚â‚ـپj‚جگي‚¢
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚W‚U‚W”N‚SŒژ‚Qپ`‚R“ْپjپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‰F“s‹{ڈé‚جگي‚¢پi‚P‚W‚U‚W”N‚Sپ`‚TŒژپjپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@”’‰حŒûپi‚µ‚ç‚©‚ي‚®‚؟پj‚جگي‚¢پi‚P‚W‚U‚W”N
پ@پ@پ@پ@پ@‚Uپ`‚VŒژپjپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@•êگ¬“»پi‚¨‚ب‚è‚ئ‚¤‚°پj‚جگي‚¢پi‚P‚W‚U‚W”N
پ@پ@پ@پ@پ@‚WŒژ‚Q‚P“ْپA‰ï’أگي‘ˆ‚ج‚P‚آپj پA
پ@پ@پ@پ@پ@‚إپAپ@گV‘I‘g‚حپAپ@–¾ژ،گVگ•{ŒRپi‹ك ‘م“ْ
پ@پ@پ@پ@پ@–{گ•{‚جŒR‘àپj‚ئگي‚ء‚ؤپA”sپi‚â‚شپj‚ê‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پ،پ@‹ك“،—E‚جژ€‹ژپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@‰؛‘چ—¬ژRپi‚µ‚à‚¤‚³‚ب‚ھ‚ê‚â‚ـپj‚جگي‚¢پi‚P‚W
پ@پ@پ@پ@پ@‚U‚W”N‚SŒژ‚Qپ`‚R“ْپj‚إپAپ@گV‘I‘g‚ج ‹ا’·‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@‹ك“،—Eپi‚±‚¤‚ٌ‚ا‚¤‚¢‚³‚فپj‚حپAپ@‚SŒژ‚R“ْ‚ة
پ@پ@پ@پ@پ@“ٹچ~‚µپAپ@‚P‚W‚U‚W”N‚SŒژ‚Q‚T“ْ‚ةپAپ@”آ‹´ŒYڈê
پ@پ@پ@پ@پ@پi“Œ‹“s”آ‹´‹و•t‹كپj‚إپA ژaژٌ‚³‚ê‚éپB
پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@پ،پ@–¾ژ،‰üŒ³پB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@‚P‚W‚U‚W”N‚XŒژ‚ةپAپu–¾ژ،پv‰üŒ³‚ئ‚ب‚éپB
پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚W‚U‚W”N‚XŒژ‚W“ْ‚ةپAŒc‰‚S”N‚ھ–¾ژ،Œ³”N
پ@پ@پ@پ@پ@‚ئ‚ب‚éپB
پ@
پ@پ،پ@گV‘I‘g‚جڈء–إپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@‚P‚W‚U‚X”Nپi–¾ژ،‚Q”Nپj‚جپA” ٹظپi”ںٹظپjگي‘ˆ
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚P‚W‚U‚X”N‚Sپ`‚TŒژپj‚إ‚حپAپ@–kٹC“¹‚جپA“ٌŒز
پ@پ@پ@پ@پ@Œûپi‚س‚½‚ـ‚½‚®‚؟پj‚جگي‚¢پi‚P‚W‚U‚X”N‚SŒژپjپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@” ٹظپi‚ح‚±‚¾‚ؤپA”ںٹظ‚ج‹Œ–¼پj‚جپA•ظ“V‘نڈê
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚ׂٌ‚ؤ‚ٌ‚¾‚¢‚خپj‚جگي‚¢پi‚P‚W‚U‚X ”N‚TŒژپj‚إپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@گV‘I‘g‚حپA–¾ژ،گVگ•{ŒR‚ئگي‚¤پBپ@
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@‘ٹ”nژهŒv‚ج—¦‚¢‚é•ظ“V‘نڈê‚ًژç”ُ‚·‚é
پ@پ@پ@پ@پ@گV‘I‘g‚حپAپ@•ظ“V‘نڈê‚إپA‚P‚W‚U‚X”Nپi–¾ژ،
پ@پ@پ@پ@پ@‚Q”Nپj‚TŒژ‚P‚S“ْ‚ة–¾ژ،گVگ•{ŒR‚ةچ~•ڑ‚µپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@” ٹظپi”ںٹظپj‚ً–{‹’‚ئ‚·‚é‹Œ–‹•{ŒR‚à‚P‚W‚U‚X
پ@پ@پ@پ@پ@”Nپi–¾ژ،‚Q”Nپj‚TŒژ‚P‚W“ْ‚ة چ~•ڑ‚µپAپ@‚±‚±‚ةپA
پ@پ@پ@پ@پ@گV‘I‘g‚حپAژlژU‚µپAڈء–إ‚·‚éپB
پ@پ@پ@پœپ@‚s‚j‚j‚hپ@ƒJƒiƒ„ƒ}’کپ@“ْ–{ژjژ«“TپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@“y•ûچخژO‚جژ€‹ژپB
پ@
پ@پ@پ@پ،پ@“y•ûچخژOپi‚ذ‚¶‚©‚½‚ئ‚µ‚¼‚¤پj‚حپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@” ٹظپi”ںٹظپjگي‘ˆپi‚P‚W‚U‚X”N‚Sپ`‚TŒژپj‚إپAپ@
پ@پ@پ@پ@پ@‚P‚W‚U‚X”Nپi–¾ژ،‚Q”Nپj‚TŒژ‚P‚P“ْ‚ةپAپ@” ٹظ
پ@پ@پ@پ@پ@پi”ںٹظ‚ج‹Œ–¼پj‚جˆê–{–طٹض–ه•t‹ك‚جگي‚¢‚إپA
پ@پ@پ@پ@پ@ڈe’e‚ة‚ ‚½‚èپAگيڈê‚إپAگيژ€ ‚·‚éپBپ@
پ@
پ@
پ@
#-appearingscenes
پ@
پôپôپ@گV‘I‘g‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،
پ@پ@پ@پ@گ[‚¢پAƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پA
پ@پ@پ@پ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپB
پ@
پڑپ@گV‘I‘g‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[
پ@پ@ ‚¢ٹضکAƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[پBپ@
پ@
پ@پ،پ@—ًژj”éکbƒqƒXƒgƒٹƒAپ@
پ@پ@پ@پwپ@گV‘I‘gچإ‹ƒqپ[ƒچپ[پIچض“،ˆêپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ`‰ï’أ”ثپEڈ¼•½—e•غ‚ئ‚جمJپ`پ@پxپBپ@
پ@پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒr ‚ج‚Q‚O‚P‚R”Nپi‚g‚Q‚T”Nپj‚SŒژ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚Q‚S“ْپE–{•ْ‘—پE—ًژjƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[
پ@پ@پ@پ@پ@پ@”ش‘gپjپB
پ@پ@پ،پ@گV‘I‘gپ@‚âپ@چض“،ˆê‚ًڈq‚ׂéپB
پ@
پ@پ،پ@•ذ‰ھˆ¤”Vڈ•‚ج‰ً–¾پI—ًژj‘{چ¸پ@
پ@پ@پ@پwپ@چإگV—ًژj‘{چ¸ƒtƒ@ƒCƒ‹‡A
پ@پ@پ@پ@گV‘I‘gپ@‹ك“،—EپE“y•ûچخژO
پ@پ@پ@پ@‚جŒ•‚ئژ€پ@پxپBپ@
پ@پ@پ@پ@پi“ْƒeƒŒپEƒeƒŒƒr‚ج ‚Q‚O‚P‚U”N‚RŒژ‚Q‚S“ْپE
پ@پ@پ@پ@پ@پ@–{•ْ‘—پE—ًژjƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[”ش‘gپjپB
پ@پ@پ،پ@گV‘I‘gپ@‚âپ@‹ك“،—EپA“y•ûچخژO‚ًڈq‚ׂéپB
پ@
پ@پ،پ@—ًژj”éکbƒqƒXƒgƒٹƒAپ@
پ@پ@پ@پwپ@‚¸‚ء‚ئ‹C’£‚ء‚ؤ‚¢‚½‚©‚ء‚½
پ@پ@پ@پ@پ@پ`گV‘I‘g “y•ûچخژO‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ گ¶‚«‚铹پ`پ@پxپBپ@
پ@پ@ پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒr ‚ج‚Q‚O‚P‚Q”N پi‚g‚Q‚S”Nپj‚TŒژ
پ@پ@پ@پ@پ@‚X“ْپE–{•ْ‘—پE—ًژjƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[”ش‘gپjپB
پ@پ@پ،پ@گV‘I‘gپ@‚âپ@“y•ûچخژO‚ًڈq‚ׂéپB
پ@
پ@پ،پ@—ًژj”éکbƒqƒXƒgƒٹƒAپ@
پ@پ@پ@پwپ@گV‘I‘gپ@‹“sگآڈtک^پ@
پ@پ@پ@پ@پ`‘fٹç‚ج‰«“cپE“y•ûپE‹ك“،پ`پ@پxپBپ@
پ@پ@ پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒrپE‚Q‚O‚O‚X”N پi‚g‚Q‚P”Nپj‚TŒژ
پ@پ@پ@پ@‚P‚R“ْپE–{•ْ‘—پEƒhƒLƒ…ƒپƒ“ƒ^ƒٹپ[”ش‘gپE
پ@پ@پ@پ@‘و‚U‰ٌپjپB
پ@پ@پ،پ@گV‘I‘gپ@‚âپ@‹ك“،—EپA“y•ûچخژO‚ًڈq‚ׂéپB
پ@
پ@
پڑپ@گV‘I‘g‚ھ“oڈê‚·‚éپA‹»–،گ[
پ@پ@ ‚¢ٹضکAƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰وپB
پ@
پ@پ@پ@پœپ@پi’چˆسپjپ@ƒhƒ‰ƒ}پA‰f‰و‚حپAƒtƒBƒNƒVƒ‡ƒ“‚إ‚·پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@—ًژj‚جƒhƒ‰ƒ}‚â‰f‰و‚حپAپ@ژjژہپi—ًژjڈم‚جژ–
پ@پ@پ@پ@ژہپjپ@‚ئپ@‰ث‹َ‚جڈo—ˆژ–‚ھپAپ@چ¬‚¶‚ء‚ؤپA•`‚©
پ@پ@پ@پ@پ@‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپ@‚ـ‚½پAŒ»‘م•—‚ةƒAƒŒƒ“ƒW‚µ‚ؤ
پ@پ@پ@پ@پ@‚ ‚è‚ـ‚·پB
پ@
پ@پ،پ@پwپ@گV‘I‘gŒŒ•—ک^پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚µ‚ٌ‚¹‚ٌ‚®‚ف‚¯‚ء‚ص‚¤‚ë‚پjپ@پx پBپ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒr‚ج‚Q‚O‚P‚P”NƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒhƒ‰ƒ}پjپB
پ@پ@پ،پ@“ْ–{‚جپA–‹––پiچ]Œثژ‘م––ٹْپj‚ً•`‚¢‚½
پ@پ@پ@پ@ƒhƒ‰ƒ}پB
پ@پ@پ،پ@–‹––‚جپAگVگï‘g‚جٹˆ–ô‚ً•`‚¢‚½ƒeƒŒƒr
پ@پ@پ@پ@ƒhƒ‰ƒ}پB
پ@پ@پ@
پ@پ@
پ@پ@پ›پ@ƒhƒ‰ƒ}پuگV‘I‘gŒŒ•—ک^پv‚ج‚o‚qƒtƒHƒgپB
پ@
پ@
پ@پ،پ@پwپ@گV‘I‘gپIپ@پi‚µ‚ٌ‚¹‚ٌ‚®‚فپjپ@پx پBپ@پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پi‚m‚g‚jƒeƒŒƒr‚ج‚Q‚O‚O‚S”N‘ه‰حƒhƒ‰ƒ}پjپB
پ@پ@پ،پ@“ْ–{‚جپA–‹––پiچ]Œثژ‘م––ٹْپj‚ً•`‚¢‚½
پ@پ@پ@پ@ƒhƒ‰ƒ}پB
پ@پ@پ،پ@–‹––پA–¾ژ،ڈ‰ٹْ‚جگV‘I‘g‚جٹˆ–ôپ@‚âپ@
پ@پ@‹ك“،—E‚â“y•ûچخژO‚جگ¶ٹU‚ً•`‚¢‚½
پ@پ@پ@پ@ƒeƒŒƒrƒhƒ‰ƒ}پB
پ@پ@پœپ@‹ك“،—Eپi‚±‚ٌ‚ا‚¤‚¢‚³‚فپj‚ً‰‰‚¶‚½
پ@پ@پ@پ@”o—D–¼پ@پFپ@چپژوگTŒلپ@پi‚r‚l‚`‚oپjپB
پ@پ@پœپ@“y•ûچخژOپi‚ذ‚¶‚©‚½‚ئ‚µ‚¼‚¤پj‚ً‰‰
پ@پ@پ@پ@‚¶‚½”o—D–¼پ@پFپ@ژR–{ چkژjپB
پ@
پ@پ@پ@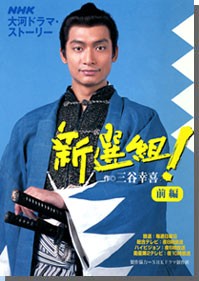
پ@پ@پ@پ›پ@ƒhƒ‰ƒ}پuگV‘I‘gپv‚جڈ‘گذ”ج‘£‚o‚qƒtƒHƒgپB
پ@
پ@
پ پ@ƒپƒjƒ…پ[ پi–عژںپj ‚جگو“ھ‚ض–ك‚éپB
پ پ@“ْ–{ژj ژ«“T ‚جگو“ھƒyپ[ƒW‚ضپ@پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@
پ پ@“ْ–{‚ج—ًژjƒnƒ“ƒhƒuƒbƒN “ْ–{Œê”إ‚ضپB
پ@
پ@
پ@
پ@پwپ@‚ ‚ب‚½‚جƒnپ[ƒg‚ة‚حپ@
پ@پ@ ‰½‚ھژc‚è‚ـ‚µ‚½‚©پHپ@پxپB
پ@
پ@
پ@
ˆبپ@پ@ڈمپBپ@پ@پ@پ@پ@
پ@