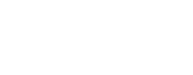マーク・トウェイン
Mark Twain(1835〜1910)作家
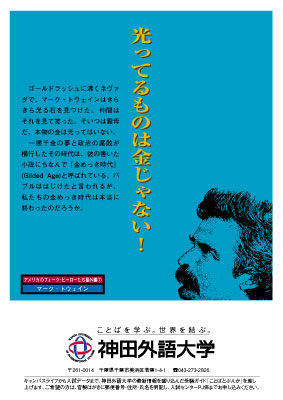
光ってるものは金じゃない!
ゴールドラッシュに沸くネヴァダで、マーク・トウェインはきらきら光る石を見つけた。仲間はそれを見て笑った。そいつは雲母だ、本物の金は光ってはいない。
一攫千金の夢と政治の腐敗が横行したその時代は、彼の書いた小説にちなんで「金めっき時代」(Gilded Age)と呼ばれている。
バブルははじけたと言われるが、私たちの金めっき時代は本当に終わったのだろうか。
掲載:NHKラジオ英会話入門2000年4月号表4
上の画像をクリックすると拡大します
参考資料

『マーク・トウェイン自伝』
マーク・トウェイン著、勝浦吉雄訳(筑摩書房、1985)
「この自伝は墓の中で書いている」とトゥエインは書き出します。「その方が自由にものが言えるから」と。印刷所の植字工の仕事から始め、蒸気船の水先案内人になり、新聞記者から作家として成功するまでのストーリーはすでに有名です。この本でおもしろいのは、その細部の部分が書かれているということでしょう。それぞれの作品を実際にどう書いたかや、講演で話すときの間の取り方や笑わせるコツ、そして娘や妻のことなどが、トウェイン流のユーモアと虚無感をもって語られています。

『マーク・トウェインの世界』
亀井俊介著(南雲堂、1995)
著者は、この本に至るまでに、『サーカスが来た』や『ハックルベリー・フィンはいま』などさまざまな著書で、マーク・トウェインについて語ってきました。その集大成がこの本でしょう。伝記的事実はもちろんのこと、アメリカ文学は著者の専門ですから、各作品についてもきちんと評価がなされているのが強みです。全編にわたり、マーク・トウェインへの愛情に満ちあふれた本になっています。

『サーカスが来た!—アメリカ大衆文化覚書 』
亀井俊介著(文藝春秋社、1980)
広大な田舎に、ことばもよくわからない移民たちが散らばっている・・・それがアメリカ。そこで、人々を楽しませるために生まれたものが、サーカス、講演、大衆小説、映画などでした。当時の普通の人々にとってどんな文化があったのかが論じられています。
各地を巡って人を集めて、外国の風物やこっけいな話などをする講演が人気を博したことがありました。マーク・トウェインもこれを仕事としていた時期があり、ここでは人気講演者としての側面を知ることができます。
『人物アメリカ史(上)』
ロデリック・ナッシュ著、足立康訳
p.271からp.323に、「マーク・トウェイン:ユーモア作家の痛恨の晩年」として伝記が出ています。
『人物アメリカ史:People America(全8巻)』
猿谷要ほか編(綜合社、1984)
「マーク・トウェイン:『トム・ソーヤの冒険』で知られるアメリカの国民作家」と題する伝記が収録されています。
『アメリカ史重要人物101』
猿谷要編(新書館、2001)
「マーク・トウェイン」の項目があります。