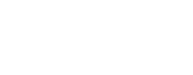ベンジャミン・フランクリン
Benjamin Franklin(1706〜1790)社会活動家

エライ人は間違わない!?
フランス公使に就任したものの、フランクリンはフランス語が得意ではなかった。そこで、フランス語のスピーチがあると隣りの婦人をまねして拍手していた。
ある時、パーティーから帰ってくると、一緒に出席した孫から言われた。
「おじいさんは、自分がほめられている時も拍手していたね」
人は必ず間違う。しかし、高い地位に着いた人は、往々にして自分の誤りを認められなくなる。そのことをフランクリンは繰り返し警告している。
間違う自分を笑いとばすことができる図太いじいさんだった。
掲載:NHKラジオ英語リスニング入門2002年4月号表4
上の画像をクリックすると拡大します
参考資料

『フランクリン自伝』
ベンジャミン・フランクリン著、鶴見俊輔訳(旺文社、1970)
これは偉人フランクリンの回顧録というような本ではありません。「息子へ」という書き出しでわかるように、もともと子どもに自分の生い立ちを語るという形で書き始められたもののようです。そのせいでしょうか、ここには私服のフランクリンが描かれています。説教臭い部分もありますが、上から目線という感じではなく、叩きあげで育ってきた人が語っているというフランクリンの人となりが伝わってくる自伝です。
書かれているのは、少年時代から51歳くらいまでのことなので、それ以後の公人としての活躍については他の本をあたる必要があるでしょう。
『人物アメリカ史(上)』
ロデリック・ナッシュ著、足立康訳
p.68からp.107に、「ベンジャミン・フランクリン:独立戦争を勝利したもっともアメリカ人らしいアメリカ人」として、伝記がでています。
『人物アメリカ史:People America(全8巻)』
猿谷要ほか編(綜合社、1984)
「ベンジャミン・フランクリン:アメリカの成功と夢、典型的アメリカ人」と題する伝記が収録されています。

『進歩がまだ希望であった頃:フランクリンと福沢諭吉』
平川祐弘著(講談社、1990)
副題にある通り、フランクリンと福沢諭吉を比較しながら、その思想・精神や影響を探っていく本です。この二人はどちらも、大きな革命を経験し、そこから社会的・思想的リーダーとなっていきました。有名な自伝を書いたことも共通しています。著者は、主にこの自伝を比較することによって、両者の特徴をよりはっきりさせることに成功しています。

『フランクリンの手紙』
蕗澤忠枝編訳(岩波書店、1951)
フランクリンには政治家としてのほかに、科学者という顔がありました。ここに集められているのはすべて、彼が手がけた科学的実験や見解を、手紙に託して述べたものです。内容は、痛風、風邪や眼鏡の選択といった健康関係から、避雷針や熱気球などの実験、そして太陽の黒点や磁気などの自然現象に至るまで多岐にわたっています。
「友よ、われわれは一世紀早く生まれすぎた。(中略)ああ、百年後に科学界は、はたして、どれほどの高さにまで進展することであろう」と語った科学者フランクリンの面目躍如といった書簡集です。
『アメリカ史重要人物101』
猿谷要編(新書館、2001)
「ベンジャミン・フランクリン」の項目があります。

『プーア・リチャードの暦』
ベンジャミン・フランクリン、真島一男監訳(ぎょうせい、2000)
日本でも、ことわざや教訓などが書いてある日めくりや暦があります。当時のアメリカでは、教訓やことわざが書かれた暦が人気があったといいます。フランクリンはリチャード・サンダースという名前で暦を発行し、そのなかでは、「プア・リチャードが言うには」という書き出しを使って、警句やことわざを紹介してきました。この本は、前半がそうした警句・ことわざとその解説、後半はフランクリンの手紙やエッセイから啓蒙的・教育的な文章を集めたものとなっています。教育的な内容と言っても、フランクリンはユーモアと皮肉を忘れません。フランクリンの教育者としての姿勢が見えてくるようです