村上瑞祥 家相風水コラム村上瑞祥 家相風水コラム
トイレの風水が教えてくれること-1
家相・風水は、中国の広大な土地と環境をベースに生み出されたものです。高層ビルが建ち並び、高気密 ・ 高断熱住宅でエアコンをつけて生活しているこの現代日本で意味はあるのでしょうか?と言うわけで、今回は現代人がより豊かで幸せな暮らしを送るためのツールとして、家相・風水を上手に取り入れる方法を掘り下げて考えてみようと思います。
キーワードは、先人たちが残した本質を見極めて取り入れること。例えばトイレ。トイレの別名は沢山あります。厠、便所、雪隠、御不浄、はばかり、手水、手洗いなどなど、キリが無いほど挙げられます。
ちょっとウンチクを言いますと、「厠」は「川屋」で古代のトイレは川の流れの中にせり出した足場の上で、川の流れにお尻を突き出す形で用を足していました。
また「便所」とは川まで行かなければ排せつが出来なかった時代に、家の近くに汲み取り式のトイレが作れるようになって「便利な場所」だからそう命名されました。
「はばかり」は大小便をするのは人前では「はばかる」行為だからですし、「手水」「手洗い」などはそのままの意味です。
雪隠は、仏話がもとになっています。昔、中国の雪隠寺という寺に雪宝というお坊さんがいまして、用を足しながら悟りを開いたという故事から命名されたと言われています。
と言うことですが、これに関してはちょっと眉唾ものです。実際には、古代の中国の寺ではトイレの ことを青椿(せいちん)と呼んでいました。これはトイレの入り口を椿の木を植えて隠したからで、その「せいちん」がなまって「せっちん」になったのが本当の理由と言われています。
ではお寺さんでは、トイレのこと雪隠と呼ぶのが習わしになっている?と聞かれると、答えはNOです。少なくても禅宗では、トイレのことは「東司」と言います。東司は古い仏教寺院の伽藍(がらん)において、とても重要な役割を担っているもので、「東浄」という神様を祀っている場所を言います。
ちなみにこの「東浄」と言う神様は、「西浄」と対をなす守護神のこと。そう、この東浄こそが便所の神様なのです。 この便所の神様は、歌のように娘を美人にするご利益は無いようですが、昔は流行病から身を守ってくれるというご利益が信じられてきました。
と、長々と書いてきましたが、どこが風水の話なの?結局、歴史ウンチクじゃないと思われたかもしれませんが、ここからが本題。それはまた次回に。
村上瑞祥
初出掲載日:2012年11月2日
最終更新日:2025年3月20日
⇒トイレの風水が教えてくれること-2へ
バナースペース
幸せになる風水の家相学
村上瑞祥監修・執筆「幸せになる風水の家相学」が出版されました。誰でも簡単にわかる本格風水、部屋別吉方位格付けランキング付きです。東急ストアなど全国の大手スーパーなどでお買い求め頂けます。
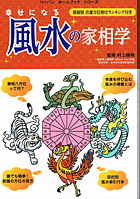
バナースペース
村上瑞祥 家相風水Q&A
家相・風水や干支、日本古来の迷信などの素朴な疑問に専門家がお答えします。
村上瑞祥 家相風水コラム
家相・風水や干支にまつわる雑学のアレコレを村上瑞祥がご紹介します。