村上瑞祥 家相風水コラム村上瑞祥 家相風水コラム
八朔とお中元、幸せな家作り
ようやく蝉の声も聴かれはじめ、夏真っ盛りの季節の到来です。夏と言えば海水浴、風鈴、かき氷、そして暑中見舞いやお中元ですが、この暑中見舞いやお中元は400年前の 「八朔の式日(はっさくのしきじつ)」 から来ています。「八朔」 とはもともと8月1日の呼び名で、米の豊作を祈る節句でした。そして徳川家康が江戸城に初めて入城したのも8月1日だったことから、この日を徳川家の式日(祝日) と定め、「八朔の式日」 と呼ばれるようになりました。
「八朔」 は本来 「田の実の祈り」 を行う祭りですが、そこから江戸市民は 「頼みの祈り」 と言い換え、日ごろお世話になって居る 「頼みの方々」 に贈り物をする日としました。これがお中元の始まりです。遠方の方にはせめて手紙でもという気持ちから暑中見舞いを送りました。
風水をはじめ、易経や姓名判断などには、「人運」 という考え方があります。これは人との出会いを司る運勢を意味し、人と人との関わりを支配すると考えられました。
八朔にはこの人運を大切にする心がこめられています。学校や会社での出会いや地域社会での人間関係は、人が生きることに直結しています。
人運は、幸せな家庭を持ち、良い家を作るためにとても大切なものなのです。 私たち日本人は、人と人との関わり 「人運」 こそが、幸せに暮らすための 「頼み」 になると古来より経験的に知っていたのでしょう。
村上瑞祥
初出掲載日:2011年8月10日
最終更新日:2025年3月20日
⇒水まわりは西に、女性はサルに?へ
バナースペース
幸せになる風水の家相学
村上瑞祥監修・執筆「幸せになる風水の家相学」が出版されました。誰でも簡単にわかる本格風水、部屋別吉方位格付けランキング付きです。東急ストアなど全国の大手スーパーなどでお買い求め頂けます。
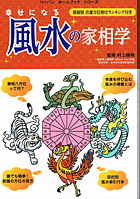
バナースペース
村上瑞祥 家相風水Q&A
家相・風水や干支、日本古来の迷信などの素朴な疑問に専門家がお答えします。
村上瑞祥 家相風水コラム
家相・風水や干支にまつわる雑学のアレコレを村上瑞祥がご紹介します。