村上瑞祥 家相風水コラム村上瑞祥 家相風水コラム
厄年の正体!
震災から早1年が過ぎ、被害に遭われた御霊の一周忌を迎えました。謹んで哀悼の意を奉げますと共に遺族の悲しみにお悔やみを申し上げます。前回の続きです。「厄」とは何か?前回、42歳や25歳と言う年齢には、ごろ合わせ以上の意味は発見されなかったとお話ししました。もちろんこれは歴史資料の中では見当たらないと言う話であって、専門の風水師や陰陽師の方々の一子相伝的な家伝書の中にあったという場合はその限りではありません。
とお断りしましたのも、資料には無くてもこれだけハッキリとした形で伝承されていると言うことは、大衆がそれを認めるだけの根拠があったという事に他なりません。文献や資料には無くても、大衆が腑に落ちる程の一般的な現象であったことを意味しています。
つまり、「大家さん、突然ぽっくり逝っちまってなぁ」「42だってよ、気の毒になぁ」とか「長崎屋の若旦那はまだ25で、嫁さんもらったばっかだったのになぁ」「大旦那もさぞ気落ちしてなさるだろう」と言うような事例が日常的に起こっていたということです。
江戸期における25歳、42歳はどういう年齢なのかと言いますと、武家の25歳は隠居した父の後を継いで当主になったばかりの頃、町人は10歳から奉公して15年の修行の甲斐あって一人前になったあたり、手代などになる頃で、仕事を任されて世間の期待も大きくなり、目も厳しくなる頃です。
42歳はといえば、武家の出世もそろそろ上がりに近く、息子に任せて隠居を考える頃で、町人は長年お世話になったお店からのれん分けしてもらって一家を構える年齢です。
このような年齢に差し掛かった人たちに世間は容赦なく、様々なプレッシャーを与え、そのストレスや不安もかなりのものだったことでしょう。 転換期ですからもちろん様々な事件、トラブルもたくさん起きたことでしょう。 そんなこんなを、「厄」として祓ってしまえばもう安心。不安な心も軽くなる。そんな感じが「厄」と「厄払い」の正体なんじゃないかと思います。
村上瑞祥
初出掲載日:2012年3月11日
最終更新日:2025年3月20日
⇒家相・風水が効く人・効かない人へ
バナースペース
幸せになる風水の家相学
村上瑞祥監修・執筆「幸せになる風水の家相学」が出版されました。誰でも簡単にわかる本格風水、部屋別吉方位格付けランキング付きです。東急ストアなど全国の大手スーパーなどでお買い求め頂けます。
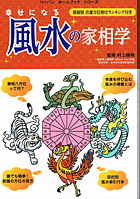
バナースペース
村上瑞祥 家相風水Q&A
家相・風水や干支、日本古来の迷信などの素朴な疑問に専門家がお答えします。
村上瑞祥 家相風水コラム
家相・風水や干支にまつわる雑学のアレコレを村上瑞祥がご紹介します。