村上瑞祥 家相風水コラム村上瑞祥 家相風水コラム
七夕の短冊の願いは祓われる?
今日は七夕です。全国各地で笹に短冊を下げたお祭りが行われていることでしょう。また七夕は旧暦の8月7日に行う、という地域も多いかと思います。七夕は五節句の一つで、本来は [しちせき] と読みます。何をする日かと言えば、物忌み、すなわち穢(けが)れ払いをする日です。
風水の基礎、陰陽思想では奇数は [陽] の数であり、陽が重複する日である3月3日、5月5日などは運気が強すぎてかえって不吉であるとしています。この不吉や穢れを払う禊の日として、節句が始まりました。
古来日本では7月15日は神がこの世に降臨する日とされました。その神がこの世に滞在中、身に着ける衣を織る棚織津女(たなばたつめ) が、穢れを払う禊をするのが7月7日。節句の中でも特に穢れ払いの意味が強い日なのです。
この神の衣を織る棚織津女が、中国から伝来した民間信仰である牛朗織女伝説 (織姫と彦星のお話) と混じり合い、現在の七夕祭りの形へと変化しました。
ちなみに穢れ払いの儀式とは、憑代(よりしろ) に穢れを乗せて海に流し、黄泉の国へ送るもので、精霊流しなどにその名残が見られます。笹船遊びも精霊流しと同じで、笹を憑代として穢れを払うものでした。
七夕で笹を使うのは、その憑代(よりしろ) からの発想で、本来なら払いたい穢れを書いた短冊を下げるべきものです。しかし江戸時代に始まった笹飾りでは、中国伝説の織姫にちなんで、「縫い物が上手になりたい」 というような願い事を書きました。
七夕祭りが一般に広まるにつれ、そこにささやかな庶民の願いがこめられ、本来の穢れを払うお祭りから願掛けのお祭りへと形を変えたのです。
村上瑞祥
初出掲載日:2011年7月7日
最終更新日:2025年3月20日
⇒八朔とお中元、幸せな家作りへ
バナースペース
幸せになる風水の家相学
村上瑞祥監修・執筆「幸せになる風水の家相学」が出版されました。誰でも簡単にわかる本格風水、部屋別吉方位格付けランキング付きです。東急ストアなど全国の大手スーパーなどでお買い求め頂けます。
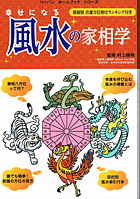
バナースペース
村上瑞祥 家相風水Q&A
家相・風水や干支、日本古来の迷信などの素朴な疑問に専門家がお答えします。
村上瑞祥 家相風水コラム
家相・風水や干支にまつわる雑学のアレコレを村上瑞祥がご紹介します。