 |
 |
| 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |||||
| 2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2010年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 2013年 6月 |
|||
| 28(金) | 「林芙美子記念館」探訪 | ||
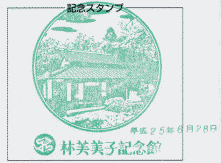 新宿区中井にある林芙美子記念館では、命日(1951年6月28日没)に因み、28、29日の2日間各60名限定で、建物内部の公開がありました。 新宿区中井にある林芙美子記念館では、命日(1951年6月28日没)に因み、28、29日の2日間各60名限定で、建物内部の公開がありました。以前から行きたいと思っていましたので、この機会に申込し、運よく当たったようです。 この家は急斜面にあり、この辺りは急坂がいくつもあって、目白台に続きます。 四の坂を上る途中に記念館入口があります。 |
|||
晩年10年ほどを暮らした屋敷です。 雑木林の中に山野草が植えられ、風情のある庭ですが、芙美子の生存中はほとんどが孟宗竹だったそうです。 直線的な性格の人は植物もまっすぐに伸びる種が好きですが、きっと芙美子もそうであったようで、玄関扉や窓の桟など、いずれも縦線の美しい連続模様でした。 |
|||
敷地は当時1000坪ほどあったそうです。 当時、裏の高台には夫の作ったバラ園があり、梅原龍三郎は「緑敏氏のバラでなければ描けない」と言うほど気に入っていたとか。また、すぐ近所に住んでいた刑部仁もここのバラを好んで描いていたそうです。 普段でも外から中の様子は見られますが、一部屋ずつ、解説を聞きながら畳に座っていると、その家に暮らしたり、訪れた人たちの感覚を重ねられるような気がします。 広々とした南向きの窓をとった居間、適度に光の入る執筆部屋・・・ ご遺族の方のご厚意で、芙美子の着物も展示されていました。 |
|||
| 22(土) | JPSパソコン郵趣部会 例会 於 切手の博物館 | ||
| 9名参加。 「テーマティク収集の流れと傾向」について、F.I.P.の"Thematic Philately Commission"が発行しているTC-News258(2013.4発行)のご紹介をしていただきました。 http://www.fipthematicphilately.org |
|||
| 12(水) | 町田趣味の切手展'13 小型印 申請中です 8/21〜25 | ||
 毎年夏ごろ開催しているJPS町田支部主催の切手展です。 毎年夏ごろ開催しているJPS町田支部主催の切手展です。切手展は町田市立国際版画美術館で開催されますが、美術館内は物品の販売ができないため、臨時郵便局を開設することができず、小型印の押印は町田郵便局で行います。 今年は「アサガオ」でとのことでした。 アサガオは自分で受粉してしまうので、昆虫を呼ぶ必要はありません。ヨトウガやアブラムシが付きもののようですので、アブラムシを退治してくれるテントウムシに登場してもらうことにしました。 |
|||
| 9(日) | JPS昆虫切手部会 例会 | ||
 ミニペックス会場へ受付で残る方もあり、例会への出席者は13名? ミニペックス会場へ受付で残る方もあり、例会への出席者は13名?いつものように会務と新切手ニュースなどで早めに切り上げました。 昆虫部会員 西田豊穂氏「昆虫郵趣ア・ラ・カルト」総集編・続編が発行されました。 部会員価格3000円、一般価格3500円です。 昆虫切手部会報に連載されていた第31回から50回までの他に、オープン切手展出品・グランプリ受賞作「虫の美術史」、金銀賞受賞「マルハナバチ」の全リーフも掲載されています。 ぜひ、お買い求めいただけたら幸いです。(メールで受付いたします) |
|||
| 第28回昆虫切手展 於 切手の博物館 晴れ 入場者数 58名 | |||
作者の解説をお聴きすると、大変理解が深まりますので、大切な時間です。 一方で、せっかく来てくださった方とお話しできずに申し訳なかったのですが…。 |
|||
| 8(土) | 第28回昆虫切手展 於 切手の博物館 晴れ 入場者数106名 | ||
| 土曜日にしては、例会がひとつだけで会議もなく、入場者は少なかったようです。 でも、例年通り遠方から参加される方や、パソコン郵趣部会のお仲間、多くの方にご覧いただきました。 |
|||
| 7(金) | 第28回昆虫切手展 於 切手の博物館 晴れ 入場者数 83名 | ||
 小型印はアポロウスバシロチョウ。細かい線も点もよく出ていて、感心しました。以前よりも細かい部分がつぶれずによく再現されていると感じます。 小型印はアポロウスバシロチョウ。細かい線も点もよく出ていて、感心しました。以前よりも細かい部分がつぶれずによく再現されていると感じます。また、昨年11月くらいから作品を温め、ようやく完成させた作品のお披露目です。 午前中は押印、受付や販売でばたばたしていましたが、遠方より参観に来てくださった方もあり、自分の作品を前にお話をすることもできました。 朝は皆、準備で余裕が無く、集合写真を撮ることも忘れており、昼過ぎに空いたときに撮りました。 |
|||
| 6(木) | 第28回昆虫切手展 設営 | ||
 夕方から設営しました。 夕方から設営しました。アポロ蝶の生息環境・スイスアルプスの風景 難波乗安 1F パルナシウス・コレクション 西田豊穂 14F 昆虫の切手帳 正野俊夫 3F スロベニアの昆虫切手 難波乗安 2F 昆虫でたどる 北杜夫「幽霊」 澤口尚子 3F 身近な蝶 池内 昇 2F すべてわたしのことである一蝶蛾の学名の中のアポローン神― 佐々木雅子 1F 台湾の天牛(カミキリムシ) 柴田 茂 1F 蝶・蛾の加刷切手 淀野孝雄 2F 国民体育大会の昆虫関係小型印等 田中克美 2F クワガタムシ 西田豊穂 6F 蜂ブドー酒 加藤利之 1F |
|||
| 昆虫でたどる 北杜夫「幽霊」 3フレーム出品しました | |||
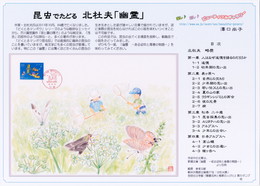 昨年は北杜夫の父・斎藤茂吉の生誕130周年記念と、北杜夫一周忌でした。 昨年は北杜夫の父・斎藤茂吉の生誕130周年記念と、北杜夫一周忌でした。駒込のファーブル昆虫館では「茂吉と宗吉の親子昆虫展」が大変小規模ながら開催されましたし、世田谷文学館の「斎藤茂吉と『楡家の人びと』展」では「どくとるマンボウ昆虫展」と題して標本が飾られました。 そう、文学作品に出てきた昆虫の標本を並べるのは一般的ですが、それを郵趣品でたどっていったらと思いました。 北杜夫が亡くなられてから、著作を読み返しましたが、「幽霊」にこんなにたくさんの昆虫が出てきたとは記憶にありませんでした。メモしていくとそれはそれはたくさんの昆虫が、想い出とともに、あるいは比喩として、美しい瑞々しい文章で綴られていたのでした。 ごく若い頃、まだ昆虫に全く興味もなく、知識もなかったころに読んでも、何もわからなかったのでしょう。 今は、その昆虫の数々の姿かたち、飛び方、生態も分かるようになったので、その情景をはっきりと思い浮かべることができます。 逆に、昆虫を知らない人には、この本をどこまで味わうことができるでしょう? 昆虫を知らない人に、ぜひ説明したいと思いました。この物語に出てくる昆虫はこんな姿をしているのですよ、あぁ、そうなのか…ときっと思っていただけるだろうと思います。 |
|||
 |
トップページへ戻ります。 |