 |
 |
| 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |||||||
| 2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2010年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 2011年 6月 |
|||
| 30(木) | 自然との共生シリーズ 第1集〜日本の希少野生動植物〜 8/23発行 | ||
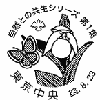 昆虫切手展の会期中に、8/23に発行される切手にチョウが入る、という噂を聞いていましたが、ようやく報道発表がありました。 昆虫切手展の会期中に、8/23に発行される切手にチョウが入る、という噂を聞いていましたが、ようやく報道発表がありました。絶滅危惧種のオオルリシジミです。5連刷10枚シートのうちの2枚ですので悩ましく、初日に京橋局に並んで切り分けてもらわなくてはならないでしょう。記念押印ももちろんしたいですし。 |
|||
 毎年8月に開催していた「川越切手展」は今年は9/8からの開催。 毎年8月に開催していた「川越切手展」は今年は9/8からの開催。小型印の1種は、ヤマトシジミペアリングで申請しているそうです。 |
|||
| 26(日) | 「漱石と文人たちの書画」展 県立神奈川近代文学館 | ||
| こちらでは夏目嘉米子氏と、夏目栄子氏から寄贈を受けた漱石の遺品が多く所蔵されており、また神奈川ゆかりの文学者による書画等、館蔵品による展覧会です。 あちこちの漱石展で観たものでも、こちらの所蔵であったことに驚くものもたくさんありました。 また、この展覧会を観て、改めて読み返したい本も、これから読んでみたい本も出てきました。 |
|||
| 文学館は港の見える丘公園の一角にあり、石川町駅から山手西洋館めぐりをしながら行くことができます。西洋館は内部見学ができるところも多く、庭で絵を描いている人も居ました。何10年ぶりかで歩くので、写真を撮りながらゆっくり向かいました。 日曜のため立ち寄ることはできませんでしたが、石川町駅前局風景印の変遷と合わせて見るとおもしろいです。できることなら絵を描いていきたいものです。 |
|||
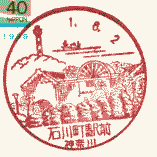 1983.11.1〜1995.3.31 1983.11.1〜1995.3.31大仏次郎記念館、港風景 |
|||
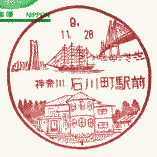 1995.4.1〜1997.11.28 1995.4.1〜1997.11.28ブラフ18番館、ベイブリッジ、日本丸、ランドマークタワー |
|||
 1997.12.1〜 1997.12.1〜重文・旧内田家住宅(外交官の家)、ベイブリッジ、ランドマークタワー 外交官の家は、ニューヨーク総領事やトルコ特命全権大使などをつとめた明治政府の外交官内田定槌氏の邸宅として、東京渋谷の南平台に明治43(1910)年に建てられました。設計者はアメリカ人で立教学校の教師として来日、その後建築家として活躍したJ.M.ガーディナーです。 横浜市は遺族から平成9年に寄贈を受け、山手イタリア山庭園に移築復元し、一般公開したそうです。 |
|||
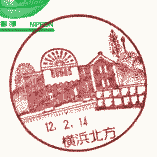 これまでの風景印もよかったですが、外交官の家は石川町駅のホームからも見えるのでよいかもしれませんね。2000.2.12からは横浜北方局で大仏次郎記念館の風景印を使い始めましたし。 これまでの風景印もよかったですが、外交官の家は石川町駅のホームからも見えるのでよいかもしれませんね。2000.2.12からは横浜北方局で大仏次郎記念館の風景印を使い始めましたし。 |
|||
| 20(月) | 町田趣味の切手展'11 8/24〜28 小型印 申請中 | ||
 今年は町田市の花の中から「スミレ」を選び、早春にのみ発生し、スミレでよく吸蜜するミヤマセセリを配しました。 今年は町田市の花の中から「スミレ」を選び、早春にのみ発生し、スミレでよく吸蜜するミヤマセセリを配しました。小型印は町田郵便局のみで使用され、切手展会場の町田市立国際版画美術館では押印できません。また、最終日は使われず、27日までとなります。 |
|||
| 19(日) | 「第26回 昆虫切手展」 最終日 | ||
| 今日は101名の来場者でした。 切手貼り絵教室や部会例会の方々も寄ってくださり、楽しんでいただきました。 午後3時から、部会員による作品解説。自分で一通り見たつもりでも、説明を聞くと聞かないのでは大違い。これは皆さんも同意見で、これからも続けていただけるでしょう。大変興味深かったです。 |
|||
それから全員で記念撮影。 |
|||
昆虫観察や採集、外国切手の入手方法、今回の作品の話など、2時間は楽しくあっという間でした。 今日は1日雨が降らずに幸いでした。 気持ちは半分、来年のミニペックスに向かっていますが、その前に「国際切手展」があり、8/24からの町田趣味の切手展もあります。 とりあえず、今年の「昆虫切手展」は、企画も部会員の協力もまとまり、ほんとうによかったと思います。 参観してくださった皆様、ほんとうにありがとうございました。 |
|||
| 18(土) | 「第26回 昆虫切手展」(無料) 6/17〜19 切手の博物館(10:30〜17:00) | ||
1時前に40名ほどでしたので心配していましたが、部会例会や会議などで郵趣人が多く集まる日であったのも幸いしました。 お声をかけていた方々も大勢いらしてくださり、感謝しております。 |
|||
| 下右は、昨日みえて、小型印がアザミに止まるチョウと知って、絵封筒を作ってこられました。絵のアザミにちょうどオオウラギンヒョウモンが止まっているように見える素晴らしい出来栄えで、部会報とHPに掲載させていただきたいと、写真を撮らせていただきました。 下左は、会場で配っていた外国のプリキャンセル切手を貼ったコンビネーションカバーです。 いろいろに楽しんでいただいて、ほんとうに嬉しいです。 |
|||
| 17(金) | 「第26回 昆虫切手展」(無料) 6/17〜19 切手の博物館(10:30〜17:00) | ||
 昨日、設営、今日から切手展開催です。 昨日、設営、今日から切手展開催です。朝から雨でしたが、83名の来場者がありました。 平日でしたが、1時までに57名もの方が見えたそうで、初日押印の方も多かったのかもしれません。ありがたいことです。 個人的には、小型印のデザイン97号になります。 |
|||
| 下左:開場前に、恒例の記念撮影です。右も開場前、部会員たちが早速昆虫グッズを前に昆虫談議です。 | |||
パソコン部会でもご一緒で、徳島名東局風景印・小型印のときから大変お世話になっており、今回の作品でもいただいた重要なマテリアルを使わせていただいています。 午後は、チェックリストの会議に参加していて、お知り合いの方が見えていたようでしたが、ほとんどお話もできずに失礼してしまいました、ごめんなさい。 写真も日中は全く撮れなかったので、会場の様子は明日以降に。 最終日の3時から、部会員の作品解説があります。 |
|||
| 15(水) | HP10周年 | ||
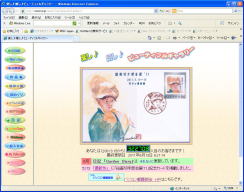 早いもので、年末のご挨拶をしてからあっという間に半年近くが経ってしまいました。 早いもので、年末のご挨拶をしてからあっという間に半年近くが経ってしまいました。HPのリニューアルを、と思いながら、既に5年以上経ってしまったようです。 時代は移り、今はブログやミクシィのような簡便な情報発信の方がはやっており、HPを持つことの意味も変わってきました。 でも、自分の記録として見やすい形はHPなので、この形にこだわっていきたいと思います。 なかなか更新できずに歯がゆい思いもし、ご心配もいただいていますが、どうぞお許しを。 ゆったり構えて見守ってきてくださった方々に、深く感謝しています。 10周年には何か新しいことをしたい思いもありましたが、無理のない範疇で続けていきたいと思います。 |
|||
| 12(日) | JPS昆虫切手部会 例会 於 切手の博物館 | ||
| 次の週末は切手展なので、今週はお休みが多く、9名の参加でした。 部会報の予定、ミニペックスの最終確認事項、昆虫切手チェックリストの打合せ等でした。 |
|||
| 「第26回 昆虫切手展」ご案内 6/17〜19 切手の博物館3階にて 入場無料です | |||
 「第26回 昆虫切手展}がJPS昆虫切手部会の主催で開催されます。 昨年のCOP10で、2011年からの10年間を「生物多様性の10年」とすることが国連で決議されたことに因み、今年の大きなテーマは「昆虫切手に見る生物多様性」です。 それに関連して、今回の記念小型印のテーマは、環境省レッドリストにより「絶滅危惧1類」に指定されている「オオウラギンヒョウモン」です。(小型印の使用は6/17・18の2日間のみ) ご好評を頂いているリーフ展示以外の昆虫標本や昆虫関連グッズ(ネクタイ、標本、陶器など)も多数展示します。 |
|||
| 出品作品は ●昆虫切手に見る生物多様性 石原 博 ●オオウラギンヒョウモン JPS 昆虫切手部会 ●クジャクチョウとキアゲハのマキシマムカード 正野俊夫 ●コロラドハムシ 西田豊穂 ●700 円カマキリ 鈴木瑞男 ●ガーナの通常切手 (1995〜2009) 加藤利之 ●ニューカレドニアの昆虫切手 松林 豊 ●第二次大戦直後のトリエステと周辺国の昆虫切手 難波乗安 ●敷島の道 昆虫採集 −昆虫の種名を詠みこんだ短歌― 佐々木雅子 ●昆虫のエログラム 柴田 茂 ●FFCに使われた蝶・蛾の切手 淀野孝雄 ●戦前の昆虫図入り絵封筒 加藤利之 ●生物多様性…日本の昆虫たちが伝えてくれること 澤口尚子 ●面白カバー集合 西田豊穂 ●蝶博士―知恵袋のふくらみ記― 加藤勝利 ●日本のみほん字昆虫切手 田中克美 わたしも3フレーム出品します。 昆虫に興味のない方でも、興味をお持ちいただけたら、との思いで作りました。 きっと新たに1種か2種の昆虫の名前を覚えてお帰りいただけるのではないかと思っているのですが、いかがでしょうか。 |
|||
 |
トップページへ戻ります。 |