|
仮定Q1:grad f(x0,y0) = ( fx(x0, y0),fy(x0, y0))=(0,0)
仮定Q2:任意の(Δx,Δy)≠(0,0)に対して、 Q(Δx,Δy)>0
ただし、Q(Δx,Δy)=(Δx)2 fxx(x0, y0)+2(Δx)(Δy) fxy(x0, y0)+(Δy)2 fyy(x0, y0)
Ⅰ.
テイラー展開の公式によって、
f(x0+Δx, y0+Δy)= f(x0, y0)+(Δx) fx(x0, y0)+(Δy) fy(x0, y0)+(1/2)Q(Δx,Δy)+R3
とおくと、
∥(Δx,Δy)∥= → 0 とすると、R3 → 0 → 0 とすると、R3 → 0
かつ
∥(Δx,Δy)∥= → 0 とすると、R3/∥(Δx,Δy)∥2=R3/{(Δx)2+(Δy)2}→ 0 → 0 とすると、R3/∥(Δx,Δy)∥2=R3/{(Δx)2+(Δy)2}→ 0
が満たされる。
したがって、ここでは、
仮定Q1「grad f(x0,y0) = ( fx(x0, y0),fy(x0, y0))=(0,0)」より、
f(x0+Δx, y0+Δy)- f(x0, y0)=(1/2)Q(Δx,Δy)+R3 …I-(1)
かつ
∥(Δx,Δy)∥= → 0 とすると、R3 → 0 …I-(2) → 0 とすると、R3 → 0 …I-(2)
かつ
∥(Δx,Δy)∥= → 0 とすると、R3/∥(Δx,Δy)∥2=R3/{(Δx)2+(Δy)2}→ 0 …I-(3) → 0 とすると、R3/∥(Δx,Δy)∥2=R3/{(Δx)2+(Δy)2}→ 0 …I-(3)
が満たされる。
Ⅱ.
任意の非零2次元数ベクトル(Δx,Δy)≠(0,0)に対して、
Q(Δx,Δy) /∥(Δx,Δy)∥2=Q(Δx,Δy) /{(Δx)2+(Δy)2}
を、(Δx,Δy)の関数としてみると、
Q(Δx,Δy) /∥(Δx,Δy)∥2=Q(Δx,Δy) /{(Δx)2+(Δy)2} の最小値Lが存在し[∵下記理由]、
仮定Q2より、
L>0
を満たす。
つまり、
(∀(Δx,Δy) )( (Δx,Δy)≠(0,0) ⇒ Q(Δx,Δy) /∥(Δx,Δy)∥2=Q(Δx,Δy) /{(Δx)2+(Δy)2}≧L>0)
なお、
(Δx,Δy)=(0,0) ⇔ ∥(Δx,Δy)∥= =0 =0
だから、
(∀(Δx,Δy) )( ∥(Δx,Δy)∥= ≠0 ⇒ Q(Δx,Δy) /∥(Δx,Δy)∥2=Q(Δx,Δy) /{(Δx)2+(Δy)2}≧L>0) ≠0 ⇒ Q(Δx,Δy) /∥(Δx,Δy)∥2=Q(Δx,Δy) /{(Δx)2+(Δy)2}≧L>0)
と言っても同じことである。
* * * * * *
別様に書くと、
『R2上の点集合』
D= {(Δx,Δy)∈R2|(Δx,Δy)≠(0,0)} = {(Δx,Δy)∈R2|∥(Δx,Δy)∥= ≠0} (∵ノルムの定義: (Δx,Δy)=(0,0) ⇔ ∥(Δx,Δy)∥=0 ) ≠0} (∵ノルムの定義: (Δx,Δy)=(0,0) ⇔ ∥(Δx,Δy)∥=0 )
において、
Q(Δx,Δy) / ∥(Δx,Δy) ∥2 の最小値Lが存在し、L>0
つまり、
(∀(Δx,Δy) ∈D)(Q(Δx,Δy) /∥(Δx,Δy)∥2 ≧L>0)
* * * * * *
「Q(Δx,Δy) /∥(Δx,Δy)∥2=Q(Δx,Δy) /{(Δx)2+(Δy)2}の最小値L」の存在証明:最大値最小値定理から。
Q(Δx,Δy) /∥(Δx,Δy)∥2
=Q(Δx,Δy) /{(Δx)2+(Δy)2}
={(Δx)2 fxx(x0, y0)+2(Δx)(Δy) fxy(x0, y0)+(Δy)2 fyy(x0, y0)} /{(Δx)2+(Δy)2}
=(Δx)2 fxx(x0, y0) /{(Δx)2+(Δy)2}+ 2(Δx)(Δy) fxy(x0, y0) /{(Δx)2+(Δy)2}+ (Δy)2 fyy(x0, y0) /{(Δx)2+(Δy)2}
= fxx(x0, y0)(Δx)2 /{(Δx)2+(Δy)2}+ 2 fxy(x0, y0)(Δx)(Δy) /{(Δx)2+(Δy)2}+ fyy(x0, y0) (Δy)2/{(Δx)2+(Δy)2}
= fxx(x0, y0){Δx/ }2 + 2 fxy(x0, y0){Δx/ }2 + 2 fxy(x0, y0){Δx/ }{Δy/ }{Δy/ }+ fyy(x0, y0){Δy/ }+ fyy(x0, y0){Δy/ }2 }2
= fxx(x0, y0){Δx/∥(Δx,Δy)∥}2 + 2 fxy(x0, y0){Δx/∥(Δx,Δy)∥}{Δy/∥(Δx,Δy)∥}+ fyy(x0, y0){Δy/∥(Δx,Δy)∥}2
すると、
「Q(Δx,Δy) /∥(Δx,Δy)∥2=Q(Δx,Δy) /{(Δx)2+(Δy)2} は、
2変数2値ベクトル値関数
φ(Δx,Δy)=( Δx/ , Δy/ , Δy/ )=( Δx/∥(Δx,Δy)∥, Δy/∥(Δx,Δy)∥ ) )=( Δx/∥(Δx,Δy)∥, Δy/∥(Δx,Δy)∥ )
と
2変数実数値関数
ψ(h1,h2)= fxx(x0, y0)h12 + 2 fxy(x0, y0)h1h2+ fyy(x0, y0)h22
との合成関数
である。
つまり、
Q(Δx,Δy) /∥(Δx,Δy)∥2=Q(Δx,Δy) /{(Δx)2+(Δy)2}=ψ( φ(Δx,Δy) )
・任意の非零2次元数ベクトル(Δx,Δy)≠(0,0)に対して、
∥ φ(Δx,Δy) ∥=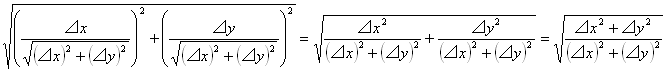 =1 =1
を満たす。
つまり、
定義域D={(Δx,Δy)∈R2|(Δx,Δy)≠(0,0)}={(Δx,Δy)∈R2|∥(Δx,Δy)∥= ≠0} に対して、 ≠0} に対して、
φ(Δx,Δy)=( Δx/ , Δy/ , Δy/ )の値域は、 )の値域は、
{(h1,h2)∈R2|∥(h1,h2)∥ =1 }
これは、要するに、原点を中心とする半径1の円周である。
・{(h1,h2)∈R2|∥(h1,h2)∥ =1 } は、有界な閉集合であって、
ψ( h1,h2 ) は、{(h1,h2)∈R2|∥(h1,h2)∥ =1 } で連続(∵h1,h2の多項式で定義されるh1,h2の2変数関数は連続)。
したがって、最大値最小値定理より、
{(h1,h2)∈R2|∥(h1,h2)∥ =1 }におけるψ( h1,h2 )の最大値・最小値が存在する。
・上記二点をあわせて考えると、
合成関数 ψ( φ(Δx,Δy) ) は、
D={(Δx,Δy)∈R2|(Δx,Δy)≠(0,0)}={(Δx,Δy)∈R2|∥(Δx,Δy)∥= ≠0} において、 ≠0} において、
最大値・最小値を有す
と結論できる。
Ⅲ. [ I-(3)を分析、Ⅱに統合 ]
・I-(3)「 ∥(Δx,Δy)∥= → 0 とすると、R3/∥(Δx,Δy)∥2=R3/{(Δx)2+(Δy)2}→ 0 」 → 0 とすると、R3/∥(Δx,Δy)∥2=R3/{(Δx)2+(Δy)2}→ 0 」
を、極限の定義に遡って書き下すと、
(∀ε>0)(∃δ>0)(∀  ∈R)(0< ∈R)(0< <δ ⇒ | R3/{(Δx)2+(Δy)2}|<ε ) <δ ⇒ | R3/{(Δx)2+(Δy)2}|<ε )
これは、実質的には、
(∀ε>0)(∃δ>0)(∀ (Δx,Δy)∈R2)(0< <δ ⇒ | R3/{(Δx)2+(Δy)2}|<ε ) <δ ⇒ | R3/{(Δx)2+(Δy)2}|<ε )
除外近傍の概念を使うと、
(∀ε>0)(∃δ>0)(∀(Δx,Δy) ∈U*δ(0,0))( R3/{(Δx)2+(Δy)2}∈ Uε(0) )
・だから、Ⅱで出てきた
「 Q(Δx,Δy) /∥(Δx,Δy)∥2=Q(Δx,Δy) /{(Δx)2+(Δy)2}の {(Δx,Δy)∈R2| ∥(Δx,Δy)∥=
 ≠0}における最小値」L(>0) ≠0}における最小値」L(>0)
から作った正値 L/2を、εの具体的な値としても、上記命題は成り立つ。
ε= L/2とすると、上記命題は、以下のようになる。
「ε= L/2にたいして、ある実数δ>0が存在し、
(∀ (Δx,Δy)∈R2)(0< <δ ⇒ | R3/{(Δx)2+(Δy)2}|<ε=L/2 ) <δ ⇒ | R3/{(Δx)2+(Δy)2}|<ε=L/2 )
を満たす。」
除外近傍の概念を使うと、
「ε=L/2にたいして、ある実数δ>0が存在し、
(∀(Δx,Δy) ∈U*δ(0,0) )( R3/{(Δx)2+(Δy)2} ∈ Uε=L/2(0) )
を満たす。」
・つまり、
Ⅱで出てきた「 Q(Δx,Δy) /{(Δx)2+(Δy)2}の {(Δx,Δy)∈R2|∥(Δx,Δy)∥≠0}における最
大値」L(<0)に対して、
(∀ (Δx,Δy)∈R2)(0< <δ ⇒ -L/2< R3/{(Δx)2+(Δy)2}<L/2 ) <δ ⇒ -L/2< R3/{(Δx)2+(Δy)2}<L/2 )
を満たす正数δが存在するといえる。
(∃δ>0)(∀ (Δx,Δy)∈R2)(0< <δ ⇒ -L/2< R3/{(Δx)2+(Δy)2}<L/2 ) <δ ⇒ -L/2< R3/{(Δx)2+(Δy)2}<L/2 )
(∃δ>0)(∀ (Δx,Δy)∈U*δ(0,0) )( -L/2< R3/{(Δx)2+(Δy)2}<L/2 )
Ⅳ [Ⅱ,I-(3)→Ⅲから、I-(1)右辺への示唆]
δを、「『Ⅱで出てきたL』に対して、Ⅲで存在が示された」正数δであるとする。
Ⅱ,Ⅲより、
(∀ (Δx,Δy)∈R2)(0< <δ ⇒ (1/2)Q(Δx,Δy)/{(Δx)2+(Δy)2}+R3/{(Δx)2+(Δy)2}≧L/2 +R3/{(Δx)2+(Δy)2} >0 ) <δ ⇒ (1/2)Q(Δx,Δy)/{(Δx)2+(Δy)2}+R3/{(Δx)2+(Δy)2}≧L/2 +R3/{(Δx)2+(Δy)2} >0 )
ということは、不等式の最左辺・最右辺に{(Δx)2+(Δy)2} (>0)をかけて、
(∀ (Δx,Δy)∈R2)(0< <δ ⇒ (1/2)Q(Δx,Δy)+R3 >0 ) <δ ⇒ (1/2)Q(Δx,Δy)+R3 >0 )
とできる。
つまり、
Ⅲで存在が示された正数δをつかった(Δx,Δy)の範囲に対する制限「0< <δ」 <δ」
を満たす限りで任意の(Δx,Δy)に対して、
(1/2)Q(Δx,Δy)+R3 >0
が満たされる。
除外近傍の概念を使って表現すると、(∀(Δx,Δy)∈ U*δ(0,0)) ( (1/2)Q(Δx,Δy)+R3 >0 )
V. 結論
δを、「『Ⅱで出てきたL』に対して、Ⅲで存在が示された」正数δであるとする。
I-(1)とⅣより、
(∀ (Δx,Δy)∈R2)(0< <δ ⇒ f(x0+Δx, y0+Δy)- f(x0, y0)=(1/2)Q(Δx,Δy)+R3>0 ) <δ ⇒ f(x0+Δx, y0+Δy)- f(x0, y0)=(1/2)Q(Δx,Δy)+R3>0 )
ということは、不等式の最左辺・最右辺だけに着目すると、
(∀ (Δx,Δy)∈R2)(0< <δ ⇒ f(x0+Δx, y0+Δy) > f(x0, y0) ) <δ ⇒ f(x0+Δx, y0+Δy) > f(x0, y0) )
つまり、
Ⅲで存在が示された正数δをつかった(Δx,Δy)の範囲に対する制限「0<∥(Δx,Δy)∥<δ」
を満たす限りで任意の(Δx,Δy)に対して、
f(x0+Δx, y0+Δy) > f(x0, y0)
が成立する。
以上を、
除外近傍の概念を使って表現すると、
「『Ⅱで出てきたL』に対して、Ⅲで存在が示された」正数δに対して、
(∀ (Δx,Δy) ∈U*δ(0,0)) ( f(x0+Δx, y0+Δy) > f(x0, y0) )
よって、仮定Q1,Q2のもとで、
(∃δ>0)(∀ (Δx,Δy)∈R2)(0< <δ ⇒ f(x0+Δx, y0+Δy)> f(x0, y0) ) <δ ⇒ f(x0+Δx, y0+Δy)> f(x0, y0) )
ないし
(∃δ>0) (∀ (Δx,Δy) ∈U*δ(0,0) ) ( f(x0+Δx, y0+Δy)> f(x0, y0) )
が示されたことになる。
(x0+Δx, y0+Δy)を(x,y)と書くと、上記命題は、
(∃δ>0)(∀(x,y)∈R2)(0<∥(x,y)-(x0, y0)∥<δ ⇒ f(x, y) > f(x0, y0) )
ないし
(∃δ>0) (∀(x,y)∈ U*δ(x0,y0) ) ( f(x, y)> f(x0, y0) )
となるから、
仮定Q1,Q2のもとで、
点(x0,y0)で、f は狭義極小である。
|
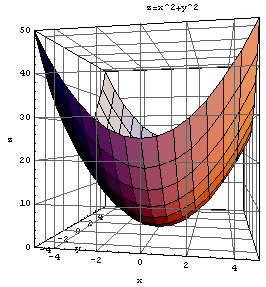
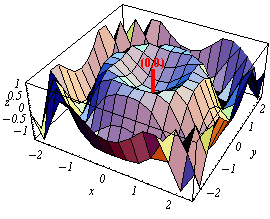
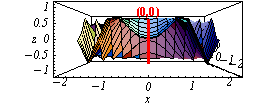
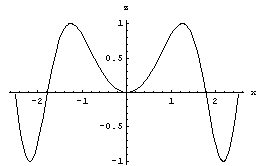
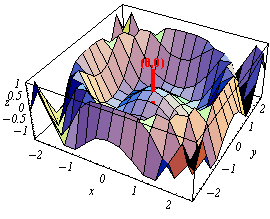
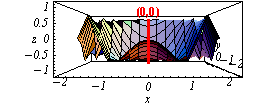
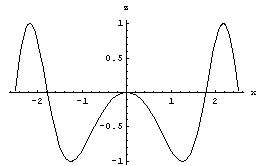
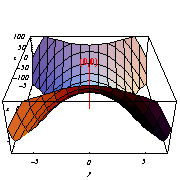
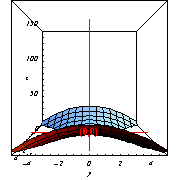
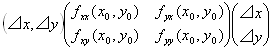
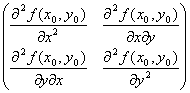
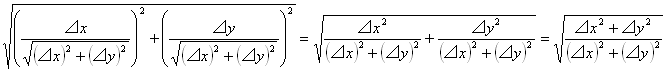 =1
=1