2006
自民党が平成19年度税制改正大綱を決定
2006年12月14日14:31 格納先: 税制改正
自民党が平成19年度税制改正大綱を決定し、ホームページにおいて配布(PDFファイル)している。以下、中小企業や納税者の関心が高いと思われるものを箇条書きする。
【経済活性化・国際競争力の強化】
減価償却制度
1 残存価額の廃止
平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産について、残存価額を廃止する。この場合の定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した数とする。
2 償却可能限度額の廃止
償却可能限度額を廃止する。
① 平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとする。定率法を採用している場合、定率法により計算した減価償却費が一定の金額を下回るときに、償却方法を定率法から定額法に切り替えて減価償却費を計算することとする。
② 平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で均等償却できることとする。
例 法定耐用年数4年のパソコンを期首に100万円で購入し使用開始。償却方法は定率法。
改正前 改正後
1年目の償却費 438,000円 625,000円
2年目の償却費 246,156円 234,375円
3年目の償却費 138,339円 87,890円
4年目の償却費 77,747円 52,734円(定額法)
5年目の償却費 43,694円
6年目の償却費 6,064円
償却費の合計額 950,000円 999,999円
3 法定耐用年数の見直し
次の3設備について、法定耐用年数を短縮する。
① フラットパネルディスプレイ製造設備 10年→5年
② フラットパネル用フィルム材料製造設備 10年→5年
③ 半導体用フォトレジスト製造設備 8年→5年
4 固定資産税の償却資産については、資産課税としての性格を踏まえ、現行の評価方法を維持する。
中小企業・ベンチャー支援
1 特定中小会社が発行した株式にかかる課税の特例(いわゆるエンジェル税制)について、次の措置を講ずる。
① 特定中小会社の要件の緩和
② 対象となる特定新規中小企業者の確認手続の合理化
③ 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の2分の1課税の特例の適用期限を2年延長する。
2 特定同族会社の留保金課税制度について、適用対象から資本金の額又は出資金の額が1億円以下である会社を除外する。
3 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き上げる。
4 中小企業等基盤強化税制について適用対象の機械装置を追加する。
5 地域産業活性化支援税制の創設
6 取引相場のない種類株式の相続税等の評価方法の明確化
7 取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例の創設
8 信用保証協会の抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
【住宅・土地税制】
住宅税制
1 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例の創設
2 住宅のバリアフリー改修促進税制の創設
等々、詳細は配布されているPDFをご覧ください。
【経済活性化・国際競争力の強化】
減価償却制度
1 残存価額の廃止
平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産について、残存価額を廃止する。この場合の定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した数とする。
2 償却可能限度額の廃止
償却可能限度額を廃止する。
① 平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとする。定率法を採用している場合、定率法により計算した減価償却費が一定の金額を下回るときに、償却方法を定率法から定額法に切り替えて減価償却費を計算することとする。
② 平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で均等償却できることとする。
例 法定耐用年数4年のパソコンを期首に100万円で購入し使用開始。償却方法は定率法。
改正前 改正後
1年目の償却費 438,000円 625,000円
2年目の償却費 246,156円 234,375円
3年目の償却費 138,339円 87,890円
4年目の償却費 77,747円 52,734円(定額法)
5年目の償却費 43,694円
6年目の償却費 6,064円
償却費の合計額 950,000円 999,999円
3 法定耐用年数の見直し
次の3設備について、法定耐用年数を短縮する。
① フラットパネルディスプレイ製造設備 10年→5年
② フラットパネル用フィルム材料製造設備 10年→5年
③ 半導体用フォトレジスト製造設備 8年→5年
4 固定資産税の償却資産については、資産課税としての性格を踏まえ、現行の評価方法を維持する。
中小企業・ベンチャー支援
1 特定中小会社が発行した株式にかかる課税の特例(いわゆるエンジェル税制)について、次の措置を講ずる。
① 特定中小会社の要件の緩和
② 対象となる特定新規中小企業者の確認手続の合理化
③ 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の2分の1課税の特例の適用期限を2年延長する。
2 特定同族会社の留保金課税制度について、適用対象から資本金の額又は出資金の額が1億円以下である会社を除外する。
3 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き上げる。
4 中小企業等基盤強化税制について適用対象の機械装置を追加する。
5 地域産業活性化支援税制の創設
6 取引相場のない種類株式の相続税等の評価方法の明確化
7 取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例の創設
8 信用保証協会の抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
【住宅・土地税制】
住宅税制
1 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例の創設
2 住宅のバリアフリー改修促進税制の創設
等々、詳細は配布されているPDFをご覧ください。
土地改良区内の農地の転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われた農地転用決済金等がある場合における譲渡費用の取扱いが変更されました
2006年12月05日10:15 格納先: 所得税
長いタイトルで恐縮です。
土地改良区内の農地の転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われた農地転用決済金等が譲渡費用に当たるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所等において、この農地転用決済金等は譲渡費用に当たるとの判決があったことから、これを受けて、一定の要件を満たす農地転用決済金等については、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用とするよう取扱いを改める、と国税庁ホームページに掲示されました。
詳しい内容はQ&Aを含んだリーフレットが国税庁ホームページにて配布されておりますので、そちらをご覧ください。
【改正の概要】
土地や建物を譲渡した場合の譲渡所得の計算は、これらの資産の譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算することとされている。
土地改良区内にある農地を農地以外に転用して譲渡する場合、土地改良法の規定などにより、土地改良区への農地転用決済金及び協力金等(以下「農地転用決算金」という。)の支払義務が生じることがあるが、これまでは、この農地転用決済金等は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用(資産の譲渡のために直接要した費用及び資産の譲渡価額を増加させるために譲渡に際して支出した費用)に当たらない取扱いがされていた。しかし、このたび、「土地改良区内の農地の転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われた農地転用決済金等が譲渡費用に当たる」とする最高裁判所及び東京高等裁判所の判決があったことから、一定の要件を満たす農地転用決算金等については、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用とするよう取扱いが改められた。
1.農地転用決算金とは?
次の①〜④のすべてを満たすものをいう。
① 売買契約で農地法の規定による農地転用の許可又は届出(以下「農地転用許可等」という)が停止条件とされているなど、売買契約において、土地改良区内の農地を転用して売買することが契約の内容となっていたものであること。
② 土地改良法第42条第2項及びこれを受けた土地改良区の規定により、土地改良区に支払うことが義務づけられている償還金、事業費等(注)であること。
(注)費用の名称については、各土地改良区により異なっている場合がある。
③ 転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われたものであること。
④ 決済の時点ですでに支払義務が発生していた決済年度以前の年度にかかる賦課金等の未納入金でないこと。
2.協力金等とは?
次の①〜④すべてを満たすものをいう。
① 売買契約で農地転用許可等が停止条件とされているなど、売買契約において、土地改良区内の農地を転用して売買することが契約の内容になっていたものであること。
② 土地改良区の規定により、土地改良区に支払うことが義務づけられている協力金、負担金等(注)であること。
(注)費用の名称については、各土地改良区により異なっている場合がある。
③ 転用された土地のために土地改良施設(注)を将来にわたって使用することを目的としたものであること。
(注)「土地改良施設」とは、農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は絵里養生必要な施設
④ 転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われたものであること。
(注)たとえば、次に掲げるものは、原則として「転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われたもの」とは認められないから譲渡費用には当たらない。
イ 農地法第4条の規定に基づいて農地を転用した際に、土地改良区に支払った農地転用決算金等
ロ 土地改良施設使用の再契約のために、土地改良区に支払った協力金等
【過去の事案に対する処置】
農地転用決済均等の金額などを明らかにした上で、税務署に更正の請求の手続きをすることができる。
農業所得など譲渡所得以外の所得の金額の計算上、その農地転用決済均等を必要経費としている場合には、農業所得など譲渡所得以外の所得についても再計算することとなる。また、再計算の結果、所得税が減額されない場合もありえる。
なお、更正の請求をすることができるのは、この「土地改良区内の農地の転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われた農地転用決済金等が譲渡費用の取扱い」の変更を知った日の翌日から2月以内とされている。
(注)法定申告期限からすでに5年を経過している年分の所得税については、法令上、減額されない。
土地改良区内の農地の転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われた農地転用決済金等が譲渡費用に当たるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所等において、この農地転用決済金等は譲渡費用に当たるとの判決があったことから、これを受けて、一定の要件を満たす農地転用決済金等については、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用とするよう取扱いを改める、と国税庁ホームページに掲示されました。
詳しい内容はQ&Aを含んだリーフレットが国税庁ホームページにて配布されておりますので、そちらをご覧ください。
【改正の概要】
土地や建物を譲渡した場合の譲渡所得の計算は、これらの資産の譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算することとされている。
土地改良区内にある農地を農地以外に転用して譲渡する場合、土地改良法の規定などにより、土地改良区への農地転用決済金及び協力金等(以下「農地転用決算金」という。)の支払義務が生じることがあるが、これまでは、この農地転用決済金等は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用(資産の譲渡のために直接要した費用及び資産の譲渡価額を増加させるために譲渡に際して支出した費用)に当たらない取扱いがされていた。しかし、このたび、「土地改良区内の農地の転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われた農地転用決済金等が譲渡費用に当たる」とする最高裁判所及び東京高等裁判所の判決があったことから、一定の要件を満たす農地転用決算金等については、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用とするよう取扱いが改められた。
1.農地転用決算金とは?
次の①〜④のすべてを満たすものをいう。
① 売買契約で農地法の規定による農地転用の許可又は届出(以下「農地転用許可等」という)が停止条件とされているなど、売買契約において、土地改良区内の農地を転用して売買することが契約の内容となっていたものであること。
② 土地改良法第42条第2項及びこれを受けた土地改良区の規定により、土地改良区に支払うことが義務づけられている償還金、事業費等(注)であること。
(注)費用の名称については、各土地改良区により異なっている場合がある。
③ 転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われたものであること。
④ 決済の時点ですでに支払義務が発生していた決済年度以前の年度にかかる賦課金等の未納入金でないこと。
2.協力金等とは?
次の①〜④すべてを満たすものをいう。
① 売買契約で農地転用許可等が停止条件とされているなど、売買契約において、土地改良区内の農地を転用して売買することが契約の内容になっていたものであること。
② 土地改良区の規定により、土地改良区に支払うことが義務づけられている協力金、負担金等(注)であること。
(注)費用の名称については、各土地改良区により異なっている場合がある。
③ 転用された土地のために土地改良施設(注)を将来にわたって使用することを目的としたものであること。
(注)「土地改良施設」とは、農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は絵里養生必要な施設
④ 転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われたものであること。
(注)たとえば、次に掲げるものは、原則として「転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われたもの」とは認められないから譲渡費用には当たらない。
イ 農地法第4条の規定に基づいて農地を転用した際に、土地改良区に支払った農地転用決算金等
ロ 土地改良施設使用の再契約のために、土地改良区に支払った協力金等
【過去の事案に対する処置】
農地転用決済均等の金額などを明らかにした上で、税務署に更正の請求の手続きをすることができる。
農業所得など譲渡所得以外の所得の金額の計算上、その農地転用決済均等を必要経費としている場合には、農業所得など譲渡所得以外の所得についても再計算することとなる。また、再計算の結果、所得税が減額されない場合もありえる。
なお、更正の請求をすることができるのは、この「土地改良区内の農地の転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われた農地転用決済金等が譲渡費用の取扱い」の変更を知った日の翌日から2月以内とされている。
(注)法定申告期限からすでに5年を経過している年分の所得税については、法令上、減額されない。
財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)
2006年11月17日10:44 格納先: 相続税
国税庁ホームページにおいて、「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」が公表されています。同ページに新旧対照表(PDFファイル)も掲載されております。
なお、同通達は平成19年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価及び平成19年分以後の地価税の課税価格の計算の基礎となる土地等の評価に適用されます。
なお、同通達は平成19年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価及び平成19年分以後の地価税の課税価格の計算の基礎となる土地等の評価に適用されます。
居住用財産の譲渡に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例が年内で期限切れ
2006年11月07日10:28 格納先: 所得税
居住用財産の譲渡に係る譲渡損失の特例である「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(買換資産に借入金がある場合の譲渡損失)及び「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(譲渡資産に借入金がある場合の譲渡損失)については、平成18年12月31日までに居住用の家屋・土地等を譲渡した場合に適用されます。適用譲渡期間があと2ヶ月未満となりました。ご注意ください。
1.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41条の5)の適用要件
【譲渡時期】
平成18年12月31日まで
【譲渡資産】
自己の居住の用に供している家屋・土地等の譲渡
【適用除外譲渡先】
譲渡した者の配偶者その他特別の関係がある者に対する譲渡
【所有期間】
譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えていること
【借入金の有無】
取得をした日の属する年の12月31日において買換え資産の取得にあたっての借入金があること
【買換資産の取得】
自己の居住の用に供する家屋・土地等の取得し、居住すること
【過去の居住用財産の譲渡の特例との関係】
譲渡の年の前年又は前々年の資産の譲渡につき居住用の特例を受けていないこと
【過去の居住用財産の譲渡損失との関係】
その年若しくはその年の前年以前3年内における資産の譲渡について特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けていないこと
【譲渡損失の金額の計算】
特例の対象となる家屋・土地等の譲渡に係る譲渡損失の額(他の分離課税に係る譲渡所得に係る損益通算後の額)
【譲渡の年の他の所得との損益通算】
損益通算可
【通算後譲渡損失の繰越控除】
譲渡の年の翌年以後3年
ただし、次の要件を満たしている場合に限る。
・合計所得金額が3千万円以下の年分に限る
・各年の12月31日現在買換資産の借入金残高があること。
・譲渡資産である土地等のうち、その面積が500㎡(平米)を越える部分に相当する金額を除く
2.特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41条の5の2)の適用要件
【譲渡時期】
平成18年12月31日まで
【譲渡資産】
自己の居住の用に供している家屋・土地等の譲渡
【適用除外譲渡先】
譲渡した者の配偶者その他特別の関係がある者に対する譲渡
【所有期間】
譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えていること
【借入金の有無】
譲渡契約締結前日において譲渡資産の取得についての借入金があること
【買換資産の取得】
買換資産の取得要件なし
【過去の居住用財産の譲渡の特例との関係】
譲渡の年の前年又は前々年の資産の譲渡につき居住用の特例を受けていないこと
【過去の居住用財産の譲渡損失との関係】
その年若しくはその年の前年以前3年内における資産の譲渡について居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けていないこと
【譲渡損失の金額の計算】
譲渡した資産の住宅借入金等の金額の合計額から譲渡資産の対価の額を控除した残額(他の分離課税に係る譲渡所得に係る損益通算後の額)
【譲渡の年の他の所得との損益通算】
損益通算可
【通算後譲渡損失の繰越控除】
譲渡の年の翌年以後3年
ただし、合計所得金額が3千万円以下の年分に限る
*注意
「特定の居住用財産の買換え及び交換の特例」(措法36条の6)及び「特定の事業用資産の買換の場合の譲渡所得の課税の特例」(措法37条)の表15号の買換につきましても、譲渡適用期限は平成18年12月31日までとなっています。
1.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41条の5)の適用要件
【譲渡時期】
平成18年12月31日まで
【譲渡資産】
自己の居住の用に供している家屋・土地等の譲渡
【適用除外譲渡先】
譲渡した者の配偶者その他特別の関係がある者に対する譲渡
【所有期間】
譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えていること
【借入金の有無】
取得をした日の属する年の12月31日において買換え資産の取得にあたっての借入金があること
【買換資産の取得】
自己の居住の用に供する家屋・土地等の取得し、居住すること
【過去の居住用財産の譲渡の特例との関係】
譲渡の年の前年又は前々年の資産の譲渡につき居住用の特例を受けていないこと
【過去の居住用財産の譲渡損失との関係】
その年若しくはその年の前年以前3年内における資産の譲渡について特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けていないこと
【譲渡損失の金額の計算】
特例の対象となる家屋・土地等の譲渡に係る譲渡損失の額(他の分離課税に係る譲渡所得に係る損益通算後の額)
【譲渡の年の他の所得との損益通算】
損益通算可
【通算後譲渡損失の繰越控除】
譲渡の年の翌年以後3年
ただし、次の要件を満たしている場合に限る。
・合計所得金額が3千万円以下の年分に限る
・各年の12月31日現在買換資産の借入金残高があること。
・譲渡資産である土地等のうち、その面積が500㎡(平米)を越える部分に相当する金額を除く
2.特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41条の5の2)の適用要件
【譲渡時期】
平成18年12月31日まで
【譲渡資産】
自己の居住の用に供している家屋・土地等の譲渡
【適用除外譲渡先】
譲渡した者の配偶者その他特別の関係がある者に対する譲渡
【所有期間】
譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えていること
【借入金の有無】
譲渡契約締結前日において譲渡資産の取得についての借入金があること
【買換資産の取得】
買換資産の取得要件なし
【過去の居住用財産の譲渡の特例との関係】
譲渡の年の前年又は前々年の資産の譲渡につき居住用の特例を受けていないこと
【過去の居住用財産の譲渡損失との関係】
その年若しくはその年の前年以前3年内における資産の譲渡について居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けていないこと
【譲渡損失の金額の計算】
譲渡した資産の住宅借入金等の金額の合計額から譲渡資産の対価の額を控除した残額(他の分離課税に係る譲渡所得に係る損益通算後の額)
【譲渡の年の他の所得との損益通算】
損益通算可
【通算後譲渡損失の繰越控除】
譲渡の年の翌年以後3年
ただし、合計所得金額が3千万円以下の年分に限る
*注意
「特定の居住用財産の買換え及び交換の特例」(措法36条の6)及び「特定の事業用資産の買換の場合の譲渡所得の課税の特例」(措法37条)の表15号の買換につきましても、譲渡適用期限は平成18年12月31日までとなっています。
印紙税の手引(平成18年10月)
2006年11月01日10:36 格納先: 印紙税
国税庁がホームページで「印紙税の手引(平成18年10月)」を配布(pdfファイル)しております。
契約書に記載された金額により貼付する印紙代が変わってくるわけですが、消費税および地方消費税の金額(以下、「消費税額等」という)を区分記載することにより、消費税額等を記載金額に含めないこととできます。つまり、消費税込み5,250万円の請負契約書を作成した場合、「請負金額 5,250万円」と記載してしまうと6万円の印紙を貼付する必要がありますが、
1.請負金額5,250万円 税抜価格5,000万円 消費税250万円
2.請負金額5,250万円 うち消費税額等250万円
3.請負金額5,000万円 消費税額等250万円 計5,250万円
4.請負金額5,250万円 税抜き価格5,000万円
のように記載することで、記載金額5,000万円の第2号文書として扱われ、貼付する印紙は2万円ですみます。
消費税の記載方法1つで、貼付する印紙額が大きく変わってきますので、ぜひご一読されることをお勧めします。
契約書に記載された金額により貼付する印紙代が変わってくるわけですが、消費税および地方消費税の金額(以下、「消費税額等」という)を区分記載することにより、消費税額等を記載金額に含めないこととできます。つまり、消費税込み5,250万円の請負契約書を作成した場合、「請負金額 5,250万円」と記載してしまうと6万円の印紙を貼付する必要がありますが、
1.請負金額5,250万円 税抜価格5,000万円 消費税250万円
2.請負金額5,250万円 うち消費税額等250万円
3.請負金額5,000万円 消費税額等250万円 計5,250万円
4.請負金額5,250万円 税抜き価格5,000万円
のように記載することで、記載金額5,000万円の第2号文書として扱われ、貼付する印紙は2万円ですみます。
消費税の記載方法1つで、貼付する印紙額が大きく変わってきますので、ぜひご一読されることをお勧めします。
平成18年9月決算法人用 指定寄附金情報
2006年10月27日09:15 格納先: 法人税
平成18年9月決算法人用の「指定寄付金」情報です。寄付金控除を受けるときの参考としてください。
1.個別指定の寄附金
【告知番号:平17.3.8 76】
募金者の名称:財団法人2005年日本国際博覧会協会
募金事務所 :愛知県愛知郡長久手町大字熊張字茨ヶ廻間乙1533-1
目的及び使途:2005年日本国際博覧会開催の費用
募集期間 :自H13.3.9至H18.3.8
【告知番号:平16.5.14 253】
募金者の名称:宗教法人専修寺
募金事務所 :三重県津市一身田町2819番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人専修寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H14.5.15至H17.5.14
【告知番号:平16.7.9 311】
募金者の名称:宗教法人萬福寺
募金事務所 :京都府宇治市五ヶ庄三番割34番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人萬福寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H15.7.11至H17.7.10
【告知番号:平16.9.16 407】
募金者の名称:宗教法人唐招提寺
募金事務所 :奈良県奈良市五條町13番46号
目的及び使途:国宝として指定されている宗教法人唐招提寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H15.9.17至H17.9.16
【告知番号:平16.4.16 217】
募金者の名称:宗教法人大覚寺
募金事務所 :京都府京都市右京区嵯峨大沢町4番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人大覚寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H16.4.16至H17.4.15
【告知番号:平16.7.1 306】
募金者の名称:大阪弁護士会
募金事務所 :大阪府大阪市北区西天満2丁目1番2号
目的及び使途:大阪弁護士会新会館の建設の費用
募集期間 :自H16.7.1至H17.6.30
【告知番号:平16.7.1 306】
募金者の名称:財団法人小倉百人一首文化財団
募金事務所 :京都府京都市中京区烏丸通夷川上る少将井町240番地京都商工会議所内
目的及び使途:博物館施設としての「時雨殿」建設の費用
募集期間 :自H15.7.11至H17.7.10
【告知番号:平16.10.21 460】
募金者の名称:宗教法人善光寺
募金事務所 :長野県長野市大字長野元善町491番地イ号
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人善光寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H16.10.21至H17.10.20
【告知番号:平17.1.21 28】
募金者の名称:財団法人海洋学園設立準備財団
募金事務所 :愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番4号JRセントラルタワーズ
目的及び使途:海洋中等教育学校設置のための校舎建設及び校地及び校具取得の費用
募集期間 :自H17.1.21至H17.9.30
【告知番号:平17.7.6 258】
募金者の名称:財団法人海外子女教育振興財団
募金事務所 :東京都港区愛宕1丁目3番4号
目的及び使途:中華人民共和国蘇州市に設置されている蘇州日本人学校の校舎改修及び校具取得の費用
募集期間 :自H17.7.6至H18.5.31
【告知番号:平17.7.6 258】
募金者の名称:財団法人海外子女教育振興財団
募金事務所 :京都府宇治市五ヶ庄三番割34番地
目的及び使途:ハンガリー共和国ブダペスト市に設置されているブダペスト日本人学校の校舎改修及び校具取得の費用
募集期間 :自H17.7.6至H18.5.31
【告知番号:平17.9.16 354】
募金者の名称:財団法人立志学園設立準備財団
募金事務所 :熊本県熊本市新屋敷1丁目3番25号
目的及び使途:九州中央リハビリテーション学院設置のための校舎建設及び校具取得の費用
募集期間 :自H17.9.16至H17.10.31
【告知番号:平17.10.18 406】
募金者の名称:宗教法人願泉寺
募金事務所 :大阪府貝塚市中846番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人願泉寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H17.10.18至H18.10.17
【告知番号:平17.10.18 406】
募金者の名称:宗教法人吉備津神社
募金事務所 :岡山県岡山市吉備津931番地
目的及び使途:国宝として指定されている宗教法人吉備津神社の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H17.10.18至H18.10.17
【告知番号:平18.2.24 74】
募金者の名称:財団法人宍戸学園設立準備財団
募金事務所 :東京都千代田区神田駿河台2丁目1番18号
目的及び使途:東京聖美医科専門学校設置のための校舎建設並びに校地及び校具取得の費用
募集期間 :自H18.2.24至H18.3.31
2.昭和40年大蔵省(現財務省)告示第154号第4号による財務大臣の承認を受けた寄附金
【告知番号:平17.9.30 365】
募金者の名称:各都道府県共同募金会
目的及び使途:社会福祉事業又は更生保護事業を営むことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用、これらの事業に係る経常的経費又は社会福祉事業に係る民間奉仕活動に必要な基金に充てるための寄附金
募集期間 :自H17.10.1至H17.12.31
3.昭和40年大蔵省(現財務省)告示第154号第5号による財務大臣の承認を受けた寄附金
【告知番号:平18.3.31 132】
募金者の名称:日本赤十字社
目的及び使途:災害救護設備の整備、災害救護物資の備蓄、採血受入機関の整備、原爆病院設備の整備及び救急医療体制の整備に宛てるための寄附金
募集期間 :自H18.4.1至H18.9.30
4.包括指定の寄附金
【学校教育関係】
第1号 :国立大学法人法に規定する国立大学法人若しくは大学共同利用機関法人に対して支出された寄附金で、同法の規定に掲げる業務に充てられるものの全額、独立行政法人国立高等専門学校機構に対して支出された寄附金で、独立行政法人国立高等専門学校機構法の規定に掲げる業務に充てられるものの全額又は地方独立行政法人法に規定する公立大学法人に対して支出された寄附金で、同法の規定に掲げる業務に充てられるものの全額
第1号の2 :学校教育法に規定する学校又は専修学校で、私立学校法に規定する学校法人が設置するものの校舎その他附属設備の受けた災害による被害の復旧のために当該学校法人に対して支出された寄附金の全額
第2号 :学校又は専修学校で、学校法人が設置するものの敷地、校舎その他附属設備に充てるために当該学校法人に対してされる寄附金であって、当該学校法人が当該寄附金の募集につき財務大臣の承認を受けた日から1年を超えない範囲内で財務大臣が定めた期間内に支出されたものの全額
第2号の2 :日本私立学校振興・共済事業団に対して支出された寄附金で、学校法人が設置する学校若しくは専修学校の教育に必要な費用若しくは基金に充てられるものの全額
第2号の3 :独立行政法人日本学生支援機構に対して支出された寄附金で、独立行政法人日本学生支援機構法に規定する学資の貸与に充てられるものの全額
【試験研究関係】
第3号 :特別の法律により設立された法人又は民法の規定により設立された法人で、国民経済上重要と認められる科学技術に関する試験研究を主たる目的とするものの当該試験研究の用に直接供する固定資産の取得のために当該研究法人に対してされる寄附金であって、当該研究法人が当該寄附金の募集につき財務大臣の承認を受けた日から1年を超えない範囲内で財務大臣が定めた期間内に支出されたものの全額
【共同募金関係】
第4号 :各都道府県共同募金会に対して社会福祉法の規定により厚生労働大臣が定める期間内に支出された寄附金で、当該各都道府県共同募金会が当該寄附金の募集につき財務大臣の承認を受けたものの全額
第4号の2 :社会福祉事業又は更生保護事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用、これらの事業に係る経常的経費又は社会福祉事業に係る民間奉仕活動に必要な基金に充てるために中央共同募金会又は各都道府県共同募金会に対して支出された寄附金の全額
【日本赤十字社関係】
第5号 :日本赤十字社に対して毎年4月1日から9月30日までのあいだに支出された寄附金で、日本赤十字社が当該寄附金の募集につき財務大臣の承認を受けたものの全額
1.個別指定の寄附金
【告知番号:平17.3.8 76】
募金者の名称:財団法人2005年日本国際博覧会協会
募金事務所 :愛知県愛知郡長久手町大字熊張字茨ヶ廻間乙1533-1
目的及び使途:2005年日本国際博覧会開催の費用
募集期間 :自H13.3.9至H18.3.8
【告知番号:平16.5.14 253】
募金者の名称:宗教法人専修寺
募金事務所 :三重県津市一身田町2819番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人専修寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H14.5.15至H17.5.14
【告知番号:平16.7.9 311】
募金者の名称:宗教法人萬福寺
募金事務所 :京都府宇治市五ヶ庄三番割34番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人萬福寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H15.7.11至H17.7.10
【告知番号:平16.9.16 407】
募金者の名称:宗教法人唐招提寺
募金事務所 :奈良県奈良市五條町13番46号
目的及び使途:国宝として指定されている宗教法人唐招提寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H15.9.17至H17.9.16
【告知番号:平16.4.16 217】
募金者の名称:宗教法人大覚寺
募金事務所 :京都府京都市右京区嵯峨大沢町4番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人大覚寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H16.4.16至H17.4.15
【告知番号:平16.7.1 306】
募金者の名称:大阪弁護士会
募金事務所 :大阪府大阪市北区西天満2丁目1番2号
目的及び使途:大阪弁護士会新会館の建設の費用
募集期間 :自H16.7.1至H17.6.30
【告知番号:平16.7.1 306】
募金者の名称:財団法人小倉百人一首文化財団
募金事務所 :京都府京都市中京区烏丸通夷川上る少将井町240番地京都商工会議所内
目的及び使途:博物館施設としての「時雨殿」建設の費用
募集期間 :自H15.7.11至H17.7.10
【告知番号:平16.10.21 460】
募金者の名称:宗教法人善光寺
募金事務所 :長野県長野市大字長野元善町491番地イ号
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人善光寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H16.10.21至H17.10.20
【告知番号:平17.1.21 28】
募金者の名称:財団法人海洋学園設立準備財団
募金事務所 :愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番4号JRセントラルタワーズ
目的及び使途:海洋中等教育学校設置のための校舎建設及び校地及び校具取得の費用
募集期間 :自H17.1.21至H17.9.30
【告知番号:平17.7.6 258】
募金者の名称:財団法人海外子女教育振興財団
募金事務所 :東京都港区愛宕1丁目3番4号
目的及び使途:中華人民共和国蘇州市に設置されている蘇州日本人学校の校舎改修及び校具取得の費用
募集期間 :自H17.7.6至H18.5.31
【告知番号:平17.7.6 258】
募金者の名称:財団法人海外子女教育振興財団
募金事務所 :京都府宇治市五ヶ庄三番割34番地
目的及び使途:ハンガリー共和国ブダペスト市に設置されているブダペスト日本人学校の校舎改修及び校具取得の費用
募集期間 :自H17.7.6至H18.5.31
【告知番号:平17.9.16 354】
募金者の名称:財団法人立志学園設立準備財団
募金事務所 :熊本県熊本市新屋敷1丁目3番25号
目的及び使途:九州中央リハビリテーション学院設置のための校舎建設及び校具取得の費用
募集期間 :自H17.9.16至H17.10.31
【告知番号:平17.10.18 406】
募金者の名称:宗教法人願泉寺
募金事務所 :大阪府貝塚市中846番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人願泉寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H17.10.18至H18.10.17
【告知番号:平17.10.18 406】
募金者の名称:宗教法人吉備津神社
募金事務所 :岡山県岡山市吉備津931番地
目的及び使途:国宝として指定されている宗教法人吉備津神社の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H17.10.18至H18.10.17
【告知番号:平18.2.24 74】
募金者の名称:財団法人宍戸学園設立準備財団
募金事務所 :東京都千代田区神田駿河台2丁目1番18号
目的及び使途:東京聖美医科専門学校設置のための校舎建設並びに校地及び校具取得の費用
募集期間 :自H18.2.24至H18.3.31
2.昭和40年大蔵省(現財務省)告示第154号第4号による財務大臣の承認を受けた寄附金
【告知番号:平17.9.30 365】
募金者の名称:各都道府県共同募金会
目的及び使途:社会福祉事業又は更生保護事業を営むことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用、これらの事業に係る経常的経費又は社会福祉事業に係る民間奉仕活動に必要な基金に充てるための寄附金
募集期間 :自H17.10.1至H17.12.31
3.昭和40年大蔵省(現財務省)告示第154号第5号による財務大臣の承認を受けた寄附金
【告知番号:平18.3.31 132】
募金者の名称:日本赤十字社
目的及び使途:災害救護設備の整備、災害救護物資の備蓄、採血受入機関の整備、原爆病院設備の整備及び救急医療体制の整備に宛てるための寄附金
募集期間 :自H18.4.1至H18.9.30
4.包括指定の寄附金
【学校教育関係】
第1号 :国立大学法人法に規定する国立大学法人若しくは大学共同利用機関法人に対して支出された寄附金で、同法の規定に掲げる業務に充てられるものの全額、独立行政法人国立高等専門学校機構に対して支出された寄附金で、独立行政法人国立高等専門学校機構法の規定に掲げる業務に充てられるものの全額又は地方独立行政法人法に規定する公立大学法人に対して支出された寄附金で、同法の規定に掲げる業務に充てられるものの全額
第1号の2 :学校教育法に規定する学校又は専修学校で、私立学校法に規定する学校法人が設置するものの校舎その他附属設備の受けた災害による被害の復旧のために当該学校法人に対して支出された寄附金の全額
第2号 :学校又は専修学校で、学校法人が設置するものの敷地、校舎その他附属設備に充てるために当該学校法人に対してされる寄附金であって、当該学校法人が当該寄附金の募集につき財務大臣の承認を受けた日から1年を超えない範囲内で財務大臣が定めた期間内に支出されたものの全額
第2号の2 :日本私立学校振興・共済事業団に対して支出された寄附金で、学校法人が設置する学校若しくは専修学校の教育に必要な費用若しくは基金に充てられるものの全額
第2号の3 :独立行政法人日本学生支援機構に対して支出された寄附金で、独立行政法人日本学生支援機構法に規定する学資の貸与に充てられるものの全額
【試験研究関係】
第3号 :特別の法律により設立された法人又は民法の規定により設立された法人で、国民経済上重要と認められる科学技術に関する試験研究を主たる目的とするものの当該試験研究の用に直接供する固定資産の取得のために当該研究法人に対してされる寄附金であって、当該研究法人が当該寄附金の募集につき財務大臣の承認を受けた日から1年を超えない範囲内で財務大臣が定めた期間内に支出されたものの全額
【共同募金関係】
第4号 :各都道府県共同募金会に対して社会福祉法の規定により厚生労働大臣が定める期間内に支出された寄附金で、当該各都道府県共同募金会が当該寄附金の募集につき財務大臣の承認を受けたものの全額
第4号の2 :社会福祉事業又は更生保護事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用、これらの事業に係る経常的経費又は社会福祉事業に係る民間奉仕活動に必要な基金に充てるために中央共同募金会又は各都道府県共同募金会に対して支出された寄附金の全額
【日本赤十字社関係】
第5号 :日本赤十字社に対して毎年4月1日から9月30日までのあいだに支出された寄附金で、日本赤十字社が当該寄附金の募集につき財務大臣の承認を受けたものの全額
平成18年10月 健康保険法の一部改正
2006年10月16日09:54 格納先: 社会保険
【高額医療費における自己負担限度額等の見直し】
高額医療費とは、被保険者本人・被扶養者ともに同一の医療機関での一人1ヶ月の窓口負担額が自己負担限度額を超えた分について、被保険者の請求により高額医療費として払い戻される制度です。
*〈 〉内の額は、多数該当の場合。
1.70歳未満の方
① 上位所得者(月収53万円以上)の自己負担限度額
150,000円+(医療費−500,000円)×1%
〈83,400円〉
② 一般の自己負担限度額
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
〈44,400円〉
③ 低所得者(住民税非課税者等)の自己負担額
35,400円
〈24,600円〉
2.70際以上の方
① 現役並み所得者(月収28万円以上、ただし収入520万円未満等の場合、届出により一般扱い)
外来・・・44,400円
自己負担限度額・・・80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
〈44,400円〉
② 一般
外来・・・12,000円
自己負担限度額・・・44,400円
③ 低所得者(住民税非課税者等)
IIの外来・・・8,000円
IIの自己負担限度額・・・26,400円
I(年金収入80万円以下等)の外来・・・8,000円
I(年金収入80万円以下等)の自己負担限度額・・・15,000円
【埋葬料、出産育児一時金の見直し】
① 埋葬料とは、被保険者が亡くなられたとき(被扶養者が亡くなられたときは、家族埋葬料)、埋葬を行った家族に、埋葬料が支給される制度です。
埋葬料及び家族埋葬料の額
従前 :被保険者が亡くなったときは、最低10万円
被扶養者が亡くなったときは、10万円
↓ ↓ ↓
改正後:一律5万円
② 出産育児一時金とは、被保険者が出産したとき(被扶養者が出産したときは同額が家族出産育児一時金として支給)、1児につき定額が支給される制度です。
出産育児一時金(又は家族出産育児一時金)の額
従前 :30万円
↓ ↓
改正後:35万円
以上、詳細は社会保険庁ホームページをご覧ください。
高額医療費とは、被保険者本人・被扶養者ともに同一の医療機関での一人1ヶ月の窓口負担額が自己負担限度額を超えた分について、被保険者の請求により高額医療費として払い戻される制度です。
*〈 〉内の額は、多数該当の場合。
1.70歳未満の方
① 上位所得者(月収53万円以上)の自己負担限度額
150,000円+(医療費−500,000円)×1%
〈83,400円〉
② 一般の自己負担限度額
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
〈44,400円〉
③ 低所得者(住民税非課税者等)の自己負担額
35,400円
〈24,600円〉
2.70際以上の方
① 現役並み所得者(月収28万円以上、ただし収入520万円未満等の場合、届出により一般扱い)
外来・・・44,400円
自己負担限度額・・・80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
〈44,400円〉
② 一般
外来・・・12,000円
自己負担限度額・・・44,400円
③ 低所得者(住民税非課税者等)
IIの外来・・・8,000円
IIの自己負担限度額・・・26,400円
I(年金収入80万円以下等)の外来・・・8,000円
I(年金収入80万円以下等)の自己負担限度額・・・15,000円
【埋葬料、出産育児一時金の見直し】
① 埋葬料とは、被保険者が亡くなられたとき(被扶養者が亡くなられたときは、家族埋葬料)、埋葬を行った家族に、埋葬料が支給される制度です。
埋葬料及び家族埋葬料の額
従前 :被保険者が亡くなったときは、最低10万円
被扶養者が亡くなったときは、10万円
↓ ↓ ↓
改正後:一律5万円
② 出産育児一時金とは、被保険者が出産したとき(被扶養者が出産したときは同額が家族出産育児一時金として支給)、1児につき定額が支給される制度です。
出産育児一時金(又は家族出産育児一時金)の額
従前 :30万円
↓ ↓
改正後:35万円
以上、詳細は社会保険庁ホームページをご覧ください。
Q&A かんたん電子申告
2006年10月05日17:52 格納先: 法人税
2004年(平成16年)6月から、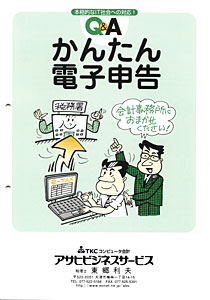 インターネットによる所得税・法人税・消費税の電子申告が、全国で一斉に始まりました。電子申告は、電子政府の実現に向けた国の施策「e-Japan重点計画」の一環であり、国民の利便性の向上と行政の事務効率化を目的とする制度です。
インターネットによる所得税・法人税・消費税の電子申告が、全国で一斉に始まりました。電子申告は、電子政府の実現に向けた国の施策「e-Japan重点計画」の一環であり、国民の利便性の向上と行政の事務効率化を目的とする制度です。
アサヒビジネスサービス及び東郷会計事務所では、当事務所のサポートのもとスムーズに電子申告に移行できるよう、クライアントの皆さんに知っておいていただきたいポイントをわかりやすく説明したQ&A形式の解説書を限定配布しております。
【目次】
Q1.電子申告が全国で始まったそうですが、その理由を教えてください。
Q2.電子申告は従来の申告と、どこが違うのでしょうか?
Q3.電子申告をするには、誰に相談すればよいのですか?
Q4.電子申告をはじめるにあたり、具体的に何をすればよいのですか?
Q5.電子署名に使う「住民基本台帳(住基)カード」とは、どんなカードですか?
Q6.申請時に必要な「電子申告開始届出書」には何を記載しますか?
Q7.電子申告で個人情報がもれる心配はありませんか?
Q8.電子申告だけでなく、電子納税もできると聞きましたが。
Q9.地方税の電子申告は、いつから始まりますか?
Q10.電子申告にすると、申告内容の信頼性は高まりますか?
Q11.電子帳簿への移行も考えています。主な留意点は?
なお、国税庁の電子申告ホームページはこちらです。
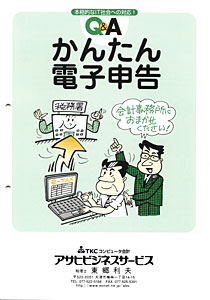
アサヒビジネスサービス及び東郷会計事務所では、当事務所のサポートのもとスムーズに電子申告に移行できるよう、クライアントの皆さんに知っておいていただきたいポイントをわかりやすく説明したQ&A形式の解説書を限定配布しております。
【目次】
Q1.電子申告が全国で始まったそうですが、その理由を教えてください。
Q2.電子申告は従来の申告と、どこが違うのでしょうか?
Q3.電子申告をするには、誰に相談すればよいのですか?
Q4.電子申告をはじめるにあたり、具体的に何をすればよいのですか?
Q5.電子署名に使う「住民基本台帳(住基)カード」とは、どんなカードですか?
Q6.申請時に必要な「電子申告開始届出書」には何を記載しますか?
Q7.電子申告で個人情報がもれる心配はありませんか?
Q8.電子申告だけでなく、電子納税もできると聞きましたが。
Q9.地方税の電子申告は、いつから始まりますか?
Q10.電子申告にすると、申告内容の信頼性は高まりますか?
Q11.電子帳簿への移行も考えています。主な留意点は?
なお、国税庁の電子申告ホームページはこちらです。
特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例に係る取扱いの改正
2006年09月22日11:16 格納先: 相続税
1.議決権に制限がある者が有する株式又は出資(租通69の5-1)
特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例の適用対象株式等には、法人の株主総会又は社員総会において議決権を行使できる事項の全部又は一部について制限された株式又は出資は含まれないこととされている。
今回の会社法の施行により、同法109条において、「公開会社でない株式会社は、第105条第1項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。」こととなった。そこで、同条を受け、その対象株式等の範囲について、法人の株主総会等において議決権を行使できる事項の全部又は一部について制限がある株主又は社員の有する株式又は出資についても、特例の適用対象株式等から場外することとされた。
(参考)会社法105条(株主の権利)
株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一 剰余金の配当を受ける権利
二 残余財産の分配を受ける権利
三 株主総会における議決権
2.清算中の法人に係る株式又は出資(租通69の5-2(3))
相続税の申告期限において特定同族会社株式等に係る法人が清算中であったときは、その特定同族会社株式等については、特例の適用対象から除外されることとなった。
3.特例適用要件である「役員である期間」(租通69の5-16)
特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例は、その適用対象資産である株式等の適用要件に、一定の期間その株式等の発行法人の役員であることが要件とされている。この役員期間の算定について、特例適用対象資産が特定受贈同族会社株式等(清算課税の適用を受けた株式等をいう)の場合は、贈与により取得した日以後に株式等発行法人に会社分割等があり、特定受贈同族会社等に対応する株式を取得した場合においては、特定受贈同族会社株式等を贈与により取得した日から対応株式を取得することとなった事由(租税特別措置法施行令42条の2の2第11項)が生じた時までの間において、その特定事業用資産相続人等が特定受贈同族会社等に係る法人の役員であった場合には、その期間において役員であった期間は、対応株式に係る法人の役員であった期間とみなして、役員である期間を判定することとなった。
特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例の適用対象株式等には、法人の株主総会又は社員総会において議決権を行使できる事項の全部又は一部について制限された株式又は出資は含まれないこととされている。
今回の会社法の施行により、同法109条において、「公開会社でない株式会社は、第105条第1項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。」こととなった。そこで、同条を受け、その対象株式等の範囲について、法人の株主総会等において議決権を行使できる事項の全部又は一部について制限がある株主又は社員の有する株式又は出資についても、特例の適用対象株式等から場外することとされた。
(参考)会社法105条(株主の権利)
株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一 剰余金の配当を受ける権利
二 残余財産の分配を受ける権利
三 株主総会における議決権
2.清算中の法人に係る株式又は出資(租通69の5-2(3))
相続税の申告期限において特定同族会社株式等に係る法人が清算中であったときは、その特定同族会社株式等については、特例の適用対象から除外されることとなった。
3.特例適用要件である「役員である期間」(租通69の5-16)
特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例は、その適用対象資産である株式等の適用要件に、一定の期間その株式等の発行法人の役員であることが要件とされている。この役員期間の算定について、特例適用対象資産が特定受贈同族会社株式等(清算課税の適用を受けた株式等をいう)の場合は、贈与により取得した日以後に株式等発行法人に会社分割等があり、特定受贈同族会社等に対応する株式を取得した場合においては、特定受贈同族会社株式等を贈与により取得した日から対応株式を取得することとなった事由(租税特別措置法施行令42条の2の2第11項)が生じた時までの間において、その特定事業用資産相続人等が特定受贈同族会社等に係る法人の役員であった場合には、その期間において役員であった期間は、対応株式に係る法人の役員であった期間とみなして、役員である期間を判定することとなった。
財産評価基本通達の一部改正に係る意見を公募
2006年09月05日09:39 格納先: 相続税
国税庁は財産評価基本通達の一部改正に先立ち、改正案を示して広く意見を募っている。一部改正案は次の通り。
なお、意見の募集は平成18年10月4日までで、改正の取扱いは平成19年1月1日以後に相続等により取得した財産の評価について適用される予定。
1.奥行価格補正率表等の改正
近年の地価の上昇傾向等を踏まえ、宅地等の評価の適正性を確保するため、路線価により評価する場合に適用する「奥行価格補正率表」等を改正する予定です。
2.国税局長の指定する株式の廃止
日本証券業協会における登録銘柄として取り扱われる基準のうち、主要な基準に該当するものに準ずると認められる株式については、「国税局長の指定する株式」とされておりました。しかし、登録銘柄の登録基準が平成16年12月13日に廃止されたことから、国税局長の指定する株式に関する取扱いを廃止する予定です。
3.類似業種比準方式の改正
(1)「資本金50円換算」方式の改正
類似業種の株価及び各比準要素の数値は、「1株あたりの資本金の額を50円とした場合の株式数」によっておりますが、会社法の改正により最低資本金制度が廃止され、資本金を資本準備金等に振り替え、資本金の額をゼロとすることも可能となったことから、「1株あたりの資本金の額を50円とした場合の株式数」を「1株あたりの資本金等の額を50円とした場合の株式数」に改正する予定です。
(参考)資本金等の額については、法人税法2条16号、同法施工例8条によります。
(2)自己株式の取扱い
保有自己株式については、法人税法上、従来、資産の部に計上しておりましたが、平成18年度の法人税法の改正により、資産の部に計上せず、資本金等の額を減少することとされました。そこで、株式評価においても、簿価純資産価額から自己株式を控除するとともに、発行済株式数からも自己株式を控除する予定です。
(3)比準要素である配当金額の改正
株式評価の比準要素の一つである「1株あたりの配当金額」は、「直前期末以前2年間におけるその会社の利益の年配当金額」を基に計算することとされておりますが、会社法においては、「配当」は旧商法が採っていた各事業年度の決算で確定した「利益処分による配当」ではなく、「剰余金の配当」とされ、株主総会の決議があれば何回でも配当することが可能とされました。これに伴い、類似業種比準方式の計算においても「1株あたりの配当金額」は、「直前期末以前2年間におけるその会社の剰余金の配当額」を基に計算する予定です。
また、配当は利益の配当以外に資本の払戻しによる「剰余金の配当」によることもできることとされたことから、株式評価上、「1株当たりの配当金額」を計算する場合には、剰余金の配当のうち資本の払戻しに該当する金額を除く予定です。
4.配当還元方式の改正
配当還元評価方式により評価する場合には、「1株あたりの資本金の額を50円とした場合の年配当金額及び株式数」を基に計算しますが、「1株あたりの資本金等の額を50円とした場合の年配当金額及び株式数」に改正する予定です。
なお、意見の募集は平成18年10月4日までで、改正の取扱いは平成19年1月1日以後に相続等により取得した財産の評価について適用される予定。
1.奥行価格補正率表等の改正
近年の地価の上昇傾向等を踏まえ、宅地等の評価の適正性を確保するため、路線価により評価する場合に適用する「奥行価格補正率表」等を改正する予定です。
2.国税局長の指定する株式の廃止
日本証券業協会における登録銘柄として取り扱われる基準のうち、主要な基準に該当するものに準ずると認められる株式については、「国税局長の指定する株式」とされておりました。しかし、登録銘柄の登録基準が平成16年12月13日に廃止されたことから、国税局長の指定する株式に関する取扱いを廃止する予定です。
3.類似業種比準方式の改正
(1)「資本金50円換算」方式の改正
類似業種の株価及び各比準要素の数値は、「1株あたりの資本金の額を50円とした場合の株式数」によっておりますが、会社法の改正により最低資本金制度が廃止され、資本金を資本準備金等に振り替え、資本金の額をゼロとすることも可能となったことから、「1株あたりの資本金の額を50円とした場合の株式数」を「1株あたりの資本金等の額を50円とした場合の株式数」に改正する予定です。
(参考)資本金等の額については、法人税法2条16号、同法施工例8条によります。
(2)自己株式の取扱い
保有自己株式については、法人税法上、従来、資産の部に計上しておりましたが、平成18年度の法人税法の改正により、資産の部に計上せず、資本金等の額を減少することとされました。そこで、株式評価においても、簿価純資産価額から自己株式を控除するとともに、発行済株式数からも自己株式を控除する予定です。
(3)比準要素である配当金額の改正
株式評価の比準要素の一つである「1株あたりの配当金額」は、「直前期末以前2年間におけるその会社の利益の年配当金額」を基に計算することとされておりますが、会社法においては、「配当」は旧商法が採っていた各事業年度の決算で確定した「利益処分による配当」ではなく、「剰余金の配当」とされ、株主総会の決議があれば何回でも配当することが可能とされました。これに伴い、類似業種比準方式の計算においても「1株あたりの配当金額」は、「直前期末以前2年間におけるその会社の剰余金の配当額」を基に計算する予定です。
また、配当は利益の配当以外に資本の払戻しによる「剰余金の配当」によることもできることとされたことから、株式評価上、「1株当たりの配当金額」を計算する場合には、剰余金の配当のうち資本の払戻しに該当する金額を除く予定です。
4.配当還元方式の改正
配当還元評価方式により評価する場合には、「1株あたりの資本金の額を50円とした場合の年配当金額及び株式数」を基に計算しますが、「1株あたりの資本金等の額を50円とした場合の年配当金額及び株式数」に改正する予定です。
Q&A 役員給与の税務
2006年08月05日17:38 格納先: 法人税
平成18年度の税制改正で、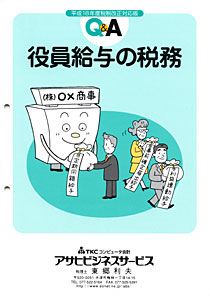 役員報酬等に関する規定が大きく変わりました。アサヒビジネスサービス及び東郷会計事務所では、この改正についてわかりやすく説明したQ&A形式の解説書をクライアントの皆様に配布しております。
役員報酬等に関する規定が大きく変わりました。アサヒビジネスサービス及び東郷会計事務所では、この改正についてわかりやすく説明したQ&A形式の解説書をクライアントの皆様に配布しております。
【目次】
Q1.法人税法では、役員の範囲はどう定められているのでしょうか?
Q2.平成18年度の税制改正で、役員報酬や賞与などに関して、大きく改正されたそうですが、どのように変わったのですか?
Q3.中間決算を迎え、上半期(6ヶ月)の業績が予算をかなり上回ったので、下半期の役員報酬(月々の支給分)を一律に引き上げたいと思いますが、この場合も定期同額給与と認められますか?
Q4.月々の定額報酬以外に、ボーナス時期等に役員に支給する賞与が損金として認められるようになったと聞いたのですが、それについて教えてください。
Q5.事前届出が必要な役員給与を支給する場合、その届出はいつまでにするのですか?
Q6.事前届出を行うに当たって、どのようなことを記載しなければならないのでしょうか?
Q7.当社の会計参与に就任してもらった税理士には、年2回(中間決算期と期末決算期)、報酬を支払う予定ですが、この場合も届出が必要ですか?
Q8,業績連動報酬が損金として認められるようになったと聞きましたが、それについて教えてください。
Q9.定期同額給与や事前確定届出給与等に該当する給与であれば、支給した全額が損金となるのですか?(当社は特殊支配同族会社ではありません)
Q10.平成18年度の税制改正で、実質的に個人事業者と変わらないような同族会社のオーナー役員の給与については、損金算入が制限されることになったと聞きましたが、それについて教えてください。
Q11.特殊支配同族会社であっても給与所得控除相当額の損金不算入が適用されない場合があると聞いたのですが、どのような場合ですか?
なお、国税庁ホームページにおきましても、「役員給与に関するQ&A(PDF書類)」が配布されております。ただし、こちらは当事務所で配布しております解説書とはまったく別のものです。
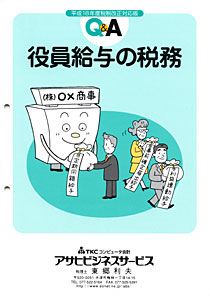
【目次】
Q1.法人税法では、役員の範囲はどう定められているのでしょうか?
Q2.平成18年度の税制改正で、役員報酬や賞与などに関して、大きく改正されたそうですが、どのように変わったのですか?
Q3.中間決算を迎え、上半期(6ヶ月)の業績が予算をかなり上回ったので、下半期の役員報酬(月々の支給分)を一律に引き上げたいと思いますが、この場合も定期同額給与と認められますか?
Q4.月々の定額報酬以外に、ボーナス時期等に役員に支給する賞与が損金として認められるようになったと聞いたのですが、それについて教えてください。
Q5.事前届出が必要な役員給与を支給する場合、その届出はいつまでにするのですか?
Q6.事前届出を行うに当たって、どのようなことを記載しなければならないのでしょうか?
Q7.当社の会計参与に就任してもらった税理士には、年2回(中間決算期と期末決算期)、報酬を支払う予定ですが、この場合も届出が必要ですか?
Q8,業績連動報酬が損金として認められるようになったと聞きましたが、それについて教えてください。
Q9.定期同額給与や事前確定届出給与等に該当する給与であれば、支給した全額が損金となるのですか?(当社は特殊支配同族会社ではありません)
Q10.平成18年度の税制改正で、実質的に個人事業者と変わらないような同族会社のオーナー役員の給与については、損金算入が制限されることになったと聞きましたが、それについて教えてください。
Q11.特殊支配同族会社であっても給与所得控除相当額の損金不算入が適用されない場合があると聞いたのですが、どのような場合ですか?
なお、国税庁ホームページにおきましても、「役員給与に関するQ&A(PDF書類)」が配布されております。ただし、こちらは当事務所で配布しております解説書とはまったく別のものです。
Q&A 交際費の税務
2006年07月15日17:13 格納先: 法人税
平成18年度の税制改正で、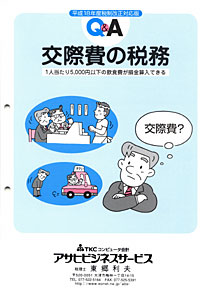 「1人当たり5,000円以下の飲食費」が交際費の範囲から除かれ、損金算入が認められることとなりました。アサヒビジネスサービス及び東郷会計事務所では、この改正についてわかりやすく説明したQ&A形式の解説書をクライアントの皆様に配布しております。
「1人当たり5,000円以下の飲食費」が交際費の範囲から除かれ、損金算入が認められることとなりました。アサヒビジネスサービス及び東郷会計事務所では、この改正についてわかりやすく説明したQ&A形式の解説書をクライアントの皆様に配布しております。
【目次】
Q1.平成18年度税制改正では、交際費の取扱いはどのように変わりましたか?
Q2.飲食費の一部が交際費から除外されるとのことですが、そのためにはどのような条件があるのですか?
Q3.「1人当たり5,000円以下の飲食費」であるかどうかは、具体的にはどのように判断すればよいのですか?
Q4.接待等の飲食費が1人当たり5,000円以下であることを証明するためには、その飲食を行ったお店の領収書があれば大丈夫ですか?
Q5.中小企業(資本金1億円以下)の場合、交際費のうち一定割合を損金に算入できるそうですが、どのように計算するのですか?
Q6.交際費とこれに隣接する費目(隣接費用)とをまちがえるケースが多いと聞きました。どんな点に気をつけたらよいでしょうか?
Q7.会議に伴って飲食をしました。こんな場合でも交際費になるのでしょうか?
Q8.社内の役職員間だけの飲食費は交際費となるのですか?
Q9.お得意さんと会社で商談を終え、接待のために「ちょっと食事でも・・・」と、タクシーで料理屋やスナックに移動しました。これは交際費ですか。
Q10.当社では、売上が成立したら紹介者に手数料を支払うようにしています。この支払手数料は交際費になるのでしょうか?
Q11.当社の社員旅行にお得意様を招待しました。この場合、社員旅行の費用はすべて福利厚生費としてもいいのでしょうか?
Q12.毎年、得意先に社名入りの手帳を配っていますが、今年は、上位顧客には高価な特別製のシステム手帳を配る予定です。特別製のものは、社名等は入れません。これは広告宣伝費となるでしょうか?
Q13.会社としてさまざまな会、クラブ等に入会しています。これらの入会金や年会費はすべて交際費になりますか?
Q14.冠婚葬祭での祝い金や見舞金、香典等は交際費になるのでしょうか?
Q15.得意先が加入する同業者団体が研究発表会を開くことになり、得意先からその団体への協賛金の協力を申し込まれました。この費用は交際費ですか?
Q16.交際費について、適切な会計処理をするためには、日頃からどのようなことに気をつければよいでしょうか?
なお、国税庁ホームページにおきましても、「交際費等(飲食費)に関するQ&A(PDF書類)」が配布されております。ただし、こちらは当事務所で配布しております解説書とはまったく別のものです。
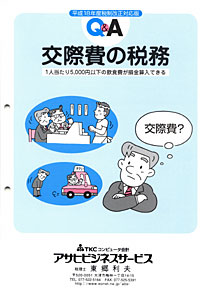
【目次】
Q1.平成18年度税制改正では、交際費の取扱いはどのように変わりましたか?
Q2.飲食費の一部が交際費から除外されるとのことですが、そのためにはどのような条件があるのですか?
Q3.「1人当たり5,000円以下の飲食費」であるかどうかは、具体的にはどのように判断すればよいのですか?
Q4.接待等の飲食費が1人当たり5,000円以下であることを証明するためには、その飲食を行ったお店の領収書があれば大丈夫ですか?
Q5.中小企業(資本金1億円以下)の場合、交際費のうち一定割合を損金に算入できるそうですが、どのように計算するのですか?
Q6.交際費とこれに隣接する費目(隣接費用)とをまちがえるケースが多いと聞きました。どんな点に気をつけたらよいでしょうか?
Q7.会議に伴って飲食をしました。こんな場合でも交際費になるのでしょうか?
Q8.社内の役職員間だけの飲食費は交際費となるのですか?
Q9.お得意さんと会社で商談を終え、接待のために「ちょっと食事でも・・・」と、タクシーで料理屋やスナックに移動しました。これは交際費ですか。
Q10.当社では、売上が成立したら紹介者に手数料を支払うようにしています。この支払手数料は交際費になるのでしょうか?
Q11.当社の社員旅行にお得意様を招待しました。この場合、社員旅行の費用はすべて福利厚生費としてもいいのでしょうか?
Q12.毎年、得意先に社名入りの手帳を配っていますが、今年は、上位顧客には高価な特別製のシステム手帳を配る予定です。特別製のものは、社名等は入れません。これは広告宣伝費となるでしょうか?
Q13.会社としてさまざまな会、クラブ等に入会しています。これらの入会金や年会費はすべて交際費になりますか?
Q14.冠婚葬祭での祝い金や見舞金、香典等は交際費になるのでしょうか?
Q15.得意先が加入する同業者団体が研究発表会を開くことになり、得意先からその団体への協賛金の協力を申し込まれました。この費用は交際費ですか?
Q16.交際費について、適切な会計処理をするためには、日頃からどのようなことに気をつければよいでしょうか?
なお、国税庁ホームページにおきましても、「交際費等(飲食費)に関するQ&A(PDF書類)」が配布されております。ただし、こちらは当事務所で配布しております解説書とはまったく別のものです。
交際費等(飲食費)に関するQ&A
2006年06月04日15:25 格納先: 法人税
平成18年度の税制改正により、法人の支出する交際費等の損金不算入制度が改正され、法人の平成18年4月1日以後開始する事業年度から適用されることとなりました。
このたび、国税庁ホームページで「交際費等(飲食費)に関するQ&A(PDF書類)」が配布されたので、お知らせします。
なお、この規定(交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費」を除外する)の適用を受けるためには、飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」という。)のために要する費用について次に掲げる事項を記載した書類を保存していることが必要とされます。
イ その飲食等のあった年月日
ロ その飲食等に参加した得意先、仕入れ先そのた事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ その飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
(注)店舗を有しないことその他の理由によりその名称又はその所在地が明らかでない場合は、領収書等に記載された支払先の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が記載事項となります。
ホ その他参考となるべき事項
このたび、国税庁ホームページで「交際費等(飲食費)に関するQ&A(PDF書類)」が配布されたので、お知らせします。
なお、この規定(交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費」を除外する)の適用を受けるためには、飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」という。)のために要する費用について次に掲げる事項を記載した書類を保存していることが必要とされます。
イ その飲食等のあった年月日
ロ その飲食等に参加した得意先、仕入れ先そのた事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ その飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
(注)店舗を有しないことその他の理由によりその名称又はその所在地が明らかでない場合は、領収書等に記載された支払先の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が記載事項となります。
ホ その他参考となるべき事項
平成17年分の所得税、消費税及び贈与税の申告状況
2006年05月28日11:38 格納先: 所得税
平成17年分の所得税、消費税及び贈与税の申告状況について、国税庁から発表があった。消費税の免税点の引き下げ(3,000万円→1,000万円)により、個人事業者の消費税申告件数が157万6千件と前年の41万6千件から大幅に増加した点が注目される。
一方、電子申告の利用件数は、所得税で34,842件、消費税で9,638件であり、申告者総数に対する割合はそれぞれ0.15%、0.06%と非常に低迷している。
国税庁から発表された申告状況の詳細は下記↓にて。
http://www.nta.go.jp/category/press/press/5056/01.htm
一方、電子申告の利用件数は、所得税で34,842件、消費税で9,638件であり、申告者総数に対する割合はそれぞれ0.15%、0.06%と非常に低迷している。
国税庁から発表された申告状況の詳細は下記↓にて。
http://www.nta.go.jp/category/press/press/5056/01.htm
相続税の物納に係る物納劣後財産
2006年05月04日16:04 格納先: 相続税
相続税の物納に充てることができる財産は、納税義務者の課税価格の計算の基礎となった財産(その財産により取得した財産を含む)で、日本国内にあるもの(管理又は処分をするのに不適格な財産を除く)に限られるが、その物納申請財産のうち、物納劣後財産を物納に充てることができるのは、税務署長が特別の事情があると認める場合を除くほか、物納財産のうち、物納劣後財産に該当しないもので納税義務者が物納の許可の申請の際、現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合に限られている。この物納劣後財産について、平成18年の税制改正において、次の通り明確化された。(相続税法41条4項、同施行令19条)
1.地上権、永小作権若しくは耕作権を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地
2.法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地
3.次の①から⑤までに掲げる事業が施行され、その施行に係る土地につき①から⑤までに規定する法律の定めるところにより仮換地(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又ははその部分を含む)又は一時利用地の指定がされていない土地(当該指定後において使用又は収益をすることができない当該仮換地又は一時利用地を含む)。
① 土地区画整理法による土地区画整理事業
② 新都市基盤整備法による土地整理
③ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業
④ 土地改良法による土地改良事業
⑤ 独立行政法人緑資源機構法11条1項7号イの事業
4.現に納税義務者の居住の用又は事業の用に供されている建物及びその敷地
5.劇場、工場、浴場その他の維持又は管理に特殊技能を要する建物及びこれらの敷地
6.建築基準法43条1項(敷地等と道路との関係)に規定する道路に2メートル以上接していない土地
7.都市計画法により開発行為について、都道府県知事の許可を受けなければならない開発行為をする場合において、当該開発行為が開発許可の基準に適合しないときにおける当該開発行為に係る土地
8.都市計画法に規定する市街化区域以外にある土地。ただし、宅地として造成することができる土地を除く。
9.農業振興地域整備計画において農用地区域として定められた区域内の土地
10.森林法により保安林として指定された区域内の土地
11.法令の規定により建物の建築をすることができない土地。なお、建物の建築をすることができる面積が著しく狭くなる土地を含む。
12.過去に生じた事件又は事故その他の事情により、正常な取引が行われないおそれがある不動産及びこれに隣接する不動産
13.事業の休止(一時的な休止を除く)をしている法人に係る株式
1.地上権、永小作権若しくは耕作権を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地
2.法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地
3.次の①から⑤までに掲げる事業が施行され、その施行に係る土地につき①から⑤までに規定する法律の定めるところにより仮換地(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又ははその部分を含む)又は一時利用地の指定がされていない土地(当該指定後において使用又は収益をすることができない当該仮換地又は一時利用地を含む)。
① 土地区画整理法による土地区画整理事業
② 新都市基盤整備法による土地整理
③ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業
④ 土地改良法による土地改良事業
⑤ 独立行政法人緑資源機構法11条1項7号イの事業
4.現に納税義務者の居住の用又は事業の用に供されている建物及びその敷地
5.劇場、工場、浴場その他の維持又は管理に特殊技能を要する建物及びこれらの敷地
6.建築基準法43条1項(敷地等と道路との関係)に規定する道路に2メートル以上接していない土地
7.都市計画法により開発行為について、都道府県知事の許可を受けなければならない開発行為をする場合において、当該開発行為が開発許可の基準に適合しないときにおける当該開発行為に係る土地
8.都市計画法に規定する市街化区域以外にある土地。ただし、宅地として造成することができる土地を除く。
9.農業振興地域整備計画において農用地区域として定められた区域内の土地
10.森林法により保安林として指定された区域内の土地
11.法令の規定により建物の建築をすることができない土地。なお、建物の建築をすることができる面積が著しく狭くなる土地を含む。
12.過去に生じた事件又は事故その他の事情により、正常な取引が行われないおそれがある不動産及びこれに隣接する不動産
13.事業の休止(一時的な休止を除く)をしている法人に係る株式
相続税の物納に係る管理処分不適格財産
2006年05月04日15:44 格納先: 相続税
相続税の物納に当てることができる財産は、納税義務者の課税価格の計算の基礎となった財産(その財産により取得した財産を含む。)で、日本国内にあるもののうち、管理又は処分をするのに不適格な財産を除いたものとされている。この管理又は処分をするのに不適当な財産については、従来、相続税基本通達において、その取扱いが示されていたが、平成18年税制改正において、次の通り管理処分不適格財産が明確された。(相続税法41条2項、同施行令18条、同施行規則21条)
1.不動産については、次に掲げるもの
(1)担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産として、次に掲げるもの
イ 抵当権の目的となっている不動産
ロ 譲渡により担保の目的となっている不動産
ハ 差押えがされている不動産
ニ 買戻しの特約が付されている不動産
ホ 上記イからニに掲げる不動産以外の不動産で、その処分が制限されているもの
(2)権利の帰属について争いがある不動産として、次に掲げるもの
イ 所有権の存否又は帰属について争いがある不動産
ロ 地上権、永小作権、賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利の存否又は帰属について争いがある不動産
(3)境界が明らかでない土地として、次に掲げるもの
イ 境界標の設置(隣地の所有者との間の合意に基づくものに限る。)がされていないことにより他の土地との境界を認識することができない土地。ただし、境界線の設置がされていない場合であってもその土地の取引において通常行われる他の土地との境界の確認方法により境界を認識できるものを除く。
ロ 土地使用収益権が設定されている土地の範囲が明らかでない土地。なお、土地使用収益権とは、地上権、永小作権、賃借権その他の土地の使用及び収益を目的とする権利をいう。
(4)隣接する不動産の所有者その他の者との訴訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産として、次に掲げるもの
イ 隣地の上に存する建物、工作物又は樹木その他これらに類するもの(以下、「建物等」という)が、土地の境界を越える場合又は境界上に存する場合における当該土地。ただし、建物のひさし、工作物又は樹木の枝その他これらに類するもの(以下、「ひさし等」という)の境界を越える度合いが軽微な場合又は境界上にある場合で、建物等の所有者が改築等を行うに際してひさし等を撤去し、又は移動することを約する時における土地は除く。
ロ 建物等がその敷地である土地の隣接地との境界を越える場合又は境界上に存する場合における当該土地(借地権を含む)。ただし、当該隣地の所有者(隣地を使用する権利を有する者がいる場合には、その者)が土地の収納後においても建物等の撤去及び隣地の使用料その他の負担を求めないことを約する場合における当該土地並びに借地権が設定されている当該土地を除く。
ハ 土地使用収益権の設定契約の内容が当該土地使用収益権を設定している者にとって著しく不利な場合における当該土地使用収益権の目的となっている建物
ニ 建物の使用又は収益をする契約の内容が当該使用又は収益をする権利を設定している者にとって著しく不利な場合における当該使用又は収益をする権利の目的となっている建物
ホ 賃貸料の滞納がある不動産その他収納後の円滑な土地使用収益契約又は建物使用収益計画の履行に著しい支障を及ぼす事情が存すると見込まれる不動産
ヘ その敷地を通常支払うべき地代により国が借り受けられる見込みがない場合における当該敷地の上に存する建物
(5) 他の土地に囲まれて公道に通じない土地で公道に至るための他の土地の通行権(民法210条)の内容が明確でないもの
(6) 借地権の目的となっている土地で、当該借地権を有する者が不明であることその他これに類する事情があるもの
(7) 他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含む)と社会通念上一体として利用されている不動産若しくは利用されるべき不動産又は2以上の共有に属する不動産として、次に掲げるもの
イ 2以上の共有に属する不動産で、次に掲げる不動産以外のもの
A 当該不動産のすべての共有者が当該不動産について物納の許可の申請をする場合における当該不動産
B 私道の用に供されている土地。ただし、一体となってその効用を有する他の土地とともに物納の許可の申請をする場合における当該土地に限る。
ロ がけ地、面積が著しく狭い土地又は形状が著しく不整形である土地でこれらの土地のみでは使用することが困難であるもの
ハ 私道の用に供されている土地。ただし、一体となってその効用を有する他の土地とともに物納の許可の申請をする場合における当該土地を除く。
ニ 敷地とともに物納の許可の申請がされる建物以外の建物。ただし、当該建物の敷地に借地権が設定されているものを除く。
ホ 他の不動産と一体となってその効用を有する土地。ただし、これらの不動産のすべてが一の土地使用収益権の目的となっている場合で収納後の円滑な土地使用収益契約の履行が可能なものは除く。
(8)耐用年数を経過している建物(ただし、通常の使用ができるものを除く。)
(9)敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産として、次に掲げるもの
イ 敷金その他の財産の返還に係る債務を国が負うこととなる不動産
ロ 次に掲げる事業(以下、「土地区画整理事業等」という。)が施行されている場合において、収納の時までに発生した当該不動産に係る土地区画整理法40条(経費の賦課徴収)の規定による賦課金そのたこれに類する債務を国が負うこととなる不動産
A 土地区画整理法による土地区画整理事業
B 新都市基盤整備法による土地整理
C 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業
D 土地改良法による土地改良事業
E 独立行政法人緑資源機構法第11条1項7号イの事業
ハ 土地区画整理事業等の清算金の授受の義務を国が負うこととなる不動産
(10)その管理又は処分を行うために要する費用の額がその収納価額と比較して過大となると見込まれる不動産として、次に掲げるもの
イ 特定有害物質(土壌汚染法2条1項に規定するもの)その他これに類する有害物質により汚染されている不動産
ロ 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律2条1項に規定するもの)その他のもので除去しなければ通常の使用ができないものが地下にある不動産
ハ 農地の転用制限(農地法4条1項)又は農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限(農地法5条1項)による許可を受けずに転用されている土地
ニ 土留その他の施設の設置、護岸の建設その他の現状を維持するための工事が必要となる不動産
(11)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある目的に使用されている不動産その他社会通念上適切でないと認められる目的に使用されている不動産として、次に掲げるもの
イ 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条1項)又は性風俗関連特殊営業(同条5項)の用に供されている不動産
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律2条2号)の事務所その他これに類するものの用に供されている不動産
(12)引渡しに際して通常必要とされる行為がされていない不動産として、次に掲げるもの((1)に掲げるものを除く)
イ その上の建物がすでに滅失している場合において、当該建物の滅失の登記がされていない土地
ロ その上に廃棄物その他の物がある不動産
ハ 生産緑地で生産緑地の管理等の法令が適用されるもの。ただし、当該生産緑地において、農林漁業を営む権利を有する者がその農林漁業を営んでいる土地を除きます。
2.有価証券については、次に掲げるもの
(1)譲渡に関して証券取引法その他の法令の規定により一定の手続きがとられていないものとして、次に掲げるもの
イ 物納に充てる財産である株式を一般競争入札により売却することとした場合(証券取引法に定める有価証券の売出しの届出及び目論見書の交付が必要とされる場合に限る)において、当該届出に係る書類及び当該目論見書の提出がされる見込みがないもの
ロ 物納財産である株式を一般競争入札により売却することとした場合(証券取引法に定める通知書の提出及び目論見書の交付が必要な場合に限る)において、当該通知書及び目論見書の提出される見込みがないもの
(2)譲渡制限株式
(3) 質権その他の担保権の目的となっている株式
(4) 権利の帰属について争いがある株式
(5) 2以上の者の共有に属する株式。ただし、共有者の全員が当該株式について物納の許可を申請する場合を除く。
3.上記1又は2に掲げる財産以外の財産
当該財産の性質が上記1又は2に掲げる財産に準ずるものとして税務署長が認めるもの
(注)この改正は、平成18年4月1日から適用される。
1.不動産については、次に掲げるもの
(1)担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産として、次に掲げるもの
イ 抵当権の目的となっている不動産
ロ 譲渡により担保の目的となっている不動産
ハ 差押えがされている不動産
ニ 買戻しの特約が付されている不動産
ホ 上記イからニに掲げる不動産以外の不動産で、その処分が制限されているもの
(2)権利の帰属について争いがある不動産として、次に掲げるもの
イ 所有権の存否又は帰属について争いがある不動産
ロ 地上権、永小作権、賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利の存否又は帰属について争いがある不動産
(3)境界が明らかでない土地として、次に掲げるもの
イ 境界標の設置(隣地の所有者との間の合意に基づくものに限る。)がされていないことにより他の土地との境界を認識することができない土地。ただし、境界線の設置がされていない場合であってもその土地の取引において通常行われる他の土地との境界の確認方法により境界を認識できるものを除く。
ロ 土地使用収益権が設定されている土地の範囲が明らかでない土地。なお、土地使用収益権とは、地上権、永小作権、賃借権その他の土地の使用及び収益を目的とする権利をいう。
(4)隣接する不動産の所有者その他の者との訴訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産として、次に掲げるもの
イ 隣地の上に存する建物、工作物又は樹木その他これらに類するもの(以下、「建物等」という)が、土地の境界を越える場合又は境界上に存する場合における当該土地。ただし、建物のひさし、工作物又は樹木の枝その他これらに類するもの(以下、「ひさし等」という)の境界を越える度合いが軽微な場合又は境界上にある場合で、建物等の所有者が改築等を行うに際してひさし等を撤去し、又は移動することを約する時における土地は除く。
ロ 建物等がその敷地である土地の隣接地との境界を越える場合又は境界上に存する場合における当該土地(借地権を含む)。ただし、当該隣地の所有者(隣地を使用する権利を有する者がいる場合には、その者)が土地の収納後においても建物等の撤去及び隣地の使用料その他の負担を求めないことを約する場合における当該土地並びに借地権が設定されている当該土地を除く。
ハ 土地使用収益権の設定契約の内容が当該土地使用収益権を設定している者にとって著しく不利な場合における当該土地使用収益権の目的となっている建物
ニ 建物の使用又は収益をする契約の内容が当該使用又は収益をする権利を設定している者にとって著しく不利な場合における当該使用又は収益をする権利の目的となっている建物
ホ 賃貸料の滞納がある不動産その他収納後の円滑な土地使用収益契約又は建物使用収益計画の履行に著しい支障を及ぼす事情が存すると見込まれる不動産
ヘ その敷地を通常支払うべき地代により国が借り受けられる見込みがない場合における当該敷地の上に存する建物
(5) 他の土地に囲まれて公道に通じない土地で公道に至るための他の土地の通行権(民法210条)の内容が明確でないもの
(6) 借地権の目的となっている土地で、当該借地権を有する者が不明であることその他これに類する事情があるもの
(7) 他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含む)と社会通念上一体として利用されている不動産若しくは利用されるべき不動産又は2以上の共有に属する不動産として、次に掲げるもの
イ 2以上の共有に属する不動産で、次に掲げる不動産以外のもの
A 当該不動産のすべての共有者が当該不動産について物納の許可の申請をする場合における当該不動産
B 私道の用に供されている土地。ただし、一体となってその効用を有する他の土地とともに物納の許可の申請をする場合における当該土地に限る。
ロ がけ地、面積が著しく狭い土地又は形状が著しく不整形である土地でこれらの土地のみでは使用することが困難であるもの
ハ 私道の用に供されている土地。ただし、一体となってその効用を有する他の土地とともに物納の許可の申請をする場合における当該土地を除く。
ニ 敷地とともに物納の許可の申請がされる建物以外の建物。ただし、当該建物の敷地に借地権が設定されているものを除く。
ホ 他の不動産と一体となってその効用を有する土地。ただし、これらの不動産のすべてが一の土地使用収益権の目的となっている場合で収納後の円滑な土地使用収益契約の履行が可能なものは除く。
(8)耐用年数を経過している建物(ただし、通常の使用ができるものを除く。)
(9)敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産として、次に掲げるもの
イ 敷金その他の財産の返還に係る債務を国が負うこととなる不動産
ロ 次に掲げる事業(以下、「土地区画整理事業等」という。)が施行されている場合において、収納の時までに発生した当該不動産に係る土地区画整理法40条(経費の賦課徴収)の規定による賦課金そのたこれに類する債務を国が負うこととなる不動産
A 土地区画整理法による土地区画整理事業
B 新都市基盤整備法による土地整理
C 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業
D 土地改良法による土地改良事業
E 独立行政法人緑資源機構法第11条1項7号イの事業
ハ 土地区画整理事業等の清算金の授受の義務を国が負うこととなる不動産
(10)その管理又は処分を行うために要する費用の額がその収納価額と比較して過大となると見込まれる不動産として、次に掲げるもの
イ 特定有害物質(土壌汚染法2条1項に規定するもの)その他これに類する有害物質により汚染されている不動産
ロ 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律2条1項に規定するもの)その他のもので除去しなければ通常の使用ができないものが地下にある不動産
ハ 農地の転用制限(農地法4条1項)又は農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限(農地法5条1項)による許可を受けずに転用されている土地
ニ 土留その他の施設の設置、護岸の建設その他の現状を維持するための工事が必要となる不動産
(11)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある目的に使用されている不動産その他社会通念上適切でないと認められる目的に使用されている不動産として、次に掲げるもの
イ 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条1項)又は性風俗関連特殊営業(同条5項)の用に供されている不動産
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律2条2号)の事務所その他これに類するものの用に供されている不動産
(12)引渡しに際して通常必要とされる行為がされていない不動産として、次に掲げるもの((1)に掲げるものを除く)
イ その上の建物がすでに滅失している場合において、当該建物の滅失の登記がされていない土地
ロ その上に廃棄物その他の物がある不動産
ハ 生産緑地で生産緑地の管理等の法令が適用されるもの。ただし、当該生産緑地において、農林漁業を営む権利を有する者がその農林漁業を営んでいる土地を除きます。
2.有価証券については、次に掲げるもの
(1)譲渡に関して証券取引法その他の法令の規定により一定の手続きがとられていないものとして、次に掲げるもの
イ 物納に充てる財産である株式を一般競争入札により売却することとした場合(証券取引法に定める有価証券の売出しの届出及び目論見書の交付が必要とされる場合に限る)において、当該届出に係る書類及び当該目論見書の提出がされる見込みがないもの
ロ 物納財産である株式を一般競争入札により売却することとした場合(証券取引法に定める通知書の提出及び目論見書の交付が必要な場合に限る)において、当該通知書及び目論見書の提出される見込みがないもの
(2)譲渡制限株式
(3) 質権その他の担保権の目的となっている株式
(4) 権利の帰属について争いがある株式
(5) 2以上の者の共有に属する株式。ただし、共有者の全員が当該株式について物納の許可を申請する場合を除く。
3.上記1又は2に掲げる財産以外の財産
当該財産の性質が上記1又は2に掲げる財産に準ずるものとして税務署長が認めるもの
(注)この改正は、平成18年4月1日から適用される。
相続税の物納制度の改正点(平成18年改正)
2006年04月25日10:19 格納先: 相続税
1.超過物納の許可(法41条1項)
物納に充てる財産の性質、形状、その他の特徴により、物納の許可限度額を超える価額の物納財産による物納については、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、物納が許可されることになった。
2.管理処分不適格財産の明確化(法41条2項、令18条)
相続税の物納に当てることができる財産は、納税義務者の課税価格の計算の基礎となった財産(その財産により取得した財産を含む。)で、日本国内にあるもののうち、管理又は処分をするのに不適格な財産を除いたものとされている。この管理又は処分をするのに不適当な財産については、従来、相続税基本通達42-2において、その取扱いが示されていたが、平成18年税制改正において、管理処分不適格財産が明確にされた。
3.物納劣後財産の明確化等(法41条4項、令19条)
物納に充てることのできる財産は、相続税法41条1項により①国債及び地方債、②不動産及び船舶、③社債及び株式並びに証券投資信託又は貸付信託の受益証券、④動産とされているが、これらの財産のうち、資産の権利関係、法令の規制、資産の計上等により物納劣後財産としており扱われるものあった。その具体的内容は示されていなかったが、平成18年税制改正において、物納劣後財産が明確にされた。
物納に充てる財産の性質、形状、その他の特徴により、物納の許可限度額を超える価額の物納財産による物納については、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、物納が許可されることになった。
2.管理処分不適格財産の明確化(法41条2項、令18条)
相続税の物納に当てることができる財産は、納税義務者の課税価格の計算の基礎となった財産(その財産により取得した財産を含む。)で、日本国内にあるもののうち、管理又は処分をするのに不適格な財産を除いたものとされている。この管理又は処分をするのに不適当な財産については、従来、相続税基本通達42-2において、その取扱いが示されていたが、平成18年税制改正において、管理処分不適格財産が明確にされた。
3.物納劣後財産の明確化等(法41条4項、令19条)
物納に充てることのできる財産は、相続税法41条1項により①国債及び地方債、②不動産及び船舶、③社債及び株式並びに証券投資信託又は貸付信託の受益証券、④動産とされているが、これらの財産のうち、資産の権利関係、法令の規制、資産の計上等により物納劣後財産としており扱われるものあった。その具体的内容は示されていなかったが、平成18年税制改正において、物納劣後財産が明確にされた。
平成18年3月決算法人用 指定寄付金情報
2006年04月18日09:39 格納先: 法人税
平成18年3月決算法人用の「個別指定の寄付金」情報です。寄付金控除を受けるときの参考としてください。
【告知番号:平17.3.8 76】
募金者の名称:財団法人2005年日本国際博覧会協会
募金事務所 :愛知県愛知郡長久手町大字熊張字茨ヶ廻間乙1533-1
目的及び使途:2005年日本国際博覧会開催の費用
募集期間 :自H13.3.9至H18.3.8
【告知番号:平16.5.14 253】
募金者の名称:宗教法人専修寺
募金事務所 :三重県津市一身田町2819番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人専修寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H14.5.15至H17.5.14
【告知番号:平16.7.9 311】
募金者の名称:宗教法人萬福寺
募金事務所 :京都府宇治市五ヶ庄三番割34番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人萬福寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H15.7.11至H17.7.10
【告知番号:平16.9.16 407】
募金者の名称:宗教法人唐招提寺
募金事務所 :奈良県奈良市五條町13番46号
目的及び使途:国宝として指定されている宗教法人唐招提寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H15.9.17至H17.9.16
【告知番号:平16.4.16 217】
募金者の名称:宗教法人大覚寺
募金事務所 :京都府京都市右京区嵯峨大沢町4番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人大覚寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H16.4.16至H17.4.15
【告知番号:平16.7.1 306】
募金者の名称:大阪弁護士会
募金事務所 :大阪府大阪市北区西天満2丁目1番2号
目的及び使途:大阪弁護士会新会館の建設の費用
募集期間 :自H16.7.1至H17.6.30
【告知番号:平16.7.1 306】
募金者の名称:財団法人小倉百人一首文化財団
募金事務所 :京都府京都市中京区烏丸通夷川上る少将井町240番地京都商工会議所内
目的及び使途:博物館施設としての「時雨殿」建設の費用
募集期間 :自H15.7.11至H17.7.10
【告知番号:平16.10.21 460】
募金者の名称:宗教法人善光寺
募金事務所 :長野県長野市大字長野元善町491番地イ号
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人善光寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H16.10.21至H17.10.20
【告知番号:平17.1.21 28】
募金者の名称:財団法人海洋学園設立準備財団
募金事務所 :愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番4号JRセントラルタワーズ
目的及び使途:海洋中等教育学校設置のための校舎建設及び校地及び校具取得の費用
募集期間 :自H17.1.21至H17.9.30
【告知番号:平17.7.6 258】
募金者の名称:財団法人海外子女教育振興財団
募金事務所 :東京都港区愛宕1丁目3番4号
目的及び使途:中華人民共和国蘇州市に設置されている蘇州日本人学校の校舎改修及び校具取得の費用
募集期間 :自H17.7.6至H18.5.31
【告知番号:平17.7.6 258】
募金者の名称:財団法人海外子女教育振興財団
募金事務所 :京都府宇治市五ヶ庄三番割34番地
目的及び使途:ハンガリー共和国ブダペスト市に設置されているブダペスト日本人学校の校舎改修及び校具取得の費用
募集期間 :自H17.7.6至H18.5.31
【告知番号:平17.9.16 354】
募金者の名称:財団法人立志学園設立準備財団
募金事務所 :熊本県熊本市新屋敷1丁目3番25号
目的及び使途:九州中央リハビリテーション学院設置のための校舎建設及び校具取得の費用
募集期間 :自H17.9.16至H17.10.31
【告知番号:平17.10.18 406】
募金者の名称:宗教法人願泉寺
募金事務所 :大阪府貝塚市中846番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人願泉寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H17.10.18至H18.10.17
【告知番号:平16.10.21 460】
募金者の名称:宗教法人吉備津神社
募金事務所 :岡山県岡山市吉備津931番地
目的及び使途:国宝として指定されている宗教法人吉備津神社の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H17.10.18至H18.10.17
【告知番号:平18.2.24 74】
募金者の名称:財団法人宍戸学園設立準備財団
募金事務所 :東京都千代田区神田駿河台2丁目1番18号
目的及び使途:東京聖美医科専門学校設置のための校舎建設並びに校地及び校具取得の費用
募集期間 :自H18.2.24至H18.3.31
【告知番号:平17.3.8 76】
募金者の名称:財団法人2005年日本国際博覧会協会
募金事務所 :愛知県愛知郡長久手町大字熊張字茨ヶ廻間乙1533-1
目的及び使途:2005年日本国際博覧会開催の費用
募集期間 :自H13.3.9至H18.3.8
【告知番号:平16.5.14 253】
募金者の名称:宗教法人専修寺
募金事務所 :三重県津市一身田町2819番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人専修寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H14.5.15至H17.5.14
【告知番号:平16.7.9 311】
募金者の名称:宗教法人萬福寺
募金事務所 :京都府宇治市五ヶ庄三番割34番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人萬福寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H15.7.11至H17.7.10
【告知番号:平16.9.16 407】
募金者の名称:宗教法人唐招提寺
募金事務所 :奈良県奈良市五條町13番46号
目的及び使途:国宝として指定されている宗教法人唐招提寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H15.9.17至H17.9.16
【告知番号:平16.4.16 217】
募金者の名称:宗教法人大覚寺
募金事務所 :京都府京都市右京区嵯峨大沢町4番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人大覚寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H16.4.16至H17.4.15
【告知番号:平16.7.1 306】
募金者の名称:大阪弁護士会
募金事務所 :大阪府大阪市北区西天満2丁目1番2号
目的及び使途:大阪弁護士会新会館の建設の費用
募集期間 :自H16.7.1至H17.6.30
【告知番号:平16.7.1 306】
募金者の名称:財団法人小倉百人一首文化財団
募金事務所 :京都府京都市中京区烏丸通夷川上る少将井町240番地京都商工会議所内
目的及び使途:博物館施設としての「時雨殿」建設の費用
募集期間 :自H15.7.11至H17.7.10
【告知番号:平16.10.21 460】
募金者の名称:宗教法人善光寺
募金事務所 :長野県長野市大字長野元善町491番地イ号
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人善光寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H16.10.21至H17.10.20
【告知番号:平17.1.21 28】
募金者の名称:財団法人海洋学園設立準備財団
募金事務所 :愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番4号JRセントラルタワーズ
目的及び使途:海洋中等教育学校設置のための校舎建設及び校地及び校具取得の費用
募集期間 :自H17.1.21至H17.9.30
【告知番号:平17.7.6 258】
募金者の名称:財団法人海外子女教育振興財団
募金事務所 :東京都港区愛宕1丁目3番4号
目的及び使途:中華人民共和国蘇州市に設置されている蘇州日本人学校の校舎改修及び校具取得の費用
募集期間 :自H17.7.6至H18.5.31
【告知番号:平17.7.6 258】
募金者の名称:財団法人海外子女教育振興財団
募金事務所 :京都府宇治市五ヶ庄三番割34番地
目的及び使途:ハンガリー共和国ブダペスト市に設置されているブダペスト日本人学校の校舎改修及び校具取得の費用
募集期間 :自H17.7.6至H18.5.31
【告知番号:平17.9.16 354】
募金者の名称:財団法人立志学園設立準備財団
募金事務所 :熊本県熊本市新屋敷1丁目3番25号
目的及び使途:九州中央リハビリテーション学院設置のための校舎建設及び校具取得の費用
募集期間 :自H17.9.16至H17.10.31
【告知番号:平17.10.18 406】
募金者の名称:宗教法人願泉寺
募金事務所 :大阪府貝塚市中846番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人願泉寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H17.10.18至H18.10.17
【告知番号:平16.10.21 460】
募金者の名称:宗教法人吉備津神社
募金事務所 :岡山県岡山市吉備津931番地
目的及び使途:国宝として指定されている宗教法人吉備津神社の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H17.10.18至H18.10.17
【告知番号:平18.2.24 74】
募金者の名称:財団法人宍戸学園設立準備財団
募金事務所 :東京都千代田区神田駿河台2丁目1番18号
目的及び使途:東京聖美医科専門学校設置のための校舎建設並びに校地及び校具取得の費用
募集期間 :自H18.2.24至H18.3.31
新会社法は平成18年5月1日施行
2006年03月29日20:09 格納先: 商法・会社法等
本日、「会社法の施行期日を定める政令(政令第77号)」が交付された。
【政令第77号】
【政令第77号】
会社法の施行期日を定める政令
内閣は、会社法(平成17年法律第86号)付則第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
会社法の施行期日は、平成18年5月1日とする。
法務大臣 杉浦 正健
内閣総理大臣 小泉純一郎
会社法成立の間隙を縫って、役員報酬の一部を損金不算入にする等、大増税に向けた準備が着々と進んでいます。小泉内閣得意の、弱者に厳しく、強者に甘い増税策が目白押しです。中小企業経営者の皆さん、そして個人事業者の皆さん。税の専門家、税理士に相談し、しっかり対策を立て、防衛されますように。
納税者勝訴率4年連続で上昇
2006年03月04日19:54 格納先: 不服審査等
国税庁は「平成16年度税務統計 不服審査、訴訟事件関係(PDFファイル)」を発表した。
それによると、訴訟事件については、平成13年度から4年連続で納税者の勝訴(納税者の主張か何らかの形で認められたもの)率が上昇している。税理士が法廷に立つことができれば、勝訴率は20%以上になるとも言われているが、今後もこの傾向(課税庁の一部敗訴および全面敗訴)が続くのか、注目される。
なお審査請求については、平成15年度には納税者の主張が認められたものの割合は22.0%であったが、平成16年度は14.6%と平年並みになった。今後も推移を見守りたい。
それによると、訴訟事件については、平成13年度から4年連続で納税者の勝訴(納税者の主張か何らかの形で認められたもの)率が上昇している。税理士が法廷に立つことができれば、勝訴率は20%以上になるとも言われているが、今後もこの傾向(課税庁の一部敗訴および全面敗訴)が続くのか、注目される。
なお審査請求については、平成15年度には納税者の主張が認められたものの割合は22.0%であったが、平成16年度は14.6%と平年並みになった。今後も推移を見守りたい。
平成18年度税制改正の問題点
2006年02月22日14:43 格納先: 税制改正
今回の税制改正で、大問題になっているところがあります。「役員報酬の一部を損金不算入にする(経費として認めない)」というところです。
平成17年12月15日に自民党がPDFで配布した「平成18年度税制改正大綱」の55ページに、以下のような記載があります。
10 法人の支給する役員給与について、次の見直しを行う。
(1) 同族会社の業務を主宰する役員およびその同族関係者等が発行済株式の総数の90%以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、当該業務を主宰する役員に対して支給する給与のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しない。
上記に該当しますと、社長に年間1,000万円の役員報酬を支払った場合、220万円が損金不算入となり、法人税等は94万円ほど増加(実効税率43%で計算)することとなります。税収不足を補うためにひねり出されたものと思いますが、中小企業にとってあまりに影響の多い改正(正しくは改悪)と思います。中小企業の経営者の皆さん。放っておくとたいへんなことになりますよ。まだ細かい計算方法等が決まっているわけではないのですが、税理士に相談し、しっかり対応しておかれることをお勧めします。
平成17年12月15日に自民党がPDFで配布した「平成18年度税制改正大綱」の55ページに、以下のような記載があります。
10 法人の支給する役員給与について、次の見直しを行う。
(1) 同族会社の業務を主宰する役員およびその同族関係者等が発行済株式の総数の90%以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、当該業務を主宰する役員に対して支給する給与のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しない。
上記に該当しますと、社長に年間1,000万円の役員報酬を支払った場合、220万円が損金不算入となり、法人税等は94万円ほど増加(実効税率43%で計算)することとなります。税収不足を補うためにひねり出されたものと思いますが、中小企業にとってあまりに影響の多い改正(正しくは改悪)と思います。中小企業の経営者の皆さん。放っておくとたいへんなことになりますよ。まだ細かい計算方法等が決まっているわけではないのですが、税理士に相談し、しっかり対応しておかれることをお勧めします。
平成18年度税制改正(案)個人所得税関連
2006年01月27日10:01 格納先: 所得税
【個人所得税関連】
○ 所得税の税率構造を5%〜40%の6段階に改める。
○ 定率減税の廃止。
○ 地震保険料控除を創設(最高5万円)。
○ 寄付金控除の適用下限額を5千円(現行1万円)に引き下げる。
○ 所得税等の申告書にかかる公示制度を廃止。
○ 源泉徴収票等の電子交付を可能にする。
○ 所得税の税率構造を5%〜40%の6段階に改める。
○ 定率減税の廃止。
○ 地震保険料控除を創設(最高5万円)。
○ 寄付金控除の適用下限額を5千円(現行1万円)に引き下げる。
○ 所得税等の申告書にかかる公示制度を廃止。
○ 源泉徴収票等の電子交付を可能にする。
平成18年度税制改正(案)法人税関連
2006年01月27日09:40 格納先: 法人税
【法人関連税制】
○ 試験研究費の総額にかかる特別税額控除制度について、比較試験研究費を上回る部分の特別税額控除割合に5%を加える措置を講ずる。
○ 情報基盤強化税制として、産業競争力の向上に資する設備等で情報基盤の強化を促すものの取得等をした場合に、基準取得価額の50%相当額の特別償却と10%相当額の特別税額控除を選択適用できる制度を創設する。
○ 中小企業投資促進税制について、対象資産に一定のソフトウェア等を加えるとともに、適用期限を2年延長する。
○ 交際費等について、損金不算入となる範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費(役職員の間の飲食費を除く)を除外する。
○ 同族会社の留保金課税制度について、同族要件を大幅に緩和し、留保控除額を引き上げる等抜本的な見直しを行う。
○ 試験研究費の総額にかかる特別税額控除制度について、比較試験研究費を上回る部分の特別税額控除割合に5%を加える措置を講ずる。
○ 情報基盤強化税制として、産業競争力の向上に資する設備等で情報基盤の強化を促すものの取得等をした場合に、基準取得価額の50%相当額の特別償却と10%相当額の特別税額控除を選択適用できる制度を創設する。
○ 中小企業投資促進税制について、対象資産に一定のソフトウェア等を加えるとともに、適用期限を2年延長する。
○ 交際費等について、損金不算入となる範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費(役職員の間の飲食費を除く)を除外する。
○ 同族会社の留保金課税制度について、同族要件を大幅に緩和し、留保控除額を引き上げる等抜本的な見直しを行う。
平成18年度税制改正(案)の概要
2006年01月27日09:00 格納先: 税制改正