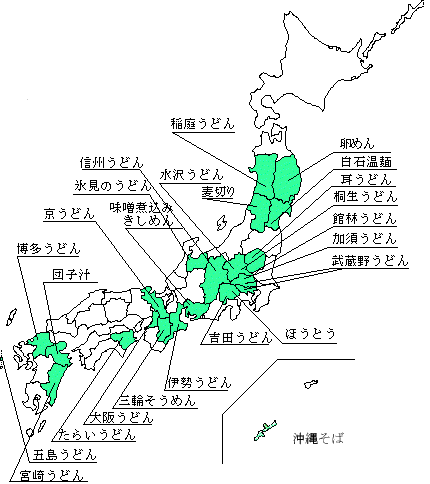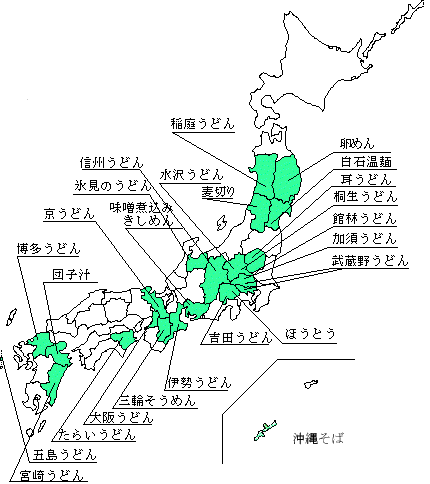武者修行の旅
香川県のうどん屋を制覇した麺聖は修行のためうどんを求め全国を旅した。このレポートは他県のうどんに対し香川県人が感じるであろう感想を麺聖が綴ったものである。あくまでも讃岐人の麺聖(他県のうどんに関してアマチュアの客)の個人的好みに基づくものである。内容に一部他県のうどんを馬鹿にしたような表現があるがご理解いただきたい。裏返して他県の人を基準にすれば我々讃岐人が讃岐うどんの長所とする点がすなわち短所に見えるのであろう。つまり全国から見れば讃岐うどんが異端なのだ。それが文化だと考える。
その土地の風土の中で育まれる食文化、国際化だのグローバリゼーションなどといった言葉に惑わされずに発展させて欲しい。
- 稲庭うどん(秋田県)
- 寛文5年稲庭吉左衛門が作り始めた稲庭うどん、細いそうめんのような乾麺だ。
- 卵めん(岩手県)
- 長崎から落ち延びたキリシタン信者が伝えたという卵めん(蘭麺)その姿を追ってみた。
- 麦切り(山形県)
- 知る人ぞ知るそば処山形、庄内地方のそば屋にある麦切りとは何?
- 白石温麺(宮城県)
- 手延べうどんの系統が太平洋側の白石に、麺のルーツにもせまる。
- 耳うどん(栃木県)
- 餃子にラーメンにそば粉食文化の盛んな栃木県、耳うどんとは果たして?
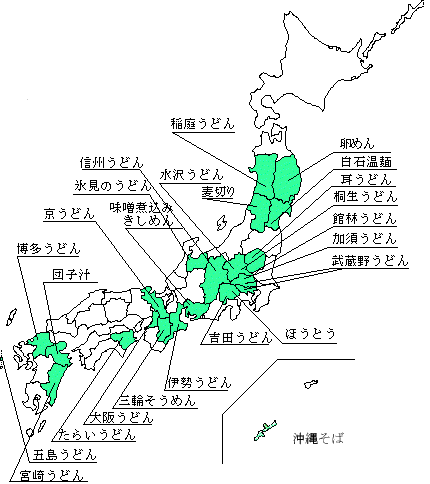
- 桐生うどん(群馬県)
- 屋号に山本が入る店がなぜか多い。78軒でうどんマップを作り町おこしをはかる。
- 水沢うどん (群馬県)
- 伊香保温泉へ行く途中10軒以上のうどん店が軒を並べるところがある。これが水沢うどんだ。
- 館林うどん(群馬県)
- 小麦の産地館林「麺のまち、うどんの里」を宣言。
- 加須うどん (埼玉県)
- 人口6万の埼玉県加須市「うどんの町」を宣言、40軒ほどが腕を競う。
- 武蔵野うどん(埼玉県、東京都)
- 関東はうどん処、大地の香りがするうどんがこっそりとある。
- ほうとう(山梨県)
- 武田信玄が兵糧として広めたと伝わるほうとう、奈良時代中国から伝えられた麺類の一種「はくたく」が音便化したと言われている。
- 吉田うどん(山梨県)
- 富士の伏流水が地下に浸透する富士吉田市には50軒以上のうどん屋がある。
- 信州うどん(長野県)
- 信州はそばどころ、それだけではありません。うどんどころです。
- 氷見のうどん (富山県)
- 稲庭と五島の間、この位置が手延べうどんの伝播にとっての重要なヒントを与えてくれる。
- きしめん (愛知県)
- 名古屋名物きしめん、井原西鶴の「好色一代男」の芋川の平打ちうどんがルーツとか。
- 味噌煮込みうどん (愛知県)
- 八丁味噌と白味噌を使った濃厚な味。
- 伊勢うどん (三重県)
- 伊勢神宮の伊勢市ここに極太の麺に黒いつゆの伊勢うどんがある。
- 京うどん(京都府)
- 薄味の料理が京料理、そんな考えは通用しません。
- 三輪そうめん (奈良県)
- うどんの先祖とも言われるそうめん、発祥の地三輪を訪ねる。
- 大阪うどん (大阪府)
- 大阪名物きつねうどんあまりに有名だがその実体は?
- たらいうどん (徳島県)
- 同じ四国のたらいうどん讃岐うどんの亜流なのか?
- 博多うどん(福岡県)
- 禅僧によって早くに中国から麺類がもたらされた博多、ラーメンほど有名でないがうどん屋は多い。
- 団子汁(大分県)
- 野菜の具が入った味噌仕立てのだんご汁に醤油仕立てのだご汁、大分を代表する味である。
- 五島うどん(長崎県)
- 長崎県は粉食文化の盛んなところ、その遙か沖合に「幻のうどん」と呼ばれる五島うどんがある。
- 宮崎うどん(宮崎県)
- ラーメン王国九州にあって宮崎の人は朝から晩までうどんを食べる。
- 沖縄そば(沖縄県)
- そばと言っても、讃岐うどんの親戚のような気がする沖縄そば!