|
 |
 |
| 「鍛冶」三代・助丸 | 「鍛冶」碓氷健吾 | 「鍛冶」梅心子 |
[道具]
 |
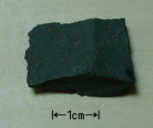 |
 |
||
| 縄文石器 | 縄文石器 | 縄文石器 | ||
 |
 |
 |
 |
|
| 縄文石器 |
黒曜石・原石 | 黒曜石・石器 | 石器製作途上に出た剥片 | |
「私の好きなもの」
| 絵具 | 和紙 | 彫刻刀 | 砥石 | 刷毛 | 竹皮 |
これらについて、私のコダワリを述べようと思います |
|||||
材料・道具には、高い物から安い物まであります。
高くて良い物、高くて良くない物、安くて良い物、安い安物、など色々あります。
高くて良い物は当たり前です。
安くて良い物は申し分ありません。
高くて良くない物、安い安物は問題外です。
高くて良い物を入手していれば良いでしよう。
私は、良い物をなるべく安く手に入れたいと考えてきました。
その為には、材料・道具の良し悪しを見分ける目が必要です。
あんがい材料・道具は、使えば解ることも多いものです。良い材料・道具探しの旅に出て下さい。
私は、版木刀をいくつも持っています。鍛治屋さんから直接から手に入れたもの、刃物店で購入したもの、
譲ってもらったもの、などなどです。
いくつもあるものの中では、使うのは限られてきます。
研いでも砥いでも、使うとすぐに刃こぼれするもの、また研いでも砥いでも刃がつかないもの、
使っていても切れ味がすぐに鈍るもの、そして砥ぎ難いもの、などあります。
鋼の材質にも色々あるようです。刃物鋼(鉄と炭素)は、殆んどありません。
今は、特殊鋼に属する鋼が殆んどです。それは鉄と炭素に様々なものが加えられています。
クロム、タングステン、モリブデン…などです。
ハイス鋼(ハイスピードスチール)も比較的安価に作られています。
ハイス鋼は、研ぐのに少し困難がありますが、その分切れ味は長持ちするとなっています。
いずれにしても、切れ味が良くて、長切れして、研ぎやすい・・・ものが最上です。
いくつも刃物があると、いやでもその違いが気になります。
鋼種が同じものでも、鍛治屋に依って随分の違いがあります。
そんな状況で、新たな鍛冶屋をITで見つけると、取り合えあず版木刀を1本買います。
それが良いものだった場合は、次々に増やすことになります。
[材料]
○水性絵具 (透明水彩絵具、不透明水彩絵具、ガッシュ、ポスターカラー、他)
◎透明 透明に絵具を使うには、色分けを工夫して、版の組み合わせを使います。
色を薄くするには、白を混ぜるのではなく、水で薄 めること。そして、白は白色として使います。
◎不透明 一版多色摺り(陰刻法)の場合は、不透明色でなくてはなりません。
私は、基本的に透明水彩を、透明に使って木版画を作るのが好きです。色を透明に使うと、掛け合わせて他の色が出せるのです。掛け合わせた色は、混色では得られない発色が得られます。しかし、そのためには絵具を選ばなくてはなりません。透明で彩度の高いものが必要です。それは、有機系の顔料の方が希望に叶います。近年は有機顔料にも、耐光性は無機に匹敵するほどのものが色々出来ています。安心して使いましよう。有機顔料は、耐光性に乏しいので・・・というのは、時代遅れです。色の化学の進歩は、いちじるしいものがあります。絵具のパンフレットには、色んな情報が記載されていますので、参考にしましよう。絵具のメーカーも各社ありますので、好みのものを探しましよう。・・・私は手元にある様々な絵具を塗布して、長期間太陽に晒して調べました。およそ90日を戸外に置きました。その結論としては、専門家用として売られている水彩絵具では、いくらか色味に変化のあるものもありましたが、ほとんど差がありませんでした。児童用に売られている絵具では、色味がすっかり無くなっているものもありました。この私のテストは過酷なものですから、一般的には明るい部屋での作品の絵具の耐久性は、専門家用の製品を選ぶならそれ程心配はないといえるでしよう。それでも例えば季節ごとに額縁の作品を入れ替えるなどをお勧めします。・・・となると、絵具の土台となる紙(和紙)の変色の方が気になるところです。和紙と名が付いていても、相当の幅があります。ほとんど洋紙といえるものでも、和紙店で売られていると和紙の仲間かと見まがうばかりです。いずれにしても、用紙のpH(ピーエッチ)が問題です。pH7が中性です。ややアルカリか中性なら永年の保存にも耐えますが、酸性に偏ったものは、湿気などで一層酸化が進み、やがて変色し、酸で繊維はもろくなり、保存に耐えなくなってしまいます。古い和紙を破いてみると、繊維が長く伸びながら引きづられるのが良いもので、繊維がちぎれて崩れるように脆いものは、酸性化が進んでいるものです。pHの計測器があれば簡単に調べることができます。
○油性絵具 (油絵具、銅版用絵具、リトグラフ用絵具、版画用絵具)
油性は、大作の板目木版画に使われます。そして木口木版画に使われます。
木口木版画用の油性絵具は、色味にコクがあって、キレのよいものが望ましいのです。
・・・
○和紙 (「11.和紙について」のページへリンク)
木版画には、和紙がのぞましいのです。木版画は、用紙を湿して水性絵具を使いますので、絵具の吸収と、バレンの摺りに耐える強さ、寸法の安定性 が求められます。それには、楮紙がよいでしよう。和紙の中では、楮の繊維がもっとも丈夫です。油性インクの場合は、洋紙でも良いのです。和紙の 素材は、楮、三椏、雁皮、麻です。洋紙は針葉樹・広葉樹の木材パルプです。木版画(水性絵具)には、楮を主とした和紙が使われます。木口木版画 (油性絵具)には、雁皮が使われます。彫りの細かさを再現するには、用紙の表面のきめこまかさが必要とされるからです。
|
 |
 |
| 「鍛冶」三代・助丸 | 「鍛冶」碓氷健吾 | 「鍛冶」梅心子 |
 |
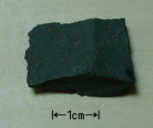 |
 |
||
| 縄文石器 | 縄文石器 | 縄文石器 | ||
 |
 |
 |
 |
|
| 縄文石器 |
黒曜石・原石 | 黒曜石・石器 | 石器製作途上に出た剥片 | |
 |
| 「肥後の守(刃渡り:8cm)」と「縄文石器」 |
| 彫刻刀(木版画用) | ||
|
版木刀 |
4.5mm(1分5厘)、6.0(2分)mm幅のものでよいでしよう。 | |
| 平刀 |
0.5mm~9.0mm(短い柄・長い柄)。 |
|
| 丸刀 | 深い丸刀、浅い丸刀。幅も、とにかく色々あると楽しい。 | |
| 三角刀 | 刃の開き角度は45度、60度、90度、120度などあります。 | |
| 見当ノミ | 15mm幅、もう少し大きな18mm幅でも良い。(平刀で代用も) | |
| その他 |
日光引っかき刀。ビュラン(レンパツなど)。釘など。 |
|
○彫刻刀には、木彫、鎌倉彫り、バードカービング、能面などいろいろあります。出来れば木版画用の彫刻刀を選ぶこと。
○木彫・鎌倉彫り用の、先曲がり(スクイ)は、柄と力の向きが一致しないので、木版画にはほとんど使えない。
○木彫の物は、概して厚刃なので向かない。
○鋼には、いろいろ種類があります。炭素鋼、特殊鋼、硬度の高いハイス鋼(ハイスピード鋼)、など。素直に研げて、使いやすい炭素鋼、硬くて研ぎ にくいけれども、なが切れするハイス鋼。いくつかを使って、使い良い、自分の好みに合うものに出会いましよう。
刃は、切れるためには硬くなくてはなりませんが、硬いばかりでは欠ける。欠けない為には、粘りが必要です。
硬さと粘りの調節が鍛冶屋の苦心です。そして、真の切れ味を発揮するためには、砥石も重要です。
○砥石(荒砥・中砥・仕上砥)(天然・合成)(水砥・油砥)
| 天然砥(水砥) | 合成砥(人造砥)・粒度 | |
| 仕上砥 | 本山、カラス、浅黄、巣板、内曇り、など | #3000以上 |
| 中砥 | 青砥、天草砥 | #800~#1200 |
| 荒砥 | 大村砥 | #800以下 |
 |
| 仕上げ砥石・カラス |
荒砥は、刃が欠けたときなどに使います。普段、切れ味の悪くなったときには、中砥で充分に「かえり」を出して、仕上砥で、裏と表を研ぎあげます。中砥は、天然の物も比較的安くて良いのですが、今日的には、ダイヤモンドの砥石などとても使い良いので、お勧めです。
ダイヤモンド砥石の長所は、研ぎおろす力の素晴らしさと、砥石の減りが極端に少ないので、砥石の平面の狂いが出来にくいことです。
平らな中砥で研いで、平らな仕上砥で仕上げるわけですから、砥石の平面の狂いを気にしなくて済むのは、なによりです。
地上で最も硬いダイヤモンドの砥粒を使うわけですから、頼もしいのです。研ぐのは、水でも良いのです。欠点は、その高価さです。
天然の中砥(青砥)は、やや青味がかった濃い灰色です。京都の近くが産地です。
仕上げ砥は、いくつもに分類され、それぞれには名称があります。黄色味の本山、黒い模様のあるカラス、青みの灰色の浅黄、茶色の模様のある巣板、刀剣用の内曇り、などなどです。
仕上げ砥の購入について、私の考える事は、財布の許す限り高い物を求めてください。安い物から段階を追ってより良い物へ買い進むようなら、思いきって高い物を購入した方が、無駄使いは少なくて済みます。
 |
 |
| 宮川刷毛ブラシ製作所 http://www17.ocn.ne.jp/~edo-hake/ |
(旧)金子竹皮店・店内 |
○刷毛 (手刷毛・ブラシ刷毛)刷毛には、馬の尾毛が使われています。
木版画の絵具は、なるべく必要最小量を版に塗り広げることです。
そのためには、毛は腰の強いものが望ましいので、わずかに毛先だけを鮫皮で刷毛おろしをして、使うのです。
こうして、腰があって毛先の当たりが柔らかい刷毛となります。
使っていくうちには、毛先は減っていきますので、その際には、また鮫皮で刷毛おろしをします。
○竹皮(バレン縄用竹皮・バレン包み用竹皮)
上記写真は、2002年7月中旬に私の住む埼玉県入間市某所の竹林にて採取した真竹の竹皮です。
木版画講座・受講生のアスリート・島田 但さんは、ジョギングしながら竹林が気になるそうで、
何ヶ所かの竹林を探し出してくれました。
孟宗か真竹かを見分けなくてはなりませんが、竹皮を見ると良く分かります。
あんがい、真竹の竹林もあるものですから、自分の身近な所での宝探しも良いものです。
幅が充分にある竹皮は、バレンを包むのに用い、小さ目の竹皮は溶き棒を作ると良いでしよう。
竹皮の保存は、乾き過ぎず(割れます)、湿し過ぎず(カビます)です。
かって竹皮は、包装に重要な役割がありましたが、今日ではバレン皮としての用途などでしようか。
天然の素材に頼る木版画には、材料探しにも楽しい世界があります。
07.バレンのページへリンク