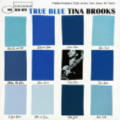ロック・ファンのためのジャズ案内のヘッダー
Rock Listner's Guide To Jazz Music
その他
| Karma / Pharoah Sanders | ||
 曲:★★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1969/2/14 [1] 1969/2/19 [2] [1] The Creator Has A Master Plan [2] Colors |
[1] Julius Watkins (frh) Pharoah Sanders (ts) James Spaulding (fl) Leon Thomas (vo, per) Lonnie L. Smith (p) Richard Davis (b) Reggie Workman (b) William Hart (ds) Nathaniel Bettis (per) [2] Julius Watkins (frh) Pharoah Sanders (ts) Leon Thomas (vo, per) Lonnie L. Smith (p) Ron Carter (b) Reggie Workman (b) Frederick Waits (ds) |
| コルトレーンのパートナーを務めていたとき、あるいはドン・チェリーの「Where Is Brooklyn? 」に参加しているときのファラオ・サンダースは、えげつないほど汚くもノイジーなサウンドを撒き散らしている。でもそんなノイズをときどき無性に聴きたくなってしまう中毒性がある(ないかな?)。では、リーダー・アルバムでたっぷり満喫させてもらおうと触手を伸ばしてみたのが本作。いかにも「濃い」感じのジャケットに大人数編成とあって、魑魅魍魎の世界を期待していたんだけれども、僕の耳には心洗われる爽やかなサウンドに聴こえてきてなんとも予想外。確かにアフリカ志向は明確ではあるもののジャズからは遠くはなれており、時にフリーキーな喧騒があるとはいえ緊張よりも癒しすら覚える。そうした音楽に主眼が置かれているためにファラオの出番も多くはない。期待したものと違ったというだけで内容が貧弱ということではないんだけれど刺激性は低い。(2007年10月9日) ファラオの音楽はどこか「歓び」があり、やはり黒人ならではのルーツ(アフリカ)が表現されている。その「歓び」を感じ取ることができれば、普通のジャズとは違う楽しさが理解できるようになってくる、と実際にライヴを観て思うようになった。ファラオはジャズの世界の住人だけれど、その枠を超えた人でもあると思う。(2009年7月6日) |
||
| Deaf Dumb Blind / Pharoah Sanders | ||
 曲:★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1970/7/1 [1] Summun, Bukmun, Umyun [2] Let Us Go Into The House Of The Lord |
Woody Shaw (tp, yodeling, per) Pharoah Sanders (ts, ss, cow horn, tritone whistle, wood flute, thumb piano, per) Gary Barts (as, per) Lonnie Liston Smith (p, thumb piano, per) Cecil McBee (b) Clifford Jarvis (ds) Nathaniel Bettis (bylophone, yodeling, per) Anthony Wiles (conga, per) |
| コルトレーン・グループに居たころやドン・チェリーの「Where Is Brooklyn?」で聴くファラオ・サンダースは、ゲテモノ系のノイジーな音を撒き散らす役割を期待され、期待通りに実行していたように思う。そのせいで音楽的な資質までエグいフリー・ジャズの人かと思ってしまうけれど、自身のリーダー・アルバムでは必ずしもそうではないということが本作(と「Karma」)を聴くとよくわかる。確かにサックスのサウンドこそ同じではあるものの、音楽そのものがアフリカ回帰を志向した(少なくとも僕には)爽やかなムードとあってフレーズにもさほど攻撃性を感じない。だから演奏は20分と17分の2曲のみという大作でありつつもそれほど難解な印象も濃い印象もない。[1]は終始、コンガ、鈴、マリンバなどのパーカッションが鳴り続けるアフリカン・ジャズとでも言える曲。役者も揃っているとはいえ曲の展開などというものはなく終始同じ調子のリズムが流れ続け、個々のパフォーマンスを楽しむというよりは全体を受け止める音楽となっている。[2]は冒頭で大げさかつ雄大なオープニングから、その流れのまま、ドラムの規則的なリズムもなく延々と曲が続く。そんなムードが楽しめるかどうかがカギ。僕は少々退屈。(2009年7月11日) | ||
| Live / Pharoah Sanders | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1981 [1] You've Got To Have A Freedom [2] Easy To Remember [3] Blues For Santa Cruz [4] Pharomba [5] Doctor Pitt |
Pharoah Sanders (ts) John Hicks (p) Walter Booker (b) Idris Muhammad (ds) |
| ファラオに初めて触れるのがコルトレーン・グループだと、ああいう人なんだと思ってしまうけれど、たまたまこれまで聴いてきたファラオのリーダー・アルバム(「Karma」「Deaf Dumb Blind」)からは、アフリカ志向のスピリチュアルなジャズを演っていたことをがわかってくる。更に実際にライヴを観たことによってようやくファラオのキャラクターがなんとなく理解できるようになってきた。そんなファラオのキャラクターが良く出ていると思うのがこのアルバム。代表曲である[1]の熱演もあって、ファンの間でも有名盤とのこと。確かにここでのファラオはかなり激烈。しかし、コルトレーン・グループのときのような宗教臭さはなく、むしろ明快に突き抜けているところが大きく違う。ジャズの典型的なフォーマットであるフォービートで演奏される[2]〜[4]は、むしろファラオの個性を知るには絶好の曲。CD化で追加された[5]がまた激烈で、ジョン・ヒックスの「泥臭さをやや抑えながらもよりスピーディなボビー・ティモンズ」的なピアノの連打がスピード感を増長させ、全体に大きく影響を与えている。81年という時代は、もっと洗練された軽い音楽が中心だったはずなのに、ある意味チャールズ・ミンガスに通じる汗臭いジャズを、超パワフルに演っていたファラオに男気を感じる。(2009年8月1日) | ||
| Doin' Allright / Dexter Gordon | ||
 曲:★★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1961/5/6 [1] I Was Doing All Right [2] You've Changed [3] For Regulars Only [4] Aociety Red [5] It's You Or No One [6] I Want More [7] For Regulars Only (alt take) |
Freddie Hubbard (tp) Dexter Gordon (ts) Horace Parlan (p) George Tucker (b) Al Harewood (ds) |
| 豪快かつ大らかささを売りにするデクスターにホレス・パーラン・トリオを組み合わせ、さらにフレディ・ハバードを加えるという、ブルーノートらしいメンツ構成。デクスターはいつもどおりの小細工抜きなおおらかな演奏で、温もりあるいかにもテナーらしい音を味わえる。ホレス・パーラン・トリオはトリオだけで楽しませる鉄壁のコンビネーションがあるだけなく、バックに回ったときの裏方サポートぶりも安定感抜群。この安楽で心地よいサウンドに合わせたハバードのトランペットがまたリラックスムード満点。ここまで良い意味で力が抜けた正統派トランペットのハバードを味わえるのは貴重で、それこそがこのアルバムの聴きどころ。[1]はデクスターのワンホーンの如く進み、途中からハバードにバトンタッチ、最後に2人で絡むという粋な構成。また、ブルースの[4]は、61年というジャズの革新進行中の時代に乗り遅れているんだけれど、これが実に心地良い。この顔ぶれと、デクスターの持ち味を引き出した本作はまさに企画(プロデュース)の勝利。個人的には、裏方に回ったときでもジョージ・タッカーの弾力性あるベースは他では得がたい個性があって、それを存分に味わうことができるアルバムでもあるところに魅力を感じる。[6][7] はボーナス・トラック。(2020年1月12日) | ||
| Go / Dextor Gordon | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★★☆ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1962/8/27 [1] Cheese Cake [2] I Guess I'll Hang My Tears Out To Dry [3] Second Balcony Jump [4] Love For Sale [5] Where Are You [6] Three O'Clock In The Morning |
Dextor Gordon (ts) Sonny Clark (p) Butch Warren (b) Billy Higgins (ds) |
| デクスター・ゴードンと言えば代表作は「Our Man In Paris」ということになっている。有名なスタンダードを多くとりあげ、基本的に軽快なテンポが中心で聴きやすくサイド・メンにはバド・パウエルにケニー・クラークといった重鎮が名を連ねたアルバムなだけにネーム・ヴァリューの点でもわかりやすい。僕もガイドブックをヒントに最初に入手したデクスターのアルバムが「Our Man In Paris」で、デクスターの気持ちよく豪快にブローするテナーを楽しめた反面、少々単調な印象を受けたこともあってあまり聴かなくなってしまった。そして期間をおいてから次に聴いてみたのがこのアルバム。編成は同じワン・ホーン・カルテットながら、選ばれた曲調とサイド・メンが違う。[1]のクールなベースの入り方がなんともいい。そして、この哀愁のメロディ・ラインをソニー・クラークのチャーミングなピアノがサポート。もちろんデクスターのテナーはここでも極めて男性的に振る舞っていて、この曲との絶妙なマッチングで独自の世界を構築している。以降も予想通りの太く実直なテナーを中心にリズム・セクションが好サポート。パウエルよりもクラークが好きな僕にとってはこちらの方が楽しめる。また、60年代のクラークにあまり冴えを感じないけれど、ここでは50年代以来の個性がよく出ていてその点でもポイントが高く、僕の苦手なヒギンズのドラムとの組み合わせにも意外と合っているように思える。どのアルバムからデクスターを聴こうかという人には、アルフレッド・ライオン&ヴァン・ゲルダー製作のこのアルバムの方が断然お勧め。(2009年4月11日) | ||
| Our Man In Paris / Dextor Gordon | ||
 曲:★★★★☆ 演奏:★★★ ジャズ入門度:★★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1963/5/23 [1] Scrapple From The Apple [2] Willow Weep For Me [3] Broadway [4] Stairway To The Stars [5] A Night In Tunisia [6] Our Love Is Here To Stay [7] Like Someone In Love |
Dextor Gordon (ts) Bud Powell (p) Pierre Michelot (b) Kenny Clarke (ds) |
| ヨーロッパに移住してから録音されたデクスター・ゴードンの最も有名なアルバム。ゴードンは決して革新的ではなく音楽家として新しいものを創造するタイプではなかった。そのサックスのスタイルは豪放で、その意味ではソニー・ロリンズと通じるところがあるものの、ゴードンのそれはどこまでも愚直で悪く言えば一本調子であるところが超一流として扱われない理由なのかもしれない。このアルバムはサイド・メンもやはり渡欧していたバド・パウエルとケニー・クラークという「過去の人」と地元のベース奏者という、なんとなく間に合わせでできた組み合わせという印象。実際、パウエルもクラークもさほどインプレッシヴな演奏はしておらず(クラークはもともと地味なドラマーだけど)脇役に徹していて、おおらかで野放図にブローするゴードンがより引き立つ成り立ちになっている。また意外や無名のベース奏者が悪くない。馴染みのスタンダードも多く気軽にテナー・サックスの太い音色を堪能できるところが人気盤の理由か。(2007年2月3日) | ||
| Groovin' With Golson / Benny Golson | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1959/8/28 [1] My Blues House [2] Drum Boogie [3] I Didn't Know What Time It Was [4] The Stroller [5] Yesterdays |
Benny Golson (ts) Curtis Fuller (tb) Ray Bryant (p) Paul Chambers (b) Art Blakey (ds) |
| ゴルソン作[1]の渋いブルースで始まるところがなんとも心地よい。他にゴルソン作は[4]だけではあるものの、オーソドックスなハード・バップをベースに全編あの柔らかいハーモニーで彩られているのだから、ゴルソン好きならたまらない。カーティス・フラーとの組み合わせとあって「Blues-Ette」を連想させるのは当然のことで、しかしそこまでカッチリ作りこまれていないところが逆に魅力的でもある。これはプレスティッジのいい加減さが良い方向に出た珍しいパターン。ゴルソンの独特な中高音を多用した早口フレーズとフラーの柔らかいトーンの組み合わせは、聴く前から予想できるとはいえ相性の良さは抜群。レイ・ブライアントは適度にシンプルで黒っぽく、クセがないところがハマっている。そしてチェンバースの躍動するベースと、ブレイキーの相変わらずのプッシュ力はさすがで、これらはジャズテットや「Blues-Ette」にはない魅力と言える。ほとんど話題になることすらないアルバムながら、ジャズテット、ジャズ・メッセンジャーズなどの要素が交じり合う好盤。(2007年5月2日) | ||
| Benny Golson and The Philadelphians | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1958/11/17 [1]-[6] 1958/12/12 [7]-[10] [1] You're Not The Kind [2] Blues On My Mind [3] Stablemates [4] Thursday's Theme [5] Afternoon Paris [6] Calgary [7] Blues March [8] I Remember Cliford [9] Moanin' [10] Stablemates (second version) |
[1]-[6] Lee Morgan (tp) Benny Golson (ts) Ray Bryant (p) Percy Heath (b) Philly Joe Jones (ds) [7]-[10] Roger Guerin (tp) Benny Golson (ts) Bobboy Timmons (p) Pierre Michelot (b) Christian Garros (ds) |
| タイトル通り、リーダーのゴルソンを筆頭にフィラデルフィア出身のメンバーで構成された同郷クインテット。ゴルソンとモーガンといえばなんと言っても「Moanin'」ということになるけれど、ここでの録音はその17日後とあってその関連性に興味が湧く。ジョン・ルイス作の[5]、メンバーであるレイ・ブライアントの書き下ろしと思われる[6]以外ははゴルソンのオリジナルという、ゴルソン中心のサウンドであることは共通。演奏の性質もトレンドもほぼ同時期の録音となれば変わるはずもない。レイ・ブライアントとパーシー・ヒースは良いプレイヤーとはいえ、それほど強烈な個性を打ち出すタイプではなく、フィラデルフィア出身であることからPhillyと名乗っているドラマーもそれほどしゃしゃり出ていないので、全体に聴くと意外とオーソドックスな仕上がり。もちろん曲も演奏(ハーモニーの付け方)にはゴルソンらしさが良く出ているのでファンなら聴いて損はない。当然ながら「Moanin'」の完成度には及ばないものの、差の要因はそれだけではない。ゴルソンの他のアルバムを聴けばわかる通り、本来のゴルソンはジャズ・メッセンジャーズのようなハードな演奏を持ち味にしていたわけではなく、このくらいの適度にリラクゼーションがあるムードを持ち味としており、その性質の差が出ているだけとも言える。あと、録音がイマイチで音の抜けが悪いのでRVG録音のように演奏の良さを伝え切れていないように思えるのも少々残念なポイント。 ボーナストラックの[7]-[10]の方は、音源としては貴重。ジャズ・メッセンジャーズはヨーロッパ・ツアー中に現地のミュージシャンといろいろと吹き込んでおり、この4曲は本来はトランペッターのロジェ・ゲランのリーダー・アルバムとして録音されたもの。完全にジャズ・メッセンジャーズ人気、、ゴルソン人気にあやかった選曲で、演奏に特筆するものはなく、特にリーダーはモーガンと比べるのも気の毒と言えるくらい実力差がある(2012年11月17日) |
||
| Cliff Jordan | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1957/6/2 [1] Not Guilty [2] St. John [3] Blue Shoes [4] Beyond The Blue Horizon [5] Ju-Ba |
Lee Morgan (tp [2][4][5]) Cliff Jordan (ts) John Jenkins (as) Curtis Fuller (tb except [5]) Ray Bryant (p) Paul Chambers (b) Art Taylor (ds) |
| ジャズにおける代表的管楽器4本が勢ぞろいした編成というのは意外とありそうでない。アンサンブルを重視したブルーノートらしい作りこまれたアルバムを想像していると、これが大違いのジャム・セッション風の典型的なハード・バップ。ベースとドラムこそお馴染みの安心感ある組み合わせとはいえ、この2人はブルーノートだけでなく当時のジャズ・シーンでの定番の組み合わせ、そしてレイ・ブライアントという組み合わせがおよそブルーノートらしくない。それをもって悪いというつもりはまったくないものの、なんと言っても主役に個性がなくパッとせず、人数の関係上、出番が多いわけでもないのにカーティス・フラーやリー・モーガンの光るプレイに耳を奪われてしまう。特に若さあふれるモーガンのプレイはやはりいい。[4]を除いたオリジナル曲はなかなかの出来栄え。こんな気軽に聴けるアルバムがブルーノートにあってもいいじゃないか、という1枚。(2007年8月2日) | ||
| A Blowin' Session / Johnny Griffin | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1957/4/6 [1] The Way You Look Tonight [2] Ball Bealing [3] All The Things You Are [4] Smoke Stack |
Lee Morgan (tp) Johnny Griffin (ts) John Coltrane (ts) Hnak Mobley (ts) Wynton Kelly (p) Paul Chambers (b) Art Blakey (ds) |
| テナー・サックス奏者を3人も集めてバトルさせてしまおうという一見イージーな企画。しかし、これでも物足りないと若きリー・モーガンを加えて、さらにブレイキーに思い切りプッシュさせてしまうところがいかにもブルーノート的な企画。このフロント・ラインの中で一般的に知名度が一番低いのは主役のジョニー・グリフィンなので、このアルバムを手に取る人はサイド・メン目当ての人が少なくないかもしれない。[1]から熱い熱いブレイキーのドラムが迸り、冒頭からグリフィンがブリブリと吹きまくって実に爽快。流れるように引き継がれるモーガンも負けじとバリバリと対抗。以降続くモブレー、コルトレーンへのソロの引渡しも実にスムーズで一見ジャム・セッションのように見えて、やはりリハーサルをそれなりに積んで練られたもののようにも聴こえる。サイド・メン目当てでこのCDを買った人は、モーガンの弾ける若さに心を躍らせ、コルトレーンの出番と存在感の少なさに落胆し、モブレーのマイペースぶりに納得し、グリフィンの迫力に圧倒されるに違いない。タイトル通りブロウイング・セッションのお手本的アルバム。(2006年12月19日) | ||
| Look Out ! / Stanley Turrentine | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★☆ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1960/6/18 [1] Look Out ! [2] Journey Into Melody [3] Return Engagement [4] Little Sheri [5] Tiny Capers [6] Minor Chant [7] Tin Tin Deo [8] Yesterdays [9] Little Sheri (45" single take) |
Stanley Turrentine (ts) Horace Parlan (p) George Tucker (b) Al Harewood (ds) |
| オーソドックスでテナーらしい太い音をアーシーに鳴らすスタンリー・タレンタインがジャズ・ファンに熱く語られることはほとんどない。それは革新的なジャズ・ミュージシャンでない場合に共通する冷遇でもある。しかもタレンタインはハード・バップの全盛期を過ぎてから出てきた世代とあってますます影が薄い。しかし、そんな世相に左右されないオーソドックスな演奏こそが持ち味である。もちろん腕は確か。このアルバムでも大らかで力強く、歌心とブルース・フィーリングに溢れたスタンリーのテナーを満喫できる。しかもバックに付いたのは個性派ホレス・パーラン・トリオとあって、どのピアニストとも異なるパーラン独特のフレーズと骨太タッカーのベースが独自のグルーヴを携え、オーソドックスな中にも確かな個性を持たせるという、簡単にできそうで実はレベルが高い内容となっている。こういう個性的で良質なジャズにはもっとスポットライトが当たってほしいもの。(2009年6月14日) | ||
| Eastern Sounds / Yusef Lateef | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1961/9/5 [1] The Plum Blossom [2] Blues For The Orient [3] Ching Miau [4] Don't Blame Me [5] Love Theme From Spartacus [6] Snafu [7] Purple Flower [8] Love Theme From The Robe [9] The Three Faces Of Balal |
Yusef Lateef (ts, oboe, fl) Barry Harris (p) Ernie Farrow (b) Lex Humphries (ds) |
| オリエンタル・ミュージックを志向したことで知られる、テナー、オーボエ、フルート奏者、ユセフ・ラティーフ。コルトレーンにも影響を与えたと言われるその音楽は、きっとアクの強い激しさを持ち合わせたものなのではないかと勝手に想像して聴いてみると、確かに東洋志向な独特な旋律を持った独自の音楽([4][5][8]以外はオリジナル)であることは分かるものの、クセや暑苦しさは予想外に少ない。曲は短いし、押し付けがましいエゴイスティックな感じもしない。[4]のように、いかにも、という感じのバラード調の曲もあるし、熱くなるというよりは落ち着いた演奏が全体を占めている。それでも「ジャズってオシャレよね」と決めているジャズ一見さんからすると、ちょっと異様な雰囲気であることもまた間違いない。東洋的な味付けでじっくりと聴き込むジャズ、というコンセプトに抵抗がなければ是非聴いておきたいアルバム。個人的にはちょっと中途半端に感じてしまう。(2012年6月3日) | ||
| Requiem / Branford Marsalis | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1998/8/17-20 [1] Doctone [2] Trieste [3] A thousand Autumns [4] Lykief [5] Bullworth [6] Elysium [7] Cassandra [8] 16th St. Baptist Church |
Branford Marsalis (ts, ss) Kenny Kirkland (p) Eric Revis (b) Jeff "Tain" Watts (ds) |
| キース・ジャレット・アメリカン・カルテットのレパートリーでポール・モチアン作の[2]を除く、全曲がブランフォードのオリジナル。90年代以降のジャズは、50年代のような大らかさはなく、60年代のような攻撃性もなく、70年代のような生き残りをかけた模索感もなく、安定感と洗練をベースに複雑味を染み込ませたスタイルが多くなっていくけれども、このアルバムもその例に漏れない。前半にコルトレーン的な要素が強く、演奏の素晴らしさは認めつつもオリジナリティの観点で物足りなさを感じる。しかし、中盤以降、ブランフォードの個性が現れ、上質かつ骨太、尚且つ現代的にオーソドックスな演奏が並んでいる。演奏力も確かで、シリアスにジャズを聴きたいと言う人の要望に応える充実したジャズがギッシリ。弟ほど伝統ジャズに偏らず、伝統にリスペクトしながらも、世紀末に王道ジャズをやろうという心意気が見えてくる。(2012年7月14日) | ||
| Upward Spiral / Branford Marsalis | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 2015/12/16-19 [1] There's A Boat Dat's Leavin' Soon For New York [2] Blue Gardenia [3] From One Island To Another [4] Practical Arrangement [5] Doxy [6] I'm A Fool To Want You [7] West Virginia [8] So Tinha De Ser Com Voce [9] Momma Said [10] Cassandra Song [11] Blue Velet [12] The Return (Upward Spriral) |
Branford Marsalis (ts, ss) Joey Calderazzo (p) Eric Revis (b) Justin Faulkner (ds) Kurt Elling (voice) |
| 自身のカルテットに、ヴォーカルのカート・エリングを迎える形で制作されたアルバム。上掲「Requiem」から17年後の本作、全体に余裕と成熟度を感じる。これがミュージシャンとしての成長なんだと容易にわかるほどの懐の深ささが印象深い。しかも表現の素晴らしさはそのまままに、2016年という時代のジャズであることを象徴するかのように適度に灰汁が抜けている。エリングのヴォーカルが入ったということが、こういった要素を引き出す大きな要因だったことは間違いない。ブランフォードが「ヴォーカル+バックバンドという形でなく、ともに即興演奏ができる楽器としてのヴォイスと一緒にやってみたかった」という狙いは上手く成功していると思う。リアルタイムのジャズにほとんど興味がない僕でも素晴らしいと思える内容、というか現代のジャズにまだこれだけの深みと面白さがあるのかと思い知ることになった。リズムセクションの演奏レベルも非常に高く、BGM的ではなく聴き応えのあるジャズとして楽しめる。(2016年7月10日) | ||
| Lou Takes Off / Lou Donaldson | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★★★☆ 評価:★★★★☆ |
[Recording Date] 1957/12/15 [1] Sputnik [2] Dewey Square [3] Strollin' In [4] Groovin' High |
Donald Byrd (tp) Lou Donaldson (as) Curtis Fuller (tb) Sonny Clark (p) George Joyner (b) Art Taylor (ds) |
| ルー・ドナルドソンといえば初期のハード・バッパーとしての活躍と「Alligator Bogaloo」や「Everything I Play Is Funky」のようなファンキー/ソウル路線での活躍とに大きく分類できる。前者の頃のドナルドソンはチャーリー・パーカー直系のアルト・サックスによる熱い演奏こそが魅力。このアルバムはそんなハード・バッパーとしてのドナルドソンの魅力が満喫できる1枚。正直なところアルト奏者としては特別な個性があるとは思わないけれど、ここでのドナルドソン、いやバンド全体の火を吹くような演奏の熱さといったらそれは凄い。ドナルド・バードもカーティス・フラーも激しくブロー、アート・テイラーのプッシュも強力、そして弾力性に富んだジョージ・ジョイナーのベースもこの上なくグルーヴィ、そこにソニー・クラークの哀愁のピアノが加わるとあっては文句のつけようがない。旧ソ連が打ち上げた人類初の人工衛星にインスパイアされて書かれた[1]は、それと関連があるとはまるで思えない典型的ハードバップで、全体を通しても革新性や斬新さとは縁のないブロウイング・セッションそのもの。でも、ハードバップの熱演が聴きたい人にとってこんなに気持ちいいアルバムはそうはない。(2007年4月21日) | ||
| LD+3/ Lou Donaldson with The Three Sounds | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1959/2/18 [1] Three Little Words [2] Smooth Groove [3] Just Friends [4] Blue Man [5] Jump Up [6] Don't Take Your Love From Me [7] Confirmation |
Lou Donaldson (as) Gene Harris (p) Andrew Simpkins (b) Billy Dowdy (ds) |
| ハッピーな曲を溌剌と演奏させたら右に出る者がいないピアノ・トリオのスリー・サウンズに、明るいトーンで気持ちよくブローするルー・ドナルドソンという、ブルーノート看板ミュージシャン達の企画アルバム。なにしろ聴きやすく親しみやすいところは狙い通りで、両者の相性の良さは抜群と言える。もちろん、ただ聴きやすいだけの軽いものになっていないのは、黒人本来のブルースやソウル魂が確かにそこに根付いているから。ありきたりなようでいて実は今の時代にこのような演奏というのは聴くことができない。そういう意味で、こういう演奏が記録として残ってそれを楽しむことができるのはジャズ・ファンとして至上の喜び。後の路線を考えるとドナルドソンのオーソドックスなアルトの歌心をたっぷりと楽しめるし、そこにジーン・ハリスの小気味よいピアノが絡むと予定調和的とわかっていても楽しい気分になる。スリー・サウンズの「なんでもこなせます」的な器用さも見事で、ドナルドソンの好演を認めつつも、「+3」どころかむしろ「3+」と聴こえなくもない。一期一会の好盤。(2009年12月26日) | ||
| Jazz Lab / Gigi Gryce and Donald Byrd | ||
 曲:★★★★☆ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1957/8/9 [1] Blue Lights [2] Onion Head [3] Isn't It Romantic [4] Bat Land [5] Bagoon [6] Imagination [7] Xtacy |
Donald Byrd (tp) Gigi Gryce (as) Hank Jones (p) Paul Chabers (b) Art Taylor (ds) |
| ドナルド・バードとジジ・グライスの双頭グループ、ジャズ・ラボラトリーのアルバム。[1][4]がグライスのオリジナル([4]はL.Searsとの共作)、[2][7]がバードのオリジナル、[5] がハンク・ジョーンズのオリジナルと自作への意欲が見られる。演奏、音楽のスタイルはとりてて斬新ではなく、時代相応のオーソドックスなハードバップで面白みやアクみたいなものはない。テーマなど、アレンジをカッチリと固めて、わかりやすく聴きやすいジャズになっている。メロディラインは、ベニー・ゴルソンのようなメロディックなものというよりは、メリハリがあって溌剌とした印象。それがジジ・グライスの個性であり、狙ったところだったんでしょう。各人のアドリブにはやはりアクはなく、そんなオーソドックスなジャズの中でバードのトランペットが快調に歌っている。60年代以降、ジャズはどう表現を広げていくかという時代になって行き、コルトレーンのような演奏スタイルが持て囃されるようになり、現在のジャズ・サックスはそうした時代を下敷きに進化したものになっているのはご存知の通り。ジジ・グライスの演奏にはコルトレーン的な要素がなく、今となってはほとんど見向きもされなくなってしまっているけれど、現在のサックスのスタイル以外にも、こういうスタイルがあったこと、その良さに気づくこともジャズの楽しさであるように思える。(2011年12月17日) | ||
| The Blues And The Abstract Truth / Oliver Nelson | ||
 曲:★★★★☆ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1961/2/23 [1] Stolen Moments [2] Hoe-Down [3] Cascades [4] Yearnin' [5] Butch And Butch [6] Teenie's Blues |
Freddie Hubbard (tp) Oliver Nelson (as, ts) Eric Dolphy (as, fl) George Barrow (bs) Bill Evans (p) Paul Chambers (b) Roy Haynes (ds) |
| 60年代に入ると旧来のハード・バップは過去のものになりつつあったし、ベタなブルースも徐々に演奏されなくなっていた。そんな時代だからこそ、例えばジョン・コルトレーンの「Plays The Blues」やジャッキー・マクリーンの「Bluesnick」のような新しいスタイルのブルースを模索したアルバムが作られた。このアルバムもそんな1枚。ブルースに敬意を表しながら、確かに50年代とは一味違うブルースが展開されている。曲の構成や厚いハーモニーを有効に使ったアレンジはもちろん、60年代を代表する豪華メンバーのフレッシュな演奏も旧来のブルースとは趣を異にする。ハバードもドルフィーも枠をはみ出す手前の程よいバランス感覚でソロを展開。サイドに回ると仕事人に徹して存在感が薄くなることが多いエヴァンスもそれなりにらしい演奏を聴かせる。保伝統的な安定感はチェンバースに任せるというコンセプトもうまく行っていると思う。録音状態のせいかドラムの音がこもっているのが少々残念ではあるけれど、ネルソン・オリジナルのブルースとして完成度はなかなか高い。(2008年12月26日) | ||
| Alive And Well In Paris / Phil Woods | ||
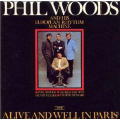 曲:★★★★☆ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1968/11/14, 15 [1] And When We Are Young [2] Alive And Well [3] Freedon Jazz Dance [4] Stolen Moments [5] Doxy |
Phil Woods (as) George Gruntz (p) Henri Texier (b) Daniel Humair (ds) |
| 先に激しいライヴ盤「At The Montreux Jazz Festival」を聴いたのは間違いだったのかもしれない。ヨーロピアン・リズム・マシーンのデビュー作にあたる本作は、そのライヴ盤で聴ける激しさに加えて、先日天に召されてしまったウッズの持ち味である抒情性がうまく融合した名作。有名な[1]を聴いてみると、評価通りの名演。この1曲にこのグループのエッセンスが凝縮されているからでしょう。それにしてもウッズのアルトは鳴りっぷりが良く、しかもアルトらしい高音の伸びやかさに満ちている。白人のみ、しかも相手はヨーロッパのミュージシャン、そして時代は68年という要因がサウンドに生気を与えている。個人的には、コモリ気味の録音状態があまり好みに合わないとはいえ、そんなことは些細なことと言いたくなるほど演奏が良い。それでいて、そしてこの時代でありながらジャズの枠からはみ出そうとしていないところもウッズの資質の成せる業、グループとして表現したいことが明確であることも充実の要因に違いない。(2015年11月4日) | ||
| At The Montreux Jazz Festival / Phil Woods | ||
 曲:★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1969/6/19 [1] Capricci Cavallereschi [2] I Remember Bird [3] Ad Infinitium [4] Riot |
Phil Woods (as) George Gruntz (p) Henri Texier (b) Daniel Humair (ds) |
| チャーリー・パーカー直径の白人アルト奏者として知られるフィル・ウッズ、白熱のライヴ盤。演奏は激しく、そして荒い。[4]を除いて10分以上の長尺演奏、ベース・ソロやドラム・ソロも長めにフィーチャーした演奏は60年代中盤までのジャズとは明らかに違う。そのサウンドを表すべく、グループ名をヨーロピアン・リズム・マシーンと名付けたのかもしれないんだけれど、その名ほどリズムに面白みがあるわけではなく、典型的なワンホーン・カルテットの編成で疾走するスタイル。タメや引きなんてものはなく、当時のオーネット・コールマン・カルテット的な勢いで、ある意味ロック的なパワーで迫る。しかし、ウッズのアルトはパーカーがコルトレーン化したようなスタイルで、オーネットのような音楽としての個性を主張するというよりもアルトのブロウで勝負している感じ。それ故にか、69年という時代ほど斬新なサウンドという印象を受けない。勢いを楽しむべきとはいえ、表面的で雑な印象は拭えず、僕はこれを「熱い」とは感じない。アルトの鳴りも、アルトのサウンドへの支配力ももう一歩。これがウッズの実力なんだろうか。(2009年9月26日) | ||
| Parker's Mood / 矢野沙織 | ||
 曲:★★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 2005/7/25 [1] I Got Rhythm [2] The Days Of Wine And Roses [3] Compositon 101 [4] Don't Explain [5] Parker's Mood [6] Bohemia After Dark [7] A Night At The Tunisia |
矢野沙織 (as) Richard Wyands (p) John Webber (b) Jimmy Cobb (ds) |
| 日本ジャズ界のアイドルとしてレコード会社が手厚くサポートし、ゴージャス仕立てのアルバムを作らされてきた感のある矢野は、傍から見ていると大人の事情が見えて痛々しい。このアルバムはニューヨーク、SMOKEというクラブでのライヴで、これまでのスタジオ盤とは一転ワン・ホーン・カルテットというオーソドックスな編成。曲はほとんどが有名な曲で占められていて、つまり最も古き良き時代のスタイルで作られていると言っても良い。しかもピアノは77歳、ドラムは76歳という古き良き時代を知る人が相手である。これがいい。かなりいい。曲も長めでライヴらしい自由な演奏が聴ける。テクニックに苦言を呈する人もいるけれど、そんなことより彼女自身の「音」を持っていることの方が重要でその点ではもう十分いいところまで行っていると思う。ピアノはファンキーで実に味があるし、クッキリ録音されたベースもいい。そしてなんと言っても50年代のころと何も変わっていないジミー・コブのドラムにビックリ。後半、[6][7]のアグレッシヴな演奏は76歳のそれとは思えない。日本ジャズ界のアイドルということを無視して、オーソドックスで上質なジャズを楽しめるアルバムだと思う。(2007年2月18日) | ||