ロック・ファンのためのジャズ案内のヘッダー
Rock Listner's Guide To Jazz Music
Cannonball Adderley
| Something Else | ||
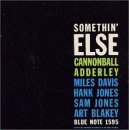 曲:★★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1958/3/9 [1] Autumn Leaves [2] Love For Sale [3] Somethin' Else [4] One For Daddy-O [5] Dancing In The Dark [6] Bagoon [7] Autumn Leaves (alt take) |
Miles Davis (tp) Cannonball Adderley (as) Hank Jones (p) Sam Jones (b) Art Blakey (ds) |
| 事実上、マイルス・デイヴィスがリーダーであるこのアルバムは、マイルスがブルーノートのアルフレッド・ライオンへの恩返しとして吹き込んだというサイド・ストーリーで有名。マイルス自身の通常の活動とは外れたところで製作され、いつものメンバーとは違うこともあって、当時最先端を走っていたマイルスのモード・ジャズとは異なるオーソドックスなハード・バップになっている。しかし、そこはマイルス。凡庸なモダン・ジャズで終わるはずがなく、クールでカッコいい唯一無二なムードと高い完成度を誇る作品になっている。恩返しゆえに、そしていつも違うメンバーゆえに、ワン・タイム・スペシャルなセッションとして情熱を傾けたとさえ思わせるくらい質が高い。キャノンボールは自身のリーダー・アルバムで聴かせる陽気なムードとは別世界のクールでよじれたフレーズを繰り出し、ナチュラルで端正な黒さを放つハンク・ジョーンズのピアノ、いつも違って抑えたブレイキーのドラム、そしてこれらが一体となって独自の世界を構築しているところも格別に素晴らしい。あるいは、契約の都合で普通の形でリーダー・アルバムを作ることができなかったという制約が生み出した故の産物と言ってもいいかもしれない。マイルスの知性と品格にリードされた傑作。(2008年5月4日) HDtrackesより96KHz/24bit音源を購入。このサイトで販売されているブルーノートの音源は大きく分けて2種類に分類されるようで、ひとつはミックスからして違うもの、もうひとつはミックスはそのままに音質の向上が図られているものに大別できる。このアルバムの音源は後者で、基本的にミックスはあまり変わらない。各楽器のの定位も変わらないけれど、音場がやや広くなっている。音の雑味がCDより明らかに減っており、楽器の音はまろやか、かつクリアになっている。音質に拘る人なら聴いてみる価値はある。(2013年6月23日) 「ブルーノート・ザ・マスターワークス」と称してして再発売されているCDは、一体何度目の再発なのかと思いつつ、一時期ネットでストリーミングのみで聴くことができた"Autumn Leaves"のTake 1が収録されたことがトピック。そのTake 1は全体に緩くて確かに仕上がり途上。マイルスのテーマのメロディ、表情付けが微妙に違い、キャノンボールがまりまりに欠くソロを吹いていることが確認できる。要は多くの別テイク同様、本テイクの完成度を知るためのものであるけれど、聴き倒した人なら楽しめる。実はこの盤の個人的なトピックは自分の所有音源にとって初のステレオ盤だったことで、音場の広さがまったく違う。音質的にもハイレゾ音源と遜色ないレベルに磨かれている。ただし、シンバルの音がかなり強調された音のバランスでミックスが異なるという違いもある。総合的に見て、モノラルのハイレゾを取るかステレオの最新リマスターを取るかは難しい選択。(2013年10月27日) |
||
| Things Are Getting Better | ||
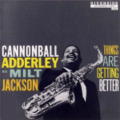 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★★★★ 評価:★★★★☆ |
[Recording Date] 1958/10/28 [1] Blues Oriental [2] Things Are Getting Better [3] Serves Me Right (take 5) [4] Serves Me Right (take 4) [5] Groovin' High [6] The Sidewalks Of New York (take 5) [7] The Sidewalks Of New York (take 4) [8] Sound For Sid [9] Just One Of Those Things |
Cannonball Adderley (as) Milt Jackson (vib) Wynton Kelly (p) Percy Heath (b) Art Blakey (ds) |
| 「with Milt Jackson」名義。個人的には組み合わせとして少し意外な感じがしないでもない。キャノンボールの陽気なキャラクターと、ミルト・ジャクソンのいぶし銀のブルース・フィーリングが直感的には結びつかないから。聴いてみると、他のアーティストにもある「ミルト・ジャクソンとの競演盤」の例に漏れず、音楽的にはミルトのフィーリングが濃厚という意外性のない音楽に仕上がっている。では質が低いのかというとそんなことはなく、これも「ミルト競演盤」の例に漏れず音楽としては大変な充実ぶり。リラックスした雰囲気の中にも骨太のブルースを中心とした、黒人のもっとも得意とする(現代ではその黒人でさえも演奏しないスタイルの)ジャズを堂々と自然体で演奏しているところが実に素晴らしい。キャノンボールは、後に自分のグループを率いて明快なファンキー・ジャズで人気を博したこともあって、彼の音楽の本質はあの陽気な世界だったと認めている人は多い。一方で、サイドに回ったときや自身のリーダー・アルバムに大物ゲストに迎えると、チャーリー・パーカー直系のハード・バッパーとして一流のアルトを聴かせる。そして、音楽的に自分のやりたいことができるようになった時代よりも、周囲に合わせてアルトをブロウさせてたころの方がサックス奏者としては充実していたのではないかというのが個人的な意見。尚、このアルバムはリズム・セクションも豪華で興味をそそられるものの、3者とも抑え気味で主役2人の引き立て役に回っている。それでもその抑え方は心得たもので、アルバム全体の底上げに貢献している。(2013年12月22日) | ||
| In Chicago | ||
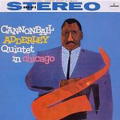 曲:★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★★ 評価:★★★★☆ |
[Recording Date] 1959/2/3 [1] Limehouse Blues [2] Star Fell On Alabama [3] Wabash [4] Grand Central [5] You're A Weaver Of Dreams [6] The Sleeper |
Cannonball Adderley (as except [5]) John Coltrane (ts except [2]) Wynton Kelly (p) Paul Chambers (b) Jimmy Cobb (ds) |
| マイルス・グループで活動中のメンバーがツアーの合間にリーダー抜きで製作したアルバム。ギラリと目を光らせるマイルスがいないために開放された気分になったのかは知らないけれど、良い意味で肩の力が抜けた気持ちよい演奏がギッチリ詰まっている。アップ・テンポの曲もバラードもどことなく楽しげ。とはいえ演奏は引き締まっていてただのムード・ミュージックに陥ることのない力強さがある。ジミー・コブの小気味良いドラムがバンドを引っ張っており、ケリーが明るいトーンを駆使したピアノで楽しげなムードを増長。録音の良さもあってチェンバースのベースの躍動感が実に気持ち良く伝わってくる。主役はもちろんキャノンボールで溌剌とキレのあるフレーズと伸びやかなバラード・プレイを披露。すでにシーツ・オブ・サウンドを確立しているコルトレーンも鋭いフレーズを連発しつつ、どこか明るくおおらか。そんなリラックスしたムードが全体に漂っていて、眉間に皺を寄せて聴こうという気になれないところがこのアルバムのセールス・ポイント。テナーとアルトの音を左右に振り分けた録音になっているのに曲によって左右入れ替わるのが不思議。(2006年11月11日) | ||
| In San Francisco | ||
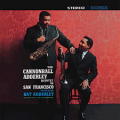 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1959/10/18 1959/10/20 [1] This Here [2] Spontaneous Combustion [3] Hi-Fly [4] You Got It [5] Bohemia After Dark [6] Straight No Chaser |
Nat Adderley (cornet) Cannonball Adderley (as) Bobby Timmons (p) Sam Jones (b) Louis Hayes (ds) |
| キャノンボール・アダレイをマイルスのつながりで聴いて行くとパーカー直系のハード・バッパーとしての姿を刷り込まれる。「Something Else」も「In Chicago」でもアルト奏者としてはハード・バッパーそのもの。そのキャノンボールの代表作のひとつとされているのが本作で、ここでは陽気で楽しい所謂ファンキー・ジャズを展開。ミドル・テンポの曲も含め、全体にノリが良く熱気溢れる演奏で[1][2]のゆったりとした長尺もの、[4][5]のようなアップ・テンポの曲、それぞれに良さがあってたまにはこういう楽しげなジャズもいいなあと思える。ナット・アダレイのコルネットは正直なところ上手いとは思わないけれど、このノリに合っていることは間違いない。そしてファンキー度を濃くしているのがティモンズのブロック・コードを連打するピアノで、この種の演奏が好きな人にはたまらないはず。もちろんキャノンボールの繰り出すフレーズも一般的にファンキー・ジャズという言葉でイメージされる通りの陽気で楽しげなもの。観客のノリの良さがそんなムードを更に助長する。シリアスなジャズを好む人は軽視するだろうけれど、これがキャノンボールの素の姿なんでしょう。(2006年8月5日) | ||
| Know What I Mean ? | ||
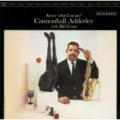 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★★★★ 評価:★★★★☆ |
[Recording Date] 1961/1/27 1961/2/21 1961/3/13 [1] Waltz For Debby [2] Goodbye [3] Who Cares? (take 5) [4] Who Cares? (take 4) [5] Venice [6] Toy [7] Elsa [8] Nancy (With The Language Face) [9] Know What I Mean? (re-take 7) [10] Know What I Mean? (take 12) |
Cannonball Adderley (as) Bill Evans (p) Percy Heath (b) Connie Kay (ds) |
| キャノンボールとビル・エヴァンスはマイルス・グループに同時期に在籍、しかしリーダーになってからの両者の音楽性はまるで違っているところが実に興味深い。ごく大雑把に言うと、陽気なファンキー・ジャズをあっけらかんと突き進んだキャノンボールに対して、ピアノ・トリオでリリシズムを極めるエヴァンスという性格分けができる。そんな両者をマイルスは自分の音楽の中に取り込んで見事に一体化、やはりマイルスのリーダーシップがあったからこそ両者が結び付いていたんだろうなと勝手に思っていた。ではマイルスが関知しない両者の競演はどうかと言うと、これがマイルス・グループとは違う形で融合しているから面白い。エヴァンスらしいピアノが優しく展開され、それに乗るキャノンボールのアルトは明快でメロディアス。とにかく聴きやすく、心地よい。そうかといって安易な感じがしないところがまた良い。この世界にパーシー・ヒースとコニー・ケイという地味めの2人を組み合わせたのも美味いキャスティング。アルトの音を生々しく捉えた録音も素晴らしい。ジャズはシリアスでないといけないという人は向いていないけれど、これほどまでに身を任せてジャズを心地よく聴けて質が高いアルバムは、そう多くはない。(2011年2月19日) | ||
| Mercy, Mercy, Mercy! | ||
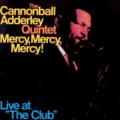 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1966/10/20 [1] Fun [2] Games [3] Mercy, Mercy, Mercy [4] Sticks [5] Hippodelphia [6] Sack O' Woe |
Nat Adderley (cornet) Cannonball Adderley (as) Joe Zawinul (p, elp) Victor Gaskin (b) Roy Mccurdy (ds) |
| どうやら60年代のキャノンボールはひたすらカジュアルでファンキーなジャズを追求していたようで、有名盤の本作もその路線。このアルバムもライヴで、いわゆる眉間に皺を寄せ、頭を垂れて聴く類のものとは正反対の陽気な観客のムードが印象的。曲に合わせて手拍子を入れ、まるでみんながビールジョッキ片手に楽しんでいるかのよう。演奏は活発そのもの。キャノンボールのアルトの音は太く鋭く、結構ハードな演奏。ナットのコルネットも同様に鋭く音を張り上げている。それでも、どこまで行っても根っこに陽気さがあるのがこのグループの個性。フォー・ビートの曲がないこともあって伝統的なコンボ編成でありながら50年代のモダンジャズの雰囲気は皆無で、むしろソウルやファンクの匂いがプンプンしている。ベースの音量が非常に小さく決してスイングしない固めスネアのドラムが目立つという音のバランスがますますジャズとは異質のサウンドという印象を増長。ジョー・ザヴィヌルは[3]を除いてアコースティック・ピアノを弾き、エレピの演奏をアコースティック・ピアノに置き換えたかのようななんとも聴きどころがない演奏に終始している。そしてその[3]がまた一段とソウル/R&B/ファンク色が濃厚。従来のジャズに拘っていないところがこのカッコいいファンキーな音楽を生む要因だったように思える。70年代に流行ったファンク・ミュージックのある意味原型かもしれない1枚。(2007年2月6日) | ||
