ロック・ファンのためのジャズ案内のヘッダー
Rock Listner's Guide To Jazz Music
John Coltrane(59-61)
| Bags & Trane | ||
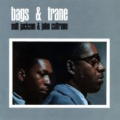 曲:★★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★★ トレーン入門度:★★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1959/1/15 [1] Stairway To The Stars [2] The Last Late Blues [3] Bags & Trane [4] Three Little Words [5] The Night We Called It A Day [6] Be-Bop [7] Blues Leagacy [8] Centerpiece |
Milt Jackson (vib) John Coltrane (ts) Hank Jones (p) Paul Chambers (b) Connie Kay (ds) |
| アトランティック移籍第一弾はミルト・ジャクソンとの競演盤。僕はアルバムのまとまりをブチ壊すボーナス・トラックを基本的に好まないんだけれど、この CD は [1] がいきなりボーナストラックという掟破りの荒業。ところがこの [1] 、いつも通り典雅に展開されるミルトのヴィブラフォンに悠然と、そして優雅かつ大胆に切れ込むコルトレーンのテナーの組み合わせが何とも素晴らしく、この曲で始まることは決まりごとであったかのようにハマッている。以降もミルトのブルージーなヴァイブとコルトレーンの硬質なテナーが絶妙に絡む、コラボレーションの典型的成功例。コニー・ケイを引き連れてきたものの、ジョン・ルイスではなくハンク・ジョーンズを起用したことにより、硬軟とりまぜてのブルース・フィーリングが濃厚。したがって音楽的な主導権を握っているのは明らかにミルト・ジャクソン。ポール・チェンバースのベースも上下自在に行き交う持ち味を存分に発揮。この後、更に飛躍するコルトレーンは出番は少なめがら、ひとたびソロが始まると存在感は絶大。好みが分かれる可能性はあるものの、反響音を伴ったサックスの音を生々しく捉えた録音の良さも独特な良さがある。適度なリラクゼーションを持ったこの種のオーソドックなジャズをコルトレーンが演奏したのは、一部企画盤を除くとこのアルバムが最後でもある。余り語られることのない作品ながら、これは隠れた名盤。曲もチャーミングなものが多く「コルトレーンはちょっと苦手かも」としり込みしていた人や、コルトレーン入門者に是非聴いてもらいたい逸品。(2006年6月11日) | ||
| Giant Steps | ||
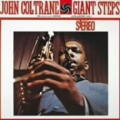 曲:★★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★ トレーン入門度:★★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1959/5/4 [3][4][11] 1959/5/5 [1][2][5][7][12][13] 1959/12/2 [6] 1959/4/1 [8][9][10] [1] Giant Steps [2] Cousin Mary [3] Countdown [4] Spiral [5] Syeeda's Song Flute [6] Naima [7] Mr. P.C. bonus track [8] Giant Steps [9] Naima [10] Like Sonny [11] Countdown [12] Cousin Mary [13] Syeeda's Song Flute |
John Coltrane (ts) Tommy Flanagan (p except [6] [8]-[10]) Wynton Kelly (p [6]) Ceder Walton (p [8]-[10]) Paul Chambers (b) Art Taylor (ds except [6] [8]-[10]) Lex Humphries (ds [8]-[10]) Jimmy Cobb (ds [6]) |
| コルトレーンはここからいよいよ自分独自の道を進み始める。全曲オリジナルで気合いの入り方がとにかく違う。サイド・メンはほぼこれまでのメンバーと同じながら、レッド・ガーランドのフィーリングよりも断然新しいトミー・フラナガンのピアノが効いている。音の感触からしてこれまでとは別モノで、タイトル通り自己の音楽確立に向けての第一歩を大きく踏み出したことをこれでもかというくらいに打ち出している。めまぐるしく変わるコードに、確立されたシーツ・オブ・サウンドを噴出させ、全体的に力漲る勢いある演奏に保守的なジャズ・ファンはついて来れなくなったはず。コルトレーン嫌いな人は、恐らくこの作品から本格的に受け付けなくなってくるのではないだろうか。とはいえ、後の作品を考えると、サイド・メンはやはり保守的であるのも確かで過渡期の1枚であるのも事実。音楽的自立を象徴的に印象付ける [1]、とにかく吹きまくるところがスリリングな [3]、一転、美しいメロディを奏でる [6]、別れが近づいているポール・チェンバースへのリスペクトの気持ちを込めた [7] などが聴きどころ。このアルバムと似た雰囲気を持ったジャズはトレーン自身のものを含めて他にはない。尚、ボーナス・トラックは別メンバーによるボツになった演奏で全体的にテンションも低くあくまでもマニア向け。[11] は演奏時間が長くて期待させるけれど、さすがに本採用されたテイクの緊張感をこれだけの時間を維持するのは難しかったようだ。(2006年6月11日) | ||
| Coltrane Jazz | ||
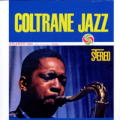 曲:★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★ トレーン入門度:★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1959/3/26 [9][11] 1959/11/24 [1][7][10] 1959/12/2 [3]-[6][8] 1960/10/21 [2][12] [1] Little Old Lady [2] Village Blues [3] My Shining Hour [4] Fifth House [5] Harmonique [6] Like Sonny [7] I'll Wait And Pray [8] Some Other Blues [9] Like Sonny [10] I'll Wait And Pray [11] Like Sonny [12] Village Blues |
[1] [3] -[8] [10] John Coltrane (ts) Wynton Kelly (p) Paul Chambers (b) Jimmy Cobb (ds) [9] [11] John Coltrane (ts) Ceder Walton (p) Paul Chambers (b) Lex Humphries (ds) [2] [12] John Coltrane (ts) McCoy Tyner (p) Steve Davis (b) Elvin Jones (ds) |
| 「Giant Steps」で、自己の音楽を高らかに宣言した次のアルバム。ボーナス・トラック([9]以降)を含めると録音日がバラついてメンバーも異なるけれど、中心となる本編の曲は、[2]を除いて「Giant Steps」と同じくコルトレーン、ケリー、チェンバース、コブのマイルス・グループと同じメンツによるカルテット。この12月2日のセッションから "Naima" のみ「Giant Steps」に収録されている。以上のような成り立ちを考えると、同質のものを想像したくなるところだけれど、前作の息詰まる緊張感と比べるとだいぶ力が抜けた演奏で、オリジナル・トラックの中で唯一の新カルテットによる [2] がオーソドックスなブルースであることも含めて普通のジャズとして聴ける。しかし、プレスティッジ時代に後戻りしているわけではなく、進化したうえでの程よい力の抜けた演奏。全体のサウンドが尖っていなくても、アドリブは確実に一歩進んだ印象で、それだけでプレスティッジ時代とまったく違う音楽として聴こえてくる。小曲 [7] でバラード・プレイのアピールも抜かりなし。前作同様、曲はコンパクトながらコルトレーンのフレーズは聴きどころが多く充実した内容の好盤。(2006年6月11日) | ||
| Live At The Jazz Gallery 1960 | ||
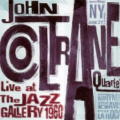 曲:★★★★ 演奏:★★★ ジャズ入門度:★ トレーン入門度:★ 評価:★★ |
[Recording Date] 1960/6/27 Disc 1 [1] Liberia [2] Every Time We Say Goodbye [3] The Night Has A Thousand Eyes Disc 2 [4] Summer Time [5] I Can't Get Started [6] Body And Soul [7] But Not For Me |
John Coltrane (ts, ss) McCoy Tyner (p) Steve Davis (b) Pete LaRoca (ds) |
| 話し声まで聞こえるオーディエンス録音で、テナーはじめすべての音が遠く、薄っぺらさが際立ついかにもブートレグ的な音質。ただ、ベースの音がほとんど聞き取れないことを除けば演奏そのものは把握できる程度ではある。このブートレグに価値があるのは、アトランティック時代のライヴ音源がオフィシャル盤にはなく、ブートレグにも少ないから。さらに、ドラマーがエルヴィン・ジョーンズではなく、ピート・ラロカというところが最大のトピックである。いきなり30分超の [1] で、吹きまくるコルトレーン。もちろん、この時期以降、吹きまくりはあたりまえのことになってくることは周知の事実でそれは特筆するほどのことではない。それよりも、言いたいことはたくさんあってどんどん言葉が出てくるけど、ところどころ詰まったり言い直したりしながら喋っているような感じという試行錯誤感こそが聴きどころでしょう。要はまだやりたいことをうまく表現できていない。そもそもアトランティック時代のコルトレーン全体に言えるこの傾向は、ライヴでより顕著になっているということ。あとは潔くなくて手数の多いラロカの立体感のないドラムとの組み合わせのレアさを楽しめるかどうか。幸い、この音質の悪さの中、テナーとドラムだけは比較的はっきりと聴き取れる。曲もアタマやオシリが切れているものも多く、貴重さ以外にあまり価値がないと思える重度なマニ向け音源というのが結論。(2012年1月29日) | ||
| The Avant-Garde | ||
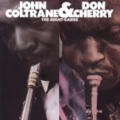 曲:★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★ トレーン入門度:★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1960/6/28 [1] [3] 1960/7/8 [2] [4] [5] [1] Cherryco [2] Focus On Sanity [3] The Blessing [4] The Invisible [5] Bemsha Swing |
Don Cherry (tp) John Coltrane (ts, ss) Charlie Haden (b [1] [3]) Percy Heath (b [2] [4] [5]) Ed Blackwell (ds) |
| ドン・チェリーとの共同名義、しかし実はチェリーのリーダー・アルバムとして録音されたもの。チェリー作が1曲、オーネット・コールマン作が3曲、モンクのスタンダードが1曲という構成。メンツもオーネットの人脈で固め、ピアノ・レスという編成であることも手伝って音の感触はオーネット・コールマンの世界にかなり近いものがある。そのフォーマットの中でコルトレーンは自信たっぷりにこれまでよりアブストラクトなフレーズを繰り出し、驚くほど違和感なく溶け込んでいるのが本作の聴きどころ。反面、オーネットのフォーマットの中に納まった演奏という言い方もできそう。そして、ここに来てついに [3] でソプラノ・サックスに着手。小粒な曲の中で軽く披露という感じで、ラフでありながらも、「My Favorite Things」での拙い演奏よりはちゃんと表現になっているように思う。それにし ても、同じレーベル所属でここまで接近しておきながらなぜオーネットとの競演が実現しなかったのか、ちょっと不思議な感じがする。[3] はオーネット・コールマンの「Something Else !!!!」の再演との聴き比べも一興。(2006年6月11日) |
||
| My Favorite Things | ||
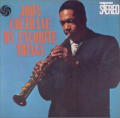 曲:★★★★ 演奏:★★★ ジャズ入門度:★★ トレーン入門度:★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1960/10/21 1960/10/24 1960/10/26 [1] My Favorite Things [2] Everytime We Say Goodbye [3] Summertime [4] But Not For Me |
John Coltrane (ts, ss) McCoy Tyner (p) Steve Davis (b) Elvin Jones (ds) |
| このアルバム、一般的には非常に評価が高い。理由はわからないでもない。エルヴィンとマッコイを迎えた初めてのフル・アルバムであること、初めて本格的にソプラノ・サックスに取り組んだこと、有名なスタンダードで構成されていること、中でも超有名曲"My Favorite Things"を取り上げたことなど。ミュージカルでヒットしたばかりの軽快な曲をこんなジャズにしたことも、珍妙なコード・チェンジの [3][4] も、発売当時は斬新だっただろうということは想像に難くない。しかしこの表題曲、エルヴィンはまだ大人しいし、マッコイもまだまだ成長途上、スティーヴ・デイヴィスは力量不足、そしてなによりソプラノ・サックスのフレーズが拙い。だけど、ミュージシャンも含めてこのアルバムを高く評価する人は非常に多い。でも、重要なステージ・レパートリーになる [1] には後にもっと良い演奏がたくさんあると思うし、[3][4]のコードチェンジは珍妙で決して万人向けではない。また、このアトランティック時代の録音はベースの音がモコモコしていて弦をハジいている感じがしないの録音もクセがあって、個人的な感覚ではあまり好きではなく、このアルバムをほとんど聴かない理由になってしまっている。さんざんけなしておいて、では良い点がないかというとそうでもない。やはり、新メンバーによる演奏はこれまでよりも新しい感覚に満ちているし、成長途上のマッコイは逆の見方をすれば初々しさを楽しめる。エルヴィンの重量感あふれるプレイは [3] で聴けるし、素晴らしいバラードの [2] も聴ける。スタンダードを並べていながらプレスティッジ時代のようにただジャムって作られただけでない完成度が美点ではある。(2006年6月11日) | ||
| Coltrane Plays The Blues | ||
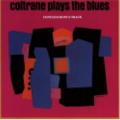 曲:★★★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★★ トレーン入門度:★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1960/10/24 1960/10/26 [1] Blues To Elvin [2] Blues To Bechet [3] Blues To You [4] Mr. Day [5] Mr. Syms [6] Mr. Knight [7] Untitled Original |
John Coltrane (ts, ss) McCoy Tyner (p) Steve Davis (b) Elvin Jones (ds) |
| タイトル通りのブルース演奏集。しかしながら、エルヴィン作の [1] を除いてコルトレーンのオリジナルという構成はプレスティッジ時代のようなジャム・セッション風のものではなく、作り込まれた印象を受ける。ゆったりした曲はもちろん、アップ・テンポの曲もあり、コルトレーンの演奏もこの時期相応のカラーで貫かれていて旧来のブルース演奏とはちょっと違うものを狙っている感じ。「Giant Steps」に至るまで、とにかく音数をいかに詰め込むかに執心だったコルトレーンは、ここに来てややそのペースを落とし、フレーズ全体のイメージを考えてプレイしているように思える。さて、曲名やブルースで統一されたイメージから、一見コンセプトを持ったアルバムに見えるこのアルバム、実は「My Favorite Things」と「Coltrane's Sound」と合わせて録音日が同じで、よって演奏の質においてこの3枚のアルバムはほとんど差はない。ソプラノ・サックスの演奏などは、「My Favorite Things」よりも熟れているほど。新メンバーでレギュラー・カルテットを組んだコルトレーンは、早々にこのマラソン・セッションに取り組み、そしてその音源をスタンダードで構成したアルバム、ブルース・アルバムという作品に分けて仕上げたのはレコード会社(プロデューサー)の手腕だったのか本人の意向だったのかは不明ながら、いずれにしてもその試みは成功していると思う。(2006年6月13日) | ||
| Coltrane's Sound | ||
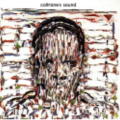 曲:★★★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★★★ トレーン入門度:★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1960/10/24 1960/10/26 [1] The Night Has A Thousand Eye [2] Central Park West [3] Liberia [4] Body And Soul [5] Equinox [6] Satellite [7] 26-2 [8] Body And Soul (alt take) |
John Coltrane (ts, ss) McCoy Tyner (p) Steve Davis (b) Elvin Jones (ds) |
| 「My Favorite Things」からのアトランティック・マラソン・セッション(?)、最後のアルバムは、[1] [4](あと[8])を除いてコルトレーンのオリジナルで、スタンダードあり、ソフトなバラードあり、ブルースあり、妙なコード進行の曲ありで、しかしながら内容は散漫になっていない。肝心のコルトレーンのプレイも低音から高音までを使いきったもので、この時期のスタイルの演奏を満喫できる。特に [5] では、後年のブヒブヒしたフレーズの芽生えも見え隠れ。この時期の3枚のセッションの中で、どれか1枚をということであればコレを推奨。ところで「My Favorite Things」「Coltrane Plays The Blues」とあわせたこのニュー・カルテットの最初のセッション、正直言うとあまり好きじゃない。モワモワしたベースの録音状態が個人的にはダメ(しつこい)というのを別にしても、奏法とサウンドの両面において過渡期で、中途半端に思えてしまう。リラックスしたプレイが聴きたければプレスティッジ時代のアルバムを、激しくハードなプレイが聴きたければインパルスのアルバムを手にしてしまう。ただ、過渡期には過渡期の面白さがあるのも確かで、コルトレーンの変遷を追うのにアトランティック時代のアルバムは当然無視できない。(2006年6月11日) | ||
| Ole | ||
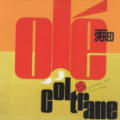 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★★☆ トレーン入門度:★★★★☆ 評価:★★★★☆ |
[Recording Date] 1961/5/25 [1] Ole [2] Dahomey Dance [3] Aisha [4] Untitled Original Ballad |
Freddie Hubbard (tp) John Coltrane (ts, ss) George Lane <Eric Dolphy> (fl, as) McCoy Tyner (p) Reggie Workman (b [1]-[3]) Art Davis (b except [3]) Elvin Jones (ds) |
| アトランティック時代最後のアルバム。最大の聴きどころはもちろんタイトル曲の [1] 。スパニッシュ・タッチの長尺演奏で、ツワモノのフロント3人衆がソロを回す。それぞれに聴きどころがある中、特に2回目のコルトレーンのソロが素晴らしい。ソプラノも完全に板に着いた印象。この曲だけでなく、コルトレーンのアドリブは一段と進化していてインパルス時代のフィーリングに近づいている。[1][2] では2ベースがなかなか効果的で特にアート・デイヴィスの変幻自在のベースワークが際立っている。左がワークマン、右がデイヴィスとなっているので、聴き比べを楽しむのであればヘッドフォンがお勧め。[1] が目立つので他の印象が薄くなりがちではあるけれど、[3][4]は甘さを抑えたクールで引き締まった、尚且つ情感も内包したバラードで聴き惚れてしまう。コルトレーンが自分のグループを率いるようになってから、このような編成のコンボというのは後にもないし、エリック・ドルフィーとの唯一のスタジオ録音という点でも貴重なセッション。(2006年6月16日) | ||
