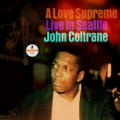ロック・ファンのためのジャズ案内のヘッダー
Rock Listner's Guide To Jazz Music
John Coltrane(65-67)
| Live In Seattle | ||
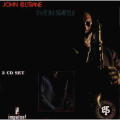 曲:★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★ トレーン入門度:★★ 評価:★★★★☆ |
[Recording Date] 1965/9/30 Disc 1 [1] Cosmos [2] Out Of This World [3] Body And Soul [4] Tapestry In Sound Disc 2 [5] Evolution [6] Afro Blue |
John Coltrane (ts, ss) Pharoah Sanders (ts) Donald Rafeal Garrett (bcl, b) McCoy Tyner (p) Jimmy Garrison (b) Elvin Jones (ds) |
| 至高のカルテットが飽和に至り、ついにコルトレーンはついにもう1人の管楽器奏者を加えて更なる別世界へと挑む。その追加された異分子、ファラオ・サンダースは、コルトレーンよりも更にフリーキーに不快な音を撒き散らしてコルトレーンの要望に応える。恐らく、現状を打破するには自分を刺激する相手が必要だったに違いなく、その試みは成功していると言えるでしょう。しかし、打破した先が多くの人にとって理解できるものであったかどうかはまた別の話。これ以降、フォー・ビートのような定速リズムを刻むことはほとんどなくなり各人が与えられたスペースを自由に演奏するというスタイルにどんどん変貌。そして、美しいとか良い曲であるとかそういう観点では聴けない、重く雄大で混沌とした音空間を創造し、聴き手はこれに身を任せることができるか否かを問われるようになってくる。グループとしての一体感や疾走感など眼中になく、呪術的ともいえるムードが延々と続く様や、[5]の冒頭における3人による雄叫びなど、かなり聴き手を選ぶことは間違いない。解体された[3]にはこれまでのカルテットの演奏とは別の美しさがあると思うし、フリーキーになったとはいえ、エルヴィンが炸裂しマッコイが疾走する[5]の後半や[6]などに至高のカルテット最後の輝きを放っているところが聴きどころ。それにしても合計で2時間超のこの2枚組、通して聴くとグッタリと疲れる。(2006年7月8日) | ||
| OM | ||
 曲:★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★ トレーン入門度:★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1965/10/1 [1] OM |
John Coltrane (ts, ss) Pharoah Sanders (ts) Donald Rafeal Garrett (bcl, fl) Joe Brazil (fl) McCoy Tyner (p) Jimmy Garrison (b) Elvin Jones (ds) |
| お経から始まり、まるで獣の悲鳴が幾十にも重なるかのような混沌とした音で始まる冒頭で引いてしまうリスナーも少ないと思われる、宗教色が強いとされている作品。途中で「オ〜ム」という低いうめき声が混じったり、通常のジャズでは使われない打楽器も聴こえてきたりしながらも、フォー・ビートのリズムもあったり、ダークなトーンながらマッコイのジャズ・ピアノも出てくるし、リズム隊もお馴染みのメンツとあって全体的にはそれほど宗教色一辺倒という印象は受けない。ただし、音楽が聴きやすいかどうかはまた別の話で、普通のジャズ・ファン、いや音楽ファンを寄せ付けないアクの強さと激しさを持っていて、後期コルトレーンの中でも難解さが際立っている。こんなの音楽じゃない、マスターベーション的集団フリー・ジャズという意見はごもっとも。僅か29分、そして1曲だけとはいえ僕はこの濃密なカオスに身を任せることに大きな悦びを感じてしまう。「A Love Supreme」を理解できない僕がなぜこれを肯定できるのか。それは恐らく行くところまで行ってしまっているからに違いない。(2006年7月1日) | ||
| Kulu Se Mama | ||
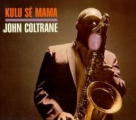 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★ コルトレーン入門度:★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1965/10/14 [1] [4] 1965/6/10 [3] 1965/6/16 [2] [5] [6] [1] Kulu Se Mama(Juno Se Mama) [2] Vigil [3] Welcome [4] Selflessness [5] Dusk Dawn [6] Dusk Dawn (alt take) |
[1] [4] Juno Lewis (vo, perc) John Coltrane (ts) Pharoah Sanders (ts, perc) Donald Rafeal Garrett (bcl, b, perc) McCoy Tyner (p) Jimmy Garrison (b) Elvin Jones (ds) Frank Butler (ds, perc) [2] John Coltrane (ts) Elvin Jones (ds) [3] [5] [6] John Coltrane (ts) McCoy Tyner (p) Jimmy Garrison (b) Elvin Jones (ds) |
| 「OM」と同じようにアフリカに最も傾倒した曲と言われる[1]は、しかし比べて聴いてみるとイメージが少し違う。こちらは音楽の中心にあるのがジュノ・ルイスの歌になっているから。成り立ちを大雑把に言うならば、コルトレーンがルイスの音楽に共感し、自分のグループでルイスの音楽を表現したいという衝動を基点としているため、コルトレーンがソロをガンガン吹きまくるシーンはなく音楽の一部としての役割に徹している。むしろ演奏で目立つのはノイズを撒き散らすファラオの方で、音楽じたいも後のファラオの「Karma」あたりでこの方向性が引き継がれている感じがする。ギャリソンとエルヴィンのリズムは重く単調でアフリカっぽさ出ている。そんなルイスとコルトレーンの音楽の融合であることこそがこの曲の聴きどころであり、ソロが云々という話は実はここではあまり重要ではない。同じ日のセッションの[4]ではルイスは打楽器に専念、フォービートも織り込んだその演奏は重苦しさが若干薄れ、通常のコルトレーン・ミュージックそのものである分、楽しめるけれど、この曲でもソロを吹きまくるシーンはなく、後半にファラオとの同時進行での吠え合いがある程度。[2][3]は輸入盤「Transition」収録と同じ、[5] は「Living Space」収録と同じというわけで、あくまでも[1][4]を聴くためのディスク。(2009年1月31日) | ||
| Meditations | ||
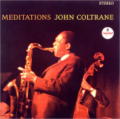 曲:★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★ トレーン入門度:★★ 評価:★★★★☆ |
[Recording Date] 1965/11/23 [1] The Father ANd The Son And The Holy Ghost [2] Compassion [3] Love [4] Consequences [5] Serenity |
John Coltrane (ts) Pharoah Sanders (ts) McCoy Tyner (p) Jimmy Garrison (b) Elvin Jones (ds) Rashid Ali (ds) |
| 2ヶ月前に至高のカルテットで録音してはみたものの、お蔵入り、その楽曲を 2人メンバーを加えて再構築したものが本作。「Live In Seattle」や「OM」で顕著なように既に定型リズムとは無縁の、ジャズとは言い難いフリーキーな演奏が繰り広げられている。曲も繋がっていて形式などないに等しいことからアナログで言うA面とB面の実質2曲に聴こえる。そしてこの時期のコルトレーンのプレイは、そんな音世界でこそ魅力を発揮。「First Meditations」より圧倒的にテンションの高い演奏が聴ける。この混沌とした騒音ワールドにファラオ・サンダースとラシッド・アリがまたよく合っていて、反面、重く躍動感のあるグルーヴ感が持ち味エルヴィンがもう合わなくなっていることも露呈。エルヴィンこそが最高のドラマーと信じて疑わない僕でも、ここで創造されている騒音の洪水にはドラムによるグルーヴを必要としておらず、エルヴィンのコルトレーン・ミュージックへの役割は終わったのだと感じる。曲や演奏を楽しむというより混沌を極めた音世界にただただ圧倒されるのが正しい聴き方。(2006年6月19日) | ||
| Live At The Village Vnguard Again | ||
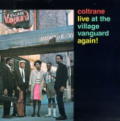 曲:★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★ トレーン入門度:★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1966/5/28 [1] Naima [2] Introduction To My Favorite Things [3] My Favorite Things |
John Coltrane (ts, ss, bcl) Pharoah Sanders (ts, fl) Alice Coltrane (p) Jimmy Garrison (b) Rashid Ali (ds) Emanuel Rahim (perc) |
| ついにマッコイとエルヴィンが脱退、フリー・ジャズ色が一層強くなった新カルテット(+1)によるライヴ盤。収録曲はおなじみの曲ながら、ほとんど解体されてしまっていて原型を留めていない。ファラオはノイジーな音を撒き散らし、アリスは現代音楽的な音を入れ込む空間を求め、アリはただただ小刻みに叩き続け、ラヒームが効果的にスパイスを効かせる。ここにはもうビートやグルーヴというものは存在しない。聴きやすいとか心地よいとかはもう関係ない世界に行ってしまっている。ウケを狙うとかそういう俗性とは無縁の道を進んでいながら、あえて古くからのレパートリーを演奏しているのはもう曲なんてどうでも良くなったからでしょう。コルトレーンの音色は徐々に低音域が増えてきて上に下にと忙しい。更に太くなっていくのはもう少し先のこと。また、ここではファラオ・サンダースがかなりフィーチャーされているのも特徴。楽器のクレジットはちょっと疑問があって、ファラオがブヒャーとやっている背後で僅かに聞こえるフルートは一体誰なんだろう。反面、コルトレーンにクレジットのあるバスクラの音は僕には聴き取れない。(2007年7月1日) | ||
| Last Performance At Newport July 2, 1966 | ||
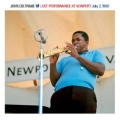 曲:★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★ トレーン入門度:★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1966/7/2 [1] My Favorite Things [2] Welcome [3] Leo/Closing Accouncement |
John Coltrane (ts, ss, per) Pharoah Sanders (ts, piccolo, per) Alice Coltrane (p) Jimmy Garrison (b) Rashid Ali (ds) |
| 恐らくCDとしては初公開と思われる音源がセミ・オフィシャル盤として登場。音質は相応にコモっているものの、今頃出てきたというわりにはまずまず聴けるレベル。もっともこの時期のコルトレーン・グループに音質はあまり関係なく、前後のアルバムと同等に激しく展開される音楽を浴びることに意義がある。ファラオ・サンダースの咆哮もいつもどおりで、しかし出番はやや少なめ、その分コルトレーンを楽しめる。わかっていることとはいえ、アリス(最後に旧姓で紹介されている)のピアノはあんまり面白くない。この混沌とした激しいサウンドと、さわやかな装いのジャケット写真とのギャップがなんだかちょっと笑える。このメンツのアルバムは多数あり、あえてこのブートレグもどきに手を出すほどの価値があるか疑問ではあるけれど、この時期のコルトレーン・ミュージックが好きな人ならば楽しめる。(2009年7月18日) | ||
| Live In Japan | ||
 曲:★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★ トレーン入門度:★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1966/7/11 1966/7/22 Disc 1 [1] Afro Blue [2] Peace On Earth Disc 2 [3] Crescent Disc 3 [4] Peace On Earth [5] Leo Disc 4 [6] My Favorite Things |
John Coltrane (ts, ss, as, per) Pharoah Sanders (ts, as, bcl) Alice Coltrane (p) Jimmy Garrison (b) Rashid Ali (ds) |
| 38分、26分、54分、25分、44分、57分。これは、この4枚組セットCD各曲の演奏時間。ファラオ、アリス、アリ中心のグループによるコルトレーンのアルバムは当時まだ発売されていなかったそうで、初めて接した日本のオーディエンスはこの音楽をどう受け止めたのだろう?と思わずにはいられない。それでも、拍手や歓声を聞いている限りでは好意的。この難解な音楽がこの時代の日本で受け入れられていたことに少し驚きを感じる。音楽的には前後の録音の流れに沿ったもので、アリスとアリの能力が前任者よりは落ちるなと思えるところまでよくわかってしまうところなどはライヴならでは。[1][3]は元の曲のメロディもところどころ出てきて比較的まとまりのある演奏。[2][4]は一定のテンポを持たない曲で激しさよりも混沌さを押し出したもの。[5]は「Interstellar Space」の同曲というよりは「Meditations」の入り部分と同じで演奏も同じ傾向。[6]は[3]同様、ギャリソンの13分以上にも及ぶ冗長なベース・ソロから始まるお得意の曲。この作品全体に言えることしてファラオ・サンダースが例のノイジーな音を抑え気味にしていて、普通の(?)フリーク・トーンで音楽的に勝負しているように感じる。従って[6]にしても「Live At The Village Vnguard Again」とは内容的にはだいぶ違う。通して聴いたらグッタリするような演奏とボリュームで後期のコルトレーン好きでもコアな人にしか勧められない。モノラルで広がり間に乏しい録音のせいもあるのか晩年のコルトレーン作品の中では力技で押し切ったとい印象はなく、少しスッキリと落ちついた演奏に聴こえる。体調が悪かったという説は本当だったのかもしれない。(2007年7月8日) | ||
| Offering: Live At Temple University | ||
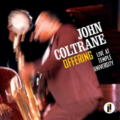 曲:★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★ トレーン入門度:★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1966/11/11 Disc 1 [1] Naima [2] Crescent Disc 2 [3] Leo [4] Offering [5] My Favorite Things |
John Coltrane (ts, ss, fl, vo) Pharoah Sanders (ts, piccolo) Alice Coltrane (p) Sonny Johnson (b) Rashid Ali (ds) Algie Dewitt (bata drum) Additional musicians: Arnold Joyner (as [2]) Steve Knoblauch (as [5]) Umar Ali (per) Robert Kenyatta (per) Chales Browwn (per) |
| この音源は当時ラジオで放送された音源で、ブートレグでは既に知られた存在。ブートレグではエアチェック故に[1]の最初のコルトレーンのソロが終わったところでラジオのアナウンスが入る。この音源の問題は、音質がクリアなのに楽器のバランスが悪く、サックスの音は明瞭に捉えている代わりにピアノやドラムは遠めで、ジミー・ギャリソンの代役が弾いているベースに至ってはほとんど聴こえないところにあった。これによりグループとしてのダイナミクスが掴みきれなくなり、スケールの小さな音楽に聴こえてしまう。さて、この音源は世界的コルトレーン研究家で有名な藤岡靖洋氏が音源所持者と出会ったことから始まり、めでたくインパルスのロゴが入ってオフィシャル化されたもの。したがって上記のアナウンスは編集でカット、初出で[4][5]が追加されている。初回プレス限定とされる藤岡氏の解説を読むと、音源との出会いや、この時の演奏会に至る経緯がわかり、よりこの音源の理解を深めることができる。氏の解説は精神性の解釈などの話になると主観が過ぎて突っ走り気味で辟易する時があるけれど、この解説は事実解明のために取材をして充実させたもので有益。その解説によると、地元のパーカッション奏者のジャム・セッションにコルトレーンが入り浸るようになり、そこから3人をここで呼び出し、更には地元学生のアルト・サックス奏者を参加させている。大学でのコンサートということで緩く考えていたのかと思うと、[3][5]でコルトレーン自身の雄叫びを上げるほど気持ちが入っていたようだ。その増員した打楽器奏者は録音のせいでよく聴き取れず、効果は不明、アルト・サックスは残念ながら力量は大したことがなく、この夜、コルトレーンが意図したことはこのCDからは掴めない。初音源化の[4][5]もそれほどハイテンションというわけではなく、そもそもこのCDは資料としての価値以外はあまり見出だせない。オフシャル化によって音質が大幅に向上しているというわけでもなく、音のバランスも従来と変わらず。それにしても今どきの技術ならもう少し音のバランスをなんとかできなかったものだろうか。聴くための音源としては少々厳しい。聴きどころは、同日録音のドン・チェリー「Where is Brooklyn」のレコーディング後に駆けつけ、2曲めからの参加になったファラオのノイズマシンぶりがいつもより一段と激しいところかもしれない。(2014年7月21日) | ||
| Stellar Regions | ||
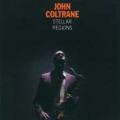 曲:★☆ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★ トレーン入門度:★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1967/2/15 [1] Seraphic Light [2] Sun Star [3] Stellar Regions [4] Iris [5] Offering [6] Configuration [7] Jimmy's Mode [8] Tranesonic [9] Stellar Regions (alt take) [10] Sun Star (alt take) [11] Tranesonic (alt take) |
John Coltrane (ts) Alice Coltrane (p) Jimmy Garrison (b) Rashid Ali (ds) |
| コルトレーンが鬼籍に入ってから28年も後になってリリースされたアルバム。ここでは静謐なムードの中にも表現の極地を追求するコルトレーンの姿が捉えられている。残されたアルバムを見る限り、晩年のコルトレーンは特にスタジオ録音においてはよりシンプルな編成での演奏を好んだように思える。このアルバムもひさびさのカルテット。しかし、ここでは至高のカルテットのような躍動感で圧倒するのではなく、タイトでフリーキーに、そして引き締まった美しさをもって演奏されている。特にピアノは浮遊感のある美しい演奏で、このアルバムで初めてアリスの良さを感じた次第。全体的にはヘヴィでダークであるものの、これ以前のひたすら重苦しい雰囲気と比較するとどこか突き抜けたかのような、まるで希望の光が仄かに差したかのような明るささえ僕は感じてしまう。一方で、[5][6][8] のような、低い音域でブヒャブヒャ吹きまくるフリー・ジャズそのものと言っても良いアグレッシヴな演奏をはじめ、コルトレーンのプレイは野生的、音は硬質で猛烈に激しい。ファラオ・サンダース抜きで純粋に晩年のコルトレーンの激烈なテナーを満喫するには最適のアルバムで、ラシッド・アリの熱演も含めてカルテットとしてのまとまりも素晴らしい。親しみやすさが殆どないのは改めて言うまでもないけれど、晩年の作品の中ではテナーの表現が比較的ストレートで曲も短く、ある意味聴きやすいのも特徴。(2006年7月1日) | ||
| Interstellar Space | ||
 曲:★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★ トレーン入門度:★ 評価:★★☆ |
[Recording Date] 1967/2/22 [1] Mars [2] Venus [3] Jupiter [4] Saturn [5] Leo [6] Jupiter Variation |
John Coltrane (ts, bell) Rashid Ali (ds) |
| ライヴでの多人数編成とは一転、ラシッド・アリとのデュオ・アルバム。低音でブヒャブヒャと吼え、中音でメロディがわずかに顔を覗かせ、高音で悲鳴をあげるというこの時期のスタイルによる演奏が全編で展開されていて晩年のコルトレーンのサックスを純粋に楽しむには絶好のアルバム。ただし、54分間聴き通すのはちょっと辛い。それは決して演奏が悪いからではなく、デュオという編成の表現バリエーションにはやはり限界があるから。僕がロックやジャズに惹かれる理由は5人前後で演奏されるからであり、そのくらいの人数で織り成す音楽は個人の表現とグループとしての表現のバランスが取れていて、状況によってどちらの美点も打ち出せるという面白みがあると思っているからである。そういうわけでデュオやソロが苦手な僕にとってこのアルバムは「たまには変わったのを聴いてみるか」という箸休め的なものに留まる。ただ、誤解なきように言っておきたいのは、コルトレーンの演奏そのものは壮絶かつ激烈で素晴らしいということ。(2006年7月1日) | ||
| Expression | ||
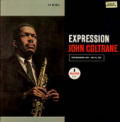 曲:★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★ トレーン入門度:★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1967/2/15 [2] [3] 1967/3/7 [1] 1967/Spring [4] [1] Ogunde [2] To Be [3] Offering [4] Expression |
John Coltrane (ts、fl [2]) Alice Coltrane (p) Jimmy Garrison (b) Rashid Ali (ds) Pharoah Sanders (piccolo [2]) |
| 全体に静謐なムードに支配された生前にリリースされた最後のスタジオ録音。リズムはもはやコルトレーンのサックスを彩るために存在しているにすぎず、決して先導することはない。テナーの音は激しさの中に落ち着きのようなものまで垣間見え、悟りの境地に至ったかのよう。フルートを初めて吹いた(しかもオーバーダビングで2本分の) [2] にその雰囲気は顕著で、重々しさの中に清々しささえ感じることができる。晩年のコルトレーンは音楽としてどう聴くかというよりは、その発せられる音をどう受け止めるかという姿勢を聴き手に要求するものであったと思うけれど、このアルバムはそのような要素を内包しつつ、身を委ねて聴くことができる。激しさ、混沌さ、重さを追求し続けてきたコルトレーンがこのような方向に向かい、生きていたら次は一体どこに向かったのか、70年代のフュージョン・ムーブメントにどう立ち向かったのかという想像を掻き立てずにはいられない。(2006年7月1日) | ||
| The Olatunji Cencert: The Last Live Recording | ||
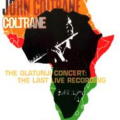 曲:★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★ トレーン入門度:★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1967/4/23 [1] Introduction By Billy Taylor [2] Ogunde [3] My Favorite Things |
John Coltrane (ts, ss) Pharoah Sanders (ts) Alice Coltrane (p) Jimmy Garrison (b) Rashid Ali (ds) Algie DeWitt (bata drum) Jumma Santos (per) |
| このアルバムは、今のところコルトレーン生前最後の音源であることこそに意義があり、だからこそ音が悪くても存在価値を認められているのかと思っていた。だから晩年のコルトレーンの特徴である過激な演奏が詰まっているのだろうというくらいの認識で最後まで手を出さずに静観していた。しかし、その認識は間違いだった。この音楽は他のどの音楽とも違うし、晩年のコルトレーンの音楽の一環として聴くことすらできない。いや、ここにあるのは音楽というものを超越した、ひたすら発散される音世界であり、ひとつの表現だとしか言いようがない。過激などといった言葉を使うとそれが嘘になってしまう、ただただ圧倒的な音の洪水。人間、ここまで行ってしまうことができるのだという感動。音質の悪さすらその演出になってしまっているこのアルバムは、ひとつの奇跡と言えるかもしれない。この世に存在するすべての音楽とは異次元の何か。それがこの記録。(2006年8月8日) | ||
| Cosmic Music | ||
 曲:★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★ トレーン入門度:★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1966/2/2 [1] [3] 1968/1/29 [2] [4] [1] Manifestation [2] Lord Help Me To Me [3] Reverend King [4] The Sun |
[1] [3] John Coltrane (ts, bcl) Pharoah Sanders (ts, picc) Alice Coltrane (p) Jimmy Garrison (b) Rashid Ali (ds) Ray Appleton (perc) [2] [4] Pharoah Sanders (ts, picc) Alice Coltrane (p) Jimmy Garrison (b) Ben Riley (ds) |
| [1][3] はコルトレーン生前の演奏、[2][4] はコルトレーンが鬼籍に入ったあとアリス主導(作曲もアリス)で録音された演奏という構成。これだけ聴くと、余りモノと主導者抜きの出がらしの寄せ集めのように見えてしまう。だが、まったくそんなことはない。生前の [1][3]の激烈で濃厚な演奏は同時期の他の演奏とまったく遜色のないクオリティ。それだけで喜べるが、予想に反して [2][4] も充実している。もちろん、圧倒されるような凄みはないものの、コルトレーン・ミュージックを見事に継承しているだけでなく、アリスのピアノがより生きた演奏になっていて聴き応えがある。1枚のアルバムとして聴いて何の違和感もなく、コルトレーンの音楽を聴く作品として十分に完成度が高い。(2016年8月5日) | ||
| Jupiter Varidation | ||
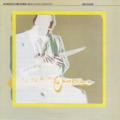 曲:★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★ トレーン入門度:★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1967/3/7 [1] 1966/2/2 [2] 1967/2/22 [3] [4] [1] Number One [2] Peace On Earth [3] Jupitor (Varidation) [4] Leo |
[1] John Coltrane (ts) Alice Coltrane (p) Jimmy Garrison (b) Rashid Ali (ds) [2] John Coltrane (ts) Pharoah Sanders (tambourine,wooden-fl) Alice Coltrane (p) Charlie Haden (b) Rashid Ali (ds) Ray Appleton (perc) [3][4] John Coltrane (ts, bells) Rashid Ali (ds) |
| [1]はコルトレーン最後のカルテットによる演奏で「Expression」収録の"Ogunde"と同日の録音。[2]は「Cosmic Music」収録の2曲と同じく66年2月2日のセッションから。この曲は後にアリス・コルトレーンの手によるストリングスを加え、ベースをチャーリー・ヘイデンに差し替えて「Infinity」というアルバムでリリースされていたらしい。ここに収録されているのはストリングスを排除して、ヘイデンのベースは差し替えたままという中途半端な状態のもの。[3][4]は「Interstellar Space」と同じ日のセッションからで、今ではその「Interstellar Space」にもボーナストラックとして収録されているもの。ただし、54分をすべてデュオで聴かされるよりも、こうして2曲だけ聴く方が集中できるし、ひとつの趣向として楽しめる。成り立ちは少々中途半端なアルバムではあるけれど、1枚通して聴くと晩年のコルトレーン・ミュージックにどっぷり浸かることができるので聴き終えたあとの充実感がある。(2016年8月5日) | ||