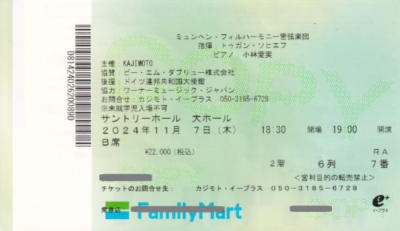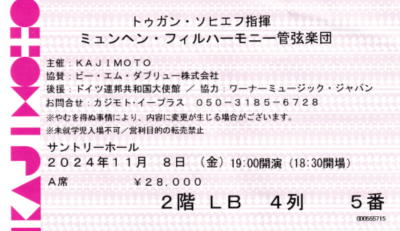���b�N�E�t�@���̂��߂̃W���Y�ē��̃w�b�_�[
Rock Listner's Guide To Jazz Music
����ς艹�y�̓��C���I
����܂łɍs�����R���T�[�g�̑S�L�^�ł��B�l���̑啔�������y�D���Ƃ��ĉ߂����Ă������Ƃ�����A�����L�����Ă��Ă��܂��܂����B����ȂƂ�����܂ߎ����̉��y�j��\���Ă�Ǝv���܂��B �L�O���ׂ����R���T�[�g�̓N�C�[���B�m���Ȃ͕����ق̌�납��3��ڂ��炢�A�X�e�[�W���Ƃ炷���̍��ȏƖ������ォ�猩��悤�Ȍ`�ł����Ԃ��������Ƃ��v���o���B���̂���́A�����ȂƂ��뉹�y�̂��ƂȂ�Ă킩���Ă��Ȃ��������A�����t���ėǂ������������킩��Ȃ������B�����A�����Ă���N�C�[���������ɋ��邾���ŗǂ������B�����čŏ�����Ō�܂ʼn̂��Ă����B����ŏ\���B�������Ȃ�̂̂��ƂȂ̂Ƀt���f�B�̃A�N�V�������n�b�L���Ǝv���o�����Ƃ��ł���B���ꂪ�Ō�̗����B�ς邱�Ƃ��ł��Ė{���ɗǂ������B |
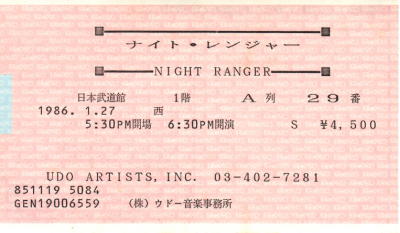 ���Z���̂���͊��S�Ƀn�[�h���b�N���m�������B�����ē����l�C�Ⓒ�������̂��i�C�g�E�����W���[�B�p�������Ȃ���W�F�t�E���g�\��������ȂɃ\��������Ă��邱�Ƃ����C�����ς�܂Œm��Ȃ������B���ƁA�o���Ă���̂��W���b�N�E�u���C�Y������܂Ƃ��Ƀx�[�X��e���Ă��Ȃ��������Ɓi��j�B���v����B���o���h���������ǂ��̃O���[�v�͂����Ȃ���R�������Ǝv���B |
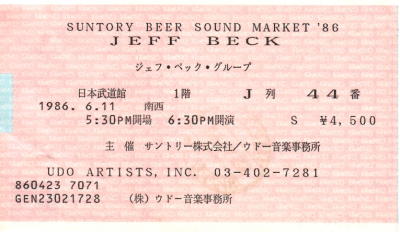 �A���o���uFlash�v�̂Ƃ��̃c�A�[�B���R�[�h�Ɠ��������f�B�����t������̂ł͂Ȃ��Ă����������̂���v���C������Ƃ����̂����߂ċ����Ă��ꂽ�̂��W�F�t�E�x�b�N�������B����ȃ��b�N�X�ł��V�����_�[�E�L�[�{�[�h������������E�n�}�[�͂��̂������J�b�R�悩�������A�������̂Ŕ��͂̃h����������T�C�����E�t�B���b�v�X�����������B�����Ƃ��e�N�j�b�N�̖ʂł��̑O�Ɋς����W���[�E�e�C���[�ƃP���[�E�P�C�M�[�Ɣ�r����̂�������������ǁB���ʁA�W�~�[�E�z�[���͐��Œ����ƃV���{�������B�����n�[�h���b�N�ȊO�Ŗ����ɂȂꂽ�̂̓W�F�t�����������B |
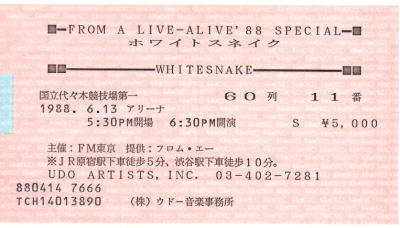 �A���o���uWhitesnake�iSurpens Albus)�v���S�Ăő�q�b�g���Ă����Ƃ����đ吷��オ��ŊςĂ������Ƃ��v���o���B�ł��A�����o�[���G�C�h���A���E�o���f���o�[�O�A���B���B�A���E�L�����x���A���f�B�E�T�[�]�A�g�~�[�E�A���h���b�W�Ƃ����A���o���Ƃ͂���Ⴄ��Ԃ�B���FM�ł��������ꂽ���̂����߂Ē����Ă����̃w���B�E���^���E�O���[�v�ɂȂ��Ă������ƂɃK�b�J�������B�J���@�[�f�C���̃��H�[�J�����G�ŁA���v���Ƃ����������ƂȂ����C���������B |
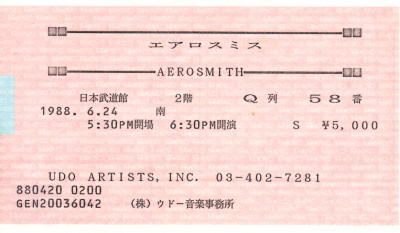 �I���W�i���E�����o�[�ŕ��������G�A���X�~�X���uPermanent Vacation�v�ŃZ�[���X�I�ɂ����������Ƃ��̗��������B�Ƃɂ������������B���b�N���E���[�����Ă���̂͂����������Ƃ������Ƃ�̂ŋ����Ă��ꂽ���C���������B�W���[�E�y���[��������Ȃ��ău���b�h�E�E�B�b�g�t�H�[�h�����[�h�E�M�^�[���R�e���Ă邱�Ƃ����߂Ēm�����B�g���E�n�~���g���̃x�[�X���J�b�R�ǂ������i�x�[�X���N�b�L���������鉹�̗ǂ��ɂ��������j���A�W���[�C�E�N���C�}�[�̃h���������ă��b�N���E���[���炵�����͂��������B���܂Ŋς����ň�Ԑ��݂����������C���B���̂���A�G�A���͂܂��D�����m�̂��߂̃o���h�������Ȃ��B |
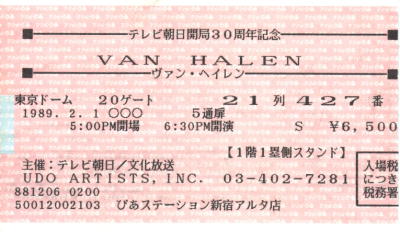 �T�~�[�E�w�C�K�[������̃��@���E�w�C�����̃��C���B�����h�[���Ń��C�����ς��̂͂��ꂪ���߂Ă������B���܂�̉��̈����Ƀr�b�N���B�J���O�ɗ���Ă����f�t�E���p�[�h�̋Ȃ��u�˂��˂��A������ăo���E�w�[�����H�v�Ɛu���Ă����l�[�`���������āA�����A���ꂾ���̋K�͂̃R���T�[�g���ƃt�@������Ȃ��l���吨����Ȃ��Ǝ��������̂����������B�̐S�̓��e�͂��܂�o���Ă��Ȃ��B���@���E�w�C�����𗝉��ł���悤�ɂȂ����̂͂��ꂩ�牽�N����ɂȂ��Ă���B |
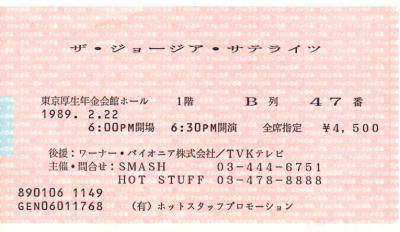 �V���v���ɂ܂�Ȃ��A�����J�암�n���b�N�o���h�A�W���[�W�A�E�T�e���C�c�B���v���ƂȂ�ł���ȃo���h������Ȃɔ��ꂽ�̂��s�v�c�Ŏd�����Ȃ��B���̐����́A�g����N���[�Y�剉�̉f��u�J�N�e���v�̃T���g���ɋȂ����قǂ������B����ȂɎ��ߋ����Ń��C�����ς��̂͏��߂Ă������Ƃ����x�т��L���Ɏc���Ă���B�o���h�̉����w���B�ł��Ȃ�n�[�h���b�N�I�������BB�����������ǁA�����o���h�������Ȃ��B���̌�A�l�C���}�~���B���U���Ă��܂����̂��c�O�B�ߏ��̃N���u�ʼn��t���Ă����A�������q�b�g�����܂��A����Ӗ��A�����J���E�h���[����̌����Ă����o���h�������Ǝv���B |
 �L���R���V�A���ŊJ�Â��ꂽ���b�N�E�t�F�X�e�B�o���AKIRIN BEER'S NEW GIGS�B���̉��ł��J�Â�����ɂ���ďo���҂�������B���̓��̏o���҂Ŋo���Ă���̂̓��`���[�h�E�}�[�N�X�A�`���b�N��x���[�B �ŏ��̃o���h�̓X�e�B�[���E���J�T�[�E�o���h�B���J�T�[���g�����H�[�J�����S���B�o���h�̃��x���̓C�}�C�`�������B 2�Ԗڂ́A�����A�����J�ő�q�b�g���Ă����o�b�h�E�C���O���b�V���B�q�b�g���������������ɂ��A�����J���ȃ��b�N�E�O���[�v�ŁA�O�̃o���h�Ɣ�ׂ�Ƃ����Ƃ������H�[�J���X�g�i�W�����E�E�F�C�g�j�����āA����ɂ���ăo���h�����܂��Č����邱�Ƃ�F���B�j�[���E�V���[���̃M�^�[�͂Ȃ�قǏ�肩�����B 3�Ԗڂ́A���̓��̏o���҂̒��łِ͈F��10�l�g�t�@���N�E�O���[�v�A�^���[�E�I�u�E�p���[�B�����L�����A�����O���[�v���������āA���̃X�e�[�W�͗��̊ј\�B�����Ċy�����B���̃z�[��������ȂɃJ�b�R�����Ƃ́B���̌サ�炭�A���̃O���[�v�ɂ̓n�}�b���B���̓����߂ăA���R�[���̗v�����o���قǃp�t�H�[�}���X�͑f���炵�����̂������B 4�Ԗڂ͂��ړ��ẴW�F�t�E�x�b�N�B���{��s�����������uGuitar Shop�v�����[�X����m����T�Ԃ��o���Ă��Ȃ����������������ƋL�����Ă�B�e���[��{�W�I�͐��r�h���}�[�Ƃ��Ė��O�����͒m���Ă��ď���ɂ��������e��z�����Ă�����A���f���̂悤�ȃ��b�N�X�ł��܂�̃J�b�R�悳�Ƀr�b�N���B�����Ĕ��͂̃h�����ɂ����������|���ꂽ�B����Ńg�j�[�E�n�C�}�X�͂��܂�X�e�[�W�����ȃ~���[�W�V�����ł͂Ȃ��Ɗ������B�䕗�ڋ߁i���������͒��~�������j�ɂ��A�r�����獋�J�B���ԔG��ɂȂ�ƊJ�������ăn�C�ɂȂ�Ƃ����o���������̂������v���o�B �Ō�́A���J�T�[�A�V���[���������� "Going Down" �����t�B���H�[�J���̓��J�T�[�i���̓��̌����ł̓W�����E�E�F�C�g���̂����炵���j�B���Ղ�Z�b�V�����ƂȂ��đ�c�~�B |
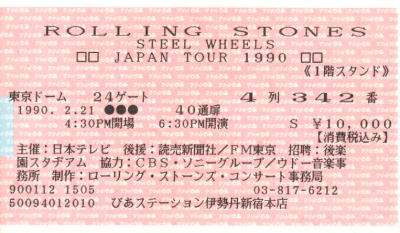 �X�g�[���Y�͌͂ꂷ���Ă��Čl�I�ɂ͂��܂�D���ł͂Ȃ��B����ł������������̘b�萫�i�����h�[����10�A�������j������A����ς萶�ŊςĂ݂����Ǝv���čs�����B���t�g�̃|�[�����烉�C�g�Ƀ|�[���܂ł��X�e�[�W�Ƃ����o�J�ł����ɋ���������ǁA�{���X�g�[���Y�̓V���v���ȃ��b�N���E���[���E�o���h�ŁA���܂�ɂ��V���E�A�b�v���ꂽ�X�e�[�W�Ɉ�a�����o�����L�����B1�ȏI��邲�Ƃɒ����C���^�[�o�����������͍̂̂����������̂��X�e�[�W�̍\�����Â������̂��B |
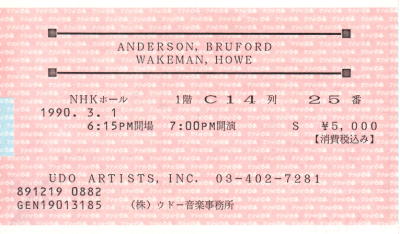 �ڍׂ́AYES�̍��ڂɂ���uAn Evening Of Yes Music Plus�v�Q�ƁBNHK�z�[���͉����ǂ������B |
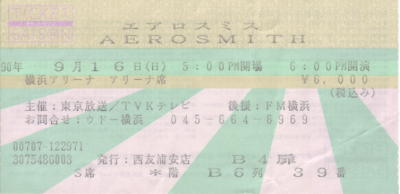 �O��̗��������Ńm�b�N�A�E�g���ꂽ�G�A���X�~�X�B���������҂��čs�����B�������A�V�����A���o�����o�����Ƃ������Ă��Â����p�[�g���[�������A�R���T�[�g���O����Z���A���ʂ̃��b�N�E�R���T�[�g�ɂȂ��Ă��܂��Ă����B�O��̍D��ۂ������̒��ő�������Ă��܂����̂�������Ȃ�����ǁA��ۂ͂��Ȃ蔖���B���ƁA���l�A���[�i�͉������������B |
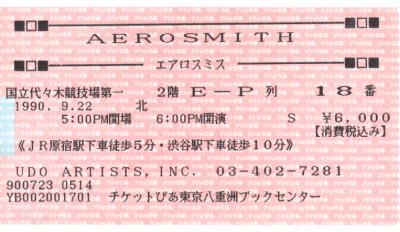 �O��̗������������܂�ɂ��f���炵���A�������ƂɃZ�b�g���X�g����������Ƃ���A���̂Ƃ��̓��{�c�A�[��2�������`�P�b�g���w���B�����ǁA�Z�b�g����X�g�͂قƂ�Lj��Ȃ������L��������B�B��o���Ă���̂� "Toys In The Attic" �����̓��͒��������Ƃ��炢�B |
 80�N��O���ɑ�q�b�g���Ă����G�C�W�A���Č����B�X�e�B�[���E�n�E�ɑ����čݐЂ��Ă����̂̓p�b�g�E�X���[���ŁA���̐��i�͂��Ȃ����ĕ��ʂ̃n�[�h���b�N�I�Ȃ��̂Ƃ������Ƃ������ăo���h�������̖��͂�����Ă����̂͊m���B����ł��A���̍��̃E�F�b�g���͐��������ڂ��\���܂Ƃ����������A���t�����肵�Ă����̂ŁA���̉h���̃G�C�W�A��̌��ł��������ł��ǂ��������ȂƁB�I�t�B�V�����E�u�[�g���O�Ƃ��Ă��̓��̃��C���Ղ��o�Ă���炵���B |
 �Č��������f�B�[�v��p�[�v�����C�A����M�������E�ށB����ɉ��������̂��W���[�E�����E�^�[�i�[�Ƃ����l������Ȃ��Ǝv�������b�`�[�ς����Ƀ`�P�b�g���Q�b�g�B���̃��b�`�[�A�A���v�̗��ɉB��Ėw�ǑO�ɏo�Ă��Ȃ����M�^�[�����C�Ȃ��B���C���{�E�̃r�f�I�Ō������A�N�V���������߂Ă������̐l�Ɠ����l���Ƃ͎v���Ȃ������B�����A���Ԃ��ƌ��������Ȃ鍓������������ǃW��������[�h�̃I���K���̑��݊��ƁA�S�������甗�͂������ꂽ���̂̓Ǝ��̃��Y�������I�����C�A����y�C�X�̃h�����͊ςĂ����ėǂ������ƍ��ł��v���B |
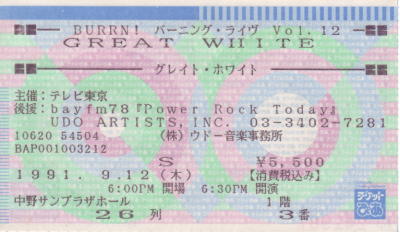 LA���^���ƌĂ�铖���̐��C�݃w���B����^���̒��ł��A�a���u���[�X��ɂ��Ă����O���C�g��z���C�g�B���v����B���o���h�������Ǝv�����ǁA�����̖l�̓u���[�W�[�̓n�[�h���b�N����D���������̂ŁA�c�{�ɛƂ��Ă����B�ł����C���̂��Ƃ͂���܂�o���Ă��Ȃ��B�W���b�N�E���b�Z���i�����������H�j�̐��̓��R�[�h�Ƒ��F�Ȃ������悤�ȋC������B |
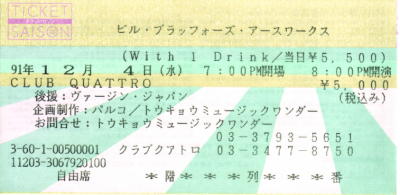 �A���_�[�\���E�u���b�t�H�[�h�E�E�F�C�N�}���E�n�E�̌����Ńu���b�t�H�[�h�̃h�����Ɋ������āA�A�[�X���[�N�X�̌����Ƀg���C�B�W���Y�̃��C���A�N���u�Ƃ������A�Ȃ��m��Ȃ��̂Ɋςɂ����Ƃ��������m�Â����̒��킾��������ǁA�V���Z�E�h��������g�����u���b�t�H�[�h�̃v���C�͊��҂Ɉ�킸�f���炵�������B�蔏�q��ׂ����p�[�J�b�V�����̉��܂Œ������鋷�����̗ǂ��������B���y���̂��̂́A�����̖l�ɂ͂�����ƃ\�t�g�߂��銴������������lj��t���ǂ������̂ŏ\���y���߂��B |
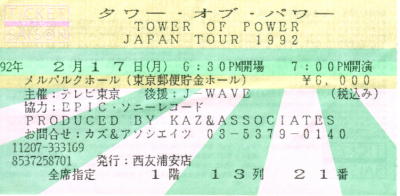 89�N�� KIRIN BEER'S NEW GIGS �ōD��ۂ������^���[��I�u��p���[�B������ CD �͖w�ǔp�Ղœ���ł��Ȃ��������Ă����i������ Amazon �Ȃ�ĂȂ�������ł���j�Ƃ���A�j���[�E�A���o���uMonster On A Leash�v�������[�X�������B�^�C�g�ȃ��Y���E�Z�N�V�����ɓS�ǂ̃z�[���E�A���T���u���A�]�T�����Ղ�̊y�����X�e�[�W�B�[���̃X�e�[�W�Ƀ��C���E�o���h�Ƃ��Ă̒�͂������B���b�N�ȊO�ɑ�D���ȃo���h���ł����u�Ԃł��������B |
 �����b�肾����8�l�C�G�X�����B�������\�����̓u���b�t�H�[�h�̎Q���͂Ȃ������Ƃ���}篒��O�ɎQ��������B���̃u���b�t�H�[�h�͐����ȂƂ��남�d�����[�h����������ǁA���̊��͂��Ղ肾��������܂���������傤���Ȃ��B���b�N�E�E�F�C�N�}���ƃg�����@�[�E���r�������ɒ����ǂ��������������Ƃ��o���Ă�����x�Ń��C���E�p�t�H�[�}���X�͋L���ɂȂ��B |
 ���Ȃ���70�N��n�[�h����b�N�̂悤�ȃT�E���h������u���b�N��N���E�Y�B���ۂ̃X�e�[�W���������Ƃ��낪�Ȃ��A�n���Ȃ��ǒn�ɑ����������b�N������[���ł����o���h�������B |
 ������70�N��I�n�[�h����b�N�A�p���̗Y�������̂����̃T���_�[�B���C���ŕ]�������߂��O���[�v���������ɂȂ��Ȃ��ǂ��p�t�H�[�}���X�������B�_�j�[��{�E�X�̐��͂悭�ʂ邵���[�N�E�����C�̂����ɂ��A�C�h���̓W�~�[�E�y�C�W�Ƃ������[�h��70�N��I�������B�����o���h�ł����ˁB |
 �o���h�Ƃ��ĐⒸ���������Ƃ��̃G�N�X�g���[���B���Ŋς�ƃh�����̗͗ʂ̂Ȃ����������Ă��܂�������ǁA�������Ƀo���h�Ƃ��Ă͐������������B�㔼�̓z�[���E�Z�N�V�����������Ẵp�t�H�[�}���X�������ƋL�����Ă���B���Ȃ݂ɕ����ق̃A���[�i�͌�ɂ���ɂ����̂Ƃ������B�ŋ߂͕����قŃR���T�[�g���ėm�y�ł͂��܂���܂���˂��B |
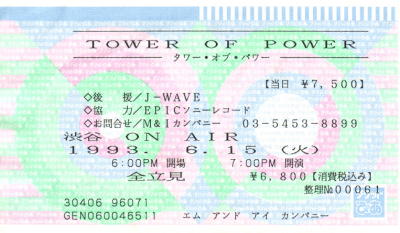 90�N��ɓ���A�����Ɋ��������͂��߂��^���[�́A�Z���C���^�[�o���ōė����B���̓I�[���E�X�^���f�B���O�̋����Ƃ���ł��̃o���h�ɂ͂悭�����Ă��������B1st �T�b�N�X���ς���Ă������x�őO��Ƃقړ��������o�[�������͂��B���̓��������̃��C���������B |
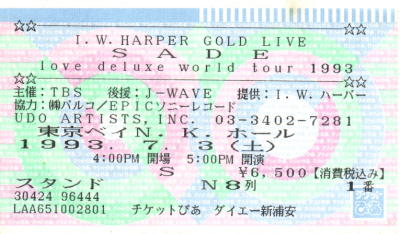 �����܂ł̗��ꂩ�炷��ƈِF�ȃA�[�e�B�X�g�Ǝv����ł��傤���A�l�� SADE ���D���B�ޏ��̎����Ă���G�L�]�`�b�N�ȕ��͋C�͍ō������A���A�̂������f���炵���B���C���ł����₩�ő�l�̉₩������ۓI�������B�o���h�̎��͂������f���炵���X�e�[�W�BSADE �͏����t�@���������悤�ʼn��ɂ͏����������B�d���Ȃ�����������ꂽ�Ǝv���鉡�ɍ����Ă����j�����́A�C�����ǂ������ɑD�𑆂��ł����B���y���킩��Ȃ��l�������������C���ɘA��Ă�����_���ł��ȁB |
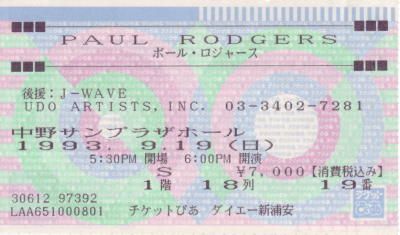 �A���o�� �uMuddy Water Blues�v �ɔ����\���E�c�A�[�B���̔N��w�������A�J����m�点��u�U�[�����Ă��S�����Ȃ����܂܉�ꂪ�Ó]�B�h�����E�X�e�B�b�N��ł��Ȃ���u�����A�g�D�[�A�����E�g�D�[�E�X���[�E�E�E�v�Ƃ����|�����ɓ�����Ȃ��n�܂�ƃX�e�[�W�����C�g�A�b�v�B�Ȃ� "Can't Get Enough"�B�X�e�[�W�����ɂ̓}�C�N�X�^���h���N���N���|�[������W���[�X���I �����Ă����l�͂��̏u�ԁA�����̗]�藧���オ���Ă����B����A���S�̂������ɗ����オ���Ă����B���b�N�E�R���T�[�g�Ƃ����ƂƂɂ��������˂Ƃ������ȋ����I�ȃ��[�h�����邯��ǁA���̂Ƃ����ɋ����l�͊ԈႢ�Ȃ��F�����I�ɗ����オ���Ă����B���̃c�A�[�́A�j�[����V���[���A�s�m�E�p���f�B�[�m�A�f�B�[���E�J�X�g���m���@�Ƃ��������c�B���t���ǂ��������ǁA�|�[���̃��H�[�J���̑f���炵���Ɉ��|���ꂽ�B�I�Ȃ́A�t���[��o�b�h��J���p�j�[�̃��p�[�g���[���o�����X�悭�D��������x�X�g�E�I�u�E�|�[���E���W���[�X�B�f���炵�������B |
 �N�C�[��������~��A����̃o���h�𗦂��Ċ������Ă����u���C�A���E���C�P�Ƃ̏������B�u���C�A���̐l���ƃN�C�[��������������Ƃ�����܂�Ƃ������Ƃ����܂��ăA�b�g�E�z�[���ȕ��͋C�������B�����͌����Ă������ē��a���I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A��������ƃn�[�h�E���b�N�ȃR���T�[�g�������̂��u���C�A���̎����ɕ����Ƃ��낪�傫���A����ɂȂ�ƌ����Ă��R�[�W�[�E�p�E�G���̑��݊������A����͂���͋������B�R�[�W�[�Ƃ����n�[�h����b�N�D��������Ȃ�x�����鍋�r�h���}�[�Ƃ��Ēm���Ă��邯��ǖl�́u�����͂Ȃ����ǂ���Ȃɐ������˂��v�Ȃ�Ďv���Ă������x�B�ł����ŊςĂ��̐����킩�����B���̐l�͖{���ɃJ�b�R�����B�Ȃ�قǁA���ꂪ�j���������ă��c�ȂȂƂ������Ƃ��v���m�炳�ꂽ�B"Since You've Been Gone"�̃��t���u���C�A�������ݎn�߂��Ƃ��ɂ͖{���ɋ������̂Ɠ����ɑ勻���B�قƂ�ǖ�������Ă��邯��ǁA�����o���h�ł�����B |
 ���o�[�g�E�v�����g���Ɍ����Ĉ꒼���������f���B�b�h�E�J���@�[�f�C�������ɖ{�ƂƑg���j�b�g�Ƃ��Ęb�肾�������̃O���[�v�B�A���o���͋Ȃ��C�}�C�`�łǂ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ���������ǃ��C���ƂȂ�Ƙb�͕ʁB�Ƃɂ������̃W�~�[��y�C�W���ς��Ƃ��������Ŗ��̂悤�ȑ̌��������B�����̃A�C�h���Ƌ������Ċ��X�Ƃ��Ă����J���@�[�f�C���͂��̍ۂ��܂�d�v�ł͂Ȃ������B�f�j�[�E�J�[�}�b�V�͔ނȂ�Ƀw���B�ȃh������@���Ă��Ęr�͊m�����Ƃ������Ƃ����������L��������B |
 �����A�l�C�Ⓒ�Ŕ�Ԓ������Ƃ��������������j�[�E�N�����B�b�c�B���l�ł����܂Ń��b�N�F�������A�t�Ɍ����ƍ����ۂ����Ȑl�͒����������B�����ɍ��l���̂��̂̐������Ƃ���͂������j�[��N�����B�b�c�̉��y�Ƃ��Đ������Ă��܂��Ƃ����������B�n�[�h����b�N�̃R���T�[�g�ƌ����Ă������x���̂Ȃ����e�������Ƃ�����ۂ����邯��ǁA�l�I�ɂ͂��̍������t�@�[�X�g�E�A���o���̂���̔ނ̕����D���B���ƁA�萔�������Ă��邳�������̃w�^�N�\�ȏ����h���}�[�͂��������Ȃ������B |
 ����܂łɕ����قʼn��x�����C�����ςĂ������̂́A��Ȃ�����Ȃɖڗ������̂͂��̂Ƃ����ŏ��ōŌ�B������2�K�̓��Ɛ��̃X�^���h�͋X�y�[�X�B�����Ƃ��l�C�̖ʂŃn�[�g�̑S�����͂Ƃ��ɉ߂��Ă����̂Ŗ������Ȃ������B����ł����e�͑f���炵�������B��͂�2�l�̃n�[���j�[�̑����̗ǂ��͑��ł͓����������̂�����B�X�e�[�W�Ō��h��������̂͋����ŃX�^�C���̂����i���V�[�ŁA�����������������ǁA�w�ǃX�e�[�W��œ������ɃA���C�W���O�ȃ��H�[�J��������A���E�E�B���\���͐����Ǝv�����B�n�[�h�ȋȂƃA�R�[�X�e�B�b�N�ȋȂX���炢�ɐD��������\����2�l�̃��H�[�J���̎��͂����\����̂Ƀs�b�^���łƂĂ��ǂ��R���T�[�g�������B |
 �uGet A Grip�v���q�b�g���A���悢���X�^�[�ɓo��߂钼�O�̂���̃G�A���X�~�X�B���C���E�p�t�H�[�}���X�͂������ɗǂ���������ǁuPermanent Vacation�v�ȍ~�A�A���o����3�����q�b�g���������������ČÂ��Ȃ������B"Train Kept A Rollin'"�����炸�Ɏ₵�������B���̓��{�c�A�[����G�A���X�~�X�̓X�^�W�A���ōs����悤�ɂȂ�B |
 ���W���[�E�e�C���[�����Ƀ\���ŗ����B1�Ȗڂ� "Kind Of Magic" �B�\���ƃN�C�[���̋Ȃ�D������̍\���������L�������邯��ǁA�o�b�N�ɃN�C�[���̎ʐ^���f���o�����肵�āA�Ȃ߂��݂���������܂����Ă����̂��u���C�A���̃\���Ƃ͈�����Ƃ���B���W���[�͓��R�X�e�[�W�����̑O��ɗ����A���������E�Ƀ^�C�R��z�u����Ƃ����Ȃ�Ƃ����ȍ\�}�ŁA�����ȂƂ���t�����g�}���Ƃ��Ă̎����͎ア�Ɗ������B"Tenement Funster"�Œ������̂ɂ͊���������������ǁB |
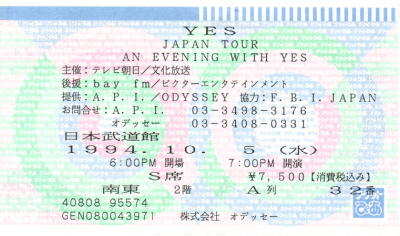 90125�C�G�X�̌����B�������̂̓g�����@�[�E���r���̑��݊��ŃL�[�{�[�h�E�\���܂Ŏ���Ă܂��Ƀo���h�̒��S�I���݂ł��邱�Ƃ����ł��킩�����B����������ĉ��U���Ă��܂���90125�C�G�X�Ȃ̂ŊςĂ����Ă悩�����B |
 94�N11���i���ɂ��͎��O�j�̃^���[�E�I�u�E�p���[�̃X�e�[�W�B�ړ��O�̃u���[�m�[�g�łƂɂ������������B���̕��A�o���h�͎��ߋ����łق��5m�O�ɂȂ��10�l�g�͔��͂����Ղ�B�{���ɐ����t���Ă���Ǝ����ł���o���������B�����̓W���Y�E�X�^�C���̃V���E�i�u���[�m�[�g��2�����j�ɓ���݂��Ȃ��A1���ԋ��Ƃ����Z�����t���Ԃ�������ƕs���ł����B |
 ���̂Ƃ��̗��������� DVD ������Ă���̂œ��e�͂悭�m����Ƃ���B�{���ɐ��������B���߂Ė{���̃v���O�����ς��Ƃ����������������B�u���b�t�H�[�h�̖{���̐�����m�����̂����̂Ƃ��B�_�u����g���I����̃N�����]���������Ƃ�����Ă����Ƃ��̃��C�����ςꂽ�͖̂{���ɍK�^�������B |
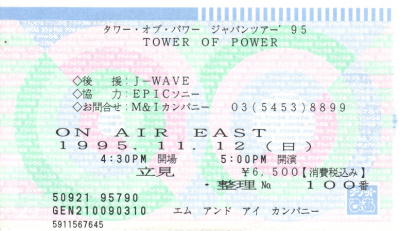 �܂��܂������A�^���[�E�I�u�E�p���[�B���̍��ɂȂ�ƁA�m���������Ď����삦�Ă��āA�h���}�[����������ł���Ƃ��낪�����Ă��������������ǁA�y������点�Ă��������܂����B |
 �Ȃ�ƍČ����������C���{�E�B�A���o���͖{���ɂ܂�Ȃ��������ǎ����̃O���[�v�Ȃ炫���ƑO��̃f�B�[�v��p�[�v���̂悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ���������ƃ��b�`�[�͂���Ă���邾�낤�Ƃ������҂������čs�����B�m���Ƀ��b�`�[�͕ʐl�̂悤�ɃA�N�V�������L���Ă������̂́A���Ă̐����͂Ȃ��u���d���v�����c����̂������B |
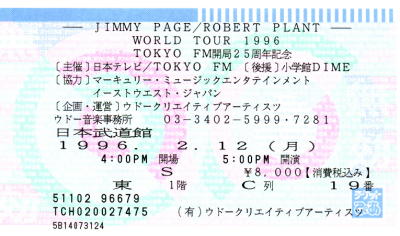 �W�~�[�E�y�C�W���ς��Ȃ�J���@�[�f�C��������ł�������A�Ǝv���ĈȑO�͊ςɍs�����̂ɂ܂������o�[�g�E�v�����g�Ƃ̑g�ݍ��킹�Ŋς邱�Ƃ��ł���Ƃ͖��ɂ��v��Ȃ������B�C���h�n�i�H�j�y��t�҂����l���ѓ������A�c�F�b�y�����̂����ЂƂ̎������ł���I���G���^���E���[�h�ȋȂ𑽂����t���Ă����̂́A�c�F�b�y�������n�[�h����b�N�E�O���[�v�Ƃ��Ă������Ă��Ȃ��l�ɂ͕s���������炵������"Kashmir"�ɑ�\�����悤�ɂ��̎�̉��y���c�F�b�y�����̑厖�ȕ����Ɨ������Ă���l�ɂƂ��Ă͂��Ȃ�y���߂��B����2�x�Ɗς�Ȃ��Ǝv���̂ōs���Ă����Ė{���ɗǂ������B |
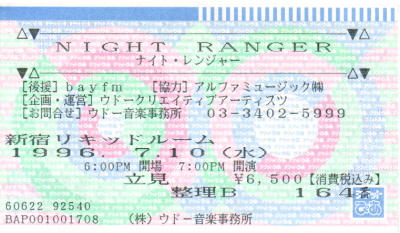 96�N�A������i�C�g������W���[�B�������A�I���W�i���E�����o�[�B����ȋ����Ƃ���Ŋԋ߂Ɋς��Ƃ́B10�N�O�ɕ����قŊς��Ƃ��ɂ̓��C���̂��ƂȂ�ĉ����킩���Ă��Ȃ���������ǁA���������ł��Ă����ÂɊς�ƌ��\�G�ȃo���h�������Ȃ��Ǝv���Ă��܂����B���Ƀh�����̃w�^���ɂ͂܂���܂����B�����v�����A�Ȃ̗ǂ������߂čĔF���B�u���b�h�E�M���X�̃v���C��10�N�O�����͂邩�ɔR���Ă����B |
 �Č������Ă����Ƃ��̗��������B�����Ċ��҂����Ă��Ȃ��ē`���̃O���[�v����x�ςĂ��������x�̃m���ōs�����B�O���b�O�E���C�N�̐��͉������S�Ɏ����Ă��āA����͂���͔߂�����������ǂ������͎d�����Ȃ��B���̑��L�[�X�E�G�}�[�\���̃p�t�H�[�}���X���y���߂����A�J�[���E�p�[�}�[���\�z�O�ɗǂ������B�A���R�[���͊m��20�����炢�̋Ȃŋx�݂Ȃ��p���t���ɒ@������h�����ɃG�C�W�A�Ƃ͈Ⴄ���̂��������B���N�̃p���[�͂Ȃ��������̂́A���e�͈����Ȃ������ł��B |
 �m��2�K�X�^���h�̌ォ��3��ڂ��炢�̐Ȃ������Ǝv���B���������B�ڂŌ���ނ�̓����Ɖ�����v���Ȃ��i�������������ĉ������B����̂��x�����Ă��Ɓj���炢���������B����ł����̔h��ȃV���E���ςāA�������ꂪ�L�b�X�̃G���^�[�e�C�����g�ȂƂ������Ƃ͗����ł����B�ł�2006�N�� UDO Music Festival �̂Ƃ��̕������e�͗ǂ������Ǝv���B |
 ���ɂ���98�N4��9����10���A�ꏊ�͐ԍ�u���b�c�ɂāAKing Crimson ProjeKct �Ƃ������`�ŁAProjeKct Two��Bruford Levin Upper Extrimities�̃W���C���g�E���C�����������BProjeKct Two�̓G�C�h���A���E�u�����[�̓Ɠ��ȃ��Y�����Ƃ��ƈ���Ŏ��Ȗ����̗̈�ɓ��肻���̓t���b�v���L���Ɏc���Ă���BB.L.U.E. �̕������C�u�Ƃ��Ă͌������������āA�����ʂ�ɕϔ��q���J��o���u���b�t�H�[�h�A�X�e�B�b�N���c�����s�ɋ�g���郌���B���A�t���b�v�ȏ�ɕςȃM�^�[�̉����o���f�C���B�b�h�E�g�[���A����C�P�����E�g�����b�^�[�Ƃ��ĕs���̒n�ʂ�z�����N���X�E�{�b�e�B�̃N�[���ŔM���v���C��ǂ��o���Ă���B���̉��́A�w�̒Ⴂ�l�ɂ͌��ɂ����āA��������ԋL���Ɏc���Ă����肷�邯��ǁB |
 �����ʂ�̊y���܂��Ă��炢�܂����B�O���b�O�E�A�_���X�����Ȃ��͎̂₵�������Ȃ��B�����ȂƂ���A���x���s���Ă���̂ŋL�����B���B |
 �u���C�A���E���C�A2���ڂ̃\���E�A���o���ɔ����c�A�[�B�������R�[�W�[�͂��炸��C�͊m���G���b�N�E�V���K�[�������ƋL�����Ă���B�G���b�N�������͂Ȃ���������ǁA�������ɃR�[�W�[�Ɣ�ׂ�ƕ��������B���C���������͑O��ƕς�炸�t�����h���[�ȃ��[�h�������ėǂ������B�u���C�A���͂����\���Ƃ��ăc�A�[����邱�Ƃ͂Ȃ����낤���獡�ƂȂ��Ă͋M�d�ȃ��C����������������Ȃ��B |
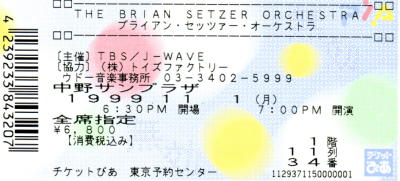 ���̃��C���͍ō��������B�Ȃ��ǂ�����������������������ǃr�b�O�o���h�Œ������Ƃ��������y���������A�o���h�Ƃ��Ă̂܂Ƃ܂���ǂ��v���̏W�c���Ȃ��Ďv�����B���C�����I��������ƍK���ȋC���ɂ����Ă��ꂽ�Ƃ����Ӗ��ł͉ߋ��̂ǂ̃��C���Ɣ�r���Ă���B�u���C�A���E�Z�b�c�@�[���J�b�R�悩�������B����ς�NJy��͐�����ԁB |
 �m�����̂Ƃ�����h�����Ƀf���B�b�h�E�K���o���f�B�����A���Ă����͂��ŁA���Ȃ���҂��čs��������LjӊO�₨�ƂȂ��ڂ̃v���C�B���t�������͈��肵�Ă��āA�����ŋ߂̃h���}�[�ɒ��ł͈�Ԃ܂Ƃ�����������ǂ�����Ƃ��d�������������̂�����Ƃ������������̂��B |
 �����������Ă悭�����܂���2000�N10��4���A�a�J����̃L���O�E�N�����]�������B�d���ŊO�������Ă���Ƃ��ɂ����Ă������W�I�Łu���ꂩ��L���O�E�N�����]�������ً̋}�\����t���܂��v�Ƃ����Ȃ�n�܂�A�g�тœd�b�������ē��肵���`�P�b�g�̓g���C�E�K���̖ڂ̑O��1��ڂ������B����Ȏ��ߋ����Ŋςꂽ���Ƃ͖{���ɍK�^�������̂ɁA����������Ă��Ă����̃��C���i�b�v�͍D���ɂȂ�Ȃ������B�r���ŃG�C�h���A���E�u�����[�̃M�^�[���特���o�Ȃ��Ȃ��āA���o�[�g�E�t���b�v�̋@���������Ȃ��Ȃ����ƃn���n���B |
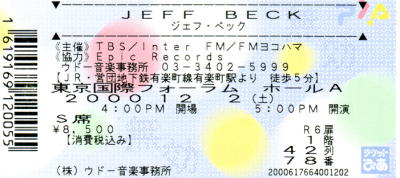 �f�W�^���H���ɂȂ��ď��߂Ċς��W�F�t�E�x�b�N�B�W�F�t�̃v���C�͖����ł��������70�N��̋Ȃ����t������ƃo�b�N�o���h���n�r�������Ƃ��������Ŕ@���Ƃ������������̂��������B�W�F�j�t�@�[�E�o�g�D���������������ƂȂ������B������Ȃ�������N�����ڂ��Ȃ��Ǝv���B |
 �Ȃ��m�炸�ɁA�����u���b�t�H�[�h�̃h���������������Ƃ��������ōs�����B�A�R�[�X�e�B�b�N�E�W���Y���̌��B�Ȃɒ�������h�����N�ƐH�ו����I�[�_�[����Ƃ����W���Y�E�N���u�̃X�^�C���ɂ��̂̂��Ȃ�������Ȃ��̂Ɍ��h���Ē������������B����͂Ƃ������A�W���Y�̂��ƂȂǂ܂������킩���Ă��Ȃ����������ł��A�ԋ߂Ŋς�u���b�t�H�[�h�̃h�����͐��������B�]�k�ł����A����O�̓�����t�߂��ǂ��悤�ɗ����Ă����ז��Ȗl�Ɂu�X�C�}�Z���v�Ɛ��������Ē��ɓ����Ă������̂̓r���ŁA���ꂾ���̂��ƂɊ������Ă����܂��܂����B |
 �v�X�̃u���b�N�E�N���E�Y�B�ނ�͌���ɂ�����ō��̃O���[�v���Ǝv���Ă������ǁA���̓��͂Ȃ����C��������オ��Ȃ����������B�D���ȃ~���[�V�����ʼn��t�������킯�ł��Ȃ��̂ɋC��������オ��Ȃ��Ƃ����Ă���ς肠��܂���ˁH |
 �A�R�[�X�e�B�b�N�E�W���Y�ɂȂ��Ă���2�x�ڃA�[�X���[�N�X�B���̂��낿�傤�ǃW���Y���͂��߂��Ƃ͂����A�܂��܂�����킩���Ă��Ȃ��������B�T�b�N�X���e�B����K�[�����h�ɑ���������ŁA����ȃW���Y�m�炸�̖l�ł��O�C�҂��͏ゾ�Ǝv�����B���̓��͐Ȃ��f���炵���o���h���u���b�t�H�[�h�̃v���C�����\���喞���B�N���u�Ŋς�W���Y�̑f���炵����������ꂽ���ł�����B |
 �O���܂�ɂ��f���炵�������̂ł��������B�x�[�X�̃A����������Ȑl�ɑ����Ă��Ė��ɂ��������������B�O��Ƃ͈قȂ�A�x�[�X�A�h�����Ƃ̃g���I�ł̉��t����I�B�I�[�v�j���O�� 007 �̃e�[�}�������̂� 007 �D���Ȗl�ɂ͌��\�n�}���Ă��܂����B�������A�ԍ�BRITZ �͓��R�������ŊJ���܂ŗ������ςȂ��A�n�܂���������\����ԂƂ����ӏ܃X�^�C���B�D��ȃW���Y�E�N���u�ł̃��C�����o���������Ƃ�����������35�̂�������ɂ͑����h�������B |
 2002�N6��15���̃G�����B���E�W���[���Y�E�W���Y�E�}�V���̃��C���B�W���Y���͂��߂Ďv�������ƁB����͑����̋��l���������ɂ��S���Ȃ�ɂȂ��Ă��邱�ƁB�܂萶�Ŋς��Ȃ��B�Ȃ�Ό��݂Ȑl�͊ςĂ������ƍl���͂��߂�����ɂ���Ă����G�����B���B���̂Ƃ�����75�B������N�̉��t�����҂��Ă����킯�ł͂���܂��A�X�e�[�W�܂ŕ����Ă��������͎�X�����u���v�����ȁv�ƐS�z�ɂȂ������̂́A�X�e�[�W�����̑O�ʂɐ����t����ꂽ�h�����Z�b�g�ɍ��|���A�J�E���g�����n�߂�ƃV���L���ƂȂ�̂���������B���Ă̍r�X�����p���[�����Ȃ��Ƃ��J��o����郊�Y�����ƍ���ɂ���͋����͊ԈႢ�Ȃ��G�����B�����̂��̂������B����2�N��ɖS���Ȃ��Ă��܂������Ƃ������Ė{���ɊςĂ����ėǂ������B |
 ���߂ẴW���Y�E�t�F�X�e�B�o���B���Ԃ͏����Č�������������ǕI�|�����̃C�X�ɐg���ς˂Ȃ���J���I�ȋ�C�̒��Œ����W���Y�͂Ȃ��Ȃ��ǂ����̂������B �ŏ��͎��䏮�q�ƃR�o�ɓ����t�B���̑g�ݍ��킹�ŁA�y����JAZZ�̑�X�^���_�[�h���B���ɃR�o�̃o���h��3�ȁB�A�R�[�X�e�B�b�N�M�^�[2�{�Ƀp�[�J�b�V�����Ƃ����g�ݍ��킹�B�u�ڂ���JAZZ�̐l����Ȃ���ł����ǁv�Ȃǂƌ����ď���U���B ���䏮�q�N�C���e�b�g�B�W���Y�E�o�C�I�����̗ǂ��͂悭�킩��Ȃ�����ǎv������艉�t���������̂ɋ������B�����ڂ��ǂ��̂ł���œ������Ă���C�����܂������B �M��JAZZ�y�c�B���������V�`���G�[�V�����Ƀs�b�^���̊y�������t�B�����A�]�T�̂���V�ѐS�݂����ȕ������ȂƂ���ɓ��{�l�̎�_���o�Ă��銴���������B �n�[�r�[�E�n���R�b�N�� Future 2 Future �o���h�B����� JAZZ ���Ⴀ��܂���ȁB����ł��o���h�̉��t���x���͍����A�����h���}�[�A�e���E�����E�L�������g���̒n�ɑ��̒������v���C�Ɋ��S�B�E�H���X�E���[�j�[�͕������܂߂�70�N��̃}�C���X�݂����������B �E�F�C���E�V���[�^�[�E�J���e�b�g�B�[��ꎞ�ɕ��V���[�^�[�̃T�b�N�X�̉��F�͐_��I�ł��炠�����B�o�b�N�o���h�̎��͂��\�����Ȃ��B �Ō�݂͂�ȂŃX�[�p�[�E�Z�b�V�����B�n���R�b�N�ƃV���[�^�[�̃O���[�v���o���B�I�}�[���E�|���g�D�I���h�D�Ƃ����V�����V���K�[�i����71�j�������B �{���̍Ōオ�A���̃I�}�[���E�|���g�D�I���h�D�̃O���[�v�ŃA�t���E�L���[�o���E�~���[�W�b�N��W�J�B���ꂪ�v���̂ق��y�����Ă悩�����B ���������ꂽ1�����������ǁA�V���[�^�[�Ŋς邱�Ƃ��ł����̂��ő�̎��n�B |
 �}���n�b�^����g�����X�t�@�[�͂��̊����ȃR�[���X�E���[�N�ƌ�y������X�e�[�W�Œ�]������̂͒m���Ă����̂ň�x�ςĂ݂悤�Ǝv�������Ă̊ӏ܁B�m���ɒ�]�ǂ���̓��e�����\�ł��܂����B�ł��A�̃��m�Ɏア�������ĔF���������Ԃł�����܂����B |
 �k�[���H�E���^����W�Ԃ��Ă�������̃N�����]���B�O��������t�����܂��������������悤�ɋL�����Ă���B���ς�炸�l�̍D�݂̃T�E���h�ł͂Ȃ��������ǁA����ȏ�ɂȂ�Ƃ����Ăق��������̂́u�X�e�e�R���v�ƌĂꂽ�G�C�h���A���E�u�����[�ƃg���C�E�K���̕����i����͈ߑ��Ƃ͌ĂׂȂ��j�B���̂Ƃ��̃��C���� DVD �uEyes Wide Open�v �Ƃ��Ă���������Ă��Ă����Ŋm�F�ł���A�Ƃ������L�^�Ɏc���Ă��܂��Ă���B |
 2�x�ڊJ�Â̓����W���Y�B���̔N�͗�Ă������̂ɂ��̓��������������B �܂��́A�O�c���j��������r�b�O�o���h�̉��t�B�u�ō��̃����o�[���W�߂��v�ƃp���t�ɏ����Ă���ʂ�A�قƂ�Ǔ��{�l�̃����o�[�̃��x���͍����B�A�t���L���[�o���ȃp�[�J�b�V�����������ĉĂ̂��������C�x���g�̃I�[�v�j���O�Ƃ��Ă͌������ƂȂ��B ���b�X�[�E���h�D�[���B���ɐ��E���ɖ����m��n��A�t���J�E�Z�l�K���̃~���[�W�V�����B�A�t���J���y�̃��[�c���x�[�X�ɂ��Ȃ��琢�E�ɒʗp����킩��₷����ʑ���������̂������Ƃ��낾�Ǝv�����B�o���h�S�̂ɍ��l�̎������ȃp���[�������āu�{���v���Ă��銴���������B �q�b�v�E�z�b�v�̃X�s�[�`�iSPEECH�j�B���^�N�V�A�q�b�v�z�b�v�����͂킩��܂���B�ދ��B �n�[�r�[�E�n���R�b�N�E�g���I�B�x�[�X�̓N���X�`�����E�}�N�u���C�h�Ƀh�������W���b�N�E�f�W���l�b�g�Ƃ������̓����o�[�B�n���R�b�N�̃s�A�m���܂߂���͊y���߂܂����B�o���\�肾�����_�C�A�i�E�N���[���i�{���͊ς��������j�����`�ŏo���L�����Z�����������߂ɃX�e�[�W�����������B �W���V���A�E���b�h�}���E�G���X�e�B�b�N�E�o���h�B���̂Ƃ����߂ăW���V���A����b�h�}����m��B�[��ꎞ�ɓ����Ă���̉��t�ŏ㔼�g���Ŋ������ɂȂ��ĔM�����郌�b�h�}���͉����邵���t���p���t���B70�N��I�ȃm�X�^���W�b�N�ȃL�[�{�[�h������T���E���G���̏a���Ǝ萔�Ԓ��̃W�F�t��o���[�h�ɂ����|���ꂽ�B���������傫�ȃX�e�[�W�ł��\��������p�t�H�[�}���X�őf���炵�������B �P��̃X�[�p�[�E�Z�b�V�����́A�X�s�[�`�ɍ��킹�ăq�b�v�E�z�b�v���ɂȂ��Ă��܂��ދ��ɂ܂�Ȃ������B |
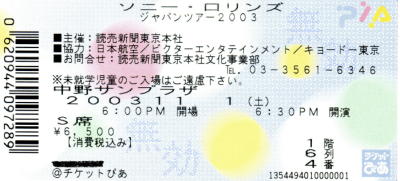 �����Ă��邤���ɃW���Y�E�W���C�A���g���ςĂ������v��̈�B1��15�����炢�̒��ډ��t����ɂ�������炸�x�e�����݂Ȃ����2���Ԑ����܂����Ă����������Y��������̃p���t�����Ɋ��Q�B |
 �~�P���E�{���X�g���b�v�Ƃ����s�A�j�X�g�ƃr���E�u���b�t�H�[�h�̃f���I�B���Ȃ葦�����ɍ������C���ʼn��x���ӏ܂���^�C�v�̉��y�ł͂Ȃ����̂́A�Ŋy��t�҃u���b�t�H�[�h�����\����ɂ͊i�D�̃t�H�[�}�b�g�������B������ 3m �O�Ƀh�����Z�b�g������Ƃ����D�Ȃ̂������ŋH��̑Ŋy��t�҂̋Z�����Ԃ���Ō��ꂽ�̂��f���炵���̌��������B |
 ����2����̓A�[�X���[�N�X�B����ς艹�y�I�ɂ͂�����̕����y���߂�B�e�B����K�[�����h�̏d�v���������O���[�v���[�����ɓ����Ă�����ۂ������B |
 ���̃g���I�̃C���v�����B�[�[�V�������D���Ȃ��ǁA���̂Ƃ��͑S�ȃX�^���_�[�h�ł�������B����͂Ƃ������A�P����������̂��݂���悤�ȃN���V�b�N�ł��������̂悤�Ȍ��i�ȉ��̃��[�h�ŁA�{�l������ȃ��[�h���܂炶��Ȃ��Ƃ��������ʼn\�ǂ���i���V�X�e�B�b�N�B�̐l�Ƌ��M�I�ȃt�@�������������������I�ȋ�C�Ɍ��C�������Ă��܂����B���Ԃ������x�ƍs���Ȃ��ł��傤�B |
 2004�N6��11���A�Z�{�T�e���h�[���ł̖�썹�D�B���͂��������N���u�ł͂����ς�Ȃ��̂��ȁH �����o�[�͌��䎠�t(tb)�A����(p)�A������(b)�A��K��Y(ds)�B�F���\�|�B�҂Ŋy���߂��B���� MC �̂Ƃ��͎��M�Ȃ����Ƀ{�\�{�\�ƒ����Ă��Ă����ɂ��܂��q���ȕ��͋C�ł������A�A���g�𐁂��n�߂�Ƃ��ꂪ�ς�邩��ʔ��������B�x�e���ԂɂЂƂ��e�[�u�����܂���Ă����̂����X���������Ȃ��B���{�l�̃W���Y����������Ȃ����Ǝv��������ǁA7������Ɍ����x�j�[��S���\�����ςĂ������ς藬��Ă��錌���Ⴄ�Ƃ��������t�̗]�T���Ⴄ�Ƃ��������߂������M���b�v�����邱�ƂŊ����Ă��܂����B |
 3��ڂ̓���JAZZ�͉���ς��ē����r�b�O�T�C�g�B�J�����͂Ȃ�����Ǘ��������K�ȂƂ���Ō���̂��������Ǝv�������̂̒��Ȃ������_�őO�r��������B�O�N�܂ł͔w������I�|���t���啿�ȃC�X�������̂ɂȂ�ƃp�C�v�C�X�B���̐l�ƌ������荇�킹�Ȃ����1���̃X�e�[�W���ς�̂͂��Ȃ�h���A�ȍ~���̃C�x���g�ɍs���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B����Ă��܂���e���L���ɂȂ��B�Ẵt�F�X�e�B�o���͉��O�J�Â�]�݂����Ƃ���B �u���[�E�G�A���m�[�c�E�I�[�P�X�g���B�����́u�X�E�B���O�E�K�[���Y�v����q�b�g���Ƃ����������������Ă����̎q�����̃r�b�O�o���h�B���e�͋L���ɂȂ��B �㌴�Ђ�݁B�L�����ŃI�[�f�B�G���X�̋��X�܂Ő�����`����قǂ̃o���h�ł͂Ȃ��Ƃ����̂������ȂƂ���B�X�P�[�����ɖR�����B���Ԃ͂����Ɨǂ��o���h�ɂȂ��Ă����Ȃ����Ȃ��B �t���C�h�E�v���C�h�B���߂�Ȃ����B�ǃw�^�ȉ̂ɒ������ǂ���Ƃ������̂�m��Ȃ��M�^���X�g�̃p�t�H�[�}���X�͑ދ��ɂ܂�Ȃ������B���ꂪ���͔h�ƌ����Ă��܂��Ƃ��낪���{�̉��y�̎���ł��傤�B ���[���E�s�[�v���B�ދ��������̂ŐȂ𗣂�ăE���E�����Ȃ���ςĂ��B�����h���̃n�E�X�E�~���[�W�b�N�n�O���[�v�B���̎�̉��y�͔��ɍ���Ȃ�����ǃq�b�v�z�b�v�قǂ͑ދ��ł͂Ȃ���Ȃ���Ƃ��낪�p���炵���Ƃ��v�����B TOTO�B�����A���� TOTO�B���̓��̃��C���i�b�v�̒��ł͕����Ă�������NJϋq�̔N��w���}�b�`���Ă����̂Ō��\�E�P�Ă����B�ł����e�̓q�h�������B�̂̓w�^�N�\�A�M�^�[�͂����r���ۂ������B���ėD�G�ȃZ�b�V������~���[�W�V�������W�܂��Ăł����Ƃ����e�N�j�b�N�͌���e���Ȃ��B�����^�W���Y��厏�Ő�^���Ă����啨�]�_�Ƃ����܂������A����ȃ��x���̃o���h�Ő�^���ꂽ��܂Ƃ��ȃ��b�N��o���h�����z�B �N�����E�}�R�g SUPER JAZZ FUNK PROJECT featuring �Ŗ������B�o���ĂȂ��B�Ȃi���V�X�g���ۂ��l���ȂƎv�������x�B �Z���j�A�X�E�����N�E�C���X�e�B�g�D�[�g�E�I�u�E�W���Y�E�A���T���u���B�m���Ƀ����N�ɒʂ���s�v�c�ȉ��y��t�ł�O���[�v�ł������A�M����O���[���Ƃ��������t�Ƃ͖����̋�C���S�n�悭�D�𑆂��n�߂�l���`���z���B���I�[�l���E���G�P�Ƃ����A�e���Ƃ������͉����o�������̃M�^���X�g�͖l�ɂ͓�����Ă悭�킩��Ȃ������B �n�[�r�[��n���R�b�N�E�J���e�b�g�B�����o�[�̓E�F�C���E�V���[�^�[�A�f�C���E�z�����h�A�u���C�A���E�u���C�h�B�Q�X�g�őO�o�̃��I�[�l���E���G�P���Q���B���e�́A�ȒP�Ɍ����ƐÂ��ɓW�J����鉹���̏��Ȃ��t���[�W���Y�B�D�𑆂��n�߂�l���o�B�ދ��B |
 2005�N1��29���̃x�j�[�E�S���\���B�f��u�^�[�~�i���v�ɏo�������̂ɍ��킹�邩�̂悤�ɗ����B�f��ł̏Љ�̂��ꂩ���̒ʂ�A���_���W���Y�S������m�鐔���Ȃ������c��Ȃ̂ŊςĂ����Ȃ��ẮA�Ƃ������Ƃōs�����B����ĉ��t�ɂ���قNJ��҂��Ă����킯�łȂ��A���ۃe�i�[�̉��t��������肵�����̂Ŋ���������̂ł͂Ȃ��������ǁA"Whisper Not""Killer Joe""I Remember Clifford""Blues March"�Ƃ������S���\���E�I���W�i�������X�ɉ��t�����Ƃ���ς���j�̈ꕔ�ȂȂ��ƌ��ł�������������Ƃ������́B�܂��A�S�̂ɗ]�T���������C�͂�͂�{���̍��l�~���[�W�V�����łȂ��Ə����o���Ȃ����̂ł��邱�Ƃ��Ɋ������B |
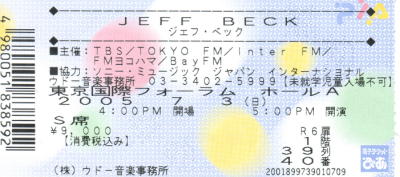 �A���o���������[�X���Ă��Ȃ��̂ɓˑR�̗����B�����ŋ߂̗��������Ƃ̓����o�[���K�����ƕς��Ẵj���[�E�O���[�v�Ń��H�[�J���Ƃ��ĂȂ�ƃW�~�[�E�z�[�����ѓ��B���e�͂���܂ł̃W�F�t�̗��j�����ǂ镝�L���I�Ȃł������A�ǂ������H�[�J���X�g������̂Ȃ�����Ɖ̂��̂�����Ăق��������B�o���h�̎��͍͂������t�͈��肵�Ă��ėǂ��������ʁA�ڐV�������Ȃ��̂��₵�������B����ł��W�F�t�̃v���C�͂������B |
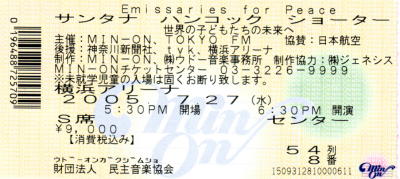 �����̓T���^�i�̃O���[�v�ɃV���[�^�[�ƃn���R�b�N���Q�X�g�Q�������`�B����ăo���h�̎��͍͂����T���^�i�̃��C���Ƃ��ď\���y���߂��B�����̓}�C���X��"In A Silent Way/It's About That Time"�����S�ɉ��t�������ƁB�͂��܂����Ƃ��ɂ͉䂪�����^���܂������A���ꂪ�����������ł��ƂĂ��ǂ��v���o�B�T���^�i�̋Ȃő̂�h�炵�Ă����l�����͌ł܂��Ă����� �i�ǐL�F���̂Ƃ��͂܂��T���^�i���W���Y�ɋ߂��l�Ƃ������Ƃ�m��܂���ł����j�B |
 2005�N9��25���̃W���V���A�E���b�h�}���B�T���E���G���ɃW�F�t�E�o���[�h�A���ƃM�^���X�g�Ƃ���4�l�Ґ��B�N���u�Ƃ������ߋ����Ŋς������������ɑ傢�Ɋ��҂����̂ł����A�ȑO�A����JAZZ�Ŋς��Ƃ������S�̂ɑ�l���������ĂȂC����������オ��Ȃ������B |
 �܂������ŃN�C�[���̋Ȃ����Ƃ����낤�Ƃ́B�����Ɍ������W���[�̐����i���^��h�����ɔ��͂����ނ������H�[�J���j�͉B���Ȃ��������A��͂蕁�ʂ̃��b�N�E�x�[�V�X�g�ł͏_��ȃN�C�[���̉��t�̗ǂ����Č��ł��Ȃ����Ƃ��v���m�炳�ꂽ��ł�����܂������A�v���Ԃ�ɉ̂���R���T�[�g�������Ƃ��������ŐV�N�����������B�|�[���E���W���[�X�̃��H�[�J���͑��ς�炸��肩������ł����A�t���[��o�b�h�E�J���p�j�[�̋ȂŐ��艺����ϋq���߂��������B�N�C�[���̋Ȃ����x�тƃN�C�[���͂����Ȃ��Ƃ����߂��݂����G�ɓ��荬���������C���������B |
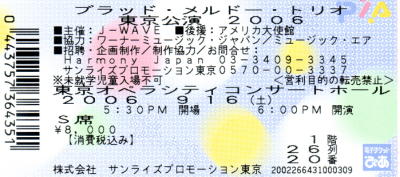 ����̃W���Y�E�~���[�W�V�����ł����Ƃ��ς��������̂����̃u���b�h�E�����h�[�B���ۉ��t�͑f���炵���\��������قNJ��҂ɉ����Ă��ꂽ�B�W�F�t�E�o���[�h�̖\����Ղ�����܂����A���ɂ͊��Q�̐�����オ���Ă����قǁB�m���A���R�[����5�炢������͂��B"Exit Music"�Œ����Ċ����B�ς�Ă悩�����B |
 �����m�A�����O�������ւ�N�C�[���̃~���[�W�J���B���t�͐��o���h�ɂ����̂ŁA���b�h�E�X�y�V������������2�l�̃M�^���X�g�A�x�[�X�A�h�����A�L�[�{�[�h3�l�A�p�[�J�b�V�����Ƃ����Ґ��B�܂��A���t�����������炽���������Ƃ��Ȃ������y���Ƃ���Ɏ�̓͂����R�s�[�Ԃ�ŁA�~���[�W�J���̔��t�Ƃ��Ă͏\���B�ϋq�ɉ��t�҂�������̂͐V�h�R�}�����ŁA�O���̌����ł͐l�ڂɂ��Ȃ����䗠�ʼn��t���Ă���̂��Ƃ��B����̕��͂Ƃ����ƁA�X�g�[���[�͑����̂Ȃ����̂ł����A����Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł��悭�ďo���҂̒B�҂ȉ̂Ɨx��ŏ\���y���߂��B�ӊO�ƌ������̑I�Ȃ������A�̎��i�������o��j���܂߂ĉ��߂Č���̋Ȃ̑f���炵����F����������B�Ƃɂ�����y�ɓO�������̓N�C�[���̖{�����p�������̂ŁA���ꂱ�����������f���炵���B�~���[�W�J���ƌ������̓��b�N�E�R���T�[�g�̃m���Ŋϋq�̐���オ����f���炵���A�R�A�ȃN�C�[���E�t�@��������Ȃɂ����Ɗ����邱�Ƃ��ł��Ĕ��Ɋ����������B���̓��̓t���f�B�̖����Ƃ������Ƃ������āA�I����A����̃s�[�^�[�E�}�[�t�B�[���X�e�[�W�ɓo��A�݂�Ȃł�����x We Will Rock You ��升������Ƃ������o���B���Ɠ��e�Ƃ͂܂������W�Ȃ���ł����A���̓��A�����������ɕ��ڂ��Ƃ�����A�l��菭����̐���̏����������|���Ă��āu��������Ȃ��Ȃ����̂ō����グ�܂��v�ƃ^�_�Ŋϐ킵�Ă��܂����B�������Ȃ͂ǐ^�̑O����3��ځi�Ȃ�4��ڂ���j�B����ȂɊy���܂��Ă�����Ė{���Ɋ��ӂ��Ă��܂��B |
 �j���[���[�N�ŃW���Y�E�N���u���A3����7���n�V�S���܂����B�ڂ����́u�W���Y�E�N���u���L Vol.1 �i2007�N�j�v���B |
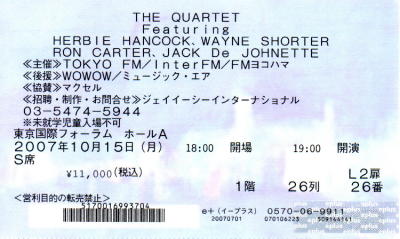 �u��������������J�[�^�[���Ă܂��ςĂȂ��Ȃ��B�����݂̂����ɊςĂ������v�B���ꂾ�����`�P�b�g�w���̌��ߎ肾�����B�����炻��ȂɊ��҂����Ă��Ȃ������B���ۂɊς���A���̒Ⴂ���҂�������鉉�t�ŎQ��܂����ˁB���ɍ��������̂̓^�C�~���O���������O���܂����Ă����V���[�^�[�B�n���R�b�N�͂��������n����������Ȃ�Ďv���Ă��Ȃ������̂őz��͈́B���ړ��Ẵ����E�J�[�^�[�͂��̓d�C�����x�[�X�̓Ɠ��ȉ��g���Łu�Ȃ�قǁv�Ƃ��������B�f�W���l�b�g�͂܂������Ɋy���߂��B�ő�̖��_��4�l�̊Ԃɋْ������܂������Ȃ��������ƂŁA�Ƃɂ�������Ȃɑދ��ȃW���Y�͏��߂Ē������B�ǂ����Ȃ�J�������Đ̂̋Ȃ�����Ηǂ������̂ɁA�����ď�����Ē��ۓI�ȋȂ܂ʼn�����̂�����A�����{���ɐQ�Ȃ�����������J�߂Ă��������C���B�A���R�[���� "Footprints" �ŁA���������̃x�[�X���t������ŃV���[�^�[�������Ă���Ƃ��낾���́u�������A�I���W�i�����v�Ǝv�������̂́A���̊����͒��������Ȃ������B���̃R���T�[�g�Ŗ����ł����l�́A����4�l�������牽�ł������Ƃ����l���Ǝv���B�����̖ړI�͒B���ł����̂ɋ������������c�����B |
 �W���E�z�[���E�g���I�B2008�N1��26���A�Z�{�̃r���{�[�h�E���C���ɂāB�S�����l�ɂ��V���v���ȃg���I�Ґ��B�z�[���̃M�^�[�E�X�^�C���͐̂ƕς�炸�A�X�^���_�[�h�Ɣ�r�I���㕗�̋�/���t��D������A��������т����~�n�̃v���C���I�B�������Ƃ͖����Ȃ���A�Ȃ��Ȃ��ς邱�Ƃ��ł��Ȃ����̃t�H�[�}�b�g�Ȃ�ł͂̊Ɂ`���u�ԁv���Ȃ�Ƃ������Ȃ��B���̕��͋C���ǂ��v���U��ɃW���Y�E�N���u�̃��[�h���y���߂܂��B����ς�W���Y�̓N���u�Œ����̂������Ȃ��ƍĔF���B���������W���Y�E�~���[�W�V�������u�b�L���O���Ă��ꂽ��r���{�[�h�ɑ����^�ԋ@������邩���B |
 2008�N5��6���`12���܂ōĂу}���n�b�^���ցB�ڍׂ́u�W���Y�E�N���u���L Vol.2 �i2008�N�j�v���B |
 2008�N5��18���A�u���[�m�[�g������ 1st set�B9�N���Ԃ�̃^���[�E�I�u�E�p���[�B�G�~���I�A�h�N�^�[�A���b�R�A�K���o���f�B��4�l�ȊO�́A������O�����ǑS���m��Ȃ��B���\�Ȃ������ĊO�������̂悤�� "You Strike My Main Nerve" "Get Yo' Feet Back On The Ground" "Time Will Tell" "It's Not the Crime" "(To Say the Least) You're the Most" "Ain't Nothin' Stoppin' Us Now" �Ƃ����a�߂̋Ȃ����X�ɏo�Ă���̂͊y���������B�������Ǝv����90�N��� "How Could This Happen To Me" ���������肵�āB�����ȂƂ���A���t�ɉ��N�̖������߂�̍������ǁA�X�e�[�W���p���t���Ŋy�����̂͑��ς�炸�B�A���R�[���� "Knock Yourself Out" �͋�������������Ȃ��B |
 80�N��ɃA�����J�̃q�b�g�`���[�g��Ȋ���������2�̃O���[�v���A���ꂩ��20�N�ȏ�̂Ƃ����o�ă_�u���E�w�b�h���C���Ŋς��Ȃ�ĒN���\�z�������낤���B����Ӗ��₵�����Ƃł͂��邯��ǁA�ς���ɂ͗\�z�O�̊y���ݕ��ł͂���B�`�P�b�g�͂�����x����Ă������̂́A�O���������܂߂ē��������̔�����Ă������ƂɎ��̗���������Ă��܂��B �n�߂Ƀ��A���Șb�����Ă��܂��ƁA�f���B�b�h�E�J���@�[�f�C���̐��̐����͉B������Ȃ��B�����80�N��㔼���猩���Ă����Ƃ͂����A���₽������ł��邾���ʼn̂ƌĂԂ��Ƃ�����R�������Ă��܂��قǂ��̃��H�[�J���͂��e���B�͂��Ⴂ�Ŋ���邾���̒��N�j�ł͎₵���B�A���o���uSerpens Albus�v�̌ォ�烍�o�[�g�E�v�����g���A�}�f�Ȃփ��B�E���^���������H���͍��ł��ς��Ȃ��B�_�O�E�A���h���b�`�ƃ��u�E�r�[�`�̃c�C���E�M�^�[���ŔƂ����o���h�̉��t�͈��肵�Ă��Ĉ����Ȃ����A���̃����c��70�N��̋Ȃ͍���Ȃ�����Ƃ�������͂���Ƃ͂����V�Ȃ��ϋɓI�Ɏ����ꂽ�Z�b�g�E���X�g�͍�����O���[�v�Ƃ��Ă̋C�T��������B ����̃f�t�E���p�[�h�́A�V�Ȃ�2�Ȃ����ł��Ƃ�80�N��S�����̃Z�b�g�E���X�g�B���ɁuHigh And Dry�v����3�Ȃ��������̂͊�������Z�B���Ƃ��Ɖ��t���x���͂����������Ƃ��Ȃ����ǁA���̑O�Ƀz���C�g�X�l�C�N���ς����Ƃ������ė]�v�ɂ܂�Ȃ��Ǝv���Ă��܂����B �ƁA�l�K�e�B���ȃR�����g�������ł��܂����B�ł͂܂�Ȃ��������ƌ����܂������t�B�v���U��̃��b�N�E�R���T�[�g�ł��̋�C�����V�N�Ɋ��������Ƃ����邯��ǁA�ނ�̑S�����̋Ȃ��f���炵�����Ƃ��ĔF����������B�p�t�H�[�}���X�Ɋς�ׂ����̂��Ȃ��Ă��ނ炪��������Y�͐F�Ă��Ȃ����Ƃ��ĔF�������B�������ŋC����20�N�O�Ƀ^�C���X���b�v�B�y���������B |
 2009�N1��4���A�p�b�g�E���Z�j�[�E�O���[�v�� 1st �Z�b�g�B�����o�[�̓��Z�j�[�̂ق��ɁA���C���E���C�Y�ikey�j�A�X�e�B�[���E���h�r�[�ib�j�A�A���g�j�I�E�T���`�F�X�ids�j�Ƃ������M�����[�E�����o�[�B�t�@���ɐ𓊂���ꂻ��������ǁA�l�̓M�^���X�g�Ƃ��Ẵ��Z�j�[�͂���قǂ����������ƂȂ��Ǝv���Ă���B���Z�j�[�̎������́A�F�ʊ��L���ȃT�E���h�Ƒ씲�����Z�p�������Ȃ�����T���ڂɎx����o�b�N�̉��t�ɂ���B�܂�p�b�g�E���Z�j�[�E�O���[�v���A�����Ă�������鉹�y�ƂƂ��Ẵ��Z�j�[���f���炵���B�v�̓��C�Y�ƃ��Z�j�[�̃T�E���h�������d�v�B���̓��̓��Z�j�[�E�O���[�v���`�Ƃ��Ă͒������N���u�ł̌����A���t��g�߂Ɋy���߂�ƂȂ�Ό��鉿�l������Ƃ������́B�X�^�W�I�Ղ�菭�Ȃ߂�4�l�Ґ��Ƃ����ăT�E���h�̐F�ʊ��ɉA�肪���邩���Ƃ������O�̌��O�͂܂������X�J�ɂ������A���ɑf���炵���p�t�H�[�}���X���y���߂��̂͂�͂胁�C�Y����������ł��傤�B���Ŋς�T���`�F�X�̃h�����͂�͂肳�����Ƃ����郌�x���ŁA���ꂾ���ł������ł����B |
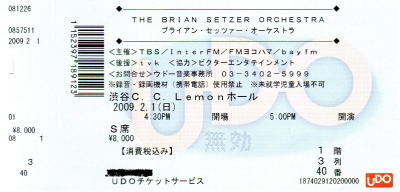 5�N���Ԃ�̃u���C�A���E�Z�b�c�@�[�E�I�[�P�X�g���B�Ȃ�3��ڂȂ���E���Ńg�����y�b�g�ƃg�����{�[���̃Z�N�V������PA�ɉB��Ă܂����������Ȃ������B�S���Ŋy�����ɐ��藧�Ă邠�̎p������Ȃ������͎̂��ɔ߂����������ǁA���̑��ɃZ�b�c�@�[�����x���ڂ̑O�ɗ��Ă��ꂽ�B���J�r���[�ɐl��������Ă����A����X�e�[�W�ɗ����Ă��邱�Ƃ��̂��̂��l���ł��邻�̐l��ڂ̓�����ɂ��Ă���ƁA����Ȕނ̐����l��S�g�Ŏ~�߂����̂悤�ȏd�݂������ėܑB���ɂ�ł��܂��B���Ղ̃g���I�ɂ��p�t�H�[�}���X�Ɋ��������Ԃ����\�����A���̕��M�^�[�����\�ł����̂��Ȃ��O�̕�����������B���J�r���[�Ƀr�b�O�o���h�Ƃ����A�����J�̕�����̌�����f���炵���p�t�H�[�}���X�ɕ��S�B |
 �����悤�ȃZ�b�g���X�g�̃��C�����d�˂�ߔN�̃W�F�t�E�x�b�N�ɏ��X���_�C�����������Ƃ�����A����̗��������͌��������ł����B�������A�G���b�N�E�N���v�g���Ƃ̃W���C���g�ƂȂ�Θb�͕ʁB �攭�̓W�F�t�B1���ԏ��X�̃R���p�N�g�ȃX�e�[�W�Ƃ͂����v���C�͍Ⴆ�Ă���B�o���h�̉��t���^�C�g�Ő��Ŋς�Ƃ���ς肢���Ȃ��Ǝv�킹��B���ʂ��T���ڂŐȂ��ǂ��������������̋K�͂̉��Ƃ��Ă͖]�O�ɉ����ǂ������̂��y���߂��v���B�^����Ƃ́u�x�[�X�A�e�v�Ƃ����T�[�r�X������܂Ŋς����Ƃ��Ȃ�����ʼn������{�l���y����ł���Ƃ��낪��ۓI�B����ł�����ς�W�F�t�ɂ͂���������ƐV�������y������Ă��炢�����Ƃ����v���͎c�����B ����ŁA����܂ŃN���v�g���ɂ͂قƂ�Nj������o�������Ƃ��Ȃ��A�Ȃ��Ȃ��ǂ��M�^���X�g���ȂƎv���Ă������x�B����ł�70�N��܂ł̃N���v�g���̉��y�͂����ȂƎv���B�ł�80�N��ȍ~�́u�M�^�[����肢�|�b�v�̎�v�ɂ��������Ȃ��B�X�e�[�W�͈�l�ŃA�R�M�̒e�����Ŏn�܂�A7�l�̃����o�[�������Ă���A���v���O�h�E���C�������炭�����Ƃ����}�b�^���\���B�X�g���g�L���X�^�[�Ɏ����ւ��Ă�����u���[�W�[�Ń|�b�v�ȉ��t�ɏI�n�A�}�b�^�����Ă���Ƃ���͕ς��Ȃ��B�Ƃ��낪�A���ꂪ���Œ����ƈӊO�Ƃ����B�����������C�����A�������Ǝv����悤�ɂȂ����͎̂����̍̂������B�z��O�������̂͂�����l�M�^���X�g�����āA������ɑ����̃\����e�����Ă��邱�ƂŁA���������̃M�^���X�g�����ɃC�C�B��͂�N���v�g���̓M�^���X�g�Ƃ��Ď�����\�����悤�Ƃ����C�������������Ƃ��킩��B�ł�����͕K�������������Ƃł͂Ȃ��A���y�ƂƂ��Ă��������݂����I�Ƃ��������̂��ƁB����2�l�̑I���͋߂��悤�ʼnʂĂ��Ȃ������A���b�N�Ƃ������y�̉��[���������Ă��܂����B�X�e�[�W��1���Ԏ�Łu�����ɖ߂��Ă��邩��v�Ƃ����N���v�g����MC�ŏI���B �Z���C���^�[�o�������݁A�N���v�g���E�o���h�ɋq������`�ŃW�F�t���o��B����2�l������ł���p�����邾���ʼn��������A���ݏグ�Ă��闈����̂�����B�u���[�X����{�ɂ����V���v���ȉ��t�ɃW�F�t�̃M�^�[���荞�ގa�荞�ށB����ȂɃA�c���W�F�t�͏��߂Č����B�����ău���[�X��e�����Ă��W�F�t�ł������蓾�Ȃ��s���t���[�Y�ň��|�I�ȉ��t������̂����犬��Ȃ��B�N���v�g���������v���C��������̂́A�I�n��l�ȑԓx�Ńo�g���ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ������̂͏��X�c�O�B����ł����̓�l�̃v���C���Ɋς��i��l�̃Z�b�V����������40�����炢�͂������͂��j�Ƃ������j�I�Ȗ�ɗ�����������ł��\��������Ƃ������̂ł��B |
 2009�N3��29���A�e�����X�E�u�����`���[�h�A�u���[�m�[�g������ 1st set�B�ŋ߂̃u���[�m�[�g�͓��j���� 1st set�������Ԃ����ԁi���̓���16���J�n�j�ɐݒ肵�Ă���B�l�I�ɂ͑劽�}�Ȃ���ǁA�N���Ɋς��p�b�g�E���Z�j�[���吷���������̂Ɣ�ׂ�ƁA���̓��̓t���A�̃e�[�u���ȁi����ȊO�͂�������ȁj�Ŕ������炢���������Ă��Ȃ������B���̎��ԑт��ƈ��H���T���ڂɂȂ邾�낤���A���̓��̂悤�ɋq�������̂��A�����Ăق����Ȃ�����Ǖ��j�ϊ������蓾�邩���B ���̂悤�ȗ]�k�͂Ƃ������A�I�[�\�h�b�N�X�̂ɕ\���ɐV�����������邱�Ƃ�����A�g�����y�b�g�A�e�i�[�E�T�b�N�X�A�s�A�m�A�x�[�X�A�h�����Ƃ����N�C���e�b�g�Ґ��ł�������ƌ���̃W���Y�����肫�������Ƃ������]���������B�m�I�ŃN�[���A����������Œ��ڂȋȂ͂�⒮�����I�Ԃ��̂́A�Ȃ��Ȃ������������̍����W���Y�Ƃ����̂͒��������Ȃ��B���ꂵ���ƌ����Ă����x���Ȃ��V���A�X�ȃ��[�h���ɘa���邽�߂��A�㔼�̓t�H�[�r�[�g�̋Ȃɂ���Confirmation�̃t���[�Y���D������A�����Ă��̘A�����ɂ��̉��y���`���̏�ɐ������Ă��邱�Ƃ���������B�t�����[�Q�����z����A�z������u�����`���[�h�̏_�炩���g�����y�b�g�̕\�����}�g�������đf���炵���A���y�S�̂��R���g���[�����Ă���Ƃ�����f���炵���B����Ȃɗǎ��ȉ��y�Ȃ̂ɂ��̊ϋq���Ƃ͓��{�̃W���Y�E�t�@��������ڂ��Ȃ��B�X�e�[�W���~���Ƃ��ɁA�x�[�X�̒j���ʘH�e�Ŕ��肵�Ă���l�̌����|���b�ƒ@���čs�����̂́A���Ȃ��ϋq�̒��A���������ȕ\������Ă������炾�낤���B |
 2009�N4��25���A�u���[�m�[�g�����ŃW���V���A�E���b�h�}���� 2nd set�B��2��uBack East�v�uCompass�v�̘H���܂����s�A�m���X�E�g���I�Ґ��Ńx�[�X�̓����[�x���E���W���[�X�A�h�����̓O���S���[�E�n�b�`���\���B3�l�̗��݂��k���Ōv�Z���ꂽ���x�Ȃ��́A���̑���\���͎��R�ɉ���܂��傤�Ƃ����̂����̃g���I�̍s�����̂悤���B�܂藍��Ō����ƃr���E�G���@���X�E�g���I�̂悤�ȗL�@�I�Ȃ��̂Ƃ������́A�I�X�J�[�E�s�[�^�[�\���E�g���I�I�ȓ����̎�ꂽ�X�^�C���B���Ƃ��ƃW���V���A�̓\�j�[�E�������Y��I�[�l�b�g�E�R�[���}���قǂɂ̓t���[�W���O�ɕ�������킯�ł͂Ȃ��A����䂦�Ƀ\���b�h�Ń^�C�g���p���t���ȃX�^�C�����Ǝ��̃g���I�\���ւƏ����錋�ʂƂȂ��Ă���B�x�[�X�E�\���̃X�y�[�X�����������̂ɂ͂�����������ǁA3�l�̒������x�ȉ��t��O�ɂ��Ă݂����Ȃ��Ƃ͍��ׂȕs���ɉ߂��Ȃ��B����܂�����W���Y�̂ЂƂ̃X�^�C���Ƃ��đ��ł͓���J�b�R�悳�Ɉ��|����郉�C���������B |
 2009�N7��6���A�u���[�m�[�g�����Ńt�@���I�E�T���_�[�X�� 1st set�B�Ґ��̓I�[�\�h�b�N�X�ȃ����E�z�[���E�J���e�b�g�B���Ȃ݂ɖl�͓��Ƀt�@���I�̃t�@���ł͂Ȃ��B�ł��A�R���g���[���E�~���[�W�b�N�̌p���҂������i���67�j�̂����ɊςĂ������Ƃ������@�B�X�e�[�W�ɓo�ꂷ���|���I�[���U�����Ă���t�@���I���������o���[�h���̂��グ��Ƃ��납��n�܂�B�ȍ~�A�����̏���ȑz���Ƃ͈���ăI�[�\�h�b�N�X�ȃt�H�[�r�[�g�E�W���Y���W�J����A���̃T�E���h���e�i�[�̉��F���ǂ����A�g�����e�B�b�N����̂���̃R���g���[����f�i�Ƃ�����B�ł��A������Ă�����Ƃǂ��Ȃ낤�B���̐l����������u�ȂR���g���[�������v�Ɣn���ɂ��ꂻ���A�ł��A��p�҂����炢�����A�Ƃ��������ł͎₵���B�t���[�W���O�ɂ̓X���[�Y�����Ȃ����A�����\���͂ŏ�������^�C�v�ł��Ȃ��B�������A���̃o�����X���C�ɓ���Ȃ��̂��I�n�G���W�j�A���ɕ���������A�}�E�X�s�[�X�����x���C�ɂ��Ă��ĉ��t�ɏW�����Ă��Ȃ��B�X�ɁA���ł���������ڂ����킹�����Ȃ��قǕ|����Ɖs������Ƃ����O���Ȃ��̂�����s�@�������Ȃ��Ƃ��̏�Ȃ��B�����̍ŏ��̃X�e�[�W�ŋC��������Ă��Ȃ��낤���ƊςĂ�������n���n�����Ă���������t�ɏW���ł��₵�Ȃ��B����ȃ��[�h�ŋC��������50�����߂��āA�����A�c�O�ȃ��C���ɂȂ��Ă��܂������ƊϔO�������Ă���ƁA"The Creator Has A Master Plan"���n�܂�A�t�@���I���}�C�N������ĉ̂��n�߁A�������˂点�͂��߂�B�l�̋��ȃt�@���I�̃��[�_�[��̋ȁA�������A����܂ł̃��[�h�Ƃ͋}�]���ăt�@���I����R�m�b�Ă���B���ꂪ�y�����B����܂ł̃t���X�g���[�V�����͂ǂ��ւ��A�t�@���I�E���[���h�Ɉ�C�Ɏ䂫���܂�Ă��܂����B�������A���ꂪ�t�@���I�E�T���_�[�X�̉��y�������Ɣ��g�Ɋ����邱�Ƃ��ł������Ƃł���܂ł̕s���͐������ł��܂����B�����A�t�@���I�̃��[�_�[�E�A���o���͒����C�ɂȂ�Ȃ���������ǁA�悤�₭���̐��E���������Ă����悤�ȋC������B����ς萶�Ō��Ă����{���������Ă���Ƃ������Ƃ��Ă���ȂƍĔF���B���ꂾ���烉�C���͂�߂��Ȃ��B �i�NjL�j�ǂ���特�̃o�����X�����X�ɋC�ɂ���̂͂悭���邱�Ƃ炵���ł��B���A�^�f���ɂ��ƃZ�b�g���X�g�͈ȉ��̒ʂ�B 1. Greatest Love Of All 2. Lazy Bird 3. A Nightingale Sang In Berkeley Square 4. Just For The Love 5. The Creator Has A Master Plan 6. Highlife |
 �����h���E�p�����s�ōs�������C���ȂǁA3�����B 2010�N9��26���A�����h���̃��j�[�X�R�b�c�B�W�F�t�E�x�b�N�̉f���������Ń��b�N�E�t�@���ɂ��L���ɂȂ������̃N���u�́A�����h���̃W���Y�E�N���u�̘V�܂Ń}�C���X��V���[�^�[�Ȃǂ̑啨�Ȃǂ��������o�����Ă����Ƃ���B�O���̃W���Y�N���u�Ƃ��Ă͍L������200�l���炢�͓��肻���B�������A�ǂ̐Ȃ���ł����₷�����Ŕ��ɗǂ��V�[�g�E���C�A�E�g�B�q�̓���͔������炢�B���Ȃ݂ɁA�H�ׂ��o�[�K�[�͂��܂���������Ȃ������B���̓��͌��Ɉ�x�� Funk Affair �̓��B���l���H�[�J���A���C�Y�E�|���b�N�Ƃ����������H�[�J���A�G���s�A�x�[�X�A�h�����i�W���~���N���C�̃f���N�E�}�b�P���W�[�j�A�Ȃɂ����3�{�̊NJy�킪�����Ƃ����Ґ��B���t��70�N��t�@���N�̍Č��ŁA���t�����Ȃ�O���[���B���n�C���x���Ŕ��Ɋy���������B���Ƀh�����͔��ɍI���Ă��������Ă͂Ȃ��ǃW���~���N���C�̃h���}�[�ɂ��Ă����ܑ͖̂̂Ȃ����炢�������B�����ȍ~�̗��s�̗\�肪�l�܂��Ă����̂�1st�Z�b�g�őޏꂵ������ǁA�ق��̋q�͒N���A��l�q���Ȃ������̂ł��̂܂������ꂻ���ȕ��͋C�������B 9��27���A�����h���̃g�b�e�i���R�[�g�ɂ���h�~�j�I���E�V�A�^�[�Ń~���[�W�J���uWe Will Rock You�v���ό��B���Ȃ�N�G�̓������Â�����ŁA���R�ɐȂ�I�ׂ邱�Ƃ��������Ƃ�3��ڂ̒������C���^�[�l�b�g�ŗ\�Ă������̂́A�X�e�[�W�̈ʒu����ύ����A��Ɍ��グ��`�ɂȂ��Đh�������B���Ԃ�10��ڂ��炢�����₷���̂ł͂Ȃ����Ǝv����B�p�ꂪ�\�z�ȏ�ɂ킩�炸����������ǁA�p�t�H�[�}���X�͊y���߂��B4�N�O�ɃR�}����Ŋς��I�[�W�[�E�L���X�g�̕����l�I�ɂ͍D���B�����Ƃ����Ċϋq�̓����6�����x��50�Έȏ�̃V�j�A�w���ڗ����Ă����B����オ��Ƃ������͋C�y�Ɋy���ރ~���[�W�J���Ƃ��Đe���܂�Ă��镵�͋C�ŁA�R�}����̂悤�ȔM�S�ȃt�@���̏W�܂�Ƃ͂����Ԏ�Ⴄ�B�ł����ꂱ�����A�p���ł͒N�ł��m���Ă���N�C�[���̐e���܂�Ă���~���[�W�J���Ƃ������ƂȂ�ł��傤�B 10��2���A�p���̃f���b�N�E�f�E�����o�[���iDuc Des Lombards�j�B������100�l���炢���L���p�̂����Ƃ����W���Y�E�N���u�B����������2�K�������Ă����ł����t��������B�H���̓p���̐H�̃��x�����l����ƃ}�Y���B�o���͏o���̓o�v�e�B�X�g�E�n�[�r���E�J���e�b�g�Ƃ����A�A���g�T�b�N�X�t�҂̃����E�z�[���B�����ȂƂ�����x���̃A���g�B���Ƀt���W�I�t�@�������Ă̂܂��܂��̔M��75������������ǁA�h�������C�}�C�`�ŁA��ׂ��Ⴂ���Ȃ����ǃj���[���[�N�̃N���u��背�x�����Ⴂ�B�~���͍���ł��A�h���u�����s�A�j�X�g���܂��܂��ǂ��������Ƃ��炢�B�p���̓W���Y�̊X�ƌ����邯��nj���ł��������������~���[�W�V�����͒m��Ȃ����A���������Ă܂��܂����̈�ۂ������Ȃ��Ă��܂����B�m��45���[�����炢�����L�������邯��ǁA���̃��x���Ȃ�}���n�b�^���Ȃ�20�h���ȉ��Ō��邱�Ƃ��ł���B �i�ԊO�ҁj 9��25���B�����h���E�o�[�r�J���E�z�[���ŃN���V�b�N�̐����t�����̌��B�������[�E�Q���M�G�t�w���̃����h�������y�c�ŋȂ́u�J�������v�ƌ��㉹�y�i�X�e�[�W�ɏオ������ȉƂƋȖ��͎��O�j�A�����āu�W����̊G�v�B�x�����ăJ���������Ȃ��Ƃ������Ԃ�Ƃ����͍̂��ł�������Ă��邯��ǁA���߂Ē������̃I�[�P�X�g���̉��̔������Ɣ��͂͂��Ȃ�̃C���p�N�g�B���Ȃ݂ɉ��t�̗ǂ������܂ł͂܂�ł킩���Ă��Ȃ��B�u�W����̊G�v�̍ŏ��̃g�����y�b�g�E�\���A�o�����ʼn�������ɊO���Ă����̂͂�����Ƃ��������ŃN���V�b�N�ł�����Ȃ��Ƃ�����A�Ǝv�����B |
 �{�Y�������I���W�i���E�����o�[�Ńo�b�h�E�J���p�j�[���Č����B����܂ł��ꎞ�I�Č����͂��������̂̐l�C�̂���A�����J�Ɍ���A����������͂Ȃ�Ɠ��{�ɂ܂ŗ��Ă��܂����B�Ƃ��낪�������O�Ƀ~�b�N�E�����t�X����p�̂��߂ɓ��{�c�A�[�Q�����L�����Z���A���Ƃ��ƃT�|�[�g�E�����o�[�Ƃ��đѓ�����\�肾�����n���[�h�E���[�X�̈�l�M�^�[�̐��Ńc�A�[�����s���邱�ƂɁB�v�����[�^�[�̔�������u�I���W�i�������o�[�v�ł��������߂������߂��܂Ŏt���Ă������Nj��炭�������l�͏��Ȃ������̂ł́H ���e�́A���_���猾���ƃC�}�C�`�ł������B�|�[���͐����I�������ς�炸���������̂̏��X�G�ŋC���������܂����ݍ����Ă��Ȃ������ŁA�T�C�����E�J�[�N�͐��Ō���ƌ����ăE�}���Ȃ��̂����߂Ă킩���Ă��܂��B�������A�A���R�[�������Ă�80���キ�炢�Ƃ����W�����ŁA2�Ȗڂ� "Can't Get Enough" �𑁂��������Ă����Z�b�g�\���͗��ځACD �uHard Rock Live�v�Ɏ��^����Ă��� "Run With The Pack" "Live For The Music" "Good Lovin' Gone Bad" ������Ȃ��̂ł͕s���̂ЂƂł����������Ȃ���Ă��B�Ƃ͂����A�|�[���̐��̂Œ����鐔�X�̃o�h�J���E�i���o�[�A���N�قǂł͂Ȃ��ɂ��Ă�����ς�J�[�N�Ȃ�ł͂̃��Y�����ł��ׂĂ�����������Ă��܂��B���ꂪ�X�^�C�����m�������҂̋��݂��낤�B�����Ȃ�ƁA���܂�e�����Ȃ��Ǝv���Ă��������t�X�̃w�i�`���R�ȃM�^�[���Ȃ������Ƃ����̂��{���ɐɂ��܂�Ă��܂��̂ł���B |
 2011�N1��14���A�u���[�m�[�g�����ɂă}�b�R�C�E�^�C�i�[�E�g���I�E�E�B�Y�E�X�y�V�����E�Q�X�g�E�G���b�N�E�A���L�T���_�[���z�Z�E�W�F�C���Y�A�g�~���[�W�b�N�E�I�u�E�W�����E�R���g���[���E�A���h�E�W���j�[�E�n�[�g�}���h �Ƃ������� 1st�Z�b�g�B ��x�͐��Ō��Ă������̂ЂƂ�A�}�b�R�C�E�^�C�i�[�B�ړI���u���Ă������v�����炵�āA72�̉��t���̂��̂ɂ͓��Ɋ��҂��Ă��Ȃ������B����ł��w�̓����Ȃ��A���Y���̂������͖ڂɗ]����̂�����A�u���̃}�b�R�C�v�Ƃ������Ƃ��ɂ͂�������鉿�l���Ȃ����炢�s�A�m�͍��������B���R�A�o���h�̃����o�[����Ƀ}�b�R�C�����Ă���Ă��邩���m�F���Ȃ���̉��t�ƂȂ�A���͂�]���]�X�Ƃ����b�ł͂Ȃ��B����ł��A�s�A�m�̃g�[��/�^�b�`�͊m���Ƀ}�b�R�C���̂�����������A����Œ����������ō���̖ړI�͊������B ���������̊��ł���A�W�����E�R���g���[�����W���j�[�E�n�[�g�}���͂܂��͉��ɒu���Ă�����"Fly With The Wind"�ŃX�^�[�g�B�g���I��2�ȖځA3�ȖڂɁuThe Real McCoy�v���^�� "Blues On The Corner"�����t�������ƁA�z�Z�E�W�F�C���Y��������āu�Č��v���n�܂�B�͍̂I�����Ƃ͍I������ǃY�o�����čI���Ƃ����Ƃ���܂ł͍s���Ă��Ȃ��B�ł��A���̐l�̉́A���ɂ͐F�C������B���b�N�X���ǂ��A���Ŋy���߂郔�H�[�J�����Ǝv�����B�����Ď�����݂̋ȂɃR���g���[�����̂��̂̃g�[���Ő����G���b�N�E�A���L�T���_�[�̃e�i�[���f���炵���B�܂�A���_�E�}�b�R�C�𗧂ĂȂ�������ʂ�Ɋy���߂����C���������B |
 2011�N2��20���A�u���[�m�[�g�����ɂă��C�E�n�[�O���[���E�N�C���e�b�g��2nd�Z�b�g�B�l�I�ɂ̓��C�E�n�[�O���[���ɓ��ʂȎv�����ꂪ����킯�ł͂Ȃ����̂́A�ŋ߁A�I�[�\�h�b�N�X�ō����ȃW���Y�����������Ƃ����v�������܂��Ă����B����Ȏv���ɉ����Ă���邾�낤�Ɗ��҂��Ẵ��C���B�I�[�\�h�b�N�X�ȃN�C���e�b�g�Ґ��A�������S�����l�Ƃ����̂͂��܂ǂ��������B�n�܂��Ă݂�ƁA�����ɂ�����̃��C���X�g���[���E�W���Y�Ƃ������t�B���Ղɕ��ʂ̃t�H�[�r�[�g�ɂ͂����A�ȑO�ς��e�����X�E�u�����`���[�h�قǂł͂Ȃ��ɂ��Ă����X������B���t���x���͑S���n�C���x���B���͍ŋߊςĂ������C���̉��t���x���̓C�}�C�`�Ȃ��̂���ŃX�g���X�����܂��Ă����B��������ׂĐ�������Ă����f���炵���B�v��������́A���̂��炢�̉��t�͂��Ăق����B���t�͏��X�ɔM��тсA���悤�ȃu���[����яo���B�n�[�O���[�����g�̃��H�[�J���i�܁A����Ȃɏ�肭�͂Ȃ����ǁj�������Ȃ���A�Ȃ�R&B�I�ȕ����ɓ]���A�킩��₷���G���^�[�e�C�����g�ɂȂ��Ă����B�����Ɍ����ƁA�����ĉ����I�ȃt���[�Y������Ă��邩�̂悤�ȃn�[�O���[���̃\���͌��ߎ�Ɍ����邵�A�A���g�̃\�������P���������Ƃ����v��������B�ł��A���ꂾ���̔M���ʼn����I�ȃW���Y�������Ă��ꂽ����喞���B����[�A�v���Ԃ�ɂ������C�����ς����Ă��炢�܂����B Roy Hargrove (tp,flh) Justin Robinson (as) Sullivan Fortner (p) Ameen Saleem (b) Montez Coleman (ds) |
 5��4���A���E�t�H���E�W�����l�ŃI�����B�G�E�V�����l�i���@�C�I�����j�A�A�����E�h�}���P�b�g�i�`�F���j�A�G�}�j���G���E�V���g���b�Z�i�s�A�m�j�ɂ��A�V���X�^�R�[���B�`�F�`�F���E�\�i�^ op.40�A���t�}�j�m�t�F���}���X op.6-1�A���t�}�j�m�t�F���H�J���[�Y�A���t�}�j�m�t�F�߂��݂̎O�d�t�ȑ�1�Ԃ��B���̎����y�n�������̑f���炵�����g�ɐ��݂��B���Ƃ̓��@�C�I���j�X�g�̕@�����r���������Ƃ��B 5��5���A�����a���i�s�A�m�j�A�W�������W���b�N�E�J���g���t�w���A�V���t�H�j�A�E���@���\���B�j�A�ɂ��A���t�}�j�m�t�F���H�J���[�Y�ƃ��t�}�j�m�t�F�s�A�m���t�� ��2�ԁB �����ЂƂA���ʓ��i�s�A�m�j�A�t�F�C�T���E�J���C�w���A�x�A�����n���|�[�nj��y�c�ɂ��A�V���X�^�R�[���B�`�F�o���G�g�ȑ�1�Ԃƃ`���C�R�t�X�L�[�F�s�A�m���t�ȑ�1�ԁB ���ɐ��I�P�̑f���炵�������\�����̂ɉ����A�N���V�b�N�ɑa���Ă��m���Ă���`���C�R�̑�2�Ԃ�����Ȃɑf���炵���Ȃ��Ƃ������Ƃ��n�߂ĔF�������B���̃C�x���g�͂��낢�뒮���ă`�P�b�g����قǂقǂȂ̂Ŋy�����B |
 �����܂ň�A�̗��ꂩ��͑z��ł��Ȃ��n��̃O���[�v�Ȃ̂́A���͍Ȃ̂��t�������ōs��������B���̎�̃O���[�v�̃��C���ɍs�����̂����߂Ăł����ȈӖ��ŐV�N�������B�n�[�h���b�N�n�����Ă����g�ɂ̓i���i�������j������ő�������Ȃ�������B�����A���t�Z�p���]�X����o���h�ł͂Ȃ����A2���Ԃ�������قǂ̋Ȃ̕������t�̐[�݂��Ȃ��B����ł��A�`���I�ȉp�����b�N�E�|�b�v���A�`���|�Ƃ��āA���������̋C�������Ȃ������Ă���p�����Ɍ����B�ܑ̂Ԃ����O���[�v���ƃA���o���E�^�C�g������C�������C����p���l���C���[�W���Ă������Ⴂ�B����ނ��낱���܂ŋC�������Ȃ��l�������������A�ǂ����Ă��K�v�Ƃ��v���Ȃ����y��t�҂�5�l���킴�킴�A��Ă��Ă���̂��A��������Ă���������l���Ă��Ȃ��̂������ς�킩��Ȃ��Ƃ��낪�ʔ����B�����Ӗ��ł̋��ɂ̃A�}�`���A�C�Y���Ő��藧���Ă����ȑ��H�n�o���h�B�ӊO�ƍ��Ƃ��Ă��璮����o���h�Ȃ̂ł́H |
 2011�N7��22���A���[�}�E�I�y�����Ń��F���f�B�́u�A�b�e�B���v���ό��B�w���̓��b�J���h�E���[�e�B�B�����ȂƂ���I�y���ɊS���������킯�ł��Ȃ�����ǁA�����������[�}�ɗ����̂łƂ������Ƃł̊ό��B�����4�l�̗̉̂͋����ɂ͈��|���ꂽ���A���̕��͋C�ɂ������B�����݂�����ǁA�l�̐��̗͂��Đ����Ǝv�����B |
 2012�N5��27���A�u���[�m�[�g�����ɂăQ�C���[�E�o�[�g���E�J���e�b�g�� 1st�Z�b�g�B Julian Lage(g) Jorge Roeder(b) Antonio Sanchez(ds) �����ȂƂ���A�u�܂��A��x���炢���Ă����Ă��������ȁv���炢�̎v���ƁA�A���g�j�I�E�T���`�F�X�Ȃ�s���Ă݂悤���Ƃ����y���m���ōs���Ă݂��B�j���[�E�J���e�b�g�ŃA���o�����o������ł̗�������������Ȃ̂��A�܂��o���h�Ƃ��Ă̏[���x�A�����x�ƃt���b�V�����������Ă��āA���҈ȏ�ǂ��납����܂łɊς����C���̒��ł��w�܂�̃p�t�H�[�}���X�ƒf���ł���f���炵���ɏI����Ă�����]�C�������Ȃ������B�Ƃ����r�b�O�l�[���̃��C���́A���t�ƂƂ��Ẵs�[�N�͉߂��Ă��āA�ј\�ƊŔ��y���ގ������́i����͂���ň����Ȃ��j������ǁA�o�[�g�����g�̉��t���܂߁A���̃J���e�b�g�̔�����I�[���͌���������̐��݁B����ł��ėǂ��Ӗ��ł̗]�T������B�T���`�F�X�̃h�����͊��Ғʂ�̃n�C���x���A�z���w�E���[�f�[���̈��芴�ƃe�N�j�b�N���ǂ���������ǁA�Z�~�A�R�[�X�e�B�b�N�E�M�^�[�̃W�����A���E���C�W�̃e�N�j�b�N�Ǝ����̃J���[���������t���[�W���O�͂܂��Ɉ�ނƌĂԂɑ��������B�ςĂ����Ė{���ɗǂ������B���ꂾ���烉�C���ɍs���̂͂�߂��Ȃ��B |
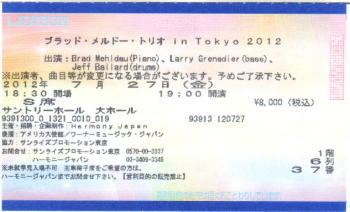 3��̃A���R�[�����܂ޖ�2���Ԃ̔M���B1�Ȗڂ��炱�̃g���I�ł����ł��Ȃ��L�@�I�ȃC���^�[�v���C�̉��V����������B�ŐV��uOde�v�̋Ȃ͉��炸�A�V���ȃs�A�m�E�g���I�̍��݂�ڎw�����̂悤�ȃ`�������W���O�ȉ��t�������B�|�[���E�}�b�J�[�g�j�["My Valetine"�A�r�[�g���Y"And I Love Her"�A�r�[�`�{�[�C�Y"Friends"���I���W�i���e�B�L���ɗ����B�������Ȃ���A�Ȓ��͂��ׂĔ������Ȃ��B���ȃ��Y���̂��̂���ŁA�o�����X�������Ă����͔̂ۂ߂Ȃ��B����̓����h�[���g���_�������̂������낤����ǁA�M�𑆂��ł����l���`���z�����������̂������B�|�b�v��"Wonderwall"��A�I�[�\�h�b�N�X��"C.T.A"�̂悤�ȋȂ������ăo�����X�ǂ�����ė~���������Ƃ����̂��{���ł���B�X�s�[�f�B�ȋȂ��Ȃ��������߂ɖ{�̂����Ă����Ƃ͌�����Ȃ�����W�F�t�E�o���[�h�̃h�����͑��ʂł���A���肵�ĂԌ����x�[�X�����ރ����[�E�O���i�f�B�A�̘r�O�͗��������B���̃g���I�̏W�听�I�ȉ��t��������̂ł́H�Ƃ������҂Ƃ͈���Ă������߁A�s�����c�����̂������Ȃ���A�O���i�f�B�A�̃A���R�e�����t�B�[�`���[���������h�[����Ȃ̃I���W�i���e�B�Ȃǂɒ����ǂ���͊m���ɂ����āA���������������̉��l�͈ꉞ�������Ƃ͎v���B SET LIST Great Day (Paul McCartney) Friends (Brian Wilson) Sanctus (Brad Mehldau) And I love her (Lennon/McCartney) Ten tunes (Brad Mehldau) My Valentine (Paul McCartney) <Encore> Untitled (Brad Mehldau) Holland (Sufjan Stevens) Cheryl (Charlie Parker) |
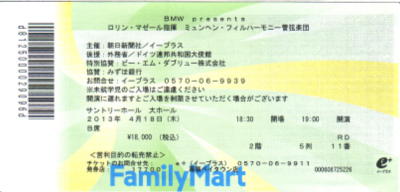 ���[�O�i�[�F�̌��u�^���z�C�U�[�v���ȁ`���F�k�X�x���N�̉��y�i�p���Łj ���[�O�i�[�F�y���u�g���X�^���ƃC�]���f��� �O�t�Ȃƈ��̎� �u���b�N�i�[�F�����ȑ�3�ԁi1889�N��3�e �m�[���@�N�Łj �i�A���R�[���j�}�C�X�^�[�W���K�[��1���O�t�� �܂��N���V�b�N���n�߂����肾�����A�����蔼�N�O����ɊC�O�̈ꗬ�I�P�������Ǝv���ă`�P�b�g���w���B���̍��A�Ȃ�ƂȂ��ǂ����킩���Ă����x�[�g�[���F���̃v���O�����͈����Ȃ����c���Ă��Ȃ������̂ŁA��͂�C�ɓ����Ă����^���z�C�U�[���Ȃ����t���邱�̓����`���C�X�B���C���̃u���b�N�i�[�͓�����3�Ԃ͒��������Ƃ���Ȃ������B���̌�4�����̗\�K���Ԃ��o�ē������}����B �܂��̓��[�O�i�[�̃^���z�C�U�[���Ȃ���B�h�C�c�ꗬ�I�P�̔������Ɨ͋�����ɐS����������Ă����B�g���X�^���ƃC�]���f�̂悤�Ȃ������Ƃ����Ȃł��ْ����������D��B�����ċx�e������Ńu���b�N�i�[�̑�3�ԁB �n�܂��Ă����A����܂łƂ܂�ňႤ��C�Ɏx�z�����B�X�ɍ����ْ����ƃX�P�[���̑傫�Ȗ�B�ŏ���3���Łu����͂������ł͍ς܂Ȃ��v�Ƃ����\��������B�\�ǂ���A���ӓI�Ƀe���|��h�炵�A�������Ƒ傫�ȕ\��������}�[�[���̎w�����X�P�[�������X�ɍL���Ă����B���悻1���Ԃ̋Ȃɒ�����݂ȂNJF���ŁA�s��ȃt�B�i�[���܂ň��|������ςȂ��������B��̊�������A�茘���悤�ɒ������Ȃ�����D��ȉ���t�ł邾���łȂ����������܂����B �܂��S�̒ꂩ��ǂ��Ǝv���Ă����킯�ł͂Ȃ������u���b�N�i�[�̊y�Ȃɂ��āu�������A������������\�������������̂��v�ƁA���[�������ł���悤�ɂȂ����̂��傫�Ȏ��n�B���Ƃ��ƃ��[�O�i�[��u���b�N�i�[�ӂƂ���~�����w���t�B�����A��͂�u���b�N�i�[�Ŏ��т̂���}�[�[�����U��B����̓��{�����ł�3�̃v���O������p�ӂ��Ă��āA���[�O�i�[�ƃu���b�N�i�[�Ōł߂����̓��̉��ڂ�������Ԃ̌����ꂾ������Ȃ����Ǝv���B�`�P�b�g�����Ƃ��͂���Ȃ��Ƃ��܂������m��Ȃ���������{���ɉ^���ǂ������Ƃ��������悤���Ȃ��B |
 2013�N5��4���A5���A���ۃt�H�[�����ɂ����ă��E�t�H���E�W�����l 2013 �u�p���A�����̎��v�łR�����B �y1�z �w���F�쐣�����Y�A�ǔ����{�����y�c�ɂ��A�f���J�X�̌������u���@�g���̒�q�v�ƃT��=�T�[���X�u�����ȑ�3�ԃI���K���t���v�B�i�ȏ�A�z�[��A�j �y2�z ���@�C�I�����F�f�{���E�l���^�k�A�w���F�t�F�C�T���E�J���C�A�������[�nj��y�c�ɂ��A�T�����T�[���X�u���t�ƃ����h�E�J�v���`���[�\�v�Ɓu�n�o�l���v�A�f���J�X�u���@�g���̒�q�v�A�V���u���G�̋��z�ȁu�X�y�C���v�B�i�z�[��A�j �y3�z �s�A�m�F���ʓ��A�w���F�p�X�J���E���t�F�A�t�����X���������[���nj��y�c�ɂ��A�����F���u����̂��ߋ��t�ȁv�Ɓu�_�t�j�X�ƃN���G��2�g�ȁv�B�i�z�[��C�j ���߂ē��{�̃I�P�����B����͎d�����Ȃ��Ƃ͂����Ⴂ�w���҂ɂ͊ј\���Ȃ�����������Ă��Ȃ���ہB���t�̓z�[��A�Ƃ��������ɕs���ȉ��ł��邱�Ƃ����������Ă��͕s���͔ۂ߂��B�s�����ōr�����ǂ̋��������������X�|�C�����Ă��܂��Ă����̂��c�O�B �����̃������[�nj��y�c�i�����������Č����ڂ��₩�j�ł�1�K�Ȃʼn�����ɔ����Ă��܂��Ƃ����X�Ɉ������������ł������ɂ�������炸�A���͖L���ʼn��t�̋Z�p���܂Ƃ܂���y���ɏ�B���R�A�����Ȃ������Ƃ�����A�w���҂ƃI�P�̊�b�̗͂̈Ⴂ�������Ă��܂����B���Ɂu�X�y�C���v��3���q�̃X�E�B���O������_�ŁA�ƂĂ��y�������t�B�����t�͂����łȂ���Ƃ�����햡���������B �Ō�̃����[���nj��y�c�̓x�e�����������Ґ��ŗ������������͋C�B���ʓ��ɖ��m�ȃ~�X�^�b�`������ꂽ�͎̂c�O�������Ƃ͂����A���肾���̃s�A�m���t�̖��Z���y���߂��B2�ȂƂ������F���̐F�ʊ��L���ȋȒ��𔗗͂����Ղ�ɁA�������]�T�������ĉ��t���Ă����Ƃ���͂������B �N���V�b�N�̉����ł���h�C�c�A�I�[�X�g���A�n�̂��̂𒆐S�Ƀ��V�A�n�̂��̂܂ł����ڂ��s���͂��Ă��Ȃ��̂������_�ł̎����̃N���V�b�N�̐��E�Ȃ̂ŁA�t�����X���̂͌�ɂȂ��Ă������ǁA�����炱�����N�̃��E�t�H���E�W�����l�̊��͋����������čs���Ă݂��B�t�����X���̂́A�h�C�c�n�N���V�b�N�Ƃ͂܂������َ��̖��͂�����A���̃J���t���������Ŋy���������E�͑��œ����Ȃ����̂ł��邱�Ƃ������ł��đ�ϊy�����o���������B�ς��t�����X�̊y�c�͌����ăg�b�v�N���X�ł͂Ȃ������̂�������Ȃ�����ǁA����ł����ꂾ���L���ȉ��y��t�ł邱�Ƃ��ł�����玩�������̒�͂Ƃ����̂͐����Ɗ�������������ł��B |
 �x�[�g�[���F���F�����ȑ�7�� �u���[���X�F�����ȑ�1�� �i�A���R�[���j �u���[���X�F�n���K���[���ȑ�5�� �m���x�A�i�Ƃ����������ł���قǍ����]�����Ă���܂ł͌����������w���҂ƃI�[�P�X�g���B���𐬂����w���ҁA�I�P�̌����Ɣ�ׂ�Ƒ�ϗǐS�I�Ȓl�t���ȂƂ���ɋp���ĕs�����������A�h���X�f���̒n�ɍ��t�����h�C�c�E�I�P�̓`���|�݂����Ȃ��̂��������Ƃ���̂ł͂Ȃ����Ƃ����v���ƁA�����ɂƂ��ĉ��j�A��փN���X���炢�D����2�Ȃ��ɒ�����v���O�����Ɏ䂩��čs���Ă݂��B �ŏ��̓x�[�g�[���F����7�ԁB���@�C�I���������E�����z�u�ɂ������C�A�E�g�͎n�߂Ă̑̌��B����7�Ԃ͑�1���@�C�I�����Ƒ�2���@�C�I�����̖������S�����\�n�b�L�����Ă��āA�����z�u�̌��ʂ��ǂ��o�Ă����悤�Ɏv���B�܂��ACD�Œ����Ă���Ƃ��͂��܂�C�t���Ă��Ȃ���������ǁA���@�C�I�����ȊO�̊e�y��̖������S���n�b�L�����Ă��āA���Ō��Ă���Ƃ��ꂼ��̃p�[�g�̖������ǂ������āA�I�[�P�X�g���[�V�����̍\������藝���ł���Ƃ��낪�ʔ��������B���t�́A�ј\�^�b�v���Ƃ܂ł͂����Ȃ����̂́A��������n�ɑ����������̂ŁA�܂Ƃ܂肪����A�w���҂̓�������������Ɨ����Ă����ہB���̉��͗D��͌����߂��ɂ��Ă��\���ɔ������A������̑����؊ǁA���ǂ����肵�Ă���悤�Ɋ������B���邭�u�₩�Ń����n���������Ď�X�����A��4�y�͂̃X�s�[�h���͂Ȃ��Ȃ��̌����ꂾ�����B �u���[���X��1�ԂɂȂ�ƁA���@�C�I�������܂߃I�[�\�h�b�N�X�Ȕz�u�ɕύX�B2�ȂƂ������ꂪ�����厖�ȃp�[�g�̃I�[�{�G�t�҂����A�R���}�X�̓R���~�X�Ɍ��A�Ґ��������Ă��d���ȉ��ɕϖe�B�Ȃ̕ω��ł����܂ŃT�E���h���ς���Ă���̂͏��߂Ă̌o���B�x�[�g�[���F���Ɣ�ׂ�ƃI�P�̊y��̎g�������܂�ňႤ���Ƃ��ƂĂ��悭�킩��B���\�Ȍ�����������ƁA�p�[�g���Ƃ̍\����ςݏd�˂ċȂ�a���ł����x�[�g�[���F���ɑ��A�I�P�S�̂ő傫�ȉ��̉���\�z����u���[���X�Ƃ��������B���Ȃ݂ɉ������̃c�C�b�^�[�ɂ��ƃx�[�g�[���F����7�Ԃ́u�����z�u�A�قڃm���r�u���[�g�A�Êy�e�B���p�j�i�u��1�ł͈Ⴄ�Z�b�g�j���g�p�����Êy�I�A�v���[�`�v�����������ŁA�u���[���X�ƃI�P�̋����������Ԉ���Ă����̂͂��̉e�����傫�������̂�������Ȃ��B �n���K���[����5�Ԃ́A�e���|�����Ȃ�傰���ɗh�蓮�����ėV�ѐS�����Ղ�B�A���R�[���͂��̂��炢�V��ł�����������y�����B�h�C�c�E�I�P�ɂ��h�C�c���ȃv���O�����A���Ғʂ�Ɋy���߂��B |
 �u���[���X�����ȑ�2�� �u���[���X�����ȑ�3�� �w���̓w���x���g�E�u�����V���e�b�g�B �����I�[�P�X�g������x��������ƒ����Ă݂悤�ƁAN����������ɑ����^��ł݂��B ���_���猾���ƁA����܂łɌ����O���I�P�Ɣ�ׂ�Ƃ�͂茩��肷��͔̂ۂ߂Ȃ��B�g�����y�b�g�ƃz�����́A��C�Ƀt�H���e�ɗ����オ��悤�ȏ�ʂʼn����ӂ���ȂǁA�s����ȂƂ��낪���ɂ��B�؊ǂ͗��ꂱ���Ȃ����̂̉��ɗ]�T���Ȃ��؊ǂȂ�ł̖͂F�������Ȃ��B���y��͋����̖L�����������ЂƂ���Ȃ����A�I�P�̕������ǂ���ł��鍇�t���̈�̊����o�Ă��Ȃ��B�e�B���p�͉����������߂������S�����A�s���芴�����Ă��܂��Ă���B�w���҂����ۃ��x���ł��A�I�P�̒n�͂̒Ⴓ�A�����̎コ�͔@���Ƃ����������Ƃ��̂������ȂƂ���B�����Đ��E�ňꗬ�̕]�����Ă���Ƃ͌�����h���X�f���E�t�B����A���E�t�H���E�W�����l�Ō��Ă����悤�Ȗ����C�O�I�P�Ɣ�ׂĂ��m���Ƀ��x���͗�����B�l�̓W���Y�ł��A���{�l�̉��t�͊�b�̗͂��Ⴍ�ĊςȂ�����ǁA�����悤�Ȃ��̂��I�[�P�X�g���Ɋ����Ă��܂����B��͂萼�m�̕����������̂��̂ɂ���Ƃ����͎̂���̋ƂŁA�܂��Ă�I�[�P�X�g���ƂȂ�Ɛ��l�������Εǂ��z���邱�Ƃ��ł���Ƃ������̂ł͂Ȃ��Ƃ����̂��n�b�L���ƌ����Ă��܂����B�Ƃ͂����A���̕��`�P�b�g��͑�σ��[�Y�i�u���ł���̂ŁA���̃I�[�P�X�g���̉���������@��Ƃ��Ă͈����Ȃ��Ƃ��v���B���ہA�u���[���X��3�Ԃ̋Ȃ��̂��̗̂ǂ������������̂͂�͂萶�̊nj��y�̉��̂������������̂�����B |
 ���[�w�i�[���F���ȁu���Ⴖ��n�Ȃ炵�v �X�g�����B���X�L�[ �F�u�̒��v �`���C�R�t�X�L�[�F�����ȑ�5�� �i�A���R�[���j�`���C�R�t�X�L�[�����X�̔����u�p�m���}�v ���̔N�A���̌��̓����͐������ƂɂȂ��Ă����B�������烄�����B���p���ǁA�����ăe�B�[���}�����E�B�[���E�t�B���������A��T���獡�T�ɂ����Ă̓����\���X���R���Z���g�w�{�E�ƃ��g�����x�������E�t�B�����o�b�e�B���O���Ă���B�L�����Z���ɂȂ��Ă��܂�������ǁA�挎�̓A�o�h&���c�F�����܂ł������邱�ƂɂȂ��Ă����B�I�[�P�X�g�����E��TOP3�Ƃ��Ē��N�m�ł���n�ʂ�ۂ��Ă���3���������݂Ń`�P�b�g��͑�ύ����ɂ�������炸�A�E�B�[���E�t�B���ƃx�������E�t�B���͎�ꂸ�A��ނ��R���Z���g�w�{�E��I�B������Ƃ������������Ƃ��Ȃ��̂̃����\���X�̓A�b�T�����Ă��Ėʔ��݂Ɍ�����Ƃ����̂�����܂ł̈�ہB �ŏ��ɂ��܂����݂̂Ȃ��u���Ⴖ��n�Ȃ炵�v�B�Z������ǁA�Z�����e�y��̌����ꂪ����y�����ȁB���������Ȃ͐��m�������I�P�S�̂����C���ǂ��X�E�B���O���Ȃ��ƋȂ̊y�������o�Ȃ��B�����]�T�����Ղ�Œ������Ă��܂����̐[���ɂ����Ɉ��|����Ă��܂����B����A�n�܂���30�b�ł����u����̓��b�`�ȉ��y���ȁv�Ǝv�킹��قǁA���������Ƃ̂Ȃ��悤�ȖF���ȉ����o�Ă���B ���Y���ɃL���������ē������������A���ǂ͂���т₩�Ȃ̂Ɏ咣�������邱�Ƃ��Ȃ����m�Ő��������i���Ƀz��������肩�����j�A�؊ǂ͑����������Ĕ������F���ȉ��F��t�ł�B���̌����ȑ������Ɣ������͂���܂łɒ��������Ƃ��Ȃ��B���E�̈ꗬ�I�[�P�X�g���Ƃ����̂͂����܂őf���炵����������̂��Ɗ�������B�����n�߂Đ����Łu�����A����͐����v�Ǝv�����̂͏t��Ɋς��~�����w���E�t�B���ȗ��̂��ƁB ���Ƃ��Ƃ���قǍD���Ȃ킯�ł͂Ȃ��u�̒��v���A���G�ȓW�J��]�T�����Ղ�ɂ��Ȃ��Ă��܂������Ɉ����͂����Ȃ��B�_�C�i�~�b�N�����W���L�����̋Ȃ̐^�̎p���������悤�ȋC������B �����ă`���C�R�t�X�L�[�����ȑ�5�ԁB����ړ��Ăɗ��������ɂ���܂�2�Ȃ��͂�����x�̊��Ғl�������Ē������B�v�������������Ǝn�܂�A����������Ă���Ɖ��y���������Ă���B�����Ǝv���Ă��������\���X�A�������Ȃ��Ǝv���Ă����R���Z���g�w�{�E�̉��́A���g�̒m���Ɗ������s�����Ă��������ȂƒɊ�����B����ɂ��Ă���2�y�͂̃X�P�[���̑傫���A�������͂Ȃ�Ȃ낤�B�t�B�i�[���̐���グ�����킴�Ƃ炵���Ȃ����R�ɁA����ł��ėY��ɍ��g������B ����A�Q��܂����B�I�[�P�X�g�����y�Ƃ����̂͂���Ȃɐ������̂��ƁB�����ă����\���X�̓A�b�T�����ł��ƂĂ��㎿��������Ƃ������Ƃ�Ɋ����܂����B����܂łɒ��������ŃI�P�̃��x���͊ԈႢ�Ȃ�No.1�B |
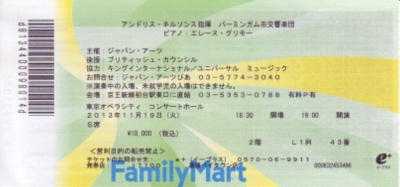 �x�[�g�[���F�� �o���G���y�u�v�����e�E�X�̑n�����v���� �u���[���X �s�A�m���t�ȑ�1�� (�s�A�m�F�G���[�k�E�O�����[) �i�A���R�[���j���t�}�j�m�t�G��I���K�ȁu���̊G�v �u���[���X �����ȑ�4�� �i�A���R�[���j�G���K�[�u���̉́v �܂��͌����炵�́u�v�����e�E�X�̑n�����v���ȁB�ŏ�����͊����鉹���o�Ă��ď��X�����B���t�̓_�C�i�~�b�N�ŁA�������ɑO���̃R���Z���g�w�{�E�Ɠ����Ƃ܂ł͂����Ȃ����̂̃I�P�̋Z�ʂɂ��s�����܂����������Ȃ��B���̉����Y��ŗǂ����Ă��邵�A�؊ǂ����ǂ����肵�Ă��Ĉ��S���Ē�����B���{�̃I�P�Ƃ͔�ו��ɂȂ�Ȃ����炢�����L���B �O�����[�̃s�A�m���t�ȑ�1�Ԃ́A�������l���\���X�w���̃o�C�G�������������y�c�ŐV���������[�X��������B�I�P�̊i����������ɃC���[�W���Ă̊ӏ܂���������ǂ�������s�����͂܂������Ȃ��B�s�A�m���_�C�i�~�b�N�ɃT�|�[�g���ACD�ł͖��킦�Ȃ��[�������ɕ�܂��B��1�y�͂̓����̌��݂ȂǂȂ��Ȃ��̂��́B�O�����[�̉��t�́ACD�ŏ��L���Ă���G�~�[���E�M�����X�̂悤�ȏd���������Ȃ����̂̒[���Ő��X�����B�Ƒt����������2�y�͂́A�o�ԍT���߂̃I�P�̍L��������܂��Ĕ������B�����Â�������̑�3�y�͂͊��Ғʂ�Ƀu���[���X�炵���d���ȃI�P�̐��i�͂ƍאg�̃O�����[�Ӑg�̑Ō��B�������m�������Ă�������Ƃ����C�����Ŗ��������B �����āA���C���̌����ȑ�4�ԁB�Ⴂ�w���҂Ȃ̂ŃX�s�[�f�B�ɂ��̂��Ǝv������o�����͂��Ȃ�������ƁB�����܂Œx���˂��Ƃ�Ƃ����i�ߕ��͑��ł͒��������Ƃ��Ȃ��B�ł����̋Ȃɂ͍����Ă��邵�A�I�P�̋������ǂ��̂ŗD��ɒ�������B����茷�̉��F���������B�؊ǂ͑S�̂ɐ����Ă����Y�킾���A���ǂ����肵�Ă���B�Ȃ̈ʒu�ɂ����̂��e�B���p�j�͂��Ȃ�̔��͂������ċ����B���̋Ȃ𖡂키�̂ɐ\�����̂Ȃ����F���������B�l���\���X�̓h���h���Ƒ��ݖ炵�A���Ɏw���䂩�炱�ڂꗎ�����Ȃ����ƐS�z�ɂȂ�قǂ̂��Ԃ���Ɖ��ړ��i�c�C�b�^�[�łǂȂ������u�����o�̂悤�v�Ə�肢���ƌ����Ă��ď��Ă��܂����j�B�I�P�̓X�P�[���̑傫���Y��ȃT�E���h�Ŏw���҂̌ە��ɉ�����B���������̂�M���ƌ�����ł��傤�B��1�y�́A��4�y�͍͂ŏ��������A�Ō�͉����ɂƂ�������グ���B��3�y�͂̔��͂������B�ׂ�������T������������A�����ĉ��y���̂����~�߂����Ȃ�B�����Č������̋ȂƂ��Ă͉A�e�̂悤�Ȃ��̂�����Ȃ���������Ȃ�����ǁA���h�ɉ��y��炵�����Ă��Ď�X�����B �c���q���v�Ȃ����ӏ܂��ꂽ�i�������O���̃R���Z���g�w�{�E�ɑ��āA�V���c�p�̎w���҂�A���R�[���O�Ƀ��B�I����ȁi���l�����{�l�炵���j�ɓ��{��ŋȏЉ����ȂǃA�b�g�z�[�������ɕ�܂ꂽ���͋C�͂���Ӗ������Ŏw���҂̌����ǂ��o�Ă�����Ȃ��ł��傤���B |
 2014�N1��2���A�u���[�m�[�g�����ɂ� HIROMI THE TRIO PROJECT featuring Anthony Jackson & Simon Phillips �� 2nd �Z�b�g�B �㌴�Ђ�݂̓��C���ɍs�������Ǝv���ɂ͂��ƂЂƉ�������Ȃ��Ƃ����̂��l�l�̏���Ȏv���������B�������A�u���[�m�[�g�Ŋς邱�Ƃ��ł���ƂȂ�Θb�͕ʁB ���G�ȋȓW�J�ƕϔ��q�𑽗p���Ȃ���ꎅ����ʉ��t�͂������ƚX�点��ɏ\���B�A���\�j�[�E�W���N�\���̓X�^�W�I�Փ��l�T���߂Ȃ���A���C���炵����莩�R�ȉ��t��6���x�[�X�̖��Z�����\�ł����B�T�C�����͑��ς�炸���E�̎葫�����R���݂Ɏg�����Ȃ��ĕ��G���V���[�v�ȃh���~���O�B�L���O���[�v�ł̑����Z�b�V�����E�h���}�[�Ƃ��Ă̎d���ł͂Ȃ��A�T�C�����E�t�B���b�v�X�̃h���������߂��ẴO���[�v�ɎQ���Ȃ����Ɏv�������@���Ă����B�����5���[�g���O�Ŋς��̂����犬��Ȃ��B �V�Ȃ�4�Ȃ���I���A��������g���I�Ƃ��čX�Ȃ�i���Ɛ[�������������鉉�t�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ͏��X�������B���̃����c�Œ��������͓�����낤�A�A���o���������炭2���ŏI���Ȃ�Ȃ����Ə���Ɏv���Ă�������ǁA4�Ȃ��Ǝ��̃A���o�������C�ł��邱�Ƃ��q�V�q�V�Ɠ`����Ă���B ������������A�W���Y�N���u�Ƃ������ɂ����Ă̓T�C�����̃��b�N�E�h���~���O�̓��E�h�߂��Ńs�A�m�̉������������Ă��܂���ʂ����Ȃ��Ȃ������B�X�^�W�I�Ղ̐▭�ȃo�����X�͎����Ă��܂��Ă���B�ł����Ԃ�͏㌴�Ђ�݂��킩���Ă���͂��ŁA����ȃo�����X���������t�̐������̂��Ă����Ȃ����Ǝv���B�s�A�m���X�^�W�I�Ղ̂悤�ȍ\���͂����������d���������̂��������A�X�^�W�I�Ղƃ��C���͐藣���čl���Ă���ɈႢ�Ȃ��B�N�����ꔭ�ڂ̃��C���A�K��̗ǂ��X�^�[�g�ł��B |
 �y���ځz �����f���X�]�[�� ���ȁu���C�E�u���X�v �����f���X�]�[�� ���@�C�I�������t�ȁi�ܓ��݂ǂ�j �i�A���R�[���jJ.S.�o�b�n�����t���@�C�I�����̂��߂̃\�i�^��2�� �V���X�^�R�[���B�` �����ȑ�5�� 1�Ȃ߂̓����f���X�]�[���́u���C�E�u���X�v�B�����o�Ă��Ă����ɖ{��h�C�c�I�P�̐��������������S�����ĂԁB�Z���Ȃ�����ǁA�����Ȃɗ��Ȃ��I�[�P�X�g���̃X�P�[����v������ȂŁA�y���ʼn₩�ȃ����f���X�]�[���炵�������𖡂킦��B���F�͂��܂�c����₩���͂Ȃ�����ǂ����͘V�܃I�[�P�X�g���̓����Ȃ̂�������Ȃ��ܓ��݂ǂ���\���X�g�Ɍ}���������f���X�]�[���̃��@�C�I�������t�ȁB��҂œ��X�Ɨ����A�̂����˂点�Ȃ��牽���Ɏ��߂��ꂽ���̂悤�Ƀ��@�C�I������e���p�̓e���r�Ŋς��ʂ�B���̌����ڂƂ͗����ɏo�Ă��鉹�͐��^�Ō����ĉߓx�ȏ�O����悹�����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��Ƃ����CD�Œ������ʂ�̈�ہB�l�͂܂��Z�p�I�ȂƂ���͂킩��Ȃ�����ǁA����ł��ǂ����t�ł��邱�Ƃ͊�����ꂽ�B�ܓ��݂ǂ�̃\���X�g�Ƃ��Ă̗͗ʂ͂ނ���A���R�[���̃o�b�n�̖����t�̕��ŁA�܂Ƃ��Ƀ��@�C�I�����E�\�������̂͏��߂ĂƂ������Ƃ������ĂȂ��Ȃ��ǂ������B�����ă��C���̓V���X�^�R�[���B�`�̌����ȑ�5�ԁB���Ȃ݂ɃV���C�[�ƃQ���@���g�n�E�X�ƌ����ƁA�x�[�g�[���F����u���[���X�̌����ȑS�W�̉����e���|�ɂ�鉉�t�̃C���[�W�������A�����ł������悤�ȉ��t���W�J����邩�Ə���ɗ\�z���Ă�����A�`������������Əd���ȓ�����B����ł��d�X�����Ƃ���܂ł͂����Ȃ��Ƃ��낪�V���C�[�̕\���Ƃ������Ƃ��B���̋Ȃɓ����Ă����R�I�P�̖肪�[�����Ă���B�L���ȃ_�C�i�~�N�X�ƃJ�b�`���Ƃ������t�\�͂��f���炵���B�t���[�g���͂��ߖ؊ǂ̔������͓��M���m�����A���ǂ̖���Ղ�ƃe�B���p�j�̋��ł͔��͂����Ղ�B�����a�߂̃T�E���h���V���X�^�R�[���B�`�̋Ȃɂ悭�����Ă���B���ʁA�o�[���X�^�C���̉��t�̂悤�ɏ�O��������������̂͂��܂�Ȃ��A�ŏI�y�͂�\�z�O�ɒx���e���|�ł������Ɛi�߂Ă����㕗�̃X�}�[�g��������B����͂���łЂƂ̑f���炵�����t�������Ǝv���B |
 ���E�t�H���E�W�����l 2014��4�����B 5/3�i�y�j �y1�z �w���F����a�T ���t�F�����s�����y�c ���ځF�x�[�g�[���F�������ȑ�3�ԁu�p�Y�v�i�z�[��C�j ���F�z�[��C �y2�z ���t�F�v���W���[�N���y�l�d�t�c ���ځF�x�[�g�[���F�����y�l�d�t�ȑ�11�ԁu�Z���I�[�\�v �x�[�g�[���F�����y�l�d�t�ȑ�7�ԁu���Y���t�X�L�[��1�ԁv ���F�z�[��B7 5/4�i���j �y3�z ���t�F�{���X�E�x���]�t�X�L�[�ip) �A�����E�h�}���P�b�g(vc) �h�~�g���[�E�}�t�`�� (vl) ���ځF�V���p�� �`�F���E�\�i�^ �V���p���s�A�m�O�d�t�� ���F��݂���z�[�� �y4�z ���t�F�g���I�E���@���_���[ ���ځF�V���[�x���g�E�s�A�m�O�d�t�ȑ�2�� ���F�z�[��B7 �y1�z ����܂œ��{�̃I�P�̎��͂ɋ^�╄�𓊂������Ă������̂́A�܂����������Ƃ̂Ȃ��s���ʼn��̓z�[��C�A�����đ�D���ȁu�p�Y�v�Ƃ����킯�őI��ł݂��B�Ȃ�1�K��8��ڂƋ߂��������Ƃ������Ă��]���̓��{�̃I�P�Ɋ����Ȃ������y��̖���Ղ�̗ǂ�����������Z�B�������������ł��܂������ꐺ�I�P�̈�̊��Ɣ��͂��~�������A�������Ȃ��������̂̋��ǂ͗]�T���Ȃ��������Ƃ�����������ǂ��A�R���}�X�̔M�̓���l���悭�A�D���������Ǝv���܂��B���Ŋς�ƃI�P�̓������킩���Ă����B�w���҂̖_�J���͒n���ŊςĂ��Ėʔ����Ƃ͂������E�E�E�B�e���|���S�̂ɒx���A�s���I�h�E�X�^�C���Ƃ͐^�t�̉��t�ŁA���ԉ��ъ����i���ɑ�2�y�́j�B �y2�z ���߂Ă�B7�z�[���͖�800�l���e�ŁA���ڂ��炠����x�l�C�Ă��邪�̂̍L�߂̉��B�Ȃ͌���ŁA���t���n�܂�Ɖ������Ȃ艓����ہB�Ƃ��������y���t�̂��߂̃z�[���ł͂Ȃ��������Ȃ�f�b�h�ʼn����قƂ�Nj����Ȃ��B�X�e�[�W���Ⴍ���o�I�ɂ���낵���Ȃ����Ō���Ȃ͂�����ƃL�c�������B���t�͈����Ƃ͎v��Ȃ���������ǁA���̃}�Y���ɕ��B���̂Ƃ��͂���Ȃ��̂��Ǝv��������ǂ��E�E�E�B �y3�z ����������߂Ă̂�݂���z�[���B�R���T�[�g�̂��߂̃z�[���ł͂Ȃ����̂́A�ꉞ���t����z�肵�Ă�Ǝv������Ƃ����Ċy��̋����͗ǍD�B�Ȃ�7��ڂ̒����Ƃ����̂�����t������������Ȃ��B��͂�O���̃z�[��B7�̉����͓��ꂾ�����Ǝv�킴������Ȃ��B�`�F���̓��肩��L���ɋ����ăI�[�f�B�I�ł͐�ɏo�Ȃ��f���炵�����������\�ł����B�s�A�m�O�d�t�Ȃł̃o�C�I�������ƂĂ��ǂ������B�x���]�t�X�L�[�̃s�A�m�̓~�X�^�b�`�������ƃc�C�[�g���ꂽ�肵�Ă�������ǖl�ɂ͂킩��Ȃ������B������ɂ��Ă�4��̃v���O�����������Ƃ��y���߂��ǂ��R���T�[�g�������B �y4�z �ēxB7�z�[���B���[�������Ƃ͂������x��8��ڂƑO�̕��ł����ԉ��͕�����������ǂ�͂肱�̉��͉��������Ȃ��B��݂���z�[���ŗǂ����Œ��������肾���Ƀ`�F���ƃ��@�C�I�����̋������ނ�Œ������Ă��܂��B�Ȃ̓V���p���ɔ�ׂ�ƌÓT�I�ł킩��₷���A��Ⓑ�߂̋ȂȂ���f���炵���R���r�l�[�V�����ʼn��t�����\�ł����B �Ƃ����킯�ŁA����͔w�L�т��Ď����y�n�𒆐S�ɑI��ł݂�����ǁA������Ɩl�ɂ͂܂����������������Ȃ��B������t�̗ǂ��A�Ȃ̑f���炵���͊�����ꂽ�̂�����ǁA��͂莺���y�n�͂���܂肵�Ă��āA������������������̂��Ȃ��̂Ŏ��ɏ��X�����Ȃ��Ă��܂����̂������B�܂��܂��A�����ƕ����Ȃ��ƁB�Ƃ͂����A�`�F���̉��̔������͈�ۓI�ł������ςĂ悩�����Ǝv���B���ƁAB7�z�[���͂�����ƍl�����́B��قǂ̃v���O�����ł��������莟��͐ϋɓI�ɑI�Ȃ��Ǝv���B |
 ���悻5�N�Ԃ�̃u���C�A���E�Z�b�c�@�[�E�I�[�P�X�g���B���̃O���[�v�̖��͂ł���A��y���ɖ������y�����G�l���M�b�V���łȃX�e�[�W��������y���߂��B�Ƃ͂����A����̓Z�b�c�@�[�̐����������Ă��܂����̂������B���ɑO���͎w������C���őS�̂ɃM�^�[�ɃL�����Ȃ������悤�Ɏv���B��������55�A�̊ς��Ƃ��ɂ͂܂�40��O�����������Ƃ��v���Ύd���Ȃ��B���ƁA����̃I�[�P�X�g���̃����o�[�̓L�������������l�����Ȃ��ăX�e�[�W�S�̂Ŋy�������A�s�[�����邱�̃O���[�v�̖��͂����������Ă����悤�ɂ��v���i���Ȃ��݂̊�����܂�����)�B���悻80���Ƃ����ڂ̒Z�����W���ŁA��������̐����������������Ƃ����炿����Ɣ߂����B����ł����̃O���[�v�͑��݂��邱�Ƃ������ɈӋ`������Ǝv����ǂ������邱�Ƃ͍�������������A���ꂩ������C�ɂ����Ƒ����Ăق����B |
 �y���ځz �����F�� �}�E���[���E���� �����F�� �s�A�m���t�ȁi�����D�j [�A���R�[��] �V���p�� ���K��op.25-1 �T��=�T�[���X �����ȑ�3�ԁu�I���K���t���v�i�I���K���F�ΊۗR���j [�A���R�[��] �t�H�[�� �p���@�[�k�A�I�b�t�F���o�b�N �V���ƒn�� �w���̓��i�[�h�E�X���b�g�L���B 1�Ȃ߂́u�}�E���[���E�����v�́A���͔��������F�̓��b�`�A�؊ǂ͖F�������ĂŁA����قǑ傫�ȉ����o����ʂ��Ȃ����ǂ��܂����芴���Q�̏�肳�i���Ƀz�����j�B���������K���K���Əo���ȂłȂ��Ƃ��F�ʂ����������鋿�����S�n�悭�A���������Ă��܂��B 2�Ȃ߂́u�s�A�m���t�ȁv�́A�I�P�̕Ґ������������̂̃����F���炵�����邢�F�ʊ��ɕx�݁A���I�P�����R�ɖ苿���Ă����ɂ��t�����X�Ǝv�킹�鉹�B�I�[�P�X�g���̎��͍͂����I�[�P�X�g���ł͏o���Ȃ������Ń`�P�b�g����v���Ƃ��Ȃ蓾�����C���ɂȂ��B�����D�̎��͂́A��ɂ���ă\���X�g�̔��f����������킹�Ă��Ȃ��l�ɂ͂킩��Ȃ���������ǁA�ޏ��̓s�A�m�Ɍ������Ă���Ƃ��̕��͋C�͗ǂ��Ӗ��ŏ��炵�����o�Ă��Ȃ��ē��X�Ƃ����Ƃ���ɍD���B �x�e��ɂ̓��C���̃T�����T�[���X�A�I���K���t���B�Ґ��͈�C�ɑ�^�����A�NJy��̑������ڂɂ��B������}���h�̋Ȃ炵���_�C�i�~�b�N�ɃI�P�������ċC�������g������B�X���b�g�L���̓X�}�[�g�Ȗ_�����ŁA�e���|�͒��f�A�ςȃA�N�Z���g�̕t������������A�����ɔC�������t�͂��Ȃ�����ǁA�I�P���L�@�I�ɁA���ɗ͋����A���ɔ������ƕ\�����L���B���x�ȃh�C�c�I�P�̂悤�ɌR�����̓����ł͂Ȃ��ǂ��Ӗ��̊ɂ�������Ƃ���̓t�����X�̃I�P�炵���Ƃ������Ƃ���Ȃ̂�������Ȃ��B���҂��Ă����I���K���́A�n�����̂悤�ȏd�ቹ�ƌ��݂̂��钆��̉���̂Ŋ�������X�P�[���̑傫�ȉ��ŁA���߂đ̌�����{���̃T�E���h�͊��҂ǂ���̔��́B�I�P�ƈ�̂ƂȂ����Ƃ��̃N���C�}�b�N�X�͂Ȃ��Ȃ������I�ŋ��������ς��ɂȂ��Ă��܂����B���̈Ⴂ�ƃI���K���̈Ⴂ�ŁA�ȑO�̓Nj��Ɣ�ׂ�̂̓t�F�A�ł͂Ȃ����Ƃ͏��m�̏�Ō��킹�Ă��炤�Ȃ�A�ʂ̋Ȃ̂悤�ɑf���炵���A���̋Ȃ͂���Ȃɂ����Ȃ������̂��ƔF�������߂邱�ƂɂȂ�قǂ������B �A���R�[���́u�V���ƒn���v�ł́A�w���҂��䂩��~��Ċϋq�Ɏ蔏�q����鉉�o�ŗz�C�ɏI���B�e���|����������ϋq�̎蔏�q������C���ō����Ă��Ȃ���������ǁA������܂��y���������B �Ȃɂ���ƂĂ��ǂ��T�E���h�̃I�P�ő�ϖ����ł���R���T�[�g�������B�L���I�P�������f���炵���킯�ł͂Ȃ����Ƃ�Ɋ��B�l�I�ɂ�3���̃V���C�[���Q���@���g�n�E�X����������̕����y���߂��B |
 2014�N8��17���ASUMMER SONIC��2���ځA�}�����E�X�e�[�W��r������B �y�ؑ��J�G���z �̂͐����ȂƂ��납�Ȃ�s����B�ł��m���̗ǂ��ȂɂȂ�Ƃ���قNjC�ɂȂ�Ȃ������B�ޏ��̓X�e�[�W�f�����邵�����ǂ��B�����Ɏx���҂������悤�ɕςɒj�ɛZ�т��Ƃ��낪�Ȃ��̂��D�������Ă邵�A���b�N�n�����V���K�[�̃X�^�[�Ƃ��đf�{�͏\���Ɍ�����B�c�O�Ȃ���Ȃɏ��Օi�I�Ȃ��̂������̂ł���������ƕ��Ր��̂��閼�ȂƌĂׂ�悤�Ȃ��̂�����Ɩ{���̈Ӗ��ł̃X�^�[�ɂȂ��̂����B �yDreams Come True�z �M�y�̒��ł͉̂���肢�Ƃ����g�c���a�ł͂��邯��ǁA���ӂȐ��悩�班���O���ƕs����ɂȂ�B����͐D�荞�ݍς݂Ȃ̂ŁA�܂���������ǁA�f���ڋ��Ȑ��ŕςȂ���ׂ����MC�ɂ͂�����ƋC�p�����������o����B�ł��A���y�͂��Ƃ��Ƃ������肵�Ă��邵�A������N�ł��m���Ă���q�b�g�Ȃ����������Ă���̂͂��������t�F�X�ł͋��݁B"Love Love Love"�Œ������疭�Ɋ������Ă��܂����B �yRichie Sambora featuring ORIANTHI�z �{���E�W�����B�̐̂̃q�b�g�ȈȊO�͐���オ��Ȃ����A�Ȃ����t���܂�Ȃ��ăO�_�O�_�B����������肢��Ȃ����Ǝv���Ă����̂��A������ԁB���Ȃ̂悤�ɃM�^�[�������ς�����̂́A���̃M�^�[�E�v���C���P���ʼn��y�ɂ������Ȃ��i�܂��A�{���E�W�����B�̃A���o���̃v���C�ł킩���Ă͂������ǁj�B��̐������Ă��܂��������ŁA���̐l�͂���ς����̘e�ɂ���|�W�V�����������Ă���̂��Ɣ[�����邱�ƂɂȂ��Ă��܂����B�b�萫�̂��鏗���M�^���X�g�����ǂ�����ɂȂ��B �yAVRIL LAVIGNE�z ����ȃ��C�N�Ńm���m���ȃ��b�N�Ƃ����C���[�W�݂̗̂\���m���Őڂ���B�o���h�͂����܂ł̏o���҂̒��ň�Ԃ̈��芴�B�y���ł��w���B�Ń��E�h�ȃT�E���h�́A�M�y�ɂ͖]�߂Ȃ�������������B�A�������͉̂����̓o���G�[�V�������Ȃ�����ǎv������萺���Y��ł悭�L�т邵���������肵�Ă���B����������ƃg���K�b���L�������Ǝv������ߑ��܂߃��u���[�ȃC���[�W�Ŕ����Ă��邱�Ƃ����߂Ēm�����B�n�܂��������́A�Ȃ��Ȃ���������Ȃ����Ǝv���Ċy����ł�������ǃX�e�[�W���i��ł������悤�ȋȂ�������{���q�B����ȂɒP���ȃX�e�[�W��60���ł�������ƃL�c�C�Ǝv���Ă��܂����B�ł��A�ޏ��̓X�^�[���͂���ς肠��܂��ˁB �yQUEEN + Adam Labbert�z �����ɍ�������Ƃ����ړI�ɗ����ɂ�������炸�A���܂���҂��Ă��Ȃ������B�C����������オ��Ȃ��܂܁A�I�[�v�j���O��SE������n�߂�B�ł��n�܂��Ă݂���A�܂������ł����ˁB�Ƃɂ�������܂ł̃o���h�Ƃ͊i���Ⴄ�B�o���G�e�B�ɕx���Ȃ̐��X�A�����ċȂ��̂��̂������ՓI�Ȗ��́B���炭�A���߂Ċς��l�����Ȃ��Ȃ������Ǝv����قږ��Ȃ̃X�^�W�A���ɂ����I�[�f�B�G���X�͗ǂ��Ȃ������Ă��邱�Ƃ̋��݂��܂��܂��ƌ�������ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B�A�_���E�����o�[�g�����ۂɌ��Ă݂�Ƃ���قLj�ۂ������Ȃ��A�����Ƀt���f�B�ւ̑��h��������Ƃ��낪���ꂵ���B�u���C�A���̃M�^�[�͂܂����������͂Ȃ��āA���t�͂��Ȃ胉�t����������Ǒ����Ĕ��͂��錻�����̂��̂̉��B���W���[�͎Ⴂ���̂悤�ȃL�����Ȃ��͎̂d���Ȃ��Ƃ���2005�N�Ɋςė��_�����Ƃ����琊���̉����͂Ȃ��Œ�C���͈ێ��A�������Ă����Ǝv���B �ăt�F�X��2003�N�̓���JAZZ�ȗ��ŁA�J���I�ȋC�����܂߂Ă��Ȃ�y���߂��B |
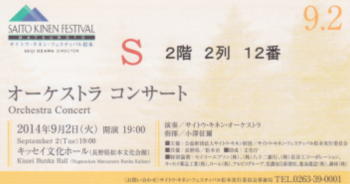 9/2 �I�[�P�X�g���E�R���T�[�g 1�Ȗڂ́A�w���҂Ȃ��ʼn��t����郂�[�c�@���g�̃Z���i�[�h��10�ԁu�O�����E�p���e�B�[�^�v�B�܂������\�K���ĂȂ������̂��I舂���������ǁA�؊�8�l�i�I�[�{�G�A�t�@�S�b�g�A�N�����l�b�g�A�o�Z�b�g�E�z�����e2�l�j��4�l�̃z�����ƃR���g���o�X1�l�Ƃ����Ґ��Ƃ������Ƃ���m�炸�A�����y�̊y���ݕ����܂��킩���Ă��Ȃ��l�ɂ͏��X����i�����鉉�t�ŁA�Ȃ��܂��v������蒷���������Ƃ������ď��X�������Ԃ��߂������ƂɂȂ��Ă��܂����B�Ƃ͂����A�I�[�{�G�ƃN�����l�b�g�̑�1�t�ҁi�O���l�j�̉��F�̑f���炵���͂���Ȗl�ł���������قǂ̂��̂Řr�̊m�����������Ŋ��Ɏ������邱�ƂɁB �����ă��C�������V�����ƃT�C�g�E�E�L�l���E�I�[�P�X�g���ɂ��x�����I�[�Y�̌��z�����ȁB��{�I�Ɉ֎q�ɍ���Ȃ���̎w���ł��鏬�V�̃A�N�V�����ɉ�����I�P�̃T�E���h�́A�����ŗ͋����A���̖���Ղ�ɍŏ����爳�|������ςȂ��������B�J�b�`���Ɠ��������Ă���Ƃ��������͂��܂肵�Ȃ����̂́A�������������ƗY�قɉ̂��B���[�c�@���g�ł������I�[�{�G�A�N�����l�b�g�ɉ����t���[�g�̖L�����N���A�łŔ������������f���炵���B����܂œ��{�̃I�P�ɗǂ���ۂ����������Ƃ��Ȃ��������Ƃ������āA���s�W�c�ƌ����ǂ����F���{�l���S�̏��тȂ̂ł́H�Ƃ������O�͍ŏ���5���Ŋ��S�ɐ������ł��܂����B�W�߂ł���Ȃ���C�O�I�P�Ƒ��F�̂Ȃ���̐�����̑S�̂Ŏ~�߂�������A�ƌ�������ǂ����낤���B�x�����I�[�Y�̌��z�����Ȃ́A�x�[�g�[���F���̏�����̎���ɏ����ꂽ�ȂȂ̂Ƀ��}���h�̉��y�Ƃ��ď\���ȐV���������邱�ƂɈ�ڒu���Ă������̂́A��D���ƌ�����قNjC�ɓ����Ă������킯�ł͂Ȃ������B�����āA�ߋ��̌o������A����قǍD���Ƃ����킯�ł��Ȃ��ȂŊ��������Ă����Ƃ����炻��̓I�P���f���炵������Ƃ����̂��l�̌����ł���A���̓��͂܂��ɂ��������v���������Ă���鉉�t�������ƌ�����B���{�l�i�Ƃ͂����Ă��NJy��͗v���ɊO���l�����邯��ǁj�ł������܂łł���Ƃ����̂͌ւ炵���B  9/3 �}�[�J�X�E���o�[�c�E�g���I�E�R���T�[�g ���t�͉��Ȃ��s���Ȃ��A�܂����ʂł����B�}�[�J�X�̓G�L�Z���g���b�N�ȃs�A�j�X�g�ł͂Ȃ����A�Ȃ��X�^���_�[�h�����S�ŏ��X�ʔ��݂̂Ȃ����e�B�Ȃ͂��̃t�F�X�p�ɑI���̂Ȃ̂��A��������Ȋ����Ȃ̂��m��Ȃ�����ǁA�]��ɂ��`���I�W���Y�E�s�A�m�E�g���I�̃I�[�\�h�b�N�X�Ȃ��̂���B�ł����ۂɒ����@��Ȃ��i������O�����ĉ��t����Ȃ��j"Billy Boy" "Armad's Blues" �Ƃ����Ƃ���������Œ��������Ƃ͂Ȃ����Ɋ����������B�x�[�X�ƃh�����͐������N���A���Ă�����̂́A����������ƈ�Ȗʔ��݂��~�����Ƃ���B |
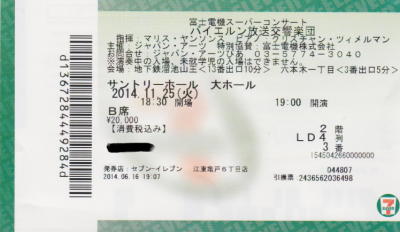 ���̓��͂܂��A�c�B�����}���̃u���[���X�̃s�A�m���t�ȑ�1�ԁB���̋Ȃ͂��傤��1�N�O�ɃO�����[�ƃl���\���XBCSO�Œ����Ă���B�R���T�[�g�����l�ɂƂ��āA���͓����Ȃ��Ⴄ���t�҂Œ����̂͏��߂Ă̑̌��ł�����B�����Ȃ��Ⴄ�̂Œ��ڂ̔�r�͈Ӗ����Ȃ��Ƃ͎v���A�����Ԃ�Ⴄ��ۂ����B�܂��A�I�P�̖���Ղ肪�\�z�قǂ͗ǂ��Ȃ��B�R���`�F���g�Ƃ��Ă͑傫�߂̕Ґ��i14�^���炢�H�j�Ȃ���A�u���`��A�����Ȃ����ǂ���Ȃ���Ȃ̂��ȁv�Ƃ����v���������悬��B����Ńc�B�����}���̃s�A�m�͒[���Ŕ������A����ł��ė͋����Ɉ��Ă��Ēj���Ȃ�ł͂̐c�̒ʂ������������B���������Œe���Ă������̂���Ƃ͊�b�̗͂̈Ⴂ�̂悤�Ȃ��̂�����A�G���W���ŗႦ�Č����̂Ȃ�A�����n�́i���ʁj���o���Ă��Ă��g���N����������G���W�����Ă��Ȃ��i�]�͂�����j�Ƃ����悤�ȈႢ��������B�c�B�����}���̉��t���āA�u�����A���̋Ȃ͂���Ȃɑ̗͂��K�v�ő�ςȋȂ������v�Ǝ������邱�ƂɂȂ����B�~�X�Ǝv����Ƃ������]���ĂƎv����Ƃ�������������A�I�P�Ƃ̂܂Ƃ܂�������ЂƂ���������ǁA��2�y�͂̔������A��3�y�͂̐����Ƃ���������̕\���͂������肵�Ă��ĉ��t�Ƃ��Ă͂ƂĂ���ۂɎc����̂������B��Ŏv���N�����Ɠ��Ƀs�A�m�̉��̈�ۂ������c���Ă��āA����̓I�P��K�v�ȏ�ɔh��ɖ炳���ɁA�����܂ł��s�A�m�Ɋ��Y�����t�����Ă�������Ȃ̂��ȁA�Ǝv���悤�ɂȂ��Ă������B �V���g���E�X�ł̓I�P�̕Ґ����X�Ɋg��A�z�����ȊO�̋��ǂ��吨�����A���ʂȑŊy���n�[�v�t�҂������B���y����S�p�[�g�����i������16�^�N���X�Ɋg��j�B�u�h���E�t�@���v�̈�ۓI�Ȗ`������I�P�̖���Ղ肪��ρA�ꗬ�I�P�Ȃ�̉��̉��o�����B�R���}�X�A�I�[�{�G�̃\���͊���̏ꂪ�������t���������������A�z�����i�傫�߂̊O�����ꔭ����������ǁj�̋������Y�傾������A�ʂ̉��t�͂����\�BCD�ŗ\�K���Ă����Ƃ��͖��R�ƒ����Ă������Ƃ������Ă������Â��ȃp�[�g���Ȃ�ƂȂ��߂��Ă�������ǁA�؊ǂ����ɔ������A���T���u���ŐF�ʂ�^���Ă��ăV���g���E�X�̋Ȃ̂�����؊ǂ̏d�v�����ƂĂ��悭�킩��B�������������������t�̑�햡�B�����\���X�͑S�̂ɂ������ƁA���ɂ�������ƃe���|�𗎂Ƃ��V�[������������Ɯ��ӓI�ȗh�炵�������Ă��āA�P���������������̂͏��X�ȊO�Ȋ����Łu�K�N�̋R�m�v�œ��ɂ��������X���������o�Ă����B�l�ɂ���Ă͗��ꂪ�����Ǝv������������Ȃ��B���́u�K�N�̋R�m�v�A�Ō�̃����c���̓��肪���̂������Y������A�S�̂�ʂ��ĉ��t�ɂ������̏������������Ƃ͔ۂ߂Ȃ�����ǁA�Ȃ��l�Ԗ��������Ă�������Ȃ����A�Ɩl�͊���Ɏ~�߂Ċy����ł��܂����B�������A�l���d������u�I�P���̂Ƃ��Ă̖�E�\���v���������肵�Ă��邩��Ƃ����O��ł���A���{�̃I�P�ł���Ȋ������Ƃ��Ԃ�u���[���v�Ǝv���Ă����Ǝv���B ����̃A���R�[���́A�Ȃ��Ȃ������Œ����@��̏��Ȃ������ŏ������߂Ē����Ă��ƂĂ��y���߂���̂�I��ł��ꂽ�悤���B���Ƀ��Q�e�B�̖����L�Y������Ȃ̓\���̌�����������Ղ�Ŋϋq���y���܂��Ă����v�f�����Ղ�̋ȁB�L���Ȃő����̐l���y���܂���̂��ǂ�����ǁA���̂悤�ɉB�ꂽ��y���L���ȋȂ����t���Ă����̂��܂��y�����B |
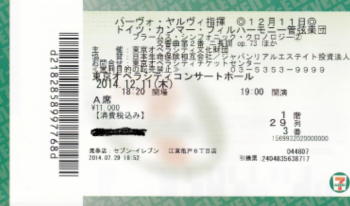 �y���ځz �u���[���X �n�C�h���̎��ɂ��ϑt�� �u���[���X���@�C�I�������t�ȁi�\���X�g�F�N���X�`�����E�e�c���t�j �i�A���R�[���jJ.S.�o�b�n �����t���@�C�I�����E�\�i�^ ��3�Ԃ��"�����S" �u���[���X�����ȑ�2�� �i�A���R�[���j�u���[���X �n���K���[���� ��3�ԁA��5�� �u�n�C�h���̎��ɂ��ϑt�ȁv�͎v������蕁�ʂȉ��t�B�Ȃ��������3��ڂƉ����������߁A���Ґ��I�[�P�X�g���̉����͂��Ă���邩���O�����������̂́A�I�P�̖肶�����͂܂��܂��B�ׂ��f���i�[�~�N�����A�����n���̂��鉉�t�ł��邱�Ƃ����Ɍ����Ă��Ă���B ���́u���@�C�I�������t�ȁv�́A�e�c���t�̍r�X�������t���N��B����܂��Ȃ��������Ƃ��特���͂����S�z���Ă�������ǁA�@�ׂȉ����܂߂ĐL�т₩�Ɏ��ɔ�э���ł��Ă܂������s�����Ȃ��B�ɏ��y�͂ł����̂��鉹�őދ������Ȃ��B��3�y�͂ł͗͂�őO�̂߂�ȓ���������A��т��čr�X���������������t���т����B�I�P���\���ɍ��킹�Ă��Ȃ����Ղ肪�}�ρB�t���E�I�[�P�X�g���̌��݂��鉹�Ƃ͂܂��ЂƖ�����������Ǖ�����Ȃ��͊����Ȃ��B�����ȂƂ���A���̋Ȃł���ȂɊy���߂�Ƃ͎v��Ȃ������B���̓��̃x�X�g�B �u�����ȑ�2�ԁv�́A���@�C�I�������t�Ȃ̐������̂܂܂ɉ��t�����B�r�q�Ń_�C�i�~�b�N�ō����B�I�P�͈ӊO�ƃJ�b�`���Ƒ����������͂Ȃ��A�؊ǂ����ǂ��O���Ȃ�����Ǎ��ꍛ�ꂷ��悤�ȖF���ȉ��F�Ƃ����킯�ł��Ȃ��A�����ȂƂ��됦����肢�Ƃ܂ł͎v��Ȃ������B�ł��K�c�K�c�Ɛ��������܂����A�������������ċ@�q�ŏu���͂̂���Ƃ���͏��l���I�P�����炱���Ȃ�ł��傤�B |
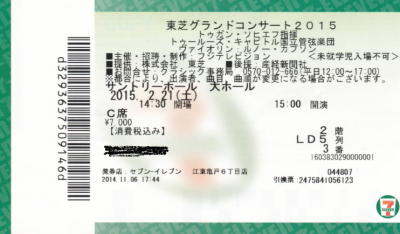 �y���ځz �h�r���b�V�[ �q�_�̌ߌ�ւ̑O�t�� �T��=�T�[���X ���@�C�I�������t�ȁi�\���X�g�F���m�[�E�J�v�\���j �i�A���R�[���j�O���b�N �����f�B ���\���O�X�L�[ ( �����F���ҋ� ) �g�� �w �W����̊G �x �i�A���R�[���j�r�[�[ �J��������3���̊ԑt�� �J��������1���̑O�t�� �h�r���b�V�[�͒��ۓI�ŐF�ʊ��̂��鉹�y�Ƃ����C���[�W�ʂ�B�t���[�g�̏_�炩�������A�I�P�̖F���ȃT�E���h���������B �T��=�T�[���X�̃��@�C�I�������t�ȑ�3�Ԃ͐L�т₩�ɉ̂��t���[�Y�������āA�J�v�\���̉��t�������Ŗ��āB�X�b�L���Ƃ킩��₷���T��=�T�[���X�炵�����悭�o�����t�������Ǝv���B���̋Ȃ͐��Œ��������ƂŌ��������B ���C���́u�W����̊G�v�͎��̓N���V�b�N�ɋ������Ȃ�����5�N�O�A�V�����s�ōs���������h���ŃQ���M�G�t�w��LSO�Ő����t�ɐG�ꂽ�v���o�̋ȁB���̂Ƃ��͐��̉��̑f���炵���ɖ������ďI����Ă��܂��A���t�̎��������o���Ă��Ȃ��B����͂�����x�N���V�b�N�ɐG��Ă���̉��t�łƂĂ��y���߂��B�Ґ����傫���A�����F���̕ҋȂ����ʂȂ��Ƃ��悭�킩�����B�剹�ʂŐ���オ��ȂȂ����łɗ��������Ŋy���߂��B |
 �u���[�m�[�g�����ɂ�MEHLIANA���ƁA�u���b�h�E�����h�[���}�[�N�E�W�����A�i�̃f���I�A3/13��1st�Z�b�g�B�A���o���̕��́A�Â��G���s��V���Z�̃T�E���h�������h�[���ɗ��������T�E���h�ɂ��܂�ǂ����G�������Ă��Ȃ���������ǁA��������ă��C���Œ����Ɠ��������ׂČ����邱�Ƃ������Ď��ۂ͑�Ⴂ�������B�͔C���ɑ���Ȃ��W�����A�i�̃h�����͍��x�Ɉ���A�ڔz�����邱�Ƃ��Ȃ�2�l�����Ă���Ɨ\�ߋȂ̗���͌��܂��Ă��邱�Ƃ��킩����̂́ACD�ł͊������Ȃ����R�ɂ���ėǂ��̈悪���炩�ɂ����āA���̏�ō��o����鉹�Ŋ����邱�Ƃ��ł���̂��u���[�m�[�g�Ƃ������Ŋς��햡���Ǝ����B�L�[�{�[�h�ƃh�����̃f���I�Ƃ����̂͂悭�l����ƃ}���n�b�^���̃W���Y�E�N���u��������ǂ����ŒN��������Ă��Ă����������Ȃ����̂ŁA����Ӗ��j���[���[�N�̓��킩�琶�܂꓾�鉹�y�̈ꕔ���ŏ�̃~���[�W�V�����Ŗ����Ă�������Ƃ������Ƃ��ł���Ǝv���B |
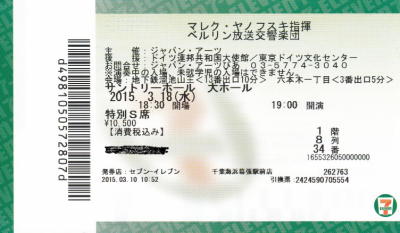 �y���ځz �u���b�N�i�[ �����ȑ�8�� ���t�́A����͂����ƂĂ��Ȃ��f���炵�������B�ׂ����_��������Α����̗���͂������Ǝv�����A�e�p�[�g���ꂼ�ꂪ���ꍛ�ꂷ��قǂ̔������������ƌ����Ƃ����܂łł͂Ȃ������Ǝv���i���{�̃I�P���͂����Ə�肢�P�h�j�B�ł��A�I�P�̖���Ղ�͐��������B���ǂ̃p���[�Ɖ��̂���؊ǁA���������łȂ��G�����܂ǂ��Ӗ��ł̑e���Ɣ����������˔��������̃o�����X���ǂ��A�܂��ɃI�[�P�X�g�������炩�ɉ̂��Ă����ԁB���ʂɉ����Ă��m�Ẩ����ʼn��t����̂ł͂Ȃ��A�����܂ł������I�ɕ\������̂��C�O�I�P�̓����ł��邱�Ƃ͉ߋ�2�N�̃R���T�[�g�ʂ��̌o���ł킩���Ă�������ǁA�����܂ŗ��h�ɃI�P�����Ă����Ԃ͂������x���o�����ĂȂ��B���̐����Ȃ������o���̂ЂƂ�2013�N�Ɋς��}�[�[���w���~�����w���t�B���̃u���b�N�i�[3�Ԃ������̂ŁA���������u���b�N�i�[�̋Ȃ��I�P�̂���������ʂ�K�R�I�Ɉ����o���A�I�P������ɉ����Ȃ��Ɛ������Ȃ����y�Ȃ̂����A�Ǝv�����������B���m�t�X�L�̎w���̓I�[�\�h�b�N�X�ŁA�e���|���グ��Ƃ���̓L���ǂ��A���߂�Ƃ���͗��߂銴���Ŗl�̍D�݂ɋ߂������̂�������傫�����Ă��ꂽ�v���B������ɂ��Ă������܂ň��|����鉉�t�������Ƃ͖{���ɍK�^�������Ǝv����B������ł��K���ɂ��Ȃ��Ă��u�����A���̂܂I��炸�ɂ����Ƒ����Ă��ꂽ�炢���̂Ɂv�Ɗ肤�悤�ȋC�����ɂȂ�邱�Ƃ͂����͂Ȃ��ɈႢ�Ȃ��B���ꂾ���̏[�����𖡂�������Ƃł̓A���R�[���Ȃ��͐����B���t�I���Ŏw���҂��^�N�g��U��グ�Ē�~�����܂܂̌��\�Ȏ��Ԃ����̂܂ܒ����Î�ɂȂ�A�^�N�g�����낷�Ɛ���Ȕ���ƃu�����H�[�Ƃ����ϋq�̃}�i�[��������{�������Ă��ꂽ�̂��f���炵���̌��������B |
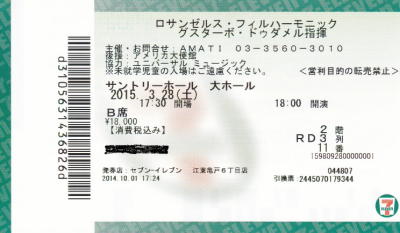 �y���ځz �}�[���[ �����ȑ�6�� ���߂Ẵ}�[���[�A���߂ẴA�����̃I�P�B �Ґ����傫���Ȃ������t�ł��f���邱�Ƃ́A�ߋ��ɒ������u���b�N�i�[�̌o������Ȃ�ƂȂ��z�������Ă�������ǁA������킩������ł���͂舳�|����Ă��܂����B�e�p�[�g�̓�������Ղ��Č��Ă��Ă����̍�ȉƂ̋ȂƂ͓������Ⴄ���A���푽�l�̊y�킪������鑽�ʂȉ���t�ł�I�[�P�X�g���[�V�����̖ʔ����������ɖ��키���Ƃ��ł��Č��Ă��Ď��ɖʔ����B�}�[���[�ł͓x�X������z������؊ǂ̎����グ�A��4�y�͂̃n���}�[�̈ꌂ�i�H�j�͎��o�I�ɂ����͖��_�A���ʂł́u�����̃V���o���v�Ǝw�肳��Ă���Ƃ���Ō�����5�l�����́u�o�b�V���[���v�Ȃlj������ʂ���������Ă��y�����ς邱�Ƃ��ł���B�u�}�[���[�͐��i���邢�͉f���j�Łv�Ƃ���������m���������R�����ł��킩�点�Ă����y�����̌��������B ���T���[���X�E�t�B���n�[���j�b�N�́A�Ƃɂ������ׂẴp�[�g�̖���Ղ肪���܂����B�Ґ����傫���Ƃ������R�͂���������ǂ��A���ǂ��؊ǂ������o���������A�����ƂĂ��ǂ��̂��B���ɖ؊ǂɈ��͂��������̂͏��߂Ă̌o���������B�I�P�S�̂������ɉ̂��Ƃ����ϓ_�Ō����A����܂łɌ����ǂ̃I�P�����ゾ�����悤�Ɏv�����A�e�p�[�g������邱�ƂȂ����t�͂������B�܂��A����͓y�n���̂����Ȃ̂��o�Ă���T�E���h�����邢�B����Ӗ��G���^�[�e�C�����g���������T�E���h���Ǝv���̂ŁA�}�[���[�Ɏ����Y�A�h���h��������O�i�Ⴆ�e���V���e�b�g�̂悤�ȁj�����߂�ƁA������ƈႤ�Ȃ��Ƃ����l������ɈႢ�Ȃ�����ǁA�ǂ�ȉ��y����{�I�ɂ͌�y�ƍl���Ă���l�̂悤�Ȑl�Ԃɂ͑傢�Ɋy���߂鐫�i�̃I�P�������B |
 ���E�t�H���E�W�����l 2015��3�����B 5/4�i���j �y1�z ���t�F�A���f�I���y�l�d�t�c ���ځF�V���[�x���g ���y�l�d�t�ȑ�14�ԁu���Ɖ����v ���F�z�[��B5 �l�͎����y�n�ɂ͂܂����܂�G��Ă��Ȃ�����ǁA���͂��̋ȁA������D���������炵���A�q���̂���ɉ��x����������Ă����̂łقƂ�Ǔ��ɓ����Ă��āA����ł͐��Œ����Ă݂悤�ƑI�v���O�����B�A���f�I���y�l�d�t�Ȃ͏����̃J���e�b�g�ŁA�`������ْ������ӂ�邱�̋Ȃ��\�t�g�Ɏn�߂āu���₨��H�v�Ǝv�������̂́A�R��ׂ��Ƃ낱�ł͗͋����A�t�B�i�[���͑��ݖ炵���肵�ĂȂ��Ȃ��̔M���ł����B�L���ɖ��ߍ��܂�Ă����Ȃ̑f���炵�����悤�₭�����ł��������ő喞���BB5���͎n�߂Ă���������ǁA������܂�Ƃ��Ă��čD��ہB �y2�z ���t�F�A���h���[�V���E�P���[�icond�Avl�j �Z���Q�E�c�B���}�[�}��(vl�j �R���`�F���g�E�u�_�y�X�g ���ځF�o�b�n 2�̃��@�C�I�����̂��߂̋��t�� �j�Z�� �o�b�n ���@�C�I�������t�ȑ�1�� �o�b�n 2�̃��@�C�I�����̂��߂̋��t�� �n�Z�� ���F�z�[��B7 �o�b�n�͂܂��^�ʖڂɒ��������Ƃ��Ȃ��A���t�������قǑ����Ȃ��̂ł���ȂƂ��ł��Ȃ���ΐ��Œ����Ȃ����Ȃ��Ǝv���Ă̑I���B����B7���͍L���i800���ȏ���e�j�̂ŁA�l�C�v���O�������������̂́A��N�ςĎv�����͍̂L�����ɂ̓X�e�[�W���Ⴍ�ĉ��t�҂������ɂ����̂ƁA���y�p�̉��łȂ��̂ʼn������̂������f�b�h�ł��������Ƃň�ۂ͍ň��łł���ΑI�т����Ȃ��������B���N�͑�^���j�^�[�����E�ɐݒu���Č��₷���ɔz������Ă��āA���̋����������Ԃ�ǂ��Ȃ����悤�Ɋ������B���̋������ǂ��������̂́A���N�̎l�d�t�c�������̂ɑ��č��N�̓`�F���o���܂�16���̊y�c�Ƀ\���X�g�Ƃ����Ґ����������������邩������Ȃ�����ǁA�������P�����낤���B�̐S�̉��t�́A���Ɉ����Ƃ��ǂ��Ƃ��v�킸�E�E�E�A�܂��A�o���b�N�͂܂��悭�킩��܂���ˁB�ł��A���̐��̃o���b�N�͐S�n�悭�������̂Ŗ����B �y3�z �w���F�A�W�X�E�V���n�L���t ���t�F�G�J�e���[�i�E�f���W�����B�i�ip) �f���b�Z���h�t�����y�c ���ځF�V���[�x���g �u���U�����f�v���� �V���[�}�� �s�A�m���t�� ���F�z�[��C ���͂��ꂪ��Ԋ��҂��Ă����v���O�����B�ӊO�Ɖ��t�@����Ȃ��A���}���`�b�N�ȃV���[�}���̃s�A�m���t�ȂŒ����Ă݂��������B����܂ł̃��E�t�H���E�W�����l�ŁA�C�O�I�P�̉��t�͂قƂ�ǍD��ۂ������̂ň�背�x���ȏ�̂��̂͒����邾�낤�Ƃ������҂��������B�Ƃ��낪�A1�Ȃ߂́u���U�����f�v����I�P�̋������キ�A���̉��₩�����Ȃ��B�����O���Ƃ������Ă��Ȃ��Ƃ��͂Ȃ����̂́A�Ƃɂ������̎咣���������Ȃ������B����̓s�A�m�����l�ŁA�����������ƌ����Ď咣��������ꂸ�B���ꂪ�|���ƌ���������Ȃ̂�������Ȃ�����ǁA����܂Ŋς��ǂ̊C�O�I�P�n�̉��t�������ɖL������������ꂸ�A�V���[�}���̗D�������ӂ�郍�}���`�b�N�����Ȃ������̂͂�����Ǝc�O�������B |
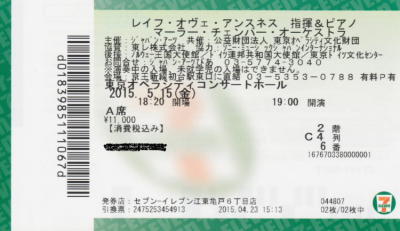 �y���ځz �x�[�g�[���F�� �s�A�m���t�ȑ�2�� �x�[�g�[���F�� �s�A�m���t�ȑ�3�� �x�[�g�[���F�� �s�A�m���t�ȑ�4�� (�A���R�[���j �x�[�g�[���F�� �o�K�e�� op. 119-8�i�W���p���E�A�[�c�̔��\���j �ŏ��͂܂��S�s�A�m���t�Ȃ̒��ł���ԕҐ�����������2�Ԃ���B�A���X�l�X���U��A�Ȃ��n�܂�Ə��Ґ��̃I�[�P�X�g���Ȃ��烊�b�`�ȉ����o�Ă���B�����؊ǂ����̖F���Ƃ��������l���Ȃ��قǏ_�炩���L���ȉ����Ă��Ē�������Ă��܂��B�������A�Ј����₯�����܂�����������킯�ł͂Ȃ�����ǁA����͋Ȃ����������v�����Ă��Ȃ����瓖����O�ŁA����ł���u�̃t�H���e�Ȃǂŏu���͂��s�����̂����邾�낤���Ƃ��_�Ԍ�����B�s�A�m�͓����ʂ�悤�ȓ������������Ă��āA���̌ÓT�I���t�Ȃ̌y�₩���������o���Ă���B�ł������Čy�X�������Ȃ��̂̓I�P���l�ɂ悭�������ď_�炩�����J�ɉ��t���Ă�������ł͂Ȃ����Ǝv���B������3�Ԃł́A�g�����y�b�g�A�N�����l�b�g�A�e�B���p�j�Ȃǂ���������A�ÓT�I��2�Ԃ��V�������o�������B����ł��I�P�̕Ґ��͏������A�������Ȃ���F�����͎����Ȃ��ǂ��납�܂��܂���������B�����̏d�������������ÓT�I�ȑf�p�������킸�ɂ��̋Ȃ̑f���̗ǂ��������o���Ă����ہB�f�p�ŐÂ��Ɏn�܂�Ƃ���Ƀx�[�g�[���F���̂������̃Z���X���f�킹���4�Ԃ́A��1�y�͌㔼�Ƒ�2�y�͂̓\���E�p�[�g�������A���̉���Ԃ��܂����������S�n�悢�B�t�B�i�[���̂����ɂ��x�[�g�[���F���炵�����g�����͋����A���̋Ȃ̗ǂ������\�����Ă������̂������B�Ȃ������Ⴄ�̂Ŕ�r����̂̓t�F�A�łȂ��Ǝv������ǁA���̃I�P�͉ߋ�2�N�ŊςĂ����Q���@���g�n�E�X�nj��y�c��o�C�G�������������y�c�A�h�C�c�E�J���}�[�t�B���Ȃǂ��������ƍI����ہB |
 �R�b�g���N���u�ɂăT�C�����E�t�B���b�v�X�E�v���g�R���A2015�N6��19�� 1st�Z�b�g�B����2�N��2�����A���o���������[�X����ȂǁA�Z�����͂��Ȃ̂Ɍ��\�{�C�ł���Ă���T�C�����̃\���E�v���W�F�N�g�B�����o�[�̓A���o���Ɠ������A�A���f�B�E�e�B�����Y�i�M�^�[�j�A�X�e�B�[���E�E�F�C���K�[�g�i�L�[�{�[�h�j�A�A�[�l�X�g�E�e�B�u�X�i�x�[�X�j�Ƃ�����Ԃ�B�A���o���ł̍��x�̉��t�����̂܂܍Č�����4�l�Ƃ��Z�ʂ͑債�����́B���ɃL�[�{�[�h�͌@��o�������Ǝv���B����ɂ��Ă��T�C�����͐����B�܂�Ȃ��Ƃ����l�����邩������Ȃ�����ǁA���̑�d�|�ȃh�����Z�b�g�������܂Ŏ����̂��̂ɂ��Ă���l�͂��Ȃ��Ǝv���B�ԋ߂Ŏv�������@���T�C�������ςꂽ�����Ŗ����B |
 2007�N�A2008�N�ɃW���Y��{��Œ������߂ɍs�����}���n�b�^���ɍs���A����̓N���V�b�N��{��Œ������߂ɃE�B�[���ƃx�������ɍs�����B �y1�z <���>�E�B�[���y�F���� �u�����V���e�b�g�w���E�B�[�������y�c <����>�x�[�g�[���F���F�����ȑ�4�� �j�[���Z���F�����ȑ�5�� ���y�̗��A��1���ڂ̓E�H�[�~���O�A�b�v�I�ɃE�B�[�������y�c�������B�������A������E�H�[�~���O�A�b�v�ƌ����Ă��܂��̂͂��܂�Ɏ���ȏ�肢�I�P�B�܂��Ȃ��Ȃ����{�ł͒����Ȃ��j�[���Z���͎����Œ����Ǝ��ɃX�P�[�����傫���A�I�P�̕\���̗Y�傳�ɂ��������B  �y2�z <���>�E�B�[���y�F���� �����\���X�w���E�B�[���E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c <����>�}�[���[�F�����ȑ�3�� �i�A���g�F�x���i���_�E�t�B���N�j �}�[���[�̑�������\���X�w���E�B�[���t�B���ŁA�����邾���Ŏ����̊�сB���������D��Ȍ��A�����ȋ����ƃA���T���u���̃E�B���i�[�z�����A���[�����狿���_��I�ȃ|�X�g�z�����A�t�B���N�̗͋������A���ʉ��Ŕ��������������A���ׂĂ������A�w�F�����L�̑��߂Ȏc�����Ɠ��Ȑ��E�ɂ��Ă��܂��B�����\���X���Ȃ̕��j�����߂Ă���̂͊ԈႢ�Ȃ��A�������I�P�̃T�E���h�ɂ͊m�ł���咣���������B  �y3�z <���>�x�������E�t�B���n�[���j�[ ���g���w���x�������E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c <����> �n�C�h���F�����ȑ�80�� ��i�i�`���E�E���X�N�j�F �\�v���m�Ɗnj��y�̂��߂́uLe Silence des Sirenes�i���̐��̒��فj�v �u���[���X�F�s�A�m���t�ȑ�1�ԁi�s�A�m�F�N���X�`�����E�c�B�����}���j �n�C�h���͎����I�P�̋K�͂ł��n�b�L���Ɩ��ĂŖL���ȉ��F�Ɗ����ȋZ�I�������B�`���E�E���X�N�̌���Ȃ� ���g�����w����ɏオ��Ƃ��̂܂ܓ��𐂂�Ă����ƐÎ~�A���炭����Ɖ�������̐����������n�߂�B�ʘH����\�v���m�̃o�[�o���E�n���j�K�����p�X�e���J���[�̔h��Ȉߑ��ʼn̂��Ȃ���o��B���̂܂܉̂��Ȃ�������ăX�e�[�W�ɏオ���čs���B����Ȃ炵���A���G���A���@���M�����h�ȃ��Y���ƃI�[�P�X�g���[�V�����A�����đ�l����v��������̑Ŋy��̕��G�ȗ��ݍ����B�n���j�K���͉������߈˂������̂悤�ɉ̂��A���Ƀ��g���Ǝ�����킹���������B�ߑ��₱��牉�o�͂ǂ�����ȉƂ��w�肵�Ă���悤�ŁA�Ȃ��I��������Ƃɓo�ꂵ����ȉƂ̒�i���n���j�K���Ɠ����悤�ȐF�ʂ̕��𒅂Ă����B �Ō�̓u���[���X�̃s�A�m���t�ȑ�1�ԁB�c�B�����}���ɂ�邱�̋Ȃ͍��H�A�����\���X�w���o�C�G�������������y�c�Œ���������ǁA�܂��͓������̃e���|�ݒ肪�����Ƒ����Ƃ��납�炵�Ĉ���Ă����B�I�P�͑@�ׂ��A���m���A���̉��₩���A�X�P�[�������ׂĂ������đ��߂̃e���|�ɓ�Ȃ��ǐ����Ă��Ċ��S�������B�c�B�����}���������̔M���ŁA�����O�̒[������ۂ��͋����A���ɐ����]���Đ摖���ʂ��B�Ȃ���͎�̓������o�b�`�������ėՏꊴ�����Ղ�Ŋy���߂��B  �y4�z <���>�x�������E�t�B���n�[���j�[ �\�q�G�t�w���x�������E�h�C�c�����y�c <����> R.�V���g���E�X�F�p�Y�̐��U ���̓��̓J�W���A���R���T�[�g�őS�Ȏ��R�A�w���҂��I�P�̃����o�[�������B�ŏ��Ƀ\�q�G�t���p��ŋȂ̉�����A�Ȃ̈ꕔ�����t�����Ȃ���20���قlj���B���ꂩ��ʂ��ʼn��t�Ƃ����i�ߕ��B�O���Ƀx�������E�t�B�����ςĂ����̂Ō���肷�邩�Ǝv������܂���������Ȃ��Ƃ��Ȃ����h�ȉ��t�Ɋ����B |
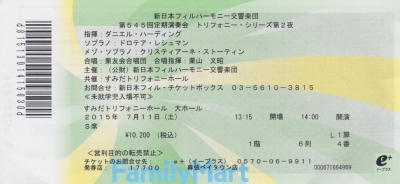 �n�[�f�B���O�w�� �V���{�t�B���n�[���j�[�����y�c ������� �\�v���m�F�h���e�A�E���V���}�� ���]�E�\�v���m�F�N���X�e�B�A�[�l�E�X�g�[�e�B�� �����F�I�F����c <����> �}�[���[ �����ȑ�2�ԁu�����v ����܂ł̌o���œ��{�̃I�P�̒n�͂̂Ȃ��͂悭�킩�������肾��������ǂ��A�V���{�t�B���A�n�[�f�B���O�͂܂����̌��ł��������ƁA�}�[���[�̕����łǂ����Ă����������Ȃ������Ƃ������Ē����ɍs�����B���_���猾���ƁA�\�z�ʂ�A���{�̃I�P�̒n�͂̂Ȃ����m�F���邱�ƂɂȂ��Ă��܂����B��1�y�͂̃V���o������Ƃ���܂łł������̋������n��ł��邱�Ƃ��I��A���ǁA�؊ǂ͂܂��܂��悭����Ă����Ǝv������ǃY�b�R�P��Ƃ�������������A��ɗ]�T�������B�S�̓I�Ɋ撣���Ă��ĔM���������Ƃ͎v������ǁA�A���T���u������������Ȃ����A���ʂ����ł��܂����Ă����������炠�����B�c�O�Ȃ��炱�ꂪ���{�̃I�P�̌���Ȃ�ł��傤�B�C�O�I�P���`�P�b�g����������A�Ƃ����̂͌�����ɂȂ�Ȃ��B�y�F����ŃE�B�[�������y�c�̈�ԍ����Ȃ͂��̓��̃`�P�b�g���������A�I�P�̎��͍��͔�r����̂��݂���قLjႤ�̂�����B |
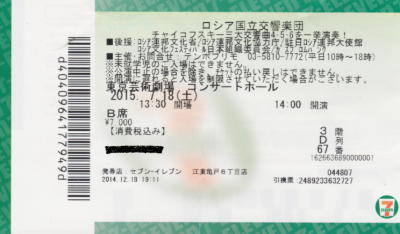 �|�������X�L�[�w�� ���V�A���������y�c <����> �`���C�R�t�X�L�[ �����ȑ�4�� �`���C�R�t�X�L�[ �����ȑ�5�� �`���C�R�t�X�L�[ �����ȑ�6�ԁu�ߑs�v ���[�Y�i�u���ȃv���C�X�Ɠ{���̃v���O�����Ɏ䂩��čs���Ă݂��B���_���炢���Ɖ��i�����Ƃ��������B�m���x�������I�P�قnj����؊ǂ������Ȃ����A���ǂ͊C�O�I�[�P�X�g���Ƃ͎v���Ȃ��قǕs����ōr���ۂ��BTwitter�Ȃǂł́u���j�Ɏc��v�ȂǂǂƏ^�̐���F�A���n�ł͉��t�I���̎c���������Ȃ��������炻����đ吨�Ŕ���Ƃ��Č������Ƃ��Ȃ��قǂ̃u���{�[���̋��т������A�Ȃ��ٗl�ȕ��͋C�B�����厖�Ȃ��̂������Ă����낤���B�u�ߑs�v�̂Ƃ��ɂ͂����Ŗ����Ă���ϋq�������������A�P�ɐH�ו���o�C�L���O�̂悤�ȃR���T�[�g�Ō����Ĕ��������͂Ȃ������B |
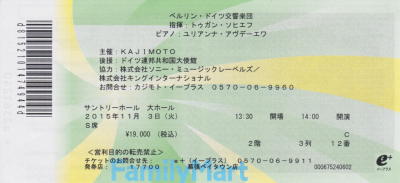 �����f���X�]�[�� ���ȁu�t�B���K���̓��A�v �x�[�g�[���F�� �s�A�m���t�ȑ�3�ԁi�s�A�m�G�����A���i�E�A���f�[�G���j �i�A���R�[���j ���V���p�� 24�̑O�t�� op.28-15�u�J����v �u���[���X �����ȑ�1�� �i�A���R�[���j ���O���[�N 2�̔߂����������u�߂����t�vop.34-2 �����[�c�@���g �u�t�B�K���̌����v���� ������S�������f���X�]�[��������ė���ƁA4�����O�ɒ������Ƃ��Ƃ͂����ԋ������Ⴄ�B�c�����Ȃ��Ė���T���ځB 2�Ȃ߂̃x�[�g�[���F���ł��I�P�̈�ۂ͕ς�炸�B���̋ȂƂ��Ă͋K�͂̑傫���Ґ��ʼn��t����Ă��ĉ��̌��݂͂������ǁA��͂艹��������ł���B�����悤�ɂ���Ă͕\�ʓI�Ȕ����������a�݂��������T�E���h�ŁA����͂���łЂƂ̌����Ǝv���Ă���B�������A������̒����ǂ���͓��R�s�A�m�B���̓��ς��A���f�[�G���́A�ƂĂ���ۂ��ǂ������B�����䂦�̃^�b�`�̌y���͓��R�̂��ƁA�������ꉹ�ꉹ�������Ăŗ��������Y��ɑ����Ă��ď����L�@�I�ɒ�������B��{�I�ɂ͗��m�I�ȉ��t�Ȃ���₽����ۂ͊F���B�����特�y�������������Ē������Ă���B�A���R�[���̃V���p�����[�����L���ȕ\���B �x�e��̃u���[���X�͕Ґ��������Ă����ƌ��݂𑝂��B���������A���̃T�E���h�������x�������Œ������i���̂Ƃ��́u�p�Y�̐��U�v�j�T�E���h�ɋ߂��B���̃I�P�͕Ґ����傫���A�d���ȋȂɍ����Ă���낤���B����ł��T�E���h�̏a�݂͂��̓��ʂ��ĕς��Ȃ���ۂŁA�����l�͌��Ƃ��Ċy���߂��B���������u���[���X�������B�܂��A�A���R�[���ʼn��t���ꂽ�Ȃ��ǂ��Ӗ��Ō��̗͂������Ă��ĊJ���I�ȃT�E���h�ɒ��������B�x�������Œ������Ƃ��̓J�W���A���R���T�[�g����������A�Ђ���Ƃ����班�����胊���b�N�X���ĉ��t�����ق������̃I�P�͗ǂ�������������Ȃ����ȁA�Ƃ��v�����B �I�P�Ƃ��ăr�b�V���ƌ��i�ɑ��������x�����邩�Ƃ����Ƃ����ł͂Ȃ��Ǝv���B�L���ɐ[�����܂�銴�������������Ƃ����Ƃ����܂łł��Ȃ��B����ł��A���L���ȃT�E���h���y���߂��ǂ��R���T�[�g�������Ǝv���B |
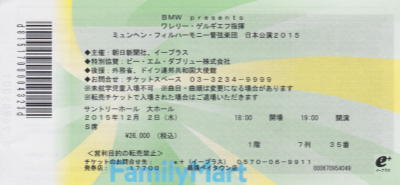 �v���R�t�B�G�t�F�w�����I�ƃW�����G�b�g�x�g�Ȃ�� ���u�����^�M���[�ƂƃL���s�����b�g�Ɓv�i��Q�g�ȑ�P�ȁj ���u�����W�����G�b�g�v�i��Q�g�ȑ�Q�ȁj ���u�C���m���[�����X��i��Q�g�ȑ�R�ȁj ���u���ʁv�i��P�g�ȑ�T�ȁj ���u�W�����G�b�g�̕�̑O�̃����I��i��Q�g�ȑ�V�ȁj R.�V���g���E�X�F�������u�h���E�t�@���v �u���b�N�i�[�F������ ��4�� �u���}���e�B�b�N�v �܂��̓v���R�t�B�G�t�̃����I�ƃW�����G�b�g����B�ꉹ�߂���������܂����L���ȉ��F��\��������Ռ��I�Ȏn�܂�B�ŏ��ɏo�Ă��鉹�ł����Ȃ舳�|����Ƃ����̂̓R���T�[�g�̍\���Ƃ��Ă͂Ȃ��Ȃ����ʓI�B�d�����Ɖ��̂��閾�邢���F�������Ƀu�����h����A���ǁA�؊ǂ̍������x���ł̈��芴���f���炵���A2�N���O�Ɉ��|���ꂽ�Ƃ��̈�ۂ��̂��́B�������w���҂��ς���ċȂ̕\���̎d�����Ⴄ���Ƃ͖����ł��邯��ǂ��A�I�P���咣���Ă��鉹�ɂ͂��������̃u���������Ȃ��B�x�������E�t�B���̓S�ǂ̃A���T���u���Ƃ͂܂��Ⴄ���̃I�P�Ȃ�ł͂̎咣�̂���܂Ƃ܂�A���������Ė{���ɑf���炵�������B �h���t�@���̓���͐����]���Ă��o���������������̂́A���������A�����ȃe���|���D�u�Ƃ�����X�����h���t�@���B�������A�y�X�����͂Ȃ��d����������Ƃ��낪���̃I�P�̗ǂ��Ƃ���B���y�ēɏA�C��������̃Q���M�G�t�̃X�^�C���ɂ̂��Ƃ�����ŁA�I�P�̎咣���������蒮������Ƃ���Ɏv�킸�X���Ă��܂��B ���C���̃u���b�N�i�[�́A�`���̐[���ȃz�����̋������\�z�ʂ�f���炵���B�u���b�N�i�[�́A�Ȃ������Ȃ̂����瓖�R�������Ƃ����[�݂̂���\�������߂���Ƃ���ŁA�I�P�͓�Ȃ���������Ȃ��Ă��܂��B�����ɃX�s�[�h���グ��Ƃ���ł͔��͂Ɛ��i�͂��K�v�ł���̂��u���b�N�i�[�A�Q���M�G�t�͑S�̂ɑ��߂̃e���|�ŃI�P�̌��݂̂��鐄�i�͂������o���B2�N���Ɋς��Ƃ��ƕς��ʑf���炵���I�P�̎��͂��ĔF�����錩���ȋ����Ɉ��|������ςȂ��������B |
 �}�[�N�E�W�����A�i�E�W���Y�E�J���e�b�g�A�R�b�g���E�N���u 2016�N1��3��1st�Z�b�g�B Mark Guiliana(ds) Shai Maestro(p) Jason Rigby(ts) Chris Morrissey(b) �u���b�h�E�����h�[�̂Ȃ���Œm�����}�[�N�E�W�����A�i���{�Ƃ̃G���N�g���b�N�H���Ƃ͕ʂɎn�߂��A�R�[�X�e�B�b�N�E�W���Y�̃J���e�b�g�B�n�܂���3�Ȃ́A�����鍡���A�R�[�X�e�B�b�N�E�W���Y�̓T�^�I�ȃT�E���h�B���Ղȃt�H�[�r�[�g�͎g�킸�A�ǂ������Ώ_��ȁA���������Β݂͂ǂ���̂Ȃ����Y���������A�W���V���A�E���b�h�}���̃O���[�v�AJames Farm�̂悤�ȍ����̃T�E���h���������Ă���B��������|�b�v������菜���Ē��ې�����⋭�����Ă���Ƃ͂����A���ꂾ���ł͌�������Ȃ����\�z�ʂ肷���Ă܂�Ȃ��B �s�A�m�̃V���C�E�}�G�X�g���̃t���[�W���O�͕��ʂ̃W���Y�E�s�A�j�X�g�̃e�C�X�g�Ɩ��炩�Ɉ���Ă��āA�d�����Ɛ��������܂��Z�������s�v�c�ȃ��[�h���ʔ����B�e�i�[�̃W�F�C�\���E���O�r�[�͂��܂�咣���Ȃ��^�C�v�ł��̃o�����X�������̃O���[�v�̎������ɂȂ��Ă���B�C�}�h�L�̃X�^�C���łȂ�ł��e�����Ȃ��x�[�X�͊�p�ł��Ȃ������Ă�����Ƃ��낪�Ȃ��D��ہB���[�_�[�̃h�����̃X�^�C���̓����h�[�̂Ƃ��قǂɂ̓O���[�������o�����ɏ��Z�Ń��Y�����x���銴���B�����ЂƂʔ����Ȃ��Ȃ��A�Ǝv���n�߂��4�Ȃ߂͓ˑR�t�H�[�r�[�g�B�����ł̃W�����A�i�̃r�[�g���̓W���Y�E�h���}�[���̂��̂ŁA�Ȃ�قNJm���ɂ��̐l�̊�{�ɂ̓W���Y������ȂƂ��������͂��������B���̌���킩��₷�����Y���̋Ȃ������n�߁A�ʂ��Ē����Ƒ��l�ȃ��Y���Ɖ��y���ɖ������O���[�v���Ƃ킩��X�e�[�W�ɂȂ��Ă����B�e�i�[�������ăs�A�m�E�g���I��ԂɂȂ����Ƃ��ɃO���[�v�̃J���[���K���b�ƕς���ʐ����ʔ����B�W�����A�i�̓g�j�[�E�E�B���A���X���A�C�h���Ƃ̂��Ƃ�����ǂ��l�͂ނ���G�����B���E�W���[���Y�̂ق��ɋߎ������������B�^���^���A�t���A�E�^���̃`���[�j���O�ƃt�B��������ɏd�X�����������āA�傫�ȃ{�[����]�������̂悤�ȃO���[���������邩��B�㔼�Ńe�i�[�ƃf���I�ɂȂ�V�[��������A�R���g���[���ƃG�����B���ւ̃I�}�[�W���ƌ��㕗���߂ɒ��������B��������ĕ��^���ɂȂ��Ă��炸���������̃J���[�ŕ\���ł��Ă���Ƃ���͎��͂����邩�炱���Ȃ�ł��傤�B |
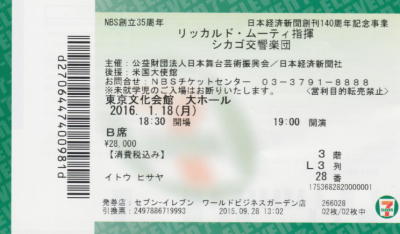 �܂��́A�x�[�g�[���F����5�ԁB���[�e�B�w���t�B���f���t�B�A�nj��y�c��CD�͑��߂̃e���|�Ői�ނ��A���̓��͂������߁BCSO�ƌ������ǂ��L���Ƃ�������ςŐڂ������̂́A���������x�[�g�[���F�������ǃZ�N�V�����͏��Ȃ߂̕Ґ��ł��邱�Ƃ�����ʐ����Ƃ�����ۂ͎Ȃ������B����������߂̌��̋����ƁA�؊ǃZ�N�V�����̃P�������̂Ȃ��L�т₩�ȉ��Ɏ���D����B�����Ď㉹���̉��̊m�����ƖL�����ɂނ����͂�������B�e�Z�N�V�����̑����������Ȃ��́B���`�A�Ȃ�ď�肢�I�P���Ă���낤�Ƃ������S�ɐZ���B���̋Ȃ����ŃI�[�f�B�G���X�𖣗����������ƌ����Ă�������������Ȃ��B �}�[���[��1�Ԃ́A�����̐Â��ȃp�[�g�Ō��̎㉹�̑f���炵�����⊶�Ȃ����������B�؊ǂ̏o�Ԃ���������A�������������̘A���ƌ����ėǂ��قǍI�������\�ł���B�����đ啝�ɑ������ꂽ���NJy��B�z�[���̃A���T���u����炵���͐����@�B�̂悤�Ȑ��m���Ƃ������̓G�l���M�b�V���ȗ͊�������́B�S�̂ɂ��������Ɖ̂킹��e���|�Ői�݁A���e���|���Ƃ��ĉ��t���ꂽ��4�y�͂̃t�B�i�[���́A���[�e�B�Ɠ��̗��߂����܂��Ĉ��|�I�ŁA�Ȃ�قǂ��ꂪ���ǂ�CSO�ƌ����鏊�Ȃ��Ɣ[��������ɏ\���ȃp�t�H�[�}���X�������B�����O�����J�b�T�t�҂̏�肳�����̃t�B�i�[���傫�����x�����Ă������Ƃ��t�������Ă��������B |
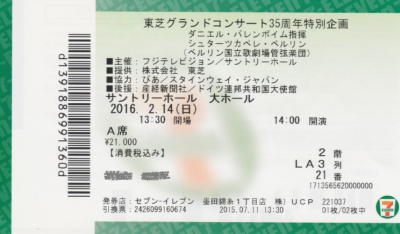 �y���ځz �u���b�N�i�[ �����ȑ�5�� �R���g���o�X�̃s�`�J�[�g�ŐÂ��Ɏn�܂�����ȑ�5�Ԃ́A�ŏ��̒������ǂ���̍��t�ɓ���ƃI�P���Y���т��グ��B���݂̒͂����ŃI�P�̎��͂��\���`����Ă���B�{�ǕҐ��ł��邱�Ƃ������Ĕ��͖��_�B�{�ǂȂ̂ň�l��l���͂�ő傫�������o���K�v���Ȃ����特�̌��݂ɖ������Ȃ��B�����Č����܂��������ɂ悭�̂��B���̌��̖肪���邩�炱���̔{�ǕҐ��Ƃ�����ۂ���Y���Ă���B�z������3�l�A5�l��2��ő�3�y�͂܂ł�5�l�݂̂łŁA�ŏI�y�͂�4�l�A4�l�̗�ɕς��8�l�ʼn��̌��݂��o���Ă����i2��Ŗ������S���������悤�ɂ������������悭�킩�炸�j�B�e�B���p�j�͓����t���[�Y��2�l�őł̂ł͂Ȃ��A��{�I�ɂ͑�1�t�҂݂̂ł̉��t�B���t�ŋ��߂ŘA�ł��Ă���Ƃ��납��}�ɐÂ��ɐ�ւ���ăe�B���p�j���キ�@���ς��Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ƃ���ŁA�������̑�1�e�B���p�j���~���[�g�Ŏ~�߂āA�ア�����2�e�B���p�j�ň����p�����Ƃŕs�v�ȋ������������Ȃ��悤�ɂ��邽�߂������ґ��2�l���g���Ă���悤�Ɍ������i�t�B�i�[����2�l�œ����A�ł��Ă�������ǁj�B����̐Ȃ���́A�w���҂̓����͂������̂��ƁA�����e�y��̓������n�b�L���ƌ����ċȂ̍\�����ƂĂ��悭�킩�����Ƃ�����������ʔ��������Ƃ���B���A�e���|�ݒ�̓x�������E�t�B���Ƃ�CD�Ǝ�����ۂő��߂̂Ƃ���͐��i�͂��d��������ہB����ł��A��4�y�͂̃t�B�i�[���͂����ƃy�[�X�𗎂Ƃ��ăX�P�[���̑傫����O�ʂɉ����o�������̂������B ���ɂ��Ă������̉��t�ŁA�ǂ̃p�[�g�����x���������A�I�P�Ƃ��Ă̂܂Ƃ܂���������ƂȂ��B��������Ă��܂��@�ׂȉ�����r�X�����i�������e������o�����������Ȃ��j�s��ȃg�D�b�e�B�܂ŕ\���̕��̍L���ɂ��X���Ă��܂��B�̌���I�P�Ǝv���Ē����O�Ƀn�[�h�����グ�Ă��Ȃ���������������Ƃ͂����A�ꋉ�i�̉��t�����Ƃ����[�����͂��Ȃ�̂��́B������������A�̂����A����̐[�����̍\�z���A�����Ă�����肢�����ł͂Ȃ����̎咣�Ƃ���������͎c�O�Ȃ�����{�̃I�P�ɂ͖]�߂Ȃ��B����Ȃɑf���炵�����t�Ńu���b�N�i�[��5�Ԃ���@��͂��������͂Ȃ���Ȃ����낤���B����Ȃ̂ɔ��������I�[�f�B�G���X�����Ȃ��Ƃ́B�������A�Ȃ��I����5�b�قǂ̐Î�������Ă���̗��̂悤�Ȕ��肪�N���Ă������Ƃ��A���̓��̃R���T�[�g�̑f���炵������Ă����Ǝv���B�I�P�̃����o�[�̕\��͐��X�����A�������u�]�O�ɑf���炵�����t���ł����v�I�ȒB�����Ƃ������́A�}�G�X�g�����܂߂āu�����ʂ肤�܂�������̂��v�Ƃ��������ŗ]�T������悤�ɂ��猩�����̂��܂���ۓI�������B 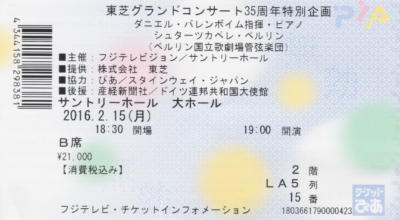 �y���ځz ���[�c�@���g �s�A�m���t�ȑ�22�ԁi�o�����{�C���e���U��j �u���b�N�i�[ �����ȑ�6�� ���̓��͂܂��̓��[�c�@���g�̃s�A�m���t�ȑ�22�Ԃ���B���̋Ȃ��܂��A�u���b�N�i�[��6�ԂƓ����悤�Ƀ��[�c�@���g�̃s�A�m���t�Ȃ̒��ł͂��a�߂̑I�ȁB���߂Đ��Œ������[�c�@���g�̃s�A�m���t�Ȃ͌y���łƂĂ��S�n�悢�B����A�d���ȋ��������Ă����I�P�́A�y�₩�Ȃ��̋Ȃł��ƂĂ��C�����悭�̂��Ă��Ă�͂���͂̊m������������B�������A����܂Ńe���r�ŊςĂ����̂Ɠ��l�Ƀs�A�j�X�g�F�o�����{�C���͓Ɠ��ȃ��Y�����Ɨh�炵���Ɍ��������āA����܂��ۂ��ǂ��Ȃ��B�Ȃ������ȂƂ��낻��قǖʔ����Ȃ��Ė����Ȃ��Ă��܂����B �x�e��̃X�e�[�W�́A�O���Ƃ͈���ĊNJy����W���Ґ��B���������A�����I�[�P�X�g���œ�����ȉƂ̉��t��2���A���Œ����Ƃ����o���͏��߂Ă̂��ƂŁA������O�̂��ƂȂ��瓯���T�E���h�������ƒ������Ă����Ƃ���Ɋ��S����i���ǁA�؊ǂ̊�Ԃ�͌��\����Ă�������ǁj�B���t�̃��x���͑O���Ɉ��������f���炵���B�ł��A����̂悤�Ȑ��݂܂łɂ͓��B���Ă��Ȃ������悤�Ɋ������B�����2�������Ē���������I�P�̉��̗\�z�����Ă��܂��Ă����i�V�N���������Ȃ����j���ƂƁA�Ȃ��قȂ�_����������������Ă������낤�Ƃ������Ƃ����R�ł͂������Ǝv������ǁA�I�[�f�B�G���X�̔M�����O���̕��������Ɛ����������Ƃ��l����ƃp�t�H�[�}���X��������ɗ^�����C���p�N�g�ɂ͂�͂荷���������Ƃ������Ƃł��傤�B |
 Queen�{Adam Lambert���ςɍs����2014�N�T�}�\�j�A�_�C�W�F�X�g�������Ă����Ƃ��ɖڂɕt�����̂����B���e�[�W�E�g���u���������B�ȗ��A��x���C�����������Ǝv���Â��Ă悤�₭�����B�^�C�E�e�C���[��"�����炳����"���\�E���t���ɉ̂��グ�Ďn�܂����X�e�[�W�́A�A�b�v�e���|�ɔ���A���ՂɃ~�h���e���|�̋Ȃ�o���[�h���A�Ō��2���̃A���o���̃I�[�v�j���O�� �hRun Like A River�h �hBlues Hand Me Down�h �Ő���グ��Ƃ����\���B�ނ�̉��t�͐��m�������x��ɂ��Ă���킯�ł͂Ȃ��A�c�{��S�����u���킩���Ă�˂��v�I�Ȃ��̂������āAR&B�A���b�N�̉��n���������肵�Ă���B�\����Ȃ�����ǁA�O���̃E���t���Y�Ƃ͉��y�̊�b�̗͂��Ⴄ�B�A���R�[����"Run Outta You"�������Ă����̂͏��X�ӊO�ŁA���H�[�J�������S�̃o���h���I�[�\�h�b�N�X��3�s�[�X�E�u���[�X���b�N�E�o���h�Ƃ��Ă̒n�͂𖣂�����Ȃ��Ȃ̒������������i�X�e�B�[���B�[�E���C�E���H�[�����Ǝv�������炢�j�B�^�C�E�e�C���[�̃p�t�H�[�}���X�́A�ǂ����|�l���̃R�~�J�������Y���Ă��āA�ǂ����������^�ʖڂ��Ɍ����鑼��3�l�Ƃ̃M���b�v�������Ėʔ����B�A���R�[�����܂߂āA����90���Ƃ����X�e�[�W�͉�������ς�������x�ǂ������������B |
 ���E�t�H���E�W�����l 2016��2���� 2016/5/4�i���j �y1�z ���t: �E�A�u�f���E���[�}���E�G�����o�V�� ����: �E�x�[�g�[���F�� �s�A�m�E�\�i�^��15�� �j���� op.28�u�c���v �E�x�[�g�[���F�� �s�A�m�E�\�i�^��17�� �j�Z�� op.31-2�u�e���y�X�g�v �E�x�[�g�[���F�� �s�A�m�E�\�i�^��21�� �n����op.53�u�����g�V���^�C���v ���:�z�[��B7 B7�z�[���͖{���͒P�Ȃ�C�x���g�X�y�[�X�Ńf�b�h�ȉ�������낵���Ȃ����Ȃ���A�����3��ڂƂ����ǐȂ���ꂽ���Ƃ������ĉ��t�ɏW���ł����B�G�����o�V���͏��߂Ē����Ă݂ĕ]���ʂ芴��}���C���B�������ƌ����ċ@�B�I�ł͂Ȃ��A�܂�ڐ������Ƃ������Ⴄ�A�����ʼn��₩�ȉ�������Y���Ȃ�Ƃ����t�ɂ���̂�������t�B�ꉹ�ꉹ�Ɉ�̑��肪�Ȃ����ݓn���������ɁA�s�A�m���Ă���ȉ����o��ƐV�N�ȋ������������B �y2�z ���t: �E�I�����B�G�E�V�������G (���@�C�I����) �E�A���k�E�P�t�F���b�N (�s�A�m) ����: �E�x�[�g�[���F���F���@�C�I�����E�\�i�^��5�� �w���� op.24�u�t�v �E�u���[���X�F���@�C�I�����E�\�i�^��1�� �g���� op.78�u�J�̉́v ���F�z�[��B7 ���ۂɉ��t���Ă���p�����āu����H�v�Ǝv�����ʂ�A���̃I�����B�G�E�V�������G�Ƃ������@�C�I���j�X�g�͏��߂�LFJ�ɍs����5�N�O�Ƀ��t�}�j�m�t�́u�߂��݂̎O�d�t�ȁv�����l�������B�������f�b�h�ȉ��̂�������≹�̐L�т�������ہB2�Ȃ�ʂ��Ē����Ă݂�ƁA30���炢�̂Ƃ��ɍ�Ȃ��ꂽ�x�[�g�[���F���̃��@�C�I�����E�\�i�^�͑f�p�Ŏ�X�����i���������Ƃ��L���j�A46���炢�ɍ�Ȃ��ꂽ�u���[���X�̃��@�C�I�����E�\�i�^�ł͍\�����������肵�Ă��Đ[�݂̂���Ȃł��邱�Ƃ��悭�킩���Ėʔ����������Ƃ��ł����B |
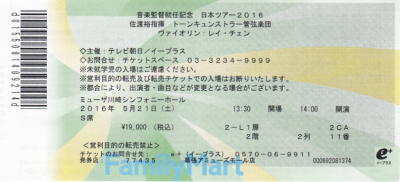 �i���ځj �E�x�[�g�[���F���F���@�C�I�������t�ȁ@�� �y�A���R�[���z �E�o�b�n�F�����t���@�C�I���� �p���e�B�[�^#2 �T���o���h �j�Z�� BWV1004 �i���@�C�I�����F���C�E�`�F���j �ER.�V���g���E�X�F �������u�p�Y�̐��U�v �y�A���R�[���z �EJ.�V���g���E�X�U �s�`�J�[�g�E�|���J �ER.�V���g���E�X �u�K�N�̋R�m�v��胏���c �܂��̓x�[�g�[���F���̃��@�C�I�������t�ȁB�x�[�g�[���F���̃s�A�m���t�ȂƓ��l�ɏ��Ґ��̃I�P�B���L�]���ƌ����郌�C�E�`�F���̓Ƒt�́A�t���b�V���ŗ͋����A���₩�ɋ����ċC�����ǂ��B���ꂩ����`�F�b�N���Ă��������Ǝv�킹�邾���̉��t�����Ă��ꂽ�B����ŁA�ȑO����v���Ă������̂́A���̋Ȃ͐��������ăx�[�g�[���F���̋Ȃ̒��ł͂��܂�ʔ����Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��ĔF�����Ă��܂����B�����f�B�ɂ����ЂƂ��͂��Ȃ��A�J��Ԃ��������ď璷�B�x�[�g�[���F���̋ȂƂ��Ă͉��t�@����܂葽���Ȃ��i���N�͑������ǁj�̂͋Ȃ̖��͂���������ł͂Ȃ����Ƃ̎v������苭���Ȃ��Ă��܂�����������Ȃ��B �x�e��́u�p�Y�̐��U�v�́A�������ɑ�Ґ��̔��͂������Ղ�B���k�ȉ��t�Ƃ����̂͂������f���炵������ǁA�l�͊y�킪�ǂ��̂��A�I�P�Ƃ��Ĉ�̉������T�E���h���o�Ă��邱�Ɓi���{�̃I�P�����Ƃ��Ă���Ƃ��낾�j�����߂Ă���̂ŁA���̓_�ł��Ȃ薞���ł�����́B�Ƃ͂����A����1�N�ňꗬ�I�P�̐��܂������t���Ă��������ɁA�����܂łɂ͎����Ă��Ȃ��Ƃ��ȂƂ����̂������ȂƂ���B���Ɉ����Ƃ����킯�ł͂Ȃ����̂́A���ǂƖ؊ǂ͋����ɏ_�炩���ƖL�����������������Ȃ��B����Ō��͂ƂĂ��ǂ��̂��A���₩���������ĂȂ��Ȃ��̂��́B���͓I�ɂ͂��悻1�N�O�Ɋς��E�B�[�������y�c�ɔ�����̂���������Ȃ����낤���B���̃E�B�[���̃I�P�Ɣ�ׂ�Ɖ��F����▾�邢�Ƃ�������̃I�P�̓������Ǝv�����B�L���ꗬ�I�P�قǂ̎��͂Ƃ͌����Ȃ���������Ȃ�����ǁA���̃I�P�̖���͂ƂĂ��D�܂����B�t��������ƁA������̑������̋Ȃő�ϑf���炵�����t�����Ă��ꂽ�R���~�X�̎��͂͂��Ȃ�̂��̂������B |
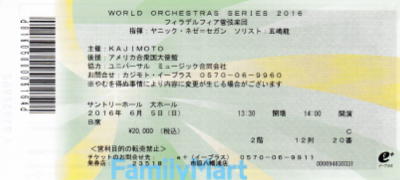 �i���ځj �EJ.�V���g���E�X�U�F�E�B�[���̐X�̕��� �E�v���R�t�B�G�t�F���@�C�I�������t�ȑ�P�� �i���@�C�I�����F�ܓ����j �E�u���[���X�F�����ȑ�2�� �y�A���R�[���z �E�o�b�n�F�r�͈��炩�ɑ���H�݁i�X�g�R�t�X�L�[�ҋȁj �A�����J�̃I�P�Ƃ��Ă͂��ӕ\��˂��I�ȁA���n���E�V���g���E�X�U����B���`��A���Ȃ��s���Ȃ��B���̉̂����A�؊Nj��ǂ̋����������͂Ȃ�����Ǘǂ����Ȃ��B�ŋߎ����삦�Ă��Ă��邹�����A�u����ς萶���t���Ă������Ȃ��v�Ƃ����܂ł̊����Ɏ���Ȃ��B �v���R�t�B�G�t�̃\���X�g�͌ܓ����B����܂������Ȃ�����ǂ���ƌ����ėǂ��Ƃ������Ȃ��B�����������̋Ȃ͉̂��グ��^�C�v�ƌ������͂��g���b�L�[�ȃt���[�Y�ŋZ�I�����C���ǂ��������邱�Ƃ��ł��邩���|�C���g�Ɩl�͑����Ă��āA���̓_�ŕ�����Ȃ��BCD�Ŏ����Ă���`�����E�L�����t�@�̉��t�͐L�т₩�ŗǂ��̂����̏��C���悳����������i�������@�ׂ�������j�̂�����A�͗ʂ̍������邱�Ƃ͎c�O�Ȃ���F�߂Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��ł��傤�B ���C���̃u���[���X��2�Ԃ͎Ⴂ�w���҂炵���A�L�r�L�r�Ɣ����Ƃ������t�ŁA�������Ɖ̂킹��Ƃ���͂���Ȃ�ɉ̂킹��X�^�C���B�������A�I�P����o�Ă��鉹�͒��f�Łu����ς�CD���Ⴑ�̉��͖��킦�Ȃ��B�����t�͂��ꂾ�����߂��Ȃ��v�Ǝv�킹��قǂ̉��̐����͂��Ȃ��B���̉��ɉ��ƓK�x�Ȃ��Ȃ₩�����Ȃ��Ăނ��돭���������T�E���h�������Ƃ��낪�l�I�ɂ͎c�O�ȂƂ���ŁA�܂��l����Ԑ����t�ɋ��߂Ă���I�P�S�̖̂�A�̂���������Ȃ��B���t�ɑ傫�ȏ����Ȃ��Ƃ��A���|�����悤�Ȏ咣�������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B |
 2016�N7��8���A�u���[�m�[�g�����Ń^���[�E�I�u�E�p���[��2nd set�B ���炭���������Ă����̂Œm��Ȃ���������ǁA�������N�̓��b�R�̑̒��s�ǂƃK���o���f�B�̒E�ނȂǂ�2�l�̑������݂͋v���Ԃ�Ƃ̂��ƁB�����āA���炭���[�h�E���H�[�J���߂Ă��������[�E�u���b�O�X�ɑ����ĐV���H�[�J���X�g�����������Ƃ̂��ƁB�u���b�O�X�͋ߔN�ł͂����Ƃ��f���炵�����H�[�J�������Ă��������ɂ����͊��Ҕ����A�s�������B �����n�܂�ƁA����Ȕ\�����Ȃǐ�����сA�v���Ԃ�̃^���[�Ƀe���V�������}�b�N�X�ɁI8�N�O�Ɂu���̃^���[�͂���Ȃ��ȁv�Ǝv�����L���������Ӗ��ő�������Ă����̂�������Ȃ�����ǁA�Ȃ�̂Ȃ�́A���t����������Ȃ����I�萔�������Ă��A�^�C�g�ŕ��G�ȃ��Y���Ə_��������K���o���f�B�̃h�����͂�͂�^���[�ɂ͌������Ȃ��B�a�C���畜�A�������b�R�̃E�l�����ߋ��Ɋς��ǂ̃��C�������O���[���������Ă��ꂽ�B�u���X�͕ς�炸���l����B�\�����Ԃ܂ŗ^����ꂽ�M�^�[���Ȃ��Ȃ����������A�n�����h����������L�[�{�[�h���C�C�B�V���H�[�J���X�g�͑O�C�҂قǂ̈��芴�͂Ȃ����̂́A��⍂�߂̐����Ń��j�E�E�B���A���X����̋Ȃ��n�}��B This Time Is Real Don't Change Horses Just When We Start Makin' It Only So Much Oil n The Ground (To Say the Least) You're The Most Just Enough And Too Much Ain't Nothin' Stoppin' Us Now ������̋Ȃ͏��߂Ă���x���炢�������C���������o�����Ȃ��A���ꂼ�ꉉ�t���ǂ��đ労�����喞���B��ԋȂƂ��ĊO���ė~�����Ȃ� What Is Hip So Very Hard To Go Soul Vaccination ���������Ă����Ă��̃Z�b�g���X�g�͊����������B1st set�ʼn��t����Ă����炵��"Down To The Night Club"��"You're Still A Young Man"�͌l�I�ɂ͏d�v�ł͂Ȃ�������2nd set�ő吳���B |
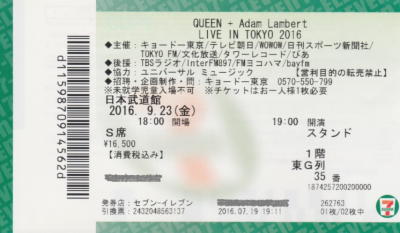 31�N�O�ɓ����ꏊ�Ŋς��N�C�[�����l�����̃R���T�[�g���������Ƃ��v���Ɗ��S�ɐZ�炸�ɂ͂����Ȃ��B�u���C�A�������W���[���A�����Ď��������������B����ł����h�Ȍ�y�V���[������Ă�����瓪��������B�A�_���̓Q�C�̃L�����N�^�[���X�ɑO�ʂɉ����o���āA���̃��C���p���j�b�g�ɍX�ɗn������ہB��Ȃ������N�C�[���̋ȂL���̂����Ȃ��A����"Who Wants To Live Forever"�̔M���̓l�b�g�ł���]���������B���o�I�ɂ�2�N�O�̃T�}�\�j�ŊςĂ��������ɃT�v���C�Y�͏��Ȃ��������̂́A���̂Ƃ��J�b�g����Ă������W���[�e�q�̃h�����o�g�������"Under Pressure"�̗���͗ǂ������B�l�I�ɂ͑�D����"Don't Stop Me Now"�����������Ƃ������������B |
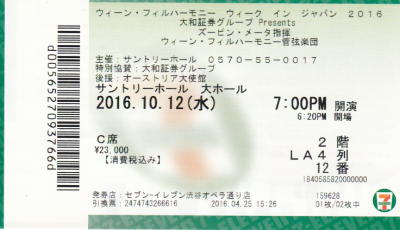 �w���F�Y�[�r���E���[�^ ���t�F�E�B�[���E�t�B���n�[���j�[�nj��y�c �\�v���m�F�g�c��� ���]�E�\�v���m�F��������q �e�m�[���F���� �h �o�X�F�t�����c=���[�[�t�E�[�[���b�q �����F�T���g���[�z�[��30���N�L�O�����c �i���ځj �E���[�c�@���g�F�����ȑ�36�ԁu�����c�v �E�x�[�g�[���F���F�����ȑ�9�ԁu�����t���v �܂��̓��[�c�@���g�́u�����c�v����B���̓��[�c�@���g�̌����Ȃ��t�Œ����̂͏��߂Ă̂��ƁB�������E�B�[���E�t�B�������爫���͂����Ȃ��B���Ґ��̌ÓT�h�����ȁi�N�����l�b�g���t���[�g�����Ȃ��؊ǕҐ��Ȃ�ď��߂Ē������j�ł����Ă��T��ɉ̂��I�P���f���炵���B�܂��ɖF���ɂ��Ĕ����B�y�F����Ŋς��Ƃ��Ƃ͐Ȃ��Ⴄ�����̋���������Ă����ɂ�������炸�A�m�łƂ����E�B�[���E�t�B���̃T�E���h�������ɂ͂������B�x�������E�t�B���̐��k�ȃA���T���u���Ƃ͌����Ă�����������炩�Ɉ���Ă��āA�����̊ɂ݂�����Ƃ��낪�A�C�f���e�B�e�B�B����͂悭������Ƃ���ł͂��邯��ǁA���g�ł���������邱�Ƃ��ł����B ���͑�1�y�͖`������A�T��ȃ��[�c�@���g�Ƃ͈�ς���B�u�����c�v�̍�Ȃ�1783�N�A����1824�N�Ƃ��̍���41�N�����Ȃ��ɂ�������炸�A���ł́u�ÓT�v�Ɩ��t�����ĔN�������̃W�������ł���ێ�I�ȉ��y���A��Ȏ҂������Ă�������ɂ͕ω��E�i���������Ă������ƂɎv�����y�ԁB�u�����c�v�Ɉ��������A�L���Ȕ����ɐg���ςˑ�����B���ꂾ���őf���炵���̌��B�����đ�4�y�͍͂X�Ɉَ����ɓ���B�l�Ԃ���������y�Ƃ����̂͂���Ȃɐ������̂ȂƎv�킹��Ȃ́A�l�I�ɂ͂��̑��������u���đ��ɂ͎v�������Ȃ��B���[�^�͂��܂�傰���ɋȂɃA�N�Z���g��t���Ȃ����A�啗�C�~���L����������Ȃ����A�I�P�Ɍ��i�������߂�킯�ł��Ȃ��B�ł��A���̖��Ȓ��̖��Ȃ��E�B�[���E�t�B���̉��F�Œ����ɂ͂���ł����B�ŋ߂̃E�B�[���E�t�B���͂��Ă̂悤�ȗD��ȋ��������ނ��A����Ɏ��c���ꂽ�I�P���ƌ����l�����邯��ǁA�܂��܂��`���̉��F�͈����p����Ă��đ��̃I�P�Ƃ͈�����悷�Ǝ��̉��F�������Ă���B�T���g���[�z�[���Œ����Ă����̉��F�͗D��ŌÏL���Ƃ�����x�ꂾ�Ƃ������Ȃ������B���ׂĂ��f���炵����������Nj����Č����Ȃ�i�u�����c�v���܂߁j�ɏ��y�͂ɂ�����������͓��ɒ����ǂ��낾�����Ǝv���B |
 2016�N10��14���A�W���V���A�E���b�h�}�����u���b�h�E�����h�[�A�R�b�g���E�N���u 2016�N10��14��2nd�Z�b�g�B ���Ƃ���f���I�ł����Ă��A�l���B�ꌻ���W���Y�E�~���[�W�V�����Œǂ������Ă���2�l�̑g�ݍ��킹�A�������W���Y�E�N���u�Ŋς��ƂȂ�Θb�͂�����ƈ���Ă���B ��͂萶�Œ����Ɖ��̋P�����Ⴄ�B�����h�[�̃s�A�m�������Ղ薡�킦���̂͂������A�W���V���A�̃T�b�N�X�������܂ŏ����ɂ�������ƏW�����Ē��������Ƃ͂���܂łɂȂ��A���̑f���炵�����F�ƕ\���͂ɚX���Ă��܂����B���t��CD�Ɏ��߂�ꂽ���̂�莩�R�z���i���炭CD�ɂ͂܂Ƃ܂�̂��鉉�t���I�ꂽ�j�ŁA���Œ������Ƃł��y���߂鉉�t�������悤�Ɏv���B |
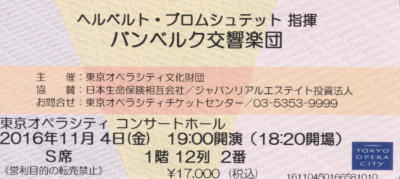 �i���ځj ���[�c�@���g�F�����ȑ�34�� �u���b�N�i�[�F�����ȑ�7�� �m�����B�u���[�g�Ōy�₩���T��ɉ��t���ꂽ���[�c�@���g���炵�ĉ����f���炵���B�����A�Ȃ��̂��̖̂��͂Ɍ�����͔̂ۂ߂Ȃ��Ƃ����v���ƁA�Ȃ��Ȃ������@��Ȃ��Ȃ����̌����ȉ��Œ������Ƃ��ł����Ƃ����C���������������B�u���b�N�i�[�͏o�������爳�|�I�B�Êy�̃A�v���[�`�����Ă������[�c�@���g����ł��ĕς���āA���B�u���[�g�����������}���h�̐����I�A�v���[�`�B�Ƃɂ����ǂ������̂����A���݂�����B�g�������̔������Ƃ������炻��͂����M��ɐs�����������B�؊ǂ͓��ʂȉ��Ƃ܂ł͌����Ȃ����̂́A���ǂ̋����ƌ��݂͂��Ȃ�̂��́B�u���b�N�i�[�Ƃ͂�������ׂ��Ƃ����m�M�ɖ������X�P�[���̑傫�ȉ��t�������B�u�����V���e�b�g�̈��肵���Ȃ̉^�ѕ��������������o���Ă��邵�A�I�P�Ƃ̈�̊����M���̌����������Ă����Ǝv���B |
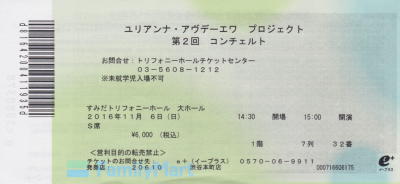 �s�A�m�F�����A���i�E�A���f�[�G�� �w���F�J�`�����E�E�H�� ���t�F�V���{�t�B���n�[���j�[�����y�c �i���ځj �X�g�����B���X�L�[�F�s�A�m�Ɗnj��y�̂��߂̃J�v���b�`�� �X�g�����B���X�L�[�F�o���G�g�ȁs�̒��t�i1919�N�Łj �`���C�R�t�X�L�[�F�s�A�m���t�ȑ�1�� �X�g�����B���X�L�[�́u�s�A�m�Ɗnj��y�̂��߂̃J�v���b�`���v�́A���܂�m���x�������Ȃ������@������Ȃ��ȁB�R���`�F���g�Ƃ͎��������ăs�A�m�ƃI�P���I�n�����悤�ȃo�����X�ŗ��ݍ����i�݁A�؊ǂƂ̃\���̊|���������y���ރ^�C�v�łȂ��Ȃ������[���ȁBCD�i�莝���̓����\���XRCO�j�Ɣ�ׂ�Ɛ����t�Ȃ�ł̓_�C�i�~�N�X�͊��������̂́A�Ȃ��̂��̖̂��͂Ƃ����Ӗ��ł͂����ЂƂƂ�������ہB �u�̒��v���āA������͂���{�̃I�P�͕͗s�����ȂƂ��݂��݊����Ă��܂����B�����ĉ���ł���Ƃ������Y��łȂ��Ƃ����������Ƃ͂Ȃ�����ǁA��͂�y�킪�̂��Ă��Ȃ����A���ɐF�C�≐������Ȃ��B�I�P�S�̂̎咣������Ȃ����A�������Ƃ����Ƃ���̍��t�̈�̊��ɖR�����B�����Č����ƁA�Ⴋ�w���҂͂ǂ�������Ȃ��A�I�P�ɉ��������ɐT�d�ɐU���Ă���悤�Ɍ������B �Ō�̓`���C�R�t�X�L�[�̃s�A�m���t�ȑ�1�ԁB�����Ƃ��Ă͑Ō��ɏ\���ȗ͋�������������1�y�͂͂����ЂƂ���Ă��Ȃ���ہB�������A��2�y�͂���͎����O�̗���Ȏw�̉^�тƖ��Ăȃ^�b�`���{�̂��A�ޏ��炵���s�A�m�����\�ł����B�Z�p���\�������Ǝv���鉉�t�������B�����A�����Ă����Ȃ�A���̋Ȃ͎��ɉߏ�Ǝv����p�b�V�������������Ȃł�����̂ŁA������Ȃ��Ɗ������l��������������Ȃ��B |
 �܂��̓����f���X�]�[���̃��@�C�I�������t�ȁB�W���V���A�E�x���͌��\�˂��Ƃ�̂킹��^�C�v�ŁA�l�I�ɂ͂ǂ��炩�Ƃ����D���ȃ^�C�v�B�ŏ��̃\�����I�����A�I�P���h�b�ƂȂ�Ƃ���Ŗl���D���ȁu�ǂ���v�I�P���Ƃ킩��B�ǂ����t���Ǝv���A���܂���荞�߂Ȃ������̂́A�����������̋Ȃ�����قǍD���łȂ�����B����قǒ����Ȃł��Ȃ��̂ŁA����ł��O�����ɒ����ʂ����Ƃ��ł����B ���āA���҂��Ă����}�[���[�B��1�y�́A�n�[�f�B���O�͂ƂĂ��������Ɛi�߂�B�o�[���X�^�C���ɕC�G����قǂ�����肷���ĉ��y�̗��ꂪ�X�|�C�������قǂ���������ǂ��A�n�[�f�B���O�͂������肽��������ł��傤�B����ŁA�e���|���グ��Ƃ���A���߂�Ƃ���ł̓L�r�L�r�ƃ����n������������B�p���ǂ́A���ǁA�؊ǂɂ��Ă͂���قLj�ۓI�ł͂Ȃ��B���ɂ��̋Ȃɂ�����ŏd�v�p�[�g�A�g�����y�b�g�͔j�]�������Ă��Ȃ��������̗̂]�T�����Ղ�ɉ̂��Ă���Ƃ����قǂł͂Ȃ������B�؊ǐw���A�����ė͕s���ł͂Ȃ��ɂ��Ă����������قǂɂ͎���Ȃ��B����ŁA���̋����͂ƂĂ��F���ŁA�������h�C�c�n�̃I�P�Ƃ͈���Ēg�F�n�̐F�ʂ�����B��4�y�͂̃A�_�[�W�F�b�g�́A����ȉ��F�̑f���炵���𑶕��ɖ��키���Ƃ��ł����Ǝv���B |
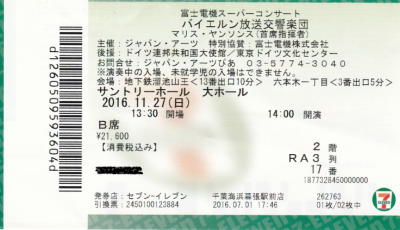 �i���ځj �}�[���[�F�����ȑ�9�� ��1�y�́B�������ƁA�Â��Ɏn�܂郔�@�C�I�����̑@�ׂȉ��ɑ����������̉��t��\��������B�Ԃ��Ȃ��P���A���悢�^�����ŏ��̃N���C�}�b�N�X�B�����ł����ܖڂɁB�����A����͂���2�N�O�Ɋς����̂Ƃ��̃o�C�G�����Ƃ͕ʂ̃I�P�̉��ɒ�������B ���@�C�I�����͌�����̑���������2���܂߂Ĕ��������ۗ����Ă���B2���O�ɒ������p���ǂ̖c�悩�Ȕ����Ƃ͈���āA�[���ȁA����ł��Ă����Ղ�Ɖ̂��������B�����\���X�Ƃ����Ƃ����P�ɏ�i���Y��Ȃ����ł܂�Ȃ��Ƃ����l�����邯��ǁA�}�[���[�͌���I�ɂ��Ȃ��Ă����|�ł���Ƃ�������{�̂悤�ȉ��t�B ���͒ጸ�̌��݂��f���炵���B�܂��A���ǂ̃n�C���x���ň��肵���������A��l���̖؊ǂ��f���炵���Ƃ������t�����o�Ă��Ȃ��B�؊NJe�p�[�g��Ȃ̃\���E�p�[�g�͘N�X�Ɖ̂��������Ɖs�������˔����Ă���B�I�[�{�G�A�N�����l�b�g�A�t���[�g�A�t�@�S�b�g�̂��ׂĂ����n�C���x���Œ�������Ă��܂��B �X�P���c�H�I�ȑ�2�y�͂͌y���ł������������A�����đ�3�y�͂̓}�[���[�Ȃ�ł͂̌������Ɉ��|�����B �����\���X��������킹�ċF���Ă��邩�̂悤�Ȏp������n�܂�����4�y�͂ł́A�܂����̒[���ł���Ȃ���F���Ŕ����������������B����Ȃɔ��������y�����̐��ɑ��݂���̂��Ƃ��������ŁA���ɖj��܂��`���n�߂�B�}�[���[���w������u���ɐ₦��悤�Ɂv�I���A�����\���X������~�낵�Ă����́A�N��������ۂސÎ₪�����B�Î~���������\���X���p��������ƁA����܂Œ��������Ƃ̂Ȃ���Ẵu���{�[�̗��B����ȏ㉽��]�ނƂ����̂��낤�B��D���ȑ�9�Ԃ�����Ȃɑf���炵�����t�Œ�����K���B |
 2017/5/5�i���j �y1�z �w���F�p�X�J���E���t�F ���t�F�t�����X���������[���nj��y�c ���ځF �E�f���J�X ���@�g���̒�q �E�T��=�T�[���X ���̕��� �E�����F���F�{���� �y2�z �w���F�p�X�J���E���t�F ���t�F�|�V���q�i���@�C�I�����j�A�t�����X���������[���nj��y�c �E�V�x���E�X�F�߂��������c �E�V�x���E�X�F���@�C�I�������t�� �܂��́y1�z�̌�������B�����[���nj��y�c�́A�����ď�肢�I�P�ł͂Ȃ��Ǝv���B�����W���[�I�P�̕����ނ����肢�͂��B�ł����̉̂����͂�͂�C�O�I�P�Ȃ�ł͂����A���F�����邭�Ă��̃t�����X���̃v���O�����͏n�ꂽ���t�ŁA�y�����������Ƃ��ł����B�ʏ�̊C�O�I�P�̃R���T�[�g�ł͈ӊO�ƒ����@��Ȃ��{���������̂����n�B���ۂɊςȂ��璮���Ă���ƃI�[�P�X�g���[�V�����̍I�݂��A�ʔ������悭�킩�邵�A�Ō�ɃR���g���o�X�������オ��̂����ԂʂɎw�������鉉�o�Ȃ�ł��傤�B�I�����A�ʗ�ǂ��蔏��ŌĂяo���ꂽ�w���҂��u����Job��Easy�ł��B�݂�ȗD�ꂽMusicisan������v�ƌ����č��}�����o���ƁA������x�u�{�����v�̏I�Ղ��I�P�����ʼn��t�A�w���҂͎w������~��ăI�P�����ʼn��t����Ƃ����]�����y�����A���Ղ�C�x���g�ɑ��������y�����v���O�����ő喞���B �y2�z�́A�l�I�Ɉ�ԍD���ȃ��@�C�I�������t�ȂŒ����Ă݂����Ƃ������R�Ń`���C�X�B�y1�z�Ǝw���҂ƃI�P���ꏏ�Ȃ̂͒P�Ȃ���R�ŁA�܂��������߂�����̂��Ⴄ�ȂŒ�����ׂ邱�Ƃ��ł���Ƃ����̂͂���͂���Ŋy���݂ɂ��Ă����Ƃ���B���_���猾���ƁA�V�x���E�X�͂����ЂƂ����������B������炩�ɍ���Ȃ��A�ǂ��Ȃ��Ƃ����قǂł͂Ȃ��������̂́A�y1�z�ł̎��R�Ŏ����I�ȁA���y�����o�銴���ɂ͋y�Ȃ��Ƃ������Ƃ����B�\���X�g�̒|�V���q�͔M���ł͂��������̂́A�V�x���E�X�̂��̋Ȃɑ��Ă݂͗͂Ǝ�Ă��܂����t�ł�����Ɗ������B�܂��A�������͖l�̊������Ȃ̂ŁA�|�W�e�B���Ɏ~�߂��l��������Ȃ����Ǝv���܂��B |
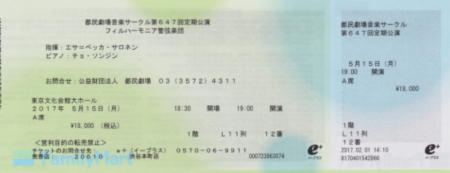 �D�u�Ɓu�h���E�t�@���v�B�Ȃ��Ȃ��C�����ǂ��o�����B�T���l���̓A�N�V�������L�r�L�r�Ǝ�X�����A�I�P�����[�h���Ă��銴���悭�o�Ă���B�������ɏ����ł̗D�������A���͂܂��܂����������������Ă���̂ɍ��ЂƂB�܂��ł��P�ȖڂȂ̂ł���Ȃ��̂ł��傤�B �x�[�g�[���F���̃s�A�m���t�ȑ�3�ԁB�`���E�\���W���͓I�m�����m�ȁA����ł��ėL�@�I�ȃ^�b�`�B�������A�ɂ���ԂƂ������]�T�����܂�Ȃ���ۂŁA��肢���Nj����Ȋ��������Ă��܂��B�������Z�p�͂������肵�Ă��邵�A�������t�ł͂Ȃ��B���肫����Ȍ������ɂȂ��Ă��܂�����ǁA�Ⴓ�A�L�������������Ă��܂��Ă����悤�Ɏv���B�A�N�V�������傫�����Ƃ��]�v�ɂ��������������̂�������Ȃ��B�D��ۂ������A���X�l�X�i���傤��2�N�O�̓������ɒ������j�A�A���f�[�G���ł̉��t�Ɣ�ׂ�ƈ�i�����邯��ǁA�����������t���D���Ƃ����l������̂�������Ȃ��B �x�[�g�[���F���̌����ȑ�7�ԁA�ŏ��́u�W���A���v�B�������A�����̊y�킪�����ɖ��Ă������ǂ��A���ʂ̓��@�C�I�����̉�����ۂɎc��Ƃ���B���̓��A�������Ă����̂̓g�����y�b�g�B�������x�z�I�Ȃقǂɑ剹�ʂ́B�u����A�g�����y�b�g�̐l�A�ŏ�������炩����������̂��H�v�Ǝv���Ă��̂܂ܒ����i��ōs���Ă��������Ƃ����Ƃ��ɑ��̊y��̉������������قǖڗ���������g�����y�b�g�B����H�����̐Ȃ̓g�����y�b�g�̉��̃z�b�g�X�|�b�g�ɓ�������������H����A�O�̋Ȃ܂ł͂���Ȃ��ƂȂ������ȁA����͈Ӑ}�I�ɂ���Ă���̂��ȁA�Ȃ�Ă��Ƃ��������邮��߂��葱���Ă��邤���ɋȂ͏I���B�v�̓g�����y�b�g�̉����I�n�ڗ��������Ă��ċȂɏW���ł��Ȃ������Ƃ������ƁB�A���R�[���̃V�x���E�X���قڋ��ǂȂ��i�z�������킸���ɕ⏕�ɓ�����x�j�̉��t�ł悤�₭���������Ē������Ƃ����̂�������Ɣ߂����B �t�B���n�[���j�A�nj��y�c�̕]���]�X�͍���͂�����Ƃł��Ȃ��B�������LFJ�Œ����������[���ǂƂ͊i���Ⴄ���A��肭�n�}�����Ƃ��͂����Ɨǂ����t�����Ă����ł��낤�|�e���V�����͊������̂ő��̃v���O�����Œ����Ă݂����Ƃ���B |
 �u���[�m�[�g�E�n���C�A5��29���A�����B���O�E�J���[�̃t�@�[�X�g�Z�b�g�B ���C���E�p�t�H�[�}���X�͂������̈ꌾ�B���@�[�m���E���[�h�͂������ɈȑO�قǂ͎w�������Ȃ��Ƃ͂����A�o���h�Ƃ��Ẳ��t�̃��x���͍����A���Ƀh�����̃E�B���A���EE�E�J���z�[���̏d���^�C�g�ȃh���~���O�́ACD����M���m��郌�x���̒ʂ�ŁA���̃h���������t�̃N�I���e�B���x���Ă��邱�Ƃ��ǂ��킩��B�Ƃɂ�����肢�B�e�N�j�b�N�ɓM���^�C�v�ł͂Ȃ��A�r�[�g�A�O���[����n�o����Ƃ����h�����̂����Ƃ��d�v�Ȏd�����n�C���x���ł��Ȃ��Ă��đf���炵���B 70�����炢�̃X�e�[�W���I��������ƁA�u���[�m�[�g�̃u�e�B�b�N�i�O�b�Y�V���b�v�j�������ƁA���@�[�m���E���[�h�ƃR���[�E�O���[���@�[���T�C���ɉ����Ă��āA�q�����Ȃ����Ƃ������Ĉꏏ�Ɏʐ^�B�e�B���@�[�m���E���[�h�Ɂu����20�N�ȏ㊈�����Ă���ˁv�ƌ����Ɓu�����A���낢�날��������ǒ�������Ă��v�ƗD�����b�������Ă�����Ċ����B�r������x�[�X�̃_�O�E�E�B���r�b�V��������A�u86�N�ɕ����قł��Ȃ��ɉ�����v�ƌ����Ɓu�~�b�N�E�W���K�[�H�v�u����A�W�F�t�E�x�b�N�v�ƌ����Ɓu�����E�n�}�[�A�W�~�[�E�z�[���A�T�C�����E�t�B���b�v�X�Ɖ������Ƃ����ˁv�ƌ����Ă���Ă���܂������B |
 2017�N6��9���A�ۂ̓��R�b�g���N���u�A�W�F�t�E�o���[�h�E�g���I��2nd�Z�b�g�B�B ���t�̕������̓W�F�t�̃\���A���o���Ɠ����ŁA�M�^�[�����Ƀx�[�X�̖�����S�����A���̌��Ԃ��W�F�t�̃h�����Ŗ��߂�A�Ɠ��̉���Ԃ��\�z�B�����A���̓����������t�ł̓X�^�W�I�Ղقǂ̉��y���̕��͊�����ꂸ�A���P���������悤�Ɏv���B���̃M�^�[���e�i�[�E�T�b�N�X���Z�ʂ͊m�����������A����������̃W�F�t�̃h�����͖������Ă����B����̑����Ґ��䂦�ɂ�����x�͒P���ɂȂ��Ă��܂��͎̂d���Ȃ��Ƃ���Ȃ̂�������Ȃ��B����ł��A�W���Y�E�N���u�ł̐����t�Ȃ�ł́A���ɋ������ɂ͂Ȃ��W�F�t�̃h�������A�{�l����肽���悤�ɒ@���Ă��鉹��̂ɗ��тĊy���ށB��`�̃��Y�������ނ����ł͂Ȃ��A�Ǝ��̃^�C�����o�ƃ^�C�g�ȃO���[�������\�ł����������ґ�Ȏ��Ԃ𖡂키���Ƃ��ł��Ė����B |
 �x�[�g�[���F���̃G�O�����g���ȁB�������Ɍl�Z���������肵�Ă��ď�肢�B���̉��͔������A�؊ǂ����ǂ������ł悭�̂��Ă���B��u�A���T���u��������ĉ��̃t�H�[�J�����Â��Ƃ�����U�����ꂽ�Ƃ͂����A�I�P�̒n�͂͊m���B �x�[�g�[���F��������8�Ԃ́A�Q���@���g�n�E�X�̘^���قǂłȂ��ɂ��Ă��V���C�[�炵���L�r�L�r�Ƃ����i�s�ŁA����̃A�N�Z���g�������n���̂��鉉�t�B�����ȂƂ���A�x�[�g�[���F���̌����Ȃ̒��ł͍ł��n���Ȃ��̋ȁA�������Č��Ȃ��璮���Ă݂�Ɩ؊ǂ̍\������������Ɨ����Ă��ėǂ��o���Ă���Ȃ��Ɗ��S���Ă��܂��B������̖؊ǂ̏�肳���������������Ă��闝�R�̂ЂƂ������̂͊ԈႢ�Ȃ��B �X�g�����B���X�L�[�̏t�̍ՓT�ɂȂ�ƕҐ�����C�ɔ{���B���ɋ��ǂƖ؊ǂ̐l���������ŁA������Ȃ��y�����������A���̋K�͂Ɗy��̎�ނ̑����̓}�[���[�̌����Ȃ������킷��s��Ȃ��̂ɂȂ�B�C���g���̃t�@�S�b�g�̉��̈�����������Ȃɒ����̂͏��߂ĂŁA�������s���R�ł������ł��Ȃ��̂́A���O�̎���Ƃ��߂���ɑ�����肳�����Ă̂��ƁB�Ȃ��i�ނɘA��A�c��Ȑ��̋��ǂƖ؊ǂ����G�ɗ��ݍ����A���ʂȂ�l�Z�̌�����ƌ�����p�[�g���u���ɂ��������ɐ�ւ��A�X�ɓ����i�s���čs���l�͑s�ςŁA�}�[���[�����ꂽ���ł��\���X�g��ڂŒǂ�������̂ɋ�J����B����́A�����Ėʔ��������łȂ����Ă��y�����ȁB�I�P�̋Z�ʂ�v��������Ȃ��A���̎��̍������t�Œ������̂͑f���炵���̌��B �g�[�^���̉��t����70�����x�̃v���O�����łŁA����N�X�Ɖ̂킹��I�ȂƂ����킯�ł��Ȃ��������߁A��╨����Ȃ������������̂́A�A���R�[���ʼn̒��u�����J�X�`�F�C�̋����ȗx��v�𔗗͂̃m���Œ������Ă��ꂽ���Ƃł���ȕs�����������ł��܂����B �I����́A�I�P�̃����o�[���m�łɂ��₩�ɏ̂������A�`�[�����[�N�̗ǂ����������ǂ��R���T�[�g�ł����B��͂�I�P�̃����o�[���y�������ɂ���Ă���R���T�[�g�͗ǂ����̂ł��B |
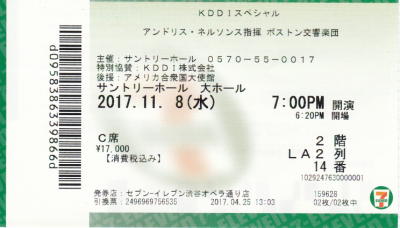 �y���ځz ���[�c�@���g�F�t���[�g�ƃn�[�v�̂��߂̋��t�� �i�A���R�[���j �C�x�[���F�ԑt�� ���t�}�j�m�t�F�����ȑ�2�� �i�A���R�[���j ���t�}�j�m�t�F���H�J���[�Y ���[�c�@���g�̓{�X�g�������y�c�̎�ȃt���[�g�t�҂ł���G���U�x�X�E���E�Ɠ���ȃn�[�v�t�҂̃W�F�V�J�E�W���E���\���X�g�߂Ẳ��t�B�y���ȃe���|�Ŏn�܂�A�����I�[�P�X�g���̂悤�ȏ��Ґ��i�؊ǂ̓I�[�{�G2�{�A���ǂ̓z����2�{�����A�`�F���ƃR���g���o�X�͂��ꂼ��4�{2�{�j�̃I�P�͗}���߂ɗD�������F�Ōy�₩�ɉ���a���B���̌���T��ȏI�n���[�c�@���g�E���[���h�B���Ƃ��Ɖ��ʂ��傫���Ȃ��y��̋��t�ȁA���[�c�@���g�͂�������ׂ��Ƃ��������B�����l�́A�����Ȕ����𖡂키���Ƃ͂ł��Ă��A�Ȃ��̂��̂͂��܂�ʔ������̂ł͂Ȃ��Ǝv���Ă����̂ŁA�S�n�悷���Ă�▰���Ȃ��Ă��܂����B ���t�}�j�m�t�͍���A���߂Đ����t�ɐڂ��Ă݂ăI�[�P�X�g���[�V�������Ɠ��ł��邱�Ƃ������B�x�[�g�[���F����u���[���X�̂悤�Ȃ�������Ƃ����p�[�g�̑g�ݗ��āA����Ɣ�ׂ�ƍ\�����������Ƃ�����ہB�܂��A�{�X�g�������y�c�̖؊Ǖ����́A�l�Z�͂܂��܂��ł���������郌�x���Ƃ܂ł͌����Ȃ��Ƃ��낪�����������������R�Ȃ̂������Ȃ��B���ǂ͂�≹���r���A���t���̐��x�������ЂƂB�ł��A�A�����J�̃I�[�P�X�g���炵���n�͂͗��������B�Ȃ��̂��̂̓��}���e�B�b�N�ŔZ���ȊÂ����������Ƃ��邾���ɁA���̕\�������߂���Ƃ���ŁA���̓_�͕�������Ȃ��B�l���\���X�̌|���������āA�������A�˂��Ƃ�Ƒt�ł錷�͗Y�قɉ̂��A��▾�邳�����F�͂���܂Œ������I�P�̒��ł��ŏ㋉�̔������B���t�}�j�m�t�͂��̂��炢�����������܂��傤�Ƃ����������ǂ��B�Ȃ̐��ʂɈʒu���Ă����������A�`�F����R���g���o�X�̗]�T�����Ղ�̖���Ղ����ۓI�������B |
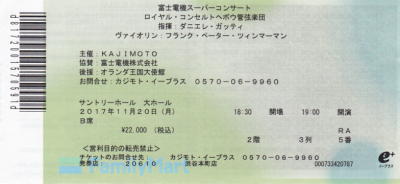 �y���ځz �x�[�g�[���F���F ���@�C�I�������t�ȁi�t�����N�E�y�[�^�[�E�c�B�}�[�}���j �i�A���R�[���jJ.S.�o�b�n�F�����t���@�C�I�����E�\�i�^��2�Ԃ��u�A���O���v �u���[���X�F �����ȑ�1�� �n�C�h����[�c�@���g�̋��t�Ȃقǂł͂Ȃ��ɂ��Ă��A�Ґ��͏����߂̃x�[�g�[���F���A���₩�Ɏn�܂�ŏ���30�b�ŁA�I�P���犊�炩�Ń��b�`�ȃT�E���h�����ݏo�ė���B�����A4�N�O�ɒ������Ƃ��Ɠ������Ȃ��A�Ǝv�킸�j���ɂ�ł��܂��B�c�B�}�[�}���́A�i�ǂ����₩�ɁA����ł��Ĕ������̂��A���ɏ�����ɂ���Ƃ����A�]�T�����Ղ�̌����ȉ��t�B�c�B�}�[�}���́A�\�����x�݂̂Ƃ��ł���P���@�C�I�����̃p�[�g�i���ɂ̓��B�I���̃p�[�g�܂Łj��e���Ƃ����A���t���̂��̂��y���ޗ]�T�܂Ō����āA�͂܂Ȃ��Ă�������𖣗��ł��邱�Ƃ������Ă����悤�Ɏv���B�c�B�}�[�}���̂��Ȃ₩���ƃI�P�̉��F�������Ȉ�v�����Ă���Ƃ�����������B ���C���̓u���[���X�̌����ȑ�P�ԁB�d���Ɏn�܂��1�y�́B�e���|�͓K�x�ɑ������Ȃ��x�����Ȃ����x�ǂ����~�B���⏭�����߂��H����ɂ��Ă��A���ǁA�؊ǂ̊e�p�[�g�̏�肢���Ə�肢���ƁB�S���̃p�[�g����肢�����łȂ��A�o�����X�����Ă��ăA���T���u���������ŁA�I�P���̂̎��͂Ƃ��Ė{���ɑf���炵���A�Ɠr�����x���X���Ă��܂����B�������܂�ɂ����X���Ă���̂Ńh�C�c�I�ȏa�݂��~�����l�ɂ͏��X������Ȃ���������Ȃ�����ǂ��̌��̊m���ȉ̂����������Ȃ��́B��4�y�͂ł̓e���|�������Ɨ��Ƃ��Ďn�܂�A�r���͑��߂ŏI�Ղ͂܂��x�߂Ƃ����W�J�B�ŋ߃����[�X���ꂽ�}�[���[��2�Ԃ�SACD������������ǁA�K�b�e�B�̓e���|�𗎂Ƃ��ƌ��߂��Ƃ���̓K�N���Ɨ��Ƃ��B�����A���̓��͑�3�y�͂܂ł̃e���|���Ƒ�4�y�͂̃e���|���̂Ȃ��肪���܂�ǂ��悤�Ɏv���Ȃ������B����ł����ꂾ���̉��Œ������u���[���X�ɖ����B���X�ȃu���[���X�͂���ł���ŃA���ł��傤�B |
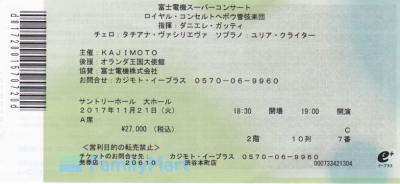 �y���ځz �n�C�h���F�`�F�����t�� ��1�ԁi�^�`�A�i�E���@�V���G���@�j �i�A���R�[���jJ.S.�o�b�n�F�����t�`�F���g�ȑ�3�Ԃ��u�v�������[�h�v �}�[���[�F�����ȑ�4�� �i�\�v���m�F�}�����E�r�X�g�����j �n�C�h���̃`�F�����t�Ȃ́A�����I�[�P�X�g���̋K�͂ɃR���Z���g�w�{�E�̃`�F����Ȃ��\���X�g�Ƃ����āA�ǂ����A�b�g�z�[���ȕ��͋C�B�K�b�e�B�̓I�P�ɂ��C����ԂŁA�Ƃ��ǂ��̂������x�B�Ȃ̊W�őO������������≹���������̂̃I�P�̔����͑��ς�炸�œT��B�ȂƂ��Ă͂���قǖʔ������̂ł͂Ȃ����̂́A���������Ȃ����܂ɂ͂������̂ł��B �}�[���[��4�Ԃ́A�؊ǃp�[�g�ɒ������ǂ��낪�����A�R���Z���g�w�{�E�͂܂��ɂ����Ă��B���ہA�f���炵�����̂��鉹�Ŗ������Ă��ꂽ���A���Ȃ��璮���Ă݂Ė؊ǂ̃I�[�P�X�g���[�V�����̖ʔ����������Ղ薡�키���Ƃ��ł����B�z�����ƃg�����y�b�g����肳���ۗ����Ă��āA��������邱�Ƃ����B�Ƃ��낪�A�Ȃ��ǂ��ɂ��l�̓��ʂɓ˂��h�����Ă��Ȃ��B����Ȃɗǂ����t���Ƃ����̂ɁB�}�ɕ����I�Ƀe���|�𑁂߂�Ƃ��낪������ƋC�ɂȂ�͂�������ǁA����Ȃ��Ƃɔ����Ђ��߂�قǖl�͐_�o���ł͂Ȃ��B��3�y�͂̏I�Ղɕ���E������\�v���m�̎肪�o�ꂵ�A�e�B���p�j�̉E�ׂɗ����Ă��̂܂ܑ�4�y�͂ɓ���Ƃ������o�B�l�I�ɂ́A���̊y�͓͂̉̂����ʂ�悤�ȗ����ȉ̂������D�݂Ȃ�ł����A����̉̎�͔����ɗh�炷�����B����ȂƂ�������܂�S������Ȃ��������R�Ȃ̂�������Ȃ��B�l�́A�ǂ̂悤�ȃX�^�C���ʼn��t���ꂽ�Ƃ��Ă������́u�����݂�ׂ��_�v�Ƃ��͎̂����Ȃ��悤�ɂ��āA�u���̎w���҂͂����\������ˁv�Ǝ~�߂�����Ǝv���Ă����ł����A��͂蔧�ɍ���Ȃ��Ƃ������Ƃ͂���̂�������Ȃ��B |
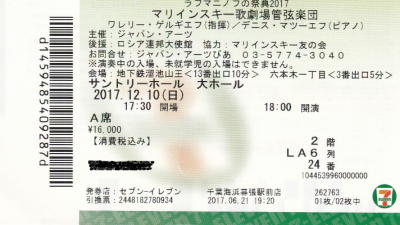 �y���ځz ���t�}�j�m�t�F �s�A�m���t�ȑ�3�� ���t�}�j�m�t�F �s�A�m���t�ȑ�4�ԁi�f�j�X�E�}�c�[�G�t�j �i�A���R�[���j���t�}�j�m�t�F���K�� �w���̊G�x Op.39-2 ���t�}�j�m�t�F�����I���� �i�A���R�[���j�����f���X�]�[���F �w�^�Ă̖�̖��x ���X�P���c�H ���̓��͒��̕��Ɩ�̕��Ńs�A�m���t��4�Ȃ����ׂĉ����Ă��܂��܂��傤�Ƃ������B��̕��݂̂̊ӏ܁B �܂��̓s�A�m���t�ȑ�3�ԁB���Ղ̕��߂���������@�ׂɒe���}�c�[�G�t�́A�ȑO�e���r�Ō����p���t���ȃC���[�W�Ƃ͈قȂ���́B�̊i�Ɏ�����ʃf���P�[�g�ȃ^�b�`�ɋ������A��3�y�͂̌������p�[�g�ł͂�͂�p���t���ɑ̂�h�炵�Ȃ��献�Ղ�@������B�������A�������ċ��ł��Ă����ۂ�A�e�G�Ȉ�ۂ͊F���ŁA�]�T�������Ĕ��͂̂���Ō����A���m���ɂ��������̉e�����^�����Ɉ��|����l�́A�P�Ȃ�͋Z�I�Ȉ�ۂƂ͂܂������قȂ���̂ŁA�܂��Ƀ��t�}�j�m�t�̃R���`�F���g��e���ɑ��������Ɖ��x���Ȓ����������Ă��܂��Ă����B��4�ԁi���̓�4�Ȗڂ̉��t�I�j�ł��}�c�[�G�t�̃G�l���M�b�V���ȉ��t�͂��������̔������������Ȃ��B������̓��t�}�j�m�t�ɂ��Ă⏭���g���b�L�[�ȃI�[�P�X�g���[�V����������Ă��āA�����ŊςĂ���Ƃ������y���߂�B �Ō�͌����I���ȁB���t�Ȃ̂Ƃ��Ɋ��Ɍ����Ă������̂́A���̃I�P�̎��͂͂Ȃ��Ȃ��債�����́B���̉��͊��炩�Ŗc�悩�ɗǂ��̂��B���ǖ؊ǂ͒����@�\�I�P�̂悤�ȃA���T���u�����Ԃł̕]����F�m�x���ւ�I�P�ɔ�ׂ�Ƃ��ɂ���ۂ͂�����̂́A���ɂ悭�̂��I�P�Ōl�I�ɂ͂ƂĂ��D���ȃ^�C�v�B�r���A�؊ǁi�������T�b�N�X�������Ă���j�̊|�������p�[�g�ŐL�ѐL�тƃR�[�������X�|���X����Ƃ���͂���Ӗ��{���̃n�C���C�g�ɂȂ��Ă����B����A���̋Ȃ������Ă݂����Ǝv�킹��f���炵���I�P�ł������B |
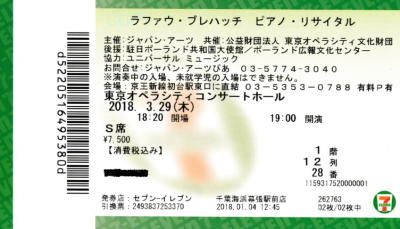 �y���ځz ���[�c�@���g�F�����h �C�Z�� K. 511 ���[�c�@���g�F�s�A�m�E�\�i�^ ��8�� �C�Z�� K. 300d �x�[�g�[���F���F�s�A�m�E�\�i�^ ��28�� �C���� Op. 101 �V���[�}���F�s�A�m�E�\�i�^ ��2�� �g�Z�� Op. 22 �V���p���F4�̃}�Y���J �@��14�� �g�Z�� Op. 24-1 �@��15�� �n���� Op. 24-2 �@��16�� �σC���� Op. 24-3 �@��17�� �σ��Z�� Op. 24-4 �V���p���F�|���l�[�Y ��6�� �σC���� ��p�Y� Op. 53 (�A���R�[���j �u���[���X�F6�̏��i Op.118 ��2�� �ԑt�ȃC���� �V���p���F�O�t�� ��7�� �C���� Op.28-7 �x�����ă��[�c�@���g�͉��O�̃X�s�[�J�[�Œ������ƂɁB����ł������s�A�m�̌y���Ȕ��������_�Ԍ�����B�s�A�m�\�i�^��8�Ԃ��I������Ƃ���œ���B �x�[�g�[���F���͎莝�����������̃o�b�N�n�E�X�A�O���_�A�o�����{�C���Ɣ�r���Ă����܂����Ă炤���Ƃ̂Ȃ��܂��Ƃ��ȉ��t�B����ł��㉹���̑@�ׂȃ^�b�`�Ɣ������A���m�ȕ\���ɂ����Ƃ肵�Ă��܂��B �V���[�}���̃s�A�m�\�i�^��2�Ԃ͎莝���̉������A�V���P�i�[�W�̂��̂ŁA��r����Ɩ`���ŏ������ߕ�������āA�����A�ƂȂ�B����ł���{�I�ȕ\���̓x�[�g�[���F���̂Ƃ��Ƒ傫���͈��Ȃ��B���̋ȂȂ�ł͏�M�I�ȃe�C�X�g���ߏ�ɂȂ�Ȃ��o�����X�ł�͂�i�ʂ̂���\���B �V���p���̃}�Y���J�͎莝�����������[�r���V���^�C���Ƃ̔�r�ŁA�������ɌÂ����[�r���V���^�C���̉��t�Ɣ�ׂ�Ƃ��Ȃ�������ꂽ�\���ŁA�����̓u���n�b�`�̌��������ɏo�Ă��銴���ł����B�p�Y�|���l�[�Y�͖{�l��CD�Ɣ�ׂĂ��ɂ������ʼn��t����A�����t�Ȃ�ł͂̓K�x�ɗ͂����������t���y���߂��Ǝv���B �A���R�[���ł́A�l�I�ɂ��܂����݂̂Ȃ��u���[���X�ɑ����āA�V���p���O�t�ȑ�7�ԁi�p���V�����̂��̋ȁj���ߏ�ȕ\����}������͂�e���݂̂��鉉�t�ł܂Ƃ߂Ă����B �S�̂�ʂ��āA�u���n�b�`�ɕ����Ă����C���[�W�ǂ���̉��t�ŁA�^�b�`�̑@�ׂ��Ɨ������̗ǂ������A���ɉ�����点�Ă����Y��Ȃ����ŏI��点�Ȃ��\���̕������\�ł����Ǝv���B���ۂɌ����u���n�b�`�͎v������菬���ŁA����32�ł���ɂ�������炸�A���삪���N�̂悤�ɗ�V�����������ȉ��y�N�Ƃ�����ۂ������̂��l�ɂƂ��Ă͂�����ƈӊO�������B����܂łɂ��܂�^���ɒ����Ă��Ȃ������s�A�m�̖ʔ����A����������ɐ[�܂����L�Ӌ`�ȃR���T�[�g�ɖ����B |
 2018/5/4�i���j �y1�z �w���F�����X�E�t�H�[�N�g ���t�F���C�����E�m�[�U���E�V���t�H�j�A ���ځF �E���[�c�@���g:�I�w�K���s�g�J���E�V�J���E�J�@���j�tK.527 ���� �E�X�g���E�J�B���X�L�[:���y�̂��߂̋��t�� �j�� �E���[�c�@���g:�����ȑ�38�� �j���� K.504�u�t�K���n�v �y2�z ���t�F�A���N�E�g���I�i�˓c�^��vl�A�R�{���Pvcl�A���V���ifp�j ���ځF �E�V���n�K��:�q�K�A�m�O�d�t�� �g�Z�� op.8 �E�g�D���[�i:�q�K�A�m�O�d�t�ȑ�2�� ���Z�� op.76 �����X�E�t�H�[�N�g���Ďw��������Ă����̂ˁA�Ƃ����y���������o���A���O���m��Ȃ��I�[�P�X�g�����B���t�ɏ����Ȃ��A�A���T���u���͗ǍD�B�����e���|�́u�v���n�v��3�y�͖͂؊ǂ���◐�ꂽ��͂��Ă������̂́A���Ȃ₩�Ȕ����̕\���i���Ɂu�v���n�v�̑�2�y�́j�͂Ȃ��Ȃ��̂��̂ŃG���U�x�X�������烍�C�����̏̍��������������Ƃ����̂������鉉�t�B�قƂ�ǒ����@��Ȃ��X�g�����B���X�L�[�̋��t�Ȃ̓Ɠ��̋������y�߂��̂��Ȃ��Ȃ��M�d�ȑ̌��������B 2�ڂ̎����y���A�Ȃ��Ȃ��ǂ������B���i�����Ȃ��Ȃ��������薡�키�Ƃ����Ӗ��ł�͂萶���t�͗ǂ��B�����y�̉��t���x���ɂ��Ă͂܂����܂�킩���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ�����A���t�Ƃ̂��Ƃ�m��Ȃ��Ă��y���߂�B�V���p���̃s�A�m�O�d�t��18�̂Ƃ��ɏ����ꂽ���̂ŁA�����x�͂قǂقǁA�C�������Ă��炸�A�V���p���炵�����D������قǑO�ʂɏo�Ă��Ȃ��ȂŁA����ł��������萶�Œ����Ă݂�ƂȂ��Ȃ��ǂ��ȂƎ�������B�킩��₷���A�X�y�C���̃e�C�X�g�����삵�Ă���g�D���[�i�̋Ȃ́A����݂��Ȃ��Ă��y���߂���̂ŁA������ʔ����������Ƃ��ł����B |
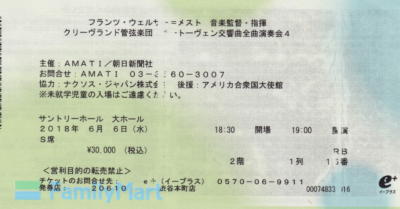 �y���ځz �����ȑ�2�� op.36 �����ȑ�6�� op.68 �u���I�m�[���v���ȑ�3�� op.72�� �܂��͌����ȑ�2�Ԃ���B�n�܂���2�������Ȃ������ɁA�������̃I�P�͏�肢�Ɗm�M�B���@�C�I�����͂悭�̂��A�������A�����������Ö��łȂ��i�������܂Ŋ���������B�`�F����R���g���o�X�̋������L���B�؊ǂ͂ǂ̃p�[�g���n�C���x���ŋ��ǂ���̑ł������Ȃ��B���M���ׂ��́A�����e�p�[�g�̃��x���̍����ɉ����āA�S�̂̃o�����X�A�A���T���u���������ł��邱�ƁB��肢����ƌ����ďo�߂����Ƃ���A�����������܂����Ƃ��낪�Ȃ��A�������I�P�S�̂͗]�T�������ĖL���ɉ���a���o���Ă�B�Ґ��Ƃ��Ă͌����đ傫���Ȃ��Ȃł���̂�������炸�A�T�E���h�����b�`�Œ��肪����B���̃I�[�P�X�g���Œ���2�Ԃ͂܂��ɋɏ�i�B���Ƃ���2�Ԃ͍D���ȋȂł͂������ǂ��A����Ȃɑf���炵���ȂȂƉ��߂Ďv���m�炳�ꂽ�B���ɑ�2�y�͂̔������ƌ������炻��͂������t�ɕ\���Ȃ��قǂŁA���U�Y����Ȃ�2�Ԃ����Ƃ����v���B �啝�ɕҐ����������ꂽ��6�Ԃ́A��͂�ꕪ�̌����Ȃ������ȉ��t�B�Ƃ��낪�e���|�ݒ肪�A�N���C�o�[���J���������Ǝv���悤�ȑ��߂̐ݒ�ŁA�l�̍D�݂��猾���Ƃ��������������������t�Œ������������Ƃ����̂������ȂƂ���B����ŁA���͟���c���Ƒ�����Ȃ�A����قǑf���炵�����t�͂Ȃ��A�Ɗ��������������ɈႢ�Ȃ��B�D�݂̃e���|�ł͂Ȃ������Ƃ��������Ŏc�O�Ǝv�����킯�ł͂Ȃ��A�f���炵�����t�����Ƃ����v���ɗh�邬�͂Ȃ��B �Ō�ɉ��t�������I�m�[���B���ꂪ�܂������B�x�[�g�[���F���̏��Ȃ͑S�W�̗]��X�y�[�X�ɓ����Ă��Ă��܂�^�ʖڂɒ����Ă��Ȃ��Ƃ����̂������ȂƂ��낾��������ǁA�����܂ł̉��t�������ƋȂ̒�͂��v���m�炳���B�㔼�̃X�e�[�W�����璮������g�����y�b�g�E�\��������͂��������ŁA����{���ɂ������̂����Ă��炢�܂����Ƒ喞���B |
 �y���ځz �o�[���X�^�C���F�����ȑ�2�ԁu�s���̎���v �i�s�A�m�F�N���X�`�����E�c�B�����}���j �h���H���U�[�N�F�X�������ȏW op.72 ���i�[�`�F�N�F�V���t�H�j�G�b�^ �܂��́A���N���a100�N���}�����o�[���X�^�C���̌����ȑ�2�Ԃ���B��Ґ��Ń_�C�i�~�b�N�ȋȂ͐��Œ����Ƃ�͂�X�P�[�������{���B�@�ׂȎ㉹����������������������i�s�A�m���K���Ă���㉹�Ƃ��̕\���̓�����킩��悤�ɂȂ����j�c�B�����}���̃s�A�m�A�����ėY�قȃI�P�̋������ꋉ�i�̉��y�ƂȂ��āA�ǂ����̂������ɖ��������B�I�P�̃��x���͐��E�ł��g�b�v�N���X�ŁA�l���I�P�̎��͂̔��f��̂ЂƂƂ��Ă���A�㉹�ł̉��̔��������\�����Ȃ��B ���́A���C�y�ɒ�����h���H���U�[�N�̃X�������ȁB�������ƃX�����L�Y�����D�̕\���̓��g���̓��ӂƂ���Ƃ���ŁA���̋ȂŃI�P�Ȍ����̉̂����Ղ肪��薾�m�ɂȂ�B�y�����Ɣ���������������̋Ȃ́A�P�ȂŃA���R�[���ɉ��t����邱�Ƃ͂悭���邯��ǁA���̃��x���̃I�P�Œʂ��Ē�����@��͏��Ȃ��A�����Ɣ������݂ɔz�����\���̗ǂ����ĔF���B�����h�������y�c�͌��ɕi�ʂ��鉐�������������������A���ǖ؊ǂ��Z�ʓI�ɗD��Ă��ăI�P�S�̂��悭�̂��B�X�ɃI�P�S�̂̃o�����X���ǂ��Ƃ��낪�f���炵���B 3�Ȗڂ̃V���t�H�j�G�b�^��P�Ȃ̍Ō��A�p�C�v�I���K���̑O��9�l�ƃg�����y�b�g�t�҂��Y�����ƕ��ԁB�`���̃g�����y�b�g�ɂ��t�@���t�@�[���́A����Ȃ�̐l���ɂ����̂��낤�Ƃ͎v���Ă������̂́A9�l�����āA���������̍����ʒu������o�����t�@���t�@�[���̋����Ɖ����͑����Ȃ��́B�I�[�f�B�I�ł͂ǂ�����Ă��Č��ł��Ȃ������Ƃ͂܂��ɂ��̂��ƁB���Œ����Ă��̋Ȃ�����Ă������͂������Ă��炦���悤�ȋC������B  �y���ځz �w�����E�O���C���F�D�萬���ꂽ��ԁi���{�����j �}�[���[�F�����ȑ�9�� 1�Ȗڂ͓T�^�I�Ȍ��㉹�y�B�����Ċy�������̂ł͂Ȃ�����ǁA20�����炢�Ƃ����đO�Ƃ��Ċy���߂��B���̂悤�ȋȂ���{�ō̂�グ��ӗ~�I�ȃv���O�����́A���̃I�P�ɂ����K���Ăق����Ƃ���i�L���Ȃ����v�������Î҂Ɗϋq�ɂ��j�B �}�[���[��9�Ԃ͕\���̐U�����傫���A�傰���ɂ�肷����ƒᑭ�ɁA�}��������ƕ�����Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ肩�˂Ȃ��̂ŁA���̃o�����X���ǂ���邩���w���҂̘r�̌����ǂ���B���g���͏d���Ȃ肷���邱�ƂȂ��A�������X�P�[���̑傫���\�����I�P��������o���B���̓����I�P�̃p�t�H�[�}���X�͑O���ƑS�������i2�������ē����I�P���ƃf�L�ɍ������邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��j�̑f���炵���B |
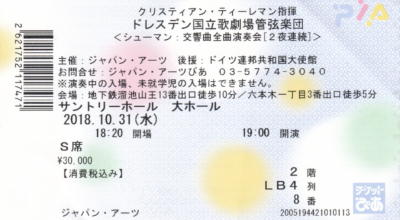 �y���ځz �V���[�}���F�����ȑ�1�� �u�t�v op.38 �V���[�}���F�����ȑ�2�� op.61 �V���^�[�c�J�y���E�h���X�f���̃T�E���h�́A���a�߂̉��F�ŁA�R���Z���g�w�{�E�̂悤�Ȓg�F�n�̉��Ƃ͑S������Ă���B�a�߂Ƃ����Ă�����͉��F�̘b�ŁA���͂悭�̂��Ă��Ď㉹�̕\���͂������B���ǁA�؊ǂ��h�肳�͂Ȃ����̂́A���Ɉ��肵�Ă��Ĉ��S���Đg��C������Z�p������A�I�P�S�̂̃��x���͔��ɍ����B�x�������E�h�C�c���������y�c�A�o���x���N�����y�c�̉��F�Ǝ����X���̂����ɂ��h�C�c�I�ȃT�E���h�Œ����V���[�}���́A�܂��Ƀh�C�c���y���̂��́B�e�B�[���}���͎��ɂ����ƃe���|�𗎂Ƃ�����A�^������Ɠ��ӂȌ|���𑶕��ɔ�I�B�P���ɂȂ肪���ȃV���[�}���̌����Ȃ́A���̂��炢��_�ɂ���Ă��ꂽ���������B���̃I�P�̃p�t�H�[�}���X���Ă���ƁA�u���b�N�i�[��u���[���X���Ă݂����Ǝv�킹��B�ł��A�V���[�}�������̎w���ҁA�I�P�ɂƂĂ��悭�����Ă���B�V���[�}���͗͗ʂ̂Ȃ��I�P��������A�D�����I�Ȏw�����Ƒދ��������Ȋ���������̂ŁA�e�B�[���}���ƃV���^�[�c�J�y���E�h���X�f���Œ����@������Ă��͖̂{���ɗǂ������B |
 2019�N2��23���i�y�j�R�u���[�m�[�g�����A�N���X�E�{�b�e�B��2nd�Z�b�g�B �Q�������o�[�F Sy Smith (vo) Andy Snitzer (sax) Joey DeFrancesco (org) Eldar Djangirov (p) Erin Schreiber (vln) Leonardo Amuedo (g) Reggie Hamilton (b) Lee Pearson (ds) ���̏����ȉ��Œ������̃g�����y�b�g�̃T�E���h�͂�͂�C�C�B�NJy��̐����i����PA�ʂ��̉��ł����j���ăC�C�Ȃ��A�Ɖ��߂Ďv���o���B1�Ȃ߂̓L�[�{�[�h�������o�b�N�ɂ����ӂ�"Ave Maria"�œ���B���̌�́A�x�[�X�i�Ȃɂ���ăE�b�h�E�x�[�X�ƃG���L���g�������j�ƃh�������o�����ς�Ȃ����ŁA���Ƃ͓�����藧������ڂ܂��邵�����t�����o�[���ς��B"I Thought About You" "So What" "When I Fall In Love" �Ƃ������}�C���X���̋Ȃ𒆐S�ɁA"Cinema Paradiso" ��A���b�h�E�c�F�b�y������ "Kashimir"�i�{�b�e�B�����ă��@�C�I�������S�j�܂Ŕ�яo�����̍L�������o�[���R���R������ւ��A����ɉ����Ă��܂��܂ȋȂ����t�����̂ŊςĂ��Ċy�����ĖO���Ȃ��B���M���ׂ��A�N��l�Ƃ��āu�܂��A���̒��x�̐l�����邩���v�Ǝv�킹��邱�Ƃ��Ȃ��S���A���t�̘r���m���Ȃ��ƁB���Ɉ�ۂɎc��̂́A�Z���g���C�X�����y�c�ŃA�V�X�^���g�E�R���T�[�g�}�X�^�[���߂Ă���Ƃ����G�����E�V�����C�o�[�̃��@�C�I�����ƁA�W���[�C�E�f�t�����Z�X�R�i12�N�O�Ƀ}���n�b�^����Jazz Standard�j�Ŋς����Ƃ�����j�̃I���K���A�����ēS�ǂ��������ǂ����S�����x�[�X�ƃh�����B�M�^�[���܂߂Ă݂�ȏ�肢�B��肷����B ���t���n�܂���1���Ԃ��炢���o�߂��āA�������낻��Ō�̋Ȃ��ȂƎv���Ă���ƁA���Ȃɉ̎�̃T�C�E�X�~�X���o�ꂵ�ĉ̂��n�߂�B�V���E�͍X�ɑ����āA�I������Ƃ��ɂ�1���Ԕ��ȏオ�o�߁A�{�����[�����ł����������ς��ɖ��������Ă����B ���t���́A���x�ݒ��̃����o�[�������̎����ꂽ��A�ϋq�ƃJ�W���A���ȉ�b��������A�Ƃɂ����y�����A�����b�N�X�����l�q�������ݍ��ށB�{�b�e�B��CD���āu�����Ȃ����Lj��y�ł������Ƃ܂������[�h�E�~���[�W�b�N�v�Ǝv���Ă�������ǁA���C���͔M�ʂ��\���������L�����A����ɂ̓o�[�g�E�o�J���b�N��g�j�[�E�x�l�b�g�̂悤�ȃA�����J���E�G���^�[�e�C�����g�̐��E�ɂ��ʂ��Ă��āA�ςĂ���҂��y���܂���V���E�Ƃ��Ĉꋉ�i�������BCD�ō��グ�Ă���C���[�W�Ƃ͈قȂ�A���C�����R�ɐL�ѐL�тƎ����̉��y�������Ă���N���X�E�{�b�e�B�̖{���̎p�͂����������̂Ƃ������Ƃ��A�Ƃ������Ƃ��悭�킩�����B |
 2019�N3��19���i���j�u���[�m�[�g�����A�}�f�����E�y���[�A2nd�Z�b�g�B �����o�[�F Madeleine Peyroux(vo, g, uke) Andy Ezrin(key) Jon Herington(g) Paul Frazier(b) Graham Hawthorne(ds) ���Ō���}�f�����E�y���[�́A�������Ƃ������Ȃ��A�i���������Ă͎���ł����j�ӂ��̂�����Ƃ�������B�W���P�b�g��A�[�e�B�X�g�ʐ^�Ɣ�ׂ�Ɓu�����Ƃ��Ɓv�Ǝv�����炢������Ȋ����ŃX�^�[�̂悤�ȃI�[���͈�Ȃ��B���܂肻�������V���[�r�W�l�X�I�Ȑ��E�ɊS������悤�ɂ͌������A�D���ȉ̂������̂��Ă���Ƃ������X�g���[�g���Y�����[�h�B���ۂɃ��C���Œ����ƁA�̂����͂��Ȃ�����Ă���A�Ƃ������������������Ɖ̂����Ƃ��Ă��Ȃ��B���������Y���̂Ƃ�������R�C�܂܂ŁA�}�C�N�Ƃ̋����̂Ƃ�������܂�C�ɂ��Ă��Ȃ��̂��A�}�C�N�z���Ɛ���������������Ē��������ʂ��������B�������A���m�ɉ̂��Ȃ��Ƃ����s���肳�ł͂Ȃ��ACD�̂悤�ɃL�b�`���̂����Ƃ��Ă��Ȃ��C������p�t�H�[�}���X�̂Ȃ��̂��āA�����A���ꂪ���i���̔ޏ��ȂȂ��Ƃ������Ƃ��ǂ��`����Ă����B���y�I�ɂ͑S�̓I�Ƀu���[�X�̉e�����l�I�ɂ͊������B���ۂɃu���[�X�F������Ȃ�1�ȉ��t���Ă�������ǁA�����������\�ʓI�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�X�e�[�W��ʂ��Ĕޏ��̍���Ƀu���[�X�Ƃ����A�����J�������y����������ƍ��Â��Ă���B�����CD����͊������Ȃ������Ƃ���ŁA���������Ƃ�������i���̔ޏ��Ɗ��������������������Ȃ��B���������Ӗ��Ō����ƁACD�͐����ƃK�b�`���ƃv���f���[�X���č��ꂽ���̂ł���Ƃ������Ƃ��悭������X�e�[�W�������B |
 LAP�̈�ۂ�4�N�O�Ƃ܂������ς��Ȃ������B�ǂ̃Z�N�V���������ɗǂ��̂��B���ǂ̉₩�ȋ����͂������A�؊ǂ̃p���[�������܂Ŋ���������I�P�͒������Ǝv���B�������ƌ����Č�����邩�Ƃ����Ƃ�����������̑@�ׂȋ������炽���Ղ�Ɖ̂킹��Ƃ���܂ŁA����͂���͌����ȋ����B�����āA���̏a�݂�A��⒤��̐[���Ƃ����\���ł͂Ȃ��A�₩�ʼn����o�����̋�����LAP�̓����ŁA4�N�Ԃ�ɊςāA����̓I�P�̎������ȂȂƊm�M�B ���������ƁA�����ӎ������}�[���[��9�Ԃ�\������ɂ͐[������؎����A�h���h�������G��������Ȃ���Ȃ����Ǝv���邩������Ȃ�����ǁA����͂��̒ʂ肾�Ǝv���B�₩�Ə������Ƃ͂����A���F����ɖ��邢�Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��A�V���A�X�ȕ\�������߂���p�[�g�ł͂�������Əd�X�������ꂽ�����̃T�E���h���o�Ă���B�����A�I�P�̎����Ă���{���I�ȕ����Ƃ��āA����Ӗ���y�I�ȕ\���ɂȂ��Ă���悤�Ɋ������A����͓y�n�����l����Γ��R�Ȃ��Ƃł�����悤�Ɏv���B �h�D�_�����̎w���Ԃ�́A�ȑO���͗��������C���̃A�N�V�����A����ł��������Ƃ����Ƃ���ł͑傫�Ȑg�U��ŃI�P�����B��1�y�͂ł́A�I�P�̂܂Ƃ܂�ɂ���H�Ɗ�����Ƃ��������������ǁA���X�ɏn��Ă��āA��3�y�͂̃t�B�i�[���̐����ƌ������́A�h�D�_����LAP�̗ǂ����ǂ��o�Ă����u�ԁB��4�y�͂ŋ��߂��錷�i���Ƀ��@�C�I�����j�̔������ƃ_�C�i�~�N�X���f���炵�������B |
 2019�N4��6���i�y�j�u���[�m�[�g�����A�`�b�N�E�R���A��2nd�Z�b�g�B Chick Corea (p) Chiristian McBride (b) Brian Brade (ds) �`�b�N�̃s�A�m�ɍ��킹�ăI�[�f�B�G���X�Ƀn�~���O������Ƃ����a�₩�ȕ��͋C���� "La Fiesta" �ɂȂ��ꍞ�ނƂ����X�^�[�g�B���t�ɓ����3�l�ٖ̋��ȃv���C�ɖڂ��B�t���ɂȂ��Ă��܂��B�N���X�`�����E�}�N�u���C�h�̍��������m�������f�B�b�N�ȃx�[�X�ƁA�����̈����o�������u���C�A���E�u���C�h�̃c�{��}�����h�����Ŗa����鉉�t��CD�Œ��������̉��t���̂��̂ŁA�v�킸�g�����o���Ē����Ă��܂��B�����͌����Ă������̓W���Y�̃��C���BCD�́A����Ӗ��J�b�`���Ƃ������t�iCD�͂�͂�J��Ԃ������ɑς���L�b�`���������t��I��ł���j�Ƃ͈ꖡ�Ⴄ�ɂ�������B���̊ɂ��́A���t���o�ɂ��Ă���Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�ǂ��Ӗ��ł̗V�т������������̂ŁA���t�̎���CD�Œ�������̂Ƃ܂��������F�͂Ȃ��B�������ACD�Ɏ��^����Ă��� "This Is New" "Alice In Wonderland" �Ȃǂ��A���̏����̋�C�ʼn��t�����B���̓��ς��X�e�[�W�ł́ACD�Ɉꕔ�ɂ������悤�ȃt���[�ȓW�J�̋Ȃ��Ȃ��A����Ƃ��āi���������Ǖ��ʂ��������Ă��܂����ƌ����A8�y�[�W�̕��ʂ��s�A�m�ɒu���Ă����j�X�p�j�b�V���E�\���O�ƏЉ�Ă����Ȃ𒆐S�Ɍ`�����L�b�`�������ȂŐ�߂��Ă�������ǁA���R�x�͎���Ƃ���ɂ����āA��͂��u����Ƃ��ڂ������Ȃ��B�W���Y�̂����炩���A�y�����������Ȃ���A�ō����x���̉��y���ƋZ�p�����������t���Ă���ƁA�C������1����15�����炢�������Ƃ����Ԃɉ߂��Ă��܂��Ă��邱�ƂɎ����ł������Ă��܂����B��������A���R�[���ɂ���ɉ����Ă܂��]�T�����Ղ�Ƀ����N�̋ȂŒ��߂Ă���đ�c�~�B�Ƃɂ����A�����������Ă��炢�܂����A�Ƃ������z�����o�Ă��Ȃ��B |
 �y���ځz �����f���X�]�[���F���@�C�I�������t�ȁi�ҍʓށj �i�A���R�[���j�o�b�n �����t���@�C�I�����p���e�B�[�^��3�� "�K���H�b�g" �}�[���[�F�����ȑ�6�ԁu�ߌ��I�v �ҍʓނ̓e���r�Ŋς���ۂ��̂܂܂̊����B���m�����y��̉̂킹�����債�����̂ŁA�Z�p�͂ƂĂ��������肵�Ă��邵�\���͂�����B�Ⴓ���钼���I�Ȑ������O�ʂɏo�����t�ŁA���y���d�����A�Ȃɐ[�����荞��œƎ��̕\���Œ�������̂͂܂��܂����ꂩ��Ƃ��������ŁA���������ƐL���B�ǂ��\�����邩�̎�@���܂߂��Z�p�͂��łɍ������x���ɂ��邯��ǁA���̋Z�p���ǂ��g�����特�y�Ƃ��đf���炵���\���ɂȂ邩�A�Ƃ������y���͂��Ȃ薢�n�Ȉ�ہB�ł��A���̎Ⴓ�i21�j�ŕ\���̐[���܂ŋ��߂�̂͗��ɍ��Ƃ������̂ŁA���ꂩ������Ɨǂ����t�ƂɂȂ��Ă����Ăق����Ɗ��Ҋ����������|�e���V�����͂���Ǝv�����B �}�[���[��6�Ԃ́A�K�b�V�������I�P�̖�ƂƂ��Ɏn�܂�A�ǂ����t�ɂȂ肻���ȗ\���B���ۂ��̃I�P�͊y��̉̂����Ղ肪�ƂĂ��ǂ��A���x�������t�҂̎����I�ȕ\�����d������l�D�݂̃^�C�v�B���ɖ؊ǂ̌��C�Ȗ���́A�Ȃ��Ȃ��̂��́B�������A�����ƒ����i�߂čs���ƁA���̑������������Ƃ��낪���Ȃ��炸����A����̊y�킪�肷���Ă����肷��Ƃ���Ȃǂ����ɕt���͂��߂�B����͎w���҂̐ӔC�ł����邯��ǁA�I�P�S�̂̃A���T���u�����ǂ��Ȃ����A�p�[�g�Ԃ̉��̂Ȃ�����ǂ��Ȃ��B�Z���ăV���v���ȋȂȂ�떂��������������Ȃ�����ǁA�}�[���[�̑�6�ԂƂ�����Ȃ��Ƃ����͂����Ȃ��B ����ł��O�q�̒ʂ�A�X�C�X�E���}���h�nj��y�c�͊y��A�I�P�̉̂����Ղ�͑f���炵���B�ߋ��ɊςĂ����I�P�̒��ł���ʂɗ���ƌ����Ă��������炢�ŁA�D�ꂽ���y�ēA�w���҂����܂������ł�����f���炵�����t�������Ȃ����Ƃ������Ҋ����������邾���̃|�e���V�����͂������Ǝv���B |
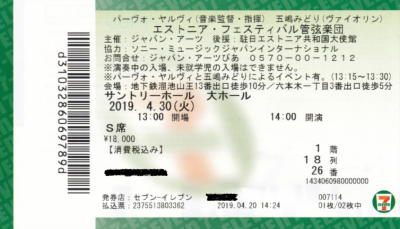 �y���ځz �y���g�F�x���W���~���E�u���e���ւ̒Ǔ��� �V�x���E�X�F���@�C�I�������t�� (�ܓ��݂ǂ�) �i�A���R�[���j�o�b�n �����t���@�C�I�����\�i�^��3�ԑ�3�y�̓����S �g�D�[���F�e���y�X�g�̎��� �V�x���E�X�F�����ȑ�2�� �i�A���R�[���j ���|�E�X�����F�X�v�����O�E�t���C �q���[�S�E�A�����F�[���F�r�����̖��̗x�� 1�Ȃ߁A�u�x���W���~���E�u���e���ւ̒Ǔ��́v�͋��ǖ؊ǔ����̕Y���悤�Ȍ��y�ȁB���������A���f�批�y�I��10�����x�̋ȁB �����āA�l�I�ɂ͖{���̃��C���ł���u���@�C�I�������t�ȁv�B�I�P���h���Ɠ����Ă���O�̖`���\�������ŋC�������������h���Ԃ�ܓ��݂ǂ�ɑ��������|����Ă��܂��B��ɂ���đ��������Ɠ����đ̂��悶�点��悤�ɒe���ܓ��݂ǂ�́A�����ڂƂ͗����ɏ�ߑ��ɂȂ�Ȃ��A�@�ׂȕ\���ɐS���ӂ����t���������Ǝv���Ă�������ǁA���̓��͑z���ȏ�ɏ�Ɉ�ꂽ�M���ŁA�������ł��i�����������������������Ă��Ȃ��Ƃ���ɒ����������B���x�̍����t���[�W���O�ł��@�B�I�ȃ��[�h�͊F���A�������A�@�ׂ��A�����ă_�C�i�~�Y�������|�I�ŁA���E�̈ꗬ�t�҂ł��邱�Ƃ𑶕��Ɍ����������t�ɁA�z���g�A�C�C���̒������Ă��炢�܂����Ƃ������ӂ̋C���������o�Ă��Ȃ��B �x�e����A�А��̂����u�e���y�X�g�̎����v������ł́u�����ȑ�2�ԁv�B�I�P�͐��s�W�c�Ƃ��������ɗ��̋����B���ǖ؊ǂ̓A���T���u���ɂƂ���ǂ�����������͂�������ǁA�\���E�p�[�g�͂܂��܂��A���͗Y�قɉ̂��A�ϋɓI�Ȏ�̐����O�ʂɏo���Ȃ��Ȃ��̎��͂̃I�P�ł��邱�Ƃ��킩��iHP�ɂ���A���c�F�����j�Պnj��y�c�ɕC�G�͌����߂������ǁj�B�V�x���E�X�̊��X�Ƃ������F�������ɕ\�����A���ɑ��i�ɍ\��������������p�[���H�̋@�q�Ȑi�s�ŃL�r�L�r�Ƃ������t�͒�������������A���߂Ē����V�x���E�X�𑶕��ɖ��키���Ƃ��ł����B |
 2019/5/3�i���j �y1�z �w���F���I�E�N�I�N�}�� ���t�F�E�����E�t�B���n�[���j�[�E���[�X�nj��y�c ���ځF �E�t�������c�F�������u�N�U���E�M���[�k�i�ԏƂ̍����j�vop.18 �E�u���b�t�F�X�R�b�g�����h���z��op.46 (vl:������[�����E�~�T]) �y2�z ���t�F�A�i�X�^�V�A�E�R�x�L�i�ivc�j�A�p���}�E�N�[�C�f���ip�j ���ځF �E�u�[�����W�F�F�`�F���ƃs�A�m�̂��߂̂R�̍�i �E�q�i�X�e���F�p���y�A�[�i ��2�� �E�t�H�[���F��肩�� op.23-1 �E�u���[���X�F�`�F���E�\�i�^��2�� �w���� op.99 �y1�z ���[�X�I�P�Ƃ������ƂŁA�n�[�h�����グ���A���C�y�ȋC�����Œ����Ă݂�B���{�����̃t�������c�̋Ȃ͒����i20���ȏ�j���ɂ́A����ƌ������W�J�������n�����Ȃ��ȂŐ����ɏP���Ă��܂��B�u���b�t�́A���C�����ς��̎Ⴂ�\���X�g�̔M���ƃI�P�̍D�T�|�[�g�������āA�Ȃ��Ȃ��̍D���B���܂�I�P�ւ̋Z�p�I�v���x�������Ȃł͂Ȃ������ł͂�������ł����A�l�̖ڂ���݂���q���݂����Ɍ�����A�����䗦8���ȏ�̎Ⴂ�����o�[�Œ������t�͗\�z�ȏ�ɗǂ����t�ŁA���܂萶�Œ����@��̂Ȃ����̋Ȃ��y���߂�v���O�����ł����B �y2�z 94�N���܂�Ƃ����Ⴋ�`�F���X�g�����C���ɁA����قǓ���ݐ[���Ȃ����Ȃƃu���[���X�̃\�i�^�Ƃ����v���O�����B����I�ȃu�[�����W�F�A���_���ȃ��e���E�e�C�X�g�̃q�i�X�e���A���}���`�b�N�ȃt�H�[���ƑI�Ȃ��ǂ������B�R�x�L�i�̃`�F���͎Ⴓ���錃�����i���ƕ@�����傫�����邯�ǁE�E�E�j�Ɛ��X���������邵�A���b�N�X���ǂ��Ă��ꂩ��X�^�[�ɂȂ�\���\���Ƃ��������ł��B���������Ⴍ�L�]�ȉ��t�Ƃ��Љ��̂�LFJ�̑厖�Ȗ����B�T�|�[�g�̃N�[�C�f���̃s�A�m���f���炵���E�E�E�Ǝv����悤�ɂȂ����͎̂����ł��s�A�m��e���悤�ɂȂ�������ŁA�����܂Ō����Ă����̂Ńy�_���̊ώ@�Ȃǂ��Ȃ��璮������܂����B��͂�v���̃s�A�j�X�g���Đ����Ȃ��E�E�E�B����܂�LFJ�Œ��������ŋ��w�̉��t�ł����B |
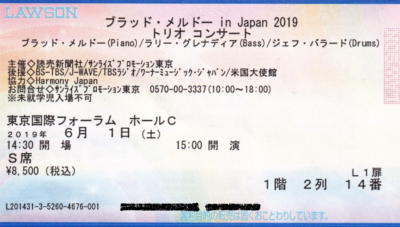 �O��A2012�N�̂Ƃ��͒��ۓI�ŃX���[�ȋȂ��قƂ�ǂƂ����āA�Ȃ��݂͂ǂ���̂Ȃ����t�ŁA�D�𑆂��I�[�f�B�G���X�����Ȃ��炸���������A���X���Ȗ����I�ȃR���T�[�g���������Ƃ��v���o���B���_���猾���ƁA����͕��ʂ̃W���Y�E�s�A�m�E�g���I�炵�����t���y���߂���e�������B�������A�ߔN�̃����h�[�͂��܂�w��Z�������t���u�����Ă��炸�A���ł�Art Of Trio����Ƃ̓X�^�C�����ς���Ă��Ă��āA���ȉ��t���ꂽ�A�b�v�e���|�̋Ȃ��܂߂ē����I�ȉ��t�ɏI�n�B�������A����͂���Ń����h�[�̖��͂ł͂������ǁA�Ⴆ�uBrad Mehldau Trio Live�v�� "Black Hole Sun" �̂悤�Ȏ��R�x�̍������t��D�������ȂǁA�����������Ă���Ă��ǂ�������Ȃ����ȁA�Ƃ����v�����߂��Ă��܂��B�������A���t�̎��͍����A���ɍ���̓W�F�t�E�o���[�h�̌���������\����A�W���Y�炵���y���݂������āA���e�ɂ��ĕs���͂�����Ƃ����l�I�Ȏv���ɉ߂��Ȃ��B�R���g���[���� "Inch Warm" ��ʔ�������������A�����h�[�����t����̂͏��߂Ē���"When I Fall In Love" �������h�[�炵���X�^�C���Ŕ��������t�����ȂǁA�����ǂ���͂���������B ����ł��l�͎v���Ă��܂��B���̃����c�ł̉��t�����������Ԓ����Ȃ�A���}���l�������Ă���̂������ł͂Ȃ����ƁB�s�A�m�E�g���I�łł��鉉�t�X�^�C���͂�͂�ǂ����Ō��E�����Ă��܂����̂ŁA����̓r���E�G���@���X��L�[�X�E�W�����b�g�ł��������Ȃ������Ƃ���B4���Ɋς��`�b�N�E�R���A�E�g���I���A���̎��A���̏�ł̌ċz��������������̂������̂ɑ��āA�Ȃ��n�܂�Ƃ��ƏI���Ƃ��ȊO�͖ڔz�������Ȃ�3�l�́A�ǂ������Ί������ꂽ�A���������Ό^�Ƀn�}�������t�������Ƃ͌�����Ǝv���B�Ȃ�Ă��낢�돑��������ǁA��͂肱��3�l�łȂ���Β����Ȃ��N�I���e�B�̉��t���������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��A�������t�������Ȃ�Č�������͂���܂���B |
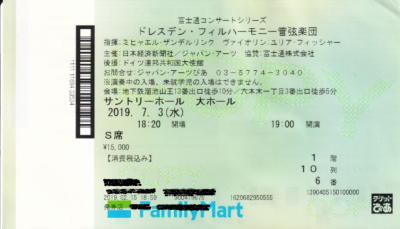 �y���ځz �u���[���X�F���@�C�I�������t�ȁi�����A�E�t�B�b�V���[�j �i�A���R�[���j�p�K�j�[�j�F24�̊�z�ȑ�2�� �u���[���X�F�����ȑ�1�� �i�A���R�[���j�u���[���X�F�n���K���[���ȑ�5�� ���̓��̂��ړ��Ă̓����A�E�t�B�b�V���[�B�[���ł���Ȃ���P�Ȃ�܂�ڐ������Ɏ��܂邱�ƂȂ��A����L���A�}����Ƃ���͗}���A�����������Ƃ���ł̍r�X���������R�����A���̕\���̕��̍L���ƋȂ̏�ʂɂ������\����̍I��������A������ȑS�̂̕\���ɏ������Ă���B�����ɃR���g���[�����ꂽ�����̔������Ƒ@�ׂȋ������o�F�ŁA��2�y�͂͑f���炵�������ǂ��낾�����B���̂܂܉��t���I���Ȃ�������̂ɁA�Ǝv�����t�������Ƃ͖{���ɍK���Ȃ��ƁB �㔼�̌����ȑ�1�ԁB�I�[�\�h�b�N�X�ȃe���|�ɂ��i�s�ƁA�֒��̂Ȃ����R�ŏ_�炩���\�����S�n�悭�A�V���^�[�c�J�y���E�h���X�f���ɂ��ʂ���h�C�c�I�P�炵�������a�߂́i�������u�����Ă��Ȃ��Ƃ�������j�T�E���h���Ȃɗǂ������Ă���B�������ڂŌ���ƁA���ǂƁi�I�[�{�G�ȊO�́j�؊ǂɗ͋����ɕ�����Ȃ����������i��肭�Ȃ��̂ɉ������ő傫�ȉ����o�������͂����ƍD�܂����j���A�e���|���}�ɏグ���Ƃ��Ɍ��̃Z�N�V���������ꂽ�肷���ʂ�����������ǁA����̋ȂƂ������Ƃ������ău���[���X�̗ǂ�����肭�\�����Ă����B |
 ���܂��ܗ��s�ɍs���Ă����n���C�̃u���[�m�[�g�ŃN���X�E�{�b�e�B 2019�N7��14���i���j1st�Z�b�g�B�q�����7�����炢�Ə�X�B2���̃u���[�m�[�g�����ŃQ�X�g�Q�����Ă����W���[�C�E�f�t�����Z�X�R�͂��Ȃ��������A�������@�C�I���j�X�g���Ⴄ�l�iMC���炱�̓��̐l���{���̃��M�����[�E�����o�[�Ȋ����j�������B���t�Ȃ͂��܂����Ă��Ȃ��������̂́A5�����O�Ɠ��e�͎����悤�Ȋ�����90�������Ղ�Ɗy���܂��Ă��ꂽ�̂����l�B���߂ĊςĎv�����̂́A�h�����ƃx�[�X���ƂĂ���肢�Ƃ������ƁB�W���Y�E�N���u�œW�J����A�����J���E�G���^�[�e�C�����g�Ƃ����W�������ɂ����Ă��A���C�����f���炵���Ǝv�����b�ƂȂ�̂͂�͂�x�[�X�ƃh�����ł��邱�Ƃ��ĔF���B���{�l�F���̋q�Ȕ����̓X�|���e�B�j�A�X���i�`�������B���̎�̉��y���ނ�ɐ[�����t���Ă��邱�Ƃ����������Ă��ꂽ���C���ł��������B |
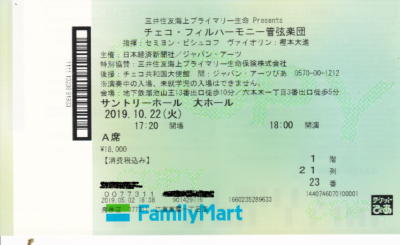 �y���ځz �X���^�i�F�����_�E�`�A��������u�킪�c���v��� �`���C�R�t�X�L�[�F���@�C�I�������t�ȁi�~�{��i�j �i�A���R�[���jJ.S.�o�b�n�F�����t���@�C�I�����̂��߂̃p���e�B�[�^ ��3�Ԃ��u�K���H�b�g�v �`���C�R�t�X�L�[�F�����ȑ�6�ԁu�ߜƁv �i�A���R�[���j�G���K�[�F�G�j�O�}�ϑt�� Op.36-9 �u�j�����b�h�v �܂��̓`�F�R�t���ɂƂ��Ă��ƌ|�ł����郂���_�E�͂������芵�ꂽ���́B�N�ł��m���Ă��Ȃ���A�ӊO�Ǝ������@����Ȃ����̋ȁA����Ȃɂ����Ȃ������̂��ƍĔF���B �`���C�R�t�X�L�[�̃��@�C�I�������t�Ȃ��A�I�P�̕\���͍D���B�������A�~�{��i�̃\���͂��܂�l�̐S�ɂ͋����Ȃ��B�������Z�p������Ȃ��Ƃ��������������Ƃ͂Ȃ�����ǁA�����݂ȃ��B�u���[�g�𑽗l���鉉�t�͈�{���q�ł����ЂƂƂ������Ƃ���B �����܂ł̉��t����A���҂����܂郁�C���̃`���C�R�t�X�L�[�����ȑ�6�Ԃ́A�������Ɖ̂킹�����t�B�ߔN�ł̓N���A�Ńe�L�p�L�������t�������A�����Ɣ�ׂ�Ɛ�������Ă��Ȃ��Ăǂ������������B�ł��A���ꂪ�`���C�R�t�X�L�[�̃o�^�L���ɂƂĂ��ǂ������Ă���B���ꂪ���R�ŁA���ӓI�Ɍ��ʂ�_�����Ƃ��낪�ǂ��ɂ��Ȃ��A�����ɂ���Ă͏��X�Â����t��������������Ȃ��B�ł��A�����������ՓI�ȉ��t���܂��������́B�I�P�̉��t�X�^�C������������Ă��Ȃ����A���̐��������x�ȉ��t�Ƃ����킯�ł͂Ȃ����̂́A�ƂĂ����肵�Ă��Ċe�p�[�g���I�P�S�̂��ƂĂ��ǂ��̂��Ă��邩����S���Đg��C���邱�Ƃ��ł���B���肻���ňӊO�ƂȂ��A�S�n�悢���t�Ƃł��������炢����ł��傤���B�o�߂����Ƃ��낪�Ȃ��A�͔C���ȂƂ�����Ȃ��A�A���T���u�����f���炵���āA�u�C�C���y�����v�Ƃ����K�����ɖ��������B |
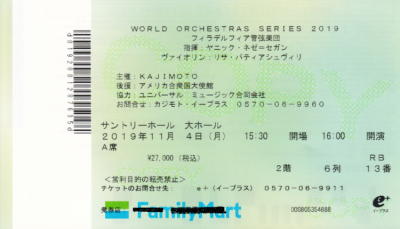 �y���ځz �`���C�R�t�X�L�[�F ���@�C�I�������t�ȁi���T�E�o�e�B�A�V�����B���j �i�A���R�[���j�}�`�����@���A�j�F�W���[�W�A�̖��w���Doluri �}�[���[�F �����ȑ�5�� 3�N�O�Ɋς��Ƃ��̈�ۂ������t�B���f���t�B�A�nj��y�c�B �܂��A�`���C�R�t�X�L�[�̃��@�C�I�������t�Ȃ͊����2�T�ԑO�̊~�{��i�ƃ`�F�R�t���Œ���������Ƃ����Ē�����ׂƂȂ����i�`�P�b�g�������ɂ̓v���R�t�B�G�t���������ǃv���O�������ύX���ꂽ�j�B �܂��A�I�P�̖肪�Ⴄ�B���̌��݁A�ꖡ�A���m���B�o�e�B�A�V�����B���̃\���͂������ŁA���߂�Ƃ���A�˂��i�ނƂ���A�̂킹��Ƃ���A���点��Ƃ���Ȃǂ̎g���������I�݂ŏ����A�S�̂�ʂ��Ē����Ă����ꂪ���R�ŕ\���Ɉ�ѐ�������Ƃ��낪�f���炵���B���b�N�X���ǂ��X�^�[�t�҂����炻�������̉��t�Ȃ̂����A�Ƃ������O�ɏ���ɑz�����������Ƃɐ\����Ȃ����犴���Ă��܂��قǂ̈����̉��t�B�����������̃`���C�R�t�X�L�[�̃��@�C�I�������t�Ȃ́A�Ȃ����킩��₷���ăV���v���ł͂��邯��ǁA�\���E�p�[�g�͑��̗L�����t�ȁi�����f���X�]�[���A�u���[���X�A�V�x���E�X�Ȃǁj�Ɣ�ׂĂ��\���̎��R�x�������A�t�҂̒�͂��������ȂŁA����̂Ɏ��͂���������ꂽ�����B�\����Ȃ�����ǁA2�T�ԑO�ɒ������ȂƓ����Ƃ͎v���Ȃ��قǂ̈Ⴂ���������B �����}�[���[�̌����ȑ�5�Ԃ��A���؈�ࣂň��|�I�ȉ��ʂ̃I�P���{�̂��B���̉̂����Ղ�͌����Œጷ�͌��݂����Ղ�A���ǖ؊ǂ����肵�Ă��Ĉ��S���Ĕ����ɐg��C�����鉉�t�B�l�[���Z�K���́A���߂�Ƃ���𗭂߂����ȑ匩����鉉�t�Ƀo�^�L����������������̂́A�G���^���������삳�����Y���т₩�ȃT�E���h�ɍ����Ă���ɂ��m���ŁA�ƂĂ��y���߂鉉�t�������B |
 �y���ځz �u���b�N�i�[�F�����ȑ�8�ԁi�n�[�X�Łj �i�A���R�[���j���[�[�t�E�V���g���E�X�u�V��̉��y�v �����A�ǂ̃I�P�̏�肳�A���邢�͑���Ă��Ȃ��Ƃ���Ȃlj��t�Z�ʂɂ��ď����Ă��܂��Ă������ǁA���̓��͂���Ȏ����̘b�ł͂Ȃ������B�ǂ̃p�[�g���f���炵���A�A���T���u���͌����A�Ȃɂ����I�P�Ƃ��Ẳ��F�ƕ\���Ɉ��|�I�Ȑ����͂�����B�I�[�P�X�g�����y�Ƃ����̂͋Z�ʂ̗ǂ����������ɂ߂邱�Ƃ����̊y���ݕ��ł͂Ȃ��A�I�P������\�����āA�Ȃ��ǂ��܂ł̎����Ɏ����Ă����邩�Ƃ������̂������A��������\����Ƃ���������O�̂��Ƃ��v���m�炳�ꂽ�B �������A���̃I�P�̃u���b�N�i�[�����đf���炵�����t�͂���ɈႢ�Ȃ��B�ł��A���̓��̉��t�́A�������A�������A���F�A�C�i�A�������ȂǑ��ɑウ�������B�ꖳ��̉��t���������Ƃ����͌�����B����ȉ��t�͂������x����������̂���Ȃ����낤�Ǝv�킹��ɏ\���ȍ��݂ɂ������B����͉��t���I�������Ƃ̃e�B�[���}���̕\��ɂ��\��Ă����悤�Ɏv���B �ʏ�͂��܂�u���b�N�i�[�̑��̂��Ƃɂ��Ȃ��A���R�[���B�l�����̑�8�Ԃ������ƂɃA���R�[�������܂蒮�������Ƃ͎v��Ȃ�����ǁA�E�B���i�[�E�����c���E�B�[���t�B���Œ����̌����܂����ʂȂ��̂������B �����������t��̌��ł��邩��R���T�[�g�ʂ��͂�߂��Ȃ��B |
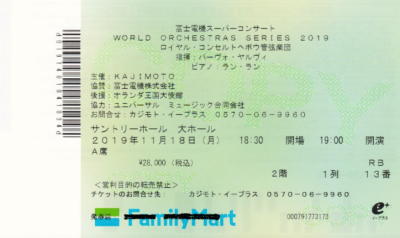 �y���ځz ���[�O�i�[�F �y���u�^���z�C�U�[�v���� �x�[�g�[���F���F �s�A�m���t�ȑ�2�ԁi�����E�����j �i�A���R�[���j�����f���X�]�[���F�w�����̏W�x���u�a���́v �u���[���X�F �����ȑ�4�� �i�A���R�[���j�u���[���X�F�n���K���[���ȑ�3�ԁA��1�� �u�^���z�C�U�[�v�͌l�I�ɍD���ȋȂŁA�ȑO�A�}�[�[���w���~�����w���E�t�B���Œ������p���łł͂Ȃ��A��ʓI�ȒZ���o�[�W�����i�E�B�[���ŁH�j�B����ł��A�I�P�̎��͂𑶕��Ɋ��������錩���ȉ��t�ŁA���[�O�i�[�Ȃ�ł͂̓Ɠ��̃I�[�P�X�g���[�V���������\�B ���́A�e���r�ł̘I�o�x�������A�����̕]�_�Ƌɂ͂��܂�]������낵���Ȃ������E�����ɂ��x�[�g�[���F���̃s�A�m���t�ȑ�2�ԁB���ۂɂ͑�1�Ԃ���ɍ�Ȃ���A�Ґ����������i�e�B���p�j���Ȃ��j�A�x�[�g�[���F���̃s�A�m���t�Ȃ̒��ł������Ƃ��ÓT�I�ŁA�v���R�t�B�G�t��t�}�j�m�t�̂悤�ȍ��x�ȋZ�p��v�������킯�ł͂Ȃ����̋Ȃ��ǂ̂悤�ɉ��t����̂��B��2�y�͂Ńs�A�j�V���̓������������������\���͂���������ƒ��������A���悻���ʂɂ͏����Ă��Ȃ��ł��낤�P�����������Ղ�̉��t�ŁA�i�������|�p�ƍ\���Ē����l�͂����Ɗ�������߂��ɈႢ�Ȃ��B�ł��A�l�͂��Ƃ��ƃN���V�b�N�ł��낤�Ƃ����y�͌�y���ƍl���Ă���̂ŁA�G���^�[�e�C�i�[�Ԃ���j���j�����Ȃ���y����Œ������Ƃ��ł����B�F���F�A�����E�����̂悤�ɂȂ��Ă��܂�����A�����������ƈႤ���낤�Ƃ͎v������ǁA�y�������ɒe�������E�����̃X�^�C���͗B�ꖳ��ŁA�l�C�����闝�R���悭�킩�����B�Ƃɂ����A����ȂɌ��I�ȃX�^�C���Ńx�[�g�[���F����e���l�͂��Ȃ��ł��傤�B ���C���́A����܂��l�I�ɑ�D���ȃu���[���X�����ȑ�4�ԁB2�N�O�ɃR���Z���g�w�{�E�Ńu���[���X�̌����ȑ�1�Ԃ����Ƃ��ɁA���̉��t�̑f���炵����F�߂��A�F�ʊ��≷���肪�\�ɏo�����Ă��āA�u���[���X�ɂ͂��������a�݂��~�����Ƃ����ґ�Ȃ��Ƃ����������̂������B�X�ɏa�݂��~�����Ǝv�킹���4�Ԃ��ǂ̂悤�ɒ������Ă����̂��B�T�E���h�͂���2�N�O�̈�ۂƂ͈���ĂƂ��Ɍ��̉��Ɍ͂ꂽ���D���Ă��čD��ہB����ł��h�C�c�̃I�P�̂悤�ȉ��Ƃ��܂��Ⴄ�R���Z���g�w�{�E�Ȃ�ł͂̃T�E���h�ł���Ƃ��낪�f���炵���B�������A�r���[�h�̂悤�Ȃƕ]����銊�炩���͂�⑹�Ȃ��Ă��āA��1�y�͂Ƒ�4�y�͂̏I�Ղ����Ȃ葬���e���|�ɂ��Ă����Ƃ��낪�D�݂ɍ��킸�A�����ɂ܂ł͎���Ȃ������̂͗v���͂��̂�����ɂ��肻���B�����͍D�݂̖��ł�����̂ŁA�܂��A�d���Ȃ��ł��傤�B����ɂ��Ă��؊Ǒt�҂͑��ς�炸�R��Ȃ��n�C���x���Œ��������Ƃ��������悤���Ȃ���肳�B�؊NJy�킪�I�P�̃T�E���h���ǂꂾ���L���ɂ��邩����������ꂽ���̂悤�B���x�����Ă��f���炵���I�[�P�X�g���ł��B |
 ����2�N�Ԃ�̃��C���̓L���O�E�N�����]���B�{�T�C�g�̓W���Y�ɋ����������Ă���l�ɏ���������Ƃ�����|�Ŏn�߂�����ǂ��A�������������Ƃ������Ď��̓L���O�E�N�����]���̏��ԑ����f�ڂ���Ă���B�����܂ł̃}�j�A�ł���l���A2014�N�Ƀg���v���E�h�����Ґ��ɂȂ��Ă���̋L������؏����Ă��Ȃ����R�͂܂�Ȃ��Ȃ��ċ����������Ă��܂�������B3�l�h�����Ґ��͒P�ɖ������S���Ă��邾���Ől���ɂ�閭���͂Ȃ����A���t���Ă���Ȃ͉ߋ��̋Ȃ���Ƃ����������o���h�ɂȂ��Ă��܂��āACD���ău���[���C�����Ă��ʔ����Ȃ������B�ł���x�����Ō��Ȃ��Ō��߂���̂͗ǂ��Ȃ��A���������̃R���i�ЂŊu������邱�Ƃ��}�킸�����A����ōŌ�ɂȂ邩������Ȃ��Ƃ������Ƃ������čs�����ƂɁB���ʁE�E�E�����Ȃ�܂����B���t�͗��ɏ�肢���A�ߋ��̖��Ȃ���������Č����Ă������A�����������Ƃ������Ƃł͂Ȃ���������ǁA�Ȃ�ł���Ȃɑދ��Ȃ낤�ƍl������ł��܂����B���_�́u�g���v���E�h����������v�B�h�����Ƃ����y��͌����܂ł��Ȃ����Y���̓y����x����̂��Ƃ��ł��d�v�Ȏd���B�ł����ꂾ���Ȃ�@�B�ɂ�点��Ηǂ��A�Ƃ����ƂɂȂ��Ă��܂��B�h���}�[�̑��݈Ӌ`�͉����ƍs������A���Y����O���[����n�o���Đ��i�͂ݏo�����Ƃɂ���Ɩl�͍l���Ă���B���̃��Y���͎w�����ꂽ�ʂ�ɐ��m�Ƀg���[�X����Ηǂ��Ƃ������̂ł͂Ȃ��A�����������I�Ƀ��Y���ƃO���[����n��o�����Ƃ��傫�Ȗ����ł���B������3�l�Ŗ������S���邩��d�������̂͘A�g�ł���A�A���T���u���ɂȂ�B�܂葼��2�l�ɍ��킹�Ē@���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ�����h���}�[�ɂƂ��Ă����Ƃ��d�v�Ȏ��������ɂȂ��Ă��܂��B�_�u���g���I����͑���ɍ��킹��Ȃ�Ă��Ƃ��ᒆ�ɂȂ��r���E�u���[�t�H�[�h���D���������Ă������炻�̂悤�Ȕ���������Ȃ���������ǁA����3�l�̓e�N�j�b�N�͂������肵�Ă��Ă�3�l�Ƃ����t�H�[�}�b�g�̒��ł������萱�ݕ����Ă��̘g�̒��Ŏd�������Ă���ɂ����Ȃ��A����3�l�����炻��������Ȃ��B����܂�CD�Œ����Ă��āu�܂�Ȃ��Ȃ��v�Ǝv���Ă������R�����Œ������疾�炩�ɂȂ����Ƃ����c�O�Ȍ��ʂɁB �ł��s���Ă����ėǂ������B�R���i�ЂŃz�e���Ɋu������邱�Ƃ��}�킸�A���{�܂ł킴�킴���Ă��ꂽ���Ƃɂ܂����ӂ������ł��B���̓��͂܂�����"Schizoid Man"�����Z�b�g���X�g�ŋ���������ǁA�ߋ��̖��Ȃ��t���b�v�̃M�^�[�Œ�����̂͋��炭���ꂪ�Ō�̃`�����X�B�I����A�X�e�[�W��1�l�c���ċq�Ȃɐ[�X�Ɠ��������Ă���t���b�v�i�O��̃c�A�[�ł�����Ă���������Ȃ����ǁj�����āA�{���ɂ���ŏI���Ȃ̂�������Ȃ��Ǝv���A����܂őf���炵�����y�����肪�Ƃ��ƐS�̒��łԂ₢�Ċ��ӂ̋C������`���܂����B�N�����]���E�}�j�A�Ƃ��āA���̂悤�ȋ@������Ă����Ƃ͍K���Ȃ��Ƃł��B |
 �㌴�Ђ�� �U�E�s�A�m�E�N�C���e�b�g�A�u���[�m�[�g�����A2022�N1��2�� 1st�Z�b�g�B ���̃s�A�m�E�N�C���e�b�g�̓R���i�ЂŊC�O�A�[�e�B�X�g�Ƃ̋���������Ȓ��ʼn����ł��邩��͍����Ċ�悳�ꂽ���̂ŁA�Ȃ��Ȃ��ǂ��A�C�f�B�A�B���R�A�r�[�g���������s�A�m�E�g���I�̂悤�ȉ��t�ɂ͂Ȃ炸�A�\�ʓI�ɂ̓A�^�b�N�������������������ȂɏI�n�������ǁA�����ʂ莩��ȂŎ����̉��y�Ƃ��ĉ��t����Ă���Ƃ��낪�����BCD�Ɣ�ׂ�ƁA���C���炵���\���E�p�[�g�𑽂߂Ɏ���Ẵp�t�H�[�}���X�B���������s�A�m�����y��̐����Œ���������̂�����A�������ł̃��C���ł͂�͂肻�̉��̐��X�������f����B�N���V�b�N�̐��E�ł͌����Đ��E�̈ꗬ�Ƃ͌����Ȃ����{�l�t�҂�����ǁA�e�l�̃\���E�p�[�g���Ă���Ɠ��{�̃g�b�v�E�I�[�P�X�g���ʼn��t���Ă邾�������Ă���������Œ����ɂ͐\�����Ȃ���肳�B�s�A�m�����̏�̋C���ɑ��������R�ȕ\���ɂȂ��Ă��ă��C���Ȃ�ł͉��t�B�u���[�m�[�g�ʼn��t����W���Y�E�~���[�W�V�����́A���\���t�Ő����ȂƂ���_�T�������̐l���������ɂ����ă^�L�V�[�h�ƃh���X�𒅂錷�y�w�ƁA�Ɠ��̃h���X�ƕ����������̃X�j�[�J�[�ł�������O�������グ�Ă���Ƃ�����ޏ��̍l����A�[�e�B�X�g�Ƃ��Ă݂̍���ւ̎v�����`����Ă���B��͂艹�y���āA�����t���Ă����ȂƍĔF�������Ă��ꂽ�㌴�Ђ�� �U�E�s�A�m�E�N�C���e�b�g�B�N�������X�ɉ��y����т����������Ă��ꂽ�㌴�Ђ�݂ƌ��y�t�҂����Ɋ��ӂł��B |
 2022�N4��29�� �g�ˎ�SOMETIME �吼���q�J���e�b�g �吼���q (p) ��V���� (per) ���z��(b) �g�Ǒn��(ds) ��N���Ƀ����[�X���ꂽ�uGrand Voyage�v�̃����o�[�ɂ����́B1�Ȗڂ��I���ƁA���̏�ɂ��������̐l�������Ă����ł��낤���Ƃ�吼���g��������Ȃ���v�킸�{�����Ăق̂ڂ̂Ƃ��������N����B�u�i�ڂ̑O�ɂ���h�������j���邳�`���v�B�S���e�n������Ď�Ƀz�[���ʼn��t���Ă���̂ŁA���t�Ҏ��g�����̋������ʼn��̃o�����X���ǂ��Ȃ����Ƃ͋�����邵���Ȃ���ł��傤�B���Œ����Ă݂ĉ��߂Ċ����邱�Ƃ̓h�����ƃp�[�J�b�V�������A���R�ȗ̈���������k���Ɍv�Z���ꂽ�A�����W�Ɋ�Â��Ĉ�̂ƂȂ��ăO���[��������Ă��邱�ƁB�吼�����ʂ����X���Ȃ��牉�t���Ă��邱�Ƃ��܂߂āA������x�̊�{���C��������������ŁA�قڃA���o�����^�Ȃ̃Z�b�g���X�g�Ȃ���ڂ������i����2nd set�͎����s�A�m�E�\����"Kippy"�������Ċe�Ȃ�15�������j�A�����ɂ��W���Y�̃��C���炵���������i���Ƀt���[�E�W���Y�I�W�J���j�ƔM�ʂ̍������t�������Ղ蒮������[���̃p�t�H�[�}���X�������B�uGrand Voyage�v���Ă���������Ƃ���ł͂������ǁA���̃O���[�v�͌`����̓s�A�m�E�g���I�{�p�[�J�b�V�����Ґ��Ȃ���A�p�[�J�b�V�����͕⑫�I�Ȗ����ł͂Ȃ��A1/4�܂��͂���ȏ�̖�����S���Ă���4�l�̃W���Y�Ƃ��Đ������Ă��邱�Ƃ����C�����Ƃ��n�b�L���Ƃ킩��B�܂��A���C���ł̓p�[�J�b�V�����Ń��e���̃e�C�X�g��O�ʂɏo�����Ƃ͂Ȃ��A�����܂ł����̃O���[�v�ɂ�����W���Y�\���̈���Ƃ��ċ@�\���Ă��邱�Ƃ����[�������ł���B���̃O���[�v�Ƃ��Ă݂̍���̓I���W�i���e�B�������A�����ƍ����]������Ă�����Ȃ����Ǝv�킸�ɂ͂����Ȃ������B |
 �吼���q�Z�N�X�e�b�g@�u���[�m�[�g����2022�N6��30�� 2nd set�B �L������ (tp) �g�{�͍h (ts, ss, fl) �a�c�[�O (tb) �吼���q (p, key) ���z�� (b, elb) �g�Ǒn�� (ds) �g�����{�[���̘a�c�[�O�͐V�����o�[�B�W���Y�E�g�����{�[���Ƃ�����J.J.�W�����\���̂悤�Ɂi�g�����{�[���Ő����ɂ͓���j�����p�b�Z�[�W�Ŏ䂫����^�C�v�̃v���C���[�����钆�A�N�X�Ɖ̂��g�����{�[���炵���\�������^�C�v�B�ǂ��炪�ǂ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ�����ǁA�O�C�҂Ɣ�ׂ�Ƃ����ЂƉ����A������Ȃ����Ă�������Ȃ����ȂƂ����̂������Ȋ��z�B������������Ȃ̂ł��ꂩ��{�̔�������̂�������Ȃ��B�h������CD�̍����M�V���J���e�b�g�̃����o�[�ł���g�Ǒn���Ƀ`�F���W�B�J���J���ƍ��߂̃X�l�A���ō��݂�������������O�C�҂ɑ��ċg�ǂ̓X�s�[�f�B�ɐ��i����^�C�v�Ƃ����ă��Y���̐i�ݕ��͏��XCD�Ƃ͈قȂ��Ă���B �Ƃ͂����A�O���[�v�S�̂̃T�E���h�u���͂���܂łƕς��͂Ȃ��A���Ғʂ�̂��́B���̓������̃��C���̂��߂�10���Ԃ����n�[�T����������ƈ�オ�R�����g�����Ă��邱�Ƃ�����i�����đS�������ʂ����Ȃ��牉�t���Ă������Ƃ�����j�킩��ʂ�A�W�����Z�b�V�����I�ȃm���ꔭ�̒P���Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�ϔ��q�𑽗l���p����ȂNjȂ̍\�����ǂ�����ꂽ���́B����ł����t�������͑O�q�̒ʂ�J�b�`���������̂ł͂Ȃ��A�����ɂ��āA�e���B �t�����g3�ǁi���Ƀg�����y�b�g�ƃg�����{�[���j�͍��x�ȃe�N�j�b�N�������Ă���킯�ł͂Ȃ��B�������W���Y�̓e�N�j�b�N������������Ă��̂ł��Ȃ��B�Z�p�Ƃ����������t�ƂƂ��Ă̎��Ȃ̉����o���������������Ƃ����Ƃ���̓��C���ŊςĂ���ۂ͕ς��Ȃ������B�x�[�X��4���Ƀg���I�Ŋς��Ƃ��Ɠ��l�A�������������芴�̂���܂��Ƀx�[�X�̖����̂���{�Ƃ������ׂ����t�B�s�A�m�͍��ƂȂ��Ă͒������`���I���l�X�^�C���̂����̃_�C�i�~�b�N�ȑ吼�߂Œ��߂̃\���E�p�[�g���������p�ӂ���Ă����B �ƁA�ʂ̉��t���ǂ��̂����̂Ƃ����̂͂��̃O���[�v�ɂƂ��Ă͂��܂�d�v�ł͂Ȃ��A�j���[���[�N�̐�[�W���Y�̃X�^�C���Ȃ�Ēm��ǓI�ȉ䓹���s�����{�l�I�ȃW���Y�\�����y���ނׂ����́B�����āA�����o�[���܂Ƃ߁A���R�ɂ�点�Ă�����R���_�N�g���Ă���吼�̃o���h���[�_�[�Ԃ���y���ނ��́B�_�C���N�g�ɁA���ł����������邱�Ƃ��ł���̂������t�̖��́B����Ȃ̓�����O����Ȃ����Ǝv���邩������Ȃ�����ǁA�ߋ�3�N�A�����t�ɐG���@����Ȃ��������炱���A������O�̖��͂ɂ��肪���݂���������邾�����B |
 2022�N11��15�� �T���g���[�z�[�� �w���F�A���h���X�E�l���\���X ���t�F�{�X�g�������y�c �y���ځz �V���E�FPunctum�i�I�[�P�X�g���Łj�m���{�����n ���[�c�@���g�F�����ȑ�40�� R. �V���g���E�X�F�A���v�X������ ����3�N�Ԃ�̃N���V�b�N�̃R���T�[�g�B�L�������C���E�V���E�̋Ȃ͌��y�݂̂ł̉��t�B�O�q���͂Ȃ��A�ł��s�v�c�ȋ����������A�Ȃ����y�I�[�P�X�g���[�V�����̋����̎���������Ă��銴���B ���̓��[�c�@���g�̌����ȑ�40�ԁB�܂�Ȃ��Ƃ����t���ǂ��Ȃ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ���������ǂ���ƌ����Ĉ�ۂɎc�炸�B��2�y�͂͂�����Ȃ�ł��e���|���x�����ďW���͂������Ȃ��B ���C���̓A���v�X�����ȁBCD�Œ����Ă������̋����͂��������y��̑g�ݍ��킹�ŏo���Ă���̂��Ƃ��������������ƂĂ������[���������B�܂��A�����̃I�[�P�X�g���̋�����CD�̘g�Ȃnjy���͂ݏo���X�P�[���Ƒ��ʁA���l�������邱�Ƃ��A���̋Ȃł͂���t��o����Ă��̃_�C�i�~�N�X�Ɉ��|����Ă��܂����B��Ґ��̐��I�[�P�X�g���A�������n�͂̂���I�[�P�X�g���Œ������Ƃł����ő�����̖��͂�����ł���Ȃ̍ʼnE���ɋ��������Ȃ��Ƃ������Ƃ��܂��܂��ƌ�������ꂽ�v��������B���̋Ȃɂ��Ă̓l���\���X�̌|���ƁA�{�X�g�������y�c�̑̊��̋��x�����n�}���Ă����B���t���Ԃ�58���ƗY�傳�������o�����d���Ă������B |
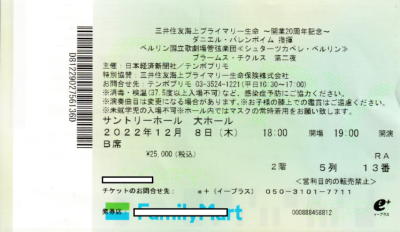 �y���ځz �u���[���X�F�����ȑ�3�� �u���[���X�F�����ȑ�4�� �o�����{�C���̑̒����ǂ��Ȃ��i�N��I�Ɏd�����Ȃ����ǁj�Ƃ����b�����炭�O����`����Ă��Ă��āA�L�����Z���ɂȂ�Ǝv���Ă���SKB�̃u���[���X�`�N���X�̓e�B�[���}��������߂��B�u���[���X�̑�3�Ԃ��n�܂�ƁA�����A�h�C�c�̃I�P�̉����Ȃ��A�v���Ԃ肾�Ȃ��̉��Ƃ������S�ɐZ��B�V���^�[�c�J�y���E�h���X�f����x�������E�h�C�c�����y�c�Ȃǂł��o�������A��₭���a�߂̌��̉��F�������I�B�؊ǐ��̈��芴�Ɖ̂킹���Ղ�������B�I�P�̑f���炵����6�N�O�Ƃ܂������ς��Ȃ��B�e�B�[���}���͋���ƃe���|�̃����n����t����w���ŁA�V���^�[�c�J�y���E�h���X�f���Ƃ̑S�W�Ɠ����|���őz��ʂ�ł͂��邯��ǁA���̐U�ꕝ�̑傫���͂�͂萶�Œ������Ƃŋ���ł��邱�Ƃ��ĔF���B�܂��ACD�̃_�C�i�~�b�N�����W�Ȃ�Đ����t�ɔ�ׂ��為�����킯�ł����瓖�R�ł͂���B���̃h�C�c���F�Œ�����4�Ԃ͂��������Ƃ��������悤���Ȃ��B�u���[���X��52�̂Ƃ��ɍ�Ȃ������̋Ȃ͎⛌���ɖ����Ă��āA�h�C�c�I�P�̏a���T�E���h�ʼn��t����邱�Ƃł��̖��킢�����[�����̂ɂȂ�B������낢��ȃX�^�C���A���F�̉��t������Ƃ��낪�N���V�b�N�̊y���݂ł͂������ǁA�V���^�[�c�J�y���E�x�����������t�����4�Ԃ͍ŏ㋉�̉��t�̂ЂƂƌ����ėǂ��f���炵�����̂������Ǝv���B���x�Ƃ����Ӗ��ł̓x�������E�t�B����o�C�G�����ɂ͊���Ȃ����ȂƂ��v������ǁA���̃I�P�͉��F�Ɖ̂������{���ɑf���炵���B |
 ���o�[�g�E�O���X�p�[�E�g���I�A�u���[�m�[�g�����A2023�N1��2����1st�Z�b�g�B Robert Glasper (p�Akey) Burniss Travis (b) Justin Tyson (ds) Jahi Sundance (DJ) �s�A�m�ƃL�[�{�[�h����ׁADJ�̃T�E���h�G�t�F�N�g���}���������̃T�E���h�͂�͂�q�b�v�z�b�v�H���B�ߔN��CD�͗l�X�ȃQ�X�g�������A�����ɍ�荞�܂ꂽ���̂ł���̂ɑ��āA���C���ł̓��C���炵�����R���ɂ����t���W�J�����B�������Y���p�^�[�����J��Ԃ��̂̓q�b�v�z�b�v�̓����̂ЂƂł͂��邯��ǁA1�Ȃ̉��t�����߁i�T��10���ȏ�j�ȂƂ���̓��C���Ȃ�ł́B6���x�[�X�̃O���[�����̓t�@���N�n�̂����W���Y�n�̂���Ƃ��قȂ�q�b�v�z�b�v�n�̃X�^�C���ŁA�����ɂ����C���ȉ��t�ɂȂ��Ă���̂͐��h�������܂߁A�l�����ރr�[�g���ɕ����Ƃ��낪�傫���A���̃O���[���ɐg��C���Ă���̂��S�n�悢�B�R���g���[����"Gianat Steps"��e�B�A�[�Y�E�t�H�[�E�t�B�A�[�Y��"Everybody Wants To Rule The World"�����`�[�t�Ƀt���L�V�u���ɋȂ�W�J�����Ċy���܂��Ă����B�������W���Y�I�ȉ��t���D������Ȃ���B��荞�܂ꂽ�X�^�W�I�E�A���o���Ƃ͏��X�قȂ�A���R�x�̍������̉��t�������O���X�p�[�̑f�̎p�Ƃ������ƂȂ̂�������Ȃ��B����͎��ɏ璷�Œ��܂肪�Ȃ��Ƃ������Ƃł��������ǁA���C���Ƃ͂����������́B���{�l�A�[�e�B�X�g�ɂ͂Ȃ����l�����o�[�ɂ�郊�Y���𖡂키���Ƃ��ł����̂����Ȃ�v���Ԃ�̂��ƂŁA���ꂪ�Ȃ������������N���������郉�C���������B |
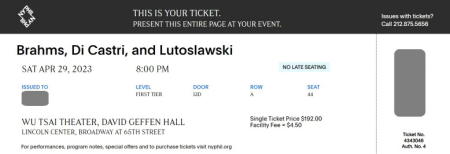 2023�N4��29�� �f�C���B�b�h�E�Q�t�B���E�z�[�� �w���F�W���i�\���E�w�C���[�h ���t�F�j���[���[�N�E�t�B���n�[���j�b�N �y���ځz �J�X�g���F���l�[�W �u���[���X�F���@�C�I�������t�ȁi�N���X�e�B�A���E�e�c���t�j ���g�X���t�X�L�F�nj��y�̂��߂̋��t�� �����́A�J���[�i�E�J�l���L�X�iKarina Canellakis�j�Ƃ��������w���҂��\�肳��Ă����Ƃ���A�R���T�[�g��2�������O�Ɍ��̃A�i�E���X������A2021�N����k���h�C�c�t�B���n�[���j�[�nj��y�c�̎�Ȏw���҂߂Ă���Ƃ����W���i�\���E�w�C���[�h�Ɍ��B 1�Ȗڂ́A�j���[���[�N�ݏZ�ł̓R�����r�A��w�̉��y�������߂鏗����ȉƁA�s�A�j�X�g�̃]�[�V���E�f�B�E�J�X�g���iZosha Di Castri�j�̃��l�[�W�iLineage�j�Ƃ�������ȁB�����ȂƂ��댻��Ȃ͂ǂ���ʔ����Ȃ��A���̋Ȃ����̗�ɘR��Ȃ����B����ł����{�ł͒����@��Ȃ����Ƃ�����A���܂ɂ͂��������Ȃ��̂��������Ȃ��Ƃ������Ƃ���B ���̓e�c���t�̃\���ɂ��u���[���X�̃��@�C�I�������t�ȁB�e�c���t�ł̓��Ȃ́A9�N�O�Ƀp�[���H�E�������B�w���h�C�c�E�J���}�|�t�B���E�u���[�����Ƃ̉��t�ŃI�y���V�e�B�Œ����Ă��āA���̂Ƃ��͏��Ґ��I�[�P�X�g���ŃX�s�[�f�B�ȉ��t������I�P���o�b�N�ɂ��Ă������Ƃ������āA�e�c���t�̉��t�͂��Ȃ�r��肾�����L��������B9�N�o���Č����e�c���t�̕��e�͂�胏�C���h�ȃI���W�����o�Ă��āA���t�̃X�^�C���͏]���Ɠ����Ƃ�����ہB���߂Ē����j���[���[�N�E�t�B���́A���A�؊ǂ͉�����̂��鉐�₩�ȃT�E���h�ƁA�n�͂̂�����肵�����ǂ����Ɏc��f���炵���T�E���h�ŁA�ߔN�͂��܂�ǂ��]�����Ȃ��I�P�Ƃ͂����A�����^�[�A�o�[���X�^�C���̎��ォ��ꗬ�I�[�P�X�g���Ə̂������͂��\������������́B�e�c���t�̗͉��́A�����������������ł̉̂킹�����Ƃ������ǂȂ��Ǝv���A����͂���ł��ł������Ȃ��Ƃ������z�B����ł��j���[���[�N�̊ϋq�ɂ͎��ǂ��I����͑吺�ł̃u�����H�[�ƃX�^���f�B���O�I�x�[�V�����Ō}���Ă����B�]�k�Ȃ����1�y�͂��I������Ƃ���Ő���Ȕ��肪�������̂̓j���[���[�N�Ƃ����y�n���̂������������炾�낤���B 3�Ȗڂ́A���{�ŊC�O�I�P�̃v���O�����Ō����������Ƃ��Ȃ����g�X���t�X�L�́u�nj��y�̂��߂̋��t�ȁv�ŁA�莝����CD�i�����\���X�w�����C�����E�R���Z���g�w�{�E�nj��y�c�Ə��V�����w���V�J�S�����y�c�j�Œ����Ă���قNJ������Ă����킯�ł͂Ȃ���������ǁA�������Ɨǂ��Ӗ��ň�ۂ���Ⴂ�������B�h��Ń_�C�i�~�b�N�ȋȂ͐����t�Œ����ƒ����f�����邵�A�I�P�̒n�͂��Ȃ̗͋����ƃT�E���h�̑N�₩��������w�����o���Ă����悤�Ɏv���B�����t�Œ����Ă݂Ȃ��ƋȂ̖��͂�^�ɗ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ����̂ȂȂ��Ƃ������Ƃ͂���܂łɉ��x���o�����Ă��邯��ǁA�����ʼn��߂čĔF���B |
 �ςɍs�����̂�2023�N4��30���i���j��2nd�Z�b�g�BCD�Ƃ͈قȂ��Ԃ�ɂ��I�[�\�h�b�N�X�ȃs�A�m�E�g���I�Ґ��i�S�����̔����͂���1�l�ʂ̃x�[�X�t�ҁj�B Samara Joy (vo) Luther Allison (p) Felix Moseholm (b) Evan Sherman (ds) ���т���o�b�N�����o�[�ɍːl�M�^���X�g�A�p�X�N�@�[���E�O���b�\�Ƃ���CD�Ɣ�ׂ�Ɖ��t�҂̃��x���͖��炩��1�����N�_�E���B�Z�V���E�}�N���[�����E�T�����@���g�́uDreams And Daggers�i�唼��Village Vanguard�̃��C���j�v�̃o�b�N�����o�[�͔��t�Ƃ��������ɓO���Ă��Ȃ�������t���x���������A����Ɣ�r���Ă�1�����N�����͔ۂ߂Ȃ����A�Z�p�I�ɂ͓��{�̃g�b�v�N���X�̑t�҂������ƌ����Ă������߂��ł͂Ȃ��B���������̊ɂ��Ɨ]�T�̍\���͒P�ɋZ�ʕs���̓��{�l�ł͏o���Ȃ��{��̉��t�Ƃ����������o���郀�[�h������A�܂��������ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�̂����Ƃ��ړI�ł���Γ��ʓ˂��������Ƃ��낪�Ȃ��Ă�����ŏ\���B�̐S�̉̂́A������{�l��1���[�g���O�̐��ʂʼn̂��Ă���̂�PA�z���̐��Ɛ������������������Ă����ԁBCD�̂悤�Ɉ܂��Ă���i�ɉ̂��Ƃ������́A�W���Y�E���H�[�J���̃X�^�C����ۂ��Ȃ���v���̂܂܂Ɏ��R�ɁA�����ĐL�т₩�ɉ̂��Ă���B���R�ƌ����Ă������̃R���g���[���ɗ���͔��o���Ȃ��A���ʂ͈����B�o�b�N�̉��t���T���߂Ƃ������Ƃ������ĉ̂��̂��̂��q�ɗ��т������Ă��邩�̂悤�B�ȊԂł̊ϋq�Ƃ̂��Ƃ�������Łu�J�b�v���ŗ��Ă���l�ǂ̂��炢����H�A��Y���ĉ��N�H�v�ƃI�[�f�B�G���X�ɖ₢������ƁuThirty Two !�v�uFourty Two !�v�Ɗ����ɔ����A������̎��ɑg�݂���ʼn̂��ȂǃA�b�g�z�[���ȃ��[�h���������Ȃ�ł́B��ÂɌ���ƃ��C���ՂƂ��Ďc����i���x���J��Ԃ������ɑς���j�����x�Ƃ͂����ȈӖ��Ō�����p�t�H�[�}���X�������͎̂����Ȃ���A�v���f���[�X���s���͂��߂��Ă���CD�Ƃ͈Ⴄ�A�̂��̂���т����o�Ă������i���̃T�}���E�W���C�������Ղ芬�\���邱�Ƃ��ł����B |
 �N���X�`�����E�}�N�u���C�h�E�j���[�E�W���[���A�u���[�m�[�g�����A2023�N5��25����2nd�Z�b�g�B [1] Head Bedlam [2] Sightseeing [3] Ballad for Earnie Washington [4] Seek The Source [5] Dolphy Dust [6] The Good Life [7] Walkin�f Funny Josh Evans (tp) Marcus Strickland (ts, bcl) Christian McBride (b) Nasheet Waits (ds) �X�^�W�I�^�������\���̐U�ꕝ�����R�傫���Ȃ�A�e�����o�[���^����ꂽ�X�y�[�X�͍L���i����1��10���ȏ�̉��t�j�A���x�ȉ��t�Z�p�ɉ��x�����ꂽ�t���[�Y�����݂Ȃ��N���o�Ă���B����͑z�肳�ꂽ�������ł͂���������ǁA�e�l�����т�������t���[�Y�̎��̍����ɃO�C�O�C�䂫������B����قnj����Ȃ����̍������t�͂Ȃ��Ȃ���������̂���Ȃ��B���R�x�������A�t���[�������B�ꂷ�鉉�t�ł���Ȃ���A�l�Ƃ��Ă��O���[�v�Ƃ��Ă��T���߂ȗ����ƒm��������������Ƃ������̐[���Ɏv�킸�X���Ă��܂��B4�l�Ƃ����t�Z�p�͍��x�Ȃ͎̂��m�̎����A���Œ����Ɠ��ɂ��̐���������������̂��}�N�u���C�h�̃x�[�X�̋Z�ʂƁA�i�V�[�g�E�E�F�C�c�̎��ɃG�h�E�u���b�N�E�F����`���[���Y�E���t�F�b�g�i2�l���I�[�l�b�g�l���̃h���}�[���j��A�z�����钵�˕���D��������r�W�[�ȃh���~���O�B |
 �吼���q�g���I�A�u���[�m�[�g�����A2023�N6��10����2nd�Z�b�g �吼���q (p) Joe Sanders (b) Greg Hutchinson (ds) [1] Almost Like Me [2] Printmakers [3] Musical Moments [4] Never Let Me Go [5] Eulogia -Encore- [6] Us Three ����܂ł̃A���o���Ɏ��^���Ă����Ȃ𒆐S�Ƃ����Z�b�g���X�g�̎��ۂ̃��C���́A���҂ɉ�������ɏ[���������t�������B�吼���q�����ݓ��{�ł̊����̎厲�Ƃ��Ă���O���[�v�́A�������s�A�j�X�g�Ƃ��Ă̌�����͂�����A�O���[�v�Ƃ��Ă̕\�����ӎ��������́A�܂�o���h�E���[�_�[�Ƃ��đS�̂���Ղ��鉉�t�ɂȂ��Ă���B���̓��́A�����������[�_�[�Ƃ��Ă̖����Ƃ������́A�s�A�j�X�g�Ƃ��Ă̑吼���q���̂��̂̉��t���S�ʂɏo�����̂ł��������Ƃ��ߋ�2��ς����C���Ƃ͑傫���قȂ�B�}���O���[�v�ł���A�O���b�O�ƃW���[���������Ă��珉�߂Ċ�����킹�����n�[�T�����o�Ẵ��C���Ȃ���ŏI��3���ڂ�2nd�Z�b�g�������������A3�l�̉��t�͈��݂̌ċz�Ői�ށB�s�A�m�͎Ⴂ���̂悤�ɃG�����g������N�̉e�����B�����Ƀp�L�b�Ɛ�̂���e�����ł͂Ȃ��A���l�s�A�j�X�g�̋��������̃��[�c���x�[�X�ɂ������Y�����͂���Ӗ��ɂ������̂ŁA����𐊂��Ƒ�����l�����邩������Ȃ�����ǁA���n���ėǂ��Ӗ��Ō��Ɨ]�T�����鉉�t�i�W���Y�͂�������܂�ڐ������e���������Ă���Ȃ��j���Ɩl�͊������B�O���b�O�̃h�����͐��m�ŃL��������A���l�Ȃ�ł͂̏d�݂�������͋����ƃE�l��������A�u���V�⏬�Z���ӂ�ɐD��������A�܂��Ɉꋉ�i�̃v���C�B�W���[�E�T���_�[�X�͌����ȉ��g���Ȃ���Z���ȃO���[����������Ƃ����A�����ɂ��x�[�X�炵�������̃x�[�X������B���O�Ɋ��҂��Ă������l�Ȃ�ł͂̃��Y���̗͋����������Ղ芬�\���邱�Ƃ��ł��Ėl�͏I�n�e���V�������オ����ςȂ��������B |
 �Z�V���E�}�N�������E�T�����@���g�A�ۂ̓��R�b�g���N���u�A2023�N6��27����2nd�Z�b�g Cecil McLorin Salvant (vo) Surivan Fortner (p) �X�^���_�[�h�A�R�e�R�e�̃u���[�X�A�~���[�W�J���ȁiMy Favorite Things�AClimb Ev'ry Mountain, Something's Coming, 10 Minutes Ago)�����S�ŁA����̃|�s�����[�Ȃ͂Ȃ��Ƃ����Z�b�g���X�g�B����ɍ��킹�Ă��A�t�H�[�g�i�[�̃s�A�m�͌ÓT�I�W���Y�̃t�B�[�����O�ŁA�Ȃ��I�݂ɓ]�����B�Z�V���͂���ɏ�邩�Ǝv���A����݂̂̂Ŏ������A�����ɂɃs�A�m���t���Ă����A�Ƃ������ω������̏��2�l�̈��݂̌ċz�Ői��ł����B�Z�V���̐��͏����\�E���n�V���K�[�̂悤�ɒ���グ�Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ɐ��̒���Ɛ��ʂ͈����B�l�I�ɂ́u���X�̃^�C�g����"Life is lonley�h�������̂�v�Ɖ̂��I��������ƂɏЉ���A�����Čl�I�ɑ�D���ȋ�"Lush Life"�����̏�Œ������Ƃ��ł��čK���ȋC���ɁB�f���I��1���Ԃ̃X�e�[�W�͒��o�݂��邩���A�Ƃ������O�͞X�J�ɏI���A�l��̃T�����ɏ�����Ē����Ă��邩�̂悤�ȃ����b�N�X�������[�h�ŁA����C�̂Ȃ�2�l�̃p�t�H�[�}���X���Ƃ����Ȃ��Ȃ�����L���Ȏ��Ԃ��߂������Ƃ��ł����B |
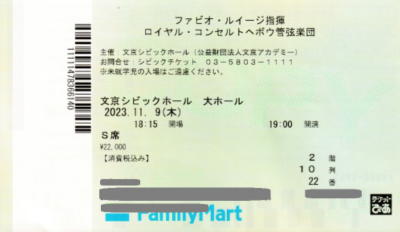 2023�N11��9�� �����V�r�b�N�z�[�� �w���F�t�@�r�I�E���C�[�W ���t�F���C�����E�R���Z���g�w�{�E�nj��y�c �y���ځz �r�[�[�F �����ȑ�1�� �h���H���U�[�N�F�����ȑ�9�ԁu�V���E���v �i�A���R�[���j �`���C�R�t�X�L�[�F�G�t�Q�j�[�E�I�l�[�M�����|���l�[�Y �r�[�[�̌����Ȃ́ACD�Œ����Ă��܂芴�����Ȃ��ȂŁA����͎����Œ����Ă����̈�ۂ͕ς�炸�B���������r�[�[���g�����\�������̂ł͂Ȃ��A��ɔ��@���ꂽ�A17�̂Ƃ��ɏ������K��Ƃ�������ȂȂ̂Ŋ����x�������Ƃ͂������ɂ������Ȃ��B���C���̃h���H���U�[�N�u�V���E���v�́A�����܂ł��Ȃ����ׂĂ̌����Ȃ̒��ł����Ƃ��L���ȋȁA�����Ċ����x�̍����ȂƂ��Ēm���Ă���B�����A�r�[�[�̌����ȂƂ͉����牽�܂Ń��x�����Ⴄ�B���������h���H���U�[�N��51�̂Ƃ��ɏ������ȂƔ�r����̂̓t�F�A�ł͂Ȃ��Ƃ͂����u�V���E���v�͍\����I�[�P�X�g���[�V�����Ȃǃo�����X�̈����⌄���܂������Ȃ��A�܂�ڐ�����������r�X����������A�����Ă������������������Ղ�Ƃ����āA�`���I�ɂ������ɂ܂Ƃ܂��Ă���Ƃ������Ƃ������Ŕ��g�Ŋ����邱�Ƃ��ł����B�ł�����~�߂邱�Ƃ��ł���B�v���O�����ňӐ}�I�ɑ_���Ă������͒肩�ł͂Ȃ�����ǁA�r�[�[�̌����ȂƔ�r���ăh���H���U�[�N�́u�V���E���v�͌��ܕ��̐l���������悻1.5�{���Ƃ����Ⴂ�͂���̂́A�؊ǁi�t���[�g2�A�I�[�{�G2�A�N�����l�b�g2�A�t�@�S�b�g2�j�Ƌ��ǁi�z����4�A�g�����y�b�g2�j�͂܂����������Ґ��A�u�V���E���v�̓`���[�o�ƃg�����{�[���������Ƃ͂����o��͂����ꕔ���݂̂ł��邱�Ƃ���A�Ȃ̍\����I�[�P�X�g���[�V�������傫���قȂ邱�ƂŁA�����y��ł�����Ȃɂ������̈Ⴄ�Ȃ��ł���Ƃ������Ƃ����������邱�ƂɂȂ��Ă����B |
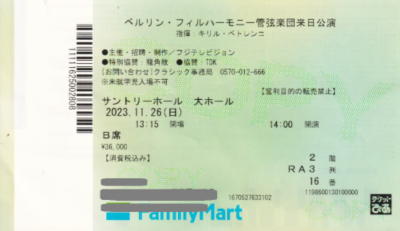 �y���ځz ���[�c�@���g�F �����ȑ�29�� �x���N�F�I�[�P�X�g���̂��߂�3�̏��i �u���[���X�F�����ȑ�4�� 8�N�Ԃ�2�x�߂́A�����ăL�����E�y�g�����R�ł̏��̃x�������E�t�B���ӏ܁B���[�c�@���g�͌y�₩�Ȑi�݁B�����A�剹�ʂ��o���ȂłȂ��ɂ��ւ�炸�I�P�S�̂��̉̂����Ղ�̗ǂ��͉B���悤���Ȃ��A�����t�����܂����Ȃ��A�݂͂��Ȃ��L���ɖ��Ă���B�ؓ����̃A�X���[�g�����C�Ȃ�����ł����x�ȑ̊��������B�ꂷ��悤�Ȋ����B�z�����ƃI�[�{�G�����̊NJy�킪���ɉ��s����^���Ă���B������������ł����̃I�P�ł͖��킦�Ȃ��悤�Ȍ����ȉ��t�B���͕��i�͒����Ȃ��x���N�B��Ґ��ɂ��A���@���M�����h�ȉ��̘A�Ȃ���x�������E�t�B���̃_�C�i�~�N�X�ƃA���T���u���ň��|�B�������Ă�����Ȉ�ۂ͕ς��Ȃ���������ǁA���̋Ȃ����h���h���Ƃ������ׂ��̂ŗ��т�̌��͂���͂���ŗB�ꖳ��̂��̂������B�u���[���X�����ȑ�4�Ԃ͑�D���ȋȂŁA�ߋ��ɑ��̃I�P��3���������Ƃ͎���������Ă����B�������ƒ��J�ɓ���ŏ��̃V�\��2�������ŐS��h�݂͂ɂ���Ă��܂��B�y�g�����R�w���̑��̋ȂƓ��l�ɑ����e���|�Ői�ނ̂ł͂Ȃ����Ə���ɗ\�z���Ă����̂ƈقȂ�A�������Ɛi�߂�B�������A�����͌ÓT�I�ł͂Ȃ��T�E���h�͐��X�����B�ߋ��̐����t�̌o�����炱�̋Ȃ͑労������^�C�v�̋Ȃ���Ȃ����ȂƎv���Ă�������Ǒ�1�y�͂̃N���C�}�b�N�X�̒��ψ��鎜�ߐ[�����Ɉ��|����Ďv�킸�܂����ڂ�Ă��܂��B��2�y�͂��������Ɛi�߁A���ǖ؊ǂ̌l�Z�ƌ����ȃA���T���u���ɃE�b�g���A��3�y�͈͂�]���č����@�����𑶕��ɔ��������ꖡ���y��i���̃e���|�ŃA���T���u��������Ȃ��̂͑��̃I�P�ł͌o�����Ȃ��j�A�Ԃ�u�����ɑ�������4�y�͂͂������Ɛi�߂ăt�B�i�[���̓I�P�̃G�l���M�[��S�J���������i�͂ƈ��͂Œ��߂�B�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A����܂Œ����Ă�����4�ԂƂ͎������Ⴄ�����̑�4�Ԃ������B |
 ���F���j�J�E�X�E�B�t�g�A�ۂ̓��R�b�g���N���u�A2024�N4��29��2nd�Z�b�g Veronica Swift (vo) Carey Frank (p, key) Gary Joseph Potter Jr. (g) Max Gerl (b) Brian Viglione (ds) �h���}�[�̈��A����A���o�����^�̃i�C���E�C���`�E�l�C���Y"Closer"���n�܂�ƃ��I�^�[�h�ɖԃ^�C�c�̃��F���j�J�������悭�X�e�[�W�ɓo��A�n�C�e���V�����̃t�@���N�Ŏ����A�����ăG�����g���̋Ȃ��uJimi Hendrix���Ɂv��"Do Nothing Till You Hear From Me"����I�����A���o���Ɠ����W�J�́A�t�@���N�A�u���[�X�E���b�N�D���Ȗl�̃c�{�Ƀn�}��B�ȍ~���ŐV�A���o���́uVeronica Swift�v�Ɠ����悤�ɁA�W���Y�ł͂Ȃ�������܂��W�������̋Ȃʼn����B�u�N�C�[���̓W���Y����Ȃ����ǁv�ƌ����Ďn�߂��̂͋����́hDreamer's Ball"�i���ԂŁA�uLive Killers�v�̃o�[�W�����Ɠ����悤�Ƀg�����{�[����͂������Ŋԑt���̂��Ƃ����}�j�A�b�N�ȉ��o����j�A�A���o���ɂ����^����Ă���"The Show Must Go On"�A"In The Moonlight"�Ȃǂɑ����ăX�^���_�[�h�́hCry Me A river"�̓T�r���I�[�f�B�G���X�ɉ̂킹�i���\�݂�ȉ̂��Ă����j�A�B��O�삩��ŏI��"Sing"�Œ��߂�ƁA�A���R�[���ł́hKeep Yourself Alive"�Ƃ��̃X�e�[�W��3�ȖڂɂȂ�N�C�[���̋ȁB���I�[�^�[�h�p�Ŕ���U�藐���A�X�^���h�}�C�N�̏㔼��������ĉ̂��p�͂������̂܂�܃t���f�B�E�}�[�L�����[�B�N�C�[���̋Ȃ��n�߁A�I�Ȃ̓o���o���A�ł��I���W�i���Ȃŕ\�����悤�Ƃ�����S�͂Ȃ������B��肽���Ȃ���肽���悤�ɉ̂��B���̎p�͂Ђ�����y�������B�L���u���[�N���邱�Ƃ͍�����Ȃ����낤���ǁA����Ӗ�����܂łɂ��Ȃ������^�C�v�̊�ȃV���K�[�ō�����������邱�Ƃ��ł������ċA�H�ɂ����̂ł����B |
 �W���V���A�E���b�h�}���E�O���[�v featuring �K�u���G���E�J���@�b�T �u���[�m�[�g���� 2024�N5��27�� 2nd�Z�b�g Joshua Redman (ts) Gabrielle Cavassa (vo) Paul Cornish (p) Philip Norris (b) Nazir Ebo (ds) �J�n�̓A���o���uWhere Are We�v��1�ȖڂƓ����W���V���A�̓Ƒt����B�������������Ŗl�͒����I�Ɂu���[�A���ꂾ��R���I�W���V���A�̃e�i�[�̉��́v�ƐS�̒��Ńj�����Ă��܂����B�ቹ�͖쑾���A�����͉s���A���L������ł����Ղ�Ƃ��������Ŕ���B�������A�W���V���A�̃e�i�[�E�T�E���h��CD�ł��\���ɂ킩������I�Ȃ��̂�����ǁA��C�̐U�����`����Ă��郉�C���̖`��1�����x�ŁA���̖��͂�S�̒�����@��N�����ꂽ�C�����ɂȂ����B �����ăK�u���G���E�J���@�b�T���̂��n�߂�B���ꂪ�A���o���Ƃ͈ꖡ����Ă��āA�L���C�ɁA���J�ɉ̂����ƂɎ������Ă��Ȃ��B�A���o���ʼn̂̏�肳�ɋ^�����Ȃ����Ƃ͏\���ɂ킩�����ǁA��肭�̂����Ȃ����Ƃ������͋C���邭�A���R�C�܂܂ɉ̂��Ă���B�X�e�[�W�o�������Ȃ��Ǝv���A�����U�镑���̓A�}�`���A�̂悤�ɑf���C�Ȃ�����ǁA�ޏ��͂������������ɂ��̎�R�Ƃ������̂�ڎw���Ă��Ȃ��B�����܂ł����R�̂ŁA���̃n�X�L�[�Ȃ̂�䆂₩�Ƃ������ł͓�����őf�p�ɉ̂��Ă��āA���ꂪ�ޏ��̒n�̎p�Ƃ��ē`����Ă����B �A���o���̓K�u���G���E�J���@�b�T�̐������������߂Ƀo���[�h�E�A���o���Ɏd�グ�Ă���A�O���̓A���o������̋ȂƂ������Ƃ������ă��C���ł����̘H���Œʂ��̂��Ǝv���Ă���ƁA�����f�B�E�j���[�}����"Boltimore"�i����͒n���ȂŃA���o���̊g��R���Z�v�g�Ƃ�������j ���牉�t����C�ɔM���Ȃ�B�R�c�k⩂�"�ԂƂ��"�i���{��̔������ƂĂ���肾�����j������ŁA���Ƀx�[�X���C���̍��݂��n�܂�ƁA�Ȃ�ƃG���X�e�B�b�N�E�o���h�����"Molten Soul"�����t�����B���ꂪ�܂��ɃW���Y�Ȃ�ł͂̃z�b�g�ȉ��t�ŁA�o�b�N�����o�[�̃\���������ė}���Ȃ�Č��������ɃG�l���M�[������̂܂܂ɕ��o���錉���B�����āA�A���R�[���̓V���p���̃v�������[�h20�Ԃ̃C���g������o���[�E�}�j���E��"Could It Be Magic�i���̓}�W�b�N�j"�Œ��߂�A�Ƃ����V�ѐS���\���Ȋy�������C���������B �ߔN�̃W���V���A�̃A���o���ł́A���̉��t�͐����������n�̐F�����������Ȃ�A���ɃA���o���uWhere We Are�v�ł͂��̉~�n���������Ă����B�W���V���A������55�A�Ⴂ���̃G�l���M�b�V���ȉ��t�͂������Ȃ��Ȃ��Ă����͎̂��R�ȗ��ꂩ�Ǝv���Ă�������ǁA�����ς��W���V���A�͗͋����Ɉ��Ă��Ėڂ������Ȃ������B���Y���E�Z�N�V���������x���������A�A���o���̂悤�ɍ�荞���t�ł͂Ȃ��A����Ӗ��ɂ������R�x�̍������t�ł͂������ǁA����Ȃ��Ƃ͒m�������Ƃł͂Ȃ��Ƃ������t�҂̓��ʂ����炯�o�����p�t�H�[�}���X���S�n�悩�����[����90���̃X�e�[�W�ɁA��͂�W���V���A�͖l�ɂƂ��Č����ō��̃T�b�N�X�E�v���C���[���Ƌ����ĔF�������Ă���������ɂȂ����B |
 2024�N6��14�� ���F�R���Z���g�w�{�E �w���F�}�����E�I�[���\�b�v ���t�F���C�����E�R���Z���g�w�{�E�nj��y�c �y���ځz �����S�����[�F �X�g���� �iStrum�j �A�_���X�F �t�B�A�t���E�V�����g���[�Y �iFearful Symmetries�j �o���g�[�N�F�nj��y�̂��߂̋��t�� ���B3��I�[�P�X�g�������ꂼ��̖{���n�Œ����B������ЂƂ̂����₩�ȖڕW�Ɍf���āA2015�N�ɃE�B�[���E�t�B���ƃx�������E�t�B�����ς邽�߂̗��s�����s�A�c����1�́i�����ȒP�ɍs���@�����킯�ł͂Ȃ����Ƃ�����j���炭���a���̏�Ԃ������B���̍Ō��1�s�[�X�߂�ׂ��A�A���X�e���_���ցB �w���҂́A���G�x�������E�t�B������ւ̏o�������܂��������w���҂̑��l�ҁi�x�������E�t�B������ŏ����w���҂��I�ꂽ�̂͏��߂Ă̂͂��j�ŃA�����J�l�̃}�����E�I�[���\�b�v�B�e�[�}�́A�A�����J���y�A���Y���A�Ƃ������Ƃł��̃v���O�����i�u�nj��y�̂��߂̋��t�ȁv�̓o���g�[�N���A�����J�ݏZ���ɏ����ꂽ���́j�B�ŏ���2�Ȃ͋��炭CD�ȂǏ��i���≉�t�@��ɂ߂ď��Ȃ�����̔����ȂŁA���O��YouTube�ŗ\�K���ē����ɗՂB 67�̃I�[���\�b�v���͊K�i���~���̂ɑ����ɕs��������̂��肷��ɂ��܂�Ȃ���̓o��B���y�����̃����S�����[���1�Ȗڂ�10�������Ƃ������Ƃ������Ă���Ȃ�I���i�I�[���\�b�v�͍��N�̏H�̃E�B�[�����������y�c�Ƃ̗��������ł����t�\��j�B2�Ȗڂ̃A�_���X�̋Ȃ͏����~�j�}���E�~���[�W�b�N�ŁA�\�K���ĉ��x�������Ă��u�܂��v�ȊO�̊��z�����o�Ă��Ȃ��ȂŁA�������Y���i���̓��̃e�[�}�̓��Y���j��25�����炢�A����̕ω��͂���ɂ��Ă����X�Ƒ����P�����̂ɁA�\����l�߂Ē��ԍs�����Ă��闷�s�҂ɂ͐����ɏP���Ȃ����������Ƃ��������B�܂��A����͗\�z���Ă������ƂȂ̂œ��ɖ��Ȃ��B ���҂��Ă����o���g�[�N�͊��Ғʂ�̑f���炵�����t�B���̏_�炩�݂���������Ɗ��炩���A�؊ǂ̃N���A�ŖF���ȋ����A���ǂ̕i����͋����Ȃǂ��R���Z���g�w�{�E�̖��͂ŁA���̃z�[���Œ����Ƃ����������_���A���{�̃z�[���Œ������������قǖ��m�ɓ`����Ă���BRCO Live�V���[�Y��SACS�}���`�`�����l���Đ��ł̓z�[���̋����̕\�����f���炵���l�������Ƃ��C�ɓ����Ă���^���ŁA���n�Œ����āA�����A���̉������̂܂܃p�b�P�[�W�������̂������ȂƂ������Ƃ��[���ł����̂ł��B |
 2024�N6��30�� �u���[�m�[�g���� ����RADIO����h������Live���̑�3�e�͍������o�[�Ńe�[�}�́u�M���D�����A�t���[�W�����i�C�g�v�B �吼���q (p, key, Music Director) ���c��� (tp) Kirk Whalum (ts, ss ,fl) Mike Stern (g) John Patitucci (b) Eric Harland (ds) [Set List] ��1�� 1. Jean-Pierre (Miles Davis) 2. Tipatina's (Mike Stern) 3. Ana Maria (Wayne Shorter) 4. Spain (Chick Corea) ��2�� 5. Direction (Joe Zawinul) 6. Cantaloupe Island (Herbie Hancock) 7. Wing and a prayer (Mike Stern) 8. Chromazone (Mike Stern) �A���R�[�� 9�DSome Skunk Funk (Randy Brecker) �����둦�ȃo���h�Ȃ̂ŁA�L���ȋȂ�y��Ɋe�����o�[�Ń\�����W�����I�ȓW�J�ɂȂ�̂͑z�肳�ꂽ���́B�ł��A�݂�ȂƂĂ��y�������ŐL�ѐL�тƉ��t���Ă���B���n�[�T������1���������Ă͂��Ȃ����̂́A����ȑO���畈�ʂ̂��Ƃ�����ċȂ̊�{�����L������Ń\�����Ă��邩��A�W���Y�t�F�X�̒Z���ԃW�����E�Z�b�V�����̂悤�Ɋɂ�Ń_���_���������̂ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�������A�悭�\�����ꂽ���t�Ƃ������Ƃł͂Ȃ�����ǁA���݂��ɗǂ��m���Ă���킯�ł��Ȃ��~���[�W�V�������W�߂āA���̏����̉��t�𐳖�2����10����������@��͂�������������̂ł͂Ȃ��A���������v���~�e�B���ȉ��t���܂��W���Y�̖��͂��ƍĔF���B�܂��A���t�҂��������������`�i�����A�[�e�B�X�g�Ƃ��ăv���t�F�b�V���i���ȉ��y�I���ʂ�ڎw���Ƃ��������A����݂̂Ȃ�������Ƌ��ɉ��t�ƂƂ��Ď��R�Ƀp�t�H�[�}���X����j�Ń��C�����s���@��͂Ȃ��Ȃ��Ȃ��Ǝv���A�y�������ɉ��t���Ă����̂͂��̂����ł������ł��傤�B ���̓��̃����o�[�ʼnߋ��ɐ����t�������Ƃ��������̂͑吼���q�i���̓��͂قƂ�ǃG���s�S���j�A�W�����E�p�e�B�g�D�b�`�i�A�R�[�X�e�B�b�N�M�^�[�x�[�X�j�݂̂ŁA���߂Đ��Œ����l�������A���Ƀ}�C�N�E�X�^�[���̃t���[�W���O�̃J�b�R�悳�͉��߂Č������Ȃ��Ă͂Ǝv�����̂ƁA���c�����C�C�l�Ǝv�����̂����n�B�ł��P�Ԉ�ۂɎc�����̂̓G���b�N�E�n�[�����h�B����قǑ��������Ă����킯�ł͂Ȃ����̂́A���̐l�̃h�����̓��Y���̃E�l���ɑ����ǂ��낪�Ȃ��Ƃ�����ۂ������Ă��āA����͐��Œ����Ă�������ہB��Ŕz�M�ʼn摜������ƃh�����Z�b�g�ɃX�l�A�ƃn�C�n�b�g��2������悤�Ɍ�����B�X�l�A�͂̍��ݕ��̓I�[�\�h�b�N�X�ȃW���Y�ł͂Ȃ��A�������ƌ����ă��b�N�I�ł��q�b�v�z�b�v�I�ł��Ȃ��A�n�C�n�b�g�ɂ͋�����t���ăV�������V���������킹�Ȃ��獏�݂��ςȂ��Ƃ����V�[���������A����ȓƓ��̃O���[�����������h���}�[�͏��߂Ċς��B�ł��A���̓Ǝ������ǂ��ɂ�����߂Ȃ��B��肢�h���}�[�͂����Ă������ɋC�ɓ������ǁA�����Ȃ�Ȃ���a�����ǂ����ɂ����āA����͂�����Ƃ��낢�뒮���Ă݂Ȃ��Ƃ����Ȃ��ȁA�Ƃ����C�ɂ�����ꂽ�̂ł����B |
 �W���Y���C�A�E�z�[�� �u���[�m�[�g���� 2024�N7��19�� 2nd set�B Jazzmeia Horn (vo) William Hill III (p) Aidan McCarthy (b) Gregory Artry (ds) �̂��n�߂Ă����ɁA���̖L���Ȑ��ʂɈ��|�����B���ʂƂ����ƈ�ʓI�ɂ͑傫�Ȑ����o���邱�Ƃ��C���[�W���邩������Ȃ�����ǁA���̐l�͐���グ���A�}�������ʂŁA�}�C�N��������20�Z���`���炢�����ĉ̂��Ă���̂ɁA�N���A���������肵�������ʂ�B�v�͔����Ɋ�b���x�����M���������قǍ����Ƃ������ƁB �X�e�[�W�ł̓J�b�`����荞�܂ꂽ�A���o�����^�Ȃ���̃`���C�X���ĉ̂��Ƃ������́A�啝�ɉ̂Ɏ��R�x�����������p�t�H�[�}���X�ŁA�܂�o�b�N�o���h�̉��t�ɉ̂��悹��Ƃ����`�Ԃł͂Ȃ��A�̂��̂��̂��h�[���ƒ��S�ɗ���B�W�����Z�b�V�����I�Ɏ��R�ɃX�L���b�g���A�o���h���ǐ��A���̃p�t�H�[�}���X��15������Ȃ�����A�̂����S�ł���Ȃ�����o���h�Ƃ��Ẵp�t�H�[�}���X�Ɉ�̊����������B �W���Y���C�A�E�z�[���͉̎����̂������X�L���b�g�̕���������Ȃ����Ƃ������R�ȉ̂����Ղ�ŁA���������̂����Ƃ��������ACD�ł͌����B�ꂵ�Ă������x�������A�t���J�̃e�C�X�g���A�i�r���ۂ��Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��j���ʂ���̖쐫���ƂȂ��ĕ\������Ă��āA���ꂪ�{���̔ޏ��̎������ȂȂƂ������Ƃ��悭�킩�����B ���b�h�E�K�[�����h��I�X�J�[�E�s�[�^�[�\���̂悤�ȓ`���I�ȃX�^�C���̃s�A�m�A�_��ł���Ȃ��烁���n���̂���r�[�g�����ރx�[�X�A�n���h�i��Œ@���j���D������Ȃ���@�ׂȃV���o�����[�N�����Ȃ��h�����̃o�b�N�����o�[�̃��x�����Ȃ��Ȃ��̂��̂ŁA�W�����Z�b�V�����I�ȋȂł��P���ɂȂ炸�A���t�҂Ƃ��ĉ��̐[����������������̂������BCD�Ƃ͈قȂ�e�C�X�g�ɂ��4�l�ł̍����p�t�H�[�}���X�A�Ō�Ɋϋq�𑍗����ɂ������̂͂��͓̂��ʂ�����鉹�y�̗͋����𑽂��̐l���~�߂�����ł��傤�B |
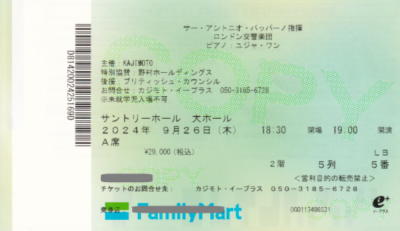 2023�N11��26�� �T���g���[�z�[�� �w���F�A���g�j�I�E�p�b�p�[�m ���t�F�����h�������y�c �y���ځz �x�����I�[�Y�F ���ȁu���[�}�̎ӓ��Ձv ���t�}�j�m�t�F�s�A�m���t�ȑ�1�ԁi���W���E�����j �i�A���R�[���j 1. �O���b�N�F�̌��u�I���t�F�I�ƃG�E���`�[�`�F�v ��2���F����̗x�� �W�����@���j �i�Y�K���o�[�e�B�ɂ��s�A�m�ҋȁj 2. �V���[�x���g/���X�g�F����a���O���[�g�q�F�� �T�����T�[���X�F�����ȑ�3�ԁu�I���K���t���v �i�A���R�[���j�t�H�[���F�p���@�[�k �y���ʼn��̐U�����傫���x�����I�[�Y�u���[�}�̎ӓ��Ձv���n�܂�ƁA�I�P�̈�ۂ�6�N�O�ɒ������Ƃ��ƂقƂ�Ǖς��Ȃ��B���͉����肪����A�ӂ��悩�ŖL���ȃT�E���h�B���ǂ͍������x���ň��肵�Ă��ċ����Ɖ��̌��݂�����A����Ŗ؊ǂ͕͗s���Ƃ܂ł͌����Ȃ�����ǁA�x�������E�t�B���A�E�B�[���E�t�B���A�R���Z���g�w�{�E�Ɣ�ׂ�Ɖ��̎咣�Ɖ̐S�����܂ЂƂ�����Ȃ��B ���t�}�j�m�t�̃s�A�m���t�ȑ�1�ԁB�o�����̋��ł̕����ŁA�������܂����Ƃ��납��T���߂ɏo�Ă��銴��������̂͂�͂菗���ł̓p���[������Ȃ�����ł��傤�B�ቹ�悾�Ɓi�s�A�m��e�������Ƃ�����l�Ȃ炲���m�̒ʂ�j�����̂ŗ͕s�����͂��܂�C�ɂȂ�Ȃ��Ȃ�B�͋������łƑ��e�������݂ɖK���悤�ȃs�A�m���A�K�c�K�c�ƒe���Ă����O�i�C���̓X�s�[�h��M���Ƃ��郆�W���E�����炵�����S�J�B����ŁA�s�A�m�̉��F�ɔ����������܂�Ȃ��ȂƊ����Ă�������ǁA�A���R�[���̋Ȃł��������_�炩�����������\�����I���A��͂肱�̃��x���̐l�������������o���Ȃ��͂����Ȃ���ˁA�Ɣ[���B�v�̓��t�}�j�m�t�̃s�A�m���t��1�Ԃ́A�i���\�ɂ܂Ƃ߂�Ɓj�n�C�X�s�[�h�̉^�w�Ƌ��ł�g�ݍ��킹���t���[�W���O�ō\������A������Ȍ|�I�ɒe�����Ƃ�������̋ȂŁA���F�̕\�����قƂ�Nj��߂��Ă��Ȃ��Ƃ����A�ɒ[�ȋȂł��邱�Ƃ��悭�킩�����B �T��=�T�[���X�́u�I���K���t���v��10�N�O�ɁA�����|�p����Ń����������nj��y�c�̉��t�Œ����Ĉȗ��̎����B�����͂܂��N���V�b�N���n�߂�����̎����ŁA���ꂩ�瑽���̃R���T�[�g���Ď����b�����Ă���̂Ŕ�r���邪�����ł����A�����������̉��t���ǂ������o���������āA���̏�ł��̓���LSO�̉��t���������Ɉꗬ�̃I�[�P�X�g���Ǝv�킹��A���F�A���x�A���͂������āA���Ƃ��Ƃ̋Ȃ̗ǂ����\���ɖ��키���Ƃ��ł����B�I���K���̉��ɂ��Ă͓����|�p����̂���͂����������Ɉ��Ɣ��͂�����A�T���g���[�z�[���̂���̓N���A�ȉ��F�������i�|���̋L�����Â��̂ŁA�����܂ł���ۂł����j�B ���߂Ē������w���҂̃p�b�p�[�m�́A�������̂킹��Ƃ���͂�������Ɖ̂킹�A�X�s�[�h����Ƃ���̓L���悭�i�ށB����̕t�������܂߁A�������V�[�����X�Ɏ��R�ɂȂ��A����̉��t�̃g�����h�ɉ��������̂ōD�����������i�l���\���X���������Ԏ�X�����j�B����ŁA�T�E���h���A���y���Ƃ����ϓ_�ł͋�����������킯�ł͂Ȃ��A����̓��{�c�A�[�Ɋւ��Ă͑I�Ȃ����肫���肾�������Ƃ�����A�����̃J���[�������Ƌ����ł��o���邩�ǂ������ۑ肩������Ȃ��B |
 �G���b�g�E�R�[�G���E�g���I�A�u���[�m�[�g���� 2024�N10��24�� 2nd set Emmet Cohen (p) Reben Rodgers (b) Joe Farnsworth (ds) ���Œ����Ď��Ɋy�������C���B�G���b�g�E�R�[�G���̉��t�͔z�M����Ō���邱�Ƃ������Đ��Œ����Ă��T�v���C�Y�͂Ȃ��B����ł����Ғʂ�ŏ�����Ȃ��uJOY�i��сj�v�ɖ������W���Y�B�G�킾�����̂́A�����̗\�肩��ύX���ꂽ�x�[�X�ƃh�����B���[�x���E���W���[�X�̗]�T�����Ղ�ŔՐ̃v���C�͂������A�W���[�E�t�@�[���Y���[�X�̓��ʐ�������t�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��̂ɍI�݂ȃu���V�A�V���o���A�X�l�A�̎g�����A�����܂ł��ȂɊ��Y�����y���̍����i�W���Y�E�h�����̂ЂƂ̗��z�^���Ƃ��猾�������Ȃ�B�X�[�c�Ƀl�N�^�C�p�Ƒ��܂��āu���v�Ƃ��������悤���Ȃ��j�B�����āA�ǂ�ȋǖʂł����Ă�3�l�̈��݂̌ċz�B���Ẵ��C�E�u���E���ƃG�h�E�V�O�y���Ƃ̃I�X�J�[�E�s�[�^�[�\���E�g���I�̂悤�Ȃ܂Ƃ܂�̗ǂ��ɁA���E�l�|�������v���������B�ڐV�������Ȃ��̂��Ƃ��Ă��A���ꂾ���̃N�I���e�B�̉��t�����ꂽ��P�`�̂��悤���Ȃ��B |
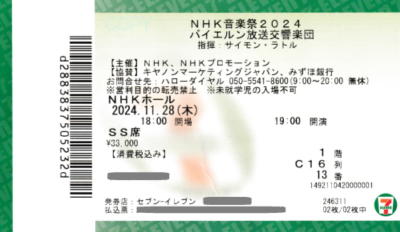 �y���ځz �o�[�g�E�B�b�X��: �T�C�����ւ̑��蕨�@2018 �}�[���[: �����ȑ�7�� 1�Ȗڂ̋��ǖ؊ǂƑŊy��݂̂̏��ȂŁA�Ȃ��ǂ̉����������ȂƂ�����ۂ�����Ȃ��烁�C���̑�7�ԂցB�e�m�[���z�����̕s���ȋ�������W�J���Ă����Ƃ�͂�u����H�v�ƂȂ�B���������ċ����Ă��Ȃ��B�Ȃ�1�K16��ڂقڒ����Ȃ̂œ��ɉ����킯�ł͂Ȃ��B�Ȃ��i��ł����Ă����̊��o�͕ς���Ă��Ȃ��B���g����69�ɂȂ��Ă��܂��ɂ��|���ɂ͂Ȃ炸�A���x�Ȑ��i�͂ŋȂ�i�߂Ă����B�I�P�����������Ă��āA���ǁA�؊ǂ̌l�Z�̍����A���̉̂����Ղ�̗ǂ��͎f����̂ɉ����͂��Ă��Ȃ����o�͍Ō�܂ŕς�炸�A�����t�Œ������̑N�x�ƃ_�C�i�~�Y�����܂�Ŋ������Ȃ��B�ߋ�2�x�ςĂ����o�C�G�����̋���������Ȃɕn��Ȃ͂����Ȃ��BNHK�z�[���̉����̕]���̈����͂������m���Ă�������ǁA�����܂ň����Ƃ́A�Ƃ����̂������Ȋ��z�BNHK�z�[���͓���������قⓌ���|�p����Ɣ�ו��ɂȂ�Ȃ����炢���������Ȃ��B11�N�O�ɂ�����N�������Ƃ��Ɉ�ۂ����������̂��I�P�̂����ł͂Ȃ��A�z�[���ɖ�肪����������ł͂Ȃ��炾�ƍ��ɂ��Ďv���悤�ɂȂ��Ă��܂����B����ł͐����t�ŋȂ̐^���𖡂�����Ƃ͓��ꌾ����A���g��������o�C�G�������������y�c�̕]���A�}�[���[�����ȑ�7�Ԃ̐^�̎p���ǂ��������̂��̕]���͕ۗ��B |