ロック・ファンのためのジャズ案内のヘッダー
Rock Listner's Guide To Jazz Music
Ornette Coleman
| Something Else !!!! | ||
 曲:★★★ 演奏:★★★ ジャズ入門度:★★★ オーネット入門度:★★★ 評価:★★☆ |
[Recording Date] 1958/2/10 1958/2/22 1958/3/24 [1] Invisible [2] The Blessing [3] Jayne [4] Chippie [5] The Disguise [6] Angel Voice [7] Alpha [8] When Will The Blues Leave? [9] The Sphinx |
Don Cherry (cornet) Ornette Coleman (as) Walter Norris (p) Don Payne (b) Billy Higgins (ds) |
| 初リーダー作。後にフリー・ジャズの象徴として祭り上げられ、未だにフリー・ジャズといえば真っ先に名前が持ち出されるオーネット、しかしこのアルバムを聴いてフリー・ジャズだと思う人はまずいないのでは。メロディやコード進行に既存のジャズとは違う手法を持ち込んだことがオーネットの価値であり批判される理由でもあったんだけれども、このアルバムではその手法じたいもまだ完成途上といった感じ。ピアノが入っているということもあってタイトルに !!!! と4つ付くほどのインパクトはなく、しごくまっとうなジャズという印象を受ける。後の強面のイメージとは違って、ここでは時にオーソドックスなジャズ特有のリラクゼーション・ムードすら発散させているほど。とはいっても、いわゆる東海岸の黒人臭ムンムンとした王道ジャズとは違うのも確か。オーネットのアルトとドン・チェリーのコルネットが織り成すハーモニーが醸し出すムード、アドリブにおけるフレーズはある程度できあがっているのでそれなりに楽しめる内容ではあるけれど、完成途上ならでは面白みというのも特になく、このアルバムをあえて聴く理由は見つからない。軽くて洗練されたウェスト・コースト・ジャズの世界から出てきたにもかかわらず、このアルバムを聴いても西海岸らしいムードがあまり感じられないのが面白いところ。[2] はチェリーとコルトレーンとの競演盤「The Avant-Garde」でも再演されている。(2007年5月26日) | ||
| Tomorrow Is The Question ! | ||
 曲:★★★ 演奏:★★★ ジャズ入門度:★☆ オーネット入門度:★★☆ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1959/1/16 [7] 1959/2/23 [8] [9] 1959/3/9, 10 [1]-[6] [1] Tomorrow Is The Question [2] Tears Inside [3] Mind And Time [4] Compassion [5] Giggin' [6] Rejoicing [7] Lorraine [8] Turnaround [9] Endless |
Don Cherry (cornet) Ornette Coleman (as) Red Mitchell (b [7]-[9]) Percy Heath (b [1]-[6]) Shelly Manne (ds) |
| !マークの数こそ減ったとはいえ、挑戦的なタイトルと強面のジャケットに後ずさりしたくなる2作目。ここからピアノ・レスになり、曲調やメロディの妙ちくりんなところもより前面出てきてだいぶ個性が確立されてきた感じ。でも、このアルバムもあまり取り上げられることがない。弱小西海岸レーベルからのリリースで、次作「The Shape Of Jazz To Come」から大手アトランティックに移籍、そしてニューヨークに進出し皆が衝撃を受けた(ことになっている)というオーネットの成り立ちの影に隠れてしまっていることが、忘れ去られている原因か。リアルタイムで接した人の受けたインパクトが後世に語リ継がれるか否かを左右するというのは音楽の世界ではよくあること。内容について話を戻すと、前半はまだ少し陽気なところがあるものの、後半の3曲は次作の収録曲に近いムードで決して質で劣っているわけではなく、オーネットの世界を理解する人なら十分に楽しめる内容でしょう。ただ、曲にしろフレーズにしろ一歩突き抜けるのはこの後からで、音楽全体のインパクトという点でも次作に及ばないのも確か。(2007年7月22日) | ||
| The Shape Of Jazz To Come | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★ オーネット入門度:★★★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1959/5/22 [1] Lonely Woman [2] Eventually [3] Peace [4] Focus On Sanity [5] Congeniality [6] Chronology [7] Monk And The Nun [8] Just For You |
Don Cherry (cornet) Ornette Coleman (as) Charlie Haden (b) Billy Higgins (ds) |
| このアルバムを初めて聴いたのは、ジャズを聞き始めてハードバップにようやく馴染んできたころで、あまりにもフィーリングが違うせいか「気持ち悪いジャズ」というのが正直な感想だった。音階やコード進行、メロディの発展のさせ方などがそれまでのハードバップや同時代のほかのジャズの斜め上を行っていて、質がまったく異なっているからそう感じたのも無理はない。フリー・ジャズとはもっと激しくリズムも奏法もメチャクチャでやかましいものだと勝手に想像していて、そういうモノを期待していた耳には「暗くて気持ち悪いジャズ」にしか聴こえなかったのは仕方のないところ。今聴くと、それほど前衛的だという印象を受けないせいもある。でも、何枚かオーネットを聴きこんでいくと彼の音楽はその独自のメロディや展開が現代においても他にない個性をもっていることが分ってくるし、それが確立されたこのアルバムがやはり代表作だと思えるようになってる。ピアノ・レス編成による空いたスペースが独特の「間」になって、何とも言えないダークで奇妙なムードが漂う。そこをどう受け止めるか、"Lonely Woman"を聴いて「??」と思うか「おおっ」と思うかによってオーネットとの接し方が決まってくるのではないだろうか。この後のチェリー入りカルテットのアルバムと比べて曲や演奏がよく練られていることも本作のセールス・ポイント。(2006年5月27日) | ||
| Change Of The Century | ||
 曲:★★★☆ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★ オーネット入門度:★★☆ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1959/10/8, 9 [1] Ramblin' [2] Free [3] The Face Of The Bass [4] Forerunner [5] Bird Food [6] Una Muy Bonita [7] Change Of The Century |
Don Cherry (pocket tp) Ornette Coleman (as) Charlie Haden (b) Billy Higgins (ds) |
| 初期のオーネットの作品はタイトルが大きい。このアルバムもその中の大きな(大げさな)タイトルの1枚と言って差し支えないと思うけれど、それほど気合いが入ったものとは思えず、この時期のレギュラー・カルテットの普段着姿と思える演奏。よって内容は地味。それでも、ヘイデンのブンブン言うベースにオーネットのアルトとチェリーのトランペットが軽快にブロウすると、オーネット・ワールドになってしまうところはさすがというべきか。もったいぶった感じがなくシリアスなムードが薄いという点でコンテポラリー時代の延長線上にあるものの、メロディやコード進行はオーネットらしい個性は確立されていて他のジャズととは質感が異なるのは確か。その個性が合わない人にまでは勧められないけれど、少しのんびりムードも漂わせながら気軽に聴けるオーネットのアルバムとしては悪くない。(2008年9月6日) | ||
| This Is Our Music | ||
 曲:★★★☆ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★ オーネット入門度:★★★☆ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1960/7/19 1960/7/26 1960/8/2 [1] Blues Connotation [2] Beauty Is A Rare Thing [3] Kaleidoscope [4] Embraceable [5] Poise [6] Humpty Dumpty [7] Folk Tale |
Don Cherry (pocket tp) Ornette Coleman (as) Charlie Haden (b) Ed Blackwell (ds) |
| このアルバムから、ドラムがエド・ブラックウェルにチェンジ。しかし、このカルテットの推進力はやはりチャーリー・ヘイデンのベースにあって、ドラムが変わったからといって大きな変化はない。ちょっとファニーなメロディをチェリーとオーネットの軽めの音で彩る形式も変わっていないし、やはりこのアルバムもあまり作り込まれた感じがしないだけに力んだタイトルほどの押しの強い内容にはなっていない。それでもヒギンズ時代のアルバムと比べると演奏にややアグレッシヴさが増したこと、曲調に幅がないところを曲順でういまく聴かせていること、ヘイデンのベースのうなりが良く捉えられているところなどに魅力がある。(2008年11月7日) | ||
| To Whom Who Keeps A Record | ||
 曲:★★★☆ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★ オーネット入門度:★★☆ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1959/10/8 [1] 1960/7/19 [2]-[7] [1] Music Always [2] Brings Goodness [3] To Us [4] All [5] P.S. Unless One Has (Blues Connotation No.2) [6] Smoke Other [7] Motive For Its Use |
Don Cherry (pocket tp) Ornette Coleman (as) Charlie Haden (b) Billy Higgins (ds [1]) Ed Blackwell (ds [2]-[7]) |
| 75年リリース。端的に言って「Change Of The Century」「This Is Our Music」の余りもの集。ここでもあまり作り込んだ感じがなくこのカルテットの自然体の演奏を楽しむ内容。「The Shape Of Jazz To Come」がしっかりと考えられた内容だったのに対して、この開放的で緩いムード、どうしてこんなギャップがあるのか、ちょっと不思議な感じがする。ほとんどの曲が同じムードで演奏されていて通して聴くと単調に感じてしまうのはこの前後のアルバム共通の弱点。それを退屈に感じない人こそが真のオーネット理解者なのかもしれない。(2006年8月5日) | ||
| Free Jazz | ||
  曲:★★☆ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★☆ オーネット入門度:★★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1960/12/21 [1] Free Jazz [2] First Take |
Heard On The Left Channel: Don Cherry (pocket trumpet) Ornette Coleman (as) Scot La Faro (b) Billy Higgins (ds) Heard On The Right Channel: Freddie Hubbard (tp) Eric Dolphy (bcl) Charlie Haden (b) Ed Blackwell (ds) |
| オーネットは数多くのアルバムを残したにもかかわらず、その余りにもわかりやすいタイトルのせいもあって代表作のように扱われているのが本作。一方で失敗作という評価もある。僕の評価はどちらかと言えば後者。基本的にはリズムを一定にした中で、それぞれのベース・プレイヤーとドラマーで役割分担、ホーン隊は与えられた時間、そのリズムの上でソロを取り、時々、他の人が絡んだり全員で咆哮するという整った内容になっていて、しかし決められた枠の中での表現となっていて怒涛の狂乱騒ぎを期待していると肩透かしを喰う。2つのカルテットでの演奏を同時進行させるということは、ダブルでなければ実現できない面白味が出るメリットと、ダブルであるからこそ制約が生じるデメリットがあり、身も蓋もないことを言ってしまえば、ここではデメリットの方が大きい。もっとも、このアルバムは、当時の最新テクノロジーであるステレオ録音のメリットを世に知らしめるという実験的な意味合いもあったそうで、いろいろな意味で過渡期を示す中途半端なものになってしまったのは仕方がないのかもしれない。参考までに、ジャケット下がオリジナルで絵の部分がくり貫きかれた凝ったものだったらしい。(2011年2月19日) | ||
| Ornette ! | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★ オーネット入門度:★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1961/1/31 [1] W.R.U. [2] T. & T. [3] C. & D. [4] R.P.D.D. [5] Proof Readers (bonus track) |
Don Cherry (pocket tp) Ornette Coleman (as) Scott LaFaro (b) Ed Blackwell (ds) |
| オーネットのカルテットに骨太な推進力を与えてきたチャーリー・ヘイデンから、「Free Jazz」で起用したスコット・ラファロへメンバー・チェンジ。ベース・ラインの感触は確かに変わった。ヘイデンのベースもいいけれど、リズムの刻み方や音程の取り方など、より幅があるラファロのベースは更にいい。そうは言ってもビル・エヴァンス・トリオでの演奏ともまた質感が少し異なる。そんなラファロの影響があったのかどうかは知らないけれど、カルテットのムードもややシリアス度を増してきているし演奏への集中力も「Change OfThe Century」以降のリラックスしたアルバムと比べると高くなっていると思う。曲の構成力もより面白みが増している点もうれしい。ベースラインだけを聴くという偏屈な聴き方にも耐える、貴重な顔合わせを記録した意外と侮れないアルバムで特にラファロのファンにはお勧できる。(2008年11月22日) | ||
| Ornette On Tenor | ||
 曲:★★★☆ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★ オーネット入門度:★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1961/3/22, 27 [1] Cross Breeding [2] Mapa [3] Enfant [4] Eos [5] Ecars |
Don Cherry (pocket tp) Ornette Coleman (ts) Jimmy Garrison (b) Ed Blackwell (ds) |
| タイトル通り、オーネットが全曲テナー・サックスで吹いているアルバム。何のためにこの企画を思いついたのかわからないほど、表現されている音楽はこれまでのオーネットと変わらない。もう笑ってしまうほど違わない。要はテナーじゃなくてもいいんじゃないかという感じ。好意的に見れば、何をやってもオーネットというのはこの時には既に確立していたということでもある。もともとアルトでもテクニックで聴かせるというよりは、音色とフレージングで聴かせるタイプなだけに、慣れないテナーだとよりフレーズのスムーズさに欠けるところは仕方がないところ。その代わり、音域が低い分だけオーネット独自の少しトボけたポップな感触が薄れているところが、強いていうなら特徴か。実はそれよりも、ヘイデンともラファロとも異質の重心の低い推進力を与えるジミー・ギャリソンが新鮮なところがこのアルバム最大のトピックかもしれない。(2008年11月29日) | ||
| Town Hall, 1962 | ||
 曲:★★★☆ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★ オーネット入門度:★★★☆ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1962/12/21 [1] Daughunt [2] Sadness [3] Dedication To Poets And Writers [4] The Ark |
[1][2][4] Ornette Coleman (as) David Izenzon (b) Charles Moffett (ds) [3] Selwart Clarke (violin) Nathan Goldstein (violin) Julien Barber (viola Kermit Moore (cello) |
| ブルーノートの4210番と4211番が割り当てられていたものの、リリースが見送られ、本人もマスター・テープの所在を知らないということで幻の音源があったと言われている。このアルバムは4211番からベース・ソロの1曲を除いてESPというレーベルからリリースされたもので、残りの曲は契約の関係で今後も日の目を見ることはないらしい。そういう資料的な価値はとりあえず横に置いておくと、このアルバムのトピックはまずは後の「At The "Golden Circle" Stockholm」と同じメンバーによるトリオ編成であるところ。ホール特有の反響音によってアルトの輝きが増したかのような印象を与え、演奏もこれ以前のスタジオ録音より緊張感があって聴き応えがある。およそ10分の [3] のみストリングス・カルテットによる演奏(後の「Skies Of America」と通じるものがある)でこのトリオとは関係ない演奏だけれど、それもこのアルバムのカラーの一部になっている。23分超の大作 [4] はアイゼンセンのノイジーかつアヴァンギャルドなアルコ弾きと変幻自在のビチカートを織り交ぜたパフォーマンスが緊張感を高め、そこに吠えるオーネットのアルトが絡む様は実にスリリング。それまでのオーネットのスタイルから一皮剥けた感もある名演集と言える。ところで、ブルーノートのアルバムというのはアルフレッド・ライオンのコントロールが効いていて、どのアルバムを聴いても「ああ、ブルーノートだな」とわかる音の感触があるんだけれど、このアルバムはブルーノートからリリースされるはずだったにもかかわらず、ブルーノートらしさがまったくない。ここに残された録音はブルーノートにとっても規格外で、それ故にお蔵入りになったんじゃないかと思える。(2009年1月10日) | ||
| At The "Golden Circle" Stockholm | ||
  曲:★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★ オーネット入門度:★★★★ 評価:★★★★☆ |
[Recording Date] 1965/12/3,4 Vol. 1 [1] Faces And Places [2] European Echoes [3] Dee Dee [4] Dawn Vol. 2 [1] Snowflakes And Sunshine [2] Morning Song [3] The Riddle [4] Antiques |
Ornette Coleman (as, violin, tp) David Izenzon (b) Charles Moffett (ds) |
| オーネットといえば真っ先に挙がるアルバムがこのVol.1。これからジャズを聴こうと思いガイドブックを開いた人は、フリー・ジャズの象徴として、そしてオーネットの代表作としてこのアルバムを聴く可能性が高い。そして聴いてみると「あれ?思ったほど特異ではないじゃないか」と思うに違いない。リズムはフォービートで妙な変拍子もない。あらゆる種類の音楽が溢れる現代においてはとりたててアヴァンギャルドという感触をこのアルバムが持ち合わせているわけではない。ところが50年代から遡ってジャズを理解して行くと、その異質さが痛いほどによくわかる。特異な音階、珍妙なメロディはオーネットでしか成し得ない不気味さで、アイゼンソンの腰が座らないベースと、落ち着きのないモフェットのドラムとで織りなす唯一無二のトリオ・ジャズの心地悪さは聴いた人でないとわからない。そもそもオーネットのアルバムはどれを聴いてもオーネット色であるんだけれど、シンプルなトリオで、狭いクラブでのライヴ盤、そして素晴らしい録音という条件が重なったことでピュアにオーネットを味わうのに最適なアルバムとなっている。Vol.1はすべてアルト・サックスで一貫性があるのに対して、Vol.2はトランペットやヴァイオリンを手にしたいかにもフリーな演奏を交えたもので、聴き所が対照的なだけに両方合わせて味わいたい。(2014年6月8日) | ||
| New York Is Now ! | ||
 曲:★☆ 演奏:★★★ ジャズ入門度:★ オーネット入門度:★★☆ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1968/4/29 [1] The Garden Of Souls [2] Toy Dance [3] Broad Way Blues [4] Round Trip [5] We Now Interrupt For A Commercial |
Ornette Coleman (as, violin) Dewey Redman (ts) Jimmy Garrison (b) Elvin Jones (ds) |
| リズム・セクションにコルトレーン・カルテットの2人を迎えた作品とあって期待が高まる。「At The "Golden Circle" Stockholm」と比較すると、サックスがオフ気味に録音されているせいかオーネットのプレイに精彩がないように感じてしまう。それに引き換えリズム・セクション、とくにエルヴィンはフリー・ジャズ系のシンボルが相手であってもいつもの通りの重量感と躍動感。いや、主役が映えないのはこのリズム・セクションの迫力のせいなのかもしれない。デューイ・レッドマンは、「ブヒョ〜〜」という何か怪物のうめき声(?)のような不気味な音を出していること以外にはさほど存在感はなく、このアルバムではあまり良さが出ていないように思う。ところで、このカルテットはオーネットが望んで組んだものなんだろうか。ブルーノート得意の、ライヴでもスペシャルな組み合わせだったような気がしてしまう。実際、オーネットがこれまで共演してきたメンバーと、エルヴィンとギャリソンは明らかに資質が違っていて、そこが面白いとはいえ、正直なところオーネットと合っているという感じがあまりしない。時期がだいぶ違いるけれど、コルトレーンとドン・チェリーの競演盤「The Avant-Garde」ではオーネット人脈がバックを固めている中でコルトレーンが活躍するというこのアルバムで、主役とバックが入れ替わったらどうなるかという視点でこのアルバムと聴き比べてみるのも一興。(2006年7月1日) | ||
| Love Call | ||
 曲:★☆ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★ オーネット入門度:★★☆ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1968/4/29, 5/7 [1] Airbone [2] Love Call [3] Open To The Public [4] Check Out Time Bonus Track [5] Love Call(alt take) [6] Chek Out Time [7] Just For You |
Ornette Coleman (as [1][3][4][6],tp [2][5][7]) Dewey Redman (ts) Jimmy Garrison (b) Elvin Jones (ds) |
| オーネットとジミー・ギャリソン&エルヴィン・ジョーンズのコルトレーン・リズム隊邂逅セッションは、68年4月29日と5月7日の2回行われ、「New York Is Now, Vol.1」(こちらは4月29日のみ)と本アルバムに分けて収録されている。本作はしかし、録音から発表までに3年を要していて、タイトルも「Vol.2」となるはずだったものが改題され、アートワークも何やら意図があるかのようなデザインに変わっている。実は長らく廃盤で法外な値段で取引きされていたものが、いつの間にか日本でのみ復刻していて慌てて買ったもの。演奏の内容は「New York Is Now!」と基本的な印象は変わらない。軽快なテンポで進める曲が幾分多いので全体にやや一本調子な感じがするものの、こちらの方がより気軽に聴けるとも言える。また、オーネットの個性的(ヘタクソとも言う)なトランペットをフィーチャーした曲が多く入ることで、一本調子な感じをある程度回避できている。これまでのオーネットのグループというのは基本的にリズムでのグルーヴ感があまりないのが特徴になっていて、本作も本質的にはその点に変わりはない。ところが、コルトレーン・リズム隊だと重みのあるグルーヴ感が抑えきれず、ほんのりと滲み出てしまうところが面白い。全体に熟れた印象を受けるのは2回めのセッションが含まれているからというのもあるかもしれない。オーネットとデューイのプレイも2回めの方がテンションが高いように思う。(2006年7月1日) | ||
| Friends And Neighbors | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★ オーネット入門度:★★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1970/2/14 [1] Friends And Neighbors (vocal) [2] Friends And Neighbors (Instrumental) [3] Long Time No See [4] Let's Play [5] Forgotten Songs [6] Tomorrow |
Ornette Coleman (as [1][3][4][6],tp [2][5][7]) Dewey Redman (ts) Jimmy Garrison (b) Elvin Jones (ds) |
| もはやジャズとは言い難いコーラス入りの風変わりな[1]からしてやはりオーネットでしかあり得ないと思わせてしまうこの堂々とした振舞いが潔い。60年代からさらに一歩進んだ独自の道を進み、もはや他の追随を許さない。こんな音楽(自宅録音と言われている)がリリースできたのはマイナー・レーベルだからこそか。復帰したチャーリー・ヘイデンの推進力とエド・ブラックウェルの小気味よい跳ねるようなドラムとのリズム・セクションはやはり個性的でオーネットのサウンドに欠かせないファクターであることを再認識。[3]以降は70年代のオーネットにとって王道的なスタイルのジャズを展開しており、60年代前半と比べるとオリジナリティもスリルも増している。録音後、間をおかずリリースされたものでありながら話題に上ることはほとんどないアルバムではあるけれど、ライヴならでは(ただし歓声はほとんど入っていない)のラフさもカッコよく埋もれさせるにはもったいない逸品。(2009年2月21日) | ||
| The Complete Science Fiction Sessions | ||
 曲:★★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★ オーネット入門度:★★★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1971/9/9 [2] [3] [7]-[16] 1971/9/10 [4] 1971/9/13 [1] [5] [6] 1972/9/7 [17] 1972/9/8 [19] Disc 1 [1] What Reason Could I Give [2] Civilization Day [3] Street Woman [4] Science Fiction [5] Rock The Clock [6] All My Life [7] Law Years [8] The Jungle Is A Skyscraper [9] School Work [10] Country Town Blues [11] Street Woman (alt take) [12] Civilization Day (alt take) Disc 2 [13] Happy Blues [14] Elizaabeth [15] Written Word [16] Broken Shadows [17] Rubber Gloves [18] Good Girl Blues [19] Is It Forever |
Don Cherry (tp [2]-[4] [10]-[12]-[16]) Bobby Bradford (tp [7]-[9] [13-[16]) Carmine Fornarotto (tp [1][6]) Genard Schwarz (tp [1][6]) Ornette Coleman (as, violin [5]) Dewey Redman (ts [1] [4]-[9] [13-[19], musette [5]) Ceder Walton (p [18] [19]) Jim Hall (g [18] [19]) Asha Puthli (vo [1] [6]) David Henderson (poet [4]) Webstar Armstrong (vo [7][8]) Charlie Haden (b) Ed Blackwell (ds [1] [5]-[9 [13-[19]) Billy Higgins (ds [2]-[4] [10]-[16], tympani [1] [6]) plus woodwind section [7] [8] |
| アルバム「Science Fiction」と「Broken Shadows(82年リリース)」のセッションを集約した2枚組。曲によってメンバーも編成も多種多様。管楽器のアンサンブルでオーネットらしい浮遊感を創出する集団前衛ものからシンプルなカルテット、果ては上手くもなんともない女性ヴォーカルやロカビリースタイルの男性ヴォーカル入り、不気味な詩の朗読に赤ん坊の泣き声までが入り混じる曲まである。そのカオスぶりが凄まじく、全体として聴いても音楽家オーネット・コールマンの世界が全開した文句なしの名盤。それゆえに散漫なところもあるのは仕方ないとはいえ、まるでLed Zeppelinの「Phisical Graffitti」のようなごった煮的統一感があるのも事実で、それはひとえに音楽に一本筋が通っているからに他ならない。演奏も非常にテンションが高く、オーネット自身のパフォーマンスも充実している。一般的に、オーネットの代表作といえば、「The Shape Of Jazz To Come」や 「At The "Golden Circle" Stockholm」と相場が決まっているものの、前者は今の耳にはさして前衛的ではなく、後者はトリオ編成のライヴで純粋にオーネットを楽しむという主旨。その他のスタジオ盤はもうひとつの代表作である「Free Jazz」を含めてプロデュースが行き届いていない完成度が低いものか、普段着姿を切り取ったものばかりで、内面に潜んだものまでを放出させてパッケージ化することができていないというのが僕の意見。従って「フリー・ジャズのシンボルと崇められているオーネット・コールマンとやらはどんなものだろう」という人に聴かせるアルバムは本作をおいて他にはないと断言したい。このワン・アンド・オンリーの世界を下支えしているのはジャズのそれともロックのそれとも質が異なるベースラインを繰り出すチャーリー・ヘイデンの鋭くも攻撃的な演奏にあることも付け加えておこう。他の項目でも書いている通り、基本的にオーネットの描く世界というのは実は常に同じで、そこが他のミュージシャンに尊敬されている理由でもあるけれど、その個性を理解するという意味でも刺激の強いこのアルバムから入ってしまった方がわかりやすいように思う。(2009年5月9日) | ||
| Whom Do You Work For ? | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★ オーネット入門度:★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1971/11/5 [1] Street Woman [2] Song For Che [3] Whom Do You Work For ? [4] Rock The Clock [5] Written Word |
Ornette Coleman (as, tp, violin) Dewey Redman (ts, musette) Charlie Haden (b) Ed Blackwell (ds) |
| このメンバーはオーネットのカルテットの中ではベストだったと個人的には思う。アルトの音はよじれて、デューイ・レッドマンのテナーも負けじとフリーキーに対抗、ヘイデンは独特のウネリを造り、ブラックウェルの軽くて潔くないドラムがスピード感を補強する。そんな演奏をたっぷりと楽しめるこのアルバムもやはり聴き応え十分。ただし、通して聴くと色彩感に乏しく単調であるのも事実で自分の精神状態とうまく合っていないときに聴くと体が受け付けないこともある。このあたり、僕はやはりオーネットの良い聴き手ではないなということを再認識することになる。そうは言ってもこカルテットのスリルは他では得難いものだし、一般にイメージできるフリー・ジャズ的な演奏を楽しめるという意味でもこのアルバムは勧められる。録音状態に少しクセがあり、ドラムの音が奥の方でこじんまり 鳴っていて全体に音に厚みがないところが少し残念。(2009年7月27日) |
||
| Live In Paris, November 1971 | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★ オーネット入門度:★★☆ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1971/11/? [1] Street Woman [2] Summer-Thang [3] Silhouette [4] Rock The Clock |
Ornette Coleman (as, tp, violin) Dewey Redman (ts, musette) Charlie Haden (b) Ed Blackwell (ds) |
| 71年の欧州ツアーでの録音。演奏の質そのものは「Whom Do You Work For?」とほぼ同等で曲も重複しているけれど、時間はこちらの方がより長尺演奏になっている。その代り演奏の密度がやや落ちてテンションが少し低い感じもしてしまう。ジャズなんだから日によってデキが違うのは当たり前といえば当たり前か。全体の印象もこちらの方が一本調子で、演奏時間が長い分だけ集中力を要求される。録音状態は少しだけ不安定で曲ごとに音像に違いを感じる。音質そのものは「Whom Do You Work For?」よりもクリア、その代りベースの輪郭がボヤけていている。オーネットのトランペットとレッドマンのチャルメラ(musetteってどんな楽器?)が狂ったように絡みながら進む [4]は中間あたりからヘイデンのベースの音にファズがかかってきてジャズの世界から逸脱しはじめ、醸し出す空気はロックと同種のものを感じさせる。この曲こそがハイライト。(2010年1月30日) | ||
| Skies Of America | ||
 曲:★★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★ オーネット入門度:★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1972/4/17-20 Part 1 [1] Skies Of America [2] Native Americans [3] Good Life [4] Birthdays and Funerals [5] Dreams [6] Sounds Of Sculpture [7] Holiday for Heroes [8] All Of My Life [9] Dancers [10] Soul Within Woman [11] Artists In America Part 2 [12] The New Anthem [13] Place In Space [14] Foreigner In A Free Land [15] Silver Screen [16] Poetry [17] The Men Who Live In The White House [18] Love Life [19] The Military [20] Jam Session [21] Sunday In America |
Ornette Coleman (as [11] [14-18] [20]) London Symphony Orchestra Conducted by David Measham |
| ロックやジャズのミュージシャンというのは、クラシックという、芸術として認められた(税金で支援してもらえる唯一の)音楽にコンプレックスがあるのか、ときどきオーケストラとの共演に挑戦する人が現れる。しかし、その殆どは熱心なファンでさえも「なかったことにしよう」的な失敗作に終わっている。理由は明快。自身の音楽をクラシックに融合させようという作り手の意気込みとは裏腹に、実はクラシックに媚びて自身の音楽を忘れてしまっているものばかりだから。要は対象をクラシックに置いている時点で既に負けている。唯一の例外としてピンク・フロイドの「Atom Heart Mother」があるものの、あれはロン・キージンが着色したシンフォニーであり、音楽的には揺るぎないフロイドそのものだったからこその成功例。そこでこのアルバム。最初の3秒を聴いただけでオーネット以外にはあり得ない音楽とわかる世界が炸裂していて最後までそれが貫かれているところに感動する。その不気味で不安定感漂う音楽性が高度だとも完成度が高いとも思わないんだけれど、そんなことは関係なく、ひたすらオーネットの音楽になっているところが潔い。クラシックに媚びず、追いつこう、追い越そうなんて思いがまったくなく、自分の音楽を描くとこにすべての情熱が注がれている。全体の3分の1くらいしか吹いていないアルトがまた効果的で絶妙。何度も繰り返して聴きたくなる音楽ではないものの、一般的な美しさや心地よさとは対極にある独自の調和は他のアルバムでも聴くことができないほど独創性豊か。ただそれだけで十分に素晴らしい。個人的にはCBS時代のオーネットは音楽家として一番クリエイティヴだったと思う。それにしても、一流オーケストラがよくもこんな音楽についてきてくれたものだと、ある意味感心する。(2018年11月3日) | ||
| Dancing In Your Head | ||
 曲:★★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★ オーネット入門度:★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1973 January [3] [4] 1975 December [1] [2] [1] Theme From A Symphony (Variation One) [2] Theme From A Symphony (Variation Two) [3] Midnight Sunrise [4] Midnight Sunrise (alt take) |
[1] [2] Ornette Coleman (as) Charles Ellerbee (g) Bern Nix (g) Jamaaladeen Tacuma (b) Ronald Shannon Jackson (ds) Bob Burford (per) [3] [4] Ornette Coleman (as) Robert Palmer (cl) with Master Musicians Of Jajouka (ghaita, stringed, Instruments, per) |
| ジャズを聴き始めたころ、オーネット・コールマンのことがよく理解できなかった。それでも我慢強くときどき聴いているうちにその個性がようやくわかるようになってきて、そんなときに触れたのがこのアルバム。真剣に音楽を聴くようになってもう25年以上、もうどんな音楽を聴いても「おお、こんな音楽は聴いたことがない」と驚きはしなくなったと思っていたのにこの音楽にはかつてないほどの新鮮さをもって魂をえぐられ、オーネットが真の異能サウンド・クリエイターであることを思い知らされた。ひとことで言えばアブストラクト・ファンク。ジャズなんてシケたもんじゃない。単調なテーマメロディに、捩れた2台のリズムギターと変態ファンク・ベースに奔放な太鼓がグチャグチャになって絡む様は言葉で表せないほど不気味で気持ちいい。こう書くと何やら高度な音楽性を持ったものであるような感じさえするものの、能天気と言っても良いテーマ・メロディが、この音楽を真剣に分析しようとする輩を鼻で笑い飛ばす。また、他に得難いグルーヴに乗るオーネットのアルトの冴え方も尋常でない。そんな [1] が終わってほっとすると、まったく同じノリで同じ曲が間髪入れずに始まるところが理解不能と思いつつ、またしてもこのグルーヴに強制的に引き戻される。こんな音楽、この世に他にない。[3][4] はオーネットらしい実験性に富んだものだけれど、[1][2]が凄すぎて霞んでしまう。(2006年7月5日) | ||
| Virgin Beauty | ||
 曲:★★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★ オーネット入門度:★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1988 [1] 3 Wishes [2] Bourgeois Boogie [3] Happy Hour [4] Virgin Beauty [5] Healing The Feeling [6] Singing In The Shower [7] Desert Players [8] Honeymooners [9] Chanting [10] Spelling The Alphabet [11] Unknown Artist |
Ornette Coleman (as, tp, violin) Jerry Garcia (g [1] [6] [7]) Bern Nix (g) Charlee Ellerbe (g) Al McDowell (b) Chris Walker (b) Denard Coleman (ds, key, per) Calvin Weston (ds) |
| プライムタイムを名乗る80年代のコールマン・グループはひとことで言えばアブストラクト・ファンク。ここでも気持ちいいんだか悪いんだかわからない珍妙なグルーヴ感の中でオーネットの軽いアルトが浮遊する。この落ち着き感のなさはオーネットが個性としてずっと持ち続けてきたもので、そういう意味では50年代からなんら変りなく、そこにオーネットの凄さを感じてしまう。グレイトフル・デッドのジェリー・ガルシアが参加していることもトピックとはいえ、オーネットの個性に埋もれて存在感が薄い感じは否めない。他人を自分のアルバムに参加させるとその個性 を埋もれさせ、自分が他人のアルバムに参加すれば自分色に染めてしまうオーネットのアクの強さはここでも健在。ただ、このアルバムに関して言えば「Dancing In Your Head」ほどの突き抜けた感じにまでは至らず、若干物足りない。(2010年6月26日) |
||
| Sound Grammar | ||
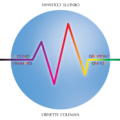 曲:★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★ オーネット入門度:★★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 2005/10/14 [1] Intro [2] Jordan [3] Sleep Talking [4] Turnaround [5] Waiting For You [6] Call To Duty [7] Once Only [8] Song X |
Ornette Coleman (as, tp, violin) Gregory Cohen (b) Tony Falanga (b) Denard Coleman (ds, per) |
| 生前最後にリリースされたライヴ盤で、ベース2人、ピアノレスのカルテット編成。フリージャズの旗手として注目されるようになってから40年の歳月が過ぎてもオーネットは良くも悪くも何も変わっていない。ああ、あのオーネットだとすぐにわかる。もう既に知り尽くされた手法で演奏を展開し、アルトを鳴らす。だから、ここで展開されている音楽はある意味古臭い。本人以外がやっていたら、何でイマドキこんな音楽を?となるはずだ。それが許され、そして違和感なく普通に受け入れられるのがオリジネーターの強み。往年のアルバムに比べるとほとんど取り上げられることが少ないアルバムながら、小細工なしでストレートに表現している分だけ、素のオーネットが表現されているし、初めて聴く人にも勧められる。内容も悪くない。(2012年10月28日) | ||
