ロック・ファンのためのジャズ案内のヘッダー
Rock Listner's Guide To Jazz Music
Eric Dolphy
| Outward Bound | ||
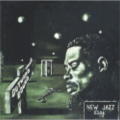 曲:★★★☆ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1960/4/10 [1] G.W. [2] On Green Dolphine Street [3] Les [4] 245 [5] Glad To Be Unhappy [6] Miss Toni [7] April Fool [8] G.W. (alt take) [9] 245 (alt take) |
Freddie Hubbard (tp) Eric Dolphy (as,bbcl, fl) Jaki Byard (p) George Tucker (b) Roy Haynes (ds) |
| ドリフィーの初リーダー・アルバム。[7] 以降はボーナストラック。後に発展させる世界を思うとオーソドックスで、ドルフィーのアドリブのキレもまだまだという感じがする。それでも60年の録音と考えるとかなり進んでいるというのも確かで、既存のアドリブの囚われないドルフィーのフレージングとハバードのキレのいいトランペット、ジャッキー・バイアードの先進的なバッキングが新しさを支えている。一方で、いつものように弾力性に富むタッカーのベースが非常にオーソドックス、そして曲も新しくなりきれていないところもあって、過渡期的な作品という印象を受ける。演奏そのものはなかなか良いので、あまり肩肘張らずにドルフィーを楽しむという意味では好アルバムであると思う。(2022年11月6日) | ||
| At The Five Spot | ||
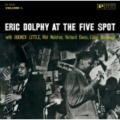 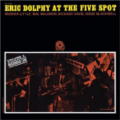 曲:★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★ ドルフィー入門度:★★★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1961/7/16 Vol.1 [1] Fire Waltz [2] Bee Vamp [3] The Prophet [4] Bee Vamp (alt take) Vol.2 [5] Aggression [6] Like Someone In Love |
Booker Little (tp) Eric Dolphy (as, bcl, fl) Mal Waldron (p) Richard Davis (b) Ed Blackwell (ds) |
| 初心者に勧めて良いと尖った演奏なのに、初心者向けガイドブックでもよく紹介されているのがこの Vol.1。パタパタとスネアの音数が多く、時に跳ねるようなリズム感が特徴のエド・ブラックウェルのドラム、太く突き上げるリチャード・デイヴィスのベース、中音域を多用して規則的にメランコリックなリズムを刻むマル・ウォルドロンのピアノで構成されるリズム・セクションは、この3人ならではの独特のムードがあるとはいえ、それじたいが前衛的というほどではない。しかし、そこに乗るドルフィーのアドリブは前衛的かつアグレッシヴなことこの上なく、ブッカー・リトルのトランペットの生気も凄まじい。[1][3]のアルト・サックスによるアドリブは、はちきれんばかりのテンションでドルフィーらしさが特に良く現れていて、Vol.1の支持が高い理由にもなっている。でも個人的にはVol.2も負けないくらい素晴らしい。Vol.2の評価が低いのはドルフィーのアルトによる演奏がないこと([5]はバス・クラ、[6]はフルート)にあると思われ、しかし、ブッカー・リトルの張りと艶のある輝かしいトランペットがそれを補って余りある。リトルを堪能するならむしろVol.2、中でもアグレッシヴな[5]が素晴らしい。[6]はドルフィーのフルートが奔放に駆け巡る冒頭からリラックスした演奏に転じ、他の曲とは一味違っているところがまたいい。生々しさを捉えた録音も良く、短期間しか存在しなかったこの素晴らしいコンボの記録が残されていた奇跡に感謝したくなる。(2006年11月16日) | ||
| Memorial Album | ||
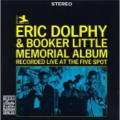 曲:★★★ 演奏:★★★ ジャズ入門度:★ ドルフィー入門度:★ 評価:★★☆ |
[Recording Date] 1961/7/16 [1] Number Eight (Potsa Lotsa) [2] Booker's Walts |
Booker Little (tp) Eric Dolphy (as, bcl, fl) Mal Waldron (p) Richard Davis (b) Ed Blackwell (ds) |
| 名盤「At The Five Spot」と同日の音源でありながら、なぜかVol.3ではなく別タイトルで発売されているアルバム。確かに同じ録音状態、同じメンツによる演奏、ただし全体的にテンションが低いというか落ち着いた感じで、Vol.1、Vol.2の張り詰めた緊張感はない。トータル約31分と時間も短めで、このファイヴ・スポットの演奏ならなんでも聴いてみたいという人以外にはあまり勧められない。冷静に考えてみると、1ステージ全曲の演奏が凄まじいということはあり得ないわけで、最良の曲を抽出したものがVol.1とVol.2で、本アルバムのような演奏もあったということがわかる。(2006年11月26日) | ||
| Here And There | ||
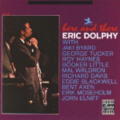 曲:★★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★ ドルフィー入門度:★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1961/7/16 [1] [2] 1960/4/1 [3] [4] 1961/9/6 [5] [1] Status Seeking [2] God Bless The Child [3] April Fool [4] G.W. (take 1) [5] Don't Blame Me (take 2) |
[1] [2] Booker Little (tp) Eric Dolphy (as, bcl) Mal Waldron (p) Richard Davis (b) Ed Blackwell (ds) [3] [4] Freddie Hubbard (tp [4]) Eric Dolphy (as, fl) Jaki Byard (p) George Tucker (b) Roy Haynes (ds) [5] Eric Dolphy (fl) Bent Axen (p) Erik Moseholm (b) Jorn Elniff (ds) |
| [1][2] はファイヴ・スポットの残り音源。しかしこの[1]がなかなかアグレッシヴな仕上がりで、リチャード・デイヴィスのブンブン言うベースと、エド・ブラックウェルの絶え間なくスネアを刻み続ける長いドラムが堪能できるし、ブッカー・リトルのトランペットとドルフィーのアルトのテンションも高い。[2]は十八番のバス・クラリネットによる独演。[3]はフルートを、[4]はアルトをフィーチャーした軽快な演奏でこれらも意外と悪くない。ドルフィーの燃焼度はまずまずで、ハバードが柔らかい高音で彩りを添える。ジョージ・タッカーも結構ブンブン言わせるタイプで、ドルフィーはこういうベース・プレイヤーがきっと好みだったんだろうと思わせる。[5]はフルートによる演奏で、冒頭のバラード・パートでは思わず聴き入ってしまうし中間のリラックスしたパートも心地よい。バラバラな音源の寄せ集めでまとまりがなくドルフィーのベストとは言い難いけれど、いろいろな面が聴けるという意味で意外と楽しめる。(2006年11月26日) | ||
| In Europe Vol.1 | ||
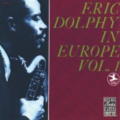 曲:★★★☆ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★ ドルフィー入門度:★★★ 評価:★★★★☆ |
[Recording Date] 1961/9/8 [1] Hi Fly [2] Glad To Be Unhappy [3] God Bless The Child [4] Oleo |
Eric Dolphy (as, bcl, fl) Bent Axen (p) Erik Moseholm (b [2] [4]) Chuck Israel (b [1]) Jorn Elniff (ds except [1] [4]) |
| 名盤とされている「At The Five Spot」「Out To Lunch」は、ドルフィーという卓越したアドリブ奏者を中心としつつ、グループとしての音楽表現に心が砕かれており、演奏も非常にアグレッシヴ。一方、「In Europe」シリーズ3枚は、独演やベースとのデュオを多く収めるなど、じっくり聴かせる演奏が多いのが特徴でドルフィーの別の一面が出ていると言える。このVol.1も、[1][3] がソロ演奏だし、[2]はフルートによる美しいバラードという構成で、ドルフィーの魅力を俯瞰できる代表作かと訊かれると「いや、ちょっと違うのでは?」と言いたくなってしまう。とはいえ、こうやって落ち着いて聴けるドルフィーのアルバムというのも味があっていいもの。熱心なドルフィー・フリークはじっくりと聴き込むタイプのドルフィーの独演を好む傾向があり、このアルバムの評価は高いようだ。クラブでの録音ということもあって反響音がなく、目の前で音を拾っているような生々しい録音状態も良い。個人的にはやはり[2]とバス・クラで自由に駈ける[4]がいい。(2006年11月13日) | ||
| In Europe Vol.2 | ||
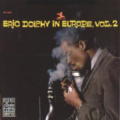 曲:★★★☆ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★ ドルフィー入門度:★★★☆ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1961/9/6 [1] Don't Blame Me [2] Don't Blame Me (take 2) [3] The Way You Look Tonight [4] Miss Ann [5] Laura |
Eric Dolphy (as, fl) Bent Axen (p) Erik Moseholm (b) Jorn Elniff (ds) |
| このVol.2もフルートとベースのデュオから始まる。途中からドラムとピアノが加わるもののフルートを控えめにサポート、あくまでも美しいバラードを堪能するための曲。[2]は「Here And There」収録と同じテイク。[3]はアップ・テンポで軽快に、そしてアドリブ・パートに入るとドルフィー節が炸裂する有名スタンダード。[4]はいかにもドルフィーらしいテーマを持ったこれもアップ・テンポの曲で「Last Date」収録テイクよりもこちらの方が締りがある。[5]はドルフィーのしばしの独演のあと、バラードに流れ込む展開に再度酔える。ドルフィーのアルトはアブストラクトに駆け巡るのにカデンツァまで含めて不思議と心地よい。このVol.2は[1]を除いてアルト・サックスのみで通しているせいか、通して聴いてもまとまりを感じる。(2006年11月13日) | ||
| In Europe Vol.3 | ||
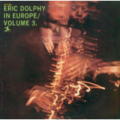 曲:★★★☆ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★ ドルフィー入門度:★★☆ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1961/9/6 [2] 1961/9/8 [1] [3] [1] Woody'n You [2] When Lights Are Low [3] In The Blues (take 1,2,3) |
Eric Dolphy (as, bcl) Bent Axen (p) Erik Moseholm (b) Jorn Elniff (ds) |
| Vol.3はたったの3曲だけでもそれぞれ、10分、12分、17分という演奏時間。[1]はこの有名スタンダードをアルトでいつものドルフィーらしく崩して行く。[2]も有名スタンダードで、バス・クラのフレーズはドルフィー的な嘶きによって、ただののんびり調の曲にしていないところは流石。[3]は、1曲扱いになっているけれど同じ曲を繰り返し演奏しているだけで、途中で演奏を止めたりなどもそのまま収録。3つのテイク、それぞれテンポを変えるなどを試みていることはわかるんだけれども、これを楽しめるのはマニアだけのような気がする。「In Eirope」シリーズ、まとまりという点では工夫がなく、コンセプトが特にあるわけでもないけれど、ジャズ・クラブでの素のドルフィーを味わう音源として楽しめる。(2006年11月13日) | ||
| Iron Man | ||
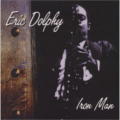 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★ ドルフィー入門度:★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1962/7/1,3 [1] Iron Man [2] Madrake [3] Come Sunday [4] Burning Spear [5] Ode To C.P. |
Woody Shaw (tp) Eric Dolphy (as, bcl, fl) Clifford Jordan (ss) Huey Simmons (as) Prince Lasha (fl) Bobby Hutcherson (vib) Richard Davis (b) Eddie Khan (b) J.C Moses (ds) |
| ドルフィーはその破天荒なアドリブとは裏腹に音楽理論や譜面に強かったそうで、例えばジョン・コルトレーンの「Africa Brass」のように大編成バンドの編曲を務めることもあった。そんなドルフィーがこのアルバムでは自身で大人数グループを編成。このときの録音はプロデューサーのアラン・ダグラスの名前を取って通称「ダグラス・セッション」と呼ばれている。[1]から厚い音でスピード感とヒネリを加えたテーマに、切れ込むアルトという展開がいかにもドルフィーらしく実にスリリング。以降、テーマ以外は割とオーソドックスにソロを回していく展開。もちろんドルフィーが一番目立っているけれど、ウッディ・ショウのシャープなトランペットも耳を惹く。そしてピアノ不在の隙間を埋めるのと同時にソロも印象的なボビー・ハッチャーソンのクールなヴァイブも印象的。また全体を通して太く突き上げるリチャード・デイヴィスのベースも存在感タップリ。[3]はアルコ弾きベースとバス・クラのデュオ、[5]はピチカート・ベースとフルートのデュオ。尚、このダグラス・セッションは昔から版権が曖昧なようで、「This Is Eric Dolphy」「Dolphy Sound」「Musical Prophet: The Expanded N.Y. Studio Sessions(2019年リリースで別テイクが7曲追加されているがなぜか全曲モノラル)」などのタイトルで下記「Conversation」とセットとして売られてしている。(2025年12月22日) | ||
| Conversations | ||
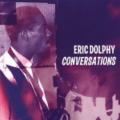 曲:★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★☆ ドルフィー入門度:★ 評価:★★☆ |
[Recording Date] 1962/7/1,3 [1] Jitterbug Waltz [2] Music Matador [3] Love Me [4] Alone Together |
Woody Shaw (tp) Eric Dolphy (as, bcl, fl) Clifford Jordan (ss) Huey Simmons (as) Prince Lasha (fl) Bobby Hutcherson (vib) Richard Davis (b) Eddie Khan (b) J.C Moses (ds) |
| 「Iron Man」と同時期セッションのもう1枚。[1][2]のような曲調はカリビアン風とでも言うんでしょうか(違ってたらごめんなさい)。いつもの鬼気迫る演奏というよりは明るく穏やかな曲で、これもドルフィーの一面なんだなあと知ることができる興味深いもの。こんな曲でもリチャード・デイヴィスのベースはいつも通り太い。以降、急に曲調が変わって[3]は約3分半ドルフィーのアルト独演、[5]はリチャード・デイヴィスとの長尺デュオ、と同じ時期のセッションでの録音ながら前半とは趣向がまったく違っていて、1枚のアルバムとしては散漫なデキになってしまっている。(2006年11月13日) | ||
| The Ilinois Concert | ||
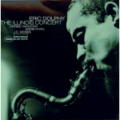 曲:★★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★ ドルフィー入門度:★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1963/3/10 [1] Softly As In A Morning Sunrise [2] Something Sweet, Something Tender [3] God Bless The Child [4] South Street Exit [5] Iron Man [6] Red Planet [7] G.W. |
Eric Dolphy (as, bcl, fl) Herbie Hancock (p) Eddie Khan (b) J.C. Moses (ds) |
| 数あるマイケル・カスクーナ発掘シリーズの中のドルフィーの1枚。発掘ものとしては音質はまずまずなんだけれど、やや反響気味で肝心のフルートの音が遠い。また、ドルフィーの演奏は、決して悪くはないものの、あまりテンションが高くないのがちょっと残念。多くのドルフィーのアルバムに入っているバス・クラ独演は[2][3](といっても連続して1曲みたいなもの)のみ。バンド全体としてもいまひとつ盛り上がりに欠け、乗り切れていない感じで、つまり、演奏は全体に平均レベル。トピックを挙げるとすれば、マイルス・デイヴィスの「Four And More」「My Funny Valentine」を録音する2日前のハンコックがいることだろうか。そのハンコックが持ち味を発揮してマイルス・グループとは一味違う、フレッシュかつイマジネイティヴなプレイを繰り広げているのが本作の聴きどころ。[6][7]はそれぞれブラス・アンサンブル/ビッグ・バンドが加わっている。(2006年11月13日) | ||
| Out To Lunch | ||
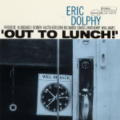 曲:★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★ ドルフィー入門度:★★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1964/2/25 [1] Hat And Beard [2] Something Sweet, Something Tender [3] Gazzelloni [4] Out To Lunch [5] Straight Up And Down |
Freddie Hubbard (tp) Eric Dolphy (as, bcl, fl) Bobby Hutcherson (vib) Richard Davis (b) Tony Williams (ds) |
| 前衛的なジャズ・ミュージシャンとして認知されているドルフィーは、実はスタンダード曲の演奏が多く音楽そのものはオーソドックスであることが多い。あくまでもその範疇でいかに独自の前衛的なアドリブで表現できるかを追求してきた人だと思う。そのせいもあってフリー・ジャズを軽蔑する保守的なジャズ・ファンの人の中にもドルフィーを評価する人は結構いるらしい。そんなドルフィー、音楽的なまとまりのないアルバムが次々と発表されていたところを見ると、実はプロデューサーに恵まれていなかったのではないかと思う。彼の持っているアドリブの個性をグループのサウンドとして、コンセプトを持った1枚のアルバムとして仕上げるプロデューサーがいたらもっと凄い音楽家として評価されていたんじゃないかと思えてならない。ブルーノートに唯一残したリーダー・アルバムである本作はそんなドルフィーの音楽性を最大限に引き出した名作。いわゆるフォー・ビートがほとんど出てこない変拍子の洪水。野太く切れ込むリチャード・デイヴィスと機械のような正確さで変幻自在なビートを刻むトニー・ウィリアムスのリズム・セクションは強力無比。ハバードもアブストラクトかつ硬質なアドリブでこのサウンドを更にスペシャルなものにしている。そしてドルフィーは自由奔放に前衛的なアドリブをいつも以上にハイテンションに繰り広げ、負けじとハッチャーソンも前衛的な彩りを加えるのと同時に、ともすれ硬すぎて息苦しくなりそうなサウンドをヴァイブの透明感溢れる音色で中和する。極めて前衛的でありながらフリーキーなアドリブの垂れ流しではなく曲もカッチリ構築されていて、その曲がまた独創的でオリジナリティは群を抜く。この時期、このメンツで、ブルーノートでなければ成し得なかった、誰にも真似できない孤高の逸品。(2006年9月13日) ハイレゾ音源をHDtracksからダウンロード。入手したのは 96KHz/24bit の音源。まったくの別物と言えるくらいCDとは違う。楽器の定位(左右の音の振り方が明確、ドラムはほぼ右のみに寄せられている)からして違い、管楽器が交じり合う部分でも音が混濁しない。個々の楽器の音の滑らかさとリアリティが大幅に向上。音場の広がりも明確に感じられ、音の雑味がなくなっていい意味でスッキリとクリアに聴こえる。これはハイレゾだからではなく、リマスタリングによる効果で、オーディオに力を入れている人なら買って後悔しないクオリティ。ただし、音場感はCDの方が一体感があって良いと思う人もいるかもしれない。(2012年8月4日) |
||
| Last Date | ||
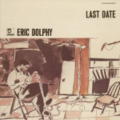 曲:★★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★ ドルフィー入門度:★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1964/6/2 [1] Epistrophy [2] South Street Exit [3] The Madrig Speaks, The Panther Walks [4] Hypochristmutreefuzz [5] You Don't Know What Love Is [6] Miss Ann |
Eric Dolphy (as, bcl, fl) Misja Megelberg (p) Jacques Schols (b) Han Bennink (ds) |
| エリック・ドルフィーの生前最後の録音としてリリースされたアルバム。この9日後の録音も発掘されている今となっては最後の録音としての意味はなくななったものの、中身の価値が下がったわけではない。この時期ドルフィーはヨーロッパに滞在中で共演者は地元のミュージシャンとあって無名な人ばかり。それにしてもドルフィーはライヴ、そしてヨーロッパでの録音が多い。レギュラー・グループを率いることはなく地元ミュージシャンを起用することが多かったことが自己の音楽を構築できなかった一因だったように思う。本作もその流れを汲んでいて、現代音楽的かつフリー・ジャズ的なフィーリングを垣間見ることができるピアニスト以外は平凡。「In Europe」シリーズとは違ってデュオやソロがなくコンボとしての演奏で占められていることや、ドルフィーのオリジナル曲が多い点で僕の好みには合っているけれど全体としてはさほどテンションが高いわけではない。フルートで演奏する有名スタンダード[5]はいかにもドルフィーらしい仕上がり。(2006年12月23日) | ||
