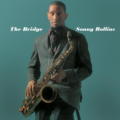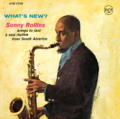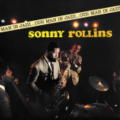ロック・ファンのためのジャズ案内のヘッダー
Rock Listner's Guide To Jazz Music
Sonny Rollins
| Tennor Madness | ||
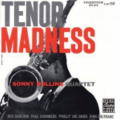 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★ ロリンズ入門度:★★★☆ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1956/5/24 [1] Tenor Madness [2] When Your Love has Gone [3] Paul's Pal [4] My Reverie [5] The Most Beautiful Girl In The World |
Sonny Rollins (ts) John Coltrane (ts [1]) Red Garland (p) Paul Chambers (b) Philly Joe Jones (ds) |
| ロリンズとコルトレーン唯一の競演で2人のバトルが聴ける[1]があまりにも有名。もともと計画的なものではなくコルトレーンの飛び入り参加だったようで、単純な曲によるリラックスしたジャム・セッションだけれども、この2人のバトルともなればそれはもう盛り上がらないはずがないというもの。テーマのあと、コルトレーン、ロリンズの順でアドリブを取り、ピアノ/ベース・ソロ、トレーン&ロリンズとフィリー・ジョーとの掛け合いを挟んだ後、いよいよ2人のバトルが始まる。お互いに相手を意識してインスパイアされながらのプレイとあってわざと似たようなスタイルでアドリブを繰り広げる。高音を駆使して速いフレーズのコルトレーンと、おおらかで太い音のロリンズという基本的なところはしっかりと出ていて、2人をよく知る人であれば聴き分けは難しくない。時期的にはコルトレーン本格化前で表現したいことにテクニックが追いついておらず、ロリンズの貫禄勝ちというのが一般的な評価のではあるけれど、決してそうは思わないし、なにより2人で楽しげに掛け合っていることこそがこの演奏の魅力。以降の曲は、当時のマイルス・クインテットのリズム・セクションを従えたいつものロリンズで、特に[2 [4 といったバラードにおけるおおらかな演奏にロリンズの持ち味が出ている。本来は落ち着いたロリンズらしさ満点のアルバムになっていたはずなのに、[1]が目立つせいで他の曲の印象が薄くなってしまっていてバランスを損なっている感は否めない。(2006年11月19日) | ||
| Saxophone Colossus | ||
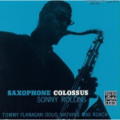 曲:★★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★★★ ロリンズ入門度:★★★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1956/6/22 [1] St. Thomas [2] You Don't Know What Love Is [3] Strode On [4] Mritat [5] Blue 7 |
Sonny Rollins (ts) Tommy Flanagan (p) Doug Watkins (b) Max Roach (ds) |
| 絶頂期のロリンズの中でも最も充実した内容を誇る名盤。軽快で親しみやすい[1]、多くのジャズ・メンに好まれるこの曲の決定版とも言える[2] 、テンポよく弾けてロリンズらしさ満開の[3]、おおらかに演奏される有名スタンダードの[4]、渋いブルースをハード・ボイルドに決める[5]と、軽快でありながら野放図で骨太、男臭くもおおらかで親しみやすいロリンズの個性が最大限に出ている。決して先進的なサウンドというわけでもないのに同時期のハード・バップと明確に違う質感を持っているのは、ロリンズのユニークな個性に加えて共演者(特にフラナガン)の好演に負うところも大きい。これを聴いて何も感じないようなら、他のロリンズのアルバムは聴かなくてもいいと言っても過言ではない。初心者にも勧めやすく、繰り返して聴いても飽きないという奥深さも魅力のジャズ史上に残る傑作。(2006年11月11日) | ||
| Sonny Rollins Vol.1 | ||
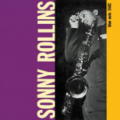 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★★ ロリンズ入門度:★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1956/12/16 [1] Decision [2] Bluesnote [3] How Are Things In Glocca Morra [4] Plain Jane [5] Sonnysphere |
Donald Byrd (tp) Sonny Rollins (ts) Wynton Kelly (p) Gene Ramey (b) Max Roach (ds) |
| ブルーノート移籍第1弾。ロリンズは若いときからジャズ・ジャイアントとしての評価を確立していたこともありワン・ホーンでの作品が多い。その点だけで貴重な本作は、しかしガイドブックであまり取り上げられる機会がない。しかし、内容はこの時期のロリンズの他のアルバムと遜色がないことを強調しておきたい。テナーはあくまでもロリンズらしく大らかに太く男性的な音圧でブロー、もちろんバラードでも男らしい優しさ(?)を発揮していて堂々たる吹きっぷり。オリジナルの[1]はヒネリの効いたテーマのブルースで、頭の天辺から爪先まで完全にロリンズ・ワールド。また、このアルバムではドナルド・バードのゆったりした演奏が素晴らしくバード不感症の僕でも思わず聴き惚れてしまうし、ロリンズとのコンビネーションもバッチリ。ケリーのピアノは後の陽気なトーンを中心としたフレーズとは違って憂いを帯びていて、これがまた味わい深い。ローチの間を活かしたリラックスしたドラムも全体のムードを決める重要なポイント。ロリンズと言えばスタンダードを演らせればピカイチという偉大な才能(そしてそれを好むファン層)のせいもあって、ここでは4曲のオリジナルで占められていることや、「Sonny Rollins Vol.2」ほどにはメンバーが豪華でないことが軽視されている原因でしょうか。オリジナル曲によるロリンズらしさの主張という意味ではベストと呼んでも過言ではないし、もっと注目されて良いとアルバムだと思う。(2006年9月13日) | ||
| Way Out West | ||
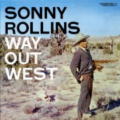 曲:★★★☆ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★☆ ロリンズ入門度:★★★ 評価:★★ |
[Recording Date] 1957/3/7 [1] I'm An Old Cowhand [2] Solitude [3] Come, Gone [4] Wagon Wheels [5] There Is No Greater Love [6] Way Out West [7] I'm An Old Cowhand (alt take) [8] Come, Gone [9] Way Out West |
Sonny Rollins (ts) Ray Brown (b) Shelly Manne (ds) |
| ロリンズのピアノ・レス・トリオ作品としては「A Night At The Village Vanguard」と並んで人気のアルバム。ところがこの2作は雰囲気がまったく違っていてとても同じ気分では聴けない。アチラはニューヨークのヴィレッジ・ヴァンガードでの熱気溢れるライヴ、対してコチラは西海岸ツアーの合間にスタジオで録音、しかもメンバーもぜんぜん違う、おまけに少々コモリ気味な録音状態だった「ヴィレッジ・ヴァンガード」に対してクリアで響きのいいスタジオ録音の本作、と相違点が多岐にわたるとなれば雰囲気が違う当然のことではある。さらに[1]に代表されるのんびりムードの曲がこのアルバムの印象を決定付けている。「おおらか」を通り過ぎて「のんびり」に感じる僕にとってこのアルバムはスリルに欠けて少々退屈に思えてしまう。演奏の質はもちろん低くないし、ロリンズのテナーに耳を傾ければ素晴らしいこともよくわかる。むしろ、隙間だらけの音空間を埋め尽くしてまったく過不足を感じさせないロリンズの凄さに唸らされてしまうほど。でも、僕はアドリブだけでなく全体のサウンドを重視するタイプでそのサウンドが肌に合わないとなるとちょっと厳しい。こういうのんびりムードを好み、バックが地味なところさえ気にならなければむしろ最高傑作になる可能性もあるアルバムで単に僕がこの音楽性を理解できないだけなんだと思う。(2006年12月5日) | ||
| Sonny Rollins Vol.2 | ||
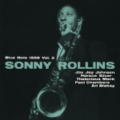 曲:★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★★★ ロリンズ入門度:★★★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1957/4/14 [1] Why Don't I [2] Wail March [3] Misterioso [4] Reflections [5] You Stepped Out Of Dream [6] Poor Butterfly |
Sonny Rollins (ts) J.J.Johnson (tb) Horace Silver (p) Theronious Monk (p [3][4]) Paul Chambers (b) Art Blakey (ds) |
| テナー・サックスとトロンボーンの組み合わせは低音系の楽器同士で実に相性が良い。ハンク・モブレーとカーティス・フラーの「The Opener」、ベニー・ゴルソンとやはりフラーの「Blues-Ette」などで聴けるハーモニーは、そんな相性の良さを示す好例。このアルバムもそんな気持ちよい組み合わせの代表的なもので、前述の2枚と比べると落ち着きよりも勢いをが前面に出ていてブローイングを楽しむ内容となっている。ロリンズの豪快で骨太なテナーにJ.J.の超絶テクニックのトロンボーン、それをさらにブレイキーが煽りに煽っているとなればそれも当然というもの。僕はビ・バップ世代のミュージシャンはどうも肌に合わなくてJ.J.もそのうちの一人なんだけど、このハード・バップ・セッションでは本当に素晴らしいブローを聴かせてくれる。ロリンズ、J.J.、ブレイキーの3人で十分楽しめるのに、ホレス・シルヴァーとセロニアス・モンクの2人のピアニストが参加、さらに[2 では競演(途中でモンクからシルヴァーに代わる)まで聴けるというのがこのアルバムの贅沢さ。もちろんロリンズ自身の充実度も最高潮でソロに入るところを間違えていることで有名な[1](そこがまたカッコいい)を含めて、本当に勢いがあって素晴らしい。また、スローな[3]でも落ち着きがないブレイキーの活躍ぶりにも思わずニヤリ。参加メンバーの点で他に類を見ない独自性があって、しかもそれぞれに持ち味が遺憾なく発揮されているというオールスター・セッションの鏡と言えるアルバム。(2006年11月30日) | ||
| The Sound Of Sonny | ||
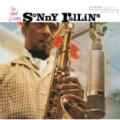 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★★★ ロリンズ入門度:★★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1957/6/11 1957/6/12 1957/6/19 [1] The Last Time I Saw Paris [2] Just In Time [3] Toot, Toot, Toosie [4] What Is There Say [5] Dearly Beloved [6] Ev'ry Time We Say Goodbye [7] Cutie [8] It Could Happen To You [9] Mangoes [10] Funcky Hotel Blues (bonus track) |
Sonny Rollins (ts) Sonny Clark (p) Percy Heath (b except [1] [4]) Paul Chambers (b [1] [4]) Roy Haynes (ds) |
| ソニー・ロリンズは物凄い量の録音が残されているにもかかわらず、取り上げられるアルバムというのは決まっている。確かに60年代以降のロリンズのアルバムには時代に合わせようと無理をしている部分もあって持ち味が出ておらず、内容的に冴えないものが少なくないために偏りが出るのも仕方がない部分もあるとはいえ50年代に録音されたものでも、「Sonny Rollins Vol.1」や「Newk's Time」などが話題に上ることはほとんどなく事実上埋もれていると言っても過言ではない。このアルバムもロリンズ絶頂期に録音されたものであるのもかかわらず、廉価版が日本で発売されるまで僕は存在すら知らなかった地味盤。ワン・ホーン編成、しかもアップテンポからバラードまで得意のスタンダードをロリンズ節で時に豪快に、時におおらかに吹きまくるという内容は同時期の他のアルバムとなんら遜色ない。しかも、ピアノはソニー・クラーク。そのクラークを筆頭にこういう曲を演奏させるのに申し分ない共演者とあっては悪いはずがない。ワン・ホーン・カルテット編成での50年代のロリンズのアルバムの充実ぶりを示す好盤。(2007年5月26日) | ||
| Newk's Time | ||
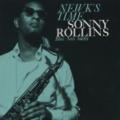 曲:★★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★★★ ロリンズ入門度:★★★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1957/9/22 [1] Tune Up [2] Asiatic Raes [3] Wonderful! Wonderful! [4] The Surrey With Fringe On The Top [5] Blues For Philly Joe [6] Namely You |
Sonny Rollins (ts) Wynton Kelly (p) Doug Watkins (b) Philly Joe Jones (ds) |
| 有名なスタンダードを中心とした聴きやすいアルバム。ケリーは陽気さを封印した憂いあるトーンで好サポート。ワトキンスは弾力性で押し、フィリー・ジョー・ジョーンズは奔放なリズムを繰り出す。ワン・ホーン編成では当然重要となるこのリズム・セクションの仕事ぶりが最高で、このアルバムの価値を高めているように思う。もちろんテナーが鳴りはじめれば、そこはもうロリンズ・ワールド。ブルーノートらしい作り込まれた印象こそ薄いものの、それすらロリンズの持ち味にプラスに作用している。改めて繰り返すまでもないのけれど、こういうオーソドックスな曲をワンホーンで演らせたときのロリンズは本当に素晴らしい。合計でも30分強という収録時間は少々淡白な印象を与えるとはいえ、ロリンズの魅力を一気に聴かせる隠れた名盤。(2006年11月11日) | ||
| A Night At The Village Vanguard | ||
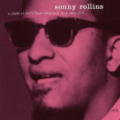 曲:★★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★☆ ロリンズ入門度:★★★★☆ 評価:★★★★☆ |
[Recording Date] 1957/11/3 [1] Old Devil Moon [2] Softly, As In A Morning Sunrise [3] Striver's Row [4] Sonnymoon For Two [5] A Night In A Tunisia [6] I Can't Get Started |
Sonny Rollins (ts) Wilbur Ware (b except [5]) Elvin Jones (ds except [5]) Donald Baily (b [5]) Pete La Roca (ds [5]) |
| 当時はまだ珍しかったと思われるピアノ・レス・トリオ編成でのライヴ。この日、昼の部は当時のロリンズのレギュラー・トリオ・メンバーであるドナルド・ベイリーとピート・ラロカで演奏。夜の部はこの録音のためのスペシャル・ユニットで、このアルバムに採用されたのは[5]を除いて夜の部となった。ピアノ・レスであることによってロリンズの野放図かつおおらかなプレイが全開、エルヴィンのプレイも瑞々しくパワフル。他のロリンズのアルバムでは味わえない、いかにもライヴらしい雰囲気がある。ここで改めてよく考えるとピアノレスのワンホーンというのはとにかくずっと1人吹きまくって魅了し続けないといけないわけで、そんな編成で通して聴いても不足感がないどころか圧倒されるばかりなのは驚異的という他ない。僕は一聴して気に入り、コンプリート盤(A Night At The Village Vanguard (Complete))を即購入。この1枚もののアルバムは中古盤屋に売ってしまった。しかし、コンプリート盤は2枚組でトータル130分もあるためになかなか気軽に聴けないこともあって本作を再度購入。ここで発見が。コンプリート盤もオリジナル盤も国内盤で購入、コンプリート盤はルディ・ヴァン・ゲルダーによるマスタリングとなっているにもかかわらず、なんとオリジナル盤の方が圧倒的に音が良い。RVGブランドも過信は禁物かもしれない。この日演奏されたのは20曲とも言われており、曲順を大幅に入れ替え、スペシャル・ユニットまで工面して製作されたこの1枚は、プロデューサーであるアルフレッド・ライオンが創り上げた「作品」である、というところに価値があると言えるでしょう。(2006年9月10日) | ||
| A Night At The Village Vanguard (Complete) | ||
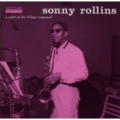 曲:★★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★ ロリンズ入門度:★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1957/11/3 Disc 1 [1] A Night In Tunisia [2] I've Got You Under My Skin [3] A Night In Tunisia [4] Softly As In A Morning Sunrise (alt take) [5] Four [6] introduction [7] Woody'n You [8] introduction [9] Old Devil Moon Disc 2 [10] What Is This Thing Called Love [11] Softly As In A Morning Sunrise [12] Sonnymoon For Two [13] I Can't Get Started [14] I'll Remember April [15] Get Happy [16] Striver's Row [17] All The Things You Are [18] Get Happy (Short Version) |
Sonny Rollins (ts) Wilbur Ware (b except [1] [2]) Elvin Jones (ds except [1] [2]) Donald Baily (b [1] [2]) Pete La Roca (ds [1] [2]) |
| 「A Night At The Village Vanguard」の完全版。この日、昼の部で5曲、夜の部で15曲が演奏されたがアルフレッド・ライオンの手によって昼の3曲と夜の1曲は廃棄された。そこから6曲を厳選して曲順を入れ替え、「作品」にしたのがブルーノート1581番の通常盤「A Night At The Village Vanguard」。このアルバムは廃棄された4曲を除いてクロノロジカルに収録されたもの。トータル130分もあるため通して聴くと疲れるけれど、この日のロリンズを骨までしゃぶりつくしたいという人には最高の記録と言えるでしょう。通常盤に収録されなかった演奏も多少ラフな感じもあるとはいえそれが却って勢いに転じている感すらある。個人的にはアナログ収録には厳しかったと思われる14分に及ぶ長尺演奏[10]に魅了される。ただし、これは僕の所有しているディスクのプレスに限ったことなのかもしれないけれど、「オリジナル・マスター・テープからルディ・ヴァン・ゲルダーによるニュー・リマスター」、しかも24ビット・リマスタリングとしていながら通常盤よりも大幅に音がコモっているのが残念。とはいえ、アルフレッド・ライオンとルディ・ヴァン・ゲルダーが、ヴィレッジ・ヴァンガードでこの日この順で曲を聴いていた、それを共有できることもまたマニアックな楽しみ方のひとつでしょう。(2006年9月10日) | ||
| East Broadway Run Down | ||
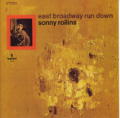 曲:★★ 演奏:★★★ ジャズ入門度:★ ロリンズ入門度:★ 評価:★☆ |
[Recording Date] 1966/5/9 [1] East Broadway Run Down [2] Blessing In Disguise [3] We Kiss In A Shadow |
Freddie Hubbard (tp [1]) Sonny Rollins (ts) Jimmy Garrison (b) Elvin Jones (ds) |
| ソニー・ロリンズの代表作は50年代に集中している。長いキャリアを誇るロリンズだけに、発表したアルバムは膨大な数に上っているのに 60年代以降はどれを聴いたら良いのだろうかと考えたときに、これといった定番がない。このアルバムはふとCDショップで目にしたもの。60年代後半という、ジャズ混迷期の録音、既に一流として確固たる地位を築いていたフレディ・ハバードにコルトレーン・グループの2人をリズム・セクションに迎えたピアノ・レス・カルテットという編成も興味深い。[1]は20分に及ぶ長尺演奏で、オーネット・コールマンかと思うようなテーマが聴こえてきて違和感たっぷり。ロリンズは本来のおおらかなソロをとりつつもフリー・ジャズ風の匂いを漂わせ、そのままハバードに引き継ぎ、それが終わるとギャリソンの長いベース・ソロとエルヴィンのドラム・ソロが入る。そこからフォー・ビートは封印、ギャリソンが同じ音で延々と単調なリズムを繰り出し、ロリンズとハバードがしつこいくらい同じフレーズを繰り返すフリー・ジャズ的な展開に。いや、これはロリンズ流のフリー・ジャズなのでしょう。ときにマウスピースだけで「ピーピー」と奇声を発するなど実に前衛的。そしてまるで似合っていない。その無理やり感がなんとも痛々しい。[2][3]はロリンズらしいおおらかなメロディのソロが聴けるとはいえ、リズム・セクションの影響かどうにも[1]の雰囲気が抜けきらず、なんとも居心地が悪い。もともと自由奔放にアドリブを取らせたら右に出るものがいないロリンズが形式にとらわれないフリージャズを演ると逆に自由さを奪われてしまって窮屈になってしまう。そんなロリンズの資質を焙り出した、そして今となっては時代に翻弄されていたロリンズの記録としての価値しか見いだせないアルバム。(2007年2月28日) | ||
| East Broadway Run Down | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★ ロリンズ入門度:★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1978/4/13-15 [1] Don't Stop The Carnival [2] Silver City [3] Autumn Nocturne [4] Camel [5] Introducing The Performance [6] Nodoby Else But Me [7] Non-Cents [8] A Child's Prayer [9] President Hayes [10] Sais |
Sonny Rollins (ts) Donald Byrd (tp & flugelhorn [6]-[10]) Mark Soskin (p, elp) Aurell Ray (g) Jerry Harris (b) Tony Williams (ds) |
| 70年代のロリンズも録音数は決して少なくなく、何を聴けば良いのかわからない状況にある。このアルバムをピックアップしたのはドラムがトニー・ウィリアムスだからという理由に尽きる。そもそも、この2人の競演盤があることすら知らなかったし、むしろもっとも相性が悪いのではないかとさえ思っていたくらいだった。[1]はロリンズがカリプソなメロディを吹き続けるところを実にイージーにトニーが合わせる。あの機械のような細かいシンバリングとは違ってラフな、しかしトニーとすぐにわかるドラムを聴くと、このドラマーはテクニックを主張するだけでなく音楽全体を考えたドラマーであることを改めて認識させてくれる。[2] はフォービートでも70年代的なサウンド。サックスの音はややドライになっていているとはいえ、ワンホーンでずっと吹き切って魅了するところは50年代と変わっていない。[3]はほとんどソロ演奏でその吹き切る印象がさらに加速。ほんの少しだけフリーキーな音が顔を覗かせるとはいえ一線は越えず、ロリンズらしさをしっかりと提示。[4]は普通のエイトビートで、エレキ・ベースのウネリとエレキ・ギターのカッティングがしっかりと入ったファンクそのもの。こういう曲だとまるでメル・コリンズ(キング・クリムゾン)のような音に聴こえ、50年代のロリンズにあった音の張りと艶が後退している感じは否めない。独特の[6]からはドナルド・バードが参加。まずはフォービート・ジャズで、トニーのあの小気味良いシンバルワークと、いつもながらどこかストイックさを伴った鮮やかなドラム・ソロが出てくる。[7]も[4]のように完全にファンクで、しかし、この種の音楽になると演奏は悪くない反面ロリンズじゃなくてもいいんじゃないかと思えてしまう。[8]のバラードもこの時代のファンク・グループがやりそうな曲と演奏。[9]はバラード調の冒頭からフォービートに突入、それでもリズム・ギターやエレキ・ベースの響きが70年代的でジャズのイメージからはやや離れる。[10] もまた完全にファンク。トニーがありきたりなファンクをやっているというのは意外と貴重かもしれない。ただし、ここで聴ける音楽がロリンズでないと得られないものか?と訊かれると、ちょっと答えに詰まってしまう。(2007年2月6日) | ||