ロック・ファンのためのジャズ案内のヘッダー
Rock Listner's Guide To Jazz Music
Joe Henderson
| Page One | ||
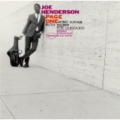 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1963/6/3 [1] Blue Bossa [2] La Mesha [3] Homestretch [4] Recorda Me [5] Jinrikisha [6] Out Of The Night |
Kenny Dorham (tp) Joe Henderson (ts) McCoy Tyner (p) Butch Warren (b) Pete La Roca (ds) |
| ジョー・ヘンダーソンの初リーダー作。ジャズ・ファンに有名な[1]は、ボサ・ノヴァ調で哀愁が漂っていて確かに分かりやすい。先発ソロを取るドーハムのトランペットが実にドーハムらしい枯れた音色とフレージングで曲のイメージを構築。続く主役はいつもの節回しでボサ・ノヴァも軽くこなすも、さほどでしゃばらず時間も短め。引き継ぐマッコイはこんなに可憐で軽快なボサ・ノヴァ調ピアノを弾けるのか、と改めて見直してしまう。ブッチ・ウォーレンの小刻みで弾力性あるベースがまたこのムードにピッタリ。[2]はマッコイの流麗なピアノが導くモーダルなバラードで、ジョー・ヘンが美しくソロを決め、ドーハムがまたドーハムにしか出せない音色で応じ、マッコイがコルトレーン・グループでの演奏でも聴けないような美しく滑らかなフレーズを繰り広げるという、すべてに聴き惚れてしまう美しさ。[3]は一転、アップテンポでスウィンギーな曲。時代相応のフレッシュな感覚のこの曲ではピート・ラロカのドラムが冴える。再びボサ・ノヴァ的リズムの[4]では、ジョー・ヘンのリラックスしつつも締まったテナー、ドーハムの枯れたトランペットのコンビネーションが素晴らしく[1]に負けない印象を残す。[5]はヒネリの効いたメロディとリズム・チェンジが印象に残る、新主流派的な演奏でジョー・ヘンらしさが良く出た、そして気負いのない演奏。最後の[6]はアート・ブレイキーの"Politely"をちょっと思い起こさせるブルース。全体を通して程よく肩の力が抜けた仕上がりで、リラックスした演奏の中にも、ただのジャム・セッションとは異なった統一感があるところはさすがブルーノートという仕上がり。(2007年1月8日) | ||
| Our Thing | ||
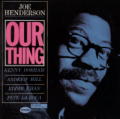 曲:★★★★☆ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1963/9/9 [1] Teeter Totter [2] Pedro's Time [3] Our Thing [4] Back Road [5] Escapade |
Kenny Dorham (tp) Joe Henderson (ts) Andrew Hill (p) Eddie Khan (b) Pete La Roca (ds) |
| このアルバムもジョー・ヘンダーソンとケニー・ドーハムの双頭コンボと言える内容で、実際、ジョー・ヘンのオリジナルが2曲、ドーハムのオリジナルが3曲という構成になっている。比較的オーソドックスなプレイをしているジョー・ヘンもいいし、サイド・メンという立場をわきまえつつもドーハムのトランペットの存在感は主役に匹敵している。この2人の組み合わといえば"Blue Bossa"が入っている「Page One」があまりにも有名。では、このアルバムがその有名盤に劣るかといえばまったくそんなことはなく、質的には同等以上ともいえる充実ぶり。リズム・セクションも60年代的なメンツで、特にアンドリュー・ヒルの参加がオリジナリティの演出に一役買っていることは間違いない。ヒルにしては普通に弾いている部類とはいえ、その異能ぶりが隠しきれるはずもなく、それゆえに「Page One」のような親しみやすさがないところが、両者の人気の差になっているように見える。一方で、それを個性として受け止めることができれば、オリジナリティ溢れ、質の高い60年代ジャズとして楽しめるに違いない。(2009年7月4日) | ||
| In 'N Out | ||
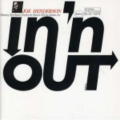 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★★★★ 評価:★★★★☆ |
[Recording Date] 1964/4/10 [1] In 'N Out [2] Punjab [3] Serenity [4] Short Story [5] Brown's Town [6] In 'N Out (alt take) |
Kenny Dorham (tp) Joe Henderson (ts) McCoy Tyner (p) Richard Davis (b) Elvin Jones (ds) |
| ジャズをかじった人なら誰でも知っている強面のリズムセクションを従えて、ドーハム+ヘンダーソンの黄金コンビがこれに応じる。この組み合わせ、ありそうで意外とないもので特にケニー・ドーハムとエルヴィン・ジョーンズの競演というのは珍しい。さて、肝心の内容はジョー・ヘンダーソン作3曲にドーハム作が2曲という構成で、新主流派的匂いが漂う瑞々しい演奏が印象的。ジョー・ヘンはボサノヴァから前衛的なものまで幅広くこなした実力者ではあるけれど、このくらいのスタイルのジャズだとアクが抜けたコルトレーン的なテナーが映えていてちょうど良い。相性バッチリのドーハムもここではフレッシュで緊張感溢れるプレイで応えていてこれがまた実にいい。リチャード・デイヴィスのベースは彼にしては攻撃的な図太さは控えめであるものの上に下に躍動しながら柔軟にフォービートを刻み、エルヴィンは手数の多い小刻みなビート感を前面に出しながらも、どちらかといえば軽快さを打ち出した重過ぎないちょうど良い加減のプレイ。マッコイはまあ、いつもどおり。ハードバップの次世代のジャズであることは明確で60年代中盤のジャズに親しむには絶好の1枚。全体のフィーリングは似たような感じとはいえ、ワン・ホーンの「Inner Urge」よりもコンボとしてオーソドックスなバランスを持つところが本作の良さ。それでいて演奏者の個性もしっかり出ているところはやはり一流ジャズ・メンが揃っているからでしょう。(2007年4月21日) | ||
| Inner Urge | ||
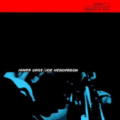 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★★★ 評価:★★★★☆ |
[Recording Date] 1964/11/30 [1] Inner Urge [2] Isotope [3] El Barrio [4] You Know I Care [5] Night And Day |
Joe Henderson (ts) McCoy Tyner (p) Bob Crashaw (b) Elvin Jones (ds) |
| 僕にとってジョー・ヘンダーソンは不可解なサックス・プレイヤー。いわゆる新主流派、あるいはコルトレーン派に位置づけられ、フリーキーなトーンまで操っておきながら意外なほど胃もたれしないアッサリ感があり、「Mode For Joe」やアンドリュー・ヒルの「Point Of Departure」のような実験的、前衛的な要素を持つアルバムでは思ったほど存在感を出すことができない。新主流派の一員かと思えば、どちらかと言えば保守派に属するケニー・ドーハムをパートナーにデビュー(「Page One」)していたりしてどうにも実態が掴みづらい。このアルバムでは、マッコイとエルヴィンを迎え[1]からコルトレーン派と感じさせる演奏を聴かせる(もっとも64年のコルトレーンはもっと先に行ってたけれど)。ユーモアを感じさせる捻ったテーマの[2]は演奏がやや平凡、[3]はくぐもったテナーの音色、曲調、アドリブも含めてかなりコルトレーン的。ここまでが自作曲。後半は、デューク・ピアソンの[4]でバラード・プレイも抜かりなく披露、最後は超有名スタンダードで軽快かつ躍動的に締める。というようになかなかバラエティに富んでいて飽きさせない内容。掴みどころのないジョー・ヘンなら、散漫なものになっても良さそうなものだけれども、統一感があり、それはマッコイの流麗なピアノとエルヴィンのグルーヴィーなドラムの下支えによってもたらされている。それに煽られてか、ジョー・ヘンのプレイも伸び伸びとしていて全体に活気のある仕上がりになっているのが本作の良さ。一般的に代表作は「Page One」ということになっているし、ドーハムとのコンビがハマっているのも事実ではあるけれど、ワン・ホーンで伸び伸びと吹き切るこのアルバムはテナー奏者としてのジョー・ヘンらしさが滲み出ていると思う。(2006年11月14日) | ||
| Mode For Joe | ||
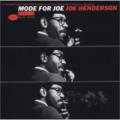 曲:★★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1966/1/27 [1] A Shade Of Jade [2] Mode For Joe [3] Black [4] Caribbean Fire Dance [5] Granted [6] Free Wheelin' [7] Black (alt take) |
Lee Morgan (tp) Joe Henderson (ts) Curtis Fuller (tb) Bobby Hatcherson (vib) Ceder Walton (p) Ron Carter (b) Joe Chambers (ds) |
| ヴァイブ入りの3管にピアノまで入っている編成というのは意外と珍しいもので、この編成と豪華メンバーをどう生かしたものにするのか、どうまとめあげるかに興味が湧く。しかし、懸念が的中したというべきか、この編成だからこそできた音楽という次元までには至っていない。ソロを取るメンバーが多すぎてやや散漫な印象を与えるのも事実でジョー・ヘンダーソンの存在感も薄く、むしろ彼がサイド・メンバーとして参加したものの方が持ち味が出ているんじゃないかと思えるほど。とはいえ、これだけのメンバーを揃えて60年代のフレッシュなジャズを演奏するとなれば演奏の質じたいは悪くはなく、それなりに聴きどころはある。中でもクールに決めるハッチャーソン、そしてシダー・ウォルトンが印象的。モーガンは出番が少ないながら、ここぞというところでブリリアント。不思議なムードを持つ[4]はクセがあるけれど、モーガン、フラー、ハッチャーソン、チェンバースが持ち味を出していて本作のベスト・トラック。(2006年11月5日) | ||
| The Kicker | ||
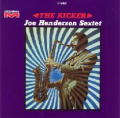 曲:★★★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1967/8/20 [1] Mamacita [2] The Kicker [3] Chelsea Bridge [4] If [5] Nardis [6] Without A Song [7] O Amor Em Paz [8] Mo'Joe |
Mike Lawrence (tp) Joe Henderson (ts) Grachan Moncur III (tb) Kenny Barron (p) Ron Carter (b) Louis Hayes (ds) |
| ブルーノートを離れてからのアルバムの中では人気盤の本作は、トランペットとトロンボーンも従えたセクステット編成([7]のみカルテット)。ジャズ・ロックなエイトビートのリズムで軽快に始まるのはこの時代の王道パターン。スピーディな[2]、しっとりとしたバラードの[3]へと続くバラエティに富んだ曲調、ハーモニーとアレンジで一気に聴かせる。演奏は標準的で緊張感と緩い部分が程よい塩梅。ルイ・ヘイズの前ノリなドラムが全体の印象に影響を与え、オーソドックスなロン・カーターのベースがまた軽妙。曲は長くても6分未満ということもあって、アッサリしていてインパクトには欠ける。アクやクセを求める向きには物足りないと思われ、言い換えるとジョー・ヘンダーソンは決して暑苦しくならないことがここでもよく分かる。完成度や聴き応えは、残念ながらブルーノート時代には及ばない。(2009年12月31日) | ||
| At The Lighthouse | ||
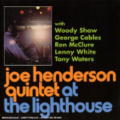 曲:★★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★☆ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1970/9/24-26 [1] Caribbean Fire Dance [2] Recorda-Me [3] A Shade Of Jade [4] Isotope [5] 'Round Midnight [6] Mode For Joe [7] Invitation [8] If You're Not Part Of Solution, ou're Part Of The Problem [9] Blue Bossa [10] Closing Theme |
Woody Shaw (tp, flugelhorn) Joe Henderson (ts) George Cables (elp) Ron McClure (b, elb [8]) Lenny White (ds) Tony Waters (conga [1] [8] [9]) |
| ライヴ録音ということもあって熱気に溢れた演奏で完成度よりもそんな荒削りなムードを楽しむアルバム。曲はジョー・ヘンダーソンの代表曲に有名スタンダードという構成でジョー・ヘンのファンには馴染みやすい。レニー・ホワイトのロック・テイストを内包したジャズ・ドラムとジョージ・ケイブルズのエレピ、ロン・マクルーアの高音域を多用したビジーなベースがいかにも70年代的カッコよさを発散していて、有名曲が過去の録音とは違った味で演奏されているところが聴きどころ。もちろん、そんなムードの中で自在にブロウするジョー・ヘンのプレイは実にカッコいい。テクニカルに吹きまくり、あるいは少々フレーズのまとまりに欠けるとも言えるウッディ・ショウのプレイは好みが分かれるかも。個人的には70年代のジャズのムードはどういうわけかあまり肌に合わないので、決して愛聴盤というわけではないんだけれどスカッとした熱い演奏を楽しみたいときに聴きたくなる1枚。(2011年8月28日 | ||
