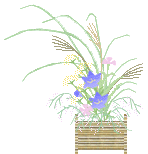
Message for you
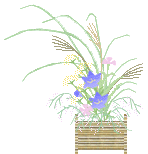
| 長月9月・・・ 秋の七草をすらすらっと言えたらすごいなあ、と思ったりするのですが・・・ 私の場合「萩、桔梗、おみなえし、後はえーと・・・(^^;」と言うところです(笑) 当然のごとく、春の七草にしても「せり、なずな、すずな、すずしろ・・・・・・(^^;」、お粗末(笑) せっかくの秋だから、秋の七草を調べてみました。 ハギ・オバナ・クズ・ナデシコ・オミナエシ・フジバカマ・キキョウ・・・続けて言うと、呪文のようですが(笑) 漢字に直すと、萩・尾花(すすき)・葛・撫子・女郎花・藤袴・桔梗。 春の七草が、いかにも素朴な野の草と言う雰囲気なのに比べ、秋の七草は、草と呼ぶにはかなり鮮やかな・・・むしろ見て楽しむことのできる花ですよね。 色合いからしても、赤紫のこぼれるような花がなんとも風情ある萩、銀色に変わる穂が美しいススキ、可憐なピンク色の撫子、濃紫が清楚な桔梗、などなど・・・ まさに、秋を彩るにふさわしい花が並んでいるようです。 でも、どうやらそれだけではないらしい。 秋の七草は、すべて薬草となるのだそうです。 おみなえしや桔梗は、なんとなく薬効がありそうだなあと思ってはいましたが。 葛と言えば葛湯? 美味しいだけでなく、そう言えば風邪の時などによく飲むなあと思っていたら、どうやら風邪のひきはじめに効果があるらしいし。他の花もそれぞれに薬効があるそうです。 秋の七草は、万葉集の中で山上憶良が詠んだ二首の歌から来ていると聞きます。 「秋の野に咲きたる花を 指折りかき数ふれば 七種の花」 「萩の花 尾花葛花なでしこの花 女郎花また藤袴朝顔の花」 この朝顔の花と言うのは、どうやら桔梗のことらしい。と言うことは、源氏物語に登場する「朝顔の斎院」も、実際には「桔梗の斎院」と言うことになるのでしょうか。イメージとしては、桔梗の方が確かに合っていますけど。 おっと、話しがずれました(^^; 万葉の時代には、若菜摘みや薬狩りなど、大勢で野に出ては、若菜や薬草を摘む行事があったそうで、それだけ野の草や花にみんな詳しく、生活に役立てていたのでしょうね。 空気が澄んでくるこの季節、秋の七草を訪ねるささやかな旅、なんてしてみたいなあと思いつつ・・・ ※秋の七草については、サイト「身近な野草」さんで調べさせていただきました。 平成15年9月1日 |
涼 |
| 2000年 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 11月 | 12月 | |||||
| 2001年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2002年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2003年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | |||||
 トップ |