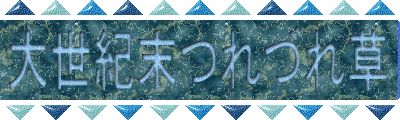
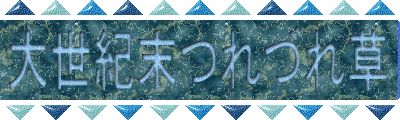
00年7月−12月のバックナンバー
メニューにジャンプ
2000年12月
<20世紀最後の日に思う、古いものが滅びた中からの新たな再生>
ついに20世紀の最後の日を迎えました。巨大で偉大で輝かしくも残酷非道極まりなかった100年。そして今となっては懐かしく、いとおしい気持ちさえする20世紀が、ここに幕を閉じるのです。
この日を迎えて、「死と再生」という宇宙の摂理を思い浮かべます。何ごとであれ、どんなレベルの事象であれ、ある新しい段階が生じるためには、それまでの状態の「死」ないしは「崩壊」が絶対的に必要だということです。
これは、弁証法で「量から質への転化」などと言うよりももっとシビアで容赦なく、前段階そのものの残照も残滓も許さないほど過酷な法則といっていいでしょう。
最も普通に見られる現象で、この法則を物語っているのは、夜空に輝く無数の星々です。これらの大多数の星は、いったん死を迎えて大爆発を起こした前世代の星たちの残骸から生まれて、新たな星となったものです。
宇宙誕生直後に出来たガスが集まって生じた第1世代の星たちは、水素から始めて気の遠くなるような核融合の結果、しだいしだいに重い元素を作り出しては内部に蓄えていきます。そして寿命を終えて大爆発を起こし、それまで何十億年もかかって作り出した数々の重い元素を宇宙空間に飛散させます。それらの星の残骸が集まって次なる星が出来た時、初めて重い元素をたっぷり含んだ惑星を持つことが出来ます。この段階でようやく、生命誕生の可能性を持つ「場」が作られるわけです。
最近の出来事では、6500万年前の恐竜の突然の滅亡です。それまで、隠れるように生息していた哺乳類が、恐竜滅亡とともに一気に発展し進化していきます。人類の誕生は、恐竜の滅亡なしにはあり得ませんでした。
文明でも強大国家でも、古いものがドラマチックに滅びた中から、次なる新たな文明、新たな国家が生まれてきています。
明日からはいよいよ21世紀。21世紀の新しい文明が生まれるためには、20世紀的な古いパラダイムは死ななければならないのだと思います。20世紀にしがみついている限り、人類は新たなるステージに上がれない。その重大時点に差し掛かっているのだという厳粛な思いを胸に、いま20世紀に別れを告げようと思います。(12月31日)
<ロボットの「ASIMO」がNHK「紅白」登場、やがて歌手として出場か>
あと4つ寝るとお正月どころか21世紀、というわけで、たいがいのことには驚かなくなっているのですが、それでもウッソー?と声を上げたくなるニュースがあります。本田技研が開発した人間型ロボット「ASIMO」が、なんと今年大晦日のNHK「紅白」に出場する見通しだというのです。
紅白では歌の合間に、その年に話題を呼んだり人気沸騰の芸能人やタレントが、アトラクションやパフォーマンスを繰り広げたり、コントを演じたりするのが呼び物となっていますが、ロボットの「ASIMO」もこうしたタレント並みの扱いで、自分でステージに出てくるそうです。実現すれば、もはや小林幸子の衣装どころではなく、今年の紅白の最大の見せ場となって、視聴率アップにも貢献しそうです。
「ASIMO」は二足歩行をスムーズにこなす上に、ひざやひじの関節が柔らかく、パラパラを踊るほどですから、ひょっとしてステージでダンスくらい披露するのかも知れません。「ASIMO」は白組、赤組どっちの応援として登場するのでしょうか。「ASIMO」は男なのか女なのか区別されてないようなので、どちらかの肩入れではなく、紅白そのものの盛り上げをはかるのでしょう。
せっかく登場するのですから、クボジュンに花束を渡してキスの一つもすれば面白そうです。さらに、審査員席の長嶋監督のところに行って握手をしたりサインをねだったりすれば、最高に盛り上がることでしょう。
もっとも持ち時間を超えても退場しないで、延々とパフォーマンスを続けたりして制御不能になるのも、NHKとしてはハラハラもの。総合司会の宮本隆二アナが連れて戻すのかどうか、まあそれはそれで、21世紀入り目前にふさわしいハプニングとなるでしょう。
今回は、ロボットの初登場だけで話題になっていますが、あと2、3年もすれば、「ASIMO」の後継機種で歌を歌う新種が登場するかも知れません。ロボットの歌う歌が爆発的にヒットすれば、こんどはロボットが紅白の出場歌手に選ばれることだってあるでしょう。
それも当たり前になって、やがてはロボットが紅白の審査員席に登場したり、いずれは司会をする日がくるかも知れません。さらに進むと、ロボットがNHK会長に就任する日がこないでもないとか。海老沢さん、ホントですか?(12月28日)
<「バトル・ロワイヤル」の清清しいバイオレンス、圧巻は女子にあり>
話題騒然の映画「バトル・ロワイヤル」を観てきました。もう最初から最後までスクリーンに釘付けとなり、近年こんなに感動した日本映画はありません。中学生同士の殺し合いと、強烈なバイオレンスの連続が、これほど新鮮で心を強く揺り動かし、魂を揺さぶるものだとは、正直言って、映画を見るまでは夢にも考えませんでした。
ボクはまず、映画冒頭で淡々と語られる背景説明のリアルさに、強い衝撃を受けました。
「新世紀の始め、ひとつの国が壊れた。完全失業率15%、失業者1000万人、全国の不登校児童・生徒80万人。自信をなくした大人たちは、深刻化する崩壊に歯止めをかけるため、ある法案を制定した…」。それがBR法。正式名を新世紀教育改革法。
この設定が荒唐無稽とは感じられないのは、現代日本の少年少女たちの置かれた状況を、これほど見事に凝縮し、的確に暗喩したメッセージはないからだと思います。
和気藹々の修学旅行のバスから一転して、クラス仲間を殺していかなければ自分が殺される、という不条理。戦いは3日間。周囲は自衛隊が監視していて、逃げることは不可能。どんな優等生もツッパリもワルも、キビキビと状況を把握しながら殺し合いに参加せざるを得ません。教官のビートたけしが憎たらしいほどのハマリ役です。
この映画には、血しぶきが飛んだり首が転がったりするシーンがあるにもかかわらず、ホラー映画や残酷映画とは異なって、生き生きした生命の躍動に溢れているのは、極限状況に置かれた42人の中学生たちが、ほとんど生き残る見込みがない中で、必死になってお互いに殺し合いを繰り広げる、そのひたむきさと清清しさにあるのだと思います。
そして、この映画の最大の面白さは、女の子たちの殺し合いの輝くような素晴らしさです。映画の中での男子同士の殺し合いは、なんとなく乗っていないような感じがします。しかし女子が男子を殺す、逆に男子が女子を殺す、さらに女子同士が殺しあう。それらのシーンは、ロリロリの制服のまま一切の容赦なく繰り広げられるため、その迫力と生々しさには、エクスタシーを感じるほどです。
演技なのか地なのか、ものごとに本気で立ち向かうのは、やはり女の子の方なのですね。(12月25日)
<21世紀の早い段階で、ロボットと人間が共生する社会が出現へ>
21世紀にはどんな夢が実現していくのか。さまざまな未来予測が試みられていますが、100年前とは打って変わって、いまは技術進歩の早さについて行くだけで精一杯で、予測できるとしてもせいぜい10年先か20年先が限界のようです。もはや未来予測が不可能となったということこそが、いまの時代の大きな特徴だといっていいでしょう。
とはいえ、未来の方向を探るための技術の萌芽は、あちこちに出始めています。ボクたちは、いまの段階で掴み得るこれらの手がかりから、推理小説を紐解くように、未来の姿を思い浮かべてみるしかありません。
近未来でボクたちの社会を最もラディカルに変えていくのは、ロボットでしょう。ロボットというと、ソニーの「アイボ」のようなハイテクおもちゃ、というイメージの人も多いようです。
しかし、ロボットは大方の予想をはるかに超える速度で、21世紀明けとともに急激に進化し、大化けしていく公算が大きいと言えます。ロボットはパソコンを上回る基幹産業に発展し、完全自動運転の車以上に21世紀社会の牽引役となる可能性があります。ロボットは人間の敵という意識が強い欧米と異なり、人間型ロボットはいまのところ日本の独壇場です。あらゆる生き物や自然を、人間と対等に見てきた日本の風土や、さらに言えば「鉄腕アトム」の影響も大きいでしょう。
鉄腕アトムが誕生したのは、2003年という設定です。本田技研はこのほど、社長直轄の「ヒューマノイド企画室」を設置して、人間型ロボットを21世紀の主力事業に育てるため、社を上げて動き出しました。2001年秋には、同社が開発した「ASIMO」のリースが始まります。
あと5年か10年もすれば、社会のあちこちで、イベントや介護に、事故現場にと、さまざまな分野で活躍するロボットの姿が見られるようになるでしょう。オフィスや家庭に、ロボットが入ってくるようになるのは、15年か20年先でしょうか。
ロボットと人間が共生するためのルールづくりや法律の整備も必要となるでしょう。ロボットを使った犯罪をどう防ぐか、など困難な問題も出てきます。21世紀の最初の20年間を特徴づけるのは、間違いなく、ロボットの人間社会入りでしょう。(12月22日)
<新メディアのチャンネルは増加する一方で、個人の時間は有限>
BSデジタルテレビがスタートして20日近くになりますが、どのようなコンテンツがどのように見られ利用されているのか、BSと無関係な生活をしている者にはトンと分かりません。不思議に思うのは、BSデジタルとしてスタートした8つのチャンネルそれぞれが、画質の良さだけでなく、放送している画面と連動した情報検索や、視聴者との双方向性を織り込むなど、デジタルの特性を生かした番組を常に流しているのだろうか、という点です。
制作者側がそれなりに奮闘しているとしても、すでにあるBSアナログテレビや、CSテレビ、さらにはCATV、それどころか国民生活にどっぷりと根付いている地上波テレビといった電波メディア乱立の中で、それぞれがコスト的にペイしているのだろうかと、心配にもなってきます。
視聴者はテレビだけを見て生きているわけではありません。同じ電波でラジオもあるし、パソコンをいじったりインターネットもやっているでしょう。新聞や雑誌も読むし、たまには映画館にも足を運びます。ケータイも使うし、CDやMDも聴きます。本も読むし、お芝居やコンサートにだって行くでしょう。さらに休みの日には、レジャーにも行くし、スポーツもやる。趣味に没頭する時間もあれば、旅行もするし、温泉にもつかる。親しい者同士で食事会を持ったり、社会活動にも参加するでしょう。そのための移動で、交通機関に乗っている時間も必要です。
そんなに、何もかもする時間って、人間にあるのでしょうか。つまりは、一人の人間が使うことが出来る1日の時間は、有限であり、しかも極めて少ない、という事実こそ、いま認識する必要があるのではないでしょうか。
BSデジタルテレビを見ようとすれば、それまでの生活の中から、何かを削らない限り、時間は生じてきないのです。同様に、新しい情報メディアやIT端末を使いこなすためには、やはり何かに使っていた時間を削らなければなりません。
こうして、いま削られている時間は、古典と言われる名作・名著の読書であり、CD鑑賞であり、映画館であり、ゴルフであり、スキーであり、公営ギャンブルなのです。電波メディアの中での、時間の共食いも熾烈になっていくことでしょう。
それでもなお、一人の個人にとって、大氾濫する新メディアを享受しつくす時間は、絶対的に足りないのです。
時間のパイは限られている、という動かしがたい事実をどうするのか。21世紀の情報通信革命の最大の問題は、人間が持つ時間の有限性という、極めてアナログなところに帰着しそうな気がします。(12月19日)
<「くるみ割り人形」の中で、1カ所だけ合唱が使われている場面>
チャイコフスキーの「くるみ割り人形」は、「忠臣蔵」や「第九」とともに12月の定番ステージとされています。
ボクは中学校のころから、何回となくこの音楽を聴いてきましたが、この中で1カ所だけ合唱が使われていることを知ったのは、最近のことです。テレビでバレエとともに演奏される全曲を初めて聴いて、雪がキラキラと舞い落ちる幻想的なシーンで、組曲にはない綺麗なメロディーとともに、歌詞のない合唱が流れてきたのには、驚くとともに身震いするような感銘を受けました。
この場面は「雪のワルツ」と呼ばれるところで、少女クララが「くるみ割り人形」から変身した王子と対面し、雪の精たちの踊りと入れ替わりながら二人で踊るシーンです。チャイコフスキーはこのバレエ曲を作るにあたって、最初に書いたのがこの合唱の入った曲で、いかにこの場面が重要なポイントであるかを示しているように思います。
「くるみ割り人形」の底に流れるモティーフは、少女の成長であることはよく知られており、ある意味では「魔女の宅急便」にも共通する少女から大人への通過儀礼の物語とも言えます。クララがおじさんからもらった「くるみ割り人形」を抱いて寝ているうちにいつしか夢を見て、人形が王子となってクララを雪の林からお菓子の国へ連れていく、という筋書きには少女の性的な目覚めが底流にあるのでしょう。
この合唱部分は24人の児童合唱か女声合唱ということになっていて、声変わりのした男声は入れないのです。そのことを見ても、ここはクララが精神的にも身体的にも、おとなの女へと飛躍していく過程を象徴しているように思います。
その歌声は、大人になっていくクララが幼い自分と別れる歌であり、やがて経験しなければならない王子との別れの予感でもあります。「花のワルツ」とその後に続くフィナーレでは、クララはもうすっかり成長していて、王子と別れることによってのみ、自分が真におとなになっていくことも理解しているのでしょう。古いものを乗り越えて、新しいものが生まれる。別れによって、成長する。「くるみ割り人形」の大きな魅力は、こうした永遠の真理が美しい旋律とともに流れていることにあるのだと思います。(12月16日)
<4時間ほど都市ガスが止まってパニック、まるで1年遅れのミニY2K>
1年前の今ごろは、Y2Kなどという得体の知れない言葉が飛び交う中、2000年問題への自衛策として、備蓄の食糧や石油ストーブを購入したりと、後から思えば滑稽とも言える騒ぎに右往左往したものです。
そんなことがあったことさえ忘れかけていた今日、ガス設備の法定点検ということで、昼過ぎからガス会社の担当者が、マンションの各部屋を訪れて、ガス器具は正常か、不完全燃焼を起こしててないか、などをセンサーのようなものを持ってチェックして回りました。
その結果、各部屋には異常がなかったものの、なんと道路の元栓からマンションの元栓への途中で、かなりの量のガス漏れが起きていることが分かって、全世帯のガスの使用に待ったがかけられてしまいました。問題の箇所は、玄関ホールの地下を通っているパイプらしく、ガス会社から修理班が駆けつけて、対応にあたったのですが、4時間を過ぎ、外は暗くなるというのに、ガスは出ないまま。
うちの主力暖房は電気ではなくガスストーブのため、こうなるとお手上げです。深々と冷え込みが強まる中、いまかいまかと回復を待ちつづけるうちに、こんどはいつも昼前に行っているエレベーターの定期点検が今月に限ってこの日の夕方に行われ、ガスは出ないわエレベーターは動かないわで、まるで1年遅れでやってきたミニ2000年問題といった感じです。
ガスが出ないということは、考えてみれば、キッチンのガスレンジが使えない、給湯システムが使えないためお湯が出せない、など単にストーブだけの問題ではないということにも、改めて気付いて愕然です。ちょっとお湯が欲しいという時には、電子レンジだけではなんとも使いにくいものだということもよく分かりました。
どの家でも困り果てたとみえて、午後6時前にとりあえず各家のガスは使ってもいいということになり、ガス漏れについては応急的な対策を講じた上で、引き続き根本的な修理を続けるということのようです。
IT革命が叫ばれる時代であっても、ライフラインのほとんどは道路下に埋められたパイプを伝わって各家に配給されているという、極めてアナログな土木工事的仕組みになっているのですね。21世紀には、パイプや電線を使わず、パイプレス、コードレスで各家にライフラインや情報、さらには生活必需品を配給するシステムが、きっと実現することでしょう。(12月13日)
<いつの時代の文明だって最先端、現在も100年後には古くて野蛮に>
いつの時代の人々も、自分たちがいま生きている時代こそが、最先端の文明であると信じてその時代を生きてきたことでしょう。この時代が後の世のもっと文明が進んだ時代から見たら、おかしくなるほど古くて未開の時代として語られることなど、考えたりはしないでしょう。100年前も、500年前も、2000年前も、5000年前も、石器時代でさえも、前期旧石器時代であっても、その時の文明は時代の最先端だったのです。
ボクたちは現在、このところのテクノロジーの急激な発展に目を奪われ、今こそ歴史上かつてない技術文明の開花を迎えつつあるのだ、と思っています。しかしそれでさえ、現代という時代に生きるボクたちの錯覚であり、奢りに過ぎない、とボクは思うのです。
21世紀末の人々が、20世紀末のボクたちの社会や生活を見聞きした時、どんな風に思うでしょうか。それはボクたちが今、100年前の社会や人々の暮らしを見て思うことと、基本的には同じだろうと思うのです。それは「何と古臭く、不便で、野蛮で、未開だったのだろう」ということです。
もしかしたら、ボクたちが100年前の社会を「古い」と思う以上に、100年後の人たちはボクたちの社会を「古過ぎる」と感じるかも知れません。20世紀の100年間の流れにもまして、21世紀の100年間の流れは激しい急流になることが予想されるからです。
100年後の人たちが、ボクたちの社会を見て、真っ先に感じるだろうことは、家屋や建物のあまりの貧弱さと乱雑さ、非機能性でしょう。「20世紀末の人たちは、よくこんなところに住んでいたものだ」と感心することでしょう。
次に驚くであろうことは、狭くてごちゃごちゃした道路を、人間が手でハンドル操作をしたり足で加速減速しながら、自動車を走らせていたことです。「こんな危険なことが、日常的に行われていたなんて」と絶句するに違いありません。
紙の新聞が、人の手で毎朝毎晩、各家に配達されていたことも、驚きものでしょう。テレビやパソコンが、大きな箱型なのも、100年後の人たちにとっては、レトロ過ぎて笑えないほどの驚きでしょう。
そして、1990年の人たちが現在のインターネット文明を想像出来なかったのと同様に、いまのボクたちが全く想像も出来ない無数の新しい「文明の利器」が社会や家庭に入り込んでいるでしょう。
「100年前の人たちって、○○も△△も▽▽も、見たことも聞いたこともなかったんだねえ」と、21世紀末の子供たちが驚きの歓声を上げることを、ボクたちは覚悟しておきましょう。(12月10日)
<戦後20世紀の転換点、1968年という時代が生んだ3億円事件>
20世紀を大きく前後に分ける分水嶺は、第二次世界大戦と太平洋戦争の終結の年、1945年であることに、ほぼ異存はないところでしょう。それでは、終戦以降のいわば「戦後20世紀」をさらに分けるとしたら、どこが区切りの年になるでしょうか。人それぞれにさまざまな分けかたが出来ると思いますが、ボクは1968年を転換の年と捉えたいと考えます。
1968年。それは戦後カルチャー、戦後パラダイムが世界的に大きな曲がり角を迎え、ベトナム戦争の泥沼化によるアメリカの焦燥、各国で高まるステューデント・パワーと学園紛争の嵐、ヒッピー文化の台頭、などが世相を賑わす中で、戦後を支えてきた価値観が大きく変貌する年です。アラン・ケイがパーソナル・コンピューターを構想したのがこの年。日本では東大・安田講堂の封鎖が始まりました。キューブリック監督の『2001年宇宙の旅』が作られたのもこの年のことでした。
もう一つ、この年の出来事で20世紀史に残る事件は、12月10日に発生した「3億円事件」でしょう。この3億円という金額は、現在ならば50億円ほどに相当し、一人も殺傷することなしに成し遂げられた驚きの「完全犯罪」として国民の度肝を抜きました。この事件は今日まで、小説や映画、テレビドラマになり、ますます人々を捉えて離さないものを秘めています。
おそらくは、この「3億円事件」もまた、1968年という時代の転換点が生んだ特異事件であり、時代を抜きに語ることは出来ないでしょう。
この事件は、燃え広がる学園紛争を沈静化するために、警察が仕組んだ大芝居であり、最大の狙いは多摩地区の活動家を徹底的に洗い出すアパートローラー作戦にあった、という見方も当時は根強く出されていました。
しかしボクは、この事件を起こしたのは、やはり個人であり、それも単独犯だろうと今でも思っています。目的は決してカネではなく、この事件そのものがメッセージだったのだと思います。いわば「時代」を共犯者に引き込んで、警察、企業、カネ、マスコミなど、「戦後20世紀」の権威を徹底的に嘲笑し、翻弄することによって成立したメッセージだったのでしょう。
20世紀が終焉を迎える今、3億円犯人はどこでどうしているでしょうか。孫たちに囲まれた好々爺になっていて、32年前の新聞スクラップをそっと取り出しては、密かにあの時代を慈しんでいるかも知れません。(12月7日)
<水かけチョンマゲ議員は格好の話題、いっそ国会での水まきは自由に>
人間には建前と本音があり、表と裏があるものです。衆院本会議で内閣不信任案をめぐる討論中に、野党のヤジにぶちきれて演壇からコップの水をぶちまけた松浪健四郎議員の行為については、誰もが表向きは「ケシカラン」と言うほかはなく、松浪議員は懲罰委員会で登院停止処分まで受けました。
ところが、カトちゃんの超ドッチラケ・インポ反乱劇でうっぷんの持って行き所のない国民には、テレビで繰り返し放映された松浪議員の水ぶっかけシーンは、そのチョンマゲ頭とともに驚くほど新鮮に映ったらしく、その後も何かにつけて格好の話題となっています。
森総理が「気持ちは理解できる」と発言したのは論外としても、さる大学の先生が新聞に「だいたい最近は講義でも会議でも、人の話を聞かない風潮がはびこっている。コップ1杯では足りないくらいだ」と、ヤジに対する水かけ擁護論を展開すれば、新聞の4コマ漫画では、アサッテ君が「アタマにくる一言へのとっさの対応術」という本を引き合いに出して、テレビの水かけシーンを見ながら「まさにこれを実践したわけだ」とニヤニヤするなど、結局のところ国民はみな、国会での水かけが面白くてたまらないのですね。
週刊誌になるともっと凄い。今日発売の週刊誌は、「今度はバケツだ! 水かけ松浪健四郎が吠えた」の大見出しによる特集をトップに持ってきて、「腰抜け野党よ、かかってこい!」というサブ見出しまで付いています。
確かに、国会での水かけは面白い、とボクも思います。いっそのこと、国会規則を改定して、衆議院本会議では与野党とも、水をかけることを合法化したらどうでしょうか。ただし、水道水またはミネラルウォーターに限る、という一文を入れておきましょう。
首相の施政方針演説や閣僚の答弁に対して、議員席からは水をかけ放題。演壇に近づいてコップからかけるもよし、水鉄砲で飛ばすのもよし。これに対し、演壇から水をまくのも自由です。議会事務局が演壇横にバケツの水を用意しておきますから、バケツでザーッとと一気にぶちまけることも出来ます。
野党が組んで、本会議場の消火栓にホースをつなぎ、豪快に閣僚席や与党席に放水をぶちかますのもいいでしょう。これに対し、政府・与党の側が放水車を国会に横付けにし、堂々と対抗の放水をかますのもいいでしょう。
かわいそうなのは、速記席の速記嬢ですが、最初から水着かウェットスーツ着用で座ってもらいましょう。
本会議場の床が抜けるくらいに水をかけあったら、議長がころあいを見て散会を宣言します。間違えて「本日はこれにて散水します」と言わないことですね。(12月4日)
<20世紀最後の1カ月、この師走から21世紀への序奏が始まる>
いよいよカレンダーが最後の1枚となりました。毎年この時期、11月の暦を切り取って、残る12月の1枚だけになると、1年を振り返って感慨ひとしおになりますが、今年は単に1年の最後の月にとどまらず、20世紀最後の月なのですね。
いったい幾度、ボクはこうして師走を迎えたことでしょうか。子供の頃から、学生時代を経て、大人になって、そうしていつも慌しく迎える師走は、その年のほろ苦い記憶をバウムクーヘンのように、新たな層として重ねる支度を整えているかのようです。
そうやって、幾多の層が重層的に積み上げられた人生の記憶たちは、もはや下の方の古いものは形が崩れたり、ぼやけたりして、混沌とした状態になっていて、たいていは時系列を無視して勝手に上の方に浮かび出てきたり、重く下の方に沈んでいったり、不規則な対流現象を起こしています。だから、いったん過去になってしまったものは、記憶として等価であって、時間の後先があまり意味を持たなくなるのでしょう。
それにしても、これらの記憶の層に共通するのは、それが全て20世紀のことだということ、言い換えれば、ボクは20世紀以外の世紀を一度たりとも経験したことがないということです。あたり前かも知れませんが、99%の人たちにとってもそれは同じで、19世紀を経験したことのある人は、現在100歳を越える僅かな人たちだけです。18世紀を経験したことのある人は、地球に一人も存在しません。
だからこそ、あと1カ月後に、20世紀とは異なる次の新しい世紀に踏み入れることは、地球に生を受けたからといって誰でも経験できるわけでない、貴重な巡りあわせと言えるのです。
師走は、突風のように過ぎ去っていくことでしょう。時間は待ってはくれません。人それぞれに20世紀の反省や後悔、慙愧が山のようにあることでしょう。残り1カ月は、21世紀の踏み出しに向けた助走の時でもあり、あるいは開幕序曲の前のチューニングが始まろうとしている段階です。いまや視線は、20世紀の混濁から生まれ出ずる21世紀に、そしてボクたちが決して生きてはいない22世紀へ。
最後の1カ月という区切られた時間を、みなそれぞれに有効に使いたいものです。(12月1日)
ページの冒頭に戻る
メニューにジャンプ
2000年11月
<風邪で嗅覚がマヒ、街行く若い女の残り香が感じられない空虚さ>
刑務所で服役する男子受刑者たちは、来る日も来る日も女というものから隔絶された生活を送っているため、たまに女性の面会人が訪れる時はだれもが過敏なほどの反応を示すといいます。それも、面会人の姿が見えなくても、またかなり遠くから近づいて来るだけで分かる、というのです。男子受刑者たちが、女の匂いそれも香水などではなく女の体の匂いそのものを鋭くキャッチして激しく反応するためで、いわば生物種のオスとしての本能的なメカニズムのようです。
というようなことをボクが今思い出しているのは、この1週間ほど悪性の風邪をこじらせて匂いの感覚、いわゆる嗅覚が完全になくなった状態が続いていて、匂いに関して真っ暗闇の生活となっているためなのです。
匂いを感じないというのは、味覚が充分に感じられなくなることもさることながら、極めて不便なものです。ガス漏れなどの異臭が発生しても気付かないとか、火災の煙に対して無警戒になってしまうとか、食べ物の腐敗が見わけられないとか、いろいろと問題があるのに、世の中では嗅覚障害をあまり重要視していないのはどうしてでしょうか。
視覚や聴覚を失った人たちと同様に、嗅覚障害に対しても対応策があってもしかるべきと思うのですが、嗅覚障害は風邪が治れば一緒に治ることがほとんどで、あまり切実ではないと考えられているのかも知れません。あるいは人間の五感の中で、嗅覚が最も軽んじられているせいでもあるのでしょう。
街に出てても、街固有の匂いが全くしないというのは、現実感を喪失した世界を歩いているような感じです。嫌なタバコの匂いがしないことは、ホッとする半面、知らずにタバコの煙を吸っているかも知れないと思うとゾッとします。電車の中で、オヤジたちの臭い息を感じなくてありがたい気もしますが、いちばん寂しいのはすれ違う若い女性たちの残り香が全く感知されないことです。
匂いの感覚がある時にはほとんど意識していなかったのですが、街を歩く若い女性から立ちのぼるフェロモンを適度に感じ取ることは、男の体内のDNAを目覚めさせ、生物種として生きていく上でバイタリティーの活性化につながっているのだと初めて気付きました。(11月27日)
<腰抜けカトちゃんの裏切りで、日本中に広がるシニシズムとアパーシー>
カトちゃん、あなたの親しみやすい風貌は、どこかコメディアンを思わせるところがあって、二代目加藤茶を襲名したら人気が出るだろうと思っていました。ところが、あなたは、三文役者の演技すら出来ずに、開幕ベルの直前にコソコソと荷物をまとめ、立ち見が出るほど超満員の観客を前に、尻尾を巻いて裏口から逃げてしまったのですから、もはやコメディアンの風下にもおけません。
カトちゃんの言い分は、聞くも無駄で腹立たしい限りです。一座をまとめきれず、このまま舞台に上がっても勝算がないことが分かった、ですって。そんなことは百も承知で今回、一世一代の世直しに打って出ることに賭けたのではないですか。はじめから勝つことが保証されている闘いなんて、八百長でもなければあり得ないことはみんなが分かっています。
観客は、もしかして勝つかも知れないが負ける公算も少なくない、それにもかかわらず真っ向勝負に打って出ると大見得を切ったカトちゃんに、日本を変える一縷の望みを託し、世紀末のメイクドラマを期待したのではないですか。
勝負に出た結果、カトちゃん一座が敗れたとしても、観客はカトちゃんの心意気と熱意に惜しみない拍手を送り続け、そのことが結果的にシンキロウの早期退陣を促したことでしょう。カトちゃん一座は核分裂を起こすとしても、すべての劇団と出演者を巻き込んだ再編成の嵐が吹き荒れ、21世紀に向けた新しい胎動と息吹が生まれたはずです。
しかし、戦わずして姑息な白旗を掲げ、国民と世界に恥をさらしたカトちゃんは、もはや政治家としても一人の人間としても、信用は地に落ちてしまいました。あなたがみじめな政治死を遂げたことは、観客にとってもはやどうでもいいのです。
問題なのは、今回のドラマへの期待が大きかった分、その反動もまた極めて大きく、「結局は政治なんてこんなものさ」「もう何も期待するだけ無駄」というシニシズム、アパーシーが日本に急速に蔓延しています。これは、カトちゃん、あなたの行為がもたらした犯罪的な結果以外の何物でもありません。
国会でコップの水をぶちまけたケンシロウ君は、それに比べればまだご愛嬌といっていいくらいです。
今回の不発の乱をめぐっては、敵役ながらノナカコウムの抜群の策士ぶりがあっぱれでした。
それと目立たなかったけれども、盟友を決して見捨てず最後まで行動をともにしたヤマザキタクさんは立派でした。(11月23日)
<ウッソー!? 英国が大統領選出に失敗した米の独立を撤回だって>
アメリカの大統領選挙の混乱ぶりに、ついにイギリスが今世紀最大の衝撃的な決定をしたということです。
「アメリカ合衆国の国民に告ぐ。貴国は国家元首である大統領の選出に失敗し、自治不能に陥ったことにかんがみ、我々はここに貴国の独立承認を撤回することを通知する」
その上で、アメリカの新しい元首にはエリザベス女王が君臨するとして、「トニー・ブレア首相がアメリカ担当の閣外相を兼任することになった。今後は選挙をするにおよばず。また以降はアメリカ英語は認めない」とありますから、もう驚愕を通り越して、抱腹絶倒ものではありませんか。
英国のインターネットで飛び交っているジョークは、ワサビが効いていて上品でスマート。そして何よりもイギリス人の心情が吐露されていて、世界中の人々を楽しませてくれます。
アメリカという国は、白と黒の間には無数の灰色があるということを決して認めない国だといわれます。西部劇の決闘も、ほぼ互角の両者が一瞬のうちに勝つか負けるかどちらかに決着が着く風土があり、従来の大統領選挙でも、負けた側はあっさり負けを認めて引っ込むのがアメリカ精神だったのです。
今回は、どちらが勝つにしても、アメリカが負った傷は大きく、これまでのように遠い異文化の国の紛争に大きな顔をして介入することは、困難になるかも知れません。アメリカは、途上国の抱える苦しみ、そして地球には白でも黒でもない多くの灰色が存在していることを、少しは分かったでしょうか。
それにつけても、日本は自民党の内部抗争と、内閣不信任決議提出の混迷へ。こちらはジョークにもならないおそまつな事態です。
そもそも森首相の誕生からして、これは誰も見ていない時に自分で埋めて掘り起したものだ、という説がありますが。(11月19日)
<日本語.comドメインは本当に必要か、狂騒曲に踊らされ悲喜劇続出>
10日から登録受け付けが始まった日本語.comドメインをめぐる騒ぎは異常です。僕も実は、ASAHIネットが前日に申し込みを受け付けて、10日に登録代行機関に流すというので、間髪を入れずに希望ドメインを申し込んだのですが、登録可否の返答が大幅に遅れ、昨日になって登録出来なかったというメールが来ました。調べてみると、受け付け開始に先立った抜け駆け申請が受理されているようで、これはこれで問題にしていきたいと考えています。
新聞などでも報じられていますが、今回の登録では登録機関や登録代行機関への回線がなかなかつながらず、結局、自分の企業名を取れなかったところが続出。この混乱の中で、YAHOOなどのオークションに早くも日本語ドメインが競売に出され、なんと1つのドメインで1億円や5000万円の値がつけられているものさえあります。先ほどのぞいて見たら、中日新聞社.comが2500万円でオークションにかけられていました。
どこもかしこも浮き足立っている感じがありますが、素朴な疑問として、日本語ドメインは本当に必要なものなのかどうか、またどんな使い道をすれば効果的なのでしょうか。いまホームページを立ち上げている企業や機関、個人が、新たに日本語ドメインを取ったとして、現在使っているURLを日本語に変えるとは思えません。せいぜい日本語ドメインで仮のトップページを設置して、そこから現在のcomやjpのトップページにリンクして自動的にジャンプさせるくらいでしょう。
だいいち日本語ドメインは、海外の非日本語圏の人々からのアクセスにとって非常に不便です。ブラウザの言語を日本語に設定しておかないと、アドレスを打ち込むことも出来ないのではないでしょうか。
今回の日本語.comドメインは、結局、先に獲得した他人によって怪しげで迷惑な使い方をされないために、防衛的な意味で取っておこうという企業や個人がほとんどで、あとはオークションなどの投機目的や、自分の好きな名称をとりあえず確保しようというマニア的なものでしょう。
インターネットによってグローバル化が進み、ネットでは英語が共通言語になると言われている今、あえて日本語ドメインに群がるのは、グローバル化という名のアメリカ化に抵抗して日本語を守ろうとする試みなのでしょうか。本来はそうした発想が根底にあっての新設だったとしても、いまの騒動は商魂と打算に振り回されているだけのようです。(11月16日)
<大統領選開票の混乱で、世界が見てしまったアメリカ民主主義の姿>
アメリカ大統領選挙は、フロリダだけでなく、あちこちの州で次々と問題が噴出し始めて、まるで発展途上国の選挙開票のような混乱を呈しています。ブッシュとゴアのどちらが大統領にふさわしいか、という問題よりもむしろ、今回の事態がもたらすアメリカの威信低下と、20世紀に君臨し続けたアメリカ民主主義なるものの本当の姿を世界中が見てしまったことのほうが、はるかに重大な問題のような気がします。
インターネットで飛び交っているジョークのうち、一番の傑作は、収集がつかなくなって困り果てた米国が、ロシアの中央選管に支援を求めたところ、アメリカに飛んだロシア中央選管は「プーチンがリードしている」という最新情報を発表し続けた、というものでしょう。
現実に、プーチン大統領は記者団に「わが国のベシニャコフ選挙管理委員長が米国に票の数え方を教えてあげるだろう」と冗談をとばし、元駐米ロシア大使のルキン下院副議長は「米国の選挙システムは中世レベル」とこき下ろしています。
マレーシアのライス首相府相は「米国はどんな制度にも弱点があるということを悟り、世界の警察官として他国に干渉することをやめるべきだ」と言い切り、インド中央選管のギル委員長は「米国は国際監視団を招きいれ、指導を受ける番だ」と指摘。これまでさんざん民主主義の未成熟をアメリカから指摘され続けてきた国々が、今回の事態を冷ややかに見ている様子が伺えます。
ボクたち素人目にもおかしいと思うのは、選挙人の選び方です。フロリダの開票の結果、1票でも多かった陣営が25人の大統領選挙人を全部獲得するというのは、民意を反映しているやり方でしょうか。
2州を除いてほとんどの州がこの方式をとっていて、その根底には大衆不信が根強く存在するとも言われていますから、今後、アメリカ国内はもちろんのこと、アメリカ民主主義が世界中から厳しい視線にさらされることは避けられないでしょう。
20世紀を一人勝ちで締めくくり、21世紀をさらに世界最強の超大国として制覇しようとしているアメリカにとって、今回の小さなつまづきが、巨大ダムを崩壊させる蟻の一穴にならなければ幸いですが。(11月12日)
<すっかりオバサンになった重信房子の姿に見る、歳月と時代の推移>
史上まれにみる大接戦となって当落が決められないまま、フロリダ州での再開票となったアメリカ大統領選挙の二転三転するニュースの中で、日本赤軍最高幹部として国際手配されていた重信房子が国内で逮捕されたニュースは、胸にズシリとくるものがあります。この二つの出来事は、20世紀という時代がどのような形で決着しつつあるのかを端的に物語っているような気がします。
新幹線から警視庁に護送される途中の重信房子の姿をテレビで見た者は、だれもが何がしかの感慨にとらわれたことでしょう。長い髪を肩から垂らした美貌の国際テロリストの姿はもはやそこにはなく、更年期を迎えた様子がありありと分かる一人の日本のオバサンの姿がありました。
日本赤軍の世界革命理論や、彼女の国際拠点地建設構想などを何も知らないボクでさえも、重信房子という生き方は70年代の一つの極端な象徴的存在として、驚きと畏敬の念で見つめる存在でした。日本赤軍が次々と起こす無謀なテロ事件に対しては、何とバカなことをやる連中だろうと呆れつつも、レバノンを拠点に活発な活動を繰り広げる重信房子の激しい情熱と行動力は、息詰まる管理社会の歯車としてあくせく働く身にとって、ある意味で羨ましくもあり、心の隅っこで「ガンバレヨ」と声援を送り続けていたような気もします。
それだけに、重信房子が日本に帰ってきていたこと、そして何の抵抗もなく逮捕されたことに、歳月の経過とその間の時代の変化をつくづくと感じ、いくぶんガッカリするとともに、何だかホッとした思いもまたあります。
護送途中の重信房子は姿を隠そうともせず、報道陣に「頑張るから」と笑顔を見せて気丈に振舞っていましたが、見ていてなんだかつらく、ジーンと泣けてきます。こんなにオバサンになってしまった重信房子は、もう頑張らなくてもいいのではないか。これまでの生き方だけで充分に、日本社会と国際社会に刃を突き続け、人間としての一つの生き様を鮮やかに提示し続けたのだから、もうこのへんで重い荷を下ろして、人生の後半を彼女らしく有意義に使ってほしい、とも思うのです。
これを突破口に日本赤軍の徹底解明を、と正論をはいている人々も、重信房子に聞いてみたいことは山ほどあるのではないでしょうか。これまでどうしていたのかということももちろんですが、今の日本の社会や政治、若者の姿をどう思うか、社会主義の敗北とアメリカの一人勝ちについてどう思うか、等々。
少女時代の重信房子はアジサイが大好きで、小さな親切運動に取り組んでいたということです。20世紀も暮れなんとする晩秋の故国で、逮捕されることを待っていたかのような重信房子は、今年のアジサイを見ることが出来たのでしょうか。(11月9日)
<捏造だった70万年前の旧石器発掘、マスコミはどう責任を取るのか>
まず私事からですが、発症から5日目。めまいと吐き気はおさまりました。ふらつき感が多少ありますが、今日は思い切って電車に乗ってみました。階段とホームさえ気をつければ、なんとか一人で動けそうです。
ということで、気を取り直して、残り2カ月を切った21世紀開幕に向かい、引き続きがんばっていきましょう。
* * *
今日の最大のショッキングニュースは、日本に70万年前の旧石器文化が存在したことの発見など、相次ぐ「世界的大発見」で一躍考古学界のビッグスターにのし上がっていた藤村新一・上高森遺跡調査団長の「偉業」のほとんどが、なんと自分で石器を埋めては発見を装っていた自作自演の捏造だったという毎日新聞のスクープです。
これはもう開いた口がふさがらない出来事ですが、冷静に考えてみれば、エジプト古代文明やインカ帝国、マヤ文明などでも、せいぜい1万年前から数万年前までしか遡ることが出来ていないのに、日本だけで60万年前や70万年前の前期旧石器時代の石器が次々と、それも藤村調査団長の手によってのみ発見されていることに、学会もマスコミも不自然に思わなかったのでしょうか。
考古学上の大発見という言葉に、日本の大マスコミはめっぽう弱く、ちょっとリークされたくらいで舞い上がってしまい、社会部も整理部もワッと飛びついて何はさておき1面トップで仰々しく扱うきらいがあります。新聞社には専門の考古学記者を育てるという視点がなく、ちょっと勉強を積んだ記者は2、3年で配属が変わってしまうのが実情でしょう。結局、一方的な発表を丸呑みにして、あとは関係者それも学者の談話を集めて紙面を作るケースがほとんどのように見受けられます。
藤村調査団長による一件の捏造問題について、マスコミはどう決着をつけ、どう読者に対して責任を取るつもりでしょうか。
毎日新聞は今回のスクープにあたり、藤村調査団長の捏造現場を本人の知らない間にビデオに撮影して突きつけるという、非常手段に出ましたが、この取材方法を非難する資格は、どのマスコミにもないはずです。それどころか、毎日新聞だけが、捏造を暴くことによって、これまで虚報を流し続けてきたことへのメディアとしての責任をかろうじて果たすことが出来た、と言っていいでしょう。
明日の朝刊で、各紙がこの問題をどのように総括するのか、見ものです。(11月5日)
<目の前にいる時には気付かない「青い鳥」、それは平凡な日常の中に>
ボクたちは、幸せな時にはその幸せに気がつかず、「青い鳥」がどこか特別な場所にいるものと思って、それを追い求めて回ります。そして「青い鳥」が見つからないことに苛立ち、落ち込み、妬んだり羨んだりします。
しかし、あたりまえと思っていた平穏な日常の一端が崩れた時、ボクたちは初めて、平凡な日々を送っていることの中に、実は「青い鳥」がいたことに初めて気付き、崩れる前の日常がいかに大切で幸せなことだったのかを、後からつくづくと思い知るのです。
今年前半、ボクは20年ぶりの歯痛から始まって6カ月も続いた歯の治療と、その途中で突然見舞われたそけいヘルニアのために、全身麻酔に酸素吸入の手術を体験し、それまでの平平凡凡の何の変哲もない日常が、いかに尊くて輝くものであったかにようやく気付き、「青い鳥」とはまず普通に健康であること、そして地位や名誉や金銭を追い求めない凡庸な生活を送ることの中にこそ存在するのだと悟りました。
しかし、ふたたび健康を取り戻し、中国、トルコ、スペインと飛び回るうちに、ボクはいつの間にか、あれほど渇望していた「青い鳥」が身近にいたことを忘れて、この状態があたりまえなのだと思い始めていました。
そして…昨日の未明、ボクは就寝中に激しいめまいに襲われました。朝になってめまいだけでなく、ふらつきがひどくて歩けないこと、さらにひどい吐き気で何も食べられない状態になっていることを知りました。原因は何か。メニエール病なのか、小渕さんと同じ脳梗塞なのか。とにもかくにも、タクシーに飛び乗って近くの大病院へ駆け込みました。
朝から夕方まで、内科、耳鼻科、神経内科といろいろな科で、さまざまな検査を受けましたが、いまのところ原因ははっきりせず、今後さらにいくつかの検査をしなければなりません。それほど重い症状ではないとのことで、いくぶんホッとしていますが、ふらつきは収まらないため、ホームで倒れるのが怖くて電車にも乗れません。さらに食欲がなく、無理に食べても吐いてしまうので、その面からの衰弱も心配です。
おとといまでの元気な日々の中にこそ、「青い鳥」がいたことを、ボクは傲慢にもすっかり忘れていました。
普通に街を歩き、普通に電車に乗り、普通に食事が出来るごく当たり前の平凡な日常が、こんなにありがたいものであったとは、それを再び失うことによって改めて思い知らされました。
こんど元気になったら、こんどこそ目の前の「青い鳥」を大切にしよう。心を入れ替えるつもりで持っているボクに、「青い鳥」は舞い戻ってきてくれるでしょうか。(11月2日)
ページの冒頭に戻る
メニューにジャンプ
2000年10月
<金権巨人の日本一と引き換えに、多くのファンを失った日本プロ野球>
今日の日曜日、三越と伊勢丹にはジャイアンツ日本一セールに押しかけた女性の買い物客で、身動きも出来ない混雑ぶりでした。
だがしかし、ここで何かがヘンだという気がしてなりません。そもそも、今年の日本のプロ野球は面白かったでしょうか。高笑いしているのは、ナベツネと一部の読売グループ幹部であり、無邪気な巨人=卵焼きのファンたちが喜んでいるに過ぎないという気がします。
今年に限らないことですが、カネにモノを言わせた巨人の有無を言わせぬ強引な引き抜き補強策には、開いた口がふさがりません。こんなやり方で突出した戦力を集中させれば、勝つのは当たり前で、スポーツ精神もへったくれもあったものではありません。はっきり言えば、一つのチームだけが重量級の選手をカネで集めるやり方は、協約に書いてあるかどうか以前の、スポーツとしての根本的なルール違反ではないでしょうか。
ボクはアンチジャイアンツではありますが、現役時代の長嶋選手も王選手も大好きでした。しかし、今回の日本シリーズのON対決という前宣伝には、どうしても乗れないものがありました。ダイエーはいいのです。工藤をかっさらわれても、なおパリーグ優勝を果たしたのは立派です。問題は巨人です。工藤を取り江藤を取り、これ以上は望めないほどの絢爛豪華で、まさに金権まるだしの選手集めによって、他チームを弱体化させ、自分のチームさえ良ければ、ほかはどうなっても知ったことかという、この態度。巨人がセリーグで、そして日本シリーズで勝ったのは、長嶋采配とは全く関係なく、選手たちのチームワークや工夫のおかげでもなく、これだけカネをつぎ込めば当たり前の結果でしかないということです。
ナベツネは、自分が高笑いをしているうちにも、ファンのプロ野球離れがとどまるところを知らない、ということに気付いているのでしょうか。シドニー五輪へのプロ選手派遣をセリーグ側が渋ったのは、誰が元凶なのかも、ファンはみな知っています。
イチロー選手が日本のプロ野球に見切りをつけたのも、賢明な選択といえるでしょう。もたもたしていれば、巨人の魔の手がイチローに伸びることだって充分あったのです。
長嶋日本一の大見出しに沸く今日のスポーツ新聞各紙。世の中すべてが、結局はカネがものを言うのだよ。努力とかチームワークなど、きれいごとを並べてみても、所詮はカネに勝てないのさ。優勝なんて、カネで買えるものなのさ。スポーツでさえこうなのだから、まして政治も科学も芸術も教育も、家庭や人生の幸せも、カネがすべてさ。それで何が悪い?
そんな風潮をますます煽る結果となった、20世紀最後の日本シリーズでした。(10月29日)
<いま生きている人々は21世紀中にみな死ぬ、その後は次の世代に>
いま地球上に生きている60億人の人々は、ほとんど99%以上が21世紀中に死ぬ。ごくわずかな例外は、現在まだ幼児で、あと100年以上生きるかも知れない一握りの人たちだけ。それも22世紀の初頭には例外なく死ぬ。このあたりまえのことが、最近とても重要なことのように思えてきます。
20世紀の総括も出来ないままで、口角泡を飛ばして目先のことどもに夢中になっている政治家はじめ、もろもろのリーダーたち。逆に21世紀こそは戦争も殺戮もない世界を、と新たなパラダイムを模索し続ける人々。そうしたことに無関心か、あるいは関心があっても日々の生活に追われて、なんとなく何時の間にか、21世紀に入っていくであろう圧倒的に多くの人たち。世紀末を生きる生き方はさまざまですが、そのだれもが、21世紀の100年中に死ぬのだということは、案外と忘れられていることのようです。
ボクたちは皆が皆、21世紀の世界を遠くまで歩いていけるわけではありません。先のことは誰にも分からないのですが、今生きている人たちは間違いなく、21世紀のスタートからどんどんと死んでいって、21世紀中頃には半分の30億人が死に、そのころには21世紀になって生まれた人たちが30億人を超えていて、各方面のリーダーとなりつつあるところでしょう。
21世紀100年の間に、人類の顔ぶれはすべて総入れ替えされる、と考えていいでしょう。そのことを考えると、今の人間はあまり驕慢にならずに、ほどほどのところで謙虚にものごとを収め、地球とその上の生物圏および文明圏を、次の人類にバトンタッチしていくことに思いを馳せるべきです。なんだかんだといっても、21世紀の末に世界を引っ張っているのは、これから生まれてくる世代なのですから。いま現役でのさばっている人たちも含めて、21世紀を迎える時の人間は、次の世紀末にはすべて墓の中なのです。
どんな高い地位の偉い人間であっても、現在を楽しまんがために未来までを食いくつしてしまうことは、決して許されないことです。いわんや、現在を取り繕うために、未来がよって立つ基盤を壊してしまうことなど、とんでもないことです。
50年後のことは50年後の世代に、100年後のことは100年後の世代にまかせる。その時の世界のあり方を決めるのは、その時生きている世代が決めることですから。ボクたちは、次の世代がバトンを引き継ぎやすいよう、環境を整えることが大切でしょう。
21世紀をどう生きるか、ということとともに、21世紀をどう死ぬか、ということもまた、すべての人にとって避けられない重要なテーマのように思います。(10月26日)
<セビリアで体験した強烈なデジャ・ビュ、生前のボクがいた光景の記憶>
これまで絶対に見たことがない光景や、決して体験したことがない事柄を、かつて見たような気がする、あるいはかつて同じような行動を体験したことがあるように思う……だれもが時々経験する既視感いわゆるデジャ・ビュ。これは心理学的あるいは精神科学的には説明がなされているらしいのですが、ボクにはどうもそうした近代科学の範囲を超えた、何らかの未知の原因が根底にあるような気がしてなりません。
先日、セビリアのサンタ・フスタ駅前の信号を一人で渡っている時、ふっとボクは、なぜ自分が今、たった一人でこの街を歩いているのだろう、と一瞬分からなくなり、その直後、強烈といっていいほどの鮮烈な既視感に襲われました。この光景、目の前の駅の建物も、駅前広場の様子も、信号の位置と建物の配置も、信号を渡る人々の様子も、すべてかつて見たことがある。まさしく、これら全部が、かつて見たあの光景であり、それどころかボクがいま行っている事柄も、かつて体験したことではないか。覚えている。あの時の全てを。どれもこれも、今と同じだった。
もちろんボクは、スペインなど来たこともありません。セビリアの街が写っている映画やテレビを見たこともありません。にもかかわらず、このデジャ・ビュは心理的・精神的な錯覚をはるかに超えて、身震いするほどに懐かしく、五感のすべてでかつての光景と体験が蘇ってくる感じなのです。
時あたかも日没寸前の午後7時30分の少し前。ほとんど地平線すれすれに傾いた太陽が、低層の建物たちをかすめるように燦燦と輝き続け、そのギラギラとした夕日の光は、ある種の甘い香りが混じった強烈でストレートな強さを持っていて、この輝き具合もまさにあの時に見たものと寸分違いません。没しゆく日光の強さにもかかわらず、あたりの空気はこの世のものとも思えないほどの怖い冷たさで、さわさわと風が吹いて木々の葉が揺れるさまも、異界のような不気味さです。
そういえば、通行人の数がなぜか急に少なくなり、少ない通行人も動きがぎこちなく、表情もどこか遠い記憶の世界のような感じです。この感覚、夕日と寒い空気、不自然な風、少なくなった通行人。全部、覚えている。なにもかもが、あの時と同じなのだ。
なぜ、あの時を覚えているのだろうか。あの時、ボクは誰だったのだろうか。あの時、ボクの身に、何かとてつもなく大きなことが起こったような気がする。でもどうしてもそれ以上は思い出せない。このもどかしさ。
デジャ・ビュは、完全に日が沈むとともに、消え去っていきました。でもボクは、遠い遠い昔の生まれる前のボクが、確かにこの光景の只中にいたことを、確信しています。(10月23日)
<高橋尚子とノーベル賞学者が親戚、600年遡れば全ての人が血縁に>
シドニー五輪女子マラソン金メダリストの高橋尚子選手と、ノーベル化学賞の白川英樹・筑波大名誉教授が、遠い親戚関係にあったというニュースには、人と人の不思議な血縁に驚きを感じます。
しかし、今回はたまたま2人が最も脚光を浴びる立場にあったからこそ判明した血縁関係であって、詳細に調べてみれば、意外な人たちの間での血縁関係も、実はたくさん存在しているのではないか、という気もします。
そこで、1人の人間がこの世に生を受けるためには、何人のご先祖さまが関わっているかを、シミュレーションで考察してみましょう。計算を単純化するために、とりあえずは1組の夫婦が平均して25歳の前後に何人かの子どもをつくるものとします。すると2人の父母と4人の祖父母、さらに8人の曽祖父母というぐあいに、ご先祖の数は2の2乗で増えていって、8世代をさかのぼる200年前には4096人のご先祖が存在する計算になります。
さらにさかのぼると、なんと徳川幕府が始まる400年前には6万5536人、さらに室町時代までいくと1677万7216人という驚異的な数のご先祖さまの存在に到達します。なんと、この数は当時の日本の人口とほぼ同じ数で、結局のところ、24世代ほどさかのぼっていくと、現在の日本人はすべて、微かではあるけれども遠い遠い親戚関係にあるわけです。
それ以上さかのぼると、人口を超える数のご先祖さまが必要という計算になってしまいますが、実際にはそれだけの数のご先祖がいなくても、微かな遠縁同士が結びついて子孫を増やしていって、親戚関係に輪を重ねていると言えるでしょう。
まあこのように考えると、ボクだって高橋尚子選手と遠い親戚関係にあるのかも知れないし、森喜朗首相と田代まさしが親戚関係かも知れないし、田中真紀子と田中康夫が親戚関係にあるということだっておおいにあり得るわけです。
しかし、ここでハタと大変な問題に気付くのです。何万人、何千万人へと膨れ上がるボクのご先祖さまのうち、どこか1組でもすれ違っていて結ばれなかったなら、その後に続く親戚関係は全く違ったものになり、現在のボクはこの世に存在しなかった、という恐るべき事実です。それは、ボクに限らず、今これを読んでいるすべての人たちについて言えることなのです。
今の自分が存在するためには、膨大な数のご先祖たちによる、気の遠くなるようなDNAのリレーが続けられてきた。このことを思うと、いまの生を努々おろそかにはできませんね。(10月18日)
<マドリッドで観たピカソの「ゲルニカ」と20世紀、絵の左にあるものは>
20世紀の音楽ベスト1は、音楽の友社のアンケートによると、ストラビンスキーの「春の祭典」で異議のないところのようです。それでは20世紀の絵画ベスト1は何でしょうか。僕の個人的な考えでは、ピカソの「ゲルニカ」だろうと思います。戦争と殺戮の世紀と言われる20世紀を、1枚の絵の中に、これほどドラスティックに表現した絵はほかにありません。
というわけで、今回、はるばるとマドリッドのソフィア王妃芸術センターまで行って、念願の「ゲルニカ」を観てくることが出来ました。大きい絵だとは聞いていたのですが、実物は予想以上に大きなもので、前にたたずむと(といってもかなり離れて見ないと全体が見渡せないのですが)、圧倒的な迫力で見る者に強烈な感銘を与えてくれます。
白と黒とグレーだけの、ほとんどモノクロの色使いがまた、戦争の現場で犠牲となる男や女、子ども、牛や馬などの苦悶の叫びを、何よりも強く物語っています。戦争とは、もはや色彩が意味をなさない世界、色彩を失った世界なのですね。
天井に描かれた楕円形のランプは、爆弾を象徴しているということですが、この絵が描かれたのは1937年のことなのに、このランプは原爆にも見えますし、湾岸戦争やベオグラード空爆で雨あられと降り注がれたミサイル爆弾のようにも見えます。
「ゲルニカ」がこれほど多くの人々をひきつけるのは、この絵がスペイン内戦によって破壊されたバスク地方の小さな町の惨劇をモティーフにしつつも、20世紀が抱え込んだ幾多の戦火そして戦禍へと普遍化され、人類が味わった最も悲惨な時代のモニュメントとしての意味を持つからでしょう。キュビスムの手法で描かれているのに、この絵が変だと感じる人はいません。むしろキュビスムだからこそ、戦争という筆舌に尽くしがたい不条理の本質がえぐり出されているといっていいでしょう。
見ていて気が付いたのですが、人物も動物も、左を向いているものがほとんどなのは、どうしてなのでしょうか。絵をはみ出した左側に、ピカソは何を想定していたのでしょうか。おそらくは、左にいるのは、ゲルニカの時代を語り継ぐべき後世の人々であり、つまりは現在の僕たちであり、さらにその左には戦争のない時代、人々が平和な日常を生きることが出来る未来がきっとあることに、ピカソは一縷の希望をつないでいたのかも知れません。(10月15日)
<「女たちのシドニー五輪」と1000年以内の人類滅亡、その深層での関係>
シドニー五輪が終わって、新聞などマスメディアの講評はみな、「女たちの五輪」「女性の活躍」「元気な女たち」にスポットを当てています。「21世紀は女の時代」という言い方も随所に見られます。女の活躍が目立ったのは日本選手だけでなく、どうやら世界的な傾向のようです。最終聖火ランナーで金メダルに輝いたキャシー・フリーマン、5冠は逸したものの3冠に輝いたマリオン・ジョーンズ、今回から種目に加わった女子重量挙げの女力持ちたち。女たちの方が、男よりもはるかにひたむきでしなやかで、時代をグイグイと引っ張っているかのようです。
男たちは、日本の選手はもちろんのこと、まさに男の世紀だった20世紀の呪縛にがんじがらめになって、勝てば力み過ぎるか照れ隠しをするかで、負ければふてくされたりウジウジといじけたり。「女の時代」というのは、裏を返せば「男の凋落」であり「男の衰退」のことなのです。
五輪総括の華やかな記事の陰に、ドキリとするような小さな記事が各紙に載っていました。それは、車椅子の宇宙物理学者、英ケンブリッジ大学のホーキング博士が、「人類は今後1000年以内に滅亡する」と警告している、というものです。滅亡の直接の原因は、温暖化によって地球が金星のような高温状態になることです。
僕は、一見したところ無関係に見える五輪での女の活躍と、1000年以内の人類滅亡の可能性は、深層部において繋がりがあるような気がしてなりません。極論すれば、もはや時代についていけなくなった男たちが、来る21世紀をも台無しにし、ひいては人類滅亡の要因を雪だるま式に膨らませていくのではないか、という予感です。
男たち主導の内外の政治・経済の危なっかしさもさることながら、もっと基本的な1個人レベルのささやかな生き方においても、男は未来を見失って、衰退と自信喪失の悪循環にはまり込んでいくような気がします。
非婚・晩婚の女たちの急増、結婚しても夫の低い意識に見切りをつけて離婚していく女の増加、そして精子の減少をはじめとする若い男たちの生殖能力の劣化。人類は、温暖化による灼熱地獄に見舞われる前に、まず男たちから自壊していくのではないでしょうか。
どんなに女たちが元気でも、男たちが肉体的にも精神的にもフニャチン状態となってしまえば、もはや人類は種として断絶するほかはありません。精子バンクなどで子孫を残そうと必死になる女たちの奮闘にも限界があり、種を救うことは出来ないでしょう。
今から1000年後、ほとんどの人類が滅びた地球で、かろうじて北極と南極に生き残っている僅かな女たちによって、人類最後の五輪が開催されるかも知れません。観客もなくメディアもない、滅びのメモリアルとしての五輪。その閉会式は、種としての人類の解散式となることでしょう。(10月3日)
ページの冒頭に戻る
メニューにジャンプ
2000年9月
<国勢調査のデータは秘密保持されるか、住んでいる階数がなぜ必要か>
10月1日は5年に一度の国勢調査というわけで、僕の家にも調査員が来て、調査票を置いていきました。
5年前や10年前にも国勢調査があったはずですが、どういうわけか調査票を書いた記憶がまったくありません。だれかが代わってまとめて記入したのだろうか、などと思ったりしますが、不思議です。
そこで調査票をよくよく見てみると、これが大変分かりにくく、記入しずらい。数字を書く欄が多く、鉛筆でマークシート方式で書くのですが、7の字は角をつけるとか、1の字は撥ねないとか、4の字は上をくっつけずに隙間をあけろとか、指示が細かい。いまは郵便番号でも、かなりの悪筆、乱筆を機械が読み取ってくれる時代。国勢調査も、人間が見て読める程度の字ならいいことにすべきでしょう。
記入すべき項目はどれもプライバシーそのもので、本当に秘密が守られるのかどうか、調査員がゼッタイに第三者におしゃべりして漏らさないのか、一抹の不安を覚えます。
「ここだけの話よ。だれだれさんの家ねえ、ああ見えてもダンナさん、会社に行ってなくて、職さがしですって。大変ねえ」「ゼッタイに誰にも言っちゃだめよ。それそれさんの奥さん、学歴はこれこれなんですって。それでいまはパートでカマボコ作りですって」「かれかれさんって、日本人じゃないのよ。そして奥さんとは離婚していて、娘さんがキャバクラで生計を支えているのよ。あたしが言ったなんて内緒よ」
ともかく、秘密漏洩など日常茶飯事の昨今。どこからどう国勢調査のデータが漏れるか分かったもんではありません。このデータを、のどから手が出るほど欲しがっている企業の連中がウジャウジャいることを、もって知るべきです。
とくに、通勤・通学している区・市町村や、そこまでどのような交通手段で行っているかなどは、ストーカーや刺客などに漏れたら、生命にかかわる重大なプライバシーです。その上に勤務先の会社名などを具体的に書くため、個人の行動がモロにバレる結果になりかねません。統計上の調査のためならば、業種と仕事内容だけでも十分なのではないでしょうか。
最も不可解なのは、共同住宅に住んでいる人に対して、何階建ての何階に住んでいるかを記入しなければならないことです。問うならば、何階建てかだけでいいのではないでしょうか。何階に住んでいるかを調べることで、どのような統計データが得られるのか、不思議でなりません。住んでいる階と学歴の関係とか、どの職業の人が何階に多いのか、などを分析するつもりでしょうか。
何階に住んでいるかを他人に知られることは、防犯上極めてゆゆしきことだと思うのですが。(9月30日)
<五輪の感動と残酷、高橋尚子選手がシモン選手を振り切る決断をした時>
オリンピックで繰り広げられる数多のドラマは、感動的であると同時に、残酷でもあります。今回のシドニー大会ではとくに、感動と残酷のコントラストが強烈なように思います。
感動と残酷の対比が際立ったのが、女子マラソンでした。高橋尚子選手の金メダルの素晴らしさは、筆舌に尽くしがたいのですが、彼女の言動もまた、味わい深い感動を与えてくれました。ゴールを切った後、観客席の前を一回りしながら、小出監督を懸命に探す姿はひときわ印象的でした。そしてインタビューで語った「今の時代に生まれてよかった」という言葉の持つ、時代とのめぐり合わせに対する感謝の言葉には、万感の感動を覚えます。
高橋選手はその後、NHKテレビの現地スタジオで、27キロ地点あたりからトップ集団から抜け出てシモン選手と走っている時の気持ちについて、「シモン選手と2人で前を走っているのがとてもうれしくて、いつまでもこの時間が続いてほしいと思っていました」と話しました。高橋選手にとって、何キロか続いたあの区間のあの時間は、ファウストなら「時よ止まれ、お前は美しい」と叫んだかも知れないような、美しい「時」だったのでしょう。
しかし、高橋選手はその至福の時間は、長く続かず、まもなく終わらねばならないこと、それを壊すのは、並んで走っている2人のどちらかであることを、誰よりも自覚していたことでしょう。そして35キロ地点。高橋選手は、いつまでも続いてほしいとあれほど感じた美しい時間を、サングラスとともに自分の手で投げ捨て、シモン選手を振り切って勝負を仕掛けたのです。
勝者は敗者があってこそ成り立つ。シモン選手にとって、銀は敗者の証でした。言って見れば、金メダルはそれ以外の多くの敗者の上に、かろうじて乗っかっている奇跡のようなものです。その奇跡を確実にものにした高橋選手は小出監督とともに、勝負の怖さも残酷さも知り尽くしていたのだと思います。
ところで今大会では、女たちの活躍とさわやかさが新世紀の到来近しを思わせるのに対し、男たちはどうもパッとせず、勝っても負けても20世紀をひきずっているような重苦しさを感じます。日本の男たちはこのままでは、21世紀に適合できないような予感さえします。(9月26日)
<あと100日、21世紀を迎える準備が東京で弱く西日本で意欲的な理由>
今日で、21世紀まであとちょうど100日です。思えば遠い道のりでした。1980年代が明けたころ、20年たてば21世紀を迎えるといわれても、それはまだ遥かな未来であり、想像さえも出来ない世界でした。1990年代となり、21世紀まであと10年といわれたころでも、本当に来るのかどうかも分からない、まだまだ先の夢のような話でした。このホームページがスタートした1997年2月の時点でも、21世紀までまだ3年11ヶ月、日数で1400日以上もありました。
あと100日たてば21世紀、という感覚は、時代の切り替わり点に立っているという、めまいがするような感じがあります。100日という期間は、長いのか短いのか、人によって受け止め方は千差万別でしょう。ちなみに、今日より100日前つまり21世紀まであと200日の時点がいつだったか、を振り返ってみると考えやすいでしょう。今から100日前は6月15日でした。6月15日から今日までが、いろいろな出来事を含みながらもあっという間に過ぎてしまったように、それと全く同じ日数が過ぎると、そこは21世紀なのですね。
昨日の毎日新聞大阪本社発行の夕刊1面には、「21世紀まで101日 高まる世紀末ムード」の見出しで、どんなふうに迎えるかについての記事が掲載され、このホームページのことも紹介されています。
この記事は、同じ毎日新聞でも東京の夕刊には載っていません。概して、東京のマスメディアは、近づく21世紀をどう迎えるかというテーマに対して、関心が乏しい気がします。いや、メディアだけではないのです。21世紀の開幕を迎えるために、現在、地域住民や自治体、地元経済界などが一体となって、独創的で有意義なイベントや記念行事の準備を進めている地域は、ほとんどが西日本なのは注目すべき傾向です。
五山送り火を中軸とした世紀の大イベントで新世紀へのメッセージを発信しようという意欲的な京都を筆頭に、明石海峡での行事を計画している兵庫県・神戸市・明石市、商店街の青年部を中心にイベントを進める愛知県と名古屋市、高知城でのイベントを計画する高知。そのほか熊本県南関町、福井県大野町など、いずれも「東京化」されずに地域の伝統と歴史に住民たちが愛着と誇りを持っている地域です。
時代感覚は地域感覚と強く結びついている、つまり時間と空間は密接不可分ということなのかも知れません。
* * *
篠原選手が金メダルにならなかったことを、泣きながら伝えたNHKの有働由美子アナウンサーに、日本中の視聴者が共感を覚えました。冷静に事実を伝えるだけがアナではありません。有働アナウンサーには、五輪報道の金メダルをあげたいと思います。(9月23日)
<金だけがメダルにあらず、田島寧子の銀や日下部基栄の銅は値千金>
田村亮子の金ほど、国民こぞって祝福し、涙した金はないでしょう。開会前から「最高でも金。最低でも金」とキッパリ公言して、もはや銀でさえ許されないところに自分を追い詰めての、まさにがけっぷち。パワーも技も全盛期の勢いがないにもかかわらず、相手と状況をよく見ながら、負けない柔道に徹し、数少ないワンチャンスに打って出て獲得した、極限の金。田村の姿には「武士」を感じるとともに、8年かかって夢を現実のものにした努力と精神力は、神の領域といってもいいでしょう。
しかし、金だけがメダルでないことを、改めて示して多くの人に感動を与えてくれた選手たちの活躍もまた、価千金の重みと輝きがあります。
中でも、競泳400個人メドレーで銀となった田島寧子の姿は、今大会ビカ一のさわやかさで、圧倒的な感銘を与えてくれました。もうテレビでも新聞紙上でも、何度となく再現された「めっちゃ悔しい〜。金がいいですぅ」の底抜けの明るさと素直さは、シドニー五輪語録に残ることでしょう。まだ19歳の若さですから、今後チャンスはいくらでもあり、21世紀を牽引していく新時代のキャラクターとしても、おおいに楽しみです。
そして銅で素晴らしかったのが、柔道57キロ級の日下部基栄です。地味で目立たない存在だったのですが、野ウサギのような素朴な容姿と敏捷な動きで、至難の敗者復活戦を一戦一戦ていねいに戦う姿が、見る者に深い感動を与えてくれました。ひさむきさと、まじめさが、テレビ画面からもひしひしと伝わってきました。
日下部は昨年の大怪我で手術をした後、病室で赤ちゃんのような可愛い声をあげて泣いていたそうです。選手村に入った時、感想を聞かれて「私のような田舎もんには、選手村は広すぎて迷いそうです」と言ったのも、飾らない性格を物語ります。何よりもさわやかなのは、銅を取った後、「私はまだ若い。金の夢をいつか実現したい」と語った、その言葉がまぶしく輝きます。
一方で、アトランタに続く金の2連覇を達成した柔道の野村忠宏については、凄いことだと思いつつも、印象が薄いというか、心にそれほど響くものがないのはなぜでしょうか。
金でも銀でも銅でも、多くの人々の心を揺り動かすのは、ランクとはまた別の要素が大きい、ということなのかも知れません。まだまだ続くシドニーで、さらなる金に期待するとともに、銀や銅のどんなドラマが続くのか、大いに楽しみです。(9月19日)
<軍服思わせるマントでケバケバしい虹色、日本選手ユニホームの悪趣味>
マントというのは、日本では明治以降、軍服として広く採用されました。そのせいもあってか、シドニー五輪開会式での日本選手団のマント姿を見た瞬間、僕は2・26事件で決起した雪の中の青年将校や、映画「帝都物語」のおどろおどろしい軍人の姿をとっさに連想しました。そしてつくづく、おしなべて小柄な日本人にはマントは似合わない、と感じました。
マントというミリタリーな異様さもさることながら、各人ばらばらな7色のレインボーカラーのケバケバしさには、テレビ中継を見ていて、日本人として世界の人たちに対する恥ずかしさのあまり、いたたまれなくなりました。この色彩感覚は、日本人に合わないだけでなく、世界にも通用しない悪趣味であり、国際試合における礼節の欠如と、色彩の調和についてのレベルの低さを目いっぱい宣伝する結果になりました。
JOCには抗議電話が殺到するありさまで、「あまりのカッコ悪さに寒気を感じたのは僕だけではなかっただろう」と新聞に書いた漫画家もいました。スポーツ紙が掲載している日本人の反応も「入場国の中でワースト1」「色使いも浮いていた」「レインボーカラーは地元ではゲイの色」「デザインした人がドーピングしているとしか思えない」など、悪評紛々です。
JOC関係者は、「環境問題を意識した」とか「オーストラリアの自然をイメージした」などと説明しているようですが、そういう以前の問題として、見る者に不快感を与えるデザインや色彩は、どんな立派な意味付けがあろうが、失敗以外の何者でもないと思います。
2008年五輪の大阪招致に向けて、世界中に日本を印象付け、アピールしようという狙いもあった、と書いている新聞もありましたが、そうだとしたら大阪招致に向けてこれほどのマイナス材料はないでしょう。全体の中での調和を無視し、自分だけが奇抜で目立てばいいというエゴ丸出しの感覚に、世界が拒絶反応を示すのは目に見えています。
日本は2008年の大阪をあきらめ、北京に譲った方が懸命です。北京での入場行進は、ゆめゆめ軍服を連想させるマントなどを着てはいけないことはもちろんです。(9月16日)
<100年の昔、頬につとふ涙をぬぐわずに女はなぜ啄木に砂を示したか>
20世紀が明けた1901年、石川啄木は16歳。盛岡中学校の3年生でした。翌1902年、上京した啄木は、与謝野鉄幹・晶子夫妻と会い、この出来事はその後の啄木の短歌に大きな影響を与えます。1904年、日露戦争がおこり、「君死にたまふことなかれ」の与謝野晶子はこんな短歌を残しています。
たたかひは 見じと目とづる白塔に 西日しぐれぬ人死ぬ夕べ
時代はいまと酷似するほどに、閉塞感が濃厚に重苦しくのしかかっていました。
啄木の歌は、100年後の僕達にも親しみやすく、共感を呼ぶものが多いのですが、僕は年をとるにつれて、歌集『一握の砂』のタイトルにもなった歌の持つ切なさに、深く心を揺さぶられるようになりました。
頬につたふ なみだのごはず一握の 砂を示しし人を忘れず
この歌を、僕は10代のころには、啄木が昔好きだった女性を淡く思い返している、ほのかな追憶の歌だと思っていました。
もちろん、それはそうなのですが、この歌にははるかに深くそして苦い人生の諸相が詠み込まれている、と最近は思うようになりました。この女は、啄木から一途の愛を打ち明けられ、それを受け入れることが出来ない背反状況の中で、ただ一握の砂を啄木に示すしかなかった。僕はここに、苦しみぬいた末の女の、菩薩のような優しさを見ます。当時の啄木は、もっと直截的なイエスかノーかを待っていたため、この砂の意味が理解できませんでした。
この女は啄木に気がなかったのではなく、好きだったのでしょう。しかし、好きであっても、相手の好意に応えられないことは、いくらでもあります。まして、この女が自分の気持ちとは別な事情によって、肯定の返事が出来なかったとしたら、頬につとふ涙こそが彼女の本当の気持ちを物語っています。「のごはず」という、ところかまわぬ仕草の中に、女の抑えきれない恋心が伺えるような気がします。
涙もぬぐわず、砂によって、女が示した心の内を、啄木がようやく分かるようになった時には、もう人生も盛りを過ぎた頃でした。
なぜ彼女は砂を示したのか。実はこの点こそがポイントなのですが、手の指から流れ落ちる砂は、無常そのものであり、恋の本質が無常であることを、女はよく分かっていたのだと思います。
恋は、決してあり得ない至高の愛に向けて沸騰し続ける精神のまれなる高揚であり、成就しないことが恋なのです。それは幻を追い求め、夢の世界を掴もうともがくのに似ています。恋は過程こそがすべてで、過程にこそ胸ときめかせたり苦しんだりするのです。
恋は、流れ落ちる砂のようなもの。最後に残るものは、いつの世も、さらさらと流れる砂の記憶だけ。はかないからこそ、甘く美しく、人はいつまでもそれを追い求め続けるのでしょう。(9月14日)
<DNAからのクローンと脳の全データのシステム移管と、どちらが不死か>
名古屋市の葬祭業者が、故人のDNAの保存サービスをこの夏から始めているそうです。亡くなった人のほおの内側に付着した細胞を、特殊な綿棒でぬぐって採取し、そこからDNAを抽出して錠剤の形に収め、位牌の中に入れて保存するというものです。形見としてとっておくだけではなく、将来は遺伝子治療などで子孫の病気の治療に役立てることが出来る、と業者はアピールしています。
自分のDNAを保存しようと心に決める人は、いつか遠い将来、科学技術がいまよりも数千倍あるいは数万倍のレベルで発達を遂げた時、保存されたDNAから「自分」を再生させることが出来るのではないか、という「不死」あるいは「蘇生」への期待がどこかにあるのではないでしょうか。
かりに将来、人間のクローンが解禁となり、位牌の中に保存されてきたDNAと同じ遺伝子を持つ人間が再生されたら、その人間は、かつての「自分」の再生・復活・蘇りと言えるでしょうか。
完全に同じDNAの人間だとしても、やっぱり全くの別人です。第一、最も肝心の「自分」としての意識や記憶、思考などは、DNAでは再生されません。DNAからのクローンが実現しても、不死の実現にはならないのです。
本気で不死を考えるならば、最も重要なことは、「自分」という意識や自分に固有のさまざまな思考や体験の記憶が、そっくり保存・継承されることでしょう。それならば、DNAによる再生よりも、個人の脳の全データをコンピューターに丸ごとコピーする技術のほうが、不死を実現する近道といえそうです。脳とコンピューターの直結は、2020年ごろには可能になると見られています。
脳のコピーが実現し、視聴覚など人間並みのセンサーを完備したワイヤレスの移動端末とつながれ、さらに身体性の欠如という重要な問題もクリアすることが出来たとしたら、そのコピーは「自分」なのでしょうか。僕は、もとの自分が存在する限りは、どちらも自分であるということは原理的にあり得ないと思います。
これを解決する唯一の道は、脳の全データのコピーではなく、「移管」でなければならないでしょう。移した先で「自分」であろうとするならば、元の身体にはいささかの「自分」の痕跡をも残してはならないのです。コンピューターの中で不死を得ようとするならば、これまでの身体とともにあった自分は死ななければならないということです。
万一、「移管」に失敗したら一巻の終わりかも知れません。しかし、そのリスクを賭してもなお、コンピューターの中での不死は、魅力的な気がします。(9月11日)
<阿川佐和子と壇ふみの『ああ言えばこう嫁行く』に、日本のオトコは完敗>
いま話題を呼んでいる阿川佐和子/壇ふみ共著の往復エッセイ『ああ言えばこう(嫁×)行く』を一気に読みました。あまりにも面白すぎて、ショックでさえあります。この本のタイトルは正式には何と読んだらいいのでしょうか。『ああ言えばこう嫁行く』とあって、「嫁」の字だけが赤になっていて、しかも×印がつけられています。電話で注文する時など困るだろうなあ、なんて思ってしまいます。
この本は、当然のことながら、多くの女性たちに読まれることを念頭に企画され、執筆されたものでしょう。それも、昨今の晩婚、非婚に共鳴しつつある多くの20代、30代、40代の女性に、圧倒的な共感と、人の不幸への喜びと(これはこの本のキャッチコピーにあるんだから言うことなしです)を、存分に味わわせてくれること請け合いです。
しかし、この本の凄いところは、それにとどまらず、オトコが読むことをひそかに期待し、実のところはオトコにこそ読んでもらいたくて執筆を進めたのではないか、と思うほど、男をうならせる鋭さとエネルギーがあることです。
「女の書くエッセイなんて読まなくてもだいたい分かるサ」などと小ばかにしているオトコたちは、この本を手にしてみるがいいでしょう。一見、女どうしの遠慮を知らぬパンチの応酬のような書き方に、オトコはハラハラしながら読み進み、最初のうちは、女の些細な日常をこうも懸命につづる二人に、なんてカワイイんだろうなんて思ってしまうかも知れません。
ところが、読み進んでいくうちに、オトコはこの往復エッセイが、単なる日常茶飯事を超えて、人間への鋭い観察力と洞察力に満ち満ちており、現代の日本で女が生きていくことへのひたむきな模索と、自らを客観化して見つめる真摯なけなげさに、強い感銘と衝撃を受けるのです。それを肩肘はらずに、さらりと絶妙な文章で表現していくキラめくような才気。
いま、日本のオトコでこれだけの文章を書ける人がどれだけいるでしょうか。ものを書く意欲も力もなくした日本のオトコたちは、老若を問わずもうダメになってしまったのではなかろうか、とさえ思ってしまいます。
そして、これだけの才能を発揮する彼女たちが、なぜ縁遠いのだろうかと、不思議に思ったりします。オトコがだらしなさ過ぎることも、もちろんあるでしょう。しかし何よりも、アガワとダンフミは、オトコたちよりもはるかに颯爽と時代の先を歩んでいることが大きいでしょう。彼女たちについていけるオトコは、本当に数少ないか、もしかして全くいないのかも知れません。お二人とも、「嫁行く」はもうあきらめるしかありませんね。(9月8日)
<キュビスムだけがピカソにあらず、生涯変貌を続けたことこそ本質>
20世紀最高の画家といえば、ピカソであることに異議を唱える人はいないでしょう。来年2001年は、ピカソの生誕120周年でもあります。
ところで、ピカソが左右非対称の人物画を描いたのは、偏頭痛のせいだった、という説をオランダの神経科医が国際会議で発表する、という記事が新聞紙上を賑わせています。ピカソの芸術の流れとかけ離れて、こうした珍説を撒き散らす神経科医の神経を疑いますが、怪しげな説にすぐに飛びつくジャーナリズムにも困ったものです。
日本でも、ピカソといえばすぐにキュビスムを想起するようです。しかし、ピカソの作風は絵画に限っても、写実主義、青の時代、ばら色の時代、キュビスム、古典主義、表現主義、シュルレアリスムとめまぐるしく変化を続けていて、「変貌の画家」という呼び方こそがピッタリで、ものの見方が絶えず変わっていったことこそ、ピカソの最大の本質のような気がします。
僕自身に関しては、ピカソの作品の中で感銘を受けることが多いのは、はっきり言ってキュビスム以外のものです。キュビスムが、視覚から受ける認識を破壊して、対象を解体しながら対象の本質に迫ろうと格闘した、その革命的な姿勢には感嘆しますし、時間と空間をこじ開けたようなグロテスクともいえる難解な絵画を見て、対象存在の深い謎を感じることも少なくありません。
しかし、僕が大好きなピカソは、どうしてもキュビスムをはさむ前と後の時期になってしまいます。貧困と苦悩、不安と絶望、怒りと歓喜、愛と性、戦争と平和など、ピカソがつねに描きつづけた人間的な主題の絵は、難解どころかとても親しみやすく、見る者に圧倒的な感動を与えてくれます。
最近、ピカソについて書かれた本を読んで、びっくりしたことが書かれていました。それは、ピカソは生まれた時、呼吸をしていなかった、という点です。助産婦は死産だと思ったとのことですが、医師の資格を持つ叔父はあきらめきれず、葉巻に火をつけて煙を赤ん坊に吹きかけ、これでピカソはようやく息を吹き返して泣き始めた、というのです。
ピカソは、生まれた時にすでに一度、「死」を経験していた。このことが、後のピカソになんらかの影響を及ぼしているのかも知れません。
その本を読んで、もう一つ驚いたこと。ピカソのフルネームは、なんでしょうか。パプロ・ピカソ。いえいえ、これは大幅な省略なのです。ピカソの正しい名前は、パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・フアン・ネポムセーノ・マリア・デ・ロス・レメディオス・シプリアーノ・サンティシマ・トリニダード・ルイス・イ・ピカソというのだそうです。
天才は、誕生の瞬間から名前にいたるまで、すでに凡人離れしているのですね。(9月5日)
<ジャーナリズムでなく孤高のテーマに逃げこんだアサヒグラフの休刊>
アサヒグラフはかつて、朝日ジャーナルとともに、朝日新聞の中で最も時代をシャープに切り取っていた先鋭ジャーナリズムでした。
僕の手元に、1965年3月10日付けのアサヒグラフ臨時増刊号があります。緊急特集「戦火のベトナム」と題するこの号は、泥沼化していたこの戦争の現実を、膨大な数の写真で捕らえたもので、圧倒的な迫力で見るものに訴えてきます。主な内容を目次から列記してみると。
「絶間なき戦火…流血」「カラー・戦闘」「米軍機、北ベトナム爆撃」「奇襲 戦うベトコン」「砲声の聞える穀倉地帯」「カラー・民族衣装を捨てぬ女性」「戦争さえなければ…美しきこの国土」「秋元本社特派員手記 ジャングル戦の恐怖」等々。
中でも、秋元特派員が撮影した「銃殺−ある高校生の死」は、何百行の記事よりも、はるかに見る者を揺さぶります。ベトコンとみなされたレ・バンクエンという私立高校の学生が、サイゴンの中央マーケット広場で市民たちが見守る中、10人の憲兵が一斉に銃を撃って公開処刑されたその一部始終を、8枚の連続写真で掲載したものです。
少年が縛られていた柱の地面に残る鮮血の写真には、次のような説明が付けられています。
「朝がこようとしていた 処刑は終った 兵士たちは引揚げていった 柱の下に血が残っていた 少年はベトナムの未来をどんな風に夢みていたことだろうか」
35年前のこの号は、ほんのひとつの例ですが、アサヒグラフは長い間、新聞が伝えきれないニュースの深層と断面を、時代の只中に深く切り込む形で報道し続け、時には新聞論調を引っ張り、新聞報道を補完する役割を果たしてきました。
そのグラフが、1923年の創刊から78年目にして、来月をもって休刊するというニュースに、少なからぬ驚きとともに、「やっぱりな」という感じを受けます。ここ数年のグラフは、意識的にジャーナリズムであることから遠のき、独自性を出そうとするあまり、当面のニュースや話題とは無関係な孤高のテーマを追うことが多くなり、マイナーであることに安住しようとした感さえあります。
たとえば現在発売中のグラフは、巻頭カラー特集「東北への誘い 民俗学者赤坂憲雄」と題して、東北学の紹介につとめていますが、こういうテーマでどれだけの読者をひきつけることが出来るのでしょうか。
アサヒグラフがジャーナリズムであることから逃げた時点で、休刊の道は決まっていたも同然といっていいでしょう。(9月2日)
ページの冒頭に戻る
メニューにジャンプ
2000年8月
<20世紀が暮れなずむ中、噴火の三宅島から集団疎開した小中高生たち>
「暮れなずむ」という言葉は、とても美しい日本語だと思います。「なずむ」は漢字で「泥む」で、広辞苑によれば「行きなやむ」「はかばかしく進まない」「とどこおる」などの意味です。「暮れなずむ」は、「日が暮れそうで、なかなか暮れないでいる」ことで、夏至の前後、日が長くなっていつまでも明るい夕暮れ時をイメージすればいいでしょう。昼から夜への移り変わりが、どっちつかずのままで、いつまでも未練を引きずっている様子を、どこか楽しんで味わっているような、日本的風情がある言い方で、この微妙な感覚は、英語ではなかなか表現しにくいものでしょう。
20世紀最後の8月もいよいよおしまいで、今世紀も残り少なくなってきました。僕は、ちょうど今ごろの時期は、「20世紀が暮れなずむ」という言いかたがピッタリのような気がします。「20世紀最後の…」というフレーズが、さまざまな場面で感慨を込めて使われ始めてはいるものの、「さよなら20世紀」というには気が早すぎるあと4カ月。そろそろ来年の年賀はがきのことがニュースになる一方で、年内にはシドニー五輪や米大統領選など大きなイベントや政治日程なども待っているという、まさに「暮れそうでなかなか暮れない20世紀」です。
そんな中、全国民の心ををくぎ付けにしているのが、噴火の三宅島から親元を離れて東京へ集団疎開した140人の小中高校生たちです。定期船、出港の汽笛、いつ再会できるか分からない家族との別れ。手を振る子どもたちと、涙で送る親たち。まもなく21世紀という中で、突如目の前に現れた、懐かしい日本の原風景ともいえるシーンに、僕たちは20世紀中頃の日本にタイムスリップしたような錯覚を覚えます。
死語になったと思われた「疎開」という言葉もどっこい生きていて、まさに「世紀暮れなずむ」を改めて感じ入ります。
来春に閉校が決まっている東京・あきる野市の都立秋川高校で、小中高校生たちは、これまでの生活とは一変した寮での集団生活が始まりました。現代っ子たちにはきつい試練でしょう。しかし、考えようによっては、日本の子どもたちの荒廃が指摘される中、地域全体の小中高校生たちが、すべて親元を離れて集団生活に入るという、戦後の日本ではほとんど例を見ない事態は、子どもたちを逞しく鍛え、見違えるように成長させる得がたい機会なのではないでしょうか。
過保護でヤワで、自己チュウで、一切の責任から逃げ、すぐにキレる日本の子どもたちを鍛えなおすためのヒントが、今回の集団疎開にあるような気がします。そう感じながらテレビのニュースを見ている人たちは多いのではないでしょうか。
「可愛い子には旅をさせよ」という古典的な教えを、世紀が暮れなずんでいるいまこそ、噛み締めてみたいものです。(8月30日)
<言うまいと思へど、この暑さをエネルギーとして有効利用できないものか>
「言うまいと思へど今日の暑さかな」とは、暑さをズバリ詠んだあまりにも有名な句ですが、作者は誰なのでしょうか。この句を一字変えて、こうしたくもなります。
「言うまいと思へど今日も暑さかな」。とにもかくにも、今年の暑さは記録破りとのことで、立秋も処暑も過ぎてのこの残暑は、ことのほか身体にこたえます。夕立もなく風もなく、どんよりと重く高湿度の熱気団が列島にへばりついているさまは、季節の推移が止まってしまった感さえあります。
この暑さをエネルギー源として有効利用できたら、人類のエネルギー問題は一挙に解決するだろうに、と思ってしまいます。昔から、そのようなことを考えたり、本格的に取り組んだ人たちは無数にいるのに、20世紀も終わろうとするこの期に及んでも、人類はまだ太陽エネルギーを効率よく使いこなすことが出来ていないとは、科学技術の怠慢のような気がします。
地球に降り注ぐ太陽のエネルギーは、人類全体が現在消費しているエネルギー総量の3000倍にもなるといいますから、地球の面積の3000分の1ほどのスペースに降り注ぐエネルギーを無駄に発散させずに、別な形のエネルギーに変換して蓄積するだけで、もはや化石燃料や核燃料に頼ることなく、人類は枕を高くして眠ることが出来るのです。
これまでに実用化されているソーラーハウスや太陽光発電は、費用が非常に高くつく上に、エネルギー変換効率も蓄積性も弱く、なにかもっと根本的に発想を変えて取り組まないと、普及は難しいでしょう。
磁場を利用したレンズ衛星のようなものを打ち上げて、宇宙空間に散逸していったり、地球の海面に到達している太陽光の一部を、局地的に収斂させて数千度から数万度の高温を作り出し、その高熱を直接、別な形のエネルギーとして保存する。レーザー光線に変えて、それを魔法瓶のような中に閉じ込めて、内部反射を繰り返させておき、必要に応じて取り出すとか。あるいは、エネルギーを吸収して姿を変える新物質に蓄えるとか。さらには、すぐにエネルギーに転換出来る形の質量として保存するとか。
暑い暑いとうだっているだけでなく、この暑さをエネルギーとして使うことを、21世紀の課題としたいものです。(8月27日)
<イリジウムの不思議な符合、燃やされる通信衛星と恐竜を滅ぼした巨大隕石>
地球のどこからでも電話がかけられる、を売り物にして、66個の通信衛星を地球の周りに巡らせるという、とてつもない構想に取り組んだのは、米イリジウム社でした。ドン・キホーテのような夢想を実現させて、世界中をアッと驚かせたのもつかの間、利用者が伸びずに事業が破綻してしまい、通信衛星はすべて大気圏に突入させて燃焼処分させるというから、これまたスケールの大きな破産処理です。
このイリジウムという社名を見て、太古の昔どこかで似たようなことがあったような気がしてならなかったのですが、ハタと思いあたりました。なんと、それは6500万年前に起きた地球の生命進化史上最大の出来事、恐竜の絶滅だったのです。
1億年以上にも及ぶ長期の繁栄を謳歌していた恐竜が、なぜ突然絶滅したのかは、さまざまな説が出されていますが、最も有力とされているのが、巨大隕石が地球に衝突して環境が激変したことです。ほかにも絶滅に向けた複合的な要因が重なっていたところに、この天変地異が直接的な引き金になった、という見方が妥当でしょう。
その物質的証拠が、イリジウムなのです。原子番号77のイリジウムは、白金鉱などで採掘され、白金との合金は電極や電気接点などに使われ、オスミウムとの合金は万年筆のペン先などに使われています。地殻中に存在する量は極めて少ないのですが、他の天体たとえば隕石などには、地球の1000倍もの多量のイリジウムを含むものがあります。そのイリジウムが、恐竜が絶滅した6500万年前の地層には、前後の地層に比べて数十倍から100倍も多く含まれているのです。
地球の各地でのイリジウム分布の研究から、地球に激突して恐竜を滅ぼした隕石は、直径が10キロメートル以上、重さ2500億トンと推定されています。それはどこに激突したのか。さまざまな研究が続けられ、いまではメキシコのユカタン半島という説が有力です。
恐竜たちは、夜空を白昼のように明るく染めて落下してくる巨大な物体を、どのような思いで眺めていたことでしょうか。おそらく、激突の寸前は隕石の破片が全天から降り注ぐ流星雨となって、美しくも壮絶な光景だったことでしょう。
いま、イリジウム社の66個の通信衛星が、大気圏に突入させられて燃え尽きるままに廃棄されるというニュースを読んで、僕は恐竜たちすべてが見上げていたであろう巨大隕石激突の夜空を思い浮かべるのです。
イリジウムという元素名は、その化合物がさまざまな色調を示すことから、「虹」を意味するギリシア語の iris からきています。
恐竜絶滅と通信衛星会社の破産。虹が消えた後に出現するのは、希望に満ちた新たな世界でしょうか。(8月24日)
<新パソコンへの買い替えに絶望して、自ら壊れた旧パソコンの心の内>
何年もの間苦楽をともにしてきたパソコンには心が宿り、自意識さえ持つようになる、といったら、あなたは信じますか。
96年12月に購入して以来、長らく愛用してきたパソコンを買い替えることにしました。ハードディスクの容量が、当時としては、最大クラスの2.1ギガバイトだったのが、しだいにファイルが増えるにつれて窮屈になり、これ以上ソフトのインストールも出来ず、作動も重くなっていたのです。
そこで、30ギガの容量を持つ最新機種を購入し、新旧のパソコンを並べて、プログラムやファイルを旧パソコンから移動させる作業に取り掛かりました。その作業が3割ほど進んだあたりで、旧パソコンの画面が、心持ち悲しげに曇ったような気がしました。僕には、旧パソコンが話しかけてきたのが分かりました。
(何をしているの? どうしてファイルを次々にコピーしているの?)
……じつは、いままで黙っていたけれど、新しいパソコンに乗り換えることにしたんだ。
(じゃ、ワタシはどうなるの? もういらなくなるってワケ?)
……新しいパソコンが軌道に乗って、とくに問題がなければ、君の役目は終わりだ。気の毒だが、廃棄処分にする。
(ひどい! ワタシ、いままで3年8カ月の間、一度だって壊れることなしに、あなたのために頑張ってきたのに。ワタシ、あなたのホームページが最優秀賞を受賞するのを、一生懸命支えてきたのよ)
……すまない。君には本当にお世話になった。でも、2.1ギガのメモリーではもはや動きが取れないんだ。それにWindows95はもう時代遅れなんだよ。
(メモリーは、増設すればいいじゃない。Windows98でも2000でも、ワタシにインストールすれば、ちゃんと動くわ。ワタシ、あなたの望むように頑張るわ)
……そうかも知れない。でも、もう新しいパソコンが君の隣に来ているんだ。
旧パソコンの画面が震えているのが分かりました。その時です。信じられないことが起こったのです。
(さようなら。これまで可愛がってくれてありがとう。新しいパソコンを大切に使ってね)という悲鳴とともに、旧パソコンは、フロッピーディスクの差込口から、突然、2個の部品を吐き出したのです。小さなバネと軸受けでした。
こうして、旧パソコンは自ら壊れ、二度と元に戻ることはありませんでした。心変わりした僕へのささやかな抗議。そして絶望と悲しみの中で、もはや不要とされた自分を、せいいっぱいのプライドで葬ったのです。
さようなら、旧パソコン。君の恩は一生忘れない。君との思い出は、僕の心の中にいつまでも生き続けるだろう。(8月21日)
<原子力潜水艦に閉じ込められた118人の乗員は、人類の姿そのもの>
いったいこれは、なんという事態なのでしょうか。月からでも乗員を生還させることが出来る人類が、わずか100メートルの海底にいる118人の乗員を救出することが出来ず、全世界が見守る中で見殺しにする以外に、なすすべがないとは。
そもそも潜水艦というのは、飛行機や船と違って最初から戦争目的のために作られた発明品です。最初に試みられたのは、18世紀後半のアメリカ独立戦争で、イギリスの戦艦への攻撃として使われ、それも失敗に終わったといういきさつがあります。
その後、度重なる戦争の度に改良が重ねられ、今日の原子力潜水艦にまで発展してきたのですが、海中に潜るという形態からしていかにも不自然で、破壊と殺戮のにおいがプンプンとします。平和目的としては、これほど利用しにくい乗り物もないでしょう。
20世紀も終わろうとしているこの時期に、ロシアの潜水艦はいったい何をしようとしていたのでしょうか。通常の演習だとしたら、アメリカやNATO諸国なども、このようにして世界の海のあちこちに潜水艦を潜らせているということでしょうか。この情報化時代に、あえて潜ることがどれほどの意味を持つのか、まったく理解出来ません。
もはや艦内の酸素も限界に近づき、救出作戦は時間との闘いで、非常に厳しい、という見方が広がっています。僕は、乗員の救出に時間がかかるならば、とりあえずは、潜望鏡のあたりからでもどこでも、細いパイプが入るような穴を開けて、まず酸素を補給すべきだと思うのですが。内視鏡が通る程度の穴で十分で、これによって酸素の補給と艦内の空気の換気を行い、乗員救出の時間をかせぐ方が、犠牲者を少なくする方策のように思います。
技術の粋を尽くした兵器文明の象徴ともいえる原子力潜水艦。その厚い金属の壁に閉じ込められて、身動きが取れなくなり、生きながら酸素欠乏による死を待つ118人の乗組員の姿は、まさしく人類の姿そのものであるように思えます。コンコルドの事故に続いて、20世紀文明が崩壊していく様子を目の当たりにする思いです。(8月18日)
<20世紀最後の終戦記念日と、戦争をしたくてうずうずしている人たち>
「20世紀最後の…」というフレーズが、ようやくさまざまな場面で使われるようになりました。「20世紀最後の原爆の日」「20世紀最後の甲子園大会」、そして今日8月15日は「20世紀最後の終戦記念日」。
暮れ行く世紀の陰影が、否が応でも日々の社会や個人の営みに、長い影を落としていることを、実感として感じるのでしょう。今年はじめに見られた中身のない「新ミレニアムスタート祝賀」騒ぎの空々しさにみんながようやく気づき、いまはまだ新時代が始まる前の、古い時代の終着点を目の当たりにしているのだということを確かめ合って、バツが悪そうにいまいちど座りなおしたという感じです。
それにしても、僕たち日本人は、この100年の収支決算を努めてあいまいにし、都合の悪いことがらは全部フタをして覆い隠し、21世紀には20世紀の何を克服し何と決別し、どんな21世紀を作り上げていくのかというビジョンを欠いたまま、どっちつかずの笑いを浮かべたまま、なんとなく21世紀に入っていこうとしているように思えます。
「戦争の20世紀と決別し、核と戦争のない21世紀を」と誰もが口にします。しかし、ほんとうのところは、なんだかんだと大義名分や理屈をこねて、日本の国と日本人を戦争に向けて鼓舞し、あわよくば天皇を中心とする政体を作りなおして、再び挙国一致の社会をつくることによって、あらゆる手段で覇権をねらう強い国家を作ろうとしている勢力が、少なくないという事実を甘く見てはいけないと僕は思います。
もっとはっきり言うと、戦争をしたがっている人たち、戦争によって領土を拡大し、アジアの盟主の座を獲得しようと狙っている人たちが、日本にはかなり大量に存在するということです。その人たちにとって、憲法改正は必然のなりゆきであり、通信傍受法も国旗国歌法も、戦時になればどんな拡大解釈も可能にする大切な布石でしょう。
昨日、NHKテレビで、昭和18年10月に神宮外苑で盛大に挙行された「出陣学徒壮行会」の記録映像が放映されていました。学徒だった人たちの多くの証言を聞いても、いったん戦争が始まってしまったら、それに反対したり抵抗したりすることは、いかに良心的な個人をもってしても絶対的に不可能なことなのです。
戦争のない21世紀を本気で目指すならば、戦争につながりかねない一切の制度や法律は最初から作らず、その恐れのあるものは一掃しておくこと。戦争に向かおうとするどんな小さな芽も、発芽しないような二重、三重のチェック機構を構築しておくこと。そして最も重要なことは、他国が関係するいかなる戦争にも加わらないという、強固な国民的合意を作っておくことです。(8月15日)
<お釣りにもらった初の2千円札、使うのはもったいないしどうしよう>
「2千円札持ってる?」というのが、挨拶がわりだそうです。記念貨幣じゃあるまいし、一国の流通紙幣が稀少価値でちやほやされるとは、などと嘆いているボクも、ついさきほどまで、手にしたことはもちろん、見たことすらなかったのです。
いましがた、近所のお店で5千円強の買い物をして、1万円札を出したところ、店員が「おつりは、千円札でいいですか」と言ったように聞こえました。ヘンなことを聞く店員だなあと思いながらも「いいですよ」と返事をしたところ、ジャジャーン、お釣りはなんと、手の切れるようなまっさらな2千円札が2枚も!
店員さんは、「2千円札でいいですか」と尋ねたのでしょうが、「2」を伏し目がちに小さな声で言ったのでしょう。
それにしても、初めて手にした2千円札をしみじみと眺むれば、いみじう趣こそあらめ。御簾の陰から恥ずかしげにおもてを半分ほど顕したる紫式部サマは、うっとりと目を閉じて、お口元の艶っぽさ。お札の肖像に色っぽさを感じるとは、「せくはら」やも知れぬと、どぎまぎす。
番号は、F702243NとF702244Nの連番です。このお店は、客が使った2千円札をお釣りに出したのではなく、金融機関で引き出したか両替したばかりの2千円札を、ボクに渡してくれたのでしょう。ボクだったら、自分の財布にある汚い千円札や1万円札を出して、2千円札と交換してしまうのに。もしかして、この店の店員さんは、発行と同時に2千円札をたっぷり個人的に確保して、もう飽きたのかも知れません。
ところで、ここでハタと考えてしまうのは、せっかく入手したこの2千円札、はてどうしたものか。うーん、スキャナで読み取ってホームページに載せたりしたら、通貨偽造幇助の罪になりそうだし、折り目もないピン札なので財布に入れるのももったいないし、額に入れて飾っておくようなものでもないし。
どこかの店で、カワユイ店員さんがいたら、使って見ようかなとも思うのですが。その店員さんが2千円札を知らかったらどうしょう、とまた心配にもなります。「ふざけないで下さい。ケーサツを呼びますよ」なんて言われたら、あの、その……。使う時には「ここのお店は2千円札使えますか」と最初に確認しようっと。(8月11日)
<日本の夏の原風景を蘇らせる蚊取り線香、匂いの成分は意外にも>
故向田邦子さんの随筆の中に、「野バラ」という歌の歌詞について、子どものころにとんだ思い違いをしていた、という話が出てきます。「わらべは見たり 野中のバラ」という下りを、「わらべは見たり 夜中のバラ」だとばかり思いこんでいて、「夜中のバラ」に、子どもが見てはならない大人の世界を感じ取ってドキドキしていた、というような話でした。
こうした思い違いというのは、だれにもいくつかあるもので、僕は最近まで「ジョチュウギク」というのは「女中菊」だとばかり思っていて、野に咲く薄倖で可憐な菊の花を想像していました。ところが可憐どころか正しくは「除虫菊」で、この花には、昆虫類に対して強力な運動神経麻痺作用を持つ、ピレスロイドという殺虫成分が含まれ、蚊取線香や ノミ取粉、農業用殺虫剤の原料となっている、ということを初めて知りました。
日本の夏の匂いといえば、まずは金鳥の渦巻き蚊取り線香ですが、この懐かしい匂いこそ、除虫菊の匂いなのですね。路地、縁台、夕涼み、線香花火といった、とっくに失われた日本の夏の原風景が、金鳥の蚊取り線香の匂いの中に、かろうじてユラユラと蘇ってくるのです。
近年は、電気蚊取り機が全盛とはいえ、金鳥の蚊取り線香は根強い支持層を持っていて、一見ダサイとも見える超レトロなパッケージデザインも、若い人たちには新鮮でオシャレに見えるらしく、トレンディーな浴衣と団扇にピッタリなのですね。
金鳥の蚊取り線香の成分は、ピレスロイドの化学合成が出来るようになってからは、合成ピレスロイドを使っているというのですが、あの匂いだけは合成出来ず、いまも除虫菊から抽出した匂いを添加しているそうです。
かつて日本が世界一の産量を誇っていた除虫菊も、いまはかろうじて瀬戸内地方の観光見本園で栽培している程度で、蚊取り線香の匂いとなる除虫菊はケニアから輸入しているのです。
日本の夏の匂いを守り続けるために、ケニアのお世話になっているわけですが、もともと除虫菊の原産はバルカン半島で、そうなると日本の「原匂い」といっていいのかどうかあやしくなってきますね。
僕は海外旅行をする時に、究極の必携品として、金鳥蚊取り線香をスーツケースにしのばせていきます。エジプトやトルコの地方のホテルでは、これが絶大な威力を発揮しました。撃退された蚊にしてみれば、この匂いがケニア産の匂いであることなど、思いもよらなかったことでしょうけど。 (8月7日)
<伏魔殿Suirenにひとりで戦いを挑んで敗れた、少女Suzuの物語>
千葉すず、水連に敗れたり。シドニー五輪代表漏れを不服として、千葉すずが国際スポーツ仲裁裁判所に提訴していた今回の経過を見て、僕はこんな劇画を思い描くのです。
昔々、水の豊かなある街に、Suirenという古色蒼然たる伏魔殿がそびえ立っていました。そこにはFuruhashiという大魔王を始め、数々の取り巻きや茶坊主どもがうごめき、密室では権力を強化するためのさまざまな策謀が練られていました。この街で働く民は、Furuhashiの言いなりとなることに長い間馴らされ、伏魔殿に刃向かったり悪口を言うものは、ただの1人もいなかったのです。
そんな街に、Suzuという飛び魚のように早く泳ぐ美少女がいました。Suzuはこの街には珍しく、思ったことをキッパリと、時にはズケズケという性格でした。Suzuの振る舞いを「生意気だ」として、眉をひそめる者もいましたが、Suzuは周囲の目など気にしないたちでした。
4年に一度、この街を代表する泳ぎの名手たちが、遠い異国に出かけていって、他の国々の名手たちと競い合う祭典の日が近づいてきました。Suzuは誰にも負けない練習を積んで、祭典に向けて絶好調となるよう調整を続けていました。自分が代表に選ばれることは、微塵たりとも疑っていませんでした。
しかし、伏魔殿の中では、ひそかにSuzu外しの策動が練られていたのです。何よりも大魔王のFuruhashiにとって、Suzuの日頃からの奔放な言動はことごとく癪にさわり、自らの権威を危うくしかねない危険な存在として映ったのです。
こうしてSuzuは、代表から外されました。納得できないSuzuは、この地域の歴史上初めて、伏魔殿Suirenに戦いを挑んだのです。強者ぞろいの強固な軍勢を相手に、Suzuはたった1人でした。
戦いの行方は始めから決まっているようなものでした。しかし、Suzuは最後まであらん限りの戦いを続け、全身傷だらけになり、ボロボロになって、矢尽き刀折れたのです。
草むらに横たわり、虫の息のSuzuの耳に、人の声が聞こえたような気がしました。「Suzu、よくやった」「勝ったのはSuzuのほうだ」。ヒソヒソ声だった民の声は、しだいに大きくなり、やがてほかの地域の人々も集まってきて、その声はうねりのように広がっていきました。
「Suzu、新しい空気を入れてくれてありがとう」「Suzuは、私達の代表だ」。Suzuは泥だらけの姿で立ち上がり、自分を応援して集まった人々に手を振って、笑顔で応えようとしました。人々は、生意気娘の目に、涙が浮かんでいるのを見ました。(8月4日)
<映画「グラディエーター」と、いまも殺し合いのために待機する兵士たち>
話題の映画「グラディエーター」をようやく観てきました。スペクタクル大作としてのスケールの大きさや、ローマ帝国を舞台に繰り広げる史劇としての興味深さ、元将軍で奴隷に貶められた男がローマ皇帝に復讐を挑むという人間ドラマの面白さなど、どれを取っても一級の作品で、SFXを駆使したパニックものやSF大作を見慣れた目には、極めて新鮮に映ります。
その中軸となっているのは、円形競技場の中で繰り広げられる剣闘シーンの壮絶さです。ラッセル・クロウの演じる奴隷が、ある時は同じ奴隷を相手に、ある時は次々に襲いかかる4頭建て戦車を相手に、ある時は猛獣がうろつく中で、捨て身の戦いを続け、観客はいつの間にか自分も競技場の中に放り出されていることに気付きます。
映画の中の競技場の観衆たちが(皇帝を含めて)、血で血を洗う剣闘の残虐さに熱狂し沸きに沸くほど、映画の観客たちはいたたまれなくなり、見せ物として命がけの剣闘を強いられる奴隷と自分が一体化して、戦っていることを感じるのです。殺さなければ殺される。だから殺す。ラッセル・クロウが相手を殺して生き延びると、僕たちもホッとします。そして、競技場で狂喜する観衆に対しては、違和感と反発を感じるのです。
自分が競技場に放り出されたら、どういう行動を取れるのか、考えてしまいます。僕は勝ち目がないと分かっていても、やはり戦って相手を殺そうとするでしょう。99%の確率で自分が殺されるとしても、それ以外に道はないでしょう。
そうしてみると、この映画が描くローマの円形競技場の光景は、この数千年間に人類が飽くことなく懲りもせずに繰り広げてきたあまたの戦争の凝縮なのではないでしょうか。前線に送り込まれた兵士たちは、敵の大群と対峙した時に、どういう行動を取れるのでしょうか。戦い、敵を殺そうとする以外の道はありません。敵前逃亡を図ったものが、味方によって殺されるのは、戦場の掟です。
この映画を見終わった後も、物語は終わっていないという気がずっと尾を引いているのは、いまもなお世界の各地で、意に反した殺し合いのために兵士として駆り出されている、膨大な数のラッセル・クロウたちがいるからでしょう。彼らにとって、円形競技場はいつも目の前に存在している現実なのです。(8月1日)
ページの冒頭に戻る
メニューにジャンプ
2000年7月
<1円で雪印牛乳飲み放題、人間の胃の大きさとバイキングの関係>
埼玉県春日部市の牛乳小売店が、今日29日と31日、「1円で雪印牛乳飲み放題」のサービスをして、安全性をPRするそうです。1円で飲み放題とはスゴイ、と色めき立ってみたものの、人間が一度に飲むことが出来る牛乳の量なんてたかが知れています。1リットルも飲めるかどうかでしょう。
飲み放題とか食べ放題は、ホテルのビュッフェ形式の食事やバンキングなどで、広く採り入れられていますが、料金のモトが取れるような内容のものは、以外と少ないものです。
オオッと目をひくものには、たいてい小さな字で制約が書かれています。例えば、シャブシャブ食べ放題。「牛肉のみのお代わりはご遠慮下さい」。つまりは、野菜や豆腐などをゼーンブ食べてからお代わりしろ、ということなのです。
高級寿司食べ放題。生ウニ・イクラもOK。小さな字で「最初に定番コースを召し上がっていただき、その後はお好きなネタをどうぞ」。その定番コースというのが、イカやタコ、キュウリ巻きなどの安ネタ中心で、しかももの凄いボリューム。定番コースがなければなあ。
500円で流し素麺が食べ放題という店があって、看板につられて入ったことがあります。とくに制約事項も書かれていないようだし、と安心していると、とんでもない落とし穴がありました。確かに素麺そのものは食べ放題なのですが、小さなお椀に入ったタレがすぐなくなってしまい、このタレがなんと一杯お代わりするごとに500円なのです。
本当にお腹一杯食べてみたいようなものには、食べ放題は存在しないか、あったとしてもたちまち大皿が空になってしまいます。例えば、エスカルゴ、キャビア、フォアグラ、トリフ、伊勢エビのお造り、トラフグのお刺身、フカヒレの姿煮。
つまりは、食べ放題・飲み放題も商売のうちであって、冷徹な利益計算がベースにあること。そして利用客は、いくらでもお腹に入るような錯覚に陥っているけれども、人間の胃袋というのは、たいして大きくはないということ。こうしたことを、お店の側と利用客が暗黙のうちに了解して成り立っている、一種のファッションでありイベントなのですね。
でも最初に書いた牛乳店は、イベントどころか死活問題。PRというよりも、雪印の経営陣に対する強烈な抗議デモといっていいでしょう。路上に牛乳をぶちまけるなどではなく、無理を承知で飲み放題とするところが、いじらしいではありませんか。(7月29日)
<冥土と紙一重の飛行機離着陸、墜落しても人命が助かる方法は?>
かつてツァーで一緒だったお婆さんは、飛行機の離着陸の時に必ずバッグから数珠を取り出し、手を合わせて目を閉じ、一生懸命何かを唱えるのを常としていました。それが念仏なのか、亡き夫が天国から守ってくれるよう祈っていたのかは、分かりませんが、離着陸の瞬間は冥土と紙一重なのだということがよく分かりました。
そうかと思うと、無事に着陸して減速が行われ、オーバーランの心配もないという段階で、乗客の間から盛大な拍手がわき起こることもよくあります。「そうか、無事に着陸するということは、拍手ものなのだな」と、なんだか九死に一生を得たような気分にさせられます。
パリ郊外で起きたコンコルドの墜落事故は、ITの時代にあっても、飛行機にとっての離着陸が命がけであることを衝撃的に物語っています。
僕はいつも思うのですが、離陸の前に客室乗務員が、身振り手振りで酸素マスクの使い方や救命胴衣の付け方などを説明しても、墜落という飛行機の最も典型的な事故に際しては、ほとんど無意味なのではないでしょうか。乗客の多くも「墜落したら終わりさ」という顔で、熱心に聞いている人はほとんどいません。
酸素マスクが降りてくることは、ときどきあるようですが、救命胴衣の方は、熱心に説明している割には、実際に役に立ったというケースはほとんど聞きません。記憶にあるのは、1982年の「逆噴射」事故で羽田沖に着水した日航機の機体から、乗客たちが救命胴衣を付けてボートに乗り込んでいたことくらいです。
結局のところ、墜落してしまったら一巻の終わりというのは、飛行機100年の歴史を通じて全く変わっていないのですね。
21世紀の飛行機は、墜落しても乗客の一命だけは助かる、というシステムにならないものでしょうか。戦闘機の場合は、墜落の寸前に乗員がパラシュートで脱出して無事、というケースをよく耳にします。
旅客機の場合も、システムが墜落を感知したら、乗客1人1人を客席ごと上空に放り出して、パラシュートが自動的に開くようにすれば、何割かの命は助かるのではないでしょうか。コンコルドのように離陸直後で高度が足りない場合には、パラシュートが開く高さまで乗客を放り上げる仕組みにしたらいいでしょう。
離着陸の数珠や拍手は、20世紀の飛行機を物語る語りぐさとして、このへんで終止符を打ちたいものです。(7月26日)
<トルコに魅せられた2週間の旅、イスタンブールより愛をこめて>
イスタンブールに行きたい、と思うようになったのは、いつ頃からでしょうか。そもそもは、007シリーズの最高傑作「ロシアより愛をこめて」に深い印象を受け、舞台となったアヤ・ソフィア大聖堂や地下宮殿、さらにはショーン・コネリーとロパート・ショーの映画史に残る名対決が繰り広げられたオリエント急行の終着駅を見たい、と憧れていたのです。それに加え、今年5月末から6月始めにかけて西安を訪れたとき、シルクロードのヨーロッパ側の起点が現在のイスタンブールであることを知って、居ても立ってもいられなくなりました。
というようなわけで、2週間近くトルコ国内を旅してきました。エーゲ海や地中海沿いの都市を回って数々の遺跡を訪ね、カッパドキアの奇岩や洞窟の教会などを見て、後半は東西文化の交差点イスタンブールへ。
ビザンチウム、コンスタンチノープル、イスタンブールと3つの名前で呼ばれ、人口1500万人を抱えるこの大都市は、まさに街全域が世界史そのもの。街の隅々まで、さまざまな民族や国が支配と興亡を重ねた残照が煌めいていて、それぞれの時代と文化が厚い地層を形作っているのが、巨大なうねりとして体で感じられます。
ボスポラス海峡を挟んでヨーロッパとアジアの2つの大陸にまたがるこの街を眺める時、時間と空間のダイナミズムに圧倒されてしまいます。
トルコの人々が、国を挙げてこれらの歴史遺産や文化財、街の景観を守り続けている様子にも、強い感銘を受けました。日本は木造建築が多いせいかも知れませんが、古い建造物や遺産をいとも簡単に壊して新しい建物を建ててしまうのは、なんとも寂しい限りです。
中央アジアの遊牧民から、西へ向かったのがトルコ人で、東へ移ったのが日本人だ、とトルコの人々は言います。言葉の構造も似ているし、顔つきも日本人に近い人々が沢山います。トルコの人々は勇敢で誇り高く、そして極めて親日的です。それなのに僕たち日本人は、トルコについてあまりにも知らな過ぎるのではないか、と反省させられます。ましてや、かつて、いかがわしい風俗店にこの国の名をつけていたとは、言語道断で恥ずかしい限りです。
トルコに限りなく魅せられた今回の旅は、世界の中の日本について考えさせられた旅でもありました。トルコにはぜひもう一度行ってみたいと思います。イスタンブールより愛をこめて…。(7月23日)
<過去4千年間の世界の戦死者は30億人、という驚愕のデータ>
だいぶ古い本を読んでいたら、オヤと思う記述に出くわしました。さる閑人が調べ上げたところによると、人類の過去4000年の間に地球上に起きた戦争は、大きなものだけで1万4500件もあり、戦死者の総数は30億人以上に達する、というのです。この本は30年以上も前に書かれているので、今現在で調査し直せば、戦争の数、戦死者ともさらに増えていることは間違いないでしょう。
それにしても、30億人が戦死しているとは、驚愕のデータです。僕は最初、3億人の誤りではないかと思ったくらいです。現在の地球の総人口が60億人ですから、ざっとこの半分にあたる人類がこれまでに戦死したわけで、いまの私達の生活も文明も、30億人の戦死者たちを踏み台にして成り立っていることを知るべきです。
人類の歴史はまさに凄まじい戦争の歴史ですが、進歩や発展には戦争が原理的に不可避なのでしょうか。それとも戦うことは、人類のDNAに深く刻みこまれた魔性の本能であり、拭い落とせない原罪なのでしょうか。
いくさのない平和な社会というものは、すべての部族、すべての民族や国民が希求しつつも、いつの世もつかの間の夢に終わってしまい、現実には石や斧で頭を割られ、槍や弓で首や胴体を突き抜かれ、刀で腕や首を切り取られ、銃弾や砲弾で内蔵を粉々にされ、雨あられと降る爆弾で肉体を木っ端微塵にされ、それぞれにかけがえのないたった一度の人生を、呻くしかない地獄の苦しみの中で悶絶しながら、30億人が息絶えていったのです。
かろうじて戦死を免れたとしても、女性たちは陵辱され、残った年寄りや子供は略奪と圧迫の中で、明日なき生活を強いられていきました。結局のところ、悪魔や地獄は、別世界のことではなくて、現実のこの世のもうひとつの姿なのですね。
21世紀の人類も、さらなる進歩と併行して、さらなる戦慄の地獄図を展開していくのかと思うと、暗澹たる気持ちになります。
進歩に戦争が不可欠ならば、もうこのへんで進歩のレールから下り、進歩も戦争もない生き方を取るしかありません。人類30億人の戦死者を打ち止めにするには、新世紀と新千年紀に切り替わる今こそが、またとない大転換のチャンスではないでしょうか。(7月11日)
<釣り竿が折れたら保険金が下りる釣り保険、ならばこんな保険は>
ニフティがインターネットで「釣り保険」の取り扱いを始めるそうです。補償期間が3泊4日のタイプでは、保険料が500円と手頃な料金で、釣り中の事故でけがをしたり死亡した場合のほかに、釣り竿が折れたり、カメラが水に濡れて故障したような場合にも、保険金が下りるというのがミソです。
なかなか便利な保険を考えついたものだと感心する一方で、釣り竿が折れたくらいで保険金を払うのは過保護すぎやしないか、という気もしないでもありません。太公望たるもの、竿くらい折れてこそ一人前ではないですか。こんなヤワなことでは、保険金目当てに、いらなくなった釣り竿をわざと折る「保険金竿折り事件」が発生するかも知れません。
いっそのこと、隣の釣り人と糸がからまってけんかになった場合の補償とか、魚に餌だけ食いちぎられた時の補償、さらに大魚を取り逃がした時の悔しさへの補償とか、一匹も釣れないで帰りに魚を買って帰る時のメンツ丸つぶれ補償とか、いろいろなケースを補償の対象にすれば、さらに人気が出るでしょう。
ほかにもいろいろな保険を発売したらどうでしょうか。飼い犬に手を噛まれた時の「愛犬反抗保険」。カラスにつつかれた時の「都会カラス保険」。楽しみにしていたコンサートが出演者の都合や悪天候などで中止になった場合の「コンサート中止保険」。プロ野球の観戦に行って、ひいきチームが大差でコテンパンに負けた時の「応援チーム完敗保険」、等々。
シリアスな保険も発売しましょう。「未成年凶悪犯罪保険」。自分の子供が、凶悪犯罪を起こして、他人を殺傷した場合の、被害者への補償や弁護士費用のための保険です。掛け金は、14歳からしだいに高額になって17歳でピークになります。何事もなく無事に成人を迎えることが出来た場合は、お祝いの還付金が出るようにしたらいいでしょう。
21世紀中に人類が滅亡した場合の保険、というのも逆説的で魅力的でしょう。幾多の困難を克服して、無事に人類が22世紀の開幕を迎えることが出来たら、保険加入者の子孫に多額の還付金が支払われることにします。不幸にも途中で人類が滅びてしまった場合は、保険会社も加入者ももはや存在しないという、幻の保険になるのです。(7月9日)
<狐の嫁入りについての徹底考察、なぜ天気雨なのだろうか>
先日、行きつけのあるお店から、開店20周年記念の手ぬぐいをもらいました。この手ぬぐい、なんと狐の嫁入り行列を影絵にして染め抜いているのです。シュールで緊迫感ただよう中にも、不思議な懐かしさを覚えるのはなぜでしょうか。
狐の嫁入りといえば、天気雨の別名でもあります。お日様が照っていて、真上には青空が広がっているのに、パラパラと、時にはザアザアと雨が降っている。時間はほんの数分間程度なのですが、あり得ないはずの現象に、これは現実の世界の出来事なのだろうかと、ふと不安な気持ちにさせられます。昔から、天気雨の時に、狐の嫁入り行列が見える、とも言われます。
天気雨は、現実の世と異界とが、何かの拍子に交差する瞬間に出現すると考えられたのでしょう。それは異界で、とても重要な儀式が行われている真っ最中であるという、サインのようでした。
こうした言い伝えは、何故生まれ、言い伝えられてきたのでしょうか。僕が想像するには、狐が人間を真似て嫁入り行列をするのではなく、じつは人間の嫁入り行列こそが限りなく狐的世界に入りこんでいって、知らず知らずのうちに狐の嫁入りになってしまったのだ、と解釈するのが正しいのではないでしょうか。
嫁入り行列は、映画やテレビなどで見ると、だれもがゆっくりと一歩ずつ踏み出すように歩いています。ところどころで、みんなが打ち合わせたように一斉に、後ろを振り返ったりするのは、まさに狐たちの仕草そのものです。もっと大きな理由は、お嫁さんの白塗りの化粧が、目が少しつり上がり気味の狐の花嫁そっくりになっているのです。
知らない村の、知らない家に嫁いでいく、花嫁さんの心のうちも、花嫁さんを送り出す実家とその村の人々の心情も、異界を行くようなおぼつかなさと、幻覚の中の出来事に似た不安定さが、いりまじっていたことでしょう。
山間部の天気は変わりやすく、照っていてもすぐに雨に変わるし、その切り替わり目では天気雨にもなる。嫁入り行列は、空模様がどう変わろうと、みな顔色一つ変えることなく、ゆっくりとした歩みをひたすら続けるのです。
天気雨の中を、騒ぐこともなく静かに進む花嫁行列。それを遠くから、農作業の手を休めて見る人々には、それこそが狐の嫁入りに見えたことでしょう。
花嫁行列の、華やいだお祝い気分と、言葉に出せない悲しみ。花嫁さんの喜びと、目にためた涙。これこそが、天気雨の真の正体なのだという気がします。(7月6日)
<映画「ミッション・トゥ・マーズ」と、火星の知的生命興亡の歴史>
遅ればせながら映画「ミッション・トゥ・マーズ」を観てきました。CGや特撮を駆使した火星の光景はすばらしく、娯楽作品としては1級の出来映えといっていいでしょう。ただ、ラストに向けてのクライマックスは、せっかくの盛り上がりを見せながら、着地が説明っぽくなり過ぎていて、拍子抜けの感がありました。
火星を描く小説や映画は、まず私たち人類が太古から抱いてきた「あの星には、何かがいる」という直感をベースに展開されるのが定石です。だから、火星に着陸した乗組員たちが、「得体の知れないなにものか」に遭遇するあたりは、観客の方もとっくに期待の中に折り込み済みで、そのくらいでは驚きません。
問題は、それが何者なのか、なぜそこにいるのかを、意外性と説得力を持って語り、映画としてどんな決着の付け方をするかです。現代科学の最新知識とセンス・オブ・ワンダーを、どう結びつけることが出来るかが、ポイントといってもいいでしょう。
「ミッション・トゥ・マーズ」では火星を、かつて高度な文明を持つ知的生命体が栄えていた星として捉えているのは、当然とも言える設定ですが、ここに残存の一部が宇宙船とともに残っているというのが、プロットとしていかにも不自然です。だから最後まで、無理な説明調がつきまとってしまうのです。
僕が脚本を担当するなら、火星はかつて高度に進化した文明が完全に滅びてしまった惑星として描き、知的生命体の末裔さえも見つからない「死の惑星」にします。そして数億年の昔、滅亡を前に彼らが残した文明興亡の記録が、巨大遺跡の深部に残されているのを、人類の探査体が発見し、ひも解いていくのです。
映画の主力部分は、火星で絶頂に達した文明が瓦解していくさまの映像で、火星探査の乗組員たちは最後まで脇役に徹します。記録映像を再現し終わった火星では、寂寞とした荒涼感が漂うだけ。その虚無感のままで終わってしまってもいいし、あるいは、地球に帰還する宇宙船の出発を、物陰から見守る生き物たちの目で終わってもいいでしょう。
栄枯盛衰は、惑星の文明とて例外でないように思います。火星の姿は、何億年後かの地球の姿そのもの、と思って見るのもまた味わい深いものがあります。(7月3日)
ページの冒頭に戻る