
ニュース&トピックス(01年−06年)
<このページの見方ガイド>
このページは、21世紀を歩くためのさまざまなニュースや情報、21世紀の行く手に関係しそうな話題、21世紀初頭に完成、オープン、スタート、実施などが計画されているプロジェクトやイベントについての情報などを、幅広く収録していきます。
2001年−2006年に報じられた次の項目については、クリックすると説明のところにジャンプします。2018年に有人月面探査、20年以内にシロクマ絶滅、小惑星衝突300分の1の確率、日本の真夏日は今世紀末に140日に、梅雨の雨量10%増、ユビキタス関連市場、アジアの原発発電量、エネルギー消費量のピーク、甲子園球場建て替え、中国が火星探査機、飯田橋に超高層ビル群、大阪駅ホームにドーム、中国のGNP、3軒に1軒が一人暮らし、日本のリンゴとミカンは壊滅、世界のすべての村をネットで、小惑星が地球に超接近、太陽系外惑星の探索、火星の凍土調べる探査機、エアバスの次世代機、2010年冬季五輪はバンクーバー、2009年までに純国産旅客機、米同時多発テロ跡地の再開発、世界の新規がん患者、70億人が水不足、燃料電池自動車年間100万台、東京湾岸に国際的映像拠点、日本の有人宇宙飛行、美術館1000館結ぶサイト、新日本石油が火力発電、TBSが赤坂に高層ビル、日本の人口は2005年がピーク、2880年に小惑星激突、NASAの次世代宇宙望遠鏡、燃料電池市場4千億円規模に、紙の薄さのディスプレイ、20年ぶり紙幣一新、小惑星が超接近、人類の発展は2030年までに下降、車交通量は2030年がピーク、新宿御苑を「環境の杜」に、次世代シャトル、ホームページによる選挙運動、東北・高崎・常磐線を東京駅に延伸、地球外文明へのメッセージ、カシオが小型燃料電池、通信衛星で超高速ネット、火星ヘ原子力探査機、日本の人口ピークは2006年、日本の人口減少早まる、日本独自の有人宇宙船、ナノテク市場は92兆円に、2015年までに月への観光旅行、DNAを使ったコンピュータ、16ギガのフラッシュ・メモリー、マッチ箱大の指紋照合装置、巨大隕石直撃は5千分の1、世界人口は2050年に93億人、東海地震2005年までに発生、腕時計型パソコン、世界の気温は5.8度上昇へ、がん細胞に寿命与え増殖防止、富士通も二足歩行ロボット、ネット利用の電子入札、近ツリが宇宙旅行クラブ、宇宙分野3機関を統合、世界人口のピーク、登記申請を電子化、家庭用燃料電池、トキの野生復帰、東京水産大と東京商船大統合、NASAが観光用宇宙船、NASAが水星探査機、口径百メートルの巨大望遠鏡、宇宙ステーションとネット授業、彗星に探査機激突計画、天然ガスの比率アップ、宇宙太陽光発電、慶大が先端生命科学研、エックス線より安全に透視、中国も国際宇宙ステーション参加、携帯電話が新幹線チケット、美醜を判断できるロボット、メタン・ハイドレート商業化、宝酒造がゲノム解析センター、蛍の発光原理生かした照明、光通信の1千万倍の量子通信、降雪量や真冬日減少、ネット上に仮想工業団地、人工衛星よるナビ・システム、甲子園球場建て替え、固定電話をネット化、チリに大型電波望遠鏡群、20社が風力発電支援、アサヒビールが風力発電使用、燃料電池バス実用化、全国大学の研究をデータベース化、「2001年宇宙の旅」がデジタル音響化、早大がインターネット授業、アジア人の遺伝子解析、クローン人間作製を証言、東京23区は1世帯2人割る、京王電鉄が情報通信事業、燃料電池使う列車、61インチのPDP、世界最大能力の光通信、富士通が全製品環境配慮型に、NASAが火星観測衛星、トミーが会話ロボット、日本製粉がDNAチップ、次々世代携帯電話、富士山噴火の訓練、温暖化ガス削減達成は困難、日本橋の首都高地下化、野鳥の12%が絶滅危機、1枚でスパコン並みの半導体、イスラエルでクローン人間作り、中国が有人宇宙船、ネットで香りを送信、中国が1万キロの高速鉄道網、ヒトの遺伝子持つクローン牛、次期エアバス、三菱化学と富士通がゲノム創薬、4000万世帯に超高速ネット、上海でリニア起工式、世界人口は2050年に93億人、風力発電の目標引き上げ、イラクが3年以内に核爆弾、ネット技術使うIP電話、花粉を出さないスギ、ポストブラウン管のPDP、天然ガスから燃料電池用水素、平均寿命は2035年に85歳、ロボットが戦場の主役、オランダがミンク毛皮生産禁止、アナログTV全廃は2011年、携帯で複数動画を再生、7社がネット放送事業、小惑星に軟着陸、温暖化の損害は年35兆円に、ソニーが環境行動計画、会話する人間型ロボット、国債残高、携帯で操作するロボット、世界水フォーラム、クローン人間誕生へ、イネゲノム完全解読、ウェアラブルパソコン、大間原発の着工、平均寿命が93歳に、燃料電池は1兆円市場に、声のタイムカプセル、光を瞬間的に停止、富士山噴火想定し大規模訓練、バイオ食品に独自マーク、南極の棚氷が崩壊危機、地上波TVデジタル化、致死性の人工ウイルス、地球環境は危険な岐路、マンションに100年コンクリート、絶滅危惧種のクローン再生、宇宙へのメッセージ募集、クローン人間作製に着手、有線放送が超高速通信、陽子崩壊観測装置、地球の平均気温上昇、映画づくりをIT化、ネットで運行状況拡大、世田谷区の公用車はディーゼル全廃、燃料電池で家庭用発電、クラーク氏がDNAを宇宙へ、各地で新世紀到来祝う、平山郁夫氏大作完成
97年2月からの「ニュース&トピックス」は、バックナバーとしてページを分けてあります。バックナンバーの説明は、このページの後方にあります。バックナンバーの方も、ぜひご覧下さい。
メニューにジャンプ
2006年
2005年
- 米航空宇宙局(NASA)が、2018年に再び有人月面探査を行う計画を発表。1972年以来となる有人月面探査で、4人の飛行士が1週間ほど月に滞在する。将来の有人火星探査への肩慣らしの意味を持つという。(8月1日夕刊各紙)
- 2029年4月13日の金曜日に直径400メートルの小惑星が地球に衝突する可能性。NASAによれば衝突の確率は300分の1で、今世紀中の衝突確立としては最高のトリノスケール2とされた。(12月25日夕刊各紙)
- 国立環境研究所と東大気候システム研究センターなどが、スーパーコンピューターを使って温暖化の影響を試算したところ、日本の真夏日は2050年ごろに20世紀中の倍の100日になり、今世紀末には140日に前後まで増加するという予測が出た。(9月17日各紙)
- 地球温暖化が進めば、日本の梅雨の雨量は2070年ごろに10%強増加する、と東大気候システム研究センターのグループが試算をまとめた。発達した梅雨前線が日本付近に停滞しやすくなり、南からの湿った気流に刺激されて、局地的に集中豪雨が激しさを増す可能性が高い、という。(8月23日日経)
- パソコンや携帯電話、家電製品などが、いつでもどこでもつながるユビキタス社会に関連する日本国内の市場は、2010年には2003年の3倍の87兆円規模になる、と2004年版情報通信白書が予測。(7月6日読売夕刊)
- アジアでの原発建設が90年代後半から急増しており、2030年には発電量が2.5倍になって世界の全発電量の27%を占める、と国際原子力機関(IAEA)が報告書で見通し。アジア地域は天然資源に乏しく、人口増でエネルギー需要が拡大しているため、としている。(6月27日読売)
- 日本の最終エネルギー消費量は2022年度をピークに減少する、と経済産業省が予測。人口の減少や生産活動の鈍化などによるもので、今後の原発増設計画など各方面に影響を及ぼすとみられる。(2月26日朝刊各紙)
- 阪神電鉄は、甲子園球場の老朽化が進んでいるため、現在と同じ天然芝の開放型球場として建て替える計画。早ければ2008年に着工し、プロ野球や春夏の甲子園大会に支障をきたさないよう、段階的に工事を進めて2010年完成をめざす。(2月4日日経夕刊)
- 東京・文京区のJR飯田橋駅北側に大規模再開発の計画。約9ヘクタールの敷地に、5棟から7棟の超高層ビルを建設し、オフィスや居住用とする。2010年の完成をめざしており、六本木ヒルズに匹敵する都心再開発となる。(12月17日読売夕刊)
- JR西日本が2011年をめどに大阪駅を大改造する計画を発表。駅北側に28階程度の高層ビルを建て、ホーム全体をドームで覆って南北連絡通路を通す。通路の上には広場を作り、ホームを行き来する列車を見下ろせる。(12月10日日経)
- 高齢化の進行により、2025年には日本の世帯の3軒に1軒が一人暮らしになることが、厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所の推計で明らかに。とりわけ、75歳以上の一人暮らしは2000年からの25年間で3倍に増えると予想。(10月17日読売)
- 農林水産省系の独立行政法人の研究によると、地球温暖化の影響で2060年には、日本の年平均気温が2.2度上昇。これにより国内のリンゴとミカンの主産地は、ほとんどが栽培に適さない地域となる。(10月4日朝日)
- 12月にジュネーブで開催される国連の「世界情報社会サミット」で、2010年までに世界のすべての村をインターネットで結ぶ行動計画案が提出され、採択をめさす。40カ国が首脳級の参加を表明しており、情報格差の解消などが主要テーマとなる。(9月23日毎日)
- 2014年3月21日に直径1.2キロの小惑星「2003QQ47」が地球に超接近。英国クイーンズ大の研究チームによれば、地球に衝突する確率は90万9000分の1程度だが、衝突すれば広島型原爆の800万倍の衝撃をもたらすという。(9月3日読売夕刊)
- 南米チリの高地に64台の大型電波望遠鏡を並べ、太陽系外惑星を探索する国際プロジェクトがスタート。日本も250億円を分担して参加することを文部科学省が決定し、2011年に建設が完成する。(8月20日読売)
- 米航空宇宙局(NASA)は、火星の北極圏付近の凍土を調べる探査機「フェニツクス」を2007年に打ち上げる。2008年に火星に着陸し、80%が水から成る凍土を採掘、生命の痕跡や火星の歴史などを調べる。(8月6日読売)
- 文部科学省の科学技術・学術審議会は、2009年までに機体からエンジンまですべて純国産の旅客機を官民で開発することなどを盛り込んだ長期計画を策定。機体を2007年までに開発して外国製エンジンで就航し、国産エンジンを2009年までに完成させる。(5月28日読売夕刊)
- 2880年3月17日に、直径1キロの小惑星「1950DA}が、1000分の1の確率で地球に激突の危険があるとNASAなどのグループが発表。太平洋に衝突すれば、日本で1万人以上の死者が出る恐れも。(9月28日朝日夕刊)
- NASAが2010年に、ハッブル宇宙望遠鏡に次ぐ次世代宇宙望遠鏡を打ち上げることを発表。ハッブルの高度が約600キロなのに対し、次世代望遠鏡は地球から150万キロ離れた空間で観測を行なう。(9月11日日経夕刊)
- 国立4大学と42企業が産学協同で、厚さ0.2ミリと紙並みの薄さのディスプレイを、5年後をめどに開発する。携帯電話などに使われている有機エレクトロルミネッセンスの技術を使い、薄さを極めたシートディスプレイをめざす。(8月9日朝日)
- NASAは、7月初めに発見された直径2キロの小惑星「2002NT7」が、2019年2月1日に地球の軌道に超接近して交差すると発表。衝突の確率は25万分の1というが、世界の天文台に観測強化を呼びかけている。(7月25日各紙夕刊)
- いまの勢いで天然資源の消費が続けば、人類の発展は2030年までに下降に転じる、と世界自然保護基金(WWF)が警告。各国は資源節約やエネルギー転換など緊急の対策を取る必要がある、としている。(7月10日毎日夕刊)
- 政府は現在禁止されている選挙期間中のホームページによる選挙運動を、2004年の参院選から解禁する方針。候補者が開設したホームページ上での動画や音声の活用や、掲示板やチャットの開設も認める。(4月8日日経)
- JR東日本は現在上野駅発着となっている東北・高崎・常磐の各線を、2009年末をめどに東京駅まで延伸する。これにより上野−御徒町間で233%となっている朝の混雑率は、180%以下に緩和される。(3月24日朝日)
- NASAは原子力エネルギーを使った宇宙探査機を、2009年に火星ヘ打ち上げる。原子力は太陽電池などに比べて高出力で寿命も長いなどの利点があり、2010年以降はロケットの推進力としても実用化を目指す。(2月5日日経夕刊)
- 国立社会保障・人口問題研究所が公表した推計によると、日本の人口は従来の予測より1年早く2006年にピークを迎え、以降は減少に転じる。少子化は一段と進み、年金や医療、雇用などさまざまな分野で影響は深刻に。(1月31日各紙夕刊)
ページの冒頭に戻る
メニューにジャンプ
2001年
- 宇宙開発事業団が日本独自の有人宇宙船構想をまとめた。総開発予算1000億円で2008年以降に打ち上げ、一般人の宇宙飛行も企画する。参加費用は一人7億円となるが、将来は数千万円に抑えるという。(12月30日日経)
- 産官学で構成する米のナノテク(超微細技術)推進組織「ナノビジネス・アライアンス」が、ナノテクを応用した製品やサービスの世界市場規模は、2008年に7000億ドル(約92兆円)に達するとの見通しを発表。(12月28日日経夕刊)
- 2015年までに月への観光旅行を実現させる民間プロジェクト「ルナ・クルーズ・プロジェクト」が、日本の研究者や若手エンジニアらが参加して28日に発足。月のホテルのデザインから資金調達までを広く手がける。(12月26日毎日夕刊)
- イスラエルのワイツマン研究所のチームは、DNA(ディオキシリボ核酸)を使ったコンピュータを開発したと発表。DNAの4種類の塩基の配列が入力、出力、およびソフトウェアの役割を担い、1秒に10億回の演算が可能という。(12月14日日経)
- シャープと東北大学は、現在の10倍以上の容量を持つ16ギガバイトのフラッシュ・メモリーを開発、2006年に実用化する。20時間分の動画を記録することが出来、DVDに替わる可能性も出てきた。(12月7日日経)
- 半導体設計などのDDS(名古屋)がオムロンと共同で、マッチ箱サイズの指紋照合装置を開発し、2002年3月に発売する。さまざまな装置に組み込めるため、プリンターなどのOA機器や車、金庫、建物の出入り口などに使えるとしている。(11月28日日経)
- シチズン時計と日本IBMは共同で腕時計型パソコンを開発した。携帯情報端末としての機能を持ち、インターネットにも接続できる。2002年3月をメドに大学関係者らに試用してもらって意見を求め、実用化につなげる。(10月12日各紙)
- 世界の平均気温は2100年までに最高5.8度上昇し、沿海や島嶼地域は居住不能になるほか、旱魃や農業への打撃などで大被害をもたらす、と世界の科学者でつくる「気象変動に関する政府間パネル」が報告書。(10月2日日経)
- ホンダのASIMOに続いて、富士通も二足歩行のヒューマノイド(人間型)ロボット「HOAP−1」を発売する。1体500万円程度となる見込みで、今後3年間で研究機関などに100体を販売する。(9月11日毎日)
- 世界の人口は2070年にピークの90億人に達する、と欧米の研究グループが英科学誌ネイチャーに発表。国連の世界人口推計では2100年に95億人に達するとされているが、今回の研究はそれを下回る。(8月2日各紙)
- 日石三菱は、家庭用の据え置型燃料電池の試験運転を7月12日から開始。ナフサから水素を取り出す方式で、2004年をメドに実用化を目指しており、家庭用燃料電池をめぐる実用化競争は一気に本格化へ。(7月5日各紙)
- NASAは1967年に発見されたテンペル第1彗星に、探査機を激突させて組成や内部構造を探るディープインパクト計画を決定。2004年に探査機を打ち上げ、2005年7月4日の米独立記念日に激突させる。(5月26日毎日夕刊)
- 経済産業相の諮問機関である総合資源エネルギー調査会の小委員会は、日本のエネルギー総供給量に占める天然ガスの比率を、現在の13%から2020年をメドに欧米なみの20%に高めることを提言。(5月24日日経)
ページの冒頭に戻る
メニューにジャンプ
- JR東海は2003年秋から携帯電話で新幹線の指定席特急券を予約し、チケット代わりに携帯電話で改札を通過できるシステムを採用する。JR東日本も2005年度をメドに、携帯電話にICチップを埋め込みチケットレス化へ。(4月26日日経)
- 美醜を判断できる人工知能ロボットを、北海道工業大学教授らとベンチャー企業が開発。美しい風景画を見せると「とてもよい景色ですね」と音声で反応し、汚れたダンボール箱を見ると「雑然としていますね」などと評価する。(4月25日読売夕刊)
- 国立天文台が欧米の機関と共同で、チリのアンデス山脈アタカマ砂漠に、直径12メートルの高精度アンテナ64基を約14キロ四方に配置する大型電波望遠鏡群を建設、2002年に着工し2010年完成目指す。(4月7日各紙)
- ソニー、セイコーエプソン、トヨタ自動車など20社が、風力発電を支援する日本自然エネルギーとグリーン電力契約制度の契約を締結。20社は風力発電事業者に、年間合わせて約1億円を15年間継続して支援する。(4月6日読売)
- 早大が4月から、総合講座「文化研究とコンピュータ」など3科目についてインターネット授業を開設、学生は教員への質問をメールや掲示板で行なう。このうち総合講座はロシアと韓国の大学にも配信される。(4月1日読売)
ページの冒頭に戻る
メニューにジャンプ
- 米下院公聴会で、ケンタッキー大学のパノス・ザボス名誉教授が、今後18カ月から24カ月でクローン人間をつくることを証言。米大陸の外でつくるとしており、「この動きは止められない」と述べた。(3月29日日経夕刊)
- トミーが、人工知能を搭載し人間の話す言葉を理解して応答する会話ロボットを今年夏に発売。約2万語の語彙を持ち、直前の会話内容を記憶して返事に反映させる。語彙にない固有名詞なども記憶させられる。(3月20日日経)
- NTTドコモは、ハイビジョン並みの高画質映像の送受信が出来る次々世代(第四世代)の携帯電話を、当初予定していた2010年から大幅に早めて2006年にも実用化し、事実上の世界標準を目指す。(3月18日読売)
- 国際NGOの「バードライフ・インターナショナル」が調査・発表したところによると、世界の野鳥約9800種の12%にあたる1186種が絶滅の危機にあり、前回6年前の調査に比べ危機種は75種増加。(3月14日毎日)
- ソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)、東芝、米IBMが、1枚の基盤でスーパーコンピューター並みの性能を持つ次世代半導体を共同開発することで合意。3社は今後5年間で480億円をかける。(3月13日朝日)
- イスラエルで多国籍の医師団が世界初のクローン人間作りを目指して近く活動を始める、とドイツの週刊誌「シュピーゲル」が報道。医師団は「ユダヤ教はクローンを明確には禁じていない」としている。(3月11日読売)
- 中国が2002年後半に有人宇宙船の打ち上げを計画。成功すればアメリカ、ロシアに続いて世界で3番目の有人宇宙飛行達成国になる。それに先立ち、中国は今年2回、来年1回、無人宇宙船を打ち上げる。(3月10日読売)
ページの冒頭に戻る
メニューにジャンプ
- インターネット技術を使ったIP電話は、2000年には国際電話全体に占める割合が3%だったが、今後急速に普及して2004年には国際電話の40%まで拡大する、と国際電気通信連合が見通し。(2月25日日経)
- NASAが1996年に打ち上げた惑星探査機「ニア・シューメーカー」が12日午後に小惑星「エロス」に軟着陸する。探査機の小惑星着陸は初めてで、太陽系の起源を解明する観測データが得られるものと期待されている。(2月5日日経)
- コンピューターソフト会社のシーエーアイとロボット開発のココロが、文章の意味を理解して会話する人間型ロボットを開発。受け付け業務などをこなすことが出来、500万円から1000万円で発売する。(2月2日各紙)
- 財務省の試算による「財政の中期展望」によると、2004年度末の国債残高は、過去の国債利払いや社会保障関係費が膨らむ一方で税収の伸びは見込めないため483兆円になり、国債依存度は41.1%になる。(2月1日各紙)
ページの冒頭に戻る
メニューにジャンプ
- 米ケンタッキー大学教授とイタリア人医師が、1、2年のうちに不妊治療としてクローン人間を誕生させる計画を発表。日本人1組を含む10組のカップルが希望しており、「地中海のある国」で実施するという。(1月29日各紙)
- 南極の棚氷が夏の気温上昇によって崩壊の危機にあり、世界規模の海面上昇を招く恐れがある、とNASAなどの研究チームが警告。南極最大のロス棚氷も、崩壊の瀬戸際に近づいてきている、としている。(1月18日毎日)
- 2003年から始まる地上波テレビのデジタル化に向け、NHKと民放、総務省で構成する検討委員会は、7月から関東や近畿、九州など55万世帯でアンテナ交換やチャンネル変更に向けた手直し工事に入る。(1月17日日経)
- オーストラリア国家科学産業機構のロン・ジャクソン博士が、ネズミの不妊ワクチンを作る実験中に偶然、致死性の人工ウイルスを作製。科学誌に顛末を掲載し、科学者が危険な生命体を作る危険性について警鐘鳴らす。(1月16日読売)
- 地球の生態系破壊が加速する一方で、環境を保護する政治力は低下しており、21世紀を迎えた地球環境は危険な岐路に立たされている、と米ワールドウオッチ研究所が2001年版の地球環境白書で警告。(1月15日朝日)
- 東京のウィルライフが宇宙ベンチャー企業の米エンカウンター2001社と提携し、宇宙へのメッセージを募集。文字や写真、イラストなどをディスクに記録して、2003年にロケットで打ち上げ。料金は2001円。(1月12日日経)
- 欧米で活動を続ける新興宗教団体「エラリアン」が設立したバイオ企業が今月末から、米国内でクローン人間作製に着手する。生後10カ月で死亡した男児の血液細胞の核を卵子に移植し、代理母となる女性信者の子宮に戻して誕生を待つ。(1月11日読売)
- 日石三菱が、無公害の新エネルギーとして期待される燃料電池による家庭用発電システムを、2004年をメドに商品化して市場に本格投入。価格は100万円程度だが、最終的には20万円程度まで下げたいとしている。(1月4日読売)
- 「2001年宇宙の旅」の原作者、SF作家のアーサー・クラーク氏が自分のDNAを人工衛星に搭載して宇宙へ送る。いつの日か、未知の生物によって、このDNAからクローンが再生される可能性に期待する、としている。(1月3日朝日)
- 大晦日深夜から元日未明にかけ、日本列島と世界の各地で新世紀到来を祝うイベントが行われた。国内のイベントの詳細は、「2001年わくわくイベント速報」のページに。昨年前倒しでミレニアムを祝ってしまった欧米は熱気なく、静かな年明けだった。(1月1日各紙)
ページの冒頭に戻る
メニューにジャンプ
ニュース&トピックスのバックナンバー
00年7月−12月
00年1月−6月
99年7月−12月
99年1月−6月
98年7月−12月
98年1月−6月
97年2月−12月
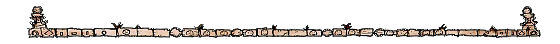
<注>このページは、全国主要新聞などの記事を短く要約して掲載しています。各項目の詳しい内容については、それぞれの新聞記事をご覧下さい。
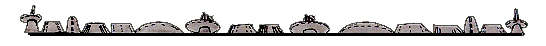
メニュー
このページでは、中川真実氏作製のJcamアプレットを使用しています。