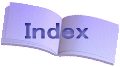 なっとく童謡・唱歌メニューページに戻る
なっとく童謡・唱歌メニューページに戻る![]() 池田小百合トップページに戻る
池田小百合トップページに戻る
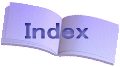 なっとく童謡・唱歌メニューページに戻る
なっとく童謡・唱歌メニューページに戻る
| 池田小百合 なっとく童謡・唱歌 |
| 戦後の童謡 昭和22年の音楽教科書 |
| 思い出 かえるの合唱 かすみか雲か かっこう 小ぎつね |
| さんぽ とうだいもり 夜汽車 |
| 童謡・唱歌 事典 (編集中) |
【新しい音楽教科書の誕生】 昭和二十二年(1947年)になると、3月31日には教育基本法が公布され、学校教育法も公布されて、従来の国民学校は廃止され、六三制が始まりました。5月3日には日本国憲法が公布されます。 文部省は新主旨に基づく編集による音楽教科書を編集し、5月に発行しました。これが、最後の文部省編の国定教科書になります。新教科書の編集委員は岡本敏明、平井保喜(康三郎)が作曲を担当、小林つやえ、勝承夫が作詞を担当しました。戦争中の国民学校の唱歌編纂に関わった委員はひとりも含まれていません。 文部省は既に唱歌教材選択の一般方針として次の三項目に該当する教材を排除することを示していました。(1)軍国主義的なもの、(2)超国家主義的なもの、(3)神道に関係あるもの。 そして、集められた教材は次のような教材でした。(1)従来の文部省唱歌にあって歌曲ともにすぐれたもの、(2)わらべうたのなかで特にすぐれたもの、(3)民間の作詞作曲家の手になった童謡ですぐれたもの、(4)新作したもの。また、このとき初めて作詞者・作曲者が明記されました。 上記の記述は、堀内敬三・井上武士(編)『日本唱歌集』(岩波文庫、1958年)によっていますが、戦争中に戦意昂揚のための少国民唱歌ばかりを教科書に掲載してきたこともあって、各学年22曲をそろえることは大変だったと思われます。特に上級生用の曲は上記の規準で削除したら、残らなくなってしまいました。 いきおい、外国曲に歌詞をあてはめた曲が多くなりました。4年生は9曲(41%)、5年生は14曲(64%)、6年生は15曲(68%)。 【子どもたちに楽しい音楽を】 それでも、昭和二十二年版の特徴のひとつは、みんなで「音楽を楽しむ」事を目的にしていることです。 優れた童謡(しょうじょうじのたぬきばやし)・唱歌(村のかじや)、新作の曲(歌のおけいこ)などを掲載し、子どもたちに楽しい音楽を与えようとしました。 また、斉唱から合唱に導入するために輪唱教材が重視されました。「かえるの合唱」(かえるのうたが きこえてくるよ。クワ クワ クワ クワ、ケケケケ、ケケケケ、クワクワクワ。)などの輪唱曲も積極的に紹介しました。このことは後の合唱ブームの先がけとなりました。 そして、だれでも伴奏ができるように全曲に伴奏譜が掲載してあります。これは、後のピアノブームに発展して行きました。 さらに、より音楽を理解することができるように、時折り楽譜についての説明文が短く書かれています。 こうして、昭和二十二年版は、戦後の新しい音楽教育の方向を示した画期的な教科書になったのです。 【検定教科書に変わった】 昭和二十四年になると、民間出版社で作られた検定教科書になり、挿絵や写真がカラーになりましたが、全てこの二十二年版の文部省の教科書をお手本にしているため、内容はあまり変わっていません。しかし、伴奏譜は削除されてしまいました。これはたいへん残念なことでした。 【昭和22年 音楽教科書の収録曲一覧】 一年生から六年生までの昭和22年の音楽教科書に掲載された曲を一覧で示します。大和淳二(監修・解説)『文部省唱歌集成』の「教科書別唱歌一覧表」を参考にしました。なお、一部誤記がありました(例えば、平岡均之の之が落ちていたりベリーニをベリーユと記したり)ので修正しました。※国民学校芸能科音楽参照
【岡本敏明の略歴】  ・作曲者の岡本敏明は、明治四十年(1907年)三月十九日、宮崎県宮崎市に生まれました。父は組合教会牧師・岡本松籟。教会に於いてオルガンの音を聴きつつ育った。 ・作曲者の岡本敏明は、明治四十年(1907年)三月十九日、宮崎県宮崎市に生まれました。父は組合教会牧師・岡本松籟。教会に於いてオルガンの音を聴きつつ育った。・大正十三年三月、福島県立福島中学校卒業。 ・昭和四年三月、東京高等音楽学院(現・国立音楽大学)高等師範科を卒業。 「浜辺の歌」「赤い鳥小鳥」「りすりす小栗鼠」の作曲者、成田爲三に師事。その関係で、成田爲三が突然亡くなると、一人になってしまった文子夫人は、爲三の門下生の岡本の家で家族と一緒に住む事になった。その後、文子夫人は高齢者介護施設「浜名湖エデンの園」に住み、亡くなった。 ・昭和四年四月から玉川学園教諭となる。昭和三十三年まで約三十年間、小原國芳園長の下で玉川学園の生活の歌を育成。玉川学園の校歌の作曲もしました。 ・昭和二十五年四月、国立音楽大学教授。 ・昭和五十年四月、国立音楽大学名誉教授。 ・昭和五十二年(1977年)十月二十一日に亡くなりました。 作曲家、音楽教育家、合唱指導者として活躍しました。東京上京以来死にいたるまで日本基督教団弓町本郷教会に所属しオルガニスト、聖歌隊指導者として活躍する傍ら、宗教音楽活動は教会内に留まらず東京YMCA合唱団の設立に携わり初代指揮者となった。また日本基督教団讃美歌委員としても活躍。 戦後は、文部省図書編集委員として小学校、中学校の音楽教科書、音楽学習の指導要領の作成に携わった。輪唱や合唱を取り入れた、楽しい音楽の普及に務めました。 <「かえるの合唱」について> 昭和二十二年版『四年生の音楽』(文部省)に掲載された。タイトルは「かえるの合唱」です。作詞 岡本敏明、作曲 ドイツ曲とある。 「かえるのうたが きこえてくるよ」という歌いだしなので、「かえるの歌」というタイトルと思っている人が多いようです。 昭和二十二年版での蛙のなきかたは「クワ クワ クワ クワ、ケケケケ、ケケケケ、クワクワクワ」。楽譜はヘ長調、四分の二拍子、四つの組に分かれて歌う四声輪唱。この曲は、子供たちに人気の曲で、合唱ブームのきっかけとなりました。
【著者より引用及び著作権についてお願い】 利用される場合は、「池田小百合なっとく童謡・唱歌」と出典を明記してください。それはルールです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【初出】 ・文部省から発行された最後の国定教科書『二ねんせいのおんがく』昭和二十二年発行に掲載されました。 ・昭和二十二年版の編集委員(歌詞)の一人だった勝承夫が、「散歩唱歌」を二番までの口語体の歌詞にまとめたものです。 ・メロディーは「散歩唱歌」と同じですが、リズムがかえてあります。 【歌詞について】 散歩をしている時の楽しい明るい気分を歌ったものです。歌詞の気分がスキップのリズムで、いっそう明快に歌い出されています。 【曲について】 ・ヘ長調、四分の二拍子。 ・旋律は一部形式(4+4+4+4)。四小節ずつ四つのフレーズでできています。 ・ヨナ抜き五音音階。伴奏も単純でⅠ・Ⅳ・Ⅴの和音でできている。 ・スキップのリズムが中心になっていて、全体が弾むような明るさで作られています。 <最初の三つのフレーズは同じリズム> 「タッカタッカ|タッカタン|タッカタッカ|ターア(付点四分音符)ン(八分休符)」このリズムの方が歌詞に合っていて「散歩唱歌」より優れている。 <最後の四小節のリズム> 「タッカタッカ|タッカタッカ|タッカタッカ|ターア(付点四分音符)ン(八分休符)」 ・「みもはずむ」は、誤唱しやすいので注意。 ・八分休符は、「はんうちやすみ」と教えていた。 【教科書での扱い】 ・『しょうがくせいのおんがく 2』(音楽之友社)昭和三十五年十二月発行掲載の「さんぽ」作詞 勝承夫、作曲 多梅稚。
<最後の四小節のリズム> 「タッカタッカ わたしも|タンタッカ いーつか|タッカタッカ うたいだ|ターア(付点四分音符)ン(八分休符) す」歌詞に合ったリズムになっている。 当時の合奏風景がp.27にある。 ・『しょうがくせいのおんがく 2』(音楽之友社)昭和三十三年十二月発行掲載の「さんぽ」作詞 勝承夫、作曲 多梅稚。 伴奏譜がついている。昭和三十五年版より優れている。
【「散歩唱歌」について】
・「鉄道唱歌」と同じコンビによる歌です。作詞は大和田建樹(おおわだたけき)、作曲は多梅稚(おおのうめわか)。「鉄道唱歌」の翌年の明治三十四年(1901年)に作られました。大和田建樹著『春夏秋冬 散歩唱歌』(開成館) 明治三十四年七月発行。 ・春は十五番まで、夏は十番まで、秋は十五番まで、冬は十番まである長い歌詞です。勝承夫は、この長い「散歩唱歌」を、よく二番までの口語体の歌詞にまとめたものです。さすがです。 ・春夏秋冬の歌詞は、堀内敬三・井上武士編『日本唱歌集』(岩波文庫)、金田一春彦・安西愛子編『日本の唱歌 明治篇』(講談社文庫)、『原典による近代唱歌集成』Ⅲ(Victor)などで見ることができます。初版と再版では、歌詞の順序や言葉が違っているところがたくさんあります。例えば岩波文庫(表紙の写真から明治三十六年六月再版のものです)の春五番は、 「黄なる菜のはな 青き麦 錦と見ゆる 野のおもの ここやかしこに おりのぼる 雲雀のうたの おもしろさ」となっています。 ・楽譜の曲名は「散歩唱歌」で、ヘ長調、四分の二拍子。 リズムは、どのフレーズも「タッカタッカ|タッカタッカ|タッカタッカ|ターア(付点四分音符)ン(八分休符)」 【アニメ映画『となりのトトロ』の主題歌「さんぽ」】 「さんぽ」作詞 中川李枝子、作曲 久石譲 は、アニメ映画『となりのトトロ』(昭和六十三年)の主題歌で巻頭に流れる。子どもたちに大人気の曲です。『音楽のおくりもの 2』(教育出版)平成二十一年発行に掲載されている。 ≪著者池田小百合≫ 【著者より引用及び著作権についてお願い】 |
|||||||||||
【発表】 文部省が昭和二十二年(1947年)に発行した音楽教科書『三年生の音楽』に、勝承夫の日本語詞とともに掲載されました。 勝承夫は、戦後の音楽教科書の編纂委員の一人として、「とうだいもり」や「かすみか雲か」など、多くの外国のメロディーに詩をつけています。
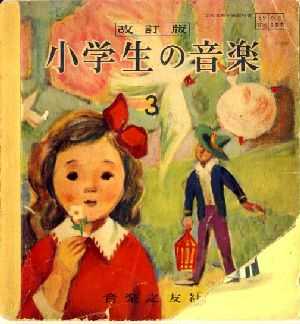 【小ぎつねを擬人化した歌詞】 【小ぎつねを擬人化した歌詞】小ぎつねが、可愛らしい女の子に化けようと思って、「草のみつぶして、おけしょうしたり」「もみじのかんざし」をしたり、いろいろ苦心している様子が、おもしろく歌われています。「コンコン」という鳴き声が、節のリズムと良く合っています。 【楽しい曲】 ハ長調の旋律は、「ドレミファソ」で始まっています。覚えやすいので子供たちに人気でした。また、反復される「山の中、山の中」のエコーが、この歌を楽しくさせています。 テンポの速い、歯切れ良い4分の2拍子の曲です。器楽合奏の教材に適しているので学芸会や学習発表会の場で頻繁に使われました。木琴、ハーモニカ、オルガンを学校で学習し、家に帰ってからも歌ったり踊ったり演奏したりして楽しみました。 【ドイツ民謡】 元はドイツ民謡で、原題は≪Fuchs,du hast die Gans gestohlen(キツネめ、おまえはガチョウを盗んだな)≫といいます。ライプチヒで音楽教師とオルガニストを務めたエルンスト・アンシュッツ(1780~1861年)が、古くからあるドイツ民謡の旋律に手を加え、1824年に作った「泥棒はいけないよ」という教訓的な内容の詞で、勝承夫の日本語詞とは、ずいぶん違うものです。(長田暁二『世界の愛唱歌』(2005年、YAMAHA)による) 金田一春彦・安西愛子(編)『日本の唱歌(中)』(講談社文庫)によれば、“ドイツ民謡「Warnung」が原曲”で、“『明治唱歌(二)』で大和田建樹が「楽しみの時」と作詞した”とありますが、この曲は「小ぎつね」と歌い出しは同じですが、中間部から後半がかなり違いますし、聞いたときの印象も違います。 ドイツ民謡には類似の曲がいくつかあったようです。
【戦後の音楽教育】 戦後、文部省が出した昭和二十二年版の音楽教科書は、かつての「文部省唱歌、校門を出でず」の悪い評判をふまえて、子供たちに楽しい音楽を与えようとする画期的なものでした。この≪小ぎつね≫は、文部省が打ち出した新方針を十分に満たし、成功した曲といえます。 今でも広く愛唱されています。 【現在は小学2年生用の教材に】 平成八年発行、平成二十一年発行『小学生の音楽2』(教育芸術社)では、二年生の音楽教材として掲載されています。教育出版も同じ。 ≪著者・池田小百合≫ 【著者より引用及び著作権についてお願い】 |
||||||||
【原曲】 ・原曲はドイツ民謡「Der Kuckuck」 ・As Dur(変イ長調) 四分の三拍子。 ・原詩は「カッコー カッコー 来て歌えよ 冬はすぎて 暖かい春の日が 訪れつつあるよ。」というものです。 【初出】 <岩佐東一郎の作詞> 雲と風 作詞 岩佐東一郎 作曲 ドイツ民謡 一 ほら ほら ごらんよ。 白雲がながれるよ、 ほら ほら お空を。 二 ほら ほら ごらんよ。 そよ風がふいてくる、 ほら ほら おいけに。 ・昭和二十二年に出版された『三年生の音楽』(文部省)に「雲と風」というタイトルで掲載されたのが最初です。ヘ長調 ♩=120。 フラットの学習のための教材。歌詞の下には「フラットは音をさげるしるしです。何という音がさがっていますか。歌い方のけいこもいたしましょう」と書いてある。 ・ドイツ民謡に歌詞をあてはめたので「ごらん」「お空」「おいけ」などアクセントが逆になってしまっている。昔から外国の曲や讃美歌に歌詞をつけたものを歌ってきた日本人は、アクセントが逆になっていても、意外と平気で歌ってしまう。 ・作詞者の岩佐東一郎(1905-1974)は詩人。東京生れ。昭和三年法政大学仏文科卒業。堀口大学に師事。『ぷろむなあど』その他の詩集の著、随筆集『茶煙閑語』がある。『四年生の音楽』(文部省)掲載の「アマリリス」作曲 フランス民謡(♪みんなできこう、たのしいオルゴールを。・・・)や、『六年生の音楽』(文部省)掲載の「よろこびの歌」作曲 ベートーベン(♪晴れたる青空、ただよう雲よ、・・・)など、昭和二十二年版の教科書には作詞の曲がいくつかある。 「かっこう」というタイトルで二年生の音楽教科書に掲載されました。教科書会社により、いろいろな人が作った歌詞が紹介してあります。あなたは、どの歌詞で歌いましたか。 <堀内敬三の作詞> かっこう 堀内敬三 作詞/ドイツ民謡 一 カッコウ カッコウ どこかに きこえるよ とりのこえ はやしの なかから 二 カッコウ カッコウ だれかを よんでるよ とりのこえ あおばの かげから ・『しょうがくせいのおんがく2』(音楽之友社) 昭和30年8月13日文部省検定済 昭和33年12月15日発行 著作者 中野義見ほか7名 昭和35年4月20日文部省検定済 昭和35年12月25日発行 著作者 堀内敬三ほか9名 ・へ長調 ♩=120位 ・四分の三拍子を学習するための教材として掲載されました。 四分音符=ひとうちおんぷ 四分休符=ひとうちやすみ。 ・この教科書を使った子どもたちは、現在六十歳代で、孫のいる世代になっています。さわやかに、ほがらかに「かっこう」を歌って、和やかな家庭を営んでいるでしょうか。 <小林純一の作詞 Ⅰ> かっこう 小林純一 作詞/ドイツ民謡 一 かっこう かっこう しずかに よんでるよ きりのなか ほうら ほうら かあさん 二 かっこう かっこう しずかに ないてるよ もりのなか ほうら ほうら あさだよ ・『小学生の音楽2』(教育芸術社) 平成7年2月15日文部省検定済(平成8年度用)。平成10年2月10日発行。 著作者 市川都志春ほか8名 ・「ドレミファソ」を学習するための教材として掲載されました。 ドレミで歌ったり、右手で鍵盤楽器を弾く指導になっている。 「ゆびの ばんごうを おぼえましょう」「ゆびづかいに 気をつけて、「かっこう」のふしを ひきましょう」と書いてある。♩=112~120。 <小林純一の作詞 Ⅱ> 一 かっこう かっこう しずかにー よんでるーよ きりのなーか ほうーら ほうーら かあさんー 二 かっこう かっこう しずかにー ないてるーよ もりのなーか ほうーら ほうーら あさだよー ・『新しい音楽2』(東京書籍) 昭和60年3月31日文部省検定済 昭和61・63年2月10日発行 ・同じ<小林純一の作詞>でも、二分音符をはっきり、わかりやすくするために「にー」「るー」としている。 ・打楽器(タンブリンやカスタネット)でタン(ウン)(ウン)や(ウン)タンタンのリズムの練習、オルガン(ハーモニカ)でドレミファソのメロディーの練習をするようになっている。♩=112~120ぐらい。 ・この教科書を使った子どもたちは、現在三十歳代で子育て中です。「かっこう」を歌って、明るく楽しい家庭を築いてほしいと願っています。 <川路柳虹の作詞>
■教材について ・ヘ長調 四分の三拍子 ♩=132 ・音域わずか五度、リズムは、ほとんど四分音符で構成され、簡単な素材で、美しい楽しい曲ができている。 ・歌い出しの「カッコー」が、いかにも、さわやかな感じがして、調子のよい三拍子である。鑑賞曲「かっこうワルツ」(ヨナーソン作曲)とともに、三拍子感を養うのに好適な教材である。(三拍子のリズム打ち=強 弱 弱) ・作詞者の川路柳虹(かわじりゅうこう 1888~1959)は、東京美術学校出身の民衆詩人、美術評論家。 ・私、池田小百合は、川路柳虹の「しずかに」の歌詞が気に入っている。主宰している童謡の会で使っている『読む、歌う童謡・唱歌の歌詞』(夢工房)改訂11版 2013年5月10日発行にも、この歌詞が掲載してあります。童謡の会で歌いましたが、みんなが、この歌詞を知っていました。 <まつい けんすけ の作詞> かっこう まつい けんすけ 作詞/外国曲 一 かっこう かっこう ないてる ふゆがすぎ はるがきて そよかぜ ふいてる 二 かっこう かっこう ないてる はながさき ちょうがまい たのしい はるだよ ・『二ねんのおんがく』(広島図書株式会社 発行)昭和26年4月1日再版発行に掲載。楽しい春の歌になっています。 文部省検定済 昭和26年9月26日発行 著作者 武蔵野音楽大学 代表者 福井直秋 編纂者 津川正美 ・「楽譜には“がいこく きょく”、歌詞には“まつい けんすけ”との記載がある」。この情報は、以前『読む、歌う童謡・唱歌の歌詞』(夢工房)改訂8版を購入していただいた方から教えていただきました。ありがとうございました(2013年11月12日)。 (註) 「けやき書店古書目録」(2013年冬)によると、広島図書株式会社は、昭和22年9月~12月に雑誌『銀の鈴 五・六年の友』二巻七号~二巻十号を発行。また昭和25年1月に『銀の鈴 五年生』五巻一号、昭和25年10月に『銀の鈴』五巻十四号を発行している。 【カッコウについて】 カッコウは、ホトトギス科に属し、日本には夏鳥として渡来繁殖する。北日本では平地のかん木林などに、中部では高原、山地に捿息する。ホトトギスやツツドリと同様、自ら巣を作らず、ホオジロ、モズ、ヨシキリなどに卵を託す。 カッコーという、そののどかな鳴き声は、オスのもので、メスは、ピッピッと、するどい声で鳴く。 夏になると、丹沢山系の西側の松田山の山中で、谷間にこだまするカッコウの鳴き声を聞く事ができます。私、池田小百合は、そんなのんびりした所に住んでいます。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 利用される場合は、「池田小百合なっとく童謡・唱歌」と出典を明記してください。それはルールです。 |
【初出】 昭和二十二年(1947年)発行の『四年生の音楽』(文部省)に掲載されました。 勝承夫(かつ・よしお)が「小鳥ならば」というドイツ民謡に日本語の詩を付けました。 【ドイツ民謡】 “原曲は Wenn ich ein Vöglein wär (小鳥ならば)というドイツ民謡。ト長調、八分の六拍子で三番まであり、「もし自分が小鳥だったら あなたのそばに飛んで行けようものを」という趣旨の内容だったのを、勝承夫が日本人らしい心情の歌に改作したものである。はじめ、ドイツの民謡研究家ヘルダー(Johann Gottfried von Helder)の『民謡集』(一七七八)に発表されたが、後に『子供の魔の笛』に採録された。”(金田一春彦・安西愛子編『日本の唱歌〔中〕大正・昭和篇』(講談社文庫)による)。『子供の魔の笛』は『子供の不思議な角笛』とも訳されます。 【「行く」の読みかた】 歌詞の二番の最後は「きえてゆく」と記されていますが、楽譜に付けられた同じ箇所の歌詞は「きえていく」と書かれています。 当時は「ゆく」「いく」と、両方の歌詞で歌われていました。この教科書を使って歌い覚えた人が沢山います。そのため大人になった今でも、「ゆく」「いく」の両方で歌われています。 【楽譜について】 ・ト長調の階名唱、四分の三拍子のリズムを学習するための曲です。 ・シドレミファソの六音音階でできています。 ・A(六小節) B(六小節)の変形二部形式です。Bの後半「遠い町を」からクレッシェンド(cresc.)して「思い出す」が、この曲の山になります。 ・輪唱ふうの二部合唱に編曲してあります。 終わりの二音を除けば、全て三度の重音です。この三度重音の美しい響きを正しく出せるようにするのが目的です。合唱の基本の学習教材です。
昭和二十二年以降、「夜汽車」の歌は、どのように扱われていったでしょうか。 【昭和四十四年発行、『新訂標準 音楽4』(教育出版)】 ヘ長調に移調された「夜汽車」は、歌詞と楽譜がともに「きえていく」に統一してあります。昭和六十三年二月発行、平成二年二月発行、『新しい音楽4』(東京書籍)も、「いく」です。 子供たちにわかりやすいように表記のように歌うようにしたのです。 平成七年を最後に掲載されなくなりました。「いく」と歌うか、「ゆく」と歌うかの問題より、掲載されなくなった方が重大問題です。 【久野静夫 作詞『「小鳥ならば」】 平成八年(1996年)発行、『小学生の音楽5』(教育芸術社)には、久野静夫作詞「小鳥ならば」という歌詞で紹介されています。さわやかな歌詞です。 「ヘ長調と階名」を学習する教材になっています。 小鳥ならば 作詞 久野静夫 小鳥ならば 青い空に はばたき 遠くの丘を はるかこえて どこまでも
【西崎嘉太郎 作詞「小鳥ならば」】 『中学音楽2』(教育出版、昭和四十六年(1971年)4月10日文部省検定済、昭和四十九年改訂検定済)には、西崎嘉太郎作詞の「小鳥ならば」が掲載されています。 一番は独唱または斉唱、二番は重唱または同声二部合唱、三番は混声三部合唱に編曲してあります。演奏形態の勉強の教材になっています。 小鳥ならば 一 翼強き 小鳥ならば 飛びゆかん 我がなつかし 母のみもと 故郷へ 二 朝に夕に 思いいずる 故郷 我がやさしき 母のいます 故郷を 三 翼強き 小鳥ならば 飛びゆかん 遠きかなた 胸に迫る 故郷へ 西崎嘉太郎は、作詞も作曲もしています。玉川学園の『愛吟集』で見る事ができます。 ・「われら愛す」(芳賀秀太郎作詞/西崎嘉太郎作曲)「♪われら愛す 胸迫る 熱き想いに この国を われら愛す・・・」。歌詞は三番まである。二部合唱曲。 ・「みんなで歌えば」(デンマーク国民歌/西崎嘉太郎作詞/岡本敏明編曲)「♪朝日は昇るよ 露草踏んで(ラララ) みんなで歌えば 心楽し・・・」。歌詞は三番まである。混声四部合唱曲。 ・「おおきな声で」(秋山日出男作詞/西崎嘉太郎作曲)「♪おおきな声で 歌いましょう 声は悪くも 音痴でも 間違ったら ごめんなさい おこらないでね」。三声輪唱曲。 ・「雨だれさん」(西崎嘉太郎作詞・作曲)「♪ポッタン ポタリコ 雨だれさん」。歌詞は二番まである。部分二部合唱曲。 ・「夏はきた」(木村健治作詞/西崎嘉太郎作曲)「♪緑の丘の 露草踏んで 山道かけて 夏は来た ヤッホー ヤッホー 夏は来た ヤッホー」。歌詞は二番まである。二部合唱曲。 ・「うるわし夏の野」(西崎嘉太郎作詞・作曲)「♪緑の(緑の) そよ風(そよ風) こずえに(こずえに) 渡りて(渡りて)」輪唱を入れた三部合唱曲。 【子どもたちに楽しい音楽を】 昭和二十二年発行の教科書には、それ以前の教科書から軍国主義的なもの、超国家主義的なもの、神道に関係あるものが削除されました。戦前、戦中の音楽教育に対する反省から、作られた教科書です。 終戦後、最初で最後の文部省編の国定教科書で、編集委員は岡本敏明、平井保喜(康三郎)、小林つやえ、勝承夫でした。 昭和二十二年版は、みんなで「音楽を楽しむ」事を目的に作られています。たとえば『四年生の音楽』では、外国の曲(アマリリス)や、過去の優れた童謡(しょうじょうじのたぬきばやし[題名は平仮名表記])・唱歌(村のかじや)、新作の曲(歌のおけいこ)などを掲載し、子どもたちに楽しい音楽を与えようと考えました。 まず、斉唱から合唱に導入するために輪唱教材が重視されました。「かえるの合唱」(かえるのうたが きこえてくるよ。クワ クワ クワ クワ、ケケケケ、ケケケケ、クワクワクワ。)などの輪唱曲も積極的に紹介しました。後の合唱ブームの先がけとなりました。 そして、だれでも伴奏ができるように伴奏譜が掲載してあります。これは、後のピアノブームに発展して行きました。 リコーダー(縦笛)のアンサンブルも盛んになりました。 より音楽を理解することができるように、時折り楽譜についての説明文が短く書かれています。「夜汽車」のページには、休符の説明がありました。 二十二年版は、戦後の新しい音楽教育の方向を示した画期的な教科書でした。 昭和二十四年以後、民間出版社で作られた検定教科書は、挿絵や写真がカラーになりましたが、全てこの二十二年版の文部省の教科書をお手本にしているため、内容はあまり変わっていません。しかし、伴奏譜は削除されてしまいました。これはたいへん残念なことでした。 子供たちには、伴奏譜はもちろんのこと、もう少し高度な合唱曲や器楽曲を与えてもいいのではないでしょうか。 【御殿場線の夜汽車は今】 私、著者池田小百合の家の前を御殿場線が走っています。小さかった頃は、蒸気機関車が走っていました。今では二両から五両の電車が一時間に一、二本走っています。 夜は、あまり乗客が乗っていません。・・・闇の中からごう音とともに現れ、昔も今も変わらずに眼の中に「窓の明かり」を残して、次の駅を目指して走り去って行きます。 『夜汽車』を歌いたくなる一瞬です。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 利用される場合は、「池田小百合なっとく童謡・唱歌」と出典を明記してください。それはルールです。 |
【原歌について】 明治から日本人の愛唱歌として親しまれて来た外国民謡の一つです。“原歌の歌詞は「Alle Vögel sind schon da すべての鳥はもう来た」という春の歌。歌詞はドイツの国歌の作詞者でもあるハインリヒ・ホフマン(Heinrich Hoffmann von Fallersleben 1798-1874)が1855年に作ったもの。メロディーは、より古く、オーストリアの民謡に基づいていると言われる。子どもの民謡として、もっともよく歌われている歌の一つ”(『原典による近代唱歌集成』の解説による)。
【タイトル「霞か雲か」】 ・文部省音楽取調掛編『小学唱歌集 第二編』(文部省編輯局蔵版、明治十六年発行)に掲載。ドイツ民謡に加部厳夫(かべいづお)が歌詞をあてはめました。加部厳夫は音楽取調掛の御用掛(現・東京芸大の国語科の教官)の一人。難しい歌詞です。楽譜はニ長調、四分の四拍子。
・文部省音樂取調掛編纂『幼稚園唱歌集 全』(文部省編輯局蔵版、明治二十年十二月出版)に掲載。目次の四番目にある。歌詞には「第四 霞か雲か」と書いてある。幼稚園児が歌うには難しい。
・教育音樂講習會編纂『新編教育唱歌集』第一集(東京 開成館蔵版)明治三十八年八月十七日修正五版発行。目次のタイトルには、二七 霞か雲か(音樂學校許可)と書いてある。文字が読みやすくなった。
[註]『新編教育唱歌集』修正五版(K120.73~41)は、八冊に分かれている。これは国立教育政策研究所教育研究情報センター教育図書館閲覧室で見ることができます(東京都目黒区下目黒6-5-22)。合本も発行されている。 『新編教育唱歌集』明治三十九年一月二十八日訂正六版発行。明治三十九年四月十日合本七版発行。大正九年一月十日合本七版再印刷と次々増刷された。人気の唱歌集だったことがわかります。 【タイトル「かすみか雲か」】 『四年生の音楽』昭和二十二年発行に掲載。戦後は小学校四年生の教材として勝承夫が作った歌詞で歌われました。タイトルは「かすみか雲か」。やさしい歌詞になりました。 平成二十一年発行の教育出版、東京書籍、教育芸術社の教科書には掲載されていません。「さくらさくら」が掲載されている。 〈歌詞について〉 霞がかかったように、野山いっぱいの桜の花盛りのようすを歌ったものです。 ・「かすみか雲か」桜の花が一面に咲いた景色が、ちょうど霞か雲のように見えること。 ・「ほのぼのと」ごくほんのりと。 ・「野山をそめる」野山を花のほんのりとした色でそめる。 ・「いこえば」やすめば。 ・「ひときわ」いっそう、いちだんと。 〈曲について〉 ・ハ長調の階名唱の教材として掲載している。歌を覚えやすい。 ・四分の四拍子は、(しぶんのしびうし)と読むように指導している。 ・「シ」をのぞく六音音階でできている。ドレミファソラ (ド) ・三部形式a(4小節)b(4)a(4) 小楽節三つからできている三部形式の曲です。 〈歌い方について〉 初めと終わりの四小節は全く同じ旋律で、真ん中の四小節は感じが変わった旋律です。初めは普通の強さで、二段目は弱く、そして感じを変えて歌います。三段目はまた初めと同じに歌いますが、二度目なので、感じを強く込めて歌います。 【勝承夫(かつよしお)の略歴】 「とうだいもり」「歌の町」「小ぎつね」「夜汽車」参照 ≪著者・池田小百合≫ 【著者より引用及び著作権についてお願い】 |
||||||||||||||||
【勝承夫の作詞】 文部省が昭和二十二年(1947年)に発行した音楽教科書『五年生の音楽』に勝承夫が作詞したものが掲載されました。 【愛唱される理由】 この原曲はイギリスの曲といわれていますが、原題も作曲者もよくわかっていません。 八分の六拍子の流れるようなメロディーに乗せて、冬の海の激しさと、燈台のともしびや、船を守る人たちの心、さらに燈台守への感謝の念が歌いこまれています。 この歌からは、ピーンと張り詰めた冷たい空気が一筋流れてくるような雰囲気が感じられます。これが歌の最大の魅力です。 一番の二行目にある「小島(おじま)」は「おーじまー」と歌います。 【原曲について】 以下は、一橋大学の櫻井雅人氏が発表した論文によるもので す。 「原曲はアメリカの日曜学校唱歌の“The Golden Rule”である。1881年New York出版の『フランクリン・スクウェア・ソング・コレクション第一集』に掲載の旋律をそのまま借用した。調性(変ロ長調)も全く同じ(ただし、“The Golden Rule”は四部合唱)であって、これが出典であることは確実であろう。作詞者は I.J.Zimmerman(経歴不明)。作曲者は不明。 “The Golden Rule”は20世紀初頭ま での、いくつかの歌集に収録されていたが、現在のアメリカでは全く知られてい ない。 櫻井氏が、論文「旅泊」その他:外国曲からの唱歌四曲(『一橋論叢』134巻3号/2005.9)に掲載している楽譜を見ると、楽譜には拍子が書いてないが、八分の 六拍子です。 ●これが、原曲だとすると、一般に知られている「イギリス曲」説、金田一春 彦・安西愛子編『日本の唱歌 明治篇』(講談社文庫)は間違いということになり ます。堀内敬三・井上武士編『日本唱歌集』(岩波文庫)も、「原曲はイギリス 曲」と書いてあります。 【勝承夫の略歴】 ・明治三十五年(1902年)一月二十九日、東京・四谷に生まれる。 ・大正八年、愛知県立第五中学校(現・県立瑞稜高等学校)卒業。 ・大正九年、東洋大学専門学部入学。学生時代から正富汪洋主宰の「新進詩人」(大正七年三月創刊)に参加し、宵島俊吉の名で詩を発表した。詩作に励み、詩話会編『日本詩集』(大正九年七月)版に新人として登場した。 ・芸術至上主義派の「詩人会」のメンバーとして活躍。「新詩人」(大正十年五月創刊)、「紀元」(大正十二年十月創刊)を出した。 ・大正十三年三月、東洋大学専門学部第三科(文化学科)卒業、聚芳閣入社、大正十四年頃退社。 ・大正十五年十月十二日、『詩話会委員諸君に宛る公開状』(「読売新聞」)を金子光晴、尾崎喜八ら六名と出すなど若い世代の詩人として活躍した。 ・昭和二年から昭和十三年まで、報知新聞社に入り社会・学芸部を経て、昭和十四年よりビクター専属作詞家として活躍、多くの詩や唱歌・童謡(「歌の町」「小ぎつね」「とうだいもり」「夜汽車」など)や校歌を作詞しました。組曲『生活の歌』『若い合唱』の作詞でも知られる。 ・詩集に『惑星』(大正十一年六月刊行 抒情詩社)『朝の微風』(大正十二年三月刊行 交香蘭社)『白い馬』(昭和八年十月刊行 素人社書屋)『航路』(昭和二十二年八月刊行 多磨書房)などがあります。 ・東洋大学理事長を務めるかたわら、昭和五十二年に日本音楽著作権協会会長に就任、五十五年まで務めた。詩と音楽の会の会長を務めていた。音楽関係作家の地位の向上に貢献しました。 ・昭和二十二年度の文部省の音楽教科書編集委員の一人で、作詞を担当した。[昭和22年の小学校音楽の教科書]参照。 ・昭和五十六年(1981年)八月三日没。 【歌碑について】 この歌の歌碑は、一周忌にあたる昭和五十七年、遺族や友人らによって谷中六丁目の大雄寺本堂前に建てられました。詩人の自筆で一番の前半が刻まれています。歌碑があることは、あまり知られていません。 【大和田建樹の作詞】 最初は、明治二十二年(1889年)、大和田建樹 奥好義(同選)『明治唱歌』第三集(中央堂)に「旅泊」というタイトルで発表されました。 大和田建樹の作詞は「磯の火細りて 更くる夜半に」と、舟旅に出た旅人の心細い気持ち、夜が明けてほっとする気持ちがよく出ています。いかにも明治時代的な日本語詞ですが、長く愛唱されました。 CD全集『原典による近代唱歌集成』(ビクター)では、「女学生の愛唱歌」として収録されています。
【佐佐木信綱の作詞】 続いて明治三十九年(1906年)には大橋銅造・納所弁次郎・田村虎蔵(共編)『高等小学唱歌』(一ノ下)国定教科書共同販売所発行に、佐佐木信綱の作詞で「助船」というタイトルで掲載されました。 助 船 佐佐木信綱 激しき雨風天地暗く 山なす荒波たけり狂う 見よ見よかしこにあわれ小舟(おぶね) 生死(しょうじ)の境と救い求む 救いを求むる声はすれど この風この波誰も行かず 見よ見よ漕ぎ出(ず)る救い小舟 健気な男子(おのこ)ら守れ神よ 【ヤマベコウゾウの作詞】 北海道在住の北島治夫さんから、教科書研究協議会編『あの音あの声』小学5年音楽教科書(教育出版)昭和25年1月20日発行〔昭和23年8月24日文部省検定済〕掲載の、「とうだいもり」の歌詞と楽譜のコピーを送っていただきました。ありがとうございました。 タイトルは、勝承夫の作詞と同じ「とうだいもり」です。
楽譜は変ロ長調、八分の六拍子。「弱起」=アウフタクトを学習するための教材として掲載されています。 ≪著者・池田小百合≫ 【著者より引用及び著作権についてお願い】 |
|||||||||
【著者より引用及び著作権についてお願い】 《著者・池田小百合》 |
【原曲】 原曲は、Long Long Agoというイギリス民謡で、十九世紀前半に活躍したイギリスの作曲家トーマス・ヘインズ・ベイリー(Thomas Haynes Bayly 1797年~1839年)が、今の形に整えたといわれている。 原詞の内容は、久しぶりに会った昔の恋人と、過ぎ去った日々の思い出を語り合い、ともに懐かしんで再会の喜びをかみしめる郷愁を感じさせるもの。 【日本初出】 日本初出は,真鍋定造監修撰譜『幼稚唱歌集 全』(普通社、明治二十年(1887年)三月)の第十五曲「むかしの昔」です。二番まで。奇妙で難解な歌詞です。これを、子供たちが声をそろえて歌ったのでしょうか。
むかしの昔 作詞者不詳 一、むかしのむかし いにしむかし おもかげうかぶ よよのゆめ きよみが関に たま津しま きよみが関に たま津しま 遊びしむかし ゆめにみゆ 二、過にしむかし いにしむかし おもかげうかぶ むねのうち をばすての月 みかのはら をばすての月 みかのはら ねざめのとこに うかぶかお 【大和田建樹(おおわだたけき)の作詞】 大和田建樹が作詞して、大和田建樹・奥好義(おくよしいさ)共編『明治唱歌』第一集(中央堂)明治二十一年(1888年)五月発行に掲載。 旅の暮 大和田建樹 一 落葉をさそふ森のしぐれ なみだと散りて顔をうつ。 ふるさと遠き旅のそら。 ゆきがた知らぬ野辺の路。 一夜をたれにやどからん。 二 すすきにむせぶ谷のあらし 夕ぐれさむく身にぞしむ。 木(こ)の間をもるる日の光。 山辺にひびく鐘のこゑ。 うれしやあれにやどからん。 三 夢にも見ゆるこひしわがや。 そなたの空は霧こめて 月影ほそくけむるなり。 なきゆく雁もあときえぬ。 あけなばいそぎ文(ふみ)やらん。 <一番の歌詞を詳しく見ましょう> おちーばをー|さそーふ|もりーの|しぐーれ| なみーだとー|ちりーて|かほーをうー|つ| ふるさととほき|たびのさら|ゆきがたしらぬ|のべのみち| ひとーよをー|たれーに|やどーからー|ん| 九小節から十二小節までは、四分音符一拍に、二つの言葉を付けています。また、八分音符には、一音ごとに細かく言葉を付けています。この四小節は、文字が多すぎてごたごたした感じを受けます。前半八小節と最後の四小節は、言葉が足りずに間延びした感じを受けます。好い歌詞とは言えません。 【近藤朔風の作詞】 “明治四十年(1907年)には近藤朔風によって原詞に忠実に「久しき昔」として訳された”(『原典による近代唱歌集成』(ビクターエンタテインメント)による)。三番まで。文語体で難解なので、原語「Long Long Ago」で歌われることのほうが多かったようです。 (註)金田一春彦・安西愛子編『日本の唱歌〔中〕大正・昭和篇』(講談社文庫)には、“大正二年、近藤朔風によって、「久しき昔」という題で次のような訳詞が作られた”と書いてある。どちらかが間違い。★調査中 久しき昔 近藤朔風 一、語れ愛(め)でし真心(まごころ) 久しき昔の、 歌え床(ゆか)し調べを 過ぎし昔の。 汝(なれ)帰りぬ ああ嬉し 永き別れ ああ夢か。 賞(め)ずる思い変わらず 久しき今も。
<楽曲について> (1)ヘ長調(F Dur)、四分の四拍子、♩=100 曲はA(aa´)B(ba´)の二部形式。 旋律aa´は山形を作り、bは下行線というふうに対照づけられている。 (2)各フレーズの終わりは、みな主音で終わっているが、aとbは第三拍目なので、フレーズとしては十分な段落を表現していない。aもbも半終止の形を成している。a´は最後の主音が、第一拍目長い音符(二分音符)で終わっているので終止感が強い。 (3)リズムは四分音符と八分音符が交互に組まれ、a´の三小節目に付点八分音符と十六分音符とのリズムが出て来る程度で、全体に非常に整った形をしている。旋律も、ほとんど音階的順次進行の形をしているが、bのフレーズで五度、七度の跳躍音程がみられる。 【古関吉雄の作詞】 古関吉雄が作詞した「思い出」が、『六年生の音楽』昭和二十二年(1947年)発行に掲載され、今でも歌われています。美しい歌詞です。 <「思い出」の歌詞について> 「かきにあかいはなさく」:歌い出しの「かき」は、「垣(かき)」=垣根であって、「柿」ではありません。「垣根に赤い花が咲く(赤い花が垣根に咲いたよ)」というのですが、歌になると「柿に赤い花咲く」と聞こえてしまいます。ここは、「柿の花は赤い」と勘違いしている人が多いようです。柿の花は白です。 「とりのうたきぎめぐり」も、「鳥の歌聞きめぐり」と誤解される歌詞です。「鳥の歌が木々をめぐる(木々をめぐる鳥の歌)」の意味です。 『六年生の音楽』昭和二十二年(1947年)発行には二部合唱の楽譜が掲載されています。
【昭和27年版 もうひとつの「思い出」】
メロディーは、『六年生の音楽』昭和二十二年発行と同じ。メロディーの下には三部のハミング伴唱が書いてある。速度標語は、♩=108。 「かきにあかいはなさく」は同じ。「とりのうたきぎめぐり」は、「とりはうたいさえずり」に変えてある。他の部分も歌詞が変更されている。一番も二番も「いつかのあのいえ」、「いえ」に統一したので覚えやすくなった。二番の「目にもうかぶあおぞら」は、「目」だけ漢字になっている。歌詞のみは掲載されていない。 思い出 (楽譜の歌詞) 一、 かきにあかいはなさく、いつかのあのいえ。 ゆめにかえるそのにわ、はるかなむかし。 とりはうたいさえずり、そよぐかぜにはなちる。 むねにひめるおもいで、はるかなむかし。 二、 しろいくものうかんだ、いつかのあのいえ。 くさのひかるそのみち、はるかなむかし。 いまもうたうあのうた、目にもうかぶあおぞら。 ひとりおもいわすれぬ、はるかなむかし。 『音楽6年』(音楽之友社)昭和四十年発行には、西崎嘉太郎編曲の三部合唱が掲載されている。指導書の解説には“この単元では、三部合唱を通して合唱能力を高め、美しい三声の響きを味わわせるとともに、旋律と和音との関係を理解させる”と書いてある。レベルが高い。監修:堀内敬三 編集:広瀬鉄雄ほか。 【古関吉雄(こせきよしお)の略歴】 福島県に生まれる。東京帝国大学国文学科卒業。音楽は福井直秋(武蔵野音楽大学の創立者)と岡本敏明(国立音楽大学教授で「どじょっこ ふなっこ」の作曲者)に学ぶ。明治大学教授、国立音楽大学講師を勤めた。ドイツ歌曲の訳詞が多い。「追憶」などの訳詞の他、校歌の作詞もしています。「小田原市曽我小学校校歌」は古関吉雄作詞、岡本敏明作曲。 昭和二十二年版『六年生の音楽』の編纂にあたった岡本敏明の推薦で、「思い出」歌詞が採用されたのでしょう。 【歌ってみましょう】 この歌には、いろいろな人の訳詞があります。藤田圭雄著『童謡の散歩道』(日本国際童謡館)には、門馬直衛の作詞(昭和三十三年『世界民謠全集』より)や、藤田圭雄自身の作詞も掲載されています。大和田建樹、近藤朔風、古関吉雄、門馬直衛、藤田圭雄の歌詞で歌ってみましょう。
唱歌には、外国の曲に日本語の歌詞をあてはめた曲が数多くあります。外国のメロディーと、日本語のアクセントをぴったり一致させる事は難しい。 結局、教科書に掲載され、全国の学校で歌われた「思い出」が今も歌い継がれています。教科書に掲載する選曲は重要です。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 ≪著者・池田小百合≫ |
||||||||||||||
【著者より引用及び著作権についてお願い】 ≪著者・池田小百合≫ |
| 【著者より著作権についてのお願い】 文章を使用する場合は、<ウェッブ『池田小百合なっとく童謡・唱歌』による>と書き添えてください。 |
メール (+を@に変えて) |
トップ |