q
![]() 池田小百合トップページに戻る
池田小百合トップページに戻る
![]() なっとく童謡・唱歌メニューページに戻る
なっとく童謡・唱歌メニューページに戻る
| 池田小百合 なっとく童謡・唱歌 |
| 映画・テレビの新しい童謡 |
| アイアイ あわてんぼうの サンタクロース 一ねんせいに なったら |
| いっぽんでもニンジン おかあさん おもいでのアルバム おもちゃのチャチャチャ 河は呼んでいる 北風小僧の寒太郎 さんぽ 幸せなら手をたたこう |
| 四季の歌 だれかが口笛ふいた 手のひらを太陽に パンの唄 |
| ひげなしゴゲジャバル まっかな秋 森の熊さん 山の音楽家 |
| 内容は「童謡・唱歌 事典」です(編集中です) |
【初放送】 昭和三十四年(1959年)八月二十四日、フジテレビの大人向けバラエティ番組『ヤマハタイム』で、「おもちゃ」をテーマにした日の番組中に一度だけ歌われたのが最初です。番組制作の「冗談工房」文芸部にいた野坂昭如(のさかあきゆき)が作詞しました。作曲は越部信義(こしべのぶよし)。 【NHK『うたのえほん』委嘱作品】 昭和三十七年(1962年)に補作詞。サトウハチロー門下で学んだ吉岡治は、NHKからの依頼で子どもの歌の詩を一度にまとめて十曲ほど書いていた時、あと一曲がなかなかできなかった。 そのとき、野坂昭如の書いた「おもちゃのチャチャチャ」を子ども向けに作りかえる事を思いついた。 野坂昭如が書いた詞は、「夜のとばりがおりまして 星がきらきら光ったら オモチャの箱は目をさます オモチャとオモチャのチャチャチャ」という歌い出しで、オモチャとオモチャが男女ペアで踊るという設定が、夜の社交場のことだと見られた。特に子どもを意識して作られた作品ではなかった。 それを「空にキラキラお星さま」にし、男の子の夢だった「なまりの兵隊」や、女の子の好きな「フランス人形」を盛り込んだ。 【『うたのえほん』で放送】 NHK総合テレビ『うたのえほん』が画期的な幼児向け番組として、昭和三十六年四月に開始された。 昭和三十七年、吉岡治さんが補作詞した、「おもちゃのチャチャチャ」は、八月の“今月の歌”として真理ヨシコさんと中野慶子さんが一週間交代で毎日歌った。委嘱作品。 ●『うたのえほん』放送の「初日に発表された」は間違い。 【『うたのえほん』の初日】 NHK総合テレビ『うたのえほん』は、昭和36年4月3日(月)、午前8時30分のスタート。『おかあさんといっしょ』とは発想の根を異にし、別の角度から、子どものうたの一面を切り開こうと始まった。 放送時間 午前8時30分~8時40分(月曜から土曜まで) 総合テレビ 対象 学令前の幼児と母親 出演者 ・真理ヨシコ 東京都立駒場高校芸術科卒、東京芸術大学声楽科在学中。本名は佐藤美子。 昭和13年生まれ ・中野慶子 長野県立松本深志高校卒、学習院大学卒。 昭和12年生まれ。 ・ピアニスト 小林道夫 三浦洋一 小島満里 ほか 昭和36年4月3日(月)歌 真理ヨシコ/体操 砂川啓一 「ぼうやがうまれて」「おすもう」「むすんでひらいて」「かわいいかくれんぼ」が歌われた。 「おすもう」佐藤義美・作詞 磯部俶・作曲は、のちに「おすもうくまちゃん」と改題。 昭和36年4月10日(月)歌 中野慶子/体操 砂川啓一 「ぼうやがうまれて」「ひらいたひらいた」「ふたこぶらくだ」「チューリップ」 上記のように真理ヨシコと中野慶子が一週間交替で出演。 「ぼうやがうまれて」が4月の“今月の歌”。 【歌詞の面白さ】 「おもちゃのチャチャチャ おもちゃのチャチャチャ」と歌詞と曲名がゴロ合わせになっているのが作詞の面白さである(服部公一著『童謡はどこへ消えた』(平凡社新書)による)。 【「チャチャチャ」大ヒット】 「おもちゃのチャチャチャ」は、日本で最初にエイトビートを用いた童謡。連続八分音符のリズムを総称してエイトビートという。 子どもたちに調子の好い「チャチャチャ」の声かけが受けて大ヒットした。一歳の子どもも聴くと手足をバタバタさせて大喜びする。「チャチャチャ」は戦後キューバで出現したリズム。 最後の「チャ チャ チャ」は、特にリズムに注意して歌いましょう。 【テレビ時代の童謡】 テレビ時代の童謡はテレビと同時に発達したコマーシャルソング(CMソング)に近い(服部公一著『童謡はどこへ消えた』(平凡社新書)による)。 【日本レコード大賞童謡賞】 昭和三十八年十二月、真理ヨシコが歌ったレコード(コロムビアレコード)は、第五回レコード大賞童謡賞を受賞しました。 【教科書での扱い】 ・『おんがくのおくりもの1』(教育出版)平成二十一年発行に「おもちゃのチャチャチャ」が掲載されている。 ・『あたらしいおんがく1』(教育芸術社)平成二十一年発行に「おもちゃのチャチャチャ」が掲載されている。 掲載の歌詞と楽譜は、日本放送協会編『NHKみんなのうた』第四集(日本放送出版協会)昭和四十一年発行と同じです。 〈その他〉 ・『小学生の音楽3』(教育芸術社)平成二十一年発行に「きょうりゅうチャチャチャ」(平野祐香里 作詞/加賀清孝 作曲)が掲載されている。 ・『音楽のおくりもの3』(教育出版)平成二十一年発行に「チャチャチャのリズムで」(横山太郎 作詞・作曲)が掲載されている。 【歌いやすくなっている】 レコード大賞当時の録音と、現在歌われている日本放送協会編『NHKみんなのうた』第四集(日本放送出版協会)昭和四十一年発行と異なる部分があります。 ・レコードは五番まであった。今の楽譜には以下はありません。 とんぼみたいな ヘリコプター ぐんとはやいな ジェットきは サイレンなれば はっしゃです うちゅうロケット チャチャチャ ・レコードの歌詞「ぶたはフースカ こねこはニャー あまちゃのみのみ チャチャチャ」は、『NHKみんなのうた』では「子羊メエメエ 子猫はニャー 子豚ブースカ チャチャチャ」に変わっています。 ・レコードの歌詞「まどにおひさま てらすころ」は、『NHKみんなのうた』では「窓にお日さまこんにちは」と歌うようになっています。 「チャチャチャ」の部分は、現在は全て同じ音形で歌っていますが、原曲では音程が上がる部分と下がる部分がある。現在歌われている方が歌いやすい。 【その後】 ・この歌を歌った真理ヨシコは、昭和三十七年九月まで、一年半の間、うたのおねえさんとしての名声を高め、竹前文子に交替した。 ・作詞者の野坂昭如は、『火垂るの墓』『アメリカひじき』で直木賞を受賞した。2015年12月9日、満85歳で逝去。 ・補作詞の吉岡治は、「天城越え」などの演歌の作詞で有名になった。 ・作曲者の越部信義は、第十回(1980年)「おもちゃのチャチャチャ」で『日本童謡賞』を受賞。 「うたのえほん」から生まれた代表的な歌に「朝いちばんはやいのは」(阪田寛夫 作詞)もある。2014年11月21日、満81歳で逝去。 この歌の作詞・補作詞・作曲者は、冗談音楽で知られる三木鶏郎(みきトリロー)の「冗談工房」に所属し、CMソングを作っていた仲間。 ・三木鶏郎(1914~1994)は、日本のコマーシャルソング作りのさきがけで、NHKラジオ『日曜娯楽版』の冗談音楽―社会風刺で一世を風靡した。その後のマスコミに大きな影響を残した。東大法学部の出身で、作詞、作曲、台本製作をこなす異才だった(服部公一著『童謡はどこへ消えた』(平凡社新書)による)。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 利用される場合は、「池田小百合なっとく童謡・唱歌」と出典を明記してください。それはルールです。 ≪著者・池田小百合≫ |
「手のひらを太陽に」の調査のために、いずみたく著『見上げてごらん夜の星を』(新日本出版社)を買った。これに、いずみたくが「幸せなら手をたたこう」ができるまでを書いていて、それは驚く内容だったので、皆さんにも、お知らせします。
【真相のまとめ】 一、 歌手の坂本九が、アメリカのフォークダンスの歌のようなものを、バスガイドさんが歌っていたのを聞いた。 二、 坂本九は、作曲家のいずみたくに、「何とかなら手をたたこうっていって手をパンパンとたたくんだ」「態度で示そうよという所もあるんだ」と言った。 (註)この時点で、歌詞も曲もあったことになる。 三、 それを聞いた、いずみたくは、「じゃあ、幸せなら手をたたこう、パンパン。とたたきゃあいいじゃないか」と、アメリカのフォークソング風ならこのようなメロディーではないかと想像しながら「幸せなら手をたたこう」と作曲してパンパンと手をたたいた。 四、 そのうちに「幸せなら手をたたこう、幸せなら態度で示そうよ、ホラ皆で手をたたこう」、というメロディーも何となく出来てしまった。 五、 いずみたく自身が作曲した歌だが、アメリカの民謡らしさを取り入れて作ったので、作曲という名前を入れるのが恥ずかしかった。メロディーは、間違いなく、いずみたく。 六、 いずみたくは、この歌一曲だけのためにペンネームを作った。「有田怜(ありたれい)」である。 七、 その後、作詩者が名乗り出た。「きむらりひと(木村利人)」という。 八、 作詞者の、きむらりひとによると、原曲は「スペイン民謡」。 スペインで歌われていたメロディーが植民地のフィリピンに伝わった。 また、アメリカ西部の開拓に関わったスペイン人がアメリカの地にも歌い広めた。 九、 作曲家の黛敏郎によると、のちにアメリカ西部の歌の、 おいらは一万年前に生まれて アダムとイブがりんごを かじつたところを 見ちゃったぜ といった一種のナンセンス・ソングにアレンジされたという。 (註)八、九、は、(金田一春彦 安西愛子編『日本の唱歌〔中〕大正・昭和篇』(講談社文庫)による)。 <きむらりひとが作詞> きむらりひと(木村利人)は、早稲田大学大学院法学研究科博士課程修了、同大学人間科学部人間健康科学科教授。 「幸せなら手をたたこう」は、学生時代にフィリピンから持ち帰ったメロディー。聖書の詩篇四十七篇「もろもろの民よ 手をうち 喜びの声をあげ 神に向かって叫べ」をヒントに作詞をした(『日本のうた こころの歌』(DeAGOSTINI)による)。 十、いずみたくは、“メロディーはボクであることは本人が言うのだから間違いない”と書いているが、「編曲 有田怜」が妥当な気がします。 【坂本九が歌う】 坂本九が歌い出すと、全国の赤ちゃんからお爺ちゃんまで歌い出して日本中に拡まった。あまりやさしいメロディーなので、すぐ覚えられてしまうので、レコード(東芝レコード 昭和39年6月発売)は少ししか売れなかったが、歌は一世を風靡した。 【誕生日にも歌おう】 みんなで誕生日に歌うと、いっそう楽しくなります。 「幸せなら 態度でしめそうよ ほら みんなで 手をたたこう」 すてきな歌詞です。 【流行った理由】 (Ⅰ) いずみたくは、その著の中で“あまりやさしいメロディーなので、すぐ覚えられてしまう”と書いています。 (Ⅱ) 詩人・川崎洋(かわさき・ひろし)は、“みんなで歌うから味が出る”と書いています。 “♪しあわせなら手をたたこう、とみんなと歌ってみると、別にしあわせでもなんでもないのに、妙に気持ちが盛り上がってしまう。これまでの人生で経験したことのない気分でした。以来、ずいぶんこの歌を歌いました。みんなで歌うから味が出るのだと思います。わたし自身がひとりで歌うなら、しあわせなら目をつぶろう、つぶってそのしあわせを噛みしめよう・・・みたいなつぶやきになってしまいそうです。”川崎洋著『心にしみる教科書の歌』(いそっぷ社)より抜粋。 川崎洋が言うように、この歌は一人で歌っても面白くありません。みんなで歌うから楽しいのです。 ●川崎洋著『心にしみる教科書の歌』(いそっぷ社) に“アメリカ民謡”と書いてあるのは間違い。原曲は「スペイン民謡」です。 <著者・池田小百合> 【著者より引用及び著作権についてお願い】 利用される場合は、「池田小百合なっとく童謡・唱歌」と出典を明記してください。それはルールです。 |
【「シャラランリン」か「リンリンリン」なのか】 童謡や唱歌を歌う会で一番困るのは、「クリスマス」です。当然だが、歌う歌が無い。しかし、嬉しい事に日本人が作った『あわてんぼうの サンタクロース』がある。子供たちが大好きな歌です。 ある年の十二月、私だけが日本放送協会・編『NHKこどものうた楽譜集 第2集』(日本放送出版協会) 1968年(昭和43年)7月20日第1刷発行 1969年(昭和44年)9月15日第5刷発行の楽譜を見て歌い、童謡の会員は、その歌詞の部分を見て歌った。五番のラストにくると、楽譜を見て歌った私だけが「シャラランリン チャチャチャ ドンシャララン」と歌い、歌詞を見て歌った童謡の会員は全員「リンリンリン チャチャチャ ドンシャララン」と歌った。私が間違えた事になってしまい、私は慌てた。 【小学二年生の音楽教科書での扱い】 平成七年二月十五日文部省検定済、平成八年発行と平成十年発行の『小学生の音楽2』(教育芸術社)を見ると、楽譜の下に「リンリンリン チャチャチャ ドンシャララン」と書いてある。 ・4分の2拍子に改訂してある。 ・五番の前半は「リンリンリン チャチャチャ ドンドンドン シャラランラン」なので、ラストは「リンリンリン チャチャチャ ドンシャララン」が妥当と思われる。この方が覚えやすいし、歌いやすい。 ・日本放送協会・編『NHKこどものうた楽譜集 第2集』(日本放送出版協会)によると歌詞37ページの五番は「リンリンリン チャチャチャ ドンシャララン」と書いてあるので、小学校二年生にわかりやすく楽譜を4分の2拍子に改訂した時に、楽譜の歌詞部分も「リンリンリン」に改訂したのでしょう。 ・これにそろえて、私の童謡の会でも「リンリンリン チャチャチャ ドンシャララン」と歌う事にした。
ところが、平成十六年二月二十九日検定済、平成二十一年一月二十日発行の『小学音楽 音楽のおくりもの2』(教育出版)を見ると、楽譜の下に「シャラランリン チャチャチャ ドンシャララン」と書いてある。私は慌てた。
【「シャラランリン」は誤植か】 もう一度、日本放送協会・編『NHKこどものうた楽譜集 第2集』(日本放送出版協会) 1968年(昭和43年)7月20日第1刷発行 1969年(昭和44年)9月15日第5刷発行の楽譜を検討して見る事にした。 「シャラランリン」という歌詞は、他に使われていなくて、突然出て来るのは不自然に思われる。これは「リンリンリン」の誤植ではないか。35ページの楽譜をよく見ると楽譜に歌詞を入れる時、楽譜右側一段目の「リンリン」「ドンドン」「チャチャ」「シャララン」を楽譜右側二段目も同じように入れてしまった可能性がある。どうだろうか。 【教育出版社からの回答】 なぜ「シャラランリン」なのか、『小学音楽 音楽のおくりもの2』の教育出版株式会社に問い合わせると、次のような回答をいただきました。
<教育出版社 まとめ> ・日本放送協会・編『NHKこどものうた楽譜集 第2集』(日本放送出版協会)1967年(昭和42年)印刷発行をもとにしている。 ・2分の2拍子だったものを、教科書掲載に際し低学年であることも鑑み、4分の2拍子に変更した。 ・歌詞はそのまま変更なく掲載した。だから「シャラランリン」。 ★教育出版株式会社からの回答によると、日本放送協会・編『NHKこどものうた楽譜集 第2集』(日本放送出版協会)は、1967年(昭和42年)印刷発行があるようだ(調査中)。1967年(昭和42年)印刷発行をさがしています。所蔵図書館を教えて下さい。 【「こどものうた楽譜集」出版の検証】 再度、日本放送協会・編『NHKこどものうた楽譜集 第2集』(日本放送出版協会)1968年(昭和43年)7月20日第1刷発行 1969年(昭和44年)9月15日第5刷発行の楽譜を検討してみる事にした。 何回見ても奥付には「1968年7月20日第1刷発行」と書いてある。 「刊行にあたって」の前書きには「昭和42年9月 日本放送協会教育局青少年部長 小山賢市」とあるので、昭和42年9月には出版の準備ができていたことになる。しかし、実際に出版されたのは1968年(昭和43年)7月20日第1刷発行。10ヵ月も遅れての出版になった。何か深い理由がありそうだ。 では、日本放送協会・編『NHKこどものうた楽譜集 第1集』(日本放送出版協会)の奥付を見ると、「1967年4月10日1刷発行 1971年2月20日10刷発行」と書いてある。この本の初版は「1967年印刷発行」。 「刊行にあたって」の前書きには「昭和42年4月 日本放送協会教育局長 吉田正」と書いてある。発行は「昭和42年4月10日」。 【歌詞集では】 私、著者 池田小百合は、日本放送協会・編『NHKこどものうた楽譜集 第2集』(日本放送出版協会) 1968年(昭和43年)7月20日第1刷発行 1969年(昭和44年)9月15日第5刷発行を持っています。この本の初版は1968年です。 歌詞37ページの五番は「リンリンリン チャチャチャ ドンシャララン」と書いてある。一方、34~35ページの楽譜は、ヘ長調で2分の2拍子。五番は「シャラランリン チャチャチャ ドンシャララン」と書いてある。 池田小百合編著『読む、歌う 童謡・唱歌の歌詞』(夢工房)は、歌詞集なので、歌詞37ページの五番にそろえて「リンリンリン チャチャチャ ドンシャララン」としている。童謡の会では「リンリンリン」と歌っています。 五番の最後は「リンリンリン チャチャチャ ドンシャララン」が自然で歌いやすい。 【一般の人は】 この歌を楽しく歌う一般の人は、以上の事情を全く知らない。「リンリンリン」と「シャラランリン」の二つの歌詞に遭遇した時、当然「どちらが正しいのだろうか」と迷う。童謡や唱歌は歌詞や楽譜を見ないで歌い、歌い継がれるものなので、覚えやすく歌いやすい方が歌われていくはずです。 そこで、作詞をした吉岡治(よしおかおさむ)氏に問い合わせるのが一番と思ったが、吉岡治氏は亡くなっていた。 【吉岡治の略歴】 Wikipediaより ・昭和九年(1934年)二月十九日、山口県阿武郡田万崎村(現・萩市江崎)で誕生。東京都で育った。文化学院卒業。 ・昭和二十八年(1953年)に詩人のサトウハチローの門を叩き、弟子となる。作詞家としてのデビューは『鳩笛ならそか』(一九五六年)。 ・昭和四十年(1965年)の松竹映画『悦楽』(大島渚監督)の主題歌『悦楽のブルース』(歌唱:島和彦)の作詞を手掛けて以降、本格的に作詞家として活動し歌謡曲、童謡、アニメソングなど幅広いジャンルの作品を世に送り出した。 ・平成二十二年(2010年)五月十七日、入院先の東京都内の病院で急性心筋梗塞のため逝去。享年七十六歳。 <歌謡曲の作詞> 島和彦『悦楽のブルース』、石川さゆり『天城越え』、石川セリ『八月の濡れた砂』、五木ひろし『北酒場』(細川たかしの同名の歌もヒット)『細雪』、大川栄策『さざんかの宿』、川中美幸『花咲港』『越前岬』『忍ぶ川』『浪花灯り』、瀬川瑛子『命くれない』、千賀かほる『真夜中のギター』、新沼謙治『情け川』、松原のぶえ『演歌みち』、美空ひばり『真赤な太陽』『龍馬残影』、都はるみ『さよなら海峡』『大阪しぐれ』、森進一『薄雪草』、山本譲二『時は流れても』ほか。 <童謡> 「おもちゃのチャチャチャ」(野坂昭如と共同)、「あわてんぼうのサンタクロース」「ヘイ!タンブリン」ほか。 <アニメソング> 光速エスパー『光速エスパーの歌』(歌:望月浩)、悟空の大冒険『悟空の大冒険マーチ』『悟空がすきすき』(歌:ヤング・フレッシュ)、魔神バンダー『魔神バンダーの歌』(歌:佐々木梨里、ハニー・ナイツ)、まんがはじめて物語『?(ハテナ)なぞ謎アイランド』(歌:岡まゆみ)、キャプテン翼『燃えてヒーロー』(歌:沖田浩之、小粥よう子、竹本孝之)『冬のライオン』(歌:沖田浩之)『明日に向かってシュート』(歌:小粥よう子)ほか。 【小林亜星(こばやし あせい)の略歴】 Wikipediaより ・昭和七年(1932年)八月十一日、東京都杉並区で生まれる。作曲家。そのほかに作詞家、俳優、タレント、歌手など、いくつもの顔も併せ持つ、多彩な才能の持ち主。一般に知られている名前の漢字表記は「亜星」だが、本人は「亞星」と書くようである。母の尊敬する演出家の息子の名前をとって「亜星」と付けられた(NHK『わたしが子どもだったころ』より)。 ・旧制慶應普通部から慶應義塾高等学校を経て、慶應義塾大学医学部入学、経済学部に転部して卒業。 ・作曲を服部正に師事した。現在、アストロミュージック所属。日本作詩作曲家協会理事。大日本肥満者連盟(大ピ連)初代会長を務めた。 ・CMソングやテレビ主題歌にヒット曲、ロングランの曲が非常に多く、そのメロディに日本人の多くが馴染んでいるという点では右に出るもののない存在。 <ヒットソング> 日立グループ「日立の樹」(この木なんの木)、ブリヂストン「どこまでも行こう」、歌謡曲「北の宿から」(歌:都はるみ)、「ピンポンパン体操」(作詞:阿久悠、作曲:小林亜星、編曲:筒井広志)。その他多数を作曲し活躍中。 【後記】 娘たちが小学生の時、子供会でクリスマス会があり、六年生の親が準備を手伝った。まず、クリスマスの歌を歌う事になり『あわてんぼうのサンタクロース』を歌った。周りで見ていた親たちは、口々に「知らない」と言っていた。五番までいく内には覚えて歌うだろうと思ったが、だれも歌わなかった。子供たちは体を揺すってリズムに乗って楽しそうに歌った。それを見た私は涙が出るほど感動した。その後、なぞなぞやケームをして遊び、用意されたプレゼントが配られ、みんなでケーキを食べた。娘たちは、このような行事には積極的に参加していたが、全く参加しない子供もあり気になった。二十年も前の事だが、歌を歌うと、このささやかなクリスマス会の思い出が蘇えって来る。 クリスマスは子供たちにとって楽しい行事です。『あわてんぼうのサンタクロース』を親子で歌えば、いっそう楽しいクリスマス会になるでしょう。日本には、こんなに素敵なクリスマスソングがある。 文化庁編『親子で歌いつごう日本の歌百選』(東京書籍)には掲載されていません。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 利用される場合は、「池田小百合なっとく童謡・唱歌」と出典を明記してください。それはルールです。 ≪著者・池田小百合≫ |
||||||||||||||||
【NHKみんなのうた】 ・阪田寛夫が作詞しました。原曲の歌詞と無関係ですが素晴らしい詩です。 ・『NHKみんなのうた』昭和四十年(1965年)五月の歌として西六郷少年少女合唱団の歌で放送されました。 ・当時販売されたテキスト『NHKみんなのうた』4・5月(1965年)には「5月(毎日)だれかが口笛ふいた」と書いてあります。 ・「だれかが口笛ふいた」の楽譜と歌詞は、日本放送協会編『NHKみんなのうた』≪第5集≫(日本放送出版協会、1966年6月25日発行)に掲載されています。NHKテキストの楽譜を再構成した『NHKみんなのうた』≪楽譜集≫が全29集刊行されています。 ●タイトルは、「誰かが口笛吹いた」は間違いで、「だれかが口笛ふいた」が正しい事になります。 ●楽譜収録は、“第六集に掲載”と書いてある物は間違いです。第六集は『NHKこどものうた楽譜集』第6集の事かと思い、手持ちの楽譜集を調べましたが、掲載されていませんでした。『NHKみんなのうた』≪第5集≫に掲載が正しい。このように、インターネット上には間違いが多い。
【阪田寛夫の仕事/略歴】1925年~2005年 【教科書の扱い】 『NHKみんなのうた』放送後、教科書に掲載され、ラジオ講座にも取り上げられました。 ・『中学生の音楽3』(音楽之友社) 昭和46年4月10日文部省検定済 昭和49年1月20日発行。 昭和49年4月10日改訂検定済 昭和50年1月20日発行。 ・高校の音楽教科書『音楽Ⅰ』(教育出版) 昭和47年4月10日文部省検定済 昭和49年1月20日発行。 昭和50年4月10日改訂検定済 昭和51年1月20日発行。 ・『NHK高校音楽Ⅰ』通信高校講座1975年4月7日~1976年4月4日、1974年4月1日~1975年4月6日 ・平成二十一年発行の小学校・中学校・高校の音楽教科書には掲載されていません。 音楽の教科書から消え、『NHKみんなのうた』の放送も遠くなると、次第に歌われなくなりました。 私、池田小百合が主宰する童謡の会で毎年取り上げても、「知らない」と言う人が増えて来ています。阪田寛夫が書いた歌詞は、すばらしいのに残念です。 【楽譜を詳しく見ましょう】
・ニ短調(6小節)→ヘ長調(8小節)→ニ短調(2小節)→ニ長調(8小節) 転調による曲の変化が効果的で、いきいきとした表情を与えています。 ・歯切れのよい行進曲ふうの伴奏にのって正確なリズムで歌いましょう。特にタッカのリズムとタタのリズムの違いに注意しましょう。 ・息つぎ(ブレス)は、必ず指示してある箇所で、瞬間的にします。曲の流れが切れないように注意しましょう。先に曲があって、それに日本語詞を乗せたので、ブレスがないと「たならのきの」になってしまいます。 「くちぶえふいた(ブレス)ならのきの」というように、ブレスで、一まとまりの言葉をはっきりさせます。この歌の場合は、特にブレスが大切です。 ●『NHK みんなのうた』第5集(昭和41年6月25日第1刷発行、昭和54年4月20日第35刷発行)の楽譜にはブレスがありません。 【季節はいつか】 一番には「くりの花」、二番には「麦笛」があります。「若葉」の季節の歌です。栗の花期は六月から七月。果期は九月から十月。 私の童謡の会では、毎年六月に歌います。私が小学生だった頃、みんなで麦笛を吹きながら好い気分で登下校したものです。麦畑には、ヒバリの巣があり、卵を見る事ができました。のんびりした時代でした。道草は楽しかった思い出ですが、今思えば、通学路沿いの農家にとっては迷惑だったことでしょう。御殿場線「相模金子駅」周辺は家が建ち、麦畑を見る事はなくなりました。ヒバリもいません。 「だれかが口笛ふいた」の原曲についてインターネットを見ると「サンブル・エ・ミューズ連隊行進曲」「サンブレ・エ・ミューズ連隊行進曲」「サンブル・エ・ムーズ連隊行進曲」「サンブル・エ・ミューズ(ムーズ)連隊行進曲」と、いろいろなタイトルが並んでいます。どれが正しいのでしょうか。解説は似ていますが、少しずつ違います。写し違いや、要約する時の解釈の違いもあるようです。それで、調べてみる事にしました。 【行進曲ができるまでの経緯】 ・原曲は、フランスのロアール地方で歌われた古い民謡で、原題は不明です。 ・このフランス民謡を題材にして、歌劇「コルネヴュの鐘」の作曲家として有名なオペレッタ作曲家ジャン・ロベール・プランケット(Jean Robert Planquette 1848年~1903年)が、シャンソンの作曲家として名を売っていた頃に「サンブル・エ・ムーズ連隊」(作曲:プランケット)の歌を作った。[米VICTOROLA 88600] のCD解説にはこう書かれているが、英語のウィキペディアの曲目解説には、「原詩は1870年にポール・セザーノ Paul Cezano によって士気を鼓舞するために書かれた。普仏戦争の初期、フランス第三共和政の最初の日々だった。フランスの農民から結成された軍隊の勇猛果敢な活躍ぶりを描いた詩」とある。 ▼「サンブル・エ・ムーズ連隊」フランス語歌詞 日本語訳(英訳を参考にした)
・1876年、フランス歩兵第十八連隊将校団のレセプションが開かれた時、この歌が歌われたところ、フェロン連隊長が気に入って、同席していた軍楽隊楽長ジョセフ・フランソワ・ラウスキ(Rauski 1837年~1910年)に、この歌をテーマに取り入れた連隊の行進曲を編曲するように要請した。編曲は1879年に完成した。 ラウスキはパリ音楽院コルネット科を優等で卒業して陸軍の楽長試験に合格し、1871年から1893年まで歩兵第十八連隊の楽長をしていた。 ・後に陸軍大臣になったフェロン将軍は、1887年に全フランス陸軍の分列行進曲に制定した。「Le Régiment de Sambre et Meuse サンブル・エ・ムーズ連隊行進曲」(編曲:ラウスキ)は、フランスで最も有名な軍隊行進曲の一つです。「Régiment」は、連隊、多数という意味のフランス語です。 (参考)〔米VICTROLA 88600〕のCD解説は北海道在住のレコードコレクター北島治夫氏所有のもの。教えていただき、ありがとうございました。プランケットが作曲した歌のタイトルは<サンブル・エ・ムーズ連隊>と書いてあります。歌手はエンリコ・カルーソー(1919年1月6日録音)。 <カルーソーのSPレーベル> レーベルは、あずき色で金色文字。
また、北島氏には次のように教えていただきました。 “原題ですが、「サンブレ」という発音は間違いです。最後のeは発音しません。もし「サンブレ」と発音するならSambréとなっているはずです。 Meuseについてはカタカナ表記がきわめて難しい発音で、「ムーズ」「ミューズ」の中間の曖昧なものですね。ドイツ語のüのような発音です。ですから、この表記はいずれでも良いと思います” ウェブで検索すると、「サンブル・エ・ミューズ(ムーズ)連隊行進曲」となっていました。 この曲はアメリカでも有名で、アメリカン・フットボールの試合の際に、オハイオ州立大学のマーチング・バンドによって演奏されています。 【川の名前】 原曲名の「Sambre サンブル」と「Meuse ムーズ」は、いずれもフランスから流れ出す川の名前です。とても美しい川です。 <Sambre サンブル川について> 北フランス、南ベルギーを流れて、ナミュール(Namur)でムーズ川に合流する。 <Meuse ムーズ川について> フランスを水源として、ベルギー南部を通ってオランダのロッテルダムでライン川と合流して北海に注ぐ。運河によってセーヌ川とも通じている。 フランス(フランス語)では Meuse ムーズと発音する。ベルギー(ワロン語)では Mouze ミューズ、オランダ(オランダ語)では Maas マースと呼ばれる。 <Namur ナミュールについて> この二つの川に挟まれた地域(旧フランス領)は、現在はベルギーのナミュール州にあたる。シーザー軍の侵攻に備えるために砦を築いたのが、ナミュールが歴史に現れる最初の事件だという。その後も、交通の要衝の故に、戦火が絶えず、破壊と復興が繰り返されてきた。歌に歌われている農民の決死部隊が理解できます。 <Muse ミューズ> フランス語。文学の神。詩の神。詩人。この歌と何も関係がない。 川については、インターネットで検索しました。インターネットは便利で、旅行後に写真を掲載している人や、地図を出している人もいて、ひとしきり、その美しい景色に見とれました。旅行に行った気分になりました。一体誰の写真でしょうか。名前が無いので、多くの場合、無責任な文になってしまう傾向があります。曲の解説も同様です。責任ある文には名前が不可欠と思います。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 利用される場合は、「池田小百合なっとく童謡・唱歌」と出典を明記してください。それはルールです。 ≪著者・池田小百合≫ |
●2015年(平成27年)4月26日(日曜日)読売新聞日曜版Aに“まど・みちお「NHKうたのえほん」(1965年) 一ねんせいに なったら”と書いてある。発表は(1965年)なのだろうか? 調べてみることにしました。  【初出発表年について】 【初出発表年について】・まど・みちお『ぞうさん』(国土社の詩の本7)1975年11月25日発行には、“一ねんせいに なったら「NHK」昭和41年”と書いてある。 ・日本児童文学別冊『少年詩・童謡への招待』(偕成社)にも、(一ねんせいに なったら 山本直純作曲「NHK」1966年)と書いてある。 ・『NHKうたのえほん3』(日本放送出版協会)1965年7月1日初版発行には掲載されていません。 初出は1965年ではなく、1966年でした。 【タイトルについて】 ・≪ぞうさん≫まど・みちお 子どもの歌102曲集(フレーベル館)1995年3月 改訂初版第1刷発行には、「一ねんせいに なったら」と書いてある。 ・まど・みちお『ぞうさん』(国土社の詩の本7)1975年11月25日発行に収録の詩も、「一ねんせいに なったら」。 ・『NHKこどものうた楽譜集 第2集』(日本放送出版協会)昭和43年発行の詩も「一ねんせいに なったら」。 ・JASRACでは、著作物題名「一年生になったら」として扱っている。これにそろえて由井龍三著『言葉をかみしめて歌いたい童謡・唱歌』(春秋社)のタイトルは「一年生になったら」で、詩は「一ねんせいに なったら 一ねんせいに なったら・・・」となっている。タイトルと詩が一致していないので奇妙な感じだ。 【歌詞について】 ・「一ねんせいに なったら」と仮定している。 ・六行三連からできている。最初の三行は三連とも同じ。「できるかな」で期待と不安がよぎります。 ・百人の希望は、「たべたい」「かけたい」「わらいたい」。 ・それが、「富士山の上」「日本中」「世界中」と広がって行きます。 【創作の背景】 まど・みちおの長男の石田京(たかし)氏によると次のようです。 「父は対人折衝(せっしょう)が下手だった。仲が悪かったわけではないが、私とも母を介して意思疎通を図ることが多く、私の入学式にも参加しなかった。創作背景も聞いた事はない。そんな父だが100歳の頃、病院に見舞いに来たひ孫と一緒にこの歌を口ずさみ、ひ孫が小学校に入学するのを楽しみにしていた」(2015年4月26日読売新聞による)。 【ほかにも「一ねんせい」の歌】 ≪ぞうさん≫まど・みちお 子どもの歌102曲集には、「一ねんせいは いいな」が収録されている。
▲「一ねんせいは いいな」團伊玖磨 作曲 【曲について】 子どもの心を弾ませる歌です。各連の最後の「ぱっくん ぱっくん ぱっくんと」「どっしん どっしん どっしんと」「わっはは わっはは わっはっは」が曲を楽しくまとめています。食べる、走る、笑うしぐさをしながら歌うと、いっそう楽しくなります。「どっしん」は、あまり乱暴にならないように。 【親子で歌いつごう】 文化庁編『~親から子、子から孫へ~親子で歌いつごう日本の歌百選』(東京書籍)には、「高校三年生」は掲載されていますが、みんなに好かれている「一ねんせいに なったら」は選ばれていません。 現在、保育園・幼稚園では先生と子どもたちが卒園を前に声を張り上げて歌っています。ランドセルを買いそろえた家庭では親子で、また、おばあちゃんが孫と手をつないで楽しそうに歌っています。みんなが小学校入学を心待ちにして歌っています。「一ねんせいに なったら」は、長く歌い継がれると思います。 【山本直純との出会い】 娘たちが小学生の頃、足柄上郡松田町の松田町民文化センターにオーケストラが来た。指揮者は山本直純。子どもを対象にしたコンサートだった。山本直純が曲の話をするというので娘たちを連れて聴きに行った。 会場に入ると、まだリハーサルをしていた。ステージから降りてきた山本直純が言った。 「こりゃあ、全然だめだな。ひどいなあ。このオケは、どうしたんだい。誰でもいいというものではない」。右側のステージ用階段のすぐ下の席にいた私は、「何の事?」と思った。リハーサルが終わってステージから団員がハケても、まだクラリネットの人が一人残って練習をしていた。彼は、なかなかステージから去らなかった。譜面にかじりついて懸命に練習をしていた。 演奏会が始まると、山本直純が言っていた事がわかった。演奏中におかしな音がする。最初は何だろうと思ったが、トランペットやトロンボーンが「ピー!」「キー!」と音を外して悲鳴をあげているのだ。つまり、ヘタなのだった。このような練習不足のオーケストラは聴いた事がない。子どもたちを見ると、椅子で遊び始めていた。キコキコキコ、バッタン、キャーキャー!・・・それで帰る事にした。音楽会の途中で帰宅したのは、初めてだった。 あのコンサートは何だったのか? 曲目も思い出せない。小編成のオーケストラだったので、プロコフィエフ作曲の『ピーターと狼』だったかもしれない。今となってはオーケストラの名前もわかりません。音楽大学を卒業したであろうオーケストラの楽団員や山本直純は、子どもたちから拍手をもらって、はずかしくなかったのでしょうか。 2015年4月11日(土曜日)、夜9時30分からEテレで『らららクラシック』を観た。今日はハチャトリアンの「剣の舞」。ハチャトリアン自身がピアノで「剣の舞」を弾いた。青少年向けのコンサートのようだ。みんなが目を輝かせて演奏に聴き入っている。微動だにしない。すばらしい演奏は、聴衆を圧倒するものです。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 利用される場合は、「池田小百合なっとく童謡・唱歌」と出典を明記してください。それはルールです。 ≪著者・池田小百合≫ |
【作詞・作曲の経緯】 フォークグループ「伝書鳩」のメンバーだった荒木とよひさが、日本大学芸術学部時代の昭和三十九年(1964年)にスキー事故(新潟県妙高市の関温泉スキー場)で足を骨折し入院していた時に作った。退院時に、親切にしてくれた看護婦にお礼としてプレゼントした歌で、それがボランティア活動をしていた看護婦仲間に広がったといわれています。芹洋子もコンサートに来ていた看護婦に楽譜をもらっています。この曲が広まった当時は、作詞・作曲者は不詳とされていました。 【初レコード化】 “昭和47年(1972年)2月、ビクターが、いぬいゆみの歌で初レコード化、続いて6月、キングでダークダックスがLP『アカペラ』の中に収録しましたが、ともに今ひとつパッとしませんでした”(長田暁二著『心にのこる日本の歌101選』(YAMAHA)による)。 昭和四十七年には片山知子の歌で東芝(LTP2643)からも発売されました。 ●長田暁二監修『日本のうた ふるさとのうた100曲』(講談社)には、“昭和四十七年(1972年)三月にはじめてレコード化され”と書いてある。“2月”か“3月”どちらかが間違い。 ●米良美一(Yoshikazu Mera)著『日本のうた300、やすらぎの世界』(講談社+α文庫)の“昭和四十六年にいぬいゆみこの歌でレコード化された”の“昭和四十六年”と“いぬいゆみこ”は間違いという事になります。この解説には、レコード会社が書かれていない。 【芹洋子と「四季の歌」の出会い】 『日本のうた こころの歌』(デアゴスティーニ・ジャパン)には、次のように書いてあります。 “NHKの音楽番組『歌はともだち』で全国のお茶の間の人気者となった芹洋子は、神奈川県川崎市で毎月コンサートを続けていました。あるときのコンサートに来ていた一人の看護婦が芹洋子のところに耳慣れない曲を持ってきました。医療関係者の間で静かにブームとなっている歌だというのです。だれが作詞作曲したのかもわからないその歌は、わずか八小節しかありませんでしたが、歌ってみると、誰にでも親しまれそうなメロディーです。じつはこれが後に大ヒットする「四季の歌」だったのです”。 【芹洋子のレコードアルバム】 昭和五十年(1975年)十二月、芹洋子は「朧月夜」「夏の思い出」「赤とんぼ」など、春夏秋冬それぞれの季節を歌った抒情歌を集めてLP『四季の抒情』(SKD312)キングレコードを発表。その一曲目にふさわしい歌として「四季の歌」を採用しました。発表してみると売れ行きは好調で、「四季の歌」が人気を呼んでいるらしいというのです。 アルバム発売後、ラジオ番組での電話リクエストがきっかけで反響があり、「四季の歌」は人気の曲となって行きました”。 <電話リクエストについて> 長田暁二著『心にのこる日本の歌101選』(YAMAHA)には、次のように書いてあります。 “昭和51年6月3日、ニッポン放送の生番組『あおぞらワイド』に横浜の主婦・宮崎良子さんが電話リクエストしたところ、司会の立川清登(本名澄人を改名)が「四季の歌」を知らなかったので、彼女は番組の中で歌って聞かせました。 そしたら<その歌なら私も知っています>と、聴取者から局にジャンジャン電話がかかってきました”。 ●私、池田小百合は、文中の“そしたら”や“ジャンジャン”は、若い人の使う言葉で、これを尊敬する長田暁二氏が書かれたものか、疑問を持ちました。 【レコード会社の競作】 昭和五十一年(1976年)には、レコード会社八社の競作により、すがはらやすのり、芹洋子、立川清登らがレコーディングし発売された。 (註)「八社競作」の情報は『日本のうた こころの歌』(デアゴスティーニ・ジャパン)による。 レコードセールスで顕著なのはキングレコードの芹洋子盤だった(1976年8月21日シングルレコード発売)。累計売上は八十万枚以上を記録し、全国的な大ヒットとなりました。歌詞に「ぼく」とあるので男性歌手のレコードがヒットするのではないかと思われますが、芹洋子の清々しい歌声が受け入れられたのでしょう。 ●長田暁二監修『日本のうた ふるさとのうた100曲』(講談社)には“レコード会社六社が競作にはいった”と書いてある。 ●長田暁二著『心にのこる日本の歌101選』(YAMAHA)には“レコード会社(RVC、東芝EMI、コロムビア、クラウン、キャニオン、キング) 7社競作になりました”と書いてあるが、レコード会社の情報は6社しか書かれていない。 【曲の変化】 フォークミュージック特有の親しみやすさがあり、自然に入って来て、自然に歌える歌です。歌い継がれていくうちに、メロディーはいくとおりにも変化して聴き覚えたメロディーで歌い継がれているようです。レコーディングした歌手も、さまざまな歌い方をしています。 <いろいろな楽譜>
【歌詞の変化】 〔Ⅰ〕元の歌詞では一番が「すみれの花のような ぼくの恋人」、三番が「愛を語るハイネのような ぼくの友だち」だったものが、曲が広まっていく過程で入れ替わってしまったという説がある。これは納得できます。 今歌われているのは「すみれの花のような ぼくの友だち」、「愛を語るハイネのような ぼくの恋人」。これでは変です。 〔Ⅱ〕「根雪を」が「ゆきを」となっている出版物も沢山あります。 『改訂 新しい中学生のうた』伴奏編2(音楽之友社)ほか。 〔Ⅲ〕この曲には、五番の歌詞が存在するが、ほとんどの場合、五番に当たるところは、ラララで表現することが多い。芹洋子がそう歌っているからです。五番は次のような、まとめの歌詞になっています。どのように歌うのでしょう。 春夏秋冬愛して ぼくらは生きている 太陽の光浴びて 明日の世界へ 【教科書の扱い】 “教科書にも載り”と書いてある解説書がありました。この場合、教科書名、出版社名、出版年月日を書いておいてほしいと思います。手持ちの中学・高等学校用音楽教科書を全て調べました。調べるのに時間がかかりました。「四季の歌」が掲載されている教科書は二冊ありました。
『中学生の音楽2』(音楽之友社)昭和61年3月31日文部省検定済、昭和64年1月20日発行。 混声3部合唱に編曲してあります。「よう な」の「な」は四回とも同音。 【荒木とよひさの活躍】 荒木とよひさは、昭和十八年、中国・大連生まれ。三十代半ばから作詞に専念。 ・森昌子の歌「哀しみ本線日本海」(浜圭介作曲)で日本作詞大賞優秀作品賞受賞。 ・わらべの歌「めだかの兄弟」(三木たかし作曲)がヒット。 ・NHKみんなのうた「一円玉の旅がらす」(弦哲也作曲)がヒット。 その他、多くのヒット曲を生み出しました。 【芹洋子の現在】 交通事故から復帰、各地でコンサートを開いておられる芹洋子さん、また、小田原市民会館大ホールに来て「四季の歌」を歌って下さい。 【後記】 (Ⅰ)「四季の歌」は、「童謡や唱歌」ではないので掲載を考えてしまいましたが、童謡の会では必ずリクエストがあります。みんなが歌いたいのです。好い歌だからです。金田一春彦 安西愛子編『日本の唱歌〔中〕』(講談社)にも掲載されているので、『池田小百合なっとく童謡・唱歌』に出すことにしました。 (Ⅱ)童謡の会の会員が喜んで歌う「四季の歌」は、平成21年度版、中学校・高等学校の教科書には掲載されていません。高橋治著『春夏秋冬ひと歌こころ』(新潮文庫)には掲載されていません。ひと時代前の歌だという事を実感しました。 (Ⅲ)長田暁二著に振り回される結果となりました。記載違いが各著書に頻繁にあるため、確かめている内に混乱し、時間がかかりました。荒木とよひさ氏には、決定版の解説を書いていただきたいものです。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 利用される場合は、「池田小百合なっとく童謡・唱歌」と出典を明記してください。それはルールです。 ≪著者・池田小百合≫ |
||||||||||||
【最初は『うたのえほん』】 井出隆夫作詞、福田和禾子(ふくだわかこ)作曲。1972年(昭和四十七年)、NHK『うたのえほん』のために作られました。 作詞家の井出隆夫は、早稲田大学卒業後、作曲家のいずみたくの仕事場で修業をしていた。1970年(昭和四十五年)頃、新進の作曲家の福田和禾子から「子供の歌を作りませんか」と誘われ、NHKで一緒に作り始めた。 1972年(昭和四十七年)のある日、NHKテレビの子供向け10分間番組『うたのえほん』の担当者の近藤康弘から「子供の演歌があってもいいよね」と言われた井出隆夫は、当時、大ヒットしていた民放のドラマ「木枯し紋次郎」のパロディーのつもりで書き始めると、故郷の長野県小海町の松原湖の湖面を行く北風を思い出し、それらを詩にまとめた。それに福田和禾子が曲を付けた。演歌風ながら、カントリー&ウエスタンの雰囲気も持つ歌になった。 歌手の田中星児は、月曜から土曜まで放送されていた『うたのえほん』の、初代うたのお兄さんだった(1971年11月~1977年3月)。初めての放送は、歌をミュージカル仕立てで見せる土曜日の「ワイド」だった。茶の間で、三度笠に縞(しま)のかっぱで扮装した男の子が歌う設定。「♪北風小僧の寒太郎」と田中星児が歌うと、うたのお姉さんの小鳩くるみが「寒太郎さーん」と合いの手を入れた。 その後、『うたのえほん』は、1976年(昭和五十一年)に『おかあさんといっしょ』に改編された。『おかあさんといっしょ』でも田中星児が股旅姿で歌い続けた。『うたのえほん』の頃は、「ヤクザ言葉は品がない」などと批判を受けたが、繰り返し放送されると、歌は広く愛された。 (註1)朝日新聞連載(2011年11月5日)『うたの旅人』「北風小僧の寒太郎」より抜粋。 (註2)NHKテレビ『おかあさんといっしょ』は、 1959年(昭和34年)10月5日に開始し、現在に至る長寿テレビ番組。1966年(昭和41年)3月より同局の幼児番組『うたのえほん』が同番組の歌および体操のコーナーとして併合されたが、1976年(昭和51年)に同コーナーが終了したことに伴い、1976年4月に放送内容を改変した。 【次に『みんなのうた』】 NHKテレビ『みんなのうた』で1974年12月-1975年1月に、堺正章と東京放送児童合唱団の歌で初放送されました。前奏で響く口笛が印象的です。  1963年に、『わんぱく王子の大蛇退治』(東映動画。原画を担当)や、テレビの『狼少年ケン』(作画監督や演出を担当)を手がけた月岡貞夫のアニメーションが絶妙でした。北風に乗って股旅姿でひとり旅の寒太郎が飛ぶ様子、笠で防いで吹雪に向って歩く様子、テレビアンテナ上で居眠りする様子。寒太郎は、けなげで可愛いキャラクターです。一連と三連の終わりでは、刀の居合抜きも見せます。 1963年に、『わんぱく王子の大蛇退治』(東映動画。原画を担当)や、テレビの『狼少年ケン』(作画監督や演出を担当)を手がけた月岡貞夫のアニメーションが絶妙でした。北風に乗って股旅姿でひとり旅の寒太郎が飛ぶ様子、笠で防いで吹雪に向って歩く様子、テレビアンテナ上で居眠りする様子。寒太郎は、けなげで可愛いキャラクターです。一連と三連の終わりでは、刀の居合抜きも見せます。月岡貞夫は『みんなのうた』のアニメーションを数多く手がけました。 『みんなのうた』では1981年12月から翌年1月にも、北島三郎とひばり児童合唱団の歌で、「北風小僧の寒太郎」は再放送されています。 【井出隆夫は山川啓介の本名】 井出隆夫(いでたかお)は、構成作家・作詞家の山川啓介(やまかわけいすけ)の本名です。1944年10月26日、長野県佐久市生まれ。2017年7月24日、肺がんのため亡くなった。享年72。 早稲田大学文学部卒業。歌謡曲でのヒットは数知れません。フォークグループ青い三角定規が歌った青春ドラマの主題歌「太陽がくれた季節」、矢沢栄吉が歌った「時間よ止まれ」、中村雅俊が歌った「ふれあい」、岩崎宏美が歌った「聖母(マドンナ)たちのララバイ」などのヒット曲のほか、ロックバンド・ゴダイゴが歌った『銀河鉄道999』の劇場映画版主題歌(共作詞)や『宇宙刑事ギャバン』など特撮テレビ番組の主題歌も手がけた。 子供向けの歌の作詞には本名を使用。NHKの幼児番組『おかあさんといっしょ』の着ぐるみ人形劇「にこにこ、ぷん」「ドレミファ・どーなっつ!」の脚本や作詞を担当した。 福田和禾子とコンビの『NHKみんなのうた』作品には、小学校卒業式の定番曲「ありがとう さようなら」(歌は中井貴一と吉田直子。1985年2月-3月)、「母さんは雪おんな」(歌は堀江美都子。柳川京子の切り絵と毛利厚のアニメ。1985年12月-1986年1月)、「ふるさとのない秋」(歌は森進一。アニメは林静一。1990年8月-9月)などがあります。 “北風小僧”は冬の歌ですが、“雪おんな”も冬、“ふるさとのない秋”は晩秋、“ありがとう さようなら”は年度の終わり。寒さという共通項が感じられませんか。 松熊由紀が歌った「あしたのあしたのまたあした」(作曲:渋谷毅)、水木一郎が歌った「ちょんまげマーチ」(作曲:渋谷毅)も子供に喜ばれました。  【作曲家・福田和禾子について】 福田和禾子は昭和十六年(1941年)11月28日東京生まれ。 父は歌謡曲の松平晃で、本名は福田恒治。昭和八年(1933年)3月新譜に、松竹映画『椿姫』の主題歌「かなしき夜」を吹きこみ、コロムビアからデビューしました。上野の音楽学校時代に、ポリドールで吹きこんだ「忘られぬ花」がヒットしたため、藤山一郎がビクターへ入社してしまって困ったコロムビアが、対抗馬として起用した歌手でした。もとはといえば、藤山一郎が、ニットーレコードに紹介した青年だったそうです。福田青年は松平晃として、1933年3月に続き、5月新譜で、「サーカスの唄」を発表します。西条八十、古賀政男コンビの作品です。その年の11月に、福田青年は東京音楽学校声楽部を中退し、スターになって、主に江口夜詩メロディーを唄うことになります。  和禾子は、東京芸術大学音楽学部作曲科を卒業後、NHK教育テレビ『おかあさんといっしょ』『いないいないばあっ!』『たんけんぼくのまち』『みんなのうた』の音楽を担当するようになります。父の親友・藤山一郎の専属ピアニストも務めていました。 和禾子は、東京芸術大学音楽学部作曲科を卒業後、NHK教育テレビ『おかあさんといっしょ』『いないいないばあっ!』『たんけんぼくのまち』『みんなのうた』の音楽を担当するようになります。父の親友・藤山一郎の専属ピアニストも務めていました。"北風"ではなく、"秋風の忘れもの"と始まる「赤鬼と青鬼のタンゴ」(福田作曲、加藤直作詞、尾藤イサオの歌、ひこねのりおのアニメ、1984年12月-1985年1月)も、冬の歌です。福田は、親しみやすい子供の歌をたくさん作りました。2008年10月5日、心不全で急逝。66歳でした。 ここにあげたNHK『みんなのうた』作品は、『みんなのうた』DVD集で見ることができます。 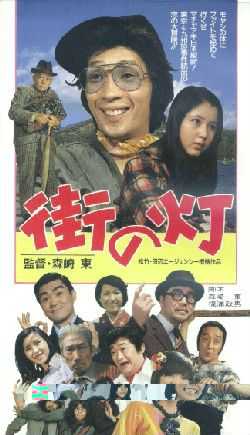 【歌手・堺正章について】 堺正章は名脇役・堺駿二の息子で、1960年代のグループ・サウンズ全盛時代に、ザ・スパイダースのメインボーカルで活躍し、2009年現在も俳優・司会などで大活躍しています。愛称は「マチャアキ」。 グループサウンズ時代の「夕陽が泣いている」(1966年)や、TBSのテレビドラマ『時間ですよ』の劇中歌「街の灯り」(1973年)などのヒット曲のほか、唯一の主演映画で笠智衆・栗田ひろみと共演したロードムービィの喜劇『街の灯』(1974年4月、松竹。森崎東監督)も傑作です。映画『街の灯』は、興行的には記録的な不入りでしたが。『北風小僧の寒太郎』も、映画と同年の1974年、暮れの放送。 氷川きよしのデビュー曲「箱根八里の半次郎」を聞いて、「北風小僧の寒太郎」を連想した人も多かったのではないでしょうか。  【著者より引用及び著作権についてお願い】 利用される場合は、「池田小百合なっとく童謡・唱歌」と出典を明記してください。それはルールです。 ≪著者・池田小百合≫ |
【NHKあなたのメロディーから生まれた傑作】 NHK『あなたのメロディー』(1963年3月-1985年3月、毎週日曜日午前11時)は、視聴者が作詞・作曲した歌を、プロが編曲してプロの歌手が歌うという画期的な番組でした。この番組からは北島三郎の「与作」、トワ・エ・モアの「空よ」などの大ヒット曲も生まれましたが、子供の歌の大傑作が、この「ひげなしゴゲジャバル」です。  いちど聞いてみれば、この歌のケタはずれな感覚が分ります。子猫のゴゲジャバルがヒゲを切られてしまったので、村の動物たちや村人たちがそろって、子猫のヒゲの再生を祈るという歌です。 いちど聞いてみれば、この歌のケタはずれな感覚が分ります。子猫のゴゲジャバルがヒゲを切られてしまったので、村の動物たちや村人たちがそろって、子猫のヒゲの再生を祈るという歌です。サビの部分の「おでましおでまし ヒゲよ、はえまし はえまし ヒゲよ」という念仏が爆笑もの。 【NHK『みんなのうた』で放送】 ペギー葉山の歌に、一ノ瀬義孝の編曲、堀口忠彦のアニメーションで『みんなのうた』に登場したのは、1974年6月-7月でした。ちなみに堀口忠彦がアニメーションを担当した「みんなのうた」の一曲、「コンピューターおばあちゃん」(1981年、伊藤良一作詞・作曲、坂本龍一編曲、酒井司優子歌)も「あなたのメロディー」から生まれた曲です。 【作者】 菊池之枝さんについては、主婦のかたという情報以外にはありませんでした。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 利用される場合は、「池田小百合なっとく童謡・唱歌」と出典を明記してください。それはルールです。 ≪著者・池田小百合≫ |
歌詞と楽譜は『NHKみんなのうた』≪第7集≫(日本放送出版協会)で見ることができます。初版は昭和42年12月20日発行。私(池田)が持っているのは昭和54年4月1日発行 第21版。歌詞は77ページ、楽譜は34~35ページに載っています。 インターネットで『NHKみんなのうた』1960年代を検索すると、「とっくりやしの木」うた:立川澄人 初回放送1966年10月~11月。「音声を発掘 映像を探しています」と書いてあります。「とっくりやしの木」に関係する正式な情報は、これ以上ありません。 ある日、池田小百合著『歌って暮らせば』(夢工房)を読んだ人からメールが届きました。内容は次のようです。 “私が聞いたのはテレビのワイドショーかと思います。昭和43年に高校を卒業し、長崎から東京へ単身就職で上京しました。ですから東京で視聴したのかもしれません。 一週間ほど今週の歌とかいうコーナーで紹介され、歌手はおそらくテノール歌手の誰かでしょう。立川さんではなかったですね。太っていましたので。「お、なかなかいい歌じゃない」と思いながら、聞き流しておりました。・・・・・・” 注目したいのは、“一週間ほど今週の歌とかいうコーナーで紹介され”「今週の歌」だったのでしょうか。そして“立川さんではなかったですね。太っていましたので。”という点です。「友竹正則さん」だったのでしょうか。音声・映像が残っていないので、わかりません。 池田小百合著『歌って暮らせば』(夢工房) 「第8章 夫婦」 より(インターネット スマホでも読むことができます)。 夫は神経が細かい人なのか、のん気な人なのかわかりません。蜘蛛の研究を趣味にしています。そのデータを見ると、きちんとした性格である事がうかがえます。字も丁寧です。しかし、難問が来ても、「なるようにしかならない。明日は明日の風が吹く」と言って大イビキをかいて寝てしまいます。 私は、細かい事を気にして、いつまでも、くよくよするタイプです。気持ちをすぐ切り換えて前に進んで行ける夫が不思議です。この夫がいてくれるので、私は愚痴をこぼしながら生きています。夫は我慢強い人で、私の救いです。つまり、夫は私の「タン壺」のようなものです。この人が現在まで私の夫をやってくれています。 夫が何かにつけて話題にする歌があります。『NHKみんなのうた』で放送されて覚えたそうです。「歌ってよ」と言うと、すぐ音程を外しながら歌ってくれます。のん気なものです。 (註)エッセイ『歌って暮らせば』には、一番「ひとりぼっちで さみしかないの」と書いてあります。これは夫が「さみしかないの」と歌っていたもので、「さびしかないの」が正しい歌詞です。 【近江靖子(おうみ やすこ)の略歴】 舟崎 靖子(ふなざき やすこ)は、詩人 児童文学作家。別の筆名として童謡・詩で近江 靖子(おうみ やすこ・本名)、小説・随筆で村上 靖子(むらかみ やすこ)として活躍する。 ・昭和十九年(1944年)五月十七日、神奈川県小田原市生まれ。祖父は東京帝国大学卒の弁護士だった。マラソン選手志望だったが、川村学園女子短期大学英文学科在学中に落馬事故で自宅療養生活を余儀なくされ、病床で読書に耽る。 ・昭和三十九年(1964年)、療養中に書いた童謡「うたう足の歌」で第九回日本レコード大賞童謡賞を史上最年少で受賞する。同年、当時学習院大学一年生だった舟崎克彦の第一詩集『いもむしの詩』(栄光社、自費出版)を買ったことがきっかけで、克彦と知り合う。高田敏子に師事し、克彦と共に高田主宰の同人誌に参加する。 ・昭和四十年(1965年)、詩集『ポテトチップ館』を刊行する。川村学園女子短期大学卒業。 ・昭和四十三年(1968年)秋、克彦と結婚する。1969年に長女を出産する。昭和四十六年(1971年)、克彦との共著『トンカチと花将軍』を福音館書店から刊行して、児童文学作家としてデビューする。1972年、長男を出産する。1976年、次女を出産する。 ・昭和五十三年(1978年)、『ひろしのしょうばい』(偕成社)で第二十五回サンケイ児童出版文化賞を受賞する。 ・昭和五十六年(1981年)、獣医の村上と恋におち、克彦と離婚、村上と結婚するが、以後も克彦とは共同の仕事を続ける。 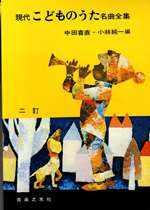 ・昭和五十九年(1984年)、絵本『やいトカゲ』(渡辺洋二絵・あかね書房)により第七回絵本にっぽん賞、『とべないカラスととばないカラス』により第十四回赤い鳥文学賞を受ける。 ・昭和六十一年(1986年)、村上靖子の名でエッセイ集『わが命の輝ける時』を刊行する。 ・平成五年(1993年)、『亀八』により第三十三回日本児童文学者協会賞および第四十回産経児童出版文学賞受賞する。 <ほかの主な作品> 絵本「やいトカゲ」、童話「ジロリのはさみ」、「あんちゃん」など。 中田喜直・小林純一編『現代こどものうた名曲全集』二訂(音楽之友社)表紙 ⇒ 二訂=第二改訂版のことです。 ▼「うたう足の歌」楽譜・歌詞 『現代こどものうた名曲全集』 182~185ページに掲載されています。
あとがき には次のように書いてあります。 “(前略)『すうじの歌』(101ページ)、『おべんとつけてどこ行くの』(156ページ)、『食いしんぼうがまってるぞ』(178ページ)、『うたう足の歌』(182ページ)などは、レコードのために作った歌です。このうち『おべんとつけてどこ行くの』は、この作品で作者の若谷和子さんがレコード大賞の新人作詩賞をうけましたし、『うたう足の歌』は同じく童謡賞になったものです。童謡賞をうけた作品は、ほかにも『ゆうらんバス』(90ページ)、『ちいさい秋みつけた』(84ページ)、『おもちゃのチャチャチャ』(153ページ)、『マーチング・マーチ』(150ページ)があり、『月火水木金土日のうた』(144ページ)が作詩賞をうけています”。 あとがき 追補 “この曲集は昭和四十四年(一九六九年)に第一刷が発行されましたが、その後約二十年間に社会の状況も、音楽の世界も色々の変化がありました。特に子どもの歌に関しては、童謡ブームといわれる程になり、新しい作品も次々と生まれてくるようになりました。そのような情勢を考えて、今回いくつかの曲を入れかえて、二訂として出すことにしました。なお共編者の小林純一さんが一九八二年に亡くなられましたので、このたびの変更は私が一人で致しました。 一九九〇年九月 中田喜直” 奥付 『二訂 現代こどものうた名曲全集』(音楽之友社) 1969年2月20日第1刷発行 1990年5月20日第32刷発行 1990年10月10日二訂第1刷発行 2003年3月31日二訂第17刷発行 (通算49刷) 【著者より引用及び著作権についてお願い】 利用される場合は、「池田小百合なっとく童謡・唱歌」と出典を明記してください。それはルールです。 ≪著者・池田小百合≫ |
【アニメ映画の挿入歌】 宮崎駿監督のアニメ映画『となりのトトロ』(1988)の巻頭、オープニングタイトルに流れる歌「さんぽ」は、終わりのエンディングタイトルに歌われる「となりのトトロ」(宮崎駿作詞)と共に、新しい時代の童謡と言ってもいいでしょう。 明るくて元気いっぱいのこの歌は、「坂道、トンネル、草っぱら」といった自然のなかで、「蜜蜂、トカゲ、ヘビ、バッタ」などいろんな生き物に出会える喜びを教えてくれます。『となりのトトロ』は、ビデオやDVDでくり返し作品を見返すことができる傑作として残る作品でしょうから、主題歌も映画の印象と記憶とともに歌いつがれていくことでしょう。 作品が成功したかどうかは、映画を見終えた人たちが劇場を出るときに主題歌を口ずさんでいるかどうかで判断できます。『となりのトトロ』を見終えた子どもたちは、「歩こう、歩こう、私は元気!」とか、「ト・トロ、ト・トロ」と口ずさんでいるのではないでしょうか。そして、歌の背景でメイが腕を振って歩いていたように、子どもたちは「どんどん」歩いていくでしょう。 歌は途中で転調しており、大変難しい曲想をもっていますが、耳で聞き覚えた子どもたちは何の苦もなく歌いこなしてしまいます。 【キネマ旬報ベストワンの映画】 『となりのトトロ』はアニメーション映画では初めて、キネマ旬報の日本映画ベスト・ワンに推奨された作品です。長い間、アニメ映画は劇映画より格下にみなされていましたが、『となりのトトロ』が公開された頃からでしょうか、アニメ映画と劇映画をことさら区別するひとは、いなくなりました。いまや日本の長編アニメ映画が世界一であることは宮崎駿監督だけでなく、多くの才能のある人々が輩出していることからも明らかです。 【音楽・主題歌】 叶精二『宮崎駿全書』から引用。 音楽は宮崎作品三作目となる久石譲。“今回は全て宮崎と打ち合わせて進められた。・・・久石は本作に強い苦手意識を感じ、どう表現するか悩んだという。 宮崎は本作の企画書に「追記 音楽について」と付記し、「快活でシンプルな歌と口ずさめる歌の二つの歌が必要だ」と強調し、「せいいっぱい口を開き、声を張りあげて唱える歌こそ、子供たちが望んでいる歌」「劇中で子供たちが唱歌のように唱える歌にしたい」と記している。本作は、宮崎と久石がはじめて本気で“主題歌”と取り組んだ作品であった。 久石は、宮崎の要望を受け、サントラ以前に全曲ヴォーカル曲のイメージアルバムを作成するという斬新な試みが行なわれた。「君をのせて」(『天空の城ラピュタ』の主題歌)で宮崎に作詞の才能を見出していた久石は、宮崎に作詞を依頼した。宮崎は「となりのトトロ」「風のとおり道」「小さな写真」の三編を提供した。 『アルプスの少女ハイジ』『赤毛のアン』で岸田衿子、『未来少年コナン』で片岡輝と、児童文学者を作詞に起用した成功例を見てきた宮崎は、『いやいやえん』の著者・中川李枝子にテーマ曲の作詞を依頼した。中川もこれを快諾し、中川は十編の詞を提供し、六編が採用された。「あるこう あるこう わたしはげんき」「すーすす すすわたり」といった中川の飾り気のない詞は、実に新鮮であった。 しかし、宮崎と中川の詞は、叙情的形容詞を連ねた流行歌と勝手が違い、なかなかメロディが浮ばず、久石は頭を抱えた。悩んだ末、「ニュアンスに富んだメロディ」「シンプルで、童謡のような楽曲」を自己課題とし、あえてイントロにバグパイプを使ったオープニングの「さんぽ」、得意のミニマル・ミュージック風のイントロで始まるエンディングの「となりのトトロ」などを仕上げていった。歌手には「君をのせて」に続いて井上あずみが起用された。 本編で使用されたヴォーカル曲はこの二曲だけであったが、「風のとおり道」「すすわたり」「ねこバス」「おかあさん」「まいご」など他の作品はインストゥルメンタルとして使用された。歌詞と格闘しながら仕上げられた各曲は、いずれも独立したメロディとしての完成度を持ち、作品をしっかりと支えた。中でも大樹のテーマともいえる「風のとおり道」は、久石が過去に別のテーマで作曲した作品で、本人の愛着も深い。” 『となりのトトロ』は、昭和三十年代を背景に描かれています。この映画を解くキイ・ワードは、ドングリが発芽した朝にサツキが「夢だけど」と言い、メイが「夢じゃなかった」と同調する言葉にあります。夜の間にトトロたちが庭の小さな畑にやって来て、お祈りをしてくれたお蔭で、ドングリは一気に発芽し、成長しました。トトロが独楽を回し、夜の空を子どもたちはトトロにつかまって飛び回ります。それは夢のなかの冒険でした。 トトロは子どもたちにしか見えません。もともと子どもの想像力が生み出した生き物なのです。ところが、目が覚めると、ちゃんと種子は芽を出していました。 映画を見ている私たちは、このサツキとメイの朝の言葉を聞くまでは、トトロは子どもたちの幻影にすぎないと解釈していました。しかし、顔を出した芽を発見した子どもたちが「夢じゃなかった」と言い切ったとき、「夢」を信じることが生きる力になることを確信できたのです。その瞬間に、トトロが実在すると思えることの大切さが理解できたのです。 そういえば、この当時は、まだどの家庭にもテレビがありませんでした。サツキたちの家にはラジオも電話もありません。子供たちは学校から帰ってくると外に飛び出して遊んだものでした。外には街灯もなく、夜中になると月明りでした。道も舗装されていませんでした。こういった情景は映画のなかで描写されています。 そこで、私たちは電灯の乏しい、テレビのない時代だからこそ、子どもたちは外でトトロのような「となりのおばけ」に会うことが出来たのだと気づかされます。家の中では、「まっくろ黒助」にも出会えたのです。ところが、テレビが普及してくると、子どもたちの想像力はテレビのなかに限定されるようになりました。トトロや猫バスのようなおばけも、テレビの中に住み場所を限定され、閉じ込められてしまったのです。テレビで見えるものは子どもたちの想像力を奪ってしまうのでした。 もし私たちがトトロに会いたければ、テレビを消すことです。そして「さんぽ」に出かけることです。子どもになりきる必要もあります。そうすれば、きっとさんぽの途中でトトロに出会えることでしょう。この映画の宣伝コピーは、父親の声で出演している糸井重里の作った「この変な生き物は、まだ日本にいるのです。たぶん」というものでした。その気になれば、トトロに出会えるという意味があります。 主題歌「さんぽ」は、『となりのトトロ』のテーマを再認識できる主題歌だったのです。 【作詞者の中川李枝子】 作詞の中川李枝子は絵本『いやいやえん』や『ぐりとぐら』などの作者です。 昭和10年(1935年)9月29日、北海道生まれ。 保母として保育園に勤務するかたわら同人誌「いたどり」に処女作『いやいやえん』を発表し、産経児童出版文化賞など数々の賞を受賞しました。6歳下の妹・山脇(旧姓大村)百合子がさし絵を描いています。『そらいろのたね』や『ぐりとぐら』はイギリスからも英訳出版されている人気絵本です。 『ぐりとぐら』の話は、たいてい午前中の出来事が多いですねと聞かれた中川李枝子はこう答えています。 「子どもの生活は午前中なんですよ。午後はおまけ。だから私ね、子どもが朝いつまでも寝てるっていうのは許せない。子どもはお日様と一緒。夜は早く寝て、朝は起きるっていうのが子どもの生活だと思うんですね。午前中めいっぱい遊んで、お昼を食べた後は昼寝して、グダグダして、夕方になるとお母さんにからんだりして、ぶうたれて、晩ご飯食べてちょっと元気になって、お風呂入って、本読んでもらってコトンと寝るっていうのがよい子の一日。よい親もそれに合わせなきゃいけない」と。 これは『となりのトトロ』のよい子の世界です。 サツキとメイのお母さんは病院ですが、エンディングのアニメーションでは最後にお母さんは家に戻っており、子どもたちに本を読んであげています。 【作曲者の久石譲】 作曲の久石譲は昭和25年(1950年)12月6日、長野県中野市生まれ。 国立音楽大学作曲科在学中より、現代音楽の作曲家として活動を開始。宮崎駿監督とは『風の谷のナウシカ』(1984)以来ずっと組んでいます。40本以上の映画音楽を担当し、日本アカデミー賞最優秀音楽賞をはじめ、数々の賞を受賞しました。2001年には音楽映画『Quartet カルテット』を製作、音楽はもちろん脚本・監督もつとめました。 この項目の参考文献 『ぼくらのなまえはぐりとぐら』(2001年,福音館書店) 叶精二『宮崎駿全書』(2006,フィルムアート社) 【著者より引用及び著作権についてお願い】 利用される場合は、「池田小百合なっとく童謡・唱歌」と出典を明記してください。それはルールです。 ≪著者・池田博明・池田小百合≫ |
【ひらけポンキッキ】 『ひらけポンキッキ』はフジテレビが始めた幼児教育番組で1973年4月2日から1993年9月30日まで放送されていました。当初は、月曜日から金曜日の午後2時30分からの放送でしたが、1979年より朝8時台の放送となり、以来「朝の顔」として親しまれていました。メイン司会のおねえさんとキャラクターの「ガチャピンとムック」が進行します。 たくさんの歌が放送されましたが、ほぼ全てがこの番組のために制作された独自の歌です。日本のシングル盤売上記録1位の『およげ!たいやきくん』(作詞:高田ひろお、作曲:佐藤寿一、うた:子門真人)のほか、『いっぽんでもニンジン』『パタパタママ』『ホネホネ・ロック』などヒット曲もあります。  【パンの唄】 『パンの唄』は大ヒットした『およげ!たいやきくん』のLPに収録されている小品(1分56秒)です。このLP(レコード番号キャニオンレコードE-1025、1976年2月発売)には、『およげ!たいやきくん』と同じ頃に放送されていた『いっぽんでもニンジン』(作詞:前田利博、作曲:佐藤寿一、うた:なぎらけんいち)や『パンダがなんだ』(作詞:海友彦、作曲:小倉靖、うた:石川進)も収録されています。 私が購入したのはLPではなく、カーステレオ用のテープでしたので、車に子供を乗せたときにはいつもかけていましたが、いちばん印象に残ったのは、スリーシンガーズがユニゾンで合唱する『パンの唄』でした。作曲をした越部信義のセンスだと思うのですが、パン屋のおばあちゃんを魔女に見立てたお店の不思議な雰囲気がよく出ています。 越部信義はこのLPでは他に『看板のうた』(作詞:前田利博、うた:菅沼宏)、『傷だらけのぼく』(作詞:高見映、うた:天地総子)、『ぼくわるかった』(作詞:高見映、うた:菅沼宏)も作曲しています。『ぼくわるかった』はみんなのうたの『ママごめんなさい』(作詞:泉恵、作曲:カポトスティ、うた:中尾ミエ、アニメ:和田誠、1964年8-9月放送)と似た歌ですが、『ママごめんなさい』の少年がママにすっかりあやまっているのに対し、『ぼくわるかった』はいじっぱりで母親にあやまれない少年の気持ちがとてもよく表現されている佳曲です。 【楽譜が無い】 テープを入れるカーステレオが使用されなくなり、車を交換したらテープを再生できなくなってしまいました。そこで、LPレコードかレコードをCD化したものを入手しようとしたのですが、なんと「無い!」。大ヒットしたのはシングル盤とはいえ、『およげ!たいやきくん』のオリジナルLPですよ! それが無いなんて・・・あらためてわが日本は児童文化に関する本や雑誌、レコードなどの資料が保存されない国なんだなあと思ってしまいました。『パンの唄』は、記憶をたよりに楽譜に起こしてみるしか、ありませんでした。 無いとなると欲しくなるのがファンの常というものです。越部信義さんのところにまで楽譜が無いかどうか、問い合わせましたが無いとのお返事でした。 それがようやく2004年のある日、偶然立ち寄った札幌市の中古レコード店にLP盤の『およげ!たいやきくん』があったのです。原価1500円でした。ほぼ30年ぶりの再会で、感無量でした。レコードを聞くにもプレーヤーを特別に準備しなければならないご時世ですが、なんとか聞けました。 【パンの唄】 LPにしか記録されていない『パンの唄』は三人の重唱のひびきが不思議な雰囲気をかもし出す作品です。西洋では教会の少年合唱隊の聖歌などで耳にするだろう美しいユニゾンが、日本では幼児番組で聞けたのでした。
【著者より引用及び著作権についてお願い】 利用される場合は、「池田小百合なっとく童謡・唱歌」と出典を明記してください。それはルールです。 ≪著者・池田小百合≫ |
【ひらけ!ポンキッキ】 フジテレビの子ども番組『ひらけ!ポンキッキ』で、繰り返し放送されました。 昭和四十九年(1974年)に作られ、同五十年十二月二十五日に高田ひろお作詞、佐瀬寿一作曲の『およげ!たいやきくん』(歌・子門真人)のB面としてフォークシンガー、なぎらけんいちの歌でキャニオンからレコードが発売されました。『およげ!たいやきくん』は、レコード 売上げ五百万枚と言われる爆発的な大ヒット曲となりました。大人も子ども歌いました。 『いっぽんでもニンジン』も人気の曲で、今でも歌われています。 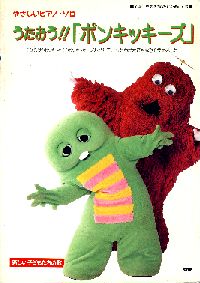 【新しい数え歌ができた経緯】 『いっぽんでもニンジン』は、数え方の学習になります。「いっぽんでも ニンジン」 「にそくでも サンダル」というように、次は何がくるだろうかと予想する、言葉遊びの歌です。 「いっぽんでも」「にそくでも」の前に、元気に「1」「2」と叫ぶと、いっそう楽しい曲になります。 「イチゴ」「ニンジン」「サンダル」と、たたみ込む様な数え歌は、現代っ子にぴったりです。明るく楽しく歌いましょう。 エーピーピーカンパニー代表の小島豊美氏に、『いっぽんでもニンジン』ができた経緯を教えていただきました。それは次のようです, 「当時番組制作費が少なかった関係から、著名な作詞家や作曲家を使えなかったので、ほとんどが、私の関係者で音楽を作りました。作曲者の佐瀬君は、作曲・編曲・ヴォーカ ルを器用にこなす才能があり、前田君は、日本大学芸術学部出身の番組スタッフでした。 当初は、詞とも言えないコンテだけを出してきたものでした。しばらく経って、フジテレビ幼児教育部の筧プロデューサーが「助数詞の歌にまとめたら」というヒントを出し、制作スタッフみんなでまとめた経緯があります。前田君には、最初のコンテを出したことに敬意を表して作詞者としましたが、事実はそういう経過でした。また、昭和四十九年、五十年当時の番組はレコ-ド発売を意識することなく、自由な発想で楽曲作りが出来ていましたので、今思うと、『水滸伝』の梁山泊のような人材の集まりだった気がします。 インターネットのAPPカンパニー「ひらけ!ポンキッキエピソード集」によると、「この詩には、ミスが一つある。歌詞の「五台でもロケット」のロケットは、五機が正しいと指摘しています,しかし、「五機」では歌詞としてなりたちません。ここは、「五台でもロケット」で、違和感なく歌うことができます。 【作詞者 前田利博について】 作詞者の前田利博氏の生年月日と出身地はなかなかわかりませんでした。 静岡県出身という情報があり、静岡県立中央図書館で検索していただきましたが、不明でした。 『いっぽんでもニンジン』の楽譜が掲載されている『うたおう!!「ポンキッキーズ」』 の出版社ケイ・エム・ピーでは、プライバシーを守るとのことで教えていただけませんでした。 フジテレビキッズにこの原稿を送り、返事をいただくことができました。 若い男性スタッフの方からの電話によると、昭和二十三年十二月十六日、静岡県静岡市の生まれとのことでした。原稿完成から一年後の平成十五年十一月二十日のことでした。(本稿は当初、「静岡県の童謡」という企画のために準備していたものでした)。 ところが、それから約一ケ月後の十二月三日、エーピーピーカンパニー代表の小島豊美氏から、「出身地は静岡県掛川市です」というメールをいただきました。 『看板のうた』『パンの唄』(越部信義作曲)、『とけいのうた』(佐瀬寿一作曲) なども、『ひらけ!ポンキッキ』で放送されヒットソングになりました。 特に、「横丁の角から三軒目 不思議なパン屋さ ‥・ほかほかほかほか 不思議なパン屋」と、シンガーズ・スリーが美しく甘い声でハモる『パンの唄』は、あたたカヽいメルヘンの世界へ連れて行ってくれる、かわいらしい歌でず。 放送後、テープは発売されましたが、『パンの唄』は楽譜が販売されていないのが残念です。子どもたちにいつまでも聞かせたい一曲です。 【作曲者 佐瀬寿一について】 作曲者の佐瀬寿一は、昭和二十四年三月三十日、千葉県で生まれました。 『およげ!たいやきくん』『いっぽんでもニンジン』のほか、高田ひろお作詞の『ハッスルばあちゃん』 『パタパタママ』『ホネホネ・ロック』『ママの右手は魔法の手』『野菜畑の音楽会』『ふ しぎなジーパン』『トランプ村の日曜日』『ニュートンファミリー』『サンデーパパ』『そらとぶさんりんしゃ』『てるてるぼうずがあるいたら』『オイラのてんきよほう』など数多くの楽しい曲を作り、活躍中です。 日本大学芸術学部在学中からビートルズのコピーバンドを組んで活動していました。『とけいのうた』は、自分で作曲し、歌ってヒット曲としました。身近な歌詞に、リズミカルな曲のついたこれらの歌は、<ひらけ!ポンキッキ>で放送されると、どの曲もたちまち子どもたちの心を捉え、人気の曲になりました。 キャンディーズが歌った『暑中お見舞い申し上げます』や、山口百恵が歌った『赤い衝撃』など、流行歌の作曲もしています。 『いっぽんでもニンジン』のイントロ部分は間奏、エンディングとともにブラスのフレーズ。ジャズっぽく演奏します(楽譜集『うたおう!「ポンキッキーズ」』(kmp)の助言より)。
【ひらけ!ポンキッキが変わった】 『いっぽんでもニンジン』が、繰り返し放送されたフジテレビの子ども番組『ひらけ!ポンキッキ』は、昭和四十八年(1973年)から放送が開始されました。平成五年(1993年)には、「ポンキッキーズ」とタイトルを変更しました。さらに平成十三年(2001年)には、『ポンキッキーズ21』となり、それまでの月曜日から金曜日だった放送形態も、(同十二年から)土曜日のみの放送になりました。三十年以上になる長寿番組でした。 番組では、マスコットのぬいぐるみのガチャピンとムックが、子どもたちに人気で活躍しました。ガチャピンは、南の国で生まれた恐竜の子孫です。ムックは、北極生まれの雪男の子孫です。 このマスコットたちは、しばしば科学実験や、スキー、スケートをやって見せてくれました。子どもたちは、心をワクワクさせました。 『ひらけ!ポン キッキ』の気球は、子どもたちに沢山の夢を運んでくれました。 ♪ポンキッキ広場の真ん中に 大きな大きな宇宙船 乗組員は僕らの仲間 【著者より引用及び著作権についてお願い】 利用される場合は、「池田小百合なっとく童謡・唱歌」と出典を明記してください。それはルールです。 ≪著者・池田小百合≫ |
【テレビから生まれた歌】 昭和三十七年二月に作られました。昭和四十二年からNHKテレビ『おかあさんといっしょ』で繰り返し歌われて、子どもたちの人気の曲になりました。 日本放送協会編『NHKこどものうた楽譜集 第一集』(日本放送出版協会)昭和四十二年発行に掲載されています。
【「木のは」の歌い方】 「木のはのおうち」の「木のは」は、「きのは」と歌います。 ・『NHKこどものうた楽譜集 第一集』・・・「きのは」 ・日本童謡協会編『日本の童謡200選』(音楽之友社)・・・「きのは」 ・『日本童謡唱歌大系』Ⅱ(東京書籍)・・・「きのは」 【「木の葉」の読み方について】 「木の葉」を何と読みますか。 「きのは」でも間違いではありません。でも、「このは」が本来の読み方です。「木」は、一字だけで 読むときは「き」ですが、「木陰・こかげ」「木立・こだち」のように、他の言葉と 合わさって一つになった言葉(複合語)では、「こ」と発音します。「梢」の漢字をあてる「こずえ」も、木の枝の末端、「木末・こずえ」のことでした。 「木の葉」「木の実」など、「の」を付けて、下に続く語を説明する形をとった場合 も、「こ」と言います。木の葉の間からもれてさす日の光を表す「木もれ日」は、 「こもれび」と読みます。古くは「く」とも言ったようです。「果物」は、もともとは「木だ物」の意味です。「だ」は、現代の日本語では「の」にあたります。「木の物」ということです。 ところで、「だ」が「の」の意味で使われている言葉に、もう ひとつ、「けだもの」があります。「毛だ物」、つまり、体中に毛が生えた動物を表 した言葉です。 (読売新聞2010年10月1日掲載 用語委員会・関根健一著『なぜな に日本語』を参考にしました。) 【「アイアイ」について】 「アイアイ」は、マダガスカル島北東部の樹林や竹林に生息するリスに似たキツネザルで、アイアイ科に属する。頭胴長四十センチくらい、尾長五十五センチから六十センチ、暗かっ色から黒色の長毛を密生、頭は丸く、目と耳は大きい。手の第三指(中指)は細長く、足の第一指には平たい爪があるが、他の指には、かぎ爪がある。歯はネズミ、リスなどに似て、犬歯を欠き、門歯は一対しかない。夜行性でラミーというマダガスカル特有の木の実を食べたり、木の内部に潜む虫、昆虫、鳥卵、樹液(サトウキビなど)を食べて生活しています。ネズミに似た門歯で木をかじり、細長い中指で甲虫の幼虫などを取り出して食べる。木の枝のまたに枯葉を集めて大きな球形の巣を作る。(今泉吉典)『世界大百科事典』(平凡社)より。絶滅が危惧されている。 Aye-ayeの画像はこちら。National geographicによる。
【うたをつくるということ】 相田裕美によると次のようです。 “(前記)百科事典のはじめのページに「アイアイ」の記述を見つけた時、「アイアイ」の詩は既に半分以上出来上がった。 アイアイというフレーズは、優しい響きを持ち、幼な児も発言しやすい。ダブルミーニングどころか、なん重にも意味と働きをもたせることができる。単純な繰り返しの、リズミカルな響き。はやしことばにして、手をたたいたり、飛び跳ね、踊ったりもできる。そして、おまけに、そんな名のかわいいおサルが存在するなんて! あとは平凡な言葉でまとめる。特に、歌うための歌には、ふっとなにげなく口をついて出たような、自然な言葉を使わないといけない。そして、なるべく推敲のあとは消す。・・・・・ 最後に、当然の事だが、「どうよう」の生命(いのち)は、詩にぴったりの曲にめぐり会い、しかもその歌を愛してくれる大勢の人たちに出会わなければ、誕生しない。こんな奇蹟にも似たいくつものめぐり会いができた「アイアイ」は、本当に幸せな歌だと、感謝の念にたえない。 動物園の係りのかたの説明によると、残念な事だが、アイアイは、まだ日本にやって来た事はないそうだ。いつか、南の島へ行って、私のかわいいもう一人の息子に対面したいものだと思っている。”(季刊『どうよう』第三号(チャイルド本社)昭和六十年十月一日発行より抜粋)。 相田裕美が、この文を書いた昭和六十年には、「アイアイ」は、日本にいなかった。相田裕美は本物の「アイアイ」を見ていなかった。 【「アイアイ」と命名】Aye-Aye:Daubentonia madagascariensis 十八世紀末、フランスの探検家が捕まえたのを見た現地人があげた驚きの声「アイアイ」を、現地名と錯覚した事により命名されたようです。日本では、この歌で親しまれていますが、マダガスカルでは不吉な動物として忌み嫌われています。 【絶滅危惧種に指定】 現在、「絶滅危惧1B類」に分類されています。 【日本初】 平成十三年十一月二十二日から、日本で初めて東京・上野動物園で雄と雌の二匹が公開されました。 【子どもたちに人気】 「アーイアイ」という(ソロ)に対して、「アーイアイ」と同じ事を(合唱)で答える面白さがあります。 しっぽの長い、目の丸いサルの可愛いイメージは、リズミカルな旋律と共に幼児にも覚えやすく、喜んで歌われています。 【楽しい歌なのに】 「童謡のコンサートで何か歌って下さい」と保育園の先生にお願いしたことがあります。「何がいいでしょうか」と保育園の先生が言われるので、「子どもたちが大好きで、保育園でいつも歌っている『アイアイ』はどうでしょうか」と言うと、「あの歌を歌う時は、ふざけてサルの真似をして歌うので、手もこんな風にして、こーんな顔で・・・。ですから、『アイアイ』はだめです」と即答で断られた事がありました。「楽しい歌なのに」と、残念に思いました。 文化庁編『親子で歌いつごう日本の歌百選』(東京書籍)には選ばれていません。 【平成二十一年版での扱い】 ・『新しい音楽 2』(東京書籍)、タイトルは「アイアイ」。 「リズムにのってうたおう」、「ひとりと みんなに わかれて うたいましょう」。 ・『小学生のおんがく 1』(教育芸術社)、タイトルは「あいあい」。 「よびかけあって うたいましょう」、「うたごえ くちの あけかたに きを つけて、やわらかい こえで うたいましょう」。 ・『おんがくのおくりもの 1』(教育出版)、タイトルは「アイアイ あいあい」、(1くみ)(2くみ)にわかれた踊りが付いている。
各自工夫して、楽しく歌い踊ってほしいと願っています。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 利用される場合は、「池田小百合なっとく童謡・唱歌」と出典を明記してください。それはルールです。 ≪著者・池田小百合≫ |
「わらべ唄」は、大多数がかなり古い時代から民間の子供たちに伝承されてきた唄で、作られた年代も中心地域もはっきりしない物が多く、作者はわかりません。その土地で歌い継がれるうちに変化し消滅して行きました。 特有の素材にして優雅な曲調、極めて平凡なメロディーと、二拍子または四拍子を主とした単純なリズムを持っています。 残念な事に、私たちの祖先が残してくれた貴重な文化遺産ではありますが、民族の声を楽譜にとどめることは困難です。どれが正しいかなどの考察には、あまり意味がありません。 <分類> ・遊戯唄 その一(手毬唄 お手玉唄 羽子突唄など玩具を以てする遊戯の唄) ・遊戯唄 その二(縄跳び かくれんぼ 関所遊び 子取り 鬼遊び 手合せなど集合遊戯の唄) 遊びのための唄が中心を占めているので、特に遊戯唄の種類が極めて多く、変化に富んでいる。女児の間に行われるのが中心をなす。歌詞内容には重きを置かない。全国共通の唄が多く、民謡のように郷土特異の曲調を持っているものが少ない。 ・子守唄(子守が子供を寝かしつけながら歌う「眠らせ唄」や「遊ばせ唄」) 子守唄は子供自身が歌う唄ではなく、ただ聞かせる対象が子供であるというに過ぎない。子供の睡眠とは関係なく、子守自身の労働苦を述懐することによって自らを慰めるものなどがある。多分に民謡や流行唄との交錯が認められるのが特色。 ・天体気象の唄(風 雨 夕焼 月 霰 雪など自然界の天体気象に関する唄) ・動物植物の唄(雀 蝸牛(かたつむり) 螢 蝙蝠(こうもり) 蜻蛉(とんぼ) 烏(からす) 土筆(つくし) 桃 茱萸(ぐみ)など動物植物に関する唄) ・歳事唄(正月 七草 鳥追い 彼岸 盆など年中行事に関する唄) ・囃し唄(種々の社会事象に関して唱えことばや囃しことば風に歌われる雑唄) ・悪口唄(からかい唄 まじない唄 軽口唄)などがある。 (いま泣いた烏が もう黙った もう黙った 神奈川)。 [類歌](いま泣いた烏が もう笑った もう笑った 神奈川西部)。 (誰かさんの頭に かんから蟲がとまった それを落すと坊主になるよ 関東地方)。 [類歌](やーだよ やだよ 誰かさんの頭に ちょんちょりんがとまった 神奈川西部)。 「わらべ唄」は、明治年間の「唱歌」や、大正中期の「創作童謡」とは全く本質を異にしたものです。「創作童謡」の中には、原型を古来の「わらべ唄」に仰ぐものがかなりある。(原曲)にその原型を求めることができる。 <「創作童謡」の中の「わらべ唄」例> ・北原白秋「赤い鳥小鳥」(赤い山青い山白い山) 赤い山青い山白い山 [北海道] ねんねの寝た間(ま)に 何(なに)せよいの 小豆(あずき)餅(もち)の 橡(とち)餅(もち)や 赤い山へ持って行(い)けば 赤い鳥がつっつく 青い山へ持って行けば 青い鳥がつっつく 白い山へ持って行けば 白い鳥がつつくよ。 ◆解説:北海道帯広附近の子守唄[眠らせ唄]として唯一のもの。北海道という所は、開拓民が寄り集ってひらけた土地柄だけに、伝統というものがない。したがって北海道特有のわらべ唄を持たない。開拓民たちが唄った子守唄は、それぞれの生まれ故郷の唄だった。 ・西條八十「烏の手紙」(烏(からす)かねもん勘三郎) 烏かねもん勘三郎 [広島] 烏 かねもん 勘三郎 わァれが家ァ 皆焼けた 早(はよ)う往(い)んで 水かけよ 水(みイず)をかける 杓(しやアく)がない 杓が無けらにゃ貸そうか 借(か)っても借っても よう払(はら)わん。 ◆解説:音戸・倉橋島地方の唄。動植物の唄[烏]。日が暮れかけて西の空が真赤に焼けたつ頃、ねぐらへ急いで帰る烏を見て歌う唄。この「お前の家が焼けるぞ」式の歌は、東北地方を除いた殆ど全国に分布する。特に西日本一帯に類歌が多い。 ・西條八十「毬と殿さま」(うぐいすや) ・蕗谷虹児「花嫁人形」(うぐいすや) うぐいすや [青森] 鶯(うぐいす)や 鶯や 梅の小枝に昼寝して 昼寝の夢には何を見た 奥の座敷を今借りて 莚(むしろ)三枚 茣蓙(ござ)三枚 六尺屏風(びょうぶ)を立て廻(まわ)し 夕べはいたる花嫁に 金襴(きんだん)緞子(どんす)を縫わせたら 襟(えり)のさしわとつけかけて ホロリホロリと泣くわいな 何が愛(いと)しゅて泣くわいな 泣くわいな。 ◆解説:青森市地方で冬、炬燵や囲炉裏を囲んで楽しむ遊びにお手玉取りがある。遊戯唄[お手玉唄]。歌詞は一般に手毬唄として全国共通の唄。後半、「泣くわいな」の次に「おらが弟の千松は、七つ八つから金山(かなやま)へ、金が無いやら死んだやら、一年たってもまだ来ない、二年たってもまだ来ない、三年先の申(さる)歳に、親のどこから文が来た・・・」と歌われるのが普通。 「はいたる」は、「入ったる」の意。「夕べ・・・」以下は山形・愛知・京都・香川の手毬唄、新潟・岡山・福岡などの子守唄に出て来る。「金襴(きんだん)緞子(どんす)」の「キンダン」は「キンラン」の訛(なまり)でしょうか。別に、緞子の地に模様を金で織り出した物を金段(きんだん)ともいう。「襟(えり)のさしわとつけかけて」は、「襟とさしわにくけかけて」の訛伝か。あるいは「襟とさしわとつけかけて」ともいう。 ・浜田廣介「こんこん小狐」(豆狸) 豆狸 [高知] 雨のショボショボ降る晩に 豆(まめ)狸(だ)が徳利(とッくり)もって酒買いに 「今晩はー」 壊(つ)えたお城の蓮池(はすいけ)で 貂(てん)が化かすき 気をつけよ 「風が出たかよー」。 ◆解説:京都・大阪・を中心に兵庫・奈良・香川・高知などにも類歌の存する唄。天体気象の唄[雨]。小雨を歌ったものだが、その小雨のために自分たちの遊びが中絶することのつまらなさも込められている。チョボチョボ・ボツボツ・シトシト・シャアシャア・ジャアジャア・ジャンジャンなどとも。マメダは方言にアナグマ(徳島)ともムジナ(上方)ともいう。「酒買いに」までが原歌。 「雪こんこお馬」の坊田かずまも「わらべ唄」の収集、教育に力をつくした。<わらべ唄・子守唄の出版について>。 私、著者池田小百合の「わらべ唄」の経験も読んで下さい。コラム〔わらべ唄と音楽教育〕。 唱歌「螢」「雪」、創作童謡「十五夜お月さん」(本居長世)にも「わらべ唄」が見られる。  <参考文献> ・町田嘉章 浅野建二編『わらべうた』(岩波文庫)・・・各地の類歌も沢山紹介されている。同じ内容の歌詞が方言に変化し、伝えられているのが興味深い。 ・藪田義雄 安倍盛編『ラジオ・テレビ・レコード わらべ唄110曲集』(全音)・・・ 藪田義雄の解説が文学的で美しい。読んで楽しい。安倍盛が楽譜を担当。こった編曲が、わらべ唄から遠くなってしまっている。 ・『にほんのわらべうた』全四巻(福音館書店)・・・子供たちの写真、イラスト、楽譜、CDで遊び方がわかります。「わらべ唄」を語るには、遊び方が不可欠。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 利用される場合は、「池田小百合なっとく童謡・唱歌」と出典を明記してください。それはルールです。 ≪著者・池田小百合≫ |
| 【著者より著作権についてのお願い】 文章を使用する場合は、<ウェッブ『池田小百合なっとく童謡・唱歌』による>と書き添えてください。 |
メール (+を@に変えて) |
トップ |