ロック・ファンのためのジャズ案内のヘッダー
Rock Listner's Guide To Jazz Music
Duke Pearson
| Profile | ||
 曲:★★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1959/10/25 [1] Like Someone In Love [2] Black Coffee [3] Taboo [4] I'm Glad There Is You [5] Gate City Blues [6] Two Mile Run [7] Witchcraft |
Duke Pearson (p) Gene Taylor (b) Lex Humphries (ds) |
| アルフレッド・ライオンがピアノ・トリオをあまり好まなかったため、ブルーノートにはピアノ・トリオの録音が少ない。作・編曲家として活躍したデューク・ピアソンは、しかしブルーノートでの最初の2枚がピアノ・トリオだった。つまり、アルフレッド・ライオンがピアニストとして高く評価したということを恐らく意味している。確かに、ここでのピアソンのピアノはいい。黒人らしいフィーリングがしっかりとありつつタッチが洒落ていて明るい。一方で、"Like Someone In Love"の一部に3拍子を挟むなど捻りを加え、ただのイージー・リスニング的なムードに陥らせない工夫があちこちに見え隠れする。曲の仕上げと演奏の良さがうまくバランスした、ある意味ピアノ・トリオのひとつの完成形とも言って良いかもしれない。黒人らしいブルース・フィーリングとコクも備えていながら、強面でダークなジャケットのイメージとは違って聴きやすさが魅力。(2025年2月1日) | ||
| Tender Feelin's | ||
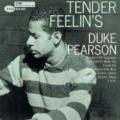 曲:★★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1959/12/16 [4] [6] 1959/12/19 [1]-[3] [5] [7] [1] Bluebird Of Happiness [2] I'm A Fool To Want You [3] I Love You [4] When Sunny Gets Blue [5] The Golden Striker [6] On Green Dolphin Street [7] 3 A.M. |
Duke Pearson (p) Gene Taylor (b) Lex Humphries (ds) |
| ドナルド・バードやグラント・グリーンのアルバムで魅了され、(個人的にはあまり好きではない)ピアノ・トリオ編成でも聴いてみたくなったのがこのデューク・ピアソン。しかし、初めて聴いたときには期待外れだった。まずオリジナルが1曲しかないところが残念。ピアノのフレージングもサイド・メンのときほどの一瞬の煌めきがなく、ありきたりなピアノ・トリオとしてまとまっているように聴こえたから。それから15年以上経過して前作「Profile」を聴いてみたところ、その印象は変わった。自分が歳を重ねて受容度が高くなったからなのか、このアルバムも「Profile」とまったく同じ魅力を備えていると思えるようになった。そもそも、同じメンバー、同じ音楽性でアルバムを制作するという安易な道を取らないブルーノートが2枚続けて、しかもあまりピアノ・トリオを好まないアルフレッド・ライオンが録音し、リリースしたとことじたいがそのクオリティを保証している。(2025年2月1日) | ||
| Wahoo! | ||
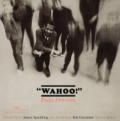 曲:★★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1964/11/21 [1] Amanda [2] Beduim [3] Farewell Machelle [4] Wahoo [5] ESP (Extra Sensory Perception) [6] Fly Little Bird Flyv |
Donald Byrd (tp) Joe Henderson (ts) James Spaulding (as, fl) Duke Pearson (p) Bob Cranshaw (b) Mickey Roker (ds) |
| ピアノ・トリオ2枚を立て続けに録音したとはいえ、さすがに3枚続けてはなし、と判断されたのか「Tender Feelin's」のあとは、ドナルド・バードやグラント・グリーンのアルバムで作・編曲に貢献しつつリーダー・アルバムが途絶えていたデューク・ピアソンが5年ぶりに録音したのが本作。[3]のみピアノ・トリオ演奏。64年相応、当時ジャズ・ロックと言われた8ビートの軽快な[1]を筆頭に、全体的に明るく開放的な印象があるのは、この後続くアルバムに共通していて、ピアソンの持つ個性を表している。実際に曲想はバラエティに富み、ピアノ・トリオのときほどベタなものではないにしてもピアソンの根底に流れるブルース・フィーリングを備えつつ、耳に心地良いアレンジ、曲が並ぶ。フロントのドナルド・バード、ジョー・ヘンダーソン、ジェームス・スポルディングは、全体を崩さない一線を守りつつ自己主張をしっかりしており、そんな好調な3管奏者のそれぞれのソロ、そしてピアソンの作・編曲の才能がうまく噛み合った快作。(2025年2月1日) | ||
| Sweet Honey Bee | ||
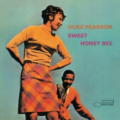 曲:★★★★★ 演奏:★★★ ジャズ入門度:★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1966/12/7 [1] Sweet Honey Bee [2] Sudel [3] After The Rain [4] Gaslight [5] Big Bertha [6] Empathy [7] Ready Rudy? |
Freddie Hubbard (tp) Joe Henderson (ts) James Spaulding (as, flute) Duke Pearson (p) Ron Carter (b) Mickey Roker (ds) |
| フロント・ラインを見れば、いずれ劣らぬ新主流派のツワモノばかりで、激しいフリー・ブローイング大会になっていてもおかしくない顔ぶれ。しかし、そこに期待すると大きな落胆を味わうことになる。曲がすべて6分未満であるところから想像できるように長尺のソロはなく、コンボとしての音楽表現に心を砕いたコンセプト。全曲ピアソンのオリジナルでアレンジャー、音楽家としてのピアソンの作品となっている。曲も演奏も親しみやすく、それでいて軽薄な感じはしない。そんなピアソンの世界を豪華なフロント・ラインで贅沢に表現する。特に[1]を筆頭に美しいフルートを聴かせるジェームス・スポルディングが光っている。アルバムとしては正直なところ地味で、作曲、編曲も、脇役で活躍をしていたドナルド・バードやグラント・グリーンのアルバムほどには冴えていないことを考えると、主役になると輝けないタイプなのかもしれない。しかし、親しみやすく心地よいこの音楽に身を任せるのもジャズの楽しみ方のひとつ。この時期のブルーノートの録音には音像のハッキリしないものが散見されるけれど、このアルバムもそんな1枚。(20250年2月1日) | ||
| The Right Touch | ||
 曲:★★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1967/9/13 [1] Chili Peppers [2] Make It Good [3] My Love Waits (O Meu Amor Espera) [4] Los Malos Hombres [5] Scrap Iron [6] Rotary |
Freddie Hubbard (tp, flh[3]) Stanley Turrentine (ts) James Spaulding (as) Jerry Dodgion (as, fl) Garnett Brown (tb) Duke Pearson (p) Gene Taylor (b) Grady Tate (ds) |
| ドナルド・バードやグラント・グリーンのアルバムで洗練された曲とピアノで大きな存在感を示していたデューク・ピアソンがトランペットなし4管のセプテットで自身の音楽を表現したアルバム。キャッチーな曲想と、随所にピアソンらしい洗練されたピアノを織り込み、4本の管楽器は音の圧力や厚みやを出すためではなく、あくまでも曲想を豊かにするための表現に心を砕いてアレンジされている。音量を抑えめにしてグルーヴ感を控えめのベースとスピーディなドラムに乗せて、心地よく活気ある演奏が展開され、ベタなスローブルースでもバタ臭くならない[5]を含めて、ピアソンの個性が溢れ出た好アルバムに仕上がっている。決してジャズ・ジャイアントではないかもしれないけれど、これだけの質のジャズをクリエイトしたピアソンはもっと評価されていいと思う。(2025年2月1日) | ||
| How Insensitive | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★ ジャズ入門度:★★ 評価:★★☆ |
[Recording Date] 1969/4/11,14 1969/5/5 [1] Stella By Starlight [2] Clara [3] Give Me Your Love [4] Cristo Redentor [5] Little Song [6] How Insensitive [7] Sandalia Dela [8] My Love Waits (O Meu Amor Espera) [9] Tears (Razao De Viva) [10] Lamento |
[1]-[5][8] Andy Bey (vo) Al Gafa (g) Duke Pearson (p, elp) Bob Cranshaw (b) Micky Roker (ds) Airto Moreira (per) The New York Group Singers' Big Band (voices) [7][9][10] Flora Purim (vo) Dorio Ferreira (g, per) Duke Pearson (p) Bebeto Jose Souza (b) Airto Moreira (ds) Micky Roker (per) |
| 1曲目はみんなが知っているあの曲、ピアノの柔らかなイントロでその曲であることに安心感を覚えると、おもむろにカーペンターズの"Sing"のようなコーラスと歌が始まる予想外の展開にズッコケる。それでも、バッキングでいつものピアソンのピアノらしい伴奏を聴くことはできる。[2]で歌の間奏でコーラスをバックに、なんとピアソンがフリューゲルホンホルンのソロを取ったり、[4]でエレピを弾いたりという意外性が上乗せさせる面白さはあるけれど、クリスマスの夜に聴きたくなるようなコーラスでしんみり曲調、曲想が前半続き、以前のピアソンのアルバムと同じ耳で聴くことはできない。フローラ・プリムが歌う[7]ではそのコーラスがなく、当時流行っていたボサノヴァのテイストで、これが実に心地よく、生き生きした演奏で、しかしそれまでのコーラス曲とのつながりがまったく感じられないと思っていると、[8]ではラテンのリズムにそのコーラスが入り、ますます頭が混乱する。[9][10]のラテン調リズムと歌の軽快さ(ボブ・クランショウの爽やかな推進力とミッキ・ローカーの軽めのリズムが絶妙に合っている)がまた素晴らしいだけに、うーん、ラテンだけで通したアルバムを1枚作ってくれていたらきっと傑作になったんじゃないだろうかと思わずにはいられない。(2025年2月1日) | ||
