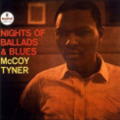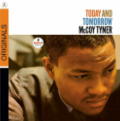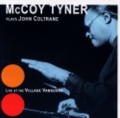ロック・ファンのためのジャズ案内のヘッダー
Rock Listner's Guide To Jazz Music
McCoy Tyner
| The Real McCoy | ||
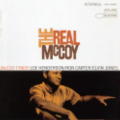 曲:★★★★☆ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★★★☆ マッコイ入門度:★★★★★ 評価:★★★★☆ |
[Recording Date] 1967/4/21 [1] Passion Dance [2] Contemplation [3] Four By Five [4] Search For Peace [5] Blues On The Corner |
Joe Henderson (ts) McCoy Tyner (p) Ron Carter (b) Elvin Jones (ds) |
| マッコイがコルトレーン・グループを離れてから製作した全曲自作によるリーダー・アルバム。同時期に脱退したエルヴィンも参加。モーダルで小気味良くストレートな演奏を聴いていると、なるほどこれがマッコイのやりたかったジャズなんだ、コルトレーンとは合わなくなって当然だったんだなあと納得させてくれる。もちろんマッコイの力強いタッチの流れるようなピアノが満喫できるし、コルトレーン・スタイルをよりわかりやすくしたかのようなジョー・ヘンダーソンのテナーとロン・カーターのベースも軽快。この2人のやや薄味なところが実に良く合っているので、「マッコイとエルヴィンは好きなんだけど、コルトレーンはちょっと胃にもたれる」という人に是非勧めしたいアルバム。薄味といっても、それはコルトレーンの音楽と比べての話で十分に聴き応えのあるガッシリした骨太なジャズなのでそこは誤解なきよう。コルトレーンの呪縛から開放されたかのようなマッコイとエルヴィンのフレッシュでパワフルな演奏が何よりも素晴らしい好盤。(2006年11月23日) | ||
| Tender Moments | ||
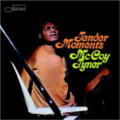 曲:★★★☆ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★☆ マッコイ入門度:★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1967/12/1 [1] Mode To John [2] Man From Tanganyika [3] The High Priest [4] Utopia [5] All My Yesterdays [6] Lee Plus Three |
Lee Morgan (tp) Bennie Maupin (ts) James Spaulding (as, fl) Julian Priester (tb) Bob Nothern (french horn) Howard Johnson (tuba) McCoy Tyner (p) Herbie Lewis (b) Joe Chambers (ds) |
| ピアニストというのは譜面に強いこともあって、大編成で音楽を作ってみたいと考える人が多いようで、マッコイも何枚かそういったアルバムを残している。このアルバムはその中でも最初期の1枚。まだアフリカ回帰志向は強まっていないこともあってどちらかといえば狭義のジャズの中で完成させているところがむしろ好印象。当然、アンサンブルに重点が置かれた曲構成で、マッコイのピアノの出番はそれほど多くなくタッチもマッコイにしては抑え気味。でも、その抑え加減こそがこのアルバムの聴きどころ。ホーン隊は人数が多いもののソロは少なめ。それでも時に切り込むモーガンは流石と思わせてくれる。ベースとドラムに重量感があって、アンサンブル重視の音楽でも骨太な感じがするのもマッコイの個性に合っている感じ。ただ、マッコイのピアノを味わいたいという向きには少し物足りないと感じるかもしれない。(2007年7月16日) | ||
| Time For Tyner | ||
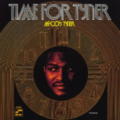 曲:★★★★☆ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★★★ マッコイ入門度:★★★☆ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1968/5/17 [1] African Village [2] Little Madimba [3] May Street [4] I Didn't Know What Time It Was [5] The Surrey With The Fringe On Top [6] I've Grown Accustomed To Her Face |
Bobby Hutcherson (vib [1]-[4]) McCoy Tyner (p) Herbie Lewis (b) Freddie Waits (ds) |
| 前作から一転、シンプルなカルテット編成のアルバム。マッコイのピアノとボビー・ハッチャーソンのヴァイブの演奏がそれぞれ良いだけでなく相性が予想以上に良い。フォービート以外のリズムを織り交ぜているのは当時では珍しくないとはいえ純粋にジャズとして楽しめる。ハービー・ルイスの骨太なベースと、エルヴィン・ジョーンズを彷彿とさせる重量感を伴ったフレディ・ウェイツのドラムがまた素晴らしく、ともすれば軽めの音楽になりがちなこの編成に迫力と緊張感もたらしている。冒頭3曲の先進的なマッコイ・オリジナルが特に冴えていて、[4][5]といったどちらかといえばほのぼの系スタンダードが続く構成は少々違和感を覚えるものの、マッコイの流麗なピアノがつなぎ合わせている印象。あまり注目されていないアルバムながらスピーディに弾きまくる[5]とソロの[6]をはじめ、マッコイのピアノを中心に楽しめるところがセールス・ポイント。(2007年5月12日) | ||
| Extensions | ||
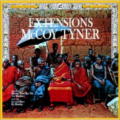 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★ マッコイ入門度:★★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1970/2/9 [1] Message From The Nile [2] Wanderer [3] Survival Blues [4] His Blessings |
Wayne Shorter (ts, ss) Gary Bartz (as) Alice Coltrane (Harp) McCoy Tyner (p) Ron Carter (b) Elvin Jones (ds) |
| 諸説あるとは思うけれど、マッコイ・タイナーが最も輝いていたのは70年代だったという意見は多いんじゃないだろうか。その黄金時代の幕開けを告げるアルバムとされているのがこの作品。ガッツリとジャズしていた「The Real McCoy」と比べると、より柔軟な曲に柔軟な演奏には確かに70年代の匂いが漂っている。それでも共演者の顔ぶれを見れば60年代ジャズを支えた強者ばかりとあって、ジャケットほどは70年代的、アフリカ的なムードは強くなく、あくまでも60年代ジャズの発展系として聴けるその過渡期的な要素がこのアルバムの面白み。マイルス・グループ加入直前のゲイリー・バーツは、まだ本領発揮前なのかそれほど存在感がなく、やはりショーターの活躍が印象に残る。時に空間を彩るアリス・コルトレーンのハープの存在は微妙で、ない方がスッキリとしているような気がするものの、このアルバムに独自性を与えているのも事実。そんなサウンドに乗るマッコイのピアノは、いつもの力強く滑らかなタッチをベースにしながらもより表現の幅が広まっているところが聴きどころ。ウネリと力強さを押し出すエルヴィンとマッコイのピアノが絡むとコルトレーンの影がチラつきつつ、コルトレーンが推し進めていたアフリカ志向をマッコイ流にわかりやすく料理したアプローチこそがこのアルバムの主軸。(2007年4月15日) | ||
| Sahara | ||
 曲:★★★☆ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★ マッコイ入門度:★★★★★ 評価:★★★★☆ |
[Recording Date] 1972/Jan [1] Ebony Queen [2] A Prayer For My Family [3] Valley Of Life [4] Rebirth [5] Sahara |
Sonny Fortune (as, ss, fl) McCoy Tyner (p, koto[3], fl[5], per[5]) Calvin Hill (b, per and reeds [3][5]) Alphonse Mouzon (ds) |
| マッコイはブルーノート在籍の後期あたりから自身のオリジナリティが明確になってきて、マイルストーン・レーベルに移った本作以降ではもう完全に独自の音楽を展開するようになってくる。[1]からソニー・フォーチュンのソプラノ・サックスが怪しく切れ込み、マッコイのピアノが躍動する。休みなくバシャバシャと叩き続けるシンバルと高音で小刻みにうねるベースがそのテンションを加速。[2]はマッコイのソロ、[3]は琴の演奏と箸休めが続いたあと[4]からまた怒涛の疾走。そして最大の聴きどころは23分にも及ぶ[5]で、疾走感だけでなく小刻みでビジーなベース・ソロ、ドラム・ソロ、フォーチュン以外全員参加のパーカッションまでがごっちゃまぜになった混沌状態。最後までスピード感を失わないそんなサウンドの中、もちろんマッコイのピアノもダイナミックに暴れまわる。このアルバム以降この路線を進むマッコイの音楽を、聴いたことがない人に説明するのはなかなか難しい。まず、コルトレーンの影響は避けては通れないのは当然として、しかしながらコルトトレーンが持っていた重さがなく、むしろ軽々しいといっても良いムードゆえにとても同じ耳では聴けない。ピアノのタッチはより明快にわかりやすく、力強い演奏に徹していて、ビジーなドラムとスピーディなベースが重なることで独自の疾走感と混沌とスリルを生み出す。また、音楽そのものがやや大袈裟、しかし高尚な感じがなく良く言えば親しみやすく悪く言えば俗っぽいところがまさにマッコイ・ワールド。そしてどこか地に足が着いていないかのような落ち着きのなさを伴うところもまた個性として備えている。嫌いな人には受け付けない類のものであることは理解できるものの、ジャズ低迷時代の70年代にあってここまでヤケクソ気味のパワー溢れる音楽をやっていたことはもう少し評価されていてもいいような気がする。(2007年5月2日) | ||
| Enlightenment | ||
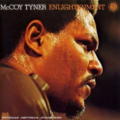 曲:★★★☆ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★ マッコイ入門度:★★★☆ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1973/7/7 [1] Presenting The McCoy Tyner Quartet [2] Enlightenment Suite, Part 1: Genesis [3] Enlightenment Suite, Part 2: The Offering [4] Enlightenment Suite, Part 3: Inner Glimpse [5] Presence [6] Nebula [7] Walk Spirit, Talk Spirit |
Azar Lawrence (ts, ss) McCoy Tyner (p) Joony Booth (b) Alphonze Mouzon (ds) |
| 下世話な感じすら伴う大袈裟な曲にマッコイのピアノが炸裂、それを更に囃し立てる賑やかなドラムに重みのないサックスが絡むというこの路線は、70年代にマッコイが到達したひとつの頂点であり、一聴して現代ではあり得ない音楽とわかりつつも意外と古びた感じがしない。73年、モントルー・ジャズ・フェスティバルでのこのライヴでもそんな特徴がそのまま出ていて、マッコイのダイナミックなピアノ・ソロ[3]から、大疾走が始まる[4]の流れこそがこのグループを象徴する展開で、わかっちゃいるんだけれど爽快で、このような狂乱をぶちまけることこそが70年代マッコイ・グループの存在意義と言ってもいいでしょう。[5]ではフォー・ビートで展開されるもエネルギーはいささかも衰えず、フツーのジャズでは許されないような強固なタッチでマッコイが躍動し続けるところがまたたまらない。そのままテンションは下がらず、ベース・ソロから反復リフが続く展開の[7]も盛り上がる。24分に及ぶその[7]は、ベースが同じリフを延々と刻むという手法はファンク的アプローチのように見えるものの、ムードは大違いで、アル・ムザーンのドラムの軽薄さがこのオリジナリティに大きく加担しているのは間違いないところ。とにかく勢いを味わうべきアルバム。(2007年5月7日) | ||
| Atlantis | ||
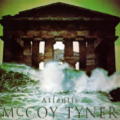 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★ マッコイ入門度:★★★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1974/8/31 1974/9/1 [1] Atlantis [2] In A Sentimental Mood [3] Makin' Out [4] My One And Only Love [5] Pursuit [6] Love Samba |
Azar Lawrence (ts, ss) McCoy Tyner (p) Joony Booth (b) Wilby Fletcher (ds) Guillerme Franco (perc) |
| 西海岸の有名クラブ、キーストーン・コーナーでのライヴ。ここでも70年代マッコイ・カルテットならではの勢いで熱烈な演奏が繰り広げられている。ジャズと呼ぶには気が引ける、より発展型の音楽性を持ちながらこのグループが(一般的に軟弱とされる)フュージョン扱いされなかったのは、電子楽器を使わなかったことと常に熱い演奏を繰り広げていたからではないかと想像する。また、サウンドの中心には確固としたマッコイのピアノがあるところも電子楽器嫌いな人の受け皿になったのかもしれない。また、狙ってそうしたのかどうかは不明ながら、サックス・プレイヤーが揃いも揃って弱いところもマッコイのピアノを引き立てる状況を作り出している。さて、このアルバムでは「Sahata」「Enlightenment」と比べるとドラムのタイト感が増していることと、パーカッション奏者が加わったことによってバンドとしての勢い、喧騒度が増しているところが魅力。それに煽られてかエイゾー・ローレンスのサックスもなかなか健闘。[3]のようなミドル・テンポの重みを必要とされる曲でもそれなりに消化できているのはそんなリズムの違い故で、このようなウネリ感のある混沌状態を作れるようになったのはバンドとしての進歩と言える。お得意のピアノ・ソロ・パフォーマンスを中心とした[4]で息抜きすると、ミドル〜アップテンポの[5]で少しずつテンション・アップ。それなりの重みを持つようになったリズム・セクションにローレンスの熱演が加わり、コルトレーン・カルテットの影がチラつくムードを醸し出すと、マッコイのソロへ展開する。最後の[6]は冒頭のパーカッション攻撃から高揚を予感させ、軽快にテーマに入ると当初の予感どおりに均一的スピード感と緊張感が延々と続く。繰り返しになってしまうけれど、ウィルビー・フレッチャーのドラム、もっと言うと右シンバルのてっぺんを小刻みに連打(想像)する音とギレルモ・フランコのパーカッションの醸し出す高揚感が素晴らしく、ジュニ・ブースの躍動やローレンスのキレにまで影響しているところがこのアルバムの聴きどころ。それにしても暑苦しい音楽だなあ(褒めてます)。(2007年5月12日) | ||
| Trident | ||
 曲:★★★★☆ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★ マッコイ入門度:★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1975/2/18,19 [1] Celestial Chant [2] Once I Loved [3] Elvin (Sir) Jones [4] Land of the Lonely [5] Impressions [6] Ruby, My Dear |
McCoy Tyner (p, harpsichord, celeste) Ron Carter (b) Elvin Jones (ds) |
| 70年代のマッコイ・タイナーは自身のコンボを率いての活動を中心としながら、ときどき本作のようなピアノ・トリオ作品を発表している。フュージョン・ムーヴメント真っ盛り、軽い音楽が支持された時代に録音されたこのアルバムは、所謂ムード優先のピアノ・トリオとは異なっていて、マッコイの力強いタッチのピアノがたっぷりフィーチャーされたパワフルな演奏で占められているのが特徴。しかも共演者がロン・カーターとエルヴィン・ジョーンズとなれば一定レベル以上の内容は保証されたようなもので、意外性こそないもののメンツ相応のスリルは十分味わえる。通常のピアノ・トリオだと音量バランスの問題でドラムが控えめにブラシを使うことが多いけれど、マッコイのダイナミックなピアノにそんな気遣いは不要で、ロンの柔軟かつスピーディなベースも良く合っている。コルトレーン縁の曲も多く、モンクとトレーンの競演で知られる[6]でしっとりと締める構成も心地よい。濃厚なアクを求める人には少々物足りないかもしれないけれど、良く聴けば3人の絡みは並みのミュージシャンではできないものであることもわかる。(2007年5月17日) | ||
| Fly With The Wind | ||
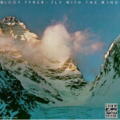 曲:★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★ マッコイ入門度:★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1976/1/19-21 [1] Fly With The Wind [2] Slvadore De Samba [3] Beyond The Sun [4] You Steped Out Of A Dream [5] Rolem |
Hurbert Laws (fl) McCoy Tyner (p) Ron Carter (b) Billy Cobham (ds) Paul Renzi (piccolo, fl) Raymond Duste (oboe) Linda Wood (harp) Guilherme Franco (tb) plus strings |
| いろんな意味でこれも70年代を濃厚に感じさせる音楽。70年代のマッコイ・グループらしい音楽でもありながら、前後のアルバムとはメンバーもガラリと変えて一味違う作品になっている。演奏の中心はマッコイのピアノを核にしたカルテットで、ロン・カーターの電化ウッド・ベース、叩きまくりのビリー・コブハムを基礎に、ストリングスやハープを含むその他大勢が大袈裟に盛りたて、リード奏者はサックスではなくフルートという構成。だから表面的にはかなり「その他大勢」が耳について壮大なシンフォニーの如く響く。そもそも、こういう編成で音楽をやろうということじたいが70年代的。ストリングスのメロディやアレンジがまた70年代的なセンスで一歩踏み外すと気恥ずかしさすら覚えるほど大袈裟。今こんな作品を発表したら鼻で笑われること必至。しかし、こんなアレンジやメロディで気分を高揚させてしまうところがまたマッコイ的だしこのアルバムの魔力でもあって、今の時代に生まれ得ないからこそ価値があるとも言える。マッコイのピアノは流麗さよりも明快さと更なる力強さが目立ち、60年代のマッコイを愛する人にはやや過剰気味かもしれないけれど、コブハムの高密度で暴れるドラミングに太刀打ちするにはこのくらいでないと通用しない。ちなみに、「ビリー・コブハムってどんなドラマーなんだろう」という人には、個性がほとんど出ていないマイルスの「ジャック・ジョンソン」ではなく、このアルバムで試してみた方がいい。(2007年5月7日) | ||
| The Greeting | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★ マッコイ入門度:★★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1978/3/17,18 [1] Hand In Hand [2] Fly With The Wind [3] Pictures [4] Naima [5] The Greeting |
George Adams (ts, ss, fl) Joe Ford (as, fl) McCoy Tyner (p) Charles Fambrough (b) Sonship (Woody Theus) (ds, orchestra bells) Guilherme Franco (perc, conga, berimbau) |
| このアルバムも西海岸でのライヴ。当時は西海岸がマッコイの本拠地だっただろうか? ここでは2人のサックスを擁した6人編成。パーカッション・パフォーマンスから穏やかにマッコイのピアノが踏み込み、そのままのムードで2人のフルートが同じメロディを繰り返すという、ちょっと変わったゆったりとしたオープニングは少しゴスペルの雰囲気も感じさせる(実際のライヴの1曲目ではないと思うけれど)。そして有名曲[2]をこの編成で。スタジオ盤のビリー・コブハムのような引き締まった弾力感を望むのは酷としても、手数の多さとビジーな感じのドラムはなかなかの健闘で、マッコイのダイナミックなピアノを盛り立てる。とはいえ、72年に録音された「Sahata」以来のマッコイ・グループ、確かにマッコイでないとできない音楽であるものの、乱暴に言えば大同小異でそれぞれに異質の感動があるわけではなく、このアルバムもそんな中の1枚。酷な言い方をするならばそこに6年間という長い時間分の進歩は特に感じられず、メンバーが変わっていても何も変わっていないのはある意味信念を持ってマッコイが音楽を作っていたのかもしれないし、ロックやフュージョンに迎合できなかかったからかもしれない。本作ならでは聴きどころをあえて探すと、曲によって2人のサックスが暴れるところとウッディ・ゼウスのドラムが結構やかましいところでしょう。ただし、バンドとしての勢いはやや後退気味。マイルストーン・レーベル時代のマッコイのライヴ盤は、アナログ2枚組をCD 1枚にまとめた長時間収録がが多く、43分でコンパクトにライヴを楽しもうという人には向いている(2007年7月29日) | ||