ロック・ファンのためのジャズ案内のヘッダー
Rock Listner's Guide To Jazz Music
Sonny Clark
| Dial "S" For Sonny | ||
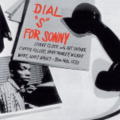 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1957/7/21 [1] Dial S For Sonny [2] Bootin' It [3] It Could Happen To You [4] Sonny's Mood [5] Shoutin' On A Riff [6] Love Walked In |
Art Farmer (tp) Hank Mobley (ts) Curtis Fuller (tb) Sonny Clark (p) Wilbur Ware (b) Louis Hayes (ds) |
| ピアニストのリーダー・アルバムにおけるコンボ編成となると、ピアノ演奏そのものよりも、作曲、編曲で何を表現するかが問われることになる。コンボで自己の音楽性を遺憾なく表現できたピアニストといえば、セロニアス・モンク、ホレス・シルヴァー、ハービー・ハンコック、アンドリュー・ヒルあたりが思い浮かぶけれど、ソニー・クラークもその中の一人。ただ、(ホレスと)クラークは、50年代の伝統的ジャズを下地にしていて、尖った音楽性を持ち味としているわけではなく、音楽家として強い印象を残すわけではない。それでも聴けばクラークならではのジャズとわかる。このアルバムではセクステットという大所帯でありながら、曲も演奏もソニー・クラークらしさがしっかりと出ているところが魅力。ピアノ演奏についてはホレスのようにシンプルすぎることもなく、ブルース・フィーリングがあると言ってもレッド・ガーランドのそれとはまた異質の哀愁があるところが持ち味。伝統を継承していながら古臭くなく、独特の翳りを帯びているところが日本での人気の秘密でしょう(アメリカでの知名度はかなり低いらしい)。共演者はコルトレーンのような革新派タイプよりは、ファーマー、モブレー、フラーといった伝統的なスタイルの方がよりクラークの個性が際立つ。このアルバムはオーソドックスなゆったりめのハードバップで、フロント3人のリラックスした味わい深いプレイ(特にモブレー)を楽しめる。「Cool Struttin'」には及ばないものの、これも捨てがたい1枚。(2007年2月16日) | ||
| Sonny's Crib | ||
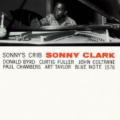 曲:★★★☆ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★★☆ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1957/9/1 [1] With A Song In My Heart [2] Speak Low [3] Come Rain Or Come Shine [4] Sonny's Crib [5] News For Lulu [6] With A Song In My Heart (alt take) [7] Speak Low (alt take) [8] Sonny's Crib (alt take) |
Donald Byrd (tp) John Coltrane (ts) Curtis Fuller (tb) Sonny Clark (p) Paul Chambers (b) Art Taylor (ds) |
| クラークの持ち味であるオーソドックスなハード・バップでありながら、他のクラーク作品とは作風が異なるのは狙ってのことでしょう。ここではなんと言ってもコルトレーンの参加が大きい。そのコルトレーンはもちろん、バードもフラーもエネルギッシュで快調なソロを連発、クラークのどのアルバムよりも力強さが全面に出ているところが特徴。また、アート・テイラーの律儀なドラムも他のアルバムとの印象を違うものにしている。曲も前半はスタンダード中心が中心というところも他のアルバムと違うところ。質は高いし、良い演奏を楽しめるアルバムながら、この元気すぎるフロント陣がクラークのピアノに合っているか、彼の個性がより発揮できているかという観点で見るとあまり高い点をつけられないというちょっと困ったアルバム。ボーナス・トラック重視の人は輸入盤をどうぞ。(2006年11月14日) | ||
| Sonny Clark Trio | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1957/9/13 [1] Be-Bop [2] I Didn't Know What Time It Was [3] Two Bass Hit [4] Tadd's Delight [5] Softly As In A Morning Suneise [6] I'll Remember Aprial |
Sonny Clark (p) Paul Chambers (b) Philly Joe Jones (ds) |
| ソニー・クラークといえば代表作として必ず挙げられるのが「Cool Struttin'」。コンボこそががクラーク本領発揮の場とわかっているものの、クインテット編成での音楽づくりに重点が置かれ、ピアノが目立つわけではない。そんなソニー・クラークのピアノをとにかく堪能したのなら、なんと言ってもこのアルバム。フィリー・ジョー・ジョーンズがあまりブラシを使わずスティックで勢い良く叩いているのに、ピアノが埋もれていないほど力強いタッチで演奏していながら、持ち味の美しさと翳りも併せ持つというクラークのピアノが満喫できる。曲は有名スタンダードが多く、収録時間が短いこともあって一気に聴けてしまうアッサリ仕上げ。(2006年8月5日) | ||
| Cool Struttin' | ||
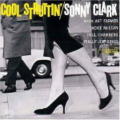 曲:★★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1958/1/5 [1] Cool Struttin' [2] Blue Minor [3] Sippin At Bells [4] Deep Night [5] Royal Flash [6] Lover |
Art Farmer (tp) Jackie MaClean (as) Sonny Clark (p) Paul Chambers (b) Philly Joe Jones (ds) |
| 初心者向けガイドブックには必ず載っている定番中の定番。告白すると僕はこのアルバムの良さがサッパリわからなかった。要はフツーでトンがった部分がない。アート・ファーマーは癖がなく個性をあまり感じない、フィリー・ジョー・ジョーンズが燃えていない、そしてサウンドじたいに派手さがない。多くの初心者が初期の段階で入手し同じような感想を持つ人が多いのか、中古盤屋に行くと山のように置いてあったりする。僕がジャズを聴きはじめのころに熱を入れていたマイルス・デイヴィス、ソニー・ロリンズ、ジョン・コルトレーン、フレディ・ハバードといった強烈な個性を持った人たちのアルバムと比べるとますますパンチがない。しかし、初めて聴いてから6年以上の歳月が過ぎ、さまざまなジャズを聴いていくうちに、地味なんだけれど、そのなんでもない普通のハード・バップにクラークの個性が滲み出ていることがようやく理解できるようになった。昔は不満と感じていた燃えていないフィリー・ジョー・ジョーンズのもうひとつの個性は、その独特の間を生かしたルーズなリズム感(アート・ペッパーの「Meets The Rhythm Section」のように)にあることを理解できるようになったのも大きい。ファーマーのプレイは確かにモーガンやハバードのような派手さはないけれどここではそれが却っていい結果を生んでいるし、マクリーンのアルトは素直でハード・バップ期の演奏としてはベストのひとつと言えるほど伸びやか。チェンバースのベースはソロもたっぷりフィーチャーされていて、ゆったりめの曲が多いこともあって彼の大股なウォーキング・ベースの魅力がよく出ている。もちろん[4]の冒頭を筆頭にクラークの哀愁度満点なピアノの魅力もたっぷり味わえる。くどいけれどここには尖がった要素は皆無。でも味わい深い。疾走感や熱狂だけがハード・バップでないことを思い知らせてくれる。(2007年8月19日) | ||
| Leapin' And Loapin' | ||
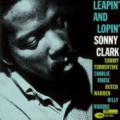 曲:★★★☆ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1961/11/13 [1] Somethin' Special [2] Deep In A Dream [3] Molody For C [4] Molody For C (alt take) [5] Eric Walks [6] Voodoo [7] Midnight Mambo [8] Zellmar's Delight |
Tommy Turrentine (tp) Charlie Rouse (ts except [2]) Ike Quebec (ts [2]) Sonny Clark (p) Butch Warren (b) Billy Higgins (ds) |
| 初心者向けガイドブックには必ず載っている定番中の定番。告白すると僕はこのアルバムの良さがサッパリわからなかった。要はフツーでとんがった部分がない。アート・ファーマーは癖がなく個性をあまり感じない、フィリー・ジョー・ジョーンズが燃えていない、そしてサウンドじたいに派手さがない。多くの初心者が初期の段階で入手し同じような感想を持つ人が多いのか、中古盤屋に行くと山のように置いてあったりする。僕がジャズを聴きはじめのころに熱を入れていたマイルス・デイヴィス、ソニー・ロリンズ、ジョン・コルトレーン、フレディ・ハバードといった強烈な個性を持った人たちのアルバムと比べるとますますパンチがない。しかし、初めて聴いてから6年以上の歳月が過ぎ、さまざまなジャズを聴いていくうちに、地味なんだけれど、そのなんでもない普通のハード・バップにクラークの個性が滲み出ていることがようやく理解できるようになった。昔は不満と感じていた燃えていないフィリー・ジョー・ジョーンズのもうひとつの個性は、その独特の間を生かしたルーズなリズム感(アート・ペッパーの「Meets The Rhythm Section」のように)にあることを理解できるようになったのも大きい。ファーマーのプレイは確かにモーガンやハバードのような派手さはないけれどクラークのピアノに良く合っているし、マクリーンのアルトは素直でハード・バップ期の演奏としてはベストのひとつと言えるほど伸びやか。チェンバースのベースはソロもたっぷりフィーチャーされていて、ゆったりめの曲が多いこともあって彼の大股なウォーキング・ベースの魅力がよく出ている。もちろん[4]の冒頭を筆頭にクラークの哀愁度満点なピアノの魅力もたっぷり味わえる。くどいけれどここには尖がった要素は皆無。でも味わい深い。疾走感や熱狂だけがハード・バップでないことを思い知らせてくれる。(2007年8月19日) | ||
