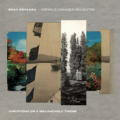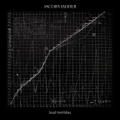ロック・ファンのためのジャズ案内のヘッダー
Rock Listner's Guide To Jazz Music
Brad Mehldau
| The Art Of The Trio Vol.1 | ||
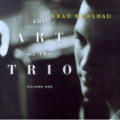 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★★☆ メルドー入門度:★★★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1996/9/4, 5 [1] Blame It On Youth [2] I Didn't Know What Time It Was [3] Ron's Place [4] Blackbird [5] Lament For Linus [6] Mignon's Song [7] I Fall In Love Too Easily [8] Lucid [9] Nobody Else But Me |
Brad Mehldau (p) Larry Grenadier (b) Jorge Rossy (ds) |
| 後に多くのアルバムを残すアート・オブ・トリオのデビュー作。1曲目からバラードでしっとりと聴かせるあたり、早くも表現力の自信のようなものさえ感じさせる。スタンダードとオリジナルが約半分ずつ、そしてそのスタンダードの解釈に独特なものを見せるところ、ビートルズの[4]を自分色に染め上げてしまうところなどは既にメルドーのアイデンティティとして確立されていて、非凡さが窺えるところはさすが。ややダークなメロディ使いも然り。派手に指が動きまわるシーンは少なく、フレージングやトーンで自分の感性を全面に出していくところは(当時)若手としては出色。ベースとドラムが脇役に徹していることもあって激しさやスウィング感を求める向きには物足りないかもしれないけれど、メルドーのピアノに心地よく身を任せて聴くには申し分のないアルバムと言える。表面的な難解さが抑えられているため上質なBGMとしての鑑賞にも耐える(根底にある捻くれた感性は既に垣間見える)。常套的なジャズ・ピアノの手段を意識的に排除しつつ、この時点で既に高い完成度を誇り、後のプレイよりもやや素直な表現を聴かせるところがこのアルバムの美点。(2009年3月15日) | ||
| The Art Of The Trio Vol.2: Live At The Village Vangurd | ||
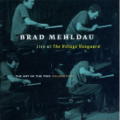 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★★☆ メルドー入門度:★★★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1997/7/29-8/3 [1] It's Alright With Me [2] Young And Foolish [3] Monk's Dream [4] The Way You Look Tonight [5] Moon River [6] Countdown |
Brad Mehldau (p) Larry Grenadier (b) Jorge Rossy (ds) |
| アート・オブ・トリオ初期の作品で、スタンダード、既存の曲だけで構成されていることもあって耳慣れた曲が多い。しかしそこはメルドーのこと、ムードだけの心地よいピアノ・ジャズに陥るわけもなく全編捻った解釈で貫かれている。このころは指の動きが忙しく、トレードマークとも言える左手アドリブの見せ場も楽しめる。このトリオの中心はあくまでもピアノにあり、そこにベースとドラムが肉付けをしていくスタイルだと個人的には思っていて、そういう意味ではキース・ジャレットのスタンダーズ・トリオと似たような形態と言えるけれど、なにぶんピアニストの性格が違いすぎるため表現手法がまったく異なるところが面白い。そのベースとドラムの絡み方が独特でスウィンギーという言葉がまったく似つかわしくない独特のタイム感覚も聴きどころ。ソロ・パートが多く、メルドーの表現も実に伸びやかで、表現は後のことを思えばストレート。時に観客から感嘆の声まで飛び交うライヴならではの臨場感もいい。繊細さを如何なく発揮する[2][5]に魅力を感じつつも、普通こんな曲を選ばないだろうという[6]はもともとコルトレーンが吹きまくっていた、曲と呼ぶほど形がはっきりしていないもので、メルドーも自由自在に弾き倒し、ときどき思い出したように少しだけ原曲のエンディングのフレーズが顔を覗かせる、という構成でピアノ・トリオ曲として見事に再構築されている。すべての曲が10分以上の長尺演奏でトータル73分の充実盤。(2007年1月19日) | ||
| The Art Of The Trio Vol.3: Songs | ||
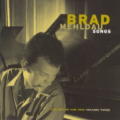 曲:★★★★☆ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★★★ メルドー入門度:★★★★★ 評価:★★★★☆ |
[Recording Date] 1998/5/27,28 [1] Song-Song [2] Unrequited [3] Bewiched, Bothered And Bewidered [4] Exit Music (For A Film) [5] At A Loss [6] Convalescent [7] For All We Know [8] River Man [9] Young At Heart [10] Sehnsucht |
Brad Mehldau (p) Larry Grenadier (b) Jorge Rossy (ds) |
| アート・オブ・トリオの第3弾はスタジオ録音盤は優雅で美しくも独特の憂いを帯びたメルドーのピアノが全編に溢れている。曲もミドル・テンポ以下の聴かせるタイプのものが多くメルドー・トーンに支配された深遠な音空間に浸ることができる(故にアグレッシヴさは期待しない方が良い)。しかし演奏の質は当然高く、決して退屈なムード音楽になっていないし、その少しひねた感性から来る音空間にメルドーならでは創造性を感じることができるはず。また、近年はやや陰鬱なトーンになりつつあるメルドーのピアノにまだ素直な感性を感じることができること、両手アドリブがところどころで聴けるのところがこの時期の聴きどころ。ソフトなムードでありながら、全体に貫かれている控えめな緊張感で高い質感を演出しているところはスタジオ録音ならではで、曲も全体的に短めなこともあって他のライヴ盤とは一味違った価値を提示できていると思う。(2007年12月8日) | ||
| The Art Of The Trio Vol.4: Back At The Vanguard | ||
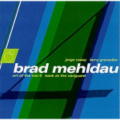 曲:★★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★☆ メルドー入門度:★★★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1999/1/5-10 [1] All The Things You Are [2] Sehnsucht [3] Nice Pass [4] Solar [5] London Blues [6] I'll Be Seeing You [7] Exit Music (For A Film) |
Brad Mehldau (p) Larry Grenadier (b) Jorge Rossy (ds) |
| 冒頭、メルドーのソロで力強くリズミカルに畳み掛け、グイグイと聴き手を惹きつけるこの緊張感が強烈。それが頂点に達したところで、ドラムとベースが加わって曲に雪崩れ込む展開はカタルシスすら感じる。以降もメルドーならではの少しダークな音使いとタッチを、これでもかというくらいに放出。曲中に用意されたメルドーの独演パートで緊張感を高め、クライマックスになるとベースとドラムが加勢する展開じたいは目新しくないとしても、この3人の組み合わせで構築されているムードは他では絶対に味わえないもの。手垢にまみれた[1][4]のスタンダードは比較的ストレートな表現ながらメルドーの世界にしっかりと染め上げることに成功している。このアルバムの良いところはメルドーのピアノに生気が漲っていて指の動きが実に滑らか、テンポもムードも自由自在、追随するベースとドラムも、疾走するフォービートから曲がりくねったウネリまでを創造し、実に多彩であるところにある。つまりメルドー自身のプレイ、トリオとしてのまとまりが最高潮ということ。メルドーのアルバムとしてはアグレッシヴな演奏が多いのも特徴で、しかし息を潜めるようなバラードがなくともタッチの繊細さを十分感じ取れるところはさすが。弾きまくっているところでも開放的な高揚感には至らず、どこかシリアスなムードに終始するところが良くも悪くもメルドー的。イージー・リスニング的な安易な演奏は皆無で、素直な演奏やムードだけが味わえれば良いというジャズ・ファンには向いていないけれど、ちょっとヒネリのあるものの方が征服しがいがあるという人には是非トライしてもらいたいピアノ・トリオ。Radioheadの[7]は美しさ、物悲しさ、力強さ、激しさが昇華した究極の名演。(2007年1月20日) | ||
| The Art Of The Trio Vol.5: Progression | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★ メルドー入門度:★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 2000/9/22-24 Disc 1 [1] The More I See You [2] Dream's Monk [3] The Folks Who Live On The Hill [4] Anone Together [5] It Might As Well Be Spring [6] Cry Me A River [7] River Man Disc 2 [1] Quit [2] Secret Love [3] Sublation [4] Resignation [5] Long Ago And Far Away [6] How Long Has This Been Going On? |
Brad Mehldau (p) Larry Grenadier (b) Jorge Rossy (ds) |
| アート・オブ・ザ・トリオ名義の最終アルバムは、ヴィレッジ・ヴァンガードでの3日間のライヴからのセレクト。トリオとしての在り方は完全にメルドーのピアノが中心になっており、ベースとドラムが追随するスタイルが完成、成熟度は行くところまで行ってしまった感がある。しかし、安易なメロディを用いない感性全開のメルドーのピアノに絡むベースとドラムに後付け感はなく、高度に融合した様は高級ワインの持つ複雑味すら連想させるほどの味わいがあり、その緊張感にグイグイと引き込まれてしまう。ただし、このタイム感覚(決してスウィングしない)が合わない人にはヒネた退屈な音楽にしか聴こえないかもしれない。以前より更に個性的かつ独特なダークさを漂わせるメルドーの音使いは、あまり強いタッチを見せず、陰鬱な浮遊感をもって展開され、幾分の難解さが同居したかなり内向的なムードに終始する。この催眠的な世界はメルドーへの入口としては不向きで、しかし上級者には堪らない世界になっている。ある意味、ジャズ・ピアノ・トリオの究極の姿のひとつがここにある。(2009年7月4日) | ||
| Largo | ||
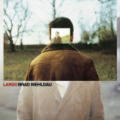 曲:★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★★ メルドー入門度:★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 2001/4/2-8 [1] When It Rains [2] You're Vibing Me [3] Dusty McNugget [4] Drojes [5] Paranoid Android [6] Franklin Avenue [7] Sabbath [8] Dear Prudence [9] Free Willy [10] Alvalando [11] Wave/Mother Nature's Son [12] I Do |
Brad Mehldau (p, vib [2][11]) Derek Oleszkiewicz (b except [1][7][9][12]) Larry Granadier (b [1][2]) Justine Meldal-Johnsen (elb [4][11]) Matt Chamberlain (ds except [2][8][10][12]) Jorge Rossy (ds [2][9]) Jim Keltner (ds [2][3][5][8]) plus ... [1] Steve Kujala (fl) David Shostac (fl) Jon Clark (oboe) Earle Dumler (oboe) Gary Gray (cl) Emile Bernstein (cl) Peter Mandel (basson) Rose Corrigan (basson) [3][6] Philip Yao (French horn) Daniel Kelly (French horn) William Reichenbach (tb) George B. Thatcher (btb) |
| 充実した成果を残したThe Art Of Trioの活動に一区切りを付け、しかし「Anythig Goes」からまたピアノ・トリオの路線を再開したメルドー。その狭間に録音されたのがこの実験性に富んだアルバム。参加メンバーのクレジットが細かいので詳細は上に記載しきれていないけれど、要はいろんなメンバーを集めて、一週間でいろいろなことをやってみましょうという企画だったようだ。実際、曲調も演奏もバラエティに富んでいて、オーソドックスなジャズ風(といってもあくまでもメルドー流)、ジャズ風でもポップな仕上げにしたもの、ロック的でノイジーなサウンドなもの、フリーなセッション風の荒っぽいもの、インダストリアル・ミュージック風、ジョシュア・レッドマンのエラスティックバンド風のものなどさまざま。それを音として表現するために、ピアノにレズリーをかませて音を歪ませたり、マイクをあえてピアノから遠く離して音の響きを変えたりと音の録り方も普通のジャズの枠に囚われない自由さで臨んでいる。曲は[5]がレディオヘッド、[8][11]がビートルズ([8]が珍しく退屈な仕上がり)、それ以外はメルドー(または参加メンバーと連名)のオリジナル。このように自由にやったというのに、どこからどう聴いてもメルドー以外に何者でもない音楽になっているところにこの人の非凡さを改めて感じる。少なくない人数でセッション風に録音したのに、よく練られていて完成度が高いところも驚き。どうせ後でいろいろ手を加えてここまで仕上げたんでしょ?という見方をする人に釘をさすように、わざわざ「オーバーダブはありません」というクレジットが入っている。というわけでメルドーファンなら、「いろいろやっているのにメルドーらしさがあって面白いね」、嫌いな人は「何をやってもメルドーは陰鬱でつまらないね」ということになりそうなアルバム。僕はもちろん前者です。同じように自作でジャズの枠を越えようとしたものとして後に「Highway Lider」が後に制作されたけれども、あちらが内向的なものであるのに対して、こちらはより拡散して外に向いているところが大きく違う。(2015年7月23日) | ||
| Anything Goes | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★ メルドー入門度:★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 2002/10/8-9 [1] Get Happy [2] Dreamsvile [3] Anythig Goes [4] Tres Palabras [5] Skippy [6] Nearness Of You [7] Still Crazy After All These Year [8] Everything In It's Right Place [9] Smile [10] I've Grown Accoustomed To Her Face |
Brad Mehldau (p) Larry Grenadier (b) Jorge Rossy (ds) |
| 名義は The Art Of The Trio でなくても、顔ぶれ同じく既に成熟の域に入った鉄壁のトリオによるスタジオ盤で、音楽的にはこれまで通りの路線。「The Art Of The Trio Vol.5: Progression」で明確になってきた、より柔軟なリズムで自由に展開するリズム・セクションにメルドー独自のメロディとトーンが絡む独自の世界をここでも展開。[1] を聴くとメルドーならではのコードの使い方と、このトリオらしい捻った解釈で流石と思わせる。音数を減らし、一音一音に意味を込める方向性になってきたメルドーが、ここでは[2][4][6][7][8][9][10] とゆったりした曲やバラード系の演奏を多く組み込むことでその傾向を一段と明確にする。このため、以前にも増して地味でより内省的な印象を受けるものの、メルドーらしさの基本は変わっていない。そういう意味でこの人はきっと相当頑固なんだろうとも思う。スタジオ盤であるせいか短めの曲が多いために聴きやすいのも特徴で、ベッド・サイド・ミュージックとしての役割にも耐え得る。(2006年11月11日) | ||
| Day Is Done | ||
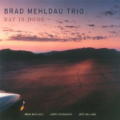 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★ メルドー入門度:★★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 2005/3/13 2005/3/14 [3] [1] Knives Out [2] Alfie [3] Martha My Dear [4] Day Is Done [5] Artis [6] Turtle Town [7] She's Leaving Home [8] Granada [9] 50 Ways To Leave [10] No Moon At All |
Brad Mehldau (p) Larry Grenadier (b) Jeff Ballard (ds) |
| 長らく活動を共にしてきたドラマー、ホルヘ・ロッシィに代えてジェフ・バラードを迎えたニュー・トリオによる第一弾。Radiohead の[1]から、瑞々しさと美しさの中にも屈折した感性を内包するメルドーらしさが良く出ていて信者を納得させるには充分。特に不協和音を多用しながらも軽快さを聴かせるビートルズの[3][7]、得意の両手奏法からクライマックスに持っていくポール・サイモンの[9]といった曲の解釈、演奏が素晴らしい。[6]のようなラテン系リズムでもダークなメロディで料理してしまうのもメルドーらしい。新ドラマーのジェフ・バラードは手数が多く軽めの疾走感を得意とするタイプで全体にスピード感をもたらしている。重いドラムを聴かせた前任者と比較すると少しアッサリした印象もあり、好みが分かれるかもしれないけれど、そのドラマーの素軽さで新しい方向性を示した1枚と言える。(2006年8月5日) | ||
| House On Hill | ||
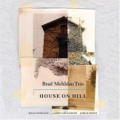 曲:★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★ メルドー入門度:★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 2002/10/8-9 2005/3/12 [1] [7] [1] August Ending [2] House On Hill [3] Bealtine [4] Boomer [5] Wait [6] Backyard [7] Fear And Trembling [8] Embers [9] Happy Tune [10] Waiting For Eden |
Brad Mehldau (p) Larry Grenadier (b) Jorge Rossy (ds) |
| 2002年10月8日と9日に行われたセッションの一部は「Anything Goes」として2004年にリリースされており、しかし、まだまだ未発表曲が数多く残っていたようで2006年7月にそのときのセッションの本作をリリース。あちらがカヴァー曲で構成されているのに対してこちらば全曲オリジナルで占められているところが大きな違い。いわゆる The Art Of Trio による演奏で、しかしながら「Day Is Done」セッションの前日録音の曲も2曲ある。ということは、そのときには前日までホルヘ・ロッシィでセッションをしていたという事実が発覚。実はジェフ・バラードだけで通すことに不安があったということか?解説を読むとメルドーの作曲に対する熱の入れようもよく伝わってくるし、実際の曲も狭義のジャズに留まらない柔軟な演奏が展開され、メルドーのオリジナリティを堪能できる。意欲に溢れ、高い音楽性を十分に感じられるものの、ちょっと自己の音楽に没頭し過ぎて、尚且つ内向的過ぎるために感情移入しきれない。選曲の良さ、それを料理する斬新さにおいてメルドーの才能を感じている僕にとっては、オリジナルだけでは色彩感がちょっと足りないと感じるのも事実。(2009年10月24日) | ||
| Metheny Mehldau Quartet | ||
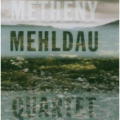 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★ メルドー入門度:★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 2005/Dec [1] A Night Away [2] The Sound Of Water [3] Fear And Trembling [4] Don't Wait [5] Towards The Light [6] Long Before [7] En La Tierra Que No Olvida [8] Santa Cruz Slacker [9] Secret Beach [10]Silent Movie [11] Marta's Theme (from "Passagio per il Paradiso") |
Pat Metheny (g) Brad Mehldau (p) Larry Grenadier (b) Jeff Ballard (ds) [2] [4] [6] [11] duets |
| 現代のジャズ・ジャイアントとして屈指の存在であるパット・メセニーとブラッド・メルドーの競演は、その顔合わせだけでも当時話題になった。編成としてはメルドーのレギュラー・トリオにメセニーが参加している形ながら、メセニーに客演感はなく、むしろメセニーのカラーの方が強いと感じる部分すらある(実際、プロデュースはメセニー)。ちなみに僕はメセニーの良さがあまりよくわからない。というかジャズにおいてギターが中心のものに興奮を覚えたことがない。さらにデュオやソロが苦手ときている。いくらメルドーが好きといっても、このアルバムにはそんな障壁があるためにやはりメルドーのリーダー・アルバムと比べると感動が薄い。特に、必然的に2人を引き立てる役割に回ることになるベースとドラムはやや抑え気味になってしまうのは仕方がないと分かりつつ、やはり物足りない。そんなことは聴く前から予想できることで、あくまでもメセニーとの地味ながら濃密なインタープレイを楽しむところこそがこのアルバムの価値だし、この2人の共演だからという部分をどこまで感じ取れるかで感動の度合いが違ってくるでしょう。(2007年4月15日) | ||
| Brad Mehldau Trio Live | ||
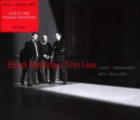 曲:★★★★☆ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★ メルドー入門度:★★★☆ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 2006/10/11-15 Disc 1 [1] Introduction [2] Wonderwall [3] Ruby's Rub [4] O Que Sera [5] B-Flat Waltz [6] Black Hole Sun [7] The Very Thourght Of You Disc 2 [1] Buddha Realm [2] Fit Cat [3] Secret Beach [4] C.T.A. [5] More Than You Know [6] Countdown |
Brad Mehldau (p) Larry Grenadier (b) Jeff Ballard (ds) |
| 2枚組。演奏は短くても8分44秒、ほとんどは10分を軽く超え、長いものでは20分をも超える。通常、ヴィレッジ・ヴァンガードでは1セットあたりせいぜい70分程度だから、11日〜15日までの5日(平日と日曜日が2セット、金土が3セットか?)の中から3セット分程度を厳選したというところか。ドラマーがジェフ・バラードに代わってから初のライヴ盤で、ジェフが加入して最初の録音から約1年半が経過、その間、多くのツアーやライヴをこなした成果としてトリオの成熟度を見せつける。ホルヘ・ロッシィ在籍時後期には、そのドラムの重さにメルドー自身の表現にダークさが増加していった時期だったこともあってやや胃もたれする感があったことを考えると、ジェフのキレとスピード感は良い意味で重苦しさを打ち消しており、メルドーのダークなトーンが生きるスロー〜ミドル・テンポの曲でも必要以上に濃くならない。この録音の1か月前の日本公演でもそのあたりを感じることができたけれど、このアルバムでの演奏の方がトリオの緊密度がさらに上と感じる(ただし、ジェフ・バラードの暴れ方は日本公演のときの方が凄かった)。これは日本公演の会場であったクラシック用のホール(オペラシティ)とニューヨークの狭い老舗クラブという環境の違いも大きい。それにしても最初にピアノが入ってくる音から、どこか頽廃的にも聴こえる美しくもダークなトーン、そして少々ヒネた感性の音使いにファンはニンマリ、嫌いな人にはウンザリというメルドー・ワールド全開。基本はミドル・テンポの曲が多く催眠的な近年のメルドー・ミュージック路線を踏襲。この辺りがやや聴き手を選ぶ感じはするものの、変幻自在に展開する演奏はジェフが加入してからの方が自由度が高いと感じる。中でも大作の[6]はかなりの聴きものでこれを聴くためにこのアルバムを入手しても良いと思えるトリオ演奏の極み、というかある意味、初めて公になったメルドー流のフリー・ジャズといえるもの。突然、妙なスタンダードを引っ張り出して面白い解釈で聴かせるところも含めて、この2枚組は濃厚なメルドー・ワールドに浸れること請け合い。録音は現代の水準で考えると超高品質とは言えないけれどクラブで聴いているかのような臨場感が生々しい。それにしてもこんな素晴らしいライヴを$35くらい(メルドーのときはもう少し高かったんだろうけれど)で気軽に観れるマンハッタンというのはなんと素晴らしいジャズ天国なんだろうと改めて思ってしまう。(2008年4月20日) | ||
| The Complete Friday Night Sets | ||
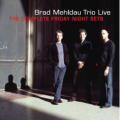 曲:★★★★☆ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★ メルドー入門度:★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 2006/10/13 1st set [1] Buddha Realm [2] O Que Sera [3] We See [4] Black Hole Sun 2nd set [1] Fit Cat [2] Wonderwall [3] C.T.A. [4] My April Heart 3rd set [1] Fear And Trembling [2] Ruby's Rub [3] Secret Beach [4] Everything In Its Right Place [5] Street Love [6] No Moon At All |
Brad Mehldau (p) Larry Grenadier (b) Jeff Ballard (ds) |
| NONESUCHレーベルのWebサイトで配信されている2006年10月13日公演を3セットすべて収録した音源。演奏の質は「Brad Mehldau Trio Live」とまったく遜色ない。逆にいえば「Brad Mehldau Trio Live」を所有している人があえてこの音源に手を出す必要があるかというと、この音源でないと味わえない世界というのはなく、マニア・コレクター向け。ならばマニアックに楽しむのが正しい。たとえば、夜の9時から1stセット(60分)を、11時から2ndセット(56分)を、12時半から最終セット(80分)を聴いてこの日のヴィレッジ・ヴァンガードを再現してみるなんてのはどうでしょう。家事でも片手間にやっていれば店員の気分も味わえるかも。MCも各セットに応じたコメントをしているし、最終セットの後にはアンコールまで入っているので仮想ヴァンガードを体験できること請け合い。 この音源に興味のある方は http://www.nonesuch.com/albums/complete-friday-night-sets-mp3s-nonesuch-store-exclusive で。お値段が$20ということを考えると「Brad Mehldau Trio Live」より安くタップリ楽しめる分お得かも。尚、「Live!」との重複は2ndセットの[1]、3rdセットの[3]のみなので熱心なファンなら両方必携。(2008年9月15日) |
||
| Highway Rider | ||
 曲:★★★★☆ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★ メルドー入門度:★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 2009/2/16-28 2009/5/12-19 Disc 1 [1] John Boy [2] Don't Be Sad [3] At The Tollbooth [4] Highway Rider [5] The Falcon Will Be Fly Again [6] Now You Must Climb Alone [7] Walking The Peak Disc 2 [1] We'll Cross The River Together [2] Capriccio [3] Sky Turning Grey ( For Elliot Smith) [4] Into The City [5] Old West [6] Come With Me [7] Always Departing [8] Always Returning |
Disc 1 [1] Joshua Redman (ss) Brad Mehldau (p) Jeff Ballard (per) Orchestra Disc 1 [2] Joshua Redman (ts) Brad Mehldau (p, pump organ) Larry Grenadier (b) Matt Chamberlain (ds) Jeff Ballard (snare brush) Orchestra Disc 1 [3] Brad Mehldau (p) Disc 1 [4] Brad Mehldau (p, YAMAHA CS-80) Larry Grenadier (b) Matt Chamberlain (ds) Disc 1 [5] Joshua Redman (ss, vo) Brad Mehldau (p, vo) Jeff Ballard (per, vo) Matt Chamberlain (per, vo) and special guest la la la vocals Disc 1 [6] Disc 2 [7] Orchestra Disc 1 [7] Joshua Redman (ts) Brad Mehldau (p, orchestral bells) Larry Grenadier (b) Jeff Ballard (ds) Matt Chamberlain (ds) Orchestra Disc 2 [1] Joshua Redman (ts) Brad Mehldau (p, orchestral bells) Larry Grenadier (b) Jeff Ballard (ds, per) Matt Chamberlain (per) Orchestra Disc 2 [2] Joshua Redman (ss, handclap) Brad Mehldau (p, handclap) Jeff Ballard (per, handclap) Matt Chamberlain (per, handclap) Disc 2 [3] Joshua Redman (ts) Brad Mehldau (p, pump organ) Larry Grenadier (b) Matt Chamberlain (ds) Disc 2 [4] [6] Brad Mehldau (p) Larry Grenadier (b) Jeff Ballard (ds) Disc 2 [5] Joshua Redman (ts) Brad Mehldau (p) Disc 2 [7] Brad Mehldau (p) Orchestra Disc 2 [8] Joshua Redman (ss) Brad Mehldau (p, orchestral bells) Larry Grenadier (b) Jeff Ballard (ds) Matt Chamberlain (ds) Orchestra |
| 自身のリーダー・アルバムではソロかトリオのスタイルで一貫してきたメルドーは、その限定された形式だけでも十分に独自の世界を作ることができる稀有のミュージシャンである。そうは言っても、もともとタダのジャズ・ピアニストという枠に納まり切らない才能の持ち主だけに、温めていたアイディアを開放するときがきたのだろう。自ら編曲したオーケストラをフィーチャーした曲が印象に残るのはもちろん、それ以外のコンボ編成の曲も含めて、ジャズに軸足を置きつつ、その枠に囚われない自由な音楽が展開される。散漫な印象を持たせないのは、どこを切ってもメルドーらしい、ダークで捻れた感性が横溢しているからに他ならない。個性的なトーンですぐにわかるジョシュア・レッドマンのサックスも、オーケストラも、すべてメルドーが創り上げる音楽の一部として機能している。全体的に刺激は少なく、落ち着いた楽曲と演奏ながらムード・ミュージックに陥っていないのは見事、と言いたいところだけれどメルドーの感性はムード・ミュージックになれないとうのが本当のところかもしれない。メルドーらしさに貫かれているという評価は、言い換えると意外性は少ないという言い方もできる。一方で順当に発展させた彼の音楽性を骨までしゃぶり尽くしたい向きには聴きごたえがあるはず。本作のような作り込んだ方向に向かわせた理由は、前作のライヴで演奏の自由さを見せつけた反動なんだろうか? もっとも、作り込んだと言っても型に嵌めたというよりは、アイディアに時間をかけて練りに練ったと思えるもので発想は自由奔放。いずれにしても、前作と本作、どちらも楽しめる人こそが真のメルドーの理解者に違いない。(2010年3月20日) | ||
| Live In Marciac | ||
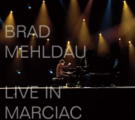 曲:★★★☆ 演奏:★★★ ジャズ入門度:★ メルドー入門度:★★ 評価:★★ |
[Recording Date] 2006/8/2 Disc 1 [1] Storm [2] It’s All Right with Me [3] Secret Love [4] Unrequited [5] Resignation [6] Trailer Park Ghost [7] Goodbye Storyteller (for Fred Myrow) [8] Exit Music (for a Film) Disc 2 [9] Things Behind the Sun [10] Lithium [11] Lilac Wine [12] Martha My Dear [13] My Favorite Things [14] Dat Dere Disc 3 (DVD) [1] Storm / It's All Right With Me [2] Secret Love [3] Unrequited [4] Resignation [5] Trailer Park Ghost [6] Goodbye Storyteller (for Fred Myrow) / Exit Music [for a Film] [7] Things Behind The Sun [8] Lithium [9] Lilac Wine [10] Martha My Dear [11] My Favorite Things |
Brad Mehldau (p) |
| 他の項目でも書いている通り、僕はバンド、コンボといったグループでの音楽を好んで聴いている。より具体的に言うならば3人以上で、その組み合わせの妙で成立している音楽が好き。デュオやソロはほとんど聴かないし、CDもほとんど持っていない。キース・ジャレットの 「The Koln Concert」にも何も感じないというソロ不感症。でも、大好きなブラッド・メルドーのピアノならイケるかも・・・そう思って買ってみた。う〜ん、やっぱりダメ。すぐに飽きる。しかも2枚組の100分越えというボリューム。もともとピアノが特別好きなわけでもないということもあるかもしれない。だから、いつものようにしたり顔してこのアルバムについて語ることができない。残念。[14] を取り上げたのはかなり意外。でも。これもそれほど面白く料理できていない。 (2011年5月14日) 歳を重ねたことでソロやデュオも楽しめるようになってきた今聴くと、それなりに楽しめる。でも、ジャズのピアノ・ソロはまだ面白さがもうひとつわからない。クラシックのピアノ・ソロは聴けるんだけれど。(2018年10月23日)。 |
||
| Ode | ||
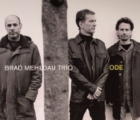 曲:★★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★ メルドー入門度:★★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 2008/11/17 2011/4/19 [3][8][10] [1] M.B. [2] Ode [3] 26 [4] Dream Sketch [5] Bee Blues [6] Twiggy [7] Kurt Vibe [8] Stan The Man [9] Eulogy For George Hamson [10] Aquaman [11] Days Of Dibert Dalaney |
Brad Mehldau (p) Larry Grenadier (b) Jeff Ballard (ds) |
| 「Day Is Done」以降、同じトリオでライヴ盤をリリースした後は、ソロ(これもライヴ)、オーケストラを導入した「Highway Rider」と活動が推移、トリオ編成でのチャレンジはしばらく横に置いておこうという感じに思えたところにまたこの鉄壁トリオでの音源をリリース。間が開いているように見えて実は3曲を除くと2008年の録音と3年以上も前、つまり「Highway Rider」の前のセッションが大半を占めているので、リリースの間隔ほどは音楽的なブランクはない。いろいろやってみても結局はトリオに戻ってくるところからすると、やはりメルドーはトリオこそが自分のホームだと思っているようにも見える。曲は「Day Is Done」とは変わって全曲オリジナル。やはり全曲オリジナルだった「House On The Hill」にはやや重苦しさを感じるけれど、今回はオリジナルだけでも妙な重さもなく楽しめる。結局僕の場合はジェフ・バラードが作るビジー感が聴けるだけで楽しめてしまうということのようだ。スタジオ録音のせいかジェフの小技もたっぷり堪能できる。タイトでクリスピーなドラムだとラリー・グラナディアの太いベースの弾み具合とのバランスもちょうどよい。メルドーのピアノはいつもどおりのやや屈折した感性を感じさせるメロディとフレージングで、いつも以上に右手と左手のバランスを考えて演奏しているように感じる。いずれにしても4ビートは少なく、昔ながらのジャズ・ピアノ・トリオとは一線を画すオリジナリティ。ビル・エヴァンス・トリオ的な、見るからに自由度の高いインタープレイとも違い、団結して進んでいるように見えて塊感の中で緻密な絡みがあるというタイトなスリル感が素晴らしく、その魅力は益々輝きを増すばかり。曲も演奏も、一貫性を持ちながら演奏の質としては幅広いという、言葉にするのは簡単でも実際には難しそうなことを普通にやってしまっていてトリオとしての成熟度が高まっていることも実感できる。マイケル・ブレッカーが亡くなって6ヵ月後に書いたという[1]がベスト。映画「イージーライダー」にインスパイアされて作ったという、[9]のインプロヴィゼーション的な展開も聴きどころ。(2012年4月7日) | ||
| Where Do You Start | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★ メルドー入門度:★★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 2008/11/17 [3][4][7][8][10] 2011/4/19 [1][2][5][6][9][11] [1] Got Me Wrong [2] Holland [3] Brownie Speaks [4] Baby Plays Around [5] Airegin [6] Hey Joe [7] Samba e Amor [8] Jam [9] Time Was Told Me [10] Aquelas [11] Where Do You Start? |
Brad Mehldau (p) Larry Grenadier (b) Jeff Ballard (ds) |
| 「Ode」と対になる作品として語られているこのアルバムは、それもそのはず、録音日が同じ2008年11月17日と2011年4月19日のセッション。ただし、こちらは2011年のセッションが多めの構成になっている。2012年7月の東京公演では、ノリやスピード感は皆無で、掴みどころのない伸縮自在なスタイルでじっくりと聴かせるステージに終始した演奏だったんだけれど、それに近いムードがある。よって「Ode」と比べるとキレやメリハリよりも、ややダークで落ち着いた演奏が多い。新しい2011年のセッションが多いからだとしたら、それが近年のメルドーの志向ということなのかもしれない。こういう演奏だと、個人的にはジェフ・バラードがもったいない気がしてしまう。もちろんそれでも全体の演奏の質は申し分ない。全曲オリジナルだった「Ode」とは異なり、[8]を除いてはすべて他人の曲を幅広く取り上げている。有名なジャズ・スタンダードである[5]は10年くらい前のメルドー的センスが良く出ていて面白い解釈。一方で[6]は曲そのものが持つ漂う雰囲気を安易に利用して二流ピアニストが客に媚びてやっているかのようで面白くない。他の曲の原曲は一般的には有名とは言い難く、安易にジャズ・スタンダードや有名曲でお茶を濁してなるものかというメルドーのひねくれた性格が出たものと思える。とはいえ、全編メルドーならではの演奏がギッシリ詰まっているので、曲はどうでも良いのかもしれない。(2012年10月8日) | ||
| Mehliana: Taming The Dragon | ||
 曲:★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★ メルドー入門度:★ 評価:★★★ |
Released in 2014 [1] Taming The Dragon [2] Luxe [3] You Can't Go Back [4] The Dreamer [5] Elegy For Amelia E. [6] Sleeping Giant [7] Hungry Ghost [8] Gainsbourg [9] Just Call Me Nige [10] Sassyassed Sassafrass [11] Swimming [12] London Gloaming |
Brad Mehldau (Key, p, voice) Mark Guiliana (ds. electronics) |
| ソロ、ピアノ・トリオ活動、パット・メセニーとのコラボ、ストリングス付き抒情詩(「Freedon Rider」)などをやってきて、ピアノ弾きとしてはもうチャレンジングと思えることがなくなってきたんだろうな、というのが1度聴いたあとの感想。ピアノはほとんど登場せず、シンセ(ムーグっぽいアナログ音多数)、エレピが中心の音使いは「メルドー初のエレクトリック・アルバム」の看板通り。とはいえ、シンセもエレピも70年代に流行った楽器で新鮮というよりはむしろ懐古的な音であり、つまりはその中で何ができるかということにチャレンジしたかったんでしょう。エレピのフレーズはピアノの延長、というかそのままピアノで弾いたらいつもの演奏とさほど違わず、かつてのチック・コリアのようにアコースティックとエレピの二面性は感じられない。むしろ、ピアノの延長として弾くことができないシンセの使いこなしの方が面白味を感じるし、結構使いこなしている印象。[5]ではアンビエントなサウンドで構成された曲で方向性はまったく違うものの冨田勲が頭をよぎったりもする。ドラマーとのデュオでどこまでバリエーション展開できるかという課題は、最小限の登場に留めたピアノを効果的にアクセントとして使うなどの工夫でクリア。ドラマーのマーク・ジュリアナは細かいスネアワークを中心としたプレイで確かなテクニックを伺わせる。シンバルを控えめかつバランス良く使い、巧みに空間を埋めるなどサウンドの一角を担う重要な役割をこなしていて非凡なセンスを感じる。全体に、決して熱く弾けはしない根暗なサウンドという意味では従来のメルドーの音楽と何ら変わらないと言えるけれど、表面的な音は当然別物で、麻薬的にハマる人と環境音楽にしか聴こえない人と評価が大きく別れると思われる。それでもメルドーが作ったものであれば、(好みは抜きにして)音楽のレベルとしては流石というレベルには仕上がっていると思う。僕のように過剰なほどCDを所有している音楽リスナーが、選んで繰り返して聴くCDは「そのCDでしか聴けない何か」があるからで、僕はメルドーのピアノ・トリオ作品の多くにその「何か」があるから聴いている。ではこのアルバムにその「何か」を感じるかと訊かれると、やや答えに困ってしまう。現時点ではメルドーの知名度と物珍しさから聴かれているであろうこのアルバムは、10年後にどう聴かれているかが最終評価ということになるでしょう。(2014年3月8日) | ||
| Blues And Ballads | ||
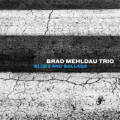 曲:★★★★☆ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★★☆ メルドー入門度:★★★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 2008/11/17 [3][4][7][8][10] 2011/4/19 [1][2][5][6][9][11] [1] Got Me Wrong [2] Holland [3] Brownie Speaks [4] Baby Plays Around [5] Airegin [6] Hey Joe [7] Samba e Amor [8] Jam [9] Time Was Told Me [10] Aquelas [11] Where Do You Start? |
Brad Mehldau (p) Larry Grenadier (b) Jeff Ballard (ds) |
| 2012年以来となるお馴染みメンバーによるピアノ・トリオ・アルバム。エレキに挑戦したメルドーは、ツアーではピアノ・トリオの活動も継続してたため、一部で表現されているようなReturn(戻ってきた)という意味合いはほとんどなく、ピアノ・トリオが活動の基幹であることに変わりはないように思う。従って、エレキを通して何が変わったかという観点で聴くのは深読みしすぎ。さて、今回はブルースとバラードというベタなテーマで来た。「夜に聴くブラッド・メルドー」と言っても差し支えない静かで落ち着いた選曲、演奏になっている。とはいえ、選曲に最近の(そして取り立てて素晴らしいとも思えない)ポール・マッカートニーのジャズ・ヴォーカル・アルバムから[7]を持ってきたり、[6]の中盤をブルースにして後半をメルドー流に崩してしまったり、演奏の捻り方も相変わらずでファンならニヤリとできるものになっている。一方で、[4]のようにベタベタないかにもピアノ・トリオ・ジャズというオーソドックスな演奏が入っているのは、ヒネり過ぎなメルドーはどうも、という人にも馴染みやすいかも。タイトルで想像するイメージに相違ない中身でメルドー作品としては身構えずに聴ける、良い意味で肩の力が抜けたアルバム。疲れているときに聴けるメルドーという意味では初期の作品以来で、それでも表現は当然より円熟したものになっている。通して56分という収録時間も重さがなくて良い。(2016年6月11日) | ||
| Chris Thile & Brad Mehldau | ||
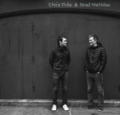 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★ メルドー入門度:★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 2015/12/30, 2016/1/2,3 Disc 1 [1] The Old Shade Tree [2] Tallahassee Junction [3] Scarlet Town [4] I Cover The Waterfront [5] Independence Day [6] Noise Machine Disc 2 [1] The Watcher [2] Daughter Of Eve [3] Marcie [4] Don't Think Twice, It's All Right [5] Tabhair Dom Do Lamh |
Chiris Thile (vo, mandolin) Brad Mehldau (p. vo) |
| 恐らくあまり知られていないであろうマンドリン奏者でヴォーカリストのクリス・シーリーとの異色デュオ。ボブ・ディランやジョニ・ミッチェルのカバー、シーリーとメルドーの共作、個々のオリジナルといった素材にバラエティがありつつも、基本はシーリーの素朴なヴォーカルとマンドリンがメインの音楽になっている。この素朴さが結構イイ。スリルやエキサイトメントとは無縁で、格調高さやシリアスさといった要素もなく、ただ素直に気持ちよく心を委ねる音楽になっている。裏方に回ってもメルドーらしさは隠しようもなく、ジョシュア・レッドマンとのデュオのときのような予想範囲内のものではない面白さがあり、リラックスして素朴な歌を味わうための音楽にメルドー色が乗った音楽として楽しめる。Disc 1が34分、Disc 2が30分の収録時間とCD 1枚で収まるにもかかわらず2枚に分けている理由はよくわからない。別々に楽しんでほしいということ?(2018年3月18日) | ||
| After Bach | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★ メルドー入門度:★★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 2017/4/17-20 [1] Before Bach: Benediction [2] Prelude No. 3 in C# Major from The Well-Tempered Clavier Book I, BWV 848 [3] After Bach: Rondo [4] Prelude No. 1 in C Major from The Well-Tempered Clavier Book II, BWV 870 [5] After Bach: Pastorale [6] Prelude No. 10 in E Minor from The Well-Tempered Clavier Book I, BWV 855 [7] After Bach: Flux [8] Prelude and Fugue No. 12 in F Minor from The Well-Tempered Clavier Book I, BWV 857 [9] After Bach: Dream [10] Fugue No. 16 in G Minor from The Well-Tempered Clavier Book II, BWV 885 [11] After Bach: Ostinato [12] Prayer for Healing |
Brad Mehldau (p) |
| ここ5年くらいでクラシックをよく聴くようになった。とはいえ、バッハはまだそれほど聴き込んでいない。バッハといえば格調高さがありながら素朴さと親しみのある古典音楽で、クラシックに馴染みのない人には少しハードルが高い印象があるかもしれない。そんなバッハにジャズ・ピアニストであるメルドーが挑んだ、というと何やら構えてしまうけれど、なんのことはない純度100%のメルドー・ワールドになっている。自作曲にバッハの曲を挟む構成で、そこに違和感はなく、クラシックのピアニストとはまったく異なるアプローチで料理されている。バッハは単なるきっかけ、素材でしかなく、ジャズ曲を採り上げるメルドーのピアノ・ソロよりもメルドーらしさがむしろ横溢しているところが面白い。ファンなら必ず満足できる、メルドー・ソロ作品の傑作に仕上がった。(2018年3月18日) | ||
| Seymour Reads The Constitution! | ||
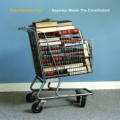 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★★ メルドー入門度:★★★★ 評価:★★★★ |
Released in 2018 [1] Spiral [2] Seymour Reads THe Constitution [3] Almost Like In Love [4] De-Dah [5] Friends [6] Ten Tune [7] Great Day [8] Beatrice [9] Middle Game (bonus track) |
Brad Mehldau (p) Larry Grenadier (b) Jeff Ballard (ds) |
| マーク・ジュリアナやクリス・シーリーといった異種音楽との共演企画、そして「Blues And Ballads」もある種の企画モノ(録音済みストックからそういう曲を集めただけだと思う)と捉えるならば、2012年の「Where Do You Start」以来となるメルドー・トリオのアルバム。録音日のクレジットはなく、いつの収録かはわからないものの、ここ4年以内あたりではないかと思う(演奏の内容からの推測)。もはや不動のメンバーと言って差し支えないこの3人になってから、ある時期にセッションを行い、使える素材が揃えばアルバムとして発売する形態を取っているようで、恐らくこのアルバムも同様な成り立ちでしょう。2005年あたり以前には、陰鬱さと、捻くれた演奏スタイル(それが魅力でもあった)が前面に出ていたものの、年齢と共に落ち着きを見せつつあると思わせたのが「Blues And Ballads」だった。そして久しぶりの直球トリオ・アルバムは、冒頭から「ああ、あのメルドーだ」と思わえる気だるさとヒネた感性を発揮、しかし、以前ほどのアクはなく、[4] エルモ・ホープ、[5] ビーチボーイズ、[7] ポール・マッカートニーの曲も軽快に料理。オーソドックスなフォービートでいかにもジャズ・ピアノ・トリオという曲もいくつかあって総じて聴きやすい。一方で、フリーでトリッキーな演奏が好きな人はオリジナルの[6]で溜飲を下げることもできる。良い意味で肩の力が抜けつつも、メルドー独自の感性もしっかりと聴かせるバランスがこのアルバムの売りか。(2018年6月24日) | ||
| Finding Gabriel | ||
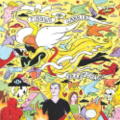 曲:★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 2017/Mar-2018/Oct [1] The Garden [2] Born to Trouble [3] Striving After Wind [4] O Ephraim [5] St. Mark Is Howling in the City of Night [6] The Prophet Is a Fool [7] Make It All Go Away [8] Deep Water [9] Proverb of Ashes [10] Finding Gabriel |
[1] Becca Stevens (voice) Gabriel Kahane (voice) Ambrose Akinmusire (tp) Michael Thomas (fl, as) Charles Pillow (ss, as, bcl) Joel Frahm (ts) Chris Cheek (ts, bs) Brad Mehldau (p, key) Mark Guiliana (ds) [2] Brad Mehldau (voice, key, p, ds) [3] Becca Stevens (voice) Gabriel Kahane (voice) Brad Mehldau (key) Mark Guiliana (ds) [4] Brad Mehldau (voice, key, p, ds) [5] Becca Stevens (voice) Gabriel Kahane (voice) Sara Caswell (vl) Lois Martin (viola) Noah Hoffeld (cello) Brad Mehldau: (voices, key, p) Mark Guiliana (ds) [6] Ambrose Akinmusire (tp) Michael Thomas (fl, as) Charles Pillow (ss) Joel Frahm (ts) Chris Cheek (bs) Brad Mehldau (key, p) Mark Guiliana (ds) [7] Becca Stevens (voice) Kurt Elling (voice) Brad Mehldau (key, p) Mark Guiliana (ds) [8] Becca Stevens (voice) Gabriel Kahane (voice) Sara Caswell (vl) Lois Martin (viola) Noah Hoffeld (cello) Brad Mehldau (p, key) Mark Guiliana (ds) [9] "Snorts" Malibu (voice) Kurt Elling (voice) Brad Mehldau (key, p, voice) Mark Guiliana (ds) Aaron Nevezie (Korg Kaoss Pad) [10] Brad Mehldau (voice, key, p, ds, per) |
| ピアノ・トリオは、メルドーの音楽活動の基軸になっているものの、ここ数年は他のミュージシャンとのデュオ活動も目立ち、特にジャズ系でない音楽への広がりを見せている。このアルバムもジャズの外の世界を見据えたもので、マーク・ジュリアナとの「Taming The Dragon」を下敷きに、より自由に、より緻密に音絵巻を作り上げた印象。他流試合をこなした成果なのか、電子系楽器やマーク・ジュリアナのビート感を自然に消化、効果的にトランペットやサックスも登場、自身のピアノもジャズ的なテイストよりは音楽の一部に徹している。部分的にはどこかで聴いたような(たとえばパット・メセニー・グループのような)サウンドとはいえ、全体を通してメルドーらしさに溢れ、アルバムとして通して聴ける流れがあり、バラエティ豊かな音楽表現と、バランスの良さも備えている。意外と言っては失礼だけれども完成度が高い。近年のメルドーのピアノ・トリオ作品は、質の高さは認めつつ、マンネリ化しているのは事実。その一方で、それ以外の活動はデュオか、ジャズに囚われない自己音楽の探求路線で後者は、正直言って未消化の印象は拭えなかった。このアルバムは筋が通っていて突き抜けた感がある。ある意味メルドーの最高傑作。(2019年11月25日) | ||