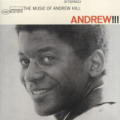ロック・ファンのためのジャズ案内のヘッダー
Rock Listner's Guide To Jazz Music
Andrew Hill
| Black Fire | ||
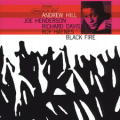 曲:★★★☆ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★ ヒル入門度:★★★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1963/11/8 [1] Pumpkin [2] Subterfuge [3] Black Fire [4] Cantarnos [5] TIred Trade [6] McNeil Island [7] Land Of Nod [8] Pinmpkin (alt take) [9] Black Fire (alt take) |
Joe Henderson (ts) Andrew Hill (p) Richard Davis (b) Roy Haynes (ds) |
| クセ者、アンドリュー・ヒルの初リーダー作。曲調もピアノもリズム感も既に個性が炸裂していてその存在感は既に他の一流ミュージシャンに引けを取らない。ここではジョー・ヘンダーソンのワン・ホーン編成で、そのジョーヘンのプレイがこのヒルの世界に見事にマッチングしていることがこのアルバムを成功に導いている要因。またこの後、競演が続くリチャード・デイヴィスの鋭利な斧のような太く鋭いベース、小刻みなビートを送り込むロイ・ヘインズのドラムの組み合わせがまたハマっている。この完成度と、ワン・ホーン・カルテットというオーソドックスな編成とが相まってヒルの作品としては一番聴きやすく仕上がっているところが特徴。ハード・バップはもちろん新主流派ジャズとも距離を置きつつ、フリー・ジャズでもなく、しかもクール。そんな革新的なヒルのイメージが良く出ているという意味でも最初の1枚としてお勧めできる。(2007年4月8日) | ||
| Smoke Stack | ||
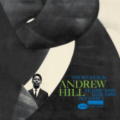 曲:★★☆ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★ ヒル入門度:★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1963/12/13 [1] Smoke Stack [2] The Day After [3] Wailing Wail [4] Ode To Von [5] Not So [6] Verne [7] 30 Pier Avenue [8] Smoke Stack (alt take) [9] The Day After (alt take) [10] Ode To Von (alt take) [11] Not So (alt take) |
Andrew Hill (p) Richard Davis (b) Eddie Khan (b) Roy Haynes (ds) |
| アルフレッド・ライオンがご執心だった独特のタイム感覚とメロディ展開が特徴のアンドリュー・ヒルは、ホーン入りコンボをその強い個性で染め上げてしまうリーダーとしてその手腕が発揮されていることが多く、ピアノ・トリオによるものが少ない(というか、ないかも)。そういう意味で、このアルバムはヒルのピアノを純粋に堪能できる貴重な作品で、しかしトリオではなく2ベース編成であるところに安易なピアノ・トリオでは済ませたくないという意欲が見える。小刻みで直線的なスネアワークをふんだんに使うヘインズと、2ベース編成のために、いつも以上にミュート気味の音を繰り出すリチャード・デイヴィスのリズムに乗り、リリカルなメロディ展開になりかけるところをあえて外し、時に無調的、そしてパーカッシヴなヒルのピアノが奇妙によじれた不安定感を醸しながら舞う。もちろんオーソドックスなフォー・ビートなどあるはずもなく独特のタイム感はここでも音楽の中心を成している。ピアニストとしてのヒルの個性が濃厚に出ているだけに、ヒルのフィーリングを受け付けない人には逃げ場がないとも言えるクセのあるアルバム。この人の辞書に予定調和という言葉はない。(2006年11月20日) | ||
| Judgement | ||
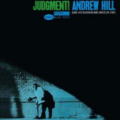 曲:★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★ ヒル入門度:★★★★★ 評価:★★★★☆ |
[Recording Date] 1964/1/4 [1] Siete Ocho [2] Flea Flop [3] Yokada Yokada [4] Alfred [5] Judgement |
Andrew Hill (p) Bobby Hutcherson (vib) Richard Davis (b) Elvin Jones (ds) |
| アンドリュー・ヒルを聴いたことがない人にその音楽性を言葉で説明するのは難しい。ひとことで言ってしまうと音楽、演奏共に不思議な感覚に満ちていたもの、となってしまう。ヒルのピアノは洗練されており、無調っぽさを漂わせながらもヒルなりの法則性があって前衛的ともまた違う美しさがある。ここではボビー・ハッチャーソンが加わることでよりクールなムードがアルバムの性格を決定付けている。この涼しげな2人の世界に、エルヴィンとリチャード・デイヴィスは変拍子で重力級のリズムを遠慮なく叩き込む。モダン・ジャズ・カルテットと同じ編成から生まれている音楽とはにわかに信じがたいほど異質だ。尚、ボビー・ハッチャーソンは後にこのレコーディングはかなり苦労したと述懐しているけれど、ここまでオリジナリティの高い音楽を創ることはやはりかなりの苦労を伴うものなんだなあと妙に納得してしまった。ヒルは「普通ならこういうセオリーで展開させる」ことをあえて外す「外しの美学」で個性を作ってきた人だと思うし、このアルバムでもそういった性格が最大限に発揮されている。(2006年9月10日) | ||
| Point Of Departure | ||
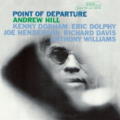 曲:★★★☆ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★ ヒル入門度:★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1964/3/31 [1] Refuge [2] New Monstery [3] Spectrum [4] Flight 19 [5] Dedication |
Kenny Dorham (tp) Joe Henderson (ts) Eric Dolphy (as, fl, bcl) Andrew Hill (p) Richard Davis (b) Tony Williams (ds) |
| メンバーが3人重複していることもあり、エリック・ドルフィーの「Out To Lunch」と相関関係にあるとされる本作。しかし、まったく似ていない。確かにドルフィーはいつもどおりの自由奔放なアドリブを繰り広げ、リチャード・デイビスも太く突き上げるベース・ラインを刻んでいる。しかし、トニーのドラムの疾走感を前面に出した直線的なビートが「Out To Lunch」と違うところ。とはいえ、このリズム・セクションなら凡庸なタイム感覚になるはずもなくそのタイム感覚の異質感こそが最大の相違点。一般的なイメージでは場違いな印象のケニー・ドーハムは、ここでは周囲のメンバーにまったくヒケを取らない尖鋭的によじれたプレイを聴かせていてミス・マッチな感じは皆無、むしろ「Black Fire」で好演していたジョー・ヘンダーソンの方が居心地が悪そうな印象。このスペシャルな顔合わせにヒルの個性はまったく沈むことなく自身の世界で支配している。演奏家の個性で音楽が決まるのではなくリーダーの音楽性でサウンドが決まるという極めて当たり前かつ重要なことを再認識させてくれる、まさにワン・アンド・オンリーの音楽性を持ったアルバム。ただし、この人数でこの組み合わせだからこそ起こったケミストリーというものは特に感じられず、良い素材(プレイヤー)だけれど組み合わせにくいものをヒルの音楽性でつなぎ合わせて使いこなしたという印象がなきにしもあらずで、バランス感が悪いという世評はそのことを指しているのかもしれない。(2007年12月16日) | ||
| Compulsion!!! | ||
 曲:★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★ ヒル入門度:★★☆ 評価:★★★★☆ |
[Recording Date] 1965/10/8 [1] Compulsion [2] Legacy [3] Premonition [4] Limbo |
Freddie Hubbard (tp, flh) John Gilmore (ts, bcl) Andrew Hill (p) Cecil McBee (b) Joe Chambers (ds) Renaud Simmons (conga) Nadi Qamar (per) |
| 革新的ミュージシャンなら一度は通らなければならない(?)集団フリー・ジャズをアンドリュー・ヒル流に実践したのがこのアルバム。ジョー・チェンバースの推進力あるドラムにコンガとパーカッションを絡ませ、どこか呪術的な混沌ムードを演出、そこに乗るヒルのピアノはいつもながらの浮遊感だけでなく時にセシル・テイラーを彷彿とさせる力強いタッチまで聴かせるところが他のアルバムと少し違うところ。僕はヒルのピアノはフリー・ジャズとも距離を置いているところが個性だと思っているので、その点でここでの演奏は彼にしてはやや凡庸であるようにも思う。そんな激しいリズム隊に負けじとフレディ・ハバードとジョン・ギルモアも前衛的なプレイで応戦。各人の演奏の方向性がしっかりと一致していて音楽としてまとまりがある。ただし。この時代のフリー・ジャズのトレンドで方向性の一致であり、ヒルのリーダーシップ感はそれほど濃くはない。それでも、これだけの人数でヒルにしては騒々しい音楽を演っていながら、ピアノは決して埋もれず曲にも独特のメロディが広がっているところはさすがと言うべきか。目いっぱい力んでいるセシル・テイラーに対して、この種のフリー・ジャズをやってもどこかクールさがあるところもヒルの個性。(2007年3月26日) | ||
| Grass Roots | ||
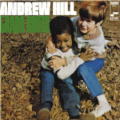 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★ ヒル入門度:★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1968/8/5 [1]-[5] 1968/4/19 [6]-10] [1] Grass Roots [2] Venture Inward [3] Mira [4] Soul Special [5] Bayou Red [6] Mc [7] Venture Inward (First Version) [8] Soul Special (First Version) [9] Bayou Red (First Version) [10] Love Nocturn |
[1]-[5] Lee Morgan (tp) Booker Ervin (ts) Andrew Hill (p) Ron Carter (b) Freddie Waits (ds) [6]-[10] Woody Shaw (tp) Frank Mitchell (ts) Jimmy Ponder (g) Andrew Hill (p) Reggie Workman (b) Idris Muhammand (ds) |
| 妙な明るさを持つ[1]のテーマを聴いただけではにわかにアンドリュー・ヒルのアルバムだと思う人は少ないに違いない。ピアノのバッキングが常識的なコード使いでヒルにしては凡庸、ソロになると音の選び方にようやくらしさが出てくる。全体的にあまり尖った感じがないのは、どういう経緯で参加したのかがよくわからないロン・カーターのいつも通りのスマートなベースに負うところが大きい。尖ったところがなければリー・モーガンがハマるかと思えばそうでもなく、ブッカー・アーヴィンの安定したマイペースぶりと、フレディ・ウェイツの重くてキレのあるドラムがヒルのいつもの世界に合っているところでなんとか落ち着きを保っている。[3]では、まるで"Recado Bossa Nova"のホロルド・メイバーンのようなラテンのリズムをヒルが刻む珍事が発生(しかし明るくないというところがヒルたしい)、[4]はモーガンのリーダー・アルバムに入っていて良いようなポップな曲で、こうなったら番外編アルバムとしてフレンドリー路線でやってくれればいいかと思っていると[5]で風変わりなテーマを持つシリアスな曲が登場し、しかしここでのソロがヒルにしては凡庸でベースのせいでハービー・ハンコックのアルバムを聴いている気分になる。全体的に興味深い顔ぶれではあるんだけれど、モーガンはあまり良さが出ていないし、ロン・カーターは自分のカラーが強すぎてこれもヒルの音楽に合っていないというなんとも微妙なアルバムになっている。[6]以降は別日のセッションでメンバーも全員異なっている。同じ曲が3曲あり、お蔵入り扱いのセッションと思われ、こちらもあまりアクが強くないレジー・ワークマンのベースが全体のムードを平凡にしている。ギターが特に面白みを出しているわけでもなく全体のデキはあまり良いとは言えないものの、トランペットに関してはモーガンよりウッディ・ショウの方はヒルの音楽に合っていると思わせる。(2024年3月24日) | ||