ロック・ファンのためのジャズ案内のヘッダー
Rock Listner's Guide To Jazz Music
Herbie Hancock
| Takin' Off | ||
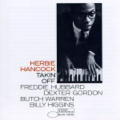 曲:★★★☆ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1962/5/28 [1] Watermelon Man [2] Three Bags Full [3] Empty Pockets [4] The Maze [5] Driftin [6] Alone And I |
Freddie Hubbard (tp) Dextor Gordon (ts) Herbie Hancock (p) Butch Warren (b) Billy Higgins (ds) |
| マイルス・クインテットに加入する前のハービー・ハンコック、初のリーダー・アルバム。若手中心のメンバーでも後の作品とは異なってずいぶんリラックスした曲と演奏で占められており、しかし全体の雰囲気は50年代のジャズとは明らかに異なった新しさがある。ハバードはドナルド・バードのようなスタイルで力みのない控えめな演奏に終始。この中ではベテランのデクスター・ゴードンは、これまたずいぶんと力みのない普通のプレイ。ヒギンズはスネアの音数こそ多いものの疾走間は控えめと、あくまでもリーダーがピアニストであることを心得たかのような抑えた演奏。ハンコックは既に自己のスタイルを確立しており、後の洗練されたスタイルと親しみやすいシンプルでファンキーなスタイルが共存。それは曲にも出ていて、[1][5]のような分かりやすい曲と、後に通じるシャープでフレッシュな感覚のスタイル、いわば建前と本音が共存した格好。こういう目配りが効くところがハンコックの良いところでもあり、悪いところでもある。(2006年11月15日) | ||
| Inventions And Dimensions | ||
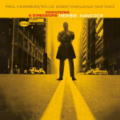 曲:★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1963/8/30 [1] Succotash [2] Triangle [3] Jack Rabbit [4] Momosa [5] A Jump Ahead |
Herbie Hancock (p) Paul Chambers (b) Whillie Bobo (ds,timbales) Osavaldo "Chihuahau" Martinez (conga, bongo, guiro) |
| ハンコックは作曲、編曲の才能に長け、バンド・リーダーとしての資質が高いこともあってピアノ主体の作品が少ない。そういう意味でこのアルバムは珍しい。しかしそこはハンコック、ただのピアノ・トリオでは終わらない。常識的に考えるとコンガなどの打楽器が入るとラテン系のムードを、そして既に時代遅れの感もあるチェンバースの起用はオーソドックスなものを狙ったのかと勝手にイメージしてしまう。しかし、ここで展開される音楽は、ラテンのニオイがする曲はあってもラテンを主軸にしたものではなく、オーソドックス路線を狙ったのでもない独特のピアノ・ジャズで、ハンコックのプレイは緊張感の高い先進的でなものが多く、曲もオーソドックスなジャズとは一線を画している(特に前半の3曲)。これだけのオリジナリティ溢れるジャズ・ピアノ作品をこのメンバーとこの編成で実現させた才能はもっと評価されてもいいんじゃないだろうか。ハンコックは(デクスター・ゴードンだったかドナルド・バードだったかに)「アルバムの半分はわかりやすい曲を、半分は自分がやりたい曲を」とアドバイスを受けたらしく、それを受け入れてどのアルバムにもわかりやすい曲が入っているけれど、このアルバムは例外ですべて自分のやりたいことで押し切っている。それ故に聴きやすいとまでは言えず、話題にならないのは親しみやすさに欠けているからに違いない。ハービー・ハンコックなんて大衆的でつまらないと思っている人にこそ聴いてほしい高品質盤。ある意味ハンコックのピアノのベスト。(2006年8月5日) | ||
| Empyrean Isles | ||
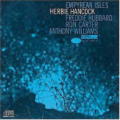 曲:★★★☆ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1964/6/7 [1] One Finger Snap [2] Oliloqui Valley [3] Cantaloup Island [4] The Egg |
Freddie Hubbard (tp) Herbie Hancock (p) Ron Carter (b) Tony Williams (ds) |
| U2によるカヴァーで知られる[3]はポップでリラックスしたムードのシンプルなエイト・ビート楽曲で個人的にはこのアルバムの中では息抜き的扱い。[1]はタイトルのイメージ通りスピード感とキレのある新主流派らしいスタイリッシュな演奏でこれこそが本作のハイライト。エンディングのトニー・ウィリアムスの抑揚が効いたドラム・ソロがいつもながらに素晴らしい。[4]はまるでプログレッシブ・ロックのような構成で演奏もかなりアブストラクト。新主流派ハンコックの音楽性が良く出ているという意味では「Maiden Voyage」に匹敵し自由度という点では上回っている。トランペットのみのワンホーンにもかかわらず全体に薄っぺらな感じがしないのはハバードの演奏の素晴らしさもさることながらトニーのドラムが空間を巧く埋めているから。このドラムを堪能するためにもスピーカーで大音量で聴くことを推奨。4曲、35分程度の短い収録時間なので一気に聴けるのも魅力。(2006年9月10日) | ||
| Maiden Voyage | ||
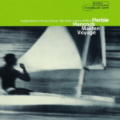 曲:★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★☆ 評価:★★★★☆ |
[Recording Date] 1965/3/17 [1] Maiden Voyage [2] The Eye Of The Hurricane [3] Little One [4] Survival Of The Fittest [5] Dolphine Dance |
Freddie Hubbard (tp) George Coleman (ts) Herbie Hancock (p) Ron Carter (b) Tony Williams (ds) |
| 作編曲やバンド・リーダーとしての評価の方が圧倒的に高いハービー・ハンコックを象徴するアルバム。同じ編成の「Takin' Off」は演奏者の音こそフレッシュだったものの、意図的にわかりやすい曲を入れたりしてやや聴き手に媚びた部分が見られるのに対し、ここでは自分のやりたい音楽を新進気鋭のクインテットで思い切りやってみたという印象。サウンドはよりソフィスティケイトされ、 わかりやすく、しかし安易でもなく、[4]のようにフリー・ジャズ的な展開まで視野に入れた非常に高度なもの。ハバードのトランペットは饒舌だしリズム・セクションは鉄壁かつ自由自在、ハンコックのピアノは瑞々しくも流麗でバッキングを含め聴き応えがある。特筆すべきはテナー・サックスがジョージ・コールマンであること。僕のような後追いのリスナーは、マイルス・クインテットにショーターが加入する前に録音したのかと思いそうになるけれど、65年録音ということは「E.S.P.」の後、つまりハンコックはあえて前任者のコールマンを選んだことになる。確かにショーターはサウンド全体にまで影響を与えるタイプでマイルス・クインテットに似すぎてしまう可能性が高く、ハンコックのカラーを出すのに支障を来すかもしれない。ここではコールマンこそが適任だとショーター・ファンの僕でも思う。全体に高度な演奏でありながら聴き手を突き放すところがないのはハンコックのバランス感覚から来ていると思うし、それもコールマン起用の一因かもしれない。それから「Empyrean Isles」に続いて本作もベースの音量を抑えた音のバランスになっているのはロン・カーターのフレージングのせいだけでなく、ベースによる過剰な躍動感(ハードバップ的なグルーヴと言い換えてもいい)をハンコック、あるいは彼のサウンドをよく理解しているプロデューサーが望んでいなかったからと予想する。ちなみに僕が所有しているCDはルディ・ヴァン・ゲルダー・リマスタリングのアメリカ盤なんだけれど、ヒスノイズが多く特に低音の輪郭がぼやけていてとても65年の録音とは思えない音質の悪さ。国内盤はどうなんでしょう?(2006年11月20日) ハイレゾ音源をHDtracksからダウンロードして聴いてみた。入手したのは 96KHz/24bit の音源。同時期リリースのブルーノート音源は、新たにリマスタリングしなおしたことによって大幅に音質向上を果たしているため、このアルバムにも当然期待が高まる。結果から言うとこれも別物と言えるくらいのクオリティアップで元が悪かっただけにその上昇幅は大きい。音像ひとつひとつが明確になり、ザラついていた管楽器やピアノの音は絹のように滑らかになり、シンバルの響きも自然になった。他のブルーノート・シリーズ同様に、楽器の音の配し方(左にトランペット、右にサックスとドラムというように片側に寄せている)まで変えていて音場感がまるで違っているところは賛否があるかもしれない。(2012年8月4日) |
||
| Speak Like A Child | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1968/3/6 1968/3/9 [1] Riot [2] Speak Like A Child [3] First Trip [4] Toys [5] Boodbye To Childhood [6] The Sorcerer |
Herbie Hancock (p) Ron Carter (b) Mickey Roker (ds) Thad Jones (fluegelhorn) Peter Phllips (bass tb) Jerry Dodgion (alt flute) |
| ピアノ・トリオは馴染みのある編成、言い換えるとよくあるフォーマットであると言える。耳当たりが良いためか日本では特に人気が高い。しかし、良く考えてみるとメロディを奏でることができるのがピアノだけというのはピアニストの力量が試される過酷なフォーマットであるとも言える。だから、どんなピアニストでも一度はこう考えるのではないだろうか。「テーマだけでも管楽器が入ればなあ」「バックでハーモニーを入れてくれれば曲を自由に盛り上げられるのに」。そうはいっても、そんなことのために伴奏してくれるホーン奏者を揃えるのは手間もお金もかかるし、実際にそれを実行するのは勇気がいることであろうと想像できる。しかし、それを実行してしまったのが本作。あくまでもピアノ・トリオ編成が基本であり、ホーンは柔らかいハーモニーを補助的に加える(フリューゲルホルンにベース・トロンボーンとフルートという編成から確信的)に留まっているけれど、このアンサンブルが実に効果的に曲に彩りを与えている。そのおかげか、ここでのハンコックのピアノは僕が知る限りもっとも美しくリリシズムに溢れてた演奏を聴かせている。高めの音程を駆使したロン・カーターのベースも素晴らしい。また意外と見落としがちなのがミッキー・ローカーの控えめかつあまり特徴のないドラムで、これによってよりハンコックのピアノがより引き立つようになっている。トニー・ウィリアムスだったらこのアルバムの美しさは形を変えてしまっていたでしょう。(2007年2月17日) | ||
| Head Hunters | ||
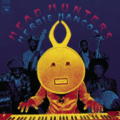 曲:★★★★☆ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1973/Fall [1] Chameleon [2] Watermelon Man [3] Sly [4] Vein Melter |
Bennie Maupin (ts, ss, bcl, saxello, fl) Herbie Hancock (key) Paul Jackson (b) Harvey Mason (ds) Bill Summers (per) |
| シンセベースが刻むリフに重いドラムが乗るイントロだけで、ファンクな世界へ。ハンコックをジャズ・ピアニストとして捉える向きには拒絶反応が出るか、いやこの人は同名異人だと自分に言い聞かせるしかない。でも思い出してみると「Takin' Off」は実にファンキーな味わいがあったではないか。それを時流に乗ったスタイルで表現してみたにすぎず、ハンコックの根底にあるものは何も変わっていないことに気づくはず。このアルバムを軽く扱う人も少なくないだろうけれど、演奏もアレンジもよく練られていて内容は実によくできている。70年代のファンクは普遍的なテイストがあるために今聴いても古びた感じになっていないところがまた幸い。ハンコックはクラヴィネットとエレピを縦横無尽に駆使してサウンドを創造、それを安定したリズム・セクションが支える構造。しかし、[3]の途中からハイパー・フュージョン的に疾走、ショーターもかくやというモウピンのソプラノ・サックスが炸裂する様は実にスリリング。こういう音楽を、しかもこの品質でシレっと作ってしまうハンコックという人の才能恐るべし。(2008年6月25日) | ||
| Herbie Hancck Trio 81 | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1981/7/27 [1] Stablemates [2] Dolpine Dance [3] A Slight Smile [4] That Old Black Magic [5] La Mason Goree |
Herbie Hancock (p) Ron Carter (b) Tony Williams (ds) |
| ここ日本では、耳当たりの良いピアノ・トリオのジャズが大人気であるにもかかわらず「ハービーのピアノ・トリオに傑作はない」と言い切る人までいるほどこの人にはピアノ・トリオの印象がない。そんなハンコックの数少ないピアノ・トリオ・アルバムのひとつがコレ。相手はお馴染みのロン・カーターとトニー・ウィリアムスで新鮮味はなく曲の方もスタンダーや有名自作曲にロンとトニーのオリジナルという無難な構成。一言で言って聴きやすい。でもその分、意外性がなく、アイディアで勝負向きでない編成であるだけトリオとしての完成度を要求される。その点でやはりこのアルバムには特別な凄味は感じない。もちろんこの3人だから演奏のレベルは非常に高い。それでも何度も繰り返して聴きたくなるような引っ掛かりがないところを考えると、やはりハンコックのピアノ・トリオには傑作はないという評価には同意せざるを得ないという結論になってしまう。(2006年12月23日) | ||
| Herbie Hancck Quartet | ||
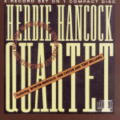 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1981/7/28 [1] Well You Needn't [2] 'Round Midnight [3] Clear Ways [4] A Quick Sketch [5] The Eye Of The Hurricane [6] Parade [7] The Sorcerer [8] Pee Wee [9] I Fall In Love To Easily |
Wynton Marsalis (tp) Herbie Hancock (p) Ron Carter (b) Tony Williams (ds) |
| お馴染みリズム・セクションに当時のニュー・スター、ウィントン・マルサリスを迎えたアルバム。このカルテットは81年にワールド・ツアーを敢行、締めとしてライヴ・アンダー・ザ・スカイ出演のために来日。そのときに東京で録音したのが本作。このときのハンコックは前日に「Herbie Hancck Trio 81」も録音していて要は気持ちが乗って充実期だったんでしょう。ここでもハンコックは独創的なピアノを聴かせているし、むしろホーンが入ることでバッキングにまわったときの実力を見せつけている。高めの音で浮遊するロンのベースも疾走感たっぷり。そしてトニーはバンバン叩きまくりで、わかっているとはいえこの3人は相当にハイレベルであると再認識。演奏の質としては V.S.O.P. と同じ類のもので、ここに当時19歳のウィントンがどう切れ込むかが聴きどころ。そのウィントンのトランペットは既に素晴らしい技巧を備えていることを見せつけ、このリズム・セクションを相手にワン・ホーンで対等に渡り合ってしまう。お馴染みの曲でも、マイルスやフレディ・ハバードとはまったく異なる個性でハイレベルな表現を見せるのだから凄い。[4]のような、形式がほとんどない自由度の高い曲でもその存在感が薄れることはない。ここまで絶賛しておいてナンですが、実は通して聴いてもどういうわけかあまり印象に残らないしアナログ2枚組のボリュームも僕にとってはちょっと重い。とはいえ今のウィントンがこの種の曲、音楽を演奏するとは考えられないし、そもそもハンコックやロン・カーターと競演することはまずないことを考えるとこの録音は貴重ではある。トランペットの音が少し弱々しく聴こえる録音がちょっと残念。(2007年1月8日) | ||
| The New Standards | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★★ 評価:★★☆ |
[Recording Date] 1995/6/14-16 [1] New York Minute (Don Henley) [2] Mercy Street (Peter Gabrial) [3] Norwegian Wood (The Beatles) [4] When Can I See You (Kenny Edomonds) [5] You've Got It Bad Girl (Stevie Wonder) [6] Love Is Stronger Than Pride (Sade) [7] Scarborough Fair (Simon & Garfunkle) [8] Thieves In The Temple (Prince) [9] All Apologies (Nilvana) [10] Manhattan (original) [11] Your Gold Theeth II (Steely Dan) |
Michael Brecker (tp) John Scofield (g) Herbie Hancock (p) Dave Holland (b) Jack DeJohnnette (ds) Don Alias (per) Woodwinds & brass ([2][3][6]) : Sam Riney (fl, alt-fl) Gary Herbig (bcl, fl) Gene Cipriano (oboe, English horn) William E. Green (fl, alt-fl) Lester Lovitt (tp, flugenhorn) Suzette Moriarty (French horn) Maurice Spears (btb) Strings ([2][3][4][6]): Lili R. Hayden (violin) Margaret R. Wootn (violin) Richard S. Greene (violin) Carmen L. Stone (cello) |
| ジャズのスタンダードと言われている曲は、基本的には50〜60年代に流行した庶民に親しまれていた歌(より具体的に言うとミュージカル)が多い。つまりジャズが最も輝いていた時代に誰もが知っていた曲がスタンダードになっている。ところが次第にオリジナル曲が重視され、有名曲を利用して演奏するスタイルから、曲も演奏も音楽性を追求するものが主流になり、流行歌とジャズの距離はずいぶんと遠いものとなってしまった。このアルバムは現代(90年代)の流行歌を取り上げて豪華メンバーでジャズを演奏するという、ありそうでなかった企画。お馴染みの曲をツワモノたちがメインストリーム・ジャズのスタイルで料理する、と言いたいところだけれど、まずアメリカ人の基準による選曲が微妙で日本人にとっては「誰でも知っている度」が低く企画の意味合いじたいが薄れてしまっているところが痛い。演奏はもちろん悪くはなく、むしろ熱演とも言えるけれど、これが現代のジャズというべきなのか根底の部分が燃えきっていないように感じてしまう。そういう意味でも極めてハービー・ハンコック的と言えるかも。個人的にはこういう企画はもっとやってもらいたいと思うけれど、これで打ち切りなところもハービー・ハンコック的かもしれない。(2007年1月26日) | ||
| The Quintet / V.S.O.P. | ||
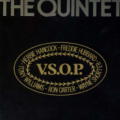 曲:★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1977/7/16 [1] One of a Kind [2] Third Plane [3] Jessica [4] Lawra [5] Darts [6] Dolores [7] Little Waltz [8] Byrdlike |
Freddie Hubbard (tp) Wayne Shorter (ts、ss) Herbie Hancock (p) Ron Carter (b) Tony Williams (ds) |
| ジャズを聴き始め、50年代のハード・バップに馴染んできたころに挑戦してみたのがこのアルバム。第一印象は「フォー・ビートなんだけどこれはジャズじゃない。気持ち悪い」というものだった。今、聴いてもそのときの印象はあながち外れていないような気がする。というのは、確かにフォー・ビート中心のアコースティック・ジャズであるんだけれど、ハード・バップはもちろん、60年代のジャズとも違うし電化した70年代初期のジャズ、フュージョンとも違っている。これらを通過したものであるために伝統的なジャズの形を借りているとはいえ曲調も各プレイヤーの演奏も明らかにこの時代のものならではの音、表現になっているから50年代のジャズとは根っこの部分から違っていて違和感を感じたとしても無理はない。書物によると V.S.O.P はアコースティック・ジャズの復権として大いにウケたことになっているけれど、保守的なジャズ・ファンは本当にこのサウンドを楽しむことができたんだろうかと僕は懐疑的になってしまう。たとえこのサウンドが合わなくても、電化ジャズやフュージョンに比べたら遥かにマシと思えるほどアコースティック・ジャズに飢えたリスナーがいたということだったんだろうか。そんな話は別にして、ここで繰り広げている演奏は相当ハイ・レベル。やはりこの5人の演奏は凄い。いたるところでインタープレイの応酬があり、それでいながら特定個人のエゴが突出することがないのは全員のミュージシャン・シップが高いからこそ可能なこと。個々で言うと特に凄いのがジャズの演奏と呼んで良いのかさえわからないムードすらあるハンコックの才気溢れるピアノと、縦横無尽、自由自在にリズムを創出するトニーのドラム。電気増幅されたロンのウッド・ベースも60年代とは一味違う(一般的には評判が悪い)。ハバードは相変わらず吹きまくっている曲はあるものの、フリューゲルホンを多用しているのでそれほど尖がった印象はない。あと、どうも V.S.O.P におけるショーターはフレーズそのものは十分にらしさを感じるものの存在感が薄いような気がしてしまう。尚、[4]ではハバードのフリューゲルホンとショーターのソプラノ・サックスのソロの同時進行という離れ業も聴ける。ある意味、今となっては時代の産物的な要素はあるものの、ある面では行くところまで行っているこのユニットはやはり賞賛に値する。(2006年11月21日) | ||
| Live Under The Sky / V.S.O.P. | ||
 曲:★★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★★ 評価:★★★★☆ |
[Recording Date] 1979/7/26 (Disc 1) 1979/7/27 (Disc 2) Disc 1 [1] Opening [2] Eye Of The Hurricane [3] Tear Drop [4] Domo [5] Para Oriente [6] Pee Wee [7] One Of Another Kind [8] Fragile Disc 2 [1] Opening [2] Eye Of The Hurricane [3] Tear Drop [4] Domo [5] Para Oriente [6] Pee Wee [7] One Of Another Kind [8] Fragile [9] Stella By Starlight [10] On Green Dolphin Street |
Freddie Hubbard (tp) Wayne Shorter (ts、ss) Herbie Hancock (p) Ron Carter (b) Tony Williams (ds) |
| 伝説と言われている、雨の田園コロシアムでのライヴ(雨音もちゃんと聴こえる)。とにかく観客の盛り上がりがジャズ・ライヴのそれではなく、まるでロック・コンサートのよう。79年の日本で、このグループがどのように受け止められていたのかがよくわかる。僕も雨の屋外ロック・コンサート経験があるんだけれど、確かに降り始めこそ「ああ、いやだなあ」とテンションが下がるものの、ずぶ濡れになると開き直って逆にテンションが上がる。だからこの観客の反応もわかる。とはいえ、そんなシチュエーションで観たのが、例えばビル・エヴァンス・トリオだったらたぶんこうはならない。V.S.O.P. の演奏がハイ・テンションでアグレッシヴだったからこそこの空気が生まれた。ハバード、ショーターがブロー、ハンコックがジャズ離れしたカッコいいフレーズを連発、電化ウッド・ベースをブンブン言わせるロン、ドシャバシャとウルサイときさえあるトニーという基本形態は、2年前の「The Quintet / V.S.O.P.」と変わらず、より自由度を増してグループとしてこなれてきているし、録音状態もこちらの方が生々しい。この5人、演奏技術があまりに高く、ジャズどころか音楽すらあまり熱心に聴いていないような「ジャズってお洒落ね」というタイプの人にはさっぱり理解できないと思われる一方、耳がある程度肥えている人であれば、高度なインタープレイとともにフュージョンを通過してきた音が聴こえてきて意外と聴きやすいことがわかるはず。尚、2枚目は伝説翌日のライヴで演奏のデキはまったく遜色ないものの、観客の盛り上がりは普通。アンコール前には司会者がマナーの悪い観客を怒鳴りつけるところまで収録されていて別の意味で生々しい。アンコールの[9][10](共にショーターとハンコックのデュオ)が入っている点を除けば本当は1枚目だけで十分ではあるものの、やはりそれなりに演奏/時間も違うのでマニアックに聴き比べるのもも楽しかもしれない。(2006年11月23日) | ||
