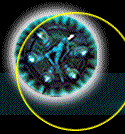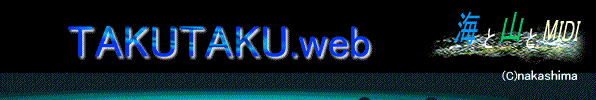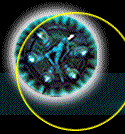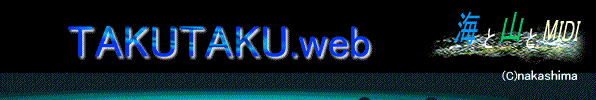|
|
|
|
■採取場所:北軽井沢
■時期:8月下旬 |
| |
イグチ科 イグチ属 |
| 大きさ |
中型~大型菌 |
| 出る時期 |
夏から秋 |
| 出る場所 |
広葉樹、松混じりの雑木林等 |
| 傘 |
黄褐色~オリ-ブ色、ビロ-ド状、時に浅くひび割れる |
| 裏 |
類白黄色~黄褐色。 菅口:幼時菌糸で塞がれる |
| 柄 |
網状紋、淡褐色~灰褐色、棍棒状で下部膨らむ |
| 食毒 |
◎ |
|
|
◇広葉樹林に生えるのはヤマドリタケモドキ
最近までヤマドリタケとヤマドリタケモドキを区別して考えたはなく、すべてヤマドリタケと読んでいました。しかし、調べたとところでは、ヤマドリタケは針葉樹林に生え、傘の表面に光沢があり、柄の途中までしか網目模様がないそうです。これに対し、ヤマドリタケモドキは広葉樹林に生え、傘はビロード状で光沢はなく、柄全体に網目模様があるとのことでした。
と、考えると今までヤマドリタケだと見ていたのは、ヤマドリタケモドキだったのですね。
|
|
◇柄は褐色で白い編み目
ヤマドリタケモドキの判断のポイントは、なんといっても柄です。柄全体に編み目が広がっていますが、上部は細かい網目模様で下に向かってだんだん網目が大きくなっていくのが特徴だと思います。
夏~秋にコナラやミズナラなどの広葉樹林で見られるもので、けっこういろいろなところで見かけると思っていたのですが、北軽ではあまり見かけない気がします。ちょうどアカヤマドリが別荘地に出るのと同じころに、近くで見つかります。どちらも大きいし美味しいキノコなので、見つかると嬉しいですね。
|
 |
|
◇ドクヤマドリと間違わないこと!
ヤマドリタケモドキの傘は茶褐色から黄褐色、後にはオリーブ褐色のような色をしています。表面はビロード状で手触りは皮っぽい感じです。初めまんじゅう形ですが、後に平らに開いてきます。柄は、淡い灰褐色で表面には網目模様があります。
ドクヤマドリと似てることもあるのですが、ドクヤマドリは柄に網目模様がないので、簡単に区別できます。ドクヤマドリは毒なので絶対間違ってはいけません。
|
 |
|
◇白くて変色しない歯ごたえのある肉
傘の裏を見ると若ければ白ですが、後に淡黄色からオリーブ色になります。ナイフで切ってみると、肉は白で、切り口は変色しません。柄の肉もしっかりしていて歯ごたえがあります。
|
 |
|
<食>
日本ではあまり馴染みがないキノコですが、ヨ-ロッパ゚では日本のマツタケ並に人気のあるヤマドリタケとよく似ているそうで、この名前になったとか・・・・
イタリア料理に登場する「ポルチーニ」に近い種類です。かなり大型のものもあります。 独特の芳香はありますが、あまりクセのない味なので、どんな料理にも合いそうです。ただし、美味いキノコだけあって、キノコムシ(キノコバエの幼虫)に食われていることが多く、なかなか状態のいいものには巡り会えません。大きいものには、間違いなくキノコムシがいますから、料理する前に塩水にひたして虫を追い出してから料理に使います。
|