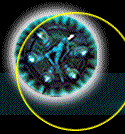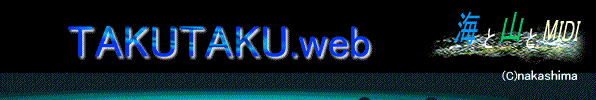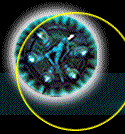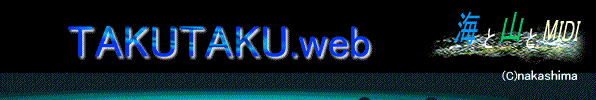|
|
|
|
■採取場所:北軽井沢
■時期:10月中旬 |
| |
キシメジ科 シメジ属 |
| 大きさ |
径4~9cm |
| 出る時期 |
8月~10月 |
| 出る場所 |
土手、道端、傾斜地、などいろいろ |
| 傘 |
成熟するとほとんど平らに開く |
| 傘の色 |
暗オリーブ褐色~灰褐色、古くなるとやや淡色 |
| 裏 |
汚白色 ヒダは密 |
| 柄 |
わずかに帯褐灰色で上部は粉状 |
| その他 |
数本または多数が根元でくっついている |
| 食毒 |
○ |
|
| おいしそうなハタケシメジを見つけました。このくらいのこぶりなのがいちばんだと思います。毎年、同じ場所に出ます。シメジの特徴である足がトックリ状に下になるほどふくらんでいたり、ニオイもモロシメジなので、とておわかりやすいです。出る場所が、別荘地の道路わきやら軒先やらだし、色は地味で薄汚れた感じで見た目のはなやかさがありませんが、なかなか美味しいキノコだと思います。 |

2006年9月上旬 |
|
◇クサウラベニタケと間違わないように!
これは上の写真のとは違う株です。こちらの足は、いまひとつトックリになっていないので、最初はハタケシメジじゃないのではと思ってしまいました。毒キノコのクサウラベニタケだったら大変なので、足を裂いてみたのですが、しっかり詰まっていましたし、ニオイはハタケシメジです。クサウラベニタケとハタケシメジの中間的なものがあり、専門家も悩むものがあるそうなので注意が必要です。なのでちょっとかじってみたのですが、これもハタケシメジでヨシとしました。
|
|
|
クサウラベニタケは、柄は白く、白いヒダも成熟すると淡紅色に着色し、単生することが多いようです。
これは、かなり開きすぎのハタケシメジです。こうなるとベローーンとして、あまりハタケシメジには見えないですね。それに味は落ちてしまいます。
|
 |
| 草に覆われてまったく目立たないところにありました。これも開きすぎくらいにひらいた、大きなハタケシメジでした。 |

2005年9月上旬 |
|
◇水につけてニオイ取り
ちょっと土っぽい香りがあるので、一晩くらい水につけておいてにおい消しします。ヒダの間に砂とかが入ってしまうことが多いので、採ったらその場でいしずきをとってビニールとかに入れて持ち帰りましょう。ヒダの間を良~く洗っておかないと、後でジャリジャリしてしまいます。
|
 |
| お汁に入れたり、炒め物につかったり、ナベに入れたりいろいろに使えます。今回はたくさん採れたので、お汁にしたのと、茹でたものをソバつゆに入れておいしくいただきました。 |
 |