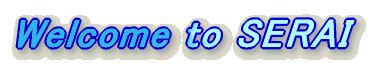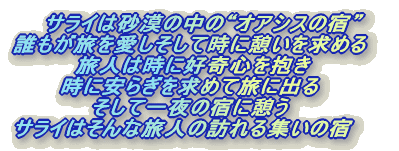| Travelling Site |
Himalaya
Everest
Trekking
�i�Q�O�P�U�j
New�I |
 |
�@�@�@�@�@�����q�}�����E�g���b�L���O�F�G���F���X�g�R�恖��
��N����n�߂��P�Ɓh�q�}�����E�g���b�L���O�h�A��N�̓l�p�[����n�k�̂��ߒf�O�����G���F���X�g�R��ɍĂђ��킵�Ă݂��B
�ő�̉ۑ�́h���R�a�h�ł������B�̗͓I�ɂ͂�����x�b�����̂Ŏ��M�͂��������A���x�����͌o�����Ȃ��A����Ă݂Ȃ���Ε�����Ȃ����E�ł���B����̍ō��x��5,600m�ł���A�ߋ��̍ō��x��4,000m���炢�ł������̂ŁA��͂��ɕs���ɉՂ܂ꂽ�B
���ʓI�ɂ͂��܂��A�W���X�g�ł��āA���R�a�ɂȂ炸�ɍς��A�������ɒ��킳�ꂽ���{�l�Ɗ؍��l��2�������R�a�ŖS���Ȃ�ꂽ�B
��͂�h���b�L�[�h�ł������ƌ��킴��Ȃ��B
���J���p�^�[���i5550m�j����ɂāF4��15��
|
Himalaya
Annapurna
Trekking
�i�Q�O�P�T�j |
 |
�@�@�@�����q�}�����E�g���b�L���O�F�A���i�v���i����
����̗��̃e�[�}�́A�h�A�W�A�̏��������h���痣��āA�h�q�}�����E�g���b�L���O�h�����݂��B
�����́A�O�����h�A���i�v���i�����R��h�A�����Č㔼�Ɂh�G�x���X�g�R��h�̒P�ƃg���b�L���O���v�悵�Ă����B
�������Ȃ���A�O���̌v������s���Ɂh�l�p�[���n�k�h�ɑ������Ă��܂����B�n�k��Q�̑傫���㔼�́h�G�x���X�g�R��h�͓��R�K����������A�v���f�O������Ȃ������B
���̑�ֈĂƂ��āA�}篁h�A���i�v���i�����R��h��
�v��ύX�����s�����B�������ŁA�A���i�v���i�S����g���b�N���邱�Ƃ��ł����B
���A���i�v���i�h�h�h��i7,555m)�Ɍ��������N�̌Q�� |
Vietnum�ELaos
���������̗�
�i�Q�O�P�S�j |
 |
�@�@�@�������������̉i���̊y������
���������͔��Q���Ȃ���R���ւƓ������݁A�ނ�̌��݂̐��ݏ��Ƃ����B�����͕W��2000�����̎R�X�Ɉ͂܂ꂽ�R���ŁA�Ζʂɐ��c������s�����݂̒I�c��z���グ���B���̒I�c���̂����R�����ł��v�ǂƂȂ�A�����Ԗ�����������މi���̊y����z���グ���B
�����̏��������n��ɑ��A�ォ�珟��ɍ������߂Ė��������f���Ă��܂����B�����A�x�g�i���A���I�X�A�^�C�A�~�����}�[�ɂ܂����邱�̈�т́A���������̉i���̊y���ł���B���̒n��̏��������̐l�X�͎��ɐ��������Ƃ��Ă��čK���������I |
China�@�M�B��
���������|�R
�i�Q�O�P�R�j |
 |
�@�@�@�@�����܂��c���Ă���������������
�M�B�Ȃɂ͂��ɂR�x���K��Ă��܂����B���̏Ȃ͒����̒��̍ŕn�ȂƂ̂��Ƃł��邪�A�ł��e�����̎������������悤�Ɋ������A�䂫������B
�o���O�ɂ͂�����x�́h���_�h���o�債�ĖK��Ă݂����A�ǂ������A�܂��܂����͓I�ȕ����������ς����B
����̒T�K�ł́A��ɏȂ̐��암�̎R�̒��ɓ��ݓ���A�~���I�i�c�j���A�����A�����A�z�ˑ��̐l�����ɂ߂������B
���̒n��͑f�p�ʼn��₩�Ȑl�X�̐������c�܂�A���傤��60�N�O�̗c�������v���N�������Ă����B���̕��������Ƃǂ̂��炢�����̂ł��낤���H |
�b���������@�_���
���������̗�-�Q
�i�Q�O11�j |
 |
�@�@�@�����}�C�E���X�g�E�Z���`�����^���E�W���[�j�[����
2006�N�ɑ����_��Ȃɂ͂Q�x�ڂ̒T�K�ŁA����͏Ȃ̓암�̎R�x�n�т̃n�j���A�C���A�����A�^�C���Ȃǂ̏�������������K��Ă݂��B������܂��u�m�X�^���W�[�̑̊��v�����߁A15���Ԃ�1500�q�̈ړ������Ȃ���̗��ƂȂ����B���̉ʂẴ~�����}�[�����̎R���܂œ��荞�ݖ���������T�����߂����A���̕Ӌ��̒n�܂ŋߑ㕶���̔g�͉����Ă���A���̋��߂�m�X�^���W�[�̑̊��͂��͂⌶���Ǝv�����B�R���̏��������ł����A�Ǝ��̑�Ȗ������������������瓾���闘���Ɏ������ڂ�����悤���B |
�b���������@�M�B��
���������̗��|�Q
�i�Q�O�O�X�j |
 |
�@�@�@�@�����m�X�^���W�[�T�K�̗�����
�M�B�Ȃ�2007�N�ɑ���2�x�ڂ̖K��ƂȂ����B
����͓��ɋM�B�Ȃ̓암�R�x�n�тɓ��荞�݁A�g�����A�c���̕�����K��A21���I�Ɏc����Ă���Ǝ��̖���������ނ�̐����̒��ŋ��Ɋ����A����̓��{�ɂ�����c�����̑̌����Ăъo�܂��u�m�X�^���W�A�T�K�̗��v�ƈʒu�Â��Ă݂��B
�Â������Ɋւ��A���ɂƂ��ĉ��Ă̂��̂͂ǂ����蕨�I�Ȉ�a�������邪�A����A�W�A�A���ɒ����암�̖��������͔��ɐe�ߊ������ĂāA�����₱�������{�����̃��[�c�ł͂Ȃ����Ǝv���ė���B |
�b���������@�M�B��
���������̗��|�P
�i�Q�O�O�V�j |
 |
�@�@�@�@�������������̏W���M�B�Ȃ̗�����
�����M�B�Ȃׂ͗�̉_��ȂƓ��l�ɏ��������̎��������F�߂�ꂽ�Ȃł���A���Ȃ������Ǝ��̕��������ł���B�M�B�Ȃ̐����n��ɕ�炷�v�C���ƁA�����ɕ�炷�~���I�i�c�j���A�g�E�`���i�y�Ɓj���A�g�����Ȃǂ���ȏ��������ɂȂ邪�A����͓����n�悾����K��邱�Ƃɂ����B
�����̏��������́A���[���b�p�̒����s�s���Ƃ������ł������悤�ɁA�������̓Ǝ��������������邱�Ƃ��������̃A�C�f���e�B�e�B�m���ɕs���ł������̂ł��낤�B�����̓Ǝ��̊X���݂▯���ߑ��A�Ɖ��Ȃǂ���̂ƂȂ��č��Ȃ����������Â��Ă���B |
�b���������@�_���
���������̗�-1
�i�Q�O�O�U�j |
 |
�����_��Ȃ͐����`�x�b�g�A����~�����}�[�A���I�X�A�x�g�i���ƍ�����ڂ��Ă���B��r�I���n�ŎR�x�������������������炵�Ă���B���ꂼ��̖����͍��Ȃ��������̒��Ő̂̕�炵�ƕ��������Ȃ��琶�����Ă��邪�A�����o�ς̔��W�ƂƂ��ɐl�X�̗������������Ă��������A�Â��ǂ��������ǂ��܂ňێ��ł���̂��H
����͏��߂Ă̒������s�ł���A����悭����Ȃ��̂ŁA��]�A�嗝�A�����Ɠs�s������n�ɗ��s�����B |
�l������������
�p�S�_�̍��̗�
�i�Q�O�O�S�j |
 |
�~�����}�[�Ɖ]����������͌R�������Ȃǂ̈Â��C���[�W����s���Ă��邪�A�����̃~�����}�[�͒|�R���v�́u�r���}�̒G�Ձv�ɒ����ꂽ���敧���̉��₩�ȍ����B�����ǂ��ɍs���Ă��o�Ƃ�����҂̏C�s�m�̑�ɏo������B���敧���ł́u�o�Ƃ��Č������C�s��ςl�݂̂������J���~����v�Ƃ̎����B���Ȃ������ǂ��ł����ȗ[�Ȃɑ���s���A����b�ސl�X������̒��ɑ��Â��Ă���h�i�ȕ������ł���B
�r���}�̏ے��ł��钆���́h�p�S�_�h�́A�����ǂ��ł������邪�A�����̃o�K���ɂ�������ۑ�����Ă���B |
�k������
�Ђ˂����̗�
�i�Q�O�O�Q�j |
 |
���{�ȏ�ɂW�O�����̍��y���R�n�Ő�߂��Ă��郉�I�X�́A�x�g�i���푈���ɂ͋��Y�Q�����̌����n�Ƃ��Ėk�x�g�i�����x�����A���̂��߁A�x�g�i���̂Q�{�ȏ�̋����ƌ����Ă���B�������A���̎����͂��܂�m���Ă��Ȃ��B���y�̑唼���R�x�n�тŐ�߂��Ă��邽�߁A��v��ʎ�i�̓��R����Ȃǂ̉͐��ʂɗ����Ă���B���Ȃ��R�Ԃ́h�쉺��h�́A���l�ɂƂ��Ă͊i�D�̗��̑�햡�ł�����B����P�O�O�����߂��̃{�[�g�ړ���A�h�Ђ˂����̂���̂��肩�ȁI�h�ƃg���b�N�̃`���[�u�ɏ�����쉺��́A�����ł������킦�Ȃ��ō����ґ�����Ȃ��B
|
| �b���������������̗��i�Q�O�O�P�j |
�r���������������@�h���������̗��i�Q�O�O0�j |
| �k�����������@�����@�t�r�` �i�P�X�W�V�|�X�T�j |
�l�������������� Clibming |
| Running |
�o������������ |
| ���ӌ������������I�@�@�@�@�@�@�@�@E���[���F�@fu5s-ymst@asahi-net.or.jp |
 |
�ŐV�X�V���F�Q�O19-�O5-06�@�@ |