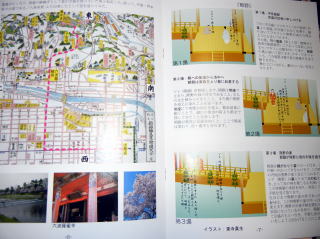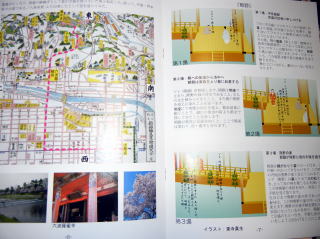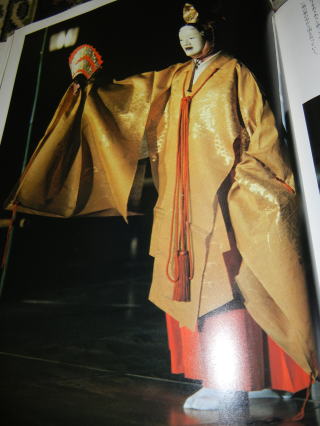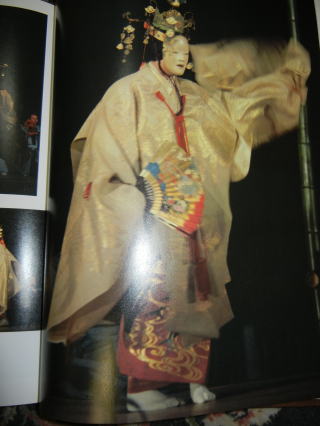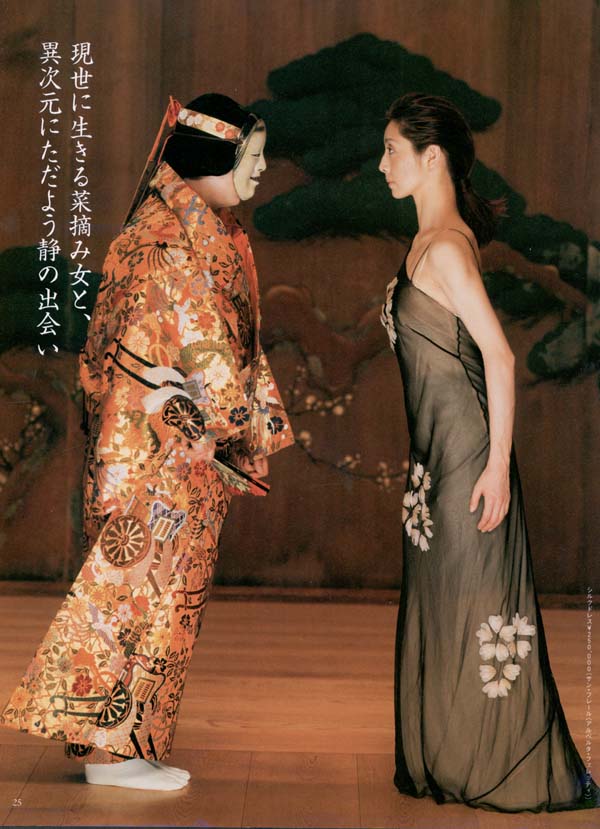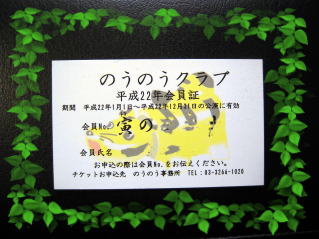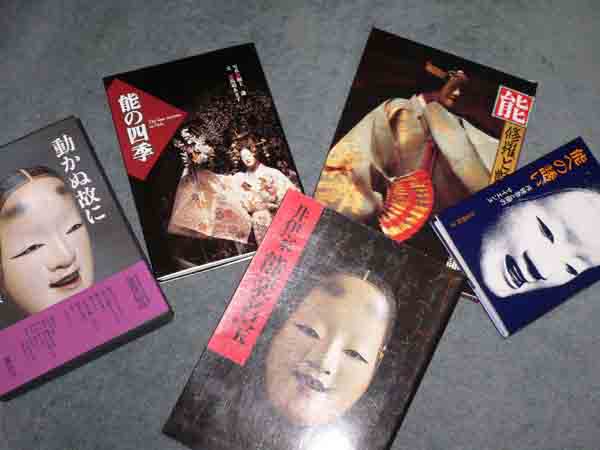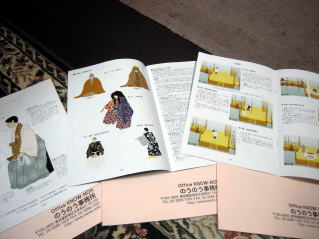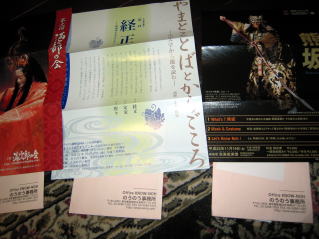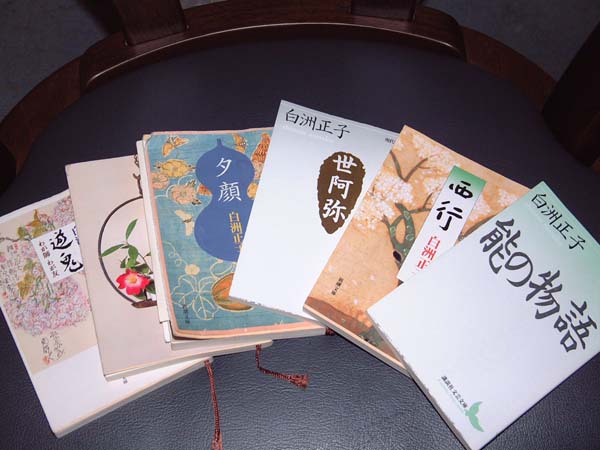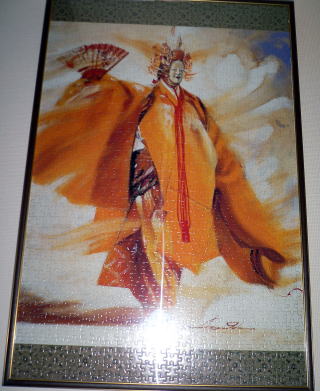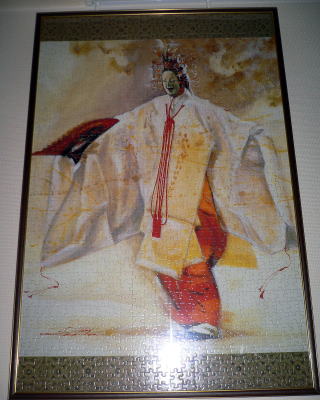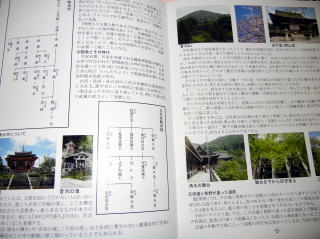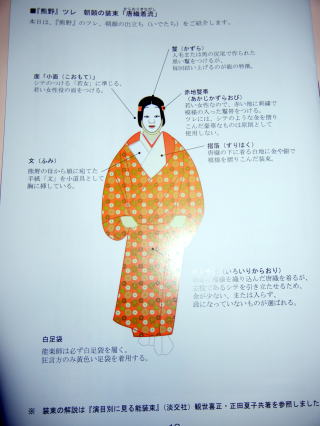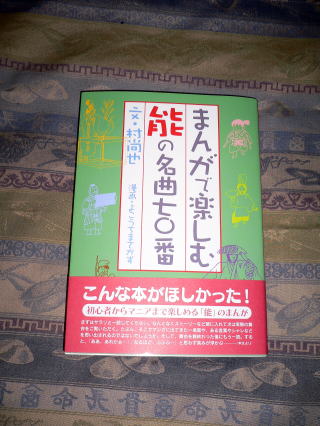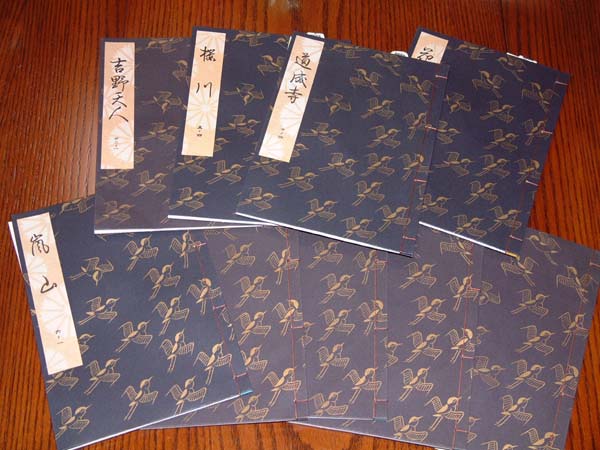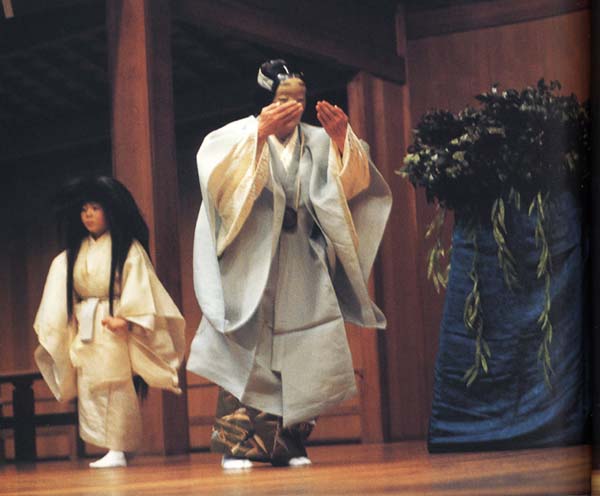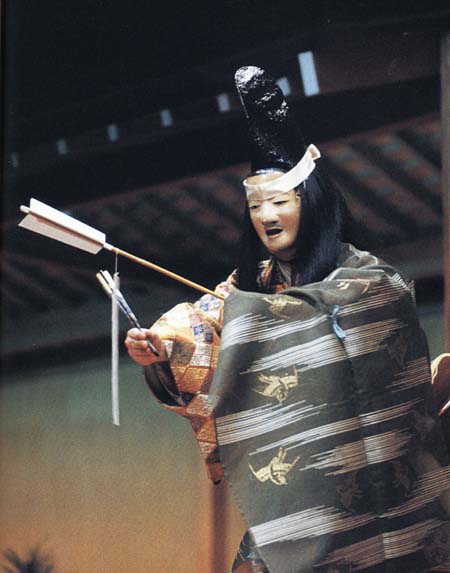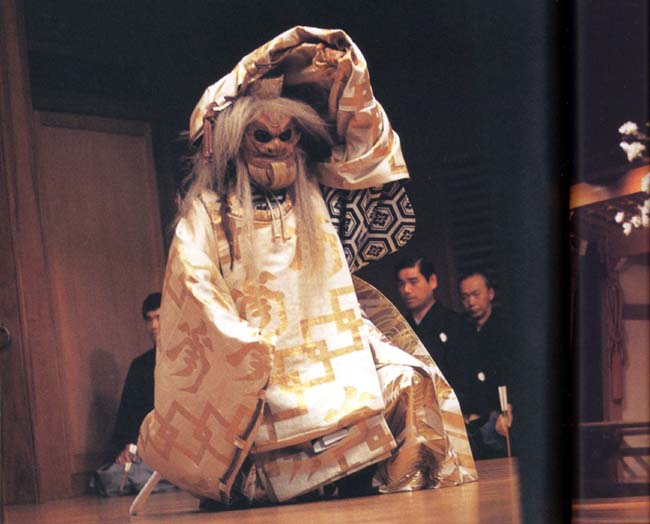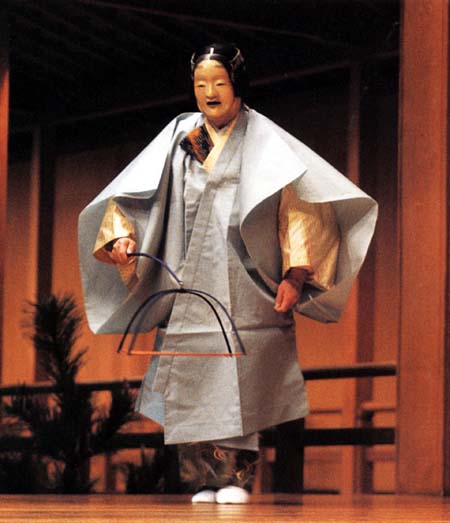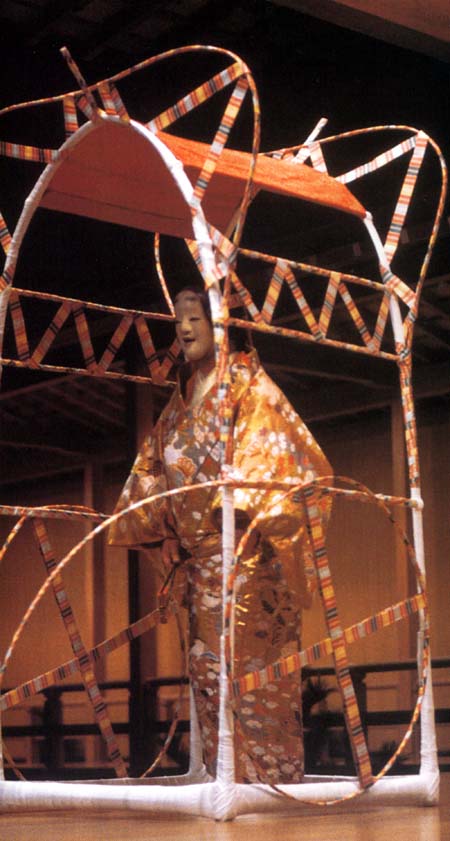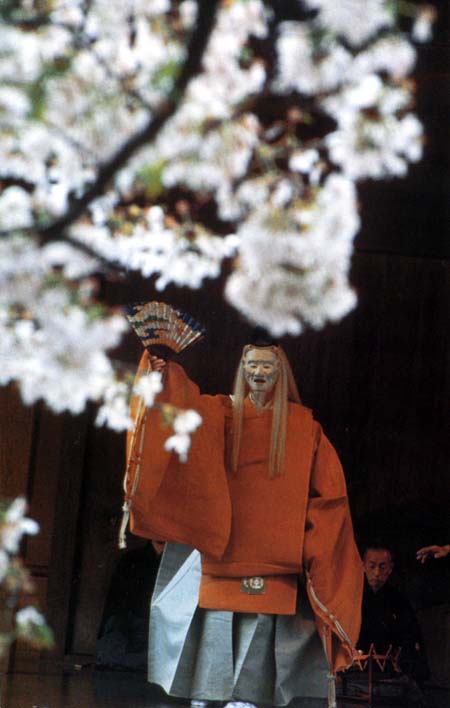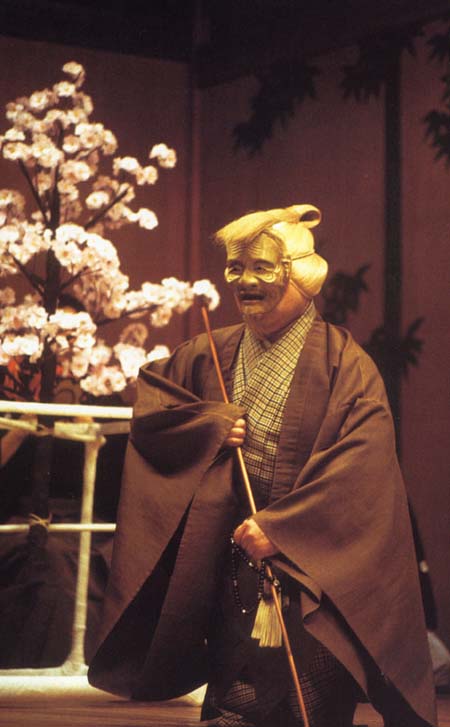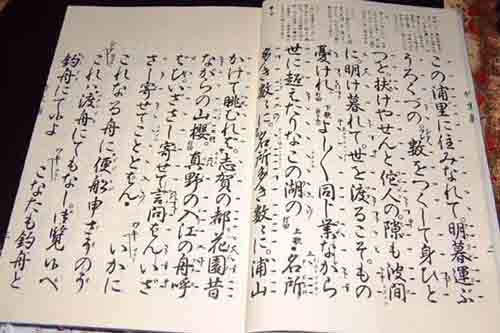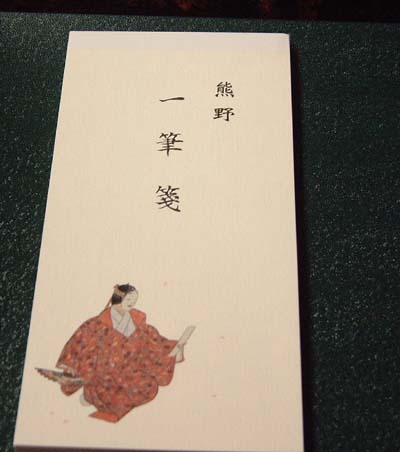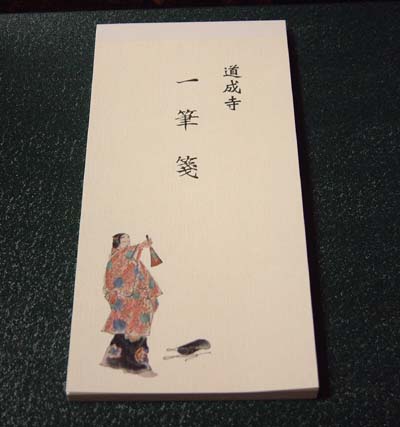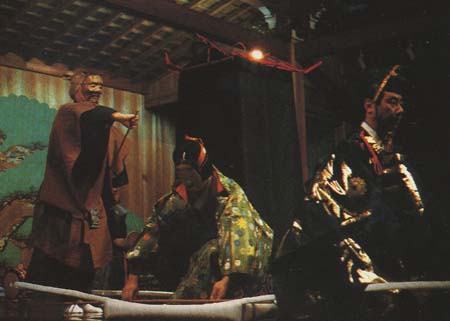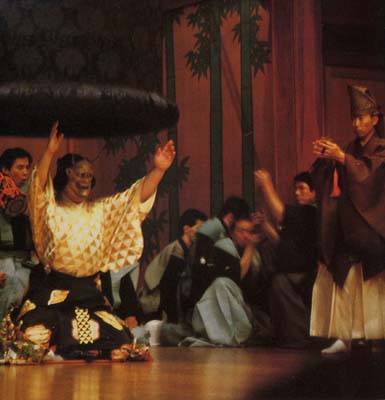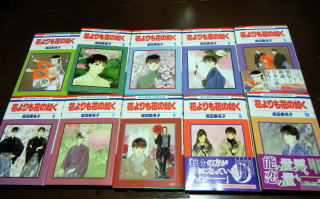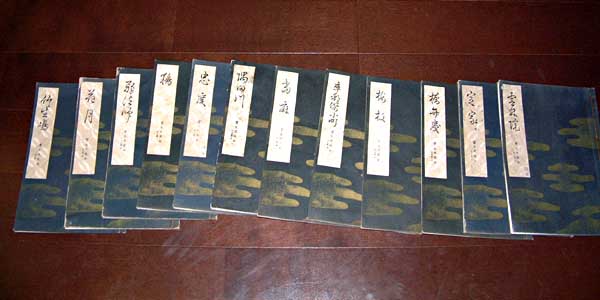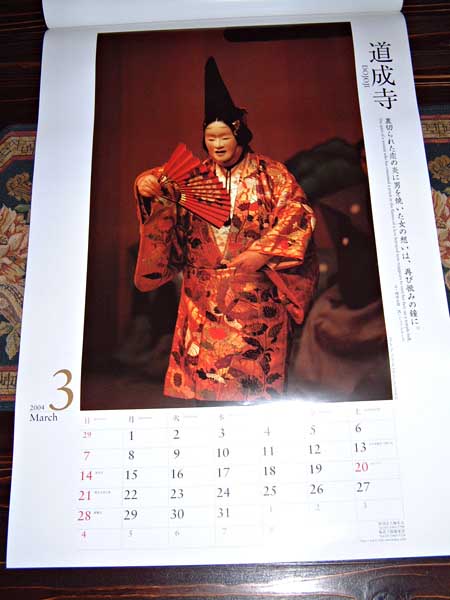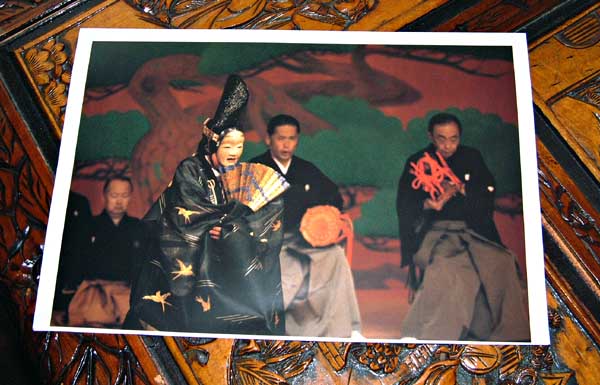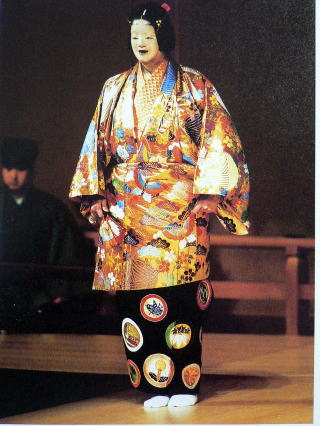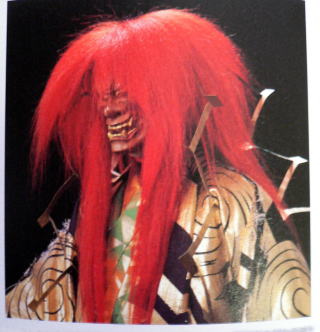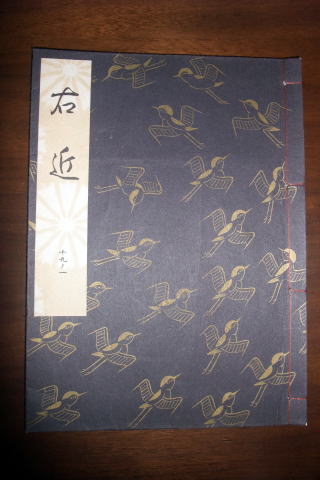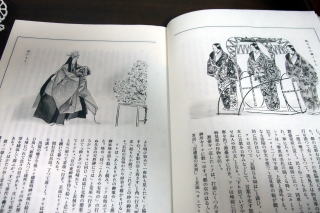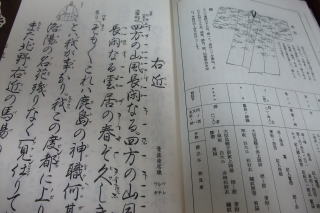日本人は昔から桜が大好き
写真: 堀上 謙氏の(左)「能の四季」 (右)「能・修羅と艶の世界」より
(2002年)
能の世界を覘いて
かつてハマッた漫画本「GALLERY FAKE」(細野不二彦作)以来の愛読漫画本「花よりも花の如く」(成田美名子作)がおもしろい。9世観世銕之丞の監修という。
月刊誌 「和楽」(小学館) より
「何を嘆くことがあるだろう。
栄枯盛衰は世のならいと思えば、
満開の桜が春の嵐に散る自然の
移り変わりとなんら異なることはない」
二人静
白洲正子の能に関する話はおもしろい
春には春の演目があるという
昔、花といえば桜を指したという
平安京では、桜の花の散り方をみて、吉凶を占ったという
少なくとも、桜の花について、昔の人々がどのような思いを込めていたか、
桜はそのまま人間のいのちの象徴であった事実に・・・・・
お奨めなもの
矢来能楽堂が発信している「のうのう講座」が面白い。
年会費2000円を納めると、会員証がおくられ、色々得点がある上、お奨めなのが、公演に行かなくても後日すてきな解説が送られてくる。これが、かなり以前、雑誌「和楽」に赤瀬川原平さんが書かれた解説文(国立劇場)を読んだ時に似たうれしさを感じながら読める。
春の演目
$吉野天人
*胡蝶
*釆女
*羽衣
*藤
*誓願時
*弱法師
$雲林院
$志賀
*雲雀山
$三山
*田村
$百万
$隅田川
$嵐山
$当麻
$道成寺
$忠度
*蟻通
*求塚
*海士
$小塩
$右近
*安宅
$鞍馬天狗
$泰山府君
$竹生島
*草子洗小町
*花月
*芦刈
$櫻川
西王母
*昭君
$熊野
$西行桜
*兼平
$重衡
$印は桜がでてくる演目
西王母
せいおうぼ
春雨の
降るは涙か
桜花
散るを惜しまぬ
人やある
親子の縁は
一代かぎりと申します
桜花
散りぬる風の名残には
水なき空に
波ぞ立ちける
散ればぞ波も桜川
散ればぞ波も桜川
流るる花を抄はん
南無や西方極楽世界
三十六万億同号同名
阿弥陀仏
花のほかには松ばかり
花のほかには松ばかり
暮れ初めて 鐘や
ひびくらん
舞台上、小道具、装束などに
桜は見あたらず・・・
「行き暮れて木の下陰を宿とせば
花や今宵の主ならまし」
世阿弥〔1363-1443:)の作の修羅能
氏神・木華開耶姫にちなんで
我が子を桜子と名付ける
少々ふざけ過ぎの感ありの一冊・・思わず吹いてしまう。。
井田益嗣氏作
「羽衣」
只、雑誌に連載中ということで、、単行本になるのは1年に1巻(2003年〜)。これが残念!!!
「花見んと群れつつ人の来るのみぞ
あたら桜の咎にはありける」
「わきて見ん老木の桜はあわれなり
今幾たびの春に逢うべき」
「大原や小塩の山も今日こそは
神代のことを思ひ出づらめ」
「春日野の若紫のすり衣
しのぶの乱れ限り知られず」
「唐衣着つつ馴れにしつましあれば
はるばる来ぬる旅をしぞ思う」
桜ではなく桃でした
世阿弥作
大和・当麻寺で老尼より当麻曼荼羅の謂われを聞く。その夜、中将姫が歌舞の菩薩となって現れ阿弥陀浄土を讃えて舞う
梅若六郎カレンダーより
(2004)
梅若六郎カレンダーより
(2004)
世阿弥〔1363-1443:)作の夢幻能
「見渡せば 柳桜をこきまぜて
都は春の錦 燦爛たり」