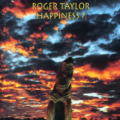Rock Listner's Guide To Jazz Music
Solo Works
| Mr. Bad Guy / Freddie Mercury |
|
クイーンのデビュー直前にラリー・ルレックス名義でひっそりとリリースされたシングル(I Can Hear Music/Going Back:これがなかなか良い)、84年に映画「メトロポリス」用に製作されたシングル"Love Kills"といったソロ活動があったものの、本格的なソロ・アルバムとしては初作品となったのが本作。当時のトレンドだったダンス・ミュージックに傾倒してたことを反映した内容でロック色は希薄(インタビューではヘヴィ・メタルみたいな音楽はもういいと発言していたほど)。バラードからオーケストラ付きの曲、そしてもちろんピアノをフィーチャーした曲も交えて、幅広く、そして純度100%のフレディ・マーキュリー・ミュージックが展開されている。なのにギターの音が妙にブライアンっぽいのがなんだか可笑しいのと同時に、そんなところにクイーンが解散しなかった理由があったのではないかなんて思わせてもくれる。"I Was Born To Love You" "Made In Heaven"はこれがオリジナル。全曲熱唱しているので悪い言い方をすると暑苦しくて、通して聴くとちょっと疲れるのも事実。85年リリース。(2006年11月1日)
2019年リマスターは、音のバランスが根底から変わる改変。曲によって改変具合が大きく異るけれど、ベース音域を膨らませ、各楽器の音を丸めて生々しさをあえて出さないことが85年当時のトレンド。2019年リマスターではベースを不必要に強調することなく、各楽器の生々しさも向上。ハイハットの音を加工して打ち込みのように聴かせていたところもハイハットらしく聴こえる。変わりすぎて旧版愛聴者は戸惑い、オリジナルへの敬意がないという人もいるかもしれない。個人的には楽器との距離感が縮まり、フレディの声がより身近に生々しく聴こえる2019リマスターを支持したい。(2019年10月20日)
評価:★★★ |
|
| The Freddie Mercury Album / Freddie Maercury |
|
「Mr. Bad Guy」が廃盤、その代わり(?)に92年にリリースされたフレディの死に便乗した感も漂うアルバム。シングルでしか入手できなかった "The Great Pretender" "Time" "Exercise In Free Love" "In My Defence" をまとめて聴けるのがありがたい。「Mr. Bad Guy」に収録されていた曲と"Love Kills"は別アレンジで重複感を与えないように考えてある。しかし、この別アレンジが実に俗っぽいハード・ロック調バージョンになっているのが問題。ソロではハード・ロック色をむしろ嫌っていたフレディの意向を反映しているとはとても思えずこの点で大幅減点。オリジナル・アレンジこそがフレディが創ったものであることを良く気に留めておきたいところ。そんな難点を吹き飛ばしてしまうのが "In My Defence"。魂のこもった歌というのはこういうものだと思う。この曲だけを目的このアルバムを買ってもいいとすら思う。(2006年11月1日)
追記:DVD「The Great Pretender」によると、自分が死んだら曲をどういうふうにイジッてもらっても構わない、好きにしてくれと言っていたらしい。そうだとすると、このアルバムのアレンジでもフレディの意向云々するのは間違っているのかもしれない。でも、このロック・アレンジは合ってません、やっぱり。
評価:★★☆ |
|
| Balcerona / Freddie Mercury & Montserrat Caballe |
|
オペラ好きが昂じてついにオペラ歌手とのデュエット作を作ってしまった、というのが一般的な受け止め方で僕も昔はそう思っていた。しかし映画「フレディ・マーキュリー 人生と歌を愛した男」を見るともっと純粋であることがわかる。パバロッティを観にいったときにフレディの目に入った、名前も知らなかったソプラノ歌手に衝撃を受け、実際に会って歌を合わせたときにお互いに精神の合致を感じたこと、アルバムを作ることすら決まっていない段階でマイク・モーランを交えた3人で一晩中濃密な時間を過ごしたことが語られている。元来、フレディの音楽のアイディアは「こんなのやってみたら面白いんじゃないか」という発想から娯楽に仕上げているものが多いんだけれど、このアルバムは「売れるか」「ウケるか」といったことをまったく考えずに、音楽家同士がお互いにインスパイアされてるという純粋な動機が昇華されたものなのだ。ロックでもオペラでもない唯一無二の作品となったのはこのような生い立ちに負うところが大きい。これほどまでに濃密な音楽家同士の関係はそうはない。88年リリース。(2006年11月1日)
評価:★★★☆
DVD「The Great Pretender」を観て、本物のオーケストラで伴奏を制作した本アルバムを知り、すぐにそのスペシャル・エディションを購入した。もともとこのアルバムの製作は入念に計画されたものではなく、2人の衝動だけで進んだものであることは、このDVDや「フレディ・マーキュリー 人生と歌を愛した男」を観ればわかる。スケジュールを合わせることも困難な中、製作されたこともあり、オーケストラをイメージした楽曲でありながら伴奏が電子キーボードの味気ない(そして今となっては古臭い)音になってしまったのは仕方がないことだったし、個人的にはとても残念だと思っていたところだった。そんな不満を完全に払拭してしまったのがこのスペシャル・エディション。生オーケストラの芳醇なサウンドは、本来こうあるべきだったという説得力があり実に素晴らしい。リリース当初の姿を尊重する気持ちもあるとはいえ、内容的には従来版はもう役目を終えたと言っていいかもしれない。きっと地獄(DVDを観た人ならわかるでしょ?)のフレディもこのスペシャル・エディションを喜んでいるに違いない。2012年リリース。(2013年1月7日)
評価:★★★★★
尚、フレディ・マーキュリーには、CD 10枚と DVD 2枚を収めた発売当時「フレ箱」と呼ばれたボックスがある。ここに紹介している3枚のアルバム、そしてこの3枚のアルバムのセッション・テイク、ゲスト参加した他のアーティストの音源(中には自分の色に染め上げてしまっているものもあって笑える)、レアなシングルや12インチ・バージョン、クイーン以前の音源などを収めたものでソロ・ワークの決定版とも言えるものですが、高価なこともありよほどのマニア以外は入手する必要はない。しかも、マイケル・ジャクソンとのセッションが含まれていないという詰めの甘さ。反面、豪華な装丁に豪華ブックレット付きとあってマニアなら所有しているだけで満たされるかも。 |
|
| Star Fleet / Brian May and Friends |
|
83年リリース。テーマ曲以外は発売を前提にぜず、気の合う仲間たちとレコーディングしてみましたという3曲だけのミニ・アルバム。ブライアン以外のメンバーはエドワード・ヴァン・ヘイレン(ギター)、フレッド・マンデル(キーボード:クイーンのツアー・サポート・メンバー)、フィリップ・チェン(ベース:ジェフ・ベックやロッドスチュワートとのとの共演歴のある有名なセッション・プレイヤー)、アラン・グラッツァー(ドラム:REOスピードワゴン)という、結構音楽背景がバラバラなメンツ。[1]はオーソドックスなブライアンらしいハード・ロック。聴きどころはお遊びムードが漂う[2][3]。共にリラックスしたブルースで、ブライアンとエディのギター・バトルが堪能できる。特にエディがブルースを演奏しているのはかなりレアで、いつものスタイルでそのままブルースのソロを弾きまくるところに改めて才能を感じる。むしろエディ・マニアこそ必聴のアルバム。(2007年3月14日)
評価:★★★★ |
|
| Back To The Light / Braian May |
|
92年リリース。結果的にフレディが天に召されてからリリースされることになったが、実は存命中から既に制作に入っていたブライアン初のソロ・アルバム。冒頭から大仰なギター・オーケストレーションが入って「おおっ」と思ってしまう。曲によってメンバーが異なるとはいえ、ドラムはコージー・パウエルが基本で、ニール・マーレイやドン・エイリーのサポートを得てハード・ロック色が強い仕上がりになったのは当然か。それでもありきたりなハード・ロック・アルバムにならず、バラエティに富んだ内容に仕上がっているのを聴くと、なるほどこれがブライアンのバランス感覚なんだなあと納得させられる。ブライアンの線の細いヴォーカルがアルバムを通して聴くにはちょっと厳しいことははじめからわかっていることで、女性コーラスを交えるなどの工夫でそれを補っている。わざわざ with Cozy Powell のクレジットが入る "Resurrection" が最大の聴きどころだし全体的にコージーあってのアルバムという印象。曲は粒ぞろいで質は決して低くない。ジョンもベースで1曲参加。(2007年3月12日)
評価:★★★☆ |
|
| Resurrection / Brian May with Cozy Powell |
|
93年リリースの来日記念盤。ミニ・アルバムという体裁ながら内容は侮れない。表題曲と "Love Token" は短縮バージョンと特筆することはないものの、"Too Much Love Will Kill You" "Back To The Light" "Tie Your Mother Down" の(MCを聴くかぎりLAでの)ライヴが聴ける。特に "Tie Your Mother Down" にはガンズ・アンド・ローゼズのスラッシュが参加しているのがトピック。さらにこのアルバムの貴重なところはCD化が絶望的と思われていた「Star Fleet」 の3曲が収録されていること。幸いにもプレミアがついていないのでエディ・マニアはゲットするべし。(2007年3月14日)
評価:★★★☆ |
|
| Live At The Brixton Academy / Brian May |
|
94年リリース。なんとライヴ盤までリリースしてしまった。それだけ自分のバンドに手応えを感じていたからなんでしょう。実際、内容はいい。聴きどころはクイーンの曲をコージー・パウエルが叩いていいることで同じ曲でも重量感を増した仕上がりになっているところ。ロジャーと比べてどちらがいいとかいう話ではなくドラマーによってこれだけ曲の印象が変わるという面白さを味わえる。圧巻はギターソロ〜 Resurrection 〜 ドラム・ソロ(コージーの十八番、1812年) 〜 Bohemian 〜 Reurrection のメドレー。ここの部分だけでも聴く価値がある。確か以前は映像(ビデオだったかな?)も発売されていたはず。僕は WOWOW で録画したものを持ってるんだけれど、やはり映像があった方が楽しめる。(2007年3月16日)
評価:★★★★ |
|
| Another World / Brian May |
|
98年リリース。ブライアンのソロ第二弾。クイーンのメンバー中、音楽的には最も保守的なブライアンであるからして基本路線は変わっていない。よりタイトで(特に冒頭2曲が)ヘヴィに仕上がっているのはツアーを経てバンド(というかコージーと)の結束が高まったからだろうか。ヘヴィな曲もあのか細い声で歌われるとブライアンの曲になるから不思議。本作でもコージー・パウエルは存在感十分で、もはやブライアンのバンドに欠かせない存在であったんだけれども、このアルバムのリリース直前に交通事故により急逝、これが遺作となってしまった。"The Guv'nor" はジェフ・ベックが参加していて「おおっ、ジェフとコージー久々の競演」と色めき立ちそうになるものの、手渡されたテープを元にジェフがギター・ソロをオーバー・ダビングしたというのが事実らしい。それでも、いろんなところでジェフのあのフレーズが出てくるし何よりも自らのアイドルだった人が参加してくれただけでもブライアンには光栄だったに違いない。シャドウズのブギー調ブルース "F.B.I" にステイタス・クォーのフランシス・ロッシとリック・パーフィットが参加、モット・ザ・フープルの "All The Way From The Memphis" にはイアン・ハンターが協力、ジミ・ヘンドリクスの "One Rainy Wish" ではエディ・クレイマーがコ・プロデューサーとしてクレジットされるなど、適材適所の共演者が揃っていて思わずニヤリとさせられる。ある意味、やりたいことを思い切りやってしまった爽快感すら感じるし、そういう意味ではクイーンの影響から抜け出してブライアンらしさを表現できた好アルバムと言える。(2007年3月12日)
評価:★★★☆ |
|
| Red Special / Brian May |
|
98年リリースの来日記念盤。98年6月のパリ公演から "On My Way Up(8分と長い)" "Hammer To Fall (前半3分の2をスローにしたバージョン)" を収録。やっぱりコージー・パウエルがいないのは寂しい。他にはアルバム未収録曲2曲。これがいい意味で遊び心に溢れたロカビリー調の曲でブライアンの隠れた一面を見ることができる。 "Business" はUSラジオ・ミックス。以上がこの CD ならではの音源。他の2曲は 「Another World」から。最後にコージー・パウエルを偲ぶブライアンのインタビューが入っている。(2007年3月17日)
評価:★★☆ |
|
| Furia / Brian May |
|
2000年リリース。フランス映画 「Furia」 のサウンド・トラックとして製作されたもので全曲ブライアンが書き下ろし、アレンジも行っている。完全に映画音楽に徹しているので曲の形も通常のアルバムとはまったく異なっていて、そういう意味では「Flash Gordon」と同じスタンスで作られたものと言える。シンセサイザーと打ち込みドラム中心のサウンドでシンフォニックな曲が多く、ギターがほとんど出てこないところにソロ・アルバムとして聴くと物足りなさを感じてしまう。レゲエ調の曲など、ブライアンが作ったとは思えない意外な一面が見れるところが興味深い。(2007年3月18日)
評価:★☆ |
|
| Anthem / Kerry Ellis |
|
2010年リリース。ミュージカル「We Will Rock You」で主演を務めたケリー・エリス単独名義につき、このページに含めるべきではないかもしれないけれど、プロデュースとアレンジでブライアンが全面参加(1曲を除きベースも演奏)し、バンドメンバーもブライアン所縁メンバーとあって、ブライアン制作のアルバムと言って差し支えないサウンド。ケリー・エリスの主戦場であるミュージカルの曲を中心にクイーン関係の楽曲では "Save Me" "No One But You" "I Loved A BUtterfly"を採り上げている。当然ながら、あくまでもケリーの歌を中心としていることから曲によってはオーケストラも加わり、高い歌唱力で美声を響かせているところが聴きどころ。主役を支えるという気楽さゆえに、自然体で肩の力が入っていないブライアンのギターをたっぷり聴くことができるし、全体に突き抜けた明るさがあって爽快。ブライアンのファンなら必聴。(2023年1月7日)
評価:★★★★ |
|
| Acoustic by Candlelight / Brian May & Kerry Ellis |
|
2013年リリース。ケリー・エリスのヴォーカルとブライアンのアコギ(と補助的にキーボード)によるライヴ盤。歌の上手さと声の通りの良さは流石の(NHK某番組で日本のミュージカル俳優と共演していて格の違いを見せていた)ケリー・エリスの歌を中心に据えたアットホームなコンサートは寛ぎ感に溢れ、心が洗われる。チャーミングな曲が並び、有名どころではカンザスの" Dust In The Wind"、ビートルズの"Something"を採り上げている他、後にQ+PRでも採り上げた "I Loved A Butterfly"、クイーンからは"Love Of My Life" "Crazy Little Thing Called Love" "Life Is Real" "No One But You "を歌っていてクイーンの曲の素性の良さを再認識。映像版では" Somebody To Love "と「やはりライヴだから盛り上げないとね」的に終盤に演奏した "Tie Your Mother Down" "We Will Rock You" も収録されている。(2022年12月28日)
評価:★★★★ |
|
| Golden Days / Brian May & Kerry Ellis |
|
2017年リリース。モントルーのライヴから4年、ケリー・エリス共演のスタジオ録音盤。バンド形式演奏が中心でコーラス、ギターのオーバーダビングも適度に施され、しっかり作り込まれている。音楽的にはライヴCDの拡張版と言えるもの、あるいはケリーの「Anthem」の続編的と言えるもので方向性は変わっていない。ケリー・エリスは声が綺麗だし、良くも悪くもミュージカル・スタイルの歌い方で、音楽も素直であることから一部ロック系チューンも爽やかな聴き心地。ゲイリー・ムーアの"パリの散歩道"を採り上げているのが意表を突く。(2022年12月28日)
評価:★★★☆ |
|
| Fun In Space / Roger Taylor |
|
81年リリース。。クイーンのアルバムで最も曲が浮いていたロジャーが最初にソロ・アルバムを発表したのは当然だったかもしれない。キーボード以外はすべて自分でこなすというマルチ・プレイヤーぶりを発揮、曲もバラエティに富んでいて自由奔放に自分らしいロックン・ロールを演っているのが心地よい。ロジャーのヴォーカルもいい感じで唸っている。スケール感には欠けるけれど後のどのソロ・アルバムより面白い。(2007年2月25日)
評価:★★★☆ |
|
| Storange Fronteer / Roger Taylor |
|
84年リリース。クイーンの状態が良くなかったころに発売されたロジャーのソロ第2弾。1作目がとりあえず自分勝手に好きにやってみました、というパーソナルな感じだったのと比べるとわりと常識的な普通のロック・アルバムになった。ロジャーと言えばクイーンの中で最もロックン・ローラーなキャラクターでハードな印象があるけれど、それはいわゆるハード・ロックとはベクトルが異なっていて、ボブ・ディランやブルース・スプリングスティーンのカヴァーを含むこのアルバムを聴くとそれがよくわかる。決してハードとは言えない曲も多く、ハード一辺倒ではないロジャーのバランス感覚も良く出ている。クイーンのライヴではもう1人のヴォーカリストと思える力量を感じさせるけれど、こうしてアルバム1枚聴くと余り幅がないことがわかってしまう。曲のメロディが平板であることもあんまりパッとしない理由。クイーンには見られない反戦曲が入っているのもロジャーならでは。この頃からクイーンでもロジャーの曲の重要性が高まっていて共通性が出てきているのも興味深い。(2007年3月14日)
評価:★★ |
|
| Happiness? / Roger Taylor |
|
94年リリース。暗〜いジャケットに裏には何かの宗教に入信したかのような妙なポーズを取るロジャー(しかも微妙にサングラスがズレてる)。そんな印象が音楽にも出ている印象。もともと色彩感に乏しいロジャーのソロ、ここでは一段とモノトーンでクールなロックを展開。それでも音楽そのものはよく考えて作られているのがわかって凡人では無理だろうと思わせるクオリティと個性がある。サウンドの印象としては後期ピンク・フロイドやロジャー・ウォーターズのアルバムを連想させるところもある。つまり、僕が嫌いな、音楽性に遊びがないメッセージ・ソングに近いものがあるし、実際に歌っている内容もメッセージ色が強いものが多い。X-Japan の YOSHIKI が2曲参加し「日英スター・ドラマーの競演」と話題にもなった。特に YOSHIKI 作の [5] は歌謡曲的盛り上がりを見せるモロ X-Japan 風。ミュージック・ステーションに2人揃って出演し、司会のタモリに「ロジャーさん」と呼ばれていたのが悲しくも懐かしい思い出。YOSHIKI の奇抜な格好をどう思うかと訊かれたロジャーは「僕も昔はそういう格好していたよ」と事も無げに答えていた。(2007年3月14日)
評価:★★ |
|
| Electric Fire / Roger Taylor |
|
98年リリース。基本的には前作の延長線上にあり、相変わらず地味な作風ながら、窮屈な印象があった前作よりもどこか吹っ切れた感じを受ける。ここでもやはりロジャーにしかできない、なかなか渋くも柔軟性のあるロックを展開しており歌メロにはザ・クロスに近いフィーリングもある。アレンジなどは十分工夫の跡が見られ実によく考えて作られていることもよくわかる。従来よりロジャーのソロは、ドラマーとしてより音楽家としての主張に注力しており、ここでもドラムは半分他人に任せて、ますますその傾向が強くなっている。それにしてもロジャーの曲というのは口ずさめるものが少ない。そこにロジャーの単一志向なヴォーカルが組み合わさるとなんとも曲が平板になってしまう。だから僕はロジャーのソロをあまり繰り返して聴く気になれない。(2007年3月14日)
評価:★★☆ |
|
| Fun On Earth / Roger Taylor |
|
2013年リリース。ソロ・デビュー作「Fun In Space」から32年。「スペース」から「地球」へたどり着いたのは悟りの境地を開いたということなんだろうか。従来までのソロ作ではドラムマシンを使っていたが、ここでは生ドラムで統一、1曲は息子に叩かせている(たいしたプレイじゃないけど)。ヘヴィでクールな [1] に従来のロジャー路線の踏襲を感じさせるものの、[2] からは意外としっとりした曲が多く、相変わらず浮き立たないメロディと相まって正直なところ大変地味な仕上がり。でも言い換えるとじっくり、しっとりとした大人なロック。サウンドも地味で以前ほど最新のサウンドを求めていないものの、音作りはしっかりなされていてサックスやヴィブラフォン(フォービートまで飛び出す)を使うなどを多用しているところなどからも目指している方向性が見える。その目指している「落ち着いて聴けるロック」としてクオリティは十分。ロジャーにまだこれだけの創造力があることに驚いた。これで3回めのスタジオ録音となる "Say It's Not True" はロジャー屈指の名曲で、今回はシンプルなサウンドにジェフ・ベックのギターが全面に乗るというボーナス付き。Q+PRの曲は "Small" も収録。まあ、一般にはまったくウケないでしょうが、ロジャーのファンなら十分納得できる仕上がりとクオリティ。(2013年11月22日)
評価:★★★ |
|
| Outsider / Roger Taylor |
|
2021年リリース。自身の既存曲のリメイク、未発表曲の仕上げを企画していたところでコロナ禍に見舞われ、じっくり時間をかけることができるようになり、ニューアルバム制作に至ったという経緯。Yoshikiとの共作の既発曲"Foreign Sand"と外部ライターによる"The Clapping Song"を除き、ロジャーの自作曲で、落ち着いた曲が多く、起伏のない曲であるところは従来と同様、また声の張りも若い頃に及ばないのも当然のことだけれど、音楽の質はまったく落ちていない。日本版ボーナス・トラックの2曲"Surrender" "London Town - C'mon Down"は「Electric Fire」収録曲のリミックス。(2022年12月28日)
評価:★★★ |
|
| The Out Sider Tour Live / Roger Taylor |
|
2022年リリース。自身のキャリアを総括するかのようなセットリスト。1曲目"Storange Frontier"冒頭で、こんなに昔の有名でもない曲を観客が歌っていて「おおっ」となる。ロジャーは時々ドラムを叩きつつも基本的にはヴォーカルにに専念(担当ドラマーもロジャーっぽく叩いている、というかほぼコピー)。もちろん、往年の声の張りはなく声量を抑えるパートでは音程が怪しくなっているものの72歳でこれだけ歌えれば十分か。「Fun In Space」とThe Crossからの曲を除いくソロの曲とクイーンの自作曲を織り交ぜ、終盤にはレッド・ツェッペリンの"Rock and Roll"、デヴィッド・ボウイの"The Hero"、そして"Radio Ga Ga"で締めてなかなか盛り上がる。正直なところ、ロジャーはソロ・アーティストとしての力量は一級レベルとは言えないけれど、それでもやはり優れたロック・ミュージシャンであることを実感する、アットホームかつ良いライヴ盤。"Tutti Frutti"と"A Kind Of Magic"にはブライアンが飛び入り参加。ALL PERFORMANCES ARE REAL AND UMTAMPERED WITH ! (演奏は本物で手を加えていない)とクレジットされている。(2022年12月28日)
評価:★★★★ |
|
| Shove It / The Cross |
|
87年に突然リリースされたロジャーのソロ・プロジェクト、ザ・クロスの1作目。自身はヴォーカルとサイド・ギターを担当し、ドラマーが別に居るということが驚きを与えたが、実はこのアルバムにはスパイク・エドニー(キーボード)以外のメンバーは参加していない。ドラムはかなり打ち込みを多用している。とはいえ、バンドを想定したサウンドにしたからかソロ・アルバムとは幾分ムードが異なる。クレジットはないものの "Heaven For Everyone" のヴォーカルはフレディ・マーキュリーで後にクイーンの演奏に差し替えたものが「Made In Heaven」に収録されることになる。(2006年11月8日)
評価:★★ |
|
| Mad, Bad And Dangerous To Know / The Cross |
|
90年リリース。詩人、バイロンを評した有名な言葉をそのままタイトルにしたのに日本のレコード会社の無知により「マッド・バッド・ロックンローラー」なる意味不明の邦題が付いていたザ・クロスの2作目。5人のメンバーによる製作となり、よりロック・バンドらしいサウンドに仕上がった実質的にはザ・クロスのデビュー・アルバムと言える作品。ロジャーの自作曲は1曲のみ、他はメンバーのオリジナルとジミ・ヘンドリクスのカヴァーという構成で、ただそのサウンドは意外と地味。良くも悪くもあまり作りこんだ印象がないのが特徴の、ヴォーカリスト/フロントマンとしての可能性を模索したロジャーの意欲作。(2006年11月9日)
評価:★★☆ |
|
| Blue Rock / The Cross |
|
91年リリース、驚くべきことに3作目まで作ってしまったザ・クロス。裏にはクイーンでの活動(特にライヴ)ができなかったという事情があるけれど、よくぞここまで続けたものだと思う。そしてこの3枚目にして最後となったアルバムは相当イイ。ロジャーはついにヴォーカルに専念、バンドとしてのまとまりも飛躍的に向上していてカッコいいロック・アルバムに仕上がっている。録音もクリアで、曲もメリハリがあって聴きやすい。個人的にはロジャーのアルバムの中で唯一繰り返し聴いたアルバムで、この先も聴いてみたかったんだけれどもクイーンあってのサイド・プロジェクトだったようで、これをもってザ・クロスの活動は終止符が打たれてしまった。(2006年11月8日)
評価:★★★★ |
|