ロック・ファンのためのジャズ案内のヘッダー
Rock Listner's Guide To Jazz Music
Miles Davis (80s〜 )
| The Man With The Horn | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★★ マイルス入門度:★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1980/May [5] 1981/Jan [2][4][6] 1981/Mar [1] 1981/5/6 [3] [1] Fat Time [2] Back Seat Betty [3] Shout [4] Aida [5] The Man with the Horn [6] Ursula |
Miles Davis (tp) Bill Evans (ss) Barry Finnerty (g [2][3][4][6]) Randy Hall (g, vo [3], synth [3][5]) Mike Stern [g [1]) Marcus Miller (elb [1][2][4][6]) Felton Crews (elb [3][5]) Al Foster (ds [1][2][4][6] Vince Wilburn (ds [3][5]) Sammy Figueroa (per [1]-[4][6]) |
| 一番音楽に刺激を受け、最も多くのものを吸収するであろう、10代からの学生時代が丸々80年代だというのに僕は80年代の音楽があまり好きではない。その10代のとき、流行っていた音楽は確かに聴いていたので耳に馴染みはある。でも、今聴くとしたらそれは懐かしんで聴く程度でしかない。その10代のころ、僕が夢中になっていたのは70年代の英国ハードロックやプログレッシヴ・ロックだった。多くのバンドは既に解散していた。それでも夢中になって聴いた理由は、単純に音楽として魅力があったから。70年代のロックは総じて創意工夫と音楽的なチャレンジに溢れていたし、個性的な自分(たち)ならでは音楽を追求しようという意欲に満ちあふれていた。そうして築かれたロック・ミュージックにより市場は拡大し、ロック(とポピュラー音楽)は大金が動くビジネスになった。80年代は売れることを狙った仕組みができあがり、音楽として何を追求するかよりも、耳あたりの良い売れる音楽作りが当たり前になってしまった。当時そんなことを考えていたわけではく、単純にリアルタイムの音楽がつまらないと感じていたんだけれど、今思えば商業化優先の音楽は面白いはずがなく、当時の音楽をつまらないと感じていた自分の感覚は今でも正しかったと思っている。更に新しい技術の台頭で、様々なエフェクトが施された加工された音作りも流行した。70年代の、楽器の音をダイレクトに録音する手法が演奏の生々しさを伝えていたのに対し、80年代のテクノロジーがもたらした音作りは音楽からダイレクト感を奪い去ってしまった。 こうした理由で80年代の音楽にネガティヴな思いを抱く僕は、マイルスに関しても、一部を少し聴いただけで、80年代以降は面白くないと思っていた。そんな自分も年を重ねて、頑なに80年代を否定するのも止めてみよう、とついにカムバック後にマイルスも聴いてみることにした。復帰第一作のこのアルバムは確かに80年代の音作りになっている。当時最新の音作りで復帰したマイルスを今、改めて正面から聴いてみると、これがまったく軽々しくない。軽快なフュージョン・ファンクとも言える[3]、ソウル的な歌モノ[5]はいかにもこの時代のサウンドながら、全体的に音楽性は幅広く、それでいて筋が通っている。70年代までに築いてきた音楽も継承されている([2][4]は「Get Up With It」に収録されていてもおかしくない)のは個人的好みの観点では嬉しいものの、この時点ではまだ音楽的には新しいものに切り替わりきれていなかったこと、時代を超えた音楽にまでは到達していないということでもある。マイルスは単にトレンドに乗った軽い音楽ではなく、マイルスにしかできない音楽でカムバックしていたのだと今になってようやくわかるようになった。もちろん、今でも僕は70年代の音楽の方がずっと魅力的だと感じているし、マイルスの音楽も70年代までの方が聴き応えがあると思っている。だから80年代のマイルスはブートレグを追いかけようとまでは思わない。それでも、マイルスの音楽は停滞していないし、これからの時代を切り開いていこうという意欲に溢れている。音だけ聴けば、軟弱で心地よいだけのフュージョンにカテゴライズされていてもおかしくないにもかかわらず、そうした扱いを受けなかったのは、やはりマイルスならでは音楽がそこにあったからに他ならない。(2020年3月31日) |
||
| We Want Miles | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★ マイルス入門度:★★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1981/6/27 [3][5][6] 1981/7/5 [2] 1981/10/4 [1][4] [1] Jean-Pierre [2] Back Seat Betty [3] Fast Track [4] Jean-Pierre [5] My Man's Gone Now [6] Kix |
Miles Davis (tp, key) Bill Evans (ss, ts) Mike Stern (g) Marcus Miller (elb) Al Foster (ds) Mino Cinelu (per) |
| 復帰二作目はすべてライヴ音源。新メンバーによるライヴ演奏の喜びが溢れ出る熱演が80分弱、たっぷりと聴ける。マイルスのテンションの高さは全歴史を紐解いてもかなり上位に来るんじゃないだろうか。ロックとして聴いても十分に凄みがある。さまざまな場所での音源を集約しているものの、メンバーは固定されており、テオ・マセロの編集(サックスやギターはかなりカットされているらしい)により、ライヴ演奏であるにもかかわらず完成度が高い。1枚のアルバムとしての統一感もある。新メンバーの演奏スタイルは当然70年代のメンバーとは異なり、洗練されている。サウンドも同様に時代相応に洗練されている。ただ、有機的なインタープレイの連続(長尺演奏もたっぷり)を聴いていると、音楽の本質的な部分、核の部分は実は70年代のときとそう変わっていないことに気づく。80年代のマイルスはどうも軽くて聴く気がしない(自分のこと)という人は、まずここから聴くのがおすすめ。キーボードの音が最小限ということもあって、サウンドに古さをあまり感じないし、バンドがタイトに聴こえるところもこのアルバムの美点。(2020年4月3日) | ||
| Star People | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★★ マイルス入門度:★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1982/8/11 [6] 1982/8/28 [1] 1982/9/1 [4][5] 1983/1/5 [2] 1983/2/3 [3] [1] Come Get It [2] It Gets Better [3] Speak [4] Star People [5] U'n'I [6] Star On Cicely |
Miles Davis (tp, key) Bill Evans (ss, ts, synth) Mike Stern (g) John Scofield (g [2][3]) Marcus Miller (elb except[3]) Tom Barney (elb [3]) Al Foster (ds) Mino Cinelu (per) |
| ヘヴィなギターサウンドに導かれ、パーカッションが乱れ打ち、アグレッシヴに始まるオープニングに魂を持っていかれる。マーカスのベースが太くウネリ、マイルスがスーパー・ハイテンションに切れ込む。ギターのカッティングも新しい。[1][3]はライヴで、特に圧倒される。曲調がアップテンポで激しければアグレッシヴという単純な話ではない。ゆったりテンポの[2]や、この時代になぜ?という18分に及ぶスロー・ブルースの[4]でも演奏は、いささかの停滞感もなく、充実した空気が漂っている。ミュートでポップなテーマを繰り返す[5]も、淡々と軽快に締める[6]も力が溢れている。サウンドは確かに、一部で当時ならではのキーボード音が入っていたり、ドラムサウンドが時代相応だったりはするものの、音楽はしっかり攻めている。だから当時の流行サウンドであっても古臭さがない。前作が新レギュラー・メンバーの演奏力を前面に押し出したものだったのに対して、その演奏力を下地にしつつ、作り込まれた音楽であり、通して聴くアルバムとして完成度が高いところも本作の魅力。(2020年4月3日) | ||
| Decoy | ||
 曲:★★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★ マイルス入門度:★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1983/6/30,7/1 [4] 1983/7/7 [5][7] 1983/9/10,11 [1][-[3][6]) [1] Decoy [2] Robot 415 [3] Code M.D [4] Freaky Deaky [5] What It Is [6] That's Right [7] That's What Happened |
Miles Davis (tp, synth) Branford Marsalis (ss [1][3][6]) Bill Evans (ss, [5][7]) Robert Irving III (synth [1][2][3][6]) John Scofield (g [1][3][5]-[7]) Darryl Jones (b except [2]) Al Foster (ds) Mino Cinelu (per) |
| 前作から1年も経っていないにもかかわらず、サウンドがガラリと変わっている。長年のパートナーとも言えるテオ・マセロがプロデューサーから外れていることが大きな要因であることは間違いない。まず、ドラム・サウンドが違う。打ち込みと聴き間違えるようなタイトで引き締まったサウンドは、ルーズなフィーリングを持つアル・フォスターの特質とはある意味真逆な音ではあるけれど、まさにこの時代の音で、従来までとサウンド・カラーが別物に聴こえる大きな要因になっている。このタイトなドラム・サウンドに乗るアーヴィングのシンセサイザーのシャープな音と、幅広く柔軟なフレージングを駆使するダリル・ジョーンズに交代したこともサウンドが数歩進んだことを印象付ける。前半にその新しさを象徴する曲を集め、「んん?アル・フォスターでなきゃいけないの?」と疑問が頭をもたげはじめると、後半の[5][7]のライヴであのリズム感が顔を出し(それでも硬い音に加工されている)、バンド全体の自由度が高まる。サウンド作りに一貫性がありつつ、前半と後半で音楽表現に幅を持たせたことで最初から最後まで一気に聴かせてしまう。前作までは、若いメンバーの演奏とその時代のテクノロジーが新しさを作っていてはいたものの、本質的には70年代マイルスの延長にあった。でも、このアルバムは音楽が明らかに新しくなっている。そして今聴いても古さを感じさせない。マイルスは前作のように吹きまくってはいないけれど、フレーズは冴えているし、本作は80年代のサウンドが板についているだけでなく、音楽としてのクオリティが高いところが魅力。あまり採り上げられることがないアルバムだけれど、間違いなく名盤。(2020年4月4日) | ||
| You're Under Arrest | ||
 曲:★★★ 演奏:★★★ ジャズ入門度:★ マイルス入門度:★★★ 評価:★★ |
[Recording Date] 1984/1/26 [1] 1984/12/26,27 [1]-[3][8][9] 1985/Jan [4]-[6] [1] One Phone Call /Street Schenes [2] Human Nature [3] Intro: MD1 /Something's On Your Mind /MD 2 [4] Ms. Morrisine [5] Katia Prelude [6] Katia [7] Time After Time [8] You're Under Arrest [9] Jean Pierre / You're Under Arrest /Then There Were None |
Miles Davis (tp, voice [1], synth[5][6]) Bob Berg (ss, ts) [1][8][9] Kenny Garrett (as [2]) John Scofield (g [1]-[3][7]-[9]) John McLaughlin (g [4]-[6]) Rovert Irving III (synth) Darryl Jones (b) Al Foster (ds [1][7]-[9]) Vince Wilburn (ds [2]-[6]) James Prindiville (handcuffs [1]) Steve Thornton (per, voice [1]) Sting (voice [1]) Marek Olko (voice [1]) |
| マイルス・デイヴィスを熱心に聴くようになってかれこれ15年以上は経つ。でも長らく、80年代のマイルスは聴いていなかった。チラッと聴いて「ポップだし音楽的にも面白くない」と思っていたから。では、そのチラッと聴いたのは何かというとこのアルバム。より詳しく言うと、誰もが知る有名曲[2][7]を聴いたことによって「何もマイルスがコレやらなくてもいいのでは?」と刷り込まれた。もちろん、有名曲を採り上げたことじたいが悪いわけではない。しかし、原曲のイメージのままで演奏し、歌メロをミュートでなぞっているだけの演奏に魅力はない。でも、それはマイルスがやりたかったことなのかもしれない。そういう意味で言うと、常に音楽的に攻め続けてきたマイルスがついに停滞した、いや後退、メロウ化した初めてのアルバムだとも言える。ほかの曲はさすがにこの2曲ほど日和っていないけれど、今となっては古臭いシンセサイザー、シンセドラムのサウンド、そしてバンドサウンドそのものがとても軽々しい。80年代の他のアルバムを聴くようになると、益々このアルバムは魅力に欠けるように思えてしまう(2020年4月5日) | ||
| Aura | ||
 曲:★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★ マイルス入門度:★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1985/1/31-2/4 [1] Intro [2] White [3] Yellow [4] Orange [5] Red [6] Green [7] Blue [8] Electric Red [9] Indigo [10] Violet |
Miles Davis (tp) Benny Rosenfeld (tp, flugelhorns) Idrees Sulieman (tp, flugelhorns) Jens Winther (tp, flugelhorns) Palle Bolvig (tp, flugelhorns) Perry Knudsen (tp, flugelhorns) Jens Engel (tb) Ture Larsen (tb) Vincent Nilsson (tb) Ole Kurt Jensen (btb) Axel Windfeld (btb) Axel Windfeld (tuba) Jesper Thilo (reeds, fl) Per Carsten (reeds, fl) Uffe Karskov (reeds, fl) Bent Jadig (reeds, fl) Flemming Madsen (reeds, fl) Bent Jadig (sax, woodwind) Flemming Madsen (sax, woodwind) Jesper Thilo (sax, woodwind) Per Carsten (sax, woodwind) Uffe Karskov (sax, woodwind) Kenneth Knudsen (key) Ole Kock Hansen (key) Thomas Clausen (key) Bjarne Roupe (g) John McLaughlin (g) Niels-Henning Orsted Pedersen (b) Bo Stief (elb) Vincent Wilburn (ds) Lennart Gruvstedt (ds) Vincent Wilburn (elds) Ethan Weisgaard (per) Marilyn Mazur (per) Lillian Thornquist (harp) Cor Angels (oboe, English horn) Niels Eje (oboe, English horn) Eva Hess-Thaysen (vo) Palle Mikkelborg (additional tp, flugelhorn) |
| リリースは89年。パレ・ミッケルボルグというデンマークのトランペッター、作曲家、アレンジャーが企画したものにマイルスが乗ったもの。大編成バンドでありながら、サウンドは当時のトレンドに乗ったもので、[1]から(当時の)モダンな音で迫る。マイルスは、ただトランペットを吹いているだけ。しかし、そのトランペットがイイ。[4]は[1]同様にアグレッシヴ路線でマクラフリンが弾きまり、引き継いでマイルスがミュートでクールに決め、オープンに切り替えて更にカッコいいソロを決める。こうしたビート(ドラムはシンセに完全に置き換わった)がハッキリした曲以外は、キーボードがフワフワと漂う(=ビート感のない音楽)中に、マイルスのリリカルなトランペットが響く曲が多い。無機質な環境音楽的シンセ・サウンド(大編成を感じさせる曲はほとんどない)はともかく、このリリカルなトランペットを堪能できるのはマイルスの全アルバムの中でも最右翼に来る(「死刑台のエレベーター的でもある)。ただし、アルバムの内容は80年代作品中では前後の連続性をあまり感じない単発企画モノといったムートが漂う1枚ではある。世間の評価は悪いらしい。ただ、マイルスのソロは聴きどころがあり、特に静かな曲での表現は50〜60年代を思い起こさせるほど素晴らしいことについては重ねて強調しておきたい。(2020年4月4日) | ||
| Rubberband | ||
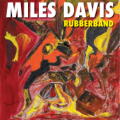 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★ マイルス入門度:★★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1985 [1] Rubberband of Life [2] This Is It [3] Paradise [4] So Emotional [5] Give It Up [6] Maze [7] Carnival Time [8] I Love What We Make Together [9] See I See [10] Echoes in Time"/"The Wrinkle [11] Rubberband |
Miles Davis (tp, key, synth) Adam Holzman (key) Neil Larsen (key) Wayne Linsey (key) Randy Hall (g, programing [8]) Zane Giles (g, b , ds programing, key) Lalah Hathaway (vo [4]) Michael Paulo (ts, as. fl) Glenn Burris (sax) Mike Stern (g [11]) Cornelius Mims (b) Vince Wilburs (ds) Steve Reid (per) |
| 「TUTU」製作の前にあったレコーディング・セッションを2019年9月に発掘リリース。仕上げたのはオリジナル・セッションのプロデューサーであったランディ・ホールとゼイン・ジャイルズ。そこにドラマーのヴィンス・ウィルバーンが加わっている。リズム・セクションを録り直したり、新たにボーカル・パートを付け足して完成させたことで、2019年に聴ける今のサウンドの仕上げで再生されている。よって、それほど古さは感じさせない。もちろん、常に一歩進んでいたマイルスであることを思うと、このサウンドでも今の耳には「進んでいる」という印象ではないけれど、2019年に聴けるアルバムとして上手く仕上がっている。内容は前後のアルバムとは異なり、ファンク、R&B(50年代のではなく90年代以降のR&Bのことです)を中心とした多彩なブラック・ミュージックという趣。恐らくオリジナル・セッションから相当手が加えられているんじゃないかと思えるくらい、今聴いて違和感はない(そうかと言って新しくもない)。しかし、上手く仕上げている故に、音楽としてのマイルスはあまり感じない。マイルスの音楽は常に独特な緊張感があるものだけれど(そこが苦手な人もいるはず)、その緊張感がここにはない。そういう意味で、やはり純度100%のマイルス・ミュージックとして聴くには抵抗がある。でも、要所でマイルスのトランペットが入るとムードが変わり、マイルスを聴いてることを強く実感させるところのもまた事実。マイルス独自の緊張感が希薄な聴きやすさの中に、マイルスのカッコよさを味わうことができるという意味で、若く新しいリスナーに80年代のマイルスを広く聴かせるという意味で、むしろ入り口に適しているかもしれない。(2020年4月5日) | ||
| TUTU | ||
 曲:★★ 演奏:★★★ ジャズ入門度:★ マイルス入門度:★ 評価:★★ |
[Recording Date] 1986/2/6 [5] 1986/2/10 [4] 1986/2/11 [1] 1986/2/13 [3] 1986/3/12-25 [2][6]-[8] [1] Tutu [2] Tomaas [3] Portia [4] Splatch [5] Backyard Ritual [6] Perfect Way [7] Don't Lose Your Mind [8] Full Nelson |
Miles Davis (tp) Marcus Miller (elb, g, synth, drum machine programming, bcl, ss, other instruments) George Duke (all instruments except per, elb, tp) [5] Adam Holzman (synth solo [4]) Bernard Wright (synth [2][7]) Micha? Urbaniak (elvln [7]) Omar Hakim (ds, per [2]) Paulinho da Costa (per [1][3]-[5]) Steve Reid (per [4]) Jabali Billy Hart (ds, bongos) |
| バッキング・トラックは、[5](ジョージ・デューク)を除いてマーカス・ミラーの制作で、生ドラムらしき部分はあるものの、基本はシンセサイザー、シーケンサー、ドラムマシンを主体にした、いわゆる80年代打ち込みサウンド。そこにマイルスのトランペットが乗ってくる。というか実際、できあがったバッキング・トラックにマイルスが音を重ねている。ロックやジャズの魅力は、人間が、人間らしい(ある意味不安定な)演奏をして、複数の人数で演奏するとできる間や空気感、ズレがあるところにあると思っている僕は、機械が演奏する100%正確な音楽には面白みをほとんど感じない。もちろん打ち込みすべてがダメだと思っているわけではない。機械のように正確だからこそ描ける(表現できる)音楽というのもあり、例えば(共同プロデュースが噂されていた)プリンスなどは打ち込みの使い方が上手く、打ち込み=音楽のクオリティが低いというわけではないことを立証している。良くも悪くも使い方次第の打ち込み、そしてこのアルバムも聴き始めは、カッコいい、さすがマイルスと言いたくなる。聴き始めだけでなく、マイルスのトランペットは一貫してカッコいい。しかし、音楽のバリエーションが乏しく、同じ様なカラーの曲がずっと並んでいるところが辛く、途中で飽きてしまう。マーカス・ミラーは音楽クリエイターとしてそこまで才能が豊かではないことが露呈してしまっているように思う(マイルスは気に入ってみたいですが)。また、今の耳で聴けば、サウンドにも新しさを感じることはなく、特にキーボードとシンセドラムの音が古めかしい。故に80年代作品の中ではもっとも陳腐化してしまったアルバムになってしまっているのが残念。ジャケットはカッコいいんだけど。(2020年4月1日) | ||
| Amandra | ||
 曲:★★★☆ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★ マイルス入門度:★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1988/Sep-1989/Jan [1] Catembe [2] Cobra [3] Big Time [4] Hannibal [5] Jo-Jo [6] Amandla [7] Jilli [8] Mr. Pastorius |
Miles Davis (tp) Marcus Miller (elb, key, bcl except [5][6]), ss [1][3]), guitar [1][4][7], ds[1]) Kenny Garrett (as except [2][8]), ss [2]) Rick Margitza (ts [5]) Michael Landau (g [2]) Foley (g [3][4][7]) Jean-Paul Bourelly (g [3][5]) John Bigham (g, key, ds programming) Billy "Spaceman" Patterson (wah-wah guitar [7]) George Duke (key) Joey DeFrancesco (key [2]) Joe Sample (p [6]) Jason Miles (synth [8]) Ricky Wellman (ds [3][7]) Omar Hakim (ds [4][6]) Al Foster (ds [8]) Don Alias (per [1][3][6]) Mino Cinelu (per [1]) Paulinho Da Costa (per [4][5]) Bashiri Johnson (per [6]) |
| マーカス・ミラーがほとんどの曲を書いたという点では、前作「TUTU」と同じではあるものの、サウンドの感触はだいぶ異なる。「TUTU」は演奏もほとんどマーカスが手掛けていたのに対して、本作は多くのメンバーが演奏に加わっているからだ。サウンドの傾向も大きく変わったわけではないけれど、音楽の色彩感が増しているのは間違いない。シンセサイザーの音と熟れてきて、サウンドの古臭さも薄まっている。それだけのことで、否、それだからこそ、音楽が豊かになっている。バンドでの演奏によることで音楽というのはこれほどまでに生きてくるのだと思い知らされる。だから、このアルバムは80年代のサウンドであっても、時代遅れな感じがあまりしないし、純粋に音楽として楽しめる。マイルス最晩年の中ではプロダクションとしてもっともまとまりがあり、演奏もクオリティが高い。(2020年4月2日) | ||
| Doo-Bop | ||
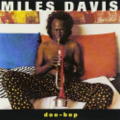 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★ マイルス入門度:★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1991/Jan-Feb [1] Mystery [2] The Doo-Bop Song [3] Chocolate Chip [4] High Speed Chase [5] Blow [6] Sonya [7] Fantasy [8] Duke Booty [9] Mystery (Reprise) |
Miles Davis (tp) Easy Mo Bee (programing, rap [2][5][7]) Deron Johnson (key) J.R (rap [2]) A.B. Money (rep [2]) |
| 音楽は、ヒップホップ/ラップ・ミュージシャンのイージー・モー・ビー。当然ながら、ヒップホップそのものの音楽。ちなみに、アメリカではヒップホップ/R&B売上がロックを超えたと言われているほどジャンルとして浸透しているらしいんだけれど、僕はあまりヒップホップは好きではない。ビートが単純で音楽的には単調、メロディがなく、音楽として面白くないから。でも、その単調なリズムに乗る歌(というか喋り)と合わせて、黒人特有のグルーヴ(僕は大柄な黒人男性がノッシノッシと歩いている姿を連想する)があり、そのグルーヴ感こそが愛されて理由であるように思う。僕だけではなく、日本にまったく浸透していないのはそのグルーヴ感が日本人には馴染みづらいから(グルーヴ感をまったく意識していない形だけの日本語ヒップホップはまったく別物)。そんな僕が苦手なヒップホップ、しかし全面的に拒絶しているかというとそうではなく、例えばロバート・グラスパーを聴くのに抵抗感はないし、80年代後半にヒップホップを積極的に採り入れていたプリンスの当時のアルバムも好んで聴いている。要は、ヒップホップそのものが退屈なのではなく、扱う人次第で良いものにも、つまらないものにもなり得る、という当たり前の結論に行き着く。本作は、そんなヒップホップに乗っかり、ミュートで切り込むマイルスを聴くアルバム。サウンドはプリンスの「Love Symbols」のころに近いように思う。曲のバリエーションに意外と幅があり、通して聴いてもまったくダレない。マイルスのミュートは終始カッコよく、今の耳には新しく聴こえるはずのない当時のサウンドが、ほとんど褪色していない。それはつまり、パフォーマーがホンモノであるからという理由に他ならない。ちなみにマイルスとイージー・モービーは6曲分を制作したところでマイルスが故人となり、ラバーバンド・セッションから[4][7]を転用、全体仕上げはイージー・モービーが行っているため、アルバムの仕上げにマイルスはかかわることができていない。(2020年4月6日) | ||
