���b�N�E�t�@���̂��߂̃W���Y�ē��̃w�b�_�[
Rock Listner's Guide To Jazz Music
���̑�
| Booker Little | ||
 �ȁF������ ���t�F�������� �W���Y����x�F���� �]���F������ |
[Recording Date] 1960/4/13 1960/4/15 [1] Opening Statement [2] Minor Sweet [3] Bee Tee's Minor Plea [4] Life's A Little Blue [5] The Grand Valse [6] Who Can I Turn To |
Booker Little (tp) Wynton Kelly (p) Tommy Franagan (p) Scott La Faro (b) Roy Haynes (ds) |
| �G���b�N��h���t�B�[�Ƃ̃R���{�ɂ��uAt The Five Spot Vol.1�v�Ȃǂł́A���܂�ɂ��f���炵�����t�ŗL���ȃu�b�J�[�E���g���̃��[�_�[�E�A���o���B�����Ɍ����ƃt�@�C���E�X�|�b�g�قǂɂ͖����ɂȂ�Ȃ��B�����͘^����Ԃɂ���B60�N���Ƃ����̂ɉ_�����������悤�Ȗ��ȃR���������邵�A�e�y��̉��������J�ɍ��E�ɐU�蕪���Ă��ċɂ߂ĕs���R�ȉ���ł���Ƃ��낪�c�O�B���y�I�Ȋϓ_�Ō���ƁA�����ł̉��t�͊m���ɃW���Y�A�������V�嗬�h�Ƃ��܂������قȂ����V�����t�B�[���[���O�������Ă���B�����q�l�����ȂƂ�╗�ς��ȃ����o�[�̑g�ݍ��킹�ɂ��A���ł͒����Ȃ��Ɠ��̃��[�h�̃W���Y�ɂȂ��Ă���̂͊m���B�\�ʓI�ɂ̓A���@���M�����h�ł͂Ȃ����̂́A���l�����ȃT�E���h�ł��Ȃ��B�܂��A�����ł̃g�����y�b�g�́A�t�@�C���E�X�|�b�g�̂Ƃ������}���ځA�������A���_�炩�߂̃g�[���ŐL�т₩�ɐ����X�^�C���ŁA�N�[���őM��������������B�X�R�b�g�E���t�@���̎Q���͋M�d�Ȃ̂Ńt�@���Ȃ瓖�R���ڂ��ׂ��B�����Ă��̃��j�[�N�ȃT�E���h�ł���a���Ȃ��n�����߂郍�C�E�w�C���Y�̌��Ɉ،h�̔O������Ă��܂��B�i2006�N9��11���j | ||
| Modern Art / Art Farmer | ||
 �ȁF�������� ���t�F������ �W���Y����x�F�������� �]���F������ |
[Recording Date] 1958/9/10 1958/9/11 1958/9/14 [1] Mox Nix [2] Fair Weather [3] Darn That Dream [4] The Touch Of Your Lips [5] Jubilation [6] Like Someone In Love [7] I Love You [8] Cols Breeze |
Art Farmer (tp) Benny Golson (ts) Bill Evans (p) Addison Farmer (b) Dave Bailey (ds) |
| �A�[�g�E�t�@�[�}�[�Ƃ����l�͂Ȃ�Ƃ��\���ɍ���g�����y�b�^�[���B���[�E���[�K����t���f�B�E�n�o�[�h�̂悤�Ƀo���o�������܂���킯�ł��Ȃ�A�}�C���X�E�f�C���B�X�̂悤�ȃN�[����������킯�ł��Ȃ��A�P�j�[�E�h�[�n���̂悤�Ȉ��D������킯�ł��Ȃ��B�������e�N�j�b�N���Ȃ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ�����ǁA����Ƃ������������Ȃ��B���̃A���o���͂Ȃ��݂̂���Ȃ����グ���Ă��邵�A�x�j�[�E�S���\���̕ҋȂƑ��܂��Ď��ɒ����₷���B���̔��ʁA����������Ƃ�������ɂȂ��A�����ȃt�@�[�}�[�̃g�����y�b�g���������薡�키�n�D�B�r���E�G���@���X�̎Q���ɖڂ��s�����̂́A�e���ɓO���Ă��ăG���@���X�炵���͔�������ȃn�[�h�o�b�v�I���t�Œʂ��Ă���A�����܂ł�����u���ȃT�E���h�ɂȂ��Ă���B�ł��l�͂Ȃ����h�i���h�E�o�[�h�����t�@�[�}�[�̏a����~���Ă��܂��Ƃ����Ƃ��ǂ�����B�i2006�N6��3���j | ||
| Meet The Jazztet / Art Farmer & Benny Golson | ||
 �ȁF���������� ���t�F�������� �W���Y����x�F���������� �]���F�������� |
[Recording Date] 1960/2/6 1960/2/9 1960/2/10 [1] Serenata [2] It Ain't Necessarily So [3] Avalon [4] I Remember Clifford [5] Blues March [6] It's All Right With Me [7] Park Avenue Potite [8] Nox Nix [9] Killer Joe |
Art Farmer (tp) Benny Golson (ts) Curtis Fuller (tb) McCoy Tyner (p) Adison Farmer (b) Lex Humphries (ds) |
| �A�[�g�E�t�@�[�}�[�A�x�j�[��S���\���A�J�[�e�B�X�E�t���[�ɂ��3�ǕҐ��̂��̃O���[�v�͓���̃��[�_�[�����߂��A�W���Y�e�b�g�𖼏��B�������Ȃ���A�Ȗڂ����Ă��\�z�ł���ʂ�S���\���̃J���[���Z���B���̃S���\���E�n�[���j�[�́A�N���̃\���ł��w��Ńn�����3�Ljȏ�̕Ґ��ł�����萶����Ƃ���������O�̂��Ƃ����߂ĔF���B�������A���̃A���o���͗��j�Ɏc��悤�Ȋv�V����ɂ������̂ł͂Ȃ��B�ʊ��Ƀ`�������W����[4]�ɂ��Ă��A�A�[�g�E�u���C�L�[�̏\����[5]�ɂ��Ă��I���W�i���̉��t�̕����ǂ��A�Ƃ������I���W�i�����z���悤�Ƃ����C�����������Ȃ��A�h�����͑S�̓I�Ƀ����b�N�X���Ē�����W���Y��ڎw���Ă���B�����āA�_���ʂ�y�����S�n�悭������̂́A��͂�S���\���̋ȂƃA�����W�ɕ����Ƃ��낪�傫���B�l�I�ɂ�[6]�Ńe�[�}�������A[7]�ł͈�]�_�炩�����F�Ŗ�������t���[�̃g�����{�[������ۂɎc��B���Ȃ݂ɂ��̃A���o���A�܂��f�p�ȃ}�b�R�C�E�^�C�i�[�̃f�r���[��Ƃ��Ă��m���Ă���B�i2006�N12��19���j | ||
| Star Bright / Dizzy Reece | ||
 �ȁF�������� ���t�F���������� �W���Y����x�F���������� �]���F���������� |
[Recording Date] 1959/11/19 [1] The Rake [2] I'll Close My Eyes [3] Groovesville [4] The Rebound [5] I Wished On The Moon [6] A Variation On Monk |
Dizzy Reece (vib) Hank Mobley (ts) Wynton Kelly (p) Paul Chambers (b) Art Taylor (ds) |
| �}�C���X�E�f�C���B�X����^�����Ƃ���邱�ƂŒm���A�������A�����Ĉ�ʓI�m���x�������Ȃ��f�B�W�[�E���[�X�B���t�̓I�[�\�h�b�N�X�Ȃ���A�Ȃ�قǂ������肵���e�N�j�b�N���������ǂ��g�����y�b�^�[�ŏ\���ɒ������l������Ǝv���B�Ȃ��I�[�\�h�b�N�X�ŁA[1]�����u���[�X�ł�������肵�Ă�����̂́A�o���[�h���Ȃ����Ƃ������ăA���o���S�̂�ʂ��Ċ��C����X�E�B���O������ۂɎc��B��������o���Ă���̂́A���͂��̃A���o���̒����ǂ���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��T�C�h���ł߂�u���[�m�[�g�Ŕ~���[�W�V���������B�����̃X���[�Y�ȃt���[�Y�̒��ɂ��͋����������Ă��郂�u���[�A�y���Ŕ����Ƃ����X�E�B���O���̒����𐬂��Ɠ����Ɍ�����������Ղ�Ƃ���E�B���g���E�P���[�A�������ƔS���ό����݂ɌJ��o���|�[���E�`�F���o�[�X�A�o��������ڗ������������Ȃ����̂̃o���h���v�b�V�����Ă���A�[�g�E�e�C���[�̃h�����A���ׂĂ��������őS�����x�X�g�ƌĂ�ō����x���Ȃ��D�v���C�B�������A59�N�Ƃ������㑊���ɁA�]���̃n�[�h�o�b�v���͏��������i�������������Ă��Â������������Ȃ��v���ɂȂ��Ă���B����̒m���x�̒Ⴓ�̂����Œ������@����Ȃ��̂��Ƃ����炠�܂�ɂ����������Ȃ��A�I�[�\�h�b�N�X�Ōy���ȃ��_����W���Y���D���Ȑl�Ȃ�K����1���B������u���[�ƃP���[�̃t�@�����K���B�i2008�N12��13���j | ||
| Smithville / Louis Smith | ||
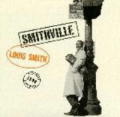 �ȁF�������� ���t�F���������� �W���Y����x�F�������� �]���F�������� |
[Recording Date] 1958/3/30 [1] Smithville [2] Wetu [3] Embraceable You [4] There Will Never Be Another You [5] Later |
Louis Smith (tp) Charlie Rouse (ts) Sonny Clark (p) Paul Chambers (b) Art Taylor (ds) |
| ����u���[�m�[�g�́A���X�̗L���A�[�e�B�X�g�̖��Ղ��������ŃW���Y�̗��j�ɖ��O���o�Ă��Ȃ��悤�Ȑl�̃��[�_�[�E�A���o�������Ȃ��炸����B���̃��C�E�X�~�X���A���̑�\�i�̈�l�B�Ȃ�ł��w�Z�̐搶���{�E�ŁA���P�����ău���[�m�[�g�Ɍ}�������ꂽ�炵���B���̃g�����y�b�g�͓��ɃN�Z������킯�ł͂Ȃ����̂́A�r�̂ق��͊m���Ńh�i���h�E�o�[�h��A�[�g�E�t�@�[�}�[�ȂǂƔ�r���Ă������Č���肵�Ȃ��B�����ɁA�������A�X�s�[�h���A�_���������\�����Ȃ��`�F���o�[�X�A�茘���\�c�̂Ȃ��A�[�g��e�C���[�A���D��тт��V���v�����u���[�W�[�ȃ\�j�[�E�N���[�N�Ƃ��������̃u���[�m�[�g�����̃��Y���E�Z�N�V���������S�̃T�|�[�g�B�Ƃ肽�ĂČ��I�ł͂Ȃ��`���[���[�E���E�Y�̃e�i�[�����̑g�ݍ��킹�ɗǂ������B�X�s�[�f�B�ȃv���C����o���[�h�܂Ńn�C���x���ł��Ȃ����[�_�[�̖��͂ƃn�[�h�E�o�b�v�Ȃ�Ր̉��t���ւ�T�C�h�E�����̌������ݏo�Ă��Ă������������ǂ��B�m���x�̒Ⴓ�����Ōh������̂͂��������Ȃ��D�ՁB�i2008�N2��16���j | ||
| Complete Communion / Don Cherry | ||
 �ȁF������ ���t�F�������� �W���Y����x�F���� �]���F������ |
[Recording Date] 1965/12/24 [1] Complete Communion a. Comlete Communion b. And Now c. Golden Heart d. Remembrance [2] Elephantasy a. Elephantasy b. Our Feelings c. Bishmallah d. Wind, Sand And Stars |
Don Cherry (colnet) Leandro " Gato" Barbieri (ts) Henry Grimes (b) Ed Blackwell (ds) |
| �I�[�l�b�g�E�R�[���}���̃p�[�i�[�Ƃ��Ēm����A�Ƃ���������ł����m���Ă��Ȃ���������h����`�F���[�̃��[�_�[�E�A���o���B�����ł��y�߂̉��Ń`�F���[�炵���v���C�����Ă���B�T�E���h�̃L�[�ɂȂ��Ă���̂̓K�g�[�E�o���r�G���ŁA�A���[���`���o�g�Ń��e���̃|�b�v�ȃt�B�[�����O���A���@���M�����h�ɒ�������v���C�̓`�F���[�̎������Ƒ������ǂ��B�Ȃ�2�Ȃ݂̂ł���������ڂł���Ȃ���A�`�F���[�ƃo���r�G���̗��݁i��Ȃ���Ă��镔���j�ƃA�h���u�E�p�[�g���I���D������ĖO�������Ȃ��B�Z�V���E�e�C���[�̃O���[�v�ł��m���A�������𑗂荞�ރw�����[�E�O���C���X�ƃX�R���X�R���Ə��C���ǂ��h���~���O�̖��F�G�h�E�u���b�N�E�F���Ƃ����I�����Ó��Ƃ��������B�������l�̏ꍇ�A�o���r�G���̃��e���Ȃ��ǃA���@���M�����h�Ƃ����������X���S�n�������A�ʂ��Ē����Ă����̃������������c���Ă��܂��B�i2008�N9��13���j | ||
| Where Is Brooklyn? / Don Cherry | ||
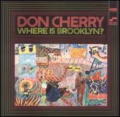 �ȁF���� ���t�F���������� �W���Y����x�F���� �]���F�������� |
[Recording Date] 1966/11/11 [1] Awake Nu [2] Taste Maker [3] Thing [4] There Is the Bomb [5] Unite |
Don Cherry (colnet) Pharoah Sanders (ts, piccolo) Henry Grimes (b) Ed Blackwell (ds) |
| ���t���T�E���h���\�z�𗠐�Ȃ����̂ŁA���̂�����Ɗ�ȃ��[�h���������f�B�ƃt���[�Y�������ʂ�ɓW�J���Ă���B�G�h�E�u���b�N�E�F���̏����݂ŏ�݂�����悤�ȃh��������ۓI�ȃs�A�m�E���X�Ґ��͋��m�̃T�C�h�E�������x���Ă���Ƃ����ĈӊO���͂Ȃ��A�D���Ȑl�ɂ͈��S���Ē�����B���̃A���o���́A����ȃ`�F���[�ɂƂ��Ẳ������y�Ƀt�@���I�E�T���_�[�X�������č��ׂ�_�����Ǝv����1���B�t�@���I�E�T���_�[�X�͈ӊO�ɂ����ʂɐ����Ă���V�[����������̂́A���̃m�C�W�[�ȃt���[�Y���y���A�`�F���[�̃R���l�b�g�Ɨ��ނƂ���͂�͂�X�������O�B�^�������ɊJ���͂��邯��ǁA�����I�ɂ̓R���g���[�����}�����`�F���[�̃��[�_�[�E�A���o���������uThe Avant-Garde�v�Ƃ̒�����ׂ��ꋻ�B�i2006�N9��9���j | ||
| Backstone Legacy / Woody Shaw | ||
 �ȁF������ ���t�F���������� �W���Y����x�F���� �]���F���������� |
[Recording Date] 1970/12/9-10 [1] Backstone Legacy [2] Think On Me [3] Lost And Found [4] New World [5] Boo-Ann's Grand [6] A Deed For Dolphy |
Woody Shaw (tp) Gary Bartz (as, ss) Bennie Maupin (ts, bcl fl) George Cables (p, elp) Ron Carter (b except [1]) Clint Houstone (b except [3]) Lenny White (ds) |
| �G���b�N�E�h���t�B�[����[�E�����O�ȂǁA60�N��̑O�q�h�~���[�W�V�����ɎႢ�Ƃ�����T�C�h�E�����Ƃ��ċN�p����Ă����E�f�B�E�V���E�B���̉s���e�N�j�J���ȃg�����y�b�g�͈�x�����u�����A�R�C�c�̓f�L��v�Ǝv�킹����͂�����Ȃ���A�Ⴆ�t���f�B�E�n�o�[�h�ȂǂƔ�ׂ�ƒm���x���Ⴂ�B�Q���A���o���ɗL���Ղ��Ȃ����Ƃ������ď����ɖڂ�ʂ��Ă����O���������邱�Ƃ͏��Ȃ��A����Ƀ��[�_�[�E�A���o���ƂȂ�Ƙb��ɂ��Ȃ邱�Ƃ���H�B�����ł��̃A���o���A���ꂪ���̃��[�_�[�E�A���o���ł����Ȃ�i�A�i���O�j2���g�A�g�[�^��78���Ƃ����{�����[���B�Ȃ͒Z����9���A14���ȏ�̋Ȃ�3�ȂƂ�����쑵���A�����ă����o�[��2�l����Ă��邱�Ƃ���`���ă}�C���X�E�f�C���B�X�́uBitches Brew�v�Ƃ̋ߎ��������w�E����Ă�����e�B����ł������Ă݂�A�Ƃɂ����J�b�R���������Ő�[�̃W���Y�B���́u�����Ő�[�v�Ƃ������t�A�����ăl�K�e�B���ȈӖ��ł͂Ȃ��A���̎���łȂ���ΐ��܂꓾�Ȃ��A�����������Ă��܂�ŌÂтĂ��Ȃ��Ƃ����^���Ǝ~�߂Ă������������Ƃ���B�����āuBitches Brew�v�̃I���W�i���e�B�Ɣ�ׂ�Ƃ����œW�J����Ă���̂͂����܂ł��W���Y�ł���Ƃ��낪�ǂ��Ƃ���B�������Ƀ}�C���X�E�O���[�v�̃����o�[�������Q�C���[�E�o�[�c�́A�����ł͌����������������d�݂����t���[�Y�ňꖡ�Ⴄ�Ƃ�������A�uBitches Brew�v�ł͒ቹ�ŕ��V���邾���������������x�j�[�E���E�s�����������ƃA�u�X�g���N�g�Ƀo�X�N���ƃe�i�[�Ō������u���[�B���[�_�[���܂߂�3�l�̃u���[�����Œ����ǂ���\���ȂƂ���A����ȃs�A�m�Ƙc�G���s��2�ʐ���ł��o���W���[�W�E�P�C�u���Y�̍D�v���C�Ń_�������B�����ăh�^�o�^�������������̂Ȃ����j�[�E�z���C�g�̃h������2�{�̃x�[�X�����݁A���ׂ��������Ă����l�͂����X�������O�Ƃ��������悤���Ȃ��B�V���E�̃g�����y�b�g�͑f���炵���A�����Ď��ɑO�q�I�ɉ̂��Ă��ĉ��t�҂Ƃ��Ă̗͗ʂ����\�ł���B���̃��[�_�[�E�A���o���ł���ȃJ�b�R�������y������Ă��܂������Ƃ����l�ɏ^�����ׂ��ł��傤�B�i2007�N4��29���j | ||
| Choices / Terence Blanchard | ||
 �ȁF�������� ���t�F�������� �W���Y����x�F�� �]���F�������� |
[Recording Date] 2009/3/5-8 [1] Byus [2] Beethoven [3] D's Choice [4] Journey [5] Hacia Del Aire [6] Jazz Man In The World Of Ideas [7] Him Or Me [8] Choices [9] Hugs (Historically Underrepresented Groups) [10] Winding Roads [11] When Will You Call [12] New Note Angel [13] New World (Created Inside The Walls Of Imagination) [14] Touched By An Angel [15] Robin's Choice |
Terence Blanchard (tp, synth) Walter Smith �V(sax) Lionel Loueke (g) Fabian Almazan (p) Derrick Hodge (b, elb) Kendrick Scott (ds, per) Dr. Cornel West (spoken word) Bilal (vo, effects) |
| 2009�N��3���Ƀu���[�m�[�g�����ŊςāA�D��ۂ������e�����X�E�u�����`���[�h�A���̒���̃A���o���B���̂Ƃ��̉��t�ȂƃJ�u���Ă��邩�ǂ����͒肩�łȂ��B�Ȃ��Ȃ�Ȃɒ݂͂ǂ��낪�Ȃ��A���ۓI�Ȃ��̂���������B�������A���C���ł̓J���e�b�g�������Ґ����g������A���H�[�J���⎍�̘N�ǂ炵�����̂���������Ƃ��Ă��A�\�����悤�Ƃ��Ă��鐢�E�͂����������u���Ă��Ȃ��B���̊i���������y���́A�C�y�ɃW���Y�����Ƃ��������ɂ͏d������B�Ƃ��������y�I�ɂ͈�ʂŃC���[�W����Ă���W���Y�̘g���͂ݏo�Ă��܂��Ă���̂͊ԈႢ�Ȃ��B����ł��A����ɂ̓W���Y�ɑ��郊�X�y�N�g�ƌւ肪�m���ɂ���A�\�ʓI�Ȍ������������ʂ���N���o��u���b�N�E�~���[�W�b�N�̐^������邱�Ƃ��ł���B����ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����̂́A����̓A���@���M�����h�ȕ������ł͂Ȃ��v���[���\���ɕ����Ƃ��낪�傫���B��x�����Ă��̖��͂𗝉����邱�Ƃ���������ɁA���̊��o�ɂЂ��������������邱�Ƃ��ł���A���̐[���m�肽���Ȃ�A���x�����������Ȃ�ɈႢ�Ȃ��B���炭�͌h������鉹�y�ɂ͈Ⴂ�Ȃ�����ǁA���ꂪ����̃W���Y�ł���Ƃ����u�����`���[�h�̎咣���т��ꂽ�R���Z�v�`���A���ȃA���o���Ɏd�オ���Ă���BBGM�Ƃ��ė����̂ł͂Ȃ��A�I�[�f�B�I�̑O�ɂ�����������Ē������݂����B�i2009�N8��23���j | ||
| Standard Time Vol.1 / Wynton Marsalis | ||
 �ȁF�������� ���t�F���������� �W���Y����x�F������ �]���F������ |
[Recording Date] 1986/5/29, 30 1986/9/24, 25 [1] Caravan [2] April In Paris [3] Cherokee [4] Goodbye [5] New Orleans [6] Soon All Will Know [7] Foggy Day [8] The Song Is You [9] Memories Of You [10] In The Afterglow [11] Autumn Leaves [12] Cherokee |
Wynton Marsalis (tp) Marcus Roberts (p) Robert Leslie Hurst III (b) Jeff Wats (ds) |
| ����̃g�����y�b�^�[�Ƃ��čō��̕]�����A�|�p�ƃW���Y�E�~���[�W�V�����Ƃ��Ĉ����Ă���Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��E�B���g���E�}���T���X�B���̒��ł������ɓn���āA�����Ƃ��x������Ă���̂����̃A���o���B������݂̋Ȃ��A���͎҃T�C�h�E�����ɏ]���ĉ��t�B���̉��t���x���͂܂��ɍŏ㋉�B�}�C���X�Ƃَ͈��̃n�[�h�{�C���h���Ŕ���[1]�A���C���ǂ��~���[�g�E�g�����y�b�g�𐁂�����ΉE�ɏo����̂��Ȃ��Ǝv�킹��[3]�A�_�炩���Â��g�[���Ŕ���[4]�ȂǁA�����ǂ���͑����A�E�B���g���̊����ȃg�����y�b�g�����\�ł���B�������A�u�ǂ����h�C�L���āv �Ƌ��₳��郀�[�h�͂����ɂ������āA���̂�����ɍD���������ʂ��Ƃ���B�{���V���v���ȓ`���I�ȃW���Y��^�ʖڂɒNjy�������邠�܂�A�����ăW���Y�������Ȍ|�p�Ƃ��ĕ\�����邱�Ƃɏ�M���X���Ă����ē�����Ă��܂����E�B���g��������ǂ��A�����ł͔�r�I�f���ȕ\���ŃX�^���_�[�h�����t���Ă���Ƃ��낪�l�C�̗��R�̂悤���B�ł��l�́A�����Ă��邤���ɂǂ�ǂނ��Ă��܂������Ȃ�E�B���g���̏d�ꂵ�����ǂ������Œ��Ղ���͂�����ƕt����������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�㔼�ł́A�e���|��A���I�����݂ɕς��čs��[11]���ʔ������Ȃ��Ǝv���邭�炢�B�i2006�N11��18���j | ||
| Selections From The Village Vanguard Box / Wynton Marsalis |
||
 �ȁF���������� ���t�F���������� �W���Y����x�F�������� �]���F���������� |
[Recording Date] 1990-94 [1] Welcome [2] The Cat In The Hat Is Back [3] Embraceable You [4] Reflections [5] Buggy Ride [6] I'll Remember April [7] Misterioso [8] Flee As A Bird To The Mountain [9] Happy Feet Blues [10] Cherokee [11] Juba And A O'Brown Squaw [12] Local Announcements |
[1] [2] [7] [10] Wynton Marsalis (tp) Todd Williams (ts, ss, clarinet) Wessell Anderson (as) Wycliffe Gordon (tb) Mercus Roberts (p) Reginald Veal (b) Herlin Riley (ds) [8] [9] Wynton Marsalis (tp) Victor Goines (ts, ss, clarinet) Wessell Anderson (as) Wycliffe Gordon (tb) Eric Reed (p) Reginald Veal (b) Herlin Riley (ds) [3]-[6] [11] [12] Wynton Marsalis (tp) Victor Goines (ts, ss, clarinet) Wessell Anderson (as) Wycliffe Gordon (tb) Eric Reed (p) Ben Wolfe (b) Herlin Riley (ds) |
| 7���g�uLive At The Village Vanguard�v�{�b�N�X�E�Z�b�g����A�^�C�g���ʂ�Z���N�g����1���Ɏ��߂����́B�Z�v�e�b�g�Ґ��Ƃ����āA�J�b�`���Ƃ����z�[���E�A���T���u���ƃX�e�f�B�ȃ��Y���E�Z�N�V�������o�b�N�ɁA�E�B���g�������R�z���ɐL�ѐL�тƃg�����y�b�g�𐁂��B�Ȃ�Ƃ����Ă��ǂ��̂́A�E�B���g�����L�̐h�C�L�����������Ȃ��Ƃ���B����͑��̃����o�[�ɂ������邱�ƂŁA�ЂƂ��ƂŌ����ĉ��t���y�����B����Ȋy�����ƍ��x�ȉ��t�����܂��o�����X�����㎿�ȃW���Y�����킦��B�N���u�ł̃��C���ł��邱�Ƃ����̊y���������o���Ă���A�Ƃ����v�f�����Ȃ��炸���肻���B�O���̓R���{�R�Ƃ������t�ŁA�㔼�̓o���h�S�̂Ō��㕗�j���[�I�[�����Y�E�W���Y���������ɍČ������Ȃ����S�Ƃ����ăE�B���g���̏o�Ԃ͂�⏭�Ȃ߂Ȉ�ہB�^�������̓o���o���Ȃ̂ɂ�������炸���ꊴ������̂��s�v�c������ǁA���̃N���u�ɂ̓o���h���C���X�p�C�A�����鉽�����������̂����B�E�B���g���̃W���Y�͓`�����d�Ă��Ȃ���A���̓`���I�W���Y�������Ă��������炩����ɂ��A�y�����Ɍ����Ă��āA�������܂�Ȃ��Ƃ����̂��l�̈ӌ��Ȃ���ǁA���̃��C���ɂ͂��������`���I�W���Y�̖��͂�����Ƃ��낪�����B�i2007�N2��11���j | ||
| Live At The House Of Tribes / Wynton Marsalis | ||
 �ȁF�������� ���t�F���������� �W���Y����x�F���� �]���F�������� |
[Recording Date] 2002/12/15 [1] Green Chimneys [2] Just Friends [3] You Don't Know What Love Is [4] Donna Lee [5] What Is This Thing Called Love [6] 2nd Line |
Wynton Marsalis (tp) Wessell Anderson (as) Eric Lewis (p) �������� (b) Joe Farnsworth (ds) Robert Rucker (per [1] [2] [5] [6]) Orland Q. Rodriguez (tambourine [6]) |
| �`������W���Y������Ɍp������ׂ��A�������蕶���I�̐l�ɂȂ��Ă��܂����E�B���g���E�}���T���X���v���Ԃ�ɃN�C���e�b�g�Ґ��ŃX�^���_�[�h�����t�A�������������ł̃��C���Ƃ����Ă��Ȃ蒍�ڂ��ꂽ�A���o���B���N�̃u���[�m�[�g�̐��_���p���W���P�b�g���܂��J�b�R�����B���Ċ̐S�̉��t�́A������Ղɂ��Ă���W���Y�E�I�[�P�X�g���Ƃ͈���ăR���{�E�W���Y�̔M�C����������B�E�B���g���͂������A�����҂̉��t���M���B�g�����y�b�^�[�Ƃ��ẴE�B���g���������Ɋ��������悭�킩��B����ŋ������̂̓A���g�E�T�b�N�X�̃t���[�W���O�����\�A���@���M�����h�Ō���I�ł��邱�ƁA�s�A�m�̃g�[�������Ȃ�_�[�N�Ȋ��������邱�ƂŁA�����V���A�X�ȉ��t�ɃE�B���g���̐��^�ʖڂ��������ƁA�Ȃ�Ƃ��u�V�сv�̂Ȃ������ȃW���Y�Ƃ�����ۂ��Ă��܂��B���肫����ȃX�^���_�[�h���A�����̂��C�y�W���Y�Ɋׂ��Ă��Ȃ��̂́A����ȃE�B���g���̌��ł���Ƃ킩���Ă��Ȃ�����A�l�͎_����Ԃő��ꂵ���Ȃ��Ă��܂��B�t�@���̐l�ɂ͓{��ꂻ�������ǁA�W���Y�̕��y�Ɏ��S���Ă���E�B���g���̃W���Y�́A���͂����Ƃ����S�҂���������C����Ɉ��Ă���悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B�i2007�N2��11���j | ||





