ロック・ファンのためのジャズ案内のヘッダー
Rock Listner's Guide To Jazz Music
Freddie Hubbard
| Open Sesame | ||
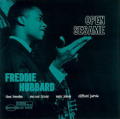 曲:★★★☆ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★ ハバード入門度:★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1960/10/19 [1] Open Sesame [2] But Beautiful [3] Gypsy Blue [4] All Or Nothing At All [5] One Mint Julep [6] Hub's Nub [7] Open Sesame (alt take) [8] Sypsy Blue |
Freddie Hubbard (tp) Tina Brooks (as) McCoy Tyner (p) Sam Jones (b) Clifford Jarvis (ds) |
| フレディ・ハバード初のブルーノートでの録音であるとともに初のリーダー・アルバム。他のブルーノートとはやや傾向が異なる人選は、ハバードの選択だったのかそれともアルフレッド・ライオンの選択だったのか。ドラマーのクリフォード・ジャーヴィスはスピーディでシャープな演奏が持ち味で、やや淡白な印象。テナーのティナ・ブルックスは適度にスタイリッシュでなかなかの腕の持ち主ながらあまりクセはない。マッコイ・タイナーは[2]のバラードでチャーミングなピアノを聴かせてはいるもののアクは控えめ。サム・ジョーンズもオーソドックスなタイプで、つまりバックの演奏は全体にアッサリ軽めな印象。たはいえ、不足感はなくハバードを引き立てる役割としてわきまえているとも言えるし、55年ころのハード・バップ世代から一世代分若い顔ぶれだけあってフレッシュな時代相応のサウンドが心地よい。コルトレーンのアルバムに参加していたころのハバードの演奏にはまだ見るべきものが少なかったんだけれど、ここでは既にハバードならではという個性が確立されていて、シャープかつ伸びやかなトーンを駆使した実に気持ち良い歌いっぷりを楽しめる。ちなみに、ハバードは後に「器用貧乏」「テクニックの見せびらかし」「アドリブに決め手がない」などと揶揄されるようになる。昔も今も技術に長けた演奏家に対して表現力がないとか深みがないとかケチをつける人が必ず出てくる。後のハバードを聴いても、そんなに技術だけに頼ったトランペッターだとはまったく思わないし、ちゃんと技術が表現に昇華してると僕は感じている。もちろんハバードのトランペットが嫌いな人がいてもいいんだけれど、テクニックを批判することでジャズの奥深さがわかっているかのように振舞う風潮は悲しい。(2006年9月12日) | ||
| Hub Cap | ||
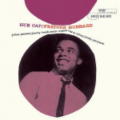 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★★ ハバード入門度:★★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1961/4/9 [1] Hub Cap [2] Cry Me Not [3] Luana [4] Osie Mae [5] Plexus [6] Earmon Jr. [7] Plexus (alt take) |
Freddie Hubbard (tp) Jimmy Heath (ts) Julian Priester (tb) Ceder Walton (p) Larry Ridley (b) Philly Joe Jones (ds) |
| トランペットに加え、テナー・サックスにトロンボーンという構成はハバード在籍時のジャズ・メッセンジャーズと同じ。思えばブルーノート時代のハバードは、ジャズ・メッセンジャーズと共通点のある編成やメンバーでリーダー・アルバムを何枚か吹き込み、それぞれになにかを試されているかのように見えなくもない。このアルバムではJM的な3管を生かした厚いハーモニーによるアレンジが随所に施されており、そこにハバードらしさを出せるかどうかのトライアルだったのだとしたら、その結果はどうだったんだろうか。硬質でいかにもテナーらしい音が特徴のジミー・ヒース、やはりいかにもトロンボーンらしいオーソドックスなサウンドのジュリアン・プリースターは、力量的にサイド・メンとしては申し分なく、シダー・ウォルンはじめリズム・セクションもソツがない。周囲に突出した個性があるわけではないところが、まず、ハバードが引き立つ要因になっている。また、厚いハーモニーがあるからこそ、ハバードのテクニカルかつよく歌うトランペットがより浮き立ち、ハバードらしさを遺憾なく発揮することができている。トライアルの結果は文句なしの合格だったに違いない。曲(ハバード4曲、ウォルトン1曲)も含めて、この時代相応の「ハードバップの次」というフレッシュな空気もいい。フィリー・ジョー・ジョーンズが比較的スマートなドラミングで通しているのでジャズ・メッセンジャーズみたいなサウンドは好きだけど、ブレイキーのあの暑苦しいドラムがどうも(そんな人いるのか?)という人にもこのアルバムはいいかもしれない。(2015年12月12日) | ||
| Ready For Freddie | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★☆ ハバード入門度:★★★★ 評価:★★★★☆ |
[Recording Date] 1961/8/21 [1] Arietis [2] Weaver Of Dreams [3] Marie Antoinette [4] Birdlike [5] Crisis |
Freddie Hubbard (tp) Wayne Shorter (ts) Bernard McKinney (euphonium) McCoy Tyner (p) Art Davis (b) Elvin Jones (ds) |
| フレディ・ハバードがサイド・メンとしての参加したアルバムは数知れないし、リーダー・アルバムも数多く残している。そんなハバード自身が、もっとも自分の意思を反映して製作できたと胸を張る1枚がこのアルバム。テクニックはあるけど自由にやらせると決め手がない、という評価もあって本人が自由にやれたからという理由で自薦するこのアルバムはどうか・・・という懸念は無用。このメンバーで悪いはずがない。ハバードは思ったほどバリバリと吹きまくっておらず、柔らかいトーンを駆使して伸び伸びと素直に歌っているところが好ましい。ショーターは出番はそこそこながらオリジナル曲の[3]を提供し、プレイも伸びやかで素晴らしい。リズム・セクションをコルトレーン・カルテットから拝借しているのは、当時のフレディの嗜好を表したものだったということでしょう。特にエルヴィンは大きなウネリを作り出しつつ、スピード感とキレも申し分ないという流石の演奏で、[2]のバラードではハバードの美しいプレイをブラッシュ・ワークで効果的に曲を盛り上げる小技も見せる(あまり話題にならないけれどエルヴィンのブラシ使いは一級品)。尚、ユーフォニウムというジャズでは馴染みのない楽器は、トロンボーンの音をホルンに近づけたような甘い音色が特徴のジャズにはあまり向いていない楽器で、プレイヤーの演奏自体も特筆するほどのものではない。3管メッセンジャーズの雛形的な役割も果たしたこのアルバムは、新主流派の緊張感の中にもリラックスした感覚に溢れていて本当に素晴らしい。[4]はV.S.O.P の「The Quintet」での演奏と、[5]はジャズ・メッセンジャーズの「Mosaic」での演奏と聴き較べるのも一興。(2006年9月11日) | ||
| Hub-Tones | ||
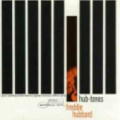 曲:★★★★☆ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★★ ハバード入門度:★★★★★ 評価:★★★★☆ |
[Recording Date] 1962/10/10 [1] You're My Everything [2] Prophet Jennings [3] Hub-Tones [4] Lament For Booker [5] For Spee's Sake [6] You're My Everything (alt take) [7] Hub-Tones (alt take) [8] For Spee's Sake (alt take) |
Freddie Hubbard (tp) James Spaulding (ts) Herbie Hancock (p) Reggie Workman (b) Clifford Jarvis (ds) |
| ハバードのリーダー・アルバムの中でも話題に上ることがほとんどない理由は、オーソドックスな内容だからと思われるけれど、[1](と別テイクの[6])を除いて全曲ハバードのオリジナルで占めるブルーノートらしい構成。50年代のハード・バップより明らかにフレッシュな響きはまさに新主流派と呼ぶにふさわしいし、音楽家として時代をリードしているという挟持も感じられる。もちろんそれはサイドメンの好演に負うところも大きく、盟友スポールディングはもちろん、やはりハンコックの瑞々しいタッチがなんとも素晴らしく、レジー・ワークマンのノリも60年代的。もちろんハバードのトランペットは快調そのものでテクニカルでありながら捻りすぎということもなく伸びやかかつブリリアント。活気に満ちた演奏だけでなく、[1]やブッカー・リトルに捧げた[4]といったバラードで見せる表現力も特筆モノ。60年代初期のジャズとしてこんなにカッコよく、しかも安心して聴けるアルバムはそうはない。(2008年6月25日) | ||
| Here To Stay | ||
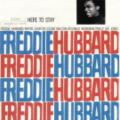 曲:★★★★☆ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★★ ハバード入門度:★★★★★ 評価:★★★★☆ |
[Recording Date] 1962/12/27 [1] Philie Mignon [2] Father And Son [3] Body And Soul [4] Nostrand And Fulton [5] Full Moon And Empty Arms [6] Assunta |
Freddie Hubbard (tp) Wayne Shorter (ts) Ceder Walton (p) Reggie Workman (b) Philie Joe Jones (ds) |
| 「Hub-Tones」からわわずか2ヵ月後の録音とあって、方向性としては延長線上にある。ハバードのトランペットは伸びやで技巧も完璧。バラードでの表現力も申し分なく歌心に溢れていて惚れ惚れする。フレディ・ハバードってどんなトランペッターなの?という方には真っ先にお勧めしたいアルバム。前作との違いはオリジナル曲が2曲だけに留まり、代わりにリー・モーガンの「Lee-Way」でも曲を提供しているカル・マッセイの曲が2曲採用されていること。共演者は在籍中のジャズ・メッセンジャーズ(以下JM)からアート・ブレイキーを除いてそのまま拝借。フィリー・ジョー・ジョーンズが独特のリズム感はそのままに意外や理性的なドラミングを披露していることから全体にフレッシュなイメージでJMと少し異なるムードになっている。また、ここではショーターの曲提供はなくテナーに専念、しかしそのテナーの響きはいつも通りでファンなら満足できるパフォーマンス。シダー・ウォルトンのピアノは「Hub-Tones」のハンコックと比べると地味ながら、垢抜けていて控えめなファンキーさが持ち味。レジー・ワークマンの柔軟なベースは少しダークな面を持ちつつ、こちらも程良く洗練されている。このように新主流派的フレッシュな演奏を求める人にも高いレベルで応えられる素晴らしく充実したサイドメンに、前述の通りハバードのカッコいいトランペットが駆け巡るところこそがこのアルバムの魅力。(2008年11月25日) | ||
| Breaking Point | ||
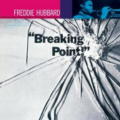 曲:★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★ ハバード入門度:★★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1964/5/7 [1] Breaking Point [2] Far Away [3] Blue Frenzy [4] D Minor Mint [5] Mirrors [6] Blue Frenzy (alt take) [7] Mirrors (alt take) |
Freddie Hubbard (tp) James Spaulding (as, fl) Ronnie Mathews (p) Eddie Khan (b) Joe Chambers (ds) |
| メンツを見るだけで先進的な内容を予感させる通り、冒頭からいきなりフリー・ジャズ的なアブストラクトな展開とムード。ハバードもスポルディングもフリーキーに切れ込み、その種の聴き手を喜ばせたかと思うと、カリプソ風に急転する展開は面白いのか気持ち悪いのかよくわからない。後のライヴ盤「The Night Of Cookers」ではそのカリプソ風の部分を延々に繰り返し、アドリブパートの下地リズムとしてダラダラ利用されていたけれど、ここでは部分的な導入に留め、あくまでもフリーキーな演奏を中心に置いているためにハバードのテクニカルかつメカニカルなトランペットが響き渡る。[2]でも新主流派的かつフリー寄りの演奏が続き、ロニー・マシューズの手堅い新感覚ピアノとジョー・チェンバースの柔軟なリズムが印象に残る。ハバードのトランペットは前述の通り、批判する人にとって絶好の餌食になりそうなくらいテクニカルで時にトリッキー。逆に言えばそんなハバードが好きな人にはたまらない自由奔放で力の入った演奏。このテンションとムードはジョン・コルトレーンの「Ascention」やウェイン・ショーターの「All Seeing Eye」と共通するものがある。[3]は3拍子のブルースでハバードのゆったりとした気持ちいい歌いっぷりとマシューズのファンキーなピアノに耳を傾けたい曲。[4]はストレート・アヘッドな新主流派ジャズで、こういう曲で伸びやかに吹くハバードのスピード感とキレは申し分なく、負けじと緊張感を高めているスポルディングのシャープなアルトも聴き逃せない。[5]はジョー・チェンバース作のバラード。美しいトランペットとフルートが印象的でコルトレーンの「Ole」に収録されている "Untitled Original Ballad" を少し連想させるのと同時に理想的なエンディングとなっている(ボーナス・トラックは無視)。硬軟とりまぜたハバードのプレイが冴えわたるハイレベルな1枚。(2007年5月11日) | ||
| Blue Spirits | ||
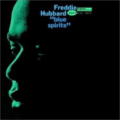 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★ ハバード入門度:★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1965/2/19 [1] [4] 1965/2/26 [2] [3] [5] 1965/3/5 [6] [7] [1] Soul Surge [2] Blue Spirits [3] Outer Forces [4] Cunga Black [5] Jodo [6] The Melting Pot [7] True Colors |
[1] [4] Freddie Hubbard (tp) Joe Henderson (ts) James Spaulding (as) Kiane Zawdi (euphonium) Harold Mabern (p) Larry Rideley (b) Cliford Jarvis (ds) Big Black (conga) [2] [3] [5] Freddie Hubbard (tp) Hank Mobley (ts) James Spaulding (as) Kiane Zawdi (euphonium) McCoy Tyner (p) Bob Cranshaw (b) Pete La Roca (ds) [6] [7] Freddie Hubbard (tp) Joe Henderson (ts) Hosea Taylor (as, bassoon) Herbie Hancock (p) Reggie Workman (b) Elvon Jones (ds) |
| 厚みのある柔らかなハーモニーを活用し、フォー・ビートに拘らない柔軟な曲で構成されつつも前衛には向かわず、トータルでフレディ流ニュー・ジャズ作りに心を砕いた印象。したがってハバードが吹きまくるというシーンは思ったよりは少なく、そこに期待すると少々ガッカリするかもしれない。それでも要所で聴かせるテクニカルなフレーズはハバードならではだし、ひけらかし的でない必然性のあるフレーズを放つ。共演者も立場をわきまえた演奏。なにぶん参加メンバーが多いので、個人に目が(耳が)行かないけれど、ジョー・ヘンダーソンとスポールディングの適度にモーダルでフリーキーな演奏が印象に残る。ハンク・モブレーも健闘しているもののここでは印象が薄い。マッコイの流暢なフレーズはいつも通りの存在感。全体としてはグループ表現を重視してじっくり聴かせることを念頭に置いており、一聴するとあまりパッとしないかもしれない。しかし音楽の質は高く、聴きこむほどに味が出てくる佳作。[6][7]はオリジナル・アルバム未収録のセッションで[7]はハンコックのチェレスタが無秩序に暴れ、ジョー・ヘンダーソンがアブストラクトなソロを展開するフリー・ジャズ・ムード漂う異色曲。全曲ハバードのオリジナルで、大編成コンボによる自己の音楽を示した意欲作。(2007年1月31日) | ||
| The Night Of Cookers | ||
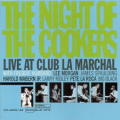 曲:★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★ ハバード入門度:★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1965/4/9,10 Vol.1 [1] Pensativa [2] Walkin Vol.2 [3] Jodo [4] Breaking Point |
Freddie Hubbard (tp) Lee Morgan (tp) James Spaulding (as) Harold Mabern (p) Larry Ridely (b) Pete LaRoca (ds) Big Black (conga) |
| フレディ・ハバードとリー・モーガンが好きな人にとってこれは堪らない。各曲約20分前後の長尺ライヴ演奏で、[1]がまさに2人のトランペット・バトル。同じ楽器の演奏者が交代でソロを取るとそれだけでバトルと称されることが多いけれど、実はただの分担であるということも少なくない中、ここで聴けるのは本当のバトル。リズム隊は、2人のトランペッターが自由にブローするために、一定のパターンを刻み続けるためだけに存在している。尚、このアルバムを手にしようとするような人にとって2人の聴き分けは容易。[2]はハバードが外れるもののアルト・サックスのスポールディングがその分を補うかのようにブローしているので悲観することはない。[3]はモーガンが外れ冒頭からハバードの熱いプレイが延々と続いたあと、中盤からベース以外の各人で長々とソロを回す。この2曲はスピーディかつアグレッシヴでリズム隊の勢いも凄い。最後は明るめのカリプソ調の曲で、[1]のようにリズム隊は同じパターンを繰り返し、ハバード、スポルディング、モーガン、メイバーン、ラロカ、ブラックの順でまたしてもソロ大会。ハイライトはもちろん[1] 。オーディエンスの盛り上がりも良く全体に楽しめる。演奏は良く言えば自由、悪く言えばダラダラとした締まりのないジャム・セッションで音楽性云々を論じるアルバムではなく、演奏も悪く言えば雑。レコードという商品の完成度を売りにするブルーノートの中では異色、そして知名度も低い作品ではあるけれど、浴びるほどトランペットを聴きたい人は是非トライを。熱い!(2006年9月9日) | ||
| Red Clay | ||
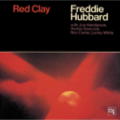 曲:★★★☆ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★ ハバード入門度:★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1970/1/27 [1] [4] 1970/1/28 [3] 1970/1/29 [2] [5] 1971/7/19 [6] [1] Red Clay [2] Delphia [3] Suite Sioux [4] The Intrepid Fox [5] Cold Turkey [6] Red Clay |
[1]-[5] Freddie Hubbard (tp) Joe Henderson (ts) Herbie Hancock (elp) Ron Carter (b) Lenny White (ds) [6] Freddie Hubbard (tp) Stanley Turrentine (ts) George Benson (g) Johnny Hammond (org/elp) Ron Carter (b) Billy Cobham (ds) Airto Moreira (per) |
| ハンコックがエレクトリック・ピアノを、ロン・カーターがエレクトリック・ベースを弾き、エイト・ビート主体のオリジナル曲を並べた、いかにも70年代を感じさせるジャズ・ロック的な作品。メンツが揃っているだけに演奏の水準は保証できる。前出の二人はマイルス・グループで初めてエレキ楽器にトライしたときにあったぎこちなさが消えて、熟れた演奏を披露していることがプラス材料。ジョー・ヘンダーソンは、フリーキーなトーンを駆使しつつも常軌を逸するまでは行かない程良いサジ加減。そして主役は、相変わらずテクニカルなフレーズを放っていて、しかし(ハバードにしては)力みが少ない。トランペットのテクニックを見せつけるというよりは音楽全体から見たプレイとでも言えば良いだろうか。それが、アルバム全体の完成度の高さとなって結実していると言える佳作。尚、ボーナス・トラックは時期の違う18分以上に及ぶ長尺ライヴ演奏で、よりオーソドックスなテナーと、よりロック的なドラマー、ギターの加入(CDにはテナー・サックスとクレジットされていてギョッとする)によって、より大衆的で聴きやすい雰囲気。言い換えるとやや凡庸ということになるか。(2006年10月29日) | ||
| Freddie Hubbard & Stanley Turrentine In Concert | ||
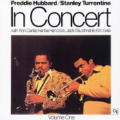  曲:★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1973/3/3 Vol1[2], Vol2 [1][2] 1973/3/4 Vol1[1], Vol2 [3][4] Vol.1 [1] Povo [2] Gibraltar Vol.2 [1] Hornets (Chicago) [2] Inrerrude [3] Hornets (Detroit) [4] Gibraltar (Detroit) |
Freddie Hubbard (tp) Stanley Turrentine (ts) Eric Gale (g) Herbie Hancock (elp) Ron Carter (elb) Jack DeJohnette (ds) |
| 当時CTIに所属していた2大スターをフィーチャーし、オールスター・メンバーでスペシャル・ライヴを行った際の記録。CTIというと、クリード・テイラーの企画力で名盤を数多く送り出してきたという印象があり、ここでもその手腕が発揮されているのではないかと期待して聴いてみる。と、ところが・・・。まず、寄せ集めメンバーとなった結果、クレジットこそ全曲メンバーのオリジナルとはいえ、かなりジャム・セッション風になっていて、まとまりやグループとしての表現を求めることはできない。ならば、自由な演奏を楽しもう。なにせこのメンバーだ。そして聴いてみると、エレクトリック・ベースとエレクトリック・ピアノによる73年という時代らしいサウンドで、自由度の高い演奏が展開されている。ところが、リーダーであり、フィーチャーしたいはずのハバードとタレンタインがそれほど目立っておらず、あくまでもジャムセッションの一員として機能している。当時、流行に遅れないために仕方なくエレクトリック・ベースを弾いていたロン・カーターがは、悪くはなんだけれどそれほど印象的なベースを弾けていない。更に驚くことに Vol.2 の[1]-[3]([2]は1分強のつなぎ曲)の演奏にはハバードとタレンタインが参加しておらず、CTIに所属してないハンコックのトリオ(ギターはいてもいなくても支障ない程度)によるパフォーマンスになっている。しかも その[1][3]は同じ曲の日にち違いで、アナログ時代ではA面に同じ曲が収録されていたということになる。ダメ押しをすると、Vol.1とVol.2でこんなにコンセプトが違うジャケットを採用するセンスも理解に苦しむ。しかし、演奏そのものは熱く、決して悪くはない。特に、聴く前には想像もしていなかった、チックとはまた違うセンスのハンコックのワイルドなエレピに耳を奪われる。マイルス・グループ時代はなんとかエレピに対応していたという印象のハンコックだけれど、ここではもう完全に自分のモノにして弾き倒している。このハンコックとドッタンバッタン、バシャバシャ叩きまくデジョネットが聴きどころ、というよくわからないコンセプトの2枚。(2011年9月23日) | ||
