ロック・ファンのためのジャズ案内のヘッダー
Rock Listner's Guide To Jazz Music
Donald Byrd
| Off To The Races | ||
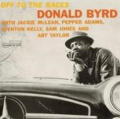 曲:★★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★★★☆ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1958/12/2 [1] Lover Come Back To Me [2] When Your Love Has Gone [3] Sudwest Funk [4] Paul's Pal [5] Off To The Races [6] Down Tempo |
Donald Byrd (tp) Jackie McLean (as) Pepper Adams (bs) Wynton Kelly (p) Sam Jones (b) Art Taylor (ds) |
| ドナルド・バードのトランペットの特徴を言葉で表現するのは難しい。もちろん一定水準以上の技量があることに疑いはなく、同業者からも理知的と評されているのに僕にはこれと言った個性を感じられない。一方で音楽家としてどうかといえば、少なくとも50年代のバードは典型的なハード・バッパーで、特にこのアルバムはそのままのイメージ。このアルバムの特徴と言えば盟友ペッパー・アダムスを含む3管編成であることで確かにバリトン・サックスの音はアクセントになっているものの、アレンジやハーモニーの点ではそれほど3管編成が取り立てて有効に生かされているようにも思えない。1曲目に有名スタンダードを持ってくるあたりもブルーノートらしからぬ没個性的な選択。アルフレッド・ライオンがこの曲を演るように指示する可能性は低いように思え、コルトレーン名義の「Black Pearls」でも取り上げていることから恐らくバードお得意のレパートリーだったのでしょう。ロリンズの[4]や、ブレイキーのブルース・マーチのドラムパターンを拝借するところなどもオリジナリティを重視するブルーノートらしからぬ構成。逆にいえばオーソドックスなハード・バップが聴きたい人には安心できる内容で、質は水準をクリア。また、バードのトランペットが実に気持ちよく歌っているのは間違いなく、その点でリーダーとしての存在感は十分示しているので「ドナルド・バードってどんなトランペッターなんだろう」という人への名刺代わりの1枚として聴ける。マクリーンは出番こそ多くないものの、あの哀愁のトーンで気持ちよくソロを放っていてその助演ぶりは隠れた聴きどころ。(2007年12月22日) | ||
| Byrd In Hand | ||
 曲:★★★☆ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1959/5/31 [1] Whichcraft [2] Here Am I [3] Devil Whip [4] Bronze Dance [5] Clarion Calls [6] The Injuns |
Donald Byrd (tp) Charlie Rouse (ts) Pepper Adams (bs) Walter Davis Jr. (p) Sam Jones (b) Art Taylor (ds) |
| マイルス・デイヴィスの、リー・モーガンの、あるいはフレディ・ハバードのトランペットが好きでたまらないというジャズ・ファンはかなり多いんじゃないかと思う反面、知名度があるにもかかわらずバードのトランペットが好きでたまらないという人はあまり見かけないのは、飛び抜けた個性を持ち合わせていないからであるように思える。このアルバムでも、そんなイメージ通りの演奏で[1]から伸びやかでリラックスしたトランペットが聴けるものの極めてオーソドックス。音楽的にはやはり適度なリラックス・ムードを備えた典型的なハード・バップで、オリジナル曲の3曲を含めて特に「バードならではの」というムードがないところがなんとも凡庸という印象に結びつく。視点を変えれば地味ながら良質のハード・バップ・アルバムでもあるので、そこに重きを置くのであれば好盤として推奨できる。同じ3管編成という点も含めて「Off To The Races」と似たムードだけれども、スタンダードを1曲だけに抑えて、オリジナリティを重んじている分だけこちらをほんの少し上と評価。(2008年1月5日) | ||
| Fuego | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1959/10/4 [1] Fuego [2] Bup A Loup [3] Funky Mama [4] Low Life [5] Lament [6] Amen |
Donald Byrd (tp) Jackie McLean (as) Duke Pearson (p) Doug Watkins (b) Lex Humphries (ds) |
| ハード・バップ時代のバードの代表作として真っ先に挙がるのがこのアルバム。というわけで、バードのアルバムとして最初に入手していたものの、さして感銘を受けたわけでもなく決して愛聴盤というわけではなかった。後に、他のリーダー・アルバムをいろいろ聴くようになった結果、なるほど、このアルバムはムードが他とは違い、独自のカラーがあることがわかってきた。ゴスペルやブルースの落ち着いたフィーリングに溢れたオリジナル曲で固められていることから全体の統一感があるし、そのムードがどこか冷めているようで演奏は熱く、「Kind Of Blue」のように聴きこむジャズとしての深みがあると言ったら褒めすぎだろうか。ここではデューク・ピアソンの洗練されたピアノとジャッキー・マクリーンの哀愁のトーンが冴え渡り、その相性がいいことも美点。バードはポケット・トランペットを吹いているせいか、微妙に軽い音色であることも他のアルバムとの差別化になっている。いずれにしても洗練されたムードのジャズを聴きたいという人は試してみる価値アリ。完成度と質の高さを認めつつ、前後のアルバムと連続性を感じないのもまたバードらしいのかも。個人的にはピアソンがMVP。(2007年10月27日) | ||
| The Cat Walk | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1961/5/2 [1] Say You're Mine [2] Duke's Mixture [3] Each Time I Think Of You [4] The Cat Walk [5] Cute [6] Hello Bright Sunflower |
Donald Byrd (tp) Pepper Adams (bs) Duke Pearson (p) Laymon Jackson (b) Philly Joe Jones (ds) |
| 「Fuego」 は、ドナルド・バードの日常の活動メンバーというよりは、一回きりの録音のためにメンバーを集めて、曲もある種のコンセプトを持たせたスペシャルなアルバムだったように思える。本作では、その「Fuego」 で素晴らしい働きをしているデューク・ピアソンをそのままに、レギュラー・グループで活動を共にしているペッパー・アダムスを再度迎え入れるという編成でスペシャル感はやや減退。バードのオリジナルが2曲に対してピアソンが3曲という構成の通り、全体的にピアソンのカラーがここでも強く、黒さと洗練のバランスが絶妙なピアソンのピアノがやはり耳を惹く。バード、アダムスのプレイも伸びやかで実に気持ちよく歌っていて、60年代のハード・バップとしてなかなか楽しめる内容。2曲で披露されているバードのミュート・トランペットも哀愁があっていい。またフィリー・ジョー・ジョーンズのルーズでラフなリズム感がなんとも魅力的。リーダーとしてのバードの存在感は?という疑問は浮かぶものの、なかなかの好盤に仕上がっている。(2007年5月31日) | ||
| Free Form | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1961/12/11 [1] Pentacostal Feeling [2] Night Flower [3] Nai Nai [4] French Spice [5] Free Form [6] Three Wighes (bonus track) |
Donald Byrd (tp) Wayne Shorter (ts) Herbie Hancock (p) Butch Warren (b) Billy Higgins (ds) |
| バードは、少なくとも50年代にはハード・バップ・スタイルのグッド・トランペッター以上の存在ではなかったと思う。しかし、このアルバムでサイドを務めるのは「合っていないのでは?」という不安を抱かせるいわゆる新主流派のショーターとハンコックに、60年代のブルーノート・ハウス・リズム・セクション。[1]でいきなり、リー・モーガンやハンク・モブレーのアルバムを思わせる、既聴感タップリの典型的な60年代ブルーノート・サウンドが聴こえてくると、「バードもそうなのか」という思いを抱いてしまう。乱暴に言えば他の曲も全体的にはその傾向にあって、ハンコック作の[2](とボーナストラックの [6])を除く全曲をバードが書き下ろしているにもかかわらず、サイド・メンのフレッシュな演奏が展開されると、ショーターかハンコックのアルバムではないかと思いそうになってしまう。ただ、そのスタイリッシュな曲とバードのトランペットは、予想と違って違和感はない。バードのコンボでデビューさせてもらったハンコックは、[2]のモーダルな美しいバラードで恩返し、ショーターはそれほどハメを外しているわけではないのに期待を裏切らない存在感。最大の聴きどころはフリーキーな[5]で、クールなスリルがたまらなくカッコいい。でも、それがバードの個性から来るものとは思えないところが少々微妙ではある。(2007年10月20日) | ||
| Mustang ! | ||
 曲:★★★☆ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1966/6/24 [1]-[6] 1964/11/18 [7] [8] [1] Mustang [2] Fly Little Bird Fly [3] I Got It Bad And That Ain't Good [4] Dixie Lee [5] On The Trail [6] I'm So Excited By You [7] Gingerbread Boy [8] I'm So Excited By You |
[1]-[6] Donald Byrd (tp) Hank Mobley (ts) Sonny Red (as) McCoy Tyner (p) Walter Booker (b) Freddie Waits (ds) [7] [8] Donald Byrd (tp) Jimmy Heath (ts) McCoy Tyner (p) Walter Booker (b) Joe Chambers (ds) |
| 66年という時代背景通りにジャズ・ロック的な軽快なリズムで[1]が始まると、なんだか「The Sidewinder」以降のリー・モーガンのアルバムを連想してしまう。スピーディーなマッコイ・タイナーのピアノに導かれて疾走する[2]もこの時代らしいムード。でもカッコイイ。ソニー・レッド、モブレー、バードのプレイにもキレがある。実は60年代のモーガンのアルバムと印象が大きく異なるところがひとつあって、それはドラマー。ビリー・ヒギンズよりも骨太なフレディ・ウェイツのドラミングはとても気持ちよく、改めてドラムの重要性を認識させてくれる。3管編成という部分をそれほど強調しているわけでなく例によってサウンド的に特筆すべき点がないバードのリーダー・アルバムだけれども、ちょっと俗っぽいソウル/ファンキーさが聴き手を選びそうな[4] 、のんびりムードの[5] 、[3]のようなバラードも織り交ぜたバラエティに富んだ曲構成とバードの伸びやかなプレイ、キレ味も流麗さも遺憾なく発揮しているマッコイの好演が印象的。ただ、アレンジやフレーズにどこかで聴いたことがあるものがチラホラ出てくるのは意図的なものなのかどうかよくわからず、僕はあんまり面白いとは感じない。64年録音のボーナストラック[7][8]はメンバーの違いがそのまま音にも出ている印象。[7]は「Miles Smiles」に収録されている演奏と比べるとなんともフツーに聴こえ、やっぱりマイル・クインテットは凄かったんだなと思うものの、ここでの軽快な演奏とよく歌っているバードのトランペットも悪くない。[8]は[6]とを聴き比べると、メンバー、編成の違いがそのまま音に現れていて、いずれにしてもごくまっとうなジャズであるところがバードという人の資質だったんだろうなと改めて思わせてくれる。(2009年3月20日) | ||

