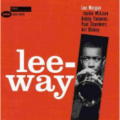ロック・ファンのためのジャズ案内のヘッダー
Rock Listner's Guide To Jazz Music
天才の名を欲しいままにしたリー・モーガン。ただし、個人的にはジャズ・メッセンジャーズのアルバムに白眉モノのプレイが多くあると思う。また、ジョン・コルトレーンの「Blue Train」における演奏は生涯でも最高のパフォーマンス。
Lee Morgan
| Lee Morgan Indeed ! | ||
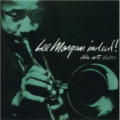 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★☆ モーガン入門度:★★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1956/11/4 [1] Rocus [2] Reggie Of Chester [3] The Lady [4] Little T [5] Gaza Strip [6] Stand By |
Lee Morgan (tp) Clarence Sharpe (as) Horace Silver (p) Wilbur Ware (b) Philly Joe Jones (ds) |
| リー・モーガンの初録音にして初のリーダー作。ちなみに、この翌日にはまったく異なるメンバーで早くも2枚目のリーダー・アルバムを録音、サヴォイから「Introducing Lee Morgan」としてリリースするという常識破りのデビュー。しかし、そんな華々しいデビューができた理由は聴けば瞬時にわかる。このトランペッターはキャリアや年齢など関係ない輝きを持っているからだということが。このブリリアントなラッパの前には、録音状態の悪さなど何のハンデにもならない。エキゾチックなメロディのテーマを持つ [1]、ベニー・ゴルソン作の [2] の2曲で弾けたトランペットを聴かせているばかりか、[3] ではバラードでの表現力も既に一流であることを見せつけている。以降も、後と比べると荒削りで未完成ながら力強くも自信に満ちたトランペットが響き続けて最後まで一気に聴かせてしまう。クラレンス・シャープのアルト・サックス、ホレス・シルヴァーのピアノ、フィリー・ジョーのドラム、いずれも主張しすぎず、しかし単なる脇役では終わらない絶妙なバランスで、アルバムのクオリティを底上げしている。トランペットとアルト・サックスの組み合わせは音が軽くて好みに合わない、ホレス・シルヴァーのピアノの良さがあまりよくわからない、という僕の苦手な要素がこのアルバムには2つもあるにもかかわらず、そんなことはまったく気にならないほどの魅力を備えている。(2006年11月19日) | ||
| Introducing Lee Morgan | ||
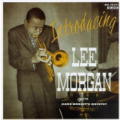 曲:★★★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★★ モーガン入門度:★★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1956/11/5 [1] Hank's Shout [2] Nostalgia [3] Bet [4] Softly, As In A Morning Sunrise [5] P.S. I Love You [6] Easy Living [7] That's All |
Lee Morgan (tp) Hank Mobley (ts) Hank Jones (p) Doug Watkins (b) Art Taylor (ds) |
| 新人の身分で、2日続けて録音したリーダー作のサヴォイ・レーベル盤。ただし、こちらはウィズ・ハンク・モブレー・クインテットという名義。初期のモーガンは音楽性云々を語るものではなく、ここでもオーソドックスなハード・バップに終始。しかし、後に多くの好盤を共に生み出すモブレーとの相性は良好で安心して聴ける。無論、注目すべきはモーガンのトランペットで、ここでも新人とは思えない華やかかつ見事な表現を聴かせる。サイド・メンは今思えばなかなか豪華であるとはいえ、どちらかといえば脇役的な顔ぶれで、ここではそれがモーガンを引き立てる形になっていてバランスが良い。ベース・ソロだけの [4] からの後半、曲が繋がっていてメドレー風に展開されるのはこの時期としては斬新なアイディアだったのかもしれないけれど、全体のまとまり、曲、ジャケット、どれを取っても「Lee Morgan Indeed!」より一段落ちるところは、そのままレーベル(サヴォイとブルーノート)との差であるとも言える。(2007年2月3日) | ||
| Lee Morgan Sextet | ||
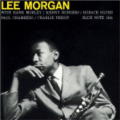 曲:★★★ 演奏:★★★ ジャズ入門度:★★★☆ モーガン入門度:★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1956/12/2 [1] Whisper Not [2] Latin Hangover [3] His Sister [4] Alightory Hep [5] Where Am I [6] D's Fink |
Lee Morgan (tp) Hank Mobley (ts) Kenny Rodgers (as) Horace Silver (p) Paul Chambers (b) Charlie Persip (ds) |
| ワイルドかつ自由奔放に吹きまくるリー・モーガンこそが最高のジャズ・トランペッターだと僕は思っている。そしてベニー・ゴルソンが作った理知的で柔らかくも洗練された曲も最高だと思っている。アート・ブレイキーのアルバム「Moanin'」は2人のコンビネーションがもたらした最高の成果であることは誰もが認めるところでしょう。ならば、ゴルソンが作曲とアレンジを4曲で担当したこのアルバムにも当然期待がかかるというもの。ところがあまり気持ちが入らない。3管のジャズテット作品「Meet The Jazztet」は気分良く聴けるし、コルトレーンの「Blue Train」におけるモーガンは最高だと思っている。なのに、どうしてこのアルバム(と次の「Lee Morgan Vol.3」)に入れ込めないのか、さんざん考えた末の結論は・・・リー・モーガンのトランペットが、過剰なゴルソン・ハーモニーに埋もれてしまっているからではないかと。ハーモニーとメロディがしっかりしすぎているカッチリしたアレンジはモーガンの手綱をガッチリと握りすぎてしまっているように思えてしまう。[1] は名曲中の名曲。それでも、「サンジェルマンのジャズ・メッセンジャーズ(au Club Saint-Germain)」の演奏の方がモーガンのトランペットが生きているように感じる。(2006年9月12日) | ||
| Lee Morgan Vol.3 | ||
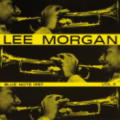 曲:★★★★ 演奏:★★★ ジャズ入門度:★★★ モーガン入門度:★★★☆ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1957/3/24 [1] Hasaan's Dream [2] Domingo [3] I Remember Clifford [4] Mesabi Chant [5] Tip Toeing |
Lee Morgan (tp) Benny Golson (ts) Gigi Bryce (as) Wynton Kelly (p) Paul Chambers (b) Charlie Persip (ds) |
| 「Lee Morgan Sextet」に引き続き、ベニー・ゴルソンの完全バックアップのもと製作されたアルバムで6人編成であるところまで前作と同じ。ただし、本作ではゴルソンがテナー奏者としても参加し、ピアノがより若い世代のウィントン・ケリーに代わっているところが違う。それでも全体の印象は前作と大差なく、3管の厚いハーモニーと柔らかなメロディに支配されたゴルソン・ワールドが全開、しっかりとデキすぎていてモーガンのトランペットが窮屈そうに感じてしまう。あと、チャーリー・パーシップは正直言って大したドラマーではないし、グルーヴ感が僕の好みに合わない。ひょっとすると前作とこのアルバムが好きになれないのはドラマーのせいかもしれないとも思えてくる。それでも前作より印象がやや良いのは、前述の通り、ゴルソンとケリーのおかげ。さんざんケチを付けておいてなんですが、曲とアレンジのクオリティは素晴らしく、普通のモダン・ジャズとは異質のサウンドは十分に個性的で、それこそがこのアルバムの価値であることに疑いはない。(2006年11月11日) | ||
| City Lights | ||
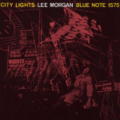 曲:★★★★☆ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★★★ モーガン入門度:★★★★ 評価:★★★★☆ |
[Recording Date] 1957/8/25 [1] City Lights [2] Tempo De Waltz [3] You're Mine You [4] Just By Myself [5] King Folks |
Lee Morgan (tp) George Coleman (ts, as) Curtis Fuller (tb) Ray Bryant (p) Paul Chambers (b) Art Taylor (ds) |
| ベニー・ゴルソンがアレンジを手がけたリー・モーガンのリーダー・アルバム最終作。前2作がそれほど気に入っていなかったにもかかわらず入手したのには理由がある。「Lee Morgan Sextet」「Lee Morgan Vol.3」の項目で、なぜ好きになれないかという推測として、トロンボーンがないからではないか、チャーリー・パーシップのドラムがいけないのではないか、という仮説を立て、その点がこのアルバムではクリアになっているから。そして結果から言うと仮説は正しかった。アート・テイラーがどんなドラマーかは他でもたくさん聴いていて知っていたとはいえ、ここで聴かせる小刻みなスネア・ワークを駆使したプレイはなかなか冴えているし、やはり安心して聴ける。そしてカーティス・フラーのトロンボーンを交えたハーモニーは心地よく、マイルス・グループで目立った成果を残せなかったという理由だけで一般的にダメなサックス奏者のレッテルを貼られているジョージ・コールマン(しかもここではアルト)がまたいい。しかし、このアルバムでフラーとコールマンはあくまでも脇役扱いで、モーガンのスペースが広いところが前2作との大きな違い。サックスとトロンボーンの柔らかいハーモニーをバックにモーガンが伸び伸びと、しかも適度にリラックスしたトーンで吹く。特に [3] は、一部ピアノ・ソロが入るものの基本的にモーガンのソロだけで、フラーとコールマンはハーモニーを付けているだけ。[4] もトランペット・ソロが長く、主役を演じている。まさにモーガンのトランペットを引き立てるための曲とアレンジ。クリフォード・ブラウンの折り目正しく律儀な演奏と違って、吹く息の強弱でアクセントを付ける奏法、そして時にわざといい加減に吹く小粋な遊び心溢れるモーガンの魅力が良く出ている。またゴルソンの曲に合った柔軟なベースを聴かせるチェンバースの活躍も聴き逃せない。適度な黒さを持つレイ・ブライアントのクセのないピアノもバランス的にちょうど良くグループとしてのまとまりという意味でもポイントが高い。モーガン=ゴルソンのコンビの最高の成果を示した1枚。(2007年4月20日) | ||
| The Cooker | ||
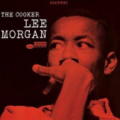 曲:★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★☆ モーガン入門度:★★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1957/9/29 [1] A Night In Tunisia [2] Heavy Dipper [3] Just One Of Those Things [4] Lover Man [5] New-Ma |
Lee Morgan (tp) Pepper Adams (bs) Bobby Timmons (p) Paul Chambers (b) Philly Joe Jones (ds) |
| 既にブルーノートにおける5枚目のアルバム、今回はクインテット編成ながら管楽器のパートナーがバリトン・サックスのひとヒネリが入る。お得意の"チュニジアの夜"はジャス・メッセンジャーズでの演奏よりもぐっとテンポを落とし、その分タメを効かせて一気に噴出するかのような熱いトランペットが炸裂、これも名演のひとつと言えるでしょう。他の曲も、モーガンのトランペットは自由奔放にブロウ。熱くブリブリと吹きまくるペッパー・アダムスのバリトンが良いスパイスとなっていて、このアルバムを特徴あるものにしているし、ティモンズのピアノは後の露骨に濃いファンキーなテイストとは違うやや控えめな感じで、そんなところもここでは吉と出ている。躍動するチェンバースに、ルーズなリズムを繰り出すフィリー・ジョーも持ち味が良く出ていて、とにかく参加しているメンバーが期待通りの働きをしているのも実はこのアルバムの美点。ゴルソンのサポートを受けていた頃のモーガンも良かったけれど、このアルバムのように自由に伸び伸びと吹いているモーガンの方がやはり魅力的。一方でベースとのデュオで始まるスローな [4] も、渋く決める [5] も素晴らしい。モーガンのリーダー・アルバムの中では話題になることがまずない本作ながら、なによりもモーガン自身のトランペットが弾けているのが大きな魅力。バリトン・サックスの重ささえ気にならなければオーソドックスなハード・バップの名作としても十分楽しめる。(2006年9月10日) | ||
| Candy | ||
 曲:★★★☆ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★☆ モーガン入門度:★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1957/11/18 1958/2/2 [1] Candy [2] Since I Fell For You [3] C.T.A [4] All The Way [5] Who Do You Love I Hope [6] Personality |
Lee Morgan (tp) Sonny Clark (p) Doug Watkins (b) Art Taylor (ds) |
| セクステットやクインテットによるアルバムばかりだった稀代の名トランペッター、リー・モーガンに次に企画されたのがワン・ホーン・カルテット編成というのは自然な流れだったのかもしれない。トランペット奏者のみのワン・ホーンとなると低音域が不足してサウンドが薄くなるため、アルバム1枚を通して聴き手を魅了し続けるのはなかなか難しく、他の一流トランペッターたちでもほとんどの場合にサックスを加えるのが通例。モーガンにとってもその条件が変わるわけではなく、いつものようにただバリバリ吹いていれば(僕はそんなモーガンが好きなんだけれど)アルバム1枚できましたというわけにはいかない。そういう理由だったかどうかは知らないけれど、ここでは、軽快な曲やスロー・バラードなどバラエティに富んだ選曲がなされ、その舞台の上でリラックスしたモーガンのプレイが堪能できる。思わず力が入ってしまうという熱演ではなく、心地よく聴けるのがポイントで、サイド・メンバーもそんな曲に合った好演で応える。特にソニー・クラークの軽快なプレイと、ブラッシュ・ワークを多用した、これまた軽快なアート・テイラーのプレイが光る。それにしても、この若きトランペッター(録音時19歳)がこのような小粋な演奏ができてしまうことに改めて感心してしまう。ただし、いくら名盤とはいえ、この1枚だけでモーガンを評価するのは早計で、ワイルドさよりも軽快さを打ち出したこのアルバムはむしろモーガンのリーダー・アルバムの中では異色作だと言える。(2006年11月11日) | ||
| Here's Lee Morgan | ||
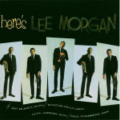 曲:★★★☆ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★☆ モーガン入門度:★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1960/2/8 [1] Terrible "T" [2] Mogie [3] I'm a Fool to Want You [4] Running Brook [5] Off Spring [6] Bess [7] Terrible (take 6) [8] Mogie (take 6) [9] I'm a Fool to Want You (take 1) [10] Running Brook (take 4) [11] Bess (take 4) |
Lee Morgan (tp) Cliff Jordan (ts) Wynton Kelly (p) Paul Chambers (b) Art Blakey (ds) |
| リー・モーガンのリーダー作の中でも人気のアルバム。録音状態も良くモーガンのトランペットも良く歌っている。特に [3](絶品バラード) [6](軽快) のようなミュート・プレイは意外と他のアルバムにはない演奏。個人的には [4] のテーマで手抜きをするところもカッコよくて好き。アート・ブレイキーのドラムは小気味良く、叩きまくりというほどではないもののブレイキーらしいプッシュはしっかり出ているし、クリフォード・ジョーダンの高音多用気味で引き締まった音色のテナーは一瞬ショーターを連想させる、というわけでちょっとジャズ・メッセンジャーズに近いムード(実際モーガン在団中)。それでも明快なトーンで明るくスウィングするケリーのピアノと、ジミー・メリットとは明らかにノリが異なるチェンバースのベースが違いを打ち出す。全体的に適度なリラックス感と緊張感を持った好演集で、メンバーはブルーノート縁の人ばかりなのにジャケットのデザインも含めて非ブルーノート的なところが面白い。尚、僕の所有している国内盤 CD は [5] を除いたすべての曲の別テイクが入っているけれど、更に別テイクを追加してオリジナル盤と2枚組に分けた輸入盤もある。(2006年11月30日) | ||
| Take Twelve | ||
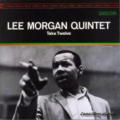 曲:★★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★★ モーガン入門度:★☆ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1962/1/24 [1] Laggedy Ann [2] A Waltz For Fran [3] Lee-Sure Time [4] Little Spain [5] Take Twelve [6] Second's Best [7] Second's Best (bonus track) |
Lee Morgan (tp) Clifford Jordan (bs) Barry Harris (p) Bob Cranshaw (b) Louis Hayes (ds) |
| 書物によると、この時期のリー・モーガンはドラッグで調子を崩していて「The Sidewinder」で見事に復活したということになっている。そんな不調時に実はリバーサイドの傍流レーベルであるジャズランドに残されていたのがこのアルバム。確かに全体にパッとしないんだけど意外と悪くない。「The Sidewinder」の布石とも思える新しいリズム感を備えた軽快な [1]、スローでムーディな [2]、オーソドックスなウォーキング・ベースで展開されるファンキーな [3]、ゆったりとしたワルツの [4] など、曲調もバラエティに富んでいて飽きさせない。クリフォード・ジョーダンは出番も多くて太く鋭いフレーズは存在感があるし、弦を弾く様子が生々しく捉えられているボブ・クランショウの自在なベース・ワークと堅実で多彩なリズムを操るルイ・ヘイズのドラムも良く、中低音を中心にブルーなトーンに徹したバリー・ハリスの地味なピアノも合っている。モーガンはオリジナル曲を4曲書き下ろし、自作への意欲が見えるし、燃焼度はそれほどでなくとも随所で聴かせる節回しはやはりさすがと思わせる。でも通して聴くとやっぱり地味。曲がパッとしないせいだろうか。(2007年5月31日) | ||
| The Sidewinder | ||
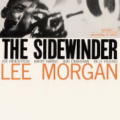 曲:★★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★★★ モーガン入門度:★★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1963/12/21 [1] The Sidewinder [2] Totem Pole [3] Gary's Notebook [4] Boy, What A Night [5] Hocus-Pocus [6] Tetem Pole (alt take) |
Lee Morgan (tp) Joe Henderson (ts) Barry Harris (p) Bob Cranshaw (b) Billy Higgins (ds) |
| リー・モーガンの代表作とされている本作は、一般的にはエイトビートを主体としたジャズ・ロックのハシリと言われている。とはいっても楽器構成は既存のジャズとなんら変わりないオーソドックスなクインテットとあって、サウンドやフレーズだけを聴いても今の耳ではさして斬新とは思えない。ごく簡単に言えば、ここで展開されているのはノリが良く親しみやすいジャズ。テーマなどはひとヒネリしながらもR&Bやファンクのようにわかりやすく、曲がよく練られたものであることが明白にわかる。そういった曲の完成度こそが本作の最大の美点で、やんちゃでどこかカッコつけたモーガンのトランペットとキャラクターが、全体のサウンドと軽快な曲によくマッチしているところがまた魅力。その溌剌としたサウンドの印象はヒギンズのいつも以上に小気味良いドラムといつになくアッケラカンとしたフレーズを放つジョー・ヘンダーソンに負うところも大きい。リー・モーガンの最初の1枚として聴かれることが多いこのアルバム、わかりやすいことに加え、ノリの良さととっつきやすさが全体に現れていて、それが統一感を生み出している反面、方向性を絞ったことでモーガンのある一面にだけフォーカスされたものであるのも確か。(2008年6月23日) | ||
| Search For The New Land | ||
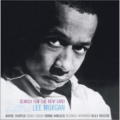 曲:★★★☆ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★ モーガン入門度:★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1964/2/15 [1] Search For The New Land [2] The Joker [3] Mr. Kenyatta [4] Melancholee [5] Morgan The Pirate |
Lee Morgan (tp) Wayne Shorter (ts) Grant Green (g) Herbie Hancock (p) Reggie Workman (b) Billy Higgins (ds) |
| 「The Sidewinder」から一転、シリアスなムードの印象が強いアルバム。メンバーで共通しているのはヒギンズのドラムだけで、こうメンバーが変われば内容もこうなります、という感じか。コルトレーンの "Spiritual" をなんとなく思わせる、15分にも及ぶ [1] はモーガンの曲の中でも異色の重厚さ。[2] [3] ではうって変わって軽快な曲で、しかしそれでも突き抜けた明るさとはまた違うどこか腰の据わった重みがあり、以降もそんな空気は最後まで続く。思うにこれはレジー・ワークマンの重いベースとショーターのムードのせいではないかという気がする。実際、ショーターのリーダー・アルバムに入っていてもいいような曲もある。モーガンもそんなムードに合わせつつ、それでもいつも通りに切れ込むあたりはさすがといったところか。ショーターと組んでもジャズ・メッセンジャーズとムードが異なるのは、ハンコックのモーダルなピアノ、ヒギンズのリズム感、そしてグラント・グリーンの泥臭いギター(ただしここではあまり個性が発揮できていない)に負うところが大きい。しかし、この組み合わせがモーガンの資質に合っているのか合っていないのかよくわからない微妙なバランスで、それこそが実はこのアルバムの聴きどころ。僕の勝手な想像では、結局この路線(?)はモーガンのキャラに合っていないと判断されて、以降継続されなかったのではないかと思うんだけれど、同じような内容のアルバムばかり作っていた60年代のモーガンの作品の中では異彩を放っているのも確か。(2007年4月30日) | ||
| Tom Cat | ||
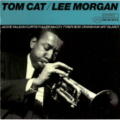 曲:★★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★★ モーガン入門度:★★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1964/8/11 [1] Tom Cat [2] Exotique [3] Twice Around [4] Twilight Mist [5] Riggarmortes |
Lee Morgan (tp) Jackie McLean (as) Curtis Fuller (tb) McCoy Tyner (p) Bob Cranshaw (b) Art Blakey (ds) |
| 60年代のリー・モーガンのアルバムでドラマーと言えばほとんどがビリー・ヒギンズ。しかし、本作はアート・ブレイキーがドラムを叩いているところが最大のトピック。その他のメンバーを見てもわかる通り、ジャズ・メッセンジャーズ番外編的アルバムでもある。内容がまたその期待を裏切らないもので、しかも演奏の質も相当高い。この時期、ニュー・ジャズ道を邁進していたマクリーンは太く鋭い音でショーターも顔負けのブロウ、フラーも充実絶頂期、マッコイ・タイナーまでもがシダー・ウォルトンに見劣りしないジャズ・メッセンジャーズ的な演奏をしているのが面白い。唸り声を上げるブレイキーの強力な推進力に乗って主役のモーガンの切れ味は増すばかりで、これがもう圧倒的という他ない。モーガンのオリジナルで占めている([4]のみマッコイ作)ものの、3管編成でどうしてもジャズ・メッセンジャーズ的になりすぎてしまっているところがお蔵入りしていた(リリースが遅れた)理由ではないかと想像してしまう。音楽的にこの時代をリードしていたかどうかはともかく、個々の演奏のスタイルは時代相応だし、いわゆるホットなジャズが好きな人なら納得できる演奏が詰まっている。エイトビートを導入してからの60年代のモーガンはどうも・・・という方に是非聴いていただきたい隠れ名盤。バンドにおけるドラマーの影響力、重要性を再認識することもできる。(2007年5月6日) | ||
| The Rumproller | ||
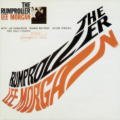 曲:★★★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★★ モーガン入門度:★★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1965/4/21 [1]-[5] 1965/4/9 [6] [1] The Rumproller [2] Desert Moonlight [3] Eclipso [4] Edda [5] The Lady [6] Venus Di Mildrew |
Lee Morgan (tp) Joe Henderson (ts) Ronnie Mathews (p) Vistor Sporiles (b) Billy Higgins (ds) |
| セールス的な成功を収めた「The Sidewinder」以降、モーガンはハード・バップの次を模索していたはず。とはいっても、60年代中盤という時代ではそれはあたりまえのことで、特に新主流派といわれる若手ミュージシャンのジャズは明らかにハード・バップとは異質の、より洗練されたものであった。そんな時代のモーガンの音楽は、時に新主流派的な演奏を取り入れつつそこまでは新しいフィーリングがあるわけではないというのが正直な印象で、エイトビートを積極的に導入して目新しさを打ち出しながら伝統的ファンキーなフィーリングが根底にはしっかりと残っているところを特徴として打ち出していたと思う。それを古臭い、あるいは中途半端と感じるか、個性と受け止めるかでこの時代のモーガンの評価が違ってくる。そんな中庸路線の始まりとなったのがこのアルバム。モーガンのトランペットは燃え盛るまでは行っていないもののまずまず好調。ジョー・ヘンダーソンも相手役として十分に期待に応えている。ヒギンズは疾走感は控えめで多彩なリズムでバラエティ豊かな曲に対応。予想外なのはロニー・マシューズがなかなかファンキーな味を出していてイイこと。ジョー・ヘンダーソンは、「The Sidewinder」よりもこちらのアルバムの方が柔軟でややルーズなムードがあって聴いた感じの印象がかなり違う。全体的に「The Sidewinder」のようなタイトさがなく、良くも悪くもルーズな演奏であるため同じものを期待して聴くと物足りないかも。あと演奏とは関係ないんだけれども、どういうわけかこのアルバム、録音状態が悪く音がコモリ気味で、そんなところも「緩い」印象を強くしている感じもする。[2] は日本の童謡 "月の砂漠"。(2007年5月11日) | ||
| The Gigolo | ||
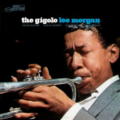 曲:★★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★★☆ モーガン入門度:★★★★☆ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1965/6/25 [2] 1965/7/1 [1][3]-[6] [1] Yes I Can, No You Can't [2] Trapped [3] Speedball [4] The Gigolo [5] You Go To My Head [6] The Gigolo (alt take) |
Lee Morgan (tp) Joe Henderson (ts) Ronnie Mathews (p) Vistor Sporiles (b) Billy Higgins (ds) |
| いかにもこの時期のモーガンお得意の、ちょっとおおらかなメロディとノリを持つエイトビートの [1] で、「ああ、またか」と思いそうになるんだけれど、ちょっとのんびりムードのこの曲がなんとも心躍るムードで良い。ヒギンズの「バシャン、バシャン」と単調でうるさいシンバルワークがなんとも俗っぽい感じがまた妙にハマっている。ショーターのソロに続いて、切れ込むモーガンは最初からキレまくり。[2] はショーター作で、確かにショーターのアルバムに入っていてもおかしくないスピーディな曲。ショーターは太い音で吹きまくり、モーガンも負けじと張りのある音と得意の節回しで応酬、そしてヒギンズがまたプッシュしまくって熱い熱い。更にショーターとモーガンのソロ・バトルが入りその熱さはもう火傷寸前。[3] のブルースもアップテンポ、この軽快さはヒギンズのドラムとメイバーンのピアノがリードしているのは間違いない。ここでもショーターはブヒブヒと吹き、モーガンが伸びやかに声高らかに歌いまくって実にカッコいい。[4]はちょっとモーダルなムードになるものの、ここでもヒギンズのドラムの元気が抑えきれないとばかりにエネルギッシュに叩きまくる。唯一落ち着き気味のエイトビート曲 [5] が最後に来るものの、これがまた流れ的にハマっているし、全体の勢いはいささかの衰えもなく、モーガンもショーターもリラックスした中にも漲る生命力を感じることができる。60年代のモーガンはちょっと気取っていて、かつての熱さがないと感じていたんだけれどこのアルバムは違う。ガイドブックに取り上げられることがほとんどないアルバムながら、ドラマーがヒギンズで定着しててからのモーガンのアルバムの中ではもっとも素晴らしい。これを聴かずして60年代のモーガンを語ってはいけない。(2007年5月1日) | ||
| Cornbread | ||
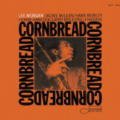 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★ モーガン入門度:★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1965/9/18 [1] Cornbread [2] Our Man Higgins [3] Ceora [4] Ill Wind [5] Most Like Lee |
Lee Morgan (tp) Hank Mobley (ts) Jackie McLean (as [1] [2] [5]) Herbie Hancock (p) Larry Ridly (b) Billy Higgins (ds) |
| ちょっと小粋なエイトビートものから始まり、いつもと変わり映えしないなあと思っていると、[2] は同時期のジャッキー・マクリーンのアルバムに入っていてもいいようなフレッシュな新主流派系の演奏になっており、曲名にしてもらった通りにヒギンズが忙しく、マクリーンを先頭にフロント・ラインが伸び伸びとブロウ。こういうスピーディな曲でのモーガンは際立つし、この時期のモブレーのテナーも侮れない。そうかと思えば [3] では一転、ラテン調リズムでのんびりとした演奏を楽しむ曲。ここではモーガンとモブレーの歌心溢れるプレイとハンコックの優しいピアノが光る。[4] もリラックスした曲でハンコックのムーディなピアノに乗ってモーガンが小粋なミュートを披露。[5] は60年代的ストレート・アヘッドな演奏で締める。突出した個性には欠けるもののバラエティに富んだ内容で、快調なフロント・ラインとハンコックの洗練されたファンキーさを楽しむ1枚。(2007年4月30日) | ||
| Delightfulee | ||
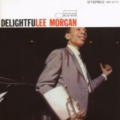 曲:★★★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★★☆ モーガン入門度:★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1966/4/8 [3] [4] 1966/5/27 [1] [2] [5] [6] [1] Ca-Lee-So [2] Zambia [3] Yesterday [4] Sunrise, Sunset [5] Night Flite [6] The Delightful Deggie |
[Recording Date] 1966/4/8 [3] [4] 1966/5/27 [1] [2] [5] [6] [1] Ca-Lee-So [2] Zambia [3] Yesterday [4] Sunrise, Sunset [5] Night Flite [6] The Delightful Deggie [1] [2] [5] [6] Lee Morgan (tp) Joe Henderson (ts) McCoy Tyner (p) Bob Cranshaw (b) Billy Higgins (ds) [3] [4] Lee Morgan (tp) Ernie Royal (tp) Wayne Shorter (ts) Phil Woods (as, fl) Tom McIntosh (tb) Jim Buffington (french horn) Danny Bank (bs, fl, bcl) McCoy Tyner (p) Bob Cranshaw (b) Philly Joe Jones (ds) |
| 僕の知識が正しければ、スタンダードと呼ばれる曲は40〜50年代に有名だったその時代の流行歌をジャズで取り上げ、その曲がジャズの演奏曲として定着したものである。そういう意味で、ビートルズ・ナンバー [3] を取り上げたのは、そういったその時代の流行歌を取り上げる手法を60年代にも適用したに過ぎない。現代のジャズ・リスナーがスタンダードと扱っている曲はオリジナル曲として有名かどうかよりも、多くのジャズ・メンが取り上げてきた曲として聴いて親しまれているのが実情。しかし、ビートルズの曲は今でも誰でも知っているためかジャズ化しなかった、いやジャズにするには向いていなかった曲だったのかもしれない。何が言いたいかというとこの曲目的でこのアルバムを聴くほどの価値はないんじゃないかなということ。5月27日のセッションは、ピアノを除いて「The Sidewinder」と同じメンバー。[1] はマッコイ・タイナーのチャーミングなピアノから始まる軽快なラテン系リズムでかなりムードが違っていて楽しい。[2] [5] は一転 「The Sidewinder」 と似たムードの新主流派系フォービート演奏でモーガンのキレ味も良好。[6] は哀愁漂うワルツでモーガンの音色とマッコイの美しいピアノが印象に残る。このアルバムのもうひとつの聴きどころはオリヴァー・ネルソンが編曲した4月8日のセッション [3] [4] で、ちょっとイージー・リスニングっぽいムード。モーガン、ショーター、マッコイのプレイはなかなか良いとはいえ、このイージーなムードが好きになれるかどうかがこのアルバムの評価の分かれ目になると思う。(2007年5月9日) | ||
| Charisma | ||
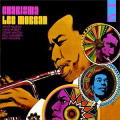 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★ モーガン入門度:★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1966/9/29 [1] Hey Chico [2] Somethin' Cute [3] Rainy Night [4] Sweet Honey Bee [5] The Murphy Man [6] The Double Up |
Lee Morgan (tp) Hank Mobley (ts) Jackie McLean (as) Cedar Walton (p) Paul Chambers (b) Billy Higgins (ds) |
| このアルバムもリラックスしたエイト・ビートから。字面を見ただけで胸が高鳴るフロント・ラインは「Cornbread」に引き続き50年代からハード・バップを支えてきた3人。モブレーは締まりのあるプレイを聴かせ、モーガンはマイ・ペース。マクリーンは同時期の自身のリーダー・アルバムにおける演奏と比べると曲によってはやや古いフィーリングで吹いている。一方でシダー・ウォルトンは50年代とは明らかに違う洗練されたファンキーさで迫り、ヒギンズの微妙にズレ感のあるタイトなドラムも健在。なるほどリズム・セクションは新しいのかと思えば、60年代になって名前を見ることが少なくなったポール・チェンバースが、エイト・ビートに合わせてベースを弾いているのがまた微妙。フロント・ラインが豪華なわりには曲が短く、つまり必然的に一人一人の出番も少なく、モーガンも以前ほどは吹きまくってはいないこともあってソロ・パートの印象はややぼやけ気味。50年代のジャズを順当に60年代へ発展させたこのサウンドも同様にぼんやりとした印象を与えるなのはこの時期のモーガン作品における共通事項で気負いのない演奏も然り。でも、そんな中庸さこそがこの時期の特徴でもある。粋で哀愁漂うテーマを持った デューク・ピアソン作の [4] がいかにもモーガンにお似合いでファンキー度満点のウォルトンのピアノも最高。[6] でブルースが出てくるあたりがまた古いんだか新しいんだかわからない微妙さだけれども、ここでもウォルトンのファンキーなピアノが炸裂。同時にモーガンの本質はやはりファンキーさにあることを再認識させてくれる。(2007年4月30日) | ||
| Standards | ||
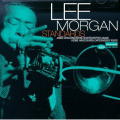 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★★ モーガン入門度:★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1967/1/13 [1] This Is The Life [2] God Bless The Child [3] Blue Gardenia [4] A Lot Of Livin' To Do [5] Somewhere [6] If I Were A Carpenter [7] Blue Gardenia (alt take) |
Lee Morgan (tp) Wayne Shorter (ts) James Spaulding (as, fl) Pepper Adams (bs) Herbie Hancock (p) Ron Carter (b) Mickey Roker (ds) |
| このアルバムのコンセプトは明確。60年代新主流派のオールスターと言ってもよい顔ぶれから刺激的な演奏を期待してしまうけれど、スタンダードをリラックスして聴かせる趣向。全曲デューク・ピアソンのアレンジでノスタルジックなムードを漂わせていて心地よい。演奏も当然それに見合ったもので、いつもは派手なブローを披露するフロント・ラインも程よく力の抜けた伸びやかなプレイ。モーガン名義のアルバムでも、モーガンのトランペットを浴びるほど聴きたいという人にはまったく向いていない。それでも演奏のスタイルそのものは確実にこの時代ならではのムードがあるし、中でも変幻自在のハンコックのピアノは確実に新しい。ノスタルジックで大らかななジャズを新しい演奏スタイルで料理するというこの企画はなかなか面白く、これはこれでアリだと思う。しかし、これもお蔵入り音源だったようで67年というジャズが混沌としていた時代にこのようなアルバムを出すことに意義が見出せないと判断されたからと想像する。尚、このリズム・セクションは後にハービー・ハンコックの「Speak Like A Child」で再会することになる。(2013年2月16日) | ||
| Sonic Boom | ||
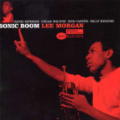 曲:★★★☆ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★ モーガン入門度:★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1967/4/14, 28 [1]-[6] 1969/9/12 & 10/10 [7]-[13] [1] Sneaky Pete [2] The Mercenary [3] Sonic Boom [4] Fathead [5] I'll Never Be The Same [6] Mumbo Jumbo [7] Free Flow [8] Stormy Weather [9] Mr. Johnson [10] The Stroker [11] Uncle Rough [12] Claw-Til-Da [13] Untitled Boogaloo |
[1]-[6] Lee Morgan (tp) David "Fathead" Newman (ts) Ceder Walton (p) Ron Carter (b) Billy Higgins (ds) [7]-[13] Lee Morgan (tp) George Coleman (ts) Julian Priester (tb) Harold Mabern (p) Walter Booker (b) Mickey Roker (ds) |
| いわゆるオクラ入りセッション2つを集約したアルバム。 1つ目は67年の録音で以前は単品としてリリースされていたものらしい。こちらのプロデュースはアルフレッド・ライオンだから、もちろんライオンの判断でオクラ入りした音源だけれど中身は相当イイ。60年代のモーガンは音楽的には主軸を見失っていると感じる部分も少なくないものの、ここでは全体的にスピーディで生気漲るストレート・アヘッドな演奏。この時期のモーガンの良きパートナー、ビリー・ヒギンズが煽り、シダー・ウォルトンが洗練されたファンキー・ピアノで料理する。つまり、当時リアル・タイムにリリースされていたアルバムと比べるとスタイルじたいがやや古いフォービート主体であることがライオンのお気に召さなかった理由なのかもしれない。しかし、今にして思えばだからこそ迷いのないカッコいいジャズに仕上がったようにも思え、やはりモーガンにはこういうスタイルが合っているんだなあと再認識させられる。馴染みの薄いテナーのデイヴィッド・ニューマンというプレイヤーも健闘しているし、アート・ブレイキーもたじろぐかのようなヒギンズの迫力がとにかく凄い。これだけ周囲が盛り立てればモーガンのトランペットが冴え渡るのも当然でしょう。以降の [4] [6] は当時のエイトビート路線、[5] はバラードで、トーンダウン。前半3曲とのギャップが大きいのが惜しまれる。最後までスピーディなフォービートで締めていれば言うことなしだった。 2つ目は69年のセッションでメンバーの重複はなく編成も3管とあって内容も当然別物。プロデュースはフランシス・ウルフ。モーガンはもともと革新的な音楽家というわけでないので、メンバーが変わったといってもとりたてて大きく音楽が変わっているわけではないけれど、ついにビリー・ヒギンズとの競演は終わり、代わりにミッキー・ローカーが加入する。ローカーはクセのないドラマーで、ビリー・ヒギンズと比べると存在感は薄いものの手堅い。このセッションではハロルド・メイバーンのピアノがいつも通りに軽快、そしてジョージ・コールマンが意外と健闘を見せる。というかコールマン、マイルス・クインテット時代の評価が芳しくないからか二流扱いされているとはいえ、他のところでの活躍を聴くと実はなかなかのプレイヤーであることがわかる。1つ目のセッションと比べると全体の勢いはやや下回っていて、カリプソ調の [12] とロック的なリズムの [13] の親しみやすさが70年代のモーガンを示唆しているのかなと感じられる程度。親しみやすく楽しいのは裏返すと深みがなく軽薄な感じという言い方もできる。モーガンのプレイも平均的。(2006年12月7日) |
||
| The Procrastinator | ||
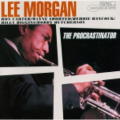 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★ モーガン入門度:★☆ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1967/7/14 [1] The Procrastinator [2] Party Time [3] Dear Sir [4] Stopstart [5] Rio [6] Soft Touch |
Lee Morgan (tp) Wayne Shorter (ts) Bobby Hutcherson (vib) Herbie Hancock (p) Ron Carter (b) Billy Higgins (ds) |
| 豪華かつ面白いメンバー構成である。共にブルーノートの看板ミュージシャンならがモーガンとハッチャーソンの顔合わせは珍しく、そこにマイルス・グループ在籍中のショーター、ハンコック、ロン・カーターを加えたとなれば質は保証されたようなもの、いやそれだけでなくスペシャルな何かが生まれるのではないかという期待が高まる。実際、この時期にモーガンが得意としていた(そして個人的にはあまり好みではない)ポップなエイト・ビートものがなく、いつになくシリアス。それでも親しみやすさを備えているところがモーガンの持つキャラクターゆえか。全体に見てメンツの割には尖がったところがなく、真っ当というか意外性はそれほどでもない。お蔵入りしていたこともなんとなく納得できる。しかし、当然ながら演奏の質は確かだし、スタイリッシュな演奏となっており、聴きこむだけの価値はある。特にショーター作の [3] [5] は彼らしいムーディかつメロディアスな曲で、ハンコックとハッチャーソンの深遠な演奏がモーガンらしからぬモード・ジャズ的なクールな面を引き出していて侮れない。この際、他の曲(それらはすべてモーガン作)もショーター作で押してしまった方が良い結果がでていたような気がしないでもない。(2014年10月19日) | ||
| The Sixth Sense | ||
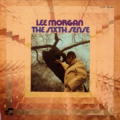 曲:★★★☆ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★☆ モーガン入門度:★☆ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1967/11/10 [1] The Sixth Sense [2] Short Count [3] Psychedelic [4] Afreaka [5] Anti Climax [6] The Cry Of My People |
Lee Morgan (tp) Frank Michell (ts) Jackie McLean (as) Ceder Walton (p) Victor Sproles (b) Billy Higgins (ds) |
| シダー・ウォルトンのピアノにビリー・ヒギンズのドラムということで典型的な60年代リー・モーガン的アルバム。つまりエイトビート、新主流派系、ちょっぴりほのぼのファンキー系(やや軽薄)といった曲の構成に、それなりのモーガンのトランペット。総じて平均的な内容とあって、モーガンのアルバムの中でも最初に勧める1枚ではなものの、この時期のマクリーンらしいシャープなアルトはまずまず楽しめる内容。フランク・ミッチェルはマクリーンに似た当時流行りのスタイルで個性はイマイチ。お勧めできないといいつつも内容は決して悪くないところがまたなんとも微妙で、ラストの渋いミュート・トランペットが意外と聴かせてくれたりもする。あと、録音がちょっと違和感があって、微かながら管楽器に妙なエコーがかかっていることやドラムが右チャンネルに偏っていることからイヤホン で聴くとちょっと気持ち悪いのが難点。(2007年5月6日) |
||
| Caramba | ||
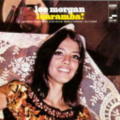 曲:★★★☆ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★☆ モーガン入門度:★☆ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1968/5/3 [1] Caramba [2] Suicide City [3] Cunning Lee [4] Soulita [5] Helen's Ritual [6] A Baby's Smile (bonus track) |
Lee Morgan (tp) Bennie Maupin (ts) Ceder Walton (p) Reggie Workman (b) Billy Higgins (ds) |
| 正直なところ、60年代中盤以降のモーガンのアルバムはあまり変わり映えしない。似たようなものが多く、本作もそんな中の1枚。メンバーがより地味になって、ますます目立たない印象。とはいえ、個々の演奏じたいのレベルは決して低くない。ベニー・モウピンのブローはなかなかの健闘、安定したファンキーさを誇るシダー・ウォルトン、柔軟なベースを聴かせるレジー・ワークマン、堅実なビリー・ヒギンズのドラムは一定のレベルで安心感がある。「つまらない」と門前払いしたくなるほど悪くはないけれど、どこか突き抜けた良さがあるわけでもないという中庸さが評価に困るところ。モーガンのプレイはいつもの粋なフレーズでありつつも、あまり弾けたところがないのはこの時期の志向性だったのかもしれないけれどやはり物足りない。70年代に向けて次の一歩に踏み出す前の力を蓄えているときだったのかも。(2007年7月7日) | ||
| Live At The Lighthouse | ||
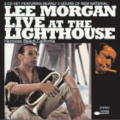 曲:★★★☆ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★ モーガン入門度:★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1970/7/10-12 Disc 1 [1] Introduction By Lee Morgan [2] Beehive [3] Absolutions [4] Peyote [5] Speedball Disc 2 [6] Nommo [7] Neophilia [8] Something Like This [9] I Remember Britt Disc 3 [10] Aon [11] Yunjanna [12] 416 East 10th Street [13] The Sidewinder |
Lee Morgan (tp, flugelhorn) Bennie Maupin (ts, bcl, fl) Harold Mabern (p) Jymie Merritt (b) Mickey Roker (ds) Jack DeJohnette (ds [5]) |
| 60年代をエイト・ビート路線で乗り切ったリー・モーガン、その路線を推進していたのはブルーノートの企画によるものだったのかも、と思わせるのが本作。フランシス・ウルフがプロデュースしてブルーノートからリリースされているとはいえ、ライヴらしく自由奔放な演奏で曲は全編フォー・ビート。しかし当然50年代とは空気が違っていて70年代のムードが漂っている。ミッキー・ローカーは堅実で地味なところはイメージ通り、ジミー・メリットが昔のようなシンプルな弾力性あるベースではなく別人のように柔軟で多彩なプレイをしているところが予想外。ベニー・モウピンはテナー・サックスがメインでウェイン・ショーターばりのパワフルなブロウを聴かせていて、意外なことに一番の聴きどころ。ハロルド・メイバーンの軽快なトーンがモウピンのその重々しいテナーをうまく中和する役割を果たしている。主役、モーガンのブロウはもちろん素晴らしいけれど、やはりどこか50年代と違ってスマートすぎる感じがして少しだけ物足りない。全体的にシリアスなムードが漂い「遊び」が少ない感じがするのは、モウピンの重々しいテナーと、モウピンやメイバーンが中心のオリジナル曲に負うところが多いように思える。それに連れて既に全盛期を過ぎたジャズという音楽の空気が漂っているところ、そして演奏者としては変わらず一級品なのに音楽家としてのモーガンのピークが過ぎた感じが漂っているところに少々寂しさを感じてしまう。[5] は一聴してそれとわかるパワフルなジャック・デジョネットのドラムがフィーチャーされていて、全曲ジャックだったらなあと思わずにはいられない。(2007年10月13日) | ||
| Lee Morgan | ||
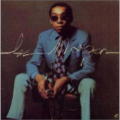 曲:★★★☆ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★ モーガン入門度:★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1971/9/17 [2]-[5] 1971/9/18 [1] [1] Capra Black [2] In What Direction Are You Headed [3] Angela [4] Croquet Ballet [5] Inner Passions Expelled |
Lee Morgan (tp, flugelhorn) Billy Harper (ts, alto-fl) Bobbi Humpherey (fl) Grachan Moncur III (tb) Harold Mabern (p, elp) Reggie Workman (b, per) Jymie Merritt (elb) Freddie Waits (ds, recorder) |
| 良く言えば柔軟、悪く言えば中途半端という路線をとり続けた63年以降のリー・モーガンは、ひらめきに満ちたフレーズを振りまきつつ、悪くはないんだけれどアルバムとして聴き応えがあるのは少ないというのが僕の中での評価。ぶっちゃけた話、50年代のやんちゃなモーガンの方が圧倒的に魅力的。とはいえ、移り変わりの激しかった60年代のジャズ・シーンを生き抜くためには60年代の中庸路線は仕方がなかったのだとも思う。そしてさらに混迷を極め、マイルスの「Bitches Brew」に代表されるクロスオーヴァーが幅を利かせてきた71年という年に製作されたこのアルバムはどうかと言えば、時代に対峙しようとするモーガンの姿をハッキリと見て取れる。一言で言えば彼のアルバム中もっとも音楽的に作りこまれている印象。従っていわゆる「やんちゃなモーガン」はここでは聴けない。その代わり、音楽家として次の時代を見据えた意欲が前面に出て、明らかに前衛的な要素(17分に及ぶ[5])さえある。すでにフォービートなどの古い手法は過去のもの、60年代のエイトビート路線ともまた違う重厚な音楽性に15分以上の大作が3曲という構成からも聴き応えある作品を目指しているのは間違いない。好きかと訊かれると素直に「はい」とは答えられないけれど、もしこの続きがあったとしたら音楽家リー・モーガンがどこに向かって行ったのか、と想像を掻き立てさせる充実した内容になっている。(2008年12月20日) | ||