ロック・ファンのためのジャズ案内のヘッダー
Rock Listner's Guide To Jazz Music
Miles Davis(49-61年)
| Birth Of Cool | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★ ジャズ入門度:★★★ マイルス入門度:★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1949/1/21 [1][2][5][7] 1949/4/22 [4][8][10][11] 1950/3/9 [3][6][9][12] [1] Move [2] Jeru [3] Moon Drems [4] Vebus De Milo [5] Budo [6] Deception [7] Godchild [8] Boplicity [9] Rocker [10] Israel [11] Rouge [12] Darn Rhat Dream |
|
| [1][2][5][7] Miles Davis (tp) Junior Collons (frh) Kai Winding (tb) Bill Barber (tuba) Lee Konitz (as) Gerry Mulligan (bs) Al Haig (p) Joe Schulman (b) Max Roach (ds) |
[4][8][10][12] Miles Davis (tp) Sandy Siegelstein (frh) J.J. Johnson (tb) Bill Barber (tuba) Lee Konitz (as) Gerry Mulligan (bs) John Lewis (p) Nelson Boyd (b) Kenny Clarke (ds) |
[3][6][9][12] Miles Davis (tp) Gunther Schuller (frh) J.J. Johnson (tb) Bill Barber (tuba) Lee Konitz (as) Gerry Mulligan (bs) John Lewis (p) Al Mckibbon (b) Max Roach (ds) Kenny Hagood (vo [12]) |
| このアルバムについては、初期マイルスの代表作としてさまざまな本で語られていて、実際に聴いてみても一般的に言われているのとほぼ同じ印象を受ける。つまり、ビバップの時代にアンサンブルを重視したジャズをあえて作ったということに尽きる。そうは言っても50年という時代ではさぞかし古臭いジャズになっているんだろうと勝手に思い込んで、ずっと聴くのを後回しにしていた。予想通り、マイルスのトランペット・ソロにそれほど見るべきものはない。でもに音楽そのものが古臭い感じがしないのは意外だった。もちろん古いことは古い。演奏スタイルが古いからそれは仕方ない。重要なのは、音楽がさほど古く感じないということでしょう。ビッグバンドのスタイルとも違って、ちゃんと独自の音楽になっているところは、生涯にわたってサウンドを追い求めてきたマイルスの面目躍如。有名盤であり、アカデミックな観点で評価されつつも、あまり愛聴されている感じがしない本作は、しかし実は今の耳で聴いても音楽的に楽しめるものであることが何よりも評価されるべきだと思う。(2016年7月8日) | ||
| The Musings Of Miles | ||
 曲:★★★ 演奏:★★★ ジャズ入門度:★ マイルス入門度:★★ 評価:★★☆ |
[Recording Date] 1955/6/7 [1] Will You Still Be Mine [2] I See Your Face Before Me [3] I Didn't [4] A Gal In Calico [5] A Night In Tunisia [6] Green Haze |
Miles Davis (tp) Red Garland (p) Oscar Petiford (b) Philly Joe Jones (ds) |
| ハードバップ創世記、そしてマイルスが真のスターになる一歩手前のころとされる55年録音のアルバム。シンバルの音が妙にシャリシャリしている録音が個人的にはやや耳障りであるという悪印象を抜きにしても、音楽的に特筆すべきところが少ない、時代相応のジャズという印象で正直なところあまりピンと来ない。帝王マイルスとて、常に斬新なアルバムばかり作り続けていたわけではないというところか。とはいえ、このアルバムがマイルス・マニアに一目置かれているのは珍しいワン・ホーンものだからという理由に尽きる。しかし、そのマイルスのプレイも後のことを考えると弱い。もちろん、ワン・ホーンだから持て余してしまっているということはさすがにないし、この編成ゆえに結果的に目立つことになったガーランドは期待通りの活躍、手堅いペティフォードとこちらも期待通りのフィリー・ジョーとサイド・ミュージシャンも悪くない。やはりハードバップが本当に盛り上がる直前という時代の音楽性相応というところが、現代の耳、そして僕の耳にはそれほど面白みを見い出せない理由。[5] のように通常熱く演奏されるような曲も軽快かつクールなトーンが貫いているところは、それでもやはりマイルス的。一方で、あまりにも俗っぽく、ガーランドのリーダー・アルバムに入っていそうなオーソドックスでコテコテのブルース [6] をマイルスが演っているところはある意味聴きどころと言えるかもしれない。[4] のようにミュートによる軽快な演奏はこの時期のマイルスの十八番。(2011年9月2日) | ||
| Walkin' | ||
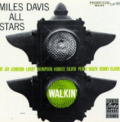 曲:★★★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★★ マイルス入門度:★★★☆ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1954/4/3 1954/4/29 [1] Walkin' [2] Blue 'N' Boogile [3] Solar [4] You Don't Know What Love Is [5] Love Me Or Leave Me |
Miles Davis (tp) J.J Johnson (tb) Lucky Thompson (ts [1] [2]) Davey Schidkraut (as [3]-[5]) Horace Silver (p) Percy Heath (b) Kenny Clarke (ds) |
| タイトル曲は、60年代クインテットのライヴ・アルバムに多くの録音が残っているあのアグレッシヴでスピード感溢れる"Walkin'"とはまったく異なり、ここではリラックスしたブルースで演奏されている。悪くはないけれど特筆するほとの演奏でもない印象。一転して2曲目はノリの良い典型的ハードバップでマイルスも J.J. も好調。しかし実は [3] 以降のマイルスのミュート・プレイこそがこのアルバムのハイライト。[3] [4] ではバラード演奏におけるマイルスの素晴らしさを堪能できる。ミュート・トランペットによる小気味良さが炸裂した [5] も素晴らしい。後年のミュート・プレイは緊張感が強すぎるという意見もあることが多いけれど、ここでの程よく力が抜けている演奏は意外と貴重なのかもしれない。(2006年5月27日) | ||
| Bags' Groove | ||
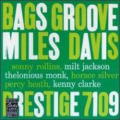 曲:★★★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★★ マイルス入門度:★★★☆ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1954/6/29 1954/12/24 [1] Bags' Groove (take 1) [2] Bags' Groove (take 2) [3] Airegin [4] Oleo [5] But Not For Me (take 2) [6] Doxy |
[1] [2] Miles Davis (tp) Milt Jackson (vib) Thelonious Monk (p) Percy Heath (b) Kenny Clarke (ds) [3]-[7] Miles Davis (tp) Sonny Rollins (vib) Horace Silver (p) Percy Heath (b) Kenny Clarke (ds) |
| セロニアス・モンクとのケンカ・セッションで有名な、[1] を収録したアルバム。そのエピソードの真偽はともかく、これは名演です。ピアノ・レス・トリオ編成でソロを取るマイルスは、トランペットという低音域をカバーできない楽器で、音数が少ないのに、空間を持て余さずに埋め尽くす。ミルトはいつも通りに得意のブルースを決める。そして、およそフレーズとは言い難いモンクの型破りなソロが素晴らしい。実は、僕はモンクの良さが理解できないのだけれど、ここでの演奏はさすがと思わされる。[3] 以降は、ロリンズ入りのクインテットで、オーソドックスな演奏ながら、曲の良さと相まって良質なハード・バップとして聴ける。この時期、マイルスが重用しているこのリズム・セクションは、正直、僕には平凡な感じに聴こえてしまう(特にケニー・クラーク)。全体的に奇をてらったところのない王道ジャズ。落ち着いて聴きたい向きには良いけれど、アクや刺激を求めるとちょっと物足りない。(2008年6月21日) | ||
| Miles Davis And The Modern Jazz Giants | ||
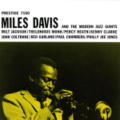 曲:★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★★ マイルス入門度:★★★☆ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1954/12/24 1956/10/26 [3] [1] The Man I Love (take 2) [2] Swing Spring [3] 'Round Midnight [4] Bemsha Swing [5] The Man I Love (take 1) |
Miles Davis (tp) Milt Jackson (vib) Thelonious Monk (p) Percy Heath (b) Kenny Clarke (ds) [3] のみ Miles Davis (tp) John Coltrane (ts) Red Garland (p) Paul Chambers (b) Philly Joe Jones (ds) |
| セロニアス・モンクとのケンカ・セッションとして有名なのは「Bag's Groove」の表題曲。しかし、実はそのときのセッションの大半が収められているのが本アルバム。つまり、マイルス、モンク、ミルトのセッションをたっぷり楽しもうと思うのならこちらの方。恐らく発売時期などの理由から影に埋もれてしまっているのでしょう。内容的にはまったく遜色ないし、いかにもプレスティッジの気軽なセッションという趣で、リラックスしつつも主役3人が十分な持ち味を生かしていて、極上のモダン・ジャズに仕上がっている。ワン・ホーンでありながら個性の強いピアノとヴァイブが入った編成は今思うとなかなかユニークで、個人的には黄金のクインテット結成前のマイルスの作品の中ではこのアルバムが一番良いと感じる。[3] のみ、有名なマラソン・セッションからの音源で、同じメンバーによる CBS 盤の同名アルバムでの名演と比較すると、基本は同じアレンジでありながら少しラフな感じになっていて、これはこれで味のある演奏。このアルバム収録曲には他にサックス入りがないためコルトレーンの存在感がより大きく感じられるのも思わぬ副産物か。(2006年11月5日) | ||
| Miles Davis And Milt Jackson Quintet/Sextet | ||
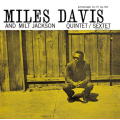 曲:★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★★ マイルス入門度:★★★☆ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1955/8/5 [1] Dr. Jackle [2] Bitty Ditty [3] Minor March [4] Changes |
Miles Davis (tp) Jackie McLean (as [1] [3]) Milt Jackson (vib) Ray Bryant (p) Percy Heath (b) Art Taylor (ds) |
| 正直なところ55年までのマイルスは、音楽的にはさほど革新的とは感じない。ハード・バップをリードしてきたということは書物を読めば理解できるものの、ハード・バップというスタイルが一般化してしまった現代においてそれが特別に響かないのは仕方ないところ。トランペット奏者としてもクールなスタイルで、ビ・バップ世代とは一線を画す個性を打ち出していたことも知識としては分かっていているものの、このスタイルじたいも今の耳では取り立てて斬新には響かない。そういうこともあって、グループとしての個性を作り上げた黄金のクインテット結成前のマイルスは音楽家、演奏家としての開花度はまだまだというのが僕の感想で、例外的にセロニアス・モンクとの有名なセッション(「Bag's Groove」「Miles Davis And Milt Jackson Quintet/Sextet」)はイイと思っていた程度だった。そんなわけで手を出すのが遅くなったこのアルバム、聴いてみるとこれがなかなかイイ。マイルスは軽快に吹いていてリラックスしたムード。若きマクリーンはプレイも若いけれどスタイルはもう出来つつある感じで、しかしここでは脇役の存在。なんといっても素晴らしいのがミルト・ジャクソン。ブルース・フィーリングをベースに軽快かつ気品あるプレイでムードを支配。つまり、「モンクとのセッションのときのマイルスはイイ」 のではなく、「ミルトと競演したときのマイルスはイイ」 ということにここで気づく。朴訥で黒っぽいレイ・ブライントのフィーリングも良く合うし、上下に幅広く音を使い分けるパーシー・ヒースはもともと僕のお気に入り、そしてうれしいのは退屈なケニー・クラークではなくアート・テイラーが小気味良いリズムで支えているところ。わずか31分強と CD 世代にはミニ・アルバムのようなものでしかないけれど、オーソドックスなジャズを聴きたいというときに期待に応えてくれる意外と侮れないアルバム。(2008年6月21日) | ||
| Miles | ||
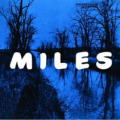 曲:★★★☆ 演奏:★★★ ジャズ入門度:★ マイルス入門度:★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1955/11/16 [1] Just Squeeze Me [2] There Is No Greater Love [3] How Am I To Know [4] S'posing' [5] The Theme [6] Stablemates |
Miles Davis (tp) John Coltrane (ts) Red Garland (p) Paul Chambers (b) Philly Joe Jones (ds) |
| 確かのあの50年代黄金のクインテットの演奏であることに間違いない。でも、やはり初めてのスタジオ録音から鉄壁だったわけではないということがこのアルバムを聴くとわかる。それにしても [1] のミドルスローな曲で空間を持て余すコルトレーンの垢抜けなさは笑いそうになる。さらにスローな [2] につないでいるせいで、なにやら随分大人しいアルバムだなと思いそうになっていると、[3] 以降に軽快な曲が続く。プレスティッジは曲順なんてあまり気にしていなかったのかもしれない。ようやくテンポが上がってくると、この5人の持ち味が良く出てくる。マイルスのミュートもガーランドのソロもチェンバースの躍動的なベースラインもフィリー・ジョーのノリも、さすが黄金のクインテット。でも、コルトレーンだけはやはり垢抜けない。よくこれでクビにならずに済んだものだ。[5] は後のマイルス・グループのテーマではなく、ジャズ・メッセンジャーズがいつも使っていた方のテーマ。尚、作曲家としてまだ泣かず飛ばずだったベニー・ゴルソンは、自分の曲 [6] がこのアルバムで取り上げられると周りの評価が一変したそうで、マイルスの影響力の大きさを後に述懐している。(2014年4月26日) | ||
| MAX 1956 (Bootleg) | ||
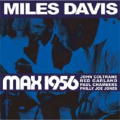 曲:★★★★ 演奏:★★★ 音質:★★★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1956/2/18 [1] Introduction By Gene Morman [2] Max Is Making Wax [3] Walkin' [4] Member Introduction [5] It Never Entered My Mind [6] Woody'n You [7] Salt Penuts [8] The Theme |
Miles Davis (tp) John Coltrane (ts) Red Garland (p) Paul Chambers (b) Philly Joe Jones (ds) |
| 56年2月18日のライヴを記録したブートレグ。今では正規盤として 「'Round About Midnight」と抱き合わせで販売されている。この時代のライヴ録音でこの良好な音質というのは奇跡的でオフィシャル盤としてリリースされたのも納得できる。さて演奏の内容は、この時期、このメンバーとしては可もなく不可もなく、それほど盛り上がっていないというのが正直なところ。時間は33分弱と短いけれど、この時代の演奏がここまでクリアな音質でこの世に出たことを素直に喜びましょう。(2008年6月21日) | ||
| 'Round About Midnight | ||
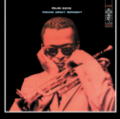 曲:★★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★★★ マイルス入門度:★★★★★ 評価:★★★★☆ |
[Recording Date] 1955/10/26 1956/6/5 1956/9/10 [1] 'Round About Midnight [2] Ah-Leu-Cha [3] All Of You [4] Bye Bye Blackbird [5] Tadd's Delight [6] Dear Old Stockholm [7] Two Bass Hit [8] Little Melonae [9] Budo [10] Sweet Sue, Just You |
Miles Davis (tp) John Coltrane (ts) Red Garland (p) Paul Chambers (b) Philly Joe Jones (ds) |
| 55年〜56年にかけて、黄金のクインテットの録音はプレスティッジのセッションとCBSのセッションに分けられ、何枚かのアルバムに分散して収録されている。そのうち、CBS分はこのアルバムに集約。既に語り尽くされているとはいえ中でも表題曲のハードボイルドなムード満点の名演、名アレンジが素晴らしい。他の曲も親しみやすく良い演奏ばかりで完成度は高い。このメンバーなら、「Relaxin'」「Cookin'」を勧めたいところだけれど、このアルバムの統一されたムードと分かり易さも捨てがたい。当時のコルトレーンを評価する人は少なく、実際、後のことを思えばまだフレーズの紡ぎ方に未熟なところを感じるものの、他のメンバーと比べて格が落ちるという印象はなく十分聴かせるプレイをしていると思う。1回目のマラソン・セッションからわずか1ヶ月しか経っていないのにここまで成長している印象を受けるのはマラソン・セッションとは違って、おそらくリハーサルを積んで臨んだからでしょう。それはマイルスのプレイにも言えることで、メロディやフレーズの完成度が高く、明らかに「アルバム作り」に心を砕いたと思える。56年の録音でここまで完成度の高いジャズ・アルバムというのもちょっと見当たらない。尚、最近の輸入盤では [7] 以降のボーナス・トラックが付くものの、ここからぐっと質が落ちるため、オリジナル通りに [6] で終わった方がスッキリする。(2006年5月24日) | ||
| Workin' | ||
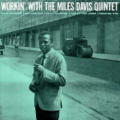 曲:★★★ 演奏:★★★ ジャズ入門度:★★★ マイルス入門度:★★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1956/5/11 1956/10/26 [1] It Never Entered My Mind [2] Four [3] In Your Own Sweet Way [4] The Theme [5] Trane's Blues [6] Ahmad's Blues [7] Half Nelson [8] The Theme |
Miles Davis (tp) John Coltrane (ts) Red Garland (p) Paul Chambers (b) Philly Joe Jones (ds) |
| このアルバムは、もう [1] にトドメを刺す。ガーランドの包み込むような優しいピアノに、マイルスのミュートがリリカルに響く。マイルス自身、他に似たような曲は以降も演奏していない。ジャズという範疇を越えた美しい曲だと思う。以降は、典型的なハード・バップ、バラード、コテコテのブルースで構成されており、十分な完成度を持っているのだけれど、もうひとつ抜けた部分がなく少し物足りない。マラソン・セッションは56年の5月と10月の2回の録音のことを指すのだけれど、このわずか5ヶ月の間のコルトレーンの成長と、バンドとしての完成度が高まりがあるために両日のセッションにはギャップを感じてしまう。このアルバムと 「Steamin'」はほとんどが5月のセッションのときのもので、世間の評価が「Relaxin'」「Cookin'」よりも低いのはそのせいでしょう。(2006年5月27日) | ||
| Steamin' | ||
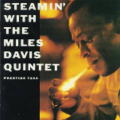 曲:★★★ 演奏:★★★ ジャズ入門度:★★★ マイルス入門度:★★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1956/5/11 1956/10/26 [1] Surrey With The Fringe On Top [2] Salt Penuts [3] Something I Dreamed Last Night [4] Diane [5] Well, You Needn't [6] When I Fall In Love |
Miles Davis (tp) John Coltrane (ts) Red Garland (p) Paul Chambers (b) Philly Joe Jones (ds) |
| [2] はフィリー・ジョー・ジョーンズのドラムを浴びるほど聴きたい人にお勧め。こんなに長いドラム・ソロをマイルスが許したのは後にも先にも例がないのでは。他にはバラードにおけるマイルスのミュート・プレイが堪能できる [3] [6] あたりが聴きどころか。[3] はコルトレーンのアルバム「Bahia」に収録されているバージョンと聴き比べるのも一興。全体の印象としては、「Workin'」とほぼ同じで、マイルスの作品であることを考えると、ちょっと物足りない。まあでも寛いで聴けるマイルスのアルバムはこの時代までくらいなので、それを素直に楽しみましょう。(2006年5月27日) | ||
| Relaxin' | ||
 曲:★★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★★★ マイルス入門度:★★★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1956/5/11 1956/10/26 [1] If I Were A Bell [2] You're My Everything [3] I Could Write A Book [4] Oleo [5] It Could Happen To You [6] Woody'n You |
Miles Davis (tp) John Coltrane (ts) Red Garland (p) Paul Chambers (b) Philly Joe Jones (ds) |
| 現在進行形タイトルのマラソン・セッション中、もっとも好きなのがコレ。「Cookin'」ももちろん素晴らしいけれど全曲のレベルの高さにおいてこちらに軍配を上げたい。会話や演奏のやり直しなども記録されていて、一発勝負のセッションであることがよく伝わってくる。口ずさめるような親しみやすい曲が多く、それをマイルスのミュート([6] を除いてすべてミュート)が奏でるだけで素晴らしい演奏になってしまう。思えば50年代のマイルスの演奏は、決められたメロディをうまく自己流に崩して演奏しているだけという曲が結構ある。"枯葉"なんてまさにその典型。アドリブの閃きというよいり、表現力で勝負しているのは非ビ・バップ的でそれこそがマイルスの目指していたものだったに違いない。アルバム全体を通じて、チェンバースの躍動するベースとガーランドの流れるピアノが光る。コルトレーンもこの時期としてはなかなか良いプレイを聴かせており、全体的にクインテットの実力を見せつける完成度の高い演奏がギッシリと詰まっている。ベストは [4] か。(2006年5月27日) | ||
| Cookin' | ||
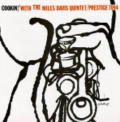 曲:★★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★★★ マイルス入門度:★★★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1956/10/26 [1] My Funny Valentine [2] Blues By Five - false start [3] Blues Five [4] Airegin [5] Tune Up 〜 When Lights Are Low |
Miles Davis (tp) John Coltrane (ts) Red Garland (p) Paul Chambers (b) Philly Joe Jones (ds) |
| 60年代に何度もライヴで演奏されていたマイルスの"My Funny Valentine"。先にそれを聴いていた僕は、「これがかの有名なマイ・ファニー・バレンタインかあ。ムードがあるリリカルな曲だけどちょっとシリアスすぎて重いかなあ」と思っていた。そしてしばらく経ってから聴いた本作。まるで違う。マイルスのミュート・プレイがやはりなんといっても素晴らしいけれど、印象を支配しているのはガーランドの哀愁を帯びていつつも親しみのあるピアノ。また、チェンバースのベースも変幻自在の好プレイ。決して凄みがあるわけでも、大げさに盛り上がるわけでもないのに素晴らしい。この演奏を聴くだけでこのアルバムは十分に価値がある。[3] はガーランドのテーマから始まるオーソドックスなブルース。特別なことをしなくてもこの5人なら手堅く納まる。[4] と [5] の前半に至るまでの勢いはフィリー・ジョー・ジョーンズの持ち味が良く出た疾走感タップリの名演。"Tune Up"が終わると実にリラックスした演奏に切り替わり、そのまま気持ち良く終わるのは意図的な構成だったのか単なる偶然なのかわからない。でもこの流れも名盤と呼ばれる所以でしょう。トータル33分と短いけれど、これもクインテットの実力を見せつける傑作。(2006年5月27日) | ||
| Dear Old Stockholm 1957 (Bootleg) | ||
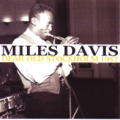 曲:★★★★ 演奏:★★★ 音質:★★★☆ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1957/7/20 [1]-[3] 1957/7/27 [4]-[6] 1957/10/17 [7] [8] 1957/12/18 [9]-[11] [1] Introduction by Guy Wallace [2] Dear Old Stockholm [3] Bags' Groove [4] Introduction by Guy Wallace [5] Bye Bye Blackbird [6] Tune Up [7] All Of You [8] Four [9] Yesterdays [10] Round About Midnight [11] Walkin' |
[1]-[6] Miles Davis (tp) Sonny Rolllins (ts) Red Garland (p) Paul Chambers (b) Art Taylor (ds) [7] [8] Miles Davis (tp) Bobby Jasper (ts) Tommy Flanagan (p) Paul Chambers (b) Philly Joe Jones (ds) [9]-[11] Miles Davis (tp) w/Erwin Iehn Orchestra |
| 記憶が確かなら、57年のマイルスは自分のグループでの録音を残していない、あるいは残っていても発表されていないはず。そこを補うこのブートレグはなかなか貴重。しかもこのメンバーとあっては尚更貴重。なんといっても、既に名声を確立したソニー・ロリンズがマイルス・クインテットにいるのだから。[1]-[6] がそのロリンズ入りで場所はカフェ・ボヘミア、[7] [8] はバードランド、[9]-[12] がシュトゥットガルトでのライヴ。音源はラジオのようで、音質はまあなんとか聴けるレベル。これなら演奏が楽しめると思っていると、至るところでトークが被り演奏に集中できない。特に [3] などは肝心の演奏がトークの BGM と化している。期待のロリンズのプレイは、それほど特筆するほどのものではなく、ちょっと期待外れ。[7] [8] もまたちょっと変わったメンツによる演奏でトークの被りも少なめで楽しめる。[9] のマイルスのバラード・プレイは素晴らしく、多くの人が注目しないであろうこの曲こそが、このディスク最大のハイライト。[10] もオープンで情感タップリに歌い上げて、オーケストラの盛り上げもいい感じ。全体的に演奏そのものは平均的で、あくまでも貴重なこのメンツの演奏を聴くためのディスク。(2006年11月7日) | ||
| Ascenseur Pour L'echafaud | ||
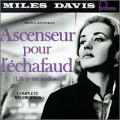 曲:★★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★ マイルス入門度:★ 評価:★★☆ |
[Recording Date] 1957/12/4 1957/12/5 [1] Generique [2] L'assassinat De Carala [3] Sur L'autoroute [4] Julien Dans L'ascenseur [5] Florence Sur Les Champs-Elysees [6] Diner Au Motel [7] Evasion De Julien [8] Visite Du Vigile [9] Au Bar Du Petit Bac [10] Chez Le Photographe Du Motel |
Miles Davis (tp) Barney Wilen (ts) Rene Urteger (p) Pierre Michelot (b) Kenny Clarke (ds) |
| 映画のサントラ用に地元フランスのミュージシャンをバックに演奏したものでジャズが映画音楽として流行ったころならではの企画。クールでシリアスなムードの演奏満載で、ところどころに小刻みなブラッシュワークとミュート・トランペットの小気味良い曲が挟まる。乱暴に言えばその2種類の曲調しか入っていない。それでもマイルスの表現力は流石で、バックが地味なだけにトランペッターとしてのマイルスの素晴らしさを実感できる。一方、サントラというだけあって雰囲気を楽しむ気分になってきたころに曲が終了。つまり曲が短く構成に凝る余地がない。繰り返すけれど、マイルスのプレイは申し分ない。クールでリリシズム溢れる演奏をさせたら右に出るものがいないことを改めて見せつける。しかしながらグループ表現を見せつけるような内容ではなく、これをアルバムとして鑑賞するのは個人的にはちょっと辛い。マイルス自身、常にグループとして音楽を作ることを目標にしてきた人だと思うので、ちょっとした気分転換的な仕事だったのかもしれない。尚、画面のフィルムを見ながら即興で演奏したというのが定説となっているけれど、解説によると試写会を見てから録音までに2週間の準備期間があり、ホテルで曲のアイディアを練っていたとのことで、演奏の方向性を決めてから録音時にフィルムを流しながら演奏したというのが真相のようです。(2006年5月27日) | ||
| Milestones | ||
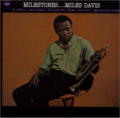 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★★ マイルス入門度:★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1958/2/4 1958/3/4 [1] Dr. Jackle [2] Sid's Ahead [3] Two Bass Hit [4] Milestones [5] Billy Boy [6] Straight, No Chaser [7] Two Bass Hit (alt take) [8] Milestones (alt take) [9] Straight, No Chaser (alt take) |
Miles Davis (tp, p [2]) John Coltrane (ts) Cannonball Adderley (as) Red Garland (p except [2]) Paul Chambers (b) Philly Joe Jones (ds) |
| ジャズを聴こうと思い立って、ガイドブックを手にする前に最初に入手したモダン・ジャスの作品がコレ。マイルスがジャズの第一人者であることは知っていたし、シャレた名前のタイトル曲も知っていたので、これを買っておけば間違いはないだろうというのがその理由だった。ジャズの演奏がどんなにスゴイか見せてもらおうじゃないか、というずいぶん不遜な態度で臨んだものだったんだけれども、いざ聴いてみると、まず管楽器奏者の良し悪しを聴き分ける耳なんて持っていないので凄さがわからない。なにしろ、コルトレーンとキャノンボールの区別すらつかなかったんだから。ならばドラムを聴いてみよう。なんだ、たいしたことないじゃないか、と思ったりした。フィリー・ジョー・ジョーンズが正確さやテクニックよりもノリやフィーリングを重視するタイプであることなんて知りらなかったから。あと、マイルスといえばミュートに持ち味があるということも知っていたんだけれど、このアルバムにはミュートによる演奏、そしてバラードが一曲も入っていなかったのも期待外れだった。というわけで、今思うとこれからマイルスを聴いてみたいという人には向いていないアルバムだったかもしれない。 そんな個人的な思い出は別にして、今の耳で聴いてみると、このアルバムはフロントの3人の熱いブローを楽しむべき作品とわかる。マイルスもトランペット奏者としての表現力がそれ以前より豊かになっていると思うし、マラソン・セッション以降、自分のリーダー・アルバムやモンクとのとの共演で腕を磨いたコルトレーンの成長ぶりは、特に目を見張るものがある。曲の印象について触れると、[2] なんて一瞬"Walkin'"の焼き直しかと思ってしまうけれど、ムードが異なっていてこれこそが3年間のマイルスの進化を示しているように思うし、その他の曲も含めて、全体的にハードバップから脱却していこうという姿勢が実感できる。ちなみに [2] では、ガーランド不在時に録音したためにマイルスがピアノを演奏。当然、マイルスがソロを吹いているときにはピアノレス・トリオの編成になるわけで、しかし、その隙間だらけの空間を支配しするマイルスの素晴らしさを確認できる。[6] のテーマは3管ならではの厚みで、この厚みがこの曲にはとても良く合う。[4] のような新しい感覚を持った曲と、[3] のような古いスタイルが混在した過渡期の作品。(2006年6月4日) |
||
| 1958 Miles | ||
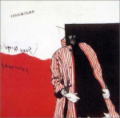 曲:★★★★☆ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★ マイルス入門度:★★☆ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1958/5/26 1958/3/4 1955/10/26 [1] On Green Dophin Street [2] Fran-Dance [3] Stella By Starlight [4] Love For Sale [5] Little Melonae [6] Little Melonae (alt take) [7] Stella By Starlight (alt take) |
[1]-[4], [7] Miles Davis (tp) John Coltrane (ts) Cannonball Adderley (as) Bill Evans (p) Paul Chambers (b) Jimmy Cobb (ds) [5] Miles Davis (tp) John Coltrane (ts) Red Garland (p) Paul Chambers (b) Philly Joe Jones (ds) [6] Miles Davis (tp) John Coltrane (ts) Cannonball Adderley (as) Red Garland (p) Paul Chambers (b) Philly Joe Jones (ds) |
| 名作「Kind Of Blue」と同一メンバーの未発表スタジオ録音を中心としたアルバムで、79年に日本で編集されたものらしい。「Kind Of Blue」が名作であることに異論はまったくないのだけれど、独特の重みと緊張感を持っていて格調高く、人を寄せ付けないムードがあるのも事実。その点、ここでは適度な緊張感と余裕があるのが特徴。別項の 「At Newport 1958」 になると、同じメンバーでありながらビル・エヴァンスらしさがあまり聴けないんだけれども、ここではそれなりにエヴァンスらしさが出ていのと同時に、このセクステットの素の姿はこうだったんじゃないかと思えるナチュラルな演奏こそが聴きどころになっている。[4] はキャノンボールの「Something Else」で取り上げた曲なだけに、キャノンボールがより生き生きしている。収録曲については若干ややこしい。[5] は55年10月26日録音で「'Round About Midnight」の数曲と同日のセッションなのでまるで雰囲気が違う。[6] は同じ曲ながら、今度は「Milestones」の数曲と同日のセッションでこちらはオリジナルLPに収録されていなかったにもかかわらず確かにアルバム・タイトルどおりの58年モノ。とはいえ、エヴァンス入りの[1]〜[4] までとはやはり雰囲気が違う。これを別テイクとするのはちょっと強引な解釈なような気がするんだけれど。(2006年5月27日) | ||
| At Newport 1958 | ||
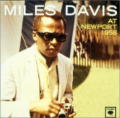 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★☆ マイルス入門度:★★☆ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1958/7/3 [1] Introduction By Willis Connover [2] Ah-Leu-Cha [3] Straight, No Chaser [4] Fran-Dance [5] Two Bass Hit [6] Bye Bye Blackbird [7] The Theme |
Miles Davis (tp) John Coltrane (ts) Cannonball Adderley (as) Bill Evans (p) Paul Chambers (b) Jimmy Cobb (ds) |
| この CD を手にしようという人は、恐らくその前に「Kind Of Blue」を聴いていることでしょう。そして、同じものを期待して裏切られているのでは?ガーランド在籍時のレパートリーが多いからかビル・エヴァンスの存在感が薄く、これはつまりエヴァンスが既存のハード・バップ系ミュージシャンとは明らかに違うことを逆説的に意味していることを思い知ることになる。そんなわけで雰囲気そのものはむしろ「Milestones」に近いように思える。そういった点を抜きにすれば、このメンバーゆえに演奏自体は悪かろうはずがない。二流扱いされるジミー・コブだけれど、僕は結構好きで、ここではドラムの音が大きめのミックス・バランスで録音されているということもあって持ち味をより楽しめる。反面、ベースとピアノの音は控えめの音量バランスで録音されており、それがこのアルバムの音の感触を特徴付けているように思う。フロントの3管はいつもどおり好調。コルトレーンは、この時期にしては少し押さえ気味かもしれないけれど、[6] ではけっこうブヒブヒやっている。新しい発見や驚きのあるアルバムではないけれど、このメンバーで、このレパートリーを楽しみたいという人なら持っていて損はない。(2006年5月25日) | ||
| Jazz At The Plaza | ||
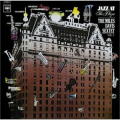 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★ マイルス入門度:★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1958/9/9 [1] If I Were A Bell [2] Oleo [3] My Funny Valentine [4] Straight, No Chaser |
Miles Davis (tp) John Coltrane (ts except [3]) Cannonball Adderley (as [2] [4]) Bill Evans (p) Paul Chambers (b) Jimmy Cobb (ds) |
| マイルスといえば真っ先に挙がる代表作「Kind Of Blue」、その同じメンバーだというのにまるで触れてはいけないかの様に無視されているのがこのアルバム。いろいろな評価を見ると、その最大の理由は録音状態にあるということで聴くのがずいぶん後回しになっていた。なるほど、マイルスのトランペットの音がずいぶん遠い。しかも [1] の冒頭少しだけは非常に近いという不安定さが聴き手の不快感を強くしてしまう。どうやら [1] のその切り替わり目でマイルのマイクがオフに、その後は他のマイクから拾った音で収録されているのではないかという恐るべき録音の失敗。ところがマイルス以外の音質は良好でクリア、コルトレーンとキャノンボールの音はバッチリなので楽しめる。[3] は「Cookin'」とも後の60年代の演奏ともまた違う仕上がりでこれが意外と新鮮。バラードということもあって、マイルス・グループのライヴでは持ち味が出てこないビル・エヴァンスもこの曲ではまずまず。[4] のラフな感じもカッコいい(そしてなぜかこの曲でマイルスの音がようやく正常に)。まとまっているけどこじんまりした演奏の「1958 Miles」よりも演奏の質としてはこちらの方が好き。それはひとえにコルトレーンとキャノンボールが気持ちよくブロウしているから。ベースの音が小さめであるところは個人的にマイナスだしマイルスのアルバムで優先的に聴くものではないだろうけれど、前述の録音の問題が気にならなくてこのセクステットが好きな人なら楽しめるはず。とはいえ、大半のマイルスの音が遠いというのはあまりにも間抜けである、というのが一般的な認識でしょう。(2011年2月12日) | ||
| Kind Of Blue | ||
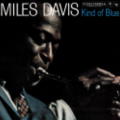 曲:★★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★ マイルス入門度:★★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1959/3/2 [1]-[3] 1959/4/22 [4]-[6] [1] So What [2] Freddie Freeloader [3] Blue In Green [4] All Blues [5] Flamenco Sketches [6] Flamenco Sketches (alt take) |
Miles Davis (tp) John Coltrane (ts) Cannonball Adderley (as except [3]) Bill Evans (p except [2]) Wynton Kelly (p [2]) Paul Chambers (b) Jimmy Cobb (ds) |
| ジャズを知らない人でも知っているマイルス・デイヴィスの名前、そしてマイルスのアルバムの中でも名盤中の名盤として知られる本作をジャズ初心者が手に取る確率は非常に高いのではないかと思う。かくいう僕もその一人だった。しかし、その他のジャズを聴けば聴くほど、このアルバムは異質であることを思い知らされる。冒頭、ビル・エヴァンスのシンプルかつリリカルなピアノから、ポール・チェンバースのリフが加わり、ジミー・コブのハイハットが被ってくる部分からして他のジャズとは一線を画す格調高いムード。全体を通してアップ・テンポでスウィンギーな曲はひとつもなく、聴かせる楽曲に聴かせる演奏はどこか確信に満ちているかのように堂々としている。確かに知的で落ち着いたムードは、「オシャレな BGM」としての役割も担えるかもしれないけれど、それだけに終わらせることができないほど、ここで展開されているジャズはワン・アンド・オンリー。そのムードは深遠で静謐と表現しても言い過ぎではないほどで、気を休めるような質は持ち合わせていない。実はこれらの評価と同じようなことがビル・エヴァンス・トリオにも言える。ビル・エヴァンスも有名なだけにやはり初心者が最初に聴く可能性が高く、他のジャズ・ピアニストを聴けば聴くほど異質であることを思い知らされるタイプのピアニスト。そういう意味でも、このアルバムはエヴァンスの音楽的資質を良く反映したものと言うことができると思う。不朽の名作。尚、SACDマルチは全体の音場が広く感じられてマルチらしさを味わえる。センターにマイルスのトランペットとベースが割り当てられるため、センター・スピーカーの能力が低いと魅力が半減してしまう。(2008年6月21日) HDtracksでリマスタリングが施されたハイレゾ配信された。サイトで丁寧なマスタリングぶりが紹介されており、従来のCDと比較して滑らかな音と美しい響きを感じ取れる仕上がり。しかし、これはもうかなりマニアックなレベルでの話で、それなりのオーディオ環境を揃えて「ああ、違うな」とわかるレベルの差だと思う。言い方を変えればある程度以上のオーディオ環境であればこの響きの良さを味わえる。より柔らかく実音により近くなったかのようなピアノの音が印象的で、このハイレゾ音源を聴くとCDの音が少し荒く聴こえてしまう。管楽器やドラムの音はややカドが取れたかな、くらいの変化ながら、スタジオの空気感まで捉えたと思えるような全体の響きの緻密さが魅力。現状では最善の状態で聴ける音源なので、このアルバムを宝物のように扱っている人には価値があると思う。(2013年11月24日) |
||
| Making Of Kind Of Blue (Bootleg) | ||
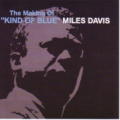 曲:★★★★★ 演奏:★★★★★ 音質:★★★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1959/3/2 [1] 1959/4/22 [2] [1] Recording Session of Freddie Freeloader, So What, Blue In Green [2] Recording Session of Flamenco Sketches, All Blues |
Miles Davis (tp) John Coltrane (ts) Cannonball Adderley (as) Bill Evans (p except [Freddie Freeloader]) Wynton Kelly (p [Freddie Freeloader]) Paul Chambers (b) Jimmy Cobb (ds) |
| 名作、「Kind Of Blue」のレコーディング・セッションを記録したブートレグ。トータル約74分。途中で演奏を止めたり、再開したりと、スタジオで起こっていたことが克明に記録されている。録音状態は文句なし。生々しい音質で楽しめる。マイルスの録音の進め方はこういう感じだったんだということも良くわかり実に興味深い。とはいえ、普通に曲を楽しむにはオリジナル・アルバムを聴けばよく、重度のマニアのみに薦められるもの。(2006年5月27日) | ||
| Spring, 1960 (Bootleg) | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★ (Disc 1) ★★★☆ (Disc 2) 音質:★★★★☆(Disc 1) ★★☆ (Disc 2) 評価:★★★★ (Disc 1) ★★☆ (Disc 2) |
[Recording Date] 1960/3/22 (Disc 1) 1960/4/9 (Disc 2) Disc 1 [1] So What [2] Fran-Dance [3] Walkin' [4] On Green Dolphin Street [5] All Blues 〜 The Theme Disc 2 [1] So What [2] On Green Dolphin Street [3] 'Round Midnight [4] Walkin' 〜 The Theme |
Miles Davis (tp) John Coltrane (ts) Wynton Kelly (p) Paul Chambers (b) Jimmy Cobb (ds) |
| 「Kind Of Blue」の後、マイルス・セクステットは解体され、キャノンボール抜き、ビル・エヴァンスではなくウィントン・ケリーを入れてのクインテットでヨーロッパ・ツアーに出る。このブートはそのうちのストックホルム公演(Disc 1)とオランダ公演(Disc 2)を記録したもの。音質については、ストックホルムの方は、オフィシャル盤で出しても問題のないレベル。オランダ公演の方は、少しシャリシャリしているのとバス・ドラムの音がやや割れ気味、2曲目以降になるとさらに劣化してちょっとキツイかもしれないけれど、こちらもなんとか鑑賞に堪えるレベル。ただし、両方とも多少音がオフ気味になる部分がある。演奏面ではコブの小気味良いリズムが印象的。マイルスはいつも通り素晴らしい。だが、このツアーでの聴きどころは、このツアー後に脱退が決まっていたコルトレーンにある。「Giant Steps」の録音を終えた時期で、既に自己のスタイルを確立しており、ここでも遠慮なくそのスタイルを披露。さぞかしアップテンポの曲で本領発揮かと思えば、ベストは Disc 1 [5] における、アブストラクトな演奏(続くケリーの明るいピアノになんとも違和感あり)。このコルトレーンを楽しめるかどうかでこのブートの評価が分かれるでしょう。Disc 2 は [3] が聴きどころでブリッジ以降のコルトレーンがまた良い感じなんだけれど、音質悪化が進行していよいよ聴くのが厳しくなっていくのが残念。Disc 2 [4] はテーマのあと、2分以上に及ぶチェンバースのアルコ・ソロから始まる珍バージョンながら、マイルスもコルトレーンも好調。いずれにしてもコルトレーンを楽しむブート。(2006年5月27日) | ||
| If I Were A Bell (Bootleg) | ||
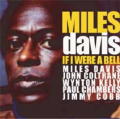 曲:★★★★ 演奏:★★★★ 音質:★★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1960/4/8 [1] If I Were A Bell [2] Fran-Dance [3] So What [4] All Blues [5] The Theme |
Miles Davis (tp) John Coltrane (ts) Wynton Kelly (p) Paul Chambers (b) Jimmy Cobb (ds) |
| 「Spring, 1960」 と同じヨーロッパ・ツアーの音源、よって聴きどころも同じ。音質は、ちょっとシャリシャリしていて聴きづらい感じもするけれど、鑑賞に耐えるレベル。このブートの目玉は [1] で、いくつか残されているこのツアーの音源の中でも、これでしか聴けない貴重なもの。コルトレーンは、この曲のイメージを壊さない程度に抑え気味ながら、音数を詰め込んだフレーズでしっかりと押しの強い個性を主張。そして、ここでの [3] はなかなか熱い。[4] はマイルスのテンションが高く、コルトレーンも「Spring, 1960」と同様なムードで快演。コルトレーン好きにとって、別れのヨーロッパ・ツアーは実に楽しめる。(2006年5月27日) | ||
| Last Spring With Coltrane (Bootleg) | ||
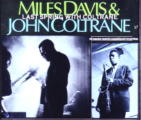 曲:★★★ 演奏:★★★★ 音質:★★★★☆ (Disc 1) 音質:★★★☆ (Disc 2) 音質:★★★★ (Disc 3) 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1960/3/22 (Disc 1) 1960/3/24 (Disc 2) 1960/4/8 (Disc 3) Disc 1 [1] So What [2] Fran-Dance [3] Walkin' / The Theme [4] On Green Dolphin Street [5] All Blues / The Theme Disc 2 [1] So What [2] On Green Dolphin Street [3] All Blues / The Theme Disc 3 [1] If I Were A Bell [2] Fran-Dance [3] So What [4] All Blues / The Theme |
Miles Davis (tp) John Coltrane (ts) Wynton Kelly (p) Paul Chambers (b) Jimmy Cobb (ds) |
| 「Spring, 1960」の Disc 1 と同じく3月22日のストックホルム、3月24日のコペンハーゲン、そして「If I Were A Bell」などとと同じ4月8日のスイスの音源を集約したブートレグ。衛星放送の再放送からの収録とのことで、ほぼオフィシャルレベルの音質。4月8日の音は相変わらずシャリシャリと高音が耳障りだけれど、従来盤よりは少し抑えられている。コペンハーゲン音源は初めて聴くので従来盤との比較ができないけれど、この中では一番音がコモっているし、ピアノの音は波打っているという不安定さ。演奏傾向としては他ディスクと同じでコルトレーンの吹きまくりがメイン。正直なところ、よほどのマニアでない限り(特にコルトレーン・マニアでない限り)3公演すべてを聴く必要はない。そのくらい演奏は一定以上の水準をクリアしているし、日によって大きく違うということでもない。音質、演奏、収録曲すべてにおいてストックホルムが一番良いので、単独のブートレグがあれば興味がある人にはお勧めしておきたい。なにしろ、マイルスの歴史上、メンバー(コルトレーン)を抑止できずに野放しにしているというのは非常に珍しく、そんな押され気味のマイルスが聴けるのはこの60年春のヨーロッパ・ツアーだけなのだから。(2012年6月17日) | ||
| Someday My Prince Will Come | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★★★ マイルス入門度:★★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1961/3/7 1961/3/20 1961/3/21 [1] Someday My Prince Will Come [2] Old Folk [3] Pfrancing (No Blues) [4] Drad Dog [5] Teo [6] I Thought About You [7] Blues No.2 [8] Someday My Prince Will Come (alt take) |
Miles Davis (tp) Hank Mobley (ts except [5]) John Coltrane (ts [1] [5]) Wynton Kelly (p) Paul Chambers (b) Jimmy Cobb (ds except [7]) Philly Joe Jones (ds [7]) |
| なんと言っても表題曲が素晴らしい。冒頭のチェンバースのブンブン・ベースに明るくクリアなケリーのピアノが舞い降り、マイルスのミュートがメロディを奏ではじめる。モブレーのほのぼのテナーがソロを取ったあと、マイルスが間を取り持ってからコルトレーンがシャープに締める。良い曲に、良いアレンジ、良い演奏と3拍子揃っている。しかしメロディをなぞっているだけなのにどうしてこんなにイイ味が出せるんだろう。このアルバムはそんなイイ味のマイルスを堪能できる作品。スタジオ盤としては「Kind Of Blue」以来の本作。常に進化を遂げてきたマイルスが、やや後退していたのが、ハンコック、ロン・カーター、トニー・ウィリアムスと出会うまでのこの時期。しかし、ここで聴ける演奏も捨てがたい。一見平凡に見える内容ながら、50年代中盤のハード・バップよりは洗練されていて、尚且つリラックスしたムードがある。それに一役買っているのがケリーの明快なピアノとモブレーの肩の力の抜けたテナー。その意味で、コルトレーンが参加している [5] はやや異質なんだけれど、ここでのコルトレーンがまた素晴らしくマイルスも緊張感溢れるプレイを展開しているのが面白い。アルフレッド・ライオンに作曲家としてその才能を認められてきたモブレーがここでは曲の提供がなく、純粋にテナー奏者として迎えられているためか持ち味が生きていないのが少々残念。(2006年5月27日) | ||
| Saturday Night At Blackhawk | ||
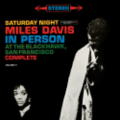 曲:★★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★★ マイルス入門度:★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1961/4/22 Disc 1 [1] If I Were A Bell [2] So What [3] No Blues [4] On Green Dophine Street [5] Walkin' [6] 'Round Midnight [7] Well You Needn't [8] The Theme Disc 2 [1] Autumn Leaves [2] Neo [3] Two Bass Hit [4] Bye Bye (Theme) [5] Love, I've Found You [6] I Thought About You [7] Someday My Prince Will Come [8] Softly As In A Morning Sunrise |
Miles Davis (tp) Hank Mobley (ts) Wynton Kelly (p) Paul Chambers (b) Jimmy Cobb (ds) |
| モブレー在籍時のライヴ盤。メンツから想像できるように、オーソドックスでリラックスした演奏内容。マイルスのアルバム中、最もケリーの個性が良く出ている作品で、何かと不評のモブレーもちゃんと「らしさ」を出している。しかし、1年前、コルトレーンとの最後のツアーで聴ける演奏内容とどちらが進歩的かかと言えば、やはり1年前の方。テナー奏者1人が違うだけで、全体的な印象まで変わってしまうというのも興味深い。Disc 1 [6]、Disc 2 [1] といった超有名曲がスタジオ盤のイメージをそこそこ残しつつも、それぞれにイイ味を出しているのも、この時期、このメンバーだからこそでしょう。非常に聴きやすいので初心者に勧めたいと思うけれど、長尺演奏が多く、2枚組ということもあって手を出しにくいのが難点。尚、このライヴ盤は、金曜日と土曜日と合わせて4枚組みのコンプリート盤として販売されているものと、金曜日と土曜日それぞれバラで販売されているものがあり、僕がなぜこれを選んだのかというと、4枚もいらないと思ったのと Disc 2 [8] が入っていたから。マイルスにしては珍しい選曲だと思っていたものの、演奏を聴いてみるとマイルス、モブレー抜きのピアノ・トリオ演奏でガックリ。また、録音状態はいいんだけれど、ベースの音が引っ込んでいてそれも残念。それでも、たまにはこういうオーソドックスなジャズを演るマイルスを聴くのもいいかなあと思わせる作品。(2006年5月27日) | ||
