| 学名 | Olea europaea |  |
| 英語名 | Olive(オリーブ) | |
| 名前の由来及び歴史 | オリーブは食用、薬用として広く利用されており、人間との付き合いは長いです。 オリーブの起源は小アジアとされ、シリアからトルコを経てギリシャへと拡がったとされています。 また、ノアの箱船に乗せられたハトがオリーブの枝をくわえて戻ってきたので洪水が治まったことを知ったという話もあり、平和と希望のシンボルとされています。 そのため、平和のシンボルとしてオリンピックの賞にも使われています。 オリーブと言えば、日本では小豆島が有名で、温暖な地方での栽培が盛んです。 オリーブは香川県の県木であり県花でもあります。 地中海気候に似ている瀬戸内海に浮かぶ小豆島は日本におけるオリーブ栽培の発祥地で、たくさんのオリーブ園があります。 名前はオランダ語の「Oliff」に由来します。 |
|
| 分類 | モクセイ科 常緑樹 | |
| 原産地 | 小アジア | |
| 特徴 | モクセイ科の常緑樹で、2年目に結実します。 オリーブの葉(オリーブ葉、オリーブリーフ)の表面は緑色をしており、裏面は白色をしています。 梅雨の前に黄白色の花をつけ、香りがあります。 オリーブの実は熟すと黒色(ブラックオリーブ、黒オリーブ)になります。 |
|
| 成分 | オリーブの実から採れるオリーブオイルは、植物油の中でも消化吸収がよく、リノール酸、リノレン酸など、豊富な油溶性ビタミン類、さらに細胞に酸素を送る働きを持つスクツレンなど、栄養的価値の高い成分が含まれています。 オリーブの果肉だけ収集したものから採取したオリーブバージンオイル(バージンオリーブオイル)の成分を分析してみると、酸化度が0.17と低く、鹸化値190、ヨウ素値83.5といずれも良いです。 脂肪酸の組成は、不飽和脂肪酸を豊富に含み、オレイン酸79.4%、パルチミン酸9.2%、リノール酸8.1%、ステアリン酸2.6%、リノレイン酸0.6%、その他プロビタミンA、ビタミンF、D、E、スクアレンなどがあります。 |
|
| 効能(効果、効用、薬効、作用) | ○コレステロール値を減らします。 ○心臓及び動脈系の病気に良いです。 ○便秘を予防し、美容やダイエットに良いです。 ○胃を守り、胃液の分泌を良くします。 ○ニキビや毛穴等、肌の洗顔(クレンジング)や保湿等のスキンケアに良いです。 ○髪の毛や頭皮等のヘアケアに良いです。 ○紫外線等、日焼けの予防に良いです。 ○歯茎の健康に良いです。 |
|
| 使い方(利用法、利用方法、活用法) | 健康食品としてはとても有名ですよネッ! オリーブの実は塩漬けやピクルスに使用(利用)します。 オリーブオイルはお料理や美容、化粧品、薬用に、また石鹸(石けん、ソープ)やクレンジング等に使用(利用)します。 オリーブの葉(オリーブ葉、オリーブリーフ)をオリーブ茶(ハーブティー、ハーブ茶、お茶)としても使用(利用)できます。 |
|
| 育て方(栽培方法、管理方法) | 日の当たる、水はけのよい土地を好みます。冬は直接冷たい風が当たらないように注意しましょう。水やりは表土が乾いたらたっぷり行います。繁殖は挿し木で行います。 | |
| 参考文献 「アロマセラピーのベースオイル」 | ||
| オリーブ関連商品の通販(通信販売)はこちらから!! | ||
| 商品名(別名) | 特徴 | 価格(税込)内容量 |
| 【量り売り・計り売りキャリアオイル(アロママッサージオイル、植物油、ベースオイル、化粧用オイル)】 オリーブオイル(オリーブ油) |
不飽和脂肪酸の成分を多く含み、皮膚を柔軟にする働きがあります。 ○別途アロマボトル(保存容器、びん、ビン、瓶など)が必要となります。 |
15円(税込)内容量1ml〜 量り売り・計り売り |
| 【ドライハーブ(乾燥ハーブ)、スパイス(香辛料)量り売り・計り売り】 オリーブの葉(オリーブ葉、オリーブリーフ) |
6000年以上も前から使用(利用)されています。オリーブオイルとしての使用(利用)は有名ですが、オリーブの葉(オリーブ葉、オリーブリーフ)もまたオリーブ茶(ハーブティー、ハーブ茶、お茶)として使用(利用)できます。 ○原産国 イタリア ○形状 カット ○使用部位 オリーブの葉(オリーブ葉、オリーブリーフ) ○使い方(利用法、利用方法、活用法) ハーブクッキング(ハーブ料理)、オリーブ茶(ハーブティー、ハーブ茶、お茶)、簡単手作りポプリ(手作りハーブポプリ)の材料、アロマバス(手作りハーブ入浴剤、ハーブ風呂)、ハーブ染め(ハーブ染色)めの材料、手作りハーブクラフト(手作りハーブ作品作り)など |
300円(税込) 内容量10g〜 量り売り・計り売り |
| ハーブ、スパイス&ポプリ、アロマセラピー(アロマテラピー)の専門店 ハーブ&アロマ花と香りの店 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-9-29第2プリンスビル608号 TEL&FAX:092-713-7459 営業時間 AM9:00〜PM6:00 店休日 日祝祭日(但し特別なイベントは除きます) |
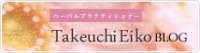

 ブログ
ブログ