| 大昔から人間は体中に色を塗って飾り立てたり、害虫や疫病から身を守るために様々な工夫をしてきました。 そしてまた布を草木で染めたり、花の汁や果実の汁、葉や根をなどを煎じて染液をつくり、糸や衣類を浸して染めました。 ハーブ(香草、薬草、植物)のもつ殺菌カを染液に封じ込め、雑菌から身を守ったり、病気の予防に使用(利用)したのです。 ミイラづくりの時の包帯もスパイス(香辛料)等で染められていたそうです。 ハーブ(香草、薬草、植物)を使用(利用)することで自然の染料が持つ、渋みのある色合いや光沢の良さを表現することができます。 日本では、古くからある紅花染め(ベニバナ、べにばな、サフラワー、コウカ)、藍染、泥染等がその代表です。 真っ赤な紅花染め(ベニバナ、べにばな、サフラワー、コウカ)はとても高貴で、何百年も色落ちせず、衣類につく虫を駆除してきました。 泥(カオリンなどの土類)染は大島紬などでおなじみで、熱を調整する働きがあります。 藍染は戦国乱世の頃に広く普及し始め、明治維新の頃にはインド藍が輸入されるようになりました。 日本ではタデ科のアイ、インドではマメ科のインドアイ、ヨーロッパではアブラナ科のヨーロッパアイと、どれも青色染料です。 外国ではインディゴブルーの名でよく知られ、ジーンズなどの染料がそれです。 インディゴブルーは、学名をポリゴナム・テインクトリゥムといい、染料用という意味を持っています。 葉や実には解毒作用があり、薬草としても知られています。 その他のハープ(香草、薬草、植物)では、タンジー、エルダー(エルダーフラワー、エルダーベリー、西洋ニワトコ、セイヨウニワトコ)、マダールート等も染料として多く使用(利用)されます。 |
| ハーブ染め(ハーブ染色)関連商品の通販(通信販売)はこちらから!! |
| ハーブ、スパイス&ポプリ、アロマセラピー(アロマテラピー)の専門店 ハーブ&アロマ花と香りの店 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-9-29第2プリンスビル608号 TEL&FAX:092-713-7459 営業時間 AM9:00〜PM6:00 店休日 日祝祭日(但し特別なイベントは除きます) |
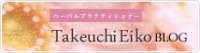

 ブログ
ブログ