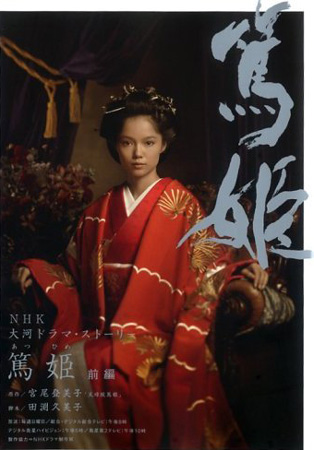
◆ TKKI カナヤマ オフィシャル ホームページ。
TKKI KANAYAMA’S OFFICIAL
HOMEPAGE.
◆ カナヤマ日本の歴史ハンドブック。
KANAYAMA’S JAPANESE HISTORY
HANDBOOK.
◆ カナヤマ 江戸幕府 大奥ガイドブック。
KANAYAMA’S GUIDEBOOK ON THE
OOKU INNER PALACE OF THE
TOKUGAWA (EDO) SHOGUNATE
GOVERNMENT.
『 (Kjhh)21726
カナヤマ 江戸幕府
大奥ガイドブック
大奥 年表
No.11。 』
■ パソコン(PC)、携帯用パソコン、タブレ
ット端末(PC)、スマートフォン、ウェアラ
ブル端末、スマートテレビ 用電子書籍。
メ ニュー (目次)
■ 次の項目から選んで、クイックして下さい。
□ 江戸幕府・大奥
簡略年表。
□ 江戸幕府・大奥
詳細年表。
□ 大奥 年表
□ 大奥 年表
□ 大奥 年表
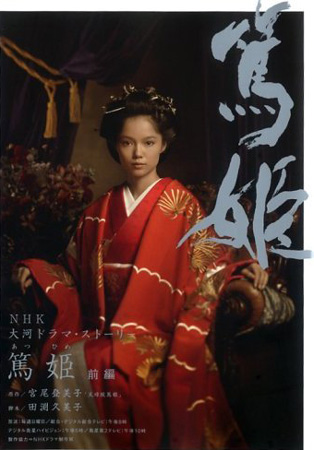
○ 幕末の江戸幕府・大奥の実力者の
天璋院・篤姫 (てんしょういん・あつ
ひめ、篤姫役: 宮崎あおい)。
○ ドラマ「篤姫」での天璋院・篤姫フォト
( 宮崎あおいが演じる篤姫)。
○ テレビ局のドラマ「篤姫」の出版本の
書籍販促用PRフォト。
■ 上位のWEBサイト。
□ (KOH) カナヤマ オフィシャル >
□ (Cse) 国際理解総合サイト >
□ (Ke) 百科事典。 >
□ (Khh) 歴史学ハンドブック。 >
□ (Kjhh) 日本史ハンドブック。 >
□ (Kjhh) 江戸幕府 大奥 ガイド >
ブック。
□ (Kjhh) 江戸幕府 大奥ガイド >
■ カナヤマ 主要 公式ホー
ムページ略語一覧表。
□ 主要サイトの略語・説明表。
□ 日本史辞典 ・日本語版へ。
◆ 江戸幕府 大奥 ガイド
ブックの内容 :
■ 江戸幕府 大奥 ガイドブック。
■ 江戸幕府 大奥の、初学者・初心者向
インターネット用 電子書籍。
■ パソコン(PC)、携帯用パソコン、タブレ
ット端末(PC)、スマートフォン、ウェアラ
ブル端末、スマートテレビ 用電子書籍。
■ 初学者・初心者用 オンライン 江戸幕府
大奥ガイドブック。
■ 江戸幕府 大奥 の 入門 ガイドブック。
■ 江戸幕府 大奥 (えどばくふ おおおく)
関連 初学者・初心者向 インターネット用
オンライン書籍(ブック)。
■ この電子書籍1冊で (この本1冊で)、
江戸幕府の、大奥のこと(概略)が、
一通り、わかる。
■ 江戸時代に、 江戸幕府の将軍が、
最高権力者として、日本を支配していた。
そして、江戸幕府(徳川宗家)の後宮
の大奥にいる将軍の母や夫人とその側
近、大奥監督者も、将軍と共に、日本の
政治を動かしていた。
■ TKKI カナヤマ著 江戸幕府・大奥
ガイドブック。
□ 日本史辞典 ・日本語版へ。
◆ (Kjhh)
江戸幕府 大奥
ガイドブック
大奥 年表。
◆ 江戸幕府 大奥
簡略年表。
(えどばくふ おおおく
かんりゃくねんぴょう)。
○ 『 では、 江戸幕府・大奥に関係
する出来事を、年代順に、見て
みよう。 』
◆ 江戸幕府・大奥 簡略年表。
■ 1590年 ● 徳川氏の関東領地換え。
(天正18年) 豊臣秀吉の命(めい、命令)により、
中部地方から関東地方への徳川氏
の領地換えにより、 江戸城が、徳
川氏の本城(ほんじょう、本拠地の
城)となり、 徳川家康の妻子が、
江戸城に移り、 江戸城の後宮の
大奥が誕生する。
● 初めは、大奥は、 徳川氏当主・
将軍の、夫人(正室夫人、側室夫
人)や 元服(成人)前の子が単に
居住する場所であった。
● 徳川家康の2人の正室夫人は
既に死去し、家康の側室夫人たち
や子供たち、家康世子 ・徳川秀忠
の乳母(うば)の大姥局(おおばの
つぼね)が、江戸城の大奥に入 り、
家康の側室夫人たちや大姥局が、
交代で、 大奥の監督者(大奥の
実務の実権をもつ人)となる。
● 家康の側室夫人たちは、15
98年(慶長3年)まで、江戸 城
の大奥に居住し、それ以後は、
家康が死去する1616年まで、
家康と共に、家康の政務居城
の伏見城、豊臣大阪城・西の丸、
江戸城、駿府城に居住する。
● 一方、家康三男の徳川秀忠
は、1590年(天正18年)に上
洛し、豊臣秀吉に謁見する。
その後、秀忠は、畿内在留の多
い家康に代わり、江戸城で関東
領国の支配に当たり、また、畿内
と関東の往復を繰り返す。
1595年(文禄4年)9月に、
秀忠は、お江(おごう)と婚儀を
結ぶ。
秀忠の正室夫人のお江与
(お江)と子(娘)は、1599年(慶
長4年)頃まで、豊臣氏の人質とし
て、畿内(きない)の大阪や伏見
の徳川屋敷に居住する。
● TKKI カナヤマ著 江戸幕府
大奥ガイドブック。
■ 1598年 ● 1598年(慶長3年)の豊臣秀吉
(慶長 3年) 死去後、京(都)の伏見城(豊臣
秀吉築・前期木幡山伏見城)を、
徳川家康が、豊臣氏大老として、
政務居城(1598年ー1599年
9月)とし、入城する。
● 家康の側室夫人達は、伏見城
に移る。
■ 1599年頃 ● 1599年(慶長4年)頃に、徳
(慶長 4年) 川秀忠の正室夫人のお江与(お
えよ、お江(おごう))と子(娘)が、
豊臣氏の人質から解放され、
畿内(きない)の大阪や伏見の徳
川屋敷から、江戸城の大奥に移
る。
■ 1603年 ● 徳川 家康 (とくがわ いえやす)
(慶長 8年) が、 征夷大将軍となり、江戸に
幕府を開き、江戸幕府(1603年
〜1867年)が樹立される。
● 家康が、江戸幕府の初代将軍
(将軍在任:1603年〜1605年)
となる。
● 家康の初代将軍時の、江戸城
の大奥の監督者(大奥の実務の
実権を握る人)は、 家康世子の
徳川秀忠の乳母(うば)の大姥局
(おおばのつぼね、生没年:152
5年〜1613年))である。
● 家康の初代将軍時、家康の側
室夫人たちは、家康と共に、政務
居城の伏見城( 家康築・後期・木
幡山伏見城)に居住する。
■ 1605年 ● 徳川 秀忠 (ひでただ、将軍在
(慶長10年) 任:1605年〜1623年、家康の
三男)が、 江戸幕府の第2代将
軍となる。
大御所(お おごしょ、引退後の
将軍)の徳川家康が、生きている
間、江戸幕府の政治の実権をもつ。
● 秀忠の2代将軍時、秀忠正室・
お江与(お 江)が、 大奥の最高
権力者となる。
また、秀忠・乳母の大姥局(お
おばのつぼね、生没年:1525年
〜1613年)が、 江戸城の大奥
の監督者(大奥の実務の実権を
握る人)となる。
● 秀忠の2代将軍時、大御所とな
った徳川家康の側室夫人たちは、
1605年から1607年まで、家 康
の政務居城の伏見城(ふしみじょ
う、家康築・後期・木幡山伏見城)
に居住し、1607年から1616年
まで、家康の政務居城の駿府城
(すんぷじょう)に居住する。
■ 1618年 ● 徳川家光・生母のお江与(おえ
(元和 4年) よ、お江(おごう)) と、 家光・乳
母 (うば)のお福(おふく、春日局
(かすがのつぼね))が、 大奥法
度(おおおくはっと)を定める。
● TKKI カナヤマ著 江戸幕府
大奥ガイドブック。
■ 1623年 ● 徳川 家光 (いえみつ、将軍在任:
(元和 9年) 1623年〜1651年、秀忠のニ男)
が、 江戸幕府の第3代将軍となる。
大御所(お おごしょ、引退後の将
軍)の徳川秀忠が、生きている間、
江戸幕府の政治の実権をもつ。
● 徳川秀忠の長男で、家光の腹
違いの兄は早世する。
● 家光の3代将軍時の、江戸城の
大奥の監督者(大奥の実務の実
権を握る人)は、 家光乳母(うば)
のお福(おふく、春日局)であり、
お福(春日局)死後は、お万(おま
ん)である。
● お福(春日局)は、町でスカウト
した、お楽(おらく、後の徳川家綱
(いえつな)生母)、 お夏(おなつ、
後の徳川家宣(いえのぶ)祖母)、
お玉(おたま、後の徳川綱吉(つな
よし)生母)、の3人の体の(じょう
ぶ)丈夫な町娘を大奥に入れる。
それら3人の町娘は徳川家光
のお手付きとなり、それぞれ家光
の男子を産む。
■ 1651年 ● 徳川 家綱 (いえつな、将軍在任:
(慶安 4年) 1651年〜1580年、家光の長男)
が、 江戸幕府の第4代将軍となる。
● 家綱の4代将軍時の、江戸城の
大奥の監督者(大奥の実務の実
権を握る人)は、家綱・乳母の矢島
局(やじまのつぼね)である。
■ 1680年 ● 徳川 綱吉 (つなよし、将軍在任:
(延宝 8年) 1680年〜1709年、家光の四男)
が、江戸幕府の第5代将軍となる。
● 綱吉の5代将軍時の、大奥の最
高権力者は、 綱吉・生母の桂昌
院(けいしょういん、お玉(おたま))
である。
● TKKI カナヤマ著 江戸幕府
大奥ガイドブック。
■ 1709年 ● 徳川 家宣 (いえのぶ、将軍在任:
(宝永 6年) 1709年〜1712年、家光の孫)が、
江戸幕府の第6代将軍となる。
● 家宣の6代将軍時の、大奥の最
高権力者は、 家宣の正室夫人の
熙子(ひろこ、天英院(てんえいい
ん))である。
■ 1713年 ● 徳川 家継 (いえつぐ、将軍在任:
(正徳 3年) 1713年〜1716年、家宣の四男)
が、 4歳位で、江戸幕府の第7代
将軍となる。
● 家継の5代将軍時の、最初の17
13〜1714年の間、大奥の最高
権力者は、 家継生母の月光院
(お喜世)(げっこういん(おきよ))
であり、月光院(お喜世)付御年寄
(おとしより、大奥上級幹部)の絵
島(えじま)が、大奥の監督者(実
務の実権を握る人)であった。
● 1714年(正徳4年)の江島生島
事件後は、 月光院(お喜世)は
面目を失い、絵島は失脚、配流
(はいる)となり、家継の7代将軍
時の、1714年(正徳4年)〜17
16年(正徳6年)の間、大奥の最
高権力者は、 6代将軍・家宣・正
室夫人の熙子(天英院)となる。
■ 1714年 ● 絵島生島(えじまいくしま)事件が
(正徳 4年) 起こり、 大奥の風紀が粛清される。
1714年(正徳4年)の絵島生島
事件後、月光院(げっこういん、お喜
世(おきよ))は、面目を失い、1714
年から1716年までの間、再び、徳
川家宣・正室夫人の天英院(てんえ
いいん、熙子(ひろこ))が、大奥の
最高権力者となる。
■ 1716年 ● 江戸幕府の6代将軍・徳川家宣
(正徳 6年) (いえのぶ)の正室夫人の天英院
(てんえいいん、熙子(ひろこ))が、
1716年(正徳6年)に、7代将軍・
徳川家継(いえつぐ)死去時、次期
8代将軍に徳川吉宗を指名する。
● TKKI カナヤマ著 江戸幕府
大奥ガイドブック。
■ 1716年 ● 徳川 吉宗 (よしむね、将軍在任:
(正徳 6年) 1716年〜1745年、家康の曾孫、
紀州藩主) が、1716年(正徳6年)
に、江戸幕府の第8代将軍となる。
● その後、8代将軍・徳川吉宗の治
世に、 財政再建の名目で、 大奥
の人員が、大幅に縮小される。
● TKKI カナヤマ著 江戸幕府
大奥ガイドブック。
■ 1745年 ● 徳川 家重 (いえしげ、将軍在任:
(延享 2年) 1745年〜1760年、徳川吉宗の長
男)が、 江戸幕府の第9代将軍とな
る。
● 家重将軍時代、 家重は、大奥に
入浸(いりびた)りとなる。
■ 1760年 ● 徳川 家治 (いえはる、将軍在任:
(宝暦10年) 1760年〜1786年、家重の長男)
が、江戸幕府の第10代将軍となる。
■ 1787年 ● 徳川 家斉 (いえなり、将軍在任:
(天明 7年) 1787年〜1837年、 吉宗の曾
孫、一橋徳川家当主・徳川治済の
長男)が、 江戸幕府の第11代
将軍となる。
● 家斉将軍時代、 家斉正室夫人の
篤姫(あつひめ、広大院(こうだいい
ん)、薩摩藩出身)が、大奥の権力者
となる。
そして、広大院・篤姫の側近の
花町(はなまち、後に大奥火事で焼
死)が、大奥の監督者(大奥の実務
の実権を握る人)となる。
家斉将軍時代の後半期は、
側室夫人の1人のお美代(おみよ)
が、大奥の監督者(大奥の実務の
実権を握る人)となる。
● 多妻多子の徳川家斉。
徳川家斉は、側室夫人・約40人、
子供・約55人をもつ。
● TKKI カナヤマ著 江戸幕府
大奥ガイドブック。
■ 1837年 ● 徳川 家慶 (いえよし、将軍在任:
(天保 8年) 1837 年〜1853年、家斉のニ男)
が、江戸幕府の第12代将軍となる。
● 家慶将軍時代に、 御年寄(おとし
より、大奥上級幹部)の姉小路(あ
ねこうじ)が、 大奥の監督者(大奥
の実務の実権を握る人)となる。
■ 1853年 ● 徳川 家定 (いえさだ、将軍在任:
(嘉永 6年) 1853 年〜1858年、家慶の四男)
が、 江戸幕府の第13代将軍となる。
● 徳川家定将軍時代に、 家定の生
母・本寿院(ほんじゅいん)と家定乳
母(うば)の歌橋(うたはし)が大奥
の最高権力者となる。
また、御年寄(おとしより、大
奥上級幹部)の滝山(たきやま、
御年寄在任:1853年〜1867
年)が、 大奥の監督者 (大奥の
実務の実権を握る人)となる。
● 第13代将軍となった、徳川家定
は体が弱かったため、 次期14
代将軍継嗣(けいし)問題が起こり、
雄藩連合政治を望み次期14代将
軍に一橋慶喜(ひとつばし よしの
ぶ、水戸藩出身・一橋家当主)を
擁(よう)する、一橋派 と、 徳川
氏独裁政治を望み次期14代将軍
に徳川 慶福(よしとみ、紀伊藩藩
主)を擁する、紀州派(南紀派)
とが、対立する (1853年頃〜
1859年頃)。
● TKKI カナヤマ著 江戸幕府
大奥ガイドブック。
■ 1858年 ● 1858年(安政5年)12月、徳川
(安政 5年) 家茂 (いえもち、 将軍在任:18
58年〜1866年、 家斉の孫、紀
州藩主・徳川慶福) が、 江戸幕
府の第14代将軍となる。
● 家茂将軍時代、天璋院・篤姫(て
んしょういん・あつひめ、家茂の義
母) と、 家茂・生母の実成院(じ
っせいいん)が、大奥の最高権力
者となる。
御年寄の滝山が、大奥の監督
者(大奥の実務の実権をもつ人)と
なる。
● TKKI カナヤマ著 江戸幕府
大奥ガイドブック。
■ 1866年 ● 1866年(慶応2年)12月に、
(慶応 2年) 徳川 慶喜 (よしのぶ、将軍在任:
1866年〜1867年、家康の子孫、
9代水戸藩主・徳川斉昭の七男、
一橋徳川家当主) が、 江戸幕府
の第15代将軍となる。
● 徳川慶喜の大奥改革に、和宮と
共に、天璋院・篤姫は、反対する。
● 慶喜の妻子は、大奥に入らず。
慶喜将軍時代は、天璋院・篤
姫(てんしょういん・あつひめ)と和宮
(かずのみや)が、大奥の最高権力
者となる。
■ 1867年 ● 大政奉還。
(慶応 3年) 1867年(慶応3年)10月に、
江戸幕府は、大政奉還(政権を朝廷
へ返上)を行う。
● 江戸幕府の大政奉還により、江戸
幕府が、名目的に、終焉(しゅうえん)
する。
■ 1868年 ● 江戸城・無血開城。
(慶応 4年) 1868年(慶応4年)4月に、江戸
幕府(徳川宗家)の本城(ほんじょう、
本拠地の城)の江戸城が、無血開城
される。 討幕軍が、江戸城に入場
する。
● 大奥法度は廃止となり、 江戸城の
後宮の大奥は、江戸城・無血開城に
より、消滅する。
● TKKI カナヤマ著 江戸幕府
大奥ガイドブック。
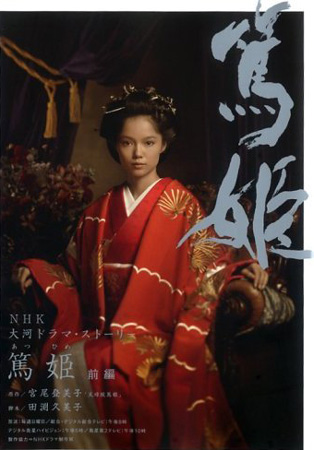
○ 幕末の大奥の実力者の天璋院・篤姫
(てんしょういん・あつひめ、篤姫役:
宮崎あおい)。
○ ドラマ「篤姫」での天璋院・篤姫フォト。
○ テレビ局のドラマ「篤姫」の出版本の
書籍販促用PRフォト。
□ 日本史辞典 ・日本語版へ。
#innerpalacedetailedchronology
◆ 江戸幕府 大奥
詳細年表
(えどばくふ おおおく
しょうさいねんぴょう)。
○ 『 では、 江戸幕府・大奥に関係
する出来事を、年代順に、見て
みよう。 』
◆ 江戸幕府・大奥 詳細年表。
□ 大奥 年表
□ 大奥 年表
□ 大奥 年表
■ 当年表は、 大奥(1590年〜1868年)
が存在した時代の詳細年表である。
■ 歴史学の立場から、年代を追って、江戸
幕府・大奥の実像 (歴史的 有名な出来
事には、虚像と実像があるが) を見てみ
よう。
■ 江戸時代については、『 近世日本歴史
年表 』を、 明治時代については、
さい。
■ より理解を深めるために、当年表と近い
時期の日本史辞典の年表 や年代順出来
初期年表、 お江(おごう) 年表、 豊臣
龍馬 年表 』 も参照して ください。
■ 天璋院・篤姫(てんしょういん・あつひめ)
の詳細 な内容に関しては、
『 天璋院・篤姫 ガイドブック 』を参照
してください。
■ 当年表は、 西暦を先に、 その後ろの
( )内に和暦を記載している。
■ 日本の暦。
■ 和暦の、旧暦(太陰太陽暦)
と 新暦(太陽暦)。
■ 日本では、 大化(たいか)元年(西
暦645年)から明治5年(西暦1872
年)まで旧暦(太陰太陽暦)を使用し 、
1873年(明治6年)から現在まで新
暦(太陽暦、現使用のグレゴリオ暦)
を使用している。
■ 日本の太陽暦の採用。
明治新政府の旧暦から新暦への切
り替え。
明治新政府(近代日本政府)は、
近代化のため、旧暦(太陰太陽暦)
の1872年(明治5年)12月2日の
翌日(12月3日)を、 新暦(太陽暦、
現使用のグレゴリオ暦)の1873年
(明治6年)1月1日とした。
■ 当書の日付(年月日)は、 一般の
日本歴史書と同様に、1872年(明
治5年)以前は日本の旧暦(太陰太
陽暦)の年月日を記載し、 1873年
(明治6年)以後は日本の新暦(太 陽
暦、現使用のグレゴリオ暦))の年月
日を記載している。
● TKKI カナヤマ著 和暦ガイドブック。
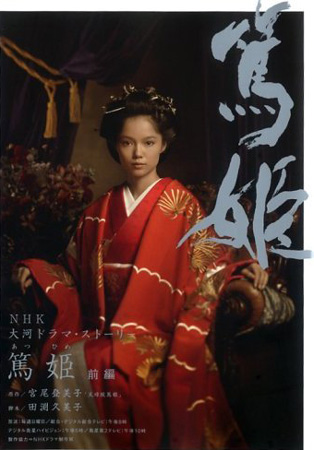
○ 幕末の大奥の実力者の天璋院・篤姫
(てんしょういん・あつひめ、篤姫役:
宮崎あおい)。
○ ドラマ「篤姫」での天璋院・篤姫フォト。
○ テレビ局のドラマ「篤姫」の出版本の
書籍販促用PRフォト。
□ 江戸幕府・大奥 詳細年表の先頭へ戻る。
□ 日本史辞典 ・日本語版へ。
#innerpalacedetailedchronology-1573
◆ 江戸幕府・大奥
詳細年表。
■ 1573年 ● 天正改元。
(天正 元年) 1573年7月28日に、 和暦
の「元亀」(げんき) が、 「 天正」
(てんしょう、天正元年・1573年・
7月28日〜 天正20年・ 1592
年・12月8日) に改元される。
■ 1590年 ● 徳川氏の関東領地換え。
(天正18年) 豊臣秀吉の命(めい、命令)により、
中部地方から関東地方への徳川氏
の領地換えにより、 江戸城が、徳
川氏の本城(ほんじょう、本拠地の
城)となり、 徳川家康の妻子が、
江戸城に移り、 江戸城の後宮の
大奥が誕生する。
● 初めは、大奥は、 徳川氏当主・
将軍の、夫人(正室夫人、側室夫
人)や 元服(成人)前の子が単に
居住する場所であった。
● 徳川家康の2人の正室夫人は
既に死去し、家康の側室夫人たち
や子供たち、家康世子 ・徳川秀忠
の乳母(うば)の大姥局(おおばの
つぼね)が、江戸城の大奥に入り、
家康の側室夫人たちや大姥局が、
交代で、 大奥監督者(大奥の
実務の実権をもつ人)となる。
● 家康の側室夫人たちは、15
98年(慶長3年)まで、江戸 城
の大奥に居住し、それ以後は、
家康が死去する1616年まで、
家康と共に、家康の政務居城
の伏見城、豊臣大阪城・西の丸、
江戸城、駿府城に居住する。
● 一方、家康三男の徳川秀忠
は、1590年(天正18年)に上
洛し、豊臣秀吉に謁見する。
その後、秀忠は、畿内在留の多
い家康に代わり、江戸城で関東
領国の支配に当たり、また、畿内
と関東の往復を繰り返す。
1595年(文禄4年)9月に、
秀忠は、お江(おごう)と婚儀を
結ぶ。
秀忠の正室夫人のお江与
(お江)と子(娘)は、1599年(慶
長4年)頃まで、豊臣氏の人質とし
て、畿内(きない)の大阪や伏見
の徳川屋敷に居住する。
● TKKI カナヤマ著 江戸幕府
大奥ガイドブック。
■ 1598年 ● 1598年(慶長3年)の豊臣秀吉
(慶長 3年) 死去後、京(都)の伏見城(豊臣
秀吉築・前期木幡山伏見城)を、
徳川家康が、豊臣氏大老として、
政務居城(1598年ー1599年9
月)とし、入城する。
● 家康の側室夫人達は、伏見城
に移る。
■ 1599年頃 ● 1599年(慶長4年)頃に、徳
(慶長 4年) 川秀忠の正室夫人のお江与(お
えよ、お江(おごう))と子(娘)が、
豊臣氏の人質から解放され、
畿内(きない)の大阪や伏見の徳
川屋敷から、江戸城の大奥に移
る。
■ 1599年 ● 徳川家康が、豊臣氏大老として、
(慶長 4年) 豊臣大阪城・西の丸を、政務居城
(1599年9月ー1600年6月)と
し、入城する。
家康の側室夫人達も、 伏見城
から豊臣大阪城・西の丸 へ移る。
■ 1600年 ● 徳川家康が、1600年(慶長5
(慶長 5年) 年)6月に、豊臣氏大老として、
豊臣大阪城・西の丸を出て、上杉
征伐のため、東国に向かう。
家康の側室夫人達も、豊臣
大阪城・西の丸から出て、東国
に向かう。
■ 1600年 ● 徳川家康が、1600年(慶長5年)
(慶長 5年) 7月に、江戸城に入る (1600年
7月〜9月)。
家康の側室夫人達も、 江戸城
の大奥に入る。
■ 1600年 ● 徳川家康が、1600年(慶長5年)
(慶長 5年) 9月の関ヶ原の戦いに勝利後、
豊臣大阪城・西の丸 を、政務居城
(1600年9月ー1601年3月)とし、
豊臣大阪城に入城する。
家康の側室夫人達も、 江戸城
から豊臣大阪城・西の丸に移る。
■ 1601年 ● 徳川家康は、 落城した伏見城を
(慶長 6年) 再建するため、豊臣大阪城・西の
丸から出て、1601年(慶長6年)
3月に伏見城に入城し再建に着手
し、1602年(慶長7年)に、伏見城
(家康築・後期・木幡山伏見城)を
再建する。 そして、1607年(慶
長12年)まで、伏見城を政務居城
(1601年3月〜1607年)とする。
家康の側室夫人たちも、豊臣
大阪城・西の丸から伏見城に移る。
■ 1603年 ● 徳川 家康 (とくがわ いえやす)
(慶長 8年) が、 征夷大将軍となり、江戸に
幕府を開き、江戸幕府(1603年
〜1867年)が樹立される。
● 家康が、江戸幕府の初代将軍
(将軍在任:1603年〜1605年)
となる。
● 家康の初代将軍時の、江戸城
の大奥の監督者(大奥の実務の
実権を握る人)は、 家康世子の
徳川秀忠の乳母(うば)の大姥局
(おおばのつぼね、生没年:152
5年〜1613年))である。
● 家康の初代将軍時、家康の側
室夫人たちは、家康と共に、政務
居城の伏見城( 家康築・後期・木
幡山伏見城)に居住する。
■ 1604年 ● お江(おごう)が、竹千代(徳川家
(慶長 9年) 光)を出産する。 徳川家康の命
(めい、命令)で、竹千代の乳母(う
ば)として、お福(おふく)が大奥に
入る。
● TKKI カナヤマ著 江戸幕府
大奥ガイドブック。
■ 1605年 ● 徳川 秀忠 (ひでただ、将軍在
(慶長10年) 任:1605年〜1623年、家康の
三男)が、 江戸幕府の第2代将
軍となる。
大御所(お おごしょ、引退後の
将軍)の徳川家康が、生きている
間、江戸幕府の政治の実権をも
つ。
● 秀忠の2代将軍時、秀忠正室・
お江与(お江))が、 大奥の最高
権力者となる。
また、秀忠・乳母の大姥局(お
おばのつぼね、生没年:1525年
〜1613年)が、 江戸城の大奥
の監督者(大奥の実務の実権を
握る人)となる。
● 秀忠の2代将軍時、大御所と
なった徳川家康の側室夫人た
ちは、1605年から1607年ま
で、家 康の政務居城の伏見城
(ふしみじょう、家康築・後期・
木幡山伏見城)に居住し、16
07年から1616年まで、家康
の政務居城の駿府城(すんぷ
じょう)に居住する。
■ 1607年 ● 大御所の徳川家康は、江戸幕
(慶長12年) 府の実権をもったまま、政務居
城(1607年ー1616年)を伏
見城(家康築・後期木幡山伏見
城)から駿府城(すんぷじょう)に
移す。
家康の側室夫人たちも、 伏
見城から家康の駿府城に移る。
■ 1611年 ● 大姥局の侍女のお静(おしづ、
(慶長16年) 生没年:1584年ー1635年)
が、2代将軍の徳川秀忠に見
初(みそ)められ、 男子の幸
松 (こうまつ、保科正之(ほし
なまさゆき、会津松平家・初代
当主、会津藩祖、生没年:16
11年ー1672年)を産む。
徳川秀忠は、正室夫人の嫉
妬深いお江与(お江)には、わ
からないように、養育させる。
● 保科正之(幼名:幸松)は、
3代将軍・徳川家光や4代将
軍・徳川家綱を補佐し、江戸
幕府の基盤を強化する。
■ 1613年頃 ● 秀忠乳母の大姥局が大奥を去
(慶長18年) り、お江与(お江)側近の民部卿
局(みんぶきょうのつぼね)と 家
光・乳母のお福(おふく)が、大
奥監督者(大奥の実務の実権を
握る人)となる。
■ 1618年 ● 徳川家光・生母のお江与(おえ
(元和 4年) よ、お江(おごう)) と、 家光・乳
母 (うば)のお福(おふく、春日局
(かすがのつぼね))が、 大奥
法度(おおおくはっと)を定める。
● TKKI カナヤマ著 江戸幕府
大奥ガイドブック。
■ 1623年 ● 徳川 家光 (いえみつ、将軍在任:
(元和 9年) 1623年〜1651年、秀忠のニ男)
が、 江戸幕府の第3代将軍となる。
大御所(お おごしょ、引退後の将
軍)の徳川秀忠が、生きている間、
江戸幕府の政治の実権をもつ。
● 徳川秀忠の長男で、家光の腹
違いの兄は早世する。
● 家光の3代将軍時の、江戸城の
大奥の監督者(大奥の実務の実
権を握る人)は、 家光乳母(うば)
のお福(おふく、春日局)であり、
お福(春日局)死後は、お万(おま
ん)である。
● お福(春日局)は、町でスカウト
した、お楽(おらく、後の徳川家綱
(いえつな)生母)、 お夏(おなつ、
後の徳川家宣(いえのぶ)祖母)、
お玉(おたま、後の徳川綱吉(つな
よし)生母)、の3人の体の(じょう
ぶ)丈夫な町娘を大奥に入れる。
それら3人の町娘は徳川家光
のお手付きとなり、それぞれ家光
の男子を産む。
■ 1626年 ● お江 (おごう、お江与、崇源院
(寛永 3年) (すうげんいん)、徳川秀忠正室
夫人、徳川家光生母、生没年:
1573年〜1626年)が、 死去
する。
■ 1643年 ● お福 (おふく、春日局(かすが
(寛永20年) のつぼね)、徳川家光・乳母(う
ば)、生没年:1579年〜1643
年)が、 死去する。
● 1643年(寛永20年)のお福
(春日局)の死後は、 以前家
光に見初(みそ)められ尼僧院
主で還俗した、お万(おまん、永
光院)が、 大奥の監督者(実務
の実権をもつ人、監督期間:16
43年〜1651年)となる。
■ 1651年 ● 徳川 家綱 (いえつな、将軍在
(慶安 4年) 任:1651年〜1580年、家光
の長男)が、 江戸幕府の第4
代将軍となる。
● 家綱の4代将軍時の、江戸城
の大奥の監督者(大奥の実務
の実権を握る人)は、家綱・乳
母(うば)の矢島局(やじまのつ
ぼね)である。
■ 1680年 ● 徳川 綱吉 (つなよし、将軍在
(延宝 8年) 任:1680年〜1709年、家光
の四男) が、江戸幕府の第5
代将軍となる。
● 綱吉の5代将軍時の、大奥の
最高権力者は、 綱吉・生母の
桂昌院(けいしょういん、お玉
(おたま)) である。
● TKKI カナヤマ著 江戸幕府
大奥ガイドブック。
■ 1709年 ● 徳川 家宣 (いえのぶ、将軍在任:
(宝永 6年) 1709年〜1712年、家光の孫)が、
江戸幕府の第6代将軍となる。
● 家宣の6代将軍時の、大奥の最
高権力者は、 家宣の正室夫人の
熙子(ひろこ、天英院(てんえいい
ん))である。
■ 1713年 ● 徳川 家継 (いえつぐ、将軍在任:
(正徳 3年) 1713年〜1716年、家宣の四男)
が、 4歳位で、江戸幕府の第7代
将軍となる。
● 家継の5代将軍時の、最初の17
13〜1714年の間、大奥の最高
権力者は、 家継生母の月光院
(お喜世)(げっこういん(おきよ))
であり、月光院(お喜世)付御年寄
(おとしより、大奥上級幹部)の絵
島(えじま)が、大奥の監督者(実
務の実権を握る人)であった。
● 1714年(正徳4年)の江島生
島事件後は、月光院(お喜世)は
面目を失い、絵島は失脚、配流
(はいる)となり、家継の7代将軍
時の、1714年(正徳4年)〜17
16年(正徳6年)の間、大奥の最
高権力者は、 6代将軍・家宣・正
室夫人の熙子(天英院)となる。
□ 日本史辞典・日本語版へ。
#innerpalacedetailedchronology-1714
■ 1714年 ● 絵島生島(えじまいくしま)事件が
(正徳 4年) 起こり、 大奥の風紀が粛清される。
1714年(正徳4年)の絵島生島
事件後、月光院(げっこういん、お喜
世(おきよ))は、面目を失い、1714
年から1716年までの間、再び、徳
川家宣・正室夫人の天英院(てんえ
いいん、熙子(ひろこ))が、大奥の
最高権力者となる。
■ 1716年 ● 江戸幕府の6代将軍・徳川家宣
(正徳 6年) (いえのぶ)の正室夫人の天英院
(てんえいいん、熙子(ひろこ))が、
1716年(正徳6年)に、7代将軍・
徳川家継(いえつぐ)死去時、次期
8代将軍に徳川吉宗を指名する。
● TKKI カナヤマ著 江戸幕府
大奥ガイドブック。
■ 1716年 ● 徳川 吉宗 (よしむね、将軍在任:
(正徳 6年) 1716年〜1745年、家康の曾孫、
紀州藩主) が、1716年(正徳6年)
に、江戸幕府の第8代将軍となる。
● その後、8代将軍・徳川吉宗の治
世に、 財政再建の名目で、 大奥
の人員が、大幅に縮小される。
● TKKI カナヤマ著 江戸幕府
大奥ガイドブック。
■ 1745年 ● 徳川 家重 (いえしげ、将軍在任:
(延享 2年) 1745年〜1760年、徳川吉宗の長
男)が、 江戸幕府の第9代将軍とな
る。
● 家重将軍時代、 家重は、大奥に
入浸(いりびた)りとなる。
■ 1760年 ● 徳川 家治 (いえはる、将軍在任:
(宝暦10年) 1760年〜1786年、家重の長男)
が、江戸幕府の第10代将軍となる。
■ 1787年 ● 徳川 家斉 (いえなり、将軍在任:
(天明 7年) 1787年〜1837年、 吉宗の曾
孫、一橋徳川家当主・徳川治済の
長男)が、 江戸幕府の第11代
将軍となる。
● 家斉将軍時代、 家斉正室夫人の
篤姫(あつひめ、広大院(こうだいい
ん)、薩摩藩出身)が、大奥の権力者
となる。
そして、広大院・篤姫の側近の
花町(はなまち、後に大奥火事で焼
死)が、大奥の監督者(大奥の実務
の実権を握る人)となる。
家斉将軍時代の後半期は、
側室夫人の1人のお美代(おみよ)
が、大奥の監督者(大奥の実務の
実権を握る人)となる。
● 多妻多子の徳川家斉。
徳川家斉は、側室夫人・約40人、
子供・約55人をもつ。
● TKKI カナヤマ著 江戸幕府
大奥ガイドブック。
■ 1830年 ● 天保改元。
(文政13年 ) 1830年12月10日に、和暦の
(天保 元年) 「文政」(ぶんせい) が、 「 天保」
(てんぽう、天保元年・1830年・
12月10日〜天保15年・ 1844年・
12月2日) に改元される。
■ 1837年 ● 徳川 家慶 (いえよし、将軍在任:
(天保 8年) 1837 年〜1853年、家斉のニ男)
が、江戸幕府の第12代将軍となる。
● 家慶将軍時代に、 御年寄(おとし
より、大奥上級幹部)の姉小路(あ
ねこうじ)が、 大奥の監督者(大奥
の実務の実権を握る人)となる。
■ 1844年 ● 弘化改元。
(天保15年) 1844年12月2日に、和暦の
(弘化 元年) 「天保」(てんぽう) が、 「 弘化」
(こうか、弘化元年・1844年・12
月2日〜弘化5年・1848年・2月
28日) に改元される。
■ 1848年 ● 嘉永改元。
(嘉永 元年) 1848年2月28日に、和暦の
「弘化」(こうか)が、 「嘉永」(かえ
い、嘉永元年・1848年・2月28日
〜嘉永7年・1854年・11月27日)
に改元される。
■ 1851年 ● 1851年(嘉永4年)2月に、島津
(嘉永 4年) 斉彬(なりあきら)が、11代薩摩藩
主となる。
□ 大奥 詳細年表の先頭へ戻る。
#innerpalacedetailedchronology-1853
■ 1853年 ● 徳川 家定 (いえさだ、将軍在任:
(嘉永 6年) 1853 年〜1858年、家慶の四男)
が、 江戸幕府の第13代将軍となる。
● 徳川家定将軍時代に、 家定の生
母・本寿院(ほんじゅいん)と家定乳
母(うば)の歌橋(うたはし)が大奥
の最高権力者となる。
また、御年寄(おとしより、大
奥上級幹部)の滝山(たきやま、
御年寄在任:1853年〜1867
年)が、 大奥の監督者 (大奥の
実務の実権を握る人)となる。
● 第13代将軍となった、徳川家定
は体が弱かったため、 次期14
代将軍継嗣(けいし)問題が起こり、
雄藩連合政治を望み次期14代将
軍に一橋慶喜(ひとつばし よしの
ぶ、水戸藩出身・一橋家当主)を
擁(よう)する、一橋派 と、 徳川
氏独裁政治を望み次期14代将軍
に徳川 慶福(よしとみ、紀伊藩藩
主)を擁する、紀州派(南紀派)
とが、対立する (1853年頃〜
1859年頃)。
● TKKI カナヤマ著 江戸幕府
大奥ガイドブック。
■ 1853年 ● 1853年6月、アメリカのペリー
(嘉永 6年) 艦隊が日本来航。 開国を要求。
■ 1853年 ● 江戸幕府の老中首座・阿部正弘
(嘉永 6年) (あべまさひろ)が、 挙国的な対策
を立てようと、 開国について、諸
大名や色々な人物に、意見を求め
たため、 これ以後、日本各地で、
外国勢力を武力で追い払うことを
主張する、尊皇(王)攘夷派( そん
のうじょういは) と、 開国し外国
勢力と協力して、先進の西洋文化
を採り入れて国を発展させること
を主張する、開国派(かいこくは)
とが対立する (1853年頃〜18
67年頃)。
■ 1853年 ● 篤姫 (あつひめ、於一(おかつ、
(嘉永 6年) 島津一)が、 島津氏本家の養女
となる。 篤姫は、島津篤子 (しま
づあつこ)と称し、篤姫(あつひめ)
と呼ばれる。
■ 1853年 ● 1853年 8月、江戸幕府の老中
(嘉永 6年) 首座・阿部正弘(まさひろ)と島津
斉彬(なりあきら)の話し合いで、
篤姫(あつひめ)の輿入(こしい)れ
が決まる(内定する)。
■ 1854年 ● 1854年3月、日米和親条約締結。
(嘉永 7年) 日本部分開国。
● 1854年〜1855年に、幕府・老
中首座の阿部正弘は、 欧米列強
の米英露蘭と和親条約を締結する。
■ 1854年 ● 安政改元。
(安政 元年) 1854年11月27日に、和暦の「嘉
永」(かえい)が、 「安政」 (あせん
い、安政元年・1854年・11月27日
〜安政7年・1860年・3月18日)
に改元される。
■ 1856年 ● 1856年(安政3年)11月、篤姫
(安政 3年) (あつひめ、近衛 敬子 (このえすみ
こ、一橋派) が、江戸城・大奥に入
る。
■ 1856年 ● 1856年(安政3年)12月、薩摩
(安政 3年) 藩出身の篤姫(近衛敬子) が、
家定(いえさだ)と婚礼 の式を挙
げ、13代将軍・徳川家定(いえさ
だ)の正室夫人となる。
■ 1858年 ● 1858年(安政5年)6月、日米
(安政 5年) 修好通商条約締結。
● 安政の5カ国条約締結。
1858年(安政5年)6月から9
月まで、江戸幕府・大老の井伊
直弼(なおすけ)は、 勅許(ち
ょっきょ)を得ず、 欧米列強の
米蘭露英仏と不平等な「安政の
5カ国条約」(修好通商条約)を
締結する。 日本完全開国。
■ 1858年 ● 1858年(安政5年)12月、徳川
(安政 5年) 家茂 (いえもち、 将軍在任:18
58年〜1866年、 家斉の孫、紀
州藩主・徳川慶福) が、 江戸幕
府の第14代将軍となる。
● 家茂将軍時代、天璋院・篤姫(て
んしょういん・あつひめ、家茂の義
母) と、 家茂・生母の実成院(じ
っせいいん)が、大奥の最高権力
者となる。
御年寄の滝山が、大奥の監督
者(大奥の実務の実権をもつ人)
となる。
● TKKI カナヤマ著 江戸幕府
大奥ガイドブック。
■ 1860年 ● 万延改元。
(万延 元年) 1860年3月18日に、和暦の「安
政」(あんせい)が、 「万延」(まん
えん、万延元年・1860年・3月18
日〜万延2年・1861年・2月19日)
に改元される。
■ 1860年 ● 桜田門外の変。
(万延 元年) 1860年3月、江戸幕府の大老・
井伊直弼(いいなおすけ)が、
江戸城外で、殺害される。
● これ以後、 江戸幕府は公武合体政
策をすすめ、 尊皇攘夷派・急進派
と、 公武合体派・佐幕派 とが対立
する (1960年頃〜1864年頃)。
■ 1861年 ● 文久改元。
(文久 元年) 1861年2月19日に、和暦の「万
延」(まんえん)が、 「文久」 (ぶん
きゅう、文久元年・1861年・2月19
日〜文久4年・1864年・2月20日)
に改元される。
■ 1862年 ● 1862年(文久2年)2月、江戸幕
(文久 2年) 府14代将軍・徳川家茂 と、 孝明
天皇の妹・皇女・和宮の婚儀が為
(な)される (公武合体の政策のた
め)。
■ 1864年 ● 元治改元。
(元治 元年) 1864年2月20日に、和暦の「文
久」(ぶんきゅう)が、 「元治」 (げ
んじ、元治元年・1864年・2月20日
〜元治2年・1865年・4月7日) に
改元される。
■ 1864年 ● 禁門の変(蛤御門の変)。
(元治 元年) 1864年(元治元年)7月に、
禁門の変 (きんもんのへん、蛤御
門(はまぐりごもん)の変)が起こる。
■ 1864年 ● 1864年(元治元年)8月、江戸
(元治 元年) 幕府は、第1次長州征討 (1864
年(元治元年)8月〜12月)を開始
する。
■ 1864年 ● 1864年 (元治元年)11月、 長州
(元治 元年) 藩は、江戸幕府に屈服し、幕府に
対し恭順(きょうじゅん)の 態度を
とる。 1864年(元治元年)12月
に、幕府軍は、 引き揚げる。
■ 1864年 ● 功山寺(こうざんじ)挙兵。
(元治 元年) 1864年(元治元年)12月
15日に、長州藩で、高杉晋作(た
かすぎしんさく)が、奇兵隊を率い
て挙兵する。
その後、高杉晋作は、江戸
幕府に恭順した長 州藩の保守派
(俗論派)を退(しりぞ)け、長州藩
の藩論を、討幕へ転換させる。
● これ以後、日本各地で、 尊皇
(王)討幕派 と 公武合体派・
佐幕派 とが対立する (1864
年頃〜1866年頃)。
■ 1865年 ● 慶応改元。
(慶応 元年) 1865年4月7日に、和暦の
「元治」(げんじ)が、「慶応」 (け
いおう、慶応元年・1865年・4月
7日〜慶応4年・1868年・9月8
日) に改元される。
■ 1866年 ● 薩長同盟成立。
(慶応 2年) 1866年(慶応2年)1月に、薩
長の反幕府政治・軍事同盟の密
約が結ばれる。
● これ以後、日本各地で、尊皇
(王)討幕派 と 公議政体派・
佐幕派 とが対立する (1866
年頃〜1867年頃)。
■ 1866年 ● 1866年(慶応2年)6月、江戸幕
(慶応 2年) 府は、長州藩に対し、第2次長州
征討(1866年(慶応2年)6月〜
7月)を開始する。
● 第2次長州征討で、坂本龍馬は、
長州藩海軍を支援する。
■ 1866年 ● 1866年(慶応2年)7月に、江戸
(慶応 2年) 幕府・14代将軍の徳川家茂(いえ
もち)死去する(病死する)。
第2次長州征討は中止となり、
事実上、失敗し、江戸幕府は、権
威を低下させる。
● TKKI カナヤマ著 江戸幕府
大奥ガイドブック。
■ 1866年 ● 1866年(慶応2年)12月に、
(慶応 2年) 徳川 慶喜 (よしのぶ、将軍在任:
1866年〜1867年、家康の子孫、
9代水戸藩主・徳川斉昭の七男、
一橋徳川家当主) が、 江戸幕府
の第15代将軍となる。
● 徳川慶喜の大奥改革に、和宮と
共に、天璋院・篤姫は、反対する。
● 慶喜の妻子は、大奥に入らず。
慶喜将軍時代は、天璋院・篤
姫(てんしょういん・あつひめ)と和
宮(かずのみや)が、大奥の最高権
力者となる。
■ 1867年 ● 1867年(慶応3年)に、大奥の
(慶応 3年) 御年寄(おとしより、大奥上級幹
部)の滝山が、大奥を去る。
滝山は、 4代の将軍時代
(家慶、家定、家茂、慶喜)の大
奥で勤務して、3代将軍時代(家
定、家茂、慶喜)の大奥の監督
者(大奥の実務の実権をもつ人)
であった。
● 滝山は、未婚のため、滝山側近
の奥女中を幼女とし、その幼女
の川口(現・埼玉県・川口市)の
実家に退く。
■ 1867年 ● 大政奉還。
(慶応 3年) 1867年(慶応3年)10月に、
江戸幕府は、大政奉還(政権を朝
廷へ返上)を行う。
● 江戸幕府の大政奉還により、江
戸幕府が、名目的に、終焉(しゅう
えん)する。
■ 1868年 ● 江戸城・無血開城。
(慶応 4年) 1868年(慶応4年)4月に、
江戸幕府(徳川宗家)の本城(ほ
んじょう、本拠地の城)の江戸城
が、無血開城される。 討幕軍が、
江戸城に入場する。
● 大奥法度は廃止となり、 江戸
城の後宮の大奥は、江戸城・無
血開城により、消滅する。
● TKKI カナヤマ著 江戸幕府
大奥ガイドブック。
■ 1868年 ● 明治改元。
(明治 元年) 1868年9月8日に、和暦の
「慶応」(けいおう) が、「明治」 (め
いじ、明治元年・1868年・9月8日
〜明治45年・1912年・7月30日)
に改元される。
□ 日本史辞典 ・日本語版へ。
『 あなたのハートには
何が残りましたか? 』。
以 上。