
 おなじみギネスブックにも認定されたパックマンをナムコの許諾を獲て電子ゲーム化。初期モンスター数が違うAMAとPROの2種類が遊べる。
おなじみギネスブックにも認定されたパックマンをナムコの許諾を獲て電子ゲーム化。初期モンスター数が違うAMAとPROの2種類が遊べる。
承知の通り 「パックマン」の商標はそもそもトミー所有のもので、元営業氏によると、ライセンスはそのバーターみたいなものだったらしい。
ただ、10年に一度のヒット作を各メーカーとも指をくわえて見ているわけにもいかなくて、世界中の玩具メーカーからパックマンに似たゲームが発売されたのは歴史が示すとおり。1981年という時代は、未だビデオゲームにおける著作権やライセンス料金がはっきり確立しない頃だったが、この世界的ヒットにともない、ナムコはライセンスの法制化に必死で取り組んでおり、国内の玩具メーカーとも水面下でいろいろあったようだ。1982年、交渉が決裂したバンダイとナムコの間でFLパックリモンスターが訴訟ざたになるのだが、後年、この両者がまさかまさか合併するとはねえ。
 ● 際立って目を引くのは、なんと言っても半円球上のキュートなボディと、堂々と輝くパックマンのロゴ(ロゴには数種類のバリエーションあり)。ソフトの方も有名なピザ欠けフォルムをはじめ、ボーナスのチェリー、面クリアすると点滅する迷路、100⇒200⇒400点と倍々ゲームになるモンスターなど、オフィシャルのなぞり方も堂に入ったものだった。
● 際立って目を引くのは、なんと言っても半円球上のキュートなボディと、堂々と輝くパックマンのロゴ(ロゴには数種類のバリエーションあり)。ソフトの方も有名なピザ欠けフォルムをはじめ、ボーナスのチェリー、面クリアすると点滅する迷路、100⇒200⇒400点と倍々ゲームになるモンスターなど、オフィシャルのなぞり方も堂に入ったものだった。
説明書に使われているカット(左)もアーケードのインストカードのほぼ再現。当時僕が祖父に買ってもらったパックモンスターのインストと比べ、否が応でも非許諾品と許諾品との差をたたきこまれる結果となった。これこそブランドの原体験、だろうか?
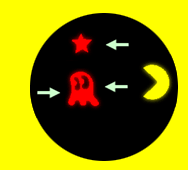 ★ 一方、右から左側方向にしかエサを食べられないシステムは、当時から僕らの間での悪評であり(だけど、右向きにモンスターをかじる/かじられることはできる矛盾)、それって、エサを食べるという感覚を維持するためのゲームデザインからくるものなのか?と思っていたが、真相は本文の通り(⇒4p)。
★ 一方、右から左側方向にしかエサを食べられないシステムは、当時から僕らの間での悪評であり(だけど、右向きにモンスターをかじる/かじられることはできる矛盾)、それって、エサを食べるという感覚を維持するためのゲームデザインからくるものなのか?と思っていたが、真相は本文の通り(⇒4p)。
結局、ゲーム展開がもたつき、全体的に動きがぎこちないのも、エレメントの少なさとフィールドサイズとのバランスに苦心した結果なのだろう。だから、いまどきの子供なんかに薦めると、数秒で投げ出されてしまいそうで怖いのだが、久々にプレイして思ったのは、全体の進行が鈍い分だけ、モンスターの動きをじっくり追うことができるということ。このため、高レベルになっても、実力さえあればなんとかクリアしていける。つまり、ゲームとしてインチキがないのだ。この骨太加減は、高レベルではパワークッキーでドーピングし続けないととてもじゃないがクリアできないような他のパックマン製品とは一線を引くコクを生み出すのである。もっとも血の気の多い少年たちからすれば、戦略よりもノンスピードで疾走する方が熱くなれたような気がするんだけれどね。
● 売り上げは台数はオフィシャルサイトの「トミー図鑑」(※現在は閉鎖)によると70万個以上。先のバンダイ訴訟記事によると、1982年5月頃の時点で電子ゲーム系パックマンは、200万個以上販売されていたらしいから占有率はいかほどか。
台数だけではない。大人だからこそわかる深みとコク。手に取る機会があったら内容もじっくり堪能してくださいな。レベルスイッチはもちろん「PRO」に入れよう。
