クロ箱 index
このサイトは?
サイトの制作者
メール送信
2005 ■ A piece of moment 1/13 年も明けて授業もはじまり、再び満員電車で通勤する日々がはじまる。 痴漢をかばう気はないが、ただこれだけぎゅうぎゅうと詰めこまれると起こるべくして起こる犯罪に思える。見知らぬ人とまるで抱き合うかのように接触することを余儀なくされるなんてどう考えても異常な事態である。人間の持つ動物的な部分の許容範囲をこえている。あの状況でむらむらと性的欲求が起こってしまうのは自然なのであって、満員電車での痴漢はモラルと法律だけでどうにかなる問題ではない。むしろ満員電車の車内が夜祭りの乱交になってしまわない乗客の行儀の良さに感心する。かくいう私は痴漢に間違われると嫌なので両手で吊革につかまるようにしている。どうせ本なんか読んでられないし。そんな異常な状況が日常である日々。 車内だけでなく駅の駐輪場も自転車であふれている。根本的に駐輪場が不足していて、無理矢理詰め込まれて壊されたり倒されたりして、自転車はすぐぼろぼろにされてしまう。壊されるのが嫌で駐輪場の外に停めると「放置」自転車と見なされて撤去される。別に放置したわけじゃないのに。あまりの状況なので市の管理課に電話をかけて問い合わせると、1年後に駅の反対側に有料駐輪場ができるという。でも、更地の無料駐輪場と違って、屋根付き電動カート付きの有料のほうは設備の充実度の点から見て、利用料金をよほど高く設定するか利用率が100%にでもならない限り、維持費はかかりそうだ。管理課の担当者に言わせると「受益者負担」の原則なのだそうで、財政難の昨今、有料の駐輪場を作ることはあっても、無料の駐輪場を増設する予定はないとのこと。なーにいってんの建設会社を儲けさせたいだけだろって感じだが、そもそも「受益者」についての認識が根本的に間違っている。駅に人が集まって利益を得るのは鉄道会社と駅前商店である。また、こういう問題は東京をはじめとした大都市圏の住宅地だけで、むしろ、日本のほとんどの地域では、逆に利用者が減って駅前がゴーストタウン化していることの方が深刻な問題になっている。都市部の行政と鉄道会社・駅前商店街は、嫌だけどぎゅうぎゅう詰めの電車を利用せざるを得ない住民の弱みにつけ込んで、問題を意図的に放置しているように見える。乗りたかったら乗せてやるぞただし混んでるなんて文句言うな、使いたかったら使わせてやるぞただし狭いなんて甘ったれんな、そんな調子で人口の多さにあぐらをかいている印象だ。高度成長期から40年、いっこうに改善されない満員電車と駅前状況を考えると日本の都市行政はあまりにも無策だ。 なんてことを市の担当者と電話で議論しても一市民の声に耳を傾けてくれるほど日本の地方行政は民主的ではないので、市議会議員に要望をあげてみることにする。方向性としては間違っていないはずだ。日本の役人は議員さんの圧力に弱いし。無料駐輪場に賛成してくれそうな市議会議員を調べてメールを送る。返ってきた返事によると、駐輪場増設についてはそれなりに活動している様子。ただ市議会の主流派でないせいか駅前再開発の方針を変えるほどの力はないみたいで、見通しは明るくない。署名活動でもして無料駐輪場の増設を求める直接請求でもするべきなんだろうか。というわけで花小金井駅前の無料駐輪場増設に賛成という方、メールください。 ■ A piece of moment 1/14 碁をおぼえる。コンピュータ相手に3勝48敗。1980円のソフト、初級・9路盤の設定なのに、ぜんぜん勝てない。図書館で借りてきた「囲碁入門」でいちおうルールは把握しているつもりなんだけど、死活がちょっと複雑になると読めない。あれここどうなってるんだろうなんて曖昧な手を打っているとコンピュータ君が容赦なく急所に打ち込んでくる。おぼえたてなんだからもうちょっと手加減してくれよ。というわけで血も涙もないコンピュータ君じゃなくて人間相手にやりたい。ただ、おぼえたばかりで碁会所の戸をたたくのは気がひけるし、初心者歓迎の囲碁教室は受講料が月1万円近くもすることが判明して打ちのめされる。ヘボ同士で石取ったり取られたりしたいだけなのに、なんでこんなに敷居が高いんだ。神の一手を極めたいってわけじゃないんだからさ。公民館あたりでただで教えてくれる囲碁講座はないんだろうか。 ■ A piece of moment 1/18 NHKの番組改編問題について授業で取り上げる。戦争責任をめぐる国内世論の分裂を示す典型的なケースとして紹介する。自民党議員の政治的圧力によって改変されたとされるドキュメンタリー番組は、従軍慰安婦を取り上げたもので、ここ十数年、右翼とタカ派がとくに神経質に噛みついている問題である。従軍慰安婦問題は、約20年ほど前に韓国人女性が「自分は戦時中、日本軍によって強制連行され奴隷的待遇の中で日本兵のための売春を強いられた」と告発をしたことに端を発している。当時も日本の右派からは「事実無根であり彼女は日本を非難することで目立ちたいだけ」「彼女はお金めあてでみずから望んで売春をしたのだ」等の批判がおこるが、やがて戦時中の資料から日本軍が組織的に関与していたことが明らかになり、90年代に入ってからは日本の歴史教科書にも記載されるに至ったという経緯がある。従軍慰安婦問題が教科書に取り上げられるようになったことについても右派は不満に思っているようで、「自虐史観」の押しつけであると批判を展開している。数年前、センター試験に従軍慰安婦問題が出題された際には、今回の渦中の人物である中川議員が文科職員に出題者は誰だと詰め寄ったことは記憶に新しい。ただ、この右派の主張が今ひとつわかりにくいのは、日本軍による地元女性への売春強要は存在しなかったと言いたいのか、それとも、日本の戦争責任を追及するべきではないと言いたいのかがはっきりしないところにある。前者はいまだにくり返されている「彼女たちはお金めあての職業売春婦」という批判で、すっかり右派の広告塔のような存在になってしまった小林よしのりの『ゴーマニズム宣言』には、戦後のパンパンそっくりに描かれたパーマ頭に厚化粧の「慰安婦」が登場する。日本軍の組織的関与を示す資料が見つかり、国連もこの問題を戦争犯罪・組織的性犯罪と指摘している今になってもこうした主張を展開しているのは、戦時中に屈辱的な体験をした女性をさらに意図的に侮辱し貶めている行為以外の何ものでもないように見えるのだが、なぜか日本国内ではこの種の言説がかなりの支持を得ている。日本は悪くなかった式の夢想家が大勢いるということなんだろうか。一方、後者は、現在の価値観で過去を裁くべきではないというもので、一見筋が通っているかのように聞こえるのだが、その実は日本を賛美する価値観は大歓迎で「公正」であり、戦争責任を指摘する言論はすべて「自虐史観」「偏ったものの見方」「左翼イデオローグ」と噛みつく子供だましの理屈にすぎない。日本の近代史における戦争責任が100年後200年後どう評価されているかわからないというのなら、右派が躍起になって糾弾している北朝鮮の拉致行為も同様にわからないのであり、すでに自己撞着が生じている。日本の強制連行を「悪くなかった」という者が北朝鮮の拉致を批判するのは論理的に破綻している。我々がすべきことは、被害者・加害者という立場を越えて過去にあったことを常に検証していくことであって、ナショナリズムをぶつけ合うことではない。被害者が自分たちの被害をアピールすることでナショナリズムを高める政治的道具にし、加害者が開き直って自分たちは悪くないといっている限り、歴史から何かを学ぶことなど不可能である。ナショナリズムのぶつけ合いから生じるのは「今度は負けない」という敵意と狡猾さだけである。たしかに「自分たちを批判するのではなく讃えよう」という政治的主張は、日本国内だけのものではなく、多かれ少なかれどこの国にも存在する。ただ、この国で問題なのはそれがきわめて大きな勢力として強い政治的影響力を持っていることにある。政治家が日本は悪くなかった式の発言をしてその度にアジア諸国から批判されるにもかかわらず、いっこうにその種の発言がなくならないのは、選挙にまったく影響しないからである。支持率が下がるどころか、むしろ、ナショナリスト気どりのパフォーマンスをすることで右派・保守層の支持を得て政治的発言力が高まるという構図がある。今回の安倍、中川はその典型といえる。記者たちから実際に圧力をかけたのかと問われた安倍は、拉致問題から目をそらすために北朝鮮に操られた者たちがしくんだ陰謀だと答えたという。いったいどういう社会感覚の持ち主だろう。世論の分断を意図してあおっているとしか見えない。ツジマンかミロシェビッチにでもなりたいのだろうか。それにしても今回の事件、あのふたりはどういうルートで放送前の番組内容を知るに至ったのだろう。会長の海老沢をはじめとしてNHK幹部に自民党との太いパイプがあることはよく指摘されているが、もしNHK内部からのリークだとしたら放送局として自殺行為に見える。 ■ A piece of moment 1/19 夜中、録りだめていたドキュメンタリー番組を見る。 興味深かったのは、今日の夜に放送されたイランの改革派新聞の活動を取材した番組。イランという国に抱くイメージ、イスラム革命による聖職者支配とイスラム原理主義、言論の弾圧のなかで窮屈な生活を余儀なくされる国民、しかしそうしたイメージに反して、番組に登場するイランの人々の社会意識は極めて高い。新聞記者たちが政治や社会の動向に敏感なのは当然だが、驚かされるのは街頭インタビューでの市民たちの意識の高さだ。イラン政府による言論統制について聞かれたおじさんは苦笑いしながらこう言う。「改革派新聞の記者は司法当局にびくびくしてる、(政府当局に取りつぶされた新聞社の)編集長たちは今も監獄だ」。また、街角の新聞スタンドで、ある女性はサダム・フセインの裁判がはじまったことをつたえる新聞の一面をみながら、こう答える。「サダムを誰が裁くの?アメリカ?サダムを生み育てたのはアメリカよ、でも彼が刃向かうとアメリカは抹殺しようとした、ビン・ラディンと同じよ」。見ていてやらせではないかと勘ぐりたくなるほど次々と切れ味の良い言葉が返ってくる。その様子からは、ブッシュの「悪の枢軸」という単純化された世界観からは見えないイラン社会の姿が浮かび上がってくる。アメリカ人の国際感覚の欠如は近年しばしば指摘されているが、イラン市民たちの様子はそれと対照的に見えた。 ■ A piece of moment 1/20 平田オリザを集中的に読んでいる。どれも面白い。彼の書く日本語論も演劇論も明快で切れ味するどい。戯曲を書く予定などないし、芝居をはじめるつもりも全くないにもかかわらず、問題点を解きほぐしていく手際の鮮やかさに夢中で読み入ってしまう。講談社現代新書に入っている「演劇入門」など、言っていることは当たり前のことだし演劇の基本中の基本なんだけど、こうしたことを理論化したものが今まで無かっただけに画期的な一冊ではないかと思う。知識人の偶像化はみっともないと思うが、それでもこういう人が同時代に存在していることを思うと嬉しくなってくる。数年前から桜美林大学で演劇講座のワークショップをやっているみたいだけど、機会を見つけて聞きに行きたいなと思う。 ■ A piece of moment 1/21 三年生の授業がすべて終了する。三学期は特別講習で少数の受講者相手にセンター試験対策やら時事問題を取り上げたりする内容だが、なぜか誰も教室に来ない。ずいぶんいいかげんだなあ半徹で資料作ってきたのにと憮然としていたら、翌日、生徒から、センセーどうして授業に来てくれないのと言われる。どうやら三年の特別講習だけ時間割が違っていて、すれ違いになったらしい。なんてこったい。授業時間が三年だけ違うのに学校側から一言の連絡もないなんてどういうこったい。「特別講習・村田・2時間目・教室番号・受講者」とだけ書いてあるぺら紙一枚が机に置かれてるだけの連絡で時間割が違うなんてわからんわい。でも確認しなかった俺も悪いのかな。ともかく生徒に謝って学校をあとにする。 ■ A piece of moment 1/24 以前、テレビで田辺聖子が関西にはちゃうちゃうがたくさんいるのよと言っていた。 「ちゃうちゃうちゃうんちゃう?」なんのこっちゃい。 それ以来、関西人がちゃうちゃうを連発しながら会話をしているのを見ると、関西でちゃうちゃうがうじゃうじゃ増殖して、そこら中で野生化してゴミ箱を荒らしたり食用にされてスーパーで売られていたり川渕チェアマンにちゃうちゃうが多すぎると文句を言われて1部リーグと2部リーグにわかれて入れ替え戦をやっていたりする場面が頭の中を駆けめぐるのであった。 ■ A piece of moment 1/25 授業のあと、新宿をぶらぶら歩く。三年の授業がなくなったので時間に余裕があるのだ。新宿はそこら中で工事をしていてビルド&スクラップのはげしい東京の縮図のよう。伊勢丹のエルメスショップのショウウィンドウを見るともなく眺めていたら、耳に押し込んだラジオのイヤホンからドンキホーテ放火事件の容疑者が捕まったというニュースが聞こえてくる。火元に落ちていたたばこの吸い殻から、唾液のDNA鑑定をして容疑者をたどったらしい。最近の警察は前科者のDNAサンプルまで登録しているんかいな。ニュースを聞きながらドンキホーテと伊勢丹とでは明らかに客層が違うことを思う。伊勢丹で有閑マダムふうのおばさんを眺めながら、日本社会の階層化は経済的だけでなく文化的にも進んでいるんじゃないかと思う。昨年、京大の経済学研究室が日本社会の貧富の差の拡大傾向を示す調査結果を発表してずいぶん話題になった。その調査では、現在、日本政府が行っている民営化推進や税制改革は、先進国の中で最も急激に貧富の差の拡大をもたらすと指摘されていて、賛否両論、議論の的になった。このレポートへの批判の中に、日本で貧富の差の拡大が進行しているのは事実だが、「階層化」というにはたんに経済格差だけでなく階層ごとに文化的な乖離がなければならないという指摘があった。つまり、日本社会では流行や文化現象はクラスレスで発生するというわけだ。例えば、ネイルアート。見るからに非実用的なファッションだが、あれはもともとアメリカの有閑マダム層で流行ったファッションなので、実用性は関係ない。彼女たちは家事雑務は一切、家政婦にまかせている人たちなので、日常生活の中で生爪をはいだり、爪水虫にかかって苦労するようなことはない。これが日本に入ってくると、富裕層もそうでない人も一斉に派手なつけ爪をはったり長々と爪を伸ばしたりするので、日常生活の中で様々なトラブルが生じる。日本のクラスレス社会の一端を示す文化現象というわけだが、でも、待てよと思う。アメリカのように極端に貧富の差が激しい社会を比較対象にすること自体、無理があるのではないか。ビル・ゲイツのような億万長者がいる一方で、6人にひとりが健康保険にすら入れない社会である。それと比較して日本は平たい社会だといったところで一体何の意味があるのだ。それは何も言っていないのと同じではないのか。また、伊勢丹を闊歩する有閑マダムたちを見ていると、そこには文化的な断絶があると考えた方が妥当に思える。彼女たちとドンキホーテ常連のヤンママに、何らかの文化的共有はあるのだろうか。なんてことを考えながら、新宿をぶらぶら歩く。お目当てのハードディスクレコーダー特価販売は見つからなかった。どう見ても自分の生活はドンキホーテのヤンママたちに近い気がする。 ■ A piece of moment 1/28 シャラポワ・フィーバーである。勝っても負けてもスポーツ新聞はシャラポワ。試合がなくてもつけ乳首疑惑でシャラポワ。もはやスポーツ新聞とおじさん週刊誌の女神様である。しかし、私および当サイトにとっての興味の対象はもちろん一球打つごとに下品な叫び声をあげるシャラポワなどではなく、だんぜんウィリアムス姉妹である。ウィリアムス姉妹の何が気になるか、もちろん、姉が「ビーナス」なのに妹が「セリーナ」である点である。どう見ても釣り合いがとれない。時代劇にたとえると、兄が「民部権大輔慶篤」なのに弟が「伝助」みたいなものである。これではお姉ちゃんとちがってあたしは拾われてきた子供なんだ橋の下に捨てられてたんだああ本当のお父さんお母さんに会いたいと思いつめても仕方ないのである。明らかに差別であり手抜きでありえこひいきであり虐待である。ねんのために語源を確認しておこう。 ・Serena 【ラテン語】平穏な 光、公正、明るい ・Venus 【ラテン語】ローマ神話の美の女神 同じラテン語源でも差は歴然である。姉が美の化身を名のるのなら、妹は「アフロディーテ」か「クレオパトラ」か「マリーアントワネット」か「タイタン」か「ヘラクレス」か「エステティックTBC」か「ああ女神さま」くらいでないと釣り合いがとれない。なんか違う気もするけどそうなのである。よって当サイトは、手抜きでえこひいきなウィリアムス親に代わって、妹を「アフロディーテTBC」ウィリアムスと命名するものである。本当はもっとならべたいところだけどこれ以上ならべるとじゅげむになってしまうのでこのへんで勘弁してやるのである。健気でいじらしい彼女は、いままで通り「セリーナ」と呼ばれても怪獣のような雄叫びをあげるくらいでじっと堪えるだろうが、当サイトは断固抗議するのである。 ■ A piece of moment 1/29 「ベネトンの広告」について、論点を整理して加筆。 →「ベネトンの広告」 ■ A piece of moment 2/4 10年近く前のことである。本屋の雑誌コーナで戦車模型専門の雑誌を発見したときの衝撃は今でも鮮明に覚えている。そんな狭い世界が雑誌として成り立つのか。棚に平積みされた雑誌を見ながら自分の目を疑った。たしかに、スケールモデルの愛好家はそれなりにいる。スケールモデルの中でも第二次大戦期の戦車模型は人気のある分野でもある。模型を作るのに4万円も5万円もするエアーコンプレッサーや旋盤を買ってしまうような熱心なマニアがいることも聞いたことはある。でも、いることはいても雑誌が成り立つほどの数とは思えない。もしも、オフィスで交わされる日常会話の中で、昼飯を吉野家にするか松屋にするかとまるっきり同じ調子で四号G型戦車と四号J型戦車の砲塔の比較が語られていたとしたら、あるいは入社3年目の女性社員たちがホカ弁をぱくつきながら、グアムでのスキューバ体験ではなく、75ミリ撤甲弾の形状について熱く語っていたとしたら、きっとその日は、いつもの場所にいつもの町並みがあるのか、今夜帰宅する先に本当に我が家があるのか、寝床の中で眠りにつくまで不安にさいなまれるはずだ。しかしそんな内容で埋め尽くされた雑誌が現実に創刊され本屋に置かれている。隔月刊の発行とはいえ驚愕である。編集長は土居雅博氏というその筋では有名なカリスマモデラー兼編集者。編集方針はもちろん一見さんお断りというかはなからまるっきり初心者など眼中にない誌面作りで、タイガー戦車の初期型・中期型・後期型の砲塔ハッチ形状の違い、東部戦線における各戦車中隊ごとの認識番号の特徴、鋳造砲塔表面の鋳型に由来する荒れの特徴、さらには東部戦線各地域における土質の違いとキャタピラについた泥の表現などなどなどが展開される。もはや子供の頃によくリモコン戦車を作ってよっちゃんとひっくり返し合戦をやったよなあとかそういう次元でついていける内容ではない。制作記事も非常に高度で、車体の前半分や上半分をフルスクラッチで作ったりキットのプロポーションを変えるために車高を2ミリ上げたり車幅を1ミリ広げたりするのは当たり前。イラストレーターが使うような高価なエアーブラシで塗装するのも当たり前。記事はそこからさらに上を目指すために、油絵の具を用いた錆の表現やパステルの粉をプラパテに混ぜ込んで作る泥汚れの表現といった職人芸の世界が繰り広げられる。六根清浄、精進あるのみ。読んでいるとたしかに作りたくはなってくるんだけど、それ以上に深い底なし沼に落ち込んでしまったような恐怖感と閉塞感をおぼえる。読者欄では、「腕を上げましたな」と互いに褒めあったり、「その解釈には致命的欠陥がある」と論争を繰り広げたりしている。資料と解釈に対して厳格であることこそマニアの証なので、些細な意見の相違はしばしば感情的な確執をもたらす。いったん深みにはまったらもう出口はないという感じだ。恐いので、数号買った後はもう見なかったことにしていたのだが、それでも本屋の雑誌コーナーに寄るたびに目に入ってきてしまう。そう、この雑誌、あれから10年たった現在もまだ続いているのである。もはや驚愕を通り越して畏敬の念すらおぼえる。日本語を用いる1億数千人のうち、いったいどれだけの人たちが吸着式地雷よけのコーティングをプラパテで表現する技法に目を輝かせているのだろう。我々が存在するこの世界は本当に10年前とつながっているのだろうか。ああ気が遠くなってくる。 ■ A piece of moment 2/6 以前から観たかった「ドッグヴィル」をレンタル店で借りてきて観る。期待に違わぬ濃厚な作品だった。観ながら心の急所をえぐられるような感覚をおぼえる。監督・脚本はラース・フォン・トリアー。彼の一連の作品は、いずれも観る者を追いつめるように物語は展開するが、今作はその中でも際だって鮮やかな手際で深いところへ引きずり込んでいく。 舞台になるのは、アメリカの山奥にある小さな村、ドッグヴィル。閉鎖的で貧しく陰気な田舎によくある同質性の強い小さな共同体だ。その村にある日、ギャングから追われている若い女が逃げてくる。彼女がギャングから追われている事情や彼女の生い立ちは語られない。ただ、彼女の派手な身なりと思いつめた表情から村人たちは事情を推察する。話し合いの末、村人たちはこのよそ者をかくまうことにする。女は献身的に村人に接し、村にとけ込もうと様々な雑務を引き受ける。彼女は派手な外見に反し、囁くような穏やかな語り口で話し、聡明でまるで信仰のように村人の善意を信じる。はじめは疑心暗鬼だった村人たちは、しだいにそんな彼女を受け入れ、陰気な村にも互いの善意がもたらす明るさと活気が生じていく。しかし、彼女が村の中にとけ込み、遠慮がなくなっていくにつれて、村人の彼女への要求はエスカレートしていく。さらにその要求は、彼女がギャングに追われているという弱みと重なって際限なくエスカレートしていく。ギャングから匿ってやっているという意識が、村人たちに自分の要求の理不尽さから目をそらせ、それは当然の代償にすぎないという自己肯定をもたらす。そうして、彼女は村人たちから奴隷か牛馬同然の扱いを受けるようになる。女はこの小さな共同体に抱いていた隣人愛の希望を失い、村の暮らしと村人たちに絶望するようになる。村人のむごい仕打ちに無言の抗議をあびせるように悲しそうなまなざしを向け、理不尽な扱いにじっと堪える。村人にとっての彼女は、欲望と不満と自尊心のはけ口であるのと同時に自分たちの醜さを暴きだす鏡でもある。その後ろめたさを心の奥底へ押し込めようと村人はよりいっそう彼女を疎んじる。当初、村に暮らしに光をもたらしていたはずの彼女の存在は、村人たちの欲望と心の奥に押し込んだ後ろめたさによって、重くよどんだ空気をもたらしていく。 エンディングで流れるアメリカを歌った歌詞は、主人公の女の信仰に似た人間性への信頼とその反動による極端な制裁を象徴していると解釈した。この物語、一見、利己心のかたまりのような村人たちが、人間性を全肯定する無垢な女を一方的に苛んでいるかのようだが、見終わって振り返ると、彼女のふるまいが村人たちを追い込んでいったようにも思える。全面的な人間性の肯定は同時に全面的な否定であり、違いを認めることのない同化は支配と服従をもたらす。あまりに重たい内容なので二度三度観たいとは思わないが、物語の場面場面が澱のようにたまって頭から離れない。 ■ A piece of moment 2/9 「まもなく!」「いよいよ!」「直前!」と四週間も前からテレビで言っていたので、とっくに終わってるのかと思ったら今日試合をやっていた。この世知辛いご時世にずいぶんと悠長なことである。しかし、私および当サイトの興味の対象は、カラス印のサッカーチームなどではなく、だんぜんアメフトである。アメフトのなにが気になるのか。もちろん、今年もスーパーボールでジャネットのオッパイぽろりが見られるかどうかである。願わくば毎年恒例の年中行事になって、アメリカ市民たちにささやかなどっきりと顰蹙を提供してほしいものである。こういうのは出る出ると思っているときの方が期待感が高まるものである。あらおじいさんたらまたジャネットですか、うむ今年は張りがいまいちだな、なんて。 私のささやかな夢は、アメフトチームのオーナー兼ヘッドコーチになることである。アメフトの場合、サッカーやラグビーと違って、完全にトップダウンのシステムでゲームは展開していく。ワンプレイごとにヘッドコーチからの指示が出て、それにもとづいて選手たちは動く。対戦チームもまた同様で、互いに作戦を読みあいながら次の一手を決めていく。アメフトの作戦はこの十年間で猛烈に複雑になっていて、まるで生身の人間を使ってやるチェスみたいな状況になっている。そのなかで屈強な大男たちを駒のように動かし、言うことを聞かないクォーターバックをロッカールームでクビをちらつかせながらネチネチと説教したり、巨大なラインバッカーを全米中継のテレビカメラの前で罵倒したり、エースランニングバックを札びら切って人身売買したり、盛りの過ぎたワイドレシーバーを食肉処理場に払い下げたり、尿検査の担当者にフロリダビーチのコテージをプレゼントしたり、対戦チームのランチに下剤を混ぜたり、黒人選手のウォークマンをヒップホップからウィンナーワルツにすり替えたりするのは、まちがいなく男の夢である。ロマンである。本宮ひろしである。人生を賭けるに値するのである。よくテレビやラジオでは今の職業についていなかったらどんな仕事がしたかったですかなんてインタビューをしているが、なぜ私には誰も聞いてくれないのだろう。 ■ A piece of moment 2/14 年末から録りだめていたドキュメンタリー番組をまとめて見る。正確に書くと、見きれないままどんどんたまっていくストックを少し消化する。半ば業務用なので、めんどくせえなと思い始めるとただ義務感だけで目を通す状態になってしまうので、気が向いたときにまとめて見るようにしている。で、その中に、日本人メージャーリーガーたちに2004年のシーズンを振り返ってもらうというスポーツドキュメンタリーがまぎれていた。興味深かったのは、野茂英雄の回。ひさしぶりに試合中継以外で見る野茂は、なぜか前歯が真っ茶色だった。いまどきヘビースモーカーのおっさんでもあんなに茶色い歯の持ち主は少ないんじゃないかっていう茶色さ具合だった。朝も晩も歯磨きしないで缶ピースを常時スパスパやってるとああなりそうだけど、メジャーリーガーって日本のプロ野球選手と違って体調管理にうるさそうだし、アクの強いドクダミ茶でも愛飲してるんだろうか。そんな歯の色ばかりが気になった30分番組。番組の野茂は、不本意な成績に終わった2004年シーズンを振り返りつつ、再帰を賭けて必死にトレーニングに励んでいた。インタビューに答える野茂はあいかわらずの木訥とした調子で、意気込んでみせることもなく感傷的になることもない。そこが彼の良いところ。もくもくと働く農耕馬を連想する。歯も茶色いし。言葉の端々に俺ってイケてるでしょという自意識が見え隠れするイチローのインタビューとは対照的だった。 ■ A piece of moment 2/16 教室にDVDプレーヤーが導入されたので、さっそくMPEGファイルからDVDを作成して使ってみる。 結論。ヒジョーに使いにくい。 いきなりの結論だが、DVDという規格自体に欠陥があるんじゃないかというくらい使いにくい。 問題点1。MPEGデータをDVDに変換するのに専用ソフトが必要である。6000円もする。今回は30日間試用期間つきというのをダウンロードして間に合わせたが、本格的にDVDを作成するとなるとソフトを買わねばならない。データを変換するだけのソフトに6000円も払うなんて馬鹿みたいだ。 問題点2。民生用のDVDプレーヤでは、安いデータ用ディスクは読んでくれない。なにやら「リージョンコード」という国別の信号があるようで、中国製の安いメディアを使うとパソコンのDVDでは使えるのに民生用プレーヤでははじかれてしまう。仕方ないのでビデオデータ用のDVD-Rを買ってきたが、1枚200円近くもする。そもそも記録用のDVDメディアはやたらと規格が乱立してしまってわけのわからない状況だし、消費者の利便性無視で事態は進行しているように見える。 問題点3。やたらと時間がかかる。4.6GBめいっぱい1枚のディスクに入れようとすると、MPEG→DVDファイルの変換に約15分、メディアへのかき込みに約20分、これではビデオテープをダビングするのと大差ない。デジタルデータであることのメリットをまったく感じない。そもそもビデオテープからデジタルデータに変換するのに手間と時間がかかっているのである。デジタルからデジタルへの転送くらい瞬時にすませてほしいものである。それによく考えたらダンボール箱7箱分のビデオテープを早く処分したくてせっせとハードディスクに動画データを入れているのに、今度はDVDのディスクが増えてしまったらまるっきり本末転倒で俺は一体なにやってるんだろうって感じだ。 せめて民生用のDVDプレーヤーがMPEGデータを読めれば良いんだけど、コピープロテクトを厳重にしたい業界の思惑なのか、ほとんどのプレーヤーでMPEGデータは利用できない。これまたユーザーの利便性は二の次という感じ。「国策」として進行中の地上デジタル放送では、放送自体にコピープロテクトがかかって録画した機器でないと再生できないようになるとかで、もうがんじがらめである。デジタルデータであることの利便性はまったくない。というわけで、DVDには見切りをつけてポータブルのハードディスクレコーダーでも探した方が良さそうである。iPodがMPEG等の動画データを使えるようになるとすごく便利なんだけど。ただ、完全に業務用の機器であることを思うと、自腹で購入するのはなにやら馬鹿らしい気がしてくる。というわけで政府は税金のブラックホールみたいな国際宇宙ステーションに1000億円もつぎ込んでないで、俺にポータブルのHDDレコーダーを支給すべきなのである。誰が何といおうと絶対そうなのであるって前にも書いたような気がするけど細かいことは気にしない気にしない。 ■ A piece of moment 2/18 社会科の教員控え室にて。進学担当のセンセーと大手予備校の営業担当氏が最近の進学傾向やら入試の出題傾向やらなんとかプロジェクトについて会話をしている。営業担当氏が立て板に水のごとくものすごい勢いでまくしたて、進学担当のセンセーがいやいやとかまあまあとか合いの手を入れる。私は嘱託のおじさんセンセーと一緒にそれを横目で見ながら、ずずずとお茶をすすり、営業担当氏のあまりに流暢でハイテンションな営業トークに圧倒されつつふたりで顔を見合わせ苦笑する。営業担当氏、大いに語り、嵐のように去る。立ち去った後もハイテンションな空気がただよっている。 「いやあすごかったですねえ」 「まさにプロって感じだねえ」 「圧倒されました」 「前の担当者がぜんぜんダメでね、上司が直接担当することになったみたいだよ」 「さぞややり手なんでしょう」 「鍛えられてるねえ」 まるで上野でパンダに会って感動している子供みたいである。営業担当氏は私にまで名刺を渡し今後ともよろしくお願いしますとあくまで慇懃に、でも一分の隙もないしぐさで会釈をしていった。サラリーマンをやめて以来、ひさしぶりにこういう人と出会った気がする。私は職業的仮面によってパーソナリティがまったく見えない人物は基本的に苦手なのだが、ここまで徹底していると隙のなさ自体が一種の職人芸のように思えてくる。先日観た岩松了の芝居に出てきた登場人物を連想する。ちょっとビバ人間である。 ■ A piece of moment 3/4 今回はめずらしく徹夜することもなく試験問題の作成が終了。論述問題を中心にわりと良い問題ができたような気がする。採点が大変そうだけど。 そんな試験期間の最中、大型バイクを買うことを決意する。ホンダのV4、1000cc。VF1000Rという20年ものの旧車で外見はかなりへたっている。こんな厄介なの俺の手に負えるんだろうか、そもそもこんなレーシングマシンみたいな大型バイクを乗りこなせるんだろうか。初っぱなから暗雲たちこめるが、それはもうほれぼれするほど美しい姿をしている。少しレトロな赤青白の三色配色も良い。車検も半年残っているし、オーナー氏がフロントフォークのスプリングも交換したと言うし、個人売買で十数万と安かったのでエイヤっと購入を決める。人生は短いのだ。「エンジンもかかりますよ」とオーナー氏、エンジンを始動させるが、燃料コックをオンにした途端、キャブレターからガソリンがだだ漏れ。ひえええ。できるだけ自分の手で整備していきたいところだけど、V型4発のぎっちり詰まったエンジンと複雑に組みあわされた4連キャブの構造を見るとちょっと自分の手には負えそうもない。これから先、バイク屋さんとの長ぁ~いお付き合いになりそうである。今後の出費を思うと気が遠のいてくる。オーナー氏は民俗学を専攻しているという大学院生。わりとご近所。若いのにこんなのに乗るなんて物好きな人である。1年半前にやはり個人売買で手に入れて半年前にはフロントフォークのスプリングも入れ替えたけど修士論文で乗るヒマがないので手放すことにしたとのこと。「今どきバイクはすっかりおじさんたちのひそかな楽しみになってるのにめずらしいですね」と言うと、仲間からは変人扱いされてますと自嘲気味に笑っていた。ふたりでそのまま立川の陸運局へ行き名義変更もすませる。週末に引き取りに行く予定である。わ~い。 ■ A piece of moment 3/7 VF1000R到着。武蔵野市の先方宅から乗って帰ってくる。 せっせと油をさしワックスをかける。オイル交換もしようと思うが、アンダーカウルが外れない。どうなってるんだこりゃ。左右分割式になっていないので、車体をつり上げでもしないと外れないじゃん。小一時間の格闘の末断念する。想像以上に整備性が悪い。でも見た目はほれぼれするようなたたずまいをしていて、写真を撮りまくる。完全におもちゃ状態。 ■ A piece of moment 3/16 今年度の授業が終了。ほっと一息と思ったら風邪でダウン。バイクもバイク屋へあずけてもう10日目。発注したパーツが入らずに作業が滞っている様子。生産終了から20年近くたつ古いバイクだけに部品の入手で苦労しそうだ。ふて寝する。 今年度の反省。今年もレポートは出させっぱなしにしてしまった。中には非常に良く書けていたものもあって、それを授業で紹介しながらクラスで問題点を再検討する時間をとりたかったんだけれど、生徒のレポートを入力し文集にまとめるだけの時間的余裕と気力がなかった。と、このところ毎年言っている気がする。インターネット上の掲示板にレポートを提出させるようにでもしないと、根本的解決にならないように思う。提出したレポートが生徒と授業担当者との間だけで完結してしまうのは、あまりにも生産性に乏しくもったいない。べつに掲示板上で討論などしなくても良い。かき込まれたレポートを他の生徒が読める状況をつくるだけでも、ああこいつこんなふうに考えてるのかとわかって刺激を与えてくれるはずなんだけど。 反省その2。今年度はクラスによる反応の違いが顕著だった。一方で好評だった授業がもう一方ではこちらが居たたまれないほど冷たい反応で、アップとダウンがはげしく一日授業をやるともうへとへとだった。イギリス下院議会のビデオなんて、自分で見ても可笑しいのに、クラスの過半数の生徒が眠そうにしたり寝てしまったりしたときにはいったい何がおきてるんだろうという感じだった。私の授業は講義で生徒を引っぱっていくのではなく、解説はほどほどにして生徒と対話しながら考察していくというスタイルなので、もともとクラスごとの差が大きいんだけど、これほど落差が大きいのははじめてだ。生徒がこちらに背を向けはじめたときの対応策を考えておかねばってなんだか実演販売のおじさんみたいですな。ちょっとオクサンまだ帰っちゃダメだよ。 ■ A piece of moment 4/9 新年度の授業が始まる。今年度の授業数は少なめ。収入は減るが、読みたい本もたまってきたし、バイクもいじりたいし、時間に余裕があるのはありがたい。 ボロバイクは問題続出。でも、ひとつひとつ直して良くなっていくのが実感できるからそれもまた楽しからずや。このところ土日の度に玄関先の道端でレンチを持ってごにょごにょいじっているので、近所のおじさんから声をかけられる。ニイチャン熱心だねぇいやいやどうもってな感じで少々照れくさい。お隣のおばさんの冷ややかな視線も気になる。ともかく、キャブレターからのガソリン漏れも止まったし、ウォータポンプからの冷却水漏れも直った。カウルの穴もふさいだし、ヘッドライトからメーター球、テールランプまで電球も全部交換した。ついでに部屋の蛍光灯まで取り替えた。高いパーツをデコデコつける趣味はないので、ともかくちゃんと走ってちゃんと止まるようになってくれさえすればいい。でも、それが難しい。すっかり顔なじみになったバイク屋のニイチャンから、温かくなってきてどこか行きましたかと聞かれ、直してばかりですよと答える。ふたりで爆笑する。 最近おぼえた言葉。 【雪月花(せつげっか)】 雪と月と花は美しいもの風流なもののシンボル。はらはらと落ちてくる風花、さえざえとして月の光、一斉に咲きほこる花、いずれも見慣れた風景を一変させてくれる。そんな美しい風物を愛で、楽しく生きていこうという意味の言葉。書でよく見かける。今日、散歩ついでに花見をしてきたが、その後、くしゃみが止まらない。鼻水ずるずるで風流もないもんだ。 【直線番長(ちょくせんばんちょう)】 大排気量の大型バイクに乗って、エンジンパワーにものを言わせて直線コースばかり速い人のこと。けっしてほめ言葉ではない。むしろ、ウデもないのに大型バイクに乗って力ずくの走りをしてるくせに、自分が速いと勘違いしてる困ったちゃんの意味が込められている。ストレートでアクセルを開けるだけならテクニックはいらないもんね。誰が言い出したのか知らないが、じつに冴えたネーミング。広辞苑にも次回改訂では掲載してほしいところである。レーサーみたいな大型バイクを買ったはいいがぜんぜん乗りこなせていない私も人ごとではないのであった。 風流といえば、こちらの草レースをしているというおじさんのレース日記は妙に枯れていて味わい深い。「ツクバの第2コーナでぜんぜんエンジンが吹けなかったのでキャブレターのセッティングをしようと思いたつが、最近、老眼がすすんで細かい作業が億劫になり途中で投げ出し一杯やって寝てしまう」なんて調子でアルコールを燃料にレースおじさんは走る。表彰台とうまい酒を夢見て。リアサスペンションを交換したときの話がいい。レース仲間が高価なスウェーデン製サスペンションをつけて良いタイムを出しているのを見て、おじさんも同じものをつけようと思いたつ。明らかに自分のボロバイクには不釣り合いだが、おじさんは清水の舞台から飛び降りるつもりで購入する。表彰台に上がっている自分の姿がアタマをよぎる。ところが、サスペンションを交換したのにぜんぜんラップタイムが縮まらない。縮まらないどころか多少のブランクで腕が鈍っているのかむしろ遅くなっている。おじさんはひたすら恥じ入る。これみよがしに高いサスペンションを入れてのろのろ走っているなんて、まるで成金オヤジのパレード走行じゃないか。こんな不様な姿を仲間に見られたらかなわない。おじさんは早々に練習走行を切り上げ、そそくさとサーキットを後にする。江戸っ子である。意外なことに、長年趣味で草レースをやってるという人にはこういう飄々とした人が多いようだ。勝利のために一直線という少年ジャンプみたいな人は長続きしないのかもしれない。なぜかおじさん、一人称はずっと「当方」。 → 酔っぱらいの国へようこそ ■ A piece of moment 4/10 レンチをまわしながらバイクを直してるんだか壊してるんだか自分でもわからなくなってきた頃、耳に押し込んだポケットラジオのイヤホンから三味線の音色が聞こえてくる。幻聴かと思ったら、音曲師の柳家紫文が登場、「長谷川平蔵市中見廻日記」のさわりを披露する。都々逸のような節まわしで、通りの向こうから粋な身なりの若い女が~と小話。おかしい。猛烈におかしい。道端でレンチを手に笑い転げる。今度、高座も見に行こうと強く決意する。世の中にこんな芸をする人がいたのかという感じ。立てつづけにすかされる感触は、いしいひさいちの「B型平次捕物帖」を連想する。 深夜2時すぎ、急に目が覚めたのでバイクを走らせにいく。耳にイヤホンを押し込み、漱石の「草枕」の朗読を聞きながらとりあえず南へ向かう。とかくこの世は生きにくい。そうね。でも、エンジン快調、道も当然空いていて、気がついたら相模湖まで来ていた。星がよく見える。東の空が明るくなりかけた頃、東京へと引き返す。朝5時、府中街道へ入る。突然、前のクルマが府中刑務所の前で停車し、見るからにマル暴なふたり組みが下りてくる。片方は禿げアタマに黒ずくめのスーツ、もう片方はオールバックに口ひげで派手なガラのジャケット。何事かと身構えるが、ふたり組みは反対車線からのクルマも押しのけるようにして道を横切り、刑務所正門へ向かう。アニキ、お勤め御苦労様ですってやつだったのであった。実物を目撃するのははじめてである。 ■ A piece of moment 4/11 新しい学校の授業もはじまる。学校まで片道10キロ弱と自転車にちょうど良い距離なので、雨の中、せっせとペダルを漕ぐ。こういう事もあろうかと冬のバーゲンでゴアテックスの雨合羽を買っておいたのだ。土砂降りでラジオを濡らしそうなので、自分の鼻歌で我慢する。突然、アタマの中に「黒猫のタンゴ」のメロディが流れる。♪僕のかわいい若い黒猫~赤いリボンが良く似合うよ~だけど時々つめを出して~僕の心を悩ませる~黒ねこのタンゴ タンゴ タンゴ~僕の恋人は黒いねこ~。ああこの歌は童謡だと思っていたけど歌詞は歳の離れた若い恋人に向かって屈折した愛情を吐露するかなりきわどい歌じゃないかとひとり合点する。かなり煮つまったゲイカップルかもしれない。夏樹マリあたりが歌ったら似合いそうだ。帰宅後、気になるので歌詞を検索する。微妙に記憶が間違っていたが、倒錯した愛の告白であることにはちがいない。4番目の歌詞があったら、僕のかわいい黒猫ちゃんはバスタブで手首を切って血まみれになっているにちがいない。そんな気まぐれな若い愛人に振りまわされつつ恍惚感に浸る痴人の愛の歌である。 黒猫のタンゴ授業のほうは生徒集会だかなんだかでなくなっていた。仕方ないので次回の授業分の資料を印刷し、初日の挨拶をすませる。たぶん来週には授業もはじまることだろう。そんな雨中サイクリングの一日。 ■ A piece of moment 4/17 2台のバイクを維持できそうもないので、2年間乗ったオフロードバイクを売りに出す。程度も良いので20万弱で売れるものと皮算用をたてていたら、買い取り業者の査定は10万円ちょい。打ちのめされる。仕方ないので、ヤフーのオークションに出品してみる。とりあえず10万円スタートにして、すぐ入札されるだろうと思ったら、3日たっても4日たっても入札者が現れない。とうとう4日目には、「8万円なら買いますよ」と本気なのかからかっているのか足もとを見るような声が質問欄に書き込まれる有様。とことん打ちのめされる。似たような中型バイクがどれくらいで取り引きされているのか気になるので、他のオークションをのぞいてみると、これはキャブレターが腐ってるんじゃないかというようなボロボロのバイクでも、5万円くらいで出品されているものにはそれなりに入札が入っている。どうやらオフロードバイクの需要というのはそういうものらしい。結局、我がバイクは、オークション最終日にバタバタと入札が入って11万ちょっとで落札される。浮き世の渡世はきびしいのであった。 昨日、オークションの落札者が来てバイクを引き取っていった。ふたりの子供がいるという40くらいのお父さん。小柄でにこやかで平田オリザのような風貌。ピカピカのオフロード用ヘルメットとゴーグルを持参してなかなか気合いが入っている。「ひさしぶりのバイクなんですよ」とお父さんは上機嫌。おじさん化が進むバイク乗りの現状を垣間見た感じがする。思った以上に程度も良いとバイクにも満足してくれた様子で、「これであちこちツーリングに行ってみようと思います」とうれしそうに語っていた。事故にあわず日々の暮らしにささやかな愉しみがもたらされることを願いつつ見送る。個人売買の良さは値段の安さよりも人とのつながりにあるのかもしれない。業者に売らないで良かった。ともかくバイク乗りのお父さんに幸あれ。 というわけで、この2年間、故障知らずでよく走ったオフロードバイクは去り、我が手元には程度が悪くて燃費も悪い20年ものの大型バイクが1台残された。我ながらひどく非合理的なことをしているような気がするが、直すと決めたんだからもう後には引かないのである。もう徹底的に直すのである。 ■ A piece of moment 4/18 1年ぶりに母親に会う。ひさしぶりにあった母親は、なぜか突然右翼になっていて、反日デモをめぐってさんざん中国と中国人の悪口を聞かされる。中国なんか国交を断絶してしまえ、あんなことされて黙っているなんて今の日本人には愛国心がたりないとまくしたてる。いったい母に何がおきたのやら。さらに北朝鮮と韓国と韓国ドラマの悪口が続く。60過ぎてヒマを持てあましたあげくワイドショーの勝谷誠彦にでもかぶれたんだろうか。でもさ、そうやって自国中心主義の愛国心と国益を互いにぶつけ合うようになったら19世紀的国際情勢に逆戻りするよ、そういう世界を望んでいるの?と口をはさむと、う~むそれはまずいと母。たいした右翼ではないようだ。やっぱり戦争はまずいから日中の自称愛国者の自国中心主義者たちを魚釣り島にでも押し込こめてバトルロイヤルで決着をつけさせれば良いのよって、アナタは中学生かいな。めまいがする。 ■ A piece of moment 4/23 古いバイクの部品はメーカーでも欠品になっているものが多いので、必然的にパーツマーケットに詳しくなってくる。感心したのはインターネットのパーツマーケットの充実ぶり。とくにヤフーのオークションには、多くの解体屋やマニアが出品していて、たいていの中古部品が千円、二千円といった安価で入手できる。実際、古いバイクに乗っている人の多くが、うまくヤフーオークションを利用しているようだ。解体屋を何軒もまわって、無愛想な解体屋のオッサンと値段の交渉をするしか中古部品を入手する手段がなかった頃を思うと、夢のような環境である。部品は車種や年式によって無数のバリエーションがあるので、適合する部品を入手できるかどうかが古いバイクを維持する最大の難関といえる。逆に現在のようにインターネットのパーツ市場が充実していれば、特殊なスキルのあるマニアでなくても古いバイクを維持できそうだ。 もうひとつ感心したのが部品メーカーの対応の良さ。いくつかの部品メーカーにメールで質問したところ、私のような小口相手にも、営業担当者がちゃんと答えてくれるし、Webサイトの適合表に間違いがあると指摘すると翌日には修正されていたりする。部品1個売って数千円、感心すると同時に製造業大変なんだろうなあと思う。 ブレーキホースを部品メーカーに注文した。やはりホンダ純正のブレーキホースは欠品になっていたので、ステンレスメッシュのホースを作っている部品メーカーにメールで質問したところ、セット販売している各ホースの長さを確認してくれた上に、追加料金無しで長さの変更もできるという。ホースを切り売りしている町のバイクショップの話ではない。メーカーが私のような小口相手にこんな事していて採算がとれるんだろうか。ともかく、バイクのブレーキホースを採寸し、長さを指定して注文する。ホースがカウルに接触してこすれるのが嫌なので、各部分を厳密に計ってミリ単位で指定する。ところが届いたホースはそれぞれ指定長より20mmほど短い。取り付けられないことはないが、ブレーキホースの遊びが足りないのは不安なので、交換してもらえないかとメールを書く。日曜日なのに即座に返事が返ってくる。メーカーの営業担当者は平謝りで交換するから宅配便でこちらまで送ってほしいという。営業に日曜日は関係ないんだろうか。配送して3日後、新しいホースが届く。作りなおしたにしてはやけに早い。メーカーには様々な長さのホースがストックしてあって、それと交換したんだろう。ところが届いたホースは今度はそれぞれ15mmずつ短い。どうなってんの。「せっかく作りなおしていただいたのに心苦しいのですが」という書き出しで再度、交換依頼のメールを送る。再び営業担当者から「お手数かけて申しわけありません」と平謝りのメールが届く。今回は向こうも動揺している様子。というわけでまたまたホースをメーカーに送り返し、交換してもらうことになった。それがおとついの出来事。つい先ほど、採寸し直して発送しましたというメールが届いたので、明日には、交換されたものが到着するはずである。二度あることは三度あるじゃなくって、三度目の正直を期待しよう。それにしてもメーカーの対応の早さと逐一状況を報告してくるていねいさに驚かされる。いや皮肉ではない。人間のやっていることなんだから手違いがあるのは仕方ないわけで、それよりも間違ったときに適切に対応できるかを評価したい。というわけで営業担当氏の心意気を買って、メーカーのWebサイトにリンクを張ることにする。リアブレーキのホースを交換するときもここに注文しようと思っている。 → プロト 4月から「おじゃる丸」の新シリーズが始まった。電ボの声が変わっている。ショックである。ドラえもんの声が変わったことよりずっとショックである。電ボの妄想が暴走するハイテンショントークこそ、あのまんがの魅力だったので、面白さ半減という感じ。新しい声の人はまだ慣れていないのか棒読み調で、セリフの説明臭さばかり気になってしまう。 ■ A piece of moment 4/26 25日、晩。この春はじめてのジィーィーを聞く。オケラが鳴くから帰るのであった。今年の春は寒い日が多かったので少し遅め。26日、朝。通勤途中の道々、細かい羽虫が飛びまわっている。この時期のみに現れる有翅のアブラムシだった。一斉に飛びまわってこの時期のみ有性生殖を行い、その後は秋まで単性生殖でどんどん増えるへんな奴。 先週末、バイクのブレーキホースは三度目の正直でちゃんとしたものが届く。土日に作業実行。ブレーキレバーも完全にへたっていたのでマスターごとオークションで落札したVTR-SPのセミラジアル(新品!)に交換。キャリパーは分解清掃してシール一式とパッドを新品に交換。うまくホースのエアが抜けなかったり、ハンドルを切ると新しいレバーがメーターに擦れたり、試走の後、ブリーダーバルブからフルードが滲んでいたりと思いのほか大仕事になってへとへと。積算走行距離は先々週に15000マイル。と思ったら、オドメーターが千マイルの位で引っかかってしまい、繰り上がらないまま十分の一マイルだけが空転している。メーターをパネルから取り外し、ギアの穴からドライバーを差し込んでそおっと千マイルの数字を繰り上げる。メンテナンスというよりレストアしている気分。月曜朝、足に激痛がはしって目を覚ます。寝てる最中に足をつったらしい。なんじゃこりゃあ。 ■ A piece of moment 5/2 駅のホームでジャリジャリという音を聞く。見るとスーツ姿の中年男性が電気カミソリで髭を剃っている。かなりあわてているようで、シャツの襟が折れ曲がってスーツからはみ出している。ちょっとほほえましい。御同輩、生きていくのは大変だという気分。そう思うと若い女性が駅のホームや車内で化粧をすることにばかり目くじらを立てるのもスジが通らない。公衆の面前で化粧するなんてという声の背景には、たんに公衆道徳ではなく女らしさを要求する性的役割の押しつけを感じる。人に冷たいこの社会では、男も女も生きていくのは大変なのだ。化粧や髭剃りくらいで目くじらを立てることないじゃないか。シャツの折れ曲がった御同輩は、髭剃りもそこそこにあわただしく上り電車に飛び乗っていった。 ■ A piece of moment 5/6 5月6日である。腹でもこわしたことにして今日休めば日曜までさらに連休はつづくどこまでもなんて怠惰な誘惑を振り払いつつ出勤する。我ながら勤勉である。どうせ生徒は半分くらい休みで中には日曜までハーワーイーなんてうらやましい奴もいたりするんだろうなあと思いつつ教室へ向かうと、ひとりの欠席もなく全員そろっている。ひえええ勤勉な人たち。恐れ入谷の鬼子母神である。そんな勤勉な人たちに脳死と臓器移植についての授業を行う。1週間ぶりの授業にもかかわらず勤勉な人たちはなにやら楽しげに授業に参加していた様子。休みボケでろれつが回らない私にも寛大なのであった。ありがたやありがたや。各クラス、半数以上の生徒たちがドナーカードの実物を見たことがないというので、ドナーカードをもらってこようと昼休みに高田馬場駅前まで足をのばして十数件のコンビニと病院を回るがどこにも置いていない。どうやら元締めの移植ネットワーク自体がドナーカードの普及に見切りをつけてしまった様子。ドナーカードの普及よりも、臓器移植法の改正によって、本人の意思表示なしでも家族の同意だけで移植を可能にしたほうが手っ取り早いと踏んだのだろうが、ちょっと露骨すぎやしませんかい。ドナーカードの普及によって脳死と臓器移植への理解を広めるというやり方は、ある意味で理想的だと思うんだけど、移植ネットワークはそうした地道で民主的な方法よりも、政治を動かして法改正を求める手法を選んだわけである。いかにも日本的である。理事長による医学界へのウラ金工作も週刊誌で暴露されていたし、政治的思惑をはらんで事態は展開しているように見える。というわけで、改正臓器移植法はまもなく国会での審議がはじまるのであった。ドナーカードは小一時間歩き回って探した後に、学校の目の前にある郵便局に3枚だけ残っていたのをもらって帰る。釈然としない気分。 毎日新聞 2005年4月9日社説 移植法改正案 ドナーカード普及が先決だ ■ A piece of moment 5/12 CS放送で「新半七捕物帖」がはじまる。楽しみ。番組は真田広之の主演で1997年にNHKで放送されたものの再放送になる。何といっても主演の真田広之が良い。8年前に見たとき、縞の着物を着てすっと立っている姿は半七そのものに思った。素早しっこい身のこなしや着物の裾を払うなにげないしぐさも良い。原作の半七と違うのは、世の中への怒りがある点だ。原作は「世の中まあそんなもんです」という諦観の言葉を話の中に織り込みながら、半七老人が過ぎ去った江戸の頃を振り返るというスタイルで、突き放されたまなざしが貫かれているのに対して、ドラマの半七は現在進行形で事件と世の中への怒りをたたえている。撮影当時の真田広之は30代半ば。小柄だが精悍で引き締まった体つきをしている。時代劇に多い恰幅の良い親分ではなく、むしろ世の中と生への諦観を拒否する若僧に見える。事件にかかわる人たちと自分の明日のあてどなさを思い「ケッ」とつぶやく。江戸の下町を舞台にした青春ドラマだと思う。エンディングロールで流れる奥田民夫の主題歌も良い。原作の69編すべてのドラマ化を期待したが、残念ながら1シリーズ15本で終わってしまった。イギリスのテレビ局がホームズやポワロの完全ドラマ化に取り組んだように、少しずつで良いから撮り続けてほしい作品だ。 → 時代劇チャンネル「新半七捕物帖」 岡本綺堂の原作はすでに著作権が切れているので、こちらで69編すべて読むことができます。 → 青空文庫「岡本綺堂」 ■ A piece of moment 5/13 この20年間で小さくなって不便になったものな~んだ?答え→納豆のパック。 20年前、100gのパックが標準だった気がする。さらに30年前は150gくらい入った藁筒が標準だったような気がする。ところがこの20年間で、いつの間にか50gに小分けされたパックが標準になって、最近では45gや40gのパックも増えてきてさらには30gのミニミニパックまで出まわったりと縮小傾向が続いている。30gや40gぽっちの納豆なんて珍味じゃあるまいしわざわざ食べる必要ないじゃん。嫌いなら食うなよ。納豆を食べるとき、私は1回に100gから150gを食べるので、ちまちましたパックに小分けされていると非常にめんどくさい。ふたを開けてビニールシートをはがして醤油と芥子をしぼってあっ醤油が飛び散ったおっと芥子が手についちゃったうううイライラするティッシュティッシュというのを3回くり返すことになる。このちまちました作業が納豆ご飯を食べるときの最大の障害で、好物のバナナを食べるためにいちいち知能テストをやらされるチンパンジーの気分になる。おまけに3食くらい納豆ご飯を食べたら、燃えないゴミの袋は納豆のスチロール製パックだけで一杯になってしまう。我が家の燃えないゴミの半分近くは納豆のパックである。ちまちまとパッケージされた納豆はどう考えても非合理的だと思うんだけど、いっこうに改められる気配のないところを見ると、メーカーは納豆のパックだけで東京湾を埋め立てようという野望を抱いているのかもしれない。 ■ A piece of moment 5/14 関西人の東京嫌いは、たんにコンプレックスによるものだけではないように見える。関西人に限らず西日本の人たちの多くが「文化は西から」という優越感を抱いていて、そのことが東京への反感につながっているのではないだろうか。西日本を文化的先進地域と見なす発想は、弥生文化の伝播以来、新たな文化は一貫して西から東へ広がっていったという誤解に満ちた歴史観によって補強され、東日本を文化的僻地として「蝦夷」「東くだり」「奥の細道」と称してきた古来の西日本中心主義が現代まで脈々とつづいているのではないかと思う。大学時代、地方出身の友人知人で、東京の暮らしや慣習を批判するのはほとんどが西日本から来た者たちだった。長崎出身の父はことさら露骨で、ことあるごとに東京を罵っていた。住みにくい、町並みが汚い、人間が冷たい、言葉に品がない、物価が高いなどなど。はては地震が多いなんてことまで非難の対象になっていた。とりわけ父の毒舌の集中砲火を浴びていたのが東京の食べ物だった。子供の頃、父と一緒に料理屋へ入る度に、「なんでも醤油味」「田舎者の味つけ」「関東のどん百姓の食い物」「東京にはうまい店はない」と悪口のフルコースを味あわされた。もちろん料理には地域差があるので、東京の味が父が幼い頃から慣れ親しんだものでないことはわかる。遠く離れるほど故郷が美化されていくのも想像つく。しかし、それが「口に合わない」という相対的評価にならずに、「関東のどん百姓の食い物」という差別的評価になってしまうところに西日本中華思想ともいうべきエスノセントリズムを感じる。つまり、関西をはじめとした西日本の人々が東京に対して抱く敵対心は、見下していた者が大きな顔をしてのさばっていることへの反感というところではないだろうか。一方、東北や北関東出身の同級生たちには地域差という視点は感じられず、都会として単純化された東京像を見ている様子だった。彼らの多くが自分のなまりを消すことに敏感だったのは、都会という一元化された尺度で出身地と東京とを比較していたからではないかと思う。いずれも東京の文化への正当な評価とはいえない。文化的差異に出くわした時、多くの者は、まず恐れ、その後に見下して拒絶するか、劣等感に陥り崇拝の対象にするか分かれる。自らの価値観を相対化し、文化的差異を面白がることができる者は稀である。もっとも、私は地域にも国家にも帰属意識を感じていないので、出身地が自分のアイデンティティの一部であるかのように所属集団と自分とを同一視する認識自体が滑稽に思える。 ■ A piece of moment 6/4 期待していたドラマの「新・半七捕物帖」はいまひとつ。以前に見た時は、原作を読むのと同時進行だったので、原作の印象と重なっていたのかもしれない。原作のもつせいせいとした感覚がなかった。残念。主役の真田広之をはじめとして配役は悪くないと思うんだけど、人物描写が単純すぎて、幕末の江戸に生きる生身の人間たちに思えなかった。まるでコントの登場人物のようで、カメラのフレームから外れた途端、書き割りのようにぱたぱたと倒れてしまうような薄っぺらい感じだった。 バイクは今週、立ちゴケをして以来、ステアリングの調子が悪い。右に切れ込む感じ。ハンドルの曲がりとフロントフォークのねじれは修正したが、症状はおさまらない。フロントフォークのオーバーホールとステムベアリングの交換までやるとなるとかなりの大仕事になる。レーシングスタンドもない状況で、道端でやるのはちょっと無謀な気がする。店に頼むと3万円コース。交換しても調子が良くなる保証はない。気が滅入る。事故は4日ほど前、Uターンの最中のこと。人通りのない路地をそろそろとUターンしている時に、自転車のおばさんがケータイ片手にふらふらと進行方向へ割り込んでくる。あろうことかおばさん、そこに停車してケータイで話しはじめる。で、こちら、曲がりきれずにバランスを崩して転倒。あ~ら大丈夫ぅごめんなさいねえとおばさん。あまりに情けないシチュエーションに泣きそうである。分析と対策その1、バイクから降りて押してUターンする。その2、「おばさん、道あけて」と一声かける。その3、自転車運転中のケータイは百叩きの刑にするべく運動する。 ■ A piece of moment 6/9 レンタル店でアニマルズを見つけ懐かしいので借りる。ストーンズの2枚組みベスト盤もあったのでこれも懐かしいので借りる。LPからデジタルに切り替わって以来、完全にコレクションの趣味はなくなってしまったので、もうベスト盤のレンタルで十分という感じ。本とCDでぼろアパートの床が抜けそうな状況なので、どうせなら全部デジタル化してハードディスクに収まってくれたらどんなにせいせいするだろう。懐かしいのでアニマルズの「朝日のあたる家」を訳してみる。 HOUSE OF THE RISING SUNアニマルズのヒットソングだけど、もとはケンタッキー州の古い民謡らしい。大げさで芝居がかった歌詞。そういえば、ずいぶん前に建設会社のテレビCMでこの歌がBGMに使われていたけど、ほとんどブラックジョークだった。歌詞の意味を理解した上でBGMにしていたんだろうか。当社は罪深い破滅の家を誠心誠意デベロップメントします、なんて。歌のなかでライジングサンと呼ばれている家はなんなのか。濃い化粧をした女たちが阿片の煙をくゆらせながらうつろな顔で男たちの相手をしているような場末の売春宿を思い浮かべるけど、悪魔崇拝の集会場だったりして。 ■ A piece of moment 6/27 期末試験1週間前になり、3年生の女の子が質問しに来る。推薦で大学進学を考えているそうで、ぜひ、政治経済で「5」をとりたいとのこと。5をつけてくれというアピールのような気もするが、3年生の1学期の成績は何かと重要だし気合いが入っているということにして質問につきあう。 「80年代末のバブル経済のしくみを教えてください」 「企業がさかんに株式投資と不動産投資を行ったために株価と地価が急上昇して……」 「バブル経済ではどうして日本企業の投資資金がこれほど急激に拡大していったんですか?」 「例えばある企業が自己資本1億円で不動産投資をしたとします。その1億円の土地を担保に銀行からお金を借りると、銀行は地価の値上がりを見越して2億、3億の資金を融資してくれる。なにせ当時、地価と株価は毎年倍々のペースで高騰していましたから。で、企業はその2億、3億の資金でさらに不動産投資をします。さらにそこで買った不動産を担保に銀行からお金を借りると、銀行は地価の値上がりを見越して今度は4億、5億の融資をしてくれる。さらにそのお金で……ということをくり返していくことで、企業は実際の資本の何倍、何十倍ものお金を不動産や株式の投資にまわすことができるわけです。つまり、アブクのように企業の投資資金がふくらんでいったわけで、この経済現象を後に「バブル」と呼ぶようになったんです。なかなか的を射たネーミングで……」 「では、なぜ80年代半ばの円高不況がバブル経済につながっていくんですか?」 「プラザ合意を発端に急激に円高に推移したため、輸出に頼っていた日本経済は大打撃を受けたんです。そこで政府は景気へのテコ入れとして公定歩合の引き下げを……」 なんて調子でなんだかこちらの方が口頭試問を受けているような気分になる。ところが、フムフムとうなずいていた彼女はなぜか円高の話になるとぽかんとしている。「ほら、ちょうど今、アメリカが中心になって中国の通貨切り上げを要求しているでしょ。中国の通貨が実質的な経済力にくらべて安すぎるために外国で買う中国製品が割安で、今、世界中に中国製品が押し寄せてきている。この押し寄せる中国製品と同じ状況が、20年前の日本製品だったわけで……」と説明してもやはりぽかんとしている。「ん?」「あのー、円が高いとか安いとかってどういう意味なんでしょうか?」「えっそれは日本のお金と外国のお金とを交換する比率のことだよ」「それに1ドル=250円が1年後に1ドル=120円になったら円安じゃないんですか?」「えっえっえっとあのその」「あとそれとどうして円高になると日本製品が外国で売れなくなっちゃうんですか?」「……」。これはもう子供電話相談室で無着成恭さんに聞いたほうがなんて言いそうになりつつ為替相場の基本的なしくみを説明するが、暗雲たちこめてくる。はたして彼女に「5」がつくのか。試験は来週、乞うご期待。なんちゃって。 使わなくなったあれこれをヤフーのオークションに出品する。10年間しまいっぱなしだったレコードプレーヤーがなんと5万円で落札される。わーい。 ■ A piece of moment 6/30 マルチナ・ヒンギスもマイケル・チャンもいなくなり、とくに誰を応援するともなくウィンブルドンの大会を見ている。男女共に完全にパワーテニス全盛になっていて、大味で面白くない。少しでも優勢に立つと「アウー」とか「オオゥ」とか動物的な雄叫びを発しながら強打を連発する展開で、テニスを見ている気がしない。ちょうどテンパイ即リーチの麻雀みたいなもので、読みも駆け引きもなく「ウラドラ期待!おりゃあ」と叫びながら互いにツモリあっている場面を連想する。強打が入ればエースでガッツポーズ、外せば自滅。なんだが大男と大女のマスターベーションという感じ。 フロリダのテニススクールがパワーテニス全盛の牽引力になった。国際大会に出場する選手の国籍は様々だが、その多くは5歳6歳でフロリダに移り住んで学校にもろくに行かずひたすらテニスの英才教育を受けてきた若者たちだ。実質的にフロリダ出身と言っていい。1980年代、スポーツ選手のマネージメントを手がける巨大企業IMGが、フロリダにあるニック・ボロテリー・テニスアカデミーを買収、巨額の資本を投下し、テニス選手の卵たちを投資の対象として育成をはじめた。それ以来、フロリダは世界のテニスのメッカとなり、若いテニス選手を大量生産する製造ラインになった。IMGは、現在、有名スポーツ選手のマネージメントだけでなく、グランドスラム大会をはじめとした大会そのものをほぼ独占的にマネージメントしている。つまり、プロテニスの世界はIMGが選手を育成し、自らの運営する大会でお披露目し、名前が売れたら各企業にスポンサー契約を持ちかけ選手のマネージメントを行うという独占体制になっている。IMGのマネージメント料は収入の25%。客を呼べるスター選手については第一線から退いた後も、エキシビションマッチやイベントを企画してくれて引退後のアフターケアーも万全。当然、フロリダには、毎年、世界中から見込みのある子供たちと自分の子供をテニス選手に仕立てて一攫千金を狙う親たちがつめかけてくる。テニススクールでは、集まってきた子供たちに有名選手になって大金持ちになれるというニンジンをぶら下げ、子供同士を徹底的に競い合わせるというアメリカンなスタイルでそれに応える。将来有望でルックスが良い子供には幼いうちからスポーツメーカーのスポンサー契約をつけ、コーチたちも特別待遇で育成にあたる。1995年にCBSが取材した際、当時13歳のアンナ・クルニコワはIMGから金のなる木と見なされ、すでに複数の専属のコーチがつけられていた。テニスコートにコーチの檄が響く。「お前ら、これは遊びじゃないんだぞ」。もちろん子供たちはそんなことは良く理解している。テニスが遊びではなく投資の対象であり、自分が商品であることを。13歳のやせっぽちの少女はテレビのインタビューに答える。「テニスでの賞金よりCM契約したスポンサーからの収入のほうがもっと多いかな、いまだっていくつものスポンサーと契約してるのよ、アディダスでしょヨネックスでしょあとIMGも、テニスが上手いだけじゃなくってイメージづくりも大事ね」。ひとりのシャラポワやクルニコワを生みだす影に数千人の夢やぶれた子供たちがいる。夢やぶれた大勢の子供たちも夢かなったひとにぎりの子供たちも、充実感と達成感を感じているならそれはそれでいいんだけど、大人たちの欲望と思惑に翻弄され、二十歳過ぎて抜け殻のような虚脱感をかかえてスーパーで万引きしたり、読み書きもあやしいままティーンエージャーの頃に抱いたスポンサー収入の夢とともに「余生」をすごすことになるとしたらあまりにも哀れだ。こうした過酷な競争をくぐり抜けてきたフロリダ出身の若い選手たちには、テニスをビジネスと割り切った発言と能面のような顔で強打を連発するスタイルという点で共通した傾向がある。試合も味気ないけど、選手たちもなんだか競走馬みたいで不気味だ。  ■ A piece of moment 7/2 【金曜日】 試験問題作成を放り出して朝方までテニスを見る。シャラポワ対ウィリアムス姉、両者一球打つごとに絶叫で怪獣映画みたいだった。キングギドラ対アンギラスとかそんな感じ。見ごたえはありました。寝不足のまま出勤し授業3連発。授業は「靖国問題」で討論会。ひさしぶりに会ったムラタ母63歳が突然右翼になって中国の反日デモとヨン様の悪口をまくしたてていたことを紹介する。生徒は笑っていたが、よく考えたら俺ぜんぜん笑えない。ムラタ母に靖国参拝の問題点と戦争責任の背景を説明したところ「オマエは中国の肩を持つのかこの非国民」と母激怒。世の中アブナイ人がふえているようで気が重いのである。帰宅して寝床へ直行。明日の問題作成にそなえてともかく寝る。 【土曜日】 「ヒロシです……」が何者なのか気になって検索する。なぜか検索にこちらのサイト(→「ハネモノ」)がヒットする。バービーなのかリカちゃんなのかはわからないがえんえんとお人形さんの写真で綴られる日記サイト。マニアなのかそういう職業なのか、ともかく熱烈な着せ替え人形への情熱があふれていて思わず見入ってしまう。写真は人形のポージングも服のコーディネイトも徹底的に細部までこだわっていて、ちょっとこれは素人の域を超えている感じ。6月30日の写真なんかモデル嬢の目に力を感じる。こうやってお人形さんの髪の毛は伸びはじめるんだな。試験問題はまだできていない。 【日曜日】 昼、どうにかこうにか月曜日のぶんの試験問題を作り終え、選挙に行く。夜、ウィンブルドンの決勝を見る。フェデラー圧勝。でもテニスウェアーが絶望的にダサイ。まるで下着姿でうろうろしている日曜日のお父さんである。例によってウィンブルドン的演出で、良い場面になると客席にいるフェデラーの「ガールフレンド」がアップで映し出される。テニス選手の「ガールフレンド」というと叶恭子みたいなツラの皮千枚張りのモデル嬢と相場が決まっているんだけど、めずらしくまともそうな感じ。フェデラー、良い奴なのかもしれない。テニスを見ていたら、二階のオッサンが、床をどしどし踏みならしはじめる。何事かと思ったら今度はどんどんと玄関を叩く音。玄関先でテレビの音下げろと怒鳴り声がする。コミュニケーションのたくみな二階の住人で心あたたまるのであった。 【月曜日】 早起きして出勤。朝イチで試験問題を印刷し、そのまま試験を実施、試験終了とともに採点に取りかかる。わりと良い問題ができたつもりだったが、生徒には難しかったのかやけにデキが悪い。ともかく採点を終え、くらくらしながら帰宅。寝床へ直行。 【火曜日】 もう一校の試験問題を作成。夜更けにようやく完成。やっぱり試験当日の朝に印刷することになる。連日ヘッドスライディングがつづく。 【水曜日】 3時間睡眠で朝5時起床。再び朝イチで試験問題を印刷してそのまま試験を実施して採点してああもう嫌。くらくらしながら午後3時すぎに採点終了。どうにか試験ウィークを乗り切ったが、精神的に完全に煮つまっている。猛然と内田百閒が読みたくなり、本屋に寄って「立腹帳」を買って帰宅。立腹立腹。寝床へ直行。夏休みが待ち遠しい日々が続く。 ■ A piece of moment 7/8 業者に表皮の張り替えを依頼していたオートバイのシートが宅配便で到着。ひびの入っていたカウルをついでに補修し、シートを装着。夜中、2週間ぶりにバイクを走らせる。ロンドンのテロ事件の影響なのか、やたらとパトカーを見かける。多摩川を越え、多摩丘陵を回って帰宅。翌朝、エンジンオイルを交換。ついでにグリスアップ。夜中、再び目が冴えバイクを走らせに行く。エンジン快調。ホイットマンのオープン・ロードの詩を連想する。 ■ A piece of moment 7/15 夜中、庭先でチチチチチチと小鳥が泣き叫ぶような声がする。つづいてガサガサバシンと何かがぶつかる音。ガサゴソバサッチチチチチチチチッ……。何事だろうとあかりをつけ窓からのぞくと軒下から真っ黒な猫がこちらをきょとんとした顔で見上げている。猫は両前足を伸ばした姿勢で何かを押さえこんでいる。どうやら犠牲者はスズメらしい。猫は突然目の前に現れた邪魔者を警戒しつつもその場から離れようとしない。ふてぶてしいのか食い意地がはっているのか愛嬌のある顔に似合わずこちらをにらみ返してくる。押さえこんだ獲物にとどめを刺したくてうずうずしている様子。はやくどっか行ってくれよおこちとら取り込んでんだからよう。しばらく顔を見合わせた状態がつづいた後、猫に気合い負けする。そおっと窓からはなれ、あかりを消す。 本日、1学期の授業がすべて終了。期末試験が終わった先々週の時点で気分はとっくに夏休みになっているのに、この数年、高校は終業式ぎりぎりまで授業をやることになっているらしい。年々世知辛くなっていてゆとりの教育ってどこの話っていう感じ。夏休み直前になってひとクラスだけヒトコマフタコマの授業があってもどうにもならんわい。2学期は今年も8月末から授業開始ですのでムラタセンセーよろしくお願いしますねって、あまりよろしくないのである。 ■ A piece of moment 7/22 21日。低温殺菌牛乳はうまいと本に書いてあったので、いつもの普通の牛乳といっしょに買ってきて飲み比べてみる。本当に味が違う。バターのような濃厚な風味。知らなかった。毎日のように飲んでいたのに牛乳なんてみんな同じ味だろうと思っていた。生きていると発見があるものだと感心する。きっとこういうささやかな発見がどうでも良くなった時に人は自殺するんだ。低温殺菌のものは日持ちしないのが欠点だけど、すぐ飲む時はこちらを買うことにしよう。 夜、「ガウディ・アフタヌーン」を観る。良かった。主演のジュディ・デイビスが良い。よく考えたら彼女の出演作ほとんどが好きな映画であることに気づく。やはり発見した気分。 日が変わって22日。お昼になんとなくテレビをつける。NHKで女性アナウンサーが愛知万博の紹介をしていたが、どう見てもNHKによるNHKのための自画自賛番組だった。「NHKの素晴らしい最新技術をご紹介します」なんてまあよくもはずかしげもなく言うもんだ。不快なりNHK。 夜中、CBSドキュメントを見る。いつもながら見ごたえのあるレポート3本。そういえばこの番組にときどき登場するアンディ・ルーニーのテレビコラムは、CBSについてもちくちくと皮肉を放つ。どうして日本のテレビジャーナリズムは所属組織に対してこういう距離の取り方ができないんだろう。給料やギャラをもらっているからって局の奴隷になったわけじゃなかろうに。職員研修でマインドコントロールでもされてるんだろうか。 ■ A piece of moment 7/25 「ラスト・ゲーム」、スパイク・リーとデンゼル・ワシントンのコンビのバスケットボールもの。期待して観たらひどい映画だった。この1年で最低。もやもやとフラストレーションばかり溜まったので内容をまとめてみる。舞台はニューヨークのスラム街。デンゼル・ワシントンは幼い息子に日々スパルタ式でバスケットボールを仕込んでいる。「お前がここから抜け出したかったらこれで這い上がるしかない」が彼の口癖。当然、子供はバスケなんかもうやりたくないと反発する。彼は力ずくで子供を従わせようとし、間に入った妻を突き飛ばす。テーブルの角に頭を強打した妻は死んでしまう。で、殺人罪で刑務所行き。アメリカには過失致死罪という概念がないらしい。主人公のバスケットボールへの思いやバックストーリーが最後まで描写されないため、なぜ彼がそれほどバスケットボールにこだわるのかがまったくわからない。せめて演じるデンゼル・ワシントンが流れるようなフォームでジャンプシュートやドリブル・ペネトレイトを決めてくれれば話にリアリティが出てくるんだけど、サッカーのスローイングみたいにぎくしゃくと放るばかり。「ザ・ハリケーン」であれほど見事にボクサー役を演じたのに、今回はバスケのトレーニングをまったくやらなかったんだろうか。ともかく6年が過ぎて、父親は依然刑務所、息子は叔母に引き取られ、なぜか高校バスケット界のスター選手になっている。あれほどバスケットを嫌がっていたいったい彼に何があったのか、この6年間のことはまったく説明されないのでわからない。ともかくスター選手になっていて、それを現役NBA選手のレイ・アレンが演じている。当然のことながら彼のプレイは高校生ばなれしていて、全米が注目するニューフェイスとさわがれる。様々な大学が奨学金やらお小遣いやら色仕掛けやら高級車のプレゼントやらをちらつかせて彼を勧誘しようとしている。そのおこぼれにあやかろうと、欲深い親戚や腹黒いガールフレンドや卑屈なコーチが彼の進路にあれこれと注文をつける。そんな中、州知事が自分の出身大学に彼を入学させようと画策し、服役中の父親に目をつける。特別措置で出所させ、息子を説得してこいできなかったらどうなるかわかっているな……って、ああもうなんというか書いていて嫌になるほどひどい話。1998年のニューヨークは悪徳保安官が支配する無法地帯なんだろうか。そんな州知事からの理不尽な注文に対し、主人公デンゼル・ワシントンは、ふざけるなと一喝し蹴っ飛ばす……なんて骨のあるところを見せたりせず、いそいそと息子のところへ行って「お前さえ言うことを聞いてくれれば俺の刑期が短くなるんだ」とせまる。最低である。もちろん息子はそんなダメおやじに反発する。自分から母親を奪った殺人者として父親を憎んでおり、口もきこうとしない。ところがラストで一転、息子は父親が言う大学への進学を決意する。感動的なBGMがじゃかじゃか鳴り響き、父親は刑務所の空を見上げ胸を熱くするジ・エンド。なんじゃこりゃ。息子が決意するに至る間、デンゼル・ワシントンは何をやったか。その1、ダウンタウンの安宿で知り合ったミラ・ジョボジョボジョボビッチ演じる娼婦と行きずりのセックスをしようとするが立たず妻の墓前で泣き崩れる。その2、息子のガールフレンドに言いがかりをつけ「息子に近づくな」と高校の正門前で突き飛ばす。その3、息子に1対1のバスケ勝負を挑み、俺が買ったらこの大学へ入れと賭けを申し出るが、スナップのぜんぜんきいていないシュートでは、レイ・アレンに歯が立つわけもなくあっさりと退けられる。以上である。あなたが息子ならそんな父親に胸をうたれますか?ともかく息子は観客には理解できない超自然的パワーで父親の熱い思いに触れてしまいハッピーエンディングをむかえるのであった。でも、そもそも父親の熱い思いってなんなんだ、最初から最後までさっぱりわかんねーぞ、そんな映画。いくつかの会話の中に例によってスパイク・リー的社会批判が散りばめられている。でも、ひとにぎりの勝者が富を独占するアメリカ社会の根本的問題については一切ふれない。バスケでスター選手になって大金持ちになるというアメリカンドリームが階層間格差の不満をガス抜きする社会的装置にすぎないことも指摘しない。スラムの黒人青年たちがアメリカンドリームを夢見てバスケとラップとギャングに夢中になっている限り、アメリカの白人支配は揺るがない。にもかかわらずスパイク・リーはアメリカンドリームという宝くじを肯定し、マイケル・ジョーダンを聖者のように崇める。だからスラムの貧困を描いてもうわべだけで問題の本質にせまることはない。一方で富のおこぼれにあやかろうと画策するスラムの住人にはその卑しさを容赦なく描写する。要するにスラムの住人は努力が足りないから貧乏なんだと言っているだけなので、そこには成功者からの視点しかない。ナイキ関係者や共和党員たちとゴルフ三昧の生活をしているとああなってしまうんだろうか。ナイキのテレビCMでも作っていた方がお似合いである。映画が描くべきことは、マイケル・ジョーダンにあこがれてバスケに明け暮れた若者たちが、夢やぶれた後にどう生きていくかではないのかと思う。映画の中で印象に残ったのは次の3点。 ・ミラ・ジョボジョボビッチは脱ぐと砲丸投げの選手のような逆三角形の体型をしている。 ・デンゼル・ワシントンのジャンプシュートはスナップがぜんぜんきいていない。 ・BGMで観客を誘導しようとする演出は最低である。 ■ A piece of moment 7/26 ふたたびスパイク・リー、「サマー・オブ・サム」。こちらはまとも。舞台になるのは1977年のニューヨーク、イタリア人街。ワル仲間が登場する。妻や子供のいるいい歳の男たちがいつも仲間内でつるんで、道端でくだを巻いたり行きつけの店でだべったり週末にはオープンカーでディスコへくり出したりしている。ほとんどイタリア人街から外へ出ることはなく閉鎖的で身内意識が強い。ちょうど中学生のワルたちがそのまま大人になったような感じ。マッチョな価値観を信奉し、黒人、ユダヤ人、外国人、同性愛者、ヒッピー、パンクロッカーが大嫌い。この辺のイタリア人街の風俗は「ドゥ・ザ・ライト・シング」と同様で誇張されているように見えるが、なかなか興味深い。同時にその論理の通じない会話と人間関係が不気味でもある。そんな中、連続殺人事件がおきる。彼らは自警団まがいの組織を作り、気にくわない者をつかまえては「怪しい」と力ずくで吊し上げはじめる。それはしだいにエスカレートし、ロンドン帰りだというパンク青年が彼らの標的になっていくとまあいう話。70年代懐古趣味的でいまさらこんな映画作ってなんになるんだという気もするけど、一方で、アメリカではいまだにゲイの青年が酒場でリンチされて殺されたなんていう事件もおきているので今日的問題なのかもしれない。観ながら思ったのは、最近やたらとあちらこちらで聞かされる「地域社会の回復」という言葉につきまとう危うさ。べったりとした人間関係の閉鎖的で同質性の強い村社会をつくれば良いってもんじゃない。むしろ互いの差異を認めつつ1対1の人間関係をうまく結べないことの方が問題なのではないかと思う。 ■ A piece of moment 7/31 捕鯨について国内の世論調査では、だいたい6割から7割の人が賛成だという。先日、永六輔のラジオを聞いていたら、ゲストに捕鯨協会の人が来て捕鯨をおこなう正当性を語っていた。捕鯨については結論が出ないまま悩んでいる問題なので、ラジオの一方的に捕鯨の正当性を説きながら皆で鯨肉を試食し、「ああクジラってとってもおいしいんですね」で締めくくってしまう扱いにもやもやしたものをおぼえる。授業であつかおうと思いつつ放り出していた事柄だったので、簡単に論点をまとめてみる。 まず、捕鯨を支持する根拠はおなじみの次の3点。 1.調査捕鯨によってクジラの数は増えていることが判明しており、これ以上、保護する必要性はない。 2.捕鯨は日本の伝統文化であり、捕らえたクジラは食べるだけでなく様々な工芸品にも無駄なく利用される。 3.捕鯨禁止の背景には、クジラを食べる習慣のない欧米諸国による文化的偏見がある。 一方、捕鯨を批判する根拠は次の3点にまとめられるのではないかと思う。 1.クジラの数が増えているというデータは商業捕鯨再開を求める国が出したデータであり鵜呑みにすることはできない。また、海洋の隅々まで調査しているわけではなく、本当にクジラが増えているのかは結論できない。絶滅のおそれがある以上は、商業捕鯨再開はするべきではない。 2.クジラはゴリラやチンパンジーや犬と同等に知的であり、自分が狩られることの恐怖を感じ、人間とコミュニケーションができるほど高度な知性を持った生命である。こうした生命を狩るという行為は、残酷であり野蛮である。 3.日本の捕鯨は近代捕鯨であり、最新装備をそなえた捕鯨船で効率良く捕獲し、水揚げされたクジラは市場原理によって取り引きされる。こうした捕鯨を北極圏のイヌイットがおこなっている伝統捕鯨と同列にして伝統文化と見なすことはできない。 2番目のクジラが知的生命で殺すのは残酷という指摘は少々なじみにくいので、チンパンジーやゴリラに置きかえてみるとわかりやすいのではないかと思う。アフリカ中央部の熱帯地域では、伝統的にチンパンジーやゴリラを食べる習慣がある。それは「ブッシュミート」と呼ばれ、市場で取り引きされている。そのため、大型霊長類の絶滅が指摘され国際条約で狩猟が固く禁じられている現代でも密猟はつづいている。欧米人や日本人にとって、チンパンジーやゴリラがきわめて人間に近い種で高い知性を持っていることはよく知られており、人間の友達というイメージが定着している。もちろんそれを食べる習慣はない。そのため、ジャングルでチンパンジーやゴリラを狩り出し、ライフル銃で仕留めるという行為は殺戮そのものに見える。しかし、現地の人たちにとっての思いは異なる。チンパンジーやゴリラは鹿やイノシシ同様に森の資源のひとつであり、長年、生活の糧としてきた。そこに欧米人が入ってきて、チンパンジーやゴリラは知的な動物だから狩猟はやめろということは、西洋的価値観の押しつけでありアフリカの文化を見下した偏見であるという反発が生じる。そこには捕鯨の賛否とまったく同じ構図がある。もちろん、チンパンジーやゴリラが絶滅寸前なのは誰が見ても明らかなので、狩猟が解禁されることなどあり得ないが、もし、チンパンジーやゴリラが十分な数が生息していたとしたらどうするのだろう。残忍な殺戮として否定されるのか、伝統文化として肯定されるのか、きわめて難しい問題だと思う。クジラが知的生命というと、欧米の自然保護団体のセンチメンタリズムとして端から聞く耳を持たない日本人は多いが、問題はそれほど単純ではないように見える。 ■ A piece of moment 8/11 夜中にテレビをつけるとマンガをやっていた。どこかで見たような聞いたようなシチュエーションとセリフだなと思いつつ見ていたら、黒沢明の「七人の侍」だった。でも、なぜかSF仕立て。村をおそう野伏せりたちは超合金ロボ、侍たちはビジュアル系なのであった。こういうのありなんでしょうか。あっけにとられてぽかんとしていたら、侍たちが戦いはじめる。刀一本で超合金ロボとどんなふうに戦うんだろと思ったら、侍たちは皆、「ルパン三世」の石川五右衛門のごとく、超合金ロボだろうが空飛ぶ巨大要塞だろうがまっぷたつにしてしまうのであった。なんじゃこりゃ。豆腐のようにすぱすぱ切り刻んだ後、ビジュアル系の人たちは「侍たる者、戦場でためらってはならぬ」とわかったようなことを言ったり、「一粒の米をおろそかにするでない」と妙に説教臭いセリフを重々しい口ぶりで言ったりするのであった。摩訶不思議な演出。シリアスなのかパロディなのか不条理なのか演出の意図がわからないまま混乱状態に陥る。凝ったアートワークと見るからにお金のかかっている緻密な絵作りなんだけど、演出の基本的な部分でなにか根本的に間違ってるというか完全に私の理解の外にあって、いったいこれはなんなんだろうと思考停止状態のまま恐いもの見たさで続きが気になっているのであった。全26話。今夜が最終回とのこと。 → 「SAMURAI7」 ■ A piece of moment 8/12 例の超合金ロボの「七人の侍」、全26話、見終わる。こんなに真剣にテレビアニメを見たのは何百年ぶりかのことである。不条理にシリアスな物語は、残念ながら最後まで理解の外にあった。個々のキャラクターはそれぞれバックストーリーを持っているようで多面的にうまく描かれていたけど、ただもう根本的にストーリーと演出が破綻しているので物語としてはどうにもならないという感じ。俺の13時間を返せ。 ■ A piece of moment 8/14 深夜1時すぎ、自転車で近所の団地前を通る。頭上から狂ったように泣き叫ぶセミたちの声。蝉時雨なんて風流なものではない。アブラゼミの耳をつんざくような金属音が誰もいない深夜の街に響きわたっている。その頭上からの音圧に押しつぶされそうになりながら自転車をこぐ。どうやらこうこうとオレンジ色に輝く団地の街灯に反応してセミたちは昼間だと勘違いしているらしい。10年ほど前、痴漢防止を目的に設置されたらしいが、セミの習性も狂わしてしまうとは誰も想像しなかったんだろう。深夜の住宅街がまるごと操業中の機械工場の中に入ってしまったような騒音である。住民から苦情が来ないんだろうか。 ■ A piece of moment 8/16 あまりの暑さに夕方ようやく起きだしてまとめて映画を観る。「スリーピー・ホロウ」、ティム・バートンとジョニー・ディップのコンビ。ティム・バートンのデコデコした風味はやや抑えめで、意外とストレートなホラー映画になっている。それにしても、日本でも海外でも映画監督というと声も態度も顔もデカイのが相場だけど、ティム・バートンみたいなオタク丸出しの映画監督というのは、どうやって撮影現場を指揮しているのか気になるところである。それ以前に、彼がスタッフとコミュケートできているのかということ自体が謎である。テレビのインタビューに出た時は、インタビュアーと目をあわさず、うつむいたままぼそぼそと話していたのが印象に残っている。「コンフェッション」、アメリカテレビ界の名物プロデューサー、サム・ロックウェルの自伝を映画化したもの。この自伝というのが、自分はテレビ業界にいながら同時にCIAの殺し屋だったという二重生活の告白で、どこまで本当かもふくめてアメリカでずいぶん話題になったもの。たしかに題材としてはショッキングで興味深いんだけど、映画としてはその素材を手堅くまとめているだけでそれ以上でもそれ以下でもないという感じ。実在のしかもまだ生きている人物の自伝が元になっているだけに、これ以上ふくらませるのは難しかったのかもしれない。監督はジョージ・クルーニー、顔に似合わず手堅い。マイケル・ムーアの「ザ・ビッグ・ワン」、あいかわらずのマイケル・ムーア節。陽気でパワフル。うれしかったのはスタッズ・ターケルが登場するところ。まだ現役でシカゴのラジオ局で番組のパーソナリティをしている様子。「ナビィの恋」、評判の良かった作品で実際に良い映画だった。沖縄の離島を舞台にした話で、連続ドラマの「ちゅらさん」に設定が似ている。ただ、連ドラみたいなもたれかかり式の人間関係や押しつけがましい家族主義はここには見られない。微妙に距離をとりながら互いを見守っている。物語は、平良とみ演じるおばあが60年越しの恋を実らせ、おじいや孫を捨てて初恋の相手とともに島を出て行く。おじいはそれについてなにも言わない。長年連れ添った相手をいたわり、むしろおばあの想いを邪魔しないようにさりげなく距離をとり、その行方をそっと見守る。おばあが去る日、おじいはいつものように畑へ出かけ、さみしそうな満ち足りたような顔で海を見る。その横顔に胸が熱くなる。テレビの連ドラでこういう芸当はできない。おじいを演じる登川誠仁が飄々とした味わいで抜群にいい。ずいぶんアドリブで喋っているように見えるんだけど、あんまり自然体なんでどこまでが演技でどこまでが地なのかわからない。畑仕事の合間、サンシンをつま弾きながら島に旅行に来たという若者にいきなりシモネタをかます。「オッパイは良いよ、うちのおばあも昔は大きかったんだよぉ、孫のは小さいけどね小さいオッパイも良いもんだよオッパイはかわいがってあげなきゃね、どううちの孫は」。思わず吹き出す。こういうおじいになるにはずいぶん修行がいりそうである。で、そのオッパイの小さい孫に西田尚美。とくに演技がうまいわけでもないし華やかなわけでもないのになぜかいつも良い役をやる。今回も良い役どころ。ファンも多い。ちょっと不思議である。私も8年前に「ひみつの花園」を見て以来、やはりなんとなく気になっている。誰かに似ているような気がしてたけど、今回、岡崎京子が描くキャラクターに似ているんだと気づいた。 →「ナビィの恋」Official Home Page ■ A piece of moment 8/17 再び晩方から映画を観る。「アンダー・ワールド」、ボスニア紛争のセミドキュメンタリーだと思って見はじめたら、なぜかコテコテの特撮の吸血鬼映画だった。どうなってんのと番組表を確認したところ、ボスニア紛争のセミドキュメンタリーのほうは「アンダー・グラウンド」というタイトルで次週放映の模様。まぎらわしい。「WXIII 機動警察パトレイバー」、劇場版パトレイバーの三作目。一作目が面白かったので二作目、三作目と期待したが、いずれも作り手の独善さと視野の狭さを感じて後味の悪い映画になっている。三作目の「WXIII」は、女性科学者が死んだ幼い娘の細胞を使って怪物を作り上げるという話。物語は事件の捜査担当である刑事の視点から描かれていく。おなじみの陽気な隊員たちはほとんど登場しない。若い刑事は女性科学者の影のある美しさに惹かれ、ふたりの関係を軸に映画はシリアスムードで展開していく。女性科学者は、幼い娘を失った悲しみのあまり、怪物を自分の娘の生まれ変わりだと信じ込もうとしている。その一方で、彼女の作りだした巨大な生物は凶暴で、東京湾岸各地で十数名の命を奪っている。湾岸工事の作業員は引き裂かれ肉塊となり、駐車中のクルマにいた青年は上半身を食いちぎられ血の海と化した車内で発見された。刑事は彼女のセンチメンタリズムに引きずられるばかりで、そのことを一言も彼女に指摘しようとしない。むしろ映画はひたすら彼女のセンチメンタリズムに寄り添うように展開し、クライマックスでは、彼女の娘がピアノで弾いたという発表会での録音が怪物に聞かせるように流される。ショパンのセレナードの感傷的なメロディが大音量で流れる中、怪物は殺され、女性科学者は死を選び自ら身を投げる。なんだか見ていて気が滅入ってくるほど、強引で独りよがりな映画。視点を相対化させる場面が一切なく、まるで主人公しかこの世界に存在しないかのような話だ。作り手の幼児性を感じる。自分の文脈でしかこの世界を解釈できない人間なんだろう。そこへ直れって気分。 深夜、十数年ぶりに「2001年宇宙の旅」を見る。美しく宗教性を帯びた映画。だが、その根底にある生命観や人間観には、きわめて古典的なキリスト教の世界観を孕んでいる。すなわち、生命の歴史は単純で「下等」な存在から知的で「高等」な存在へと至る歩みであり、人間はその頂点に位置し神に最も近い存在であるという認識である。この尊大さ、生命を序列化し神へ至る道とする世界観には、強い拒絶反応をおぼえる。それは敵意に近い怒りだ。知性など命のゆらぎが生みだしたひとときの夢ではないのか。「2001年宇宙の旅」の取り澄ました美しさは、西洋文明を中心とする近代的秩序そのものに感じる。その意味でオープニングで流れる「美しき青きドナウ」はこの映画全体を象徴している。人間社会を「原始的」な社会から高度に「洗練された」文明社会に至り、さらに知性をとぎすましていくことで神に近づいていくとする歴史観は、19世紀ヨーロッパの植民地主義者たちの戯言としか思えない。十数年ぶりの再見で何か新たな発見があるかと期待したが、やはり苛立ちがつのるばかりだった。 ■ A piece of moment 8/18 ひさしぶりに髪を切る。いつものオッチャンがいなかったので、まだ修行中ですという感じの若いニイチャンに切ってもらう。毎度のことながら、とくに髪型をどうしたいということもなく、長くなって鬱陶しくなったから来ただけなので良いようにやってくれといいかげんな注文をする。我ながら最低の客である。伸びたから切りに来ただけなんて、まるで子供の散髪ではないか。自分の姿形をこうしたいという意志すら持てないなんて生きているのをやめた方が良い。いつもそう思うのだが、散髪の度にあいまいでてきとうな注文を述べ、毎回かわりばえのしない髪型にしてもらい、GAPの8割引セールで買ったあり合わせの服をてきとうに着て、とりあえず腹がふくれれば良いと松屋の豚丼をかき込みつつ暮らしているわけで、我ながら情けない限りである。「良いようにやってくれなんて言われるとやる気しなくなるでしょ」と尋ねると、「いやいやいやいやいや……」とニイチャンは苦笑いしていた。「ラモスみたいにしてほしいとか、ダンスマンでお願いしますなんて言われたほうが張り合い出ませんか」とさらに聞くと、「いやいやまあその……そういうお客さんのほうが少ないですよ、男性の場合は伸びたから切りにきたで良いんじゃないでしょうか」とニイチャン。そんなもんでしょうかねえ。なんだか自分が若い美容師をこまらせて面白がっているオバタリアンになった気分。彼はいま髪を伸ばしはじめたところだという。自分も伸ばそうと思うことはよくあるけど、3ヶ月も切らないと格好がつかなくなって、半年もするとまるで秋葉原で紙袋を下げてうろうろしている怪しい人みたいになってしまう。そう彼に言うと、大笑いしながら「伸ばす場合でも1ヶ月おきくらいにハサミを入れて形を整えていくんですよ、矛盾してるみたいですが、伸ばしかけの微妙な時期を越えるのが難関なんです」とのこと。ひとつ賢くなったのであった。 いつものオッチャンはものすごく手が早くて、まるで羊の毛の刈り取りのようにばばばばばとハサミを入れていくが、今回のニイチャンはゆっくりとねらいを定めるようにハサミを入れていった。一抹の不安がよぎったが、丁寧にやってくれたようでそれなりに仕上がる。次回も彼にたのんでみようと思う。なかなかハンサムで日焼けした胸元がセクシーだったし。なんちゃって。 ■ A piece of moment 8/19 夏休み前に靖国問題について授業でとりあげたので、Webにまとめてみようと思いたつ。靖国神社の歴史的背景と戦争責任の問題、首相の参拝の何が問題なのか、参拝を支持する者はどんな主張をしているのか、書くべきことは見えている。構成もだいたい決まっている。でも、筆がいっこうに進まない。出来事をならべるのは簡単だが、いざ抽象的な事柄を文章で表現しようとすると主語と述語がうまく結びつかなくなる。我ながら自分の言語能力のお粗末さにあきれる。言葉を探しながらひとつひとつ主語と述語を結びつけ、その文章のたどたどしさに苛立ち、戻って書き直す。書き直す度に文章が硬くなってきて、意味ははっきりするが文章がごつごつして前後のつながりが悪くなってくる。気に入らないのでまた戻って書き直す。それをくり返しているうちに窓の外が白々と明るくなってくる。書いていて楽しい内容ではないし一銭にもならないのに徹夜とは物好きなものだ。 すっかり明るくなった朝7時、突然、電話が鳴る。「タナカですが……」聞き覚えのない男の声が不機嫌そうに話しはじめる。男は自分が送った商品がこちらに届かず、宅配会社によって送り返されてきたという。なんだこれは、まるで安部公房の小説みたいだ。なんのことかわからずぼんやり聞と男の不機嫌そうな抑揚のない声を聞く。大丈夫かこの人。どうやら、先週、こちらがヤフーオークションで落札したCDのことを言っているらしい。月曜日にお金を振り込んだきり先方から連絡が来なかったので、どうなっているのかメールで尋ねたのだった。不機嫌な声の主は、こちらの住所を確認し、再度、宅配便に送り直してみると告げる。それにしても朝7時から宛先確認の電話とはずいぶんさわやかな人物である。電話を切り、意識が朦朧としてきたので寝ることにする。 ■ A piece of moment 8/21 食事をしながらちらちらとNHKの大河ドラマを見る。不思議なことに弁慶に女房がいる。弁慶といえば男色と相場が決まっているし、そのためにわざわざマツケンサンバがキャスティングされて、どっちもOKそうなジャニーズ君の義経とコンビを組んでるんだろうと思っていたのに、どうやらそういう展開にはなっていないらしい。NHKも中途半端なことをする。一方、きのう、おとついとやっていた「ウォーターボーイズ」はそっちの皆さんへのサービスシーン満点で、きっと新宿三丁目のお姉さん方も堪能されたのではないかと思う。いっしょに見ていた友人は、「あら、この子の腹筋セクシーね」とまるっきり若いコ好きのおばさん状態。こういう発言をババアギャグと呼ぶことにしている。人はこうしておばさんになっていくのだ。 ひさしぶりに自分のサイトを検索にかけてみる。誰かが名作マンガ「おるちゅばんエビちゅ」のサイトと一緒にここにリンクを張っているのを見つける。ありがたいことである。この素敵なセンスの持ち主はいったいどんな人物だろうと思ってよく見たら、小学校時代の同級生がつくっているWebサイトだった。世間は狭いのであった。 疑問のページの「フニクリフニクラ」を加筆する。 ■ A piece of moment 8/22 アマゾン.comのWeb広告がまるで自分の好みを見透かしたようにピンポイントでねらい打ちしているような感覚をおぼえた人はいませんか。あれは過去に購入したりチェックしたりした商品データーが全部あちらのサーバーに記録されていて、それにもとづいてユーザーの好みを解析し、似た傾向の商品広告を発信してくるというしくみになっている。当然、アマゾンを利用する機会が増えるほど、データの蓄積量も増えて購買傾向の解析精度が上がり、よりこちらの好みにあった広告を発信してくるようになる。あなたのライフスタイルに最適化したサービスをお届けしますというわけだ。だから、酔っぱらった勢いで、どぎついスカトロものなんかを何本も注文してしまうと、次回そんなことすっかり忘れて昼飯を食いながらアマゾンを覗いた時に鼻から牛乳とツナサンドを吹き出すなんてことになるわけである、たぶん。このシステムを考えたプログラマーはアタマ良いなあと感心する一方で、その小賢しさにいらだつ。まるで、自分の好みを先回りして囲い込まれていくような息苦しさを感じる。もしこのシステムを、自分の好みにあった商品をすばやく知ることができて便利だなんて思っている奴がいたら、名を名乗れ、そこに直れ、目を閉じて歯を食いしばれって感じである。その小賢しさは、木下藤吉郎や石田三成の逸話を連想する。十やそこらの小坊主が、一杯目の茶をぬるめに出し二杯目は熱くして出すなんてあざとい芸当をしたら、そのねっちりとした気のまわしように気色悪いガキのアタマを二三発はたいてやりたくなるでしょ。けっして気が利いていてかわいいとは思わない。情報化社会の商売は、誰もがその気色悪いガキになろうとしているみたいで、息苦しいのである。欲しけりゃ自分で検索して注文するわい。 ■ A piece of moment 8/24 てくてくと歩きながら、なぜかアタマの中にポリスの「Don't Stand So Close To Me」のサビの部分がリフレインする。なんだこれは。潜在的願望なんだろうか。家に帰って押入を引っかきまわすと古いCDが出てきたので、歌詞を訳してみることにする。 Don't Stand So Close To Me (The Police 1980)あと一歩でほとんどエロ小説です。最後にナボコフの「ロリータ」を持ち出してくるのはベタすぎるけど。あと曲のチャカポコしたアレンジが邪魔。こういう曲はもっとねっちりと演奏してほしいところ。ポリスはアレンジが安っぽいと思う。スティングがソロになってバックにうまいミュージシャンをずらっとそろえたのはわかる気がする。ところで大学に勤める知人は、夫婦して大学院生と不倫で家庭崩壊状態なんて話をしていたけど、世の中のあちこちでそんな面白いことがおきていたりするんでしょうか。なんだか高校生に政治経済を教えているよりもエロ小説でも書いていた方が自分に向いているような気がしてきたのであった。 ■ A piece of moment 8/25 ってよく考えたらエロ小説書いて食っていけるんだったらたいていの人はそうしたいわけで、満員電車に2時間も詰め込まれることもなく上司の顔色をうかがうこともなくプレゼンで失敗して胃がキリキリして昼飯がのどを通らないなんてこともなく日々妄想の世界に漂うことができる。肝心なのはそれで食っていけるかどうかなわけで、我ながらいい年してなに甘っちょろいこと言ってるんだろって感じである。1本や2本くらいなら思いつきと勢いでなんとかなるかもしれない。でも、読み手を意識しつつ、毎年、コンスタントに長編数本、短編数十本と書き続けるのは底力以外の何ものでもない。というわけでエロ小説家というのは、なりたくてもなれない世のあこがれの職業のひとつなのであり、人々の羨望の的だったのである。おそまきながら不肖ワタクシ、そのことにたったいま気づいた。エロ小説家の皆さまに申し訳ないかぎりである。明日のご飯のために2学期の授業の準備をしよう。 家にいたくない気分だったが、台風直撃で夜遊びもできずぼんやりと家ですごす。部屋の空気が薄くなったような息苦しさを感じる。しんどい夜である。で、なにもする気がおきないので、この文章を書いている。 まとめてマンガを読んだ。面白かったのは諸星大二郎「私家版鳥類図譜」と陽気婢「内向エロス」1巻。陽気婢「内向エロス」のほうはここ何年かに読んだマンガ・ベスト・オブ・ベスト。すごいわ、この人。エロマンガなので誰にでも勧められるわけではないが、ストーリーテラーとしての底力に圧倒される。 物語は、複雑な入れ子構造になった短編連作で構成されていく。絵柄は80年代風少女マンガを簡略化した感じ。繊細な絵柄で物語に入りやすい。全体の主人公といえるのかどうか微妙な存在として、竹井という若い教師が登場する。高校で社会科を教えているふぬけた雰囲気の男。(誰ですか、変な想像してるの!)彼は学校には内緒でエロマンガを描いており、陽気婢というペンネームで雑誌にレギュラー連載をもっている。つまり、このマンガ自体を彼が書いていることになっている。入れ子のメビウスの輪というわけです。ストーリーは、1話ごとにその彼と彼をとりまく人々の日常と、劇中の「陽気婢」が描いたエロマンガとが交互に展開していく。劇中劇になるのは20ページ程度の短編で、いずれも若者たちのある状況を切り取り、そこでの微妙な心理をすくいとってみせる。ほのぼのとした恋愛ものあり、しんみりした思い出話あり、さらにはぶっ飛んだSFやほとんどアイデア勝負のナンセンスありとイマジネーションの振幅は大きい。20ページ程度なので複雑なストーリーはないが、若者たちの微妙な関係をベースにして、時々突拍子もなく不条理に展開したりするので油断できない。なにより、その微妙な心理描写と会話が抜群にうまい。映画でもそうだけど、何げない会話を上手に描けている作品というのはそれだけで良い作品だと思う。エロマンガなのでセックスシーンは多いが、よくできた物語の一部として構成され、コミュニケーションの表現として描写されているため、良くも悪くもあまりいやらしくはない。むしろ、読み終わって人恋しくなる感じ。一方、竹井の日常のほうは、たんなる現実ではない。創作の過程で彼が落ちていく妄想の世界や過去の記憶といった意識下の世界が交錯し、変容した現実として提示される。竹井の妄想の橋渡し役として、ある時は美術教師だったりある時は犬だったりする謎の存在がちらちらと現れる。クローネンバーグの映画や筒井康隆の「脱走と追跡のサンバ」みたい。そこでは、竹井はエロマンガを描いていることが学校にバレるんじゃないかとびくびくしながら勤務し、そつなくまとまっているが熱意のない授業をおこない、なかなか進展しない同僚の若い女教師との関係に妄想をふくらませ、生徒たちに日々からかわれている。(誰ですか、また変な想像してるの、実在のマンガだってば。)それにしても教員同士の関係など、学校での人間関係はやけにリアルだ。こちらでは竹井をとりまく奔放な女生徒たちが同級生の男の子とセックスを繰り広げる。それは閉じた物語の一部になっていないぶん、妙に生々しく刺激的だ。入れ子構造が効いている感じ。2巻目以降は、竹井の妄想世界が現実を浸食していき、彼の日常を描いた部分は消滅していく。結果的に、入れ子構造は崩壊し、彼の妄想の産物である各話完結した物語がならべられた普通の短編連作になっていく。なので、構成的には1巻目が面白い。2巻目以降は毎話完結した短編が続くため、いくらバラエティに富んでいても少し単調になる。20ページにすっきりまとまっていることがかえってマイナスに働いてあっさり味になっている感じ。雑誌で読むとまた違うのかな。ともかくまあそんなマンガで、やっぱりこれくらい底力がないとエロ作家で食っていけないのである。まったくもって恐れ入りましたという感じです。 こういうマンガを読むと、当然、実際の陽気婢さんのほうがどういう人なのか気になるわけですが、大学卒業後、1年間の銀行勤めを経て、以来、十数年にわたって専業のマンガ家として活動している様子。もちろん高校の社会科教師ではない。(当然といえば当然で、もし俺が学校に内緒でエロマンガを書いていたら、やっぱり自分を投影させたキャラクターを社会科教師としては登場させないもん。)1966年大阪生まれの男性。内気な優等生として学生時代を過ごし、作品はそのころの自分を投影したものが多い。竹井の風貌や妄想癖のある性格は、かなり忠実にご本人を反映している様子。本名も竹井さんだといっそう入れ子が補強されて面白いんだけど、できすぎかな。ホームページもあって掲示板もあるので、なにか書き込んでみようかとも思ったけど、ご本人の掲示板に論評めいた感想を書くのも失礼だし場違いなので、ひとまず、上の文章にまとめてみたというしだい。エロマンガに抵抗がなければおすすめです。 → 陽気婢自由帳 → 漫画街 30の質問 あ、このページ、高校生も読んでいたりするのかな。もちろん高校生にエロマンガをすすめる気はないけど、ただ、高校生といっても精神的な成熟度も様々だし性体験も様々だから、一律に18歳未満禁止とする発想はあまり意味がないような気がする。それよりも問題なのは、エロマンガの性質上、登場人物たちが繰り広げるセックスがやたらと刺激的で気持ちいいものとして表現されることで(まあそうでないと役割を果たさないわけでエッチな空想をふくらませたい時に倦怠期夫婦のしらけた性交渉を見せられてもね)、そのため、セックスや異性に過剰な幻想を抱きがちな人は注意が必要だと思う。とくに性体験や恋愛経験がほとんどない人がこの種のマンガで幻想をふくらませてしまうと、現実の相手とうまくつきあえなくなってしまう危険性がある。その点では成人も未成年も関係ないし男も女も関係ない。もっとも逆に、暑くて億劫だし疲れるしと夏場にすぐセックスレスになってしまう人やバイクいじってるほうが楽しいしと遊びにきた彼女を追い返してしまうような人も問題ある気がするけど。 【追記】 継続して作品を追っているような熱心な読者がコアなファン層としてついている作家のようです。Webにはそうした読者による数多くの感想が書かれていました。そのなかに彼が描く何げない瞬間のうまさについて、上手に表現している文章があったのでリンクしときます。ハタチそこそこくらいの若い方のようです。ときめいているようです。 → 不時着カロン舟のミスナビ 2003.1.2 ■ A piece of moment 8/28 電車の中で内田百閒のエッセイを読む。じわじわ来る可笑しさがある。1ページ2ページと内田百閒の不機嫌節が続き、3ページ目くらいからその不機嫌節がじわじわと可笑しくなってくる。4ページ目、5ページ目くらいで吹き出しそうになる。人混みの中でニタニタするのはちょっと恥ずかしい。 国分寺のGAPはいつも売れ残り品を8割引くらいで売っている。シャツ800円、カバン700円、短パン900円とかそんな感じ。この定価との落差は何なんだ。ガレージセールみたいな値段をみる度に、値段っていったい何なんだろうという気分になる。GAPの値付けは、新製品=定価→3ヶ月経過=4割引→さらに売れ残った処分品=8割引という感じみたいだけど、国分寺店の場合は商品の回転が悪いのか常に処分品が充実している。ひと月に1度、処分品コーナーを覗くのが生活の一部になっている感じ。今回は、800円の開襟シャツを買って、レジでタグを外してもらい、その場で着て出かけることにした。荷物にもならず合理的である。もうひとつGAPで不思議なことは、客の雰囲気が男女で明らかに落差があること。国分寺店のような小さい店舗は別にして、新宿南口にあるような大きな店舗に入ると、女性客はわりとこざっぱりとした格好をしていて、たまにはGAPもという感じなのに対して、男性客は圧倒的に服なんかもうGAPでいいじゃんという投げやりな雰囲気を全身から滲ませている。この男女格差はなんなの。俺も人のこと言えないけどさ。 選挙もからんで政治は郵政民営化一色という状況。この郵政民営化ですったもんだしていた6月の国会で、ひっそりと刑務所民営化法が成立した。いえ、ブラックジョークではありません。またムラタがデタラメを言い出したと思ってる方は政府のWebサイトでも見て確認してください。ほとんどニュースにも取り上げられず、かくいう私も深夜にNHKでやっている「今日の成立法案」一覧で知ったしだい。日本の政治は1980年代の中曽根政権以来、一貫してアメリカの「小さい政府」政策の後追いだけど、とうとうここまで来たかという感じ。90年代にアメリカで刑務所の民間委託がはじまった時、これは悪い冗談かと思った。案の定、問題続出で、ある民間委託刑務所は利益を上げるため、職員のトレーニングもろくにしないままホテルの空き室を埋めるかのように凶悪犯を定員以上に受け入れたあげく、脱走事件が発生。ほとんどモンティパイソンの世界である。日本もこんな法律とおして、本気で刑務所を民間委託しようとしてるだろうか。刑務所より国会を民営化したほうが良いんじゃないの。日本から脱走したい気分。 800円のシャツ。定価は謎の6200円。 ■ A piece of moment 8/29 右の胸がむずむずする。興奮した彼が湿った舌でアタシの乳首をリズミカルに……じゃなくって、シャツの上から触ってみると右の乳首が二つになったような出っ張った感触。なんだろうとシャツをまくると、脇の下から右乳首にかけて赤い発疹が帯状に連なっている。大きいの小さいの繋がってるの離れてるのと複雑な地形のようで、インドネシアのアーキペラゴみたい。熱を持って地腫れしている。こんなじんましんができるなんて、夜遊びがすぎたのか変なものでも食ったのかたんに体力が落ちてるのか、心当たりがありすぎて原因不明。乳首が増えてもうれしくないので医者に行くことにする。かゆい。 医者は一目見るなり、「ああ、これは帯状疱疹だね、じんましんじゃないですよ」と言った。ウィルス性の発疹でヘルペスの一種だとのこと。帯状疱疹は、体に潜伏した水疱瘡のウィルスが体力が弱った時に発症するもので、発疹が神経にそって帯状に連なるのが特徴だと医者は言う。「背中にもあるね、右胸の神経にそって発症してるようだ、痒くないですか」と医者。ま、むずむずします。水疱瘡が部分的に発症してるのと同じだから、何日かしたら発疹にカサブタができるという。発疹にできた薄いカサブタをぺりぺりめくる様子を想像してうっとりする。ちょっと楽しみ。 薬局へ行き処方箋を渡す。「あらウィルス性の発疹、ヘルペスですか」と薬局のおばさん。帯状疱疹だというと、あらそれは大変ですね痒いでしょとおばさん。「右の胸なんですけど、出っ張ったのがむずむずしてはじめ乳首が二つになったのかと思いました」というと、おばさんウハウハ笑う。楽しんでいただけて何よりです。薬局のおばさんからは、抗ウィルス薬は値段が高くてすいませんとやけに恐縮されて何事かと思ったら、5日分、内服薬30錠とチューブ入り軟膏1本で6500円も取られる。うぐっ。 ■ A piece of moment 8/30 病気見舞ということで友人宅で夕飯をごちそうになる。豚肉とゴーヤと豆腐の炒め物にやたらと具の多い山菜汁。たらふく食す。食事をしながら帯状疱疹を見せびらかす。友人激怒。瀬戸内海の離れ小島に隔離するべきだと言い出す。こうして無知が差別の歴史をつくりだすのである。いっぺん水疱瘡をやっている人にはうつらないんだってば。 ■ A piece of moment 8/31 どんなに立派なことを言っていても、ある一言でそれまでの言葉ががらがらと崩れていくことがある。「文句があるなら日本から出て行け」という発言はその典型的なひとつといえる。発言者の意識の低さをこれほど端的にあらわしている言葉もない。この発言が出てきたら、それまでの言い分がどれほど優れていたとしても、もうそれ以上、読んだり聞いたりするに値しないと判断すべきだろう。 言うまでもなく、批判的精神こそが社会を改革していく原動力である。批判的に物事を見て、何が間違っているのかを指摘し、どうすべきなのかを検討していくことでしか社会は改革されない。この言論の自由の保障が近代民主社会を支えている。それは基本原理であり、どのような政治主張をする場合でも、この原理は変わらない。郵政民営化を支持する者しない者、首相の靖国参拝を支持する者しない者、憲法9条改正を支持する者しない者、どのような立場をとり、どのような発言をしようと、その根底には批判精神を尊重する原則が不可欠である。「文句があるなら日本から出て行け」という発言は、この原則そのものを否定し、政治プロセスに議論も検証も不必要だと主張する。しかし、批判的精神が失われ、人々がただ政府の政策を無批判に受け入れ、服従する、その不気味な社会の行く先は火を見るより明らかだ。20世紀の様々な歴史は、失われた多くの人命と踏みにじられた多くの精神によって、そのことを示している。「文句があるなら出て行け」式の発言は、自らそういう社会を望んでいることに他ならない。まともな判断力のある者の発言とは思えない。にもかかわらず、インターネットの文章を見ると、様々な場面でこの種の発言に出くわす。それは日本だけの現象ではなく、アメリカでも中国でも愛国心をとなえる声の高まりと共に増加傾向だという。多くの人がこの種の発言に触れたとき、なーに馬鹿なこと言ってんのとその愚かさを見抜く判断力を持っていることを願う。 二学期の授業では、在日外国人の参政権問題についてクラス討論する予定だけど、生徒がこの種の発言を口にしだしたらどうしよう。討論の展開は生徒たちの発言にまかせ、こちらから口をはさまないのが基本方針だけど、「文句があるなら出て行け」式の発言の愚かさについては、はじめにことわっておくべきだろうか。 ■ A piece of moment 9/1 陽気婢、女友達には不評。セックス描写よりも、作者の願望を前面に出した都合の良い展開と現実味のない女性像が気になって、まともに読めなかったとのこと。内容をどうこう言う以前の問題なのでそれ以上はノーコメントだそうで、でもこのマンガに他者と他者がぶつかりあうことで生じるドラマ性を要求するのは読み違えてるんじゃないのこれは都合よく他者性を喪失した自己の分身たちと同一化していくことへの渇望感と快感を描いた妄想の世界なわけでと弁護してみるがダメでした。どうもエロと関係ない部分で読み手は限定されるようです。NHKでやっていた「ポワロ」の新作四本。楽しみにしていたのに「ハードディスクが容量不足です」とのことで、「五匹の子豚」の一本しか録画できていなかった。「五匹の子豚」はいままでのシリーズよりもずっとシリアスな内容。ポワロ役のデビッド・スーシェも抑えめの演技で聞き役に徹し、登場人物たちが織りなす濃密な人間関係を浮かび上がらせていく。(それにしてもスーシェも熊倉一雄も老けた。)物語は、14年前に殺害された画家と殺人犯として処刑されたその妻、この不在の二人を中心に、彼らをとりまく人々の複雑な人間関係といびつな恋愛感情が関係者の証言によって描かれていく。若い愛人への嫉妬、人を支配し独占ことの欲望と快感、富と才能をあわせ持つ者の傲慢さ、恋する者の卑屈さ、若く一途な情熱と策略、幼なじみへの押し殺した同性愛、見ていて背筋がぞくぞくする。(こちらは他者と他者とが濃密に絡み合い互いに精神的殺戮を繰り広げる世界。)心の中のもろい部分をぐりぐりとえぐられるような感触で、見終わってしばしのたうち回る。犯人さがしやトリックの仕掛けというミステリーの部分はもうどうでもいい。それよりもひとりの人間をこの世界から抹殺しようと思うに至るはげしい感情とそこに追いつめていく濃密な人間関係のほうに圧倒される。ときどき人から自虐趣味がありませんかと聞かれることがあるけど、本当にそうなのかもしれない。アップを多用し、冷たく冴えた映像も見事だった。あんな物語が書けたらなと思う。今回録画できなかった「ナイルに死す」「杉の柩」「ホロー荘の殺人」もなんとしても入手したいところ。急にプイグの「蜘蛛女のキス」が読みたくなる。20年近く前に観た映画はもうストーリーも忘れてしまった。舞台で再演するとのことでこちらも気になるところ。あいかわらず授業の準備が手につかない。 疑問のページに「2005年度版 バイク乗り考」を追加。けっこう力作。 ■ A piece of moment 9/3 夜9時すぎ、都心部へ向けてバイクを走らせる。8月の猛暑とくらべてこのところ少し気温も下がってきたし、混んでる時間もすぎたしと油断していたら、中野のあたりで水温計が「H」を振り切り、リザーバータンクから冷却水が噴き出してくる。200メートルごとに信号にかかる東京の道が悪いのか、1000ccのエンジンが大きすぎるのか、ともかくこの調子では、都市生活者にはきびしい。緊急事態で高田馬場の職場まで行かなきゃならないなんて場合でも、バイクに飛び乗ってエイヤっていうのはちょっと無理そう。エンジン出力が多いぶん、発熱も大きいわけで、それにあっという間に100キロ150キロと加速していくので、都市の渋滞路を40キロくらいでもたもた走っているとやたらとストレスがたまる。バイクも前へ出たがってうずうずしている感じがする。この手の大型車は山梨あたりから高速をつかって東京に通勤なんていう人には良いのかもしれないけど、東京に住む者にとってはあまりに実用性に欠ける。ある程度予想はしていたけど、これほどひどいとは思わなかった。大型バイクに乗るようになって、かえって出不精になっている気がする。長く乗りつづけているオーナーのほとんどが田舎暮らしなのは自然淘汰の結果だったのである。10月には車検。いちおう通すつもりだけど、私とこの巨大なV型4気筒のバイクとの関係に未来があるような気がしないのであった。 疑問のページに「仔ワニ500円」を追加。 ■ A piece of moment 9/6 高田馬場で「ムーランルージュ」と「オペラ座の怪人」の2本立て。「授業をサボってぇ~♪」って教える側にまわってしまうとそうもいかないので、パレスチナ問題の授業3連発の後に映画館へ入る。「ムーランルージュ」は作家のタマゴとキャバレーの踊り子さんとのねっちりとした恋愛ものだと思っていたら、なぜか特撮全開のドタバタミュージカルで、韓国焼酎のテレビコマーシャルみたいだった。ストーリーの暗さと外連味たっぷりのスラップスティックな演出とが合っていないと思ったけど、隣の席で見ていた女性はラストでボロボロ泣いていたので、ああいう変化球もありなのかな。大勢のダンサーをバックにニコール・キッドマンが踊る場面は圧巻。ニコール・キッドマンはドタバタのシーンでは素で笑ってる感じで、めずらしく気立ての良い陽気なお姉さんに見える。個人的には、いつもの情念と怨念と野心のかたまりみたいなキャラクターより、こっちのほうがずっと良い。もっとコメディもやればいいのに。「オペラ座の怪人」のほうは、ファントム氏が劇場に住みつくようになったいきさつがわからない。寮長みたいなおばさんとファントム氏との間に何やらいわくありげな雰囲気だったけど、母親と息子ってわけでもなさそうだし、これも最後まで判然としない。映画版はストーリーを端折ってるんだろうか。 ■ A piece of moment 9/7 6500円もした抗ウィルス薬の効能なのか、帯状疱疹はカサブタもできずに発疹の腫れもひく。ただ、右胸から背中にかけて、打ち身や火傷のあとのようなひりひりした痛みが残る。しくみはよくわからないが、神経を刺激するので痒みよりもむしろ痛みが出ると医者は言っていた。このひりひり感が気になって、右の胸をもむ癖がついてしまった。昨日は混雑した西武新宿線の車内で、自分の胸に手を当ててモミモミしそうになったところで我に返り踏みとどまる。この状態が続くとそのうち授業中にオッパイをモミモミしてしまいそうで、自分の自制心のなさに不安が広がっていくのであった。 当サイトの紹介文を少し手直ししました。読んだことのない方はご一読を。 → information Box96 ラジオからシンディ・ローパーの"Time After Time"が流れてきたついでに、疑問のページの37番目、「タイム・アフター・タイム」を加筆修正する。 ■ A piece of moment 9/10 授業はパレスチナ問題の3回目。ナショナリズムが連鎖していく問題とアメリカによるイスラエル支援を説明する。アメリカによるイスラエル支援は、中東戦争での軍事支援、イスラエル建国から継続的におこなわれている経済支援、国連での擁護と広範囲におよぶ。パレスチナ自治区への入植政策について、安保理ではたびたび反対決議がおこなわれようとしてきたが、その度にアメリカは拒否権を発動。このパレスチナ問題でのアメリカの拒否権発動は冷戦終結後だけで十数回におよぶ。その結果、戦争でぶんどった占領地に自国民を入植させ、既成事実として領土化するという現代社会にあるまじき野蛮なやり方がずるずると30年以上にわたって続いている。そうしたアメリカの姿勢が、アラブ諸国、イスラム諸国の反米感情を生んできた。とここまで説明したところで生徒から質問。「どうしてアメリカはそこまでイスラエルに肩入れするんですか?」あっ良い質問です。やっぱり不思議だよね、と生徒と一緒に不思議がっているだけでは話が進まないので、いちおう二つの点を指摘する。ひとつはアメリカ国内でのユダヤ系財界人の社会的・政治的影響力の大きさ。ユダヤ系の人口自体は数パーセント程度でたいした数ではないが、テレビ、新聞業界をはじめとしたマスコミ関係にユダヤ系の財界人が多く、ホワイトハウスとしては彼らの支持をつなぎ止めておきたい。ただ、興味深いことにアメリカ在住のユダヤ系市民には民主党支持のリベラル派が多く、彼らはブッシュ政権のイラク問題やパレスチナ問題での強硬なやり方を批判していて、この点ではアメリカ世論にねじれ現象がおきている。もうひとつは福音派をはじめとしたアメリカの保守的なクリスチャンに、親イスラエル・反イスラムの意識が強いこと。そのため福音派を主な支持母体とするブッシュ政権になってから、パレスチナ和平の仲介よりもシャロン政権の強硬路線を支持する立場を打ち出している。「でも、三つの宗教はルーツが同じで、キリスト教もイスラム教も同じ神を信仰してるんじゃないんですか?」ああ優秀な生徒、キミはインタビュアーか。えーと、アメリカでキリスト教の神とイスラム教の神とが同じ存在であることを知っている人はほとんどいません。多くのアメリカ人はイスラム教を狂信的な原理主義宗教だと考えていて、キリスト教とは相容れない異質の宗教と思っています。その認識は、湾岸戦争やイラク戦争の時にテレビのコメンテーターが「キリスト教徒の神とイスラム教の神のぶつかり合いです」なんてデタラメな発言をしても受け入れられてしまうくらい定着している。あと、アメリカの子供向けのテレビ番組では、悪者というとたいてい褐色の肌にターバンを巻いていて髭もじゃの人物が登場する。さらにその悪者は、やたらとマシンガンをぶっ放す残忍なテロリストだったりもします。これがアメリカ大衆文化に登場するアラブ人とイスラム教徒のステレオタイプ。なので、教育のない人ほど「アラブ人=悪者」の短絡的イメージを抱いているようです。こうしたステレオタイプが形成された背景に、アメリカの敵としてわかりやすい悪者を求めるネオコンの動きがあったという指摘もされているけど、その点ははっきりとはわかりません。個人的にはアメリカ人の国際問題への関心の低さが最大の問題だと思っています。ほとんどのアメリカ人は、イランで優れた映画がたくさん作られていることも知らないし、カンヌの映画祭でイラン映画がパルムドールを受賞していることも知りません。そうしてアメリカ大衆文化に「アラブ人、イスラム教徒=悪者」という単純化されたイメージが定着していることが、ブッシュ政権のイラク政策をアメリカ世論が受け入れる背景になった。あ、イランはアラブ人じゃないけど。そもそもまともな感覚があったら「悪の枢軸」なんて発言、悪い冗談としか思えないもんね。てな感じで、本日の授業もつつがなく終了。夏休みに遊び呆けていたわりに2学期の滑り出しは順調な気がするが、生徒に司会してもらっているような感じもするのであった。彼をサクラとして雇って、すべてのクラスに潜り込ませたいところである。 ■ A piece of moment 9/11 授業のページの「所沢高校入学式事件」を7年ぶりに加筆修正。事件から7年も経過して、いまさらという気もするけど、その後も似たようなケースはあちこちの学校で起きているし、今年は勤め先でも卒業式のあり方をめぐって、校長と一部生徒との対立もあって、改めて考えてみたしだい。 → 所沢高校入学式事件 ■ A piece of moment 9/13 仕事の帰りに「パッチギ」と「69 Sixty nine」の青春映画2本立て。先週の「ムーランルージュ」と「オペラ座の怪人」は女性客大入りだったのに、こちらはがらがら。「パッチギ」は評判通り良い作品。「69 Sixty nine」は最低。7月に観た「ラスト・ゲーム」とならんで最近のワースト、と文句だけ言って、書き逃げしてしまうのも気がひけるので、「69 Sixty nine」の何がダメか挙げてみることにする。我ながら職業的訓練による忍耐力のたまものである。 時代は学生運動はなやかなりし頃の1969年。主人公は高校生の男の子。妻夫木聡演じるお調子者で口が達者なハンサム君。退屈な日常と窮屈な高校生活に、なんかおもしろいことしたいなあ、みんなをあっと驚かせるようなことがしたいなあと思っている。まあたいていの人にはそんな経験ありますね。で、その彼が、安藤政信演じるもうひとりのハンサム君と知り合い、意気投合し、学校をバリケード封鎖しようということになる。バリケード封鎖をする政治主張や思想なんかはどうでも良くて、ともかくパフォーマンスとしてみんなが驚くようなことがしたいわけである。そこまでは良い。それもありだ。でも、このハンサム二人組み以外の登場人物たちは、いずれもブサイクでどんくさくて小心者の三枚目として描かれる。愚かな彼らは主人公に突っ込まれるとまったくなにも言い返せない。映画の中の笑いは、すべてこのどんくさい脇役たちを主人公のハンサムふたり組みがからかい、見下し、笑い者にすることで成り立っている。じつに感じが悪い。コンプレックスのかたまりみたいなクラスメイトを使いっ走りにして、彼がドジる度にふたりで小突き回す。運動もどきをしている連中を主人公は得意の口からでまかせで自分の計画に巻き込み、彼らがなにも言い返せないと見るや、手下としてあごで使う。彼らがその小心ぶりと三枚目ぶりを発揮するたびにふたりは笑い転げる。なんて嫌らしいんだろう。一方、教師たちはそろって感受性の欠落したステレオタイプとして描かれる。主人公が毎度のごとく口からでまかせで挑発する。「ベトナムで戦争が起きているのになにも行動せず、ただシェークスピアを読んでいるなんてくだらないと思いませんか」。その口先だけの批判に対して、教師はなにも答えられない。うっと言葉に詰まり、代わりに乱入してきたただ暴力装置として存在しているかのような体育教師が主人公をぶん殴る。おいおい……。我々が生きているのは極論するとシェークスピアを読むためである。政治とは人間がより良く暮らしていくための手段にすぎない。政治に関する問題提起や行動は、より良くシェークスピアを読める社会環境をつくるために行わるのである。人は天下国家のために生きているのではなく、人の暮らしを良くするために天下国家が存在する。これが近代社会の基本原理である。したがってシェークスピアを読むことを否定してしまったら、社会改革など無意味である。主人公の政治を論じることこそが上等であるかのような言い分は、お国のために滅私奉公をとなえた国家主義者と変わらないではないか。なーんて議論は一切なく、感性の欠落した教師はバカ面を下げてただ規則をとなえ、主人公はそれをあざ笑う。なんて薄っぺらい登場人物たち。おまけに学校一の美少女は、主人公の口先だけの社会批判に感動してしまい、彼に恋してしまうのであった。どこまでも主人公にムシのいい話で、おいしいところは独り占めである。やがて、主人公はバリケード封鎖の首謀者であることが発覚し、警察の取り調べを受けた末に謹慎処分となる。さらに謹慎期間中にヌードダンスとロックのイベントを企画したことで、とうとう退学処分になりそうになる。主人公はそれに猛反発する。なんでよ。あれだけ学校に不満をまき散らし、口先だけとはいえ「学校解体!」と校舎のそこら中にペンキで書き殴ったではないか。どうしていまさら退学になることに異議申し立てするの。そんな学校やめちゃってせいせいすればいいじゃん。要するに、主人公はちょっと暴れて目立ってみたかっただけで、本気で学校のあり方を改革しようなんて思っていないことはもちろん、進学校の生徒という社会的に有利な立場を捨てる気もなく、自らの言動の落とし前をつける気すらない。「学校解体!」と言いつつ、学歴だけはちゃっかり欲しいわけである。とことん嫌らしい奴。そんな主人公は退学をせまられた末、学校中の生徒を扇動し、全生徒たちに学校への不満をぶちまけさせる。退学させたいのなら生徒全員をやめさせてみろと逆に教師にせまる。そりゃあ誰だって窮屈な日常にどこかしら不満はある。でも、ただ自分がいい格好をしたいだけの底意地の悪い主人公に、なぜ、彼らが動かされるのか、まったくわからない。どこまでも主人公に都合良くできている話で、なんじゃこりゃまったくと思っていたら、最後でどんでん返し。(あ、以下「ネタバレ」ってやつです。)ラストでいきなり冒頭の教室でだべっている場面に巻き戻され、「なーんて話はどうかな」と主人公。ぬおおおおお夢オチかよ。なーんて話はどうかなじゃねえよ、なめんな。要するに観客は、ボクちゃん大活躍・ボクちゃん人気者・ボクちゃんモテモテというただ自己愛を垂れ流しただけの主人公の妄想に2時間もつき合わされたわけである。エンディングのスタッフクレジットを見ながらこの悪趣味な映画を作った連中に殺意をおぼえたのであった。脚本と監督は復讐ノートにメモってやる。もしあなたがこの映画を好きだとしたら、私はあなたのことも嫌いです。村上龍の原作はもう少しマシだったような記憶があるんだけど、映画はとにかく最低である。星マイナス5つです。 「パッチギ」の主人公も、ヒロインが美少女というだけでひと目ぼれしてしまい猛アタックするといういい加減さでは同じである。ヒロインの女の子は朝鮮高級学校の生徒で彼女のお兄さんは京都中に名の知られた番長。でも、そこから彼は、彼女に少しでも近づこうと朝鮮語を学び、彼女が演奏していた「イムジン川」を一緒に歌えるようになりたいとギターを練習し、歌詞の意味と彼女が日本社会の中でおかれている状況を読み解こうとしていく。もう、こころざしと決意が決定的に違うのである。それでも在日の人々が日本へ抱く敵意と不信感によって、主人公は在日コミュニティからはじかれる。彼らが体験した出来事を知ることはできても、彼らがその体験で抱いた思いを共有することはできない。憤り、打ちのめされ、主人公は「イムジン川」を歌う。その歌声が地元の小さなラジオ局から流される。ヒロインの女の子はラジオから流れてくる彼の歌を聞き、涙ぐむ。そして、彼の思いを家族に伝えようとラジオのボリュームを上げる。印象的なシーンでした。同じ時代の同じようにマンガチックにデフォルメされた高校生たちの青春群像にもかかわらず、そこに登場する若者たちのリアリティと想いの深さに決定的な差のあるふたつの映画だった。 ■ A piece of moment 9/14 疑問のページの「バレエダンサー」に追記と佐藤さんからのメールを追加。 → 「バレエダンサー」 授業のページに「専業主夫」を追加。 → 「専業主夫」 ■ A piece of moment 9/15 ここ数週間、アタマの中で同じメロディが鳴っていた。気がつくと口ずさんでいたり、アタマの中で鳴っているメロディにあわせて歩いていたり、皿を洗う手を動かしたりしていた。当然、聞き覚えはあるんだけどなんの曲かわからない。歌詞もおぼえていない。友人にさびの部分を歌ってきかせてもただニヤニヤと笑われるだけ。手がかりなしであきらめかけていたところ、昨日、古いCDの山の中からそれらしいのが出てきました。ああ、これこれ。こんな歌でした。 Hang Down Your Head (Tom Waits 1985) 浮気した女に語りかけている歌です。流れ者の男が何年も女を放っておいたあげく、彼女に別の男ができたことを風の便りに聞いて、遠く彼方の彼女へ歌いかける。そんな西部劇みたいなシチュエーションを思い浮かべるわけです。ただ、男はかなり未練があるみたいで泣きが入っている感じ。ことさら「俺は行かなきゃならない」なんて強調したりして。で、問題なのは次のさびの箇所。 So hang down your head for sorrow, hang down your head for me Hang down your head tomorrow, hang down your head Marie 「お前の首をつるせ」!?「お前の首をぶら下げてやる」!?○□△*……。 「明日こそお前の首をつるしてやる」・・・・「つるしてやるからな、マリー」!!ぎょぇぇぇぇ……。 さびに来て突然の血まみれ殺人事件発生でサイコホラーでスプラッターな急展開にどきどきしたんだけど、違うよね。まさかね。ありえないよね。こんな歌を口ずさみながら皿洗いを……いやいやいや。えーっと、英和辞書によると「hang one's head」で「(恥ずかしくて)こうべをたれる」ってあるから、こちらだと思うんだけど、どうなんでしょう。 なぜかいまさら、「クリントン、セックススキャンダル」を加筆修正する。読み返しながら、文章がまるで酒場の酔っぱらいによる無責任な政治放談みたいで笑う。授業のページの中で一番可笑しい気がする。わずか7年前の出来事なのになんだか遠い昔のことのように思える。アメリカも日本ものんきだった時代ののんきな授業。 → 「クリントン、セックススキャンダル」 「モーターサイクル・ダイヤリーズ」他、映画3本まとめて観る。「モーターサイクル・ダイヤリーズ」の主人公は若き日のチェ・ゲバラ。ただし、革命家としてのゲバラではなく、スクリーンの中の彼は、茫洋とした将来に不安を抱く繊細な23歳のひとりの若者にすぎない。医学部を休学し、年上の友人とポンコツのオートバイに二人乗りして一年におよぶ放浪の旅に出る。オートバイは古いノートンの単気筒。出発の時からすでにオイルが焼けて白い煙を上げている。ついついキャブレターのオーバーホールとピストンリングの交換をしなきゃなんてことが気にかかる。陰影の濃い南米の風景の中をオートバイは走り、主人公の家族へ宛てた手紙がモノローグとして語られる。そこからは家族思いの文学青年としての若きゲバラの姿が浮かび上がってくる。旅の前半は、恋人との再会や見知らぬ女性たちとの出会いを求め、その中でひとりの若い魂が解放されていく様子が描かれる。中盤、転倒と故障の連続でなかばスクラップと化したオートバイを手放したあたりから物語のトーンは変化する。主人公はより密接に人々とかかわるようになり、そこで出会った貧しき者、虐げられた者とのかかわりから、南米社会の抱える社会的矛盾に思いをはせ、しだいに共産主義者としての自分を自覚していく。最近観た日本やハリウッドの青春映画がどれもマンガチックにデフォルメされた演出に満ちていたのとは対照的に、劇的な場面や大げさなセリフを避け、何げない描写やさりげない会話から揺れ動く若者の心理をすくいとってみせる。やはり映画はこうあって欲しい。我々はマンガのパロディとして生きているのではないんだから。それにしても南米の人たちは踊る。映画は50年も前の出来事だけど、そこでは誕生日、週末、歓送迎会、ことあるごとにダンスパーティを開き、老いも若きも機械工も療養所職員も、みんな踊る。ダンスが習い事や都会の風俗ではなく、生活の一部になっている様子はちょっとうらやましい。あと驚いたのはロバート・レッドフォードがプロデューサーとしてかかわっていること。20年ほど前に監督をした「ミラグロ」では、メキシコのスラムを逃れてアメリカに密入国する子供たちを描いていたけど、今回はチェ・ゲバラだし、アメリカの中南米政策に批判的な政治思想の持ち主なんだろうか。ハリウッドスターと社会主義者の取り合わせというのは、ちょっとイメージしにくいんだけど。 ■ A piece of moment 9/16 職場に「モーターサイクル・ダイヤリーズ」を観たという人がいたので、なぜ、いまだにゲバラだけは人気があるのかと聞いてみる。共産主義の理想は色あせ、毛沢東もフィデル・カストロも評価は地に落ちたというのに。返ってきたのは「やっぱりハンサムだからでしょう」と単刀直入なお答。「ハンサムな文学青年で、文章も若々しくて理想主義的だし、あの時代を体験した人にとってジョン・レノンとゲバラは特別なんじゃないかな。それに若死にして権力者としての醜態をさらさなかったっていうのも大きいと思いますよ」とのこと。うーむやっぱりカオとイメージですか。そういえば、60過ぎて突如右翼になった母はことあるごとに中国政府の悪口を言っていたのに、周恩来だけはハンサムで男らしくて立派な政治家だったと褒める。アンタは周恩来の業績の何を知ってるんだって感じだけど、男の価値は顔に現れると本気で信じている母には何を言っても無駄なので、ああそうと聞き流すのであった。 2年ほど前、見知らぬ人からメールをもらった。丁寧な文章で書かれた所沢高校入学式事件についてのメールだった。その人は当時、所沢高校の1年生として在籍していて、自分が体験したあの出来事を考えてみようと、当時の資料を集めているとのことだった。日本の学校の卒業式・入学式のあり方について、どうも大学の卒論か研究室のレポートとして発表するみたいだった。私がWebに書いた所沢高校入学式事件の中のビデオ資料がどうしても入手できないので、もしよかったらダビングしてもらえないかと書いてあった。もちろん引き受けた。ただ、ちょうど期末試験直前でバタバタしていたので、少し待ってほしいとつけくわえた。ようやく答案の採点も終わり、ビデオテープのダビングもできたので、自宅宛てでも研究室宛てでも宅配便で送ると連絡した。ところが、やけに遠慮がちな人で、それは申し訳ないので近くの駅まで行くから待ち合わせしましょうと返事が来る。かえってその方が面倒な気がするけど、メールの主がどんな人なのか興味もあって会うことにした。数回のメールのやりとりで待ち合わせ場所と時間を決めるが、なかなかうまく互いの時間の都合がつかない。そうこうしているうちに、先方の研究発表も終わってしまったようで、メールの文章もトーンダウンしていった。研究発表に間に合わなくて申し訳ない、もし今でも必要ならテープを宅配便で送るとメールしたところ、再び、それではあまりに厚かましいので近くの駅で待ち合わせしてと返事が来る。まだるっこしいなあ。そこでもやはりうまく時間の都合がつかず、しだいにメールのやりとりもなくなり、2年が過ぎていった。棚の目立つところにおかれたままになっているビデオテープは、埃と煙草の煙で少し黄色くなっていて、それを見る度に夏休みの宿題をやり残した小学生のような気分になる。先日、Webの所沢高校入学式事件の文章を書き直したのを機に、2年ぶりにメールを送ってみた。2年もたてばアドレスも変わってしまってもう届かないかなと思ったが、予想に反して「MAILER-DAEMON」からの不在通知は来なかった。でも、それから1週間経過するが、返事はこない。なにをいまさらと腹をたてているのか、それともアドレスだけ残っていてもう使われていないのか。ひとまずビデオテープの埃を落として棚の奥にしまい込むことにした。 ■ A piece of moment 9/19 80番目の疑問を追加。悩めるタナカくんの巻。 → 「だめんずうぉ~か~」 炎天下の中、アタマから汗を流してバイクのチェーンに油をさし、ワックスをかける。車検にそなえて気合いを入れてみたのである。雨の中走って泥まみれだったアンダーカウルも分解洗浄。ぴかぴかである。隣の建築現場の兄ちゃんが邪魔だと言わんばかりにこっちをじろじろ見ていたので、ガンを飛ばしあう。邪魔はそっちじゃ。ぴかぴかになって気分も良いので記念写真も撮ってみる。バイク様とその下僕の図という感じ。 ■ A piece of moment 9/21 このサイト、何かがたりないと思っていたんですが、「FAQ」がないことに気づき、新設してみました。 → FAQ ■ A piece of moment 9/25 唯一、楽しみにしていたドラマ「シックス・フィート・アンダー」が13回であっさりと終わってしまった。放送開始時の番組宣伝では、「エミー賞6部門受賞!全米を震撼させた衝撃のドラマ、いよいよ放送スタート!」なんて大げさにぶちあげていたから、50本くらい一気に放送するのかと思っていたのに、なんともあっけない幕切れ。最終回の後に「今回をもって番組を終了します」の字幕が出ただけだった。わずか3ヶ月足らず。1stシリーズだけの放送契約だったようだ。あまりにも放送期間が短かったために、最終回の放送終了後にもプレゼント告知で、「番組放送開始を記念してマグカップをプレゼント」となんてやっていた。間の抜けた話。アメリカでは5thシリーズまでつくられているみたいだけど、CSで今後の継続放送をどうするのかについては一切告知がなかった。いいかげんだなあ。 → スーパーチャンネル「シックス・フィート・アンダー」 惰性で見ている「ER」と「スタートレック・エンタープライズ」はまだ放送が続く様子。もう200話くらい続いている「ER」はメインキャストが次々と入れ替わり、その度にトーンダウンしてもう出がらしという感じ。「スタートレック・エンタープライズ」は最近のアメリカを反映してか、やたらと好戦的な内容で見る度に不愉快な気分になる。「スタートレック」シリーズは、前作の「ヴォイジャー」あたりからCGを駆使した活劇調に雰囲気が変わっていて、このシリーズの本来の魅力だった思索的な部分は影をひそめ、「やっちまえ」という暴力性がやたらと前面に出てくる。「エンタープライズ」はさすがにアメリカのファンにも嫌がられたようで、4thシリーズで放送打ち切りとのこと。ちょっとほっとしている。新番組では、以前、町山智浩がコラムで紹介していた、「デスパレート」がNHK・BSで放送が始まるみたいで、これは少し楽しみにしている。もっともこの所、精神的に落ち込んでいて、テレビドラマを見る気分ではないんだけど。 ひさしぶりにラジオで「伊集院光の日曜日の秘密基地」を聞く。番組の企画やテンポの良い会話は面白いんだけど、メインパーソナリティの伊集院光の発想が保守的すぎて、少々げんなり。「プロジェクトX」が大好きと公言し、彼氏以外の相手と手をつないでデートするという投稿に「そんなのありなの?!」とわいわい騒ぐ様子に、ちょっと勘弁してくれよって感じ。「プロジェクトX」のなんでも美談に仕立ててスタジオのおじさんたちに泣かせる演出は悪趣味の極みだと思うし、彼氏がいようが旦那がいようが、他の男と手をつないでデートするくらい別にいいじゃない。スワッピングパーティに参加したってわけじゃないんだから。それに「プロジェクトX」は、成功者のみを取り上げることで、日本企業が体質的に抱えている問題から意図的に目をそらそうとしているように見える。あれを見て泣いちゃう人の単純なメンタリティは不気味である。Webサイトを見ると、彼のラジオ番組はおたく系の人々に絶大な人気があるみたいだけど、無茶な企画をやってはじけているようでいて、保守的でマイホーム志向なところで丸く収まっていることに安心感をおぼえたりしているんだろうか。こちらはその丸く収まり具合にやけに居心地の悪さをおぼえる。 先日、喫茶店でカウンター席に座ったら、隣のふたり組みが見るからにヤクザだった。ふたりとも40代半ば、サロン焼け、金髪、ぶっとい金のネックレス。片方は金髪を短く刈り込んでいて巨漢、服は黒ずくめ。もうひとりは肩までのロング、シャツのボタン4つあけて紫がかった紺のスーツ。当然、彼らがどんな会話をしているのか気になるので、本を読むふりをしてそれとなく耳を傾ける。 「なあおい、豆乳ってカラダに良いんだって」 「らしいな、でも砂糖が入って甘いのはダメだ」 「ああ、甘いの飲むくらいなら豆腐か納豆でも食った方が絶対良いって」 「俺よ、一日一回は納豆食うようにしてるぜ」 「ああ、納豆は良いよな、ありゃ完全栄養食だってよ」 「納豆食ってりゃ肉食わなくても十分だって聞いたぜ」 なんだか老人介護のヘルパーさんみたいな会話。ヤクザの地味な食生活を垣間見た気分である。「俺よ、一日一回は納豆食うようにしてるぜ」ってあたりで思わずコーヒーを吹き出しそうになる。あぶないあぶない。ヤクザもヘルシー指向の時代なんだろうか。豆乳と納豆で、今日も元気にヤミ金の取り立てをしちゃうのである。 ■ A piece of moment 9/28 バイク、車検の日。もちろんユーザー車検。半年かけてぼろバイクの修理と整備をくり返してきたわけで、いまさら車検ごとき恐れるに足りずなのである。ここまできて誰かにまかせるなんて考えられないのである。ちょろいのである。どこからでもかかってこいなのである。エンジンオイルが漏れてるけどさ。ただ、バイクの車検を通すのは学生の頃以来16年ぶりなので、「オートバイのユーザー車検」の本を古本屋で買ってきて、あらかじめ予習する。ずいぶん制度が簡素化されたみたいで、車検費用も安くなっている様子。前は税金と自賠責だけで6万円くらいかかって個人的に経済破綻をきたしたけど、今回は3万弱でいけそう。ハーレーダビッドソンあたりが大型バイクを日本で売りやすくするために外圧をかけた成果なんだろうか。ともかく、立川の車検場の予約を取り、自賠責を更新し、ワックスをかけて磨き上げ、今日の日がやってきたわけである。朝9時出発、15分に車検場到着。30分かけて書類を作成、いよいよ検査。書類を書きながら、車検場まで独立法人化されていたことに気づき、妙な感慨に浸る。「はい、ヘッドライトを上下切り替えてください、次、ウィンカー、ブレーキランプ、前ブレーキだけ握ってください、次、リアブレーキのフットペダル……」、車検場の茶髪の兄ちゃんに言われるままに動かす。兄ちゃんが茶髪でロンゲでひげ面なのも独立法人化による規制緩和なんだろうか。ともかく、ライトはヘッドライトからテールライトまで全部新品に取り替えているので、文句なんて言わせないのである。「じゃあ、前に進んで掲示板の表示に従って操作してください、あ、となりに立って説明しましょうか」「あ、お願いします、車検16年ぶりなもんで」「はいはいはい」。茶髪の兄ちゃん結構いい奴。前輪をフリーにしてローラーに載せ、40km/hのメーター検査。そのまま前ブレーキの利きのテスト、ローラーを後輪にずらして後ブレーキのテスト。さらに前に出て、ヘッドライトの光軸・光量の検査。「はい、おしまいです」というわけであっけなく1発で通る。所要時間15分。同じバイクのオーナーたちの車検体験談によると、製造から20年経ったバイクなので配線の劣化から、ヘッドライトの光量不足で落とされることが多いとのことだったけど、とくに問題もなかった模様。そもそもヘッドライトが暗いのは気にくわないから、ヤフオクで買った中古のリレーとマルチリフレクターを半年前に組み込んでおいたので、それなりに明るいのである。というわけで、書類手続きを済ませ、新しい車検証と国土交通省マークのついた新しいシールをもらって帰宅。正味1時間かからなかった。というわけで今回はなんだかボクちゃん大活躍とでも言いたげな嫌味な近況報告になってしまって申し訳ないです。予想外のトラブルでアタマを抱えてる自分を思い描いていたんだけど。ともかく、これでまたこの先の2年間、合法的に乗り回すことができるわけである。 ・自賠責保険 2万円弱 ・書類 30円 ・予約申し込みの電話代 50円 ・重量税印紙 5000円 ・検査登録印紙 1400円 ・ユーザー車検の本 500円 しめて約2万7千円也。 FAQを加筆しました。へんなところから反響がありました。 → FAQ ■ A piece of moment 9/29 81番目の疑問の泡を追加。 → 「合コン」 ■ A piece of moment 9/30 勤務先の高校では、植え込みの秋の花が満開。たくさんの虫たちが花の蜜を求めて集まり、飛び交っている。タテハチョウ、アオスジアゲハ、クマバチ、ミツバチ、ハナアブ、都心といってもこの辺は庭木の種類も多いし、広い公園もあるので、かえって郊外の住宅地よりも虫の種類は豊富だ。その中になぜかひときわ大きいスズメバチが混ざっている。オオスズメバチである。スズメバチも花に集まるんだっけ肉食専門じゃなかったっけと不思議に思っていたら、オオスズメバチは花の周囲を旋回し、やおら空中でハナアブを羽交い締めに抱え込んで器用に麻酔処理をし、そのまま巣に連れ帰っていった。花粉をなめつつ花に集まる虫を狙っていたのであった。一石二鳥。こんな都市部でもオオスズメバチの巣があるんだと感心する。スペクタクルシーンを生で見て得した気分。 授業では、今年も在日外国人の参政権問題を取り上げる。昨年つくった資料を少し手直しして使うことにする。資料の会話文には、次の文章をつけくわえた。 「民族主義によって社会をまとめようとするやり方は、「同じ」であることを社会の求心力にするわけだから、そういう社会では、マイノリティや立場の異なる人を差別・排除しようとする傾向が強まる危険をはらんでいるよ。この同質性を指向する社会傾向が、日本ではアイヌの人々や在日朝鮮の人々への差別につながっていったわけでしょ。確かにナショナリズムは自分たちは同じだという意識によって強い団結力を生みだすから、19世紀の帝国主義の時代には外国の侵略に対抗するという意味で効果があった。でも、現在は国際情勢も大きく変わったわけだよね。もはやナショナリズムという同質性で社会をまとめようとする発想自体が現代の社会にそぐわないと思うよ。」この10年間、ナショナリズムの問題について自分なりに考えた結論である。 ■ A piece of moment 10/3 今年度は授業のレポートをまめに文集にまとめている。いままでやったテーマは、「クローンと遺伝子組み換え」「脳死」「原発の是非」「靖国問題」「カースト制」で、それぞれA4で12枚程度の文集をつくってまとめた。手書き原稿を入力しているとこちらが死んでしまうので、生徒にはなるべくメールで提出してもらっている。本当はインターネット上の掲示板に提出といきたいところだけど、インターネットに接続できない環境の生徒もいるし、ほとんどキーボードで文章を入力できない生徒もいるみたいなので、「できればメールで、もちろん手書きでもOK」というスタイルを今年度から採用している。メールと手書きの比率はほぼ半々、やや手書き優勢という感じ。なかには800字指定のレポートをケータイメールで送ってくる強者もいたりする。で、メール提出ぶんのレポートを省エネ運営で文集にまとめ、生徒たちと一部学校関係者に配布している。本当はこのWebサイトにも載せたいところだけど、個人情報の問題もあるし、現在進行形でおこなっている授業でもあるので、学校内のみの配布ということにしている。そんなわけで、このWebサイトはもともと生徒のレポート集を載せるためにはじめたものだけど、最近ではすっかり資料のみの公開になってしまっている。そろそろこのWebサイトの存在意義を問いなおす時期に来ているように思う。今夜は、「カースト制」のレポート集を作成したせいか、アタマの中でゴダイゴの「ガンダーラ」が鳴っている。 ■ A piece of moment 10/9 以前、中学校で教えていた頃に受けもった生徒と町で出くわす。もう大学も卒業して、いまはドイツ留学のために準備中だという。若者はどんどん育ってこちらの成長のなさを突きつけてくる。喫茶店で2時間以上もだべる。大学のこと、就職した友達のこと、家族のこと、留学のこと、国籍のこと、将来のこと。彼女の頭の回転の速さと生きる力にあふれている様子に圧倒される。いい女になっていた。それはこちらにこの8年で少しは賢くなったのかと問いかけてくるようだった。どうしたらあんなに屈託なく自分と自分を取り巻くものについて話せるんだろう。こっちのほうがいまだに自分を持てあまし気味で、まるで出来の悪い弟になった気分だった。すまん、ねえさん、おれ、まだバイク乗りまわしてるよ、なんて。 放ったらかしにしていたリンクを修正。 → 検索とリンク ■ A piece of moment 10/11 500年ぶりに六本木へ行く。六本木ヒルズは子供を押しつぶす回転ドアのあるただのビルなのかと思っていたら、中層のビルが複雑に組みあわされた巨大な立体区画になっていた。うーむここが三木谷やホリエモンのいる六本木ヒルズかあ、たのもう一手お手合わせ願いたい、拙者、生国は武蔵の国、一刀流を少々、どこからでもかかってきなさい。あ、待った、その前にトイレ、でも、ここはきっとトイレの注意書きにも「FAQ」なんて書いてあったりするのかな、ちょっと嫌かも、そういや公衆電話が1台もねえでやんの、とまるっきりのおのぼりさん状態で、うろうろしてるうちに迷子になる。くねくねと曲がった通路、なぜか地下1階から1階、2階を飛ばして屋上へ行くエスカレーター、いちいち階上の広場を通らないと移動できない各セクション、この奇妙な立体構造は何かに似ていると思いながらうろうろしてると、突然思い出した。シロアリの蟻塚である。中心部に巨大なタワーがあって、中層の建築物がそれを取り巻き、内部の温度と湿度を一定に保つため換気ダクトをかねた吹き抜け空間が随所に設けられ、地下にすべてがつながった巨大フロアーがあるという構造は、アフリカやオーストラリアに生息するシロアリの蟻塚にそっくりである。きっと最下層部ではキノコの培養をおこなっているにちがいない。迷いに迷った末に、3Fから階上の広場に出ようとエレベーターに乗り込むが、ドアが開いた先はなぜかいきなりコカコーラのオフィスになっていて、スーツを着込んだ働きアリさんたちがケータイをいじりながらこちらを見てへんな顔をしていた。なんじゃこりゃ。 六本木ヒルズ (写真は「武蔵野学院大学やきもの美術館」より)  ■ A piece of moment 10/13 試験問題作成中。もう徹夜はしたくないので、早めに取りかかってます。「疑問の泡」に新たな謎を追加。自己紹介なんだかどうかよくわからないページの文章と写真を修整・変更。試験問題を作成しはじめると、なぜかやたらとWebの文章の筆が進みます。 → バーチャルアイドル IM-2005号 → slices of time ■ A piece of moment 10/14 朝、目ざめると腰が痛くて立ち上がれない。寝てる間に何があったんだろう。授業を終えて夕方になっても痛みがおさまらないので、近所の整形外科に通院することにする。整形外科の待合室で去年教えた生徒とばったり会う。最近こういうの多いな。人混みの中で「あれぇムラタセンセー」って、なんかテレます。ペンギンのようによたよた歩いて帰宅。 動画再生のできるipodが発売開始。これを待っていたんだよ。このために授業の資料映像をデジタル化してきたんだよ。やっとビデオテープの山から解放される日が来るのである。もう出勤時間を気にしながらその日の授業で使うビデオテープが見つからなくてパニックなんてことともオサラバである。と思ったら、MPEG2形式の動画再生には対応していない様子。対応フォーマットはMPEG4とAVC(H.264)という独自形式のみ。なんじゃそりゃ。意味ないじゃん。MPEG4だってフォーマットが固まってるとはいえない状態だし、なんでこんな中途半端なことするんだろう。パソコンにテレビチューナーカードを入れてデジタル録画している人のほとんどがMPEG2のフォーマットだし、もちろん我が家の動画データもすべてMPEG2である。MPEG2に対応してないポータブルの動画プレイヤーなんて、何を再生するっていうんだろう。そもそも音楽データの再生機器として、ipodが日本製デジタルプレイヤーを蹴散らして国際市場の75%を独占できたのは、MP3というコピープロテクトのない共通フォーマットに対応していたからのはずだ。動画データへの対応になって独自形式のみ対応なんて、マーケットシェアを確保して保身に走ったとしか思えない。それとも小型ハードディスクの場合、技術的にMPEG2の再生に問題があるんだろうか。ともかくMPEG2対応の動画プレイヤーが発売されるまでは絶対に買わない。ipod用に400時間分の動画データーをわざわざMPEG4に再変換するくらいなら、ビデオテープで十分である。 → 動画再生できる「iPod」発売へ 米アップル 朝日新聞 2005年10月13日10時59分 → Apple、QVGA液晶搭載MPEG-4/H.264対応の新「iPod」 AV watch 2005年10月13日 ■ A piece of moment 10/15 朝の整形外科はジジババで満員。やたらと待たされる。年取るとたいていどこかここか痛いもんだからまあ仕方ないのかな。整形外科でリハビリを受ける場合は、午後のほうが空いているようです。腰も痛いし、コンピュータに向かうのがしんどいので、試験問題作成は後回しにして寝ることにする。撮りだめた「おじゃる丸」でも見よう。 ■ A piece of moment 10/17 10年ほど前から背中に小指の先くらいのできものができた。脂肪のかたまりのようで、固くしこっている。それが先々週あたりからぶよぶよと柔らかい感触になってきた。気になるので、指先で強く押すと脂肪のかたまりが指先についた。ちょうどチューブ入りワサビのような感じで、小さなつぶつぶがゲル状に固まっている。10年も背中にとどまっていたせいなのか、脂肪は酸化しまだら状に茶色く変色して、古くなったサラダ油のようなすえた臭いがする。ここぞとばかり力を入れて、できものの中身をすべてひねり出す。脂肪はにゅるにゅるにゅると大量に出てきて、人差し指と親指の間にべったりと付着する。指先で丸めてみたり、臭いを嗅いでみたりする。紙になすりつけ、ムラタの背アブラと命名する。試験問題を作成していると、ふだん思いつかないことに情熱をそそいだりするのである。ちなみに夏目漱石は、原稿が行き詰まると鼻毛をむしる癖があったそうで、漱石の書生をしていた内田百閒によると、鼻毛の毛根部分を原稿用紙に張りつけ、ぶちぶちと抜いた鼻毛を何列にも原稿用紙に植毛していたとのこと。ほんまかいな。 ■ A piece of moment 10/20 試験日までまだ1週間もあるというのに、めずらしく試験問題が作り終わる。やりはじめると一気に仕上げたくなって、締め切りが迫っているわけでもないのにけっきょく今回も徹夜。アホじゃ。来週は楽したいところだけど、500字指定の論述問題を出題したので、採点で泣きそうな気がする。腰痛激化。只今、低周波治療器の購入を検討中。6000円も出せばちゃんとしたのが買えるらしい。 → ヨドバシ・ドット・コム ■ A piece of moment 10/24 職場で歴史のセンセーとパレスチナ問題について話す。昨年死去したアラファト議長がムスリムではなくクリスチャンだったと指摘される。知らなかった。奥さんがアメリカ人でやたらと若くて金髪なのは気になっていたけど。何億ドルともいわれた彼の隠し資産はいまどこにって話でもりあがる。 バイクを飛ばしながらふとアタマの中に「お言葉少女」という言葉がちらつく。あまりの脈略のなさに自分に戸惑う。「ごめんあそばせ」「ご機嫌よろしゅう」って、なんだったのアレなんてぼんやり思っていたらブレーキのタイミングが遅れて冷や汗をかく。へんな宗教団体の教祖にまつられた女の子が予言めいた「お言葉」を発することで話題になったのかと思っていたんだけど、どうもそれはまた別の女の子のことでワイドショーネタが自分の中でごっちゃになっていたようだ。気になるので帰宅して調べたところ、マルシア語もしくは真珠夫人用語みたいな不思議な言語を話す「お上品な」小学生の女の子がいるってことが地元広島で話題になり、その後、ワイドショーにも取材されて全国的に知られるようになったというだけのことらしい。実家は裕福な神社、現在はなぜかミッション系の金持ち女子大に通学中とのこと。たんに丁寧に話すよう教育されたというのではなく、社会階層を「古き良き時代」に回帰させようという周囲の政治的意図を感じる。不愉快なり。教祖にまつられた女の子のほうのその後が気になる。腰痛は少しおさまってきた。 ■ A piece of moment 10/25 ひと月半ぶりにバイクのタイヤに空気を入れる。空気圧指定は前2.5、後2.9。それぞれコンマ5ほど抜けていた。以前乗っていたオフロードバイクと違ってチューブレスタイヤなので空気が抜けやすいようだ。涼しくなるこの時期、タイヤの空気圧は2週間おきに入れる必要がありそう。ボロバイクは手間がかかる。近所のガソリンスタンドにある空気入れはエアゲージがいいかげんなので、東八道路沿いにあるバイク用品店の空気入れを利用することにしている。精密なエアゲージつきのエアコンプレッサーが二輪駐車場に備え付けてあって、無料で使えるようになっている。すごく良心的。いつも空気入れだけ使わせてもらってなんだか悪いので、たまには何か買って帰ろうと思うんだけど、整備もひと段落ついて最近はとくに買うものもない。いつもスイマセンって感じです。店はこちら。 → ナップス三鷹東八店 中間試験で授業もないので、バイクの整備をする。雨の日も乗るので、下まわりが泥まみれ。 ■ A piece of moment 10/26 消極的千葉ロッテファンを10年やってきましたが、日本一になる日がくるなんて思ってもいませんでした。川崎にホームグラウンドがあった頃、秋口にはとっくに優勝戦線から脱落して、がらがらのスタンドでは、客がコタツを持ち込んで麻雀やってたり、ひげ面の面々がモツ鍋つつきながら一升瓶抱きかかえて宴たけなわだったり、ホームレスのおじさんみたいに寝袋にくるまって寝ながら観戦してたりとやる気のなーい雰囲気が常に漂っていて、いつかは自分もあの無気力パフォーマンス集団の一員になろうと夢を抱いていたのである。千葉に移ってファンの雰囲気はすっかり変わったみたいだけど、私はあいかわらず消極的ファンなので、テレビ中継をみながらグーグーと寝てしまい、日本一決定のシーンを見逃してしまう。目が覚めたらビールかけやってやがんの。リーグ優勝の時もそうだったので、ビールかけを見ながらとうとうフラッシュバックが来たのかと思った。というわけで、日本一を記念して疑問のページの「バレエダンサー」にボビーさんについて追記する。きっと年末には2005年の顔としてボビー羽子板も登場するんだろう。 → 「バレエダンサー」 ■ A piece of moment 10/27 となりの部屋の住人が電話に向かって叫んでいる。「マジぃ?マジマジマジマーーージぃマジかよーマジ、マジマジマジマジマジマジマジマージぃ……」。まだまだ続くがまあこのへんで。彼の言う「マジ」には微妙にアクセントやイントネーションの異なる用法があって、語尾が上がる場合は疑問形、語尾が強まる場合は驚きの表現としての感嘆詞、さらに連呼する場合は驚きの強調となる。したがって上記の会話は疑問を抱きつつ驚き大いに感嘆している状態を表現している。電話の内容は、緑色の宇宙人にレイプされたという彼女からのものか、友人が蠅男に変身しているという田舎の同級生からのものであることが推測できるわけである。この興味深い言語を自在に操る住人は学芸大で体育を専攻しているという地方から出てきた青年。運動部の練習で真っ黒に日焼けしておつむもちょっと弱そうだし、学芸大体育科はギャル系だったらしい。この出来事は約7年ほど前のことである。きっと今頃はどこかの中学校だか高校だかで生徒たち相手に「マージぃー」を連発しているんだろう。べつにいいけど。ともかく彼の存在によって、私は「マジ」を多用した会話術を学んだ。その後、「マジ、ヤバイっす、村田さん」なんて言う30男にも出会ったりして、「マジ」の普及率が上昇していることを感じている。しかし残念ながらまだ自分で試したことはない。マジ恥ずかしいもんで。 話かわって、NEET。「ニート」と発音する。なんのことかと思えば、「プー太郎」または「すねかじり」「ゴンたくれ」のことらしい。べつにプー太郎って言ってりゃあいいじゃんか、なんでわざわざこんな無機的な用語を当てるんだろうと思ったら、どうも意図的に個人的視点を排して「社会問題」としての視点からのみとらえようとする政治的背景があるようだ。この言葉、もともとはイギリスの社会学者が働かない若者を総称してつけた名称で、学際用語なので、そこには「社会現象」というマスの視点しかない。若者個人の内面性や生き方の問題という個人的視野はすっぽりと抜け落ち、「社会問題」というマスの視点でのみ働かない若者をとらえようとする。厚生労働省がこの言葉を導入し、NHKはじめマスメディアがさかんに用いるようになった背景には、若者を労働資源としか見なしていない政治的意図を感じる。マスの視点からのみ人間の生き方をとらえようとするので、そこに社会生産性からみて邪魔者という批判的眼差しを付与しやすい。「ニートが増えたら私たちの年金はどうなる」というわけだ。窮屈な日本社会らしいといえばらしいんだけど、NHKが番組をあげて「アナタの子供がニートになったらどうしますか!?お困りご近所の悩み解決!」なんてアピールしてる様子をみると、まるで戦前の隣組を復活させようとしているかのようで不気味である。この構図は1980年代はじめのモラトリアム批判にそっくりである。「モラトリアム」は青年期の長期化を指摘するためにアメリカの心理学者が使い始めた言葉だが、日本に輸入した慶応大の小此木敬吾によって、最近のふぬけた若い連中は「大人」になる自覚に欠けてけしからんという保守的な政治意図が付与され、やはり「社会問題」とされた。でも、社会体制の維持に参加することこそ正しいとする発想は、社会になんら問題がない場合にのみ成立する。現代社会が様々な矛盾を抱えていることは明らかだし、若者がそうした矛盾に疑問を発するのはそれなりに意義がある。盲目的に現状に乗っかっているよりはずっと良い。で、やがてモラトリアム批判はすたれて、今度はニートというわけだ。芸のなさに笑っちゃいます。 ■ A piece of moment 10/28 このところ急に冷え込んできたので、扇風機の埃を落とし仕舞う。代わりに押入からファンヒーターを出そうかとも思ったけど、まだ、早いかなと今回は見合わせる。おとつい、明治通りで半袖短パンのおじさんがバイクで爆走しているのを見かける。罰ゲームだろうか。 講談社現代新書から先月出たばかりの「人類進化の700万年」を読む。この分野、新たな人類化石が発見されるたびに定説が塗り替えられるので、研究は日進月歩というか朝三暮四というか、いままでの定説がどんどん古くなるので、最新の研究事情が知りたかったのである。まるでそんな私のために書かれたかのような一冊。よく歴史教科書の冒頭に載っている「アウストラロピテクス」→「ハビリス原人」→「ネアンデルタール人」→「ホモ・サピエンス」という一本道の人類進化の図式は、もう30年以上前に否定されていてるのに、いまだに教科書が改められないのは怠慢な気がする。人類進化はもっと細かく分岐していて、現代人につながらない道を歩んだ絶滅人類が10~20種いることがわかっている。本書ではそのへんの研究成果がほぼ網羅されていて、すっきりとわかりやすい文章で解説されている。著者は読売新聞で科学欄を担当している若い記者。研究者自身が書いたものと異なり、仮説は仮説と一歩引いた視点で最新学説を紹介しているので、各研究者によって異なる見解を比較しながら現在の研究状況を俯瞰するように見ることができる。ずいぶんもめていたホモ・サピエンス進化の単系説と多系説の対立もようやくアフリカ単系説で決着がついたようだ。欧米の研究者が1980年代末にはアフリカ単系説でほぼ一致していたのに対して、日本ではつい最近まで国立科学博物館を中心に世界各地の原人がホモ・サピエンスに進化したとする多系説を主張していて、これもその後どうなったのかとずっと気になっていた。国立科学博物館で7年くらい前にひらかれた「ジャワ原人展」では、「ジャワ原人はアジア人の祖先」なんてキャッチコピーまでつけていたけど、遺伝子解析の結果がいずれも、世界各地の現代人の遺伝子が20万年前のアフリカにいた祖先に由来するのを示していることに加えて、2003年にはアジアの原人化石がホモ・サピエンスの系統につながらない証拠も出てきて、ようやく多系説の敗北を認めた様子。読み終わってすっきり気分。ぜひ、5年ごとに改訂版を出してくれるよう希望する。 ■ A piece of moment 10/30 押入の奥の方にあったCDを引っ張り出して、片っ端からituneに入れていく。サイモン・ラトルが指揮したシベリウスの交響曲全集があったり、ピエール・ブーレーズによるウェーベルンの全曲集があったり、カール・ベームが1970年代に録音したブラームスの交響曲3枚組みがあったりと、けっこう値のはるセットがあれこれ出てくる。おもに15年くらい前に集めたものだけど、なんでこんなに金があったのか不思議である。ブルックナーの第8交響曲やバルトークのピアノ協奏曲は3枚も4枚も出てくる。重たい曲ばっかり。シェーンベルクの「清められた夜」はアレンジ違いで3種類あって、カラヤンがベルリンフィルを指揮したフルオーケストラ版は重厚でやけに深刻だし、オルフェウス室内楽団による室内楽版はシャープできらきらした感じで、ラサール・カルテットによる弦楽4重奏版は枯れてて思索的と編成の規模や演奏スタイルで雰囲気が違っていたりする。こういう聞き比べみたいな集中力を必要とする聴き方はもうすることはないだろう。ベーム指揮のブラームス第1交響曲も録音年代別に3枚あって、ベームが歳をとるにしたがって演奏がスローテンポになっていく様子がなんだか可笑しい。3日がかりで100枚ちょっとituneに登録する。 ■ A piece of moment 10/31 昨夜、授業のプリントをつくろうと思いたつが、うまくまとまらずに徹夜する。寝不足でくらくらしながら授業4連発。アドリブが効かず、けっきょくただプリントを解説するだけの授業をする。生徒諸君、申し訳ない。 ホリエモンのTシャツは2万円のプラダだそうで、ユニクロの500円セールかと思ってた。高いほうが恥ずかしい場合だってあるのだ。ちなみに「現代用語の基礎知識」によると、「エグゼTシャツ」と呼ばれてるって、いったいどこの誰がそんな言葉つかってるの、出てきて俺の前で言ってみろ声が小さいっもう一回って感じである。寝る。 夜中、目が覚めて、組閣のニュースを見る。猪口邦子のドレスにずっこける。ドレスというより衣装である。熟女メイドカフェ。そっちの趣味の人なんだろうか。クマさんのぬいぐるみでも抱いて出てくればいいのに。サプライズである。 ■ A piece of moment 11/5 深夜、バイクを飛ばしていると、ラジオのイヤホンからアストル・ピアソラのタンゴが流れてくる。バンドネオンの湿った響きとモダンジャズみたいに前へ前へ進んでいくドライブ感。クルマのほとんどない青梅街道は時間が止まったみたいだった。そういえば、映画「12モンキーズ」の音楽も全編ピアソラ。あの映画でのピアソラの曲は、不安を駆りたてるような響きで、奇妙な登場人物たちと不条理なストーリーを音楽が際だたせていた。 映画「サハラに舞う羽根」を観る。舞台は19世紀、アフリカ・スーダンの植民地戦争に送り込まれたイギリス軍の若い士官たちの友情物語なんだけど、植民地支配にまったく悪びれることなく大英帝国の栄光をたたえる上流階級の若者たちのメンタリティにまったく感情移入できない。彼らが友人の戦死に涙し、再会に肩を抱き合い、恋愛の三角関係に苦悩していても、いい気なもんだと白けるばかり。むしろ次々と射殺されていく現地スーダンの反乱軍兵士たちの方に目がいくが、彼らは残忍で理解不能の「蛮族」として描かれるばかりで、内面描写はまったくない。こんな映画が作られるなんて、現代のイギリス人に植民地支配への後ろめたさはないんだろうか。この居心地の悪さは、「アラビアのロレンス」の脳天気な英雄賛美に感じた不快感によく似ている。BBCのニュースを見ていると時々、「ヨーロッパの植民地支配でアフリカに近代文明がもたらされたのです」なんて論調で報道しているものがあるけど、アタマの中身はいまだに19世紀なんだろうか。現代アフリカの混乱がまるでヨーロッパ諸国がアフリカから手を引いたからみたいな言いぐさだけど、多くの場合、内戦の原因は植民地時代の統治に利用された部族対立に行きつく。西欧近代文明を尺度にして人間の暮らしを序列化する発想は、いまだに欧米では根強いように見える。1950年代、レヴィ=ストロースをはじめとした文化人類学者たちが西洋中心主義批判をくり返したが、多文化主義が大衆文化に定着しているとはいえない。5年ほど前、アフリカ諸国が植民地時代に行われた搾取と弾圧について、旧宗主国であるヨーロッパ各国に謝罪と損害賠償を求める決議をしたが、ヨーロッパ諸国は黙殺した。その理由として、あまりにも規模が大きいために、頭を下げ責任を認めたら賠償額が天文学的になるからではないかと言われていたが、もしかしたら半分くらいは本気で植民地支配はアフリカを文明社会にするために行った「援助行為」だと認識しているのかもしれない。野蛮人と見下していたくせに。この映画、監督・脚本がインド出身の人。これまた不思議。 風邪をこじらせて熱を出す。最近の風邪薬が効くのを実感する。飲んで小1時間もすると、のどの痛みと発熱がすっとおさまってくる。効きすぎて少しこわい。 ■ A piece of moment 11/9 風邪が治らず寝てすごす。熱のため手足の関節がしびれる。ちょうど電動歯ブラシのように細かく振動している感じで、くすぐったい。あまりのくすぐったさにニヤニヤしながらのたうち回る。電話が鳴る。「もしもし……」、自分の声が電子音のように聞こえる。こりゃいかんわ。寝る。 スーパーのレジで、前のおばさんが小銭をじゃらじゃらさせながら、89円あるわいちにぃさんしぃと1円玉を数えるのをいらいらしながら待つ。1円玉9枚と10円玉8枚を出した後、おばさん今度はスタンプカードあるわと財布をひっくり返しはじめる。おいおい。近所のスーパーやドラッグストアでは、なぜかスタンプカードが大流行。おばさんたちはこういうちまちましたものを貯めるのが大好きみたいで、ヤンママからヨボヨボまでならんでいる誰もがスタンプカードを持っている。殺意が込み上げてくる。1389円の買い物して10円分だか20円分だかポイントを貯めて何がうれしいんだ。ヨドバシカメラやヤマダ電機のように何万円もする買い物をする店ならまだポイントシステムも理解できるが、ネギとダイコンと牛乳とリップクリームを買ってスタンプスタンプあらこれはドラッグサンのカードでこっちはいなげやってああもうそのみみっちさに目眩がしてくる。おばさん、自己嫌悪に陥りませんか。スタンプカードで豚みたいにふくらんだ財布を見て人間やってるのが嫌になったりしないの。レジの行列にたたずみながらショットガンを乱射する妄想に浸る。割高でもかまわないからスタンプカードのない店で買い物がしたい。 ■ A piece of moment 11/14 なすびかじゃがいもみたいな形をした下図の動物はカピバラである。齧歯類でネズミの仲間。写真だとただの丸っこいネズミに見えるが、実物は50kgくらいある。大きいのである。南米の湖沼の多い草原地帯に生息し、足には水かきがあり器用に泳ぐ。草食。水辺に暮らす生態はカバに似ている。短い足でもこもこと歩く。カピバラのような大型の齧歯類は妙に収まりが悪い感じがする。ようするに見れば見るほどなんか変なのである。その違和感が気になって落ち着かなくなる。体重50kgもある巨大なネズミがゆっくりした動作で草をはんでいる様子は現実感に欠けているのである。ハンナ&バーベラの「チキチキマシン」に登場した毛むくじゃらの原始人に似ているような気もする。小さくてつぶらな目、昼寝中のハムスターのような温和そうな表情、丸い胴体、短い足、見ているとしだいに思考力が停止して笑いが込み上げてくる。なんかもうどうでもいいやという気分になる。深夜、翌日の授業の準備をしながらカピバラの姿が思い浮かぶ。もこもこと歩いている。カピバラが1匹、カピバラが2匹、カピバラが……。いいやもう寝ちゃおう。カピバラが出てくるようじゃもうお仕舞い。カピバラとコミュニケーションはとれるんだろうか。牧場の牛のように親しい相手には「グゥー」とか「ボェー」とか鳴くんだろうか。もちろんカピバラと親しい関係をつくりたいわけではなく、ときおり不機嫌で投げやりな声を発しながらもこもこと動いている様子を見たいだけである。羊は目つきが意地悪そうでこちらを値踏みしているようなこすっからい印象を受けるが、カピバラの顔はどこか諦観したような感じがする。長崎にある動物園ではカピバラが放し飼いになっていて、さわることもできるという。きっと人間になど興味ないという調子でもこもこ歩いているんだろう。ちょっとさわってみたい。毛はたわし状の剛毛だそうだ。  ビーバーも齧歯類。正面から見るとネズミの顔をしている。体重は約30kg。かなり大きい。体重だけでくらべるとジャーマンシェパードくらいある。ネズミの顔をした大型動物というのは、やっぱりなんか収まりが悪くて妙な違和感を感じる。手足が短く、信楽焼のタヌキのようなずんぐりした体型。水中で尾びれの役割をするシッポはシャモジの形をしている。水中では活発に泳ぐが、陸に上がるとやけにどんくさい。ビーバーエアコンのビーバーはスマートでくりくりした目の利発そうなキャラクターとして描かれているが、実際のビーバーは見るからに臆病そうで不機嫌な顔をしている。カピバラほどケセラセラな感じはしない。むしろ臆病さに突き動かされるように、せっせと立木を囓り倒し、巨大なビーバーダムをつくりあげる。丸太や小枝を泥で塗り固めて堤防を築いて、小川をせき止める。水位は微妙に調整されている。ビーバーもカピバラと同じく草食なので、つくったダムを魚の生け簀にしているわけではない。ダムは捕食者から逃れるための要塞で、中心に築かれた浮島がビーバーの巣になっている。巣の入り口は下部の水中に開いており、上部は出入り口のないドーム状をしている。堀に囲まれた臆病者の城という感じ。太ったネズミ顔の生き物が丸太をせっせと運ぶ姿は、世界への恐れに突き動かされているかのように見える。その情熱が世界を変容させる。巨大なダムは何世代にもわたって増築され、何段にも築かれる。それは建築物というよりも体の一部のようだ。歪な形にふくらみ、生き物のようにぬくもりをたたえている。内部は胎内のように自分の他者の境目がない世界が広がっているんじゃないかと想像する。子供の頃、廃材置き場につくった秘密基地を思い出す。ああビーバーになりたい。 → Wikipedia ネズミ目 → 羽村市動物公園 アメリカビーバー  カピバラ正面図。つぶらな目。50kgの巨体。性質温和。水かきもちゃんとあります。でもそこはかとなくネズミ。本当はすごくさわりたい。 ■ A piece of moment 11/16 大学受験はミスコンテストのようなものだと思っている。まあお好きな人はどうぞとそんな感じである。大学を受験するという人は、大学に行ってまで勉学にはげみたいという物好きな人なのだろうから、きっと誰それの講義を受講したいとか、何々講座のゼミに参加したいとか希望があるんだろう。少なくとも建て前としては。でも、べつにその大学の学生にならなくても、講義を受講したりゼミに参加するのはいくらでも可能だ。大学なんてニセ学生がまじっていてもわかるわけないのである。むしろニセ学生のほうがたいてい熱心に質問したりノートをとったりするので、彼らが多く入り込んでいる大学ほど講義やゼミに活気がある。時には自主ゼミの発起人がニセ学生だったなんてケースもあったりする。それに教える側から言うと、ただ卒業単位のためだけに嫌々出席してぜんぜん授業を聞いていない学生よりも、学生でもないのにわざわざ自分の講義を受講するためにやってくるニセ学生のほうがよっぽどかわいい奴に思える。もし「実はここの学生ではないんですが」とことわった上でゼミへの出席許可を求めたとしても、たいていの教師は苦笑いしながら受け入れてくれるはずだ。というわけで、大学の本質的役割を学問研究だと解釈した場合、どこの大学に入学するかはたいした問題ではない。希望する大学に合格したところで、学問的探求という点では、たんに気をつかわずに講義やゼミに出席できる程度の御利益しかない。なので、受験勉強はバカにならない程度にほどほどにやればいいんじゃないという感じである。教育者としては、「そんな無意味なことに時間を費やしてないで良い映画でも見なさい」と若者を諭すのが本筋なのかもしれないけど、それもまたよけいなお世話のような気もするので、まあお好きな人はどうぞというところに落ちつくわけである。 一方、現在の日本の大学は実質的に就職予備校になっている。学校の役割として、内容よりも学歴を重視する傾向は、日本に限らず、学校教育を国力増進と産業発展のための手段としてきたアジア各国に共通して見られる現象である。こうした社会において若者を勉学に向かわせる原動力は受験競争でしかない。学ぶことは目的ではなく、競争に勝ち抜いて上位階層の一員になるための手段である。学ぶことは自分の知的能力の向上のためという意識が確立しているヨーロッパの個人主義社会とは対照的である。とくに韓国は暗記中心の学習内容や高校が大学入試のための受験予備校になっているところまで日本そっくりであり、さらに日本以上に大卒と高卒とではっきりと社会階層が分離する。じつに嫌な社会である。したがって、大学はホワイトカラーとしての職を得るための窓口であり、卒業資格はホワイトカラー候補者になるための証明書といえる。こちらの点から大学を考えた場合、学問研究はほとんど意味をなさない。たとえ「キルケゴールとイングマール・ベルイマンの信仰における相似性」について、斬新な切り口で精緻な研究論文を書き上げたとしても、そんな学生、どこの企業も欲しがらないのである。研究者になるか評論家になるかでもしないと、才能を職業に生かす道はないだろう。同様に「冷戦後の核管理と流出問題」について、膨大なデータを読み解き、新たな国際関係の指針になるような研究論文を書き上げたとしても、やはり研究職か国連にでも就職しないかぎり仕事に結びつけるのは難しい。さらに言えば、夏目漱石の小説をすべて読破していることよりも、「夏目漱石」と漢字で書けることのほうが就職先でずっと高く評価されるのである。いくら「草枕」や「夢十夜」を愛読していても、とっさに「漱」の字が出てこなかったら、「坊っちゃん」を3ページしか読んでない係長に「キミ、教養ないね」としたり顔で添削されるはずである。もちろん企業側は、大学との文化的ズレを百も承知しているので、一部の技術系研究職を除いて、就職面接で学生に論文の研究テーマを尋ねたりしない。たとえば大手商社の場合、入社志望の学生に求めるのは次の三つである。 1.体育会サークルに所属し、体が丈夫でガッツがあること。 2.英会話が達者なこと。 3.入試の合格偏差値が高い大学であること。 いずれも学問研究とは無縁である。1と2は兵隊としての実用性。3は大学の入試問題を能力評価テストとして企業が信頼しているというわけではぜんぜんなくて、競争に勝ち抜いたという資質と学閥による人脈形成という点で重視しているだけである。センター試験に詰め将棋が出題されたところで、企業としてはいっこうにかまわないはずである。したがって、大学をホワイトカラー就職予備校としてとらえた場合、カリキュラムは全面的に改める必要がある。そもそも日本の企業に就職するのに帰国子女のほうが優遇されるという現状は、日本の大学制度が企業の求めているものと大きくズレていることを如実に表している。というわけで、新カリキュラムでは、午前中は全部英語、午後は全部第二外国語。どこかの私立高校みたいに体育会系サークルへの入部を必修として出席もとる。また、夜は積極的に合コンとパーティへ参加することを学生に奨励する。コミュニケーション能力とマネージメント能力の向上と人脈形成を促すためである。そして最終的には就職活動そのものが卒業研究となる。就職予備校なので当然である。就職が決まった時点で卒業資格を与え、3年生でも飛び級で卒業を認める。学内の競争を活性化させ、大手に就職した卒業生とのパイプを太くしていくことは大学の資産になるはずである。最近はやりの「勝ち組」育成であり、ビジネスマン養成所としてはきわめて合理的なカリキュラムではないかと思う。企業の新人研修で似たようなことをやっているところも多いのではないだろうか。これを4年間みっちりやれば、英語も中国語もぺらぺらで毎晩パーティの主役になれる24時間戦う優秀なビジネスマン候補生ができあがるというわけである。大学の本質を学問研究の場と考える物好きな人々は、こうしたやり方に眉をひそめるかもしれないが、大手企業に続々と人材を輩出し、卒業生の平均所得が日本の平均よりも70%も高いとなったら、入学希望者は殺到するはずである。キルケゴールより「ドラゴン桜」のほうが若者に人気があるようなので、すでに素地はできていると言えるだろう。考えようによっては、現在の大学がそうなっていないために、学生たちは授業をサボって自主的にこのカリキュラムを自らに課しているのだと見ることができる。ただ、これを「大学」と呼べるかどうかは微妙なところである。先の学問研究の場としての大学とはあきらかに水と油である。同じ敷地内にあったら、学生も教師も互いに険悪なムードになることは容易に想像がつく。両者をはっきり分け、どちらかが「大学」を名のるのをやめて、「学問所」もしくは「就職予備校」と名前を改めればきわめてすっきりするのだが、「大学」の方がなんだか学校として立派なような印象を与えるので、名称の取りあいでもめそうなのが唯一の気がかりである。 ■ A piece of moment 11/17 気ままな散策者にしてうちの同居者。忘れた頃に現れ、吸盤つきの大きな手でひょこひょこと壁をつたい下りてきては壁の隙間に消えていく。平たい体、背中は灰色ですべすべしている。最近、ちびヤモリも加わって二世帯。食料も豊富にあるようだ。大小ヤモリのアタマのサイズはほとんど同じで、ちびヤモリは体だけ小さい。3等身でマンガのキャラクターのよう。そろそろ今年も冬ごもりである。 ■ A piece of moment 11/18 先日の学校の話の続き。放課後、職場のオジサンたちと茶菓子をかじりながら、最近の大学の授業風景のひどさについてだべる。多くの大学で授業が成立しないほど学生の授業態度が悪くなっているという。1時間目は出席者名簿に記名した途端に寝てしまい、2時間目以降は携帯をいじっているかマンガを読んでいるかだべっているかで、学生の私語で授業にならないとのこと。まるでどこかで見たような風景。前に受けもった工業高校では、授業中に後のほうでサッカーボール蹴っ飛ばしてたぞ。「大学で学級崩壊だなんて世も末だねえ」とずるずるお茶を飲みながらオジサン。でもよく考えたら、学校に通う目的が学歴でしかない社会の場合、競争がゆるくなったらそうなるのは必然的といえる。少子化で誰でも大学に入れる時代になり、産業構造の変化でホワイトカラーのリストラが増加して学歴の「うまみ」もなくなりつつある中で、学生の意識もとりあえず大学に来ているという傾向が強まっているんだろう。そういう意味ではもはや高校生と一緒である。本質的な改善方法は、学ぶことは自分の知的能力を高めて視野を広げるためという意識を社会の中に定着させていく必要があるということになるんだけど、どう見てもいまの日本社会にこうした個人主義的価値観が定着する気配はない。結局、日本もアメリカみたいに貧富の格差が広がる状況で、「勝ち組」「負け組」で若い人たちを脅しつけながら、彼らに競争をたきつけることでしか、学ぶ原動力にならないように思える。なんて嫌な社会。さらには、アメリカの大学みたいに毎回大量の課題を出して、それをこなせない学生はどんどん留年させるようにしようという声も出てくるだろう。「とりあえず」大学にやってくる若者たちを相手に、もはや「大学は自分から学ぶところ」なんて悠長なことは言ってられないというところなのかもしれないけど、やはり本末転倒に見える。外的動機づけである「有利な就職」「課題」「競争」といったムチとニンジンがないと学ぶ気がしないというのは、根本的に勉学に向いていない人たちなんだから大学なんて行かなくていいのにという気もする。何かを学んだり考えたりすることの最大の利点は、それによって自分の思いこみや不合理な慣習から解放されることにある。「ああそうだったのか」といままでと違う視点で考えるようになる。そのときの胸のすくような快感こそが物事を考える原動力になり、その成果として得られたものは、日々の暮らしにおける自らの意識を変化させる。それは実務的なハウツーとは関係なくても、自らの意識そのものを変化させるため、日々の暮らしの中で広く影響をおよぼし、同時に広い意味で「実用的」である。ただ、そうした成果はあくまで自ら考えた末に得られるもので、制度化され体系化された知識を効率良くおぼえるという手法ではたどり着くことはできない。したがって逆にいうと、授業がテキストを効率良くおぼえることを主目的とする内容である限り、その学校のカリキュラムは卒業後の実務に直結する内容であるべきだ。だって何にもちいるもわからない知識をただおぼえさせられるなんてやってられないじゃない。ほとんどの若い人たちが就職のためのステップとして「とりあえず」進学しているのなら、半数くらいの大学を実務的なカリキュラムに特化した就職予備校に改変して、そちらを充実させた方が合理的である。ビジネス英会話とか表計算ソフトの使い方とか商法の基礎とか簿記とか宅建とか。なんだか商業高校の延長みたいだけど、けっしてそれらの実用的な知識や技能を見下しているわけではない。実務的ハウツーを「学問」や「教養」よりも低く見る傾向は、知識階層のエリート意識がつくりだしたこっけいな幻想にすぎない。それにしても、最近の大学の教師は学生を叱らないんだろうか。べらべら喋ってる学生を教室から叩き出したところで、大学ならべつに問題ないんじゃないの。 ■ A piece of moment 11/20 すっかり寒くなってきて、バイクの整備も億劫に。整備は億劫だけど、我がぼろバイクは常にオーバーヒート気味なので乗るぶんにはちょうど良い感じ。それなりに距離も走っているし、まあ仕方ないかと整備にとりかかる。キャリパーの分解は面倒だから、とりあえずクリーナーを吹き付けてブレーキダストを落とす。前後ともブレーキがキヨキヨと鳴いて不愉快だけど、効くことは効くので今回はまあいいや。汚れ落としとワックスがけが同時にできますという手抜きワックスで車体とホイールを磨く。手抜きなのであまりぴかぴかにはならない。小雨の日に走ったので下まわりがやけに汚い。バッテリーは弱り気味。この冬もたせるか悩むところ。新品に交換すると8000円の出費、うーむ。チェーンの掃除と注油は面倒だからサボる。アンダーカウルの分解清掃も面倒だからサボる。いちおうエンジンオイルのチェックはする。オイルはあいかわらずじわじわとミッション左側から漏れ続けていて、非常に気分が悪い。ずいぶん漏れてるはずなのに、なぜかオイルレベルは規定量入っている。よっぽど多めに入れていたらしい。オイル管理くらいはきちんとやりたいところである。三鷹のバイク用品店まで走ってタイヤに空気を入れる。前回、2週間おきにタイヤの空気圧はチェックするべきなんて偉そうなこと言ってたのに、やっぱり1ヶ月ぶり。前後ともコンマ4ほど抜けていた。東八道路を走っていると、ラジオのイヤホンから、RCサクセッションの「どかどかうるさいロックンロールバンド」が聞こえてくる。ひさしぶりに聞いたら歌詞がやけに格好いい。いつかカラオケで歌おう。帰宅してテレビをつけると東京女子マラソンをやっていた。高橋尚子復活優勝で、小出カントクがどんなコメントをするのか期待していたのにインタビューはなし。べろべろに酔っぱらってしょうもないことをぼやいてる姿をみなさん期待してるんじゃありませんか。どうよ。 ■ A piece of moment 11/24 疑問のページに→「うちの嫁さん」を追加。 ■ A piece of moment 11/26 このところ、別役実のエッセイをまとめて読んでいる。微妙に論理がずらされ、乾いた笑いがこみあげてくる。次第にものの考え方が別役調になってくる。さっき書いた文章を読み返したら、あきらかに影響されていてる。恥ずかしい。 →「うちの嫁さん」を加筆修正。 →「合コン」に追記。 ■ A piece of moment 11/28 授業で、小泉政権の民営化推進政策を検証する。「小さな政府」と「大きな政府」の長所短所を説明し、例によって、でどうすればいいのかと生徒に尋ねる。うーんどっちのほうが良いんでしょうかねえと生徒。いやいや聞き返さないでよ、それを考えるのが今回のみんなの課題なんだから。この問題、いずれにしても一長一短あるわけだから、最終的な判断材料は、みんなが将来どんな社会に暮らしたいかっていう好みの問題だよと説明する。生徒たち、ふーむという様子で、その中のひとりが「ではセンセーはどう考えるの」と聞いてくる。おっとっと。 「えーとそうだね、まず、公務員の数はこれ以上減らすべきじゃないと思うよ。人口あたりの公務員数では、日本は先進国中最低でヨーロッパ諸国の1/2から1/3程度しかいない。公務員数でいえば、日本はとっくに小さな政府になっているわけだし、これ以上減らしたら、行政サービスに支障をきたす危険性が高いよ。実際、JR西日本の尼崎線での大事故やマンションの耐震性の手抜きも利益最優先で安全面を軽視する傾向がもたらしたわけだから、なんでも民営化すれば良いってわけじゃない。逆に、公務員の既得権益は大きく減らすべきだと思う。この場合の既得権益は権限と給料。日本の場合、役所の裁量権が大きいから、企業は関係官庁にアタマが上がらないっていう構図があるよね。結果的に、公務員がパブリックサーバントっていう国民に奉仕する立場ではなく、まるで国や自治体の支配者のような意識を持ってしまう。これはアジア諸国の国家主導による開発独裁でよくあるケースだけど、民主制が十分機能していないという点では日本も変わらないよね。だから、裁量権をもっと限定したりオンブズマン制度を国も導入して業界との癒着をチェックしたり天下りを制限したりする必要がある。公務員の数を減らすより、こちらのほうがずっと優先課題じゃないかな。とくに財務省は権限が集中しているから、2つか3つに分割するべきなのに、小泉改革は郵政民営化ばかりで、財務省解体はぜんぜん言わなくなってしまったのは本末転倒だと思うよ。あと、給料、公務員の給料はだいたい半分くらいでいいんじゃない。退職金は1/5で十分だと思うよ。国や自治体の赤字財政を理由に社会保障を削ろうっていうなら、国民にツケをまわす前に、まず赤字財政にした張本人である公務員から責任をとらないとね。それができるまでは社会保障の削減には手をつけるべきじゃないよね。政府は赤字財政を理由にまず社会保障から削ろうとしているけど、順番は逆だよね。もともと産業構造の変化で日本社会の所得格差は開く傾向にあるわけだから、社会保障はむしろ充実させるべきで、それを削減するのは最後の手段にするべきだよ。まあ、公務員給与の減額っていっても、月給18万円の新人職員から減額するのはかわいそうだから、そのへんは累進的に高額所得者から減額するってことで」。しどろもどろで答える。お粗末。 公務員の給料を減らせというと、たいていの公務員が憮然とした顔をする。まあ当然といえば当然なんだけど、現職にとっては、公務員数の削減よりも給料の減額のほうが嫌らしい。いくら財政が逼迫していても、いったん手に入れたパイを人と分けあうのはまっぴらというわけだ。それにしても、区役所職員から公立高校の教員、国立大の教授まで、みんな同じ反応をする。何を言うかというと、かならず「銀行員は30代で年収2千万だしねえ」である。大笑いである。なぜ比較対象がよりによって銀行になるんだ。役所の業務が民間委託されて、どこの銀行が役所の下請けを引き受けますかってんだ。学校給食が民間委託された場合、民間の給食センターで働く人たちは月収12万円の低賃金パートである。彼らに退職金などまったくない。警備が民間委託された場合も似たり寄ったりである。だから逆にいえば、民間委託が「安上がり」になるのである。要するに民間の低賃金労働との格差が「民営化は財政の節約」という論理を支えているわけである。したがって、公務員の給与の比較対象は、こうした民間委託した場合の低賃金労働者であるのが論理的だし、公務員の給料を彼らと同程度にまで引き下げるべきである。むしろ、将来的な保障のない彼らのほうが公務員よりも高額の給与でなければ給与バランスがとれない。区役所の正規職員ひとりぶんのパイで、嘱託や臨時職員なら3人、民間委託の低賃金労働者なら4人雇えるというのは、どう考えても異常な状況である。以前勤めていた中学校で、職員室で給食を食べながらひとりの教師があっけらかんとこう言い出した。「給食は民間委託しちゃえば経費は1/5ですむのよねえ」。なんて無神経な奴。同じ職場で働く者の解雇を示唆するほど経費削減を気にかけているなら、まず自分が退職金返上で辞職してお前の授業を民間委託しろよ。自分だけ安全なところに身を置いて、立場の弱い者を切り捨てようとするのは卑劣である。こういう輩に限って給与削減の話になると大騒ぎし、「銀行員は30代で年収2千万だしねえ」などと言う。そのツラの皮の厚さには、開いた口がふさがらない。 そもそも銀行員が高額の給与をもらっているのが間違っているのである。ほとんどの銀行がバブル期にヤクザと組んで不動産融資に奔走し、濡れ手に粟の泥棒商売をした。そのあげくにバブル崩壊で不良債権を抱えてどこの銀行も倒産寸前。すると自業自得にもかかわらず開き直って、「銀行が倒産したら日本経済は崩壊するぞ」と国民を脅しつけ、恐喝屋に変身する始末。税金から何十兆円もの公的資金を引き出し、不良債権を肩代わりさせたわけである。ヤクザよりもよっぽど悪質である。少なくともヤクザは公的資金で救済などされていない。公的資金を何兆円もつぎ込んでもらってどうにか倒産を免れた銀行で、30代の行員が年収2千万円、頭取の退職金が8億円というのはどう考えても異常であり、これほど理不尽なことはない。年収2百万円でももらいすぎに見える。それを批判せずに、「銀行員は30代で年収2千万だしねえ」と泥棒商売を自分の給与の比較対象にするというのは、「私にはまったく職業倫理がありません」と自ら暴露しているのと同じである。大学院時代に世話になった国立大の教授が、ゼミの前の茶飲み話で、自らの薄給を嘆きつつ「銀行員は」と言うのを聞いて愕然としたことがある。なんてさもしい小役人。それ以来、私は彼を尊敬には値しないと思っている。 ■ A piece of moment 11/30 前回書いた格差社会についての続き。高度成長期の人海戦術で安価なものを大量生産していた「労働集約型社会」から、現在のような商品やサービスの付加価値が重視される「知識集約型社会」に産業構造が転換すると、必然的に高度な専門性が要求される業務についている者とそうでない者との間に所得格差が広がる。ひとにぎりの高度な専門職には高額の給与が保障され、それ以外の者は、発展途上国の低賃金労働と労働市場を競うことになり、失業するか低賃金のパート・アルバイト労働しかないという状況が生じる。さらに現在、日本ですすめられている「小さな政府」づくりは、そうした格差社会をいっそう押しすすめることになる。行きつく先はアメリカ型の社会である。人口で20%の富裕層が富の90%以上を独占し、ビル・ゲイツのような国家予算なみの億万長者がいる一方で、6人にひとりは健康保険にも入れないという社会。どう見ても楽しい社会とは思えないんだけど、官僚や大手企業に勤めるホワイトカラーには「アメリカでは」とアメリカ型社会を指向する「出羽守」が多い。自分が「勝ち組」だという意識が強いんだろう。たしかに、格差社会は競争を活性化し、短期的には経済効率を向上させる。しかし、「人より良い暮らしがしたい」という競争意識が経済活動の原動力になっている社会では、勝者は「次は負けるかもしれない」という不安から休むことなく仕事に駆りたてられ、敗者は「あいつらばかり良い思いをして」と勝ち組への不満と社会への不信感をつのらせる。死ぬまで続く競争はゲームと違って、勝っても負けてもあまり楽しそうではない。勝者も敗者も自分の生活を守るのに精一杯で、他者に手をさしのべようとはしなくなる。「なんでおいらの税金で見ず知らずの貧乏人を救ってやらなきゃならないんだ」というビートたけしみたいな人間が増えて、その結果、ともに社会を支えていくという連帯感は失われる。社会への不満と貧困によって、治安も悪化する。この10年で、アメリカの平均労働時間は日本を抜いて世界一長時間となり、犯罪はいくら刑罰を重くしてもいっこうに減らない。「ウイナーズ・テイク・オール」で2割の勝者が社会の9割の富を独占し、残り8割の人々は1割の富しかありつけないんだから当たり前である。日本も同じ道を歩みはじめた。もはや、たけしの発言は多数派の声であり、ちっとも「過激」ではない。ただえげつないだけである。こうした社会においては、治安対策として警察と軍隊が強化され、同時に、人々の意識を国家につなぎ止めておくためにナショナリズムが声高にとなえられるようになる。ああいつかどこかで見た風景。歴史は繰り返すで、我々は20世紀の歴史から何も学んでいないんだろうか。そうして、フランスではルペンやサルコジのような右翼が支持率を上げ、アメリカでは「私は新聞を読まない」というアホのブッシュが再選され、日本では小泉純一郎や安倍晋三や石原慎太郎の人気が高まる。「小さな政府」をとなえる連中が愛国者を気どり、他人にも押しつけがましく愛国心を要求するのは、あまりにも古典的でわかりやすい図式だ。市場競争万能をとなえる新古典主義者はネオコンとリンクする。 よく聞くラジオ番組に、火曜のお昼2時からTBSラジオで放送されている町山智浩のラジオコラムがある。アメリカ在住の映画評論家で、毎回、アメリカの社会事情や映画やテレビ番組の裏事情を紹介するという内容。以前は授業時間と重なってなかなか聞くことができなかったが、10月からはインターネット上にもMP3ファイルでアップされていて、パソコンにダウンロードして聞けるようになっている。 → TBSラジオ「podcasting954」より「11/29コラムの花道」 今回、11/29の放送は、アメリカのウォルマートの実態を描いたドキュメント映画「ハイコスト・ロープライス」の話で、ウォルマート従業員の低賃金労働にみるアメリカの格差社会の様子が紹介されている。ウォルマート従業員の平均年収は約200万円。この数字は経営者や管理職もふくめての年収なので、ほとんどの従業員は年収180万円くらいということになる。週5日、朝から晩までフルタイムで働いて年収180万円である。当然、健康保険にも年金にも加入していない。この低賃金労働が大規模店舗の激安商売を可能にしている。日本では1980年代にディスカウントストアが進出してきたが、たしかにそれによって色々なものが安くなった。とりわけ自転車と家電製品は、中国や東南アジアで製造されたものをディスカウントストアが輸入販売するようになって、価格がヒトケタ下がった。アメリカではこの現象を「ウォルマート・エフェクト」と呼んでいるという。そうしてアメリカ各地では、ウォルマートのような大規模ディスカウントストアが「価格破壊」で地域の商店を圧倒し、家族経営の個人商店や中小スーパーは倒産、大規模店の独占状態が形成された。つぶれた商店の主やスーパーに勤めていた従業員は他に働き口がないので、ディスカウントストアでの低賃金労働を余儀なくされる。さらに、ビジネスのグローバル化で中国やインドで製造された低価格製品に押されて、国内の製造業は工場閉鎖が相次ぎ、そこで働いていた人々もディスカウントストアの低賃金労働者になっていく。こうしてウォルマートをはじめとしたディスカウントストアはさらに規模を拡大して他の地域に進出し、そこでまた同じことがくり返される。現在、ウォルマートの全従業員数は千8百万人。東京都の人口よりも多いという。興味深かったのは、こうした格差社会をアメリカ政府が政策として意図的につくりだしているという話。国内に一定量の貧困層を作っておくことで、企業は低賃金労働を確保して利益を出し、アメリカ企業の国際競争力を高めているという。実際、ウォルマートは世界最大の小売業となり、日本にも西友への資本提供を通して進出しはじめている。さらにこの低所得者層の存在がアメリカの軍隊も支えている。町山智浩は皮肉混じりに笑いながら話していたが、聞いていて気が滅入ってきた。「百姓は生かさず殺さず」の発想は江戸時代の日本だけではないらしい。「勝ち組」「負け組」の人生ゲームに参加するつもりはさらさらないが、私のような低所得者にとってこの状況は他人事ではない。 ■ A piece of moment 12/4 家にこもって試験問題作成。どうにか徹夜せずに間に合いそうなめどが立つ。ふう。職場で「試験さえなければこの仕事、ずっと楽になるのにねえ」と愚痴をこぼしあう。授業のページに「コンピュータチェス」を追加。 →「コンピュータチェス カスパロフ対ディープブルー」 ■ A piece of moment 12/7 期末試験、一校ぶん採点まで終了。もう一校は問題作成中。あと3問、なかなか良い問題が思いつかない。 「コンピュータチェス」の課題部分を加筆修正。わりと良い課題ができた気がする。来年度、もしこのテーマを取りあげる機会があればこれでいこう。アタマを使う日々が続いて知恵熱が出そう。問題作成は明日にしてビールでも飲んで寝よう。採点をしながら、「魔法使いサリー」の主題歌を歌う加藤登紀子のものまねをする清水ミチコのものまねというのを思いつく。誰もいない社会科準備室で歌ってみる。出だししか歌詞を思い出せない。 ■ A piece of moment 12/8 「コンピュータチェス」の課題部分をさらに書き足す。すっかり長文になってしまって、こりゃ高校生向けの課題にならないんじゃないかという気もしてきた。高校1年生たちに、AとBの主張の先を考えろっていうのはちょっとひどいように見える。自分でも文章を読み返すのが億劫である。まあ、この手の話が好きな生徒が面白がってくれればそれでいいのかな。チェス・アルゴリズムの技術的な話は別にして、私たちがふだんどの様にして物事を判断し、考えているのかというのは、好奇心をかきたててくれる話題じゃないかと思う。なので、プログラムの技術的な解説は最小限にとどめて、できるだけ触れないようにした。局面の評価関数プログラムなんて、いくら解説を読んでもしくみがよくわからんのだ。 →「コンピュータチェス カスパロフ対ディープブルー」 夏に途中まで書いて放り出した「靖国問題」、論理の進め方の何が問題だったのか見えてきた。満員の通勤電車で後ろに立ったピアスだらけの兄ちゃんからゲホゲホと咳を浴びせかけられながら突然ひらめいた。小泉首相の参拝について、賛成・反対の2つの軸で考えると、それぞれ内部での考えに差が大きすぎて話がかみ合わないのである。次の4つくらいにわけるとちょうど良いのではないかと思う。 A.日本は悪くない。アジア侵略もしていないし、A級戦犯も悪くない。靖国神社も悪くない。 戦没者は国家的英雄であり、首相の参拝は当然。 中国・韓国の靖国批判は反日を政治的に利用しているだけ。聞く必要ない。参拝はぜひ8月15日に。 B.日本はアジアを侵略したし、靖国神社が主張していることも間違い。 ただし、戦没者は時代と国の政策の犠牲者であり、首相の参拝は必要。 C.日本はアジアを侵略したし、靖国神社が主張していることも間違い。 アジア諸国の感情を考慮して、A級戦犯が合祀されているかぎり、首相の参拝はダメ D.日本はアジアを侵略したし、靖国神社が主張していることも間違い。 アジア諸国の批判やA級戦犯の合祀に関係なく、戦争責任と政教分離の点から、首相の参拝はダメ。 空襲や原爆の犠牲者を無視して、軍人だけを神として祀る軍国神社に参拝しても平和を願うことにならない。 授業でやった感じだと生徒の反応は、Aが1割、Bが3割、Cが3割、Dが3割。同じ首相の参拝支持でも、Aの戦没者を「国家的英雄」とみなす立場とBの「犠牲者」と見なす立場とでは、あまりにも差が大きい。数でいうとAが最も少ないんだけど、発言が圧倒的に攻撃的で活発なため、クラスで議論すると押し気味になる。じゃあ議論が白熱するかというとそうではなく、他の生徒がその攻撃的発言にうんざりして白けた空気が漂うという感じ。このあたりは、最近の世論状況を反映している。 期末の問題は未だ完成せず。論述問題として出題するフランスの暴動事件について、解説文を書いたり消したりをくり返していて、ちっとも先に進まない。嫌な予感がする。 ■ A piece of moment 12/11 どうにかこうにか期末の問題完成。エイドリアーン!って感じ。3日も家にこもってぐちゃぐちゃ文章を書き直していたら、しだいにテンションと集中力が上がってきて、最後は半ばトランス状態で書き上げる。それなりにまともな文章になった気がする。論述問題は力作。どうも書きながら考えるのが習慣になっていて、書くことではじめて気づいたこともあったりする。ふだんぼーっととしているので、後で自分の書いた文章を読み返すと他人が書いたもののような気がするのであった。A4に文章びっちり12枚。生徒たち苦しめ。なんちゃって。そんなわけで昨日のバスケはまたサボる。こうも欠席が続いていると、サボっているというより実質的に幽霊部員状態で、出席して驚かれる気がする。やる気は十分なのに。 何度かメールをもらった人から、立花隆がWeb版の「日経BP」に連載しているコラムを教えてもらう。面白かったのでリンクに追加した。→立花隆の「メディア ソシオ-ポリティクス」バックナンバー ■ A piece of moment 12/12 連日の寒さでバイクのバッテリーがいかれる。「うわああ授業時間ぎりぎりぃー」と今朝、大わらわでバイクのスターターを押すと、セルモーターが力無くウィウィと唸る。こういう忙しいときに限って、機械はトラブルをおこすのである。やればやるほどセルは回らなくなっていくので、あきらめて自転車で行くことにする。片道10kmの道のりを酸欠状態でせっせとこぐ。15分の遅刻。今期2度目で、生徒たちは「またですかい」と暖かい眼差し。ごめんよー。 バッテリーは夏にチェックしたときもだいぶ弱っている感じだったので、じたばたあがくのはやめて新品に交換することにした。ヤフーオークションでちょうど良いのを半額セールしてたのでさっそく注文。20年ものの古いバイクなので指定タイプは「YB16B-A1」という開放型バッテリーなんだけど、いまさら開放型に交換するのも持ちが悪そうで不経済だし、同じサイズのシールドタイプにした。古河電池製FTH16-BS、7500円+送料500円也。やたらと安い気がする。我が家のぼろバイクはヤフーオークションによって維持されているのであった。 ■ A piece of moment 12/13 期末の採点、すべて終了。2学期は期末の採点が終わっても、さあ夏休みーとはいかないのであまり開放感がない。ちょっとひと息という感じで、とりあえず、試験期間中に散らかしっぱなしにしていた部屋の片づけをはじめる。ほこりだらけの部屋の掃除をして、たまった洗濯物をまとめて洗い、人間らしい生活を取り戻すことにする。 今回の論述問題は次の3問。いずれ演習授業のページに資料つきで載せる予定。 1.日本社会における男女間の賃金格差は、交通事故で子供が死亡した際の賠償金額にも影響を与えています。交通事故の賠償金額は、主に慰謝料(いしゃりょう)と逸失利益(いっしつりえき)から成ります。慰謝料は、子供を失った心の傷について支払われるもので、こちらは男女間で差はありません。それに対して、逸失利益は、その子が生きていれば得られたはずの収入への保障です。逸失利益は、働いている成人が交通事故で死亡した場合、死亡時の収入に基づいて算定されます。ところが、子供の場合は、現在の平均賃金から算定されます。この平均賃金の算定方法が、保険会社によっては、しばしば男女別の平均で算定され、結果的に女の子の賠償金額のほうが安いという状況が生じています。この男女別の算定方法については、法の下の平等に反するとして、全国各地で数多くの民事訴訟が起きています。裁判所の判決は、近年、男女共通の算定方法を支持する傾向がみられますが、最高裁でも裁判官によって判断がわかれており、男女共通にするか男女別にするか結論が出ていない状況です。(新聞記事を参照) 逸失利益 女児交通死2件で算定方法統一できず 異なる判決も次のAとBの主張を参考にして、あなたの考えを根拠を示しながら述べなさい。(約200字6点) A 子供が定年をむかえ、生涯の全収入を得るのは50年以上も先のことである。こうした未来においても現在の男女間の賃金格差がそのまま続くとする発想には、合理的根拠がない。現在、男女雇用機会均等法や男女共同参画社会基本法が施行され、男女間の収入格差は縮まってきており、今後も是正されていくはずである。こうした動きを無視して、現在の男女格差をそのまま未来にもあてはめようとする発想は差別的である。また、子供の逸失利益はあくまで「平均値」からおおよその収入を類推するものなので、男女別・地域別に細かく分類して算定するのは無意味である。したがって、男女別にわけず、全体の平均賃金で算定するべきである。 B 逸失利益の保障とは、あくまでその事故がなければ得られたであろう収入を埋め合わせるものであり、命の価値を決めるものではない。子供の場合は現時点で収入があるわけではないので、将来の収入を現在の社会情勢をもとに算定することになる。そのため、現在の平均収入をできるだけ正確に逸失利益の算定に反映させることが望ましい。現在、居住地域や男女間で平均収入には格差がある状況なので、正確に算定するためには、地域別・男女別に算定する必要がある。したがって、逸失利益の保障額も現状の男女格差に基づいて男女別に将来の収入を算定するのは合理性があり、差別とはいえない。 2.日本で飛び入学や飛び級を積極的に導入することの問題点を指摘した次の主張を読み、あなたの考えを述べなさい。(約200字6点) フィンランドをはじめとした北ヨーロッパ社会では、学ぶことは、視野を広げ、心を豊かにするという個人を尊重する価値観が定着している。そのため、勉強で他の生徒と競い合うという意識はほとんどない。クラスでは、「競争」よりも、勉強のできる子が他の子に教えるという「助け合い」のほうが重視されている。競争に勝つことよりも、自分の能力や意識を高めていくことが学ぶ原動力になっているため、学力に問題があると教師から指摘された場合、生徒みずから留年を希望するケースもある。そうした選択をした者は、「落ちこぼれ」とはみなされず、むしろ「意欲がある」と評価される。こういう社会ならば、飛び入学や飛び級も自分の能力を高めるひとつの選択肢として受けとめることができる。 しかし、日本では、学ぶことを学歴を得るための手段、競争に勝ち抜いて高い社会的地位や収入を得るための手段として認識する傾向が強い。このような競争原理が基本になっている社会で、飛び入学や飛び級を積極的に導入した場合、それは「自分の能力を高めるひとつの選択肢」とは認識されず、「人よりも先に進む手段」と見なされ、進学競争をあおることになる。現在の飛び入学制度は、「たぐいまれなユニークな才能の持ち主」を対象とした研究者育成コースとして位置づけられているが、積極的に導入され、学力上位者に適用されることになった場合、「先に進む手段」として潜在的な希望者は多いはずだ。 すでに現在、日本の高校生は学力別に振り分けられることによって、学力の低い高校では、多くの生徒が挫折感を抱いており、自分に自信を持てなくなっている。飛び入学や飛び級の積極的な導入は、学力による振り分けをいっそうすすめることになる。競争の過熱化は、敗者には挫折感と社会への不満をもたらし、勝者には次は負けるかもしれないという不安からさらなる競争をもたらす。こうした競争のプレッシャーが強い社会では、勝った者も負けた者も自分のことで精一杯で、利己的になっていくのではないだろうか。たしかに、産業の発展には効率的かもしれないが、このような息苦しい社会で、楽しく暮らせるとは思えない。 3.2005年10月からはじまったフランスの暴動事件は、その背景に移民の子孫である若者たちの社会への不満あると指摘されています。フランスの移民は、高度経済成長期に建設現場や工場で働くために北アフリカから出かせぎに来た人々です。そのほとんどは、肌の色が褐色のアラブ系で、イスラム教徒です。フランスの国籍制度では、両親が移民でもフランス国内で生まれた子供には、フランス国籍が保障されます。しかし、フランス国籍は持っていても、就職で不利になるケースが多く、定職に就くことができない若者が大勢います。現在、フランス全体の失業率は約10%ですが、移民やその子孫の失業率はだいたい30%にも上ると見られています。そのために、移民家庭の多くは低所得層に集中している状況です。このことが、移民の子孫の若者たちに、社会から差別され、疎外されているという思いをもたらしています。今回の暴動事件では、たんに警察の力で暴動を鎮圧しても、移民の若者たちのおかれた状況を改善しなければ、本質的な問題解決にはならないと指摘されています。その改善策のひとつとして、移民やその子孫を対象としたマイノリティ優遇政策を実施する必要があるという声が出てきています。これは、移民家庭を対象とした生活保護、また、企業や役所が人材を募集する際に移民やその子孫を優先的に採用する一定の枠を設定するというものです。このマイノリティ優遇政策について、次のAとBの主張を参考にして、あなたの考えを述べなさい。(約400字10点) A 現代の社会では、日本もふくめて、社会的格差が広がってきており、社会は貧しい人々や疎外されてきた人々に手を差しのべようとしなくなってきている。こうした状況を改善し、共に社会を支えていこうとしないかぎり、社会的弱者へのしわ寄せが続くことになる。長年、差別され、虐げられてきた人々は、たとえ差別がなくなったとしても平等な社会的地位を得ることは困難である。フランスの移民たちは、社会の中で建設現場や工場での低賃金労働を割り当てられ、不安定な生活を強いられてきた。近年の不況で、まずはじめに解雇されたのも彼らである。これは実質的に、移民やその子孫たちがフランス社会の中で二級市民として扱われてきたことを意味している。そのため、差別がなくなったとしても、フランス社会において、移民の子孫たちが人生のスタートラインで大きく遅れをとっているのは変わらない。したがって、就職や解雇で、民族・宗教を理由に差別をした企業への罰則強化をするのと同時に、マイノリティ優遇政策を導入して、移民やその子孫たちの生活状況を改善していく必要がある。これは、アメリカでの黒人を対象としたアファーマティブアクションやインドでの不可触民出身者を対象とした優遇措置として、すでに世界各国で実践されている。長年虐げられてきた人々に社会的平等を保障するためには、何らかのこうした支援プログラムが必要である。重要なことは、どのようにその支援が行われるかである。移民の若者たちが、自分は社会から支援されていると感じ、社会への参加意識を持てるような支援プログラムになることが望ましい。 B たとえ長年差別されてきたとしても、ある特定の集団に優遇措置をとることは、社会に不公平感をもたらし、その恩恵を受けられない人々の不満をまねくことになる。フランス社会における就職難は、移民の若者だけでなく、すべての若者にあてはまる問題である。そういう中で、移民の子孫を対象にした特別枠をもうけて企業が採用するようになったら、他の人々はイスラム教徒やアラブ系市民への不信感や不満をさらにつのらせることになる。このことは、フランス社会に民族や宗教による分断・対立をもたらす危険性がある。また、移民の子孫に優遇措置を設定することは、自ら努力して働こうとする意欲を彼らから奪い、社会保障にたよって生活しようとする者を増やすことになる。そもそも、マイノリティ優遇政策というのは、対象になる人々を「立場が違う特殊な存在」と見なすことである。しかし、フランス社会は、移民を受け入れ、フランス国籍を保障し、共に社会を支えていこうとする理念をかかげてきた。そのため、フランスでは、移民をできるだけ特別あつかいしないことで、同じ社会の一員という意識を形成しようとしてきた。マイノリティ優遇政策は、こうしたフランスの同化政策と相容れないものである。たしかに現状では、移民への差別は存在し、経済格差も大きい。そのため、就職希望者や従業員に民族的・宗教的な理由で差別的な対応をした企業への罰則を強化するなど、差別をなくしていくことで、同じ社会の仲間という意識をつくりあげていくべきである。政策はそちらに専念し、特定集団を特別あつかいすることになるマイノリティ優遇政策は導入するべきではない。 50分の制限時間がきびしかったようで、書けていない生徒多数。論述以外の分量も多かったので、60分から70分くらい欲しいところだけど、定期試験は完全にフォーマットができあがってしまっているので、試験時間を柔軟に対応することはできないらしい。他の回答欄の様子からあきらかにわかっている感じなのに、時間が足りなくて後のほうがずらっと空欄になっている生徒についてどう配慮するか思案中。 「ゲド戦記」宮崎アニメの次回作にという新聞記事。へえと思ったら、「監督は宮崎駿氏の長男」ってなんだそれ。アニメ監督も最近は世襲制なんかい。宮崎駿はそういうの嫌いそうに見えたけど、歳とって呆けてきたか。 ■ A piece of moment 12/14 掃除・洗濯で一日が終わる。冬休みになると生活が崩壊して、「ああ3日も寝てすごしてしまった、寝過ぎでダルいから吾妻ひでおのマンガでも読んでまた寝ちゃおう」となるのが目に見えているので、いまのうちに雑務をすませておかねばとムチを入れる。ラジオで手抜きマンション事件の証人喚問を聞きながら掃除機をかける。渦中の人、姉歯元建築士登場。なんだけれど、一人目の質問者が延々と演説をはじめてしまってぜんぜん「喚問」にならない。自民党のワタナベなる国会議員。なんなんだこいつ。自分の一方的な解釈とこの事件が社会におよぼした影響の解説を浪花節調で語り続け、肝心の姉歯から話を引き出すそぶりも見せない。「私はこの事件の全容をこのように見ているのです」「私がいま指摘したこの点は非常に重要です」……おいおい。発言の9割がこのアホの発言で、姉歯が話している時間は1割程度。姉歯がちょっと長めに話すと、「時間も限られているので」と言葉をさえぎって、さらに演説しはじめる始末。「証人喚問」とは何かわかっていないのか、「政治屋」をやりすぎて人と対話する能力が欠落してしまったのか、ともかく、こういうアホを代表質問に立たせるっていうのは党の見識も問われるのである。洗濯をひと段落させて、夕方、午後の部の証人喚問をテレビで見る。再び自民党の議員が延々と演説を続け、ヨシダロクザエモンなる議員は、証人から間違いを逆に指摘されしどろもどろになる始末。あまりにもお粗末。自民党、土建業界からの献金漬けで、問題を追求する気がないように見える。施行での手抜きと行政との癒着が常識の業界だけに、根は深いはずなんだけど。 ■ A piece of moment 12/15 引きつづき洗濯。夕方4時、宅配便でバイクのバッテリー到着。日暮れまでぎりぎりだけど、毎度のごとく見切り発車で作業開始。説明書を読みながら電解液を注入し、約30分ほど放置。希硫酸が反応してポコポコと泡が出てくる。いい感じ。30分待つ間に、古いバッテリーを取り外し、ついでにグリスを車体のあちこちに塗りたくる。うちのぼろバイクはシートからリアカウルまで全部外さないとバッテリーまで手が入らないのでけっこう面倒。日も暮れて暗くなりはじめる中、新しいバッテリーをはめ込み端子を接続。シートとリアカウルをはめ込んで、どうにか暗くなって見えなくなる前に終了。ついでに、漏れて減ったエンジンオイルを足しておく。古いバッテリーは近所のガソリンスタンドまで自転車でえっちらおっちら運ぶ。レジのお姉さんは「ああいいですよ」と嫌な顔もせず引き取ってくれる。いつもすいませんって感じ。さあ、バイクのスターターオン。一発でかかる。わーい。しばし乗り回す。三鷹のバイク用品店までタイヤに空気を入れに行く。「いま無料点検サービスやってます」と店員氏。冬場でバイク乗りが減って、整備員が手持ちぶさたなんだろうか。でも、そこまでしなくてもいいのに。不景気なんだろうか。今回も何も買わなかったので、点検サービスは辞退し、自分でタイヤに空気を入れる。なにはともあれエンジン快調。オイル漏れが気になるけど。 明日、期末試験の答案返却の予定。前回、中間試験の答案を返した際、残り時間すべてを使って問題解説したところクラスのほとんどが寝てしまう。「点数だけを気にしてないで出来なかった所を見なおしてこそ力がつくんだよ」などというこちらの説教はありがたく聞き流して、やらされる側としては終わった試験なんてさっさと忘れたいのである。ああ、俺もそうだったよ。というわけで、今回は論述問題として出題したアファーマティブアクションの資料として、ビデオを2本、見ることにする。ふたつとも「CBS 60mins」からで、1本目は、アファーマティブアクションの廃止運動をする黒人実業家、ワード・コナリーについてのレポート。2本目は、人種問題のネタにする黒人コメディアン、クリス・ロックのステージとインタビュー。  ■ A piece of moment 12/20 2学期の授業もどうにか終わったので、押入から資料用の古いビデオテープを引っ張り出し、パソコンのハードディスクに記録していく。量が多いので、こういう時でもないとなかなか手をつけられない。雑然とダンボール箱に詰め込まれたテープの中から、デジタル化するものをより分けていく。V・E・フランクルの1994年のインタービュー、永山則夫の裁判記録、ワイツゼッカーが1995年に行った来日公演、1997年に成立したアイヌ新法について語る萱野茂、1995年にスミソニアン博物館によって企画された「原爆展」をめぐる論争、NHKが1995年に特集番組として放送した映像記録「映像の世紀」などなど。 パソコンのモニターに映し出されたワイツゼッカーが語る。「自らの歴史と取り組もうとしない人は、自分がなぜそこにいるのかがわからない」、「過去を否定する人は過去をくり返す危険にさらされている」。この言葉は、その後、様々なところで引用され、すっかり有名になった。だが、個人的体験を越えた「自らの歴史」とはいったいなんだろう。民族や国家へ安易に帰属意識を抱き、「我々の歴史」として過去を認識することは、新たなナショナリズムを生みだす。「ドイツ人として」ユダヤ人のホロコーストに後悔し、「日本人として」アジアの植民地化とそこでの虐殺に後ろめたさを感じることは、ナショナリズムの裏返しでしかない。ナショナリズムの犯罪をナショナリズムで乗り越えることなどできるはずがない。 私たちは、何も知らず何もわからないままこの世界に放り出され、ただ暗闇の中をおびえながら手探りで歩いている子供のようなものではないかと思う。唯一のかすかな道しるべは、過去にあった出来事をできるだけ正確に知り、その過去があったことで現在に至っていることに思いをはせ、社会が同じ道をたどらないよう考え、発言し、行動していくことでしかない。現在に生きるひとりの個人として過去の出来事と対峙せず、国家的利益の点から過去の問題をとらえ、それを利用して政治的優位を得ようとするかぎり、ナショナリズムによる過ちは何度でも繰り返される。それはちょうど、暗闇の中で雄叫びをあげながら断崖へ向けてチキンレースをしている姿を連想させる。 たしかにナショナリズムは強い結束力をもたらす。そのため、外国による植民地支配に対して蜂起する際、しばしば指導者は人々のナショナリズムに訴えかける。日本や欧州諸国の支配下にあった中国で孫文が中国の自立を呼びかけた言葉やイギリスの支配下でガンジーがインド人のアイデンティティとして糸車をまわす姿には感銘を受ける。それを否定するつもりはない。日本の支配下にあった戦時中の中国や朝鮮半島でナショナリズムが高まったのも当然といえる。しかし、「我々」が同質であることを求心力とするナショナリズムは、同時に異質な者への排他性と外部への攻撃性をそなえる。迫害を逃れ安住の地を求めてパレスチナへ集まってきたユダヤ人は、今度はそこで自分たちがアラブ人を迫害する側に回る。彼らはただ安心して暮らせる場所が欲しかっただけで、アラブ人を追い出すつもりはなかったと言う。しかし、「安心して暮らせる場所」というのがユダヤ人だけの国であるのなら、その後のパレスチナの混乱は起こるべくして起きたといえる。むしろイスラエルは多くの点でナチス時代のドイツによく似ている。ある集団のナショナリズムはそこで迫害された者たちのナショナリズムを連鎖的に生みだす。 以前、授業の中で生徒にこう話したことがある。もし、中国や韓国へ行って、「日本人である」というだけで地元の人から敵意の目で見られたとしても、後ろめたく感じる必要はない、君らが弾圧や殺戮を行ったわけじゃないんだから、毅然としていればいい。ある者の犯罪を、人種や民族が同じというだけで他に転嫁する考え方は、ナチスや差別主義者の発想だ。「親の罪を子が贖う」という儒教的発想は間違っている。もちろんそれは「日本は悪くなかった」と開き直ることではないし、「自分には関係ない」と無視することでもない。その過去があったことで現在の社会が存在するのだから、そこで何があったのかは知る必要があるし、同じことをくり返さないためにどうすればよいのか考える必要がある。だから、近代史の中で何が起きたのかを考えるとき、国籍や被害者・加害者という立場に関係なく、また、ナショナリズムや愛国心の道具に利用するのではなく、現在に生きる者として同じ方向を向いて、同じことをくり返さないために、どうすれば良いのか一緒に考えて欲しい、と。これはいまでも間違っていないと思っている。ただ、国家による犯罪の場合、国の責任とその国に所属する個人の責任とをどこでどう線を引いたらいいのだろう。いつもそこで考えが止まってしまう。 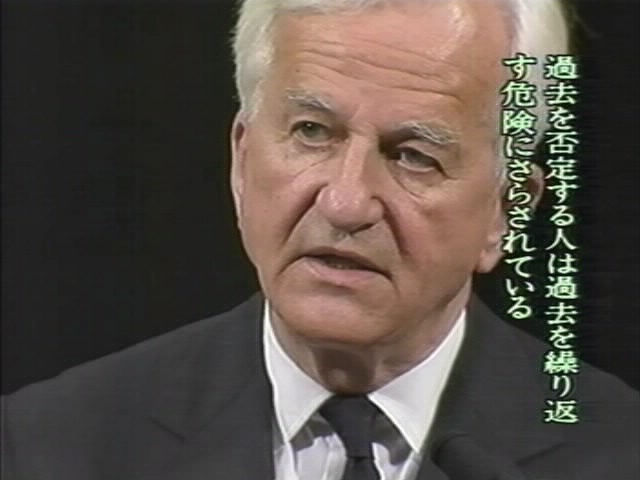 ■ A piece of moment 12/31 年の瀬でラジオは昭和歌謡の特集番組をやっている。江利チエミの「テネシーワルツ」に笠置シズコの「東京ブギ」。植木等の「スーダラ節」や美空ひばりの「東京キッド」もかかる。「東京キッド」は「歌も楽しや 東京キッド~♪」ではじまり「左のポッケにゃ チュウインガム♪」のおなじみのフレーズに続く1950年のヒット曲。戦後の焼け跡と混乱とアメリカ文化へのあこがれを時代背景に、まだ子役時代の美空ひばりが、カネはないけど夢はあるよと東京の暮らしを陽気に歌う。有名な曲だけど、よく考えたら歌詞をちゃんと聞くのははじめてだ。歌詞を気にしながら聞いていたら、「もぐりたくなりゃ マンホール~♪」のフレーズが妙に気になってくる。なぜマンホールにもぐるんだろう。こんな歌詞である。 東京キッド 作詞・藤浦 洸 作曲・万城目 正東京キッドは歌とチューインガムが好き。ビルの谷間から空を見上げることもある。フランスの香水やチョコレートを夢見たりもする。通りまで響いてくるジャズを聞きながらリズムに合わせてジッターバグをおどる。そこまではいい。でも、なぜ「もぐりたく」なってしまうのか、展開が唐突で、ここに来ると東京キッドの気持ちが理解できなくなる。しかも、よりによってマンホールに。1番から3番まで、「もぐりたくなりゃ マンホール~♪」のフレーズをくり返しているところを見ると、あきらかに作詞家は意図して「もぐりたくなる気分」と「マンホールのモチーフ」を東京キッドのキャラクターづくりに用いている。よっぽどマンホールに思い入れがあるんだろうか。もしかしたら酔っぱらうとマンホールにもぐりたくなる趣味の持ち主だったのかもしれない。ちなみにこの歌は美空ひばりが主演した同名映画の主題歌である。時代的にもしや映画は「マンホールで暮らす戦災孤児」の物語なのかとも思ったが、調べてみたところやはり違うようだ。(映画については→こちらのブログで詳しく書かれている。)あるいは、「もぐりたくなりゃ マンホール~♪」の歌詞について、半世紀以上もとくに誰も異議申し立てすることもなく、広く受け入れられているということは、潜在的にマンホールにもぐりたい人が大勢いるということを意味しているのかもしれない。東京のある自治体では、成人式の式典のあとで振り袖姿や紋付き袴姿の新成人たちがマンホールにもぐるのが毎年恒例の行事になっていて、マンホールにもぐらない奴は地域社会の中で一人前として認められなかったりするのである。ええっマンホールにもぐったことないってえお前さん東京もんじゃないなってまあそれは良いとして、実際のところ、「もぐりたくなりゃ マンホール~♪」の歌詞にどんな意図が込められているのか、事情をご存知の方、メールください。 2006 ■ A piece of moment 1/2 2006年である。悪い冗談のような気がする。年末から家にこもって、仕事の資料用ビデオをパソコンに取り込んでデジタル化している。大半が10年くらい前のニュース番組とドキュメンタリー番組で、久米宏が「明日、いよいよ臓器移植法が施行されます」なんて語っていたり、国谷裕子が「東海村の原子力施設で放射能漏れ事故が発生しました」と深刻な顔をしていたりする。そんなビデオを百時間近く見ていると、鴨長明が川の流れにたとえた過去から未来へ流れる時間の感覚がしだいに失われていく。録画されたニュースの中では断片的な過去が時系列とは関係なく現在進行形で語られ、1997年の出来事と1999年の出来事が同時進行的に全部「いま」に思えてくる。どうも、2000年をすぎたあたりから時間の感覚がずれているように感じていたが、こういう仕事をしていることが原因なんじゃないかという気がしてきた。10年近く前の出来事なのに少しも過去として収まってくれないのである。というわけで2006年である(らしい)。こんな新聞記事を見かけた。 NBAドレスコード、黒人選手と白人観客の意識に違いマイケル・ジョーダンもいなくなって人気低迷のプロバスケットボールがイメージを変えようとしているという記事。だぼだぼのジャージはギャングを連想してガラが悪いから規制しようという。プロスポーツは人気商売なのでイメージづくりは大事ということなんだろうけど、気になるのは最後のノースイースタン大の先生の取って付けたようなコメント。人に不快感を与えない服装なんて、まるで企業の新人研修みたい。「相手への配慮」というのは保守的な価値観を押しつける際にしばしば用いられる。でも、誰からも不快感を抱かれない服装なんて存在しないわけで、世の中にはビジネススーツとネクタイに大いに不快感を抱く私のような人間もそれなりに存在する。そちらへの配慮はぜんぜんない発言で、鈴木健二の「気くばりのすすめ」を思い出したのであった。時間は流れないのである。そもそもプロスポーツの選手はひとりひとりが看板背負って立っているエンターテナーなのに、こういう人にビジネススーツを着せようっていう発想自体がひどくゆがんでいるように見える。 ■ A piece of moment 1/7 近所のコンビニにバイクを停めていたら、見知らぬ兄ちゃんから「ああっVF!懐かしいっすねえ」と声をかけられる。なんかてれくさいですな、こういうの。ピカピカですねえコンディション良さそうですねえと持ち上げられて逃げ出したくなる。実のところは、エンジンオイルの漏れがあまりにひどいので、どこから漏れているのか確認するために昨日、分解清掃したばかりなのであった。彼は30年もののCBヨンフォアに乗っているという。ヨンフォアやZ1は完全にプレミアムバイクの世界なので、我が家のただの程度の悪い中古バイクとは次元が違うのである。きっとフルレストアで新車以上の状態のはずである。くらべないでちょうだい。エンジンの調子はどうですかと聞かれ、「いちおう4発とも爆発してるみたいです」と答える。ふたりで笑う。 うちの庭をなわばりにしている猫がいる。真っ黒い奴で、顔は目が大きくて愛嬌があるんだけど、こいつがじつにふてぶてしい。夏に窓を開けて寝ていたら、寝返りをうった瞬間、目の前に黒い猫がいる。こっちはぎょっとしたが、向こうはまったく動じていない様子で、後ずさりもせずににらみ返してくる。1分近いにらみあいの末、負ける。秋口には、夜中にガサガサ音がするから何かと思ったら、こいつがすました顔をしてスズメをくわえていやがる。じつにけしからん。このふてぶてしい奴が、バイクカバーにいつもマーキングをしていく。マメな性格で、毎日定期的に巡回しているらしく、油断するとまだおしっこで濡れていたりしてズボンに強烈な臭いがついてしまう。ますますもってけしからん。とは言うものの、窮屈なこの土地でいっしょに生きてる仲間のようにも思えて、追い立てる気にはならない。そんなわけでうちのバイクは、ファブリーズと黒猫印の香りがするのである。 ●●
|