「被団協」新聞2025年8月号(559号)
2025年8月号 主な内容
被団協運動を支えた人々
県議会議事堂で原爆展
6月25日、26日の2日間
 |
| 富山県議会議事堂原爆展開会式(6月25日) |
富山県被爆者協議会
富山県被爆者協議会は6月25、26日の両日、県議会議事堂で原爆被害を収めた写真パネルを紹介する原爆写真展を開きました。広島・長崎への原爆投下から80年の節目に合わせて企画したものです。同協議会が写真展を県議会議事堂で開くのは初めて。
県議会議員や県職員と多くの県民に被爆の実相を広く知ってもらおうと、県議会の協力を得ての開催となりました。富山県議会では今年2月に日本被団協の金本弘代表理事らを招いて全県議が参加した勉強会が開かれており、継続した取り組みとなりました。
協議会が所有するパネルのうち、今回は47枚を展示。戦争の悲惨さを生々しく伝えました。
25日に開会式があり、武田慎一県議会議長があいさつで「被爆の実相を知り、今後の取り組みに活かしていきたい」などと話しました。
(小島貴雄)
沖縄で浄土宗平和誓願の集い
 |
和田征子
沖縄平和祈念公園内にある施設で6月26日、浄土宗平和協会主催、九州地区各教区共催の「浄土宗平和誓願の集い」が開かれました。各地から住職の方々、一般の皆さんが参加され、沖縄被爆協のみなさんもご参加くださいました。
摩文仁の丘に建つ沖縄平和祈念堂での法要では、沖縄戦をはじめ戦没者の追悼と世界平和を祈って平和祈念像前で読経があり、私も献花をさせていただきました。
集会では廣瀬卓爾協会理事長の「宗教界が戦時下で国に抗うことをしなかった」という資料の解説を興味深く聞きました。私は講演で「世界へ届けたい被爆者の声」をテーマに、オスロ報告を含めて話し、多くの質問もいただきました。
翌日は沖縄平和資料館、平和の礎、ひめゆりの塔(写真)と資料館も見学することが出来ました。
沖縄の空はどこまでも青く、広がる下に、土砂を満載したダンプトラックが延々と並び、その先には、基地建設に反対の声を上げる人たちのグループが。戦後が終わる前に、また戦前になるのでしょうか…。
核兵器廃絶と平和を自分事に
沖縄全戦没者追悼式とシンポジウムに
 |
| 田中重光代表委員の出席・発言を伝える沖縄の地元紙 |
田中重光代表委員
沖縄慰霊の日の6月23日、沖縄県からの招待を受け、日本被団協の田中重光代表委員が沖縄全戦没者追悼式に出席しました。日本被団協代表の出席は初めてです。
田中重光代表委員はまた、24日に開かれた沖縄県主催の「戦後80周年の沖縄から国際平和を考える」シンポジウムで基調講演を行ないました。「核兵器は絶滅を目的とした悪魔の兵器、地球上に一発たりとも置いてはならない。日本政府には一日も早く核兵器禁止条約を批准してもらいたいが、残念ながら批准せず条約の締約国会議にオブザーバー参加もしていない。まだまだ私たち国民の声が小さく、政府に届かないからだ。核兵器の課題は被爆者だけの問題ではなく、地球上のすべての人の課題だ。特に未来をつくる若い人には、核兵器廃絶や平和について自分事として考え、行動してほしい。そして核兵器廃絶を目指してきた日本被団協の運動を継承してもらいたい」などと話しました。
同じく基調講演を行なった中満泉国連事務次長は、世界中で戦火が起こり拡大している情勢に触れ、「沖縄はアジアの玄関口。民間外交を沖縄から発信してほしい。冷戦の最中、アメリカで軍拡競争に抗議する大きなデモがあり、政策転換を促すひとつの要因になった。少人数から声が広がって世界を変えることを疑ってはいけない」などと話しました。
基調講演のあと、玉城デニー沖縄県知事と慶応大4年の崎浜空音さんが加わってパネル討論が行なわれ、戦争体験の継承や、沖縄が国際平和のために果たす役割などを話しあいました。
シンポジウムには県からの招待で沖縄県原爆被爆者協議会の被爆者も会場参加しました。
原稿募集
「被団協」新聞では、読者の皆さんの「声」を募集しています。
「『基本要求』を読んで」、「ノーベル平和賞受賞を受けて」、「『被爆者からあなたに』を読んで」などのほか、地元被爆者の会、その他グループでの、各種イベントや証言活動、署名や街頭行動などの報告を、写真と共にお送りください。開催予定のイベントの告知もお待ちしています。
また、身のまわりで起こったことや、ふと思いついたこと、日頃思っていること、「被団協」新聞の感想なども、気軽にお送りください。
氏名、年齢、住所、電話番号を明記して、郵送かEメールまたはFAXで。写真はEメールに添付かプリントの郵送を。
郵送先=〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-5ゲイブルビル9階 日本被団協
FAX=03-3431-2113
Eメールはkj3t-tnk@asahi-net.or.jpまで。
被爆80年の運動、全力で
来年の日本被団協結成70周年見すえ
 |
木戸季市前事務局長(今年の定期総会で顧問)が就任されたのは、2016年6月でした。同年4月から日本被団協が呼びかけ広島、長崎の原爆被爆者9人(海外在住を含む)を呼びかけ人とする「ヒロシマ、ナガサキの被爆者が訴える核兵器廃絶国際署名」(ヒバクシャ国際署名)がスタートした時でした。核兵器廃絶を願い、核兵器を禁止し廃絶する条約を結ぶことを世界の全ての国に求めるこの署名運動は、結成60年を迎えた日本被団協が「ふたたび被爆者をつくるな」と願い続けてきた核兵器廃絶を、世界の人々に直接呼びかけたものでした。
ヒバクシャ国際署名開始の翌2017年に122カ国の賛成で核兵器禁止条約が成立。その後も署名を積み上げ、2021年の発効に至るまでの動きを大きく後押しする画期的な取り組みとなりました。
「証言」の大運動を
2024年日本被団協は、ノーベル平和賞を受賞しました。地獄の体験を地球上のだれにも味わわせてはならないと、自らの苦しい体験を「証言」を通して訴えてきた活動が評価されました。ノルウェーノーベル委員会は、今日の核兵器が使用されかねない国際情勢のもと、核兵器は使われてはならいないとういう「核のタブー」が揺らぎつつある今だからこそ被爆者の声が必要と「日本被団協」に授与しました。
今年6月の日本被団協第70回定期総会で、被爆80年の取り組みとして、証言の掘り起こしと語り継ぐ運動を一番に掲げました。核兵器と人類は共存できないこと、核兵器の非人道性を「証言」を通して国の内外で訴える大運動を広げていきたいという思いからです。
秋に集会、行動
10月11日には、多くの団体の支援、特に若い皆さんの力を得て、日本被団協の核兵器廃絶と原爆被害者への国の償いを求める運動を、朗読劇などを通して訴えます。
また、10月あるいは11月に、核兵器禁止条約に日本政府が署名、批准するよう訴える行動を展開します。核兵器禁止条約への署名、批准国を広げるためには、各国の在日大使館に要請したいと考えています。そして、世界を視野に入れた日本被団協の運動と組織の在り方を検討します。
全力で取り組む
広島の胎内被爆者として2015年から事務局次長、昨年10月から事務局長代行を務めてきました。6月の総会で事務局長を担うこととなりましたが、日本被団協の二つの専門部、各委員会の活動を基に、今年の方針に基づく運動に全力で取り組むとともに、来年は被団協結成70年を迎えることを見通しながら活動を進めてまいります。
ご協力、よろしくお願いいたします。
 |
手帳所持者数9万9130人
2024年度末 平均年齢86.13歳
2024年度(25年3月末)の被爆者健康手帳所持者数、諸手当受給者数などが、厚生労働省から発表されました。
手帳所持者は全国で9万9130人。前年度と比べ7695人の減少となりました。葬祭料の給付は8713件でした。平均年齢は前年度から0・55歳上昇して86・13歳でした。
健康管理手当など諸手当の受給者数は合計9万888人で、手帳所持者の91・7%でした。
都道府県別では、手帳所持者が6人の山形が最少、次いで秋田が12人、岩手が15人です。諸手当の受給率は秋田と青森が100%。介護手当と家族介護手当のどちらも支給件数が0のところが15道県あり、昨年度より3県増えました。
被爆80年
日本被団協 日本原水協 原水禁が共同アピール
日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)と原水爆禁止日本協議会(日本原水協)、原水爆禁止日本国民会議(原水禁)の三者は7月23日、初の共同アピールを発表しました。核兵器廃絶に向けて国民的なとりくみを呼びかけるものです。
 記者会見には日本被団協の田中熙巳代表委員と濱住治郎事務局長、日本原水協の安井正和事務局長と土田弥生事務局次長、原水禁の谷雅志事務局長と山本圭介事務局次長が出席。田中代表委員は「核兵器廃絶運動の大きな2つの団体と共にアピールを発表することができ感慨深い」、濱住事務局長は「被爆者の高齢化がすすむこの時期のアピールは大きな意味がある」などと述べました。
記者会見には日本被団協の田中熙巳代表委員と濱住治郎事務局長、日本原水協の安井正和事務局長と土田弥生事務局次長、原水禁の谷雅志事務局長と山本圭介事務局次長が出席。田中代表委員は「核兵器廃絶運動の大きな2つの団体と共にアピールを発表することができ感慨深い」、濱住事務局長は「被爆者の高齢化がすすむこの時期のアピールは大きな意味がある」などと述べました。
被爆80年を迎えるにあたって
ヒロシマ・ナガサキを受け継ぎ、広げる
国民的なとりくみをよびかけます
1945年8月6日広島・8月9日長崎。アメリカが人類史上初めて投下した原子爆弾は、一瞬にして多くの尊い命を奪い、生活、文化、環境を含めたすべてを破壊しつくしました。そして、今日まで様々な被害に苦しむ被爆者を生み出しました。このような惨劇を世界のいかなる地にもくりかえさせぬために、そして、核兵器廃絶を実現するために、私たちは被爆80年にあたって、ヒロシマ・ナガサキの実相を受け継ぎ、広げる国民的なとりくみを訴えます。
2024年、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)がノーベル平和賞を受賞しました。凄惨な被爆の実相を、世界各地で訴え続け、戦争での核兵器使用を阻む最も大きな力となってきたことが評価されたものです。一方今日、核兵器使用の危険と「核抑止」への依存が強まるなど、「瀬戸際」とも言われる危機的な状況にあります。
ウクライナ侵攻に際してロシアの核兵器使用の威嚇、パレスチナ・ガザ地区へのイスラエルのジェノサイド、さらに、イスラエルとアメリカによるイランの核関連施設(ウラン濃縮工場)への先制攻撃など、核保有国による国連憲章を踏みにじる、許しがたい蛮行が行われています。核兵器不拡散条約(NPT)体制による核軍縮は遅々として進まず、核兵器5大国の責任はいよいよ重大です。
しかし、原水爆禁止を求める被爆者を先頭とする市民運動と国際社会の大きなうねりは、核兵器禁止条約(TPNW)を生み出しました。これは、核兵器の非人道性を訴えてきた被爆者や核実験被害者をはじめ世界の人びとが地道に積み重ねてきた成果です。同時にそれは今日、激動の時代の「希望の光」となっています。この条約を力に、危機を打開し、「核兵器のない世界」へと前進しなければなりません。アメリカやロシアをはじめ核兵器を持つ9カ国は、TPNWの発効に力を尽くしたすべての市民と国々の声に真摯に向き合い、核兵器廃絶を決断すべきです。
唯一の戦争被爆国である日本政府はいまだTPNWに署名・批准しようとはしません。核保有国と非核保有国の「橋渡し」を担うとしていますが、TPNWに参加しない日本への国際社会の信頼は低く、実効性のある責任を果たすこととは程遠い状況にあります。アメリカの「核の傘」から脱却し、日本はすみやかに核兵器禁止条約に署名・批准すべきです。
原爆被害は戦争をひきおこした日本政府が償わなければなりません。しかし、政府は放射線被害に限定した対策だけに終始し、何十万人という死者への補償を拒んできました。被爆者が国の償いを求めるのは、戦争と核兵器使用の過ちを繰り返さないという決意に立ったものです。国家補償の実現は、被爆者のみならず、すべての戦争被害者、そして日本国民の課題でもあります。
ビキニ水爆被災を契機に原水爆禁止運動が広がってから71年。来年は日本被団協結成70周年です。被爆者が世界の注目をあつめる一方、核使用の危機が高まる今日、日本の運動の役割はますます大きくなっています。その責任をはたすためにも、思想、信条、あらゆる立場の違いをこえて、被爆の実相を受け継ぎ、核兵器の非人道性を、日本と世界で訴えていくことが、なによりも重要となっています。それは被爆者のみならず、今と未来に生きる者の責務です。地域、学園、職場で、様々な市民の運動、分野や階層で、被爆の実相を広げる行動を全国でくりひろげることをよびかけます。世界の「ヒバクシャ」とも連帯して、私たちはその先頭に立ちます。
2025年7月23日
日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)
原水爆禁止日本協議会(日本原水協)
原水爆禁止日本国民会議(原水禁)
あの日、
「見すててしまった」「助けてあげられなかった」「私がまだ生きている」
…1985年原爆被害者調査から
被爆40年の1985年、日本被団協は大規模な原爆被害者調査を行ないました。1万3千人余から回答が寄せられ、その自由記述欄に記された言葉は『「あの日」の証言』1・2、『被爆者の死』1・2の4冊にまとめて出版。多くのボランティアの力を得て英訳も出版しました。国連をはじめ各国大使館等に届けたほか、現在は日本被団協のホームページに全文掲載。人間として到底「受忍」することができない原爆被害を読み取ることができます。
<以下抜粋。〔 〕内は被爆地・被爆状況・性別・被爆時年齢>
母と姉、妹と私が同じ部屋で被爆した。私は下敷きになったが、傷を受けなかった。姉と妹は焼死。母は重傷を負いながらなんとか助かった。
40年たったいま、満員電車の人ごみの中でもまれる時、また、部屋の壁に向かって座ったり、立ったりすると息苦しく感じ、頭の中は下敷きになっていたあの息苦しさが、当時のまま浮かんでくる。
下敷きになっていた姉と妹を、火の回りが早くて助け出せなかった。私(8歳)自身、当時は逃げることに夢中で、後になって時がたつとともに、あの日なすべきことをしなかった、見捨ててしまったという意識が、どうしてもとれない。
〔広島・直爆1.5㎞・男・8歳〕
自分が逃げることのみに汲々として、助けを求める人を見殺しにしたことが、今も心に重くのしかかっている。橋の上に横たわっていた人を、渡る時にふみつけざるを得なかったが、それは死体ではなく生きていて、「助けてくれ」と叫んで足をつかまれ、その人はそのまま死んでいった。
原爆被爆者は被害者にはちがいないが、私の場合は加害者でもある。それが今もつらい。
〔広島・直爆2㎞・男・15歳〕
同じ建物にいた戦友が建物の下敷きになり、助け出そうにも出されず、そのうち火がまわり、目の前で足や手、また頭の順で焼ける様子、地獄なり。馬を飼っていたが、馬屋に繋がれたまま焼けるさまは可哀想よりむごかった。今も目に浮かぶ。
戦友と一緒に逃げる途中で川に飛び込むも、戦友は力尽きて泳げず、そのまま死んだことを10日後ぐらいに知った。一緒に泳いでいるとばかり思っていた。自分自身のことで精いっぱいだったとはいえ、助けてあげられなかったこと、つらかった。
〔広島・直爆1㎞・男・19歳〕
地獄そのもの。生きている人も、死んでいる人も、人間には見えず、身ぶるいをした。家屋の中で助けを呼ぶ声(40代女性の)が、今も耳に残っている。何もできなかったので。姿は見えなかった。
トラックでの宇品方面への被爆者輸送時に、軍人らしき者の「女、子どもと年寄りは乗るな。男の若者のみ乗れ、戦争はこれからだ」は忘れられない。「戦争とは?」を骨の髄まで考えさせられた。
〔広島・直爆1.5㎞・男・20歳〕
あの惨状をそのままペンや口で表現することは不可能です。警戒警報が解除されて、人々がホッとした時に、突然太陽が爆発し、ヒロシマを根こそぎ飛散させたのです。そうとしか思えません。ボロになった人々が、七転八倒してモガキ苦しむのを見ながら、自分が助かることしか考えなかった私は、現在でもその人々の怨念が私に襲いかかってくるような思いで、いたたまれないのです。それは私がまだ生きているから。
日ごろ差別されていた町内の朝鮮の人たちが、自分の国の言葉で、断末魔をノタウチマワッテ絶叫していたのも、この40年間忘れられないのです。
〔広島・直爆2㎞・女・24歳〕
父は頭の毛は焼けてしまい、顔の皮はむけてたれさがり、言葉も出ないようになって死んでいった(10日死亡)。母は目がとびだしたようにはれあがり、のどの痛みをうったえ、もだえにもだえて亡くなりました(21日死亡)。19歳の妹は右半身焼けて、胸の傷口にうじ虫がわき出るようにいて、うめき声が耳底に残って消えない(25日死亡)。12歳の妹は死ぬ3日前から鼻血が出て止まらず、髪の毛は抜け落ちてしまって、その上家の下じきになって這い出して出る時右の乳を真二つにたてに割っていた姿、ザクロのように真っ赤になっていた。
〔長崎・直爆3㎞以上・女・32歳〕
母(直爆0・5㎞、55歳)は台所で、仰向けに片足を立て、手は両手とも上に横に伸ばし、首はありませんでした。なんとなくお腹のあたりブヨブヨしていたようです。もう炭のように真っ黒でした。父(直爆0・5㎞、50歳)は防空壕近くの土の中から出てまいりました。これも首はなく、長い間中風で半身不随でしたので着物を着ていました。その羽織の裏の布に見覚えがあり、骨にくいついていましたので父とわかりました。何も悪いことをしない者が戦争のために犠牲にされ、むごい死に方。自分のみ助かったことが悔やまれ残念です。父を、母を、失った人を返せ、大きな声で叫びたいです。
〔広島・直爆2㎞・女・18歳〕
7歳の長男と5歳の次男は私と共に歩行中、15~6歩ぐらい前を歩行中に被爆。火傷や怪我でもだえ苦しんでいたと思われ、未だに行方不明。1歳の長女を背負って3歳の三男の手を引いていたが、(二人は)生前のおもかげもなく大火傷で死亡。あまりにも死に方がむごすぎます。子どもだけ死んで自分だけ助かったことが申し訳ないような気がします。失った子どもを返せと叫びたい。死にものぐるいで長崎より夢中で生まれ故郷へと乞食同様で帰ってきて、その後の生活の苦しみは話しようがない。
〔長崎・直爆1.3㎞・女・31歳〕
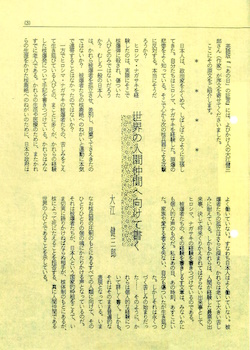 |
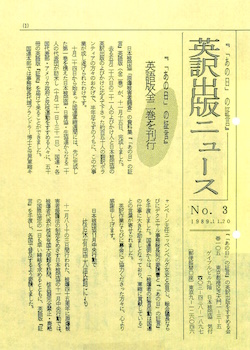 |
1ページ(右)と3ページ(左、大江健三郎さんによる「序文」)
ノルウェー・ノーベル委員会
フリードネス委員長来日
広島・長崎を初訪問
広島
日本被団協に昨年のノーベル平和賞を授与したノルウェー・ノーベル委員会のフリードネス委員長が22日、広島市を訪れ、広島被爆者7団体などと交流しました。
フリードネス氏は広島市に平和賞メダルのレプリカを貸与し、原爆資料館を見学した後、7団体や原水禁団体、市民団体の代表など約30人と懇談しました。
昨年末の授賞式に参列した箕牧智之代表委員(広島県被団協理事長)は被爆地での再会に謝意を表明。田中聰司代表理事(同理事)は、核保有国のリーダーたちに被爆者の声を聞く場を設けるよう呼びかけてほしいと要望しました。
朝鮮半島をはじめアジア出身の膨大な人々が被爆した事実が語られ、高校生が被爆証言を基に描いた「原爆の絵」を説明。70周年を迎える原水爆禁止世界大会の願いが伝えられました。
フリードネス氏は今に続く被爆の実相の甚大さに驚き、多くの「不屈の魂」に敬意を表明しました。
7団体は懇談会の前に平和記念公園で、日本政府に核兵器禁止条約への署名・批准を求める署名活動を実施。炎暑の中30分間で176筆が集まりました。(田中聰司)
長崎
ノーベル委員会のフリードネス委員長ら4人は23日、長崎市を訪問し鈴木史朗市長と面会して平和賞メダルのレプリカを貸与しました。爆心地公園で献花のあと長崎原爆資料館を訪れ、夏休みに向けて再展示されている「日本被団協ノーベル平和賞記念展」を合わせて見学しました。
国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館でフリードネス氏は芳名帳に「ここ長崎で想像を絶する苦しみを永遠に続く平和への叫びに変えた方々に対し心からの称賛を贈る」と記帳しました。
長崎被災協の講堂で田中重光日本被団協代表委員(長崎被災協会長)とフリードネス氏は「再び会えて嬉しいです」と笑顔で硬い握手を交わしました。被爆者4団体の代表らと、ノーベル平和賞受賞、そしてフリードネス氏の言葉に被爆者はたいへん励まされたこと、被爆の実相を語り伝えることの重要性、今の危機的な世界の状況だからこそ抑止論ではなく対話をと若者に訴えていくこと、など懇談しました。
フリードネス氏らは「長崎で若者と語り合い大変有意義だった。この被爆者との懇談がまた重要な時間となった」と述べました。(柿田富美枝)
 |
 |
| フリードネスさん | 広島・箕牧さんと |
 |
 |
| 長崎・田中さんと | 長崎被災協講堂で |
中学生が平和宣言
 |
第39回宮城県原爆死没者追悼平和祈念式典が7月20日、仙台市戦災復興記念館で執り行なわれました。
仙台二華中学校2年生の小野寺ゆまさんが平和宣言。日本被団協のノーベル平和賞受賞を讃えるとともに、今も原爆と放射線の影響に苦しむ人々に心を寄せ、「本来科学技術は人々を幸せにするためにある」ときっぱり述べました。そして「本当の平和とは、ただ戦争がないことではなく、互いを尊重し、助け合い、理解しあう世の中にある、その小さな積み重ねを大切にしたい」と結び、会場には感動の波が広がりました。
追悼の言葉は原爆被害者の会会長木村緋紗子さんが核兵器廃絶の想いを決意込めて訴え、宮城県知事(代理)、仙台市長、県内の主な政党の代表があいさつしました。
最後に、木村会長と被爆者の伊藤さんが並び、被爆者の想いを込めて挨拶。被爆二世3人が紹介され、代表して木村仁紀さんが「できることを一つひとつやっていきたい、お力添えをお願いしたい」と述べました。
追悼合唱は、合唱団ふきのとうと宮城のうたごえ協議会が務め、式典を通して塚野淳一さんにチェロを奏でていただきました。(核兵器廃絶ネットワークみやぎ)
相談のまど
住宅改修に援助の制度は?
介護保険や自治体の制度活用を
【問】夫婦2人世帯です。まだ2人とも介護保険は利用していません。
最近足腰が弱り、外出のため玄関から外に出るのに不安があります。また、2階への上り下りがつらくなってきて「手すり」があるといいな、と話し合っているのですが、わずかな年金生活では、すぐに工事を頼むこともできません。少しでも援助の制度があれば助かるのですが。
* * *
【答】2階への上り下りや玄関から外に出る際のわずかの階段も、高齢になると危険を伴うこともあるし、不安を感じることも増えてきますね。
住宅改修については被爆者健康手帳での助成はありませんが、介護保険制度の住宅改修は介護度「要支援1」から、ひとり20万円の範囲で利用できます。自己負担額は利用料負担割合によって1割、2割、3割のいずれかです。
まだ介護保険サービスを利用していないとのことですが、各自治体で、65歳以上の人を対象に同様の制度が実施されています。
すでに介護保険を利用している場合にはケアマネジャーに、利用していない場合は地域包括支援センターか自治体の高齢者支援課などに相談してみてください。
住宅改修は①手すりの設置 ②段差解消 ③滑り防止で床材の変更 ④浴室のドアを折れ戸にする、などが対象です。
事前申請が必要です。知り合いに大工さんがいるからと工事を頼むと助成の対象にはなりませんので気をつけましょう。
あなたの場合は役所から担当者が自宅訪問し、状況を判断することになります。必要書類などその時に教えてくれますので、準備してください。


